

| 継体天皇(???-527?) | |
| 欽明天皇(???-571) | |
| 敏達天皇(???-585) | |
| 押坂彦人大兄(???-???) | |
| 舒明天皇(593-641) | |
| 天智天皇(626-672) | 越道君伊羅都売(???-???) |
| 志貴親王(???-716) | 紀橡姫(???-709) |
| 光仁天皇(709-782) | 高野新笠(???-789) |
■コラム
| ■藤原親正について (附 功徳院僧正快雅、律師聖円) |
| ■永福寺(三笠山永福寺)について |
| ■「鎌倉家」家政機関と執権および「得宗」家について |
| ■常陸入道念西とその周辺 |
千葉氏五代。四代・千葉介常重の嫡男。母は平政幹娘。妻は秩父太郎大夫重弘娘。元永元(1118)年5月24日誕生(『吾妻鏡』建仁元年三月廿四日条)。位階は正六位上。職は下総権介(在国司職)、相馬郡司。荘官としては相馬御厨下司職、千葉庄検非違所。
 |
| 千葉介常胤像(千葉市立郷土博物館蔵) |
常胤は千葉氏を国衙在庁の地位から、公卿(鎌倉家)御家人の筆頭の地位まで昇らしめた千葉家中興の祖。下総千葉惣領家をはじめ、九州の小城千葉氏、勅撰歌人を輩出した東氏、東北は相馬氏や亘理氏といった室町、戦国大名の遠祖であり、岩手県や宮城県などの東北地方に多い千葉家も彼の血を受け継ぐといわれている。常胤以降、千葉氏やその一族は諱に「胤」の一字を用いることが多くなる。
源頼朝の挙兵が成功したのは、千葉介常胤・上総権介広常といった両総平氏の協力が非常に大きい。頼朝は常胤をして「師父」と呼び、弟・範頼に宛てた手紙の中でも「およそ、常胤の大功においては、生涯さらに報謝を尽くすべからざる」ことを申し送っている。また、「千葉介、殊に軍にも高名し候ひけり。大事にせられ候ふべし」と但し書きがなされる(『吾妻鏡』)ほど、戦の上手としても頼朝の信任あつい人物であった。
常重、常胤の所職「下総権介」は国衙の在国司職で、在庁官人の実務官である。国司より在国司職として補任され、実務官として国政を担った。常重や常胤も下記のような国司庁宣を以って補任されたと思われる。
●久安5(1149)年7月「日向国司庁宣案写」(『平安遺文』2673号):関幸彦『「在国司職」成立に関する覚書』1979
常重の弟(常胤の叔父)海上余一常衡も「下総権介」であるが、在国司職の「権介」は除目により補任される律令国司とは異なり、同時期に複数存在する例があり(寛治七年八月廿九日「日向国符宣」『平安遺文』1320:関幸彦『「在国司職」成立に関する覚書』)、常衡は常重または常胤と同時期に「権介」だった可能性もある。常衡はその通称「余一」から平常兼の十一男(常重の弟)とされているが、鎌倉期成立の『徳嶋本千葉系図』『桓武平氏諸流系図』によれば、常衡(常平)はいずれも常重よりも輩行が前にあり、「実常兼子」の註があるように実際には常兼の庶長子だったのだろう。彼は祖父・千葉大夫常長の十一男に擬されているように、祖父常長の養子とされている。
『桓武平氏諸流系図』(中条家文書) 千葉常永―+―千葉恒家 |
『徳嶋本千葉系図』 千葉常長――+―千葉常兼――+―海上常衡 |
常衡は海上郷の地理的条件の中、内海(香取海)を通じて隣り合う常陸大掾家と縁戚関係にあったと推測され、「常衡」やその子「常幹」の片諱にある「衡」「幹」がそれをうかがわせる。常衡自身も「余一平(余一兵衛の意)」(『徳嶋本千葉系図』)とあるように兵衛尉に任官していた形跡があり、常衡の孫・常親は「大夫=五位」と、東国の豪族が与えられる官位としては相当高いものであった(常胤は「正六位上」)。
■海上氏略系図
⇒平常兼―海上与一介常衡―介太郎常幹―小大夫常親―小大夫次郎常宗
・海上与一介常衡⇒「海上庄」を領した「下総権介」平氏の十一男(与一)の常衡
・海上介太郎常幹⇒「下総権介」の「長男=太郎」である常幹
・小大夫常親⇒「五位=大夫」である父・常幹の子の「五位=大夫」の常親
・小大夫次郎常宗⇒「小大夫」の常親の「次男=次郎」の常宗
なお、父・常重は康治2(1143)年までの存命は確認できるが、久安2(1146)年には常胤が常重に代わって「相馬郡司」に補され、「親父常重」の契状に基づいて「(常重子孫が継承する)御厨下司」になっていることから、常重は康治2(1143)年から久安2(1146)年までの間に亡くなったと推測される。
平安時代末期、相馬郡内の相馬御厨は権力闘争の渦に巻き込まれていた(野口実『中世東国武士団の研究』高科書店 1994年)。
 |
| 御厨南限の手下水海(手賀沼) |
下総国相馬郡は、「自経兼五郎弟常晴相承」(永暦二年二月廿七日『正六位上行下総権介平朝臣常胤解写』)とあるように、千葉次郎大夫常兼(常重父)から五郎弟の五郎常晴へ「相承(相伝承継)」された。これは常晴が相馬郡内「地主職」に関わる公験をすでに承継していたことを意味する。そして常晴は「相承之当初、為国役不輸之地」と、地主職に任じられた地のうち「藺沼(柏市上利根一帯の低地)」の内海を中心とする一帯を伊勢皇太神宮に寄進(「布瀬墨埼御厨」とみられる)し、不輸の国免を得た。
さらに常晴は郡務承継の「進退(領)掌之時、立常重於養子」とあるように、相馬郡を承継したのと同時に甥・常重を養子とした(この時点では郡内地主職の継承はない)。つまり、相馬郡承継は当初より常晴から常重への承継が前提として常晴に譲られたものと想定できる。推測だが常兼が急病等で弟の常晴にまだ若い常重を託したものと思われる。
なお、常重には異母兄と思われる「常衡(常平)」がおり、彼は早々に常兼父の千葉大夫常永(常長)の養子(つまり祖父養子)とされ、在国司職「下総権介(余一介)」を務めた。その後、下総国海上郡へ移り「海上」を称している。常永(常長)からは常兼に譲られたであろう海上郡「立花郷(橘川郷)」「小見郷(麻續郷)」を除く、「木内郷(城上郷)」「三埼郷(三前郷)」「阿玉郷(編玉郷)」など海上郡一帯の地主職を譲られていたのだろう。
●『桓武平氏諸流系図』(中条家文書) 千葉常永―+―千葉恒家 |
●『徳嶋本千葉系図』 千葉常長――+―千葉常兼――+―海上常衡 |
■10世紀当時の下総(之毛豆不佐)郡郷(『和名類聚抄』)
| 郡 | 郷 |
| 葛飾郡 | 度毛、八嶋、新居、桑原、栗原、豊嶋、餘戸、驛家 |
| 千葉郡 | 千葉、山家、池田、三枝、糟[草冠+依]、山梨、物部 |
| 印旛郡 | 八代、印旛、言美、三宅、長隈、島矢、吉高、舩穂、日理、村神、餘戸 |
| 迊瑳郡 | 野田、長尾、辛川、千俣、山上、幡間、石室、迊瑳、須加、大田、日部、玉作、田部、珠浦、原、栗原、茨城、中村 |
| 相馬郡 | 大井、相馬、布佐、古溝、意部、餘戸 |
| 猨嶋郡 | 塔陁、八侯、高根、石井、葦津、色益、餘戸 |
| 結城郡 | 茂治、高橋、結城、小埇、餘戸 |
| 豊田郡 | 岡田、飯猪、手向、大方 |
| 海上郡 | 大倉、城上、麻續、布方、軽部、神代、編玉、小野、石田、石井、橘川、横根、三前、三宅、舩木 |
| 香取郡 | 大槻、香取、小川、健田、磯部、譯草 |
| 埴生郡 | 玉作、山方、麻在、酢取 |
その後、常晴は地主職を常重に譲り、おそらくその直後と思われる天治元(1124)年6月、常重へ「所譲与彼郡也」(久安二年八月十日『正六位上平朝臣常胤寄進状』(『櫟木文書』:『鎌倉遺文』所収))した。そして、この四か月後の天治元(1124)年10月、国司は常重に「可令知行郡務之由」の「国判」を下した(久安二年八月十日『正六位上平朝臣常胤寄進状』(『櫟木文書』:『鎌倉遺文』所収))。これにより、常重は正式に「相馬郡司」となった。
●久安2(1146)年8月10日『正六位上平朝臣常胤寄進状』(『鏑矢伊勢宮方記』:『千葉県史料』中世編)
平常晴は兄・常兼から相馬郡を「相承之当初」に「為国役不輸之地」として申請し、認可された。この「為国役不輸之地」は当然ながら「(相馬)郡」という公的行政区分を指すのではなく、郡内で代々開発を続けて「地主職」に任じられた相伝私領のうち、皇太神宮領として寄進された「布瀬墨埼御厨」である。その庄域は、のちの「相馬御厨=布瀬(布施)郷」と同域と思われ、相馬郡衙・於賦駅のある相馬郡の中心地「黒埼郷」(「意部郷」「布佐郷」(我孫子市東部から利根町立木))と、「相馬郷」(我孫子市西部から野田市東部の木野埼・目吹、守谷市から取手市)から成り、低湿地域は餘戸として民家が点在した状況だったのではなかろうか。「布瀬郷(布施郷)」は「布瀬郷内保村田畠在家海船等注文」(大治五年六月十一日『下総権介平経繁副状写』(『櫟木文書』:『鎌倉遺文』所収)とあるように、郷内に国衙領の保や村が複数存在し、内海(中心域に広がる藺沼や衣河の河口付近であろう)に面して多くの船もあったことがわかる。そして、この「布瀬墨埼御厨」の領家は「前大蔵卿殿」だった。
■布施(布瀬)郷(「布施墨埼御厨」)の推定地
| 郷名 | 『倭名類聚鈔』旧郷 | 現在地 |
| 相馬郷 | 相馬郷、餘戸 | 野田市東部から柏市、我孫子市西部、守谷市、取手市 |
| 黒埼郷 | 意部郷、布佐郷、餘戸 | 我孫子市東部~利根町、つくばみらい市 |
かつての「布瀬墨埼御厨」に関する公験は、大治5(1130)年6月の寄進に際して「若横人出来、号地主有相論時、為証文所令進上也」(大治五年六月十一日『下総権介平経繁副状写』(『櫟木文書』:『鎌倉遺文』所収)とした常重所持の五通の「相馬郡布瀬郷証文」に含まれており、「国司庁宣布瀬墨埼為別符時、免除雑公事案」で「別符」の国宣が下され「免除雑公事」された荘園(御厨)であった。
その後、常重は「為仰神威、定永地」という祈念のもと、後述の通り、大治5(1130)年6月11日、「相馬郡布施郷(布瀬郷)」を「貢進太神宮御領」した(大治五年六月十一日『下総権介平朝臣経繁寄進状』(『櫟木文書』:『鎌倉遺文』所収))。先述の通り、この寄進地「布施郷(布瀬郷)」については、かつて常晴が「為国役不輸之地」と認められた「布瀬墨埼御厨」と同じ範囲と思われ、「相馬郷、意部郷、布佐郷の総称」であろう。
■相馬郡布施郷=相馬御厨の四至
・限東…蛟蛧境(利根町立木、小文間、布川周辺)
・限南…志古多谷并手下水海(柏市篠籠田、手賀沼)
・限西…廻谷并東大路(野田市木野埼)
・限北…小阿高、衣河流(つくばみらい市小足高、小貝川)
常重が大治5(1130)年6月に伊勢皇太神宮へ寄進するきっかけとなったのは、おそらく副状の三条目にある領家の「前大蔵卿」が、死去等により不在になったことと思われる。常重は新たな領家を探すべく、知己の「散位源朝臣支定」を口入人として皇太神宮の権禰宜延明に繋ぎをつけ、彼を口入神官として皇太神宮への寄進まで漕ぎつけたのだろう。なお、「布瀬墨埼御厨」の領家だった「前大蔵卿殿」について、文書に具体的な名前はみられないが、承保2(1075)年から長承3(1134)年までの大蔵卿は、以下の通り。
■歴代の大蔵卿(『公卿補任』)
| 大蔵卿の姓名 | 就任期間 | 大蔵卿辞後 |
| 藤原長房 | 承保2(1075)年6月~寛治6(1092)年9月7日 | 播磨権守兼大宰大弐 |
| 藤原通俊 | 寛治6(1092)年9月7日~寛治8(1094)年 | 治部卿 |
| 源道良 | 寛治8(1094)年~天永2(1111)年4月24日 | 死亡 |
| 大江匡房 | 天永2(1111)年7月29日~天永2(1111)年11月5日 | 死亡 |
| 藤原為房 | 天永3(1112)年正月26日~永久3(1115)年4月2日(4月1日出家) | 出家、翌日死亡 |
| 藤原長忠 | 永久3(1115)年8月13日~大治4(1129)年11月3日(10月5日出家) | 出家、まもなく死亡 |
| 源師隆 | 大治4(1129)年~長承3(1134)年 |
常重が「相馬郡布瀬郷」の寄進状を提出した大治5(1130)年6月当時の大蔵卿は源師隆で、その「前大蔵卿」は藤原長忠である。長忠は永久3(1115)年から大蔵卿であり、相馬常晴が「布瀬墨埼郷」を寄進した時期と矛盾はない。また、常重が証文を提出する半年前の大治4(1129)年10月5日に大蔵卿を辞しており、常重の証文中の「前大蔵卿」は長忠で間違いないだろう。長忠は辞任後直後の大治4(1129)年11月3日に薨じている。
+―藤原道隆―――藤原伊周――女子
|(関白) (内大臣) ∥
| ∥
藤原師輔―――藤原兼家――+―藤原道長 ∥―――――藤原能長
(右大臣) (関白) (関白) ∥ (内大臣)
∥ ∥ ∥
∥――――――――――――藤原頼宗 ∥―――――藤原長忠
醍醐天皇―+―源高明―――――源明子 (右大臣) ∥ (大蔵卿)
|(左大臣) +=(高松殿) ∥
| | ∥
+―盛明親王―+ ∥
|(上野太守) ∥
| ∥
+―村上天皇――――冷泉天皇―――花山天皇――昭登親王――女子
(中務卿)
常重は「但至于田畠所当官物者、令進退当時領主給」としているように(大治五年六月十一日『正六位上行下総権介平朝臣経繁解申永奉附属所領地事』)、本来国衙に納めるべき得分以外の「田畠所当官物」を「当時領主」への給分と定めたことがわかる。この寄進時においては相馬御厨の「田畠所当官物」は「当時領主」の皇太神宮(実質的には一禰宜荒木田元親、権禰宜荒木田延明)の「進退」となり、「田畠所当官物」も「地利上分」に充当されたとみられる(村川幸三郎『古代末期の「村」と在地領主制』)。相馬御厨の「所当官物」を「地利上分」に含めることは、のち常胤が出した寄進状の記載でも明らかなように、国衙に認められていた。
●大治5(1130)年6月11日『下総権介平朝臣経繁寄進状写』(『櫟木文書』:『鎌倉遺文』所収)
●大治5(1130)年6月11日『下総権介平朝臣経繁寄進状写』(『櫟木文書』:『鎌倉遺文』所収)
寄進に際して「相副調度文書等、永令附属仮名荒木田正富先畢」しているが、この副状には「布瀬郷証文」「布瀬郷内保村」とあるように、寄進地として「布瀬郷」が記されている。
●大治5(1130)年6月11日『下総権介平経繁副状写』(『櫟木文書』:『鎌倉遺文』)
常重からの寄進状や副状、条件を記した起請などの附嘱状は、散位源友定を通じて口入神主・荒木田延明(仮名正富)へと渡され、8月22日に延明が請文二通を認めて禰宜荒木田元親へ提出。一通は両通同定を経て延明へ返却され、寄進が成立した(大治五年八月廿二日『権禰宜荒木田延明請文写』)。
●大治5(1130)年8月22日『権禰宜荒木田延明請文写』(『鏑矢伊勢宮方記』:『平安遺文』)
荒木田延明請文に付された常重の起請には、開発田数に任せて地利上分・土産物等の上納が示されており、常重とその子孫は「得分」として「加地子」を取る権利を得た。寄進条件は、毎年「供祭料」として「地利上分(田:段別一斗五升、畠:段別五升)」と「土産物(雉佰鳥、鹽曳鮭佰尺)」を皇太神宮の「一禰宜荒木田神主元親」と口入神主「権禰宜荒木田神主延明」に納めることであった。
■常重が寄進した相馬御厨の荘官及び荘園領主
| 職 | 人物 | 得るもの | 備考 |
| (本家) | 荒木田元親神主(その子孫) | 地利上分+土産物の半分 (件濟物之内、相分半分定) →供祭料 |
一禰宜(皇太神宮) |
| (領家) | 権禰宜荒木田延明(その子孫) | 地利上分+土産物の半分 (件濟物之内、相分半分定) |
口入神主(皇太神宮) |
| 預所 | 散位源朝臣支定(その子孫) | 荘園からの貢物の一部 | 口入人 |
| 下司職 | 下総権介常重(その子孫) | 加地子(貢物:地子に追加した徴収物) | 開発領主 |
■相馬御厨の寄進条件の貢納品(荒木田元親、荒木田延明)
| 供祭料 | 地利上分 | 田:段別1斗5升 畠:段別5升 |
| 土産物 | 雉:100羽 塩曳鮭:100尾 |
■皇太神宮「御厨」の支配構造
そして、四か月後の大治5(1130)年12月、「領使権守藤原朝臣」の「庁宣」によって「相馬郡司(常重)」による「布瀬郷」の皇太神宮寄進は公式に認められた。この「庁宣」は「権守藤原朝臣」を署名者としていることから、この時点で「下総守」の在国はなかったことがわかる。
●大治5(1130)年12月『下総国司庁宣案』(『櫟木文書』:『鎌倉遺文』所収)
当時の「下総守」については、翌天承元(1131)年11月17日、大殿忠実の夕刻院参につき忠実の「前駈六人」として加わった一人に「下総守盛邦」(『時信記』天承元年十一月十七日条)が見える。この「盛邦」は姓が闕であるが、源盛邦(『尊卑分脉』醍醐源氏)であろう。盛邦は関白忠実の前駈であるため家人とみられる。つまり、下総国は摂関家の知行国と考えられる。翌長承元(1132)年4月21日、齋院御祓に際して賀茂斎院恂子内親王(のちの上西門院統子)の父院・鳥羽院は三條殿より出御され、東洞院西辺に牛車を立ててご覧になった。その「祓斎」の「前駈」として、斎院長官源資賢(左兵衛権佐)の代理として「左兵衛佐代下総守盛固」(『中右記』長承元年四月廿一日条)が見えるが、「固」は「國」の誤記であろう。
| 禊齋上卿 | 新大納言実行 |
| 宰相中将宗能、左少弁公行、権少外記中原義収、史齋部孝隣 | |
| 前駈 | 左衛門佐経雅、右衛門佐季兼、左兵衛佐代下総守盛固、右兵衛佐盛章、右衛門権少尉平時作、 検非違使左衛門権少尉源親康、検非違使左兵衛権少尉源行賢、右兵衛権少尉源次清、 次第使右馬助源光成、左馬少允宮道式成 |
| 斎院長官 | 左兵衛佐参河守資賢 |
齋院御祓から七か月後の同長承元(1132)年11月23日当時、「守下向国々」(『中右記』長承元年十一月廿三日条)として「下総」が見られるように「下総守」は下総国に下向していたことがわかるが、盛邦であろう。
藤原定隆
(左京大夫)
∥
醍醐天皇―――源高明 +―女子
(左大臣) |
∥ |
∥―――――源忠賢―――源守隆―――源長季―――源盛長―――源盛家―――源盛邦――+―源家季
∥ (右兵衛佐)(右馬頭) (備前守) (淡路守) (摂津守) (下総守カ)
藤原師輔―+―女子
(右大臣) |
+―藤原兼家――藤原道長――藤原頼通――藤原師実――藤原師通――藤原忠実――藤原忠通
(関白) (関白) (関白) (関白) (関白) (関白) (関白)
盛邦の次の下総守は下野国(待賢門院領か)から国替した藤原親通であった。親通は保延4(1138)年11月6日、「守藤原朝臣親通募重任功、造進彼社(香取大神宮)」によって重任(「安芸国厳島社神主佐伯景弘解」『広島県市古代中世資料編Ⅱ』)していることから、おそらく長承3(1134)年閏12月15日の「秋除目」で任官した「別事功過定三ヶ国不見、相伝國四ヶ國、任人凡四十八人也」(『中右記』長承三年閏十二月廿四日条)の一人なのだろう。
長承3(1134)年閏12月24日に左大臣が奏上した「当年荒奏」の「当年不堪六通、副文下総国不堪五通、同減省一通」(『中右記』長承三年閏十二月廿四日条)とある通り、下総国は当年については「荒(凶作)」のため「不堪(納貢不能)」の郡郷が六か所、「減省(軽減)」を求める郡郷が一か所ある旨、下総国司が請しているが、これは前司盛邦の奏となる。
常胤は保延元(1135)年までに秩父出羽権守重綱孫娘(秩父重弘女)と婚姻している。保延元(1135)年は常胤十八歳であった。保延2(1136)年に嫡男胤正が誕生、その三年後の保延5(1139)年には二男師常が誕生している。下総国の千葉氏の十八歳以下の嫡子と武蔵国の秩父畠山氏の女子が婚姻関係を結ぶにあたっては、当然ながら当人同士が直接的に関わったとは考えられない。つまり「外部」の影響があったことは確実であろう。
当時の秩父重綱は故陸奥守源義家の子・検非違使尉源為義の家人の立場にあったとみられ、後述の通り、為義嫡子の義朝、その嫡子義平は重綱が世話をしている。また、為義嫡子義朝は「上総介常澄」と関わりを有していることから、為義は上総国とも関わりがあったことがわかる。武蔵国と上総国を挟む下総国とも関わりがあった可能性はあろう。為義は上野国、下野国にも家人を有しているように関東各地に家人がおり、それらを繋ぐネットワークがあったと考えられる。常胤と秩父重弘女との婚姻は為義の仲介が強く関わっていると考えられよう。
常胤嫡子胤正が生まれた年である保延2(1136)年7月15日、常重は「国司藤原朝臣親通」によって「有公田官物未進」の罪で拘束された(久安二年八月十日『正六位上平朝臣常胤寄進状』)。未進とされたのは、親通が補任された保延元(1135)年分の官物であろう。その前年の未進分であれば、新司親通から前司源盛邦に対する不与解由状が提出され、盛邦は官途に就くことができないためである。しかし、盛邦は下野守となっており、解由が認められたことがわかる。つまり、常重の官物未進は親通補任後のことであり、保延元(1135)年の官物と考えられるのである。
相馬御厨は「国免」の荘園であるため、親通が国司免判を与えなければ不輸権は認められず、保延元(1135)年中は与えていなかったのだろう。この前年長承3(1134)年閏12月に朝廷に報告された「不堪佃田」(『中右記』長承三年閏十二月廿四日条)については、下総国が「不堪」の申請をしているように凶作だったことから、常重は相馬郷(=布施郷+黒埼郷一帯)および海上郡立花郷に関する官物貢進が果たせなかったのではなかろうか。結局、常重は拘束されて未納分が「勘」考された。その調査期間が「旬月(数日の意味だろう)」の拘束であろう。そして未進分は「准白布七百弐拾陸段弐丈伍尺五寸」と算出されたのである。
この未進分「准白布七百弐拾陸段弐丈伍尺五寸」がどれほどの量だったのか。当時の基準が残されていないため厳密な計算はできないが、久安2(1146)年に常胤が国庫に進済した「上品八丈絹参拾疋、下品七拾疋、縫衣拾弐領、砂金参拾弐両、藍摺布上品参拾段、中品五拾段、上馬弐疋、鞍置駄参拾疋」がそれと同等の価値だった可能性が高いだろう。
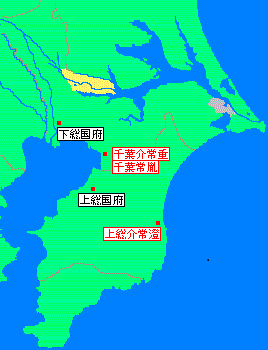 |
| 布施郷(西)・立花郷(東)の大体の位置 |
国司親通は、未進分「勘負准白布七百弐拾陸段弐丈伍尺五寸」に対する「辨進」として、保延2(1136)年11月13日、庁目代散位紀季経に指示をして「押書相馬立花両郷之新券恣責取署判」し、相馬郷と立花郷を「妄企牢籠」た(久安二年八月十日『正六位上平朝臣常胤寄進状』)。これらは「相馬立花弐箇處私領辨進之由、押書新券」(永万二年六月十八日『荒木田明盛和与状写』)とあるように官物未納の「辨」であるため、親通は常重に反論の余地を与えないために「私領辨進」の「押書」を取り、公験(正文ではなく案であろう)とともに押収したのだろう。ただしこれは「担保」物件であるため、「押書」には未進分を「進済於国庫」に際しては、新券の「返与」が明記されていたとみられる。なお、のちに義宗が主張する中に「依官物屓(負)累、譲国司藤原親通」(永暦二年正月『正六位上前左兵衛少尉源義宗寄進状』)とあるが、官物は国庫に納めるもので国司個人への債務ではなく、当然ながら義宗の主張は虚偽である。
こうして、常重から「相馬立花両郷」の「弁進」を受けた国司親通は、この新券を以て両郷を「形式上」は国衙管理とした。それはこの常重「新券」が次の下総国司にも継承されていたことからも明らかであろう。相馬御厨の国免も下された形跡はなく、相馬郷からの貢物が規定通り行われたかも定かではなく、常重が下司職を継続できたかも不明である。なお、この両郷は実際には親通が押領したとみられ、後述の通り、立花荘は私君の関白忠通へ寄進され、相馬郷は二男親盛へ譲られた。なお、『尊卑分脉』では親盛は三男で、長男は親頼(右馬助)、次男は下総守親方である。親頼らについては後述。
-千田庄藤原氏家系図-
藤原師輔―+―兼家――+―道綱 +―伊周 +―親頼――+―親長 +―親長――――+―宣親
(関白) |(関白) |(右大将)|(内大臣) |(右馬助)|(皇嘉門院判官代)|(皇太后宮亮)|(日向守)
| | | | | | |
| +―道隆――+―隆家 | +―親能――――――+―親光 +―忠能
| |(関白) (太宰権帥) | (散位) (律師)
| | |
| +―道長――――頼通―――師実―――… +―親方(源?)―――――二条院内侍
| (関白) (関白) (関白) |(下総守) |
| | ↓
+―為光――――公信――――保家―――公基―――伊信―――親通――+―親盛―――+=====二条院内侍
(太政大臣)(権中納言)(春宮亮)(周防守)(長門守)(下総守)|(下総大夫)| ∥
| | ∥
| | ∥――――資盛
| | ∥ (右少将)
| | +―平清盛―――重盛
| | |(太政大臣)(内大臣)
| | |
| | +―娘 +―功徳院快雅
| | ∥ |(功徳院僧正)
| | ∥ |
| +―千田親雅――――+―聖円
| |(皇嘉門院判官代) (権律師)
| |
| +―盛光
| |(筑前権守)
| |
| +―盛保
| |(散位)
| |
| +―顕盛==日野邦俊――邦行―――種範―――俊基
| | (彈正少弼)(大学頭)(治部卿)(少納言)
| |
| +―円玄
| |(法橋)
| |
| +―弁然
|
|
+―承元―――+―承長
| |
| |
+―円空 +―覚経
|
|
+―忠顕
(阿闍梨)
相馬御厨は千葉介常胤の父・常重が相馬郡布施郷(相馬郷と同意か)を伊勢内宮に寄進して成立した寄進地系の荘園である。相馬御厨(布瀬墨埼御厨を含め)は千葉介常重、源義朝、千葉介常胤、源義宗、千葉介常胤と、大治5(1130)年から永暦2(1161)年の三十年にわたって六回の寄進が行われている。ただし、常重は布施郷を寄進する以前、天治元(1124)年10月から大治4(1129)年までの間に、相馬郡内の「布瀬郷」「墨埼郷」の別符地の二郷を大蔵卿藤原長忠を領家として伊勢内宮に寄進しており、これが相馬御厨の前身となる「布瀬墨埼御厨」である。
『下総権介平朝臣経繁寄進状写』によれば、「経繁相伝之私領」である「相馬郡布施郷」を寄進する旨が記され、その「四至」として、東は蚊虻境、南は志子多谷・手下水海、西は廻谷・東大路、北は小阿高・衣川流が記されている。
| 年月日 | 東端 | 南端 | 西端 | 北端 | 文書 | |
| 前身 | 天治元(1124)年10月 ~大治4(1129)年 |
不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 布瀬墨埼御厨 『下総権介平経繁布瀬郷文書注進状写』 |
| 1 | 大治5(1130)年 6月11日 |
蚊虻境 | 志子多谷并手下水海 | 廻谷并東大路 | 小阿高并衣河流 | 『下総権介平朝臣経繁寄進状写』 |
| 2 | 天養2(1145)年 3月 |
須渡河江口 | 藺沽上大路 | 繞谷并目吹岑 | 阿太加并絹河 | 『源義朝寄進状写』 |
| 3 | 久安2(1146)年 8月10日 |
逆川口・笠貫江 | 小野上大路 | 下川辺境并木埼廻谷 | 衣川・常陸国境 | 『平朝臣常胤寄進状写』 |
| 4 | 永暦2(1161)年 正月日 |
常陸国堺 | 坂東大路 | 葛餝・幸嶋両郡堺 | 絹河・常陸国境 | 『前左兵衛少尉源義宗寄進状写』 |
| 5 | 永暦2(1161)年 2月27日 |
逆川口・笠貫江 | 小野上大路 | 下川辺境并木埼廻谷 | 衣川・常陸国境 | 『下総権介平常胤解案写』 |

<1>蚊虻境 <2>須渡河江口 <3><5>逆川口・笠貫江 <4>常陸国堺
<1>「蚊虻境=蛟蛧境」については、現在の茨城県北相馬郡利根町立木周辺は古代、大蛇=蛟(みずち)のように川筋が入り混じっていて、一帯は「蛟蛧(こうもう)」と呼ばれていた。延喜式内社として「蛟蛧神社」があり、現在でも台地上に二つの蛟蛧神社がある。とくに「奥ノ宮」と呼ばれる東の神社は台地の最東端に位置しており、平安期にはこのあたりまで「衣川(鬼怒川=小貝川)」が入り込み、蛟蛧神社直下の笠貫江は常陸国境と接していた。
<2>「須渡河江口」については、現在の竜ケ崎市須藤堀町周辺と思われ、「須渡河」の「江口」のことと推測される。「須渡河」は現在の河川には見えないが、蛟蛧神社眼前に河口があった衣川の一流であろう。
<3><5>「逆川口」「笠貫江」については、「逆川」は不詳だが潮の満ち引きで内海の水が河口を遡上した川であり、須渡河と同一の河川であろう。「笠貫江」に関しては、蛟蛧神社の南東に広がっていた衣河の河口であろう。「笠貫」は「文間明神ノミタラシヲ笠貫ト云」(『下総国旧事考』)とあり、蛟蛧神社の「御手洗(禊をする場所)」を指した。
これらから、<1><2><5>とおそらく<3>もいずれも蛟蛧神社の東側を流れる河川によって相馬御厨の境界が定められており、それらはすべて小貝川の河口付近に設定されていて、<4>「常陸国堺」に通じている。
<1>志子多谷并手下水海 <2>藺沽上大路 <3><5>小野上大路 <4>坂東大路
<1>「志子多谷并手下水海」については、「志子多谷」は現在の柏市篠籠田(しこだ)のことで、手賀沼へ流れ込む大堀川の南側にある。「手賀水海」は現在の手賀沼のことで、古代から中世にかけて千葉県北部に広がっていた広大な入江・香取海の一部を形成している。
 |
| 藺沼のイメージ |
<2>「藺沽上大路」の「藺沽」は「藺沼(いぬま)」のことで、菅生沼(水海道市菅生町)から利根川に注ぐ「飯沼川」周辺、現在の東海寺(布施弁天)北麓の水田地一帯、取手市・我孫子市・柏市あたりにあった大きな沼地(飯沼=幸嶋広江)と思われる。「大路」は官道を指しており、国府と国府を結ぶ重要な道路であった。相馬郡内には、下総国府から常陸国府へ至る大路が現在の柏市藤心(茜津駅)あたりから根戸(我孫子市根戸)の津または船戸(我孫子市船戸)の津への船道を経て、東の文間まで直進していたと思われ、その大路を指していると思われる。
<3><5>「小野上大路」についても、上記<2>「藺沽上大路」や<4>「坂東大路」<4>と同じ大路と思われる。
<1>廻谷并東大路 <2>繞谷并目吹岑 <3><5>下川辺境并木埼廻谷 <4>葛餝・幸嶋両郡堺
<1><2>「廻谷并東大路」の「廻」は「メグリ」とよみ、境界線を表す。東大路の存在は不明だが、<2>に見られる「繞谷」の「繞」も「メグリ」と読み、同一の地域を指していると思われる。つまり、<1>の「東大路」が走っていたところと「目吹岑」がほぼ同じ地域にあったと思われる。「目吹岑」は現在の野田市目吹付近の「岑」のことと思われ、熊野神社・香取神社などがある丘一帯か。
<3><5>「下川辺境」は葛飾郡下河辺庄の境目である太日川(大井川=江戸川)、「木埼」は現在の野田市野木埼に相当すると思われ、目吹とは北接している。木野埼は平安時代にはまだ川が流れていたと思われ、南の瀬戸と北の目吹の間に谷を形成して、「廻谷」と呼ばれていたのかもしれない。
<4>「葛餝(葛飾)・幸嶋両郡堺」については、葛飾郡・猿島郡の境であるから、目吹の前を流れる利根川、さらには南に下って下河辺庄との境の太日川、東経139度54分付近が西の境界となっていたか。
<1>小阿高并衣河流 <2>阿太加并絹河 <3><5>衣川・常陸国境 <4>絹河・常陸国境
<1>「小阿高并衣河流」と<2>「阿太加并絹河」については、「小阿高」「阿太加」は現在の稲敷郡伊奈町足高と推測され、「衣河流」「絹河」は小貝川(=鬼怒川)のことであり、現在の伊奈町城中にある城中八幡神社が中世の陸地の東端であったと推測される。<3><5>「衣川・常陸国境」、<4>「絹河・常陸国境」についても、ほぼ同じく現在の牛久沼の南端を指していると思われる。
なお、相馬御厨としてそれぞれが寄進した範囲はすべて同一の地域を指しているとみられる。「藺沽上大路」「小野上大路」「坂東大路」は、下総国衙から常陸国衙を繋ぐ官道で、手賀沼北岸(現在の柏市東部から我孫子市東部まで)を東西に直行する部分を指すと思われる。
源義朝は、鳥羽院に仕える源為義と院近臣藤原忠清の女子を母として京都で生まれた。若くして東国に下向した理由は諸説あるが、為義が鳥羽院の信任を失って摂関家に近づくにあたり、院近臣の娘を母とする義朝を廃嫡し遠ざける意味があったという説が通説となっている。しかし、義朝は東国に下向して以降、秩父権守重綱の男衾郡を拠点として、上総国、相模国などの地方豪族の間を動きつつ、京都と関東を幾度も往復しており、義朝が関東へ下ったのはあきらかに為義による一族経営の一環である。
義朝が最初に関東へ下向した時期については定かではないが、異母弟の義賢が東宮體仁親王(のち近衞天皇)の春宮坊帯刀先生となった保延5(1139)年8月17日よりも前であろう。「永治二年(1142)」に「被下奉免宣旨也」(『神宮雑書』)された上野国緑野郡高山御厨(藤岡市神田周辺)への「故左馬頭家御起請寄文」(『神宮雑書』)した時点では、すでに関東で行動している。
藤原忠清――女子
(淡路守) ∥―――――――源義朝―――源頼朝
∥ (下野守) (右近衛大将)
源為義
(左衛門大尉)
∥
∥―――――+―源義賢―――源義仲
∥ |(帯刀先生)(伊予守)
∥ |
某重俊―――女子 +―源義憲
(六条大夫) (帯刀先生)
上記の高山御厨(飯能市高山)は「天承元(1131)年建立」の神宮領で、為義が相伝した上野国の私領であろう。その後、「永治二年(1142)」に「故左馬頭家御起請寄文」(『神宮雑書』)に基づき「被下奉免宣旨也」(『神宮雑書』)された。「代々国判」とあることから高山御厨は国免荘である。為義はおそらく亡父義家の譲りを受けた高山郷(御厨建立後は高山御厨)の権益を有し、義朝がこれを嫡子として継承したと思われ、のちに高山御厨が没官されたのは義朝が平治の乱で討たれたためだろう。高山御厨は義朝が下司職となり、実務は「秩父権守(秩父重綱)」(『小代宗妙置文』:石井進『鎌倉武士の実像』平凡社1987)の三男・三郎重遠が派遣されていたのだろう。義朝で没官された高山御厨は、その後、建久6(1190)年8月に「可早任宣旨并故左馬頭家御起請寄文代々国判等旨、如本奉免、被令知行所」として奉免されることとなる。これは同年6月まで在京し、故義朝の復権に尽力した義朝の子・源頼朝の強い働きかけによるものであろう。
高山御厨は、のちに源義賢(義朝異母弟)が館を構えた上野国多胡館(多野郡吉井町多胡)に直線で約7キロと近く、義賢は国司となったために上洛した義朝に代わって、秩父氏との紐帯のために下向を指示されたとみられる。「上野国多胡」は「八幡殿」がこの地の義家郎従とみられる「多胡四郎別当大夫高経」が後三年の役に従わなかったため、「依不奉従于仰、兒玉有大夫広行承討手、以舎弟有三別当為代官、討取四郎別当」(『小野氏系図』)したとあり、もともと上野国南西部には将軍頼義、陸奥守義家の所領が広っていて、為義が高山御厨を建立し、義朝を秩父権守重綱のもとへ遣わしたのも、義朝が下野守となり常京になるに及んで弟の義賢が多胡に派遣されたのも、為義による河内源氏の東国経営が最たる理由であろう。なお、後年、義賢遺児で信濃国木曾郡で平家政権への反旗を翻した木曾冠者義仲は一時多胡郡に立ち寄ったのも、故義賢の誼を通じての軍勢催促であり、治承5(1181)年、越後国から信濃国に攻め込んできた平家党の越後平氏・城越後守資職と千曲川の横田河原合戦の際には義仲方の「上野国住人高山党三百騎」が参戦し、城資職方の老将・笠原平五頼直一党八十五騎と交戦している。頼直は寡勢にもかかわらず奮戦し、高山党は九十三騎にまで討ち減らされたという。ただしこの高山党の中には「上野国住人西七郎広助」という「俵藤太秀郷が八代末葉、高山党に西七郎広助」がおり、上野国高山党とは高山氏のみで構成されたものではなかったようである(『源平盛衰記』)。
義朝の嫡男、源太義平が生まれたのは、永治元(1141)年(『平治物語』より逆算)で、義朝十八歳の時であるが、母は「橋本遊女或朝長同母」(『尊卑分脈』)とある。義平がどこで誕生したのかは不明だが、「秩父権守重綱室妻(児玉党の有三別当経行女)」(『兒玉党系図』)を「号乳母御前」(『小代宗妙置文』)、「号乳母御所、悪源太殿称御母人」(『兒玉党系図』)として慕っていることから、重綱とその妻に養育されて成長したことがわかる。おそらく武蔵国比企郡に誕生したのだろう。義朝は義平を嫡男として扱い、その後見を秩父権守重綱に託したこととなる。このことからも重綱と為義・義朝との間に深い主従関係が構築されていることがわかる。
なお、義朝は武蔵国に常駐していたわけではなく、京都と東国諸国(相模国、上総国、安房国など)の家人の間を行き来し、家人の在庁官人らを使嗾して相模国大庭御厨に乱入させた天養元(1144)年中には上洛して院近臣藤原季範女子と通じ(翌年長女「右武衛室」誕生)、天養2(1145)年には摂津国江口宿にも通い(翌年次女「江口腹の御女」誕生)、季範女子とも通じている(翌年三男頼朝が誕生)。また、五男(四男?)範頼は「於遠州蒲生御厨出生」で「母遠江国池田宿遊女」であり、義朝は京都と関東を往復していたことがわかる。
●源義朝等の動向
| 年 | 月日 | 義朝年齢 | 義朝の所在 | 義朝の動向 | 出典 |
| 保安4年 (1123) |
1歳 | 京都 | 源為義の嫡子として京都に誕生。 | ||
| 天承元年 (1131) |
正月29日以降 | 9歳 | 京都か |
上野国緑野郡高山保?をおそらく父・ 為義が神宮へ寄進して御厨を建立。 |
『神宮雑書』 |
| 天承元(1131)年~保延5(1138)年頃の間に、義朝は関東へ下る。 | |||||
| 保延5年 (1139) |
8月17日 | 16歳 | 武蔵国比企郡か | 弟の源義賢、體仁親王(のち近衛天皇)の立坊に伴い、春宮坊帯刀先生となる。 | 『古今著聞集』より推定 |
| 保延6年 (1140) |
17歳 | 武蔵国比企郡か | 源義賢が瀧口源備殺害に関与していたことが判明して、春宮坊帯刀先生を罷免される。 | 『古今著聞集』巻十五 闘争第廿四 | |
| 永治元年 (1141) |
18歳 | 武蔵国比企郡 |
嫡男の源義平が誕生。 母は橋本遊女。乳母は秩父重綱妻(児玉党の有三別当経行女)。義平は重綱妻を「御母人」と呼ぶ。 |
『兒玉党系図』 | |
| 永治2年 (1142) |
4月28日以前 | 19歳 | 武蔵国比企郡 | 「故左馬頭家御起請寄文」に基づき、上野国緑野郡高山御厨(藤岡市神田周辺)に「被下奉免宣旨」された。 | 『神宮雑書』 |
| 康治2年 (1143) |
20歳 | 上総国一宮か | 「前下野守源朝臣義朝存日、就于件常晴男常澄之浮言、自常重之手、康治二年雖責取圧状之文」と、上総権介常澄と組んで、下総国相馬御厨を千葉常重から圧し取る。 | 『櫟木文書』 | |
| 相模国鎌倉 | この頃、義朝は相模国松田郷を中心とする一帯を抑える波多野義通妹と通じており、鎌倉へ本拠を移したとみられる。このとき、上総国から付けられたのが常澄の八男、介八郎広常であろう。広常は鎌倉北東部に館を構えている。 | 『天養記』 | |||
| 天養元年 (1144) |
21歳 | 相模国鎌倉 | 二男の源朝長が誕生。 母は波多野義通妹。「此殃義常姨母者中宮大夫進朝長母儀典膳大夫久経為子、仍父義通、就妹公之好、始候左典廐」という。朝長は波多野氏のもとで成長し「松田御亭故中宮大夫進旧宅」に住んだという。 |
『吾妻鏡』治承四年十月十七日、十八日条 | |
| 9月上旬 | 相模国鎌倉 | 大庭御厨内の鵠沼郷(神奈川県平塚市鵠沼)は鎌倉郡内であると難癖をつけて領有を主張し、郎従清大夫安行らを鵠沼郷に差し向けて伊介神社の供祭料を強奪した。さらに抗議に出た伊介社祝・荒木田彦松の頭を砕いて重傷を負わせ、神官八人をも打ち据えた。 | 『天養記』 | ||
| 10月21日 | 相模国鎌倉 | 義朝は田所目代源頼清と結託し、「上総曹司源義朝名代清大夫安行、三浦庄司平吉次、男同吉明、中村庄司同宗平、和田太郎助弘」等に命じて再度大庭御厨に濫妨をはたらく。 | 『天養記』 | ||
| 10月22日 | 相模国鎌倉 | 御厨の境界を示す傍標を引き抜き、収穫の終わったばかりの稲を強奪し、下司職景宗の館に乱入して、家財を破壊して奪い取り、家人を殺害した。 | 『天養記』 | ||
| 相模国鎌倉 | 御厨定使散位藤原重親、下司平景宗(大庭景宗)が荘園領主の神宮に急使を派遣して濫妨を訴えた。 | ||||
| 尾張国か | 院近臣藤原季範(熱田大宮司)の女子と通じる。 | ||||
| 天養2(1145)年 | 3月4日 | 22歳 | 尾張国か | 朝廷より義朝らの濫妨停止の官宣旨が出される。 | 『天養記』 |
| 尾張国か | 「恐神威永可為太神宮御厨之由、天養二年令進避文」と、相馬御厨を神宮に寄進する。 | 『櫟木文書』 | |||
| 京都 | 京都近辺に在住か(摂津国江口に通う範囲) | ||||
| 京都 | 長女の「右武衞室」が誕生。 母は院近臣藤原季範女子で頼朝同母姉。 |
『吾妻鏡』建久元年四月二十日条より逆算 | |||
| 久安2年 (1146) |
23歳 | 京都 | 次女の「江口腹の御女」が誕生。 母は摂津国江口の遊女。 院近臣藤原季範女子と通じる。 |
『平治物語』より逆算 | |
| 久安3年 (1147) |
24歳 | 京都 | 三男の源頼朝が誕生。 母は院近臣藤原季範女子。外祖父季範は在京とみられるが、頼朝自身の出生地は京都か尾張熱田かは記録がない。 |
||
| 久安4年 (1148) |
25歳 | 京都⇒関東⇒ 京都か |
五男(四男?)の源範頼が誕生か。 母は「遠江国池田宿遊女」。 「於遠州蒲生御厨出生」で、藤原範季に養育される。 |
||
| 久安5年 (1149) |
26歳 | ||||
| 久安6年 (1150) |
27歳 | ||||
| 仁平元年(1151) | 28歳 | 京都 | 院近臣藤原季範女子と通じる。 | ||
| 仁平2年(1152) | 29歳 | 京都 | 四男(五男?)の源希義が誕生。 母は院近臣藤原季範女子で頼朝同母弟。 |
『平治物語』より逆算 | |
| 仁平3年(1153) | 3月28日 | 30歳 | 京都 | 義朝、従五位下下野守に任官 叙任は「故善子内親王未給合爵」による4。 |
『兵範記』仁平三年三月廿八日条 |
| 夏頃 | 弟義賢、上野国多胡郡に居住。 | 『延慶本平家物語』第三本 | |||
| 同年中 | 義賢の子、義仲が上野国に誕生。 | ||||
| 同年中 | 九條院雑仕常盤と通じる。 | ||||
| 久寿元(1154)年 | 31歳 | 京都 | 六男の醍醐禅師全成が誕生。 母は「九條院雑仕常盤」。 |
『尊卑分脈』より逆算 | |
| 久寿2年(1155) | 8月16日 | 32歳 | 京都 | 源義賢、武蔵国比企郡大蔵館で、比企郡小代郷から攻め寄せた悪源太義平に討たれる。 | |
| 九條院雑仕常盤と通じる。 | |||||
| 保元元(1156)年 | 33歳 | 京都 | 七男の卿公義円が誕生。 母は「九條院雑仕常盤」。 |
『尊卑分脈』より逆算 | |
| 12月29日 | 重任、下野守義朝、造日光山功 | 『兵範記』保元元年十二月廿九日条 | |||
| 保元2(1157)年 | 正月24日 | 34歳 | 京都 | 従五位上 平重盛 父清盛朝臣召進忠貞賞 源義朝 召進盛憲賞 右兵衛佐平頼盛 使左衛門少尉平信兼 |
『兵範記』保元二年正月廿四日条 |
| 10月22日 | 正五位下 源義朝、北廓 | 『兵範記』保元二年十月廿二日条 | |||
| 保元3(1158)年 | 35歳 | 京都 | 九條院雑仕常盤と通じる。 | ||
| 平治元(1159)年 | 36歳 | 京都 | 八男の源義経が誕生。 母は「九條院雑仕常盤」。 |
『尊卑分脈』より逆算 | |
●兒玉党系譜(『小代宗妙置文』)
有道遠峯―+―兒玉弘行――兒玉家行
(有貫主) |(有大夫) (武蔵権守)
|
+―有道経行――女子 秩父権守号重綱(室)也 彼重綱者高望王五男村岡五郎義文五代後胤
(有三別当)(号乳母御前) 秩父十郎平武綱嫡男也、
秩父権守平重綱為養子令相継秩父郡間改有道姓移テ平姓、以来於行重子孫稟平姓者也、
母秩父十郎平武綱女也
下総権守 秩父平武者 武者太郎 蓬莱三郎 母江戸四郎平重継女也、
行重 行弘 行俊 経重 経重者畠山庄司次郎重忠一腹舎兄也、
重綱の娘は武蔵国埼玉郡大田郷(行田市小針周辺)を本拠とする藤原秀郷の末裔、大田大夫行政の子・三郎行光に嫁ぎ、大田太郎行広と大河戸行方を産んでいる(『続史籍集覧』「秀郷流藤原氏諸家系図 上」)。大田氏が本拠とする大田郷は、荒川を挟んで秩父氏の支配地と隣接しており、こうしたことから婚姻関係が成立したものとみられる。『尊卑分脈』では「大田大夫行政」の弟「大田四郎行光此義正説也、或行政子」の子「号大河戸 下総権守行方」の項に「母秩父太郎重綱女」とあるが、弟の行広の母は記されていない。なお『尊卑分脈』の小山氏周辺の系譜は人名や罫の攪乱が多い。
小山四郎政光と下河辺五郎行義も大田行光の子があるが、彼らの母は兄の行広と行方とは異なるのだろう。政光と行義はともに武蔵国を離れ、政光は下野国衙付近の小山郷に進出し、行義は下総国下河辺庄の庄司となっている。大田行政は兄弟子息らの名字地を見るに、上野国から武蔵国、下野国、常陸国にまで広がる強大な勢力を誇っていたことがわかる。のちに秩父平氏から別当が輩出されることとなる都幾川上流の名刹慈光寺別当に、古くは大田行政の弟・阿闍梨快実が別当職となっており、その勢力の大きさがうかがわれる。
●『秀郷流藤原氏諸家系図』と秩父氏系図
+―法橋厳耀 +―畠山重保
|(慈光寺別当) |(六郎)
| |
秩父重綱―+―秩父重弘―+―畠山重能――――畠山重忠―+―円耀
(秩父権守)|(太郎太夫) (畠山庄司) (庄司次郎) (慈光寺別当)
|
+―女子 +―大田行広――――大田行朝―――大田行助
∥ |(太郎) (大田権守) (七郎)
∥ |
∥――――+―大川戸行方―+―清久広行―――清久広綱―――清久秀衡
∥ (下総守) |(太郎)
∥ |
∥ +―大川戸秀行――大川戸秀綱――大川戸秀胤
∥ |(次郎) (三郎兵衛) (孫三郎)
∥ |
∥ +―高柳秀行
∥ |(三郎)
∥ |
∥ +―大川戸行基
∥ |(四郎)
∥ |
∥ +―葛浜行平
∥
大田宗行―+―大田行政―――大田行光―――大田政光====吉見頼経
(下野大介)|(下野大介) (下野大介) (下野大掾) (三郎)
| ∥
+―快実 ∥―――――+―小山朝政
(慈光寺別当) ∥ |(小四郎)
∥ |
八田宗綱―――女子 +―長沼宗政
(武者所) (寒河尼) |(五郎)
|
+―小山朝光
(七郎)
重綱室の一人、横山次郎大夫経兼娘の従姉妹(近衛局、兵衛局)は常陸国八田郷の八田権守宗綱の室となるが、彼女は「八田権守妻、宇都宮左衛門尉朝綱之母也、右大将家御乳母也、近衛局兵衛局也」(『小野氏系図』「続群書類従」第七輯上)とあるように、頼朝の乳母となっている。そしてその娘(のち寒河尼)も頼朝乳母となり、小山政光に嫁いで小山朝政、長沼宗政、結城朝光を産んでいる(『続史籍集覧』「秀郷流藤原氏諸家系図 上」)。のちに義朝が下野守となるに及び、秩父氏と重縁にあたる小山政光を何らかの所役に起用しているのかもしれない。比企郡司の女子(のち比企尼)や八田宗綱室(兵衛局)、小山政光室(のち寒河尼)を頼朝の乳母としたのも、秩父氏所縁の女性という事が大きな理由であろう。
このほか、「武衛御誕生之初、被召于御乳付之青女今日者尼、號摩摩、住国相摸早河庄」(『吾妻鏡』治承五年閏二月七日条)とあるように、相模国中村党の女性も頼朝の最初期乳母として召されていたことがわかる。なお、「故左典厩御乳母字摩摩局、自相摸国早河庄参上、相具淳酒献御前、年歯已九十二、難期且暮之間、拜謁之由申之幕下、故以憐愍給、是有功故也」(『吾妻鏡』建久三年二月五日条)とあるように、義朝自身の乳母も相模国中村党の女性であった。義朝は相模国山内庄の首藤刑部丞俊通の妻(のちの山内尼)も頼朝の乳母としており、為義、義朝の東国の拠点の中心は武蔵国と相模国にあったと推測される。
【重綱養子】
+―秩父行重――――――――――秩父行弘―――秩父行俊====蓬莱経重
|(平太) (武者所) (武者太郎) (三郎)
| ↑
|【重綱養子】 |
+―秩父行高――――――――――小幡行頼 |
|(平四郎) (平太郎) |
| |
兒玉経行―+―女子 +―宇都宮朝綱 |
(別当大夫) (乳母御前) |(三郎) |
∥ | |
∥ 八田宗綱 +―八田知家 |
∥ (八田権守) |(四郎) |
∥ ∥ | |
∥ ∥―――――――+―女子 +―小山朝政 |
∥ ∥ (寒河尼) |(小四郎) |
∥ ∥ ∥ | |
∥ ∥ ∥――――+―長沼宗政 |
∥ ∥ ∥ |(五郎) |
∥ ∥ ∥ | |
+―小野成任――∥―――女子 +――――小山政光 +―結城朝光 |
|(野三太夫) ∥ (近衛局) | (下野大掾) (七郎) |
| ∥ | |
| ∥ +―横山孝兼――――――女子 +―法橋厳耀 | +―畠山重秀
| ∥ |(横山大夫)| ∥ |(慈光寺別当) | |(小太郎)
| ∥ | | ∥ | | |
横山資隆―+―横山経兼――∥―+―女子 | ∥――――+―畠山重能 +―畠山重光 +―畠山重保
(野三別当) (次郎大夫) ∥ ∥ | ∥ (畠山庄司) |(庄司太郎) |(六郎)
∥ ∥ | ∥ ∥ | |
∥ ∥―――――――――秩父重弘 ∥―――――+―畠山重忠――+―阿闍梨重慶
∥ ∥ | (太郎大夫) ∥ (庄司次郎) |(大夫阿闍梨)
∥ ∥ | ∥ |
∥ ∥ | +―江戸重継―+―女子 +―円耀
∥ ∥ | |(四郎) | |(慈光寺別当)
∥ ∥ | | | |
∥ ∥ | +―高山重遠 +―江戸重長 +―女子
∥ ∥ | |(三郎) (太郎) | ∥
∥ ∥ | | | ∥
∥ ∥ | +―女子 +―大田行広 | 島津忠久
∥ ∥ | | ∥ |(太郎) |(左兵衛尉)
∥ ∥ | | ∥ | |
∥ ∥ | | ∥――――+―大河戸行方 +―女子
∥ ∥ | | ∥ (下野権守) ∥
∥ ∥ | | ∥ ∥
∥ ∥ +――|―藤原行光 足利義純
∥ ∥ |(四郎) (上野介)
∥ ∥ |
秩父武綱―+―秩 父 重 綱―――――+―秩父重隆―――葛貫能隆――+―河越重頼――+―河越重房
(十郎) |(秩 父 権 守) (次郎大夫) (葛貫別当) |(太郎) |(小太郎)
| ∥ | |
+―女子 ∥ +―妹 +―河越重員
∥―――――――――――+―秩父行重 ∥ (三郎)
∥ ∥ |(平太) ∥
∥ ∥ | ∥
有道遠峯―+―兒玉経行――女子 +―秩父行高 ∥―――――+=小代俊平
(有貫主) |(別当大夫)(乳母御前) (平四郎) ∥ |(二郎)
| ∥ |
+―兒玉弘行――――――――――入西資行―――小代遠広――――小代行平 +―小代弘家
(有大夫) (三郎大夫) (二郎大夫) (右馬允)
●源氏の人々の乳母等
| 人名 | 乳母名 | 乳母夫 | 国 | 備考 | 出典 |
| 源為義 | 廷尉禅室御乳母 | 山内首藤資通入道 (仕八幡殿) |
相模国 | 『吾妻鏡』 治承四年十一月廿六日条 |
|
| 源義朝 | 摩摩局 |
中村党か | 相模国 | 故左典厩御乳母、年歯已九十二 康和3(1101)年生まれ 相摸国早河庄 |
『吾妻鏡』 建久三年二月五日 |
| 源義広 | 乳母某 () |
多和山某 | 不明 | 乳母子、多和山七太 | 『吾妻鏡』 治承五年閏二月廿三日条 |
| 源義平 | 乳母御所 | 秩父権守重綱 | 武蔵国 | 有三別当経行の女子 | 『小代宗妙置文』 『兒玉党系図』 |
| 源頼朝 | 摩摩 | 中村宗平? | 相模国 | 武衛御誕生之初、被召于御乳付之青女 住国相摸早河庄 |
『吾妻鏡』 治承五年閏二月七日条 |
| 乳母某 | 三善氏 | 京都 | 乳母妹の子が三善康信 | 『吾妻鏡』 治承四年六月十九日条 |
|
| 乳母某 | 不明 | 不明 | 久安5年、頼朝のために十四日間清水寺に参篭し、二寸銀正観音像を得る | 『吾妻鏡』 治承四年八月廿四日条 |
|
| 山内尼 【武衞御乳母】 |
山内首藤俊通 | 相模国 | 山内瀧口三郎経俊の老母 | 『吾妻鏡』 治承四年十一月廿六日条 |
|
| 比企尼 【武衞乳母】 |
掃部允 | 武蔵国 | 義員姨母、甥義員を猶子とする。武蔵国比企郡を請所として夫の掃部允を相具して下向している | 『吾妻鏡』 寿永元年十月十七日条 |
|
| 兵衛局 【右大将家御乳母】 |
八田権守宗綱 | 下野国 | 宇都宮左衛門尉朝綱之母 | 『小野氏系図』 | |
| 寒河尼 【武衛御乳女】 |
小山下野大掾政光 | 下野国 | 故八田武者宗綱息女 | 『吾妻鏡』 治承四年十月二日条 |
|
| 源義仲 | 乳母某 | 中三権守兼遠 | 上野国 または信濃国 または京都 |
『吾妻鏡』 治承四年九月七日条 |
永治2(1142)年の高山御厨寄進後、義朝は幼い嫡子義平を重綱に預け、上総国の「上総介常澄」のもとへ移り「上総曹司源義朝」(『天養記』天養二年三月四日)と称されている。義朝は武蔵国比企郡を拠点に、上総国埴生庄の常澄や相模国鎌倉郡など、関東に形成されていた為義家人のネットワーク間を移動していたとみられる。保延元(1135)年までには常胤(保延元年当時十八歳)が秩父重綱孫娘(秩父重弘女子)と婚姻している(翌保延二年に嫡子胤正誕生)ように、常胤の結婚もこの為義家人のネットワーク中で結ばれたものであろう。保延元(1135)年当時、義朝は十三歳でまだ在京であったと思われるため、常胤と重綱女の婚姻を推進したのは為義と考えられる。
ところが義朝は、康治2(1143)年に下総国「相馬郡」について「源義朝朝臣就于件常時男常澄之浮言、自常重之手」から「責取圧状之文」るという事件を起こしている(久安二年八月十日『正六位上平朝臣常胤寄進状』:『櫟木文書』)。このときの譲状に付されたものは「相馬郷」に関する継承の案文で、これを公験として署判したものが義朝に渡された可能性があろう。なお、常重は相馬「郡司職」を解任された形跡はなく、かつて天治元(1124)年に常重が養父常晴から「天治元年六月所譲与彼郡」(永暦二年二月廿七日『正六位上行下総権介平朝臣常胤解写』)と同様に「相馬郡」を常重から譲渡させたのだろう。
義朝が常重から「相馬郡(郡司職)」「相馬郷(地主職)」の権利を圧し取った康治2(1143)年は、年初で下総守が交替した年であった。康治2(1143)年正月27日の除目で「従五位下源親方」が「前司親通進衛料物功」で「下総守」となっている(『本朝世紀』康治二年正月廿七日条)。この交替のタイミングで義朝が常重から相馬郷の圧状を責め取ったのは、新司親方から「相馬郡司」の「国判」を得ることと、相馬御厨の「免判」を得るための可能性があろう。また、常重はこれ以降公的な文書に名を見せずに子息常胤が登場していることから、「常時男常澄之浮言」とは常重の重病等を知った常澄の横やりを指すのかもしれない。
なお、親通の後継国司となった「源親方」は親通の子「従五位下下総守親方」(『尊卑分脈』)と同一人物とされる(野口実『中世東国武士団の研究』高科書店 1994年)。親通は保延4(1138)年11月6日、「守藤原朝臣親通募重任功、造進彼社(香取大神宮)」によって重任しており(「安芸国厳島社神主佐伯景弘解」『広島県市古代中世資料編Ⅱ』)、親通―親方という親子での継承だったことがわかる。親族で国司が継承される場合は姓を改めて記載される例があるという(野口実『中世東国武士団の研究』高科書店 1994年)。
| (1) | 相馬郡司職の補任 | 平常澄の希望であろう。「常時男常澄之浮言」により相馬郡を奪取し、常澄を相馬郡司職に就ける。おそらくいったんは認められ、常澄の九男・九郎常清が相馬郡に入ったと思われるが、「圧状」であることが発覚したためか、久安2(1146)年までに罷免(辞任)とみられる。 |
| (2) | 相馬御厨の寄進 | 国免荘としての相馬御厨を成立させるため、新下総守から国判を得る意図か。 相馬郷に関する公験は新下総守親方の父親通が保有しているが、義朝が親通と接触した形跡はない。親通が得ていた相馬郷に関する公験一切は、二男の親盛へ譲られており、義朝は継承していないが、義朝は天養2(1145)年3月11日に寄進状を奉呈しており、国判を得ていたと思われる。 |
なお、義朝は康治2(1143)年に常重から「相馬郡」「相馬郷」を「掠領」したが、「相馬郷」に関しては天養2(1145)年まで何ら沙汰もなく寄進もしていない。「相馬郡」に関しては常重は郡司職を停止され、おそらく常澄が継承し、その子九郎常清がこれをさらに譲られたと想定される。相馬郡及び相馬郷を譲ったことで、常重は相馬御厨の下司職もまた放任された可能性があるが、それ以前に常重が亡くなっていた可能性があろう。
その後義朝は「称伝得字鎌倉之楯、令居住之間」とあるように「鎌倉之楯」を「伝得」して相模国鎌倉に移り住んでいる(「官宣旨案」『平安遺文』2544)。鎌倉へ移った義朝は(このとき常澄の子、八郎広常が鎌倉に同道したと思われる)、大庭御厨に含まれる「高座郡」の「鵠沼郷」を理由もなく「鎌倉郡内」と称し、9月上旬、義朝と結託した相模国在庁の田所目代源頼清の下知のもと、義朝郎従清大夫安行、新藤太、庁官等が大庭御厨に乱入した。さらに10月21日にも「田所目代散位源朝臣頼清」ら在庁および「義朝名代清大夫安行、三浦庄司平吉次、男同吉明、中村庄司同宗平、和田太郎助弘」ら千余騎による狼藉が行われた(『天養記』天養二年三月四日)。この濫行で御厨内「伊介神社」の祝であった荒木田彦松が頭を割られて殺されている。
 |
| 鵠沼神明社(伊介神社) |
その後、常重が相馬郷を寄進した際の口入神官である荒木田延明が「沙汰」したことで(仁安二年六月十四日『荒木田明盛神主和与状』)、義朝は天養2(1145)年3月11日、「為募太神宮御威、限永代所寄進也」(天養二年三月十一日『源某寄進状』)、「恐神威永可為太神宮御厨之由、天養二年令進避文」(仁安二年六月十四日『荒木田明盛神主和与状』)とある通り、神宮から「御勘発(譴責)」され、「永可為太神宮御厨之由」の寄進状(避文)を皇太神宮へ奉った(天養二年三月「源某寄進状写」『鏑矢伊勢方記』)。
この相馬御厨寄進については、「御勘発」によるものであるため、この前年天養元(1144)年9月、10月に義朝が起こした相模国大庭御厨濫行も関係していた可能性があり、相馬御厨領主の荒木田延明は、大庭御厨で殺害された神官荒木田彦松と同族であろう。
天養2(1145)年3月4日、朝廷は相模国司(藤原頼憲)に対して義朝へ御厨への狼藉停止を命じる宣旨を下し、これを「伊勢大神宮司」へ伝えている(天養二年三月四日『宣旨案』:『天養記』)。義朝が荒木田延明の沙汰で相馬御厨の避状(寄進状)を奉呈したのはこの七日後であり、これ以前に延明からの抗議があった可能性があろう。当時の相模守は藤原頼憲(美福門院近臣の藤原憲方子息)で、天養元(1144)年正月24日の除目により前任藤原親家から引き継いで相模守となっている。
荘園領主側としては、常重であろうが義朝であろうが、年貢供祭を確実に実行されれば、下司職が誰であろうと構わなかったということがわかる。ただし、この寄進状は下司職の条件も署名も明確ではなく拙い内容となっている。そしてこの寄進に対する神宮側の対応は全く伝わらず、寄進成立後に国判が出されたという文書もないため、実際に寄進が成立したのかは不明である。
●天養2(1145)年3月11日『源某寄進状写』(『鏑矢伊勢方記』)
なお、義朝は東国家人の再編成の過程で神宮領への狼藉が発生せざるを得ない中、神宮を畏敬していた様子がうかがわれる。安房国丸御厨は「左典厩義朝令請廷尉禅門為義御譲給之時、又最初之地也」(『吾妻鏡』治承四年九月十一日条)で、「而為被祈申武衛御昇進事、以御敷地去平治元年六月一日奉寄 伊勢太神宮給」(『吾妻鏡』治承四年九月十一日条)というものであり、為義、義朝の神宮信仰心は、故義朝を敬愛する頼朝へと引き継がれ、頼朝は鶴岡八幡宮寺と並んで甘縄神明社を深く崇敬した。そして従者(源頼政または熱田大宮司家と関わりのある人物か)で側近の藤九郎盛長を源家別邸の甘縄邸に置いてこれを管理させ、数度にわたって神明社を参詣しているのである。
平貞盛―――女 +―藤原隆時―――藤原清隆
(信濃守) ∥ |(因幡守) (中納言)
∥ |
∥――――+―藤原範隆―――藤原資隆
∥ (甲斐守) (上西門院蔵人)
藤原清綱
(左衛門佐)
∥――――+―藤原隆能
∥ |(主殿頭)
∥ |
後三条天皇――高階為行――女 +―藤原忠清―+―藤原惟忠――――――藤原惟清
(信濃守) |(淡路守) |(太皇太后宮大進)
| |
| +―藤原清兼――――+―藤原清長
| |(太皇太后宮大進)|(太皇太后宮大進)
| | |
| | +―藤原康俊
| | |(待賢門院蔵人)
| | |
| | +―藤原惟清
| | (左大臣勾当)
| |
| +―藤原行俊――――――藤原清定
| |(待賢門院蔵人) (八条院蔵人)
| |
| +―女
| ∥―――――――――源義朝
| ∥ (下野守)
| 源為義
| (検非違使)
|
+―藤原隆重―+―藤原政重
(筑前守) |(白河院蔵人)
|
+―平忠重【刑部卿平忠盛為子改姓】
|(散位)
|
+―藤原清重――――――藤原在重
|(蔵人) (上西門院判官代、下総守)
|
+―右衛門佐
(後白河院宮女)
∥
藤原信西
(少納言入道)
その後、義朝の相馬御厨の寄進を知った(荒木田延明または子・明盛からの報告であろう)常胤は、父常重が国司親通に譲った相馬郷・立花郷の「新券」を取り戻すべく、久安2(1146)年に「上品八丈絹参拾疋、下品七拾疋、縫衣拾弐領、砂金参拾弐両、藍摺布上品参拾段、中品五拾段、上馬弐疋、鞍置駄参拾疋」を国庫に「進済」した。
| 保延2(1136)年: 常重未進分 |
(1)准白布726段2丈5尺5寸 | 「弁進」相馬立花両郷 |
| 久安2(1146)年: 常胤進済分 |
(1)上品八丈絹:30疋 (2)下品:70疋 (3)縫衣:12領 (4)砂金:32両 (5)藍摺布上品:30段 (6)中品:50段 (7)上馬:2疋 (8)鞍置駄:30疋 |
「所不被返与件新券」 ※其中一紙先券之内、被拘留立花郷壱處許之故 ↓ (1)「被拘留立花郷壱處」 ⇒理由は不明だが、親通から関白忠実に寄進されたか。 (2)「至于相馬地者、且被裁免畢」 ⇒「以常胤為相馬郡司、可令知行郡務之旨、去四月之比国判早畢」 |
これにより、下総守は常重の官物未納の「進済」を認め、久安2(1146)年4月、常胤は「国判」を以て正式に「相馬郡司職」に還任され「可令知行郡務」とされた。このとき「其中一紙先券之内、被拘留立花郷壱處許之故、所不被返与件新券也」(久安二年八月十日『正六位上平朝臣常胤寄進状』(『櫟木文書』:『鎌倉遺文』所収))とあるように、常重が保延2(1136)年に国司藤原親通に遣わした「相馬立花弐箇處私領辨進之由、押書新券」(永万二年六月十八日『荒木田明盛和与状写』)である「一紙先券」のうち、立花郷は「被拘留」されたため、国司から出された新券は相馬郷のみであった。なお「立花郷」が返されなかった理由は、親通から私君の関白藤原忠実へ寄進されたためであろう。立花郷は「橘」庄が立荘され、隣接する木内郷(木内庄)とともに摂関家領となった。その後「橘幷木内庄」は忠実・忠通を経て、忠実の子・権大納言兼房へ譲られており、文治2(1186)年3月12日当時、「二位大納言家」領として「貢未済庄々」(『吾妻鏡』文治二年三月十二日条)に列記されている。
具平親王―――源師房 +―源国信――――――――――――源信子
(中務卿) (太政大臣) |(権中納言) ∥
∥ | ∥ 【近衞殿】
∥――――+―源顕房―+―――――――――源師子 ∥――――――――藤原基実
∥ |(右大臣) ∥ ∥ (関白)
∥ | ∥ ∥
+―藤原尊子 +―源麗子 ∥ ∥ 【九條殿】
| ∥――――――藤原師通 ∥――――――藤原忠通 +―藤原兼実
| ∥ (関白) ∥ (関白)∥ |(関白)
| ∥ ∥ ∥ ∥ ∥ |
| ∥ ∥ ∥ ∥ ∥―――+―藤原兼房
| ∥ ∥ ∥ ∥ ∥ |(権大納言)
| ∥ ∥ ∥ ∥ ∥ |
藤原道長―+―藤原頼通―――藤原師実 ∥――――――藤原忠実 ∥ 加賀局 +―慈円
(関白) |(関白) (関白) ∥ (関白) ∥ (天台座主)
| ∥ ∥
+―藤原頼宗―――藤原俊家―+―藤原全子 ∥――――――――藤原聖子
(右大臣) (右大臣) | ∥ (皇嘉門院)
| ∥ ∥
+―藤原宗通――――――――――藤原宗子 崇徳天皇
(権大納言)
 |
| 伊勢内宮 |
一方で、裁免された「至于相馬地者、且被裁免畢」(久安二年八月十日『御厨下司正六位上平朝臣常胤寄進状写』)の「相馬地」とは、「立花郷」との対比および立花郷新券不与の文意から「相馬郷」のことと判断される。つまり常胤は相馬郷(手賀沼以北の旧相馬御厨エリア)を取り戻したことがわかる。しかし、この国司新券には、常重から親通への譲状に付された公験(継承証文の案文)は附されなかったとみられる。その公験はすでに親通から次男下総大夫親盛へ継承されていたためである。これがのちに「匝瑳北条之由緒」により在京官吏の前左衛門少尉源義宗の手に渡り、常胤と相馬御厨の下司職を争うこととなる。
その後、久安2(1146)年8月10日に常胤はかつて常重が内宮と交わした「常重契状」に基づき、「御厨下司正六位上平朝臣常胤」として内宮へ相馬郷を寄進する(久安二年八月十日『正六位上平朝臣常胤寄進状写』)。寄進時に於いて常胤がすでに「御厨下司」と称しているのは、「常重契状」に「下司職者以経重子孫」(大治五年十二月『下総国司庁宣写』)などの一文が入っていたためと思われ、源義朝の寄進を強烈に否定する意味もあったのだろう。
●久安2(1146)年8月10日『正六位上平朝臣常胤寄進状』(『鏑矢伊勢宮方記』:『千葉県史料』中世編)
寄進については、4月の「進済」と「相馬郡司」補任から7月までの間に内宮との間で細かい取り決めが済んだとみられ、寄進日付で、加地子・下司職は常胤の子孫に相伝され、「預所職」は「本宮御牒使清尚」の子孫に相承されるべきこと寄進条件が追加された正式な寄進状が作成された(久安二年八月十日『御厨下司正六位上平朝臣常胤寄進状写』)。結果的に源義朝の寄進は否定されたことになる。
久安7(1151)年正月、藤原信成が下総守となる。彼は久寿2(1155)年2月25日、「下総、伊豆、佐渡 已上延任各二年」とあることから、四年の任期後に二年の延任が認められている。ただし、同じく春日祭に従った「諸大夫」の「院北面 下総守信成」(『兵範記』仁平四年正月三十日条)は、「下総前司」とされているが(『兵範記』仁平四年ニ月ニ日条)、その後も信成が在任していることが確認できることから、『兵範記』の誤記であろう。
前任の下総守の親方と弟・親盛(故親通男、下総大夫)は仁平4(1154)年正月30日、春日祭上卿となった「左府家嫡中納言中将殿(藤原兼長)」に従う「散位」の「地下君達」として名が見えており(『兵範記』仁平四年正月三十日条)、氏長者の頼長の家人で嫡子・兼長に付されたと推測される。その後任は摂関家の家人ではなく、院の影響下にあった人物が就いていることから、下総国は摂関家から鳥羽院へ移ったのであろう。
| 任官・在任年 | 在任 | 人名 | 備考 | 出典 |
| 【除目】 大治2(1127)年 正月20日 |
大治2(1127)年~ 大治5(1130)年 |
藤原茂明 | 大治5(1130)年、讃岐介に転じる | 『中右記』 大治二年正月廿日条 |
| 【在任】 天承元(1131)年11月17日 |
源盛邦 | 大殿忠実の院参先駈 | 『時信記』 天承元年十一月十七日条 |
|
| 【在任】 長承元(1132)年 4月21日 |
源盛固 =源盛邦 |
斎院御祓に際し、斎院長官資賢の代理として先駈 | 『中右記』 長承元年四月廿一日条 |
|
| 【在任】 長承元(1132)年 11月23日 |
源盛邦か | 当時、下総国に下向していた | 『中右記』 長承元年十一月廿三日条 |
|
| 【在任】 長承3(1134)年 閏12月24日 |
源盛邦か | 長承3(1134)年閏12月24日、「下総国不堪」の奏上 | 『中右記』 長承三年閏十二月廿四日条 |
|
| 【除目?】 保延元(1135)年 正月? |
保延元(1135)年~ 康治元年(1142)年 |
藤原親通 | 下野国から名替? ※大治2(1127)年正月20日には下野守任中(『中右記』大治二年正月廿日条) |
|
| 【在任】 保延2(1136)年 7月15日 |
藤原親通 | 官物未納のため常重拘束 | ||
| 【在任】 保延2(1136)年 11月13日 |
藤原親通 | 散位紀季経に指示をして 常重から新券を押し取る |
||
| 【重任】 保延4(1138)年 11月6日 |
藤原親通 | 香取大神宮の造替の功で重任 | 「安芸国厳島社神主佐伯景弘解」 | |
| 【除目】 康治2(1143)年 正月27日 |
康治2(1143)年~ 久安2(1146)年? |
源親方 | 前司親通進衛料物功 従五位下 |
『本朝世紀』 康治二年正月廿七日条 |
| 大江元重 | 下総介(史宿) 従五位下 |
|||
| 【在任】 久安2(1146)年 4月 |
久安2(1146)年?~ 久安6(1150)年? |
藤原在重? | 常胤を相馬郡司職に任じた | |
| 【除目】 久安7(1151)年 正月 |
久安7(1151)年~ 保元3(1158)年? |
藤原信成 | 院北面。藤原信頼の同族で院近臣。 時期的に久寿二年に延任の下総守と同一人物。 仁平3(1153)年3月28日に院蔵人。仁平4(1154)年正月30日当時に下総前司とあるが、兵範記の誤記か。 その後、遠江守となっている。 久寿元(1154)年2月2日「下総前司信成」 |
『勘例』(『国司補任』) 『兵範記』 仁平三年三月廿八日条 『兵範記』 仁平四年ニ月ニ日条 |
| 【延任二年】 久寿2(1155)年 2月25日 |
藤原信成? | 延任各二年 | 『兵範記』 久寿二年二月廿五日条 |
|
| 【在任】 保元2(1157)年 10月22日 |
藤原信成 | 従五位上に昇叙 | 『私要抄』(『国司補任』) | |
| 【除目】 保元4(1159)年 正月29日 |
保元4(1159)年~ 仁安2(1167)年? |
源有通 | 大蔵卿源行宗の子で、のち大納言成通の養子となって藤姓に改める。 | 『極秘大間記』 |
| 【除目】 仁安2(1167)年 正月? |
仁安2(1167)年 | 藤原高佐 | 仁安元(1166)年9月は飛騨守在任 仁安2(1167)年8月は「前下総守」 仁安3(1168)年6月は「前下総守」 |
『兵範記』仁安二年八月六日条 『兵範記』仁安三年六月廿日条 |
| 【除目】 仁安2(1167)年 2月21日 |
仁安2(1167)年~ | 藤原実仲 | 仁安2(1167)年2月21日に父(伯父)公通が権大納言を辞す代わりに下総守となる。 | 『尊卑分脈』 『公卿補任』 |
久寿3(1156)年に入ると鳥羽院は体調の不良が目立ち始め、改元して保元元(1156)年5月には食事も摂れないほど悪化する。摂食不良とその後の腹部の膨張(腹水貯留であろう)ならびに手足の浮腫から消化器系疾患か。5月中には死を覚悟していたとみられ、自分の死後、上皇(のちの崇徳院)や左大臣頼長らによる政権樹立を嫌い、有力武家貴族らに対して招集する院宣を発している。「去月朔以降、依院宣、下野守義朝幷義康等」が禁中の守護として宿営し、「出雲守光保朝臣、和泉守盛兼、此外源氏平氏輩、皆悉率随兵祇候于鳥羽殿」と、出雲守源光保、和泉守平盛兼ほか源平諸氏が鳥羽殿の警衛に参じた(『兵範記』保元元年七月十日条)。鳥羽院は「義朝、義康、頼政、季実、重成、惟繁、実俊、資経、信兼、光信」らを後白河天皇に付属させるべく遺詔を残していたというが(『保元物語』)、この院宣であろうか。
7月2日、鳥羽院は鳥羽安楽寿院で崩御した(『兵範記』保元元年七月二日条)。五十四歳。その死からわずか三日後の7月5日には後白河天皇が蔵人雅頼を通じ、検非違使を動員して「京中武士」の動きを停止させた(『兵範記』保元元年七月五日条)。これは「蓋是法皇崩後、上皇左府同心発軍、欲奉傾国家」という風聞が京中に流れたことによる。鳥羽院の崩御とともに後白河天皇は、鳥羽院の兄上皇および左大臣頼長勢力を鎮圧すべくさまざまな画策を実行に移していく。
7月6日には、左衛門尉平基盛が東山法住寺辺で、左大臣頼長に祇候する大和源氏源親治を追捕した(『兵範記』保元元年七月六日条)。
さらに7月8日、後白河天皇は諸国司に対して「入道前太政大臣幷左大臣、催庄園軍兵之由、慥可令停止」を勅した(『兵範記』保元元年七月八日条)。そして「蔵人左衛門尉俊成幷義朝随兵等」に勅して頼長邸「東三條」邸を接収した。頼長は当時宇治にあって東三條邸を留守にしていたときを狙ったものであった。天皇側による圧力が強まっている様子がうかがえる
こうした状況を知った上皇(崇徳院)は怒り、滞在していた鳥羽田中御所から夜陰に紛れて白河前斎院御所へと遷幸し(『兵範記』保元元年七月九日条)、翌10日には移った白河殿で軍勢を集め始める(『兵範記』保元元年七月十日条)。しかし、それに応じたのは上皇や左府頼長の家人など所縁の人物ばかりであった。
崇徳院・頼長に加わった諸士(『兵範記』保元元年七月十日条)
| 上皇祇候 | 散位平家弘、大炊助平康弘、右衛門尉平盛弘、兵衛尉平時弘、判官代平時盛、蔵人平長盛、源為国 |
| 故院勘責 今当召出 |
前大夫尉源為義、前左衛門尉源頼賢、八郎源為知(為朝)、九郎冠者(為仲) |
| 左府祇候 | 前馬助平忠正、散位源頼憲 |
後白河天皇に加わった諸士(『兵範記』保元元年七月十日条)
| 下野守義朝、右衛門尉義康、安芸守清盛朝臣、兵庫頭頼政、散位重成、左衛門尉源季実、平信兼、右衛門尉平惟繁、常陸守頼盛、淡路守教盛、中務少輔重盛 |
7月11日早朝、御所高松殿から「清盛朝臣、義朝、義康等」が六百余騎を率いて白河御所へ進軍した。平清盛は三百余騎を率いて二條大路から、源義朝は二百余騎を率いて大炊御門大路から、源義康は百余騎を率いて近衞大路からそれぞれ攻め上がったという。さらに前蔵人源頼盛が郎従数百人を揃え、源頼政、源重成、平信兼らが重ねて白河へと派兵された(『兵範記』保元元年七月十一日条)。
保元の乱相関図(■:崇徳上皇方、■:後白河天皇方)
|
~天皇、上皇、親王ほか~ 藤原璋子 |
~摂関家~ 藤原忠実―+―藤原忠通――藤原基実 |
|
~河内源氏~ 源義家―+―源義親――――源為義――+―源義朝 |
~伊勢平氏~ 平正盛―+―平忠盛―+―平清盛 |
この合戦の様相は、日記の故記録では『兵範記』が唯一のものであるが、そこでは7月11日「彼是合戦已及雌雄由使者参奏、此間主上立御願、臣下祈念、辰剋、東方起煙炎、御方軍已責寄懸火了云々、清盛等乗勝逐逃、上皇左府晦跡逐電、白川御所等焼失畢齋院御所幷院北殿也」とあり、平清盛を筆頭とする官軍が上皇及び左大臣頼長の軍勢を打ち破り、白河御所などが焼失したことを伝えている。午剋には清盛以下の大将軍はみな内裏へ帰参し、平清盛と源義朝はとくに朝餉間へと召され、上皇、左大臣頼長、源為義以下の人々は行方知れずとなったことを報告している。
この白河御所での戦いについては、『保元物語』によるほかないが、多分に誇張表現や筆者による加筆があり、信憑性については甚だ疑問が多いため、参考程度となるが、この保元の乱では、「上総ニハ介乃八郎弘経、下総ニハ千葉介経胤」(『保元物語』)とあって、当時三十九歳の常胤は上総権介常澄の八男・介八郎広常や相模国鎌倉党の大庭景義・景親兄弟らとともに源義朝に随って後白河天皇方として崇徳上皇(後白河天皇の兄)方と戦ったとされている。
介八郎広常の父・常澄は武蔵国秩父から移ってきた義朝を一年程度上総国内に住まわせており(為義の依頼か)、広常は義朝の郎従となって鎌倉にも館を構えたことから、当初より積極的に参戦したと思われる。一方、常胤は元来、千葉庄を通じて鳥羽院(八条院)に仕えた人物であり、後白河天皇方として参戦しているものの、義朝に応じたのではなく、故鳥羽院の遺詔により後白河天皇の勅を受けた諸国司の催促に応じたものであると考えられる。常胤は義朝との相馬御厨を巡る対立関係は解消されておらず、永暦2(1161)年4月1日の段階で相馬御厨は「雖然非彼朝臣所知之由、証文顕然候」(永暦二年四月一日『下総権介平申状案』:『櫟木文書』)と述べているように、常胤は広常とは立場が異なっていた。
保元の乱に義朝に随った人々(『保元平治物語』慶長本)
| 鎌田次郎正清 | 後藤兵衛実基 | ||||
| 近江国 | 佐々木源三 | 八嶋冠者 | |||
| 美濃国 | 平野大夫 | 吉野太郎 | |||
| 尾張国 | 舅・熱田大宮司(家子・郎等) | ||||
| 三河国 | 志多良 | 中条 | |||
| 遠江国 | 横地 | 勝俣 | 井八郎 | ||
| 駿河国 | 入江右馬允 | 高階十郎 | 息津四郎 | 神原五郎 | |
| 伊豆国 | 狩野宮藤四郎親光 | 狩野宮藤五郎親成 | |||
| 相模国 | 大庭平太景吉 | 大庭三郎景親 | 山内須藤刑部丞俊通 | 瀧口俊綱 | 海老名源八季定 |
| 秦野二郎延景 | 荻野四郎忠義 | ||||
| 安房国 | 安西 | 金余 | 沼平太 | 丸太郎 | |
| 武蔵国 | 豊嶋四郎 | 中条新五 | 中条新六 | 成田太郎 | 箱田次郎 |
| 川上三郎 | 別府二郎 | 奈良三郎 | 玉井四郎 | 長井斉藤別当実盛 | |
| 斎藤三郎実員 | |||||
| (横山党)悪次 | 悪五 | ||||
| (平山党)相原 | |||||
| (児玉党)庄太郎 | 庄次郎 | ||||
| (猪俣党)岡部六弥太 | |||||
| (村山党)金子十郎家忠 | 山口十郎 | 仙波七郎 | |||
| (高家)河越 | (高家)師岡 | (高家)秩父武者 | |||
| 上総国 | 介八郎弘経 | ||||
| 下総国 | 千葉介経胤 | ||||
| 下野国 | 瀬下太郎 | 物射五郎 | 岡本介 | 名波太郎 | |
| 上野国 | 八田四郎 | 足利太郎 | |||
| 常陸国 | 中宮三郎 | 関二郎 | |||
| 甲斐国 | 塩見五郎 | 塩見六郎 | |||
| 信濃国 | 海野 | 望月 | 諏方 | 蒔葉 | 原 |
| 安藤 | 木曾中太 | 木曾弥中太 | 根井大矢太 | 根川神平 | |
| 静妻小二郎 | 片切小八郎大夫 | 熊坂四郎 |
ここに挙げられた人々は、後述の平治の乱当時も義朝の「郎従」として名がみえる人々が多く見られるが、このうち「長井齋藤別当、片切小八郎大夫等」は「于時各六條廷尉御家人」(『吾妻鏡』治承四年十二月十九日条)とあるように、もともと六條判官為義の家人であった。その六條判官為義の家人であったはずの人々がいずれも義朝に従属している当時の認識からも、前述の通り、義朝の「廃嫡」という事実はなく(東国経営主体として東国・京都を往復させた義朝と、在京官吏を探らせた義賢とでは、為義にとっての「活用」手段が異なるため、そもそも同列に扱うべき単純なものではない)、義朝がすでに為義家人を被官化していた(すでに義朝が譲りを受けていた可能性)ことがうかがえる。
「保元の乱」は結果として後白河天皇(官軍)の勝利に終わり、同日夕刻、合戦の勲功として、安芸守平清盛は播磨守へ、右馬助源義朝は右馬権頭へ、右衛門尉源義康は左衛門尉兼検非違使へと任官することとなるが、義朝は同日、右馬権頭から一気に左馬頭へと昇み、十九年にわたって左馬頭を務めてきた藤原隆季は「雖無所望」と、強制的に左京大夫へ転じることとなる(『公卿補任』保元三年)。『保元物語』によれば義朝が恩賞の不足を訴えたとされる(『保元物語』)。
保元元(1156)年:褒章された人々(『兵範記』より)
| 日時 | 名前 | 褒賞 | 備考 |
| 7月11日 | 藤原忠通 | 氏長者 | 関白前太政大臣。 |
| 小僧都覚継 | 左府頼長より収公された所領 | 興福寺権別当。 | |
| 平清盛 | 安芸守⇒播磨守 | 安芸守より転任。 | |
| 源義朝 | 右馬助⇒右馬権頭⇒左馬頭 | 下野守兼任。同日、左馬頭隆季が左京大夫へ遷任される。 | |
| 源義康 | 右衛門尉⇒左衛門尉 | 検非違使。蔵人。右衛門尉より陞任。 8月6日夕方、従五位下に昇叙。 |
|
| 7月16日 | 平頼盛 | 昇殿 | 常陸介。兄の清盛が申請。 |
| 平教盛 | 昇殿 | 淡路守。兄の清盛が申請。 |
7月13日、上皇は実弟の仁和寺五宮(覚性法親王)のもとに出頭し、16日には為義が出家姿で義朝のもとへ出頭している。そして17日には諸国の国司に対して、前太政大臣忠実と左大臣頼長の所領を没官することを通達し、21日は流矢を受けて負傷死したと伝えられた頼長の遺骸が「般若山辺」で掘り起こされて実検された。
7月23日、上皇(讃岐院。のち崇徳院)は讃岐国へ流され、7月28日から30日にかけて、上皇および左大臣頼長の主な戦力として加担した人々が処刑された。8月3日には頼長有縁の公卿の流罪が執行され、「保元の乱」は幕を閉じるが、皇位継承については様々な蟠りが残されたまま引き継がれ、再び内紛の様相が露呈し始める。
保元元(1156)年:罪に問われた人々(『兵範記』より)
| 名前 | 処罰 | 官職等 | 備考 |
| 藤原兼長 | 出雲国へ流罪 | 権中納言兼 右近衞大将 |
左府頼長次男。母は権中納言源師俊女。次男だが、母の家格が高いことから、嫡子とされた。 8月3日、山城国稲八間庄へ追放 (使:右衛門尉平維繁、左衛門府生安倍資良)。保元三年正月出雲国で薨去。二十一歳。 |
| 藤原師長 | 土佐国へ流罪 | 権中納言兼 左近衞中将 |
左府頼長長男。母は陸奥守源信雅女。母は兼長母同様、村上源氏出身だが、受領層であったため、長男であったが次男扱いとされた。 8月3日、山城国稲八間庄へ追放 (使:右衛門尉平維繁、左衛門府生安倍資良)。土佐に配流されるが許されて帰国したのち、皇后宮大夫、内大臣、右大将と昇進。後白河院のもと、摂関に成りうる立場であったが、政治的配慮により太政大臣とされ、摂関の道をあきらめさせられる。 |
| 藤原隆長 | 伊豆国へ流罪 | 右近衞中将 | 左府頼長三男。 8月3日、山城国稲八間庄へ追放(使:右衛門尉平維繁、左衛門府生安倍資良)。伊豆国へ配流されたのちの動向は不明。 |
| 範長 | 安房国へ流罪 | 大法師 | 左府頼長四男。 8月3日、山城国稲八間庄へ追放 (使:右衛門尉平維繁、左衛門府生安倍資良)。安房国へ配流されたのちの動向は不明。 |
| 尋範 | 所領没官 | 権大僧都 | 興福寺別当。藤原頼通の孫で関白忠通、左府頼長の大叔父。 |
| 千覚 | 所領没官 | 権律師 | 藤原盛実の子で、左府頼長の母方の叔父。13日に瀕死の頼長が頼り、14日、その房で頼長は薨じる。 |
| 信実 | 所領没官 | 大法師 | 興福寺上座。悪僧として知られ、興福寺へ大きな影響力を持っていた。 |
| 玄実 | 所領没官 | 信実の子。 | |
| 清頼 | 蔵人大夫 | 7月13日、捕縛。左大臣家職事。 | |
| 藤原教長 | 常陸国へ流罪 | 右京大夫 | 7月14日、広隆寺辺で出家し参上。左衛門尉季実が具す。 8月3日、被行流罪(使:左衛門尉平実俊) |
| 親頼 | 治部丞 | 7月16日、捕縛。左大臣家侍所司。兵庫頭頼政が召し出す。 | |
| 藤原忠実 | 所領没官 | 前太政大臣。 | |
| 源成雅 | 越後国へ流罪 | 左近衞中将 | 8月3日、被行流罪(使:右衛門大志坂上兼成)。皇后宮亮信雅の子。 |
| 藤原成隆 | 阿波国へ流罪 | 皇后宮権亮 |
8月3日、被行流罪(使:右衛門少志中原業倫)。御二条院師通の庶子・少納言家隆の子。妹は待賢門院女房となり平忠盛に嫁ぎ、平教盛を産む。 |
| 藤原実清 | 土佐国へ流罪 | 前右馬権頭 | 8月3日、被行流罪(使:右衛門少志中原業倫)。大蔵卿公信の長男。 子・仁和寺の賢清権少僧都は『養和二年後七日御修法記』(『続群書類従』第二十五輯下に所収)を著している。 |
| 俊通 | 上総国へ流罪 | 散位 | 8月3日、被行流罪(使:右衛門志佐伯国忠) |
| 藤原盛憲 | 佐渡国へ流罪 | 散位 | 8月3日、被行流罪(使:左衛門尉平実俊)。勧修寺流。二条院御世に赦免され帰京する。頼長の母方の従兄弟にあたり、子の勧修寺重房は宗尊親王に従って鎌倉に下向し、関東管領上杉氏の氏祖となった。 |
| 平忠貞 | 7月28日六波羅辺で斬刑 | 前右馬権助 | 前名忠正。平正盛の子で清盛の叔父。 |
| 道行 (忠貞郎従) |
7月28日六波羅辺で斬刑 | ||
| 藤原憲親 | 下野国へ流罪 | 皇后宮権大進 | 8月3日、被行流罪(使:右衛門志佐伯国忠)。勧修寺流。上記藤原盛憲の弟にあたる。母は安芸守尹通の娘で信西入道の従姉妹である。 |
| 藤原経憲 | 隠岐国へ流罪 | 散位 | 8月3日、被行流罪(使:右衛門志清原能景)。下総守宗国の子。 |
| 源為義 | 7月28日船岡山辺で斬刑 | 前大夫尉 | 河内源氏。八幡太郎義家の孫とも子ともされる。院や摂関家に仕えるが、自身のみならず郎従らの乱行が目立ち、出世することができなかった。ただし、安房国丸御厨や、次男・義賢の「芳躅」である上野国多胡庄、鎌倉郡内など東国に荘園や私領が散在するほか、三浦氏や鎌田氏、波多野氏ら東国の武士たちとも深い関わりを有し、長男義朝を鎌倉の館も譲り渡している。保元の乱では乱の直前に頼長に徴発され、子息らを率いて参戦。戦後、流浪ののちに長男の義朝のもとに出頭し、その後斬刑に処された。 |
| 平家弘 | 7月30日大江山辺で斬刑 | 右衛門大夫 | 桓武平氏。検非違使正弘の子。 |
| 源頼憲 | 散位 | 多田源氏。久安3(1147)年6月9日夜、六位ながら昇殿を聴された初昇殿した「源頼憲前下野守明国孫、散位行国男」として名が見える(『本朝世紀』)。 量刑不明だが、「保元乱斬首」(『尊卑分脈』)。子の盛綱も「父同時被斬首」とある。 |
|
| 平康弘 | 7月30日大江山辺で斬刑 | 大炊助 | 桓武平氏。 |
| 平盛弘 | 7月30日大江山辺で斬刑 | 右衛門尉 | |
| 平時弘 | 7月30日大江山辺で斬刑 | 兵衛尉 | |
| 平国正 | |||
| 平正弘 | 陸奥国へ流罪 | 散位。 | 桓武平氏。出羽守貞弘の子。源義家の孫で為義の従姉妹子にあたる。 8月3日、被行流罪(使:右衛門志佐伯国忠)。 |
| 平長盛 | 7月28日六波羅辺で斬刑 | 院蔵人 | |
| 源頼賢 | 7月28日船岡山辺で斬刑 | 前左衛門尉 | 六条判官為義の四男。兄義賢の養子で、久安3(1147)年12月21日「左兵衛少尉源頼方 督重通卿請奏」とあり、左兵衛少尉となる(『本朝世紀』)。久安4(1148)年4月10日の「賀茂斎親王禊」に際し、「御禊前駈」の一人として「(左兵衛)権少尉源頼賢」が見える(『本朝世紀』)。久安5(1149)年4月9日、左兵衛少尉から左衛門少尉に進む(『本朝世紀』)。しかし、久寿2(1155)年5月15日、春日社の訴えによって解官され(『台記』)、それ以降は散位であったようだ。 弟左兵衛尉頼仲ほか弟とともに斬刑に処される。 |
| 平忠綱 | 7月28日六波羅辺で斬刑 | 左大臣家匂当 | |
| 平正綱 | 7月28日六波羅辺で斬刑 | ||
| 平正方 | |||
| 源為成 | 7月28日船岡山辺で斬刑 | 六条判官為義の七男。八幡七郎。 | |
| 源為宗 | 7月28日船岡山辺で斬刑 | 六条判官為義の六男。六郎。 | |
| 源為知 | 六条判官為義の八男。鎮西八郎。乱後は逃亡し、近江国坂田辺に隠棲していたが、8月26日、前兵衛尉源重貞に捕縛されるが、その後の動向は不明。『保元物語』では伊豆大島へ流されたとされるが、事実不祥。なお、源重貞は為知捕縛の功により、翌27日、右衛門尉に転任する。 | ||
| 源九郎冠者 | 7月28日船岡山辺で斬刑 | 六条判官為義の九男。九郎為仲。 | |
| 平光弘 | 7月30日大江山辺で斬刑 | 平家弘の子。 |
保元の乱の後、鳥羽院女御であった美福門院は、養子でもある後白河天皇の皇子・守仁親王の即位を願い、後白河天皇の乳父で碩学と謳われた藤原信西入道に働きかけた。これにより保元3(1158)年8月4日、仁和寺において信西と美福門院は後白河天皇から守仁親王への譲位を決定する。俗に「仏と仏との評定」(『兵範記』)と称されるものだが、関白・藤原忠通にも知らされないという異例のものだった(7)。
譲位された新天皇(二条天皇)は、美福門院を筆頭に藤原経宗(後白河院、忠実従弟)、藤原惟方らに擁立され、実父・後白河院の院政を阻止せんと図った。これに対し、後白河院は寵臣・権中納言藤原信頼を御厩別当に任じて抵抗を図った。
 |
| 三条南殿趾(元加賀守家通邸を白河院が購入) |
こうした天皇親政派と院政派の対立の中でも、朝廷内での権勢が高まる信西一門への反発が強まっていく。
反信西派は平治元(1159)年12月9日深夜、藤原信頼が院近臣の源光保、源義朝らを主力とする軍勢を、信西入道がいる院御所三条殿に派遣して焼き討ちし、後白河院の玉体を内裏一本御書所へ移すという暴挙に出る(『平治物語絵巻模本(三条殿焼討)』:東京国立博物館蔵)。しかし、目的の信西入道はすでに逃亡しており、後を追った源光保が山城国田原で自害していた信西入道の首を切って都へ戻っている(7)。
なお『愚管抄』によれば、源義朝は「信西ガ子ニ是憲トテ…婿ニトラン」と信西に申し入れたが、信西は「我子ハ学生也、汝ガ婿ニアタハズト云」って断ったという。しかしその後、信西は「当時ノ妻ノキノ二位ガ腹ナルシゲノリヲ清盛ガ婿」に迎えたことで、義朝は信西に敵意を催し、これが義朝が信頼と結んで兵を挙げた一因とする。これにつき、是憲が学者筋であって義朝からの縁談が断られることは「わかりきって」おり、これを挙兵の原因とするのは考えられないと排除する説も存在する。しかしながら『愚管抄』が認められた当時、少なくともこのような解釈が存在したのは事実である。これを否定する傍証もないままに恣意的な解釈を行うことはあまりに危険である。『愚管抄』にみられる義朝の思惑がなかったと言い切ることは不可能である。
こうして信頼は一時的に朝廷の権力を握ることに成功するが、信西亡き後、共通の敵を失った二條親政派と後白河院政派は再度対立。信西追捕の際、熊野へ外出中だった平清盛が親政派に推されて信頼打倒を模索した。これを受けて、12月25日夜、後白河院は内裏から仁和寺に脱出する。さらに翌26日には二條天皇も六波羅邸へ遷り奉ったのだった。摂津源氏の兵庫頭頼政及び美濃源氏の出雲前司光保、出羽判官光基は、信頼派の武士として合戦に加わっていたのではなく、あくまでも仕える二條天皇の行動如何で去就が変わるため、二條天皇が六波羅に迎え入れられた時点で、摂津源氏、美濃源氏一党は信頼勢から離脱することとなる。こうして、信頼への追討宣旨が出されるに到った(7)。
平治の乱相関図(■:藤原信頼方、■:後白河院方)
■藤原家
→藤原道長――藤原頼通――藤原師実―+――藤原師通―――藤原忠実―――藤原忠通―――藤原基実
(関白) (関白) (関白) | (関白) (関白) (関白) (摂政)
| ∥――――――近衞基通
| ∥ (関白)
| 藤原基隆―――藤原忠隆 +―女
| (修理大夫) (大蔵卿) |
| ∥ |
| ∥――――+―藤原信頼―――藤原信親
| ∥ (右衛門督) ∥
| ∥ ∥
|+―藤原顕隆―――藤原顕頼―+―藤原公子 +―娘
||(権中納言) (民部卿) | |
|| | |
|+―女 +―藤原惟方 平清盛――+―娘
| ∥ (参議) ∥
| ∥ ∥
+――藤原経実―+―藤原経宗 藤原通憲―――藤原成憲
(大納言) |(左大臣) (入道信西)
|
+―藤原懿子
(女御)
∥――――――二条天皇
∥
後白河天皇
■諸源氏
【摂津源氏】
→源満仲―+―源頼光――…+―…―――源頼政
(摂津守)|(内蔵頭) | (兵庫頭)
| |
| +―…―+―源光保【寝返る】
| |(出雲前司)
| |
| +―源光信――――源光基【寝返る】
| (検非違使) (出羽判官)
|【河内源氏】
+―源頼信――…+―…―+―源義朝――+―源義平
(甲斐守) | |(下野守) |(悪源太)
| | |
| +―源義盛 +―源朝長
| (十郎) |(中宮大夫少進)
| |
+―…―――源義信 +―源頼朝
(四郎) (右兵衛権佐)
■伊勢平氏
→平忠盛―+―平清盛――――+―平重盛
(讃岐守)|(太宰大弐) |(左兵衛佐)
| |
+―平経盛 +―平基盛
|(蔵人) (大夫判官)
|
+―平教盛
|(淡路守)
|
+―平頼盛
(三河守)
平治の乱の上皇方の人々(『平治物語』)
※義平十七騎は青字
| 大将軍 | 悪右衛門督信頼 | |||
| 信頼親族 | 新侍従信親(子息) | 兵部権大輔基家(舎兄) | 民部権少輔基通(舎兄) | |
| 尾張少将信俊(舎弟) | ||||
| 堂上等 | 伏見源中納言師仲 | 越後中将成親 | 治部卿兼通 | |
| 伊与前司信員 | 壱岐守貞知 | 但馬守有房 | ||
| 兵庫頭頼政 | 出雲前司光保 | 伊賀守光基(光保甥) | ||
| 河内守季実 | 左衛門尉季盛(季実子) | |||
| 河内源氏 | 左馬頭義朝 | |||
| 鎌倉悪源太義平(義朝嫡子) | 中宮大夫進朝長(義朝次男) | 右兵衛佐頼朝(義朝三男) | ||
| 陸奥六郎義隆(義朝叔父) | 新五十郎義盛(義朝弟) | |||
| 佐渡式部大夫重盛(義朝従子) | 平賀四郎義信(義朝従子) | |||
| 義朝郎従 | 鎌田兵衛正清 | 後藤兵衛実基 | 佐々木源三秀義 | |
| 熱田大宮司太郎(義朝小姑) 家子・郎等を遣わす |
||||
| 三河国 | 重原兵衛父子 | |||
| 相模国 | 波多野次郎義通 | 三浦荒次郎義澄 | 山内須藤刑部尉俊通 | |
| 滝口俊綱(俊通子) | ||||
| 武蔵国 | 長井斎藤別当実盛 | 岡部六弥大忠澄 | 猪俣小平六範綱 | |
| 熊谷次郎直実 | 平山武者所季重 | 金子十郎家忠 | ||
| 足立右馬允遠元 | 上総介八郎広常 | |||
| 常陸国 | 関次郎時貞 | |||
| 上野国 | 大胡 | 大室 | 大類太郎 | |
| 信濃国 | 片切小八郎大夫景重 | 木曾中太 | 木曾弥中太 | |
| 常葉井 | 榑 | 強戸次郎 | ||
| 甲斐国 | 井沢四郎信景 | |||
介八郎広常は『平治物語』においては、義朝に呼応して上洛し、待賢門の戦いで義朝の長男・鎌倉悪源太義平に従って平重盛(平清盛の嫡男)を追い回したという「伝承」がある(『平治物語』)。なお、なぜか上総介八郎広常は武蔵国の郎従のくくりとなっている。この待賢門の合戦での駆け合いは内裏の構造上疑わしいという事実(谷口耕一「平治物語の虚構と物語―「待賢門の軍の事」の章段をめぐって―)があるとともに、義朝の郎従として『平治物語』の中で前述され、且つ名が判然とする人々をただ順番通りに列記して作られた感が否めない。あくまで軍記物における「伝」と捉えるべきであるが、義朝は若いころに広常の父・常澄のもと上総国にも住んでおり(為義の指示であろう)、広常が義朝に従うのは至極自然であったのだろう。また広常は義朝が(為義から)「称伝得字鎌倉之楯、令居住」(「官宣旨案」『平安遺文』2544)した鎌倉にも屋敷があり、早くから義朝の郎従として活動をしていたことがうかがえる。
「平治の乱」は結局、二条天皇を擁する平清盛や、六波羅へ移徒せざるを得なかった大殿忠通・関白基実ら内裏勢力の勝利に終わり、敗れた藤原信頼は仁和寺に出頭し、罪状勘文もないままに河原で斬首。源義朝ら一党も竜華峠での山門僧との戦いで叔父・陸奥六郎義隆が討死。長男・源太義平は北陸へ別れ、次男・朝長も美濃国で死去。三男・頼朝も尾張国で平頼盛の被官・左兵衛少尉平宗清に捕縛されて京都へ移送され、義朝自身も尾張国内海(知多郡南知多町)で在郷の家人・長田庄司忠致によって殺害され、事実上、河内源氏義家流はここで壊滅することとなった。
源隆長――――女子
(参河守) ∥―――――源義親―――+―源義信――――延朗
∥ (対馬守) |(対馬太郎) (松尾上人)
∥ |
∥ +―源義俊
∥ |(対馬次郎)
∥ |
∥ +―源義泰
∥ |(対馬三郎)
∥ |
源頼義――――源義家―+―源義宗 +―源義行
(鎮守府将軍)(陸奥守)|(左衛門少尉) (対馬四郎)
∥ |
∥ +―源為義―――――源義朝
∥ |(左衛門大尉) (下野守)
∥ |
∥ +―源義時―――――石川義基
∥ |(陸奥五郎) (下総権守)
∥ |
∥ +―源義隆―――――若槻頼隆
∥ (陸奥六郎) (伊豆守)
∥
∥―――+―源義國―――+―新田義重
∥ |(加賀介) |(大炊助)
∥ | |
∥ | +―足利義康
∥ | (陸奥守)
∥ |
藤原有網―――女子 +―源義忠―――+―源経國
(中宮亮) (河内守) |(河内源太)
∥ |
∥ +=源為義
∥ (左衛門大尉)
∥
∥―――――――源義清
∥ (兵庫助)
平忠盛―+―女子
(刑部卿)|
|
+―平清盛
(太政大臣)
平宗清
桓武平氏。仁安3(1169)年7月4日、右衛門権少尉から左衛門権少尉に昇進。同日に主の平頼盛は右兵衛督を兼ねている(『兵範記』仁安三年七月四日条)。
義朝邸(六条堀川)または母方の藤原季範邸(六条坊門烏丸)にいたであろう頼朝実弟・希義(八歳)や、愛妾常葉とその子三人(今若、乙若、牛若)、陸奥義隆の嬰児(のちの毛利頼隆)らはいずれも捕われたものの、みな死罪に問われることはなかった。これは幼少であったことが大きい。藤原信頼の子・信親は「彼卿死罪之時、依五歳幼稚無沙汰」とあり(『兵範記』嘉応二年五月十六日条)、首謀者として「死罪」となった人物の子であっても幼少を理由に沙汰を逃れていることがわかる。ただし、これはおそらく院の意思によって流刑の執行を延期されたものであって、嘉応2(1170)年5月16日、十六歳で伊豆国へと流罪とされた。
 |
| 六条坊門烏丸(現五条烏丸交差点) |
一方で、義朝一党の遺児たちへの刑の執行は延期されず、まず永暦元(1160)年2月に陸奥六郎義隆の子・頼隆(配流時は生後百日余)が「仰常胤配下総国」されている(『吾妻鏡』治承四年九月十七日条)。平治の乱では常胤は義朝に属しておらず、朝廷は常胤と義朝との間に主従関係はないと認識していたことがわかる。また、朝廷が常胤に下総国への配流を命じていることから、当時常胤は在京中であった可能性が高い。そうであれば、常胤は大番等のために上洛しており、内裏勢力として召集された可能性もあろう。
そして、義朝三男・頼朝も、頼隆配流の翌3月11日、伊豆国へ流されることとなる。彼ら敗将の子らの助命に際して、『平治物語』によれば池禅尼や平重盛が平清盛への口添えをしたとされている。『吾妻鏡』においても「池禅尼恩徳」(『吾妻鏡』寿永三年四月六日条)とあり、また、重盛についても「平治逆乱之時、故小松内府、為源家被施芳言訖」(『吾妻鏡』建久五年五月十四日)とあることから、池禅尼や重盛が諫言を行ったことは事実であろう。清盛は当時は正四位下で参議でもなく、当然陣定にも列席していないが、平治の乱では二条天皇が六波羅邸へ行幸するなどその影響力は強かったことから、罪名宣下に於いてもその意思は考慮されたのだろう。
余談だが、池禅尼と北条時政の後室牧の方が縁戚であるという説(杉橋隆夫「牧の方の出身と政治的位置~池禅尼と頼朝と~」)が定説化しつつあり、この説を論拠のひとつとなって展開される論文等があるが、牧の方の父である「大舎人允宗親」が説のように「諸陵助宗親」と同一人物であるとすると、保延2(1136)年に諸陵助に任官した藤原宗親(池禅尼の兄弟)は、六十年後の建久6(1195)年に「武者所」だったことになり、頼朝に供奉して上洛していたことになる。初任二十歳としても建久6年では八十歳を超えた高齢であり、こうした高齢の人物を上洛の供奉とする例を寡聞にして知らない。こうしたことから考えて牧の方の父「大舎人允宗親」と、池禅尼兄弟の「諸陵助宗親」はまったくの別人であり、「宗親」を通じた池禅尼と牧の方に血縁関係はない(牧氏と牧ノ方について)。
頼朝は上西門院には皇后時代から皇后宮少進、転じて上西門院蔵人として仕え、さらに二条天皇蔵人に移るなど、天皇や上西門院にゆかりのある人物であった。また、母や伯母が上西門院や美福門院女房であり、上西門院や美福門院らが助命に働きかけたともされるが、頼朝が上西門院や蔵人として出仕した期間は非常に短く、女院が積極的に働きかけるほど親密な関係にあったとは考えにくい。『吾妻鏡』に述べる通り、上西門院や美福門院の要請というよりも、やはり池禅尼や平重盛の諫言が罪名勘考に関して大きく働いたのであろう。
また、『平治物語』によれば「法性寺の大殿(藤原忠通)」が信西入道の追捕を実行して院の怒りを買い「死罪」と決まっていた新大納言経宗、検非違使別当惟方の処分につき、「公卿の死罪いかゞあるべかるらむ、其上、国に死罪をおこなへば、海内に謀叛の者たえずと申せば、かたがたもて死罪一等をなだめて遠流にや処せられん」と発言し、諸卿も「尤大殿の仰然るべし」と同意したことで、経宗・惟方は遠流へと減刑されたとある(『平治物語』)。この記述は軍記物の性格上、断定できるものではないが、保元の乱のように公的に死罪を言い渡された者が見えないことから、この大殿忠通の死罪忌諱の発言は事実に近いのではないだろうか。忠通の発言は死罪全体への警鐘であることから、頼朝以下の源氏遺児に対する量刑にも当然影響したであろう。その結果、永暦元(1160)年3月11日、平治の乱の罪科による遠流が執行され、経宗・惟方・師仲・頼朝と同母弟・希義(配流当時九歳)が京都を発した(『清獬眼抄』)。
永暦元(1161)年3月11日「配流公卿殿上人事」(『清獬眼抄』)
| 流人 | 官途 | 配流国 | 追使 |
| 藤原経宗 | 大納言 | 阿波国 | 章貞(左衛門志中原章貞) |
| 源師仲 | 中納言 | 下野国 | 信隆(右衛門尉惟宗信隆) |
| 藤原惟方 | 参議、検非違使別当 | 長門国 | 能景(左衛門志清原能景) |
| 源頼朝 | 右兵衛権佐 | 伊豆国 | 友忠(左衛門府生三善友忠) |
| 源希義 | (頼朝舎弟) | 土佐国 | 予(左衛門府生清原季光か) |
なお、頼朝の流刑地が伊豆となった理由は、遠流の国が選ばれただけであって、実弟の希義が土佐国へ流されたことと同様、偶然である。頼朝には二人の供人が付いたのみで、検非違使の左衛門府生三善友忠が護送した(『清獬眼抄』)。このうちの一人は、母方叔父の「祐範」が付けた「郎従」であるが、彼が安達氏の祖である藤九郎盛長の可能性もあろう(安達氏について)。
頼朝が流された永暦元(1160)年3月当時の伊豆守は平義範と推測される。義範は『尊卑分脈』に名は見えないが、『兵範記』から摂関家司・右大弁平範家の二男であることがわかる。一年半前の保元3(1158)年11月26日、安房守義範(十五歳)は、伊豆守藤原経房(十七歳)と相伝名替によって伊豆守に転じた(『兵範記』保元三年十一月廿六日条)。
『尊卑分脈』に記載はないが、従三位右大弁平範家の二男。母は正二位太宰権帥藤原清隆娘(義範元服時「今冠者等外祖父也」とある)。兄は七歳上の親範、弟は二歳下の行範、六歳下の棟範。天養元(1144)年生まれ。
仁平2(1152)年8月7日夜、範家の勘解由小路万里小路亭で「蔵人弁二三両男加首服」が行われ、一門左衛門尉平信範もこれに加わっている(『兵範記』仁平二年八月七日条)。義範九歳、行範七歳。加冠は外祖父清隆が務めた。名字を撰したのは治部少輔藤原俊経(従兄)。蔵人に任じられた。
藤原清隆―+―藤原隆能
(大宰権帥)|(主殿頭)
|
+―女
| ∥――――――藤原重頼
| ∥ (中宮権大進)
| 藤原重方 ∥
|(右中弁) ∥
| ∥
| 源頼政――+―二条院讃岐
|(兵庫頭) |
| +―源仲綱
| (伊豆守)
+―女
∥――――+―平親範――――平基親
∥ |(蔵人頭) (左大弁)
∥ |
平実親――+―平範家 +―平義範――――平範子
(参議) |(右大弁) |(伊豆守) (少将局)
| | ∥
| | ∥――――――惟明親王
| | ∥ (三品)
| | 高倉天皇
| |
| | 【平戸記著者】
| +―平行範――――平経高――――平経氏
| |(治部大輔) (蔵人頭) (右衛門権佐)
| |
| +―平棟範――――平棟基――――平棟子
| |(右大弁) (勘解由次官)(准三后)
| | ∥
| +―女 ∥
| ∥――――――藤原定房 ∥――――――宗尊親王
| ∥ (安房守) ∥
| ∥ ∥
| 藤原経房 後嵯峨天皇
| (伊豆守)
+―姉か
∥――――――藤原俊経
藤原顕業 (左大弁)
(左大弁)
仁平2(1152)年12月19日夕刻、「前女御基子未給」により、従五位下に叙爵(『兵範記』仁平二年十二月十九日条)。12月30日、安房守(『兵範記』仁平二年十二月卅日条)。九歳での任官であり、当時の安房国知行国主は父・平範家であろう。
保元2(1157)年10月22日、従五位上に昇叙。これは「造内裏勤賞叙位并節会」による除目で「平義範、外進物所」(『兵範記』保元二年十月廿二日条)とあるように、外進物所の造営を担当したことによる昇叙である。父の譲りではないため、十四歳で造営担当したという事であろう。
保元3(1158)年11月26日、十五歳で安房守から伊豆守に相伝名替(『兵範記』保元三年十一月廿六日条)。仁安2(1167)年6月28日、二十四歳で後白河院皇女・休子内親王の初斎宮の際に勅別当後見となったことが知られる(『顕広王記』仁安二年六月廿八日裏書)。親族と思われる「同親家」も見える。
仁安3(1168)年3月15日、二十五歳で臨時給として正五位下に叙される(『兵範記』仁安三年三月十五日)。9月18日、御禊行幸の供奉列に定められる(『兵範記』仁安三年九月十八日条)。治承3(1179)年4月11日時点で「故入道前宮内少輔義範」とあることから(『山槐記』治承三年四月十一日条)、若くして亡くなっていたことがわかる。そしてこの年、娘の掌侍平範子が高倉天皇皇子の惟明を産んでおり、安徳天皇皇嗣の有力候補であったが、典侍藤原殖子を母とする尊成親王(後鳥羽天皇)が皇嗣となった。
藤原経房は仁平元(1151)年、十歳のときに伊豆国の知行国主であった父・藤原光房のもと伊豆守となった。しかし、経房が十三歳の久寿元(1154)年11月、父・光房が急死したため、伊豆国の知行国主は別の人物へと変わったとみられる。保元3(1158)年11月26日、経房は平義範と相伝名替して安房守となっているが、同じ年、経房は平範家娘との間に長男・定経を儲けており、当時の伊豆国の知行国主は平範家の可能性が高いだろう。
藤原俊忠―+―藤原俊成――――藤原定家
(権中納言)|(皇太后宮大夫)(権中納言)
|
+―藤原忠成――――高倉局
|(民部大輔) (仕上西門院)
| ∥
+―帥法印禅智 ∥―――――――常興寺僧正真性
|(随以仁王) ∥ (天台座主)
| ∥
| 暲子内親王===以仁王
|(八条院) (高倉宮)
|
+―娘
∥―――――――藤原経房
∥ (伊豆守、上西門院判官代)
藤原光房 ∥
(権右中弁) ∥
∥
平範家―――――娘
(非参議)
伊豆守平義範の後任の伊豆守は、美福門院に仕える源頼政の子・源仲綱であった。仲綱の伊豆守就任時期は不明だが、仁安2(1167)年7月7日当時「伊豆守」であることから、応保4(1164)年の任官であろう。頼朝が伊豆に流された四年後のことである。
源仲綱
摂津源氏源頼政の長男。久寿2(1155)年9月23日、立太子した美福門院養子・守仁親王(二条天皇)の東宮坊蔵人三﨟(『山槐記』久寿二年九月廿三日条、『兵範記』久寿二年九月廿三日条)。父・頼政同様に美福門院との繋がりが強かった。
その後、伊豆守となるが、就任時期は不明。ただし、前任の平義範が保元3(1158)年11月26日の就任から四年の任期を全うしたとすると、仲綱は応保3(1163)年中の任官となるが、仁安2(1167)年7月7日、法勝寺で行われていた御八講結願の日、「伊豆守仲綱」が法会の列に加わり、同年12月30日、後白河院の近臣・隠岐守中原宗家と相伝名替によって隠岐守に転任(『兵範記』仁安二年十二月三十日条)しており、仲綱の伊豆守就任は応保4(1164)年と考えられ、前任の平義範は一年の延任があったのかもしれない。仲綱は頼朝配流後四年目での就任ということになる。
仁安3(1168)年9月18日、「従五位下源朝臣仲綱」が御禊行幸の供奉列に定められる(『兵範記』仁安三年九月十八日)。
仲綱は隠岐守ののち、再び伊豆守となる。この伊豆守任官は、伊豆国の知行国主となっていた兵庫頭源頼政の選任である。伊豆国は承安2(1172)年7月9日以前から「頼政朝臣知行国」(『玉葉』承安二年七月九日条)であり、仲綱が隠岐守として四年の任期を全うして伊豆守に転じたとすると、仲綱の伊豆守就任は承安2(1172)年の除目であると考えられ、頼政の伊豆国知行国主もその時期であろう。安元2(1176)年4月27日当時も仲綱が「伊豆守」であり(『吉記』安元二年四月廿七日条)、重任していることがわかる。
仲綱は仁安2(1167)年12月30日、後白河院の近臣である隠岐守中原宗家と相伝名替によって隠岐守に転任した(『兵範記』仁安二年十二月三十日条)。仲綱は頼朝配流後、四年にわたって伊豆守であり、頼朝が二条天皇蔵人であったこともあり、美福門院とその娘・八条院に仕えていた仲綱との間に交流があってもおかしくはなく、この時点で頼朝と仲綱父・兵庫頭源頼政が繋がりをもった可能性もあろう。頼政は自身に所縁のある一族の孤児を積極的に養子としており、謀叛の罪で討たれた実弟・源頼行の子である兼綱らはもちろん、近衞天皇(美福門院皇子)の東宮時代に帯刀先生だった源義賢(頼朝叔父)の遺児・源仲家(八条院蔵人)や同族・源国政も養子としている。頼朝も仲綱を通じて頼政の庇護のもとにあったと考えられる。
中原宗家
後白河院近臣。従五位下隠岐守。仁安2(1167)年12月30日、伊豆守源仲綱と相伝名替によって隠岐守に転じた(『兵範記』仁安二年十二月三十日条)。仁安3(1168)年3月20日、皇太后宮(建春門院平滋子)大属となる(『兵範記』仁安三年三月廿日条)。
仲綱の伊豆守就任は承安2(1172)年の除目であると考えられ、以降治承4(1180)年まで伊豆守であった。安元元(1175)年9月に起こった「武衛御座豆州之時者、安元々年九月之比、祐親法師、欲奉誅武衛、九郎聞此事潜告申間、武衛逃走湯山給、不忘其功給之處有孝行之志如此」(『吾妻鏡』養和二年二月十五日条)という事件の際も仲綱が伊豆守であった時期であり、この伊東祐親入道による頼朝誅殺計画は、祐親入道の子・伊東九郎(頼朝乳母比企尼の女婿)によって頼朝に知らされ、頼朝は走湯山へ逃れたとされる。なお、当時の頼朝が居住していた配流地は伊東であり、その後に蛭嶋へ移ったとされる(坂井孝一『源頼朝の流人時代に関する考察』)。
 |
| 蛭嶋周辺(狩野川) |
その後、治承4(1180)年まで頼政が伊豆国知行国主として続き、頼朝はその庇護のもとで、頼政の主・八条院の所領である下総国下河辺庄の庄司・下河辺氏や同族で乳母家の小山氏らとの接触、伊豆国の在庁官人の狩野氏をはじめとして、北条氏、天野氏、堀氏、仁田氏ら国人層との接触を重ねたと思われる。頼朝は頼政の係累を尊重する立場を取り、頼政の末子・源広綱は「広綱、自幼稚住洛陽之歟、謂官位者又就最初御吹挙任之間、於一族為上臈」(『吾妻鏡』建久二年十一月二十七日条)とある通り、実弟範頼や義経、血縁の足利義氏を差し置いて門葉の上臈として遇されていた。また、頼政女婿の藤原重頼も鎌倉に招請されて、傍近くで処遇されている。
平治の乱後、相馬御厨は謀叛人義朝の知行とみなされ「自国衙被没収」されてしまった(永暦二年四月一日『下総権介平某申状写』)。しかし、常胤は、相馬郷は源義朝と無関係であることを証文とともに国衙を通じて国司・源有通へ訴えたのだろう。これを受けて永暦元(1160)年秋、下総守源有通は常胤の訴えを認め、相馬御厨について「非彼朝臣所知之由、証文顕然候、如本可被奉免立券候之旨」と、奉免立券した。源有通は保元4(1159)年正月29日の除目で「従五位下源朝臣有通」として下総守に任じられている人物で(『極秘大間書』)、小一条院敦明親王の曾孫である(『尊卑分脈』)。この後のことであるが、平治元(1159)年10月15日に出家辞官した前大納言藤原成通の猶子となり、藤原姓に改姓している。
三条天皇――敦明親王――源基平――源行宗――+―源有通
(小一条院)(侍従) (大蔵卿) |(下総守)
|
+=女
信縁――――(兵衛佐局)
(法勝寺執行) ∥―――――重仁親王
∥
崇徳天皇
 |
| 伊勢外宮 |
ところが「如本可被奉免立券」し、在庁が地頭らに検注させたが、その「国吏裁定」が「無音」という状況が続いたことから、常胤は国衙に出向いて子細を訪ねた。しかし、なぜか審理が長引いて「国吏裁定」が滞っていたことが判明した。その滞った理由は、おそらく相馬御厨の庁判や公験を所有し、寄進を謀った前左兵衛少尉源義宗なる在京官吏の存在と見られる。
常胤は因縁深い故親通の公験を所有する義宗の寄進に対抗するべく、「因之令訴申権門候」と中央の権力者を頼り、その結果「右大臣殿(藤原公能)」から計らい沙汰すべき旨の指示が「祭主殿」に出された(永暦二年四月一日『下総権介平某状』)。当時の伊勢祭主は、正月25日までは大中臣親章、その後は大中臣為仲、大中臣師親と相次いで変わっているが、右大臣公能が指示したのはおそらく大中臣為仲であろう。
■伊勢祭主(『祭主補任』:「神道大系」)
| 祭主名 | 最終官途 | 在任 | 備考 |
| 大中臣朝臣親章 | 従三位 | 保元2(1157)年8月13日~永暦2(1161)年正月25日(薨去 五十七歳) | |
| 大中臣朝臣為仲 | 正四位下 | 永暦2(1161)年正月30日~同年9月19日停任 | 元待賢門院侍 |
| 大中臣朝臣師親 | 正四位上 | 永暦2(1161)年9月19日~永万元(1165)年5月4日停任 |
常胤は「八条院御領(当時は安楽寿院領か)」(『吾妻鏡』文治二年三月十二日条)の千葉庄の荘官であり、暲子内親王に仕える身であった。当時、暲子内親王は二条天皇准母であり、皇后藤原多子(永暦元年正月廿六日入内)の実父は当時「一上」(『公卿補任』)の右大臣公能であった。公能は多子入内の年、永暦元(1160)年8月11日、二の権大納言から重通、宗能の二名を超越して右大臣となっており、これは外戚は任大臣の慣例によるものとみられる。常胤が右大臣公能を頼ったのは、八条院庁を通じた依頼であった可能性があろう。
なお、突如相馬御厨の寄進を行おうとした源義宗は、故源義朝の遠祖・鎮守府将軍源頼義の実弟の源頼清の子孫である(佐々木紀一「『平家物語』の中の佐竹氏関係記事について」(『山形県立米沢女子短期大学紀要』44))。
源頼信―+―源頼義――源義家――源為義―――源義朝――――源頼朝
(伊予守)|(陸奥守)(陸奥守)(検非違使)(下野守) (右兵衛権佐)
|
| +=源義宗
| |(判官代)
| |
+―源頼清――源家宗――源家俊―+―源重俊――+―源宗信―――源義宗〔恐與上文重俊子義宗同人〕
(陸奥守)(美作守)(左馬助)|(左衛門尉) (上野冠者)(高松院判官代)
|
+―源俊宗――――源義宗〔為重俊子〕
源義宗は常胤が「権門」を頼って解決しようとしたことに、「此国者惣根本当宮御領也、仍雖権門勢家、敢以不致相論也」と反発し、「常澄常胤等之妨」と主張している(永暦二年正月日『前左兵衛少尉源義宗寄進状』)。この批判は永暦2(1161)年正月の段階のものであることから、常胤が「権門(藤原公能)」へ訴えたのは、奉免立券した永暦元(1160)年秋以降、10~12月であると思われる。なお、義宗の批判の対象になぜか「常澄」も含まれているが、常胤の寄進状の中に常澄が登場することはなく、さらに常澄の介入も見られないことから、義朝と関わった常澄と常胤を敵対勢力と考えて記載したのであろう。彼らを「大謀叛人前下野守義朝朝臣年来郎従等」と誹謗し(永暦二年正月日『前左兵衛少尉源義宗寄進状』)、彼らに相馬御厨に介入する権利はないとするところからも察せられる。
 |
| 内宮(皇太神宮)を流れる五十鈴川 |
義宗が相馬御厨の知行の根拠と主張したのは、藤原親通の「二男親盛朝臣」から「而依迊瑳北條之由緒、以当御厨公験所譲給」ったことである(永暦二年正月日『前左兵衛少尉源義宗寄進状』)。「迊瑳北條之由緒」がどのようなものかははっきりしないが、「匝瑳北条」に義宗が持っていた土地に関する何らかの権益を親盛へ渡した過去があり、その対価として相馬御厨の「公験」が譲られたのかもしれない。実際に親盛の子・藤原親雅(千田判官代)は、匝瑳北条の内山に館を構えていたとされ、親盛が匝瑳北条に権利を持っていたことが推測される。なお、親盛は『尊卑分脈』には「従五位下、散位、下総守」とあるが(『尊卑分脈』)、仁安2(1167)年8月18日に行われた摂政基房の「若君沐浴」で、「鳴弦」を行った六名「正遠、信方、懐成、延清、俊光、親盛已上三人六位、女院等判官代」の一人が親盛となっている(『愚昧記』仁安二年八月十八日条)。当時の「女院」は「皇嘉門院(聖子)」「上西門院(統子内親王)」「高松院(姝子内親王)」「八條院(暲子内親王)」であるが、基房との直接的な血縁は姉の皇嘉門院のみであり、ここで指す「女院等」は皇嘉門院のことであろう。ただし、『尊卑分脈』に指す親盛には女院判官代の経歴はないため、両親盛が同一人物である確証はない。
源義宗は河内源氏の一流・源頼清(源頼義弟)の子孫で、上野冠者宗信の子である(佐々木紀一「『平家物語』の中の佐竹氏関係記事について」(『山形県立米沢女子短期大学紀要』44))。宗信の曽祖父(頼清の子)源家宗は関白師実・師通に仕え、承暦2(1078)年に上野介となって任国に赴任し、承暦4(1080)年5月6日、「上野介家宗、依公家召自任国罷上」(『水左記』承暦四年五月六日条)ことが、権大納言源俊房のもとに報告されている。その後、応徳元(1084)年4月11日までの在任が確認できる(『後二条師通記』応徳元年四月十一日条)。家宗の子・家俊は寛治8(1094)年12月6日の賀茂臨時祭において舞人となった「左兵衛尉源家俊」として名がみえる(『中右記』寛治八年十二月六日条)。義宗の義兄・源宗信も「上野冠者」と称されていることから、義宗の系統は上野国に利権を有していた可能性があろう。そして、藤原親盛の父・藤原親通も、大治元(1126)年に上野権介に就いており、ともに在京の身であることから、義宗の父・源宗信と親盛の父・藤原親通の間に接点が生じた可能性があろう。そしてこれが「匝瑳北条之由緒」へと繋がっていったのかもしれない。
また、義朝の嫡子、源太義平に討たれた帯刀先生義賢の母は「六条大夫重俊女」(『尊卑分脈』)とあるが、もし六条大夫重俊が義宗の養父・左衛門尉重俊と同一人物であったとすれば、為義の六条堀川邸と近隣の好みで交流を持ち、姻戚関係となっていた可能性もあろう。事実上、義甥の義賢を追討した義朝を「大謀叛人」と称し、常澄、常胤をその家人と誹謗したのも、義朝に対する敵愾心があったから、という可能性はないだろうか。
義宗は永暦2(1161)年正月、相馬郷寄進の解状を伊勢内外二宮へ送るが(永暦二年正月日『前左兵衛少尉源義宗寄進状』)、相馬御厨をそれまでの内宮一宮から内外二宮への寄進としている。さらに翌2月には供祭料についての請文を内外二宮に発給している。
●永暦2(1161)年正月日『前左兵衛少尉源義宗寄進状』(『鏑矢伊勢宮方記』:『千葉県史料』中世編)
常胤は義宗の二宮寄進を知ると、これまでの内宮一宮への寄進から内外二宮へ義宗と同条件の寄進に切り替え、2月27日に寄進の決裁のための「解」を「二所太神宮庁」へ発した(永暦二年二月廿七日『正六位上行下総権介平朝臣常胤解写』)。そこには「代代国判次第調度文書公験等」が付されており、常胤も正式な「公験」を有していたことがわかる。
●永暦2(1161)年2月27日『下総権介平朝臣常胤解案』(『櫟木文書』:『鎌倉遺文』)
これにより、神宮庁では義宗(永暦二年正月日寄進)、常胤(永暦二年二月廿七日寄進)の寄進状の両案を勘案した。常胤は4月1日にもこれまでの相馬御厨に関するいきさつを主張した「申状」を「稲木大夫(荒木田明盛)」へ提出し、祭主(大中臣為仲)からの尋ねがあれば申状の旨を説明してほしいと依頼している(永暦二年四月一日『下総権介平申状案』)。
常胤は相馬御厨が平治の乱後に義朝所領として国衙に没収されたが、義朝の所領であった事実はないことが判明し、永暦元(1160)年秋、下総守(源有通)は相馬御厨を以前の通り奉免・立券させるべく、地頭に実検させよと在庁官人に命じている。ところがその後国衙から音沙汰がないため、常胤は国衙に出向いて状況の確認をした。すると在庁は「国吏裁定不早候之歟」と説明したため、常胤は私君(推定)である藤原公能に訴え、公能は祭主(大中臣為仲)に対し、この件を沙汰するよう命じている。
●永暦2(1161)年4月1日『下総権介平申状案』(『櫟木文書』:『鎌倉遺文』)
結局、これが奏功したか、常胤の寄進に対して「然則件相馬御厨、任申請旨、為二宮御領、可令備進供祭上分之状、与判如件」と「判」が捺され、その寄進が認められた(永暦二年二月廿七日『正六位上行下総権介平朝臣常胤解写』)。ところが「抑件御厨依下総権介平常胤寄文、近日雖成与二宮庁判」(永暦二年正月日『前左兵衛少尉源義宗寄進状』)というときに、神宮庁は態度を一転させ、「如今寄文者、理致分明之上、不知子細之旨常胤誓言状具也者、毀先判改与判如件」(永暦二年正月日『前左兵衛少尉源義宗寄進状』)として、義宗が永暦2(1161)年正月に提出した寄進状に対して「判」を与え、常胤の「誓言状」は「不知子細」であるとし、先に常胤へ与えた寄進状は破棄した(永暦二年正月『正六位上前左兵衛少尉源義宗寄進状写』)。そして長寛元(1163)年、相馬御厨は「源義宗沙汰」として宣旨が下されることとなり(建久三年八月『伊勢太神宮神領注文』)、常胤は相馬御厨に関する権利を完全に失うこととなった。
神宮庁が常胤の寄進状を破棄して義宗の寄進状に判を与えた時期は不明だが、この急な神宮庁の態度の変化は、常胤が相馬御厨の騒擾を訴えた右大臣公能が永暦2(1161)年8月11日に急死したことが関係しているのかもしれない。当時の義宗は二条天皇中宮姝子内親王に出仕(のち義宗は高松院判官代となっている)していたと思われ、中宮権大夫実長らによる口入があったのかもしれない。
しかし、頼朝の平家追捕と下総国が「関東御知行国」(『吾妻鏡』文治二年三月十二日条)となったことにより、常胤はふたたび相馬御厨に入部することになったと思われる。文治2(1186)年3月12日の時点で、相馬御厨は後白河院の「院御領」とされている(『吾妻鏡』文治二年三月十日条)ことから、相馬御厨は伊勢二宮領から後白河院領に転じた(寄進か)ことがわかる。
文治5(1189)年8月20日、頼朝による奥州藤原氏との合戦時、頼朝が翌21日に「ほうてう、みうらの十郎、わたの太郎、さうまの二郎、おやまたたのもの、おくかたせんちしたるものとん、わたの三郎」が平泉へ必ず到着するよう命じた文書(文治五年八月廿日『源頼朝書状』)。に「さうまの二郎」が見えるが、彼は常胤の次男・相馬二郎師常とみられ、すでに師常が相馬御厨に入部していたことがわかる。
建久3(1192)年8月5日、「下総国住人常胤」は政所下文の通り「仍相伝所領、又依軍賞充給所々等地頭職」を頼朝から認められており(『金沢文庫』:「鎌倉遺文」所収)、おそらくこの「相伝所領」の中には相馬郷ならびに立花郷が入っていたものと思われ、正式に相伝所領を取り戻したのだろう。
「源義宗」は「佐竹義宗」ではない
(※源義宗を佐竹義宗ではないとした初見論文(8)(9))
この相馬御厨の権利に関して、これまでは常胤と争った「源義宗」は常陸国の佐竹冠者昌義の子・佐竹義宗のこととされていたが、誤りであったことが証明されている(佐々木紀一「『平家物語』の中の佐竹氏関係記事について」:『山形県立米沢女子短期大学紀要』44)。
保延2(1136)年、下総守藤原親通が平常重から「官物負累」を理由に責め取った相馬御厨の証文および公験は、親通から次男・親盛へ譲り渡され、さらに「匝瑳北条之由緒」により源義宗へ譲り渡された。「匝瑳北条」とは匝瑳北条内山に屋敷を構えた親通流藤原氏のこととすれば親通流藤原氏と「源義宗」は親密な関係にあったことは推測できる。
しかし、ここから「源義宗」を「佐竹義宗」と同定し、平家―親通流藤氏―佐竹義宗―佐竹氏というような図式を成立させるのは非常に困難である。そもそも、親通流藤氏と佐竹氏が結びついていた傍証はない上に、佐竹氏が本拠とした常陸北部と相馬郡とでは地縁的な関わりが無いこと、佐竹氏討伐後に頼朝が没収した佐竹氏領の中には常陸国北部以外のものは含まれていないこと、佐竹義宗自身は院の「判官代」ではなかったこと、活動の時期が「源義宗」の方が一世代前であることなど、「源義宗」を「佐竹義宗」とする条件は大変厳しい。
「佐竹義宗」は承安4(1174)年3月14日当時、「■(佐)竹冠者昌義、同男雅楽助、大夫義宗」(『吉記』)と見え、父の「佐竹冠者昌義」とともに「蓮華王院領常陸国中郡庄下司経高濫行」を抑えるため、在庁らと協力すべきことが指示されており、父もまだ健全ないまだ青年の面影を感じる人物と思われる。なお「雅楽助」と「大夫義宗」が同一の人物かどうかは不明。ただ、佐竹義宗はこれ以前に在京して五位に叙爵していることがうかがえる。
一方、布施郷を寄進した「左兵衛少尉正六位上源義宗」は、久安5(1149)年12月22日の小除目で「去頃於陣辺搦犯人之賞」(『本朝世紀』)として賞に預かった人物で、当時「女院侍長」(『本朝世紀』)であった。佐竹義宗が常陸で活躍するよりも二十五年も前のことである。つまり義宗は美福門院侍長として美福門院に出仕していた在京の武士であり(賊を逮捕したのも左兵衛陣の辺りだろう)、久寿2(1155)年3月23日の石清水臨時祭では舞人の一人として「兵衛尉源義宗」が見えている(『兵範記』久寿二年三月二十三日条)。その後、布施郷を伊勢二宮に寄進した永暦2(1161)年正月までの間に左兵衛少尉を辞官していたことがわかる。
なお、『寛政重修諸家譜』の佐竹家譜に見える佐竹義宗の項目に「皇嘉門院侍長」とあるのは、『本朝世紀』の久安5(1149)年12月の源義宗の「女院侍長」とある記述を引いていると思われるが、当時の女院・美福門院を、二か月後に女院となった皇嘉門院と誤って「皇嘉門院侍長」とした可能性があろう。
仁安2(1167)年6月15日、伊勢外宮禰宜・度会某(度会彦章)が「源判官代」に対し、相馬御厨について内宮権禰宜荒木田明盛と外宮禰宜度会彦章との相論(権禰宜荒木田は千葉氏からの相馬御厨寄進の際の口入神主の家柄で領家的存在であり、対して外宮の禰宜度会は義宗の代弁を行う存在であった。)が永万2(1166)年6月3日に決着し、荒木田明盛から度会彦章へ避文を渡し和與がなったことの報告をしている(ただし、権禰宜荒木田は彦章を信用しておらず、御厨に関する文書は荒木田が保管している)。義宗が内宮荒木田明盛の避文を欲していることの他、文章の内容から、この「源判官代」と「源義宗」は同一人物とみられる。
結論から言えば、禰宜度会から報告がなされた「源判官代」は、おそらく伊予守源頼信の子・源頼清の子孫である「高松院判官代源義宗」と思われる(『尊卑分脉』)。義宗と義朝の関係は、義朝の叔母の甥孫となり又従兄弟には下総守藤原在重がいる。在重はおそらく千葉介常胤を相馬郡司に任じた人物であろう。
源頼信―+―源頼義――源義家――源為義――――源義朝――――源頼朝
(伊予守)|(陸奥守)(陸奥守)(左衛門大尉)(下野守) (右兵衛権佐)
|
| +=源義宗
| |(判官代)
| |
+―源頼清――源家宗――源家俊――+―源重俊――+―源宗信―――源義宗〔恐與上文重俊子義宗同人〕
(陸奥守)(美作守)(左馬助) |(左衛門尉) (上野冠者)(高松院判官代)
|
+―源俊宗――――源義宗〔為重俊子〕
なお、源義宗は源頼清(源頼義弟)の子孫で、上野冠者宗信の子である(佐々木紀一「『平家物語』の中の佐竹氏関係記事について」(『山形県立米沢女子短期大学紀要』44))。宗信の曽祖父(頼清の子)源家宗は関白師実・師通に仕え、承暦2(1078)年に上野介となって任国に赴任し、応徳元(1084)年4月11日までの在任が確認できる(『後二条師通記』応徳元年四月十一日条)。
■相馬御厨の寄進事項時系列
| 大治5(1130)年6月11日 |
『下総権介平朝臣経繁寄進状』→相馬御厨(布瀬墨埼御厨)の成立 |
| 保延元(1135)年2月 |
常胤、18歳で「相馬御厨下司職」を継承。 |
| 保延2(1136)年7月15日 | 藤原親通、相馬郡司常重の官物未進を責めて、常重を逮捕し、相馬郷・立花郷の新券を押し取る。 |
| 康治2(1143)年 | 源義朝、上総権介常澄の「浮言」を理由に、常重から相馬郷を責め取る(圧状)。 |
| 天養2(1145)年3月 | 源義朝、神威を恐れて(大庭御厨濫行か)相馬郷を伊勢二宮に寄進(ここでの避状=寄進状)。 |
| 久安2(1146)年4月 | 常胤、国衙に税を納めて、正式に相馬郡司に任じられる(立花郷は返還されず) |
| 8月10日 | 『御厨下司正六位上平朝臣常胤寄進状』→常胤によるはじめての寄進。 常胤、伊勢皇太神宮(内宮)より御厨下司職に改めて任じられる |
| ???? | 常胤、このころ「下総権介」に任じられるか |
| 保元元(1156)年7月 | 「保元の乱」が起こる。 常胤、上総介八郎広常(上総権介常澄八男)とともに源義朝に随って参戦 |
| 平治元(1159)年12月 | 「平治の乱」が起こる→源義朝、敗れて尾張にて殺害される。 常胤は参戦せず、広常は参戦。 |
| 永暦元(1160)年 | 常胤、相馬御厨を「謀叛人義朝領」として国衙に没収される |
| 秋 | 常胤、相馬御厨は千葉氏相伝の地であって義朝領ではなく、「神宮領」として国衙に奉免を求める。国司源有通もこれを認め、在庁に対して現地調査を命じる。 |
| 常胤は前年秋の相馬御厨奉免の決済が降りないので、国衙に参上して問い合わせを行っている。しかし、早々に決が下りる様子がないため、権門に注進。右大臣より伊勢祭主に調査の指示が出る。 | |
| 永暦2(1161)年1月日 | 『前左兵衛少尉源義宗寄進状』→源義宗による突然の寄進。 |
| 2月27日 | 『下総権介平常胤解案』→相馬御厨を内宮だけではなく、外宮にも寄進することを述べる。 |
| 3月中 | 『下総権介平常胤解案』の判以降→常胤の二宮への寄進状を認め、判が捺される。 |
| 3月中 | 『前左兵衛少尉源義宗寄進状』の判以降→先日の常胤へ与えた先券を破棄し、義宗の寄進状に判が捺される。 |
| 4月1日(16日着) | 『下総権介平申文案』→常胤、伊勢の稲木大夫に自分の正当性について口利きを依頼するが、実らず。 |
| 長寛元(1163)年 | 相馬御厨について「源義宗沙汰」の宣旨。 |
| 永万2(1166)年6月3日 | 常胤側の口入神主・荒木田明盛(内宮権禰宜)から、源義宗側の口入神主・度会彦章(外宮禰宜)へ避文が渡され、和與が成立。ただし、明盛は義宗を信用せず、御厨に関する書類一切は手元に保管。 |
| 仁安2(1167)年6月15日 | 度会彦章より「源判官代」に対し、相馬御厨について荒木田明盛との相論が決着した報告がなされる。 |
千葉氏は常兼・常重以来、代々「下総権介」に就いており、館は遠祖千葉大夫常長以来の千葉庄(千葉市千葉寺周辺)に存在していたと考えられるが、下総国衙付近(市川市国府台)にも進出し、国分寺領の支配をしていたと思われる。常胤の五男・五郎胤通は国分館に住し、国分五郎を称していた。
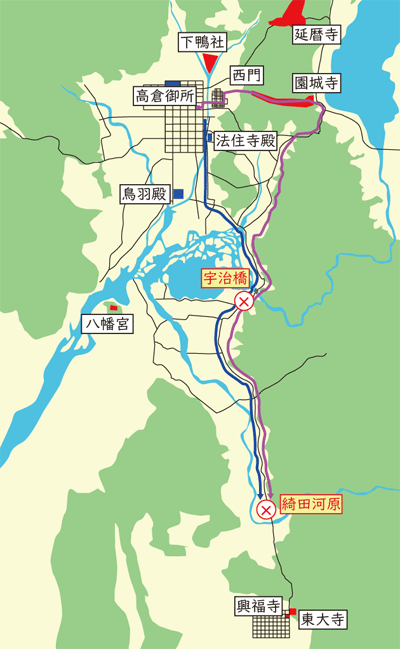 |
| 紫線は以仁王の逃走ルート(推定) 青線は検非違使の追撃ルート(推定) |
また、常胤の六男・六郎胤頼は大番として上洛し瀧口に詰めたのち、上西門院蔵人だったと思われる遠藤左近将監持遠の推挙で上西門院統子内親王(鳥羽院の皇女)に仕えて「五位」を給され、「千葉六郎大夫」と称した。そして大番の任期が切れて帰国予定だった治承4(1180)年5月、以仁王(後白河院の皇子)が源三位頼政入道と結んで挙兵(以仁王の乱)、以仁王に近侍した常胤の子・園城寺律静房日胤が宇治の南、綺田の大寺・光明山寺の鳥居前で戦死したとされる(『玉葉』治承四年五月廿六日条)。
以仁王の乱が鎮定されたのち、六郎胤頼は三浦次郎義澄とともに東国へ帰国を企てるも、両名は「依宇治懸合戦等事、為官兵被抑留之間」とある通り身柄を拘束された。胤頼の兄「律上房(日胤)」が乱の「張本」(『玉葉』治承四年五月十九日条)である以上、胤頼は当然嫌疑をかけられただろうが、三浦義澄が拘束された理由は不明。しかし、半月ほど拘留されたのち胤頼たちは釈放され、帰国の途についた。胤頼・義澄が具体的に宇治合戦に関わった証左はないが、胤頼の周辺を見ると乱に関わった人物が散見され、胤頼・義澄も関係していた可能性は高いだろう。
東下した胤頼と三浦義澄はまず伊豆国田方郡北条の前右兵衛権佐源頼朝のもとを訪れた。ここで彼らは以仁王や頼政入道の挙兵や京都における平家政権の状態を告げたと思われる。以仁王の乱が勃発するまで伊豆国は源頼政入道が知行国主となっており、目代も頼政入道所縁の人物であったと考えられ、承安2(1172)年7月9日以前から続いていた「頼政朝臣知行国」(『玉葉』承安二年七月九日条)のもと、下総国八条院領の下河辺庄司である下河辺氏、その一族で乳母家の小山氏らとの接触など、頼政の関係者との接触はそれほど厳しいものではなかったのかもしれない。
ところが、以仁王、源頼政入道の乱によって、伊豆国は収公され、平清盛の義弟・平時忠が知行国主となり、伊豆守は平時兼(時忠養子)、目代は当国流人だった平兼隆が起用された。兼隆は治承3(1179)年正月19日に父・平信兼の申請によって「解官右衛門尉平兼隆」(『山槐記』治承三年正月十九日条)とあるように、検非違使判官ならびに右衛門尉を解かれ、その後伊豆国へ遠流された稀有な人物で、在所は北条館に近い山木郷であった。兼隆は安元2(1176)年、平時忠が検非違使別当であった時期に「右衛門尉正六位上 平兼隆」と初見されることから、時忠のもとでおよそ半年あまり(時忠は辞官してしまう)検非違使であり、目代起用にはこうした過去の関係があったのかもしれない。
胤頼・義澄は頼朝との対面後、それぞれ郷里に帰り、頼朝は源頼政入道から遣わされた叔父・新宮十郎行家から「前伊豆守正五位下源朝臣(源仲綱)」の名による「以仁王の令旨」を受け取った。ところが、この頼政入道挙兵により、清盛入道は「近曾為追討仲綱息素住関東云々、遣武士等大庭三郎景親云々、是禅門私所遣也」(『玉葉』治承四年九月十一日条)と、以仁王の乱の首謀者である前伊豆守仲綱(源頼政嫡子)の子息を追討するべく、被官の大庭三郎景親を関東に差し遣わした。清盛入道の地方武士追討の方針は「遣禅門私郎従等、其後可被遣追討使」(『玉葉』治承四年十一月十二日条)というもので、大庭景親の下向もこれに当たるものであろう。しかし、この「仲綱息」は「迯脱奥州方了」(『玉葉』治承四年九月十一日条)とすでに奥州へ逃れ去っていた。
ところが、この清盛入道の大庭三郎景親の関東下向の沙汰を漏れ聞いた在京の頼朝支援者(頼朝乳母甥)の散位三善康信が弟の康清を使者として頼朝に用心を重ねるよう諭した。6月19日に「参著于北條」した康清からこの報告を受けた頼朝は、康信の功に感謝した「大和判官代邦道右筆」での「被加御筆并御判」の「委細御書」を認めると康清に託した(『吾妻鏡』治承四年六月廿二日条)。康清が22日に北條を発して上洛の途に就くと、「入道源三品敗北之後、可被追討国々源氏之條」という「康信申状」は「不可被處浮言」として、「遮欲廻平氏追罰籌策」し、6月24日、側近の藤九郎盛長に小中太光家を副えて「被招累代御家人等」て挙兵の協力を頼むこととした(『吾妻鏡』治承四年六月二十四日条)。
三善康光 +―三善康信
(権少外記) |(中宮大夫属入道善信)
∥ |
∥―――――+―三善康清
+―妹 (隼人佐入道善清)
|
|
+―頼朝乳母
右筆の「大和判官代邦道」は、藤九郎盛長が在京時に「因縁」のあった人物で、盛長の推挙で伊豆に下向し頼朝に伺候していた。その出自は北家魚名流の末裔であるとされる(野口実『中世東国武士団の研究』高科書店1994)。 なお、邦道の四代前に見える友房は、嘉承3(1108)年正月24日の除目で「受領被任次第」として「大和守藤友房」とあるように大和守に任じられている(『中右記』嘉承三年正月廿四日条)。この除目について中御門宗忠は「管国肥前公文、儒者四位也、被成此国、誠以不便歟」と管轄外の受領となることへの同情を述べている。
建久2(1191)年3月3日、翌日の「鎌倉大火災」を予言した人物として「広田次郎邦房」が見えるが、彼は「大和守維業男」で「継家業者、雖有儒道之号」(『吾妻鏡』建久二年三月三日)という人物だった。「大和守維業」は邦道の叔父にあたり、邦房は邦道の従兄弟にあたる。「広田」は越中国「弘田御厨」に由来しているとみられる。「弘田御厨二宮」は仁平3(1153)年までに建立された御厨で「給主散位故友業子息」とあり、おそらく友業が建立し、子である「大和守維業」が給主となってこれを管理したものだろう。「件御厨、去仁平年中建立、同三年被下奉免宣旨之後、度々 宣旨重畳也」(『神宮雑書』)という。
●大和判官代邦通の系譜(野口実『中世東国武士団の研究』高科書店1994、『尊卑分脈』)
藤原魚名―鷲取――――藤嗣――高房―――山蔭―――公利――――守義――為昭―則友―+―国成――+
(左大臣)(中務大輔)(参議)(越前守)(中納言)(但馬権守)(参議) | |
| |
+―国長 |
|
+―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――+
|
+―友房――盛友――友業―――+―友長――――邦道
(大和守) (大和進士)| (大和判官代)
|
+―藤原維業
|(六条院蔵人)
|
+―藤原盛国
(諸陵頭)
以下は史料的価値は低いが、『源平盛衰記』にみられる藤九郎盛長の「被招累代御家人等」の説話である。
盛長はまず相模国の波多野右馬允義常のもとを訪れたという(『源平盛衰記』)。ところが義常は日和見的な態度を示す。
次に義常の義兄にあたる懐島権守景義を訪れた。景義は弟の大庭三郎景親のもとを訪れて「和殿はいかゞ思」うかと問うと、景親は「源氏は重代の主にて御座ば、尤可参なれ共、一年囚に成て既に切らるべかりしを、平家に奉被宥、其恩如山、又東国の御後見し、妻子を養事も争か可奉忘なれば、平家へこそ」と答える。これに景義は「源氏へ参らんと存ず、但軍の勝負兼て難知し、平家猶も栄え給はば和殿を憑べし、若又源氏世に出給はば我をも憑給へ」と、弟の豊田次郎景俊とともに頼朝方へ参ずることを決め、景親は末弟の俣野五郎景久とともに平家方についたという(『源平盛衰記』)。ただし、当時景親は在京のためこの話は史実ではない。
次に盛長は山内首藤瀧口三郎経俊、四郎の兄弟に触れるが、経俊は弟に「是聞給へ、人の至て貧に成ぬれば、あらぬ心もつき給けり、佐殿の当時の寸法を以て、平家の世をとらんとし給はん事は、いざいざ富士の峯と長け並べ、猫の額の物を鼠の伺ふ喩へにや、身もなき人に同意せんと得申さじ」と嘲ったという(『源平盛衰記』)。
その後、三浦大介義明のもとを訪れると、義明は涙を流して「故左馬頭殿の御末は、果て給ひぬるやらんと心憂く思ひつるに、此殿ばかり生残御座て、七十有余の義明が世に、源氏の家を起し給はん事の嬉しさよ、唯是一身の悦也、子孫催し聚て、御教書拝み奉るべし」と喜び、一族を集めて「一味同心して兵衛佐殿へ参べし」と申し述べたという(『源平盛衰記』)。
その後、盛長は海を渡って下総国に至り、千葉介常胤と面会したという(『源平盛衰記』)。『吾妻鏡』ではこの説話は9月1日から9日までの間の話であって時期が異なるが、『吾妻鏡』6月24日条にもみられるように、挙兵に際して故義朝と所縁のある諸豪族には悉皆触れたと想像され、挙兵以前に頼朝と常胤は連絡を取っていた可能性が高いだろう。とくに常胤の六男・六郎大夫胤頼が頼朝の配流先にまで訪れていることからも、挙兵以前に頼朝と常胤は接触を持ったことが想像される。
『源平盛衰記』によれば、盛長が訪問すると、常胤は「此事上総介に申合て、是より御返事申べし」と、上総介八郎広常との相談の上返事すると即答を避けたという。ところが、盛長の帰途に鷹狩り帰りの常胤の嫡子・小太郎胤正と出会う。胤正は盛長を見て「如何に」と問うており、説話上ではすでに顔見知りであった様子がうかがえる。盛長の話しを聞いた胤正は盛長を伴って館に帰ると、常胤に「恐ある事に候へ共、院宣の上御教書成侍ぬ。先度の御催促に参上の由御返事申されぬ、其上上総介に随たる非御身、彼が参らばまゐらん、不参は参らじと仰候べき歟、全不可依其下知、只急度可参由御返事申させ給ふべし」と常胤に迫ると、常胤も「可参」と返答したという(『源平盛衰記』)。さらに広常のもとを訪れて触れた際には「生て此事を奉る身の幸にあらずや、忠を表し名を留ん事、此時にあり」と、広常は積極的な参加を約した(『源平盛衰記』)。
なお、この広常と常胤の招聘に関する説話は、後述の通り『吾妻鏡』とは真逆の設定となっているが、『源平盛衰記』は成立年代が遅く、さらに『平家物語』をベースに説話を増補した軍記物である以上、『吾妻鏡』より信を置くことは不可であろう。
広常との逸話については、「上総介ノ八郎広経カ許ヘ行テ勢ツキニケル」(『愚管抄』巻五)とというものもあるが、実際には安房国で平家与党の長狭常伴の襲撃計画を知り、道を変更して下総国へ北上しているため、広常のもとに向かってはいない。『愚管抄』が記されたころにはすでに治承寿永の乱から数十年の時を経ている上に、もとより慈円は東国の出来事は伝聞を書き留めているに過ぎない。そのため頼朝挙兵時に「梶原平三景時、土肥次郎実平、舅ノ伊豆ノ北條四郎時政、是等ヲ具シテ東国ヲウチ従ヘントシケル」など、梶原景時が当初より頼朝に従属していたと誤解していたり(これはのちに梶原景時、土肥実平の両名が平家の追捕使として中国地方に派遣されたバイアスによる誤解だろう)、平家に伺候していた「畠山庄司、小山田別当」の子「庄司次郎ナド云者共ノ押寄テ戦ヒテ箱根ノ山ニ逐コメテケリ」と、実際には石橋の陣に参戦していない畠山庄司次郎重忠が押し寄せたと誤解していたりするなど、挙兵時の東国に関する情報は錯綜したまま慈円は理解しているのである。『愚管抄』の東国に関する情報、とくに、突然の東国騒乱に情報がひどく錯綜していた治承4年当時については、京都に情報源を持つ事柄に比べて信憑性は低いものと疑うべきである。
7月10日、盛長一行は伊豆の頼朝のもとに帰参し報告を行う(『吾妻鏡』治承四年七月十日条)。盛長らは相模国内の諸士を味方につけることに成功するも、波多野右馬允義常、山内首藤瀧口三郎経俊は応じなかったことが伝えられた。さらに、5月の源三位の乱で平家に動員された東国武者たちが続々と関東に帰還するという状況も発生する。
8月、頼朝は挙兵の手始めとして、試みに平家被官である伊豆国目代「散位平兼隆」を討つべく計画を立て、右筆の大和判官代邦道を兼隆の屋敷へ送り込んだ。この大和判官代邦道は「邦道者洛陽放遊客也、有因縁盛長依挙申」(『吾妻鏡』治承四年八月四日条)とあるように、藤九郎盛長がまだ在京時に「因縁」があり、盛長の推挙で頼朝に伺候していた。邦道は治承4(1180)年6月22日の時点ではすでに頼朝の右筆として見えるが(『吾妻鏡』治承四年六月二十二日条)、いまだ兼隆に悟られていないことから、盛長の推挙後間もないのだろう。邦道が山木兼隆を訪れた際、兼隆は酒宴や郢曲を催して歓待し、数日にわたって逗留させていることから、兼隆と邦道は京都で顔見知りだったことがわかる。
8月4日、邦道は頼朝のもとに戻り、写し取った山木周辺の絵図面を披露する、頼朝は北条時政を配所に招くと、襲撃の計画を立てた。そして、8月17日、三島社の祭礼にあわせて山木館を襲うことを決定し、工藤介茂光、土肥次郎実平、岡崎四郎義実、宇佐美三郎助茂、天野藤内遠景、佐々木三郎盛綱、加藤次景廉らをひとりひとり配所に招いて合戦について議し、「令議合戦間事給雖未口外、偏依恃汝被仰合」と一人ひとりに慇懃に声をかけたため、みな勇を励む決意を新たにしたという(『吾妻鏡』治承四年八月四日条)。
そして8月17日、挙兵の決行日に頼朝は藤九郎盛長を使者として三島社へ奉幣し、その後、盛長の僕童が配所の釜殿で兼隆の雑色男を生け捕った。この雑色男は配所の下女と婚姻していたことから、夜々配所に妻訪に現れていた人物であった。頼朝は普段はそのままにしていたが、今夜は挙兵のために諸士群集しており、兼隆に注進される恐れがあるため、召し取るよう命じている。そして、北条時政以下の諸士を山木館へ向けて進発させ、山木判官兼隆とその後見の堤権守信遠を討ち取ることに成功する(『吾妻鏡』治承四年八月十七日条)。
兼隆は前年の治承2(1178)年正月19日に解官され(『山槐記』治承二年正月十九日条)、配流はさらに後日であったことになる。おそらく伊豆へたどり着いたのは早くとも3月以降であろうと推測され、その後、目代として起用されるまで流人であった。『吾妻鏡』によれば配流後「漸歴年序之後、借平相国禅閤之権、輝威於郡郷、是本自依為平家一流氏族也」とあるが、流人ながら平氏一族だったことから権威を奮ったのだろう。しかし兼隆は父・信兼の望みとして配流されていることから、信兼一族の支援は考えられず、私兵を蓄える財もなかったであろう。また、目代となったのは知行国主が平時忠へ移った治承4(1180)年7月以降(以仁王の乱は5月26日に終結しており、その後の頼政党類の収公処理や除書等の作成、伊豆国への伝達を考えれば、最短でも一月程度は必要であろう)であることから、頼朝挙兵まで長くとも一か月程度しかない。「後見」の堤信遠については、後見が親類を主とすることから兼隆の親類でともに下向していたのだろう。
そして8月19日、頼朝は「在当国蒲屋御厨」った「兼隆親戚史大夫知親」が日ごろから非法を行って民を苦しめていると称し、その権限を停止させた。これが「関東事施行之始」であったという(『吾妻鏡』治承四年八月十九日条)。中原知親が兼隆とどのような親戚関係にあったかは定かではないが、知親は「平知親」とも称され(『吉記』治承五年三月廿六日条)、藤原忠清のように平姓の呼称を持つほど近い親類であったのだろう。彼は治承5(1181)年3月26日、県召除目で検非違使となり、左衛門尉に就いている(『吉記』治承五年三月廿六日条)。4月16日の賀茂祭では検非違使の筆頭として加わっている。
治承4(1180)年の頼朝の挙兵は「義重入道故義国子、以書状申大相国、義朝子領伊豆国、武田太郎領甲斐国」と、上野国の新田義重入道によって清盛入道へと伝えられて発覚している。義重入道は「義重在前右大将宗盛命相乖、彼家宗、坂東家人可追討之由仰下、仍所下向也者」と、宗盛の命によって坂東追討のために上野国へ下向していた人物であった(『山槐記』治承四年九月七日条)。
治承4(1180)年9月5日、高倉院御所において頼朝挙兵に対する追討使派遣について評議が行われ、その結果、「維盛、忠度、知度等」を追討使とする官宣旨が下され(『玉葉』『山槐記』治承四年九月九日条)、22日に追討使下向が決定された。
■治承四年九月五日「源頼朝等追討官宣旨」(『山槐記』治承四年九月五日条)
右弁官下 東海道諸国
応追討伊豆国流人源頼朝幷与力輩事
右 大納言藤原朝臣実定宣奉 勅頼朝忽相語凶徒凶党、欲慮掠当国隣国、叛逆之至既絶常篇、宣令右近衞権少将平維盛朝臣、薩摩守同忠度朝臣、参河守同知度等、追討彼頼朝及与力輩、兼又東海東山両道堪武勇者同令備追討、其中抜有殊功輩、加不次賞者、諸国宣承知依宣行之
治承四年九月五日 左大史
平氏政権は地方叛乱勢に対しては、追討使下向までの間に在地勢力にその鎮定を命じる向きがあり、今回も「伊豆国伊東入道、相模国大庭三郎」(『山槐記』治承四年九月七日条)に頼朝追討が命じられることとなった。大庭三郎景親はもともと「近曾為追討仲綱息素住関東云々、遣武士等大庭三郎景親云々、是禅門私所遣也」(『玉葉』治承四年九月十一日条)といい、清盛入道が私的に遣わした人物であったが、「忽頼朝之逆乱出来」(『玉葉』治承四年九月十一日条)たため、頼朝追討に切り替えられたものだった。
8月23日、「武衛相率北條殿父子、盛長、茂光、実平以下三百騎、陣于相摸国石橋山給、此間以件令旨、被付御旗横上」(『吾妻鏡』治承四年八月廿三日条)と、頼朝は三百騎ほどを率い、以仁王(最勝王)の令旨を旗の上に掲げて相模国石橋山に布陣したという。これに対し、平氏方の「同国住人大庭三郎景親、俣野五郎景久、河村三郎義秀、渋谷庄司重国、糟屋権守盛久、海老名源三季貞、曾我太郎助信、瀧口三郎経俊、毛利太郎景行、長尾新五為宗、同新六定景、原宗三郎景房、同四郎義行并熊谷次郎直実以下平家被官之輩、率三千余騎精兵、同在石橋辺、両陣之際隔一谷也」(『吾妻鏡』治承四年八月廿三日条)で、さらに「伊東二郎祐親法師率三百余騎、宿于武衛陣之後山兮、欲奉襲之」という陣容であった。
また、頼朝と合流すべく石橋山へ向かっていた「三浦輩者」は「依及晩天、宿丸子河辺、遣郎従等、焼失景親之党類家屋、其煙聳半天」と、大庭景親与党の家屋に放火した。かなりの人家を燃やしたと見え、「入夜甚雨如沃」という天候の中でも「其煙聳半天」というほどであったという。景親はこれを石橋辺から「遥見之、知三浦輩所為之由訖」と悟ったという。この三浦勢の動きに景親は「今日已雖臨黄昏可遂合戦、期明日者三浦衆馳加、定難喪敗歟」と主張し、「数千強兵、襲攻武衛之陣」した。この大庭勢の急襲を受けた頼朝勢は「而計源家従兵、雖難比彼大軍、皆依重旧好、只乞効死、然間、佐那田余一義忠并武藤三郎及郎従豊三家康等殞命、景親弥乗勝、至暁天」という大敗を喫することとなる。
敗れた頼朝が「令逃于椙山之中給、于時疾風悩心、暴雨労身、景親奉追之、発矢石」という逃避行の最中、「依奉通志於武衛、雖擬馳参、景親従軍列道路之間、不意在彼陣」だった「景親士卒之中、飯田五郎家義」がにわかに景親を裏切り「為奉遁武衛、引分我衆六騎、戦于景親」ったため、頼朝は「以此隙令入椙山給」うことができたという(『吾妻鏡』治承四年八月廿三日条)。
翌8月24日、頼朝は「陣于椙山内堀口辺給」った(『吾妻鏡』治承四年八月廿四日条)。大庭景親はなおも追跡の手を緩めず、頼朝は「令逃後峯給」った。この間、「加藤次景廉、大見平次実政」が踏みとどまって景親の追跡を防ぎ、これに「景廉父加藤五景員、実政兄大見平太政光」も加わり、さらに「加藤太光員、佐々木四郎高綱、天野藤内遠景、同平内光家、堀藤次親家、同平四郎助政」も轡を並べて攻め戦い、景員以下の乗馬の多くは矢に当たって斃れた。頼朝も得意の弓箭を以て敵を防いだものの、「箭既窮」となり、加藤景廉が頼朝の乗馬の轡を引いてさらに深山へ入らんとする所を「景親群兵近来于四五段際」と追いすがったことから、「高綱、遠景、景廉等」が数反戻って防ぎ矢を射たという(『吾妻鏡』治承四年八月廿四日条)。この間に彼らは頼朝とはぐれたようである。
このとき「北條殿父子三人」もまた景親に追われ戦っていたが、「筋力漸疲兮、不能登峯嶺之間、不奉従武衛」と、頼朝らとは別行動を取っていた。ここに合流した「景員、光員、景廉、祐茂、親家、実政等、申可候御共之由」を北條時政に願い出たが、時政は「敢以不可然、早々可奉尋武衛之旨」を命じたという。「被命」とあるところから北條史観による記述であるが、頼朝の舅である時政が命じることは事実とみてよいだろう。
時政の指示を受けた景員らは「各走攀登数町険阻」して頼朝を探し回ったところ、「武衛者、令立臥木之上給、実平候其傍」であったという。頼朝は「令待悦此輩之参着給」し、土肥次郎実平は「各無為参參上、雖可喜之、令率人数給者、御隠居于此山、定難遂歟、於御一身者、縦渉旬月実平加計略、可奉隠」と伝えた。これに景員らは「申可候御共之由」を述べたため、頼朝も「有御許容之気」を示すが、実平は「今別離者、後大幸也、公私全命、廻計於外者、盍雪会稽之耻哉」と頼朝や景員らの主張を強く抑えて、少人数での行動とするよう述べたことから、彼らは「依之皆分散、悲涙遮眼、行歩失道」(『吾妻鏡』治承四年八月廿四日条)という。
こののち、飯田五郎家義が頼朝を慕って参上し、頼朝が路頭に落とした「日来持給」の御念珠を探し求めて持参した。これに頼朝は「御感及再三」している(『吾妻鏡』治承四年八月廿四日条)。このとき家義は御供を申し出るも、実平は頼朝を諫めたため、家義は泣く泣く退去した。また、北條時政と小四郎義時は「経筥根湯坂、欲赴甲斐国」を志し(ただし甲斐行きは中止)、別行動の時政長男の北條三郎宗時は「自土肥山降桑原、経平井郷」のところ、早川の辺で「被圍于祐親法師軍兵、為小平井名主紀六久重、被射取訖」した。また、狩野介茂光は肥満体であり、戦傷を負うと「依行歩不進退自殺」した(『吾妻鏡』治承四年八月廿四日条)。
8月28日に同地を発した脚力からの報告によれば、「伊豆国伊東入道、相模国大庭三郎」が「相模国小早河」において頼朝の軍勢と合戦に及び、「伊豆国伊東入道(祐親入道)」の親族とみられる「伊東五郎」ならびに「相模国大庭三郎(景親)」に随っていた「甲斐国平井冠者」が討たれたこと、敵の「兵衛佐同心輩」として、「駿河国小泉庄次郎」「伊豆国北条次郎、兵衛佐舅」「同薫藤介用光」「新田次郎」を討ち取り、「兵衛佐残少被討成、箱根山遁籠了」(『山槐記』治承四年九月七日条)ということであった。なお、北条次郎は頼朝の小舅・北条三郎宗時、薫藤介用光は工藤介茂光、新田次郎は仁田次郎(仁田四郎忠常の兄か)であろう。その兵力は「群賊纔五百騎許、官兵二千余騎」であったという(『玉葉』治承四年九月九日条)。
9月7日、戦いの結末が「義朝子慮掠伊豆、坂東国之輩追討之伐取舅男、於義朝子入筥根山」と報告されている(『山槐記』治承四年九月七日条)。
石橋山合戦ののち、頼朝に協力すべく伊豆へ向かっていた三浦義澄率いる三浦勢は、8月24日早朝、酒匂川の畔で「自去夜相待曉天、欲参向之處、合戦已敗北」の報を聞く。このため「慮外馳帰」こととなるが、その路次の「由井浦(鎌倉市由比ガ浜)」で「与畠山次郎重忠、数尅挑戦、多々良三郎重春并従石井五郎等殞命、又重忠郎従五十余輩梟首之間、重忠退去」という(『吾妻鏡』治承四年八月廿四日条)。
この小坪合戦から三日後の8月26日早朝、秩父党の人々が攻め寄せるという風聞が三浦党の耳に入り、「一族悉以引篭于当所衣笠城」(『吾妻鏡』治承四年八月廿六日条)という。まず大手に当たる「東木戸口」は「次郎義澄、十郎義連」、「西木戸」は「和田太郎義盛、金田大夫頼次」、「中陣」は「長江太郎義景、大多和三郎義久等」がこれを固めた(『吾妻鏡』治承四年八月廿六日条)。
秩父党襲来の知らせを受けてわずか数時間後の辰刻、「河越太郎重頼、中山次郎重実、江戸太郎重長、金子、村山輩已下数千騎攻来」った(『吾妻鏡』治承四年八月廿六日条)。義澄等は河越勢から防戦するも、先日の由比合戦ですでに人々は疲労しており、新手の兵との戦いは厳しいものだったろう。さらに矢も射尽くして「臨半更捨城逃去」という。このとき三浦の人々は「欲相具義明」したが、義明は、
「吾為源家累代家人、幸逢于其貴種再興之秋也、盍喜之哉、所保已八旬有余也、計余算不幾、今投老命於武衛、欲募子孫之勲功、汝等急退去兮、可奉尋彼存亡、吾独残留于城郭、摸多軍之勢、令見重頼」
と同道を拒絶した。義澄らは「涕泣雖失度」が、義明の命に従いその場を去った(『吾妻鏡』治承四年八月廿六日条)。
 |
| 伝三浦義明墓(材木座来迎寺) |
翌8月27日朝、小雨の降る中、河越重頼、江戸重長らが衣笠城に攻め入り、「辰尅、三浦介義明年八十九、為河越太郎重頼、江戸太郎重長等被討取、齢八旬余、依無人于扶持也」という(『吾妻鏡』治承四年八月廿七日条)。なお『源平盛衰記』では七十九歳とする。この戦いに畠山重忠の姿はなく、由比・小坪合戦での疲労及び大きな被害により差し控えられたのだろう。合戦後、「景親率数千騎雖攻来于三浦、義澄等渡海之後也、仍帰去」という(『吾妻鏡』治承四年八月廿七日条)。
8月26日夜、すでに小雨が舞っていたであろう夜、衣笠を脱出した義澄らは、安房国へ向かった。おそらく衣笠城の西側丘陵地を下り小田和湾から出航したのだろう。
安房国への途次「北條殿、同四郎主、岡崎四郎義実、近藤七国平等、自土肥郷岩浦令乗船、又指房州解纜、而於海上並舟船、相逢于三浦之輩、互述心事伊欝」といい(『吾妻鏡』治承四年八月廿七日条)、安房国へ向かう北條時政らの船と三浦義澄らが海上で合流している。石橋山合戦後、どのような伝手で頼朝が安房へ向かったことが伝えられたのかは定かではないが、そもそも三浦氏の故地の一つが安房国であり、三浦郡を落ちた三浦氏が向かうのは安房以外には想定されず、この合流自体は偶然かもしれない。
この北条・三浦の船が安房国に着いた日は不明だが、朝には小雨(『吾妻鏡』の衣笠合戦二日目の記録で「朝間小雨、申剋已後風雨殊甚」と具体的な時間まで記載されていることから、衣笠合戦に加わっていた秩父党の記録が用いられた可能性があろう)が降っており、目印となる星も見えない中(この日は雨でなければ三日月が見えた)は三浦半島東岸など夜の早いうちに三浦・北条は合流して、翌27日には房総半島に上陸したのであろう。
一方、石橋山での大庭勢の探索を切り抜けた頼朝は、8月28日、「武衛、自土肥真名鶴崎乗船、赴安房国方」いた。舟などはすでに接収されていたと思われるが、土肥領主の土肥次郎実平は「仰土肥住人貞恒、粧小舟」(『吾妻鏡』治承四年八月廿八日条)て、頼朝の乗船としている。大庭勢は8月27日には「景親率数千騎雖攻来于三浦、義澄等渡海之後也、仍帰去」(『吾妻鏡』治承四年八月廿七日条)とあるように、三浦半島に攻め寄せており、景親は26日中には兵をまとめて三浦へ進発していて、石橋山周辺にはすでに大庭勢はいなかったのかもしれない。
8月29日、頼朝は土肥実平の仕立てた船で「安房国平北郡猟嶋(安房郡鋸南町竜島)」に着岸する(『吾妻鏡』治承四年八月廿九日条)。竜島からは三浦半島の東岸の岩壁や木まではっきり視認でき、先に安房国へ上陸していた人々は頼朝の姿を探して浦賀水道を行き来したのかもしれない。
この頼朝の安房上陸の報が京都へ齎されたのは10月6日もしくは7日であった。10月7日、平時忠が高倉院御所で中山忠親に告げたところによれば「頼朝已虜領安房国頭弁知行国也之由、頭弁経房朝臣付我奏親院、注進脚力申詞者」と、時忠と経房(安房国知行国主)が高倉院に脚力の報告を奏上したという。忠親はその脚力の齎した報告書を披見すると「駿河国住人五百余騎発向伊豆国攻頼朝、頼朝党引籠筥根山、八月晦日頼朝等出筥根山乗船、夜半着安房国、九月一日分与諸郡於与力輩、追捕人家、奪取調物、此旨具所注進也」とあった(『山槐記』治承四年十月七日条)。
安房国に上陸した頼朝は、まず「御幼稚之当初、殊奉昵近者」であった安西三郎景益に「令旨厳密之上者、相催在庁等可令参上、又於当国中京下之輩者、悉以可搦進之」と指示をし、三浦義澄の手引きで安房国最大の平氏党・長狭常伴を追討。9月1日、「上総介八郎広常」「千葉介常胤」に親書を送った。なお、頼朝は安房上陸後、「分与諸郡於与力輩」「追捕人家、奪取調物」と狼藉を働いたようで、安房守藤原定長(『吉記』安元二年四月廿七日条、『公卿補任』文治五年)の目代もまた「当国中京下之輩者、悉以可搦進之」として追捕の対象とされたであろう。頼朝は安西景益に在庁を率いさせて、敵対行為を行わせたとみられる。
| 藤原定長 | 安元二(1175)年正月五日 叙正五位下院御給 安元二(1175)年正月卅日 任安房守 治承四(1180)年正月廿八日 重任(安房守) 養和元(1181)年十一月廿八日 任兵部権少輔、補蔵人 |
なお、当時の安房国は「安房国頭弁知行国也」(『山槐記』治承四年十月七日条)とあるように、定長の実兄・左中弁藤原経房(蔵人頭)の知行国であった。経房はかつて皇后宮権大進に就き、少進頼朝の上職であった。その後、上西門院庁が開かれると、院司判官代となった経房は、蔵人に移った頼朝の上職となっており、のち頼朝の武威が認められると親密な関係を築くこととなる。しかし、少なくとも頼朝が安房国へ上陸した当時は、安房国(目代か)からの「分与諸郡於与力輩」「追捕人家、奪取調物」という報告に対し、頼朝へ対する強い脅威を感じて頼朝の振舞を院に奏上している。さらに、後日追討使維盛らを破った「頼朝」「武田」をして「逆徒」「東国逆徒」(『吉記』寿永四年十一月丗日条等)と呼び、敵意を表しているように、経房は頼朝に対する私情は持っていない。上西門院の蔵人だったという記憶すらなかったのであろう。11月8日には蔵人頭左中弁の職掌として「伊豆国流人源頼朝」ならびに「甲斐国住人源信義」への「追討間事宣旨」を認めて「左大将(藤原実定)」へ下しているが、実定はこの宣旨案を突き返しており(強硬な反平家)、経房はやむなく太宰帥隆季(親平家)へ下している(『吉記』治承四年十一月八日条)。
●上西門院院司以下(『山槐記』保元四年二月十九日条)
| 院司 | 別当 | 権中納言実定 (元皇后宮大夫) |
右衛門督信頼 (元皇后宮権大夫) |
刑部卿憲方朝臣 (元皇后宮亮) |
右馬頭信隆朝臣 (元皇后宮職事) |
左少将実守 (元権亮、五位) |
| 判官代 | 安房守経房 (元皇后宮権大進) |
|||||
| 主典代 | 検非違使安倍資良 (元皇后宮属) |
左衛門府生安倍資成 (元皇后宮属) |
左衛門府生安倍資弘 (元皇后宮属) |
中原兼能 | ||
| 殿上人 | 修理大夫資賢朝臣 | 大弐清盛朝臣 | 治部卿光隆朝臣 | 内蔵頭家明朝臣 | 右中将実国朝臣 | |
| 右馬頭信隆朝臣 | 頭権左中弁俊憲朝臣 | 左中将成親朝臣 | 右中将実房朝臣 | 左中将成憲朝臣 | ||
| 左中将忠親朝臣 | 大宮権亮実経朝臣 | 左少将頼定朝臣 | 左少将家通朝臣 | 左衛門権佐頼憲 | ||
| 能登守基家 | 蔵人弁貞憲 | 中宮大進長方 | 中宮権亮実家 | 左兵衛佐脩憲 | ||
| 右少将信説 | 右少将実宗 | 但馬守有房 | 兵部少輔時忠 | |||
| 蔵人 | 左兵衛尉頼朝 (元皇后宮少進) |
藤原仲重 | ||||
9月6日夜、上総介八郎広常へ遣わした和田義盛が帰参。その復命した内容によれば、広常は「談千葉介常胤之後、可參上之由」だったという。これは『源平盛衰記』が伝える説話とは真逆のものであるが、『源平盛衰記』は成立年代及び軍記物『平家物語』異本に過ぎない以上、史料的価値は『吾妻鏡』に及ばない。『吾妻鏡』が常胤を忖度して広常の上位に据える必要はないため、『吾妻鏡』の説話は事実と捉えてよいだろう。上総平氏は両総平氏が入部して歴史の浅い上総国の開発を推し進めたことで、すでに開発の手が進んで数代を経た下総国の同族たちよりもその勢力を大きく伸ばすことができたとみられ、広常の同族勢力(姻戚の臼井氏、大須賀氏ら下総平氏を含む)は千葉介常胤を凌ぐ勢力を持っていた。ただし、広常が族長権を以て常胤に指図した形跡はなく、両者は同族としての関わり以上のものはなかったのである。
 |
| 頼朝の挙兵から佐竹氏討伐までの日程(『吾妻鏡』) |
9月9日には藤九郎盛長が千葉より帰参して千葉介常胤の協力が得られたことを復命し、「当時御居所非指要害地又非御曩跡、速可令出相摸国鎌倉給」と、鎌倉を推薦したという(『吾妻鏡』治承四年九月九日条)。
なぜ常胤は頼朝に加担することを決めたのだろうか。
常胤の本拠である千葉庄は「八条院庁分」であり、いわゆる八条院領であった。常胤は八条院暲子内親王に仕える立場にあり、八条院猶子である以仁王とも関係を持っていたであろう。常胤の子(庶長子であろう)の律静房日胤が以仁王(八條院猶子)に侍り「以仁王の乱」の首謀者とされたことからも、常胤と八条院には密接な繋がりがあったことが予想される。当然、八条院に仕えた源三位頼政や伊豆守仲綱とも関わりがあったと思われ、頼朝との関係は八条院・頼政との関わりの中で生まれ、頼朝挙兵について加担を決めるポイントになったと考えられよう。
9月12日、常胤は子息親類を率いて上総国へ向かおうとするが、六男・胤頼がこれを制して、平氏方である目代を追捕することを主張した。
成胤と胤頼は郎従を率いて下総目代の館(市川市国府台か)へと馳せ向かうが、「目代元自有勢者」とあるように「令数十許輩防戦」して、成胤・胤頼は攻めあぐねたが、北風が強いことに目をつけて、成胤は郎党をひそかに館の裏手に回らせて火をつけた。突然の出火に目代館は混乱し、防戦を忘れて逃げ惑った目代を胤頼が討ちとったとある。
 |
| 亥鼻城の土塁(室町期) |
この「当国目代」がいかなる人物かは不明だが、当時の下総守は平氏と強い繋がりを持っていた人物であったことがうかがえる。なお、「当国目代」は「元自有勢者」であることから、以前から当地で勢力を広げていた人物であって、当時の下総守からの目代ではないと考えられる。治承3(1179)年2月当時には「前下総守藤原朝臣高佐」が見えるが(『山槐記』治承三年二月廿九日条)、彼は代々摂関家の氏家司の家柄であり、かつ平清盛入道と血縁的に近いとみられる伊勢守平貞正の女子を娶っている血縁者でもあった(『尊卑分脈』)。伊勢守貞正の系譜は定かではないが、治承2(1178)年8月初頭に卒したとみられ、8月2日、中宮平徳子の御産所(六波羅泉殿)への参入公卿に定められていた「右兵衛督頼盛、平宰相教盛」が「依軽服不参前伊勢守貞正事也」(『御産部類記』治承二年八月八日条)と喪に服している。
また、高佐の兄・藤原清頼も久安3(1167)年6月9日、内大臣藤原頼長の推挙により、源頼憲(前下野守明国孫)とともに六位にも関わらず昇殿の栄に浴すなど(『本朝世紀』)、一族を挙げて摂関家に随従する立場であったが、のち太皇太后宮(平滋子)権大進として太皇太后宮亮平経盛(平清盛弟)の下にあって、平氏政権との関わりも深かった。
源頼義
(陸奥守)
∥―――――源義家――――源義親――――源為義―――――源義朝――――源頼朝
平維時―+―平直方―――女 (陸奥守) (対馬守) (左衛門大尉) (播磨守) (右兵衛権佐)
(上総介)|(上野介)
|
+―女
∥―――――藤原永業――藤原季永―――藤原清高―+―藤原清頼
∥ (遠江守) (大和守) (上総介) |(上総介)
∥ |
藤原永信 +―藤原高佐
(遠江守) (下総守)
∥―――――――藤原季佐
平貞正――――女 (宮内大輔)
(伊勢守)
 |
| 千田庄 |
頼朝に呼応した常胤が下総目代を追捕した際、平氏血縁者の千田庄判官代藤原親政(親雅)が常胤追討のために兵を率いて攻め寄せ、常胤の孫・成胤がこれを返り討ちにしたという。
この事件は『吾妻鏡』によれば、治承4(1180)年9月14日、「下総国千田庄領家判官代親政」が「聞目代被誅之由」いて、「率軍兵欲襲常胤」したことから、「常胤孫子小太郎成胤相戦」って、「遂生虜親政」ったと記されている(『吾妻鏡』治承四年九月十四日条)。
この事件は『千学集抜粋』によれば、治承4(1180)年9月4日、安房の頼朝を迎えるため「常胤、胤政父子上総へまゐり給ふ」と、常胤と胤正のみが上総国へと向かったとあり、他の諸子は従った形跡はない。成胤についても記載があり、「加曾利冠者成胤たまゝゝ祖母の不幸に値り、父祖とも上総へまゐり給ふといへとも養子たるゆゑ留りて千葉の館にあり、葬送の営みをなされける…程へて成胤も上総へまゐり給ふ…ここに千田判官親政ハ平家への聞えあれハとて、其勢千余騎、千葉の堀込の人なき所へ押寄せて、堀の内へ火を投かけける、成胤曾加野まて馳てふりかへりみるに、火の手上りけれは、まさしく親政かしわさならむ、此儘上総へまゐらむには、佐殿の逃たりなんとおほされんには、父祖の面目にもかゝりなん、いさ引かへせやと返しにける」と、成胤は祖母の葬送のために遅れて父祖の上総国へと向かったが、蘇我野で振り返ると千葉に火の手が上がっており、引き返したとされる。その後、「結城、渋河」で親政の軍勢と出会い、散々戦って「親政大勢こらえ得す落行事二十里、遂に馬の渡りまてそ追打しにける」と、親政を討ち取ったことになっている(『千学集抜粋』)。
また、『源平闘諍録』では、治承4(1180)年9月4日、頼朝は常胤率いる「新介胤将・次男師常・同じく田辺田の四郎胤信・同じく国分の五郎胤通・同じく千葉の六郎胤頼・同じく孫堺の平次常秀・武石の次郎胤重・能光の禅師等を始めと為て、三百余騎の兵」を先陣として上総国から下総国へと向かったという。このとき、藤原親正は「吾当国に在りながら、頼朝を射ずしては云ふに甲斐無し、京都の聞えも恐れ有り、且うは身の恥なり」と、千田庄内山の館を発して「千葉の結城」へと攻め入ったとする。このとき「加曾利の冠者成胤、祖母死去の間、同じく孫為といへども養子為に依つて、父祖共に上総国へ参向すといへども、千葉の館に留つて葬送の営み有りけり」とされ、「親正の軍兵、結城の浜に出で来たる由」を聞いた成胤は、上総へ急使を発する一方で「父祖を相ひ待つべけれども、敵を目の前に見て懸け出ださずは、我が身ながら人に非ず、豈勇士の道為らんや」と攻め懸けるも無勢であり、上総と下総の境川まで追われるが、「両国の介の軍兵共、雲霞の如くに馳せ来たりけり」と、千葉介常胤、上総介八郎広常の軍勢が救援に加わったことで「親正無勢たるに依つて、千田の庄次浦の館へ引き退きにけり」と千田庄へと退いたとされる(『源平闘諍録』)。そして、この「養子」という説話は、「祖母死去」に係るものであり、成胤は「千葉家に入った養子」ではなく「祖母の養子」なのであって、成胤は養母の葬送のために千葉に残ったという説話と理解すべきだろう(実際は祖母はその後も健在である)。成胤の祖母(常胤妻)は秩父平氏(秩父重弘は秩父盆地には居住していないが)出身であることから、秩父の妙見と千葉との繋がりを引くための説話と思われ、成胤は「秩父=妙見」の養子としてその加護を受ける存在であるとされたのではあるまいか。
『千学集抜粋』と『源平闘諍録』はともに妙見説話を取り入れ、成胤を「養子」とする同一の方向性をもつ内容で、物語性の強い『源平闘諍録』はより詳細に記載されている傾向にある。またいずれも千葉の結城浜を戦いの舞台としていることが共通点に挙げられる。しかしながら、『千学集抜粋』『源平闘諍録』はあくまでも説話集と物語であって、そのまま史実と受け取ることはできない。『千学集抜粋』はその妙見信仰と千葉氏を結びつける説話という性格上、まだ妙見信仰の成立していなかった平安時代末期の千葉氏に、妙見信仰の伝承を挿入する上で『源平闘諍録』の妙見説話を取り込んだ可能性が高く、千葉氏を賞賛する創作がかなり強いと考えられる。
『吾妻鏡』も全体をそのまま史実とするには危険な部分を含んでいるものの、後世北条氏にとって頼朝挙兵に伴う千葉氏の活躍を改変する必要性は全くないので、これは当時の記録に基づく史実として受け取ってよいと思われる。
親雅は9月13日の成胤と胤頼による下総目代追捕の翌日、14日に「聞目代被誅之由、率軍兵、欲襲常胤」と常胤の襲撃を企てたという(『吾妻鏡』治承四年九月十三日、十四日条)。なお、この一連の合戦譚は、その状況の要点を詳細に押さえていることからみて、千葉氏の記録を採用したとして間違いないだろう。
下総目代屋敷が当時どこにあったのかは定かではないが、目代屋敷は必ずしも国府直近にあるものでもなく、千葉庄付近に置かれていた可能性が高いだろう。目代追討翌日に成胤が親雅と合戦して捕縛しているためである。
親雅の進軍は千葉氏攻めではなく、下総目代と連携して頼朝追捕のために西下総へ進軍したのだろう。親政勢は「北条内山ノ館」を発すると、「武射ノ横路」(山武郡芝山町小池~高田あたりか)を通って、「白井ノ馬渡ノ橋」(佐倉市坂戸付近)を渡り、千葉庄に向かっていた(『源平闘諍録』)とされる。親雅が千葉庄に攻め入った理由は「聞目代被誅之由」なのであり、それまで親雅は常胤を軍勢催促に応じた者と見ていたことは確実で、常胤の勢力範囲に入ったところを常胤の叛旗に遭遇したわけである。それまで味方と信じる常胤に親雅は行軍のスケジュールを逐一伝えていたであろう。これにより親正の動きは丸裸となり、常胤は親雅が千葉に近づく頃合いに、千葉小太郎成胤と千葉六郎大夫胤頼をして下総目代を襲撃して殺害したのだろう。そして取って返した千葉小太郎成胤が千葉庄付近で「聞目代被誅之由、率軍兵欲襲常胤」していた親雅を攻めて合戦になったのだろう。藤原親政(親雅)が率いるのは粟飯原家常と子息の粟飯原権太元常・粟飯原次郎顕常ら(『千学集抜粋』)を千田庄司常益の子孫たちであった。
なお、千葉介常胤が9月17日に「相具子息太郎胤正、次郎師常号相馬、三郎胤成武石、四郎胤信大須賀、五郎胤道国分、六郎大夫胤頼東。嫡孫小太郎成胤等参会于下総国府、従軍及三百余騎也、常胤先召覧囚人千田判官代親政」と、常胤以下の千葉一族が上総国で面会したはずの頼朝に同道せず、別行動をして下総国府にいた不自然な記録が見える。
■『吾妻鏡』治承四年九月十七日条
この時点で常胤が頼朝に同道していたのであれば、上記のように下総国府で初対面の居ずまいで出迎える必要はなく(嘉例の儀式として考えることもできる)、このときに「陸奥六郎義隆男、号毛利冠者頼隆」を頼朝に引き合わせるのも不自然である。すでに成人した人物であれば、常胤が頼朝に同道時にすでに面会は行われていたと考えるのが妥当であるためである(源家胤子の温存を意図し下総国に残した可能性もある)。
つまり、常胤ら千葉一族は、上総国に向かって頼朝と合流し、下総行きに同道したのではなく、13日に成胤・六郎大夫胤頼を下総目代追討に差し向けて国府一帯から平氏勢力を駆逐する一方で、翌14日に「率軍兵欲襲常胤」した千田判官代親正を千葉庄内で打ち破り、「生虜」とした上で、17日に下総国府(市川市国府台)へ頼朝を迎え入れたと考えられる。
戦場は千葉の「結城浜」とされるが、この戦いは千葉小太郎成胤を妙見菩薩に守られた特別な存在(平良文や平将門と共通する存在)とみる妙見説話と結びつけられた合戦譚となっている(『源平闘諍録』『千葉妙見大縁起絵巻』『千学集抜粋』)。『源平闘諍録』では寡勢の千葉小太郎成胤が親正勢に結城浜まで押された際に「僮ナル童」で具現した妙見菩薩が親正勢の矢を防ぎ、その間に「両国ノ介ノ軍兵共」が救援に駆けつけて親正を追い払ったという(『源平闘諍録』)。なお、この妙見説話は、後世、千葉介成胤の子・千葉介胤綱、千葉介時胤代に妙見信仰が千葉氏に取り入れられ(胤綱・時胤と同世代または一世代前に、同族原氏出身の如圓が妙見座主となり、その子も名は不明ながら妙見座主の人物がいる(『神代本千葉系図』))、成胤を妙見菩薩の加護を受けた特別な者と見るために創作された逸話と考えられる。そしてこの頃、戦場となった結城浜を妙見神を迎え入れる前浜とする妙見宮が造営(金剛授寺尊光院)されたのではなかろうか。なお、関東の妙見信仰は多分に平将門との結びつきが見られ、千葉氏も将門との関わりを有する伝承(良文と将門の関係、平忠常の母が将門娘、相馬氏は将門子孫等)があることから、千葉氏における将門信仰と関東の妙見信仰の親和性により容易に取り入れられたのかもしれない。
親雅は皇嘉門院判官代の経歴を有したが(『尊卑分脈』)、女院判官代在任のまま京都から下総国千田庄に下向することは考えにくい。治承4(1180)年5月11日時点の皇嘉門院領に千田庄は含まれておらず(「皇嘉門院惣処分状」『鎌倉遺文』三九一三)、皇嘉門院と千田庄には関わりはなく、親政もこの時点では女院司を辞していたと思われ、「千田判官代」は「皇嘉門院判官代」ではなく、荘園管理者としての「判官代」であると考えられる。当時の千田庄領主は不明だが、親雅の出身である親通流藤原氏は摂関家家人であり、千田庄はもともと摂政藤原基実を本所とし、親雅が「領家」だったと思われる。親雅は仁安元(1166)年7月27日の基実薨去後は、摂関家私領を継承した北政所・平盛子のもとで千田庄判官代として実地支配を行ったため、千田庄平氏の統率を行い得たと考えられる。親雅下向は、現実的には清盛が妹婿を下向させた具体的な東国管理の一端であったろうが、親政はあくまで摂関家家人の立場で千田庄を支配していたのである。
親雅を捕らえた常胤は、9月17日に「相具子息太郎胤正、次郎師常号相馬、三郎胤成武石、四郎胤信大須賀、五郎胤道国分、六郎大夫胤頼東、嫡孫小太郎成胤等参会于下総国府、従軍及三百余騎也、常胤先召覧囚人千田判官代親政」と、下総国府で親雅を頼朝の面前に引き据えている。
なお、この『吾妻鏡』の記事は、いまだその地を領していない師常を「相馬」、胤信を「大須賀」、胤頼を「東」と記すように、後世の記録をもとに挿入されている逸話である。おそらく千葉氏について詳細に記していることから、千葉氏側から提供された家伝記録に基づいていると考えられよう。
藤原親頼
下総守藤原親通の長男。久寿2(1155)年9月15日の「巳刻許遂令崩給了」の「北政所(忠通室宗子)」につき、遺言により継続される仏事に「可籠候人々」として「右馬助親頼」(『兵範記』久寿二年九月十五日条)が見えるように、関白忠通室に仕えていた摂関家人だったことがわかる。妻は宗子息女・皇太后宮聖子(のち皇嘉門院)の女房因幡。
長男の親長は皇嘉門院聖子の判官代として仕えた。二男の親能は因幡を母として生まれ、従五位下に叙爵している。親能の子親長は皇太后藤原忻子の皇太后宮亮に補任された。元久2(1205)年12月4日、高陽院殿(土御門天皇里内裏)で後鳥羽院御臨のもと仁王講が行われる予定の中、これに先立つ神事の御祈祷を始めるにあたり、仮御祓の専使を「皇太后宮亮親長」が領状を提出しているにも拘らず「不参」という失態を犯している(『伏見宮御記録』利四十七上 仙洞御移徙部類記十五)。
その子宣親は「居住大谷辺日向前司宣親奉公権亮親長子也」(『明月記』嘉禎元年三月廿八日條)とあるように、大谷辺に住んでいたが、文暦2(1235)年3月26日に殺害された。宣親は「為不善姫君後見」とあるように、おそらく九條家姫君(彦子等)の後見でもあったのだろう。ところが、宣親は日頃から家人に「随分為備非常、令持剣楯」ており、その中に「悪之者成群盗嫌疑」をかけられていた者があり、3月26日に大谷の宣親邸で「日向客人会飲」がある情報を入手した「大炊助入道不知実名、筑紫大鞆之子也云々」が「欲搦取」と機会を窺っていたが、「入道(大友大炊助親秀入道)在他所」のとき、親秀入道の「所従等、成此儀先触六波羅」たが、「不聞返事之前、日向客人会飲之輩逃散之由聞之、無是非襲寄」と、六波羅からの返事を待っている間に、日向宣親邸の会飲が解散するという情報が入ったため、親秀入道所従らは宣親邸をやむなく襲撃。会飲の輩は逃亡したが、主催者である宣親はこの襲撃に「日向入切抜求」と、斬り渡ったため、親秀入道所従ら「之突殺了、斬頸」という所行を行った。宣親が抵抗したのは群盗と繋がっていたためなのか、襲撃に抵抗しただけなのかは定かではない。
宣親の子は「日向子為座主宮童」とあるように、天台座主宮尊性の侍童となっているが、『尊卑分脉』には伝わらない。ただ、宣親の子は座主侍童のほか「有山法師」ったり「其妻兄弟為武者」であったりしたため、この襲撃に対して「又為執仇已欲企合戦」という騒動に発展してしまう。これを危惧した「駿州(重時)」が「制止」し、「此子細於関東、可随成敗之由示含」という。
藤原親雅
「親政」「親正」とも記される。『尊卑分脈』によれば、皇嘉門院判官代。号して智田判官代。阿波守。常重・常胤と橘庄および相馬御厨を巡って争った下総守藤原親通の孫で、平清盛の姉妹を妻とし、平資盛の叔父という平氏の重縁者であった。
皇嘉門院判官代の経歴を有したが(『尊卑分脈』)、女院判官代在任のまま京都から下総国千田庄に下向することは考えにくい。治承4(1180)年5月11日時点の皇嘉門院領に千田庄は含まれておらず(「皇嘉門院惣処分状」『鎌倉遺文』三九一三)、皇嘉門院と千田庄には関わりはなく、親政もこの時点では女院司を辞していたと思われ、「千田判官代」は皇嘉門院判官代ではなく、荘園管理者としての千田庄の判官代であろう。
当時の千田庄の荘園領主は不明だが、親政の出身である親通流藤原氏は摂関家家人であり、摂関家を本所としていたと思われる。千田庄は祖父・下総守親通の頃に千田常益から寄進を受け、それが摂関家に寄進されていた可能性があろう。親盛は領家職を継承して千田平氏を従属下に千田庄一帯を支配し、その子親政は仁安元(1166)年7月27日の基実薨去後、摂関家私領を継承した北政所・平盛子(清盛娘)のもとで摂関家領判官代として実地支配を行ったため、千田平氏の統率を行い得たと考えられる。親政下向は、現実的には清盛が妹婿を下向させた具体的な東国管理の一端であったろうが、親政は公的には摂関家家人の立場で千田庄を支配していたのである。
親政は親族が下総守を歴任しているが、いずれも二十年以上も前のことであり、父祖の直接的な恩恵を受けることはなかったであろうが、父・下総大夫親盛は「匝瑳北条」に何らかの権益を有しており、親政はそれを継承して匝瑳北条内山に屋敷を持っていた(『吾妻鏡』)。長男の快雅が生まれたのが仁安元(1166)年、次男・聖円はその後の誕生(ただし聖円は快雅の庶兄の可能性が高い)であるから、親政が下総国に下向したのは少なくとも仁安元(1166)年の摂政基通の死後と考えられ、北政所盛子(親政から見ると義姪)の代に下総に下向したとみられる。
なお、親政は阿波守の経歴があったとされる(『尊卑分脈』)。阿波国は仁平元(1155)年までは摂関家知行国であったとみられるが、それ以降、治承3(1179)年まで後白河院御分国となっており、親政の阿波守受領は摂関家知行国当時、つまり康治2(1144)年以前となるが、この頃は親政の祖父や叔父が下総守に就いている時期であるため不可である。また、治承3(1179)年以降であるとすると、平宗親よりも後任となるが、このころ親政はすでに下総国にあり、これも時代的に合わない。仮に親政が阿波守に就いたとすれば、千葉氏との戦いに敗れて頼朝の面前に引き据えられた後、助命されて京都へ戻り、後年阿波守に任官したということになろうか。次男の慈円灌頂の弟子・聖円律師は「阿波阿闍梨」という号があり(『門葉記』建仁三年二月八日平等院修法)、この「阿波」は父・親雅の受領名によるところであろう。
子息二人(快雅・聖円)はいずれも関白九条兼実実弟・慈円門下であり、快雅は九條家出身の将軍・頼経の護持僧として鎌倉に下るなど、摂関家と深く繋がっていたことがわかる。
●12世紀中ごろの阿波守
| 任 | 任期 | 名前 | 備考 | 出典 |
| 康治2(1144)年 正月30日 |
康治2(1144)年 ~久安3(1147)年 |
藤原頼佐 | 1155年当時、前阿波守(『兵範記』) | 『本朝世紀』 |
| 久安3(1147)年 正月28日 |
久安3(1147)年 ~久安4(1148)年 |
藤原保綱 | 父は崇徳院近臣藤原実清。 | 『本朝世紀』 |
| 久安4(1148)年 正月28日 |
久安4(1148)年 | 中原頼盛 | 『本朝世紀』 | |
| 久安4(1148)年 2月か? |
久安4(1148)年? ~仁平元(1151)年 |
藤原保綱 | ||
| 仁平元(1151)年 2月1日 |
藤原保綱 | 重任するが、7月14日解却。 | 『本朝世紀』 | |
| 仁平元(1151)年 | 不明 | |||
| 仁平2(1152)年 正月28日 |
仁平2(1152)年 ~久寿3(1156)年 |
藤原成頼 | 周防守から名替 | 『山槐記除目部類』 |
| 久寿3(1156)年 2月2日 |
久寿3(1156)年 ~保元3(1158)年 |
藤原光方 | 左衛門督光頼の長男。叔父成頼の後任。 成頼は勘解由次官へ転ずる |
『兵範記』 |
| 保元3(1158)年 8月1日 |
保元3(1158)年 ~? |
藤原惟定 (惟雅) |
父・光方の後任として阿波権守から転ずる。 光方は勘解由次官へ転ずる |
『山槐記』 『兵範記』 |
| 治承3(1179)年 11月17日 解官 |
? ~治承3(1179)年 |
藤原孝貞 | 平清盛入道によって解官 | 『兵範記』 |
| 治承3(1179)年 11月19日 |
治承3(1179)年 ~寿永4(1185)年? |
平宗親 | 『兵範記』 |
功徳院僧正快雅(松田宣史『比叡山仏教説話研究 -序説-』三弥井書店、『吾妻鏡』、『門葉記』)
千田判官代親雅の長男または次男。仁安元(1166)年誕生。律師、僧都、権僧正。卿阿闍梨。勅撰歌人。比叡山延暦寺功徳院主。
「快雅」の法名は師の慈円(道快)の一字と父・親雅の一字を受けたものと考えられる。建久9(1198)年3月24日、聖蓮房阿闍梨恵尋より谷流の一派三昧流の血脈を受ける。天台座主慈円を師として研鑽を積み、慈円門下の碩学として成長。慈円の高弟として大懺法院の供僧となった(『門葉記』)。
建仁3(1203)年2月8日、平等院において師の前大僧正慈円を導師として、後鳥羽院の為の大熾盛光法が修されているが、助修として「聖円阿闍梨阿波」「快雅大徳卿」らが加わっている(『門葉記』)。「聖円阿闍梨」は快雅の弟であるが、快雅よりも伝法灌頂の時期が二年から三年ほど早いと予想され、僧位や修法の席次も常に上回っていることから、聖円は実際には快雅の兄の可能性が高い。
元久元(1204)年、阿闍梨宣旨を受けて以降、祈祷や五壇法など多くの修法に携わる。承元元(1207)年6月20日、押小路殿での院への七仏薬師修法に際し、慈円の伴僧の一人として「聖円権律師」「快雅灌頂阿闍梨」が見える。修法の中、後夜行法に際して参勤の公円法印が所労余気のため、快雅が後夜日中護摩勤仕する。系譜上で弟の聖円はすでに権律師となっており、快雅に先行している。
承元2(1208)年3月25日、青蓮院本堂で「懺法院供僧」として慈円に従って「聖円阿闍梨」「快雅阿闍梨」らが大熾盛光法を修している(『華頂要略門主伝第三』『門葉記』)が、ここから聖円、快雅は慈円の自房である大懺法院供僧であったことがわかる。
承元4(1210)年7月8日、青蓮院大熾盛光堂での大熾盛光法の修法に伴僧として「聖円律師」「快雅阿闍梨」が見られ(『門葉記』)、この時点でも快雅は任官していない。その後、建暦2(1212)年8月4日の慈円が導師を務めた大熾盛光法修法の伴僧として「快雅已講」が護摩壇手代を勤めており(『門葉記』)、已講となっていたことがわかる。さらに建保2(1214)年3月12日の後鳥羽院の賀陽院殿での御祈祷では已灌頂となっており、前年の建保元(1213)年に小灌頂阿闍梨を経て已灌頂となったと思われる。
建保3(1215)年11月6日、青蓮院大成就院における熾盛光法の修法に慈円の助修として聖円律師とともに快雅律師が見え(『門葉記』)、快雅は権律師となったことがわかる。また、これを最後に弟・聖円律師の名は見えなくなっており、この頃聖円は寂したのかもしれない。
快雅はその後も慈円門下として師とともに多くの修法に参じ、その功を以て昇進を続けることとなる。建保5(1217)年6月14日より慈円の吉水本坊の御念誦堂で後鳥羽院の為に佛眼法が修され、伴僧として快雅律師が見える(『僧事伝僧都』)。その翌月7月15日から28日まで修された賀陽院殿での後鳥羽院瘧気のための御祈祷では「権少僧都」となっており(『五壇法日記』)、佛眼法修法での功による昇任であろう。その翌年建保6(1218)年9月20日には、一条室町殿下御所で中宮(のち東一条院)の御産祈祷の五壇法が修され、導師慈円のもと金剛夜叉明王に修法した。その功績により、9月27日宣下で「権少僧都快雅 任大僧都」(『門葉記』五壇法二)に陞る。ただ、まだ皇子誕生がなかったためか、10月1日には一条殿で中宮御産祈祷として、七仏薬師法を大阿闍梨権僧正良快の伴僧として修法し、10月10日、無事に皇子降誕につき結願。10月17日、御産祈祷を修法した僧侶に叙任が行われ、快雅は権少僧都から権大僧都へと昇任する(『五壇法日記』)。
寛喜2(1230)年正月20日の一条殿での中宮(のち藻壁門院)の御産御祈祷においては、「法印権大僧都」として見え、その後も中宮御産祈祷などの修法を行う。しかし、その後は摂関家、とくに慈円所縁の九条家や西園寺家との関わりを強め、九条道家と西園寺公経息女・藤原倫子の間に生まれ、鎌倉殿となっていた将軍頼経の招聘のもと、貞永元(1232)年11月29日には雪の永福寺で歌会に参加しており、さらにその後は京都へ戻って貞永3(1234)年12月4日には、一条殿で北政所(九条教実室・藤原嘉子[西園寺公経息女]か)の御産御祈祷を行っている。さらに貞永4(1235)年4月4日、六波羅殿で将軍頼経のための御祈祷を執り行った。暦仁2(1236)年正月28日には西園寺五大堂(増長心院)で「入道大相国公経」のための御祈が行われ、快雅もこれに加わった。
嘉禎3(1237)年3月8日、故師の慈円に対して「賜諡号慈鎮和尚」の宣下があり、3月26日に廟所の無動寺本坊大乗院に勅使が参入。権僧正慈賢法印以下、快雅、貞雲、成源、聖増、隆承ら僧綱が南庭に東西に列した(『華頂要略門主伝第三』)。
 |
| 比叡山西谷の法然堂(功徳院跡) |
そして延応元(1239)年8月28日には天台座主慈源の申請により、「勧賞以快雅法印被任権僧正了」と、ついに権僧正へと昇りつめた。
なお、これ以降と思われるが、比叡山西谷功徳院(現在の法然堂)の洛中里坊(現在の功徳院知恩寺:百万遍)に住したことで、功徳院僧正と称された。
仁治3(1242)年7月3日、天変地異の祈祷を九条道家入道の法性寺殿荘厳蔵院で五壇法を修法。寛元2(1244)年2月10日には「関東将軍大納言入道殿(頼経)の御祈祷」を行い、4月15日にも「関東大納言入道殿(頼経)」の御祈祷で中壇(不動明王)を修法した。そして、5月15日の五壇法では僧正快雅、東大寺道禅法印、園城寺猷尊法印、猷聖法印、定親法務が修法した(『五壇法四』)。
寛元3(1245)年12月24日には、頼経入道のために一字金輪護摩を修法するなど、頼経入道の護持僧的な立場にあったことがわかる。寛元4(1246)年、頼経入道の帰洛に同行したとみられ、翌宝治元(1247)年12月12日、八十三歳で入滅(松田宣史『比叡山仏教説話研究 -序説-』)。灌頂の弟子としては正二位実清(為公経公子)の弟、比叡山東南院の「公源法印資」となった良覚大僧正がみられる(『尊卑分脈』)。
●『続古今和歌集』一首入選
●『五壇法日記』『門葉記』『比叡山仏教説話研究』より(快雅および聖円)
・建仁3(1203)年5月27日:法勝寺での八万四千塔供養で、師・慈円の讃衆(聖円阿闍梨、快雅大徳)(『門葉記』)
・建仁4(1204)年2月8日:平等院にて慈円助修として大熾盛光法を修す(聖円阿闍梨阿波、快雅大徳卿(『門葉記』))
・元久元(1204)年5月7日:吉水殿で如法経修法(聖円阿闍梨)(『門葉記』)
・元久2(1205)年2月21日:法勝寺で大熾盛光法を修法(聖円阿闍梨、快雅阿闍梨)(『門葉記』)
・元久2(1205)年8月15日:水無瀬殿での仏眼法修法の助修(聖円、快雅)(『門葉記』佛眼法二)
・元久2(1205)年11月22日:賀陽院殿で安鎮法修法の助修(阿闍梨聖円、阿闍梨快雅)(『門葉記』)
・建永元(1206)年7月15日:青蓮院にて慈円伴僧として大熾盛光法を修す(聖円阿闍梨)(『門葉記』)
・建永2(1207)年2月20日:賀陽院殿で七仏薬師法の修法で伴僧の一人として列す(阿闍梨快雅)(『門葉記』)
・建永2(1207)年3月22日:青蓮院大成就院で伴僧の一人として大熾盛光法を修す(快雅阿闍梨)(『門葉記』)
・承元元(1207)年6月20日:押小路殿での七仏薬師修法に際し伴僧の一人として列す(聖円権律師、快雅灌頂阿闍梨)。修法の中、後夜行法に際して参勤の公円法印が所労余気のため、快雅が後夜日中護摩勤仕する。(『門葉記』)
・承元2(1208)年3月25日:青蓮院本堂で「懺法院供僧」として大熾盛光法を修す(聖円阿闍梨、快雅阿闍梨(『華頂要略門主伝第三』『門葉記』))。
・承元3(1209)年正月8日:青蓮院本堂で大熾盛光法を修法(聖円阿闍梨、快雅阿闍梨)(『門葉記』)
・承元4(1210)年正月22日:吉水懺法印熾盛光堂で鳥羽院のために普賢延命法修法の伴僧(律師聖円、阿闍梨快雅)(『門葉記』)
・承元4(1210)年7月8日:青蓮院大熾盛光堂で大熾盛光法修法の伴僧(聖円律師、快雅阿闍梨)(『門葉記』)
・承元4(1210)年10月4日:彗星出現により大熾盛光堂で大熾盛光法修法(聖円律師、快雅阿闍梨)(『門葉記』)
・承元5(1211)年正月25日:水瀬殿蓮華樹院での仏眼法修法の助修を務める(快雅阿闍梨)(『門葉記』仏眼法一)
・建暦元(1211)年4月11日:大成就院での仏眼法修法の助修を勤める(快雅阿闍梨)(『門葉記』仏眼法一)
・建暦元(1211)年11月16日:五壇法修法で阿闍梨快雅(『門葉記』五壇法四)「功徳院卿僧正」の記
・建暦2(1212)年正月10日:青蓮院本堂での大熾盛光法臨時修法の助修(権律師聖円、快雅阿闍梨)(『門葉記』)
・建暦2(1212)年8月4日:熾盛光法修法が始められ、伴僧として護摩壇手代を務める(快雅已講)(『門葉記』)
・建暦3(1213)年7月16日:青蓮院大成就院における鳥羽院のための熾盛光法の修法に助修として加わり、護摩壇手代を務める(聖円律師、快雅灌頂)。役人として弟・聖円を筆頭に快雅も加えられている。(『門葉記』)
・建暦3(1213)年8月6日:高陽院殿での佛眼法修法で助修に快雅灌頂(『門葉記』佛眼法二)
・建保2(1214)年3月12日:後鳥羽院の賀陽院殿で御祈祷(已灌頂快雅 功徳院僧正)(『五壇法四』)
・建保2(1214)年5月8日:大成就院にて高倉院のために如法経修法(快雅灌頂阿闍梨)
・建保2(1214)年11月13日:大成就院で熾盛光法修法で助修として務める(聖円律師、快雅灌頂)(『門葉記』)。役人として弟・聖円を筆頭に快雅も加えられている。
・建保3(1215)年11月6日:青蓮院大成就院における熾盛光法の修法に助修として加わる(聖円律師、快雅律師)(『門葉記』)
・建保4(1216)年6月12日:賀陽院殿で御祈祷(権律師快雅)(『五壇法日記』)
・建保4(1216)年10月20日:賀陽院殿で天変のために五壇法を修法(権律師快雅)(『五壇法日記』)
・建保4(1216)年11月3日:3月23日に火災で焼失し、再建された青蓮院本堂での大熾盛光法修法の助修(快雅律師)(『門葉記』)
・建保5(1217)年6月14日:吉水本坊御念誦堂で院の為に佛眼法修法、伴僧として快雅律師が見える(二十一日、僧事伝僧都)
・建保5(1217)年7月15~28日:賀陽院殿で院の瘧気のため御祈祷(権少僧都)(『五壇法日記』)
・建保5(1217)年8月5日:青蓮院本堂で院御悩(瘧気だろう)のため大熾盛光法を修法した際の助修(快雅権少僧都)
・建保6(1218)年2月7~15日:御所道場(仁和寺)で修法(権少僧都快雅)(『門葉記』五壇法四、『五壇法日記』)
・建保6(1218)年9月20日:一条室町殿下御所で中宮(のち東一条院)御産祈祷、金剛夜叉明王に修法(権少僧都快雅)(『五壇法日記』)
⇒『門葉記』五壇法二においては、9月27日宣下で「権少僧都快雅 任大僧都」とみえる。
・建保6(1218)年10月1日:一条殿で中宮(のち東一条院)御産祈祷、七仏薬師法を大阿闍梨権僧正良快の伴僧として修法(快雅僧都)(『五壇法日記』)
・建保6(1218)年10月10日:皇子降誕につき結願。17日、修法の僧侶に叙任(権少僧都⇒権大僧都)(『五壇法日記』)
・建保6(1218)年11月21日:二条町口卿二位宿所で立坊御祈が行われ、仏眼法が修法(快雅僧都)(『門葉記』五壇法四)。
・建保6(1218)年12月2日:最勝四天王院において慈円門下の道覚入道親王(後鳥羽院皇子・十五歳)へ伝法灌頂が行われ、その讃衆二十名の僧綱として「快雅権大僧都」が名を連ねる(『華頂要略門主伝第六』『伝法灌頂日記下』)
・建保7(1219)年正月22日:五壇法修法で権大僧都快雅(『門葉記』五壇法四)
・承久元(1219)年正月22日:賀陽院殿で御祈祷(権大僧都)(『五壇法日記』)
・承久元(1219)年7月5~13日:賀陽院殿で院の夢想(金剛夜叉異常形像)によって御祈祷(権大僧都)(『五壇法日記』)
・承久2(1219)年2月6~1■日:水無瀬殿で御祈祷(権大僧都快雅)(『門葉記』五壇法四、『五壇法日記』)
・承久2(1219)年9月18日:五壇法修法で権大僧都快雅(『門葉記』、五壇法四)
・承久3(1220)年正月13~20日:賀陽院殿で御祈祷(権大僧都)。同勤の前大僧正真性は以仁王子(『五壇法日記』)
・安貞3(1229)年2月12日:五壇法修法で権大僧都快雅(『門葉記』五壇法四)
・寛喜2(1230)年正月20日:一条殿で中宮(のち藻壁門院)の御産御祈祷(法印権大僧都)(『五壇法日記』)
⇒『門葉記』五壇法二においては、「法印権大僧都快雅 以経承任律師」とある
・寛喜2(1230)年11月13日:本坊での天変御祈修で佛眼法を修法し助修(快雅阿闍梨)(『五壇法日記』)
・寛喜3(1231)年正月21日:五壇法修法で法印権大僧都快雅(『門葉記』五壇法四)
・寛喜3(1231)年2月6日:一条殿で中宮(のち藻壁門院)の御産御祈祷で普賢延命法修法を天台座主良快大僧正の助修筆頭として護摩壇勤仕する(法印前権大僧都快雅)(『五壇法日記』)
・貞永元(1232)年8月14日:一条殿で中宮(のち藻壁門院)の御産御祈祷(法印快雅)(『門葉記』五壇法四、『五壇法日記』)
・貞永元(1232)年9月12日:一条殿で中宮(のち藻壁門院)の御産御祈祷の七仏薬師法の修法で伴僧筆頭(快雅法印)(『五壇法日記』)
・貞永3(1234)年12月4日:一条殿で北政所の御産御祈祷(法印)(『五壇法日記』)
・貞永4(1235)年4月4日:六波羅殿で将軍頼経御祈祷(法印)(『五壇法日記』)
・暦仁2(1236)年正月26日:五壇法修法で法印快雅(『門葉記』五壇法四)
・暦仁2(1236)年正月28日:西園寺五大堂(増長心院)で入道大相国公経の御祈祷(法印)(『五壇法日記』)
・嘉禎3(1237)年12月4日:五壇法修法で法印快雅(『門葉記』五壇法四)
・嘉禎4(1238)年4月4日:五壇法修法で法印快雅(『門葉記』五壇法四)
・延応元(1239)年5月20日:九条道家入道の病気平癒の御祈祷(法印)(『五壇法日記』)
・延応元(1239)年8月28日:天台座主慈源の申請により「勧賞以快雅法印被任権僧正了」(『五壇法日記』)
・仁治3(1242)年7月3日:九条道家入道の法性寺殿荘厳蔵院での御祈祷(前権僧正)(『華頂要略門主伝第五』)
・寛元元(1243)年12月10日:五壇法修法で僧正快雅(『門葉記』五壇法四)
・寛元2(1244)年2月10日:関東将軍大納言入道殿(頼経)の御祈祷(権僧正)(『五壇法日記』)
・寛元2(1244)年4月15日:関東大納言入道殿(頼経)の御祈祷で中壇(不動明王)を修法(僧正)(『五壇法日記』)
・寛元2(1244)年5月15日:五壇法を修す(僧正快雅、東大寺道禅法印、園城寺猷尊法印、猷聖法印、定親法務(『五壇法四』)
律師聖円
千田判官代親雅の次男(実際は長男か)。阿波阿闍梨。天台座主・慈円灌頂の弟子。慈円の修法した法会等に加わり、兄弟の快雅とともに慈円の自房であった大懺法院の供僧となった。
建仁3(1203)年2月8日、平等院において師の前大僧正慈円を導師として、後鳥羽院の為の大熾盛光法が修されて、助修として「阿波聖円阿闍梨」「卿快雅大徳」らが加わっている(『門葉記』)。快雅が阿闍梨灌頂を受けたのは翌元久元(1204)年であることや、修法の序列が聖円が常に上位にあることから、聖円が快雅の兄である可能性が高い。
建仁3(1203)年5月27日、法勝寺における後鳥羽院の八万四千塔供養(五寸多宝塔、実数は十三万二千基)が行われた際、導師である「前座主大僧正慈円」の「讃衆三十人」の一人として、讃頭快智のもと加わっている(『門葉記』)。
建永元(1206)7月15日、青蓮院に新造された大熾盛光堂にて、導師慈円の伴僧として「聖円阿闍梨」が大熾盛光法を修す(『門葉記』)。なお、この修法に快雅は加わっていない。
承元4(1210)年7月8日、青蓮院大熾盛光堂での大熾盛光法の修法に伴僧として「権律師聖円」「快雅阿闍梨」が、さらに同年10月4日には大熾盛光堂で彗星出現による祈祷で大熾盛光法が修法され、「聖円律師」「快雅阿闍梨」が見られ(『門葉記』)、この時点で権律師となっていた。
建保3(1215)年11月6日、青蓮院大成就院における熾盛光法の修法に、慈円の助修として快雅律師とともに聖円律師が見える(『門葉記』)が、これを最後に聖円の名は慈円修法から消えており、おそらくこの頃聖円は入寂したのだろう。
千葉氏が下総目代を討った同日の9月13日、頼朝は三百余騎の軍勢を率いて安房国を出立し上総国へ向かった。このとき広常は「而廣常聚軍士等之間、猶遅参」とあるように、軍勢を集め纏めるのに手間取ったという(『吾妻鏡』)。広常の本拠は国府付近ではなく上総国一宮(長生郡一宮町)であり、平氏を知行国主とする上総国での軍勢催促、さらに頼朝の要請からわずか数日という、いささか無理のある要請であったと言わざるを得ないだろう。
安房国から上総国に入った頼朝勢三百余騎は上総国府を襲ったと思われる。かねて下総国府の陥落の報は上総国府にも届いていただろう。報を受けた上総国府の混乱は想像を絶するものであったろう。そして、「治承四年庚子九月」の「上総国」での戦いで、平氏方の高倉院武者所「平七武者重国」が「源家」によって討たれた(『高山寺明恵上人行状』)。彼は「本姓者伊藤氏、養父の姓によて藤を改て平とす」と伊勢平氏の根本被官伊藤氏の出身者であり、国司・上総介忠清の同族であった。忠清は在京であることから、目代であったのかもしれない。
頼朝が上総国府を攻めた記録はないが、頼朝の上総国滞在期間は四日に及ぶも、その間に上総国府が頼朝に対して対応した形跡はない。また頼朝は官道を進んだと考えられることから、その進行ルート上、国府に主敵が健在であることは許されない。必然的に頼朝は国府を占拠したとしか考えられないのである。そして、頼朝は国府を占領して四日間、広常の参着を待ったのだろう。ところが広常はそれでも参着しなかったことから、9月17日に至り、頼朝は上総国府を出立して下総国に入ったと思われる。この国府攻めは広常が行ったともされるが、広常が合流したのは後日、隅田河畔とされており、もし上総国府を攻め落としていたとすれば、この時点で頼朝勢と合流しない理由はないのである。つまり、上総国府を攻めたのは広常ではない。
下総国府では常胤が「相具子息太郎胤正、次郎師常号相馬、三郎胤成武石、四郎胤信大須賀、五郎胤道国分、六郎大夫胤頼東。嫡孫小太郎成胤等参会于下総国府、従軍及三百余騎也、常胤先召覧囚人千田判官代親政」と、常胤以下の千葉一族が頼朝に面会。囚人の藤原親雅を引き据えたのち、駄餉が献じられたが、このとき「武衛令招常胤於座右給、須以司馬為父之由被仰」と告げたという。
その後、常胤は「陸奥六郎義隆男号毛利冠者頼隆」を頼朝に引き合わせている。平治の乱当時、父・陸奥六郎義隆(八幡太郎義家の子)が源義朝に属して比叡山龍華越えで討死を遂げた際、まだ生後五十余日の乳児だった頼隆を朝廷は常胤に命じて下総国へと配流に処したが(『吾妻鏡』治承四年九月十七日条)、常胤はそれ以降二十年にわたって養育を続けていたのであった。
そして9月19日、広常はようやく上総国周西・周東・伊北・伊南・庁南・庁北郡の武士団二万余騎を引き連れて「参上隅田河辺」に参陣したという(『吾妻鏡』治承四年九月十九日条)。ただし、頼朝はいまだこの時点では隅田川はおろか太日川も渡っておらず、日時の誤謬か川名の誤りであろう。このとき、頼朝は広常の遅参を激しく叱責し、広常は面食らって遅参を詫びると同時に頼朝を頼むに足る大将とみとめたとされる(『吾妻鏡』治承四年九月十九日条)。なお、広常の軍勢には国衙のあった「市東」「市西」が含まれておらず、国衙周辺には目代勢力が置かれていて、上総平氏の勢力は及んでいなかったのであろう。
頼朝側の主な構成
| 在庁官人 | 平 広常…上総平氏。上総権介の八男。 千葉常胤…下総平氏。下総国在庁。在国司職の下総権介。「千葉介」を称する。 小山朝政…秀郷流藤原流。下野在庁。 狩野茂光…南家藤原氏流。伊豆国在庁。在国司職の相模介。「狩野介」を称する。 三浦義明…相模国在庁。在国司職の相模介。頼朝の挙兵時から従う。「三浦大介」を称する。 比企能員…武蔵国比企郡司。阿波国出身で頼朝の乳母 ・比企尼の甥で養子。 河越重頼…武蔵国留守所惣検校職。後年、頼朝に疑われて誅されたのち、惣検校職は重忠に移る。 北条時政…伊豆国在庁。長女(のち政子)は頼朝室。 平 広幹…代々常陸大掾を勤める家。頼朝に降伏したのち重用された。のち八田知家と争い梟首された。 |
| 任官者 | 宇都宮朝綱…下野国宇都宮検校。八田権守宗綱の子息。左衛門権少尉。秩父党・稲毛重成の叔父。 工藤行政…頼朝の縁戚で鎌倉に招かれて永福寺辺に住み二階堂を称する。 武田有義…武田信義息。重盛に仕えて左兵衛尉に進むが、父に従ったため妻子の首を京の武田邸前に晒された。 千葉胤頼…千葉常胤息。上西門院に仕えて従五位下に叙される。子孫の東氏は代々歌人として著名。 新田義重…清和源氏。新田庄下司職。従五位下大炊助。はじめ頼朝に敵対していたため冷遇される。 足利義兼…八条院蔵人。頼朝近親で頼朝に合流。子孫は北條氏と重代の縁戚となり、尊氏を生む。 後藤基清…左兵衛尉。父仲清は摂政家随身。叔父義清は鳥羽院北面で、出家後は「西行」を称する。 足立遠元…右馬允。もと武者所。武蔵国足立郡の豪族で、頼朝とは挙兵以前からの知己。 天野遠景…内舎人。伊豆国田方郡の豪族で工藤氏同族。頼朝とは挙兵以前からの知己。 …等々多数 |
| 荘官 | 下河辺行平…源頼政郎党・下河辺庄司行義の子で、八条院領・下河辺庄の庄司をつとめた。 葛西清重…武蔵国葛西庄の荘官。所領が隣接する秩父党や千葉氏と関わりが深かった。 …等々 |
| 豪族 | 土肥実平、佐々木定綱 …等々 |
| 平氏家人 | 熊谷直実…武蔵熊谷郷の人。一谷で平敦盛を討った人物。伯父との所領問題で遁世し、法然門人となる。
武藤資頼…一貫して平氏被官として頼朝に敵対するが、捕縛されたのち御家人となった。少弐氏の祖。 渋谷重国…武蔵国澁谷庄司。石橋山では頼朝に弓を引いたが、その後降伏して活躍。頼朝の信任を得る。 畠山重忠…弱冠十七歳で、惣領河越重頼らの援助を受けて三浦氏を攻める。その後頼朝に降伏。 江戸重長…武蔵国在庁。頼朝が挙兵したときは、武蔵国の棟梁と目されていた。 梶原景時…かつて大庭景親のもとで頼朝と戦うが、のち降伏して重用される。知略と剛腕で知られた人物。 小山田有重…平家の家人として木曽義仲と戦う。その後、頼朝に帰参し、子息・稲毛重成らとともに活躍。 …等々 |
| 京出身 | 藤九郎盛長…頼朝の古い被官人でのち宿老。妻は比企尼娘ではない。また足立遠元とも血縁上の関係はない。 藤大和判官代邦通…藤九郎盛長と「因縁」の人物で、盛長の推挙により頼朝の側近となる。 |
頼朝は下総国では「鷺沼御旅館」に逗留しており、下総国と武蔵国の境に留まっていたと思われる。「鷺沼」については、
| 習志野市鷺沼 | 国府から15kmも東に退く理由はないため不可 |
| 葛飾区新宿字鷺沼 | 鷺沼は太日川より東でなければならないため不可 |
| 市川市国府台付近 | 国府付近の谷津沼(現在のじゅんさい池=国分沼)のように「鷺沼」があったのだろう。 |
下総国府の麓の谷津には海退による沼沢地が広がっており、その名残として現在も「じゅん菜池」緑地が整備されている。「鷺沼」はこうした国府に隣接した沼の一つであり、頼朝の「鷺沼御旅館」は沼を望む高台に設けられていた国府付属の建物であることが想定される。頼朝は17日の国府到着以降「大井隅田両河」を渡る10月2日までの半月間をこの鷺沼で過ごし、すでに兵を挙げていた甲斐源氏や武蔵秩父党との折衝、相模国の動向などを入念に調査していたと考えられる。
また、10月1日には鷺沼御旅館に京都醍醐寺の僧であった異母弟・悪禅師全成(義経実兄。幼名今若)が訪れて頼朝と対面している。全成は以仁王(最勝王)の「最勝王宣」が頼朝に下されたことを京都で伝聞し、醍醐寺を密かに脱して修行者を装って鷺沼まで到来したことを告げ、頼朝は「泣令感其志給」ったという(『吾妻鏡』治承四年十月一日条)。
翌10月2日、頼朝一行は広常・常胤が調達した舟筏に乗って「大井隅田両河」を渡って武蔵国に入った。このとき頼朝が布陣した場所は「豊島御庄瀧ノ河(北区)」(『源平闘諍録』)とされるが、「豊島権守清元、葛西三郎清重等最前参上、又足立右馬允遠元、兼日依受命、為御迎参向」とあることから、豊島清元と葛西清重の父子が頼朝の麾下に加わったのは、葛西清重が荘官を勤めていた「大井」と「隅田」の中州の肥沃地・下総国葛西庄以外にあり得ず、さらに同日、頼朝の乳母「故八田武者宗綱息女」(小山下野大掾政光の妻。のち寒河尼)が十四歳の末子を連れて「隅田宿(現在の台東区橋場周辺)」に参向し、頼朝はそこで少年に「朝」字を与え、「小山七郎宗朝(のちの結城朝光)」と名乗らせたとあることから(『吾妻鏡』治承四年十月二日条)、頼朝勢は下総国府から豊嶋郡衙(北区西ヶ原)へ向かう官道を通って隅田宿へ入り、その後は豊島清元の案内によって武蔵野台地の急崖を経て豊嶋郡衙へ進んだのだろう。豊嶋郡衙は下総国府と武蔵国府を繋ぐ中継地で、大井駅へ向かって南下する官道も走っている要衝であった。
→藤原宗円―――八田宗綱―+―宇都宮朝綱
(宇都宮座主)(権守) |(左衛門尉)
|
+―八田知家―――八田朝重
|(右衛門尉) (太郎)
|
+―寒河尼 +―小山朝政
【頼朝乳母】|(下野大掾)
∥ |
∥―――+―長沼宗政
小山政光 |(淡路守)
(下野大掾)|
+―結城朝光
(左衛門尉)
10月3日の頼朝の動向は伝わらないが、この日、頼朝は常胤へ上総国の伊北庄司常仲(広常の甥)の追討を命じており、常胤は「子息郎従」に厳命を含んで上総国に遣わした(『吾妻鏡』治承四年十月三日条)。このとき、頼朝一行が武蔵国府へと向かっていたとすれば、胤正らは相当な距離を戻ることとなるため、3日も豊嶋郡内に逗留していたと考えられる。実際に伊北庄へ派遣されたのはこれより以前で10月3日は常仲が討たれた日である可能性も考えられるが、この上総国への派兵には前日に参向した葛西清重も加わっており(『吾妻鏡』文治六年正月十三日条)、10月2日以前の派兵ではないことがわかる。つまり、胤正ら常胤の子息・郎党および葛西清重は10月3日に豊嶋郡から上総国伊北庄(いすみ市岬町一帯)へと遣わされたのである。彼らは百kmを超える道を進んで伊北庄に常仲らを誅した(『吾妻鏡』治承四年十月三日条)。
なお、上総国伊北庄に展開した千葉胤正らの軍勢が、駿河国東部へ進んでいた頼朝と合流するには、三浦半島を経由したルートだとしても百キロ超えの軍旅となるため、胤正勢はもともと上総国への派遣が計画されていて、征西軍への再合流は考えられていなかったのだろう。
常仲が追討の対象とされたのは「長狭常伴の外甥」であったためとされる(『吾妻鏡』治承四年十月三日条)。常伴は頼朝を討とうとした平家与党であるが、広常の率いた手勢に「伊北」の人々は加わっており、事実であれば伊北常仲は叔父・広常の軍勢徴発に従わずに伊北庄に留まったと考えられる。これが長狭常伴の外甥という血縁関係もあって、頼朝が敵視したということだろう。常仲の父・伊南新介常景は弟の印東次郎常茂に殺害されたが、常景の版図を引き継いだのは常景・常茂の末弟とも言うべき八郎広常であった。そのため、常仲は広常に対して反発していたのかもしれない。
 |
| 畠山重忠と三日月 |
10月4日、「長井渡」の頼朝の陣に平家与党であった秩父党・畠山庄司次郎重忠が投降。さらに、河越太郎重頼や江戸太郎重長が次々に頼朝勢に参加した。畠山重忠は祖・秩父武綱が「後三年の役」で先陣をつとめて戦功を挙げた吉例があったため、以降、儀式や戦陣においては畠山重忠が先陣を、殿軍は千葉介常胤が務める慣わしとなった。
武蔵国は当時、平知盛の知行国であり、武蔵国の武士団を纏め上げ「平家世ヲ知リテ久シクナリケレバ、東国ニモ郎等多カリケル中ニ、畠山荘司、小山田別当ト云フ者、兄弟ニテアリケリ」(『愚管抄』)と記されているように、畠山重忠の父・畠山庄司重能やその弟・小山田別当有重は東国の平家郎等として認識されていたことがわかる。また、頼朝挙兵当時も「重能、有重、折節在京」(『吾妻鏡』治承四年九月二十八日条)とあるように平家に仕えており、秩父党は本来であれば平家与党であって、頼朝に組する存在ではなかった。さらに頼朝の手勢にはわずか一月前に干戈を交えた三浦党が加わっており、頼朝が「存忠直者更不可貽憤之旨、兼以被仰含于三浦一党、彼等申無異心之趣」(『吾妻鏡』治承四年十月四日条)と釘を刺すほどであった。このような秩父党がなぜこぞって頼朝の陣に帰参することになったのか。理由は定かではないが、秩父党は積極的に「頼朝党」に加わったというよりも強大な兵力が俄かに武蔵国へ迫ったことで強い危機感に苛まれたのではなかろうか。
9月28日、江戸太郎重長に使者を出して「依景親之催、遂石橋合戦、雖有其謂守令旨可奉相従、重能、有重、折節在京、於武蔵国、当時汝已為棟梁、専被恃思食之上者、催具便宜勇士等、可予参之由」を命じた(『吾妻鏡』治承四年九月廿八日条)。平安時代中期、秩父氏惣領が兼帯していた武蔵国の留守所惣検校職は、河越太郎重頼が任じられていたが、当時において秩父一族は一門としての紐帯はあったものの、族長権者が一族を取りまとめていたわけではない。これは両総平氏や三浦氏についても言えることではあるが、彼らが直接行い得たのは、家父長権による催促に限られていた。頼朝が江戸太郎重長へ言ったとされる「重能、有重折節在京、於武蔵国、当時汝已為棟梁」の「棟梁」とは「武蔵国」で中心的な者という意味であって、秩父党の族長という意味ではない。
しかし、重長は参向する気配を見せなかったようで、翌29日、頼朝は「試昨日雖被遣御書、猶追討可宜之趣、有沙汰、被遣中四郎惟重於葛西三郎清重之許、可見大井要害之由、偽而令誘引重長、可討進」を指示した(『吾妻鏡』治承四年九月廿九日条)。ただ、この謀略は中止されたようで、それは重長から何らかの返答があった可能性が高い。これは10月4日に畠山重忠、河越重頼、江戸重長の三名が揃って降伏し、しかもその降伏前に、頼朝が「重長等者、雖奉射源家、不被抽賞有勢之輩者、縡難成歟、存忠直者更不可貽憤」ことを「兼以被仰含于三浦一党、彼等申無異心之趣」(『吾妻鏡』治承四年十月四日条)していることからも明らかであろう。
10月2日、下総国から武蔵国へ渡った頼朝勢は(『吾妻鏡』治承四年十月二日条)、その二日後の10月4日、頼朝は「長井渡」で「畠山次郎重忠」及び「河越太郎重頼、江戸太郎重長」と参会し、その降伏を受け容れた(『吾妻鏡』治承四年十月四日条)。なお、畠山重忠らが集った「長井渡」が現在どこかは不明だが、少なくとも武蔵国府近辺ではない。平家与党である秩父党が蟠居する武蔵国の深入りはリスクが著しく高く、相模国へ急行する中で武蔵国府を経由するメリットは皆無だからである。
頼朝一行は、武蔵国豊嶋郡衙から官道を南下して大井駅を経由し、荏原郡衙、橘樹郡衙、久良岐郡を経て相模国鎌倉郡へ入るルートをとったとするのが自然であろう。そうであれば「長井渡」は武蔵国東部の津戸となり、ここに秩父党の首脳らが参集したとすれば、橘樹郡内の石瀬川(多摩川)の津戸であろう。鎌倉への日程を考えると、おそらく10月4日は石瀬川を北に望む橘樹郡衙(川崎市高津区千年)に滞陣したのではなかろうか。
その後、頼朝はさらに南下して、翌10月5日には相模国境に近い久良岐郡衙(横浜市南区弘明寺町)に駐屯したのだろう。この日、頼朝は江戸重長に「武蔵国諸雑事等、仰在庁官人幷諸郡司等、可令致沙汰之旨、所被仰付江戸太郎重長也」と、武蔵国内の政務について在庁官人及び郡司らに沙汰することを命じている(『吾妻鏡』治承四年十月五日条)。
 |
| 寿福寺 |
そして翌10月6日、頼朝は畠山重忠を先陣、常胤を後陣として「着御于相模国」した。この「相模国」は相模国鎌倉郡へ入ったということと同時に、朝比奈方面から鎌倉内に入ったということであろう。朝比奈方面にはもともと上総権介広常の屋敷地があったと思われ、12月12日、頼朝が新造の御亭(鎌倉市雪ノ下)に移る際には「上総権介広常」の屋敷(鎌倉市十二所カ)から移っている。重忠を先陣としつつも、鎌倉の地理を熟知する広常の案内は重要であったろう。ただ、その日は「楚忽之間、未及営作沙汰、以民屋被定御宿館」とある通り、進軍があまりに急であったために、鎌倉の街中に頼朝が宿営できる場所を造っておらず、やむなく民家を陣所とした(『吾妻鏡』治承四年十月六日条)。
翌10月7日、頼朝は鎌倉北部から由比浜辺に建つ古社「鶴岡八幡宮」を遥拝したのち、「故左典厩義朝之亀谷御旧跡」(現在の寿福寺の地)を監臨して、ここに館を構えようとした。ところが狭小の上に、すでに岡崎平四郎義実が建てた義朝の菩提を弔う堂宇があったことから、結局この地をあきらめ、大倉の地に御所を建てることになる。
一方、東国における頼朝らの「叛乱」を鎮圧するべく、9月21日、東国追討使の「右少将維盛朝臣、薩摩守忠度朝臣、武蔵守知度等」(『山槐記』治承四年九月九日条)が新都福原京を出立した。官宣旨では22日が出門日であったが、21日が「吉日」(庚午の大明日であろう)であったため「出門」の日とし、22日は摂津国小屋郷(伊丹市昆陽周辺)に宿陣。23日に入洛して、27、8日に故都(京都)を「首途」と決定している(『玉葉』治承四年九月廿三日条)。ところが、この計画を知らなかったと思われる権中納言藤原忠親は、入洛後、追討使が「其後于今所逗留也」と不審に思っている様子が窺える。
 |
| 畠山重忠と三日月 |
ただし、追討使の27日または28日の六波羅出立は、23日の入洛時点ですでに決定事項であったことが『玉葉』からわかり(『玉葉』治承四年九月廿三日条)、28日が正式な六波羅出立の日だったが、維盛の乳父・上総介忠清が「於此都忌十死一生日」と主張して出兵を渋り、これに対して、維盛は新都福原京を出立した22日が門出基準であり、六波羅は「於今者途中儀、於旧都可忌日次」と主張している。しかし、忠清は「六波羅者先祖旧宅也、争不被忌者」(『山槐記』治承四年九月廿九日条)として譲らなかったという。十死一生日はまさに28日「丁丑」に該当しており、これを不吉としたものだろう。ただ、吉凶が行動規範の根本であった当時にあっては、以前から28日が忌日である事は周知の事実であったことは間違いない。その日に六波羅を出立することは清盛入道も当然認識していたはずであり、忠清の主張は維盛を前線に送ることを厭う口実であった可能性もあろう。忠清は後白河院に近い小松家の宿老として、平時子・宗盛ら平家主流と距離を取っており、その後の忠清の行動を見ると、源氏勢力との和睦を見据えていた可能性がある。この忠清の維盛を押し止める態度は実は源三位の乱でも見られ、南都追捕を主張する維盛を抑えている。
六波羅駐屯の期間が数日設けられたのは、越前国、近江国、美濃国など諸国からの軍勢催促のためである可能性が高いだろう。なお、結果として追討使の六波羅出陣は28日は避けられて、29日早朝となった。ただし、当初の28日計画から大きな齟齬があったわけではなく、維盛と忠清の相論によって出立が大幅に遅れたために、富士川合戦の敗退に繋がったという説は頷首しがたい。後述の富士川合戦における追討使の大敗は、行動の遅れから起こされたものではなく、駿河目代の失策及び、追討使自体の士気の低さが引き起こした必然的なものであった。
一方、以仁王の「最勝王宣」を受けて挙兵した武田太郎信義・安田三郎義定ら甲斐源氏は、駿河・遠江国への進出を謀り、追討使を迎え撃つべく軍勢を南下させた(『吾妻鏡』治承四年十月十三日条)。この甲斐源氏の駿河進出を察した内大臣宗盛の家人「駿河守維時」(『山槐記』治承三年正月六日条)の目代「駿河目代遠茂」は、「当国目代橘遠茂、催遠江駿河両国之軍士、儲于興津之辺」(『吾妻鏡』治承四年十月一日条)とあるように、興津辺りに在陣していたようであるが、「長田入道」の謀計を以て、甲斐国を衝くべく富士野を廻って北上した(『吾妻鏡』治承四年十月十三日条)。長田入道は国府近辺の長田村を本貫とする在地武士であろう。
駿河目代勢の甲斐侵攻を知った甲斐源氏勢は、目代勢を待ち構える作戦をとり、富士北麓の若彦道を越えて西回りに駿河国へと向かった。
翌10月14日、駿河目代橘遠茂率いる三千余の軍勢は春田路を北上。鉢田の細い山道に布陣する甲斐源氏勢に遭遇し、武田信光と加藤次景廉の手勢に襲われて敗北。結果、目代は捕縛され、長田入道子息二人は梟首、主だった人々八十余が討死し駿河勢は壊走するという、追討使にとっては前哨戦に大敗を喫する不吉な一報を受けることとなる(『吾妻鏡』治承四年十月十四日条)。京都へは追討使が駿河国高橋宿に到着した10月16日以前に、「彼国目代、及有勢武勇之輩三千余騎、寄甲斐武田城之間、皆悉被伐取了、目代以下八十余人切頸懸路頭」(『玉葉』治承四年十一月五日条)と伝えられている。
10月17日朝、武田信義は「年来雖有見参之志、于今未遂其思、幸為宣旨使、有御下向、雖須参上程遠隔一日云々、路峻、轍難参、又渡御可有煩、仍於浮嶋原、甲斐与駿河之間広野云々、相互行向、欲遂見参」という書状を使者二人に持たせて維盛の陣へと派遣した。駿河目代を討ち取るという反抗を見せた翌日であり、武田方の挑発行為に他ならないだろう。これに上総介忠清が激怒。「使者二人切頸了」という行動に出た(『玉葉』治承四年十一月五日条)。なお、『山槐記』では、10月19日に「頼朝党営于不志河送使、不知其状、維盛朝臣問所為於忠景、忠景曰、兵法不斬使者、然而此條私合戦之時事也、今為追討使、可及返答哉、先問彼方子細可斬者、維盛朝臣従此言令痛問、使者云、軍兵有数万、敢不可為敵対者、問此後斬首了」と、この使者は「頼朝党」が遣わしたものとしている。そして、維盛は使者の扱いを忠景(忠清)に問い、使者の口上を聞いたのち斬首したとされる(『山槐記』治承四年十一月六日条)。
追討使として下向した官兵はわずかに千余騎、これに加えて諸国から徴発された兵士で構成されていたが、諸国の兵士は「内心皆在頼朝、官兵互恐異心、暫逗留者欲圍塞後陣」と、戦う意欲はまったくなかったという。忠景(忠清)もこの状況を聞いて「無欲戦之心」という状況にあったとされる(『山槐記』治承四年十一月六日条)。平家が甲斐源氏の使者を斬った日付には『玉葉』と『山槐記』には数日の誤差がみられるが、その伝えられる内容は全く異なることから、それぞれ違う情報源からのものであろう。
翌10月18日、追討使は富士川辺に進出して陣所を定め、19日に武田勢へ攻め懸るべく準備を行っていたところ、「官兵之方数百騎、忽以降落、向敵軍城了」という状態となり、「無力于拘留、所残之勢、僅不及一二千騎」と、五千余騎という大勢で出陣した追討使のうち、過半が逐電する体たらくであったという。対する「武田方四万余」とし、「忠清之謀略」を以て「依不可及敵対、竊以引退」したとする。維盛に退却の意思はなかったが、忠清が説得し、諸将もこれに同調したため、京都へ戻ったという(『玉葉』治承四年十一月五日条)。また、「宿傍池鳥数万俄飛去、其羽音成雷、官兵皆疑軍兵之寄来夜中引退、上下競走、自焼宿之屋形中持雑具等、忠度知度不知此事、追退帰、忠景向伊勢国、京師維盛朝臣入京、着近州野路之時有五六十騎」(『山槐記』治承四年十一月六日条)という報告もあった。
11月1日には上総介忠清が駿河国から発した書状が前右大将宗盛に届き、「頼朝党数万騎也、十一ヶ国已同志、官兵纔千騎也、不可敵対、暫去駿河国欲着遠江国府、可然之人々猶可被下向也、又以景清被任信濃守可為追討使歟者、駿河目代為頼子(頼朝カ)被伐了、或曰、目代一人存命」(『山槐記』治承四年十一月四日条)とあったという。
駿河国富士川辺での追討使敗退の一報は10月28日に京都に届き、頭弁経房が中山忠親に「頼朝党進出駿河国富士河辺合戦、追討使官軍敗向伊勢国之由」を伝えている(『山槐記』治承四年十月廿八日条)。実際は甲斐源氏は「頼朝党」ではなく、以仁王の「最勝王宣」を奉じて蜂起した源氏の一つであり、京都でも「甲斐国住人源信義猥成雷同」とあるように、頼朝とは別に挙兵した勢力として把握されていたが、頼朝と同意した「頼朝党」として見られていたため、頼朝党が駿河富士川で追討使を破ったとの報告につながったものであろう。このことから、頼朝は勢力として過大評価されていたことがわかる。
以上「富士川合戦」を『玉葉』『山槐記』『吉記』を総合的に考察すると、駿河国目代・橘遠茂が二、三千余騎で甲斐源氏追討のために甲斐国へと進軍したが、退路を断たれて大敗を喫した。その後、追討使維盛以下三千余騎が駿河国手越宿、高橋宿を経て富士川辺へ着陣するが、すでに官兵の士気は阻喪しており、このような中、甲斐源氏から使者二名が維盛のもとへ送られ、挑発する書状を渡した。これを読んだ上総介忠清は激怒し、使者二人を賊使として斬首する。ところが平家に従う官兵は恐怖し、次々と逃走する有様であった。こうした状況に上総介忠清はもはや戦う状況にないと判断。維盛に退陣を勧めた。維盛勢が退陣を命じたことで、甲斐源氏を恐れる官兵は我先に逃れようとして壊走が始まり、手越宿の仮宿も自焼し(間者による放火とも)、事情を知らない忠度、知度も維盛勢を追って近江へと退却したのであろう。
頼朝はこのとき、富士川の東の大湿地帯に浮かぶ賀島(富士市加島町)まで出ていたとされ(『吾妻鏡』治承四年十月廿日条)、飯田五郎家義と子息・飯田太郎が富士川を渡って平家勢を追撃し、「伊勢国住人伊藤武者次郎」と組打した飯田太郎が討死するも、家義が伊藤武者次郎を討ち取るという激戦が起こっていたという。また、上総介八郎広常の兄・印東次郎常義(『源平盛衰記』では先陣押領使)も加島に近接する鮫島で討死(『吾妻鏡』治承四年十月廿日条)しており、「為弟弘常被害」(『桓武平氏諸流系図』「中条家文書」)と見えることから、広常もこの合戦に加わっていた可能性が高い。
維盛は11月7日、近江国勢多まで戻り、ここから西八條の祖父・清盛入道のもとに状況報告のため馬允満季を派遣した。これで仔細を知った清盛入道は「承追討使之日、奉命於君了、縦雖曝骸於敵軍、豈為耻哉、未聞承追討使之勇士、徒赴帰路事、若入京洛、誰人可合眼哉、不覚之耻貽家、尾籠之名留世歟、早自路可暗趾也、更不可入京」と激怒し、維盛はその怒りを恐れてか密かに入洛して検非違使忠綱邸に匿われたという。一方、知度は西八條邸に入ったという(『玉葉』治承四年十一月五日条)
富士川から撤退した平家勢を追うため、10月21日に追撃して上洛すべしと諸士に命じたが、「常胤、義澄、広常等」は「常陸国佐竹太郎義政幷同冠者秀義等、乍相率数百軍兵未帰伏、就中、秀義父四郎隆義、当時従平家在京、其外驕者猶多境内、然者先平東夷之後、可至関西」と説得。頼朝はこれを容れて黄瀬川へ戻って宿陣したという(『吾妻鏡』治承四年十月廿一日条)。
そしてこの日、頼朝の旅館を訪ねてきた一人の若者がおり、土肥実平、土屋宗遠、岡崎義実がこれを怪しんで対面を拒んだ。そのとき、この騒ぎを聞いた頼朝は「思年齢之程、奥州九郎歟」と、早々に対面させるよう指示した。実平がこの若者を頼朝の面前へ連れてくると、果たして九郎義経であった。頼朝と義経は「互談往事、催懐旧之涙」したという(『吾妻鏡』治承四年十月廿一日条)。
義経は往還の大宿とはいえ、黄瀬川宿という非常にピンポイントな場所に過たずたどり着いており、頼朝が黄瀬川にいることを把握していた可能性が高い。当時の相模国や駿河国は平家党が潜伏し、「頼朝党」も入り混じる混沌とした地であり、少人数での行動が危険が伴ったであろう。義経は奥州藤原氏から多くの手勢を付けられ、頼朝はこの奥州藤原氏からの軍勢を得たことで秀衡という後顧の憂いがなくなったとみたという説も存在するが、当時の奥州藤原氏は頼朝にとっては佐竹氏と血縁のある敵性勢力であったことは言うまでもなく、その軍勢が関東へ入ったとすればその報が入った時点で頼朝は軍勢を東へ転じるであろう。また、佐竹氏や新田氏ら平家と直接繋がる勢力がこれに応じる可能性も高いだろう。ところが、少なくとも『吾妻鏡』においては、頼朝はまったく動かず、その他の勢力も特段の動きを見せていない。つまり義経に奥州藤原氏から「多くの」軍勢が付けられていたことはあり得ないことを意味する。
黄瀬川宿は伊豆国府や三島、北条氏館に近接しており、義経は奥州からいったん相模国鎌倉、もしくは伊豆国北条を訪ねたのではあるまいか。また記載はないが、頼朝の陣所または三島や鎌倉など周辺域に義経実兄・醍醐悪禅師全成も駐屯していたと考えられ、北条氏や全成によって黄瀬川の陣所を知らされていたのかもしれない。
この日、頼朝は三島社に参詣しているが、その際に伊豆国河原谷郷(三島市加茂川町)と長崎郷(伊豆の国市長崎)を寄進している。
この寄進状は室町期にも残っており、応永25(1418)年8月3日、瀬下掃部助知行であった長崎郷を上杉憲実被官がこの「治承四年十月廿一日右大将家御寄進状」と「建武二年十二月十一日長寿寺殿御判」に基づいて三島社の東大夫に沙汰付下地を守護代とみられる「大石遠江入道殿(大石信重入道)」に指示している(応永廿五年八月三日「上杉憲実家奉行人連署奉書」『三島社文書』神:5574)。
10月23日、相模国府に到着した頼朝は、「北條殿及信義、義定、常胤、義澄、広常、義盛、実平、盛長、宗遠、義実、親光、定綱、経高、盛綱、高綱、景光、遠景、景義、祐茂、行房、景員入道、実政、家秀、家義以下、或安堵本領、或令浴新恩」したという(『吾妻鏡』治承四年十月廿三日条)。また、大庭三郎景親、長尾新五為宗、長尾新六定景、河村三郎義秀、瀧口三郎経俊らが頼朝のもとに出頭した。なお、武田信義と安田三郎義定ら甲斐源氏は頼朝とはまったくの別勢力であり、彼らが実際に相模国府へ入ったかも不明だが、このことが頼朝の麾下に入ったことを意味するわけではなく、この時点においてはともに戦った源氏一族という立場であったろう。
翌26日、頼朝は鎌倉への帰途、大庭景親らを片瀬川で処断した(『吾妻鏡』治承四年十月廿六日条)。なお、頼朝の「相模国小早河」大敗以降の動向として、9月11日、九条兼実のもとに「而其後上総国住人介八郎広常幷足利太郎故利綱子云々等余力、其外隣国有勢之者等、多以与力、還欲殺景親等了之由、去夜飛脚到来、事及大事」(『玉葉』治承四年九月十一日条)と、上総広常や足利太郎(「故利綱子」とあるが、利綱=足利俊綱は生存しており、兼実が足利俊綱と足利義康を誤って認識していたとすれば、頼朝親族の足利義兼となろう。そのように考えれば、宇治川合戦で以仁王と干戈を交えた足利忠綱を、平家の任官問題で一旦は頼朝に随ったのち再び離反したと牽強付会する必要もない)、その他近隣の有力者が頼朝に協力して景親を討ち取った、という報告がなされている。
片瀬川での景親梟首ののち、鎌倉へ帰還したかどうかははっきりしないが、翌27日には佐竹氏討伐のために常陸国へ向けて出立したという(『吾妻鏡』治承四年十月廿六日条)。『吾妻鏡』によれば、頼朝は常陸国へ進出し、11月4日には常陸国府で上総介八郎広常・千葉介常胤・三浦介義澄・土肥次郎実平ら宿老を召集して軍議を行い、在京中で平家に伺候する惣領・佐竹四郎隆義の庶兄である「佐竹太郎義政(太郎忠義)」を招いて謀殺するため、彼の縁者の広常に指示して、国府向こうの園部川の大矢橋の中央に義政を誘い出し殺害させたという(『吾妻鏡』治承四年十一月四日条)。しかし、義政(忠義)は本当に寄手の誘引に素直に応じて、麾下の将士を橋辺に残してのこのこと敵中に一人進み出る(『吾妻鏡』治承四年十一月四日条)不可解極まる行動をしたのであろうか。可能性があるとすれば和平の対話のためであろうか。
一方、太郎義政(忠義)の甥で「其従兵軼於義政」の惣領嫡子・佐竹冠者秀義は、在京の父隆義の事も考えると容易に頼朝に加担することはできないとして、久慈川の氾濫原を望む久慈郡佐竹郷(常陸太田市磯部町)から久慈川を遡上し、北西の堅牢な金砂城(常陸太田市上宮河内町)へと引き退いている(『吾妻鏡』治承四年十一月四日条)。
その後、頼朝は金砂城へ籠っていた佐竹冠者秀義を攻めるべく「所謂下河辺庄司行平、同四郎政義、土肥次郎実平、和田太郎義盛、土屋三郎宗遠、佐々木太郎定綱、同三郎盛綱、熊谷次郎直実、平山武者所季重以下輩」を派遣したが、金砂城は堅固この上なく「自城飛来矢石、多以中御方壮士、自御方所射之矢者、太難覃于山岳之上、又厳石塞路、人馬共失行歩、因茲軍士徒費心府、迷兵法、雖然不能退去、憖以挟箭相窺之間、日既入西月又出東」と、味方の損害が出るばかりで攻めあぐねた(『吾妻鏡』治承四年十一月四日条)。
この状況に困り果てた実平や宗遠は頼朝へ使者を遣わし「佐竹所搆之塞、非人力之可敗、其内所籠之兵者、又莫不以一当千、能可被廻賢慮者」(『吾妻鏡』治承四年十一月五日条)と具体的な対応策を求めている。これを受けた頼朝は「及被召老軍等之意見」したところ、広常が「秀義叔父有佐竹蔵人、ゝゝ者智謀勝人欲心越世也、可被行賞之旨有恩約者、定加秀義滅亡之計歟者」(『吾妻鏡』治承四年十一月五日条)と提案したことから、頼朝はこれを容れて広常を秀義叔父の佐竹蔵人のもとに遣わした。佐竹蔵人の陣所がいずこにあったのかは不明だが、佐竹蔵人は広常の来臨を喜び、歓待したという。広常はここで「近日東国之親疎、莫不奉帰往于武衛、而秀義主独為仇敵、太無所拠事也、雖骨肉客何令与彼不義哉、早参武衛討取秀義、可令領掌件遺跡者」(『吾妻鏡』治承四年十一月五日条)と説得すると、佐竹蔵人は頼朝への帰順を誓い、早速広常を伴って金砂城の後ろに回り込むと、鬨の声をあげて城内の佐竹秀義勢を威した。するとこの声に秀義と郎従等は不意を突かれて慌てふためき、広常は混乱に乗じて襲い掛かると秀義勢は算を乱して壊走。秀義は行方をくらました。
翌11月6日、広常は金砂城へ入るとこれを焼き払い、兵を分けて佐竹秀義の追跡を行ったが、すでに秀義は「奥州花園城」(北茨城市華川町花園)まで逃れ去った風聞があったことから、広常らは頼朝のもとに帰還し「合戦次第及秀義逐電、城郭放火等事」(『吾妻鏡』治承四年十一月六日条)を報告した。とくに「軍兵之中、熊谷次郎直実、平山武者所季重、殊有勲功、於所々進先登更不顧身命、多獲凶徒首」と熊谷直実と平山季重の活躍を聞いた頼朝は、彼らは「其賞可抽傍輩之旨、直被仰下」(『吾妻鏡』治承四年十一月六日条)と指示した。また、この戦いの勝敗を決定づけた佐竹蔵人も参上しており「可候門下之由望申」したため、これを功績を以て許容した。そして、「今日志太三郎先生義広、十郎蔵人行家等、参国府、謁申」(『吾妻鏡』治承四年十一月七日条)とあるように、11月7日、頼朝は常陸国府(石岡市)で叔父の志太義広、十郎行家と対面している。志太三郎義広は当時、八条院領の常陸国信太庄(稲敷郡美浦村信太周辺)の荘官とみられ、おそらく弟の八条院蔵人十郎行家とともに行動をしていたのだろう。どういった話がなされたのかは不明だが、これは「最勝王宣旨(以仁王の令旨)」に応じて、義広、行家が主導し、甥の頼朝、義仲と連携した対平氏の組織づくりを模索したのではなかろうか。このとき義広・行家と頼朝との間に敵意はなかったであろうが、頼朝はこの提案を拒絶したのだろう。義広、行家はその後頼朝と袂を分かち、義広は源義仲(木曾義仲)との連携を選んでいる。これは義広が義仲の実叔父(義広は義仲実父義賢の同母弟)であったことが大きく影響しているのであろう。なお、義広はその後義仲との合流を模索して常陸国から下野国の東山道を進むことになるが、ここで起こった事件が治承5(1181)年閏2月23日の小山朝政一党と義広の「宮木野合戦」である。また、行家は義広とは別行程を経て義仲と合流することになるが、義仲はすでに八條院猶子だった故以仁王の遺児(のち北陸宮と称される)との繋がりを得ていて、義仲との関係を選んだ可能性がある。
これら佐竹氏との戦いには、おそらく常陸平氏の協力があったのだろう。彼らはいずれも千葉介常胤と相当に濃い血縁者(多気義幹らは常胤娘の子とされるが、世代的にみて常重娘の子が妥当か)であり、千葉介常胤とも連携があった可能性があろう。那珂郡馬場(水戸市)の馬場小次郎資幹(多気太郎義幹弟)は頼朝の信任厚く、のち、かつて氏族が世襲していた常陸大掾に就任することになる。また、筑波山地の西側、多気・真壁・下妻一帯を主な支配領域としていた地理的関係上、隣接する小山・下河辺氏との結びつきが考えられる。さらに頼朝は翌治承5(1181)年3月には、鹿嶋郷を支配していた鹿嶋政幹を鹿嶋宮「惣追補使」(『吾妻鏡』治承五年三月十二日条)に補任しており、常陸平氏は頼朝勢に協力の姿勢を示していた可能性が高いだろう。
※『源平盛衰記』には富士川合戦時の平家方の押領使として常陸国の佐谷次郎義幹の名がみえ、多気義幹と同一人物という説が提唱されている(野口実氏「平氏政権下における坂東武士団」『坂東武士団の成立と発展』所収)が、常陸平氏惣領が累代の本拠である多気ではなく、佐谷を優先して名乗る理由も不可解であることや、そもそも軍記物という性格上厳密ではないが、輩行名の不一致から、佐谷次郎義幹は多気太郎義幹とは別人と考える。常陸平氏の中にも国府に近い土地を所領としていた一族は国府の影響力が及び、国衙方・平家党となる庶子もいた可能性はあろう。史上、文書や史書に名を見せる人物はその世に生きた人々のほんの一握り。幾度も見られるような人はさらにそのうちのごく僅かな人々である。こうした中でも諱が同じ、生きた地域が同じ、関わった人が共通するなど、偶然にも同じ「ような」姿で見える人々もいる。ただし、彼らが本当に同一人物であるかは厳密な考証が必要になるであろうし、矛盾が生じればそれは間違いなく別人であろう。矛盾が解決されれば同一人物である可能性はまた復活し、別の視点での考証が必要になる。人物だけではなく漢文の誤読による矛盾も然り。ところが、現状では矛盾が解決されないままに通説化され、それを無批判に受け入れた説が再生産されていることが間々見られる。「通説」とは「事実」ではなく、矛盾を解決する常に考証することこそ必要なのではないだろうか。
佐竹義業 +―佐竹義政
(進士判官代) |(太郎)
∥ |
∥――――――佐竹昌義――+―佐竹義宗
∥ (相模三郎) |(三郎)
∥ |
多気繁幹―+―吉田清幹―+―女子 +―佐竹隆義―――佐竹秀義
(太郎) |(多気権守)| |(四郎) (太郎)
| | |
| +―鹿嶋成幹―――鹿嶋政幹 +―佐竹義季
| (三郎) (三郎) (蔵人)
|
+―多気致幹―+――――――――多気直幹
|(多気権守)| (平太)
| ? ∥
| +―――女子 ∥―――――+―多気義幹
| ∥ ∥ |(太郎)
| ∥ ∥ |
| ∥ ∥ +―馬場資幹
| ∥ ∥ |(小次郎)
| ∥ ∥ |
| ∥ ∥ +―下妻広幹
| ∥ ∥ |(四郎)
| ∥ ∥ |
| ∥ ∥ +―東条忠幹
| ∥ ∥ |(五郎)
| ∥ ∥ |
| ∥ +―女子 +―真壁長幹
| ∥ ? (六郎)
+―石毛政幹―――女子∥ |
(荒四郎) ∥ ∥―?+―千葉介常胤―――千葉介胤正
∥―∥―?―(下総権介) (千葉介)
∥ ∥
千葉常兼―――千葉介常重
(千葉大夫) (下総権介)
この頼朝と佐竹氏の合戦は12月3日頃に「上野常陸等之辺、乖頼朝之輩出来」(『玉葉』治承四年十二月三日条)という情報として兼実に届いている。
上野国の「乖頼朝之輩」とは、頼朝挙兵の報を受けた前右大将宗盛の命によって上野国へ下向した新田大炊助義重入道上西がその一人であろう(『山槐記』治承四年九月七日条)。上野国に下った義重入道は、東国が様々な勢力が入り乱れて統一されていない現実を見て「以故陸奥守嫡孫」という血筋を以って自立を志したようである(『吾妻鏡』治承四年九月三十日条)。義重入道は頼朝からの書状を無視し、却って寺尾城(高崎市寺尾町)に拠って軍兵を集めた。ところが、頼朝は瞬く間に安房、上総、下総を皮切りに武蔵国の秩父党をもその麾下に組み込み、義重入道と対立関係にあった下野の足利俊綱が頼朝に下り、義重入道の周りは確実に埋められていた。ついに義重入道は頼朝の召しに応じて鎌倉の玄関口である山ノ内に参着するも入境は許されず、漸く12月22日、鎌倉へ参上して頼朝と面会した(『吾妻鏡』治承四年十二月廿二日条)。予て義重入道が兵を集めて上野国寺尾館に立て籠もったという風聞を受け、頼朝は藤九郎盛長を使者として義重入道に遣わし子細を尋ねたところ「心中更雖不存異儀、国土有闘戦之時、輙難出城之由、家人等依加諌、猶豫之處、今已預此命、大恐畏」と述べたため、藤九郎盛長は義重入道の言い分を「殊執申之」し、頼朝も義重入道を赦し、鎌倉召喚をしたものであった。
11月8日、「被収公秀義領所常陸国奥七郡并太田、糟田、酒出等所々、被宛行軍士之勲功賞」と、常陸国奥七郡のほか太田、糟田、酒出等を勲功賞として常陸攻めの人々へ宛がわれた(『吾妻鏡』治承四年十一月八日条)。その後、鎌倉への帰還の途につき、路次にある小栗十郎重成の「小栗御厨八田館(筑西市八田)」に入御している。
11月10日、頼朝は下総国葛西庄(葛飾区葛西)の葛西三郎清重邸に止宿している(『吾妻鏡』治承四年十一月十日条)。ここで清重へ武蔵国丸子庄が下された。ここで2日ほど逗留し、11月12日に武蔵国へ入った。ここで頼朝は萩野五郎俊重を斬罪に処した(『吾妻鏡』治承四年十一月十二日条)。これまで頼朝に従属して功績も挙げていたようだが、かつて石橋山合戦で大庭三郎景親に属して頼朝に弓引いた恨みがあったとみられ、「日者候御共雖似有其功、石橋合戦之時令同意景親、殊現無道之間、今不被糺先非者、依難懲後輩如此」(『吾妻鏡』治承四年十一月十二日条)という。
そして11月17日、頼朝は鎌倉へ帰着。和田小太郎義盛を侍所別当に補した。これは「是去八月石橋合戦之後、令赴安房国給之時、御安否未定之處、義盛望申此職之間、有御許諾、仍今閣上首、被仰」(『吾妻鏡』治承四年十一月十七日条)ものであった。頼朝の家人・郎従を管理する秘書官的な職務である。「侍所」は頼朝に伺候する家人・郎従の着到や行動を管理する秘書官的な職務である。この逸話は『平家物語』の中でも見られるが、「上総守忠清カ平家ヨリ八ヶ国ノ侍ノ別当ヲ給」たことを侍別当を望む理由に出している。建仁3(1203)年には「遠州侍所」(『吾妻鏡』建仁三年九月四日条)、鎌倉末から建武期の千葉家には「千葉侍所」(「悟円書状」『金澤文庫文書』)など、有力武家には被官を管理する部門である侍所が設けられており、義盛が望んだのはこうした秘書官的立場であった。
そして、12月12日、頼朝の鎌倉における新造の屋敷が落成し、それまで住んでいた上総介八郎広常の屋敷から移ることとなった。その供奉に千葉介常胤、胤正、胤頼が随っている。胤頼は常胤の六男にも関わらず、嫡子の胤正とともに栄誉に浴しており、ほかの兄たちと比べて優遇されていることがわかる。頼朝の挙兵を影から支えていたと思われることや、位階を得ていることなどがあるのだろう。新造の大倉邸には十八間の侍所が設けられ、北条時政以下の諸将が二列に並び、その数三百十一人であったという(『吾妻鏡』治承四年十二月十二日条)。
■治承4(1180)年12月12日渡御(『吾妻鏡』)
| 先陣 | 和田小太郎義盛 | ||||
| 駕左 | 加々美次郎長清 | ||||
| 駕右 | 毛呂冠者季光 | ||||
| 扈従 | 北条四郎時政 | 江間小四郎義時 | 足利冠者義兼 | 山名冠者義範 | 千葉介常胤 |
| 千葉太郎胤正 | 千葉六郎大夫胤頼 | 藤九郎盛長 | 土肥次郎実平 | 岡崎四郎義実 | |
| 工藤庄司景光 | 宇佐見三郎助茂 | 土屋三郎宗遠 | 佐々木太郎定綱 | 佐々木三郎盛綱 | |
| 後陣 | 畠山次郎重忠 | ||||
治承5(1181)年正月1日、頼朝は鶴岡若宮を参詣した。これを先例とし、鎌倉時代を通じて元旦をもって奉幣の日と定められる。この時は三浦介義澄、畠山次郎重忠、大庭平太景義が郎従を率いて辻を警護している。その後、頼朝は騎馬で到着し、神馬一疋を宇佐美三郎祐茂、仁田四郎忠常が曳いて奉納し、法華経供養と説教を聞いた後、屋敷へ帰還した。参詣ののち、千葉介常胤が椀飯を献じている。その後、次第に大規模で形式が固まっていく元旦参詣だが、この時は大変おおらかな雰囲気が感じられる。
2月1日には京都に頼朝の常陸攻めが届いている。それによれば「常陸国勇士等、乖頼朝了、仍欲伐之處、還散々被射散了、此由飛脚到来、今明被遣官兵者、自彼可攻之由申上」(『玉葉』治承五年二月二日条)という。「常陸国勇士等」とは佐竹氏とみられるが、彼らは「乖頼朝」いて凶賊頼朝を討たんとしたが、却って散々に打ち負かされたという。これについては「但実否難知歟」と記すが、翌々日2月3日には続報として「頼朝寄攻常陸国之間、始一両度雖被追帰、遂伐平了」(『玉葉』治承五年二月三日条)を得ている。当初の打ち破られた佐竹勢からの使者の申上(自彼国上洛之者説)は、今明の官兵派遣がされれば頼朝勢を討つとのものであったが、3日の続報は「常陸国」へ攻め寄せた頼朝に、佐竹勢は数度追い返されるなど不利な立場にあったが、ついに頼朝勢を討伐したというものであった。兼実のもとには「縦横之説、随聞及注之、但於事外之浮説者、不能注、遂可見虚実歟」といくつもの情報が届けられ、情報を取捨選択しながら虚実の判断を行っていた。佐竹氏は頼朝に敗れた際に「官兵」と協力して攻めることを申上しており、おそらく国府は機能し続けていたと考えられる。
京都への報告の時期からして、この頼朝の二度目の常陸攻めは治承5(1181)年正月中のことであったことが推測できる。『吾妻鏡』では治承5(1181)年は正月24日以降の日記はなく、此の後の事であろうか。兼実はこの合戦の情報が実否か知り難いとしているが、「自彼国上洛之者説(常陸佐竹氏の使者であろう)」であることからこの戦闘は事実であろう。当時の常陸国司は、治承3(1179)年11月18日の除目で「常陸介平宗実」(『玉葉』治承三年十一月十八日条)とあり、平重盛の末子・十四歳の平宗実であった。知行国主は養父・左大臣藤原経宗であることから、目代も経宗の関係者であろう。経宗は平家と協調関係にありつつも後白河院に非常に近く(血統上も八歳違いの従兄である)、常陸国は院に近い体制が敷かれていたと思われる。朝廷にとって頼朝は「凶徒」「凶賊」であり、国衙が平家党佐竹氏と協調して「凶徒」頼朝と対峙することは当然のことであった。しかしながら、頼朝が後白河院を蔑ろにすることは考えにくく、常陸国府を占拠することはなかったのではあるまいか。
4月20日には「或人」の下人が「自常陸国、有上洛」し、翌21日に「或人」が兼実に常陸国の状況を話している(『玉葉』治承五年四月廿一日条)。この「或人」は常陸国知行国主の左府経宗かもしれない。この下人は「四十余日、遂前途、廻北陸道入洛」(『玉葉』治承五年四月廿一日条)と、東海道を経由して上洛することが叶わず、常陸国から北陸道を経由する形で四十余日かけて入洛したという。彼が語るには、「秀衡已没之由無実也」と、「頼朝可娶秀衡娘之由、相互雖成約諾、未遂其事」と、「凡関東諸国、一人而無乖頼朝旨者、佐竹之一党三千余騎、引籠常陸国、依思其名、一矢可射之由令存」ということが語られ、「其外一切無異途」であるという。これは2月下旬から3月上旬頃の常陸国府の情報であり、秀衡の死を否定するなど信憑性は高いだろう。ということは、頼朝と秀衡女子との間で縁談が進められていることもまた事実だったのではなかろうか(当然『吾妻鏡』で記されない部分である)。そして佐竹氏は頼朝の鎌倉帰還後も抵抗を続けていた様子がうかがえる。
その後、平清盛入道は威信をかけて造営した福原京を廃して、京への還都を決断。これをきっかけに平家政権と敵対する勢力への本格的な軍事行動を開始する。
治承4(1180)年11月21日、「近江国又以属逆賊了、前幕下之郎従、下向伊勢国之間、於勢多及野地等之辺、昨今両日之間、十余人梟首了、其中有飛騨守景家彼家後見、優勢武勇者也、姪男、彼伐了云々、甲賀入道年来住彼国源氏之一族云々、幷山下兵衛尉同源氏云々等、為張本」とあり、前右大将宗盛の後見・飛騨守藤原景家の甥を含む郎従らが、所用で伊勢国へ赴く途次、瀬田付近で何者かに襲われて十余人が梟首されるという事件が起こった(『玉葉』治承四年十一月廿一日条)。
宗盛家人を討った犯人は、近江国甲賀郡に勢力を持つ「甲賀入道(義兼法師)」「山下兵衛尉(義経)」であった。甲賀入道は甲賀郡柏木御厨一帯(甲賀市水口町柏木)を、山下兵衛尉は山本郷(東近江市五個荘山本町)を支配する源氏の兄弟であり、その支配領域が京都から伊勢・伊賀へ通じる要衝であることから、彼らの反旗は平家にとって本拠の伊勢・伊賀との経路が遮断されることを意味し、ただちに行動に移したのであろう。「柏木入道法師兄弟在三井、為房覚弟子、同可召進之由、可仰長吏房覚者」(『吉記』治承四年十一月廿九日条)とある通り、甲賀入道と山下兵衛尉は園城寺長吏房覚の弟子であり、甲賀郡一帯は甲賀入道らの祖・新羅三郎義光以来、園城寺との関わりが非常に深かったことが知られる。
平家方は12月1日、伊賀国の平家家人「平田入道(平家継)」が近江国へ進行して甲賀入道を城から追い落とし、翌2日、平家政権は近江国、伊賀国、伊勢国の反平家勢力を駆逐するべく追討使(近江国大将軍:知盛卿、伊賀国大将軍:少将資盛、伊勢国大将軍:伊勢守清綱)が派遣され、翌3日早朝には、近江国の叛乱勢力を追捕している(『玉葉』治承四年十二月三日条)。
しかし、延暦寺もこの近江国の叛乱に敏感に反応し、12月1日には「山大衆三方相分了」とあるように延暦寺も平家に属する者、座主七宮を擁して中立の立場を取る者、近江源氏を支える者の三勢力に分裂している。その後、平家方の攻勢によって「江州武士等併落了」となり、延暦寺の三分の二が平家方に属したが、残りの三分の一は「其残引籠城」と近江源氏勢を支えたという(『玉葉』治承四年十二月四日条)。
ところが、12月9日には甲賀入道と山下兵衛尉義経が「延暦寺衆徒之中、凶悪之堂衆三四百人許」とともに、「以園城寺為城、六波羅可入夜打、又所進向近江国之官軍等、塞其後、自東西可攻落之由、成結構」と反撃の様相を呈した(『玉葉』治承四年十二月九日条)。これにより、平家は「清房禅門息、淡路守」を園城寺へと派遣。12日夜、官兵は園城寺へと攻め込み、敗れた園城寺大衆は山下兵衛尉らと合流した(『玉葉』治承四年十二月十二日条)。そして翌13日、「知盛、資盛等」は「甲賀入道並山下兵衛尉義経等、徒党千余騎」の籠もる「馬淵城(近江八幡市馬淵町)」(『山槐記』治承四年十二月十三日条)を攻落し、二百余人を梟首、四十余人を捕らえたという(『玉葉』治承四年十二月十五日条)。その落城後、「甲賀入道、山下兵衛尉」は近接の山下城へ逃れ、翌16日には官兵が「近江山下城」を攻撃している。山下城は急峻な山上に築かれており、官兵は攻めあぐね、23日「維盛朝臣為副将軍、下向近江国」という措置がとられている。そして翌24日には、山下城の甲賀入道らに「尾張美濃等武士、欲相加彼」という伝聞が京都へ齎される(『玉葉』治承四年十二月廿四日条)。なお、『吾妻鏡』によれば近江を逃れた「山本兵衛尉義経」は12月10日に鎌倉に参着し、土肥実平の案内で頼朝と面会したという記録もあるが(『吾妻鏡』治承四年十二月十日条)、当時の山下義経は兄・柏木甲賀入道とともに平家と戦っており、この『吾妻鏡』の記述は本来異なる時期の記事が混入されたものであろう。
また、平家政権は12月25日、「蔵人頭重衡朝臣」を大将軍とした南都の追討軍を派遣。25日夜は「宿宇治」(『山槐記』治承四年十二月廿五日条)、26日に「南都追討使、今日経廻宇縣」(『玉葉』治承四年十二月廿六日条)とあるように宇治に逗留した。これは「依雨雪」ためであった(『山槐記』治承四年十二月廿六日条)。27日には「自河内地方、被寄官兵之間、為大衆被射危、三十余人被射取了、其後被追帰了」(『玉葉』治承四年十二月廿七日条)とあるが、「南都追討使重衡朝臣宿狛、先陣阿波国住人民部大夫成良、軍兵向泉木津為一陣、与衆徒合戦、矢放一両、依日暮不戦」(『山槐記』治承四年十二月廿七日条)とあり、重衡の先陣として阿波民部成良の一軍が木津川を渡った泉木津で南都衆徒と合戦したことがわかる。
そして28日夜、「重衡朝臣寄南都、其勢依莫大、忽不能合戦云々、狛川原之辺在家併焼払、或又欲焼光明山」(『玉葉』治承四年十二月廿八日条)と、奈良に攻め寄せた。これにより興福寺や東大寺以下の堂宇伽藍がほぼ焼失し、東大寺は大仏殿に引火して大仏の頭が溶け落ちる事態となり、九条兼実は「七大寺、悉灰燼之条、為世為民仏法王法滅尽了歟、凡非言語道之所及、非筆端之可記」と嘆いている(『玉葉』治承四年十二月廿九日条)。
このような中、治承5(1181)年正月14日、高倉院は二十一歳で崩じた(『玉葉』治承五年正月十四日条)。高倉院政はここに終わり、平家にとっては鬼門である一院後白河が復帰することで、後白河院はふたたび治天として君臨することとなる。
平家政権側は一定の軍権を確保し、畿内を襲った飢饉の中での兵糧米の確保と近畿一帯を守衛するために「故院被仰置」いた「五畿内及近江伊賀伊勢丹波等国可被補武士、以禦遠国之凶徒之由」を実行するべく「件等国、総而可被置管領之司」(『玉葉』治承五年正月十六日条)を決し、宣旨を求めた。これにより「前大将平朝臣(宗盛)」に対して「為五畿内及伊賀伊勢近江丹波等総官之由」の宣旨が下され(『玉葉』治承五年正月十九日条)、畿内五か国および伊賀国・伊勢国・近江国・丹波国の権限を平宗盛が差配(畿内惣官)することとなった。「惣官(総管)」は「総而可被置管領之司」(『玉葉』治承五年正月十六日条)の略称であろう。近江国の甲賀入道らの執拗な叛乱、尾張国から美濃国を窺う「謀叛賊源義俊為義子、号十郎蔵人」の軍勢、駿河国、遠江国を抑える武田信義・安田義定、坂東に控える源頼朝勢など源氏の勢力が畿内を窺うまでに伸張していたことに平家政権が大きな危機意識を持ったことがわかる。
2月8日、前越中守平朝臣盛俊を以て「丹波国諸庄薗総下司」とする宣旨が下った(『玉葉』治承五年二月八日条)。これは宗盛の五畿内等総官の宣旨に基づくもので、庄園からの兵糧米等の徴収権を盛俊が得たものだろう。
翌2月9日、「関東反賊等及半、越来尾張国、以十郎蔵人義俊、為大将軍云々、其勢不知幾千万」という風聞が流れた(『玉葉』治承五年二月九日条)。実際に尾張国に侵攻した「十郎蔵人義俊(行家)」は頼朝が派遣した大将軍ではなかったが、京都では同一視されていたことがわかる。常陸国府で頼朝と対面した後、行家は独自の軍勢を募り、おそらく東山道を西へ侵攻したと思われる。
こうした源氏諸勢力の伸張に対し、2月26日、「俄前将軍宗盛已下、一族武士、大略可下向来月六七日之比」という前将軍宗盛を大将とする追討使の派遣が決定され、さらに鎮西へ下向する予定であった蔵人頭重衡の下向も停止された。これは追討使に勇名高い重衡も加えられたことを意味するものであろう(『玉葉』治承五年二月廿六日条)。この事態に対応するべく、すでに美濃国には平家与党が派遣されていて、「尾張之賊徒等、少々越来美乃国、射散阿波民部重良之徒党、相互被疵之者有数、官軍方、有云池田太郎之者、捕件者、乍生持去了」とあるように、「十郎蔵人義俊」らとの戦いが起こっていた(『玉葉』治承五年二月廿九日条)。
ところが、閏2月1日、九州の賊徒討伐のために派遣されていた「筑後国司貞能」から「兵粮米已尽了、於今者無計略」という悲観的な文書が届いた(『玉葉』治承五年閏二月一日条)。「在美乃追討使等、一切無粮料之間、可及餓死」(『玉葉』治承五年閏二月三日条)というように、東へ向った追討使もすでに兵糧がなく、官軍は東西ともに「天下飢饉」のために兵糧を失った状態で駐屯していた。こうした状況に宗盛は「為総攻、前幕下俄欲下向」と下向を決意するが、「依禅門之病、後了」と出兵は見送りとなってしまう(『玉葉』治承五年閏二月三日条)。
閏2月4日朝、清盛入道は円実法眼を通じて「愚僧早世之後、万事仰付宗盛了、毎時仰合、可被計行也」と、宗盛を後継者と定め、万事を宗盛と相談して計るよう後白河院に奏上している(『玉葉』治承五年閏二月五日条)。ところが、後白河院は「勅答不詳」と明確に返答せず、清盛入道は「爰禅門有含怨之色」と怒り、左少弁行隆を召して「天下事、偏前幕下之最也、不可有異論」と後白河院を恫喝するに至った(『玉葉』治承五年閏二月五日条)。そしてその日のうちに「禅門薨去」した(『玉葉』治承五年閏二月四日条)。
平家と政権を強力に牽引し、老獪な後白河院とも渡りあった実力者・平清盛の薨去は、その後、実権を取り戻すことになる後白河院の暗躍と源氏諸勢力の勢力伸張により、平家は瞬く間に凋落してゆくこととなる。
閏2月6日、院において関東乱逆への対応についての詮議が行われたが、ここに出席した宗盛は、後白河院に「故入道所行等、雖有不叶愚意之事等、不能諌争、只守彼命、所罷過也、於今者、万事偏以院宣之趣、可存行候」と父清盛入道の意に逆らえなかったことを陳謝し、今後は後白河院の意に従う旨を公にした。これは清盛入道が死の直前に後白河院へ放った「天下事、偏前幕下之最也、不可有異論」という恫喝を全否定するものであった。その上で「先関東兵粮已尽、無力征伐、如故入道之沙汰者、西海北陸道等運上物、併点定、可宛彼粮米云々、此条又何様可候哉、若有可彼宥行之儀者、可被計仰下歟、又猶可被追討者、可存其旨、召公卿等於院、僉議之後、奉一決之趣、可進退也」と、故清盛入道の沙汰通りに西国や北陸道の運上物を兵糧米に宛てるかどうか、さらに和睦か追討かの「詮議」を院に委ね、その結果をもってどのようにするか決める旨を伝えたのである(『玉葉』治承五年閏二月六日条)。これを受けて7日早朝、院で詮議が行われた結果「大略、暫休征伐、先以院宣可被宥之儀候歟」(『玉葉』治承五年閏二月七日条)と、飢饉等による影響も鑑みて宥和が大勢を占め、院議定は院宣を以て追討を中断することとされた。
院は詮議一決を受けて、側近の静賢法印を宗盛のもとに遣わし、宗盛邸門外で宗盛近臣・能円法師を通じて宗盛へ院議定の内容を伝達した。宗盛はすぐに返奏するが、そこには「猶於重衡者、来十日一定可下遣也」と記され、重衡を東国追討使として尾張国へ下向させることはすでに決定した事案だとして譲らず、さらに「然者、東国勇士等、乖頼朝、可随重衡之由、可載院宣者」と、院宣の文言に「頼朝に背いて重衡に従え」という一文を加えろという要求までしたのである(『玉葉』治承五年閏二月七日条)。
さすがの静賢法印も「若為此儀者、被遣院宣無益、只一向不可変征伐之儀事歟、素付令申給之状、已有群議、今被報奏之旨、依違了、何様可候哉」と抗議したところ、宗盛も「招頼盛、教盛等卿相議、重可令申」と、頼盛、教盛らを招いて相談の上、重ねて返答することを告げた(『玉葉』治承五年閏二月七日条)。
しかし、結局宗盛は折れず、閏2月9日、大納言隆季、中納言忠親ら院司によって作成された院庁下文には「東国勇士等、乖頼朝、可随重衡之由」が載せられたとみられ、この院庁下文を見た後白河院は自身の意向が無視され激怒したのだろう。院はこの内容を「不可然」としたが、再度意向は無視され、宗盛に院宣が下賜された。故清盛入道は「我子孫、雖一人生残者、可曝骸於頼朝之前」という遺言を残しており、宗盛は「然者、亡父之誡、不可不用、仍於此條者、雖為勅命、難申者也」と、頼朝との戦いにおいては、故清盛入道の遺言が後白河院の勅命に優先すると宣言している(『玉葉』養和元年八月一日条)。
宗盛は院議定の内容を無視して源氏勢力の追討を継続するが、これはあくまで「追討之間事、偏大将軍之最也」(『玉葉』治承五年八月六日条)、「仍於此條者、雖為勅命、難申者也」(『玉葉』養和元年八月一日条)とある通り、軍事に関する事項に限っては宗盛の管轄であると認められていたことが窺える。宗盛が後白河院へ示した「僉議之後、奉一決之趣、可進退也」(『玉葉』治承五年閏二月六日条)は、あくまで院御所での院・公卿による議定を要請したもので、その報告を踏まえて軍権を掌握する宗盛が和睦か追討かの最終決断を行い、それに基づいた院宣を乞うというものであった。
結局、重衡を大将軍とする追討使の派遣が決定され、閏2月10日早朝に「検非違使景高」が尾張国へ出立(『玉葉』治承五年閏二月十日条)、五日後の15日、「追討使蔵人頭正四位下平重衡朝臣」が一万三千余騎を率い、院宣を帯して京都を出立した(『玉葉』治承五年閏二月十五日条)。重衡に随ったのは、「左少将維盛朝臣、越前守通盛朝臣、薩摩守忠度朝臣、参河守知度、讃岐守左衛門尉盛綱號高橋、左兵衛尉盛久等」であった(『吾妻鏡』治承五年三月十日条)。
京都を出立した重衡は、宇治を経て、「十郎蔵人行家本名義俊」鎮撫のために尾張国へ進み、3月10日、墨俣川で五千余騎の「賊党等千余人被梟首、其後三百余人溺河水亡滅了」という戦果を挙げる(『玉葉』治承五年三月十三日条)。
●墨俣合戦の戦果(『吉記』治承五年三月十三日条)
| 将軍 | 首級 | 討たれた源氏方大将軍 |
| 頭亮(蔵人頭重衡) | 二百十三人(生捕八人) | 和泉太郎重満(重衡方の左兵衛尉平盛久が討つ) 同弟高田太郎(盛久郎等が討つ) |
| 越前守(越前守通盛) | 六十七人 | |
| 権亮(前春宮権亮維盛) | 七十四人 | |
| 薩摩守(薩摩守忠度) | 二十一人 | 十郎蔵人息字二郎 |
| 参河守(三河守知度) | 八人 | |
| 讃岐守(讃岐守高橋盛綱):重衡支配 | 七人 | 蔵人弟悪禅師(実際は甥の円済:義円) |
| 以上 | 三百九十人(うち源氏方大将軍四人) |
この合戦で「蔵人次郎為忠度被生虜、泉太郎、同弟次郎被討取于盛久」とあるように、行家の子息・蔵人次郎光家、泉太郎重光らが捕殺され(『吾妻鏡』治承五年三月十日条)、十郎蔵人行家は「被疵入河了」と、負傷して川に流されたことが記される。『吉記』によれば、泉太郎と弟次郎の兄弟は、重衡に属していた左兵衛尉平盛久の手によって討たれたことがうかがえる(『吉記』治承五年三月十三日条)。また、行家の陣中には、頼朝の義弟「僧義円號卿公」がいたとされ、この合戦で高橋盛綱に討たれたという(『吾妻鏡』治承五年三月十日条)。彼に相当するのが「蔵人弟悪禅師」であり、重衡支配の讃岐守高橋盛綱によって討たれたことがわかる(『吉記』治承五年三月十三日条)。なお、「蔵人弟」とある部分は実際は甥であるが、彼らの年齢はそれほど離れておらず、陣中では弟として遇されていたのかも知れない。また、光家については実際は生存しており、その後、義経とともに検非違使となっている。
重衡らはさらに墨俣川を渡って行家残党を追撃し、数か月にわたり官軍を苦しめてきた尾張国の源氏勢力は壊滅した。そして重衡は3月25日夜半、京都へ無事帰還する(『玉葉』治承五年三月廿六日条)。
一方、院政を復活させた後白河院は、軍権は持たないものの、政治的な行動や人事を積極的に行い、一度は壊滅してしまった政治基盤の再構築を図り始める。まず行ったのは、故清盛入道がほぼ強奪の形で西八條の平頼盛邸に移していた安徳天皇の閑院御所(中京区押西洞院町)への行幸であった(『吉記』治承五年四月十日条)。八條御所は諸司の邸から遠く役人の遅延が頻発して大変評判が悪く、閑院への遷皇居は「天下上下皆以悦予、尤可謂善政歟」とも評された(『吉記』治承五年四月十日条)。これはまず主上を平家西八條邸から引き離し、王家所縁の閑院へ新造内裏に擬して遷幸することが目的であったと考えられる。
関東では、墨俣合戦と同時期の治承5(1181)年3月27日、下総国の豪族・片岡次郎常春に謀叛の風説があり、頼朝は雑色を「彼領所下総国」に遣わして常春を召した所、常春は「称乱入領内、乃傷御使面縛」という狼藉を働いたという(『吾妻鏡』治承五年三月廿七日条)。頼朝は常春の所領を没収した上、早々に雑色を解き放し返すことを命じている。
常春の謀叛の伝とは「片岡八郎常春同心佐竹太郎常春舅」というもので、頼朝に殺害された佐竹太郎(忠義)の女婿であったことを理由に謀叛したと記されたものであろう。常春が「被召放領所」は「下総国三崎庄、舟木、横根」であったが(『吾妻鏡』文治五年三月十日条)、三崎庄は治承4(1180)年5月11日、皇嘉門院から猶子の権中納言良通(九条兼実長男)へ伝領した「しもふさ みさき」(『皇嘉門院惣処分状』「平安遺文」3913)で、常春はおそらくその荘官であり、勅勘の流人で「凶賊」源頼朝に膝を屈する理由などなく、その「逆賊」の雑色が三崎庄に入れば、常春がこれを面縛するのは当然の成り行きであったろう。このように当時の頼朝は公的には流人であって、実際には彼に随わない権門庄園の荘官や地頭、国衙在庁などの諸勢力は関東各地に存在していたと考えられる。
さて、墨俣合戦で大敗を喫したのち、三河国に隠遁していた十郎蔵人行家は5月19日、「参河国御目代大中臣以通」を通じて、伊勢内外二宮に「密勒告文、相副幣物等」して平家追討の祈祷を依頼した。なお「参河国御目代」は三河守知度の目代ではなく、三河国に数多く存在した神宮領を管轄する「神目代」である。しかしこの行家の祈祷願も5月29日、内宮権神主から峻拒の返状が届けられている。このように、当時にあっては頼朝はもちろん、その他の源氏諸勢力はあくまで「逆賊」であって、その基盤は甚だ不安定であったことがわかる。実権威に担保されない集団である頼朝党は、わずかなきっかけで崩壊する危険性があったのである。これを防ぐため、頼朝は「至干東国者、諸国一同庄公皆可為御沙汰之旨 親王宣旨状明鏡也者」(『吾妻鏡』治承四年八月十九日条)とあるように、自身の東国支配の根拠を以仁王の「最勝王宣」に据え、その影響力を担保として勢力を維持したのであろう。
6月13日から14日、「越後国勇士、城太郎助永弟助職、国人号白川御館云々、欲追討信濃国、依故禅門前幕下等命也」(『玉葉』治承五年七月一日条)と、宗盛の命を受けた越後平氏の城太郎助永・助職兄弟が「数万余騎」を率いて信濃源氏追討のために信濃国に攻め入った。彼らは蒲原郡白川庄(阿賀野市)から阿賀川上流の藍津(会津若松市)周辺を勢力下に収める強大な一族で、信濃川・千曲川流域に沿って信濃国に入ったと思われる。
越後平氏勢は抵抗を受けることなく進軍するが、「疲嶮岨之軍旅等」となっていた。こうした状況の中で「信濃源氏等、分三手、キソ党一手、サコ党一手、甲斐国武田之党一手、俄作時攻襲之」ことから、千曲川北岸の横田河原(千曲市大字雨宮)で越後平氏勢は「不及射一矢、散々敗乱了」と大敗を喫し、城助職は甲冑を脱ぎ捨てて越後へ逃れ、多くの兵士が斃れた(『玉葉』治承五年七月一日、二日条)。なお、木曽義仲は約半年前に上野国西部から信濃国へ戻っており、佐久平から上田盆地あたりに駐屯していたと思われ、ここで佐久党、南部の甲斐武田党と連携したと考えられよう。なお、甲斐武田氏はこの頃は木曽義仲と連携して平家党と戦っていたことがうかがえ、ここからも治承5(1181)年当時の甲斐源氏は頼朝に従属する存在ではなかったことがわかる。
ただ、越後へ逃れたとはいえ、城助職の勢力は「勢又強不減」(『玉葉』治承五年七月廿二日条)とある通り、いまだ強勢を保ち、信濃源氏等は越後国へ攻め入ることができずにいたという。しかし、この頃「越中、加賀等国人等、同意東国、漸及越前」と、北陸道の国人らが源氏に呼応したという風聞が京都に届いており(『玉葉』治承五年七月十七日条)、能登国では国司教経の目代の逃亡も伝えられている(『玉葉』治承五年七月廿四日条)。当時の木曽義仲が越後国を経ずに北陸方面へこれを受けて、越前守平通盛を大将軍とした追討使の派遣が決定することとなる(『玉葉』治承五年七月十八日条)。
このような中、頼朝は密かに後白河院へ奏状し、その中で「全無謀叛之心、偏為伐君之御敵也、而若猶不可被滅亡平家者、如古昔、源氏平氏相並、可召仕也、関東為源氏之進止、海西為平氏之任意、共於国宰者、自上可被補、只為鎮東西之乱、被仰付両氏天、蹔可有御試也、且両氏執守王化、誰恐君命哉、尤可御覧両人之翔也」と述べたという(『玉葉』治承五年八月一日条)。後白河院は内々に宗盛へ頼朝との和平案について伝えたが、宗盛は「此儀尤然可」と一応の賛意を述べながらも、故清盛入道が「我子孫、雖一人生残者、可曝骸於頼朝之前」という遺言を残していたことを述べて、「然者、亡父之誡、不可不用、仍於此條者、雖為勅命難申者也」と拒絶したのである(『玉葉』治承五年八月一日条)。宗盛は諸方の叛乱と飢饉の対応がとても厳しい状況にあり、和平案は大変魅力的なものであったと考えられる。宗盛自身は頼朝との個人的関係は皆無であることから怨恨は深いものではなかったろう。しかし、宗盛はこれを拒絶してしまう。後白河院という稀有の策士からの提言ということもあろうが、清盛入道生前からその言葉は勅命に勝ると考えていたことを考えると、故清盛入道の呪縛から脱しきれなかった宗盛の素直な善人性がうかがえるのである。
このころの平家はすでに「前幕下、其勢逐日減少、諸国武士等、敢不参洛」という状況であり(『玉葉』治承五年八月一日条)、「貞能、鎮西下向必定」という情報を聞いた九条兼実は「大略逃儲之料者」と予想している。
宗盛は戦況打開のための策を練り上げて、後白河院に「関東賊徒猶未及追討、余勢強大之故也、以京都官兵、輙難攻落歟、仍以陸奥住人秀平可被任彼国史判之由」を奏上。すでに「件国素大略虜掠、然者拝任何事之有哉、如何」という理由によるものであった。さらに「越後国住人平助成、依宣旨向信濃国、依勢少軍敗者、全非過怠、志之所及、已不惜身命、忠節之至、頗可有恩賞歟」として、城助成(助職)を越後守に補するよう推薦している。
このことにつき、院は頭弁経房を兼実に遣わしてその意見を求めている(『玉葉』治承五年八月六日条)が、兼実は「追討之間事、偏大将軍之最也、而前大将被申計之趣、不可及異議」と賛成するが、補任等に関する意見は宗盛に批判的であった。しかし、結局宗盛の意見が通り、8月14日夜の除目で、「陸奥守藤原秀平、越前守平親房、越後守平助職」が決定することとなる(『玉葉』『吉記』養和元年八月十五日条)。
●治承五年八月十四日除目(『玉葉』『吉記』養和元年八月十五日条)
| 玉葉 | 吉記 |
| 陸奥守藤原秀平 | 陸奥国 守従五位下藤原朝臣秀衡 |
| 越前守平親房 | 越前国 守従五位下平朝臣親房 |
| 越後守平助職 | 越後国 守従五位下平朝臣助職 |
秀衡の陸奥守任官は、背後から東国を攻めることを期待したものである。なお、追討使として北陸攻めが決定している越前守平通盛を平親房に改める人事は、兼実も「不得心」と不審を持っている。親房は「基親息、前近江守」(『吉記』養和元年八月十五日条)であるように、武力を持たない堂上平氏であり、混乱の続く国の人事としては他の二例とは異なっている。親房は後白河院近臣であることから、実は越前国の混乱に紛れて後白河院が平家から越前国を再度奪取した人事だったのだろう。兼実の「不得心」は真実を知った上での曖昧な批判と考えられる。
藤原経清
(亘権守)
∥
∥―――――藤原清衡―――藤原基衡―――藤原秀衡
∥ (陸奥押領使)(陸奥押領使)(陸奥守)
安倍頼良――――女子
∥
∥―――――清原家衡
∥
清原武則――+―清原武貞
(鎮守府将軍)|(太郎)
|
+―清原武衡――女子
(将軍三郎) ∥――――――城助職
∥ (越後守)
城資国
(九郎)
8月15日と翌16日にかけて、北陸道追討使として「但馬守経正朝臣」と「中宮亮通盛朝臣」が京を進発し、通盛は越前国国府へと入府した。ところが、8月23日に加賀国から「賊徒乱入国中」し、大野坂北両郷を焼き払った(『吉記』養和元年九月一日条)。もはや北陸道は「北陸道賊徒熾盛、通盛朝臣、不能征伐、加賀以北越中国中、猶有不従命之族」(『玉葉』養和元年九月二日条)という状況になっていたが、9月6日、通盛は兵衛尉清家を大将軍とした一軍を加賀境まで派遣するが、清家に従っていた「当国住人新介実澄、前従儀師最明検非違使友実弟」らが寝返り、通盛の主だった郎従八十余人が討死を遂げて大敗を喫した。通盛は越前国府(越前市府中)にあったが、無勢で追加で出兵はできず「引退敦賀」いた(『吉記』養和元年九月十日条)。この敗報は兼実の元にも届いており、通盛が「津留賀城」まで退いたことが記される(『玉葉』養和元年九月十日条)。このとき通盛が戦ったのは、『吾妻鏡』によれば「木曽冠者為平家追討上洛、廻北陸道、而先陣根井太郎至越前国水津、与通盛朝臣従軍、已始合戦」(『吾妻鏡』養和元年九月四日条)とある通り、おそらく木曽義仲の軍勢であろう。勅命によって義仲を攻めんとしていた「越後守資永(助職)」は9月3日朝に急死しており(『吾妻鏡』養和元年九月三日条)、義仲の軍勢はすでに越後から加賀を経て越前方面まで展開していたことを物語る。
通盛は若狭国に駐屯していた但馬守平経正に援兵を要請するも、経正は若狭国に留まって兵を差し向けなかったことで通盛が大敗を喫したと噂されて、散々な評判であった(『玉葉』養和元年九月十二日条)。平家政権は北陸への援軍派遣を計画するも、兵力不足などから延引を繰り返す始末であり、単独で戦い続けた通盛もついに支えきれずに敦賀を撤退。11月21日、帰京した(『吉記』養和元年十一月廿一日条)。
しかし、諸方への兵力分散や「東国、北陸、共以強大、官軍旺弱」(『玉葉』治承五年九月廿日条)という中で、平家政権は「四方之賊勢甚強大、官軍非可敵対歟、若然者、奉具至尊時、山已下、為宗之臣下等、定令西行歟」(『玉葉』養和元年九月十六日条)という悲観論に包まれ、「君臣引率、可赴海西之由、已被一定了」(『玉葉』養和元年九月十九日条)と、平家政権は天皇、院を奉じ、主だった公卿を伴って西へ逃れることを決定したのである。宗盛は、もはや平家が以前のような政権を維持することは困難であると判断したことの表れであった。ただ西行は「忽不可然、関東已攻来之時、可有其儀」と、東国勢が明確に京都に攻め寄せた際に実行することとし、さらに宗盛は「不可知天下之事之由、令起請了」(『玉葉』養和元年九月廿九日条)た。宗盛が政権自体の放棄をおそらく後白河院に起請文で奉じたのであろう。さらに宗盛は9月28日、大外記頼業のもとに使者を送り「天下事、於今者、武力不可叶、可廻何計略哉」と相談している(『玉葉』養和元年九月卅日条)。今更ではあるが、宗盛は追討使による頼朝党の壊滅は無理であり、別の方法による鎮撫を図っていたことがわかる。
このような中、京都に「頼朝必定已企上洛」という報が届いた(『玉葉』治承五年十月廿七日条)。すでに10月21日には尾張国保野宿に到達しているといい、「竹園(以仁王)」は「上総国住人広常称介八郎」が守護し、相模国に留め置いているという報告ももたらされた(『玉葉』治承五年十月廿七日条)。源三位の乱では以仁王や源仲綱の首級が確認できず、彼らの生存は京都では実しやかに伝えられており、宗盛も「故頼政法師郎等弥太郎盛兼」や以仁王の側近であった「前少納言宗綱入道」を捕らえて以仁王の所在を尋問するほどであった(『吉記』養和元年九月廿一日条)。盛兼は「於前按察(源資賢入道)侍家」で襲撃を受けて自害、「前少納言宗綱入道」も「資賢卿之許」で逮捕された。いずれも源資賢入道と関わっているが、彼は後白河院の最側近であり、「前少納言宗綱入道」は「資賢卿聟」という関係にあった。頼政入道と以仁王の乱の背景に後白河院の「関わり」があったことは明白であろう。なお、余談だが後白河院と以仁王との関わりは公然の秘であったようで、のちに九条兼実は延暦寺円融房において、後白河院に「余奉問両条之不審、…、一者、三條宮存否事」と直聞している。結局後白河院は以仁王の存否については知らなかったようで、「両事共不知真偽、但風聞之旨、共以不実歟」(『玉葉』寿永二年七月廿六日条)と応えている。頼朝は東国支配の根拠を最勝親王(以仁王)の「親王宣旨」に置いて勢力を拡大しており、平家政権は自ら追討した以仁王の「幻影」によって追い詰められる事態となっていたのであった。
こうした平家政権の弱体化とは対照的に、法皇は「治承三年十一月政変」で故清盛入道に解官された院近臣の復権を謀っており、養和2(1182)年3月8日の除目で、藤原兼雅が権大納言へ、高階経泰が大蔵卿へそれぞれ還任し、「権大納言兼雅卿、権中納言実守卿、参議不被任、定能卿中将、光能卿右兵衛督、泰経朝臣大蔵卿等、皆以還任了、凡去治承三年解官人々、去冬今春除目、過半還補了歟」(『玉葉』養和二年三月八日条)と、院政体制の復活が着実に進められていた。宗盛はこの人事に困惑と怒りを覚えたとみられ、法皇に意見を奏上したようである。これに対して3月12日、法皇は近臣平親宗(宗盛には義叔父)を宗盛邸へ派遣したが、宗盛は親宗に会わず、人を介して「天下之乱、君之御政不当等、偏汝所為也」と親宗をなじり、故清盛入道が遺恨を伝えたときは院は直に報答したにも関わらず、宗盛に対しては「存尋常、万事如不存如不知、仍於事損面目、頗所恨申」と強く批判している(『玉葉』養和二年三月十二日条)。兼実は院使が宗盛邸に行った理由を「不知何事」と嘯いているが、治承三年解官の院近臣の巨魁を還任させた直後の批判であり、この除目に対する批判以外には考えられないだろう。
ただし、右府兼実は院を積極的に推してはおらず、東国追討には否定も肯定もしない立場であった。寿永元(1182)年7月13日、宗盛から大嘗会の年における追討は憚りがあるかどうかの問い合わせについては、「被罷征伐、可謂正道、但若可及大事者、又非此限者」と返答をしている(『玉葉』寿永元年七月十三日条)。この大嘗会に合わせ、8月14日、朝廷は後白河院の第一皇女・前斎宮亮子内親王を二条天皇皇后藤原多子の例に倣って立后し、安徳天皇の准母となった。これは以前から生母の建礼門院徳子の推挙により准母となっていた藤原通子(近衞基通妹)を廃し、亮子内親王を准母と定めたもので、天皇と平家の関わりを断たせるものであった。さらに亮子内親王は以仁王の同母姉であり、またその皇后宮職は亮子内親王の肉親や院近臣で固められた後白河院の意向が反映された人選となっている。
皇后宮(亮子内親王)職
| 大夫 | 正二位 | 藤原実房 | 亮子内親王又従兄弟。 |
| 権大夫 | 正三位 | 藤原実守 | 亮子内親王又従兄弟。 |
| 亮 | 正四位下 | 高階泰経 | 院近臣。 |
| 権亮 | 正五位下 | 藤原公衡 | 亮子内親王又従兄弟。 |
| 大進 | 正五位下 | 藤原親雅 | 皇后宮大夫実房妻の祖父経実(関白師実子)の義弟 |
| 権大進 | 正五位下 | 藤原定経 | 院近臣。治承三年政変で解官。 |
| 権大進 | 従五位下 | 藤原長経 | |
| 少進 | 従五位下 | 藤原家実 | |
| 権少進 | 正六位上 | 藤原光茂 | |
| 大属 | 従五位下 | 大江景宗 | 院近臣。後白河院庁主典代。 |
| 少属 | 正六位上 | 中原元康 | |
| 権少属 | 正六位上 | 中原清重 | 院近臣。 |
藤原公実―+―藤原季成―――藤原成子 +―亮子内親王
(権大納言)|(権大納言) ∥ |(皇后宮)
| ∥ |
+―藤原璋子 ∥――――――+―以仁王
|(待賢門院) ∥ (高倉宮)
| ∥ ∥
| ∥――――――後白河法皇
| ∥ ∥
| 鳥羽法皇 ∥――――――――二条院
| ∥ ∥
+―藤原公子 ∥ ∥
| ∥――――+―藤原懿子 +―藤原多子
| ∥ | |(大宮)
| ∥ | |
| ∥ | |【権大夫】
| 藤原経実 +―藤原経宗 +―藤原実守
|(大納言) (左大臣) |(権中納言)
| |
| |【権亮】
+―藤原実能―――藤原公能―――+―藤原公衡
|(左大臣) (右大臣) (右近衞権少将)
|
| 【大夫】
+―藤原実行―――藤原公教―――――藤原実房
(太政大臣) (内大臣) (左大臣)
∥
藤原師実―――藤原経実―――藤原経宗―――――女子
(関白) (大納言) (左大臣)
∥
+―女子
|
|【大進】
藤原親隆―+―藤原親雅
(参議) (参議)
ただ、院や朝廷にとっては平家のもつ軍事力のみが「賊」と対峙しうる唯一の軍事力であり、後白河院は院政という枠組みの中で、宗盛を政権の実務首班とし、各地で同時多発的に起こっている兵乱に対応する必要があると感じていたのではなかろうか。そのほか院は宗盛について、実務官を長く務めてきた経歴を評価していたと考えられ、寿永元(1181)年6月28日に摂政基通が辞して以降、闕となっていた内大臣に宗盛を当てることを決定する。内大臣は故清盛入道も任官した官であり、事実上の宗盛首班体制を確立させ、諸方に対応させることが目的であったのだろう。
ところが、当時の宗盛は散位であり、院は8月23日、その前段階として、まず宗盛を権大納言へ還任させる臨時除目を行うことを内々に命じ(『玉葉』寿永元年八月廿三日条)、9月4日、「前大納言兼右大将平宗盛」を権大納言へ任じた(『玉葉』『吉記』寿永元年九月四日条)。この宗盛を内大臣とすることを前提とした人事について、9月27日、大外記頼業が九条兼実邸を訪れて「任大臣事、大略ハ彼人滅亡在近之由」(『玉葉』寿永元年九月廿七日条)と述べており、不吉なものという認識があったことがわかる。
そして10月3日の除目で、権大納言末席だった宗盛は「超越上臈五人」(『公卿補任』)とあるように、藤原実定、源定房、藤原実房、藤原実国、藤原宗家の五人の正権大納言を超えて「内大臣」(『玉葉』寿永元年十月三日条)に任じられることとなる。これに留まらず、翌寿永2(1182)年正月21日には従一位へ昇叙され、摂政基通、左大臣経宗、右大臣兼実と並ぶ地位となる。後白河院の強力な引合だが、宗盛は2月17日夕方、皇后宮亮子内親王の入内を滞りなく済ませたのち、2月21日に安徳天皇の法住寺殿行幸を行い、六日後の2月27日に内大臣の上表を奉じた。
こうした中、兼実は4月13日に「武者郎従等、苅取近畠之間狼藉」と日記に記す(『玉葉』寿永二年四月十三日条)。翌14日にも兼実には同様な報告があったが、実際はここ数日にわたって兼実の耳にはこうした乱暴狼藉が伝わっていたようで、「凡近日天下依此事、上下騒動、人馬雑物、随懸眼路横奪取」(『玉葉』寿永二年四月十三日条)とあり、兼実は宗盛に麾下の狼藉を制圧するよう訴えるも「雖訴前内大臣、不能成敗、雖有制止、更以不拘制法」という状況で、平家方の兵士は宗盛の制止すらきかないほど無規律化していたようだ。その最大の原因が西日本一帯を猖獗の巷に陥れていた大飢饉であった(『玉葉』寿永二年四月十四日条)。故清盛入道が沙汰していた西国・北陸道の運上物を兵糧米に宛てるという方策も、北陸道の死守に失敗した現状では兵糧米の確保もままならず、兵士等の狼藉を抑えることは叶わなかった。一方で「凶賊」への警戒のため、解兵することもできなかったのである。宗盛は進退窮まった状態にあったのである。この直後から宗盛は以前から出征の留保が続いていた諸所の「征討将軍等」を次々に発向させており、23日には「今日皆了」となった(『玉葉』寿永二年四月廿三日条)。畿内への「凶賊」侵入の阻止ならびに、京都で倦む兵士の狼藉を防ぐため の宗盛の緊急の策であったのだろう。追討使が出征したのちの25日、左大臣経宗からの令によって左中弁兼光が認めた「源頼朝同信義等」追討令が宗盛へ下されており(『玉葉』寿永二年四月廿五日条)、急遽練られたものであったことが伺われる。
なお、軍記物『源平盛衰記』の記述ではあるが、寿永2(1183)年の「三月の比より、兵衛佐と木曾冠者と中悪き事出来れり」という。これは「甲斐源氏武田太郎信義が子に五郎信光が讒言」によるものであったという。信光が愛娘と木曽義仲の嫡子「清水冠者」との婚姻を希望したところ、義仲に「娘持給たらば被進よ、清水冠者に宮仕はせん、妻までの事は不思寄」と虚仮にされたことで遺恨を含み、頼朝に「木曾義仲、去々年越後の城太郎資永を打落てより以来、北陸道を打領じて、其勢雲霞の如し、今平家誅戮のために上洛の由披露あり、実には小松大臣の女子の十八に成給を、伯父宗盛養子にして木曾を聟にとらんと、忍々に文ども通ずと承る、角して平家と一に成て、当家を亡さんと云梟悪の企あり、不知召もや」と内々に告げたという(『源平盛衰記』)。頼朝は叔父行家が頼朝を見限って義仲のもとへ赴いたことを知っており、さらに義仲が平家と姻戚となれば由々しいことであるとして、頼朝みずから「上野と信濃との境なる臼井坂」に進発したという。これを聞いた義仲は、今井兼平、樋口兼光を呼んで「此事如何が有べき」と問うと、彼らは「今は別の子細侍まじ、富部太井に城構して支戦はんに、なじかは軍に負べき、はやはや兵を汰へ給へ」という。義仲は暫し思案し、「平家追討の大事を閣て、兵衛佐と軍するならば、一門の滅亡、他人の嘲哢最恥」(『源平盛衰記』)とし、越後国へ引退する。頼朝は鎌倉へ帰還するが、「天野藤内民部遠景、岡崎四郎義真」の両名に雑色の「安達新三郎清経」を越後国の義仲のもとに派遣して行家を放逐することを要求。できないのであれば「志水殿を是へ渡し給へ、父子之儀をなし奉るべし、両条之内一も承引なくんば、兵を指遣して誅し奉るべし」と通告したという。この結果、義仲は清水冠者を呼び「己をば兵衛佐の子にせんと宣へば遣す也、相構て悪れずして、一方の固め共なれ」と告げ、さらに岡崎義実と面会して饗応しつつ「十郎蔵人に意趣御座ましけん事は不存知、又呼越たる事もなし、打憑見え来給たれば、只自然の情を存る計に候、誠に平家追討の大事を閣て、何の遺恨ありてか謀叛の企あるべき、人の讒言に侍か、信用に及べからず、又清水冠者事は未東西不覚の者候、仰を蒙て進せねば所存を籠たるに似たり、召に随て是を進す、不便にこそ思召れめ、義仲角て候へば、一方の固めには憑思召べし」(『源平盛衰記』)と言い、清水冠者義高を岡崎義実、天野遠景の両使へと預け、両使は畏まってこれを鎌倉へ相具したという。義高の供には同い年の「宇野太郎行氏(海野太郎幸氏)」が付けられたという(『源平盛衰記』)。
4月26日、平家率いる「官軍攻入越前国」という(『玉葉』寿永二年五月一日条)。さらに5月3日には「官軍攻入加賀国合戦、両方多死傷之者」という激戦が行われた(『玉葉』寿永二年五月十二日条)。加賀国の合戦で大勝を収めた官軍は、5月11日には「官軍前鋒乗勝入越中国」(『玉葉』寿永二年五月十六日条)と、勝ちに乗じて越中国へとなだれ込んだ。ところが、ここで「木曾冠者義仲、十郎蔵人行家、及他源氏等迎戦、官軍敗績、過半死了」(『玉葉』寿永二年五月十六日条)という大敗を喫する。北陸での官軍の苦戦の報が重なるや、6月3日、院は追討の祈祷のために大神宮を含めた大社十社に奉幣使を派遣。「関東北陸」の「凶賊」追討を祈った(『吉記』寿永二年六月三日条)。
しかし、その祈りも空しく、翌6月4日明方、「北陸官軍、悉以敗績」の飛脚が到来する(『玉葉』寿永二年六月四日条)。「官兵之妻子等、悲泣無極」であった。そして翌5日、兼実が「前飛騨守有安」から官軍敗走の子細を聞いている。それによれば「四万之勢、帯甲冑之武士、僅四五騎許、其外、過半死傷、其残皆悉棄物具、交山林、大略争其鋒甲兵等、併以被討伐了云々、盛俊、景家、忠経等、已上三人、彼家第一之勇士也、各小帷ニ前ヲ結テ、本鳥ヲ引クタシテ逃去、希有雖存命、不伴従僕一人」(『玉葉』寿永二年六月五日条)という、散々たるものであった。そして6月6日、連日の雨にぬかるみ、飢饉で死屍と死臭の溢れる初夏の熱気の中「敗軍等今日多入洛」し、京都は混沌とした世界が広がっていたであろう。宮中ではこの状況を打開するために議定が行われているが、もはや重ねての追討は不可能であるとし、院も宗盛も入洛を目指す「凶賊」を防ぐ現実的な術を失い、ただひたすら神仏にすがるほかなかったのである(『玉葉』寿永二年六月六日条)。
6月12日、朝廷は近江守護の兵士を徴発・派遣し、宗盛も主だった家人を派遣し、肥後守貞能も数万の兵を率いて近江国都賀へと付くが(『吉記』寿永二年六月十二日条)、翌13日には「源氏等已打入江州」と近江国に侵入してきた一団があったようで、筑後前司重貞は敗れて「単騎迯上」だったという(『吉記』寿永二年六月十三日条)。6月18日には「肥後守貞能」が残兵わずか千余騎で入洛し、「洛中之人頗失色」(『吉記』寿永二年六月十八日条)だったという。7月1日には「賊徒今日可入洛」という風聞が流れており、院は兼実のもとに右大弁親宗を派遣して、賊徒の京中乱入となった際の安徳天皇の法住寺殿行幸と剣璽および賢所の先例のない京外移転(法住寺殿は京外に存在する)について問い合わせている(『玉葉』寿永二年七月ニ日条)。また、兼実の伝聞ではあるが、「頼朝忽不可出、只木曾冠者、十郎等分手於四方、可寄之由」であったという。木曾義仲と十郎行家は頼朝の麾下にあると認識されていたことがわかる(『玉葉』寿永二年七月ニ日条)。また「日来入江州源氏ハ末々者」であり、「木曾冠者已入了」(『吉記』寿永二年六月廿九日条)という風聞があった。そして、木曾勢らは「待関東之勢、九十月比可入洛」(『玉葉』寿永二年七月三日条)と巷間で騒がれていたようである。
そして7月14日には「源氏称十郎蔵人行家者、已入伊賀国」と、伊賀国へと侵攻し、「家継法師号平田入道貞能兄」と合戦に及び、「号三河冠者源氏」も大和国へと侵攻したという(『吉記』寿永二年七月十六日条)。さらに行家は宇陀郡に駐屯して吉野大衆らと結んだという(『玉葉』寿永二年七月廿二日条)。一方、薩摩守忠度は丹波追討使として丹波国へ百騎程度を率いて発向しているが(『吉記』寿永二年七月十六日条)、当然のことながら百騎ばかりでは寡少に過ぎ、戦いにならずに大江山に駐屯したという(『玉葉』寿永二年七月廿二日条)。
また、7月21日の猛暑の最中、三位中将資盛を大将軍とした追討使が宇治田原を経て近江へと発向した。追討軍には資盛舎弟の備中守師盛、筑前守定俊、肥後守貞能らが加わっている。公称は三千余騎であったようだが(『吉記』寿永二年七月廿一日条)、その勢は密かに見物した兼実の家僕が数えたところ、実数で千八十騎と少なく、兼実は追討は「有名無実之風聞、以之可察歟」と手厳しく感想を述べている(『玉葉』寿永二年七月廿一日条)。追討使の人々はいずれも小松家に属する人々であることから、資盛に付属する軍勢のみでの出兵であったのだろう。なお、この行列には「法皇密々有御見物」と、資盛を鍾愛する後白河院がその門出を見送っている(『吉記』寿永二年七月廿一日条)。実は後日資盛らの追討使は「資盛卿者、給宣旨人也、自院可被召遣、至于自余輩者、私遣了、直可召返之由、前内府被申」(『吉記』寿永二年七月廿四日条)とあり、宗盛が派遣した追討使ではなく、後白河院が派遣を命じたものであったことがわかる。故清盛入道ですら統御し得なかった一門の独立性向を子世代の宗盛が統制できるはずもなく、宗盛は一門を統率する力を失っていたのである。
資盛らは伊賀から大和に進んだ十郎蔵人行家に備えるため、近江進軍を中止して宇治田原に駐屯した(『玉葉』寿永二年七月廿二日条)。院はこの夜、急ぎ法住寺殿へと移っているが、これは翌22日に安徳天皇を御所から迎え取るための臨幸であった(『玉葉』寿永二年七月廿一日条)。ところが翌22日、天皇の法住寺殿行幸が「復日」の理由から25日まで延引となる(『玉葉』寿永二年七月廿ニ日条)。
 |
| 近江国から見る比叡山 |
この頃、近江国の武士等はすでに六波羅辺に現れていたという。さらに比叡山には武士等が登っていて、講堂前に集まっていたという。日頃は比叡山の僧房に留まっていた僧綱等は、東塔無動寺の慈円法印含めて、みな山を下り、天台座主明雲のみが比叡山に留まったという(『玉葉』寿永二年七月廿二日条)。木曾勢は近江から比叡山や龍華越、三井寺などを経由した入京ルートを利用していたのかもしれない。また、日ごろは平家に属していた多田源氏の惣領・多田蔵人大夫行綱も摂津・河内両国の人々を麾下とし(『玉葉』寿永二年七月廿二日条)、小掠池から淀川への河尻では、多田行綱の下知を受けた太田太郎頼助が鎮西からの兵糧米を強奪、舟や人家を破壊するといった狼藉を働いて平家に背いた(『吉記』寿永二年七月廿四日条)。もはや畿内における平家の威信は完全に失墜していたのである。「六波羅之辺、歎息之外無他事」であったという(『玉葉』寿永二年七月廿三日条)。
比叡山の近江武士らは延暦寺内に駐屯を続けており、23日早朝には座主明雲が比叡山から下山して参院。戦いになれば「天台仏法令破滅歟」として和平を院奏している(『吉記』寿永二年七月廿三日条)。一方、洛中では延暦寺に籠もる近江武士らが24日に京洛へ夜討ちをかけるという風聞が立ち、九条兼実は暴風雨と雷雨の中、九条邸から鴨川を渡り、東の法性寺へと避難をしている(『玉葉』寿永二年七月廿四日条)。平家の軍事力はすでに払底し、守護者のいない京都は前例のない混乱の極みにあったことがうかがえる。
寿永2(1183)年7月25日、「法皇御逐電」(『玉葉』寿永二年七月廿五日条)の一報が兼実のもとに届く。未明に「法皇出御法住寺殿、不知何方逐電令密幸給」(『吉記』寿永二年七月廿五日条)ったものだった。実は24日夜、後白河院は「若及火急者、何様可令存知御乎、臨期定令周章歟、可被申其子細」と、今後の危急の際の対応について書面で宗盛を問い質していた。これに対して宗盛は「無左右参入可候御所者、奉具法皇主上、無左右可逃退海西」と返答した(『吉記』寿永二年七月廿五日条)。これを聞いた後白河院は京洛からの退避を厭い、法住寺殿から逐電したのである。実は院は20日頃には宗盛と重衡らによる「奉具法皇、可赴海西」という密議を聞いた摂政基通から「女房故邦綱卿愛物、白川殿女房冷泉局」を通じて知らされており、22日の急な院の法住寺殿臨幸と翌日に予定されていた安徳天皇の院御所行幸は、これを警戒したものであったのだろう。
院は北面等わずかな供回りとともに鞍馬路を経て比叡山横川へ入り、その後東塔の円融房に入ったという(『吉記』寿永二年七月廿五日条)。この「院密幸」は数時間後には宗盛に報告されているが、もはや宗盛は院を追うことをせず、ただちに左中将清経を閑院御所に遣わして「行幸早可成之由」を摂政基通へ告げている。公卿等は反対するが「不及是非、可為御車」と強要され、ついに安徳天皇は閑院御所を離れ(『吉記』寿永二年七月廿五日条)、「六波羅ヘ行幸」(『愚管抄』)した。六波羅には在京の「一家ノ者ドモ集」まっていたが、宗盛は近江武士の山科経由での侵攻を抑えるため、「山科ガタメニ大納言頼盛」の派遣を指示したという(『愚管抄』)。頼盛入道は「ナガク弓箭ノミチハステ候ヌル由、故入道殿ニ申テキ、遷都ノ比奏聞シ候キ、今ハ如此事ニハ不可供奉」(『愚管抄』)と再三固辞するが、宗盛はこれを聞かずに強請。やむなく頼盛入道は山科へ向ったという。その後、宗盛らは安徳天皇と神器を奉じて「鳥羽ノ方ヘ落テ船ニ乗リ四国ノ方ヘ向ヒケリ、六波羅ノ家ニ火カケテ焼ケレバ、京中ニ物ドリト名付タル者イデキテ、火ノ中ヘアラソヒ入テ物トリケリ」(『愚管抄』)とあるように、宗盛らは「六波羅、西八條等舎屋不残一所併化灰燼了、一時之間、煙炎満天」(『玉葉』寿永二年七月廿五日条)、「六波羅已下家同時放火」(『百錬抄』)と、六波羅と西八條の平家邸街に放火して焼き尽くしたようである。
なお、この離京に際し、宗盛は「頼盛ガ山科ニアルニモ告ザリケリ」(『愚管抄』)と、山科出兵を命じた頼盛入道を置き去りにしたという(『愚管抄』)。この知らせを聞いた頼盛入道は激怒し、「子ノ兵衛佐為盛ヲ使ニシテ鳥羽ニ追付テイカニ」と宗盛を詰問したという。しかし宗盛は「返事ヲダニモエセズ、心モウセテミエ」るほど動揺していたので、為盛は馳せ帰って頼盛入道に報告。いったんは宗盛一行の下へ向うも、鳥羽から北上して、院御所の法住寺殿へ入った(『愚管抄』)。また、院の覚えめでたい三位中将資盛も鳥羽から法住寺殿に入り、両者は比叡山の院に事の次第を報告する。院は頼盛入道には八条院のもとへ行くよう指示するが、資盛は「申入ル者モナクテ御返事ヲダニ聞カザリケレバ」、やむなく宗盛を追って西へ落ちて行った(『愚管抄』)。藤原経房は「就中件卿故入道相国之時、度々雖有不快事、今度殊造意不聞、只為一族許歟、尤可被寛宥」と頼盛入道を擁護しており、これに「人々皆一同」と理解を示している(『吉記』寿永二年七月廿八日条)。
宗盛は24日の後白河院の質問に対して事実を正直に返答していることから、京中が戦場になった際には、後白河院と安徳天皇、神器を戦場である京洛から西へ逃した上で、改めて「凶賊」と対峙する目的だったのだろう。当然、それは宗盛が法皇・天皇・朝廷の防衛を行う正統な軍事指揮権者だったためであり、あくまでも官軍として「凶賊」との戦いを継続する計画だったのである。ただし、京都はいまだ戦場ではなく「西海」への行幸は最悪の状況で採り得る案だったこともあり、摂政基通をはじめとする公卿たちとのしっかりとした話し合いや根回しはこれからだったのであろう。しかし、京洛への凶賊侵攻が現実味を帯びる中、院から今後「もしも火急の事態が起こった場合」の対応を問われ、場合によっては西遷案もあり得ることを伝えたのではないだろうか。なお、宗盛は返奏ののちも院の脱出を警戒していないところから、法皇が行幸を拒んで逐電するとは微塵も感じていなかったのだろう。ところが、宗盛の予想に反して返奏から数時間後には後白河院は法住寺殿から姿を消す。院の逐電を知って危機感を募らせた宗盛は、「院密幸」が発覚した辰刻から二、三時間後の巳刻には御所から安徳天皇と神器を遷して西海へ発向している。25日に「都落ち」を行うことになったことは、おそらく宗盛にとって計算外であったのではないだろうか。そのことは急遽知らせを受けた平家一門が右往左往する様からもうかがえるのである。そして院という最大の権威者を同道できなかった代償は大きく、平家と行動を共にするであろうとみられていた摂政基通すら屋敷を脱出して比叡山の院のもとへ逃れており、安徳天皇と宗盛に随った一門以外の公卿はほとんど存在しなかったのであった。
 |
| 比叡山延暦寺 |
平家一門の「都落ち」から一夜明けた7月26日、兼実は延暦寺円融房に御座す法皇への面会のため、比叡山の道を急いでいるが、その途路、山から降る権中納言源雅頼と偶然出くわし、輿を降りて談話しているが、雅頼は「神璽、宝剣、内侍所、賊臣悉奉盗取了、而無左右、可追討平氏之由、被仰下之条、甚不便、先可有剣璽安全之沙汰、仍奏聞此旨有勅許、以親宗、御教書遣多田蔵人大夫行綱之許了、此事猶荒沙汰也、仍内々可被仰遣女院、若時忠卿件卿伴賊之許之由、重以奏聞可然之由有仰」(『玉葉』寿永二年七月廿六日条)という。都落ち翌日にはすでに平家は「賊臣」呼ばわりされ、「可追討平氏之由、被仰下」ていた様子がうかがえるが、神器を平家が保有している状況下にあっては無策に追討を行うのは宜しくなく、雅頼はまず「剣璽安全」を考えるべきと「奏聞」して「勅許」を得、平親宗を使者に「御教書(院宣)」を多田蔵人大夫行綱に遣わして交渉を命じている。西へ下る平家がまず接触するのが多田行綱であることから、彼に白羽の矢が立ったのだろう。
27日、兼実のもとに「前内大臣已下追討事」の形式について問い合わせがあり、天皇が連れ去られている現状では院宣での対応とすべきことを告げるとともに、早々に「義仲木曾、行家十郎等」に武士の狼藉を停止させた上で入京を急がせ、早いうちに院も仙洞御所へ還御すべきことが望ましいことを述べている(『玉葉』寿永二年七月廿七日条)。
この後、院は下山の日取を確かめるも、いずれも良い日がなく、結局、即日下山と決定され、近江武者の「錦部冠者義経男」や「恵光房阿闍梨珍慶山悪僧、着錦直垂腹巻等、為有識者豈可然哉、万人属目」を護衛として比叡山を下り、法住寺殿に程近い蓮華王院へ入った(『吉記』寿永二年七月廿七日条、『百錬抄』)。『愚管抄』では「廿六日ノツトメテ御下京」とあるが、おそらく慈円の記憶違いであろう。そして、院還御に伴い「近江ニ入タル武田先参リヌ、ツヅキテ又義仲ハ廿六日ニ入ニケリ」(『愚管抄』)となった。なお、このとき入京した源氏混成軍には「武田」が加わっていたことがわかる。「武田」は信濃国での城助職との戦い以来、木曾勢とともに平家と戦っていたと思われ、甲斐源氏は頼朝とは独立した別勢力であったことがここでもわかる。彼らは「六條堀川ナル八條院ノハハキ尼ガ家」に宿所を割り当てられたという(『愚管抄』)。
28日、「上皇、召公卿有議定、前内大臣已下奉具幼主、赴西海之間、神鏡、剣璽已下取畢、何様可有沙汰哉事」(『百錬抄』)が議され、その結果を受けたとみられるが、宗盛に随って西へ下った「時忠卿」へ「早可有還宮」の使者が遣わされている(『吉記』寿永二年七月廿八日条)。宗盛は「七月行幸西海之時、自途中可還御之由、院宣到来、備中国下津井御解纜畢」(『吾妻鏡』寿永三年二月廿日条)と述べており、これは『玉葉』に見える7月28日に時忠へ遣わした院使であると考えられる。当時の宗盛一行はすでに備中国まで下っていたが、この院宣を受けて、宗盛は備中国下津井の湊から還都を試みるも「依洛中不穏、不能不日立帰、愁被遂前途候」と考えて上洛を延期し、西へ向かった。
法皇は時忠へ「還宮」の院宣を下したのち、「義仲行家等自南北義仲北、行家南」(『玉葉』寿永二年七月廿八日条)を蓮華王院へ招くと、検非違使別当・藤原実家を通じて「可追討進前内大臣党類」(『吉記』寿永二年七月廿八日条、『百錬抄』)を命じている。義仲、行家両名は跪いてこれを承けたという。このとき兼実は彼らが「参入之間、彼両人相並、敢不前後、争権之意趣以之可知」と、両人が権勢を争う姿を看過していた。退出後、両名は「京中狼藉可停止」が命じられた(『玉葉』寿永二年七月廿八日条)。
義仲、行家の風体(『吉記』寿永二年七月廿八日条)
| 人名 | 年齢 | 続柄 | 装束等 |
| 木曾冠者義仲 | 三十余 | 故義方(義賢)男 | 錦直垂、黒革威甲、石打箭、折烏帽子 |
| 十郎蔵人行家 | 四十余 | 故為義末子 | 紺直垂、黒糸威甲、宇須部箭、立烏帽子 |
また、同7月28日、院は「下遣御使於頼朝許、庁官康定下向」(『百錬抄』)している。当然ながらこの使者が帯した書状も平家追討に大きく関わる内容と推測され、兼実が「或人」からの伝聞として、頼朝の返答「折紙三箇条」の中に「今当伐君御敵之任」、二日後に現物を実見して「今討朝敵」と記していることから、義仲・行家と同様に「可追討進前内大臣党類」を命じた院宣であった可能性が高いだろう。
翌7月29日には、「上総介忠清、検非違使貞頼等出家、忠清在能盛許、貞頼在兼豪法印許」(『吉記』寿永二年七月廿九日条)にあるという風聞が伝わっている。そして夜には祇園から五条坊門以南が焼け、六波羅蜜寺も焼失。さらに故平正盛の常光院も燃亡してしまったという(『百錬抄』)。
翌7月30日には、「可被行賞事頼朝、行家、義仲、関東北陸庄園可被遣使事、京中狼藉可被制止事等」(『吉記』寿永二年七月卅日条、『百錬抄』)が定められた。吉田経房は議定に加わっていないため「委不聞之」であったが、当事者の右大臣兼実がその議定を克明に記している。
翌7月30日早旦、院司高階泰経が兼実家司の源季長のもとに書を送り、「於院可被議定大事」のため、巳刻に参院すべきことが指示され(『玉葉』寿永二年七月卅日条)、兼実は午一點に蓮華王院(現在の三十三間堂)に参じた。列した公卿は左大臣経宗、大納言実房、権大納言忠親、権中納言長方で「堂南廊東面座」して着した。ここに院は頭左中弁兼光を通じて左大臣経宗に「條々事可計申者其事三ヶ條」を命じた。その内容は、
| 内容 | 議定の人々の意見 | |
| 一 | 仰云、今度義兵、造意雖在頼朝、当時成功事、義仲、行家也、且欲行賞者、頼朝之鬱難測、欲待彼上洛、又両人愁賞之晩歟、両ヶ之間、叡慮難決、兼又三人勧賞可有等差歟、其間子細可計申者 | 人々「不可被待頼朝参洛期、加彼賞、三人同時可被行、頼朝賞、若背雅意者、随申請改易、有何難哉、於其等級者、且依勲功之優劣、且随本官之高下、可被計行歟、惣論之、第一頼朝、第二義仲、第三行家也」 |
| 二 | 仰云、京中狼藉、士卒巨万之所致也、各可滅其勢之由、可被仰下之處、不慮之難、非無所恐、為之如何、兼又縦雖非滅人数、無兵粮者、狼藉不可絶、其用途又如何、同可令計奏者 | 於今者余党之恐、定不及成群歟、被減士卒人数、可謂上計、兵粮事、頗有異議 忠親、長方「各賜一ヶ国、可充其用途」 兼実「勧賞任国之外、更賜国之條、如何」 忠親、長方「其用訖者、被任他人、有何難」 兼実「理可然、但彼等定含収公之恨歟、只没官地之中、択可然之所、可充給歟、不然又以一ヶ国可分賜両人歟、但此條頗為喧嘩之基歟、猶賜没官之所可宜」 経宗「両方之儀各可然、可在勅定、頗被同余議歟」 |
| 三 | 仰曰、神社仏寺及甲乙所領、多在関東北陸、於今者各遣其使、可致沙汰之由、可被仰本所歟 | 一同「不可有異議、早可被仰者」 |
というものであった。まず、平家の洛中放逐に関する行賞については、「賊臣」平家を追いやり院を救った「義兵」であるが、挙兵したきっかけを作った頼朝を重んじるべきか、実際に平家一門を追った義仲、行家を行賞すべきかで議場は紛糾する。いずれも一長一短があり、なかなか決しなかったが、結局は「第一頼朝、第二義仲、第三行家也」と決する(『玉葉』寿永二年七月卅日条)。
| 順 | 人名 | 授与官途 | 備考 |
| 第一 | 頼朝 | 京官・任国・加給 | 左大臣経宗 「於京官者、参洛之時可任」 右大臣兼実 「不可然、同時可任」 権中納言長方「(兼実)同之」 |
| 第二 | 義仲 | 任国・敍爵 | 但以国之勝劣任之、尊卑可差別 大納言実房 「義仲従上、行家従下宜歟」 |
| 第三 | 行家 | 任国・敍爵 |
第二議案は、京中の狼藉を停止させるための方策であった(『玉葉』寿永二年七月卅日条)。これについては、兵士の養いのために義仲・行家に彼らの任国とは別に各々に一国を一時的に供与する案が権大納言忠親、権中納言長方から出されている。これに対して兼実は義仲・行家に賜う国のほかに各一国を遣わすというのはいかがなものかと反対するが、忠親らはこの用が終われば解任して他の者を任ずればよいと述べる。この現実を見ない意見に兼実は、確かにそうではあるが、彼らは国を収公されたと恨むであろう。平家没官領を充てるか一ヶ国を両名に賜うか。ただこれは喧嘩のもとであろうからやはり没官領を充てるべきだろう、という案が議されている。
第三議案は、平家が国司となるなど影響力が強かった関東や北陸から平家与党の勢力が減退したため、寺社を本所とする所領へ各々が使者を遣わして本来の沙汰をすべきことであった(『玉葉』寿永二年七月卅日条)。これは同年10月14日に下される宣旨(寿永二年十月十四日宣旨)と深く関係する議案となる。
列する人々の申状を取り集めた頭弁兼光は、議奏のため御所へと戻っていった。その後、数刻後に蓮華王院に戻ってきた兼光から「各議奏之趣、皆以可然、早此定可被行者、於今者、各可有御退出者」と議奏の報告を受け、兼実以下の列議の公卿衆は退出した。なお「京中追捕物取」が行われて各地で合戦も起こったという。また、同30日、院宣によって義仲が京中守護の責任者とされ、諸氏の割り当てがなされている。
京中守護(『吉記』寿永二年七月三十日条)
| 守護 | 人物 | 氏族等 |
| 京中守護 | 義仲 | |
| 大内裏~替川(天神川) | 源三位入道子息(大内頼兼か) | 摂津源氏 |
| 一条大路より北 朱雀大路より西(梅宮まで) |
高田四郎重家(高田三郎重宗か) 泉次郎重忠 |
尾張源氏 |
| 一条大路より北 東洞院大路より西(梅宮まで) |
出羽判官光長 | 美濃源氏 |
| 一条大路より北 東洞院大路より東(会坂まで) |
保田三郎義定(安田三郎義定) | 甲斐源氏 |
| 五条大路より北 河原より東(近江境まで) |
村上太郎信国 | 信濃源氏 |
| 七条大路より北、五条大路より南 河原より東(近江境まで) |
葦敷太郎重隆 | 尾張源氏 |
| 七条大路より南 河原より東(大和境まで) |
十郎蔵人行家 | 義仲叔父 |
| 四条大路より南、九条大路より北 朱雀大路より西(丹波境まで) |
山本兵衛尉義経 | 近江源氏 |
| 二条大路より南、四条大路より北 朱雀大路より西(丹波境まで) |
甲斐入道成覚 | 山本義経兄・柏木義兼入道 |
| 鳥羽四至内 | 仁科次郎盛家 | 信濃平氏 |
| 九重内 その他所々 |
義仲 |
8月2日には、隠退していた「入道関白(松殿基房)」が院御所北対に参じ、摂政基通を停止して、自身の子「前中納言師家生年十二歳」を「可為摂簶之由注所望」した。摂政基通はもとより法皇の「御愛物」であり、当然ながら法皇はこの申し出を拒絶している(『玉葉』寿永二年八月二日条)。
ただ、入道関白からの申出を受けて、法皇は師家を拒否した対案として「存右府当任之由」を基房入道に告げたという(『玉葉』寿永三年二月十一日条)。基房入道は「摂簶若入右府之家者、永可留彼家、不可雪我恥、仍不可被改本人、且依此申状無動揺」と基通留任を承諾したという。基房と兼実は政治的には激しい対立関係にあったが、個人的には兄基房が弟基実へ有職故実を手ずから教え諭し、基実もその学識には敬意を以て接するという複雑な関係にあった。それだけに基実の能力を知り抜いていた基房が、愚鈍な甥・基通の摂政留任のほうがましであると思ったのは妥当であろう。
8月17日には、兼実の世評の高さを警戒するあまり、入道関白基房は院参して「経東宮傅之人、不在摂簶」という(『玉葉』寿永二年八月十七日条)。さらに9月6日にも家司少将顕家を備前守行家のもとへ遣わし「先於摂簶職者、非家嫡者、雖及二男、未有及三男之例、而下官当仁之由、世間謳歌太不当也云々、又被奏院之旨同然」という。いずれも兼実は基房がこのようなことを言うのは「不信受」だが事実と聞いて「奇」とする。いずれも先例に最も明るいはずの基房が言うこととは思えない、という皮肉である。「凡天子之位、摂簶之運、全非人力之所及、結構之体、事似軽々加之」という前提のもと、「不及三男之由如何、貞信公、大入道殿、御堂、此三代之例棄置歟」と、忠平(四男)、兼家(三男)、道長(四男)の三代の例はどう説明するのかと批判している。また、法皇に対しても「法皇不弁黒白、源氏不知是非、只以一言之狂惑、欲惣之巨務、謀計之至、冥罰定速歟、可指弾」と痛烈に批判する(『玉葉』寿永二年九月六日条)。ただし、「乱世之執柄非所好」と、この乱世での摂政の任は好まざる所であるとしている。
『玉葉』から兼実の本意は汲み取ることは大変難しいが、兼実自身が摂政の地位を欲していることは確かである。ただし、政治的な情勢がまったく見通せない中での執政は拒否する考えのようである。そこにおいて、外部からの余計な詮索や推測があると、現在の状況においては摂政就任は本意ではないので、否定的な反応を示すのであろう。安定した状況になることを望み、そこにおいて摂政に就任することが最大の目的であるから、安定した世情を阻害する人々に対しては徹底的な嫌悪感を示す。それは身分の上下にかかわらず、政治的に無能な治天・後白河法皇に対しても強烈に批判し、その君側で院の意向を示す近臣たちを「小人」として蔑むのである。
基房入道はその後、頼朝に使者を送り「摂政可推挙之由」を指示しているが、頼朝は「答不能口入之由」として、政治介入を避けた(『玉葉』寿永三年二月十一日条)。頼朝は諸所の伝聞から兼実を推しており、京都の人事事情を熟知していたからこその対応であろう。子息を摂政とする企てを拒絶された基房入道は法皇に「然者、一所庄々、少々可分賜」と摂関家領からの分領を申し出たが、これも法皇は「摂政氏長者無改易者、何及所領之違乱哉」(『玉葉』寿永三年二月十一日条)として拒否するが、基房入道はこの院の言質を後々利用することになる。
そして8月6日、天皇不在という危機的状況の中、院は「立王事」について「先可奉待主上還御哉、将又且雖無剣璽、可奉立新主哉」を占わせたところ、結果は半々であった。兼実は「先京華狼藉于今不止、是人主不御座令然也」、「被急征討之處、平氏等奉具主上、及三神、已赴海西、不立主有征伐、於議有妨」、そして剣璽なき「践祚」については、継体天皇の「即被移皇居、其後得剣璽即位」の例を挙げ、践祚後に剣璽を得て「即位」すれば問題はなく、新たな天皇を「践祚」させることを推した。「凡天子之位、一日不可曠、政務悉乱云々、于今遅々之条、万事違乱之源也、早速可有沙汰、不可有異議」と主張し、左大臣経宗もこれに同意する(『玉葉』寿永二年八月六日条)。そして、同日、平家一門は解官された。その数「解官二百余人」(『玉葉』寿永二年八月九日条)とされるが、「時忠卿不入其中、是被申可有還御之由之故也」と、時忠は解官の対象外とされている。去月28日に時忠に安徳天皇と神器の還御を指示していたためである。
8月11日、義仲と行家に対する除目が行われたが、行家はこの除目内容を「是与義仲賞懸隔」だと「称非厚賞」と「忿怒」して閉門辞退している(『玉葉』寿永二年八月十二日条)。都は「上御沙汰違乱之上、源氏等悪行不止、天下忽欲滅亡」(『玉葉』寿永二年八月十日条)とあり、義仲とともに京中に入った人々による狼藉があとを絶たなかった様子がうかがえる。
寿永二年八月十一日除目(『玉葉』寿永二年八月十一日条)
| 人物 | 官位 | 京官 | 外官 |
| 源義仲 | 従五位下 | 左馬頭 | 越後守 |
| 源行家 | 従五位下 | 備後守(辞退) |
また、夜には時忠の返書が院に奏上されているが、「京中落居之後、可有還幸剣璽已下宝物等事、可被仰前内府歟」というゼロ回答であった。これは兼実も「事躰頗似有嘲弄之気」と怒りをにじませている(『玉葉』寿永二年八月十二日条)。
天皇の還御が見通せず、政務の停滞が顕著となる中、剣璽もないままに先例を勘考しながら、次の天皇の践祚を進めていた院は、その候補を「高倉院宮二人」に絞っていた。ひとりは「義範女腹五歳」、もう一人は「信隆卿女腹四歳」で、いずれも後白河院の孫にあたる。なお「義範」は摂関家家司平範家(『兵範記』著者)の次男で、娘・少将局範子が高倉院掌侍となり三宮(のち惟明親王)を生んでいた。ところが、ここに「以外大事出来了」という事態が起こる。義仲が大蔵卿高階泰経のもとを訪問し、「故三條宮御息宮在北陸、義兵之勲功在彼宮御力、仍於立王事者、不可有異議」と主張したのである(『玉葉』寿永二年八月十四日条)。泰経は「高倉院宮両人御坐、乍置其王胤、強被求孫王之条、神慮難測、此条猶不可然歟」と拒否するが、義仲は「於如此之大事者、源氏等雖不及執申、粗案事之理、法皇御隠居之刻、高倉院恐権臣、如無成敗、三條宮依至孝亡其身、争不思食忘其孝哉、猶此事難散其欝、但此上事在勅定」と主張し、泰経は兼実に「此事如何可計奏者」とすがっている。兼実は「於他朝議者、不顧事之許否、毎有諮詢述愚款、至王者之沙汰者、非人臣之最」として返答せず、御占を行うことを勧めつつも「只以叡念之所欲、可令存天運之令然之由御歟」(『玉葉』寿永二年八月十四日条)と述べている。
8月16日、院御所で除目が行われ、義仲は伊予守に、行家は備前守に遷っている(『百錬抄』)。
寿永二年八月十六日除目(『百錬抄』)
| 人物 | 官位 | 京官 | 外官 |
| 源義仲 | 従五位下(ママ) | 左馬頭(ママ) | 伊予守 |
| 源行家 | 従五位下(ママ) | 備前守 |
8月18日、雨の降り続く中、議定で弟宮(四宮)が次の天皇に立てられることとなった。はじめに三宮、四宮の高倉院両宮で御占が行われ、いずれの陰陽師も「以兄宮為吉」という結果となった。ところが、その後、「御愛物遊君今ハ号六條殿」女房丹波の夢で「弟宮四位信隆卿外孫也、有行幸、持松枝行之由見之」を聞いた院が「仍乖卜筮」て「立四宮」という、政治的な考えとはまったく異なる理由で四宮を立王することを決定してしまった(『玉葉』寿永二年八月十八日条)。院は松殿基房入道、摂政基通、左大臣経宗、右大臣兼実(病で不参)を召してその意見を聴くが、いずれも「北陸宮一切不可然」という結論であった。ただし、理由もなく北陸宮を拒否すれば「武士之所申不可不恐」であり、再度御占に委ね、「第一四宮、第二三宮、第三北陸宮」という結果となる(『玉葉』寿永二年八月十八日条)。当然ながら院の意向が最大限反映された結果であるが、とくに「第三始終不快」となり、院は義仲と親しい僧正俊堯を派遣して義仲へ伝達したのであった。
結果を知らされた義仲は「先以北陸宮可被立第一之處、被立第三無謂、凡今度大功、彼北陸宮御力也、争黙止哉、猶申合郎従有私事歟」と「大忿怨申」したという(『玉葉』寿永二年八月十八日、十九日条)。義仲に対して批判的な兼実もこのときばかりは、立王に際する乱暴な決定方法については相当に怒りを感じていたようで、「小人之政、万事不一決」と強く批判している。
同日、四宮の名字勘問が為され、式部大輔俊経卿の撰により「永仁」「尊成」の二案が奏上され、最終的には明主であった後三条院の「尊仁」、村上天皇の「成明」のそれぞれの御諱をもつ「尊成」が採用されることとなった。そして翌8月20日、四宮尊成は四歳で「立皇」された。のち様々な方面に天賦の才を示した後鳥羽天皇である。新帝は院御所で御着袴を済ませたのち閑院御所に移り、蔵人頭には左中将隆房、左中弁兼光が就き、蔵人は左衛門権佐親雅、右衛門権佐定長、宮内少輔親経が就任した。いずれも先帝安徳代と同じ人物である。そのほか、六位蔵人には行家の子・源家光が末席に連なった(『玉葉』寿永二年八月廿日条)。なおこれはあくまで「践祚」であって「即位」ではない。即位には神器の継承が必須であり、それには平家が持ち去った神器の還御が求められたのであった。
しかし、新天皇践祚があったものの、養和から続く激しい飢饉と戦乱の影響で世情の状況は悪化の一途をたどっており、西の平家や義仲、東の頼朝らによる諸道不通の状況により、庄公の運上物もまったく京都に届かない状況にあった。兼実はこれを「四方皆塞」(『玉葉』寿永二年九月三日条)と表現している。
『玉葉』寿永二年九月三日条
凡近日之天下、武士之外無一日存命計略、仍上下多逃去片山田舎等云々、四方皆塞四国及山陽道安芸以西、鎮西等平氏征討以前、不能通達、北陸山陰両道義仲押領、院分已下宰吏一切不能吏務、東山東海両道頼朝上洛以前、又不能進退云々、畿内近辺之人領、併被苅取了、段歩不残、又京中片山及神社仏寺人屋在家悉以追捕、其外適所遂不慮之前途之庄(公)之運上物、不輸多少、不嫌貴賤、皆以奪取了、此難及市辺、昨日失売買之便云々、天何棄無罪之衆生哉、可悲々々
こうした状況を、兼実は「如此之災難、出自法皇嗜慾之乱世与源氏奢逸之悪行」(『玉葉』寿永二年九月三日条)と、法皇の欲心と源氏の乱行が招いたものと断じた。そして院はこの国難を敢えて見ようとせず、「近日被始大造作云々、院中之上下、歎息之外無他事歟、誠仏法王法滅尽之秋也」と兼実は嘆く(『玉葉』寿永二年九月五日条)。
このような中、京都には「頼朝、去月廿七日出国、已上洛云々、但不信受、義仲偏可立合支度云々、天下今一重暴乱出来歟」と、頼朝上洛の風聞も入っており、不和と噂された義仲との合戦も予想される事態でもあった。ただ、頼朝上洛の風聞は、義仲の追捕を含めた期待を以て見られていた。実際に兼実は「義仲院御領已下併押領、日々陪増、凡緇素貴賎無不拭涙、所憑只頼朝之上洛云々、彼賢愚又暗以難知、只我朝滅亡、其時已至歟」と期待をこめつつも、頼朝が義仲と同類であれば国の滅亡は必至であると述べている(『玉葉』寿永二年九月五日条)。
義仲は故兄八條院蔵人仲家(源三位頼政猶子)とは異なり、上野国で生まれたのち在京経験はなく公家との折衝に未熟であり、政治的に翻弄されやすかったと思われる。故実の大家であった入道関白との連携はこうした点を補強するものではあったが、入道関白自身が法皇と激しい対立関係にあったことは、法皇との意思疎通を困難にする要因ともなった。また、義仲勢は諸勢力の混成軍であったことで指揮系統が定まらずに兵士の狼藉が頻発。義仲自身も放置し、民衆や公家らの信認をますます失うこととなる。北陸宮(以仁王子)を旗印に奉じるも有効に活かせぬまま祖父法皇の手に委ねてしまうなど、義仲の評判は崩壊していくことになる。
頼朝の上洛については、9月2日に源中納言雅頼子・左少弁兼忠の乳母夫の齋院次官中原親能から齎された情報で「頼朝必定可上洛」であり、「十日余之比、必可上洛、先為頼朝之使、有申院事、親能可上洛也、万事次可申承」ということであった(『玉葉』寿永二年九月四日条)。齋院次官親能は「与頼朝甚深之知音」で当時頼朝のもとに逃れており、彼からの飛脚であることから頼朝の意思が働いた情報であったことがうかがえる。さらに観性法橋の報告では「頼朝今月三日出国、来月一日可入京、是必定之説也」という。ただ兼実は「猶不被信受事也」と疑いを解いてはいない。ただし、当時の頼朝は、正妻の北条氏(のちの平政子)が臨月を迎えて諸事慌ただしく、飢饉の中での大軍を率いた上洛など思いもよらない時期である。親能が雅頼へ発した上洛に言及した使者は、頼朝が義仲を牽制する目的で流した飛語ではなかろうか。
なお、頼朝御台所の出産については、8月11日夜、御台所が産気づいたことから、頼朝は祈祷のために伊豆山権現、箱根権現ならびに近国宮社に奉幣使を立て、常胤の孫「千葉小太郎」は「下総香取社」への使者となっている(『吾妻鑑』寿永二年八月十一日条)。翌12日、「御台所男子御平産」と、嫡男頼家が誕生している(『吾妻鑑』寿永二年八月十二日条)。8月16日の「若君五夜之儀」は「上総介広常」が沙汰し、8月18日の「七夜之儀」は常胤の沙汰で執り行われ、妻・秩父重弘女が頼朝に陪膳した。常胤と六人の子息は白水干袴の装束で侍の上に着し、その後、嫡男・胤正と次男・師常が甲冑、三男・胤盛と四男・胤信が鞍置馬、五男・胤通が弓、そして六男・胤頼は剣を進物として捧げ、庭に居並んだ。「兄弟皆容儀神妙壮士」という姿を見た頼朝は「殊令感之給」い、侍に居並んだ「諸人又為壮観」と賞賛したという(『吾妻鑑』寿永二年八月十八日条)。
『吾妻鏡』寿永元年八月十八日条
このころ平家は「余勢全不減、四国並淡路、安芸、周防、長門、幷鎮西諸国一同与力了」であり、さらに「貞能已下、鎮西武士菊池原田等、皆以同心、鎮西已立内裏随出来、可入関中云々、明年八月可京上之由結構云々、是等皆非浮説也」(『玉葉』寿永二年九月五日条)と伝わり、平家党はもともとの勢力圏である九州および西国に盤石の勢力を確保していた。東海道、近畿京洛、北陸道での平家の敗戦は、大飢饉による兵糧不足からの軍勢催促の停滞、士気の低下、軍規の乱れなどを発端としたものであって、平家の勢力は決して弱体化していなかった。院は義仲に平家追討を命じるべく、9月19日、院御所に義仲を召すと「天下不静、又平氏放逸、毎事不便也」と告げる。義仲は「可罷向ハ、明日早天可向」と請け、院は手ずから御剣を義仲に授け、20日、義仲は「左馬頭義仲、為追討平氏、下向西国」した(『百錬抄』)。しかしこの出立はあまりに急であり、「義仲今日俄逐電、不知行方、郎従大騒、院中又物騒」とその郎従も知らされないほどであった。実は院は行家も同道するよう再三伝えていたものの義仲は拒絶。この俄な出立は行家の同道を嫌ったためであった。
なお、義仲の平家追討の目的の一つは、のちに義仲が帰洛した際に院へ伝えた「忽討平家事不可叶、平氏猶存者、西国之運上、又不可叶」(『玉葉』寿永二年閏十月十八日条)からもわかる通り、鎮西・西国を支配し運上物を掠取する平家から、運上物を回復させることだったことがわかる。
寿永2(1183)年9月28日頃、平家が京都を脱出してわずか三日後の7月28日に関東へ下向した「先日所遣頼朝許之院庁官(中原康定)」が帰洛した(『玉葉』寿永二年十月一日条)。
康定は頼朝から「三ヶ條事」の要望を記した折紙を預かり持ち帰っている(『玉葉』寿永二年十月二日条)。兼実は実見していないが「或人」から大まかな内容を聞き、日記に記している。兼実が「或人」と記す場合は、兼実がそれほど面識のない廷臣や院祗候の人(いずれも殿上人)のことと思われるが、直接その「或人」から「情報」を聞いた場合であろう。
●「或人」から兼実への伝聞
| 1 | 平家押領之神社仏寺領、慥如本可付本社本寺之由、可被下宣旨、平氏滅亡為仏神之加護之故也 | 平家が押領した寺社領を、本主へ返付することの宣旨を下すこと。平氏の滅亡は神仏の加護である。 |
| 2 | 院宮諸家領、同平氏多以慮掠云々、是又如本返給本主、可被休人怨 | 権門領も多く平氏に奪われており、これも本主へ返すこと。 |
| 3 | 帰降参来之武士等、各宥其罪、不可被行斬罪、其故何者、頼朝昔雖為勅勘之身、依全身命、今当伐君御敵之任、今又落参輩之中、自無如此之類哉、仍以身思之、雖為敵軍、於帰降之輩、寛宥罪科、可令存身命 | 降参する武士等は宥免して斬罪の処することのないように。理由は、自分が助命されたことで、朝敵を討つ任を得た。将来謀反の輩が出ないとも限らず、そのとき私のような輩が同じように朝敵を討つかもしれないからである。 |
その二日後の10月4日夜、「大夫史隆職」が兼実を訪問し、「密々持来頼朝所進合戦注文并折紙等、院御使庁官所持参」という。隆職が密かに頼朝からの文書を院御所から持ち出して兼実に見せたのであろう。兼実はこれを読んで、10月2日に聞いた内容と差異がないことを確認しつつ、「然而為後代注置之」と、頼朝の折紙の内容をメモしている。ただ「合戦注文」については兼実は興味がなかったのか「合戦記、不遑具注」と写していない。
●頼朝所進の「折紙」
一 可被行勧賞於神社仏寺事
右、日本国者神国也、而頃年之間、謀臣之輩、不立神社之領、不顧仏寺之領、押領之間、遂依其咎、七月廿五日忽出洛城、散亡處所、守護王法之仏神、所加冥顕之罰給也、全非頼朝微力之所及、然者、可被行殊賞於神社仏寺候、近年仏聖灯油之用途已闕、如無先跡、寺領如元可付本所之由、早可被宣下候、
一 諸院宮博陸以下領、如元可被返付本所事
右、王侯卿相御領、平家一門押領数所、然間、領家忘其沙汰、不能堪忍、早降聖日之明詔、可払愁雲之余気、払災招福之計、何事如之哉、頼朝尚領彼領等者、人之歎相同平家歟、宜任道理有御沙汰者、
一 雖奸謀者、可被寛宥斬罪事
右、平家郎従落参之輩、縦雖有科怠、可被助身命、所以者何、頼朝蒙勅勘雖坐事、更全露命、今討朝敵、後代又無此事哉、忽不可被行斬罪、但随罪之軽重、可有御沙汰歟
以前三ヶ條事、一心所存如此、早以此趣可令計奏達給、仍注大概上啓如件、
この記述は、几帳面な兼実が記したメモであり、頼朝の折紙をほぼそのまま記している可能性が高い。頼朝の主張は、大略寺社領の本主返付(平家の都落ちは神仏の罰で頼朝の力ではない)、諸院宮・卿相以下、平家一門に押領された所領の本主返付(押領による家政の困窮を解消)、降参する平家与党の助命(将来朝敵が生じたときに助命した者が朝敵を討つかもしれない可能性)というものである。また、7月28日の院宣には頼朝に対しても「今当伐君御敵之任」「今討朝敵」が記されていたことが判明する。
続けて、10月6日には頼朝からの使者が大蔵卿泰経のもとを訪れ、「所欝申、義仲等可伐頼朝之由、結構事」の奏状が泰経を通じて院奏された。兼実は二日後の10月8日に報告を受けているが(『玉葉』寿永二年十月八日条)、中原康定のもたらした頼朝折紙と同様、具体的な内容を知らされなかった。翌10月9日、院近臣の静賢法印が兼実を訪れて「談世間事等」しているが、このとき頼朝の使者が「忽不可上洛」を述べたことを伝えている(『玉葉』寿永二年十月九日条)。
頼朝の上洛延引は、「秀平隆義等、可入替上洛之跡」と「率数万之勢入洛者、京中不可堪」の二つの理由があり、とくに東西飢饉と運上の途絶による消費都市京都が飢餓に見舞われている中、数万にも及ぶ軍勢が上洛した場合の惨状を鑑みてのことで、今は頼朝自ら上洛することは差し控えるべきとの判断を下したとみられる。この使者から頼朝の人物像を聞いたのか、静賢法印は頼朝の印象を「凡頼朝為躰、威勢厳粛、其性強烈、成敗分明、理非断決」と述べる(『玉葉』寿永二年十月九日条)。
●『方丈記』より養和の飢饉の状況
また、養和のころとか、久しくなりて覚えず、
二年があひだ、世の中飢渇して、あさましき事侍りき、或は春夏ひでり、或は秋大風、洪水など、よからぬ事どもうちつづきて、五穀ことごとくならず、夏植うるいとなみありて、秋刈り、冬をさむるぞめきはなし、これによりて、国々の民、或は地をすてて境を出で、或は家を忘れて山に住む、さまざまの御祈りはじまりて、なべてならぬ法ども行わるれど、さらにそのしるしなし、
京のならひ、何わざにつけても、みなもとは田舎をこそ頼めるに、絶えて上るものなければ、さのみやは操もつくりあへん、念じわびつつ、さまざまの財物、かたはしより捨つるがごとくすれども、さらに目見立つる人なし、たまたま換ふるものは金を軽くし、粟を重くす、乞食道のほとりに多く、憂へ悲しむ声耳に満てり
頼朝が今回京都に使者を遣わしたのは、この「忽不可上洛」とともに法皇へ「所鬱申」が主題であった。頼朝が述べる不満は静賢法印によって以下の二点が兼実に報告されている(『玉葉』寿永二年十月九日条)。
(1)「三郎先生義広上洛也本名義範」
(2)「義仲等不逐平氏、乱朝家尤奇怪、而忽被行賞之條、太無謂」
これに対して兼実は「申状等、有其理歟」と一応納得する姿勢を示している。とくに(2)については、頼朝は親交のあった高尾神護寺の文覚上人を通じて義仲を勘発しており、「頼朝以文覚聖人、令勘発義仲等云々、是追討懈怠、並損京中之由云々、即付件聖人陳遣」(『玉葉』寿永二年九月廿五日条)と平家追討の懈怠と京中の混乱について責めたという。
去る8月11日、義仲と行家は除目によってそれぞれ「従五位下」へ昇叙し、義仲は左馬頭兼越後守、行家は備後守に補任されていた(『玉葉』寿永二年八月十二日条)。それにも拘わらず、勲功第一という頼朝はなおも流人で勅勘が解かれていない状況にあった。頼朝の「鬱」はこれに対する理不尽を述べたものだろう。頼朝の奏状を受けたわずか三日後の10月9日夜、法皇は「頼朝復本位之由」を指示する(『玉葉』寿永二年十月九日条)。こうして流人源頼朝は本位の従五位下へ復し、勅勘が解かれた。ただし、官職には任じられることはなく「前右兵衛権佐」のままであった。
10月13日、兼実のもとに「大夫史隆職」が来訪し「談世上事等」したが(『玉葉』寿永二年十月十三日条)、このとき隆職は「先日為御使、向頼朝許、去比帰洛」した「院庁官々史生泰貞」が「重為御使、可赴板東」ことを伝えている。これは、翌10月14日に下される「依頼朝申行」って定められた「東海、東山、北陸三道之庄薗、国領如本可領知之由、可被宣下之旨」(『百錬抄』)を伝える使者であろう。それとともに、「与義仲可和平之由」(『玉葉』寿永二年閏十月十三日条)をも命じる使者とみられる。このとき、隆職も頼朝の印象を兼実に伝えているが、兼実は「不遑記」と素っ気なく記しており、頼朝の為人については興味を抱くレベルではなかったようだ。
宣旨が下される前日の10月13日、兼実は家領ながら不通となっていた能登国若山庄を「今遭善政、欲休愁憤」として当知行領掌についての解状を朝廷に提出している(寿永二年十月十九日「官宣旨」『宮内庁書陵部所蔵九条家文書』)。
この文書に見える「殊被下宣旨」が10月14日に「東海 東山 北陸 寿永二十」と見える東海道、東山道、北陸道の三道の寺社権門ら庄園の本家本所などに下された「御領重宣旨」に相当する(寿永78二年十月十九日「官宣旨」『宮内庁書陵部所蔵九条家文書』)。能登国若山庄はもちろん、三道に所在する九條家の庄園に対しても宣旨が下されており、宣旨には「端云、応令右大臣家如元領掌諸国所在御厨并庄園、位田、大番舎人、庁宣等名田事」が記されていた。九條家に下された宣旨は国別に十五通にのぼった。
| 東海道 | 尾張国内杜庄 下総国三崎庄 伊賀国(四か所) 伊勢国御厨・家領等(五か所) 武蔵国(四か所) 伊豆国(三か所) 遠江国尾奈御厨 常陸国(三か所) 三河国吉良庄 |
| 東山道 | 美濃国(二か所) 近江国位田・大番舎人・庁宣等 |
| 北陸道 | 越後国白川庄 若狭国(二か所) 能登国若山庄 加賀国(二か所) |
そして、10月14日、朝廷は頼朝が求める「東海、東山、北陸三道之庄薗、国領如本可領知之由」の宣旨を下した(『百錬抄』)。宣旨の文は遺されていなことから、全体像は掴めないものの、後日義仲が「東海、東山、北陸等之国々所被下之宣旨云、若有不随此宣旨之輩者、随頼朝命可追討」(『玉葉』寿永二年閏十月廿日条)ことに強烈な不満を述べているため、次の二つの内容が記されていたことは確実である。
●寿永二年十月十四日「東海東山北陸等之国々所被下之宣旨」等の内容
| (1) | 東海、東山、北陸三道之庄薗、国領如本可領知 |
| (2) | 若有不随此宣旨之輩者、随頼朝命可追討(東海、東山道等庄土、有不服之輩者、触頼朝可致沙汰) |
この宣旨は(1)が主文であることは明白なので、宣旨の「事書」部分に(2)は記されないと考えられる。つまり(2)はあくまでもその「執行のために付された条件」に過ぎず、これを以て頼朝が東国行政権を取得したと考えるのは誇大解釈であろう。
しかし、頼朝にとっては(2)の条件が非常に重要な意味を持ったことは確実であり、頼朝は院との交渉によって、この付帯文を宣旨に入れることに成功した。これにより、義仲が勢力下においていた北陸道について「若有不随此宣旨之輩者、随頼朝命可追討」ということであれば、例えば義仲の影響下にある北陸道の在庁や国人らが抵抗(抵抗せずとも抵抗したと称すれば済む)した場合は、頼朝が公的に「不随此宣旨之輩者」を追捕できるという意味を持ったのである。義仲がこれに嚙みついたのは当然であろう。
なお、「沙汰」は「追討」のことであって、決して国衙行政に関する権限ではない。あくまでも庄園の本主返付の宣旨に背いた者を追捕する「だけ」の権限である。しかし、この権限は頼朝をして東海道、東山道、北陸道の諸国庄園に介入が「でき得る」公権となり、これを堂々と前面に押し出して、後日、九郎義経を大将軍とする使者が伊勢国へと派遣された。「頼朝使、雖来伊勢国、非謀叛之儀、先日宣旨云、東海東山道等庄土、有不服之輩者、触頼朝可被沙汰云々、仍為施行其宣旨、且為令仰知国中、所遣使者也」(『玉葉』寿永二年閏十月廿日条)と見るように、義経の伊勢発向の目的の一つは「宣旨」の施行と周知であったことがわかる。伊勢国は東海道と畿内を結ぶ要衝鈴鹿山があり、義経はここで鈴鹿山付近に広く蟠踞する伊勢平氏の一族・前出羽守信兼を麾下に収めている。これも宣旨の(2)を根拠として協力を求めた結果の可能性があろう。
この「十月十四日宣旨」に基づいて、東海東山北陸三道の諸国の国衙に対し、10月14日以降、官宣旨が下されており、前述のように兼実も10月19日に能登国若山庄の知行回復の官宣旨が下されている(九條家は10月13日に解を提出している)。なお、当時の能登国司は院近臣高階隆経であったが、彼は11月28日に下巻された。吉田経房はその理由は「不知是非、嗟嘆、悲哉々々」と記し(『吉記』寿永二年十一月廿八日条)、「今度逢事人、皆射山近習之輩也」とあることから、後述の義仲による法住寺合戦後の法皇近臣への懲罰人事である。
そして、10月14日頃に「与義仲可和平之由」(『玉葉』寿永二年閏十月十三日条)の院宣(カ?)、ならびに「東海、東山、北陸三道之庄薗、国領如本可領知」と、「東海、東山、北陸等之国々」で「若有不随此宣旨之輩者、随頼朝命可追討」(『玉葉』寿永二年閏十月廿日条)の宣旨を伝える院使中原康定が再度関東へ下った。
なお、10月23日、兼実は「或人」から「義仲ニ可賜上野、信濃、不可虜掠北陸之由、被仰遣了、又頼朝之許ヘモ件両国可賜義仲、可和平之由被仰了」という話を聞く(『玉葉』寿永二年十月廿三日条)。これは「此事依或下臈之申状」を「俊堯僧正一昨日参院御持仏堂時」して「申此由法皇」したところ、法皇は「称善、即従奏上諫言、忽被降此綸旨了」というものだった。兼実はこれを聞いて「此條愚案一切不可叶、凡国家滅亡之結願、只在此事、可指弾々々々」と痛烈に批判している(『玉葉』寿永二年十月廿三日条)。
ただし、この風聞は当事者の誰にもメリットをもたらさず疑問が多い。下記の理由から、この件は結局事実に即したものではなく、さらにその後この話に基づく事象はなく、誤伝であった可能性が高いと考える。
| 「或下臈」が申状を出した目的 | 不明だが、可能性としては北陸道の回復と、義仲・頼朝との和睦により、東国及び北陸道からの運上物を京都へ届くようにするため。 ただし、10月14日の宣旨ですでに東海・東山・北陸三道への宣旨は発出されていることや、この宣旨に反対の者は頼朝が討つ旨を知らせており、わざわざ改めて「或下臈」の申状を受けて綸旨を出す必要はない。そのため、この「或下臈」の申状は、風聞の可能性が高いのではなかろうか。 |
|
| 院近臣たる俊堯僧正と繋がることができる「或下臈」とは誰か | (一)源義仲方 | 俊堯は義仲昵懇の僧侶であり、義仲(下臈ではないが)またはその与党が持ち掛けた可能性も否定できないが、そもそもこの下臈案は、義仲が事実上支配している北陸道を放棄し上野国と信濃国を賜うよう求めるもので、義仲がこのような案を自ら提示することは考えにくい。 |
| (ニ)源頼朝方 | 「朝廷」に東海道、東山道、北陸道の諸庄園などを本主へ戻すべき宣旨を下すよう求めており、東山道に属する上野国を義仲に渡す謂れはなく可能性は低い。さらに上野国を放棄してまで和睦を提案するメリットもない。 | |
| (三)平家方 | 宣旨に関してはまったく関わりがなく可能性はない | |
| (四)院(朝廷) | 三道の庄園国領の本主返還の宣旨を履行するためには、北陸道の回復は必須だが、東山道に属する上野国や信濃国を渡すこともまた、宣旨の履行には逆行するため、院や朝廷の意向とも合致しない。 | |
| 地下人であろう「下臈」が高度な政治的機微を知り得ている理由 | 不明。 | |
この翌日の10月24日、兼実は院使中原康定が関東へ伝えた和平の綸旨について、「頼朝、先日付院使泰貞也、令申事等、各無許容、天下者君之令乱給ニコソ」と述べて「挙縁即塞其路、美乃以東欲虜掠」という伝聞を受けている。ただ、兼実は三ヶ条の折紙から頼朝の考えを確認しており、「但此條不知実説」と疑義を以て記している(『玉葉』寿永五年十月廿四日条)。実際に頼朝からの使者が届いていたのかは不明だが、この当時、中原康定は鎌倉にいたであろうことは確認できる。
さらに、10月28日に兼実に届いた伝聞では、頼朝は去10月19日に鎌倉を出立し、11月1日頃に入京するという。兼実は「是一定説」とやや確信を持って受け止めているようである(『玉葉』寿永二年十月廿八日条)。兼実が強く信用している点から、雅頼卿の言であろう。雅頼の家人・斎院次官中原親能が頼朝に出仕しており、その情報が伝えられていたとみられるためである。また、義仲も10月26日に備前国を出立して上洛の途に就いていて、11月4日か5日の入洛するという。平家との戦いの最中に帰還を企てるという不可解な情報に「与頼朝為決雌雄」ということが噂され、院以下の人々は戦々恐々としていた(『玉葉』寿永二年十月廿八日条)。ところが「頼朝難成上洛之間、其実不可然」と聞こえ、一方で「義仲今両三日之間可帰洛」であって、兼実は「洛中又可滅亡」と嘆いている(『玉葉』寿永二年閏十月六日条)。
こうした中、閏10月13日、大夫史隆職が兼実を訪れ、「談世間事」しているが、「院御使庁官泰貞、去比重向頼朝之許了、与義仲可和平之由也」と語っている。これは通説的には10月14日とは別の「閏十月」の宣旨を伝えるために、さらに中原康定が関東下向(十月十四日宣旨を伝えたのちに帰洛し、三度目の下向)したとされるが、隆職が語った「院御使庁官泰貞、去比重向頼朝之許了」は、文面上からも十月十四日宣旨で下向した際の話であることは明らかであり、閏十月の宣旨は存在しない。
●『玉葉』寿永二年閏十月十三日条
十三日戊申 天晴 及晩大夫史隆職来、談世間事、(前略)…院御使庁官泰貞、去比重向頼朝之許了、仰趣無殊事、与義仲可和平之由也、抑、東海、東山、北陸三道之庄薗、国領如本可領知之由、可被宣下之旨、頼朝申請、仍被下宣旨之處、北陸道許、依恐義仲、不被成其宣旨、頼朝聞之者、定結鬱歟、太不便事也云々、此事未聞、驚思不少々々、此事隆職不耐不審、問泰経之處、答云、頼朝ハ雖可恐在遠境、義仲当時在京、当罰有恐、仍雖不当被除北陸了之由令答云、天子之政、豈以如此哉、小人為近臣、天下之乱無可止之期歟、…(後略)
十三日戊申 天晴 晩に小槻隆職が亭に来て世上の話をした。(前略)「…院御使庁官の中原泰貞は去比に再度頼朝のもとに下向した(7/28関東下向⇒9/28以前帰洛⇒10/14再度関東下向)。院の仰せは特別なものではなく、義仲と和睦せよというものだった。さて、東海、東山、北陸の三道の庄薗と国領を本主が領知すべしと宣下されるよう、頼朝が申し請うたため、宣旨が下されたが、北陸道だけは義仲の反発を恐れてその宣旨はならなかった。頼朝がこれを聞いたら間違いなく不満を示すであろうし、甚だけしからん事である」と語った。
このような事は聞いたことはなく非常に驚いた。小槻隆職はこのような事が本当にあり得るのか訝しく思い、院の近臣である大蔵卿泰経に問うたところ、泰経は「(この決定については)頼朝は恐るべき人物だが在所は遠く、反対に義仲は現在在京であり逆恨みされる恐れがある。このため不当とはわかっているが、北陸道は除いた」との返事だった。
天皇の政治はこのようなものか。いやそうではない。器量のない者が近臣となって天下の乱れを止めることができないためか。
隆職の話によれば、頼朝の申請「東海、東山、北陸三道之庄薗、国領如本可領知之由、可被宣下之旨」に基づいて10月14日に「仍被下宣旨」たが(『玉葉』寿永二年閏十月十三日条)、このとき「北陸道許、依恐義仲、不被成其宣旨」と、頼朝の要求していた荘園や国衙領の本所返付の宣旨が、義仲を恐れた法皇によって、急遽北陸道が対象外とされたという。隆職は「頼朝聞之者、定結欝歟、太不便事也」と怒りの言葉を発し(『玉葉』寿永二年閏十月十三日条)、兼実は「此事未聞、驚思不少」と初耳で驚きを禁じ得ず、隆職もこれを聞いたときはあまりのことに院近臣高階泰経に問うたところ「頼朝ハ雖可恐在遠境、義仲当時在京、当罰有恐、仍雖不当被除北陸了」という。これを聞いた兼実は「天子之政、豈以如此哉、小人為近臣、天下之乱無可止之期歟」と語っている。兼実の嘆息が聞こえるようである。
ただし、兼実は10月19日に能登国若山庄に対する宣旨を下されていることから、この北陸道を除くという宣旨が「実際に出されたとすれば」少なくとも19日以降となる。しかし、閏10月13日まで兼実が噂レベルでも知り得ていないということは、北陸道の庄公への宣旨がしっかり下され遅滞はなかったということになろう。閏10月15日に急遽中国地方から帰洛した義仲の屋敷に、20日、院が静賢法印を遣わした際に、「奉怨君事二ヶ条」のひとつとして「東海東山北陸等之国々所被下之宣旨云、若有不随此宣旨之輩者、随頼朝命可追討」(『玉葉』寿永二年閏十月十六日条)とあることからも、義仲のもとに下された宣旨にもしっかり「北陸道」が記されていて、それが削られた宣旨は伝えられていなかった=存在しなかったことがわかる。
●「寿永二年十月宣旨」の時系列
| 7月28日 | 「下遣御使於頼朝許、庁官康定下向」している。内容は推測だが以下の通り。 (1)同日に義仲・行家に下された平家追討令と同内容の可能性。 ⇒10月の頼朝返書に「今討朝敵」(「或人」の意訳で「今当伐君御敵之任」)とある (2)「関東北陸庄園、京中狼藉可被止事」が下命されている可能性。 ⇒二日後の7月30日に頼朝・義仲・行家に命じられている。 |
『百錬抄』 『吉記』 |
| 7月30日 | 「頼朝、義仲、行家等勧賞并関東北陸庄園、京中狼藉可被止事也」 | 『百錬抄』 |
| 9月28日以前 | 院使中原康定が帰洛。関東から「合戦注文并折紙」を持ち帰り、院奏。 静賢法印、小槻隆職らは実見か。 |
『玉葉』 |
| 10月1日 | 兼実、中原康定の帰洛を伝え聞く。 | 『玉葉』 |
| 10月2日 | 「或人(源雅頼カ)」から頼朝折紙の内容(三ヶ条)を聞く。 ・寺社領の本主返付の宣旨要求 ・院宮諸家領の本主返付 ・降参する武士の助命 ※このほか、頼朝は「東海、東山、北陸三道之庄薗、国領如本可領知之由、可被宣下之旨」を申し請うた。 |
『玉葉』 |
| 10月4日 | 兼実、小槻隆職が密々で持参した頼朝の「合戦注文并折紙」を実見しメモする。 | 『玉葉』 |
| 10月6日 | 頼朝の使者が高階泰経を訪れて法皇に二ヶ条を報告 ・義仲等が頼朝討伐の用意をしていることへの不満 ・信太義広の上洛 ・義仲等が平家追討もしないのに行賞されるのはまったく道理に合わない ⇒義仲等は従五位下と国司に叙任。頼朝は勅勘の流人のまま。 ・頼朝自身の上洛は延引する ・藤原秀衡、佐竹隆義が頼朝関東留守中に攻め入る噂 ・数万の兵が入洛した場合、飢饉の京都は壊滅する |
『玉葉』 |
| 10月8日 | 兼実、頼朝使者の上洛を聞く。 | 『玉葉』 |
| 10月9日 | 兼実、静賢法印から頼朝使者の申状を聞く。 夜除目で、頼朝、従五位下の復本位。 |
『玉葉』 |
| 10月13日 | 兼実、小槻隆職から「去比帰洛」した中原康定が、再度鎌倉へ下る計画であることを伝えられた。翌月閏10月13日の記事から、「与義仲可和平之由」を伝えることが主目的の使者である。 この他、翌日下される宣旨内容も伝えたとみられる。 |
『玉葉』 |
| 10月14日 | 朝廷、頼朝の申請に基づき (1)「東海、東山、北陸三道之庄薗、国領如本可領知之由、可被宣下之旨」に則った宣旨 が下され、三道諸国の寺社領や庄園へ個々に宣旨が記されていった。 (2)「東海、東山道等庄土、有不服之輩者、触頼朝可致沙汰」された。 この「沙汰」とは「若有不随此宣旨之輩者、随頼朝命可追討」と同義であることから、頼朝に不満分子を追討させることである。 ※「北陸道許、依恐義仲、不被成其宣旨」ともされるが、事実ではない可能性が高い。 |
『百練鈔』 |
| この頃 | 中原康定が関東へ下向したとみられる。目的は「仰趣無殊事、与義仲可和平之由」である。その「和平」についての内容は不明だが、10月9日除目の頼朝の復本位の除書が伝えられたか。 | |
| 10月21日 | 「下臈(義仲か)之申状」を義仲入魂の俊堯僧正が院に伝えたという。内容は、 ・義仲へ上野国、信濃国を賜う代わりに北陸道の慮掠を禁じる ・頼朝には両国を義仲に賜い、和平する というもの。院もこれを「善」としてすぐさま「綸旨」が下されたという。 ただし、前後の状況から、この風聞は事実ではない可能性が高い。 |
『玉葉』 |
| 10月23日 | 兼実、「或人」から21日の綸旨のことを伝えられ、「此條愚案一切不可叶、凡国家滅亡之結願、只在此事、可弾指々々」と激怒する。 | 『玉葉』 |
| 10月24日 | 兼実、院が示した頼朝・義仲との和平案に頼朝が「各無許容、天下者君之令乱給ニコソ」と述べたという伝聞が届く。また「挙縁即塞其路、美乃以東欲虜掠」とも伝わるが、兼実はこの情報には疑義を感じている。 | 『玉葉』 |
| 閏10月13日 | 兼実、小槻隆職から去る10月14日宣旨の成立過程を聞く。 ・頼朝は「東海、東山、北陸三道之庄薗、国領如本可領知之由、可被宣下之旨」を申請し、院もこの意向に沿って東海道、東山道、北陸道の諸国の寺社領や庄園などに宣旨を出したが、その後、「北陸道許、依恐義仲、不被成其宣旨」されたという。兼実は「此事未聞、驚思不少々々」と驚愕している。隆職は、頼朝はまだ北陸道が除かれた理由を知らないが「頼朝、聞之者、定結鬱歟、太不便事也」と感想を述べている。 |
『玉葉』 |
一方、このころ、西下していた義仲勢の一部が備前国に攻め入り、備前国及び備中国で蜂起した平家方の国人と合戦し、これを悉く討ち取った上、その跡を焼き払って備前国に退いたという(『玉葉』寿永二年十月十七日条)。
平家の軍勢は「頗洛中令属静謐之由依有風聞、去年十月、出御鎮西、漸還御之間」と、寿永2(1183)年10月に九州の御所を出御して上洛の途に就いたという(『吾妻鏡』寿永三年二月廿日条)。ここに「閏十月一日、称帯 院宣、源義仲於備中国水嶋、相率千艘之軍兵、奉禦万乗之還御」と、木曾義仲が院宣を帯びていると称して備中国水島に攻め寄せ、安徳天皇の還御を妨害したという(『吾妻鏡』寿永三年二月廿日条)。平家の主張は、そもそも西国都落ちは「全非驚賊徒之入洛、只依恐 法皇御登山也」とあるように、法皇の俄かな比叡山行幸(逃亡)により法皇の理解が得られないと判断し、西国行幸することになったとするが、実際は義仲からの天皇及び法皇、神器の死守と西国での形勢立て直しのためであろう。
軍記物ではあるが『源平盛衰記』によれば、「水島合戦」は四国へ渡らんと柏島東岸に布陣する平家勢を、水島海峡を挟んで東の乙島から抑えにかかった義仲勢がぶつかった海戦である。この戦いで義仲は「矢田判官代義清、仁科次郎盛宗、高梨六郎高直、海野平四郎幸広」ら大将格の人々を失うという壊滅的な敗北を喫したという(『源平盛衰記』)。平家は「然而為官兵、皆令誅伐凶賊等畢」(『吾妻鏡』寿永三年二月廿日条)と、自ら官兵を称して「凶賊」義仲を追討したと主張する。平家は天皇及び神器を擁する正規の官軍として振舞っていた様子がうかがえる。水嶋合戦とほぼ同時期、義仲勢は倶利伽羅峠の合戦で降伏していた備前国人妹尾太郎兼康の離反に対応してこれを討ち滅ぼしたとする(『源平盛衰記』)。水嶋合戦は『玉葉』でも「前陣之官軍、多以被敗了」(『玉葉』寿永二年閏十月十四日条)のため義仲勢は播磨国から備中国へ移ったという風聞があった。
その後、院は義仲に上洛せずに駐屯するよう指示。義仲はこれを了承するが、義仲は閏10月13日夕刻、軍勢を返して15日早朝に上洛すると突如院に報告し、「院中之男女、上下周章無極」と院以下は大慌てとなっている。「恰如交戦場」という情報が漏れたため、京中の人々も避難を始めて「一天騒動」という状況であった。兼実はこの情報を聞くのが遅れたため、家司である「範季院臣」に問うと「事已実也」であった。
そして15日、義仲は帰京するが、「其勢甚少」という状況であった(『玉葉』寿永二年閏十月十五日条)。前線に多くの兵士を残しての帰京であるために従兵は少なかったが、水島合戦での大敗によりかなりの兵士を失っていたと思われる。ただ、翌16日に参院した義仲は「平氏一旦雖乗勝、始終不可及不審、鎮西之輩、不可与力之由仰遣了、又山陰道武士等併在備中国、更不可及恐」と、平家勢は恐れるものではないと報告し、帰京した理由は「頼朝弟九郎不知実名、為大将軍、卒数万騎之軍兵、企上洛之由、所承及也、為防其事可忩上洛也、若事為一定者、可行向、為不実者非此限、今両三日之内、可承其左右」という(『玉葉』寿永二年閏十月十七日条)。
二条目が義仲帰京の直接的な原因となったことは確実であろう。ただ、藤原範季が兼実に告げた、義仲が「忽棄敗績之官軍、所迷上洛也」の真の理由は「義仲之所存、君偏庶幾頼朝、殆以彼欲殺義仲歟之由、成僻推歟」というものであった(『玉葉』寿永二年閏十月十八日条)。これでは「忽討平家事不可叶、平氏猶存者、西国之運上、又不可叶」であり、範季の個人的考えであるが「為令討平氏、且為協義仲之意趣、法皇起自叡慮、早可令赴西国御也、只先可有臨幸播磨国、然者南西国等之住人等、皆向風子来也、其時発鎮西等之勢、可誅伐平氏了、以後可有還御也、此外凡無他計」と、法皇の播磨行幸で義仲を支援し、平家追捕を行って還京する計を述べている。
兼実も「其理可然歟」とその理念は理解するも「範季等之議、可謂小人之謀」であり、結局法皇は「偏被釣具義仲等、違乖頼朝之由、決定令存歟」と平家同様に義仲に利用されるだけで頼朝と敵対することになることを危惧。兼実は「此天下猶雖一日、頼朝有可執権之運歟之由、素所愚案也、然者偏被変彼頼朝之条、尤可有思慮歟」と、兼実は頼朝の器量を認め、天下の平穏に一縷の望みをかけていたことが伺える(『玉葉』寿永二年閏十月十八日条)。そして、「只先猶可討平氏之由、被仰義仲、以別使者、又頼朝之許、可被仰遣子細也」とし、法皇下向は「非王者之翔歟」(『玉葉』寿永二年閏十月十八日条)と批判している。
また、義仲は院に対する不満を口にし、関東下向を計画していることが院の耳に入る。閏10月20日、院は義仲の屋敷に静賢法印を遣わして「其心不説之由聞食、仔細如何、不申身暇、俄可下向関東云々、此事等所驚思食也」と問い質した(『玉葉』寿永二年閏十月廿日条)。これに義仲は「奉怨君事二ヶ条」として、「被召上頼朝事、雖申不可然之由、無御承引、猶以被召遣了」ということ、もう一点は「東海東山北陸等之国々所被下之宣旨云、若有不随此宣旨之輩者、随頼朝命可追討」(『玉葉』寿永二年閏十月廿日条)という、いわゆる『寿永二年十月宣旨』の内容に対する不審を強く訴え、「此状為義仲生涯之遺恨也」と激しく批判している。義仲が水島合戦ののち、小勢で慌てて帰京した真の理由は、義仲が留守の間に頼朝と結んだ院が、頼朝代官を入京させようとした事実を把握したためであろう。「東海東山北陸等之国々所被下之宣旨云、若有不随此宣旨之輩者、随頼朝命可追討」については、兼実も「東海東山道等庄土、有不服之輩者、触頼朝可致沙汰」(『玉葉』寿永二年閏十月廿二日条)ことを聞いていることから、事実であろう。頼朝も10月14日の『寿永二年十月宣旨』を受けて、九郎義経を大将とした「頼朝使」を派遣しており、閏10月22日頃「頼朝使、雖来伊勢国、非謀叛之儀、先日宣旨云、東海東山道等庄土、有不服之輩者、触頼朝可被沙汰云々、仍為施行其宣旨、且為令仰知国中、所遣使者也」(『玉葉』寿永二年閏十月廿日条)という
また、義仲は東国下向の件について、「頼朝上洛者、相迎可射一矢之由素所申也、而已以差数万之精兵、令企上洛云々、仍為相防欲下向、更不可驚思食、抑、奉具君可臨戦場之由、議申之旨聞食、返々恐申、無極無実也」と申状に認めて奏上している(『玉葉』寿永二年閏十月廿日条)。義仲はこの申状では不安であったのか、静賢法印が帰ったあと使者を送り、「猶々関東御幸之条、殊恐申、早可承執奏之人云々、件事昨日行家以下一族源氏等会合義仲宅、議場之間、可奉具法皇之由、其議出来、而行家光長等一切不可然、若為此儀者、可違背之由、執論之間、不遂其事、以件子細、行家令密達天聴」と重ねて述べている(『玉葉』寿永二年閏十月廿日条)。
このころ、平家はすでに備前国に進み、美作より西はすべて平家党となっているという風聞があり、播磨へ迫る勢いだという(『玉葉』寿永二年閏十月廿一日条)。義仲が平家と繋がっているという噂もあったようである。義仲は平家に大敗し、院や貴族にも見放され、東には頼朝という強大な敵を控えるという孤立状態に陥っている中で、頼朝は東海・東山・北陸道の庄園・公領を返付する宣旨に基づき、これに異を唱える者を追討する権限を公認され、「仍為施行其宣旨、且為令仰知国中、所遣使者」(『玉葉』寿永二年閏十月廿一日条)という権限も付託されていた。すでに「頼朝使」は宣旨に基づいて東海道を上っており、伊勢国鈴鹿山で起こった戦乱が、宣旨に反発する人々と「頼朝使」との合戦であるとの風聞があるほどであった(『玉葉』寿永二年閏十月廿二日条)。
閏10月22日夜、義仲は自ら参院して、先日も同様の内容を静賢法印を通じて奏上しているが「奉取院、可引籠北陸之由風聞、以外無実、無極之恐」であり、これらは「所相伴之源氏等指行家已下」が勝手に執奏したことで返す返すも恐れ多いことであると主張。また、水島合戦での大敗によって「平氏当時無追討使、尤不便」であるとして、自分の実叔父「三郎先生義広」を追討使に任じることを要請、そして平氏の入洛を恐れて様々に右往左往するのを制止すべきであると奏上した。院は「可奉取院」については世間の風評に過ぎず沙汰に及ばずとし、義広の追討使任命についても許可しなかったが、この内々の理由は彼が「頼朝殊存意趣之者歟」だったためであった。遡ること九か月前の2月、義広は常陸国信太庄に居住していたとみられるが、何らかの理由で頼朝と対立し北関東で合戦に及ぶも敗れた。義広は義仲父・帯刀先生義賢の同母弟(『尊卑分脈』)であり、義仲にとっては実叔父に当たる。ただし義広は関東で頼朝に敗れたのちも義仲に合流することはなく、8月頃に自力で上洛している。もしも義広が敗戦後に義仲と行動をともにし、7月30日の京都守護拝命の時点ですでに同陣していたとすれば、守護地割当に当然義広も含まれているはずである。少なくとも義広上洛はその後で、頼朝がそれを知って院に不満を述べた9月中旬までの一月あまりの間のことである。
●推測系譜(『尊卑分脈』)
源頼信―+―源頼義――源義家―――――――――――――――源為義――――源義朝―――源頼朝
(伊予守)|(陸奥守)(陸奥守) (検非違使) (下野守) (右兵衛権佐)
| ∥
| ∥ +―源義賢
| ∥ |(帯刀先生)
| ∥ |
| ∥――――+―源義広
| +―女子 (帯刀先生)
| ?
| |
| +=源義宗
| |(判官代)
| |
+―源頼清――源家宗――源家俊―+―源重俊――+―源宗信――――源義宗〔恐與上文重俊子義宗同人〕
(陸奥守)(美作守)(左馬助)|(左衛門尉) (上野冠者) (高松院判官代)
|
+―源俊宗――――源義宗〔為重俊子〕
義広の追討使就任が不許可とされたことから、閏10月24日、義仲は再び「以義広可追討平氏之由、申請不許之条、未得其意、猶枉欲遣義広、兼又賜備後国於彼義広、以其勢可討平氏」と奏上。これに院は「全非不許之儀、件男聞食尩弱之由、仍不可叶之由思食、不被仰左右也、而猶可宜之由、於計申者、不可及異儀」と義広が弱いために任命できないが、もしそうではないというのであれば、任命を拒むものではないと返答している(『玉葉』寿永二年閏十月廿四日条)。そして11月1日、源行家が平家追討のため鎮西下向が決定。在京の石川判官代義兼は行家に従軍することとなり、閏10月28日に所領の河内国石川へ戻るために兼実へ暇乞いに訪れている(『玉葉』寿永二年閏十月廿七日条)。このころ「義仲与行家已以不和」であり、義仲が関東下向に際して行家に相供を命じるがこれを拒否。彼らは毎日のように口論するほど険悪となっていた。結局、11月1日は院の御衰日にあたったことから、11月8日に行家と義仲の鎮西下向が決定する。
そのころ京都の風聞では、頼朝は閏10月5日、五万の精兵を率い「相模国鎌倉城」を発って北陸、東山、東海、南海道から上洛を開始したものの、今は遠江国に留まっているという。これは「可討義仲等、為令沙汰事」(『玉葉』寿永二年閏十月廿五日条)であるが、「奥州秀平又率数万之勢、已出白川関云々、仍疑彼襲来、逗留中途、可伺形勢」のためだという(『玉葉』寿永二年閏十月廿二日条)。ところがその後、頼朝は平頼盛入道の鎌倉下向に際して鎌倉に帰還し、「其替」として弟の「九郎御曹司誰人哉可尋聞」に上洛を命じたという。その率いる軍勢は「五千騎勢」で、11月4日には「布和関」に到着したという。九郎御曹司は院庁へ「随御定可参洛、義仲行家等於相防者、任法可合戦、不然者過平事、不可有之由仰合」と奏上(『玉葉』寿永二年十一月四日条)。これを知った義仲は、11月8日の鎮西下向に加わらず「与頼朝軍兵可決雌雄」という(『玉葉』寿永二年十一月五日条)。
この頃には頼盛と子息は鎌倉に到着し、頼朝は御所で郎従五十人ばかりを随えて対面した(『玉葉』寿永二年十一月六日条)。また頼朝の義弟である一条能保は、頼朝邸から一町ばかりの所にあった「悪禅師家」に宿したという。悪禅師は頼朝の異母弟で九郎義経の実兄、醍醐悪禅師全成である。また、頼盛は相模国府に戻って宿所としたという。これは「目代」を後見としていたためである。なお、寿永3(1184)年3月28日、「頼盛卿後見侍清業」が上洛し、兼実を摂政とするよう「余事又奏法皇」(『玉葉』寿永三年四月一日条)じたことが見え、頼盛卿を後見した「目代」は「頼盛卿後見侍清業」に該当するか。彼は源中納言雅頼とも連絡を取っており、4月7日、兼実邸を訪れた雅頼卿が「頼盛卿後見史大夫清業」からの言葉を伝えている。彼は「史大夫」であり、かつて弁官を務めた経歴をもつことがわかる。『官吏補任』によれば保元3(1158)年に六位史であった中原清業で、どのような経緯で相模国目代となり、頼盛との関わりを持ったのかは不明。
11月7日、「頼朝代官今日着江州」ということだったが、なんと「其勢僅五六百騎」という。これは「忽不存合戦之儀、只為供物於院之使」(『玉葉』寿永二年十一月七日条)とあり、この頼朝代官は合戦が目的ではなく、ただ院への供物を届けるための使者であったという。このときの頼朝代官は「次官親能広季子、幷頼朝弟九郎」と判明する(『玉葉』寿永二年十一月七日条)。頼朝と京都を繋いでいた斎院次官親能(権中納言雅頼の家人)が代官の一人であることから、朝廷・院への使者の性格も帯びていたことがうかがえる。親能は九郎義経に「付」された(『玉葉』寿永三年正月廿八日条)とあることから、九郎義経が全体の指揮官であると考えられるが、親能は「万事為奉行之者」という位置付けであり、諸事に経験の浅い義経は親能に万事を諮ることを命じられていたと思われる。また、義仲とともに上洛した保田遠江守義定の任国・遠江国を問題なく通過していることから、保田義定はすでに義仲から離れていたのであろう。
翌11月8日、当初の予定通り「備前守源行家」が平家追討のため西へ向った。義仲は東への対応のために前日に離脱している。兼実が見物者から聞いたところによれば、行家の軍勢は「其勢二百七十余騎」(『玉葉』寿永二年十一月八日条)であるという。兼実は「太為少如何」と疑問を呈しているが、これが行家自身の配下および郎従であったのだろう。義仲の援兵がなかったのは当然であるが、義仲勢の一翼を担っていた行家の軍勢はこの程度であり、もはや義仲勢自体が寡少であったことを意味するのであろう。
行家勢はそのまま西へ下り、一気に備前国まで進んだ。行家は国守として出京直後から備前国に軍勢催促を命じたとみられ、国検非違使所別当の惟資や国武者(国衙の武士であろう)が行家に同調している。この動きに対し、三位中将重衡を大将軍とした三百余騎が「備前国東川(吉井川)」まで進軍。備前国府(岡山市国府市場)の検非違使別当惟資らが攻め懸かったものの敗北。行家の軍勢も加わっていたとみられ「武蔵国住人■四郎介并子息被打取了」と武蔵国の「■四郎介」という人物が討たれている。検非違使別当惟資は国府へと退き、北部の山中へと入った後、「西川(旭川)」から千騎ばかりを率いて再び平家勢に襲いかかったが敗れる。日暮れとなり、国人らは明暁攻め寄せんと言う所を、惟資は「即時令寄」と、三度攻め寄せたため、平家勢は敗走。「平氏方五十四人被打取、源氏方国人雑人廿人許被打了」であった(『吉記』寿永二年十一月廿八日条)。
11月10日、院は澄憲法印を近江に駐屯する「頼朝使」の源九郎冠者のもとに遣わし、さらに義仲にも「頼朝使入京、不可欝存之由」を伝えている。義仲は「不悦之色」を見せながらもやむなくこれを了承。さらに「於無勢者強不可相防之由」も伝えている(『玉葉』寿永二年十一月十日条)。院は義仲をすでに見限っており、義仲の排除のために、宿直に義仲一人召さない、義仲が嫌う頼朝の代官入京に対して文句を言わさないなど、只管に彼を孤立させ徹底的に追い詰めていったのである。義仲はすでに疑心暗鬼の塊になっており、「義仲因可被征伐之由、殊用心欝念之余、如此承及之由、令申院」(『玉葉』寿永二年十一月七日条)という状況であった。
寿永2(1183)年11月16日、法皇は「可臨幸南殿、御用心之体、万倍於日来」(『玉葉』寿永二年十一月十六日条)という。義仲に対する警戒であった。さらに「今夕所々堀堭溝釘抜、別段之沙汰」と法住寺殿の周囲に堀をめぐらし、木戸を立ち上げて防衛体制の強化をはかった(『玉葉』寿永二年十一月十六日条)。義仲謀叛の風聞に対する防衛措置であるが、さらに翌17日には「院中武士群集、京中騒動」という状況となった。義仲が「可襲院御所之由、風聞院中」であったためである。一方で義仲邸には「自院可被討義仲之由伝聞彼家」という、まったく逆の情報が寄せられており、兼実は「両方以偽詐有告言之者歟、依如此浮説、彼是堤騒、敢不可」と、両者に偽りの話を流布する人物がいて、両者ともにその詐説に踊らされていると推測している(『玉葉』寿永二年十一月十七日条)。そして「義仲忽無可奉危国家之理、只君構城集兵、彼驚衆之心之條、専至愚之政、是出自小人之計歟」と、義仲が自発的に謀叛を起こすことはなく、これらの騒ぎは院近臣が引き起こしたものだと痛烈に批判している。
そして11月17日、院は「御愛物」の摂政基通を法住寺殿に招いて遊興にふける中、権中納言長方卿を召すと、義仲への侮辱とも取れる内容と平家追討を命じる院宣を下すことを命じ(『玉葉』寿永二年十一月十七日条)、長方卿は「悲泣而退出」する有様であった。
院庁ではこの下命に基づき院宣を作成。院宣は「謀叛之条、雖諍申告言之人、称其実者、不及遁申歟、若事為無実者、速任勅命、赴西国可討平氏、縦又乖院宣、雖可防頼朝之使、不申宣旨、一身早可向也、乍在洛中、動奉驚聖聡、令騒諸人、太不当也、猶不向西方、逗留中夏者、風聞之説、可被處実也、能思量可進退」(『玉葉』寿永二年十一月十七日条)という内容であった。
義仲は以前より謀叛の風聞は事実ではないと使者や自身の参院など三度にわたって奏上し続けており、不実であったと思われるが、院は遊興のままにこのような内容の院宣を下すことを命じたのである。兼実は使者を遣わして「物騒之仔細委可被告示」と院に告げるが、返答はおおよそ義仲謀叛の風聞内容と同様であった。院は謀叛の風聞については一旦は風聞に過ぎないため沙汰に及ばないとしていたにも拘らず、一転してその罪状を問うのである。すでに追い詰められている義仲に対する侮辱ともとれる内容である。
義仲謀叛を疑う者は「明暁可被攻義仲歟」という。しかし兼実は「不能左右、義仲其勢雖不幾、其衆太為勇云々、京中之征伐、古来不聞、若不慮之恐者、後悔如何、小人等近習之間、遂至于此大事、君之不見士之所致也、日本国之有無、一時可決歟、無犯過之身、只奉仕仏神耳」(『玉葉』寿永二年十一月十七日条)と、院近臣の愚かさがこの危機を招いていると口を極めて批判する。そして、その根本的な原因は院の「不見士」、つまり近臣の資質を判断できない、つまり政治に関する直接的な関心のなさであるとしている。結局、法皇の無能ぶりが近臣の増長を招いていると批判しているのである。養和2(1182)年3月12日、前内府宗盛が叔父の院近臣・平親宗を「天下之乱、君之御政不当等、偏汝所為也」(『玉葉』養和二年三月十二日条)と激しく罵倒しているように、院近臣が政務壟断し、「近習卿相等和讒歟云々、所謂朝方、親信、親宗也、小人近君、国家憂、誠哉此事」(『玉葉』寿永三年正月廿七日条)と捉えられていたのである。
翌11月18日、兼実は法皇の召しに応じて法住寺殿に参院し、前日17日の院から義仲へ下された院宣内容が報告される(『玉葉』寿永二年十一月十八日条)。義仲はこの院宣に対し「先可奉立合君之由、一切不存知、因茲度々書進起請了、今被尋下之条、生涯之慶也、於下向西国、頼朝代官引率数万之勢、可入京者、一矢可射之由素所申也、彼不可被入者、早可下向西国」と報奏したという(『玉葉』寿永二年十一月十八日条)。義仲の素願は平家追討とともに頼朝代官との合戦である。院自ら「縦又乖院宣、雖可防頼朝之使、不申宣旨、一身早可向也」と頼朝代官との戦いを認めているのである。もちろん暗に否定的な言い分ではあるが、義仲はこれを逆手に取り「今被尋下之条、生涯之慶也」と暗に院を嘲弄するのである。院宣に載せられている以上、宣旨も必要なく頼朝代官との戦いは認められたことになる。
一方、院は泰経を通じ、兼実に「頼朝代官」の扱いと新帝の法住寺殿行幸を諮るが、兼実は「義仲忽無可奉危国家之理、只君構城集兵、被驚衆之心之条、専至愚之政也、是出自小人之計歟」(『玉葉』寿永二年十一月十七日条)という気持ちがあり、「先院中御用心之条、頗過法、是何故哉、偏被敵対義仲也、太以見苦、非王者之行、若有犯過者、只任其軽重、可被加刑罰」と批判する(『玉葉』寿永二年十一月十八日条)。法住寺殿の周囲を堀で囲み、木戸を設けて城塞化する理由は何なのか。下臈の義仲と直接争うつもりなのか。甚だしく見苦しく「王者之行」とは到底言えない。もし罪を犯しているのであれば、その軽重に応じた罰を与えればよいのだと訴えるのである。そして、義仲を敵視し、院を城塞化する提案をした「小人」すなわち院近臣らを強く批判したのである。
さらに、「如被仰下者、申状已穏便歟、然者先被遣可然之御使、且被尋間浮言之次第、且被勘発所行之不当、若指申告言之輩者、任法可被行刑罰、先罷当時敵対之儀、尤宜歟」(『玉葉』寿永二年十一月十八日条)と、義仲の言い分を聞けば穏便なことしか言っていないではないか。院はまず義仲謀叛の浮言の出所をしっかりと調べ上げ、このようなことを「申告言之輩」を問い詰めて刑罰を行い、義仲との敵対を止めることが優先されることではないかと訴える。兼実の言う「申告言之輩」とはすなわち院近臣を指すとみられる。
そして「義仲若伏理有和顔者、何不赴征伐哉、縦雖可有罪科、出境之後有其沙汰者、不可有当時之怖畏歟、洛中咫尺之間、被敵対君之条、当時後代、朝之恥辱、国之瑕瑾、何事過之哉、若又猶不肯受勅命者、彼時任法可有科断歟、如今之沙汰者、王化如無、甚以見苦歟」(『玉葉』寿永二年十一月十八日条)と、院が正しく義仲と和解して義仲もその理に伏せば、義仲は勇んで平家討伐へ赴くだろう。しかし、もし罪科があったとしても、京都から出征後にその罪を問うべきだとする。これは洛中での混乱を防ぐための措置である。洛中で院が下臈の義仲と戦うことは前代未聞の「朝之恥辱、国之瑕瑾、何事過之哉」ということになる。さらに勅命に背くというのであれば、そのときには法に照らして処罰すればよい。とにかく兼実は「如今之沙汰者、王化如無、甚以見苦歟」(『玉葉』寿永二年十一月十八日条)と、泰経の面前で院の対応の稚拙さを口を極めて諫めるのであった。まさに兼実でなければ為しえない強い諌奏であり、ここでも泰経を含めた「小人為近臣」による「天下之乱無可止之期歟」(『玉葉』寿永二年閏十月十三日条)を暗に強く批判したのである。
法皇はその後、院御所に天皇の行幸を仰ぎ、御所とするのが望ましいかどうかを問うている。兼実は「忽不可然歟」と行幸を否とするが、天皇は閑院御所から法住寺殿へと密かに行幸してしまう(『玉葉』寿永二年十一月十八日条)。誰が行幸を主導したのか不明で「院不知食」で「不図之外有行幸」という。法皇主導の行幸であることは明白であるが、兼実もそれは言い得ない。院御所に行幸させてしまうという既成事実を作ったのち、法皇は兼実に白々しく「不図之外有行幸、以此亭可皇居歟、将又猶以閑院可為皇居歟、可計申」と定長をして問うのである(『玉葉』寿永二年十一月十八日条)。当然兼実は反発して「行幸之条太奇、仍只殿上已下事、可在閑院歟」と院御所は相応しくないと答えた。定長も「左大臣被申旨同前」という。その後、この事に対する問い合わせがあろうかと院中に控えていたが、とくに無いようなので、兼実は泰経に退出の意を伝えて九条邸へ帰還している。その後、大外記頼業が九条邸を訪れて談話し、「摂政自今夜被参宿御所云々、仁和寺宮、八条宮、鳥羽法印等、皆自日来被候院中」(『玉葉』寿永二年十一月十八日条)という。このときの摂政基通の御所泊は「御愛物」という理由ではなく、天皇および摂政を院御所に置くことで、義仲を牽制したものであろう。
兼実は、義仲挙兵があり得ないことであるという判断のもと、行幸は不必要であると考えていたと思われるが、院はおそらく院近臣から得た独自の情報から義仲謀叛の企ては事実と察し、事は喫緊であるとの判断だったのだろう。それに基づいて、急遽法住寺殿を城砦化し、急ぎ天皇、摂政、親王、天台座主らを法住寺殿へ招集、在京武士の催促を行ったと思われる。在京武士では「多田蔵人大夫行綱已下済々焉相従、義仲輩大略参入歟」(『吉記』寿永二年十一月十八日条)とあるように、義仲麾下の人々も大方が法皇方となり、多田行綱と同役の「伯耆守光長」も応じた。また、天台座主明雲を召したのは、延暦寺の僧綱僧兵の参入を期待したものであり、園城寺長吏の円恵法親王の参院により、園城寺僧兵もここに加わっていたのだろう。また、武士らは法住寺殿各所を警固、逆茂木の設置など臨戦態勢を整えている。蔵人頭経房はこれを「非言語之所及也、但偏是天魔之結構也」(『吉記』寿永二年十一月十八日条)と嘆いている。
一方で、義仲入洛以降、仁和寺宮や八条宮などとともに法住寺殿で生活していた「高倉宮号北陸宮」は「女房一両奉具之、去夜令逐電給」うという事変も起こっていた。北陸宮は他の宮とは異なり、以仁王の子という政治的に特別な人物であり、もっとも利用される可能性が高いことから、法皇は万が一に備えて他所へ遷した可能性が高いだろう。その後、北陸宮が義仲と合流することはなく、頼朝のもとへ逃れている。
そして翌11月19日早朝、兼実のもとに義仲挙兵の報が伝えられた。早朝の「義仲已欲襲法皇宮」という一報に、兼実は「不信受之間、蹔無音」(『玉葉』寿永二年十一月十九日条)とショックを受けている。兼実が家司藤原基輔を法住寺殿に遣わして仔細を確認させたところ、基輔は昼頃に帰宅して「已参上之由、雖有其聞、未無其実、凡院中之勢甚為少、見者有興違之色」であったが、その後、左少弁光長の報によれば「義仲之軍兵、已分三手、必定寄之風聞」があるという。兼実はなおも「不信用」であったが、「事已実」であった(『玉葉』寿永二年十一月十九日条)。確たる証拠もないままに義仲挙兵は有り得ないと信じていた兼実の衝撃は大きかったであろう。まさに法皇の予想が的中した形であった。
兼実は九条邸が「大路之頭」であったことから戦乱に巻き込まれかねないと、子息の良通邸へと避難する(『玉葉』寿永二年十一月十九日条)。その途路「黒煙見天」えたが、「是焼払河原之在家」であるという。法住寺殿の西には川沿いに在家が並んでおり、戦闘に巻き込まれたとみられる。また「作時両度」と、合戦の鬨の声も聞えていた(『玉葉』寿永二年十一月十九日条)。また、経房は午の刻、勘解由小路邸から南方に火焔が上がっているのを見る。「奇見之處、院御所辺」(『吉記』寿永二年十一月十九日条)であった。驚いた経房は馬を駆って「再三雖進入」するも「依為戦場、敢以不通、雖馳意馬、不能参入」であった。
法住寺殿の戦いは、「義仲軍破入所々」で「御所四面皆悉放火、其煙偏充満御所中、万人迷惑」(『吉記』寿永二年十一月十九日条)と御所の門や塀は義仲勢に次々に破られて放火されたという。「我勢落ナンズ、落ヌサキニトヤ思ヒケン」(『愚管抄』)という危機感もあったように、多くの麾下源氏が院方へ味方する中、義仲勢は根本被官の「山田、樋口、楯、根井ト云四人ノ郎従」が中心となった軍勢であったようである(『愚管抄』)。また、「三郎先生ト云源氏」こと三郎先生義広も「義仲ニ心ヲアハセテ最勝光院ノ方ヲカタメタリケル」と、御所南部の最勝光院を固めていたことがわかる(『愚管抄』)。
法皇は輿に乗って東へと逃れ、参院の公卿ら十余人は馬や徒歩で四方へ逃げ奔った。女房等も多くは裸形という有様で、防戦に及んだ「伯耆守光長、同子廷尉光経」以外の武士たちも逃げ去ったという(『吉記』寿永二年十一月十九日条)。義仲は法皇を逃すまじと追跡し、「清隆卿堂」のあたりで法皇の輿に追いついた。義仲はここで「脱甲冑参会」すると「有申旨、於新御所辺駕御車、于時公卿修理大夫親信卿、殿上人四五輩在御供、渡御摂政五条亭」(『吉記』寿永二年十一月十九日条)として、院を摂政基通邸へと遷した。すると、花山院大納言兼雅以下十七名の公卿と、頭弁兼光以下の殿上人が五条亭に参入している。
法住寺殿での合戦は武士だけではなく、兼実と親しい大外記清原頼業の二男・主水正「近業」も討たれている(『玉葉』寿永二年十一月廿二日条、『清原氏系図』)。彼は「後白川院上北面」(『清原氏系図』)で治承元(1177)年正月より「直講」に任じられており(『外記補任』)、この日も院に出仕していたのだろう。しかし義仲の攻撃により「中流矢死去卅二」(『玉葉』寿永二年十一月廿二日条、『清原氏系図』)という。また、そのほか、「越前守信行、前近江守高階重章」も「被斬首了」(『皇帝紀抄第七』)といい、さらに、「山ノ座主明雲、寺ノ親王八條宮円慧法親王ト云院ノ御子コレ二人ハウタレ給ヌ」(『愚管抄』)とある通り、延暦寺の長・天台座主明雲と、園城寺の長・八条宮円恵法親王が犠牲となっている。明雲は馬に乗って弟子僧少々とともに蓮華王院の西側の築地を南へ向けて逃れたが、南端(八条坊門小路の延長線上の鴨川東)で田井に落ち、討たれた。なお、このとき同道していた弟子僧の院宮(のちの梶井宮承仁法親王)は「十五六ニテ有ケルガ、カシコク、ワレハ宮ナリト名ノラレ」たので、慌てた武士等は宮を武士の小屋に奉じて唐櫃に据えたという(『愚管抄』)。明雲の首は持ち去られ、西洞院川で発見され、顕真が持ち帰ったという。「八條円恵法親王」は山科の「崋山寺辺被伐取了」(『玉葉』寿永二年十一月廿二日条)とされ、東山を越えて園城寺へ向かっていたのだろう。兼実は「未聞貴種高僧遭如此之難、為仏法為希代之瑕瑾、可悲」と嘆いている。
兼実はこの法住寺殿の合戦を「夢歟非夢歟、魂魄退散、万事不覚、凡漢家本朝天下之乱逆、雖有其数、未有如今度之乱」と嘆くとともに、「義仲者是天下之誡、不徳之君使也、其身滅亡、又以忽然歟、愗生見如此之事、只可恥宿業者歟、可悲」と、ここでも法皇を強く非難する(『玉葉』寿永二年十一月十九日条)。法皇はいわば被害者であるが、その根本的原因をつくったのは法皇自身およびその近臣である。まったくもって自業自得、もはや兼実は院をまったく信用していない様子がうかがえる。「法皇暗文簿、不知先例」(『玉葉』元暦二年正月廿日条)と記すなど、兼実は法皇の資質についても言及している。
一方で「官軍悉敗績」して「奉取法皇了」という結果に、法皇に虐げられ鬱屈していた「義仲士卒等、歓喜無限」と溜飲を下ろしたのであった(『玉葉』寿永二年十一月十九日条)。藤原経房はこの状況を「院御方令逃落給之由有風聞、嗚咽之外更他事不覚」(『吉記』寿永二年十一月十九日条)と嘆き悲しむ。
法皇御所を攻める叛逆行為を働いたにもかかわらず、義仲は謀叛人として咎められていない。もはや義仲を謀叛人だと糾弾できる公卿は兼実を含めて存在しなかったのだろう。義仲は夜に入って「入道関白(松殿基房入道)」を「五条亭(摂政基通邸)」に招き(『玉葉』寿永二年十一月廿日条)、翌21日には「義仲内々示云、世間事申合松殿、毎事可致沙汰」という指示を出しており、義仲挙兵から松殿復権までわずかに2日という手際の良さから、義仲と松殿基房入道は以前から繋がっていたことがわかる。新院御所の亭主で院の「御愛物」であった摂政基通は合戦以前に宇治へ逃亡しており、摂政亭に基通は不在であった。
義仲は入京後、平家と後白河院によって失脚し隠棲していた松殿基房入道を頼り、基房も宿敵平家を京中から追い出した義仲を通じて復権を目指すべく暗躍したのだろう。義仲にとっても平家の息のかかった摂政基通は疎ましい存在であったであろうから、義仲と基房は共通した利害関係を持っていたのである。
寿永2(1183)年11月21日夕刻、宇治へ逃がれていた摂政基通が帰還するが「前駈六人、共七八人、済々威光」(『玉葉』寿永二年十一月廿一日条)という派手なものであった。これを知った兼実は「忍テ可被入京歟」と苦言を呈している。なぜ基通がこのような振舞をしたのかは不明だが、摂政・氏長者の威光を主張したものであろうか。
ところが夜になり、「停摂政前内大臣、以権大納言藤原朝臣師家可為摂政藤氏長者」と、基通の摂政停止、入道関白基房の子・権大納言師家(十二歳)の任内大臣・摂政就任が行われ、同時に藤氏長者も基通から師家へと「相譲」られた(『玉葉』寿永二年十一月廿二日条)。これは「自非参議任大臣幷摂籙事今度始之」(『山槐記』寿永二年十一月廿一日条)という先例なき任大臣であった。藤氏長者の「譲」によって「一ノ所ノ家領文書ハ、松殿皆スベテサタセラルベキ」とされ、「近衞基道殿ハ、ホロホロトナリヌル」(『愚管抄』)状態であった。殿下渡領および摂関家領と伝来の文書は、藤氏長者師家の父・松殿基房入道の沙汰とし、前摂政基通はこれらを強制的に接収された。基通は「ホロホロ」と打ち萎れて院に相談したのだろう。院は義仲に「賀陽院方ノ領ト云ハ、近衞殿ノテテノ中基実殿、賀陽院ノ御子ニナリテ伝ヘ給ヘル方ナレバ、ソレバカリヲバ近衞殿ニユルサルベシヤ」(『愚管抄』)と告げるも、義仲はこれを受け入れなかった。そして、義仲は法住寺殿で敵対した相伴源氏「伯耆守光長已下首百余」(『吉記』寿永二年十一月廿一日条)を五条河原に曝した。
11月28日、新摂政師家の下文で義仲は八十余箇所の所領を賜る。実際は入道関白基房の沙汰によるものであるが、兼実はこれを「狂乱之世也」と嘆いている(『玉葉』寿永二年十一月廿八日条)。そして翌29日夜、院方に属した人々に対する解官処分が行われることとなる。まさに清盛入道が後白河院に対して起こしたクーデター「治承三年十一月政変」を彷彿とさせる「寿永二年十一月政変」の報復人事であった。
●寿永二年十一月政変の解官等者(『吉記』寿永二年十一月廿八日条)
| 人名 | 官途 | 続柄 | 備考・後任 |
| 藤原朝方 | 中納言 | ||
| 藤原基家 | 参議、右京大夫 | ||
| 藤原実清 | 太宰大弐 | ||
| 高階泰経 | 大蔵卿 | ||
| 平親宗 | 参議、右大弁 | ||
| 源雅賢 | 右近衞中将、播磨守 | ||
| 源資時 | 右馬頭 | ||
| 源康綱 | 肥前守 | ||
| 源光遠 | 伊豆守 | ||
| 藤原章綱 | 兵庫頭 | ||
| 平親家 | 越中守 | ||
| 藤原朝経 | 出雲守 | ||
| 平知親 | 壱岐守 | ||
| 高階隆経 | 能登守 | ||
| 源政家 | 若狭守 | ||
| 源資定 | 備中守 | ||
| 平知康 | 左衛門尉 | ||
| 中原知親 | 左衛門尉 | 頼朝挙兵時の伊豆目代(山木兼隆親類) | |
| 藤原信盛 | 左衛門尉 | ||
| 橘貞康 | 左衛門尉 | ||
| 源清忠 | 左衛門尉 | ||
| 清原信貞 | 左衛門尉 | ||
| 藤原資定 | 左衛門尉 | ||
| 藤原信景 | 左衛門尉 | ||
| 卜部康仲 | 左衛門尉 | ||
| 源季国 | 右衛門尉 | ||
| 藤原友実 | 右衛門尉 | ||
| 安倍資成 | 右衛門尉 | ||
| 藤原時成 | 左兵衛尉 | ||
| 藤原定経 | 左兵衛尉 | ||
| 藤原実久 | 左兵衛尉 | ||
| 平重貞 | 左兵衛尉 | ||
| 藤原家兼 | 左兵衛尉 | ||
| 大江基兼 | 右兵衛尉 | ||
| 平盛茂 | 右兵衛尉 | ||
| 藤原基重 | 右兵衛尉 | ||
| 藤原重能 | 左馬允 | ||
| 藤原道貞 | 左馬允 | ||
| 藤原基景 | 左馬允 | ||
| 藤原遠明 | 左馬允 | ||
| 中原親仲 | 左馬允 | ||
| 中原親盛 | 左馬允 | ||
| 平盛久 | 左馬允 | ||
| 解職 | |||
| 紀頼兼 | 官掌 | ||
| 被止出仕 | |||
| 藤原兼雅 | 権大納言(無解官) | ||
一方、備前守行家は11月9日の備前国府付近での戦いで敗れて以降、播磨国まで追い落とされていた。11月28日の合戦で「行家郎従百余人死去、或被生虜」という大敗を喫し、行家に属していた「■■■号木良先生参河■■■平氏也、国平男」という人物が京都へ帰還し、藤原経房に次第を報告している(『吉記』寿永二年十二月七日条)。また、『玉葉』では一日遅い11月29日に合戦が行われ、行家は「忽以敗績、家子多以被伐取了」であったと記されている。そして平家勢は「忽企上洛」という(『玉葉』寿永二年十二月二日条)。
この「号木良先生参河■■■平氏也、国平男」なる人物は、その後に具体的な活躍は見られないが、彼は常陸介平維衡の子、右衛門尉貞衡の子孫とみられる(『桓武平氏諸流系図』)。貞衡の五男・度津五郎貞国は三河国宝飯郡渡津庄(豊川市小坂井町)に入り、その孫の五郎行衡が幡豆郡吉良庄(幡豆郡吉良町)に入り「吉良五郎」を称している。その子・右衛門大夫良衡は五位の右衛門尉となるなど在京武官となっていたことがうかがえ、世代から見て「木良先生」とはこの「良衡右衛門大夫」と同世代となる(正確な系譜は不明である)。なお、右衛門尉貞衡の長男・安津三郎貞清は伊勢国安野津(津市)を本拠とし、その子・鷲尾次郎清綱は備前守忠盛の有力家子として活躍をしている。そして、その孫の鷲尾三郎家綱は「住三川国吉良庄」といい、平家滅亡後に吉良庄の同族を頼ったものか。建久6(1195)年3月10日の頼朝東大寺参詣の供奉人交名に随兵として「吉良五郎」が見えるが、足利家諸氏はまだ吉良庄に入っていないので、彼はこの三河平氏の人物と考えられ、行家の麾下を離れたのちは御家人に列したと思われる。
●三河平氏系図(『桓武平氏諸流系図』)
平維衡――平貞衡――+―平貞清―――平清綱―――平維綱――+―平顕綱
(常陸介)(右衛門尉)|(安津三郎)(鷲尾二郎)(右衛門尉)|(鷲尾次郎)
| |
+―平貞仲 +―平家綱 住三川国吉良庄
|(陽明門院侍長) (鷲尾三郎)
|
+―平貞国―――平遠衡―――平行衡――――平良衡
(度津五郎) (吉良五郎) (右衛門大夫)
●三河平氏系図(『尊卑分脈』)
平維衡――平正度―――平貞衡―――――+―平貞清―――+―平家衡 住伊勢国 +―平顕綱――――平顕清
(常陸介)(帯刀先生)(安濃津左衛門尉)|(中宮侍長) |(鷲尾太郎) |
| | |
| +―平清綱―――平維綱――――+―平良平――+―平良基
| (鷲尾次郎)(鷲尾右衛門尉)|(桑名九郎)|(桑名孫太郎)
| | |
+―平貞国―――――平遠衡 +―女子 +―平桓平
(陽明門院侍長)(住三川国吉良) ∥ (摂津守)
∥
∥――――――平家清
∥
平宗清
(柘植弥平二左衛門尉)
寿永2(1183)年12月2日、播磨国室泊(たつの市御津町)に駐屯していた平家勢に、義仲は「平氏之許、乞和親」という非常手段をとった(『玉葉』寿永二年十二月二日条)。また、法住寺合戦で義仲と対立した多田蔵人大夫行綱は、摂津国多田庄の「引篭城内、不可従義仲命」(『玉葉』寿永二年十二月二日条)という態度を示し、同類とみられていた行家の救援に向うことはなかった。義仲はすでに平家と対峙する力はなく、平家もこれを見越して義仲が乞うた和親についても「平氏不承引」という態度をとった(『玉葉』寿永二年十二月五日条)。
当時、「頼朝代官九郎幷齋院次官親能等」は伊勢国におり、去る11月21日、「院北面之下臈二人公友也」が伊勢国へ下って、九郎らに義仲乱逆の次第を告げている。九郎義経らはただちに鎌倉に使者を送り、使者が戻ったのちにその命に従って入京する旨を伝えた(『玉葉』寿永二年十二月一日条)。代官九郎義経等の軍勢はわずかに五百騎であったが、「其外伊勢国人等多相従云々、又和泉守信兼同以合力」と、伊勢国の国人らならびに和泉守平信兼(頼朝が討った伊豆目代兼隆の父)らも義経に合力した。信兼は伊勢平氏庶流だが平家家人ではなく、保元の乱(1156)時に朝廷に勅定により参会した武士として「下野守義朝、右衛門尉義康、候于陣頭、此外安芸守清盛朝臣、兵庫頭頼政、散位重成、左衛門尉源季実、平信兼、右衛門尉平惟繁」(『兵範記』保元元年七月十日条)が見えるとおり、独立した在京の代表的な武士だったのである。義経に合力したのも平家家人ではなく、義仲の院御所攻めに反発してのものであろう。
12月1日、義仲は院御厩別当となり、朝廷のみならず院の牛馬をも管理する権限を得ることとなる。院御厩案主は「八嶋冠者」とあり(木村真美子氏『中世の院御厩司について』―西園寺家所蔵「御厩次第」を手がかりに―:「学習院大学史料館紀要」10)、尾張源氏の佐渡式部大夫重成の子・八嶋二郎時清か(『尊卑分脈』)。同族の葦敷太郎重隆、高田四郎重家、泉次郎重忠も義仲の有力同盟者として名を連ねる。
12月3日、義仲は院に「頼朝代官日来在伊勢国、遣郎従等追落了、其中為宗之者一人、乍生搦取了」と、頼朝代官を追捕したことと「院中警固、近日陪於日来、至女車マテ、加検知」と、警固のために女車まで検知することを奏上し、院の動きを牽制した(『玉葉』寿永二年十二月四日条)。さらに義仲のもと洛中守護を行っていた挙兵以来の同盟者と言える佐渡守源重隆、右馬助源信国(村上信国)や、右衛門尉源有綱らが相次いで解官されているが(『吉記』寿永二年十二月四日条)、法住寺合戦時に多田行綱や源光長と同様に院方となって義仲と対立した可能性が高いだろう。とくに右衛門尉有綱は源三位頼政入道の嫡子・伊豆守仲綱の子で挙兵以前より頼朝と交流を持っていた人物とみられ、「為征土佐国住人家綱、俊遠等、被差遣伊豆右衛門尉有綱、於彼国有綱、以夜須七郎行家、為国中仕承、今暁首途、件家綱等、依誅土左冠者科如此」(『吾妻鏡』寿永元年十一月廿日条)とあるように、寿永元(1182)年11月20日に頼朝の命により土佐国へ向けて鎌倉を出立している。
●寿永二年十一月政変の解官等者(『吉記』寿永二年十一月廿八日条)
| 人名 | 官途 | 続柄 | 備考 |
| 源重隆 | 佐渡守 | 尾張源氏 | 八島佐渡守重隆 |
| 源信国 | 右馬助 | 信濃源氏 | 村上太郎信国 |
| 藤原助頼 | 左衛門尉 | 利仁流藤氏 | 越前国人・右衛門大夫宗景の子。義仲に協力した稲津新介実澄の従兄弟。 |
| 源経国 | 左衛門尉 | 摂津源氏 | 源頼政入道の叔父・山縣三郎国直の曾孫 |
| 平盛家 | 左衛門尉 | 伊勢平氏 | |
| 源有綱 | 右衛門尉 | 摂津源氏 | 源頼政入道の子・伊豆守仲綱の一子。のち、源義経の家人となる。 |
| 源義任 | 左兵衛尉 | 河内源氏? | 源義佐か。 |
| 平康盛 | 右兵衛尉 | 伊勢平氏? | 「故伊豆右衛門尉家人前右兵衛尉平康盛也」(『吾妻鏡』建久二年十一月十四日条) |
義仲は後白河院を平家のように政権から締め出して幽閉するようなことはせず、入道関白基房と結んで、その子・師家を藤氏長者・内大臣、摂政に祭り上げ、院の権威を利用して事実上の政権運営者となる道を選んでいる。五条亭を院御所として公卿等の参院も許していたが、その参院の人物調査は女車も含めて徹底的に行われた。また左馬頭、院御厩別当として朝廷及び院の公的な行事や軍事実務権も掌握。12月3日、入道関白によって義仲は「領八十六箇所」が与えられ(『玉葉』寿永二年十二月三日条)、12月5日に院庁下文で「平家領義仲可相領之由」(『玉葉』寿永二年十二月五日条)が仰せ下された。もとより後白河院の本心ではなかろうが、事実上、院や朝廷の守護を行う公的な立場を手に入れている。
しかし、西からは平家、東からは頼朝代官の手勢が近づいており、叔父の行家や盟友であった源氏諸勢力も多くが義仲から離れてしまった今、義仲には叔父の美濃守義広の軍勢と家子しか残されていなかった。義仲にはすでに実戦力はほとんどなく、実態は張り子の虎だったのである。それだけに義仲は「与平氏和平事、義仲内々雖骨張」と、平家との「和平」に一縷の望みをかけていたのであった。しかし、弱みを見せたくない義仲は表向き「外相示不受之由」していたのであった。
このような中、平家方が京に迫ったことで義仲は、「来十日、義仲奉具法皇、可向八幡辺、自彼為討平氏、可赴西国」(『玉葉』寿永二年十二月七日条)と、院を奉じて平家を討つことを宣言。「当時御所五条殿」に怪異があったため、法皇は「欲有遷御八条院」と、八条院への遷御を望んだが、義仲はこれを拒んで「為討西国可罷向也、而法皇御在京、非無不審、山門騒動之由風聞、仍奉具法皇欲下向」という提案をしていた。占いでも「不快」との結果であったが、左大臣経宗は「御占事不可及沙汰、義仲所申可然、早可有御幸」と義仲の案に賛成する(『玉葉』寿永二年十二月九日条)。彼らは当初の考え通り、院の影響力を以て戦乱の早期解決を望んでいたのであろう。そして、義仲は「忽八幡御幸之儀」を行おうとするが、兼実が「賢名之士」と認める藤原長方卿が使者を通じ「穢中八幡御幸如何、縦雖無御参社、猶神慮有恐、太以不可然」と義仲を説得。義仲もこれを受け入れ「因茲忽然而延引、穢以降可給候御幸之由定仰了」と行幸延期と決定する。
この当時、義仲は盛んに平家との和親を進めており、俄かに平家追討の軍を起こすとは思えず、さらに追討できる軍事力もなかった。法皇の八幡御幸については「縦雖有御幸、法皇之外他人不可参、不可有行幸、入道関白已下諸卿留洛中、万事可致沙汰、為不損亡京都、申行御幸之由、義仲令称」と、義仲は八幡御幸には法皇のみが行き、天皇はもちろん松殿基房入道以下の諸卿もすべて京都に留まることを指示している。これは平家が和睦の条件として法皇の身柄を要求したことに他ならないのではなかろうか。そして敵対不能な義仲は当然呑まざるを得ず、八幡御幸へと繋がったものであろう。
そして12月10日、「可追討頼朝之由、改宣旨被成下院庁下文」と、義仲は頼朝追討の院庁下文を下されている。夜には入道関白の沙汰により臨時除目が行われているが、この際みずから左馬頭を辞任している(『吉記』寿永二年十二月十日条)。この左馬頭辞任も不自然であることから、代々平家が担ってきた左馬頭の辞任も平家の要求のひとつであった可能性が高いだろう。
●寿永二年十二月十日臨時除目(『吉記』寿永二年十二月十日条)
| 人名 | 官途 | 続柄 | 備考 |
| 藤原俊経 | 参議(兼) | 勘解由長官、式部太輔、備後権守(『公卿補任』) | |
| 藤原隆房 | 参議 | 元蔵人頭、左近衞中将 | |
| 藤原兼光 | 参議 | 元蔵人頭、左中弁、右大弁 | |
| 藤原光雅 | 左中弁 | 元右中弁 | |
| 藤原行隆 | 右中弁 | 元権右中弁 | |
| 藤原光長 | 権右中弁 | 元左少弁 | |
| 源兼忠 | 左少弁 | 元右少弁 | |
| 平基親 | 右少弁 | 還任 | |
| 藤原泰能 | 式部少輔 | ||
| 藤原範遠 | 兵部少丞 | ||
| 惟宗友成 | 少内記 | ||
| 源義経 | 若狭守 | 山本義経。元伊賀守。 | |
| 藤原済基 | 丹波守 | 藤原済綱子、義仲猶子 | 義仲為猶子申補、可知行云々 |
| 藤原忠良 | 右近衞権中将 | 元右兵衛督、無望推被任、及彼御辺成不審歟 | |
| 藤原隆房 | 右兵衛督 | ||
| 源通資 | 蔵人頭 | ||
| 藤原光雅 | 蔵人頭 | ||
| 辞退 | |||
| 源義仲 | 左馬頭 | ||
| 僧事 | |||
| 俊堯 | 天台座主 | 権僧正 本来は昌雲を第一、全玄が第二であったが、 義仲との仲で補任されたとする |
|
これ以降、義仲は平家追討を止め、頼朝追討へと完全に軸足を移すこととなる。そして12月13日、「与義仲和平事一定」となり、「平氏入洛来廿日云々、或又明春」(『玉葉』寿永二年十二月十三日条)という風聞があった。そして12月15日、左大弁経房のもとに「鎮守府将軍秀衡」宛の「早左馬頭源義仲相共率陸奥出羽両国軍兵、可追討前兵衛佐頼朝」(『吉記』寿永二年十二月十五日条)という院庁下文案が寄せられ、経房はこれに加判して返却している。この院庁下文も後白河院が直接指示をしたとは考えられず、松殿基房入道と義仲による院庁への強要であろう。これは12月10日の義仲への「可追討頼朝之由」の院庁下文と対を成しており、義仲は奥州の秀衡にも院庁下文を通じて頼朝追討について同調を命じ、頼朝との対決に突き進んだのであろう。義仲と平家の和睦は「平氏入洛来廿二五八日之間必然也、門々戸々営々、或説与義仲和親、或不然」(『吉記』寿永二年十二月十五日条)と、諸説入り乱れる状況にあり、12月24日に兼実邸を訪れた大外記頼業は、義仲と平家の和平が成立し「西海主君入御者、当今如何、若六条院之躰歟」と不安を述べている。
12月29日、小槻大夫史隆職が兼実を訪ねて「平氏義仲和平、一定之由、以忠清法師説聞了云々、今日和奏云々、左大臣参陣、有不堪定」と、平家家人の「忠清法師」から聞いたという報告があった(『吉記』寿永二年十二月廿九日条)。義仲は平家との和平を成立させたのは確実で、一尺の鏡面を鋳造して八幡に奉納し、起請文を奉じたという(『玉葉』寿永三年正月九日条)。
ところが、翌寿永3(1184)年正月4日、兼実は「頼朝今日出門、決定可入洛」との風聞を耳にする。例の如く「虚言歟」と信じていないが(『玉葉』寿永三年正月四日条)、翌5日、前源中納言雅頼が兼実邸を訪れ「頼朝之軍兵在墨俣、今月中可入洛之由」(『玉葉』寿永三年正月五日条)を聞く。雅頼の家人である齋院次官親能は頼朝代官として近江・伊勢におり、その情報には一定の信憑性があったとみられる。さらに翌6日には「坂東武士已越墨俣入美乃了」という情報が齎され、「義仲大懐怖畏」という(『玉葉』寿永三年正月六日条)。
義仲の軍勢はその数を著しく減らし、すでに大軍を迎え撃つことは不可能であった。ともに京洛の地を守衛した諸源氏勢力の支持を失って離散・仲違いし、また平家によって討ち果たされていたためである。義仲は頼朝との戦いに勝ち目はないことを悟り、正月11日明方に「奉具法皇、決定可向北陸、公卿多可相具」(『玉葉』寿永三年正月十日条)こととしたのであった。ところが、直前になって北陸下向を停止している(『玉葉』寿永三年正月十一日条)。これは、義仲のもとにいた平家の使者の指示によるものであった。平家側は義仲に「依再三之起請、存和平義之處、猶奉具法皇、可向北陸之由聞之、已為謀叛之儀、然者同意之儀可用意」と通告していたのである。和平の条件のひとつが法皇の身柄引渡しであったと考えられることから、義仲の行動を平家方が強く非難したのであろう。これを受けた義仲は、北陸下向のために院中守護として配置していた兵士らを「第一之郎従字楯」を遣わして召し返した(『玉葉』寿永三年正月十二日条)。平家の脅迫に抗えなかったためである。
正月13日、本来はこの日に平家は入洛の予定であったが、
(1)義仲による院の北陸奉具の風聞
(2)和平成立後の丹波国での敵対行為
(3)十郎蔵人行家の摂津国渡邊での敵対行為
上記の三か条を挙げ、義仲および院を牽制して入洛を拒絶した(『玉葉』寿永三年正月十三日条)。
このほか、義仲は近江国に駐屯する鎌倉勢への対応にも苦慮しており、義仲自身の出陣も「有無之間変々七八度、遂以不下向」と見送られる有様であった。義仲はこれを「是所遣近江之郎従以飛脚」からの情報として「九郎之勢僅千余騎云々、敢不可敵対義仲之勢」であり、併せて院へも「仍忽不可有御下向云々、因之下向延引」という苦しい言い訳をしているが、鎌倉勢の実情を熟知している義仲は、もはや身動きがとれない状況となっていたのであった。
一方、このころ鎌倉においても波乱が起こっていた。頼朝は「介八郎ヲ梶原景時シテウタセ」(『愚管抄』)たのである。時期は一説に「而寿永元十二廿二父子共為鎌倉大将被誅了」(『中条家文書』)とあることから、年は誤謬として寿永2(1183)年12月22日と思われる。
この日、上総介八郎広常は梶原景時と「双六」を打っていたが、景時は「サリゲナシニテ盤ヲコヘテ、ヤガテ頸ヲカイキ」ったという(『愚管抄』)。「東国ノ勢人」で「功アル者」であった広常を討った理由は、事実かは不明だが、建久元(1190)年12月に頼朝が法皇に面会した際に、広常を討った理由を、広常が「ナンデウ朝家ノ事ヲノミ身グルシク思ゾ、タダ坂東ニカクテアランニ、誰カハ引ハタラカサン」(『愚管抄』)と発言したことを朝廷に対する「謀反心ノ者ニテ候」(『愚管抄』)と捉え、「カカル者ヲ郎従ニモチテ候ハバ、頼朝マデ冥加候ハジト思ヒテ、ウシナイ候」と申し上げたという。
広常の殺害は翌寿永3(1184)年正月1日に「去冬依広常事、営中穢気之故也」とあることから、おそらく営中で起こった事件と考えられ、侍所であろう。嫡男・小権介能常も誅され、兄弟一族は捕らえられて所領を没収された。頼朝はこの広常殺害により穢れがあることから、鶴岡八幡宮への参詣を見送り、藤判官代邦通を奉幣の御使としている(『吾妻鏡』寿永三年正月一日条)。
正月8日、上総国一ノ宮の神主・兼重から「故介広常存日之時有宿願、奉納甲一領於当宮宝殿」ことを聞いた頼朝は「定有子細事歟、被下御使、可召覧之」と言って、藤判官邦通と一品房昌寛を玉前神社へと派遣。広常奉納の甲冑を引き取るに当たり、「彼奉納甲者、已為神宝、無左右難給出之故、以両物取替一領之条、神慮不可有其崇歟」と、玉前神社へ代わりの「御甲二領」を納めた。頼朝は広常の「宿願」を「定有子細事」と表現しており、以前より謀叛の風聞があったのかもしれない。
正月17日、邦通・昌寛・兼重は広常奉納の甲冑(小桜皮縅)を相具して鎌倉に帰還。幕府に運ばれた鎧櫃は、さっそく頼朝の手によって開けられ、鎧の高紐に結び付けられていた願文を繙く。ところが、その願文は「奉祈武衛御運之願書」であった。
●『上総権介平朝臣広常願文』(『吾妻鏡』)
敬白
上総国一宮宝前
立申所願事
一 三箇年中、可寄進神田二十町事
一 三箇年中、可致如式造営事
一 三箇年中、可射万度流鏑馬事
右志者、為前兵衛佐殿下心中祈願成就東国泰平也、如此願望、令一々円満者、
弥可奉崇神威光者也、仍立願如右
治承六年七月日 上総権介平朝臣廣常
頼朝はこれを読み、広常は「不存謀曲之條、已以露顕之間、被加誅罰事、雖及御後悔」んだものの、殺害してしまった以上は「於今無益、須被廻没後之追福」こととした。そして、広常に縁座して囚人とされていた広常弟・天羽庄司直胤、相馬九郎常清らは「優亡者之忠」て、ただちに厚免。頼朝は2月14日、「上総国御家人等」に「多以私領本宅如元可令領掌」ことの御下文を下したという。
ただし、寿永3(1184)年に広常は無実であったことが発覚していたにもかかわらず、前述のように建久元(1190)年12月、頼朝は法皇に広常を討った理由を謀叛の疑いのためと話している。これは法皇からの問いに誤って殺害したとは言えず、このような発言になった可能性もあるが、実際は法皇も広常が誤殺された真実を重々知りながら敢えて頼朝に広常殺害の理由を問うたのだろう。そして、頼朝はその意図を瞬時に理解し、却って朝廷を重んじる機転を聞かせた返答をしたのであろう。そしてこの掛け合いの様子を聞いた慈円も、為政者同士の静かな鍔迫り合いを察して「コマカニ申サバ、サルコトハヒガ事モアレバ、コレニテタリヌベシ、コノ奏聞ノヤウ誠ナラバ、返々マコトニ朝家ノタカラナリケル者カナ」(『愚管抄』)と含みを持った感想を記したと思われる。
義仲は寿永3(1184)年正月14日に「奉具法皇、可向近江国云々、事已一定也」(『玉葉』寿永三年正月十四日条)と、法皇を奉じて近江への出陣を決断したが、前日の15日に法皇は「御赤痢」を理由に「義仲独可向云々、或云、不可向」と峻拒した(『玉葉』寿永三年正月十五日条)。そしてこの日、義仲は「可為征東大将軍之由、被下宣旨了」とあるように「征東大将軍」の宣旨を下された。頼朝追討の院庁下文、奥州秀衡への頼朝追討の院庁下文と合わせて、征東大将軍に任じる宣旨が下されたことで、義仲は頼朝を追討する大義名分を得たこととなった(『玉葉』寿永三年正月十五日条)。
一方で翌16日、「義仲所遣近江国之郎従等、併以帰洛、敵勢及数万、敢不可及敵対之故」(『玉葉』寿永三年正月十六日条)と、近江に派遣されていた義仲郎従が戦わずして京都へ戻ってきた。その理由は、頼朝勢が大軍であり、もはや敵対できないということであった。「敵勢及数万」は近江国に隠れて展開していた蒲冠者範頼率いる軍勢とみられる。
当時の義仲は、平家の要求を呑んでその帰京を推進する、平家にとっての「捨て駒」となっていたのであろう。しかも平家側の敵対勢力の追討も指示されていたと思われ、寡兵にもかかわらず「分遣軍兵於行家許可追伐」(『玉葉』寿永三年正月十六日条)とあるように、摂津渡邊で平家と交戦した十郎行家を討つ軍勢を派遣せざるを得なかったのはその表れであろう。
義仲は樋口次郎兼光を和泉国へ派遣することとなるが、もともと行家は義仲と対立関係にはあったが、直接交戦しておらず、行家追討は義仲にとって喫緊の問題ではなかった。それにもかかわらず、寡兵を分けてまで追討していることは、行家追討は平家の示唆以外に考えられず、平家は義仲の弱みをうまく利用して還都ならびに法皇奪取、行家追捕ならびに頼朝追討、そして義仲自身の滅亡までも策中にあったと考えられる。「凡義仲日来無支度、毎年越度且相待平氏之間、如此被打了、其勢無幾、勝劣可然事云々、是偏蒙天責也」(『歴代皇紀』)とあることからも、無勢の義仲の足元を見た平家が、義仲の和平案を受け入れる代償として、平家を京都へ招き入れることを指示していたと考えられよう。正月16日、「今日奉具法皇、義仲可向勢多」という風聞があったが、取り消されて、義仲郎従は「如元警固、院中可祇候」(『玉葉』寿永三年正月十六日条)ということとなっている。これも平家による圧力の結果であろう。この日、頼朝勢が少々勢多まで到着したという報告が入っている。
正月19日、「義広三郎先生」を大将軍とした「武士等多向西方」といい、これは行家追討の軍勢または宇治田原方面への防衛兵であろうと推測されている(『玉葉』寿永三年正月十九日条)。また、頼朝勢は勢多方面に展開しているものの、まだ橋を渡って石山方面に進出はしていないという(『玉葉』寿永三年正月廿日条)。ところが、石山方面へ進むべく控えていた軍勢は蒲冠者範頼の隠れた本隊であって、実戦を主目的としない「頼朝代官」の九郎義経・斎院次官親能の五百余騎は、勢田から京への玄関口である田原口を経由して宇治へ進軍していた。
一方、義仲は宇治を固めるべく「大将軍美乃守義広」をして「自昨日在宇治」に展開しており、正月20日、「九郎頼朝舎弟、於宇治合戦等」した。この合戦で義経勢は「三郎先生義広為義子也、無程被打落事、即九郎先陣懸入京中於六条川原」(『歴代皇紀』)と、義広勢を打ち破り、その勢いのまま大和大路を経て六条川原から京都へとなだれ込んだ。「即東軍等追来、自大和大路入京於九条川原辺者、一切無狼藉最冥加也、不廻踵到六条末了」(『玉葉』寿永三年正月十九日条)とあり、義経勢は鴨川の東側を南北に走る大和大路を北上して、六条大橋から京都に入ったとみられる。
義仲は「独身在京之間、遭此殃」い、急遽参院して法皇に御幸を求め、御輿を寄せて乗せ奉ろうとしたところ、「敵軍已襲来」と、五条御所に義経勢が襲来。もはや法皇を具しての逃亡は無理であると判断。突然の襲来に率いる兵はわずかに三、四十騎あまり。一矢を射ることもできずに逃げ落ちたという(『玉葉』寿永三年正月廿日条)。また、「始義仲聞之、郎等楯行綱雖向戦、無程被打落了」ともあり、側近の楯六郎親忠とともに六条川原へ迎え撃つも敗北した可能性もある(『歴代皇紀』)。
 |
| 義仲寺境内の義仲墓 |
その後、義仲はいったんは丹波国へ逃れんと西の長坂方へ進んだが、思い直して勢多あたりの軍勢と合流しようと東山を越えて近江国へ至った。「義仲向大津手字今井方、雖落加今井、九郎手猶自京追責、終義仲幷今井打取斬首了、大津方東国手蒲冠者、甲斐武田一族也」(『歴代皇紀』)とあり、義仲は近江国大津にいた今井次郎兼平の軍勢との合流を図ったようである。そして、大津のあたりに展開していた頼朝代官・蒲冠者範頼と甲斐武田一族との合戦の末、「阿波津野辺」で合戦となり、討ち取られた(『玉葉』寿永三年正月廿日条)。享年三十一。
また、義仲近臣・根井小弥太行親(楯六郎親忠父)も「義仲為宗郎等根井行親等於京被打了」(『歴代皇紀』)とあるように、京中で討たれたという。樋口次郎兼光は義仲の命を受けて備前守行家追討のために和泉国へ派遣され、行家勢を打ち破って行家を負傷させたうえ、その郎従を多く討ち取っていたが、おそらく宇治田原手の義広壊走の報を受けたのだろう。「二月十日」に京都へ戻り、七條朱雀辺で九郎義経勢と合戦して敗北。鞍馬山へと逃れるが、捕縛された。
義仲郎従の「信乃高梨」も清水寺で捕われて首を落とされ、正月26日、検非違使義経の沙汰で「義仲幷高梨、根井、今井頸四」が大路渡され、兼光は生きたままで曳かれたという(『歴代皇紀』)。なお、兼光が入京した「二月十日」では時系列的に有り得ず、義経勢が入京した「二十日(廿日)」の誤記である。「後日樋口被切首事」(『歴代皇紀』)とあり、2月2日に斬首されて梟首された(『吾妻鏡』寿永三年二月二日条)。樋口兼光は捕縛ののちは渋谷庄司重国に預けられていたが、「武蔵国兒玉輩」と親昵であり、兒玉等の人々は「彼等勲功之賞」の代わりに兼光の助命を九郎義経に嘆願。これを感じた義経も兼光助命を院奏しているが、兼光の罪科は軽からずとして許されず、処刑されるに至った。重国郎従の「平太」が処置を命じられたが、斬り損じるという不始末を犯す。見かねた重国次男・渋谷次郎高重は片手負傷の身ながら、兼光の首を片手切りに打ち落とした(『吾妻鏡』寿永三年二月二日条)。
入京した「東軍一番手」は「九郎軍兵加千波羅平三」であり、義経に付けられていた梶原平三景時である。その後、五条御所のあたりに軍兵が集まり、「法皇及祇候之輩、免虎口」との安堵とともに、「不焼一家、不損一人、独身被梟首了、天之罰逆賊、宣哉」(『玉葉』寿永三年正月廿日条)と兼実は喜びを爆発させる。義仲入京から半年、法住寺合戦で院から実権を奪取してから六十日ということに、兼実は平治の乱を思い起こしていた。
義仲が討たれたことにより、義仲と組んで復権を果たした「入道関白」は一気にその権勢を失うこととなる。「入道関白」は右少将顕家を二度にわたって法皇のもとに遣わし「上書」するが、法皇は「無答」であった。義仲と結んだことの弁解書であろうが、都合よく利用された法皇の怒りは大きかったのであろう。またこのとき「新摂政(師家)」も顕家の車に同乗して参院していたが「被追帰了」という(『玉葉』寿永三年正月廿日条)。
翌21日、兼実を「諫人」は「新摂政不可安堵、下官可出馬」(『玉葉』寿永三年正月廿一日条)という。師家の摂政続投を許すべきではなく、兼実が摂政の任に就くべきであると。このときの「諌人」とは前中納言雅頼である。兼実邸を訪れた雅頼卿は、頼朝代官として入洛した「齋院次官親能前明法博士広季子」との話を語っている。親能は主君である前中納言雅頼卿の邸宅を訪問、寄宿するが、このとき「若可被直天下者、右大臣殿可知食世也、無異議」と述べたという。雅頼は「此条可及上奏歟如何」と問うが、親能は「若有尋者可申此旨之由所存也」と答えた。しかし、「無尋者可黙止歟」と聞くと「可進申之由ハ不承」という(『玉葉』寿永三年二月一日条)。兼実はなんとも頼りない親能を「不覚人」と記すが、頼朝が兼実を推していることははっきりし、また雅頼も摂政として名乗りを挙げるよう勧めたのであった。
ただ、兼実はこれを喜ぶ様子はない。兼実は「末世之作法進退、有恐天下不棄国之条、雖似有憑政道之治乱、偏可在君之最、我君治天下之間、乱亡不可止、不肖之者、不当委任之仁、恐必有後悔歟、加之、微臣於社稷不惜身命之条、仏天可有知見、然則若有世之運者、天下可棄士、無運者又所不欲一旦之浮栄也」という思いを吐露する。
結局、法皇の意向によって、摂政は「前摂政可還補之由」という。兼実は前摂政基通が「法皇之愛物也」であり、還補は「尤可然、弥下官不能出詞」と強く反発している(『玉葉』寿永三年正月廿一日条)。法皇は「入道関白」に対しては大きな嫌悪感があり、かつて子息の権中納言師家を摂政に据えんと画策したこと、法皇が摂関家領分与を否定する勅言を逆手にとって、師家が摂政・氏長者となった際には基通に僅かな荘園すら譲ることなく独占したこと、そして平家追討に際して西国行幸をしきりに勧めたことなど、数々の恨事を「難忘」(『玉葉』寿永三年二月十一日条)と言って基房入道を排除し、師家の続投も考慮しなかった。
正月22日、法皇は今後のことについて兼実に問うた。まず神器を保持する平家追討について。兼実は神器の安全が謀れるならば追討すべきであるが、頼朝にも諮るべきだという。義仲の首については大路を渡すべきであるとし、頼朝の賞については頼朝の望むもの、頼朝の上洛はすぐに行うべきであるとした。また御所についてはこの旧五条摂政亭から至急移るべきで、八条院御所の他はないと述べている(『玉葉』寿永三年正月廿二日条)。なお、頼朝へは前日21日に使者を派遣しており、2月20日に京都に帰参した使者によれば、「頼朝申云、勧賞事只在上御計、過分事一切非所欲」という(『玉葉』寿永三年三月廿日条)。
一方で、平家方は還都のために指嗾した義仲が、頼朝勢に為す術なく滅ぼされてしまったことで、無条件の還都計画は水泡に帰した。法皇は平家追討を行う意向を示し、兼実邸には観性法橋と藤原範季両名が院使として訪れ「平氏猶可被追討之由被仰下了」ことを伝えた(『玉葉』寿永三年正月廿三日条)。兼実は拙速な平家追討は神器の安全にも関わることであるとして反対の立場を取っていたが、大外記頼業の注進によれば、平家追討の宣旨はすでに前日の22日に下されていたのだった。
寿永3(1184)年正月26日、範頼・義経が率いる追討使は出門し、29日の出京に備えていたが、前日28日に突如「九郎之従類」が「大夫史隆職」邸を追捕して乱暴を働き、隆職が兼実に助けを求めるという事件が起こった(『玉葉』寿永三年正月廿九日条)。なんら身に覚えのない隆職は義経に使者を送って「縦其身雖有罪科、可停止当時狼藉」と怒りを込めて要求。さらに書面を齋院次官親能(頼朝代官)の主君・前中納言源雅頼に送り、雅頼邸に寄宿している親能へ状況説明を求めた。
義経はすぐに「此事、平氏上書札於京都、被搦取件使者、各持報札云々、其中有之、史大夫之者可召進之由、為左衛門尉時成奉行、自院被仰下、仍相尋之間、罷向大夫史之宅、次第不敵、於狼藉者早可止」と、院北面の藤左衛門尉時成から齎された院宣を誤解していたと弁明。狼藉の停止を約束した。また、これは義経の独断で行ったことで親能はまったく知らされていなかったようで、雅頼からの返事にも「親能申一切不知之由」とのことであった。雅頼は嫡子・左少弁兼忠(親能が乳父を務めていた)の舅である「宰相中将(藤原定能)」にも問い合わせ、返事はやはり「全不知食事」であった(『玉葉』寿永三年正月廿九日条)。法皇からの突然の命であったとはいえ、「史大夫」と「大夫史」を間違えるという、熟れない義経の粗忽さが表れている。それ以上に万事を諮るべき親能にも相談しないままに行われた狼藉であることは、その後の義経の行動にもあるように、直情独断的な性格が垣間見えるのである。
翌正月29日、蒲冠者範頼と九郎義経は出京。大手の「加羽冠者」(蒲冠者範頼)は浜地から福原を目指し、「九郎」(九郎義経)は搦手として丹波国を経由して福原へ向かう二手からの進軍計画であった。なお、「東国九郎、加羽、保田等」が「丹波路、摂津路」の二路に分かれて進軍した(『歴代皇紀』)とあり、実際には範頼、義経に加えて「保田(安田義定)」が独立した勢力として加わっていたことがうかがえる。『吾妻鏡』では安田義定は義経のもと搦手の一人とされており、義経・義定勢が丹波経由の軍勢であったとみられる。
2月1日の報によれば、「向西国追討使等、暫不遂前途、猶逗留大江山辺云々、平氏其勢非尩弱、鎮西少々付了云々、下向之武士、殊不好合戦」(『玉葉』寿永三年二月二日条)とあり、この軍勢は丹波へ向かう義経勢であろう。
なお、平家と安徳天皇は法皇の院宣に従って、正月26日には「解纜遷幸摂州、奏聞事由、為随 院宣行幸近境」と、摂津国福原へ行幸しているが、2月4日に「亡父入道相国之遠忌、為修仏事」を執り行わんとするも、不穏な状況下に「不能下船」であり、福原の南の「輪田海辺」に滞在していたという(『吾妻鏡』寿永三年二月四日条)。
一方、2月3日には備前守行家が法皇の召しによって入洛した(『玉葉』寿永三年二月三日条)。行家は「其勢僅七八十騎」という状況で、行家は平家だけではなく、その意を受けた義仲家子・樋口兼光にも大敗しており、すでに限界であったのだろう。当時の法皇は八条院を御所として八条院と同居しており、八条院蔵人の肩書であった行家は八条院に泣きつき、法皇から頼朝へ行家赦免の使者が送られたのであろう。これにより頼朝も勘気を免じたという。
2月5日、蒲冠者範頼、九郎義経の両勢がそれぞれ摂津国に着陣(『吾妻鏡』寿永三年二月五日条)。京都へ発せられた飛脚は翌2月6日に入洛しており、「平氏引退一谷、赴伊南野云々、但其勢二万騎云々、官軍僅二三千騎云々、仍可被加勢之由申上」という(『玉葉』寿永三年二月六日条)。このとき常胤は蒲冠者範頼の大手勢として加わり、相馬次郎師常・国分五郎胤通・東六郎大夫胤頼を同伴している(『玉葉』寿永三年二月六日条)。
●摂津侵攻の追討使(『玉葉』寿永三年二月六日条)
| 大手軍 【大将】 蒲冠者範頼 ●五万六千余騎 |
小山四郎朝政 | 武田兵衛尉有義 | 板垣三郎兼信 | 下河辺庄司行平 | 長沼五郎宗政 | 千葉介常胤 |
| 佐貫四郎広綱 | 畠山次郎重忠 | 稲毛三郎重成 | 榛谷四郎重朝 | 森五郎行重 | 梶原平三景時 | |
| 梶原源太景季 | 梶原平次景高 | 相馬次郎師常 | 国分五郎胤通 | 東六郎胤頼 | 中條藤次家長 | |
| 海老名太郎 | 小野寺太郎通綱 | 曾我太郎祐信 | 庄三郎忠家 | 庄五郎広方 | 塩谷五郎惟広 | |
| 庄太郎家長 | 秩父武者四郎行綱 | 安保次郎実光 | 中村小三郎時経 | 河原太郎高直 | 河原次郎忠家 | |
| 小代八郎行平 | 久下次郎重光 | |||||
| 搦手軍 【大将】 九郎義経 ●二万余騎 |
遠江守義定 | 大内右衛門尉惟義 | 山名三郎義範 | 齋院次官親能 | 田代冠者信綱 | 大河戸太郎広行 |
| 土肥次郎実平 | 三浦十郎義連 | 糟屋藤太有季 | 平山武者所季重 | 平佐古太郎為重 | 熊谷次郎直実 | |
| 熊谷小次郎直家 | 小河小次郎祐義 | 山田太郎重澄 | 原三郎清益 | 猪俣平六則綱 |
平家は「同三年正二月比、平家悉発西国、軍勢福原以南群居播磨室幷一谷辺」と、すでに正月中に旧都福原周辺に陣所を築いて、福原周辺の守備を固めていたのである。西側の要衝一ノ谷には「為其城重々堀池等」という堅固な陣を構築し、その勢は公称「六万騎」という(『歴代皇紀』)。
こうした状況の中で2月6日に宗盛のもとに届けられた「修理権大夫送書状」によれば、「依可有和平之儀、来八日出京、為御使可下向、奉勅答不帰参之以前、不可有狼藉之由、被仰関東武士等畢、又以此旨、早可令仰含官軍等者」といい、「和平之儀」について、来る8日出京の院使が安徳天皇の勅答を賜って帰京するまでは、戦闘行為を行わないことを関東武士等に順守させるので、平家においても守るよう要請したのである(『吾妻鏡』寿永三年二月廿日条)。
当時の源平の兵力は、権中納言雅頼から兼実への戦況報告の中でも「平氏奉具主上着福原畢、九国未付、四国紀伊国等勢数万云々、来十三日一定可入洛云々、官軍等分手之間、一方僅不過一二千騎云々、天下大事、大略分明」(『玉葉』寿永三年二月四日条)とある通り、追討使の源氏勢が平家勢の十分の一程度のでしかないという悲観的な内容であった。実数は不明だが、平家勢はいまだ九州の兵力が加わっていない状況にあっても追討使より圧倒的な優位に立っていたことは間違いなく、また瀬戸内の制海権も掌握していた中で、追討使が正面から攻撃することは現実的ではなかったであろう。法皇は平家追討使を派遣させた直後に、理由もなく「和平之儀」を持ち出すことは考えにくく、この院宣は法皇による明らかな偽計であろう。
一方、院宣に応じた宗盛は、「相守此仰、官軍等本自無合戦志之上、不及存知、相待院使下向」(『吾妻鏡』寿永三年二月廿日条)と、約定を守り、8日出京という「和平之儀」の院使を待っていたという。ただし、ただ手を拱いていたわけではなく、源氏勢が二手に分かれたことを聞いた平家は、「新三位中将資盛卿、小松少将有盛朝臣、備中守師盛、平内兵衛尉清家、恵美次郎盛方」らを「当国三草山(加東市上三草)」に送り、西から一ノ谷へ向かう九郎義経勢に備えている。義経勢は三草山の東側に布陣して平家勢と対峙し、その距離はおよそ三里程度であった(『吾妻鏡』寿永三年二月五日条)。
●三草山の平家勢
| 新三位中将資盛卿 ●七千余騎 |
小松少将有盛朝臣 | 備中守師盛 | 平内兵衛尉清家 | 恵美次郎盛方 |
その他、平家の人々が福原周辺にどのように在陣していたのかは具体的には不明ながら、「浜地」を福原に向かっていた大手の範頼勢に備えたと思われるのが「本三位中将重衡」「通盛卿、忠度朝臣、経俊」(『吾妻鏡』寿永三年二月十五日条)、西の一ノ谷から山手方面を抑えていたのは「新中納言知盛卿」(『源平盛衰録』)や「経正、師盛、教経」「敦盛、知章、業盛、盛俊」(『吾妻鏡』寿永三年二月五日条)であったろう。
宗盛は院使「修理権大夫」の「不可有狼藉之由」をあくまで守り、「官軍等本自無合戦志」という状況にあったという(『吾妻鏡』寿永三年二月五日条)。ところが、三草山東側に布陣していた義経は「如信綱、実平加評定」と、田代冠者信綱・土肥次郎実平と評定を行うと、2月6日早暁に「襲三品羽林」ってこれを潰走させた(『吾妻鏡』寿永三年二月五日条)。
三草山を破った義経勢は南下して、2月7日未明、一ノ谷の後山(鵯越)まで進んだ。このとき「武蔵国住人熊谷次郎直実、平山武者所季重等」が別動し、早朝に一ノ谷陣の海側から源氏の先陣と高名して攻め寄せたという。これを聞いた平家方の「飛騨三郎左衛門尉景綱、越中次郎兵衛尉盛次、上総五郎兵衛尉忠光、悪七兵衛尉景清等」が二十三騎で木戸口から繰り出して合戦となった(『吾妻鏡』寿永三年二月七日条)。
『歴代皇紀』によれば7日卯剋、まだ夜も明けぬ早朝、源氏勢は「自後山偸入放火」(『歴代皇紀』)したという。『玉葉』においては、参議定能に宛てられた義経と範頼からの合戦子細の報告で「自辰刻至巳刻、猶不及一時、無程被責落了、多田行綱自山方寄、最前被落山手」(『玉葉』寿永三年二月八日条)とあり、多田蔵人大夫行綱が先陣となって山手の平家勢を追い落としたとみられる。搦手は「九郎」「保田」に加えて多田勢の三手に分かれて攻めかかったのだろう。このとき福原へ攻め寄せたのは「東国九郎、加羽、保田等」(『歴代皇紀』)とあるように、「保田」こと安田遠江守義定が九郎義経、蒲冠者範頼と並ぶ源氏の大将のひとりとして認識されており、それは『吾妻鏡』においても義定が範頼、義経とともに大将軍の扱いとして単独で記録されていることからも推測できる。
この攻撃により「大略籠城中之者不残一人」(『玉葉』寿永三年二月八日条)と、一ノ谷の要害は陥落。さらに「但素乗船之人々四五十艘許在島辺云々、而依不可廻得、放火焼死了、疑内府等歟」(『玉葉』寿永三年二月八日条)と、もともと陸陣だけではなく海上の兵船四五十艘ばかりにも人々は乗船し、「島辺」に停泊していたが、一ノ谷の火の手が見えても彼らは「而依不可廻得」と救援に向かうことなく「放火焼死了」という(『玉葉』寿永三年二月八日条)。
また、東側から福原をうかがう大手の蒲冠者範頼勢も攻め寄せ、源平入り乱れての激戦となり、本三位中将重衡は明石浦で「景時、家国」に捕らわれた(『吾妻鏡』寿永三年二月七日条)。また、長く北陸で義仲と戦い続けた越前三位通盛は湊川辺で「源三俊綱」に討ち取られた。なお、俊綱は「近江国住人、佐々木三郎成綱参上、子息俊綱、一谷合戦之時、討取越前三位通盛」(『吾妻鏡』寿永三年二月廿七日条)とあるように、近江佐々木一族であることがわかる。そのほか「薩摩守忠度朝臣、若狭守経俊、武蔵守知章、大夫敦盛、業盛、越中前司盛俊、以上七人」が範頼・義経勢に討ち取られたと報告され、それぞれ「通盛卿、忠度朝臣、経俊」は「蒲冠者討取之」、「経正、師盛、教経」は「遠江守義定討取之」、「敦盛、知章、業盛、盛俊」は「義経討取之」という結果であったという(『吾妻鏡』寿永三年二月七日条)。なお、教経については「被渡之首中、於教経者一定現存」(『玉葉』寿永三年三月十九日条)と、能登守教経は別首であったとする。
そして、戦いは巳時には「平家散々落了、大将軍十人平家族也、交名有利参位中将重衡生取、打取之前帝幷女房等前内大臣等中納言教盛、知盛、参議経盛等乗船逃了、凡所打取上下千三百余人」という源氏勢力の勝利に終わった(『歴代皇紀』)。その戦いは、翌2月8日に参議定能宛の義経報告にも「自辰刻至巳刻、猶不及一時」(『玉葉』寿永三年二月八日条)とある通り、一刻にも満たないほどの短期決戦で終わったことがわかる。なお、福原近辺での合戦の官軍勝報は2月8日未明に兼実家司・式部権少輔範季のもとに「平氏皆悉伐取了」(『玉葉』寿永三年二月八日条)という梶原平三景時からの飛脚が初報である(『玉葉』寿永三年二月八日条)。範季は大手大将軍の蒲冠者範頼の育ての父であり、範頼は軍監である景時を通じて範季に伝えたのであろう。続いて、参議定能からの義経・範頼の報告で合戦子細が伝わっている。義経付属の中原親能が定能女婿・源兼忠の乳母夫であったため、その筋からの通達であろう。また報告では神器の安否は不明だという。
兵力や兵船数において追討使の数倍の勢力を有した平家勢が、わずか一刻の合戦で壊滅するという通常考えられない。これはやはり、宗盛が院宣を順守して敵対行為を停止していた中、「同七日、関東武士等襲来于 叡船之汀」(『吾妻鏡』寿永三年二月五日条)であったが、「依 院宣有限、官軍等不能進出」と、なおも院宣を守って敵対せずに引き退いたものの「彼武士等乗勝襲懸、忽以合戦、多令誅戮上下官軍畢」(『吾妻鏡』寿永三年二月五日条)として、法皇に対し「此條何様候事哉、子細尤不審」と強く批判しているように、法皇の裏切り行為が大きな原因なのだろう。ただし、法皇の愚劣な考えを知り尽くしているであろう宗盛が対応を怠り、攻め寄せる「凶賊」に対し対応できなかった事実は指揮官としては失策である。
2月9日、「源九郎主入洛」(『吾妻鏡』寿永三年二月九日条)し、捕虜の「三位中将重衡」は「土肥二郎実平頼朝郎従為宗者也」(『玉葉』寿永三年二月九日条)の預けとなった。また同時に討ち取られた平家方の人々の首級も齎されたと思われ、法皇はこの首級の扱いについて翌2月10日、「平氏首等、不可被渡旨思食」す院宣を下す(『玉葉』寿永三年二月十日条)。「九郎義経、加羽範頼等」はこの院宣に「被渡義仲首、不被渡平氏首之条、太無其謂、何故被渡平氏哉」と噛み付いたため、法皇は兼実の意見を問うているが、範頼もまた10日までには帰京していることがわかる。
兼実は「論其罪科、与義仲不齋、又為帝外戚等、其身或昇卿相、或為近臣、雖被遂誅伐、被渡首之条、可謂不義」と拒絶し、さらに「神璽宝剣猶在残之賊手、無為帰来之条第一之大事也、若被渡此首者、彼賊等弥令励怨心歟、仍旁不可被渡其首、将軍等只一旦申所存歟、被仰子細之上、何強執申哉、頼朝定不承申此旨歟、此上左右可在勅定者」と意見を述べた。これに左大臣経宗や内大臣忠親らも同調し「各申不可被渡之由」で一決(『玉葉』寿永三年二月十日条)。ただし、平家首級の大路渡については、諸卿の反対意見をよそに法皇は範頼や義経の抗議に強ちに抵抗しても仕方がないとして「仍仰可渡之由了」(『玉葉』寿永三年二月十一日条)となる。
また、三位中将重衡が神器を取り戻すべく、郎従を前内府宗盛のもとに遣わす提案をしている(『玉葉』寿永三年二月十一日条)。多くの一門将士が討たれたのち、平家の生き残る道を模索する重衡の苦悩の表れかもしれない。朝廷はこの提案を容れて、2月15日、重衡郎従の「左衛門尉重国」を使者として派遣している。そして、重衡は尋問の中で「下官可知天下之由、平氏議定之間令申」ということを述べる。これについて、兼実は平家との音信を疑われて覆問され「其条一切不然、只依為傍若無人、当其仁」と弁明している。
2月13日、範頼や義経の強請に折れた法皇が許した「平氏首其数十」の大路渡が行われた(『玉葉』寿永三年二月十三日条、『歴代皇紀』)。ただし、法皇は「公卿頭不可被渡」は許さず、範頼・義経等は不満を述べたという。しかし「通盛卿首同被渡了」と、寿永2(1183)年2月21日に従三位となった平通盛卿の首が渡されており、このことを兼実が強く非難している(『玉葉』寿永三年二月十三日条)。おそらく義経以下の東国武士の鬱屈を減じるための法皇の指示であろう。
2月16日、雅頼卿が兼実邸を訪れ、「頼朝四月可上洛」ことを伝えた。これは齋院次官親能からの報告と思われるが、当の親能は「為院御使、下向東国」という。法皇は「頼朝若不上洛者、可有臨幸東国之由」を告げたのだという。兼実は「此事殆物狂、凡不能左右」(『玉葉』寿永三年二月十六日条)と呆れ果てた様子がうかがえる。
そのころ、福原近郊での戦いに敗れた平家は四国へ渡り「平氏帰住讃岐八島」であった。また「其勢三千騎許」であるという。そして「維盛卿、三十艘許相率指南海去了」(『玉葉』寿永三年二月十六日条)と、小松家の平維盛卿はすでに戦列を離脱したという。
寿永3(1184)年2月18日、頼朝は鎌倉から京都へ「洛陽警固以下事」の決定の使者を送っている(『吾妻鏡』寿永三年二月十八日条)。実質義経への指示であろう。そのほか「播磨、美作、備前、備中、備後、已上五ケ国、景時、実平等遣専使、可令守護之由」と、中国地方の五か国は実平と景時の両名を「近国惣追補使」と定め(『吾妻鏡』元暦二年四月廿六日条)、彼らが「専使(眼代であろう)」を遣わして守護することを命じた。ただしこの五か国は頼朝の管国とされたわけではなく、あくまでも平家との関りが深い瀬戸内五か国の守護及び「公田庄園」の保障がその任務である。頼朝は2月19日の宣旨で「諸国七道」における「神社仏寺幷院宮諸司及人領」への狼藉を取り締まることが認められ、「五畿内諸国七道」の国司に対して、治承以降平家が行い、義仲が権柄を握っても改められなかった悪しき慣例の「公田庄園兵糧米」を停止するよう宣旨が下された。ただし、これは国内支配権を確立したものではない。
こののち、兼実邸を訪れた左大弁経房は「諸国兵糧之責幷武士押取他人領事、可停止之由被下宣旨」ことを兼実に伝えているが(『玉葉』寿永三年二月廿二日条)、兼実は数度に渡って宣旨が下されながらも一向に狼藉がなくならないことに「更以不可叶事歟、有法不行、不如無法」(『玉葉』寿永三年二月廿二日条)と嘆いている。これらの宣旨を帯びた勅使は3月9日、鎌倉に到着し(『吾妻鏡』寿永三年三月九日条)、武士による「諸国庄園」の押領を停止し、頼朝にその取り締まりを命じている。頼朝が西国諸国に対する権限を得たのは、文治元年に上洛した「頼朝代官北条丸(北条時政)」が要求した「件北条丸以下郎従等、相分賜五畿山陰山陽南海西海諸国、不論庄公、可宛催兵糧段別五升、非啻兵糧之催、惣以可知行田地」(『玉葉』文治元年十一月廿八日条)というのちのことである。
2月25日、「朝務事、武衛注御所存、條々被遣泰経朝臣之許」とある通り(『吾妻鏡』寿永三年二月廿五日条)、頼朝の使者が高階泰経のもとを訪れ、「朝務事」についての要望をしている。このことは兼実も伝え聞いており、泰経到着の二日後、2月27日に「又以折紙計申朝務」(『玉葉』寿永三年二月廿七日条)と記している。
一 朝務等事
右、守先規、殊可被施徳政候、但諸国受領等尤可有計御沙汰候歟、東国北国両道国々、追討謀叛之間如無土民、自今春浪人等帰往旧里、可令安堵候、然者来秋之比、被任国司、被行吏務可宜候
一 平家追討事
右、畿内近国、号源氏平氏携弓箭之輩幷住人等、任義経之下知可引率之由、可被仰下候、海路雖不輙、殊可急追討之由、所仰義経也、於勲功賞者其後頼朝可計申上候
一 諸社事
我朝者神国也、往古神領無相違、其外今度始又各可被新加歟、就中、去比鹿嶋大明神御上洛之由、風聞出来之後賊徒追討、神戮不空者歟、兼又若有諸破壊顛倒事者、隨功程、可被召付處、功作之後可被御裁許候、恒例神事、守式目、無懈怠可令勤行由、殊可有尋御沙汰候
一 仏寺間事
諸寺諸山御領、如旧恒例之勤不可退転、如近年者、僧家皆好武勇、忘仏法之間、行徳不聞、無用樞候、尤可被禁制候、兼又於濫行不信僧者、不可被用公請候、於自今以後者為頼朝之沙汰、至僧家武具者任法奪取、可与給於追討朝敵官兵之由、所存思給也
頼朝は朝廷の選任事項である国司任命にも言及し、寺社仏寺への介入も示唆するなど、兼実はこの条々について「人以不可為可」と批判しながらも、頼朝の天も恐れぬ要求に対し、「頼朝若有賢哲之性者、天下之滅亡弥増歟」と頼朝が賢哲の器であれば、政治的に暗愚な法皇を操り、朝務を恣に動かすことも可能であることを述べる(『玉葉』寿永三年二月廿七日条)。平家追討に対しては、「畿内近国、号源氏平氏携弓箭之輩幷住人等」は、追討使である義経の下知に随い、急ぎ追討を行うべきことを要求し、さらに「於勲功賞者其後頼朝可計申上候」と、平家追討に対する行賞は頼朝を介して行うことを明言した。
ところが、頼朝の四か条の要求が朝廷に届いた四日後の2月29日、「九郎為追討平氏、来月一日可向西国之由有議、而忽延引」(『玉葉』寿永三年二月廿九日条)ということとなる。延引の理由は定かではないが、日時的には頼朝の2月18日に鎌倉を発した「洛陽警固以下事」の使者が上洛する頃合いであった。四か条の「朝務等事」には「洛陽警固以下事」は含まれていないため、高階泰経に披露された「朝務等事」と「洛陽警固以下事」は別物であり、「朝務等事」の使者が発せられたのちに「洛陽警固以下事」の使者が後追いで送られたのであろう。こののち、約一年に亘って義経は京都警衛を主任務としていることから、頼朝の命による所役の変更とみられる。
なお、同日の2月29日、重衡の遣わした郎従重国が屋島の前内府宗盛からの返書を京都へ齎した。宗盛からの返事には「畏承了、於三ケ宝物幷主上女院八条院殿者、如仰可令入洛、於宗盛ハ不能参入、賜讃岐国可安堵、御共等ハ清宗ヲ可令上洛」(『玉葉』寿永三年二月廿九日、卅日条)とあったとされ、和親を申し述べたという。この和平案が成れば朝廷は神器と安徳天皇を取り戻し、女院(建礼門院)と八条院殿(二位尼)の還京が実現することとなり、兵乱鎮定が実現味を帯びることとなる。
ただし、『吾妻鏡』で宗盛が齎した返事は、2月21日に重国の書状を請け取り、2月23日に書面を認めたことを記し、「主上国母可有還御之由、又以承候畢」(『吾妻鏡』寿永三年二月廿日条)と、法皇からの要請を理解した旨を記した。ただ、宗盛は福原での敗戦について、法皇の卑怯な「奇謀」に対して大きな不満を抱いており、法皇が「若為緩官軍之心、忽以被廻奇謀歟、倩思次第、迷惑恐歎、未散朦霧候也」(『吾妻鏡』寿永三年二月廿日条)と非難し、合戦により「還御亦以延引、毎赴還路武士等奉禦之、此條無術事候也、非難澁還御之儀、差遣武士於西海依被禦、于今遅引、全非公家之懈怠候也」(『吾妻鏡』寿永三年二月廿日条)と、法皇は天皇の還御を求めながら、その都度武士を派遣して妨害するという行為で、結局その還御が遅引しており、これはまったく安徳天皇の懈怠ではないとした。さらに「其後又称 院宣、源氏等下向西海、度々企合戦、此條已依賊徒之襲来、為存上下之身命、一旦相禦候計也、全非公家之発心、敢無其隠也」(『吾妻鏡』寿永三年二月廿日条)と、たびたびの源氏との合戦は、天皇を脅かす「賊徒」の襲来を防いだに過ぎず、合戦はまったく天皇が企てたものではないと強く主張した。そして、「云平家、云源氏、無相互之意趣、平治信頼卿反逆之時、依 院宣追討之間、義朝朝臣依為其縁坐、有自然事、是非私宿意、不及沙汰事也、於 宣旨院宣者非此限、不然之外、凡無相互之宿意、然者、頼朝与平氏合戦之條、一切不思寄事也、公家仙洞和親之儀候者、平氏源氏又弥可有何意趣哉、只可令垂賢察給也」(『吾妻鏡』寿永三年二月廿日条)と、そもそも平氏と源氏にことさら宿意はなく、天皇と法皇の和親が成れば、いよいよ平氏と源氏には何ら意趣はないこととなり、「和平儀可候者、天下安穏、国土静謐、諸人快楽、上下歓娯、就中合戦之間、両方相互殞命之者、不知幾千万、被疵之輩、難記楚筆、罪業之至、無物于取喩、尤可被行善政、被施攘災、此條、定相叶神慮仏意歟」(『吾妻鏡』寿永三年二月廿日条)と和平を推進すべきことを伝え、法皇は「早停合戦之儀、可守攘災之誠候也、云和平、云還御、両條早蒙分明之 院宣、可存知候也、以此等之趣、可然之樣、可令披露給、仍以執啓如件」(『吾妻鏡』寿永三年二月廿日条)と要請したという。
『吾妻鏡』においては、『玉葉』が記すような、宗盛が和平を積極的に受け入れつつ「賜讃岐国可安堵、御共等ハ清宗ヲ可令上洛」ということは記されていないが、穏便に批判を展開している。讃岐国を与えるというものは、法皇が提示しようとした条件なのかもしれない。『吾妻鏡』と『玉葉』に共通する「所詮源平相並可被召仕之由」については、兼実は「此條頼朝不可承諾歟、然者難治事也」と嘆いている。おそらくその後、頼朝へ使者が遣わされ、結果としてこの和平案は実行されることはなかった。兼実の予想通り、頼朝が反発したのであろう。そして平家方も態度を硬化したとみられ、元暦元(1184)年7月6日に左大弁経房が中山忠親に報告したことによれば、九州へ遣わした「院召使」を平家が「被着印於面」する恥辱を与え、さらに同道したと思われる「鎌蔵雑色十余人」については斬首したという(『山槐記』元暦元年七月六日条)。
一方、『源平盛衰記』では、宗盛は「通盛已下当家数輩、於摂津国一谷已被誅畢、何重衡一人可悦寛宥之院宣、抑我君者、受故高倉院之御譲、御在位既四箇年、雖無其御恙、東夷結党責上、北狄成群乱入之間、且任幼帝母后之御歎尤深、且依外戚外舅之愚志不浅、固辞北闕之花台、遷幸西海之薮屋、但再於無旧都之還御者、三種神器争可被放玉体哉」と正統性を主張。法皇に対しては「就中亡父太政大臣、保元平治両度合戦之時、重勅威、軽愚命、是偏奉為君非為身」と批判し、頼朝についても「父左馬頭義朝謀叛之時、頻可誅罰之由、雖被仰下于故入道大相国、慈悲之余所申宥流罪也、爰頼朝已忘昔之高恩、今不顧芳志、忽以流人之身、濫列凶徒之類、愚意之至思慮之讐也、尤招神兵天罰速、期廃跡沈滅者歟」と忘恩の徒と糾弾。「但君不思召忘亡父数度之奉公者、早可有御幸于西国歟、于時臣等奉院宣、忽出蓬屋之新館、再帰花亭之旧都」と、法皇の西国行幸を要請し、その後、安徳天皇を奉じて屋島から還都することを述べている。『源平盛衰記』は宗盛の強硬ぶりが際立っているが、『玉葉』が伝える内容と勘案すると『吾妻鏡』の記述が実際に近く、『源平盛衰記』は宗盛ら平家側の心情を代弁した表記なのではなかろうか。
3月2日、重衡の身柄は土肥次郎実平から梶原平三景時へ移され、京都の宿所へ置かれ(『源平盛衰記』)、3月5日には検非違使義経の手によって「主馬入道盛国父子五人」が捕縛されている(『源平盛衰記』)。そして、3月7日、「板垣三郎兼信、土肥次郎両人」がふたたび西国の抑えのために京都を出立している(『源平盛衰記』)。
3月10日、重衡は「頼朝所申請」により鎌倉へ下向することになる(『玉葉』寿永三年三月十日条)。重衡には「梶原平三景時相具之、是武衛依令申請給也」(『吾妻鏡』寿永三年三月十日条)であった。一行は3月27日に伊豆国府へ到着。当時、頼朝は伊豆国北条にいて国府とは指呼の距離であり、景時に北条へ相具して参るよう命じた(『吾妻鏡』寿永三年三月廿七日条)。
翌28日に北条館で重衡と面会した頼朝は、
「且為奉慰君御憤、且為雪父尸骸之耻、試企石橋合戦以降、令対治平氏之逆乱如指掌、仍及面拝不屑眉目也、此上者謁槐門之事、亦無所疑歟者」
と述べた。頼朝の挙兵は法皇幽閉の御憤を鎮めるとともに、父義朝の恥を雪ぐものであり、平家逆乱を鎮圧することで重衡卿と面会できたのはこの上ない名誉であり、そのうち宗盛卿とも面会できることは疑いないことでしょうと語ると、重衡は、
「源平為天下警衛之處、頃年之間当家独守朝廷之、許昇進者八十余輩、思其繁栄者二十余年也、而今運命之依縮、為囚人参入上者不能左右、携弓馬之者為敵被虜、強非耻辱、早可被處斬罪」
と滔々と述べた(『吾妻鏡』寿永三年三月廿八日条)。その堂々とした受け答えに「聞者莫不感」だったという。その後、狩野介宗茂へ預けられることとなるが、頼朝はちょうど十歳年下の重衡をいたく尊重し、鎌倉に移されたのちは、その無聊を慰めるために謡や今様、管弦などが催されている。なお、『源平盛衰記』では面会の地は鎌倉の御所となっている。
寿永3(1184)年3月16日、兼実邸を大外記清原頼業が訪れる(『玉葉』寿永三年三月十六日条)。兼実は頼業と日頃のことについて話しているが、頼業は子息の近業が法住寺殿で流れ矢に当たって死去しており、とりわけ法皇に対する不信感を持っていたと思われる。頼業は「先年通憲法師」が語った法皇の人物評を兼実に話しているが、通憲入道信西の後白河天皇評は「当今謂法皇也、和漢之間少比類之暗主也、謀叛之臣在傍、一切無覚悟之御心、人雖奉悟之、猶以不覚、如此之愚昧、古今未見未聞者也、但其徳有二、若叡心有欲果遂事者、敢不拘人之制法、必遂之此条於賢主為大失、今暗愚之余、以之為徳、次自所聞食置事、殊無御忘却、年月雖遷不忘心底給、此両事為徳」(『玉葉』寿永三年三月十六日条)というものであった。法皇の乳母夫でありもっとも側近くで雅仁天皇(後白河院)を見ていた「通憲法師(信西入道)」は、その資質を「和漢の間でも前例のない暗愚」と言い切ったという。まさに兼実の見立てと同一のものであった。
3月23日、権右中弁光長が兼実邸を訪問し、前明法博士中原広季から「頼朝奏条々事於院、其中下官可為摂政藤氏長者之由令挙了之由、広元之許広季之男也所告送也」という。広季は兼実家司であるが、彼の養子・中原広元は、義兄・齋院次官親能とともに鎌倉にあり、広元が認めた書状が19日に高階泰経のもとに届けられて奏院されたという。父・広季にもこれを知らせる書状が届けられたのだろう。21日、法皇より返事が頼朝へ向けて発せられ、兼実は「急可申左右之由被仰云々、大略此事被仰不可然者歟」という内容であろうと推測している。
藤原光能――――中原親能
(参議) (斎院次官)
↓
中原広季――+=中原親能
(前明法博士)|(斎院次官)
|
+=中原広元
(安芸権介)
↑
大江維光――――中原広元
(式部大輔) (安芸権介)
頼朝の院奏について兼実は「凡此事次第、可謂難堪叡念也、所参無疑下官之懇望也、縦雖有此疑、已無其実、強不可為告、不事而成就者、以之可為験之處、法皇遏絶之御心已切、引級摂政之条、已有御贔屓、此上頼朝不可及執申、然者遂以可黙止歟」と、兼実自身が望んだものでもないのに疑われることは迷惑至極で、頼朝からの推挙は停止すべきだとこの上ない不快感を示し、「而当時洛中之貴賤上下、道俗男女、下官可有吉慶事之由、謳哥、殆過法云々、此事已嗚呼也、又尾籠也、取諸身無冥顕之過怠、何因氏明神幷本尊三宝、可令顕尾籠之名於後代哉、冥鑑之處、只奉仰仏神者也、中心此事乱世間、弥以不庶幾者也」と、世間は兼実が摂政になることを信じているようだが、まったく以て「嗚呼」「尾籠」と続けて言うほど否定し、いよいよ願うものではないと悲壮感までうかがえる(『玉葉』寿永三年三月廿三日条)。
3月28日には「頼盛卿後見侍清業」が上洛し「余事又奏法皇」(『玉葉』寿永三年四月一日条)という。鎌倉または相模国府に居住している平頼盛入道からの使者であるが、これは頼朝の意見を具申したものである。4月7日、兼実邸を訪れた雅頼卿が「頼盛卿後見史大夫清業」が語ったこととして「下官事、頼朝推挙存堅事」と話している(『玉葉』寿永三年四月七日条)。また、3月19日に奏院された頼朝の兼実推挙状については「奏聞之日、於八幡頼朝奉祝云々、宝前能致祈念之後、仰広元令書」という(『玉葉』寿永三年四月七日条)。頼朝は兼実を摂政とするべく、鶴岡八幡宮に参籠して祈念したのち、広元に奏状を書かせたという。これについても兼実は反応しておらず、打ち棄てているが、兼実としてはまったく意に染まぬ事柄であったろう。
3月28日、朝廷は頼朝の奏上通り、頼朝を「正四位下」に叙した。そして翌29日には、入道関白と摂政基通がそれぞれ鎌倉の頼朝のもとに使者を送っている(『玉葉』寿永三年三月廿九日条)。贈り物または陳状を添えたものであったという。摂政基通も入道関白もそれぞれ頼朝にみずからの支援を行うよう依頼した可能性が非常に高いだろう。すでに世間では兼実が首班となるのではないかという風聞があったため、両者が慌てて行動に出たとみられる。また、頼朝は義仲解官後不在となっていた院の「御厩司」に義経を推しており、4月27日、義経が院御厩司に補任されている(木村真美子氏『中世の院御厩司について:西園寺家所蔵「御厩司次第」を手がかりに』『吾妻鏡』文治五年閏四月三十日条)。その補佐として案主に後藤右兵衛尉基清を任じている。後藤基清は頼朝義弟・藤原能保の家人でもあり、能保が後見として期待されていた可能性があろう。
4月14日、改元されて元暦元年となり、夜に法皇は八条院御所から白川金剛勝院に修造した御所(押小路御所)へと遷っている(『玉葉』元暦元年四月十四日条)。改元のことは昨年から議されていたが、天皇即位(践祚は行われたが神器がないため即位がいまだできていない)以前ということで延引されていたが、世の中の騒乱が鎮まらないことから、即位以前に行われることとなったのであるが、兼実は「愚意猶未甘心」と不満を述べる。
4月24日、大夫史隆職が兼実邸を訪れて「語密々事等」ことには、「頼朝令申下官事、有深意趣等、欲申其事、七ヶ日参籠八幡宮頼朝祈所奉祝云之後、於宝前書折紙令進上云々、偏依思天下事令申」(『玉葉』元暦元年三月廿四日条)という。兼実は頼朝からの支援を快く思ってはおらず、これに関しても自分の意思を示すことはなかった。しかし、摂政への嘱望は心の中に燃えており、たびたび夢見や吉祥を気にして日記に書き留めている。そして4月28日、頼業から「荒聖人聞覚、公朝等、一昨日夕入洛、今日、件聖人参院云々、以件聖人、余事猶申院」(『玉葉』元暦元年四月廿八日条)ということを聞いている。神護寺の文覚が参院して兼実を摂政とするよう法皇に直談判したのである。寿永2(1183)年9月25日に文覚は頼朝から義仲を勘発するよう指示を受けていることから、この文覚の参院と強訴は頼朝の意思を反映したものと考えられよう。兼実は文覚の訴えにつき「実是神明之加護歟、将又不祥之根元歟、未弁是非、不如固辞遁也」と困惑しつつも、拒否感は薄い。「去三月廿八日暁、季広夢想云、下官着束帯立家南庭、而問、日輪自東飛来、余以袖奉受之了云々、今暁、女房見吉夢、又資博見最吉夢、大職冠御加護之由也」(『玉葉』元暦元年四月廿八日条)と自らの立身を示唆するような吉瑞を挙げており、摂政への望みは非常に大きいものがあったのは確実である。ただ、それは後年、実際に摂政就任時のときに見るように、兼実でなければ成し得ない状況に法皇から乞われての登壇を期待したものである。現摂政基通や法皇との関わりを含めたタイミングもあり、頼朝からの推挙で就任することは断固拒否する姿勢は変わっていないだろう。それは「摂政之辺人、讒余事於頼朝、因之先日奏聞之大事、黙止了」という一報を受けた事に対し、兼実は「余聞如此事可悲」として「推挙専非所好、讒言何可痛哉、只家之前途、国之重事、懸田夫野臾之詞之條、悲而有余者歟」という、「田夫野臾(頼朝)之詞」は迷惑千万と述べている(『玉葉』元暦元年十一月二日条)。
元暦元(1184)年6月16日、「平氏党類、追散在備後国之官兵」という情報が京都に伝わった(『玉葉』元暦元年六月十六日条)。備後国を守っていたのは「土肥二郎実平頼朝郎従息男早川太郎」であったが、この早川太郎遠平が大敗を喫したため、「在播磨国之梶原平三景時同郎従、超備後国了」と、梶原景時が救援に駆けつけたという。なお、3月末に重衡を伊豆国北条へ護送した梶原景時が6月上旬には最前線の播磨国にいるということは、景時は重衡護送後、日を経ず上洛し、播磨国へ急行したことになる。
土肥勢を破った平家勢は備後国から東へと進み、播磨国室泊(たつの市御津町室津)まで進出、周辺を焼き払った(『玉葉』元暦元年六月十六日条)。平家軍を率いていた人物の名は伝わらないが、三備に顕在していた平家党の国人であろうか。この官軍敗報を受けた朝廷は、事態の悪化に「被催遣京都武士等」という沙汰を発出する。兼実はこうした相も変らぬ状況に「凡追討之間、沙汰太如泥、大将軍在遠境、公家事無人于沙汰、只天狗奉行万事之此也、無沙汰無祈祷、以何可期安全哉、可悲」と悲嘆を込めて述べている(『玉葉』元暦元年六月十六日条)。さらに伝え聞くところによれば、「平氏其勢強云々、京勢僅不及五千騎」という状況であるという(『玉葉』元暦元年六月十八日条)。頼朝は8月に上洛するという風聞だが(『玉葉』元暦元年六月廿一日条)、「平氏之勢太強、源氏武士等気色損了、大略如平氏落之時、決定大事出来歟」という(『玉葉』元暦元年六月廿三日条)。これまで頼朝が追討使発遣の奏上をせず、郎従の梶原・土肥を「近国惣追捕使」として派遣し、美作・播磨・三備の五か国の警衛と庄公領の管理のみ行わせている状況に、朝廷は不安と不信感を募らせていたことが伺える。
頼朝としても本来であれば鎌倉から追加の軍勢を差し向けて対処すべきところであるが、奥州や北関東にはいまだ不穏な動きがある上に兵糧の問題もあり、軽々に兵を動かすことはできなかったのだろう。また、前線で戦う梶原・土肥の両名はあくまでも山陽五か国の治安維持、庄公領の狼藉防止が本務の惣追捕使であり、本格的に平家追討を担う軍勢ではなかったと思われる。このように、当時の頼朝もまた末期の義仲同様、兵力と兵糧コストの問題に陥っていたのである。ただ、このままの状況も捨て置けず、京都の情勢も鑑みて、頼朝は義経を「追討使」として西国へ派遣することを決定。京都に使者を遣わし、7月3日に義経の「可遣西海事」を法皇に奏上したのであった(『吾妻鏡』元暦元年七月三日条)。
ところが義経の追討使任命から数日後、「伊賀伊勢国人等謀叛了」(『玉葉』元暦元年七月八日条)という風聞が京都に広まった。
伊賀国は「大内冠者源氏、知行」であり、大内冠者惟義は伊賀国各所に郎従を派遣して統治していたが、7月7日夕刻、「家継法師平家郎従、号平田入道是也」が大将軍となって兵を挙げ「大内郎従等悉伐取了」という(『玉葉』元暦元年七月八日条)。これに呼応して伊勢国でも「信兼和泉守」が鈴鹿山を切り塞いだという。なお、『吾妻鏡』では7月5日に鎌倉に惟義の飛脚が届き「去七日於伊賀国、為平家一族被襲之間、所相恃之家人多以被誅戮」(『玉葉』元暦元年七月五日条)と報告したというが、これは伊賀平氏挙兵前であり、明らかな時期誤謬である。また、報告を受けた頼朝が「伊賀国合戦之間事、被経其沙汰」したのは7月18日であるが、7月5日に報告から沙汰まで十日以上を経ていることも不審である。これらから、大内惟義の飛脚が鎌倉に到着したのはおそらく7月15日であり、『吾妻鏡』の7月5日の記事は「十」が抜け落ちている可能性が高いだろう。
この伊賀平氏挙兵には、伊藤忠清法師や富田進士家資ら伊勢国に拠点を置いていた旧平家家人も加わっているが、彼らはいずれも維盛、資盛ら小松家所縁の人々であって宗盛ら「主流の平家」とは縁遠く、宗盛等と彼らが連携していた様子も見られない。「伊賀伊勢平家郎等反」(『山槐記』元暦元年七月八日条)とも見えるが、彼らは「主流の平家」のために挙兵をしたわけではなく、伊賀国内に派遣された大内惟義の家人との対立から暴発したと考えるほうが妥当であろう。
頼朝は7月18日、大内惟義ならびに「加藤五景員入道父子、及瀧口三郎経俊等」に伊賀伊勢平氏の追捕を命じた(『吾妻鏡』元暦元年七月十八日条)。大内惟義、山内経俊はそれぞれ伊賀国、伊勢国の「守護(国惣追捕使)」であるが、頼朝が叛乱の追捕を発令した時点で、すでに挙兵後十日が経過し、さらに飛脚が大内らのもとに戻るまで数日かかる中、大内・山内が頼朝の命を待ってから軍事行動を起こすことは非現実的である。彼らは謀反人追捕の権限(後の守護の権限の一つに繋がるか)は与えられており、頼朝はその追認を行ったという事であろう(『吾妻鏡』元暦元年七月十八日条)。また、頼朝はこの畿内の大規模な兵乱を受けて、予定していた義経の検非違使補任を急いだと思われ、後述のように8月7日に「九郎可任官」(『玉葉』元暦元年八月七日条)にこぎつけている。これにより義経は京洛取り締まりの公的な権限を得たこととなる。
伊賀平氏に呼応して「鈴鹿山」こと東海道の鈴鹿関を遮断した「信兼和泉守」は「関出羽守信兼相具姪伊藤次」(『吾妻鏡』治承五年正月廿一日条)とあるように、伊勢平氏根本被官である伊藤氏と縁戚関係にあり、伊藤忠清法師との縁により挙兵した可能性があろう。かつて信兼は義経上洛に際して伊勢国から義経とともに木曽義仲と戦うなど、平家政権とは距離を置いた在京武官家であり「楊梅南、朱雀西」(『吾妻鏡』文治二年七月廿七日条)に屋敷地を有しながらも、国司在任期間にも拘らず、本貫の伊勢国に居住することが多かったようである。
伊賀・伊勢平氏は挙兵後、近江国へ進出するが、7月19日に「与官兵合戦、官軍得理、賊徒退散、為宗者伐取了」という(『玉葉』元暦元年七月廿日条)。この戦いには「官兵源氏郎等」(『山槐記』元暦元年七月十九日条)とあるが、義経の麾下は京都常駐が可能な人数に過ぎないことを考えると、大内・山内の軍勢であろう。彼らは伊賀・伊勢平氏と「近江国大原庄」(『山槐記』元暦元年七月十九日条)でも合戦しており、「平田入道貞能兄」らは近江国東部にまで進出したことがうかがわれる。その後、官軍は伊賀平氏勢を破り、7月21日、「謀叛大将軍平田入道家継法師」は梟首されるも、「忠清法師、家資等籠山了」という。この戦いでは「官軍之内、大佐々木冠者不知名」が討たれ、「官兵之死者及数百」という苦戦であった(『玉葉』元暦元年七月廿一日条)。『吾妻鏡』でも「佐々木源三秀能相具五郎義清、合戦之處、秀能為平家被討取畢」とあり(『吾妻鏡』元暦元年八月二日条)、秀義はすでに近江国に居住しており、末子の五郎義清とともに動いていたことがうかがえる。
『吾妻鏡』においては「討亡者九十余人、其内張本四人、富田進士家助、前兵衛尉家能、家清入道、平田太郎家継入道等也、前出羽守信兼子息等并忠清法師等者逃亡于山中畢」とあり、伊勢・伊賀平氏の四人が討たれ、伊勢平氏の信兼子息らと忠清法師が山中へ逃れたとする。ただし、『玉葉』においては「家資」は逃れ、信兼については触れられていない。
8月2日、鎌倉に伊賀・伊勢平氏の鎮圧が完了した旨が報告され(『吾妻鏡』元暦元年八月二日条)、翌8月3日、義経に「今度伊賀国兵革事、偏在出羽守信兼子息等結構歟、而彼輩遁圍之中、不知行方云々、定隠遁京中歟、早尋捜之、不廻踵可令誅戮之趣」(『吾妻鏡』元暦元年八月三日条)ことを伝える安達進三郎を派遣した。
そして、平家所縁の人々による兵乱を受けた頼朝は、平家追討を急ぐ方針に転換し、8月6日、御所に「招請参河守、足利蔵人、武田兵衛尉給、又常胤已下為宗御家人等依召参入」(『吾妻鏡』元暦元年八月六日条)し、西国出兵の陣容を整える命を下し、西海出陣の餞別として終日の酒宴を開いて、各々に馬を一匹ずつ下賜。とくに「参州分、秘蔵御馬也、剩被副甲一領」(『吾妻鏡』元暦元年八月六日条)している。そして8月8日、「参河守範頼、為平家追討使赴西海、午尅進発」し、常秀は祖父・千葉介常胤とともに「扈従輩」に加わった。木曾義仲追討及び一ノ谷合戦の軍勢には常秀は加わらず、叔父三人(相馬師常、国分胤通、東胤頼)が出征していたが、今回の平家追討戦に加わった千葉一族は、千葉介常胤と常秀のみである。父・千葉新介胤正と兄・小太郎成胤は平氏との戦いには一切参戦していないが、祖父・千葉介常胤の指示によるものであろう。
●元暦元年八月八日西海派兵の将士(『吾妻鏡』元暦元年八月八日条)
| 大将軍 | 三河守範頼(紺村濃直垂、小具足、栗毛馬) | |||
| 扈従の輩 | 北条小四郎義時 | 足利蔵人義兼 | 武田兵衛尉有義 | 千葉介常胤 |
| 境平次常秀 | 三浦介義澄 | 三浦平太義村 | 八田四郎武者朝家 | |
| 八田太郎朝重 | 葛西三郎清重 | 長沼五郎宗政 | 結城七郎朝光 | |
| 比企藤内所朝宗 | 比企藤四郎能員 | 阿曽沼四郎広綱 | 和田太郎義盛 | |
| 和田三郎宗実 | 和田四郎義胤 | 大多和次郎義成 | 安西三郎景益 | |
| 安西太郎明景 | 大河戸太郎広行 | 大河戸三郎 | 中条藤次家長 | |
| 工藤一臈祐経 | 工藤三郎祐茂 | 天野藤内遠景 | 小野寺太郎道綱 | |
| 一品房昌寛 | 土佐房昌俊 | |||
このころ、京都では頼朝上洛の風聞があり、「木瀬川伊豆与駿河之間」に滞陣中と伝わっていた(『玉葉』元暦元年八月廿一日条)。京都への飛脚によれば「已所上洛仕也、但ひきはりても不上洛候也、先参河守範頼蒲冠者是也、令相具数多之勢、所令参洛也、雖一日不可逗留京都、直可向四国之由所仰含也」(『玉葉』元暦元年八月廿一日条)とあり、まず三河守範頼が派遣されるが、滞京することなく四国へ向かう旨を伝えている。京都へ伝わった風聞は8月8日に鎌倉を出立した範頼のことであろう。なお、頼朝が範頼に命じていたのは『玉葉』によれば四国の平家中枢への攻撃であったことがわかる。
8月7日には在京の「九郎可任官」(『玉葉』元暦元年八月七日条)の除目が行われ、義経は左衛門少尉、検非違使として洛中を公的に取り締まる権限を得る。なお『吾妻鏡』によれば、義経の左衛門少尉任官報告の使者は8月17日に鎌倉に到着し(『吾妻鏡』元暦元年八月十七日条)、任官について「去六日任左衛門少尉、蒙使宣旨、是雖非所望之限、依難被默止度々勲功、為自然朝恩之由被仰下之間、不能固辞」(『吾妻鏡』元暦元年八月十七日条)と、院からの強い要望により固辞できなかったと釈明したという。頼朝はこれに「武衛御気色」と怒りを露わにし、頼朝が「起自御意被挙申」した「範頼義信等朝臣受領事」について「於此主事者、内々有儀、無左右不被聴之處、遮令所望歟」だったという。そして、義経の「被背御意事、不限今度歟」という態度から、「依之可為平家追討使事、暫有御猶予」(『吾妻鏡』元暦元年八月十七日条)という。ただし、義経の主任務は「洛陽警固以下事」(『吾妻鏡』寿永三年二月十八日条)を代官として勤めることであり、当然頼朝が定めたものである。義経の任官はすでに頼朝からの推挙を得ていたものと考えられる。もし義経が「被背御意事、不限今度歟」であれば、範頼や惟義と交代させればよいだけで、何ら不都合はない。義経が6月5日の除目で国司に洩れたのは、頼朝が推挙を予定していた検非違使が国司を兼ねない例のためであろう。
また、『大夫尉義経畏申記』(『群書類従』巻百八)によれば、元暦2(1184)年正月1日に「新大夫判官義経朝臣」が左右の看督長を招いた埦飯に際して「大井次郎実春為因幡御目代勤仕之」という記述があることから、これは因幡守中原広元の目代として大井実春が埦飯の沙汰を行ったことがうかがわれ、この埦飯は頼朝の指示であった可能性が高い(菱沼一憲氏『源義経の合戦と戦略―その伝説と実像―』角川選書)。義経はその後「御共衛府」の「左衛門尉藤時成、左衛門尉藤康言、土屋兵衛左兵衛尉平義行、師岡兵衛左兵衛尉平重保、源八兵衛左兵衛尉藤弘綱、渋谷馬允左馬允重資、予(清原某)無官」のほか「武士百騎許」を従えて参院。装束や車を賜った(『清獬眼抄』)。
さて、義経の検非違使補任からわずか三日後の8月10日夜、義経は「有示子細事」して「召寄出羽守信兼男三人」を自邸に招いた。この三人は兼時、信衡、兼衡(『尊卑分脈』)であるが、六条堀川邸または六条室町邸に招請したのだろう。結局、三名は義経邸で「件三人或自殺、或被切殺」(『山槐記』元暦元年八月十日条)という。『吾妻鏡』では「於宿廬誅戮之」(『吾妻鏡』元暦元年八月廿六日条)とある。これは8月3日、頼朝が雑色・安逹新三郎を「源九郎主許」へ派遣し「今度伊賀国兵革事、偏在出羽守信兼子息等結搆歟、而彼輩遁圍之中、不知行方云々、定隠遁京中歟、早尋捜之、不廻踵可令誅戮之趣」(『吾妻鏡』元暦元年八月三日条)を命じたためと解せるが、義経が三人を召し寄せることができた、つまりそもそも居住地を知っていたことになる。そして、彼らは招請に素直に応じていることから、義経とはつながりを保っていた可能性が高い。こうしたことから、彼らが直接父に同調して叛乱に加担した可能性は低いだろう。ましてや結構して乱の首謀者となったことなど考えにくい。彼らは信兼に連座したものであろう。
信兼子息が討たれた翌日の8月11日、信兼も解官され(『吾妻鏡』元暦元年八月廿六日条)、翌12日、義経は「為伐出羽守信兼」に伊勢国に発向している(『山槐記』元暦元年八月十二日条)。ただし、義経麾下の兵は在京に耐えうる最低限の人数であり、官兵および検非違使らから編成された追捕の軍勢であったろう。山内経俊の軍勢も加わった可能性があり、8月26日の時点で「故出羽守信兼」(『山槐記』元暦元年八月廿六日条)とあることから、信兼は討たれたことがわかる。この戦いは7月の伊賀平氏の乱の延長線上であるが、この追捕を命じた主体は忠清法師ら平家旧家人を極度に恐れる法皇である可能性が高く、頼朝の関与は考えにくい。なお、翌元暦2(1185)年6月15日、頼朝は「故出羽守平信兼党類領」であった「伊勢国波出御厨」の地頭職に「左兵衛尉惟宗忠久」を補している(『島津家文書』)。
そのころ平家は讃岐国屋島に本拠を定めつつ、8月中には鎮西にもその地盤を固めつつあり、その持つ船は七百艘にも及んでいるという(『山槐記』元暦元年九月廿四日条)。一方、土肥実平・梶原景時の両名は、6月には播磨国まで平家の侵攻を許していたが、7月中には近国惣追捕使の任国西限の備後国あたりまでは押し戻していたようである。ただ、「鎮西多与平氏了、於安芸国与官軍早川云々、六ヶ度合戦、毎度平氏得理」(『玉葉』元暦元年八月一日条)と、安芸国での戦いでは、実平嫡子・早川太郎遠平が六度にわたって敗北するという知らせが京都に届いている。さらに、長門国の平教盛らの軍勢によって「長門国之源氏葦敷、被追落了」といい、「平氏五六百艘着淡路」という不確実ながら風聞が寄せられている(『玉葉』元暦元年九月十三日条)。
元暦元(1184)年8月26日、在京の義経は「賜平氏追討使官符」った(『吾妻鏡』文治五年閏四月卅日条)。これは範頼と義経の両将を追討使とした本格的な西国出兵構想であった。なお、義経の追討使官符下賜のタイミングは範頼上洛に合わせたものとみられ、翌27日に三河守範頼が入洛している(『吾妻鏡』元暦元年九月十二日条)。範頼にもこの二日後の8月29日に追討使の官符が下されており(『吾妻鏡』元暦元年九月十二日条)、福原攻めの際と同様、二手から四国屋島を攻めるものであったことがわかる。
9月1日、範頼勢は京都を出立した(『吾妻鏡』元暦元年九月十二日条)。範頼は鎌倉出立の際に頼朝から「一日不可逗留京都、直可向四国之由」(『玉葉』元暦元年八月廿一日条)を命じられており、入洛翌日の出征という非常に速やかな発向になった。ただ、このとき西国へ出向したのは範頼勢のみであり、義経は京都にとどまっている。さらに、範頼は当初予定の四国ではなく山陽道を西進している。これは、8月27日から29日の間に頼朝の使者が京都に到着し、範頼と義経に追討計画の変更を伝えたためであろう。変更の大きな要因は、伊賀伊勢平氏の挙兵であろう。この兵乱の勃発を受けた頼朝は、範頼・義経のいずれかを畿内警衛として留め置く必要に迫られたと思われる。ただ、範頼はもともと追討使として上洛していたことと、義経がすでに上方の情勢に精通し人脈も構築していたことから、義経を留守居として留めたのだろう。そして、義経発向の延引により四国屋島を攻める手はずも変更され、範頼勢は惣追捕使土肥・梶原勢への救援と、源氏に心寄せる九州国人を率いて屋島を攻める戦略に改められたと思われる。
土肥・梶原の惣追捕使両名は、安芸国などでの敗戦はあったものの、9月には周防国にまで兵を進めており、追討使範頼の軍勢もとくに抵抗に遭うこともなく周防国へ至っている。しかし、この間に平家勢により米穀は刈り取られており、範頼勢は兵糧米の補給に苦しみ、著しい兵糧不足に陥っている。兵舟も知盛が押収していたため、知盛の拠点である彦島を攻めることもできず、範頼勢は長門国での長滞陣を余儀なくされた。こうした状況により、範頼勢の士気は低下の一途を辿り、扈従の宗たる「和田太郎兄弟、大多和二郎、工藤一臈以下侍数輩、推而欲帰参」るほどの状況に陥ってしまう。兵站の喪失により極限の状態に追い込まれた範頼は、11月14日、物資の輸送を鎌倉の頼朝に求めたのであった(『吾妻鏡』元暦元年十一月十四日条)。実はこれ以前にも範頼は鎌倉に兵糧と兵船支援の要請を行っており、頼朝は「日来有沙汰、用意船可送兵粮米之旨、所被仰付東国也、以其趣、欲被仰遣西海」(『吾妻鏡』元暦二年正月六日条)と、伊豆国に東国各地から集めた兵船に兵粮米を積み込んで繋留していた。そしてこの頃、頼朝は義経に四国出兵を命じる使者を遣わした可能性が高く、翌元暦2(1185)年正月8日に義経は西海出兵の奏上を行っているのは、頼朝の意向を受けたものであろう。
元暦2(1185)年正月6日、鎌倉から範頼への御書を持った雑色が出立した。この書状には、九州国人の反発を買う行動の禁止、九州急派の自粛、天皇・二位尼の無事な奪還(当時の公卿衆や院が最も拘った神器について触れられない不審がある)が認められ、とくに天皇の救出と宗盛の生捕を指示していることから、頼朝が範頼に命じていることは、九州攻めではなく明らかに四国屋島御所を攻めることであったことがわかる。なお、この書状の九番目に「千葉介ことに軍にも高名し候けり、大事にせられ候べし」(『吾妻鏡』元暦二年正月六日条)と、とくに千葉介常胤に対する扱いを加えている。おそらくこの雑色は2月初旬頃に範頼のもとへ到着したのであろう。
また、別に認められた書状には、東国で徴発した兵船は2月10日には発向する予定の旨を伝え、九州の諸国人らを味方にしたらば「当時は搆へて搆へて、国の者をすかしてよき樣にはからはせ給へ、筑紫の者にて、四国をは責させ給へく候」と指示し、彼らを以って四国を攻めるよう命じたのであった。ここでも頼朝が範頼に命じていたのはあくまでも四国攻めであったことがうかがえる。一方で、頼朝は九州国人らに宛てて「御下文一通」を発給し、院宣及び三河守範頼の下知に随うよう命じた(『吾妻鏡』元暦二年正月六日条)。
この「御下文」の年次は元暦元年であるが編纂作業での誤記であろう。そのほか内容にも不審があるため、編纂時に書き改めた可能性がある。
この下文は「参河守向九国、以九郎判官所被遣四国也」とあるため、義経に対する四国出兵の指示を発したのちに認められたものである。下文にある「参河守向九国」はあくまでも範頼が九州の管領であることを九州国人へ伝える意図であり、頼朝の本心は2月13日に鎌倉に到着した「伊澤五郎(石和五郎信光)」からの書状の返答に記す「依無粮退長門之條、只今不相向敵者有何事哉、攻九国事当時不可然歟、先渡四国、与平家可遂合戦」(『吾妻鏡』元暦二年二月十三日条)とある通りであろう。ただ、九州に進出することを禁じていたわけではなく、「令談于土肥二郎、梶原平三、可召九国勢、就之若見帰伏之形勢者、可入九州、不然者与鎮西不可好合戦、直渡四国可攻平家者」と(『吾妻鏡』元暦二年二月十四日条)、土肥・梶原と相談の上、九州国人が靡くようであれば九州にわたり、もし靡かないようであれば九州は攻めずに四国を攻めるよう指示したのであった。
ただし、石和信光や範頼の使者が鎌倉へ到着した2月中旬頃には、範頼はすでに北九州を制圧しており、さらに頼朝の返書が範頼のもとに届いたのは、すでに壇ノ浦の戦いが終わり、平家が滅んだ後であったとみられる。つまり範頼が認識していた頼朝からの指示は『吾妻鏡』によれば、あくまで四国攻めだけであるはずだが、実際には範頼は九州へ渡海している。範頼が頼朝の命を違えて九州に渡ることは考えにくく、義経に四国渡海を指示したとみられる元暦元(1184)年12月末頃には、範頼にも「可召九国勢、就之若見帰伏之形勢者、可入九州、不然者与鎮西不可好合戦、直渡四国可攻平家者」(『吾妻鏡』元暦二年二月十四日条)と同様の内容が伝えられていたと考えられ、「爰参州入九国之間、可管領九州之事、廷尉入四国之間、又可支配其国々事之旨、兼日被定處」(『吾妻鏡』元暦二年五月五日条)とあることから、範頼は九州に入ったらば九州を管領し、義経は四国に入ったらば四国の国々を支配することが定められていたという。
さて、長門国赤間が関まで進出して「新中納言知盛相具九国官兵、固門司関、以彦嶋定営、相待追討使」(『吾妻鏡』元暦二年二月十六日条)を牽制しつつも、兵糧の欠乏と士気の低下に悩まされていた範頼は、陣中で「志在源家之由、兼以風聞」があった豊後国の臼杵惟隆・緒方惟栄の兄弟に対して「召船於彼兄弟、渡豊後国、可責入博多津之旨」(『吾妻鏡』元暦二年正月十二日条)という戦略を決定し、正月12日、長門国からいったん周防国(防府市国衙か)へと戻った。「粮尽之間、又引退周防国訖」(『吾妻鏡』元暦二年二月十三日条)とされるが、豊後国臼杵・緒方の兵船融通を前提にした帰国であった。ただ、長門国での兵糧米の確保は不可能な状況にあったのは間違いなく、周防国おろか安芸国までの撤退も計画されていたという(『吾妻鏡』元暦二年二月十三日条)。
その直後、豊後国臼杵・緒方が召しに応じて八十二艘の兵船を献上。さらに周防国人の「宇佐那木上七遠隆」からは兵糧米の提供があった。なお、「伊澤五郎」が頼朝に苦境を訴える飛脚を飛ばしたのはちょうどこの時期であった。「東国之輩、頗有退屈之意、多恋本国、如和田小太郎義盛、猶潜擬帰参鎌倉、何况於其外族矣」という状況にあり(『吾妻鏡』元暦二年正月十二日条)、範頼は「軍士等漸有変意不一揆」と統制が取れないほど混乱した様子を伊豆の頼朝のもとへ報告している(『吾妻鏡』元暦二年二月十四日条)。
その後、「和田太郎兄弟、大多和二郎、工藤一臈以下侍数輩、推而欲帰参之間、抂抑留之、相伴渡海畢」(『吾妻鏡』元暦二年三月九日条)とあるとおり、範頼は和田義盛以下の人々を無理やり押し留め、正月26日、九州へ相伴させることになるが、この報告を受けた頼朝は範頼と御家人らに「仍今度不遂合戦、令帰洛者有何眉目哉、遣粮之程令堪忍可相待之、平家之出故郷在旅泊、猶励軍旅之儲、况為追討使、盍抽勇敢思乎」(『吾妻鏡』元暦二年正月十二日条)と叱咤している。なお、千葉介常胤も老体をおして孫の境平次常秀とともに渡海している(『吾妻鏡』元暦二年正月廿六日条)。
●範頼渡海軍従軍諸士(『吾妻鏡』元暦二年正月廿六日条)
| 北条小四郎義時 | 足利蔵人義兼 | 武田兵衛尉有義 | 小山兵衛尉朝政 | 長沼五郎宗政 |
| 結城七郎朝光 | 武田兵衛尉有義 | 齋院次官中原親能 | 千葉介常胤 | 境平次常秀 |
| 下河辺庄司行平 | 下河辺四郎政能 | 阿曽沼四郎広綱 | 三浦介義澄 (周防駐屯) |
三浦平太義村 (周防駐屯か) |
| 八田四郎武者知家 | 八田太郎朝重 | 葛西三郎清重 | 渋谷庄司重国 | 渋谷二郎高重 |
| 比企藤内所朝宗 | 比企藤四郎能員 | 和田小太郎義盛 | 和田三郎宗実 | 和田四郎義胤 |
| 大多和三郎義成 | 安西三郎景益 | 安西太郎明景 | 大河戸太郎廣行 | 大河戸三郎 |
| 中条藤次家長 | 加藤次景廉 | 工藤一臈祐経 | 宇佐美三郎祐茂 | 天野藤内所遠景 |
| 一品房昌寛 | 土佐房昌俊 | 小野寺太郎道綱 |
範頼は渡海に際し、周防国の留守を任すべき人物について、「周防国者、西隣宰府、東近洛陽、自此所通子細於京都与関東、可廻計略之由、有武衛兼日之命、然者、留有勢精兵、欲令守当国、可差誰人哉」(『吾妻鏡』元暦二年正月廿六日条)と諸将に問うと、常胤が進み出て、「義澄為精兵、亦多勢者也、早可被仰」と三浦介義澄を推したのである。これを受けて、範頼は義澄に周防国守護を指示したが、義澄は「懸意於先登之處、徒留此地者、以何立功哉」と強く辞退した。これに範頼は「撰勇敢被留置之由」を述べて再三に渡って命じたため、義澄も折れて周防国に留まることを了承した(『吾妻鏡』元暦二年正月廿六日条)。
周防国での範頼の所在地はおそらく周防国府(防府市国衙)であろうから、臼杵・緒方の提供した兵船は国衙外港の船所(防府市国衙五丁目)に繋留されたと考えられよう。ここから出帆した範頼らは、向島や田島などの浮かぶ湾を南下し、豊後国府の外港(大分市坂ノ市)に上陸したのではなかろうか。国東半島の北側には平家と関係の深い宇佐神宮があることから上陸は忌避することが予想され、別府から日出、宇佐方面へ向かい、京都郡内を経て遠賀川を遡上したと思われる。
上陸から数日後の2月1日、「北条小四郎、下河辺庄司、澁谷庄司、品河三郎等」を先登に遠賀川河口の葦屋浦に進出した範頼勢は、鎮西平家方の重鎮であった「太宰少弐種直、子息賀摩兵衛尉等」と合戦に及び、渋谷重国勢は原田種直・賀摩種国勢を散々に射倒し、下河辺庄司行平は種直の弟・美気三郎敦種を射殺している(『吾妻鏡』元暦二年二月一日条)。範頼勢は豊後国北東部から豊前国北東部一帯を制圧することで、豊前国彦島の知盛は周防国の三浦介義澄との間に挟まれる形となり、積極的な身動きが取れない状況に陥った。
平重盛====女子
(内大臣) ∥
∥
原田種雄―+―原田種直――賀摩種国
(大宰大監)|(大宰少弐)(兵衛尉)
|
+―美気敦種
(三郎)
京都警衛の必要性から、義経の西国下向に踏み切れない頼朝は、元暦元(1184)年9月19日、文武に通じた側近・橘次公業を「為一方先陣」として屋島のある讃岐国へ派遣し、5月に交名を提出した「各令帰伏搆運志於源家之輩」に「可隨公業下知之由」を命じている(『吾妻鏡』元暦元年九月十九日条)。橘公業は京都に伺候していた藤大夫資光以下の讃岐国人を率いて讃岐国へ赴いており、義経に頼朝からの四国攻めに関する何らかの通達を伝えているのは確実であろう。元暦元年中、四国を攻めることができない追討使の両名に代わり、讃岐国内で平家を牽制していたのは彼らであった。
●源氏御方奉参京都候御家人交名(『吾妻鏡』元暦元年九月十九日条)
| 藤大夫資光 | 新大夫資重(資光子) | 新大夫能資(資光子) | 藤次郎大夫重次 | 六郎長資(重次舎弟) |
| 藤新大夫光高 | 野三郎大夫高包 | 橘大夫盛資 | 三野首領盛資 | 仲行事貞房 |
| 三野九郎有忠 | 三野首領太郎(盛資子か) | 次郎(盛資子か) | 大麻藤太家人 |
・讃州藤家系図(『吾妻鏡』より推測)
藤原某―+―藤原資光―+―藤原資重
|(藤大夫) |(新大夫)
| |
| +―藤原能資
| (新大夫)
|
+―藤原重次
|(次郎大夫)
|
+―藤原長資
(六郎)
・讃州藤家系図(『史料叢書』南海通記)
藤原家成 +―藤原親高
(中納言) |(周防守)
∥ |
∥―――――藤原資高―+―藤原有高 +―藤原資幸
∥ (羽床庄司)|(藤太夫) |(藤太夫)
∥ | |
綾貞宣――女子 +―藤原重高 +―藤原信資
(綾大領) |(藤太夫) |(次郎左衛門)
| |
+―藤原資光――+―藤原資村
(藤太夫) (左近将監)
橘公業はもともと父・右馬允橘公長や兄・橘太公忠とともに「左兵衛督知盛卿家人」であったが、治承4(1180)年12月19日、父や兄とともに鎌倉に帰参したとされ(『吾妻鏡』治承四年十二月十九日条)、頼朝の信任を得て側近となった人物である。
|
惟宗忠康 |
元暦元(1184)年8月26日に「賜平氏追討使官符」っていた義経であったが(『吾妻鏡』文治五年閏四月卅日条)、京都を含めた畿内の不安定な状況によって発向が延引されていた。
このころ義経は頼朝の命を受けて、伊賀伊勢平氏の乱の収束活動を行っているが、9月9日、頼朝は義経へ「出羽前司信兼入道已下、平氏家人等京都之地」について義経の沙汰とする旨の御書を遣わしている。京内における平家没官領の管理を義経に一元化して、武士らが勝手に没官領の沙汰をすることを禁じ、その扱いは法皇の御定とすると伝えている(『吾妻鏡』元暦元年九月九日条)。ただし、このうち「信兼領」については「義経沙汰」と別扱いしており、これは義経が直接管轄すべきものとしている。法皇御定の地とはいえ、実質的に義経へ宛がわれた恩賞とみるべきか。
そのわずか五日後の9月14日には、鎌倉から義経の妻女となる「河越太郎重頼息女」が上洛の途に就いた(『吾妻鏡』元暦元年九月十四日条)。これはもともと頼朝と義経の間での「約定」のためであったが、頼朝が信認する比企尼所縁の女子を義経に縁づけることで、より義経との紐帯を固めようとする頼朝の考えが強かったことがうかがわれる。
頼朝が範頼やほかの門葉ではなく義経を京都代官として起用し続けたのも、彼の警衛能力や公家衆との折衝能力を認めていたことに他ならないだろう。当時、義経の身辺には朝廷に伝手のある中原親能も中原広元も不在であり、義経は院近臣や後藤基清など公卿と関係のある在京御家人が義経の活動を支え、義経も直に公家衆と交わりながら、その政治的な役割を磨いていたと思われる。俗説のような政治的能力の欠如は認められず、混沌とする畿内、近国の国領・庄園など所領の管理・監督、狼藉の鎮定及び治安維持、朝廷や法皇との際どい折衝、平家への対応など多岐にわたる諸役を一手にこなす手腕を発揮していたのである。さらに頼朝は義経の叙爵を推しており、9月18日の大除目で義経は従五位下となる(『山槐記』元暦元年九月十八日条)。さらに10月15日には院の内昇殿が聴され(『吾妻鏡』元暦元年九月廿四日条)、義経は法皇とのスムーズな折衝が可能となった。
●元暦元年九月十八日大除目(『山槐記』元暦元年九月十八日条)
| 人名 | 官位 | 官位 (現) |
備考 |
| 任官 | |||
| 藤原朝方 | 権中納言(還任) | 正二位 | 院近臣 |
| 藤原定能 | 権中納言 参議 左近衞権中将 |
正三位 | |
| 藤原経房 | 中納言 参議 左大弁 |
従三位 | |
| 藤原基家 | 参議 | 正三位 | |
| 平親宗 | 参議 | 正三位 | 院近臣 |
| 藤原兼光 | 左大弁 | 従三位 | |
| 藤原光雅 | 右大弁 | 正四位下 | |
| 源兼忠 | 権右中弁 | 正四位下 | 入道前権中納言正二位源雅頼卿二男。 母は正二位行中納言藤原家成女。 乳母夫は斎院次官親能。 |
| 平基親 | 左少弁 | 正五位下 | 院近臣。入道参議正三位行民部陽親範卿の子。 母は若狭守従五位下高階泰重女。 |
| 藤原定長 | 右少弁 蔵人左衛門権佐 |
正五位下 | 故権右中弁兼中宮亮光房五男。 母は故丹後頭藤原為忠女(官女)。 |
| 藤原範光 | 式部権少輔 | 正五位下 | |
| 平範経 | 宮内少輔 | ||
| 藤原宗綱 | 大膳大夫 | ||
| 高階経仲 | 右馬頭 | 従四位上 | 院近臣。 大蔵卿高階泰経長男。 母は故三位従五位下藤原行広女。 |
| 藤原実明 | 美濃守 右近衞少将 |
正四位下 | |
| 藤原範季 | 備前守 | 従四位上 | 院近臣。 故従四位下行式部少輔能兼三男。 母は散位従五位下高階為賢女。 三河守範頼の養父。 |
| 中原広元 | 因幡守 | 従五位上 | のちの大江広元 |
| 叙位 | |||
| 平為盛 | 従四位下 | 平頼盛入道の子 | |
| 藤原朝仲 | 正五位下 | 右大臣兼実甥 | |
| 源義経 | 従五位下 | 左衛門少尉、検非違使 | |
| 藤原家通 | 検非違使別当 右衛門督 |
従二位 | |
後日、義経追捕が行われた際、頼朝が「今度同意行家義経之侍臣并北面輩事」として「侍従良成、少内記信康伊与守右筆、右馬権頭業忠、兵庫頭章綱、大夫判官知康、信盛、左衛門尉信実、時成等」(『吾妻鏡』文治元年十二月六日条)の懲罰を求め、「同意行家義経等欲乱天下之凶臣也」として「参議親宗、大蔵卿泰経、右大臣光雅、刑部卿頼経、右馬頭経仲、右馬権頭業忠、左大史隆職、左衛門少尉知康、信盛、信実、時成、兵庫頭章綱」(『吾妻鏡』文治元年十二月六日条)の解官を要求しているように、義経は院近臣を通じて法皇との間に強いパイプを構築していた様子がうかがえる。なお、「侍従良成」は「故長成朝臣男」であるが、母は九条院雑仕常盤であり、義経の異父弟にあたる。
10月6日、鎌倉において「新造公文所吉書始」が執り行われ、別当に「安芸介中原広元」が就き、長年京都に祗候した経験を持つ「斎院次官中原親能、主計允藤原行政、足立右馬允藤内遠元、甲斐四郎大中臣秋家、藤判官代邦通等」が寄人となった。
■公文所吉書始(『吾妻鏡』元暦元年十月六日条)
| 別当 | 安芸介中原広元 |
| 寄人 | 斎院次官中原親能 主計允藤原行政 足立右馬允藤内遠元 甲斐四郎大中臣秋家 藤判官代邦通 |
判官代邦通が吉書を書き広元が頼朝に披露している。その後、「千葉介」が垸飯を行ったというが(『吾妻鏡』元暦元年十月六日条)、「千葉介」常胤は範頼に随って中国地方を転戦しており、この「千葉介」は常胤子息・千葉太郎胤正であろう。また、広元は義経の叙爵と同日の9月18日、因幡守となっているが、前官職の安芸介と記されていることから、除書がまだ鎌倉に着いていなかったということか。
元暦2(1185)年正月8日、大蔵卿泰経は院中で会った権中納言経房に「廷尉義経可向四国之由」(『吉記』元暦二年正月八日条)を語っている。すでに義経からこの旨が法皇には奏上されていたが、法皇が難色を示していたようである。これに義経は「而自身可候洛中、只可差遣郎従歟」ということを「申被人(法皇や一部の院近臣であろう)」もあるが、これは「忠清法師在京之由風聞、定挿凶心歟」のためであろうという予測を述べている。忠清法師は伊賀伊勢平氏の乱に加担しており、法皇は忠清法師への強い危機感を持っていたことを物語る。義経の平家追討延引はこの忠清法師ら平家残党を恐れる法皇が頼朝に働きかけた結果であろう。
しかし、西国の参河守範頼の軍勢は「二三月兵糧尽了」という状況が京都にも伝わっており、義経は「範頼若引帰者、管国武士等猶属平家、弥及大事歟」と強く主張した(『吉記』元暦二年正月八日条)。経房はこの義経の意見を聞き「義経申状、尤有其謂、大将軍不下向、差遣郎従等之間、雖有諸国費、無追討之実歟、範頼下向之後、及此沙汰歟、然者今春義経発向尤可決雌雄歟」と義経の西国下向案を推した(『吉記』元暦二年正月八日条)。たとえ義経が下向したとしても、「猶於可然之輩者、差分可令祇候京都之由、尤可被仰合也」と、京都にも守衛の武士は残されることも述べている。ただ、法皇が恐れる件の忠清法師は、経房にとっては「於忠清法師事者、不及沙汰歟、但可搦進其身之由、尤可被宣下歟」(『吉記』元暦二年正月八日条)とあるようにもはや脅威ではなく、捕らえて進上する旨の宣旨を下しておけばよいという程度の認識であった。結局、経房の推挙もあったか、義経の西国下向は認められ、正月10日に「大夫判官義経、発向西国」(『吉記』元暦二年正月十日条)と、平家討伐のために京を出立した。
義経は淀川の河口、摂津国渡邊へと移り、その後ひと月あまりこの地に駐屯した。この不自然な滞陣の理由は不明だが、当時「平家者結陣於両所、前内府以讃岐国屋嶋為城郭、新中納言知盛相具九国官兵、固門司関、以彦嶋定営、相待追討使」(『吾妻鏡』元暦二年二月十六日条)という状況の中、瀬戸内への玄関口である渡邊津で、四国を攻めるための軍勢催促が行われていたのであろう。京都には兵粮の問題から、京都駐屯が可能な人数しか配されていなかったことは確実であり、追討使拝命後は「畿内近国、号源氏平氏携弓箭之輩幷住人等、任義経之下知可引率之由、可被仰下候」(『玉葉』寿永三年二月廿七日条)とあるように、畿内・近国の国人を中心に兵力を整えていたとみられる。こうした中で、範頼は豊後国人らの協力を得られる確証を得て長門国で豊後渡海を議定し、正月26日に渡海を果たし、2月1日に豊前国葦屋浦(福岡県遠賀郡芦屋町)での戦いに勝利。彦島(下関市彦島)の南対岸に進んだとみられる。権中納言知盛の九州渡海を防ぎ、平家勢の兵力補充を阻害したのである。
一方、範頼から九州渡海の報を受けた義経は、単独で讃岐国屋島の御所を攻めることとなったが、2月16日、法皇は大蔵卿泰経を義経が滞陣する「渡邊」へ派遣し、院宣を以て「為制止義経発向」を命じた(『玉葉』元暦二年二月十六日条)。それは「是京中依無武士為御用心」という法皇の不安から出たものであったが、義経は「敢不承引」であった(『玉葉』元暦二年二月十六日条)。範頼が北九州で知盛を抑えることで、四国へ進む可能性がなくなった以上、義経の出陣が必須となったためであろう。泰経は「泰経雖不知兵法、推量之所覃、為大将軍者、未必競一陣歟、先可被遣次将哉」と説得するが、義経は「殊有存念、於一陣欲棄命」と告げたという(『吾妻鏡』元暦二年二月十六日条)。兼実は法皇が公卿たる泰経にこのようなくだらない使者をさせることを強く批判している(『玉葉』元暦二年二月十六日条)。
頼朝は2月5日に「典膳大夫中原久経、近藤七国平、為使節上洛」(『吾妻鏡』元暦二年二月五日条)させているが、これは義経・範頼両将の西国出兵の完了を受けたものであろう。久経・国平両名は「是追討平氏之間、寄事於兵粮、散在武士於畿内近国所々致狼藉之由」の報告があるため、「仍雖不被相待平家滅亡、且為被停止彼狼唳、所被差遣」た使節であった。彼らは「先相鎮中国近辺之十一ケ国、次可至九国四国」という任務を請け負っており、この「中国近辺之十一ケ国」は「不被相待平家滅亡」とあることから、平家が管領していた梶原・土肥が惣追捕使を務める五か国を含む山陽地方であろう。そのほか「為鎮畿内近国狼唳」(『吾妻鏡』元暦二年三月四日条)ともあり、畿内の武士による狼藉を鎮めることも彼らの任務であった。
彼らは「今両人雖非指大名」と頼朝も認識している通り大身ではなく、義経の代理ではない。彼等には義経の「職務の一部」である狼藉防止の任務が与えられたとみられるが、何事も「悉以経奏聞、可随 院宣」を指示しており、ただ院宣に随うという「此一事之外、不可交私之沙汰之由」をきつく申し付けられているのである。なお、この使節が上洛したのは時期的に2月15日前後と考えられることから、法皇は彼らを心許なく思い、頼りとなる義経を呼び戻そうと試みた可能性があろう。なお、義経がいたのは『延慶本平家物語』などでは「大物の浦」であるが、実際には『玉葉』『吾妻鏡』に見える通り摂津国「渡邊」(『玉葉』元暦二年二月十六日条)である。
法皇使の高階泰経が到来した2月16日(『吾妻鏡』では前日15日より宿泊)、義経は渡邊津を「十六日解纜」(『玉葉』元暦二年二月廿七日条、三月四日条)した。『玉葉』の記述は、義経からの「申上状」を受けた小槻隆職が兼実に注送したものであるため、信憑性は高い。『吾妻鏡』でも16日に「関東軍兵為追討平氏赴讃岐国、廷尉義経為先陣、今日酉尅解纜」(『吾妻鏡』元暦二年二月十六日条)とあり、朝廷に伝えられた出航日は2月16日だったことがわかる。『吾妻鏡』には船の数は記されていないが、軍記物『平家物語』(延慶本)の記述では集結した船は「百五十艘」とある(『延慶本平家物語』)。
『玉葉』では義経申上状の記述から、予定通り2月16日に「十六日解纜」(『玉葉』元暦二年二月廿七日条、三月四日条)し、翌17日には「十七日着阿波国」(『玉葉』元暦二年三月四日条)となっていて、しかも「無為著阿波国了」(『玉葉』元暦二年二月廿七日条)とあるように、何ら問題なく阿波国に到着したという。ところが『吾妻鏡』では、16日夜に暴風に見舞われ、破損する兵船が続出(『吾妻鏡』元暦二年二月十八日条)し、暴風を恐れた「士卒船等一艘而不解纜」という状況が起こっていたという。ここで義経は「朝敵追討使暫時逗留、可有其恐、不可顧風波之難」(『吾妻鏡』元暦二年二月十八日条)と将士を鼓舞したが、士卒らの多くは危険回避のために渡海を拒絶したため、義経は明けて17日深夜丑刻(午前1時~3時頃)に同調する人々とともに「先出舟五艘」に分乗して出航し、数時間後の「卯尅着阿波国椿浦」という(『吾妻鏡』元暦二年二月十八日条)。義経が朝廷に伝える上では、とにかく無事に阿波国についたことは間違いなく、過程は省かれた可能性も十分にある。
なお、史料的価値は疑問の軍記物『延慶本平家物語』では「俄かに又南風激しく吹きて、船七八十艘、渚に吹き上げられ、散々に打ち破れたり」(『延慶本平家物語』)とあり、『源平盛衰記』『平家物語』ではこのとき義経と景時が激しく口論したと記される。「凡和田小太郎義盛与梶原平三景時者、侍別当所司也、仍被発遣舎弟両将於西海之時、軍士等事為令奉行、被付義盛於参州、被付景時於廷尉」(『吾妻鏡』元暦二年四月廿一日条)とあるように梶原景時は義経に付属していた代官であったことは間違いないだろう。ただ、この頃景時は「淡路国広田庄者、先日被寄附広田社之處、梶原平三景時為追討平氏、当時在彼国之間、郎従等乱入彼庄、妨乃貢歟」(『吾妻鏡』元暦元年十月廿七日条)とあるように、かなり早い段階から屋島を牽制するように淡路国に駐屯していた様子も見られ、実際に口論があったかは不明である。
『吾妻鏡』の記述では、17日早朝に「阿波国椿浦」に到着し、百五十騎が上陸したという(『吾妻鏡』元暦二年二月十八日条)。「椿浦」は阿南市椿町浜、阿南市椿泊町、阿南市椿町那波江、阿南市椿町楠ケ浦など、阿南市椿泊町のある半島上の泊の何れかであろう(桂浦説は、あくまでも『吾妻鏡』での記述だが「路次」であるため、ここではないだろう)。
義経に付随して渡海した際の交名は伝わっていないが、義経には「渡部党源五馬允」(『吾妻鏡』元暦二年三月廿四日条)も随っており、水運に長けた摂津渡邊党の協力があったのだろう。このほか、軍記物『延慶本平家物語』では「百五十艘の船の内、只五艘出だして走らかす、残りの船は皆留まりにけり、一番判官の船、二番畠山、三番土肥次郎、四番伊勢三郎、五番佐々木四郎已上五艘ぞ出だしたりけり」(『延慶本平家物語』)とあり、畠山次郎重忠、土肥次郎実平、伊勢三郎義盛、佐々木四郎高綱を主たる御家人とする「畠山を初めとして、一人当千の棟との者共六十余人、判官に付きにけり」という(『延慶本平家物語』)。ただ、この『延慶本平家物語』の記述は軍記物の特性上、信は置けない。このほか「田代冠者信綱、金子十郎家忠、同余一近則」(『吾妻鏡』元暦二年二月十九日条)や「後藤兵衛尉実基、同養子後藤新兵衛尉基清等」(『吾妻鏡』元暦二年二月十九日条)がいたという。
義経に従って阿波国に上陸したのは「則率百五十余騎上陸」(『吾妻鏡』元暦二年二月十八日条)とあるが、「百五十騎」を五艘で渡るには単純計算で一艘に五十人の将士と乗馬を乗せる必要があり、不可能である(平安期の大陸への渡航で用いられたような外洋船であっても漕手などを除けば一艘十数名と推測:(榎本渉「日宋・日元貿易船の乗員規模」『国立歴史民俗博物館研究報告』2021年3月)より考察)。もし百五十騎の上陸が事実であるとすれば、阿波へ渡る船は外洋船より小規模な兵船であったと考えれば、三十~四十艘規模の船団が必要となり、嵐で渡海ができなかったという説話には疑問符がつくことになる。
彼らが「上陸」した阿波国「椿浦」は阿波国中部の椿泊半島近辺と思われるが、義経は阿波国板西郡の「当国住人近藤七親家」を召して屋島までの道案内としたとある(『吾妻鏡』元暦二年二月十八日条)。坂西郡は吉野川流域という椿浦からは相当北に位置する地域であり、近藤親家にはあらかじめ到着する地点を指示しておく必要がある。暴風による漂着という不確定事項ではこの説話は成立困難となる(あらかじめ近藤親家が渡邊津の義経陣にいれば別である)。
義経は「赴讃岐国」(『吾妻鏡』元暦二年二月十六日条)とあるが、これは目的地としての讃岐国を指すか。『吾妻鏡』によれば、義経率いる百五十騎は椿浦から勝浦郡「桂浦(徳島市勝占町)」へ進出し、桂浦を望む中山に城塞を築いていた平家方の「桜庭介良遠」を攻めて追い落とした(『吾妻鏡』元暦二年二月十八日条)。桂浦は現在は海から数キロ離れているが、当時は羽ノ浦、立江、田浦から続く浜辺を形成していたのであろう。「桜庭介良遠」は「散位成良弟」であるが、「散位成良」は阿波国有力在庁で平重衡の麾下として宇治や美濃など各地を転戦した「阿波民部大夫成良(田口成良)」である。
義経は桜庭介良遠を追い落としたあと、桂浦から北上して吉野川に進出。西へ転じて「阿波国与讃岐之境中山」へと進んでいる。おそらくこの頃、橘次公業ら讃岐国に先陣として派遣されていた御家人と合流しているのだろう。その後、夜間に山を越えた義経勢は、19日未明に「屋嶋内裏之向浦(高松市新田町)」まで進み、「牟礼、高松民家」を焼き払ったという(『吾妻鏡』元暦二年二月十九日条)。『吾妻鏡』の記述からは、屋島の海峡を挟んだ南部と東部に侵攻したということになる。
ただし、椿浦から屋島までの道のりは陸行で約百二十キロメートルあり、途中の戦闘および登山を伴う陸行ではほぼ不可能な旅程である。『玉葉』では大夫史隆職からの注送で義経からの申状の内容が記されているが、こちらでは「去月十六日解纜、十七日着阿波国、十八日寄屋島、追落凶党了」(『玉葉』元暦二年三月四日条)とあり『吾妻鏡』の内容とは一日のずれが生じている(なお、前述の通り、『吾妻鏡』元暦二月十六日条の渡辺津出航の記述は義経が朝廷に送った申状に則った記載がなされ、その出典は『玉葉』をベースにしているとみられるが、翌二月十七日条ではまだ渡辺津から出航していないという前日と矛盾した状態が記載されていて、別の出典から齎されているとみられる。その後の『吾妻鏡』における義経の行動も16日の『玉葉』とは異なる出典から採用されており、義経の申状とは1日のずれが生じている)。『玉葉』は義経の「申状」の内容を機械的に記録しているものであるから『吾妻鏡』よりも信憑性が高いであろう。また、陸路で進軍したとすれば船は椿浦へ置くことになるが、屋島はその名の通り島であり、船を使わずに攻め入ることは不可能である。屋島周辺の船舶は当然接収されていたと考えられることから、義経は自前の船を持ったまま屋島に着陣していることになる。つまり、時間の点からも船の点からも、義経勢は阿波国椿浦から羽ノ浦、立江、田浦の海岸線を船で北上し、屋島へ向かったというのが現実的であろう。
なお、屋島侵攻を受けた宗盛は安徳天皇を奉じて海へ逃れ、義経は彼らを追って「田代冠者信綱、金子十郎家忠、同余一近則。伊勢三郎能盛等」を率いて汀を馳せ向かい、平家の兵船に矢を射かけ、平家側からも矢が放たれている。この間に別働の「佐藤三郎兵衛尉継信、同四郎兵衛尉忠信、後藤兵衛尉実基、同養子後藤新兵衛尉基清等」が空き家となった屋島内裏へ侵入するが、「越中二郎兵衛尉盛継、上総五郎兵衛尉忠光」は兵船から降りて屋島御所の宮門前に陣しており、佐藤継信を討ちとっている(『吾妻鏡』元暦二年二月十九日条)。
その後、別働隊は内裏と前内府宗盛の屋敷などを焼き払っており(『吾妻鏡』元暦二年二月十九日条)、平盛嗣、藤原忠光は退いたと思われる。戦後、義経は腹心・佐藤三郎継信の亡骸を僧侶に託して千株松の根元に埋葬し、法皇から給わった名馬・大夫黒を回向のため僧侶に給わったという(『吾妻鏡』元暦二年二月十九日条))。この屋島の戦いは京都に報告され、3月4日に大夫史隆職から兼実のもとに「寄屋島、追落凶党了」(『玉葉』元暦二年三月四日条)の報告がなされている。
屋島から東へ逃れた平家勢は「讃岐国志度道場(志度寺)」に籠り、2月21日、義経率いる八十騎がこれを攻め、平家は再び海へと逃れて西へ向かった。この合戦で「平氏家人田内左衛門尉」が義経に帰服した(『吾妻鏡』元暦二年二月廿一日条)。田内左衛門尉(田口左衛門尉教良)は前述の阿波民部大夫成良の子であるが、父や叔父が平家党として合戦している最中になぜ寝返ったのかは不明である。そのほか、伊予国人・河野四郎通信も三十艘の兵船を率いて義経勢に参戦。京都では「熊野別当湛増」も源氏へ属して渡海したという風聞が流れた(『吾妻鏡』元暦二年二月廿一日条)。実際に3月9日に鎌倉に届けられた範頼の書状でも「熊野別当湛増、依廷尉引汲、承追討使、去比渡讃岐国」ったといい(『吾妻鏡』元暦二年三月九日条)、義経の調略によって熊野別当が源氏側となったことが報告されている。なお、その際、湛増が義経の引汲によって「追討使」を拝命した風聞に不満を感じていることを述べている。この使者は3月10日に鎌倉に届くが、頼朝は湛増が渡海した風聞は「無其実」であると返答している。
湛快――――+―湛増
(熊野別当) |(熊野別当)
|
| 平忠度
|(薩摩守)
| ∥
行範 +―女子
(熊野別当) ∥――――女子
∥ ∥
∥―――――――行快
∥ (僧都)
源為義――+―鳥居禅尼
(六条判官)|
∥ |
∥ +―源行家―――――源光家
∥ (備前守) (左衛門少尉)
∥
∥――――――源義朝―――――源頼朝
藤原忠清―――女子 (左馬頭) (前右兵衛権佐)
(淡路守)
また「自関東所被差遣之御家人等、皆悉可被憐愍、就中千葉介常胤、不顧老骨堪忍旅泊之條、殊神妙、抜傍輩可被賞翫者歟、凡於常胤大功者、生涯更不可尽報謝之由」(『吾妻鏡』元暦二年三月九日条)と、頼朝は、とくに常胤について言及している。
そして、志度合戦の翌2月22日、屋島の磯に「梶原平三景時以下東士、以百四十余艘」が到着した(『吾妻鏡』元暦二年二月廿二日条)。景時は当時、淡路国に在陣していたと思われ、屋島から立ちのぼる黒煙などを見て、急ぎ馳せ参じたものではなかろうか。義経が2月19日に鎌倉へ遣わした飛脚は屋島合戦の前に陣を離れていたが、「而於播磨国顧後之處、屋嶋方黒煙聳天、合戦已畢、内裏以下焼亡無其疑」(『吾妻鏡』元暦二年三月八日条)と頼朝に報告しており、播磨国からも望める黒煙であった。
3月12日、頼朝は範頼が依頼していた兵船の補給として、伊豆国鯉名・妻郎津に繋留した兵船三十二艘に兵粮を乗せ、筑後権守藤原俊兼を奉行として西海に派遣する命を下した(『吾妻鏡』元暦二年三月十二日条)。もともと2月10日に解纜の予定であったが、ひと月あまりの遅延となっている。兵糧米の不足があった可能性があろう。3月14日には鬼窪小四郎行親を使者として、九州の範頼へ「是追討可廻遠慮事、賢所并宝物等無為可奉返入事等」との書状を遣わしている。三種神器の京都奉還は後鳥羽天皇の即位を行うにあたり必須であり、頼朝は安徳天皇の身柄よりも神器の無事な回収を優先していたのである。それは在京の貴族も同様であった。また神器の奉還は法皇からも強く要請されていたと思われ、すでに3月8日には義経、翌9日には範頼からの使者が鎌倉に到着し、頼朝は西国の戦況を把握していたと考えられることから、平家を追い詰め、神器を取り返すのも時間の問題であることを感じていたのだろう(『吾妻鏡』元暦二年三月十四日条)。
さて、志度寺の敗戦により、西へ向かった前内府宗盛ら平家一門は、まず「在讃岐国シハク庄」に拠った(『玉葉』元暦二年三月十六日条)。塩飽諸島のいずれかの島に拠点を構えんとしたのであろう。ところがここにも義経勢が攻め懸り、平家勢は「不及合戦引退、著安芸厳島了」で、その勢は「僅百艘許」であったという(『玉葉』元暦二年三月十六日条)。そのほか「平氏或在備前小島、或在伊予五々島」と瀬戸内の島嶼に拠っているが、ここに平家方として「鎮西勢三百艘相加」という伝聞が京都に届いた。兼実はこれらの報に「但実否難知、近日異説非一」と慎重な姿勢を示している(『玉葉』元暦二年三月十七日条)。
頼朝は「四国事者、義経奉之、九州事者、範頼奉之」(『吾妻鏡』元暦二年三月九日条)と指示しているように、義経は四国追討を任とし、範頼は九州追討が所役となったと思われる。ただし、飢饉による兵糧不足や厭戦気分の蔓延があったことから、平家追捕は持久戦になる可能性も高く、範頼と義経は担当地域に応じた活動は命じられていたものの、具体的な戦略は遼遠の地ということもあって彼らに委任され、その状況報告は逐一鎌倉へ送られる形だったのであろう。ただし、範頼と義経の両将は、神器と主上・国母奪還という共通目的を持ち、範頼は大宰府など平家の九州の拠点を掌握しながら彦島(下関市彦島)の南岸まで進出し、平家勢の九州渡海を阻止する一方、彦島の権中納言知盛と合流して九州への渡海を図るであろう前内府宗盛らを周防国の三浦介義澄が抑える戦略を取ったのだろう。範頼の九州封鎖は平家勢の行先を奪う目的があったと考えられる。
一方、屋島の平家党の追捕に成功した義経は、瀬戸内に逃れた宗盛らの追捕を敢行することとなる。宗盛らは安徳天皇を奉じて九州での態勢挽回のため西へ向かっており、まずは彦島に布陣して九州の平家与党を組織していた権中納言知盛との合流を図ったのである。宗盛勢を追捕するには、累代の平家与党が多く存在する瀬戸内を経て攻め上ることになり、義経勢は宗盛勢を「讃岐国シハク庄」から「安芸厳島」へ追ったものの、すでに権中納言知盛が張っていた警戒線が芸予海峡を塞ぐように「伊予五々島(愛媛県興居島)」(『玉葉』元暦二年三月十七日条)、「周防国大島(周防大島町)」にも「件島、平氏知盛卿謀反之時、構城郭所居住也、其間住人字屋代源三、小田三郎等令同意、始終令結構彼城畢」(『前右大将家政所下文』「鎌倉遺文」594)されていたのである。
こうした中、義経勢には伊予西部の氏族を支配下に置く(『関東下知状』「鎌倉遺文」1570)河野四郎通信の船団三十艘が加わっていたものの、寡兵に変わりはなく、平家勢が潜む瀬戸内を進むことは容易ではなかったはずである。義経は、宗盛が拠った芸州厳島へ向かわずに芸予海峡の島嶼をくぐり抜けると、周防国府(防府市国衙)傍の「大津嶋(周南市大字大津島)」へ上陸した(『吾妻鏡』元暦二年三月廿二日条)。これは宗盛勢の動向を窺うとともに周防国留守居の三浦介義澄との連携を図ったものであろう。
3月21日、義経は周防国で「聚乗船廻計」(『吾妻鏡』元暦二年三月廿二日条)し、「為攻平氏、欲発向壇浦」の予定であったが、この日は「甚雨」であり「延引」された(『吾妻鏡』元暦二年三月廿一日条)。義経は大津島に在陣していたと思われるが、周防国衙在庁で「依為当国舟船奉行」の船所五郎正利が、義経に「数十艘」の船を献じたという(『吾妻鏡』元暦二年三月廿一日条)。これが義経の要請があったものかは不明だが、義経勢には圧倒的に船が足らなかったのだろう。厳島の宗盛との戦いを避けて周防国に拠ったのも、兵船補給や補修の意図があったと思われる。周防船所からの兵船供与はこの上ないものであったろう。義経は正利の協力に対し「与書於正利、可為鎌倉殿御家人之由」(『吾妻鏡』元暦二年三月廿一日条)を証する文書を発給したという。そして翌3月22日、義経は「促数十艘兵船、差壇浦解纜」した(『吾妻鏡』元暦二年三月廿二日条)。
この出帆に先立ち、周防国留守居の三浦介義澄が、義経の「自昨日聚乗船廻計」を聞いた周防国府(防府市国衙)から大津島へ参会し、義経と対面している。義経出帆が程近いことを察したものであろう。ここで義経は義澄に「汝已見門司関者也、今可謂案内者、然者可先登者」(『吾妻鏡』元暦二年三月廿二日条)と命じている。これを受けた義澄は「進到于壇浦奥津邊去平家陣卅余町也」に船を進めたという。ただ、義澄は範頼に付属された人物で、範頼の命によって周防国の留守居を任された身であり、義経が義澄に出兵を命じることは明確な越権行為となろう。こうした行為が、頼朝の怒りを買う一因になっているのかもしれない。
なお、義経に付けられた代官の梶原平三景時は、去る2月22日に屋島の磯に「百四十艘」の船を率いて到着しているが(『吾妻鏡』元暦二年二月廿二日条)、義経が大津島を出帆した際には「数十艘」の船であったとされることから、義経は梶原景時とは合流していないことになる。また、屋島合戦以降、船を大量に徴発する時間的な余裕はないことから、義経麾下の船は、渡邊津を出帆した船および、河野通信の三十艘、周防船所提供の数十艘を加えた百艘に満たない兵船が義経が率いたすべてであったと思われる。ここに義澄が用いた兵船(これも周防国船所の船であろう)を加えても、さほど多くない数であったろう。
その頃、陣容を整えた安徳帝を奉じる平家勢が厳島から彦島方面へと向かっていったと思われる。この航行の様子は、大津嶋からも望めたであろう(対岸の姫島から大津嶋を望むことができる)。そして、彦島からも権中納言知盛自ら率いる軍勢が「赤間関」を経て「田之浦」沖に進み、安徳帝一行を海上で迎えて合流を果たしたと思われる。本来は陸上の御所にあるべき安徳天皇や女官も乗船して戦陣に身を置いていることを考えると、宗盛や知盛はすでに葦屋合戦で壊滅した北九州からの上陸を諦め、南下して九州への上陸を企図したのではなかろうか。ここに3月24日、義澄を「先登」とした義経勢が進出し、「壇浦奥津邊」でぶつかったのだろう。「壇ノ浦の戦い」である。
なお、「壇浦奥津邊」は、少なくとも田之浦(北九州市門司区田野浦)沖よりも東の長府沖であると考えられ、現在の下関市壇ノ浦町から北東方向一帯が「壇浦」と称されていたと思われる。
ところで、屋島を追われた安徳天皇や宗盛以下の平家勢は合戦までの間、どこにいたのだろうか。長門国彦島に上陸したという説もあるが、彦島上陸を証明する資料はない。『玉葉』からの足取りでは、宗盛は「厳島」へ到着したとの報告が兼実に届いているほか、「備前小島(玉野市周辺)」や「伊予五々島(愛媛県興居島)」に分散していた様子がうかがえる(『玉葉』元暦二年三月十七日条)。厳島へ上陸した安徳帝以下の平家勢は、即座に厳島や周防大島などからの援兵により兵力を回復したと思われる。
義経勢と衝突した平家方は、まず葦屋合戦後に知盛陣に遁れたと思われる「山峨兵藤次秀遠」と、肥前国「松浦党」が大将軍となって合戦がはじまった。義経は範頼との連携を図るための具体的な戦略を立てる前に知盛麾下の軍勢と遭遇しており、義経は自勢と三浦介義澄勢で平家勢と戦うこととなっている。範頼勢が海戦に参戦しなかったのは、範頼が牽制役に徹したのではなく、戦いの発生過程にあったとみられる。
義経の兵力は大津島を出帆する際に「数十艘」とあることから、義澄が率いた船を加えてもそれほど大兵力ではなかったと思われる。また宗盛率いる屋島平家勢は「僅百艘許」(『玉葉』元暦二年三月十六日条)で、彦島に籠っていた知盛勢も、山鹿・松浦党の残兵を加えたとしても、それほど大きな兵力を有し得なかったであろうから、義経が頼朝へ報告した「浮八百四十余艘兵船、平氏又艚向五百余艘合戦」(『吾妻鏡』元暦二年四月十一日条)という陣容での合戦は考えにくいであろう。
合戦は義経勢が平家勢を次第に押してゆき、「及午剋、平氏終敗傾」という結末を迎えた。このとき、故清盛入道正室の「二品禅尼(平時子)」は神器のひとつ「宝剣」を持ち、「按察使局」は先帝安徳天皇を抱き、壇ノ浦に入水した(『吾妻鏡』元暦二年三月廿四日条)。安徳天皇生母・建礼門院平徳子も入水したが、義経麾下の渡邊源五允によって救出され、安徳天皇を抱いて入水した按察局も引き上げられている。しかし、八歳の先帝安徳天皇(兼実は一時的に「西海王」と呼んでいる)と宝剣はついに浮かび上がってくることはなかった。七歳の「若宮今上兄」も平家とともに行動していたが救出されている。のちの守貞親王(後堀河天皇実父、後高倉院)である。平家方の宗たる人々では、「前中納言教盛、号門脇」「前参議経盛」「新三位中将資盛、前少将有盛朝臣等」が入水死、「前内府宗盛、右衛門督清宗等」は入水するも義経腹心の伊勢三郎能盛によって生け捕られた(『吾妻鏡』元暦二年三月廿四日条)。御座船に乱入して賢所を開けんとする東国武士に対しては、これを守衛していた「平大納言時忠」が強く制止している(『吾妻鏡』元暦二年三月廿四日条)。兵士らは「于時両眼忽暗、而神心惘然」となって逃げたというが、事実であれば時忠卿に目の前のものが神器であると告げられ、突然の事態に兵士らが慄き慌てたということかもしれない。時忠は平家一門とはいえ、清盛妻二位尼の弟という血縁関係となり、血統としてはまったく別流の桓武平氏である。その鎮西行への同行は、平家との関係というよりも先帝安徳天皇の大伯父、乳父という立場での行動であったろう。
●長門国平家与源氏合戦(『醍醐雑事記』)
| 生取 | 内大臣宗盛 | 三十九歳 | 故清盛入道の三男。 |
| 右衛門督清宗 | 十五歳 | 前内府宗盛の長男。 | |
| 大納言時忠 | 五十六歳 | 兵部権大輔時信の長男。故清盛入道の義弟。 | |
| 讃岐中将時実 | 三十五歳 | 大納言時忠卿の長男。 | |
| 内蔵頭(平信基) | 院近臣。兵部卿信範の長男。 | ||
| 二位僧都全真 | 院近臣藤原親隆の子で、時忠卿の母方の甥。 伯母にあたる八条殿時子の猶子。 |
||
| 法性寺執行能円 | 近臣藤原顕憲の子で、時忠卿の異父弟。 | ||
| 阿波民部大夫成良 | 阿波国の在庁で、壇浦合戦で源氏方に寝返った伝もあるが、 『醍醐雑事記』『吾妻鏡』いずれにも生捕の人数にあり、 彼の寝返りの伝は疑わしい。 |
||
| 藤内左衛門信康 | 平家家人。 | ||
| 女院 | 三十一歳 | 建礼門院。御諱は徳子。 | |
| 若宮 | 七歳 | 故高倉院第二皇子。平知盛室治部卿局を乳母とする。 のち守貞親王となり、皇子は後堀河天皇となる。 |
|
| 降人 | 源大夫判官季貞 | 平家家人。検非違使。 | |
| 摂津判官盛澄 | 平家家人。検非違使。 | ||
| 自害 | 中納言教盛 | 五十八歳 | 故忠盛卿の三男。門脇殿。母方は摂関家庶流という貴種。 こうした血統ゆえか、嫡子通盛は平家庶流中で唯一の公卿となる。 |
| 中納言知盛 | 三十四歳 | 故清盛入道四男。 | |
| 能登守教経 | 二十六歳 | 門脇中納言教盛の子。一ノ谷の合戦で討死したともされるが、 壇之浦合戦での活躍もみられ、真相不明。 |
|
| 殺人 | 左馬頭行盛 | 故清盛入道次男・基盛の子。播磨守という受領の上臈を経て、左馬頭へと昇る。ただし、行盛は従五位上、そしてのちに伊予守となった義経は従五位下であったように、この時点で伊予国や播磨国といった「四位上臈」任国の格は失われていたことがわかる。 | |
| 小松少将有盛 | 故小松内府重盛の子。『吾妻鏡』では入水したとある(『吾妻鏡』元暦二年三月廿四日条)。 | ||
| 備中吉備津宮神主 | |||
| 権藤内貞綱 | |||
| 権藤内貞綱舎弟 | |||
| 菊池二郎 | |||
| 刎頸者八百五十人 | |||
| 不知行方人 | 先帝 | 安徳天皇。 | |
| 八条院 | 二位尼平時子。 | ||
| 修理大夫経盛 | 六十二歳 | 故忠盛卿の次男。母は源信雅女。母方は名門村上源氏であるが、庶家の受領層であったため、摂関家庶家を外戚とする教盛や、当腹嫡子の頼盛といった異母弟より一段下に置かれていた。そのためか異母兄清盛や平家一門との関係よりも、姻戚関係にあった藤原師長や院司として仕えた太皇太后宮、その実家である閑院家の藤原実定らとの結びつきが強かった。壇之浦合戦では「前參議経盛出戦場、至陸地出家、立還又沈波底」(『吾妻鏡』元暦二年三月廿四日条)とあるように、いったん上陸して出家したのちに戻り、入水したという。 | |
| 内侍所御坐 | |||
| 進正御坐 | |||
| 宝剣不見 | |||
| 女院 | |||
| 二宮 |
壇ノ浦の戦いから四日後の元暦2(1185)年3月27日、京都の兼実のもとに「平氏於長門国被伐了、九郎之功」(『玉葉』元暦二年三月廿七日条)という「伝聞」が届いた。ただ、兼実は例の如く「実否未聞、可尋之」とさらなる情報を待つ姿勢を示す。
翌3月28日、兼実は経房の弟、右少弁定長を通じて、この伝聞の出所が「佐佐木三郎ト申武士説」であることを知る。彼は義経勢に加わっている佐々木三郎盛綱であるが、兼実はなおも「義経未進飛脚、不審尚残」として慎重な姿勢を崩していない(『玉葉』元暦二年三月廿八日条)。
翌3月29日、権中納言定能が兼実邸を訪問し「語平氏之間事、如昨日定長語」(『玉葉』元暦二年三月廿九日条)という。
そして4月3日夜、「追討大将軍義経」からの飛脚が届いた旨が報告された(『玉葉』元暦二年四月四日条)。飛脚に副えられた札によれば、「去三月廿四日午刻、於長門国団合戦、於海上合戦云々、自午正至哺時、云伐取之者、云生取之輩、不士知其数、此中前内大臣、右衛門督清宗内府子也、平大納言時忠、全真僧都等為生慮云々、又宝物等御座之由、同所申上也、但旧主御事不分明」という。法皇は平時は兼実を敬遠しているが、兼実ほど故実に通じた現役公卿はなく、今回も「事何様可被行哉」と兼実に諮問している(『玉葉』元暦二年四月四日条)。翌4月4日にも義経の使者「源兵衛尉弘綱」が入京し、「註傷死生虜之交名、奉 仙洞」という(『吾妻鏡』元暦二年四月四日条)。おそらく鎌倉へ下した交名と同じ内容であったと思われるが、前述の『醍醐雑事記』の内容とは若干の相違を見る。
●『註傷死生虜之交名』(『吾妻鏡』元暦二年四月十一日条)
そして4月4日早旦、兼実は「於長門国誅伐平氏等了」を聞き、午後を回って未刻、「為大蔵卿泰経奉行、義経伐平家了由言上」につき、法皇より兼実に「有可被仰合事、可参入之由、被仰下之」という指示が届く。兼実は持病の腰痛の灸治に事寄せて参院を渋り「相労今両三日之間、可参之由」(『玉葉』元暦二年四月四日条)の返答をしている。法皇に対する不信による事実上の参院拒否であった。しかし、事は重大であり、頭弁光雅が院使として九条邸に遣わされ、義経からの報告の詳細が説明された。
翌4月5日、法皇は院北面「大夫尉信盛」を勅使として長門国へ派遣し、その大功を称賛するとともに、「宝物等無為可奉入之由」を義経に命じたのであった(『吾妻鏡』元暦二年四月五日条)。
また、4月11日には鎌倉にも義経の使者が到着している。このとき、鎌倉では故源義朝の遺骨を祀る御願寺南御堂(勝長寿院)の立柱の儀が執り行われており、頼朝もそこに臨んでいた。ここに義経からの「申平氏討滅之由、廷尉進一巻記」が届けられ、「藤判官代」が頼朝の御前で読み上げた(『吾妻鏡』元暦二年四月十一日条)。ただ、頼朝や義経が法皇から厳命されていたであろう神器については「内侍所神璽雖御坐、宝剣紛失」であり、二位尼とともに赤間関沖に入水した宝剣は海中に没し、義経は「愚慮之所覃奉捜求之」という報告に留まった。
その後、頼朝は書簡を手に取ると「向鶴岳方令坐給、不能被発御詞」(『吾妻鏡』元暦二年四月十一日条)であったという。柱立上棟の儀が終了すると、急ぎ御所へ帰営。義経からの使者を召すと、合戦の状況をつぶさに訪ねたという(『吾妻鏡』元暦二年四月十一日条)。そして、頼朝は迅速な戦後処理を行うべく営中にて群議を行い、「参州暫住九州、没官領以下事可令尋沙汰之」と「廷尉相具生虜等可上洛之由」を定め、雑色の時澤・里長らを九州へと派遣した(『吾妻鏡』元暦二年四月十二日条)。
この報告を受けた頼朝は、義経の功を評価して「予州事」とある通り、御分国の一つ伊予国の国司に推挙した。具体的な日にちは分かっていないが、「去四月之比、内々被付泰経朝臣畢」とある通り、四月中であったことは確かである。また、義経からの報告には法皇の内示によるとみられる任官者(頼朝の推挙なき自由任官)の報告があったと考えられ、頼朝は4月15日、「関東御家人、不蒙内挙、無巧兮多以拝任衛府所司等官」につき、「不云先官当職、於任官輩者、永停城外之思、在京可令勤仕陣役」として、東国に戻ろうとする者は本領を没収し、斬罪とする旨を通達したという(『吾妻鏡』元暦二年四月十五日条)。
その後、4月21日に鎌倉に届いた梶原使者から義経の「而彼不義等雖令露顕」したという。その「不義」は「伊予守」補任を白紙とする程のものであったようだが、「今更不能被申止之、偏被任勅定」であるという(後述のように奏上の撤回は可能であったろう)。これが事実であるとすれば義経への伊予守任官の推薦は、義経の使者到着の4月11日から「不義」露顕の21日までの間となろう。なお、4月14日に「大蔵卿泰経朝臣使者参着関東、追討無為、偏依兵法之巧也、 叡感少彙之由可申之趣、所被 院宣也」(『吾妻鏡』元暦二年四月十四日条)とあることから、頼朝が義経の伊予守任官の推薦を託したのはこの使者と考えられ、同時に翌15日に内挙を経ない自由任官の警告を発したと考えられる。
これらは「自由拝任」者への強い警告であるが、自由拝任自体の罪科はもちろんだが、そもそも任官とは「或以上日之労賜御給、或以私物償朝家之御大事、各浴 朝恩事也」である習いの中で、「徒抑留庄園年貢、掠取国衙進官物、不募成功、自由拝任、官途之陵遲已在斯、偏令停止任官者、無成功之便者歟」という、頼朝が寿永二年十月宣旨で下されて以降も法皇から要求されながら、当の「東国之輩」が「徒抑留庄園年貢、掠取国衙進官物」ことを犯し、成功も行わず勝手に拝任し、官途がすでに意味をなくしている状況だが、ここで任官者の官職を停止させれば成功の意味もなくしてしまうと述べる。一向に解決できない庄園国衙領の保障に対する問題と同時に、官途の秩序に対する強い思いが感じられる。
この問題は、具体的には「内藤六が周防のとを以志をさまたけ候、以外事也」(『吾妻鏡』元暦二年正月六日条)というものや、「淡路国広田庄者、先日被寄附広田社之處、梶原平三景時為追討平氏、当時在彼国之間、郎従等乱入彼庄、妨乃貢歟」(『吾妻鏡』元暦元年十月廿七日条)や「武勇之輩耀私威、於諸庄園致濫行歟、依之去年春之比、宜従停止之由、被下綸旨訖、而関東以実平、景時、被差定近国惣追補使之處、於彼両人者雖存廉直、所捕置之眼代等各有猥所行之由、漸懐人之訴」(『吾妻鏡』元暦二年四月廿六日条)という、御家人自身による狼藉、眼代による濫行が訴えられており、こうした濫行狼藉を行った当の御家人が、成功もせず勝手な任官を求める状況に怒った頼朝が、彼らの狼藉を禁じる一方で、武士の統率と国家秩序の維持のための自由拝任の禁止を再度通達したものであろう。
頼朝は以前にも「朝務等」以下四か条の要求を行っているが、その際にも任官は頼朝の推挙によって行うものとしており、平家の脅威が去った今、綱紀粛正が図られたということとみられる。師岡右兵衛尉重経のような相当以前に任官している人々も対象となる「不云先官当職於任官輩者」の東帰禁止という難題も、絶対的権威たる朝廷から軽々しく官職を求めることの戒め、また拝任したのであれば覚悟を以て京洛以外のことは一切捨て、命がけで務めよ(自身がその任に相応しい者か弁えよ)という、あくまでも頼朝の強烈な意志を御家人らに知らしめるためのジェスチャーであり、こき下ろされた任官御家人らの中で実際に罰せられた者はいない(ただし、実際に御家人の列から脱した人などに対しては解官要求をしている)。
なお、義経の左衛門少尉・検非違使補任もこの自由拝任の認識と混同する傾向があるが、義経の任官に頼朝の推挙があったのは確実で、この自由拝任に対する御家人への下文と、後日の義経への譴責にはなんら関係はない。
●件名字載一紙面々被注加(『吾妻鏡』元暦元年四月廿六日条)
| 人名 | 実名 | 続柄 | 任官(初出) | 内容 |
| 兵衛尉義廉 | 不詳 | 不詳 | 不詳 | 鎌倉殿ハ悪主也、木曽ハ吉主也ト申シテ、始父相具親昵等、令参木曽殿ト申テ、鎌倉殿祗候セバ、終ニハ落人ト、被處ナントテ候シハ、何令忘却歟希有悪兵衛尉哉 |
| 兵衛尉忠信 | 佐藤四郎兵衛尉忠信 | 佐藤庄司四男 | 元暦二(1185)年 2月19日 |
秀衡之郎等、令拜任衛府事、自徃昔未有、計涯分、被坐ヨカシ、其氣ニテヤラン、是ハイタチニヲヅル |
| 兵衛尉重経 | 師岡兵衛尉重経 | 河越重頼弟 義経義兄 |
寿永元(1182)年 8月12日 |
御勘当ハ、粗被免ニキ、然者可令帰府本領之處、今ハ本領ニハ、不被付申之 |
| 渋谷馬允 | 渋谷右馬允重助 | 渋谷庄司重国子 | 不詳 | 父在国也、而付平家令経廻之間、木曽以大勢攻入之時付木曽留、又判官殿御入京之時又前参、度々合戦ニ心ハ甲ニテ有ハ、免前々御勘当可被召仕之處、衛府シテ被斬頚ズルハ、イカニ能用意ニ語于加治テ、頚玉ニ厚ク頚ニ可巻金也 |
| 小河馬允 | 不詳 | 不詳 | 不詳 | 少々御勘当免テ、可有御糸惜之由思食之處、色樣不吉、何料任官ヤラン |
| 兵衛尉基清 | 後藤新兵衛尉基清 | 後藤兵衛尉実基養子 ※一条能保家人 |
元暦元(1184)年 6月1日 |
目ハ鼠ノ眼ニテ、只可候之處、任官希有也 ※院厩案主(元暦元年) ・木村真美子氏『中世の院御厩司について:西園寺家所蔵「御厩司次第」を手がかりに』 |
| 馬允有経 | 不詳 | 不詳 | 不詳 | 少々奴、木曽殿有御勘当之處、少々令免給タラバ、只可候ニ五位ノ補馬允、未曾有事也 |
| 刑部丞友景 | 梶原刑部丞朝景 | 梶原平三景時弟 | 元暦2(1185)年 4月15日 |
音樣シワカレテ、後鬢サマテ刑部ガラナシ |
| 同男兵衛尉景貞 | 梶原兵衛尉景貞 | 梶原刑部丞朝景 | 元暦2(1185)年 4月15日 |
合戰之時心甲ニテ有由聞食、仍可有御糸惜之由思食之處、任官希有也 |
| 兵衛尉景高 | 梶原兵衛尉景高 | 梶原平三景時二男 | 元暦2(1185)年 4月15日 |
悪気色シテ、本自白者ト御覧セシニ、任官誠ニ見苦シ |
| 馬允時経 | 中村右馬允時経 | 中村貫主時重子 | 元暦2(1185)年 4月15日 |
大虚言計ヲ能トシテ、エシラヌ官好シテ、揖斐庄云不知アハレ水駅ノ人哉、悪馬細工シテ有カシ |
| 兵衛尉季綱 | 不詳 | 不詳 | 元暦2(1185)年 4月15日 |
御勘当、スコシ免シテ有ヘキ處、無由任官哉 |
| 馬允能忠 | 本間右馬允義忠 | 海老名源八季貞子 | 元暦2(1185)年 4月15日 |
御勘当、スコシ免シテ有ヘキ處、無由任官哉 |
| 豊田兵衛尉 | 豊田兵衛尉義幹 | 石毛三郎政幹子 | 元暦2(1185)年 4月15日 |
色ハ白ラカニシテ、顏ハ不覚気ナルモノ、只可候ニ、任官希有也、父ハ於下総度々有召ニ不参シテ、東国平ラレテ後参ル、不覚歟 |
| 兵衛尉政綱 | 関政綱 | 関太郎五郎政家子 | 元暦2(1185)年 4月15日 |
|
| 兵衛尉忠綱 | 足利忠綱 | 足利俊綱子 | 元暦2(1185)年 4月15日 |
本領少々可返給之處、任官シテ、今ハ不可相叶、嗚呼人哉 |
| 馬允有長 | 不詳 | 不詳 | 元暦2(1185)年 4月15日 |
|
| 右衛門尉季重 | 平山右衛門尉季重 | 元暦2(1185)年 4月15日 |
久日源三郎、顔ハフワヽトシテ、希有之任官哉 | |
| 左衛門尉景季 | 梶原源太左衛門尉景季 | 梶原平三景時長男 | 元暦2(1185)年 4月15日 |
|
| 縫殿助 | 不詳 | 不詳 | 元暦2(1185)年 4月15日 |
|
| 宮内丞舒国 | 不詳 | 不詳 | 元暦2(1185)年 4月15日 |
於大井渡、声樣誠臆病気ニテ、任官見苦事歟 |
| 刑部丞経俊 | 首藤山内刑部丞経俊 | 元暦2(1185)年 4月15日 |
官好無其要用事歟、アワレ無益事哉 | |
| 右衛門尉友家 | 八田右衛門尉知家 | 元暦2(1185)年 4月15日 |
件両人下向鎮西之時、於京令拝任事、如駘馬之道草喰、同以不可下向之状如件 ※治承五年閏二月廿三日以降、右衛門尉任官まで「武者所」。八田四郎武者。 |
|
| 兵衛尉朝政 | 小山兵衛尉朝政 | 元暦2(1185)年 正月26日 |
件両人下向鎮西之時、於京令拝任事、如駘馬之道草喰、同以不可下向之状如件 ※元暦元年九月二日、小山小四郎朝政、下向西海可属参州之由被仰云々、又彼官途事所望申左右兵衛尉也 |
|
| 此外輩 | 其數雖令拝任、文武官之間、何官何職分明不知食及之故、委不被載注文、雖此外、永可令停止城外之思歟矣 |
元暦2(1185)年4月14日、鎌倉に「波多野四郎経家号大友」が帰参し、頼朝は「則召御前、令問西海合戦間之事給」っている(『吾妻鏡』元暦二年四月十四日条)。義経からの壇ノ浦合戦の一報が鎌倉に届いたのが4月11日であることを考えると、経家は壇ノ浦合戦の直後に帰東の途についたと考えられる。頼朝が参戦者から直接報告を受けたのはこれが初めと思われる。
4月19日、「神鏡等已着御渡邊之由」が義経の飛脚から院庁に齎された。これを受けた法皇は、兼実に神鏡等の「御入洛之日、可被択日次」ことを諮問している。また、建礼門院と前内府宗盛の取り扱いについても内々に問い合わせており、建礼門院は「古来、女房之罪科不聞事也」として片山里へ置くことが望ましいと答えている。「前内府事」については義経の問い合わせとして、まず「相具可入京歟、将又可留置河陽之辺歟」という事、さらに「死生之間事、可被仰合頼朝歟、私申遣了、飛脚未到、進退惟谷者、此上如何可計申」と問うた。兼実は宗盛が追討の対象であって梟首相当ではあるが、「為生慮参上、其上可賜死之由難被仰、我朝不行死罪之故也」を主張し、「今度無左右可被處遠流也、而其国可有用意」が妥当とした(『玉葉』元暦二年四月廿一日条)。
4月21日、鎌倉に梶原景時が九州から発遣した使者(梶原の親類)が到着し、合戦次第と「廷尉不義事」を訴えた(『吾妻鏡』元暦二年四月廿一日条)。梶原使者によれば、義経の戦場での様子は「仍討滅平家之後、判官殿形勢殆超過日来之儀、士率之所存、皆如踏薄氷、敢無真実和順之志、就中、景時為御所近士、憖伺知厳命趣之間、毎見彼非據、可違関東御気色歟之由諌申之處、諷詞還為身之仇、動招刑者也、合戦無為之今、祗候無所據、早蒙御免、欲帰参」という(『吾妻鏡』元暦二年四月廿一日条)。そして「廷尉者、挿自専之慮、曾不守御旨、偏任雅意、致自由之張行之間、人々成恨、不限景時」と報告した(『吾妻鏡』元暦二年四月廿一日条)。
4月24日夜、神鏡と神璽が入洛。羅城門から朱雀大路、東大路を経て待賢門より宮中東門に入御する(『吾妻鏡』元暦二年四月廿四日条)。なお「宝剣」は「投海海底訖」(『吉記』元暦二年五月六日条)であった。
4月26日には「前内府并時忠卿以下」が車駕で入洛。土肥二郎実平と伊勢三郎能盛が前内府宗盛の乗る八葉車を前後から守護し、その他武士等が周りを囲繞した(『玉葉』元暦二年四月廿六日条)。土肥実平は頼朝代官、伊勢義盛は義経代官の立場であろう。「盛澄、季貞以下生慮并帰降之輩」は、騎馬でそれに付き従った(『玉葉』元暦二年四月廿六日条)。宗盛、時忠、清宗卿らは義経の六条室町邸に留め置かれ、「来月四日相具義経可赴頼朝之許」という(『玉葉』元暦二年四月廿六日条)。鎌倉下向の日付も5月4日と決定(実際は三日遅れの5月7日)していることから、頼朝雑色の時澤・里長は入京して義経を迎え、生慮の鎌倉移送を指示したものと想定される。
なお、頼朝が範頼に「参州暫住九州、没官領以下事、可令尋沙汰之」の指示を伝え、義経に「廷尉相具生虜等可上洛之由」を伝える使者(頼朝雑色の時澤、里長)が鎌倉を発して九州へ向かったのは4月12日である(『吾妻鏡』元暦二年四月十二日条)。義経はこの指示を待たずに神器や捕虜を擁して上洛の途に就いているが、このとき範頼も上洛せずに九州に駐屯していて、実質的に12日の関東指示と同じ行動がとられていることから、すでに戦後に関する頼朝の指示は両将軍に伝えられていたと考えるのが妥当だろう。
この日、法皇が頭弁光雅を兼実邸に派遣し、頼朝の賞について問い合わせている。その功績が著しいことから「越階之恩」の対象として「正三位」に叙すべきであるが、これは清盛の先例によって不快、「従三位」であった場合は源三位頼政入道の「雖無指功叙之、不可必庶幾歟」であり、「従二位」も理由は不明だが「可有其難哉」という。ところが兼実は「正三位清盛之例、従三位頼政之例、頼朝共以不可嫌申事歟」と、いずれにしても頼朝がこれらを嫌うとは思えないと指摘するが、「雖然若有其疑者、被叙二位有何難哉、勲功之超先代、和漢無比類之故也」と答えている。ただし、内心は「太為過分、只被叙三位、可被相加官也」という気持ちであった。結局27日、頼朝は「被宣下頼朝賞、叙従二位」された(『玉葉』元暦二年四月廿八日)。
4月29日、頼朝は義経付属の田代冠者信綱へ「所詮於向後者、存忠於関東之輩者不可随廷尉之由、内々可相触」を伝えた(『吾妻鏡』元暦二年四月廿九日条)。これは、4月21日に鎌倉に入った梶原景時使者の伝える事に加えて、帰東御家人から得たであろう情報を総合的に判断し、義経は大きな越権行為を行っていたと断定したためであろう。
御家人等の情報をまとめると、義経は「所相従之東士事、雖為小過不及免之、又不申子細於武衛、只任雅意、多加私勘発之由有其聞、縡已為諸人愁」というものや、「今度廷尉遂壇浦合戦之後、九国事悉以奪沙汰之」(『吾妻鏡』元暦二年五月五日条)という「爰参州入九国之間、可管領九州之事、廷尉入四国之間、又可支配其国々事之旨、兼日被定處」(『吾妻鏡』元暦二年五月五日条)に背いた越権行為があった。義経が範頼管轄の九州で沙汰を行ったとみられるのは、後に義経が後白河院より「九国之地頭」に補されていること(『玉葉』文治元年十二月廿七日条)や「豊後武士等」が義経勢に加わっていた事実(『玉葉』文治元年十一月八日条)、のち義経が「鎮西」への下向を企てたことから、事実と考えられる。こうしたことに頼朝は「非御許容之限、還為御忿怒之基」であったという(『吾妻鏡』元暦二年五月七日条)。
5月4日、梶原使者が鎌倉から鎮西へ帰還するにあたり、頼朝は義経を「勘発」したので御家人等は従うべからずとの書状を持たせている(『吾妻鏡』元暦二年五月四日条)。おそらく頼朝は4月21日の梶原景時の報告をもとに調査を加え、4月下旬に義経を「勘発」する使者を京都に発遣したのだろう。5月初頭にこの使者の報告を受けた義経は、すぐさま「不義」を詫び、異心を抱かない旨の「起請文」を持たせた郎従の亀井六郎重清を鎌倉へ下しており、起請文は5月7日に頼朝のもとに届けられた。しかし、頼朝は「科又難被宥、仍廷尉蒙御気色先畢」という様子だったという(『吾妻鏡』元暦二年五月七日条)。
結局、頼朝の怒りは収まることなく、6月13日に義経の「偏為一身大功之由廷尉自称」による罰として「所被分宛于廷尉之平家没官領二十四ケ所、悉以被改之」ている(『吾妻鏡』元暦二年六月十三日条)。義経は「不義」に対して異心を持たないことを誓う「起請文」を行っていることから、義経は「不義」に心当たりがあったことになり、梶原やそのほかの御家人らが伝えたであろう戦陣での行為はおおむね事実であったのだろう。
ただし、義経の戦陣での数々の行為は、決して頼朝に対する異心ではなく、想定以上の強行軍を行うなど独断傾向のあった義経の性質によるものであろうし、頼朝もその部分は理解はしていたであろう。結局、頼朝は義経を「勘発」と鎌倉下向時の面会拒否、没官領没収のみという穏便な措置で済ませている。その後、頼朝は義経の伊予守の推任の停止及び解官を要請することもなく、検非違使・左衛門少尉・院御厩司の留任も認めていることを考えると、頼朝は義経を京都警衛の担当者としてその後も継続させる意図があったことは明確であろう。
5月7日早朝、「前内府申請関東間事」(『吉記』元暦二年五月六日条)を受けて、「左馬頭能保、大夫尉義経等」は「前内大臣父子并郎従十余人」を鎌倉へ下すために離京した(『玉葉』元暦二年五月七日条)。「前内府」は「張藍摺輿」に乗り、「前右衛門督清宗」は騎馬で扈従している(『吉記』元暦二年五月七日条)。また、義経下向の数日後の5月13日には「忠清法師」が「姉小路河原辺被梟首了」という(『吉記』元暦二年五月十四日条)。忠清法師は「伊勢国鈴香山」で捕縛されており(『吉記』元暦二年五月十四日条)、先に討死を遂げていた平信兼と同様、鈴鹿山近辺に本拠を定めていたことがうかがえる。ただし、『吾妻鏡』では5月10日に「志摩国麻生浦」で加藤太光員郎従が「平氏家人上総介忠清法師」を捕縛したという(『吾妻鏡』元暦二年五月十日条)。
そして5月15日夜、義経は相模国酒匂宿に到着した(『吾妻鏡』元暦二年五月十日条)。一条能保も同道したが、旅程は若干能保がゆっくりとなり、鎌倉参着は5月17日となっている。なお、義経は事前に酒匂宿に着す旨を鎌倉に伝えていたため、頼朝からは使者として北条時政が「武者所宗親、工藤小次郎行光等」を相具して前内府宗盛等を迎え取るため参じている。また、小山七郎朝光が義経に対する使者として派遣され、義経に「無左右不可参鎌倉、暫逗留其辺、可随召之由」を伝えたという。前述の「不義」に対する罰の一つである。
| 日程 元暦二年 (1185) |
義経 在所 |
使者等 | 出来事 | 出典 |
| 3月24日 | 長門国 | 「団合戦」により平氏一統は敗北する。 | ||
| 3月30日辺 | ●「源廷尉使」→京都へ ◎「源兵衛尉弘綱」→京都へ ▲「西海飛脚」→鎌倉へ |
義経が京都(「源廷尉使」と「源兵衛尉弘綱」)及び関東への使者(「西海飛脚」)を発する。このほか同じ情報を持った使者は複数いたと思われる。 | 推測 | |
| この頃 | 義経→長門出立 | 範頼は上洛せず九州に駐屯し、義経は上洛するという、4/12の関東指示と同じ行動がとられており、これはすでに指示があったものと推測できる。 | 推定 | |
| 4月3日夜 | 上洛中 | ●「源廷尉使」→京都着 ※合戦から9日 |
夜、「平家悉以討滅之由」を伝える「源廷尉使」が京都に馳せ入った。 | |
| 4月4日 | ◎「源兵衛尉弘綱」→京都着 ※合戦から10日 |
義経の使者、「源兵衛尉弘綱」が入京し、平家の「傷死生虜之交名」を後白河院に奉じる。 | ||
| 4月5日 | ★院使「大夫尉信盛」→長門 | 法皇勅使「大夫尉信盛」が長門へ派遣され、義経の大功を褒めるとともに「宝物等」を無事に入洛させるよう命じる。 | ||
| 4月11日 | ▲「西海飛脚」→鎌倉着 ※合戦から17日 |
「西海飛脚」が鎌倉に到着し、「申平氏討滅之由、廷尉進一巻記」が藤判官代により頼朝面前で読まれた。 ※合戦から17日後であり、4月3日または4日に入京した義経使者と同時に長門を発った使者とみられる |
『吾妻鏡』 元暦2年4月11日条 |
|
| 4月12日 | ■「雑色時澤、里長等」→九州 | 頼朝は、追討使二名について事後処理を命じるため、「雑色時澤、里長等」を「鎮西」に派遣する。 (1)「参州暫住九州、没官領以下事可令尋沙汰之」 →参河守範頼には九州駐屯の上、没官領以下の沙汰 (2)「廷尉相具生虜等可上洛之由」 →義経には捕虜を伴い上洛 |
『吾妻鏡』 元暦2年4月12日条 |
|
| 4月14日 | 大友経家→鎌倉着 | 「波多野四郎経家号大友」が鎌倉に帰参し、頼朝は「則召御前、令問西海合戦間之事給」っている。とくに義経に対する情報はない。 | 『吾妻鏡』 元暦2年4月14日条 |
|
| この辺り | ★院使「大夫尉信盛」 | 「宝物等(所謂神器か)」入洛を義経に伝達。 | 推定 | |
| 4月19日 | 摂津渡邊付近か | 義経使者→京都着 | 義経は「神鏡等已着御渡邊之由」を院庁に伝達。また、生慮らを「相具可入京歟、将又可留置河陽之辺歟」も問い合わせており、後白河院はこれを兼実に諮っている。 | 『玉葉』 元暦2年4月19日条 |
| この辺り | ■「雑色時澤、里長等」→京都着 | 4月12日鎌倉出立し、この辺りで入洛し留まったのだろう。 | 推定 | |
| 4月21日 | 梶原景時の使者→鎌倉着 ※合戦から27日 |
「梶原平三景時飛脚」(景時親類)が鎮西から鎌倉に到着し、頼朝に書状を献上。 ①「合戦次第」、②「廷尉不義事」 |
『吾妻鏡』 元暦2年4月21日条 |
|
| この頃 | 義経詰問の使者→鎌倉発 | 梶原景時の報告を受け、義経に対する詰問の使者を上洛させる。 | 推定 | |
| 4月24日 | 京都 | 義経入洛 | 「賢所神璽令着今津辺御」し、頭中将通資が御迎として参向。夜、入洛して待賢門、東門を経て宮中朝所に渡御。 この間、「大夫判官義経、着鎧供奉、候官東門、看督長着布衣、取松明在前」という。 |
『吾妻鏡』 元暦2年4月24日条 |
| 4月25日 | 神鏡と神璽が入洛。(実際は前日夜中) ※頼朝雑色時澤らが義経に内府宗盛等を伴って鎌倉への下向日を伝えたとみられる。 |
『玉葉』 元暦2年4月25日条 |
||
| 4月26日 | 土肥二郎実平→京都着 伊勢三郎能盛→京都着 ※合戦から32日 |
「前内府并時忠卿以下」が入洛。 土肥実平と伊勢義盛が前後を固めているが、実平は頼朝代官、義盛は追討使義経代官であろう |
『玉葉』 元暦2年4月26日条 |
|
| この頃 | 義経詰問の使者→京都着 | 頼朝からの詰問の使者が入洛し、義経に伝達する。 | 推定 | |
| 4月29日 | 頼朝は義経付属の御家人、田代冠者信綱へ「所詮於向後者、存忠於関東之輩者不可随廷尉之由」を内々に伝える使者を京都に発する。 | 『吾妻鏡』 元暦2年4月29日条 |
||
| この頃 | 亀井重清→京都出立 | 先日の詰問に対する弁明の使者として鎌倉へむけて出立 | 推定 | |
| 5月4日 | 義経が宗盛等を伴って鎌倉下向予定(7日に延引) | 『玉葉』 元暦2年4月26日条 |
||
| 梶原景時使者→鎌倉出立 | 梶原景時の使者の帰国に際し、京都の御家人は義経に従うべからずとの書状を持たせる。 | 『吾妻鏡』 元暦2年5月4日条 |
||
| 5月5日 | 小山朝光→鎌倉着 | 小山七郎朝光が鎌倉に帰参する。 | 『吾妻鏡』 元暦2年5月5日条 |
|
| 5月7日 | 義経、一條保能→京都出立 | 内府宗盛等を伴って鎌倉へ下向 | 『玉葉』 元暦2年5月7日条 |
|
| 亀井重清→鎌倉着 | 「源廷尉使者号亀井六郎自京都参着、不存異心之由、所被獻起請文」を提出するも、頼朝の怒りは解けず。 | 『吾妻鏡』 元暦2年5月7日条 |
||
| 5月15日 | 相模国 酒匂宿 |
義経、酒匂宿に到着 | 北條時政が内府宗盛らの身柄を引き取る。 | 『吾妻鏡』 元暦2年5月10日条 |
5月16日に北条時政らに護衛されて鎌倉に入った前内府宗盛は頼朝邸へ招かれ、西対が居所として提供された(『吾妻鏡』元暦二年五月十六日条)。そして、その後半月にわたって鎌倉に留め置かれたのち、6月7日、西侍で御簾越しに頼朝と対面。頼朝は「於御一族雖不存指宿意、依奉 勅定、発追討使之處、輙奉招引辺土、且雖恐思給、尤欲備弓馬眉目者」と比企四郎能員を介して言葉をかけたという(『吾妻鏡』元暦二年六月七日条)。翌6月9日、鎌倉を出立し上洛の途に就いた宗盛等は、酒匂宿に駐屯する義経に迎え取られた。宗盛には「橘馬允、浅羽庄司、宇佐美平次已下壮士等」が副えられていた(『吾妻鏡』元暦二年六月九日条)。また、伊豆国狩野に軟禁されていた三位中将重衡もともに上洛の途に就いた。
なお、このとき義経は「令参向関東者、征平氏間事具預芳問、又被賞大功、可達本望歟之由、思儲之處、忽以相違、剩不遂拝謁而空帰洛、其恨已深於古恨」(『吾妻鏡』元暦二年六月九日条)であったという。しかし、義経は出京前に起請文を提出しており、頼朝の怒りを知っていることは明白であることから、当然「具預芳問、又被賞大功」があろうわけがないことはわかっていたはずである。この一連の記述は状況に合わず、後世の挿入話と考えられるが、義経には少なからず「剩不遂拝謁而空帰洛、其恨已深於古恨」という気持ちはあったであろう。頼朝が猶子義経と、妹婿藤原能保をともに下向させているのは、義経に対する頼朝の労いの意味が込められており、本来であれば義経に対する「征平氏間事具預芳問、又被賞大功」のためであることは明白であろう。ところが、この義経下向を命じる使者が京都へ届くとほぼ同時期に梶原報告があったのである。実際に頼朝が御家人に義経への不従を内々に決定したのは4月29日であり、5月4日出立予定(7日に延引)の義経・能保の諸所の計画を変える事が使者の到着時期を考えても困難だったために、計画通り決行されたと思われる。
5月20日、京都では九名の僧俗の流刑が執行されている(『玉葉』元暦二年五月廿一日条)。
| 平時忠卿 | 能登国 | 時忠卿依神鏡事、可被宥否事(『吉記』元暦二年五月六日条) |
| 平信基 | 備後国 | 時忠の一族。前内蔵頭。 |
| 平時実 | 周防国 | 前大納言平時忠の嫡子。 |
| 藤原尹明 | 出雲国 | |
| 前大僧都良弘 | 阿波国 | |
| 前僧都全真 | 安芸国 | |
| 前律師忠快 | 伊豆国 | 門脇中納言教盛の子で、天台座主慈円の門人。 |
| 法眼能円 | 備中国 | 法性寺執行。二位尼の義弟にあたる。 娘の在子が後鳥羽院の後宮に入り、為仁親王を生む。のちの土御門天皇である。 |
| 熊野別当行命 | 不明 |
酒匂宿からの上洛に際し、義経は頼朝から「前内府并其息清宗、三位中将重衡等、義経相具所参洛也、而乍生入洛無骨、於近江辺可梟首其首、可渡使庁哉、将可棄置哉、可随院宣之由」の「頼朝卿令申旨」を言い含められており、義経は上洛時に院庁に問い合わせ、判断に迷った法皇は高階泰経を通じて兼実に諮問している(『玉葉』元暦二年五月廿二日条)。これに対して兼実は「此事左右只可在勅定者」と突き放している。結局、宗盛父子は梟首の上で検非違使へ首渡、重衡は「遣南都」という院宣が出されたようであるが、窮余にあった法皇は「此事難計申之由令申、太以無本意、自今以後如此事、不可被仰合歟」と兼実の対応に不満を述べている(『玉葉』元暦二年五月廿三日条)。この院宣を受けた義経は、近江国で宗盛・清宗を斬首した。『吾妻鏡』によれば場所は近江国篠原宿、『愚管抄』では「セタノ辺」であった。義経は「橘馬允公長」に命じて宗盛を斬り、清宗は「堀弥太郎景光」が梟した(『吾妻鏡』元暦二年六月廿一日条)。橘右馬允公長は宗盛実弟・知盛の旧家人であり、宗盛からの要請または義経の温情があったのかもしれない。「前内大臣宗盛首」「前右衛門督清宗首」(『吉記』元暦二年六月廿二日条)は22日晩に六条川原で検非違使庁へと渡され、法皇がこれを御見物になったという(『玉葉』元暦二年五月廿三日条)。
一方、「遣南都」という指示のあった重衡は、6月21日入洛し(『吾妻鏡』元暦二年六月廿一日条)、翌22日に「蔵人大夫頼兼、右衛門尉有綱等」(『吉記』元暦二年六月廿二日条)によって南都まで護送されることとなる。彼らは源三位頼政入道の養子と孫であり、かつて以仁王の乱で南都へ逃れようとして討たれた源三位入道に肖って選ばれたのかもしれない。南都はかつて重衡が主将として攻め入った際に、兵火によって諸堂を焼失させ、東大寺の大仏の首が溶け落ちる事件が発生し、南都の僧たちの恨みを一身に買っていたためであった。その過程は『愚管抄』に述べられているが、
と、大津から醍醐を経て日野方面へと進んだとみられる。このとき重衡は、壇ノ浦の戦いで入水したものの救出され、醍醐と日野の間に隠棲していた妻女・大納言典侍(藤原輔子)との別れを許され、そこで泣く泣く輔子は重衡の小袖を替えたという(『愚管抄』)。また、『醍醐寺雑事記』によれば、
とあり、大納言典侍は行迎寺(醍醐寺の塔頭か)の故寺主の住房を借りて住んでおり、重衡が立ち寄ったことが記される(『醍醐寺雑事記』十)。
その後、重衡は木津川を奈良側へ渡ったほとり、「泉木津辺」で処断され、首は「奈良坂」に懸けられた(『玉葉』元暦二年五月廿三日条)。重衡を斬ったのは故頼政入道孫の伊豆右衛門尉有綱であった(『醍醐寺雑事記』十)。重衡はかつて以仁王追捕に際して、実戦に加わってはいないものの右少将維盛とともに主将を務めており、切手に選ばれたのもこうした経緯があったのかもしれない。
6月30日には除目が行われ、頼盛入道には「院分国」の「備前播磨」が与えられるが、義経には何ら行賞が行われず、兼実は「九郎無賞如何、定有深由緒歟、凡夫不覚得之」と疑義を呈している(『玉葉』元暦二年六月丗日条)。頼朝は6月13日、「所被分宛于廷尉之平家没官領二十四箇所、悉以被改之、因幡前司広元、筑後権守俊兼等奉行之」と、中原広元と藤原俊兼の両名を奉行として義経に宛がった平家没官領二十四か所を没収する沙汰を行っている。これは頼朝が、「偏為一身大功之由廷尉自称、剰今度及帰洛之期、於関東成怨之輩者可属義経之旨吐詞」という義経の発言を聞き、「縦雖令違背予、爭不憚後聞乎、所存之企太奇怪」と激怒したためであるという(『吾妻鏡』元暦二年六月十三日条)。6月30日に義経への行賞が行われなかったのは、こうした経緯があったためか。
このような中、8月4日、頼朝は「前備前守行家」が「当時半面西国、以関東之親昵、於在々所々、譴責人民、加之挿謀反之志、縡既発覚」により、近江在住の佐々木太郎定綱に「相具近国御家人等」追討を命じる書状を送ったという(『吾妻鏡』文治元年八月四日条)。行家が頼朝に反旗を翻した理由は「其故者、可誅其身之趣、鎌倉二位卿所命、達行家後聞之間、以何過怠可誅無罪叔父哉之由、依含欝陶也」のためであった(『吾妻鏡』文治元年十月十三日条)。当時の行家は近江国にあったか。ただし、京都周辺での兵乱は記されておらず、具体的に佐々木定綱が動いたかどうかは不明。ただし、定綱は9月10日当時には「左衛門尉」に任官しており(『吾妻鏡』文治元年九月十日条)、行家追捕の公的担保として左衛門尉に推任されていたのかもしれない。
| 名前 | 受領 | 備考 |
| 源義範 | 伊豆守 | 山名義範 |
| 源惟義 | 相模守 | 大内惟義 |
| 源義兼 | 上総介 | 足利義兼 |
| 源遠光 | 信濃守 | 加賀美遠光 |
| 源義資 | 越後守 | 保田義資 |
| 源義経 | 伊予守 | 源義経 |
そして、8月16日には「依頼朝申」の除目が行われ「受領六ケ国、皆源氏」であった。「是当時関東御分国」であるが、この中でもとくに目を引いたのは「義経任伊予守、兼帯大夫尉」で、兼実は受領と検非違使の兼帯が前代未聞のことであり「未曾有」と驚愕している(『玉葉』文治元年八月十六日条)。この除目の内容については頼朝は「至今度予州事者、去四月之比、内々被付泰経朝臣畢、而彼不義等雖令露顕、今更不能被申止之、偏被任 勅定」であったという(『吾妻鏡』文治元年八月廿九日条)。なお、伊予守は播磨守と並ぶ「四位上臈任之」という最上格の受領であるが、当時においては、平行盛(従五位上当時の任)の播磨守、木曽義仲(従五位下当時の任)の伊予守というように、すでに「四位上臈任之」という先例は廃れていたことは明白である。頼朝が関東御分国の中でもとくに「伊予守」を推挙したのは、義経が四国平定の大功者であったのと同時に、他の受領源氏の人々とは異なり、伊予守頼義直系たる栄誉を授けた可能性があろう。
しかし、法皇を畏敬しつつも自らが必要と思う事については、たとえ叡慮に背く事でも要求し、兼実をして「頼朝乖法皇叡慮之事太多」(『玉葉』文治元年十月十三日条)と言わしめる頼朝が、義経任官を「今更不能被申止之」(『吾妻鏡』文治元年八月廿九日条)ことなど考えられない。義経が伊予国の国務を遂行しようとしている(『玉葉』文治元年十月十七日条)ことから、これは『吾妻鏡』の創作または頼朝の言い訳であろう。また、前述のように頼朝は義経を伊予守に推しながら検非違使も留任させており、義経後の京都守護が急場凌ぎの場当たり的な人事であったことからも、義経の京都守護を続投させることを強く示唆したと考えるのが自然であろう。
| 当時の受領源氏 | 受領 | 備考 | |
| 源広綱 | 駿河守 | 源広綱 | 【摂津源氏】源頼政の末子 |
| 源範頼 | 参河守 | 源範頼 | 【河内源氏】源義朝の子 |
| 源義定 | 遠江守 | 保田義定 | 【甲斐源氏】逸見義清の子 |
| 源義信 | 武蔵守 | 平賀義信 | 【甲斐源氏】平賀盛義の子 |
| 源義範 | 伊豆守 | 山名義範 | 【上野源氏】新田義重の子 |
| 源惟義 | 相模守 | 大内惟義 | 【甲斐源氏】平賀義信の子 |
| 源義兼 | 上総介 | 足利義兼 | 【下野源氏】足利義康の子 |
| 源遠光 | 信濃守 | 加賀美遠光 | 【甲斐源氏】逸見義清の子 |
| 源義資 | 越後守 | 保田義資 | 【甲斐源氏】保田義定の子 |
| 源義経 | 伊予守 | 源義経 | 【河内源氏】源義朝の子 |
この除目はあくまでも「依頼朝申」で行われたものであり、兼実も義経の検非違使兼帯に法皇の介入を記しておらず、法皇の叡慮が働いたものではないだろう。義経の「伊予守」補任は功績に対する行賞であり、他の受領源氏の末席に連なったこととなる。また元暦元年以来の「院御厩司」(木村真美子氏『中世の院御厩司について:西園寺家所蔵「御厩司次第」を手がかりに』)も留任していると思われ、院厩の支配も依然として義経が支配していた。
ただ、頼朝は「於関東成怨之輩者、可属義経之旨吐詞」という義経を警戒する意識が生じていたことは間違いなく、9月2日、頼朝の使者として「梶原源太左衛門尉景季、義勝房成尋等」が鎌倉を発ち、12日に入洛している。これは表向きは「南御堂供養導師御布施并堂荘厳具大略已調置京都為奉行」であるが、その実は「平家縁座之輩未赴配所事」の沙汰を早く行うことと、義経の様子を窺うための使者であった。『玉葉』によれば、前述のように、5月20日に「僧俗并九人」の流罪が執行された(『玉葉』文治元年五月廿一日条)ことが記されているが、時忠、時実父子の配流は停止されていた。頼朝は「予州、為件亜相聟、依思其好抑留之」と、時忠配流の抑留は義経が時忠の女婿となったためと疑っている。
この頼朝の意向を受けたことにより、義経は9月23日に「前大納言時忠卿、下向配所能登国」を執行する(『玉葉』文治元年九月廿三日条)。頼朝代官とはいえ、公的には一検非違使に過ぎない義経には配流可否の権限はないと考えられ、その意思決定は法皇にあったであろう。ただし、義経は法皇と繋がりが深く、時忠が義経の縁者となったことから配流が延引された可能性は高い。そのほか、時忠は平家とともに西海へ逃れたとはいえ賢所を守り切った功績を認められており、法皇はこの点を考慮したのかもしれない。
頼朝は景季等に「御使」として義経邸を訪問し、「尋窺備前々司行家之在所、可誅戮其身之由相触」た上で、義経の様子を窺うよう命じている。「引級備前々司行家、擬背関東之由、風聞之間如斯」とあるように、行家が頼朝に反旗を翻していることはすでに7月には露顕しており、8月4日には佐々木定綱にその追捕を指示している。六年後の建久2(1191)年当時の佐々木定綱は「近江国総追捕使」(『玉葉』建久二年四月二日条)であり、おそらくこの頃も国内の謀叛人追捕を行い得る近江国惣追捕使だったのだろう。ただ、行家追捕は実際には行われなかったようで、洛中守護の義経に在所の探索及び誅殺を命じており、義経への踏み絵的な指示であったのだろう。
景季等は上洛し六条油小路の旅宿に入ったのち、頼朝の使者として上洛した旨を伝えるため、六条堀川の「参向伊予守」した(『吾妻鏡』文治元年十月六日条)。しかsこの日義経は「称違例無対面」であり、景季等は「仍此密事以使不能伝、帰旅宿六條油小路」であったという。この様子では翌日も対面は叶わないと感じたのだろう。翌々日に景季等は六条堀川邸を再度訪問した。このときの義経は、脇足に体を預け憔悴しきり灸治の跡も見られたという。景季等は「而試逹行家追討事」たところ、義経は「所労更不偽、義経之所思者、縦雖為如強竊之犯人、直欲糺行之、况於行家事哉、彼非他家、同為六孫王之余苗掌弓馬、難准直也人、遣家人等之許、輙難降伏之、然者早加療治、平愈之後可廻計之趣、可披露之由(病はまったく偽りではない。義経は、たとえ強竊犯であろうと直に理非を裁断しようと思っている。ましてや行家は他人ではなく同じく六孫王の末孫だ。他人と同様に裁断し難く、家人らを遣わして降伏させることもまた難しい。私自身が早く病を治し、平癒後に何らかの沙汰を行うことを二品にお伝えしてほしい)」を述べたという。おそらく義経はこの頃には「行家已反頼朝了」に対して幾度となく「加制止」えていたと思われるが、「可誅其身之趣、鎌倉二位卿所命」を耳にした行家が「以何過怠、可誅無罪叔父哉」と激怒しており(『吾妻鏡』元暦二年十月十三日条)、受け入れられなかったとみられる。こうした中で義経は頼朝からも行家誅戮の命を受け、板挟みになっていたとみられる。景季が感じた義経の「其躰誠以憔悴」の様子は、行家の説得に難航していた姿だろう。
文治元(1185)年9月26日、九州で治安維持と「種直、隆直、種遠、秀遠(原田種直、山鹿秀遠、菊池隆直、板井種遠)」の平家没官領の処理に当たっていた「蒲冠者範頼」が入洛している(『玉葉』元暦二年九月廿六日条)。もともと範頼は、頼朝から「八月中可参洛之由」を命じられていたが、「依風波之難遅留」し「今月相搆可入洛」と鎌倉へ使者を送っている(『吾妻鏡』文治元年九月廿一日条)。範頼はその後鎌倉へ帰還するが、その郎従たちは京都に残されている。これは行家への対応であろう。範頼下向の具体的な日は不明だが、勝長寿院供養の導師である七十六歳の公顕僧正を伴う下向であり、二十日程度と考えられる。彼らの鎌倉下着は10月22日であることから、出京は10月初旬であろう。
範頼よりも数日はやい9月末に京都を発したとみられる梶原源太左衛門尉景季は、10月6日に鎌倉に帰着し、御所に参じて頼朝に京都での情勢を伝えている(『吾妻鏡』文治元年十月六日条)。義経と初日には会えず翌々日に会えたこと、病のため憔悴していること、灸治をしていたこと、病が癒えた後に行家に沙汰することなどを伝えるよう要請された旨が伝えられた。これに頼朝は「同意行家之間、搆虚病之條已以露顕」と言ったといい、傍らの梶原平三景時は「初日参之時、不遂面拝隔一両日之後有見参、以之案事情、一日不食一夜不眠者、其身必悴、灸者又雖何ケ所一瞬之程可加之、况於歴日数乎、然者一両日中被相搆如然之事歟、有同心用意分不可及御疑貽」と加えたという。兼実が「若依傍輩之讒口、暗加私刑者、尤不便事歟」(『玉葉』文治元年十月十四日条)と、頼朝が側近の讒言を信じて大功ある義経に密かに私刑を加えていることを批判していることからも、景時らによる讒言があったことは事実であったのだろう。
景季や範頼が離京した数日後の10月11日、義経は「行家已反頼朝了、雖加制止不可叶、為之如何者」と院奏している(『玉葉』文治元年十月十七日条)。景季から伝えられた頼朝の命もあって、行家の叛心を必死に制止するが、行家の怒りを抑えることはできず、如何ともしがたく法皇に縋る様子がうかがえる。
義経の院奏に対して法皇は「相構可加制止者」と、行家の暴走を何とか食い止めるよう命じている(『玉葉』文治元年十月十七日条)。これを受けて、義経はふたたび行家を説得したが、行家の憤怒は止まるところを知らず「行家謀叛雖加制止、敢不承引」であり、義経の説得は失敗に終わる(『玉葉』文治元年十月十七日条)。ところが、その後「仍義経同意了」とあるように義経は行家に同調した(『玉葉』文治元年十月十七日条)。『吾妻鏡』では「而義経亦退平氏凶悪、令属世於静謐、是盍大功乎、然而二品曾不存其酬、適所計宛之所領等悉以改変、剩可誅滅之由有結搆之聞、為遁其難已同意行家」と非難する(『吾妻鏡』文治元年十月十三日条)。
義経と行家が同調したとの情報を得た兼実家司源季長は、13日早朝に九条邸を訪れ「義経行家同心反鎌倉、日来有内議、昨今已露顕」(『玉葉』文治元年十月十三日条)を伝えている。これは「義経之辺、郎従之説」であり、巷説だが浮言ではないという。行家と義経の同心疑惑は「昨今已露顕」(『玉葉』文治元年十月十三日条)とあるように、以前から噂になっていたことがわかる。両者は「日来有内議」という噂が立つほど密に連絡を取り合っていた可能性は高い。この深い接触は行家説得のためであったのかもしれないが、義経は後述の三か条の通り「頼朝失義経之勲功、還有遏絶之気、義経中心結怨」(『玉葉』文治元年十月十三日条)という感情があったのは確かで、さらに「鎌倉之辺、郎従親族等、為頼朝失生涯、結宿意之輩、漸以数積、彼等内々令通義経行家等之許」というように、頼朝によって郎従や親族を粛清された宿意を持つ御家人らも義経・行家のもとに参じ(『玉葉』文治元年十月十三日条)、さらに「頼朝乖法皇叡慮之事太多」(『玉葉』文治元年十月十三日条)という状況にあった。義経は世の形勢を考えた末、法皇に「竊奏」した。そして、この義経の密奏に法皇は「頗有許容」であったという。季長はこれにより「仍忽及此大事」と言い、「或云、秀衡又与力」とも伝えている。ただし、これらはいずれも季長が風聞を伝え聞きで報告しているため、兼実は「於子細者雖実説不定」としつつも、「於蜂起者已露顕也」と記した(『玉葉』文治元年十月十三日条)。なお、義経行家同心が院奏されたのは、「十三日、又申云、行家謀叛雖加制止、敢不承引、仍義経同意了」(『玉葉』文治元年十月十七日条)ということから、10月13日のこととされるが、家司源季長が兼実邸を訪れて同心の一報を伝えたのは13日早旦であり、義経の「竊奏」は12日のことであることがわかる。
義経が「義経行家同心反鎌倉」した理由は、次の(一)(二)(三)の三点であった。
(一)義経は「奉身命於君」て頼朝の代官として大功を挙げ「殊可賞玩之由令存」た結果、「適所浴恩之伊予国」したが、伊予国は地頭によって国務不履行な状況であったとの主張である。山名義範や平賀惟義ら義経以外の国司補任者五名は、「其外五ケ国事者、任人面々直懇望申之間、且募勲功之賞、且為添二品眉目、殊所及厳密御沙汰也云々、各可令知行国務之由」(『吾妻鏡』文治元年八月廿九日条)とあるように、国務を知行すべきことが命じられているが、義経は最初から国務知行を認められていなかったと考えられよう。国務は義経目代ではなく、知行国主たる頼朝の代官によって公庄の地頭の支配がなされていた可能性が高いだろう。
(二)「没官所々廿余ヶ所、先日頼朝分賜、而今度勲功之後、皆悉取返、宛給郎従等了、於今者、生涯全以不可執思」については、『吾妻鏡』においても6月13日、「平家没官領二十四箇所、悉以被改之」られて、因幡前司中原広元らが奉行となって収公されたとある(『吾妻鏡』元暦二年六月十三日条)。なお「二十四箇所」は「廿余ヶ所」の誤記と考えれば、これも『吾妻鏡』編纂時に『玉葉』を底本として採られた資料と考えられよう。これは、義経が宗盛等を連れて帰京した際に「於関東成怨之輩者可属義経之旨吐詞」たことを頼朝が咎めた結果とすることから、遠因は壇ノ浦合戦時やそれ以降に義経が行った「不義」にあるものであろう。前述の通り義経は戦陣における「不義」を認めており、当然の措置であったと思われる。なお、常胤は平家没官領の地頭職を賜るが、薩摩国においては、島津庄寄郡内祁答院・甑島没官領地頭、高城郡没官領地頭、入来院内没官領地頭、東郷別府没官領地頭などが与えられている。
ただ、上記二点以上に、義経反旗の直接的かつ決定的な原因は、最後に記された、(三)義経を誅殺する刺客が派遣された確報であろう。
頼朝は9月12日に入洛した梶原景季、義勝房成尋を通じて「尋窺備前々司行家之在所、可誅戮其身之由相触」(『吾妻鏡』文治元年九月十二日条)を義経に伝えているが、義経は前述の通り「縦雖為如強竊之犯人、直欲糺行之、况於行家事哉、彼非他家、同為六孫王之余苗掌弓馬、難准直也人、遣家人等之許、輙難降伏之、然者早加療治、平愈之後可廻計」(『玉葉』文治元年十月十四日条)と返答し、これが10月6日に頼朝に復命され(『吾妻鏡』文治元年十月六日条)、捨て置けぬ案件として「可誅伊予守義経之事、日来被凝群議」した。そして10月9日、義経を討つことを自ら申し出た土佐房昌俊を京都に発した(『吾妻鏡』文治元年十月九日条)。
昌俊は「三上弥六家季昌俊弟、錦織三郎、門真太郎、藍澤二郎」ら八十三騎で出立。京都まで九日の行程で進むことが指示されたという(『吾妻鏡』文治元年十月九日条)。昌俊は老母の事を頼朝に託していることから、すでに死を覚悟した決意であったことがうかがえる。なぜなら、10月12日時点で義経が「遣郎等、可誅義経之由、慥得其告」(『玉葉』文治元年十月十三日条)とある通り、義経に通告されていたものであったためである。つまり、この義経追捕は決して奇襲ではなく、逆に義経への「行家之在所、可誅戮其身」を決意させるための最後通告であったと考えられるのである。頼朝はぎりぎりまで義経を討つことをためらっていた様子がうかがえる。ところが、義経はこれを明確な敵意と取った。11日までは行家の説得に努めていた義経が、翌12日には行家と同心した上「雖欲遁不可叶、仍向墨俣辺射一箭、一決死生之由所存也」と敵対を鮮明にした核心的理由は、11日または12日に受け取った軍勢派遣の確報だったのである。
しかし、12日における義経と行家の同心及び頼朝への敵対は、あくまで私的な対立であり、義経は「行家謀叛雖加制止、敢不承引、仍義経同意了、其故者、奉身命於君、成大功及再三、皆是頼朝代官也、殊可賞玩之由令存之處、適所浴恩之伊予国、皆補地頭不能国務、又没官所々廿余ヶ所、先日頼朝分賜、而今度勲功之後、皆悉取返、宛給郎従等了、於今者、生涯全以不可執思、何況遣郎等、可誅義経之由、慥得其告、雖欲遁不可叶、仍向墨俣辺射一箭、一決死生之由所存也(行家の謀叛を留めようとしましたが、まったく承引がなかったため、(頼朝に意趣を含む)義経も同意いたしました。その意趣とは、身命を法皇に捧げ大功を再三立てましたが、これはみな身が頼朝代官として果たしたものです。これにより頼朝がとりわけ賞玩の由聞き及び、伊予国の国司に適されました。ところが伊予国にはみな地頭が補され国務を行うことができなかった上、平家没官領として頼朝より賜った二十余箇所は、今回の勲功ののち没収されて、頼朝麾下の郎従に充行われました。もはや生涯に全く執心はなくなりました。さらに頼朝は義経を討つための郎従等を遣わしたという確かな報告を受けました。もはや逃げることもかないますまい。よって墨俣辺に馳せ向かいせめて一矢を報い、死生を決せんという所存です。)」(『玉葉』文治元年十月十七日条)と法皇に「竊奏」したに過ぎず、私戦として義経と行家が墨俣へ下向して鎌倉勢と決戦することを奏上していただけだったのである。この義経の「竊奏」を法皇は「頗有許容」とした(『玉葉』文治元年十月十三日条)。「頼朝乖法皇叡慮之事太多」(『玉葉』文治元年十月十三日条)ということも「頗有許容」の理由のひとつであろう。
12日夜、兼実邸に法性寺座主慈円法印(兼実実弟)門弟の「慶俊律師」が訪れ、慈円が法性寺座主の辞退を院奏したものの許されなかった旨の報告をしているが、彼は「行家子」であった。彼は「今旦向江州了」と13日早朝に近江国へ出立しているが、法皇謁見時に「其勢非幾」であったため甲冑が下賜されたという。この慶俊律師の近江行きは、義経・行家の墨俣下向計画の一部であった可能性が高いだろう。兼実はこのことを「凡事之次第如夢如幻」と惘然としていることから、法皇の行動に驚きを隠せなかったと思われる。この慶俊律師が法皇から甲冑を賜ったことは、兼実が直接聞いているので事実である。しかし、17日の時点では法皇は義経から墨俣で決戦する旨を聞いた際に「殊驚思食、猶可制止行家者」であったといい、とても「頗有許容」とは言い難いのである。義経らの計画の重大さに気づいた法皇が考えを変えた可能性も考えられる。
そして、義経の「竊奏」後、しばらくは「其後無音」という状況だったが、17日早朝、院使として大蔵卿泰経が九条邸を訪れた。兼実は触穢のため家司季長が門前で院宣を受けたが、それによれば義経は「去夜重申云、猶同意行家了、子細先途言上、於今者、可追討頼朝之由、欲賜宣旨、若無勅許者、給身暇可向鎮西云々、見其気色、主上法皇已下、臣下上官、皆悉相率可下向之趣也」とあるように、義経は16日夜に激怒して院奏し、「子細先途言上(前述の三か条)」によって頼朝追討の宣旨を下されるよう奏上。これが認められなければ「給身暇可向鎮西」と告げている。なお、この「給身暇」は京都から九州へ立ち退くことであり、『吾妻鏡』では「勅許者両人共欲自殺」(『吾妻鏡』文治元年十月十三日条)と誤訳されている。義経との抗争について『玉葉』からの引用と思われる部分が多く見られるが、この誤訳からも『玉葉』の記述が多く引用され、『吾妻鏡』史観で記述し直されていることがわかる。
法皇の諮問を受けた兼実は、頼朝の「追討宣旨」について、
「罪犯八虐、為敵於国家之者、蒙此宣旨者也」とした上で、「頼朝若有重科者、可被下宣旨、何及異議、若又無指罪科者、可被追討之由、更以難量申、但平家及義仲之時、雖不起自叡念、暗被下此宣旨了、天下乱逆、即在如此之漸、然而為避当時之難、可被追彼等例哉否之条、宜在聖断、敢非臣下之最歟者(頼朝に重科があるならば追討宣下すればよい。もし然したる罪もなければ追討するのは量り難い。ただし、平家や義仲のときは、たとえ法皇の考えから出たものではないにしろ、暗に頼朝追討の宣旨を下している。天下乱逆はつまりこのことにあるのだ。ただ今目の前の難を避けるためにその「天下乱逆」の例を行うのか否かは、ただただ法皇の聖断にあって、臣下が決定すべきことではない)」
とそっけない返事をしている。人々はこの頼朝追討の宣旨について「皆可然ト申ケル」と賛同する中で、ひとり「九條兼実右府一人」のみが「追討宣旨ナド申事ハ依其罪科候事也、頼朝罪過ナニ事ニテ候歟、イマダ其罪ヲシラズ候ヘバ、トカクハカライ申ガタキ由」を主張したという(『愚管抄』)。
これに対して院使泰経は、
「頼朝過怠全不候、追討之条又不思食寄(法皇は頼朝には全く科はなく、当然ながら追討の事もまったくお考えにない)」
ことを伝えた上で、
「然而義経等結構之趣、可謂勿論、仍只可給件宣旨之由、内々有天気、為御存知、竊所申也、而如今令申御者、已追討猶予之趣也、外聞之処、似引級頼朝且者、去年聊有申旨、為報彼芳言、抑留此追討歟之由、若君有御疑殆者、尤無由事也、随又彼両度不意之宣旨、頼朝更不為怨、今度又可同歟、仍宣下之条、旁何難之有哉、猶分明可令申切給歟(義経らが兵を集めていることは疑いない。よって院は宣旨を下す意向を内々にお持ちだ。それをお知らせするべく密かに申し入れているが、今お聞きしたことは法皇の御意向とは反対の、頼朝追討を猶予すべきとのお考えであり、この返事を法皇が聞かれ、あなたを摂政に推す頼朝に報いるために追討を遅らせようとしているのだと御疑いを持たれたら、それこそ詮無きことである。頼朝は過去にも追討宣旨を受けたがいずれも怨みを持っていないという。今回もきっと同じで、追討宣下には何の問題もないだろう。もっと明確に言い切るべきだ)」
と重ねて迫ったのである。
この言い様に、兼実は怒りを含んで、
「朝家大事、可依私阿容之由、於御疑殆者、更不及申左右、凡者被尋問事、愚慮之所及全不憚時議、是存忠之故也、而無罪之者、可被追討之由、争令言上哉、為遁当時之害、可被宣下哉否之条者、只可在勅定事也、若於有一決者、更非申止之議、抑、以前両度宣旨、頼朝不結怨、今度可同之条、頗不可似彼例歟(朝廷国家の大事についての発言を、兼実自身の利益のためのものと疑われては、もはや何も申し上げられない。無罪の者を追討せよということをどうして言上できようか。今一時の害から逃れるために追討の宣旨を下すというのであれば、もはや何をかいわんや、勅定のままにする他ないではないか。すでに一決しているのであればこれを申し止める儀にもあらず。平家や義仲が頼朝に下した追討宣旨では頼朝は怨みを抱かなかったというが、今度のことは両度宣旨とはまったく異なるものであろう)」
と断じた上で、
「凡此時愚意之所及、先被誘仰義経等、可被問子細於頼朝也、義経已有度々之勲功、且依為汝代官偏憑思食之処、聞可有濫刑之由、恐申旨如此之条、罪科何事哉、若依傍輩之讒口、暗加私刑者、尤不便事歟、又其罪無疑、必可行科断者、召下其身可致其沙汰也、乍置京都差上武士可誅之由風聞、狼藉之条已似忘朝章、若又義経等聞謬説令驚申歟、早聞食子細、可有成敗之由、可被仰遣也、而猶乖勅命企濫吹之時、処違勅可被下追討宣旨歟、不定罪科宣下之条、若奈後悔何(まず法皇は義経らを諭されつつ、頼朝には『義経は数々の勲功を挙げた上、汝の代官であるから義経を偏に頼みにしてきたのに、義経は汝から濫りに刑に処されんことを聞いて恐れているのだ。そもそも義経に何の罪科があるのか。もし汝が義経の傍輩の讒口を信じて密かに私刑を加えんとしているのであれば以ての外だ。義経の罪科が疑いなく刑を加えるのであれば、義経の身を鎌倉へ召し下したうえで沙汰せよ。武士を上洛させて義経誅殺を謀る風聞があるが、まったく朝廷を蔑ろにする狼藉に他ならない。汝は義経の謬説を聞いて誤解をしているのではないか』と頼朝に子細を問わしめ、処置を行う由を仰せ遣わすべきである。それでもなお勅命に背き、義経を討とうと企てるのであれば、そのとき違勅の罪で追討宣旨を下すべきである。罪科が定まらない中で頼朝の追討宣旨を下されれば、後悔しても仕方のないことになろう。)」
と述べた。
このとき、兼実が法皇の言葉として頼朝に伝えるべきだとした言葉は、この当時の兼実の本心を代弁したものと考えられ、明らかに頼朝を非難し、義経を擁護する心情にあったことがわかる。もし確たる罪があれば鎌倉に召し下すべき、という仮定は、そんなことはないだろうが、という否定的な意味合いを含んでいるのだろう。頼朝の措置によって心中不満を抱えていた義経が行家と同調し「竊奏」して安穏の世を乱す結果となったことを、兼実は激怒しており、この比の頼朝に対する心情は「平氏誅罰之後、頼朝在世之間、忽可及大乱之由、万人不存事歟、苛酷之法殆過秦皇帝歟、仍親疎含怨之所致也」(『玉葉』文治元年十月十四日条)というもので、義経・行家の頼朝に対する反抗は、「世人之謂以、今度天下之結願歟」(『玉葉』文治元年十月十四日条)であったという。
しかし、兼実は重ねて、
「但此議於今者難叶歟、去十一日、始達天聴之剋、被仰義経、暫抑狼藉、可被達子細於関東カリケル事歟、濫行風聞之後者、縦被仰遣、定無承引歟、誠是難治次第也、今私被示之旨、偏引級頼朝抑留追討之由也、此条返々有恐、於不思得事者、小事猶難申切、況大事哉、是全非申止、只申理之所当許也者(しかし、もはや遅いのかもしれない。これは去る11日に義経がはじめて法皇に行家の事について訴えた時点で、義経の狼藉を抑えた上で、頼朝にも子細を達すべきことであったろう。義経等の濫行の噂が広まった後では、たとえ義経等に行動を慎むよう仰せ遣わした所で承引しないであろう。もはや収拾し難いことである。そして、今私に『頼朝に贔屓して追討を抑留しているのだろう』という事を示されたが、このように考えられるのは残念でならない。思い得ないことはたとえ小事でも言い切ることは難しい。ましてや大事においては猶更であろう。しかし、何も申し上げないのではない。道理のある所は申し上げる)」
と語った。その後、泰経は兼実の言葉を承って九条邸を退出し、法皇へ復命に戻った。
泰経退出後、兼実はひとり物思いに耽る。
「余聞此事神心惘然、天下之滅亡、結句在此時歟、頼朝失義経之勲功、殆及害命之条、事若実者、義経起逆心之条、一旦可然、頼朝之心操、以之可察事歟、但又義経於頼朝偏父子之義也、忽申下追討宣旨、欲誅滅頼朝之条、大逆罪也、自他共失道理、天魔豈不得便乎、不能左右(頼朝追討の宣旨を下すということを聞いて非常に驚いた。天下の滅亡はまさにこのときにあるかと。頼朝が義経の勲功を無いものとした上にその命を奪おうとすることが事実であれば、義経の頼朝に対する逆心はやむなき仕儀である。頼朝の考えはこの事を以て察するべきか。ただし、義経は頼朝とは父子の義を結んでおり、義経が頼朝追討の宣旨を奏上して、義父たる頼朝を誅滅を図ることは大逆罪である。道理を失うこととなり、戦乱を呼び覚ますことになろう。もはやどうすることもできない)」と。
泰経から復命を受けた法皇は、左大臣経宗と内大臣実定に参院を命じ、頼朝追討についての諮問を行っている(『玉葉』文治元年十月十九日条)。はじめに参院した実定は、法皇の諮問に対して一存で決め難く左大臣の意見を求めた。その後参院した左大臣経宗は、「凡不可及意議、早々可下宣旨也」と主張した。その理由としては「当時在京武士、只義経一人也、被乖彼申状、若大事出来之時、誰人可敵対哉、然者、任申請可有沙汰也、更不可及議定(いま在京の武士はただ義経一人である。彼の申状に反対したことで謀反が起こった場合、誰が義経を抑え込むことができようか。もはや追討の宣旨を下す他なく、これ以上議定に及ばず)」というものであった。態度を明確にしない内府実定も結局同意することとなり、同席していた経房卿は「聞此事頗傾奇」と批判している。
左府、内府の同意が得られたことで、10月18日、義経の要望通り「被下頼朝追討宣旨」(『玉葉』文治元年十月十八日条)が、翌19日早朝に上卿を左大臣経宗とし、右大弁光雅が認めてが発布されることとなった(『玉葉』文治元年十月十九日条)。
文治元年十月十八日 宣旨
従二位源頼朝卿偏耀武威已忽諸 朝憲宜前備前守源朝臣行家左衛門少尉同朝臣義経等追討彼卿
蔵人頭右大弁兼皇后宮亮藤原光雅奉
義経が私的な敵対行為から、頼朝を朝敵として討つ公戦を目論むほど態度を硬化させた背景は、土佐房昌俊以下八十騎余りの入洛であろう。八十三騎もの軍勢が入洛すれば付随する郎従も含めれば数百人の軍勢となる。当然、義経はこの入洛を察知したであろう。『吾妻鏡』では17日に「土左房昌俊、先日依含関東厳命、相具水尾谷十郎已下六十余騎軍士、襲伊予大夫判官義経六條室町亭」とある(『吾妻鏡』文治元年十月十七日条)。『吾妻鏡』によれば当時不可解なことに「于時予州方壮士等、逍遥西河辺」といい、六条室町亭には家人が少なかったという。
ところが、襲撃を受けた義経は、佐藤四郎兵衛尉忠信らを率いて自ら昌俊勢に当たり、形勢危うきところを、駆けつけた行家勢とともに前後から昌俊勢を押しつぶしたという。義経は事前に行家と図って昌俊の誘殺を目論んだのかもしれない。
結果として頼朝による義経殺害は失敗に終わり、昌俊は逃亡して義経の家人がこれを追撃。昌俊らは鞍馬山の奥の方へと逃れたが「土佐房昌俊并伴党三人、自鞍馬山奥、予州家人等求獲之」えられ、26日「於六條河原梟首」された(『吾妻鏡』文治元年十月廿六日条)。義経は襲撃を受けたのち参院している(『吾妻鏡』文治元年十月十七日条)。『玉葉』では、
「亥剋、人走来告云、北方有作時之音、余聞之、事已実也、未知何事、然間人又告云、武士打囲法皇宮云々、神心失度、奉念三宝之外無他、堅閉門戸待動静之間、襲院御所之条已僻事也、頼朝郎従之中、小玉党武蔵国住人卅騎許、以中人之告、寄攻義経家、院御所近辺也、殆欲乗勝之間、行家聞此事馳向、追散件小玉党了云々(午後十時ごろ、慌ただしく人が駆けつけてきて、北の方で鬨の声が上がったという。自分もこれを聞き、事実である。何事が起ったのか判らぬまま、また人が駆けつけてきて言うには、武士等が法皇の御所を取り囲んだという。まさに法住寺合戦の再来か。心落ち着かず、三宝に祈るほかなかった。堅く門を閉じて動静を窺っていると、どうやら院御所の襲撃は誤伝で、頼朝郎従の児玉党三十騎ばかりが院御所近くの六条室町にある義経邸を襲撃したものだった。児玉党は義経勢をほとんど制圧せんとするとき、十郎行家の軍勢が馳せ参じ、児玉党を追い散らしたという)」(『玉葉』文治元年十月十七日条)
と伝えている。この合戦は、『愚管抄』においては「頼朝郎従ノ中ニ、土佐房ト云フ法師アリケリ、左右ナク九郎義経ガモトヘ夜打ニ入ニケリ、九郎ヲキアイテヒシヒシトタタカイテ、ソノ害ヲノガレ」たとする(『愚管抄』)。『百練抄』では「今夜子刻許、義経宅六条堀川、軍兵等自四方攻寄之、有夜打之企、義経忽合戦、襲来之勇士皆悉逃散了、此間院中騒動、四面門等被閉了、義経進使云、奇怪之輩追散了、不可驚思食者、件張本者于土佐房」とある。合戦が亥剋以前に起こっていたことは兼実が実聞しており、『百練抄』の「子刻」は誤りだが、戦闘の終了が子刻であったのかもしれない。なお『愚管抄』ではこの事件を「文治元年十一月三日、頼朝可追討宣旨給リニケリ」ののちのこととするが、『玉葉』においても10月の事件としていることから、慈円の記憶違いである。
以上から、土佐房昌俊らは頼朝が私的に遣わした義経追討使であって「暗殺」を狙ったわけではなかったことがわかるのである。そして、昌俊らは午後十時頃、六条室町邸(現在の東本願寺北縁)に攻めかかり、義経らはこれを防戦し、さらに追撃に転じた。六条室町邸から九条邸(九条跨線橋西側)まで直線千五百メートルの距離にもかかわらず、鬨の声が聞こえるほどの規模の合戦が行われたことがわかる。結果として、この夜戦により、義経は頼朝と完全に決別するに至った。
ところが、追討の宣旨が下されたものの、義経・行家が奏上していた法皇の鎮西行幸はことごとく拒否され、義経等はこれを撤回する(『玉葉』文治元年十月廿一日条)。さらに「始推雖申下可追討頼朝之宣旨、事不起自叡慮之由、普以風聞」というように、この追討宣旨が法皇の意思から出たものではないと伝わったことから、在京武士等は行家・義経に加担することなく「近江武士等、不与義経等、引退奥方」(『玉葉』文治元年十月廿二日、廿三日条)という状況であった。「還以義経等處謀反之者、加之、引率法皇已下可然之臣下等、可向鎮西之由、披露之間、弥乖人望、其勢逐日減少、敢無与力之者」(『玉葉』文治元年十一月三日条)とある。義経はあくまでも頼朝代官であり、在京御家人らがその行いを頼朝に対する反逆と認識したであろうことは容易に想像できる。御家人らは当然ながら義経との深い紐帯はなかったであろう。もはや義経や行家に敢えて加担する武士などあるわけがなかったのである。
このころ鎌倉では9月3日、「故左典厩御遺骨副正清首奉葬南御堂之地」している。六条源氏の菩提所として建立されていた勝長寿院の落慶供養前の埋葬である。勝長寿院は幕府南側の川を挟んだ谷津に、北向きに造営された南北に長い広大な寺院で、後述の通りおそらく興福寺系の法相宗寺院であったと考えられる。落慶法要には源氏とゆかりの深い園城寺の本覚院僧正公顕を導師に招いていた。11月14日、前中納言源雅頼が九条邸を訪問し、頼朝の使者「相模国住人其名有久」から伝えられたことを兼実に伝えているが(『玉葉』文治元年十一月十四日条)、それによれば「京事、十月廿三日聞候、範頼并公顕僧正、廿二日下著、然而範頼成憚直不申、粗披露傍輩云々、廿四日堂供養、…、自廿四日有上洛沙汰、有久廿七日出国、次官親能、今四ケ日之後可出国云々、頼朝一定可京上之由風聞、已超足柄関之由、於路頭所承也、非如先々決定可上洛之由、下知郎従等」という。
10月22日、範頼と公顕僧正は鎌倉へ下着。24日には「堂供養、卯時事始、申剋終、願主浄衣云々、布施物之長櫃百八十合、導師馬卅疋十疋置鞍、讃衆廿口、各三疋一疋置鞍」滞りなく勝長寿院供養が挙行された。この供養に際して、常胤は頼朝の「御後五位六位」の一人として、五位の六男・六郎太夫胤頼とともに従っている。また、御後に供奉する「前対馬守親光」は、「対馬守親光者武衛御外戚也」(『吾妻鏡』元暦二年三月十三日条)とある通り、系譜上では頼朝との関係は定かではないが、頼朝の外戚に当たる人物であった。この親光の姉妹は「権中納言平教盛室」となり「従三位通盛母」となった人物で、通盛と頼朝は何らかの血縁関係にあったことがうかがえる。
●文治元年勝長寿院供養に供奉した千葉一族(『吾妻鏡』文治元年十月廿四日条)
| 随兵(先陣) | 畠山次郎重忠 | 千葉太郎胤正 | 三浦介義澄 | 佐貫四郎大夫広綱 | 榛谷四郎重朝 |
| 葛西三郎清重 | 八田太郎朝重 | 加藤次景廉 | 藤九郎盛長 | 大井兵三次郎実春 | |
| 山名小太郎重国 | 武田五郎信光 | 北條小四郎義時 | 小山兵衛尉朝政 | ||
| 持御剣 | 小山五郎宗政 | ||||
| 着御鎧 | 佐々木四郎左衛門尉高綱 | ||||
| 懸御調度 | 愛甲三郎季隆 | ||||
| 御後 五位六位 〔布衣下括〕 |
源蔵人大夫頼兼 | 武蔵守義信 | 参河守範頼 | 遠江守義定 | 駿河守広綱 |
| 伊豆守義範 | 相摸守惟義 | 越後守義資 〔御沓〕 |
上総介義兼 | 前対馬守親光 | |
| 上野介範信 | 前宮内大輔重頼 | 皇后宮亮仲頼 | 大和守重弘 | 因幡守広元 | |
| 村上右馬助経業 | 橘右馬助以広 | 関瀬修理亮義盛 | 平式部大夫繁政 | 安房判官代高重 | |
| 藤判官代邦通 | 新田蔵人義兼 | 奈胡蔵人義行 | 所雑色基繁 | 千葉介常胤 | |
| 千葉六郎大夫胤頼 | 宇津宮左衛門尉朝綱 〔御沓手長〕 |
八田右衛門尉知家 | 梶原刑部丞朝景 | 牧武者所宗親 | |
| 後藤兵衛尉基清 | 足立右馬允遠元 | ||||
| 随兵 | 下河辺庄司行平 | 稲毛三郎重成 | 小山七郎朝光 | 三浦十郎義連 | 長江太郎義景 |
| 天野藤内遠景 | 澁谷庄司重国 | 糟谷藤太有季 | 佐々木太郎左衛門尉定綱 | 小栗十郎重成 | |
| 波多野小次郎忠綱 | 広澤三郎実高 | 千葉平次常秀 | 梶原源太左衛門尉景季 | 村上左衛門尉頼時 | |
| 加々美二郎長清 | |||||
| 随兵六十人:被清撰弓馬逹者皆供奉最末、御堂上後各候門外東西 | |||||
| 東方 | 足利七郎太郎 | 佐貫六郎 | 大河戸太郎 | 皆河四郎 | 千葉四郎 |
| 三浦平六 | 和田三郎 | 和田五郎 | 長江太郎 | 多々良四郎 | |
| 沼田太郎 | 曾我小太郎 | 宇治蔵人三郎 | 江戸七郎 | 中山五郎 | |
| 山田太郎 | 天野平内 | 工藤小次郎 | 新田四郎 | 佐野又太郎 | |
| 宇佐美平三 | 吉河二郎 | 岡部小次郎 | 岡村太郎 | 大見平三 | |
| 臼井六郎 | 中禅寺平太 | 常陸平四郎 | 所六郎 | 飯冨源太 | |
| 西方 | 豊島権守 | 丸太郎 | 堀藤太 | 武藤小次郎 | 比企藤次 |
| 天羽次郎 | 都筑平太 | 熊谷小次郎 | 那古谷橘次 | 多胡宗太 | |
| 莱七郎 | 中村右馬允 | 金子十郎 | 春日三郎 | 小室太郎 | |
| 河匂七郎 | 阿保五郎 | 四方田三郎 | 苔田太郎 | 横山野三 | |
| 西太郎 | 小河小二郎 | 戸崎右馬允 | 河原三郎 | 仙波二郎 | |
| 中村五郎 | 原二郎 | 猪股平六 | 甘糟野次 | 勅使河原三郎 | |
その後、導師公顕への布施として馬三十疋が納められるが、そのうち十疋はセレモニー的に御家人が引いた。その際、千葉介常胤が足立右馬允遠元と組んで一之御馬を納め、九之御馬は千葉二郎師常が一族の印東四郎と組んで納めている。
●文治元年勝長寿院供養の馬牽(『吾妻鏡』文治元年十月廿四日条)
| 一之御馬 | 千葉介常胤、足立右馬允遠元 |
| 二之御馬 | 八田右衛門尉知家、比企藤四郎能員 |
| 三之御馬 | 土肥次郎実平、工藤一臈祐経 |
| 四之御馬 | 岡崎四郎義実、梶原平次景高 |
| 五之御馬 | 浅沼四郎広綱、足立十郎太郎親成 |
| 六之御馬 | 狩野介宗茂、中條藤次家長 |
| 七之御馬 | 工藤庄司景光、宇佐美三郎祐茂 |
| 八之御馬 | 安西三郎景益、曽我太郎祐信 |
| 九之御馬 | 千葉二郎師常、印東四郎(師常) |
| 十之御馬 | 佐々木三郎盛綱、二宮小太郎 |
勝長寿院より御所に帰還すると、頼朝は侍所の監督人である和田義盛・梶原景時両名を召して、明日の上洛進発について軍士の着到を指示する。これは伊予守義経と備前守行家を追討するための軍勢催促であり、これに応じた群参の御家人は「常胤已下」主だったものは二千九十六人であった。このうち上洛に付き従うものは、小山朝政、結城朝光ら五十八人とされた。
翌25日早朝には、「差領状勇士等、被発遣京都」とおそらく先遣の御家人(先陣の土肥次郎実平か)が鎌倉を出立しており、彼等には「入洛最前可誅行家義経、敢莫斟酌、若又両人不住洛中者、暫可奉待御上洛者」と指示を行っている(『吾妻鏡』文治元年十月廿九日条)。明確に行家と義経を誅殺すべきことを命じている。そして29日、「予州・備州等」の叛逆を追討すべく、軍勢を京都へ向けて進発する。その先陣は土肥次郎実平、後陣は千葉介常胤が務め、おそらく東海道を進む陣容であったとみられる。そのほか、東山道、北陸道の二道からも進発しており、三道からの大規模な上洛軍であった。
文治元(1185)年10月25日、ふたたび院使として泰経が九条邸を訪れ、
「遣使於頼朝之許、可被披陳子細歟、而隠而遣之者、義経等之伝聞有恐、仍只仰聞件両将、且暫被止当時之狼藉、被遣顕露之御使、其次含密語、被加披陳之詞如何、可計奏者(使者を頼朝のもとに密かに遣わして追討宣旨の子細を弁明したいが、義経等に洩れる恐れがある。そのため両名には頼朝に狼藉を停止させる使者を遣わす旨を伝えるが、実際には追討宣旨の子細の密語の使者を遣わそうと考えるが、如何か)」
との院宣を伝えている。兼実はこれを聞いたとき、追討宣旨の宣下によって近国武士等を催したものの思惑が外れて加担する武士が集まらず、慌てた人々が法皇に奏上した結果このような院宣が下されたのだろうと推測している(『玉葉』文治元年十月廿五日条)。兼実は虫のいい事をいうと思ったのだろう。
「事已発覚、被下追討宣旨畢、其上更被仰遣和平之儀、頼朝豈可受勅語哉、暗可有推察歟、但於其条者、縦不承引、推而可遣歟、頼朝之忿怒、雖遣使、雖不遣使、更不可有差別之故也、而在京之武士等被仰合之時、各欝申者如何、若可有此儀、不被下追討宣旨之以前者、頗叶物議歟、先日被尋問之時、内々存申之趣已是也、而不事問、被下宣旨之後、更此儀出来、首尾似不相応歟、惣非愚意之所及者(追討宣旨を下しているのに和平の使者も遣わすという理解できない勅語に頼朝が応じるはずもないことは分かり切っている。頼朝の忿怒は使者を遣わす遣わさないに拘らず、変わらない。義経等に迎合して私の意見に反対した人々が今更何を言うのか。この儀は追討宣旨以前に行うべきものであり、先日尋ねられた時に申し上げたことはまさにこの事だ。結局、私の言葉を思わずに宣下してこの体たらく。今更諮問されても首尾相応せざるところであり、もはや愚意の及ぶところではない)」
と突き放した。これに泰経は「左大臣申云、早可被遣、尤上計也」を伝えて早々に帰参した(『玉葉』文治元年十月廿五日条)。
ただ、このとき泰経が密かに語ったこととして、
「法皇只不可知食天下也、我君治天下、保元以後、乱逆連々、自今以後又不可絶、仍只為全玉体、枉可有此儀者(法皇は天下を治めるべきではない。法皇が天下を治めてから、保元の乱以降、乱が収まらずこの先も同様だろう。よって、法皇の玉体を守らんがため、枉げて法皇を政務から遠ざけたい)」
という。院近臣の重鎮であり、もっとも近くで法皇を見てきた泰経のただただ実感であろう。
この泰経の「密語」は陳状を送ることの可否についてではなく、「法皇只不可知食天下」ことを「仍只為全玉体、枉可有此儀」というものである。法皇の一貫した行動は、生来の政治に対する無関心と自らの保身に汲々とするものであった。泰経はこうした法皇の側近としてその意を汲み、表に立って行動してきた人物である。法皇の無能ぶりにほとほと疲れていたのだろう。法皇の支離滅裂な言葉を陳状として頼朝に送らなくてはならない者として、また今後の法皇の身の上を案じる者として、もはや法皇と権勢を引き離す必要を感じていたと思われる。
しかし、法皇の近臣に対する先入観を強く持っていた兼実は、泰経の計画に対し、
「君不知食天下者、誰人可行哉(では法皇以外に、誰が天下を治めるのか)」
と問うた。これに泰経は、
「只臣下可議奏也(臣下が議奏して行う)」
という。しかし、すでに院政が開かれて百年、上皇という存在なくして政治が動く世の中ではなかったこともまた事実である。兼実は法皇を頂点に置き、主上を奉じて摂簶と公卿がこれを輔弼する政権体制(御堂道長の摂関政治体制)の維持を理想としていた。法皇という絶対者なくしてこの混乱した世をまとめることは不可能と考えていたのである。法皇の能力云々ではなく、法皇の存在そのものが必要だったのである。そのため、兼実は、
「此事都不可叶、只以法皇御力、可被直天下也(それは不可能だ。法皇の御力のみが天下を正しい方向に導くことができるのだ)」
と泰経の考えを真っ向から否定した。兼実と泰経の間には、根本的な理解の相違があることがわかる。兼実とは別の視点を持つ泰経は、
「極難有其恐、於被直之条者、一切不可叶、可被直得、はやく直て、天下安穏にてこそは人はてましか(そのようなことはまず有り得ない。法皇の御力で世の中が改善されるということは絶対にない。それで世の中の混乱が収まるのであれば、とうに天下安穏になっていよう)」
と強烈に反論しているのである(『玉葉』文治元年十月廿五日条)。ただし、泰経は兼実とは相容れない意見のへだたりがあるが、泰経もまた戦乱のない安穏な世、安定した社会を目指す「方向性」だけは同じであり、院近臣でありながら法皇政治の終焉を強く願っていたのである。
このころ義経はすでに法皇らを伴って鎮西に下向する意向を放棄していたが、巷説ではいまだその風説が収まっていなかった。法皇はなお不安であり、泰経を義経のもとに遣わして誓状を取っている(『玉葉』文治元年十月廿九日条)。
義経等は11月1日早朝に九州へ下向することを決定する。この下向を待ち構える形で、「摂州武士太田太郎已下、構城郭、九郎十郎等、若赴西海者、可射之由結構」という(『玉葉』文治元年十月卅日条)。この太田太郎は、かつて多田蔵人行綱の麾下として平家の兵糧米を強奪するなど対峙している(『玉葉』寿永二年七月廿四日条)。義経は郎従の紀伊権守兼資に西国へ下るための船を用意させるべく、摂津国へと下したが、兼資はこの太田太郎頼助らによって討ち取られたという。これにより、義経等は鎮西ではなく北陸へ向かうという風聞が伝えられた(『玉葉』文治元年十月卅日条)。『吾妻鏡』では義経は「大夫判官友実」に乗船の手配を命じたとあり(『吾妻鏡』文治元年十一月二日条)、人物名が異なる。なお、友実は手配の途路、「庄四郎元与州家人、当時不相従」と出会い、庄から「今出行何事哉」と問われたという。友実は庄に問われるままに義経から船の調達の指示を受けていることを告げている。庄はすでに義経から離れているが、「庄偽示合如元可属与州之趣」を告げると、友実は庄を伴って義経のもとに戻るが、庄は義経に討たれたという。友実は船の手配を行わずに帰還したことになるが、その後ふたたび手配に動いたかどうかは不明。なお「件庄、実者越前国斎藤一族也、垂髪而候、仁和寺宮首服時属平家、其後向背相従木曾、々々被追討之比、為予州家人」という経歴の人物であった(『吾妻鏡』文治元年十一月二日条)。
こうした「依路次狼藉」によって11月1日の義経下向は3日早朝に延引されているが(『玉葉』文治元年十一月一日条)、鎮西下向に際して「聊有申請旨」を奏上している。それは次の二つの項目の弁明及び要求であった。
| (一) | 可奉動君之由、達天聴、依有其恐、書進起請先畢、其上不可有疑之由存之處、院中祗候之輩、猶致発向之用意云々、此事都不可候事也、郎従等雖遂先途、猶臨幸可宜之由雖令申、於義経内心者、更不可乖叡慮、敢以不可有御不審抑 |
| (二) | 山陽西海等庄公、共為義経之沙汰、調庸租税年貢雑物等、慥可沙汰進上之由、欲被仰下、兼又、豊後武士等、被召院、義経行家等殊可扶持之由、欲仰下 |
法皇はこの両条について仰せ下すべきか否かを、右少弁定長を院使として九条邸に遣わし兼実に諮問した(『玉葉』文治元年十一月一日条)。これに兼実は、
「可追討頼朝之由、被下宣旨之上、如此細々事、更不可及議定、於今者、只任申請有其沙汰、早速可被出洛陽歟(頼朝追討の宣旨という大事を行った上は、義経等の細々した要求などまったく議定に及ぶような内容ではない。ただ申請に任せて沙汰し、早々に出京させるべきである)」
と答えている。これを受けて法皇は早速院宣を作らせ、夜に入って義経に院宣を下した(『玉葉』文治元年十一月二日条)。この院宣には義経が要求した「山陽西海等庄公、共為義経之沙汰、調庸租税年貢雑物等、慥可沙汰進上之由、欲被仰下」について「以義経補九国之地頭、以行家被補四国之地頭」(『玉葉』文治元年十二月廿七日条)という丸呑みのものであった。そして「九国之地頭」にともない、義経または範頼が同伴したとみられる「豊後武士等」を院に招いて義経・行家麾下とすべきことを認めさせている。
11月3日朝方、「前備前守源行家、伊予守兼左衛門尉大夫尉也従五位下同義経為殿上侍臣」は、各々法皇に出京のことを告げて、二百騎あまりを率い鎮西へ向けて京を出立した(『吾妻鏡』『玉葉』文治元年十一月三日条)。なお、『吾妻鏡』では「為遁鎌倉譴責、零落鎮西、最後雖可参拝、行粧異躰之間、已以首途」(『吾妻鏡』文治元年十一月三日条)という、義経は頼朝からの譴責を避けるために九州へ赴く旨を述べたといい、しかも甲冑に身を包んでいるため法皇には会うことなく出立したことを告げたという。『玉葉』では義経は頼朝との対立姿勢を鮮明とし、さらに四国と九州を統べる院宣を帯しての下向であり、『吾妻鏡』とはまるで異なる。兼実は当日に義経の要求についての諮問を受けており、『玉葉』に述べていることは事実である。つまり、『吾妻鏡』のこの部分は鎌倉史観で歪曲されていることがわかる。
●義経行家随行の人々(『吾妻鏡』文治元年十一月三日条)
| 前中将時実 | 平大納言時忠卿長男。義経義兄。 |
| 侍従良成、義経同母弟、一條大蔵卿長成男 | 藤原長成卿子。母は常葉。義経義弟。 |
| 伊豆右衛門尉有綱 | 伊豆守仲綱子。義経女婿とあるが不明。 |
| 堀弥太郎景光 | 義経郎従。 |
| 佐藤四郎兵衛尉忠信 | 義経郎従。 |
| 伊勢三郎能盛 | 義経郎従。 |
| 片岡八郎弘経 | 義経郎従。 |
| 弁慶法師 | 義経郎従。 |
兼実は、「是則無指過怠、為頼朝欲被誅伐、為免彼害所下向也、始推雖申下可討頼朝之宣旨、事不起自叡慮之由、普以風聞之間、近国武士不従将帥之下知、還以義経等處謀反之者、加之、引率法皇已下可然之臣下等、可向鎮西之由、披露之間、弥乖人望、其勢逐日減少、敢無与力之者、仍於京都難支関東之武士、是以下向云々、院中已下諸家、京中悉以安穏、義経等之所行、実以可謂義士歟、洛中之尊卑無不随喜、若如以前風聞者、王侯卿相一人而不可全身、然則人別争有失生涯之果報哉、因茲無此濫吹歟、可悦」(『吾妻鏡』文治元年十一月三日条)と、京都での戦闘を避けるとともに略奪を伴わなかった義経の整然とした退京を「義士」と称賛している。一連の頼朝追討の宣旨に関する問題につき、兼実は公的な立場においては、頼朝追討の正当性を暗に疑問を呈する一方で、私情では「頼朝失義経之勲功、殆及害命之条、事若実者、義経起逆心之条、一旦可然」とあるように、理解を示していたのである。
京都を出立した義経・行家勢は予定通り、摂津国からの船出を敢行しており、船の集まっていた長洲御厨の神崎川河口へ向かったとみられる。先日、義経が船集めのために摂津国に紀伊権守兼資を遣わしていたが、太田太郎頼助によって討たれていた。このときに集められた船かは不明だが、神崎川河口の大物浦周辺には多田蔵人行綱の家人・太田太郎頼助が布陣していたのだろう。義経は京都を出立したその日のうちに「河尻辺(尼崎市付近か)」まで進み、太田太郎の手勢を踏み潰している(『玉葉』文治元年十一月四日条)。なお『吾妻鏡』では、まるで反対に「摂津国源氏多田蔵人大夫行綱、豊嶋冠者等遮前途、聊発矢石、予州懸敗之間、不能挑戦、然而与州勢多以零落、所残不幾」と、多田勢の勝利と記す(『吾妻鏡』文治元年十一月五日条)。
その後「大物辺」に宿して出帆の時期を窺ったとみられる。ところが、義経等の出京を受けて「京中所残留之武士等、少々為追義経等下向」と、在京御家人らが私的に義経追捕のために彼らを追跡し(『玉葉』文治元年十一月三日条)、さらに翌日にも「今日又武士等追行義経」と追跡の武士が摂津へ向かっている(『玉葉』文治元年十一月四日条)。彼らは義経等が宿陣した「大物辺」の「寄宿近辺在家」して義経・行家を遠巻きに窺っている。この追跡を主導したのは「手島冠者并範季朝臣息範資等、為大将軍云々、件範資雖生儒家、其性受勇士、加之、蒲冠者範頼、親昵之間、催具在京之範頼之郎従等、行向」(『玉葉』文治元年十一月八日条)とあるように、在京の蒲冠者範頼従者を率いた手島冠者と藤原範資(兼実家司の藤原範季の子)であった。範資は「其息範資、追戦九郎党類之間事、愚父一切不知之由、立誓言争申之」(『玉葉』文治元年十一月十日条)とあるように、父・範季に無断で義兄・範頼の郎従を率いて出兵したことがわかる。
藤原範季―+=源範頼
(木工頭) |(参河守)
∥ |
∥ +―藤原範資
∥ (八条院蔵人)
∥
∥――――+―藤原範茂
∥ |(甲斐守)
∥ |
平教盛――――平能子 +―藤原重子
(中納言) (従三位) (修明門院)
∥――――――順徳院
∥
後鳥羽院
11月5日、「関東発遣御家人等入洛、二品忿怒之趣、先申左府経宗」(『吾妻鏡』文治元年十一月五日条)と、御家人らが入洛したという。ただし、『玉葉』ではとくに記述はなく、大規模な入洛ではなかったとみられる(『玉葉』では11月13日「関東武士、多以入洛」とあり、「入洛武士等之気色大有恐」とある)。一方で、これ以前に伊予守義経・前備前守行家は京都から逃れており、その報告を受けた頼朝は11月8日、上洛を取りやめて黄瀬川宿から鎌倉へ戻っている(『吾妻鏡』文治元年十一月八日条)。
11月5日夜、義経、行家等の軍勢は河尻から出帆することとなるが、この日は「自夜半大風吹来」という荒天で、本来であれば出帆するような状況にはない。もちろん強風に乗って早々に西へ向かうことを想定していたのかもしれないが、おそらくは近辺に追い迫る在京武士の攻撃を恐れた結果であろう。彼らとは「未合戦之間」とある通り、合戦には及んでいないが、夜半の荒天時に出帆する理由としては自然であろう。結果としてこの出帆は失敗し、「九郎等所乗之船、併損亡、一艘而無全、船過半入海、其中、義経行家等、乗小船一艘、指和泉浦逃去了」という(『玉葉』文治元年十一月八日条)。「相従予州之輩纔四人、所謂伊豆右衛門尉、堀弥太郎、武蔵房弁慶并妾女字静一人也」であったといい、「天王寺辺」に宿したという(『吾妻鏡』文治元年十一月六日条)。また、11月6日には「近江美濃源氏武士為討義経下向西国畢」(『百練抄』文治元年十一月六日条)と、近江源氏、美濃源氏が義経追討に加わったという。
義経遭難の風聞は11月7日夜には兼実のもとに届いており、速報という事で「雖不詳、解纜不安穏歟、事若実者、仁義之感報已空、雖似遺恨為天下大慶也、彼等若籠鎮西者、為追討之武士等、巡路之国弥可滅亡、関東諸国又依此乱不可通其路、仍中夏之貴賤、可無活計之術、而不遂前途滅亡、豈非国家之至要哉、義経成大功、雖無其詮、於武勇与仁義者、貽後代之佳名者歟、可歎美可歎美」と、頼朝の卑怯な仕打ちと非情さを非難し、結果として起こったこの義経の身の上に対する同情心が垣間見える。義経に対しては不憫ながらも、国家として考えれば義経等の滅亡は大慶であり、もし彼らが鎮西に籠ったとすれば、追討の武士等によって通路の国々は狼藉を受けてますます疲弊してしまうだろう。義経の挙げた大功は詮無くなってしまうが、その武勇と仁義は後代までの佳名として残るであろうと餞の言葉を送っている。兼実個人としては義経への深い同情を示し、頼朝に対しては「頼朝在世之間、忽可及大乱之由、万人不存事歟、苛酷之法殆過秦皇帝歟、仍親疎含怨之所致也」(『玉葉』文治元年十月十四日条)という嫌悪の念を持つが、国家全体としては義経の滅亡を大慶としてとらえていることがわかる。義経の存在は「凡五濁悪世、闘諍堅固之世、如此之乱逆継踵而不絶歟」の元凶であったのだ(『玉葉』文治元年十一月七日条)。
義経や行家らは和泉国へと船で向かうも、摂津国大物あたりに吹き戻された人々もおり、行家の嫡子・大夫尉家光も「於家光者梟首了」とある通り殺害された。さらに「豊後武士等之中、或為降人来範資之許、又乍生被捕取了」とあり(『玉葉』文治元年十一月八日条)、義経の中核をなす豊後武士らも藤原範資らに下ったことがわかる。また、同道していた前少将平時実(平時忠嫡子で義経義兄弟)も生け捕られている(『玉葉』文治二年正月十七日条)。
そして11月7日、「義経被解却見任、伊与守検非違使」という措置が取られることとなる(『吾妻鏡』文治元年十一月七日条)。なお、同日条には「右府兼実頗被扶持関東之旨、風聞之間、二品欣悦給」とあるが、当時の兼実は頼朝を秦の始皇帝に準えて嫌悪しており、兼実が頼朝を快く思っているというこの記述は後年の『吾妻鏡』の創作である。
11月11日、前中納言雅頼卿が九条邸を訪問し、「示合三位中将改名之間事」った(『玉葉』文治元年十一月十一日条)。三位中将とは兼実の嫡子「中将名良経」のことである。「九郎名義経也、良与義其訓惟同、義経須改名也、而敢以不改、然間忽類刑人滅亡、於今者中将之改名不可及異議歟、仍内々問其字於長光法印之處、択申云、良輔、経通云々、輔字九条殿御名、経通雖為公卿之名、無彼子孫、当時非可憚、被用有何事哉」(『玉葉』文治元年十一月十一日条)と雅頼に問うた。これに雅頼は「経通為勝、被用宜歟」と答えている。なお11月17日、大外記頼業が兼実のもとを訪れて「中将名可改哉否之由」を問い「雖不改何事哉、若改者、可用良輔、於経通者公卿名、猶可被避」(『玉葉』文治元年十一月十七日条)と、もし改名するとすれば「良輔」とすることを申し述べているが、実際には義経の名が「義行」と改められたため、三位中将良経の名が「良輔」に改められることはなかった。
11月12日夜、兼実のもとに蔵人頭藤原光長が参じて「被下諸国、御教書」の「義経行家等可奉召之由、被下院宣」のことを伝えている(『玉葉』文治元年十一月十二日条)。この院宣を奉じたのが大宰権帥経房であることから、実弟の光長に伝えられたものであろう。
被院宣尓、源義経同行家、巧反逆、赴西海之間、去六日於大物浜忽逢逆風云々、漂没之由、雖有風聞、亡命之条、非無狐疑、早仰有勢武勇之輩、尋捜山林川沢之間、不日可令召進其身、当国之中、至于国領者、任此状令遵行、於庄園者、触本所致沙汰事、是厳密也、曾勿懈緩者、院宣如此、悉之、謹状
十一月十二日 大宰権帥経房
和泉守殿
兼実はこの院宣の内容について諮問されておらず、法皇は兼実の反発を予想して独断で行ったのだろう。内容を聞いた兼実は「件両将昨日ハ蒙可討頼朝之宣旨、今日ハ又預此宣旨、世間之転変、朝務之軽忽、以之可察、可指弾可指弾」(『玉葉』文治元年十一月十二日条)と呆れ果てた様子を記録している。そして、この日「三条宮息、年来被座北陸之宮生年十九、雖加元服、未有名字」といい、これは「頼朝之沙汰」であったという(『玉葉』文治元年十一月十四日条)。そして翌11月13日からは「関東武士、多以入洛」という(『玉葉』文治元年十一月十三日条)。この武士らは「入洛武士等之気色大有恐」であり、「大略天下大可乱、法皇御辺事、極以不吉」を予感させるものであった(『玉葉』文治元年十一月十四日条)。
文治元(1185)年11月12日、鎌倉では河越重頼が所領を収公された(『吾妻鏡』文治元年十一月十二日条)。重頼の娘が義経の正室という「義経縁者」だったためである。重頼の所領のうち「伊勢国五ヶ郷」については大井兵三次郎実春がこれを給わっている。ただし、そのほかの所領は「重頼老母」の預かりとされた。また、重頼の女婿である下河辺四郎政義も同じく義経相聟ということで所領没収の憂き目をみている。
11月14日、中原有安が女房冷泉殿から聞いた言葉を兼実に伝えている。それによれば、11月3日に女房冷泉殿が参院した際、法皇が眼前で、
「今日可参向摂政第、可申之様ハ、世間事、於今者、雖帝王雖執柄、更不可遁恥辱、今度之怖畏、倩案次第、偏朕之運報之尽也、何況、頼朝忿怒之由有其聞、摂政之辺事不受之由、自元風聞、右府辺事、殊為賢相之由令庶幾云々、去年比、再三有申旨、然而依朕之抑留、不遂其意、今度定重有申事歟、於今者、非朕之力所及、仍未聞其事以前、遮目避職、右府令沙汰天下事尤穏便歟、但自是之使トテハ不可申、只伺気色可告也(今日、摂政邸に参向して『もはや今となっては帝王といえども摂政といえども恥辱を逃れることはできない。今の世間の混乱を見て考えるに、偏に朕の運は尽きたという事だ。その上頼朝が忿怒の様相と聞く。(無能な)摂政も頼朝は受け入れがたいという。それに対して頼朝は右府兼実が殊に賢相であるから去年から再三にわたって摂政にと希っている。しかし、朕がこれを認めなかったことで頼朝の意見は通ることはなかった。今回のことで必ず再度の申請があろう。もはや朕の力が及ぶところではないから、その申請を聞くよりも前に目を瞑って摂政を退き、兼実に摂政を任せることがもっとも穏便ではなかろうか。ただし、この事は使者を以て申すものではなかろうから、朕自ら摂政邸に参じて基通の気色を伺いながら告げるべきであろう』)」
と述べたという(『吾妻鏡』文治元年十一月十四日条)。その後有安は院使として摂政基通邸に馳せ参じ、法皇の語った言葉を伝えたが、基通は、
「其気色甚不請、殆被處御使之過怠、一切無御返報、只参上可承候許被示、事体依不足言、彼日不帰参、翌日四日也参上、奏此旨、其後無沙汰云々(摂政は法皇の要請を受け入れる様子はなく、(法皇がそんなことを仰せになるわけがあるまい)有安の過怠ではないかとまで言い、法皇へのご返報もないが、参院する旨は示した。摂政の様相は予想通りで急ぎ復命するほどのことでもなく、翌4日に奏上したが、その後摂政から何の沙汰もない)」
という様子だったという(『玉葉』文治元年十一月十四日条)。
兼実はこの報告を受けて、
「若実者、法皇仰尤可謂有理致歟、凡如此事、只天運之令然也、但乱代執朝之柄事、太不甘心、法皇与当時摂政、尤相似タル君臣也、疎遠不得心之愚翁、太以不足其器、又不叶時議歟(もしこの話が事実であるとすれば、法皇の仰せは理に適ったものだが、このようなことは天運によるものだ。ただ混乱の世に執柄となることは御免被りたい。法皇と基通は似た者同士の君臣だ。法皇と疎遠の私ではその心を得ることはできず、当代の摂政に相応しくない。時宜にも叶うものではない)」(『吾妻鏡』文治元年十一月十四日条)
と感想を述べている。
さらに11月18日にも中原有安の報告があり、同僚の舞人近久(左大臣経宗、内大臣実定の近習で能の名手)から聞いたこととして、「大蔵卿泰経語可然之人々、入道関白可執行天下之由結構云々、禅門相国并資賢入道同心」(『玉葉』文治元年十一月十八日条)という情報が兼実に届いた。高階泰経は入道関白基房を摂政に登壇させることを企て、禅門相国忠雅、源資賢入道らの協力を取り付けたという。これを聞いた摂政基通は大いに歎息して女房を通じて奏院し、
「天下事不可知食之由、人々結構、敢不可有御承引候、只如本可有御沙汰也(法皇に天下を治めることを拒否せんとする人々が結託しているが、これを御承引されないように。ただこれまで通り御沙汰あるべし)」
と述べたという。しかし、法皇は摂政の奏文に対して、
「可遁世事之條、更非依人之勧、朕自所案也、云世之運、云身之運、更以不可執著、於今者、一向思往生之大事、之不懸最殃之条、深々所庶幾也、朕雖不知天下執柄之運、全不可依其事(遁世せんとすることは決して人の要請によるものではなく、自分自身の考えによるものだ。世の中や自分自身の運にもはや執着はない。今や一向に往生を思い、災いを避けることを只管に希うのみだ。朕は摂政の運を知る由もないが、朕の遁世に影響されないよう)」
と返答している(『玉葉』文治元年十一月廿三日条)。また、法皇は内々にも勅諚を基通に下しているが、
「摂政不熟政事之由、人口難塞歟、摂簶之初、殊親昵右府云々、彼間殊違失事不聞歟、近年頗疎遠歟、尤不便、猶示合万事、可有沙汰ものを(摂政は政事に無能であるという噂を消すことは難しい。摂政就任のころは右府と昵懇にしていたことで大きな失態もなかったが、今や疎遠と聞く。まったく以て宜しくないことだ。(政事の失態をこれ以上曝す前に)全てを相談し沙汰すべきものであるのに)」
と記されていた(『玉葉』文治元年十一月廿三日条)。
法皇が基通への摂政辞任を強く求めた背景としては、兼実の議奏の旨が悉く当たったということに加えて、「頼朝追討之宣下」について、法皇の諮問に今後の状況の把握をすることもできずに「此沙汰之間、摂政被申之旨、不足言」という「非管轄之器量之由、御覧取畢」だったことによるという(『玉葉』文治元年十一月廿三日条)。法皇から見ても摂政基通は無能そのものだったのである。しかし、この無能さはもちろん生来の愚鈍さもさることながら、政道の何たるかを学び取る前に父基実を喪い、政略の前に実務官である中納言や大納言を経験することなく、突如摂簶の座に祀り上げられてしまった基通の生い立ちにも問題があったのだろう。
また、11月14日、前中納言源雅頼が九条邸を訪問した際に、頼朝の使者「相模国住人其名有久」から伝えられたことを兼実に伝えているが(『玉葉』文治元年十一月十四日条)、「有久」は相模国糟屋の御家人で、頼朝実甥・一条高能(頼朝妹婿一条能保の嫡子)の義兄にあたる糟屋有久であろう。それによれば「京事、十月廿三日聞候、範頼并公顕僧正、廿二日下著、然而範頼成憚直不申、粗披露傍輩云々、廿四日堂供養、…、自廿四日有上洛沙汰、有久廿七日出国、次官親能、今四ケ日之後可出国云々、頼朝一定可京上之由風聞、已超足柄関之由、於路頭所承也、非如先々決定可上洛之由、下知郎従等」(『玉葉』文治元年十一月十四日条)という。勝長寿院の御堂供養導師・公顕僧正は当時七十六歳であり、道中は通常よりゆっくり進んだと思われる。10月22日に範頼とともに鎌倉へ下着したことを逆算すると、範頼らが京都を出たのは9月末から10月1、2日頃と思われることから、義経・行家による頼朝追討の宣旨が下されるだいぶ以前に離京していることになる。途中で頼朝追討の宣旨が下された報告を受けていたとみられるが、範頼が頼朝に報告したことは寿永二年に平清経が法住寺殿から持ち出した法皇御剣「吠丸、鵜丸」のひとつ「仙洞重宝御剣鵜丸」を「於鎮西尋取」して法皇に進上したことのみ報告されている。なお、吠丸(義朝献上物)はすでに検非違使大江公朝によって探し出されており(『吾妻鏡』文治元年十月十九日条)、二腰の名刀はともに法皇御所へと戻されている。
一方で「範頼成憚直不申、粗披露傍輩」と、追討の宣旨の事を頼朝に直に伝えることは憚り、大体の内容を「傍輩(中原広元らであろう)」に伝えるに止めている(『玉葉』文治元年十一月十四日条)。23日にこの「傍輩」から頼朝追討宣旨のことを伝え聞いた頼朝は、とくに動揺することもなく、翌24日には勝長寿院供養を行っている(『吾妻鏡』文治元年十月廿四日条)。
勝長寿院供養ののち、頼朝は侍所へ御家人らの「上洛沙汰」を指示し、御家人らはその沙汰に随って上洛の準備を行い、数日の間に鎌倉を出立したのであろう。糟屋有久は10月27日に鎌倉を出立し(『玉葉』文治元年十一月十四日条)、斎院次官親能は有久出立の四日後に出立したという。
播磨国や淡路国などの惣追捕使である梶原平三景時の「代官下向播磨国、追出小目代男、倉々ニ付封了」という。播磨国は「院分国」であり、頼朝の牽制として受け止められたようである(『玉葉』文治元年十月廿七日条)。さらに頼朝自身の上洛も決定しており、11月18日には兼実に「頼朝卿決定出国、当時就駿河国、自彼国先立、上洛之武士説云々、其後、於参河遠江辺、一両日可逗留云々、計入洛之行程、可及今月廿五六日」という(『玉葉』文治元年十一月十八日条)。
そして11月19日には、「今度被支配国々精兵之中尤為専一」の「土肥次郎実平、相具一族等、自関東上洛」した(『吾妻鏡』文治元年十一月十九日条)。実平は平家との戦いでは梶原平三景時とともに中国地方の近国惣追捕使として瀬戸内一帯での戦いを主導した重鎮であり、北条四郎時政の入洛の先陣と考えられる。
その五日後の11月24日、「頼朝宣下之間事、頗有忿怒之気之由、上洛武士所申也」という中で、「頼朝妻父、北条四郎時政」が千騎を率いて入洛する(『玉葉』文治元年十一月廿四日条)。
時政は近畿周辺の武士の統率権を与えられていた。これは、かつて義経が「畿内近国、号源氏平氏携弓箭之輩并住人等、任義経之下知可引率之由、可被仰下候」(『玉葉』寿永三年二月廿七日条)とあるのと同様の権限を与えられていたとみられ、時政は義経に代わる洛中代官としての上洛であることがわかる。実平はその後「西海」へ下っており、惣追捕使当時と同様に瀬戸内一帯の没官領を拝領し、地頭職を有したと思われる。実平は時政が洛中守護を行っていた当時は安芸国に駐屯していたとみられ、以仁王の侍でその逃亡を助けた右兵衛尉長谷部信連が安芸守から「安芸国検非違所并庄公」を給わっていて、頼朝は実平に信連の庇護を命じている(『吾妻鏡』文治二年四月四日条)。嫡子「土肥弥太郎(遠平)」は「備後国太田庄」の地頭となっており(『吾妻鏡』文治二年七月廿四日条)、法皇の御願により「為被宥平家怨霊」の大塔が建立され、その供料所として太田庄が寄進された際に土肥遠平の同地地頭職を停止している。
11月25日夜、頼朝から泰経のもとに追討院宣の陳状に対する返書が院御書に届けられた。ところが泰経はおそらく居留守をつかったとみられる。使者は泰経に頼朝の書状を届けたい旨を「相尋」たが、「当時不祗候之由、人々答之」という。人々とあることから、この使者は院中の人々何人かに問うていることがわかる。結局、居留守を察したのだろう。使者は激怒し、書状を文箱ごと中門廊へ投げつけて院御所から退出した(『玉葉』文治元年十一月廿六日条)。右少弁定長がこの文箱を拾って披見し院奏されることとなる。法皇はこの「頼朝卿申状」を兼実に送り、泰経の処置について諮問をしている。兼実が頼朝書札を披見するに、表書きには「大蔵卿殿御返事」とあり、その下に署名はなかった。その内容は、
行家義経謀叛事、為天魔之所為之由被仰下、甚無謂事候、天魔者、為仏法成妨、於人倫致煩者也、頼朝降伏数多之朝敵、奉任世務、於君之忠、何忽変反逆、非指叡慮之被下院宣哉、云行家云義経、不召取之間、諸国衰弊、人民滅亡歟、日本国第一之大天狗ハ更非他者候歟、仍言上如件
というものであった。しかし兼実は法皇からの諮問に対し「偏可在叡慮者」といつもの如く判断を避けて返奏している。なお、頼朝書状に見られる「日本国第一之大天狗」は法皇を指すというのが一般的であるが、
(一)頼朝は追討宣旨の伝奏公卿であった泰経に対する私信として書簡を送っていること
(二)泰経は頼朝に対して「殊結意趣」とされていて「此事尤不便事歟」と評されていること
(三)頼朝は法皇を治天として尊奉し、法皇をして安穏の世の柱とする理想だったこと
(四)治天に対する表現として「更非他者候歟」という無礼な書様を行うとは考えづらいこと
以上から、この書簡に見える「日本国第一之大天狗」とは、院近臣として追討宣旨の実質的責任者となり、さらに陳状も書いた泰経を指していることは明白であろう。ただし、批判の対象に法皇も含まれていることは間違いないだろう。「抑大蔵卿殿、刑部卿殿并北面人々事者、可處霜刑之族不思知者也、後毒之眷也、然者就顕就冥、深依恐 叡慮、令申其旨許也、此条ハ自君之御心不発候事にて候ヘハ」(『吾妻鏡』文治二年四月一日条)と、頼朝追討宣旨の黒幕は大蔵卿泰経と刑部卿頼経の両近臣であると断罪し、法皇については「此条ハ自君之御心不発候事」と不問としているのである。当然ながら頼朝は、この追討宣旨を許した人物が、義経に怯えた法皇であることは百も承知である。しかし、今後も法皇の「存在」に重きを置く頼朝が、法皇を責めることは不可能である。院近臣を罷免してその怒りを表現したものであろう。このことは、3月16日に頼朝が発した書状にもみられ、「可被處刑輩事欝存候、子細者先度次第令申候畢、其許否者所詮可随御計候、不起自御意、近習者御勘気可候之由者、不能欝申候、其恐候之故也、但 君者雖為不知食候事、已称御定、令下 宣旨候之條、無謂所行候歟、以此旨可令披露給候」(『吾妻鏡』文治二年三月十六日条)と、法皇を直接的ではないが暗に批判する姿が見えるのである。
11月28日、「頼朝代官北条丸、今夜謁経房云々、定示重事等歟」という(『玉葉』文治元年十一月廿八日条)。その内容は「件北条丸以下郎従等、相分賜五畿山陰山陽南海西海諸国、不論庄公可宛催兵糧段別五升、非啻兵糧之催、惣以可知行田地」であるという。この要求に兼実は「凡非言語之所及」と激怒する(『玉葉』文治元年十一月廿八日条)。北条時政のことを、先述で「北条四郎時政」としていたものが、この日の記述では「北条丸」と蔑称となっているのは、気持ちによって言い方が変化する兼実の性格がそのまま反映したものであろう。同様の記述は「若宮別当丸頼朝近臣日来在京」(『玉葉』文治元年十一月九日条)という部分にも見られ、怒りのない記述では「若宮別当玄雲頼朝之専一之者、所奉祝彼本国之八幡今宮別当也、仍有此号」(『玉葉』文治元年十一月十八日条)とある。
頼朝の要求は、畿内から九州にかけての諸国荘園公領を問わない「段別五升」の兵糧米徴収権であった。これは寿永3(1184)年2月19日に頼朝によって停止され宣旨が下された、かつて平家や義仲が設定していた悪評高い「公田庄園兵粮米」の復活に他ならなかった。しかも「兵糧米之催」だけではなく「惣以可知行田地」とあるように、すべての田地の知行権、つまり「地頭」を置くことをも要求したものであった。兼実が言語道断と激怒するのも止むを得ない内容であった。
一方、この頃、逃亡中の義経は大和国多武峰に隠遁しており、「十字坊」が匿っていたが、多武峰はさほど広くない上に住侶も少なく、長く隠し通せることが難しいとして、11月29日、義経に「自是欲奉送遠津河辺、彼所者人馬不通之深山也者」と、人馬も通らないほど山深い十津川へ落ち延びることを勧めたという(『吾妻鏡』文治元年十一月廿九日条)。義経もこれに「大欣悦」といい、十字坊は「道徳、行徳、拾悟、拾禅、楽円、文妙、文実等」八名の悪僧に護衛させて送り出したという。ただし十津川はあまりに遠方であり、その後の義経の動向をみるとおそらく十津川には行っていないと思われる。
11月30日、まさに法皇から見ても摂政基通は無能そのものだったのである。しかし、この無能さはもちろん生来の愚鈍さもさることながら、政道の何たるかを学び取る前に父基実を喪い、政略の前に実務官である中納言や大納言を経験することなく、突如摂簶の座に祀り上げられてしまった基通の生い立ちにも問題があったのだろう。当時、「当時頼朝在駿河国」(『玉葉』文治元年十一月卅日条)という、当時駿河国黄瀬川に在陣していた頼朝(頼朝は上洛を止めたため8日に黄瀬川宿を離れている)の様子が伝えられているが、頼朝は追討宣旨について「泰経卿殊結意趣、又射山不可知食天下事之様令存」(『玉葉』文治元年十一月卅日条)とあるように、泰経卿が追討宣旨を主導し、表向きは法皇は天下を治めていないという認識であるという。そして12月8日、「或人云、泰経親宗等之所領、自頼朝之許可注送之由、仰遣北条之許云々、両人損亡決定歟」という(『玉葉』文治元年十二月八日条)。
そして12月17日、左大臣経宗の下知のもと、高階泰経ら五名が解官された(『玉葉』文治元年十二月十八日条)。
| 高階泰経 | 大蔵卿兼備後権守 | |
| 高階経仲 | 右馬頭 | 高階泰経嫡子 |
| 藤原能成 | 侍従 | 故大蔵卿長成嫡子、義経異母弟。12月3日早旦、保田(保田義定)子男を具して鎌倉へ下向した |
| 高階隆経 | 越前守 | |
| 中原信康 | 少内記 | 義経に従軍した官僚 |
さらに12月23日には「明日、左相府上表」という情報が兼実に入る(『玉葉』文治元年十二月廿三日条)。兼実は左府経宗を無能にもかかわらず、長年在任して辞職しない厚顔無恥な人物と感じていたが、急に辞職を表明したことに若干の驚きを示している。兼実は「若依追討宣旨事、頼朝成怨之由風聞之間、恐而被辞歟、事甚似周章、猶過此時可被辞遁歟」と、経宗が義経を恐れるあまり追討を推して追討宣旨の上卿にまでなっていたことを、今になって慌てて辞職を申し出たのではないかと推測している。しかもその辞職ももはや遅すぎると嘲笑の気配を以て認めている。しかし、経宗も追討宣旨を下したことを決して後悔はしていなかった。実は経宗は12月、頼朝に使者を送っていて、この際頼朝は「被下官符於予州等事、依左府計議之由風聞之旨、頗以不快」という(『吾妻鏡』文治二年正月十七日条)。経宗が法皇の「内々有天気」の追討宣下に賛同し、宣旨の上卿を務めたことは事実であり、頼朝から疑いを抱かれるのも当然であった。しかし、経宗は「不被宣下者、行家義経於洛中企謀反歟、給官苻赴西海之故、君臣共安全、是何被處不義哉」と強く頼朝に抗議し、頼朝も「二品承披由被諾申」であったという。
そして12月26日、頼朝雑色鶴二郎が入洛し(『吾妻鏡』文治二年正月七日条)、北条時政のもとに参じたと思われる。その後、権右中弁光長へ届けられた頼朝書状(12月6日付。宛名は光長だが「以此旨可令洩申右大臣殿給之状」とあり、事実上兼実へ宛てた書状)は、翌27日午の刻、光長が九条邸に持参している。兼実はその衝撃的な内容に驚き「如夢如幻、依為珍事、為後鑑続加之」として詳細に書き残している。内容は
というものであった。院宣に基づいて関東武士等の狼藉を鎮撫する代官・中原久経と近藤国平を「鎮西四国」に進発しているにも拘わらず、「以義経補九国之地頭、以行家被補四国之地頭」(『玉葉』寿永三年二月廿七日条)とする宣旨の矛盾を非難する一方で、義経・行家両名の捕縛のために諸国荘園に地頭を配置することを宣言する。これは頼朝の利潤のためではなく、彼らが朝廷に反感を持つ国人や武士らと手を組んで反抗することを防ぐためとする。そしてこれは兼実知行国として推挙している伊予国でも庄園公領を論ぜず、同様に地頭による執行とする。ただし、地頭が公領の正税などの国役や庄園の本家雑事の遂行に背いたり懈怠があった場合には、地頭には譴責を加え執行させる旨も伝えている。
そして最後に「今度天下之草創也、尤可被究行淵源候、殊可令申沙汰給也、天之所令奉与也、全不可及御案候」と締め、兼実の登壇を前提に「天下之草創」として、混乱した世の立て直しと道理に基づいた政治を行うことを願ったのであった。頼朝の真意は、後述のようにその半年後に兼実に理解されることとなるが、この時点ではまだ知る由もなく、頼朝が書状とともに送った折紙状で示した「同意謀反人行家義経之輩、先可被解官追却交名」と推任、知行国、議奏公卿の指定は、兼実が以前から恐れていた「頼朝若有賢哲之性者、天下之滅亡弥増歟」(『玉葉』寿永三年二月廿七日条)が現実のものとなったと感じられたことだろう。ただただ嫌悪感を示すのみであった。
●『玉葉』文治元年十二月廿七日条
一 議奏公卿
右大臣可被下内覧宣旨 内大臣
権大納言実房卿 宗家卿
忠親卿
権中納言実家卿 通親卿
経房卿
参議雅長卿 兼光卿
已上卿相朝務之間、先始自神祇、次至于諸道、依彼議奏可被計行之
一 摂簶事
可被下内覧宣旨於右大臣也、但於氏長者々、本人不可有相違云々
一 蔵人頭
光長朝臣 兼忠朝臣
二人相並可被補歟、光雅朝臣被下追討宣旨了、天下草創之時、不吉之職事也、早可被停廃之
一 院御厩別当
朝方卿、本奉行之職也、可被還補歟
一
大蔵卿
宗頼朝臣、可被任之
一 弁官事
親経可被採用歟
一 右馬頭
侍従公佐可任之
一 左大史
日向守広房失任国、可被任之、隆職成追討宣旨、天下草創之時、禁忌可候者也、仍可被停廃
一 国々事
伊予 右大臣
越前 内大臣
石見 宗家卿
越中 光隆卿
美作 実家卿
因幡 通親卿
近江 雅長卿
和泉 光長朝臣
陸奥 兼忠朝臣
豊後
頼朝欲申給、其故者、云国司云国人、同意行家義経謀反、仍為令尋沙汰其党類、欲令知行国務也
一 闕官事
撰定器量可被採用之
一 解官事
参議親宗 大蔵卿泰経
右大弁光雅 刑部卿頼経
右馬頭経仲 左馬権頭業忠
左大史隆職
左衛門尉知康 信盛
信実 時成
兵庫頭章綱
同意行家義経、欲乱天下之狂臣也、早解官見任、可被追却之、兼又此外、行家義経家人、追従勧誘之客、相尋浅深於官位輩者、一々可被解官停廃之
十二月六日 頼朝
兼実はこの頼朝の折紙の内容を「旁以不可然」としたうえで、経房卿を屋敷に招き、夜に訪問した経房に頼朝消息文と折紙を託して院に進上。その上で内覧に関して「申固辞之子細」を記した書状を付した。兼実は、
「自頼朝卿許注遣旨如此、須待仰下之處、近日武士奏請事、不論是非有施行、仍若無左右被宣下者、後悔無益、仍忌憚遮以所言上也、以不肖之身、当重任乗仁、雖似可悦、不当非一、先此事、依何事其沙汰出来哉、由緒不審、如申状者、天下之草創也、可究尽政道之淵源云々、已是可鎮乱致治歟、而内覧両人之条、偏禍乱之源也、敢非静謐之計、延喜仁平之例、古今寡少之非據也、醍醐帝者、雖我朝無双之聖代、以菅丞相事為失、是則其権分二之故也、鳥羽法皇者、末代之賢主也、而依寵賞凶悪之臣宇治左大臣是也、顕万代之失、保元以後、天下乱逆、論其源非因仁平之両権哉、上古中古、治世之代、其乱猶如此、末代末世、乱逆之今、其禍又不可疑、欲致治似求乱、譬猶加薪求焔消、攪水期流清、是一、帝王政者、兼鑑将来塞其乱待其治者也、当時天下之緇素、以延喜仁平之例、偏處不吉、殆及忌憚、世忌其例、人断其望之處、此時若貽其例者、後代為例、継踵不絶歟、亡国之基、無過於斯、争以人君之政萌乱亡之源哉、是二、成人御時、以可覧天子之文書、先触委任之臣、謂之内覧、幼主之儀、摂政就南面、代君摂天子之政、仍摂政之時、別置内覧之臣者、以可覧摂政之文書、先可触内覧之人、以之謂之摂政、与内覧殆似、有君臣之礼、加之、叙位除目官奏等、於摂政之直盧所行也、其外有内覧臣者、相分又於彼直盧可行歟、旁以無其謂、仍古来未有比例、縦雖無例、有叶時議事者、隨宜立法、是聖代之流例也、於此事者、依無理又無例、縁底忘当時後代之禍乱、可被行古今無例之新儀哉、是三、縦雖有三ケ之非據、若致万機之懇望者、以為一人枉法之謂、可有此議歟、而乱世之執権、愚心全不欲者也、然則、為世為君為身、此事惣無所據、固辞之趣如此如之由、須被仰遣関東也(頼朝卿の消息はかくの如しである。すべては叡慮が下されるのを待つところであるが、ここ最近はすっかり武士の奏請があれば議論もすることなく宣旨を下す傾向にある。後悔しても無益なこととなるので忌憚なく言上するが、不肖の身を以て内覧という重任となることは悦ぶべきことのようだが、実際は不当なことが一つではない。まず、なぜこのような沙汰が出てきたのか全く不明なことだ。頼朝の申状に見る如く『天下之草創也、可究尽政道之淵源云々』ということは、乱を鎮めて治を致すべきだろう。それなのに内覧を二人置くのは禍乱を招くもとでわざわざ静謐を乱す行いである。醍醐天皇の菅公は権力を二分した例だ。鳥羽法皇の宇治左府の例もあり、保元以降の天下乱逆は偏に両権を置いたことによる失策は疑う余地もない。治を致さんと欲して乱を招くが如しだ。二点目は帝王の政治は乱を防いで治を待ち将来の鑑となることである。今のような天下の状況を将来に遺すことはまったくよろしくない。亡国の基であり乱亡の源である。三点目は、主上成人の時は主上の文書をまず委任の臣が拝する。これを内覧という。幼主の時は摂政として政治を行う。摂政の時に別に内覧を置いた場合は、摂政が見るべき文書をまず内覧が見ることになり、摂政と内覧はほとんど変わらないこととなる。また、叙位除目などは摂政が直盧に於いて執り行うものだが、摂政のほかに内覧を置いたときは摂政と同じ直盧で見るのか。古来より例はないが、例はなくとも時議に叶うものであれば新たに立法することは延喜天暦からの流れであるが、理なく例なくとも後代の禍乱を忘れても、今回のことは新儀として行うのか。この三つの非據があるというのに懇望するとすれば、これはただ一人のために法を枉げることに他ならない。乱世の執権などまったく欲してもいない。世のため、法皇のため、そして自分のためを考えても、まったく根拠のない人事である。固辞する理由はこういったものであり、すべて頼朝に伝えてほしい)」
と述べた(『玉葉』寿永三年二月廿七日条)。
つまり、武士を恐れて唯々諾々とその要求を呑むようになった慣習を非難し、自身の内覧については、その推挙の理由の不明瞭さと、同列の権威を二つ置くことによる朝政の混乱の危惧を挙げ、さらには乱世での執権など御免被るという明確な拒否を伝奏するよう要請したのである。
これに対して経房は、
「頼朝卿所申、抽賞刑罰其事已多、必悉不可叶叡慮、然而偏任彼奏請、併可被行云々、而至于此大事、被仰返子細者、定乖彼意趣歟、此條何様可被仰遣乎、勅定之趣、定如此歟、仍乍恐為存知所驚申也(頼朝卿は抽賞刑罰に慣れており、必ずしもすべてを奏上して叡慮に沿う必要もないだろう。この上は頼朝の奏請に任せた人事を行うべきだ。もはや子細を仰せ返せば必ず頼朝の考えに背くことになろう。法皇のお考えも定めてその通りだろう)」
という(『玉葉』寿永三年二月廿七日条)。
しかし兼実は、
「此事奉為上、全以不可及御煩、其故者、宥刑抑賞者、可乖奏請之旨趣、尤可有御猶予、至此事者、可蒙恩之者、自致辞遁、具述子細、於被仰遣其趣者、敢不可為君御抑留、若有権臣之欝者、其恐可在愚臣者也、只枉可被仰遣之由、可被奏聞者(このことについて法皇は全くご心配に及ばない。頼朝奏請の趣旨に反すると心配するが、恩を受ける私自身がこれを辞退しているのだ。もし頼朝が不満を述べるのであれば私に対してであろう。この人事については枉げて奏聞するように)」
というと、経房は反論できず帰参していった(『玉葉』寿永三年二月廿七日条)。
この中で経房は、法皇はすでに定長を摂政邸に派遣し、早く宣旨を下されるべきの院宣を遣わしており、この話は法皇よりもまず摂政に伝えるべきだと忠告しており、兼実は、経房の退出後、ただちに家司光長を摂政宅に派遣して、
「頼朝申送旨、経院奏了、若有被宣下事者、暫令待重院宣給哉、暗非可有御抑留、院宣之儀、只申達子細之間、片時可被相待、於宣下之後者、無由于奏聞之故也(頼朝人事案の宣下については次の院宣までしばし待つように)」
と申し入れている。摂政宅から帰宅した光長は、続けて経房とともに参院して兼実の希望をつぶさに法皇に奏聞したが、法皇は、
「先例之有無不可及議、自関東恣行任官解官等、言上之条有先例事歟、此上事、万事不可及沙汰、只任彼申旨可被宣下也(もはや先例が云々という議論は意味をなさない。そもそも関東から恣に任官解官を行うこと自体、先例などないだろう。もはやすべて終わったのだ。ただ頼朝の申す旨に任せて宣下せよ)」
という(『玉葉』寿永三年二月廿七日条)。もはや法皇からは万事を放棄した気配すらうかがわれる。
その後、兼実は法皇からの「於院雖承、不被許御辞退之由」の返答を聞いたが、そのままでいることもできず、自ら摂政邸に赴いたが、対面することも叶わなかった。すると、先ほど法皇から摂政に遣わされた定長が二度目の院使として摂政邸に参上している。続けて光長が院使として摂政邸に遣わされ、兼実の申し分の子細を基通に述べた。このとき基通が述べた返事は、
「此事已御定切了、此上於中、雖片時雖抑、只可有還迹也云々、今日次第如此云々(頼朝申状について法皇はすでに決定された。この上はもはや抑え難くただ随うのみだ)」
というものだった。そのほか、定長が密かに告げた摂政の様子として、
「摂政披見折紙状云、此事如状不限内覧一事歟、於氏長者々、不可有相違之由已載之、爰知相違事決定在之歟、仍此事奉行宣下、猶以有恐、只自院直仰上卿、可被宣下歟云々(摂政、頼朝の折紙状を披見して、これはただ内覧のみの事ではなく氏長者の一事もあろう。頼朝申状に相違なき旨は記されているが、氏長者については例外であるとの宣下が欲しいので、法皇直々に上卿に仰せて宣旨を下されたい)」
というものだった。この基通の不審に対して法皇は、
「如状云、二人内覧トコソ見タレ、不可及不審云々(申状の通りで二人内覧のみに言及しているから、不審に及ばず)」
と返答した(『玉葉』寿永三年二月廿七日条)。
兼実は翌12月28日に法皇に面会すべく久方ぶりに参院する(『玉葉』寿永三年十二月廿七日条)。あらかじめ定能卿に参院の旨を伝えており、定能を通じて法皇に閲する予定であったが、あろうことか定能は遅参(と称して)して不在であった。親信卿が参院したため、彼を通じて法皇に面会の許可を得ようとするが、法皇は「隠而不出来」と居留守を使う有様であった。執拗に法皇への面会を求める兼実は「法皇愛妾号丹後、近日朝務、偏在彼唇吻」に要請するが、これも断られてしまう。ここまで法皇への対面が叶わないのは「疑有法皇之制止歟」と、さすがの純粋一徹な兼実も疑いをもっている。帰邸後に訪れた院使は「自頼朝之許所申事、一事無違乱可令致沙汰者」といい、兼実の申状はまったく無視する有様であった。その後もはっきりした勅答も得られないまま、逆鱗の気配さえも伝えられている。
夜に入って、蔵人少輔親経が院使として兼実邸を訪れ、院宣を伝えた。その院宣は、「任官解官等事、仰摂政之處、申不可下知之由、汝慥可奉行」という。摂政基通が頼朝申状に基づく人事宣旨の執行を拒否したため、兼実に代執行を命じたものだった。基通の不執行は明らかに法皇の指図によるものであり、内覧を拒否する兼実自身に自ら内覧の任官を下知させる法皇の企てに他ならない。当然、兼実は抵抗し、
「微臣奉行之条、未得其心、若為上卿可参陣歟、然者、上表之後、未返預其表、前官之者不能奉行公事、又依執政之儀可加下知歟、於件條者、今旦参入述所思致固辞、不承分明之仰退出、未被下件宣旨以前、雑事奉行如何、縦雖被下宣旨、不見吉書以前、先例如此事不執行者也、今仰旁以無其理、若是伝言之誤歟、慥可返奏此趣者(私に宣旨を奉行せよとの条、いまだ納得していない。上卿として参陣すべしというのであれば、昨年に提出した右大臣の辞表が未だ戻されておらず、前右大臣の身で公事は行えない。それとも宣旨に見るような執政としての資格で下知すべきというのか。この件については今朝参院して固辞する旨を申し述べたが、対面叶わず退出しており不分明のままである。宣旨がないままに宣旨内容に基づいて奉行せよというのは道理に合わない。たとえ宣旨が下されたとしても、内覧就任の吉書前に執行はできない。法皇の仰せはまったく理に叶っておらず、もしや院使が伝言を間違えたのではないか。この旨を伝奏せよ)」
と返答している。もはや有無を言わさぬ理攻めで法皇の要請を拒否するのであった。
しかし、もはや法皇は「任官解官事等」について、頼朝案を呑むこと以外に考えていなかった。翌29日には兼実の申状はほぼ無視され、法皇から人事の諮問が行われたのである。
このように、頼朝は流人として東国に移って以来、一度も上洛することなく理想の「安穏」の世を築くための「天下之草創」を妨げる人々、とりわけ法皇周辺の院近臣や「一切不被知万機」(『玉葉』文治二年七月三日条)という摂政基通や無能な公卿・官僚を排除し、兼実をはじめとする有能な人々を抜擢する人事案を朝廷に呑ませたのである。
文治元(1185)年11月30日、鎌倉から「大蔵卿泰経、刑部卿頼経等、同意行家義経者也、早可被處遠流、一人伊豆、一人安房云々、可付経房之由、仰光長了」という書状が兼実のもとに届けられた。兼実はこれを光長に託して帥卿経房へ付し、経房が法皇の言葉として「任申請早可有沙汰」を返札した。そしてこの状を関東に遣わすよう光長に命じたという(『玉葉』文治元年十一月卅日条)。
兼実の抵抗もむなしく、12月28日深更、兼実への「内覧」は「被宣下」され、翌29日朝には、史頼清、大外記頼業が九条邸に「持来内覧宣旨」(『玉葉』文治元年十二月廿九日条)。ただし兼実は「聊有所思之故」を以て、この内覧宣旨を「各不披見、後自是告仰之日、可持来」と告げて受け取らなかった。この「聊有所思」とは、「明春撰日可見吉書、彼時為又有所思之故、今日所不召見也」ということだった。
兼実はそもそも右大臣の上表が返付されないままに内覧宣旨が行われることに強く反発してきていたが、内覧の宣旨文には兼実を「本官(右大臣)」としていた。これは宣旨文を作成したときがすでに深夜であったため、頼清と頼業の相談によって記入されたものであったが、「此程沙汰、全不可為後難之由、上卿已下議定」であるという。しかし、議定にほぼ不参の兼実は議定の詳細を知らず、「余不知此事、暗被載本官了、更不能申是非、事頗雖不穏、又不及私之進退事歟」と、とくに問題視しない議定の内容に反発している(『玉葉』文治元年十二月廿九日条)。なお、兼実の内覧については、兼実が宣旨を受理しなくともすでに既定事項となっており、翌30日にはさっそく昨夜の「任官解官等」についての聞書が届けられ、兼実は内覧の実務を行っている。
こうした朝廷の動きは北条時政から逐一報告されていたと思われるが、このような中で12月30日、頼朝は「阿闍梨季厳」を「六条八幡宮別当職」に補任した(海老名尚、福田豊彦『「六条八幡宮造営注文」について』、『関東御教書案』「醍醐寺文書之二」295の1)。阿闍梨李厳は「大膳大夫広元子(実際は弟か)」(海老名尚、福田豊彦『「六条八幡宮造営注文」について』)で、北条時政と連携して御所及び仙洞御所の状況把握の拠点として機能したのではなかろうか。なお、この補任は公文所および政所を経ない頼朝直任で、頼朝以降も執権・連署による下知状で補任される通り、鎌倉家と直接的な繋がりを持っていたことがわかる。
年が明けて文治2(1186)年正月1日には、兄・入道関白基房が家司少将忠季を遣わして内覧の慶賀を述べたのを皮切りに、帥卿経房や内大臣公守、そのほか補任の弁官等が慶賀に訪れ「人々多以来」という状況になっており、兼実は好むと好まざるとにかかわらず「内覧」となっていたのである。しかし、五位蔵人定経が兼実のもとを訪れ、法皇や主上の出御に「摂政不被参者」という状況になった場合、どうしたらよいのか(内覧の兼実が参じてもらえるのか)を問うた際には、「雖被下宣旨未受取、又不見吉書、仍如此事不能」と、宣旨不受理を理由に断っており、兼実の内覧は本人が認めないまま、臨時で職務を代行している状況にあった(年末の「任官解官等」についての内覧も本人不受理のままの代行である)。兼実は摂政不参の事態が発生した場合には「是非早経院奏并摂政可進止者」と、早々に奏院し摂政の進退を諮るべしと強く批判している(『玉葉』文治二年正月一日条)。規律の緩み切った朝政を兼実は許せなかったのだろう。法皇や基通だけではなく「当時公相之中、頗為下人」(『玉葉』文治元年十二月廿九日条)とこき下ろした経房卿など、自身の考えと異なる考えや行動をする人々を非難し、自分の信じる考えを押し通すのである。この他人に非情なまでに厳しい性格は、のちに親しい人からも見限られ、真に心を許せる人を持つこともできずに自らの政治生命を絶つ元となってしまうのである。
さて、その頃鎌倉では正月3日、義経謀反のこともあって延期されていた頼朝の従二位陞爵の御直衣始が鶴岡山八幡宮寺で行われた。左馬頭能保や前少将時家もこれに参列している(『吾妻鏡』文治二年正月三日条)。頼朝に供奉したのは「武蔵守義信、宮内大輔重頼、駿河守広綱、散位頼兼、因幡守広元、加賀守俊隆、筑後権守俊兼、安房判官代高重、藤判官代邦通、所雑色基繁、千葉介常胤、足立右馬允遠元、右衛門尉朝家、散位胤頼等」であった。
 |
| 鶴岡八幡宮 |
参詣ののち、八幡宮寺にて埦飯が行われ、供奉人が宮寺庭に左右に居並んで座ったが、このとき散位胤頼は父・千葉介常胤に相対して着座した。これを「人不甘心」と見咎めたが、これは「常胤雖為父六位也、胤頼者雖為子五品也、官位者君之所授也、何不賞哉」という頼朝の指示によるものであった。胤頼は常胤子息中でもっとも頼朝と深く関わり、「文覚在伊豆国時令同心、有示申于二品之旨、遂挙義兵給之比、勧常胤、最前令参向、兄弟六人之中殊抽大功者也」とある通り、頼朝に挙兵を勧め、常胤にも参戦を呼びかけた大功ある者として頼朝の信頼は殊に厚かったが、この逸話は胤頼を重んじたというよりも、法皇をはじめとする朝廷重視の姿勢をアピールするものであろう。
正月9日、兼実はようやく内覧宣旨を受理し、家司の伊予守源季長が奉行として儀式が執り行われた(『玉葉』文治二年正月九日条)。大外記頼業が内覧宣旨を持参して兼実が披見ののち季長が持って退出し、その後、吉書始の儀が行われた。伊予国は兼実の知行国であったため、家司の源季長が伊予守となったとみられる。
正月13日、兼実の歌師・藤原俊成入道は兼実の内覧の補任の賀を祝す歌を送っている(『玉葉』文治二年正月十三日条)。
ところが兼実は、
と返歌している。摂政在職中に、別に内覧が補された例はなく(混乱を招く)先例なき内覧に就任することを厭う姿がありありと浮かび上がる。
文治二年は「法皇今年六十御宝算」であり、正月21日、頼朝は「上絹三百疋、国絹五百疋、麞牙等、此外斑幔六十帖」を京都へ発遣した(『吾妻鏡』文治二年正月廿一日条)。そのほか「去年被言上条々、悉以被施行之上者、流刑等事、早可被行之由被申之、大夫属入道令執沙汰此間事」と指示している。贈り物と同時に、年末に要求していた朝廷人事が施行された上は、流刑も早々に行うよう「大夫属入道」に沙汰させたのである。この進物は2月12日、「越前介兼能」が使者として京都へ参着し、『吾妻鏡』とほぼ同内容の「頼朝別進法皇、上絹三百疋、国絹五百疋、幔三十帖」が献じられたことが報告されている(『玉葉』文治二年二月十二日条)。
このような中で、正月26日に「摂簶事、早可被宣下之由」を要求する頼朝の飛脚が入洛した(『吾妻鏡』文治二年正月廿六日条)。これは「当執柄依伊予守義経謀逆事、有雑説等之故」であるが、後述の通り「当摂政殿基通本自為平氏縁人、関東有御隔心之處、去年義経顕逆心之時給追討 宣旨、偏依彼御議奏之由風聞」(『吾妻鏡』文治二年二月廿七日条)とともに、兼実の「和漢才智頗令越人給」を主な理由としている。また、申状に実際に記されていた内容は「摂簶事」だけではなく、正月28日に花山院大納言忠雅が九条邸を訪問して兼実に披露した「去此自鎌倉飛脚到来、今朝被仰遣御返事」にあるが(『玉葉』文治二年正月廿八日条)、ここには、
(一)経房不可下向 先日為御使可向之由示送云々、其返事歟
(二)甘苔六百帖所進事
(三)去冬奏聞条々任官解官、只雖奏愚案之趣、所詮可在勅定事
(四)義経謀反之間、追討宣旨事、不起自叡慮之由聞披之由事
とあった。翌29日には「泰経不過之由、殊被仰遣、又北面下臈等、糸惜思食之由有仰」という内容の院宣が下されたという(『玉葉』文治二年正月廿九日条)。これは法皇が頼朝の要求する泰経ら院近臣および院北面の人々の解官を拒否する旨を伝えたものであった。
その後、兼実は正式に内覧として政務に携わるが、摂政基通は相変わらず出仕を拒んでいた。このような時に兼実のもとへ頼朝の「書札有三通」が届けられていた。いずれにも摂政基通の行状が記されていたという。兼実は左少弁定長を通じて頼朝書札を法皇に奏聞している。その頼朝書札には摂政基通に対する意見として、
という内容が記されていた。つまり頼朝は摂政基通を無能と断じて改易するよう要求してきたのである。この頼朝の要求に、法皇は「置文之条不可然、其事不可有其益、無故不及改易、於今者如本内覧文書、叙位除目毎事示合右大臣可被行之由」と、春日社神前での置文による摂政の改変を拒むと同時に、院使定長を摂政基通に遣わし、兼実とともに政務を行うよう指示をしたという(『玉葉』文治二年二月十三日条)。
しかし19日、この異例の内覧・摂政の並立に反発する兼実は「内覧辞退」を奏上する。これを受けた法皇も、自分の考えは13日に返答した通りであるとして「於今者、朕天下事不及口入、摂政相共可有御沙汰也」(『玉葉』文治二年二月十九日条)と、兼実の辞意を請けず摂政基通とともに政務を見るよう返答している。詳細には「辞退之由、被仰遣関東事ハ、一切不可有事也、朕不可知天下、於今者、摂政与汝示合、可執行万事、此旨被仰摂政了、汝又可示摂政」(『玉葉』文治二年二月廿六日条)である。さらに摂政にもこの旨を言い含めており、摂政基通も「毎事無隔心之躰可被示合」といい、法皇は「凡不可有異議」と言い切る。この法皇の書き様に、兼実は「此條天気之善悪不見得、大略猶以不快歟」と法皇はおそらく不快であろうと察している。
結局、「自去冬以来之次第、大概示之、凡此職無例、又無其用之故」とあるように、摂政と内覧が両立する前代未聞の様相はその後も続くことになるが、法皇が摂政基通に命じた件についても改善が見られず「日来閣下不覧文書、近日僅雖有御覧文書、又無成敗、其上微臣又不能成敗、法皇不可知食天下之由有仰、両執政共相譲、無成敗之間、近日朝務偏如無」とあるように、兼実は摂政基通と法皇の対応が朝務の停滞の原因であると批判する。ただ、兼実は法皇と摂政を非難する一方で、先例に拘る兼実自身も積極的に改善しようという様子は見られない。この解決策として「此条尋其源、只在愚臣之故、仍雖致辞退、無勅許、此上次第何様可存哉、雖自今以後、万事於無御成敗、在臣又不判是非左右之間、進退維谷、請承分明之御答、欲存愚暗之進退者」と主張する(『玉葉』文治二年二月廿六日条)。摂政と内覧の二人が存在し、意思決定の所在があいまいで混乱のもととなる状況に身を置きたくない兼実の嫌悪ぶりが如実に見て取れる。
ところが、2月26日には「経房卿許密々注送頼朝申状、其趣下官猶可為摂政之趣云々、実不知洛中之有様歟、所謂下官之不祥也、不能左右」(『玉葉』文治二年二月廿六日条)とあるように、頼朝から帥卿経房に兼実の摂政推挙状が届けられる。兼実はこの相変わらずの頼朝の推挙に「実不知洛中之有様歟」と心底うんざりしている(『玉葉』文治二年二月廿六日条)。一方で、先に摂政基通からに遣わしていた政務についての申状に対し、基通から氏家司の藤原高佐が兼実邸に遣わされ「如蒙仰尤畏申、如仰万事事可申合之由所存也、但今暫ハ不可及朝議成敗也、只依院宣時々出仕并文書許ハ雖令内覧、万機ハ不可成敗」と返答している(『玉葉』文治二年二月廿七日条)。しかしこれは兼実が求めた内容からはかけ離れたもので、朝議にも出なければ内覧にも向き合う気がない様子である。兼実は「此条依自院被仰下所令申也、而如今仰者、相違院宣之趣、其条早可令申院給歟、法皇不可知食天下之由有仰、又不可有御沙汰云々、其上一身朝務奉行、更不可思寄事歟」と激怒し、高佐はこの旨を服膺して帰参していった(『玉葉』文治二年二月廿七日条)。
このころ「散位源邦業」が頼朝によって「是為御一族功士下総国、同為御分国之間、被挙申之」と、御分国「下総守」に推挙された(『吾妻鏡』文治二年二月二日条)。具体的な活躍はとくに見られないが「功士」であったという。その出自は清和源氏ではなく醍醐源氏であるが、「源」氏という認識であろう。邦業は「院北面衆」(『吾妻鏡』建久元年十二月一日条)として法皇に仕える身でもあったが、頼朝とも深く交流し、のちに家司中原広元とともに初期の鎌倉殿政所別当となっている。ちょうどこの頃、常胤は下総国に帰国しており、邦業の目代との間で政務上の調整が行われたと思われる。
藤原経邦――――藤原盛子
(皇后宮大進) (贈正一位)
∥――――+―藤原伊尹 +―藤原基実
∥ |(摂政) |(摂政)
∥ | |
藤原師輔 +―藤原兼通――藤原顕光 +―藤原忠通―+―藤原兼実
(右大臣) |(関白) (左大臣) |(摂政) (摂政)
| |
+―藤原兼家――藤原道長――藤原頼通――藤原師実――藤原師通――藤原忠実―+―藤原頼長―――藤原師長
|(摂政) (摂政) (摂政) (関白) (摂政) (摂政) (左大臣) (太政大臣)
|
+―女子 +―源忠賢 +―源盛業
∥ |(左兵衛佐) |
∥ | |
∥―――+―源守隆―――源長季―――源盛長―――源盛家―+―源盛定――+―源忠光――――源時長―――源家長
醍醐天皇―+―源高明 (少納言) (少納言) (淡路守) (摂津守)|(少進) (筑後守) (大膳亮) (但馬守)
(左大臣) |(左大臣) |
| +―源盛邦――+―源家季 +―源政綱
| | |
| | |
| +―源邦憲 +―源盛朝
| | |
| | |
| +―源邦業―+―源業政――+―源長政
| (下総守)| |
| | |
| | +―源俊政
| | |
| | |
| | +―源基政
| | |
| | |
| | +―源為政
| |
| |
| +―女子
| ∥――――――藤原朝光
| ∥ (伊賀守)
| 藤原光郷
| (散位)
|
+―盛明親王─―源則忠――─源道成─――源兼長─――源清長─―――源俊兼─―源季兼――――源季長
(四品) (左京大夫)(右馬権頭)(右兵衛佐)(勘解由次官)(土佐守)(石見守) (伊予守)
2月13日、鎌倉に在京の北条時政が遣わした「当番雑色」が参着して「北條殿状等、静相催可送進」した(『吾妻鏡』文治二年二月十三日条)。2月18日には「予州隠住多武峯事風聞」(『吾妻鏡』文治二年二月十八日条)が鎌倉へ伝わっている。後年の記述とみられるが、義経は11月29日までは多武峰にあったという(『吾妻鏡』文治元年十一月廿九日条)。また「依之彼師壇鞍馬東光坊阿闍梨、南都周防得業等、有同意之疑」も鎌倉へ報じられ、頼朝は得業坊を「可被召下之」と命じている。そして3月1日、「予州妾静」が「母礒禅師伴之」って鎌倉に到着し、主計允藤原行政の沙汰において、頼朝が信頼を置く雑色「安逹新三郎宅」に招き入れられた(『吾妻鏡』文治二年三月一日条)。
この頃、諸国の「不論庄公、可宛催兵糧段別五升」(『玉葉』文治元年十一月廿八日条)は、当然ながら地頭の狼藉が発生するなど混乱も多く、兼実が激怒したように権門庄園からの反発はとくに強かった。もともと兵粮米については「所宛諸国之兵粮、皆可募官物内之由、下知之間、庄公之運上不通、人命殆不可待元正」(『玉葉』文治元年十二月八日条)と、諸国の宛行分は公領の官物より、庄園からは貢物から徴収された。この兵粮米の(再)施行により公領庄園問わず運上が滞り、人々の生活にも強い影響が及ぶことが懸念されていたが、その懸念通り、施行後さっそく高野山衆徒が地頭の狼藉を訴える事件が起こり、文治2(1186)年正月29日、「紀伊国高野山御庄々」は「件御庄々、彼御山所被仰下也」で「可早令停止兵粮米并地頭等事」が指示されている(『吾妻鏡』文治二年正月九日条、『鎌倉遺文』四二)。そのほか丹波国「弓削庄」や肥前国「神埼御庄」も同様に沙汰されている(『吾妻鏡』文治二年二月十九日条)。
なお、「高瀬庄」についても頼朝から「不可交武家沙汰之由」が北条時政へ下されていたが、時政は「注所存於折紙、被付帥中納言」と、自らの存念を帥卿経房へ伝えている(『吾妻鏡』文治二年正月十一日条)。それは「高瀬庄事、雖令究済兵粮米候、於地頭惣追捕使者被補候畢、但於狼藉者可令停止候也」というものであった。高瀬庄は河内国にあり、義経捜索の最重要地点の一つであったため、頼朝から庄園に対する地頭の介入が禁じる指示はあったものの、現実的な対応措置をとる必要から、時政は兵粮米徴収は行わないが、地頭の設置と惣追捕使の補任については行う旨を伝えている。ただし、地頭の運上等への狼藉は禁じることも付した。時政は頼朝からの意見であっても修整しているが、時政に付された権利か独断かは不明である。
これらの状況報告を受けた頼朝は、2月28日、時政に伝達する条々を決定(『吾妻鏡』文治二年二月廿八日条)し、京都へ発している。
一 仰五畿七道諸国庄園免除兵粮米未進可令安堵土民事
依此米催事、民戸殊費、於今者、殆無乃貢運上計之由、頻有領家訴之間、及此儀、然者、賦遣使者可触廻之由、可被仰北条殿者
一 肥前国神崎御庄可停止武士濫行事
可被仰天野藤内遠景之許者
一 上皇御潅頂用途早可沙汰進上事
一 筑後介兼能使節間、有称無実已背叡慮之由、粗就承之、永不可召仕事
以上両条、可被申師中納言経房者
まず、兵粮米については「仰五畿七道諸国庄園免除兵粮米未進可令安堵土民事」と、「諸国庄園」の兵粮米の未進分を免除して、庶民を安堵するよう指示した。兵粮米の徴収は民の疲弊を招くもとであり、領家からは運上が全く停止してしまっているとの訴えが頻繁であったため、兵糧米未進分を免除する旨の使者を遣わして対処するよう、時政へ命じている。これにより、諸国・庄園からの兵粮米徴収は撤回されることとなる。
次の神崎御庄については院御領であり、予てより法皇は経房を通じて時政に兵粮米の停止を求めていたが、2月22日に時政は「且任府宣、且相尋子細、可致沙汰之由、被示遣天野藤内遠景、其上被申関東」と返答している。ただし28日時点で頼朝はこの事態を把握していることから、時政は経房に返答すると同時に関東へ使者を送ったとみられる。
続いての二条は、法皇の熊野詣の院宣(2月9日鎌倉到来)の用途進上と、法皇への六十賀詞を届けた使者・兼能の失態についての処罰についてである。兼能の失態は具体的には記されていないが、頼朝が贈った贈物の数と実際に届けられた数が幔だけ著しく減っており(斑幔六十帖→三十帖)、兼能が紛失した可能性があろう。ただ、帥卿経房は「兼能事、返々不便候、別奇恠思食事不候、傍輩沙汰之間、被仰出事許にて候歟」と、彼がとくに問題のある人物ではなく兼能の傍輩が話したことを頼朝が真に受けたことによるものではないかと指摘している。それどころか、兼能は「院中如召次訴訟なとにても、随分抽忠、為人不悪事等候」と評価は非常に高かった。「大事御使をはせて候なん」と、大事の使者に用いるべき人物であると進言している(『吾妻鏡』文治二年四月五日条)。
この頃、洛中守護の北条時政は、積極的に義経追捕と洛中治安維持、諸国地頭の狼藉停止を進めており、この在京中に「九條入道大納言光頼侍」であった「右近将監家景」(『吾妻鏡』文治三年二月廿八日条)と知己となり、「試示付所々地頭事之處、始終无誤」という実績をあげたという。家景は平季貞の子・粟田兼信の子(『岩手県史』)とされ、時政が頼朝に推挙して文治3(1187)年2月に鎌倉に招いている。
時政は洛中に跋扈する盗賊らに対しては強硬に対応し、「正月廿三日、同廿八日、洛中群盜蜂起、則搦獲之」(『吾妻鏡』文治二年二月十三日条)と、二度にわたって群盗蜂起を鎮圧し十八人を捕縛した。その後「於六條河原刎群党十八人首、凡如此犯人者不可渡使庁、直可處刎刑」(『吾妻鏡』文治二年二月一日条)とあるように、捕縛した十八人の賊を検非違使に付さず、時政の指示で六条河原に刎首している。
時政はこうした武断的な能力には長けていたが、公卿衆との折衝は不得手であったとみられ、頼朝もこれを感じて、相談役として鎌倉に置いていた左馬頭能保を緊急で京都に戻し、時政と替えることを決定する。頼朝は「典厩御在鎌倉者、諸事被申合間、雖為至要、当時於京都、巨細無人于媒介、仍令急給」(『吾妻鏡』文治二年二月六日条)と、時政の折衝手腕に不安を抱き、能保に「神仏事并禁裏仙洞等事、節会除目及予州事、可被触申于議卿事等、注條々具示付給」という朝務折衝への期待がみえる。そして2月6日、「左典厩能保帰洛、相伴室家姫公二人等」と、鎌倉を発って帰洛の途に就いた(『吾妻鏡』文治二年二月六日条)。この「姫公二人」は、のちにそれぞれ藤原良経、藤原公能の正室となっている。能保一行が入洛したのは2月20日前後と思われ、2月24日、頼朝からの「左馬頭能保可被任衛府督之由」が経房を通じて奏院されている(『玉葉』文治二年二月廿四日条)。これは能保を検非違使別当とするための布石と考えられるが、衛門督の要職に欠員があろうはずはなく、法皇も頼朝の無理強いに「而当時無闕、何様可被行哉」と兼実に下諮している。これに兼実は「私不可申左右、只可有御定、又可申摂政」と、法皇と無責任な摂政基通へ判断を丸投げした。なお摂政には法皇からも「被命旨同前」が下されたが、結局、この頼朝の要求は認められなかった。
3月1日、時政は「各為令遂勧農候、可令辞止之由所令存候」により「七ケ国地頭職之條」を辞止する申状を帥卿経房へ言上し、経房から左少弁定長へ付されて奏聞された(『吾妻鏡』文治二年三月一日条)。
なお、時政の要望の条々は、実際にはこれ以前に上表されていたが、重ねて経房へ託されたものである。この「七ケ国」は「近国等可為件武士之進止」(『玉葉』文治元年十一月廿五日条)とあるように、時政の施政下に置かれた五畿周辺であろう。時政が抵抗もなく辞止していることから、これはいわば洛中守護に付帯する地頭職であって、義経と同様の権限であったのではなかろうか。ただ、これは「洛中守護に必ず付帯するもの」ではなく、やはり頼朝の進止に属するものであったと思われ、時政の帰倉の決定に伴い、軍事的な緊張が低下した畿内にあっては「勧農」が優先されることとなったと思われる。ただし「惣追捕使」は行家義経の件が解決していないために守補する措置が採られたのだろう。おそらく時政の帰倉決定も、軍事的緊張の緩和と朝廷内の粛清完了に伴うものであって、2月28日の使者派遣(兵粮米の未済分徴収停止)以前に七ケ国地頭職の廃止を時政へ指示していたのであろう。2月20日頃に到来したと思われる時政召還の指示とともに、この旨が指示されていたのかもしれない。ただ朝廷も「惣追捕使事、雖替其名、只同前歟」とあるように、時政が辞止を奏上した「七ケ国地頭職」との違いが理解できていなかった様子がうかがえる。
(一)時政給七ケ国地頭職者、各為令遂勧農候、可令辞止之由所令存候也
(二)於惣追捕使者、彼凶党出来候之程、且為承成敗、可令守補之由所令存知也
(三)凡国々百姓等、兵粮米使等寄事於左右、押領所々公物之由、訴訟不絶候也、且糺明如此等之次第、若兵粮米有過分者、即糺返件過分、又百姓等令未済者、計糺田数、早可令究済
※諸国の田堵等が兵粮米分と称して公物を押領して訴訟になることが頻発しており、時政はその状況を糾明し、過徴分の返却、未済分の徴収を厳正に行うこと旨の御下知を法皇に求めている。なお、この時点では2月28日の兵粮米未済分の免除を指示する使者は当然入洛しておらず、時政は頼朝の意思をまだ知らない。
(四)没官之所々、蒙 院宣并二位家仰候之間、可令見知之由、同所令存也
時政は「七ケ国地頭」は辞止するが「惣追捕使」は「彼凶党出来候之程、且為承成敗、可令守補之由所令存知」として守補すること、兵粮米は前述の通り厳正な返付徴収、没官領は「院宣并二位家仰候之間、可令見知之由、同所令存也」という申文をまとめ、「大夫属殿(帥卿経房の家司か)」に送っている。
また同日、右大弁光長が「九郎行家追討宣旨」を内大臣実定邸に持ち向かい、これを下知したことを兼実に報告している(『玉葉』文治二年三月一日条)。この宣旨は鎌倉へも発遣され、3月14日に鎌倉に到来している(『吾妻鏡』文治二年三月十四日条)。
翌3月2日、「今南、石負庄兵粮米」を停止すべしとする院宣が帥卿経房から時政へと伝えられた(『吾妻鏡』文治二年三月二日条)。
また、左少弁定長が申状に基づく法皇の「内々御気色」を時政に伝えてきたが、
というものであった。
その後、2月28日に鎌倉を発した「仰五畿七道諸国庄園免除兵粮米未進可令安堵土民事」の指示が時政のもとに届き、時政は、兵粮米の未進分については免除する趣旨を奏聞したのだろう。3月7日に正式に院宣を定長が承り、帥卿経房から時政に下されている(『吾妻鏡』文治二年三月七日条)。院宣は、
という内容であり、兵粮米の問題は3月2日の状況とは変わり、解決されていたことがわかり、3月16日に頼朝が京都に派遣した文書でも「諸国兵粮米催事、漸可被止之由、被仰北條殿」とある。
文治2(1186)年3月10日、頼朝から「摂簶事重奏院」が行われた(『玉葉』文治二年三月十日条)。これは2月27日に頼朝が雑色安達新三郎を遣わせたもので「可被下摂政詔於右府之事在其内歟」という(『吾妻鏡』文治二年二月廿七日条)。頼朝が兼実を推す理由について「和漢才智頗令越人給」を挙げ、「当摂政殿基通本自為平氏縁人、関東有御隔心之處、去年義経顕逆心之時給追討 宣旨、偏依彼御議奏之由風聞、仍可被挙申之趣」ことを「内々被啓右府」という。兼実はこれまで記す通り摂政就任をひたすらに拒んでいるが、頼朝は「而不可叶時宣之旨、右府雖有御猶予、遂被申之歟」(『吾妻鏡』文治二年二月廿七日条)と、事情は分かっているが敢て推挙しているという。
この頼朝申状は、摂政の改易がなされない状況にしびれを切らした頼朝から、法皇および摂政基房へ宛てられた強い圧力であろう。そして法皇は摂政基房へ万策尽きたことを伝えたろう。翌11日早旦、定長から家司右大弁光長のもとに「摂政氏長者事、今日可被仰下」という院宣が届けられた。この一報を伝え聞いた兼実は突然のことに「驚思無限」であった(『玉葉』文治二年三月十一日条)。そして昼頃、正式な院使として頭右中弁源兼忠が父の前中納言雅頼を伴って九条邸を訪問し、法皇の言葉として「摂政藤氏長者事、可被宣下之由可申案内旨有仰、於長者事者、重而所被辞申也」と伝えた。
兼実は「摂政藤氏長者事、可被宣下之由」を聞き、「此事承驚不少、思緒何事哉、就中、本人上表事未聞、旁以為恐、忽宣下事、専不可(有?)事也」と述べている。ここからこの時点で摂政基房はまだ上表していなかったことがわかる。その後、兼実は左少弁定長を招いて「条々子細」を述べて「■念不快并天下政猶不及■素者、天下奉行弥以不可叶、非此時者雖申披存旨、宣下之後令申者、可無其詮、仍就此仰所述思緒、若悔非帰正、治政有御贔屓者、不顧身之不省、可披腹心歟、其事不可然者、此大事一切所不致也、更以不可被宣下」と、法皇へ対しての治世に対する姿勢の変化を強く要求すると同時に自らも身を捨てて政務を行う覚悟を示し、法皇にその覚悟がなければ私は一切の政務を放棄するので摂政ならびに氏長者の宣下を行わないよう迫ったのである。
夜に入り、院使として左少弁定長が兼実邸に遣わされたが、法皇の答えは「其趣太以神妙、敢無逆鱗、実以不可説也」という意外なものだった。子細は「全不被置御心天下事、細々臣務一向可申沙汰也、於大事者又争不聞食哉、被直乱世之条尤神妙、頼朝之所申、頗不当事等雖相交、又於有理事者、何無御承引哉、凡遁万機御事、非依此大事、年来之御畜懐也、而前摂政一切無承諾之間、自然所行也、於今者、一向可申沙汰之由也、御定甚以委細、不遑記録」という返事である。定長の言う「此事偏為春日大明神御計之由思食、賢所見給也」という言葉にも背中を押され、兼実はようやく摂政を受諾した。頼朝からの推挙は只管に固辞したが、頼朝追討宣旨の失策により法皇は窮地に陥り、頼朝は朝廷人事へ介入。その要求のままに宣旨が下され、兼実は形式上、治天からの強い推挙による任摂政となり、長年の悲願が叶ったことで「神仏冥助、紅涙満眼」という感想を遺した(『玉葉』文治二年三月十一日条)。
そして3月12日に摂政詔書宣下ならびに「長者事、一座事」の宣下を行うよう院宣が下され、13日巳刻、大外記頼業が「氏長者宣旨」を九条邸に持参して、3月16日に摂政詔が下された。こうして摂政ならびに氏長者についた兼実は、政所始儀、朱器御覧、諸方吉書、家司・職事補任、興福寺長者宣など、様々な儀式を行ったのち、24日、始見厩馬の儀を行い、厩関係の人事等を行った。
朝廷人事の完了を見届けると、3月23日に時政は「可帰関東」ことを奏聞した(『吾妻鏡』文治二年三月廿三日条)。法皇は「公家殊被惜思食」を帥卿経房から時政に伝奏させている。法皇は時政の治安維持の成果を認めていたと思われ、不在を不安視したとみられる。法皇は「仍洛中事、可示付何人哉」という勅問があり、時政は京中の守護のために武士を留めること、ならびに左馬頭能保を洛中守護に依頼したことを帥卿経房に付して返奏している。
鎌倉御返事、謹給預候畢、早可令進候也、時政下向事、自鎌倉殿度々被仰下候之條、廿五日一定之由、所令存候也、云天王寺御幸、云京中之守護、可差留武士等候事、左馬頭殿能保御在京候、不可有御不審候、且此両條可令申含給候歟、以此旨可令申上給候、時政恐惶謹言
三月廿三日 平時政〔請文〕
そのほか法皇は「且其身雖令下向、差置穏便代官、可令執沙汰地頭等雜事之旨」を度々時政に要請したが、時政は「敢無其仁、重一旦 勅定、差置非器代官等、若有現不当之事者、還可有其恐歟」として、再三にわたって固辞した(『吾妻鏡』文治二年三月廿四日条)。ただし、洛中警衛については「平六時定」を残している。
翌3月24日、時政は鎌倉に戻るに際して、諸卿邸を訪問して暇乞いをしていたようである。その後、前宰相兼雅卿が九条邸を訪れて兼実と語らい「北条時政頼朝妻父近日珍物歟、来、明曉下向関東」と述べている。また「以季長朝臣仰聞条々事、件男又進籍与季長朝臣、其次第可咲云々、田舎之者尤可然、物体太尋常也」(『玉葉』文治二年三月廿四日条)という。兼雅は兼実嫡子・右大将良通の舅に当たり、兼実とは親密な関係にあった公卿である。時政の関東下向指示は2月27日に鎌倉を発った安達新三郎が齎した頼朝書状にあり、「北條殿早可被帰参之由被仰遣、於関東事可有御談合事有数、洛中守護者已可被仰左典厩能保之故也」といい、洛中守護は左馬頭能保が担うこととなった(『吾妻鏡』文治二年二月廿七日条)。
頼朝の帰国指示を受けたのちも、一月にわたって在京していたのは、院宣への対応として、惣追捕使としての所役、没官領の沙汰、能保への洛中守護の継承等があったと思われ、3月27日、鎌倉への帰途に就いた(『吾妻鏡』文治二年三月廿七日条)。このとき、時政は「仍為警衛洛中、撰定勇士被差置之」措置を取り、平六傔仗時定以下の三十五人の御家人が選抜され、交名が帥卿経房に提出されている(『吾妻鏡』文治二年三月廿七日条)。
注進 京留人々
合
平六傔仗時定(平六傔仗時定) あつさの新大夫(梓新太夫)
のたの平三(野太平三) やしはらの十郎(矢之原十郎)
くはヽらの次郎(桑原二郎) ひせんの江三(肥前江三)
さかを四郎(坂尾四郎) 同八郎(坂尾八郎)
ないとう四郎(内藤四郎) 弥源次
ひたちはう(常陸房昌明?) へいこの二郎(?)
ちうはち(中八) ちうた(中太)
うへはらの九郎(上原九郎) たしりの太郎(田尻太郎)
いはなの太郎(岩名太郎) 同次郎(岩名次郎)
同平三(岩名平三) やわたの六郎(八幡六郎)
のいよの五郎六郎(野与五郎六郎) 同三郎(野与三郎)
同五郎(野与五郎) しむらの平三(志村平三)
とのおかの八郎(殿岡八郎) ひろさわの次郎(広沢次郎)
同弥四郎(広沢弥四郎) 同五郎(広沢五郎)
同六郎(広沢六郎) かうない(江内)
大方の十郎(大方十郎) 平一の三郎(平一三郎)
いかの平三(伊賀平三) 同四郎(伊賀四郎)
同五郎(伊賀五郎)
以上三十五人
三月二十七日 平(判)
時政の帰国に伴い、頼朝から洛中守護を託された左馬頭能保は、時政が帰国した27日の夜、九条邸を訪れて兼実と対面。兼実と「談関東子細等」した(『玉葉』文治二年三月廿七日条)。
4月1日、東下中の時政は尾張国萱津宿で、3月16日に鎌倉を発した京都への使者・山城介久兼と出会った(『吾妻鏡』文治二年四月一日条)。頼朝は兵粮米停止に関する報告のほかに、法皇が求めていた前大蔵卿泰経、前刑部卿頼経、下北面らの宥免については、「其許否者所詮可随御計候、不起自御意」としながらも、「但 君者雖為不知食候事、已称御定、令下 宣旨候之條、無謂所行候歟」と、天下を治めずと御定しながら頼朝追討の宣旨を下さしめたことはいったいどういうことかと、苦情を帥卿経房に伝えている(『吾妻鏡』文治二年三月十六日条)。法皇に対する直接的な強い抗議であるが、時政はこの旨を受けつつ、「此條ハ自君之御心不発候事にて候ヘハ、於今者只可為 君御意之由、所被仰下候也者」(『吾妻鏡』文治二年四月一日条)と、言葉を和らげた副状を認めて久兼に託しているが、この時政の取成の副状からは逆に凄味が感じられる。
4月2日、頼朝は伊豆配流中の高階泰経の帰京を許可する旨を京都へ発し、同時に「北面之輩誇 朝恩有驕逸之思、殊加御誡、可召仕之由」を伝えさせている。16日の申状は法皇への強い諫奏であるとともに、泰経の赦免を匂わすものであった。
4月13日、北条時政が鎌倉に帰参した。時政は幕府に参上して頼朝に面会し、朝廷とのやり取りの子細を報告している(『吾妻鏡』文治二年四月十三日条)。
一方、京都では北条時政の帰国後、鳴りを潜めていた群盗がふたたび暗躍を始めたという。「北條殿被帰関東之後、洛中之狼藉不可勝計、去月廿九日夜、上下七ケ所群盜乱入」という大規模な狼藉に発展していた。法皇としては、治安維持のために時政の在京を依頼するも、時政は頼朝の命を含んで帰京してしまい、残された武士らでは重みも力もまったく比較にならず、このような状況になってしまったと嘆いている。義経行家らが洛中にいるという風聞もあるが、これが事実であったならば一向に捕縛できない理由は何なのだろうか。延暦寺衆徒の中に義経等と結んでいる輩がいるというが、証拠もなしに無理強いに捜索すれば天台仏法の衰退を招くだろう。ただただ嘆くばかりであるとの院宣を認め、5月6日に頼朝使・紀伊刑部丞為頼に託して関東に下し(『吾妻鏡』文治二年五月十三日条)、5月13日、鎌倉に到来した(『吾妻鏡』文治二年五月十三日条)。
世上嗷々事、定以令聞及給歟、閭巷之説雖不可有御信受、如此人口先々不空歟、時政在京、旁依穏便思食、於他武士者、縦雖召下於彼男者、勤仕洛中守護可宜之由、度々被仰遣之上、直被仰含畢、然而猶以下向之間、如此事等出来歟、義経行家等在洛中之由風聞、事若実者、天譴已至歟、何不被尋出哉、或説、叡山衆徒之中、有同意之輩云々、中々如此披露、若為実事者、為朝家神妙事歟、日来雖被仰所々、無聞食出事、於今者、被捜尋有其便歟、但以無証拠事搆出者、適所残之天台仏法魔滅之因録歟、云彼云是、旁歎思食者也、如此事出来ぬれハ、奉為君無曲事のみ出来ハ、旁驚 思食者也、去月廿日御消息使侍為頼、一昨日到来、付其便、雖仰遣此旨、且有懈怠之疑、且為散不審、重所被仰也者 院宣如此、仍執啓如件
五月六日 経房
謹上 源二位殿
5月10日、権中納言定能が院使として兼実邸(兼実は摂政・氏長者宣下以降は直盧や九条亭への宿泊が続いたが、4月28日に右兵衛督隆房から借用していた「冷泉万里小路家(中京区俵屋町五丁目)」に移っている。修理して使用していたが、前年の大地震で大きく破損したため、ほとんど新造となっていた。九条邸は子息の良通・良経が居住したとみられる)を訪れ、院からの諮問を受けている。「義行々家等在射山并前摂政家中、仍可捜求之由事」と、義経・行家が院御所や前摂政基通邸に匿われているとして、武士等による捜索の対象とされていた。『玉葉』では5月10日時点で義経を「義行」としているが、『吾妻鏡』によれば、義経が「義行」と改名させられたのは二か月後の閏7月10日のこととされ、「義経者与殿三位中将殿良経依為同名、被改義行之由」(『吾妻鏡』文治二年閏七月十日条)とある。これは『吾妻鏡』の記述が後世に記された際に時期を誤ったものであろう。法皇は「前摂政の可夜打」の噂を気にしていて、左馬頭能保を院御所に召し、丹後局を通じて「前摂政ハ殊糸惜ク思食人也、万人云付虚言云々、尤不便、耻かましき事なとなき様ニ可致沙汰、毎時不可見放」と縋りついている(『玉葉』文治二年五月十一日条)。
このような中、5月15日辰刻、家司光長からの書状が齎され「和泉国搦得備前々司行家了、北条時政代官平六傔仗時貞相親者国人相共捕之也」とあった(『玉葉』文治二年五月十五日条)。これを読んだ兼実は「天下之運報未尽、可悦可悦」と喜悦の気持ちを認めている。昨年11月5日の大物浦での遭難後、行家は義経と別れて本拠の和泉国、河内国の辺りでの活動が伝えられ、北条平六時定らが捜索を続けていたようである。その後、行家が「和泉国一在庁日向権守清実」の「小木郷宅」に匿われているという密告があり(『吾妻鏡』文治二年五月廿五日条)、5月12日、平六時定らが「小木郷宅」を取り囲んだ。
行家は襲撃を知ると「迯到後山、入或民家二階之上」と、「小木郷宅」の後山の民家二階へと逃れたが、そこを「時定襲寄於後、昌明競進於前」と、平六時定が後ろ、常陸房昌明が前から攻め懸ると「備州所相具之壮士一両輩雖防戦」と、行家郎従の勇士「駿河二郎」(『玉葉』文治二年五月十六日条)が一人立ち塞がって防いだが、衆寡敵せず常陸房昌明に捕縛された。そこに平六時定が加わり、行家の首を刎ねたという(『吾妻鏡』文治二年五月廿五日条)。
行家が住んでいた在庁清実の小木郷宅は後背地が山だったことがわかるが、近木川沿いの千石橋西側の山地(貝塚市橋本)であろうか。行家の首は翌16日に入洛するが、これに先立って院使として左馬頭能保が九条邸を訪れて「行家首渡大路、可給使庁歟如何」と諮問、兼実はいつもの如く「申院可随仰者」と返答している。その結果、翌17日に「行家首遣関東」とされ(『玉葉』文治二年五月十七日条)、大路渡しは行われなかった。なお、『吾妻鏡』では行家子息の大夫尉光家も同じく討ち取ったとあるが、『玉葉』では昨年11月5日に吹き戻されて「於家光者梟首了」とされている。
5月20日、兼実は異母弟「奈良僧正(興福寺別当信円)」から「被召送南都寺僧大進君、行家兄弟云々、若無指犯過者、及恥辱之条、尤不便之由被示」と、興福寺僧の大進君が行家の兄弟であるという理由で捕縛される恥辱を受けたという報告が入った。これは勅命による捕縛ではなく「平六兼丈時貞、以私使者召之」であるという(『玉葉』文治二年五月廿日条)。兼実はただちに左馬頭能保に使者を遣わし、「御寺事、偏長者之最也、若有犯人者、触長者自氏院下知御寺、可召進也、武士直以郎従譴責之条、太可謂狼藉、如此之事尤可被禁遏也、兼又所被召之僧、自長吏僧正之許所被召送也、若可献歟、但為寺僧之者、無指過怠者及恥辱之条、尤不便歟。委被尋被召置之犯人等、指而有犯科者非此限、当時在兄弟経光法師許、母同行家、父同経光、可被重令申者」と強い懸念を伝えた(『玉葉』文治二年五月廿日条)。これを受けた能保は、興福寺への狼藉は初耳で大変驚いている旨を伝えるとともに、今後はこのような狼藉は停止させることを約束している。ただし、大進君は頻りに異母兄経光法師のもとを訪れているので、もしまた何か問い質すことがあった場合は兼実へ言上してから行う旨を述べた。
藤原忠清―――女子
(淡路守) ∥――――――源義朝―――――源頼朝
∥ (左馬頭) (前右兵衛権佐)
∥
∥ 湛快――――+―湛増
∥ (熊野別当) |(熊野別当)
∥ |
∥ | 平忠度
∥ |(薩摩守)
∥ | ∥
∥ 行範 +―女子
∥ (熊野別当) ∥――――女子
∥ ∥ ∥
源為義 ∥―――――+―行快
(六条判官) ∥ |(僧都)
∥ ∥ |
∥――――+―鳥居禅尼 +―長詮
∥ |(義朝妹公)
∥ |
某氏―――女子 +―源行家―――+―源光家
∥ (備前守) |(左衛門少尉)
∥ |
∥――――+―経光法師 +―慶俊
∥ | (律師)
∥ |【興福寺僧】
某 +―大進君
一方、義経の行方はつかめなかったものの、鞍馬寺の僧円豪から延暦寺西塔院主法印実詮に鞍馬山内に匿われているという報告があり、実詮から能保に報告がなされた。この報告を能保が院奏するが、法皇は武士派遣は鞍馬山滅亡の可能性があるとして、鞍馬山別当禅師(入道関白基房子)に義経を捕縛するよう入道関白と相談するよう院宣を下している(『玉葉』文治二年六月二日条)。ただ基房入道は法皇の気持ちを知ってか知らずか、早々に武士を遣わすべきことを法皇へ伝えている。その後、鞍馬寺には官兵が入って捜索したが「於本寺、義行不可留跡」であった(『玉葉』文治二年六月四日条)。
6月4日、院使として兼実邸を訪れた右少弁親経は、左馬頭能保の言葉として「可被下宣旨於諸国、兼又土左君云僧、彼寺住侶、義行知音也、付本寺可被召出彼僧」と告げている。兼実はこのことについて「尤可然」として賛成している。兼実の推察としてはすでに義経は逃れ去ったか、もしくは人々の裏をかいて山中に隠れている可能性もあろうと述べている。そして6月6日、近江、丹波、五畿内など二十か国に義経追捕の宣旨が下されることとなる(『玉葉』文治二年六月六日条)。殺害も已む無いが「猶欲擒充」としており、「令搦進義行身」と生捕にすべきこととしている。また、「先搦取母并妹等、問在所之處、称在石蔵之由、遣武士之處、義行逐電了、捕得房主僧了」(『玉葉』文治二年六月六日条)であったという。
また、6月13日に鎌倉へ着いた当番雑色宗廉の報告として「去六日、於一條河崎観音堂辺、尋出予州母并妹等生虜、可召進関東歟由」(『吾妻鏡』文治二年六月十三日条)とあるが、6月6日時点ですでに「先搦取」ていて、尋問の末に岩倉に官兵を派遣してそこの某寺の住持を捕縛して戻っていることから、母常葉と義経義妹(一条長成娘)の捕縛は6日以前であることは間違いなく、『吾妻鏡』の記事は創作の可能性が高いだろう。ただし、「一條河崎観音堂辺」はおそらく「予州母并妹等」の住居であった一条能成邸の近辺であったとみられ、捕縛地は河崎観音堂付近であったのだろう。また、6月22日に鎌倉に着いた能保の飛脚によれば「予州隠居仁和寺、石倉辺之由、依有其告、雖遣刑部丞朝景、兵衛尉基清已下勇士無其実、而当時在叡山、悪僧等扶持之由風聞」(『吾妻鏡』文治二年六月廿二日条)と、風聞に基づいて仁和寺と岩倉に梶原朝景、後藤基清勢が向かったものの誤伝であり、義経は延暦寺に匿われているという風聞があったという。
藤原顕季―――女子
(修理大夫) ∥
∥
藤原基貞―――女子 ∥――――――藤原公教――――藤原実房【三条家】
(信濃守) ∥ ∥ (内大臣) (左大臣)
∥ ∥
∥――――――藤原実行
∥ (太政大臣)
∥
∥ 藤原忠教―女子
∥(大納言) ∥
∥ ∥
藤原公実 ∥――――――藤原公通――――藤原実宗【西園寺家】
(権大納言) ∥ (権大納言) (内大臣)
∥ ∥
∥――――+―藤原通季
∥ |(権中納言)
∥ |
藤原隆方―――藤原光子 +―藤原実能
(但馬守) (大蔵三位)|(左大臣)
| ∥
| ∥――――――藤原公能
| ∥ (右大臣)
| 藤原顕隆女 ∥―――――――藤原実定【徳大寺家】
| ∥ (右大臣)
| 藤原俊忠―+―藤原豪子
|(権中納言)|
| |
| +―藤原俊成――――藤原定家【御子左家】
| |(皇后宮大夫) (権中納言)
| |
| +―藤原俊子
| ∥
| ∥―――――――平滋子
| 平時信 (建春門院)
| (兵部権大輔) ∥
| ∥
+―藤原璋子 +―崇徳天皇 ∥――――――高倉天皇
|(待賢門院)| ∥
| ∥ | ∥
| ∥――――+―――――――――後白河天皇
| 鳥羽天皇
|
+―藤原公子
|(三位)
| ∥――――――藤原経宗――――藤原頼実【大炊御門家】
| ∥ (内大臣) (太政大臣)
| ∥
| 藤原経実 源義朝 +―全成
|(大納言) (左馬頭) |(醍醐悪禅師)
| ∥ |
+―藤原実子 ∥――――+―円成
(典侍) ∥ |(卿公)
∥ ∥ |
∥――――――藤原忠能 常葉 +―源義経
∥ (修理大夫) ∥ (伊予守)
+―藤原師信――――藤原経忠 ∥ ∥
|(権大納言) (内蔵頭) ∥ ∥――――+―藤原能成
| ∥ ∥ |(侍従)
| ∥ ∥ |
| ∥―――――――藤原長成 +―女子
| ∥ (大蔵卿) (妹)
| ∥
| 藤原能長――――藤原長忠―+―女子 女子
|(内大臣) (大蔵卿) | ∥――――――藤原基成―――女子
| | ∥ (陸奥守) ∥――――藤原泰衡
| +―女子 ∥ ∥ (小次郎)
| ∥―――――――藤原忠隆 +―藤原信頼 藤原秀衡
| ∥ (大蔵卿) |(右中将) (陸奥守)
| ∥ ∥ |
藤原隆家―――藤原経輔――+―藤原師家――――藤原家範―――藤原基隆 ∥――――+―女子
(中納言) (権大納言) |(右中弁) (大膳大夫) (修理大夫) ∥ ∥
| ∥ ∥――――――藤原基通
+―女子 藤原顕隆―――藤原顕頼――――女子 藤原基実 (摂政)
∥ (権中納言) (刑部卿) (摂政)
∥ ∥
∥ ∥―――――+―藤原光頼
∥ ∥ |(権大納言)
∥ ∥ |
∥―――――――藤原俊忠―+―藤原俊子 +―藤原惟方
∥ (権中納言)|(三位) |(参議)
∥ | |
藤原道長―+―藤原長家――――藤原忠家 | +―藤原成頼
(関白) |(権大納言) (大納言) | |(参議)
| | |
+―藤原頼宗――――藤原能長 | +―藤原祐子
(右大臣) (内大臣) | ∥――――――平滋子
| ∥ (建春門院)
| ∥ ∥――――――高倉天皇
| ∥ ∥
| 平時信 後白河法皇
| (兵部権大輔)
|
+―藤原俊成――――藤原定家
|(皇太后宮大夫)(権中納言)
|
藤原公実――――藤原実能 +―藤原豪子
(権大納言) (左大臣) ∥
∥ ∥―――――――藤原実定
∥――――――藤原公能 (右大臣)
∥ (右大臣)
藤原顕隆――+―女子
(権中納言) |
|
+―藤原顕頼
(刑部卿)
6月12日、「北条時政代官時貞称平六傔仗」は「義行在所聞得之由」て「竊欲搦遣云々、在大和国宇多郡辺」という(『玉葉』文治二年六月十二日条)。翌13日には「時貞丸来光長許、義行事重有申事在所一定宇多郡」という(『玉葉』文治二年六月十三日条)。そして16日、「平六傔仗時定於大和国宇多郡、与伊豆右衛門尉源有綱義経聟合戦、然而有綱敗北、入深山自殺、郎従三人傷死了、搦取残党五人、相具右金吾首、同廿日伝京師云々、是伊豆守仲綱男也」(『吾妻鏡』文治二年六月廿八日条)と、時貞は宇陀郡に兵を派遣して「義経聟」であった伊豆右衛門尉有綱を追捕し、山中で自害した有綱の首を20日に京都へ齎した。また、18日には「隠置義行之由有指申者」という「多武峯悪僧、龍諦房」を召し出して京都へ連行し、左馬頭能保のもとで尋問するが、口を割らなかった(『玉葉』文治二年六月十八日条)。こうした時貞の活躍を賞した頼朝は22日、「時貞勧賞事」の申状を奏上した(『玉葉』文治二年六月廿二日条)。
6月23日に院宣にて諮問を受けた兼実は「時貞事尤可然、且尋問可令申」という答申を能保に行っている(『玉葉』文治二年六月廿三日条)。能保から再度鎌倉に返答が行われたとみられ、7月1日、頼朝は「以平六傔仗時定、可被任左右兵衛尉之由、被申京都、是依有度々勲功也」(『吾妻鏡』文治二年七月一日条)と、時定を兵衛尉に推挙した。ただし有綱自害の一報が鎌倉に伝えられたのは6月28日であり(『吾妻鏡』文治二年六月廿八日条)、頼朝の時貞勧賞には有綱追捕の功は含まれておらず、この功績も併せて7月19日の小除目で「左兵衛尉」に任じられることとなる(『玉葉』文治二年七月十九日条)。なお、有綱は「義経聟」とあるが、義経娘は当年の生まれであり、有綱は義経との間で婚姻の約定を行っていたということかもしれない。
磯禅尼――――静
∥――――――男子
∥ (1185年生まれ)
源義朝――――源義経
(左馬頭) (伊予守)
∥――――?―女子
∥ (1185年生まれ)
河越重頼―――女子 ∥
(太郎) (1168生まれ) ∥
∥
源頼政――+―源仲綱――――源有綱
(従三位) |(伊豆守) (右衛門尉)
|
+=源頼兼
(検非違使)
このころの頼朝の法皇や摂籙についての考えは、6月29日頃に鎌倉から京都に帰還した院使「検非違使公朝院近臣候下北面」の奏上した「頼朝卿申状」(『玉葉』文治二年七月三日条)から窺い知れるが、頼朝は一貫して「万事可為君御最之由」を思い、それに伴うものとして「其次有摂簶事等」という。頼朝の「天下之草創」の思想の中心には法皇の存在が不可欠であり、それを輔弼して安穏の世を作り出す有能な摂政が必要だと考えていたとみられる。それは法皇が頼朝追討の宣旨を下すことを認めた(義経に脅されたとはいえ)張本であったことや、法皇が天下を治めずと宣言していても、頼朝はこれらを承知の上で法皇を奉じることを重んじた。そして「摂簶事」では兼実の推挙に至った理由などを明確にしているが「此事全非彼懇望、又非有引級之思、為身無其益、只衆口之所寄、其仁在彼人指余也、前摂政一切不被知万機之由、世上謳哥、仍偏思天下事及君御事之故、所申出此事也、隨又有天許、而今被仰下旨其趣不知、不能左右、是非只在叡念」(『玉葉』文治二年七月三日条)というものであった。頼朝の兼実推挙は、決して兼実からの要望ではなく、頼朝の利益のためでもなく、ただ彼こそが摂政の器であると人々が語っているためである。逆に前摂政基通の無能の噂を述べて、頼朝は天下安穏と法皇の御事のみを思い、この摂政人事を奏上していると宣言しているのである。この頼朝の考えを知った兼実の感想は特にないが、頼朝の「当時殿下、一切不被知家領、尤不便、前摂政又併被避所領、尤可有其糸惜、然者以高陽院方、為前摂政領、以京極殿方、為当時殿下領、尤可宜歟」と、兼実に家領を譲るよう法皇及び前摂政に圧力をかけていることについては、法皇らの評定の結果「大略所領事、一向可付前長者之由歟」であるといい、兼実も摂関家領の不預については「愚察不驚、只所仰春日大明神御計也、非人力之所覃耳、中心之所思、上天定照鑑歟」(『玉葉』文治二年七月七日条)と春日大明神の御計であると平静を装うも、内心は忸怩たる思いがあふれているようである。
7月11日、鎌倉では「被訪故前備前守行家去五月十三日誅戮歿後、明日依可被修仏事」ため、頼朝は筑後権守俊兼に命じて、施物や僧食等を行慈法橋へと届けさせている(『吾妻鏡』文治二年七月十一日条)。大学房行慈(上覚)は高尾の文覚上人の弟子僧で、主要寺院の住持をしていた「宿老僧」の一人だったが、どこの住持だったかは不明(のち頼朝法華堂別当坊)。行家は勅勘の身であるが、もとは頼朝の私的な対立であって、首級も大路渡も獄門も行われずに5月17日、「行家首遣関東」とされている(『玉葉』文治二年五月十七日条)ように鎌倉へと下されたとみられる。この追善仏事は、その首を埋葬するにあたり執り行われたものであろう。修法の導師が大学房行慈という頼朝の信任あつい人物であることや、二日後には勝長寿院で「是奉為二親以下尊霊得脱」のための盂蘭盆の万灯会が行われていることから、行家の首が埋葬されたのは源氏菩提所たる勝長寿院であり、法橋行慈は勝長寿院別当であったのかもしれない。
7月12日には、頼朝の使者として「前因幡守広元」が上洛し、帥卿経房の屋敷に入って頼朝からの条々を披露した(『玉葉』文治二年七月十二日条)。
翌13日早旦には経房が兼実邸を訪問して、広元が持参した関東書札の条々につき兼実に告げているが、兼実は「皆是天下之至要也、可随喜可随喜」と歓喜している(『玉葉』文治二年七月十三日条)。その内容は『玉葉』に記載はないため不明ながら、7月7日に鎌倉から京都に送られた「諸国地頭職事、平家没官領并梟徒隠住所處之外、於権門家領等者可令停止之由」(『吾妻鏡』文治二年七月七日条)であろう。「平家没官領」と「梟徒隠住所處」以外は地頭職を停止するという画期的なもので「於権門家領等」がその対象となっていた。ただし逆に言えば「権門家領」ではない公領や「梟徒隠住所處」と認定された庄園(権門家領も含むのだろう)には地頭職が置かれることを示唆している。しかし、兼実はその部分については意見を述べていない。なお、広元が上洛した理由は、14日に光長が兼実を訪れて報告したことによれば「今朝広元来臨、示条々事等云々、其内去比公朝来関東、為余吐様々悪言等、偏蔑爾射山振己威、停廃院御領、解官院近習者凡不能左右、因茲法皇不剃頭不切手足爪、寝食不通閇籠御持仏堂中、以所修行業、可廻向悪道之由、摧肝胆、任悪心偏忘他事、有御念願、所積為尊下指頼朝也、太無要之由、構弁説称之、頼朝頗雖驚奇、所示過法、仍還又有不信用之気色、仍為糺此真偽、俄所差上広元也」(『玉葉』文治二年七月十四日条)ということだった。院使の大江公朝が鎌倉で「兼実が法皇を軽んじて院御領を停廃したり院近習の解官を進めたりして、法皇は持仏堂に籠り、頭も剃らず爪も切らず寝食もままならない状態となっている、頼朝の事もまったく必要なしと述べている」という悪口を散々吐いたが、その内容があまりにもおかしいので、広元がその確認のために上洛してきたという顛末であった。これについて兼実は「蒼穹在頂、全不為苦、中心奉公之志、仏神定有照鑑歟」と、全くの潔白と法皇への奉公の志は仏神が照覧していると記す。広元の養父「掃部頭朝臣中原広季」は兼実の「家司」であり(『玉葉』文治二年十月廿日条)、兼実との直接対話も目的の一つであったのだろう。
そして15日、経房が兼実のもとを訪れ、「頼朝卿申状」に記された「申家領可被分之子細」について「依此事法皇逆鱗之趣也」という報告を受けた(『玉葉』文治二年七月十五日条)。法皇寵愛の基通に付されている摂関家領を、新摂政・氏長者たる兼実へ移すべきであるという頼朝の要求に対して激怒していることがわかる。ところが、16日に中原広元が院に召されて参院した際には「家領之間事逆鱗之儀、忽変只平ニ令乞請給」とひたすらに低姿勢で基通に付したままにするよう懇請したという。また、「其中ニハ余不忠之由、粗有其趣等」という(『玉葉』文治二年七月十七日条)。兼実はこの法皇からの不忠の指摘に何ら反応を示さずに次の話題に転じており、もはや謂うも詮無しの心地が感じられる。院近臣の大江公朝が頼朝に述べたという兼実に対する「所示過法」悪口は、法皇が浅はかに指示したものであったことが濃厚であろう。
24日夜、兼実は冷泉邸から九条邸に移り、内密に広元を召して謁見し、「粗陳鎌倉子細、又仰所思了」(『玉葉』文治二年七月廿四日条)という。これまでの頑ななまでの頼朝に対する嫌悪感が一気に和らいでいる感を受ける。これは「頼朝卿申状」にみられる頼朝の主たる思想(「万事可為君御最之由」を思い、それに伴う「其次有摂簶事等」を重視する政治体制によって安穏の世を導く思想)と「此事全非彼懇望、又非有引級之思、為身無其益」の宣言、地頭職の「於権門家領等者可令停止」がもっとも大きい理由だろう。兼実はここで広元に頼朝の思惑を聞き取り、自分の所存を述べたのであろう。頼朝を秦の始皇帝に準えて嫌悪していた(『吾妻鏡』文治元年十一月七日条)評価は「彼卿志在四海」(『玉葉』文治二年閏七月十五日条)と激変している。
25日午の刻、兼実は冷泉邸に戻ったが、左馬頭能保の伝えるところでは「九郎義行郎従、伊勢三郎丸梟首」という(『玉葉』文治二年七月廿五日条)。彼は義経腹心で、かつて平家追討の際に内府宗盛入洛の護衛に選ばれたほどの勇士であったが、ついに力尽きた。そして29日、法皇からの数十枚の御書を遣わされるのを待ち続けた中原広元はようやく帰途に就く(『玉葉』文治二年七月廿九日条)。
7月30日深夜、法印慈円の使者として慶俊律師(行家子)が遣わされ、「今朝能保朝臣参彼法印許、義行在山悪僧許之由有風聞」という(『玉葉』文治二年七月卅日条)。能保は比叡山に義経が匿われていることを鎌倉にも遣わしており、閏7月10日、鎌倉に能保の書状が到来している。詳細は「搦前伊与守小舎人童五郎丸」であり、義経の行方を尋問すると「至于去六月廿日之比、隠居山上候之旨」であった(『吾妻鏡』文治二年閏七月十日条)。これはちょうど岩倉に義経等が隠居しているとの情報に基づいて朝景・基清の手勢が馳せ向かったものの謬説であり、比叡山に義経が逃れているという風聞があった時期と重なる(『吾妻鏡』文治二年六月廿二日条)。能保は「叡山悪僧俊章、承意、仲教等」が義経に同心していた旨を座主僧正全玄と殿法印慈円に伝え、さらに法皇にも奏上したという。
ところがその知らせを聞いた彼らは「各居籠凶徒等欲捕取之間、方人少々出来、打破逃了」(『玉葉』文治二年閏七月十六日条)という。これにより「而山門衆徒忘朝憲、容隠之條、甚不当、如土肥二郎実平之武士等、偏堅坂本、可捜山上」と在京の武士等が比叡山を攻めようとするに至り、能保は「廻様々計略、所加制止也」という(『玉葉』文治二年閏七月十六日条)。兼実も諸卿に諮った上で、「於襲寄山門之条者、一切不可然」とした上で、座主已下には「武士等之所欝至極之理也」と怠慢を叱責した上で、座主僧綱らは叡山へ登り、門徒らを遣わして俊章、承意、仲教三名の捕縛を厳命した(『玉葉』文治二年閏七月十六日条)。21日には「中教已搦取了」と、三人の悪僧のうちの一人が捕縛されている(『玉葉』文治二年閏七月廿一日条)。このうちの「俊章」が「年来与予州、成断金契約、仍今度牢籠之間、数日令隠容之、又至赴奥州之時者、相率伴党等送長途」とあるように、奥州まで送った人物である(『吾妻鏡』文治四年十月十七日条)。平泉毛越寺は比叡山との関わりが深く、本尊も比叡山と同じく薬師如来である。義経は年来懇意の悪僧俊章、承意、仲教の伝手で奥州平泉を頼ったのだろう。
また、兼実邸には9月20日には「藤内朝宗」が「九郎義行郎従二人堀弥太郎景光、四郎兵衛尉忠信、搦取了、忠信自殺、景光被捕得」(『玉葉』文治二年九月廿日条)という一報が届く。続けて翌21日、今日から始められる予定であった法皇の熊野御精進は、「伝聞昨日比木藤内朝宗頼朝卿郎従、搦取義行郎従等堀弥太郎、佐藤兵衛尉等」により、穢気として七日間延引となる(『玉葉』文治二年九月廿一日条)。「義行郎従堀弥太郎景光、為藤内朝宗被搦取了、即究問之處、白状旨顕然、而所追捕也」と、比企藤内朝宗は堀弥太郎景光を尋問して義経の居所を聞き出し、「卯刻、武士二三百騎、打囲観修房得業聖弘房称放光房云々、忽以追捕寺家」と、南都に急行して興福寺観修房得業の「聖弘房称放光房」を取り囲んで狼藉を働いたという(『玉葉』文治二年九月廿一日条)。「聖弘得業義行縁者」(『玉葉』文治二年十月十七日条)とあり、義経の師壇であった(『吾妻鏡』文治三年三月八日条)。興福寺別当大僧正信円(兼実異母弟で入道関白基房実弟)はこの追捕寺家について何ら知らされておらず、朝宗に使者を遣わして子細を問い質すが、朝宗は「九郎判官義行在此家、仍為捕取也」として狼藉が続けられたが「聖弘逐電了」という。なお、『吾妻鏡』では堀弥太郎及び佐藤四郎兵衛尉を追捕したのは、糟谷藤太有季であるとされ、有季が「予州家人堀弥太郎景光此間隠住京都」を生け捕った(『吾妻鏡』文治二年九月廿二日条)という。さらに有季は中御門東洞院に隠れ住んでいた義経腹心の佐藤四郎兵衛尉忠信(以前に宇治辺で義経と別れている)を襲撃したという。忠信は激しく抵抗するが、忠信の手勢は郎従二人のみであり、主従三名は自害した。時定は連行された景光を尋問すると、「予州、此間在南京聖弘得業辺」という(『吾妻鏡』文治二年九月廿九日条)。さらに景光は義経の使者として「度々向木工頭範季之許、有示合事」という。時定はこのことを左馬頭能保に付して奏上の上、比企藤内朝宗に五百余騎を副えて義経捜索に向かわせた(『吾妻鏡』文治二年九月廿九日条)。
南都に急行した比企藤内朝宗は奈良に乱入し、聖弘得業辺を探し回るも義経は見つからず、ただただ南都の僧侶の大きな恨みを買うのみで、得るものなくむなしく引き上げたという(『吾妻鏡』文治二年十月十日条)。『玉葉』においても「武士無成事即帰洛」(『玉葉』文治二年九月廿二日条)とあり、『吾妻鏡』と同様の内容である。結局、聖弘房は別当信円大僧正に召され、10月18日、所司二名に伴われ能保のもとに遣わされたのち「比木藤内朝宗」のもとへと送られた(『玉葉』文治二年十月十八日条)。なお、堀弥太郎景光はその後処断されたという報もなく、生死は不明である。
藤原忠隆――+―藤原信頼
(大蔵卿) |(右中将)
|
+―女子
∥―――――――藤原基通
∥ (普賢寺関白)
+―藤原基実
|(中関白)
|
| 藤原忠雅女
| ∥―――――――藤原師家
| ∥ (摂政)
源国信―――女子 +―藤原基房
(中納言) ∥ |(松殿関白)
∥ |
∥ |【興福寺別当】
∥―――――+―信円
∥ (大僧正)
∥
藤原忠通 +―藤原兼実
(法性寺関白)|(月輪関白)
∥ |
∥―――――+―藤原兼房
∥ |(太政大臣)
∥ |
∥ |【天台座主】
藤原仲光――――――加賀局 +―慈円
(太皇太后宮大進) (家女房) (大僧正)
なお、尋問を受けた景光の申し条には甚だ不審がみられる。義経は風聞から足跡を辿ると、大物浦での難破後、和泉国へ上陸し、吉野川を遡って大和国吉野に入り、多武峰、岩倉、鞍馬、比叡山と移っていったと考えられる。比企朝宗が捕らえた興福寺聖弘房の下僧が「義行隠居之条実説也」と述べていることから、義経が聖弘房に隠居していたのは事実だろうが、風聞と考えあわせると、南都に滞在していたのは多武峰から岩倉へ移る間であろうから八~九か月前と考えられ、尋問に対して景光が答えたものは明らかな揺動であろう。義経はこの頃にはすでに比叡山からも撤退し、比叡山僧俊章の案内のもと「相具妻室男女、皆仮姿於山臥并児童等」(『吾妻鏡』文治三年二月十日条)して奥州平泉への道を辿っていた。さらに「木工頭範季」に自分が度々使いをした事実を告げたのも、義経の鎮西行きの際に追捕してきた人物が範季の子・範資であったことへの意趣返しの可能性があろう。また、範季が三河守範頼の義父であることも景光の考えには入っていたのかもしれない。範季同心の報を受けた頼朝は、10月16日、時定宛に範季同心について奏上するよう指示している(『吾妻鏡』文治二年十月十六日条)。
その後、「示送経房卿許」として「自頼朝卿之許、件朝臣有同意義行之聞、奇怪之由」が報告されている(『玉葉』文治二年十月廿八日条)。ただし「殊雖非奏聞之趣」であったといい、『吾妻鏡』の記述とは全く異なる。兼実は奏聞に及ぶものではないとしながらも「事体難黙止」として、家司でもある範季を召して義経との関りを問い質している。結果として、範季は「於堀弥太郎景光者、一両度謁了」ではあったが、義経との同心は無実であった(『吾妻鏡』文治二年十月廿八日条)。ただし、景光に謁しながら捕らえなかったことは過怠であり、その旨を関東に遣わすよう指示している。
範季の報告が頼朝に届けられると、その怒りが爆発した。11月5日、頼朝は「義行于今不出来、是且公卿侍臣皆悉悪鎌倉、且京中諸人同意結搆之故候、就中範季朝臣同意事所憤存候也、兼又仁和寺宮御同意之由承及候、子細何様事哉」(『吾妻鏡』文治二年十一月五日条)という書状を帥卿経房へ宛てて送っている。『玉葉』によれば頼朝申状には「義行事、南北二京、在々所々、多与力彼男、尤不便、於今者若差進二三万騎武士、山々寺々、今可捜求也、但事定及大事歟、仍先為公家沙汰、可被召取也、随重仰可差上武士也、兼又仁和寺宮後高野御室道法、始終有御芳心之由所承也」とあり、最大級の脅しを含んだ要求を行っている。なお、このころ仁和寺宮(以仁王子宮で八条院猶子。当時十八歳で病気がちであった)この報告を受けた法皇は11月16日、「頼朝卿申旨如此被下書札也、為朝之大事、宜様可計沙汰者」と兼実に伝え、兼実は「明日召諸卿於院殿上、可被予議也、頼朝所申尤理也、力之所及、尤可有御沙汰」(『玉葉』文治二年十一月十六日条)と答えている。翌17日での院殿上での僉議ではその状が披露されている。
兼実は「此條所申至極之理也、又朝家之大事也、自本有御沙汰之上、弥依此申状驚思食、各廻意慮委可定申之、兼又縡已大事也、輙以人力難成其功、猶祈祷神仏、可顕効験也」と諸卿に対して述べ、11月24日、兼実は「義行改名之間事、余所案之名義顕尤宜」と権中納言兼光を通じて法皇へ達し、上卿を左大臣経宗として「被下義顕追討事」が下されることとなる(『玉葉』文治二年十一月廿四日条)。以前、兼実が範季のことを鎌倉に伝えた際に大夫属入道善信(三善康信入道)に対して「義行者其訓能行也、能隠之儀也、故于今不獲之歟、如此事尤可思字訓、可憚同音云々、依之猶可為義経之由」と、「義行」を「義経」のままとするよう述べていたが(『吾妻鏡』文治二年十一月五日条)、早々に顕われるようにとの願いから「義顕」と改められたものである。そしてこのことは左馬頭能保から鎌倉に報じられ、11月29日に鎌倉に届いている(『吾妻鏡』文治二年十一月廿九日条)。なお、左馬頭能保は12月15日の除目で右兵衛督に任じられ、子息の高能に左馬頭が譲られている(『尊卑分脈』)。
12月1日、千葉介常胤は下総国から鎌倉に帰参した(『吾妻鏡』文治二年十二月一日条)。十か月前の2月2日に御分国の下総守に源邦業が就いており、常胤はその関係で下総国に帰国した可能性が考えられよう。鎌倉に帰還した常胤は、御所西侍に出向いて頼朝と対面し盃酒を賜っている。この席には小山左衛門尉朝政、大夫属入道善信、岡崎三郎義実、足立左衛門尉遠元、藤九郎盛長以下の宿老が列しており、久しぶりの邂逅に花が咲き、たくさんの瓜が出された宴会となっている。六十九歳の常胤は座を起って踊り、善信入道は催馬楽を歌うなど、楽しげな雰囲気が伝わっている。
文治3(1187)年正月12日、頼朝と若公の御行始が行われ、南御門前にある八田右衛門尉知家の南御門宅へと移っている(『吾妻鏡』文治三年正月十二日条)。「千葉小太郎」が御剣を持ってこれに従っている。千葉小太郎は常胤の孫、小太郎成胤である。
文治3(1187)年2月10日、兼実のもとに「故三条宮子宮名道性入滅」の報が入る(『玉葉』文治三年二月十日条)。彼は「八条院為子、生年十八、究竟法器人云々、自去年病悩、遂以如此、可惜ゝゝ」とその死を惜しんでいる。かつて義経が西国へ向かわんとする際に船の手配として摂津国に派遣したという「大夫判官友実」はかつて「垂髪而候、仁和寺宮首服時属平家、其後向背相従木曾、々々被追討之比、為予州家人」という経歴の人物であり(『吾妻鏡』文治元年十一月二日条)、彼の居宅は仁和寺近隣にあって、「此屋自御室借給友実之條、露顕之間、頗非無御同心之疑」と義経との関わりを疑われていた。
3月12日、兼実邸を訪れた右兵衛督能保は、「所召取之義顕縁者等、非可免、又武士等之許、無其期、非可召置、内舎人朝宗来十四日下向坂東、付被下遣宜歟如何」と尋ねるが、兼実は「此條、日来所申也、度々余示能保也」と、何度も同じ事を尋ねてくる能保にややうんざりした様子がうかがえる(『玉葉』文明三年三月十二日条)。「所召取之義顕縁者」とは「聖弘得業義行縁者」(『玉葉』文治二年十月十七日条)とあることから、聖弘房であることがわかる。3月14日に京都を発した比企藤内朝宗と聖弘房が鎌倉についた時期は不明。なお『吾妻鏡』では実際の京都出立(3月14日)よりも前の8日に「南都周防得業聖弘依召参向、為予州師檀之故也」(『吾妻鏡』文治三年三月八日条)とあり、明らかな誤記が見られる。
鎌倉へついた周防得業聖弘は小山七郎朝光に預けられており、3月8日、御所に召されて頼朝と対面となったとする(『吾妻鏡』文治三年三月八日条)。実際は3月20日前後に鎌倉着と考えられるが、聖弘房に対して頼朝は、
「予州者欲濫邦国之凶臣也、而逐電之後、捜求諸国山澤、可誅戮之旨、度々被 宣下畢、然者、天下尊卑皆背彼之處、貴房独致祈祷、剩有同意結搆之聞、其企如何者(義経は国を乱す凶臣である。そのため義経が逐電ののち、諸国を探し求めて誅戮すべきという宣旨が下されている。そのため、天下の人々はみな義経に背いているのに貴房は一人彼のために祈祷し、あまつさえ彼に同意しているという。なぜそのようなことを行うのか)」(『吾妻鏡』文治三年三月八日条)と問い質した。これに対して聖弘房は、
「予州為君御使、征平家刻、合戦属無為之樣可廻祈請之旨、慇懃契約之間、年来抽丹誠、非報国之志乎、爰予州称蒙関東譴責逐電之時、以謂師檀之好、来南都之間、相搆先遁一旦害、退可被謝申于二品之由、加諷詞、相副下法師等、送伊賀国畢、其後全不通音信、謂祈請不祈謀叛、謂諷詞和逆心畢、彼此何被處与同哉、凡倩案関東安全、只在予州武功歟、而聞食讒訴、忽忘奉公、被召返恩賞地之時、発逆心之條、人間所堪可然事歟、速翻日来御気色、就和平之儀、被召還予州、兄弟令成魚水思給者、可為治国之謀也、申状更非引級之篇、所求天下静謐之術也者(予州はあなたの御使として平家追討に赴くとき、合戦が無事に終わるため祈祷するよう慇懃に契約に訪れて以来、私は祈祷を続けていたが、これを国に奉じる志と言わずして何というのか。予州が関東の譴責を受けて逐電し、師壇の関係から南都を訪れた時には「まずは一旦逃れたのち二品に謝しなさい」と諫めて、下法師を副えて伊賀国へ送ったが、その後は音信不通である。この祈祷は謀叛を祈るものではなく逆心を和するものである。これを以てどうして謀叛の与同とするか。つらつら考えれば、関東の安全はひとえに予州の武功によるものではないか。それを朋輩の讒言を信じて彼の奉公を忘れ恩賞地を収公すれば、逆心を起こすなど当然ではないか。早々に怒りを解いて和平の心を持ち、予州を召還して兄弟隔心なく国を治めるべきだろう。これは予州を引級しているわけではなく、天下静謐のためである)」(『吾妻鏡』文治三年三月八日条)と厳しく頼朝に意見したのである。
頼朝はこの聖弘房の言葉を聞いていたく感じ入り、すぐさま勝長寿院供僧職となして「可抽関東御繁栄御祈祷之由」を要請したという。
聖弘房の情報以降、「予州在所未聞、於今者非人力之所覃」(『吾妻鏡』文治三年四月四日条)という状況であったが、若宮別当法眼が「於上野国金剛寺可逢予州」という夢を見たという。そのため4月4日、藤九郎盛長に「彼寺住侶等各可抽御祈祷丹誠之旨、可相觸之趣」を命じたという。なお、藤九郎盛長は元暦元(1184)年7月16日以前に上野国の「国奉行」であった(『吾妻鏡』元暦元年七月十六日条)。ただし、これ以前に「前伊予守義顕、日来隠住所々、度々遁追捕使之害訖、遂経伊勢美濃等国、赴奥州、是依恃陸奥守秀衡入道権勢也」(『吾妻鏡』文治三年二月十日条)という記事も存在するが、後日『吾妻鏡』が編纂された際に差し込まれた文である。後日の調査で、この頃には義経が奥州にいた情報から挿入されたものであろう。
4月30日、「義顕於美作国山寺被斬畢、其次第、逃去南都移住美州山寺、而近辺寺僧、告達関東、頼朝卿専一之郎従加藤太光員、弟加藤次光■、与件山寺僧為知音、仍遣告云々、件加藤次丸猶成疑殆、自身不上洛、差遣郎従五人、其中一人有見知義顕之者也、以件案内者、為示承入件山寺、即梟義顕頭了、于時出家入道偏纒病痾、集臥炉辺」(『玉葉』文治三年五月四日条)という。この病に臥せっていた僧侶の首は5月3日に入洛し、翌4日に関東へと下された。兼実は「事若実者、天下之悦也」と述べている。ただし、この首について『吾妻鏡』には記載されていない。
8月15日、鶴岡山八幡宮寺での放生会が行われ、参河守範頼、武蔵守義信、信濃守遠光、遠江守義定、駿河守広綱、小山兵衛尉朝政、千葉介常胤、三浦介義澄、八田右衛門尉知家、足立右馬允遠元ら門葉宿老らが扈従した(『吾妻鏡』文治三年八月十五日条)。
そして8月19日、「洛中狼藉事、連々被下 院宣之間、且尋問子細、且為相鎮之」として、千葉介常胤、下河辺庄司行平の両名に上洛が命じられた(『吾妻鏡』文治三年八月十九日条)。これは、8月12日に右兵衛督能保から「当時京中群盜乱入所處、尊卑爲為之莫不消魂、就中去年十二月三日、強盜推参太皇太后宮、殺害大夫進仲賢以下男女以来、太略隔夜有此事、差勇士等、殊可警衛給之由、有天気」という書状が到来したことによる(『吾妻鏡』文治三年八月十二日条)。当時、京都には時政が残してきた東国武士のほか、兵粮米の沙汰、大番勤仕の武士が多く上洛しているが、うまく鎮撫の機能が働いていないばかりか、御家人が強盗の張本である可能性もあると噂されているという。閑院殿修造の監督者として「当時、親能広元雖在京候」と、中原親能、中原広元兄弟が在京であったが、彼らはそもそも武力を持たず、鎮定を行うことはできないとして、能保に「仍常胤行平を差進候、於東国有勢者候之上、相憑勇士候也、自余事ハ知候はす、方武士等中狼藉ハ此両人輙可相鎮候、見器量計進候、能々可被仰付候」と伝えている(『吾妻鏡』文治三年八月十二日条)。ただし、広元は7月13日夜に上洛し、当時在京だった「次官親能」は翌14日、兼実邸を訪れて「明日下向関東之由」を告げ、兼実から「仰条々事了以国行仰之」せを受けている(『玉葉』文治三年七月十四日条)。7月15日に広元の上洛は兄・親能との交代であろうことは推測でき、『吾妻鏡』の記述が事実であるとすると、親能は鎌倉帰還の直後に再度上洛したことになる。
頼朝から上洛を命じられた常胤と行平は、御所に召されて餞別ならびに馬を賜り、様々に指示を受けている。そして彼らは軍旅の体裁を整え、8月27日に出立することとなるが、常胤は「違例」のため延引され、27日は行平のみの上洛となった(『吾妻鏡』文治三年八月廿七日条)。そして30日、病の平癒した常胤も続けて鎌倉を出立した(『吾妻鏡』文治三年八月卅日条)。なお、常胤の手勢には嫡男・千葉新介胤正は加わっておらず、目代真正の奸曲によって召人となった従兄弟・畠山二郎重忠の身柄を屋敷に預かっている(『吾妻鏡』文治三年九月廿七日条)。
常胤、行平は「於東国有勢者候之上、相憑勇士候也」という頼朝の全幅の信頼を得て出立している。宿老の常胤と行平の両名が派遣されていることから、「洛中狼藉」の重大さを頼朝が認識していたこと、つまり8月12日に届けられた能保からの書状から、頼朝は「洛中狼藉」に在京御家人の加担の可能性が高いことを認識したとみられる。常胤・行平という強大な実力を持つ両者を派遣することで、在京御家人の緊張を高めて規律を引き締めるとともに、京都へ再度武威を示す目的があったとみられる。この両名はともに八条院領の千葉庄、下河辺庄の荘官であり、敢えてこの両名が選ばれているのは、有力者である八条院家人として京都でも名声が高かったためか。
また、法皇もこれらの狼藉には在京御家人が関わっていることは認識していたとみられ、頼朝の8月19日および27日に到来した申状(後述の通り、常胤がもたらしたものであろう)に対し、9月20日、
「本自関東武士所行をも全不風聞、又不仰遣其旨、只近代使庁沙汰、遂日■弱、偏如鴻毛、在京守護武士合力致沙汰者、何不被禁遏乎之由依思食、殊可有尋沙汰之由、所被仰遣也、就中実犯之輩、号武士威之時、使庁弥迷成敗云々、尤可有推察事歟、然而可為使庁沙汰之由、令計申給之條、法之所指尤可然事也、仍殊可有御沙汰之由、被申摂政畢、但於武士可合力事歟(法皇は、もとより関東武士の狼藉とはまったく聞いていないし、そのような旨を遣わしてもいない。ただ、近頃では検非違使は日に日に力を失い、在京武士が合力して沙汰せずばどうして狼藉を停止させられようか、と思し召され、とくにあなたに尋ねられるよう沙汰があり、仰せ遣わされたのものである。とくに狼藉者が「御家人だ」と威したときに検非違使が捕縛するのを躊躇うことがあるのは、推察すべきだろう。こうした狼藉者の取り締まりは検非違使が行うべきであるというあなたの申し分は法の定めるところでもっともではあるが、このことを摂政兼実へ申すと、在京武士も合力すべきである、という申し分である)」(『吾妻鏡』文治三年十月三日条)
と、含み言葉ではあるが、逆説的に在京武士が狼藉に関わっているのだから、在京武士を検非違使と協力させてこれを取り締まれ。これは其方が推す摂政兼実も言っていることだ、と返書しているのである。
上洛を命じられた行平は9月11日に入洛し、常胤は遅れて9月14日に上洛を果たした(『吾妻鏡』文治三年十月八日条)。『玉葉』では9月12日に「経房卿以有経、見送頼朝書状、泰経、頼経、範季等事猶欝申歟」(『玉葉』文治三年九月十二日条)とあることから、この書状は下河辺行平が経房に届けたものであろう。また、9月15日には8月19日付と8月27日付の「洛中群盜以下條々」(『吾妻鏡』文治三年十月三日条)も届けられており、これは前日14日に入洛した常胤が経房に持参したものとみられる。この常胤が持参の頼朝申状二通も経房卿を通じて奏院され、9月20日の返書(奉経房)となる。
9月11日に入洛した下河辺庄司行平は、その夜のうちに「窺兼承及群盜衆会之所々、令郎従致夜行」ている。在京御家人が盗賊化しているかどうかの調査のための出動とみられるが、行平郎従は白河尊勝寺辺で八名の怪しい集団を捕縛している。彼らは「尋明所犯」たことから、行平は常胤の入洛を待たず、検非違使にも連絡することなく「任北條殿之例、刎彼等首訖」という(『吾妻鏡』文治三年十月八日条)。時政の例を引いていることから、行平は彼らを盗賊として処刑したとみられるが、御家人やその郎従であっても盗賊として処断することを指示されていたのかもしれない。常胤や行平が上洛前に「承條々仰」(『吾妻鏡』文治三年八月十九日条)っているが、そこにはこの旨があったのかもしれない。
9月14日、常胤が入洛するが、そこから日数を経ずして「更不聞狼藉事、自然无為」であった。これは常胤と行平の「群盜」に対する強大な影響力をあらわすものであろう。端的に表すものは、常胤と行平による在京武士の招集であろう。常胤らは呼び出した在京御家人らに狼藉について質しているが、その追及に在京武士の中には「非无子細」者が炙り出され、彼らが提出した陳状は五十三通にも及んだ。彼らは狼藉に加担または郎従等に関係者がいた人々とみられるが、結局、狼藉の証拠はないとされ、沙汰に及ばずと裁断された(『吾妻鏡』文治三年十月八日条)。しかも、この五十三通の陳状を帥卿経房へ提出すべきだろうという沙汰(洛中守護の右兵衛督能保か?)があったが、行平・常胤は「関東武士所行とハ全不風聞之由、被載院宣之間、加斟酌不備進之、令持参之由」と、院宣の言葉を逆手にとって提出しなかった。この院宣は9月20日に下され鎌倉へ送られているが、常胤・行平が院宣の内容を知っていることから、帥卿経房から常胤・行平の手を経て鎌倉へ下されたのだろう。そして、在京御家人の五十三通の陳状は常胤・行平が鎌倉へ持ち帰っており、洛中の狼藉には在京御家人が何らかの形で関係していたことがうかがえ、頼朝は行平らが朝廷に「件陳状」を提出しなかった機転を「此事其理可然、仍又有御感」と賞している(『吾妻鏡』文治三年十月八日条)。
9月20日に法皇から返された頼朝申状に対する返書には経房の追記も記されているが、ここには「兼又群盗事、付常胤行平、雖令献御札給、為省紙筆、以一通申御返事候也、彼両人上洛以後、洛中以外静謐、能々可被感仰之旨候也」と、千葉介常胤と下河辺庄司行平の両名が上洛した直後から洛中は「群盗」も消え「以外静謐」になったとして、法皇が「可被感仰」ことを伝えている(『吾妻鏡』文治三年十月三日条)。
常胤・行平は「洛中狼藉」を抑え込むと、9月末から10月1日頃には京都を離れて鎌倉への帰途に就く。9月11日から14日の上洛からわずか半月余りでの撤退だが、その目的は前述の通り「群盜(狼藉に加担する在京武士)」の取り締まりであって、洛中の治安維持ではないため、目的を達成すると同時に帰途に就いたのであろう。頼朝の考えは洛中の治安維持は基本的には検非違使庁が管轄し、謀叛人らの追討は洛中守護の右兵衛督能保が在京御家人を動かして対応するものだったのだろう。常胤と行平は10月8日に鎌倉に帰参すると、頼朝からの召しで御所に出仕。頼朝から「上洛之間、京中静謐之由及叡感、尤為御眉目」と賞され(『吾妻鏡』文治三年十月八日条)、さらに前述の通り、狼藉に関わったとみられる在京御家人の五十三通の陳状を持ち帰ったことも賞されている。
一方、9月4日、奥州平泉の藤原秀衡入道のもとへ遣わした雑色が帰参した(『吾妻鏡』文治三年九月四日条)。これは「秀衡入道扶持前伊予守、発反逆之由、二品令訴申給」たために、「去比被下庁御下文於陸奥国」ときに、頼朝も「同被遣雑色」たもので、秀衡入道は「謝申无異心之由」を述べたというが、雑色が見たところでは「既有用意事歟」というものだった。そのため、頼朝はこの雑色を上洛させて、奥州の情勢を法皇へ報告させたとする。この使者は「雑色沢方」(『玉葉』文治三年九月廿八日条)で、9月28日、帥卿経房に付しているが、その内容は義経に関するものではなく、
(1)平家に奥州へ流された前山城守基兼(元院近臣、北面下臈)が秀衡入道に召禁されて上洛できない事
(2)東大寺大仏の鍍金用の砂金三万両の陸奥貢金についての事
という「両条」であって、義経についての要望はない。この「件両条賜別御教書、欲仰遣秀衡之許者」を経房に要請し、経房は摂政兼実に御教書を申請している。これに対し、兼実が認めた御教書は「基兼事、砂金事并度度追討等之間、無殊功事等」が記されている。両条に追加して記載された「度度追討等」は「頼朝申状」には含まれておらず(頼朝申状には「秀衡不重院宣殊無恐色、又被仰下両条共以無承諾、頗在奇怪歟」)、「且又子細、可召問使男」とある通り、雑色沢方の口頭での要請の可能性もあるが(『玉葉』文治三年九月廿八日条)、秀衡のもとに義経がいることが判明しているのであれば、「基兼事、砂金事」などよりも優先される問題であり、兼実が「并」で記した「度度追討等」は秀衡にも命じられていた義経追討のことで、「無殊功事等」ことへの譴責とみられる。つまり、この時点で朝廷も頼朝も義経の行方を把握できていなかったことが想定できるのである。
11月11日、頼朝は法皇への「貢馬三疋」を佐々木次郎経高を使者として上洛させた(『吾妻鏡』文治三年十一月十一日条)。三頭の馬はそれぞれ千葉介常胤(黒)、小山兵衛尉朝政(葦毛)、宇都宮左衛門尉朝綱(毛駮)が進上したもので、佐々木二郎経高、下河辺四郎政義、千葉四郎胤通(胤信か)が騎乗して上洛の途に就いた。佐々木経高は正使であるが、下河辺四郎政義、千葉四郎胤信の上洛は、二か月前に上洛して在京御家人を震撼させた下河辺行平と千葉介常胤の縁者として、御家人らへの強い牽制の意味も含んでいるのだろう。ただ、この馬は法皇の御意に叶わなかったようで、12月18日、院近臣の大夫尉公朝が鎌倉へ到着しているが、公朝は法皇の言葉として「今年所進貢馬頗異樣、後年殊可有勤厚歟」と不満を伝えている(『吾妻鏡』文治三年十二月十八日条)。
11月13日、京都では頼朝の尽力により再建された閑院へ天皇(後鳥羽天皇)の遷幸があった(『玉葉』文治三年十一月十三日条)。兼実はまず法皇御所の六条殿へ参じたものの、その日法皇は「而院於前摂政第乱遊之間、今夜不可還御」という為体であり、兼実は空しく法皇御所を退出して直に参内し、閑院への行幸となる。その後、院宣により「閑院修造賞、武蔵国重任也、頼朝可叙正二位之由、予有沙汰、然而依申不可有賞之由、不被仰下也、此次斎宮群行用途料被仰、相模国重任了、広元閑院修造、可為両国重任之由雖令申、無天許也」(『玉葉』文治三年十一月十三日条)という。これは頼朝があらかじめ広元に「閑院修造勧賞事、可辞申之旨」(『吾妻鏡』文治三年十一月廿八日条)を伝えていたため、広元がこれらを辞退したのだが、閑院御所の修造功を武蔵国と相模国の重任のみとする頼朝の態度に、11月16日、「相摸武蔵両国可為重任之由、被仰之許也、仍被下御感 院宣」(『吾妻鏡』文治三年十一月廿八日条)が帥卿経房が奉じ、11月28日に鎌倉に届けられた。
このころ、それまでまったく不明だった義経の所在についてひとつの情報が兼実に伝えられている。文治4(1188)年正月9日、「或人」が兼実に伝えたことによれば「去年九十月之比、義顕在奥州、秀衡隠而置之、即十月廿九日秀衡死去之刻、為兄弟和融、兄他腹之嫡男也、弟当腹太郎云々、以他腹嫡男令娶当時之妻云々、各不可有異心之由、令書祭文了、又義顕同令書祭文、以義顕為主君、両人可給仕之由有遺言、仍三人一味、廻可襲頼朝之籌栄」(『玉葉』文治四年正月九日条)というもので、義経が奥州にいる可能性が発覚した史料上の初見となる。『吾妻鏡』ではこれ以前の文治3(1187)年10月29日に「鎮守府将軍兼陸奥守従五位上藤原朝臣秀衡法師」の卒去が伝えられ、「秀衡入道於陸奥国平泉舘卒去、日来重病依少恃、其時以前、伊予守義顕為大将軍可令国務之由、令遺言男泰衡以下」(『吾妻鏡』文治三年十月廿九日条)とあり、泰衡らに義経を大将軍として陸奥国の「国務」を行うべきことを遺言していたと記している。ただし、頼朝はこの当時「是与州義経在所未聞」(『吾妻鏡』文治四年正月十八日条)であって、『吾妻鏡』の秀衡卒去及び遺言の事は後世『吾妻鏡』編纂時に挿入されたものである。その内容は『吾妻鏡』の記述と一致することから、『吾妻鏡』はこの記事については『玉葉』から取ったものである可能性が高い。また、『愚管抄』にも「秀衡ガ子ニ母太郎父太郎トテ子二人有ケリ、康衡ハ母太郎也、ソレニ伝ヘテ父太郎ハ別ノ所ヲスコシエテアリケル、父太郎ハ武者ガラユゝシクテ、軍ノ日モヌケ出テアハレ物ヤト見ヘケル」(『愚管抄』第五)と、こちらの記述も『玉葉』に近く、慈円僧正は実兄兼実から日記を借り受けて記載したとみられる。
【父太郎】
+―藤原信頼 藤原国衡
|(右近衞権中将) (信寿太郎)
| ∥
+―藤原基成―――――――後室 【当腹太郎】
(民部少輔) ∥―――――――――藤原泰衡
∥ (小次郎)
∥
+―藤原基衡―――――――藤原秀衡――――――藤原高衡
|(出羽押領使) (陸奥守) (四郎)
| ∥ ∥
| ∥ ∥―――――+―藤原忠衡
| ∥ ∥ |(泉三郎)
| ∥ ∥ |
| ∥ 女子 +―藤原通衡
| ∥ (泉七郎)
| ∥
| ∥ 【父太郎】
| ∥―――――――――藤原国衡
| 先妻 (信寿太郎)
|
+―藤原清綱―――――+―藤原俊衡――――+―藤原師衡
(亘十郎) |(樋爪入道蓮阿) |(太田御館)
| |
| +―藤原兼衡
| |(次郎)
| |
| +―藤原忠衡――――聖円
| (河北冠者) (延暦寺僧)
|
+―藤原季衡――――――藤原経衡
|(樋爪五郎) (新田冠者)
|
| +―佐藤継信
| |(三郎兵衛尉)
佐藤氏 +―女子 |
∥ ∥―――――――+―佐藤忠信
∥ ∥ (四郎兵衛尉)
∥――――――――――信夫佐藤庄司
∥ (湯庄司)
+―女子
|
+―河辺高経
|(太郎)
|
+―伊賀良目高重
(七郎)
頼朝が義経の情報を把握した正確な時期は不明だが、「二位大納言(兼房。摂政兼実の実弟)」が出羽国に派遣した「法師昌尊」が義経に追われて鎌倉に一報したときであろう(『玉葉』文治四年二月八日条)。法師昌尊が鎌倉に到着した日時もはっきりしないが、文治4(1188)年2月8日には兼実に報告されていることから、正月20日前後と考えられる。「法師昌尊」は「義顕在奥州、即件昌尊出自出羽国之間、与彼軍兵合戦、希有逃命来着鎌倉」とあるように出羽国からの帰途に義経勢と「合戦」に及び、命からがら鎌倉まで逃れてきたものであった。「合戦」とあることから、「法師昌尊」には国衙兵が護衛として付けられていたのだろう。鎌倉で頼朝から「早申国司可経院奏之由」と告げられた入道昌尊は急ぎ上洛し、出羽守藤原保房(国主兼房義父の従弟)に報告したのだろう。この報告は保房から兼房に伝えられ、2月8日に兼房から兄・摂政兼実に報告されることとなる(『玉葉』文治四年二月八日条)。
ただ、兼実は入道昌尊の申状が「雖委細不能具録」であり、義経の軍に襲われて逃げた、という内容のみ読み取れたようである。兼実は入道昌尊の言い分では「子細猶有疑」ったので、昌尊とともに「大納言副使者」ていた脚力を召して子細を聞いたところ、「申状同昌尊書状」であったことで、翌2月9日、兼実は家司盛隆を通じて法皇に奏聞する。しかし法皇も「此事争無御信用哉」という(『玉葉』文治四年二月九日条)。兼実は「此事已大事也、争私申返事哉、猶院有議定、可被遣別御使歟、被成宣旨院宣等宜歟者」と答えている。
なお、『吾妻鏡』によれば、文治3(1187)年3月5日に「予州義顕在陸奥国事、為秀衡入道結搆之由、諸人申状府合之間、厳密可被召尋之旨、先度被申京都訖」ことにつき、「及御沙汰之由」という法皇の言葉を右兵衛督能保が鎌倉に伝えており、頼朝が「先度被申京都訖」したのは少なくとも文治3(1187)年2月半ばとなる。しかし、『吾妻鏡』には、文治3(1187)年4月4日時点で「予州在所未聞、於今者非人力之所覃」(『吾妻鏡』文治三年四月四日条)、さらに翌文治4(1188)年正月18日時点でも「是与州義経在所未聞」(『吾妻鏡』文治四年正月十八日条)とも記されており、『吾妻鏡』の編纂過程では様々な記録の寄せ集めで相当な混乱が生じている。
源俊房――――源方子
(左大臣) ∥――――――藤原得子
∥ (美福門院)
∥ ∥―――――――近衞天皇
∥ ∥
∥ 鳥羽天皇 藤原基衡―――――藤原秀衡
∥ (出羽押領使) (陸奥守)
∥ ∥―――――――藤原泰衡――万寿
∥ +―藤原基成―――――女子 (小次郎)
∥ |(陸奥守)
∥ |
∥ 藤原忠隆――+―藤原信頼
∥ (大蔵卿) |(右近衞権中将)
∥ |
∥ +―女子
∥ | ∥――――――――藤原基通
∥ | 藤原基実 (摂政)
∥ |(摂政)
∥ |
藤原顕季―+―藤原長実―――藤原顕盛 +―女子
(修理大夫)|(権中納言) (備前守) ∥――――――――藤原隆房
| ∥ (大納言)
| ∥
+―藤原家保―+―藤原顕保 +―藤原隆季―――+―女子
|(参議) |(播磨守) |(権大納言) | ∥――――――藤原兼良
| | | | ∥ (大納言)
| +―藤原家成――+―藤原成親 | 藤原兼房
| |(中納言) (権大納言) |(権大納言)
| | |
| +―藤原家房 藤原能保 +―女子
| (右衛門佐) (右兵衛督) ∥
| ∥ ∥ ∥
| ∥ ∥――――――――藤原高能
| ∥ ∥ (左馬頭)
| ∥ +―女子
| ∥ |
| ∥ +―源頼朝
| ∥ (権大納言)
| ∥
| ∥―――――――藤原保房
| ∥ (出羽守)
| 藤原通憲―――女子
|(信西入道)
|
+―女子
∥――――――藤原忠親
∥ (内大臣)
藤原忠雅
(太政大臣)
文治4(1188)年2月13日、兼実邸に蔵人藤原盛隆が院使として訪問し、「追討宣旨事、人々一同計申、依彼趣可被仰下歟、但能保朝臣去夜有申旨、刑部丞成綱上洛、頼朝卿申送云、義顕在奥州事已実也、但頼朝為亡母造営五重塔婆、今年依重厄禁断殺生了、仍雖承追討使、雖可遂私宿意、於今年者一切不可及此沙汰、若彼輩於来襲者非此限、其條又忽非可思寄事、随又安平也云々、仍自公家直仰秀平法師子息於秀平者十月二十九日逝去了、可被召進彼義顕也、且是彼子息等与義顕等、同意之由風聞、為顕其真偽也、但此條頼朝故不能奏達、只内々能保可相計云々者、已上頼朝詞、能保申旨如此、然者宣旨之状可載此趣歟者」(『玉葉』文治四年二月十三日条)と告げた。兼実もこれらについて「所申尤可然、不可及異議可被載此由也」とし、奥州へは「官吏生之兼院庁官之者可差遣云々、縦雖向奥州、其仁不可変易歟」とすべきことを述べている。晩に及んで右兵衛督能保が兼実邸を訪れ、「頼朝不申院、不示此辺、推其意趣、今度宣旨為表起自叡襟之由歟」と困惑の様子がうかがえる。頼朝はこの申状は能保への報告であり、法皇や院近臣らへ知らせることを拒否する旨を能保に伝えていたのである。結局、頼朝の申状は法皇に奏聞され、翌2月14日、院使平棟範が兼実邸を訪れ、追討宣旨を院御所に持参したところ、法皇から早々に下すべき由を承ったという(『玉葉』文治四年二月十四日条)。また、経房は「宣旨使院使一人可宜之由雖存、被遣奥州者、両人可宜之由所存也」という。兼実はこれらを受けて、早々に左大臣経宗亭へ赴き、宣旨を下すべきことを指示し、同日「宜令前鎮守府将軍秀衡子息等、追討彼義顕并同意輩」の宣旨を下したのであった。
2月17日、蔵人藤原盛隆が兼実邸を訪れ、「頼朝卿申状」についての院宣を伝えている(『玉葉』文治四年二月十七日条)。頼朝の消息は二通で、そのうちの一通が「義顕可召進之由、可被仰秀衡法師子息、並改名不可然反本名之由事」であった。法皇はこれらを「任申請可被行歟」と諮問している。兼実は「義顕之間事、改名之條不可及異議、早可被摺改宣旨歟、仰可使秀衡法師子息等追討義顕之由、被下宣旨之條、若乖頼朝意趣哉否、聊可有思慮、其故ハ如今申状者、件泰衡季衡也与義顕同意、已為謀叛者之由言上、而無左右追討使之由、被載宣旨如何、若可有議定哉、但已被下之宣旨被召返之條、又於理不可然、尤可有予議歟如何」と答えている。
頼朝は義経を「義顕」と改めている現状を快く思っておらず、「反本名之由」を要求。兼実ももとより違和感を感じていた様子で、早々に義経に戻すことを答申する。この事も含めて義経に対する頼朝の何らかの意図を感じたのだろう。さらに申状では義経の「追討」ではなく、泰衡らに「召進」めるようという要望が汲み取れ、いったい頼朝の真意は何なのか、兼実は測りかねており「仰可使秀衡法師子息等追討義顕之由」が「若乖頼朝意趣哉否、聊可有思慮」と促すとともに「而無左右追討使之由、被載宣旨如何、若可有議定哉」と慎重を期すことを提言している。一方、すでに下してしまった追討に関する宣旨を召し返すことはよろしくなく、よくよく話し合うことが肝要であると述べている(『玉葉』文治四年二月十七日条)。
その後、院御所から再度戻ってきた盛隆からの報告では、法皇は兼実の意見を容れ「以謀叛者被載追討使之條、最不可然、如頼朝卿申状、先載庁御下文、可被下遣也者」と、頼朝の申状にあるようにまず院庁下文を遣わすことを兼実に伝えている(申状の詳細な内容の記録はないが、義経の名前の事と追討宣旨への慎重な要望とみられる)。これに兼実は「此事猶可被仰合能保朝臣也、已被下宣旨、被召返之條、事渉禁忌、又在京之武士等定令申歟、可被改宣旨状哉、猶只可被下御下文許歟、此條能可有計御沙汰也」と、すでに下されている追討宣旨の扱いに関して能保とよく相談して沙汰すべきことを進言した(『玉葉』文治四年二月十七日条)。
2月18日早旦、兼実は参院するも、いまだ近習の人々も出仕しておらず、「女房丹三位等」に出会うも、今回の参院の目的である「義顕之間事非女房之可奏事」と思って、判官代盛隆の参院を待ち、「猶被召返宣旨事可有思慮、只可被直宣下之趣也、宣旨院宣両方被下、尤可宜歟、可直之趣、今日尤可有議定、兼雅、経房、兼光卿等、尤可予議者」と奏聞した。その後、盛隆が戻って告げるには「所申可然、其趣被人々可議申者」であり、いまだ参院していなかった奉行職事平棟範を召し出すと、宣旨の趣を伝えた(『玉葉』文治四年二月十八日条)。
こうした中、兼実に悲劇が襲い掛かった。2月18日夜、参院ののち、次男左中将良経とともに、翌19日に行われる「故殿(忠通)御忌日」の法会及び舎利講論のために九条本邸へ赴いた。同じく内府良通もここ三日余りで体調の回復が見られたため、母とともに九条邸を訪れ、翌日、兼実、良通、良経らは法会を聴聞し、良通は兼実と同車で冷泉邸へと帰宅した。その帰途の車中では兼実は法華経などを念誦し、良通はこれを「閑聞之」であったという。なんとなく不調な様子が感じられる。
その後、良通は別車で冷泉邸に到着した母を伴って戻り、数刻の間、二人を前に雑事を談じている。深夜亥刻に「大原上人本成房湛教」が来たため、兼実は大原上人との対話に移るが、良通はなお母と話をしていたという(『玉葉』文治四年二月十九日条)。日付が代って子刻、良通は就寝。兼実も上人が帰ると就寝したが、その後しばらくすると、「内府方女房帥(良経乳母の帥局か)」が慌てて走り来て「大臣殿絶入」を告げた。兼実は跳ね起きると良通のもとへ走るが「身冷気絶、一塵ノ無憑」という状況であり、兼実は良通の急死という現実を受け止めると、その傍らで尊勝陀羅尼経を念誦。「事已一定、雖不能扶救、志之所之所々修誦経、宝物厩馬等献諸社、又如祭祓如雲霞修之」とし、知らせを受けた先ほどの大原上人が呼び戻され、はやくも「奉始仏教躰」されるが、事があまりにも危急であったため「已不能秘計、只唱神呪在傍」であった。これはまず智詮阿闍梨へ急使を送るが、阿闍梨の居住は九条であったため、阿闍梨が到来したのは20日卯刻であった。良通の面貌は「終焉之躰非罪業人歟、面貌端正仰而臥之、是善人々相」といい、兼実の祈祷僧であったとみられる仏厳聖人は、良通は「生天上歟」と述べる(『玉葉』文治四年二月十九日条)。実は仏巌聖人と経円阿闍梨は良通の臨終間際に呼び出されていたようで、仏巌が戒師となって良通は出家を遂げており、法名増道を授けられていた(『玉葉』文治四年二月廿日条)。智詮阿闍梨を呼んだものの、すでに「閉眼之後経二時所来也」であり、「加持、更有何益哉」という(『玉葉』文治四年二月廿日条)。加持は「凡為邪気絶入之人、依仏法之威験蘇生、其例甚多、今之有様非絶入之儀、如法之閇眼也、於今者百千万総計不所及」であり、この突然の嫡子の死去は「余及女房此後心身迷乱、万事不覚」であったという。
翌2月21日、「神心未安堵」の中で「被下義経追討之宣旨」の沙汰を行っている(『玉葉』文治四年二月廿一日条)。これは「去十八日於院被定仰其趣、同十九日棟範持来九条堂令見之、余粗有令改直事」という修正宣旨案を「今日重持来、即宣下左大臣」と確認後、左大臣経宗に宣下すべき旨の指示をした。
文治四年二月廿一日 宣旨
出羽守藤原保房言上 仰東海東山両道国司并武勇輩、被追討其身源義経及同意者等、乱入当国以毀破旧符偽号当時 宣旨致謀叛事
仰、件義経忽図逆節猥乖憲條、然間、神明垂鑑賊徒敗奔、仍仰五畿七道諸国、慥可索捕之由 宣下先訖、爰義経無所容身逃下奥州、撃先日之毀符、称当時之詔命、相語辺民、欲令野戦云々、件符者、縡不出従叡襟、自由之結構、武威之所推也、因茲可毀破之由、即被下 綸旨畢、何以其状、今欲遵行哉、奸訴之趣、責而有余、加之如風聞者、前民部少輔基成并秀衡法師子息泰衡等、与彼梟悪、既背鳳銜、虜掠陸奥出羽之両州、追出国衙庄家之使者、普天之下、寰海之内、何非王土、誰非王民、爭存違勅、可同暴虐乎、而隠居凶徒令巧謀叛、倩憶所行之躰、殆超造意之旨、但泰衡等無同心儀者、且召進義経身且受用庄公使、猶不拘 朝章爭可免天譴哉、不日遣官軍共可致征伐也、件等輩、早変容隠之思、宜抽勲功之節、縦云辺胡更莫違越
蔵人右衛門権佐平棟範奉
そして2月26日、兼光卿を上卿として「追討官符請印」し、「被成同庁御下文」も下されることとなる(『玉葉』文治四年二月廿六日条)。
院庁下 陸奥出羽両国司等
応任 宣旨状、令前民部少輔藤原基成并秀衡法師男泰衡等、且召進義経身且受用国司及庄役使等事
右、源義経并同意輩乱入当国、更以毀破旧符偽号当時 宣旨、致謀叛之由、出羽国司勒在状経言上、仍就彼状被下 宣旨既畢、基成泰衡等縦如風聞之説謬与狼心之群 勅命是重、慥改前非而守宣下状、召進義経身、件義経尋前咎後過、雖載 綸旨、積悪之余、天譴云臻、奸謀無成、空以敗亡之後、竊捧毀符、遁赴奥州云々、誠雖云辺民之至愚、爭可随奸心之余党哉、加之秀衡法師子息等、不顧責於幽顕、只寄事於左右、陸奥出羽両国吏務自由抑留、追却使者、結構之趣還渉疑慮、事若実者、被處謀叛之同罪、令官軍以征伐、若鸞鳳銜、捕搦螫賊者、随其勲労、須有優賞之状、所仰如件、両国司等宜承知勿違失、故下
文治四年二月廿六日 主典代織部正大江朝臣
別当左大臣藤原朝臣 判官代河内守藤原朝臣
右大臣藤原 民部少輔兼和泉守藤原朝臣
大納言源朝臣 左近衞権少將藤原朝臣
大納言兼右近衞大將藤原朝臣 散位藤原朝臣
權大納言藤原朝臣 紀伊守藤原朝臣
權大納言藤原朝臣 土佐守藤原朝臣
權大納言藤原朝臣 勘解由次官平朝臣
權中納言兼陸奥出羽按察使藤原朝臣 右衛門権佐藤原朝臣
權中納言藤原朝臣 右少弁藤原朝臣
權中納言兼右衛門督藤原朝臣 防鴨河使左衛門権佐平朝臣
權中納言藤原朝臣 大工頭藤原朝臣
權中納言源朝臣 左少弁藤原朝臣
權中納言兼大宰権帥藤原朝臣
權中納言藤原朝臣
參議備前守藤原朝臣
參議左大弁兼丹波権守平朝臣
參議左兵衛督藤原朝臣
右京大夫兼因幡守藤原朝臣
宮内卿藤原朝臣
内蔵頭藤原朝臣
右近衞権中将播磨守藤原朝臣
修理大夫藤原朝臣
修理右宮城使右中弁平朝臣
造東大寺長官権右中弁藤原朝臣
修理権大夫藤原朝臣
丹波守藤原朝臣
2月28日、22日に「嵯峨辺小堂」に移された内府良通の葬送の儀が行われた。日ごろ良通が語っていた「火葬有功徳、土葬不甘心」を尊重して、薪を用いず藁による火葬が執り行われた。翌29日、慈徳寺法印によって二瓶に収骨され、ひとつは宇治木幡の摂関家菩提寺・浄妙寺に収められた(『玉葉』文治四年二月廿九日条)。
2月29日、鎌倉に右兵衛督能保からの書状が届いているが、能保は「予州事、為被仰奥州泰衡、被遣勅使官史生国光、院庁官景弘等、来三月可下向」との情報を伝えている(『吾妻鏡』文治四年二月廿九日条)。
3月15日には梶原景時の宿願であった大般若経供養が鶴岡山八幡宮寺で執り行われ、頼朝も列席した。なお、このとき、武田兵衛尉有義が路次の御剣役を命じられるも渋り、頼朝の激怒を受けて逐電する騒ぎがあった。頼朝に供奉した行列として、先陣随兵八人の一人に「千葉次郎師胤(千葉次郎師常の誤記)」、御後二十二人の一人に「千葉介」、後陣随兵八人には「千葉大夫胤頼」、路次随兵三十三人には「千葉五郎(胤通)」の名が見られる(『吾妻鏡』文治四年三月十五日条)。
| 先陣随兵 | 小山兵衛尉朝政 | 葛西三郎清重 | 河内五郎義長 | 里見冠者義成 |
| 千葉次郎師胤 (千葉次郎師常) |
秩父三郎重清 (長野三郎重清) |
下河辺庄司行平 | 工藤左衛門尉祐経 | |
| 源頼朝 | ||||
| 御後:各布衣 | 参河守 | 信濃守 | 越後守 | 上総介 |
| 駿河守 | 伊豆守 | 豊後守 | 関瀬修理亮 | |
| 村上判官代 | 安房判官代 | 藤判官代 | 新田蔵人 | |
| 大舎人助 | 千葉介 | 三浦介 | 畠山次郎 | |
| 足立右馬允 | 八田右衛門尉 | 藤九郎 | 比企四郎 | |
| 梶原刑部丞 | 梶原兵衛尉 | |||
| 後陣随兵 | 佐貫大夫広綱 | 千葉大夫胤頼 | 新田四郎忠常 | 大井次郎実春 |
| 小山田三郎重成 | 梶原源太左衛門尉景季 | 三浦十郎義連 | 同平六義村 | |
| 路次随兵 各相具郎等三人 |
千葉五郎 | 加藤太 | 加藤藤次 | 小栗十郎 |
| 八田太郎 | 渋谷次郎 | 梶原平次 | 橘次 | |
| 曽我小太郎 | 安房平太 | 二宮太郎 | 高田源次 | |
| 深栖四郎 | 小野寺太郎 | 武藤次 | 熊谷小次郎 | |
| 中條右馬允 | 野五郎 | 佐野太郎 | 吉河次郎 | |
| 狩野五郎 | 工藤小次郎 | 小野平七 | 河匂三郎 | |
| 広田次郎 | 成勝寺太郎 | 山口太郎 | 夜須七郎 | |
| 高木大夫 | 大矢中七 |
3月29日、奥州平泉の「前民部少輔基成并秀衡法師子息泰衡等」へ「可搦進予州之由」を命じる宣旨(二月廿一日付)と院庁下文(二月廿六日付)を帯びた勅使官史生国光と院庁官景弘が京を出立した。途中、4月9日に鎌倉に寄って頼朝に謁し、頼朝はその帯びた宣旨および院庁下文を内々に披見している。また、勅使の扱いについて頼朝への指示があり、頼朝は接待役として稲毛三郎重成、畠山次郎重忠、江戸太郎重長の三名を指定して「仍守其旨、無懈緩之儀、可致沙汰」と命じている(『吾妻鏡』文治四年三月廿九日条)。その後、鎌倉を発った勅使・院使は、武蔵国、下野国を通って奥州へと下っており、武蔵国と下野国での勅使接待を行った御家人が「雑事等致丁寧畢」を幕府に報告している(『吾妻鏡』文治四年五月四日条)。
9月14日、昼前に参内した兼実は、御所で蔵人平棟範と対面し、「頼朝卿請文」「先日遣奥州官使持参泰衡請文」「両府申状之返状」が渡されているが、兼実は「左右只可在勅定」という(『玉葉』文治四年九月十四日条)。「頼朝卿請文」は頼朝が申請した「諸国可禁断殺生之由 宣旨状」(『吾妻鏡』文治四年八月卅日条)に対する請文と思われる。また、「先日遣奥州官使持参泰衡請文」は義経捕縛の宣旨に対する請文であろう。ところがここには何らかの「子細」が記されており、泰衡は義経の捕縛を拒否していたとみられる。そればかりではなく、義経は奥州藤原氏の影響下内での自由な行動及び軍勢を動かす権限(結果としてこれが義経が奥州にいることが発覚するきっかけとなっている)を付与されていたのである。これに対して10月12日、朝廷は泰衡に義経を「召進」ことを強く命じる宣旨を下すこととなる(『吾妻鏡』文治四年十月廿五日条)。
文治四年十月十二日 宣旨
前伊予守源義経、忽挿奸心、早出上都、恣巧偽言、渉赴奥州、仍仰前民部少輔藤原基成并秀衡子息泰衡等、可召進彼義経之由被下 宣旨先畢、而不恐皇命、猥述子細、普天之下、豈以可然哉、加之義経当国之中廻出之由慥有風聞、漸送月緒委加捜索、定無其隠歟、偏与野心、非軽 朝威哉、就中泰衡継祖跡於四代、施己威於一国、境内之俗誰不随順、重仰彼泰衡等、不日令召進其身、於有同意之思者、定遺噛臍之恨歟、専守鳳衙之厳旨不同梟悪之誘引、随其勲功賜以恩賞、若従凶徒、猶図逆節、差遣官軍宜令征伐、王事靡監、敢勿違越
蔵人右衛門権佐藤原朝臣定(奉)
10月17日、頼朝は「年来与予州、成断金契約、仍今度牢籠之間、数日令隠容之、又至赴奥州之時者、相率伴党等送長途」した比叡山悪僧の「俊章」が帰洛ののちに謀叛を企てているという風聞があり、その在京御家人に対して動向を窺って捕縛するよう指示している(『吾妻鏡』文治四年十月十七日条)。俊章は鞍馬から比叡山へ逃れ、さらに奥州へと向かった際に協力した三人の悪僧の一人である。
そして11月、先日下された義経を捕縛する宣旨に副えて院庁下文が「陸奥出羽両国司等」に下されたのだった(『吾妻鏡』文治四年十二月十一日条)。
院庁下 陸奥出羽両国司等
可早任両度 宣旨状、令前民部少輔藤原基成并秀衡法師子息泰衡等不日召進源義経事
右、件義経、可令彼基成泰衡等召進之由、去春被下 宣旨并院宣之處、泰衡等不敍用 勅命、無驚 詔使、猥廻違越之奸謀、只致披陳於詐偽、就中、義経等猶結群凶之余燼、慥住陸奥之辺境云々、露顕之趣風聞已成、基成泰衡等、身為王民、地居帝土、何強背鳳詔、盍可与蜂賊哉、結搆若為実者、縡既絶篇籍歟、同意之科責而有余、慥任両度 宣旨、宜令召進彼義経身、若猶容隠不遵苻旨者、早遣官軍可征伐之状、所仰如件、両国司等宜承知勿違失、故下云々
文治四年十一月日
この院庁下文から、泰衡は基成とともに秀衡入道卒去から一年にわたりその身を庇護し、隠遁していたことがわかる。それは事態が発覚したのちも、宣旨や院庁下文をまったく無視した態度を取り続けたことがわかる。
文治5(1189)年正月13日、兵衛尉時定が兼実邸を訪れて、「有九郎還京都之消息等」を持った「手光七郎」なる人物を捕らえたと報告し、手光七郎が持っていた消息を兼実に届けている。ところが兼実は「実不可思議事也」と深く怪しんでいる様子がみえる(『玉葉』文治五年正月十三日条)。
2月22日、頼朝は雑色時沢を京都へ遣わし、義経に与同する人々への懲罰など条々の要求をしたという(『吾妻鏡』文治五年二月廿二日条)。
一、奥州住人藤原泰衡令容隠義顕之上与同叛逆、無所疑歟、蒙御免欲加誅罸事
一、頼経卿同意義顕之臣也、可被解官追放之由先度言上畢、而雖有勅勘之号、于今在京鬱訴相貽事
一、按察大納言朝方卿、左少将宗長、出雲侍従朝経、出雲目代兵衛尉政綱、前兵衛尉為孝、
此輩依同意義顕之科、可被解却見任事
一、山僧等横兵具同意義顕事、結搆之至可有御誡之由、先日言上之間、其旨 宣下畢之趣、雖有
勅答、猶弓箭太刀刀繁昌山上之由有風聞事
一、依 上皇御夢想、平家縁坐流人可被召返事、如僧并時実信基等朝臣、有何事哉、被召返條可有
勅定事
一、崇敬六條若宮、為御所近辺、就祭祠等事、定狼藉事相交歟、殊恐存事
この頼朝の要求を受けた法皇は、3月8日に「関東申頼経配流事、可急申沙汰之由」(『玉葉』文治五年三月八日条)を指示し、10日には帥卿経房が法皇の意向をまとめて朝廷に奉書する(『吾妻鏡』文治五年三月廿日条)。この結果、翌11日には「此日被行流人、前刑部卿頼経流伊豆国」(『玉葉』文治五年三月十一日条)が決定され、翌12日早々に宣下(『吾妻鏡』文治五年三月廿日条)されることとなる。また、9日には経房のもとに「奥州基成朝臣并泰衡等請文」が届き、そこには「可尋進義顕之由載之」だったという。この請文は天王寺で仏事中の法皇に届けられ、法皇は「早可召進之由、重可被仰之旨、自彼寺態以被申殿下」と、早々に義経等を召し進めるよう泰衡へ指示するよう兼実へ命じている(『吾妻鏡』文治五年三月廿日条)。なお、『玉葉』にはこの法皇の指示についての記載はない。
右兵衛督能保は頼経配流宣下の翌13日、鎌倉へ「前刑部卿頼経卿可被配流伊豆国之由宣下、子息宗長同前、此外事等、條々皆可有勅裁之」ことや、泰衡が進めた請文を送っている。ただし、朝方の件については、法皇は「抑彼卿鬱結之條、依何由緒哉、更不思食寄事也、返々驚聞食者也、若為僻事、為人尤不便事也、如此事、被尋决真偽可宜歟、件消息早可令進覧給、可披見之故也、彼卿無左右書進誓状、令恐驚申之條、以之可令推察歟」と拒む旨をしたためた(『吾妻鏡』文治五年三月廿日条)。
この能保の書状を受けた頼朝は、3月22日、側近の成勝寺執行法橋昌寛を帥卿経房のもとに消息を派遣した(『吾妻鏡』文治五年三月廿二日条)。その内容は「是泰衡自由請文、聊非御許容之限、速可被下追討 宣旨之由、依重被申也」ことが主題で、ほかは「鶴岡塔供養願文、可調給之旨、内々所望給」ことと「同導師可然之僧一人、可令計申請給者」の二点であったとする。ただし、これはあくまでも後世に記述された『吾妻鏡』の記述であり、頼朝が主として行った「泰衡追討」「鶴岡山八幡宮寺供養」を主眼に置くための記載とも考えられ、ほかのことも書かれていたであろう。この消息文は天王寺で経房が受けたのち法皇に奏ぜられた。一品房昌寛の天王寺着日時は不明だが、4月4日夜、法皇は兼実に「頼朝卿申、朝方卿同意行家之間事」(『玉葉』文治五年四月四日条)を告げており、これ以前という事になる。頼朝消息文には朝方の解却を望む理由として「朝方卿同意行家」(『玉葉』文治五年四月六日条)と明記されていたが、これは『吾妻鏡』の「同意義顕」とは明確に異なっている。そして翌4月5日夜半、頼朝消息文は経房から弟の蔵人頭定長へ届けられ、翌6日、奏上前に兼実が内覧している(『玉葉』文治五年四月六日条)。この消息は「頼朝卿重申朝方卿事」だったとあり、『吾妻鏡』が主題とする「泰衡」追討のことや「鶴岡塔供養願文」は『玉葉』には記されず、朝方の去就のみが記されているのは、兼実にとって泰衡追討等は興味の他であったためと考えられよう。
4月8日、帥卿経房は院宣を消息に認め、在京の梶原平三景時が郎従に託し、使者は19日に鎌倉に到着している(『吾妻鏡』文治五年四月十九日条)。この中で、法皇は怒りを込めて「頼経卿父子、朝方卿父子事、任令申請給之旨、被沙汰切畢」と、頼朝の申請に任せて頼経・宗長父子、朝方・朝経父子を処分したことを報告(9日に朝方の解官及び停国の沙汰が決定され、13日に解官)した上で、「且彼政綱通義顕之状、早可進覧」と、出雲守朝経の目代・兵衛尉政綱が義経と通じていたという明確な証拠を早々に進覧せよと命じた。また、叡山の武装停止を座主に命じたこと、「奥州事」は摂政以下諸卿との話し合いの上で勅答することを伝えた。この院宣を見た頼朝は法皇の逆鱗を感じたのだろう。「被進 院宣御請文、所被染自筆也」と自ら「出雲国目代兵衛尉政綱事」について弁明の書を記し、、法皇に対する敵対心はないことを表し、朝方らによく仰せ含められ重罪にせぬようにと奏上している(『吾妻鏡』文治五年四月廿一日条)。
また4月9日、奥州追討の事につき、蔵人大輔定経を奉行として禁裏において討議され、泰衡の申状は「前後相違、返々奇恠」であるが、いまだ遣わされた官使が戻っていない状態では追討の宣旨を下すことはできないこと、泰衡の更なる申状を待つべきであること、追討の祈祷を行うことによる冥助を頼り殊に念じる事こそ重要であるとして、現時点での追討宣旨は見送られることとなり、経房より鎌倉へ子細を伝えている(『吾妻鏡』文治五年四月廿二日条)。
文治5(1189)年3月10日、片岡次郎常春が「召放領所等下総国三崎庄、舟木、横根、如元被返付」について、沙汰人等が「以日者之融令忽諸之由」を訴えたことから、頼朝はこの返付の停止を指示した(『吾妻鏡』文治五年三月十日条)。常春が返付された領所「下総国三崎庄、舟木、横根」は、常春が「同心佐竹太郎常春舅」と同調したという疑いで召し放たれ、文治元(1185)年10月28日に「賜千葉介常胤依被感勤節等也」という地であり(『吾妻鏡』文治元年十月廿八日条)、頼朝は三崎庄を常胤から悔い返した上で常春に返付したことになる。ただ、この三崎庄についてはその後、常胤の六男・六郎大夫胤頼が地頭職として入っており、常胤に再度付与されたと思われる。
4月18日、常胤は北条時政の三男の元服式に、嫡孫・成胤とともに列席。時政三男は三浦義連の加冠によって元服し、偏諱を受けて「五郎時連」(のちの時房)を称した。
閏4月8日、法皇は奥州追討の件につき、五位蔵人家実(のちの帥中納言資実。基通嫡子諱を避けて名を資実と替える。日野氏祖)を天王寺から兼実のもとに遣わし「追討事自本可然之由思食之上、如此令申尤神妙歟、思食早可成賜宣旨、来六月塔供養之由聞食、若過彼間可遣歟、将今明可遣歟、可随令申、且又官使出立之間、自経日数歟、仍且為用意所仰遣也」(『玉葉』文治五年閏四月八日条)と、法皇は追討自体を然るべき事として捉えており、早々に追討宣旨を下すことを望んでいたことがわかる。ただし、来る六月に鶴岡八幡宮寺において塔供養があることに配慮し、塔供養後に遣わすべきか、まさに今遣わすべきか、諮問している。
これをうけた兼実は「抑、伊勢遷宮并造東大寺者、我朝第一之大事也、而赴征伐之間、諸国定不静歟、然者可成彼両事之妨、件條殊召仰不可致造宮造寺之害、為公為私以之可用追討之祈祷也、以此趣経房卿可書遣御教書於頼朝卿許者」(『玉葉』文治五年閏四月八日条)と返奏し、伊勢遷宮や東大寺再建の妨げとなる追討宣旨下賜を回避しようと考えていた。兼実は遠境へ逃れ去った義経を脅威とは感じず、それよりも国家の大行事である「造宮造寺之害」を恐れていたことは明白である。兼実は蔵人家実へただちに帥卿経房邸に行って子細を報告するよう指示している(『玉葉』文治五年閏四月八日条)。
一方、8日の追討宣旨不可の子細は経房卿から頼朝へ送られたと考えられ、21日、頼朝は「泰衡容隠義顕事、公家爭可有宥御沙汰哉」と朝廷の沙汰に不満を述べるとともに、「任先々申請之旨、早被下追討 宣旨者、塔供養之後、可令遂宿意之由」と、再度の追討宣旨下賜を帥卿経房へ要請した(『吾妻鏡』文治五年閏四月廿一日条)。なお、頼朝が望んでいた「追討」の対象は義経ではなく、義経の召進を無視し続ける泰衡であることがわかる。泰衡は義経召進の勅命及び院宣を受けながらも一年以上にわたって「前後相違、返々奇恠」という申状を奏聞し、事実上朝命を無視し続けていたが、当然頼朝からも征討を直言する文書が届けられていたと考えられよう。これにより泰衡は頼朝の圧力に抗いきれないと感じたのだろう。閏4月30日、「於陸奥国、泰衡襲源予州」した。この日「予州在民部少輔基成朝臣衣河舘、泰衡従兵数百騎馳至其所合戦」(『吾妻鏡』文治五年閏四月卅日条)と、外祖父基成の衣川舘に住む義経を数百騎の兵で襲ったのである。泰衡への勅命および院宣(頼朝の意向を受けたもの)はあくまでも義経の身柄の召進であって、泰衡の行動も義経の身柄を押さえることが目的であったろう。しかし攻められた義経側は「予州家人等雖相防悉以敗績」し、「予州入持仏堂、先害妻廿二歳、子女子四歳、次自殺」と、基成邸の持仏堂に籠り、妻子ともども自害してしまうのであった。
 |
| 平泉高舘より衣川を望む |
鎌倉に泰衡からの「去閏四月晦日、於前民部少輔基成宿館奥州誅義経畢」(『吾妻鏡』文治五年五月廿日条)という報告が届いたのは、事件から二十日以上経た5月22日のことだった。これを受けた頼朝は、ただちに義経誅殺の旨を急ぎ京都に奏達したが、義経死去により、親族である頼朝は障りを受け、6月9日に予定されていた鶴岡山八幡宮寺の塔供養は延引されることとなる。しかしこの塔供養は、供養願文から導師の選定まで法皇に依頼し決定している以上、延引はあってはならない事態である。頼朝も奥州追討は「塔供養之後」と予定するほど慎重だったにもかかわらず、泰衡の勝手な行動(義経の捕縛ではなく殺害)によって、仏事の延引を法皇に奏聞することを余儀なくされたのである。これも泰衡に対する更なる遺恨となったのであろう。
5月29日、頼朝からの書状を受けた右兵衛督能保は、兼実のもとに「九郎為泰衡被誅滅了」という一報を届けている(『玉葉』文治五年五月廿九日条)。5月22日に鎌倉を発した頼朝消息は右兵衛督能保へ宛てられたものだったのだろう。なお、この頼朝の消息は塔供養の延引が主題で、義経が討たれたことは塔供養延引の理由として副えられている程度である。それほどに法皇までをも動かした塔供養の延引は一大事だったのだろう。また、この消息を見た兼実は「天下之悦何事如之哉、実仏神之助也、抑又頼朝卿之運也、非言語之所及也」(『玉葉』文治五年五月廿九日条)と喜びを示しているが、これは義経という「個人」が討たれたことに対する喜びではない。義経誅殺により頼朝の奥州追討の名分が失われ、兼実が強く進める神宮遷宮や東大寺造営という朝廷の大事、さらに氏長者として行う興福寺復興事業への障りがなくなったこと、及び安穏の世の到来を予感したためであろう。
これ以降『玉葉』には朝廷及び氏長者としての重要な事柄が記載される一方で、関東及び奥州の事件はほぼ掲載されなくなる。その後も『吾妻鏡』の記述によれば頻繁に京都への使者が遣わされているが、これらについて兼実は触れておらず、もはや兼実にとって関東からの戦乱報告や追討宣旨の要求は興味の薄いものになっていたことがわかる。
6月3日、宮寺塔供養の導師として、天台座主僧正全玄の代官・中納言法橋観性が佐々木四郎左衛門尉高綱に伴われて鎌倉に到着。幕府南門近くにあった八田知家邸が宿所と定められ、頼朝は三浦平六義村を遣わして菓子を供した(『吾妻鏡』文治五年六月三日条)。法皇には塔供養延引を奏聞したものの、すでに導師法橋観性は鎌倉への途路にあり、法皇からも馬などが下されていたことから、塔供養の延引は不可能と判断し、決行へと方針を変えた(『吾妻鏡』文治五年六月三日条)。頼朝自身の参会についても「御軽服三十余日馳過訖」と、義経の死からすでに三十日以上経っており、内陣に入らなければ差し支えなしとされたのである。
また、6月6日、北条時政は奥州征討の祈念のために、伊豆国田方郡北条内に下向し、新寺院の立柱ならびに上棟供養を行い「願成就院」と名付けた(『吾妻鏡』文治五年六月六日条)。
「願成就院」という寺号は、奥州征討後の人々の往生救済を願い、本尊として奈良仏師運慶による「阿弥陀三尊并不動多聞形像等」を奉じたのであった。不動明王は泰衡ら謀叛人の鎮圧と救済、多聞天は奥州からの鎌倉守護を意図したものであろう。後年「伊豆国願成就院北畔為被搆二品御宿館犯土、忽掘出古額、其文願成就院」(『吾妻鏡』文治五年十二月九日条)と、願成就院の北に頼朝の宿所(現在の堀越公方御所跡の地か)を造営するべく土木工事を行ったところ、古い額が掘り出され、そこにはなんと「願成就院」と記されていた。「寺号又任御心願之所催、兼被撰定之處、重今依無一字之依違有自然之嘉瑞、即加修飾、可被用于当寺之額」と、この奇瑞を以て寺の額としたという。ただし実際はもともと「願成就院」という阿弥陀如来を祀る廃寺の伝があり、時政はその謂れから同名の寺院を再建を志したのか。
6月8日、京都から帥卿経房の返報が鎌倉に到着した。5月29日に右兵衛督能保に着いた消息の返報であろう。法皇は「義顕誅罸事、殊悦聞食之由」とともに「彼滅亡之間、国中定令静謐歟、於今者可嚢弓箭之由、内々可申之旨、其沙汰候」(『吾妻鏡』文治五年六月八日条)と、義経を討ったからには国は鎮まるであろうから、兵を収めるべしという内々の法皇の意向を伝えている。ところが、頼朝の目的は穢を伴う義経殺害ではなく、あくまでも泰衡追討による奥州鎮圧である。この頼朝の思惑と奥州征討を拒否する朝廷の間には著しい認識の乖離があった。
翌9日、鎌倉鶴岡山八幡宮寺では、塔供養が予定通り行われた(『吾妻鏡』文治五年六月九日条)。出御にあたり、法橋観性を導師に、若宮別当法眼円曉を呪願として挙行され、頼朝は義経の服喪中のため馬場柵付近に桟敷を構えて儀式を見物。隼人佐三善康清と梶原平三景時の両名が行事を執行した。列後には千葉介常胤、千葉大夫胤頼(東六郎大夫)、後陣の随兵には千葉太郎胤正が随っている。
| 先陣随兵 | 小山兵衛尉朝政 | 土肥次郎実平 | 下河辺庄司行平 | 小山田三郎重成 |
| 三浦介義澄 | 葛西三郎清重 | 八田太郎朝重 | 江戸太郎重継 | |
| 二宮小太郎光忠 | 熊谷小次郎直家 | 信濃三郎光行 | 徳河三郎義秀 | |
| 新田蔵人義兼 | 武田兵衛尉有義 | 北條小四郎 | 武田五郎信光 | |
| 次御歩(束帯) | 源頼朝 | |||
| 御剣 | 佐貫四郎太夫広綱 | |||
| 御調度 | 佐々木左衛門尉高綱 | |||
| 御甲 | 梶原左衛門尉景季 | |||
| 列御後(布衣) | 武蔵守義信 | 遠江守義定 | 駿河守広綱 | 参河守範頼 |
| 相摸守惟義 | 越後守義資 | 因幡守広元 | 豊後守季光 | |
| 皇后宮権少進 | 安房判官代隆重 | 藤判官代邦通 | 紀伊権守有経 | |
| 千葉介常胤 | 八田右衛門尉知家 | 足立右馬允遠元 | 橘右馬允公長 | |
| 千葉大夫胤頼 | 畠山次郎重忠 | 岡崎四郎義実 | 藤九郎盛長 | |
| 後陣隨兵 | 小山七郎朝光 | 北條五郎時連 | 千葉太郎胤政 | 土屋次郎義清 |
| 里見冠者義成 | 浅利冠者遠義 | 三浦十郎義連 | 伊東四郎家光 | |
| 曽我太郎祐信 | 伊佐三郎行政 | 佐々木三郎盛綱 | 新田四郎忠常 | |
| 比企四郎能員 | 所六郎朝光 | 和田太郎義盛 | 梶原刑部丞朝景 |
供養後の布施として、法皇からの布施である赤、青の錦被物は、それぞれ駿河守広綱、皇后宮権少進(中原盛景カ)が、帥卿経房からの紫錦被物は安房判官代源高重が献じ、神馬は、四御馬を千葉次郎師常(相馬次郎師常)、千葉四郎胤信(多部田四郎胤信)がそれぞれ曳いている。
| 一御馬 | 葦毛(仙洞御馬) | 畠山次郎重忠、小山田四郎重朝 |
| 二御馬 | 河原毛 | 工藤庄司景光、宇佐美三郎祐茂 |
| 三御馬 | 葦毛 | 藤九郎盛長、渋谷次郎高重 |
| 四御馬 | 黒 | 千葉次郎師胤、千葉四郎胤信 |
| 五御馬 | 栗毛 | 小山五郎宗政、下河辺六郎 |
6月13日、泰衡の使者・新田冠者高衡(秀衡四男)が義経の首級を腰越浦に持参し、その旨を鎌倉に言上した。これを受けた頼朝は、和田義盛と梶原景時に武装させた上、甲冑の郎従二十騎を具して腰越に遣わしている(『吾妻鏡』文治五年六月十三日条)。この首級持参は5月22日に泰衡が約した「其頚追所進」によるもので、6月7日に頼朝が塔供養に際して穢を防ぐために「与州頚、無左右不可持参、暫可令逗留途中之旨、被遣飛脚於奥州」(『吾妻鏡』文治五年六月七日条)と指示していたものであった。義経の首は、そのころすでに関東近辺まで上っていたと思われるが、塔供養が終わるまで留め置かれていたのであろう。義経の首級は黒漆の櫃の中に満たされた美酒の中に安置されていたが、高衡の僕従二名が担っていた。謀叛人とはいえ義経は平家追討の殊勲者であることは衆人の認めるところであり、また御家人の記憶にも新しいものであった。そのような人物が、泰衡代の高衡の従類如きに担がれている様子に「観者皆拭双涙、湿両衫」(『吾妻鏡』文治五年六月十三日条)であったという。
6月20日、鶴岡山八幡宮寺の臨時祭が挙行され、流鏑馬や競馬など神事が催されたが、頼朝は義経の服喪中であったため参宮および奉幣は行われなかった。義経の自害は閏4月30日であり、「兄弟軽服、日数為五十日」(『吾妻鏡』弘長元年六月廿七日条)の例もあり、例の通り五十日であればこの臨時祭当日が忌明となり、忌明けを以て奥州追討について具体的に動き始めたとみられる。
6月24日、頼朝は「奥州泰衡、日来隠容予州科、已軼反逆也、仍為征之、可令発向給之間、御旗一流可調進之由、被仰常胤」と、奥州追討について御旗一流の調進を常胤に命じた(『吾妻鏡』文治五年六月廿四日条)。常胤へが選ばれたのは「治承四年、常胤相率軍勢参向之後、諸国奉帰往、依其佳例」(『吾妻鏡』文治五年七月八日条)のためであった。旗のもととなる絹布は小山兵衛尉朝政が献じたものであった。朝政が絹布献上を任されたのも「先祖将軍輙亡朝敵之故也」(『吾妻鏡』文治五年七月八日条)という先例に沿ったものである。この日の夜、京都より右兵衛督能保の消息が到着した。法皇が内々に仰せられるには「連々被経沙汰此事、関東鬱陶雖難黙止、義顕已被誅訖、今年造太神宮上棟、大仏寺造営、彼是計会追討之儀、可有猶予者、其旨已欲被献殿下御教書」(『吾妻鏡』文治五年六月廿四日条)というものであった。ところが、頼朝はこの法皇の内々の指示にも拘わらず、これを全く拒絶して「奥州事、猶可被下追討 宣旨之由、重被申京都」(『吾妻鏡』文治五年六月廿四日条)という。
6月26日には、奥州で泰衡が弟の泉三郎忠衡を誅殺したことが鎌倉に伝えられている。これは忠衡が義経に加担していたため「依有 宣下旨也」(『吾妻鏡』文治五年六月廿六日条)という。しかし、二度にわたって出された宣旨は義経追討ではなく「可召進彼義経之由被下 宣旨先畢」であり、奥州追討の噂が現実味を帯びる中、義経と親しかった忠衡を誅殺することで頼朝に対する恭順の意を示したのだろう。ところが、頼朝は「此間奥州征伐沙汰之外無他事」(『吾妻鏡』文治五年六月廿七日条)と記されるほど、奥州攻めの準備は確実に進行していた。諸国から鎌倉へ集まる軍勢もすでに一千人に及び、和田義盛、梶原景時の両司を奉行として交名を注し、前図書允清定がそれを記録している。その規模は「伊澤五郎之催」で「安芸国大名葉山介宗頼」が鎌倉へ向かっていることから(『吾妻鏡』文治五年十月廿八日条)、国惣追捕使に任じられていた御家人は管国内の軍勢催促権を有し、招集していたと考えられる。なお、武蔵国と下野国は奥州への順路であることから、両国の御家人は鎌倉に来るに及ばず、用意のみ行っておき、進発の追討軍に加わるよう命じている(『吾妻鏡』文治五年六月廿七日条)。
奥州進発の用意が整いつつあった6月30日、頼朝は「武家古老、兵法存故実」として重用されていた、大庭平太景能を御所に召し、いまだ宣旨がもたらされない今「奥州征伐事」を問うた。頼朝は「此事窺天聴之處、于今無勅許、憖召聚御家人、為之如何、可計申者」と聞くと、景能は何ら考えることなく「軍中聞将軍之令、不聞 天子之詔云々、已被経 奉聞之上者、強不可令待其左右給、隨而泰衡者、受継累代御家人遺跡者也、雖不被下 綸旨、加治罰給有何事哉、就中、群参軍士費数日之條、還而人之煩也、早可令発向給者」と、『漢書』の例を引いて勅許がなくとも早々に泰衡を追捕すべきと語っている。頼朝の父・義朝以来の古老である景能の言葉に頼朝は深く感じ、小山七郎朝光に指示して御厩の鞍置馬を景能に給わった。三十年以前の保元の乱に際し、鎮西八郎為朝の強弓を足に受けて以来歩行が儘ならず、御所縁側から庭上に降りることができない景能に対し、朝光は馬の差縄を縁側へ投げて受け取り、体裁を保った。
その後、景能は孫ほども歳の離れた朝光を招くと、「吾老耄之上、保元合戦之時被疵之後、不行歩進退、今雖拝領御馬、難下庭上之處、被投縄、思其芳志直千金」と賀している(『吾妻鏡』文治五年六月卅日条)。
7月8日、千葉介常胤は命じられていた新調の御旗を頼朝に献じた。その長さは「前九年の役」の「入道将軍家頼義」の旗と同じ一丈二尺の二幅で、上にはそれぞれ伊勢大神宮、八幡大菩薩が、下には相対する二羽の鳩が縫い取られていた(『吾妻鏡』文治五年七月八日条)。
この旗は三浦介義澄の手で鶴岡八幡宮に奉納され、七日間の祈祷ののち、奥州征討の旗とされた。また同日、下河辺庄司行平が新調の鎧を頼朝に献じた。このとき、頼朝は袖につけられるべき笠標が兜の後ろについているのを見て不思議に思い、「此簡付袖為尋常儀歟、如何者」(『吾妻鏡』文治五年七月八日条)と問うた。これに行平は「是曩祖秀郷朝臣佳例也、其上、兵本意者先登也、進先登之時、敵者以名謁知其仁、吾衆自後見此簡、可必知某先登之由者也、但可令付袖給否可在御意」と答えている。これに頼朝は「調進如此物之時用家様者故実也」(『吾妻鏡』文治五年七月八日条)として行平を賞した。
7月16日、京都から右兵衛督能保の使者として在京御家人・後藤兵衛尉基清と、京都へ遣わしていた頼朝使者が鎌倉に帰着し、能保からの朝廷の情勢を伝えている。基清が言うには、
「泰衡追討 宣旨事、摂政公卿已下被経度々沙汰訖、而義顕出来、此上猶及追討儀者、可為天下大事、今年許可有猶予歟之由、去七日被下 宣旨也、早可達子細之由、師中納言相触之、可為何様哉」(『吾妻鏡』文治五年七月十六日条)
という。6月24日の頼朝の申状は法皇や朝廷の意思を覆すことはできず、しかもこれまでは曖昧な不戦の指示であったり、法皇の内々の意向に留まっていたものが、7月7日、不戦を命じる「宣旨」が正式に下された。ところが頼朝は「令聞此事給、殊有御鬱憤、軍士多以予参之間、已有若干費、何期後年哉、於今者必定可令発向給之由、被仰」と、宣旨に背いて強引に奥州発向を決定した(『吾妻鏡』文治五年七月十六日条)。本来であれば違勅の重罪であるが、もはや頼朝の影響力、軍事力、統治力は朝廷のそれを遥かに凌駕しており、実力を以て自己の理想を貫いたのであった。
一方、法皇は「奥州追討事、一旦雖被制止」したものの、頼朝の再三の要請を拒否することは後顧の憂いにならんと考えたのだろう。「仰重被計申之旨、尤可然之由」と前言を翻し、結局摂政已下も追討を認めることに改め、7月19日、頼朝に泰衡追討の宣旨を下したのであった(『吾妻鏡』文治五年九月九日条)。この宣旨は7月24日に蔵人宮内大輔家実が奉じ、26日に帥卿経房から右兵衛督能保に送られ、28日に出京して東国へと下された。しかし、このころの兼実は日記を毎日書かずに興味や後勘のあった場合にのみ記しており、この宣旨については一言も記していない。
ただ、頼朝はこの泰衡追討の宣旨を知ることなく奥州征討を北陸、東海、大手の三軍で行うことを決定。東海道大将軍は千葉介常胤、八田前右衛門尉知家の両将、北陸道大将軍は比企藤四郎能員、宇佐美平次実政の両将、頼朝は大手軍を率いて奥州へ向かうことと定め、留守は大夫属三善善信入道を主将に、その弟の隼人佐三善康清ほか大和判官代藤原邦通、佐々木次郎経高、大庭平太景能、義勝房成尋已下の人々に命じている(『吾妻鏡』文治五年七月十七日条)。
| 大将軍 | 相具 | 経路 | |
| 東海道大将軍 | 千葉介常胤 八田右衛門尉知家 |
一族等 常陸下総国両国勇士等 |
行方⇒岩城⇒岩崎⇒渡遇隈河湊 |
| 北陸道大将軍 | 比企藤四郎能員 宇佐美平次実政 |
上野国高山、小林、大胡、佐貫等住人 | 越後国⇒出羽国念種関 |
| 大手 | 源頼朝 | 武蔵、上野両国内党者等者、 従于加藤次景廉、葛西三郎清重等 |
中路可有御下向 |
7月18日、頼朝は伊豆山の専光房を鎌倉に召して奥州追討の祈祷を依頼。出立して二十日後、御所の後山に梵宇を草創せよと命じた(『吾妻鏡』文治五年七月十八日条)。専光房みずからが柱だけでよいのでこれを立てて仮の梵宇と為し、持仏の正観音像を安置することとし、実際に堂を建立するのは後日の指示とすることを伝えている。そして、追討軍の第一陣として北陸道大将軍の比企藤四郎能員が鎌倉を出陣した。
翌19日、頼朝率いる大手軍が鎌倉を発った(『吾妻鏡』文治五年七月十九日条)。このとき、梶原平三景時は囚人であった城四郎長茂の起用を勧めている。かつて平家政権のなか、信濃国で挙兵した木曾次郎義仲の鎮定を期待されて治承5(1181)年8月14日に越後守に任じられ(当時の諱は助職)、越後国から木曾義仲を追捕するべく信濃国に攻め入ったものの横田河原の戦いで敗走。平家の没落と同時に解官されたとみられ、8月10日には木曾義仲が「左馬頭兼越後守」に任じられている(寿永三年正月廿日条)。彼は無双の勇士とされ、頼朝も彼の起用を認めている。これを聞いた長茂は喜び、頼朝から旗の貸与が示されるも、以前の旗を用いることを願い出た。これは旗を見た旧郎従等が集まってくるであろうという意図であった(『吾妻鏡』文治五年七月十九日条)。
○大手勢(鎌倉出御勢一千騎)
| 先陣 | 畠山次郎重忠 | 長野三郎重清 | 大串小次郎 | 本田次郎 | 榛澤六郎 | 柏原太郎 |
| 御駕 | 源頼朝 | |||||
| 御供輩 | 武蔵守義信 | 遠江守義定 | 参河守範頼 | 信濃守遠光 | 相摸守惟義 | 駿河守広綱 |
| 上総介義兼 | 伊豆守義範 | 越後守義資 | 豊後守季光 | |||
| 北條四郎 | 北條小四郎 | 北條五郎 | 式部大夫親能 | 新田蔵人義兼 | 浅利冠者遠義 | |
| 武田兵衛尉有義 | 石和五郎信光 | 加々美次郎長清 | 加々美太郎長綱 | 三浦介義澄 | 三浦平六義村 | |
| 佐原十郎義連 | 和田太郎義盛 | 和田三郎宗実 | 岡崎四郎義実 | 岡崎先次郎惟平 | 土屋次郎義清 | |
| 小山兵衛尉朝政 | 小山五郎宗政 | 小山七郎朝光 | 下河辺庄司行平 | 吉見次郎頼綱 | 南部次郎光行 | |
| 平賀三郎朝信 | 小山田三郎重成 | 小山田四郎重朝 | 藤九郎盛長 | 足立右馬允遠元 | 土肥次郎実平 | |
| 土肥弥太郎遠平 | 梶原平三景時 | 梶原源太左衛門尉景季 | 梶原平次兵衛尉景高 | 梶原三郎景茂 | 梶原刑部丞朝景 | |
| 梶原兵衛尉定景 | 波多野五郎義景 | 波多野余三実方 | 阿曽沼次郎広綱 | 小野寺太郎道綱 | 中山四郎重政 | |
| 中山五郎為重 | 渋谷次郎高重 | 渋谷四郎時国 | 大友左近将監能直 | 河野四郎通信 | 豊嶋権守清光 | |
| 葛西三郎清重 | 葛西十郎 | 江戸太郎重長 | 江戸次郎親重 | 江戸四郎重通 | 江戸七郎重宗 | |
| 山内三郎経俊 | 大井二郎実春 | 宇都宮左衛門尉朝綱 | 宇都宮次郎業綱 | 八田右衛門尉知家 | 八田太郎知重 | |
| 主計允行政 | 民部丞盛時 | 豊田兵衛尉義幹 | 大河戸太郎広行 | 佐貫四郎広綱 | 佐貫五郎 | |
| 佐貫六郎広義 | 佐野太郎基綱 | 工藤庄司景光 | 工藤次郎行光 | 工藤三郎助光 | 狩野五郎親光 | |
| 常陸次郎為重 | 常陸三郎資綱 | 加藤太光員 | 加藤藤次景廉 | 佐々木三郎盛綱 | 佐々木五郎義清 | |
| 曽我太郎助信 | 橘次公業 | 宇佐美三郎祐茂 | 二宮太郎朝忠 | 天野右馬允保高 | 天野六郎則景 | |
| 伊東三郎 | 伊東四郎成親 | 工藤左衛門祐経 | 新田四郎忠常 | 新田六郎忠時 | 熊谷小次郎直家 | |
| 堀藤太 | 堀藤次親家 | 伊澤左近将監家景 | 江右近次郎 | 岡辺小次郎忠綱 | 吉香小次郎 | |
| 中野小太郎助光 | 中野五郎能成 | 渋河五郎兼保 | 春日小次郎貞親 | 藤澤次郎清近 | 飯富源太宗季 | |
| 大見平次家秀 | 沼田太郎 | 糟屋藤太有季 | 本間右馬允義忠 | 海老名四郎義季 | 所六郎朝光 | |
| 横山権守時広 | 三尾谷十郎 | 平山左衛門尉季重 | 師岡兵衛尉重経 | 野三刑部丞成綱 | 中條藤次家長 | |
| 岡辺六野太忠澄 | 小越右馬允有弘 | 庄三郎忠家 | 四方田三郎弘長 | 浅見太郎実高 | 浅羽五郎行長 | |
| 小代八郎行平 | 勅使河原三郎有直 | 成田七郎助綱 | 高鼻和太郎 | 塩屋太郎家光 | 阿保次郎実光 | |
| 宮六傔仗国平 | 河勾三郎政成 | 河勾七郎政頼 | 中四郎惟重 | 一品房昌寛 | 常陸房昌明 | |
| 尾藤太知平 | 金子小太郎高範 |
7月25日、頼朝は下野国古多橋駅に到着。一宮の宇津宮に奉幣して祈願している(『吾妻鏡』文治五年七月廿五日条)。その後、宿所では小山下野大掾政光入道が駄餉を献じている。このとき、頼朝の御前にいた紺直垂の武士に目が留まった政光入道は、頼朝に「何者哉」と問うた。頼朝は「彼者、本朝無双勇士、熊谷小次郎直家也」と紹介すると、政光入道は「何事無双号候哉」と再び問う。頼朝は「平氏追討之間、於一谷已下戦場、父子相並欲棄命、及度々之故也」と答えると、政光入道は破顔して「為君棄命之條、勇士之所志也、爭限直家哉、但如此輩者依無右顧眄之郎従、直励勲功揚其号歟、如政光者、只遣郎従等抽忠許也、所詮於今度者自遂合戦、可蒙無双之御旨」と子息の朝政、宗政、朝光ならびに猶子の宇都宮頼綱に下知した。頼朝はこのことに非常に興に入っている。
翌26日には、かつて頼朝と激しく交戦した佐竹氏の惣領「佐竹四郎(佐竹冠者秀義か)」が常陸国から参じている(『吾妻鏡』文治五年七月廿六日条)。このとき佐竹四郎が持参した旗が「無文白旗」で、頼朝の旗と同じであったため、頼朝はこれを咎め、同じ旗を用いるべからずと命じた。かつての遺恨があったことも咎め立てした理由の一つとみられるが、頼朝は佐竹四郎に「御扇出月」を下し、佐竹四郎はこれを白旗に括り付けたという。以降、佐竹氏はこれを自家の定紋として用いることとなる。
27日に奥州との国境である下野国新渡戸駅で着到注進を行ったのち、29日、白河関を越えて陸奥国へと入った(『吾妻鏡』文治五年七月廿九日条)。さらに進軍して8月7日、伊達郡阿津賀志山辺の国見駅まで進んだ。泰衡は「泰衡日来聞二品発向給事、於阿津賀志山、築城壁固要害、国見宿与彼山之中間俄搆口五丈堀、堰入逢隈河流柵」(『吾妻鏡』文治五年八月七日条)とあるように、阿津賀志山に城塞を築き、国見宿と山との間に幅五丈の堀割と土塁を構築し、堀には阿武隈川の水を流入させていた(『吾妻鏡』文治五年八月七日条)。ただし、阿武隈川から阿津賀志山頂まで南北に築かれた防塁は三キロを超える長大なものであり、数年をかけて築かれたと推測される。おそらく秀衡が統治していた頃からすでに築かれていた防塁があり、泰衡が手を加えたものではなかろうか。頼朝があらかじめ八十名の工兵を手配していることから、この防塁は頼朝の周知するところであったと思われる。また、阿津賀志山の麓を北行する奥大道は防塁を貫通しており、この開口部には木戸が設けられ、平時から関所のような役割を担っていたのではなかろうか。泰衡が防塁を構築したとすれば、阿津賀志山より北方の狭隘地、貝田や越河にみられる石塁か。
阿津賀志山要害を守るのは、泰衡の義兄にして義父にあたる西木戸太郎国衡(信寿太郎殿)と金剛別当秀綱、下須房太郎秀方已下の部隊であった。金剛別当は苅田郡の金剛蔵王権現の別当であろうか。泰衡自身は国分原の鞭楯(仙台市宮城野区安養寺二丁目付近か)に布陣し、名取川と広瀬川の急流には大綱を引いて渡河の妨害を図っている。名取川と広瀬川の大綱と泰衡自身の国分原付近への布陣は、国府防衛を目的としたものである。さらに平泉の玄関口にあたる栗原、三迫、黒岩口、一野のあたりには若九郎大夫、余平六らを大将軍とした部隊を配置し、出羽国には田河太郎行文、秋田三郎致文の両名を遣わしたという。ただし、もともと田河行文は出羽国田河郡、秋田致文は秋田郡の支配層であったと考えられ、奥州藤原氏の支配領域の広さがうかがわれる。
8月7日夜、頼朝は主だった郎従に対し、翌8日曉方に阿津賀志山へ進むことを伝達。戦陣の畠山次郎重忠が率いてきた八十名の土木部隊によって堀が密かに埋められ、これを知った頼朝寝所伺候の小山七郎朝光は先陣を狙って寝所を出て、兄・小山左衛門尉朝政の郎従を拝借して阿津賀志山へと向かっている。ただ朝光がこのとき合戦に臨んだかは不明。
翌8日、金剛別当秀綱が阿津賀志山前に布陣した(『吾妻鏡』文治五年八月八日条)。頼朝勢は早朝卯刻、試みに「畠山次郎重忠、小山七郎朝光、加藤次景廉、工藤小次郎行光、同三郎祐光等」を派遣して箭合を行わせている。秀綱等は防戦するが、巳刻には退いて大木戸付近まで馳せ帰り、大将軍藤原国衡に戦況を報告。国衡は「泰衡郎従信夫佐藤庄司、又号湯庄司、是継信忠信等父也、相具叔父河辺太郎高経、伊賀良目七郎高重等」を「石那坂之上(福島市飯坂町湯野坂ノ上)」に遣わして、「堀湟懸入逢隈河水於其中、引柵、張石弓、相待討手」った(『吾妻鏡』文治五年八月八日条)。その眼前を流れる阿武隈川(摺上川)内に柵を引いて頼朝勢を待ち受けた。一方、頼朝勢からは「常陸入道念西子息常陸冠者為宗、同次郎為重、同三郎資綱、同四郎為家等」が秣の中に甲冑を隠して伊達郡沢原辺(摺上川周辺の肥沃地か)まで進み、佐藤庄司らが布陣する「石那坂之上」に迫り、合戦に及んだ。佐藤庄司はこれに激しく応戦し、寄手の為重、資綱、為家が負傷する激戦となった。常陸冠者為宗は奮戦し、佐藤庄司已下十八人の首を挙げ(ただし、佐藤庄司は十月二日に名取郡司、熊野別当とともに赦免されており、討死していないと思われる)、後日、為宗らはこれらの首級を奥大道沿いの経ケ丘(国見町大字大木戸経ケ岡)に梟首している(『吾妻鏡』文治五年八月八日条)。
9日夜、頼朝は翌10日早朝に阿津賀志山を越えて合戦すべきことを決定した(『吾妻鏡』文治五年八月九日条)。ところが、深夜のうちに「三浦平六義村、葛西三郎清重、工藤小次郎行光、同三郎祐光、狩野五郎親光、藤澤次郎清近、河村千鶴丸年十三才、以上七騎」が先陣と定められていた畠山次郎重忠の陣を越して抜け駆けした(『吾妻鏡』文治五年八月九日条)。この抜け駆けを察知した重忠郎従の榛沢六郎成清が重忠に「今度合戦奉先陣、抜群眉目也、而見傍輩所、爭難温座歟、早可塞彼前途、不然者訴申事由、停止濫吹、可被越此山」と訴えている。これに重忠は「其事不可然、従以他人之力雖退敵、已奉先陣之上者、重忠之不向以前合戦者、皆可為重忠一身之勲功、且欲進先登之輩事、妨申之條非武略本意、且独似願抽賞、只作惘然、神妙之儀也」と言って、動くことはなかった。
抜け駆けした七騎は、終夜阿津賀志山を登って木戸口(奥大道の木戸前の曲輪的な部分であろう)にたどり着くと、各々名乗りを上げた。すると泰衡郎従で「六郡第一強力者」である伴藤八やそのほか屈強な武士が馳せ寄せて、工藤小次郎行光と狩野五郎親光が先頭を切って突入し、行光と伴藤八は互いに轡を並べて組み合い、行光はその首を挙げているが、狩野親光は討死した。親光は頼朝の挙兵時から従う最古参の御家人であった(『吾妻鏡』文治五年八月九日条)。行光は伴藤八の首級を馬鞍に括り付けたのち、さらに木戸に向けて馳せ進むと、武士二名が組討をしている現場に遭遇する。行光が名を尋ねると「藤澤次郎清近欲取敵」という。これを聞いた行光は早速清親に加担して敵の首を取った。その後、休息の後、清親は行光に感謝し、すぐさま行光息男を清親の娘婿とする約定を交わした。また、葛西三郎清重と河村千鶴丸も奮戦して敵を討ち、中宮大夫進親能猶子・左近将監能直は初陣ながら、親能から補佐を依頼された宮六傔仗国平のもと、国衡近臣の佐藤三郎秀員と戦い、討ち取っている。
+―斎藤実盛
|(長井別当)
|
+―女子
∥―――――宮道国平
∥ (宮六傔仗)
宮道某
8月10日未明、予定通りに「重忠、朝政、朝光、義盛、行平、成広、義澄、義連、景廉、清重等」が木戸口に攻め寄せた。しかし、国衡麾下の将士も堅く防いで容易に陥落するとは思われなかった。実は頼朝は前夜のうちに「小山七郎朝光并宇都宮左衛門尉朝綱郎従紀権守、波賀次郎大夫已下七人、以安藤次為山案内者、面々負甲疋馬、密々出御旅館、自伊逹郡藤田宿向会津之方」に派遣しており、「越于土湯之嵩、鳥取越等、樊登于大木戸上国衡後陣之山」と、藤田宿から峯沿いに阿津賀志山の北側に回り込み、阿津賀志山中腹、防塁の大木戸内側に布陣する国衡本陣を望む高台に攀じ登ると、鬨の声を上げて矢を射かけた。この小山朝光勢の奇襲に国衡勢は「搦手襲来」と大混乱を来たし、国衡勢は「無益于搆塞」と逃亡していった。しかし、この中で「金剛別当子息下須房太郎秀方年十三」は黒駮馬に跨って踏み止まり、攻め寄せる関東勢を防いでいた。ここに工藤行光が駆け付けて秀方に馬を並ばせんとしたとき、行光の郎従藤五が割って入り、秀方と組討した。このとき藤五は秀方の顔を見て、子供と知る。姓名を問うが何も語らなかった。しかし、この場に一人留まるほどであれば何らかの謂れのある人物なのだろうとして討ち取っているが、その剛力は幼少に似合わぬものであったという(『吾妻鏡』文治五年八月十日条)。また、その父親の金剛別当秀綱は小山朝光に討たれている。そして早朝卯刻、頼朝はすでに戦乱の終わった阿津賀志山の堅陣を越え、奥大道を北上する。
国衡は高楯黒という名馬を駆って北方へ逐電し「芝田郡大高宮辺(柴田郡大河原町金ケ瀬新開)」からさらに「大関山(柴田郡川崎町大字今宿大森辺)」を越して出羽国へ向かおうとしていたが、和田小太郎義盛が大高宮辺を疾走する国衡を発見。「可返合」と呼びかけた。すると国衡は名乗って馬を廻らすと、互いに弓手に向き合い、国衡は「十四束箭」の巨大矢を手挟んだが、義盛は素早く「十三束箭」の矢を国衡に射掛けた。矢は国衡の射向けの袖を射通して腕に突き刺さり、国衡は痛みに耐えかねて馬を退いた。義盛は二の矢を構えて狙ったが、距離が開いてしまった。ここに走り来た畠山重忠の一軍が義盛を追い抜き、重忠の客将・大串小次郎が国衡に迫った。これに驚いた国衡は誤って馬を深田(大河原町金ケ瀬馬取前)に入れてしまい、身動き儘ならない中、義盛の矢で負傷していたことも重なって首を取られた(『吾妻鏡』文治五年八月十日条)。
8月12日、頼朝は船迫駅家(柴田郡柴田町船岡中央か)を経て、夕刻には多賀城国府へ到着した。泰衡は多賀城国府へと通じる国分原の鞭楯(仙台市宮城野区安養寺二丁目付近か)に布陣していたが、ここに阿津賀志山からの敗残兵がたどり着いて敗報を受けると、泰衡は驚いて退却しており、とくに抵抗もなく入部したのあろう。その後、「海道大将軍千葉介常胤、八田右衛門尉知家等参会、千葉太郎胤正、同次郎師常、同三郎胤盛、同四郎胤信、同五郎胤通、同六郎大夫胤頼、同小太郎成胤、同平次常秀、八田太郎朝重、多気太郎、鹿嶋六郎、真壁六郎等」が阿武隈川の湊を渡って国府へと参上した(『吾妻鏡』文治五年八月十二日条)。
8月13日、北陸道軍として日本海側から奥州へ進んでいた比企藤四郎能員、宇佐美平次実政は出羽国に討ち入り、泰衡が派遣していた「田河太郎行文、秋田三郎致文等」と戦い、梟首したという。『吾妻鏡』編纂時に当日の出来事として記録されたものであろう。
8月14日、逐電した泰衡が国衙北部の「玉造郡」にいるという風聞が届いた。しかし、もう一報で「国府中山上物見岡取陣」もあることから、頼朝は思慮の末に玉造郡へと進軍。国府を出立して黒河を経由して玉造郡へと向かった。一方で、国府中山上の物見岡にも「小山兵衛尉朝政、同五郎宗政、同七郎朝光、下河辺庄司行平等」を派遣して取り囲んだところ、泰衡は事実そこに陣していたが、すでに逐電し、幕と四、五十人ほどの泰衡郎従が守衛しているのみであり、朝政らは難なく攻め落とした。その後、朝政は「吾等者経大道、於先路可参会歟」と諮ると、行政は「玉造郡合戦者可為継子歟、早追可参彼所者」と、頼朝との合流を提案。朝政もこれを受け入れ、行平とともに玉造郡へと向かった(『吾妻鏡』文治五年八月十四日条)。この合戦には藤九郎盛長のもとにあった囚人・筑前房良心(刑部卿忠盛孫・筑前守時房の子)が従軍しており、その軍功によって厚免されている。
8月20日、頼朝は黒河郡(富谷市から大和町、大衡村)を経て玉造郡の「多加波々城」を取り囲んでいる(『吾妻鏡』文治五年八月廿日条)。「多加波々城」の現在地は不明だが、その後の頼朝のルートが葛岡郡を経て津久毛橋へと進んでいることから、江合川の氾濫原が眼下に広がる要害の地、のちの岩出山城(大崎市岩出山城山)の可能性もあろう。泰衡はここに在城していたが、頼朝が取り囲んだ際にはすでに城をあとにしており、頼朝は城を落とすと、泰衡を追って「葛岡郡(葛岡要害付近か)」を経由し、暴風雨の中「松山道」を通って三迫川に懸る「津久毛橋(栗原市金成大原木井戸端辺りか)」を渡った。この暴風雨は時期からして台風であろう。なお、ここで梶原平次景高が一首詠んでいる。
陸奥乃勢ハ御方ニ津久毛橋渡して懸ン泰衡頚
陸奥国の人々を従えて泰衡の首を取り、大路渡して獄に懸けるとの意気込みを津久毛橋を渡ることに掛けた歌であり、頼朝はこれを祝い言と感心したという(『吾妻鏡』文治五年八月廿一日条)。
 |
| 平泉の毛越寺跡の池 |
このころ泰衡は「自宅(伽羅御所か)」門前を通過して平泉を後にして出羽国へ向かっており、平泉の屋敷には郎従を遣わして火を放ち、「杏梁桂柱之搆、失三代之旧跡、麗金昆玉之貯、為一時之新灰」(『吾妻鏡』文治五年八月廿一日条)と、平泉の荘厳な屋敷は忽ち灰燼に帰した。ただし、泰衡が燃やしたのは自らの屋敷にとどまったとみられるが、すでに平泉の住人たちは逃散しており、翌22日申刻、頼朝が平泉に入った際には「家者又化烟、数町之縁辺、寂寞而無人、累跡之郭内弥滅而有地、只颯々秋風雖送入幕之響、蕭々夜雨不聞打窓之聲」(『吾妻鏡』文治五年八月廿二日条)と、ただ無人のまちが広がっていた様子がうかがえる。
なお、伽羅御所の南西の一角に倉がひとつ焼け残っており、頼朝は葛西三郎清重と小栗十郎重成を遣わして検分させたところ、「沈紫檀以下唐木厨子数脚在之、其内所納者、牛玉、犀角、象牙笛、水牛角、紺瑠璃等、笏、金沓、玉幡、金花鬘以玉飾之、蜀江錦直垂、不縫帷、金造鶴、銀造猫、瑠璃灯炉、南廷百各盛金器等也、其外錦繍綾羅、愚筆不可計記者歟」というほどの宝物が残されていた。頼朝は清重に「象牙笛、不縫帷」を与え、「可庄厳氏寺之由」を述べた重成にも望みの「玉幡、金花鬘」を授けた(『吾妻鏡』文治五年八月廿二日条)。
 |
| 平泉高舘より衣川を望む |
8月23日、頼朝は「八月八日同十日両日遂合戦、昨日廿二日、令着平泉候訖、而泰衡逃入深山之由、其聞候之間、重欲追継候也」という消息をしたためると、雑色時沢に託して京都の右兵衛督能保へ遣わした(『吾妻鏡』文治五年八月廿三日条)。そして25日、泰衡の行方をつかめないことから、さらに北方を追奔すべきことを御家人らに通達している(『吾妻鏡』文治五年八月廿五日条)。また、柳之御所に隣接する衣河館にはいまだ前民部少輔基成とその子息三人が残っており、頼朝は千葉六郎大夫胤頼に彼らを召し出すよう指示した。さっそく胤頼は衣河館に赴き、彼らを生け捕ろうとするが、基成らは抵抗することもなく降伏したことから、胤頼は彼らを伴って頼朝のもとに戻っている(『吾妻鏡』文治五年八月廿五日条)。
8月26日、泰衡の使者が頼朝の宿所(加羅御所跡)に一通の書状を投げ入れて逐電した。その書状の表書きには「進上鎌倉殿侍所 泰衡敬白」と記されていたという。その書状には、
という内容が記されており、土肥次郎実平は「試捨置御返報於比内辺、潜付勇士一両於其所、為取御書、有窺来者之時、搦取可被問泰衡在所」と進言するが、頼朝はすでに奥羽南部をその手中に収めている中で、そのような消極的な手段をとる必要はなく「不及其儀、可置書於比内郡之由、泰衡言上之上者、軍士等各可捜求彼郡内」と、泰衡が比内郡に返書を置くよう依頼している上は、兵士を比内郡に派遣して捜索すればよいと命じた(『吾妻鏡』文治五年八月廿六日条)。
9月2日、頼朝は平泉を出立し、岩井郡厨川辺(盛岡市天昌寺町一帯か)へ向けて北上川に沿って北上した。めざす厨川柵は、遠祖の将軍頼義が前九年合戦で安倍貞任らを討った場所で、佳例を引いて厨川に至ればきっと泰衡の首を得ることができるであろう、との願掛けであったという(『吾妻鏡』文治五年九月二日条)。厨川柵は北上川と雫石川の合流点に設けられた堅城でかつての陸奥安倍氏の館(盛岡市安倍館町)があったという。9月4日、頼朝一行は志波郡に到着し、「陣岡蜂社(紫波郡紫波町宮手字陣ヶ岡)」に陣所を定めた(『吾妻鏡』文治五年九月四日条)。「陣岡蜂社」はかつて将軍頼義と義家が布陣した陣所で、義家が厨川合戦で勝利の一因となった蜂を祀った神社であり、頼朝はこの佳例を尊んだと思われる。北陸道を攻め上った比企藤四郎と宇佐美平次の軍勢も合流して、岡には白旗が多くたなびいたという。また、頼朝の進軍を聞いて樋爪館(紫波郡紫波町南日詰箱清水)から逃れた「俊衡法師(樋爪入道蓮阿)」を三浦介義澄と弟・十郎義連、子の平六義村に追わせている(『吾妻鏡』文治五年九月四日条)。
ところが9月6日、比内郡贄柵(大館市二井田贄ノ里)の柵主で奥州藤原氏の「数代郎従河田次郎」が泰衡の首級を持参して陣岡蜂社の頼朝の陣所へ現れた(『吾妻鏡』文治五年九月六日条)。泰衡は平泉を出たのち、陸奥国「糠部郡」を経て「夷狄嶋」への逃亡を図っており、道筋にある比内郡贄柵の河田次郎のもとに逗留する予定で、その途次にあらかじめ頼朝に「若垂慈恵有御返報者、可被落置于比内郡辺」と私信を送ったものと思われる。
しかし、9月3日、泰衡一行が贄柵へたどり着くと、河田次郎は泰衡を取り囲んで殺害。河田次郎はその首を頼朝に献じるべく馬を走らせたという(『吾妻鏡』文治五年九月三日条)。泰衡の首は和田小太郎義盛と畠山次郎重忠両名による実検が行われ、囚人赤田次郎に確認させたところ、本人に間違いないということで、首は義盛に預けられた。一方、泰衡の首級を持参した河田次郎には「汝之所為、一旦雖似有功、獲泰衡之條、自元在掌中之上者、非可借他武略、而忘譜第恩梟主人首、科已招八虐之間、依難抽賞、為令懲後輩、所賜身暇也者」と告げて、小山朝光へ預け、処断している(『吾妻鏡』文治五年九月六日条)。頼朝の脳裏には、平治の乱の際、父・義朝が、尾張国内海庄の郎従・長田庄司忠致を頼って殺害された記憶がよぎっていたのではなかろうか。
その後、泰衡の首級は、前九年合戦の貞任の先例に倣い、横山小権守時広に首の請け取りを命じ、時広の子・太郎時兼が梶原景時から請けると、郎従の七太広綱が長さ八寸の鉄釘で泰衡首級を柱に打ち付けた。貞任の先例では時広曽祖父・横山野大夫経兼が将軍頼義から貞任の首を請け取り、その郎従惟仲(七太広綱の祖)が柱に打ち付けたという(『吾妻鏡』文治五年九月六日条)。
9月8日、帥卿経房への消息を工藤主計允行政に書かせ、雑色安達新三郎を飛脚として京都へ遣わした(『吾妻鏡』文治五年九月八日条)。この消息は10月10日に入洛。その日の夜、右馬頭能保が兼実に「頼朝卿申遣云、去九月三日誅泰衡了」(『玉葉』文治五年十月十日条)を伝えている。兼実は「天下之慶也」と評すも、非常に素っ気なく追記されるのみである。神事や造営、主上や二宮元服、女宮親王宣下の件、そして最も気にかけていた娘の入内であろう。朝廷や自身にとっての重大事が重なるときの戦闘行為及び穢事を兼実は厭い、大変不本意な気持ちなのだろう。10月17日午刻、長らく天王寺詣を行ってきた法皇が入洛して六条御所に還御(『玉葉』文治五年十月十七日条)。翌18日、院使の頭中将成経が兼実を訪ねて「頼朝賞之間事也、申子細了」(『玉葉』文治五年十月十八日条)という。
9月9日夜には右兵衛督能保の使者が陣岡の頼朝陣所に到着し、7月19日の泰衡追討の宣旨及び追討容認の院宣を届けた(『玉葉』文治五年九月九日条)。頼朝の奥州追討が公的に認められたこととなる。また、翌10日、頼朝は源忠已講、心蓮大法師、快能等の平泉の寺院の住侶らを陣岡に集めて寺領安堵等を行うと、七日間在陣した陣岡を後にして厨川柵へ移った(『吾妻鏡』文治五年九月十一日条)。すると15日、樋爪館から逃れていた奥州藤原一門の「樋爪太郎俊衡入道并弟五郎季衡」が厨川に出頭してきた。俊衡は「太田冠者師衡、次郎兼衡、同河北冠者忠衡」の三人の子息、季衡も子息「新田冠者経衡」を伴っていた。歳六十を超え「頭亦剃繁霜、誠老羸之容貌」の俊衡入道を見た頼朝は憐れみを感じ、八田知家へ彼らを預けている。知家は彼らを陣所へ伴うが、俊衡入道はただひたすらに法華経を読誦のほか一言も発せず、仏法を深く崇敬する知家はこの姿に深い感慨を覚えている(『吾妻鏡』文治五年九月十五日条)。翌日、知家は頼朝の陣所に参じると、俊衡入道の法華経転経について言上した(『吾妻鏡』文治五年九月十六日条)。頼朝は日ごろより法華経への信心が篤く、俊衡等については罪に問わず、樋爪の本所を安堵することを下知したが、これは法華経の「我等亦欲擁護読誦受持法華経者」(『妙法蓮華経陀羅尼品 第二十六』)という「十羅刹」の御照覧によるものであると言い含めている(『吾妻鏡』文治五年九月十六日条)。さらに18日には秀衡四男・本吉冠者高衡と泰衡後見の熊野別当が降伏。頼朝は京都の帥卿経房へ彼ら降人の交名を遣わした。なお、この交名とみられる「能保卿示送云、奥州事併召取了、不漏一人云々、送注文一紙、実天之令然也、非言語之所及」(『玉葉』文治五年十月廿日条)が兼実に示されたのは10月20日のことで、一か月余り兼実へ報告がなされていなかったことになる。法皇還御からわずか二日後であり、奥州追討に関して否定的な兼実へ直接送られることは憚られたのか。翌10月21日には定長が院使として兼実邸を訪問し「奥州之間事」を諮問している(『玉葉』文治五年十月廿一日条)。
19日、厨川柵から平泉に向けて出立し、翌20日に平泉で「奥州羽州等事、吉書始之後、糺勇士等勲功、各被行賞訖」(『吾妻鏡』文治五年九月廿日条)された。その恩賞の御下文は「而千葉介最前拝領之、凡毎施恩以常胤可為初之由、蒙兼日之約者」(『吾妻鏡』文治五年九月廿日条)と、約定通り千葉介常胤から下された。21日に胆沢鎮守府(奥州市水沢佐倉河渋田)に到着し、翌22日に「陸奥国御家人事、葛西三郎清重可奉行之、参仕之輩者属清重可啓子細之旨」(『吾妻鏡』文治五年九月廿二日条)を命じた。
23日、頼朝は平泉に入り、伽羅御所の北西斜向かいにあった無量光院を参詣、翌24日には葛西三郎清重に平泉郡内の検非違使所を管領すべきことを命じた。葛西三郎清重は今回の奥州合戦での勲功が殊に群を抜いていたため、この要職を任されたという。また、地頭職も「伊澤、磐井、牡鹿等郡已下拝領数ケ所」という。ただし、「是於当郡(岩井郡)者、行光依可拝領、別以被仰下之間、及此儀」(『吾妻鏡』文治五年九月十二日条)とある通り、工藤小次郎行光も岩井郡を拝領したことになっており、清重はこれら郡全体を支配した地頭ではないのだろう。
10月1日、多賀国府に入部。翌2日、囚人の「佐藤庄司、名取郡司、熊野別当」が厚免を蒙って、本所へと帰還した。佐藤庄司はかつて阿津賀志山の戦いで討死して梟首されたとされるが、赦免されたとされており、討死または赦された記録のいずれかが誤伝なのだろう(『吾妻鏡』文治五年十月一日条)。10月19日、頼朝は下野国宇都宮に逗留して報賽のため奉幣し、荘園を寄進した。また樋爪入道一族を宇都宮の職掌に任じたという(『吾妻鏡』文治五年十月十九日条)。ただし、後日彼ら一族のうち高衡、師衡、経衡、隆衡の四名は相模国、景衡は伊豆国、兼衡は駿河国へと流罪となり、俊衡弟の季衡は在下野国のまま下野国配流と決定されている(『吾妻鏡』文治五年十月一日条)。そして10月24日申刻、頼朝は鎌倉に帰還。実に三か月にわたる遠征であった。その後、諸所に亘る戦後処理を行い、奥州を守る葛西三郎清重に対して沙汰をしている。
11月3日、鎌倉に帥卿経房から奥州平定の勲功として、頼朝の「按察使」への推任や「郎従之中有功之輩可注申、尤可被行其賞」(『吾妻鏡』文治五年十一月三日条)という「被下御感 院宣」がもたらされた。これに対し頼朝は家司中原広元を上洛させて「勧賞事、固被辞申、亦御家人勲功事可注申有功輩之由、有 院宣、可被行賞故歟、辞申之上者不及子細」(『吾妻鏡』文治五年十一月七日条)と返答するよう指示している。広元は8日に上洛の途に就くが、このとき頼朝は「龍蹄百余疋云々、二品賜鞍馬十疋、於京都為令送人々也云々、又被奉綿千両於 仙洞、是駿河国富士郡済物也」(『吾妻鏡』文治五年十一月八日条)と、「於京都為令送人々」という馬百頭ならびに鞍置馬十頭、そのほか法皇へ献上する綿千両を同道させている。相当大がかりな上洛である。「於京都為令送人々」には、兼実も含まれているとみられるが『玉葉』にその記録はない。当時の兼実は娘の入内準備、高倉院若宮二人(二宮守貞、三宮惟明)の親王宣下、法皇寵姫丹後局腹の姫宮の名字決定(覲子)及び親王并准后宣下、天皇元服などの重要事項が重なっており、すでに解決した奥州追討に関わる事柄には興味が薄かったとみられる。
一方、頼朝はこの広元の上洛に際し、兼実とは別に法皇とのより強い提携を模索したと思われ、そのキーパーソンとして丹後局との関係強化を図ったのだろう。家司広元はその後、京都と鎌倉を行き来しながら一年以上にわたって朝廷と応対を重ねており、とくに法皇の「代理人」的存在の丹後局ならびに、丹後局腹の覲子内親王の「可補勅別当之人」(『玉葉』文治五年十二月五日条)たる「右衛門督(源通親)」と深く交流し、この伝手を通じて頼朝は長女(大姫)の入内を企てることとなる。
上洛後、広元は帥卿経房を通じて頼朝の所存を奏院したとみられるが、法皇はこれを受理しない一方で「依泰衡征伐事、猶可被行勧賞之趣」を帥卿経房を通じて再度頼朝へ伝えている(『吾妻鏡』文治五年十二月六日条)。しかし、頼朝はさらにこれを拒絶するのである。ただ、「奥州羽州地下管領間事、明春可有御沙汰歟之由」を述べ、「降人等事、可被下配流官府之趣」についても要請している。恩賞云々ではなくただひたすらに粛々と戦後処理を行っている様子がうかがえる。そして、法皇からは「於伊豆相摸両国者、永代早可知行之由被仰下」(『吾妻鏡』文治五年十二月廿五日条)という院宣が届けられ、これに対して頼朝は「被申領状訖」という。また、同時に「可上洛之由、同所被仰也」という上洛の命に対し、「討平奥州畢、於今者罷入見参之外無今生余執、臨明年可参洛者」と返奏している。
これらから、法皇は頼朝に対して恩賞という「束縛」を以て懐柔し、二位の公卿が関東に常住する異常事態を解消し、秩序の回復を図る思惑があったと思われ、この頃から頼朝の京都常住の手管を考えていたのであろう。一方、頼朝も公卿の辺境常住が異例であることは当然承知しており、法皇の思惑は感づいていただろう。頼朝は一貫して恩賞としての官途は拒絶しながらも、地方行政に関する任用は受け入れるなど「実」は得ている。上洛するからには当然最大限の利益を計画したであろう。しかしそれは官途による束縛から逃避するため、恩賞は当初から想定になかったであろう。
このころ京都では、11月3日夜に権中納言兼光が参内し、兼実に「有入内予議」(『玉葉』文治五年十一月三日条)を伝えた。兼実の娘の入内についての予議であった。兼実はまず家司の蔵人頭宗頼を通じて「仰女子名字可択申之由」を指示したのち、兼実は実弟の大納言兼房とともに上達部座へ出座し、権中納言兼光を交えて様々に打ち合わせ、蔵人頭宗頼を以って「明年正月十一日可有入内之由奏内、依永久例也」と決定。11月15日には「女子叙三位、又定入内雑事」(『玉葉』文治五年十一月十五日条)、兼実邸を訪れた兼光が持参した名字勘文の五案「典子、立子、任子、位子、諦子」から「任子」に決定される。兼実の願いは「宇治殿以降絶而無此事、為取其始終、尤可祈申此両所歟、入内之本意、只在皇子降誕者歟」(『玉葉』文治五年十一月廿八日条)というもので、頼通以降絶えてしまった外戚政治であった。
鎌倉では11月17日、鷹場歴覧のため、頼朝は郎従等を従えて大庭御厨の辺まで出立。その後、渋谷庄へと歩みを進めた。そして夜の闇が覆い始めたころ、狐一匹が頼朝の馬前を走り抜けた。頼朝は鏑矢を番えて狐を狙い定めて射た。このとき、弓の上手である「千葉四郎胤信郎従号篠山丹三」が頼朝の右側に進み寄って頼朝と同時に矢を射た。頼朝の矢は狐に当たらず篠山の矢が狐の腰に命中。篠山は一瞬の間に下馬し、狐に突き立った自分の矢を頼朝の鏑矢に取り換え、頼朝のもとに捧げ参じた(『吾妻鏡』文治五年十一月十七日条)。頼朝は胤信に彼の名前を尋ねており、翌18日に鎌倉帰還後、胤信に申して篠山丹三を御所に召すと、「是昨日所為、御感之余」に「可候恪勤之由」を告げている(『吾妻鏡』文治五年十一月十八日条)。頼朝直属か胤信郎従のままかは不明だが、頼朝近侍として取り立てられる栄誉を得た。
そして12月9日、「令覧泰衡管領之精舎」したことで、鎌倉に寺院建立を決定した(『吾妻鏡』文治五年十二月九日条)。いまだ寺名は決定せず、建立場所も考えられていなかったが、構想は決められた。のちに「永福寺」と称され、「且宥数万之怨霊、且為救三有之苦果也」という理念の下で現在の鎌倉市二階堂の地に造営された浄土庭園寺院である。
■永福寺(三笠山永福寺)について
永福寺は、中尊寺大長寿院の二階大堂を模し、扉と後背の壁画は毛越寺金堂円隆寺の絵画を模写(『吾妻鏡』建久三年十月廿九日条)した「二階堂」を中心に、南に阿弥陀堂(阿弥陀如来)、北に薬師堂(薬師如来)を備えた独特な伽藍配置の頼朝御願寺である(下図は『発掘調査報告書・遺構編』平成12年鎌倉市教育委員会を参考)。

「今廻関東長久遠慮給之余、欲宥怨霊、云義顕云泰衡、非指朝敵、只以私宿意誅亡之故也、仍其年内被始営作、隨而壇場荘厳、偏被摸清衡、基衡、秀衡以上泰衡父祖等建立平泉精舎訖」(『吾妻鏡』宝治二年二月五日条)とある通りに、浄土庭園の広がる毛越寺や観自在王院、無量光院をモデルとした浄土庭園である。
鎌倉期の永福寺は「霊場を拝し奉れば、安養の聖容は無辺の光を垂れ、浄瑠璃医王善逝、一代牟尼の尊像、諸聖衆みな各々因位の誓約に答つつ、過現の利益たのもしきぞや覚」(福田誠『鎌倉永福寺の発掘庭園』所収:『玉林苑』[「続群書類従」十九輯下])とあり、「安養の聖容」即ち阿弥陀如来、「浄瑠璃医王」即ち薬師如来、「一代牟尼の尊像」即ち釈迦如来が祀られていた。つまり、三堂の中央にある「二階堂」の本尊は釈迦如来であったことがわかる。
なお、「二階堂」のモデルとなった中尊寺の二階大堂は「号大長寿院、高五丈、本尊三丈金色弥陀像、脇士九躰同丈六也」(『吾妻鏡』文治五年九月十七日条)という御堂で、本尊は永福寺二階堂とは異なり、三丈の巨大な金色阿弥陀仏、脇士は「九躰同丈六」とあることから九品の丈六阿弥陀如来であった。
永福寺は、第一義は「宥数万之怨霊」すなわち「云義顕云泰衡、非指朝敵、只以私宿意誅亡」のほか、東北における諸合戦の怨霊の鎮魂を目的としたものだった。そのほか「為救三有之苦果」の法華経の理念を求し、阿弥陀如来、釈迦如来、薬師如来の三世仏を本尊とする寺を廻廊で繋ぎ、三有の苦果からの救済を求めた寺院であった。
南北に並立する「阿弥陀堂」と「薬師堂」は永福寺境内に建立された独立寺院であり、これらを一つにつなぐことで西方極楽浄土(阿弥陀如来)、霊山浄土(釈迦如来)、東方瑠璃光浄土(薬師如来)の三浄土を結び、ひとつの浄土庭園を形成させたものだろう。そして、頼朝の求めた「安穏」の世の草創という理想を具現化し、奥州合戦を日本における最後の戦いと誓い、「永福寺」の建立をその証としたのではなかろうか。
永福寺ならびに阿弥陀堂や池、総門など寺院自体の大部分の造作は建久3(1192)年11月20日までに完成し、「雲軒月殿、絶妙無比類、誠是西土九品荘厳、遷東関二階梵宇者歟」(『吾妻鏡』建久三年十一月廿日条)と、西方浄土を彷彿とさせる伽藍であった。おそらく阿弥陀堂には平泉と同様、阿弥陀九品が安置されていたのだろう。薬師堂は建久4(1193)年11月27日に建立されている。その翌年の建久5(1194)年12月26日にも永福寺の傍らに薬師堂が建立されて落慶供養が行われている(『吾妻鏡』建久四年十一月廿七日条)。これはおそらく永福寺惣門脇に建てられた医王山東光寺の前身となる法華堂ではなかろうか。いずれも長女大姫の病気快癒の祈りが込められていたと思われる。
永福寺の立地は平泉の無量光院と金鶏山の関係と同様に、西方浄土と鶴岡山八幡宮寺(大臣山)を直線に結び、僧房等も配することができる広い平地と、水が豊かに存在する場所が選ばれたと考えられる。
こうした頼朝の誓いの寺院建立計画が実行に移されようという中、12月22日夜、奥州からの飛脚が鎌倉に届いた。奥州では「予州義経并木曽左典厩義仲子息義高、及秀衡入道男等者、各令同心合力、擬発向鎌倉之由有謳歌説」という(『吾妻鏡』文治五年十二月廿三日条)。このような「亡霊」を奉じて敵対勢力を糾合することは、かつては平正盛に討たれたはずの前対馬守源義親が何人も現れて混乱期の朝廷を疑心暗鬼に陥れたように、不安定要素のある地域では一定の効果があるものだった。彼らが各々同心して鎌倉へ向かっているという報告を受け、翌23日、頼朝は北陸道を経由しての奥州派兵について議した(『吾妻鏡』文治五年十二月廿三日条)。結果、御家人らには深雪の時期だが、再度の出兵を用意すべしと指示し、小諸太郎光兼、佐々木三郎盛綱ら信濃国、越後国の御家人に出兵指示の書状を送っている。そして、その翌24日、鎌倉から工藤小次郎行光、由利中八惟平、宮六傔仗国平らが奥州へ出立した(『吾妻鏡』文治五年十二月廿四日条)。ただし、彼らの派遣は「可致防戦用意之故」という理由であることや、彼らがいずれも大名ではないことから、先遣隊の意味があったのだろう。
この奥州再乱は「奥州故泰衡郎従大河次郎兼任以下、去年窮冬以来企叛逆、或号伊予守義経、出於出羽国海辺庄、或称左馬頭義仲嫡男朝日冠者、起于同国山北郡、各結逆党」(『吾妻鏡』文治六年正月六日条)で、泰衡郎従の一人、大河次郎兼任らが伊予守義経や左馬頭義仲嫡男朝日冠者と号して起こしたもので、出羽国海辺庄や山北郡で軍勢を集めたものだった。大河兼任には弟が二人おり、奥州合戦の際に弟の藤次忠季は捕虜となったのちに赦されて御家人に列していた。忠季は頼朝の命によって東北へ向かっていたが、兼任が乱を起こしたことを聞いて鎌倉に戻って兼任の叛乱を報告。また、忠季の兄・新田三郎入道も兼任に背いて鎌倉に参上して子細を報告した。頼朝は彼らからの報告によって事の次第を知るとともに、平盛時、工藤行政に相模国以西の御家人に参上を命じさせている(『吾妻鏡』文治六年正月七日条)。
この頃、兼任は嫡子鶴太郎、次男畿内次郎らを相具して鎌倉へ向けて進軍を始めるが、出羽国小鹿嶋付近に駐屯していた鎌倉先遣隊の一人、由利中八惟平へ使者を送って、泰衡の敵を討つ存念を伝えている。これを受けた中八惟平は「小鹿嶋大社山毛々佐田之辺」まで馳せ向かい、進んでくる大河勢を防ぎ戦ったが、討死を遂げた。
さらに兼任は仙北郡山本から津軽郡へ進軍すると、この地を守っていた宇佐美平次実政ほか大見平次家秀、石岡三郎友景以下の御家人ならびに頼朝雑色沢安らを討ち取り、橘次公成を放逐した。彼らは頼朝挙兵から従う最古参の重鎮であり、彼らの討死は事の重大さを物語り、葛西三郎清重をはじめとする奥羽在国の御家人らは事の次第をしたためて各々飛脚を鎌倉へ飛ばしている(『吾妻鏡』文治六年正月六日条)。
そして、正月8日、頼朝は奥羽再派兵を決定し、海道大将軍は千葉介常胤、山道大将軍は比企藤四郎能員がこれを拝命している(『吾妻鏡』文治六年正月八日条)。ただし、東海道岩崎の海道平氏らは常胤の到着を待たずに進発する旨を伝えてきており、この常胤と比企藤四郎による進軍計画はすでに工藤行光ら先遣隊の出立時には決定していたのだろう。そのほか、小山七郎朝光ら奥州に所領を請けた御家人は一族等が同道して進軍するのではなく、各々が個々に急ぎ下向するよう指示している。大河兼任の叛乱を早々に鎮圧しなければ権威の失墜に繋がりかねないことや、奥州に遺している葛西三郎清重已下の救援を行う必要のためなど、早急に動く必要があったと考えられる。
正月13日、上野国、信濃国などの御家人に奥州出兵を指示。上総介義兼を追討使に任じて奥州へ向かわせた(『吾妻鏡』文治六年正月十三日条)。義兼が今回の奥州出兵の総大将ということであろう。今回の進軍も「是於三方、依可遂合戦」(『吾妻鏡』文治六年二月五日条)であることから、義兼は前回の頼朝と同様に奥大道を進んだとみられる。一方で、五日前の決定では千葉介常胤が海道大将軍と定められていたものが、一転して「千葉新介胤正承一方大将軍」とされている。七十三歳の常胤を厳冬の奥州へ出兵させることを断念した頼朝が胤正に替えた、または常胤自身の健康問題なのかもしれない。ただ、信濃国の小諸太郎光兼は「已老耄之上、病痾纏身之由」を聞いていたが、頼朝は「依為殊勇士、今度重被差遣奥州」(『吾妻鏡』文治六年正月廿二日条)と指示している。挙兵以来の重鎮常胤と義仲麾下から御家人となった光兼はその扱いが異なっていたとも考えられるが、老体を押して合戦に臨んでいた光兼自身の勇敢な姿を頼朝が認め、その影響力を期待していた可能性が高いだろう。
胤正は治承四年の上総国伊北庄合戦で葛西三郎清重を同伴してその戦いぶりを目に留めており、奥州出兵に当たり、頼朝に「葛西三郎清重者殊勇士也、先年上総国合戦之時、相共遂合戦、今度又可相具之由欲被仰含」と依頼しており、頼朝はこれを認めて「可相伴于胤正之旨、被下御書於清重」と清重に胤正との同道を指示する下知状を遣わした(『吾妻鏡』文治六年正月十三日条)。
正月15日、頼朝は常胤嫡孫「千葉小太郎」が今回の奥州合戦の働きぶりを賞して感状が遣わされたが、そこには「但合戦不進于先登兮、可愼身」という戒めも記された。頼朝はこの日二所詣に出ており、小太郎成胤は頼朝近習として供奉していたとみられ、今回の奥州合戦には出陣していなかったのだろう。
正月18日、伊豆山の頼朝のもとに葛西三郎清重からの使者が到着し(『吾妻鏡』文治六年正月十八日条)、宇佐美平次や大見平次ら最古参の御家人たちの討死が伝えられた。宇佐美平次は藤原泰衡追討戦では北陸道大将軍という御家人中の最重鎮であり、大見平次もその麾下として迎え撃ったのだろう。頼朝の受けた衝撃は大きかったと思われる。正月24日には、「去年合戦以後預恩赦安堵私宅許之族、金剛別当郎等以下悉以可追放之由」を奥州御家人らに命じている(『吾妻鏡』文治六年正月廿四日条)。また、2月4日には「来十月依可有御上洛、随兵以下事被触諸国御家人等」(『吾妻鏡』文治六年二月四日条)と、10月に上洛することを決定し、随兵などの人選を行うことを諸国御家人に触れている。2月5日には雑色の真近、常清、利定三名を検見のため、北陸道、奥大道、東海道それぞれに派遣する(『吾妻鏡』文治六年二月五日条)。彼らは奥羽の兵乱が御家人らの手に余るようであれば頼朝自らが出陣するので、その旨を申すべきことを千葉新介胤正以下の御家人に伝えた。
奥州下向の追討使足利上総前司義兼以下、「小山五郎、同七郎、葛西三郎、関四郎、小野寺太郎、中條義勝法橋、同子息藤次」らの人々は2月11日、平泉を通過。泉田まで進出し、兼任勢の行方を住民らに問うた(『吾妻鏡』文治六年二月十一日条)。すると、兼任はすでに平泉を出立したというので、平泉方面へと進軍した。そして翌12日、千葉新介胤正らも合流して「栗原一迫」で合戦して打ち破った。兼任は五百騎余りを率いて平泉衣河を前面に陣を張るが、ここも打ち破られ、北上川を渡って逃亡。その後、追討使上総前司義兼のもとに「於外浜与糠部間、有多宇末井之梯、以件山為城郭、兼任引篭之由風聞」という情報が届き、急行。足利義兼らは兼任勢に襲い掛かってこれを壊滅させている(『吾妻鏡』文治六年二月十二日条)。そして23日「胤正、清重、親家等」が奥州から遣わした飛脚が鎌倉に到着し、戦勝を報告。また、「其間能直、国平等尽兵略」と、古庄能直と宮道国平の戦いぶりが伝えられている。
島田景近―+―島田景重――――――近藤国澄――――近藤国平
(駿河権守)|(八郎大夫) (近藤八) (近藤七)
|
+―近藤景頼――+―――――――――――近藤能成
(近藤武者所)| (近藤太)
| ∥―――――――大友能直
| ∥ (左近将監)
| +―波多野経家―+―女子
| |(四郎) |
| | +―女子
| | ∥
| | 中原親能====大友能直
| | (斎院次官) (左近将監)
| |
| +―波多野義通―――波多野義常
| |(次郎) (右馬允)
| |
| | 源義朝
| |(左馬頭)
| | ∥―――――――源朝長
| | ∥ (中宮少進)
| +―女子
| ∥―――――――中原久経
| ∥ (典膳大夫)
| 中原某
|
+===武藤頼平==+―武藤資頼
(大蔵丞) |(筑前守)
|
藤原某―――+―藤原頼方
(監物) (監物太郎)
そして3月10日、進退窮まっていた兼任が一人で栗原寺まで逃れ来たところ、「着錦脛巾、帯金作太刀」を身につけた姿を怪しんだ「樵夫等」十数名に取り囲まれ、斧で殺害されたという。その首級は千葉新介胤正のもとへ運ばれて実検された(『吾妻鏡』文治六年三月十日条)。また、いまだ奥州再乱の鎮定が伝わらない中で、頼朝は3月15日、「左近将監家景号伊澤」を「可為陸奥国留守職之由被定」ている(『吾妻鏡』文治六年三月十五日条)。その所役は「聞民庶之愁訴、可申達」ことである。直前までの陸奥国の「新留守所、本留守」が兼任に同意の罪科があり、本来であれば誅殺すべきであるが、葛西清重の預かりとなって「甲二百領之過料」(『吾妻鏡』文治六年二月六日条)が命じられたことに伴い罷免され、家景が新しい留守職に任じられたと思われる。「文治五年討取伊予守義顕、又入奥州征伐藤原泰衡、令皈鎌倉給之後、陸奥出羽両国可令知行之由、被蒙 勅裁、是依為泰衡管領跡也」(『吾妻鏡』宝治二年二月五日条)とあるように、泰衡追討後に頼朝が陸奥国と出羽国の知行国主となった可能性が高い(ただし国司は朝廷から補任されることとしている)。これに基づき、頼朝は陸奥国衙の留守職任免権を行使して、兼任に加担した「新留守所、本留守」を更迭し、伊澤左近将監を陸奥国衙留守所に抜擢したとみられる。そして、3月25日、鎌倉に兼任誅殺の報告が届けられることとなる(『吾妻鏡』文治六年三月廿五日条)。
4月11日、幕府南庭で頼朝嫡子・頼家(九歳)のはじめて小笠懸の儀が行われた。弓の師・下河辺庄司行平が介添えを行い、的は三浦介義澄、馬は千葉介常胤、鞍は小山田三郎重成が献じた。装束は八田右衛門尉知家が行騰と沓を、宇都宮左衛門尉朝綱が水干袴を進上した(『吾妻鏡』建久元年四月十一日条)。
京都では文治6(1192)年正月3日、「天皇御元服」が執り行われ、兼実は加冠、理髪は左大臣実定、能冠は内蔵頭範能がそれぞれ務めた。ただ、御剣の沙汰を行う職事家実の懈怠により晩に入ってから事始となり、天皇の東拝は日没となり、加冠の礼は掌灯後となっている(『玉葉』文治六年正月三日条)。
正月11日には「此日有入内事、余長女、生年十八、余卌二、早旦、宗頼朝臣参上、使立宣令勤事、御着裳并立御帳、日時等、見了返給了」(『玉葉』文治六年正月十一日条)と、兼実長女任子の入内が行われ、14日、「露顕、女御宣下」(『玉葉』文治六年正月十四日条)と、女御となった。そして4月26日、「此日、女御任子有冊命立后事、延喜大后穏子四月廿六日有立后、待賢門院、正月廿六日己酉又立后、日月叶延長例、支干付永久跡、可吉祥耳」と中宮に冊立された(『玉葉』建久元年四月廿六日条)。
●中宮職(『玉葉』建久元年四月廿六日条)
| 大夫 | 正二位 | 藤原兼房 | 大納言 | 中宮叔父 |
| 権大夫 | 従三位 | 藤原家房 | 左近衞中将 | 伯父松殿基房入道の子 |
| 亮 | 正四位下 | 藤原宗頼 | 蔵人頭 | 兼実家司(権大納言光頼の子) |
| 権亮 | 正四位下 | 藤原兼良 | 右近衞中将 | 中宮従兄(中宮大夫兼房の子) 伯父松殿基房入道の猶子 |
| 大進 | 正五位下 | 藤原長房 | 右衛門権佐 | 兼実家司(勘解由長官光長の子) |
| 権大進 | 従五位上 | 藤原長兼 | 甲斐守 | 兼実家司(権中納言長方の子。母は信西入道娘) |
| 少進 | 従五位下 | 藤原兼時 | ||
| 少進 | 正六位上 | 藤原行方 | ||
| 大属 | 従五位下 | 大江政職 | ||
| 少属 | 正六位上 | 三善仲親 | ||
| 権少属 | 正六位上 | 安倍資兼 |
関白兼実は「御堂者、累祖之中為帝外祖之人雖多、繁華之栄、莫過彼公、宇治殿以降、絶而無此事、為取其始終、尤可祈申此両所歟、入内之本意、只在皇子降誕者歟」(『玉葉』文治五年十一月廿八日条)と入内の目的を明確に皇子降誕としており、宇治殿頼通以降絶えていた天皇外戚たる摂関家の復活を目指していた。そしてそれは兼実一門が故殿忠通を継承する摂関家嫡統という意図であり、当時の上卿の多くが兼実係累に属していたのである。さらに「無才漢、無労積、只以先公之旧労」と酷評する実弟兼房を建久2(1191)年3月28日に太政大臣に推挙し(『玉葉』建久二年三月廿八日条)、建久3(1192)年11月29日に弟・権僧正慈円を天台座主に据え、政治・宗教の面からも強力に兼実系で固めることに成功した。
■建久元(1190)年公卿補任(異動者)
| 摂政 | 藤原兼実 | 4月19日、太政大臣の上表 | 中宮任子の父 |
| 太政大臣 | (藤原兼実) | 4月19日、兼実上表 | |
| 左大臣 | 藤原実房 | 7月17日、実定の辞職(男公継の任参議)に伴い、右大臣から転任 | 兼実実弟・兼房の義兄 |
| 右大臣 | 藤原兼雅 | 7月17日、実房の左大臣転任に伴い、内大臣から転任 兼実との交流もあったが、その政敵となった源通親とも血縁上親密であった |
兼実嫡子・故良通の舅 |
| 内大臣 | 藤原兼房 | 7月17日、兼雅の右大臣転任に伴い、任大臣(前大納言、前中宮大夫) | 兼実実弟 |
| 大納言 | 藤原実家 | 7月17日、兼房の任大臣により、権大納言筆頭の実家が大納言に転じる | 兼実親交 (送り人事) |
| 中宮大夫 | 藤原良経 | 7月18日、兼房の任大臣により、闕となった中宮大夫を兼務 | 兼実嫡子 |
| 権大納言 | 藤原頼実 | 7月17日、実家の大納言転任により、中納言筆頭の頼実が権大納言に転じる | 兼房義弟 (送り人事) |
| 中納言 | 藤原定能 | 7月18日、辞左衛門督(婿兵部大輔源定忠への左近権少将任官申請のため) | |
| 中納言 | 源通親 (源氏長者) |
7月17日、頼実の権大納言転任により、権中納言筆頭の通親が中納言に転じる 7月18日、左衛門督定能の辞任に伴い右衛門督から左衛門督に転任、補検非違使別当 |
(送り人事) |
| 権中納言 | 藤原隆房 | 7月18日、源通親の左衛門督転任に伴い、右衛門督に就く | |
| 権中納言 | 藤原兼光 | 7月18日、右兵衛督能保の左兵衛督転任に伴い右兵衛督に就く | |
| 権中納言 | 源通資 | 7月17日、権中納言新任 | |
| 参議 | 藤原能保 | 7月18日、右兵衛督から左兵衛督に転任 | |
| 参議 | 藤原公継 | 7月17日、父左大臣実定の辞任に伴い参議に就任 | (譲り人事) |
またこの頃、鎌倉では頼朝が法皇との約定通り上洛の計画を進めており、9月15日、公文所の民部丞行政、三善善信入道、民部丞盛時、隼人正康清に指示し、上洛路地の諸奉行の人事沙汰を行わせた(『吾妻鏡』建久元年九月十五日条)。この上洛は法皇へも院奏され、これまで京都に頻繁に流れた頼朝上洛不定の噂とは画した正式なものであった。なお、宿事を葛西三郎清重が任じられていることから、清重はこの頃には奥州から鎌倉に帰還していることがわかる。
御京上間奉行事(『吾妻鏡』建久元年九月十五日条)
| 貢金以下進物事 | 民部丞行政、法橋昌寛 |
| 先陣隨兵事 | 和田太郎義盛 |
| 後陣隨兵事 | 梶原平三景時 |
| 御厩事 | 八田右衛門尉知家、千葉四郎胤信 |
| 御物具事 | 三浦十郎義連、九郎藤次 |
| 御宿事 | 葛西三郎清重 |
| 御中持事 | 堀藤次親家 |
| 雑色以下々部事 | 梶原左衛門尉景季、梶原平次景高 |
| 六波羅御亭事 諸方贈物事 |
掃部頭中原親能、因幡前司中原広元 |
◎工藤氏略譜
※時理は諱及び子の維永の不審等から時信と同一人物としている。
藤原維幾
(木工助)
∥――――藤原為憲―+―藤原時輔
∥ (木工助) |(工藤太)
∥ |
平高望――女子 +―藤原時信―+―藤原維景――+―藤原維職―――藤原維次――+―藤原家次―+―藤原祐次――+―藤原祐経
(上総介) (駿河守) |(駿河守) |(伊豆押領使)(狩野九郎) |(狩野四郎)|(武者所) |(工藤左衛門尉)
| | | | |
| | | | +―藤原祐茂
| | | | (宇佐美三郎)
| | | |
| | | +―藤原祐家――――藤原祐親
| | | (六郎大夫) (河津次郎)
| | |
| | +―藤原茂光―+―藤原宗茂
| | (工藤介) |(狩野介)
| | |
| | +―女子
| | ∥―――――――源信綱
| | ∥ (田代冠者)
| | 後三条天皇―+―輔仁親王―+―源有仁――?―源為綱
| | |(無品) |(左大臣) (伊豆守)
| | | |
| | | +―行恵―――+―円曉
| | | (法眼) |(宮法眼)
| | | |
| | | +―尊曉
| | | (宰相阿闍梨)
| | |
| | +―高階為行―――女子
| | (信濃守) ∥――――――藤原忠清――――女子
| | ∥ (淡路守) ∥―――――――源義朝
| | 具平親王―――藤原頼成――――藤原清綱 源為義 (左馬頭)
| |(一品)
(因幡守) (左衛門佐) (左衛門大尉)
| |
| +―藤原景任―――藤原資広――――藤原行景―――藤原景澄――――藤原景光
| (工藤庄司)
|
+―藤原維清――+―藤原維仲―――藤原師清――――藤原清仲―+―藤原清行――――藤原清益
|(入江右馬允)|(工藤大夫) (原権守) (遠江権守)|(原四郎) (原三郎)
| | |
| | +―藤原維次――――藤原維忠
| | |(橋爪五郎) (中庄二郎)
| | |
| | +―藤原宗仲――――藤原忠宗
| | (六郎) (久野四郎)
| |
| +―藤原維綱―――藤原清綱――――藤原泰綱―――藤原忠綱――――藤原時綱
| |(船橋四郎) (岡部権守) (岡部権守) (岡部八郎) (岡部左兵衛尉)
| |
| +―藤原清定―+―藤原家清――――藤原家貞―――藤原家実――――藤原家綱
| (入江権守)|(大田権守) (野辺三郎) (野辺次郎) (野辺小次郎)
| |
| +―藤原清実――――藤原清親―――藤原清章――――藤原祐清
| |(蒲原権守) (武者所) (池屋次郎) (原八郎)
| |
| +―藤原景兼――+―藤原遠兼―――藤原景貞――+―藤原兼貞
| (入江右馬允)|(渋河権守) (瀧口) |(渋河中務丞)
| | |
| | +―藤原為貞
| | |(野辺左衛門尉)
| | |
| | +―藤原惟貞
| | (舟越右馬允)
| |
| +―藤原景義―――藤原経義――――藤原友兼
| (右馬三郎) (吉香三郎) (吉香左衛門尉)
|
+―藤原維遠――――藤原維兼―――藤原維行――――藤原行遠
(駿河守) (駿河守) (白尾三郎)
∥――――――藤原行政――――藤原行光
∥ (二階堂主計允)(民部丞)
藤原季範――+―女子
(熱田大宮司)|
+―女子 藤原能保
∥ (右兵衛督)
∥ ∥―――――――藤原高能
∥ ∥ (左馬頭)
∥――――+―妹
∥ |
源義朝 +―源頼朝
(左馬頭) (右近衞大将)
翌9月16日には武蔵国から畠山次郎重忠が上洛供奉のために鎌倉に参着(『吾妻鏡』建久元年九月十六日条)。9月21日には伊豆国寺宮庄の北条時政ら鎌倉近郊二十余ヶ所を所領する御家人から鎌倉留守居の兵士の徴収がなされ、民部丞行政を奉行とする。また、中原広元は「先上洛」とあるように、頼朝に先行して上洛した。これは「御入洛以前於京都有可致沙汰事等故也」(『吾妻鏡』建久元年九月廿一日条)という。「於京都有可致沙汰事」がどのような事か具体的に記載されないことから、記載の憚られる事柄であったと思われ、頼朝長女大姫入内に関する事柄ではなかったか。この入内の話が後述の覲子内親王の院号宣下へと繋がっている可能性があろう。
つまり頼朝の上洛は、後白河院との対面及び京洛の人々への存在感のアピール、摂政兼実との対談、そして最大の目的として長女大姫の入内を推し進めることにあったと考えられる。大姫入内の布石は前述の通り、前年文治5(1191)年12月の中原広元上洛の時点から敷かれ始め、9月の広元上洛で凡その同意が為されたのだろう。その過程で、頼朝は「仙洞女房三位局」が比叡山で仏事を修することを聞いて「砂金帖絹等」を差し遣わすなど(『吾妻鏡』建久元年五月廿三日条)、入内の折衝は丹後局を窓口としていたと思われる。一方、法皇は頼朝を「京官」に就けることで公卿常京の規律に従わせようと企てていたと思われる。
鎌倉出立は翌3日と決定し(『吾妻鏡』建久元年十月三日条)、当日には幕府南庭に主だった御家人が待機し、大名は頼朝出座のもと御所内で軍議が行われていた。本来は午前中の出立予定だったと思われるが、常陸国から下っていた八田右衛門尉知家が午刻にようやく参上。行騰をつけたまま南庭を回って直に沓解へ昇り、ここで行騰を脱いで頼朝の傍らに用意されていた座に着いた。当然頼朝は不快であり、「依有可被仰合事等、被抑御進発之處遅参、懈緩之所致也」と叱りつけた。知家は「所労之由」を述べて遅参を詫びるとともに「先後陣誰人奉之哉、御乗馬被用何哉者」と問うた。頼朝は「先陣事重忠申領状訖、後陣所思食煩也、御馬被召景時黒駮者」と答えている。これを聞いた知家は「先陣事尤可然、後陣者常胤為宿老可奉之仁也、更不可及御案事歟、御乗馬彼駮雖為逸物、不可叶御鎧之馬也、知家用意一疋細馬、可被召歟者」と、先陣は重忠で相応しく、後陣は千葉介常胤が宿老として奉じるべき仁であって、まったくお悩みになるようなことではないと意見している。乗馬についても知家が持参したすらりとした体高八寸の黒馬を紹介し、頼朝は見るなり気に入っている。ただし細馬ということもあり、「但御入洛日可被召之、路次先試可被用件駮者」と、路次では梶原景時進上の逞しい黒駮を用いるよう述べている。頼朝は知家の意見を容れて常胤を御前に召すと「相具六郎大夫胤頼、平次常秀等、可供奉最末之旨」を指示した。その後、頼朝は鎌倉を出立するが程なく黄昏となり、相模国懐島に宿すこととなった。後陣はまだ鎌倉から出ていない状況で、懐島権守の大庭平太景能が駄餉を献じている(『吾妻鏡』建久元年十月三日条)。
10月5日、「関下(南足柄市関本)」のあたりで「陸奥目代解状」が到来した(『吾妻鏡』建久元年十月五日条)。「陸奥目代」はこの時点では即ち陸奥国留守所の伊澤左近将監家景を指すとみられるが、「陸奥国諸郡郷新地頭等」の所務について定め、「可早従留守并在庁下知、先例有限国事致其勤事」を命じた。「且御目代不下向之間、隨留守家景并在庁之下知可致沙汰、但留守家景可問先例於在庁也、国司者自公家被補任、在庁者国司鏡也、於先例沙汰来之事者、不憚人無偏頗可致沙汰」としている。この当時、頼朝は「陸奥出羽両国可令知行之由、被蒙 勅裁」(『吾妻鏡』宝治二年二月五日条)とあるように陸奥出羽両国の知行国主だったと思われるが、建久元(1190)年12月1日以降に陸奥守に任じられた前右馬助朝房(『吾妻鏡』建久元年十二月一日条)は「院北面衆」であることから、陸奥国は事実上院御領として存続しており関東御分国ではなかった。秀衡が薨去した文治3(1187)年10月29日から建久元(1190)年12月1日以降ある時点までの陸奥守は不明であり、この間「国司者自公家被補任」「御目代不下向」とあることから、国司が闕だった可能性が高いだろう。その後、院近臣藤原朝房が陸奥守となり、建久3(1192)年7月に遠江守へ移っている(『吾妻鏡』建久三年七月廿六日条)。目代不在の間、奥州御家人らは「留守家景并在庁」の下知に随うべしと定められ、留守家景は在庁に先例を問いながら沙汰すべきことが指示された。荒廃した国を復興させるためにはただ勧農を沙汰し、国務に従わない所々は家景自身が赴いて検分し下知すべきとした。
10月22日、法皇より兼実に「来廿五日、於直盧、新制定可有之由、被仰下」(『玉葉』建久元年十月廿二日条)たが、25日、26日は「物忌」であったことで、結局11月1日に延期されたと思われる。兼実は召しにより参院し、法皇に「新制」について申し述べた後、内裏に参じて直盧において「意見新制等目六」に目を通した。その後、内府兼房已下の公卿が召され「新制議定事」が行われている。まず神事の事が議論され、続けて仏事、その後に「他雑事等」が話し合われた。そして11月4日午刻、摂政兼実は参院し、「新制之間事」を奏上して「条々被仰下」た。また「奏頼朝卿可被授官之由」しており、法皇も「可然之由有仰、其儀可問人々」との返答であった。これに対し兼実は「広不可被問、右大臣、民部卿、宜歟」と右大臣兼雅と民部卿経房(正月24日に辞帥、8月13日任民部卿)のみに問うことを述べた(『玉葉』建久元年十一月四日条)。その後、近江国野路宿(草津市野路)の頼朝のもとに「然者可為何官哉之由、有 勅問」った。そして、後藤基清と小山朝光の両名が先駆けの御使として入洛している(『吾妻鏡』建久元年十一月四日条)。
京都では11月4日、内裏の兼実のもとへ右大臣兼雅が訪れ、「丹三品腹姫宮、可有院号之由、母儀存知、而奏聞有憚、余可発言」(『玉葉』建久元年十一月四日条)という。法皇と丹後局の娘・覲子内親王に対する「院号」下賜の奏聞依頼であった。すでに丹後局も了承しているが、憚りがあるため兼実からの奏聞を要請している。この「有憚」とは、兼実が二の足を踏む「余モ頗可有其恐歟」というものと同一の事、すなわち皇后・中宮でもなければ天皇の母・准母でもない女性が女院になった前例はないにも拘わらず、覲子内親王に院号を与えようとすることである。そして、この異例の措置を、兼雅は先例に極めて厳格なはずの兼実から奏聞するよう求めたのである。
兼実は娘・任子を中宮としており、その兼実が覲子内親王に異例の院号奏聞をしたとすれば、それは「且是似被妨后位之故也」と受け取られる可能性が極めて高かった。しかし、兼雅は「全不可然、彼本意、只在院号」と、丹三位の望みはただ娘を女院としたいのみであり、「以御消息、内々可触遣歟」と丹後局へ内々に手紙を遣わせばよいのではないかという。兼実は「此事雖不可然、為天下頗穏便之沙汰也」と、渋々ながら天下のためには妥当であると考えるが、兼実の内心は、入内の噂があった覲子内親王が「忽有此沙汰」という院号を下される沙汰となったのは「誠天之助也、中宮之御運也」と歓喜しているのである。
しかし、これら一連の奏上劇は、頼朝娘入内の布石とともに、兼実の評判を貶める策でもあったのだろう。実は兼雅の姉は兼実の政敵となっていた中納言源通親の室であり、兼雅と通親は結びついていた可能性が高い。そして中宮任子の対立相手が消えることに気を取られていた兼実は、この謀に気づかずにいたのだろう。
源師房――源麗子
(右大臣) ∥―――――藤原師通―――藤原忠実―――藤原忠通――+―藤原基実――藤原基通
∥ (摂政) (関白) (関白) |(摂政) (関白)
∥ |
藤原頼通―藤原師実 +―藤原基房
(関白) (関白) (関白)
∥―――――藤原家忠 ∥―――――藤原師家
∥ (左大臣) ∥ (摂政)
源頼国――女子 ∥――――――藤原忠家 +―女子
(美濃守) ∥ (権中納言) |
藤原定綱――女子 ∥――――――藤原忠雅――+―女子
(播磨守) ∥ (太政大臣) ∥―――――源通宗
∥ ∥ ∥ (右近衞中将)
∥ ∥ 源通親
∥ ∥ (内大臣)
∥ ∥
藤原家保―+―女子 ∥―――――――藤原兼雅
(参議) | ∥ (右大臣)
| ∥ ∥
+―藤原家成―――女子 ∥―――――藤原忠経
|(中納言) ∥ (右大臣)
| ∥ ∥
| 平清盛―――――女子 ∥―――――+―藤原忠頼
| (太政大臣) ∥ |(右近衞中将)
| ∥ |
| 源義朝―――+―源頼朝 ∥ +―藤原定雅
| (下野守) |(右大将) ∥ (右近衞大将)
| | ∥
| 藤原通重 +―女子 ∥
| (丹波守) ∥―――――女子
| ∥ ∥
| ∥―――――――藤原能保
| +―女子 (権中納言)
| |
| 藤原公能―+―藤原実守
|(右大臣) (権中納言)
| ∥
+―女子 ∥
∥――――――女子
∥
源顕通――+―源雅通――――源通親
(権大納言)|(内大臣) (内大臣)
|
+―明雲
(天台座主)
覲子内親王は「世上之謳歌、有大事」と入内の噂があったが、前述のような急な院号宣下への流れとなっている。この急な展開の理由かは明らかにされていないが、この奏聞依頼は「二品御入洛可為今明之由、達叡聞之間」(『吾妻鏡』建久元年十一月四日条)と見える通り、頼朝入洛予定日が法皇に伝えられた当日であり、頼朝はその後二日間、京都の手前で雨や「御衰日」を理由に留まり入洛しなかった。これは、覲子内親王の院号宣下に関わる報告も関わっていたのかもしれない。
藤原忠通――――藤原兼実――――――――藤原任子
(関白) (摂政) (中宮)
∥
藤原信隆――――藤原殖子 ∥――――――昇子内親王
(修理大夫) (七条院) ∥ (春華門院)
∥ ∥
∥ 源頼朝――嫡女 ∥
∥ (前右大将)∥ ∥
∥ 【計画】 ∥
∥ ∥ ∥
平滋子 ∥―――――――後鳥羽天皇
(建春門院) ∥ ↑
∥ ∥ 【乳母】
∥ ∥ 藤原範子
∥ ∥ (刑部卿三位)
∥ ∥ ∥
∥―――――――高倉天皇 源通親
∥ (中納言)
後白河法皇 【勅別当】
∥ ↓
∥―――――――――――――――覲子内親王
∥ (宣陽門院)
丹後局
(三位)
その後、兼実は法皇より「五日、余依右大臣風諫、以消息粗示遣之、相計可披露之由」の命を受けている。また、法皇からの頼朝任官について諮問を受けていた兼実は、翌5日に右大臣兼雅に面会し「頼朝若可被任大将、更不可惜之由」を述べている。兼雅は当時右近衞大将を兼ねており、頼朝を右大将とするため、兼雅には「頼朝若可被任大将、更不可惜之由」を告げて、右大将を辞するよう要請している(『玉葉』建久元年十一月五日条)。
11月6日、近江国野路宿に逗留(『吾妻鏡』建久元年十一月六日条)していた頼朝は、当日入洛の予定を、障りの日であるとして朝廷に「而依道虚衰日、延引、明日」と報告した(『玉葉』建久元年十一月六日条)。実際は大雨による見物人の減少や印象への影響を考慮したものであろう。そして翌7日、頼朝は入洛を果たすこととなる(『吾妻鏡』『玉葉』建久元年十一月七日条)。
頼朝にとっては永暦元(1160)年3月11日に離京して以来、実に三十年半ぶりの京都であった。入洛は7日の「申剋先陣入花洛」とあり、日の傾いた頃の入洛であった(『吾妻鏡』建久元年十一月七日条)。ただし、『玉葉』によれば「日昼騎馬入洛有存旨」、「申刻、着六波羅新造亭」(『玉葉』建久元年十一月七日条)とあり、先陣以下の入洛はこれ以前で、頼朝が六波羅邸に入ったのが申刻であったとみられる。『吾妻鏡』でも「秉燭之程、令着六波羅新御亭、故池大納言頼盛卿旧跡、此間被建之、給」とある。入洛は「三條末西行、河原南行、令到六波羅給」(『吾妻鏡』建久元年十一月七日条)というルートから、山科を経て粟田口より三条末に出ると、三条大橋から鴨川を渡るが、京洛には入らずに鴨川沿いを南下し、五条大橋または六条大橋あたりから鴨川を再度渡り、六波羅に入ったと思われる。六波羅邸には先行していた小山七郎朝光や、在京の家司下総守邦業、前掃部頭親能、因幡前司広元や宇都宮左衛門尉朝綱らがすでに入っており、頼朝を迎えている。
関東勢の行列は、まず先陣の畠山次郎重忠が家子一人と郎等十名を具して進むと、続けて先陣随兵百八十騎が三騎並んで進み、続けて頼朝の姿が現れた。『玉葉』によれば頼朝の装束は「騎馬帯弓箭、不着甲冑」(『玉葉』建久元年十一月七日条)という。『吾妻鏡』では「折烏帽子、絹紺青丹打水干袴、紅衣、夏毛行騰、染羽野箭、黒馬、楚鞦、水豹毛泥障」とある(『吾妻鏡』建久元年十一月七日条)。「水豹毛泥障」は奥州より取り寄せたものだろう。また駕した黒馬は鎌倉出立時に八田知家から献じられた体高四尺八寸の細黒馬であろう。続けて頼朝同様に水干に野箭を着す十騎が進み、後陣随兵百三十八騎が続いた。そのあとに梶原景時が郎従数十騎を率い、最末は「千葉介以子息親類等為随兵」が列した。
随兵の御家人ら三百騎余は入洛時にはいずれも郎従を具さず、総勢でも四百騎に満たない(『愚管抄』第六によれば「三騎々々ナラベテ武士ウタセテ、我ヨリ先ニタシカニ七百余騎アリケリ、後ニ三百余騎ハウチコミテ有ケリ」とある)ものであるが、先陣随兵は三騎横並びに六十組(百八十騎)、後陣随兵は四十六組(百三十八騎)が軍律の行き届いた行列を見せた。かつての木曽義仲が入洛したときとはまったく異なる印象を与えるものだったろう。「院已下洛中諸人見物」(『玉葉』建久元年十一月七日条)と、法皇は鴨の河原道に車を停めて見物し、洛中の人々もこの東国武家の棟梁の入洛を見物している。なお、兼実はこの行列を見ていないが、この直後の会談で、頼朝は兼実に法皇への聞こえを恐れて「外相雖表疎遠」と述べているように、よそよそしさを感じていたためか。そして兼実は「日昼騎馬入洛有存旨」と頼朝の狙いについて暗に言及する。
(1)関東勢の姿を強く印象づけるとともに、関東勢の規律の強さを強調する
(2)総大将の自分自身が武装しないことにより乱世の終焉を印象づける
(3)行列を含め軍勢を入京させずに六波羅へ留める配慮を見せる
木曽義仲及び平家を討ち、奥州平定も成し遂げるなど武威は十分京都に伝わっており、今更「挑発的」な武力を見せつける必要はなく、いわば強大な武威を示しながらも「儀式的」で安穏な世の到来の「象徴的」な入洛を展開したのであろう。
■建久元年十一月七日入洛勢(『吾妻鏡』建久元年十一月七日条)
| 先 | 貢金辛櫃一合 | |||
| 先陣 | 畠山次郎重忠 ・着黒糸威甲 |
家子一人 郎等十人等 |
||
| 先陣隨兵: ・一騎別張替持一騎 ・冑腹巻行騰 ・小舎人童上髪 ・負征箭、着行騰 ・其外不具郎従 |
一番 | 大井四郎太郎 | 大田太郎 | 高田太郎 |
| 二番 | 山口小七郎 | 熊谷小次郎 | 小倉野三 | |
| 三番 | 下河辺四郎 | 渋谷弥五郎 | 熊谷又次郎 | |
| 四番 | 仙波次郎 | 瀧野小次郎 | 小越四郎 | |
| 五番 | 小河次郎 | 市小七郎 | 中村四郎 | |
| 六番 | 加治次郎 | 勅使河原三郎 | 大曽四郎 | |
| 七番 | 平山小太郎 | 樟田小次郎 | 古郡次郎 | |
| 八番 | 大井四郎 | 高麗太郎 | 鴨志田十郎 | |
| 九番 | 馬場次郎八 | 嶋六郎 | 多加谷小三郎 | |
| 十番 | 阿加田沢小太郎 | 志村小太郎 | 山口次郎兵衛尉 | |
| 十一番 | 武次郎 | 中村七郎 | 中村五郎 | |
| 十二番 | 都筑三郎 | 小村三郎 | 石河六郎 | |
| 十三番 | 庄太郎三郎 | 四方田三郎 | 浅羽小三郎 | |
| 十四番 | 岡崎平四郎 | 塩谷六郎 | 曽我小太郎 | |
| 十五番 | 原小三郎 | 佐野又太郎 | 相摸豊田兵衛尉 | |
| 十六番 | 阿保六郎 | 河匂三郎 | 河匂七郎三郎 | |
| 十七番 | 坂田三郎 | 春日小次郎阿 | 佐美太郎 | |
| 十八番 | 三尾谷十郎 | 河原小三郎 | 上野沼田太郎 | |
| 十九番 | 金子小太郎 | 駿河岡部小次郎 | 吉香小次郎 | |
| 二十番 | 小河次郎 | 小宮七郎 | 戸村小三郎 | |
| 廿一番 | 土肥次郎 | 佐貫六郎 | 江戸七郎 | |
| 廿二番 | 寺尾太郎 | 中野小太郎 | 熊谷小太郎 | |
| 廿三番 | 祢津次郎 | 中野五郎 | 小諸太郎次郎 | |
| 廿四番 | 祢津小次郎 | 志賀七郎 | 笠原高六 | |
| 廿五番 | 嶋楯三郎 | 今堀三郎小 | 諸小太郎 | |
| 廿六番 | 土肥荒次郎 | 広沢三郎 | 二宮小太郎 | |
| 廿七番 | 山名小太郎 | 新田蔵人 | 徳河三郎 | |
| 廿八番 | 武田太郎 | 遠江四郎 | 佐竹別当 | |
| 廿九番 | 武田兵衛尉 | 越後守 | 信濃三郎 | |
| 三十番 | 浅利冠者 | 奈胡蔵人 | 伊豆守 | |
| 卅一番 | 参河守 | 相摸守 | 里見太郎 | |
| 卅二番 | 工藤小次郎 | 佐貫五郎 | 田上六郎 | |
| 卅三番 | 下総豊田兵衛尉 | 鹿嶋三郎 | 小栗次郎 | |
| 卅四番 | 藤沢次郎 | 阿保五郎 | 伊佐三郎 | |
| 卅五番 | 中山四郎 | 中山五郎 | 江戸四郎 | |
| 卅六番 | 加世次郎 | 塩屋三郎 | 山田四郎 | |
| 卅七番 | 中沢兵衛尉 | 海老名兵衛尉 | 豊嶋兵衛尉 | |
| 卅八番 | 中村兵衛尉 | 阿部平六 | 猪股平六 | |
| 卅九番 | 駒江平四郎 | 西小大夫 | 高間三郎 | |
| 四十番 | 所六郎 | 武藤小次郎 | 豊嶋八郎 | |
| 四十一番 | 佐々木五郎 | 糟江三郎 | 岡部右馬允 | |
| 四十二番 | 堀四郎 | 海老名次郎 | 新田六郎 | |
| 四十三番 | 葛西十郎 | 伊東三郎 | 浦野太郎 | |
| 四十四番 | 小沢三郎 | 渋河弥五郎 | 横山三郎 | |
| 四十五番 | 豊嶋八郎 | 堀藤太 | 和田小次郎 | |
| 四十六番 | 山内先次郎 | 佐々木三郎 | 筥王丸 | |
| 四十七番 | 右衛門兵衛尉 | 尾藤次 | 中條平六 | |
| 四十八番 | 三浦十郎太郎 | 後藤内太郎 | 比企藤次 | |
| 四十九番 | 小山四郎 | 右衛門太郎郎 | 岡部与一太 | |
| 五十番 | 糟谷藤太 | 野平右馬允 | 九郎藤次 | |
| 五十一番 | 多気太郎 | 小平太 | 宇佐美小平次 | |
| 五十二番 | 波多野小次郎 | 新田四郎 | 机井八郎 | |
| 五十三番 | 小野寺太郎 | 足利七郎四郎 | 足利七郎五郎 | |
| 五十四番 | 佐貫四郎 | 足利七郎太郎 | 横山太郎 | |
| 五十五番 | 梶原兵衛尉 | 和田小太郎 | 宇治蔵人三郎 | |
| 五十六番 | 梶原左衛門尉 | 宇佐美三郎 | 賀嶋蔵人次郎 | |
| 五十七番 | 小山田四郎 | 三浦平六 | 小山田五郎 | |
| 五十八番 | 和田三郎 | 堀藤次 | 土屋兵衛尉 | |
| 五十九番 | 千葉新介 | 氏家太郎 | 千葉平次 | |
| 六十番 | 小山田三郎 | 北條小四郎 | 小山兵衛尉 | |
| 御引馬一疋 | ||||
| 御具足持一騎 | ||||
| 御弓袋差一騎 | ||||
| 御甲着一騎 | ||||
| 二位家(源頼朝) ・折烏帽子、絹紺青丹打水干袴、紅衣 ・夏毛行騰、染羽野箭 ・黒馬、楚鞦、水豹毛泥障 |
||||
| 著水干輩 ・負野箭 |
一番 | 八田右衛門尉 | 伊東四郎 | 加藤次 |
| 二番 | 三浦十郎 | 八田太郎 | 葛西三郎 | |
| 三番 | 河内五郎 | |||
| 四番 | 三浦介 | |||
| 五番 | 足立右馬允 | 工藤左衛門尉 | ||
| 後陣隨兵 | 一番 | 梶原刑部丞 | 鎌田太郎 | 品河三郎 |
| 二番 | 大井次郎 | 大河戸太郎 | 豊田太郎 | |
| 三番 | 人見小三郎 | 多々良四郎 | 長井太郎 | |
| 四番 | 豊嶋権守 | 江戸太郎 | 横山権守 | |
| 五番 | 金子十郎 | 小越右馬允 | 小沢三郎 | |
| 六番 | 吉香次郎 | 大河戸次郎 | 工藤庄司 | |
| 七番 | 大河戸四郎 | 下宮次郎 | 奥山三郎 | |
| 八番 | 海老名四郎 | 宇津幾三郎 | 本間右馬允 | |
| 九番 | 河村三郎 | 阿坂余三 | 山上太郎 | |
| 十番 | 下河辺庄司 | 鹿嶋六郎 | 真壁六郎 | |
| 十一番 | 大胡太郎 | 祢智次郎 | 大河戸三郎 | |
| 十二番 | 毛利三郎 | 駿河守 | 平賀三郎 | |
| 十三番 | 泉八郎 | 豊後守 | 曽祢太郎 | |
| 十四番 | 村上左衛門尉 | 村上七郎 | 高梨次郎 | |
| 十五番 | 村上右馬允 | 村上判官代 | 加々美次郎 | |
| 十六番 | 品河太郎 | 高田太郎 | 荷沼三郎 | |
| 十七番 | 近間太郎 | 中郡六郎太郎 | 中郡次郎 | |
| 十八番 | 秩父平太 | 深栖太郎 | 倉賀野三郎 | |
| 十九番 | 沼田太郎 | 志村三郎 | 臼井六郎 | |
| 二十番 | 大井五郎 | 岡村太郎 | 春日与一 | |
| 廿一番 | 大胡太郎 | 深栖四郎 | 都筑平太 | |
| 廿二番 | 大河原次郎 | 小代八郎 | 源七 | |
| 廿三番 | 三宮次郎 | 上田楊八郎 | 高屋大郎 | |
| 廿四番 | 浅羽五郎 | 臼井余一 | 天羽次郎 | |
| 廿五番 | 山上太郎 | 武者次郎 | 小林次郎 | |
| 廿六番 | 井田太郎 | 井田次郎 | 武佐五郎 | |
| 廿七番 | 目黒弥五郎 | 皆河四郎 | 平佐古太郎 | |
| 廿八番 | 鹿嶋三郎 | 広沢余三 | 庄太郎 | |
| 廿九番 | 上野権三郎 | 大井四郎 | 相摸小山太郎 | |
| 三十番 | 塩部四郎 | 塩部小太郎 | 中條藤次 | |
| 卅一番 | 小見野四郎 | 庄四郎 | 仙波平太 | |
| 卅二番 | 片穂平五 | 那須三郎 | 常陸平四郎 | |
| 卅三番 | 塩谷太郎 | 毛利田次郎 | 平子太郎 | |
| 卅四番 | 遠江浅羽三郎 | 新野太郎 | 横地太郎 | |
| 卅五番 | 高橋太郎 | 印東四郎 | 須田小大夫 | |
| 卅六番 | 高幡太郎 | 小田切太郎 | 岡舘次郎 | |
| 卅七番 | 筥田太郎 | 長田四郎 | 長田五郎 | |
| 卅八番 | 庁南太郎 | 藤九郎 | 成田七郎 | |
| 卅九番 | 別府太郎 | 奈良五郎 | 奈良弥五郎 | |
| 四十番 | 岡部六野太 | 瀧瀬三郎 | 玉井太郎 | |
| 四十一番 | 玉井四郎 | 岡部小三郎 | 三輪寺三郎 | |
| 四十二番 | 楠木四郎 | 忍三郎 | 忍五郎 | |
| 四十三番 | 和田五郎 | 青木丹五 | 寺尾三郎太郎 | |
| 四十四番 | 深浜木平六 | 加冶太郎 | 道後小次郎 | |
| 四十五番 | 多々良七郎 | 真下太郎 | 江田小太郎 | |
| 四十六番 | 高井太郎 | 道智次郎 | 山口小次郎 | |
| 後陣 | 勘解由判官 | |||
| 梶原平三 【相具郎従数十騎】 | ||||
| 千葉介 【以子息親類等為随兵】 | ||||
翌11月8日、兼実は法皇より「為家実奉行、被仰頼朝賞之間事、申所存了、尤可被任大将歟、而忽無沙汰歟、右大臣申可避之由」が伝えられている(『玉葉』建久元年十一月八日条)。翌9日、頼朝は前日に勅許された直衣を適して申刻に六波羅を出立し参内した。この参内に当たって、辻々は佐々木左衛門尉定綱が警固した。
| 随兵 | 三浦介義澄【最前一騎】 | ||
| 小山兵衛尉朝政 | 小山田三郎重成 | ||
| 御車 | 二位家(源頼朝) | ||
| 歩行御車傍 | 小山五郎宗政 | 佐々木三郎盛綱 | 加藤次景廉 |
| 御調度懸 | 中村右馬允時経 | ||
| 布衣侍 【二騎列】 |
宇都宮左衛門尉朝綱 | 八田右衛門尉知家 | |
| 工藤左衛門尉祐経 | 畠山次郎重忠 | ||
| 梶原平三景時 | 三浦十郎義連 | ||
| 随兵 | 千葉新介胤正 | 梶原左衛門尉景季 | 下河辺庄司行平 |
| 佐々木左衛門尉定綱 | 和田太郎義盛 | 葛西三郎清重 | |
| 武田太郎信義【最末一騎】 | |||
この「頼朝卿初参」は「先参院、其後参内、於昼御座有召」と、まず六条仙洞御所に参じ、民部卿経房の案内のもと常御所において浄衣の法皇と謁見するというものだった。頼朝は法皇とは「勅語移尅、及理世御沙汰歟、他人不候此座」と、法皇から世の理についての沙汰を受けたという。頼朝は幼少時に法皇の実姉・統子内親王(のち上西門院)の皇后宮権少進を務めており、硬い話の中にも上西門院に関する話も交わされたことだろう。そして夜に及んで仙洞御所を退出すると、そのまま御所へ向かった。この退出時、法皇からの内示を受けた経房卿が「有可被仰事之旨」のため留まるよう頼朝に要請するが、「後日可参之由」を告げて退出した。経房卿はこの旨を法皇に返奏すると、法皇は「可任大納言之由可仰遣、定令謙退歟、不可待請文、今夜可被行徐書」と、頼朝を大納言に任ずるよう指示するとともに、必ず謙退するであろうから、彼の請文を待たず、今夜早々に除目を行うよう命じた(『玉葉』建久元年十一月九日条)。
一方、閑院御所に参内した頼朝は、蔵人頭宗頼の奏上で昼御座に召され、主上(後鳥羽天皇)に謁した。その後、昼御座を退出した頼朝は鬼間に案内され、摂政兼実に初めて謁した(『玉葉』建久元年十一月九日条)。
頼朝は兼実に「依八幡御託宣、一向奉帰君事、可守百王」と、八幡からすべてを「君」に帰し、百王(帝王)を守るべしという託宣を受けたことを述べている。続けての「当時法皇執天下政給、仍先奉帰法皇也、天子ハ如春宮也、法皇御万歳之後、又可奉帰主上、当時モ全非疎略」とは、頼朝が仙洞御所を経て参内したことへの兼実の不満に対しての返事と考えられ、現在は法皇が天下の権を握り主上は春宮の如き立場にあるので、まず法皇に従ったまでであり、法皇崩御後は主上に従うことは当然で、まったく主上を蔑ろにしているわけではないとの弁解である。また、兼実との関係については「外相雖表疎遠之由、其実全無疎簡、深有存旨、依恐射山之聞、故示疎略之趣也」と、表向き疎遠を演じているが、実際はまったく疎遠には思っておらず、「深有存旨」るが故に法皇から疑いをかけられたくないために疎遠な態度をしめしているのだ、と語る。その後の頼朝の態度から見てこの答えは本心であろう。しかし、頼朝は積極的に兼実を摂簶臣へ登らしめることを支援し、前摂政基通から兼実への所領返付を要請するなど、頼朝が兼実を支援していることは、当然法皇も知っているにも拘わらず、「外相雖表疎遠」を「依恐射山之聞」とすることは不可解である。「深有存旨」がその理由とされているが、これは後述の嫡女入内計画を指す可能性が高いだろう。頼朝と兼実の面会はその後は帰倉直前の計二回だけであり、法皇への手前、兼実とは積極的な関わりを見せないが、法皇崩御後の連携を視野に入れて友好関係を保ったことは間違いないだろう。また、兼実は頼朝の言の感想を「而所示之旨、太甚深也」(『玉葉』建久元年十一月九日条)と述べており、深く共感していることがわかる。
そして頼朝は最後に「義朝逆罪、是依恐王命也、依逆雖亡其身、彼忠又不空、仍頼朝已為朝之所大将軍也」と、父義朝の逆乱は王命を恐れた(二条天皇を奉じた信頼卿に従った)がためであり、その身は滅ぶといえどもその忠節が実り、頼朝は「已為朝之所大将軍」なのだと、故義朝の正当性を強く述べている(『玉葉』建久元年十一月九日条)。これまで常に頼朝の心にあったのは、やはり父・義朝の雪辱であり、義朝の功績を以て頼朝は「朝之大将軍」になっていると主張している。
頼朝の狙いは一貫して、法皇または天皇を要とし、輔弼の賢相や朝臣がこれを支えた「安穏」の世を築き、自らはその安穏の世を担保するため、入内を通じて朝廷との関わりを強くする中で、唯一の軍事指揮権者として朝廷を補翼するというものではなかっただろうか。
頼朝は兼実との対談を終えて御所を退出するとそのまま六波羅へ帰館するが、ここで民部卿経房より院宣を受けた(『吾妻鏡』建久元年十一月九日条)。
依勲功賞、所被任権大納言也、度々雖被仰遣依令謙退申、于今無其沙汰、而忽有上洛、爭背先規哉、参入之時、先欲被触仰之處、令早出給之間、無左右所被行除書也、於今者不可有異儀、可令存其旨給、兼又可聴 勅授之由、同被宣下畢者 院宣如此、仍執達如件
十一月九日 民部卿
謹上 新大納言殿
法皇は、これまで度々勲功の賞について頼朝へ遣わしているが、その都度謙退されたためにいまだに沙汰が行われておらず、このことはいささか先規に背いてはいまいか(秩序が成り立たない)とやや怒りを含んで諭し、上洛した今においては異議なく受けよと命じるとともに、法皇直々に授けることも述べた。
これに対して、頼朝は一品房昌寛に請文を認めさせているが、「勲功賞」についてはこれまでも辞退していることから、今回も辞退すると申し出ているが「頼朝被任大納言也、雖辞推而任之」(『玉葉』建久元年十一月九日条)と、強制的に勅授され、頼朝はやむなく権大納言を拝任することとなる。そもそも大納言は正権合わせて定員五名のところ、近年は六名が定着し、この頼朝の権大納言任官によって一時的に七名になっているが(文治三年十一月四日にも還任により七名となった時期があり、このとき兼実は「縦雖為要須、被待闕、何強有怨哉」と激怒している)、頼朝の任権大納言については法皇の対応ともども批判していない。
11月11日、「新大納言頼朝卿」は六条若宮ならびに石清水八幡宮を参詣し(『吾妻鏡』『玉葉』建久元年十一月十一日条)、その日は八幡宮での祈祷のために宿泊し、翌12日、六波羅へと帰還する(『吾妻鏡』建久元年十一月十二日条)。
■建久元(1190)年11月12日供奉交名(『吾妻鏡』建久元年十一月十二日条)
| 先陣隨兵 | 小山兵衛尉朝政 | 小山田三郎重成 | 越後守義資 | 加々美次郎長清 |
| 土肥次郎実平 | 梶原左衛門尉景季 | 村上左衛門尉頼時 | 武田兵衛尉有義 | |
| 千葉新介胤正 | 葛西三郎清重 | |||
| 御車 | 源二位頼朝 | |||
| 歩行御車左 | 新田四郎忠常 | 糟屋藤太有季 | 佐々木次郎経高 | 佐々木三郎盛綱 |
| 大井次郎実春 | 小諸太郎光兼 | |||
| 歩行御車右 | 金子十郎家忠 | 河匂七郎政頼 | 本間右馬允義忠 | 猪俣平六範綱 |
| 御調度懸 | 武藤小次郎資頼 | |||
| 後騎(浄衣) | 参河守範頼 | 駿河守広綱 | 相摸守惟義 | 伊豆守義範 |
| 村上右馬助経業 | 北條小四郎 | 三浦介義澄 | 宇都宮左衛門朝綱 | |
| 八田右衛門尉知家 | 足立右馬允遠元 | 比企四郎能員 | 千葉介常胤 | |
| 後陣随兵 | 畠山次郎重忠 | 八田太郎朝重 | 毛利三郎頼隆 | 村山七郎頼直 |
| 小山七郎朝光 | 千葉次郎師常 | 佐々木左衛門尉定綱 | 加藤次景廉 | |
| 信濃三郎光行 | 三浦十郎義連 | |||
| 最末(浄衣) | 和田太郎義盛 | 梶原平三景時 |
11月13日、頼朝は伊賀前司仲教(中原広元女婿)を民部卿経房のもとに遣わし、法皇への進上物の解文を奏上した(『吾妻鏡』建久元年十一月十六日)。その進上物は「砂金八百両、鷲羽二櫃、御馬百疋」という膨大なもので、このほかに禁裏へも馬十頭が進上された。11月16日には「辛櫃二合蒔鶴」を法皇寵姫の「女房三位局」へ送った。この唐櫃には「桑絲二百疋、紺絹百疋」が納められていた。さらに11月23日には「長絹百疋、綿千両、紺絹卅端」を御所「内台盤所」へ納め(『吾妻鏡』建久元年十一月廿三日条)、12月5日には民部卿経房にも馬を献じている。法皇や朝廷への取次役である経房に対しての礼品であろう。
頼朝は18日に清水寺に参詣、19日未刻には右兵衛督能保とともに仙洞御所に参じて法皇と対面し、数刻に渡って対談をおこなっている(『吾妻鏡』建久元年十一月十九日条)。この中で、頼朝に対する右近衞大将への任官指示と、頼朝の謙退の意思表明などの駆け引きも行われたと推測されるが、結局は権大納言任官時と同様に任官を呑まざるを得ないこととなる。これを受けて22日、経房卿は「大納言家可被任大将之由」の院宣を頼朝へ伝えた(『吾妻鏡』建久元年十一月廿二日条)。頼朝は経房卿を通じて「不慮之外雖任大納言、顧涯分之處、重又被任大将、不及申左右」という請文を提出し、兼実には不本意ながらも「無左右可被任付之」を要請し、兼実もこの請文を披見し「不可有異儀之由」を述べている(『吾妻鏡』建久元年十一月廿二日条)。
11月23日、頼朝は仙洞御所に参じ、終日法皇との対談に過ごしているが、右近衞大将任官の受諾問題や大姫入内の取り決め、その後の朝廷の運営等なども話し合われたことだろう(『吾妻鏡』建久元年十一月廿三日条)。そして翌24日、右大臣兼雅は以前から法皇や兼実から要請されていた「右大臣上大将辞状」し、夜の除目で予定通り「頼朝卿任右大将」(『玉葉』建久元年十一月廿四日条)となった。宣下は蔵人右少弁家実、上卿は中納言通親が務めた。通親が上卿を務めたのは彼が源氏長者であったということも関係しているのかもしれない。なお、これ以前に法皇は経房卿を通じて「亜相可被任右大将事」の院宣を下しているが、頼朝は「辞退之志者多之、所望之儀者無之、何様可令奉哉」(『吾妻鏡』建久元年十一月廿四日条)との請文を進めている。
11月29日夜、頼朝は仙洞御所に参じており、この際、狩衣下に腹巻を着した布衣の侍十二名を伴ったが、千葉新介胤正がその一人に選ばれている(『吾妻鏡』建久元年十一月廿九日条)。
| 三浦介義澄 | 足立右馬允遠元 | 下河辺庄司行平 | 小山七郎朝光 | 千葉新介胤正 | 八田太郎朝重 |
| 小山田三郎重成 | 三浦十郎義連 | 三浦平六義村 | 梶原左衛門尉景季 | 加藤次景廉 | 佐々木三郎盛綱 |
12月1日、頼朝は右大将拝賀を行い、申一剋、仙洞御所に参じた(『吾妻鏡』建久元年十二月一日条)。このとき右大将の格として随身が付され、院御舎人が随従、前駈は「馴京都輩」がとくに法皇からの指示で決定された。この前駈のうち弟の前三河守範頼と親類の七条院非蔵人範清以外の八名は「皆院北面衆被催遣之」であり、頼朝の右大将任官が法皇の積極的関与のもと行われたものだったことがうかがわれ、頼朝が「一族之功士」として重用し、のちに二位家(頼朝)家司となって、政所別当として家政を司った前下総守源邦業も院北面であったことがわかる。なお、この前駈の栄誉をめぐっては、頼朝の意見が反映されなかったことで後日珍事が起こっている。
●右大将拝賀の路次行列(『吾妻鏡』建久元年十二月一日条)
| 前駈十人 ※範頼、範清外八人、 皆院北面衆被催遣之 |
七條院非蔵人範清 | 河内守光輔 | 皇后宮大進行清 | 散位成輔 | 前右馬助朝房 |
| 前尾張権守仲国 | 前下総守邦業 | 前左馬助成実 | 内蔵権頭国行 | 前参河守範頼 | |
| 番長 | 秦兼平〔左府生也、依清撰被下之、白狩袴、壷脛巾、負狩胡録、従者八人、傍路前行〕 | ||||
| 御車 | 二位大納言頼朝 | ||||
| 持御剣 | 糟屋藤太有季 | ||||
| 在御車左右 立車副傍 |
前左衛門尉朝綱 前右衛門尉知家 |
||||
| 近衞五人 | 播磨貞弘 | 下毛野敦季 | 秦兼峯 | 秦頼任 | 佐伯武文 |
| 侍七人〔布衣〕 | 三浦介義澄 |
千葉新介胤正 | 左衛門尉祐経 | 前右馬允遠元 | 前左衛門尉基清 |
| 葛西三郎清重 | 八田太郎朝重 | ||||
| 扈従人々 | 左兵衛督(能保) | ||||
| 左少将公経朝臣 | |||||
| 御調度懸 | 前右馬允時経 | ||||
| 隨兵七騎 | 北條小四郎 | 小山兵衛尉朝政 | 和田太郎義盛 | 梶原平三景時 | 土肥次郎実平 |
| 比企藤四郎能員 | 畠山次郎重忠 | ||||
頼朝の一行は仙洞御所を退ったのち、六条大路を東行し、東洞院大路を北行して閑院内裏に参内して昼御座にて主上に拝謁し(『吾妻鏡』建久元年十二月一日条)、翌2日には右大将としての直衣始が行われ、仙洞御所および閑院内裏に参じている。
| 前駈六人 | 皇后宮大進行清 | 散位成輔 | 前尾張権守仲国 | 前下総守邦業 | 内蔵権頭国行 | 前参河守範頼 |
| 番長 | 秦兼平 | |||||
| 下臈五人 | ||||||
| 隨兵八人 | 小山田三郎重成 | 葛西三郎清重 | 千葉平次常秀 | 加藤次景廉 | 三浦十郎義連 | 梶原三郎景茂 |
| 佐貫四郎広綱 | 佐々木左衛門尉定綱 |
そして翌12月3日、「右大将頼朝、着直衣出仕云々、只参院、不参内、日昼出仕、前駆六人」(『玉葉』建久元年十二月三日条)と、直衣を着て仙洞御所へ参じた。先駈の六人は前日の六人であろうか。この参院は「令上両職辞状納筥不裹之」が理由であり、右近衞少将保家に両職の辞状を上表、頭中将(蔵人頭右近衞権中将実明)から法皇へと奏上された(『吾妻鏡』建久元年十二月三日条)。これを受けた法皇は留任を指示するも、頼朝は中原親能に指示して、右近衞大将に付されていた随身に還録し、番長秦兼平に馬を三疋、色々布百段を授け、播磨貞弘、下毛野敦季、秦兼峯、秦頼任、佐伯武文の五名にそれぞれ馬三疋と布三十段を与えている(『吾妻鏡』建久元年十二月三日条)。
ところが兼実はこの両職辞任という重大事をまったく記録に残していない。なお、近衞大将はかつて平重盛や平宗盛も任官した武官の最たる名誉職であるが、平重盛や平宗盛が就任したのは、武門の棟梁という理由ではなく、任大臣への必須官であったために過ぎない。その後も宮廷公卿が就任している通り武門が尊んだ形跡はなく、決して武家の棟梁を象徴する官職ではない。
権大納言、右近衞大将という在京が必須である顕官を法皇主導で与えられていることから、法皇は頼朝の在京常駐を企てていたと考えられよう。そして、近衞大将任官者はほぼ例外なく(権)大納言(摂関嫡流は権中納言での兼官が通例、基通は父早世等により議政官としての実務を経ず。また、大将任官が先の場合もあり)を経験して、内大臣(例外は公能、実房、頼実の右大臣)へ進んでおり、頼朝も権大納言を経て右近衞大将へ進んでいる(頼朝は他官を経ず、散位から権大納言に直任)ことを考えれば、在京していれば任大臣宣旨が下される可能性は極めて高い。しかし、頼朝は京都に留まる気持ちはなく、任官することで法皇の顔を立てるとともに、官途による束縛を忌避し、鎌倉下向に伴って両官を辞任することとなる。
●内大臣(一部右大臣、除名者)任官者の経歴(『公卿補任』)
| 名前 | (権)大納言 | 近衞大将 | 内大臣(含兼) |
| 藤原忠通 | 永久3(1115)年正月19日~ 永久3(1115)年4月28日 |
元永2(1119)年2月6日(左大将)~ 保安2(1121)年3月11日 |
永久3(1115)年4月28日~ 保安3(1122)年12月17日 |
| 源有仁 | 保安元(1120)年12月14日~ 保安3(1122)年12月17日 |
保安2(1121)年3月12日 | 保安3(1122)年12月17日~ 大治6(1131)年12月22日 |
| 藤原宗忠 | 保安3(1122)年12月17日~ 天承元(1132)年12月22日 |
―――― | 天承元(1132)年12月22日~ 保延2(1136)年12月9日 |
| 藤原頼長 | 長承3(1134)年2月22日~ 保延2(1136)年12月9日 |
長承4(1135)年2月8日 | 保延2(1136)年12月9日~ 久安5(1149)年7月28日 |
| 源雅定 | 保延2(1136)年11月4日~ 久安5(1149)年7月28日 |
保延6(1140)年12月7日(左)~ 仁平4(1154)年8月18日 |
久安5(1149)年7月28日~ 久安6(1150)年8月21日 |
| 藤原実能 | 保延2(1136)年12月9日~ 久安6(1150)年8月21日 |
保延5(1139)年12月16日~ 仁平4(1154)年8月18日 |
久安6(1150)年8月21日~ 保元元(1156)年9月13日 |
| 藤原兼長 | 仁平3(1153)年閏12月23日(権中納言)~ 保元元(1156)年8月3日(除名配流) |
仁平4(1154)年8月18日~ 保元元(1156)年8月3日(除名配流) |
―――― |
| 藤原伊通 | 保延7(1141)年12月2日~ 保元元(1156)年9月13日 |
―――― | 保元元(1156)年9月13日~ 保元2(1157)年8月19日 |
| 藤原公教 | 久安6(1150)年8月21日~ 保元2(1157)年8月19日 |
久寿3(1156)年3月4日(左大将)~ 永暦元(1160)年7月7日 |
保元2(1157)年8月19日~ 永暦元(1160)年7月9日(薨) |
| 藤原公能 | 保元2(1157)年8月19日~ 永暦元(1160)年8月11日 |
保元元(1156)年9月8日~ 永暦2(1161)年8月11日(薨) |
永暦元(1160)年8月11日(右大臣)~ 永暦2(1161)年8月11日(薨) |
| 藤原基房 | 永暦元(1160)年2月28日~ 永暦元(1160)年8月11日 |
永暦元(1160)年8月14日(左大将)~ 永万2(1166)年8月17日 |
永暦元(1160)年8月11日~ 永暦2(1161)年9月13日 |
| 藤原宗能 | 久安5(1149)年7月28日~ 応保元(1161)年9月13日 |
―――― | 応保元(1161)年9月13日~ 長寛2(1164)年閏10月13日 |
| 藤原兼実 | 永暦2(1161)年9月13日~ 寛2(1164)年閏10月23日 |
永暦2(1161)年8月19日~ 仁安元(1166)年8月27日 |
長寛2(1164)年閏10月23日~ 仁安元(1166)年11月11日 |
| 平清盛 | 長寛3(1165)年8月17日~ 仁安元(1166)年11月11日 |
―――― | 仁安元(1166)年11月11日~ 仁安2(1167)年2月11日 |
| 藤原忠雅 | 永暦元(1160)年4月2日~ 仁安2(1167)年2月11日 |
仁安元(1166)年8月27日~ 仁安3(1168)年8月10日 |
仁安2(1167)年2月11日~ 仁安3(1168)年8月10日 |
| 源雅通 | 永暦元(1160)年8月11日~ 仁安3(1168)年8月10日 |
仁安3(1168)年8月12日~ 仁安3(1168)年11月21日(解却) 仁安3(1168)年12月16日(還任)~ 承安4(1174)年7月8日(依病也) |
仁安3(1168)年8月10日~ 承安5(1175)年11月27日(薨) |
| 藤原師長 | 仁安元(1166)年11月3日~ 安元元(1175)年11月28日 |
仁安3(1168)年9月4日(左大将)~ 仁安3(1168)年11月21日(解却) 仁安3(1168)年12月16日(還任)~ 安元3(1177)年正月24日 |
安元元(1175)年11月28日~ 安元3(1177)年3月5日 |
| 平重盛 | 仁安2(1167)年2月11日~ 仁安3(1168)年12月13日(依病辞退) 嘉応2(1170)年4月21日(更任)~ 嘉応2(1170)年12月30日(辞) 承安元(1171)年12月8日~ |
承安4(1174)年7月8日~ 安元3(1177)年正月24日(転左大将) 安元3(1177)年正月24日(左大将)~ 安元3(1177)年6月5日(勅許定) |
安元3(1177)年3月5日~ 治承3(1179)年3月11日 |
| 藤原基通 | ―――― | 承安2(1172)年10月26日(右中将)~ 治承3(1179)年11月17日 |
治承3(1179)年11月17日~ 寿永元(1182)年6月28日 |
| 平宗盛 | 治承2(1178)年4月5日~ 治承3(1179)年2月26日 治承3(1179)年9月4日(還任)~ 治承3(1179)年10月3日 |
安元3(1177)年正月24日~ 治承3(1179)年2月26日 |
寿永元(1182)年10月3日~ 寿永2(1183)年2月27日 |
| 藤原実定 | 長寛2(1164年)閏10月23日~ 寿永2(1183)年4月5日 |
治承元(1177)年12月27日(左大将)~ 寿永2(1183)年11月21日(停) 寿永3(1184)年正月22日(還任)~ 文治2(1187)年11月27日 |
寿永2(1183)年4月5日~ 寿永2(1183)年11月21日(停) 寿永3(1184)年正月22日(還任)~ 文治2(1186)年10月29日 |
| 藤原師家 | 寿永2(1183年)8月25日~ 寿永2(1183)年11月21日 |
治承2(1178)年閏6月7日(左中将)~ 治承3(1179)年11月17日(解官) |
寿永2(1183)年11月21日~ 寿永3(1184)年正月22日 |
| 藤原良通 | 治承3(1179)年11月19日(権中納言)~ 文治2(1186)年10月29日 |
治承3(1179)年11月20日~ 文治2(1187)年11月27日(転左大将) 文治2(1187)年11月27日(左大将)~ 文治4(1188)年2月20日(頓薨) |
文治2(1186)年10月29日~ 文治4(1188)年2月20日(頓薨) |
| 藤原実房 | 仁安3(1168)年8月10日~ 文治5(1189)年7月10日 |
文治2(1186)年11月28日~ 文治4(1189)年10月14日(左大将) |
文治5(1189)年7月10日(任右大臣)~ 建久元(1190)7月17日(任左大臣) |
| 藤原兼雅 | 寿永元(1182)年3月8日~ 文治5(1189)年7月10日 |
文治4(1188)年10月14日~ 建久元(1190)年11月24日 |
文治5(1189)年7月10日~ 建久元(1190)年7月17日(任右大臣) |
| 藤原兼房 | 元暦2(1185)年正月20日~ 建久元(1190)年7月17日 |
―――― | 建久元(1190)年7月17日~ 建久2(1191)年3月28日 |
| 源頼朝 | 建久元(1190)年11月9日~ 建久元(1190)年12月4日 |
建久元(1190)年11月24日~ 建久元(1190)年12月4日 |
権大納言、右近衞大将の 両職を辞して関東帰還 |
| 藤原忠親 | 寿永2(1183)年正月22日~ 建久2(1191)年3月28日 |
保元3(1158)年5月21日(左中将)~ | 建久2(1191)年3月28日~ 建久5(1194)年7月26日 |
| 藤原良経 | 文治5(1190)年7月10日~ 建久6(1195)年11月10日 |
文治5(1190)年12月30日(左大将)~ 建久9(1198)年正月19日 |
建久6(1195)年11月10日~ 正治元(1199)年6月22日 |
| 藤原頼実 | 建久元(1190)年7月17日~ 建久9(1198)年11月14日 |
建久2(1191)年3月6日~ 建久10(1199)年正月19日 |
建久9(1198)年11月14日(右大臣)~ 正治元(1199)年6月22日 |
| 源通親 | 建久6(1195)年11月10日~
正治元(1199)年6月22日 |
正治元(1199)年1月20日~ 建仁2(1202)年10月20日(頓死) |
正治元(1199)年6月22日~ 建仁2(1202)年10月20日(頓死) |
翌12月4日には京中の主要な寺社に絹布を施入(『吾妻鏡』建久元年十二月四日条)、5日には石清水八幡宮へ詣でており(『吾妻鏡』建久元年十二月五日条)、離京の報告と思われる。また、八田右衛門尉知家と千葉四郎胤信を奉行として、在京時に様々に世話を焼いてくれた経房卿に馬を献じ、前駆の皇后宮大進行清、散位成輔、尾張権守仲国、前下総守邦業、内蔵権頭国行、前参河守範頼が馬を曳いた(『吾妻鏡』建久元年十二月五日条)。
12月7日、頼朝は丹後局から法皇意向の扇百本を餞別として下賜され、8日には八幡太郎義家が帰依して御髪を埋めた園城寺青竜院の修理料として剣一腰と砂金十両を園城寺に奉納。9日には法皇より下された半蔀車に駕して仙洞御所に参院した(『吾妻鏡』建久元年十二月七日条)。『玉葉』によれば、この「前大将乗半蔀車参院」は8日の事と記しており、実際は8日の事だったのだろう。兼実は頼朝が半蔀車で参院したことについて「此事如何、然者、大将辞退以前可乗歟、教訓人有若亡歟、前大納言前大将、乗半蔀車出仕未曾聞、是院宣也、勿論ゝゝ(これは如何なることか。大将辞退以前に乗るべきであろう。教訓の人は無能か。前大納言や前大将で半蔀車で出仕するなど聞いたことがないがこれも院宣であるという)」(『吾妻鏡』建久元年十二月九日条)と頼朝へ誰も教諭しないことを非難し、相も変わらず故実を乱す法皇を批判している。
12月10日、頼朝は帰倉に備えて、六波羅邸の留守居を実甥の左馬頭高能とし、11日に参院して数刻法皇と対談し、法皇は「度々勲功之労、可挙申廿人之旨、所被仰下也」と、辞退され続けた「勲功賞」を、頼朝個人にではなくその郎従への任官に切り替え、二十人推挙すべきことを指示した。頼朝はこれも「頻雖被辞申之」と辞退の姿勢を見せたが、法皇は執拗に郎従の任官を迫ったため「勅命再往之間、略而被申任十人」とし、「御家人十人募成功、被挙任左右兵衛尉左右衛門尉等」した(『吾妻鏡』建久元年十二月十一日条)が、常胤の孫・千葉平次常秀が推挙の対象となっている。
●挙任人々十人(『吾妻鏡』建久元年十二月十一日条)
| 官途 | 人物 | 賞過程 |
| 左兵衛尉 | 平常秀(千葉平次常秀) | 祖父常胤勲功賞譲 |
| 平景茂(梶原三郎景茂) | 父景時勲功賞譲 | |
| 藤原朝重(八田太郎朝重) | 父知家勲功賞譲 | |
| 右兵衛尉 | 平義村(三浦平六義村) | 父義澄勲功賞譲 |
| 平清重(葛西三郎清重) | 勲功賞 | |
| 左衛門尉 | 平義盛(和田小太郎義盛) | 勲功賞 |
| 平義連(三浦五郎義連) | 勲功賞 | |
| 藤原遠元(足立右馬允遠元) | 勲功賞(元前右馬允) | |
| 右衛門尉 | 藤原朝政(小山右兵衛尉朝政) | 勲功賞(元前右兵衛尉) |
| 藤原能員(比企藤四郎能員) | 勲功賞 |
ただし、『玉葉』ではこの一日前の十日条に「前大将郎従之中、成功之輩、注進交名」(『玉葉』建久元年十二月十日条)とある。11日は「前大将参内、予謁之」とあって、頼朝は参内して兼実に謁見している(『玉葉』建久元年十二月十一日条)。『吾妻鏡』に見える11日の頼朝参院は『玉葉』には見られず、連日参院する理由もないことから、実際は『玉葉』の通り、10日に頼朝は参院して勲功賞を賜い、11日は参内して兼実と謁見を行ったのであろう。頼朝は「天下政忽可直立之由、全不見給、然而御申之所及不可懈緩云々、又世間事将来まても不可有不審、巷間説、定不可被信用、巨細雖多不能具記也」と語っている。
そして12日、法皇は「被仰前大将勲功賞大功田之間事」という、兼実が予て申し出ていた頼朝への大功田の沙汰を行った。また頼朝は恩賞とは別件で、「公事用途依欠如、成功之者廿五人、前大将進交名」とあるように、法皇は朝廷の公事用途の欠如を補填するため、頼朝郎従から二十五人へ官途を推挙させ、交名を進めさせている。また、法皇は12月1日の右大将拝賀の際に頼朝の「直垂者持太刀」を見て、頼朝に彼の姓名を問うた際、法皇は「無官不可然、早可被授兵衛尉之由有 勅定」と命じている。拝賀の際の頼朝の太刀持は糟屋藤太有季(ただし装束は直垂ではない)であり、彼は翌建久2(1193)年8月には「糟屋藤太兵衛尉」とみえることから(『吾妻鏡』建久二年八月六日条)、糟屋有季もこのとき兵衛尉に任官したのかもしれない。
そして12月13日、法皇は兼実の申請の通り「被仰大功田百町可下宣旨之由」の院宣を下した。また「勲功賞衛庁十人可被任之由」の院宣を下したが、今日は日次が良くないため、翌14日に「大功田事可被行」こととされたが「将軍明日下向」であることから、明日早朝に大功田事を宣下するよう院宣が下り、頼朝が交名を進めた千葉常秀ら十名の臨時除目については大原野に行幸している主上との兼ね合いもあり、「行幸還御以後可被行之由」が指示され、兼実はこれらを奏上している(『玉葉』建久元年十二月十三日条)。そして14日深夜子終刻、主上が還御。すぐさま臨時除目により十名の頼朝郎従は任官し、頼朝には「大功田百町」が宣下されたとみられ、その後、頼朝は離京して鎌倉へ下向の途についた。
●建久元年の京都における頼朝のスケジュール
| 日にち | 面会 | 行動 | 行動 | 出典 |
| 11月7日 | 入洛 六波羅亭 |
源二位頼朝卿入洛、申刻、着六波羅新造亭 | 『玉葉』 | |
| 11月9日 | 法皇 | 仙洞御所 | 入夜参内、今夜頼朝卿初参、 此夜被行小除目、頼朝被任大納言也、雖辞推而任之 |
『玉葉』 |
| 天皇 | 閑院御所 (昼御座) |
『玉葉』 | ||
| 九条兼実 | 閑院御所 (鬼間) |
依八幡御託宣、一向奉帰君事、可守百王云々、是指帝王也、 仍当今御事、無双可奉仰之、 然者、当時法皇、執天下政給、仍先奉帰法皇也、天子ハ如春宮也、 法皇御万歳之後、又可奉帰主上、当時モ全非疎略云々、 又下官辺事、外相雖表疎遠之由、其実全無疎簡、深有存旨、 依恐射山之聞、故示疎略之趣也 又天下遂可直立、当今幼年、御尊下又余算猶遥、頼朝又有運者ハ、 政何不反淳素哉、当時ハ偏奉任法皇之間、万事不可叶云々、而所示之旨、 太甚深也、 又云、義朝逆罪、是依恐王命也、依逆雖亡其身、彼忠又不空、 仍頼朝已為朝大将軍也 |
『玉葉』 | |
| 11月11日 | 石清水八幡宮 | 新大納言頼朝卿参詣八幡 | 『玉葉』 | |
| 11月12日 | 石清水八幡宮 六波羅亭 |
入夜自石清水令還六波羅給云々 | 『吾妻鏡』 | |
| 11月13日 | 六波羅亭か | (法皇へ)新大納言家御別進(砂金八百両、鷲羽二櫃、御馬百疋)、 (天皇へ)龍蹄十疋所被進禁裏 |
『吾妻鏡』 | |
| 11月15日 | 六波羅亭か | 大納言家、御所進御馬、被分進諸社 | 『吾妻鏡』 | |
| 11月16日 | 六波羅亭 | 大納言家、送遣辛櫃二合於御所女房三位局、 被納桑糸二百疋、紺絹百疋 |
『吾妻鏡』 | |
| 11月17日 | 清水寺 | 於彼寺令衆僧読誦法華経、施物多々 | 『吾妻鏡』 | |
| 11月19日 | 法皇 | 仙洞御所 | 大納言家御参 仙洞、左武衛被参会、法皇御対面及数尅 |
『吾妻鏡』 |
| 11月21日 | 六波羅亭か | 近国地頭不当之輩可停止云々 職事一人承仰、可被尋ね諸国并社寺其所等領 |
『玉葉』 | |
| 11月22日 | 六波羅亭か | (兼実)夜に院使経房が兼実邸に来訪。 頼朝に右大将打診するも辞されたため、 重ねて右大将任命を申し伝えたという。 |
『玉葉』 | |
| 11月23日 | 法皇 | 仙洞御所 | 終日令候御前 | 『吾妻鏡』 |
| 11月24日 | 六波羅亭か | 夜の除目で頼朝を右近衞大将に任ず。 ※右大臣兼雅は兼帯の右大将の辞状を奏上 |
『玉葉』 | |
| 11月29日 | 法皇 | 仙洞御所 | 入夜、右大将家御 院参、布衣侍十二人在御共、各狩衣下着腹巻云々 | 『吾妻鏡』 |
| 12月1日 | 法皇 | 仙洞御所 | 右大将拝賀 | 『玉葉』 『吾妻鏡』 |
| 天皇 | 閑院御所 (昼御座) |
『吾妻鏡』 『玉葉』 |
||
| 12月2日 | 法皇 | 仙洞御所 | 右大将家御直衣始(今日上下装束、皆以自院被調下之) |
『吾妻鏡』 |
| 天皇 | 閑院御所 | 『吾妻鏡』 | ||
| 12月3日 | 法皇 | 仙洞御所 | (玉)右大将頼朝、着直衣出仕云々、只参院、不参内、日昼出仕、前駆六人 (吾)右大将家令上両職辞状給、右少将保家為使、頭中将請取之奏院、 被留申云々、今日賜随身還録 |
『玉葉』 『吾妻鏡』 |
| 12月4日 | 六波羅亭か | 前右大将家以絹布等令施入京中可然神社仏寺給云々 | 『吾妻鏡』 | |
| 12月5日 | 石清水八幡宮 | 前右大将家令詣八幡給 | 『吾妻鏡』 | |
| 12月7日 | 丹後三位 | 仙洞御所か | 前右大将家、関東御下向近々之間、御所女房三位局、 被送餞物等、扇百本在其中、是依内々御気色及此儀云々 |
『吾妻鏡』 |
| 12月8日 | 法皇 | 仙洞御所 | 頼朝は法皇が用意した「半蔀車」で参院するが 半蔀車は大将現任が乗るべきものと非難 |
『玉葉』 |
| 六波羅亭か | 前右大将家、御剣一腰、砂金十両、被施三井寺青龍院修理料、 此霊場者、八幡殿殊御帰敬、被埋御髪云々 |
『吾妻鏡』 | ||
| 12月9日 | ※法皇 | ※仙洞御所 | ※前右大将家駕半蔀車、令参院給、件車自院所被調下也 (『吾妻鏡』の日時誤述とみられる) |
『吾妻鏡』 |
| 12月10日 | 法皇 | 仙洞御所 | 法皇、「前大将郎従之中成功之輩、注進交名」 | 『玉葉』 |
| 六波羅亭か | 六波羅御留守事、今日被定之 | 『吾妻鏡』 | ||
| 12月11日 | 九条兼実 | 閑院御所 | 前大将参内、予謁之 | 『玉葉』 |
| 法皇 | 仙洞御所 | 前右大将家令参院内給、数尅御祗候、御家人十人募成功、 被挙任左右兵衛尉左右衛門尉等、是依度々勲功之労可挙申廿人之旨、 所被仰下也、幕下頻雖被辞申之、勅命再往之間、略而被申任十人云々 |
『吾妻鏡』 | |
| 12月12日 | 六波羅亭か | 法皇、兼実の申出通り 「被仰前大将勲功賞大功田之間事」を指示 |
『玉葉』 | |
| 六波羅亭か | 頼朝、法皇の依頼により 「公事用途依欠如、成功之者廿五人、前大将進交名」 |
『玉葉』 | ||
| 12月13日 | 六波羅亭か | 法皇、「被仰大功田百町可下宣旨之由」の院宣を下す | 『玉葉』 | |
| 12月14日 | 六波羅亭か | 臨時除目により頼朝郎従への任官 頼朝へは大功田百町を賜う宣旨が下ったと思われる |
『玉葉』 | |
| 離京 | 『玉葉』 |
なお、この頼朝下向時にひとつの事件が起こっている。「駿河守広綱今曉忽逐電、家人等皆不知之、仰天」(『吾妻鏡』建久元年十二月十四日条)という。広綱はかつて頼朝が伊豆国へ配流された際の庇護者とみられる故伊豆守仲綱の子(実は三位頼政入道の実子)であり「於一族為上臈」(建久二年十一月廿七日条)として遇されていた。とくに懈怠もなく、まったく不意の逐電であって、家人すら知らないというものだった。
すでに行方も分からず頼朝も対処の仕様がなく打ち捨てられていたが、およそ一年後の建久2(1191)年11月27日夜、幕府北面の簀子に佇んでいた頼朝の足下の庭上に一人の法師が踞いた。怪しんだ頼朝は宿直の三浦太郎景連に尋ねさせたが、彼はかつて広綱に仕えていた童の加世丸であった。図らずも彼の口から広綱逐電の理由が判明するが、それは、頼朝の右大将拝賀の際、前駈として十名の「撰馴京都輩被定」にも拘わらず「自幼稚住洛陽」んで京に慣れていた上に「謂官位者又就最初御推挙任之間、於一族為上臈」の自分がその列に漏れたことへの強烈な失望と、駿河守にも拘わらず駿河国務が認められなかったことへの不満であった。実際は前駈については法皇指示の者であったこと、駿河国務についても法皇の許可が下りていなかったことが原因であって、いずれも広綱の誤解であったが、広綱は上醍醐ですでに僧侶となり、頼朝没後の菩提を弔って恩に報いるという。景連は頼朝へ事の次第を報告すると、頼朝は陳謝の状を遣わすという。景連はこれを加世丸に伝えんとしたが、すでに彼はその場から消え去っており、広綱のその後も不明となる(『吾妻鏡』建久二年十一月廿七日条)。
頼朝は建久元年内に鎌倉へ到着するスケジュールで離京日を設定していたと考えられ、鎌倉帰参の翌日が建久2(1191)年正月1日となる。元日の鶴岡山八幡宮寺参詣は行われなかったようだが、これは石清水八幡宮参詣を行っていたためか。
元日の埦飯は千葉介常胤が務め、その料理は大変に素晴らしいものだったという(『吾妻鏡』建久二年正月一日条)。これは「御昇進故」(権大納言、右近衞大将)であったが、常胤以下の千葉一族はいずれも頼朝に随って上洛しており、元日埦飯は頼朝上洛前に常胤と定められ、常胤は料理の材料の手配などを済ませて上洛に加わったと思われる。上洛に際し朝廷は頼朝に対して何らかの勲功賞を行うことは容易に想像でき(頼朝は固辞する覚悟であるが常胤は知る由もないだろう)、常胤も記念すべき日の元日埦飯を任される栄誉に浴し感無量であったろう。
埦飯は午の刻、頼朝は御所南面に出座し、前少将時家(大納言時忠子)が御簾を揚げた。ここで常胤率いる子息一門から進物の儀が行われ、常胤は剣を献じ、弓箭を新介胤正、行騰・沓を二郎師常、砂金を三郎胤盛、鷲羽〔納櫃〕を六郎大夫胤頼がそれぞれ進めた。また、馬は四郎胤信と孫の平次兵衛尉常秀が一の馬を曳き、二ノ馬は臼井太郎常忠と天羽次郎直常の上総介広常の縁者の両名がその栄誉を受ける。広常の名誉回復の意味があったのかもしれない。続けて三ノ馬は五郎胤通ともう一名(不詳)、四ノ馬は寺尾大夫業遠ともう一名(不詳)、五ノ馬は左右いずれも名が伝わっていないが、計五頭が頼朝に献上された(『吾妻鏡』建久二年正月一日条)。その儀が終わると御簾が下ろされ、御所西面の母屋に移り、ようやく歌舞も行われる酒席がはじまった。
■建久二年正月一日献埦飯(『吾妻鏡』建久二年正月一日条)
| 御剣 | 御弓箭 | 御行騰、沓 | 砂金 | 鷲羽(納櫃) | 御馬 |
| 千葉介常胤 | 新介胤正 | 二郎師常 | 三郎胤盛 | 六郎大夫胤頼 | 一、千葉四郎胤信、平次兵衛尉常秀 |
| 二、臼井太郎常忠、天羽次郎直常 | |||||
| 三、千葉五郎胤道 、(不明) | |||||
| 四、寺尾大夫業遠 、(不明) | |||||
| 五、(不明) |
正月2日の埦飯は三浦介義澄の沙汰で行われ、進物は三浦介義澄が剣を献じ、弓箭は岡崎四郎義実、行騰は和田三郎宗実、砂金は三浦左衛門尉義連、鷲羽は比企右衛門尉能員がそれぞれ献じた。馬は一ノ馬を三浦平六義村と三浦太郎景連が進めた以外は伝わらない。
正月3日の埦飯は、小山右衛門尉朝政の沙汰で、進物は剣を下河辺庄司行平、弓箭を小山五郎宗政、行騰・沓を小山七郎朝光、鷲羽を下河辺四郎政義、砂金は最末に朝政自身が捧げ持った。また五疋の馬も献じられているが、曳手は不明。
正月8日、頼朝は若宮供僧、伊豆山、箱根山の衆徒に対し「今年中際、可読誦毎日十二巻薬師経之由」を命じている(『吾妻鏡』建久二年正月八日条)。先月京都で練られてきた大姫入内の前準備として、大姫の体調平癒が念じられたものであろう。
正月11日、帰倉後はじめての鶴岡若宮社参が行われ、神馬三疋が献じられ、梶原兵衛尉景高、千葉二郎師常、葛西十郎(清宣)がそれぞれ奉納している(『吾妻鏡』建久二年正月十一日条)。
そして正月15日、政所吉書始が行われ、その後、「諸家人」に対して以前発給された「或被載御判、或被用奉書」の文書をいったん収公した上で、「可被成改于家御下文之旨被定」た。この「鎌倉家」(建久三年八月「伊勢大神宮神領注文」『鎌倉遺文』614)の家政機関から下される事務的な「家御下文」は、千葉介常胤や小山朝政ら頼朝との紐帯を重んじる気風を持った郎従(御家人)から大きな反発を買うこととなるが、この御判文書と政所下文を交換する措置は「而御上階以前者、被載御判於下文訖、被始置政所之後者被召返之、被成政所下文」(『吾妻鏡』建久三年八月五日条)とある通り、この前右大将家政所の「被始置政所」によるものであることがわかる。なお、「御上階」は通常は官位昇叙のことだが、政所設置の時期を鑑みると数年を経ていて相応しくない。同義の「御昇進」が建久元年の権大納言及び右大将への任官を指すことから「御上階」もまた権大納言及び右大将任官を指すのであろう。
鎌倉家政所は、文治元(1185)年4月27日、頼朝は従二位となった(『公卿補任』)ことで開設された(政所初見は文治元年九月五日の訴訟)が、当時の政所の別当以下の寄人は、公文所当時の人事とほとんど変更がなく、公文所から若干の改組(公文所を政所の一機構に位置付けた)のみで、実質的な運営はほぼ変わらぬ状態だった。その後、文治5(1189)年正月5日に正二位へ陞爵するが、これもとくに大きく変更されることはなかったのであろう。従二位とはいえ当時の頼朝は無官であり、朝廷との官途上で具体的な関わりはなかったのである。
●新造公文所諸役(『吾妻鏡』元暦元年十月六日条)
| 別当 | 安芸介中原広元 | ||||
| 寄人 | 齋院次官中原親能 | 主計允藤原行政 | 足立右馬允藤内遠元 | 甲斐四郎大中臣秋家 | 藤判官代邦通 |
●公文所諸役(『吾妻鏡』文治元年四月十三日条)
| 別当 | 因幡守中原広元 | ||||
| 連署(寄人か) | 主計允行政 | 右馬允遠元 | 甲斐小四郎秋家 | 判官代邦通 | 筑前三郎孝尚 |
●政所諸役(『吾妻鏡』文治元年九月五日条)
| 別当 | 前因幡守中原広元 | |||||||
| 加署判(寄人か) | 主計允行政 | 大中臣秋家 | 右馬允遠元 | 新藤次俊長 | 小中太光家 | 惟宗孝尚 | 橘判官代以廣 | 藤判官代邦通 |
ところが、権大納言および右近衞大将という顕官を経、関白兼実や法皇、天皇との政務上の関わりが多くなるに至り、頼朝の立場は私的なものから公的立場へと変化せざるを得なかったのではなかろうか。その中で、家人・郎従との関わり方も、頼朝個人の家人・郎従から、鎌倉家家政機関に登録される鎌倉家家人・郎従という公的結びつきへと変化したのであろう。これを一気に進めるため、頼朝御判による私的保証を強制的に収公し、政所下文という公的保証の発給へと切り替えたと考えられよう。
■「鎌倉家」家政機関と執権および「得宗」家について
鎌倉家の家政機関は、京都の公卿のそれと同様の機関であって、いわゆる「鎌倉幕府(表現的には誤り)」だけの特別なものではなく、「鎌倉幕府」の政所、「鎌倉幕府」の侍所ではない。また、政所・侍所の長官は「別当」、問注所の長官は「執事」とあるのは、単なる名称の差異ではなく、それぞれ別の意味を持つ職掌であって同列に論じることは誤りと考える。
家政機関の「政所」「侍所」は、それぞれ家司が所宛により「別当」と「職事」が任じられた。「問注所」は政所の内局の一つであり、そのトップが「執事」としてこれを執り行ったのである。つまり、三つが同列に並ぶことは誤りである。「鎌倉幕府」の機構と在京公卿の家政機関のしくみは、大枠において同じである。
前右大将家(鎌倉家)の家政機関は、もともと頼朝「個人」のものではなく「家」を管理する独立した機関であり、家領政務や御家人等の訴訟を受け持つ政所と、鎌倉殿と主従関係にある「家人郎従(御家人はもちろん、北条氏や安達氏ら家子も例外ではなく支配下に置かれた)」の着到や出仕、招集、配置などの管理・監督を行う侍所の二つに大別され、建久2(1191)年正月15日に開かれた政所は、その内局となった公文所別当であった別当家司・前因幡守中原広元が「別当」に任じられた(『吾妻鏡』建久二年正月十五日条)。また、鎌倉家司では別当(政所別当と同義ではない)に次ぐ「令」が政所執事として実務を掌握していたのである。また、家司数名が政所諸役を務め、下家司の知家事、案主が実務を行った。
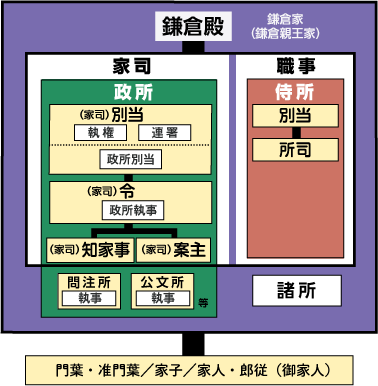
●建久2(1191)年正月15日前右大将家政機関(『吾妻鏡』建久二年正月十五日条)
| 政所 | (政所) | 別当 | 前因幡守中原朝臣広元 | ||
| 家司 | 別当 | ||||
| 令 | 主計允藤原朝臣行政 | ||||
| 案主 | 藤井俊長 鎌田新藤次 | ||||
| 知家事 | 中原光家 岩手小中太 | ||||
| (政所) | 執事 | (主計允藤原朝臣行政カ) | |||
| (問注所) | 執事 | 中宮大夫属三善康信法師 法名善信 | |||
| (公文所) | |||||
| 侍 | 所司 | 別当 | 左衛門少尉平朝臣義盛 治承四年十一月奉此職 | ||
| 所司 | 平景時 梶原平三 | ||||
| 公事奉行人 | 前掃部頭中原朝臣親能 筑後権守藤原朝臣俊兼 前隼人佑三善朝臣康清 文章生三善朝臣宣衡 民部丞平朝臣盛時 左京進中原朝臣仲業 前豊前介清原真人実俊 |
||||
| 京都守護 | 右兵衛督 能保卿 | ||||
| 鎮西奉行人 | 内舎人藤原朝臣遠景 号天野藤内左衛門尉 | ||||
なお、公卿家においては家職として、家司、知家事・案主(下家司)、職事などが任じられるが、家政機関を統括する政所の職員は主に家司から任じられ、侍所別当は職事から任じられる(『台記別記』久安六年正月十九日条)。摂関家においては侍所別当のもとに数名の所司や勾当が任じられた。鎌倉家の中では建久二年の政所吉書始では、和田義盛が「侍所別当」に任じられているが、彼は治承4(1180)年11月17日に彼の望みのままに「侍所別当」補任を約束され(『吾妻鏡』治承四年十一月十七日条)、頼朝新邸に設けられた侍の別当として、頼朝の家人・郎従(御家人)を管理していた。当初義盛が補された「侍(所)別当」は、頼朝の家人となった人々の管理官であったが、のちにそのまま公卿「鎌倉家」の家政機関である侍所別当へと移行させたものと思われ、別当和田義盛、所司梶原景時は鎌倉家当主側近たる「職事」となったのだろう。
なお、鎌倉家侍所は「但義盛、景時等者、依為侍所司、令下知警固事」(『吾妻鏡』建久六年三月十二日条)とある通り、義盛も景時も「侍所司」であり、義盛は侍所別当であるから彼は侍所司の筆頭、景時は次席の所司であった。『吾妻鏡』においては侍所の所司は彼ら二人のみが見えるため、当初は二名体制であったと推測される。その後、所司五名が任じられるような複数所司体制(『吾妻鏡』建保六年七月廿二日条)へと移行したとみられる。
ただし、義盛の侍所別当職は、中央貴族の家政機関である侍所別当とはやや様相が異なり、建久3(1192)年に義盛が服喪の機会に所司梶原景時へ別当が改替されたのちも、建久4(1193)年5月28日、富士の牧狩りでは「義盛、景時承仰、見知祐経死骸」、さらに建久5(1195)年5月24日には「侍所着到等事、義盛、景時故障之時者、可致沙汰之由、被仰付大友左近將監能直」とみえ、義盛は別当景時の上席だった形跡がみられる。
景時が有した侍所別当は、中央貴族と同じ職掌(侍品の家人の出仕や管理監督)を持つ、公卿家としての鎌倉家家政機関の侍所を統べるもので、文筆に明るい景時が委託され、これまでの別当義盛は役職名は不明ながら侍所の上席に置かれた事がうかがえる。なお、義盛及び景時はいずれも政争によって滅ぼされ、その後、侍所別当となったのは鎌倉家別当として政所を差配していた北条氏であり、「執権」は侍所別当を継承したことによる呼称ではなかろうか。
また、『吾妻鏡』の書様から、問注所は政所の内局の一つであり、所長は「執事」と称した。同日の交名に記されていないが、政所の実務部門として政所「執事」も設置されており、この部門長たる執事には、政所令の民部丞行政(以降、行政子孫の二階堂氏が代々就任する)が任じられたとみられる。つまり、別当や令といった家司(案主、知事家は下家司)が就く政所の所役は家政機関の責任者(役職者)であって、それが直接政所の実務担当官を意味するわけではなかったのである。別当は鎌倉家の家司筆頭として政所全体の監督を行い、次席の令が「執事」として実務を掌握したと思われる。
建久3(1192)年6月3日頃には政所別当に前下総守源邦業も加えられ(『鎌倉遺文』594、『吾妻鏡』建久三年八月五日条)、その後、建久3(1192)年6月20日在任の「散位中原(中原親能?)」(『吾妻鏡』建久三年六月廿日条)、承元3(1209)年7月28日在任の「別当書博士中原朝臣(中原師俊)、右近衞将監源朝臣(源親広)」(『筑前宗像神社文書』「鎌倉遺文」1797)がみえる。師俊は親能の胤子であり、広元の子・源親広とともに別当職を継いだのであろう。
●建久3(1192)年6月3日前右大将家政機関(『政所下文』「鎌倉遺文」594)
| 別当 | 前因幡守中原朝臣(中原広元) 前下総守源朝臣(源邦業) 散位中原(中原親能?) |
| 令 | 民部少丞藤原朝臣(藤原行政) |
| 案主 | 藤井(藤井俊長) |
| 知家事 | 中原(中原光家) |
●建久3(1192)年8月5日将軍家政所始の所役(『吾妻鏡』建久三年八月五日条)
| 別当 | 前因幡守中原朝臣広元 前下総守源朝臣邦業 |
| 令 | 民部少丞藤原朝臣行政 |
| 案主 | 藤井俊長 |
| 知家事 | 中原光家 |
| (公事奉行人) | 大夫屬入道善信 筑後権守俊兼 民部丞盛時 藤判官代邦通 前隼人佐康清 前豊前介実俊 前右京進仲業 |
●承元3(1209)年6月16日政所所役(『将軍家下文案』「鎌倉遺文」1794号)
| 別当 | 書博士中原朝臣(中原師俊) |
| 令 | 散位藤原朝臣(藤原行政) |
| 案主 | 散位中原朝臣(中原仲業) |
| 知家事 | 前図書允清原朝臣(清原清定) 惟宗(惟宗孝実) |
●正嘉元(1257)年9月14日政所所役(『将軍家政所下文』相良家文書)
| 別当 | 武蔵守平朝臣(北条政村) 相模守平朝臣(北条長時) |
| 令 | 右衛門尉藤原 |
| 案主 | 清原 |
| 知家事 | 清原 |
さて、北条氏と家政機関(政所・侍所)との関わりが初めて史料から見られるのは、建永2(1207)年の事である。
建永2(1207)年6月2日、「天野民部入道蓮景俗名遠景」より款状が「先進相州」ぜられた。これは「恩澤所望」の款状であり、「始自治承四年八月山木合戦以降」の数々の勲功について十一か条にもわたって述懐されて、「大官令(中原広元)」が将軍実朝へ執申した(『吾妻鏡』建永二年六月二日条)。恩賞については政所の所管であることから、「先進相州(義時)」もこの時点で政所と何らかの関わりを持っていたと推測されるが、天野の款状が進められる二日前の6月4日に発給された政所下文の別当は「書博士中原朝臣(中原師俊)」であり(『肥前青方文書』「鎌倉遺文」1687)、義時の名は見られない。
鎌倉における「執権」とは、若年または幼少の鎌倉家当主を補佐する「征夷将軍之御後見」(『金澤文庫文書』31089号)であるが、鎌倉家別当として政所を統べ、侍所別当をも兼帯し、鎌倉家の所領と家人を管理監督した職である。
北条氏は、もともと「右京兆于時江馬小四郎為家子専一也」(『吾妻鏡』宝治二年閏十二月廿八日条)とあるように、鎌倉家「家人郎従」である千葉氏、三浦氏、小山氏、土肥氏、梶原氏らとは一線を画す頼朝「家子」であり、源氏「門葉」ともまた異なる位置づけであった。そして、もともとの従者である藤九郎盛長とともに「家子」北条氏をとくに重用し、内向きの家政を任せたのだろう。
頼朝の死後、まだ若い鎌倉家当主の頼家を支えるため、「家子」の家格で祖父でもある北条時政が「御後見」となり、以降の先例が生まれたのだろう。ただ「御後見」はあくまでも鎌倉家当主が若年時に、蔵人(職事)的な代行者として下知状の発給などを主とする職務であって、それ自体強い権限を持った職ではないだろう。その権限の担保は、家司に加わり国司(遠江守)及び従五位下へ叙爵されたことだろう。ただし、時政は家司別当につくことはなかったようで、あくまでも「御後見」(執権)のみであったようである。
元久2(1205)年閏7月19日、義時は牧氏の陰謀の加担者として父「遠州禅室(時政入道)」を伊豆へ追放し「相州令奉執権事給」(『吾妻鏡』元久二年閏七月廿日条)と「御後見」を継承し、以降、北条家当主(のちは一族も)が鎌倉家別当へ就任して政所を統括する通例が生まれたと考えられる。なお、義時が文書上で家司別当となり政所下文に署名したことが見えるのは、承元3(1209)年12月11日の『関東御教書』の「別当相模守平朝臣」(『鎌倉遺文』1821号)である。同年7月28日の政所下文(『鎌倉遺文』1797号)には家司別当に義時の名は見えないため、8月から112月の間に別当家司になったとみられる。
これ以降、執権職は本来の「征夷将軍之御後見」(執権)という職務とは別に、別当家司の一人として家政機関の監督を行うこととなるが、北条氏が権力を一手に収めることになるのは、政所の統括だけが理由ではないだろう。政所はあくまでも「鎌倉家領」や「家人郎従」領の管理、裁判等の監督を行う行政官僚の集団であって、政所は家司別当となった北条氏が統括し、家令が政所執事として、実務官の下家司を統括した。
では、北条氏が強い権限を一手に握ることができるようになったのはいかなるわけであったのだろう。そのきっかけは、建暦3(1213)年5月の「和田合戦」であろう。
建暦3(1213)年5月5日の和田合戦後の所領収公および勲功賞が「相州、大官令、被申沙汰之」(『吾妻鏡』建暦三年五月五日条)とあるように、義時は復帰した広元とともに政所の政務を沙汰するが、(『吾妻鏡』建暦三年五月五日条)とあるように、和田義盛の闕を襲って侍所司も兼任し、侍所別当に就任することに「侍別当事、以義盛之闕、被仰相州」なるのである。ここに義時は鎌倉家家政機関の政所・侍所を統べる立場となる。義時は侍所の支配をとくに強化しており、翌6日には有力被官(御家人身分であろう)の金窪左衛門尉行親を侍所司の一人に抜擢するなど、自勢力を介入させていくこととなる。この侍所別当の兼職が、北条氏の権力を肥大化させるきっかけであったと考えられる。
頼朝の鎌倉家侍所は、もともとは地方領主としての鎌倉家家人の統率、管理をその職掌とし、侍所司のうち長官の別当を和田義盛、次席を梶原景時が任じられたとみられる。その後、公卿となった鎌倉家は京都の公卿と同様の家政機関が定められ、家職が任命される。侍所は当初はそのまま別当を和田義盛が担当するが、建久3(1192)年に侍所別当は和田義盛から梶原景時に変更となる。ただし、義盛はその後も景時の上席であったことは変わっておらず、この侍所別当の変更は義盛更迭ではなく、公卿家として以前より家人の着到や管理監督を執り行い、行政にも通じた景時を侍所別当へ据えた組織変容であったのではなかろうか。
その後、義時の嫡流子孫は、他の北条一門とは別格の「得宗」と称される家格を保持するが、得宗家は御家人を管理・監督する侍所に義時の先例同様、被官人(御内人)を就任させているのである。これはもともと執権職時として侍所と関わりを持っていた北条家が影響力をより強化させるべく自勢力を扶植し、鎌倉家の御家人全体を事実上統括する体制を確立させる意図があると考えられる。おそらく得宗家当主は慣例として侍所別当を保持し続け、他流の北条氏庶家が鎌倉家別当についた際には、政所のみ監督したのではなかろうか。一方、得宗家当主が執権になると政所の統括及び侍所別当を兼任し、執権を辞する際には次の執権に政所の統括を譲ったが、侍所別当は保持し続けたのであろう。これが得宗家ならびに御内人の権力が強大になった最大の理由ではなかろうか。
●建暦三年五月六日(和田合戦後)当時政所、侍所所司の判明分(建暦三年五月六日条)
| 担当所役 | 所司名 | |
| 政所 | 別当 | 北条相模守義時 前大膳大夫中原広元 |
| 侍所 | 別当 | 北条相模守義時 |
| 所司 所司? 所司? |
金窪左衛門尉行親(義時被官人⇒相州被拝領胤長荏柄前屋地、則分給于行親忠家) 山城大夫判官行村 安東次郎忠家(義時被官人⇒相州被拝領胤長荏柄前屋地、則分給于行親忠家) |
建保6(1218)年7月22日、「侍所司五人」が定められ、侍所別当には泰時が義時より譲られる形で就任したとみられ、所司には義時縁者の伊賀光宗が就任している(建保六年七月廿二日条)。ただし光宗の祖母は別当前下総守邦業の娘、母が令民部允行政の娘という家司および政所の所役出身家を血縁としており、このことが義時との縁戚以上に政所別当に抜擢された理由の一つに挙げられよう。
●建保六年侍所所司(建保六年七月廿二日条)
| 担当所役 | 所司名 | |
| 侍所司 | 別当 | 式部大夫泰時 |
| 可奉行御家人事 | 山城大夫判官行村 三浦左衛門義村 |
|
| 可申沙汰御出已下御所中雑事 | 江判官能範 | |
| 可催促御家人供奉所役以下事 | 伊賀次郎兵衛尉光宗 |
正月23日、「伊達常陸入道念西息女」の「女房大進局」が頼朝の子を出産する(『吾妻鏡』建久二年正月廿三日条)。ただ、このことが露顕したことで御台所が激しく頼朝に怒っており、頼朝は母子の安全のため「可令在京之由、内々被仰含、仍就近国便宜、被宛伊勢国歟」と当面は伊勢国への避難を内々に指示した。
■常陸入道念西とその周辺
大進局の父「常陸入道念西」は頼朝の御家人として名が見えないことから、いかなる人物かは定かではないが、文治2(1186)年2月26日に生まれた若公の伝で「二品若公、誕生御母、常陸介藤時長女也」(『吾妻鏡』文治二年二月廿六日条)とあり、「御母」はすなわち「伊達常陸入道念西息女」であるから両者は同一人物で、常陸入道念西は常陸介藤原時長なる人物の後身ということとなる。なお、のちの仙台藩主伊達家はこの念西の末裔とされ、その遠祖は清和陽成朝の中納言山蔭というが、この山蔭子孫説も確たる証拠はなく、山蔭同母弟の「常陸介時長」(『尊卑分脈』)が大進局父の「常陸介時長」と同名であったことから、山蔭中納言との「接点」にされた可能性が高いだろう。また、『尊卑分脈』「貞曉」の項には「母伊達蔵人藤原頼宗」と見えるが、もともと常陸入道念西は「伊達」氏ではなく、『尊卑分脈』が室町期の作であることから伊達氏の系譜が取り込まれた影響かもしれない。「伊達」は念西の子・為宗らが軍功によって新補地頭として与えられた地であり、入道念西は次郎為重、四郎為家とともに地頭職として伊達郡内へ移っていったのかもしれない。建久2(1191)年正月23日の記事においては、大進局は「伊達常陸入道念西息女」(『吾妻鑑』建久二年正月廿三日条)と記載されている。この記述が後年の追記であったとしても、念西が伊達郡と関わりを持ったことは間違いないだろう。
さて、入道念西の俗名は『吾妻鏡』の記述から「時長」であろうと思われるが、 『尊卑分脈』では当時の藤姓「時長」が三人みられる。まず、前述のとおり常陸介「時長」は山蔭中納言の実弟であり、利仁将軍の父だが、時代が全く合わない(のちに仙台藩主伊達家が山蔭中納言の末裔を称したのはこの常陸介時長の伝を引いた可能性があろう)ので明らかな別人である。
次に、権中納言長方(皇后宮権大進)の子に、春宮権大進時長(母は少納言通憲娘)が見える。ただし、時長の同母兄・藤原宗隆が仁安元(1166)年の誕生(『公卿補任』より逆算)であり、時長がその弟であるにも拘らず、長兄・宗隆が二十一歳である文治2(1186)年に、すでに入道して五人の成人した子女と孫がいることは考えられないので、この人物もまた別人である。
また、鳥羽院近臣・権中納言顕時の孫、民部少輔時長がいるが、彼の叔父・中宮大進盛方は治承2(1179)年11月12日に四十二歳で亡くなっている(『尊卑分脈』)ことから逆算すると、盛方は保延4(1138)年の生まれであることがわかる。時長はその甥で一世代後の人物であることから、先の春宮権大進時長と同時代の人物と言える。
つまり、『尊卑分脈』から「常陸介時長(常陸入道念西)」に該当する人物をみつけることはできない。ただ、『尊卑分脈』には記載のない人物も多数おり、時長(実はこの名も正しいものかは不明)もそうした一人であった可能性は高い。念西は仁平~保元年中頃に常陸国に関わる地方官途に就いた藤原姓の人物であろうと考えられる。
また大進局の凡その年齢(当時の結婚適齢期からして十代であろう)および「常陸冠者為宗」(『吾妻鏡』文治五年八月八日条)という呼び名から推定して、為宗が「皇后宮大進」となり得るのは、現実的に考えると安徳天皇の准母・亮子内親王(殷富門院)であろう。ただし、文治3(1187)年6月28日に亮子内親王は皇后宮が停止され、女院庁へと替わっていることから、建久5(1194)年正月7日時点で「皇后宮権大進」(『吾妻鏡』建久五年正月七日条)である為宗は、文治3(1187)年6月以前に皇后宮職に就いていたことになる。つまり、文治5年の奥州合戦当時、「常陸冠者為宗」はすでに(前)皇后宮(権)大進であったということになる。そして官途は従五位上から正五位下という頼朝の郎従の中でも屈指の位階であったことがうかがえる。
●直近の皇后宮
| 藤原忻子(後白河院皇后) | 保元4(1159)年2月13日~承安2(1172)年2月10日 |
| 藤原育子(六条天皇母后) | 承安2(1172)年2月10日~承安2(1172)年8月14日 |
| 亮子内親王(安徳天皇准母) | 寿永元(1182)年8月14日~ 文治3(1187)年6月28日(殷富門院) |
ただし、五年間で確認できる亮子内親王の皇后宮職に為宗の名は見られず、大進は藤原親雅、権大進は藤原定経が五年間を通じて在職しているが、権大進藤原長経が元暦2(1185)年8月13日までの間に辞去するなど、若干の動きがあることから、記録に残らない間に就任・離任し、関東へ下向した可能性が考えられる。
●亮子内親王(皇后宮)の皇后宮職
| 大夫 | 権大夫 | 亮 | 権亮 | 大進 | 権大進 | 少進 | 権少進 | 大属 | 少属 | |
| 寿永元年 8月14日 (皇后宮) |
藤原実房 | 藤原実守 | 高階泰経 | 藤原公衡 | 藤原親雅 | 藤原定経 藤原長経 |
藤原家実 | 藤原光茂 | 大江景宗 | 中原基康 中原清重 |
| 元暦2年 8月13日 |
藤原実房 | (藤原実家) | 藤原光雅 | (藤原公衡) | 藤原親雅 | 藤原定経 | (藤原家実) | (藤原光重) | 大江景宗 | |
| 文治3年 6月28日 (女院庁) |
(院司公卿) 藤原実房 |
(院司公卿) 藤原実家 |
(院司公卿) 藤原光雅 |
(別当) 藤原公衡 |
(別当) 藤原定長 |
(判官代) 藤原定経 |
(判官代) 藤原家実 |
(判官代) 藤原光重 |
(主典代) 大江景宗 |
若公(のちの貞暁)母「大進局」は、権大進為宗は兄弟の為宗の官途にちなんだ称であり、「若公七歳、御母常陸入道娣」(『吾妻鏡』建久三年四月十一日条)の「常陸入道娣」は「娘」の誤記であろう。
文治5(1189)年8月8日、「常陸入道念西子息、常陸冠者為宗、同次郎為重、同三郎資綱、同四郎為家」の兄弟が奥州合戦に従軍し、伊達郡内で佐藤庄司らの軍勢と戦って功績を挙げたことは前述の通りであるが(『吾妻鏡』文治五年八月八日条)、この軍功に対して頼朝は為宗に伊達郡の地頭職を与えたのだろう。そして為宗はこの新補の地を弟の常陸次郎為重、常陸四郎為家に分与し、彼らはそれぞれ「伊達次郎」「伊達四郎(伊達右衛門尉為家)」と名乗った。のちの仙台藩伊達家の系譜には、念西の子として、この四人以外の子も記載されるが、『吾妻鏡』でもこの四人以外の兄弟は見られず、輩行も矛盾がないことから、文治5年当時には念西入道の子は男子が四人、女子が一人(大進局)の計五人のみであろう(ただし、念西の伊達郡下向後に新たに子どもが生まれた可能性は否定できない)。
一族の惣領・権大進為宗は本領の常陸国伊佐郡の地頭として続き、弟の常陸三郎資綱も伊佐郡内に残って御家人として続いている。
このころ京都では、前年10月以来練られてきた新制につき、建久2(1191)年3月22日に後鳥羽天皇口宣「建久新制」(『三代制符』)が下されたが、その十六条には、
とあり、「右近衞大将源朝臣」と「京畿諸国所部官司等」に「海陸盗賊并放火」の輩の捕縛を命じるとともに、検非違使庁の怠慢を叱責しつつ鼓舞している。一般にはこれをして諸国守護権が認められたとするが、この宣旨を見る限りそのような根拠は見いだせない。そもそも「海陸盗賊并放火」の輩を搦進する主体は「使庁」にあって、その怠慢によってどこもかしこも盗賊や放火の賊が跋扈するようになったことを叱責し、以降は「右近衞大将源朝臣」と「京畿諸国所部官司等」に取り締まりを命じるとしたものである。その及ぶ範囲はあくまでも「京畿諸国」に留まっており、全国に及ぶものではない。当時頼朝はすでに近畿近国及び瀬戸内にかけて盗賊や謀叛人を取り締まる「惣追捕使」を置いており、例えば建久2(1191)年4月2日の「近江国惣追捕使」は佐々木定綱であった(『玉葉』建久二年四月二日条)。惣追捕使はしばしば守護と同意で用いられているが、建久2(1191)年5月14日に院使が兼実に伝えた頼朝申状に載せられた「山門衆徒奇怪之由也、又近江守護事等申之」についての兼実の返答は「衆徒事、以此状賜座主、可披露山上歟、近江守護事、有御計、可被仰御返事歟者、愚案、猶頼朝卿以直正之武士可令守護事歟」(『玉葉』建久二年五月十四日条)と、近江「守護」とはあくまで近江国を守衛するという字義通りの認識である。頼朝も適切な人材を派遣して「近江守護」を行わんとしたもの(後年「守護」には国内御家人への「軍事」指揮権はない。あくまでも管轄御家人の大番催促権と謀叛人等の追捕・検断権に関わる指揮権のみである)であり、ここに見る「近江守護」と、後年の「守護」の概念は異なるものと思われる。ただし、大番役の催促は美濃国惣追捕使である大内惟義が命じられていることからも、惣追捕使が後年の「守護」へと転換していったことは間違いないだろう。
建久2(1191)年4月1日に行われた除目で「因幡前司中原広元大博士広季男也、頼朝卿腹心也、任明法博士剰任無先例歟、并左衛門大尉上古任大尉、近代頗希、為義任大尉云々、即蒙使宣旨」と、在京中の頼朝家司中原広元(明経家)が、先例のない明法博士に「剰任」され、兼官の「左衛門大尉」及び「使宣旨」を蒙った事に対し、兼実は「此事如何、家已文筆之士也、所期大外記明経博士也、而今之所任驚天下之耳目、此事通親卿為追従加諷諫云々、人縦加教訓、身自不可用、或云、遂可転靫負佐、是允亮等例也云々、凡非言語之所及、恐頼朝卿運命欲尽歟、誠是師子中蟲如喰師子歟、可悲々々」(『玉葉』建久二年四月一日条)と痛烈に批判している。
広元の出身家である中原家は大外記や明経博士を家官とする「明経家」であって、明法道を家学とする別流の中原家が任官する明法博士(兼左衛門少尉、検非違使)には就かない慣例であった。それにも拘わらず、本来任官の資格のない中原広元が、闕のない明経博士(兼左衛門大尉、検非違使)の官に「剰任(前例もない)」するという事態を激しく非難し、しかも、「此事通親卿為追従加諷諫」と、自身と対立する中納言源通親が、頼朝への追従のために中原広元の官途推挙を諷諫したという説や「遂可転靫負佐、是允亮等例也」という長徳事件での靫負佐允亮による検非違使を率いた中納言家や内府伊周らの捕縛を例に引き(通親が広元を使って自らの左遷を企てるかという疑心であろう)、「凡非言語之所及」と痛烈に批判するのである。この除目に兼実の怒りは収まらず、「恐頼朝卿運命欲尽歟」と評し、その腹心中原広元という「獅子身中蟲」が「獅子(頼朝)」を喰らうが如きことであると記すほどであった。
ただ、広元が左衛門大尉及び検非違使へ補されたのは、兼実が疑心暗鬼に陥ったような自分の失脚を狙う源通親の策謀などではなく、除目の十日ほど前の3月22日に下された後鳥羽天皇口宣「建久新制」(『三代制符』)に基づくものであろう。その十六条には「自今已後、慥仰右近衞大将源朝臣并京畿諸国所部官司等、令搦進件輩、抑度々雖被仰使庁、有司怠慢無心糺弾、若尚懈緩処以科責、若只有殊功者随状抽賞」と、頼朝と官司による治安維持が決定され、さらに最近の検非違使怠慢の叱責と今後の対応が記されており、ここから頼朝家司たる広元の大夫尉補任が進められたのだろう。
さらに、3月下旬に起こった延暦寺僧による近江国佐々木庄濫妨の対応という法的な問題への対応に絡み、広元を無理筋の明経博士へ剰任し、喫緊に行われるであろう明経勘問の際に関東の意見を述べるために布石を敷いた可能性があろう。明経博士は衛門尉と検非違使を兼ねる慣例があることから、官途的な矛盾は生ぜず、当時の左衛門督中納言源通親(『公卿補任』)および庁別当参議藤原能保(『検非違使補任』)が、京都の警衛という頼朝の意志を反映する働きかけを行ったのだろう。
佐々木庄は「延暦寺千僧供領」であったが、去年の水害によって「乃貢太闕乏間」という状況にあり、地頭の佐々木定綱は沙汰しようにも納めるものがなかった。そのため延暦寺衆徒が「去月下旬」に日吉社宮仕らと結託して佐々木定綱宅に乱入し乱暴狼藉を働いた。そのため留守をしていた佐々木小太郎兵衛尉定重が激怒し、郎従等に抵抗を命じ、その結果、日吉社宮仕一人を刃傷、日吉社の神鏡も誤って破損してしまった(『吾妻鏡』建久二年四月五日条)。当然、延暦寺側の反発は想定され、危機感を覚えた庁別当能保は、在京中の鎌倉家家司の中原広元の明経博士剰任及び、左衛門大尉・検非違使補任を通親と諮って奏上したのではなかろうか。この事件はただちに頼朝に伝えられており、4月5日には、能保と広元の騒動に関わる文書が鎌倉に届けられている(『吾妻鏡』建久二年四月五日条)。その後、広元の任官は鎌倉でも公認となっており、5月2日に鎌倉へ届いた騒動に関する書状では「大夫尉広元飛脚」と見え(『吾妻鏡』建久二年五月二日条)、その後、広元は本官であるはずの「明法博士」を「祗候関東之輩、以顕要之官職恣兼帯不可然」という頼朝の命で辞していることから(『吾妻鏡』建久二年十月廿日条)、頼朝は現状においては広元に治安維持を集中的に行わせる判断をしたのではあるまいか。広元は五位の左衛門大尉・検非違使というかつての義経とまったく同様の立場(義経は左衛門少尉)で洛中守護の地位となったということであろう。兼実の通親憎しの思いは、通親の正当な行いもすべて批判的に見せてしまうのかもしれない。
このような中で4月5日、兼実の耳に「或人云、頼朝卿女子来十月可入内」(『玉葉』建久二年四月五日条)という情報が入る。頼朝は前年11月9日の兼実との初対談時に大姫入内については「深有存旨」という内容で伝えていたのではなかろうか。ただ、その具体的な日時等は伝えられておらず、改めて接した詳細な内容に「如此之大事、只大神宮八幡春日御計也、非人為之成敗者歟、今日巳剋聞此事」(『玉葉』建久二年四月五日条)と述べているのだろう。ただ、兼実は大姫については中宮任子を脅かす存在とみているわけではなさそうで、それよりも頼朝女子の入内が武家による皇家介入の再来となることを恐れたのかもしれない。兼実はこの入内は、皇祖神「大神宮」、源氏神「八幡」、藤氏神「春日」の神意によるもので人意ではないとして、諦めの気持ちが見られると同時に入内自体への批判はなく、『玉葉』ではその後この件に関する記述はない。
6月5日には法皇より「去夜除目有被任漏之者、追密々可書入召名之由」の院宣が届けられ、兼実は上卿の兼光卿に早々に行うよう指示している(『玉葉』建久二年六月五日条)。除目に漏れた者の一人に「駿河守藤憲朝、頼朝卿推挙」がおり、彼の任についても特に意見しておらず、妥当と判断している。なお、憲朝は頼朝の実従弟であり、鎌倉伺候の公家の一人であった。
頼朝は法皇との協調関係、大姫入内のため、法皇寵姫の丹後局とも強い関係を保っているが、そこには兼実を追い落とす、真から疎遠になるという感情はない。法皇や丹後局、中納言通親といったキーパーソンと兼実の関係は頗る悪化しているが、それは頼朝の考える「安穏」な世をもたらす政体には何ら影響はなく、頼朝は法皇存世中は法皇を憚り兼実との表立った交流は控えているが、水面下では交流が続けられていたと思われる。つまり、頼朝は基本的には両陣営ともに必要に応じて接しているのである。そして、すでに高齢の法皇の世は早晩終わることが予想され、その際には主上を輔弼し、中宮任子の父である関白兼実が中心となった朝政が行われることは必然であった。頼朝の実姪(藤原能保嫡女)と兼実嫡子・左大将良経の縁組も進められているが、これも頼朝と兼実が協同して進めたものである。従来言われている、兼実と頼朝の「疎遠」な関係は一切なかったのである。
藤原季範――+―藤原範忠――+―藤原忠季
(熱田大宮司)|(熱田大宮司)|(蔵人所雑色)
| |
| +―女子
| ∥――――――足利義兼
| ∥ (上総介)
| 足利義康
| (蔵人)
|
+―藤原範信――+―藤原憲朝
|(上野介) |(駿河守)
| |
| +―藤原範清
| (上西門院蔵人)
|
+―藤原範雅――――藤原範経
|(熱田大宮司) (熱田大宮司)
|
+―範智――――――三位局
|(三位法眼) (右大将家官女)
|
+―祐範――――――任憲
|(法橋) (法眼)
|
+―千秋尼
|(上西門院女房)
|
+―大進局
|(待賢門院女房)
|
+―女子
| ∥―――――――源頼朝
| 源義朝 (前右大将)
|(下野守)
|
+―女子
∥―――――――源隆保
源師経 (左馬頭)
(参河守)
良経と能保嫡女の縁組においては、兼実は「此日以使者大将迎婦之儀、猶不可然、随又無其家、力不及之由」(『玉葉』建久二年六月二日条)という意見を能保へ遣わしている。しかし、能保は予てより頼朝から「可進娘、不可奉迎之由」を伝えられており、兼実の主張する「大将迎婦之儀、猶不可然」ことは「力不及之由」を兼実に「再三示」したという(『玉葉』建久二年六月二日条)。頼朝は能保娘を良経のもとへ遣わす婚姻形態(嫁入婚)を推していたが、兼実は先例主義により妻女のもとに大将良経が出向く(招請婚)ことを主張して譲らず、兼実はこのことを認めた書状を広元に託して関東に送らせており、6月1日夜、能保のもとに頼朝から「偏可随殿下御定之由」という返書が届いた。兼実は「仍於今者、可奉迎大将也、進娘之儀不可候」と日記に記している。なお、実弟の太政大臣兼房を「無才漢、無労積、只以先公旧労、下官所推挙也、為上古之政者、猶可謂非拠者歟」(『玉葉』建久二年三月廿八日条)と酷評する兼実が、能保については「検非違使別当任日労効尤深、才漢奉公共範、然而東将之縁也、為当時之珍」(『玉葉』建久二年三月廿八日条)と非常に高く評している。
なお、能保の一条閑院西町邸には左大将良経を迎えるにふさわしい部屋はなかったが、兼実は「一条家、何事有哉、又陣中家不可有難者、狭少不可煩歟、陣中之条、猶不打任事歟、仍一条家可宜」(『玉葉』建久二年六月二日条)ことを伝えている。その後、日取りなどが打ち合わされ、6月25日申刻より「左大将渡別当能保卿、一条室町亭」が行われている(『玉葉』建久二年六月廿五日条、『吾妻鏡』建久二年七月十一日条)。この良経と能保娘の孫がのちに関東へ下り、四代鎌倉殿の藤原頼経となる。
北条時政――+―北条義時――――北条泰時
(遠江守) |(陸奥守) (左京権大夫)
|
+―平政子
∥―――――+―源頼家―――――――――――女子
源義朝 ∥ |(右兵衛督) (竹御所)
(左馬頭) ∥ | ∥
∥―――――+―源頼朝 +―源実朝 ∥
∥ |(前右大将) (右大臣) ∥
∥ | ∥
藤原季範――――女子 +―妹 ∥
(熱田大宮司) ∥ ∥
∥―――――+―藤原高能 ∥
∥ |(左馬頭) ∥
∥ | ∥
藤原能保 +―藤原全子 ∥
(権中納言) | ∥――――――藤原綸子 ∥
| ∥ (従一位) ∥
| 藤原公経 ∥ ∥
|(太政大臣) ∥ ∥
| ∥ 【四代鎌倉殿】
+―嫡女 ∥――――――藤原頼経
∥ ∥ (権大納言)
∥――――――藤原道家
∥ (関白)
藤原兼実――――藤原良経
(関白) (左近衞大将)
このころ鎌倉では7月28日、先日(3月4日)の鎌倉大火によって焼失した頼朝邸(幕府)の寝殿、対屋、御厩などの再建が完成(『吾妻鏡』建久二年七月廿八日条)。頼朝は御所焼失以来過ごしていた源家別邸の甘縄邸(藤九郎盛長邸)から入御した。供奉は「武蔵守、参河守、上総介、伊豆守、越後守、大和守、千葉介、小山左衛門尉、三浦介、畠山二郎、八田右衛門尉、同太郎左衛門尉、土屋三郎、梶原平三、和田左衛門尉」が務め、梶原左衛門尉景季が御剣、橘右馬允公長が御調度を舁き、河匂七郎が御甲を着してこれに随った。また、随兵は十六騎がこれに続いた。その先陣随兵八騎の一人に千葉四郎胤信が加わり、続いて葛西三郎清重の名も見える。
●建久二年七月二十八日幕府新邸移渉供奉(『吾妻鏡』建久二年七月廿八日条)
| 供奉 | 武蔵守(大内義信) | 参河守(源範頼) | 上総介(足利義兼) | 伊豆守(山名義範) |
| 越後守(保田義資) | 大和守(藤原重弘) | |||
| 千葉介(千葉介常胤) | 小山左衛門尉(小山朝政) | 三浦介(三浦介義澄) | 畠山二郎(畠山重忠) | |
| 八田右衛門尉(八田知家) | 八田太郎左衛門尉(八田知重) | 土屋三郎(土屋宗遠) | ||
| 梶原平三(梶原景時) | 和田左衛門尉(和田義盛) | |||
| 御剣 | 梶原左衛門尉景季 | |||
| 御調度 | 橘右馬允公長 | |||
| 御甲 | 河匂七郎 | |||
| 先陣 | 三浦左衛門尉義連 | 長江太郎明義 | 小野寺太郎道綱 | 比企四郎右衛門尉能員 |
| 千葉四郎胤信 | 葛西三郎清重 | 小山五郎宗政 | 梶原三郎兵衛尉景茂 | |
| 源頼朝 | ||||
| 後陣 | 江間四郎殿 | 修理亮義盛 | 村上左衛門尉頼時 | 里見太郎義成 |
| 工藤左衛門尉祐経 | 狩野五郎宣安 | 伊澤五郎信光 | 阿佐利冠者長義 |
8月1日、新邸での大庭平太景能の献盃の儀が行われ、「足利上総介、千葉介、小山左衛門尉、三浦介、畠山二郎、八田右衛門尉、工藤庄司、土屋三郎、梶原平三、同刑部丞、比企右衛門尉、岡崎四郎、佐々木三郎等」(『吾妻鏡』建久二年八月一日条)が座に列した。頼朝はここで各々に往時を問い、とくに景能が語った保元の乱についての話が記録に残されるものとなった。景能は大炊御門河原で敵方の強弓の人、鎮西八郎為朝に弓手方向で出会ってしまった際、為朝が身長に過ぎたる長さの大弓を持っていることを見て、騎射での技術は然程ではないと感じ、とっさに馬手に回ったことで為朝の狙いが逸れて膝に当たるにとどまったことを述べ、「勇士只可達騎馬事也、壮士等可留耳底、老翁之説莫嘲哢」(『吾妻鏡』建久二年八月一日条)と、人々にひたすらに騎馬術を磨くことが重要であり、年寄りの戯言と思うこと勿れと教唆し、「常胤已下当座皆甘心、又蒙御感仰」という。
8月18日、幕府内に新造の御厩へ収める馬の選別が行われた(『吾妻鏡』建久二年八月十八日条)。もともと御厩に置かれていた馬と、新たに献じられた十六疋の馬を新邸南庭に並べて選別された。このとき常胤は粕毛の駒一疋を献じている。
11月5日、京官除目について法皇より兼実へ沙汰があり、「寛治例」の通り行うよう、仰下されている(『玉葉』建久二年十一月五日条)。「寛治例」とは寛治4(1090)年12月の摂政藤原師実の「止摂政可為関白」(『中右記』寛治四年十二月廿日条)であろう。また、法皇からは成功の人々少々を補任するよう院宣があり、「兵衛佐教成丹二位子」を近衞少将に、藤原範能の子・有範を兵衛佐に、前摂政基通の子・藤原家実を正四位下に叙し(越階)、さらに藤原実保、基範、高能の三名を近衞中将へ任ずべしとのことであった(『玉葉』建久二年十一月五日条)。
兼実は「少将、武衛、越階等事承候了」の三点は了承するが、「中将事」については「只在勅定」としつつも、「一度三人過分歟」と返答し、結局兼実は三人の中将任官については「凡ハ中将数人、強無其人者、不可被登用歟」と拒否する。また、右大臣兼雅が法皇へ求めた「加階」の希望についても、右大臣兼雅、左大臣実房、太政大臣兼房いずれもが正二位であり、右大臣兼雅が従一位へ昇叙となれば、上席の左大臣、太政大臣の官位を超越するという「未曾聞」という事態になり、もし兼雅への昇叙を許すとすれば「太相、左相同可被叙歟」を行う必要があり「事為大事、世又可傾、仍乍恐言上子細者」と法皇へ返奏している(『玉葉』建久二年十一月五日条)。
すると、深夜に法皇より御書が到来し、能保の懇望により高能を中将に任ぜられるよう、さらなる指示があった。また、右大臣の昇叙のことについては「僻事」で、実際は兼雅の次男・家経の昇叙依頼であったとすり替えている(『玉葉』建久二年十一月五日条)。
兼実は高能の中将任官についての再度の依頼については、現任の左馬頭との兼職は例がなく、左馬頭は辞して収公または他人の任官となるが、この点について法皇からの指示が不分明であると返奏。結果、法皇は「然者今度総不可任中将、追可有沙汰」と答えている。また能保からも内々で兼実のもとに使者を送り「雖任中将、可被馬頭歟、一切非所望、縦追可補馬頭之由、雖被仰下、同時不被任者、猶可有不審、仍今夜中将事、不可有其沙汰歟」と辞退の返事が届いた。高能は兼実にとっては娘婿という身内であるが、兼実の厳格な考え方がうかがえる。しかし、兼実は自分のこうした強烈な保守先例主義の信条が人々の反感を買っていることや、法皇とも容れない原因であることは自覚しており、「無権之執政、孤隨之摂簶、薄氷欲破、虎尾可踏、半死々々」(『玉葉』建久二年十一月五日条)と、自分は無権の執政であり、相談する者もない孤独な摂簶であると自嘲、行うことは法皇の意に悉く反し、薄氷を破り虎の尾を踏むごときものであると嘆息する。そして「又聞、通親卿如例致種々讒奏」と、「例の如く」通親があることないこと讒奏していることも批判するが、宣陽門院(覲子内親王)別当として法皇や丹後局と強く結びつく源通親の暗躍には手の出しようがなかったのであろう。しかし、法皇も唯々諾々と丹後局や通親の言いなりになっていたわけではなく、讒訴は讒訴と判断して「然而法皇無勅答」し、兼実はこれを「一之冥加也」と喜ぶ姿も見える(『玉葉』建久二年十一月五日条)。
12月17日、兼実は復辟して摂政を辞し准摂政宣旨を給わった。輔弼たる関白へ遷るための措置である。12月26日には法皇の六条仙洞御所で「二宮御元服守貞親王、世称今宮」が行われ、左大臣実房が加冠、頭中将実明が理髪を務めた(『玉葉』建久二年十二月廿六日条)。「保延例法皇御元服也」に則った形で行われている。保延5(1140)年12月17日の法皇元服の際には「故殿者不参給」であったため、今回の元服に際しては兼実も不参となっている。そしてその二日後、京官除目が行われ、兼実としては准摂政として初度の議となった(『玉葉』建久二年十二月廿八日条)。
建久2年冬頃から法皇の体調はすこぶる悪化していたが、12月9日、兼実は屋敷を訪れた右大弁親雅に「法皇御寸白事」を問うも、特別なことは行っていないという(『玉葉』建久二年十二月九日条)。12月16日には頼朝が再建した「東山南殿世謂之法住寺殿」へ御渡し、兼実已下、右大将頼実、新大納言忠良ら公卿衆はが騎馬で供奉している(『玉葉』建久二年十二月十六日条)。そして20日には最勝光院南萱御所へ渡御するが(『玉葉』建久二年十二月廿日条)、定長卿が伝えるところによれば、法皇はすでに「御不食、自廿日有御増気、又御脚腫給、痛御灸治、御心地六借御」という病態にあったという。さらに泰経卿が兼実邸を訪れて法皇の容態を語っているが「依灸治、苦痛無術不謁云々、又女房二位殿云、御不食有少増、御腫相加、御看病之間、無其隙、雖存可見参之由、不得便宜者」という(『玉葉』建久二年十二月廿五日条)。
その後も症状は改善することなく、閏12月2日からは三七御逆修が始まっている。閏12月12日、兼実が参院して法皇寵姫「女房二品(丹後局)」に容態を尋ねると「御不食之上、御痢病相加之、大略憑少之体令存歟」(『玉葉』建久二年閏十二月十二日条)という。医師らに問うても「難治歟」との返答であり、16日に医師の診察を受けた法皇は「御腹張満、始如当月妊者、又御脛股腫無減之上、御腰猶腫給、昨日又御面少腫給、御痢度数雖有減、其体太不心得、不覚而洩云々、是不快之相也、御不食猶未減、帯四腫病気、力不衰微、起居軽利、行法伝経如日来、死相一切不現給云々、又隨服薬、御悩陪増、偏邪気所為」(『玉葉』建久二年閏十二月十六日条)というものだった。法皇は腹水による腹部膨隆、顔面及び脚部の浮腫、不食、下痢、腹痛といった深刻な症状が続いているものの、精神的にはいまだ自我を保っている様子であった。また夜には「痢病度数僅両三度」と症状が若干軽減し、「聊有御膳事」といい「人気色頗安堵之体」(『玉葉』建久二年閏十二月十七日条)という。
しかし、21日には再び「法皇猶不快御座、今日御膳又不通了、御腫并御腹張満、凡無減、殆於御腫者、有増気」(『玉葉』建久二年閏十二月廿一日条)と法皇の体調は再び悪化。22日には「院御逆修結願」した(『玉葉』建久二年閏十二月廿二日条)。年末には「天気快然但御病等ハ無減」(『玉葉』建久三年正月三日条)というが、「昨今頗不快」で建久3(1192)年元日からは「御陰大腫、雖別苦痛、起居礼拝等之間、又非無苦痛云々、医師殊恐申」と腹水による陰嚢水腫が発出した(『玉葉』建久三年正月三日条)。
正月末からは「夜々御辛苦、事外有御増」(『玉葉』建久三年二月四日条)といい、2月16日深更には「院辺物騒云々、聊雖有御悩乱、不及絶入給」(『玉葉』建久三年二月十六日条)、「事外辛苦給云々、其後雖落居、猶不快」(『玉葉』建久三年二月十七日条)という。
法皇はこの頃にはすでに覚悟を決めており、2月18日に孫の主上(後鳥羽天皇)が仙洞御所へ行幸なった際には数刻対面し、「有少御遊主上御笛、女房安芸弾箏、法皇并親能教成等今様、院御音如例」と今生最後の今様会が催された。そして主上還御後、兼実邸に丹後局が訪れて法皇の言葉を伝えている。それによれば「白川御堂等、蓮華王院、法華堂、鳥羽、法住寺等、皆可為公家御沙汰、自余散在所領等、宮達有分給事等、随聞食及面々可有御沙汰云々、此外、今日吉、今熊野、最勝光院、後院領、神崎、豊原、倉賀、福地等、皆可為公家御沙汰、但金剛勝院一所、可為殷富門院領」と細かく院御領の処分を伝えている。兼実は「此御処分之躰、誠穏便也、鳥羽上皇者、普通之君也、而於処分者、尤遺恨、併被委謝美福門院、法皇崩後、女院被分献公家今法皇御宇也也、後鑑之所覃、法皇之御耻也、而今法皇於遺詔者、已勝保元之先跡百万里、人之賢愚得失、誠無定法事歟」と、遺領について明確な処分を定めた遺詔を関白たる自分に伝える配慮に感じ、父院・鳥羽院に勝ると賞賛している。この明確な遺領処分により、後白河院も若年から心に深く暗く刻まれた戦乱の世へ繋がる萌芽を摘むこととなったのである。
その後も法皇の病状は一進一退を繰り返しつつも、2月末からは「無御増、御手腫減了、御足頗減、無御辛苦、夜快有御寝、御膳ハ来廿三日之後、猶以不快」(『玉葉』建久三年三月三日条)という。そして、3月9日夜には「頗有御振」という症状が発出しており、おそらくこの頃には昏睡状態に陥っていたと思われる。11日夕方には「大略御絶入」(『玉葉』建久三年三月十二日条)、そして3月13日未明「太上法皇、崩御于六条西洞院御年六十六」した(『玉葉』建久三年三月十三日条)。
法皇は「召大原本成房上人、為御善知識、高声御念仏七十反、御手結印契臨終正念、乍居如睡遷化」(『吾妻鏡』建久三年三月十六日条)とあり、崩御直前に意識を取り戻したのかもしれない。兼実は崩御の報を受け「寛仁稟性、慈悲行世、帰依仏教之徳、殆甚於梁武帝、只恨忘延喜天暦之古風、自去年初冬、御悩始萌、漸々御増、遂以帰泉、天下皆愁之」との言葉を残している。同日中に院司公卿が参集して「被定院号、後白河院」(『玉葉』建久三年三月十五日条)と定められ、15日に「後白河院御葬送」が行われた(『玉葉』建久三年三月十五日条)。これは法皇の遺詔で崩御の「第三日可行之由、被仰置」というものに拠っている。法皇の尊骸は「法住寺法華堂」(『吾妻鏡』建久三年三月廿六日条)に納められた。
■法皇の症状(『玉葉』より)
| 建久2 (1191)年 |
12月 | 御寸白 | 建久二年十二月九日条 |
| 御不食、自廿日有御増気、又御脚腫給、痛御灸治、 御心地六借御 |
建久二年十二月廿日条 | ||
| 御不食有少増、御腫相加 | 建久二年十二月廿五日条 | ||
| 閏12月 | 御不食之上、御痢病相加之、大略憑少之体令存歟 | 建久二年閏十二月十二日条 | |
| 御面少腫給、御痢度数雖有減、其体太不心得、不覚而洩云々、 是不快之相也 |
建久二年閏十二月十六日条 | ||
| 御腹張満、始如当月妊者、又御脛股腫無減之上、御腰猶腫給 | 建久二年閏十二月十六日条 | ||
| 御不食猶未減、帯四腫病気 | 建久二年閏十二月十六日条 | ||
| 痢病度数僅両三度 | 建久二年閏十二月十七日条 | ||
| 聊有御膳事 | 建久二年閏十二月十七日条 | ||
| 法皇猶不快御座、今日御膳又不通了、御腫并御腹張満、 凡無減、殆於御腫者、有増気云々 |
建久二年閏十二月廿一日条 | ||
| 建久3 (1192)年 |
正月 | 昨今頗不快 | 建久三年正月三日条 |
| 御陰大腫、雖別苦痛、起居礼拝等之間、又非無苦痛云々、 医師殊恐申云々 |
建久三年正月三日条 | ||
| 2月 | 夜々御辛苦、事外有御増 | 建久三年二月四日条 | |
| 院辺物騒云々、聊雖有御悩乱、不及絶入給云々 | 建久三年二月十六日条 | ||
| 事外辛苦給云々、其後雖落居、猶不快云々 | 建久三年二月十七日条 | ||
| 3月 | 無御増、御手腫減了、御足頗減、無御辛苦、夜快有御寝、 御膳ハ来廿三日之後、猶以不快云々 |
建久三年三月三日条 | |
| 頗有御振 | 建久三年三月九日条 | ||
| 大略御絶入云々 | 建久三年三月十二日条 | ||
| 太上法皇、崩御于六条西洞院、御年六十六 | 建久三年三月十三日条 |
始めは食欲の不振(腹痛)があり、12月20日からは脚部の浮腫が現れ、25日には脚部浮腫が進行し、閏12月11日頃には下痢も始まった。続けて15日には顔の腫れ、翌16日には腹水によって腹部肥大とともに腰部の腫れも現れた。年末ごろには腹水の影響と思われる陰部浮腫が始まり、その後も様々な症状が続いた様子がうかがえる。
3月16日午後にははやくも鎌倉に法皇崩御の一報が届けられており、京都を発した飛脚は鎌倉までわずか三日で到着したことになる(『吾妻鏡』建久三年三月十六日条)。この一報を聞いた頼朝は「幕下御悲歎之至、丹府砕肝胆、是則忝合体之儀、依被重君臣之礼也」と甚だ悲嘆したという。3月19日、幕府で宝蔵坊義慶を導師に迎えて法皇初七日の御仏事が修せられ、七日ごとに「御潔齋、御念誦」を決めている(『吾妻鏡』建久三年三月十九日条)。そして、5月8日の四十九日の仏事は勝長寿院にて催され、百僧供を以って修された(『吾妻鏡』建久三年五月八日条)。頼朝が鎌倉で仏事を行った話は5月1日に京都へ伝えられており、兼実は「頼朝卿修仏事、施物之体、尤可然之由、人々感心」(『玉葉』兼任三年五月一日条)と記す。頼朝も兼実も、法皇の実務能力は擱くとして、国家の精神的主柱として強い敬愛の念を抱いており、その死に強い衝撃を受けている。
一方、鎌倉では7月に頼朝の御台所が臨月を迎え、7月4日、頼朝は三浦介義澄、千葉介常胤を奉行とし、義澄・常胤はそれぞれ三浦義村、千葉常秀に命じて調度を御産所に調えさせている(『吾妻鏡』建久三年七月四日条)。なお、このときの御産所は御所内に設けられていたと思われるが、7月18日、頼朝は御産所を「名越御館号浜御所)に変更して御台所が移っており(『吾妻鏡』建久三年七月十八日条)、調度もこの時に移されているのだろう。浜御所がどこにあったのかは不明だが、頼朝亡き後北条時政に譲られたとみられ、名越の浜辺を望む高台に設けられていた。現在の材木座長勝寺裏手の山部南側であろうか。
このころ京都では、7月9日、関白兼実が家司大蔵卿宗頼を内府忠親のもとに遣わし「前右大将頼朝申改前大将之号、可被仰大将軍之由、仍被問例於大外記師直、大炊頭師尚朝臣之処、勘申旨如此、可賜何号哉者」(櫻井陽子「頼朝の征夷大将軍任官をめぐって ―『三槐荒涼抜書要』の翻刻と紹介―」:『三槐荒涼抜書要』 国立公文書館蔵)と諮問した。頼朝は「前右大将」の号を改めて、「大将軍」を望んでいるという。これは、頼朝が兼実に述べている「為朝之所大将軍」(『玉葉』建久元年十一月九日条)の朝廷からの公認を欲したのであろう。この諮問を受けて、忠親は「惣官、征東大将軍、近例不快、宗盛惣官、義仲征東、依田村麿例、征夷大将軍可宜歟者」と答申している。また「別当兼光」の意見として「上将軍、征夷将軍之間、可宜歟之由所申也」という案も伝えられたが、忠親は「上将軍者漢家有此号、征夷大将軍者本朝有跡之由、上田村麿為吉例、強不可求異朝歟」と答えている。
この内府忠親の言を受けて、兼実は頼朝を「征夷使」の「大将軍」に補任することを決定。12日夜に小除目が行われ、頼朝は「征夷使大将軍源頼朝」とされ、左兵衛督能保はこの一報を鎌倉へ遣わし、20日、頼朝のもとへ届けられた(『吾妻鏡』建久三年七月廿日条)。頼朝はこの補任について「其除書、差 勅使欲被進之由」を希望し、能保へ返答している(『吾妻鏡』建久三年七月廿日条)。頼朝の要求した「大将軍」は、近衞大将のような形式的な武官ではなく朝廷の軍権掌握を目したものだが、具体的に「征夷使大将軍」を指定したものではない。なお『三槐荒涼抜書要』(国立公文書館蔵)を見る限り、頼朝は以前から「前右大将頼朝申改前大将之号、可被仰大将軍之由」を関白兼実に訴えていた様子がうかがえるが、これを主張したきっかけはやはり3月13日の法皇崩御であろう。ただし、俗説のような法皇が頼朝の将軍補任を拒絶していたためということではなく、頼朝からの自発的な主張である。
頼朝は多くの「郎従(御家人)」を率いた唯一の公的軍隊の指揮権者となり、「安穏」の世を軍事面で保障する担保にしようと図ったのではなかろうか。同時にこれまでの朝敵追討という「価値」の上に治外法権的な立場で行動してきた(公的には伊豆流人源頼朝の叛乱を発端とするもので、偶々「朝敵」の追討に成功し、強大な軍事力を背景に流刑の赦免及び復位・昇進を果たしたに過ぎない)頼朝が膨れ上がっていた郎従を統率する公的根拠を欲したのかもしれない。すでに敵対勢力は駆逐され、今更強力な軍権は必要ない状況にある中、本来は必要のない「大将軍」を「宣旨」によって求めたのは、上記のような政治的理由によるものと考えられよう。そしてそれが法皇崩御後わずか四か月後に宣下されているということは、それよりも一か月程度前には頼朝の要望が鎌倉を発していたと考えられ、頼朝の「大将軍」宣下は、やはり法皇崩御が直接のきっかけであった可能性が高いだろう。
頼朝の朝廷政策の考えは、一貫して「万事可為君御最之由」を思い、それに伴うものとして「摂簶事」を規範としていた。頼朝の「天下之草創」の思想の中心には常に法皇の存在があり、また頼朝が兼実を推挙することについては「此事全非彼懇望、又非有引級之思、為身無其益、只衆口之所寄、其仁在彼人指余也、前摂政一切不被知万機之由、世上謳哥、仍偏思天下事及君御事之故、所申出此事也、隨又有天許、而今被仰下旨其趣不知、不能左右、是非只在叡念」(『玉葉』文治二年七月三日条)とあるように、天下を輔弼して「安穏」の世を導くためには有能な摂関の存在が必要であることを法皇へ説いている。そして兼実に対しては「一向奉帰君事、無双可奉仰之、然者、当時法皇、執天下政給、仍先奉帰法皇也、天子ハ如春宮也、法皇御万歳之後、又可奉帰主上、当時モ全非疎略」と、法皇がまず第一であり、法皇崩御後は「執天下政給」は「可奉帰主上」と述べていた(『玉葉』建久元年十一月九日条)。頼朝が幼少時に仕えていた上西門院統子は法皇の実姉(准母)で大変仲が良かったことから、頼朝も若き日の法皇と幾度となく対面していた可能性がある。頼朝の法皇への「万事可為君御最之由」はこうした頼朝の法皇への畏敬の念があったものではなかろうか。
そして、後白河院崩御後、新帝後鳥羽天皇は「殿下、鎌倉ノ将軍仰セ合セツゝ世ノ政ハアリケリ」(『愚管抄』第六)と、天皇は関白兼実と頼朝との政治的結束の中、協調して朝政を行ったのである。後述の通り、兼実と頼朝との政務に関する関係も兼実の関白辞任まで続いており、関白としての兼実が最後に頼朝に諮問の条々を送ったのは建久7(1196)年11月初旬頃とみられる。しかし11月25日に兼実が関白を辞任してしまい、頼朝からの返状が届けられたのは兼実辞任後であった。そのため、兼実はこの政務に関する頼朝の返事は奏上すべきと判断し、建久7(1196)年12月4日夜、「九条殿御時被仰遣条々之返事」である「前右大将申状等」を蔵人長兼に託し、左大弁に奏聞させた。すると天皇は内容を見て「件状可申殿下」と仰せ下されたため、長兼は関白基通邸を訪問している(『三長記』建久七年十二月五日条)。ここから見ても、兼実と頼朝の間には疎遠な関係は全くなかったと判断できるのである。
建久3(1192)年7月26日、勅使として「庁官肥後介中原景良、同康定等」が鎌倉に参着(『吾妻鏡』建久三年七月廿六日条)。「征夷大将軍」の除書を持参して鶴岡山八幡宮寺に参じると、「以使者可進除書」と頼朝に伝達。これを受けて、頼朝は三浦介義澄に比企右衛門尉能員と和田三郎宗実の両名を随わせ、各々甲冑を着した郎従十名とともに宮寺へ派遣し、その除書の拝領を命じた。
宮寺に到着した三浦介義澄は勅使景良より名字を問われ、「介除書未到之間、三浦次郎之由」を名乗ったという。三浦「介」が「相模介」という意味合いで遠慮したということだろう(本来の三浦「介」の「相模介」が県召除目による官途か在国司職なのかは不明だが、もともと義澄の「三浦介」は頼朝から認められた自称であって公的なものではないため、称を憚ったとみられる)。
征夷大将軍の除書を請け取った義澄が幕府へ帰参すると、すでに頼朝は束帯を着して西廊に控えており、義澄は除書を捧げ持って膝行、頼朝へ進上した。義澄を使者に選んだのは、治承四年の昔に頼朝挙兵の礎として討死を遂げた義澄父・故三浦大介義明への報謝であったという。
(前闕とみられる)
右少史三善仲康 内舎人橘実俊
中宮権少進平知家 宮内少丞藤原定頼
大膳進源兼元 大和守大中臣宣長
河内守小槻広房辞左大史任 尾張守藤原忠明元伯耆守
遠江守藤原朝房元陸奥守 近江守平棟範
陸奥守源師信 伯耆守藤原宗信元近江
加賀守源雅家 若狹守藤原保家元安房
石見守藤原経成 長門守藤原信定
対馬守源高行 左近将監源俊実
左衛門少志惟宗景弘 右馬允宮道式俊
建久三年七月十二日
征夷使
大将軍源頼朝
従五位下源信友
(後闕とみられる)
8月5日、頼朝は政所に渡御し、将軍補任後の政所始が行われた。政所には将軍家家司十二名が列席し、「千葉介常胤先給御下文」る儀が行われた(『吾妻鏡』建久三年八月五日条)。これは、恩賞はまず常胤を以て始めとする約定によるものである。ただ、常胤はもともと「被始置政所之後者被召返之、被成政所下文」(『吾妻鏡』建久三年八月五日条)ということに強い反発心を持っており、今回の将軍家政所始で、再び同様に政所御下文による恩賞沙汰が行われたことで不満が爆発。「謂政所下文者、家司等署名也、難備後鑑、於常胤分者別被副置御判、可為子孫末代亀鏡」と、家政機関に過ぎない政所を運営する家司の署名など後世で何の証拠にもならないと、頼朝の袖判下文を求めたのであった(『吾妻鏡』建久三年八月五日条)。
●建久3(1192)年8月5日政所所役(前右大将家家司が就任)
| 家司 | 別当 | 前因幡守中原朝臣広元 |
| 前下総守源朝臣邦業 | ||
| 令 | 民部少丞藤原朝臣行政 | |
| 下家司 | 案主 | 藤井俊長 |
| 知家事 | 中原光家 | |
| (公事奉行人) | 大夫屬入道善信、筑後権守俊兼、民部丞盛時、 藤判官代邦通、前隼人佐康清、前豊前介実俊、前右京進仲業 | |
頼朝はこの常胤の訴えに折れて袖判下文も発給しているが、政所下文(文面不明)は撤回していない。同年9月12日には小山朝政にも「将軍家政所下文」とともに頼朝御判の下文が給されたが、頼朝袖判を下しながらも政所御下文も給することで、これからは頼朝個人の「郎従」ではなく、頼朝の興した「鎌倉家」の家政機関(政所・侍所)の管理下に置かれる「御家人」へ在り方が変化し、地頭職は「鎌倉家」政所を通じて差配される支配形態となったのである。
●政所下文(「茂木文書」『栃木県史』中世2)
将軍家政所下 下野国本木郡住人■
補任 地頭職事
前右衛門尉藤原友家
右、治承四年十一月廿七日御下文■■■■以件人補任彼職者、今依■■■■成賜政所下文之状如件、以下、
建久三年八月廿二日 案主藤井(花押)
令民部少丞藤原(花押) 知家事中原(花押)
別当前因幡守中原朝臣(花押)
前下総守源朝臣
●「源頼朝袖判下文」(神奈川県立博物館蔵)
〔御判〕
下 下野国左衛門尉朝政
可早任政所下文旨領掌所々地頭職事
右、件所々所成賜政所下文也
任其状可領掌之状如件
●政所下文(『吾妻鏡』建久三年九月十二日条)
将軍家政所下 常陸国村田下庄 下妻宮等
補任地頭職事
左衛門尉藤原朝政
右、去寿永二年、三郎先生義廣発謀叛企闘乱、爰朝政偏仰朝威、独欲相禦、即待具官軍、同年二月廿三日於下野国野木宮辺合戦之刻、抽以致軍功畢、仍彼時所補任地頭職也、庄官宜承知、不可違失之状、所仰如件、以下、
建久三年九月十二日 案主藤井
令民部少丞藤原 知家事中原
別当前因幡守中原朝臣
前下総守源朝臣
●政所下文(「松平基則氏所蔵文書」『栃木県史』中世2)
将軍家政所下 下野国日向野郷住人
補任地頭職事
左衛門尉藤原朝政
右、寿永二年八月 日御下文云、以件人補任彼職者、今依仰成賜政所下文之状如件、以下、
建久三年九月十二日 案主藤井(花押)
令民部少丞藤原(花押) 知家事中原(花押)
別当前因幡守中原朝臣(花押)
前下総守源朝臣
なお、「而御上階以前者、被載御判於下文訖、被始置政所之後者被召返之、被成政所下文」(『吾妻鏡』建久三年八月五日条)というように、「御上階」以前は頼朝の花押が置かれた御下文であったが、「被始置政所之後」は政所からの下文となったという。
ここで常胤が述べている「御上階」とは、
(一)元暦2(1185)年4月27日の正四位下から従二位へ昇叙
(二)文治5(1189)年正月5日の従二位から正二位への昇叙
のいずれかと思われるが、常胤が主張したかった「御上階」とは官位の上階ではなく、権大納言及び右近衞大将となった「令備羽林上将給」のことを指している可能性が高そうである。
従二位への昇叙によって、それまで鎌倉家の家領や領内検断などの管轄を行っていた家政機関・公文所は政所の内局となり、家人から政所別当以下の職員が宛てられた。また、鎌倉家の家政を含めた内外の管理監督を行う家司が設置されることとなったが、常胤は「被始置政所之後者被召返之、被成政所下文」とある通り、政所を設置した後から御判のある御下文が没収され、代わりに政所下文へ変わったと述べている。ただし、元暦2(1185)年6月15日に伊勢国波出御厨地頭職補任について「左兵衛尉惟宗忠久」へ給された地頭補任状は頼朝の袖判があり、没収された形跡もない。
おそらく元暦2(1185)年に政所が設置されたが、しばらくは政所下文という形を経ず、頼朝の袖判による文書が下されていたのだろう。
あることから、「被行政所吉書始、前々諸家人浴恩沢之時、或被載御判、或被用奉書、而今令備羽林上将給之間、有沙汰、召返彼状、可被成改于家御下文之旨被定」(『吾妻鏡』建久二年正月十五日条)とある建久2(1191)年正月15日の政所吉書始を以て、事実上政所が稼働したことがわかる。つまり「御上階」とは文治5(1189)年正月5日の正二位への昇叙を指すこととなるが、この年は義経捜索及び奥州藤原氏との戦い、奥州再乱、上洛という繁多な事情があり、政所設置に時間を要したのではなかろうか。文治5年から建久元年にかけて政所設置が進められ、「令備羽林上将給」ことで、建久2(1191)年正月15日を以て「前右大将家政所」が成立したのだろう。そして建久3(1192)年7月26日、鎌倉に征夷使大将軍の除書が到着(『吾妻鏡』建久三年七月廿六日条)したのち、8月5日の「令補将軍給之後、今日政所始」(『吾妻鏡』建久三年八月五日条)を以て「前右大将家政所」は「将軍家政所」と改められたのだろう。以降、下文も「将軍家政所下」と記載されている。
建久3(1192)年8月9日早朝から御台所の産気が始まったため、鶴岡山八幡宮寺別当の宮法眼円曉に加持を、鶴岡供僧の義慶坊・大学房が祈祷を行うとともに、相模国諸寺社二十七箇所への神馬奉納と誦経の依頼が行われた(『吾妻鏡』建久三年八月九日条)。鶴岡への神馬奉納は常胤孫「千葉平次兵衛尉」と三浦太郎(佐原太郎景連か)がそれぞれ行っている。そして同日巳刻、御台所は男子を出産した。幼名は千万(千幡)とされた。のちの右大臣実朝である。常胤は「因幡前司、小山左衛門尉」他の御家人らとともに御加持験者等への「献御馬御剣等」ている。そして8月12日、常胤は若君四夜の儀を沙汰した(『吾妻鏡』建久三年八月十二日条)。
8月20日、頼朝は名越の御産所に赴き、「父母兼備射手」を召して「草鹿」を射る勝負を行い、常胤孫の兵衛尉常秀が三番を射た(『吾妻鏡』建久三年八月廿日条)。
| 一番 | 梶原左衛門尉(梶原左衛門尉景季) | 比企弥四郎(比企弥四郎時員) |
| 二番 | 三浦兵衛尉(三浦兵衛尉義村) | 三浦太郎(三浦太郎景連) |
| 三番 | 千葉兵衛尉(千葉兵衛尉常秀) | 梶原兵衛尉(梶原兵衛尉景定)刑部丞子 |
11月29日、若君千幡の五十日百日の儀が外祖父時政の沙汰で執り行われ、叔父の「江間殿(江間四郎義時)」が御剣、砂金、鷲羽を進上。「武州、上州、参州、相州、因州、常胤、朝政、朝光、重忠、義澄、宗平中村庄司、行平、知家、遠光、盛長、清重、義盛、景廉、景時、朝景、景光等」は饅頭を献じている(『吾妻鏡』建久三年十一月廿九日条)。
12月5日、頼朝は若君千幡が逗留する浜御所(名越御館号浜御所)の北面十二間(侍か)に「武蔵守、信濃守、相模守、伊豆守、上総守足利、千葉介、小山左衛門尉、下河辺庄司、小山七郎、三浦介、佐原左衛門尉、和田左衛門尉等」を招き集めると、頼朝は千幡を抱いて出御し、「各一意而可令守護将来之由、被尽慇懃御詞」と各々に力を合わせて千幡の守護をすべしと慇懃に言葉をかけた(『吾妻鏡』建久三年十二月五日条)。その後、各々が千幡を抱き、引出物として腰刀を献じた後、退出した。
年が明けて、建久4(1193)年正月1日、頼朝は鶴岡山八幡宮寺へ参詣し、御所へ帰還ののち、千葉介常胤が椀飯を沙汰した(『吾妻鏡』建久四年正月一日条)。
「千葉大夫胤頼役沙金、千葉介常胤鷲羽、次引進御馬五疋、常胤子息三人孫子二人引之、所謂師常、胤信、胤道、胤秀等也」(『吾妻鏡』建久四年正月一日条)という。胤頼が砂金、常胤は鷲羽をそれぞれ献じ、常胤の子・次郎師常、四郎胤信、五郎胤通と、孫「胤秀等」の合わせて五人で馬を曳いたという。なお、三男の三郎胤盛は建久2(1191)年元日の椀飯以降姿を見せておらず、翌建久6(1195)年5月20日の頼朝の天王寺参詣に伴う随兵には胤盛の子「千葉三郎次郎(胤重)」が加わっていることから(『吾妻鏡』建久六年五月廿日条)、胤盛はすでに亡くなっていたと考えられる。また、孫の「胤秀等」は記録時に「成胤常秀等」が結合してしまったものだろう。
3月4日、来る13日の「法皇御周闋」につき「被供養千僧」ことを決定。「若宮、勝長寿院、永福寺、伊豆山、筥根山、高麗寺、大山寺、観音寺」の八寺に百名の僧侶を鎌倉へ送る旨を沙汰している(『吾妻鏡』建久四年三月九日条)。そして3月13日に鎌倉において「旧院御一廻忌辰」の千僧供養が執り行われた(『吾妻鏡』建久四年三月十三日条)。この一周忌を以て頼朝は「諸国被禁狩猟」を解禁し、3月21日には「下野国那須野、信濃国三原等狩倉」の巡見を行うために鎌倉を出立。その際「被召聚馴狩猟之輩也、其中令達弓馬、又無御隔心之族、被撰二十二人、各令帯弓箭」(『吾妻鏡』建久四年三月廿一日条)という。そこに選抜された一人に常胤の嫡孫・千葉小太郎(成胤)の名がみえる。
●下野国那須野、信濃国三原等狩倉扈従の二十二人
| 江間四郎(江間四郎義時) | 武田五郎(石和五郎信光) | 加々美二郎(加賀美二郎遠光) |
| 里見太郎(里見太郎義成) | 小山七郎(小山七郎朝光) | 下河辺庄司(下河辺庄司行平) |
| 三浦左衛門尉(三浦左衛門尉義連) | 和田左衛門尉(和田左衛門尉義盛) | 千葉小太郎(千葉小太郎成胤) |
| 榛谷四郎(榛谷四郎重朝) | 諏方大夫(諏方大夫盛澄) | 藤澤二郎(藤澤二郎清親) |
| 佐々木三郎(佐々木三郎盛綱) | 澁谷二郎(澁谷二郎高重) | 葛西兵衛尉(葛西兵衛尉清重) |
| 望月太郎(望月太郎重義) | 梶原左衛門尉(梶原左衛門尉景季) | 工藤小二郎(工藤小二郎行光) |
| 新田四郎(新田四郎忠常) | 狩野介(狩野介宗茂) | 宇佐美三郎(宇佐美三郎祐茂) |
| 土屋兵衛尉(土屋兵衛尉義清) |
那須野から帰還後、続けて駿河国の富士野藍沢狩倉への巡見を行うべく、5月2日に北条時政が派遣され、「御旅館已下事、仰伊豆駿河両州御家人等、狩野介相共可令沙汰給」ことを命じた(『吾妻鏡』建久四年五月二日条)。そして5月8日、頼朝はこの狩倉での夏狩を見るために鎌倉を出立した。扈従のうち、「千葉太郎」はおそらく小太郎成胤であろう。
●駿河国富士野藍沢狩倉へ扈従の御家人
| 江間殿(江間義時) | 上総介(上総介義兼) | 伊豆守(伊豆守義範) |
| 小山左衛門尉(小山左衛門尉朝政) | 小山五郎(小山五郎宗政) | 小山七郎(小山七郎朝光) |
| 里見冠者(里見冠者義成) | 佐貫四郎大夫(佐貫四郎大夫広綱) | 畠山二郎(畠山次郎重忠) |
| 三浦介(三浦介義澄) | 三浦平六兵衛尉(三浦平六兵衛尉義村) | 千葉太郎(千葉小太郎成胤) |
| 三浦十郎左衛門尉(三浦十郎左衛門尉義連) | 下河辺庄司(下河辺庄司行平) | 稲毛三郎(稲毛三郎重成) |
| 和田左衛門尉(和田左衛門尉義盛) | 榛谷四郎(榛谷四郎重朝) | 浅沼二郎(阿曽沼次郎廣綱) |
| 工藤左衛門尉(工藤左衛門尉祐経) | 土屋兵衛尉(土屋兵衛尉義清) | 梶原平三(梶原平三景時) |
| 梶原源太左衛門尉(梶原源太左衛門尉景季) | 梶原平二(梶原平次景高) | 梶原三郎兵衛尉(梶原三郎兵衛尉景茂) |
| 梶原刑部丞(梶原刑部烝朝景) | 梶原兵衛尉(梶原兵衛尉景定) | 糟谷藤太兵衛尉(糟谷藤太兵衛尉有季) |
| 岡部三郎 | 土岐三郎 | 宍戸四郎(宍戸四郎家政) |
| 波多野五郎(波多野五郎義景) | 河村三郎(河村三郎義秀) | 加藤太(加藤太光員) |
| 加藤次(加藤次景廉) | 愛甲三郎(愛甲三郎季隆) | 海野小太郎(海野小太郎幸氏) |
| 藤澤二郎(藤澤二郎清親) | 望月三郎(望月三郎重隆) | 小野寺太郎(小野寺太郎道綱) |
| 市河別当(市河別当行房) | 沼田太郎 | 工藤庄司(工藤庄司景光) |
| 工藤小次郎(工藤小次郎行光) | 祢津二郎(祢津二郎宗直) | 中野小太郎(中野小太郎助光) |
| 佐々木三郎(佐々木三郎盛綱) | 佐々木五郎(佐々木五郎義清) | 澁谷庄司(澁谷庄司重国) |
| 小笠原次郎(小笠原次郎長清) | 武田五郎(武田五郎信光) |
その後、5月15日の藍沢狩倉、5月16日から十日間以上に及ぶ富士野での狩猟が執り行われるが、5月28日深夜、「故伊藤次郎祐親法師孫子、曾我十郎祐成、同五郎時致」が富士野神野の頼朝旅館に推参し、工藤左衛門尉祐経を殺害するという事件が勃発した(『吾妻鏡』建久四年五月廿八日条)。
祐成等は「討父敵之由」を声高に叫び、「依之諸人騒動」という有様となる。この騒ぎを聞いて宿直の武士が駆け付けるも、雷雨の中で身動きもままならず、祐成等によって「平子野平右馬允、愛甲三郎、吉香小次郎、加藤太、海野小太郎、岡辺弥三郎、原三郎、堀藤太、臼杵八郎」らが負傷し、「宇田五郎已下」が殺害されたという(『吾妻鏡』建久四年五月廿八日)。
結局、十郎祐成は仁田四郎忠常に討たれるが、五郎時致は「差御前奔参、将軍取御剣欲令向之給」と、頼朝の御前にまで推参し、頼朝が剣を持ち身構える状況となった。ここに近習の左近将監能直が入って頼朝を押し留め、小舎人童の五郎丸が時致を取り押さえて大見小平次へ引き渡すこととなる。
翌5月29日、時致は庭上に召し出されて頼朝直々に尋問を加えるが、この席に主要な郎従二十人余りが列し、中に「千葉太郎」の名も見える。時致は、安元2(1176)年10月に祐経が父・河津祐泰を伊豆奥の狩場で射殺したことへの強い恨みにより殺害を企てたとし、頼朝の御前に走った理由は、拝謁したのち自害するためであると弁明した。頼朝は時致を「五郎為殊勇士之間、可被宥歟」と宥免せんとしたが、祐経の子・犬房丸が泣いて時致の身柄引き渡しを望んだため、やむなく下げ渡し、犬房丸は郎従とみられる鎮西忠太をして時致を梟首した。
狩野家次―+―工藤祐継―+―工藤祐経―――+―伊東祐時
(四郎大夫)|(武者所) |(左衛門尉) |(犬房丸、大和守)
| | |
| | +―伊東祐長
| | (六郎左衛門尉)
| |
| +―宇佐美祐茂――+―宇佐美祐政
| (三郎右衛門尉)|(左衛門尉)
| |
| +―宇佐美祐員
| (三郎右衛門尉)
|
| 曾我祐信===+―曾我祐成
| (太郎) |(十郎)
| ∥ |
| 女子 |
| ∥――――――+―曾我時致
+=伊東祐家―――河津祐親―――+―河津祐泰 |(五郎)
|(六郎大夫) (河津入道) |(三郎) |
| | |
| +―伊東祐清 +―律師
| (九郎) ↓
| ∥ ↓
| 比企尼――――――女子=======律師
| ∥
| 大内義信
| (武蔵守)
|
+―工藤茂光―+―狩野宗茂―――+―狩野宗時
(工藤介) |(狩野介) |(狩野新介)
| |
| +―女子―――――――田代信綱
| (田代冠者)
|
+―工藤行光―――――工藤為佐
(武者所) (左衛門尉)
この富士牧狩りの噂はたちまち広まり、近国の郎従(御家人)が鎌倉へと馳せ参じたことから、諸国はにわかに騒ぎとなった。
このような中、6月4日には常陸国で権勢を競う八田右衛門尉知家と多気太郎義幹のもとにも知らせが届いた。知家と義幹はもともと互いに宿意はなかったが、その領地は隣り合い、知家はこの鎌倉参上の混乱に乗じて義幹を討って常陸国における権勢を広げようと諮り「内々有奸謀所存、遣如疋夫之男於義幹之許」と、匹夫に装わせた男を義幹のもとへ密かに遣わして「八田右衛門尉相催軍士、欲討義幹之由令搆之」と伝えさせた。驚いた義幹は一族を集めて「多気山城」に立て籠ったことで常陸国は騒動となった(『吾妻鏡』建久四年六月五日条)。
その後、知家は素知らぬふりで雑色を義幹のもとに遣わし、「於富士野御旅館有狼藉之由風聞之間、只今所参也、可同道者」と声をかけたが、義幹は知家を疑っており、「有所存不参」と返答し、さらに防御を固めたという。まさに義幹は知家の術中に嵌った形で、6月12日、八田知家は頼朝に「訴申義幹有野心之由」を訴え(『吾妻鏡』建久四年六月十二日条)、驚いた頼朝は義幹に召喚の使者を送ることになる。
その後、多気義幹が召しに応じて鎌倉へ参着。知家も召し出して三善善信入道および筑後権守俊兼を奉行として対決させた(『吾妻鏡』建久四年六月二日条)。三善善信と俊兼が列していることから御所内の問注所でのこととみられる。義幹は陳謝するといえどもその説明が不明と断じられ、軍勢を集めて籠城したことは認めたことから、義幹は「常陸国筑波郡南郡北郡等領所」を没収され、身柄は岡部権守泰綱に召し預けられた。そして6月22日、一族の馬場小次郎資幹にその所領が与えられた。7月3日には鹿嶋造営行事の一族小栗十郎重成が心神耗弱の病危急のため、「令拝領多気義幹所領、已為当国内大名」たる資幹がそれに代わった(『吾妻鏡』建久四年七月三日条)。
結果として八田知家の策略は成就せず、義幹旧領は同族の資幹へ交代されるのみとなっている。なお、義幹の実弟「常陸国住人下妻四郎弘幹」は頼朝の命を受けた「前右衛門尉知家」によって処断され梟首されている(『吾妻鏡』建久四年十二月十三日条)。罪状は「是於北條殿有挿宿意事、常咲中鋭刀只心端以簧、而近日自然露顕之故也」であったが、多気太郎義幹の縁座であろう。
11月27日には「永福寺傍建梵宇、被安置薬師如来像」(『吾妻鏡』建久四年十二月八日条)とあるように、永福寺の傍らに薬師堂を建て、京都から招いた前権僧正真円を導師に供養が挙行された。薬師堂は「永福寺薬師堂供養也、将軍家渡御寺内」(『吾妻鏡』建久四年十二月廿七日条)と、永福寺内に建立されたものである。ただし、一年後の建久5(1194)年12月26日にも永福寺「新造薬師堂供養」が前権僧正勝賢を導師として執り行われている。一年前に建立されて供養も終えている「永福寺傍建梵宇」の薬師堂を新造とするのは考えにくく、「永福寺傍建梵宇」と「新造薬師堂」は別の建物と考えられる。「永福寺傍建梵宇」は薬師如来を祀る医王山東光寺(現鎌倉宮の場所)となる寺院の可能性もある。
「永福寺傍」の薬師堂供養に出席した頼朝に供奉して、御剣を孫の千葉小太郎成胤が持ち、後陣随兵には二男・相馬次郎師常が加わっている。
| 御剣 | 千葉小太郎成胤 | |||
| 懸御調度 | 愛甲三郎季隆 | |||
| 先陣隨兵 | 畠山次郎重忠 | 葛西兵衛尉清重 | 蔵人大夫頼兼 | 村上左衛門尉頼時 |
| 氏家五郎公頼 | 八田左衛門尉知重 | 三浦介義澄 | 和田左衛門尉義盛 | |
| 下河辺庄司行平 | 後藤左衛門尉基清 | |||
| 後陣隨兵 | 北條五郎時連 | 小山七郎朝光 | 梶原源太左衛門尉景季 | 梶原刑部左衛門尉定景 |
| 相馬次郎師常 | 佐々木左衛門尉定綱 | 工藤小次郎行光 | 新田四郎忠常 |
しかし、この薬師堂供養の際に越後守義資が聴聞にいた御所女房に艶書を投じる事件が発覚する。この女房は後害を恐れて黙っていたが、この経緯を知っていた梶原源太左衛門尉景季の妾・竜樹前(官女か)が景季に告げたことから発覚。景季が父の景時に告げたことで、頼朝は真偽究明のために女房らに問うたところ、事実であると判明した(『吾妻鏡』建久四年十一月廿八日条)。そのため、加藤次景廉に命じて義資を梟首。父の保田遠江守義定も縁座して強い譴責を被った。
保田氏は平家との戦いでも一ノ谷合戦では一手の大将軍を務めるなど活躍し、頼朝からも父子で門葉に遇され受領に預かった例は、保田義定・義資と大内義信・惟義父子のみ(ただし義定は頼朝による推挙ではない)であって、保田義定・義資父子は相当高い評価を受けていたことがわかる。義定は京都に明るい事を以って、大内守護の蔵人大夫頼兼、京都守護・別当の中納言能保と協働して「禁裏守護番」(『吾妻鏡』建久二年五月二日条)として御所周辺の警衛を行っていたとみられ、佐々木定綱と延暦寺の佐々木庄の年貢未進をめぐる抗争の中で、山門衆徒が強訴に及んだ際には、兼実の命によって「仍能保差使、触院近臣、武士、前将軍之侍三人時定、高綱、成綱之中、相并不及五六十騎」(『玉葉』建久二年四月廿六日条)とともに、「遠江守義定去此下坂東了、郎従十騎許」が召されて内裏を守衛している。
この突然の義資処断は甲斐源氏の勢力排斥という説が有力であるが、彼等も確立された前右大将家の家政機関を通じて支配される立場にあり、もはや勢力を恐れるが故の処刑ではない。永福寺は頼朝にとって最も神聖な衆生救済の寺院であり、「永福寺傍建梵宇」の薬師堂は長女大姫の快癒祈願を意図していたものと思われ、尊厳が守られるべき場における義資の不埒な振る舞いが咎められたのだろう。
大姫については、その後も体調の復調が見られないためか、頼朝は甥の右兵衛督高能との婚姻へかじを切っている。
建久5(1194)年正月1日の鶴岡山八幡宮寺参詣後の椀飯の沙汰人は述べられていないが(『吾妻鏡』建久五年正月一日条)、上総介義兼が御征箭や馬を献じ、里見冠者義成が御剣を持っていることから、上総介義兼が椀飯を沙汰したとみられる。
2月2日夜、幕府西侍で行われた江間四郎義時の嫡男・金剛(十三歳)の元服の儀が行われた(『吾妻鏡』建久五年二月二日条)。常胤は武蔵守義信とともに脂燭役として上座の左右に列し、四男の大須賀四郎胤信も席に列している。
●金剛元服の想像図(幕府西侍配置)
|
|||||||||||||||||||||||
金剛は頼朝から加冠を受け、頼朝の諱字を給わり「太郎頼時(のちの泰時)」と称した。その後、三浦介義澄が頼朝に召され、頼時を婿とすべき指示を受ける。義澄はこれを受けて孫娘の婿とする旨を返答している。この孫娘は嫡男義村の娘(のちの矢部尼)で、四代執権経時、五代執権時頼の母となる。
5月29日、頼朝は東大寺供養のための雑事総目録を奏上するため民部卿経房へ送進し、さらに「御布施并僧供料米等事」については郎従(家人)等に勧進を命じ進上するよう命じた(『吾妻鏡』建久予五年五月廿九日条)。かつて治承の乱で平重衡の失兵火により焼失した東大寺の再建につき、頼朝の「最初建立以来、以奉加成大功訖、今尤可奉助成」という考えのもと、将軍家政所が主導し、家司の因幡前司広元と三善大夫属入道善信を奉行として「被下御書於諸国守護人、可致勧進国中之由」を指示した。ただし、この当時「諸国守護人」という言葉が存在していたかは疑わしく、建久2(1191)年4月2日当時は佐々木定綱が「近江国惣追捕使」であり(『玉葉』建久二年四月二日条)、『吾妻鏡』執筆時に於いて守護人と記載されたものか。
用材は頼朝の仰せにより、佐々木四郎左衛門尉高綱が周防国で調達したものがとくに用いられた。また頼朝がとくに御家人に造立を命じた大仏殿内に安置される「二菩薩四天王像」の担当は、如意輪観世音菩薩が宇都宮左衛門尉朝綱法師、虚空蔵菩薩が中原親能(穀倉院別当)、増長天は畠山次郎重忠、持国天は武田太郎信義(武田信義は文治二年三月九日に五十九歳で卒したというが、建久元年十一月七日の頼朝入洛、九日の仙洞御所および閑院御所参内の供奉に列した記録があり、実際は生存していたとみられる)、多聞天は小笠原次郎長清、広目天は梶原平三景時が受け持った。また、戒壇院の営作は小山左衛門尉朝政、千葉介常胤が命じられていたが、いずれも竣工期限を大幅に超えており、6月28日、頼朝は工事を急ぐよう催促している(『吾妻鏡』建久五年六月廿八日条)。
| 大仏殿 | 如意輪観世音菩薩 | 宇都宮左衛門尉朝綱法師 | |
| 虚空蔵菩薩 | 中原親能(穀倉院別当) | ||
| 増長天 | 畠山次郎重忠 | ||
| 持国天 | 武田太郎信義 | ||
| 多聞天 | 小笠原次郎長清 | ||
| 広目天 | 梶原平三景時 | ||
| 戒壇院 | 小山左衛門尉朝政 | 千葉介常胤 |
このような中、7月29日夜には大姫の体調が悪化している。こうした体調悪化はいつものことであったが、今回は「殊危急」であったという(『吾妻鏡』建久五年七月廿九日条)。この病は「志水殿有事之後、御悲歎之故、追日御憔悴」とあるように、かつて大姫の聟として鎌倉に留め置かれた木曽義仲の子・志水冠者義高(義基)が、義仲誅殺後に頼朝に殺害されたときから続いており、慢性的なうつ症状と思われる。ただ、当時としては「不堪断金之志、殆沈為石之思給歟、且貞女之操行衆人所美談也」と、美談とされていた。大姫の体調悪化を受け、8月8日早朝、頼朝は「於当国効験無双」との評判が高い相模国日向山(相模原市日向)の「薬師如来霊場」の参拝を行った(『吾妻鏡』建久五年八月八日条)。頼朝騎馬の御後には千葉新介胤正、後陣随兵には相馬次郎師常、境兵衛尉常秀の名がみえる。
●相模国日向山薬師参詣時の供奉(『吾妻鏡』建久五年八月八日条)
| 先陣隨兵 | 畠山次郎重忠 | 土屋兵衛尉義清 | 八田左衛門尉知重 | 曾我太郎祐信 |
| 足立左衛門尉遠元 | 比企弥四郎時員 | 澁谷庄司重国 | 岡崎先次郎政宣 | |
| 三浦左衛門尉義連 | 梶原左衛門尉景季 | 加々美次郎長清 | 里見冠者義成 | |
| 北條五郎時連 | 小山左衛門尉朝政 | |||
| 御剣 | 結城七郎朝光 | |||
| 御調度懸 | 愛甲三郎季隆 | |||
| 源頼朝(騎馬、着水干) | ||||
| 御後 (着水干) |
武蔵守義信 | 上野介憲信 | 上総介義兼 | 伊豆守義範 |
| 関瀬修理亮義盛 | 因幡前司廣元 | 下河辺庄司行平 | 下河辺四郎政義 | |
| 千葉新介胤正 | 千葉六郎大夫胤頼 | 三浦介義澄 | 三浦兵衛尉義村 | |
| 稲毛三郎重成 | 葛西兵衛尉清重 | 八田右衛門尉知家 | 佐々木中務丞経高 | |
| 佐々木三郎盛綱 | 加藤次景廉 | 江兵衛尉能範 | 和田左衛門尉義盛 | |
| 梶原平三景時 | 北條小四郎 | |||
| 後陣隨兵 | 武田五郎信光 | 榛谷四郎重朝 | 小山五郎宗政 | 江戸太郎重長 |
| 長江四郎明義 | 梶原三郎兵衛尉景高 | 相馬次郎師常 | 野三刑部丞成経 | |
| 新田四郎忠常 | 下河辺六郎光修 | 所六郎朝光 | 境兵衛尉常秀 | |
| 梶原刑部丞朝景 | 佐々木五郎義清 | |||
途次、因幡前司広元が地頭職を務める下毛利荘で駄餉を献じ、参拝ののちは「依為放生会忌」って宿泊せずに深夜に鎌倉へと帰還している。
8月14日、六波羅亭の留守居を任されている右兵衛督高能が鎌倉に下着した(『吾妻鏡』建久五年八月十四日条)。鎌倉に到着した高能は実伯父の頼朝邸へ参じて対面を果たし、宿所は邸内の小御所が宛がわれた。この高能下向は御台所の希望を受けて頼朝が催促したものであろう。目的は大姫と高能の縁談である。すでに大姫入内は健康面からも無理と判断されたと見られ、頼朝は一条家を通じた摂関家との繋がりを求めたのかもしれない。
翌15日には鶴岡放生会が催され、高能は頼朝とともに参列し、鶴岡山八幡宮寺廻廊に着して舞楽を鑑賞する(『吾妻鏡』建久五年八月十五日条)。翌日の宮寺馬場にて行われた流鏑馬に高能が出席したかは不明だが、「江間太郎(頼時=泰時)」が初めて流鏑馬を射て頼朝から録を給わっている(『吾妻鏡』建久五年八月十六日条)。
翌18日、大姫は「姫君御不例復本給之間、有御沐浴」と奇跡的に沐浴ができるほど体調は回復するが、そのうつ症状の原因は父頼朝による志水冠者殺害にあり、うつ症状はまだ見られたのだろう。「然而非可有御恃始終事之由」と、人々は「人皆含愁緒」み、頼朝も「是偏御歎息之所積也」という(『吾妻鏡』建久五年八月十八日条)。
御台所は大姫に内々に「可令嫁右武衛高能給之由」(『吾妻鏡』建久五年八月十八日条)を告げたものの、大姫は「敢無承諾」という態度で「及如然之儀者、可沈身於深淵」と強く拒絶した。「是猶御懐旧之故歟」と記すが、それも含めて父頼朝に対する強い不信と反発であろう。このことを伝え聞いた高能も「更不可思召寄」と女房を通じて謝し(『吾妻鏡』建久五年八月十八日条)、沙汰止みとなってしまう。そしてその翌日の8月19日、頼朝は故義資の父・遠江守義定を「去年被誅子息義資、収公所領之後頻歌五噫、又相談于日来有好之輩類欲企反逆、縡已発覚」(『吾妻鏡』建久五年八月十九日条)という罪で捕らえ、即日処刑し梟首した。享年六十一。
翌8月20日には和田義盛の手により「遠江守伴類五人、名越辺被刎首」(『吾妻鏡』建久五年八月廿日条)という。翌21日、義盛は義定伴類五名の誅戮の賞と「勲功及度々」を合わせ、新恩が給与された(『吾妻鏡』建久五年八月廿一日条)。義定は義資がたかだか付文だけで誅殺されたことに対し、頼朝や梶原景時・景季への強い敵意を持ったであろうことは想像に難くない。義定は主な郎従五名に頼朝または梶原父子の暗殺(企反逆)を命じた可能性があろう。しかし、和田義盛によって発覚し、義定は殺害されることとなる。この計画はおそらく彼ら五名を含む義定側から漏れ、侍所別当義盛の聞き及ぶところとなったと推測される。
| 前瀧口榎下重兼 | 義定が禁裏守護番時に郎従化した在京武官 |
| 前右馬允宮道遠式 | 義定が禁裏守護番時に郎従化した衛府出仕の「式」を通字とする宮道氏 |
| 麻生平太胤国 | 義定が下総守在任時に郎従化した下総平氏一族(埴生庄麻生郷)か |
| 柴藤藤三郎 | 不明 |
| 武藤五郎 | 義定挙兵時にはすでに家人であったとみられる。かつて義定の使者として遠江国から鎌倉へ赴いた |
義定の屋敷地は閏8月7日に「江間殿」が拝領し(『吾妻鏡』建久五年閏八月七日条)、美濃国にあった義定地頭地は「相模守惟義、賜美濃国中没収地等」(『吾妻鏡』建久五年閏八月十日条)と美濃国惣追捕使の惟義が給わった。直さなくて、義定の屋敷地については「自故将軍御時、一族領所収公之時、未被仰他人」(『吾妻鏡』建暦三年三月廿五日条)とあるように、本来同族が引き継ぐべきであった。この闕所地を義時が継承しているのは、北条氏と義定は血縁関係にあったためではなかろうか。頼朝が石橋山合戦に大敗した直後、北条時政が義時を伴って甲斐源氏を頼っているのもこうした関わりがあったためであろう。義時の「義」も義定の一字ではなかろうか。
その後、頼朝は10月17日には「辞将軍」の上表をしている(石井良助「鎌倉幕府職制二題」「再び『征夷大将軍と源頼朝』について」『大化改新と鎌倉幕府の成立』所収:国立公文書館蔵『公卿補任』昌平坂学問所旧蔵文書より)。頼朝が征夷大将軍の辞状を奏上した理由や背景は不明であるが、「征夷大将軍」の号もすでに頼朝にとって不要なものであったことは間違いないだろう。二度にわたって上表していることから強い辞意を感じるが、征夷使は外官でさらに令外官であり、辞意の理由は権大納言や右近衞大将の際とは異なるとみられる。
そもそも「亦依忠文宇治民部卿之例、可有征夷将軍 宣下歟之由有其沙汰、而越階事者彼時准拠可然、於将軍事者賜節刀被任軍監軍曹之時被行除目歟」(『吾妻鏡』寿永三年四月十日条)と、本来は征夷使の将軍(忠文は征東使の大将軍だが、征東使と征夷使は同義である(『日本紀略』延暦十二年二月十七日条))は、節刀を賜り、軍監や軍曹が決定したのちに除目が行われることになっていたが、頼朝は節刀も賜らず、属官も任じられていない、正式な手続きを踏んだ「将軍」ではないのである。公的担保のない「大将軍」は頼朝の望んだものではなく、結果この空虚な「征夷使 大将軍」の辞状を奏上した可能性もあろう。しかし、この上表は認められず、さらに11月17日に「重上状」するも「十二月日被返遣辞状」とあって、朝廷からは理由は不明ながら受理されずに鎌倉へ返送されたようである(石井良助「鎌倉幕府職制二題」「再び『征夷大将軍と源頼朝』について」『大化改新と鎌倉幕府の成立』所収:国立公文書館蔵『公卿補任』昌平坂学問所旧蔵文書より)。『玉葉』『三長記』『明月記』『吉記』など当時の公家の日記も建久5(1194)年11月は闕となっており、詳細は不明である。
12月26日、前述の通り永福寺の「新造薬師堂供養」が前権僧正勝賢を導師として招いて執り行われている(『吾妻鏡』建久五年十二月廿六日条)。永福寺内にはこの「新造薬師堂」の一年以上前の建久4(1193)年11月27日に供養がなされた「永福寺傍建梵宇」の薬師堂(のちの医王山東光寺のもととなる薬師堂の可能性)もあるが、これは「新造薬師堂」は別物であろう(永福寺二階堂の北に廊で繋がる薬師堂か)。千葉介常胤は下河辺庄司行平と並んで供奉を務め、東大夫胤頼・境兵衛尉常秀もこれに従った。また、頼朝の随兵八騎はいずれも頼朝の信頼篤い武士であり、千葉新介胤正と葛西兵衛尉清重が並んで供奉した。
●建久五年十二月二十六日の永福寺新造薬師堂供養の行列(『吾妻鏡』建久五年十二月廿六日条)
| 御剣 | 北条五郎時連 | |
| 懸御調度 | 愛甲三郎季隆 | |
| 供奉人:布衣 | 源蔵人大夫頼兼 | 武蔵守義信 |
| 信濃守遠光 | 相摸守惟義 | |
| 上総介義兼 | 下総守邦業 | |
| 宮内大輔重頼 | 駿河守宗朝 | |
| 右馬助経業 | 修理亮義盛 | |
| 前掃部頭親能 | 前因幡守広元 | |
| 民部大夫繁政 | 小山左衛門尉朝政 | |
| 下河辺庄司行平 | 千葉介常胤 | |
| 三浦介義澄 | 三浦兵衛尉義村 | |
| 八田右衛門尉知家 | 足立左衛門尉遠元 | |
| 和田左衛門尉義盛 | 梶原刑部丞朝景 | |
| 佐々木左衛門尉定綱 | 佐々木仲務丞経高 | |
| 東大夫胤頼 | 境兵衛尉常秀 | |
| 野三刑部丞成綱 | 後藤兵衛尉基清 | |
| 右京進季時 | 江兵衛尉能範 | |
| 最末 | 梶原平三景時 | |
| 隨兵八騎 | 北條小四郎 | 小山七郎朝光 |
| 武田兵衛尉有義 | 加々美次郎長清 | |
| 三浦左衛門尉義連 | 梶原左衛門尉景季 | |
| 千葉新介胤正 | 葛西兵衛尉清重 | |
| 布施取 | 右兵衛督高能朝臣 | 左馬權助公佐朝臣 |
| 上野介憲信 | 皇后宮大夫進為宗 | |
| 前対馬守親光 | 豊後守季光 | |
| 橘右馬権助次広 | 工匠蔵人 | |
| 安房判官代高重 |
6月26日、「法皇最第三姫宮覲子内親王、有院号事、母法皇愛妃丹三品也」は「宣陽門院」の院号が下された(『玉葉』建久二年六月二十六日条)。
建久6(1195)年2月12日早朝、比企藤四郎右衛門尉能員、千葉平次兵衛尉常秀(常胤孫)の両名が使節として上洛の途に就いた(『吾妻鏡』建久六年二月十二日条)。これは「前備前守行家、大夫判官義顕残党等、于今在存於海道辺、伺今度御上洛之次、欲遂会稽本意之由巷説出来」のためであった。両名は東海道の駅々に子細を尋問し、これらが事実であれば策を巡らして捕縛するよう命じられている。そしてその二日後の2月14日、頼朝は東大寺供養のため上洛の途に就く。「御台所并男女御息等同以進発給」(『吾妻鏡』建久六年二月十四日条)とあり、御台所および頼家、大姫も同伴している。そして半月ほどの旅程を経て、3月4日夕刻、頼朝一行は六波羅亭に入御した(『吾妻鏡』建久六年三月四日条)。「見物輩貴賤成群」(『愚管抄』第十)だったという。
3月9日、頼朝は石清水八幡宮ならびに左女牛若宮(六条若宮)の臨時祭に御参。頼家と御台所が同道し、随兵の先陣六騎のうちに千葉新介胤正と葛西兵衛尉清重が並んで供奉している。そしてこのまま石清水八幡宮へ宿泊している(『吾妻鏡』建久六年三月九日条)。
■石清水八幡宮寺供奉の家子郎従(『吾妻鏡』建久六年三月九日条)
| 先陣六騎 | 畠山二郎重忠 | 稲毛三郎重成 | |
| 千葉新介胤正 | 葛西兵衛尉清重 | ||
| 小山左衛門尉朝政 | 北條五郎時連 | ||
| 御乗車(網代車) | 前右大将源頼朝 | ||
| 檜網代車 | 若公(一幡、万寿) | ||
| 八葉車 | 御台所 | ||
| 乗出車 (相具衛府二人) |
左馬頭隆保 | 越後守頼房 | |
| 後騎 | 源蔵人大夫頼兼 | 上総介義兼 | 豊後守季光 |
| 後陣六騎 | 下河辺庄司行平 | 佐々木左衛門尉定綱 | |
| 結城七郎朝光 | 梶原源太左衛門尉景季 | ||
| 三浦介義澄 | 和田左衛門尉義盛 |
翌3月10日、頼朝は石清水八幡宮より東大寺へと出立し、東大寺南東院に入った。このときの供奉は御家人二百七十四騎に加えて御家人の家子郎従が随い、さらに後陣の梶原平三景時、千葉新介胤正は各々数百騎の郎従を従えており、総勢は二千人を超える人数であったろう。主上も丑刻に美豆頓宮へ行幸し未刻に東大寺内頓宮へ着御となる。その後、申刻に兼実已下行事公卿が少々、大仏殿に参じた。この際、兼実は頼朝へ「雑人禁止之間事、仰頼朝卿畢」(『玉葉』建久六年三月十日条)と依頼している。この「雑人」が何を指すかはわからないが、供養に際して関係者以外の立入を禁じるよう警衛を依頼したものではなかろうか。
■建久六年東大寺参詣供奉人交名に見える千葉一族(『吾妻鏡』建久六年三月十日条)
| 先陣 | 畠山二郎 | ||
| 和田左衛門尉 | |||
| 車前隨兵 ・三騎相並 |
江戸太郎 | 大井次郎 | 品河太郎 |
| 豊嶋兵衛尉 | 足立太郎 | 江戸四郎 | |
| 岡部小三郎 | 小代八郎 | 山口兵衛次郎 | |
| 勅使河原三郎 | 浅見太郎 | 甘糟野次 | |
| 熊谷又次郎 | 河匂七郎 | 平子右馬允 | |
| 阿保五郎 | 加治小二郎 | 高麗太郎 | |
| 阿保六郎 | 鴨志田十郎 | 青木丹五 | |
| 豊田兵衛尉 | 鹿辺六郎 | 中郡太郎 | |
| 真壁小六 | 片穂五郎 | 常陸四郎 | |
| 下嶋権守太郎 | 中村五郎 | 小宮五郎 | |
| 奈良五郎 | 三輪寺三郎 | 浅羽三郎 | |
| 小林次郎 | 林三郎 | 倉賀野三郎 | |
| 大胡太郎 | 深栖太郎 | 那波太郎 | |
| 渋河五郎 | 吾妻太郎 | 那波弥五郎 | |
| 佐野七郎 | 小野寺太郎 | 園田七郎 | |
| 皆河四郎 | 山上太郎 | 高田太郎 | |
| 小串右馬允 | 瀬下奥太郎 | 坂田三郎 | |
| 小室小太郎 | 祢津次郎 | 祢津小次郎 | |
| 春日三郎 | 中野五郎 | 笠原六郎 | |
| 小田切太郎 | 志津田太郎 | 岩屋太郎 | |
| 中野四郎 | 新田四郎 | 新田六郎 | |
| 大河戸太郎 | 大河戸次郎 | 大河戸三郎 | |
| 下河辺四郎 | 下河辺藤三 | 伊佐三郎 | |
| 泉八郎 | 宇都宮所 | 天野右馬允 | |
| 佐々木三郎兵衛尉 | 中沢兵衛尉 | 橘右馬次郎 | |
| 大島八郎 | 海野小太郎 | 牧武者所 | |
| 藤沢次郎 | 望月三郎 | 多胡宗太 | |
| 工藤小次郎 | 横溝六郎 | 土肥七郎 | |
| 糟谷藤太兵衛尉 | 梶原刑部兵衛尉 | 本間右馬允 | |
| 臼井六郎(有常) | 印東四郎(師常) | 天羽次郎(直胤) | |
| 千葉二郎(師常) | 千葉六郎大夫(胤頼) | 境平二兵衛尉(常秀) | |
| 広沢余三 | 波多野五郎 | 山内刑部丞 | |
| 梶原刑部丞 | 土屋兵衛尉 | 土肥先二郎 | |
| 和田三郎 | 和田小二郎 | 佐原太郎 | |
| 河内五郎 | 曾祢太郎 | 里見小太郎 | |
| 武田兵衛尉 | 伊沢五郎 | 新田蔵人 | |
| 佐竹別当 | 石河大炊助 | 沢井太郎 | |
| 関瀬修理亮 | 村上左衛門尉 | 高梨二郎 | |
| 下河辺庄司 | 八田右衛門尉 | 三浦十郎左衛門尉 | |
| 懐嶋平権守入道 | |||
| 北條小四郎 | 小山七郎 | ||
| 御車 | 前右大将源頼朝 | ||
| 狩装束 | 相摸守 | 源蔵人大夫 | 上総介 |
| 伊豆守 | 源右馬助 | ||
| 因幡前司 | 三浦介 | ||
| 豊後前司 | 山名小太郎 | 那珂中左衛門尉 | |
| 土肥荒次郎 | 足立左衛門尉 | 比企右衛門尉 | |
| 藤九郎 | 宮大夫 | 所六郎 | |
| 御随兵 ・三騎相並 |
小山左衛門尉 | 北條五郎 | 平賀三郎 |
| 奈古蔵人 | 徳河三郎 | 毛呂太郎 | |
| 南部三郎 | 村山七郎 | 毛利三郎 | |
| 浅利冠者 | 加々美二郎 | 加々美三郎 | |
| 後藤兵衛尉 | 葛西兵衛尉(清重) | 比企藤次 | |
| 稲毛三郎 | 梶原源太左衛門尉 | 加藤太 | |
| 阿曾沼小次郎 | 佐貫四郎 | 足利五郎 | |
| 小山五郎 | 三浦平六兵衛尉 | 佐々木左衛門尉 | |
| 小山田四郎 | 野三刑部丞 | 佐々木中務丞 | |
| 波多野小次郎 | 波多野三郎 | 沼田太郎 | |
| 河村三郎原 | 宗三郎 | 同四郎 | |
| 長江四郎 | 岡崎与一太郎 | 梶原三郎兵衛尉 | |
| 中山五郎 | 渋谷四郎 | 葛西十郎(清宣) | |
| 岡崎四郎 | 和田五郎 | 加藤次 | |
| 小山田五郎 | 中山四郎 | 那須太郎 | |
| 野瀬判官代 | 安房判官代 | 伊達次郎 | |
| 岡辺小次郎 | 佐野太郎 | 吉香小次郎 | |
| 南條次郎 | 曾我小太郎 | 二宮小太郎 | |
| 江戸七郎 | 大井兵三次郎 | 岡部右馬允 | |
| 横山権守相摸 | 小山四郎 | 猿渡藤三郎 | |
| 笠原十郎 | 堀藤次 | 大野藤八 | |
| 伊井介 | 横地太郎 | 勝田玄番助 | |
| 吉良五郎 | 浅羽庄司三郎 | 新野太郎 | |
| 金子十郎 | 志村三郎 | 中禅寺奥次 | |
| 安西三郎 | 平佐古太郎 | 吉見二郎 | |
| 小栗二郎 | 渋谷二郎 | 武藤小次郎 | |
| 天野藤内 | 宇佐美三郎 | 海老名兵衛尉 | |
| 長尾五郎 | 多々良七郎 | 馬塲二郎 | |
| 筑井八郎 | 臼井与一(景常) | 戸崎右馬允 | |
| 八田兵衛尉 | 長門江七 | 中村兵衛尉 | |
| 宗左衛門尉 | 金持二郎 | 奴加田太郎 | |
| 大友左近将監 | 中條右馬允 | 井沢左近将監 | |
| 渋谷弥五郎 | 佐々木五郎 | 岡村太郎 | |
| 猪俣平六 | 庄太郎 | 四方田三郎 | |
| 仙波太郎 | 岡辺六野太 | 鴛三郎 | |
| 古郡二郎 | 都筑平太 | 苔田太郎 | |
| 熊谷小次郎 | 志賀七郎 | 加世次郎 | |
| 平山右衛門尉 | 藤田小三郎 | 大屋中三 | |
| 諸岡次郎 | 中條平六 | 井田次郎 | |
| 伊東三郎 | 天野六郎 | 工藤三郎 | |
| 千葉四郎(胤信) | 千葉五郎(胤通) | 梶原平次左衛門尉 | |
| 後陣 ・郎従数百騎 |
梶原平三 | ||
| 千葉新介(胤正) | |||
| 最末 ・已上水干 ・相具家子郎等 |
前掃部頭 | 伊賀前司 | |
| 縫殿助 | 遠江権守 | ||
| 源民部大夫 | 伏見民部大夫 | 中右京進 | |
| 善隼人佑 | 善兵衛尉 | 平民部丞 | |
| 越後守(越後守頼房)※ |
※関白師実孫・権中納言経定の孫にあたる。建久六年当時は侍従に越後守を兼職。十八歳。
3月11日、頼朝は「馬千疋」を東大寺に施入し「八木一万石、黄金一千両、上絹一千疋」を納めている(『吾妻鏡』建久六年三月十一日条)。そして翌12日、国家的事業として進められてきた「東大寺供養」が遂に挙行された(『吾妻鏡』『玉葉』建久六年三月十二日条)。導師は興福寺別当僧正覚憲、咒願は東大寺別当権僧正勝賢である。権僧正勝賢は鎌倉永福寺の薬師堂供養の導師にも招かれた頼朝とは知己の僧侶であり、その他、仁和寺の守覚法親王以下の一千もの僧侶も列席する壮大な供養会となった。
12日は午後から大雨となり地震も起きている。この大雨は「雨師風伯之降臨」であり「天衆地類之影向、其瑞揚焉」という吉瑞と評されている(『吾妻鏡』建久六年三月十二日条)。
頼朝は朝方から「隆保、頼房等朝臣」とともに車で参堂し「伊賀守仲教、蔵人大夫頼兼、宮内大輔重頼、相模守惟義、上総介義兼、伊豆守義範、豊後守季光等」の京都に慣れた鎌倉家祗候の公家や家子が随っている。
平忠盛
(刑部卿)
∥――――――平頼盛
∥ (権大納言)
藤原宗兼―+―藤原宗子
|(池禅尼)
|
+―女子
∥――――――高階泰経
∥ (大蔵卿)
高階泰仲―+―高階重仲―――高階泰重
(伊予守) |(近江守) (若狭守)
|
+―女子
∥――――+―藤原懐季
∥ |(少納言)
∥ | 【天台座主】
∥ +―藤原実明―――全玄
∥ |(少納言) (大僧正)
∥ |
藤原懐平―+―藤原経通―+―藤原経季―+―藤原季仲 +―藤原仲光―――藤原仲経―+―藤原季光
(右衛門督)|(治部卿) |(中納言) |(太宰権帥) (山城守) |(豊後守)
| | | |
| | +―藤原通家―+―藤原重実―――藤原忠成 +―藤原季綱―?―泉八郎
| | |(右京大夫)|(美濃守) (民部丞) (泉次郎)
| | | |
| | | +―藤原季忠 後白河天皇
| | | |(美濃守) ∥
| | | | ∥――――――以仁王
| | | +―女子 ∥ (高倉宮)
| | | ∥――――――藤原季成―――藤原成子
| | | ∥ (権大納言) (高倉三位)
| | | 藤原公季―――藤原公実
| | |(太政大臣) (権大納言)
| | | ∥
| | | ∥――――+―藤原通季
| | | 藤原光子 |(権中納言)
| | | |
| | | +―藤原実能
| | | |(左大臣)
| | | |
| | | +―藤原公子
| | | | ∥
| | | | ∥――――――源懿子
| | | | 藤原経実 ∥
| | | |(大納言) ∥――――――二条天皇
| | | | ∥
| | | | 鳥羽天皇 ∥
| | | | ∥――――+―後白河天皇
| | | | ∥ |
| | | | ∥ |
| | | +―藤原璋子 +―崇徳天皇
| | | (待賢門院) ∥
| | | ∥――――――重仁親王
| | +―藤原季実―――信縁――――――――――――女子
| | (木工権守) (法勝寺修理別当) (兵衛佐)
| |
| +―藤原経平―+―女子
| (太宰大弐)| ∥――――――藤原公実―+―藤原実能
| | ∥ (権大納言)|(左大臣)
| | ∥ |
| | 藤原実季 +―藤原璋子 +―崇徳天皇
| |(大納言) (待賢門院)|
| | ∥ |
| | ∥――――+―後白河天皇
| +―女子 白河天皇―――鳥羽天皇
| ∥ ∥
| ∥――――――藤原長実 ∥――――+―近衞天皇
| ∥ (権中納言) ∥ |
| ∥ ∥ ∥ |
| ∥ ∥ ∥ +―暲子内親王==以仁王
| ∥ ∥ ∥ (八条院)
| ∥ ∥ ∥
| 藤原顕季 ∥――――+―藤原得子=+―二条天皇
| (修理大夫) ∥ |(美福門院)|
| ∥ | |
| 源俊房――――源方子 +―藤原顕盛 +―重仁親王
| (左大臣) (備前守)
|
+―藤原資平―――藤原義綱―――藤原仲季―――仲祐上座―――藤原仲教―――藤原仲能
(大納言) (肥後守) (内匠助) (七宮坊官) (伊賀守) (伊賀左近蔵人)
∥
∥――――――法印教厳
+―中原広元―――女子 (六条若宮別当)
|(因幡守)
|
+―僧都季厳
(六条若宮別当)
寅一點、鎌倉家の侍所別当和田義盛と所司梶原景時が「数万騎」の鎌倉家の家子や郎従を差配して、東大寺四面を警固。随兵は辻々に配置され「寺内門外」を固めた。兼実からの「雑人禁止之間事、仰頼朝卿畢」(『玉葉』建久六年三月十日条)の依頼の履行であろう。とくに「惣門左右脇」には「海野小太郎幸氏、藤澤二郎清親以下撰殊射手」して座さしめている。頼朝に随ってきた郎従等は「武士等ウチマキテアリケル、大雨ニテ有ケルニ、武士等ハレハ雨ニヌルルトダニ思ハヌケシキニテ、ヒシトゾ居カタマリタリケルニコソ、中々物ミシレラン人ノ為ニハヲドロカシキ程ノ事ナリケレ」(『愚管抄』巻六)と、大雨にも拘わらずまったく動じず控える姿に、慈円は物事をよくわかる人にとっては非常に驚くべきことであろう、と頼朝郎従たちの忍耐強さと統率がとれた態度に感じ入っている。
頼朝の御供随兵として伺候するのは特に選ばれた二十八騎で、前後に分かれて供奉した。和田義盛と梶原景時は侍所司として御家人らに下知する役目があったため、これらを手配し終えたのち、そのまま頼朝のもとに馳せ参じ、最前に和田義盛、最後尾に梶原景時が加わった。
■東大寺供養の御供随兵(『吾妻鏡』建久六年三月十日条)
| 先陣随兵 | 和田左衛門尉義盛 | |
| 畠山二郎重忠 | 稲毛三郎重成 | |
| 千葉新介胤正 | 葛西兵衛尉清重 | |
| 梶原源太左衛門尉景季 | 佐々木三郎兵衛尉盛綱 | |
| 八田左衛門尉朝重 | 岡崎与一太郎 | |
| 宇佐美三郎祐茂 | 土屋兵衛尉義清 | |
| 里見太郎義成 | 加々美二郎長清 | |
| 北條小四郎義時 | 小山左衛門尉朝政 | |
| 後陣隨兵 | 下河辺庄司行平 | 佐貫大夫広綱 |
| 武田五郎信光 | 浅利冠者長義 | |
| 小山七郎朝光 | 三浦十郎左衛門尉義連 | |
| 比企右衛門尉能員 | 天野民部丞遠景 | |
| 佐々木左衛門尉定綱 | 加藤二景廉 | |
| 氏家太郎公頼 | 江戸太郎重長 | |
| 三浦介義澄 | 千葉二郎師常 | |
| 梶原平三景時 |
頼朝が堂前の庇の前に着座したとき、見物のために東大寺衆徒が群れを成して門内に入ろうとして、警固の御家人ともめ事となった。この報告を受けた梶原景時は怒気を含んで「聊現無礼」と彼らに退去を命じたと思われる。しかし、衆徒らはこれを無礼として「甚相叱之」り、互いに「狼藉之詞」で口論となった。この口論はエスカレートし、頼朝も捨て置けずに大床の上から庭上に控える小山七郎朝光を差し招くとなにやら告げて「可相鎮」と命じた。朝光は命を含んで衆徒のもとへ赴くと、騒ぐ衆徒の前に跪いて敬屈し「前右大将家使者」と告げると、衆徒らは朝光の礼に感じて騒ぎを止めた。ここで朝光は、
「当寺為平相国回禄、空残礎石悉為灰燼、衆徒尤可悲歎事歟、源氏適為大檀越、自造営之始、至供養之今、励微功成合力、剩断魔障為遂仏事、凌数百里行程、詣大伽藍縁辺、衆徒豈不喜歓哉、無慙武士猶思結縁、嘉洪基之一遇、有智僧侶、何好違乱妨吾寺之再興哉、造意頗不当也、可承存歟者」
と滔々と衆徒を諭した。
これを聞いていた衆徒らは「忽耻先非、各及後悔」という。朝光の冷静さと梶原景時の傲岸さの差を強調する『吾妻鏡』の創作もあるのかもしれないが、「数千」という衆徒は一斉に静謐したという。そして、この使者となった二十八歳の「勇士」が「容貌美好、口弁分明、匪啻達軍陣之武略、已得存霊場之礼節」と、衆徒らは朝光に敬服し、衆徒は彼が「何家誰人哉」と「為後欲聞姓名可名謁」としきりに尋ねたという。朝光は名の知られた「小山」は憚られると思ったか、「結城七郎」と号して元の座に帰参した(『吾妻鏡』建久六年三月十二日条)。
騒動が収まったのち、頓宮から主上の行幸があり、関白兼実、太政大臣、左大臣以下の諸卿が供奉し、大仏殿に入御。和舞、東舞、誦経など供養が盛大に行われ、秉燭のころ主上は頓宮へ還御となった(『玉葉』建久六年三月十二日条)。「誠是朝家武門之大営、見仏聞法之繁昌也」(『吾妻鏡』建久六年三月十二日条)という朝廷と鎌倉による大営と称賛の言葉が認められる。
翌3月13日、寅刻に主上は南都を離れ帰京の途に就く。兼実は春日社への参詣のため供奉せずに佐保殿へ入った(『玉葉』建久六年三月十三日条)。これはおそらく中宮任子の皇子降誕の祈願であろう。一方頼朝は大仏殿へ参詣し、改めて大仏を拝している(『吾妻鏡』建久六年三月十三日条)。大仏造営を行った宋の仏師陳和卿を「殆可謂毘首羯摩之再誕、誠匪直也人歟」と評し、勧進の重源上人を伝手として結縁のために陳和卿を招いた。ところが和卿は、「国敵対治之時、多断人命、罪業深重也、不及謁」と再三に渡って固辞。この和卿の態度に頼朝は感涙し「奥州征伐之時以所着給之甲冑并鞍馬三疋金銀等」を造営料として和卿に贈り、和卿はこの罪業深き甲冑は造営釘料として東大寺へ施入し、鞍についても同様に寄進したが、馬については受領できないとしてすべて返却された。
翌3月14日、頼朝は帰洛の途に就き(『吾妻鏡』建久六年三月十四日条)、六波羅へ入ったとみられる。15日には中宮任子の大炊御門邸への里下と「御着帯事」の帯の祈祷が執り行われ、さらに薬師法に修せられる(『玉葉』建久六年三月十五日条)。
3月16日夜、頼朝は今回の上洛での初の貴顕との面会として宣陽門院(覲子内親王)を訪問しているが、これはかつて大姫入内を願う頼朝が、入内予定のあった姫宮覲子内親王を、その母・尼丹後(尼丹後二品)との話し合いの末に院号宣下(入内断念)という大きな代償を払わせた詫びと感謝の念を伝えたものであろう。参内よりも前に訪問するという異例のものであった。また、『愚管抄』では「コノ頼朝ガムスメヲ内ヘマイラセンノ心フカク付テアル」(『愚管抄』第六)ときに、頼朝は権大納言通親に「サラニワガムスメマイラセム」という「文カヨハシケリ」(『愚管抄』第六)と、通親に「改めて大姫を帝へ献じる(入内)つもりだ」という文書を送っていた。「サラニ」とあることから、一度断念したのちの入内計画であり、この上洛時のことと推測される。通親は宣陽門院の女院別当であるとともに、源氏長者(淳和院奨学院別当)であり、通親を窓口に入内が進められたかは不明であるが、頼朝は家司広元を通じて通親とも密接にかかわっていたのである。
3月20日、頼朝は禁裏に貢馬二十疋を献上。27日に参内した。前駈は三名(具体名はないが伊賀守仲教、相模守惟義、豊後守季光の三人か)、随兵は八名という行粧であった(『吾妻鏡』建久六年三月廿七日条)。
■建久6(1195)年3月27日参内の随兵八騎(『吾妻鏡』建久六年三月廿七日条)
| 北條小四郎義時 | 宇佐美三郎祐茂 | 小山七郎朝光 | 榛谷四郎重朝 |
| 三浦平六兵衛尉義村 | 梶原平二左衛門尉景高 | 下河辺庄司行平 | 千葉平二兵衛尉常秀 |
3月29日、頼朝は尼丹後を六波羅邸に招き「御台所、姫君等対面給」と、御台所と大姫を対面させた(『吾妻鏡』建久六年三月廿九日条)。大姫入内についての打ち合わせを兼ねた対面であろう。一方、尼丹後も頼朝へ要請する事柄があったと思われ、それは宣陽門院が故院より継承した長講堂領のうちの「七ケ所事」の扱いであろう。この「七ケ所」は故院在世時に荘園が停止され、その後頼朝が地頭職を置いた地であろう(のち頼朝が申し行うことにより乃貢の進済が定められている)。故院が死に臨んで覲子内親王へ長講堂領を譲った際に「故院遺勅」として再度立荘が指示された(『吾妻鏡』建久六年四月廿一日条)ようだが、尼丹後はこの件について頼朝に善処を求めたと思われる。対談後、頼朝は尼丹後へ「御贈物銀作蒔筥、納砂金三百両、以白綾三十端飾地盤」を贈り、古庄左近将監能直、八田左衛門尉朝重に命じて、尼丹後扈従の諸大夫や侍にまで引出物を下している(『吾妻鏡』建久六年三月廿九日条)。
翌3月30日、頼朝は二度目の参内を行った。今度の上洛では頼朝は積極的に参内しているが、後鳥羽天皇からの召しによるものか、参内を取り付けているのかは不明。この日、御所内で今回の上洛ではじめて兼実と対面している(『吾妻鏡』『玉葉』建久六年三月卅日条)。この対面で兼実は「謁頼朝卿、談雑事」(『玉葉』建久六年三月卅日条)と雑事を談じている。その話題は深い内容ではなさそうであるが、翌4月1日、頼朝は兼実へ「頼朝卿送馬二疋」っている。どういった趣旨の馬二頭なのか記載がないが、前日の頼朝との対談によるものであろう。しかし、この馬を見た兼実は「甚乏少、為之如何」(『玉葉』建久六年四月一日条)と記録している。
通説ではこれは頼朝が兼実を軽視したものと受け取られているが、これは「如何」と「何如」を混同した誤訳と思われ、「為之如何」は、兼実に対する贈物が少ないための「不満」ではなく、たった二疋の馬でどうすればいいのかという「困惑」である。兼実は前日の頼朝との対談で馬の提供を求め、頼朝もこれに応じたが、具体的な頭数などは伝えていなかったのであろう。頼朝が「送」ってきた馬はわずか二頭であり、何用の馬だったかは不明だが、この頭数では行い得ず悩んでいるに過ぎない。その翌日から9月まで日記は闕となり、その具体的な用件は不明である。
頼朝は法皇在世中は、兼実とは水面下での交流を続けているが、その交流の目的は天皇を奉じ、それを輔弼する賢相兼実、朝臣の存在により、安穏の世が作られるという理想に基づくものであった。一方で安穏の世を安定させる一つとして公武の縁組が想定され、それが大姫入内へと繋がっていると考えられる。この入内話は建久2年の頼朝の初度上洛前から後白河法皇と頼朝(家司中原広元を京都に派遣)を中心に進められていたものと考えられ、その仲介者が広元と旧知の中納言源通親と丹後局(尼丹後二品)だったのである。頼朝は政治的な運営(兼実)と公武関係の安定(源通親・丹後局)の両面から朝廷との関係強化を図っていたと思われる。
しかし、法皇・丹後局と兼実の間は至って険悪であり、法皇在世中に兼実と親密な関わりを持つことは危険であり、建久二年の上洛時に頼朝が兼実に語った「外相雖表疎遠之由、其実全無疎簡、深有存旨、依恐射山之聞、故示疎略之趣也」はまさにそのことであった。しかし故院崩御後は、憚る必要のある存在はなくなり、頼朝は兼実との強調関係を深めながら、大姫入内計画も同時に粛々と進めたのである。
4月10日、頼朝は三度目の参内を行い、兼実と再度の対面を行った(『吾妻鏡』建久六年四月十日条)。
■建久6(1195)年4月10日参内の車後の随兵十騎(『吾妻鏡』建久六年四月十日条)
| 小山左衛門尉朝政 | 北條五郎時連 | 宇佐美三郎祐茂 | 佐々木三郎兵衛尉盛綱 | 三浦十郎左衛門尉義連 |
| 梶原三郎兵衛尉景茂 | 葛西兵衛尉清重 | 加藤二景廉 | 稲毛三郎重成 | 千葉四郎胤信 |
この対談は相当長く行われ「及深更御退出」という。どのような話題が話し合われたのか、この時期の『玉葉』は闕となっており伺い知ることはできないが、当面の政権運営についてや大姫入内の件も話し合われたことだろう。
なお、この頃、天皇近侍の女官の一人(通親妻で天皇乳母・藤原範子の連れ子。おそらく母範子の伝手で後鳥羽天皇に近侍したと思われる)も天皇の子を妊娠しており、出産時期から逆算してその兆候がみられる時期であるが、その後も兼実及び蔵人長兼ですら懐妊の情報を述べていないことから、範子と通親のみが情報を有し、ひっそりと里邸に下された可能性が高いだろう。頼朝にも兼実にも伝えられなかったのは当然として、尼丹後二品も関わっていない可能性もあろう。
この女官は天皇乳母の藤原範子(刑部卿範兼の娘)と法勝寺執行能円法印(治部卿盛実の子)の間に生まれた女性であるが、父母いずれも中級官吏の諸大夫層出身で、しかも父は僧侶であることから、当時懐妊していた中宮藤原任子の対抗馬になり得る存在ではなかった。当然生まれた子も男子であれば出家の道を辿ることになろうことから、源通親の指示で女官の存在ともども出産まで秘されたとみられる。もし中宮任子の子が姫宮で、範子女子の子が皇子であった場合は、この皇子は後鳥羽天皇の第一皇子となり、範子の女子を通親が養女とすれば、皇子は十分に儲君になることが可能となるのである。
藤原盛実――藤原顕憲―――――藤原盛憲――藤原清房――藤原重房―――+―藤原頼重―+――――――藤原清子 +―足利尊氏
(治部卿) (左大弁) (少納言) (出羽守) (式乾門院蔵人)|(修理亮) | ∥ |(権大納言)
∥ | | ∥ |
∥ | +―上杉憲房 ∥――――+―足利直義
∥ | (蔵人) ∥ (左兵衛督)
∥ +―女子 ∥
∥ ∥――――――足利家時 ∥
∥ ∥ (伊予守) ∥
∥――――――――能円 足利頼氏 ∥ ∥
∥ (法印) (治部大輔) ∥――――足利貞氏
∥ ∥ ∥ (讃岐守)
∥ ∥―――――源在子 北条重時―――――北条時茂―――女子
∥ ∥ (承明門院)(陸奥守) (陸奥守)
∥ ∥ ∥
∥ 藤原範兼―――藤原範子 ∥―――――為仁王
∥(刑部卿) (三位) ∥ (土御門天皇)
∥ ∥ ∥ ∥
∥ ∥ 後鳥羽天皇 ∥――――――――邦仁王
∥ ∥ ∥ (後嵯峨天皇)
∥ ∥―――+―源通光 ∥
∥ ∥ |(太政大臣) ∥
∥ ∥ | ∥
∥ ∥ +―源定通 ∥
∥ ∥ (内大臣) ∥
∥ ∥ ∥
官女 源通親===源在子 ∥
(二条大宮半物) (内大臣) (承明門院) ∥
∥ ∥ ∥
∥ ∥―――――源通宗―――源通子
∥ ∥ (参議)
∥ 藤原忠雅―――女子
∥(太政大臣)
∥
∥――――――+―平時子
∥ |(二位尼)
∥ |
平時信 +―平時忠
(兵部権大輔) (大納言)
4月15日、頼朝は若公(一幡・万寿)を伴って石清水八幡宮へ車で出立した。供奉は伊賀守仲教、相模守惟義、豊後守季光ら鎌倉祗候の公家や京都に慣れた家子が先駆として扈従し、そのほか、頼朝の信任厚い家子・郎従が車の前後に随兵として随った。
■建久6(1195)年4月15日石清水八幡宮寺参詣の随兵廿騎(『吾妻鏡』建久六年四月十五日条)
| 先陣 | 北條小四郎義時 | 小山左衛門尉朝政 | 三浦兵衛尉義村 | 葛西兵衛尉清重 |
| 大友左近将監能直 | 新田四郎忠常 | 後藤左衛門尉基清 | 八田左衛門尉朝重 | |
| 里見太郎義成 | 武田五郎信光 | |||
| 車 | 前右大将源頼朝 | |||
| 後陣 | 千葉新介胤正 | 土屋兵衛尉義清 | 稲毛三郎重成 | 梶原左衛門尉景季 |
| 佐々木左衛門尉定綱 | 土肥先二郎 | 足立左衛門尉遠元 | 比企右衛門尉能員 | |
| 小山七郎朝光 | 南部三郎光行 |
4月17日には「丹後二品局」がふたたび六波羅亭を訪問。「御台所、姫公」と対面した(『吾妻鏡』建久六年四月十七日条)。3月29日と同様、御台所と大姫の両名に面会しており、大姫入内の調整に関する事が伝えられたと考えられるが、尼丹後の本題は前回話された「長講堂領七ケ所事」の件だったろう。またこの日、頼朝は「今日殿下参賀茂社給」ことに関して、家子・郎従に対して「此事為見物不可罷出云々、是依無御見物也」(『吾妻鏡』建久六年四月十七日条)と、兼実の賀茂社参の行列を勝手に見物することを禁じている。ただし、これは「是依無御見物也」という理由である。この日、頼朝は尼丹後二品を六波羅に迎えており、当然迎える側の亭主が抜け出すことはない。つまり、兼実忌避ではなく家人への規律の問題である。
4月21日、頼朝は四度目の参内を行った。御所を退がった頼朝は再び宣陽門院を訪れ「長講堂領七ケ所事、任故院遺勅、可被立之由」について沙汰する旨を述べている(『吾妻鏡』建久六年四月廿一日条)。翌4月22日にも五度目の参内をしているが、前日の目的と関わるための参内であろう。おそらく頼朝が「長講堂領七ケ所事、任故院遺勅、可被立之由」を「依令申行給」たことにより、兼実を含めた公卿衆での陣定で話し合われた結果であろう。そして4月24日に「長講堂領七ケ所、如元可進済乃貢之由」が治定した(『吾妻鏡』建久六年四月廿四日条)。
頼朝は上洛後、主要な郎従を京洛の警衛に派遣しており、4月1日、「於勘解由小路京極、結城七郎朝光、三浦平六兵衛尉義村、梶原平三景時、搦取平氏家人等、是前中務丞宗資父子也、此十余年晦跡」(『吾妻鏡』建久六年四月一日条)と、勘解由小路京極において前中務丞宗資父子を捕縛したという。これは建久2(1191)年3月22日の後鳥羽天皇口宣「建久新制」(『三代制符』)の十六条目にある「自今已後、慥仰右近衞大将源朝臣并京畿諸国所部官司等、令搦進件輩」の実行であろう。
5月18日、頼朝は天王寺御参に際し、以前、能保二位入道が「陸地不可叶之由」(『吾妻鏡』建久六年五月十八日条)を告げていたことから船で向かうことで決定したが、この天王寺御参により頼朝に随う予定の能保入道を含めた朝臣らは「為献路次雑事、被支配所領之由、或触申之、或風聞之」としたことから、頼朝は驚いて早々にこのような事は停止するよう指示した。頼朝としては「是為仏事値遇、企霊場参詣、若令成人費者、還可乖仏意歟、殊有御慎」(『吾妻鏡』建久六年五月十八日条)と所存を述べている。この「太不叶賢慮」ために、二日後の5月20日に天王寺へ出立の際は同道を約していた能保入道の船を断って同道を中止した。「若令成人費者、還可乖仏意歟、殊有御慎」がその理由である。そして尼丹後二品の船を借用し、鳥羽より天王寺へと出立。日中に摂津国渡邊に到着し、ここで車に乗り、御台所や女房も続いた(『吾妻鏡』建久六年五月廿日条)。頼朝が尼丹後二品の船を借用したのは、尼丹後への肩入れではなく、天王寺御参に加わった人々のうち、船をわざわざ用意していたのが能保入道(頼朝の指示で用意)と尼丹後のみであったためであろう。
■建久6(1195)年4月20日天王寺参詣の随兵(『吾妻鏡』建久六年四月廿日条)
| 先陣随兵 | 畠山二郎重忠 | 千葉二郎師常 |
| 村上判官代基国 | 新田蔵人義兼 | |
| 安房判官代高重 | 所雑色基繁 | |
| 武藤大蔵丞頼平 | 野三刑部丞成綱 | |
| 加藤二景廉 | 土肥先二郎惟平 | |
| 千葉三郎次郎 | 小野寺太郎道綱 | |
| 梶原刑部丞朝景 | 糟屋藤太兵衛尉有季 | |
| 宇佐美三郎祐茂 | 和田五郎 | |
| 狩野介宗茂 | 佐々木中務丞経高 | |
| 千葉兵衛尉常秀 | 土屋兵衛尉義清 | |
| 後藤左衛門尉基清 | 葛西兵衛尉清重 | |
| 三浦左衛門尉義連 | 比企右衛門尉能員 | |
| 下河辺庄司行平 | 榛谷四郎重朝 | |
| 御車 | 前右大将源頼朝 | |
| 御後 ・水干 |
源蔵人大夫頼兼 | 越後守頼房 |
| 相摸守惟義 | 上総介義兼 | |
| 伊豆守義範 | 前掃部頭親能 | |
| 豊後守季光 | 前因幡守広元 | |
| 左衛門尉朝政 | 右衛門尉知家 | |
| 左近将監能直 | 右京進季時 | |
| 三浦介義澄 | 梶原平三景時 | |
| 後陣随兵 | 北條小四郎義時 | 小山七郎朝光 |
| 修理亮義盛 | 奈胡蔵人義行 | |
| 里見太郎義成 | 浅利冠者長義 | |
| 武田兵衛尉有義 | 南部三郎光行 | |
| 伊澤五郎信光 | 村山七郎義直 | |
| 北條五郎時連 | 加々美二郎長清 | |
| 八田左衛門尉朝重 | 梶原左衛門尉景季 | |
| 阿曾沼小二郎 | 和田三郎義宗 | |
| 佐々木三郎兵衛尉盛綱 | 大井兵三次郎実治 | |
| 小山五郎宗政 | 所六郎朝光 | |
| 氏家太郎公頼 | 伊東四郎成親 | |
| 小山田三郎重成 | 宇都宮所信房 | |
| 千葉新介胤正 | 足立左衛門尉遠元 | |
| 最末 ・相具家子郎等 |
和田左衛門尉義盛 |
午の刻、頼朝は四天王寺に着し、門外の御念仏所に参ったのち、如意輪観音を拝仏。その後、灌頂堂で待つ天王寺長吏の定恵法親王(故院皇子)に謁拝し、重宝等を拝見したのち旅宿へ帰還。翌5月21日晩に帰洛となった。そしてその翌22日には六度目の参内を果たし、その後「殿下御対面、都鄙理世事、御談話非一」(『吾妻鏡』建久六年四月廿日条)とあるように、兼実と都ならびに地方のことなどさまざまな事柄について談話に及んでいる。のち、後鳥羽天皇が「殿下、鎌倉ノ将軍仰セ合セツゝ世ノ政ハアリケリ」(『愚管抄』第六)とあるように、天皇は兼実、頼朝と朝務に関する情報や問題点を共有していたことがうかがえ、兼実と頼朝との関係も良好であったと推測されるのである。そして「内裏ニテ又度々殿下見参シツゝアリケリ、コノ度ハ万ヲボツカナクヤアリケム」(『愚管抄』第六)とある通り、慈円からみても「万ヲボツカナ」い雰囲気が感じられたようで、初度の上洛とは打って変わってすべてにわたって親密に話し合われたようである。
「ヲボツカナ(シ)」とは不審な様を表す一方で、会いたくて待ちわびるという意味があり、文脈から考えてこの場合の「ヲボツカナ(シ)」は、明らかに後者である。これを否定的に誤訳してしまったものが、近年の頼朝と兼実の関係を否定的にとらえるベースのひとつとなっている。
その後の兼実と頼朝との関係は、後述のように兼実が関白を辞する直前まで政務に関して条々を交わし続け、関白を辞したのちも交流を続けており、実際は至って良好な関係が続いていたのである。前述の「馬二疋」についても、兼実は不満を述べているわけではなく、ただ述懐を記しているだけである。
兼実と頼朝の関係を「否定的」なものとして考えるバイアスを排除して両者の関係を見直さなければ、誤った兼実と頼朝の関係が「史実」として定着してしまうだろう。
翌23日、故院御所であった六条西洞院の「六条殿」に参内しており、その後、法住寺殿内に造営されていた「旧院法華堂」に参詣している(『吾妻鏡』建久六年五月廿三日条)。関東下向に際して後白河院に帰国の報告を行ったものだろう。しかし、頼朝の関東下向は重源上人が行方知れずになり、その捜索のために延引された。その後、所縁の高野山に移っていることが判明し、24日、前掃部頭親能が頼朝の使者として高野山へ向かい帰洛を説得している。重源上人はこれに応じて帰洛の途に就いた。
6月3日、若公一幡(頼家)がはじめて参内した。このとき十四歳。網代車に駕しての参内であった。頼朝はその介添えに従弟の左馬頭隆保を依頼している(『吾妻鏡』建久六年六月三日条)。供奉人は家子郎従あわせて十二名が選ばれ、車の左右に候じた。
| 右 | 相模守惟義 | 伊豆守義範 | 近将監能直 | 左衛門尉義盛 | ||
| 左 | 重朝 (榛谷四郎) |
景季 (梶原源太左衛門尉) |
左兵衛尉清重 (葛西左兵衛尉) |
常秀 (千葉平次兵衛尉) |
景茂 (梶原三郎兵衛尉) |
右京進季時 |
| 小山五郎宗政 | 佐々木中務丞経高 |
6月8日、頼朝は六条西洞院の六条殿に参じ、6月13日、故院法華堂に参詣した(『吾妻鏡』建久六年六月十三日条)。先月の帰国予定が延引されたことから、再度の六条殿への参殿および法華堂の参詣となったと思われる。法華堂の参詣が13日だったのは、故院の命日が13日(建久三年三月十三日)だったためであろう。
6月14日、京洛の警衛に当たっていた下河辺庄司行平が「平氏家人桂兵衛尉貞兼」が召し取られた。その諱からの伊賀国伊賀郡桂村を本貫とする伊賀平氏とみられる(『吾妻鏡』建久六年六月十四日条)。
そして6月23日、頼朝は25日に関東下向することを方々へ伝え、24日に若公一幡を連れて七度目の参内を果たし、主上へ「令申関東御下向暇給」という(『吾妻鏡』建久六年六月廿四日条)。翌25日、時々雨が降る天候の中で頼朝は関東へと下向していった。供奉人は入洛のときと同じだが、ここに「畿内西海之間、為宗之輩多以扈従」(『吾妻鏡』建久六年六月廿五日条)と畿内や九州からの主だった新規郎従が加わったという。また、門脇中納言教盛卿の子・中納言律師忠快(慈円門弟)、新中納言知盛卿の子・中納言禅師増盛、前美濃守源則清の子息を鎌倉へ伴っている(『吾妻鏡』建久六年六月廿五日条)。「是皆平氏縁坐也」とあるように、平氏の縁者を選んだものであり、平家一門の後世を祈る意味があったのだろう。
6月28日、近江から美濃へ入り、「青波賀駅(大垣市青墓町)」に到着した(『吾妻鏡』建久六年六月廿八日条)。以降、頼朝が鎌倉へ至る間の宿所はいずれも遊女が集まる大規模な要衝の宿場が選ばれている。率いる郎従等の人数も含め、相当な数に上っていることが主な理由であることと同時に、郎従やその従者らの人々と宿場の遊女や傀儡女らとの交流を許す目的もあった可能性もあろう。
この青墓宿は頼朝父・義朝が青墓宿の長者「大炊」を寵愛しており、また頼朝祖父・為義は「大炊姉」を最後の妾として召し、乙若以下四人の男子を産んでいるという、頼朝にとっては遠い縁戚でもあった。建久元(1190)年10月29日には、初めての上洛に際してこの青墓宿に立ち寄り、「被召出長者大炊息女等有纏頭」という(『吾妻鏡』建久元年十月廿九日条)。この「大炊息女」はおそらく頼朝異母妹にあたるのであろう。また、異母兄朝長を亡くした地でもあり、頼朝にとっては先祖由緒の地であった。なお、この五年ぶりの来宿に大炊や息女が召されたかは不明である。
内記行遠―+―姉
(大夫) | ∥――――+―乙若
| 源為義 |
|(六条判官)|
| ∥ +―亀若
| ∥ |
| ∥ |
| ∥ +―鶴若
| ∥ |
| ∥ |
| ∥ +―天王
| ∥
| ∥――――――源義朝
| 藤原忠清娘 ∥
| ∥―――?―大炊息女
+――――――――大炊
| (青墓長者)
|
+―内記政遠
|(平太)
|
+―内記眞遠
(平三・出家後号鷲栖源光)
青墓宿では美濃国守護の相模守惟義が駄餉を献じている。なおこの日、関東からの急使が青墓に到着し、「稲毛三郎重成妻北條殿息女、於武蔵国病悩太危急之由」を伝えている。これを頼朝は重成に黒の駿馬一頭を下賜し、ただちに帰国する指示をしている(『吾妻鏡』建久六年六月廿八日条)。
翌29日、頼朝一行は尾張国萱津宿(あま市下萱津)に着陣する。萱津宿は庄内川を臨む港湾流通宿で、いわばハブ宿として近隣経済の中心ともなっていた場所である。ここでの「雑事(駄餉)」は尾張国守護人の小野刑部丞成綱であった(『吾妻鏡』建久六年六月廿九日条)。翌7月1日には熱田社に社参。従弟に当たる熱田大宮司範経と面会し、馬ならびに御剣を奉じた(『吾妻鏡』建久六年七月一日条)に着陣する。
藤原季範―+―藤原範忠―+―藤原忠季
(大宮司) |(大宮司) |(所雑色)
| |
| +―藤原清季――藤原朝季――藤原朝氏
| (大宮司) (大宮司) (大宮司)
|
+―藤原範信―+―藤原憲朝
|(上野介) |(駿河守)
| |
| +―藤原信綱
| |(駿河守)
| |
| +―藤原範清
| (蔵人)
|
+―藤原範雅―+―藤原範高
|(大宮司) |(大宮司)
| |
| +―藤原範経
| (大宮司)
|
+―範智―――――智円
|(粟田口法眼)(法眼)
|
+―祐範
|(法橋)
|
+―千秋尼
|(上西門院女房)
|
+―大進局
|(待賢門院女房)
|
+―女子
| ∥――――――源頼朝
| ∥ (右近衞大将)
| 源義朝
|(左馬頭)
|
+―女子
∥――――――源隆保
∥ (左馬頭)
源師経
(三河守)
7月1日の宿場は記されていないが、距離からして、三河国矢作宿(岡崎市矢作町)であろう。翌7月2日には遠江国橋本駅(湖西市新井町(現在は浜名湖中に沈んでいる))に着陣する。「当国在庁并守護沙汰人等予参集」とあるように、予め在庁と守護沙汰人を招集しておいた。なお遠江国の守護は不明であり、沙汰人もまた具体名はみえない。彼らを集めた頼朝は、遠江国司だった「義定朝臣之後、国務及検断等事、就淸濁、聊有令尋成敗給事」といい、在庁へは国司不在中の国務、守護沙汰人には守護不在中の検断について尋ねたものである(『吾妻鏡』建久六年七月二日条)。
7月3日、4日、5日の宿場も不明ながら、3日は遠江国掛川宿(掛川市)、4日は安倍川を臨む駿河国手越宿(静岡市駿河区手越)、5日は駿河国蒲原宿(静岡市清水区蒲原中)であろう。
7月6日、黄瀬川宿へ到着し、「駿河伊豆両国訴事等條々、令加善政給」(『吾妻鏡』建久六年七月六日条)とあり、この数か月間の頼朝留守中に処理できなかったとみられる訴えに対して指示を行っている。
7月7日の宿場の記載はないが、酒匂宿(小田原市酒匂)か。そして7月8日申刻、鎌倉へ入った(『吾妻鏡』建久六年七月八日条)。
7月19日、若君一幡の御厩が初めて建てられた。そこへ収められた馬は三頭で、千葉介常胤進上の黒駁、小山左衛門尉朝政進上の鴇毛、三浦介義澄進上の河原毛であった(『吾妻鏡』建久六年七月廿日条)。8月15日には鶴岡放生会が行われ、伊豆守義範、豊後守季光ら家子をはじめ、千葉介常胤、三浦介義澄、小山左衛門尉朝政、八田右衛門尉知家、比企右衛門尉能員、足立左衛門尉遠元ら主だった郎従が鶴岡の廻廊に召されている(『吾妻鏡』建久六年八月十五日条)。翌16日には馬場儀が執り行われ、流鏑馬が奉納された。十六騎の弓の上手がこれを行っている。そのうちの四番を常胤の孫「東平太」が務めている(『吾妻鏡』建久六年八月十六日条)。
■建久六年八月十六日放生会流鏑馬(『吾妻鏡』建久六年八月十六日条)
| 一番 | 三浦和田五郎 | 和田五郎義長 |
| 二番 | 里見太郎 | 里見太郎義成 |
| 三番 | 武田小五郎 | 武田小五郎信政 |
| 四番 | 東平太 | 東平太重胤 |
| 五番 | 榛谷四郎 | 榛谷四郎重朝 |
| 六番 | 葛西十郎 | 葛西十郎清宣 |
| 七番 | 海野小太郎 | 海野小太郎幸氏 |
| 八番 | 愛甲三郎 | 愛甲三郎季隆 |
| 九番 | 伊東四郎 | 伊東四郎家光 |
| 十番 | 氏家太郎 | 氏家太郎公頼 |
| 十一番 | 八田三郎 | 八田三郎知基 |
| 十二番 | 結城七郎 | 結城七郎朝光 |
| 十三番 | 下河辺四郎 | 下河辺四郎政義 |
| 十四番 | 小山又四郎 | 小山又四郎朝長 |
| 十五番 | 江間太郎 | 江間太郎頼時 |
| 十六番 | 梶原三郎兵衛尉 | 梶原三郎兵衛尉景茂 |
一方京都では、8月12日辰刻、兼実のもとへ中宮属資兼より大炊御門の中宮里邸(兼実邸)において「聊有御産気」(『三長記』建久六年八月十二日条)の一報が伝えられ、兼実兄の太政大臣兼房や左大臣実房ほか出仕の公卿が悉皆参集した。なお、右大臣兼雅は「漸有憚事」として不参であったが、兼実家司の長兼は「是彼室家有懐孕之聞、無其実故歟」と疑いを持っている。実際は彼が兼実の政敵・源通親と縁戚のためであろう。中宮は「御産気或急速、或落居」と陣痛が繰り返される時期となっており、「自戌剋聊有御気色」という状況が続く中で「此間天已曙了」と朝になった。昨晩から降り続く雨はやむ気配もないなかで、静かに掌灯は片づけられ、昨夜から読まれる誦経の声が響き続けていた。そして巳刻に及び、「平安遂御 皇女也」と皇女を出産した。亭主の祖父兼実は、皇女の御耳元で祝詞を三反誦している。
皇女降誕に家司長兼は「抑日来可皇子降誕之由、或有霊夢、或依偏天下一同謳哥之、亦御祈等超過先御例、修法及卌壇、其外不可勝計、寛弘以降藤氏后妃無此儀、今有此事、定皇子御歟之由世推之、今如此、頗以似遺恨、但以平安可為大慶歟」(『三長記』建久六年八月十三日条)という感想を述べている。
8月16日、蔵人長兼は中宮権大進として参宮し、姫宮の諸行事を執り行った。また中宮女房に謁した際には「御産日七条院無渡御、雖為皇女、猶可有御幸也、皇女何事御哉之由、主上令申給云々、但件条女院不令変御行之儀給、自本所故障申之歟」と、後鳥羽天皇は実母・七条院殖子に対して皇女であろうと渡御があって然るべしと述べたという。七条院が渡御しなかった理由は、兼実に含むものがあったためであろう。
七条院はもともと典侍として出仕していた際に高倉天皇に気に入られ、守貞親王と後鳥羽天皇の二親王を産んだ。ただし、正式に入内しておらず后妃ではないため、故実に厳格な兼実は先例に則った対応を続けていたのである。その具体的な対応としては、建久6(1195)年元日の拝礼が挙げられよう。兼実は「余以人、人々早々可被参七条院之由示之、依可有拝礼也」(『玉葉』建久六年正月一日条)と、左大臣実房以下の人々へは早々に七条院へ拝礼へ赴くべしと伝えているが、当の兼実本人は七条院に「不参」で、宮中へ参内した。その後、酉の刻に七条院から帰ってきた左大臣以下の諸卿が参内し、以降は通例の小朝拝の儀からの新年の儀が粛々と進められることとなる。兼実が七条院に拝礼に赴かなかったのは「美福門院拝礼、故殿不立給、雖為帝母、未必可受摂籙之拝歟、況於今之女院者、非上皇之同居哉、是以不参」(『玉葉』建久六年正月一日条)と、故殿忠通が美福門院に拝礼しなかった先例に随ったものであった。たとえ女院が帝母であったしても摂籙が必ず女院へ拝礼すべき例はなく、ましてや后妃でなかった七条院に拝礼に赴く謂れはないというのが理由である。ただし、これは摂籙に限ったものであり、左大臣以下には七条院への拝礼を示唆していることから、兼実は決して七条院を避けたわけではなく、生来の超保守的な考え方(自家を至上とし他を純粋に悪気なく卑下する)によるものだろう。しかし、七条院がこの先例を知る由もなく、兼実を疎ましい存在に感じたと思われる。そして、七条院は中宮任子に皇子が誕生しなかったことで、姪の女官(坊門局)を後鳥羽天皇に近づけたのであろう。坊門局は間もなく懐妊し、建久7(1196)年10月16日に皇子を産む(『仁和寺御伝』「群書類従」第五輯)。その直後、兼実は関白を辞することになるが、辞任のきっかけの一つが、この七条院姪の皇子降誕だったのかもしれない。
9月25日、中宮任子の皇子降誕が叶わなかったためか、兼実と親しい左大臣実房は「依重厄天変也」として辞大臣を上表するが、辞状は「即被返之」(『公卿補任』)と受理されなかった。
こうした中、10月1日に「或人夢云、大一霊告、今冬可有皇子懐孕之慶云々、仰而可信着胎」(『玉葉』建久六年十月一日条)と、兼実の夢に現れた信頼のおける「或人」が、今年の冬に中宮任子が皇子を懐妊すると述べたことに嬉々とし、兼実はこれを「可信着胎」としている。姫宮降誕の衝撃から立ち直るきっかけとなったと思われる。
10月7日、「今上第一皇女御五十日」の儀が行われ、兼実は束帯を着して中宮里邸の大炊御門の自邸に参じ、その後、左大臣や右大臣、右大将をはじめとする諸卿が参集し、盛大な儀式が行われた(『玉葉』建久六年十月七日条)。10月13日には「中宮御産以後始有御入内、姫宮亦有御行始事、内裏即当吉方、仍同有御入内也」(『三長記』建久六年十月十三日条)と、中宮在子が姫宮を伴って初めて入内した。10月16日には「被下姫宮親王宣下」され、名字勘文により「在」「瑛」「昇」の三つの案が示され、「昇」と決定された(『三長記』建久六年十月十六日条)。同日、昇子内親王の勅別当に伯父の左大将良経(兼実嫡子)が就き、家司は丹後守長経、伊予守能季、職事頭は左中将公房、蔵人は源国朝、侍者は源季忠(祖父伊予守季長は兼実家司、父兼親は中宮任子の中宮六位進)、御監は中宮長兵衛尉源重継、年預は中宮属資兼が就いた。23日に「姫宮侍初事」が行われ、里邸の大炊御門亭へ還御した(『三長記』建久六年十月十六日条)。なお、昇子内親王は翌建久7年4月16日、「今日姫宮准后」(『明月記』建久七年四月十六日条)と、二歳で准后とされた。
12月3日、兼実は凝華舎の直盧での宿侍のため参内。定朝朝臣より奏事があり、「伊勢国住人季廉等狼藉事」との報告がなされた。これは「守護人経俊」からの報告であったという(『三長記』建久六年十二月三日条)。狼藉を働いたという人物「季廉」は諱から見て伊勢平氏とみられ、「守護人経俊(山内首藤経俊)」がこれを報告したことがわかる。「守護人」とあることから、この時点で鎌倉家が国ごとに置いた「守護人」が国惣追捕使に代って用いられていたことがうかがえる。経俊は国惣追捕使から引き続き、義務の一つである謀反人の追捕を行ったのであろう。
12月5日夜、姫宮昇子内親王は「行啓于八条院」した(『三長記』建久六年十二月五日条)。これは「御猶子之儀也、於女院可奉養育也」といい、昇子内親王は八条院の猶子となることが決定。亥刻、御所の飛香舎の北門に車を寄せ、上東門より出御した。随ったのは「高倉源中納言、別当、中宮権大夫、右三位中将、右大弁供奉、此他太相国内大臣殿令扈従給、又殿下有御参会、殿上人頭亮以下廿人供奉、後騎丹後守長経朝臣」(『三長記』建久六年十二月五日条)ら兼実已下の公卿や殿上人らであった。なお、「高倉源中納言」は頼宗流藤家の藤原泰通のことで源氏ではない。八条院のもとにはすでに子息の右中将良輔(母は八条院女房三位局(『尊卑分脈』))が猶子として入っており、兼実との紐帯も確かなものであったためであろう。
宇多天皇―+―敦実親王―――源雅信―――源倫子 +―藤原経実――――藤原経宗―――藤原頼実
|(式部卿) (左大臣) ∥ |(大納言) (左大臣) (右大将)
| ∥ |
| ∥――――+―藤原頼通―――藤原師実―+―藤原師通――――藤原忠実 +―藤原基実
| ∥ |(関白) (関白) (関白) (関白) |(摂政)
| ∥ | ∥ |
| ∥ +―藤原妍子 ∥――――――藤原忠通―+―藤原基房
| ∥ | ∥――――――禎子内親王 ∥ (関白) |(摂政)
| ∥ | ∥ ∥ ∥ |
| ∥ | 三条天皇 ∥――――――後三条天皇 ∥ +―藤原兼実
| ∥ | ∥ ∥ |(関白)
| 藤原兼家――藤原道長 +―藤原彰子 ∥ ∥ |
| (摂政) (関白) (上東門院) ∥ ∥ +―藤原兼房
| ∥ ∥――――――後朱雀天皇 ∥ |(太政大臣)
| ∥ ∥ ∥ |
| ∥ 一条天皇 ∥ +―慈円
| ∥ ∥ (天台座主)
| ∥――――――藤原尊子 ∥
+―醍醐天皇―+―源高明―――源明子 ∥――――――源顕房 +―女子 +―明雲
| ∥ (右大臣) | |(天台座主)
| ∥ ∥ | |
+―村上天皇――具平親王―――源師房 ∥――――――――――――+―源雅実――――源顕通――+―源雅通 +―源親通
(中務卿) (右大臣) ∥ (太政大臣) (権大納言) (内大臣) |(内大臣)
∥ ∥ |
源高明―――源俊賢――――源隆俊――――源隆子 ∥――――+―源通資
(左大臣) (権大納言) (権中納言) ∥ (権大納言)
∥
藤原道隆―――藤原隆家―+―藤原経輔――+―藤原師信―+―藤原基信―――藤原長信―――女子
(摂政) (中納言) |(権大納言) |(内蔵頭) |(陸奥守) (典薬助) (美福門院女房)
| | |
| | +―藤原経忠―+―藤原忠能―――藤原長成
| | (中納言) |(修理大夫) (大蔵卿)
| | |
| | +―藤原信輔―――藤原信隆―――藤原殖子
| | (右京大夫) (修理大夫) (七条院)
| | ∥
| | 白河天皇―――堀河天皇―――鳥羽天皇―――後白河天皇――高倉天皇
| |
| +―藤原師家―――藤原家範―――藤原基隆―――藤原忠隆―――藤原信頼
| (右中将)
| 平忠盛
| (刑部卿)
| ∥――――――平頼盛
| ∥ (権大納言)
+―藤原良頼――――藤原良基―――藤原隆宗―――藤原宗兼―――藤原宗子
(権中納言) (太宰大弐) (近江守) (少納言) (池禅尼)
鎌倉では12月12日、千葉介常胤が「款状」を頼朝宛に捧提した。直接ではなく政所を通じての提出であろう。「款状」には「抽毎度之勲功、励警夜巡昼節、積連年之勤労、潜論其貞心、恐似無等類」という趣旨を述べ、「老命難期後栄、世事只憑上賞、早存日之際、浴恩沢、欲省数輩子孫」と、余命幾何もない身にあっては、ただ子孫のために恩賞に浴すことのみが望みであると強く主張し、「殊称有由緒」として「美濃国蜂屋庄」を給わることを望んだ。この「款状」を受け取った頼朝は「功績誠被世、燐恤隨軼人也、仍連々被加恩賞訖、重可被仰之條、曾不思食忘」と常胤の働きを賞しこれまでも恩賞を加えたが、さらなる加賞も忘れていないとする。しかし「但於蜂屋庄者、故院御時依仰令停止地頭職之間、今更申請之不能宛賜歟」と、蜂屋庄については、かつて故後白河院の仰せによって地頭職を停止し、今は長講堂領に編入された荘園であることから宛がうことはできないとする一方、「以便宜之地、必可有御計」と約束した返書を常胤へ遣わした。この返書を読んだ常胤は「太落涙」し、「慇懃御気色已顕訖、武将御籌策又無止、於今者雖不賜其地非恨限」と申し述べたという(『吾妻鏡』建久六年十二月十二日条)。常胤が申した「由緒」は定かではないが、遠祖・平忠常が美濃国厚見郡(または不破郡野上、山県郡、加茂郡蜂屋庄)で卒したことによるものかもしれない。
関白兼実は長女任子の入内について「御堂者、累祖之中為帝外祖之人雖多、繁華之栄、莫過彼公、宇治殿以降、絶而無此事、為取其始終、尤可祈申此両所歟、入内之本意、只在皇子降誕者歟」(『玉葉』文治五年十一月廿八日条)と述べる通り、その目的を明確に皇子降誕としており、宇治殿頼通以降絶えていた天皇外戚たる摂関家の復活を目指していた。またそれは兼実一門が摂関家嫡統となる意図であり、無能と酷評する実弟兼房をも太政大臣に推任し、その弟・慈円を天台座主として、政治・宗教の両面から強力に兼実系で固めたのである。建久元(1190)年7月17日の除目で異動した右大臣兼雅(兼実嫡子・故良通の舅。のち兼実から離れて源通親と親しむ)や左大臣実房(兼房義兄)ら上卿の多くが兼実係累に属していたのである。
■建久元(1190)年公卿補任(異動者)
| 摂政 | 藤原兼実 | 4月19日、太政大臣の上表 | 中宮任子の父 |
| 太政大臣 | (藤原兼実) | 4月19日、上表 | |
| 左大臣 | 藤原実房 | 7月17日、実定の辞職(男公継の任参議)に伴い、右大臣から転任 | 兼実実弟・兼房の義兄 |
| 右大臣 | 藤原兼雅 | 7月17日、実房の左大臣転任に伴い、内大臣から転任 | 兼実嫡子・故良通の舅 |
| 内大臣 | 藤原兼房 | 7月17日、兼雅の右大臣転任に伴い、任大臣(前大納言、前中宮大夫) | 兼実実弟 |
| 大納言 | 藤原実家 | 7月17日、兼房の任大臣により、権大納言筆頭の実家が大納言に転じる | (送り人事) |
| 中宮大夫 | 藤原良経 | 7月18日、兼房の任大臣により、闕となった中宮大夫を兼務 | 兼実嫡子 |
| 権大納言 | 藤原頼実 | 7月17日、実家の大納言転任により、中納言筆頭の頼実が権大納言に転じる | (送り人事) |
| 中納言 | 源通親 | 7月17日、頼実の権大納言転任により、権中納言筆頭の通親が中納言に転じる | (送り人事) |
しかし、こうした兼実の計画が成立するためのすべての要となっていたのは、中宮任子の皇子降誕であった。このもっとも重要な結点が不確定要素であるという計画であったが、兼実は幾度となく祈祷を繰り返したり忌事を排除したりして皇子降誕を願い、霊夢にまで見て皇子降誕を疑わなかったのである。しかし、実際に誕生したのは姫宮であったことで、兼実の落胆は相当なものであった。ただ、その後に霊夢で「今冬可有皇子懐孕之慶云々、仰而可信着胎」(『玉葉』建久六年十月一日条)を見て、皇子降誕をまた強く信じたのである。建久6年末ごろの時点で兼実には関白を退く予定などはまったくなかったとみてよいだろう。
ところが、冬が過ぎて年が明けた建久7(1196)年正月になっても中宮に懐妊の兆しはなかった。さらに姫宮昇子内親王を託した八条院も重病に陥るという事件も重なった。
正月10日、兼実は八条院へ参向し、邸に詰めていた仁和寺宮守覚法親王に謁見。「被示女院御後事等、大略無其憑御座」ことが知らされる(『玉葉』建久七年正月十日条)。女院の意思は、遺骸は仁和寺に葬し、居住の八条殿は御喪家と定めた。その二日後の12日、「賜自筆之書、三条宮姫宮、可被下親王宣旨之由、可奏聞之旨被仰、即以奏聞、父宮非親王、其子為親王例、問外記、無先規」(『玉葉』建久七年正月十二日条)と、八条院は長らく養育してきた三条宮以仁王の姫宮に親王宣下するよう自筆の書状で兼実に要請している。八条院が闕となっても姫宮が八条院領を経済基盤として自立できるとの親心であろう。要請を受けた兼実は、父宮が親王でない王が親王宣下された例を外記局に問い合わせ、その先例はないとの返事を受けている。
藤原兼実―+―藤原良経
(関白) |(内大臣)
|
+―藤原良輔
|(右中将)
|
+―崇徳天皇―――――重仁親王 +―藤原任子
| (中宮)
| ∥――――――昇子内親王
藤原璋子 | +―高倉天皇―――後鳥羽天皇
(待賢門院)| |
∥――――+―後白河天皇――+―二条天皇
∥ ∥
∥ ∥ +―守覚法親王
∥ ∥ |(仁和寺宮)
∥ ∥ |
∥ ∥――――――+―以仁王――――姫宮
鳥羽天皇 藤原成子 (三条宮) (三条宮姫宮)
∥ (高倉三位局)
∥
∥――――+―暲子内親王――+=二条天皇
∥ |(八条院) |
∥ | |
∥ +―近衞天皇 +=以仁王
∥ |(三条宮)
∥ |
藤原得子―+=二条天皇 +=姫宮
(美福門院)| |(三条宮姫宮)
| |
+=重仁親王 +=藤原良輔
|(右中将)
|
+=昇子内親王
翌正月13日、参内した兼実は大外記良業を召して、八条院への公的な答えとするべく「問父非親王之人、蒙親王宣旨例」(『玉葉』建久七年正月十三日条)を勘申するよう指示し、帰参後に届いた勘申はやはり「曾無其例」であった。翌14日、八条院から年預別当の丹後守長経が来訪し「被献御跡事、被奉処分姫宮之状所被進也」(『玉葉』建久七年正月十四日条)といい、兼実は「即奏事由御返事了」と返答している。
広大な八条院領の処分内容は「安楽寿院、歓喜光院等所被奉也、又庁分御庄々等、分賜中将良輔之外、併可有姫宮御分也、但故三条宮御娘、先年可被相承女院御跡之由、御処分了、仍被一期之間、不可有相違、其後、此姫宮一向可為御沙汰之由、所被申置也」というものであった。つまり、八条院領は以仁王姫君がすでに継承していることから、以仁王姫君一期ののちに、中将良輔(兼実子)と昇子内親王(兼実孫)に分賜するという遺言であった。
正月15日、兼実は八条院に参向して仁和寺宮守覚法親王に謁し、「先日女院所被申、三条姫宮親王宣旨事」について報告をした(『玉葉』建久七年正月十五日条)。兼実は「父非親王之人、蒙此宣旨之例、未曾有也、加之父宮已為刑人被除名了、其子忽預此恩、尤乖物義歟、仍此事不被問人々之由」と述べている。翌16日に仁和寺宮より兼実に「八条院、三条院姫宮親王宣旨、内々示合左大臣之處、深不被甘心」と左大臣実房に難色を示されたことを伝えられている。兼実は盟友実房の実直さに「尤可然、左大臣尤可謂直人歟、可感可感」と評し「専不可及御沙汰事也」としている(『玉葉』建久七年正月十六日条)。
正月17日、兼実のもとに実弟「太相国(藤原兼房)」が訪れ「可上表事、被示合也」(『玉葉』建久七年正月十七日条)というが、兼実は「不可被早了之由」を返答している。兼房は故院に捻じ込まれた形の太政大臣に嫌気が差していた事に加え、中宮任子の皇女降誕に失望した可能性もあろう。一方、正月30日に兼実が八条院に参向したところ、八条院の「御悩頗有御減」という慶事もあった(『玉葉』建久七年正月卅日条)。
しかし、3月23日、盟友であった左大臣実房が「依病上表」してしまう(『公卿補任』)。さらに家司の権中納言兼光も「依腫物病」により3月28日に上表し、4月12日に出家を遂げた上、23日に急死してしまうという悲劇もあった(『公卿補任』)。さらに7月22日には甥で兼実の信頼も厚かった中宮大夫権中納言家房(兄の入道関白基房の子)が病死し(『公卿補任』)、7月26日には家司蔵人長兼の舅である参議雅長も五十二歳で逝去してしまう(『公卿補任』)。この年は兼実と親しい公卿が多数廟堂から姿を消してしまったのである。兼実は実房辞職後、一上たる左大臣を闕とし、右大臣兼雅の転任を行っていないのは、兼雅が政敵たる権大納言通親と繋がる人物であったことが大きな理由であろうが、我が嫡子・内大臣良経の就任も視野に入れていたのかもしれない。結論から言えばこの兼実の企ては失敗し、関白基通政権(事実上の源通親政権)の中で兼雅は左大臣に転じ、右大臣は権大納言頼実が大納言実宗、内府良経を超越して任大臣宣旨を受けて右大臣に就いている。一方で、4月16日には昇子内親王が二歳で「姫宮准后」(『明月記』建久七年四月十六日条)となっている。
その後、半年あまりの間は4月18日の園城寺長吏定恵法親王の薨去、7月8日の内裏などへの落雷、11月2日の「後白河院法華堂僧房焼亡」などの事件がみられるが(『百錬抄』)、兼実らの動きを見ることはできない。しかし、この記録のない時期にひとつの事件が起こっていた。10月16日、兼実とは疎遠の女院・七条院殖子(後鳥羽天皇生母)の実姪・坊門局の皇子(三宮)出産である。兼実はこの情報を得ていたのではなかろうか。これも兼実辞任の一因となった可能性があろう。
三宮降誕からおよそ一月後の11月18日、兼実家司の蔵人長兼が兼実邸を訪れると何やら騒ぎになっていた(『三長記』建久七年十一月十八日条)。長兼が驚いて尋ねると「輔弼可令退給之由巷説嗷々、此事兼日頗有」という。長兼は「然而不存只今之由」であり、兼実邸の人は「宣帝亡霍氏猶霍禹之時也、自御在位之初、大略奉輔宸儀、以治道啓沃、兼有此事有子細等」という。長兼はこのことについて「記而無益」と感想を述べているが、噂を信じていないのか、嘆息なのかはわからない。ところが、翌19日夜に長兼が蔵人の諸事を済ませたのち兼実の直盧へ参じると、兼実より「有被奏之事、座主房領事等也」(『三長記』建久七年十一月十九日条)の指示を受ける。これは兼実実弟の天台座主慈円の管領する座主房領の譲りの事であり、御所内は「衆口嗷々、事已露顕歟、天亡良弼歟、可悲々々」(『三長記』建久七年十一月十九日条)と、兼実の関白辞職は公然となっていたのである。翌20日、蔵人長兼は参内して「奏座主房領事」し、「可宣下之由有仰」という(『三長記』建久七年十一月廿日条)。次に召しによって「参太相国御許」じ「三位中将二品所望之間事」を聞き、次に兼実の直盧に赴いて「申太相国并座主御房之領等勅答者」している。また、慈円兼帯の「無動寺楞厳三昧院検校」は弟子僧の「殿法印良尋」に譲となり補任している。これは本来は陣定で宣下すべきだが、今回は「有事煩」ということで右大臣兼雅の邸で宣下すべしと長兼へ指示している(『三長記』建久七年十一月廿一日条)。「煩」とは兼実の関白辞任のことであろう。なお、「殿法印良尋」は兼実の子息であり、無動寺と横川の楞厳三昧院の管轄は慈円系に継承されたことになる。兼実による九条流を絶やさぬ手配の一つであろう。
11月21日、長兼は前日の「三位中将二品所望」という「太政大臣被申之趣」を奏上するが、「無左右仰」であった(『三長記』建久七年十一月廿一日条)。おそらくこれも兼実の朝廷内における九条流の楔の一つであったと思われるが、兼房が太政大臣を辞するかわりに、子息の右中将兼良の昇叙を望んだものであろう。結局この願いは叶うことはなく、兼良は建久9(1198)年正月5日に従二位に昇った。
11月23日、夜に入って甚だ雨が降る中、参内した兼実に長兼は「今夜中宮行啓八條殿、当太白方之由」を啓達した。御所から見て八條殿の方角は太白方であり、これを慎むべきかと問うたのである。しかし兼実は「暁鐘以降可宜、其由可催也」(『三長記』建久七年十一月廿三日)とし、暁鐘以降の行啓となった。これに供奉するのは坊門大納言、権大夫、左大弁、右三位中将、皇太后宮大夫、大蔵卿、次将成定、定家、中宮権亮以下の人々であった。この行啓は「巷説嗷々、事已露見、仍中宮有行啓于八條殿」(『三長記』建久七年十一月廿三日)といい、兼実の関白辞任はすでに公然の秘であり、憚りによって「中宮有行啓于八條殿」という措置が取られたのであろう。
翌11月24日、蔵人長兼は兼実と八条院の中宮任子に参じたのち参内し、前日の23日夜に付けられた少納言頼房の辞状を弁掌侍を通じて奏上している(『三長記』建久七年十一月廿四日)。長兼はこの頼房辞状について「有存旨歟、如予憗拝趨、可耻々々」と批判する。
藤原通家―――女子
∥――――――藤原季成―――藤原成子 +―守覚法親王
∥ (権大納言) (高倉三位) |(仁和寺宮)
∥ ∥ |
藤原公実 鳥羽天皇 ∥―――――+―式子内親王
(大納言) ∥ ∥ |
∥ ∥ ∥ |
∥ ∥――――――後白河天皇 +―以仁王
∥ ∥ (高倉宮)
∥――――――藤原璋子
∥ (待賢門院)
∥
藤原宣孝―――藤原隆光――藤原隆方―+―藤原光子 +―藤原為隆―+―藤原憲方――+―藤原頼憲―+―藤原頼房
(右衛門佐) (左京大夫)(但馬守) | |(大蔵卿) |(右馬頭) |(中宮大進)|(少納言)
∥ | | | | |
∥――――――藤原賢子 +―藤原為房―+ | | +―藤原親頼
∥ (大弐三位) (右大弁) | | | (薩摩守)
紫式部 ∥ | | +―女子
∥―――――高階為家―――高階為章 | | | ∥――――+―藤原公国
高階成章 (播磨守) (丹波守) | | | ∥ |(権中納言)
(太宰大弐) | | | ∥ |
| | | 藤原実家 +―藤原公明
| | |(大納言) (非参議)
| | |
| | +―小宰相
| | |(上西門院女房)
| | | ∥
| | | 平通盛
| | |(越前守)
| | |
| | +―女子
| | | ∥――――――藤原実国
| | | ∥ (権大納言)
| | | 藤原公教
| | |(内大臣)
| | |
| | +―女子
| | ∥――――――藤原光忠
| | ∥ (民部卿)
| | 藤原師実――――藤原経実
| |(関白) (大納言)
| |
| +―藤原光房――+―藤原経房
| (中宮亮) |(権大納言)
| |
| +―藤原定長
| |(参議)
| | 【兼実家司】
| +―藤原光長―――藤原長房
| (左大弁) (民部卿)
|
| +―藤原顕能――――藤原重方―――藤原重頼
| |(右衛門権佐) (中宮権大進)(宮内権大輔)
| |
+―藤原顕隆―+―藤原顕頼 +―藤原光頼
(権中納言) (民部卿) |(参議)
∥ ∥ |
∥ ∥―――+―藤原惟方
∥ ∥ (参議)
∥ ∥
∥ 藤原俊忠―+―藤原俊成――藤原定家
∥(中納言) |(三位入道)(権中納言)
∥ |
∥ +―女子
∥ ∥―――――藤原長方
∥ ∥ (権中納言)
∥ ∥ ∥ 【兼実家司】
∥――――――藤原顕長 ∥――――――藤原長兼
源顕房―+―女子 (権中納言) ∥ (権中納言)
(右大臣)| ∥
| 藤原通憲――――女子
| (信西入道)
|
+―源雅実――――源顕通―――――源雅通――――源親通
|(太政大臣) (権大納言) (内大臣) (内大臣)
|
+―源師子
∥――――――藤原忠通――――藤原兼実
∥ (関白) (関白)
藤原忠実
(関白)
そして11月25日朝、兼実は「頭右兵衛督令辞申給」とある通り、蔵人頭高能に関白を辞去する旨を口頭で申し伝えた。なお兼実は「不被進御上表」(『三長記』建久七年十一月廿五日)とあるように上表はしなかった。これは『公卿補任』においても「無上表事」と注されており、辞状を奏じないまま辞任したことは確実である。長兼はこの兼実の関白退任について、周公旦が甥の成王を補佐して縦横に活躍したが、側近の讒言によって成王と対立し身を引いた故事を引き「抑殿下以伊尹之嚢行奉佐万機給、世属静謐、政及淳素、忽納邪佞之諫、退忠直之臣、天之与善蒙竊■、但周公之大聖、成王信流言、一旦退之、奸臣乱朝、蓋従昔而然、況乎於濁世哉、於戯悲哉々々、巷説縦横、記而無益、可以目耳」(『三長記』建久七年十一月廿五日)と、嘆く様子が見える。
兼実が関白を退く決断をした背景には、中宮任子の皇子誕生が叶わなかったことと歩調を合わせているかのように見えるが、実際は宮中の機微を知る立場にあった蔵人長兼の嘆きに周公旦と成王の仲違いが例示される如く、天皇と兼実の関係が悪化したことがもっとも大きな原因であろう。その理由もまた長兼の嘆息にある「忽納邪佞之諫、退忠直之臣」「成王信流言」「奸臣乱朝」ということではあるまいか。これを裏付けるような話も『愚管抄』に見られ、兼実はこれまで「皆頼朝ニ云合セツゝ、カノマ引ニテコソアリト、誠ニモコレ善政ナリト思ハレ」たので、「法皇ウセヲハシマシケルトキ、ニハカニ大庄ヲ播磨備前ナドニタテラレタルヲ、タテラレニキ」と、後白河院崩御後に梶井宮(後白河院皇子の承仁法親王)と「浄土寺ノ二位」こと尼丹後二位(承明門院源在子母)が結託した播磨や備前での立荘を認めず、さらに藤原成経や実教といった諸大夫を宰相中将へのぼらせんとした企みも認めなかった。これらを尼丹後二位が非難するが、尼丹後自身は天皇に対する直接的な影響力は強くないため、「内ヘ日々ニ参リナド」している梶井宮と繋がり、源通親にも不満を述べたとする。梶井宮は通親の伯父・天台座主明雲の門弟であり、通親とは予てより親しい間柄だったのであろう。彼らが「内ノ御気色ヲウカゞ」うと、天皇は「イタウ事ウルハシクテ、善政ゝゝトノミ云テ御遊トモ憚ラシク思召ケンヲモ見マイラセ」と、たいそう生真面目に「善政、善政」と言って「御遊」も行わないほどだったという。これは「善政」を頻りに吹聴する兼実や頼朝の影響と考えられ、後白河院崩御の後、白河法皇以来続いた院政が終わり、後見のいない後鳥羽天皇による新政が行われる中、まだ若い天皇は「殿下、鎌倉ノ将軍仰セ合セツゝ世ノ政ハアリケリ」(『愚管抄』巻六)とあるように、兼実と頼朝の両者と仰せ合わせつつ政務を行っていたことがわかる。このように、天皇は関白兼実と頼朝の補佐と教育を受け入れていたのであるが、梶井宮や源通親らは、天皇に事あるごとに「頼朝ガ気色カウ」と告げ、頼朝へは「君ノ御気色ワロク候」と言い、兼実に対する不信感を天皇と頼朝両者に植え付けようと企んだようである(『愚管抄』巻六)。この「奇謀」が奏功し、兼実は天皇の信認を失ってしまったということになろう。ただし、頼朝は関白退任後も兼実との協調関係を保っていることから、頼朝は彼らの讒言を信用しなかったことがわかる。
慈円によれば「摂籙臣九條殿ヲイコメラレ給ヌ、関白ヲバ近衞殿ニカヘシナシテ、中宮モ内裏ヲ出テ給ヒヌ」(『愚管抄』)と記すように、関白は前摂政基通へ継承されたのであるが、どうしてこのような事になったのか、慈円が耳にしたところでは、前述の梶井宮と尼丹後二位、そして通親の暗躍ならびに、「コノ頼朝ガムスメヲ内ヘマイラセンノ心フカク付テアルヲ、通親ノ大納言ト云人、コノ御メノトナリシ刑部卿三位ヲメニシテ、子ドモ生セタルヲコメ置タリシヲ、サラニワガムスメマイラセムト云文カヨハシケリ」(『愚管抄』巻六)が原因であるという。頼朝が大姫の入内について強く願い、大納言通親へ宛てて「我が娘を主上に献じ申し上げるつもりである」という手紙を送ったことも一つの要因であったようである。すでに発覚していたと思われる坊門局所生の皇子の存在に加えて、頼朝娘の入内話も現実味を帯び、そこに通親らの讒言による天皇の不信という拭い難い現実を突きつけられたのではなかろうか。
兼実が蔵人頭高能へ関白辞任を口頭で伝えて「停関白前太政大臣職」(『百錬抄』)したのち、「上卿土御門大納言、右少弁親国、蔵人佐朝経等奉行、大内記宗業、大外記師直参仕也」(『三長記』建久七年十一月廿五日)により「関白詔事」がなされ、「以前摂政藤原朝臣、可為氏長者并関白之由被宣下」(『百錬抄』)となった。兼実は関白退任と同時に氏長者も停止されたのである。
翌26日、「今日座主上表給云々、天台座主法務権僧正悉辞退、又御持僧内御祈願被進御巻数、被返進御本尊」と慈円は座主職と付帯職を辞退し、祈願巻数もすべて返進した。慈円の座主辞退は兼実との強い関係によるもので「御連枝之中殊令奉憑給、仍令辞申給也」という(『三長記』建久七年十一月廿六日)。おそらく頼朝は蔵人頭高能から関白辞任や座主辞退といった一連の政変を伝えられたと思われるが、頼朝にとってこの情報は実に寝耳に水のものであったと思われる。慈円の座主辞退を受けた頼朝は「頼朝モ大ニウラミヲコセリ」だったという(『愚管抄』巻六)。
『愚管抄』によれば、兼実が関白辞退ののち、通親は兼実に対し「流罪ニヲヨバント、此人々申ヲコナイケレ」ども、天皇は「ソレヲバツヨク御気色エアラジト思召タリケレバ、云ツグベキ罪過ノアラバヤハ、サシテモ申ベキナレバサテヤミニケリ」と拒絶し、兼実配流の企ては立ち消えになったという(『愚管抄』巻六)。
+―藤原頼経【関東将軍】
|(右近衞中将)
|
藤原公経 +―藤原教実
(太政大臣) |(関白)
∥ |
∥―――――――藤原綸子 +――――――――――――藤原仁子
∥ ∥ | ∥
+―藤原全子 ∥――――+―藤原竴子 ∥
| ∥ (藻璧門院) ∥
藤原能保―+―女子 ∥ ∥ ∥
(権中納言) ∥―――――――藤原道家 ∥―――――四条天皇 ∥
∥ (関白) ∥ ∥
藤原兼実―――藤原良経 ∥ ∥
(関白) (摂政) ∥ ∥
∥ ∥
+―守貞親王―――――――――――茂仁王 ∥―――――藤原宰子
|(後高倉院) (後堀河天皇) ∥ ∥
| ∥ ∥
高倉天皇―+―後鳥羽天皇 藤原基通―――藤原家実―――――――藤原兼経 ∥――――――惟康親王【関東将軍】
∥ (関白) (関白) (関白) ∥ (二品親王)
∥ ∥
∥―――――――為仁王 平棟子 ∥
∥ (土御門天皇) ∥――――――――――――――――宗尊親王【関東将軍】
∥ ∥ ∥ (中務卿)
+=源在子 ∥――――――邦仁王 ∥――――――瑞子女王
|(承明門院) ∥ (後嵯峨天皇) ∥ (永嘉門院)
| ∥ ∥ ∥
+―源通宗―――――源通子 ∥ 後宇多天皇
|(参議) ∥
| ∥
源通親――+―源通具 ∥
(大納言) (大納言) ∥
∥ ∥―――――――源具実――+―源具教――――――――――――――女子
藤原範子 +―按察局 (内大臣) |
(三位) |(院女房) |
∥ | |
∥――――+―源在子 +―源基具
∥ (承明門院) (太政大臣)
能円法印
兼実、慈円の辞任から三日後の11月28日、兼実家司の蔵人長兼へ「或人告示云」こととして、「参九条殿之人、関東将軍成咎、可用心」(『玉葉』建久七年十一月廿八日条)という情報が入る。長兼はこの情報に対しては怒りを含み「此事不可信、縦又雖成咎、以御恩立身之者不可有不参、運命在天、宿報也、不可諂々々々」(『玉葉』建久七年十一月廿八日条)と、この情報は信ずるに足らずと一蹴し、またたとえ咎を受けるとしても、九条殿の御恩を受けて立身した者が参じないわけがなかろうとしている。
兼実辞任の噂は11月18日に宮中または大炊御門邸で出たものが初出であり、それ以降に鎌倉へ伝えられたとしても、諸所のタイムラグを考えると現実的には往復7、8日程度となろう。後白河院薨去の一報は片道3日で鎌倉に到達した記録はあるが、今回に関しては鎌倉から京都へ伝える緊急的な通達があるわけではなく、「参九条殿之人、関東将軍成咎、可用心」の噂の発信源は京都である可能性が非常に高い。長兼へ用心すべしという噂を流した「或人」が発信源ではないかもしれないが、少なくとも兼実に批判的な人物であろう。
11月30日、慈円後任の天台座主は「加持井宮」が定められ、「今日被宣下天台座主」られた(『玉葉』建久七年十一月卅日条)。「加持井宮」は後鳥羽天皇とも親しい二十八歳の梶井宮承仁法親王(故院皇子)であり、尼丹後二品とも通親とも親しく、通親らによる推挙であろう(尼丹後二品と梶井宮は醜聞すらあった)。
建久8(1197)年正月1日の節会から関白基通の不規則な宮中作法を伝え聞いた兼実は、「公家催辞退、弥可招恐怖、暗被懸勾、可謂冥如歟」(『玉葉』建久八年正月一日条)と嘲り恐れる。なお、正月6日の叙位儀についても、「関白不待参議着座、不応主上之喚、進着廉下円座」(『玉葉』建久八年正月六日条)と、関白基通の無作法を批判している。また、この年の12月15日の除目で、通親妻・刑卿三位範子の義兄(実際は実叔父)である六十八歳の散位藤原範季が従三位に叙されているが(『公卿補任』)、これもまた梶井宮の座主と同様に通親らによる推挙であろう。
関白在任中の兼実は、頼朝と頻繁に意見を交換しつつ朝政を行い、建久7(1196)年10月中~11月上旬ごろにも政務についての「条々」を鎌倉へ送っていた。「条々」を諮っていることから、この頃の兼実に関白退任の意思はなかったと考えられる。
このような中で10月16日に誕生したのが、七条院姪・坊門局を母とする天皇第二皇子(長仁親王。のちの道助入道親王)であった。七条院も兼実とは疎遠であり、その後、皇子降誕の報を受けたことが兼実の退任の一因だったと考えてもおかしくはないだろう。そして、兼実は10月中旬から11月18日までの間に辞意を固め、11月25日に上表なしの口頭のみで関白を辞した(『玉葉』建久七年十一月廿五日条)。
そして、辞任から数日後の建久7(1196)年12月5日、「九条殿御時被仰遣条々之返事」である「前右大将申状等」が兼実のもとに届いた。兼実はこの頼朝返事を家司蔵人長兼に託して左大弁に奏聞させている。政務に関する条々であることからすでに兼実には無用のものだが、奏聞すべきものであり、これを受けた天皇は内容を見て「件状可申殿下」と仰せ下されたため、長兼は関白基通邸を訪問し、これを渡している(『三長記』建久七年十二月五日条)。このように、頼朝は兼実とは最後の最後まで互いに政務について連絡を取り合っており、まったく疎遠な空気はなかったことがわかる。
しかし、頼朝にとって建久7(1196)年11月の兼実関白辞任以降から翌建久8(1197)年にかけては大災厄が重なる年となった。兼実の関白辞任後、その地位を継いだのは無能の前摂政基通であり、その背後に権大納言通親が控えて政務を行う状況に変わった。兼実退任直後から通親の台頭が見え始めており、兼実辞任の翌月である建久8(1197)年正月29日の除目では、執筆予定であった右大臣兼雅が「依所労不被参」という理由で「権大納言通親卿」が執筆となった(『猪隈関白記』建久八年正月廿九日条)が、通親は大納言最末であり、大納言実宗以下五人の上臈ならびに内大臣良経を超越しての執筆であり、異例中の異例であった。兼雅が通親に通じて不出仕した可能性が高く、当時の『玉葉』は遺されていないものの、記事が遺されていれば相当激しい怒りが綴られたと思われる。
一方、頼朝は家司中原広元を介して通親と大姫入内交渉を進めていたと思われるが、大姫は相も変らぬ体調であったと思われ、頼朝は大姫の病を癒すため「京ヨリ実全法印ト云験者クダシタリ」(『愚管抄』)と、神仏へ救いを求めていた。3月23日には前後に随兵を従えた大規模な信濃善光寺参詣を行っており(『相良家文書』:「大日本古文書 家わけ五」)、これも大姫病気平癒の祈願の一環であった可能性があろう。なお、この随兵には、先陣に常胤次男「千葉次郎(師常)」、後陣に嫡子「千葉新介(胤正)」と孫の「千葉平次兵衛尉(常秀)」が扈従している。
■建久8(1197)年3月23日『右大将家善光寺御参隨兵日記』(『相良家文書』所収)
(前略)
隨兵
先陣
佐原十郎左衛門尉(佐原義連) 長江四郎(長江明義)
千葉次郎(相馬師常) 和田次郎(和田義茂)
武田兵衛尉(武田有義) 平井四郎
(中略)
後陣
千葉新介(千葉胤正) 葛西兵衛尉(葛西清重)
北条五郎(北条時連、のち時房)佐々木五郎(佐々木義清)
千葉平次兵衛尉(千葉常秀) 梶原刑部兵衛尉(梶原景定)
八田太郎左衛門尉(八田朝重) 江戸太郎(江戸重長)
(後略)
しかし、これらの加験も空しく、大姫は7月14日に「久シクワヅライテウセニケリ」(『愚管抄』)という最悪の結末に至る。頼朝はすでに大姫の病を癒すため、法印実全を招聘して祈祷を行わせていたが、「全クシルシナシ」であり、頼朝は神仏の望みも失せたと感じたか、法印実全に気を遣って、大姫は「ヨロシク成タリト披露」して実全を京都へ帰した。しかし実全が「イマダ京ヘノボリツカヌ先ニ、ウセヌルヨシ聞ヘテ後」に入京したので、都では実全に大姫を「祈殺シテ帰リタル」という疑いがかけられたという(『愚管抄』)。
続けて10月13日には、頼朝の義弟にして朝廷との橋渡しであった「能保入道ハウセニケル」(『愚管抄』)という事態も起こった。頼朝は朝廷政治を掌握していた源通親とも懇意であったが、兼実とは異なり権謀術数の駆け引きが必要な人物であったことから、兼実退任に続く能保入道の死は表裏のない政治的な意思疎通が難しくなったことを意味するものであった。さらにこの頃から、後鳥羽天皇の譲位をめぐる通親と七条院(後鳥羽天皇生母)の水面下の動きが始まったと思われる。12月15日の除目で、頼朝嫡子・頼家が「従五位上」に叙され「右近衞権少将」に任じられた(『公卿補任』)ことも、その動きの一つと考えられよう。
初叙が「従五位上」以上で初任が「近衞少将」以上は摂関家子息の特権であるが、通親は鎌倉家を摂関家に次ぐ家格として推したことになろう。頼家は二年後の建久10(1199)年正月20日には五位のまま「左近衞権中将」に任じられているが、これも摂関家子息の特権である「五位中将」であり、初叙からおおむね3~5年程度で従三位となる摂関家子息の例にも当てはまり、鎌倉家の公的な家格として認められたとみられる。後年、九條家の藤原頼経が鎌倉に下り得たのも、皇統からの鎌倉下向が叶ったのも、関東の隠然たる力も然ることながら、先例と秩序のもとに鎌倉家が摂関家に准じる家格であるという公的担保があったからに他ならないのではなかろうか。
なお、頼家への叙爵及び任官は公家子弟に見られるような元服に伴うものではない。頼家は鎌倉在住の公家・藤原雅経(将軍被成猶子)の建久8(1197)年2月3日の日記によれば「太郎殿頼家」(『革菊別記』建久八年二月三日条:「大日本史料」第四編之五)とあるように、叙任の一年前時点ですでに元服済みである。つまり、鎌倉家は当初から摂関家に准じる家格だったのではなく、頼朝への「協力」を求め、その見返りの必要性を感じた人物、つまり今上一宮を儲君の候補に擁し、その践祚を目論む「源博陸(土ミカド)」権大納言通親の主導で急遽行われた措置であり、鎌倉家家司の中原広元がその仲介をしていたと考えられる。
●頼家と摂関家子息の初叙等の比較(『公卿補任』)
| 名前 | 続柄 | 初叙 | 初任 侍従を除く |
次叙 | 次任 | 四位 | 三位 |
| 源頼家 | 源頼朝 一男 |
建久8(1197)年 12月15日 ●従五位上 (16歳) |
初叙同日 右近衞権少将 (16歳) |
建久9(1198)年 11月21日 ●正五位下 (17歳) |
建久10(1199)年 正月20日 左近衞権中将 (18歳) 【五位中将】 |
正治2(1200)年 正月5日 ●従四位上 (19歳) |
正治2(1200)年 10月26日 ●従三位 (19歳) ※初叙から3年 |
| 名前 | 続柄 | 初叙 | 初任 侍従を除く |
次叙 | 次任 | 四位 | 三位 |
| 藤原基実 | 藤原忠通 息 |
久安6(1149)年 12月25日 ●正五位下 (元服:7歳) |
元服同日 左近衞権少将 (7歳) |
久安7(1150)年 正月6日 ●従四位下 (7歳) |
仁平2(1152)年 9月9日 左近衞中将 (9歳) |
久安7(1150)年 正月6日 ●従四位下 (7歳) |
仁平2(1152)年 3月8日 ●従三位 (9歳) ※初叙から3年 |
| 藤原基房 | 藤原忠通 二男 |
保元元(1156)年 8月29日 ●正五位下 (元服:13歳) |
保元元(1156)年 9月8日 左近衞権少将 (13歳) |
保元元(1156)年 11月28日 ●従四位下 (13歳) |
保元元(1156)年 9月17日 左近衞権中将 (13歳) 【五位中将】 |
保元元(1156)年 11月28日 ●従四位下 (13歳) |
保元2(1157)年 8月9日 ●従三位 (14歳) ※初叙から1年 |
| 藤原兼実 | 藤原忠通 三男 |
保元3(1158)年 正月29日 ●正五位下 (元服:10歳) |
保元3(1158)年 3月13日 左近衞少将 (10歳) |
保元3(1158)年 10月21日 ●従四位下 (10歳) |
保元3(1158)年 4月2日 左近衞中将 (10歳) 【五位中将】 |
保元3(1158)年 10月21日 ●従四位下 (10歳) |
永暦元(1160)年 2月8日 ●従三位 (12歳) ※初叙から2年 |
| 藤原兼房 | 藤原忠通 四男 |
応保2(1162)年 2月21日 ●従五位上 (19日元服:10歳) |
応保3(1163)年 正月24日 左近衞少将 (11歳) |
応保2(1162)年 2月25日 ●正五位下 (10歳) |
長寛2(1164)年 正月21日 左近衞中将 (12歳) 【五位中将】 |
長寛2(1164)年 正月5日 ●従四位下 (12歳) |
仁安元(1166)年 正月12日 ●従三位 (14歳) ※初叙から4年 |
| 藤原基通 | 藤原基実 一男 |
嘉応2(1170)年 4月23日 ●正五位下 (元服:11歳) |
嘉応2(1170)年 12月5日 右近衞権少将 (11歳) |
承安2(1172)年 正月5日 ●従四位下 (13歳) |
承安2(1172)年 10月26日 右近衞中将 (13歳) 【五位中将】 |
承安2(1172)年 正月5日 ●従四位下 (13歳) |
承安4(1174)年 8月2日 ●従三位 (15歳) ※初叙から4年 |
| 藤原忠良 | 藤原基実 二男 |
治承4(1180)年 11月10日 ●正五位下 (元服:17歳) |
養和元(1181)年 12月4日 左近衞中将 (18歳) |
養和元(1181)年 11月28日 ●従四位下 (18歳) |
寿永2(1183)年 4月9日 右兵衛督 (20歳) |
養和元(1181)年 11月28日 ●従四位下 (18歳) |
寿永2(1183)年 正月5日 ●従三位 (20歳) ※初叙から3年 |
| 藤原師家 | 藤原基房 三男 |
治承2(1178)年 4月26日 ●正五位下 (元服:7歳) |
治承2(1178)年 6月10日 左近衞少将 (7歳) |
治承2(1178)年 閏6月10日以降 ●従四位下 (7歳) |
治承2(1178)年 閏6月10日 左近衞中将 (7歳)『山槐記』 【五位中将】 |
治承2(1178)年 閏6月10日以降 ●従四位下 (7歳) |
治承3(1179)年 10月7日 ●従三位 (8歳) ※初叙から1年 |
| 藤原忠房 | 藤原基房 四男 |
建仁2(1202)年 12月 ●従五位上 (元服:12歳) |
建仁3(1203)年 10月24日 右近衞少将 (13歳) |
建仁3(1203)年 正月5日 ●正五位下 (13歳) |
元久元(1204)年 4月12日 右近衞中将 (14歳) 【五位中将】 |
元久元(1204)年 正月5日 ●従四位下 (14歳) |
建永2(1207)年 正月13日 ●従三位 (15歳) ※初叙から4年 |
| 藤原良通 | 藤原兼実 一男 |
承安5(1175)年 3月7日 ●従五位上 (元服:9歳) |
治承元(1177)年 11月15日 右近衞中将 (11歳) |
安元元(1175)年 12月10日 ●正五位下 (9歳) |
治承3(1179)年 11月17日 権中納言(従二位) (13歳) |
安元2(1176)年 12月5日 ●従四位下 (10歳) |
治承2(1179)年 12月24日 ●従三位 (13歳) ※初叙から4年 |
| 藤原良経 | 藤原兼実 二男 |
治承3(1179)年 4月17日 ●従五位上 (元服:11歳) |
養和元(1181)年 12月4日 右近衞少将 (12歳) |
治承4(1180)年 4月21日 ●正五位下 (12歳) |
寿永元(1182)年 11月17日 左近衞中将 (13歳) 【五位中将】 |
寿永2(1183)年 正月7日 ●従四位下 (14歳) |
元暦2(1185)年 正月6日 ●従三位 (17歳) ※初叙から6年 |
| 藤原良輔 | 藤原兼実 三男 (八条院猶子) |
建久5(1194)年 4月23日 ●正五位下 (元服:10歳) |
建久5(1194)年 10月30日 右近衞権少将 (10歳) |
建久7(1196)年 正月6日 ●従四位下 (12歳) |
建久6(1195)年 2月2日 右近衞権中将 (11歳) 【五位中将】 |
建久7(1196)年 正月6日 ●従四位下 (12歳) |
正治3(1201)年 10月26日 ●従三位 (17歳) ※初叙から7年 |
| 藤原兼良 | 藤原兼房 一男 (基房猶子) |
承安5(1175)年 4月7日 ●従五位上 (元服:9歳) |
文治2(1186)年 12月15日 右近衞少将 (20歳) |
治承2(1178)年 正月5日 ●正五位下 (12歳) |
文治4(1188)年 正月24日 右近衞中将 (22歳) |
文治3(1187)年 正月7日 ●従四位下 (21歳) |
建久元(1190)年 6月19日 ●従三位 (24歳) ※初叙から15年 |
| 藤原家実 | 藤原基通 一男 |
建久元(1190)年 12月22日 ●正五位下 (元服:12歳) |
建久元(1190)年 12月25日 右近衞少将 (12歳) |
建久2(1191)年 6月4日 ●従四位下 (13歳) |
建久2(1191)年 2月5日 右近衞中将 (13歳) 【五位中将】 |
建久2(1191)年 6月4日 ●従四位下 (13歳) |
建久2(1191)年 12月28日 ●従三位 (13歳) ※初叙から1年 |
| 藤原道経 | 藤原基通 二男 |
建久6(1195)年 12月16日 ●従五位上 (元服:12歳) |
建久8(1197)年 12月15日 右近衞権少将 (14歳) |
建久8(1197)年 12月15日 ●正五位下 (14歳) |
建久9(1198)年 12月9日 左近衞権中将 (15歳) 【五位中将】 |
建久10(1199)年 正月5日 ●従四位下 (16歳) |
正治元(1199)年 6月23日 ●従三位 (16歳) ※初叙から4年 |
| 藤原兼基 | 藤原基通 三男 |
建久8(1197)年 12月30日 ●従五位上 (元服:13歳) |
正治元(1199)年 12月29日 右近衞権中将 (15歳) 【五位中将】 |
建久9(1198)年 2月28日 ●正五位下 (14歳) |
元久元(1204)年 3月6日 権中納言 (20歳) |
正治元(1199)年 11月27日 ●従四位下 (15歳) |
正治2(1200)年 10月26日 ●従三位 (16歳) ※初叙から3年 |
| 藤原道家 | 藤原良通 息 |
建仁3(1203)年 2月13日 ●正五位下 (元服:11歳) |
建仁3(1203)年 4月25日 左近衞少将 (11歳) |
建仁3(1203)年 12月20日 ●従四位下 (11歳) |
建仁3(1203)年 7月8日 左近衞中将 (11歳) 【五位中将】 |
建仁3(1203)年 12月20日 ●従四位下 (11歳) |
元久2(1205)年 正月19日 ●従三位 (13歳) ※初叙から2年 |
年が明けて建久9(1198)年正月2日、兼実は「東札到来、此事聞驚也、誰言之」(『玉葉』建久九年正月二日条)と驚きを隠せなかった。「東札」は京都から何らかの情報が鎌倉へ流れ、その情報に対して頼朝が兼実に送った書状である。兼実は「此事」に非常に驚き、一体誰が洩らしたのだと記しているが、この情報は後鳥羽天皇の譲位に関するものだろう。
兼実は関白を退いたとはいえ、朝廷内には蔵人長兼をはじめとする兼実与党が実務官として活躍しており、前年12月前半頃にはすでに譲位案件は把握していたであろうが、宮中でもこの機微を知る者は限られた人々であったろう。事実、兼実に「或人云、可有譲位云々、明後日許、幸大炊殿、以閑院可為新帝宮云々、一昨日東脚到来、其後事一定」(『玉葉』建久九年正月六日条)という譲位の詳細情報が伝えられたのは正月6日の事であった。また、兼実邸に出仕する藤原定家ですら「青侍等説云、可有譲位云々、辰時許或人告云、此条実説也、来九日行幸大炊殿、十三日可有伝国」(『明月記』建久九年正月七日条)と、情報に接したのは翌7日であり、蔵人長兼が「譲位事已露顕」(『三長記』建久九年正月七日条)と、譲位の件が明るみになってしまった、というニュアンスで記したのも同日である。このような中で、頼朝は昨年半ばには譲位の情報を入手し、「幼主不甘心之由、東方頻雖令申」(『玉葉』建久九年正月七日条)という手紙を京都に数通送り届けている。はじめて兼実に届いたのは正月2日の「東札」であり、前年12月20日前後に鎌倉を発したものであろう。
譲位の件を頼朝へ伝えた情報源は兼実ではないことは明らかだが、能保入道も亡き今、情報を鎌倉に流した人物については推測するほかないものの、家司中原広元と親しい権大納言通親の可能性が高いだろう。この頃は儲君は決定しておらず、「或云、二三宮之間践祚、当今王子立坊、或云、直皇子践祚」(『玉葉』建久九年正月六日条)と、七条院の推す高倉院二宮(守貞親王。後鳥羽天皇実兄)もしくは三宮(惟明親王。後鳥羽天皇異母弟で天皇母七条院の猶子)が践祚して今上の皇子(能円孫、信清孫、範季孫)の何れかが立太子する、という人もあれば、今上の皇子がそのまま践祚すると言う人もいたほど譲位の情報は錯綜していた。通親は自分の養女とした源在子(妻・刑部卿三位の連子)が産んだ今上一宮を推しており、頼朝には譲位の情報とともにその旨を伝えていたのだろう。
通親が擁する今上一宮は「桑門之外孫」という大きな弱みを持っていた。しかし、七条院が擁する皇子たちは年齢・資質ともに儲君に申し分はなかったが、すべて前代高倉院系という強大な壁があったのである。天皇に問題がなくその皇子にも問題がないにも関わらず、前代の系統に儲君を求めることは前例がなく、こうした例を踏まえれば、今上一宮または三宮(通親室範子の従妹・重子所生)がもっとも儲君として相応しいことになる。また、当然譲位する天皇の意思が最も重要であり、自らの皇子が何人もいる中で、はじめから実弟守貞や義弟惟明を推すこと は念頭になかったであろう。今上一宮と三宮についても、三宮はまだ誕生間もない上に、「源博陸」の異称をもつ通親とは直接的な血縁関係がないとすれば、通親が養女所生の今上一宮を儲君として推すのは自然の流れであろう。
藤原能兼 +―藤原範兼――+=藤原範季――+―藤原範茂
(式部少輔) |(刑部卿) |(木工頭) |(参議)
∥ | | |
∥―――――+―藤原範季 +―藤原範光 +――――――藤原重子
高階為賢―女子 (木工頭) |(権中納言) | (修明門院)
| | ∥
| 能円 +=源範頼 ∥
|(法勝寺執行) (参河守) ∥
| ∥ ∥ 【範季孫】
| ∥―――――――源在子 ∥―――――――――守成親王(順徳天皇)
| ∥ (承明門院)∥
+―藤原範子 ∥ ∥ 【範兼孫】
|(刑部卿三位) ∥――――――――――――――為仁王(土御門天皇)
| ∥ ∥
| 藤原頼実 ∥ ∥
|(太政大臣) ∥ ∥
| ∥ ∥ ∥
+―藤原兼子 ∥ ∥
(後鳥羽天皇乳母)∥ ∥
∥ ∥
藤原信輔―――藤原信隆 +―藤原信清―――――――――――――坊門局
(右京大夫) (修理大夫)|(内大臣) ∥ ∥ ∥
∥ | ∥ ∥ ∥ 【信清孫】
∥――――+―藤原殖子 ∥ ∥ ∥―――――長仁親王(道助入道親王)
+―藤原基頼―――藤原通基―+―女子 (七条院) ∥ ∥ ∥
|(中務大輔) (左京大夫)| ∥ ∥ ∥ ∥
| | ∥ ∥ ∥ ∥
| | ∥―――――+―尊成親王(後鳥羽天皇)
| | ∥ | ∥
| | ∥ |【二宮】 ∥
| | 高倉天皇 +―守貞親王 ∥
| | ∥ (後高倉院)∥
| | ∥ ∥ ∥ 【三宮】
| | ∥――――――――――――――――――――――惟明親王(聖円入道親王)
| | ∥ ∥ ∥ (三品)
| | 平義範――――平範子 ∥ ∥
| |(伊豆守) (少将局) ∥ ∥
| | ∥ ∥
| +―藤原基家 ∥―――――――――茂仁親王(後堀河天皇)
| (権中納言) ∥ ∥ ∥
| ∥ ∥ ∥ ∥
| ∥――――――――――――――藤原陳子 ∥ ∥――――秀仁親王(四条天皇)
| ∥ (准三后) ∥ ∥
| ∥ ∥ ∥
| 平頼盛――――女子 ∥―――――――――昇子内親王
| (権大納言) ∥ ∥ (春華門院)
| ∥ ∥
| +―――――――――――――――――――――藤原任子 ∥
| | (宜秋門院)∥
| | ∥
| 藤原兼実―+―藤原良経 ∥
| (関白) (関白) ∥
| ∥ ∥
+―藤原通重―――藤原能保 ∥――――――藤原道家――+―――――――――――藤原竴子
(丹波守) (権中納言) ∥ (関白) | (藻璧門院)
∥ ∥ |
∥――――+―女子 +―藤原頼経
∥ | (権大納言)
∥ | ∥
源義朝――+―女子 +―藤原高能 ∥
(左馬頭) | (参議) ∥
| ∥
+―源頼朝――――源頼家――――――――――――女子
(権大納言) (右衛門督) (竹御所)
また、兼実のもとには、正月4日にも「頼朝卿札到来、被免造作者、移徒又可恐、早可遂云々、可有中宮入内之由雖奏聞、依此仰不可奏」(『玉葉』建久九年正月四日条)とあるように、頼朝からの書状が届けられており、閑院殿修築が遅延(兼実家司長兼が監督人)していることにつき、新天皇の移徒(以閑院可為新帝宮)への影響を考えて早々に行うよう要請するとともに、頼朝が奏聞していた八条院居住の中宮任子の入内については、譲位が行われる状況となった上は奏上すべからずと告げている。このように、頼朝は関白を退いたのちの兼実とも連絡を取り合い、内裏を離れている中宮任子の入内まで奏上しており、頼朝は建久九年においても兼実との協調体制を維持していたのである。
正月7日の「白馬節会」に際して、兼実は内弁として節会を差配する大宮大納言実宗と話した際、実宗は「右大臣叙一位、定勤内弁、立叙列歟之由、世以存之、而無出仕之条、還又為奇云々、譲位事、譲国等事、自元不及沙汰」と、右大臣兼雅の懈怠を批判するとともに、朝廷に頻繁に届けられた頼朝からの「幼主不甘心之由、東方頻雖令申」(『玉葉』建久九年正月七日条)について、天皇が「綸旨懇切」し、近臣・大江公朝法師を鎌倉に下して「被仰子細」したため、頼朝も「憖承諾申」と、しぶしぶ承諾の意を示したと語った(『玉葉』建久九年正月七日条)。
この子細には天皇の意思としては、儲君を御乳母三位範子の孫である皇子(能円孫)と考えていることが含まれていたのだろう。頼朝が承諾(関東許可)したのち、「敢取孔子賦、又行御占、皆以能円孫為吉兆云々、仍被一定了」と、占卜の結果によって「皆以能円孫為吉兆云」といい、「此旨以飛脚、被仰関東了」した(『玉葉』建久九年正月七日条)という。そして「不待彼帰来、来十一日可有可有伝国之事」というように、頼朝の返答を待たず、正月11日に「伝国之事」を行うことを決定した。
こうした話を聞いた兼実は「外祖猶必可補大臣歟、彼時、又内府可被収公大臣之条、無異議、於此等之次第者、更不足為愁、猶恐只濫刑也」と、外祖父は必ず大臣に補される慣例のため、権大納言通親がその地位を確立すれば任大臣により内大臣となることが想定され、その際には内府良経は大臣を辞することを拒めないであろうと愁う(『玉葉』建久九年正月七日条)。
さらに実宗は「桑門之外孫、曾無例、而通親卿為振外祖父之威、嫁彼外祖母了故也、二三歳践祚、為不吉例之由申出云々、信清孫三歳、範季孫二歳」(『玉葉』建久九年正月七日条)と、僧侶の孫が帝位についた例はなく、さらに二、三歳の幼帝も不吉であると天皇に申し出るとともに「而博陸又饗応、尤可被忌例、不可及外祖之沙汰之由、再三被申行、是則其息新侍従兼基為桑門之孫、世人為奇異、為休其嘲忘帝者之瑕瑾、同通親謀」と、関白基通の通親への阿りは最も忌例であり、通親が外祖父として振る舞わぬよう天皇に再三に渡って申し上げたという。建久8(1197)年12月30日の小除目で基通の子息・兼基は従五位上・侍従に叙任されたが、彼は僧侶(法眼最舜)を外祖父とし、この叙任は奇異であった。これらは僧侶が外祖父に持つ兼基への「嘲」を霞ませる小細工であり、今上一宮の「瑕瑾(外祖父が僧侶の能円)」をないものとする通親の策謀と同様であると批判する。
源師房 +―源雅実―――――――――――源顕通――――源雅通―――源通親
(左大臣) |(太政大臣) (権大納言) (内大臣) (内大臣)
∥ |
∥―――――源顕房――+―源国信―――――――――+―源信時――――源顕信―――源顕子
∥ (右大臣) |(権中納言) |(越後守) (治部卿) ∥
∥ | | ∥
∥ | +―源信子 ∥――――――藤原家実
∥ | | ∥ ∥ (関白)
∥ | | ∥――――――藤原基実――藤原基通
∥ +――――――源師子 | ∥ (摂政) (関白)
∥ ∥ | ∥ ∥
∥ ∥――――――藤原忠通――――藤原兼実 ∥――――+―藤原兼基
+―藤原尊子 ∥ |(関白) (関白) ∥ |(大納言)
| ∥ | ∥ ∥ |
| ∥ | ∥――――――藤原基房 ∥ +―藤原基教
藤原道長―+―藤原頼通――藤原師実―――藤原師通――藤原忠実 +―源俊子 (関白) ∥ |(右近衞中将)
(関白) |(関白) (関白) (関白) (関白) ∥ |
| ∥ +―円忠
+―藤原長家――藤原忠家―+―藤原俊忠――藤原俊成――――藤原定家 ∥ |(園城寺長吏)
(民部卿) (大納言) |(権中納言)(皇太后宮大夫)(権中納言) ∥ |
| ∥ +―円静
+―藤原顕良――栄全――――+―法眼最舜―――――――――女子 |(園城寺長吏)
(民部少輔)(権少僧都) |(法勝寺執行) (少将局) |
| +―円基
+―最尊 |(天台座主)
(三位) |
+―法印仁澄
(清水)
兼実はこの関白基通と通親の「謀」について、「愚哉、以小人入魂、為小童之才学、国家之滅亡挙足可待歟、於占卜之吉兆、及孔子賦等之條者、如此之事、只依根元之邪正、有霊告之真偽也」と、「小人」同士の繋がりを痛烈に扱き下ろし、占卜の結果にも疑問を呈した(『玉葉』建久九年正月七日条)。結果ありきの偽の占卜であろうという含みが感じられる。しかし、いくら不満を並べたところで、すでに実権を喪った兼実には為す術はなく、「通親、忽補後院別当、禁裏仙洞可在掌中歟、彼卿日来猶執国柄、世称源博陸、又謂土御門」(『玉葉』建久九年正月七日条)と、正月5日に後院庁別当に定まり、新帝も新院も掌中に収めるであろう通親は、すでに天下の権を掌握して「源博陸」と称され、さらに彼の里邸「土御門(ツチミカド=土帝)」とも異称されたという。「土帝」通親は、兼実をして「今仮外祖之号、独歩天下之躰、只可以目歟」(『玉葉』建久九年正月七日条)とまで言わしめる権勢を振るっていたのであった。
新帝践祚に当たっては「将軍両人、必可供奉」ということもあり、兼実嫡子・内大臣良経は「仍内大臣被停左大将了」と、兼帯していた左近衞大将を辞することを示した(『玉葉』建久九年正月七日条)。なお後任の左大将は「明日、中納言中将可補」と、基通の嫡子・権中納言家実が補されることが決定している。また、「可被行任大臣、右大将昇丞相、奪其将軍、通親可拝」と、通親は権大納言頼実を大臣に昇らせる一方で、彼の右大将を解いて自分が拝領するのだろうという噂も立った(『玉葉』建久九年正月七日条)。藤原定家も「伝国十一日云々、儲君必定能円孫一宮也、可為源大納言外孫云々、依帝王祖禰弥可任大臣云々、頼実卿又為令去大将任之」(『明月記』建久九年正月七日条)と頼実の右大将辞任の噂を述べている。また、ある人が言うには「或云、右府可勝太政大臣、事次可有立坊、七条院之内如滅火」(『明月記』建久九年正月七日条)と、右大臣兼雅が太政大臣に転じる噂もあり、さらに今上一宮の立坊の噂により、高倉院二宮守貞親王(藤原信清女子・坊門局所生)または、高倉院三宮惟明親王(平範子所生・七条院猶子)を推していた七条院内は火の消えたような体であったという。
なおこの日、「今日東札到来、其詞快然、還為恐」(『玉葉』建久九年正月七日条)と、兼実のもとに頼朝からの手紙が届く。文面は「快然」たるものであったようで、幼帝の践祚を幾度にわたって反対していた頼朝の言葉とは思えなかったのだろう。兼実は頼朝の言葉に気味悪さを感じているようであるが、すでに後鳥羽天皇の内意を受けて「憖承諾申」(『玉葉』建久九年正月七日条)を示した今は、譲位に関する不満を記すことはなかったのだろう。また、この書状は日数的にみて、頼朝嫡子・頼家が「従五位上」に叙され「右近衞権少将」に任じられた12月15日の小除目(『公卿補任』)が鎌倉に届けられたのちに記されたと思われることから、そのことも影響しているのではなかろうか。
正月8日、関白子息の中納言中将家実が参陣し、良経が辞せんとする左大将につき「奉可任大将之仰云々、来十九日可儲饗」(『玉葉』建久九年正月八日条)と、正式に任大将の宣旨を受け、19日の就任が決定する。ただ、良経は「大将事、雖有解退之志、依不出仕、不能奉辞状之由」(『玉葉』建久九年正月九日条)であると権中納言光雅に述べているように、「而籠居之間、奉解状之條有恐、若有天許者、身雖不出仕、欲献状、又雖不進解状、只以詞可申者、可付職事、又只可収公歟、条々欲従勅命者」と、籠居の身で左大将の辞状を奉じることは憚られるが、もし勅許があればみずからは出仕せずに辞状を献じ、また辞状を出さずに職事を通じて辞意を伝えるともいい、ただ勅命を以て左大将を停止することも甘んじて拝受することも述べている。兼実は「只依勅勘之、重有此停任歟、然者、弥可成恐也」と良経の左大将は「勅勘」によって停止される可能性に言及し、そうであれば恐ろしいことであると述べている。
藤原定家は風聞として「明夕行幸大炊殿、十一日暁行幸大内、其日譲位、其夜御幸大炊殿、廿一日初度御幸」(『明月記』建久九年正月八日条)という情報を載せており、具体的な内容がすでに明らかにされていた。「儲君第一皇子、範子内親王高倉帝一女坊門院必定可有立后、為同輿」と、想定通りに能円孫の一宮が「儲君」となり、伯母の範子内親王の立后が「必定」とする(『明月記』建久九年正月八日条)。また、「可有任大臣、或云、内大臣殿可被任太政大臣、為絶望」と、内大臣良経を太政大臣とする(つまり摂関への道を閉ざす)という噂もあった。
正月9日夜、天皇は予定通り大内裏から大炊御門邸に内侍所を伴って行幸するが(『百錬抄』)、これは11日の譲位のための行幸で、「即以此内裏可為新帝皇居之故也」(『三長記』建久九年正月九日条)という。これ以前に「殿下、左大臣、右大臣、土御門大納言、民部卿別当等」が鬼間で「予議定譲位事、親王宣下、依光孝天皇例、不可被宣下」と一宮への親王宣下については「光孝天皇例(光仁天皇の誤り)」を以て行わないと決定。「無親王宣旨立坊事」(『百錬抄』)であった。また、「御名字事同議定、可被用為仁云々、式部大輔光範卿撰進」(『三長記』建久九年正月九日条)と、一宮の名前を「為仁」とする旨を議定。このことは翌10日に「或人云、一宮御名、為仁云々、光範卿択申」(『三長記』建久九年正月十日条)とあるように、「譲位於第一皇子、春秋四歳、御名為仁」(『百錬抄』)と定められた。
この日、兼実出仕の左少将定家も参内の際に顔見知りと思われる兵衛府「吉上」と言葉を交わしているが、彼から「明後日可参行啓」と言われた定家はカチンときて、「行啓トハ何事ゾ」と問い返した。兵衛府吉上は「東宮行啓也」と答えるが、定家はさらに「東宮トハ誰人事乎」と怒りを含んで問い返すと、吉上も負けじと「明日可立給也」と答える。定家は「然者、東宮行啓近衞司不参歟、兵衛司可参歟、慥問外記可来」と、左少将たる自分が東宮とやらの行啓を聞いていないということは、近衞司は東宮行啓に不参であるが、吉上所属の兵衛司は参加するということか、この辺りを外記に問い合わせてこい、と指示している(『明月記』建久九年正月九日条)。定家は兵衛府吉上の言う「東宮」については一宮為仁王であることは重々承知していながら、兼実が敵視する通親卿所縁の話であることから怒りを覚えたのであろう。その後、定家は故障を理由に屋敷へ帰ってしまうが、屋敷を外記が訪れ、兵衛府吉上の「申僻事了、全無東宮之儀、明後日御譲位可参者」ということであった。定家は11日の譲位の席へ参じることは承了するが、外記も譲位がどこで行われるかの情報を持たずに定家邸へ来たため、定家の「問其所」の確認のため再度外記局まで走り帰り、再度定家邸を訪問して「大炊殿也」と返答している(『明月記』建久九年正月九日条)。
正月11日、「此日譲位也、自大炊御門被渡剣璽於閑院」(『玉葉』建久九年正月十一日条)と、戌の刻に譲位のために剣璽が大炊御門殿から閑院殿へと遷された(『百錬抄』)。関白、右大将以下の公卿衆が供奉している。為仁王は今朝まず関白基通邸に渡御しており、ここから閑院へと遷った(『玉葉』建久九年正月十一日条)。なお、この日は新院御所となる二条御所上棟の日であったが、「工興工事闘諍、及刃傷殺害云々、其血流剣璽之幸路、事甚不吉」(『玉葉』建久九年正月十一日条)という事件が起こっている。これは定家も「闘乱刃傷或及死門、或舁出之間、剣璽之料作路血先流云々、又作路之間、闘乱刃傷」(『明月記』建久九年正月十一日条)と記録している。これは結局「三人被疵一人死了云々、縁者下人等喚競争、如陣作時声」という慶日にそぐわない物騒な事件であった。また蔵人長兼も九日の陣定で決定した事柄について「以為仁皇子為皇太子、即可有譲位云々、是光仁之例云々、弓削法皇誰人乎、如何如何」(『三長記』建久九年正月十一日条)と、もし光仁即位の例に倣っているといのであれば、失脚した「弓削法皇」はいったい誰にあたるのだ(我が主の兼実か)と痛烈に批判。少将定家も「此諱光範卿撰進云々、為人之音、如何如何、非為身事歟、尤可忌歟、其反音又院音也、尤可憚歟」(『明月記』建久九年正月十一日条)と、その諱の付け方にも強く反発する。「為人」という音が物事を全うできない事を想起させるとともに、反音が「院」という音韻であることから「為院」となり、甚だ憚りありということであろう。これらは兼実をはじめ、長兼、定家といういずれも親兼実派の意見であるが、この他にも為仁王(土御門天皇)の出自への疑問、ならびに践祚日の穢を感じる公卿はいたのではなかろうか。
幼帝践祚とともに基通は関白を改め摂政となった(『百錬抄』)。その後、殿上人や女官らの定めなどが行われ、新院においても院殿上人や院司など院庁諸役定められている。院別当は権大納言通親を筆頭(執事別当)に、権中納言忠経、右衛門督信清、左中将藤原公経と頭中将源通宗が任じられ、後日、高階経仲と藤原資実も追加された(『三長記』建久九年正月十一日条)。
●後鳥羽院司
| 別当 | 源通親 (権大納言) |
藤原忠経 (権中納言) |
藤原信清 (右衛門督) |
藤原公経 (蔵人頭、 左中将) |
源通宗 (蔵人頭、 左中将) |
高階経仲 (内蔵頭) |
藤原資実 (右中弁) ※摂政基通家司 |
藤原伊輔 【追加】 |
藤原隆衡 【追加】 |
| 判官代 | 藤原範光 (丹後守) |
藤原長房 | 藤原親綱 | 藤原信綱 | 藤原忠綱 (左近将監) |
源仲清 | 藤原光親 【追加】 ※摂政基通家司 |
||
| 主典代 | 中原政経 〔年預〕 (左衛門尉) |
安倍資兼 (右衛門志) |
|||||||
| 蔵人 | 藤原康業 (左衛門尉) |
源仲家 (中務丞) |
源家長 | 橘以忠 | |||||
| 非蔵人 | 藤原重輔 (一臈判官) |
源重定 |
正月20日、「太上皇尊号詔書」が奉じられ、右大臣兼雅が参陣し、頭中将通宗が尊号を宣下(『三長記』建久九年正月廿日条)。21日には院は生母の七条院殖子の御所である三条殿へ初御幸した(『三長記』建久九年正月廿一日条)。正月30日には除目が行われ、頼朝嫡子の源頼家は讃岐権介に任じられる(『三長記』建久九年正月卅日条)。また同日、頼朝の郎従である惟宗忠久も「左衛門尉惟宗忠久」とあるように左衛門尉に任じられている(『三長記』建久九年正月卅日条)。関白基通被官でもある忠久はその所縁を以って任官したものか。忠久の挙任も当然頼朝が推挙していたはずであり、通親を経由しての奏上であったのだろう。
その後の関東および朝廷の様子はうかがえないが、3月3日の「今日天皇春秋四歳、即位之日也」(『三長記』建久九年三月三日条)に際して、鎌倉家家司の「兵庫頭広元、位袍、巡方」が役人として儀式に加わっており、頼朝は通親とも良好な関係が窺える。
このように、事実上の天皇外祖父の地位を手に入れ、順風満帆の通親であったが、5月6日には嫡子の参議通宗が三十一歳の若さで急死するという事件が起こる(『尊卑分脈』第六)。新院別当ならびに参議と順調に昇進を重ねていた中での悲劇であった。また、9月17日には頼朝の実甥「高能卿ウセニキ」(『愚管抄』巻六)という悲劇も起こった。こちらもまだ二十三歳という若さでの卒去であった。高能の死去により頼朝妹と直接血縁のある公卿家は九条家(藤原兼実嫡子良経の子どもたち)と西園寺家(藤原公経の子たち)、そして花山院家(左大臣兼雅の子・忠経の子どもたち)のみでいずれも幼児であった。能保の女婿である藤原公経、藤原忠経の両者は院庁別当として執事別当通親の影響下にあり、内府良経は逼塞の身にあった。また高能の異母弟である信能(不明)、実雅(三歳)もまた幼少であり、一条藤原家は堂上での存在感を失うこととなる。なお、信能は承元5(1211)年閏正月28日に順徳天皇中宮藤原立子(良経女子)の中宮権亮として出仕していることから、高能亡き後の一条家は良経室(藤原能保女子)の縁を以って九条家の庇護下に入ったと推測される。
源為義――――源義朝 +―源頼朝―――――源頼家
(左衛門大尉)(左馬頭)|(前右大将) (右少将)
∥ |
∥ | 藤原基房――――女子
∥ |(入道関白) ∥―――――――――――藤原頼氏【二歳】
∥ | ∥
∥―――+―女子 +―藤原高能
藤原季範―――女子 ∥ |(参議)∥――――――――藤原能氏【幼少】
(熱田大宮司) ∥ | ∥∥ ∥
∥ | ∥∥ 糟屋有季女
∥ | ∥∥
∥ | ∥∥――――――――――藤原行能【幼少】
∥ | ∥∥
∥ | ∥藤原兼光女
∥ | ∥
∥ | ∥―――――――――――藤原能継【幼少】
∥ | ∥
∥ | 藤原隆季女
∥ | 順徳天皇
∥ | ∥――――――――仲恭天皇
∥ | ∥
∥―――――+―女子 +―藤原立子【八歳】
藤原能保 | ∥ |
(権中納言) | ∥―――――――――+―藤原道家【七歳】
| ∥ |
| 藤原良経【三十歳】 +―藤原教家【六歳】
|(内大臣)
|
+―藤原全子 +―藤原掄子【八歳】
| ∥ |
| ∥―――――――――+―藤原実氏【六歳】
| ∥
| 藤原公経【二十九歳】
|(蔵人頭)
|
+―藤原保子
∥―――――――――――藤原忠頼【一歳】
∥
藤原忠雅―+―藤原兼雅――――藤原忠経【二十六歳】
(太政大臣)|(左大臣) (権中納言)
|
+―女子
∥―――――――源通宗
∥ (参議)
源通親
(権大納言)
建久9(1199)年の頼朝の動向は『吾妻鏡』も闕のため不明瞭だが、頼朝は「猶次ノムスメヲ具シテノボラン」(『愚管抄』巻六)と、二女の乙姫を入内させるために上洛する計画であったことがわかる。新帝践祚ののちの政道に関し、兼実や通親との対談といった政治的な理由も大きかったと思われる。
また、すでに征夷大将軍を辞したとはいえ、頼朝の軍事指揮権者としての立場は揺らいでおらず、建久9(1198)年11月1日に興福寺衆徒が頼朝へ送った「和泉国司(平親信)」と父・親宗の処罰の要求、強訴決行などを条々にした文書に対し、頼朝は「誅伏衆徒之後、天下静謐之今、所焼失之東大寺被改作候、被興亡廃之基跡了、衆徒且可廻仏法修学之慶、依被国司狼藉時、衆徒振春日神輿、擬群参之条、可謂返逆候歟」と手厳しく批判。「御禊大嘗会者一代一度嘉礼、国家福祐之大基候、随則期日近々、厳重異他、縦雖有可訴申之事、退可左右候歟」と(下らぬ)強訴を起こして国家の大慶たる大嘗会を妨害することは断じて許さないと強く牽制。「朝家大礼之時、依少事欲成違乱、非朝敵哉、頼朝奉勅命追討凶党之後、雖為武士之身、興隆仏法之志甚深也、仍雖不存殺罪之計候、憖禀弓嚢之芸、事君之日、何不鎮背聖化之事候哉、衆徒企参洛候者、且差遣前駈之武士可相禦候、猶不拘皇威、旋及訴逆者、頼朝雖自身可馳参候歟、相禦之間、衆徒等之及合戦者、不慮之外殺罪出来候歟、抑高能卿早世之間、暫殺生(後闕)」(『興福寺牒状』「大日本史料」第四編)と、秩序を乱す輩は遠慮なく武士を派遣して防ぐと宣べ、高能卿の死により暫く殺生を断っているが、不慮の殺傷はおこることを覚悟しておくようにという姿勢を興福寺に示したのである。すでに京都には大嘗会に伴う軍勢が集結しており、この返牒を受け取った興福寺は戦慄して「弥衆徒上洛停了」(『古記部類 秋寺社之事』「大日本史料」第四編)と、強訴を取りやめている。兼実失脚のために通親に利用された上、頼朝自身も朝廷に対する威勢を失ったというような論調が見られるが、決してそのようなことはなく、頼朝は通親との連携のもと、かつて後白河院ですら手を焼いた興福寺を手紙一通で黙らせるほど強烈な威勢が健在だったのである。
11月21日、大嘗会前日の叙位で「院御給」により頼家は正五位下に叙された。後鳥羽院と頼朝との間には直接的な関わりはなく、院庁執事別当たる通親の推挙があったのかもしれない。そして翌22日、今上(土御門天皇)の大嘗会が行われた。
京都で大嘗会が催され、新帝の御代がはじまろうとしていた矢先、鎌倉では前代未聞の大事件が起こっていた。「去建久九年、重成法師新造之、遂供養之日、為結縁之、故将軍家渡御、及還路有御落馬、不経幾程薨給畢」(『吾妻鏡』建暦二年二月廿八日条)と、稲毛重成法師が亡妻(北条時政娘)の追善供養のために相模川に橋を架けた際の供養に参列した頼朝が帰途に落馬して程なく薨じたというのである。橋が完成したのは「同九十二、稲毛重成入道為亡妻追賞建立相模河橋」(『尊卑分脈』)とあるように、建久9(1198)年12月のことであった。その後、追善供養が行われ、頼朝が落馬したのは「同廿七、遂供養仍為結縁右大将被相向之處、於帰路落馬受病気了」(『尊卑分脈』)とある通り、12月27日のことであった。
頼朝は「前右大将卿依飲水重病」(『猪隈関白記』建久十年正月十八日条)であったといい、以前より「飲水重病(重い糖尿病)」の噂は京都まで伝わっていたようである。糖尿病に伴うものかは不明だが、幾度にわたり「御歯労」(『吾妻鏡』建久五年八月廿二日条、九月廿二日条、建久六年八月十九日条)が見られるように、齲歯または歯周炎も発症していた。建久七年から建久十年正月の頼朝入道入滅月まで『吾妻鏡』は闕記となっており、この頃の頼朝の様子を具体的に窺うことはできないが、なんらかの糖尿病性の症状が出ていた可能性はあろう。「落馬」は低血糖による心神喪失であった可能性も考えられよう。
建暦2(1212)年10月11日、三善善信入道が述懐している中で、
と見えるように、頼朝は12月中にはすでに「御病中」であった。三善善信入道が霊夢を報告したのが、相模橋供養前か後かは定かではないが、橋供養が12月27日、この年の12月晦日は29日であることから、相模川から鎌倉への帰還を考えると、善信入道が頼朝に伝えたのは供養以前と見るのが妥当だろう。つまり、頼朝の病状は以前から悪化していたのである。善信入道の報告に、頼朝は病気平癒のあかつきには「精舎」の「堂舎造営」を誓っている。相模川の橋供養はこうした病状をおして参じたものだったとみられる。その無理が祟った結果、病状はますます悪化してしまったということではなかろうか。
翌建久10(1199)年正月、頼朝は「九條殿(兼実)」に宛てて「今年心シヅカニノボリテ、世ノ事沙汰セント思ヒタリケリ、万ノ事存ノ外ニ候」(『愚管抄』巻六)という書状を送っている。頼朝は今年は落ち着いて(帝位も定まり世情も物騒がしさもなくという意か)上洛し、(兼実も含めてか)「世ノ事沙汰セン」と思っていたが、「万ノ事存ノ外ニ候(万事思い通りにならないものだ)」と伝えている。自らの意見を伝えていることから、落馬後も頼朝の意識ははっきりしており、年が明けてからも自らの状況を客観的に捉えられる状態にあった。つまり、脳出血等による高次脳機能障害は起こっていない。
しかし病態は重く、十日余りの闘病の末、正月11日に「前右大将依所労獲麟」(『明月記』建久十年正月十八日条)って出家を遂げる。再起が叶わないことを認識した措置か。そして、正月13日、頼朝入道は入滅する。五十三歳であった。
頼朝出家の風聞は正月18日に権大納言家実の耳に入っている(『猪隈関白記』建久十年正月十八日条)。また、18日の「早旦閭巷説」で「前右大将依所労獲麟、去十一日出家之由、以飛脚夜前被申院、仍以公澄為御使、夜中可下向由被仰、父公朝法師又為宣陽門院御使相共馳下云々、朝家大事何事過之哉、怖畏逼迫之世歟、又或説云、已早世云々、午時許参角殿謁女房、又参新御所、於不吉必然歟、不聞分存亡之実、蓮華王院御幸止了」(『明月記』建久十年正月十八日条)と、18日の蓮華王院行幸が予定されていたが俄に中止となる。御所には17日夜には頼朝の出家だけではなく、入滅の報告があったとみられ(鎌倉から通親への書状か。ただし通親は公的にはこれを奏聞しなかったとする)、行幸の中止は「依頼朝卿事無御幸、被止呪師猿楽等」(『百錬抄』)という「頼朝卿事(入滅)」によるものである。この報告は院にも奏され、院はただちに大江公澄を院使に、その父で頼朝昵懇の大江公朝法師を宣陽門院の女院使として、夜のうちに鎌倉へ馳せ下した。定家はまだ重病と出家の報告のみを得ていて(関白基通嫡子・家実も出家の風聞のみ聞いており、卒去の報は20日である)、頼朝入道入滅は、御所および院内の一部のみが把握する事実であったようである。しかし、定家はどこからか頼朝がすでに卒去しているという風聞を聞き、午刻に御所角殿に参じて女房に謁し、さらに新御所にも参じて情報を集めたところ、頼朝入道入滅はどうやら真実のようだという結論に達している。
京都では、頼朝入滅の報告から三日後の正月20日、「前将軍去十一日出家、十三日入滅、大略頓病歟、未時許除目、頭権大夫承仰内覧、殿下即参内、可書下由有院宣」(『明月記』建久十年正月廿日条)と、関白基通に「臨時除目」の内覧を経て大間書の執筆を命じる院宣が下された。そして、「其後隆保朝臣参入、申必定入滅由、飛脚到来云々、除目此事以前之由有沙汰」(『明月記』建久十年正月廿日条)と、頼朝の従弟である左馬頭源隆保から正式に頼朝入道入滅が報告された。この除目には頼朝嫡子・頼家の任官が含まれているが、除目は報告前だったという体が採られることで、除目自体には問題がないとされたようである。
■建久十年正月二十日臨時除目(『明月記』『業資王記』)
| 官途 | 名前 | 備考1 | 備考2 |
| 右近衞大将 | 源通親 | 後鳥羽院別当。同日、右大将頼実が辞状を上表している。 | |
| 左近衞中将 | 源頼家 | 関東息 | |
| 少納言 | 藤原忠明 | 故中山内府(藤原忠親)息 | |
| 内蔵頭 | 藤原仲経 | 伯耆守如元 | 後鳥羽院別当。別当高階経仲の後任 |
| 造東大寺長官 | 藤原資実 | 後鳥羽院別当。摂政基通家司 |
しかし定家は「今朝早々右大将上表使成定朝臣、少納言忠明、内蔵頭仲経兼、右近大将通親、中将頼家、造東大寺長官資実、遭喪之人、本官猶以服解、今聞薨由被行任官、頗背人倫之儀歟、春除目以前、臨時除目頗珍事歟、後聞、内覧極僻事也、此除目并十四日僧事不内覧」(『明月記』建久十年正月廿日条)とあるように、本来遭喪の人は服解すべきであるにも拘わらず、いま頼朝薨去の聞が来たのに(頼朝子息頼家の)任官が行われたことは頗る人倫の道に背くことであると批判。さらに春除目以前に臨時除目が行われることも極めて珍事であり、関白基通に至ってはこの除目も僧事も内覧していない言語道断の所行に激怒している。
この臨時除目は頼朝入道入滅が公表される前に、通親が主導的立場となって急遽行われたとみられ、本来は春除目後に行われる予定であった臨時除目と、予定になかった頼家の除目を加えて行われたのであろう。この日「右丞相被献辞右近大将之状」(『猪隈関白記』建久十年正月廿日条)とある通り、右大臣頼実から右近衞大将の辞状が上表され、通親は即日新右近衞大将(兼右馬寮御監)となった(『公卿補任』)。この右近衞大将は任大臣の布石であり、同時に頼家は五位のまま左近衞中将に任じられた。これは摂関家子息と同等の「五位中将」の待遇を以っての任官であった。通親が頼朝との関係を重視していたこととともに、頼朝亡き後、その膨大な家子・郎従(いわゆる御家人)の動揺が再乱の発生へとつながることを危惧し、「安穏」の世を担保する公的保障(摂関家に準じる家格と官途)を緊急で与えたのではなかろうか。本来は服喪となるべき頼家を、頼朝の死を隠して急ぎ任官させる理由はこの他に考えにくい。
ところが、頼朝薨去が公表されるや、翌21日から通親は「右大将自初任翌日閉門」(『明月記』建久十年正月廿二日条)と、就任初日から出仕を取りやめている。その理由は「前将軍有事之由不奏聞朋輩又如此、称見存由、行除目之後聞薨逝、忽驚歎之由、為相示閉門」(『明月記』建久十年正月廿二日条)であったが、定家はこれを「奇謀之至也」と批判する。通親は除目に際して頼朝薨去を(実際は知っていたのに)奏聞しせず、頼朝は生存していると称して除目を行い、除目後に薨去の報告を聞いて驚嘆し「閉門」したという。ところがこの「閉門」は自亭への謹慎ではなく院中籠居であった。巷間では「院中物騒、上辺有兵革之疑、御祈千万被引神馬、新大将籠候御所不出里亭、是有事故」(『明月記』建久十年正月廿二日条)とあるように、何か故ある事であるとされ、その内容は世間には伝わっていなかったとみられる。
通親の籠居は、通親が「頼家ガ世二成テ、梶原ガ太郎、左衛門尉二ノボリタリケル」(『愚管抄』巻六)から「能保入道、高能卿ナドガ跡ノタメニムゲニアシカリケレバ、ソノ郎等ドモニ基清、政経、義成ナド云三人ノ左衛門尉」(『愚管抄』巻六)が「此源大将ガ事ナドヲイカニ云タリケルニカ、ソレヲ又カク是等ガ申候」(『愚管抄』巻六)という一報を受けたためとみられる。この「梶原ガ太郎」が如何なる人物かは定かではない。源太景季はすでに左衛門尉に任官して十四年経っており、当然彼ではない。次男の平次左衛門尉景高は妻(野三刑部丞成綱女)が騒擾の張本の一人・小野左衛門尉義成の姉妹であり、可能性はありそうだが、景高妻は「尼御台所宮女、御寵愛無比類」(『吾妻鏡』正治二年六月廿九日条)ということから、鎌倉在住が想定され、在京の義成から景高妻を経由して情報が流れる可能性は低い。三男の景茂も兵衛尉であって左衛門尉ではなく、それ以下の弟たちは任官していないことから、景時子息たちに該当者はいないことになる。一方、景時の弟・梶原六郎朝景の嫡子・定景(通称不明だが太郎か)は建久4(1193)年11月27日現在、「刑部左衛門尉」となっている。梶原平三景時、刑部丞朝景の兄弟はいずれも故左府実定(能保実叔父)の家人であり、一条家との関わりもあったであろう。たびたび上洛していた刑部丞朝景系の梶原家のほうが可能性が高いとすれば、通親に情報を流したのは、梶原刑部左衛門尉定景であった可能性があろう。
襲撃の噂を聞いた通親は、「ヒシト院ノ御所ニ参リ籠リテ、只今マカリ出デバ殺サレ候ナンズトテ、ナノメナラヌ事」(『愚管抄』巻六)と、二条仙洞御所に逃げ籠った。この騒動の張本である「左衛門尉中原政経、藤原基清、小野義賢」は後鳥羽院と関わりが深く「参院御所、是件三人可乱世間之由」(『百錬抄』)と伝わるが、彼らは事実上の執政である通親が高能薨後、一条家を無下に蔑ろにしたことに強く反発したためであったようである。「巷説、京中騒動、衆口狂乱、院中又物騒、新大将猶恐世間」(『明月記』建久十年正月廿六日条)と、通親が身の危険を感じている様子が見え、28日も「世間狂言逐日嗷々、院中警固如軍陣」(『明月記』建久十年正月廿八日条)と、在京御家人(政経は院主典代として院中にあったのだろう)が院中警固を物々しく行っており、後藤基清、小野義成も参じ、通親襲撃の機会をうかがっていたのであろう。
このような中、鎌倉から「掃部頭親能来廿九日可上洛」(『明月記』建久十年正月廿七日条)という知らせが届けられる。鎌倉には通親から「頼家ガリ広元ハ方人ニテアリケルシテ」(『愚管抄』巻六)と、親密な関係にある鎌倉家家司中原広元(この頃広元は鎌倉にいた)へ京都の情勢が「ヤウゝゝ」(基清らによる謀議か)記載された書状が送られており、広元を通じて頼家に治安維持を依頼したのであろう。頼家は親能上洛ののち「其時可有成敗」(『明月記』建久十年正月廿七日条)と伝えている。
正月26日、朝廷は左中将頼家に「続征夷将軍源朝臣遺跡」と「宜令彼家人郎従等如旧奉行諸国守護者」の宣旨を下した(『吾妻鏡』建久十年二月六日条)。これは頼朝入道入滅に伴う正月20日の緊急措置(臨時除目)に続く、頼家の鎌倉家継承を宣旨によって公認するものであった。この宣旨は2月6日に鎌倉に到着し、同日「吉書始」が行われた(『吾妻鏡』建久十年二月六日条)。頼朝の死から二十日を経ない時期ではあったが、綸旨が到来したために内々に執り行われたという(『吾妻鏡』建久十年二月六日条)。
吉書始に際しては、北条四郎時政、兵庫頭広元、三浦介義澄、前大和守光行、中宮大夫属入道善信、八田右衛門尉知家、和田左衛門尉義盛、比企右衛門尉能員、梶原平三景時、藤民部丞行光、平民部丞盛時、右京進仲業、文章生宣衡が「政所」に列し、仲業が清書した吉書を広元が寝殿の頼家のもとへ持参した。彼らはいずれも鎌倉家の家政職員に選ばれた人々とみられ、鎌倉行政の中枢の人々であった。また、この使者には通親から基清ら「三金吾」の対処についての問い合わせがあったとみられ、おそらく頼家は基清らを召取るために、使者の帰京に合わせて「新中将雑色」を同道させたと思われる。
一方、京都では2月9日に「京中忽騒動」(『明月記』建久十年二月十一日条)という騒擾が起こった。藤原定家は前日から妻室とともに嵯峨清涼寺を参詣していて騒動を実際に見聞きはしていないが、京より忠行少将が定家を訪問してきたため、寺近くの東屋に迎えて面会し、騒動の内容を聞いている。それによれば、左馬頭源隆保が、北小路東洞院へ行き向かい、「喚集諸武士議定、依此事天下又狂乱、衆口嗷々」(『明月記』建久十年二月十一日条)のためであるという。定家は「是皆不幸之人、可招殃之故歟」(『明月記』建久十年二月十一日条)と感想を漏らしている。
藤原忠実
(関白)
∥――――――藤原忠通――藤原兼実―――藤原良経
∥ (関白) (関白) (関白)
源隆俊―――――源隆子 +―源師子
(権中納言) (従二位) |
源明子 ∥ |
∥―――+――――――――藤原尊子 ∥――――+―源雅実――――源顕通―――源雅通――――源親通
∥ | ∥―――――――源顕房 (太政大臣) (右大臣) (内大臣) (内大臣)
∥ | ∥ (右大臣)
藤原道長| 具平親王―――源師房
(関白) |(中務卿) (左大臣)
| ∥―――――――源師忠――――源師隆 +―源俊隆―――隆曉=====藤原能保
| ∥ (大納言) (大蔵卿) |(大宮権亮)(仁和寺法印)(権中納言)
+―藤原頼宗―+―女子 ∥ |
|(右大臣) | ∥ | +―藤原通重―――藤原能保――藤原全子
| | ∥ | |(丹波守) (権中納言) ∥
| | ∥ | | ∥
| | ∥ | | 藤原公通 ∥
| | ∥ | |(権大納言) ∥
| | ∥ | | ∥――――――藤原実宗 ∥
| | ∥ | | ∥ (内大臣) ∥
| | ∥ | | ∥ ∥―――――藤原公経
| | ∥ +―女子 +―女子 +―女子 (太政大臣)
| | ∥ | ∥ | |
| | ∥ | ∥―――+―藤原基家―+―藤原保家
| | ∥ | ∥ (権中納言) (権中納言)
| | ∥ | 藤原通基
| | ∥ |(左京大夫)
| | ∥ |
| | ∥――――+―源師経
| | ∥ (三河守)
| | +――女子 ∥―――――源隆保
| | | ∥ (左馬頭)
| | | 藤原季範――+―女子
| | | |
| | | +―女子
| | | ∥―――+―源頼朝
| | | ∥ |(右近衞大将)
| | | ∥ |
| | | 源義朝 +――――――――――――――女子
| | | (左馬頭) ∥
| | | ∥
| | +―藤原為房―+―藤原顕隆――――女子 ∥――藤原高能
| | |(大蔵卿) (権中納言) ∥―――――藤原公能――女子 ∥ (左馬頭)
| | | ∥ (右大臣) ∥ ∥
| | | 藤原公実 +―――――――――藤原実能 ∥――――――藤原能保
| | |(権大納言)| (左大臣) ∥ (権中納言)
| | | ∥ | ∥
| | | ∥――――+―藤原璋子 ∥
| | | ∥ (待賢門院) ∥
| | 藤原隆方―+―藤原光子 ∥―――――――後白河天皇 ∥
| |(但馬守) ∥ ∥
| | 鳥羽天皇 ∥
| | ∥
| +―藤原俊家―――藤原基頼―――藤原通基――+―――――――――――――藤原通重
| (右大臣) (中務大輔) (左京大夫) | (丹波守)
| |
| +―藤原基家――藤原保家
| (権中納言)(権中納言)
|
+―藤原長家―――藤原忠家―+―藤原俊忠―――藤原俊成――――藤原定家
(太政大臣) (大納言) |(権中納言) (皇太后宮大夫)(権中納言)
|
+―藤原顕良―+―藤原親能
(民部少輔)|(若狭守)
|
+―栄全――――――最舜――――女子
(権少僧都) (法眼) (少将局)
∥―――――藤原兼基
∥ (大納言)
藤原忠通――――藤原基実――藤原基通
(関白) (摂政) (関白)
翌12日昼頃、京都に戻った定家は「関東飛脚帰京、右大将放光、可損亡人々等多」(『明月記』建久十年二月十二日条)と記す。関東から戻った飛脚(正月26日に鎌倉へ下った使者であろう)から、頼家または広元からの騒動について具体的な返答があったのだろう。その後、定家が「右大将放光」と述べているように、それまでの「新大将猶恐世間」という態度から一転、威勢を見せており、処罰される人々はさぞ多いことだろうと述べる。「関東飛脚」が帰京に際して齎した事柄は記されていないが、通親懸案であった張本三名の捕縛であろう。前述のように関東飛脚は帰京に伴い「新中将雑色」が同道していたと思われ、入洛二日後の2月14日、「新中将雑色」が「左衛門尉三人基清、政経、義成」を召し取り、「先向惟義許、武士守護被渡院御所、給武士三人」(『明月記』建久十年二月十一日条)と、源惟義から院へ引き渡されたのである。それを受けて、同日「殿下参御院、武士事有沙汰」(『猪隈関白記』建久十年二月十四日条)と、摂政基通が参院し、彼らの行動に対する沙汰を行った。
そして2月17日早朝、「宰相中将公経卿、保家朝臣、隆保朝臣、被止出仕云々、巷説公卿七人可滅亡、不知誰人」(『明月記』建久十年二月十七日条)と、「院殿上人」(『明月記』建久九年正月十一日条)である院別当公経(能保女婿)、右中将保家(能保従弟)の両名と、故高能後任の左馬頭であった源隆保(能保コトニイトヲシクシテ左馬頭ニナシタリシ)らが出仕を止められている。夜には「年来依前大将之帰依、其威光充満天下、諸人追従僧也」の文覚上人を検非違使に「守護(管理下に置く)」させる旨の宣旨が下され、3月5日に佐渡へ配流に処された。文覚も一条家関係の騒擾に関わった可能性があろう。
ただ、いくら一条家が蔑ろにされたとはいえ、政経、基清、義成の三人の左衛門尉と一条家ゆかりの公家数名が通親を排除し政変を企てるほどのものであったとは思えないのである。とくに院庁主典代中原政経は一条家とは何ら所縁が見られず、彼が首謀者の一人と目された理由は現状不明である。
一条家は「右武衛能保姫公為御乳母依可有参内」(『吾妻鏡』文治三年七月四日条)とあるように、能保女子が後鳥羽天皇乳母であった関係で上皇との距離がかなり近く、建久7(1196)年から建久8(1197)年10月まで「一条中納言能保」が院御厩別当を務め、その死後は嫡子「左兵衛督高保」がこれを継承している。また、御厩案主は建久7(1196)年から建久9(1198)年9月の高能薨去まで、後藤左衛門尉基清が勤めているのである(木村真美子『中世の院御厩司について』―西園寺家所蔵「御厩司次第」を手がかりに―)。さらに、高能薨後は建久9(1198)年10月頃から正治元(1199)年7月12日(『明月記』正治元年七月十五日条)まで、能保女婿で後鳥羽院別当の「西園寺太政大臣公経公(当時は従三位左中将)」が御厩別当であった。また、能保は後白河院政時代の文治5(1189)年から建久元(1190)年までも院御厩別当を勤めていて、その当時の御厩案主は小野左衛門尉義成の兄弟と思われる「安房刑部丞盛綱」であった(木村真美子『中世の院御厩司について』―西園寺家所蔵「御厩司次第」を手がかりに―)。このように一条家と後鳥羽院は当初から強い紐帯があったことが想定される。後年の事となるが、後鳥羽上皇が北条義時の追討を企図した所謂「承久の乱」で、宮方の大将の一人として加わったのが、能保の子・右中将信能とその弟・法勝寺執行法印尊長であり、故高能舅の糟屋左衛門尉有久や小野左衛門尉盛綱、後藤左衛門尉基清らも後鳥羽上皇のもと、鎌倉勢と戦っている。
こうしたことから、この通親襲撃計画の根本は、通親に対して内心憚りを感じ、思う様に事を成し得ない後鳥羽院の関わり(というよりも計画主導者か)の可能性を否定できないだろう。以降は想像であるが、頼朝薨去の報を受けた上皇は、宮中の混乱に乗じて通親の排除を行おうとしたのではなかろうか。上皇より直接指示を受けたのは、院殿上人である公経または保家で、年預主典代の左衛門尉中原政経が窓口となり、実質的に指揮を取った左馬頭源隆保(公経、保家両者の近親であり、頼朝の従弟という血統ならびに、一条家と同じ中御門流の子孫でもあり一条家とは親密であったろう。同族の通親に敵愾心を持っていたのかもしれない。)へ伝達されたのであろう。一条家と所縁のない中原政経が首謀者として捕縛された理由はここにあるのであろう。
隆保の指示のもと、一条家郎従の後藤左衛門尉基清、小野左衛門尉義成が実行者として院御所に参じて控えるも、計画は小野の義兄弟・梶原左衛門尉景高から通親に漏洩。首謀者が上皇であれば通親は抗議することは不可能であるが、実行人である後藤基清や小野義成は鎌倉家の家人であり、その許可を得れば捕縛は可能であったろう。そのため、通親は頼家への遺跡継承を認める正月26日宣旨の使者に今騒動の顛末を認めた書状を副えて送り、その対処を求めたのではなかろうか。その結果、朝廷の使者とともに頼家雑色が同道して上洛し、基清らの捕縛へと繋がったと思われる。そして、この事件に関わった公経、保家、隆保らも出仕停止処分となったのであろう。
その後、公経は数か月後の11月12日に閉門が解かれている(『公卿補任』正治元年)。保家が謹慎を解かれた日は不詳だが、建仁2(1202)年10月20日に通親が「頓死」すると、その九日後の10月29日に従三位に昇叙する(『公卿補任』正治元年)。隆保は3月24日に「解官 左馬頭兼安芸守源隆保」(『明月記』正治元年三月廿三日条)と解官され、「隆保朝臣武士等被召合事等粗語之、隆保武士同座坐地上」(『明月記』正治元年四月廿六日条)により、4月21日「源隆保朝臣遣土佐国」され、5月21日に「前左馬頭隆保、去夜配流土佐国、夜中出京」(『明月記』正治元年五月廿二日条)という。そして通親薨去から八か月後の建仁3(1203)年6月25日、「前左馬頭隆保復本位」(『百錬抄』十一)と、本位に戻っている(これ以前に帰京したか)。このように、一連の騒乱に関わった人々は通親薨去後にすべて復帰しており、後藤基清、小野義成も重い罪科となることなく在京御家人として復帰を果たし、院に伺候している。これらから、この騒動の背後にはおそらく後鳥羽上皇という絶対的存在があり、通親薨去によって”首謀者”たちは赦免されたのだろう。
この政変未遂後の2月26日、鎌倉からの使者「親能今朝入洛、天下事可決」(『明月記』建久十年二月廿六日条)という。「天下事可決」という鎌倉からのかなり大きな使命を受けていたとみられる。すでに騒動は決着し、関わった人々は捕縛または閉門の措置となっていた。親能上洛は騒擾の後始末は行う可能性はあるが、主目的はそれではないだろう。親能は頼朝が「猶次ノムスメヲ具シテノボラン」(『愚管抄』巻六)とした次女乙姫の乳母夫であることから、乙姫の入内話が本題ではなかろうか。ところが、「故将軍姫君、号乙姫君、字三幡、自去比御病悩、御温気也、頗及危急、尼御台所諸社有祈願、諸寺修誦経給、亦於御所、被修一字金輪法、大法師聖尊号阿野少輔公、奉仕之」(『吾妻鏡』建久十年三月五日条)とあるように、乙姫はここのところ病に臥せっており、3月頃には重態に陥っている。親能は正月29日に上洛の途に就く予定であったが、彼の入洛日を考えると二十日余り出立が延期されたとみられる。おそらく乙姫の病のためであろう。この間に鎌倉からは京都へ「当世有名名医誉」である針博士丹波時長の招聘を依頼する使者が遣わされていたが、時長はこれを頻りに固辞し続けた。大姫の前例(法印実全の祈殺の噂)を嫌ったためかもしれない。
3月4日、「三人金吾昨今下向関東云々、不同道、各武士等預之相具、此輩七人父子解官」(『明月記』建久十年三月四日条)と後藤基清ら三名は鎌倉へ下されることとなる。後藤基清は讃岐国の守護であったが、これを停止され、近藤七国平に補された(『吾妻鏡』建久十年三月五日条)。本来、頼朝が定めた国司や諸職は改めることはないと決められていたが、朝廷に関わる事件であったためか「幕下将軍御時被定置事被改之始也」と評されている。
6月22日、「任大臣」が行われ「太政大臣頼実、左大臣良―(経)、右大臣家実、内大臣通親超実定、定隆、忠良三卿、権大納言泰通超親宗、隆房、通資、権中納言実教、兼良参議、参議家経」(『明月記』正治元年六月廿二日条)となった。太政大臣に移された前右府頼実は「不被仰可任之由、俄推任、聞此事閉門」(『明月記』正治元年六月廿二日条)と、兼宣旨もなく望んでもいない太政大臣に移されたことに激怒。閉門した上に「土佐国務同辞之、相国上表」と土佐国の返上ならびに上表をしたという。
■六月二十二日除目(『公卿補任』)
| 22日 任官 |
任官 | 前官 | 官位 | 名前 | 備考1 | 備考2 |
| 摂政 | ― | 従一位 | 藤原基通 | 4月18日、上表、辞内舎人随身 | ||
| 〇 | 太政大臣 | 右大臣 | 正二位 | 藤原頼実 | 正月20日、右大将辞任⇒権大納言源通親が即日後任 | |
| 〇 | 左大臣 | 内大臣 | 正二位 | 藤原良経 | 前関白兼実嫡子。6月22日、従一位兼雅が辞左大臣による | |
| 〇 | 右大臣 | 権大納言 (六大納言) |
従二位 | 藤原家実 | 左大将 | 関白基通嫡子。末席の大納言から右大臣となる |
| 〇 | 内大臣 | 権大納言 (第四大納言) |
正二位 | 源通親 | 右大将 | 実宗、隆忠、忠良の三名を超越し、第四大納言から内大臣となる 天皇外祖父は大臣(兼大将)となる先例による |
| 大納言 | ― | 正二位 | 藤原実宗 | 西園寺家当主。兼実派の筆頭であり、隆忠、定家を女婿とする | ||
| 大納言 | ― | 正二位 | 藤原隆忠 | 松殿基房長男。実宗女婿 | ||
| 権大納言 | ― | 正二位 | 藤原忠良 | 中摂政基実の庶子 | ||
| 権大納言 | ― | 正二位 | 藤原経房 | 民部卿 | ||
| 〇 | 権大納言 | 権中納言 (第一中納言) |
正二位 | 藤原泰通 | 中御門為通の子 | |
| 〇 | 権大納言 | 権中納言 (第四中納言) |
従二位 | 源通資 | 内大臣通親実弟。上臈親宗、隆房を超越 6月22日、左衛門督、検非違使別当を辞する |
|
| 〇 | 中納言 | 権中納言 | 正二位 | 平親宗 | 7月17日薨去 | |
| 〇 | 中納言 | 権中納言 | 従二位 | 藤原隆房 | ||
| 〇 | 中納言 | 権中納言 | 従二位 | 藤原忠経 | 皇后宮大夫 | |
| 権中納言 | ― | 従二位 | 藤原光雅 | 大宮権大夫 | ||
| 権中納言 | ― | 従二位 | 藤原公継 | 中宮権大夫 | ||
| 〇 | 権中納言 | ― | 正三位 | 藤原宗頼 | 左衛門督 検非違使別当 |
6月22日、左衛門督、検非違使別当を兼ねる |
| 〇 | 権中納言 | 参議 (第一参議) |
従二位 | 藤原実教 | 皇后宮権大夫 | 6月22日、参議、右衛門督を停止 |
| 権中納言 | ― | 従三位 | 藤原道経 | 左近衞中将 | ||
| 参議 | ― | 正三位 | 源兼忠 | 備中権守 | ||
| 〇 | 参議 | ― | 正三位 | 藤原実明 | 伊予権守 | |
| 参議 | ― | 従三位 | 藤原兼宗 | 左近衞中将 加賀権守 |
||
| 〇 | 参議 | ― | 従三位 | 藤原信清 | 左兵衛督 右衛門督 |
|
| 参議 | ― | 従三位 | 藤原公経 | 左近衞権中将 | 2月院勘により閉門、11月12日被免開門 | |
| 参議 | ― | 従三位 | 藤原定経 | 越前権守 | ||
| 参議 | ― | 正四位下 | 藤原宗隆 | 左大弁 勘解由長官 備後権守 |
勧学院別当 | |
| 〇 | 参議 | 左近中将 | 正四位下 | 藤原家経 |
建久10(1199)年正月20日に緊急で行われた臨時除目で、前述の通り頼朝嫡子・右近衞少将頼家が「左中将」に転じ、26日には遺跡の継承が認められ、家人郎従等の支配を命じる宣旨が下された(鎌倉殿の継承)。この宣旨は2月4日に鎌倉に届けられ、吉書始が執り行われ、3月11日には延引されていた鶴岡山八幡宮寺参詣を行うなど、新鎌倉家当主としての行事を滞りなく行っている。
一方、頼家実妹の乙姫は日に日に容態が悪化しており、鎌倉家は3月13日、鎌倉下向を固辞し続ける医師丹波時長招聘のため、「今日被差上専使、猶以令申障者、可奏達子細於仙洞之旨、被仰在京御家人等」(『吾妻鏡』建久十年三月十三日条)という、後鳥羽院に達して院宣による半ば強制的な鎌倉下向を在京御家人に指示した。さらに3月23日、頼家は「依有殊御宿願」によって「太神宮御領六箇所被止地頭職」を行った。「御宿願」とは、当時病に臥せっていた実妹・乙姫(三幡)の病気平癒であろう。
「太神宮御領六箇所」とは、遠江国から尾張国にかけての伊勢皇太神宮領であり、遠江国蒲御厨は北条時政による下知状が出されている通り、祖父の北条時政が御厨内の地頭職であったことがわかる。また、三河国の四箇所の御厨は、盛長の代官が「御奉免之後更以不交其沙汰」と言っている事から(『吾妻鏡』正治元年十月廿四日条)、おそらく盛長が地頭職であったと思われる。
| 御厨 | 地頭 | 現在地 | 建久三年当時の給主 (『鎌倉遺文614』) |
成立等 |
| 遠江国蒲御厨 | 北条四郎時政 | 浜松市神立町一帯。 | 内宮一禰宜成長等 | 嘉承注文・永久宣旨。 |
| 尾張国一楊御厨 | 不明 | 名古屋市中川区中郷一帯。 | 外宮禰宜元雅 | 嘉承注文・永久宣旨。 |
| 三河国飽海本神戸 | 藤九郎盛長入道 | 豊橋市飽海町一帯。 | 内外二宮。国造貢進。 | |
| 三河国新神戸 | 藤九郎盛長入道 | 豊橋市神明町一帯。 | 内外二宮 | 天慶三年勅願。 |
| 三河国大津神戸 | 藤九郎盛長入道 | 豊橋市老津町一帯。 | 内外二宮 | 天慶三年勅願。文治元年官符等。 |
| 三河国伊良胡御厨 | 藤九郎盛長入道 | 田原市伊良湖町一帯。 | 外宮権神官貞村等 | 嘉承注文・永久宣旨。 |
これら六箇所の地頭職を停止したことは、乙姫の件もあるが、北条時政や盛長入道への対立意識が働いていたと推測されよう。また荘園の惣追捕使もあわせて停止されており、それらの荘園での「謀反狼藉之輩出来者、自神宮可被搦出、且又可触申案内之旨」を伊勢祭主に申し伝えている。祖父・時政や盛長入道は頼家を頼朝の後継者として厳しく教育していた可能性があり、頼家は彼らを快く思っていなかったのかもしれない。
また、家政機関の組織改編として、4月1日、政所の部局として執事三善善信入道宅に仮設(もともとは営中一角に置かれていたものを喧騒とを理由に移されていた)されていた「問注所」を新築の別郭へ移した。頼家新政をきっかけにしたものであろう。4月12日、「諸訴論事、羽林直令聴断給之條、可令偏止之」ことが定められ、今後は何事も十三人の家職・奉行人に計らい訴訟を行うべきことが決定された(『吾妻鏡』建久十年四月十二日条)。なお、「可令偏止之」とあることから、尼御台による指示であったと推測される。
●頼家が訴訟時に計ることが定められた鎌倉家家職(『吾妻鏡』建久十年四月十二日条)
| 名 | 家司 | 家政機関 | 備考 |
| 北條四郎時政 | |||
| 江間四郎義時 | |||
| 兵庫頭中原広元 | 別当 | 政所別当 | 家司別当として鎌倉家政所を統括する。 |
| 大夫屬三善康信入道善信 | 問注所執事 | ||
| 掃部頭中原親能(在京) | |||
| 三浦介義澄 | |||
| 八田右衛門尉知家 | |||
| 和田左衛門尉義盛 | 建久3(1192)年にあった義盛の服喪の機会に侍所別当を所司景時に改代。 景時死後の正治2(1200)年2月5日に別当に還補。 ただし、建久4(1193)年5月28日、富士の牧狩りで「義盛、景時承仰、見知祐経死骸」と見え、さらに建久5(1195)年5月24日には「侍所着到等事、義盛、景時故障之時者、可致沙汰之由、被仰付大友左近將監能直」とみえ、義盛は侍別当を景時に譲ったものの、侍所に関わる職にあり、景時の上席にあった様子がみられる。 |
||
| 比企右衛門尉能員 | |||
| 藤九郎入道蓮西 | |||
| 足立左衛門尉遠元 | |||
| 梶原平三景時 | 侍所別当 | ||
| 民部大夫藤原行政 | 令 | 政所執事 |
かつて家人郎従(御家人)の訴訟は問注所での弁論を経て、頼朝が直裁する通例であったが、新鎌倉殿頼家は政務の経験が浅く、御家人との紐帯の根底を為す訴論を直裁することは危険と見なされたのだろう。しかも頼家は近臣を重用し、狼藉の揉み消しや訴訟介入もあったのだろう。将軍の訴訟親裁の停止に伴い、十三名以外の「其外之輩、無左右不可執申訴詔事」ことが明確に定められているのは、頼家側近への警告とであろう。
ところが4月20日、頼家はこれに抵抗して、梶原平三景時、右京進中原仲業らに、我が側近の「小笠原弥太郎、比企三郎、同弥四郎、中野五郎等」が鎌倉中で狼藉を働いたとしても敵対することを禁じ、五人の側近以外の者は、別な召しがなければ頼家との面会を許さずという命を下す(『吾妻鏡』正治元年四月廿日条)。5月16日には、三河国の伊勢神領「薑御厨」「橋良御厨」の地頭職を停止する。この地も盛長入道が地頭職を有していた場所であったと推測される。
| 御厨 | 地頭 | 現在地 | 建久三年当時の給主 (『鎌倉遺文614』) |
成立等 |
| 三河国薑御厨 | 藤九郎盛長入道 | 豊橋市二連木町一帯。 | 外宮一禰宜雅元等 | 嘉承注文・永久宣旨。 |
| 三河国橋良御厨 | 藤九郎盛長入道 | 豊橋市橋良町一帯。 | 内宮禰宜重章等 | 嘉承注文・永久宣旨。 |
これは乙姫の体調悪化が続いていることから、3月23日の「依有殊御宿願」の追加措置が行われたと思われるが、盛長入道の地頭職がまたも停止されており、盛長入道への対立意識が強かったのだろう(『吾妻鏡』正治元年五月十六日条)。
5月7日、在京の左近将監能直が医師丹波時長を伴って鎌倉に参着した。鎌倉からの願いを受けた後鳥羽上皇が時長へ早々に鎌倉へ下るべしとの院宣を下したことで、渋る時長も下向することとなったのであった。旅宿は家職の兵庫頭広元および八田右衛門尉知家が沙汰し(『吾妻鏡』正治元年五月七日条)、時長はまず乙姫乳父の掃部頭親能の亀谷邸に入ったのち、御所南御門に隣接する畠山次郎重忠邸が宿所と定められている。
翌5月8日、時長は早速乙姫のもとを訪れて診察を開始し、朱砂丸を処方した。これによって砂金二十両が下されている。朱砂丸は辰砂を主原料とする精神安定に効能を持つ丸薬であったとみられ、大姫同様に精神面での病も併発していたのであろう。処方が何度行われたかは不明だが、5月29日、乙姫はやや体調の回復が見られ、「今夕、姫君聊有御食事」(『吾妻鏡』正治元年五月廿九日条)と、夕に少し食事がとれるようになり、「上下喜悦之外無他」であったという。
しかし、その後ふたたび乙姫の体調は悪化。6月12日には「御目上腫御」の症状が出、時長は驚いて「此事殊凶相之由」を述べた。乙姫の容体は「於今者少其恃歟、凡匪人力之所覃」であったという(『吾妻鏡』正治元年六月十四日条)。重い何らかの甲状腺疾患であったのだろうか。時長はすでに頼家から帰洛の許可を得ていたが、京都で「沙汰重事」を行っていた掃部頭親能が「姫君御事」を聞いて鎌倉へ向かっている報告により、その鎌倉帰参を待つこととした。乙姫の容体についての説明も行われる予定だったのだろう。そして6月25日に親能が鎌倉へ参着(『吾妻鏡』正治元年六月廿五日条)。翌26日、時長は帰洛の途についた(『吾妻鏡』正治元年六月廿六日条)。帰洛に当たり頼家からは馬五頭などの餞別が下されている。
そしてその四日後、6月30日午の刻、乙姫が亡くなった(『吾妻鏡』正治元年六月卅日条)。享年十四。「尼御台所御歎息、諸人傷嗟不遑記之」と鎌倉中の悲嘆が聞かれ、乳母夫の掃部頭親能は宣定法橋を戒師として出家を遂げた。夜戌の刻、乙姫を親能邸の亀谷堂脇に埋葬し墳墓堂とし、初七日7月6日に宰相阿闍梨尊曉を導師として仏事が修せられた(『吾妻鏡』正治元年七月六日条)。京都には7月上旬には情報が届けられており、藤原定家は7月10日、これまで巷説だった「故前大将第二娘、又如姉長病逝去」が「漸聞定説也、晦日逝去、生年十七」(『明月記』正治元年七月十日条)という確定的情報を得ている。また後鳥羽院もこの情報に触れ、鎌倉に「仙洞御使左衛門少尉信季」を下向させた(『吾妻鏡』正治元年七月廿三日条)。弔意を示すためであろう。
この乙姫の仏事から四日後の7月10日夜、三河国から飛脚が到来し、「室平四郎重広、率若干強竊盗人等於当国駅之振武威」という報告が伝えられた(『吾妻鏡』正治元年七月十日条)。室平四郎重広は伊勢皇太神宮に去り渡された「橋良御厨」に西隣する牟呂郷(豊橋市牟理呂町周辺)の御家人であると思われ、叛乱の報は伊勢神官からの通報によるものと思われる。叛乱の原因は不明だが、5月15日の橋良御厨地頭職停止と関わりがあると思われる。
この報を受けた頼家は、7月16日、頼家は三河国奉行人・盛長入道の嫡男「安達弥九郎景盛」を討伐の討伐の使節として派遣する(『吾妻鏡』正治元年七月十六日条)。実はこれ以前から景盛は追討使節を頼家から打診されていたが固辞し続けていた。固辞した理由は「去春之比、自京都所招下好女、愁片時別離之故歟」とされるが、頼家は「是日来重色之御志、依難禁被通御書、御使徃復、雖及数度、敢以不諾申之間」と、景盛の側妾に目をつけて度々御書を送っていたことを景盛が知っていたためと思われる。こうした濫行は乙姫薨去により、頼家の精神状況に何らかの影響を与えられた可能性があろう。
出征を固辞し続けていた景盛であったが、三河国は「已為父奉行国」であったため、断ることはできず景盛は三河国へと出立する。奉行人である盛長ではなく嫡子・景盛へ追討使を命じているのは、盛長がすでに家督を景盛へ譲っていたためと思われる。ただし、盛長は出家後も三河国の国奉行であり、甘縄邸も盛長が握り、景盛は別に屋敷を与えられていたのだろう。盛長が景盛へ家督を譲った時期は、頼朝薨去直後と思われ、当時在京の景盛を鎌倉へ呼び戻したものと推測される(景盛はのちに「和漢古事」を将軍家に指南する学問所番となっており、在京時にこれらを修めていたのだろう)。
景盛が三河へ出立して四日後の7月20日早朝、頼家は側近の中野五郎能成を景盛邸に遣わして、景盛が春に京都から招いた妾女を攫い、小笠原弥太郎長経の屋敷に移してしまう(『吾妻鏡』正治元年七月廿日条)。おそらく景盛がもっとも懸念していたことが現実となってしまった。さらに26日には彼女を「北向御所」へと移し、「小笠原弥太郎長経、比企三郎、和田三郎朝盛、中野五郎能成、細野四郎」以外はこの御所へ近づくことを禁じた(『吾妻鏡』正治元年七月廿六日条)。
そして8月18日、追討を終えた景盛が三河国から帰参すると、屋敷に妾女がいないことが発覚する。景盛はおそらく頼家に対し激しい怒りを覚えたであろう。翌19日、頼家は景盛が「怨恨」を抱いているという「讒者」の訴えを以って、「小笠原弥太郎、和田三郎、比企三郎、中野五郎、細野已下」側近を北向御所に集めて景盛誅罰を議し、晩に至って小笠原弥太郎長経が挙兵して「藤九郎入道蓮西」の甘縄邸へ兵を進めた。まかりなりにもこれは将軍頼家の命による追討であり、鎌倉中の御家人がこぞって参集する事態となった(『吾妻鏡』正治元年八月十九日条)。なお、この「讒者」は梶原平三景時であったことが、のちの三浦義村の述懐(『吾妻鏡』正治元年十月廿七日条)から明らかとなる。
この大事を聞いた尼御台は、ただちに甘縄の盛長入道邸に入御すると、側近の藤原行光(家令の山城判官行村弟)を頼家に遣わし「幕下薨御之後不歴幾程、姫君又早世悲歎非一人之處、今被好闘戦是乱世之源也」と激しく叱責。さらに「就中、景盛有其寄、先人殊令憐愍給」と景盛は頼朝の覚えめでたき人物であったことを指摘し、「令聞罪科給者我早可尋成敗、不事問被加誅戮者、定令招後悔給歟、若猶可被追討者、我先可中其箭」と伝えると、乙姫の事も引き合いに出されたことも影響したか、頼家も渋々兵を引き上げる。
尼御台は翌20日まで甘縄の盛長邸に逗留する。ここで景盛を召して、一旦は頼家の謀議を食い止めることはできたが、自分はすでに老耄であり今後の彼の宿意を抑えることは難しいと、頼家に対して「起請文」を献じることを勧めて御所へと帰還すると、「佐々木三郎兵衛入道(佐々木盛綱)」を使者として景盛からの起請文に添えて「諷諫之御詞」を頼家に渡す。
尼御台はこの諷諫状で「昨日擬被誅景盛楚忽之至、不儀甚也」と叱責した上で、「凡奉見当時之形勢、敢難用海内之守、倦政道、而不知民愁、娯倡棲、而不顧人謗之故也」と無策ぶりを激しく非難。「所召仕更非賢哲之輩、多為邪侫之属」と側近たちの奸悪ぶりを指摘した。一方で源氏一門や北条氏を重用せず、御家人等を諱で呼びつけていることを非難し、まつりごとを疎かにすることのないよう指示している(『吾妻鏡』正治元年八月廿日条)。ただ、中原広元はこの頼家の挙をかつて鳥羽院が近臣源仲宗妻・祇園女御を寵愛したことを引き合いに「如此事非無先規、鳥羽院御寵愛祗園女御者源仲宗妻也、而召 仙洞之後、被配流仲宗隠岐国」と擁護する姿勢を示している。
10月25日、結城七郎朝光は御所侍で、伺候している傍輩の御家人に夢想があったとして、故頼朝のために「人別一万反弥陀名号」を勧めた(『吾妻鏡』正治元年十月廿五日条)。このとき朝光は「吾聞、忠臣不事二君云々、殊蒙幕下厚恩也、遷化之刻、有遺言之間不令出家遁世之條、後悔非一、且今見世上、如踏薄氷」と嘆息を漏らしたが、この話した内容が梶原景時を通じて頼家の耳に入ってしまう。
10月27日、幕府内にいた朝光は、女房阿波局(御台所政子妹)から「依景時讒訴、汝已擬蒙誅戮其故者、忠臣不事二君之由令述懐謗申当時、是何非讎敵哉、為懲肅傍輩、早可被断罪之由具所申也、於今者不可遁虎口之難歟」と伝えられた(『吾妻鏡』正治元年十月廿七日条)。朝光は驚き、親友の三浦前右兵衛尉義村に相談すべく、彼の屋敷を訪れて事の顛末を告げる。義村は「凡文治以降、依景時讒殞命失滅之輩不可勝計、或于今見存、或累葉含愁憤、多之、即景盛去比欲被誅、併起自彼讒、其積悪定可奉帰羽林、為世、為君、不可有不対治、然而決弓箭勝負者、又似招邦国之乱、須談合于宿老等」と、景時のこれまでの讒言に対して宿老を結集して対応を協議すべきと、各宿老に専使を送った。知らせを受けた藤九郎盛長入道と和田左衛門尉(和田義盛)がこれを受けて早速三浦邸にやってきた。
藤九郎入道と和田義盛は、三浦義村から事の顛末を聞くと激怒し、「早勤同心連署状可訴申之、可被賞彼讒者一人歟、可被召仕諸御家人歟、先伺御気色、無裁許者、直可諍死生、件状可為誰人筆削哉」と、頼家に宿老連署の景時弾劾状を提出すべきと主張。藤九郎入道は先日、甘縄邸を囲まれる被害を蒙ったばかりであり、景時にはことのほか強い怒りを持っていただろう。彼らは頼家に「讒者」景時一人を賞するか、諸御家人を召し使うかを問いただし、返答なくば景時を討つことを計画する。弾劾状の作成には、景時に宿意のある政所奉行人で筆の達者である右京進中原仲業が適当ではないかとして、義村は仲業を屋敷に招いた。仲業はその趣旨を聞いて喜び、弾劾状を認めることとなる。
翌10月28日巳の刻、三浦義村の使いを受けた宿老のうち、六十六人が鶴岡山八幡宮寺の回廊に結集。景時弾劾の訴状に各々が署判し、和田左衛門尉義盛・三浦兵衛尉義村が中原広元のもとへ持参した(『吾妻鏡』正治元年十月廿八日条)。この景時弾劾連署状の筆頭に常胤がみえるほか、胤正および孫の平太重胤も名を連ねている(『吾妻鏡』建久十年十月廿七日条)。
●正治元(1199)年10月27日 梶原景時弾劾状署名宿老六十六名(『吾妻鏡』正治元年十月廿七日条)
| 千葉介常胤 | 三浦介義澄 | 千葉太郎胤正 | 三浦兵衛尉義村 | 畠山次郎重忠 | 小山左衛門尉朝政 |
| 小山七郎朝光 | 足立左衛門尉遠元 | 和田左衛門尉義盛 | 和田兵衛尉常盛 | 比企右衛門尉能員 | 所右衛門尉朝光 |
| 二階堂民部丞行光 | 葛西兵衛尉清重 | 八田左衛門尉知重 | 波多野小次郎忠綱 | 大井次郎実久 | 若狭兵衛尉忠季 |
| 渋谷次郎高重 | 山内刑部丞経俊 | 宇都宮弥三郎頼綱 | 榛谷四郎重朝 | 九郎盛長入道 | 佐々木三郎兵衛尉盛綱入道 |
| 稲毛三郎重成入道 | 足立藤九郎景盛 | 岡崎四郎義実入道 | 土屋次郎義清 | 東平太重胤 | 土肥先次郎惟光 |
| 河野四郎通信 | 曾我小太郎祐綱 | 二宮四郎 | 長江四郎明義 | 毛呂二郎季綱 | 天野民部丞遠景入道 |
| 工藤小次郎行光 | 右京進中原仲業 | 小山五郎宗政 | 他27名 |
ところが広元はこの連署状の扱いに一人困ってしまった。「於景時讒侫者、雖不能左右」であるとはいえ「右大将軍御時、親致昵近奉公者也」であり、「忽以被罪科、尤以不便條、密可廻和平儀歟之由猶予」と両者の関係の修復を目論んだ(『吾妻鏡』正治元年十一月十日条)。しかし11月10日、御所に参じていた和田義盛に「彼状定披露歟、御気色如何」と問われた。やむなく広元は「答未申之由」を述べると、義盛は目に怒りを含み「貴客者為関東之爪牙耳目、已歴多年也、怖景時一身之権威、閣諸人之欝陶、寧叶憲法哉」と述べた。広元は「全非怖畏之儀、只痛彼損亡許也」と答えるが、義盛は広元の座の傍らに居寄せると、「不恐者、爭可送数日乎、可被披露否、今可承切之」と詰め寄ったのである。広元はもはやこれまでと察し「称可申之由」して座を立った。
11月12日、広元は六十六人の連署状を頼家に提出した(『吾妻鏡』正治元年十一月十二日条)。提出された連署状を一読した頼家は、その場に座していた景時にこれを下し、「可陳是非之由」を告げた。景時はその場で申し披きできずに退いた。そして翌13日、景時は「子息親類等」を率いて館のある相模国一宮(高座郡寒川町一之宮)へ下向していった。頼家は景時一族の一宮下向に対して措置を行っておらず、景時の一宮下向は、宿老に対して遺恨のある頼家の密かな指示だったのかもしれない。12月9日、景時が一宮から鎌倉に帰参しているが(『吾妻鏡』正治元年十二月九日条)、これは先日の連署状についての沙汰を行うために、頼家から公的に召し出されたものであったとみられる。そして12月18日、和田左衛門尉義盛、三浦兵衛尉義村が奉行となって景時の鎌倉追放を沙汰した。これを受けた景時は即日鎌倉を退転して一宮へ帰還し、鎌倉の梶原邸は収公されて破却され、永福寺僧坊へ寄付されることとなった(『吾妻鏡』正治元年十二月十八日条)。
常胤は下総国で最大の鎌倉家の家人であるが、明確に下総国惣追捕使及び守護であったと記す文書は見つかっていない。ただし、承元3(1209)年12月15日、将軍実朝より「近国守護補任」についてその由緒を調査する「御下文」が発せられた際に、常胤孫の千葉介成胤は「右大将家御時、以常胤、被補下総一国守護職之由申之」があったことを主張しており、補任の文書等はないものの、常胤は下総国守護の地位にあったと考えられる。
なお、下総国は頼朝からの信頼及び勢力規模の大きさから考えて、常胤ではない他人が国惣追捕使として補されることは想定しづらく、当初より常胤は国惣追捕使として下総国の鎌倉家家人郎従の大番催促をはじめ、犯人追捕などの役割を担っていたのであろう。そして建久以降、国惣追捕使の号が廃されて国守護に改められたと思われる。
正治2(1200)年正月2日、常胤は埦飯を沙汰する(『吾妻鏡』正治二年正月二日条)。元日に埦飯を務めた北条時政(筆頭家司)に次ぐ沙汰であり、常胤は御家人筆頭にしてその長老という存在であった事がわかる。しかし、これが常胤が行う最後の埦飯となった。正月3日は三浦介義澄、正月4日は兵庫頭広元、正月5日は八田右衛門尉知家、正月6日は相模守惟義、正月7日は小山左衛門尉朝政がそれぞれ埦飯を行っているが、おそらく常胤と義澄は老衰により傍目から見ても身体の状態や体調が思わしくない状況にあったのではあるまいか。とくに義澄は病であればかなり重篤な状態にあったと思われ、埦飯から二十日後の正月23日、七十四歳で卒去している(『吾妻鏡』正治二年正月廿三日条)。後述の梶原平三景時の死から三日後であった。
正月15日、京都より頼家を従四位上ならびに聴禁色の除書(正月五日の加除儀による)が参着する(『吾妻鏡』正治二年正月十五日条)。これは後鳥羽院の当年御給によるものであった(『明月記』正治二年正月六日条)。『吾妻鏡』では禁色を聴されたのは8日とあるが、『明月記』では叙位同日「左中将頼家禁色」とある。
正月22日、相模国の原宗三郎景房の急使が鎌倉に参着した。それによれば「梶原平三郎景時、此間於当国一宮搆城郭、備防戦之儀、人以成恠之處、去夜丑剋、相伴子息等倫遜出此所、是企謀反有上洛聞」(『吾妻鏡』正治二年正月廿日条)という。去年12月18日に鎌倉を追放された景時は、相模国一宮の旧館の修築を行って防戦に備えていたが、21日深夜丑刻、俄かに館を引き払い、一門を率いて上洛の途に就いたという。これは謀反の企てによるものだという。梶原景時からすれば、傍輩からの弾劾と鎌倉からの追放という状況の中で一宮に留まることは滅亡を意味することであり、活路を見出すとすれば上洛以外に選択肢はないだろう。この一報を受けた鎌倉家職事の北条時政、兵庫頭広元、大夫属入道善信は御所に参じて頼家に報告するとともに対応を協議。景時追討のため「三浦兵衛尉、比企兵衛尉、糟谷藤太兵衛尉、工藤小次郎已下軍兵」の派遣を指示した。
一方、22日の夜亥刻ごろ、「駿河国清見関」あたりに到着した景時父子は、たまたま射的の会から帰途についていた武士等の一団と遭遇してしまう。彼らは駿河国有渡から庵原一帯に強力な地盤を持っていた駿河工藤党の人々で、梶原勢はこの夜道の遭遇に怪しんで矢を射かけてしまう。このため、「廬原小次郎、工藤八、三沢小次郎、飯田五郎」らがこれを追撃し、「狐崎」で景時が返し合わせて合戦に及んだため、工藤党では「飯田四郎等二人」が討たれている。また、庵原小次郎勢に吉香小次郎、澁河次郎、船越三郎、矢部小次郎が加勢に駆け付け、吉香小次郎は梶原三郎兵衛尉景茂と戦ってともに討死を遂げた。兄弟の「六郎景国、七郎景宗、八郎景則、九郎景連等」も見事な戦いぶりを演じるも、六郎景国、八郎景則は庵原小次郎に、九郎景連は工藤八に討たれ、七郎景宗も討死を遂げた。また、文武に秀で頼朝にも愛された景時嫡子・源太左衛門尉景季と平次左衛門尉景高はいったん後山へ引いて戦うも矢部平次との戦いの中で討死。梶原平三景時も矢部小次郎との戦いで討死した(『吾妻鏡』正治二年正月廿日条)。景時、景高、景則の首級が見当たらず、家人によって打ち落とされたのち山中に隠されたとみられ、おそらく彼らは討死ではなく自害であろう。首は翌日発見され、三十三名の家子郎従の首がさらされている(『吾妻鏡』正治二年正月廿一日条)。
●正治2(1200)年1月20日条(『吾妻鏡』)
| 梶原平三景時 | 矢部小次郎に討たれた。郎従が首を山中に隠す。翌日発見され晒された。 |
| 梶原源太左衛門尉景季 | 矢部平次に討たれた。三十九歳。 |
| 梶原平次左衛門尉景高 | 矢部平次に討たれた。 |
| 梶原三郎兵衛尉景茂 | 吉香小次郎友兼と組み打ち、相討。三十六歳。 |
| 梶原七郎景宗 | 討死するが郎従が首を山中に隠す。翌日発見され晒された。 |
| 梶原八郎景則 | 討死するが郎従が首を山中に隠す。翌日発見され晒された。 |
| 梶原九郎景連 | 工藤八郎に討たれた。 |
正月24日、在京の大内惟義、佐々木広綱らへ「平景時有用意事之由依有其聞加誅罸候畢、伴類多在京云々、仍可捜求」の指示を記した頼家御教書が雑色安達源三郎親長を使節として遣わされた(『吾妻鏡』正治二年正月廿四日条)。また、景時朋友であった加藤次景廉は所領を収公されている。翌25日には景時父子に補されていた美作国守護職以下、所領が収公された。そしてその晩、景時の弟・刑部丞友景(六郎朝景)が時政邸に出頭し、工藤小次郎行光に武器を付して献じた(『吾妻鏡』正治二年正月廿五日条)。ただ、朝景が景時と行動を共にしていた様子はなく、そのまま鎌倉に残っていたのかもしれない。朝景はその後許され、子息の次郎景衡、三郎景盛、七郎景氏らとともに御所に出仕するしている。また、景時の滅亡により、景時に侍所別当を奪われていた和田左衛門尉義盛が侍所別当に還補された(『吾妻鏡』正治二年二月五日条)。「景時逐電畢」という報は26日夕刻酉剋に「自関東飛脚到来」により届けられ、翌27日明方には御占が行われたという(『玉葉』正治二年正月廿六日条)。この時点ではまだ景時が討たれた事実は伝わっておらず、29日には上皇は「梶原景時蒙頼家中将勘当逐電之間、天下可警衛之由沙汰之又申院」(『玉葉』正治二年正月廿九日条)と上皇は梶原景時の逐電を不安視し、警衛を強化するよう沙汰している。
そして2月2日、「景時討伐必然」(『玉葉』正治二年正月廿六日条)と、兼実のもとに景時の追討が確報として届けられている。定家も同日「人云、景時已被討了云々、未知其旨」(『明月記』正治二年正月廿六日条)と人伝で一報を入手している。この報に接した兼実は「天下悦也、積悪之輩、尽数滅亡、趙高独運未消、如何」(『玉葉』正治二年正月廿六日条)と、景時を秦の宰相趙高に見立てて、その追討を天下悦と評しているのである。そして29日、兼実はより詳細な情報を「或人」から入手している。その状況によれば「梶原景時企上洛、於駿河国高橋、自鎌倉京方へ五ヶ日之路也云々、為上下向武士併土人等被伐取了、景時、景茂自殺、景季、景高等被討伐畢云々、於法勝寺領古橋庄内、有此事云々、但不知実説、可尋問」(『玉葉』正治二年正月廿九日条)という。2月7日、定家のもとに「三名乳母」が来て語るには、「梶原滅亡事等、其余党等追捕之間、京并辺土多以有事」(『明月記』正治二年二月七日条)という。正月24日に鎌倉から大内惟義、佐々木広綱宛に遣わされた「伴類多在京云々、仍可捜求」の御教書による京中御家人の景時余党の捜索活動であろう。
正治2(1200)年4月1日、鎌倉家の筆頭家司となっていた北条四郎時政に従五位下への叙爵及び遠江守への任官が為された。当時六十三歳(『吾妻鏡』正治二年四月九日条、「将軍執権次第」『群書類従三 補任部』)。この除書は4月9日に鎌倉に到来している(『吾妻鏡』正治二年四月九日条)。そして10月26日、頼家は「中将家任左衛門督、叙従三位給、又所被挙申之、安達源三親長、山城次郎行村等、任少尉」(『吾妻鏡』正治二年十一月七日条)とある通り、従三位に昇り公卿家たる鎌倉家が再興する。また、頼朝雑色だった安達源三親長と、家令の散位行政の子・次郎行村が頼家挙任の通り左衛門少尉に任官している。なお、行村の父である鎌倉家家令の散位藤原行政が山城守に任じられたのは、元久元(1204)年4月13日の臨時除目で「山城藤行政」(『明月記』元久元年四月十三日条)とあり、当時の行村は「山城次郎」ではなく、後年記載された際の誤記とみられる。
頼朝亡き後、鎌倉家の政体は若年の頼家を奉じつつも、実権は蔵人的立場で補佐をする執権の北条氏、家司や職事が主体となった家政機関(政所、侍所)を中心に有力な家人らが政務に参与し、公卿鎌倉家の家政は大きな合議体制へと変化していった。こうした体制の中、常胤は老境にあってこれらに参与することはなかった。
 |
| 千葉山の古墳 |
建仁元(1201)年3月24日、常胤は八十四歳で世を去った(『吾妻鏡』建仁元年三月廿四日条)。その遺骸は「千葉山」に葬られたとされ、金剛授寺尊光院の北部にある千葉山(稲毛区園生町)がその地ではないかと伝えられている。法名は浄春院殿貞見、涼山円浄院。 千葉山には現在でも中世につくられた古墳群が数基現存しており、この地に葬られた可能性が高いと考えられる。この墳丘墓からは鎌倉時代初期の常滑の骨蔵器が発掘されている。
常胤を継承した嫡子胤正も、常胤死去の翌年「建仁二年壬戌七月」(『本土寺過去帳』七日上段)に卒去し、常胤および胤正の父権による統率がなくなってしまったことで、常胤の子や孫は一族としての紐帯は残しつつも(下総国守護としての千葉惣領家による大番催促召集権に基づく一定の支配権も残っている)、常胤の子、胤正の子たちはそれぞれ独立した鎌倉家郎従(御家人)として千葉惣領家からは独立した存在になっている。しかしながら、千葉氏は常胤以来の大名として尊重され、大きな合戦のない時期は歴史的な存在感は見えないものの、以降四百年にわたり下総国主として大きな軍事力と経済力を以て君臨することとなる。
常胤の次男・相馬二郎師常の子孫は下総と奥州とにわかれ、奥州に下っていった相馬家末裔の相馬盛胤・相馬義胤は伊達政宗との戦いで有名。子孫は陸奥中村藩六万石の藩主となった。
三男の武石三郎胤盛の子孫も下総と奥州とにわかれ、奥州へ下った末裔は「亘理氏」となり、室町時代後期の亘理元宗(元安齋)・亘理美濃守重宗は伊達政宗の一門として活躍。子孫は仙台藩一門に遇せられる。
四男の大須賀四郎胤信・五男の国分五郎胤通の子孫も下総と奥州とにわかれたが、下総に残った惣領家は千葉宗家の一族として深く関わった。
六男・六郎太夫胤頼の子孫は歌道を追い求め、藤原俊成、定家、為家ら平安末期から鎌倉初期にかけて構築された歌道を代々伝えることとなった。室町中期の美濃郡上東氏の東下野守常縁は古今和歌集の解釈の根本を切紙で伝える「古今伝授」を確立。後の歌道に大きな影響を与えることになった。
(1)野口実『坂東武士団の成立と発展』弘生書林1982
(2)竹内理三編『平安遺文』東京堂出版
(3)岡田清一『中世相馬氏の基礎的研究 東国武士団の成立と展開』崙書房出版1978
(4)『我孫子市資料 古代・中世編』我孫子市史編さん室1978
(5)柳晃「相馬御厨の四至の変遷について」(『我孫子市史研究』2)1977
(6)岡野浩二「相馬御厨の成立とその前提」(『野田市史研究』)1996
(7)元木泰雄『平清盛と後白河院』角川学芸出版2012
(8)佐々木紀一「『平家物語』の中の佐竹氏関係記事について」(『山形県立米沢女子短期大学紀要』44)
(9)野口実「平清盛と東国武士 : 富士・鹿島社参詣計画を中心に」(『立命館文學』624)
(10)海老名尚、福田豊彦「「六条八幡宮造営注文」について」
(11)『猪隈関白記』『業資王記』は『大日本史料』第四之五、六所収
(12)『明月記』(国書刊行会)
(13)『図書寮叢刊 九条家本 玉葉』(宮内庁書陵部編)
(14)『史料大成25 三長記』(内外書籍株式会社)
(15)『国史大系第九巻 公卿補任』(経済雑誌社)
(16)『新訂増補国史大系 尊卑分脉』(吉川弘文館 黒板勝美、国史大系編修会編)
(17)『将軍執権次第』(「群書類従」第三輯 続群書類従完成会)
(18)『史料大成続編37 三長記補遺』(内外書籍株式会社)
(19)遠藤悦子『建長七年の九条兼実「関白辞職」』(法政史学46)1994
(20)元木泰雄『平安後期の侍所について:摂関家を中心に』(史林64)1981
(21)『国史大系第十四巻 愚管抄』(経済雑誌社)
(22)菱谷武平『「願成就院と永福寺」考:文化指向に関する一示唆』(社会科学論叢6)1956
(23)杉橋隆夫『鎌倉初期の公武関係:建久年間を中心に』(史林56)1971
(24)塩原浩『三左衛門事件と一条家』(立命館文学624)2012
(25)櫻井陽子「頼朝の征夷大将軍任官をめぐって―『三槐荒涼抜書要』の翻刻と紹介―」
(26)『三槐荒涼抜書要』 国立公文書館蔵