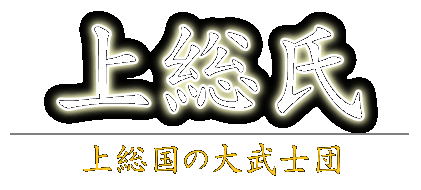
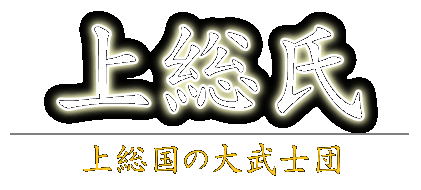
|ページの最初へ|トップページへ|上総氏について|千葉宗家の目次|千葉氏の一族|
| 【一】 | 上総氏について |
| 【二】 | 上総平氏は両総平氏の「惣領」なのか |
| 【三】 | 頼朝の挙兵と上総平氏 |
平常長――+―平常家
(下総権介)|(坂太郎)
|
+―平常兼―――平常重――――千葉介常胤――千葉介胤正―+―千葉介成胤――千葉介時胤
|(下総権介)(下総権介) (下総権介) |
| |
| +―千葉常秀―――千葉秀胤
| (上総介) (上総権介)
|
+―平常晴―――平常澄――+―伊南常景―――伊北常仲
(上総権介)(上総権介)|(上総権介) (伊北庄司)
|
+―印東常茂
|(次郎)
|
+―平広常――――平能常
|(上総権介) (小権介)
|
+―相馬常清―――相馬貞常
(九郎) (上総権介?)
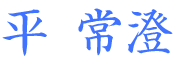 (????~1160頃)
(????~1160頃)
上総介常晴の嫡男。官途は「同(上総)権介」(『桓武平氏諸流系図』)、のち「(下総)権介」(某年「平常澄解」『醍醐寺本醍醐雑事記七裏文書』)。通称は不明。兄弟に戸気五郎長実が見える(『徳嶋本千葉系図』)。「上総氏(上総介平氏)」という武士団の事実上の始祖。
父・相馬五郎常晴は天治元(1124)年6月、甥・平常重を養子とし、さらに下総国相馬郡を常重に継承させた。常晴は相馬郡を継承すると、まず相馬郡布瀬郷、墨埼郷を「別符」の地として国府に申請。その地を伊勢内宮へ寄進し、「布瀬墨埼御厨」を成立させて「大蔵卿(藤原長忠か)」を領家とした。
その後、常晴は甥の常重を養子とした。その時期は「令進退(領)掌之時、立常重於養子」とあることから、常晴が「布瀬墨埼御厨」を成立させたのち養子に迎えたとみられる。そして、天治元(1124)年6月、常晴は常重に「譲与彼郡」し、10月、常重は国判を以て相馬郡司となる。常重を養子とした理由は不明ながら、常晴が常重の父・常兼(常晴兄)の養子となって相馬郡(郡司職含め)を継承したため、その相馬郡を常重に戻す意図か。
●久安2(1146)年8月10日『正六位上平朝臣常胤寄進状』(『鎌倉遺文』)
大治5(1130)年6月11日、相馬郡内布施郷(布瀬郷と同じ)を伊勢内宮に寄進し、8月22日に毎年納められるべき供祭料が決められた。そして12月に寄進が正式に認められ、常重は「下司之職」に任じられた(『下総権介平経繁寄進状』)。その後、保延元(1135)年2月、「地主職(公権とは別の私領主としての権限)」は常重から十八歳になった嫡男・平常胤(のち千葉介常胤)へと譲られた(久安二年八月十日『正六位上平朝臣常胤寄進状』)。
しかし、翌保延2(1136)年7月15日、国司藤原親通は「公田(相馬郡に限ったものではないだろう)」からの税が国庫に納入されなかったという理由で、在国司下総権介常重を逮捕した。こののち、子の常胤が「准白布七百弐拾陸段弐丈伍尺五寸」を勘負したが、押籠は解かれず、親通は11月13日、庁目代の紀朝臣季経に命じて常重から相馬郷・立花郷の「両所私領弁進之由」の新券(地券・証文)を押書し署判を責め取り、そのうちの「相馬郷」についてはのちに次男・親盛に譲られている。公田からの税未進が常重の責任となるということは、常重は親通以前の国司在任中も在国司「権介」として、徴税等の責任者でもあったのだろう。しかし、親通が下総守となるにおよんで未進分が発覚したのかもしれない。未進分は前任分であっても上乗課税されるため、常重を逮捕して未進分を徴税すると称し、それを上回る常重の私領の搾取をしたのかもしれない。
一方、常重の相馬郡継承を快く思っていなかったと思われる常澄は、康治2(1143)年、上総国にあった「上総曹司源義朝」を利用して相馬郡の奪取を図っており、この当時、常澄は上総国にいたことがわかる。
娘 +―平常兼―――千葉介常重――千葉介常胤【下総国千葉庄】
∥ |(下総権介)(下総権介) (下総権介)
∥ |
∥―?―+―相馬常晴――平常澄――――平広常
∥ (相馬五郎)(上総権介) (上総権介)
∥
⇒平常長――+―白井常親・・・【下総国白井庄】
(下総権介)|(次郎)
|
+―鴨根常房・・・【上総国夷隅郡鴨根郷】
|(三郎)
|
+―大須賀常継・・【下総国香取郡大須賀郷】
|(八郎大夫)
|
+―埴生常門・・・【下総国埴生郷】
(九郎)
源義朝は、武蔵国や上総国、相模国などの関東南部各地の源氏勢力の間を渡っており、常澄の「浮言(常澄が相馬郡の領有権を主張したものと思われる)」を利用して、康治2(1143)年、常重から布施郷の「圧状之文(無理矢理書かせた譲状で違法文書)」を取って実質的に押領した。なお、この「布施郷」はもともと下総守藤原親通が常重から圧し取り、次男・藤原親盛(下総大夫)を経て、「匝瑳北条之由緒」によって「源義宗」が譲り受けたものであった。そして源義宗は皇太神宮(内宮)ならびの豊受太神宮(外宮)へ寄進してその下司職となった。この領域と常胤・義朝が寄進した領域はほぼ一致することから、同一の地域であることになる。
義朝は翌天養元(1144)年9月には房総半島を離れて相模国鎌倉郡に移っており、内宮御厨であった大庭御厨に相模国在庁官人・清原安行(義朝郎従)のほか、「三浦庄司吉次、男同吉明、中村庄司同宗平」らとともに御厨下司の大庭景宗の館に押し入って、官物・財物を奪い取る濫妨をはたらいた。景宗はこれを内宮に訴え、朝廷は義朝に濫妨停止および犯人の逮捕の宣旨を発布している。これに対して義朝は伊勢内宮の怒りを解くためか、「恐神威永可為太神宮御厨之由」として、天養2(1145)年3月、布施郷を皇太神宮へ寄進する。「重又令進別寄文」(永暦二年二月二十七日『下総権介平朝臣常胤解案』)や「重寄進了」(永万二年六月十八日『荒木田明盛請文写』)など、二重寄進の実態がうかがえる。
義朝が相馬郡を寄進したことを知った常胤は「上品八丈絹参拾疋、下品七拾疋、縫衣拾弐領、砂金参拾弐両、藍摺布上品参拾段、中品五拾段、上馬弐疋、鞍置駄参拾疋」を国衙に納めたことから、久安2(1146)年4月、下総守は相馬郷の券文を常胤に返還し、国判を以て常胤を相馬郡司職に任じた。ただし、このとき立花郷の返還は認められず、支配権が戻るのは約四十年ののちのことになる。返還されなかったのは、親通流藤原氏が領家を務めることとなる千田庄(この時点で親通領だったかは不明)や、匝瑳北条庄に隣接する地域であって、常胤に返還されなかったのは、親通流藤原氏の地縁的理由が考えられる。
8月10日、常胤は相馬郷については「且被裁免畢」として、改めて皇太神宮(内宮)に寄進し、「親父常重契状」の通り、領主の荒木田正富(荒木田延明の仮名)に供祭料を納め、加地子・下司職を常胤の子孫に相伝され、「預所職」は「本宮御牒使清尚」の子孫に相承されるべきことの新券を奉じた。この時点で常胤は「御厨下司正六位上」を称している。
その後、「平治の乱」で敗れた源義朝が永暦元(1160)年に殺害されると、永暦2(1161)年正月、親通流藤原氏と何らかの所縁(血縁関係か)のあった「源義宗」が、保延2(1136)年11月発給の常重譲状(国司藤原氏へ押書(ただし限りなく圧状に近い)して譲った分)を継承したとして御厨下司職を主張。常澄・常胤を「大謀叛人前下野守義朝朝臣年来郎従等、凡不可在王土者也」として、その正当性を否定した。
なお、常澄と常胤が共闘して義宗に対抗した記録は残っていないが、義宗の御厨下司職に対して常澄が何らかの妨害工作を行っていたことがわかる。常澄の九男・平常清は「相馬九郎」を称しているが、常澄が相馬郡についての権利を行使したことを傍証する文書は遺されておらず、さらに相馬郡は国庁宣によって常胤が相馬郡司たることは確実なので、もし常清が相馬郡内に居住していたとすれば、常澄と常胤は相馬郡の権利に関して一定の妥協を見出し、常清は郡司常胤のもと何らかの協力関係を保ったと見ることもできるか。
これ以降、常澄が相馬御厨に関わった記録は残っていない。
常澄は子息たちを上総国内各地に移して上総平氏の勢力を拡大した。どういった権限によりこうしたことを成し得たのかは定かではないが、長元の乱後に上総国は荒廃し、戦乱前には「二万二千九百八十余町」(『左経記』長元七年十月廿九日條)の公定田(本田)があったが、長元4(1031)年の時点(上総介維時)で「十八余町」にまで激減していたと報告されている。これが、平維時後任の上総介辰重(時重)の補任初年で「五十余町」、四年目の長元7(1034)年で「千二百余町」になったといい、四年間で19分の1回復したことになる。単純に同ペースで興復したとすれば、元に戻るまでは八十年ほど要する計算となるが、人的資源・復興に回す経済的限界も含めると、さらに多くの時間を要したと推測される。
●『左経記』(長元七年十月廿九日條)
こうした中で、下総平氏の千葉三郎常房は、拠点を置いていた匝瑳郡千田郷周辺から上総国夷隅郡鴨根郷へと進出している。これがどういった権限を持って越境したのかは定かではない。しかし、常房の子は総じて匝瑳郡千田郷周辺に拠点を置いて上総国への進出は見られないことから、常房は鴨根郷へ進出するも死去などのため、開発を進めることはなかったと思われる。その跡を継承したとみられるのが常澄の父・常晴であった。常晴は「上総在国分(介)」(『中条家文書』「桓武平氏諸流系図」)、「上総介常晴」(永暦二年四月一日『下総権介平申状案』)と見えるように上総在庁の上職にあり、上総国内(とくに一宮付近や夷隅郡)に権益を築いていた可能性がある。常澄も「同(上総)介」(『中条家文書』「桓武平氏諸流系図」)と見えるように、父常晴の在庁職を継いで「介」となっていたのだろう。常澄は上総在庁時に夷隅郡内の私領を寄進して「伊隅庄」を成立させたと思われ、これを足掛かりに上総国各地に進出していったと思われる。下総国の印東、木内、匝瑳は常澄がもともと私領を有していた地であろう。
●常澄の子の名字地
| 伊南 | 上総国夷隅郡 | いすみ市南部 | 上総初期進出の地 |
| 印東 | 下総国印旛郡 | 酒々井町周辺 | |
| 木内 | 下総国香取郡 | 香取市木内周辺 | |
| 佐是 | 上総国市原郡 | 市原市佐是 | 国衙付近 |
| 大椎 | 上総国山辺郡 | 千葉市緑区大椎 | 国衙付近 |
| 埴生 | 上総国埴生郡 | 長生郡長南町周辺 | 一宮付近 |
| 匝瑳 | 下総国匝瑳郡 | 匝瑳市周辺 | |
| 相馬 | 下総国相馬郡 | 柏市周辺 | |
| 天羽 | 上総国天羽郡 | 富津市周辺 | |
| 金田 | 上総国望陀郡金田 | 木更津市金田東周辺 |
伊隅庄は「上総国伊隅庄事、金剛門院領也」(『吾妻鏡』文治四年六月四日條)とあるように、久寿元(1154)年7月9日に法要が行われた洛南鳥羽の「院新造御堂(金剛心院)」(『宇槐記抄』久寿元年七月九日條)を本家または本所としており、常澄は鳥羽院へ同地を寄進したと思われる。
さらに常澄は息子で望陀郡金田郷(木更津市金田東周辺)の金田頼次を相模国在庁の三浦介義明の女婿として。その地が金田村(三浦市南下浦町金田)になったという。これにより上総平氏と三浦氏との間に強い同盟関係が結ばれたことを意味する。
下総国印東庄預所・勾当菅原定隆との間で、本家(醍醐寺か)に納める馬が遅延したことについて定隆の責任であると主張する解文には「前権介平常澄」とあり、さらに常澄は「地主」であったことも記述がある(『平常澄解』:「醍醐寺本醍醐雑事記七裏文書」)。印東庄は下総国の荘園であることから、常澄は在庁官人「権介」として下総国衙に出仕していた経歴を持っていたことがわかる。菅原定隆は久寿2(1155)年8月10日発給とみられる書状によれば「守親国」の滞納している年貢の弁済を行っており(「菅原定隆書状」「醍醐寺本醍醐雑事記七・八裏文書」『平安遺文』4752)、常澄はこの頃には在庁を辞し、印東荘に居を構えていたことがわかる。
常澄の従兄弟に当たる海上与一介常衡もまた在庁として「介」に補任されており、常衡は常兼の実子ながら祖父・常長の養子となり、末子の扱いとして与一を称したのだろう。
●『桓武平氏諸流系図』(中条家文書) 千葉常永―+―千葉恒家 |
●『徳嶋本千葉系図』 千葉常長――+―千葉常兼――+―海上常衡 |
常澄の没年は不明だが、永暦2(1161)年正月には「自国人平常晴今常澄父也」(『前左兵衛少尉源義宗寄進状』:『鏑矢伊勢宮方記』)とあり「故」とは記されていないが「今常澄父也」と見えることから、すでに没していたと考えられる。
●『平常澄解』(『醍醐寺本醍醐雑事記七裏文書』:『市川市史』所収)