

| 継体天皇(???-527?) | |
| 欽明天皇(???-571) | |
| 敏達天皇(???-584?) | |
| 押坂彦人大兄(???-???) | |
| 舒明天皇(593-641) | |
| 天智天皇(626-672) | 越道君伊羅都売(???-???) |
| 志貴親王(???-716) | 紀橡姫(???-709) |
| 光仁天皇(709-782) | 高野新笠(???-789) |
| 桓武天皇 (737-806) |
葛原親王 (786-853) |
高見王 (???-???) |
平 高望 (???-???) |
平 良文 (???-???) |
平 経明 (???-???) |
平 忠常 (975-1031) |
平 常将 (????-????) |
| 平 常長 (????-????) |
平 常兼 (????-????) |
千葉常重 (????-????) |
千葉常胤 (1118-1201) |
千葉胤正 (1136-1203) |
千葉成胤 (1155-1218) |
千葉胤綱 (1208-1228) |
千葉時胤 (1218-1241) |
| 千葉頼胤 (1239-1275) |
千葉宗胤 (1265-1294) |
千葉胤宗 (1268-1312) |
千葉貞胤 (1291-1351) |
千葉一胤 (????-1336) |
千葉氏胤 (1337-1365) |
千葉満胤 (1360-1426) |
千葉兼胤 (1392-1430) |
| 千葉胤直 (1419-1455) |
千葉胤将 (1433-1455) |
千葉胤宣 (1443-1455) |
馬加康胤 (????-1456) |
馬加胤持 (????-1455) |
岩橋輔胤 (1421-1492) |
千葉孝胤 (1433-1505) |
千葉勝胤 (1471-1532) |
| 千葉昌胤 (1495-1546) |
千葉利胤 (1515-1547) |
千葉親胤 (1541-1557) |
千葉胤富 (1527-1579) |
千葉良胤 (1557-1608) |
千葉邦胤 (1557-1583) |
千葉直重 (????-1627) |
千葉重胤 (1576-1633) |
| 江戸時代の千葉宗家 | |||||||
 (975?-1031)
(975?-1031)
| 生没年 | 天延3(975)年9月13日?~長元4(1031)年6月6日 |
| 別名 | 忠経(『正六位上平朝臣常胤寄進状』) |
| 父 | 平経明 (陸奥介平忠頼?) |
| 母 | 左京大夫藤原教宗女(伝) 平将門女(伝) |
| 室 | 常陸介平正度女(『総葉概録』『千馬家系図』) 武蔵守平公雅女(『千葉大系図』) |
| 位 | 不明 |
| 職 | いずれも在国司職か。 ・上総介(『百練抄』『日本紀略』): ・下総権介(『応徳元年皇代記』):下総帰国後に私領の相馬郡司等に補され、在庁の「権介」となるか。 |
| 所在地 | 下総国(『日本紀略』、『左経記』) ※通説では『今昔物語集』の説話を根拠に香取郡大友とされるが、『今昔物語集』の説話による所在は明確に「彼ノ忠恒カ栖ハ、内海ニ遥ニ入タル向ヒニ有ル也」とある以上は、香取海の入口付近である香取郡に同定はできない。対立関係にあったとされる平維幹は「水漏大夫」と称されるように、その拠点は香取郡から遠く離れた筑波山麓の水守(つくば市水守)一帯でもあり、忠常が香取郡に本拠を有した場合に、どういった対立構図にあったか説明が難しい。 『今昔物語集』で見る「忠恒カ栖」は、忠常子孫が地主職を持ち、且つ香取海に面した地とすれば、印旛郡が妥当であろう。また、相馬郡も香取海に面した地であり、当地には強い将門伝承が残る。忠常と将門の伝承は親和性があり(ともに坂東に乱を起こした平氏という同一性から関連する系譜的・紋様等の伝承)、相馬郡に存在する将門伝承のいくつかは忠常由来のものが相当あるのではなかろうか。 |
| 法号 | 常安 |
良文流平氏四代。平経明の子(『櫟木文書』。諸系譜では陸奥介平忠頼の子)。母は左京大夫藤原教宗女とも平将門女とも(左京大夫教宗の実在は確認できない)。官職は上総介(『百練抄』『日本紀略』)。のち下総権介(『応徳元年皇代記』)だが、いずれも在国司職か。
父は一般には「平忠頼」とされるが、子孫の千葉介常胤が相馬郡を伊勢内外二宮に寄進した久安2(1146)年の寄進状である久安二年八月十日『御厨下司正六位上平朝臣常胤寄進状』と、相馬郡をめぐる左兵衛少尉源義宗との争いの中で、自家が相馬郡を正当に継承してきたことを伊勢神宮に訴えた永暦2(1161)年の永暦二年二月廿七日『正六位上行下総権介平朝臣常胤解案』には、
とあり、平安時代後期には、千葉氏の祖は「忠頼」ではなく「経明」と認識されていたことになる。 これを系譜に直すと、以下のようになる。
平良文―経明―忠経―経政―経長―+―経兼―常重
|
+―常晴
「平忠頼」は寛和2(986)年ごろ、「忠光」とともに、平繁盛(平国香の子で陸奥守貞盛の弟)の比叡山へ金泥大般若経を納めるための使者を武蔵国で妨害すると脅している(実際に行為に及んだ記述はない)。寛和3(987)年正月24日の太政官符によれば、繁盛は忠頼・忠光を「旧敵」と呼んでおり、両者の間には何らかの確執があったことがわかる。忠頼と忠光の関係は『続左丞抄』に記載はないが、平安時代末期成立の『掌中歴』『懐中歴』をベースとする『二中歴』によれば「陸奥介忠依、駿河介忠光忠依弟」とあり、兄弟であることがわかる。
一方、「忠経(平忠常)」は、凡そ長保2(1000)年頃にはすでに両総に勢力を広げており、常陸介源頼信と合戦して家人となっていることから、寛和3(987)年に活躍していた忠頼・忠光との活動時期はほぼ同一とみてよいだろう。世代的なことや「忠頼」「忠光」「忠常」の通字(当時の通字は兄弟で共通字を用いる傾向にあった)を考えると、忠頼・忠光・忠常は兄弟であった可能性も想定できる。また、忠頼は「陸奥介」、忠光「駿河介」を称しているように、それぞれの国の「介」であった。ただし、忠頼・忠光がそれぞれの国の在庁官人とするには不自然であるため、その地位を買官していた可能性も否定できない(関幸彦『「在国司職」成立に関する覚書』参考)。忠頼、忠光が下総国から移ったのちも、忠常は下総国に残ったと考えることもできよう。
また、忠常の父は平良兼流「平致経」とされるものも存在し、奥州千葉氏や新渡戸氏、郡上東氏の一部の系譜に認められる。ただし、「平致経」は伊勢の住人で忠常と同時期に伊勢で同族の平正輔と闘争して朝廷からの譴責を受けていることから、史実ではないだろう。
平高望―+―平良兼―+―平公雅―――+―平致利 +―平致経――?―平忠常
(上総介)|(下総介)|(上総掾) |(出羽守) |(左衛門大尉)(上総介)
| | | |
| | +―平致成 +―平公親――――平公経
| | |(出羽守) |(内匠允)
| | | |
| | +―平致頼―――+―平公致
| | (左衛門尉) |
| | |
| | +―平致光
| | (大宰大監)
| |
| +―平公連
| (下総権少掾)
|
+―平良文―――平経明―――+―平忠頼===?=平忠経
(五郎) |(陸奥介) (上総介)
|
+―平忠光
|(駿河介)
|
+―平忠経―――――平経政――――平経長
(上総介)
●桓武平氏の活躍時期と世代(野口実氏『中世東国武士団の研究』を参考に一部改変して作成)
| 初代 | ニ代 | 三代 | 四代 | 五代 |
| 国香 ・鎮守府将軍 ・常陸大掾 ・935没 |
貞盛 ・940頃活躍 ・947鎮守府将軍 ・972丹波守叙任 ・974陸奥守 ・976馬を貢進 |
維敏 ・982検非違使尉に推薦 ・990頃、肥前守 ・994没 |
||
| 維将 ・973左衛門尉 ・994肥前守 |
維時 ・988右兵衛尉在任 ・1016常陸介在任 ・1029上総介叙任 ・1028上総介辞任 |
直方 ・1028忠常追討使 ・1028追討使更迭 |
||
| 維叙 ・973右衛門少尉在任 ・996前陸奥守 ・999常陸介在任(維幹の誤) ・1000頃常陸介 ・1012上野介在任 ・1015上野介辞任 |
維輔 ・1005検非違使任 |
|||
| 維衡 ・974左衛門尉在任 ・998伊勢で致頼と合戦 ・1006伊勢守→上野介 ・1020常陸介 ・1028郎従が伊勢で濫妨 |
正輔 ・1019伊勢で致経と合戦 ・1030安房守 |
|||
| 繁盛 ・940頃活躍 ・986忠頼らと紛争 |
維幹 ・999常陸介在任 ・1016左衛門尉在任 |
為幹 ・1020常陸で濫妨 |
||
| 兼忠 ・980出羽介→秋田城介 ・1012以前没 |
維茂 ・1012鎮守将軍 ・1017以前没 |
|||
| 維良(維吉) ・1003下総国衙焼討 ・1012頃鎮守将軍 ・1018陸奥国司と乱闘 ・1022没 |
||||
| 良兼 ・931将門と紛争 ・上総介 ・939没 |
公雅 ・940上総掾 ・942武蔵守 |
致頼 ・998伊勢で維衡と合戦 ・1011没 |
致経 ・1019伊勢で正輔と合戦 |
|
| 公連 ・940押領使 ・940下総権少掾 |
||||
| 良持 ・鎮守府将軍 |
将門 ・935国香討つ ・939没 |
|||
| 良文 ・? |
経明(系譜未載) | 忠頼(系譜上は良文男) ・986陸奥介在任 |
||
| 忠光 ・986駿河介? |
||||
| 忠常(系譜上は忠頼男) ・1000~1012源頼信家人 ・1027安房国司を焼殺 ・1028以前上総介辞 ・1031没 |
常昌 ・1031降伏 |
|||
| 常近 ・1031降伏 |
忠常の前半生はまったく知られていないが、後述のように、源頼信が常陸介として下向していた時期の長保2(1000)年頃から寛弘9(1012)年頃には、忠常は「下総国住人」として下総国を本拠に上総国にも影響力を持つほどの勢力を持っていた。
また、忠常は筑波山西麓の筑波郡水漏郷(つくば市水守)から多気(つくば市北条)方面一帯を支配する「水漏大夫」「多気大夫」(『常陸大掾系図』)こと「左衛門大夫平惟基(平維幹)」と予てから敵対関係にあり、「惟基ハ先祖ノ敵」(『今昔物語集』巻廿五第九「源頼信朝臣責平忠恒語」)と述べている。
忠常が述べる「先祖ノ敵」という言葉と、寛和2(986)年7月以前に武蔵国で平繁盛の比叡山への大般若経送達を妨害した「陸奥介平忠頼、忠光等」の「為遂彼旧敵」(『続左丞抄』寛和三年正月廿四日条)という「平繁盛(維幹実父)」と「平忠頼(系譜上忠常父)」の対立構図を重ね合わせて、維幹と忠常は父の代から対立関係だったというのが通説となり、貞盛流平氏と良文流平氏が対立していたという構図の根拠のひとつとなっているが、忠常は「惟基ハ先祖ノ敵」と称しているように、惟基「自身」を先祖(父経明となろう)と認識しており、決して先代同士の対立を持ち出しているわけではない。「惟基(維幹)」と「経明」(永暦二年二月廿七日『正六位上行下総権介平朝臣常胤解案』)の対立も不明である。ただ、「経明」は相馬郡を継承していたことは史料上明確であるため、維幹との対立は、相馬郡の北、筑波郡の南にある常陸国河内郡を挟んだ領地的が介在したものだった可能性が考えられよう。
忠常の下総国における居住地は、子孫の動向や『今昔物語集』の説話、千葉郡東光寺の伝承、平将門説話との親和性、平維幹との対立構図をみると、『今昔物語集』の説話当時の「忠恒カ栖」は、千葉郡、相馬郡、印旛郡(とくにのちの埴生庄、印東庄、印西庄)あたりが妥当であろう。『今昔物語集』からもうかがえるように、当時の忠常は香取海の船を常陸国側のものまでも隠匿できる権勢があり、内海の津々に強い影響力を及ぼしていたと考えらえる。
●忠常の拠点と推測される地
| 郡 | 平安後期 | 凡そ現在地 | 備考 |
| 千葉郡 | 千葉庄 | 千葉市内 | ・忠常開基と伝わる広徳寺、子・常将の建立とされる平山寺の後身と伝えられる平山東光院(緑区平山町)が残る。 ・上総・下総国府にも官道で繋がる要衝。 ・在庁官人忠常の在郷居館としては国府に繋がる有益な地である。 【将門と忠常の伝承的親和性】 ・将門伝承が継承されている。 |
| 相馬郡 | 相馬御厨 | 柏市 鎌ケ谷市 我孫子市 守谷市 周辺 |
・「彼ノ忠恒カ栖ハ内海ニ遥ニ入タル向ヒ」に相当する。 ・相馬郡には将門伝承が多く残されており、その中には忠常由来のものもあるか 【将門と忠常の伝承的親和性】 ・忠常妻は将門女子 ・忠常子孫の相馬氏は将門子孫の伝承 ・忠常子孫が用いる九曜紋と将門の九曜紋(両者ともに牛頭信仰の影響か) |
| 印旛郡 | 印東庄 | 酒々井町 八街市 佐倉市 富里市 周辺 |
・「彼ノ忠恒カ栖ハ内海ニ遥ニ入タル向ヒ」に相当する。 ・印東庄は子孫常澄が地主職。 【将門と忠常の伝承的親和性】 ・いずれの地にも将門伝承が継承されている。 |
| 印西庄 | 印西市周辺 | ||
| 埴生庄 | 成田市 栄町 周辺 |
||
| 臼井庄 | 佐倉市臼井周辺 |
『今昔物語集』の説話によれば、常陸介頼信の追捕に屈した忠常は降伏して名簿を差し出す。おそらくその後、藤原教通の知遇を得てその家人となったのだろう。のちに長元の乱に際して忠常は教通に使者を送って働きかけをしており、教通も忠常とは面識を持っていたのだろう。その後、忠常は「上総介」(『百練抄』『日本紀略』)に就いている。
なお、この「上総介」は在国司職と思われるが、上総国においては「介」が事実上の最上位であるため、在庁が上総国において「介」を称することがあったのかは不審である。忠常が「上総権介」だったとする史料はなく、この「上総介」が除目によるものであれば、忠常は受領である。ただし、受領補任には通常は京官を経る必要があり、さらに位階も上総介であれば「従五位下」が通例である。つまり、忠常が受領であれば数年から十数年間の在京を必要とするが、そもそも忠常の父祖が京官を経た形跡もなく、その先例を見る限り、忠常が受領として上総国に下向していたということはほぼあり得ない。つまり、忠常は上総国の在庁官人で在国司職「介」であったと推測される。彼の子孫の常晴は「上総在国介」、その子常景も「同介」とみられるため、彼等も「上総介」ということになるが、子孫の上総「権介」秀胤もまた「上総在国介」とあるため(『桓武平氏諸流系図』)、「上総在国介」とはすなわち「上総権介」を指すものかもしれない。
上総国にあった当時の忠常は、在庁最高位に位置していたと思われ、上総国府(市原市村上付近歟)付近に居住しつつ、同時に上総一宮の玉前神社(長生郡一宮町一宮)周辺にも館があったのだろう(のちに忠常が夷隅山に籠った例や、子孫の一宮館居住もまたその名残といえよう)。
その後、忠常は上総国から下総国に戻り、下総国の在庁になり「下総権介」に就いたと思われる。なお、忠常の本貫はあくまでも下総国であって上総国ではない。子孫が上総国に進出するのは千葉三郎常房が千田郷を通じて夷隅郡へ入部するまで二百年を要するのである。長元の乱当時の忠常は「下総権介平忠常」(『応徳元年皇代記』千鳥家本、『編年残篇』)であり、忠常は下総国の私営田を地盤としてその勢力を拡大していったのだろう。
在庁下総権介としての忠常の居館は、まず国府に近い千葉郡にあったのだろう。子孫の千葉氏が早々にここを拠点としているように(千葉氏が大友→大椎→千葉という経路をたどって入部したなどという伝承は当然史実ではなかろう。とくに「大椎」は、後世に系譜で常重の脇註に記した尊称「大権介」を誤読した可能性が高い)、古くから忠常が開発した地であったと想定される。千葉郡には忠常ゆかりの伝承のある東光寺があり、さらに上総と下総を繋ぐ陸路の要衝でもあった。
また、古くから忠常私領として確認できる相馬郡は、子孫の千葉介常胤が「是元平良文朝臣所領、其男経明、其男忠経…」と「先祖相伝領地」(永暦二年二月廿七日『正六位上行下総権介平朝臣常胤解案』)と述べる地であり、「天治元年六月所譲与彼郡也、隨即可令知行務郡務之由、同年十月賜国判之後…」(久安二年八月十日『正六位上平朝臣常胤寄進状』(『鏑矢伊勢宮方記』:『千葉県史料』中世編))とあるように、相馬郡司職も相伝しており、忠常もまた相馬郡司だった可能性を示唆する。
■久安2(1146)年8月10日『正六位上平朝臣常胤寄進状』(『鎌倉遺文』櫟木文書)
■桓武平氏略系図(太字は貞盛の子、および養子になったと思われる人物)
平高望―+―平国香―――+―平貞盛――――+―平維敏
|(常陸大掾) |(鎮守府将軍) |(肥前守)
| | |
| | +―平維将――――平維時―――平直方
| | |(肥前守) (上総介) (右衛門少尉)
| | |
| | +=平維叙――――平維輔
| | |(常陸介) (左衛門尉)
| | |
| | +=平維衡―――………………―平清盛
| | |(伊勢守)
| | |
| | +=平維幹
| | |(常陸介)
| | |
| | +=平維忠
| | |(出羽守)
| | |
| | +=平維時
| | |(上総介)
| | |
| | +=平維輔
| | |(左衛門尉)
| | |
| | +=平維茂
| | |(鎮守府将軍)
| | |
| | +=平維良
| | (鎮守府将軍)
| |
| +―平繁盛――――+―平維幹―――………………―常陸大掾家
| (武蔵権守) |(常陸大掾)
| |
| +―平維忠
| |(出羽守)
| |
| +―平兼忠――+―平維茂
| (上総介) |(鎮守府将軍)
| |
| +―平維良(維吉)
| (鎮守府将軍)
|
+―平良持―――――平将門――――――娘
|(鎮守府将軍) (小次郎) (忠頼妻?)
| ∥?
+―平良文―――――平経明――――――平忠常
(陸奥守) (上総介)
『今昔物語集』には、河内源氏の源頼信が「常陸守(常陸介)」のときに忠常と下総国に戦い、降伏した話が伝わっている(『今昔物語集』巻廿五第九「源頼信朝臣責平忠恒語」)。
●『今昔物語集』巻廿五 第九「源頼信朝臣責平忠恒語」
『今昔物語集』にみられる忠常が「惟基ハ先祖ノ敵也」と述べる「左衛門大夫平惟基」は、通説では上記の平維幹と同一人物とされている。
平維幹は長保元(999)年12月9日当時、「常陸介」(『小右記』長保元年十二月十一日条)だったが、『今昔物語集』にみられる維幹は「左衛門大夫平惟基」とあり、五位の左衛門尉である。当時、国司を経て左衛門尉へ任官する例はなく、維幹が「左衛門大夫」であったとするならば、当然常陸介就任前である。つまり、平維幹=左衛門大夫平惟基であるならば、頼信と忠常の戦いは、維幹が常陸介在任中の長保元(999)年以前となる。しかし、長保元年以前の頼信は「上野介」であり、常陸介に補任される前なのである。
ただし、この矛盾については『今昔物語集』は伝承を後世に説話集としてまとめたもので、「左衛門大夫平惟基」については一般的に流布伝承されていた通称が用いられた可能性もある(頼信については「河内守源頼信朝臣」が「頼信常陸守ニ成テ其国ニ下リ有ケル間」が事件の時期の前提であるため、伝承と記述は同じである)。
●十一世紀初頭の常陸介の予想任期
| 名前 | 補任 | 離任 ※離任日不明のため、離任直近除目日 |
備考 |
| 平維幹 | 不明 | 長保2(1000)年 正月22日? |
長保元(999)年12月9日 「常陸介維幹朝臣、先年所申給、崋山院御給爵料不足料絹廿六疋及維幹名簿等送之、以維幹可預栄爵者、維幹余僕也、進馬三疋毛付、以院判官代為元令奉絹及維幹名簿等」 (『小右記』長保元年十二月十一日条) ――――――――――――――――――――――同(寛仁)4(1020)年7月3日 「常陸介惟通妻子為維幹息被取事於任国卒去時」 (『小記目録』) ―――――――――――――――――――――― 寛仁4(1020)年閏12月13日 「漏聞召為幹朝臣之使貞光密々来云、為幹入京、可令候之處事、示遣史奉親朝臣所、未仰左右、仍密々預前常陸介維時朝臣、明曉罷向随身為幹、借小人宅令候、可待宣旨者、是余指示也、彼奪取命婦、太皇太后御使相共同入京者」 (『小右記』寛仁四年閏十二月十三日条) |
| 平維敍 | 長保2(1000)年 正月22日? |
長保6(1004)年 正月22日? |
実右大将済時卿男か。 小一条院敦明親王の叔父 正暦6(995)年に陸奥守離任か ※その三、四年後に常陸介(『今昔物語集』) 長徳2(996)年5月当時、「陸奥の国の前守維敍」 (『栄花物語』) |
| 某 | 寛弘4(1007)年 正月26日? |
※長和2(1013)年正月20日、「入夜、前常陸介師長密語云、蔵人登任初可着綾、可用左三位中将蘇芳下襲、無頼殊甚、万計難施者、有歎息気、仍興未着之桜色下襲、感悦将去」(『小右記』長和二年正月廿日条) | |
| 源頼信 | 寛弘4(1007)年 正月26日? |
寛弘7(1010)年 正月? |
寛弘9(1012)年閏10月23日 「入夜前常陸守頼信、献馬十疋」 (『御堂関白記』寛弘九年閏十月廿三日条) とある。しかし、常陸介退任後の受領功過定において、 長和5(1016)年正月12日 「依相府被示、余召受領功過文書相定、相模守孝義有事、亦常陸介頼信状帳、填交替欠事不明、仍令召税帳又神社事不修一社」(『小右記』長和五年正月十二日条)など、在任中の官物貢納の不備や神社不修のため、その後数年は受領になれなかった(検非違使だった)。そして寛仁3(1019)年正月22日の受領功過定(二日目)において、「前常陸介頼信不与状、神社数事年来有疑無一定、後々司実録言上、依彼帳可有定之由、頼信所申」(『小右記』寛仁三年正月廿二日条)との主張が左中弁経通を通じて摂政に伝えられた。結果としては陣定で主張は容れられたようで、頼信は翌23日の除目で受領に推されることとなる。この際、私君頼通の引級で遠江守に補されると大方の予想だったが、実際に遠江守に補されたのは藤原兼成だった(予想では任石見守)。これは頼通が実資の助言を受けた結果で、頼通は家人の頼信を「若以頼信任遠江、必可有謗難歟者」として、実資に感謝を述べている。結果、頼信は石見守となり、同年7月8日「石見守頼信、触明日向任国之由、呼前給禄」と、実資は頼信を邸に招いて禄を与えた。実資は「頼信入道、殿近習者也」(『小右記』寛仁三年七月八日条)と記しており、頼信は頼通の近習だったことがわかる。 頼信の父満仲と平維幹は従兄弟(『系図纂要』)。 子の頼義は小一条院敦明親王判官代 |
| 藤原通経 | 寛弘8(1011)年 2月2日「常陸守」(『小右記』) |
長和4(1015)年? |
紫式部の従兄弟 |
| 平維時 | 長和4(1015)年 | 寛仁3(1019)年 正月21日? |
紫式部の従兄弟 |
| 藤原惟通 | 寛仁3(1019)年 7月13日 「任常陸、敍一階若然歟」(『小右記』) |
紫式部の弟 |
光孝天皇―――宇多天皇
∥
∥――――――醍醐天皇―――村上天皇―+―冷泉天皇―+―花山天皇
∥ | |
∥ | |
∥ | +―三条天皇
∥ | ∥――――――敦明親王
∥ | ∥ (小一条院)
∥ | 藤原済時―+―藤原娍子
∥ |(右大将) |
∥ | |
∥ | +―平維敍
∥ | (常陸介)
∥ |
+―藤原高藤―+―藤原胤子 藤原忠幹―――女子 +―円融天皇―――一条天皇―――後朱雀天皇――後三条天皇
|(内大臣) | (筑前守) ∥
| | ∥――――――藤原通経―――藤原章祐
| | ∥ (常陸介) (上総介)
| +―藤原定方―+―女子 +―藤原為長
| (右大臣) | ∥ |(陸奥守)
| | ∥ |
| | ∥――――+―藤原為時―+―藤原惟規
| | ∥ (越後守) |(散位)
| | ∥ |
| | ∥ +―藤原惟通
| | ∥ |(常陸介)
| | ∥ |
| | ∥ +―女子
| | ∥ (紫式部)
| | ∥ ∥――――――女子
| | ∥ ∥ (大弐三位)
| +―∥――――――藤原為輔―――藤原宣孝
| ∥ (権中納言) (右衛門佐)
| ∥
| ∥ +―藤原為頼
| ∥ |(太井皇太后宮大夫)
| ∥ |
藤原良門―+―藤原利基―――藤原兼輔―――藤原雅正―+―女子
(内舎人) (右中将) (中納言) (豊前守) ∥――――――平維時――――平直方
∥ (上総介) (上野介)
平国香――+―平貞盛――+―平維将
|(陸奥守) |(上総介)
| |
| +―平維時
| |(上総介)
| |
| +―平維幹
| |(常陸介)
| |
| +=平維敍
| (常陸介)
|
+―平繁盛
(常陸大掾)
∥――――+―平維幹
∥ |(常陸介)
∥ |
清和天皇―――貞純親王―+―女子 +―平兼忠――+―平維吉
(中務卿) | (上総介) |(鎮守府将軍)
| |
| +―女子
| ∥
| 藤原正雅―――藤原師長―――藤原登任
|(伊予守) (常陸介) (陸奥守)
|
+―源経基――――源満仲――――源頼信
(武蔵介) (陸奥守) (常陸介)
『今昔物語集』の説話を見る限りでは、当時の忠常は頼信自身に対して敵対行為をしていたわけではなく、ましてや平維良(「故兼忠朝臣男維吉」(『御堂関白記』寛弘九年閏十月十六日條)と同一人物だろう)のように、長保5(1003)年正月頃、下総国府を攻めて「燃亡府館、掠虜官物」(『百錬抄』長保五年二月八日条)し、「蒙追捕官符」(『小右記』長和三年二月七日条)るような叛乱も起こしてもいない。ところが、頼信はなぜか任国ではない「下総国」の住人忠常に対して「常陸守ノ仰」を伝えているのである。
忠常は「上総下総ヲ皆我マゝニ進退シテ、公事ヲモ事ニモ不為リケリ」とあるように、上総国、下総国における「公事」を怠っていたというが、頼信はこの事についてはおそらく不介入であった。他国の内政に関与することは当然越権行為である以前に、説話上のこの文意は、あくまでも忠常の非道ぶりを記している形容的なものだからである。頼信が問題視したのは次の話題である「亦、常陸守ノ仰ヌル事ヲモ、事ニ触レテ忽緒ニシケリ」という部分であろう。ただ、この「常陸守ノ仰ヌル事」が具体的に何を指すのか、残念ながら『今昔物語集』には記されていない。しかし、頼信が「大キニ此レヲ咎メテ、下総ニ超テ忠恒ヲ責メム」(『今昔物語集』巻廿五第九「源頼信朝臣責平忠恒語」)と、越権行為である他国に越境してまで攻めようとしたのは、常陸国に関する何らかの侵害があったと考えるのが妥当であろう。推測するに、それは忠常が「惟基ハ先祖ノ敵也」と述べる「左衛門大夫平惟基」との対立と関係があろう。のち頼信が下総国へ越境するにあたり、忠常は「其ノ渡ノ船ヲ皆取リ隠シテケリ、然ルハ可渡キ様モ無ク」(『今昔物語集』巻廿五第九「源頼信朝臣責平忠恒語」)と、あるように、常陸国内海にも強い影響力を持っていた様子をうかがわせる。頼信は忠常の常陸国における何らかの行為を咎めて、その停止を「仰ヌル事ヲモ」、忠常は「事ニ触レテ忽緒ニシ」たため、頼信は激怒したと考えられる。
なお、他国への犯罪者の対応としては、当該国の「押領使」が他国に越境して、他国に逃亡した犯罪人の捕縛を認める規定もあった。これは長保5(1003)年正月頃の平維良の叛乱を受けて設けられたものかもしれない。平維良の叛乱から二年後の寛弘2(1005)年4月14日、上野介橘忠範はこの規定についての意見として「被載許雑事三箇条事」を申請している(「寛弘二年四月十四日条事定文写」『平安遺文』439)。
この二条目で、凶賊追捕のために「下野、武蔵、上総、下総、常陸等国」に「押領使」の補任を申請している。押領使については「当国押領使及随兵等、任前例可被裁許歟」と見えることから、これまでと同様に国司等の兼帯での押領使官符となろう。また一方で、三条目にあるように凶党が隣国から移り住んできた際に、「隣国々司并隨兵郎等、恣越来残滅所部」ことを停止してほしい旨も伝えているように、押領使たる隣国国司はその追捕のために、本来管轄外の国へ「恣越来、残滅所部」というように、村落などに壊滅的な被害を与えることも少なくなかった。陣定では「隣国凶党、若有越住当境者、待国司之移蝶、慥可糺行」ことを追認しているように、他国に逃げ込んだ凶党を引き続き追捕することは認めるが、「待国司之移蝶」という条件が付けられ、且つ「恣以越来、残滅所部」は認めず「早可給制符歟」としている。それでも「若不憚制止、猶有越来之者」については「言上解文之日、隨其状迹可定行歟」とし、他国押領使等の侵攻による村落被害は罪過に問われる可能性を示唆する。
『今昔物語集』の頼信による下総越境事件は、上記の例のように、常陸国の「押領使(記録はない)」として下総国の忠常を追捕した、という構図が想定される。
頼信が下総国に忠常を攻めるという話を聞いた「左衛門大夫平惟基」は、
と大軍を以って攻めることが肝要と説いた。こうして「惟基」は三千騎の軍勢を整えて鹿島宮の社前に集結。また頼信も「舘ノ者共、国ノ兵共」二千人ばかりを集めて「鹿島ノ郡ノ西ノ浜辺」に集まった(『今昔物語集』巻廿五第九「源頼信朝臣責平忠恒語」)。
忠常の当時の本拠は、
という位置にあった。
「衣河(キヌガワ)」とは現在の小貝川(こかいがわ)のことで、この「衣河ノ尻」つまり小貝川から香取海(内海)にそそぐ河口部分は、現在の竜ケ崎市から利根町のあたりにあり、幾重にも分かれた小川が蛇(蛟蛧=文間)のように複雑に流れて内海へ注いでいた。また、この内海は「鹿島梶取ノ前ノ渡ノ向ヒ顔不見エ程也」とあるが、鹿島神宮前浜と香取神宮前浜の間は十キロメートル程度離れており、人すら認識できる距離ではない。つまり、イメージを持たせる記載であろう。
なお、この文は、
(1)「衣河ノ尻ヤガテ海ノ如シ、鹿島梶取ノ前ノ渡ノ向ヒ顔不見エ程也」→→内海の状況を説明
(2)「而ニ彼ノ忠恒ガ栖ハ、内海ニ遥ニ入リタル向ヒニ有ル也」→→内海に対する忠常の住地を説明
とあるように(2)の文頭で「而ニ」という転換を意味する接続詞が用いられており、前文と後文は文意が直接的につながらないことがわかる。つまり(1)と(2)は相関関係ではなく、(1)(2)にある「鹿島梶取ノ前ノ渡」と「忠恒ガ栖」は「内海」に関わる別の文であって、忠常の拠点を香取郡と示しているわけではない。忠常の拠点を香取郡とするのは(1)(2)を連続した文と誤読した結果によるものであろう。『玉葉』に見られる「如何」「何如」の誤読も然り。過去に誤読された通説(または確たる証拠ではなく推論に推論を重ねた通説)が、無検証のまま用いられている現状が、結局回収できない矛盾をいくつも生んでいく。
忠常の在所については、この説話には「彼ノ忠恒ガ栖ハ、内海ニ遥ニ入リタル向ヒニ有ル也」と明確に記されている。「遥ニ入リタル」とは、内海の入口(現在の神栖市と銚子市の境)を起点として、遥かに奥に入った地と考えるよりほかにない。そして「向ヒ」とは、物語の主体である常陸介頼信の任国常陸国を起点と考えるため、常陸国から見た内海を挟んだ下総国ということになる。
この情報を総合的に判断すると、『今昔物語集』でいう忠常の「栖」は、「良文朝臣」以来忠常も私有し、千葉氏へと継承された相馬郡、または印旛郡(のちの印東庄や印西庄、埴生庄など)に相当しよう。とくに相馬郡は、
(1)下総国府(市川市)・上総国府(市原市)ともに近い。
(2)相馬郡の内海沿いには陸の官道や駅、郡衙が存在し、東西の水運・軍事・流通の要であった。
(3)両総平氏は相馬郡を「平良文朝臣」以来の私領として大変に尊重している。
という理由により、忠常の拠点としても相応しい。また、平維幹との確執についても、香取海のもっとも奥まった相馬郡であれば、彼の拠点がある筑波山麓とも河内郡を挟んで隣り合い、土地を巡る紛争があったとしてもおかしくはない。さらに、平忠常と平将門の説話は親和性が高く、相馬郡に残る将門伝承、とくに相馬郡南部から印旛郡にかけては、本来将門とは関わりのない地であるにも拘らず将門伝承が盛んである。これらは忠常と将門の伝承が交わりあった結果であるのかもしれない。
●房総平氏と相馬氏●
⇒平常長―――+―千葉介常兼―千葉介常重―――――千葉介常胤―+―千葉介胤正
(上総権介) |(下総権介)(下総権介) (下総権介) |(千葉介)
| ↑ ↑ ↑ |
| | | | +―相馬師常
| 相馬郡譲渡 対 立 (次郎)
| ↑ |
| | ↓
相馬郡継承⇒+―相馬常晴―――――平常澄――+―平広常
(上総権介) (上総権介)|(上総権介)
|
+―相馬常清
(九郎)
ただし、『今昔物語集』での忠常の「栖」は相馬郡ではなかろう。おそらく印旛郡の入江(現在の成田市土屋付近など入江の奥まった部分か)が可能性としては高いと思われる。その理由としては、後述のように国司頼信と維幹が勢を揃えたのが鹿嶋宮前であるという点である。
相馬郡は筑波郡に近く、常陸国府から繋がる官道も通る陸路の要衝である。つまり相馬郡に向かうのであれば鹿嶋宮に揃う必要もない。しかし、印旛郡であれば鹿嶋から行方郡を通り香取郡へ渡るルートが最も近くなる。このルート上には、西側と北側からの流入口の合流点があり、砂が集まりやすかったためか、いくつかの浅瀬が形成されていたようである。後世に内海に土砂の堆積により陸地化していく過程で十六島と呼ばれる砂州地が形成されていた。のちに頼信が馬で渡ったというのは、この地か。
さて、鹿島宮の西の浜辺に滞陣した頼信・惟基の軍勢だが、「其ノ渡ノ船ヲ皆取リ隠シテケリ、然ルハ可渡キ様モ無クテ、浜辺ニ皆打立テ、可廻キニコソ有ヌレナト」(『今昔物語集』巻廿五第九「源頼信朝臣責平忠恒語」)と、舟はすでに忠常に奪取されており、内海を渡る術がなかった。内海の舟を忠常は内海の権益に影響力を及ぼしていた様子がうかがえる。このため、頼信は常陸国衙在庁と思われる「大中臣成平」を召し、彼を使者として忠常のもとに派遣し、
と最後通牒を送り、不戦で降伏させようと試みた。その後、忠常のもとから戻った成平は、
と、頼信を尊重しているが、その麾下にいる「先祖ノ敵」惟基の前に跪くことはできないと、降伏を断った。そこで頼信は内海の縁を廻って攻めるべきだとする軍兵の反対を押し切り、忠常の裏をかいて、今日中に海を渡って進発することを命じた。舟の無い中で海を押し渡ることについて頼信は、
と、浅瀬を渡って対岸へ向かうことを提案。ここに「真髪ノ高文」という人物が名乗りをあげ、浅瀬を案内した。二度ばかり泳ぐ箇所があったものの、頼信は軍勢のうち五、六百人あまりとともに下総国へ上陸したという。この浅瀬とは、前述のように砂州の形成されやすい海流があったと思われる、潮来町と香取神宮を結ぶ幅五キロほどの海域か。
このとき忠常は、頼信らには舟がないため、陸路を廻ってくるものとして策を立てていたが、郎従らがあわてて忠常のもとへ飛び込み、
常陸殿ハ此海ノ中ニ浅キ道ノ有ケルヨリ、若干ノ軍ヲ引具シテ既ニ渡リ御スルハ、何カセサセ給ハム
と狼狽して言うと、忠常も計画が水泡に帰したことを悟り、
今ハ術無術無進テム
と降伏を決意。「名符」と「怠状」を具し、郎従に持たせて小舟で頼信の陣所へ遣わした。頼信も「不戦ト思ハバ速ニ参来」という考えであり、降伏したのちは「強チニ責メ可罰キニ非ズ、速ニ此ヲ取テ可返キ也」と言って、軍勢を常陸へ返したという(『今昔物語集』巻廿五第九「源頼信朝臣責平忠恒語」)。「名符=名簿」を差し出すことは臣従の意味合いがあり、忠常は頼信の家人となった。
この『今昔物語集』巻廿五第九「源頼信朝臣責平忠恒語」の説話はいつの事なのだろうか。
説話では源頼信が常陸介だった時期の出来事であるが、源頼信が「常陸守(常陸介)」だった期間の頼信に関する記録は残念ながら遺されていない。
●源頼信の官途
源頼信の史料上の初見は、寛和3(987)年2月19日の慧心院造堂の成功による叙位で、当時左兵衛尉であった(『小右記』寛和三年二月十九日条)。永承3(1048)年9月1日、七十五歳で卒去(『系図纂要』)とすると、十四歳のときである。
正暦5(994)年3月6日、朝廷は「召武勇人源満正朝臣、平惟時朝臣、源頼親、同頼信等、差遣出々、令捜盗人」(『日本紀略』)とあるように、叔父満政や兄の頼親らとともに武勇の人として認識されていた。当時二十一歳である。この後、上野介に補任されており、長保元(999)年9月2日には「上野守(上野介)」として藤原道長に馬を献じている(『御堂関白記』長保元年九月二日条)。頼信は受領として上野国に赴任しており、『今昔物語集』にその記述がみられる。
●「藤原親孝為盗人被捕質依頼信言免」(『今昔物語集』語第十一)
その後、頼信は常陸介に転任している。補任時期は明確ではないが、
(1)「左衛門大夫惟基(平維幹)」よりも後に常陸介に補任
(2)維幹から頼信までは、少なくとも平維敍、藤原師長の二名が常陸介に補任されている
(3)寛弘9(1012)年閏10月23日当時、頼信は「前常陸守」(『御堂関白記』寛弘九年閏十月廿三日条)
ということから考えると、頼信の常陸介任官期間は、寛弘4(1007)年正月26日の縣召除目(『権記』寛弘四年正月廿六日条)から寛弘8(1011)年2月2日の除目以前までと推測される。
●平維幹の官途
「左衛門大夫平惟基」こと平維幹は、出羽守繁盛の子で伯父の陸奥守貞盛の養子になった人物。常陸大掾家の祖であるが、奥州伊達家の祖でもあろう。
平国香――――平繁盛 +―平為幹―――…―大掾家 +―伊佐為宗
(鎮守府将軍)(出羽守) |(散位) |(皇后宮大進)
∥ | |
∥―――――平維幹――+―平為賢―――………――――――――――常陸入道――+―伊達為家
∥ (陸奥守) (散位) (西念) |(右衛門尉)
∥ |
貞純親王―+―女子 +―大進局
| ∥
+―源経基―+―源満仲――+―源頼光 ∥
(武蔵介)|(陸奥守) |(摂津守) ∥
| | ∥
+―源満政 +―源頼親 ∥
(陸奥守) |(大和守) ∥
| ∥
+―源頼信――源頼義――源義家――源為義――――源義朝――源頼朝
(河内守)(陸奥守)(陸奥守)(左衛門大尉)(下野守)(権大納言)
長保元(999)年12月9日、「常陸介維幹朝臣、先年所申給、崋山院御給爵料不足料絹廿六疋及維幹名簿等送之、以維幹可預栄爵者、維幹余僕也、進馬三疋毛付、以院判官代為元令奉絹及維幹名簿等」(『小右記』長保元年十二月十一日条)と見えるように、維幹は長保元(999)年当時、常陸介であった。このとき、維幹は私君である中納言実資に先年「崋山院恩給」による昇進を依頼していたが、爵料が不足しており叶わなかった。そこで維幹は「不足料絹廿六疋」と「維幹名簿」を実資に馬三疋とともに送付した。これを受けた実資は花山院判官代為元を通じて花山院に奉献し、御給による維幹の昇進を依頼している。この願いは二日後の12月11日、「為元朝臣来、院仰云、常陸介維敍(維幹)朝臣進絹令納給了、但以明年御給栄爵可給維幹之由可仰遣者」(『小右記』長保元年十二月十一日条)と、明年正月除目により、維幹の「御給栄爵」が決定された旨が実資に伝えられている。これにより翌長保2(1000)年正月22日の「除目儀」(『権記』長保二年正月廿二日条)の「院宮御給」で「以上今日可給、又任国公事究済旧吏一束」とある通り、常陸介維幹が常陸国の公事を究済していた場合は、この御給によって叙爵(従五位下)したと思われる。
その後の維幹の官途は伝わっていないが、維幹は常陸介が秩満後も帰洛せずに常陸国に在国して在国領主化し、下総国の平忠常との間に何らかの紛争があった可能性がある。
なお、同日条の「常陸介維敍」(『尊卑分脈』の註では「実右大将(済)時卿男」と見える)は、文意から見ても「常陸介維幹」の誤記である。維敍が常陸介になったのは、後述の通り維幹の後である。
●平維敍の官途
平維幹の後任常陸介である平維敍の官途は、永観元(983)年8月の除目で「任肥前国守(当時従五位下)」(『類聚譜宣抄』八 任符事)、次いで正暦2(991)年正月の除目で陸奥守に補任されたとみられ、正暦元(990)年時点の陸奥守(『本朝世紀』)藤原国用の秩満後、「陸奥守維敍」として陸奥国に「著任」(『北山抄』吏途指南)している。
その後、陸奥守として四年の任期を全うし、正暦6(995)年正月13日の縣召除目で左近衛中将実方が陸奥守に補任(『中古歌仙三十六人伝』)されるまで陸奥国に在国。秩満後は帰京し、それから三、四年後に「常陸ノ守」に補任されたという(『今昔物語集』卅二「陸奥国神報平維叙語」)。藤原隆家らが花山院を射た罪で邸を囲まれた長徳2(996)年5月当時、内裏は「内には陣に陸奥の国の前守維敍、左衛門尉維時、備前前司頼光、周防前司頼親など云ふ人々」が護衛した(『栄花物語』)とあるが、その記述に矛盾はない。
『今昔物語集』の通り、陸奥国から帰洛後三、四年後に常陸介に補任されたとすれば、維敍の常陸介任官期間は、維幹の常陸介在任が確認できる長保元(999)年12月以降から長保6(1004)年正月までと推測されるため、維幹の後任常陸介が維敍となろう。
その後十年余りの間、維敍の名は史料から見えなくなるが、長和元(1012)年閏10月17日には「上野守維敍、献馬十疋」(『御堂関白記』長和元年閏十月十七日条)と見え、この時期には上野介在任中であったことがわかる。その後、長和4(1015)年8月27日に任期途中で「上野守維敍辞退、仍被任弾正小弼定輔」と上野介を辞退した(『御堂関白記』長和四年八月廿七日条)。病のためと思われる。
翌長和5(1016)年5月15日に「前上野介維敍、今日可出家之由、昨日令申摂政殿云々、仍差忠時問遣、即帰来云、近日所労更発、未死前、今朝遂本意了者、重令労問」(『小右記』長和五年五月十五日条)とあり、重病に陥ったために出家した。その後一時的に快復したようで、翌寛仁元(1017)年9月17日、「維敍法師、献馬一疋」(『御堂関白記』寛仁元年九月十七日条)している。ただ、それからわずか一月後の寛仁元(1017)年10月16日に亡くなったという(『系図纂要』)。
寛弘9(1012)年閏10月23日当時、頼信は「入夜前常陸守頼信、献馬十疋」(『御堂関白記』寛弘九年閏十月廿三日条)とあるように、これ以前の頃、忠常は「下総国」に住む強勢の「兵」であり、いまだ官に就いたことがなかったであろう。その後、上総国府に在庁官人の最上位の在国司「介」として赴任したとみられる。彼を在国司に補任した受領は、長和6(1017)年正月24日に上総介に補任された菅原孝標以降、万寿2(1025)年2月25日に得替となった藤原為章あたりか。忠常は万寿5(1028)年当時には「前上総介」(『百錬抄』)とあるように、すでに上総国を去って下総国に移っているとみられる。
●十一世紀初期の上総介の予想任期
| 名前 | 上総介以前の 前の官歴 |
上総介補任 | 離任 | 備考 |
| 藤原長能 | 天元5(982)年右近将監 永観元(983)年左近将監 永観2(984)年蔵人 寛和2(986)年近江少掾 永延2(988)年図書頭 |
正暦2(991)年 4月26日 |
正暦6(995)年 正月13日? |
藤原長能者、讃岐権助惟岳孫、伊勢守倫寧二男、…正暦二年四月廿六日、任上総介、寛弘二年正月廿七日、叙従五位上治国賞、同六年正月廿八日、任伊賀守(『長能集』) ―――――――――――――――――――――― 長保三(1001)年七月廿一日「前上総介長能」 (『権記』長保三年七月廿一日条) ―――――――――――――――――――――― 寛弘二(1005)年正月廿二日「前上総介長能朝臣」 (『小右記』寛弘二年正月廿二日条) |
| 平兼忠 | 天元3(980)年出羽介 | 不明 | 不明 |
(参考)
左中将藤原実方の陸奥守任期である 長徳元(995)年正月十三日(『公卿補任』)から 長徳四(999)十一十三日於任所薨(『尊卑分脈』) の間に、奥州で子息余五将軍維茂と藤原諸任の合戦があった。その将軍維茂は陸奥国在住中に兼忠の上総介就任を聞いて上総国を訪問している(『今昔物語集』) 寛弘九(1012)年閏十月十六日には「故兼忠朝臣男維吉、献馬六疋、二疋兼忠申置」(『御堂関白記』寛弘九年閏十月十六日条)とあり、兼忠子息の維吉(維良)が兼忠遺言も含めた献馬を行っており、兼忠はこの頃亡くなったとみられる。 |
| 菅原孝標 | 長保2(1000)年 蔵人右衛門尉 検非違使尉 |
長和6(1017)年 正月24日 |
寛仁5(1021)年 正月 |
寛仁元年正月廿四日任上総介 四十五 五年正月得替 四十九(『更級日記』) |
| 平輔忠 | 寛仁5(1021)年 正月 |
寛仁5(1021)年 2月28日卒 |
治安元年二月廿八日、上総介輔忠、阿闍梨固縁、日如、已講法修等卒事(小記目録) | |
| 藤原為章 | 長保元(999)年前伊豆守 長保4(1002)年散位 長和2(1013)年任伊勢守 |
寛仁6(1022)年? | 万寿2(1025)年 2月25日 |
「今年得替国司上総介為章、若狭守遠理、淡路守信成等、入已官物不済公事出家、終無其弁、以財物可令弁進、若無其弁、可令子孫弁済者、仰左中弁経頼了」(『小右記』万寿二年二月廿五日条) |
| 縣犬養為政 | 長徳4(998)年任左志 検非違使志 寛弘元(1004)年右衛門大志 寛弘2(1005)伝尉 寛弘4(1008)年左衛門少尉 寛弘5(1009)年左衛門大尉 |
万寿2(1025)年 3月9日 |
長元2(1029)年 正月22日か |
「上総介為政宿祢、申任符使禄、令給疋絹」 (『小右記』万寿二年三月九日条) ―――――――――――――――――――――― 「入夜厩舎人申云、□□従上総罷上、介為政朝臣貢馬、□□、馬二疋、手作布百四端、鴨頭草、□□、鮑等、馬頗宜、令立厩」 (『小右記』長元元年七月十三日条) ―――――――――――――――――――――― 「上総介為政妻子、近日申可令上道由、而依件事国人弥不聞国司事歟、国司在忠常之掌握、生死被任彼心、濫吹事逐日不断、忠常従者入乱館内、打縛国司従類之由、厩舎人友成所申、最可歟、可指弾、可殊労上」 (『小右記』長元元年七月十五日条) |
| 平維時 | 永延2(988)年右兵衛尉 正暦5(994)年散位 長徳2(996)年左衛門尉 長和5(1016)年常陸介 寛仁2(1018)年常陸介 治安3(1023)年前常陸介 |
長元2(1029)年 正月23日 (首途) |
長元4(1031)年 6月27日 |
長元二年正月廿三日 「上総介維時申、明日首途事」 (『小右記』長元二年正月廿二日条) ――――――――――――――――――――――長元四年六月廿七日 「上総介維時朝臣辞書」 (『左経記』長元四年六月廿七日条)――――――――――――――――――――――長元四年六月廿七日 「上総介維時朝臣申、被停所帯職事、如申状、年齢衰老之上、病痾頻犯、不堪分憂之任者、依請被停止、以可然者可被任歟」 (『左経記』長元四年六月廿七日条) |
長元2(1029)年6月13日「遣検非違使、捜求平忠常郎等住宅」(『日本紀略』)とあることから、忠常が下総国へ戻ったのちも忠常の郎等の中には留京または上洛し住宅を持っていた人物がいたようである(仮住まいの場所であった可能性もある)。また、子息の一人が出家して在京していたが、これは頼信の家人になった際に随身したものか。
万寿4(1027)年12月4日、朝廷の実力者であった藤原道長が死去しておよそ五か月後の万寿5(1028)年5月頃、下総国の平忠常の軍勢が安房国司館を攻めて「安房守惟忠、為下総権介平忠常被焼死了」(『編年残篇』)という。「長元の乱」である。
高望王―+―平国香―――平貞盛―+―平維将――――平維時――――平直方――+―平維方――――平盛方
(上総介)|(常陸大掾)(陸奥守)|(肥前守) (上総介) (右衛門尉)|(蔵人雑色) (左衛門尉)
| | |
| +=平維時 +―女子
| |(常陸介) ∥――――――源義家―――源為義
| | ∥ (陸奥守) (左衛門大尉)
| +=平維衡――+―平正輔 源頼信――――源頼義
| (常陸介) |(安房守) (甲斐守) (伊予守)
| |
| +―平正度――――平正衡――――平正盛――――平忠盛―――平清盛
| (常陸介) (出羽守) (讃岐守) (刑部卿) (太政大臣)
|
+―平良兼―――平公雅―+―平致頼――+―平致経
|(上総介) (武蔵守)|(平五大夫)|(右兵衛尉)
| | |
| | +―平公親
| | |(内匠允)
| | |
| +―平致秋 +―平公致
| |(左衛門尉)|
| | |
| +―入禅 +―平致光
| (比叡山僧) (大宰権大監)
|
+―平良文―――平経明―――平忠常――+―平常昌――――平常長
(陸奥守) (上総介) |(武蔵押領使)(武蔵押領使)
|
+―平常近
(安房押領使)
下総国の在庁官人である忠常が、みずから片道百キロメートルを超える安房国府まで出張し(しかも上総国を経由)、国司館を襲撃することは常識的に考えにくい。忠常が追討使派遣に当初より反論したり、京都との連絡を試みたり、追討使直方に贈物を送ったり、私君教通に書状を送ったりしているのは、叛乱が忠常自身の想定していない部分で生じたものだったため、つまり、この乱は安房国の在地勢力が引き起こした兵乱だった可能性が考えられる。なお、忠常の次男・平常近(恒親)は「安房押領使」とされ(『松羅館本千葉系図』)、もしも彼の「安房押領使」が事実で忠常叛乱以前に就任していたとすれば、常近と安房国司館の焼打には何らかの関係があるのかもしれない。追討の対象が「平忠常并男常昌等可追討宣旨事」(『小記目録』十七 臨時七)とあるように、京都には兵乱の首謀者は忠常と常昌(常将)であると報告されていたのは確実である。
一方で、挙兵の原因は同族平氏との対立があるというものが通説となっているが、忠常と同族平氏で対立関係があったと確認できる記録は『今昔物語集』にみられる「平左衛門大夫惟基(平維幹とされる)」以外はない。つまり、忠常の乱を同族の対立構造に結び付ける説は史料的な解釈としては問題があると言わざるを得ない。
この安房国司惟忠焼殺の直後、忠常郎等は上総国司館にも乱入し、国司の「上総介為政(縣犬養為政)」を拘禁しており、上総国と安房国は忠常勢力の行動範囲だったことがわかる。忠常の本貫である下総国については、国府が攻められた報告はなく下総国府の状況は不明。ただ、同年下総守として赴任した「下総守為頼」は、任国下向後程なくしてこの叛乱に遭遇し、「相営追討忠常事之間、人物共已弊」(『左経記』長元四年六月廿七日条)と見えるため、国衙兵を動かして忠常勢と対峙した様子がうかがえる。
忠常の乱以前の下総守は藤原如信で、万寿4(1027)年8月8日、香取社が「以守如信、令造立御社雑舍玉垣等、被延四个年任事」(『小右記』万寿四年八月八日條)という解文を朝廷に送達しているように、この年は式年遷宮の年に当たり(『香取社造営次第案』より逆算:『香取文書』)、如信はその大役を担い香取社からも四年重任の願いが出されたのである。この解文は実資から頭弁重尹に付しており、この重任が認められていれば、忠常が叛乱を起こしたときの下総守は藤原如信となったが、長元4(1032)年3月1日時点で「下総守為頼、申被重任」(『小右記』長元四年三月一日條)していることから、「(藤原歟)為頼」が長元元(1029)年より下総守となったことがわかり、藤原如信の重任が認められなかったことがわかる。
●『小右記』(万寿四年八月八日條)
藤原宇合――藤原綱手――藤原菅継――藤原真野麿――藤原豊仲―――藤原真常――藤原時範――藤原雅量――藤原為輔――藤原如信
(式部卿) (内舎人) (周防守) (右近衞少将)(上野介) (式部丞) (左少弁) (甲斐守) (下総守)
●『小右記』(長元四年三月一日條)
藤原良門――藤原利基――藤原兼輔――藤原為頼――藤原伊祐――藤原公輔――藤原頼長――藤原為頼――藤原為能――藤原能盛
(内舎人) (右中将) (中納言) (丹波守) (讃岐守) (出雲権守)(民部丞) (武蔵権守)(左衛門尉)
長元の乱は、具体的な月日は不明ながら、万寿5(1028)年5月頃、「安房守惟忠、為下総権介平忠常被焼死了」(『皇代記』後一条)という事件により発生する。この報告は5月末には京都に伝えられている。
安房国司焼殺の件につき、6月5日、朝廷は「平忠常并男常昌等可追討宣旨事」(『小記目録』十七 臨時七)と決定し、6月18日には「被定忠常追討使事」(『小記目録』十七 臨時七)られた。これを受けて6月21日に宮中左近衛府での陣定において「居住下野平忠常」(『左経記』万寿五年六月廿一日條)の追討使が選定されることとなる。
●『左経記』(万寿五年六月廿一日條)
●万寿5(1028)年6月21日仗座公卿●
| 記録 | 名前 | 官位 | 官途 | 年齢 | 人物 |
| 右大臣 | 藤原実資 | 正二位 | 右大臣 | 72 | 右近衛大将。藤原斉敏(従三位・右衛門督)の子。『小右記』作者。 |
| 内大臣 | 藤原教通 | 正二位 | 内大臣 | 33 | 左近衛大将。藤原道長の子。 |
| 中宮両大夫 | 藤原斉信 | 正二位 | 中宮大夫 | 62 | 大納言・民部卿。藤原為光の子。 |
| 中宮両大夫 | 藤原能信 | 正二位 | 中宮権大夫 | 34 | 藤原道長の次男で頼通・教通とは異母兄弟。 |
| 権大納言 | 藤原長家 | 正二位 | 権大納言 | 23 | 藤原道長の六男で御子左家祖。 |
| 左衛門督 | 藤原兼隆 | 正二位 | 左衛門督 | 44 | 左衛門督。二条関白道兼の嫡男で、祖父・兼家の養子。 |
| 源中納言 | 源道方 | 従二位 | 権中納言 | 61 | 宮内卿。道長正室・源倫子の従弟(源重信五男)。 |
| 春宮権大夫 | 源師房 | 従三位 | 春宮権大夫 | 19 | 権中納言。村上天皇皇子・具平親王の子。村上源氏の祖。 |
| 左右兵衛督 | 藤原経通 | 正三位 | 左兵衛督 | 46 | 参議・治部卿。権中納言・藤原懐平(実資弟)の子。 |
| 左右兵衛督 | 源朝任 | 正四位下 | 右兵衛督 | 40 | 参議。従二位・権大納言・源時中(道長正室・源倫子兄)の子。 |
| 左宰相中将 | 藤原資平 | 正三位 | 左近衛中将 | 43 | 参議。権中納言・藤原懐平(実資弟)の子で、叔父・実資の養嗣子。 |
| 新宰相 | 藤原公成 | 正四位下 | 参議 | 30 | 近江権守。権中納言・藤原実成の子。 |
追討使は「頼信、正輔、直方、成通等」(『小記目録』十七 臨時七)の四名が候補として挙げられ、出席公卿らは「伊勢前守頼信朝臣」こそ適任であると推薦した(『左経記』万寿五年六月廿一日條)。この候補順は官位順に記されており、頼信は当時正五位上(翌年従四位下に昇叙)、次の正輔は翌年安房守となっており従五位下または従五位上であろう。直方は右衛門少尉で正六位上であろう。
| 案 | 名前 | 官途 | 私君 | 備考 |
| 頼信 | 源頼信 | 伊勢前守 | 藤原頼通 | 源満仲の子。当時は散位か。 寛仁3(1019)年7月8日、実資は「頼信入道、殿近習者也」(『小右記』寛仁三年七月八日条)と記しており、頼信は頼通の近習だったことがわかる。 |
| 正輔 | 平正輔 | 不明 | 藤原実資 | 平維衡の子。当時の官途は不明。 父の維衡は寛仁4(1020)年12月3日当時、実資の「家人」(『小右記』寛仁四年十二月三日條)であり、治安3(1023)年11月22日、「常陸介維衡息正輔朝臣」が実資邸を訪れて、常陸国の交替使問題について切々と述べている(『小右記』治安三年十一月廿ニ日條)。正輔が父維衡と実資の主従関係を継続したかは不明だが、正輔もまた実資家人だった可能性があろう。 ~常陸介平氏(貞盛子息)と藤原実資の関係~ 平維幹:常陸介。寛仁4年閏12月13日当時「前常陸守」であり、さらに実資の「僕」(『小右記』長保元年十二月九日條)だった。 平維敍:常陸介。実資家人。 平維時:常陸介。子の直方とともに実資邸に頻繁に通う。維時は関東下向に際しても実資邸を訪れているように実資の家人であった可能性が高い。 貞盛流平氏は常陸国との関わりが深く、貞盛の子維衡、維幹、維時、維敍の兄弟は実資家人であり、藤原実資は常陸国に権益を持っていた可能性がある。 |
| 直方 | 平直方 | 右衛門少尉 | 藤原頼通 藤原実資 |
平維時の子。当時は検非違使。父の維時とともに実資邸を頻繁に訪問する。 |
| 成通 | 中原成通 | 右衛門少志 | 不明 | 父は不明。当時は検非違使。 |
前述のとおり、当初は頼信を追討使とすることが公卿一同の意見であった(以前に常陸介として忠常を従えた実績を買われたものか)。その後、公成らにより意見が取りまとめられ、関白頼通に申し伝えられるが、その後関白(または天皇)から決裁内容が戻されると、その内容は「右衛門尉平朝(臣)直方、志中原成道等」を追討使とするというものだった(『左経記』万寿五年六月廿一日條)。なぜ、陣定での意見ではなく、直方・成道を追討使とすることにされたのだろうか。
この人選に当たっては頼信・正輔が外されていることから、選任に際しては位階の上下は関係なかったことがわかる。また、直方が東国(とくに相模国※)に地盤を持っていたからその軍事力に期待して追討使に選ばれた等の説もあるが、史実的な根拠に基づかない説である。
※平直方が当時、東国に関わりを有していた形跡は史料上ない。のち、「平将軍貞盛孫上総介直方、鎌倉に家居す、鎮守府将軍兼伊予守源頼義、いまだ相模守にて下向せし時、直方が婿となり給ひて、八幡太郎義家出生し給ひしかば、鎌倉を譲り給ひし」(『詞林采葉抄』)という説話があるが、この説話を「史実」として、それを基礎として展開される説が存在する(なぜこの説話が史実として受け入れられるのか疑問である)。
そもそもこの説話が採用された『詞林采葉抄』は、十四世紀の僧由阿が、当時の伝承を採集したもので、鎌倉北条氏の世を経た説話であり、北条氏というフィルターを通った後のものである。鎌倉期に北条氏が源氏将軍との紐帯を強調した事が否定できない以上、史料的信憑性は低いとせざるを得ず、これを機微な問題に関する史的根拠とするのは当然不可であろう。鎌倉と頼義の関わりが仮に「あったとすれば」、頼義が長元9(1036)年10月14日以前に補任された相模守(『範国記』長和九年十月十四日条)の任期中に、房総と交通の要衝である鎌倉郡を重視した結果であろう。
長元9(1036)年当時の直方は受領経験もない一介の検非違使尉であり、説話にある「上総介直方」であるはずもない。すでにこの時点でこの説話に不審を感じなければならない。父維時も相模守の経歴はなく、直方と相模国との関係は史料上から見ることはできない。
直方の父維時は、ほかの兄弟・義兄弟(維幹、維衡、維敍)と同様、常陸介に補任されていることから、常陸国に私領を有していた可能性は否定できないが、子の直方は常陸国との関わりはないため、根本的な私領として発展した可能性はないだろう。
維時はのち一時的に上総介に補任されて下向するが、これは忠常追討使の直方を補佐する意味合いが強く、忠常追討後、任期中に辞退している。このことから上総国にも私領形成はなかったものと思われる。また、直方が忠常を「旧敵」と見て、東国に勢力を広げるために忠常追討を推進し、ほかの同族とともに忠常を討って勢力拡大を図ったとする説もあるが、直方はそれほど積極的に忠常追討に邁進した形跡はなく、他国から兵站や人を援助されていながら忠常を捕えられず、挙句に忠常の所在地が不明と白状して更迭されるという結果を迎えるほどである。
また、直方をして貞盛流平氏の惣領家とする説もみられるが、忠常追討使に擬された平正輔もまた貞盛流平氏に属し、さらに直方よりも位階は上であるため、不可解な説は到底不可である。
陣定での協議の詳細は残されていないが、後日の傍証から見る限り、陣定の結論にある伊勢前司頼信は武官ではなく、忠常の「追討」は検非違使による追捕での対応が妥当と判断され、関白頼通はその旨を天皇に奏聞して宣旨が下されたとみられる。その結果、四人の候補者から検非違使の直方、成通が忠常追討使に選ばれたのであろう。直方らに下された官符は「当初猶可搦捕之由、重可給官符歟」(『小右記』長元三年六月廿三日條)とあるように「搦捕」が主目的だったのだろう。この人選に実資ものちに「件事、只差遣検非違使、所被追捕也、異給節刀之使」(『小右記』万寿五年七月十五日条)とあるように、検非違使での追捕が妥当であると理解していたことがわかる。そしてほかの出席公卿一同もまた納得の結論であったのだろう。
忠常の叛乱は、百年前の「承平の乱」と比べて朝廷の危機感は低かった(承平の乱では坂東九国が将門の手中に帰すほどの大乱であり、参議藤原忠文が節刀され征東大将軍として関東に派遣された)。今回の叛乱は、安房国館の襲撃と国司殺害のみ報告されており(この時点では上総国司館が襲撃された報告はない)、承平の乱のように燎原の火にはならないと想定されたのだろう。一方で、東海道・東山道諸国には、忠常追討に関する太政官符を発給することもまた決定された(『日本紀略』万寿五年六月廿一日条)。兵士供出と兵站の支援であろう。そして、追討使首途の日は7月21日と定められた。
●『日本紀略』(長元元年六月廿一日条)
ところが万寿5(1028)年7月8日、実資のもとを訪れた大外記清原頼隆は、「追討使成通持来■公家雑事九箇条申文、件事等更不可■■」(『小右記』万寿五年七月八日條)と、中原成通は「件事等更不可」という九箇条の申文草案を清原頼隆へ渡したことを述べている。「件事」とは忠常追討に付随する事項と考えられるが、具体的な内容は不明である。ただ、第二條に「追討事、不可被行下弦血忌日等事」(『小右記』万寿五年七月十日條)があり、第二條は忠常追討首途日に関する反対意見である。なお、この申文は実資から養子・宰相中将資平に届けられ、資平も意見を表しているが「追討史(ママ)申請事九ヶ条文中、中将伝見、是成通所進、但以使部可為証人事、頗無便宜、仰此由了、自余條々有可止事等、然而不仰子細(追討使申請の九ヶ条を中将資平が伝え見た。この申文草案は成通が著したものだが、検非違使の使部を使者とすべきだという点は大変不都合という。その他の条々も申状に載せるべきではないこともあると言っているが、それぞれの詳細は述べなかった)」といい、申文の何條かに「以使部可為証人事」があったこともわかる。
この成通の申文以降、首途日の吉凶により、陰陽道の人々の見解の差異などがあり、実際の追討使出立の日取りが決定できない事態に陥っていく。
7月10日早朝、「維時朝臣持来追討使申請申文九ヶ条」(『小右記』万寿五年七月十日條)と、平維時(追討使直方の父)もまた成道が著した追討使申文九ヶ条を実資のもとに持参した。この申文を見た実資は、
「九ヶ条太多、又有不可申請事等、三ヶ條許宜歟、第二條事追討事、不可被行下弦血忌日等事、可入條右状中、是一日所見文也、成通筆作者、内々覧関白、可進(九か条は多すぎる上に、申請すべきではない事柄もある。三か条程度が適当であろう。第二条にある、追討の事は下弦と血忌日は行ってはならない事、という項目は申文に含めるべきだ。この申状は前日とおなじものであり、内々に関白の内覧に供してから持参するよう)」(『小右記』万寿五年七月十日條)
と維時に伝えた。
維時・直方はおそらく成通から九ヶ条の申文を渡され、21は忌日である旨の説明も受けていたと思われる。そのため、維時は実資に「問進発日」たが、実資は追討使下向日と勘申されている7月21日について、
「廿一日者、件日公損、亦血忌日、下絃日、若如何(七月二十一日は、朝廷の悪日、また血忌日でもある。下弦の日でもあり、どうかと考えている)」(『小右記』万寿五年七月十日條)
と答えている。すると維時も、
「示気色、公損字有事忌、又血忌日、暦序云、不可行刑戮者、亦下絃字読頗劣也(懸念を示し、『公損』の字義は行動を忌むと。また血忌日は『暦序』によれば刑の執行を行うべきではない日とされます。さらに『下絃』の字も「頗劣」と読みます)」(『小右記』万寿五年七月十日條)
と答えて懸念を伝え、首途日の変更を求めたのだろう。維時は追討使ではないが、子息の追討使直方が何らかの事由で実資のもとへ来ることができなかったため、その代理で訪問したものだろう。おそらく維時も維幹、維敍らほかの兄弟と同様に実資家人であったのだろう。
実資は大外記頼隆に21日の忌日について質問すると、頼隆は、
「三ヶ難尤優也、可忌避也、後日問勘日時之人、守道朝臣所勘也(公損、血忌、下弦の三難がとりわけ重なっており、忌避すべきです。後日、二十一日を勘申した人を問うたところ、賀茂守道朝臣でした)」(『小右記』万寿五年七月十日條)という。さらに、
「帰宿勘見、公損日、易卦深可忌刑殺事、多不記耳(外記局保管の宿曜勘文の先例を見たところ、公損日は刑罰、殺生を深く慎むべき日でした。ただ、多くは記されていませんでした)」(『小右記』万寿五年七月十日條)
と述べた。後日、頼隆は『損卦林(卦の凶に関する例集か)』に書いてあるものとして、
(1)是剋損已身、以益他人之卦、是有所費損事(自身を損ない、他人を利する卦であり、これは費用・損失を伴うであろう)
(2)出軍不利(出征は利あらず)
(3)攻伐不得(攻伐も結果は出ない)
(4)追亡有相剋不成(匪賊を追亡しようと思っても、内部対立で成功しない)
(5)凶咎(禍が降りかかる)
という調査報告を実資に報告。実資も「追討使不可用此日也、譬如土用事日不可犯土、損卦用事日、不可行征討也(追討使を二十一日に派遣することはできない。例えば土用には土関係の行事は不可であるように、「損卦」が出た日に征討は不可なのだ)」(『小右記』万寿五年七月十日條)との考えを記している。
7月13日夜、実資に厩舎人(伴友成)から「■■(為政家人だろう)、従上総罷上、介為政朝臣貢馬進御馬、雑物、馬二疋、手作布百四端、鴨頭革■■■■鮑等」(『小右記』長元元年七月十三日条)が届けられた報告があった。為政家人がこれら貢物を実資邸に運んできたのだろう。実資がみると「馬頗宜」ので「令厩立」た。おそらく上総介縣犬養為政は実資家人とみられる。同日条には見られないが厩舎人伴友成と為政家人はおそらく顔見知りであり、上総国の状況を伝え聞いている。
7月15日夕刻、平直方は「師光」に実資に「令申追討雑事」たが、「迺呼前聞所陳之旨、廿三日、有種々忌由有所伝承(先日の忌日の件ですが、「二十三日も様々に忌むべきことがある」と伝え聞きます)」(『小右記』長元元年七月十五日条)ことを伝えた。これを聞いた実資は「即乍驚罷向守道朝臣許、触此由(驚いて賀茂守道朝臣のもとへ行き、二十三日も忌日と聞いたが本当かと確認をした)」ると、守道は「殊無所申(とくに申す事はありません)」と答え、さらに「彼日不宜者、廿六日吉日、而主上御衰日、廿五日宜日也、彼廿五日夜半首途可宜者(二十三日が不吉であれば、二十六日が吉日となります。ただ、その日は主上の凶日で二十五日は吉日です。ですから二十五日夜半に首途すればよいでしょう)」(『小右記』長元元年七月十五日条)という。
また、直方の言として「申請条々事、以前日含父維時之趣、申関白了、被仰可然之由、即返遣草案文于成道所、未申左右、又関白曰、早詣右府申承件事等可進止者(九ヶ条の申請の件は、先日、父維時の意向も含めて関白に申し上げ、関白からは「もっともだ」との仰せを受けております。そこですぐに申文の草案文を成通のもとへ返送して再作成を願いましたが、未だ何ら連絡はありません。また、関白は「早々に右大臣(実資)のもとへ参上し、この件の判断を仰ぎなさい」と言われております)」(『小右記』長元元年七月十五日条)と実資に伝えられた。
実資は「申請事々甚多々、三箇条可宜由先日所示也、成通確執不改止条々事等者、亦申事由、於関白下向有何事乎、若有可申請事等、於途中若事発所国言上事由、更何事之有也(申請された事柄は非常に多く、三ヶ条にまとめるのがよいと先日成通に指示したが、成通は頑なに改めず、止めるべき条々も主張しているという。また、成通の主張を関白に報告したところで何の意味があるのだ。もし申請すべきことがあるのであれば、東下途次にその国から報告すればよいことで、それ以上何があろうか)」(『小右記』長元元年七月十五日条)と答えている。実資はこのほかにも返答したようだが、「其外事等不記子細」と記録に残さなかった。
またこの日、「厩舎人友成」は実資に「上総介為政妻子、近日申可令上道由、而依件事、国人弥不聞国司事歟、国司在忠常之掌握、生死被任彼心、濫吹事逐日不断、忠常従者入乱館内、打縛国司従類之由(上総介為政の妻子が、近日上洛するとのことです。忠常反乱により、国人はますます国司の命令を聞かなくなったようです。国司為政は忠常に囚われ、その生死は忠常の心次第です。好き勝手な命令が毎日出され、忠常の従者たちは国司館に乱入して国司の従者たちを縛り上げているという話です)」(『小右記』長元元年七月十五日条)を伝えている。これは伴友成が上総国から貢物を運んだ為政従者から聞いた情報なのだろう。
このとき実資ははじめて家人の上総介為政が国司館を占領されて囚われの身であることを知ったのだろう。実資は「最可歎、可指弾、可殊労止之由(これ以上なく嘆かわしく非難すべきことだ、とくに為政妻子等を救済するように)」事を追討使の直方に伝えるべく、厩舎人友成を直方邸に返答の使者として遣わした。友成は「可令守上為政朝臣妻子等之事、同仰直方朝臣了」し、直方も「申可労止之由訖」(『小右記』長元元年七月十五日条)した。
このほか実資が友成に言い含めたのは「抑首途日、可避有指忌之日許、強不可択優吉日、件事、只差遣検非違使所被追捕也、異給節刀之使、至尋常、遠近追捕、不撰善悪日、奉宣旨馳向之例也、事可同彼意、然而程在遼遠、仍猶可撰吉日也、此由等具相含了(そもそも首途の日は、忌むべき日だけを避ければよく、強いて吉日を選ぶ必要はない。もともとこの件は、ただ検非違使を遣わして追捕するというだけの案件であり、節刀を給わる追討使とは根本的に異なる。遠近を問わず追捕については善悪日を撰ばず、ただ宣旨を奉じて馳せ向かうのが通例である。したがって、本件もその考えに準ずべきである。ただ、叛乱の地が遙かに遠いため、やはり吉日を選ぶべきだ。これらの事を詳細に言い含めた)」(『小右記』長元元年七月十五日条)というものだった。そして「若求優吉日、旬月相移、賊徒廻謀歟、甘心退去、夜中可申関白者(もし吉日を求めれば、月日が過ぎて賊徒が謀略を巡らせて退散することも考えられる。この旨を夜のうちに関白へ申上げよ)」(『小右記』長元元年七月十五日条)と伝えた。
実資は、今回の忠常追討は節刀を給わる追討使(征夷大将軍、征東大将軍等)ではなく、ただ検非違使を差し遣わして追捕するだけのもので、吉日にこだわる必要はないという認識であった。前述のとおり、忠常追討使を検非違使に選んだのは、陣定での認識が単発で国府を攻めるような地方紛争の一つ(たとえば平維良による下総国府攻め)であって、大きな叛乱ではないという軽い認識が共有されたため、大仰な追討使ではなく、検非違使に東海東山諸国を協力させて捕えることになったためであろう。関白頼通も報告を受けた際にこうした認識のもとで決定されたと思われる。
ところが7月15日深夜、陰陽頭惟宗文高は実資邸を訪ね、門外に師重(実資家人の陰陽師か)を招いて言うには「廿三日追討忠常之使発遣之由、伝所承也、須件日陰陽寮勘申也、而不被仰下也、守道朝臣勘申云々、廿三日最悪日也、以此由可申公家、然而有所思不令奏、只為触下官参也、能可撰申之日也、天下大事只在斯者、不聞返事逐電退去(『二十三日に忠常追討使が発遣されると伝え聞いた。本来は発遣日は陰陽寮が勘して申し上げるべきことだが、今回はそのような仰せはない。二十三日の事は守道朝臣が勘したというが、二十三日は最悪の日だ。この理由を奏聞すべきだが、思うところあってあえて奏しなかった。ただ私として命令を受けたので参じただけである。改めて吉日を選び直して申し上げるのがよいだろう。天下の大事はまさにここである』と言い、返答も聞かずに急ぎ退去した)」(『小右記』長元元年七月十五日条)とのことだった。23日の追討使下向日も実資が守道の意見を聞いて評議に諮ったとみられ、陰陽寮を統べる陰陽頭惟宗文高はこれを懸念して、「須件日陰陽寮勘申也、而不被仰下也」(『小右記』長元元年七月十五日条)と伝えたのだろう。
7月16日夜、「直方朝臣」が実資のもとにきて何かを「申請」している(『小右記』長元元年七月十六日条)。詳しい内容は擦消しているため不明だが、「已有許容、是下官指示之趣而已」といい、おそらく直方のもとに「即返遣草案文于成道所、未申左右」(『小右記』長元元年七月十五日条)の修正後申文草案が成通から直方に届けられたのだろう。その修正案は実資から指示された通り三ヶ条に修正されていたものだった。直方はその草案を了承したか。
二日後の7月18日深夜、「■■(直方?)朝臣来■■■事、首途日来月五日」(『小右記』長元元年七月十八日条)と、平直方が実資を訪問して首途の日の報告をした。ただ直方は「卯日向卯方如何、是心中所思」と、「方位注」の悪日で内心思うところがあるとして、8月5日の出立の懸念を伝えている。また「申請事、如余示仰、注三ヶ条者」という申文と、「■申駅鈴者」という駅鈴下賜を求めている(『小右記』長元元年七月十八日条)。結局、首途日は8月5日で決着したようだ。
7月23日、実資のもとに頭弁重尹が「追討使申請三箇条文、不可奏■■、頃之来、下給追討使文、乍三ヶ条依請■■宣旨之由、可追下国々司事、不可載宣旨■■、使部可追下也(追討使が申請した三か条の文書については、■■のため奏聞できませんでした。 このたび追討使文が下されましたが、三か条の申請により■■■ながら宣旨の内容を諸国司に伝えるべき事を宣旨に載せるべきではありません。使部を以って伝えるべきです)」(『小右記』長元元年七月廿三日条)との報告に訪れた。
また、「上総介為政宿禰妻子、無方上道之由、付厩舎人友成所申、就中追討忠常之間、州民弥無相送之心歟、仍仰追討使直方、亦仰遣路次国々、即以友成為其使、友成申云、直方朝臣書付遣所々(上総介為政宿禰の妻子が上洛に際して方角もわからず困惑しているとの事を、厩舎人友成が申し出てきた。 とりわけ忠常追討につき、上総国の民もいよいよ彼らを送ろうという気持ちはないのだろう。そこで、追討使直方や官道諸国に上総介為政妻子の保護・護送を命じ、友成をその使者としたが、友成が申すには、「直方朝臣が書状を各所に遣わした」という)」という。
こうした中で7月25日、実資のもとに検非違使別当経通が訪れて語ったところでは、「今日可有赦令、可被免軽犯者歟、定有宣旨歟、可令道官人勘申」と考えたが、麾下の「為長遭喪、成通煩小瘡、不出仕」と、明法道の豊原為長、中原成通ともに出仕していなかった。経通は忌中ではない「煩小瘡」の成通に「縦雖未参仰、可進軽犯者勘文」と指示するが、成通は「目并手腫、不能勘申」という。経通は「令見気色似遁追討使節、勘文事為之如何者(成通は追討使から遁げたいという気持ちが見える。勘文の事はどうしたらよいだろう)」と悩み、実資に相談に来たのだった。これに実資は「軽犯勘文、雖非道官人勘申歟、別当宣佐奉之例也、別当参議時称内侍宣(軽罪人に関する勘文は、明法道の官人でなくてもよい。これは別当宣を補佐する先例である。別当が参議だった時は、これを「内侍宣」と称した)」と述べている。経通は「無道官人之由、至今不可申関白、成道依此事為致披露歟(明法道の官人がいないことを、これまで関白に申し上げていなかったが、成道はこの件について報告したのだろうか)」と述べている。
また同日、改元の元号勘申があり、下記の案の中から「長元」が選ばれた。
| 勘申 | 元号案 |
| 為政 | 天祐、長元、長育 |
| 通直 | 玄通 |
| 挙周 | 延世、延祚、政善 |
長元元(1028)年8月1日夕刻、左中弁経頼は関白殿(高陽院、賀陽院)に参じた(『左経記』長元元年八月一日條)。経頼は関白頼通の従兄で日頃から深く交流していた。
藤原冬嗣―+―藤原良門―――藤原高藤―――藤原胤子 +―醍醐天皇―――村上天皇―――円融天皇
(左大臣) |(内舎人) (内大臣) ∥ | ∥――――――――――――一条天皇
| ∥ | ∥ ∥
| ∥ | 藤原兼家―+―藤原詮子 ∥
| ∥ | (関白) | ∥
| ∥ | | ∥
| ∥――――+――――――――敦実親王 +――――――――藤原道長 ∥
| 仁明天皇―+―光孝天皇―――宇多天皇 (式部卿) (関白) ∥
| | ∥ ∥ ∥
| | ∥ ∥―――+―藤原彰子
| | ∥ ∥ |
| | ∥ ∥ |
| | ∥ +―源倫子 +―藤原頼通
| | ∥ | |(関白)
| | ∥ | |
| | ∥――――+―源雅信――+―源時中 +―藤原教通
| | ∥ |(左大臣) |(大納言) (内大臣)
| | ∥ | |
| +―人康親王―――女子 +―女子 +―源重信 +―源扶義―――源経頼
| (弾正尹) ∥ | (左大臣) (参議) (参議)
| ∥ |
| ∥――――+―藤原時平―+―女子
| ∥ |(左大臣) ∥―――――藤原斉敏
| ∥ | ∥ (参議)
+―藤原良房==========藤原基経 +―藤原忠平―+―藤原実頼 ∥――――+―藤原懐平―+―藤原資平
|(摂政) (関白) (関白) |(関白) ∥ |(権中納言)|(宰相中将)
| | ∥ | |
+―藤原長良―――藤原基経 | 藤原尹文――女子 | +―藤原経通
(権中納言) (関白) |(播磨守) | (検非違使別当)
| |
| +―藤原実資===藤原資平
| (右大臣) (宰相中将)
|
+―藤原師輔――藤原兼家―――藤原道長―――藤原頼通
(右大臣) (関白) (関白) (関白)
ちょうどこのとき邸内では懐妊中の頼通室祇子の「犬産礼」が行われていたようで、経頼は殿中を憚り南庭の階段下に伺候して、頼通から雑事を承っていたところ、信濃前司維任が「左衛門志豊道等申、忠経従者依有入京聞、依別当宣尋捕持参者(検非違使志の粟田豊道等が、忠常従者が入京したという情報を受けて、別当宣により忠常従者を捕えて連行してまいりました)」と頼通へ報告に上がった。頼通はすぐに「可令問忠経有様者(その男から忠常の情報を聞き出すように)」(『左経記』長元元年八月一日条)と指示している。
●『左経記』(長元元年八月一日条)
夜になって、大外記清原頼隆が実資邸を訪れ、夕方の「検非違使捕得忠常従者」(『小右記』長元元年八月一日条)の事件を報告している。
翌8月2日朝、実資甥の検非違使別当藤原経通が、昨日の男は尋問結果から忠常従者ではなく郎等従者だったことが伝えられ、「後聞、忠常郎等従者」(『小右記』長元元年八月一日条)と『小右記』に追記訂正されている。
翌8月2日朝、実資は検非違使別当藤原経通から昨日の忠常従者捕縛の情報が伝えられた。その書状には「忠常脚力、夜部令搦奉関白殿了、則被問、申云、件男忠常郎等之従者、不知子細、実忠常脚力二人也、一人在運勢許、一人在通朝臣許之由、証申了(忠常の脚力を夜中に捕らえ、関白殿に奉りました。すぐに尋問したところ、この男は忠常郎等の従者であり、詳細は知らないとのことです。実際に入京している忠常の脚力は二人いて、一人は運勢法師のところにおり、もう一人は在通朝臣のところにいるという旨の言質が取れました)」とあった。
この捕物騒ぎについて、忠常の私君である「内府(藤原教通)」は「頗傾思侍、乍置実忠常脚力、郎等之従者在所ヲ被尋申、頗孫本文也者(はなはだ疑問である。実際の忠常の脚力を放置して、郎等の従者の所在に踏み込むとは、はなはだ本末転倒である)」と述べている。
●『小右記』(長元元年八月一日、二日条)
検非違使に捕縛された「忠常郎等之従者」は、当然「不知子細」(『小右記』長元元年八月一日条)であった。また、「実忠常脚力二人也」とあるように、忠常の「脚力(使者)」は二名入京し、それぞれ「運勢法師」「明通朝臣」のもとに滞在していることも判明する(『小右記』長元元年八月一日条)。「運勢法師」は由来不明ながら平時には忠常とも関わりがあった人物であろう。「明通朝臣」については、検非違使を務めた左衛門少尉藤原明通で、従姉妹に教通実姉・上東門院(藤原彰子)に仕えた女房(紫式部)がおり、自身も教通実妹・藤原威子(後一条天皇中宮)の中宮少進を務めていたことから、藤原明通は教通の家人であり、忠常とは知己の人物だったと推測される。
●藤原明通周辺系図
藤原長良――+―藤原国経――藤原忠幹――――藤原文信―――藤原惟風―――藤原惟経
(権中納言) |(大納言) (勘解由長官) (鎮守府将軍)(中宮亮) (太皇太后宮大進)
| ∥
+―藤原基経 ∥――――――藤原棟綱
|(太政大臣:叔父良房養嗣子) ∥ (相模守)
| 平直方――+―女
| (上野介) |
| +―女
| | ∥―――――――――――藤原朝憲
| | ∥ (陸奥守)
| | 藤原憲輔 ∥
| |(宮内卿) ∥―――――藤原説定
| | ∥ (駿河守)
| | +―源頼清――源兼宗――女
| | |(陸奥守)(上野介)
| | |
| | +―源頼義
| | (陸奥守)
| | ∥――――源義家
| | ∥ (陸奥守)
| +―――女
|
|
+―藤原高経―――藤原惟岳―――藤原倫寧―――藤原理能―――藤原為祐
|(右兵衛督) (左馬頭) (常陸介) (肥前守) (駿河守)
|
+―藤原遠経―+―藤原良範―――藤原純友 藤原為時
|(右大弁) |(太宰大弐) (伊予掾) (越後守)
| | ∥――――――上東門院女房
| +―藤原尚範 +―娘 (紫式部)
| (上野介) |
| |
+―藤原清経―――藤原元名―――藤原文範―――藤原為信―+―藤原理明―――藤原明通
(右衛門督) (宮内大輔) (権中納言) (右近衛少将)(筑後守) (中宮少進)
∥
∥――――――藤原元範
∥ (式部少輔)
源致明――+―娘 ∥
(和泉守) | ∥
| ∥
+―娘 ∥――――藤原国綱
∥ ∥ (刑部大輔)
∥ ∥
藤原伊周 ∥
(内大臣) ∥
∥
藤原為時―+―藤原惟通―――娘
(越後守) |(常陸介)
|
+―上東門院女房
(紫式部)
8月3日夜、実資邸に「直方朝臣来、言雑事、明後日必可首途者(直方朝臣が来訪していろいろな用件について話し、明後日には必ず出発できると思います)」(『小右記』長元元年八月三日条)と語っている。
8月4日、時折小雨の降る中、朝から左中弁源経頼は関白邸の高陽院へ参じ、頼通から用件の指示を受けていると、平直方が「為祐朝臣(上記系譜の高経末孫か)」に取次を依頼し、頼通に「明日寅刻欲進発、主税頭守道称忌日不返閉、為之如何者(明日の寅刻に東下の首途をしたいのですが、主税頭賀茂守道が「忌日」と言って返閉を拒んでおり、どうすればよいでしょうか)」(『左経記』長元元年八月四日條)と問合せてきた。
●『左経記』(長元元年八月四日条)
これに関白頼通は「称忌日、強不可被催、如惟宗如文高可令行也(忌日を理由にしている者を無理に催促することはできない。惟宗文高に返閉を行わせよ)」と指示し、直方は惟宗文高のもとへ赴いて返閉の約束を取り付けており、午刻、実資邸に「直方、令申文高有約束之由」を伝えている(『小右記』長元元年八月四日条)。この際、実資は直方に「前日、成道問駅鈴可請哉否之由、其事如何(昨日、中原成通から「駅鈴を請うことができるか」と質問されたが、その件はどうなったのか)」と問うている。これに直方は「尋問人々不可請者、不申請(人々に問い尋ねると、請うべきではないとのことでしたので、申請しませんでした)」と答えており、追討使として平直方と中原成通は連携して進発の準備を行っていたことがうかがえる。
夕方、允が実資邸を訪れて告げるには、「忠常従者随身消息文等、来著運勢房奉内府文云々、運勢密々令申事由於関白殿、仰検非違使令捕(忠常従者が書状を携えて運勢房のもとに来て、忠常私君の内府(教通)への文を奉ったとのことです。運勢がその事情を秘かに関白邸に伝えたことで、関白頼通は検非違使に命じて捕えさせよと命じました)」とのことだった(『小右記』長元元年八月四日条)。
こうして「運勢」が「廻謀略令捕」た郎等従者(脚力)は、検非違使志の粟田豊道、生江定澄に引き渡され、「将参関白第」た(『小右記』長元元年八月四日条)。この脚力は四通の書状を持っており、関白頼通は右兵衛督頼任にそのうちの一通を読ませている。内容は「聞可被追討之由、可申所々事等」(『小右記』長元元年八月四日条)とあるように、自分が追討対象となったことを聞き、忠常がこのような事になった理由を主張を累々記したものであった。残りの三通は未開封で、一通は内府教通、一通は新中納言師房、一通は宛名がないもので、すべて未開封のまま検非違使に返却された。内府教通は忠常私君であるが、「新中納言殿(権中納言師房)」への上書の理由は不明。師房が私君教通の実妹聟であったためか。
●『小右記』(長元元年八月四日条)
「聞可被追討之由、可申所々事等」(『小右記』長元元年八月四日条)という忠常の願いも空しく、8月5日亥の刻、忠常追討使として検非違使平直方、中原成通の両名が首途した。その際の反閉には「陰陽頭惟宗文高朝臣」が行った。付随するのは二百余人ばかりであるため、検非違使の下僚が主力であろう。
この出立を見るために亥刻(午後十時頃)にも拘わらず「見物車有数」あったという。その行装を一目見ようと「見物上下、馳馬飛車会集如雲」という。その後「臨暗少々分散」という。実資は「先日白昼首途、可無便之由示含惟時朝臣并直方朝臣等已了、若信其事歟、先年忠義朝臣為追討阿波海賊之使、夜半首途云々(先日、白昼の首途は都合が悪い旨を平維時および直方らに既に伝えてあったが、もしかするとその件を信じたのだろうか。先年、忠義朝臣が阿波の海賊追討の使者となった時は、夜半に首途したということである)」と述べている。
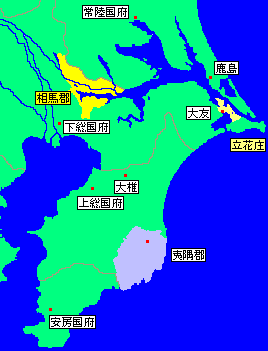 |
| ■夷隅郡(内の・が国府台) |
8月8日、実資は「忠常脚力」について甥の検非違使別当経通に問い合わせたところ、「先脚力ハ是忠常郎等従者、不知子細、但於内者所申ハ相具精兵之由ヲ申者、是云々説云々(先の脚力は忠常の郎等従者であり、詳細は分かりません。ただし、内の者が申したところによれば、精兵を連れ具している旨を申す者がいる、これこれしかじかと説明したという)」という。また、「彼脚力ハ実忠常使也、所申子細不相具、至于忠常随身二、三十騎許可罷入伊志みの山、若有内府解文御返事可来彼山辺之由ヲ申侍り、是実正歟(その脚力は実際に忠常の使者である。申した詳細は一致しないが、忠常は『随身二、三十騎ほどで伊志みの山に入ります。もし内府教通の解文の御返事があれば、山のあたりまで来てください』という旨を申しておりましたと申している。これは本当のことだろうか)」(『小右記』長元元年八月四日条)という。
内府教通の御教書であれば夷隅山のあたりに来るよう要請しているということは、その御教書の内容によっては降伏するという意思表示であった可能性が高いだろう。ちなみに「伊志み」とは、『和名抄』に見える「伊志美」であると考えられ、上総国夷隅郡(いすみ市)にあたる。なお、いすみ市には「国府台」と呼ばれる渓谷を眼前に控えた要害地(地図)がある。
●『小右記』(長元元年八月四日条)
長元元(1028)年8月5日に京を出立した追討使であったが、5~6日経ってもまだ美濃国に在陣しており、8月16日に「宰相中将」が実資邸を訪問して語るには「追討忠常等使右衛門志成通、従美濃国言上、八旬母煩病、俄有万死一生告之由云々、此由令申関白者(忠常追討使の右衛門志成通が美濃国からへ言上してきました。八十歳の母が病によりもはや助かる見込みがないとの報告です。これを関白に直接伝えたのです)」(『小右記』長元元年八月十六日条)とのことであった。成通が八十歳の母親が瀕死の重病に陥ったという知らせを得て、直接関白にその旨を伝えたというのである。この文書には成通が「どうしたいのか」という具体的な内容は記されていないが、成通は追討使辞退を申請した可能性が高いだろう。それは次の別当経通が弟の宰相中将資平に語っていることからも想像される。
別当経通は資平に「件事、可言上左大史貞行宿禰所歟、追討使従官所宣下也、更経他方令申故障、理不可然、既有事疑(この件は関白ではなく、左大史貞行宿禰に伝える内容だ。追討使に関する官符は弁官局から宣下されるものだからだ。他に故障を申し述べることは道理が通らない、以前から疑うような事もあった)」(『小右記』長元元年八月十六日条)と話したという。ただ、明法家成通が申請手続きを知らないはずはなく、左大史貞行は8月4日、四條邸への落雷により母の従女が亡くなるという穢があり(『小右記』長元元年八月四日条)、京都から成通へ母の容態を伝えた使節がその旨を伝えている可能性があろう。
別当経通が先日資平に語ったこととして「成通与直方朝臣不和、成通談或者云、於美濃国可申故障云々(成通と直方朝臣は不仲であり、成通がある者に『美濃国まで来たら、故障を申し立てるつもりだ』と語ったという)」という事実の発覚により、実資は「爰知故障之不実、真偽遂露顕歟(彼の申し立てた故障が虚偽であることが知られ、真偽が露顕したか)」(『小右記』長元元年八月十六日条)と感想を語っている。母の容態悪化の知らせと美濃国から故障を申し立てようとしていた時期が、たまたま重なった可能性もあろう。
●『小右記』(長元元年八月十六日条)
同16日朝、頭弁重尹が右中弁経頼に「右衛門志済道、従美濃申老母重煩之由、仰云、命可然之人、令検実否、随軽重可左右者、是済道内々令申(右衛門志成通が美濃から老母が重病であると申し出てきた。関白は『然るべき人物に命じて、母親の病の実否を検分させ、その病の軽重によって処置を決めよ』との仰せであった。この件は成通が内々に関白に申し立てたことのようだ)」(『左経記』長元元年八月十六日条)と語っている。関白頼通は、成通母右京の病状を検分の上、その報告により指示する旨を仰せられたという。
●『左経記』(長元元年八月十六日条)
そのため、即日太政官で「成通母病実不(成通母の病の真偽)」が調査されたようである。頼通はこの報告がなかなか上がってこないためか、宰相中将資平に調査結果を問い合わせてきた(『左経記』長元元年八月十七日条)。資平は関白使者に「日来有所煩、而一両日頗平復、不可死(ここのところは病床にありましたが、一両日で大いに回復しました。死ぬことはありません)」と報告すると、頼通は「仍仰遣其由於成通了者(母親の状況を成通へ遣わすように)」と太政官に指示した。
●『小右記』(長元元年八月十六日条)
この由は美濃国の成通へ即時遣わされたと考えられ、その後に成通が反応を示した形跡がないことから、追討使一行は東国へと下向していったと思われる。その後、追討使に関する資料はしばらく見えず、一行が関東(下総国)に到着した日時は不明。次に忠常追討に関する情報が史料上で見られるのは、長元2(1029)年2月1日である。
長元2(1029)年2月1日早朝、右少弁家経が実資邸に「東海、東山、北陸等道并追討使直方等官符草」(『小右記』長元二年二月一日条)を持参した。「追討使直方申請官符事」(『小記目録』)とあるように、正月末頃、京都に追討使直方からの忠常追討に関する官符発給依頼が到着し、その内容から急遽官符の発給が論ぜられて、実資は管轄の右弁官局にその作成を指示。この日早朝、その草案の確認のため実資に齎されたものである。ただ、使者の右少弁家経は「重服」のため邸内を憚り「於門外伝人進之」ている。彼の話によれば「一昨夜、以小臣申旨、伝申関白、命云、以件趣可作官符、先令見小臣、随示可持来也、但昨今春日祭日、於門外以人可進者、示可令覧由畢(一昨日の夜、右府からの趣旨を関白に伝えました。関白は『その趣旨に基づいて官符を作るように。まず私に見せ、そのあと右府へ持参するように。ただし、近頃は春日祭日があるので、門外で人を介して右府へ進上するように』とのことでした。ご覧ください)」(『小右記』長元二年二月一日条)とのことである。
●『小右記』(長元二年二月一日条)
忠常追討に関しては、京都出立以前の6月21日に「給官符等於東海東山道」(『日本紀略』長元元年六月廿一日条)されているが、実際には東海道、東山道諸国からの人的・物的支援は寡少であったのだろう。追討使が率いたのはわずかにそのために追討使直方は難儀が生じて京都に支援を求め、改めて国々に忠常追討に協力を命じる官符を下すことになったのだろう。その際には旧官符にあった東海道、東山道に加えて北陸道もその対象に加えられたと思われる。
そして2月5日、朝廷は「諸国相共可追討忠常之官符請印」(『日本紀略』)を下した。結果として「前使直方時、坂東諸国多属追討」(『左経記』長元四年六月廿七日条)と、坂東諸国の多くが忠常追討のために協力することとなった。さらに追討使直方の支援のためとみられるが、補任時期は不明ながら、直方の父・平維時が上総介に補任され、2月23日、京都を出立した(『小右記』長元二年八月廿二日条)。前日の2月22日、維時は実資邸を訪れて「明日首途事」を報告している。維時も兄弟の維幹、維敍、維衡らと同様、実資家人だったのだろう。
●『小右記』(長元二年二月廿二日条)
しかし、その後も追討使に忠常追捕に関する成果は上がらず、6月8日には追討使を直方から別人に代えるべきか否かの詮議が行われている(『小記目録』)。また、6月13日には、「遣検非違使、捜求平忠常郎等住宅」(『日本紀略』)とあり、京都にあった忠常郎等の住宅を検非違使が家宅捜索している。
●『小記目録』(長元二年六月八日条)
また、7月2日に行われる石清水奉幣の宣命に「追討事」が洩れていたので、もし許されるのであれば、別紙に忠常追討の旨を記して宣命に加える旨を伝えている(『小記目録』、『小右記』長元二年七月一日條)。
●『小右記』(長元二年七月一日条)
ところが、その後も忠常追討はまったく進展せず、長元2(1029)年12月5日、「追討使直方并上総介維時等解文書状到来事」(『小記目録』)と、戦況を記した解文が京都に届けられた。これにより12月8日に「陣定事追討使直方事」(『小記目録』)が行われ、解文に基づいた対策が練られたとみられる。一方で追討に消極的な中原成通は「不言上追討忠常之事」ため、この陣定で「停検非違使志中原成道」が決定した(『日本紀略』長元二年十二月八日條)。そして、長元3(1030)年2月4日、「可追討忠常事」(『小記目録』)と決定する。
このような中、3月27日に「安房守藤原光業」が突如上洛した(『日本紀略』長元三年三月廿七日条)。これは「依忠常乱逆、棄印鑰上洛」という為体であった。安房国は万寿5(1028)年5月頃に国司館が襲撃されて国司惟忠が焼死している地であり、忠常勢も蔓延る国である。光業がもし安房国に赴任したとすれば、当然ながら上総介維時と同じく追討使の援助を兼ねたものであったろう。長元2(1029)年2月23日に維時が下向したときにともに下ったか。しかし、光業は安房国府の印を国衙に置いて京都に逃げ帰った。このため朝廷は3月29日、当初、追討使の候補に挙げられた平正輔を「安房守」に任じた(『日本紀略』長元三年三月廿九日条)。
●『日本紀略』(長元三年四月廿九日条)
5月14日、頭弁経頼が実資邸を訪問し、「安房守正輔申」こととして以下の経過を報告している(『小右記』長元三年五月十四日条)。正輔は忠常追討に際して、
(1)船を国ごとに二十艘
(2)不動米穀(正倉に備蓄される非常用の米穀)を国ごとに五百石
を要求する申文を右弁官局に提出した。船については、相模国三浦郡から任国安房国への海道を渡る際に必要だったための要求か。不動米穀は軍費・兵站であろう。その結果、正輔には五百石ではなく「示被裁許、毎国百石」されたが、
(1)「不動之有無、暗以難知」(不動米があるかどうか判然としない)
(2)「無不動之国、強難責」(不動米がない国に強いて課すのは難しい)
(3)「縦雖多不動之国、裁許非(非裁許歟)不能催責」(不動米の多い国でも裁許がなければ催促はできない)
という理由で、正輔に「任申請数、可有裁許由、重以令申、即申関白(申請数によって裁許を願いたいという旨の申文を再度提出させ、すぐに関白に伝えました)」という。これを受けた関白頼通は「可令所司勘申国々不動数者、宣可令勘申之由(所司に国ごとの不動米穀の数を勘申させよ。勘申させるよう宣せよ)」と命じた。また、「追討使解文事」についても関白は「籠伊志見山并隨兵減小由所推量(忠常は伊志見山に籠り、また随兵の数も減少してきていると推量される)」とし、諸卿も「依件解文、無可給官符之事(この解文の内容に基づけば、官符を給うべき事由はない)」と言っており、当たらな官符発給は行わないこととしたのだろう。
さらに「前安房守光業申文檀紙、仍不能令見非急速事、過此間可令見歟(前安房守光業の申文は急ぎの案件ではないので見せていないが、あとで見せるか)」と頭弁に問うているが、「已被解官、至今不可経営、過此間令奏聞何事之有也(光業はすでに解官され、国務は執れません。今更奏聞した所で何になりましょう)」と答えている。
●『小右記』(長元三年五月十四日条)
高望王―+―国香――――貞盛――+―維将――――維時―――――直方――――+―維方―――――盛方
(上総介)|(常陸大掾)(丹波守)|(肥前守) (常陸介) (左衛門少尉)|(蔵人雑色) (左衛門尉)
| | |
| +=維時 +―女
| |(常陸介) |(陸奥守源義家母)
| | |
| +=維衡――+―正輔 +―女
| (常陸介)|(安房守) (相模守藤原棟綱母)
| |
| +―正度―――――正衡――――――正盛―――――忠盛―――――清盛
| (常陸介) (出羽守) (讃岐守) (刑部卿) (太政大臣)
|
+―良兼――――公雅――――致頼――――致経
|(上総介) (武蔵守) (散位) (左衛門尉)
|
+―良文――――経明――――忠常――+―常将―――――常長
(陸奥守) (上総介)|(武蔵押領使)(武蔵押領使)
|
+―恒親―――――恒仲――――――頼任
(安房押領使) (村上貫主)
一方、5月20日に実資に届けられた直方の書状には「犯人忠常出家事」(『小記目録』)が記されており、忠常が出家したことが伝えられた。
こうした中、6月23日、頭弁源経頼のもとに「追討使直方并上総武蔵国司言上解文」が届けられた。経頼はこの解文をおそらく関白頼通の内覧を経て奏上。勅命を受け取り、その深更、経頼は実資邸に「追討使平直方、上総介平維時、武蔵守平致方等言上解文事」について、「件追討事、忠常如言上不知在所者(件の追討のこと、忠常が言上の通り所在不明)」であるのであれば、忠常追討について再考すべき案を検討するよう命じる勅書を届けている。
| (1)坂東国々依追討事■■召■直方付国々可令勤追討事歟 | 坂東諸国を追討のために召し、直方のもとに付けて諸国に追討を勤めさせるべきか |
| (2)当初猶可搦捕之由、重可給官符歟 | 当初のように、なおも忠常を搦め捕るべしとの官符を重ねて給すべきか ※当初の官符は「追討」ではあるが、その実、忠常の捕縛を命じるものだったことがわかる |
(1)については、すでに東海道、東山道、北陸道の三道に追討に協力するよう命じる官符が出されており、東海道、東山道に関しては二度出されている。(2)については、根本的な官符を再度給して対応するのか。追討使が発遣されて約二年経過しているにも拘わらず事態の進展が見られない状況に、天皇も具体的な打開策を検討するよう苦言を呈したものだろう。
ただし、「件追討事、忠常如言上不知在所者(件の追討のこと、忠常が言上の通り所在不明)」であるというのは、5月14日、頭弁経頼が実資に報告した中で、「追討使解文事」について関白が「籠伊志見山并隨兵減小由所推量」と述べているように、忠常の所在は「伊志見山」であることははっきりしており、なぜ追討使直方は「忠常如言上不知在所」との報告をしたのか不明である。「伊志見山」という山の「具体的などこか」が判明していないという意味か。後世、忠常末裔の千葉三郎常房は、下総国香取郡千田郷を経て夷隅郡鴨根郷に入っており、鴨根郷周辺の山地を「伊志見山」と呼んでいたのかもしれない。
忠常の在所は、実資は「可令兼光申、忠常在所歟(兼光に忠常の所在を申し立てさせるべきか)」(『小右記』長元三年六月廿三日条)と考えている。それは直方の解文に「忠常、志直方之雑物兼光伝送、仍可知彼在所者(忠常が直方への贈物の雑物を兼光へ伝送しています。よって、兼光は彼の所在を知っているでしょう)」(『小右記』長元三年六月廿三日条)とあったためで、実資はこの件については「此間、諸卿相共可定申者(諸卿らとの評議して決定する)」と述べ、朝に奏上。「直方并維時、致方解文等返給」は返却された。ここに見える武蔵守平致方は、系譜にその名が見えず、出自は不明であるが、直方の近親か。
●『小右記』(長元三年六月廿三日條)
しかし、こうした朝廷内での働きかけにも拘わらず、やはり追討に進展はなかった。この根本的な問題としては、追討使がすでに兵站を維持するだけの兵粮を確保できなかったことであろう。そのため、戦闘行為の継続が不可能なほどに兵士も逃散、士気も低下し、山に籠る忠常を追捕することなど不可能な状況になっていたことは容易に想像できる。
忠常の乱に対応するため、上総国では「当国依為忠常住国、為使直方并諸国兵士等、三箇年被調三ヶ物一塵不遺」というように、貢物は追討使や諸国から派遣された兵士の糧として徴収され「一塵不遺」ほど搾取されたという(『左経記』長元七年十月廿九日條)。下総国も「下総国依追討忠常之事、亡弊殊甚」と、同様にひどい有様となっていたことがわかる。また、忠常の乱以降「散在他国々之人民多以帰来」(『左経記』長元七年十月廿九日條)、「逃散民諸国事」(『小右記』長元四年三月一日條)とあるように、多くの人々が房総半島から避難し、「安房上総下総已亡国也」(『小右記』長元四年三月一日條)という状況となっていたのだった。
上総国は忠常の勢力範囲だが、忠常は「下総国住人前上総介忠常」(『日本紀略』長元元年六月廿一日条)「下総国ニ平忠恒ト云フ兵有ケリ、私ノ勢力極テ大キニシテ、上総下総ヲ皆我マゝニ進退シテ、公事ヲモ事ニモ不為リケリ」(『今昔物語集』)、とあるように本貫は「下総国」であって、忠常と上総国の関わりを示唆する史料は残されていない(その時代の金石文や仏像等があったとしても、それが忠常と間接的にでも関係があることが確認できなければ、それは無数にある可能性の一つに過ぎず、それを以て上総国が忠常と強い関係があるとすることは不可である)。忠常と上総国の関係が確認できるのは北東部の夷隅郡のみであり、ここは一宮玉前神社付近であることから、忠常はこの地に受領当時より拠点を持っていた可能性があろう。しかし、上総国に忠常を強く支える勢力が形成できていたとは考えられない。ましてや忠常が追討の対象となれば、逃散し兵士の調達にも苦慮することは「承平の乱」を見ても明らかであろう。忠常自身も「伊志見山」に籠った状態で、しかも「籠伊志見山并隨兵減小由所推量」(『小右記』長元三年五月十四日条)という見込みもあるように、忠常勢も追討使同様に兵粮米の確保ができず、麾下の人々は日を追うごとに消えていったのあろう。
追討使側も忠常側も戦闘継続は不可能で、もはや戦いもしばらく行われていなかったのではなかろうか。どちらかが退くまでの長期対陣が続いたと思われる。
●『小右記』(長元四年三月一日條)
●『左経記』(長元七年十月廿九日條)
そして9月2日、甲斐守源頼信を新たに追討使に任じることとし、頼信ならびに坂東諸国に対して忠常を追討すべきことを決定。同時に現任追討使である平直方は「無勲功」のため追討使を解任され、召還が命じられた(『日本紀略』『小記目録』)。
9月6日、関白から実資へ遣わされた頭弁経頼から、甲斐守源頼信が忠常追討の官符を給わり、諸国にも忠常追討の宣旨が仰せ下されたことの報告がなされている(『小右記』長元三年九月六日條)。
●『日本紀略』(長元三年九月二日條)
●『小右記』(長元三年九月六日條)
■武蔵守平致方の出自
長元元(1028)年8月5日、追討忠常使の検非違使平直方は京都を発して上総国へと向かった。しかし、朝廷の予想に反して忠常追討は長期化した。そのため、長元2(1029)年正月頃、直方の父・平維時が上総介に補任され、2月23日、京都を出立した(『小右記』長元二年八月廿二日条)。これは追討使直方への支援の意味合いが強いと思われる。同じ頃、安房守には藤原光業が補任されたが、これも直方支援の為と思われる(ところが光業は印鑰を棄てて上洛。解任後は直方従兄にあたる平正輔が安房守に補され、忠常追討の支援のため安房下向を企図している)。また、この時期、平致方が武蔵守として登場し、上総介維時とともに直方を強力に支えている。致方の父は平致成だが(『桓武平氏諸流系図』)、父の上総介平維時、従兄の安房守平正輔と同様に、武蔵守平致方も直方の縁者の可能性があろう。
平良兼―+―平公雅―+―平致秋
(上総介)|(武蔵守)|(出羽守)
| |
+―平公連 +―平致成――――平致方――――定尊
(六平次)| (武蔵守)
|
+―平致頼――+―平致経――+―平公致―――平致広
|(平五大夫)|(左衛門尉)|(平八大夫)(修理進)
| | |
+―平致光 | +―平致清―――平忠致―――平景致
|(権大監) | (壱岐守)
| |
+―平致遠 +―平致任
|(大夫) |(石見守)
| |
+―平時通 +―平為景――――平景清―――平為俊
(検非違使) (駿河守)
●『検非違使補任』(続群書類従完成会)
| 平致方 | 長和2(1013)年8月15日(現任) | 右衛門尉 | 検非違使 | 『小右記』 |
| 長和3(1014)年2月1日(現任) | 右衛門尉 | 検非違使 | 『小右記』 | |
| 長元3(1030)年6月23日(現任) | 武蔵守 | 『小右記』 | ||
| 長元4(1031)年3月12日(現任) | 武蔵守 | 『小右記』 | ||
| 長元5(1032)年8月1日 | 前武蔵守 | 『小右記』 | ||
| 平正輔 | 寛弘3(1006)年6月(現任) | 東宮帯刀 | 『本朝通鑑』 | |
| 寛仁2(1018)年正月10日(使宣) | 左衛門尉 | 検非違使補任 | 『左経記』 | |
| 寛仁2(1018)年閏4月9日(現任) | 左衛門尉 | 『御堂関白記』 | ||
| 寛仁4(1020)年6月4日(現任) | 左衛門尉 | 『左経記』 | ||
| 治安3(1023)年正月10日(停止) | 左衛門尉 | 停止検非違使 | 『小右記』 | |
| 長元3(1030)年3月29日(補任) | 安房守(補任) | 『日本紀略』 | ||
| 長元4(1031)年5月2日(現任) | 安房守 | 『小記目録』 | ||
| 長元4(1031)年閏10月24日(現任) | 安房守 | 『小記目録』 |
平直方は追討使解任後、長元3(1030)年11月に帰京している(『応徳元年皇大記』)。
翌長元4(1031)年には「大夫尉」(『二中歴』)とあるため、おそらく関東下向の勲功が認められて従五位下に叙されたと想像される。その後、直方は源頼義に女子を娶せ「義家母者直方娘也」(『中外抄』仁平四年三月廿九日条)として嫡子義家が誕生している。
なお、「平将軍貞盛孫上総介直方、鎌倉に家居す、鎮守府将軍兼伊予守源頼義、いまだ相模守にて下向せし時、直方が婿となり給ひて、八幡太郎義家出生し給ひしかば、鎌倉を譲り給ひし」(『詞林采葉抄』)という説話を「史実」と認め、それを基礎として展開される説が存在する。ただ、この話はすでに鎌倉北条氏の世というフィルターを通った後の十四世紀、僧由阿が当時残っていた伝承を採用した説話集のものであり、直方を祖と称する鎌倉北条家が自らと将軍鎌倉家との由緒を示した説話が存在していて、これが採録されたと考える方が自然であろう。何より、京都召還後の直方は京都に在住し、相模国はもちろん京外に住んだ形跡はない。頼義が相模守に補されたのは、長元9(1036)年10月14日の除目(『範国記』長和九年十月十四日条)であるが、頼義が相模守任期中の長暦3(1039)年2月17、18日の連日、山徒の強訴が関白殿高陽院門前に衆参して「をめきのゝしる声おびたゞしくぞ侍りける」際、頼通は「平の直方、同繁貞」に命じてこれを防がせている(『古今著聞集』)。繁貞は検非違使であるため、直方もまた検非違使であり、追討使の頃と変わらず検非違使として京都の治安維持に当たっていたのである。つまり、平直方(当然受領の経験もない)が鎌倉を頼義に譲ったという「説話」を「史実」として採用することは不可、ということになる。
平維茂―――+―平繁貞―――平繁清――+―平繁貞―+―平繁賢――+―平維繁――――+―平繁隆
(鎮守府将軍)|(検非違使)(検非違使)|(隠岐守)|(隠岐判官)|(検非違使) |(九條院判官代)
| | | | |
| | | | +―平維輔――――――平維継
| | | | |(上西門院蔵人)
| | | | |
| | | | +―平維長
| | | | |(中宮侍長)
| | | | |
| | | | +―平長繁
| | | | |(木工助)
| | | | |
| | | | +―平宣盛
| | | | (右近将監)
| | | |
| | | +―基繁―――――+―平繁継
| | | |(美福門院侍長)|(殷富門院蔵人)
| | | | |
| | | | +―平繁氏――――――平時繁
| | | | |(北白河院蔵人)
| | | | |
| | | | +―平繁村――――――平繁親
| | | | |(北白河院蔵人)
| | | | |
| | | | +―平親繁――――――平忠繁
| | | | |(左近将監) (左兵衛尉)
| | | | |
| | | +―平光繁 +―平繁継
| | | |(大学助)
| | | |
| | | +―平実繁――――――平繁雅――――+―平信繁――――+―平繁茂
| | | (修理亮) (河内守) |(殷富門院蔵人)|(後堀河院近習)
| | | | |
| | +―平清賢――――平貞清 | +―平繁俊
| | |(検非違使) (左衛門尉) | |(蔵人)
| | | | |
| | +―平貞賢 | +―平繁澄
| | (豊前守) | |(左衛門尉)
| | | |
| +―平繁忠―――平繁仲 | +―平繁直
| | | (左兵衛尉)
| | |
| +―平忠清 +―平季繁――――+―平繁兼
| | |(右馬権頭) |(左衛門尉)
| | | |
+―平繫兼―――平貞兼 +―平盛清 | +―平繁朝
| (平八) | (左衛門尉)
| |
+―平繁成―――平貞成――+―平推家 |
|(秋田城介)(城太郎) |(城太郎太郎) | 藤原定家―――――藤原為家
| | |(権中納言) (権大納言)
+―平繁職―+―平重房 +―平長基――+―平永家―――+―平資国――+―平資長 | ∥―――――――藤原為相
|(飛騨守)| (城次郎) |(奥山黒太郎)|(城鬼九郎)|(城太郎) | ∥ (権中納言)
| | | | | +―平度繁――――+―安嘉門院四條
+―良覚 +―平繁家 +―平長繁 +―平家成 +―平長茂 |(佐渡守) |(阿仏尼)
|(城太郎) (豊田太郎) (城四郎) | |
| | +―平繁親
+―平繁頼 | |(兵衛尉)
(濱次郎) | |
| +―平繁仲
| |(大学助)
| |
| +―平繁宗
| (兵衛尉)
|
+―平邦繁――――――平繁綱
(右馬助)
このように在京の直方が、遠く東国に「家居」していた「可能性」を示唆できる何らかの傍証がない以上、
(1)鎌倉を直方が領有し、在地に住んでいた
(2)直方が義家誕生に伴って、頼義に鎌倉を譲った
という事は「伝承」であって「史実」として認めることは不可である。つまり、直方が鎌倉を領したという説話は蓋然性がなく、史的根拠として用いることはできない。
藤原惟風―――藤原惟経
(中宮亮) (太皇太后宮大進)
∥
∥―――――――藤原棟綱
∥ (相模守)
平直方――+―女
(上野介) |
+―女
| ∥――――――――――――藤原朝憲
| ∥ (陸奥守)
| 藤原憲輔 ∥―――――藤原説定
|(宮内卿) ∥ (駿河守)
| ∥
| +―源頼清―――源兼宗――女
| |(陸奥守) (上野介)
| |
| +―源頼義
| (陸奥守)
| ∥―――――源義家
| ∥ (陸奥守)
+―――女
直方には「維方 使 上総介 従五上」(『尊卑分脈』『桓武平氏諸流系図』)という子があったことが諸系譜に見られる。維方は長久2(1041)年に「大夫尉」(『二中歴』)となっている。
その子には「盛方 左衛門尉」が見える。彼は権大納言源俊房の「年来家人」(『水左記』承暦四年閏八月十日条)である「左衛門尉盛方」と同一人物であれば、盛方の生年は長元6(1033)年となり、直方が京都へ召還されたのちにうまれた孫となる。従弟の陸奥守義家とは五歳違いである。「左衛門尉盛方」は承暦3(1079)年4月13日の「平野賀茂供競馬」(『十三代要略』)で「舞人」の年長者となり、「右衛門尉平兼衡、平正衡、左衛門尉藤季光、右衛門尉平宗盛、高階盛業、同成定、平兼季已上不謂左右年歯立次第」(『為房卿記』承暦三年四月十三日条、『参軍要略抄』承暦三年四月十三日条)を伴い神前に舞を披露した。しかし、翌承暦4(1080)年閏8月10日、四十八歳で亡くなっており(『水左記』承暦四年閏八月十日条)、主人の権大納言俊房はその死去を聞いて「可憐ゝゝ」と述べる。なお、別説として武蔵熊谷氏の祖になったともされるが、熊谷氏の伝承では盛方は白河院北面に仕えていたものの誅殺されたとある。
『桓武平氏諸流系図』には盛方の兄弟に「聖範 阿多美禅師」が見えるが、彼が伊豆北條家の祖となった人物とされる。盛方は長元6(1033)年であることから、北條四郎時政の生まれた保延4(1138)年までおよそ百年の開きがある。単純計算で四代程となり、世代上の矛盾はない。ただ、平直方、平維方、平盛方の三代は主に京都で活動していたにも拘わらず(直方、維方は受領だったのかは不明)、突如として伊豆山権現に聖範が入った理由は不明。
●『桓武平氏諸流系図』(『中條家文書』)
平直方―――平維方―+―平盛方――――平俊範――――平実俊
(右衛門尉)(上総介)|(右衛門尉) (玄蕃助大夫)
|
+―聖範―――――平時家――+―平時綱
(阿多美禅師)(北條四郎)|(北條三郎)
|
+―平時兼―――――北條時政
(北條四郎大夫)(北條四郎)
長元3(1030)年9月2日、「仰甲斐守源頼信并坂東諸国司等、可追討平忠常状、依右衛門尉平直方無勲功、召還之」(『日本紀略』長元三年九月二日條)と、新しい追討使は、かつて忠常を降伏させた甲斐守源頼信であった。頼信に平忠常追討が指示されると同時に、追討使だった右衛門尉平直方には召還の命が下された。具体的な宣旨が下されたのは9月6日で、「頭弁(蔵人頭源経頼)」が右大臣実資へ「甲斐守頼信、殊給官符国々相倶可追討忠常事」等五通の宣旨(及び宣旨目録)を持参している(『小右記』長元三年九月六日條)。万寿5(1028)年当時、追討使に擬された「頼信、正輔、直方、成通」(『小記目録』十七 臨時七)の四人は、当初忠常の叛乱を軽く見て検非違使直方、成通の派遣で収めようとしたものの失敗。梃入れで直方の実父維時を上総介として派遣するも戦果は上がらず、かつて追討使に擬された平正輔を安房守に抜擢したが、下向道中の伊勢国で同族の平致経と交戦したため任国へたどり着くことができなかった。結局、当初擬された四名すべてが忠常追討使に選任されることとなった。
9月11日、「甲斐守頼信」は実資に「絲十絢、紅花二十斤」を志した(『小右記』長元三年九月十一日條)。忠常追討使への起用に対する礼か。翌9月12日、実資は右大弁源経頼が「持来給甲斐守頼信官符」等の案を関白頼通に覧せ、「可清書之由」の指示を受けている(『小右記』長元三年九月十二日條)。
9月23日、実資は頭弁経頼が持参した「給甲斐守頼信、追討忠宗(ママ)之官符草」を検見して返し、清書するよう指示を出した(『小右記』長元三年九月廿三日條)。その後、具体的な期日は不明ながら長元3(1030)年中にまず任国である甲斐国へ下向した。その際、頼信は「忠常子法師」を「相従」えており(『左経記』長元四年六月十一日條)、当初より忠常を降伏させることを企図していたとみられる。
長元4(1031)年正月6日、任国甲斐に在国中の甲斐守頼信は「申治国加階事、可令外記勘申者」として「今日入眼請印」し、宣旨が下されて、頼信は「従四位下」に叙された(『小右記』長元四年正月六日条)。
2月13日、頭弁経頼が実資に報告した中に、「流人光清使左衛門府生永正、於駿河国、為甲斐国調庸使被射殺、即使永正母進可給使随身雑物之由」との事があり、実資は「駿河国司言上解文歟、依其可被仰下歟」(『小右記』長元四年二月十三日条)と答えている。このとき、甲斐国には忠常追討使として頼信が着任しており、頼信は追討使としての官務と同時に国司としての公務もこなし、この流人使左衛門府生永正が駿河国で甲斐国調庸使に射殺された事件を調査して弁官局へ報告している。
●『小右記』(『左経記』長元四年二月廿三日條)
その後、頼信は「欲行向上総」(『左経記』長元四年四月廿八日條)ており、4月初旬には下総国府に入り、上総国府へ軍陣を動かしていたのだろう。すると、忠常が「随身子二人、郎等三人進来了」(『左経記』長元四年四月廿八日條)という。時期としては4月20日頃であろう。この降伏は、
(1)忠常勢は戦闘継続は不可能な状況に陥っていたとみられる
(2)忠常は5月末時点で「重病」に陥り、6月6日に病死しているように、4月末時点ですでに病状は相当に悪化した状態にあった
(3)新手の追討使が派遣され、しかも追討使は主の源頼信だった
(4)頼信が随従した「忠常子法師」をして忠常と交渉した?
というような要因が考えられよう。とくに、(2)のような状況であったとすれば、身動きは儘ならず、最短距離でしかもそこに頼信がいる状況で降伏しなければならない。つまり、すでに忠常から頼信に降伏の意図が伝えられており、その交渉は(4)のように「忠常子法師」が介在し、頼信が忠常を事実上「受け取る」ために上総国へ赴いたと考えることが妥当ではなかろうか。
この「甲斐守頼信、申上忠常将参由事」(『小記目録』長元四年廿五日條)は、4月25日に実資に届いている。その後、頼信が「権僧正(尋円)」へ送った書状が関白頼通に披露され、4月28日、関白頼通は参内の際、同道した従兄の右大弁経頼に「甲斐守頼信、送権僧正許書」を見せている(『左経記』長元四年四月廿八日條)。
●『権僧正書状』(『左経記』長元四年四月廿八日條)
5月20日には「常陸介兼資」からも「忠常帰降間事」が右大臣実資に届けられている(『小記目録』長元四年五月廿日条)。ただ、この報告は忠常降伏からひと月近く経過しており、すでに朝廷は忠常降伏および上洛に関して把握しており、この常陸国解がどういった意味で出されたものなのかは定かでない。
藤原中正―+―藤原安親―+―藤原為盛――――藤原親国――――藤原親子
(摂津守) |(参議) |(越前守) (大舎人頭) (白河院御乳母)
| | ∥――――――――藤原顕季
| | ∥ (修理大夫)
| | 藤原隆経
| | (美濃守)
| |
| +―藤原守仁――――藤原尚賢――――藤原兼資
| (山城守) (越後守) (常陸介)
|
| 源雅信――+―源扶義―――――源経頼
|(左大臣) |(参議) (右大弁)
| |
| +―源倫子
| ∥
+―藤原時姫 ∥―――――+―藤原頼通
∥ ∥ |(関白)
∥ ∥ |
∥――――+―藤原道長 +―藤原彰子 +―後一条天皇
藤原兼家 |(関白) ∥ |
(関白) | ∥ |
| 円融天皇 ∥―――――+―後朱雀天皇
| ∥ ∥
| ∥―――――――一条天皇
| ∥ ∥
+―藤原詮子 ∥
|(東三条院) ∥
| ∥
+―藤原道隆――+―藤原定子
|(関白) |(皇后宮)
| |
+―藤原道兼 +―藤原伊周
(関白) |(内大臣)
|
+―藤原隆家
(中納言)
源頼信と平忠常入道の上洛ルートは定かではないものの、上総介菅原孝標が上総国から帰京するルートとして東海道を通っていることから、彼等も東海道を経由したものと想定される。
長元4(1031)年6月7日(または6日か)に右大弁経頼のもとへ届けられた「自甲斐守送忠常帰降之由申文」は、「自美乃国大野郡送之由」で、内容は「忠常帰降之由」(『左経記』長元四年六月十一日条)と、「兼又忠常従去月廿八日爰重病、日来辛苦、已万死一生也、雖然相扶漸以上道(忠常は先月28日から重病となりました。日頃から苦しんでおり、すでに明日をも知れぬ状態です。それでも扶けながら、なんとか上洛の道を進んでいます)」(『左経記』長元四年六月七日条)との報告であった(なお、この頼信書状が京都に届いた日、忠常入道は死去している)。ただ、この書状に「不副忠常降順状」であったため、頼信に「早可上之由示送了」と、忠常から降順状を提出させる指示をしている(『左経記』長元四年六月七日条)。それに伴い、頼信からの国解はしばらく留めて「副彼状可付奏者也」と指示した(『左経記』長元四年六月七日条)。
●『左経記』(『左経記』長元四年六月七日條)
ところが6月11日、経頼のもとに「修理進忠節」が訪れて報告するには、忠節のもとに「忠常子法師、去年相従甲斐守頼信朝臣、下向彼国」が「而只今京上」し、「忠常、去六日、於美濃国野上と云所死去了、仍触在国司、令見知并注日記、斬首令持彼従者上道者、令且注此由、可被申事由(忠常は六月六日、美濃国野上という所で死去致しました。よってこの旨を美濃国の在国司に報告し、実検ならびに日記に記録させたうえで、忠常の首を斬り、忠常従者に持たせて上洛いたします、とのことです。この旨を注し、事の次第を報告されるように)」(『左経記』長元四年六月十一日条)という。忠常の没年齢不詳。出家して法号は常安。
●『左経記』(『左経記』長元四年六月七日條)
これを聞いた経頼は「驚此告」き、「以前日、所送之忠常帰降之由申文、付頭弁令奏、是死去之由不申、以前可急也(先日、送られてきた忠常帰降の旨の申文を、頭弁経任に付して奏上させたが、これは忠常が死亡したということは申していない。以前から急ぐべきだった)」と述べている。なお、忠常死去の情報は同日に右大臣実資も「降人忠常死去事」(『小記目録』長元四年六月十一日条)と共有している(ただし、小右記本文(同日記録は散逸)に実資が後日追記し、目録時には同日のこととされた可能性もある)。
翌6月12日、「修理進忠節」は再び経頼邸を訪れて「持来甲斐守消息」て経頼にこれを渡した。経頼がこの消息を披いて見ると「有忠常死去国解」であった。この頼信の(甲斐国)国解の内容は前日に「忠常子法師」が伝えた情報と同じであったが、死去の場所が「美濃国厚見郡死去」(『左経記』長元四年六月十二日條)とあるように、「於美濃国野上と云所死去了」とは異なっていた。また、国解には、
(1)美乃国司返牒
(2)日記
(3)忠常降順状一枚(是前日依遺取所送)
が副えられており(降順状は昨日送り忘れていたため本日同送されたもの)、忠常は死去直前に降順状を認めていた可能性がある(頼信方の代筆かもしれない)。こうして7日に経頼が頼信に指示した「而依不副忠常降順状、早可上之由示送了、暫留国解、副彼状可付奏者也」(『左経記』長元四年六月七日條)は、国解に降順状一枚を副えて送達したことで、報告は完了したことになる。
●『左経記』(『左経記』長元四年六月十二日條)
翌6月13日、「忠常、志直方之雑物兼光伝送」(『小右記』長元三年六月廿三日條)した「兼光」が「兼光出家事有与忠常同意之聞」(『小記目録』)と、忠常と同意の人物と疑われ、出家した。なお、「兼光」が出家したのは忠常の死が朝廷に伝わった直後であり、当時在京の人物である。「兼光」は直方と親しく、また、忠常とも交流のあった人物であったため、忠常からの直方宛の贈物を取り次いだとみられる。忠常の在所を知っていると認識されているという事は、「兼光」は夷隅山付近に布陣し、その雑物を自陣に搬入を見届けている人物となり、追討使直方とともに下向していた将の一人だろう。その後、京都にいたということは、長元3(1030)年11月に直方とともに京都へ戻ったのであろう。
●頼信の上洛ルートと忠常死去の場所
源頼信の上洛ルートは、前述のとおり前上総介菅原孝標の上洛ルートと同様、東海道を経由したものと考えられる。尾張国府以降の美濃路の東海道は、古渡、下津、牛野、黒田を経由、境川を渡って美濃国厚見郡へ入り、墨俣から杭瀬川を渡り、美濃国府へと延びているが、頼信はおそらく境川を渡った付近では東海道を通ってくるも、そこから美濃国府方面へ西上せず、北上して大野郡へ入った。理由は不明だが、中山道へ「道を変える必要があった」可能性がある。推測ではあるが、頼信一行は墨俣から中山道の大野郡美江寺へ道を変更し、その後は関ケ原方面へ向かったと考えられる。
忠常入道死去の場所については、6月11日に「忠常子法師」が上洛して修理進忠節に説明した忠常死去の場所は、「美濃国野上と云所」(『左経記』長元四年六月十一日條)であった。しかし翌6月12日に経頼邸を訪れた「修理進忠節持来甲斐守消息」の「忠常死去国解」によれば「美濃国厚見郡死去」とあった。なお、忠常の死去は「今月六日」であるため(『左経記』長元四年六月十二日條)、大野郡より南東の厚見郡ではない。
「美濃国野上」は現在の関ケ原町野上と推測される。野上には現在「しゃもじ塚」(関ケ原町大字野上382-1)と呼ばれる伝忠常墓が祀られている。
このほか歿地としては、「美濃国山縣」(『百錬抄』『扶桑略記』)、「美濃国蜂屋庄」(『千葉大系図』)も見える。ただし、いずれも6月上旬に頼信が忠常重病の申文を発した「大野郡」(『左経記』長元四年六月七日条)よりも東に位置していることから、歿地としては不可である。
| 没地 | 現在地 | 資料 |
| 美濃国野上 | 不破郡関ヶ原町野上 | 『左経記』長元四年六月十一日條(頼信が派遣した忠常子法師の報告) |
| 美濃国厚見郡 | 岐阜市の一部 | 『左経記』長元四年六月十二日條(頼信の国解による報告) |
| 美濃国山縣 | 山県市、岐阜市・関市の一部 | 『百錬抄』『扶桑略記』 |
| 美濃国蜂屋庄 | 美濃加茂市蜂屋町 | 『千葉大系図』 |
以上を踏まえて、忠常死去までの道のりを想像してみる。
東海道を西上していた、源頼信と忠常入道であったが、長元4(1031)年5月28日に忠常入道は厚見郡柳津あたりで容体が急変した。そのため、頼信は十一面観音を祀る大野郡美江寺へ道を変更し、忠常入道の後生救済を図った。その後、中山道を通って赤坂、垂井を経て、6月6日、不破の関へと向かう最中の野上で、忠常入道は死去した。頼信は至急国衙に実検を依頼し、在庁の在国司がこれを記録した。上洛に当たっては忠常入道の首級のみを持参すれば事足りるため、斬首して遺体は当地に埋葬した(しゃもじ塚)。
なお、忠常の死から百六十年ほどのちの建久6(1195)年12月12日、千葉介常胤が「老命、後栄を期し難し」として「警夜巡昼の節を励まし、連年の勤労を積む。潜かにその貞心を論ずるに、恐らくは等類無きに似たり」と、恩賞を求める「款状」を頼朝に提出した(『吾妻鏡』建久六年十二月十二日条)。この中で常胤は「殊に由緒あり」として「美濃国蜂屋庄」の地頭職を望んでいるが、常胤が伝えたこの「由緒」こそ、平忠常の葬地なのかもしれない。結局、蜂屋庄は「故院の御時、仰せに依りて地頭職を停止」した荘園であり、頼朝も如何ともしがたい土地である旨を伝え、「便宜の地を以ちて、必ず御計らい有るべきの旨」を記載した書状を遣わしている。
忠常首級については、6月14日に「帰降者首、可梟哉否事」(『小記目録』十七 臨時七 追討使事)が議論されている。その二日後の16日に「頼信朝臣、梟平忠常首入京」(『日本紀略』長元四年六月十六日条)、「甲斐守頼信、随身忠常首入洛事」(『小記目録』十七 臨時七 追討使事)しているが、このときには忠常の首級は「梟平忠常首」とあるように、鉾に直接または布に巻かれてぶら下げられていたと思われる。ただ、その後は忠常が神妙に降伏したことが考慮されたのか、獄門に懸けられることなく忠常の「従類」へ返却された。
6月27日の陣定において、「甲斐守源頼信進忠常帰降之由、申文并常安降状忠常法名也、忠常死去之由解文并美濃国司等実検日記等被下云」ことについて、「頼信朝臣令帰降忠常之賞可有哉否」と「忠常男常昌常近不進降状、猶可追討哉否之由」が議題に上がった。これに右大弁経頼は、
「頼信朝臣令帰降之賞、尤可被行也、但於其法者、先符云、随其状可給官位者、先被召問頼信朝臣、随彼意趣可被量行歟、又忠常男常昌常近等不進降順状、其身雖死去、於男常昌等者未降来、何黙止被免哉、須任先符猶被追討也、而前使直方時、坂東諸国多属追討、衰亡殊甚云々、重遣使乎、若賜早可撃之符、偏経営此事之間、諸国弥亡、興復難期歟、暫被優廻、頗興復之後、左右可被行歟者(頼信朝臣が忠常入道を帰降させた賞については、まことに行うべきである。ただ、法に従うならば、先の追討官符には「状況に応じて官位を与えるべし」とあるので、まず頼信朝臣を召して意向を聞き、それに基づいて行賞の程度を決めるべきか。また、忠常の子の常昌、常近はいまだに降順状を提出していない。忠常入道はすでに死去しているとはいえ、その子常昌らはまだ降伏していない。どうして黙って免ぜられようか。やはり先符に従い、追討を行うべきである。ただし、前使直方の時に坂東諸国の多くが追討に加わり、衰亡が非常に甚だしい。もしも再び追討使を派遣して早々に攻めよと命じれば、国衙は追討に加わることとなり、諸国はますます荒廃し、復興は難しくなるであろう。したがって、しばらくは猶予を与え、国がある程度復興した後で追討すればよいだろう)」(『左経記』長元四年六月廿七日条)
と主張した。
一方、左大弁藤原重尹は、
「頼信朝臣賞同余詞、但常昌等事者、為造意首忠常已以帰降、常昌等是従也、雖不被追討有何事哉者(源頼信朝臣への賞については、私(経頼)と同意見だった。ただし、常昌らの件については、首謀者の忠常がすでに帰降し、常昌らもまたこれに従った。追討しなかったからといって何の差し支えがあろうか)」(『左経記』長元四年六月廿七日条)
と主張。左兵衛督公成もまた、
「頼信朝臣賞事同下官申旨、但於常昌等事者、常安降状頗見男等降帰気色之中、忠常於途中死去、獄禁者遭父母喪之時給其暇云々、況未被禁者哉、被優免有何事哉(源頼信朝臣への賞については、私(経頼)と同意見だった。ただし、常昌らの件については、常安の降順状にその子らの降伏も記されている。忠常は途中で死去しているが、獄に繋がれている者でも、父母の喪に遭えば暇が与えられる。まして禁獄されてもいない者であれば猶更であろう。常昌らを宥免することに何の問題があろうか)」(『左経記』長元四年六月廿七日条)
という。このほか「新中納言以上被申之趣大略同余詞(新中納言以上が申される趣は、おおよそ自分と同じであった)」といい、陣定出席の公卿の大半は、頼信への行賞と常昌等の追討について経頼同様の意見だったようだ。なお、「新中納言」については、長元2(1029)年正月24日に権中納言となった藤原経通、藤原資平、藤原定頼のいずれかとなろう(『公卿補任』長元二年)。彼らはいずれも小野宮流藤原氏に属する公卿である。
+―文徳天皇―+―清和天皇―+―陽成天皇
| | |
| | |
| | +―貞純親王―――源経基
| | (中務卿) (大宰少弐)
| |
| +―源能有―――――――――――源昭子
| (右大臣) ∥
| ∥―――――――藤原師輔 +―藤原伊忠
| ∥ (右大臣) |(太政大臣)
| ∥ ∥ |
| ∥ ∥―――――+―藤原兼通 +―藤原道隆―――藤原伊周
| ∥ ∥ |(関白) |(関白) (内大臣)
| ∥ ∥ | |
| ∥ 藤原経邦――藤原盛子 +―藤原兼家―+―藤原道兼
| ∥(武蔵守) (関白) |(関白)
| ∥ |
| ∥ +―藤原道長―――藤原頼通
| ∥ (関白) (関白)
| ∥
| ∥ +―藤原経通
| ∥ |(権中納言)
仁明天皇―+―光孝天皇―+―人康親王―――女子 ∥ |
|(弾正尹) ∥――――+―藤原忠平 +―藤原懐平―+―藤原資平
| ∥ |(関白) |(権中納言) (大納言)
| ∥ | ∥ 【小野宮】 |
| 藤原基経 | ∥―――――――藤原実頼 +―藤原斉敏―+―藤原実資===藤原資平
| (関白) | ∥ (関白) |(参議) (右大臣) (大納言)
| | ∥ ∥ |
+―宇多天皇―+―――――――源順子 ∥―――――+―藤原頼忠
| | ∥ (関白)
| +―藤原時平――――女子 ∥
| (左大臣) ∥――――――藤原公任
| ∥ (権大納言)
| +―代明親王――――――――――――厳子女王 ∥
| |(中務卿) ∥――――――藤原定頼
| | ∥ (権中納言)
+―醍醐天皇―+―村上天皇――+―昭平親王―――――――――――女子
|(常陸太守)
|
+―円融天皇――――一条天皇
|
|
+―具平親王――――源師房
(中務卿) (右大臣)
その後、常昌・常近の追捕は行われていないが、「頗興復之後、左右可被行歟者」(『左経記』長元四年六月廿七日条)が前提であったためであろう。また、再度の荒廃を恐れて追討使派遣は事実上不可能だったと思われる。
上総国については、「則前司維時朝臣任終年徴符案随身令見之、国内通計所作之田十八町余也、前司署名明白也、敢无事疑、彼国本田二万二千九百八十余町云々、将門乱間雖最亡、未若此時云々、而辰重到任之年五十余町、次々年逐年加作、今年内検定千二百余町」(『左経記』長元七年十月廿九日條)とあるように、二万二千九百八十余町の公定田(本田)があったが、長元4(1031)年の時点で十八余町にまで激減していたと報告されている。これが、平維時の後任である上総介辰重(時重)の補任初年で五十余町、四年目の長元7(1034)年で千二百余町になったといい、四年間で19分の1回復したことになる。仮にこのペースで興復したとすれば、元に戻るまでは八十年ほど要する計算となる。
上総国と同じく、下総国も激しく荒廃した様子がうかがえ、長元4(1031)年3月1日の朝議において「諸国事」につき、関白頼通から「下総守為頼申被重任■■逃散民勧農業者■給申文」についての「御消息」があった。それによれば「(忠常追)討之間、有勧之由云々、若可有裁許哉何如」とのことだった。これに右大臣実資は「(下総)国依追討忠常之事、亡幣殊甚云々、為頼云、■■貯可及飢餓、亦妻并女去年憂死道路、依無辜、京中之人見歎之由云々、先被優二箇年任、若(為頼)良吏之聞、臨彼時可被延今二箇年歟、抑安(房、上総)下総已亡国也、被加公力、令期興復尤佳」と報告している(『小右記』長元四年三月一日条)。実資は為頼についてはまず二年の重任を認め、彼が良吏であるとの報告があれば、さらに二年の延長を認めてはどうかという内容である。また、忠常の影響により安房・上総・下総三か国はすでに大きく荒廃しており、朝廷からの支援により復興させることが重要であると述べている。
6月27日の朝議に提出された「下総守頼重(ママ)任八箇年間、啓四年公事預勧賞申文」(『左経記』長元四年六月廿七日条)につき、右大弁経頼は「下総守為頼申、重任八箇年之中、啓四箇年公事、預勧賞事、如申状者、罷下之後不幾程、相営追討忠常事之間、人物共已弊、忽難興復、若無裁許何済公事云々、所申可然、依請可被免歟」(『左経記』長元四年六月廿七日条)と意見を述べた。為頼が下総国下向後程なくして忠常追討の事があり、下総国は戦場となり国兵の提供や兵粮供出などがあったのだろう。「人物共已弊」じており下総国の再興には援助が必要であるという為頼の申状は尤もであると意見したのである。なお、申状の「下総守頼重」は「下総守為頼」の誤記である。
忠常の子・常昌(常将)は両総平氏の祖となり、弟・常近(恒親)は武蔵七党のひとつ、村山党の祖になったとされる。また、忠常の兄(または甥)である将恒(武蔵権大掾)は、武蔵国秩父牧に権益を得て秩父党の祖となったとされる。
◆良文流平氏系譜(想像)
+―忠頼――――将恒―――――秩父武基――――武綱――――――重綱――――重隆
|(陸奥介) (武蔵権守) (秩父別当大夫)(秩父武者十郎)(出羽権守)(留守所惣検校職)
|
平良文―――経明―?―+―忠光――――為通―――――三浦為継――――義継――――――義明――――義澄
(陸奥守) |(駿河介) (平太夫) (平太郎) (三浦庄司) (三浦大介)(三浦介)
|
+―忠通――――章名―――――鎌倉景成――――景正――――――景継――――長江義景
|(小五郎) (甲斐権守 (権守) (権五郎) (小太夫) (太郎)
|
+―忠常――+―常将―――――常長――――+―千葉常兼――――常重――――常胤
(上総介)|(武蔵押領使)(武蔵押領使)|(下総権介) (下総権介)(下総権介)
| |
| +―平常晴―――――常澄――――広常
| (上総権介) (上総権介)(上総権介)
|
+―恒親―――――恒仲――――――頼任
(安房押領使) (村上貫主)
忠常がどういった伝手を以て、選りによって律令大国「上総国」の国司となることができたのか。当時国司となるには下記の『枕草子』に見るように、相当な努力を必要とした。忠常は藤原教通の家人であるため、かつて上洛して教通に仕えていたことがきっかけである可能性もあるが、どういった経緯で受領となるに至ったのかは謎である。
●『枕草子』第三段「正月一日は」
●『枕草子』第廿三段「すさまじきもの」
忠常が「上総介」であったことは間違いないが、上総介を辞した後は下総国に移り住んだようである。また、他の古文書に見えない記述として『応徳元年皇代記』には忠常は「下総権介」だったと記されている。
●忠常について伝える史書
| 史書 | 忠常について | 住居 | 成立 |
| 『百練抄』 | 前上総介忠常 | 13c末 | |
| 『小記目録』 | 平忠常并男常昌等 | ||
| 『日本紀略』 | 前上総介平忠常 | 下総国住人 | 長元9(1036)年まで |
| 前上総介平忠常 | 下総国 | ||
| 『左経記』 | 平忠経 | 住下野(下総の誤りか) | 長元8(1035)年まで |
| 『応徳元年皇代記』 (春日若宮千鳥家本) |
下総権介平忠常 | 12c半 |
●忠常の所在
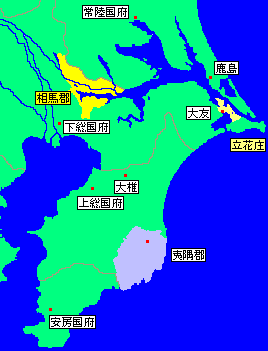 |
| 古代の房総地図(想像) |
下総国での忠常の所在は、通説では立花庄大友(香取郡東庄町大友)とされており、同地には「良文貝塚」が残されている。しかし、忠常以前に良文、忠頼(または経明)が下総にいたことを示す傍証はない。彼らは武蔵国内での動向が記録に残されていることから、武蔵国を根拠としていたと考えられる。ただし、子孫の千葉常胤が相馬御厨下司をめぐる相論の中で記した文書によれば(久安二年八月十日『正六位上平朝臣常胤寄進状』)、下総国相馬郡について、
「……右当郡者、是元平良文朝臣所領、其男経明、其男忠経、其男経政、其男経長、其男経兼、其男常重、而経兼五郎弟常晴、相承之当初為国役不輸之地……」
とあることから、千葉介常胤(当時29歳)は相馬郡が良文、経明、忠経(忠常)…と相伝してきた所領と認識していたことがわかる。しかし、立花庄については由来が記述されず、下総平氏がいつ頃から関わりを持つようになったのか不明である。
立花郷と相馬郷は保延2(1136)年11月13日、下総守藤原親通によって平常重・常胤父子の手から奪われたが、立花郷については取り返すことに執着していないにもかかわらず、相馬郷については相当に執着しており、両総平氏にとって相馬郡は立花郷とは比較にならない重要な由緒があったとみられる。これは相馬郷が良文以来の所領で、遠祖・忠常の下総での住居が相馬郷にあった可能性があったためか。
●『千葉大系図』忠常の項●
忠常 上総介。武蔵押領使。天延三年九月十三日誕生。居上総国大椎城。長元元年戊辰、依浮説而征討使下向、相闘有年。既而同四年辛未四月、服源頼信之言、棒名符怠状。赴洛途中罹病、同五月十五日、死于美濃国蜂屋庄。年五十六。故嫡子常将蒙勅免矣。
【参考】
●関幸彦「在国司職」成立に関する覚書(学習院大学学術成果リポジトリ)