

 (????-1237?)
(????-1237?)
葛西氏初代。豊嶋権守清元の子。母は秩父十郎重弘の女とされる。通称は三郎。官位は従五位下。官職は左兵衛尉、左衛門尉、壱岐守。出家して壱岐入道定蓮。妻は従妹にあたる畠山庄司重能の娘。千葉介常胤は義理の伯父にあたり、千葉胤正・師常・胤盛・胤信・胤通・胤頼や畠山重忠とは従兄弟の間柄となる。頼朝からはとくに「於源家抽貞節者也」と評された人物である。
豊島清元
(豊島権守)
∥
∥――――――葛西清重
∥ (三郎)
秩父重弘―+―娘 ∥―――――――葛西朝清――――――――――――葛西清時
(十郎) | ∥ (六郎左衛門) (新左衛門)
| ∥ ∥
+―畠山重能―+―娘 ∥
|(畠山庄司)| ∥
| | ∥
+―娘 +―畠山重忠 ∥
∥ (次郎) ∥
∥ ∥
∥――――――千葉介胤正―――千葉介成胤―――千葉介胤綱―――娘
千葉介常胤 (千葉介) (千葉介) (千葉介)
(下総権介)
『沙石集』の第六巻「芳心有人事」の記述によれば、「故葛西ノ壱岐ノ前司トイヒシハ秩父ノスエニテ弓箭ノ道ユリタリシ人也」と、秩父氏の一族で武勇の人であった事がうかがえる(『沙石集』)。また、和田合戦では和田一族を駆け散らすなど「心モタケクナサケモアリケルヒト也」(『沙石集』)と評されている。
兄・豊島太郎左衛門尉有経が豊島氏を継ぎ、清重は下総国葛西庄の庄官となった。四男・笑田四郎有光は武蔵国都筑郡荏田村、五男・豊島五郎家員は豊島郡内に所領を有したのだろう。文治5(1189)年7月19日、奥州藤原泰衡との戦いに祖父の豊嶋権守清元、父の清重とともに従軍している「十郎」は末弟の十郎清宣か。
一説によれば、清重は承安3(1173)年、葛西庄の下司職・葛西重隆(重高)の養子となって葛西を称したといわれているが不明。この葛西重隆は千葉介常胤の弟とされるが、実在した可能性の高い常胤の弟は椎名胤光・小見胤隆のみであり、重隆は実在の人物であったとしても、千葉氏とは血縁関係のない秩父一族だったのであろう。
●「葛西氏系図」(『桓武平氏諸流系図』:『奥山庄史料集』所収)
次男 号六郎大夫 平傔仗 豊島三郎 左衛門尉
●将恒――――武恒―――――経家―――康家――――+―清元―+―有経
武蔵権守 | |
| | 壱岐三郎 四郎
| +―清重――――+―重元
| | |
| | 笑田四郎 | 伯耆守 三郎左衛門
| +―有元 +―清親――――時清
| | |
| | 豊島五郎 | 六郎左衛門
| +―家員 +―朝清
| |
| | 七郎左衛門
| +―時重
| |
| | 八郎左衛門
| +―清秀
|
| 豊島四郎 兵衛尉
+―俊経――――遠経
|
+―平塚入道
『吾妻鏡』によれば、治承4(1180)年9月3日、石橋山合戦に敗れて安房国にあった頼朝は、上総介八郎広常・千葉介常胤に使者を送る一方、下野国の在庁・小山四郎朝政とその同族である下河辺庄司行平、そして武蔵国境に所領を持つ豊嶋権守清元・葛西三郎清重にも参向するよう使者を派遣し、「而其居所、在江戸河越等中間、進退難治定歟、早経海路可参会之旨」を申し伝えている(『吾妻鏡』治承四年九月三日条)。また頼朝は、当時大番役で上洛中していた清重甥の「豊嶋右馬允朝経」の妻女に対して綿衣を調進するよう指示をしており、千葉氏同様、配流時代からすでに豊島氏や清重とは連絡を取り合う仲にあったと推測される(『吾妻鏡』治承四年九月三日条)。
9月29日、頼朝は「依令与景親」って今なお帰参しない「江戸太郎重長」を追捕すべく、側近の「中四郎惟重」を清重のもとに遣わし、「可見太井要害之由」と偽って重長を誘き出して討つべしと指示を出した。江戸氏は太日川(隅田川)河口周辺に大きな勢力を持っていた豪族であり、平家方に属していた。江戸氏・葛西氏ともに同じ秩父一族であるが、頼朝は「清重ふたごころを存ぜざるによって」この密計を授けたという。頼朝の清重に対する信頼感をうかがうことができる。しかし、清重は重長の暗殺をすることはなかった。
『沙石集』にはこの頼朝の太日川渡河の際の頼朝と清重とのやりとりが記載されている。頼朝は江戸重長の所領を召上げて、「葛西ノ兵衛」に与えようと言うが、清重は「御恩ヲ蒙リ候ハ、親キ者共ヲモカヘリミンタメナリ、身一ハトテモカクテモ候ヌヘシ、江戸シタシク候、僻事候ハヽ、メシテ他人ニコソタヒ候ハメ」と、親戚である江戸重長の領地を清重が受けることはできない、もし彼にやましいことがあるならば、彼の所領を召し上げて他の人に給え、とこれを固辞した。頼朝はこれを聞いて「イカテ給ハラサルヘキ、モシ給ハラスハ汝カ所領モ召取ヘシ」と清重の所領を召上げると怒った。これに清重は「御勘当蒙ルホトノコトハ運ノキハマリニテコソ候ハメ、力オヨハス、サレハトテ給ハルマシキ所領ヲハ争カ給フヘキ」と、義を曲げてまで今の所領を欲しないと主張した。
10月2日、頼朝一行は広常・常胤が調達した舟筏に乗って「大井隅田両河」を渡って武蔵国に入った。このとき頼朝が布陣した場所は「豊島御庄瀧ノ河(北区)」(『源平闘諍録』)とされるが、「豊島権守清元、葛西三郎清重等最前参上、又足立右馬允遠元、兼日依受命、為御迎参向」とあることから、豊島清元と葛西清重の父子が頼朝の麾下に加わったのは、葛西清重が荘官を勤めていた「大井」と「隅田」の中州の肥沃地・葛西庄以外にあり得ず、さらに同日、頼朝の乳母・寒河尼(八田権守宗綱の娘で小山政光の妻)が十四歳の末子を連れて「隅田宿(現在の台東区橋場周辺)」に参向し、頼朝はそこで少年に「朝」字を与え、「小山七郎宗朝(のちの結城朝光)」と名乗らせたとあることから(『吾妻鏡』治承四年十月二日条)、頼朝勢は下総国府から豊嶋郡衙(北区西ヶ原)へ向かう官道を通って隅田宿へ入り、その後は豊島清元の案内によって武蔵野台地の急崖を経て豊嶋郡衙へ進んだのだろう。豊嶋郡衙は下総国府と武蔵国府を繋ぐ中継地で、大井駅へ向かって南下する官道も走っている要衝であった。
→藤原宗円―――八田宗綱―+―宇都宮朝綱
(宇都宮座主)(権守) |(左衛門尉)
|
+―八田知家―――八田朝重
|(右衛門尉) (太郎)
|
+―寒河尼 +―小山朝政
【頼朝乳母】|(下野大掾)
∥ |
∥―――+―長沼宗政
小山政光 |(淡路守)
(下野大掾)|
+―結城朝光
(左衛門尉)
10月3日の頼朝の動向は伝わらないが、この日、頼朝は常胤へ上総国の伊北庄司常仲(広常の甥)の追討を命じており、胤正は父・常胤の厳命を受けて、上総国に派遣された(『吾妻鏡』治承四年十月三日条)。豊嶋郡から上総国伊北庄(いすみ市岬町一帯)へと遣わされたのである。彼らは百kmを超える道を進んで伊北庄に常仲らを誅した(『吾妻鏡』治承四年十月三日条)。上総国の伊北庄司常仲は、頼朝に敵対して滅ぼされた長狭六郎常伴の外甥だった関係で頼朝から追討の対象とされたようであるが、実は常仲は頼朝に味方した上総介八郎広常の兄・権介常景の嫡子であり、この追討には少なからず広常および常胤の意向が関係しているのだろう。
平常長―――+―平常兼――――千葉介常重―――千葉介常胤――千葉介胤正
(上総権介?)|(下総権介?)(下総権介) (下総権介) (下総権介)
|
| +―長狭常伴
| |(六郎)
| |
| +―娘
|【上総権介】 ∥――――――伊北常仲
+―相馬常晴―――平常澄―――+―伊南常景 (伊北庄司)
(上総権介) (上総権介) |(上総権介)
|
+―平広常
(上総権介)
この戦いでは葛西三郎清重も上総国に出陣していたことが、文治6(1190)年正月13日の胤正の上申に「葛西三郎清重者、殊勇士也先年上総国合戦之時、相共遂合戦」(『吾妻鏡』文治六年正月十三日条)とあることからわかるが、平安時代末期にはすでに千葉氏と葛西氏は下総国の有力官人の二頭であり、一宮香取社の造営を交替で行っており、互いに交流を持っていたと推測される。
| 名前 | 被下宣旨 | 御遷宮 |
| 台風で破損し急造 (藤原親通) |
保延3(1137)年丁巳 | |
| ―――――― | 久寿2(1155)年乙亥 | |
| 葛西三郎清基 | 治承元(1177)年12月9日 | |
| 千葉介常胤 | 建久4(1193)年癸丑11月5日 | 建久8(1197)年2月16日 |
| 葛西入道定蓮 | 建保4(1216)年丙子6月7日 | 嘉禄3(1227)年丁亥12月 |
なお、上総国伊北庄に展開した胤正らの軍勢が、その頃駿河国東部へ進んでいた頼朝と合流するには、三浦半島を経由したルートだとしても百km超の軍旅となるため、胤正勢はもともと上総国の平家与党鎮圧の別働部隊として派遣され、征西軍への再合流は考えられていなかったのだろう。
その後の頼朝一行は、おそらく武蔵国豊嶋郡衙から官道を南下して大井駅を経由し、荏原郡衙、橘樹郡衙、久良岐郡を経て相模国鎌倉郡へ入るルートをとったとするのが自然であろう。頼朝はさらに南下して、翌10月5日には相模国境に近い久良岐郡衙(横浜市南区弘明寺町)に駐屯したのだろう。そして翌10月6日、頼朝は畠山重忠を先陣、常胤を後陣として「着御于相模国」した。この「相模国」は相模国鎌倉郡へ入ったということと同時に、朝比奈方面から鎌倉内に入ったということであろう。朝比奈方面にはもともと上総権介広常の屋敷地があったと思われ、12月12日、頼朝が新造の御亭(鎌倉市雪ノ下)に移る際には「上総権介広常」の屋敷(鎌倉市十二所カ)から移っている。重忠を先陣としつつも、鎌倉の地理を熟知する広常の案内は重要であったろう。ただ、その日は「楚忽之間、未及営作沙汰、以民屋被定御宿館」とある通り、進軍があまりに急であったために、鎌倉の街中に頼朝が宿営できる場所を造っておらず、やむなく民家を陣所とした(『吾妻鏡』治承四年十月六日条)。
翌10月7日、頼朝は鎌倉北部から由比浜辺に建つ古社「鶴岡八幡宮」を遥拝したのち、「故左典厩義朝之亀谷御旧跡」(現在の寿福寺の地)を監臨して、ここに館を構えようとした。ところが狭小の上に、すでに岡崎平四郎義実が建てた義朝の菩提を弔う堂宇があったことから、結局この地をあきらめ、大倉の地に御所を建てることになる。
先の頼朝追討の官符を奉じた平維盛を主将とする追討使は、10月18日に富士川辺にまで進出して陣所を定め、19日に甲斐源氏へ攻め懸るべく準備を行っていたところ、「官兵之方数百騎、忽以降落、向敵軍城了」という状態となり、「無力于拘留、所残之勢、僅不及一二千騎」と、五千余騎という大勢で出陣した追討使のうち、過半が逐電する体たらくであったという。対する「武田方四万余」とし、「忠清之謀略」を以て「依不可及敵対、竊以引退」したとする。維盛に退却の意思はなかったが、忠清が説得し、諸将もこれに同調したため、京都へ戻ったという(『玉葉』治承四年十一月五日条)。また、「宿傍池鳥数万俄飛去、其羽音成雷、官兵皆疑軍兵之寄来夜中引退、上下競走、自焼宿之屋形中持雑具等、忠度知度不知此事、追退帰、忠景向伊勢国、京師維盛朝臣入京、着近州野路之時有五六十騎云々」(『山槐記』治承四年十一月六日条)という報告もあった。
富士川から撤退した平家勢を追うため、頼朝は10月21日、彼らを追撃して上洛すべしと諸士に命じたが、「常胤、義澄、広常等」は「常陸国佐竹太郎義政并同冠者秀義等、乍相率数百軍兵未帰伏、就中、秀義父四郎隆義、当時従平家在京、其外驕者猶多境内、然者先平東夷之後、可至関西」と説得。頼朝はこれを容れて黄瀬川へ戻って宿陣したという(『吾妻鏡』治承四年十月廿一日条)。
その後、相模国府において論功行賞が行われ、10月27日には早くも佐竹氏討伐のために常陸国へ向けて出立したという(『吾妻鏡』治承四年十月廿六日条)。『吾妻鏡』によれば、頼朝は常陸国へ進出し、11月4日には常陸国府で上総介八郎広常・千葉介常胤・三浦介義澄・土肥次郎実平ら宿老を召集して軍議を行い、在京中で平家に伺候する惣領・佐竹四郎隆義の庶兄である「佐竹太郎義政(太郎忠義)」を招いて謀殺するため、彼の縁者の介八郎広常に指示して、国府向こうの園部川の大矢橋の中央に義政を誘い出し殺害させたという(『吾妻鏡』治承四年十一月四日条)。
しかし、義政(忠義)は本当に寄手の誘引に素直に応じて、麾下の将士を橋辺に残してのこのこと敵中に一人進み出る(『吾妻鏡』治承四年十一月四日条)不可解極まる行動をしたのであろうか。可能性があるとすれば和平の対話のためであろうか。一方、太郎義政(忠義)の甥で「其従兵軼於義政」の惣領嫡子・佐竹冠者秀義は、在京の父隆義の事も考えると容易に頼朝に加担することはできないとして、久慈川の氾濫原を望む久慈郡佐竹郷(常陸太田市磯部町)から久慈川を遡上し、北西の堅牢な金砂城(常陸太田市上宮河内町)へと引き退いている(『吾妻鏡』治承四年十一月四日条)。なお、頼朝が常陸国府を占拠することは後述のように後白河院に近い藤原経宗知行国ということもあって想定しづらく、さらに頼朝が布陣していたのは国府付近ではなく、筑波山の西側である小栗御厨(筑西市小栗)近辺と推測されることから、園部川の合戦は上総介八郎広常を派遣してのものであったのかもしれない。
その後、頼朝は金砂城へ籠っていた佐竹冠者秀義を攻めるべく「所謂下河辺庄司行平、同四郎政義、土肥次郎実平、和田太郎義盛、土屋三郎宗遠、佐々木太郎定綱、同三郎盛綱、熊谷次郎直実、平山武者所季重以下輩」を派遣したが、金砂城は堅固この上なく「自城飛来矢石、多以中御方壮士、自御方所射之矢者、太難覃于山岳之上、又厳石塞路、人馬共失行歩、因茲軍士徒費心府、迷兵法、雖然不能退去、憖以挟箭相窺之間、日既入西月又出東云々」と、味方の損害が出るばかりで攻めあぐねた(『吾妻鏡』治承四年十一月四日条)。
この状況に困り果てた実平や宗遠は頼朝へ使者を遣わし「佐竹所搆之塞、非人力之可敗、其内所籠之兵者、又莫不以一当千、能可被廻賢慮者」(『吾妻鏡』治承四年十一月五日条)と具体的な対応策を依頼している。これによって頼朝は「及被召老軍等之意見」したところ、広常が「秀義叔父有佐竹蔵人、ゝゝ者智謀勝人欲心越世也、可被行賞之旨有恩約者、定加秀義滅亡之計歟者」(『吾妻鏡』治承四年十一月五日条)と提案したことから、頼朝はこれを容れて広常を秀義叔父の佐竹蔵人のもとに遣わした。佐竹蔵人の陣所がいずこにあったのかは不明だが、すると佐竹蔵人は広常の来臨を喜び、歓待したという。広常はここで「近日東国之親疎、莫不奉帰往于武衛、而秀義主独為仇敵、太無所拠事也、雖骨肉客何令与彼不義哉、早参武衛討取秀義、可令領掌件遺跡者」(『吾妻鏡』治承四年十一月五日条)と説得すると、佐竹蔵人は頼朝への帰順を誓い、早速広常を伴って金砂城の後ろに回り込むと、鬨の声をあげて城内の佐竹秀義勢を威した。するとこの声に秀義と郎従等は不意を突かれて慌てふためき、広常は混乱に乗じて襲い掛かると秀義勢は算を乱して壊走。秀義は行方をくらました。
翌11月6日、広常は金砂城へ入るとこれを焼き払い、兵を分けて佐竹秀義の追跡を行ったが、すでに秀義は「奥州花園城」北茨城市華川町花園)まで逃れ去った風聞があったことから、広常らは頼朝のもとに帰還し「合戦次第及秀義逐電、城郭放火等事」(『吾妻鏡』治承四年十一月六日条)を報告した。とくに「軍兵之中、熊谷次郎直実、平山武者所季重、殊有勲功、於所々進先登更不顧身命、多獲凶徒首」と熊谷直実と平山季重の活躍を聞いた頼朝は、彼らは「其賞可抽傍輩之旨、直被仰下云々」(『吾妻鏡』治承四年十一月六日条)と指示した。また、この戦いの勝敗を決定づけた佐竹蔵人も参上しており「可候門下之由望申」したため、これを功績を以て許容した。さらに、志太三郎義広は当時、八条院領の常陸国信太庄(稲敷郡美浦村信太周辺)の荘官であり、おそらく弟の八条院蔵人・十郎行家とともに行動をしていたのだろう。行家は義広及び佐竹氏にも以仁王の令旨を齎していたであろうから、頼朝の佐竹氏討伐に対して反対の立場を訴えたのかもしれない。また、義広もその後、頼朝と合戦の上、行動を異にすることから、義広も行家同様に頼朝を詰問したのかもしれない。
合戦後の11月8日、「被収公秀義領所常陸国奥七郡并太田、糟田、酒出等所々、被宛行軍士之勲功賞云々」と、常陸国奥七郡のほか太田、糟田、酒出等を勲功賞として常陸攻めの人々へ宛がわれた(『吾妻鏡』治承四年十一月八日条)。その後、鎌倉への帰還の途につき、路次にある小栗十郎重成の「小栗御厨八田館(筑西市八田)」に入御している。鎌倉への帰途に八田館が存在しているという事は、頼朝は当時、筑波山を挟んだ南東の国府付近にいたとは考えにくく、常陸大掾系氏族の勢力圏を押さえつつ、筑波山を挟んで頼朝(西部)と広常(東部)の二面から北上していたのではなかろうか。
そして二日後の11月10日、頼朝は下総国葛西庄(葛飾区葛西)の清重邸に止宿している(『吾妻鏡』治承四年十一月十日条)。ここで清重へ武蔵国丸子庄が下された。このとき「清重、令妻女備御膳、但不申其実、為御結構自他所招青女之由言上云々」(『吾妻鏡』治承四年十一月十日条)と、清重は若妻を他所から招いた女性だと偽って頼朝の御膳の給仕に侍らせている。頼朝は葛西邸に2日間逗留し、11月12日に武蔵国へ入ったが、ここで頼朝は突然荻野五郎俊重を斬罪に処した(『吾妻鏡』治承四年十一月十二日条)。これまで頼朝に従属し、功績も挙げていたようだが、かつて石橋山合戦で大庭三郎景親に属して頼朝に弓引いた恨みがあったとみられ、「日者候御共雖似有其功、石橋合戦之時令同意景親、殊現無道之間、今不被糺先非者、依難懲後輩如此云々」(『吾妻鏡』治承四年十一月十二日条)という。
そして11月17日、頼朝は鎌倉へ帰着。和田小太郎義盛を侍所別当に補した(『吾妻鏡』治承四年十一月十七日条)。これは石橋山合戦後に安房国へ逃れた際、義盛がこの職を望み許諾していた約定を履行したものであった。頼朝の家人・郎従を管理する秘書官的な職務である。そして、12月12日、頼朝の鎌倉における新造の屋敷が落成し、それまで住んでいた上総介八郎広常の屋敷から移ることとなった。このとき胤正は父・常胤、弟・胤頼とともに頼朝に扈従した(『吾妻鏡』治承四年十二月十二日条)。
■新邸移渉の扈従家人郎従(『吾妻鏡』治承四年十二月十二日条)
| 先陣 | 和田小太郎義盛 | ||||
| 駕左 | 加々美次郎長清 | ||||
| 駕右 | 毛呂冠者季光 | ||||
| 扈従 | 北条四郎時政 | 江間小四郎義時 | 足利冠者義兼 | 山名冠者義範 | 千葉介常胤 |
| 千葉太郎胤正 | 千葉六郎大夫胤頼 | 藤九郎盛長 | 土肥次郎実平 | 岡崎四郎義実 | |
| 工藤庄司景光 | 宇佐見三郎助茂 | 土屋三郎宗遠 | 佐々木太郎定綱 | 佐々木三郎盛綱 | |
| 後陣 | 畠山次郎重忠 | ||||
治承5(1181)年4月7日、頼朝は御家人の中から、とくに弓術に優れ、なおかつ頼朝への忠節深い者を選び、毎晩寝所の近くに伺候すべきことが定められた。葛西三郎清重もその一人に選ばれている(『吾妻鏡』治承五年四月七日条)。清重は武術と忠節とをあわせもった人物として、頼朝の信任も厚い人物だったことがうかがえる。
| 江間四郎義時 | 下河辺庄司行平 | 結城七郎朝光 | 和田次郎義茂 | 梶原源太景季 | 宇佐美平次実政 |
| 榛谷四郎重朝 | 葛西三郎清重 | 三浦十郎義連 | 千葉太郎胤正 | 八田太郎知重 |
7月3日、鶴岡山八幡宮寺若宮の造営の沙汰があったが、当時の鎌倉にはいまだ宮寺を造営できる工匠がおらず、一品房昌寛を奉行として「武蔵国浅草大工字郷司」を召し進めるべき旨の御書を浅草の沙汰人へ遣わしている(『吾妻鏡』治承五年七月三日条)。そして7月8日、浅草から大工が鎌倉に参上して若宮の造営が始まり、8月15日の正殿遷宮までの造営を指示した(『吾妻鏡』治承五年八月十五日条)。7月20日には若宮宝殿の上棟が行われたが、この上棟式ののち頼朝が退出したときに、「爰未見今見之男一人、相交供奉人頻進行于御後、其長七尺余、頗非直也者」という不審な人物が紛れ込んでいた。頼朝はこれを見て「聊御思慮令立留給」と立ち止まり、捕縛を命じようとしたところ、やはり不審を感じていた下河辺庄司行平が彼を捕らえ、頼朝邸の庭に曳き出した。彼は直垂の下に腹巻を着ており、さらに髻の中には「安房国故長佐六郎々等左中太常澄」の書付が入っていた。彼は先年の安房国で討たれた長狭六郎常伴の郎従であり、「去年冬於安房国、主人蒙誅罰之間、従類悉以牢籠、寤寐難休其欝陶」というように常伴滅亡後には彼の従類は牢籠を余儀なくされ、左忠太常澄は彼らの総意として宿意を果たすべく頼朝を付け狙っていたという。頼朝を討っても討てなくとも常澄の前途は死であり、「曝死骸之時為令知姓字於人髻付簡」と、姓名を記した書付を髻に収め、常澄の死後に頼朝へ強い警告を発することを狙っていたことがわかる。頼朝は行平の行動を賞賛し、「募此賞所望一事直可令逹者」と伝えると、行平は「雖非指所望、毎年貢馬事、土民極愁申事也」という。そこで頼朝は「行勲功賞時可庶幾者、官禄之両途也、今申状雖為比興、早可依者」として、「下総国御厨別当所」に対して、下河辺行平の知行地に対する貢馬は免除すべき旨の御下文を発している。そして7月21日夜、頼朝の夢想で僧侶が枕辺に立ち、「左中太者武衛先世之仇敵也、而今造営之間露顕」(『吾妻鏡』養和元年七月廿一日条)といい、目が覚めた頼朝は「謂造営者奉崇重大菩薩、宮寺上棟之日有此事、尤可信者」と、若宮上棟日に左忠太常澄の計画露顕は八幡大菩薩の御加護であるとして、清重を使者として御厩に「奥駮」と号する馬を奉納した(『吾妻鏡』養和元年七月廿一日条)。
またこの上棟式とほぼ同時期の7月下旬ごろには、下野国足利庄の「足利俊綱有背頼朝」があり、8月12日には京都の右府兼実のもとに届けられている(『玉葉』養和元年八月十二日条)。当然鎌倉にもこの報は届けられていたとみられ、9月7日、「近年令属平家」し、嫡子の又太郎忠綱が頼朝に敵対する「三郎先生義広」に同意し、頼朝に参じない「従五位下藤原俊綱字足利太郎」を追捕すべく、和田次郎義茂に「俊綱追討御書」を下し、三浦十郎義連、葛西三郎清重、宇佐美平次実政を副えて下野国へ派遣している(『吾妻鏡』養和元年九月七日条)。ところが義茂らが下野国足利庄へ到着する以前に、俊綱専一の郎従「桐生六郎」が「為顕隠忠」して俊綱を殺害して深山に籠り、義茂が足利庄へ到着するとその陣所に出頭している。しかし六郎は「於彼首者称可持参不出渡之、何様可計沙汰哉」という。つまり桐生六郎は「俊綱」の首を持参せずに出頭したため、義茂は扱いに困り、鎌倉へ対処を求めたのである。義茂の使者は9月13日に鎌倉へ参着し、報告を受けた頼朝は「早可持參其首之旨」を命じ、使者は馳せ帰っている(『吾妻鏡』養和元年九月十三日条)。
その後、「桐生六郎」は「俊綱」の首を持参し、義茂や清重らはまず武蔵大路から侍所の梶原平三景時に使者を送って、どのように処置すべきかの案内を乞うている。景時からは「而不被入鎌倉中、直経深澤、可向腰越之旨」が指示され、腰越において実検が加えられた。頼朝は「見知俊綱面之者有之歟」を家人らに尋ねるが、人々は「不合眼之由」を述べる。このとき佐野七郎が「下河辺四郎政義、常遂対面云々、可被召之歟云々」と申上した。その後、政義が召され「俊綱」の首実検に派遣されるが、「刎首之後、経日数之故、其面殊改雖令変、大略無相違云々」と返答している(『吾妻鏡』養和元年九月十六日条)。9月18日、「桐生六郎」は梶原景時に「依此賞、可列御家人云々」と願い出るも、頼朝は「而誅譜代主人造意之企、尤不当也、雖一旦不足賞翫、早可誅」と「桐生六郎」を処刑し、「俊綱」の首の隣に並べて梟首した。ところが、寿永2(1183)年2月25日、又太郎忠綱が三郎先生義広とともに小山一党と戦った「野木宮合戦」で小山一党に敗れた後、上野国山上郷に隠遁した際に「招郎従桐生六郎許、数日蟄居、遂随桐生之諫、経山陰道、赴西海方」(『吾妻鏡』寿永二年二月廿五日条)とあり、桐生六郎はいまだ生存していて俊綱子・又太郎忠綱の専一郎従として重用されているとみられることから、俊綱の殺害及び謀叛したという桐生六郎はいずれも身代わりのフェイクであった可能性があろう。
寿永元(1182)年8月11日、政子の安産祈願のために関東の諸社に使いが差し向けられたが、その使者はその神社のある国の主だった豪族の子息が選ばれていた。このうち、武蔵国六所宮(大国魂神社:東京都府中市宮町)には「葛西三郎」が使者として使わされた(『吾妻鏡』寿永元年八月十一日条)。清重の所領は「下総国葛西庄」であって、下総の豪族の位置づけのはずであるが、父親の豊島清元が武蔵国の豪族であるため、その三男である清重が使者として選ばれたと思われる。
●寿永元(1182)年8月11日に一宮に発った使者
| 派遣された神社 | 現在の神社名 | 所在地 | 派遣された人物 |
| 伊豆山 | 伊豆山神社 | 熱海市伊豆山上野地1 | 土肥弥太郎遠平(土肥実平の嫡男) |
| 筥根山 | 箱根神社 | 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根 | 佐野太郎忠家 |
| 相模一宮 | 寒川神社 | 神奈川県高座郡寒川町宮山3916 | 梶原平次景高(梶原景時の次男) |
| 三浦十二天 | 十二所神社 | 神奈川県横須賀市芦名1-21-10 | 佐原十郎義連 |
| 武蔵六所宮 | 大国魂神社 | 東京都府中市宮町3-1 | 葛西三郎清重 |
| 常陸鹿嶋 | 鹿島神宮 | 茨城県鹿嶋市宮中2306-1 | 小栗十郎重成(常陸大掾一族) |
| 上総一宮 | 玉前神社 | 千葉県長生郡一宮町一宮3048 | 上総小権介良常(上総権介広常の嫡男) |
| 下総香取社 | 香取神宮 | 千葉県佐原市香取1697 | 千葉小太郎成胤(千葉太郎胤正の嫡男) |
| 安房東條社 | 天津神明神社 | 千葉県安房郡天津小湊町天津2954 | 三浦平六義村(三浦介義澄の嫡男) |
| 安房洲﨑社 | 洲崎神社 | 千葉県館山市洲崎1697 | 安西三郎景益 |
平家との戦いでは父・豊嶋清元とともに頼朝軍の一翼として活躍。元暦元(1184)年8月8日、頼朝代官・三河守源範頼に随い西国へ赴いた。頼朝はこれを長谷の稲瀬川に桟敷を敷いて見送った。
●元暦元(1184)年8月8日「西国下向御家人交名」(『吾妻鏡』元暦元年八月八日条)
| 三河守範頼 | 江間小四郎義時 | 足利蔵人義兼 | 武田兵衛尉有義 | 千葉介常胤 | 境平次常秀 | 三浦介義澄 |
| 三浦平六義村 | 八田四郎武者朝家 | 八田太郎朝重 | 葛西三郎清重 | 長沼五郎宗政 | 結城七郎朝光 | 比企藤内所朝宗 |
| 比企藤四郎能員 | 阿曽沼四郎広綱 | 和田太郎義盛 | 和田三郎宗実 | 和田四郎義胤 | 大多和次郎義成 | 安西三郎景益 |
| 安西太郎明景 | 大河戸太郎広行 | 大河戸三郎 | 中条藤次家長 | 工藤一臈祐経 | 宇佐美三郎祐茂 | 天野藤内遠景 |
| 小野寺太郎道綱 | 一品房昌寛 | 土佐房昌俊 |
9月2日、京都を出陣した範頼の軍勢は西に向かい、翌元暦2(1185)年1月26日、範頼は「壇ノ浦の戦い」でも参戦している。豊後国の臼杵次郎惟隆・緒方三郎惟栄兄弟が進呈した八十二艘の兵船に乗って、豊後に渡った。このとき、周防国宇佐郡の木上七郎遠隆から兵糧米が献じられた。
●元暦2(1185)年1月26日「豊後国渡海御家人交名」(『吾妻鏡』元暦ニ年一月二十六日条)
| 三河守源範頼 | 北条小四郎義時 | 足利蔵人義兼 | 小山兵衛尉朝政 | 長沼五郎宗政 | 結城七郎朝光 | 武田兵衛尉有義 |
| 斎院次官中原親能 | 千葉介常胤 | 境平次常秀 | 下河辺庄司行平 | 下河辺四郎政義 | 阿曽沼四郎広綱 | 三浦介義澄 |
| 三浦平六義村 | 八田四郎武者朝家 | 八田太郎朝重 | 葛西三郎清重 | 渋谷庄司重国 | 渋谷二郎高重 | 比企藤内所朝宗 |
| 比企藤四郎能員 | 和田太郎義盛 | 和田三郎宗実 | 和田四郎義胤 | 大多和次郎義成 | 安西三郎景益 | 安西太郎明景 |
| 大河戸太郎広行 | 大河戸三郎 | 中条藤次家長 | 加藤次景廉 | 工藤一臈祐経 | 宇佐美三郎祐茂 | 天野藤内遠景 |
| 一品房昌寛 | 土佐房昌俊 | 小野寺太郎道綱 |
そして3月24日、長門国壇ノ浦において彦島から進出した平知盛勢と、御座船を追って西航する源九郎判官義経・三浦介義澄らが長門国府沖合の壇ノ浦で衝突した。これを俗に壇ノ浦の戦いという。清重自身は範頼勢に加わっていたことから、この合戦に直接参加することはなかったとみられる。
合戦は当初は平家勢優勢に進んでいたというが、次第に義経勢が平家勢を押してゆき、「及午剋、平氏終敗傾」という結末を迎えた。このとき、故清盛入道正室の「二品禅尼(平時子)」は神器のひとつ「宝剣」を持ち、「按察使局」は先帝安徳天皇を抱き、壇ノ浦に入水した(『吾妻鏡』元暦二年三月廿四日条)。安徳天皇生母・建礼門院平徳子も入水したが、義経麾下の渡邊源五允によって救出され、安徳天皇を抱いて入水した按察局も引き上げられている。しかし、八歳の先帝安徳天皇(兼実は一時的に「西海王」と呼んでいる)と宝剣はついに浮かび上がってくることはなかった。七歳の「若宮今上兄」も平家とともに行動していたが、救出されている。のちの守貞親王(後堀河天皇実父)である。平家方の宗たる人々では、「前中納言教盛、号門脇」「前参議経盛」「新三位中将資盛、前少将有盛朝臣等」が入水死、「前内府宗盛、右衛門督清宗等」は入水するも義経腹心の伊勢三郎能盛によって生け捕られた(『吾妻鏡』元暦二年三月廿四日条)。御座船に乱入して賢所を開けんとする東国武士に対しては、これを守衛していた「平大納言時忠」が制止している(『吾妻鏡』元暦二年三月廿四日条)。兵士らは「于時両眼忽暗、而神心惘然」となって逃げたというが、事実であれば時忠卿に目の前のものが神器であると告げられ、突然の事態に兵士らが慄き慌てたということかもしれない。
●長門国平家与源氏合戦(『醍醐雑事記』)
| 生取 | 内大臣宗盛 | 三十九歳 | 故清盛入道の三男。 |
| 右衛門督清宗 | 十五歳 | 前内府宗盛の長男。 | |
| 大納言時忠 | 五十六歳 | 兵部権大輔時信の長男。故清盛入道の義弟。 | |
| 讃岐中将時実 | 三十五歳 | 大納言時忠卿の長男。 | |
| 内蔵頭(平信基) | 院近臣。兵部卿信範の長男。 | ||
| 二位僧都全真 | 院近臣藤原親隆の子で、時忠卿の母方の甥。 伯母にあたる八条殿時子の猶子。 |
||
| 法勝寺執行能円 | 院近臣藤原顕憲の子で、時忠卿の異父弟。前妻・藤原範子との間の実娘(後鳥羽天皇宮廷女官)は、後鳥羽天皇の皇子(為仁王。土御門天皇)を出産したのち、範子が嫁いだ源通親卿の養女(源在子)となり、女院承明門院となる。為仁王は実祖父が僧侶の能円であることから、本来であれば皇位継承はなく、九条兼実や源頼朝らの反対があるものの、後鳥羽天皇の意思(源通親らの意見か)として頼朝は渋々承認。親王宣下はないままに後鳥羽天皇の譲位によって為仁王は践祚(土御門天皇)した。 | ||
| 阿波民部大夫成良 | 阿波国の在庁で、平家の郎従として美濃や宇治の戦いで活躍する。壇浦合戦でも平家方として源氏方に寝返った伝もあるが、『醍醐雑事記』『吾妻鏡』いずれにも生捕の人数にあり、 彼の寝返りの伝は疑わしい。 | ||
| 藤内左衛門信康 | 平家家人。 | ||
| 女院 | 三十一歳 | 平清盛の娘で女院建礼門院。御諱は徳子。 | |
| 若宮 | 七歳 | 故高倉院二宮。平知盛室治部卿局を乳母とする。のち守貞親王となり、皇子は後堀河天皇となる。 | |
| 降人 | 源大夫判官季貞 | 平家家人。検非違使。 | |
| 摂津判官盛澄 | 平家家人。検非違使。 | ||
| 自害 | 中納言教盛 | 五十八歳 | 故忠盛卿の三男。門脇殿。母方は摂関家庶流という貴種。 こうした血統ゆえか、嫡子通盛は平家庶流中で唯一の公卿となる。 |
| 中納言知盛 | 三十四歳 | 故清盛入道四男。 | |
| 能登守教経 | 二十六歳 | 門脇中納言教盛の子。一ノ谷の合戦で討死したともされるが、 壇之浦合戦での活躍もみられ、真相不明。 |
|
| 殺人 | 左馬頭行盛 | 故清盛入道次男・基盛の子。播磨守という受領の上臈を経て、左馬頭へと昇る。ただし、行盛は従五位上、そしてのちに伊予守となった義経は従五位下であったように、この時点で伊予国や播磨国といった「四位上臈」任国の格は失われていたことがわかる。 | |
| 小松少将有盛 | 故小松内府重盛の子。 | ||
| 備中吉備津宮神主 | |||
| 権藤内貞綱 | |||
| 権藤内貞綱舎弟 | |||
| 菊池二郎 | |||
| 刎頸者八百五十人 | |||
| 不知行方人 | 先帝 | 安徳天皇。 | |
| 八条院(八条殿の誤記) | 平清盛の正室・平時子。二位尼 | ||
| 修理大夫経盛 | 六十二歳 | 故忠盛卿の次男。母は源信雅女。母方は名門村上源氏であるが、庶家の受領層であったため、摂関家庶家を外戚とする教盛や、当腹嫡子の頼盛といった異母弟より一段下に置かれていた。そのためか異母兄清盛や平家一門との関係よりも、姻戚関係にあった藤原師長や院司として仕えた太皇太后宮、その実家である閑院家の藤原実定らとの結びつきが強かった。壇之浦合戦ではいったん上陸して出家したのちに戻り、入水した。 | |
| 内侍所御坐 | |||
| 進正御坐 | |||
| 宝剣不見 | |||
| 女院 | 建礼門院。「生取」に見られる。 | ||
| 二宮 | 安徳天皇異母弟でのちの守貞親王。 |
頼朝は範頼に戦後処理を早めに済ませて8月中に入洛するよう厳命していたが、おそらく台風による風雨にあって9月26日の入洛となっている。おそらく清重も同道したのだろう。その後、範頼とともに鎌倉へ戻った。
文治元(1185)年10月24日、鎌倉の長勝寿院(南御堂)の供養が行われた。巳の刻(午前九時)になって頼朝は大倉御所から徒歩で長勝寿院へと向かい、数多くの御家人が随兵としてこれに付き従った。
●長勝寿院供養に供奉した御家人(『吾妻鏡』文治元年十月二十四日条)
| 随兵十四人 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小山五郎宗政(御剣)、佐々木四郎左衛門尉高綱(御鎧)、愛甲三郎季隆(御調度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五位六位 三十二人 (布衣下括) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 随兵十六人 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 随兵の長官 | 和田小太郎義盛・梶原平三景時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 随兵六十人〔東〕 (弓馬の達者) ⇒門外左右に伺候 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 随兵六十人〔西〕 (弓馬の達者) ⇒門外左右に伺候 |
|
平家追討戦が終わるや、追討使の一角で洛中守護の伊予守義経と、義父である頼朝の関係が急激に悪化することとなる。その大きな原因は、頼朝に敵意を示す叔父の前備前守行家追討の拒絶である。
頼朝は文治元(1185)年9月12日に入洛した梶原景季、義勝房成尋を通じて「尋窺備前々司行家之在所、可誅戮其身之由相触」(『吾妻鏡』文治元年九月十二日条)を義経に伝えたが、義経は「縦雖為如強竊之犯人、直欲糺行之、况於行家事哉、彼非他家、同為六孫王之余苗掌弓馬、難准直也人、遣家人等之許、輙難降伏之、然者早加療治、平愈之後可廻計」(『玉葉』文治元年十月十四日条)と返答。これが10月6日に頼朝に復命されている(『吾妻鏡』文治元年十月六日条)。頼朝はこの返答を聞き、捨て置けぬ事として「可誅伊予守義経之事、日来被凝群議」した。そして10月9日、義経を討つことを自ら申し出た土佐房昌俊を京都に発する(『吾妻鏡』文治元年十月九日条)。昌俊は「三上弥六家季昌俊弟、錦織三郎、門真太郎、藍澤二郎」ら八十三騎で出立。京都まで九日の行程で進むことが指示されている(『吾妻鏡』文治元年十月九日条)。昌俊は出立に先立ち、老母の事を頼朝に託していることから、すでに死を覚悟した決意であったことがうかがえる。なぜなら、10月12日時点で義経が「遣郎等、可誅義経之由、慥得其告」(『玉葉』文治元年十月十三日条)とある通り、その出立はすでに義経に通告されていたものであったためである。つまり、この義経追捕は奇襲などではなく、逆に義経への「行家之在所、可誅戮其身」を決意させるための最後通告であったと考えられるのである。頼朝はぎりぎりまで義経を討つことを回避しようとしていた様子がうかがえる。ところが、義経はこれを明確な敵意と取ったとみられる。11日までは行家の説得に努めていた義経が、翌12日には行家と同心した上「雖欲遁不可叶、仍向墨俣辺射一箭、一決死生之由所存也」と敵対を鮮明にした核心的理由は、11日または12日に受け取った軍勢派遣の確報だったのである。
しかし、12日における義経と行家の同心及び頼朝への敵対は、あくまで私的な対立であり、義経は「行家謀叛雖加制止、敢不承引、仍義経同意了、其故者、奉身命於君、成大功及再三、皆是頼朝代官也、殊可賞玩之由令存之處、適所浴恩之伊予国、皆補地頭不能国務、又没官所々廿余ヶ所、先日頼朝分賜、而今度勲功之後、皆悉取返、宛給郎従等了、於今者、生涯全以不可執思、何況遣郎等、可誅義経之由、慥得其告、雖欲遁不可叶、仍向墨俣辺射一箭、一決死生之由所存也」(『玉葉』文治元年十月十七日条)と法皇に「竊奏」したに過ぎず、私戦として義経と行家が墨俣へ下向して鎌倉勢と決戦することを奏上していただけだったのである。この義経の「竊奏」を法皇は「頗有許容」とした(『玉葉』文治元年十月十三日条)。「頼朝乖法皇叡慮之事太多」(『玉葉』文治元年十月十三日条)ということも「頗有許容」の理由のひとつであろう。
そして、義経の「竊奏」後、しばらくは「其後無音」という状況だったが、17日早朝、院使として大蔵卿泰経が九条邸を訪れた。兼実は触穢のため家司季長が門前で院宣を受けたが、それによれば義経は「去夜重申云、猶同意行家了、子細先途言上、於今者、可追討頼朝之由、欲賜宣旨、若無勅許者、給身暇可向鎮西云々、見其気色、主上法皇已下、臣下上官、皆悉相率可下向之趣也」とあるように、義経は16日夜に激怒して院奏し、「子細先途言上(前述の三か条)」によって頼朝追討の宣旨を下されるよう奏上。これが認められなければ「給身暇可向鎮西云々」と告げている。
法皇は頼朝追討の宣旨につき、左大臣経宗と内大臣実定に参院を命じて諮問を行っている(『玉葉』文治元年十月十九日条)。はじめに参院した実定は、法皇の諮問に対して一存で決め難く左大臣の意見を求めた。その後参院した左大臣経宗は、「凡不可及意議、早々可下宣旨也」と主張した。その理由としては「当時在京武士、只義経一人也、被乖彼申状、若大事出来之時、誰人可敵対哉、然者、任申請可有沙汰也、更不可及議定云々」というものであった。態度を明確にしない内府実定も結局同意することとなり、同席していた経房卿は「聞此事頗傾奇」と批判している。
結局、左府と内府の同意が得られたことで、10月18日、義経の要望通り「被下頼朝追討宣旨」(『玉葉』文治元年十月十八日条)が、翌19日早朝に上卿を左大臣経宗とし、右大弁光雅が認めてが発布されることとなった(『玉葉』文治元年十月十九日条)。
義経が私的な敵対行為から、頼朝を朝敵として討つ公戦を目論むほど態度を硬化させた背景は、土佐房昌俊以下八十騎余りの入洛であろう。八十三騎もの軍勢が入洛すれば付随する郎従も含めれば数百人の軍勢となる。当然、義経はこの入洛を察知したであろう。『吾妻鏡』では17日に「土左房昌俊、先日依含関東厳命、相具水尾谷十郎已下六十余騎軍士、襲伊予大夫判官義経六條室町亭」とある(『吾妻鏡』文治元年十月十七日条)。『吾妻鏡』によれば当時不可解なことに「于時予州方壮士等、逍遥西河辺」といい、六条室町亭には家人が少なかったという。
ところが、襲撃を受けた義経は、佐藤四郎兵衛尉忠信らを率いて自ら昌俊勢に当たり、形勢危うきところを、駆けつけた行家勢とともに前後から昌俊勢を押しつぶしたという。義経は事前に行家と図って昌俊の誘殺を目論んだのかもしれない。結果として頼朝による義経殺害は失敗に終わり、昌俊は逃亡して義経の家人がこれを追撃。昌俊らは鞍馬山の奥の方へと逃れたが「土佐房昌俊并伴党三人、自鞍馬山奥、予州家人等求獲之」えられ、26日「於六條河原梟首」された(『吾妻鏡』文治元年十月廿六日条)。義経は襲撃を受けたのち参院している(『吾妻鏡』文治元年十月十七日条)。この夜戦により、義経は頼朝と完全に決別するに至った。
ところが、追討の宣旨は下されたものの、義経・行家が奏上していた法皇の鎮西行幸はことごとく拒否され、義経等はこれを撤回することとなる(『玉葉』文治元年十月廿一日条)。さらに「始推雖申下可追討頼朝之宣旨、事不起自叡慮之由、普以風聞」というように、この追討宣旨が法皇の意思から出たものではないと伝わったことから、在京武士等は行家・義経に加担することなく「近江武士等、不与義経等、引退奥方」(『玉葉』文治元年十月廿二日、廿三日条)という状況であった。「還以義経等處謀反之者、加之、引率法皇已下可然之臣下等、可向鎮西之由、披露之間、弥乖人望、其勢逐日減少、敢無与力之者」(『玉葉』文治元年十一月三日条)とある。義経はあくまでも頼朝代官であり、在京御家人らがその行いを頼朝に対する反逆と認識したであろうことは容易に想像できる。御家人らは義経との深い紐帯はなかったであろうから、義経や行家に敢えて加担する武士などなかったのである。
このころ鎌倉では9月3日、「故左典厩御遺骨副正清首奉葬南御堂之地」している。六条源氏の菩提所として建立されていた勝長寿院の落慶供養前の埋葬である。勝長寿院は幕府南側の川を挟んだ谷津に、北向きに造営された南北に長い広大な寺院で、後述の通りおそらく興福寺系の法相宗寺院であったと考えられる。落慶法要には源氏とゆかりの深い園城寺の本覚院僧正公顕を導師に招いていた。11月14日、前中納言源雅頼が九条邸を訪問し、頼朝の使者「相模国住人其名有久」から伝えられたことを兼実に伝えているが(『玉葉』文治元年十一月十四日条)、それによれば「京事、十月廿三日聞候、範頼并公顕僧正、廿二日下著、然而範頼成憚直不申、粗披露傍輩云々、廿四日堂供養、…、自廿四日有上洛沙汰、有久廿七日出国、次官親能、今四ケ日之後可出国云々、頼朝一定可京上之由風聞、已超足柄関之由、於路頭所承也、非如先々決定可上洛之由、下知郎従等云々」という。
10月22日、範頼と公顕僧正は鎌倉へ下着。24日には「堂供養、卯時事始、申剋終、願主浄衣云々、布施物之長櫃百八十合、導師馬卅疋十疋置鞍、讃衆廿口、各三疋一疋置鞍」滞りなく勝長寿院供養が挙行された。この供養に際して、常胤は頼朝の「御後五位六位」の一人として、五位の六男・六郎太夫胤頼とともに従っている。
●文治元年勝長寿院供養に供奉した千葉一族(『吾妻鏡』文治元年十月廿四日条)
| 随兵(先陣) | 畠山次郎重忠 | 千葉太郎胤正 | 三浦介義澄 | 佐貫四郎大夫広綱 | 榛谷四郎重朝 |
| 葛西三郎清重 | 八田太郎朝重 | 加藤次景廉 | 藤九郎盛長 | 大井兵三次郎実春 | |
| 山名小太郎重国 | 武田五郎信光 | 北條小四郎義時 | 小山兵衛尉朝政 | ||
| 持御剣 | 小山五郎宗政 | ||||
| 着御鎧 | 佐々木四郎左衛門尉高綱 | ||||
| 懸御調度 | 愛甲三郎季隆 | ||||
| 御後 五位六位 〔布衣下括〕 |
源蔵人大夫頼兼 | 武蔵守義信 | 参河守範頼 | 遠江守義定 | 駿河守広綱 |
| 伊豆守義範 | 相摸守惟義 | 越後守義資 〔御沓〕 |
上総介義兼 | 前対馬守親光 | |
| 上野介範信 | 前宮内大輔重頼 | 皇后宮亮仲頼 | 大和守重弘 | 因幡守広元 | |
| 村上右馬助経業 | 橘右馬助以広 | 関瀬修理亮義盛 | 平式部大夫繁政 | 安房判官代高重 | |
| 藤判官代邦通 | 新田蔵人義兼 | 奈胡蔵人義行 | 所雑色基繁 | 千葉介常胤 | |
| 千葉六郎大夫胤頼 | 宇津宮左衛門尉朝綱 〔御沓手長〕 |
八田右衛門尉知家 | 梶原刑部丞朝景 | 牧武者所宗親 | |
| 後藤兵衛尉基清 | 足立右馬允遠元 | ||||
| 随兵 | 下河辺庄司行平 | 稲毛三郎重成 | 小山七郎朝光 | 三浦十郎義連 | 長江太郎義景 |
| 天野藤内遠景 | 澁谷庄司重国 | 糟谷藤太有季 | 佐々木太郎左衛門尉定綱 | 小栗十郎重成 | |
| 波多野小次郎忠綱 | 広澤三郎実高 | 千葉平次常秀 | 梶原源太左衛門尉景季 | 村上左衛門尉頼時 | |
| 加々美二郎長清 | |||||
| 随兵六十人:被清撰弓馬逹者皆供奉最末、御堂上後各候門外東西 | |||||
| 東方 | 足利七郎太郎 | 佐貫六郎 | 大河戸太郎 | 皆河四郎 | 千葉四郎 |
| 三浦平六 | 和田三郎 | 和田五郎 | 長江太郎 | 多々良四郎 | |
| 沼田太郎 | 曾我小太郎 | 宇治蔵人三郎 | 江戸七郎 | 中山五郎 | |
| 山田太郎 | 天野平内 | 工藤小次郎 | 新田四郎 | 佐野又太郎 | |
| 宇佐美平三 | 吉河二郎 | 岡部小次郎 | 岡村太郎 | 大見平三 | |
| 臼井六郎 | 中禅寺平太 | 常陸平四郎 | 所六郎 | 飯冨源太 | |
| 西方 | 豊島権守 | 丸太郎 | 堀藤太 | 武藤小次郎 | 比企藤次 |
| 天羽次郎 | 都筑平太 | 熊谷小次郎 | 那古谷橘次 | 多胡宗太 | |
| 莱七郎 | 中村右馬允 | 金子十郎 | 春日三郎 | 小室太郎 | |
| 河匂七郎 | 阿保五郎 | 四方田三郎 | 苔田太郎 | 横山野三 | |
| 西太郎 | 小河小二郎 | 戸崎右馬允 | 河原三郎 | 仙波二郎 | |
| 中村五郎 | 原二郎 | 猪股平六 | 甘糟野次 | 勅使河原三郎 | |
頼朝は勝長寿院から御所に帰還すると、家人郎従に関する着到から人事・事務まで行う管理官・和田義盛と梶原景時の両名を召して、明日の上洛進発について軍士の着到を指示する。これは伊予守義経と備前前司行家を追討するための軍勢催促であり、これに応じた群参の御家人は「常胤已下」主だったものは二千九十六人であった。このうち上洛に付き従うものは、小山朝政、結城朝光ら五十八人とされた。
翌25日早朝には、「差領状勇士等、被発遣京都」とおそらく先遣の御家人(先陣の土肥次郎実平か)が鎌倉を出立しており、彼等には「入洛最前可誅行家義経、敢莫斟酌、若又両人不住洛中者、暫可奉待御上洛者」と指示を行っている(『吾妻鏡』文治元年十月廿九日条)。明確に行家と義経を誅殺すべきことを命じている。そして29日、「予州・備州等」の叛逆を追討すべく、軍勢を京都へ向けて進発する。その先陣は土肥次郎実平、後陣は千葉介常胤が務め、おそらく東海道を進む陣容であったとみられる。そのほか、東山道、北陸道の二道からも進発しており、三道からの大規模な上洛軍であった。具体的な陣容は記されていないが、「於東国健士者直可被具之」とあることから、頼朝の信頼篤い清重もこの陣中にあったと思われる。
11月3日朝方、「前備前守源行家、伊予守兼左衛門尉大夫尉也従五位下同義経為殿上侍臣」は、各々法皇に出京のことを告げて、二百騎あまりを率い鎮西へ向けて京を出立した(『吾妻鏡』『玉葉』文治元年十一月三日条)。そして頼朝も、義経・行家が京都から離れた報告を受け、11月8日に上洛を取りやめて黄瀬川宿から鎌倉へ戻っている(『吾妻鏡』文治元年十一月八日条)。
11月5日夜、義経、行家等の軍勢は摂津国の河尻から出帆することとなるが、この日は「自夜半大風吹来」という荒天で、本来であれば出帆するような状況にはない。もちろん強風に乗って早々に西へ向かうことを想定していたのかもしれないが、おそらくは近辺に追い迫る在京武士の攻撃を恐れた結果であろう。彼らとは「未合戦之間」とある通り、合戦には及んでいないが、夜半の荒天時に出帆する理由としては自然であろう。結果としてこの出帆は失敗し、「九郎等所乗之船、併損亡、一艘而無全、船過半入海、其中、義経行家等、乗小船一艘、指和泉浦逃去了」という(『玉葉』文治元年十一月八日条)。「相従予州之輩纔四人、所謂伊豆右衛門尉、堀弥太郎、武蔵房弁慶并妾女字静一人也」であったといい、「天王寺辺」に宿したという(『吾妻鏡』文治元年十一月六日条)。また、11月6日には「近江美濃源氏武士為討義経下向西国畢」(『百練抄』文治元年十一月六日条)と、近江源氏、美濃源氏が義経追討に加わったという。
こうした劣勢に立たされた義経らはすでに敗将と認識されており、11月7日に「義経被解却見任、伊与守検非違使云々」という措置が取られることとなる(『吾妻鏡』文治元年十一月七日条)。そして11月12日夜、兼実のもとに蔵人頭藤原光長が参じて「被下諸国、御教書」の「義経行家等可奉召之由、被下院宣」のことを伝えている(『玉葉』文治元年十一月十二日条)。この院宣を奉じたのが大宰権帥経房であることから、実弟の光長に伝えられたものであろう。
兼実はこの院宣の内容について諮問されておらず、法皇は当初から頼朝追討宣旨に反対していた兼実の反発を予想して独断で行ったのだろう。内容を聞いた兼実は「件両将昨日ハ蒙可討頼朝之宣旨、今日ハ又預此宣旨、世間之転変、朝務之軽忽、以之可察、可指弾々々々」(『玉葉』文治元年十一月十二日条)と呆れ果てた様子を記録している。
その後、頼朝は逃避行を続ける義経の行方を追うとともに、兼実の摂政擁立工作、諸国に対する安全保障上の諸権の設定などを要求。文治4(1188)年正月頃にようやく義経が奥州平泉に隠遁していることが発覚したのであった。義経の居場所が発覚すると、頼朝は朝廷に「申状」を送り、「義顕可召進之由、可被仰秀衡法師子息」ことを要求した。法皇はこれを容れ、2月18日、追討宣旨の内容について院御所に於いて決定の上、2月19日に兼実が宣旨案を披見。21日、細かい部分が直された宣旨を確認後、左大臣経宗を上卿として「義経追討之宣旨」(『玉葉』文治四年二月廿一日条)が下された。26日には追討官符が下され、院庁御下文も発せられている(『玉葉』文治四年二月廿六日条)。
2月29日、右兵衛督能保からの書状が届いているが、能保は「予州事、為被仰奥州泰衡、被遣勅使官史生国光、院庁官景弘等、来三月可下向」との情報を伝えている(『吾妻鏡』文治四年二月廿九日条)。
3月15日には梶原景時の宿願であった大般若経供養が鶴岡山八幡宮寺で執り行われ、頼朝も列席した。このときの先陣随兵八人の一人に「葛西三郎清重」の名が見られる(『吾妻鏡』文治四年三月十五日条)。
| 先陣随兵 | 小山兵衛尉朝政 | 葛西三郎清重 | 河内五郎義長 | 里見冠者義成 |
| 千葉次郎師胤 (千葉次郎師常) |
秩父三郎重清 (長野三郎重清) |
下河辺庄司行平 | 工藤左衛門尉祐経 | |
| 御後:各布衣 | 参河守 | 信濃守 | 越後守 | 上総介 |
| 駿河守 | 伊豆守 | 豊後守 | 関瀬修理亮 | |
| 村上判官代 | 安房判官代 | 藤判官代 | 新田蔵人 | |
| 大舎人助 | 千葉介 | 三浦介 | 畠山次郎 | |
| 足立右馬允 | 八田右衛門尉 | 藤九郎 | 比企四郎 | |
| 梶原刑部丞 | 梶原兵衛尉 | |||
| 後陣随兵 | 佐貫大夫広綱 | 千葉大夫胤頼 | 新田四郎忠常 | 大井次郎実春 |
| 小山田三郎重成 | 梶原源太左衛門尉景季 | 三浦十郎義連 | 三浦平六義村 | |
| 路次随兵 各相具郎等三人 |
千葉五郎 | 加藤太 | 加藤藤次 | 小栗十郎 |
| 八田太郎 | 渋谷次郎 | 梶原平次 | 橘次 | |
| 曽我小太郎 | 安房平太 | 二宮太郎 | 高田源次 | |
| 深栖四郎 | 小野寺太郎 | 武藤次 | 熊谷小次郎 | |
| 中條右馬允 | 野五郎 | 佐野太郎 | 吉河次郎 | |
| 狩野五郎 | 工藤小次郎 | 小野平七 | 河匂三郎 | |
| 広田次郎 | 成勝寺太郎 | 山口太郎 | 夜須七郎 | |
| 高木大夫 | 大矢中七 |
3月29日、奥州平泉の「前民部少輔基成并秀衡法師子息泰衡等」へ「可搦進予州之由」を命じる宣旨(二月廿一日付)と院庁下文(二月廿六日付)を帯びた勅使官史生国光と院庁官景弘が京を出立した。途中、4月9日に鎌倉に寄って頼朝に謁し、頼朝はその帯びた宣旨および院庁下文を内々に披見している。また、勅使の扱いについて頼朝への指示があり、頼朝は接待役として稲毛三郎重成、畠山次郎重忠、江戸太郎重長の三名を指定して「仍守其旨、無懈緩之儀、可致沙汰」と命じている(『吾妻鏡』文治四年三月廿九日条)。その後、鎌倉を発った勅使・院使は、武蔵国、下野国を通って奥州へと下っており、武蔵国と下野国での勅使接待を行った御家人が「雑事等致丁寧畢」を幕府に報告している(『吾妻鏡』文治四年五月四日条)。
9月14日、昼前に参内した兼実は、御所で蔵人平棟範と対面し、「頼朝卿請文」「先日遣奥州官使持参泰衡請文」「両府申状之返状」が渡されているが、兼実は「左右只可在勅定云々」という(『玉葉』文治四年九月十四日条)。「頼朝卿請文」は頼朝が申請した「諸国可禁断殺生之由 宣旨状」(『吾妻鏡』文治四年八月卅日条)に対する請文と思われる。また、「先日遣奥州官使持参泰衡請文」は義経捕縛の宣旨に対する請文であろう。ところがここには何らかの「子細」が記されており、泰衡は義経の捕縛を拒否していたとみられる。そればかりではなく基成や泰衡は義経を国内に限るが、自由な行動を許していたのである。これに対して10月12日、朝廷は泰衡に義経を「召進」ことを強く命じる宣旨を下すこととなる(『吾妻鏡』文治四年十月廿五日条)。
10月17日、頼朝は「年来与予州、成断金契約、仍今度牢籠之間、数日令隠容之、又至赴奥州之時者、相率伴党等送長途」した比叡山悪僧の「俊章」が帰洛ののちに謀叛を企てているという風聞があり、その在京御家人に対して動向を窺って捕縛するよう指示している(『吾妻鏡』文治四年十月十七日条)。俊章は鞍馬から比叡山へ逃れ、さらに奥州へと向かった際に協力した三人の悪僧の一人である。
そして11月、先日下された義経を捕縛する宣旨に副えて院庁下文が「陸奥出羽両国司等」に下されたのだった(『吾妻鏡』文治四年十二月十一日条)。
右、件義経、可令彼基成泰衡等召進之由、去春被下 宣旨并院宣之處、泰衡等不敍用 勅命、無驚 詔使、猥廻違越之奸謀、只致披陳於詐偽、就中、義経等猶結群凶之余燼、慥住陸奥之辺境云々、露顕之趣風聞已成、基成泰衡等、身為王民、地居帝土、何強背鳳詔、盍可与蜂賊哉、結搆若為実者、縡既絶篇籍歟、同意之科責而有余、慥任両度 宣旨、宜令召進彼義経身、若猶容隠不遵苻旨者、早遣官軍可征伐之状、所仰如件、両国司等宜承知勿違失、故下云々
文治四年十一月日
泰衡は基成とともに秀衡入道卒去から一年にわたりその身を庇護し、隠遁していたのである。それは事態が発覚したのちも、宣旨や院庁下文をまったく無視した態度を取り続けたことがわかる。
文治5(1189)年閏4月8日、法皇は奥州追討の件につき、五位蔵人家実(のちの帥中納言資実。基通嫡子諱を避けて名を資実と替える。日野氏祖)を天王寺から兼実のもとに遣わし「追討事自本可然之由思食之上、如此令申尤神妙歟、思食早可成賜宣旨、来六月塔供養之由聞食、若過彼間可遣歟、将今明可遣歟、可随令申、且又官使出立之間、自経日数歟、仍且為用意所仰遣也」(『玉葉』文治五年閏四月八日条)と、法皇は追討自体を然るべき事として捉えており、早々に追討宣旨を下すことを望んでいたことがわかる。
ところが右大臣兼実は「抑、伊勢遷宮并造東大寺者、我朝第一之大事也、而赴征伐之間、諸国定不静歟、然者可成彼両事之妨、件條殊召仰不可致造宮造寺之害、為公為私以之可用追討之祈祷也、以此趣経房卿可書遣御教書於頼朝卿許者」(『玉葉』文治五年閏四月八日条)と返奏し、伊勢遷宮や東大寺再建の妨げとなる追討宣旨下賜を回避しようと考えていた。兼実は遠境へ逃れ去った義経を脅威とは感じず、それよりも国家の大行事である「造宮造寺之害」を恐れていたことは明白である。兼実は蔵人家実へただちに帥卿経房邸に行って子細を報告するよう指示している(『玉葉』文治五年閏四月八日条)。
一方、8日の追討宣旨不可の子細は経房卿から頼朝へ送られたと考えられ、21日、頼朝は「泰衡容隠義顕事、公家爭可有宥御沙汰哉」と朝廷の沙汰に不満を述べるとともに、「任先々申請之旨、早被下追討 宣旨者、塔供養之後、可令遂宿意之由」と、再度の追討宣旨下賜を帥卿経房へ要請した(『吾妻鏡』文治五年閏四月廿一日条)。なお、頼朝が望んでいた「追討」の対象は義経ではなく、義経の召進を無視し続ける泰衡であることがわかる。泰衡は義経召進の勅命及び院宣を受けながらも一年以上にわたって「前後相違、返々奇恠」という申状を奏聞し、事実上朝命を無視し続けていたが、当然頼朝からも征討を直言する文書が届けられていたと考えられよう。これにより泰衡は頼朝の圧力に抗いきれないと感じたのだろう。閏4月30日、「於陸奥国、泰衡襲源予州」した。この日「予州在民部少輔基成朝臣衣河舘、泰衡従兵数百騎馳至其所合戦」(『吾妻鏡』文治五年閏四月卅日条)と、外祖父基成の衣川舘に住む義経を数百騎の兵で襲ったのである。泰衡への勅命および院宣(頼朝の意向を受けたもの)はあくまでも義経の身柄の召進であって、泰衡の行動も義経の身柄を押さえることが目的であったろう。しかし攻められた義経側は「予州家人等雖相防悉以敗績」し、「予州入持仏堂、先害妻廿二歳、子女子四歳、次自殺」と、基成邸の持仏堂に籠り、妻子ともども自害してしまうのであった。
 |
| 平泉高舘より衣川を望む |
鎌倉に泰衡からの「去閏四月晦日、於前民部少輔基成宿館奥州誅義経畢」(『吾妻鏡』文治五年五月廿日条)という報告が届いたのは、事件から二十日以上経た5月22日のことだった。これを受けた頼朝は、ただちに義経誅殺の旨を急ぎ京都に奏達したが、義経死去により、親族である頼朝は障りを受け、6月9日に予定されていた鶴岡山八幡宮寺の塔供養は延引されることとなる。しかしこの塔供養は、供養願文から導師の選定まで法皇に依頼し決定している以上、延引はあってはならない事態である。頼朝も奥州追討は「塔供養之後」と予定するほど慎重だったにもかかわらず、泰衡の勝手な行動(義経の捕縛ではなく殺害)によって、仏事の延引を法皇に奏聞することを余儀なくされたのである。これも泰衡に対する更なる遺恨となったのであろう。
5月29日、頼朝からの書状を受けた右兵衛督能保は、兼実のもとに「九郎為泰衡被誅滅了」という一報を届けている(『玉葉』文治五年五月廿九日条)。5月22日に鎌倉を発した頼朝消息は右兵衛督能保へ宛てられたものだったのだろう。なお、この頼朝の消息は塔供養の延引が主題で、義経が討たれたことは塔供養延引の理由として副えられている程度である。それほどに法皇までをも動かした塔供養の延引は一大事だったのだろう。また、この消息を見た兼実は「天下之悦何事如之哉、実仏神之助也、抑又頼朝卿之運也、非言語之所及也」(『玉葉』文治五年五月廿九日条)と喜びを示しているが、これは義経という「個人」が討たれたことに対する喜びではない。義経誅殺により頼朝の奥州追討の名分が失われ、兼実が強く進める神宮遷宮や東大寺造営という朝廷の大事、さらに氏長者として行う興福寺復興事業への障りがなくなったこと、及び安穏の世の到来を予感したためであろう。
これ以降『玉葉』には朝廷及び氏長者としての重要な事柄が記載される一方で、関東及び奥州の事件はほぼ掲載されなくなる。その後も『吾妻鏡』の記述によれば頻繁に京都への使者が遣わされているが、これらについて兼実は触れておらず、もはや兼実にとって関東からの戦乱報告や追討宣旨の要求は興味の薄いものになっていたことがわかる。
6月3日、宮寺塔供養の導師として、天台座主僧正全玄の代官・中納言法橋観性が佐々木四郎左衛門尉高綱に伴われて鎌倉に到着。幕府南門近くにあった八田知家邸が宿所と定められ、頼朝は三浦平六義村を遣わして菓子を供した(『吾妻鏡』文治五年六月三日条)。法皇には塔供養延引を奏聞したものの、すでに導師法橋観性は鎌倉への途路にあり、法皇からも馬などが下されていたことから、塔供養の延引は不可能と判断し、決行へと方針を変えた(『吾妻鏡』文治五年六月三日条)。頼朝自身の参会についても「御軽服三十余日馳過訖」と、義経の死からすでに三十日以上経っており、内陣に入らなければ差し支えなしとされたのである。
6月8日、京都から帥卿経房の返報が鎌倉に到着した。5月29日に右兵衛督能保に着いた消息の返報であろう。法皇は「義顕誅罸事、殊悦聞食之由」とともに「彼滅亡之間、国中定令静謐歟、於今者可嚢弓箭之由、内々可申之旨、其沙汰候」(『吾妻鏡』文治五年六月八日条)と、義経を討ったからには国は鎮まるであろうから、兵を収めるべしという内々の法皇の意向を伝えている。ところが、頼朝の目的は穢を伴う義経殺害ではなく、あくまでも泰衡追討による奥州鎮圧である。この頼朝の思惑と奥州征討を拒否する朝廷の間には著しい認識の乖離があった。
翌9日、鶴岡山八幡宮寺では、塔供養が予定通り行われた(『吾妻鏡』文治五年六月九日条)。出御にあたり、法橋観性を導師に、若宮別当法眼円曉を呪願として挙行され、頼朝は義経の服喪中のため馬場柵付近に桟敷を構えて儀式を見物。隼人佐三善康清と梶原平三景時の両名が行事を執行した。列後には千葉介常胤、千葉大夫胤頼(東六郎大夫)、後陣の随兵には千葉太郎胤正が随っている。
| 先陣随兵 | 小山兵衛尉朝政 | 土肥次郎実平 | 下河辺庄司行平 | 小山田三郎重成 |
| 三浦介義澄 | 葛西三郎清重 | 八田太郎朝重 | 江戸太郎重継 | |
| 二宮小太郎光忠 | 熊谷小次郎直家 | 信濃三郎光行 | 徳河三郎義秀 | |
| 新田蔵人義兼 | 武田兵衛尉有義 | 北條小四郎 | 武田五郎信光 | |
| 次御歩(束帯) | 源頼朝 | |||
| 御剣 | 佐貫四郎太夫広綱 | |||
| 御調度 | 佐々木左衛門尉高綱 | |||
| 御甲 | 梶原左衛門尉景季 | |||
| 列御後(布衣) | 武蔵守義信 | 遠江守義定 | 駿河守広綱 | 参河守範頼 |
| 相摸守惟義 | 越後守義資 | 因幡守広元 | 豊後守季光 | |
| 皇后宮権少進 | 安房判官代隆重 | 藤判官代邦通 | 紀伊権守有経 | |
| 千葉介常胤 | 八田右衛門尉知家 | 足立右馬允遠元 | 橘右馬允公長 | |
| 千葉大夫胤頼 | 畠山次郎重忠 | 岡崎四郎義実 | 藤九郎盛長 | |
| 後陣隨兵 | 小山七郎朝光 | 北條五郎時連 | 千葉太郎胤政 | 土屋次郎義清 |
| 里見冠者義成 | 浅利冠者遠義 | 三浦十郎義連 | 伊東四郎家光 | |
| 曽我太郎祐信 | 伊佐三郎行政 | 佐々木三郎盛綱 | 新田四郎忠常 | |
| 比企四郎能員 | 所六郎朝光 | 和田太郎義盛 | 梶原刑部丞朝景 |
6月13日、泰衡の使者・新田冠者高衡(秀衡四男)が義経の首級を腰越浦に持参し、その旨を鎌倉に言上した。これを受けた頼朝は、和田義盛と梶原景時に武装させた上、甲冑の郎従二十騎を具して腰越に遣わしている(『吾妻鏡』文治五年六月十三日条)。この首級持参は5月22日に泰衡が約した「其頚追所進」によるもので、6月7日に頼朝が塔供養に際して穢を防ぐために「与州頚、無左右不可持参、暫可令逗留途中之旨、被遣飛脚於奥州」(『吾妻鏡』文治五年六月七日条)と指示していたものであった。義経の首は、そのころすでに関東近辺まで上っていたと思われるが、塔供養が終わるまで留め置かれていたのであろう。義経の首級は黒漆の櫃の中に満たされた美酒の中に安置されていたが、高衡の僕従二名が担っていた。謀叛人とはいえ義経は平家追討の殊勲者であることは衆人の認めるところであり、また御家人の記憶にも新しいものであった。そのような人物が、泰衡代の高衡の従類如きに担がれている様子に「観者皆拭双涙、湿両衫云々」(『吾妻鏡』文治五年六月十三日条)であったという。
6月20日、鶴岡山八幡宮寺の臨時祭が挙行され、流鏑馬や競馬など神事が催されたが、頼朝は義経の服喪中であったため参宮および奉幣は行われなかった。義経の自害は閏4月30日であり、「兄弟軽服、日数為五十日」(『吾妻鏡』弘長元年六月廿七日条)の例もあり、例の通り五十日であればこの臨時祭当日が忌明となり、忌明けを以て奥州追討について具体的に動き始めたとみられる。
6月24日、頼朝は「奥州泰衡、日来隠容予州科、已軼反逆也、仍為征之、可令発向給之間、御旗一流可調進之由、被仰常胤」と、奥州追討について御旗一流の調進を常胤に命じた(『吾妻鏡』文治五年六月廿四日条)。常胤へが選ばれたのは「治承四年、常胤相率軍勢参向之後、諸国奉帰往、依其佳例」(『吾妻鏡』文治五年七月八日条)のためであった。旗のもととなる絹布は小山兵衛尉朝政が献じたものであった。朝政が絹布献上を任されたのも「先祖将軍輙亡朝敵之故也」(『吾妻鏡』文治五年七月八日条)という先例に沿ったものである。この日の夜、京都より右兵衛督能保の消息が到着した。法皇が内々に仰せられるには「連々被経沙汰此事、関東鬱陶雖難黙止、義顕已被誅訖、今年造太神宮上棟、大仏寺造営、彼是計会追討之儀、可有猶予者、其旨已欲被献殿下御教書」(『吾妻鏡』文治五年六月廿四日条)というものであった。ところが、頼朝はこの法皇の内々の指示にも拘わらず、これを全く拒絶して「奥州事、猶可被下追討 宣旨之由、重被申京都」(『吾妻鏡』文治五年六月廿四日条)という。
6月26日には、奥州で泰衡が弟の泉三郎忠衡を誅殺したことが鎌倉に伝えられている。これは忠衡が義経に加担していたため「依有 宣下旨也」(『吾妻鏡』文治五年六月廿六日条)という。しかし、二度にわたって出された宣旨は義経追討ではなく「可召進彼義経之由被下 宣旨先畢」であり、奥州追討の噂が現実味を帯びる中、義経と親しかった忠衡を誅殺することで頼朝に対する恭順の意を示したのだろう。ところが、頼朝は「此間奥州征伐沙汰之外無他事」(『吾妻鏡』文治五年六月廿七日条)と記されるほど、奥州攻めの準備は確実に進行していた。諸国から鎌倉へ集まる軍勢もすでに一千人に及び、和田義盛、梶原景時の両司を奉行として交名を注し、前図書允清定がそれを記録している。その規模は「伊澤五郎之催」で「安芸国大名葉山介宗頼」が鎌倉へ向かっていることから(『吾妻鏡』文治五年十月廿八日条)、国惣追捕使に任じられていた御家人は管国内の軍勢催促権を有し、招集していたと考えられる。なお、武蔵国と下野国は奥州への順路であることから、両国の御家人は鎌倉に来るに及ばず、用意のみ行っておき、進発の追討軍に加わるよう命じている(『吾妻鏡』文治五年六月廿七日条)。
奥州進発の用意が整いつつあった6月30日、頼朝は「武家古老、兵法存故実」として重用されていた、大庭平太景能を御所に召し、いまだ宣旨がもたらされない今「奥州征伐事」を問うた。頼朝は「此事窺天聴之處、于今無勅許、憖召聚御家人、為之如何、可計申者」と聞くと、景能は何ら考えることなく「軍中聞将軍之令、不聞 天子之詔云々、已被経 奉聞之上者、強不可令待其左右給、隨而泰衡者、受継累代御家人遺跡者也、雖不被下 綸旨、加治罰給有何事哉、就中、群参軍士費数日之條、還而人之煩也、早可令発向給者」と、『漢書』の例を引いて勅許がなくとも早々に泰衡を追捕すべきと語っている。頼朝の父・義朝以来の古老である景能の言葉に頼朝は深く感じ、小山七郎朝光に指示して御厩の鞍置馬を景能に給わった。三十年以前の保元の乱に際し、鎮西八郎為朝の強弓を足に受けて以来歩行が儘ならず、御所縁側から庭上に降りることができない景能に対し、朝光は馬の差縄を縁側へ投げて受け取り、体裁を保った。
その後、景能は孫ほども歳の離れた朝光を招くと、「吾老耄之上、保元合戦之時被疵之後、不行歩進退、今雖拝領御馬、難下庭上之處、被投縄、思其芳志直千金云々」と賀している(『吾妻鏡』文治五年六月卅日条)。
7月8日、千葉介常胤は命じられていた新調の御旗を頼朝に献じた。その長さは「前九年の役」の「入道将軍家頼義」の旗と同じ一丈二尺の二幅で、上にはそれぞれ伊勢大神宮、八幡大菩薩が、下には相対する二羽の鳩が縫い取られていた(『吾妻鏡』文治五年七月八日条)。
この旗は三浦介義澄の手で鶴岡八幡宮に奉納され、七日間の祈祷ののち、奥州征討の旗とされた。また同日、下河辺庄司行平が新調の鎧を頼朝に献じた。このとき、頼朝は袖につけられるべき笠標が兜の後ろについているのを見て不思議に思い、「此簡付袖為尋常儀歟、如何者」(『吾妻鏡』文治五年七月八日条)と問うた。これに行平は「是曩祖秀郷朝臣佳例也、其上、兵本意者先登也、進先登之時、敵者以名謁知其仁、吾衆自後見此簡、可必知某先登之由者也、但可令付袖給否可在御意」と答えている。これに頼朝は「調進如此物之時用家様者故実也」(『吾妻鏡』文治五年七月八日条)として行平を賞した。
7月16日、京都から右兵衛督能保の使者として在京御家人・後藤兵衛尉基清と、京都へ遣わしていた頼朝使者が鎌倉に帰着し、能保からの朝廷の情勢を伝えている。基清が言うには、
「泰衡追討 宣旨事、摂政公卿已下被経度々沙汰訖、而義顕出来、此上猶及追討儀者、可為天下大事、今年許可有猶予歟之由、去七日被下 宣旨也、早可達子細之由、師中納言相触之、可為何様哉云々」(『吾妻鏡』文治五年七月十六日条)
という。6月24日の頼朝の申状は法皇や朝廷の意思を覆すことはできず、しかもこれまでは曖昧な不戦の指示であったり、法皇の内々の意向に留まっていたものが、7月7日、不戦を命じる「宣旨」が正式に下された。ところが頼朝は「令聞此事給、殊有御鬱憤、軍士多以予参之間、已有若干費、何期後年哉、於今者必定可令発向給之由、被仰」と、宣旨に背いて強引に奥州発向を決定した(『吾妻鏡』文治五年七月十六日条)。本来であれば違勅の重罪であるが、もはや頼朝の影響力、軍事力、統治力は朝廷のそれを遥かに凌駕しており、実力を以て自己の理想を貫いたのであった。
一方、法皇は「奥州追討事、一旦雖被制止」したものの、頼朝の再三の要請を拒否することは後顧の憂いにならんと考えたのだろう。「仰重被計申之旨、尤可然之由」と前言を翻し、結局摂政已下も追討を認めることに改め、7月19日、頼朝に泰衡追討の宣旨を下したのであった(『吾妻鏡』文治五年九月九日条)。この宣旨は7月24日に蔵人宮内大輔家実が奉じ、26日に帥卿経房から右兵衛督能保に送られ、28日に出京して東国へと下された。しかし、このころの兼実は日記を毎日書かずに興味や後勘のあった場合にのみ記しており、この宣旨については一言も記していない。
ただ、頼朝はこの泰衡追討の宣旨を知ることなく奥州征討を北陸、東海、大手の三軍で行うことを決定。東海道大将軍は千葉介常胤、八田前右衛門尉知家の両将、北陸道大将軍は比企藤四郎能員、宇佐美平次実政の両将、頼朝は大手軍を率いて奥州へ向かうことと定め、留守は大夫属三善善信入道を主将に、その弟の隼人佐三善康清ほか大和判官代藤原邦通、佐々木次郎経高、大庭平太景能、義勝房成尋已下の人々に命じている(『吾妻鏡』文治五年七月十七日条)。
| 大将軍 | 相具 | 経路 | |
| 東海道大将軍 | 千葉介常胤 八田右衛門尉知家 |
一族等 常陸下総国両国勇士等 |
行方⇒岩城⇒岩崎⇒渡遇隈河湊 |
| 北陸道大将軍 | 比企藤四郎能員 宇佐美平次実政 |
上野国高山、小林、大胡、佐貫等住人 | 越後国⇒出羽国念種関 |
| 大手 | 源頼朝 | 武蔵、上野両国内党者等者、 従于加藤次景廉、葛西三郎清重等 |
中路可有御下向 |
7月18日、頼朝は伊豆山の専光房を鎌倉に召して奥州追討の祈祷を依頼。出立して二十日後、御所の後山に梵宇を草創せよと命じた(『吾妻鏡』文治五年七月十八日条)。専光房みずからが柱だけでよいのでこれを立てて仮の梵宇と為し、持仏の正観音像を安置することとし、実際に堂を建立するのは後日の指示とすることを伝えている。そして、追討軍の第一陣として北陸道大将軍の比企藤四郎能員が鎌倉を出陣。 翌7月19日、頼朝率いる大手軍が鎌倉を発った(『吾妻鏡』文治五年七月十九日条)。ここに父の豊島権守清光と葛西三郎清重、末弟の十郎清宣が随っている。
○大手勢(鎌倉出御勢一千騎)
| 先陣 | 畠山次郎重忠 | 長野三郎重清 | 大串小次郎 | 本田次郎 | 榛澤六郎 | 柏原太郎 |
| 御駕 | 源頼朝 | |||||
| 御供輩 | 武蔵守義信 | 遠江守義定 | 参河守範頼 | 信濃守遠光 | 相摸守惟義 | 駿河守広綱 |
| 上総介義兼 | 伊豆守義範 | 越後守義資 | 豊後守季光 | |||
| 北條四郎 | 北條小四郎 | 北條五郎 | 式部大夫親能 | 新田蔵人義兼 | 浅利冠者遠義 | |
| 武田兵衛尉有義 | 石和五郎信光 | 加々美次郎長清 | 加々美太郎長綱 | 三浦介義澄 | 三浦平六義村 | |
| 佐原十郎義連 | 和田太郎義盛 | 和田三郎宗実 | 岡崎四郎義実 | 岡崎先次郎惟平 | 土屋次郎義清 | |
| 小山兵衛尉朝政 | 小山五郎宗政 | 小山七郎朝光 | 下河辺庄司行平 | 吉見次郎頼綱 | 南部次郎光行 | |
| 平賀三郎朝信 | 小山田三郎重成 | 小山田同四郎重朝 | 藤九郎盛長 | 足立右馬允遠元 | 土肥次郎実平 | |
| 土肥弥太郎遠平 | 梶原平三景時 | 梶原源太左衛門尉景季 | 梶原平次兵衛尉景高 | 梶原三郎景茂 | 梶原刑部丞朝景 | |
| 梶原兵衛尉定景 | 波多野五郎義景 | 波多野余三実方 | 阿曽沼次郎広綱 | 小野寺太郎道綱 | 中山四郎重政 | |
| 中山五郎為重 | 渋谷次郎高重 | 渋谷四郎時国 | 大友左近将監能直 | 河野四郎通信 | 豊嶋権守清光 | |
| 葛西三郎清重 | 葛西十郎 | 江戸太郎重長 | 江戸次郎親重 | 江戸四郎重通 | 江戸七郎重宗 | |
| 山内三郎経俊 | 大井二郎実春 | 宇都宮左衛門尉朝綱 | 宇都宮次郎業綱 | 八田右衛門尉知家 | 八田太郎知重 | |
| 主計允行政 | 民部丞盛時 | 豊田兵衛尉義幹 | 大河戸太郎広行 | 佐貫四郎広綱 | 佐貫五郎 | |
| 佐貫六郎広義 | 佐野太郎基綱 | 工藤庄司景光 | 工藤次郎行光 | 工藤三郎助光 | 狩野五郎親光 | |
| 常陸次郎為重 | 常陸三郎資綱 | 加藤太光員 | 加藤藤次景廉 | 佐々木三郎盛綱 | 佐々木五郎義清 | |
| 曽我太郎助信 | 橘次公業 | 宇佐美三郎祐茂 | 二宮太郎朝忠 | 天野右馬允保高 | 天野六郎則景 | |
| 伊東三郎 | 伊東四郎成親 | 工藤左衛門祐経 | 新田四郎忠常 | 新田六郎忠時 | 熊谷小次郎直家 | |
| 堀藤太 | 堀藤次親家 | 伊澤左近将監家景 | 江右近次郎 | 岡辺小次郎忠綱 | 吉香小次郎 | |
| 中野小太郎助光 | 中野五郎能成 | 渋河五郎兼保 | 春日小次郎貞親 | 藤澤次郎清近 | 飯富源太宗季 | |
| 大見平次家秀 | 沼田太郎 | 糟屋藤太有季 | 本間右馬允義忠 | 海老名四郎義季 | 所六郎朝光 | |
| 横山権守時広 | 三尾谷十郎 | 平山左衛門尉季重 | 師岡兵衛尉重経 | 野三刑部丞成綱 | 中條藤次家長 | |
| 岡辺六野太忠澄 | 小越右馬允有弘 | 庄三郎忠家 | 四方田三郎弘長 | 浅見太郎実高 | 浅羽五郎行長 | |
| 小代八郎行平 | 勅使河原三郎有直 | 成田七郎助綱 | 高鼻和太郎 | 塩屋太郎家光 | 阿保次郎実光 | |
| 宮六傔仗国平 | 河勾三郎政成 | 河勾七郎政頼 | 中四郎惟重 | 一品房昌寛 | 常陸房昌明 | |
| 尾藤太知平 | 金子小太郎高範 |
7月25日、頼朝は下野国古多橋駅に到着。一宮の宇津宮に奉幣して祈願している(『吾妻鏡』文治五年七月廿五日条)。その後、宿所では小山下野大掾政光入道が駄餉を献じている。このとき、頼朝の御前にいた紺直垂の武士に目が留まった政光入道は、頼朝に「何者哉」と問うた。頼朝は「彼者、本朝無双勇士、熊谷小次郎直家也」と紹介すると、政光入道は「何事無双号候哉」と再び問う。頼朝は「平氏追討之間、於一谷已下戦場、父子相並欲棄命、及度々之故也」と答えると、政光入道は破顔して「為君棄命之條、勇士之所志也、爭限直家哉、但如此輩者依無右顧眄之郎従、直励勲功揚其号歟、如政光者、只遣郎従等抽忠許也、所詮於今度者自遂合戦、可蒙無双之御旨」と子息の朝政、宗政、朝光ならびに猶子の宇都宮頼綱に下知した。頼朝はこのことに非常に興に入っている。
翌26日には、かつて頼朝と激しく交戦した佐竹氏の惣領「佐竹四郎(秀義)」が常陸国から参じている(『吾妻鏡』文治五年七月廿六日条)。このとき佐竹四郎が持参した旗が「無文白旗」で、頼朝の旗と同じであったため、頼朝はこれを咎め、同じ旗を用いるべからずと命じた。かつての遺恨があったことも咎め立てした理由の一つとみられるが、頼朝は佐竹四郎に「御扇出月」を下し、佐竹四郎はこれを白旗に括り付けたという。以降、佐竹氏はこれを自家の定紋として用いることとなる。
27日に奥州との国境である下野国新渡戸駅で着到注進を行ったのち、29日、白河関を越えて陸奥国へと入った(『吾妻鏡』文治五年七月廿九日条)。さらに進軍して8月7日、伊達郡阿津賀志山辺の国見駅まで進んだ。泰衡は「泰衡日来聞二品発向給事、於阿津賀志山、築城壁固要害、国見宿与彼山之中間俄搆口五丈堀、堰入逢隈河流柵」(『吾妻鏡』文治五年八月七日条)とあるように、阿津賀志山に城塞を築き、国見宿と山との間に幅五丈の堀割と土塁を構築し、堀には阿武隈川の水を流入させていた(『吾妻鏡』文治五年八月七日条)。ただし、阿武隈川から阿津賀志山頂まで南北に築かれた防塁は三キロを超える長大なものであり、数年をかけて築かれたと推測される。おそらく秀衡が統治していた頃からすでに築かれていた防塁があり、泰衡が手を加えたものであろう。頼朝があらかじめ八十名の工兵を手配していることから、この防塁は頼朝の周知するところであったと思われる。また、阿津賀志山の麓を北行する奥大道は防塁を貫通しており、この開口部には木戸が設けられ、平時から関所のような役割を担っていたのではなかろうか。泰衡が防塁を構築したとすれば、阿津賀志山より北方の狭隘地、貝田や越河にみられる石塁か。
阿津賀志山要害を守るのは、泰衡の義兄にして義父にあたる西木戸太郎国衡(信寿太郎殿)と金剛別当秀綱、下須房太郎秀方已下の部隊であった。金剛別当は苅田郡の金剛蔵王権現の別当であろうか。泰衡自身は国分原の鞭楯(仙台市宮城野区安養寺二丁目付近か)に布陣し、名取川と広瀬川の急流には大綱を引いて渡河の妨害を図っている。名取川と広瀬川の大綱と泰衡自身の国分原付近への布陣は、国府防衛を目的としたものである。さらに平泉の玄関口にあたる栗原、三迫、黒岩口、一野のあたりには若九郎大夫、余平六らを大将軍とした部隊を配置し、出羽国には田河太郎行文、秋田三郎致文の両名を遣わしたという。ただし、もともと田河行文は出羽国田河郡、秋田致文は秋田郡の支配層であったと考えられ、奥州藤原氏の支配領域の広さがうかがわれる。
8月7日夜、頼朝は主だった郎従に対し、翌8日曉方に阿津賀志山へ進むことを伝達。戦陣の畠山次郎重忠が率いてきた八十名の土木部隊によって堀が密かに埋められ、これを知った頼朝寝所伺候の小山七郎朝光は先陣を狙って寝所を出て、兄・小山左衛門尉朝政の郎従を拝借して阿津賀志山へと向かっている。ただ朝光がこのとき合戦に臨んだかは不明。
翌8日、金剛別当秀綱が阿津賀志山前に布陣した(『吾妻鏡』文治五年八月八日条)。頼朝勢は早朝卯刻、試みに「畠山次郎重忠、小山七郎朝光、加藤次景廉、工藤小次郎行光、同三郎祐光等」を派遣して箭合を行わせている。秀綱等は防戦するが、巳刻には退いて大木戸付近まで馳せ帰り、大将軍藤原国衡に戦況を報告。国衡は「泰衡郎従信夫佐藤庄司、又号湯庄司、是継信忠信等父也、相具叔父河辺太郎高経、伊賀良目七郎高重等」を「石那坂之上(福島市飯坂町湯野坂ノ上)」に遣わして、「堀湟懸入逢隈河水於其中、引柵、張石弓、相待討手」った(『吾妻鏡』文治五年八月八日条)。その眼前を流れる阿武隈川(摺上川)内に柵を引いて頼朝勢を待ち受けた。一方、頼朝勢からは「常陸入道念西子息常陸冠者為宗、同次郎為重、同三郎資綱、同四郎為家等」が秣の中に甲冑を隠して伊達郡沢原辺(摺上川周辺の肥沃地か)まで進み、佐藤庄司らが布陣する「石那坂之上」に迫り、合戦に及んだ。佐藤庄司はこれに激しく応戦し、寄手の為重、資綱、為家が負傷する激戦となった。常陸冠者為宗は奮戦し、佐藤庄司已下十八人の首を挙げ(ただし、佐藤庄司は十月二日に名取郡司、熊野別当とともに赦免されており、討死していないと思われる)、後日、為宗らはこれらの首級を奥大道沿いの経ケ丘(国見町大字大木戸経ケ岡)に梟首している(『吾妻鏡』文治五年八月八日条)。
9日夜、頼朝は翌10日早朝に阿津賀志山を越えて合戦すべきことを決定した(『吾妻鏡』文治五年八月九日条)。ところが、深夜のうちに「三浦平六義村、葛西三郎清重、工藤小次郎行光、同三郎祐光、狩野五郎親光、藤澤次郎清近、河村千鶴丸年十三才、以上七騎」が先陣と定められていた畠山次郎重忠の陣を越して抜け駆けした(『吾妻鏡』文治五年八月九日条)。この抜け駆けを察知した重忠郎従の榛沢六郎成清が重忠に「今度合戦奉先陣、抜群眉目也、而見傍輩所、爭難温座歟、早可塞彼前途、不然者訴申事由、停止濫吹、可被越此山云々」と訴えている。これに重忠は「其事不可然、従以他人之力雖退敵、已奉先陣之上者、重忠之不向以前合戦者、皆可為重忠一身之勲功、且欲進先登之輩事、妨申之條非武略本意、且独似願抽賞、只作惘然、神妙之儀也」と言って、動くことはなかった。
抜け駆けした七騎は、終夜阿津賀志山を登って木戸口(奥大道の木戸前の曲輪的な部分であろう)にたどり着くと、各々名乗りを上げた。すると泰衡郎従で「六郡第一強力者」である伴藤八やそのほか屈強な武士が馳せ寄せて、工藤小次郎行光と狩野五郎親光が先頭を切って突入し、行光と伴藤八は互いに轡を並べて組み合い、行光がその首を挙げているが、狩野親光は討死した。親光は頼朝の挙兵時から従う最古参の御家人であった(『吾妻鏡』文治五年八月九日条)。行光は伴藤八の首級を馬鞍に括り付けたのち、さらに木戸に向けて馳せ進むと、武士二名が組討をしている現場に遭遇する。行光が名を尋ねると「藤澤次郎清近欲取敵」という。これを聞いた行光は早速清親に加担して敵の首を取った。その後、休息の後、清親は行光に感謝し、すぐさま行光息男を清親の娘婿とする約定を交わした。また、葛西清重と河村千鶴丸も奮戦して敵を討ち、中宮大夫進親能猶子・左近将監能直は初陣ながら、親能から補佐を依頼された宮六兼仗国平のもと、国衡近臣の佐藤三郎秀員と戦い、討ち取っている。
+―斎藤実盛
|(長井別当)
|
+―女子
∥―――――宮道国平
∥ (宮六兼仗)
宮道某
8月10日未明、予定通りに「重忠、朝政、朝光、義盛、行平、成広、義澄、義連、景廉、清重等」が木戸口に攻め寄せた。しかし、国衡麾下の将士も堅く防いで容易に陥落するとは思われなかった。実は頼朝は前夜のうちに「小山七郎朝光并宇都宮左衛門尉朝綱郎従紀権守、波賀次郎大夫已下七人、以安藤次為山案内者、面々負甲疋馬、密々出御旅館、自伊逹郡藤田宿向会津之方」に派遣しており、「越于土湯之嵩、鳥取越等、樊登于大木戸上国衡後陣之山」と、藤田宿から峯沿いに阿津賀志山の北側に回り込み、阿津賀志山中腹、防塁の大木戸内側に布陣する国衡本陣を望む高台に攀じ登ると、鬨の声を上げて矢を射かけた。この小山朝光勢の奇襲に国衡勢は「搦手襲来」と大混乱を来たし、国衡勢は「無益于搆塞」と逃亡していった。しかし、この中で「金剛別当子息下須房太郎秀方年十三」は黒駮馬に跨って踏み止まり、攻め寄せる関東勢を防いでいた。ここに工藤行光が駆け付けて秀方に馬を並ばせんとしたとき、行光の郎従藤五が割って入り、秀方と組討した。このとき藤五は秀方の顔を見て、子供と知る。姓名を問うが何も語らなかった。しかし、この場に一人留まるほどであれば何らかの謂れのある人物なのだろうとして討ち取っているが、その剛力は幼少に似合わぬものであったという(『吾妻鏡』文治五年八月十日条)。また、その父親の金剛別当秀綱は小山朝光に討たれている。そして早朝卯刻、頼朝はすでに戦乱の終わった阿津賀志山の堅陣を越え、奥大道を北上する。
国衡は高楯黒という名馬を駆って北方へ逐電し「芝田郡大高宮辺(柴田郡大河原町金ケ瀬新開)」からさらに「大関山(柴田郡川崎町大字今宿大森辺)」を越して出羽国へ向かおうとしていたが、和田小太郎義盛が大高宮辺を疾走する国衡を発見。「可返合」と呼びかけた。すると国衡は名乗って馬を廻らすと、互いに弓手に向き合い、国衡は「十四束箭」の巨大矢を手挟んだが、義盛は素早く「十三束箭」の矢を国衡に射掛けた。矢は国衡の射向けの袖を射通して腕に突き刺さり、国衡は痛みに耐えかねて馬を退いた。義盛は二の矢を構えて狙ったが、距離が開いてしまった。ここに走り来た畠山重忠の一軍が義盛を追い抜き、重忠の客将・大串小次郎が国衡に迫った。これに驚いた国衡は誤って馬を深田(大河原町金ケ瀬馬取前)に入れてしまい、身動き儘ならない中、義盛の矢で負傷していたことも重なって首を取られた(『吾妻鏡』文治五年八月十日条)。
8月12日、頼朝は船迫駅家(柴田郡柴田町船岡中央か)を経て、夕刻には多賀城国府へ到着した。泰衡は多賀城国府へと通じる国分原の鞭楯(仙台市宮城野区安養寺二丁目付近か)に布陣していたが、ここに阿津賀志山からの敗残兵がたどり着いて敗報を受けると、泰衡は驚いて退却しており、とくに抵抗もなく入部したのあろう。その後、「海道大将軍千葉介常胤、八田右衛門尉知家等参会、千葉太郎胤正、同次郎師常、同三郎胤盛、同四郎胤信、同五郎胤通、同六郎大夫胤頼、同小太郎成胤、同平次常秀、八田太郎朝重、多気太郎、鹿嶋六郎、真壁六郎等」が阿武隈川の湊を渡って国府へと参上した(『吾妻鏡』文治五年八月十二日条)。
8月13日、北陸道軍として日本海側から奥州へ進んでいた比企藤四郎能員、宇佐美平次実政は出羽国に討ち入り、泰衡が派遣していた「田河太郎行文、秋田三郎致文等」と戦い、梟首したという。『吾妻鏡』編纂時に当日の出来事として記録されたものであろう。
8月14日、逐電した泰衡が国衙北部の「玉造郡」にいるという風聞が届いた。しかし、もう一報で「国府中山上物見岡取陣」もあることから、頼朝は思慮の末に玉造郡へと進軍。国府を出立して黒河を経由して玉造郡へと向かった。一方で、国府中山上の物見岡にも「小山兵衛尉朝政、同五郎宗政、同七郎朝光、下河辺庄司行平等」を派遣して取り囲んだところ、泰衡は事実そこに陣していたが、すでに逐電し、幕と四、五十人ほどの泰衡郎従が守衛しているのみであり、朝政らは難なく攻め落とした。その後、朝政は「吾等者経大道、於先路可参会歟」と諮ると、行政は「玉造郡合戦者可為継子歟、早追可参彼所者」と、頼朝との合流を提案。朝政もこれを受け入れ、行平とともに玉造郡へと向かった(『吾妻鏡』文治五年八月十四日条)。この合戦には藤九郎盛長のもとにあった囚人・筑前房良心(刑部卿忠盛孫・筑前守時房の子)が従軍しており、その軍功によって厚免されている。
8月20日、頼朝は黒河郡(富谷市から大和町、大衡村)を経て玉造郡の「多加波々城」を取り囲んでいる(『吾妻鏡』文治五年八月廿日条)。「多加波々城」の現在地は不明だが、その後の頼朝のルートが葛岡郡を経て津久毛橋へと進んでいることから、江合川の氾濫原が眼下に広がる要害の地、のちの岩出山城(大崎市岩出山城山)の可能性もあろう。泰衡はここに在城していたが、頼朝が取り囲んだ際にはすでに城をあとにしており、頼朝は城を落とすと、泰衡を追って「葛岡郡(葛岡要害付近か)」を経由し、暴風雨の中「松山道」を通って三迫川に懸る「津久毛橋(栗原市金成大原木井戸端辺りか)」を渡った。この暴風雨は時期からして台風であろう。なお、ここで梶原平次景高が一首詠んでいる。
陸奥乃勢ハ御方ニ津久毛橋渡して懸ン泰衡頚
陸奥国の人々を従えて泰衡の首を取り、大路渡して獄に懸けるとの意気込みを津久毛橋を渡ることに掛けた歌であり、頼朝はこれを祝い言と感心したという(『吾妻鏡』文治五年八月廿一日条)。
 |
| 平泉の毛越寺跡の池 |
このころ泰衡は「自宅(伽羅御所か)」門前を通過して平泉を後にして出羽国へ向かっており、平泉の屋敷には郎従を遣わして火を放ち、「杏梁桂柱之搆、失三代之旧跡、麗金昆玉之貯、為一時之新灰」(『吾妻鏡』文治五年八月廿一日条)と、平泉の荘厳な屋敷は忽ち灰燼に帰した。ただし、泰衡が燃やしたのは自らの屋敷にとどまったとみられるが、すでに平泉の住人たちは逃散しており、翌22日申刻、頼朝が平泉に入った際には「家者又化烟、数町之縁辺、寂寞而無人、累跡之郭内弥滅而有地、只颯々秋風雖送入幕之響、蕭々夜雨不聞打窓之聲」(『吾妻鏡』文治五年八月廿二日条)と、ただ無人のまちが広がっていた様子がうかがえる。
なお、伽羅御所の南西の一角に倉がひとつ焼け残っており、頼朝は葛西三郎清重と小栗十郎重成を遣わして検分させたところ、「沈紫檀以下唐木厨子数脚在之、其内所納者、牛玉、犀角、象牙笛、水牛角、紺瑠璃等、笏、金沓、玉幡、金花鬘以玉飾之、蜀江錦直垂、不縫帷、金造鶴、銀造猫、瑠璃灯炉、南廷百各盛金器等也、其外錦繍綾羅、愚筆不可計記者歟」というほどの宝物が残されていた。頼朝は清重に「象牙笛、不縫帷」を与え、「可庄厳氏寺之由」を述べた重成にも望みの「玉幡、金花鬘」を授けた(『吾妻鏡』文治五年八月廿二日条)。
 |
| 平泉高舘より衣川を望む |
8月23日、頼朝は「八月八日同十日両日遂合戦、昨日廿二日、令着平泉候訖、而泰衡逃入深山之由、其聞候之間、重欲追継候也」という消息をしたためると、雑色時沢に託して京都の右兵衛督能保へ遣わした(『吾妻鏡』文治五年八月廿三日条)。そして25日、泰衡の行方をつかめないことから、さらに北方を追奔すべきことを御家人らに通達している(『吾妻鏡』文治五年八月廿五日条)。また、柳之御所に隣接する衣河館にはいまだ前民部少輔基成とその子息三人が残っており、頼朝は千葉六郎大夫胤頼に彼らを召し出すよう指示した。さっそく胤頼は衣河館に赴き、彼らを生け捕ろうとするが、基成らは抵抗することもなく降伏したことから、胤頼は彼らを伴って頼朝のもとに戻っている(『吾妻鏡』文治五年八月廿五日条)。
8月26日、泰衡の使者が頼朝の宿所(加羅御所跡)に一通の書状を投げ入れて逐電した。その書状の表書きには「進上鎌倉殿侍所 泰衡敬白」と記されていたという。その書状には、
という内容が記されており、土肥次郎実平は「試捨置御返報於比内辺、潜付勇士一両於其所、為取御書、有窺来者之時、搦取可被問泰衡在所」と進言するが、頼朝はすでに奥羽南部をその手中に収めている中で、そのような消極的な手段をとる必要はなく「不及其儀、可置書於比内郡之由、泰衡言上之上者、軍士等各可捜求彼郡内」と、泰衡が比内郡に返書を置くよう依頼している上は、兵士を比内郡に派遣して捜索すればよいと命じた(『吾妻鏡』文治五年八月廿六日条)。
9月2日、頼朝は平泉を出立し、岩井郡厨川辺(盛岡市天昌寺町一帯か)へ向けて北上川に沿って北上した。めざす厨川柵は、遠祖の将軍頼義が前九年合戦で安倍貞任らを討った場所で、佳例を引いて厨川に至ればきっと泰衡の首を得ることができるであろう、との願掛けであったという(『吾妻鏡』文治五年九月二日条)。厨川柵は北上川と雫石川の合流点に設けられた堅城でかつての陸奥安倍氏の館(盛岡市安倍館町)があったという。9月4日、頼朝一行は志波郡に到着し、「陣岡蜂社(紫波郡紫波町宮手字陣ヶ岡)」に陣所を定めた(『吾妻鏡』文治五年九月四日条)。「陣岡蜂社」はかつて将軍頼義と義家が布陣した陣所で、義家が厨川合戦で勝利の一因となった蜂を祀った神社であり、頼朝はこの佳例を尊んだと思われる。北陸道を攻め上った比企藤四郎と宇佐美平次の軍勢も合流して、岡には白旗が多くたなびいたという。また、頼朝の進軍を聞いて樋爪館(紫波郡紫波町南日詰箱清水)から逃れた「俊衡法師(樋爪入道蓮阿)」を三浦介義澄と弟・十郎義連、子の平六義村に追わせている(『吾妻鏡』文治五年九月四日条)。
ところが9月6日、比内郡贄柵(大館市二井田贄ノ里)の柵主で奥州藤原氏の「数代郎従河田次郎」が泰衡の首級を持参して陣岡蜂社の頼朝の陣所へ現れた(『吾妻鏡』文治五年九月六日条)。泰衡は平泉を出たのち、陸奥国「糠部郡」を経て「夷狄嶋」への逃亡を図っており、道筋にある比内郡贄柵の河田次郎のもとに逗留する予定で、その途次にあらかじめ頼朝に「若垂慈恵有御返報者、可被落置于比内郡辺」と私信を送ったものと思われる。
しかし、9月3日、泰衡一行が贄柵へたどり着くと、河田次郎は泰衡を取り囲んで殺害。河田次郎はその首を頼朝に献じるべく馬を走らせたという(『吾妻鏡』文治五年九月三日条)。泰衡の首は和田小太郎義盛と畠山次郎重忠両名による実検が行われ、囚人赤田次郎に確認させたところ、本人に間違いないということで、首は義盛に預けられた。一方、泰衡の首級を持参した河田次郎には「汝之所為、一旦雖似有功、獲泰衡之條、自元在掌中之上者、非可借他武略、而忘譜第恩梟主人首、科已招八虐之間、依難抽賞、為令懲後輩、所賜身暇也者」と告げて、小山朝光へ預け、処断している(『吾妻鏡』文治五年九月六日条)。頼朝の脳裏には、平治の乱の際、父・義朝が、尾張国内海庄の郎従・長田庄司忠致を頼って殺害された記憶がよぎっていたのではなかろうか。
その後、泰衡の首級は、前九年合戦の貞任の先例に倣い、横山小権守時広に首の請け取りを命じ、時広の子・太郎時兼が梶原景時から請けると、郎従の七太広綱が長さ八寸の鉄釘で泰衡首級を柱に打ち付けた。貞任の先例では時広曽祖父・横山野大夫経兼が将軍頼義から貞任の首を請け取り、その郎従惟仲(七太広綱の祖)が柱に打ち付けたという(『吾妻鏡』文治五年九月六日条)。
9月8日、帥卿経房への消息を工藤主計允行政に書かせ、雑色安達新三郎を飛脚として京都へ遣わした(『吾妻鏡』文治五年九月八日条)。この消息は10月10日に入洛。その日の夜、右馬頭能保が兼実に「頼朝卿申遣云、去九月三日誅泰衡了云々」(『玉葉』文治五年十月十日条)を伝えている。兼実は「天下之慶也」と評すも、非常に素っ気なく追記されるのみである。神事や造営、主上や二宮元服、女宮親王宣下の件、そして最も気にかけていた娘の入内であろう。朝廷や自身にとっての重大事が重なるときの戦闘行為及び穢事を兼実は厭い、大変不本意な気持ちなのだろう。10月17日午刻、長らく天王寺詣を行ってきた法皇が入洛して六条御所に還御(『玉葉』文治五年十月十七日条)。翌18日、院使の頭中将成経が兼実を訪ねて「頼朝賞之間事也、申子細了」(『玉葉』文治五年十月十八日条)という。
9月9日夜には右兵衛督能保の使者が陣岡の頼朝陣所に到着し、7月19日の泰衡追討の宣旨及び追討容認の院宣を届けた(『玉葉』文治五年九月九日条)。頼朝の奥州追討が公的に認められたこととなる。また、翌10日、頼朝は源忠已講、心蓮大法師、快能等の平泉の寺院の住侶らを陣岡に集めて寺領安堵等を行うと、七日間在陣した陣岡を後にして厨川柵へ移った(『吾妻鏡』文治五年九月十一日条)。すると15日、樋爪館から逃れていた奥州藤原一門の「樋爪太郎俊衡入道并弟五郎季衡」が厨川に出頭してきた。俊衡は「太田冠者師衡、次郎兼衡、同河北冠者忠衡」の三人の子息、季衡も子息「新田冠者経衡」を伴っていた。歳六十を超え「頭亦剃繁霜、誠老羸之容貌」の俊衡入道を見た頼朝は憐れみを感じ、八田知家へ彼らを預けている。知家は彼らを陣所へ伴うが、俊衡入道はただひたすらに法華経を読誦のほか一言も発せず、仏法を深く崇敬する知家はこの姿に深い感慨を覚えている(『吾妻鏡』文治五年九月十五日条)。翌日、知家は頼朝の陣所に参じると、俊衡入道の法華経転経について言上した(『吾妻鏡』文治五年九月十六日条)。頼朝は日ごろより法華経への信心が篤く、俊衡等については罪に問わず、樋爪の本所を安堵することを下知したが、これは法華経の「我等亦欲擁護読誦受持法華経者」(『妙法蓮華経陀羅尼品 第二十六』)という「十羅刹」の御照覧によるものであると言い含めている(『吾妻鏡』文治五年九月十六日条)。さらに18日には秀衡四男・本吉冠者高衡と泰衡後見の熊野別当が降伏。頼朝は京都の帥卿経房へ彼ら降人の交名を遣わした。
なお、この交名とみられる「能保卿示送云、奥州事併召取了、不漏一人云々、送注文一紙、実天之令然也、非言語之所及」(『玉葉』文治五年十月廿日条)が兼実に示されたのは10月20日のことで、一か月余り兼実へ報告がなされていなかったことになる。法皇還御からわずか二日後であり、奥州追討に関して否定的な兼実へ直接送られることは憚られたのか。翌10月21日には定長が院使として兼実邸を訪問し「奥州之間事」を諮問している(『玉葉』文治五年十月廿一日条)。
19日、厨川柵から平泉に向けて出立し、翌20日に平泉で「奥州羽州等事、吉書始之後、糺勇士等勲功、各被行賞訖」(『吾妻鏡』文治五年九月廿日条)された。その恩賞の御下文は「而千葉介最前拝領之、凡毎施恩以常胤可為初之由、蒙兼日之約者」(『吾妻鏡』文治五年九月廿日条)と、約定通り千葉介常胤から下された。21日に胆沢鎮守府(奥州市水沢佐倉河渋田)に到着し、翌22日に「陸奥国御家人事、葛西三郎清重可奉行之、参仕之輩者属清重可啓子細之旨」(『吾妻鏡』文治五年九月廿二日条)を命じた。
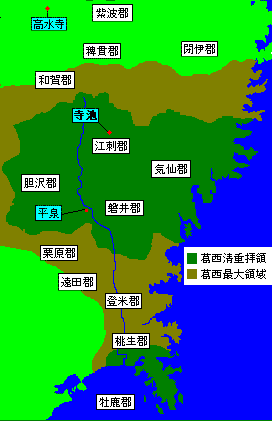 |
| 葛西氏の所領(緑部分内の各地) |
23日、頼朝は平泉に入り、伽羅御所の北西斜向かいにあった無量光院を参詣、翌24日には葛西三郎清重に平泉郡内の検非違使所を管領すべきことを命じた。葛西三郎清重は今回の奥州合戦での勲功が殊に群を抜いていたため、この要職を任されたという。また、地頭職も「伊澤、磐井、牡鹿等郡已下拝領数ケ所」という。ただし、「是於当郡(岩井郡)者、行光依可拝領、別以被仰下之間、及此儀云々」(『吾妻鏡』文治五年九月十二日条)とある通り、工藤小次郎行光も岩井郡を拝領したことになっており、清重はこれら郡全体を支配した地頭ではないのだろう。
10月1日、頼朝は多賀国府に入部。翌2日、囚人の「佐藤庄司、名取郡司、熊野別当」が厚免を蒙って、本所へと帰還した。佐藤庄司はかつて阿津賀志山の戦いで討死して梟首されたとされるが、赦免されたとされており、討死または赦された記録のいずれかが誤伝なのだろう(『吾妻鏡』文治五年十月一日条)。10月19日、頼朝は下野国宇都宮に逗留して報賽のため奉幣し、荘園を寄進した。また樋爪入道一族を宇都宮の職掌に任じたという(『吾妻鏡』文治五年十月十九日条)。ただし、後日彼ら一族のうち高衡、師衡、経衡、隆衡の四名は相模国、景衡は伊豆国、兼衡は駿河国へと流罪となり、俊衡弟の季衡は在下野国のまま下野国配流と決定されている(『吾妻鏡』文治五年十月一日条)。そして10月24日申刻、頼朝は鎌倉に帰還。実に三か月にわたる遠征であった。その後、諸所に亘る戦後処理を行い、奥州を守る葛西三郎清重に対して沙汰をしている。
頼朝は奥州からの帰途に「葛西三郎清重母所勞」の事を聞き、さっそくに使者を下総国葛西の住所に送った。頼朝が鎌倉へ到着した二日後の10月26日、使者は鎌倉へ帰還した。報告によると清重の母の所労はそれほど重篤なものではなかった。
このような中、12月22日夜、鎌倉に奥州からの飛脚が鎌倉に届いた。奥州では「予州義経并木曽左典厩義仲子息義高、及秀衡入道男等者、各令同心合力、擬発向鎌倉之由有謳歌説」という(『吾妻鏡』文治五年十二月廿三日条)。このような「亡霊」を奉じて敵対勢力を糾合することは、かつては平正盛に討たれたはずの前対馬守源義親が何人も現れて混乱期の朝廷を疑心暗鬼に陥れたように、不安定要素のある地域では一定の効果があるものだった。彼らが各々同心して鎌倉へ向かっているという報告を受け、翌23日、頼朝は北陸道を経由しての奥州派兵について議した(『吾妻鏡』文治五年十二月廿三日条)。結果、御家人らには深雪の時期だが、再度の出兵を用意すべしと指示し、小諸太郎光兼、佐々木三郎盛綱ら信濃国、越後国の御家人に出兵指示の書状を送っている。そして、その翌24日、鎌倉から工藤小次郎行光、由利中八惟平、宮六兼仗国平らが奥州へ出立した(『吾妻鏡』文治五年十二月廿四日条)。ただし、彼らの派遣は「可致防戦用意之故」という理由であることや、彼らがいずれも大名ではないことから、先遣隊の意味があったのだろう。
この奥州再乱は「奥州故泰衡郎従大河次郎兼任以下、去年窮冬以来企叛逆、或号伊予守義経、出於出羽国海辺庄、或称左馬頭義仲嫡男朝日冠者、起于同国山北郡、各結逆党」(『吾妻鏡』文治六年正月六日条)で、泰衡郎従の一人、大河次郎兼任らが伊予守義経や左馬頭義仲嫡男朝日冠者と号して起こしたもので、出羽国海辺庄や山北郡で軍勢を集めたものだった。大河兼任は安倍貞任弟・安倍家任の子孫で弟が二人おり、奥州合戦の際に弟の藤次忠季は捕虜となったのちに赦されて御家人に列していた。忠季は頼朝の命によって東北へ向かっていたが、兼任が乱を起こしたことを聞いて鎌倉に戻って兼任の叛乱を報告。また、忠季の兄・新田三郎入道も兼任に背いて鎌倉に参上して子細を報告した。頼朝は彼らからの報告によって事の次第を知るとともに、平盛時、藤原行政に相模国以西の御家人に参上を命じさせている(『吾妻鏡』文治六年正月七日条)。
●大河氏略系図(『岩手県史』第二巻中世篇上)
安倍忠良――頼良―+―貞任
|
+―娘 【奥州藤原氏】
| ∥――――――清衡――基衡――秀衡―+―国衡
| 藤原経清 |
|(亘理権大夫) +―泰衡
|
+―家任―――――秀任――祐任――武嗣―+―近綱
(三郎)|(新田三郎)
|
+―兼任――――+―鶴太郎
|(大河次郎) |
| |
+―忠季 +―畿内次郎
(二藤次)
大河兼任は嫡子鶴太郎、次男畿内次郎らを相具して鎌倉へ向けて進軍を始めるが、出羽国小鹿嶋付近に駐屯していた鎌倉先遣隊の一人、由利中八惟平へ使者を送って、泰衡の敵を討つ存念を伝えている。これを受けた中八惟平は「小鹿嶋大社山毛々佐田之辺」まで馳せ向かい、進んでくる大河勢を防ぎ戦ったが、討死を遂げた。
さらに兼任は仙北郡山本から津軽郡へ進軍すると、この地を守っていた宇佐美平次実政ほか大見平次家秀、石岡三郎友景以下の御家人ならびに頼朝雑色沢安らを討ち取り、橘次公成を放逐した。彼らは頼朝挙兵から従う最古参の重鎮であり、彼らの討死は事の重大さを物語り、文治6(1190)年正月6日、葛西三郎清重をはじめとする奥羽在国の御家人らは事の次第をしたためて各々飛脚を鎌倉へ飛ばしている(『吾妻鏡』文治六年正月六日条)。
そして、文治6(1190)年正月8日、頼朝は奥羽再派兵を決定し、海道大将軍は千葉介常胤、山道大将軍は比企藤四郎能員がこれを拝命している(『吾妻鏡』文治六年正月八日条)。ただし、東海道岩崎の海道平氏らは常胤の到着を待たずに進発する旨を伝えてきており、この常胤と比企藤四郎による進軍計画はすでに工藤行光ら先遣隊の出立時には決定していたのだろう。そのほか、小山七郎朝光ら奥州に所領を請けた御家人は一族等が同道して進軍するのではなく、各々が個々に急ぎ下向するよう指示している。大河兼任の叛乱を早々に鎮圧しなければ権威の失墜に繋がりかねないことや、奥州に遺している葛西三郎清重已下の救援を行う必要のためなど、早急に動く必要があったと考えられる。
正月13日、上野国、信濃国などの御家人に奥州出兵を指示。上総介義兼を追討使に任じて奥州へ向かわせた(『吾妻鏡』文治六年正月十三日条)。義兼が今回の奥州出兵の総大将ということであろう。今回の進軍も「是於三方、依可遂合戦」(『吾妻鏡』文治六年二月五日条)であることから、義兼は前回の頼朝と同様に奥大道を進んだとみられる。一方で、五日前の決定では千葉介常胤が海道大将軍と定められていたものが、一転して「千葉新介胤正承一方大将軍」とされている。七十三歳の常胤を厳冬の奥州へ出兵させることを断念した頼朝が胤正に替えた、または常胤自身の健康問題なのかもしれない。ただ、信濃国の小諸太郎光兼は「已老耄之上、病痾纏身之由」を聞いていたが、頼朝は「依為殊勇士、今度重被差遣奥州」(『吾妻鏡』文治六年正月廿二日条)と指示している。挙兵以来の重鎮常胤と義仲麾下から御家人となった光兼はその扱いが異なっていたとも考えられるが、老体を押して合戦に臨んでいた光兼自身の勇敢な姿を頼朝が認め、その影響力を期待していた可能性が高いだろう。
胤正は治承四年の上総国伊北庄合戦で葛西三郎清重を同伴してその戦いぶりを目に留めており、奥州出兵に当たり、頼朝に「葛西三郎清重者殊勇士也、先年上総国合戦之時、相共遂合戦、今度又可相具之由欲被仰含」と依頼しており、頼朝はこれを認めて「可相伴于胤正之旨、被下御書於清重」と清重に胤正との同道を指示する下知状を遣わした(『吾妻鏡』文治六年正月十三日条)。
正月15日、頼朝は常胤嫡孫「千葉小太郎」が今回の奥州合戦の働きぶりを賞して感状が遣わされたが、そこには「但合戦不進于先登兮、可愼身」という戒めも記された。頼朝はこの日二所詣に出ており、小太郎成胤は頼朝近習として供奉していたとみられ、今回の奥州合戦には出陣していなかったのだろう。
2月6日、奥州からの飛脚(正月23日発)が鎌倉へ参着した。いまだ鎌倉からの軍兵が着いておらず、大河兼任の軍勢が雲霞のごとく集まっていることを伝えた。国中の御家人たちは、一旦は兼任の猛威に怖れて、兼任軍に降伏したものの、その真実の志は定めて鎌倉方にあるので、もし帰参した場合には減刑する旨を国中に触れさせたという。この報告の中で、「新留守所、本留守」はともに大河兼任に降伏していたことが見え、本来彼らは誅殺されるべき罪科だが、清重へお預けになり、甲二百領を納める過料とされた。
2月11日、鎌倉勢第三軍として足利上総前司義兼が率いる鎌倉勢は平泉を出立し、泉田(宮城県栗原郡一迫町?)に参着した。ここで義兼は兼任の在所を尋ねると、平泉から一万騎を率いて行軍中であるという。義兼はただちに小山五郎宗政、結城七郎朝光、葛西三郎清重、葛西四郎、小野寺太郎通綱・中条義勝法橋・中条藤次家長ら諸将を率いて泉田を出立した。しかし夜になってしまったため一迫に行くことができず、途中の民家に分宿した。その間に、兼任の軍勢は一迫を馳せ過ぎた。翌2月12日、義兼軍に千葉新介胤正の軍勢が加わり、一迫にて激戦が繰り広げられた。
戦いは鎌倉勢の勝利に終わり、大河勢は散り散りなり、兼任は五百騎を率いて平泉衣川を渡って陣を敷いた。奥六郡の入口・衣川関は北上川に囲まれ、切り立った崖の上にある天然の要害で、南からの攻撃には抜群の守備能力を持った天然の要害であった。しかし、鎌倉勢の大軍は衣川を渡り、大河勢を壊走させた。千葉新介胤正・葛西三郎清重・堀藤次親家はさっそく飛脚を発し、2月23日に飛脚が鎌倉に着した。
大河兼任は壊走ののち、ひとり山中に逃れていたが、華山(栗原郡花山村)、千福、山本を経て、亀山を越えて栗原寺に出た。しかし、そこにいた樵夫が、兼任の錦の脛巾、黄金作の太刀を見て怪しみ、仲間数十人とともに彼を囲み、手にした斧で兼任を殺害した。時に3月10日。樵夫たちは鎌倉勢の大将・千葉新介胤正に首を差し出し、大河の乱は平定された。
3月15日、先に解任された「留守所」の後継として、新たに伊澤左近将監家景が「留守職」に任命された。留守職は「被定住彼国、聞民庶之愁訴、可申達」とあるように、民事・行政官としての職である。彼の子孫が留守氏として発展していく。
9月15日、来月に控えた頼朝の上洛に伴なう諸事の奉行のうち、御宿の奉行に「葛西三郎清重」が任じられた。
建久2(1191)年8月15日、鶴岡八幡宮の放生会が行われたが、この時「葛西三郎」は鴾毛の馬を一疋奉納している。清重はこののち、兵衛尉へ任官しており、建久3(1192)年11月25日の永福寺供養の供奉人に「葛西兵衛尉清重」が見える。これが清重が「兵衛尉」を称している初出である。
建久4(1193)年3月21日、頼朝は下野国那須野、信濃国三原などの狩倉を覧るために鎌倉を出発した。この旅の供には狩に慣れ親しんだものを選んでいるが、そのうち日頃から隔心なく交わっている二十二名の御家人にのみ弓箭を帯びることを許した。その二十二人のなかに「葛西兵衛尉」が見える。また、11月27日、永福寺供養に先陣の隨兵として「葛西兵衛尉清重」の名が見える。
建久5(1194)年2月2日、御所において北条義時の嫡男・金剛(のちの泰時)が十三歳にて元服した。この式にに参列した「葛西兵衛尉清重」が見える。
●金剛元服の想像図(幕府西侍配置)
|
|||||||||||||||||||||||
元服式では、祖父の北条時政が金剛の手を引いて西侍にあらわれたのち、頼朝が上座に座り元服式が執り行われた。このとき、脂燭の役を務めたのが、最前に列する武蔵守義信と千葉介常胤であった。元服後は頼朝の一字を賜り「太郎頼時」と改められた。その後の歌舞宴ののち、頼朝は三浦介義澄を傍に召して「この冠者を以て聟と為すべし」と申し含め、義澄は「孫女の中より好婦を撰びて、仰せに随うべし」と返答したという。こののち、頼時に嫁いだ娘(三浦義村娘)がのちの矢部禅尼で、北条時頼の祖母になる女性である。
北条時政―――北条義時――北条頼時[泰時]
(四郎) (小四郎) (金剛)
∥――――――――北条時氏
∥ (太郎)
三浦介義澄――三浦義村――娘 ∥―――――――北条時頼
(荒次郎) (平六) (矢部禅尼) ∥ (最明寺入道)
∥
安達盛長――安達景盛―――――娘
(藤九郎) (弥九郎) (松下禅尼)
10月22日、「葛西兵衛尉清重」は頼朝に白い大鷹一羽を献上した。無双の逸物と評判で、結城七郎朝光に預けられた。鷹や馬は奥州所産のものが有名であり、献上された鷹もおそらく清重が奥州から取り寄せたものなのだろう。
12月26日、永福寺内に新たに建立された薬師堂供養の際、将軍・頼朝の隨兵八騎に「葛西兵衛尉清重」の名が見える。
建久6(1195)年2月2日、頼朝は2月14日の上洛行の路地の沙汰を命じ、2月14日、畠山重忠を先陣に鎌倉を発した。今回の上洛は東大寺供養への参列が目的であった。3月4日、上洛を果たした頼朝は、六波羅邸に入御した。そして五日後の3月9日、奈良東大寺へ向けて出発した。このときの隨兵先陣六騎のうちに「葛西兵衛尉清重」の名が見える。翌日、奈良南東院へ到着。ここで参列にあたって再編が行われ、頼朝の車の後を固め隨兵中に「葛西兵衛尉」「葛西十郎」が見える。この葛西十郎は、文治5(1189)年に奥州藤原氏との戦いで豊島清元・葛西清重とともに参戦していた葛西十郎と同一人物か。
●建久6(1195)年3月10日『東大寺参詣供奉人交名』(『吾妻鏡』)
|
先陣 ●各々相並ばず |
畠山次郎重忠 | 和田左衛門尉義盛 | |||
|
隨兵 ●三騎相並ぶ |
江戸太郎重長 | 豊嶋兵衛尉 | 岡部小三郎 | 勅使河原三郎有直 | 熊谷又次郎 |
| 大井次郎 | 足立太郎 | 小代八郎 | 浅見太郎 | 河匂七郎 | |
| 品河太郎 | 江戸四郎 | 山口兵衛次郎 | 甘糟野次 | 平子左馬允 | |
| 阿保五郎 | 阿保六郎 | 豊田兵衛尉 | 真壁小六 | 下嶋権守太郎 | |
| 加治小次郎 | 鴨志田十郎 | 鹿嶋六郎 | 片穂五郎 | 中村五郎 | |
| 高麗太郎 | 青木丹五 | 中郡太郎 | 常陸四郎 | 小宮五郎 | |
| 奈良五郎 | 小林次郎 | 太胡太郎 | 渋河太郎 | 佐野七郎 | |
| 三輪寺三郎 | 小林三郎 | 深栖太郎 | 吾妻太郎 | 小野寺太郎 | |
| 浅羽三郎 | 倉賀野三郎 | 那波太郎 | 那波彌五郎 | 園田七郎 | |
| 皆河四郎 | 小串右馬允 | 小室小太郎 | 春日三郎 | 小田切太郎 | |
| 山上太郎 | 瀬下奥太郎 | 禰津次郎 | 中野五郎 | 志津田太郎 | |
| 高田太郎 | 坂田三郎 | 禰津小次郎 | 笠原六郎 | 岩屋太郎 | |
| 中野四郎 | 大河戸太郎 | 下河辺四郎 | 泉八郎 | 佐々木三郎兵衛尉盛綱 | |
| 新田四郎忠常 | 大河戸次郎 | 下河辺藤三 | 宇都宮所 | 海野小太郎幸氏 | |
| 新田六郎親範 | 大河戸三郎 | 伊佐三郎 | 天野右馬允 | 橘右馬次郎 | |
| 大嶋八郎 | 藤澤次郎清親 | 工藤小次郎 | 糟屋藤太兵衛尉 | 臼井六郎 | |
| 中澤兵衛尉 | 望月三郎 | 横溝六郎 | 梶原刑部兵衛尉景定 | 印東四郎 | |
| 牧武者所 | 多胡宗太 | 土肥七郎 | 本間右馬允 | 天羽次郎直胤 | |
| 千葉次郎師常 | 広澤与三 | 梶原刑部丞朝景 | 和田三郎義茂 | 河内五郎 | |
| 千葉六郎大夫胤頼 | 波多野五郎 | 土屋兵衛尉義清 | 和田小次郎 | 曽祢太郎 | |
| 境平次兵衛尉常秀 | 山内刑部丞 | 土肥先次郎 | 佐原太郎 | 里見小太郎義成 | |
| 武田兵衛尉有義 | 佐竹別当 | 関瀬修理亮 | 下河辺庄司行平 | 懐嶋平権守景義入道 | |
| 伊澤五郎信光 | 石河大炊助 | 村上左衛門尉 | 八田右衛門尉朝重 | 江間小四郎義時 | |
| 新田蔵人義兼 | 澤井太郎 | 高梨次郎 | 三浦十郎左衛門尉義連 | 小山七郎朝光 | |
| 御車 | 右近衛大将源頼朝 | ||||
| (一門相並ぶ) | 相模守惟義 | 伊豆守義範 | 因幡前司大江広元 | ||
| 源蔵人大夫頼兼 | 源右馬助経業 | 三浦介義澄 | |||
| 上総介義兼 | |||||
| 車後一列 | 豊後前司季光 | 土肥荒次郎 | 山名小太郎 | 那珂中左衛門尉 | 足立左衛門尉遠元 |
| 比企右衛門尉能員 | 藤九郎盛長 | 宮大夫 | 所六郎 | ||
|
車後隨兵 ●三騎相並ぶ |
奈古蔵人 | 南部三郎 | 浅利冠者長義 | 後藤兵衛尉基清 | 稲毛三郎重成 |
| 徳河三郎 | 村山七郎 | 加々美次郎長清 | 葛西兵衛尉 | 梶原源太左衛門尉 | |
| 毛呂太郎 | 毛利三郎 | 加々美三郎 | 比企藤次 | 加藤太 | |
| 阿曽沼小次郎 | 小山五郎宗政 | 小山田四郎 | 波多野小次郎 | 河村三郎 | |
| 佐貫四郎広綱 | 三浦平六兵衛尉 | 野三刑部丞成綱 | 波多野三郎 | 原宗三郎 | |
| 足利五郎 | 佐々木左衛門尉定綱 | 佐々木中務丞経高 | 沼田太郎 | 原四郎 | |
| 長江四郎明義 | 中山五郎 | 岡崎四郎 | 小山田五郎 | 野瀬判官代 | |
| 岡崎与一太郎 | 渋谷四郎 | 和田五郎 | 中山四郎 | 安房判官代 | |
| 梶原三郎兵衛尉 | 葛西十郎 | 加藤次景廉 | 那須太郎 | 伊達次郎 | |
| 岡部小次郎 | 南条次郎 | 江戸七郎 | 横山権守 | 笠原十郎 | |
| 佐野太郎 | 曽我小太郎 | 大井平三次郎 | 相模小山四郎 | 堀藤次 | |
| 吉香小次郎 | 二宮小太郎 | 岡部右馬允 | 猿渡藤三郎 | 大野藤八 | |
| 井伊介 | 吉良五郎 | 金子十郎家忠 | 安西三郎景益 | 小栗次郎 | |
| 横地太郎 | 浅羽庄司三郎 | 志村三郎 | 平佐古太郎 | 渋谷次郎高重 | |
| 勝田玄番助 | 新野太郎 | 中禅寺奥次 | 吉見次郎 | 武藤小次郎 | |
| 天野藤内遠景 | 長尾五郎 | 筑井八郎 | 八田兵衛尉 | 宗左衛門尉 | |
| 宇佐美三郎祐茂 | 多々良七郎 | 臼井与一 | 長門江七 | 金持次郎 | |
| 海老名兵衛尉 | 馬場次郎 | 戸崎右馬允 | 中村兵衛尉 | 奴加田太郎 | |
| 大友左近将監 | 渋谷弥五郎 | 猪俣平六範綱 | 仙波太郎 | 古郡次郎 | |
| 中条右馬允 | 佐々木五郎義清 | 庄太郎 | 岡部六弥太忠澄 | 都築平太 | |
| 伊澤左近将監 | 岡村太郎 | 四方田太郎 | 鴛三郎 | 筥田太郎 | |
| 熊谷小次郎直家 | 平山右衛門尉 | 諸岡次郎 | 伊東三郎 | 千葉四郎胤信 | |
| 志賀七郎 | 藤田小三郎 | 中条平六 | 天野六郎 | 千葉五郎胤通 | |
| 加世次郎 | 大屋中三 | 井田次郎 | 工藤三郎 | 梶原平次左衛門尉景高 | |
| 後陣 ●各々相並ばず ●郎従数百騎 |
梶原平三景時 | 千葉新介胤正 | |||
| 最末(相並ぶ) | 前掃部頭中原親能 | 縫殿助 | |||
| 伊賀前司 | 遠江権守 | ||||
| 最末(並ばず) | 源民部大夫 | 伏見民部大夫 | 右京進中原仲業 | 三善隼人佐康清 | 三善兵衛尉 |
| 平民部丞盛時 | 越後守義資 | ||||
9月3日、平泉の寺塔の修理を「葛西兵衛尉清重並伊澤左近将監家景」が命じられた。戦いによって荒廃した平泉の寺社は、もともと戦いには関係なく、もとのごとく戻すようにとの命であった。さらに9月29日には、故藤原秀衡入道の後家がいまだ平泉に生きており、頼朝は「葛西兵衛尉清重、伊澤左近将監」に彼女を手厚く保護するよう命じた。両人は「奥州惣奉行」であるが故であったという。おそらくこのころ清重は奥州へ赴任していたのだろう。
建久8(1197)年3月23日、頼朝が信濃国善光寺へ参詣した際に後陣の隨兵として「葛西兵衛尉」の名が見える(『相良家文書』:「大日本古文書 家わけ五」)。
●『右大将家善光寺御参隨兵日記』(『相良家文書』:「大日本古文書 家わけ五」所収)
|
(前略) 隨兵 先陣 佐原十郎左衛門尉(佐原義連) 長江四郎(長江明義) 千葉次郎(相馬師常) 和田次郎(和田義茂) 武田兵衛尉(武田有義) 平井四郎 (中略) 後陣 千葉新介(千葉胤正) 葛西兵衛尉(葛西清重) 北条五郎(北条時連、のち時房)佐々木五郎(佐々木義清) 千葉平次兵衛尉(千葉常秀) 梶原刑部兵衛尉(梶原景定) 八田太郎左衛門尉(八田朝重) 江戸太郎(江戸重長) (後略) |
建久10(1199)年10月27日、梶原景時の弾劾状には六十六名の宿老に名を連ね、正治2(1200)年2月26日に頼家の鶴岡八幡宮社参に供奉している。
●梶原景時弾劾状署名宿老六十六名(『吾妻鏡』正治元年十月廿七日条)
| 千葉介常胤 | 三浦介義澄 | 千葉太郎胤正 | 三浦兵衛尉義村 | 畠山次郎重忠 | 小山左衛門尉朝政 |
| 小山七郎朝光 | 足立左衛門尉遠元 | 和田左衛門尉義盛 | 和田兵衛尉常盛 | 比企右衛門尉能員 | 所右衛門尉朝光 |
| 二階堂民部丞行光 | 葛西兵衛尉清重 | 八田左衛門尉知重 | 波多野小次郎忠綱 | 大井次郎実久 | 若狭兵衛尉忠季 |
| 渋谷次郎高重 | 山内刑部丞経俊 | 宇都宮弥三郎頼綱 | 榛谷四郎重朝 | 九郎盛長入道 | 佐々木三郎兵衛尉盛綱入道 |
| 稲毛三郎重成入道 | 足立藤九郎景盛 | 岡崎四郎義実入道 | 土屋次郎義清 | 東平太重胤 | 土肥先次郎惟光 |
| 河野四郎通信 | 曾我小太郎祐綱 | 二宮四郎 | 長江四郎明義 | 毛呂二郎季綱 | 天野民部丞遠景入道 |
| 工藤小次郎行光 | 右京進中原仲業 | 小山五郎宗政 | 他27名 |
葛西氏の鎌倉における屋敷は、現在でも「葛西ガ谷」と呼ばれ、鎌倉に東側に位置している。おそらく奥州の所領は代官(地頭代)に任せていたのだろう。葛西氏の代官として文書に見える人物に「青戸二郎重茂」「二江入道承信」がいる。「青戸(葛飾区青戸)」「二江(江戸川区二之江町)」はいずれも葛西庄内の地名である事から、葛西庄内の郎従を奥州へ派遣して支配していたと考えられる。ほか、奥州葛西氏の重臣として見える「岩淵氏」についても葛西庄の北方にある「岩淵(北区岩淵)」の在地豪族(下河辺氏流)だったのだろう。実際に葛西氏当主と奥州のかかわりが見られるようになるのは、約半世紀後の「葛西経蓮」からである。
『香取神社造営次第』によれば、建保4(1216)年6月7日に宣旨を受けて香取神社遷宮を十二年にわたって奉行した「葛西伊豆入道定蓮」が見えるが、「定蓮」は葛西清重のことなので、この文書が作成された際に「壱岐入道」と「伊豆入道」が誤記されたと思われる。
建暦3(1213)年8月20日、将軍・実朝が新御所へ移転することとなり、夕刻にいたって大江広元(前大膳大夫)の屋敷より新御所へ移ることとなった。その供奉人として「葛西兵衛尉清重」が見える(『吾妻鏡』建暦三年八月廿日条)。その翌年の建保2(1214)年7月24日、鎌倉大蔵に建立された大慈寺(新御堂)の供養が行われた。供養には栄西が導師として招かれており、盛大なものとなった。このとき将軍に供奉した「葛西兵衛尉清重」が見える(『吾妻鏡』建保二年七月廿四日条)。
清重がいつごろから壱岐守に任官したかはわからないが、建保7(1219)年正月1日の将軍・実朝の鶴岡八幡宮参詣供奉人に「壱岐守清重」の名が見え(『吾妻鏡』建保七年正月一日条)、建保2(1214)年7月24日から建保7(1219)年正月1日までの間に壱岐守に任じられたことがわかる。かつては源氏の一族か血縁に限られた「受領」であったが、頼朝の死後は緩和されていたようだ。
「承久の乱」の際には、「右京兆・前大膳大夫入道覺阿・駿河入道行阿・大夫屬入道善信・隠岐入道行西・壱岐入道・筑後入道・民部大夫行盛・加藤大夫判官入道覺蓮・小山左衛門尉朝政・宇都宮入道蓮生・隠岐左衛門入道行阿・善隼人入道善清・大井入道・中條右衛門尉家長」ら「宿老」は上洛は免除された。「壱岐入道」が清重である。各々鎌倉に留まり、勝利の祈祷や軍勢を遣わしたという(『吾妻鏡』承久三年五月二十二日条)。
承久4(1222)年5月24日、幕府は天地災変の御祭を行っているが、祭料を「壱岐入道定蓮」が沙汰している。
貞応3(1224)年閏7月1日、執権職をめぐる北条政子派(北条泰時を推す)と伊賀氏・三浦義村(北条政村を推す)との確執の中で、政子は泰時邸に義村をはじめ、「壱岐入道(葛西清重)・出羽守(中条家長)・小山判官(小山朝政)・結城左衛門尉(結城朝光)」ら「宿老」を招き、将軍家に忠節を尽くす事を依頼した。
 |
| 伝葛西清重と妻の墓 |
この記事を最後に、清重の名は『吾妻鏡』から見えなくなる。清重の死亡年については、
(1)暦仁元(1238)年9月14日説
(2)嘉承3(1237)年12月5日説
(3)貞応元(1222)年3月14日説
(4)承久3(1221)年8月25日説
の四説があるが、嘉禄3(1227)年の香取大社造営雑掌に「壱岐入道」の名が見えることから、この頃までの生存は確認されるため、嘉承3(1237)年または、暦仁元(1238)年あたりということになるか。
●葛西氏系図1(『桓武平氏諸流系図』:『奥山庄史料集』所収)
次男 号六郎大夫 平■仗 豊島三郎 左衛門尉 四郎
将恒――――武恒―――――経家―――康家――――+―清元―+―有経 +―重元
武蔵権守 | | |
| | 壱岐三郎 | 伯耆守 三郎左衛門
| +―清重――――+―清親――――時清
| | |
| | 笑田四郎 | 六郎左衛門
| +―有元 +―朝清
| | |
| | 豊島五郎 | 七郎左衛門
| +―家員 +―時重
| |
| | 八郎左衛門
| +―清秀
|
| 豊島四郎 兵衛尉
+―俊経――――遠経
|
+―平塚入道
●葛西氏系図2(『米良文書』笠井氏系図)
笠井三郎清重法名道蓮―西三郎―+―三郎太郎■清――――又太郎兵衛―+―孫左衛門平源重
| |
| +―左衛門四郎平安■―――彦三郎清安―――三郎太郎行貞
| |
| +―左衛門五郎重銀
| |
| +―左衛門六郎重行
|
+―小三郎左衛門平光清―+―孫左衛門時清
|
+―孫三郎重景―――孫三郎入道道蓮(西小松別当房)
|
+―左衛門三郎清成
●葛西氏系図3(『米良文書』笠井氏系図)
壱岐守、後出家 嫡子
清重―――――――+―伯耆前司
|
| 二男
+―伊豆守
|
| 三男
+―井澤七郎左衛門尉
|
| 四男 葛西河内守 葛西河内四郎左衛門尉
+―重村――――――――+―友村
|
| 葛西四郎左衛門尉嫡女
+―平氏女
|
| 四郎左衛門尉嫡子 号丸子八郎
+―清友
乾元二年閏四月廿二日 御先達越後律師祐玄 在判
………………………………………………………………………………………………
葛西八郎平清基 在判
弘安三年二月十八日
………………………………………………………………………………………………
葛西伯耆四郎左衛門五郎清氏 在判
藤原氏女
同子息彦五郎重盛 在判
正応五年十一月十三日