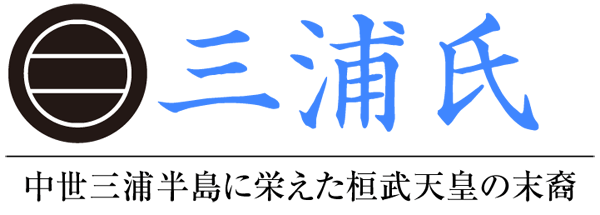
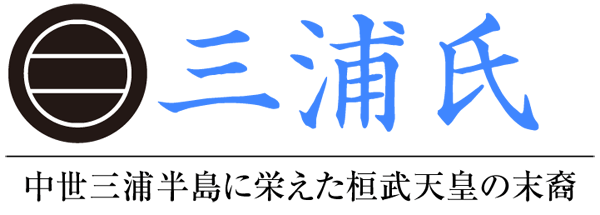
| 平忠通 (????-????) |
三浦為通 (????-????) |
三浦為継 (????-????) |
三浦義継 (????-????) |
三浦介義明 (1092-1180) |
| 杉本義宗 (1126-1164) |
三浦介義澄 (1127-1200) |
三浦義村 (????-1239) |
三浦泰村 (1204-1247) |
三浦介盛時 (????-????) |
| 三浦介頼盛 (????-1290) |
三浦時明 (????-????) |
三浦介時継 (????-1335) |
三浦介高継 (????-1339) |
三浦介高通 (????-????) |
| 三浦介高連 (????-????) |
三浦介高明 (????-????) |
三浦介高信 (????-????) |
三浦介時高 (1416-1494) |
三浦介高行 (????-????) |
| 三浦介高処 (????-????) |
三浦介義同 (????-1516) |
三浦介盛隆 (1561-1584) |
 (1092-1180)
(1092-1180)
三浦氏三代当主。三浦庄司義継の嫡男。母は不詳。妻は秩父荘司重綱娘。通称は三浦大介。相模国検断職。荘官としては三浦庄司。
●三浦氏・秩父氏・上総氏の関係図●
●秩父重綱―+―秩父重隆―――――葛貫能隆―――河越重頼
|(留守所) (葛貫別当) (武蔵国留守所惣検校職)
|
+―秩父重弘―――+―娘
|(秩父荘司) | ∥――――――千葉介胤正
| | 千葉介常胤 (千葉介)
| |(千葉介)
| |
+―娘 +―畠山重能―――畠山重忠
∥ (畠山荘司) (荘司次郎)
∥
∥ 上総常澄―+―上総広常
∥(上総権介)|(上総権介)
∥ |
∥ +―金田頼次
∥ (権大夫)
∥ ∥
三浦義明―――+―娘
(三浦介) |
+―三浦義澄
(荒次郎)
 |
| 大庭御厨と大庭氏館遠景(左の丘) |
天養元(1144)年当時、父・義継(吉次)が「三浦庄司」であり(『天養記』)、義明が三浦氏の惣領となったのはこれ以降となる。天養元(1144)年10月21日、鎌倉または逗子付近に居住していた源義朝(二十二歳)は、「田所目代散位源朝臣頼清并在庁官人及上総曹司源義朝名代清大夫安行、三浦庄司平吉次、男同吉明、中村庄司同宗平、和田太郎同助弘、所従千余騎押入御厨内不輸是非所令停廃也」等を大庭御厨に乱入させて、翌22日に稲を強奪。さらに御厨下司の平景宗の館に乱入して家財を奪い取り、家人を殺害した。御厨の中心となる伊介社(現在の鵠沼神明社)にも乱入して神人を打ち据えて供祭料を強奪している。
●『天養記』
左辨官下、伊勢大神宮司
応且任度度宣旨、停止其妨、備進供祭物、且令国司辨申子細、相模国田所目代源頼清并同義朝郎従散位清原安行、恣巧謀計、以大庭御厨高座郡内鵠沼郷、俄号鎌倉郡内、運取供祭料稲米、旁致濫行事
右、得祭主神祇大副大中臣清親卿、去月十二日解状称、太神宮禰宜等同月日解状称、伊勢恒吉今月七日解状傳、謹撿案內、当御厨者、本自荒野地也、誠無田畠之由、見子国判也、而彼国住人故平景正、相副国判、寄進太神宮御領之刻、永所附属恆吉也、即為御厨令開発、備進供祭上分、漸経年序之間、就在庁官人等之浮言、国司度度令経奏聞之処、被下宣旨、院宣等於本宮、召問子細之後、全無ノ停癈綸旨之上、被問両代宰吏就彼請文殊被下奉免宣旨之日、国祇承庁官散位平高政、同惟家、紀高成、平仲廣、同守景朝臣等、臨地頭任文書堺四至打傍示立劵言上、其四至云、東玉輪庄堺俣野川、南海、西神郷堺、北大牧埼者、其最中高座郡内字鵠沼郷、今俄称鎌倉郡内、寄事於彼目代下知、義朝郎従清大夫安行并字新藤太及庁官等、去年九月上旬之比、致旁濫行、打破伊介神社祝荒木田彦松頭、令及死門、打損訪行神人八人身、踏穢供祭料魚、所苅取郷内大豆小豆等也、訴申其旨之処、本宮解状祭主奏状已畢、而間同十月廿一日、田所目代散位源朝臣頼清并在庁官人及字上総曹司源義朝名代清大夫安行、三浦庄司平吉次、男同吉明、中村庄司同宗平、和田太郎同助弘、所従千余騎、押入御厨内、不論是非、所令停療也、爰承彼等所帯宣旨状之処、更不入御厨之事、只非指官省符新立庄薗本庄之外加納一色別符可入勘之由也、又隣国他堺高家若悪僧等、可停止乱入之状許也、仍為神宮御領尤大悦也、加之、於当御厨者、奉免宣旨有限之由、雖披陳、敢無承引、神人等不及敵対之間、始従同廿二日卯時、在庁官人等押入郷、抜取膀示畢、又御厨作田玖拾伍町苅穎肆万柒佰伍拾束、下司家中私財雑物悉以押取、神人紀恒貞、志摩則貞、国元、末永、重国、兼次等、巻竇令及死門、或所被凌轢也、此外供祭料米農料出挙并甲乙輩私物及有事縁所宿置熊野僧供米等捌佰余斛、負人仕人迯脱之間、不知行方、是非他、義朝与頼清成同意、出立名代之由、御厨定使并浜御薗検校散位藤原朝臣重親、下司平景宗等所言上也、就其状檢案内、於勅免神領者、縦従国衙雖有可令沙汰之事、若申下宣旨、若相具本宮使、令進止之例也、爰当御厨四至内字殿原、香川郷、背宣旨代代国判、令充国役事、度度相触彼目代頼清朝臣之次、上件子細披露已畢、皆有返報、而御厨之事、専不入宣旨状之上可停廃之由、殊無国定云々計也、以高座郡内、今俄称鎌倉郡内、令成濫行之条、依為玄隔之事、為省彼等之所行、惣所令牢籠御厨歟、因茲熟察子細、為致沙汰、先経訴国司之処、於義朝濫行之事者、不能国司進止、至于擬令停廃之事者、尋問在国、可左右之由、依令返報、暫雖相待彼裁許、寄事於左右、敢無其沙汰之間、義朝乱行事、被宣下已畢、雖然停廃事、重不被奏達者、殿原、香川郷其妨不絶歟、就中伐充国役於御厨田、曳成御厨田於宮寺浮免、勘責弥重之間、僅所残住人、又以迯脱之由、下司重言上也、重検案内、以神宮御領号院宮御領被押取之時、従本宮言上子細之日、可停止其妨之旨、被宣下之例、諸国繁多也、而今停止勅免神領、曳成宮寺浮免之条、神事不信不浄之基、何事可過斯哉、又訪先例、刄傷職掌人、殺害神人等、取穢供祭物、奪取神民貯之輩、随罪之軽重、或任法科罪、或所令乱行人致解謝也、而彼等所為、一而不尋常、先以他郡号鎌倉郡内之条、誠矯餝之甚也、各召証文之日、敢無所遁歟、加之、宣旨立券時、祇承官人、皆以見在之輩也、又以庄薗宣旨、巧謀計、令停廃御厨之条、是唯非蔑爾神威、将所違背綸言也、然則於義朝濫行者、任宣下之旨、雖令致沙汰、猥至于抜取牓示者、尤加厳制、懲向後、如本可被令立牓示哉、又所押取供祭上分料獲稲見米并所司住人私物等、悉以可被糺返哉、如此等之所行、早非被糺断者、神威凌遅、諸国狼藉、積習倍増者歟、望請宮庁哉、且重経奏聞、且早牒送留守所、被糺行者、将仰神威之不朽、厳綸言之軽矣者、就解状加覆審、以可入勘庄薗加納之由宣旨、擬令停廃有限勅免神領之條、非蔑爾神威、已違乖綸言者歟、望請祭主裁、重経奏聞、早被糺行者、仍相副言上如件、望請天裁、任禰宜等解状、早被糺行者、権大納言源朝臣雅定宣、奉 勅、宜任度度宣旨、停止其妨、備進供祭物、兼又令国司弁申子細者、同下知彼国既畢、宮司宜承知、依宣行之、
天養二年三月四日
大史中原朝臣(花押)
少辨源朝臣(花押影)
【大略訳】
左弁官から伊勢大神宮の宮司へ下す。
これまでたびたびの宣旨に基づき、源義朝の濫妨を停止させ、供祭物を備え進め、あわせて国司に事情を弁申させ、相模国の田所目代源頼清ならびに源義朝郎従の散位清原安行が勝手に策略をめぐらし、大庭御厨高座郡内鵠沼郷を俄かに「鎌倉郡内」と称し、供祭料の稲米を運び取り、濫暴を働いている事
右の件について、祭主で神祇大副の大中臣清親卿の去月十二日の解状、太神宮禰宜らの同日解状、また伊勢恒吉の今月七日の解状を受け取り、つぶさに案内を調べるに、この御厨はもとは荒れ地であり、まったく田畑がなかったことは国司の判文に見えている。しかるに、かの国住人の故平景正が国判を添えて大神宮に寄進した時から、伊勢恒吉に永代付属させ、ただちに御厨として開発し、供祭の上分を備進してきた。漸次年月を経る間に、在庁官人らの虚言により、国司がたびたび奏聞したところ、宣旨や院宣が本宮に下された。仔細を召し問うた後も、停廃の綸旨はまったくなく、両代の宰吏にその請文を問いただし、勅免の宣旨が下った日には、国祇承庁の官人で散位の平高政、同惟家、紀高成、平仲廣、同守景朝臣らが臨んで、地頭の任文をもって境界の四至を打ち示し、立券して言上した。その四至は、東は玉輪庄の境・俣野川、南は海、西は神郷の境、北は大牧崎である。その最中、義朝は高座郡内鵠沼郷をにわかに鎌倉郡内と称し、件の目代の下知に寄せて、義朝郎従清大夫安行、字新藤太および庁官らが、去年九月上旬のころ、横暴な乱行をなし、伊介神社の祝・荒木田彦松の頭を打ち破って死に至らしめ、訪行の神人八人の身を傷つけ、供祭料の魚を踏み汚し、郷内の大豆・小豆を刈り取ったのである。その旨を訴え申し上げたところ、本宮の解状・祭主の奏状がすでにあった。ところが、同じく十月二十一日、田所目代で散位の源朝臣頼清および在庁官人、さらに字上総曹司源義朝の名代である清大夫安行、三浦庄司平吉、その子同吉明、中村庄司同宗平、和田太郎同助弘らが従者千余騎を率いて御厨内に押し入り、是非を論じることなく停廃させた。そこで彼らの帯びる宣旨状を承ったところ、さらに御厨に入ることはなく、ただ官符や省符に指された新立庄・本庄以外に加納・一色の別符は勘に入るべし、との由であった。また隣国や他境の高家や悪僧らの乱入を停止すべきとの状ばかりであった。よって神宮御領としてはいよいよ大悦であった。しかしながら、この御厨について、勅免の宣旨があるにもかかわらず、披露しても承引せず、神人らは対抗するすべもなく、同月二十二日の卯の刻より、在庁官人らが郷々に押し入り、牓示を抜き取り終え、さらに御厨の作田九十五町、刈穎四万七百五十束、下司や家中の私財雑物をことごとく押し取った。神人の紀恒貞、志摩則貞、国元、末永、重国、兼次らは打ち破られ、死に至らされた者もあり、あるいは凌轢された者もあった。このほか供祭料の米、農料の出挙、また甲乙の輩の私物、および熊野僧の供米八百余斛など、借人・仕人が逃亡したため行方知れずとなった。是非を問うまでもなく、義朝と頼清が成って同意し、名代を立てたというのは、御厨定使および浜御薗検校・散位藤原朝臣重親、下司平景宗らの言上によるものである。その状に基づき検案するに、勅免神領においては、たとえ国衙から沙汰すべき事があっても、もし宣旨が下され、あるいは本宮の使を相具すれば、進止すべき例である。しかるに、この御厨四至の内、殿原、香川郷において、宣旨や国判を背き、国役に充てさせ、たびたび件の目代頼清朝臣に相触れ、上件の仔細を披露し終えても、すべて返報があり、御厨の事は宣旨状に専ら入らず、停廃すべしとの由、殊更国の定めもないことを計った。高座郡内を今にわかに鎌倉郡内と称して濫行をなすのは、まことに隔絶した事である。そこで彼らの所行を省みれば、御厨全体を牢籠すべきか。よってこの仔細を熟察し、沙汰を致すため、先に国司に訴えたところ、義朝の濫行については国司は進止できず、停廃を擬することについては在国を尋問して左右すべしとの由、返報を得た。しばしその裁許を待ち、寄せて事を左右したが、その沙汰なく、義朝の乱行についてはすでに宣下があった。しかるに停廃の事は重ねて奏達されず、殿原・香川郷の妨害は絶えない。とりわけ御厨田に国役を伐ち充て、御厨田を宮寺の浮免に曳成し、勘責はいよいよ重く、わずかに残る住人もまた逃げ去ったと、下司が重ねて言上している。さらに検案するに、神宮御領を院宮御領と号して押し取られた時、本宮から言上があり、妨害を停止すべしとの旨が宣下された先例は諸国に数多ある。しかるに今、勅免神領を停止し、宮寺の浮免に曳成するのは、神事の不信・不浄の基であり、これにまさることはない。さらに先例を訪ねれば、職掌の人を刃傷に及ぼし、神人を殺害し、供祭物を汚し、神民の貯えを奪った輩は、罪の軽重に従い、法科の罪に処せられ、あるいは乱行人をして解謝させた。ところが彼らの所為は、ひとえに尋常ならざるものであり、まず他郡を以て鎌倉郡内と号したのは、まことに矯飾の甚しきことである。各々の証文を召し問う日に、逃れることはあるまい。加えて、宣旨立券の時に祇承した官人は、みな当時現存の輩である。また庄薗宣旨をもって巧みに計略し、御厨を停廃せしめんとするは、これただ神威を蔑ろにし、綸言に違背するものではないか。しかるに義朝の濫行について、宣下の旨に任せて沙汰を致すといえども、猥りに牓示を抜き取るに至ったのは、いよいよ厳しく制し、後を懲らしめ、もとのごとく牓示を立てさせるべきではないか。また押し取った供祭上分料の稲や米、ならびに所司や住人の私物等は、ことごとく糺して返さしめるべきではないか。このような所行を早く糺断しなければ、神威は凌辱され遅れ、諸国の狼藉、積習ますます増大するであろう。宮庁に請うべきである。また重ねて奏聞し、早く留守所に牒送し、糺行されれば、神威の不朽を仰ぎ、綸言の軽んぜられることを防ぐであろう。解状に就き覆審し、庄薗加納に入勘すべき由の宣旨や、勅免神領を停廃すべき条は、神威を蔑ろにし、すでに綸言に違背することではないか。祭主の裁を請い、重ねて奏聞し、早く糺行されることを望む。よって相副えて言上するところは以上のごとし。天裁を請い、禰宜らの解状に任せ、早く糺行されるべきである。
権大納言・源朝臣雅定が宣す。
勅を奉じて曰く、しかるべくはたびたびの宣旨に任せ、妨害を停止し、供祭物を備進すべし。あわせて国司に仔細を弁申させるべし。同じく彼の国に下知すること既に畢んぬ。宮司はよく承知すべし。宣旨に依ってこれを行え。
義明は父の「三浦庄司平吉次」とともにこの濫妨に加わっていることがうかがえる。当時義明はすでに五十二歳(『吾妻鏡』治承四年八月二十七日条より逆算)であり、父の「三浦庄司平吉次」はすでに七十を超えていたと考えられる。「中村庄司同宗平」は五十年後の建久5(1194)年12月15日当時も生存しており(『吾妻鏡』建久五年十二月十五日条)、天養元(1144)年時点ではまだ二十代であろう。なお、義朝には「故左典厩御乳母字摩摩局、自相模国早河庄参上相具淳酒、献御前年歯已九十二」(『吾妻鏡』建久三年二月五日条)という乳母(摩摩局)がいたが、その居住から考えて中村党の女性と考えられる。康和3(1101)年生まれの彼女は、義朝誕生の保安4(1123)年当時は二十三歳であり、中村庄司宗平の母の可能性があろう。
●中村氏想像系図
+―女子
| ∥―――――+―土屋義清
| ∥ |(次郎)
| ∥ |
| 岡崎義実 +―佐奈田義忠
|(三郎) (余一)
|
+―中村重平――+―中村景平
|(太郎) |(太郎)
| |
平恒宗 | +―中村盛平
(笠間押領使) | (次郎)
∥ |
∥―――――+―中村宗平――+―土肥実平――――小早川遠平
∥ |(中村庄司) |(次郎) (弥太郎)
∥ | |
摩摩局 +―摩摩 +―土屋宗遠====土屋義清
(源義朝乳母) (源頼朝乳母)|(三郎) (次郎)
|
+―二宮友平
(四郎)
久寿2(1155)年8月16日、「小代ノ岡(東松山市正代)」に居住する鎌倉源太義平は、至近の比企郡大蔵に居住していた叔父・前帯刀先生源義賢とその後援者の秩父重隆(武蔵国留守所惣検校)を攻めて討ち取った。この一報は、8月27日に京都の主君、左大臣頼長のもとに「或人、源義賢、為其兄下野守義朝之子、於武蔵国見殺」(『台記』久寿二年八月廿七日条)へ届けられている。「近日風聞云、去十六日、前帯刀長源義賢与兄子源義平於武蔵国合戦」とも伝えられている(『百錬抄』)。
軍記物『源平盛衰記』の記述ではあるが、このとき重隆の甥・畠山庄司重能が義平軍に加わっていて「悪源太は義賢を討て京上しけるが、畠山庄司重能に云置けるは、駒王をも尋出して必害すべし、生残りては後悪るべし」(『源平盛衰記』)と、義平は上洛するに当たり、畠山重能に「駒王」=「義仲」の殺害を命じたという。義平は重能の祖父で秩父重隆の父である秩父権守重綱のもとで成長し、重綱の妻を乳母として「御母人」と呼んで慕うほどの深い関わりがあり、義朝の上洛に伴ってその代わりに下向してきた叔父の義賢が、にわかに重隆との関わりを強めたため、秩父氏の縁戚であった小代氏の館に住む義平がこれを討ったものであろう。
なお、義平は義明女子を母とする伝も存在するが(『続群書類従』第五輯上)、義平自身が義明はもちろん三浦一族と協力交流を持った形跡はまったくなく、秩父権守重綱のもとその妻女(有道三郎別当経行女子)を乳母(「御母人」「乳母御前」)として育っている事実を鑑みれば、三浦氏との血縁関係は想定しづらく、義平母は『尊卑分脈』等が伝える橋本遊女であろう。
また、畠山重能の妻も三浦義明女子とされるが、重能の前妻は同族の江戸四郎重継女子(『児玉系図』:石井進『鎌倉武士の実像』平凡社)であり、長男の庄司太郎重光、庄司次郎重忠、蓬莱三郎経重(『小代宗妙置文』には「母江戸四郎平重継女也、経重者畠山庄司次郎重忠一腹舎兄也」とあるが、経重は三郎のため重忠舎弟と思われる)が生まれている。重忠自身に三浦氏との血縁関係はないが、重能が後妻として義明女子を迎えた可能性は否定できない。その時期については、重忠の生年が長寛2(1164)年であることから、少なくともこれより二年以上後となる(弟に三郎経重がいるため)。
●兒玉党系譜(『小代宗妙置文』)
有道遠峯―+―兒玉弘行――兒玉家行
(有貫主) |(有大夫) (武蔵権守)
|
+―有道経行――女子 秩父権守号重綱(室)也 彼重綱者高望王五男村岡五郎義文五代後胤
(有三別当)(号乳母御前) 秩父十郎平武綱嫡男也、
秩父権守平重綱為養子令相継秩父郡間改有道姓移テ平姓、以来於行重子孫稟平姓者也、
母秩父十郎平武綱女也
下総権守 秩父平武者 武者太郎 蓬莱三郎 母江戸四郎平重継女也、
行重 行弘 行俊 経重 経重者畠山庄司次郎重忠一腹舎兄也、
義明は娘を前述の畠山庄司重能のほか、上総平氏の金田小大夫頼次(上総権介常澄の子)、大庭御厨鎌倉党の長江太郎義景に嫁がせており、各氏族との関係を深めている。金田頼次は上総国長柄郡金田保(長生郡長生村金田)の領主であったが、義明の女婿となって三浦郡内に所領(現在の三浦市南下浦町金田)を与えられて移住し、三浦党として活躍する。長江太郎義景もまた三浦郡長江郷(葉山町長柄)へ移住して三浦党の一員となった。また、義明弟の四郎義実は中村党の中村庄司宗平の女婿となって、中村党の一員となり大住郡岡崎郷へ移住している。
義明は前述の通り、天養元(1144)年10月21日の源義朝と田所目代源頼清が結託した大庭御厨乱入に際して、義朝名代の清大夫安行のもと、父「三浦庄司平吉次」とともに同調するなど、義朝との関わりを持っていた。義朝は永治2(1142)年に上野国緑野郡高山御厨の神宮寄進を済ませると、幼い嫡子義平を秩父権守重綱に預けて比企郡を出立し、上総国の上総権介常澄のもとへ移った。上総国には永治2(1142)年中から天養元(1144)年まで滞在しており、「上総曹司源義朝」と称されたようである(『天養記』天養二年三月四日)。その後、義朝は相模国鎌倉へ移り、大庭御厨内の鵠沼郷は鎌倉郡内だとして、天養元(1144)年10月の大庭御厨乱入事件を起こすこととなる。
鎌倉郡は「後冷泉院御宇、伊予守源朝臣頼義奉 勅定、征伐安部貞任之時、有丹祈之旨、康平六年秋八月、潜勧請石清水、建瑞籬於当国由比郷今号之下若宮、永保元年二月、陸奥守同朝臣義家加修復」(『吾妻鏡』治承四年十月十二日条)という河内源氏所縁の地であり、頼義以降、四代にわたる関わりが続いていたと考えられる。特に上総氏は上総権介常澄がおそらく為義の依頼を受けて義朝を庇護し、子の八郎広常は義朝に従って鎌倉に入った際に鎌倉と六浦を結ぶ要地に館を構えたとみられ、関東における義朝の動きを考えれば、上総氏は武蔵秩父氏、相模中村氏、三浦氏と並んで為義、義朝の郎従であったと考えてよいだろう(『吾妻鏡』において御家人が頼義、義家以来の関係を述べることに際し、ことさらに否定する説がみられるが、敢えて否定する必要もないだろう)。
保元元(1156)年7月11日に勃発した保元の乱では、三浦介義明、畠山庄司重能、小山田別当有重はいずれも戦いには参加せずに東国にあったことが『保元物語』に記載されており、三浦介義明は、国衙守護人として相模国府守護のために上洛できなかったのかもしれない。また、 畠山重能・小山田有重は、重隆亡きあとの秩父党の混乱の対応に追われていたのだろう。
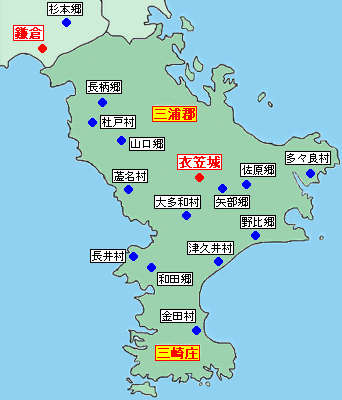
|
| 三浦郡 |
●三浦氏略系図
三浦義継―+―三浦義明――+―杉本義宗―+―和田義盛
(三浦庄司)|(三浦介) |(太郎) |(小太郎)
| | |
+―津久井義行 | +―和田義茂
|(次郎) | (小次郎)
| |
+―芦名為清 +―三浦義澄―――三浦義村
|(三郎) |(三浦介) (駿河守)
| |
+―岡崎義実 +―大多和義久
(悪四郎) |(三郎)
|
+―多々良義春
|(四郎)
|
+―長井義季
|(五郎)
|
+―杜戸重連
|(六郎)
|
+―佐原義連
(十郎)
義明の長男・太郎義宗は三浦半島から出て鎌倉郡杉本郷に館を構え、杉本を名字とした。この義宗の長男・小太郎義盛もはじめは杉本城にあって杉本太郎と称していたが、父・義宗が安房国において戦死したのちは弟・小次郎義茂が杉本館に拠り、義盛自身は三浦郡和田に移り住み、和田を称した。和田義盛は頼朝の挙兵以来の重鎮として、叔父の三浦介義澄らとともに活躍し「侍所別当」として大いに権勢を振るった。しかし、鎌倉幕府成立後、北条義時と激しく対立して討死を遂げている。
義宗の三弟・大多和三郎義久は大多和村に、多々良四郎義春は多々良村に、長井五郎義季は長井村に、杜戸六郎重連は杜戸村に、佐原十郎義連は佐原郷にそれぞれ住んで、郷村地を名字とした。さらに、義明の弟・津久井次郎義行は津久井村を、蘆名三郎為清は蘆名村を領し、末弟の岡崎悪四郎義実は相模の内陸部・大住郡岡崎郷をそれぞれ領している。
三浦一族の所領は義明の代に大きくなり、三浦半島全域、相模中央部の大住郡東部一帯、愛甲郡石田郷、国府のある余綾郡大磯郷はじめ二宮庄のほか、安房国平北郡も支配下において、現在の東京湾の入り口である浦賀水道、ほかおそらく国府をのぞむ相模灘周辺の海域も事実上管轄していたのかもしれない。三浦一族が治めていた土地はその多くが海に面しており、三浦氏が海を非常に重要視していたことがわかる。三浦氏が海上交流を盛んにしていたことを裏付けるように、義明の嫡男・杉本太郎義宗は安房国平北郡に所領を有した。
平治元(1159)年に勃発した平治の乱では、次男・荒次郎義澄が義朝に随って上洛して活躍をするが、平清盛の勢に打ち破られた。義澄は近江国で義朝一行と別れており、そのまま三浦へと帰国したと考えられる。平治の乱以降、相模国では三浦氏の力は弱まり、代わって鎌倉党の大庭三郎景親が「相模国守護人」として平家の威勢のもとで相模の豪族たちを支配下に収め、源氏に心を通じていた兄・大庭御厨司景義、豊田次郎景俊や三浦党・中村党などを圧迫していった。
もともと三浦氏は国衙守護人として、国府に隣接する大住郡岡崎に岡崎四郎義実を派遣しており、さらに西相模最大の武士団・波多野一族の大友経家とも縁戚関係をもち、波多野大友氏=三浦氏=岡崎氏=中村党が結びついて西湘に影響力を強めていた。
●波多野・三浦氏・中村氏周辺の関係図●
波多野経範――経秀―――秀遠―――遠義―――+―波多野義通―――波多野義常
(波多野荘司)(民部丞)(刑部丞)(筑後権守)| (右馬允)
|
+―河村秀高――――河村秀清
|
| 中原氏
| ∥――――――中原久経
| ∥ (典膳大夫)
+――娘
| ∥――――――源朝長
| 源義朝 (中宮大夫)
|
+―大友経家
(大友四郎)
∥―――――――娘
三浦義継―+――娘 ∥
(三浦荘司)| ∥
+―三浦義明 +―中原親能===大友能直
|(三浦介) |(掃部頭) (左近将監)
| |
| 藤原光能――+―大江広元
|(上野介) (掃部頭)
|
+―岡崎義実 +―土屋義清
(悪四郎) |(小次郎)
∥ |
∥――――+―佐奈田義忠
中村宗平―+――娘 (与一)
(中村庄司)|
|
+―土肥実平――――土肥遠平
|(二郎) (弥太郎)
|
+―土屋宗遠====土屋義清
(三郎) (小次郎)
しかし、義明も時代の流れには逆らえず、二男の荒次郎義澄が大番役として平家政権の京都に上洛している。このころ下総国の在庁官人・千葉介常胤の六男である六郎胤頼も上洛しており、治承4(1180)年5月におきた以仁王の乱では、胤頼とともに平家の命によって大番役の延長を命じられている。そして以仁王・源頼政が宇治で討たれると、彼らはようやく役を解かれて5月中旬に帰国が許された。義澄・胤頼二人はその帰途、6月27日に伊豆国田方郡蛭島の頼朝のもとを訪ねて、頼朝と「御閑談」におよんでいる。「他人これを聞かず」とあり、義澄・胤頼は京都の状況、挙兵の手はずを打ち合わせていた可能性がある。以仁王・源頼政の打倒平家の挙兵計画は、5月10日、頼政の郎従・下河辺庄司行平(八条院御領下総国下河辺庄司)によってすでに頼朝のもとに届けられている。
●『吾妻鏡』治承四年六月廿七日条
8月17日、頼朝が挙兵すると、義明は二男・荒次郎義澄を大将として一党を召集した。20日に頼朝の軍と合流する手はずであったが、折からの嵐(台風と思われる)によって海が荒れたために出陣できず、22日、ようやく次郎義澄、十郎義連、大多和三郎義久、大多和次郎義成、和田太郎義盛、和田次郎義茂、和田三郎宗実、多々良三郎重春、多々良四郎明宗、津久井次郎義行らが精兵を率いて三浦郡を出発した。ただ、相模国内陸の岡崎村の岡崎四郎義実(三浦介義明弟)は、末子の佐奈多与一義忠とともにいちはやく頼朝のもとに駆けつけている。
頼朝は三浦党本隊の到着が遅れていたため、20日、伊豆・相模の御家人を率いて伊豆から相模国土肥郷に進んで陣を張った。このころすでに、平家方の大庭三郎景親は、伊豆南部の伊東次郎祐親入道(三浦義澄の舅)と連絡をとって頼朝討伐の軍勢を伊豆に向けて出陣しており、23日、三浦勢がようやく土肥郷を望む丸子河(酒匂川)に到着したころには、頼朝勢と景親勢はわずか谷を一つ隔てるだけというほど接近していた。
23日夕刻、義澄は景親に荷担する豪族の家屋に放火。黒々と立ちのぼる煙を見た景親は、三浦一党が近づいてきていることを知り、
として夜戦を決し、暴風が強まる中、石橋山に頼朝勢を襲った。この戦いで佐奈多与一義忠が討死(25歳)している。敗れた頼朝は箱根山中に逃れ、景親は頼朝を追って山中を追跡したが、飯田五郎家義がにわかに景親に対して反乱をおこして頼朝を逃がし、大庭一族の梶原平三景時も頼朝を探し当てたが見ぬ振りをしたため、頼朝は無事に景親の包囲を逃れることに成功し、土肥次郎実平の用意した舟に乗って伊豆の真鶴岬から安房国へと逃れることができた。
一方、24日朝に頼朝の陣に参向しようと丸子川辺に陣を張っていた三浦党だったが、頼朝の敗北を伝え聞くと、義澄はただちに軍勢をまとめて三浦郡へ向かった。その途路、鎌倉の由比ガ浜において、平家に加担する畠山次郎重忠と合戦し、一族の多々良三郎重春、郎従石井五郎が討死を遂げた。しかし、ここに上総権介広常の弟・金田小大夫頼次が七十余騎を率いて三浦勢に加わり、勢いを取り戻した三浦勢は畠山勢に襲い掛かって郎党五十余人を討ち取り、畠山勢は退却した。
|
東木戸 |
三浦次郎義澄、佐原十郎義連 |
|
西木戸 |
和田太郎義盛、金田大夫頼次 |
|
中陣 |
長江太郎義景、大多和三郎義久 |
しかし26日、畠山重忠は秩父党惣領である河越太郎重頼や江戸太郎重長に出兵を要請し、これに応じた河越重頼は武蔵七党の金子氏・村山氏など武蔵の武士団を率いて三浦郡へ侵攻。三浦党の重だった一族は居館・衣笠城の各城門を守備して迎え撃った(『吾妻鏡』治承四年八月廿六日条)。
■『吾妻鏡』治承四年八月廿六日条
寄手は河越重頼の指揮のもと攻め寄せたが、衣笠山の上に建てられていた衣笠城は攻めるに難く、初日の戦いは黄昏時を迎えたため、寄手はいったん軍勢を引いた。一方、守る三浦勢は兵数において劣り、連日の戦いで力も失っており、義澄は「昨由比戦今両日合戦、力疲矢尽、臨半更捨城逃去、欲相具義明」と、父の義明を伴って城から落ちることを勧めた。しかし義明は、
と、義明は城に残り、義澄らには城を脱出して頼朝を捜し求めることを命じた。こうして三浦義澄・和田義盛以下、三浦党は義明の厳命に従い、泣く泣く衣笠城を脱出し、城東の栗浜から安房国へ向けて船出をした。そして一人残った義明は翌朝、小雨の降る中で河越重頼と江戸重長らの勢に討ち取られた。享年八十九歳(『吾妻鏡』治承四年八月廿七日條)。
■『吾妻鏡』治承四年八月廿七日条
ただ、義明の最期については、もう少し生々しいものも伝わっている。平家物語の古体を残していると伝わる『延慶本平家物語』には、義明はひとり城に残ると言ったが、子孫たちは義明の言葉に反して「手輿ニ大介ヲ掻キ乗セテ」、ともに遁れようとした。しかし義明は体が大きく、手輿にも入りきらなかったという。肥満体であったのかもしれない。それでも子たちはなんとか義明を輿に押し乗せると、衣笠城から遁れ出た。
衣笠を脱出した一門の者たちは、久里浜の岬に用意してあった舟に次々に乗り込み、安房国へと船出していった。しかし、巨体の義明を乗せた手輿は動きが遅く、敵が迫り来ると、輿を担いでいた雑色たちは輿を捨てて逃げ出してしまった。このため、義明は側室一人とともに、敵中に取り残される形となってしまった。
敵は、義明を取り囲むと、彼の衣装を剥ぎ取り始めた。義明は、
と叫ぶが、彼ら敵の雑兵たちは聞く耳を持たない。ついには義明の直垂をも奪い取ってしまった。義明は、
と、娘の子・畠山次郎重忠の手にかかって死ぬことを望んだ。しかしその願いすら叶わず、江戸太郎重長が馳せ来て、義明の首を取った。のちに人々は、
と語ったという。
和田義盛や荒次郎義澄らが祖父であり、父である義明を救いたい一心で義明の言葉に反することをしたがために、却って義明の最期を恥で塗りつぶしてしまったという話である。『吾妻鏡』の伝えるものよりも、生々しく事実を伝えているように感じられる。
『吾妻鏡』によれば、建久5(1194)年9月29日、頼朝は、義明の菩提を弔うために衣笠城下の大矢部村に一堂宇を建立し、御霊大明神と名づけた。現在の滿昌寺(横須賀市大矢部1)がこれにあたり、義明の菩提を弔っている。また、鎌倉の材木座にある来迎寺にも義明と多々良重春の墓と伝わる五輪塔が遺されている。
 |
| 来迎寺の伝・三浦義明、多々良重春墓 |
●頼朝の挙兵に従った武士(『吾妻鏡』治承四年八月廿日条)
■:三浦・中村党 ■:鎌倉党 ■:伊豆工藤党 ■:中村党
| 名前 | 所領 | 氏族 | その他 |
| 北条四郎時政 | 伊豆国田方郡北条郷 | 伊豆在庁・北条氏 | 頼朝の舅。幕府初代執権。 |
| 北条三郎宗時 | 〃 | 〃 | 時政の嫡子。石橋山の戦いで伊東祐親の郎党・紀久重に射殺される。 |
| 北条四郎義時 | 〃 | 〃 | 時政の子。北条政子の弟で、のちの鎌倉幕府2代執権。 |
| 北条平六時定 | 〃 | 〃 | 時政の甥。父は伊豆介時綱。のち、畿内で時政の代官をつとめた。 |
| 藤九郎盛長 | ? | 熱田大宮司家所縁か | 頼朝の乳母・比企尼の聟。頼朝の側近。 |
| 工藤介茂光 | 伊豆国田方郡狩野庄 | 伊豆国工藤党 | 伊豆介。工藤氏の惣領。石橋山の戦いで負傷し、自害する。 |
| 工藤五郎親光 | 〃 | 〃 | 茂光の子。 |
| 宇佐美三郎祐茂 | 伊豆国加茂郡宇佐美庄 | 〃 | 工藤一族。 |
| 土肥次郎実平 | 相模国足下郡土肥郷 | 相模国中村党 | 中村党の惣領。頼朝の近習筆頭として、厚い信任を得る。 |
| 土肥弥太郎遠平 | 〃 | 〃 | 実平の嫡男。小早川氏の祖。 |
| 土屋三郎宗遠 | 相模国大住郡土屋郷 | 〃 | 土肥実平の弟。三浦氏と関わりが深く、岡崎義清を養子に迎える。 |
| 土屋次郎義清 | 〃 | 〃 | 宗遠の養子。父は岡崎義実、母は土肥実平の妹。 |
| 土屋弥次郎忠光 | 〃 | 〃 | 宗遠の子。 |
| 岡崎四郎義実 | 相模国大住郡岡崎郷 | 相模国三浦党 | 三浦義明の末弟。三浦郡ではなく西湘に勢力を築いた。 |
| 佐奈田与一義忠 | 相模国大住郡佐奈田郷 | 〃 | 岡崎義実の末子。頼朝の寵臣で、石橋山で俣野景久に討たれる。 |
| 佐々木太郎定綱 | 佐々木氏 | 佐々木秀義の嫡男。母は宇都宮氏の娘で、下野国宇都宮に住んでいた。 | |
| 佐々木次郎経高 | 〃 | 佐々木秀義の二男。弓の名手。渋谷重国の婿養子となっていた。 | |
| 佐々木三郎盛綱 | 〃 | 佐々木秀義の三男。烏帽子親は安達盛長。 | |
| 佐々木四郎高綱 | 〃 | 佐々木秀義の四男。母は頼朝の叔母。兄達と頼朝の近習を勤めていた。 | |
| 天野藤内遠景 | 伊豆国田方郡天野庄 | 伊豆在庁か。初代の鎮西奉行として九州を治めた。 | |
| 天野六郎政景 | 〃 | 遠景の嫡男。 | |
| 宇佐美平太政光 | 伊豆国加茂郡宇佐美庄 | 桓武平氏 | 宇佐美祐茂とは別流の、桓武平氏の宇佐美氏。 |
| 大見平次実政 | 〃 | 〃 | 宇佐美政光の弟。 |
| 大庭平太景義 | 相模国大庭御厨懐島郷 | 相模国鎌倉党 | 敵の大将・大庭景親の兄。大庭御厨司をつとめる。 |
| 豊田次郎景俊 | 相模国大住郡豊田庄 | 〃 | 大庭景親の兄。父・大庭景宗の墓所・豊田庄の荘官をつとめる。 |
| 仁田四郎忠常 | 伊豆国田方郡仁田郷 | 剛勇で知られた武士で、つねに同郷の北条時政とともに行動する。 | |
| 加藤五景員 | 伊豆国工藤党 | 伊勢宮司・大中臣家家司の家柄。工藤茂光の聟。 | |
| 加藤太光員 | 〃 | 光員の嫡男。 | |
| 加藤次景廉 | 〃 | 景廉の二男。持病を持っていた様子。数々の功績をたて幕府宿老となる。 | |
| 堀藤次親家 | 伊豆国田方郡 | 天野氏と同族か。 | |
| 堀平四郎助政 | 〃 | 〃 | |
| 天野平内光家 | 伊豆国田方郡天野庄 | 天野遠景の一族。 | |
| 中村太郎景平 | 相模国余綾郡中村庄 | 相模国中村党 | 発祥は不明。実平の兄・中村太郎重平の子か? |
| 中村次郎盛平 | 〃 | 〃 | 景平の弟と思われる。 |
| 鮫島四郎宗家 | 駿河国富士郡鮫島郷 | ||
| 七郎武者宣親 | |||
| 大見平次家秀 | 伊豆国加茂郡大見郷 | ||
| 近藤七国平 | 伊豆国 | ||
| 平佐古太郎為重 | 相模国三浦郡平佐古 | 相模国三浦党 | 三浦義明の弟・芦名三郎為清の孫。 |
| 那古谷橘次頼時 | 伊豆国田方郡那古谷郷 | ||
| 澤六郎宗家 | 伊豆国田方郡沢郷 | ||
| 永江蔵人大中臣頼隆 | 頼朝の祈祷師 | 伊勢神宮神官一族。波多野義常の庇護の後、頼朝の祈祷師となる。 | |
| 義勝房成尋 | 頼朝の近臣か。 | 秀郷流藤原氏の小野成任の子。八田知家の娘婿。 | |
| 中四郎惟重 | 〃 | 中原氏か。 | |
| 中八惟平 | 〃 | 惟重の弟か。 | |
| 藤井新藤次俊長 | 〃 | ||
| 小中太光家 | 〃 | 中原光家。 |
●岡崎義実と西湘の豪族
●三浦荘司義継―+―三浦介義明―――三浦介義澄―――三浦義村――+―三浦泰村
|(1092―1180) (1127―1200) (????―1239)|(1184―1247)
| |
+―津久井義行―――矢部為行――+―矢部義郷 +―三浦光村
|(????―????) (????―????)|(????―????) (1205―1247)
| |
+―岡崎義実 +―▲土屋義清 +―二宮義国
(1112―1200)|(????―1213)|(????―????)
∥ | |
∥――――+―佐奈田義忠 +―平塚為高
∥ |(1156―1180) (????―????)
中村宗平―+―娘 |
(中村荘司)| |
+―土肥実平=+―土肥惟平
|(????―1191)(先次郎)
|
+―土屋宗遠===▲土屋義清
(????―????)(小次郎)
●和田義盛と横山氏
●和田義盛―和田常盛
∥ ∥
横山●●―+―娘 +―妹
| |
+―時広―+―時兼
(右馬允・淡路守護職)
●三浦氏の惣領家●
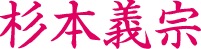 (1126-1164)
(1126-1164)
三浦氏四代惣領。三浦介義明の長男。母は不明。通称は太郎。
 |
| 大倉山杉本寺 |
義宗は三浦半島から鎌倉郡杉本村に進出して館を築き、杉本と号した。いかなる理由で義宗が鎌倉郡内に入り得たかは不明。母は不明ながら杉本に所領を有する家で、譲渡された可能性もあろう。
杉本の地は六浦路が眼前を通り、六浦の良港に向かう道を押さえる要衝であった。義宗が住んでいたとされる杉本館は、この六浦路を望む大倉山杉本寺の背後とされている。
三浦氏の所領は六浦の対岸、安房国平北郡にもあり、領地をめぐって長狭郡の長狭六郎常伴とは対立関係にあったようである。義宗は長寛元(1163)年秋、常伴の居館のある長狭郡金山(鴨川市金山)を攻めるべく、渡海して安房国(おそらく平北郡猟島(鋸南町保田)あたりであろう。)へ上陸を試みたものの、常伴は海岸から矢を射て上陸を阻止し、義宗も負傷して三浦郡に退却。百日満たずして没した。享年三十九。法名は後世とみられるが仏頂院義宗大禅定門(『仏頂山薬王寺位牌』)。これらから、この合戦は常伴が長狭郡から平北郡に侵入したため、義宗が合戦に及んだものと推測される。
■『延慶本平家物語』第二末十二条
■『系図簒要』平氏三・和田義宗項
義宗が没した年、彼の父・義明はすでに七十三歳(『吾妻鏡』治承四年八月廿七日條より逆算)であった。義宗の嫡子の和田小太郎義盛は当時十七歳で、もし義宗が「三浦」氏の家督を継承していたとすれば、義盛がその跡を継いだであろうが、実際には義宗の弟の二郎義澄が三浦氏を継承していた。三浦氏は「義盛、左衛門ト云三浦ノ長者」(『愚管抄』)にもみられるように、三浦一族の中でもっとも官途が高い「長者(棟梁)」であるという認識があったように、三浦の分家ながら、。義宗は一族としての紐帯を保ちつつ、鎌倉杉森へと進出したのだろう。
天養2(1145)年、鎌倉の源義朝は大庭御厨に乱入しているが、この乱入に三浦庄司義継・義明父子が参加しており、このころ三浦氏が鎌倉に勢力をのばしはじめていたのかもしれない。
義宗の嫡男はのち幕府の侍所別当となった和田義盛で、幕府の成立後、三浦党は嫡男=義宗系である和田氏と、家督を継承した二男=義澄系にわかれた。ただし互いに敵対関係になったわけではなく、一族同士の協力関係を保っていた。しかし、建保元(1213)年、和田義盛と北条義時の対立から引き起こされた鎌倉合戦の際には、和田義盛に協力を誓書を提出して約束していた三浦義村(三浦義澄嫡子)が裏切って北条義時のもとに参じた。義村は「近親の訴えを聞いて代々の主に弓引くことはできない」として突然に寝返ったのだが、実際は和田氏と三浦氏の間には嫡宗家をめぐる根深い対立があったのかもしれない。
この和田合戦での功績により、義村は侍所所司五名の一人に選ばれた。だが、結局は大きな勢力を持ちすぎた三浦党は、北条家の餌食となり、義村・泰村の代を最盛期に、急速に衰えていった。
●三浦氏と和田氏の関係図
●三浦義明―+―杉本義宗――和田義盛
(三浦介) |(太郎) (小太郎)
|
+―三浦義澄――三浦義村
(三浦介) (駿河守)