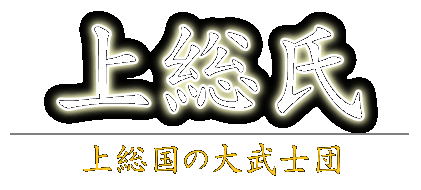
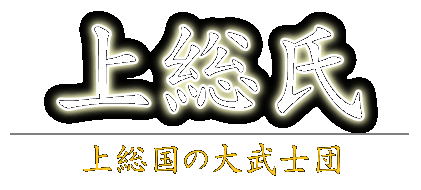
|ページの最初へ|トップページへ|上総氏について|千葉宗家の目次|千葉氏の一族|
| 【一】 | 上総氏について |
| 【二】 | 上総平氏は両総平氏の「惣領」なのか |
| 【三】 | 頼朝の挙兵と上総平氏 |
平常長――+―平常家
(下総権介)|(坂太郎)
|
+―平常兼―――平常重――――千葉介常胤――千葉介胤正―+―千葉介成胤――千葉介時胤
|(下総権介)(下総権介) (下総権介) |
| |
| +―千葉常秀―――千葉秀胤
| (上総介) (上総権介)
|
+―平常晴―――平常澄――+―伊南常景―――伊北常仲
(上総権介)(上総権介)|(上総権介) (伊北庄司)
|
+―印東常茂
|(次郎)
|
+―平広常――――平能常
|(上総権介) (小権介)
|
+―相馬常清―――相馬貞常
(九郎) (上総権介?)
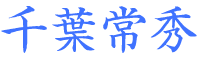 (????~????)
(????~????)
千葉介胤正の次男。母は不明だが建久3(1192)年8月20日時点で健在(『吾妻鏡』建久三年八月廿日条)。通称は平次。官途は兵衛尉、左衛門尉、下総守、上総介。上総守護職。名字は堺(境)。兄は千葉介成胤。
「上総介」ではあるが、上総権介広常の系統とは血縁・養子関係ではなく、広常系統の上総介は、広常が殺された時点で消滅した(ただし、相馬常清の子・相馬貞常が「上総介」を私称した可能性はある)。常秀は広常を継承したというわけではなく、千葉宗家から派生した新たな別家御家人である(六党派生と同様)。
『源平闘諍録』によれば、常秀は頼朝の挙兵時にはすでに「堺平次常秀」(『源平闘諍録』巻第五)として見えるが、『吾妻鏡』で彼の名が初めて見えるのは元暦元(1185)年8月8日の源範頼の麾下の一将「(千葉)平次常秀」(『吾妻鏡』元暦元年八月八日条)である。
常秀は千葉一族中では大きな権威を有した存在であったことは間違いないが、その地位は決して千葉惣領家を凌ぐものではなく、通説で語られる所領についても根拠が薄いものが多い。常秀の官途は平家(奥州)追討による功績を主としたもので、かつ京都に所縁があったことで譲られたものであり、特別なものではない。常秀の京都との繋がりは、「馴京都輩」(『吾妻鏡』建久元年十一月廿九日条)であった父胤正の影響(指示か)と思われる。
また、承久の乱に際しては子息を率いて甥の東海道大将軍千葉介胤綱に従って上洛したとみられ、その後十四年あまり在京し、その最中に「下総守」に任官した。彼らは任官後も在京を続けたとみられる。ただし、そこには千葉惣領家を超越する意図はまったく感じられない。
「堺(境)」の名字地は通説では上総国山辺北郡堺郷(比定地不明。東金市丹尾ともされるが遺称地はない)とされるが、武射北郡堺郷(芝山町境)ともされているが、頼朝挙兵当時の千葉介常胤が支配していたのは千葉庄内のみであって、常胤子息や孫はすべて千葉庄に居住し、所領もまた千葉庄の処々であったと考えられる。
軍記物『源平闘諍録』では治承4(1180)年の頼朝挙兵時から「境平次常秀」と見えるが、『吾妻鏡』の初見となる元暦元(1184)年8月8日条では常秀は「千葉」名字で「堺(境)」は称しておらず、その後も「千葉」を主として用いている。これは千葉介常胤の孫子に共通するもので、いずれも「千葉」名字を主として用い、他名字は余り用いられない。
『吾妻鏡』では治承4(1180)年9月13日条のように、頼朝挙兵当時には東庄を領していない六郎大夫胤頼が「東六郎大夫胤頼」と記されていたり、相馬郡を領していない次郎師常が「号相馬」、大須賀保を領していない四郎胤信が「号大須賀」と記されたりしているように、「未来の情報」が『吾妻鏡』に反映されている。つまり、鎌倉で公的機関による記録が始まる以前の『吾妻鏡』の記述は、氏族伝等を編纂資料に用いた可能性があり、時制的矛盾もそのまま掲載されたのだろう。常胤の孫子は千葉庄内に所領を得ているため、名字地は「千葉」であり、東胤頼も元久元(1204)年冬、京都で「大番の武士、千葉の六郎大夫胤頼」が発心出家、法然給仕の弟子となって「千葉六郎大夫入道法阿」と称した(『法然上人絵巻』)とあるように、晩年においても「千葉胤頼」だったのである。常秀もこの例にもれず千葉名字を用いて主として「千葉常秀」を名乗っており、常秀の名字地も千葉庄内に存在していたと考えることが自然であろう。現在の千葉市内に「(堺)境」の地名はないが、かつて千葉寺町境(千葉市中央区末広)、上総国との国境付近(境川=村田川の付近))などに「境」の字があり、勢力圏外の上総国山辺北郡堺郷や武射北郡堺郷という遠境を領したとは考えられない。
●常秀の称(『吾妻鏡』/特記は『源平闘諍録』『明月記』)
| 治承4(1180)年9月4日 | 堺平次常秀 | 『源平闘諍録』巻第五 | |
| 元暦元(1184)年8月8日 | 境平次常秀 | 参河守範頼に随って西海へ赴いた一人 | |
| 元暦2(1185)年正月26日 | (千葉)平次常秀 | 千葉介常胤、同平次常秀 | |
| 文治元(1185)年10月24日 | 千葉平次常秀 | ||
| 文治2(1186)年5月14日 | 千葉平次常秀 | ||
| 文治2(1186)年11月12日 | 千葉平次常秀 | 若公御参鶴岡八幡宮、被用御輿小山五郎宗政、同七郎朝光、千葉平次常秀、三浦平六義村、梶原三郎景茂、同兵衛尉景定等、供奉還御、 | |
| 在京期間か | (3年間記述なし) | (この時期、他の千葉常胤孫子は『吾妻鏡』に散見) | |
| 文治5(1189)年8月12日 | (千葉)平次常秀 | (奥州出陣)千葉介常胤、八田左衛門尉知家等、参会千葉太郎胤正、同次郎師常、同三郎胤盛、同四郎胤信、同五郎胤通、同六郎大夫胤頼、同小太郎成胤、同平次常秀、…相具于常胤知家、各渡逢隈湊参上云々 | |
| 建久元(1190)年10月3日 | 平次常秀 | 常胤、相具六郎大夫胤頼、平次常秀等、可供奉 | |
| 建久元(1190)年11月7日 | 千葉平次 | ||
| 建久元(1190)年12月2日 | 千葉平次常秀 | 隨兵八人、小山田三郎重成、葛西三郎清重、千葉平次常秀、加藤次景廉、三浦十郎義連、梶原三郎景茂、佐貫四郎廣綱、佐々木左衛門尉定綱 | |
| 建久元(1190)年12月11日 | 左兵衛尉平常秀 | 左兵衛尉平常秀(祖父常胤、勲功賞讓) | |
| 建久2(1191)年正月1日 | 平次兵衛尉常秀 | ||
| 建久3(1192)年7月4日 | 常秀 | 御産間、御調度等今日調進于御産所、三浦介、千葉介等、差義村、常秀令奉行之亦被定 | |
| 建久3(1192)年8月9日 | 千葉平次兵衛尉 | ||
| 建久3(1192)年8月20日 | 千葉兵衛尉 | ||
| 建久4(1193)年正月1日 | 胤秀(成胤、常秀が混同か) | 常胤子息三人、孫子二人引之所謂、師常、胤信、胤道、胤秀等也 | |
| 建久4(1193)年8月16日 | 千葉平次兵衛尉 | ||
| 建久5(1194)年8月8日 | 境兵衛尉常秀 | 相模日向山参詣の随兵 | |
| 建久5(1194)年11月21日 | 境兵衛尉常秀 | 三島社神事(鶴岡の三嶋別宮に参詣)後、前浜で小笠懸 | |
| 建久5(1194)年12月26日 | 境兵衛尉常秀 | 永福寺内新造の薬師堂供養の供奉人 | |
| 建久6(1195)年2月12日 | 千葉平次兵衛尉常秀 | 比企藤四郎右衛門尉能員とともに使節として上洛 | |
| 建久6(1195)年3月10日 | 境平二兵衛尉 | 頼朝の東大寺供養随兵 | |
| 建久6(1195)年3月27日 | 千葉平二兵衛尉常秀 | 頼朝参内の随兵 | |
| 建久6(1195)年5月20日 | 千葉兵衛尉常秀 | 天王寺参詣に至るまでの経緯と随兵交名 | |
| 建久6(1195)年6月3日 | 常秀 | 若公参内の供奉人 | |
| (2年間) | (記述なし) | ||
| 建久8(1197)年3月28日 | 千葉平次兵衛尉 | 建久8年3月28日の「右大将家善光寺御参随兵日記」より(『相良家文書』) | |
| (3年間) | (記述なし) | ||
| 正治2(1200)年2月26日 | 千葉平次兵衛尉常秀 | 頼家の鶴岡八幡宮寺参詣の供奉人 | |
| 建仁3(1203)年10月8日 | 千葉平次兵衛尉常秀 | 実朝元服の儀 | |
| 建仁3(1203)年11月15日 | 千葉兵衛尉 | ||
| 建仁3(1203)年12月14日 | 千葉兵衛尉 | ||
| 元久元(1204)年10月14日 | 千葉平次兵衛尉 | ||
| 元久2(1205)年6月22日 | 堺平次兵衛尉常秀 | ||
| (2年間) | (記述なし) | ||
| 建永2(1207)年3月3日 | 常秀 | ||
| 在京期間か | (5年間記述なし) | ||
| 建暦2(1212)年3月16日 | 堺平次兵衛尉 | ||
| 建暦3(1213)年8月20日 | 堺平次兵衛尉常秀 | ||
| 建暦3(1213)年8月26日 | 堺兵衛尉常秀 | ||
| 在京期間か | (6年間記述なし) | ||
| 建保7(1219)年正月27日 | 堺兵衛尉常秀 | 将軍実朝右大臣拝賀の鶴岡八幡宮寺供奉(実朝暗殺) | |
| 建保7(1219)年7月19日 | 堺兵衛太郎(秀胤) | ||
|
在京期間か |
(6年間) | (記述なし) | 【承久の乱で上洛したのち、兵衛尉として在京か】 |
| 元仁2(1225)年正月24日 | 下総平常秀 | 『明月記』同日除目で「下総(守)」に補任 | |
| (10年間) | (記述なし) | 【在京か】この間に「上総介」に補任か? | |
| 文暦2(1235)年2月9日 | 上総介太郎(秀胤) | 秀胤は常秀の子で小笠懸の射手。 『桓武平氏諸流系図』においては常秀の官途は「下総守」で上総介はない。 『神代本千葉系図』『入来院系図』では常秀は「上総介」とある |
|
| 文暦2(1235)年6月29日 | 上総介常秀 上総介太郎(秀胤) |
将軍頼経の新造御堂の参堂の先陣随兵 同じく車左右列歩 |
|
| 嘉禎2(1236)年8月4日 | 上総介 上総介太郎(秀胤) |
「將軍家、若宮大路新造御所御移徙」の供奉人 | |
| 嘉禎4(1238)年正月1日 | 上総介太郎(秀胤) 同(上総介)次郎(時常) |
埦飯に際し、兄弟で三御馬を曳く | |
| 嘉禎4(1238)年2月17日 | 上総介太郎(秀胤) | 将軍家(頼経)入洛「御所隨兵」の騎乗「五十二番」 | |
| 在京期間か | (1年半記述なし) | 【頼経上洛以降在京か。下記はこの期間に任官】 秀胤:上総権介 時秀:式部丞(京官) 政秀:修理亮(京官) 泰秀:左衛門尉 |
|
| 仁治元(1240)年8月2日 | 上総権介 上総五郎左衛門尉(泰秀) |
将軍家二所御参詣の行列。御駕籠後騎。 ※式部丞時秀、修理亮政秀は在京ママ? |
|
| 仁治2(1241)年正月23日 | 上総権介(秀胤) | ||
| 仁治2(1241)年8月15日 | 上総式部丞時秀 | ||
| 仁治2(1241)年8月25日 | 上総修理亮政秀 | ||
| 仁治2(1241)年11月10日 | 上総権介平秀胤 | 叙爵(『関東評定伝』) | |
| 仁治3(1242)年正月13日 | 上総式部丞時秀 | 『鎌倉年代記裏書』 | |
| 寛元元(1243)年7月17日 | 上総権介(秀胤) 上総式部大夫(時秀) 上総修理亮(政秀) 上総五郎左衛門尉(泰秀) |
臨時御出供奉人 上旬:上総権介、上総式部大夫(すでに叙爵) 中旬:上総修理亮 下旬:上総五郎左衛門尉 |
|
| 寛元元(1243)年閏7月27日 | 上総権介平秀胤 | 従五位上(『関東評定伝』) | |
| 寛元元(1243)年8月16日 | 上総権介(秀胤) | ||
| 寛元元(1243)年9月5日 | 上総権介(秀胤) | ||
| 寛元2(1244)年 | 下総前司常秀男(秀胤) | 『関東評定伝』評定衆。 | |
| 寛元2(1244)年4月21日 | 上総権介(秀胤) | ||
| 寛元2(1244)年6月 | 埴生次郎平時常 | 「埴生神社神輿一基(亡)『地理誌』」 (「三宮埴生神社神輿銘」『千葉県史 金石文』) |
|
| 寛元2(1244)年8月15日 | 上総権介秀胤 上総修理亮政秀 |
||
| 寛元3(1245)年8月15日 | 上総権介秀胤(五位) 上総式部大夫時秀 上総五郎左衛門尉泰秀(五位) 上総六郎秀景 |
鶴岡放生会 先陣随兵:上総式部大夫時秀 御車:上総六郎秀景 御後五位:上総権介秀胤、上総五郎左衛門尉泰秀 |
|
| 寛元3(1245)年8月16日 | 上総介 子息六郎 |
流鏑馬 四番 上総介(上総権介秀胤) 射手、子息六郎(秀景) 的立、内藤肥後前司盛時 |
|
| 寛元3(1245)年10月16日 | 上総権介秀胤 | ||
| 寛元4(1246)年6月7日 | 上総権介秀胤 | ||
| 寛元4(1246)年6月13日 | 上総権介秀胤 | ||
| 宝治元(1247)年6月6日 | 上総権介秀胤 | ||
| 宝治元(1247)年6月7日 | 亡父下総前司常秀 上総権介秀胤 嫡男式部大夫時秀 次男修理亮政秀 三男左衛門尉泰秀 四男六郎景秀 秀胤舎弟下総次郎時常 |
「秀胤舎弟相伝亡父下総前司常秀遺領垣生庄之處、為秀胤被押領」 | |
| 宝治元(1247)年6月22日 | 上総権介秀胤 同子息式部大夫時秀 同修理亮政秀 同五郎左衛門尉泰秀 同六郎秀景 垣生次郎時常 |
||
| 宝治元(1247)年7月14日 | 上総権介(遺跡) | ||
治承4(1180)年9月14日、「下総国千田庄領家判官代親政」が「聞目代被誅之由」いて、「率軍兵欲襲常胤」したことから、「常胤孫子小太郎成胤相戦」って、「遂生虜親政」ったという(『吾妻鏡』治承四年九月十四日条)。その後、9月17日に国府に参会した中に常秀はなく、『吾妻鏡』での常秀の初出は元暦元(1184)年8月8日条の西海範頼勢の交名である。
●『吾妻鏡』治承四年九月十七日条(『吾妻鏡』)
一方、『千学集抜粋』によれば、治承4(1180)年9月4日、安房の頼朝を迎えるため「常胤、胤政父子上総へまゐり給ふ」と、常胤と胤正のみが上総国へと向かったとあり、庶子が従った形跡はない。常秀兄の成胤については、「加曾利冠者成胤たまゝゝ祖母の不幸に値り、父祖とも上総へまゐり給ふといへとも養子たるゆゑ留りて千葉の館にあり、葬送の営みをなされける…程へて成胤も上総へまゐり給ふ…ここに千田判官親政ハ平家への聞えあれハとて、其勢千余騎、千葉の堀込の人なき所へ押寄せて、堀の内へ火を投かけける、成胤曾加野まて馳てふりかへりみるに、火の手上りけれは、まさしく親政かしわさならむ、此儘上総へまゐらむには、佐殿の逃たりなんとおほされんには、父祖の面目にもかゝりなん、いさ引かへせやと返しにける」と、成胤は祖母の葬送のために遅れて父祖の上総国へと向かったが、蘇我野で振り返ると千葉に火の手が上がっており、引き返したとされる。その後、「結城、渋河」で親政の軍勢と出会い、散々戦って「親政大勢こらえ得す落行事二十里、遂に馬の渡りまてそ追打しにける」と、親政を討ち取ったことになっている(『千学集抜粋』)。
『源平闘諍録』では、治承4(1180)年9月4日、頼朝は常胤率いる「新介胤将、次男ハ師常、同田辺田四郎胤信、同国分五郎胤通、同千葉六郎胤頼、同孫堺平次常秀、武石次郎胤重、能光禅師等為始、引率三百余騎之兵ヲ打向下総国」(『源平闘諍録』巻第五)という。このとき、藤原親正は「聞右兵衛佐ノ謀反ヲ吾乍在当国、不射頼朝ヲ者無云甲斐、京都ノ聞モ有恐、且身ノ恥也」(『源平闘諍録』巻第五)と、千田庄内山の館を発して「千葉の結城」へと攻め入ったとする。このとき「加曾利冠者成胤、祖母死去之間、為同孫依為養子、父祖共雖参向上総国、上総国(下総国の誤)千葉館ニ有葬送之営」(『源平闘諍録』)とされ、この説話は前文の『千学集抜粋』にも取り込まれている。
「親正の軍兵、結城の浜に出で来たる由」を聞いた成胤は、上総へ急使を発する一方で「父祖を相ひ待つべけれども、敵を目の前に見て懸け出ださずは、我が身ながら人に非ず、豈勇士の道為らんや」と攻め懸けるも無勢であり、上総と下総の境川まで追われるが、「両国の介の軍兵共、雲霞の如くに馳せ来たりけり」と、千葉介常胤、上総介広常の軍勢が救援に加わったことで「親正無勢たるに依つて、千田の庄次浦の館へ引き退きにけり」と千田庄へと退いたとされる(『源平闘諍録』)。
『千学集抜粋』と『源平闘諍録』はともに妙見説話を取り入れ、成胤を養子とする同一の方向性をもつ内容で、物語性の強い『源平闘諍録』はより詳細に記載されている傾向にある。またいずれも千葉の結城浜を戦いの舞台としていることが共通点に挙げられる。しかしながら、この『千学集抜粋』と『源平闘諍録』はあくまでも説話集と物語であって、そのまま史実と受け取ることはできない。『千学集抜粋』はその妙見信仰と千葉氏を結びつける説話という性格上、まだ妙見信仰が成立していない平安時代末期の千葉氏に、妙見信仰の伝承を挿入する上で『源平闘諍録』の妙見説話を取り込んだ可能性が高く、千葉氏を賞賛する創作がかなり強いと考えられる。
一方、『吾妻鏡』も全体をそのまま史実とするには危険な部分があるものの、後世北条氏にとって頼朝挙兵に伴う千葉氏の活動を改変する必要性は全くないので、これは当時の記録に基づく史実として受け取ってよいと思われる。
親雅は9月13日の成胤・胤頼による下総目代の追捕の翌日、14日に「聞目代被誅之由、率軍兵、欲襲常胤」と常胤の襲撃を企てたとされている。当時の下総国においては国衙は留守所として平家家人の目代が差配し、千田庄(盛子が本家か)の判官代として千田庄に赴任していた平家親類・摂家家人である親雅と連携して支配していたのだろう。目代館はその性質上、国府近辺であることから、目代館から親雅の内山館までは40~50km程であろうと考えられる。目代の使者が千葉勢襲撃の直後に内山館へ向かったとすると、時間にもよるが水行を含めて当日中の到達は可能であろう。しかし、親雅がそこから周辺氏族を動員して匝瑳郡を出立したのでは翌日に西総に至ることは不可能である。おそらく親雅の軍勢催促は頼朝の安房上陸の一報によるもので、親雅の西行は本来は千葉氏追討ではなく頼朝を討つためのもので、上総国府への官道が通る千葉庄へ進んだものと考えられる。
ところが、その進軍の最中に親雅は目代使者から目代館襲撃の一報を受けたのだろう。その頃には目代館はすでに成胤、胤頼によって攻略され、下総国府もまた彼らの手に落ちていたと考えるのが妥当だろう。そして当然ながら成胤と胤頼はいずれか、または両名がそのまま駐屯したと考えられよう。攻め落とした目代館や国府から撤退する合理性がないためである。つまり、『源平闘諍録』が伝えるように成胤は千葉で親雅と戦い、胤頼は父常胤に随って上総へ向かうことは非常に不自然なのである。
さらに常胤ら千葉一族が頼朝を迎えるために本拠を空け、その守備を目代館追討に派遣した成胤を戻して守らせ、あわや親雅に敗れかける(『千学集抜粋』)という不可解極まりない作戦をとっていることになるのである。下総目代を攻めることで旗幟鮮明となれば、当然ながら上総国府、千田判官代親雅という平氏勢力が侵入する可能性も高くなる。このような中で本拠を空にし、頼朝を迎えに行って千葉を取られては本末転倒であり、このような作戦を取ることは通常考えにくい。
これらのことから、常胤らは頼朝の出迎えのために上総国へ向かってはおらず、本拠の千葉に残留し、平氏方の藤原親雅や南隣する上総国府の国ノ兵に予め備えつつ、成胤・胤頼を下総目代追討に派遣して国府一帯(市川市国府台)を占拠する方策を取ったのではないだろうか。
千葉の結城浜での所謂「結城浜の合戦」の伝承は、妙見神を具現化するために妙見神の所縁の地での戦いが染井川の戦いや蚕飼川の戦いのように必要とされ、それが妙見宮前浜である結城浜が選ばれたと思われ、この結城浜の合戦自体は創作である可能性が高いだろう。また、たとえあったとしても、染井川の戦いや蚕飼川の戦いのような、別にあった戦いに拠った創作、または後世の合戦などが仮託されたものではないだろうか。
上総国では「治承四年庚子九月」に高倉院武者所の「平七武者重国高倉院武者所」が討死している(『高山寺明恵上人行状』)。彼は「本姓者伊藤氏、養父ノ姓ニヨテ、藤ヲ改テ平トス」とあるように、伊勢平氏の根本被官伊藤氏の出身者であり、国司・上総介忠清の同族であった。その父は「祖父平七左衛門宗国」(『禅浄房記』「上人之事」山城高山寺所蔵)という。上総介忠清は遙任国司で在京のため、彼が目代であった可能性もあろう。この「治承四年庚子九月」はまさに頼朝が安房国から上総国へ入った月であり、頼朝以下三百騎は上総国府を実際に攻めて占拠したのであろう。安房国から上総国へ入ったのが9月13日であり、上総国から下総国へ入ったのが9月17日であることから、その四日間のいずれかで国府の占拠が行われたと思われる。おそらく頼朝は国府にあって介八郎広常の参着を待ったものの、広常は広範な軍勢催促に手間取ったため、その参着を待たずに頼朝は9月17日に下総国へと移ったのであった。
下総国中西部一帯の平氏党は13日から14日にかけて平氏党はほぼ壊滅しており、頼朝はその日のうちに下総国府へと入り、そこで待っていた常胤は「相具子息太郎胤正、次郎師常号相馬、三郎胤成武石、四郎胤信大須賀、五郎胤道国分、六郎大夫胤頼東、嫡孫小太郎成胤等参会于下総国府、従軍及三百余騎也、常胤先召覧囚人千田判官代親政」と、頼朝との面会を果たし、捕縛していた親雅が頼朝の見参に入れられている。この面会時に常秀の名は見えない。
なお、この親雅の子・功徳院快雅は延暦寺の碩学としてのちの鎌倉とは良好な関係を築き、将軍家御侍僧となり、関東の重要修法に際して下倉している。
その後、京都においては後白河院と結んだ木曾義仲による平家の追い落としが成功し、平家勢は西国へと落ちて行った。ところが木曾勢はその後の政策に失敗し、後白河院や貴族らとの関係が悪化する。さらに平家勢が西国で勢いを盛り返し、備前国水島合戦で木曾勢は大敗を喫した。木曾義仲はすでに叔父の備前守行家と激しい対立を起こしており、後白河院は鎌倉の頼朝に京都の安定を求める望みを求め、義仲に対しては直ちに平家追討のため西国へ下向せよと命じ、事実上京都から追い出す方針を決定したのであった。こうしたことに寿永2(1183)年11月19日早朝、木曾義仲は後白河院の御所・法住寺殿を襲い、院近臣らを捕縛、殺害した(法住寺合戦)。その後、木曾義仲は雌伏していた藤原基房入道を担ぎ出し、「停摂政前内大臣、以権大納言藤原朝臣師家可為摂政藤氏長者」と、基通の摂政停止、藤原基房入道(入道関白)の子・権大納言師家(十二歳)の任内大臣・摂政就任が行われ、同時に藤氏長者も基通から師家へと「相譲」られた(『玉葉』寿永二年十一月廿二日条)。
11月28日、新摂政師家の下文で義仲は八十余箇所の所領を賜る。実際は入道関白基房の沙汰によるものであるが、兼実はこれを「狂乱之世也」と嘆いている(『玉葉』寿永二年十一月廿八日条)。そして翌29日夜、院方に属した人々に対する解官処分が行われることとなる。まさに清盛入道が後白河院に対して起こしたクーデター「治承三年十一月政変」を彷彿とさせる「寿永二年十一月政変」の報復人事であった。ところが、平家との戦いは苦戦が続いており、義仲勢はすでに寡少となっていた。このため、12月2日、播磨国室泊(たつの市御津町)に駐屯していた平家勢に、義仲は「平氏之許、乞和親」という非常手段をとった(『玉葉』寿永二年十二月二日条)。ところが、平家も義仲の内情を見越しており、義仲が乞うた和親についても「平氏不承引」という態度をとった(『玉葉』寿永二年十二月五日条)。義仲にはすでに実戦力はほとんどなく、張り子の虎だった。それだけに義仲は「与平氏和平事、義仲内々雖骨張」と、平家との「和平」に一縷の望みをかけていたのであった。しかし、弱みを見せたくない義仲は表向き「外相示不受之由」していたのであった。
その後の義仲は、和平をタテに平家の要求のままに行動する平家の「捨て駒」となり、12月10日、「可追討頼朝之由、改宣旨被成下院庁下文」と、義仲は頼朝追討の院庁下文を下された。これ以降、義仲は平家追討を止め、頼朝追討へと完全に軸足を移すこととなる。夜には入道関白の沙汰により臨時除目が行われているが、この際みずから左馬頭を辞任している(『吉記』寿永二年十二月十日条)。この左馬頭辞任も不自然であることから、代々平家が担ってきた左馬頭の辞任も平家の要求のひとつであった可能性が高いだろう。そして12月13日、「与義仲和平事一定」となり、「平氏入洛来廿日云々、或又明春」(『玉葉』寿永二年十二月十三日条)という風聞が流れた。
寿永3(1184)年正月4日、兼実は「頼朝今日出門、決定可入洛」(『玉葉』寿永三年正月四日条)との風聞を耳にする。例の如く「虚言歟」と信じていないが、翌正月5日、前源中納言雅頼が兼実邸を訪れ「頼朝之軍兵在墨俣、今月中可入洛之由」(『玉葉』寿永三年正月五日条)を聞く。雅頼の家人である齋院次官親能は、源九郎義経とともに頼朝代官としてすでに近江・伊勢におり、その情報には一定の信憑性があったとみられる。さらに翌正月6日には「坂東武士已越墨俣入美乃了」という情報が齎され、「義仲大懐怖畏」という(『玉葉』寿永三年正月六日条)。
義仲の軍勢はその数を著しく減らし、すでに鎌倉勢を迎え撃つことは不可能であった。ともに京洛の地を守衛した諸源氏勢力の支持を失い、平家との戦いでも消耗していたためである。義仲は頼朝との戦いに勝ち目はないことを悟り、正月11日明方に「奉具法皇、決定可向北陸、公卿多可相具」(『玉葉』寿永三年正月十日条)こととしたのであった。ところが、直前になって北陸下向を停止している(『玉葉』寿永三年正月十一日条)。これは、義仲のもとにいた平家の使者の指示によるものであった。平家側は義仲に「依再三之起請、存和平義之處、猶奉具法皇、可向北陸之由聞之、已為謀叛之儀、然者同意之儀可用意」と通告していたのである。和平の条件のひとつが法皇の身柄引渡しであったと考えられることから、義仲の行動を平家方が強く非難したのであろう。これを受けた義仲は、北陸下向のために院中守護として配置していた兵士らを「第一之郎従字楯」を遣わして召し返した(『玉葉』寿永三年正月十二日条)。平家の脅迫に抗えなかったためである。
正月13日、本来はこの日に平家は入洛の予定であったが、
(1)義仲による院の北陸奉具の風聞
(2)和平成立後の丹波国での敵対行為
(3)十郎蔵人行家の摂津国渡邊での敵対行為
上記の三か条を挙げ、義仲および院を牽制して入洛を拒絶した(『玉葉』寿永三年正月十三日条)。
このほか、義仲は近江国に駐屯する鎌倉勢への対応にも苦慮しており、義仲自身の出陣も「有無之間変々七八度、遂以不下向」と見送られる有様であった。義仲はこれを「是所遣近江之郎従以飛脚」からの情報として「九郎之勢僅千余騎云々、敢不可敵対義仲之勢」であり、併せて院へも「仍忽不可有御下向云々、因之下向延引」という苦しい言い訳をしているが、鎌倉勢の実情を熟知している義仲は、もはや身動きがとれない状況となっていたのであった。
正月16日、「義仲所遣近江国之郎従等、併以帰洛、敵勢及数万、敢不可及敵対之故」(『玉葉』寿永三年正月十六日条)と、近江国に派遣されていた義仲郎従が戦わずして京都へ戻ってきた。その理由は、頼朝勢が大軍であり、もはや敵対できないということであった。「敵勢及数万」は近江国に隠れて展開していた蒲冠者範頼率いる軍勢とみられる。この軍勢には千葉一族としては千葉介常胤、相馬次郎師常、国分五郎胤通、東六郎胤頼が加わっていたとみられるが、常秀は加わっていない。
源九郎義経率いる搦手勢は伊勢国から宇治に入り、宇治に布陣していた義仲方の「大将軍美乃守義広」がこれを迎え撃つも、正月20日、「九郎頼朝舎弟、於宇治合戦等」して大敗を喫した(『歴代皇紀』)。勝ちに乗じた義経勢は「三郎先生義広為義子也、無程被打落事、即九郎先陣懸入京中於六条川原」(『歴代皇紀』)と、義広勢を追ってその勢いのまま大和大路を経て六条川原から京都へとなだれ込んだ。「即東軍等追来、自大和大路入京於九条川原辺者、一切無狼藉最冥加也、不廻踵到六条末了」(『玉葉』寿永三年正月十九日条)とあり、義経勢は鴨川の東側を南北に走る大和大路を北上して、六条大橋から京都に入ったとみられる。
義仲は「独身在京之間、遭此殃」い、急遽参院して法皇に御幸を求め、御輿を寄せて乗せ奉ろうとしたところ、「敵軍已襲来」と、五条御所に義経勢が襲来。もはや法皇を具しての逃亡は無理であると判断。突然の襲来に率いる兵はわずかに三、四十騎あまり。一矢を射ることもできずに逃げ落ちたという(『玉葉』寿永三年正月廿日条)。また、「始義仲聞之、郎等楯行綱雖向戦、無程被打落了」ともあり、側近の楯六郎親忠とともに六条川原へ迎え撃つも敗北した可能性もある(『歴代皇紀』)。
 |
| 義仲寺境内の義仲墓 |
その後、義仲はいったんは丹波国へ逃れんと西の長坂方へ進んだが、思い直して勢多あたりの軍勢と合流しようと東山を越えて近江国へ至った。「義仲向大津手字今井方、雖落加今井、九郎手猶自京追責、終義仲幷今井打取斬首了、大津方東国手蒲冠者、甲斐武田一族也」(『歴代皇紀』)とあり、義仲は近江国大津にいた今井次郎兼平の軍勢との合流を図ったようである。そして、大津のあたりに展開していた頼朝代官・蒲冠者範頼と甲斐武田一族との合戦の末、「阿波津野辺」で合戦となり、討ち取られた(『玉葉』寿永三年正月廿日条)。享年三十一。
また、義仲近臣・根井小弥太行親(楯六郎親忠父)も「義仲為宗郎等根井行親等於京被打了」(『歴代皇紀』)とあるように、京中で討たれたという。樋口次郎兼光は義仲の命を受けて備前守行家追討のために和泉国へ派遣され、行家勢を打ち破って行家を負傷させたうえ、その郎従を多く討ち取っていたが、おそらく宇治田原手の義広壊走の報を受けたのだろう。「二月十日」に京都へ戻り、七條朱雀辺で九郎義経勢と合戦して敗北。鞍馬山へと逃れるが、捕縛された。
義仲郎従の「信乃高梨」も清水寺で捕われて首を落とされ、正月26日、検非違使義経の沙汰で「義仲幷高梨、根井、今井頸四」が大路渡され、兼光は生きたままで曳かれたという(『歴代皇紀』)。なお、兼光が入京した「二月十日」では時系列的に有り得ず、義経勢が入京した「二十日(廿日)」の誤記である。「後日樋口被切首事」(『歴代皇紀』)とあり、2月2日に斬首されて梟首された(『吾妻鏡』寿永三年二月二日条)。樋口兼光は捕縛ののちは渋谷庄司重国に預けられていたが、「武蔵国兒玉輩」と親昵であり、兒玉等の人々は「彼等勲功之賞」の代わりに兼光の助命を九郎義経に嘆願。これを感じた義経も兼光助命を院奏しているが、兼光の罪科は軽からずとして許されず、処刑されるに至った。重国郎従の「平太」が処置を命じられたが、斬り損じるという不始末を犯す。見かねた重国次男・渋谷次郎高重は片手負傷の身ながら、兼光の首を片手切りに打ち落とした(『吾妻鏡』寿永三年二月二日条)。
入京した「東軍一番手」は「九郎軍兵加千波羅平三」であり、義経に付けられていた梶原平三景時である。その後、五条御所のあたりに軍兵が集まり、「法皇及祇候之輩、免虎口」との安堵とともに、「不焼一家、不損一人、独身被梟首了、天之罰逆賊、宣哉」(『玉葉』寿永三年正月廿日条)と兼実は喜びを爆発させる。義仲入京から半年、法住寺合戦で院から実権を奪取してから六十日ということに、兼実は平治の乱を思い起こしていた。
義仲が討たれたことにより、義仲と組んで復権を果たした「入道関白」基房入道は一気にその権勢を失うこととなる。「入道関白」は右少将顕家を二度にわたって法皇のもとに遣わし「上書」するが、法皇は「無答」であった。義仲と結んだことの弁解書であろうが、都合よく利用された法皇の怒りは大きかったのであろう。またこのとき「新摂政(師家)」も顕家の車に同乗して参院していたが「被追帰了」という(『玉葉』寿永三年正月廿日条)。
翌21日、兼実邸を訪れたある「諫人」が「新摂政不可安堵、下官可出馬」(『玉葉』寿永三年正月廿一日条)という。師家の摂政続投を許すべきではなく、兼実が摂政の任に就くべきであると。このときの「諌人」とは前中納言雅頼である。兼実邸を訪れた雅頼卿は、頼朝代官として入洛した「齋院次官親能前明法博士広季子」との話を語っている。親能は主君である前中納言雅頼卿の邸宅を訪問、寄宿するが、このとき「若可被直天下者、右大臣殿可知食世也、無異議」と述べたという。雅頼は「此条可及上奏歟如何」と問うが、親能は「若有尋者可申此旨之由所存也」と答えた。しかし、「無尋者可黙止歟」と聞くと「可進申之由ハ不承」という(『玉葉』寿永三年二月一日条)。兼実はなんとも頼りない親能を「不覚人」と記すが、頼朝が兼実を推していることははっきりし、また雅頼も摂政として名乗りを挙げるよう勧めたのであった。ただ、兼実はこれを喜ぶ様子はない。兼実は「末世之作法進退、有恐天下不棄国之条、雖似有憑政道之治乱、偏可在君之最、我君治天下之間、乱亡不可止、不肖之者、不当委任之仁、恐必有後悔歟、加之、微臣於社稷不惜身命之条、仏天可有知見、然則若有世之運者、天下可棄士、無運者又所不欲一旦之浮栄也」という思いを吐露する。
結局、法皇の意向によって、摂政は「前摂政可還補之由」という。兼実は前摂政基通が「法皇之愛物也」であり、還補は「尤可然、弥下官不能出詞」と強く反発している(『玉葉』寿永三年正月廿一日条)。法皇は「入道関白」に対しては大きな嫌悪感があり、かつて子息の権中納言師家を摂政に据えんと画策したこと、法皇が摂関家領分与を否定する勅言を逆手にとって、師家が摂政・氏長者となった際には基通に僅かな荘園すら譲ることなく独占したこと、そして平家追討に際して西国行幸をしきりに勧めたことなど、数々の恨事を「難忘」(『玉葉』寿永三年二月十一日条)と言って基房入道を排除し、師家の続投も考慮しなかった。
正月22日、法皇は今後のことについて兼実に問うた。まず神器を保持する平家追討について。兼実は神器の安全が謀れるならば追討すべきであるが、頼朝にも諮るべきだという。義仲の首については大路を渡すべきであるとし、頼朝の賞については頼朝の望むもの、頼朝の上洛はすぐに行うべきであるとした。また御所についてはこの旧五条摂政亭から至急移るべきで、八条院御所の他はないと述べている(『玉葉』寿永三年正月廿二日条)。なお、頼朝へは前日21日に使者を派遣しており、2月20日に京都に帰参した使者によれば、「頼朝申云、勧賞事只在上御計、過分事一切非所欲」という(『玉葉』寿永三年三月廿日条)。
一方で、平家方は還都のために指嗾した義仲が、頼朝勢に為す術なく滅ぼされてしまったことで、無条件の還都計画は水泡に帰した。法皇は平家追討を行う意向を示し、兼実邸には観性法橋と藤原範季両名が院使として訪れ「平氏猶可被追討之由被仰下了」ことを伝えた(『玉葉』寿永三年正月廿三日条)。兼実は拙速な平家追討は神器の安全にも関わることであるとして反対の立場を取っていたが、大外記頼業の注進によれば、平家追討の宣旨はすでに前日の22日に下されていたのだった。
寿永3(1184)年正月26日、範頼・義経が率いる平家追討使は出門し、正月29日、蒲冠者範頼と九郎義経は出京。大手の「加羽冠者」(蒲冠者範頼)は浜地から福原を目指し、「九郎」(九郎義経)は搦手として丹波国を経由して福原へ向かう二手からの進軍計画であった(『玉葉』寿永三年正月廿九日条)。なお、「東国九郎、加羽、保田等」が「丹波路、摂津路」の二路に分かれて進軍した(『歴代皇紀』)とあり、実際には範頼、義経に加えて「保田(安田義定)」が独立した勢力として加わっていたことがうかがえる。『吾妻鏡』では安田義定は義経のもと搦手の一人とされており、義経・義定勢が丹波経由の軍勢であったとみられる。
2月1日の報によれば、「向西国追討使等、暫不遂前途、猶逗留大江山辺云々、平氏其勢非尩弱、鎮西少々付了云々、下向之武士、殊不好合戦」(『玉葉』寿永三年二月二日条)とあり、この軍勢は丹波へ向かう義経勢であろう。
なお、平家と安徳天皇は法皇の院宣に従って、正月26日には「解纜遷幸摂州、奏聞事由、為随 院宣行幸近境」と、摂津国福原へ行幸しているが、2月4日に「亡父入道相国之遠忌、為修仏事」を執り行わんとするも、不穏な状況下に「不能下船」であり、福原の南の「輪田海辺」に滞在していたという(『吾妻鏡』寿永三年二月四日条)。
2月5日、蒲冠者範頼、九郎義経の両勢がそれぞれ摂津国に着陣(『吾妻鏡』寿永三年二月五日条)。京都へ発せられた飛脚は翌2月6日に入洛しており、「平氏引退一谷、赴伊南野云々、但其勢二万騎云々、官軍僅二三千騎云々、仍可被加勢之由申上」という(『玉葉』寿永三年二月六日条)。千葉介常胤は蒲冠者範頼の大手勢として加わり、相馬次郎師常・国分五郎胤通・東六郎大夫胤頼を同伴している(『玉葉』寿永三年二月六日条)。
●摂津侵攻の追討使(『玉葉』寿永三年二月六日条)
| 大手軍 【大将】 蒲冠者範頼 ●五万六千余騎 |
小山四郎朝政 | 武田兵衛尉有義 | 板垣三郎兼信 | 下河辺庄司行平 | 長沼五郎宗政 | 千葉介常胤 |
| 佐貫四郎広綱 | 畠山次郎重忠 | 稲毛三郎重成 | 榛谷四郎重朝 | 森五郎行重 | 梶原平三景時 | |
| 梶原源太景季 | 梶原平次景高 | 相馬次郎師常 | 国分五郎胤通 | 東六郎胤頼 | 中條藤次家長 | |
| 海老名太郎 | 小野寺太郎通綱 | 曾我太郎祐信 | 庄三郎忠家 | 庄五郎広方 | 塩谷五郎惟広 | |
| 庄太郎家長 | 秩父武者四郎行綱 | 安保次郎実光 | 中村小三郎時経 | 河原太郎高直 | 河原次郎忠家 | |
| 小代八郎行平 | 久下次郎重光 | |||||
| 搦手軍 【大将】 九郎義経 ●二万余騎 |
遠江守義定 | 大内右衛門尉惟義 | 山名三郎義範 | 齋院次官親能 | 田代冠者信綱 | 大河戸太郎広行 |
| 土肥次郎実平 | 三浦十郎義連 | 糟屋藤太有季 | 平山武者所季重 | 平佐古太郎為重 | 熊谷次郎直実 | |
| 熊谷小次郎直家 | 小河小次郎祐義 | 山田太郎重澄 | 原三郎清益 | 猪俣平六則綱 |
平家は「同三年正二月比、平家悉発西国、軍勢福原以南群居播磨室幷一谷辺」と、すでに正月中に旧都福原周辺に陣所を築いて、福原周辺の守備を固めていたのである。西側の要衝一ノ谷には「為其城重々堀池等」という堅固な陣を構築し、その勢は公称「六万騎」という(『歴代皇紀』)。
こうした状況の中で2月6日に宗盛のもとに届けられた「修理権大夫送書状」によれば、「依可有和平之儀、来八日出京、為御使可下向、奉勅答不帰参之以前、不可有狼藉之由、被仰関東武士等畢、又以此旨、早可令仰含官軍等者」といい、「和平之儀」について、来る8日出京の院使が安徳天皇の勅答を賜って帰京するまでは、戦闘行為を行わないことを関東武士等に順守させるので、平家においても守るよう要請したのである(『吾妻鏡』寿永三年二月廿日条)。
当時の源平の兵力は、権中納言雅頼から兼実への戦況報告の中でも「平氏奉具主上着福原畢、九国未付、四国紀伊国等勢数万云々、来十三日一定可入洛云々、官軍等分手之間、一方僅不過一二千騎云々、天下大事、大略分明」(『玉葉』寿永三年二月四日条)とある通り、追討使の源氏勢が平家勢の十分の一程度のでしかないという悲観的な内容であった。実数は不明だが、平家勢はいまだ九州の兵力が加わっていない状況にあっても追討使より圧倒的な優位に立っていたことは間違いなく、また瀬戸内の制海権も掌握していた中で、追討使が正面から攻撃することは現実的ではなかったであろう。法皇は平家追討使を派遣させた直後に、理由もなく「和平之儀」を持ち出すことは考えにくく、この院宣は法皇による明らかな偽計であろう。
一方、院宣に応じた宗盛は、「相守此仰、官軍等本自無合戦志之上、不及存知、相待院使下向」(『吾妻鏡』寿永三年二月廿日条)と、約定を守り、8日出京という「和平之儀」の院使を待っていたという。ただし、ただ手を拱いていたわけではなく、源氏勢が二手に分かれたことを聞いた平家は、「新三位中将資盛卿、小松少将有盛朝臣、備中守師盛、平内兵衛尉清家、恵美次郎盛方」らを「当国三草山(加東市上三草)」に送り、西から一ノ谷へ向かう九郎義経勢に備えている。義経勢は三草山の東側に布陣して平家勢と対峙し、その距離はおよそ三里程度であった(『吾妻鏡』寿永三年二月五日条)。
●三草山の平家勢
| 新三位中将資盛卿 ●七千余騎 |
小松少将有盛朝臣 | 備中守師盛 | 平内兵衛尉清家 | 恵美次郎盛方 |
その他、平家の人々が福原周辺にどのように在陣していたのかは具体的には不明ながら、「浜地」を福原に向かっていた大手の範頼勢に備えたと思われるのが「本三位中将重衡」「通盛卿、忠度朝臣、経俊」(『吾妻鏡』寿永三年二月十五日条)、西の一ノ谷から山手方面を抑えていたのは「新中納言知盛卿」(『源平盛衰録』)や「経正、師盛、教経」「敦盛、知章、業盛、盛俊」(『吾妻鏡』寿永三年二月五日条)であったろう。
宗盛は院使「修理権大夫」の「不可有狼藉之由」をあくまで守り、「官軍等本自無合戦志」という状況にあったという(『吾妻鏡』寿永三年二月五日条)。ところが、三草山東側に布陣していた義経は「如信綱、実平加評定」と、田代冠者信綱・土肥次郎実平と評定を行うと、2月6日早暁に「襲三品羽林」ってこれを潰走させた(『吾妻鏡』寿永三年二月五日条)。
三草山を破った義経勢は南下して、2月7日未明、一ノ谷の後山(鵯越)まで進んだ。このとき「武蔵国住人熊谷次郎直実、平山武者所季重等」が別動し、早朝に一ノ谷陣の海側から源氏の先陣と高名して攻め寄せたという。これを聞いた平家方の「飛騨三郎左衛門尉景綱、越中次郎兵衛尉盛次、上総五郎兵衛尉忠光、悪七兵衛尉景清等」が二十三騎で木戸口から繰り出して合戦となった(『吾妻鏡』寿永三年二月七日条)。
『歴代皇紀』によれば7日卯剋、まだ夜も明けぬ早朝、源氏勢は「自後山偸入放火」(『歴代皇紀』)したという。『玉葉』においては、参議定能に宛てられた義経と範頼からの合戦子細の報告で「自辰刻至巳刻、猶不及一時、無程被責落了、多田行綱自山方寄、最前被落山手」(『玉葉』寿永三年二月八日条)とあり、多田蔵人大夫行綱が先陣となって山手の平家勢を追い落としたとみられる。搦手は「九郎」「保田」に加えて多田勢の三手に分かれて攻めかかったのだろう。このとき福原へ攻め寄せたのは「東国九郎、加羽、保田等」(『歴代皇紀』)とあるように、「保田」こと安田遠江守義定が九郎義経、蒲冠者範頼と並ぶ源氏の大将のひとりとして認識されており、それは『吾妻鏡』においても義定が範頼、義経とともに大将軍の扱いとして単独で記録されていることからも推測できる。
この攻撃により「大略籠城中之者不残一人」(『玉葉』寿永三年二月八日条)と、一ノ谷の要害は陥落。さらに「但素乗船之人々四五十艘許在島辺云々、而依不可廻得、放火焼死了、疑内府等歟」(『玉葉』寿永三年二月八日条)と、もともと陸陣だけではなく海上の兵船四五十艘ばかりにも人々は乗船し、「島辺」に停泊していたが、一ノ谷の火の手が見えても彼らは「而依不可廻得」と救援に向かうことなく「放火焼死了」という(『玉葉』寿永三年二月八日条)。
また、東側から福原をうかがう大手の蒲冠者範頼勢も攻め寄せ、源平入り乱れての激戦となり、本三位中将重衡は明石浦で「景時、家国」に捕らわれた(『吾妻鏡』寿永三年二月七日条)。また、長く北陸で義仲と戦い続けた越前三位通盛は湊川辺で「源三俊綱」に討ち取られた。なお、俊綱は「近江国住人、佐々木三郎成綱参上、子息俊綱、一谷合戦之時、討取越前三位通盛」(『吾妻鏡』寿永三年二月廿七日条)とあるように、近江佐々木一族であることがわかる。そのほか「薩摩守忠度朝臣、若狭守経俊、武蔵守知章、大夫敦盛、業盛、越中前司盛俊、以上七人」が範頼・義経勢に討ち取られたと報告され、それぞれ「通盛卿、忠度朝臣、経俊」は「蒲冠者討取之」、「経正、師盛、教経」は「遠江守義定討取之」、「敦盛、知章、業盛、盛俊」は「義経討取之」という結果であったという(『吾妻鏡』寿永三年二月七日条)。なお、教経については「被渡之首中、於教経者一定現存」(『玉葉』寿永三年三月十九日条)と、能登守教経は別首であったとする。
そして、戦いは巳時には「平家散々落了、大将軍十人平家族也、交名有利参位中将重衡生取、打取之前帝幷女房等前内大臣等中納言教盛、知盛、参議経盛等乗船逃了、凡所打取上下千三百余人」という源氏勢力の勝利に終わった(『歴代皇紀』)。その戦いは、翌2月8日に参議定能宛の義経報告にも「自辰刻至巳刻、猶不及一時」(『玉葉』寿永三年二月八日条)とある通り、一刻にも満たないほどの短期決戦で終わったことがわかる。なお、福原近辺での合戦の官軍勝報は2月8日未明に兼実家司・式部権少輔範季のもとに「平氏皆悉伐取了」(『玉葉』寿永三年二月八日条)という梶原平三景時からの飛脚が初報である(『玉葉』寿永三年二月八日条)。範季は大手大将軍の蒲冠者範頼の育ての父であり、範頼は軍監である景時を通じて範季に伝えたのであろう。続いて、参議定能からの義経・範頼の報告で合戦子細が伝わっている。義経付属の中原親能が定能女婿・源兼忠の乳母夫であったため、その筋からの通達であろう。また報告では神器の安否は不明だという。
兵力や兵船数において追討使の数倍の勢力を有した平家勢が、わずか一刻の合戦で壊滅するという通常考えられない。これはやはり、宗盛が院宣を順守して敵対行為を停止していた中、「同七日、関東武士等襲来于 叡船之汀」(『吾妻鏡』寿永三年二月五日条)であったが、「依 院宣有限、官軍等不能進出」と、なおも院宣を守って敵対せずに引き退いたものの「彼武士等乗勝襲懸、忽以合戦、多令誅戮上下官軍畢」(『吾妻鏡』寿永三年二月五日条)として、法皇に対し「此條何様候事哉、子細尤不審」と強く批判しているように、法皇の裏切り行為が大きな原因なのだろう。ただし、法皇の愚劣な考えを知り尽くしているであろう宗盛が対応を怠り、攻め寄せる「凶賊」に対し対応できなかった事実は指揮官としては失策である。
2月9日、「源九郎主入洛」(『吾妻鏡』寿永三年二月九日条)し、捕虜の「三位中将重衡」は「土肥二郎実平頼朝郎従為宗者也」(『玉葉』寿永三年二月九日条)の預けとなった。また同時に討ち取られた平家方の人々の首級も齎されたと思われ、法皇はこの首級の扱いについて翌2月10日、「平氏首等、不可被渡旨思食」す院宣を下す(『玉葉』寿永三年二月十日条)。「九郎義経、加羽範頼等」はこの院宣に「被渡義仲首、不被渡平氏首之条、太無其謂、何故被渡平氏哉」と噛み付いたため、法皇は兼実の意見を問うているが、範頼もまた10日までには帰京していることがわかる。
兼実は「論其罪科、与義仲不齋、又為帝外戚等、其身或昇卿相、或為近臣、雖被遂誅伐、被渡首之条、可謂不義」と拒絶し、さらに「神璽宝剣猶在残之賊手、無為帰来之条第一之大事也、若被渡此首者、彼賊等弥令励怨心歟、仍旁不可被渡其首、将軍等只一旦申所存歟、被仰子細之上、何強執申哉、頼朝定不承申此旨歟、此上左右可在勅定者」と意見を述べた。これに左大臣経宗や内大臣忠親らも同調し「各申不可被渡之由」で一決(『玉葉』寿永三年二月十日条)。ただし、平家首級の大路渡については、諸卿の反対意見をよそに法皇は範頼や義経の抗議に強ちに抵抗しても仕方がないとして「仍仰可渡之由了」(『玉葉』寿永三年二月十一日条)となる。
また、三位中将重衡が神器を取り戻すべく、郎従を前内府宗盛のもとに遣わす提案をしている(『玉葉』寿永三年二月十一日条)。多くの一門将士が討たれたのち、平家の生き残る道を模索する重衡の苦悩の表れかもしれない。朝廷はこの提案を容れて、2月15日、重衡郎従の「左衛門尉重国」を使者として派遣している。そして、重衡は尋問の中で「下官可知天下之由、平氏議定之間令申」ということを述べる。これについて、兼実は平家との音信を疑われて覆問され「其条一切不然、只依為傍若無人、当其仁」と弁明している。
2月13日、「平氏首、聚于源九郎主六條室町亭、所謂通盛卿、忠度、経正、教経、敦盛、師盛、知章、経俊、業盛、盛俊等首也」(『吾妻鏡』寿永三年二月十三日条)し、範頼や義経の強請に折れた法皇が許した「平氏首其数十」の大路渡が行われた(『玉葉』寿永三年二月十三日条、『歴代皇紀』)。ただし、法皇は「公卿頭不可被渡」は許さず、範頼・義経等は不満を述べたという。しかし「通盛卿首同被渡了」と、2月21日に従三位となった平通盛卿の首が渡されており、このことを兼実が強く非難している(『玉葉』寿永三年二月十三日条)。おそらく義経以下の東国武士の鬱屈を減じるための法皇の指示であろう。
2月16日、雅頼卿が兼実邸を訪れ、「頼朝四月可上洛」ことを伝えた。これは齋院次官親能からの報告と思われるが、当の親能は「為院御使、下向東国」という。法皇は「頼朝若不上洛者、可有臨幸東国之由」を告げたのだという。兼実は「此事殆物狂、凡不能左右」(『玉葉』寿永三年二月十六日条)と呆れ果てた様子がうかがえる。
そのころ、福原近郊での戦いに敗れた平家は四国へ渡り「平氏帰住讃岐八島」であった。また「其勢三千騎許」であるという。そして「維盛卿、三十艘許相率指南海去了」(『玉葉』寿永三年二月十六日条)と、小松家の平維盛卿はすでに戦列を離脱したという。
寿永3(1184)年2月18日、頼朝は鎌倉から京都へ「洛陽警固以下事」の決定の使者を送っている(『吾妻鏡』寿永三年二月十八日条)。実質義経への指示であろう。そのほか「播磨、美作、備前、備中、備後、已上五ケ国、景時、実平等遣専使、可令守護之由」と、中国地方の五か国は実平と景時の両名を「近国惣追補使」と定め(『吾妻鏡』元暦二年四月廿六日条)、彼らが「専使(眼代であろう)」を遣わして守護することを命じた。ただしこの五か国は頼朝の管国とされたわけではなく、あくまでも平家との関りが深い瀬戸内五か国の守護及び「公田庄園」の保障がその任務である。頼朝は2月19日の宣旨で「諸国七道」における「神社仏寺幷院宮諸司及人領」への狼藉を取り締まることが認められ、「五畿内諸国七道」の国司に対して、治承以降平家が行い、義仲が権柄を握っても改められなかった悪しき慣例の「公田庄園兵糧米」を停止するよう宣旨が下された。ただし、これは国内支配権を確立したものではない。
こののち、兼実邸を訪れた左大弁経房は「諸国兵糧之責幷武士押取他人領事、可停止之由被下宣旨」ことを兼実に伝えているが(『玉葉』寿永三年二月廿二日条)、兼実は数度に渡って宣旨が下されながらも一向に狼藉がなくならないことに「更以不可叶事歟、有法不行、不如無法」(『玉葉』寿永三年二月廿二日条)と嘆いている。これらの宣旨を帯びた勅使は3月9日、鎌倉に到着し(『吾妻鏡』寿永三年三月九日条)、武士による「諸国庄園」の押領を停止し、頼朝にその取り締まりを命じている。頼朝が西国諸国に対する権限を得たのは、文治元年に上洛した「頼朝代官北条丸(北条時政)」が要求した「件北条丸以下郎従等、相分賜五畿山陰山陽南海西海諸国、不論庄公、可宛催兵糧段別五升、非啻兵糧之催、惣以可知行田地」(『玉葉』文治元年十一月廿八日条)というのちのことである。
2月25日、「朝務事、武衛注御所存、條々被遣泰経朝臣之許」(『吾妻鏡』寿永三年二月廿五日条)とある通り、頼朝の使者が高階泰経を訪れ、「朝務事」についての要望をしている。このことは兼実も伝え聞いており、泰経到着の二日後、2月27日に「又以折紙計申朝務」(『玉葉』寿永三年二月廿七日条)と記している。
一 朝務等事
右、守先規、殊可被施徳政候、但諸国受領等尤可有計御沙汰候歟、東国北国両道国々、追討謀叛之間如無土民、自今春浪人等帰往旧里、可令安堵候、然者来秋之比、被任国司、被行吏務可宜候
一 平家追討事
右、畿内近国、号源氏平氏携弓箭之輩幷住人等、任義経之下知可引率之由、可被仰下候、海路雖不輙、殊可急追討之由、所仰義経也、於勲功賞者其後頼朝可計申上候
一 諸社事
我朝者神国也、往古神領無相違、其外今度始又各可被新加歟、就中、去比鹿嶋大明神御上洛之由、風聞出来之後賊徒追討、神戮不空者歟、兼又若有諸破壊顛倒事者、隨功程、可被召付處、功作之後可被御裁許候、恒例神事、守式目、無懈怠可令勤行由、殊可有尋御沙汰候
一 仏寺間事
諸寺諸山御領、如旧恒例之勤不可退転、如近年者、僧家皆好武勇、忘仏法之間、行徳不聞、無用樞候、尤可被禁制候、兼又於濫行不信僧者、不可被用公請候、於自今以後者為頼朝之沙汰、至僧家武具者任法奪取、可与給於追討朝敵官兵之由、所存思給也
頼朝は朝廷の選任事項である国司任命にも言及し、寺社仏寺への介入も示唆するなど、兼実はこの条々について「人以不可為可」と批判しながらも、頼朝の天も恐れぬ要求に対し、「頼朝若有賢哲之性者、天下之滅亡弥増歟」と頼朝が賢哲の器であれば、政治的に暗愚な法皇を操り、朝務を恣に動かすことも可能であることを述べる(『玉葉』寿永三年二月廿七日条)。平家追討に対しては、「畿内近国、号源氏平氏携弓箭之輩幷住人等」は、追討使である義経の下知に随い、急ぎ追討を行うべきことを要求し、さらに「於勲功賞者其後頼朝可計申上候」と、平家追討に対する行賞は頼朝を介して行うことを明言した。
ところが、頼朝の四か条の要求が朝廷に届いた四日後の2月29日、「九郎為追討平氏、来月一日可向西国之由有議、而忽延引」(『玉葉』寿永三年二月廿九日条)ということとなる。延引の理由は定かではないが、日時的には頼朝の2月18日に鎌倉を発した「洛陽警固以下事」の使者が上洛する頃合いであった。四か条の「朝務等事」には「洛陽警固以下事」は含まれていないため、高階泰経に披露された「朝務等事」と「洛陽警固以下事」は別物であり、「朝務等事」の使者が発せられたのちに「洛陽警固以下事」の使者が後追いで送られたのであろう。こののち、約一年に亘って義経は京都警衛を主任務としていることから、頼朝の命による所役の変更とみられる。
なお、同日の2月29日、重衡の遣わした郎従重国が屋島の前内府宗盛からの返書を京都へ齎した。宗盛からの返事には「畏承了、於三ケ宝物幷主上女院八条院殿者、如仰可令入洛、於宗盛ハ不能参入、賜讃岐国可安堵、御共等ハ清宗ヲ可令上洛」(『玉葉』寿永三年二月廿九日、卅日条)とあったとされ、和親を申し述べたという。この和平案が成れば朝廷は神器と安徳天皇を取り戻し、女院(建礼門院)と八条院殿(二位尼)の還京が実現することとなり、兵乱鎮定が実現味を帯びることとなる。
ただし、『吾妻鏡』で宗盛が齎した返事は、2月21日に重国の書状を請け取り、2月23日に書面を認めたことを記し、「主上国母可有還御之由、又以承候畢」(『吾妻鏡』寿永三年二月廿日条)と、法皇からの要請を理解した旨を記した。ただ、宗盛は福原での敗戦について、法皇の卑怯な「奇謀」に対して大きな不満を抱いており、法皇が「若為緩官軍之心、忽以被廻奇謀歟、倩思次第、迷惑恐歎、未散朦霧候也」(『吾妻鏡』寿永三年二月廿日条)と非難し、合戦により「還御亦以延引、毎赴還路武士等奉禦之、此條無術事候也、非難澁還御之儀、差遣武士於西海依被禦、于今遅引、全非公家之懈怠候也」(『吾妻鏡』寿永三年二月廿日条)と、法皇は天皇の還御を求めながら、その都度武士を派遣して妨害するという行為で、結局その還御が遅引しており、これはまったく安徳天皇の懈怠ではないとした。さらに「其後又称 院宣、源氏等下向西海、度々企合戦、此條已依賊徒之襲来、為存上下之身命、一旦相禦候計也、全非公家之発心、敢無其隠也」(『吾妻鏡』寿永三年二月廿日条)と、たびたびの源氏との合戦は、天皇を脅かす「賊徒」の襲来を防いだに過ぎず、合戦はまったく天皇が企てたものではないと強く主張した。そして、「云平家、云源氏、無相互之意趣、平治信頼卿反逆之時、依 院宣追討之間、義朝朝臣依為其縁坐、有自然事、是非私宿意、不及沙汰事也、於 宣旨院宣者非此限、不然之外、凡無相互之宿意、然者、頼朝与平氏合戦之條、一切不思寄事也、公家仙洞和親之儀候者、平氏源氏又弥可有何意趣哉、只可令垂賢察給也」(『吾妻鏡』寿永三年二月廿日条)と、そもそも平氏と源氏にことさら宿意はなく、天皇と法皇の和親が成れば、いよいよ平氏と源氏には何ら意趣はないこととなり、「和平儀可候者、天下安穏、国土静謐、諸人快楽、上下歓娯、就中合戦之間、両方相互殞命之者、不知幾千万、被疵之輩、難記楚筆、罪業之至、無物于取喩、尤可被行善政、被施攘災、此條、定相叶神慮仏意歟」(『吾妻鏡』寿永三年二月廿日条)と和平を推進すべきことを伝え、法皇は「早停合戦之儀、可守攘災之誠候也、云和平、云還御、両條早蒙分明之 院宣、可存知候也、以此等之趣、可然之樣、可令披露給、仍以執啓如件」(『吾妻鏡』寿永三年二月廿日条)と要請したという。
『吾妻鏡』においては、『玉葉』が記すような、宗盛が和平を積極的に受け入れつつ「賜讃岐国可安堵、御共等ハ清宗ヲ可令上洛」ということは記されていないが、穏便に批判を展開している。讃岐国を与えるというものは、法皇が提示しようとした条件なのかもしれない。『吾妻鏡』と『玉葉』に共通する「所詮源平相並可被召仕之由」については、兼実は「此條頼朝不可承諾歟、然者難治事也」と嘆いている。おそらくその後、頼朝へ使者が遣わされ、結果としてこの和平案は実行されることはなかった。兼実の予想通り、頼朝が反発したのであろう。そして平家方も態度を硬化したとみられ、元暦元(1184)年7月6日に左大弁経房が中山忠親に報告したことによれば、九州へ遣わした「院召使」を平家が「被着印於面」する恥辱を与え、さらに同道したと思われる「鎌蔵雑色十余人」については斬首したという(『山槐記』元暦元年七月六日条)。
一方、『源平盛衰記』では、宗盛は「通盛已下当家数輩、於摂津国一谷已被誅畢、何重衡一人可悦寛宥之院宣、抑我君者、受故高倉院之御譲、御在位既四箇年、雖無其御恙、東夷結党責上、北狄成群乱入之間、且任幼帝母后之御歎尤深、且依外戚外舅之愚志不浅、固辞北闕之花台、遷幸西海之薮屋、但再於無旧都之還御者、三種神器争可被放玉体哉」と正統性を主張。法皇に対しては「就中亡父太政大臣、保元平治両度合戦之時、重勅威、軽愚命、是偏奉為君非為身」と批判し、頼朝についても「父左馬頭義朝謀叛之時、頻可誅罰之由、雖被仰下于故入道大相国、慈悲之余所申宥流罪也、爰頼朝已忘昔之高恩、今不顧芳志、忽以流人之身、濫列凶徒之類、愚意之至思慮之讐也、尤招神兵天罰速、期廃跡沈滅者歟」と忘恩の徒と糾弾。「但君不思召忘亡父数度之奉公者、早可有御幸于西国歟、于時臣等奉院宣、忽出蓬屋之新館、再帰花亭之旧都」と、法皇の西国行幸を要請し、その後、安徳天皇を奉じて屋島から還都することを述べている。『源平盛衰記』は宗盛の強硬ぶりが際立っているが、『玉葉』が伝える内容と勘案すると『吾妻鏡』の記述が実際に近く、『源平盛衰記』は宗盛ら平家側の心情を代弁した表記なのではなかろうか。
3月2日、重衡の身柄は土肥次郎実平から梶原平三景時へ移され、京都の宿所へ置かれ(『源平盛衰記』)、3月5日には検非違使義経の手によって「主馬入道盛国父子五人」が捕縛されている(『源平盛衰記』)。そして、3月7日、「板垣三郎兼信、土肥次郎両人」がふたたび西国の抑えのために京都を出立している(『源平盛衰記』)。
3月10日、重衡は「頼朝所申請」により鎌倉へ下向することになる(『玉葉』寿永三年三月十日条)。おそらく範頼率いる大手勢も鎌倉へ下ったとみられる。重衡には「梶原平三景時相具之、是武衛依令申請給也」(『吾妻鏡』寿永三年三月十日条)であった。一行は3月27日に伊豆国府へ到着。当時、頼朝は伊豆国北条にいて国府とは指呼の距離であり、景時に北条へ相具して参るよう命じた(『吾妻鏡』寿永三年三月廿七日条)。
翌28日に北条館で重衡と面会した頼朝は、
「且為奉慰君御憤、且為雪父尸骸之耻、試企石橋合戦以降、令対治平氏之逆乱如指掌、仍及面拝不屑眉目也、此上者謁槐門之事、亦無所疑歟者」
と述べた。頼朝の挙兵は法皇幽閉の御憤を鎮めるとともに、父義朝の恥を雪ぐものであり、平家逆乱を鎮圧することで重衡卿と面会できたのはこの上ない名誉であり、そのうち宗盛卿とも面会できることは疑いないことでしょうと語ると、重衡は、
「源平為天下警衛之處、頃年之間当家独守朝廷之、許昇進者八十余輩、思其繁栄者二十余年也、而今運命之依縮、為囚人参入上者不能左右、携弓馬之者為敵被虜、強非耻辱、早可被處斬罪」
と滔々と述べた(『吾妻鏡』寿永三年三月廿八日条)。その堂々とした受け答えに「聞者莫不感」だったという。その後、狩野介宗茂へ預けられることとなるが、頼朝はちょうど十歳年下の重衡をいたく尊重し、鎌倉に移されたのちは、その無聊を慰めるために謡や今様、管弦などが催されている。なお、『源平盛衰記』では面会の地は鎌倉の御所となっている。
寿永3(1184)年2月18日、頼朝は鎌倉から京都へ「洛陽警固以下事」の決定の使者を送っているが(『吾妻鏡』寿永三年二月十八日条)、義経への指示であろう。そのほか「播磨、美作、備前、備中、備後、已上五ケ国、景時、実平等遣専使、可令守護之由」と、中国地方の五か国は実平と景時の両名を「近国惣追補使」と定め(『吾妻鏡』元暦二年四月廿六日条)、彼らが「専使(眼代であろう)」を遣わして守護することを命じた。ただしこの五か国は頼朝の管国とされたわけではなく、あくまでも平家との関りが深い瀬戸内五か国の守護及び「公田庄園」の保障がその任務である。頼朝は2月19日の宣旨で「諸国七道」における「神社仏寺幷院宮諸司及人領」への狼藉を取り締まることが認められ、「五畿内諸国七道」の国司に対して、治承以降平家が行い、義仲が権柄を握っても改められなかった悪しき慣例の「公田庄園兵糧米」を停止するよう宣旨が下された。ただし、これは国内支配権を確立したものではない。
元暦元(1184)年8月6日、頼朝は「招請参河守、足利蔵人、武田兵衛尉給」い、さらに「常胤已下為宗御家人等依召参入」(『吾妻鏡』元暦元年八月六日条)した。御所では「此輩為追討平家、可赴西海之間、為御餞別」のため「終日有御酒宴」が行われ、帰り際には「各引賜馬一疋」った。とくに「参州分、秘蔵御馬也、剩被副甲一領」(『吾妻鏡』元暦元年八月六日条)という。
8月8日、「参河守範頼、為平家追討使赴西海、午尅進発」し、常秀は祖父・千葉介常胤とともに「扈従輩」に加わった。木曾義仲追討及び一ノ谷合戦の軍勢には常秀は加わらず、叔父三人(相馬師常、国分胤通、東胤頼)が出征していたが、今回の平家追討戦に加わった千葉一族は、千葉介常胤と常秀のみである。父・千葉新介胤正と兄・小太郎成胤は平氏との戦いには一切参戦していないが、祖父・千葉介常胤の指示によるものであろう。
●元暦元(1184)年8月8日、三河守範頼の西海出征に扈従の輩(『吾妻鏡』元暦元年八月八日条)
| 大将軍 | 三河守範頼(紺村濃直垂、小具足、栗毛馬) | |||
| 扈従の輩 | 北条小四郎義時 | 足利蔵人義兼 | 武田兵衛尉有義 | 千葉介常胤 |
| 境平次常秀 | 三浦介義澄 | 三浦平太義村 | 八田四郎武者朝家 | |
| 八田太郎朝重 | 葛西三郎清重 | 長沼五郎宗政 | 結城七郎朝光 | |
| 比企藤内所朝宗 | 比企藤四郎能員 | 阿曽沼四郎広綱 | 和田太郎義盛 | |
| 和田三郎宗実 | 和田四郎義胤 | 大多和次郎義成 | 安西三郎景益 | |
| 安西太郎明景 | 大河戸太郎広行 | 大河戸三郎 | 中条藤次家長 | |
| 工藤一臈祐経 | 工藤三郎祐茂 | 天野藤内遠景 | 小野寺太郎道綱 | |
| 一品房昌寛 | 土佐房昌俊 | |||
元暦元(1184)年8月26日、在京の義経は「賜平氏追討使官符」った(『吾妻鏡』文治五年閏四月卅日条)。これは範頼と義経の両将を追討使とした本格的な西国出兵構想であった。なお、義経の追討使官符下賜のタイミングは範頼上洛に合わせたものとみられ、翌27日に三河守範頼が入洛している(『吾妻鏡』元暦元年九月十二日条)。範頼にもこの二日後の8月29日に追討使の官符が下されており(『吾妻鏡』元暦元年九月十二日条)、福原攻めの際と同様、二手から四国屋島を攻めるものであったことがわかる。
9月1日、範頼勢は京都を出立した(『吾妻鏡』元暦元年九月十二日条)。範頼は鎌倉出立の際に頼朝から「一日不可逗留京都、直可向四国之由」(『玉葉』元暦元年八月廿一日条)を命じられており、入洛翌日の出征という非常に速やかな発向になった。ただ、このとき西国へ出向したのは範頼勢のみであり、義経は京都にとどまっている。さらに、範頼は当初予定の四国ではなく山陽道を西進している。これは、8月27日から29日の間に頼朝の使者が京都に到着し、範頼と義経に追討計画の変更を伝えたためであろう。変更の大きな要因は、伊賀伊勢平氏の挙兵であろう。この兵乱の勃発を受けた頼朝は、範頼・義経のいずれかを畿内警衛として留め置く必要に迫られたと思われる。ただ、範頼はもともと追討使として上洛していたことと、義経がすでに上方の情勢に精通し人脈も構築していたことから、義経を留守居として留めたのだろう。そして、義経発向の延引により四国屋島を攻める手はずも変更され、範頼勢は惣追捕使土肥・梶原勢への救援と、源氏に心寄せる九州国人を率いて屋島を攻める戦略に改められたと思われる。
土肥・梶原の惣追捕使両名は、安芸国などでの敗戦はあったものの、9月には周防国にまで兵を進めており、追討使範頼の軍勢もとくに抵抗に遭うこともなく周防国へ至っている。しかし、この間に平家勢により米穀は刈り取られており、範頼勢は兵糧米の補給に苦しみ、著しい兵糧不足に陥っている。兵舟も知盛が押収していたため、知盛の拠点である彦島を攻めることもできず、範頼勢は長門国での長滞陣を余儀なくされた。こうした状況により、範頼勢の士気は低下の一途を辿り、扈従の宗たる「和田太郎兄弟、大多和二郎、工藤一臈以下侍数輩、推而欲帰参」るほどの状況に陥ってしまう。兵站の喪失により極限の状態に追い込まれた範頼は、11月14日、物資の輸送を鎌倉の頼朝に求めたのであった(『吾妻鏡』元暦元年十一月十四日条)。実はこれ以前にも範頼は鎌倉に兵糧と兵船支援の要請を行っており、頼朝は「日来有沙汰、用意船可送兵粮米之旨、所被仰付東国也、以其趣、欲被仰遣西海」(『吾妻鏡』元暦二年正月六日条)と、伊豆国に東国各地から集めた兵船に兵粮米を積み込んで繋留していた。そしてこの頃、頼朝は義経に四国出兵を命じる使者を遣わした可能性が高く、翌元暦2(1185)年正月8日に義経は西海出兵の奏上を行っているのは、頼朝の意向を受けたものであろう。
元暦2(1185)年正月6日、鎌倉から範頼への御書を持った雑色が出立した。この書状には、九州国人の反発を買う行動の禁止、九州急派の自粛、天皇・二位尼の無事な奪還(当時の公卿衆や院が最も拘った神器について触れられない不審がある)が認められ、とくに天皇の救出と宗盛の生捕を指示していることから、頼朝が範頼に命じていることは、九州攻めではなく四国屋島御所を攻めることであったことがわかる。なお、この書状の九番目に「千葉介ことに軍にも高名し候けり、大事にせられ候べし」(『吾妻鏡』元暦二年正月六日条)と、とくに千葉介常胤に対する扱いを加えている。おそらくこの雑色は2月初旬頃に範頼のもとへ到着したのであろう。
また、別に認められた書状には、東国で徴発した兵船は2月10日には発向する予定の旨を伝え、九州の諸国人らを味方にしたらば「当時は搆へて搆へて、国の者をすかしてよき樣にはからはせ給へ、筑紫の者にて、四国をは責させ給へく候」と指示し、彼らを以って四国を攻めるよう命じたのであった。ここでも頼朝が範頼に命じていたのはあくまでも四国攻めであったことがうかがえる。一方で、頼朝は九州国人らに宛てて「御下文一通」を発給し、院宣及び三河守範頼の下知に随うよう命じた(『吾妻鏡』元暦二年正月六日条)。
この「御下文」の年次は元暦元年であるが編纂作業での誤記であろう。そのほか内容にも不審があるため、編纂時に書き改めた可能性がある。
この下文は「参河守向九国、以九郎判官所被遣四国也」とあるため、義経に対する四国出兵の指示を発したのちに認められたものである。下文にある「参河守向九国」はあくまでも範頼が九州の管領であることを九州国人へ伝える意図であり、頼朝の本心は2月13日に鎌倉に到着した「伊澤五郎(石和五郎信光)」からの書状の返答に記す「依無粮退長門之條、只今不相向敵者有何事哉、攻九国事当時不可然歟、先渡四国、与平家可遂合戦」(『吾妻鏡』元暦二年二月十三日条)とある通りであろう。ただ、九州に進出することを禁じていたわけではなく、「令談于土肥二郎、梶原平三、可召九国勢、就之若見帰伏之形勢者、可入九州、不然者与鎮西不可好合戦、直渡四国可攻平家者」と(『吾妻鏡』元暦二年二月十四日条)、土肥・梶原と相談の上、九州国人が靡くようであれば九州にわたり、もし靡かないようであれば九州は攻めずに四国を攻めるよう指示したのであった。
ただし、石和信光や範頼の使者が鎌倉へ到着した2月中旬頃には、範頼はすでに北九州を制圧しており、さらに頼朝の返書が範頼のもとに届いたのは、すでに壇ノ浦の戦いが終わり、平家が滅んだ後であったとみられる。つまり範頼が認識していた頼朝からの指示は『吾妻鏡』によれば、あくまで四国攻めだけであるはずだが、実際には範頼は九州へ渡海している。範頼が頼朝の命を違えて九州に渡ることは考えにくく、義経に四国渡海を指示したとみられる元暦元(1184)年12月末頃には、範頼にも「可召九国勢、就之若見帰伏之形勢者、可入九州、不然者与鎮西不可好合戦、直渡四国可攻平家者」(『吾妻鏡』元暦二年二月十四日条)と同様の内容が伝えられていたと考えられ、「爰参州入九国之間、可管領九州之事、廷尉入四国之間、又可支配其国々事之旨、兼日被定處」(『吾妻鏡』元暦二年五月五日条)とあることから、範頼は九州に入ったらば九州を管領し、義経は四国に入ったらば四国の国々を支配することが定められていたという。
さて、長門国赤間が関まで進出して「新中納言知盛相具九国官兵、固門司関、以彦嶋定営、相待追討使」(『吾妻鏡』元暦二年二月十六日条)を牽制しつつも、兵糧の欠乏と士気の低下に悩まされていた範頼は、陣中で「志在源家之由、兼以風聞」があった豊後国の臼杵惟隆・緒方惟栄の兄弟に対して「召船於彼兄弟、渡豊後国、可責入博多津之旨」(『吾妻鏡』元暦二年正月十二日条)という戦略を決定し、正月12日、長門国からいったん周防国(防府市国衙か)へと戻った。「粮尽之間、又引退周防国訖」(『吾妻鏡』元暦二年二月十三日条)とされるが、豊後国臼杵・緒方の兵船融通を前提にした帰国であった。ただ、長門国での兵糧米の確保は不可能な状況にあったのは間違いなく、周防国おろか安芸国までの撤退も計画されていたという(『吾妻鏡』元暦二年二月十三日条)。
その直後、豊後国臼杵・緒方が召しに応じて八十二艘の兵船を献上。さらに周防国人の「宇佐那木上七遠隆」からは兵糧米の提供があった。なお、「伊澤五郎」が頼朝に苦境を訴える飛脚を飛ばしたのはちょうどこの時期であった。「東国之輩、頗有退屈之意、多恋本国、如和田小太郎義盛、猶潜擬帰参鎌倉、何况於其外族矣」という状況にあり(『吾妻鏡』元暦二年正月十二日条)、範頼は「軍士等漸有変意不一揆」と統制が取れないほど混乱した様子を伊豆の頼朝のもとへ報告している(『吾妻鏡』元暦二年二月十四日条)。
その後、「和田太郎兄弟、大多和二郎、工藤一臈以下侍数輩、推而欲帰参之間、抂抑留之、相伴渡海畢」(『吾妻鏡』元暦二年三月九日条)とあるとおり、範頼は和田義盛以下の人々を無理やり押し留め、正月26日、九州へ相伴させることになるが、この報告を受けた頼朝は範頼と御家人らに「仍今度不遂合戦、令帰洛者有何眉目哉、遣粮之程令堪忍可相待之、平家之出故郷在旅泊、猶励軍旅之儲、况為追討使、盍抽勇敢思乎」(『吾妻鏡』元暦二年正月十二日条)と叱咤している。なお、千葉介常胤も老体をおして孫の境平次常秀とともに渡海している(『吾妻鏡』元暦二年正月廿六日条)。
●文治元(1185)年正月26日、三河守範頼の九州渡海の扈従の輩(『吾妻鏡』)
| 大将軍 | 三河守範頼 | |||
| 扈従の輩 | 北条小四郎義時 | 足利蔵人義兼 | 小山兵衛尉朝政 | 小山五郎宗政 |
| 小山七郎朝光 | 武田兵衛尉有義 | 斎院次官中原親能 | 千葉介常胤 | |
| 千葉平次常秀 | 下河辺庄司行平 | 下河辺四郎政能 | 浅沼四郎広綱 | |
| 三浦介義澄 | 三浦平六義村 | 八田武者知家 | 八田太郎知重 | |
| 葛西三郎清重 | 渋谷庄司重国 | 渋谷二郎高重 | 比企藤内朝宗 | |
| 比企藤四郎能員 | 和田小太郎義盛 | 和田三郎宗実 | 和田四郎義胤 | |
| 大多和三郎義成 | 安西三郎景益 | 安西太郎明景 | 大河戸太郎広行 | |
| 大河戸三郎 | 中条藤次家長 | 加藤次景廉 | 工藤一臈祐経 | |
| 工藤三郎祐茂 | 天野藤内遠景 | 一品房昌寛 | 土佐房昌俊 | |
| 小野寺太郎道綱 |
範頼は渡海に際し、周防国の留守を任すべき人物について、「周防国者、西隣宰府、東近洛陽、自此所通子細於京都与関東、可廻計略之由、有武衛兼日之命、然者、留有勢精兵、欲令守当国、可差誰人哉」(『吾妻鏡』元暦二年正月廿六日条)と諸将に問うと、常胤が進み出て、「義澄為精兵、亦多勢者也、早可被仰」と三浦介義澄を推したのである。これを受けて、範頼は義澄に周防国守護を指示したが、義澄は「懸意於先登之處、徒留此地者、以何立功哉」と強く辞退した。これに範頼は「撰勇敢被留置之由」を述べて再三に渡って命じたため、義澄も折れて周防国に留まることを了承した(『吾妻鏡』元暦二年正月廿六日条)。
周防国での範頼の所在地はおそらく周防国府(防府市国衙)であろうから、臼杵・緒方の提供した兵船は国衙外港の船所(防府市国衙五丁目)に繋留されたと考えられよう。ここから出帆した範頼らは、向島や田島などの浮かぶ湾を南下し、豊後国府の外港(大分市坂ノ市)に上陸したのではなかろうか。国東半島の北側には平家と関係の深い宇佐神宮があることから上陸は忌避することが予想され、別府から日出、宇佐方面へ向かい、京都郡内を経て遠賀川を遡上したと思われる。
上陸から数日後の2月1日、「北条小四郎、下河辺庄司、澁谷庄司、品河三郎等」を先登に遠賀川河口の葦屋浦に進出した範頼勢は、鎮西平家方の重鎮であった「太宰少弐種直、子息賀摩兵衛尉等」と合戦に及び、渋谷重国勢は原田種直・賀摩種国勢を散々に射倒し、下河辺庄司行平は種直の弟・美気三郎敦種を射殺している(『吾妻鏡』元暦二年二月一日条)。範頼勢は豊後国北東部から豊前国北東部一帯を制圧することで、豊前国彦島の知盛は周防国の三浦介義澄との間に挟まれる形となり、積極的な身動きが取れない状況に陥った。
平重盛====女子
(内大臣) ∥
∥
原田種雄―+―原田種直――賀摩種国
(大宰大監)|(大宰少弐)(兵衛尉)
|
+―美気敦種
(三郎)
京都警衛の必要性から、義経の西国下向に踏み切れない頼朝は、元暦元(1184)年9月19日、文武に通じた側近・橘次公業を「為一方先陣」として屋島のある讃岐国へ派遣し、5月に交名を提出した「各令帰伏搆運志於源家之輩」に「可隨公業下知之由」を命じている(『吾妻鏡』元暦元年九月十九日条)。橘公業は京都に伺候していた藤大夫資光以下の讃岐国人を率いて讃岐国へ赴いており、義経に頼朝からの四国攻めに関する何らかの通達を伝えているのは確実であろう。元暦元年中、四国を攻めることができない追討使の両名に代わり、讃岐国内で平家を牽制していたのは彼らであった。
●源氏御方奉参京都候御家人交名(『吾妻鏡』元暦元年九月十九日条)
| 藤大夫資光 | 新大夫資重(資光子) | 新大夫能資(資光子) | 藤次郎大夫重次 | 六郎長資(重次舎弟) |
| 藤新大夫光高 | 野三郎大夫高包 | 橘大夫盛資 | 三野首領盛資 | 仲行事貞房 |
| 三野九郎有忠 | 三野首領太郎(盛資子か) | 次郎(盛資子か) | 大麻藤太家人 |
・讃州藤家系図(『吾妻鏡』より推測)
藤原某―+―藤原資光―+―藤原資重
|(藤大夫) |(新大夫)
| |
| +―藤原能資
| (新大夫)
|
+―藤原重次
|(次郎大夫)
|
+―藤原長資
(六郎)
・讃州藤家系図(『史料叢書』南海通記)
藤原家成 +―藤原親高
(中納言) |(周防守)
∥ |
∥―――――藤原資高―+―藤原有高 +―藤原資幸
∥ (羽床庄司)|(藤太夫) |(藤太夫)
∥ | |
綾貞宣――女子 +―藤原重高 +―藤原信資
(綾大領) |(藤太夫) |(次郎左衛門)
| |
+―藤原資光――+―藤原資村
(藤太夫) (左近将監)
橘公業はもともと父・右馬允橘公長や兄・橘太公忠とともに「左兵衛督知盛卿家人」であったが、治承4(1180)年12月19日、父や兄とともに鎌倉に帰参したとされ(『吾妻鏡』治承四年十二月十九日条)、頼朝の信任を得て側近となった人物である。
|
惟宗忠康 |
元暦元(1184)年8月26日に「賜平氏追討使官符」っていた義経であったが(『吾妻鏡』文治五年閏四月卅日条)、京都を含めた畿内の不安定な状況によって発向が延引されていた。
このころ義経は頼朝の命を受けて、伊賀伊勢平氏の乱の収束活動を行っているが、9月9日、頼朝は義経へ「出羽前司信兼入道已下、平氏家人等京都之地」について義経の沙汰とする旨の御書を遣わしている。京内における平家没官領の管理を義経に一元化して、武士らが勝手に没官領の沙汰をすることを禁じ、その扱いは法皇の御定とすると伝えている(『吾妻鏡』元暦元年九月九日条)。ただし、このうち「信兼領」については「義経沙汰」と別扱いしており、これは義経が直接管轄すべきものとしている。法皇御定の地とはいえ、実質的に義経へ宛がわれた恩賞とみるべきか。
そのわずか五日後の9月14日には、鎌倉から義経の妻女となる「河越太郎重頼息女」が上洛の途に就いた(『吾妻鏡』元暦元年九月十四日条)。これはもともと頼朝と義経の間での「約定」のためであったが、頼朝が信認する比企尼所縁の女子を義経に縁づけることで、より義経との紐帯を固めようとする頼朝の考えが強かったことがうかがわれる。
頼朝が範頼やほかの門葉ではなく義経を京都代官として起用し続けたのも、彼の警衛能力や公家衆との折衝能力を認めていたことに他ならないだろう。当時、義経の身辺には朝廷に伝手のある中原親能も中原広元も不在であり、義経は院近臣や後藤基清など公卿と関係のある在京御家人が義経の活動を支え、義経も直に公家衆と交わりながら、その政治的な役割を磨いていたと思われる。俗説のような政治的能力の欠如は認められず、混沌とする畿内、近国の国領・庄園など所領の管理・監督、狼藉の鎮定及び治安維持、朝廷や法皇との際どい折衝、平家への対応など多岐にわたる諸役を一手にこなす手腕を発揮していたのである。さらに頼朝は義経の叙爵を推しており、9月18日の大除目で義経は従五位下となる(『山槐記』元暦元年九月十八日条)。さらに10月15日には院の内昇殿が聴され(『吾妻鏡』元暦元年九月廿四日条)、義経は法皇とのスムーズな折衝が可能となった。
●元暦元年九月十八日大除目(『山槐記』元暦元年九月十八日条)
| 人名 | 官位 | 官位 (現) |
備考 |
| 任官 | |||
| 藤原朝方 | 権中納言(還任) | 正二位 | 院近臣 |
| 藤原定能 | 権中納言 参議 左近衞権中将 |
正三位 | |
| 藤原経房 | 中納言 参議 左大弁 |
従三位 | |
| 藤原基家 | 参議 | 正三位 | |
| 平親宗 | 参議 | 正三位 | 院近臣 |
| 藤原兼光 | 左大弁 | 従三位 | |
| 藤原光雅 | 右大弁 | 正四位下 | |
| 源兼忠 | 権右中弁 | 正四位下 | 入道前権中納言正二位源雅頼卿二男。 母は正二位行中納言藤原家成女。 乳母夫は斎院次官親能。 |
| 平基親 | 左少弁 | 正五位下 | 院近臣。入道参議正三位行民部陽親範卿の子。 母は若狭守従五位下高階泰重女。 |
| 藤原定長 | 右少弁 蔵人左衛門権佐 |
正五位下 | 故権右中弁兼中宮亮光房五男。 母は故丹後頭藤原為忠女(官女)。 |
| 藤原範光 | 式部権少輔 | 正五位下 | |
| 平範経 | 宮内少輔 | ||
| 藤原宗綱 | 大膳大夫 | ||
| 高階経仲 | 右馬頭 | 従四位上 | 院近臣。 大蔵卿高階泰経長男。 母は故三位従五位下藤原行広女。 |
| 藤原実明 | 美濃守 右近衞少将 |
正四位下 | |
| 藤原範季 | 備前守 | 従四位上 | 院近臣。 故従四位下行式部少輔能兼三男。 母は散位従五位下高階為賢女。 三河守範頼の養父。 |
| 中原広元 | 因幡守 | 従五位上 | のちの大江広元 |
| 叙位 | |||
| 平為盛 | 従四位下 | 平頼盛入道の子 | |
| 藤原朝仲 | 正五位下 | 右大臣兼実甥 | |
| 源義経 | 従五位下 | 左衛門少尉、検非違使 | |
| 藤原家通 | 検非違使別当 右衛門督 |
従二位 | |
後日、義経追捕が行われた際、頼朝が「今度同意行家義経之侍臣并北面輩事」として「侍従良成、少内記信康伊与守右筆、右馬権頭業忠、兵庫頭章綱、大夫判官知康、信盛、左衛門尉信実、時成等」(『吾妻鏡』文治元年十二月六日条)の懲罰を求め、「同意行家義経等欲乱天下之凶臣也」として「参議親宗、大蔵卿泰経、右大臣光雅、刑部卿頼経、右馬頭経仲、右馬権頭業忠、左大史隆職、左衛門少尉知康、信盛、信実、時成、兵庫頭章綱」(『吾妻鏡』文治元年十二月六日条)の解官を要求しているように、義経は院近臣を通じて法皇との間に強いパイプを構築していた様子がうかがえる。なお、「侍従良成」は「故長成朝臣男」であるが、母は九条院雑仕常盤であり、義経の異父弟にあたる。
10月6日、鎌倉において「新造公文所吉書始」が執り行われ、別当に「安芸介中原広元」が就き、長年京都に祗候した経験を持つ「斎院次官中原親能、主計允藤原行政、足立右馬允藤内遠元、甲斐四郎大中臣秋家、藤判官代邦通等」が寄人となった。
■公文所吉書始(『吾妻鏡』元暦元年十月六日条)
| 別当 | 安芸介中原広元 |
| 寄人 | 斎院次官中原親能 主計允藤原行政 足立右馬允藤内遠元 甲斐四郎大中臣秋家 藤判官代邦通 |
判官代邦通が吉書を書き広元が頼朝に披露している。その後、「千葉介」が垸飯を行ったというが(『吾妻鏡』元暦元年十月六日条)、当時「千葉介」常胤は範頼に随って中国地方を転戦しており、この「千葉介」は常秀の父・千葉新介胤正であろう。また、広元は義経の叙爵と同日の9月18日、因幡守となっているが、前官職の安芸介と記されていることから、除書がまだ鎌倉に着いていなかったということか。
元暦2(1185)年正月8日、大蔵卿泰経は院中で会った権中納言経房に「廷尉義経可向四国之由」(『吉記』元暦二年正月八日条)を語っている。すでに義経からこの旨が法皇には奏上されていたが、法皇が難色を示していたようである。これに義経は「而自身可候洛中、只可差遣郎従歟」ということを「申被人(法皇や一部の院近臣であろう)」もあるが、これは「忠清法師在京之由風聞、定挿凶心歟」のためであろうという予測を述べている。忠清法師は伊賀伊勢平氏の乱に加担しており、法皇は忠清法師への強い危機感を持っていたことを物語る。義経の平家追討延引はこの忠清法師ら平家残党を恐れる法皇が頼朝に働きかけた結果であろう。
しかし、西国の参河守範頼の軍勢は「二三月兵糧尽了」という状況が京都にも伝わっており、義経は「範頼若引帰者、管国武士等猶属平家、弥及大事歟」と強く主張した(『吉記』元暦二年正月八日条)。経房はこの義経の意見を聞き「義経申状、尤有其謂、大将軍不下向、差遣郎従等之間、雖有諸国費、無追討之実歟、範頼下向之後、及此沙汰歟、然者今春義経発向尤可決雌雄歟」と義経の西国下向案を推した(『吉記』元暦二年正月八日条)。たとえ義経が下向したとしても、「猶於可然之輩者、差分可令祇候京都之由、尤可被仰合也」と、京都にも守衛の武士は残されることも述べている。ただ、法皇が恐れる件の忠清法師は、経房にとっては「於忠清法師事者、不及沙汰歟、但可搦進其身之由、尤可被宣下歟」(『吉記』元暦二年正月八日条)とあるようにもはや脅威ではなく、捕らえて進上する旨の宣旨を下しておけばよいという程度の認識であった。結局、経房の推挙もあったか、義経の西国下向は認められ、正月10日に「大夫判官義経、発向西国」(『吉記』元暦二年正月十日条)と、平家討伐のために京を出立した。
義経は淀川の河口、摂津国渡邊へと移り、その後ひと月あまりこの地に駐屯した。この不自然な滞陣の理由は不明だが、当時「平家者結陣於両所、前内府以讃岐国屋嶋為城郭、新中納言知盛相具九国官兵、固門司関、以彦嶋定営、相待追討使」(『吾妻鏡』元暦二年二月十六日条)という状況の中、瀬戸内への玄関口である渡邊津で、四国を攻めるための軍勢催促が行われていたのであろう。京都には兵粮の問題から、京都駐屯が可能な人数しか配されていなかったことは確実であり、追討使拝命後は「畿内近国、号源氏平氏携弓箭之輩幷住人等、任義経之下知可引率之由、可被仰下候」(『玉葉』寿永三年二月廿七日条)とあるように、畿内・近国の国人を中心に兵力を整えていたとみられる。こうした中で、範頼は豊後国人らの協力を得られる確証を得て長門国で豊後渡海を議定し、正月26日に渡海を果たし、2月1日に豊前国葦屋浦(福岡県遠賀郡芦屋町)での戦いに勝利。彦島(下関市彦島)の南対岸に進んだとみられる。権中納言知盛の九州渡海を防ぎ、平家勢の兵力補充を阻害したのである。
一方、範頼から九州渡海の報を受けた義経は、単独で讃岐国屋島の御所を攻めることとなったが、2月16日、法皇は大蔵卿泰経を義経が滞陣する「渡邊」へ派遣し、院宣を以て「為制止義経発向」を命じた(『玉葉』元暦二年二月十六日条)。それは「是京中依無武士為御用心」という法皇の不安から出たものであったが、義経は「敢不承引」であった(『玉葉』元暦二年二月十六日条)。範頼が北九州で知盛を抑えることで、四国へ進む可能性がなくなった以上、義経の出陣が必須となったためであろう。泰経は「泰経雖不知兵法、推量之所覃、為大将軍者、未必競一陣歟、先可被遣次将哉」と説得するが、義経は「殊有存念、於一陣欲棄命」と告げたという(『吾妻鏡』元暦二年二月十六日条)。兼実は法皇が公卿たる泰経にこのようなくだらない使者をさせることを強く批判している(『玉葉』元暦二年二月十六日条)。
頼朝は2月5日に「典膳大夫中原久経、近藤七国平、為使節上洛」(『吾妻鏡』元暦二年二月五日条)させているが、これは義経・範頼両将の西国出兵の完了を受けたものであろう。久経・国平両名は「是追討平氏之間、寄事於兵粮、散在武士於畿内近国所々致狼藉之由」の報告があるため、「仍雖不被相待平家滅亡、且為被停止彼狼唳、所被差遣」た使節であった。彼らは「先相鎮中国近辺之十一ケ国、次可至九国四国」という任務を請け負っており、この「中国近辺之十一ケ国」は「不被相待平家滅亡」とあることから、平家が管領していた梶原・土肥が惣追捕使を務める五か国を含む山陽地方であろう。そのほか「為鎮畿内近国狼唳」(『吾妻鏡』元暦二年三月四日条)ともあり、畿内の武士による狼藉を鎮めることも彼らの任務であった。
彼らは「今両人雖非指大名」と頼朝も認識している通り大身ではなく、義経の代理ではない。彼等には義経の「職務の一部」である狼藉防止の任務が与えられたとみられるが、何事も「悉以経奏聞、可随 院宣」を指示しており、ただ院宣に随うという「此一事之外、不可交私之沙汰之由」をきつく申し付けられているのである。なお、この使節が上洛したのは時期的に2月15日前後と考えられることから、法皇は彼らを心許なく思い、頼りとなる義経を呼び戻そうと試みた可能性があろう。なお、義経がいたのは『延慶本平家物語』などでは「大物の浦」であるが、実際には『玉葉』『吾妻鏡』に見える通り摂津国「渡邊」(『玉葉』元暦二年二月十六日条)である。
法皇使の高階泰経が到来した2月16日(『吾妻鏡』では前日15日より宿泊)、義経は渡邊津を「十六日解纜」(『玉葉』元暦二年二月廿七日条、三月四日条)した。『玉葉』の記述は、義経からの「申上状」を受けた小槻隆職が兼実に注送したものであるため、信憑性は高い。『吾妻鏡』でも16日に「関東軍兵為追討平氏赴讃岐国、廷尉義経為先陣、今日酉尅解纜」(『吾妻鏡』元暦二年二月十六日条)とあり、朝廷に伝えられた出航日は2月16日だったことがわかる。『吾妻鏡』には船の数は記されていないが、軍記物『平家物語』(延慶本)の記述では集結した船は「百五十艘」とある(『延慶本平家物語』)。
『玉葉』では義経申上状の記述から、予定通り2月16日に「十六日解纜」(『玉葉』元暦二年二月廿七日条、三月四日条)し、翌17日には「十七日着阿波国」(『玉葉』元暦二年三月四日条)となっていて、しかも「無為著阿波国了」(『玉葉』元暦二年二月廿七日条)とあるように、何ら問題なく阿波国に到着したという。ところが『吾妻鏡』では、16日夜に暴風に見舞われ、破損する兵船が続出(『吾妻鏡』元暦二年二月十八日条)し、暴風を恐れた「士卒船等一艘而不解纜」という状況が起こっていたという。ここで義経は「朝敵追討使暫時逗留、可有其恐、不可顧風波之難」(『吾妻鏡』元暦二年二月十八日条)と将士を鼓舞したが、士卒らの多くは危険回避のために渡海を拒絶したため、義経は明けて17日深夜丑刻(午前1時~3時頃)に同調する人々とともに「先出舟五艘」に分乗して出航し、数時間後の「卯尅着阿波国椿浦」という(『吾妻鏡』元暦二年二月十八日条)。義経が朝廷に伝える上では、とにかく無事に阿波国についたことは間違いなく、過程は省かれた可能性も十分にある。
なお、史料的価値は疑問の軍記物『延慶本平家物語』では「俄かに又南風激しく吹きて、船七八十艘、渚に吹き上げられ、散々に打ち破れたり」(『延慶本平家物語』)とあり、『源平盛衰記』『平家物語』ではこのとき義経と景時が激しく口論したと記される。「凡和田小太郎義盛与梶原平三景時者、侍別当所司也、仍被発遣舎弟両将於西海之時、軍士等事為令奉行、被付義盛於参州、被付景時於廷尉」(『吾妻鏡』元暦二年四月廿一日条)とあるように梶原景時は義経に付属していた代官であったことは間違いないだろう。ただ、この頃景時は「淡路国広田庄者、先日被寄附広田社之處、梶原平三景時為追討平氏、当時在彼国之間、郎従等乱入彼庄、妨乃貢歟」(『吾妻鏡』元暦元年十月廿七日条)とあるように、かなり早い段階から屋島を牽制するように淡路国に駐屯していた様子も見られ、実際に口論があったかは不明である。
『吾妻鏡』の記述では、17日早朝に「阿波国椿浦」に到着し、百五十騎が上陸したという(『吾妻鏡』元暦二年二月十八日条)。「椿浦」は阿南市椿町浜、阿南市椿泊町、阿南市椿町那波江、阿南市椿町楠ケ浦など、阿南市椿泊町のある半島上の泊の何れかであろう(桂浦説は、あくまでも『吾妻鏡』での記述だが「路次」であるため、ここではないだろう)。
義経に付随して渡海した際の交名は伝わっていないが、義経には「渡部党源五馬允」(『吾妻鏡』元暦二年三月廿四日条)も随っており、水運に長けた摂津渡邊党の協力があったのだろう。このほか、軍記物『延慶本平家物語』では「百五十艘の船の内、只五艘出だして走らかす、残りの船は皆留まりにけり、一番判官の船、二番畠山、三番土肥次郎、四番伊勢三郎、五番佐々木四郎已上五艘ぞ出だしたりけり」(『延慶本平家物語』)とあり、畠山次郎重忠、土肥次郎実平、伊勢三郎義盛、佐々木四郎高綱を主たる御家人とする「畠山を初めとして、一人当千の棟との者共六十余人、判官に付きにけり」という(『延慶本平家物語』)。ただ、この『延慶本平家物語』の記述は軍記物の特性上、信は置けない。このほか「田代冠者信綱、金子十郎家忠、同余一近則」(『吾妻鏡』元暦二年二月十九日条)や「後藤兵衛尉実基、同養子後藤新兵衛尉基清等」(『吾妻鏡』元暦二年二月十九日条)がいたという。
義経に従って阿波国に上陸したのは「則率百五十余騎上陸」(『吾妻鏡』元暦二年二月十八日条)とあるが、「百五十騎」を五艘で渡るには単純計算で一艘に五十人の将士と乗馬を乗せる必要があり、不可能である(平安期の大陸への渡航で用いられたような外洋船であっても漕手などを除けば一艘十数名と推測:(榎本渉「日宋・日元貿易船の乗員規模」『国立歴史民俗博物館研究報告』2021年3月)より考察)。もし百五十騎の上陸が事実であるとすれば、阿波へ渡る船は外洋船より小規模な兵船であったと考えれば、三十~四十艘規模の船団が必要となり、嵐で渡海ができなかったという説話には疑問符がつくことになる。
彼らが「上陸」した阿波国「椿浦」は阿波国中部の椿泊半島近辺と思われるが、義経は阿波国板西郡の「当国住人近藤七親家」を召して屋島までの道案内としたとある(『吾妻鏡』元暦二年二月十八日条)。坂西郡は吉野川流域という椿浦からは相当北に位置する地域であり、近藤親家にはあらかじめ到着する地点を指示しておく必要がある。暴風による漂着という不確定事項ではこの説話は成立困難となる(あらかじめ近藤親家が渡邊津の義経陣にいれば別である)。
義経は「赴讃岐国」(『吾妻鏡』元暦二年二月十六日条)とあるが、これは目的地としての讃岐国を指すか。『吾妻鏡』によれば、義経率いる百五十騎は椿浦から勝浦郡「桂浦(徳島市勝占町)」へ進出し、桂浦を望む中山に城塞を築いていた平家方の「桜庭介良遠」を攻めて追い落とした(『吾妻鏡』元暦二年二月十八日条)。桂浦は現在は海から数キロ離れているが、当時は羽ノ浦、立江、田浦から続く浜辺を形成していたのであろう。「桜庭介良遠」は「散位成良弟」であるが、「散位成良」は阿波国有力在庁で平重衡の麾下として宇治や美濃など各地を転戦した「阿波民部大夫成良(田口成良)」である。
義経は桜庭介良遠を追い落としたあと、桂浦から北上して吉野川に進出。西へ転じて「阿波国与讃岐之境中山」へと進んでいる。おそらくこの頃、橘次公業ら讃岐国に先陣として派遣されていた御家人と合流しているのだろう。その後、夜間に山を越えた義経勢は、19日未明に「屋嶋内裏之向浦(高松市新田町)」まで進み、「牟礼、高松民家」を焼き払ったという(『吾妻鏡』元暦二年二月十九日条)。『吾妻鏡』の記述からは、屋島の海峡を挟んだ南部と東部に侵攻したということになる。
ただし、椿浦から屋島までの道のりは陸行で約百二十キロメートルあり、途中の戦闘および登山を伴う陸行ではほぼ不可能な旅程である。『玉葉』では大夫史隆職からの注送で義経からの申状の内容が記されているが、こちらでは「去月十六日解纜、十七日着阿波国、十八日寄屋島、追落凶党了」(『玉葉』元暦二年三月四日条)とあり『吾妻鏡』の内容とは一日のずれが生じている(なお、前述の通り、『吾妻鏡』元暦二月十六日条の渡辺津出航の記述は義経が朝廷に送った申状に則った記載がなされ、その出典は『玉葉』をベースにしているとみられるが、翌二月十七日条ではまだ渡辺津から出航していないという前日と矛盾した状態が記載されていて、別の出典から齎されているとみられる。その後の『吾妻鏡』における義経の行動も16日の『玉葉』とは異なる出典から採用されており、義経の申状とは1日のずれが生じている)。『玉葉』は義経の「申状」の内容を機械的に記録しているものであるから『吾妻鏡』よりも信憑性が高いであろう。また、陸路で進軍したとすれば船は椿浦へ置くことになるが、屋島はその名の通り島であり、船を使わずに攻めることは不可能である。屋島周辺の船舶は当然接収されていたと考えられることから、義経は自前の船を持ったまま屋島に着陣していることになる。つまり、時間の点からも船の点からも、義経勢は阿波国椿浦から羽ノ浦、立江、田浦の海岸線を船で北上し、屋島へ向かったというのが現実的であろう。
なお、屋島侵攻を受けた宗盛は安徳天皇を奉じて海へ逃れ、義経は彼らを追って「田代冠者信綱、金子十郎家忠、同余一近則。伊勢三郎能盛等」を率いて汀を馳せ向かい、平家の兵船に矢を射かけ、平家側からも矢が放たれている。この間に別働の「佐藤三郎兵衛尉継信、同四郎兵衛尉忠信、後藤兵衛尉実基、同養子後藤新兵衛尉基清等」が空き家となった屋島内裏へ侵入するが、「越中二郎兵衛尉盛継、上総五郎兵衛尉忠光」は兵船から降りて屋島御所の宮門前に陣しており、義経郎従の佐藤三郎継信が討死している(『吾妻鏡』元暦二年二月十九日条)。
その後、義経勢の別働隊は内裏と前内府宗盛の屋敷などを焼き払っており(『吾妻鏡』元暦二年二月十九日条)、平盛嗣、藤原忠光は退いたと思われる。戦後、義経は腹心・佐藤三郎継信の亡骸を僧侶に託して千株松の根元に埋葬し、法皇から給わった名馬・大夫黒を回向のため僧侶に給わったという(『吾妻鏡』元暦二年二月十九日条))。この屋島の戦いは京都に報告され、3月4日に大夫史隆職から兼実のもとに「寄屋島、追落凶党了」(『玉葉』元暦二年三月四日条)の報告がなされている。
屋島から東へ逃れた平家勢は「讃岐国志度道場(志度寺)」に籠り、2月21日、義経率いる八十騎がこれを攻め、平家は再び海へと逃れて西へ向かった。この合戦で「平氏家人田内左衛門尉」が義経に帰服した(『吾妻鏡』元暦二年二月廿一日条)。田内左衛門尉(田口左衛門尉教良)は前述の阿波民部大夫成良の子であるが、父や叔父が平家党として合戦している最中になぜ寝返ったのかは不明である。そのほか、伊予国人・河野四郎通信も三十艘の兵船を率いて義経勢に参戦。京都では「熊野別当湛増」も源氏へ属して渡海したという風聞が流れた(『吾妻鏡』元暦二年二月廿一日条)。実際に3月9日に鎌倉に届けられた範頼の書状でも「熊野別当湛増、依廷尉引汲、承追討使、去比渡讃岐国」ったといい(『吾妻鏡』元暦二年三月九日条)、義経の調略によって熊野別当が源氏側となったことが報告されている。なお、その際、湛増が義経の引汲によって「追討使」を拝命した風聞に不満を感じていることを述べている。この使者は3月10日に鎌倉に届くが、頼朝は湛増が渡海した風聞は「無其実」であると返答している。
湛快――――+―湛増
(熊野別当) |(熊野別当)
|
| 平忠度
|(薩摩守)
| ∥
行範 +―女子
(熊野別当) ∥――――女子
∥ ∥
∥―――――――行快
∥ (僧都)
源為義――+―鳥居禅尼
(六条判官)|
∥ |
∥ +―源行家―――――源光家
∥ (備前守) (左衛門少尉)
∥
∥――――――源義朝―――――源頼朝
藤原忠清―――女子 (左馬頭) (前右兵衛権佐)
(淡路守)
また「自関東所被差遣之御家人等、皆悉可被憐愍、就中千葉介常胤、不顧老骨堪忍旅泊之條、殊神妙、抜傍輩可被賞翫者歟、凡於常胤大功者、生涯更不可尽報謝之由」(『吾妻鏡』元暦二年三月九日条)と、頼朝は、とくに常胤について言及している。
そして、志度合戦の翌2月22日、屋島の磯に「梶原平三景時以下東士、以百四十余艘」が到着した(『吾妻鏡』元暦二年二月廿二日条)。景時は当時、淡路国に在陣していたと思われ、屋島から立ちのぼる黒煙などを見て、急ぎ馳せ参じたものではなかろうか。義経が2月19日に鎌倉へ遣わした飛脚は屋島合戦の前に陣を離れていたが、「而於播磨国顧後之處、屋嶋方黒煙聳天、合戦已畢、内裏以下焼亡無其疑」(『吾妻鏡』元暦二年三月八日条)と頼朝に報告しており、播磨国からも望める黒煙であった。
3月12日、頼朝は範頼が依頼していた兵船の補給として、伊豆国鯉名・妻郎津に繋留した兵船三十二艘に兵粮を乗せ、筑後権守藤原俊兼を奉行として西海に派遣する命を下した(『吾妻鏡』元暦二年三月十二日条)。もともと2月10日に解纜の予定であったが、ひと月あまりの遅延となっている。
3月14日には鬼窪小四郎行親を使者として、九州の範頼へ「是追討可廻遠慮事、賢所并宝物等無為可奉返入事等」との書状を遣わしている。三種神器の京都奉還は後鳥羽天皇の即位を行うにあたり必須であり、頼朝は安徳天皇の身柄よりも神器の無事な回収を優先していたのである。それは在京の貴族も同様であった。また神器の奉還は法皇からも強く要請されていたと思われ、すでに3月8日には義経、翌9日には範頼からの使者が鎌倉に到着し、頼朝は西国の戦況を把握していたと考えられることから、平家を追い詰め、神器を取り返すのも時間の問題であることを感じていたのだろう(『吾妻鏡』元暦二年三月十四日条)。
さて、志度寺の敗戦により、西へ向かった前内府宗盛ら平家一門は、まず「在讃岐国シハク庄」に拠った(『玉葉』元暦二年三月十六日条)。塩飽諸島のいずれかの島に拠点を構えんとしたのであろう。ところがここにも義経勢が攻め懸り、平家勢は「不及合戦引退、著安芸厳島了」で、その勢は「僅百艘許」であったという(『玉葉』元暦二年三月十六日条)。そのほか「平氏或在備前小島、或在伊予五々島」と瀬戸内の島嶼に拠っているが、ここに平家方として「鎮西勢三百艘相加」という伝聞が京都に届いた。兼実はこれらの報に「但実否難知、近日異説非一」と慎重な姿勢を示している(『玉葉』元暦二年三月十七日条)。
頼朝は「四国事者、義経奉之、九州事者、範頼奉之」(『吾妻鏡』元暦二年三月九日条)と指示しているように、義経は四国追討を任とし、範頼は九州追討が所役となったと思われる。ただし、飢饉による兵糧不足や厭戦気分の蔓延があったことから、平家追捕は持久戦になる可能性も高く、範頼と義経は担当地域に応じた活動は命じられていたものの、具体的な戦略は遼遠の地ということもあって彼らに委任され、その状況報告は逐一鎌倉へ送られる形だったのであろう。ただし、範頼と義経の両将は、神器と主上・国母奪還という共通目的を持ち、範頼は大宰府など平家の九州の拠点を掌握しながら彦島(下関市彦島)の南岸まで進出し、平家勢の九州渡海を阻止する一方、彦島の権中納言知盛と合流して九州への渡海を図るであろう前内府宗盛らを周防国の三浦介義澄が抑える戦略を取ったのだろう。範頼の九州封鎖は平家勢の行先を奪う目的があったと考えられる。
一方、屋島の平家党の追捕に成功した義経は、瀬戸内に逃れた宗盛らの追捕を敢行することとなる。宗盛らは安徳天皇を奉じて九州での態勢挽回のため西へ向かっており、まずは彦島に布陣して九州の平家与党を組織していた権中納言知盛との合流を図ったのである。宗盛勢を追捕するには、累代の平家与党が多く存在する瀬戸内を経て攻め上ることになり、義経勢は宗盛勢を「讃岐国シハク庄」から「安芸厳島」へ追ったものの、すでに権中納言知盛が張っていた警戒線が芸予海峡を塞ぐように「伊予五々島(愛媛県興居島)」(『玉葉』元暦二年三月十七日条)、「周防国大島(周防大島町)」にも「件島、平氏知盛卿謀反之時、構城郭所居住也、其間住人字屋代源三、小田三郎等令同意、始終令結構彼城畢」(『前右大将家政所下文』「鎌倉遺文」594)されていたのである。
こうした中、義経勢には伊予西部の氏族を支配下に置く(『関東下知状』「鎌倉遺文」1570)河野四郎通信の船団三十艘が加わっていたものの、寡兵に変わりはなく、平家勢が潜む瀬戸内を進むことは容易ではなかったはずである。義経は、宗盛が拠った芸州厳島へ向かわずに芸予海峡の島嶼をくぐり抜けると、周防国府(防府市国衙)傍の「大津嶋(周南市大字大津島)」へ上陸した(『吾妻鏡』元暦二年三月廿二日条)。これは宗盛勢の動向を窺うとともに周防国留守居の三浦介義澄との連携を図ったものであろう。
3月21日、義経は周防国で「聚乗船廻計」(『吾妻鏡』元暦二年三月廿二日条)し、「為攻平氏、欲発向壇浦」の予定であったが、この日は「甚雨」であり「延引」された(『吾妻鏡』元暦二年三月廿一日条)。義経は大津島に在陣していたと思われるが、周防国衙在庁で「依為当国舟船奉行」の船所五郎正利が、義経に「数十艘」の船を献じたという(『吾妻鏡』元暦二年三月廿一日条)。これが義経の要請があったものかは不明だが、義経勢には圧倒的に船が足らなかったのだろう。厳島の宗盛との戦いを避けて周防国に拠ったのも、兵船補給や補修の意図があったと思われる。周防船所からの兵船供与はこの上ないものであったろう。義経は正利の協力に対し「与書於正利、可為鎌倉殿御家人之由」(『吾妻鏡』元暦二年三月廿一日条)を証する文書を発給したという。そして翌3月22日、義経は「促数十艘兵船、差壇浦解纜」した(『吾妻鏡』元暦二年三月廿二日条)。
この出帆に先立ち、周防国留守居の三浦介義澄が、義経の「自昨日聚乗船廻計」を聞いた周防国府(防府市国衙)から大津島へ参会し、義経と対面している。義経出帆が程近いことを察したものであろう。ここで義経は義澄に「汝已見門司関者也、今可謂案内者、然者可先登者」(『吾妻鏡』元暦二年三月廿二日条)と命じている。これを受けた義澄は「進到于壇浦奥津邊去平家陣卅余町也」に船を進めたという。ただ、義澄は範頼に付属された人物で、範頼の命によって周防国の留守居を任された身であり、義経が義澄に出兵を命じることは明確な越権行為となろう。こうした行為が、頼朝の怒りを買う一因になっているのかもしれない。
なお、義経に付けられた代官の梶原平三景時は、去る2月22日に屋島の磯に「百四十艘」の船を率いて到着しているが(『吾妻鏡』元暦二年二月廿二日条)、義経が大津島を出帆した際には「数十艘」の船であったとされることから、義経は梶原景時とは合流していないことになる。また、屋島合戦以降、船を大量に徴発する時間的な余裕はないことから、義経麾下の船は、渡邊津を出帆した船および、河野通信の三十艘、周防船所提供の数十艘を加えた百艘に満たない兵船が義経が率いたすべてであったと思われる。ここに義澄が用いた兵船(これも周防国船所の船であろう)を加えても、さほど多くない数であったろう。
その頃、陣容を整えた安徳帝を奉じる平家勢が厳島から彦島方面へと向かっていったと思われる。この航行の様子は、大津嶋からも望めたであろう(対岸の姫島から大津嶋を望むことができる)。そして、彦島からも権中納言知盛自ら率いる軍勢が「赤間関」を経て「田之浦」沖に進み、安徳帝一行を海上で迎えて合流を果たしたと思われる。本来は陸上の御所にあるべき安徳天皇や女官も乗船して戦陣に身を置いていることを考えると、宗盛や知盛はすでに葦屋合戦で壊滅した北九州からの上陸を諦め、南下して九州への上陸を企図したのではなかろうか。ここに3月24日、義澄を「先登」とした義経勢が進出し、「壇浦奥津邊」でぶつかったのだろう。「壇ノ浦の戦い」である。
なお、「壇浦奥津邊」は、少なくとも田之浦(北九州市門司区田野浦)沖よりも東の長府沖であると考えられ、現在の下関市壇ノ浦町から北東方向一帯が「壇浦」と称されていたと思われる。
ところで、屋島を追われた安徳天皇や宗盛以下の平家勢は合戦までの間、どこにいたのだろうか。長門国彦島に上陸したという説もあるが、彦島上陸を証明する史料はない。『玉葉』からの足取りでは、宗盛は「厳島」へ到着したとの報告が兼実に届いているほか、「備前小島(玉野市周辺)」や「伊予五々島(愛媛県興居島)」に分散していた様子がうかがえる(『玉葉』元暦二年三月十七日条)。厳島へ上陸した安徳帝以下の平家勢は、即座に厳島や周防大島などからの援兵により兵力を回復したと思われる。
義経勢と衝突した平家方は、まず葦屋合戦後に知盛陣に遁れたと思われる「山峨兵藤次秀遠」と、肥前国「松浦党」が大将軍であった。義経は範頼との連携を図る前に知盛麾下の軍勢と遭遇してしまい、自勢と三浦介義澄勢で平家勢と戦った。範頼勢が海戦に参戦しなかったのは、範頼が牽制役に徹したのではなく、戦いの発生過程にあったとみられる。
義経の兵力は大津島を出帆する際に「数十艘」とあることから、義澄が率いた船を加えてもそれほど大兵力ではなかったと思われる。また宗盛率いる屋島平家勢は「僅百艘許」(『玉葉』元暦二年三月十六日条)で、彦島に籠っていた知盛勢も、山鹿・松浦党の残兵を加えたとしても、それほど大きな兵力を有し得なかったであろうから、義経が頼朝へ報告した「浮八百四十余艘兵船、平氏又艚向五百余艘合戦」(『吾妻鏡』元暦二年四月十一日条)という陣容での合戦は考えにくいであろう。
壇ノ浦合戦は義経勢が平家勢を次第に押してゆき、「及午剋、平氏終敗傾」という結末を迎えた。
このとき、故清盛入道正室の「二品禅尼(平時子)」は神器のひとつ「宝剣」を持ち、「按察使局」は先帝安徳天皇を抱き、壇ノ浦に入水した(『吾妻鏡』元暦二年三月廿四日条)。安徳天皇生母・建礼門院平徳子も入水したが、義経麾下の渡邊源五允によって救出され、安徳天皇を抱いて入水した按察局も引き上げられている。しかし、八歳の先帝安徳天皇(兼実は一時的に「西海王」と呼んでいる)と宝剣はついに浮かび上がってくることはなかった。七歳の「若宮今上兄」も平家とともに行動していたが救出されている。のちの守貞親王(後堀河天皇実父、後高倉院)である。平家方の宗たる人々では、「前中納言教盛、号門脇」「前参議経盛」「新三位中将資盛、前少将有盛朝臣等」が入水死、「前内府宗盛、右衛門督清宗等」は入水するも義経腹心の伊勢三郎能盛によって生け捕られた(『吾妻鏡』元暦二年三月廿四日条)。御座船に乱入して賢所を開けんとする東国武士に対しては、これを守衛していた「平大納言時忠」が強く制止している(『吾妻鏡』元暦二年三月廿四日条)。兵士らは「于時両眼忽暗、而神心惘然」となって逃げたというが、事実であれば時忠卿に目の前のものが神器であると告げられ、突然の事態に兵士らが慄き慌てたということかもしれない。時忠は平家一門とはいえ、清盛妻二位尼の弟という血縁関係となり、血統としてはまったく別流の桓武平氏である。その鎮西行への同行は、平家との関係というよりも先帝安徳天皇の大伯父、乳父という立場での行動であったろう。
●長門国平家与源氏合戦(『醍醐雑事記』)
| 生取 | 内大臣宗盛 | 三十九歳 | 故清盛入道の三男。 |
| 右衛門督清宗 | 十五歳 | 前内府宗盛の長男。 | |
| 大納言時忠 | 五十六歳 | 兵部権大輔時信の長男。故清盛入道の義弟。 | |
| 讃岐中将時実 | 三十五歳 | 大納言時忠卿の長男。 | |
| 内蔵頭(平信基) | 院近臣。兵部卿信範の長男。 | ||
| 二位僧都全真 | 院近臣藤原親隆の子で、時忠卿の母方の甥。 伯母にあたる八条殿時子の猶子。 |
||
| 法性寺執行能円 | 近臣藤原顕憲の子で、時忠卿の異父弟。 | ||
| 阿波民部大夫成良 | 阿波国の在庁で、壇浦合戦で源氏方に寝返った伝もあるが、 『醍醐雑事記』『吾妻鏡』いずれにも生捕の人数にあり、 彼の寝返りの伝は疑わしい。 |
||
| 藤内左衛門信康 | 平家家人。 | ||
| 女院 | 三十一歳 | 建礼門院。御諱は徳子。 | |
| 若宮 | 七歳 | 故高倉院第二皇子。平知盛室治部卿局を乳母とする。 のち守貞親王となり、皇子は後堀河天皇となる。 |
|
| 降人 | 源大夫判官季貞 | 平家家人。検非違使。 | |
| 摂津判官盛澄 | 平家家人。検非違使。 | ||
| 自害 | 中納言教盛 | 五十八歳 | 故忠盛卿の三男。門脇殿。母方は摂関家庶流という貴種。 こうした血統ゆえか、嫡子通盛は平家庶流中で唯一の公卿となる。 |
| 中納言知盛 | 三十四歳 | 故清盛入道四男。 | |
| 能登守教経 | 二十六歳 | 門脇中納言教盛の子。一ノ谷の合戦で討死したともされるが、 壇之浦合戦での活躍もみられ、真相不明。 |
|
| 殺人 | 左馬頭行盛 | 故清盛入道次男・基盛の子。播磨守という受領の上臈を経て、左馬頭へと昇る。ただし、行盛は従五位上、そしてのちに伊予守となった義経は従五位下であったように、この時点で伊予国や播磨国といった「四位上臈」任国の格は失われていたことがわかる。 | |
| 小松少将有盛 | 故小松内府重盛の子。『吾妻鏡』では入水したとある(『吾妻鏡』元暦二年三月廿四日条)。 | ||
| 備中吉備津宮神主 | |||
| 権藤内貞綱 | |||
| 権藤内貞綱舎弟 | |||
| 菊池二郎 | |||
| 刎頸者八百五十人 | |||
| 不知行方人 | 先帝 | 安徳天皇。 | |
| 八条院 | 二位尼平時子。 | ||
| 修理大夫経盛 | 六十二歳 | 故忠盛卿の次男。母は源信雅女。母方は名門村上源氏であるが、庶家の受領層であったため、摂関家庶家を外戚とする教盛や、当腹嫡子の頼盛といった異母弟より一段下に置かれていた。そのためか異母兄清盛や平家一門との関係よりも、姻戚関係にあった藤原師長や院司として仕えた太皇太后宮、その実家である閑院家の藤原実定らとの結びつきが強かった。壇之浦合戦では「前參議経盛出戦場、至陸地出家、立還又沈波底」(『吾妻鏡』元暦二年三月廿四日条)とあるように、いったん上陸して出家したのちに戻り、入水したという。 | |
| 内侍所御坐 | |||
| 進正御坐 | |||
| 宝剣不見 | |||
| 女院 | |||
| 二宮 |
壇ノ浦の戦いから四日後の元暦2(1185)年3月27日、京都の兼実のもとに「平氏於長門国被伐了、九郎之功」(『玉葉』元暦二年三月廿七日条)という「伝聞」が届いた。ただ、兼実は例の如く「実否未聞、可尋之」とさらなる情報を待つ姿勢を示す。
翌3月28日、兼実は経房の弟、右少弁定長を通じて、この伝聞の出所が「佐佐木三郎ト申武士説」であることを知る。彼は義経勢に加わっている佐々木三郎盛綱であるが、兼実はなおも「義経未進飛脚、不審尚残」として慎重な姿勢を崩していない(『玉葉』元暦二年三月廿八日条)。
翌3月29日、権中納言定能が兼実邸を訪問し「語平氏之間事、如昨日定長語」(『玉葉』元暦二年三月廿九日条)という。
そして4月3日夜、「追討大将軍義経」からの飛脚が届いた旨が報告された(『玉葉』元暦二年四月四日条)。飛脚に副えられた札によれば、「去三月廿四日午刻、於長門国団合戦、於海上合戦云々、自午正至哺時、云伐取之者、云生取之輩、不士知其数、此中前内大臣、右衛門督清宗内府子也、平大納言時忠、全真僧都等為生慮云々、又宝物等御座之由、同所申上也、但旧主御事不分明」という。法皇は平時は兼実を敬遠しているが、兼実ほど故実に通じた現役公卿はなく、今回も「事何様可被行哉」と兼実に諮問している(『玉葉』元暦二年四月四日条)。翌4月4日にも義経の使者「源兵衛尉弘綱」が入京し、「註傷死生虜之交名、奉 仙洞」という(『吾妻鏡』元暦二年四月四日条)。おそらく鎌倉へ下した交名と同じ内容であったと思われるが、前述の『醍醐雑事記』の内容とは若干の相違を見る。
●『註傷死生虜之交名』(『吾妻鏡』元暦二年四月十一日条)
そして4月4日早旦、兼実は「於長門国誅伐平氏等了」を聞き、午後を回って未刻、「為大蔵卿泰経奉行、義経伐平家了由言上」につき、法皇より兼実に「有可被仰合事、可参入之由、被仰下之」という指示が届く。兼実は持病の腰痛の灸治に事寄せて参院を渋り「相労今両三日之間、可参之由」(『玉葉』元暦二年四月四日条)の返答をしている。法皇に対する不信による事実上の参院拒否であった。しかし、事は重大であり、頭弁光雅が院使として九条邸に遣わされ、義経からの報告の詳細が説明された。
翌4月5日、法皇は院北面「大夫尉信盛」を勅使として長門国へ派遣し、その大功を称賛するとともに、「宝物等無為可奉入之由」を義経に命じたのであった(『吾妻鏡』元暦二年四月五日条)。
また、4月11日には鎌倉にも義経の使者が到着している。このとき、鎌倉では故源義朝の遺骨を祀る御願寺南御堂(勝長寿院)の立柱の儀が執り行われており、頼朝もそこに臨んでいた。ここに義経からの「申平氏討滅之由、廷尉進一巻記」が届けられ、「藤判官代」が頼朝の御前で読み上げた(『吾妻鏡』元暦二年四月十一日条)。ただ、頼朝や義経が法皇から厳命されていたであろう神器については「内侍所神璽雖御坐、宝剣紛失」であり、二位尼とともに赤間関沖に入水した宝剣は海中に没し、義経は「愚慮之所覃奉捜求之」という報告に留まった。
その後、頼朝は書簡を手に取ると「向鶴岳方令坐給、不能被発御詞」(『吾妻鏡』元暦二年四月十一日条)であったという。柱立上棟の儀が終了すると、急ぎ御所へ帰営。義経からの使者を召すと、合戦の状況をつぶさに訪ねたという(『吾妻鏡』元暦二年四月十一日条)。そして、頼朝は迅速な戦後処理を行うべく営中にて群議を行い、「参州暫住九州、没官領以下事可令尋沙汰之」と「廷尉相具生虜等可上洛之由」を定め、雑色の時澤・里長らを九州へ派遣した(『吾妻鏡』元暦二年四月十二日条)。
義経の使者からの報告を受けた頼朝は、義経の軍功を評価して「予州事」とある通り、御分国の一つ伊予国の国司に推挙した。具体的な日にちは分かっていないが、「去四月之比、内々被付泰経朝臣畢」とある通り、四月中であったことは確かである。また、義経からの報告には法皇の内示によるとみられる任官者(頼朝の推挙なき自由任官)の報告があったと考えられ、頼朝は4月15日、「関東御家人、不蒙内挙、無巧兮多以拝任衛府所司等官」につき、「不云先官当職、於任官輩者、永停城外之思、在京可令勤仕陣役」として、東国に戻ろうとする者は本領を没収し、斬罪とする旨を通達したという(『吾妻鏡』元暦二年四月十五日条)。
その後、4月21日に鎌倉に届いた梶原使者から義経の「而彼不義等雖令露顕」したという。その「不義」は「伊予守」補任を白紙とする程のものであったようだが、「今更不能被申止之、偏被任勅定」であるという(後述のように奏上の撤回は可能であったろう)。これが事実であるとすれば義経への伊予守任官の推薦は、義経の使者到着の4月11日から「不義」露顕の21日までの間となろう。なお、4月14日に「大蔵卿泰経朝臣使者参着関東、追討無為、偏依兵法之巧也、 叡感少彙之由可申之趣、所被 院宣也」(『吾妻鏡』元暦二年四月十四日条)とあることから、頼朝が義経の伊予守任官の推薦を託したのはこの使者と考えられ、同時に翌15日に内挙を経ない自由任官の警告を発したと考えられる。
これらは「自由拝任」者への強い警告であるが、自由拝任自体の罪科はもちろんだが、そもそも任官とは「或以上日之労賜御給、或以私物償朝家之御大事、各浴 朝恩事也」である習いの中で、「徒抑留庄園年貢、掠取国衙進官物、不募成功、自由拝任、官途之陵遲已在斯、偏令停止任官者、無成功之便者歟」という、頼朝が寿永二年十月宣旨で下されて以降も法皇から要求されながら、当の「東国之輩」が「徒抑留庄園年貢、掠取国衙進官物」ことを犯し、成功も行わず勝手に拝任し、官途がすでに意味をなくしている状況だが、ここで任官者の官職を停止させれば成功の意味もなくしてしまうと述べる。一向に解決できない庄園国衙領の保障に対する問題と同時に、官途の秩序に対する強い思いが感じられる。
この問題は、具体的には「内藤六が周防のとを以志をさまたけ候、以外事也」(『吾妻鏡』元暦二年正月六日条)というものや、「淡路国広田庄者、先日被寄附広田社之處、梶原平三景時為追討平氏、当時在彼国之間、郎従等乱入彼庄、妨乃貢歟」(『吾妻鏡』元暦元年十月廿七日条)や「武勇之輩耀私威、於諸庄園致濫行歟、依之去年春之比、宜従停止之由、被下綸旨訖、而関東以実平、景時、被差定近国惣追補使之處、於彼両人者雖存廉直、所捕置之眼代等各有猥所行之由、漸懐人之訴」(『吾妻鏡』元暦二年四月廿六日条)という、御家人自身による狼藉、眼代による濫行が訴えられており、こうした濫行狼藉を行った当の御家人が、成功もせず勝手な任官を求める状況に怒った頼朝が、彼らの狼藉を禁じる一方で、武士の統率と国家秩序の維持のための自由拝任の禁止を再度通達したものであろう。
頼朝は以前にも「朝務等」以下四か条の要求を行っているが、その際にも任官は頼朝の推挙によって行うものとしており、平家の脅威が去った今、綱紀粛正が図られたということとみられる。師岡右兵衛尉重経のような相当以前に任官している人々も対象となる「不云先官当職於任官輩者」の東帰禁止という難題も、絶対的権威たる朝廷から軽々しく官職を求めることの戒め、また拝任したのであれば覚悟を以て京洛以外のことは一切捨て、命がけで務めよ(自身がその任に相応しい者か弁えよ)という、あくまでも頼朝の強烈な意志を御家人らに知らしめるためのジェスチャーであり、こき下ろされた任官御家人らの中で実際に罰せられた者はいない(ただし、実際に御家人の列から脱した人などに対しては解官要求をしている)。
なお、義経の左衛門少尉・検非違使補任もこの自由拝任の認識と混同する傾向があるが、義経の任官に頼朝の推挙があったのは確実で、この自由拝任に対する御家人への下文と、後日の義経への譴責にはなんら関係はない。
●件名字載一紙面々被注加(『吾妻鏡』元暦元年四月廿六日条)
| 人名 | 実名 | 続柄 | 任官(初出) | 内容 |
| 兵衛尉義廉 | 不詳 | 不詳 | 不詳 | 鎌倉殿ハ悪主也、木曽ハ吉主也ト申シテ、始父相具親昵等、令参木曽殿ト申テ、鎌倉殿祗候セバ、終ニハ落人ト、被處ナントテ候シハ、何令忘却歟希有悪兵衛尉哉 |
| 兵衛尉忠信 | 佐藤四郎兵衛尉忠信 | 佐藤庄司四男 | 元暦二(1185)年 2月19日 |
秀衡之郎等、令拜任衛府事、自徃昔未有、計涯分、被坐ヨカシ、其氣ニテヤラン、是ハイタチニヲヅル |
| 兵衛尉重経 | 師岡兵衛尉重経 | 河越重頼弟 義経義兄 |
寿永元(1182)年 8月12日 |
御勘当ハ、粗被免ニキ、然者可令帰府本領之處、今ハ本領ニハ、不被付申之 |
| 渋谷馬允 | 渋谷右馬允重助 | 渋谷庄司重国子 | 不詳 | 父在国也、而付平家令経廻之間、木曽以大勢攻入之時付木曽留、又判官殿御入京之時又前参、度々合戦ニ心ハ甲ニテ有ハ、免前々御勘当可被召仕之處、衛府シテ被斬頚ズルハ、イカニ能用意ニ語于加治テ、頚玉ニ厚ク頚ニ可巻金也 |
| 小河馬允 | 不詳 | 不詳 | 不詳 | 少々御勘当免テ、可有御糸惜之由思食之處、色樣不吉、何料任官ヤラン |
| 兵衛尉基清 | 後藤新兵衛尉基清 | 後藤兵衛尉実基養子 ※一条能保家人 |
元暦元(1184)年 6月1日 |
目ハ鼠ノ眼ニテ、只可候之處、任官希有也 ※院厩案主(元暦元年) ・木村真美子氏『中世の院御厩司について:西園寺家所蔵「御厩司次第」を手がかりに』 |
| 馬允有経 | 不詳 | 不詳 | 不詳 | 少々奴、木曽殿有御勘当之處、少々令免給タラバ、只可候ニ五位ノ補馬允、未曾有事也 |
| 刑部丞友景 | 梶原刑部丞朝景 | 梶原平三景時弟 | 元暦2(1185)年 4月15日 |
音樣シワカレテ、後鬢サマテ刑部ガラナシ |
| 同男兵衛尉景貞 | 梶原兵衛尉景貞 | 梶原刑部丞朝景 | 元暦2(1185)年 4月15日 |
合戰之時心甲ニテ有由聞食、仍可有御糸惜之由思食之處、任官希有也 |
| 兵衛尉景高 | 梶原兵衛尉景高 | 梶原平三景時二男 | 元暦2(1185)年 4月15日 |
悪気色シテ、本自白者ト御覧セシニ、任官誠ニ見苦シ |
| 馬允時経 | 中村右馬允時経 | 中村貫主時重子 | 元暦2(1185)年 4月15日 |
大虚言計ヲ能トシテ、エシラヌ官好シテ、揖斐庄云不知アハレ水駅ノ人哉、悪馬細工シテ有カシ |
| 兵衛尉季綱 | 不詳 | 不詳 | 元暦2(1185)年 4月15日 |
御勘当、スコシ免シテ有ヘキ處、無由任官哉 |
| 馬允能忠 | 本間右馬允義忠 | 海老名源八季貞子 | 元暦2(1185)年 4月15日 |
御勘当、スコシ免シテ有ヘキ處、無由任官哉 |
| 豊田兵衛尉 | 豊田兵衛尉義幹 | 石毛三郎政幹子 | 元暦2(1185)年 4月15日 |
色ハ白ラカニシテ、顏ハ不覚気ナルモノ、只可候ニ、任官希有也、父ハ於下総度々有召ニ不参シテ、東国平ラレテ後参ル、不覚歟 |
| 兵衛尉政綱 | 関政綱 | 関太郎五郎政家子 | 元暦2(1185)年 4月15日 |
|
| 兵衛尉忠綱 | 足利忠綱 | 足利俊綱子 | 元暦2(1185)年 4月15日 |
本領少々可返給之處、任官シテ、今ハ不可相叶、嗚呼人哉 |
| 馬允有長 | 不詳 | 不詳 | 元暦2(1185)年 4月15日 |
|
| 右衛門尉季重 | 平山右衛門尉季重 | 元暦2(1185)年 4月15日 |
久日源三郎、顔ハフワヽトシテ、希有之任官哉 | |
| 左衛門尉景季 | 梶原源太左衛門尉景季 | 梶原平三景時長男 | 元暦2(1185)年 4月15日 |
|
| 縫殿助 | 不詳 | 不詳 | 元暦2(1185)年 4月15日 |
|
| 宮内丞舒国 | 不詳 | 不詳 | 元暦2(1185)年 4月15日 |
於大井渡、声樣誠臆病気ニテ、任官見苦事歟 |
| 刑部丞経俊 | 首藤山内刑部丞経俊 | 元暦2(1185)年 4月15日 |
官好無其要用事歟、アワレ無益事哉 | |
| 右衛門尉友家 | 八田右衛門尉知家 | 元暦2(1185)年 4月15日 |
件両人下向鎮西之時、於京令拝任事、如駘馬之道草喰、同以不可下向之状如件 ※治承五年閏二月廿三日以降、右衛門尉任官まで「武者所」。八田四郎武者。 |
|
| 兵衛尉朝政 | 小山兵衛尉朝政 | 元暦2(1185)年 正月26日 |
件両人下向鎮西之時、於京令拝任事、如駘馬之道草喰、同以不可下向之状如件 ※元暦元年九月二日、小山小四郎朝政、下向西海可属参州之由被仰云々、又彼官途事所望申左右兵衛尉也 |
|
| 此外輩 | 其數雖令拝任、文武官之間、何官何職分明不知食及之故、委不被載注文、雖此外、永可令停止城外之思歟矣 |
元暦2(1185)年4月12日、頼朝は範頼に「参州暫住九州、没官領以下事、可令尋沙汰之」の指示、義経に「廷尉相具生虜等可上洛之由」を伝える使者(頼朝雑色の時澤、里長)を遣わした(『吾妻鏡』元暦二年四月十二日条)。義経はこの指示を待たずに神器や捕虜を擁して上洛の途に就いているが、このとき範頼も上洛せずに九州に駐屯していて、実質的に12日の関東指示と同じ行動がとられていることから、この使者が遣わされる以前に、すでに戦後に関する頼朝の指示は両将軍に伝えられていたと考えるのが妥当だろう。なお、この使者は常胤を「鎮西奉行」に補任し、範頼を補佐する指示も伝えていたと思われる。
そして文治元(1185)年9月26日、九州で平家没官領の処理に当たっていた「蒲冠者範頼」が入洛している(『玉葉』元暦二年九月廿六日条)。もともと範頼は、頼朝から「八月中可参洛之由」を命じられていたが、「依風波之難遅留」し「今月相搆可入洛」と鎌倉へ使者を送っている(『吾妻鏡』文治元年九月廿一日条)。
範頼はその後鎌倉へ帰還するが、郎従は京都に残されている。これは行家への対応であろう。常胤ら扈従の御家人もともに関東へ下向したとみられる。範頼下向の具体的な日は不明だが、勝長寿院供養の導師である七十六歳の公顕僧正を伴う下向であり、行程は二十日程度と考えられる。彼らの鎌倉下着は10月22日であることから、出京は10月初旬であろう。
文治元(1185)年10月24日、勝長寿院供養が行われた際、常秀は随兵十六名の一人に選ばれている。祖父の千葉介常胤、父の胤正、叔父の師常、胤信、胤頼、一族の天羽次郎、臼井六郎、印東四郎もこれに列した。
◎勝長寿院供養に見える千葉氏
| 先陣随兵 | 14人 | 千葉太郎胤正 | ||
| 五位六位 | 32人 | 千葉介常胤 | 千葉六郎大夫胤頼 | |
| 随兵 | 16人 | 千葉平次常秀 | ||
| 後陣随兵 | 60人 (弓馬達者) |
千葉四郎胤信 | 天羽次郎 | 臼井六郎 |
| 馬三十疋を 導師に曳き渡す |
一ノ馬 | 千葉介常胤 | ||
| 九ノ馬 | 千葉二郎師常 | 印東四郎 |
翌文治2(1186)年5月14日、「左衛門尉祐経、梶原三郎景茂、千葉平次常秀、八田太郎朝重、藤判官代邦通等、面々相具下若等、向静旅宿、玩酒催宴、郢曲尽妙、静母磯禅師又施芸」(『吾妻鏡』文治二年五月十四日条)と、工藤祐経を始めとする人々が上酒を持参して静御前の旅宿を訪れて酒宴を行った。静の無聊を慰めるものか静の舞踊を期待したものかはわからないが、彼らはそれぞれ得意の楽器を奏で歌唱し、静の母が舞踊する京馴の酒宴だったとみられる。工藤祐経は「鼓」「今様」に長けており(『吾妻鏡』元暦元年四月廿日条)、景茂の兄弟「景季」は「神楽曲」、「景高」は「唱歌」を修めているように景茂も音曲には嗜みがあったと思われる。「藤判官代邦通」は「邦道者、洛陽放遊客也」(『吾妻鏡』治承四年八月四日条)とあるように京都の人物であり、彼らはいずれも京都と深く関わる人物で「馴京都輩」であったのだろう。
建久8(1187)年3月23日には、頼朝の「善光寺参詣随兵」として、後陣に父「千葉新介」とともに「千葉平次兵衛尉」が見える(「右大将家善光寺御参随兵日記」『相良家文書』)。父の千葉新介胤正とは別家として侍所に把握されていたことが確認される。
●建久8(1187)年3月23日「右大将家善光寺御参随兵日記」(『相良家文書』1)
| 随兵先陣 | 佐原十郎左衛門尉(義連) | 長江四郎(明義) |
| 千葉次郎(師常) | 和田次郎(義茂) | |
| 武田兵衛尉(有義) | 平井四郎 | |
| 里見太郎(義成) | 里見五郎 | |
| 伊澤五郎(信光) | 南部三郎(光行) | |
| 加々美次郎(長清) | 村山七郎(義直) | |
| 浅利冠者 | 新田蔵人(義兼) | |
| 村上判官代(基国) | 佐竹別当 | |
| 所雑色(基繁) | 橘次(公業) | |
| 江間太郎(泰時) | 小山七郎(朝光) | |
| 随兵後陣 | 千葉新介(胤正) | 葛西兵衛尉(清重) |
| 北条五郎(時房) | 佐々木五郎(義清) | |
| 千葉平次兵衛尉(常秀) | 梶原刑部兵衛尉(景定) | |
| 八田太郎左衛門尉(知重) | 江戸太郎(重長) | |
| 土屋兵衛尉(義清) | 長井六郎 | |
| 佐々木三郎兵衛尉(盛網) | 加藤次(景廉) | |
| 梶原源太左衛門尉(景季) | 野三刑部丞(盛綱) | |
| 望月三郎(重隆) | 相良四郎(頼景) | |
| 海野小太郎(幸氏) | 藤沢四郎(清親) | |
| 小山五郎(宗政) | 三浦平六兵衛尉(義村) |
常秀はその後、2年ほど『吾妻鏡』から姿を消す。この間、上洛していた可能性があろう。
文治5(1189)年8月12日、奥州藤原泰衡追討戦では、海道大将となった千葉介常胤に従って出陣。父の胤正はじめ、叔父の師常・胤盛・胤信・胤通・胤頼、兄の成胤とともに平泉平定に功績を挙げた。翌文治6(1190)年正月には奥州藤原氏の遺臣が挙兵して平泉を攻め落とすが、この際には父・胤正が海道大将軍として鎌倉から下向している。兄・成胤もこの合戦に加わっているが、頼朝は兄・成胤に対して「千葉小太郎、今度奥州合戦抽軍忠之間、殊有御感」(『吾妻鏡』文治六年正月十五日条)と賞賛する一方で、「但合戦不進于先登兮、可慎身之由」という注意をしていることから、成胤自ら先頭に立って奮戦した様子がうかがえる。これは成胤が父・胤正同様、頼朝に特に気に入られて近習として抜擢されていたためと思われ、成胤は別格であった。
11月7日、常秀は頼朝入洛に際して「先陣六十番」のひとりとして供奉。頼朝は後白河院と後鳥羽天皇に拝謁した。このとき頼朝は権大納言・右近衛大将に任じられた。翌12月2日、頼朝の「御直衣始」に際しては随兵として供奉。11日、常秀は祖父・常胤の勲功を譲られて「左兵衛尉」に任官した。この任官は後述の通り、常秀が「馴京都之輩」かつ、平家(または奥州の)合戦で軍功があったためと推測できる。
その後は頼朝の側近くに仕え、建久5(1194)年12月26日、鎌倉二階堂の永福寺に新築に作られた薬師堂供養に叔父の胤頼とともに供奉。建久6(1195)年、頼朝は再び上洛のために供奉の人数をそろえていたが、頼朝に滅ぼされた源義経・源行家の残党が不穏の動きをしている噂があったため、2月12日、「勇敢」の名の高い比企能員・千葉常秀らが先発隊として派遣され、頼朝の本隊が続いた。そして3月10日、奈良の東大寺供養に出席した頼朝に供奉し、叔父の「千葉二郎師常、千葉六郎大夫胤頼」と列席した。27日の参内には三浦義村とともに「随兵八騎」の一人として供奉した。5月20日の天王寺参詣に随兵として供奉。6月3日の「若公万寿(頼家)」参内にも供奉した。
正治2(1200)年2月26日、頼家の鶴岡八幡宮参詣に、小山朝政らとともに供奉し、建仁3(1203)年10月8日、頼朝の次男・千幡(実朝)の元服式に、佐々木広綱らとともに鎧・馬などを奉じている。11月15日に鎌倉中の寺社奉行が定められた際には薬師堂の奉行に任じられている。また、12月14日の永福寺供養にも供奉している。
元久元(1204)年10月14日、将軍・実朝の御台所として坊門信清息女を鎌倉に迎えるため、北条時政と牧ノ方の子・北条政範(左馬権助)を筆頭に、京都を良く知る若者12人、すなわち結城朝広(七郎)・千葉常秀(平次兵衛尉)・畠山重保(六郎)・筑後朝尚(六郎)・和田朝盛(三郎)・土肥惟光(先次郎)・葛西清宣(十郎)・佐原景連(太郎)・多々良明宗(四郎)・長江義景(太郎)・宇佐美祐能(三郎)・佐々木小三郎・南條平次・安西四郎が上洛の途についた。なお、牧の方は時政の後妻として権勢を振るった女性である(牧の方の出自について)。『吾妻鏡』では御台所迎えの武士は十五名だが、『明月記』においては「来迎武士廿人」(『明月記』元久元年十二月十日条)とある。
千葉介常胤 +―千葉介成胤
(千葉介) | (千葉介)
∥ |
∥――――――千葉介胤正―+―千葉常秀
秩父重弘―+―女 (千葉介) (平次兵衛尉)
(秩父庄司)|
|
+―畠山重能―――畠山重忠
(畠山庄司) (次郎)
∥―――――――畠山重保
∥ (六郎)
北条時政―――女
∥
∥ 平賀朝雅
∥ (武蔵守)
∥ ∥
∥――+―女
牧ノ方 |
+―北条政範
(左馬権助)
一向は11月3日、京都に到着したが、政範は「自路次病悩」しており(『吾妻鏡』元久元年十一月十三日条)、上洛早々の11月5日に「遂及大事」んだ(『吾妻鏡』元久元年十一月十三日条)。享年十六。翌6日には「東山辺」に葬られた(『吾妻鏡』元久元年十一月廿日条)。在京中には「二人死去馬助、兵衛尉」と政範ともう一名が死去しているが名は伝わらない。ただし事件性はないとみられ、欠員の「其替親能入道子」を追加するが「今一人猶欠」であった(『明月記』元久元年十二月十日条)。11月13日、政範の死が鎌倉にもたらされ、時政と牧ノ方は悲嘆に暮れたという。
政範卒去の前日の4日、六角東洞院にある平賀武蔵前司朝雅の邸で上洛祝いの酒宴が執り行われたが、この席で畠山重保と朝雅が争論を起こした。朋輩がなだめたため事なきを得たが、争論の原因は政範の病悩と関係があったのだろう。朝雅と重保の争論は時政の怒りを買い、重保を含め、娘婿の重忠をも非としたのだろう。
元久2(1205)年6月22日、謀反人とされた畠山重忠を討つための幕府軍では、後陣を千葉一族が固めており「堺平次兵衛尉常秀、大須賀四郎胤信・国分五郎胤通・相馬五郎義胤・東平太重胤」が出陣した。大須賀胤信は常秀の叔父、義胤・重胤は従兄弟にあたる。常秀はその後も幕府の重鎮として将軍家に伺候し、諸処に供奉している。
建暦3(1213)年2月15日、信濃国の泉親衡が故将軍・源頼家の次男である千寿を将軍に擁立する企てが発覚した。この謀叛の企ては、親衡の使僧・安念房が千葉介成胤を説得に来て、逆に捕縛されて義時に突き出されたことでおおやけとなった。この企てには御家人百三十余人、伴類二百人が加わっていたが、和田義盛の子・和田義直、義重、甥の和田胤長らの名もあったことから、騒ぎは大きくなった。この事後処理の問題によって、和田義盛が挙兵して滅ぼされることとなるが、すべて北条氏による筋書きであった可能性がある。
この叛乱に加わった人物の中に「上総介八郎甥臼井十郎」の名が見える。「臼井十郎」とは臼井太郎常忠の十男・臼井十郎俊常のことと思われ、俊常は「上総介八郎」広常の甥だったことがわかる。広常挙兵の際に下総国の臼井氏が広常に従ったのは、臼井氏と広常が近親だったためであろう。
平常兼――+―平常澄――+―平広常――――平能常
(上総権介)|(上総権介)|(介八郎) (小権介)
| |
| +―娘
| ∥――――――臼井常俊
| ∥ (十郎)
+―臼井常安―――臼井常忠
(六郎) (太郎)
承久元(1219)年正月27日、実朝が右大臣拝賀のために鶴岡八幡宮寺に参詣の際、従兄弟の東兵衛尉重胤とともに供奉したが、このとき実朝は甥の別当公曉(こうぎょう。頼家の子)によって暗殺された。公暁は実朝(および北条義時か)を「親ノ敵」と吹き込まれており、実朝の首を取ったのち、三浦義村の館に遁れようとしたとき、鶴岡八幡宮の裏山で三浦義村の郎従・長尾定景によって殺害され、その首は義村によって北条邸に持参されている。
常秀は千葉一族内部ではどのような地位にあったのであろうか。彼は源氏勢が平家を西海に攻めた際には、千葉一族として常胤のもと唯一参陣している。一方で父の胤正や兄の成胤は平家との戦いにはまったく出兵した形跡がない。胤正や成胤は千葉惣領家を継承する身であることに加え、成胤は頼朝から「但合戦不進于先登兮、可慎身之由」」(『吾妻鏡』文治六年正月十五日条)という注意を受けているように、頼朝のお気に入りの側近として出仕していた可能性があり、戦いには老体ながら京都までその名が知られていた祖父・千葉介常胤が蒲冠者範頼を支える老練の大将として加わった。
その後、「通説」によれば、常秀は祖父・常胤から下記のような多大な地頭職を譲られたとされる。しかし、それは事実なのだろうか。実は下記に見える所領について、常秀が常胤から継承したということを示す史料は一切存在しない。ただし、状況証拠として見れば、常秀の子・上総権介秀胤が薩摩国内にあった千葉介常胤(「当御庄寄郡五箇郡者、以常胤令補郡司職了」)由緒の地頭職を継承した形跡があるため、薩摩国内の没官領地頭職については、千葉介常胤から譲られた可能性は高いだろう。その所領については下記に検証する。
●常秀が伝領したとされる所領(通説)→見え消しは根拠の薄いもの
| 上総国 | 山辺北郡堺郷 市東郡・市西郡 玉﨑庄 武射南郷 |
| 下総国 | 埴生庄 埴生西条 印西庄 平塚郷 |
| 薩摩国 | 島津庄寄郡五箇郡郡司職(文治二年八月三日「源頼朝下文」『鎌倉遺文』) 没官御領四一一町地頭職 |
| 豊前国 | 上津毛郡内成恒名 |
●常秀の有した地頭職・請所(推定)
| 上総国 | 市東郡・市西郡(請所→辞職) 玉崎庄(常秀領有の根拠はないが、長男の秀胤が領有しており、常秀から継承の可能性もある) ※武射北郡境郷(可能性のひとつ) |
| 下総国 | 千葉庄境 埴生庄 匝瑳南条庄 |
| 薩摩国 | 島津庄寄郡五箇郡※郡司職 ※下記(1)~(5)の「寄郡」 高城郡 (1)公領(但し万得除く) (2)東郷別符内公領 薩摩郡 (3)入来院 (4)祁答院 甑島郡 (5)甑島 上記内の没官領三百七十八町(薩摩国内没官領では四百十一町)の地頭職 |
| 大隅国 | 島津庄大隅方「菱刈郡」内「入山村筥崎宮浮免田」(面積不明) |
●上総国山辺北郡堺郷、武射北郡堺郷
上総国山辺北郡堺郷については、前述の通り、通説では現在の東金市丹尾ともされるが遺称地はなく、慎重を期すべきである。また、上総国武射北郡堺郷(武射郡芝山町境)も名字地の候補であるが、これら両方の地は、
(1)千葉庄からは隔絶した土地であること
(2)治承4(1180)年当時、二十歳前後(兄成胤が24歳)の常秀が遠境に入部することは考えにくいこと
(3)千葉氏との関わりで当地が一切史料に見えないこと
以上の事から、治承4(1180)年8月の段階で、常秀の名字地とするのは疑問が大きい。常秀が千葉名字を主として使いながらも「堺」名字を用い始めた建久5(1194)年以降にこの地を給わった(鎌倉家政所または千葉介常胤譲)とすれば、上総国山辺北郡堺郷、または上総国武射北郡堺郷(武射郡芝山町境)が名字地となった「可能性」はある。どちらかといえば、承久元(1219)年8月8日、「大檀那平常秀 平氏」が薬師如来を納めた古屋薬王院(匝瑳南条庄)と同じ栗山川水系にある上総国武射北郡堺郷(武射郡芝山町境)が可能性としては高いだろう。匝瑳南条庄については下記。
ただし、常秀の子・太郎秀胤(上総権介)や下総次郎時常が「境(堺)」を名字としたことはなく、とくに秀胤は「千葉」名字のみを名乗り、「千葉上総権介秀胤」として寛元2(1244)年に評定衆に列している(『関東評定伝』寛元二年甲辰条)ことを考えると、「境(堺)」は千葉庄内の地である可能性が高いのではなかろうか。
●上総国市東郡、市西郡
上総国市東郡、市西郡については「市東西常秀請所」であった(『鎌倉遺文』3562)。常秀は市東郡、市西郡にあった地頭領を除く公領を管理していたとみられるが、ある年の「新介」補任のとき「一定辞申請所」という。ところが、いざ国検を行うに当たって常秀は国検を拒絶したようだ。しかし、請所であっても国司の「一任度可遂国検」は行われる規則であり、ましてや常秀は請所を「况已辞退申了」しており、なんら検注に関わる資格のない人物として、目代ら国衙側は検注すべしと実務官に催促している(『鎌倉遺文』3562)。
治承4(1180)年9月19日、上総介八郎広常が隅田川の頼朝の陣に参向した際、広常率いる軍勢は「当国周東、周西、伊南、伊北、庁南、庁北輩等」の約二万騎だったという(『吾妻鏡』治承四年九月十九日条)。しかし、この中には本来は真っ先に挙げられるべき国府を擁する「市東」「市西」が含まれておらず、広常は当時国衙を掌握していなかったと考えられる(当時の広常は庶子であり、公官を有していない)。当時の上総国衙には在京の上総介藤原忠清が派遣した目代(平重国か)が存在しており、彼の勢力が市東西の公領及び私領を抑えていたのだろう。頼朝が広常を頼ろうとした際に、安西屋敷から一宮方面へ向かったのも、広常が一宮付近に居住していたためであろう。
●「書陵部蔵九条家本中右記/元永元年秋巻紙背文書」(『鎌倉遺文』3562)
●上総国玉崎庄
上総国玉崎庄については、上総平氏の本拠地で上総国長柄郡一宮(玉前社)一帯の庄園だが、常秀がこの地を常胤から譲られた史料はない。そもそも上総介八郎広常が誅殺されたのち、常胤が上総国内の広常遺領に地頭職を有した史料も形跡もまったくないのである。
ただし、常秀の子・秀胤は「上総国一宮大柳之舘」(長生郡睦沢町大谷木)を保有しており、秀胤が「上総権介」に補任される根拠のひとつで、「上総介」を公称(介八郎広常同様、正式な補任ではなく公称であり、正式な官途は下総守)した常秀からの継承であった可能性が考えられる。
●上総国武射南郷
上総国武射郡南郷(山武市上横地西部一帯)。南郷は上総平氏の所領であったが、この地がなぜ常秀と関わりをもって語られるのかは不明。
●上総国諸所
宝治元(1247)年7月14日、「足利左馬頭正義、依今度合戦賞、拜領上総権介秀胤遺跡」(『吾妻鏡』宝治元年七月十四日条)とあるように、足利義氏入道正義は「上総権介秀胤遺領」を宝治合戦の恩賞として給わる。具体的な「遺領」は不明だが、下記の下総国埴生庄のほかは不明。
鎌倉期の足利家領地には奉行人が置かれており、足利貞氏代に作成されたと考えられる『足利氏所領奉行人交名』には守護国として「上総国」「参河国」が載せられ、それぞれ担当奉行人が記されている。鎌倉時代後期の足利家は上総国には「市東西両郡」の地頭職を有している。「市東西両郡」はかつて常秀の請所であったが、その後辞しており、常秀の流れで継承した地ではなく、足利義兼が上総介に補任された際に受けた地と考えるのが妥当か。
奉行人に名を見せる根本被官のうち、上総国に所領を有したのが、有木氏、村上氏、倉持氏、粟飯原氏で、有木氏、村上氏は上総国市原郡の氏族である。倉持氏、粟飯原氏は下総国千田庄を本貫とする氏族だが、倉持氏の所領は市西郡にあった。粟飯原氏は下総千葉氏の有力被官にして妙見信仰と深く関わる一族だが、建武2(1335)年9月24日、足利尊氏が「篠村八幡宮」に「上総国梅佐古粟飯原五郎跡」を寄進しているように上総国に所領を持つ、足利家根本被官となった一族もあった。宝治元(1247)年7月14日、「足利左馬頭正義、依今度合戦賞、拜領上総権介秀胤遺跡」(『吾妻鏡』宝治元年七月十四日条)とあるように、秀胤の遺領を拝領しているが、そのうち埴生庄で召されたのが倉持氏や粟飯原氏か(彼らは秀胤被官だった可能性もあろう)。
●『足利氏所領奉行人交名』(青森県『倉持文書』:『群馬県史』資料編所収)
倉持新左衛門尉(倉持家行)は、永仁4(1296)年3月11日、足利貞氏から陸奥国賀美郡穀積郷などを安堵され(永仁四年三月十一日「足利貞氏安堵状」『倉持文書』)、六年後の乾元2(1302)年閏4月12日、倉持家行の子左衛門尉次郎(倉持師経)は、足利貞氏から所領継承を認められている(乾元二年閏四月十二日「足利貞氏安堵状」『倉持文書』)。いずれも足利家領内からの扶持である。
●倉持氏所領
| 下野国 | 足利庄内赤見駒庭郷半分、同国府野屋敷給田畠、同木戸郷内屋敷田畠、同加子郷内屋敷田畠 |
| 陸奥国 | 賀美郡穀積郷、同沼袋郷半分、同中新田郷内屋敷田畠 |
| 上総国 | 市西郡内海郷、同勝馬郷内小堤田畠屋敷 |
| 相模国 | 宮瀬村 |
| 三河国 | 額田郡萱薗郷、同仁木郷内屋敷田畠、同便(賞)寺屋敷田畠 |
| 相模国 | 鎌倉屋地同屋形 |
●下総国匝瑳南条庄
常秀が承久元(1219)年に薬師如来を納めた古屋薬王院(横芝光町)は栗山川を南に望む崖上にあり、下総国南条庄に属する。常秀がこの地に薬師如来を収めていることは、この地が常秀と所縁のあった地に他ならない。しかし、下総国南条庄は暦仁元(1238)年12月17日時点で椎名氏が勢力を有しており(文永九年十二月廿七日「関東下知状」『鎌倉遺文』11169)、その後の常秀や秀胤の活動が見られないことから、すでに常秀はこの地を領していなかったのだろう。
●下総国垣生庄
下総国埴生庄(成田市西部~印旛沼畔)は、常秀の次男「下総次郎時常」が「相伝亡父下総前司常秀遺領」した所領で、「為秀胤被押領之間、年来雖含欝陶」(『吾妻鏡』宝治元年六月七日条)という土地であった。常秀から相伝したことが明記されており、常秀が下総国埴生庄の地頭職だったことは間違いない。
宝治元(1247)年7月14日、「足利左馬頭正義、依今度合戦賞、拜領上総権介秀胤遺跡、而相兼公私祈祷、以件上分、可奉寄太神宮之由、被伺申左親衛尤可然之旨免許、仍被遣寄進状於本宮」(『吾妻鏡』宝治元年七月十四日条)と、足利義氏入道正義は「上総権介秀胤遺領」を宝治合戦の恩賞として給わるが、そこからの「上分」を「可奉寄太神宮」したいと時頼に願い出て許されている。実際に埴生庄は足利家の「所領」となっており、埴生庄は「秀胤遺跡」に含まれていたことは確実である。
ところが、「足利左馬頭正義」から嫡子足利泰氏に相伝された「下総国恒生庄」は建長3(1251)年12月2日、「宮内少輔泰氏朝臣、所領於下総国恒生庄、潜被遂出家年三十六、即年来遂素懐云々、偏山林斗数之志挾焉」(『吾妻鏡』建長三年十二月二日条)とあるように、足利泰氏は鎌倉に無断で垣生庄で出家し、12月7日、「宮内少輔泰氏、自申出家之過、依之所領下総国恒生庄、被召離之、陸奥掃部助実時給之、是不諧之上、小侍別当労依危也」(『吾妻鏡』建長三年十二月七日条)と、埴生庄は足利家から金澤北条家に移った(「造営所役注文写」『香取神宮文書』)。
このほか、文化5(1808)年頃成立とみられる埴生庄龍角寺の略縁起ではあるが、「順徳院の御宇、承久二年庚辰、千葉家九代胤政六男、前の下総守平の常秀、当寺の破壊をかなしまれ修造を企るのところ、印旛沼津に材木を積、水主一人乗りて龍角寺造営のため施入し奉ると云置て失せぬ、常秀はじめ衆人ともに、さては本願龍女の使かと、これを悦び、感歎肝に銘じその材木をもつて本堂修造せられ又石灯篭一基建立せらる、今尚堂の前に存せり、沼津より五六町へだてて坂あり、材木を曳あげし地なれば字木引坂と申つたへける」(『下総国埴生郡龍角寺略縁起』)とも伝える。
●「造営諸役注文写」等『香取神宮文書』
| 式年造営 社殿等 |
担当諸役郡郷 ・地頭(雑掌人) 寛元元(1243)年? 「造営所役注文写」 | 担当諸役郡郷 ・地頭(雑掌人) 寛元元(1243)年? 「造営所役注文断簡」 | 担当諸役郡郷 ・地頭(雑掌人) 弘長元(1261)年~ 「造営記録断簡」 | 担当諸役郡郷 ・地頭(雑掌人) 康永4(1345)年3月 「造営所役注文」 |
| 正神殿 | (造営奉行人) ・千葉介 |
(造営奉行人) ・千葉介 | (造営奉行人) ・葛西新左衛門入道経蓮 |
(造営奉行人) ・千葉介貞胤 |
| (大床、舞殿) | 幸嶋 ・千葉介 |
幸嶋 ・不明 | ― | 当国上猿嶋郡 ・常陸前司跡 |
| 火御子社 | 萱田郷 ・千葉介か |
萱田郷 ・千葉介 | 建久以降始募立 用公田四ケ所当 ・千葉介頼胤 以遠山方二丁、 葛東二丁造進之 | 吉橋郷 ・千葉介 |
| 於岐栖社 | 吉橋郷 ・千葉介 |
吉橋郷 ・千葉介 | 吉橋郷 ・千葉介頼胤 | 吉橋郷 ・千葉介 |
| 一鳥居 | 印東庄 ・千葉介 |
印東庄 ・千葉介 | 印東庄 ・千葉介頼胤 | 印東庄 ・千葉介 |
| 勢至殿社 | 神保郷 ・千葉介 |
神保郷 ・千葉介 | 神保郷 ・千田尼 | 仁保代枝 ・千葉大隅守跡 |
| 不開殿社 | 小見郷 ・木内下総前司 |
小見郷 ・木内下総前司 | 小見郷 ・弥四郎胤直 | 小見郷 ・小見四郎左衛門入道跡 |
| 佐土殿社 (佐渡殿) | 匝瑳北条 ・千葉八郎 |
匝瑳北条 ・千葉八郎 | 匝瑳北條 ・地頭等 | 北條庄 ・飯高彦二郎 |
| [女盛]殿社 | 大戸庄 ・国分小次郎跡 神崎庄 ・千葉七郎跡 |
大戸庄 ・国分小次郎跡 神崎庄 ・千葉七郎跡 | 大戸庄 ・地頭等 神崎庄 ・地頭等 | 大戸庄 ・不明 神崎庄 ・不明 |
| 仮[女盛]殿 | ― | ― | ― | 大戸庄 ・不明 神崎庄 ・不明 |
| 東廊 | 風早庄 ・不明 | 風早郷 ・不明 | 風早郷 ・左衛門尉康常 | 風早庄 ・不明 |
| 中殿 | 垣生西 ・掃部助 |
垣生西 ・掃部助殿 |
垣生西條 ・越後守実時 | 大行事造進所々 |
| 北庁屋(庁屋) | 大須賀 ・胤信跡 |
大須賀 ・胤信跡 | 大須賀郷 ・地頭等 | 大須賀保 ・大須賀下総前司入道跡 |
| 南庁 | ― | ― | ― | 結城山川庄 ・結城七郎跡 ・山川判官跡 |
| 瞻男社 | ― |
垣生西内富谷郷 ・不明 | 垣生西條内富略 ・越後守実時 |
不明 ・不明 大行事造進所々 |
| 三鳥居 | 大方郷 ・関左衛門尉 |
大方郷 ・関左衛門尉 | 大方郷 ・諏方三郎左衛門入道真性 |
当国大方庄 ・不明 |
| 火王子社 (日王子社) | 下野方 ・不明 |
下野方 ・不明 | 下野方郷 ・武藤左衛門尉長頼 | 仁保代枝 ・千葉大隅守跡 |
| 息洲社 | ― | ― | ― | 仁保代枝 ・千葉大隅守跡 |
| 忍男社 | 下野方 ・不明 |
下野方 ・不明 | 下野方郷 ・武藤左衛門尉長頼 | 千田庄 ・不明 大行事造進所々 |
| 祭殿 | ― | 結城郡 ・下野入道 |
結城郡 ・上野介広綱等 | ― |
| 内院中門 | 匝瑳北条 ・飯高五郎跡 |
匝瑳北条 ・飯高五郎跡 | 匝瑳北条 ・地頭等 | 北條庄南北 ・飯高彦二郎以下輩 |
| 外院中門 | ― |
印西 ・掃部助殿 | 印西條 ・越後 |
印西 ・不明 |
| 西廊 | 矢木郷 ・不明 | 矢木郷 ・不明 | 矢木郷 ・式部大夫胤家 | 矢木庄 ・不明 |
| 若宮社 | (造営奉行人) ・千葉介 |
(造営奉行人) ・千葉介 | ― | |
| 東脇門 | 平塚郷 ・掃部助殿 |
平塚郷 ・掃部助殿 |
平塚郷 ・越後守実時 | 印西庄 ・不明 |
| 西脇門 | 平塚郷 ・掃部助殿 |
平塚郷 ・掃部助殿 |
平塚郷 ・越後守実時 | 印西庄 ・不明 |
| 酒殿 (高倉) | ― | 遠山方 ・不明 |
河栗遠山方 ・地頭等 |
遠山形 ・不明 |
| 渡殿 | ― | 上野方 ・不明 |
上野方郷 ・幸島地頭等 | ― |
| 宝殿 | 猿俣 ・壱岐入道跡 |
猿俣 ・壱岐入道跡 | 猿俣郷 ・葛西新左衛門入道経蓮 |
小鮎猿俣 ・葛西伊豆四郎入道 (葛西伊豆入道明蓮跡) |
| 二鳥居 | 下葛西 ・壱岐入道跡 |
下葛西 ・壱岐入道跡? | 葛西郡 ・伯耆左衛門入道経蓮 |
不明 ・葛西伊豆入道明蓮跡 |
| 楼門 | 埴生印西 ・不明 |
垣生印西 ・不明 | ― | 埴生印西庄 ・不明 |
| 内殿、 御輿、 諸神宝物 | ― | 国司御沙汰 | 正神殿雑掌 | 大行事造進所々 |
| 大炊殿 | 国司御沙汰 | 国司御沙汰 |
無足之間、 以庄々作料官米内、 為行事所沙汰、 造進之 | 大行事造進所々 |
| 薦殿 | 国司御沙汰 | 国司御沙汰 |
無足之間、 以庄々作料官米内、 為行事所沙汰、 造進之 | 大行事造進所々 |
| 脇鷹社 (脇鷹天神社) | 国司御沙汰 | 国司御沙汰 |
無足之間、 以庄々作料官米内、 為行事所沙汰、 造進之 | 大行事造進所々 |
| 鹿嶋新宮社 | 国司御沙汰 | 国司御沙汰 |
無足之間、 以庄々作料官米内、 為行事所沙汰、 造進之 | 大行事造進所々 |
| 馬場殿 (馬場殿社) | ― | 国司御沙汰 | ― | 大行事造進所々 |
| 八龍神社 | 国司御沙汰 | 国司御沙汰 | ― | 大行事造進所々 |
| 八郎王子社 | ― | 国司御沙汰 | ― | 大行事造進所々 |
| 玉垣卅一丈六尺 | 国司御沙汰 | 国司御沙汰 | 無足之間、 以庄々作料官米内、 為行事所沙汰、 造進之 | 大行事造進所々 |
| 雷神社 | ― | ― | ― | 大行事造進所々 |
| 印手社 | ― | ― | ― | 大行事造進所々 |
| 又見社 | ― | 国司御沙汰 | ― | 大行事造進所々 |
| 返田悪王子 | ― | 国司御沙汰 | ― | 大行事造進所々 |
| 御幣棚 | ― | (闕) | ― | 大行事造進所々 |
| 四面釘貫 四百五間 (四面八町釘貫) | 不明 | (闕) |
国分寺 ・弥五郎時道女房 | 大行事造進所々 |
| 馬庭埒 | 国分寺 | (闕) | ― | ― |
●下総国埴生西條
下総国埴生西条(印西市北部~白井市)。埴生庄とは香取海の湾(現印旛沼)を挟んだ西岸に位置する。
建長3(1251)年12月2日、足利泰氏の自由出家により「埴生庄」は足利家から金澤北条家に移されたが、埴生西條は埴生庄ではないことから足利家が地頭職だった根拠はなく(つまり常秀が地頭だった根拠もない)、地頭職は当初から金澤北条家だった可能性があろう。埴生庄が金澤北条実時に下されたのも、もともと金澤北条家が埴生西條(平塚郷や富谷郷)、印西(印西條、印西庄)の地頭職だったためか。
●下総国印西條
下総国印西庄(印西市南部)。鎌倉初中期に印西庄内に千葉一族や上総平氏流の氏族の名字地は見えないことから、この地も千葉氏由緒の所領とは言い難い。もともと金澤北条家が地頭職だったと考えられる。
ただし、相馬郡に近接していることや、印西庄「角田」が上総平氏流の相馬常清流角田氏の名字地であれば、上総平氏との関わりも考えられ、香取海の小弯(印旛沼)を挟んだ印東庄ともつながりを持っていた可能性はあろう。
●下総国平塚郷
下総国埴生西条平塚郷(白井市平塚)。この地及び南部の富谷郷(白井市復)は、当初より金澤北条家が地頭職を務めていたと考えられ、千葉一族や上総平氏一族の領有の痕跡はない。常秀が領有した根拠もない。
●薩摩国島津御庄寄郡五箇郡郡司職
千葉介常胤は薩摩国高城郡、薩摩郡、甑島郡内の島津庄寄郡を含む没官領「惣地頭」に補された。近衞家を本家とする島津庄は、薩摩国のみならず日向国(島津庄日向方)、大隅国(島津庄大隅方)にもまたがる広大な荘園で、庄内には公領ながら領家に官物を折半納付し、雑役は荘園領主へ納める(雑役免)の支配形態を持つ「寄郡」が形成されていた。
常秀祖父の千葉介常胤は平家との戦いののち、「元暦二(1185)年五月」までに「鎮西守護人」に補任されており(「建部清忠解状断簡」『禰寝文書』)、3月24日の壇ノ浦合戦直後にその職に就いたとみられる。具体的には、4月11日、「廷尉進一巻記中原信泰書之」が南御堂(勝長寿院)立柱式に届けられ、「去月廿四日於長門国赤間関海上、浮八百四十余艘兵船、平氏又艚向五百余艘合戦、午尅逆党敗北」(『吾妻鏡』元暦二年四月十一日条)が頼朝に報告された。これを受けて翌4月12日、頼朝は「平氏滅亡之後、於西海可有沙汰条々、今日被経群議」し、「参州暫住九州、没官領以下事、可令尋沙汰之、廷尉相具生虜等、可上洛之由、被定」られ、「雑色時澤、里長等、為飛脚赴鎮西」(『吾妻鏡』元暦二年四月十二日条)した。おそらくこの際に範頼に付けられていた常胤が範頼を補佐する「鎮西守護人」に補されたのだろう。
島津庄薩摩方においては「千葉介雖給惣地頭」とあるように、島津庄の高城郡、薩摩郡、甑島内没官領の「惣地頭」に補され、島津庄大隅方では寄郡の「菱刈郡」(138町1段)のうち、面積不明ながら「入山村筥崎宮浮免田」を沙汰した(「大隅国図田帳古写本」『桑幡家文書』)。大隅方については「千葉兵衛尉(常秀)」が「同(大将殿)御下文」によって支配根拠を得ていることから、千葉介常胤からの譲りではなく、建久2(1191)年)正月15日以前の頼朝御下文で直々に地頭職を受けたと考えられる。
●『薩摩国図田帳写』(建久八年六月)
※1 安楽寺:大宰府天満宮安楽寺
※2 弥勒寺:宇佐弥勒寺
※3 大隅正八幡宮:現鹿児島神宮
※4 万得御領:大隅八幡宮御領
| 合計(薩摩国全体) | 4,010.7 | |
| 一円国領 | 211(国衙領計) | |
| 寺社領 | 655(寺社領計) | |
| 安楽寺御領※1 | 154.4 | |
| 国分寺 | 104.5 | 郡々散在下司僧安静 |
| 天満宮 | 7.5 | 宮里郷内下司在庁道友 |
| 老松庄 | 24.4 | 山門院内 |
| 温田浦 | 18 | 高城郡内没官御領地頭千葉介 |
| 弥勒寺御領※2 | 196.1 | 領家即別当 |
| 五大院 | 91.1 | 郡々散在下司僧安慶 |
| 八幡新田宮 | 35 | 郡々散在下司僧経宗 |
| 八幡新田宮比野 | 15 |
入来院内没官領地頭千葉介 御下司在庁種明 |
| 日置庄 | 30 | 入来院北郷内下司小野太郎家綱 |
| 益山庄 | 25 | 加世田別符内下司塩田太郎光澄 |
| 大隅正八幡宮御領※3 | 225 | |
| 一円御領荒田庄 | 80 | 鹿児島郡内地頭掃部頭 |
| 万得御領※4 |
145.3 郷々散在(57.5) | 嶋津御庄論 |
| ※此外没官御領内 阿多久吉内 伊作御庄内 |
0.8 22.5 | 正宮注進定 |
| 府領社三箇所 | 53.7 | 正八幡論下司見郡 |
| 開門宮 | 42 |
□□□□□ 加治木知覧社注文定 |
| 新田宮 | 10 | 河野辺郡内 |
| 中嶋宮 | 1.7 | 薩摩郡内 |
| 府領社二ケ所 | 25.5 |
五ケ社内 地頭右衛門兵衛尉 |
| 伊作知佐 | 18 | 谷山郡内 |
| 郡本社 | 7.5 | 鹿児島郡内地頭右衛門兵衛尉 |
| 嶋津御庄一円御領 | 635(領家計) | 右衛門兵衛尉 |
| 没官御領 | 285 | ― |
| 伊作郡 正八幡宮論田 |
200 (22.5) | 地頭右衛門兵衛尉 |
| 日置北郷 | 70 | 本郡司小藤太貞隆 |
| 日置南郷内外小野 | 15 | 地頭右衛門兵衛尉 |
| 和泉郡 | 350 | 下司小大夫兼保 |
| 残田 | 2,725.7 | |
| 御庄寄郡内没官御領 | 610.2(寄郡没官領計) | |
| 378.3 | 地頭千葉介 | |
| 232 | 地頭右衛門兵衛尉 | |
| 阿多久吉 | 210.4 | 地頭佐女嶋四郎 |
| 市来院 | 150 |
院司僧相印 地頭右衛門兵衛尉 |
| 満家院 | 130 |
院司業平 地頭右衛門兵衛尉 |
| 河辺郡 | 220 | 地頭右衛門兵衛尉 |
| 府領社 | 10 | 下司平太道綱 |
| 公領 | 210 | 郡司道綱 |
| 阿多郡 | 250 | |
| 寺領 弥勒寺 | 44.8 | 下司僧安慶 |
| 社領 弥勒寺 | 4 | 下司僧経宗 |
| 寺領 安楽寺 | 5 | 下司僧安静 |
| 社領 正八幡宮論一宮 | 0.8 | |
| 公領 | 195.4 | 没官御領地頭佐女嶋四郎 |
| 久吉 | 145.4 | 本名主在庁種明 |
| 高橋 | 50 | 同地頭佐女嶋四郎 |
| 高城郡 | 255 | 嶋津御庄寄郡 |
| 寺領 安楽寺 |
53 ※他の安楽寺領は、 温田浦を抜いた35町 | 下司僧安静 |
| 温田浦 | 18 |
没官御領地頭千葉介 下司在庁師高 ※温田浦18町は高城郡内没官領地頭千葉介 |
| 社領 弥勒寺 | 30 | 下司僧経宗 |
| 寺領 弥勒寺 | 30 | 下司僧安慶 |
| 公領 |
142 ※118.5(万得領除く) | 没官御領地頭千葉介 |
| 若吉 | 36 | 本郡司薬師丸 |
| 時吉 | 18 | 名主在庁道友 |
| 得末 | 2 | 肥後国住人江田太郎実秀 |
| 吉枝 | 19 | 名主在庁師高 |
| 武光 | 33.5 | 名主在庁師高 |
| 三郎丸 | 10 | 名主在庁種明 |
| 万得 | 15 | 名主在庁師高 |
| 草道万得 嶋津御庄論 | 15 | 名主紀大夫正家 |
| 大河 嶋津御庄論 | 3.5 | 万得 |
| 東郷別符 | 53.2 | |
| 寺領 弥勒寺 | 8.5 | 下司僧安慶 |
| 社領 正八幡宮領 | 2 | 下司在庁道友 |
| 公領 | 42.7 | 没官御領地頭千葉介 |
| 時吉 | 15 | 郷司名主在庁道友 |
| 得末 | 4 | 名主肥後国住人江田太郎実秀 |
| 吉枝 | 7 |
嶋津御庄寄郡 名主在庁師高 |
| 若吉 | 6 |
嶋津御庄寄郡 名主小大夫兼保 |
| 時吉 | 10.7 |
嶋津御庄寄郡 郷司在庁道友 |
| 薩摩郡 | 351.3 | |
| 寺領 安楽寺 | 26.8 | |
| 寺領 弥勒寺 | 5.8 | |
| 社領 府領五ケ社 | 1.7 | |
| 公領 | 317 | |
| 成枝 | 86 | 郡司忠友 |
| 光富 廿町万得 | 49 | 名主新河太郎種房 |
| 是枝 | 9 | 名主在庁家広 |
| 時吉 | 69 |
嶋津御庄寄郡 名主在庁道友 地頭右衛門兵衛尉 |
| 若松 | 50 |
嶋津御庄寄郡 名主在庁種明 地頭右衛門兵衛尉 |
| 永利 | 18 |
嶋津御庄寄郡 名主在庁種明 地頭右衛門兵衛尉 |
| 吉永 | 12 |
嶋津御庄寄郡 名主当国拒捍使崎田五町 地頭右衛門兵衛尉 |
| 火同丸 | 14 |
嶋津御庄寄郡 弁済使 |
| 都浦 | 10 | 万得 |
| 宮里郷 | 70 | |
| 社領 安楽寺 | 7.5 | 下司在庁道友 |
| 社領 弥勒寺 | 1 | 下司僧経宗 |
| 公領 | 61.5 |
嶋津御庄寄郡 郷司紀六大夫正家 地頭右衛門兵衛尉 |
| 入来院 | 92.2 | 没官御領地頭千葉介 |
| 寺領 安楽寺 | 0.2 | 下司僧安静 |
| 寺領 弥勒寺 | 2 | 下司僧安慶 |
| 社領 弥勒寺 | 15 |
下司在庁種明 ※八幡新田宮比野15町は入来院内没官領地頭千葉介 |
| 公領 | 75 | 嶋津御庄寄郡 |
| 弁済使 | 55 | 本地頭在庁種明 |
| 郡名分 | 20 | 本郡司在庁道友 |
| 祁答院 | 112 |
嶋津御庄寄郡 没官御領地頭千葉介 |
| 富光 | 54 | 本郡司熊同丸 |
| 倉丸 | 30 |
本主瀧聞太郎道房 本名主在庁道友 |
| 時吉 | 15 |
本主瀧聞太郎道房 本名主在庁道友 |
| 得末 | 13 | 本名主肥後国住人江田太郎実秀 |
| 牛屎院 | 360 |
嶋津御庄寄郡 右衛門兵衛尉 |
| 永松 | 240 | 院司元光 |
| 幸万 | 55 | 嶋津御庄方弁済使 |
| 木崎 | 15 | 名主前内舎人康友 |
| 光武 | 50 | 名主九郎大夫国吉 |
| 山門院 | 200 | 嶋津御庄寄郡 |
| 老松庄 安楽寺 | 24.4 | |
| 公領 | 175.6 | 地頭右衛門兵衛尉 |
| 光則 | 133.6 | 院司秀忠 |
| 弁済使分 | 27 | 名主嶋津御庄領家沙汰 |
| 高橋 | 15 | 本名主是兼入道死去後 |
| 莫禰院 | 40 |
嶋津御庄寄郡 地頭右衛門兵衛尉 |
| 延武 | 35 | 院司成光 |
| 土師浦 | 5 | 名主小大夫兼保 |
| 甑島郡 | 40 |
嶋津御庄寄郡 没官御領千葉介 |
| 上村 | 20 | 本地頭在庁道友 |
| 下村 | 20 | 本地頭薬師丸 |
| 日置庄 北郷内 弥勒寺 | 30 | 下司小野太郎家綱 |
| 日置庄南郷 | 36 | 没官御領地頭右衛門兵衛尉 |
| 加世田別符 | 100 | |
| 社領 弥勒寺 | 25 | 下司塩田太郎光澄 |
| 公領 | 75 | 地頭右衛門兵衛尉 |
| 山田村 | 20 | 名主肥後国住人石居入道 |
| 千与富 | 40 | 郷司弥平五信忠 |
| 村原 | 15 | 没官御領地頭佐女嶋四郎 |
| 知覧院 | 40 | 嶋津御庄寄郡 |
| 府領社 正八幡宮論 | 9.7 | 下司忠答 |
| 公領 | 30.3 |
郡司忠答 地頭右衛門兵衛尉 |
| 穎娃郡 | 57 | 嶋津御庄寄郡 |
| 府領社 正八幡宮論 | 23 | 下司穎娃次郎忠康 |
| 公領 | 34.7 |
本郡司在庁種明 地頭右衛門兵衛尉 |
| 揖宿郡 | 47 | 嶋津御庄寄郡 |
| 府領社 正八幡宮論 | 9.3 | 下司忠元 |
| 公領 | 37.7 |
下司平三忠秀 地頭右衛門兵衛尉 |
| 給黎院 | 40 |
嶋津御庄寄郡 郡司小大夫兼保 |
| 谷山郡 | 200 | 嶋津御庄寄郡 |
| 府領社 | 18 | |
| 公領 | 182 | |
| 鹿児島郡 | 322 | 嶋津御庄寄郡 |
| 寺領 安楽寺 | 37.5 | 下司僧安静 |
| 社領 正八幡宮領 | 80 | |
| 府領社 | 7.5 | 下司前内舎人康友 |
| 公領 | 197 |
郡司前内舎人康友 地頭右衛門兵衛尉 但、本宮司平忠純 |
| 伊集院 | 180 | |
| 上神殿 万得 | 18 | |
| 下神殿 万得 | 16 | |
| 来羽田 万得 | 5 | |
| 野田 万得 | 6 | 嶋津御庄論 |
| 大田 万得 | 26 |
嶋津御庄論 本主在庁道友 |
| 寺脇 万得 | 8 |
嶋津御庄論 名主在庁道友 |
| 時吉 万得 | 25 | 名主在庁道友 |
| 末永 万得 | 25 | 院司八郎清景 |
| 続飯田 万得 | 8 | 名主権太郎兼直 |
| 土橋 万得 | 13 | 名主紀四郎時綱 |
| 河俣 万得 | 10 | 名主僧忠覚 |
| 谷口 万得 | 14 | 没官御領地頭右衛門兵衛尉 |
| 十万 万得 | 6 | 名主紀平二元信 |
| 飯牟禮 万得 | 3 | |
| 松本 万得 | 18 |
●『薩摩国図田帳写』より(建久八年六月)
| 掃部頭 | 18町 |
| 右衛門兵衛尉(島津忠久) | 2591.6町 |
| 千葉介(千葉介常胤) | 411.2町 |
| 佐女嶋四郎 | 214.4町 |
| 方々権門領寺社 | 506.5町 |
●薩摩国の「地頭千葉介」の面積
| 所領 | 面積(全体) | 面積(寄郡) ※半不輸租田 |
種別 | 備考 |
| 嶋津御庄内没官御領 | 411.2町 | 378.3町 | 没官領 | |
| 高城郡 | ※安楽寺領温田浦18町を除く | |||
| 公領 | 142町 | 118.5町 | 没官御領 | |
| 東郷別符 | 42.7町 | 42.7町 | 没官御領 | |
| 薩摩郡入来院 | 75町 | 75町 | 没官御領 | ※弥勒寺領比野15町、寺領2.2町を除く |
| 祁答院 | 112町 | 112町 | 没官御領 | |
| 甑島郡 | 40町 | 40町 | 没官御領 | |
| 合計 | 411.7町 | 388.2町 |
●島津庄大隅方の「千葉兵衛尉」所領(「大隅国図田帳古写本」『桑幡家文書』)
| 菱刈郡 (138町1段) |
郡本 ※面積不明 | 三郎房相印の知行(賜大将殿御下文) |
|
入山村筥崎宮浮免田 ※面積不明 | 千葉兵衛尉(常秀)が沙汰(賜大将殿御下文) |
●豊前国上毛郡成恒名
相良頼俊が秀胤追討軍に加わり先陣の功を立てたことにより、父相良長頼が給わった地というのみで、成恒名が千葉氏と関わりがあった根拠はない。
相良六郎頼俊は宝治元(1247)年6月6日、上総国一宮に蟄居する上総権介秀胤追討を命じられた大須賀左衛門尉胤氏・東胤行入道素暹の軍勢と同道していたとみられ、「上津房介もつすの時、子息六郎頼俊、依懸前勲功賞」(建長三年三月廿二日「相良迎蓮譲状」『相良家文書』)とあるように軍功を挙げ、宝治3(1249)年3月27日、父の相良三郎法師(長頼法師蓮佛)が「宝治勲功の地」(弘安十年五月二日「相良迎蓮譲状」『相良家文書』)として、豊前国上毛郡成恒名を給わった(宝治三年三月廿七日「鎌倉家政所下文」『相良家文書』)。
●宝治3(1249)年3月27日「将軍家御下文」(『相良家文書』10)
●建長3(1251)年3月22日「相良蓮佛譲状」(『相良家文書』5)
建久元(1190)年11月7日、源頼朝は入洛した(『吾妻鏡』『玉葉』建久元年十一月七日条)。頼朝にとっては永暦元(1160)年3月11日に伊豆国へ流刑に処せられて以来、実に三十年半ぶりの京都であった。その主目的は後白河院との対面、摂政兼実との対談、そして最大の目的として長女大姫の入内を推し進めることにあったと考えられる。木曽義仲及び平家を討ち、奥州平定も成し遂げるなど武威は十分京都に伝わっており、今更「挑発的」な武力を見せつける必要はなく、いわば強大な武威を示しながらも「儀式的」で安穏な世の到来の「象徴的」な入洛を展開したのであろう。入洛時の頼朝の供奉隨兵では、常秀は父の千葉新介胤正と並び、先陣隨兵五十九番として列している。
■建久元年十一月七日入洛勢(『吾妻鏡』建久元年十一月七日条)
| 先 | 貢金辛櫃一合 | |||
| 先陣 | 畠山次郎重忠 ・着黒糸威甲 |
家子一人 郎等十人等 |
||
| 先陣隨兵: ・一騎別張替持一騎 ・冑腹巻行騰 ・小舎人童上髪 ・負征箭、着行騰 ・其外不具郎従 |
一番 | 大井四郎太郎 | 大田太郎 | 高田太郎 |
| 二番 | 山口小七郎 | 熊谷小次郎 | 小倉野三 | |
| 三番 | 下河辺四郎 | 渋谷弥五郎 | 熊谷又次郎 | |
| 四番 | 仙波次郎 | 瀧野小次郎 | 小越四郎 | |
| 五番 | 小河次郎 | 市小七郎 | 中村四郎 | |
| 六番 | 加治次郎 | 勅使河原三郎 | 大曽四郎 | |
| 七番 | 平山小太郎 | 樟田小次郎 | 古郡次郎 | |
| 八番 | 大井四郎 | 高麗太郎 | 鴨志田十郎 | |
| 九番 | 馬場次郎八 | 嶋六郎 | 多加谷小三郎 | |
| 十番 | 阿加田沢小太郎 | 志村小太郎 | 山口次郎兵衛尉 | |
| 十一番 | 武次郎 | 中村七郎 | 中村五郎 | |
| 十二番 | 都筑三郎 | 小村三郎 | 石河六郎 | |
| 十三番 | 庄太郎三郎 | 四方田三郎 | 浅羽小三郎 | |
| 十四番 | 岡崎平四郎 | 塩谷六郎 | 曽我小太郎 | |
| 十五番 | 原小三郎 | 佐野又太郎 | 相摸豊田兵衛尉 | |
| 十六番 | 阿保六郎 | 河匂三郎 | 河匂七郎三郎 | |
| 十七番 | 坂田三郎 | 春日小次郎阿 | 佐美太郎 | |
| 十八番 | 三尾谷十郎 | 河原小三郎 | 上野沼田太郎 | |
| 十九番 | 金子小太郎 | 駿河岡部小次郎 | 吉香小次郎 | |
| 二十番 | 小河次郎 | 小宮七郎 | 戸村小三郎 | |
| 廿一番 | 土肥次郎 | 佐貫六郎 | 江戸七郎 | |
| 廿二番 | 寺尾太郎 | 中野小太郎 | 熊谷小太郎 | |
| 廿三番 | 祢津次郎 | 中野五郎 | 小諸太郎次郎 | |
| 廿四番 | 祢津小次郎 | 志賀七郎 | 笠原高六 | |
| 廿五番 | 嶋楯三郎 | 今堀三郎小 | 諸小太郎 | |
| 廿六番 | 土肥荒次郎 | 広沢三郎 | 二宮小太郎 | |
| 廿七番 | 山名小太郎 | 新田蔵人 | 徳河三郎 | |
| 廿八番 | 武田太郎 | 遠江四郎 | 佐竹別当 | |
| 廿九番 | 武田兵衛尉 | 越後守 | 信濃三郎 | |
| 三十番 | 浅利冠者 | 奈胡蔵人 | 伊豆守 | |
| 卅一番 | 参河守 | 相摸守 | 里見太郎 | |
| 卅二番 | 工藤小次郎 | 佐貫五郎 | 田上六郎 | |
| 卅三番 | 下総豊田兵衛尉 | 鹿嶋三郎 | 小栗次郎 | |
| 卅四番 | 藤沢次郎 | 阿保五郎 | 伊佐三郎 | |
| 卅五番 | 中山四郎 | 中山五郎 | 江戸四郎 | |
| 卅六番 | 加世次郎 | 塩屋三郎 | 山田四郎 | |
| 卅七番 | 中沢兵衛尉 | 海老名兵衛尉 | 豊嶋兵衛尉 | |
| 卅八番 | 中村兵衛尉 | 阿部平六 | 猪股平六 | |
| 卅九番 | 駒江平四郎 | 西小大夫 | 高間三郎 | |
| 四十番 | 所六郎 | 武藤小次郎 | 豊嶋八郎 | |
| 四十一番 | 佐々木五郎 | 糟江三郎 | 岡部右馬允 | |
| 四十二番 | 堀四郎 | 海老名次郎 | 新田六郎 | |
| 四十三番 | 葛西十郎 | 伊東三郎 | 浦野太郎 | |
| 四十四番 | 小沢三郎 | 渋河弥五郎 | 横山三郎 | |
| 四十五番 | 豊嶋八郎 | 堀藤太 | 和田小次郎 | |
| 四十六番 | 山内先次郎 | 佐々木三郎 | 筥王丸 | |
| 四十七番 | 右衛門兵衛尉 | 尾藤次 | 中條平六 | |
| 四十八番 | 三浦十郎太郎 | 後藤内太郎 | 比企藤次 | |
| 四十九番 | 小山四郎 | 右衛門太郎郎 | 岡部与一太 | |
| 五十番 | 糟谷藤太 | 野平右馬允 | 九郎藤次 | |
| 五十一番 | 多気太郎 | 小平太 | 宇佐美小平次 | |
| 五十二番 | 波多野小次郎 | 新田四郎 | 机井八郎 | |
| 五十三番 | 小野寺太郎 | 足利七郎四郎 | 足利七郎五郎 | |
| 五十四番 | 佐貫四郎 | 足利七郎太郎 | 横山太郎 | |
| 五十五番 | 梶原兵衛尉 | 和田小太郎 | 宇治蔵人三郎 | |
| 五十六番 | 梶原左衛門尉 | 宇佐美三郎 | 賀嶋蔵人次郎 | |
| 五十七番 | 小山田四郎 | 三浦平六 | 小山田五郎 | |
| 五十八番 | 和田三郎 | 堀藤次 | 土屋兵衛尉 | |
| 五十九番 | 千葉新介 | 氏家太郎 | 千葉平次 | |
| 六十番 | 小山田三郎 | 北條小四郎 | 小山兵衛尉 | |
| 御引馬一疋 | ||||
| 御具足持一騎 | ||||
| 御弓袋差一騎 | ||||
| 御甲着一騎 | ||||
| 二位家(源頼朝) ・折烏帽子、絹紺青丹打水干袴、紅衣 ・夏毛行騰、染羽野箭 ・黒馬、楚鞦、水豹毛泥障 |
||||
| 著水干輩 ・負野箭 |
一番 | 八田右衛門尉 | 伊東四郎 | 加藤次 |
| 二番 | 三浦十郎 | 八田太郎 | 葛西三郎 | |
| 三番 | 河内五郎 | |||
| 四番 | 三浦介 | |||
| 五番 | 足立右馬允 | 工藤左衛門尉 | ||
| 後陣隨兵 | 一番 | 梶原刑部丞 | 鎌田太郎 | 品河三郎 |
| 二番 | 大井次郎 | 大河戸太郎 | 豊田太郎 | |
| 三番 | 人見小三郎 | 多々良四郎 | 長井太郎 | |
| 四番 | 豊嶋権守 | 江戸太郎 | 横山権守 | |
| 五番 | 金子十郎 | 小越右馬允 | 小沢三郎 | |
| 六番 | 吉香次郎 | 大河戸次郎 | 工藤庄司 | |
| 七番 | 大河戸四郎 | 下宮次郎 | 奥山三郎 | |
| 八番 | 海老名四郎 | 宇津幾三郎 | 本間右馬允 | |
| 九番 | 河村三郎 | 阿坂余三 | 山上太郎 | |
| 十番 | 下河辺庄司 | 鹿嶋六郎 | 真壁六郎 | |
| 十一番 | 大胡太郎 | 祢智次郎 | 大河戸三郎 | |
| 十二番 | 毛利三郎 | 駿河守 | 平賀三郎 | |
| 十三番 | 泉八郎 | 豊後守 | 曽祢太郎 | |
| 十四番 | 村上左衛門尉 | 村上七郎 | 高梨次郎 | |
| 十五番 | 村上右馬允 | 村上判官代 | 加々美次郎 | |
| 十六番 | 品河太郎 | 高田太郎 | 荷沼三郎 | |
| 十七番 | 近間太郎 | 中郡六郎太郎 | 中郡次郎 | |
| 十八番 | 秩父平太 | 深栖太郎 | 倉賀野三郎 | |
| 十九番 | 沼田太郎 | 志村三郎 | 臼井六郎 | |
| 二十番 | 大井五郎 | 岡村太郎 | 春日与一 | |
| 廿一番 | 大胡太郎 | 深栖四郎 | 都筑平太 | |
| 廿二番 | 大河原次郎 | 小代八郎 | 源七 | |
| 廿三番 | 三宮次郎 | 上田楊八郎 | 高屋大郎 | |
| 廿四番 | 浅羽五郎 | 臼井余一 | 天羽次郎 | |
| 廿五番 | 山上太郎 | 武者次郎 | 小林次郎 | |
| 廿六番 | 井田太郎 | 井田次郎 | 武佐五郎 | |
| 廿七番 | 目黒弥五郎 | 皆河四郎 | 平佐古太郎 | |
| 廿八番 | 鹿嶋三郎 | 広沢余三 | 庄太郎 | |
| 廿九番 | 上野権三郎 | 大井四郎 | 相摸小山太郎 | |
| 三十番 | 塩部四郎 | 塩部小太郎 | 中條藤次 | |
| 卅一番 | 小見野四郎 | 庄四郎 | 仙波平太 | |
| 卅二番 | 片穂平五 | 那須三郎 | 常陸平四郎 | |
| 卅三番 | 塩谷太郎 | 毛利田次郎 | 平子太郎 | |
| 卅四番 | 遠江浅羽三郎 | 新野太郎 | 横地太郎 | |
| 卅五番 | 高橋太郎 | 印東四郎 | 須田小大夫 | |
| 卅六番 | 高幡太郎 | 小田切太郎 | 岡舘次郎 | |
| 卅七番 | 筥田太郎 | 長田四郎 | 長田五郎 | |
| 卅八番 | 庁南太郎 | 藤九郎 | 成田七郎 | |
| 卅九番 | 別府太郎 | 奈良五郎 | 奈良弥五郎 | |
| 四十番 | 岡部六野太 | 瀧瀬三郎 | 玉井太郎 | |
| 四十一番 | 玉井四郎 | 岡部小三郎 | 三輪寺三郎 | |
| 四十二番 | 楠木四郎 | 忍三郎 | 忍五郎 | |
| 四十三番 | 和田五郎 | 青木丹五 | 寺尾三郎太郎 | |
| 四十四番 | 深浜木平六 | 加冶太郎 | 道後小次郎 | |
| 四十五番 | 多々良七郎 | 真下太郎 | 江田小太郎 | |
| 四十六番 | 高井太郎 | 道智次郎 | 山口小次郎 | |
| 後陣 | 勘解由判官 | |||
| 梶原平三 【相具郎従数十騎】 | ||||
| 千葉介 【以子息親類等為随兵】 | ||||
頼朝はすべての日程を終了し、正月元日までに鎌倉に戻るために12月10日、帰東に備えて、六波羅邸の留守居を実甥の左馬頭高能と決定。翌12月11日、参院して数刻法皇と対談した。このとき法皇は「度々勲功之労、可挙申廿人之旨、所被仰下也」と頼朝に指示をする。これ以前から法皇は「勲功賞」を頼朝に辞退され続けており、この日、法皇は頼朝個人にではなくその郎従への任官に切り替え、二十人を推挙すべきことを指示したのだった。頼朝はこれも「頻雖被辞申之」と辞退の姿勢を見せたが、法皇は執拗に郎従の任官を迫ったため、頼朝は「勅命再往之間、略而被申任十人」とし、「御家人十人募成功、被挙任左右兵衛尉左右衛門尉等」したとする(『吾妻鏡』建久元年十二月十一日条)。この中に「平常秀」が推挙されている。
●挙任人々十人(『吾妻鏡』建久元年十二月十一日条)
| 官途 | 人物 | 賞過程 | 「馴京都輩」 |
| 左兵衛尉 | 平常秀(千葉平次常秀) | 祖父常胤勲功賞譲 | 父胤正「馴京都輩」(建久元年十二月三日条) |
| 平景茂(梶原三郎景茂) | 父景時勲功賞譲 | 兄景季「馴京都輩」(建久元年十二月三日条) | |
| 藤原朝重(八田太郎朝重) | 父知家勲功賞譲 | 「馴京都之輩」(元暦元年六月一日条) 「馴京都輩」(建久元年十二月三日条) |
|
| 右兵衛尉 | 平義村(三浦平六義村) | 父義澄勲功賞譲 | 「馴京都之輩」(元暦元年六月一日条) 「馴京都輩」(建久元年十二月三日条) |
| 平清重(葛西三郎清重) | 勲功賞 | 建久元(1190)年12月3日 頼朝の両職辞職時の供奉「侍」七人の一人 |
|
| 左衛門尉 | 平義盛(和田小太郎義盛) | 勲功賞 | 元久元(1204)年10月14日 子息朝盛は実朝室坊門氏を迎える使者の一人 |
| 平義連(三浦五郎義連) | 勲功賞 | 「馴京都輩」(建久元年十二月三日条) | |
| 藤原遠元(足立右馬允遠元) | 勲功賞(元前右馬允) | 「馴京都之輩」(元暦元年六月一日条) | |
| 右衛門尉 | 藤原朝政(小山右兵衛尉朝政) | 勲功賞(元前右兵衛尉) | 「馴京都之輩」(元暦元年六月一日条) |
| 藤原能員(比企藤四郎能員) | 勲功賞 |
『玉葉』では12月10日に「前大将郎従之中、成功之輩、注進交名」(『玉葉』建久元年十二月十日条)とある。翌11日には「前大将参内、予謁之」とあって、頼朝は参内して兼実に謁見している(『玉葉』建久元年十二月十一日条)。兼実は頼朝が10日に「成功之輩、注進交名」をの旨を聞き、翌11日は参内して兼実と謁見を行ったのであろう。頼朝は「天下政忽可直立之由、全不見給、然而御申之所及不可懈緩云々、又世間事将来まても不可有不審、巷間説、定不可被信用、巨細雖多不能具記也」と語っている。その後、頼朝は参院したか。
12月12日、法皇は「被仰前大将勲功賞大功田之間事」という、兼実が予て申し出ていた頼朝への大功田の沙汰を行った(『玉葉』建久元年十二月十二日条)。また頼朝は恩賞とは別件で、「公事用途依欠如、成功之者廿五人、前大将進交名」とあるように、法皇は朝廷の公事用途の欠如を補填するため、頼朝郎従から二十五人へ「成功」を募って官途を推挙させ交名を進めさせた(10日に兼実が聞いた「成功之輩、注進交名」を実際に院へ提出したという事であろう)。また、法皇は12月1日の右大将拝賀の際に頼朝の「直垂者持太刀」を見て、頼朝に彼の姓名を問うた際、法皇は「無官不可然、早可被授兵衛尉之由有 勅定」と命じている。拝賀の際の頼朝の太刀持は糟屋藤太有季(ただし装束は直垂ではない)であり、彼は翌建久2(1193)年8月には「糟屋藤太兵衛尉」とみえることから(『吾妻鏡』建久二年八月六日条)、糟屋有季はこのとき兵衛尉に任官したのだろう。
そして12月13日、法皇は兼実の申請の通り「被仰大功田百町可下宣旨之由」の院宣を下した。また、先日の成功分とは別の「勲功賞、衛庁十人可被任之由」の院宣を下したが、今日は日次が良くないため、翌14日に「大功田事可被行」こととされた。しかし、「将軍明日下向」であることから、明日早朝に大功田事を宣下するよう院宣が下り、頼朝が交名を進めた千葉常秀ら十名の臨時除目については大原野に行幸している主上との兼ね合いもあり、「行幸還御以後可被行之由」が指示され、兼実はこれらを奏上している(『玉葉』建久元年十二月十三日条)。そして14日深夜子終刻、主上が還御。すぐさま臨時除目により十名の頼朝郎従は任官し、頼朝には「大功田百町」が宣下されたとみられ(なお、この十名は成功を募った二十五名とは別枠であろう)、その後、頼朝は離京して鎌倉へ下向の途についた。
このとき、勲功により衛府に補された十名を見ると、上記表の通り、いずれも「馴京都之輩」であった。建久元(1190)年12月14日の衛府吹挙は、御家人中でもとくに平家・奥州の合戦で軍功があり、かつ在京官仕の経験を持つ人々だったと推測できる。常秀が「右兵衛尉」に任官し得たのは、常胤子孫のうち平家追討と奥州合戦に参加し、且つ上洛した経験(文治2年末~文治5年8月以前)があるのは常秀のみだったためで、常胤がとくに常秀を優遇したというわけではないだろう。
建仁2(1202)年7月7日、父の千葉介胤正が六十七歳で卒去(『本土寺過去帳』七日上段)すると、常秀の兄・成胤が千葉介家を継承する。これは元久元(1204)年4月20日、実朝が頼朝から自筆の書状を給わった御家人に対して成敗の内容を写し取るため提出を求めているが、5月19日に成胤がこの命に応じて所有する文書数十通を提出していることから、成胤に惣領家継承を確認できる。元久2(1205)年正月3日には成胤が北条時政の次に埦飯を献じていることを見ても、家格の高さが際立っていることがわかる。さらに、建暦2(1212)年2月7日、成胤は「一族を率いて」御所を造営し、翌建保元(1213)年5月3日、和田義盛の乱には「党類を率いて」北条義時の館に駆けつけていることから、常秀が千葉家内で兄の成胤を超越した立場にあったことは考えられず、常秀は千葉六党と同様の立場にあった可能性が高いだろう。官途は常秀は五位であるが、惣領家の千葉介成胤の官途は不明で比較することは不可能である。また「官途の超越」が一族内の惣領権と直接関係がないことは、千葉家にあっては千葉六郎大夫胤頼が惣領となっていないことや、三浦一族の「長者」たる和田左衛門尉義盛が三浦介家を継承していないことでも明白である。
常秀は建保7(1219)年正月27日の将軍家実朝の右大臣拝賀のための鶴岡八幡宮寺参詣の供奉(この拝賀の際に実朝暗殺される)として列したことを最後に、実に十六年にわたって『吾妻鏡』から姿を見せなくなる。子息の「堺兵衛太郎(秀胤)」もまた、承久元(1219)年7月19日、鎌倉家の跡を継ぐべく京都から鎌倉に入った藤原三寅(九條道家禅門の三男で、のちの四代将軍権大納言頼経)に供奉して義時邸に入って以降、文暦2(1235)年2月9日まで父と同様に『吾妻鏡』から姿を消す。常秀一族が承久元(1219)年7月19日から文暦2(1235)年2月9日までの十六年間、『吾妻鏡』に一切登場しない理由は、彼らが鎌倉を不在にしていたためであると考えられる。その常秀一族の上洛は、おそらく承久3(1221)年の「承久の乱」であると推測され、常秀は承久3(1221)年5月25日、甥の惣領家・東海道大将軍千葉介胤綱に従って上洛したと推測される。
●承久3(1221)年5月25日までに出立した幕府軍大将の編成(『吾妻鏡』)
| 東海道大将軍 (十万余騎) |
相州 (北条時房) |
武州 (北条泰時) |
同太郎 (北条時氏) |
武蔵前司義氏 |
| 駿河前司義村 | 千葉介胤綱 | |||
| 東山道大将軍 (五万余騎) |
武田五郎信光 | 小笠原次郎長清 | 小山新左衛門尉朝長 | 結城左衛門尉朝光 |
| 北陸道大将軍 (四万余騎) |
式部丞朝時 | 結城七郎朝広 | 佐々木太郎信実 |
●上総千葉氏と千葉宗家
千葉介胤正―+―千葉介成胤――千葉介胤綱――千葉介時胤
(千葉介) |(千葉介) (千葉介) (千葉介)
|
+―千葉常秀―――千葉秀胤 +―千葉時秀
(上総介) (上総権介)|(式部丞)
∥ |
∥――?―+―千葉政秀
三浦義村―+―女子 |(修理亮)
(駿河守) | |
+―三浦泰村 +―千葉泰秀
(若狭守) |(左衛門尉)
|
+―千葉秀景
(六郎)
なお、『慈光寺本承久記』(『承久記』諸本のうち鎌倉期成立の古態本とされる。ただし、あくまでも著作者のいる軍記物であって創作が含まれる可能性があり、史料としては参考にとどまる)によれば、第五陣に「紀内殿、千葉次郎」とある。これによれば千葉勢を率いたのは幼少時の惣領に代わり鎌倉家の営所に出仕していた胤綱叔父・千葉次郎泰胤となる。「紀内殿」については世代的に見て「木内」下総前司胤朝とも思えるが、「殿」付で記されており、千葉家庶流東氏のさらに庶子家である木内氏とは考えにくい。
●承久3(1221)年5月25日までに出立した鎌倉勢大将軍の編成(『吾妻鏡』)
| 東海道大将軍 (十万余騎) |
北条相模守時房 | 北条武蔵守泰時 | 北条武蔵太郎時氏 | 足利武蔵前司義氏 | 三浦駿河前司義村 | 千葉介胤綱 |
| 東山道大将軍 (五万余騎) |
武田五郎信光 | 小笠原次郎長清 | 小山左衛門尉朝長 | 生野右馬入道 | 諏訪小太郎 | 伊具右馬允入道 |
| 北陸道大将軍 (四万余騎) |
北条式部丞朝時 | 結城七郎朝広 | 佐々木太郎信実 |
●『慈光寺本承久記』の鎌倉勢の編成(『慈光寺本承久記』)
| 三手 | 陣 | (大将軍) | 此手ニ可付人数 | ||||
| 海道 (七万騎) |
先陣 (二万騎) |
相模守時房 | 城入道 | 森入道 | 石戸入道 | 本間左衛門 | 伊藤左衛門 |
| 加持井 | 丹内 | 野路八郎 | 河原五郎 | 強田左近 | |||
| 大河殿 | 大見左衛門 | 宇佐美左衛門 | 内田五郎 | 久下三郎 | |||
| 勾当時盛 | |||||||
| 二陣 (二万騎) |
武蔵守泰時 | 関左衛門 | 新井田殿 | 森五郎 | 小山左衛門 | 新左衛門 | |
| 善左衛門 | 宇津宮入道 | 中間五郎 | 藤内左衛門 | 安藤兵衛 | |||
| 高橋与一 | 卯田右近 | 卯田刑部 | 阿夫刑部 | 大森弥次二郎兄弟 | |||
| 保威左衛門 | 蜂河殿 | 讃岐右衛門五郎 | 駄手入道 | 駄手平次 | |||
| 金子平次 | 伊佐三郎 | 固共六郎 | 丹党 | 小玉党 | |||
| 野田党 | 金子党 | 措二郎 | 有田党 | 弥二郎兵衛 | |||
| 駿河二郎康村 | 武蔵太郎時氏 | ||||||
| 三陣 | 足利殿 | ||||||
| 四陣 | 佐野左衛門政景 二田四郎 |
||||||
| 五陣 | 紀内殿 千葉次郎 (千葉泰胤か) |
||||||
| 山道 (五万騎) |
武田 小笠原 |
南部太郎 | 秋山四郎 | 三坂三郎 | 二宮殿 | 智戸六郎 | |
| 武田六郎 | |||||||
| 北陸道 (七万騎) |
式部丞朝時 | ||||||
。承久の乱における常秀の活動はうかがい知ることはできないが、『承久三年四年日次記』によれば、六條河原に布陣していた「海道手」の武士らの軍陣に勅使大夫史国宗が「故右府実朝公家司」の「主典代中宮権属中原俊職」を伴って訪れ、「義時朝臣追討宣旨可被召返」の勅諚を伝えている(『承久三年四年日次記』)。この勅諚を受けたのが、「武蔵守泰時、駿河守義村、堺兵衛尉常秀、佐竹別当能繁」らであったといい、常秀は承久の乱の軍陣にあり、上洛していたことがわかる。
その後、常秀の一族はそのまま十四年余りにわたって在京していたと思われる。その後、文暦2(1235)年2月9日までの間、『吾妻鏡』に常秀一族が一切登場しない理由は、彼らが鎌倉を不在にしていたためであると考えられる。元仁2(1225)年正月24日、常秀は「下総平常秀」(『明月記』元仁二年正月廿四日条)とあるように下総守に任官の上「従五位下」に叙爵した。また、同日に小山左衛門尉朝政も「下野藤朝政」とあるように下野守に補任され同じく「五位下」に叙爵している(受領となるに当たり左衛門尉は辞官と考えられる)。小山朝政もまた貞応3(1224)年9月16日の流鏑馬警固役「小山判官朝政」(『吾妻鏡』貞応三年九月十六日条)以降、嘉禎4(1238)年3月30日の「小山下野守、従五位下、藤原朝臣朝政法師法名生西、卒年八十四」(『吾妻鏡』嘉禎四年三月卅日条)の薨伝まで十四年間『吾妻鏡』に登場しておらず、元仁2(1225)年正月24日当時は両名ともに在京していたと推測できる。
●元仁2(1225)年正月24日任官(『明月記』)
| 侍従 | 藤公蔭、源定具 |
| 山城守 | 中原定職 |
| 大和守 | 紀久直 |
| 参河守 | 藤為綱 |
| 下総 | 平常秀(堺常秀) |
| 下野 | 藤朝政(小山朝政) |
| 播磨守 | 信広 |
| (播磨)権守 | 国通 |
| 讃岐権守 | 隆親 |
| 大隅 | 江信房 |
| 対馬 | 藤範房 |
| 左少将 | 源家定 |
| 右少将 | 実経 |
| (使宣旨) 検非違使 |
左衛門藤忠尚 |
| (辞少納言) | 経基(高階経基か) |
| ・文官廿二人 | |
| ・諸国遙掾介 | |
| ・左右将監五人 | |
| ・左門四人 | |
| ・右(右門)五人 | |
| ・少志十二人 | |
| ・左兵七人 | 兵衛尉藤為光 |
| ・右兵六人 | |
| ・左右馬三人 | 左馬允忠政(臨時) |
●元仁2(1225)年正月24日叙位(『明月記』)
| 正五位下 | 敦直、高階経基、藤公輔、藤定雅 |
| 従五位下 | 朝政、常秀 |
常秀は文暦2(1235)年2月9日以前に「上総介」に補任された(長男の太郎秀胤が「上総介太郎」を称している)とみられるが補任記録はない。その時期からみて在京中に補任されたと思われる。常秀帰東の記録はないが、文暦2(1235)年2月9日に子息の「上総介太郎(秀胤)」が将軍頼経の後藤基綱邸での遊興に小笠懸に出馬しており、この日までに鎌倉に戻っていたとみられる。
嘉禎4(1238)年正月20日、将軍・藤原頼経は上洛のため秋田城介景盛の甘縄邸に入った。時胤もすでに下総国内の地頭に対し大番催促をしていたが、当年は香取社造営期間の年であり、時胤は鎌倉家政所に「香取造営之間、大介不出国境」と主張し、これを受けて三日後の正月23日、鎌倉家は時胤に「御京上御共止、可被在国之状」の御教書を下した(嘉禎四年正月廿三日『関東御教書写』)。こうして時胤自身は上洛供奉を免除され、正月28日、将軍・藤原頼経の一行は鎌倉を出立して十か月にわたる上洛の途についた。まさに土壇場で供奉免除を申請し認められたのだった。
●嘉禎4(1238)年正月23日「関東御教書写」(「下総香取文書」:『鎌倉遺文』所収)
なお、この当時千葉介時胤は「大介」を称しているように「下総守(国司)」に補されていたとみられ、実際に国衙へ国宣を出し得る立場にあったと考えられる。時胤の下総守補任は文暦2(1235)年までの間に為されたとみられ、翌嘉禎2(1236)年6月に香取社遷宮の宣旨が下された。常秀は北条掃部助実時とともに「埴生印西」の地頭職として「楼門」の造営担当を務めたのだろう。
そして6月29日には将軍頼経の新造御堂の安鎮祭随兵として常秀は「上総介常秀」とあるように「上総介」の官途として『吾妻鏡』に登場する(『吾妻鏡』文暦二年六月廿九日条)。常秀の上総介官途は翌嘉禎2(1236)年8月4日の将軍頼経の「若宮大路新造御所」への移徙供奉人までみられるが、その後、常秀の名は『吾妻鏡』から消える。
また、時期は不明だが、常秀は「上総」「丹後」守護職となっている(渡辺正男「丹波篠山市教育委員会所蔵『貞永式目追加』」:『史学雑誌』一二八編第九号所収、野口実氏の指摘を参考)。
常秀の没年は不明だが、「上総介(常秀)」は嘉禎2(1236)年8月4日の頼経頼経の宇都宮御所への移徙供奉以降、『吾妻鏡』から見えなくなる。子息の「上総介太郎(秀胤)」は嘉禎4(1238)年2月17日の頼経上洛の供奉以降、仁治元(1240)年8月2日までの約二年半、その行跡は知れなくなる。
ただし、この2年半余りの間に、常秀は「上総介」から「下総守」に移り、あまり時を置かずに辞し(秀胤を「下総前司常秀男」、二男を「下総次郎時常」は「亡父下総前司常秀」から埴生庄を譲られたとあり、常英最終官途は下総守だったことが分かる)、子息の秀胤は父の上総介を引き継ぎ、おそらく六位の「上総権介」に任官したと思われる。『吾妻鏡』で姿の見えないこの二年余りは、常秀一族はおそらく上洛していたと考えられる。秀胤の長男・時秀は「式部丞」、二男の政秀は「修理亮」、三男の泰秀は「左衛門尉」にそれぞれ任官している。式部丞も修理亮も京官であることから、在京を前提に補任された可能性があろう。彼らが補任された除目は暦仁元(1239)年~翌暦仁2(1239)年となるが、史料は残っていない。
仁治元(1240)年8月2日、嫡子・秀胤が「上総権介」を称しており(『吾妻鏡』補遺/仁治元年八月二日条)、このころ常秀は家督を譲ったか死亡したものと思われる。寛元2(1244)年6月時点で次男の「埴生次郎平時常」はすでに「相伝亡父下総前司常秀遺領垣生(埴生)庄」(『吾妻鏡』宝治元年六月七日条)しており、三宮埴生神社に神輿一基を寄進(「三宮埴生神社神輿銘」『千葉県史 金石文』)していることから、具体的には寛元2年までには亡くなっていたとみられる。
宝治元(1247)年6月7日、「亡父下総前司常秀」(『吾妻鏡』宝治元年六月七日条)とあるように、常秀の官途は「下総守」で終わっている。