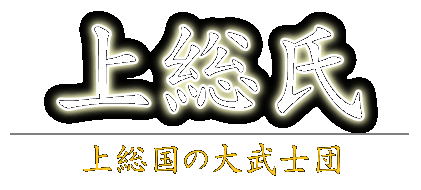
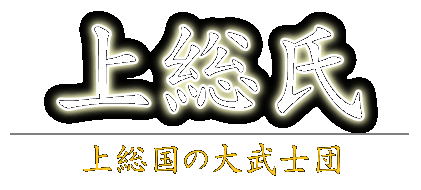
|ページの最初へ|トップページへ|上総氏について|千葉宗家の目次|千葉氏の一族|
| 【一】 | 上総氏について |
| 【二】 | 上総平氏は両総平氏の「惣領」なのか |
| 【三】 | 頼朝の挙兵と上総平氏 |
平常長――+―平常茂
(下総権介)|(坂太郎)
|
+―平常兼―――平常重――――千葉介常胤――千葉介胤正―+―千葉介成胤――千葉介時胤
|(下総権介)(下総権介) (下総権介) |
| |
| +―千葉常秀―――千葉秀胤
| (上総介) (上総権介)
|
+―平常晴―――平常澄――+―伊南常景―――伊北常仲
(上総権介)(上総権介)|(上総権介) (伊北庄司)
|
+―印東常茂
|(次郎)
|
+―平広常――――平能常
|(上総権介) (小権介)
|
+―相馬常清―――相馬貞常
(九郎) (上総権介?)
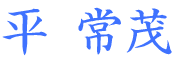 (????~1180)
(????~1180)
上総介常澄の次男。母は不明。名は常義ともされるが「義」字の誤記であろう。通称は「印東次郎」(『吾妻鏡』『神代本千葉系図』『平朝臣徳嶋系図』『源平闘諍録』)、「印南次郎」(『桓武平氏諸流系図』)。
常茂は父・常澄が地主職(公権とは別の私領主としての権限)を務めていた印東庄を受け継いで、「印東次郎」(『吾妻鏡』『神代本千葉系図』『平朝臣徳嶋系図』『源平闘諍録』)を称したが、「印南次郎」(『中条家文書』:「桓武平氏諸流系図」)とも見える。常茂は後述のように兄の上総介常景を殺害しており(『桓武平氏諸流系図』)、その遺領である伊南庄に入った可能性もある(『吾妻鏡』治承四年十月三日條)。
長寛年中(1163~1166)、兄・伊南常景を殺害した(『中条家文書』:「桓武平氏諸流系図」)。
●『桓武平氏諸流系図』(『中条家文書』)
ただし、常茂がなぜ常景を殺害したのかは定かではない。合戦があったのかも不明である。兄の常景は伊隅郡伊南庄及び伊北庄を寄進して荘園化していたとみられるが、常茂は上総国内には伊南庄(いすみ市周辺)と隣接する長南(長生郡長南町)、武射南郷(山武市上横地周辺)、戸田(山武市戸田)の地主職を有しており、長南太郎重常、印東別当頼常、南郷四郎師常、戸田七郎常政の子が見える(『神代本千葉系図』)。私領を巡る争いがあった可能性はあろう。
上総国では介常景亡きあと、常茂がいかなる勢力を有したのか、上総国における常茂の活動は皆無であり、平家政権のもと「大番役」で上洛し、治承の乱でも平氏方として出陣している(『吾妻鏡』)、子息らも広常に従っていた様子も窺えることから、すでに上総国との関係は隔絶していたのかもしれない。上総国の上総平氏は弟・八郎広常が実質的に実権を握り、嘉応2(1170)年以降に「伊藤右衛門尉忠清被配流、上総国の時、介八郎広常志を尽し、思を運て賞翫し、愛養する事甚し」とあるように、上総国へ流罪となった平家郎従の右衛門少尉藤原忠清を広常が歓待した様子がうかがえる(『源平盛衰記』)。
治承4(1180)年8月4日、源頼朝は以仁王の令旨(最勝王宣)を奉じ、伊豆守平時兼(知行国主平時忠の養子)の目代であった平兼隆(前検非違使判官)を討って、平氏に反旗を翻した。しかし、平清盛禅門は故前伊豆守仲綱の子息を追討するべく、8月2日に私兵の大庭三郎景親を関東に戻していた。その仲綱息はすでに奥州へ逃れていたが、頼朝の挙兵に応じて景親は頼朝追討に転じている。
頼朝は8月23日、相模国石橋山中での大庭景親率いる相模国平氏党との戦いに大敗。土肥次郎実平の斡旋によって真鶴より出帆して安房国へと逃れることに成功。安西景益、千葉介常胤、広常の協力のもと両総を攻め上って武蔵国に入り、10月6日に父祖の故地鎌倉に入部した。その後、東下する平氏の追討使を迎え撃つべく、西に進むが、その途次で降伏した大庭景親を梟首、駿河国に入って富士川岸に陣を張った。
一方、播磨国福原から京都を経て、はるばる東国に攻め下ってきたのは、総大将を若い近衛権少将平維盛とする平氏の正規軍であった。この軍勢に「上総国住人 印東次郎常茂」が「常陸国住人佐谷次郎義幹」とともに先陣押領使として加わっていた(『源平闘諍録』)。また「伊南介常義」とも(『四部合戦状本平家物語』)。
| 伊南介常義 | 『四部合戦状本平家物語』 | |
| 印東次郎常茂 | 『源平闘諍録』巻第五 |
上総国住人 先陣押領使 |
| 印東次郎常義 | 『吾妻鏡』治承四年十月廿日条 | 於鮫嶋被誅 |
このとき、駿河国はすでにその大半が甲斐源氏・武田信義の一党によって平定されており、頼朝は地理に詳しい信義に先陣を依頼し、信義は夜営している平家軍を奇襲するため、10月23日、富士沼(富士川の岸は中世は泥湿地だった)に入ったが、『吾妻鏡』によれば、沼地で休んでいた数万羽の水鳥が軍勢の気配に驚いて一斉に飛び立ち、これに驚いた平氏の兵士たちが戦う前に西へ壊走してしまったという。この戦いで「印東次郎常義」は駿河国鮫島で追いすがる源氏の兵によって討ち取られた(『吾妻鏡』治承四年十月廿日条)。なお「義」「茂」の行書体は酷似しており「印東次郎常義」は「印東次郎常茂」と見られる。
●『吾妻鏡』治承4(1180)年10月20日条
頼朝勢の中には常茂の弟・広常も加わっていたと思われるが、「為弟弘常被害」(『中条家文書』「桓武平氏諸流系図」)とあり、常茂を討ったのは広常の手勢か。
●『桓武平氏諸流系図』(『中条家文書』)