

| 継体天皇(???-527?) | |
| 欽明天皇(???-571) | |
| 敏達天皇(???-584?) | |
| 押坂彦人大兄(???-???) | |
| 舒明天皇(593-641) | |
| 天智天皇(626-672) | 越道君伊羅都売(???-???) |
| 志貴親王(???-716) | 紀橡姫(???-709) |
| 光仁天皇(709-782) | 高野新笠(???-789) |
| 桓武天皇 (737-806) |
葛原親王 (786-853) |
高見王 (???-???) |
平 高望 (???-???) |
平 良文 (???-???) |
平 経明 (???-???) |
平 忠常 (975-1031) |
平 常将 (????-????) |
| 平 常長 (????-????) |
平 常兼 (????-????) |
千葉常重 (????-????) |
千葉常胤 (1118-1201) |
千葉胤正 (1141-1203) |
千葉成胤 (1155-1218) |
千葉胤綱 (1208-1228) |
千葉時胤 (1218-1241) |
| 千葉頼胤 (1239-1275) |
千葉宗胤 (1265-1294) |
千葉胤宗 (1268-1312) |
千葉貞胤 (1291-1351) |
千葉一胤 (????-1336) |
千葉氏胤 (1337-1365) |
千葉満胤 (1360-1426) |
千葉兼胤 (1392-1430) |
| 千葉胤直 (1419-1455) |
千葉胤将 (1433-1455) |
千葉胤宣 (1443-1455) |
馬加康胤 (1398-1456) |
馬加胤持 (1437-1456) |
岩橋輔胤 (1416-1492) |
千葉孝胤 (1443-1505) |
千葉勝胤 (1471-1532) |
| 千葉昌胤 (1495-1546) |
千葉利胤 (1515-1547) |
千葉親胤 (1541-1557) |
千葉胤富 (1527-1579) |
千葉良胤 (1557-1608) |
千葉邦胤 (1557-1583) |
千葉直重 (????-1627) |
千葉重胤 (1576-1633) |
| 江戸時代の千葉宗家 | |||||||
| 1.都鄙対立と篠川殿満直の関東介入 | 2.篠川満直の「三ヶ条にもとづく罰状」の提案 | 3.管領斯波義淳の抵抗 | 4.諸大名、将軍と東使の対面を求める | 5.将軍義教、御対面を受け入れ、都鄙和睦が成立する |
| 6.義教の駿河下向計画 | 7.義教の駿河下向 | 8.今川家の内紛 | 9.山門騒動 | 10.関東騒擾の風聞(1) |
| 11.山門討伐 | 12.延暦寺中堂炎上と 関東騒擾の風聞(2) |
13.三宝院満済の死 | 14.関東騒擾の風聞(3) ~信濃国への関東介入~ |
15.関東騒擾の風聞(4) ~鎌倉内紛~ |
| 16.都鄙決裂 ~永享の乱~ |
17.足利持氏の降伏と死 | 18.大御堂殿成潤の挙兵 | 19.大御堂殿成潤、 結城氏朝を恃む |
20.安王丸の挙兵 |
| 21.結城氏朝離反が発覚 | 22.小山攻めの失敗と 結城籠城 |
23.結城合戦(一) | 24.結城合戦(二) | 25.結城合戦(三) 結城城落城 |
| 26.安王丸、春王丸の処刑 | 27.将軍義教、殺害される(赤松乱) | 28.将軍義勝の継家と 赤松追討軍 |
29.赤松追討の綸旨と 播磨攻め |
30.足利「万寿王丸」は創作か |
| 31.上野国と常陸国の騒擾 | 32.足利義勝の七代将軍就任と急死 | 33.南朝皇胤の蜂起と鎮圧 | 34.京都武家の騒乱の萌芽 |
35.上杉憲実入道への関東管領留任綸旨 |
| 36.足利成氏の出京 | 37.足利成氏の鎌倉還御 | 38.江ノ島合戦 | 39.成氏と関東管領上杉憲忠の確執 | 40.享徳の乱勃発 |
| 41.成氏追討使の派遣 | 42.千葉内乱 | 43.胤直入道の死 ~多古嶋合戦~ |
 (1413-1455)
(1413-1455)
| 生没年 | 応永20(1413)年~亨徳4(1455)年8月15日 |
| 父 | 千葉介兼胤 |
| 母 | 上杉氏憲入道禅秀女(『鎌倉大草紙』) |
| 妻 | 不明 |
| 官位 | 不明 |
| 官職 | 不明 |
| 役職 | 下総国守護職 上総国守護職(守護的代官) 鎌倉侍所司か |
| 所在 | 下総国千葉庄 鎌倉 |
| 法号 | 相應寺殿真西一閑臨慎阿弥陀仏 常瑞(入道号) |
| 墓所 | 土橋東禅寺(伝五輪塔) 千葉大日寺 千葉相應寺 |
千葉氏十五代。千葉介兼胤の嫡子。母は上杉氏憲入道禅秀女(『鎌倉大草紙』)。生年は『本土寺過去帳』によれば「第十二胤直四十三 享徳四年乙亥八月十五日」(『本土寺過去帳』「千葉介代々御先祖次第」)とあることから、逆算すると応永20(1413)年の生まれとなる。号は常瑞・日瑞。
 |
| 胤直花押 |
永享2(1430)年6月に父が亡くなったため、十八歳で家督を継ぐ。胤直が守護職補任を受けた記録はないが、先例から下総守護補任の吹挙はなされたと思われる。永享4(1432)年の持氏による相模大山寺造営に際しての献馬では20歳にも拘わらず無官の「平胤直」と見える(『大山寺造営奉加帳』)。ただし、奉加帳の中では大山寺のある相模国の守護「散位持家」(御一家)よりも上位にあることから、外様の大名衆は鎌倉殿の被官よりも高い家格にあったと考えられる。
胤直の諱を見ると、満胤、兼胤二代のように鎌倉殿から片諱を拝領した形跡はない。胤直が十六歳の応永35(1428)年は将軍義持の薨去があり、もしこの年以降に胤直の元服があったとすれば、持氏が「持」字を下すことを憚った可能性もあろう。なお、胤直以降の千葉惣領家も鎌倉殿(古河公方家)からの片諱拝領はないが、それについては『千学集抜粋』の中に、文明3(1471)年ごろ、千葉介孝胤が古河公方足利成氏が、千葉から古河へ俄かに帰還する際、「六崎」(佐倉市六崎)に出迎えた孝胤が、篠塚(佐倉市小篠塚)の成氏陣所から遣わされた「本間殿」から「御子一人御字を於請」うべきことを述べるが、孝胤は「某代々妙見菩薩の宮前において元服いたすことなれば」と、成氏からの片諱拝領を婉曲に拒否したという。すると、本間はさらに、長男は無理ならば「第二の御子を」と言うと、孝胤は「某の家は二男ハ嫡子に一字を申請」うとして、こちらも断ったという(『千学集抜粋』)。あくまでも『千学集抜粋』の記録ではあるが、千葉家は長男は元服を妙見社にて行い、次男は嫡子からの一字(新字か「胤」字かは不明)拝領による決まりがあったとする。ただし、兼胤までの歴代当主の諱を見る限り、彼らはいずれも当時の権力者(得宗、足利将軍、鎌倉殿)からの一字拝領があることから、『千学集抜粋』に見るような妙見社前での儀式が執り行われるようになったのは、胤直以降となろう。
関東と奥州との関わりは、明徳2(1391)年7月頃に「陸奥出羽両国事、可致沙汰之由、所被仰下也」(明徳三年正月十一日「足利氏満御教書」『結城小峰文書』)とあるように奥羽二国が関東に移管されたことにはじまる。これにより、明徳3(1392)年から応永2(1395)年までの間に、鎌倉は篠川に奥州探題家の斯波刑部大輔満持を遣わしたが、伊達、葦名、田村庄司ら中奥州の国人層が関東支配に反発。応永2(1395)年9月に田村庄司が叛乱し、篠川城を攻められるも斯波満持の手により鎮定された。
この直後、応永2(1395)年11月までの間に、鎌倉殿氏満の子(二男か)足利四郎満貞が篠川に派遣されている。当時満貞は十代半ばであり、鎌倉の直接的な関わりのもとで奥州探題・斯波刑部大輔満持が彼を補佐したのだろう。その経済基盤もまた、南奥州の白河結城氏、石川氏らから提供された御料所に頼る脆弱なものであった。軍事的な対応についても斯波満持や持詮ら奥州探題家、上杉右衛門佐氏憲ら鎌倉からの直接派遣部隊によって解決が図られている。
ところが、応永16(1409)年7月22日に鎌倉殿満兼が三十二歳で急死。満兼嫡男の幸王丸(持氏)が十三歳で継承するが、翌応永17(1410)年8月15日、持氏は「依虚事子細、八ヽ十五ヽ若公管領宿所山内へ出御」(『生田本鎌倉大日記』)という。原因は「満隆御陰謀雑説故歟」(『鎌倉大日記』)とあるように、持氏叔父の満隆による陰謀であり、騒動は管領憲定入道の骨折りで満隆が持氏に陳謝して収まり、持氏は「同九ヽ三ヽ御所へ還御座」(『鎌倉大日記』)した。
しかし満隆の陰謀を収めた安房入道長基も病のために管領職を辞し、応永19(1412)年「十二ゝ十八ゝ、長基頓滅」(『鎌倉大日記』)した。すると、鳴りを潜めていた満隆が管領氏憲入道禅秀と組み、若い持氏を差し置いて、ふたたび鎌倉の政務に口を出し始める。氏憲入道禅秀は奥州への介入も行ったとみられ、応永20(1413)年から22(1415)年ごろまでに、満隆は弟・満直を新たな奥州篠川殿として派遣したと思われる。満隆は自身が幼いころに奥州篠川へ下っていた兄の満貞との関係は希薄であったと思われ、満隆は自分とともに鎌倉で育った弟・満直を奥州に遣わして影響力を強めようとしたと考えられる。
足利氏満―+―足利満兼―――――+―足利持氏――+―尼昌泰
(左兵衛督)|(左兵衛督) |(左兵衛督) |(太平寺住持)
| | |
| +―足利持仲 +―足利義久
| (乙御前) |(賢王丸)
| |
|【篠川殿→稲村殿→二橋御所】 +―成潤
+―足利満貞=======足利安王丸 |(勝長寿院門主)
|(四郎) |
| +―足利春王丸
|【新御堂小路殿】 |
+―足利満隆=======足利持仲 |
|(新御堂小路殿) (乙御前) +―足利安王丸
| |
|【篠川殿】 |
+―足利満直 +―足利成氏
(左兵衛佐) |(永寿王丸)
|
+―定尊
|(若宮別当)
|
+―周昉
|(長春院主)
|
+―尊僌
(若宮別当:古河自称カ)
こうして、篠川殿満貞は二十年あまり治めた篠川の地から、南の稲村(須賀川市稲御所館)へ移され、篠川には新たに足利満直が着任したのだろう。満貞が鎌倉へ戻されなかったのは、満貞が満隆の兄であり、且つその名声を危険視した可能性があろう。満隆はこれまで歴代鎌倉殿が祈願寺としていた安房国長狭郡龍興寺に、応永22(1415)年12月19日に祈願(応永廿二年十二月十九日「足利満隆書下」『保坂潤治氏所蔵文書』室1505)しており、みずから鎌倉殿に成り代わる野心があったと推測される。この満隆と管領氏憲入道を後ろ盾とした新たな篠川殿満直が鎌倉と連携していく体制を確立させようとしたのだろう。
ところが、その赴任からわずか1、2年後の応永23(1416)年10月、鎌倉で満隆と管領禅秀入道が御所の鎌倉殿持氏を襲撃するも持氏は鎌倉を脱出して駿河へ逃れた。そして、満隆・禅秀入道は鎌倉殿への反逆を将軍義持から咎められ、義持の協力を得た持氏に討たれた(上杉禅秀の乱)。突然後ろ盾を失った満直は驚愕しただろう。しかし、満直が鎌倉を頼ることは不可能であり、持氏と「京都御扶持之輩」との軍事的な対立を利用して京都と繋がりを持つ選択をして、鎌倉殿の座を狙ったと思われる。
その後も京都と鎌倉の間では、持氏と「京都御扶持之輩」との抗争が続き、大規模な「京都御扶持」の人々の「関東への叛乱」である常陸国小栗城が応永30(1424)年8月2日に陥落すると、その報告を受けた義持は、9月中旬までに「関東、此間或毎時任雅意、自是加扶持者共悉及沙汰候」ことを理由に「佐々河方急打越鎌倉、可致行沙汰候」した(応永卅年九月廿四日「足利義持御教書案写」『足利将軍御内書并奉書留』室2078)。これが義持が篠川満直を事実上新たな鎌倉殿として認めた初見となる。
しかしその後、関東持氏方が一定の成果を果たしたためか謝罪したことで都鄙和睦となり、満直の鎌倉殿補任は立ち消えとなった。応永31(1424)年10月頃には稲村の満貞(前篠川殿)が鎌倉へ帰参しており、和睦のひとつの条件であった可能性もあろう。ところが、義持は応永35(1428)年正月18日に臀部の壊死性筋膜炎とみられる症状で薨去。室町殿の跡を継いだ実弟義宣(のちの将軍義教)も義持の重職の衆議政策を継承し、彼等の都鄙融和の政策を続け、正長元(1428)年頃には持氏が佐竹祐義ら「京都御扶持之輩」と再び戦いに及んでも京都から関東への強い対応は取られなかった。当時上方でも称光天皇の崩御(7月20日)や伊勢国司北畠満雅らの挙兵もあり、関東に目を向ける隙はなかったのだろう。
ただ、関東の事も捨て置くことはできず、義宣は篠川満直に下野那須氏、常陸佐竹氏の御扶持を指示する御教書発給を計画した。関東進止国の両国へ篠川満直を介入させ、関東の牽制を図ろうと考えたと思われる。義宣は事実上、関東での京方旗頭となっていた篠川満直を重視せざるを得なかったのであろう。しかし、この策は三宝院満済をはじめとする融和派の反対に合い、実行に移すことができなかった。とくに満済は篠川満直の尊大にして傲慢な態度を嫌って手厳しく批判しており、とりわけ満済が強く反対した理由は、満直が信用の置けない人物と評したためであろう。
当時、篠川満直は南奥州の二大勢力である白河結城氏朝※と石川駿河守義光の対立について、白河結城氏に肩入れしていた。白河結城氏朝は彼が上杉禅秀入道の縁戚に当たる那須氏から入嗣した関係によるものとみられ、白川結城氏朝は故禅秀女婿の那須越後守資之と連携を深めている。
※氏朝の父は「兵部少輔資朝」といい、通説では「資」字から那須氏出身とみられている。ところが、彼は那須氏の系譜にも見えず、その活動もまったく見えない人物である。資朝は「朝」字が見えるように小山氏や結城氏の出身とも想定可能である。また文書の中には、資朝が白河満朝に実子・氏朝を譲り「御親子」にした理由として「殊に今一族中、相背き申候之間、如此令申候」とあるように、資朝は一族の惣領的立場だが一族がみな背いていることを示している。応永10年当時、那須地方においては内紛は確認されず、比較的安定した時代であり、一族が資朝に背いた傍証も見えない。つまり、資朝が那須氏である確実な証拠はない。
●応永10(1403)年3月27日『兵部少輔資朝契状』(『史料編纂所所蔵白川文書』)
この白河結城氏と篠川満直の蠢動に、正長元(1428)年10月頃、関東進止国ではない越後国に対して軍勢催促をしてしまう。越後守護代長尾氏からの報告でこの事実を知った義宣は持氏に不審を抱き、京都の対関東の融和策を一転させてしまう。
永享元(1429)年8月頃、「自関東使者僧上洛」しており、持氏は京都に何らかの主張をしている(『満済准后日記』正長二年八月廿六日条)。
当時、持氏が京都に対して敵意を示した文書は一切存在せず、持氏が退治を試みた相手は、あくまでも管国関東・奥州の秩序を乱し続ける元凶・篠川殿と、白河氏朝、那須資之、佐竹祐義ら「京都御扶持(京都の支援を受けている)」を標榜して関東祗候の義務を果たさない人々であり、彼らは京都との関わりを強調し、京都を巻き込んでいたに過ぎない。篠川満直も、兄の満隆、前管領禅秀亡き後、彼等を追討した鎌倉を頼ることができずに京都を利用したに過ぎず、その権勢を利用して鎌倉殿の座を狙っていた人物であり、これらの企みを看破していたのが満済であった。
一方、持氏の主張は一貫しており、3月5日に帰洛した使僧大安和尚の報告に「大安和尚、於御前無殊申旨、関東之儀、毎事無為」(『満済准后日記』正長二年三月五日条)とあるように、京都への敵意はなかった。義教が硬化した越後国守護代長尾邦景入道や国人へ持氏が御教書を発給していた事実も、敵対する白河結城氏への出兵協力を意図したものと思われ、京都への敵意ではない。ただし、管領山内上杉家の同族が守護職とはいえ管国外の越後へ介入したことは持氏の不用意であった。
関東使者僧は10月下旬と思われるが、管領義淳を通じて将軍義教との対面を要請したものの将軍はこれを承引しなかった。そこで管領義淳は満済に「関東使節西堂御対面事、此間種々雖申、無御承引上者無力可下遣、就其條々申子細候哉、此門跡ヘ旁令同道、委細直令尋聞食、御披露可畏入(関東使節西堂との御対面につき、様々に申し入れたものの御承引ないので、もはや関東へ下向させようと思います。ただ、使者僧が申したい條々があるやもしれませんので、門跡が同道の上で直に委細をお尋ねいただき、その條々を室町殿にお伝え願いたい)」(『満済准后日記』永享元年十月廿五日条)ことを伝えたが、満済も「如此及両度雖申候、予対面事旁無益(このようなことを二度聞いているが、私が対面することはまったく意味がない)」と伝え、これを断っている。しかし、満済も独断で決定することには慎重であり、10月25日に室町殿へ参じて、使者僧と管領義淳とのやり取りの仔細を報告し、「令故障了、可為何様哉(管領の依頼は断りましたが、どうすればよいでしょう)」と裁決を仰いでいる。これに義教は「不可有殊申事歟、爾者対面無益(とくに話すこともない。そうであれば対面も意味がなかろう)」と答え、対面はなされなかった(『満済准后日記』永享元年十月廿五日条)。
そして、管領義淳は将軍義教から「可罷下由被仰下(関東へ戻るよう仰せ下された)」ことを関東使西堂へ伝えるよう指示された(『満済准后日記』永享元年十一月廿一日条)。管領義淳がこの旨を西堂へ伝えたところ、「一途無御左右者難罷下、所詮此様可令注進間、平ニ在京事御免可畏入(結論がいただけないので帰国できないことを関東に注進させますので、どうか在京をお許しいただきたい)」と訴えられ、困った管領義淳は満済に「可為何様哉」と相談している(『満済准后日記』永享元年十一月廿一日条)。また、西堂は関東管領安房守憲実宛ての管領書状も要請しており、これもまた「可遣候哉」と諮問している。
なお、11月21日から27日まで将軍義教は石清水社頭に参篭し、管領義淳は、畠山満家入道、細川右京大夫持之とともに供奉しており、その直前に飯尾美作守に満済に諮問するよう指示したのだろう。
| 内容 | 満済の返答 | |
| (一) | 関東使節僧西堂、可罷下由被仰下間、其旨仰含處、一途無左右者難罷下、所詮此様可令注進間、平ニ在京事御免可畏入 | 此使節強在京事ハ無力次第歟、此由お可被達上聞歟 |
| (二) | 管領書状お関東阿房守方へ此使節所望申事候 | 御状事、可被遣関東房州條、若猶可有思案事歟 |
そして、満済はこの管領からの相談に、「此使節強在京事ハ無力次第歟、此由お可被達上聞歟(使節が強いて在京することはやむを得ないでしょう。この件を室町殿にお伝えするべきでしょう)」とし、管領御書の発給の要望については、「御状事、可被遣関東房州條、若猶可有思案事歟(管領御状を関東管領憲実へ遣わされる件については、もうすこし思案すべきでしょう)」と返答を保留している。その結末は不明であるが、おそらく、管領から使僧西堂の将軍対面不可の件について、関東管領憲実に管領義淳から書状が送られ、京都の不穏な情勢が関東に伝わったのだろう。ここで持氏は上洛の使者を、通常の外交使である五山僧ではなく、関東行政職のトップである政所執事・二階堂信濃守盛秀とすることを決定するのであった。
翌永享2(1430)年正月20日頃、管領義淳のもとに「自関東、使者二階堂信濃守、来月可京着旨(管領義淳宛てに、関東からの使者二階堂信濃守が来月京都に到着する予定との連絡)」が伝えられ、正月20日、管領から満済に「自管領内々可達上聞由申送(管領から内々上聞に達するよう言われました)」られたが、満済は「雖爾粗忽披露斟酌之由、令返答(失礼ながら報告は辞退すると返答)」し、義教へ「内々達上聞也(これらを内々室町殿にお伝えした)」した(『満済准后日記』永享二年正月廿五日条)。ただし、結局はこの二階堂信濃守の上洛は認められ、日限も決定されたようで、2月13日、関東管領憲実は二階堂盛秀に書状を遣わしている(年不詳二月十三日「上杉憲実書状写」『静嘉堂本集古文書』)。
●年不詳2月13日『上杉憲実書状写』(「静嘉堂本集古文書」シ)
おそらく「仍京都領事、自已前如被仰出、不可有相違之由 上意候(関東における京都御料を返上する件は、以前から仰せられている通り間違いないという持氏の御意思)」という件での議題を提示したと思われる。
一方、その2月20日頃には「篠河申状」が京都に届けられ、24日以前に将軍義教が諸大名に内々に「篠河申状」への対応の相談を行った(『満済准后日記』永享二年四月廿四日条)。篠川満直申状の内容は「両三ヶ国御勢事、近日可令発向関東歟之由事」というもので、前年7月の「自奥篠川殿、注進状」と同様、京方三ヶ国(越後、信濃、駿河国)を以て鎌倉を攻めたい(正長2年は満済らにより拒否された)というものだった。管領斯波義淳は松田対馬守、飯尾加賀守の両奉行を通じ「畠山、右京大夫、山名、赤松、畠山大夫、細河讃岐入道、一色修理大夫七人方」へ篠川状の内容について意見聴取を行ったところ、悉く「只今御勢仕事、不可然、京鎌倉無為之條、殊簡要存」(『満済准后日記』永享二年四月廿四日条)との否定意見であった。満済は2月28日に上京すると御所に参じ「去廿四日両奉行来申入、就篠河被申入事、大名意見廿五日披露」を伝え、「所詮諸大名意見、粗忽ニ御勢仕事不可然由、一同申入」れている。これを受けた義教も「先只今御下知被閣之」として、前年に引き続き、篠川満直による鎌倉攻めの要望を却下した。
一方で、二階堂信濃守盛秀の上洛についても、延引されたようである。
また、京都では永享元(1429)年12月21日、南朝皇胤小倉宮を擁立して兵を挙げていた伊勢国司北畠少将満雅は安濃郡で討死を遂げ、首級は「其首、宮こへのぼりて四塚に懸らる」(『椿葉記』)とみえ、京南端の四塚(南区四ツ塚町)に晒されたことがわかる。この結果、満雅の弟・北畠顕雅は降参について「歎申入」し(『満済准后日記』永享二年四月二日条)、小倉宮もまた帰京を求めていたため、永享2(1430)年4月2日、将軍義教は管領以下に條々の談合を指示した。伊勢関連については「小倉宮、参洛可為近日由、頻自彼方懇望」の案件については「面々相談、早々参洛尤可宜歟之旨、先別而被仰談畠山也」として「召遊佐仰付」た。
同時に、「伊勢国司御免事、去年以来歎申入也、可為何様哉、且面々意見可被尋聞食如何」と指示した(『満済准后日記』永享二年四月二日条)。畠山満家入道はすでに前年8月に管領職を辞して斯波左兵衛佐義淳が就いていたが(固辞する義淳を強引に説得して管領としている)、義教は老練な満家入道を信頼し、やる気のない管領ではなく満家入道に意見の具申を行ったとみられる。これに対し畠山満家入道は「小倉宮御入洛事、早々尤宜存候」と述べるとともに、「御料所定間ハ諸大名為国役可致其沙汰由、旧冬申入了、如然可被仰付管領歟、御出立用脚万疋等事、以此支配内可被進也、此等儀、公方様ハ不被知食、管領相計進様儀尤可宜」と、この件については管領斯波義淳が万事差配すべきと意見した。結果、小倉宮は「またさがへ帰り入せ給」った(『椿葉記』)。
また「伊勢国司御免事」についても「自管領面々畠山、右京大夫、山名意見相尋取調可申入旨被仰間、召飯尾美作守申遣管領了」と答えている(『満済准后日記』永享二年四月二日条)。その結果、伊勢国司の赦免は受け容れられ、4月26日、「伊勢国司號北畠少将顕雅御免、御対面、赤松入道同道」であった。赤松満祐入道の同道は「此事予執申了、依赤松入道申也」とあるように満祐入道から満済に申入れがあり、満済から義教に執進して実現したものである。顕雅は義教に「三万疋、太刀、馬進上」している(『満済准后日記』永享二年四月廿六日条)。
4月27日、「伊勢国司顕雅」が法身院に満済を訪ね「五千疋」を献じた。御対面の口入に対する御礼とみられる。満済は返礼として「盆香合、太刀一腰」を遣わしている(『満済准后日記』永享二年四月廿七日条)。6月9日、「伊勢国司知行分」として相国寺領「壱志、飯高両郡安堵」が与えられた件に付き、替地として「長野」が付された。
越後国における持氏の軍勢催促問題で一旦は冷え込んだ都鄙関係は、京都と鎌倉の有司同士の意思疎通により、再び融和路線へと転換された。そして、永享2(1430)年6月20日には満済のもとに「自関東興国寺長老方書状到来」した(『満済准后日記』永享二年六月廿日条)。持氏は建長寺明窓長老を通じて満済に「為使節二階堂信濃守、可令参洛、可加扶持」旨を依頼しており、満済は「返報則遣之」(『満済准后日記』永享二年六月廿日条)している。
翌6月21日、満済は醍醐寺から出京して室町殿で義教に対面し、「来月(大将)御拝賀事、如康暦大略被治定了」ことを報告したのち、前日に到来した「興国寺長老明窓和尚状備上覧」した(『満済准后日記』永享二年六月廿一日条)。義教はこれを読むと「佐々川へ進人、関東、使節可令参洛云々、然者以無為之儀可有御対面條尤宜也」と述べたという。篠川へ人を遣わし、持氏が使節を参洛させる旨を伝えてきたので、使節との対面が和平のために最も望ましいことであると述べており、当初義教は関東使節との対面に積極的だったことがうかがえる。ただ、同時に「佐々川并奥白川以下御扶持御合力不可依、此儀由内々可申遣」も付け加え、篠川や白河等の「御扶持、御合力」には些かも影響はないことも内々に申し遣わすよう指示。さらにこの対面のことは「且不可有上意候儀也、堅固自私可申入分由」とするよう指示した。対面は義教の意志ではなく、管領らの意志であるという、篠川満直との関係にも配慮するよう求めたのである。満済はこの意趣を細川右京大夫持之や石橋左衛門佐満博入道に「其旨堅申遣了」し、彼等から「可存知由京兆返事、石橋入道同前之儀也」の返答を受け取っている。また、義教は「自予方モ佐々(川)此次第具令申可下状之由承間、内々用意也」(『満済准后日記』永享二年六月廿一日条)と、満済からも篠川満直へこの件についての詳細な説明を下すよう指示した。
6月29日、先日の義教の「内々時宜」により、管領斯波義淳及び右京大夫持之は「就関東使節参洛近々事、可有御対面歟由可被申旨、奥ノ佐々河へ以状申了」と、近々上洛予定の二階堂信濃守との対面についての篠川殿への意見聴取で、案文を室町殿の見参に入れた(『満済准后日記』永享二年六月廿九日条)。内容は、義教の「御対面事、自奥佐々河不被申者、堅可有御斟酌由、去年以来被仰定了(御対面の件は奥州篠川から(対面してもよいと)何も申してこなければ、固く遠慮する旨を去年以来仰せ定められている)」(『満済准后日記』永享二年七月六日条)という心情を、管領以下の言葉として「自関東使者参洛時、可有御対面歟事(関東からの使者が参洛したとき、御対面を行うべきか意見を述べよ)」(『満済准后日記』永享二年九月五日条)というもので「此使者僧、自右京大夫方今月一日已下遣了」(『満済准后日記』永享二年七月七日条)と、7月1日に細川持之が満済と管領義淳の書状を持った使僧を篠川へ発した。
7月6日、満済のもとに「石橋左衛門佐入道為御使来」て、「自関東、使節二階堂信濃守近日参洛云々、仍御対面事、自奥佐々河不被申者、堅可有御斟酌由、去年以来被仰定了、此事管領以下内々申談、佐々河へ進使者、此御対面事、平ニ可被申入旨申之也、此使者僧、自右京大夫方一日已下遣了、予状并管領状、以此僧進佐々河了(関東からの使節二階堂信濃守が近日参洛するとのこと。よって御対面の件は奥州篠川より何も申してこなければ、固く遠慮する旨を去年以来仰せ定められている。このことは管領以下と内々に話し合い、篠川へ使者を送り、この御対面の事につき、なんとか意見を申し入れるべしと申した。この使僧は細川右京大夫方からすでに7月1日に篠川へ下向させており、私の手紙と管領状をこの使僧に持たせて篠川に送った)」との報告があり、さらに「然自石橋方又可下遣使節也、管領状、自石橋方可下遣處、無左右自右京大夫方下條、何様子細哉、次管領状案文被御覧處、文章以外大様ニ思食也、愚身意見歟、所詮重委細状以石橋下向使者可下遣旨、申管領(石橋左衛門佐入道からもまた使者を遣わす。管領状は本来石橋方から遣わすべきところを、無造作にも細川右京大夫方から遣わしてしまった。いったいどんな理由があったのだ。次に管領状の案文を見たところ、文章がなんとも要点の定まらない不出来なものと感じた。これは満済の意見か。細かいことを記した書状を石橋方からの使者に再度持たせて遣わす旨を管領に伝えよ)」(『満済准后日記』永享二年七月六日条)という。
これを受けた満済は「此書状事、以右京大夫下遣僧、可進佐々河由、先日申入候歟之由存候き(この篠川状の件については、細川右京大夫が遣わす使僧に持たせて篠川へ送るよう、先日申し入れたかと存じますが)」と反論し「管領書状文言、不及意見候、去晦日自管領使者飯尾美作持来間、一見條勿論候也、其時不備上覧條越度至由申了、則以慶円法眼申遣管領、重書状遣石橋左衛門佐入道方了、備上覧(管領書状の文言については、意見していません。6月30日に管領使者が持ってきた案文は当然一見しています。そのときには、室町殿に見せていない事は落度の至りと、慶円法師を管領邸に遣わして、再度石橋左衛門佐入道の使者に書状を持たせました)」と述べた。
ところが8月6日、満済のもとに細川持之から内々に「白河方(白河氏朝)注進」が届けられた。内容を見た満済は、早々に宝池院壇所にいる義教へその報告を行っている(『満済准后日記』永享二年八月六日条)。その内容とは「一色宮内大輔為大将、重可罷向那須城由有風聞、定可為大勢歟、於此時者、自京都無御合力之儀者、可及生涯」という、かなり切羽詰まったものだった。一色宮内大輔は持氏親族の一色宮内大輔直兼で、彼が率いる軍勢が「京都御扶持之輩」である那須太郎氏資の「那須城」へ向かっているという風聞だった。那須城にともに籠っている白河氏朝は、一色直兼の軍勢であれば「定可為大勢歟」と推測し、もし京都の合力がなければ自刃するほかないと京都側の合力を要請している。
これを聞いた義教は、白河救援のために正長2(1429)年8月18日の三国合力の御教書に加えて、再度「三ヶ国越後、信濃、駿河可合力旨、重被仰付了」ている。その担当は「越後、信濃両国事、畠山方」で「駿河国事并信州大文字一揆事、山名方」と定め、それぞれに申し伝え、彼らも「可申下由申了」と了承している(『満済准后日記』永享二年八月六日条)。ただし、これはあくまでも牽制であって実際に軍勢を当地に介入させるものではない。ただ、この那須氏攻めの一報は義教の関東への心証を害したと思われる。
また、この頃、駿河国から「碩蔵」という「駿河国よりのほりたる僧あり、守護上総介範政ゆかりあり」(『草根集』巻二)が上洛しており、義教に何らかの報告をした可能性がある。彼は今川了俊門人の招月庵正徹との交流があり、8月18日、何らかの「其祈禱のためとて住吉法楽百首」を奉納している。
9月4日、「自右京大夫方下遣佐々川方使者僧参洛」(『満済准后日記』永享二年九月四日条)した。使僧は「京兆使有岡同道」して満済を訪れ、「自佐々川此門跡へ返報并右京大夫方へ返事等悉持来了」という。その内容は以下の通り(『満済准后日記』永享三年三月廿日条に大意が載る)。
| 篠川殿の意見 | 大意 |
| 当御代、関東不儀以外候哉、已御料所足利庄お為始、京都御知行所々不残一所悉押領 | 当御代になって、持氏の不義は論外であろう。すでに御料所足利庄をはじめとして、京都の御知行は一所残らず押領している。 |
| 御代初、最前可被進使節處、于今無其儀 | 御代初に際しては、真っ先に使節を遣わして祝意を述べるべきなのに、持氏はいまだにそれがない。 |
| 那須、佐竹、白河以下京都御扶持者共、可加対治旨加下知、已合戦及度々了、 雖然此方堅固故ニ于今無為、是併又京都御扶持ノ儀ニ依テ奥者共、悉致無二忠節也、仍関東挿野心、京都ヘ可罷上結構雖在之、奥者共不及同心、剰及合戦間、自然遅引了、然東使近日参洛事ハ京都お出抜申さむ為の料簡也、若不事問東使ニ御対面事在ハ、於奥者共者、悉退屈仕、可失力、此條若偽申入ハトテ種々及告文状了 | 持氏は、那須、佐竹、白川以下の京都御扶持の者どもに対して、退治するよう下知し、すでに合戦があちこちで起こっている。 しかし、我らは堅固に守っているので、関東の情勢は変わらない、これは京都御扶持によって奥州の者どもが悉く無二の忠節を尽くしているからである。それによって持氏が野心を持って上洛を企てても、奥州の者どもが同心せず、さらには合戦して上洛を遅らせているのである。もし、このまま関東使節と御対面などすれば、奥州の者どもはみな戦う気力を失うだろう。このことは誓紙を以て偽りでないことを証明する。 |
これらに基づき「御対面事、不可然也、乍去、諸大名可有御対面由意見申入上ハ、縦御対面アリトモ、此次ニ関東事、堅可有御沙汰條、尤可目出、不然ハ御後悔事可在之條勿論」ことを「載誓言被申」というものであった(『満済准后日記』永享二年九月四日条)。ただ、篠川満直は、関東使者との対面は「不可然」だが、諸大名が御対面あるべしとの意見であれば御対面もやむを得ない。ただ、たとえ御対面あっても次は堅く拒絶すべきで、そうでなければ必ず後悔することになると述べている。
満済は右京大夫使僧に、篠川状を右京大夫持之から上覧に供するよう伝え、満済宛てで届けられている満直返書も使僧に渡している。
9月6日、満済のもとに「自右京大夫方使者有岡参」って述べるには、「先日自佐々川御返報等、昨日五日、懸御目」たという。篠川満直からの返報には、前記の関東使節との対面事案以外に、奥州懸田氏の反抗について述べられており、義教は「就其懸田事、可有御治罰歟由、佐々川ヘ御教書お被成遣、伊達、葦名、白川以下奥大名方へ悉可被成御教書、就其ハ自右京大夫方、懸田御対治事、先如此御教書おハ雖成遣候、懸田若御対治無左右難叶様候者、先可被閣候歟、両篇重可被申入旨可申下(懸田の件は、討つべきかどうかを篠川へ御教書を遣わして問い、伊達、葦名、白河らの奥州大名方へも悉く御教書を送るべきだ。この件は右京大夫からは、懸田対治の事は、まず御教書を遣わすが、懸田対治がもしうまく行かなければ、退治を中止するべきか。篠川は両案について返答するよう命じよ)」ことを細川持之に「内々被仰下」たという。また、義教は「所詮、此等子細可為何様候哉、可尋申門跡意見由被仰出」と、満済の意見も求めるよう指示した(『満済准后日記』永享二年九月六日条)。
なお「懸田」は、正長2(1429)年以来鎌倉に「伊達、懸田其方可合力」(正長二年二月九日「足利持氏書状」『石川家文書』室2518)し(ただし伊達持宗の合力は誤伝)、「懸田、相馬忠節誠神妙候」(正長二年五月廿六日「足利持氏書状」『石川家文書』室2538)、「常州并那須口等事、上杉三郎、一色宮内大輔可有発向候、仍其方事、令談合懸田播磨入道、可然様可致料簡候也」(正長二年?六月十一日「足利満家書状」『石川家文書』室:2546)とあるように、懸田播磨入道が関東方に合力したことがわかる。
持之のこれらの知らせに満済は「於懸田御対治一段者、善悪之儀更不存知候、就中治罰御教書おハ乍被成遣候、自右京大夫方対治難事行候者、先被閣重可被申由可被申下條ハ、可有如何候歟、若得上意内々如此被申下候様ニ、佐々川以下輩、推量候者、只今御教書凌爾ニ可成歟、於御條ハ若猶可有御思案歟由(どちらが対立の発端を作ったのかもわからず、懸田を治罰すべき御教書を下しながら討伐が難儀な事態となった場合は討伐を中断する指示を出すとすれば、御教書の威信にも関わる問題となる)」(『満済准后日記』永享二年九月六日条)を返答し、御教書を下すことに反対を示した。
また「内々右京大夫方へ申遣分」として満済の真意を「有岡」に述べているが、「懸田只今御治罰事ハ、旁卒爾覚候、奥事おハ毎時被任申佐々川、依彼御注進様御成敗ハ尤可宜事歟、関東ノ大敵ヲ置ナカラ、御敵之内ニテ不慮弓矢出来ハ、万一関東ノ得理ニヤモト覚候、此條ハ努力ゝゝ不可及披露由(懸田を今退治することは時期尚早と思う。奥州は篠川に任せている以上は、彼の注進を待つことがよいだろう。奥州に関東の大敵を置きながら、奥州京方の仲間割れが起これば関東を利するだけです。ただこの件は室町殿にはよくよく内密に)」(『満済准后日記』永享二年九月六日条)と申し伝えている。
9月10日、室町殿で連歌が行われるが、満済は集合時間よりも早く一人で参上し、義教と対面した。すると義教は「奥佐々河方へ重下使節、自関東使者参着ハ可有御対面歟、先度被尋遣處、佐々川御返事趣、於御対面、旁於奥并京都方御扶持者、雖難治至極、京都大名頻可有御対面之由、意見申入云々、然者可有御対面歟、但於此次関東事厳密ニ可被仰付條可宜」という9月4日の篠川満直返報の内容を述べ、「就此返事、関東使者御対面事、佐々川心中未分明間、所詮サハゝゝト御対面有無被申様、管領、右京大夫并予状等可下遣由承了」と、関東使者との対面について、「対面はまったく困難だが、諸大名が頻りに対面すべしと言うなら行うべきだ、という『曖昧な』返事ではなく、対面は可か不可か『明確な』意見を述べよ」という書状を管領義淳、右京大夫満之、満済から篠川へ遣わすよう指示している。
これを受けた満済は、室町殿の意趣を「仍以慶円法眼申遣管領并右京大夫方也、可令存知旨共申入」(『満済准后日記』永享二年九月十日条)た。翌9月11日、右京大夫持之から有岡が満済を訪れ「佐々河方へ可進状案文賜之、為御一見」(『満済准后日記』永享二年九月十一日条)した。満済はこれを添削すると「少々相違處可直之由意見」し、翌12日、修正した書状案を「可備上覧由、右京大夫方了」(『満済准后日記』永享二年九月十二日条)し、右京大夫満之から「明後日十四日、可備上覧」(『満済准后日記』永享二年九月十二日条)との返事が届けられた。
9月14日、篠川殿への書状案を室町殿に見せた右京大夫持之から「自右京大夫方使者有岡」が満済に派遣され、「佐々河へ御状案自此門跡、備上覧候處、少々被加入事候、白河、佐竹、那須両三人殊可有御扶持由、可被入此御案文云々、其外無殊事、珍重由被仰出(満済が作成した篠川への御状案を室町殿の上覧に備えたところ、白河、佐竹、那須の三名はとくに支援しているという一文を加えるよう指示をうけたが、その他は問題ないとの仰せを受けた)」(『満済准后日記』永享二年九月十四日条)ことを報告した。満之は「加此詞、案文重可備上覧由」を告げたので、満済も「書遣了」した(『満済准后日記』永享二年九月十四日条)。その書状の主旨には義教の本音が端的に表れているが、「猶京都諸大名、定東使ニ御対面事可被申歟、天下無為儀お専被思食處、東使御対面儀無之ハ、天下無為儀不可在間、御政道相違也、御対面ニハ不可依事間、可為何様哉由(京都の諸大名は関東使節との御対面を行うよう言ってくるであろう。天下無為の儀を考えると、御対面がなければ天下無為は成し得ないこととなり、御政道と反する。では、御対面に反対する篠川殿としては、御対面に依らない天下無為の方法があるのか、その解決方法を述べよ)」(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)というものであった。
この内容の書状(管領状、右京大夫状、満済状の三通と思われる)は10月初旬には篠川に到着したと思われるが、満直が返報を記したのは2か月後の「永享二閏十(一)月八日」(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)であり、閏11月下旬に京都の「右京大夫并管領両所」(『満済准后日記』永享二年閏十一月廿四日条)に届いているように、かなり時間がかかっている。到着日時は不明ながら、右京大夫持之と管領義淳が室町殿義教に「返報文書」を見せ、満済は閏11月24日に義教へ「自佐々河返報進之了」(『満済准后日記』永享二年閏十一月廿四日条)した。義教はこの時点で右京大夫持之、管領義淳が持参した文書をすでに見ており、いずれも同文であったため「定此状モ同前歟、仍不及被御覧」として一見もせず「則返賜候了」している。
「永享二閏十(一)月八日」の篠川状の内容は「先度東使御対面難儀題目、載告文言雖申入、重被仰出上ハ兎モ角モ可為時宜、乍去、無一篇目御対面事、余々京都御為、奧以下諸侍存候はんする處、無勿体候へハ、向後那須、佐竹、白河以下京都御扶持者共、無左右為関東計不可退治由、関東ヨリ罰状お被召置、其お一面ニせラレ御対面可宜(先だって関東使節との御対面は難しい理由を誓書にて申し入れましたが、重ねての仰せの上は、兎も角も室町殿の御意のままに。ただし、何の条件も付けずに御対面することは、京都の御為に働く奥州以下の諸侍がいるなかでは問題であり、今後は那須、佐竹、白河以下の京都の支援を受けている者らに対し、鎌倉から追討は行わないという内容の熊野誓紙を持氏から出させてのちの御対面がよいでしょう)」(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)というものだった。
この「御対面」を質に取って、関東の持氏の動きを封じる誓紙提出を促すことは、義教の目指す「天下無為」への考えと一致するものだった(ただし、罰状の提出が拒否された場合は和平が遠のく危険も孕むものでもあった)。篠川からの罰状の要求は、以下の三ヶ条から成っていたようである。
●罰状三ヶ条の要求内容(『満済准后日記』永享三年四月十一日、同月十三日条)
| 4月11日条 |
那須、佐竹、白河事、向後可被停止治罰之儀事 |
那須氏資、佐竹祐義、白河氏朝に対して、今後は追捕の兵を出さないこと |
| 宇都宮藤鶴丸事、如元可被沙汰付事 | 宇都宮藤鶴丸に、宇都宮ほか所領を元のように返付すること | |
| 佐々河事、別而御扶持上者、可被得其意事 | 篠川満直は京都からとくに支援しているので、そのことを心得ること | |
| 4月13日条 | 那須、佐竹、白川向後不可有対治儀事 |
那須氏資、佐竹祐義、白河氏朝に対して、今後は追捕の兵を出さないこと |
| 宇都宮藤鶴丸如元可被沙汰居事 | 宇都宮藤鶴丸に、宇都宮ほか所領を元のように返付すること | |
| 佐々川事、京都御扶持異他、可令存知給事 | 篠川満直は京都がとりわけ支援しているので、そのことを心得ること |
義教はこの篠川満直の提案が大変心に刺さったのだろう。合議制を重んじる義教に似合わず「乍卒爾被一決」し、満済にすら内緒で「閏十一月廿七日、以石橋左衛門佐入道状并使節、佐々河へ重被仰出趣、則被載御自筆御書了」と、石橋左衛門佐満弘入道に自筆の返書を篠川へ重ねて送るよう命じた(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)。その書状の内容は「如佐々河被申、白河、佐竹、那須、宇都宮藤鶴事等三ヶ條、自関東以罰状被申者、使節ニ可有御対面由已仰定了」と、持氏に「三ヶ条(上記)」についての誓書提出を命じるとともに「如此乍卒爾被一決上ハ、自関東罰状無之ハ、使節御対面事不可在由、為管領可召仰二階堂(誓書提出要請を軽率とは思うが独断で決定した以上は、罰状提出がなければ御対面はできない旨を、管領斯波義淳から上洛する二階堂信濃守へ伝える)」こととした旨が記載されていた。誰にも諮らずに決定したのは「天下無為」を急ぎ実現したい義教が、この提案に強い望みをかけたためではなかろうか。
閏11月27日に石橋左衛門佐入道を通じて満直に送られた室町殿義教の自筆状および石橋状は、おそらく12月半ばには奥州篠川へ到着しているとみられ、翌永享3(1431)年「同三正月廿九日石橋方ヘ状」に認められた篠川満直状は、石橋左衛門佐入道へ宛てて送達された。京都到着日は記されていないが、篠川状が記された時期から考えると2月中旬であろう。満済の与り知らぬ義教独断の書状への返信であったため、満済はその内容を記述しておらず、内容は不詳だが、御対面の条件についての了承と思われる。
12月29日、この日は法身院の満済のもとに来客が多く訪れている。「檀那院僧正」、「富樫介、浴場時分間不及対面」、「上杉中務少輔、同四郎来」、「武田刑部大輔入道来」、「土佐守護代横尾来」とあるように、年末の挨拶を兼ねた依頼であろう。とくに「上杉中務少輔」は上杉禅秀の子で京都四条高倉の上杉左馬助氏朝の養子となった上杉持房、「同四郎」は持房の子(「上杉系図」『続群書類従』)、「武田刑部大輔入道」は持房の叔父に当たる甲斐守護武田信重入道であり、関東使節との御対面問題や篠川満直との繋がりがあったのかもしれない。翌永享3(1431)年正月7日に「武田刑部少輔来、太刀遣之」(『満済准后日記』永享三年正月七日条)、正月8日には「上杉中務大輔来、太刀一腰献之了」(『満済准后日記』永享三年正月八日条)とあり、武田信重入道と上杉持房は新年にも法身院に満済を訪れており、満済はそれぞれ太刀を遣わしている。
【四条高倉上杉家】
+―上杉朝房===上杉氏朝===上杉持房――+―上杉教房
|(中務大輔) (左馬助) (中務少輔) |(中務少輔)
| |
| +―武田信重 +―上杉■■
| |(刑部大輔) |(四郎)
| | |
| +―武田信長 +―上杉憲秀
| |(右馬頭) (刑部大輔)
| |
| 武田信満―+―女子 +―上杉憲方 +―上杉政憲
|(安芸守) ∥ |(伊予守) |(治部少輔)
| ∥ | |
| ∥――――+―上杉教朝――+―一色政熈
| ∥ (治部少輔) (式部少輔)
| ∥
上杉憲藤―+―上杉朝宗―+―上杉氏憲―+―上杉憲秋――+―上杉憲定
(中務大輔) (中務大輔)|(左衛門佐)|(宮内大輔) |(刑部大輔)
| | |
+―上杉氏朝 +―上杉持房 +―上杉憲久
(左馬助) |(中務少輔) (五郎)
|
+―上杉憲春
|(五郎)
|
+―実性院快尊
(大納言僧都)
なお、この頃の関東では、永享2(1430)年11月2日に関白二条持基の長者宣が香取大宮司大中臣元房へ下され、造替役人の「千葉介」へ早々に造替を遂げるよう指示するよう命じている。この時点で、すでに鎌倉末期の造替から百年近い年月が経過している。
●永享2(1429)年11月2日『二条持基長者宣』(『香取神宮文書』室2641)
その後、記録は残っていないが、香取大宮司から千葉介胤直に『長者宣』に基づき、造替の早期完了を指示する文書が出されたと思われる。
●香取社遷宮の担当者(『香取社造営次第案』:『香取文書』所収)
| 名前 | 被下宣旨 | 御遷宮 | 遷宮期間 |
| 台風で破損し急造 (藤原親通) |
―――――― | 保延3(1137)年丁巳 | |
| ―――――― | ―――――― | 久寿2(1155)年乙亥 | 21年 |
| 葛西三郎清基 | ―――――― | 治承元(1177)年12月9日 | 21年 |
| 千葉介常胤 | 建久4(1193)年癸丑 11月5日 | 建久8(1197)年2月16日 ※「依大風仮殿破損之間、俄有聖断、以中間十九年」(正和五年二月「大禰宜実長訴状写」『香取神宮所蔵文書』) | 19年 |
| 葛西入道定蓮 | 建保4(1216)年丙子 6月7日 |
嘉禄3(1227)年丁亥12月 ※本来は承久元(1219)年遷宮予定(21年)だったが、「同年鎌倉右大臣家、若宮御参詣時、被打給畢、同三年公家与関東御合戦之間、依大乱、自建久年至于嘉禄三年、卅一ヶ年、御遷宮不慮令延引者也」(正和五年二月「大禰宜実長訴状写」『香取神宮所蔵文書』) 。 | 31年 |
| 千葉介時胤 | 嘉禎2(1236)年丙申 6月日 | 宝治3(1249)年己酉3月10日 | 21年 |
| 葛西伯耆前司入道経蓮 | 弘長元(1261)年辛酉 12月17日 | 文永8(1271)年12月10日 | 21年 |
| 千葉介胤定(胤宗) | 弘安3(1280)年庚辰 4月12日 | 正応6(1293)年癸巳3月2日 | 21年 |
| 葛西伊豆三郎兵衛尉清貞 大行事与雑掌清貞 親父伊豆入道相論間、延引了 | 永仁6(1298)年戊戌 3月18日 | 元徳2(1330)年庚午6月24日 ※正和3(1314)年2月18日仮殿上棟(正和五年二月「大禰宜実長訴状写」『香取神宮所蔵文書』)。ただし材木が揃わず、14本の柱のうち7本はまだ組まれてもおらず、桁梁も縄で代用という有様。 | 36年 |
| 千葉介貞胤・氏胤・満胤・兼胤・胤直 (造営次第にはない) |
元弘3(1333)年? |
康永4(1345)年3月『造営所役注文』が定められる。 観応元(1350)年庚寅の遷宮予定も遷宮できず(貞治五年『香取文書』断簡)。 延文2(1357)年10月24日時点で仮殿上棟以降進展なし(氏胤は大禰宜長房に神官と中村入道を、仮殿所役を懈怠する大戸・神崎地頭のもとへ遣わして譴責するよう指示)。 貞治4(1365)年9月13日、氏胤死去でまた暗雲。 前回の遷宮から75年経過した応永12(1405)年11月25日時点でまだ造作は終わっていない。 さらに永享2(1429)年11月2日時点でも終わっておらず、実に百年レベルの遅滞となっている。 | ? |
永享3(1431)年2月29日、「越後国紙屋庄実相院門跡領事、可被進佐々河、於実相院者近所ニ替地可有御計之由被仰出」ているが(『満済准后日記』永享三年二月廿九日条)、これは正月29日記の篠川状への義教の対応である可能性があろう。満済は義教から実相院にこの件について沙汰するよう指示されている。越後国は京都管掌国であることから、篠川満直は支配面からも完全に関東とは切り離されていることがわかり、紙屋庄は満直の要求であったと思われる。かつて宇都宮氏が関東を避けて越後ルートで使者を京都に送っていたことからも想定されるように、満直もまた当然越後ルートで使者を上洛させていたと思われ、その経由地である紙屋庄に所領を設定することで、中継地としての機能を図ったのかもしれない。
そして3月8日、「自駿河守護方注進」として「関東使節二階堂信濃守、去月廿六日見付マテ上着由」(『満済准后日記』永享三年三月八日条)が「一色左京大夫」から室町殿義教に注進され、満済は「先珍重」と答えている。おそらく二階堂信濃守は2月20日頃に鎌倉を出立して2月22日頃には駿府に到着し、2月26日に駿河守護今川範政の送使とともに遠江国府(磐田市見付)に到着したのだろう。遠江守護は管領斯波義淳であり、ここで彼の代官に引き継がれたと思われる。3月12日、「関東使節二階堂信乃守、今日可京着由風聞」(『満済准后日記』永享三年三月十二日条)が満済の耳に入っているが、実際はその二日後、3月14日に「関東使節、今日申初、京着」している(『満済准后日記』永享三年三月十四日条)。
しかし、3月17日、管領斯波義淳の使者として飯尾美作守が醍醐寺三宝院に満済を訪れ「関東使節、未及対面候、自阿房守方書状等、昨日以赤松播磨守備上覧候處、来廿日以此門跡委細可被仰、其以後管領彼使節ニ可有対面由、被仰出候、所詮早々公方様モ御対面ニ可申入」という。これに満済は「東使参洛先以珍重、就其被仰出旨候者、何様得御意可申入」と飯尾に話すと、御所近習の赤松播磨守満政に「来廿日可出京之由」を伝えた(『満済准后日記』永享三年三月十七日条)。
翌3月18日には「自関東興国寺長老明宗和尚方状到来」した。使者は「琳首座」(『満済准后日記』永享三年三月十八日条)。しかし、この日満済は「持病」のため琳首座との対面は行っていない。建長寺の明窓宗鑑長老の申状は「今度関東使節参洛、最前ニ門跡ヘ可被申案内候、毎事可預御扶持者可畏入、年来檀那聞執申入」とある。満済はこれに「使節参洛先以珍重、相応御用事ハ何様不可有等閑之儀、於公儀者難叶、内々事ハ可承」と、内々に支援すること返答をしている。
3月20日昼前、満済は先日17日の管領からの知らせの通り、室町殿を訪れ義教と対面している(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)。義教は「今度関東使節二階堂信濃守参洛事ニ付テ、管領ヘ可被仰事、為門跡内々可召仰(今度の関東使節二階堂信濃守盛秀の参洛につき、管領へ伝える事を内々に満済に伝えておく)」と述べ、まず「就東使参洛御対面事、去年及三ヶ度、被申談奥ノ佐々河方旨在之」として、篠川満直の意見を伝え、篠川満直の返答が、対面が可なのか不可なのか断言しないことについて「佐々川心中未分明間、所詮サハゝゝト御対面有無被申様」を問い質す書状を篠川へ送ったことを述べ、その後、篠川からは前述のように、御対面には三ヶ条に関する熊野誓紙を提出させた上で御対面すべきとの返事が届いたことを語った。これは(1)持氏の武力行使を停止させることができる(2)関東使節との対面ができる、という「天下無為」を推進するための条件が揃っており、義教はこの案を早速採用し、ここでこれまで満済にも話していなかった石橋左衛門佐満弘入道を経由(公務の奥州申次である細川右京大夫は関わっていない私的なもの)して、篠川へ持氏からの罰条提出を対面条件とする旨を伝えたことを白状する。
義教は「永享二年閏十(一)月八日」と、義教独断で篠川へ送達した書状の返信「同三正月廿九日石橋方ヘ状」の篠川状二通を満済に渡すと、「管領以下畠山左衛門督入道、山名右衛門督入道、細川右京大夫、赤松左京大夫入道等、此仰旨并佐々河状可見云々、此等子細、自管領此四人大名方ヘハ可申遣由被仰出了(管領以下、畠山満家入道、山名時熈入道、細川持之、赤松満祐入道らに対面には罰状提出を条件とする旨ならびに、その根拠となった篠川状を見せるように。この子細は、管領からこの四人に申し遣わすよう仰せられた)」(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)ことが指示された。これを受け、満済は「仍管領内者甲斐、二宮越中入道両人召寄、此仰趣申了」した(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)。
その晩頭、「自管領以甲斐、二宮、飯尾美作三人」が満済を訪問し、管領義淳の意見を伝えている。その内容は「被仰出趣委細被仰下候、今度関東使節、偏以無為廉御祝着御使候、然ニ罰状等事、可被仰條旁不可然、御対面以後何様題目可被仰條宜存候(今回の関東使節は和平のための御使で、対面は罰状提出を条件とするなど以ての外、罰状を求めるのであれば対面以後に仰せられればよい)」(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)という、罰条提出に強烈に反対するものだった。管領義淳はこれに先立ち「隨而内々関東時宜趣、使節内者お両人召寄」て意見を聞いており、罰状の事柄について問うと「那須御退治事、先京都ヘ聞ヘ候分大ニ相違候」ということがわかった。
管領義淳に招かれた二階堂被官人二名が語るところによれば、那須合戦の真相は「那須五郞お総領ニ可被成儀ニテ御沙汰分曾ナキ事候、那須五郞庶子分澤村ト申知行分お総領太郞押領間、自鎌倉殿及度々御成敗處、太郞不応御下知間、彼在所ヲ五郞ニ為被沙汰居被仰付了、雖然猶不事行間、可被治罰處、那須事為京都内々扶持事候間、不可然由、上杉阿房守一向支申間、于今無其儀候(鎌倉殿持氏が「那須五郎(澤村五郎資重)」を那須家の惣領と定めた事実はありません。資重の「庶子分澤村」を惣領の太郎氏資(資重甥)が「押領」していたため、持氏が氏資にたびたび資重へ澤村返付を命じるも氏資が応じなかったため、今度は氏資在所を五郎資重へ宛行いましたが、氏資はこれにも応じませんでした。そのため、持氏は氏資追討軍を派遣しようとしましたが、管領上杉憲実が「那須は京都から内々扶持を受けており、追討は然るべからず」と差し止めたため、現在でも出征の事実はありません)」(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)という。
二階堂被官人の言うことが正しければ、昨永享2(1430)年8月6日に満済に届けられた白河結城氏朝の「一色宮内大輔為大将、重可罷向那須城由有風聞、定可為大勢歟、於此時者、自京都無御合力之儀者、可及生涯」(『満済准后日記』永享二年八月六日条)の主張は虚言になるが、結城氏朝自身も「有風聞」と確定を避けており、事実に基づかない情報だが緊急性を要する風聞が入ったため、京都に送達した可能性がある。
二階堂被官人は続けて「已京都御無音時サヘ如此、関東ハ京都お被憚申斟酌事候、今ハ已都鄙無為ノ儀ヲ深思食被進使節事候間、不可限此一事、向後ハ可為京都御成敗候哉、此那須事ナト可被仰出事、更不存寄候間、於関東不及伺時宜候、仍是非ヲ不弁候由申入候、如此申間、只今被仰出趣雖申付候、無為御返事申候ヘシトモ不存候、然者只今可被仰出事尤無益ニ存、以此趣可披露申條畏存(持氏は常に室町殿を憚り、遠慮の心を持ち、「都鄙無為」のことを深く思われて我ら使節を派遣しているのであるから、これに限らず今後は京都のお指図によって沙汰することは当然です。この那須の一件などまったく身に覚えもなく持氏の考えを聞くまでもない。また、罰状提出を持氏が許諾するはずもなく、今回の仰せは全く無益であるとお伝えください)」(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)と管領義淳に依頼している。二階堂自身ではなく、被官人二名が関東使節の意志を決裁しており、彼らは二階堂盛秀から全権委任されて管領亭を訪れたとみられる。
管領義淳が満済に伝えた「今度関東使節、偏以無為廉御祝着御使候、然ニ罰状等事、可被仰條旁不可然」(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)という主張は、二階堂被官人の話を聞いて強く納得した結果であろう。
「那須五郎(澤村五郎資重)」は常陸守護佐竹家と縁戚関係にある那須家の有力庶家で、上杉禅秀の外孫にあたる「総領太郞(太郎氏資)」とは激しい対立関係にあった。もともと氏資の父・越後守資之と五郎資重が対立し、資重が居地の澤村を追われたことが根底にあり、「総領太郞押領」は父資之が資重から奪った澤村をそのまま惣領家が保有していたことを示すのだろう。資重は「応永二十一■移烏山」(「那須系図」『那須隆氏蔵系図』)とみえ、鳥山(『那須記』に見える稲積城のことか)を拠点としたのだろう。その後の上杉禅秀の乱で越後守資之が舅の禅秀に加担して鎌倉殿持氏と敵対した際には資重は持氏方となり、禅秀追討後、持氏は「那須五郞お総領ニ可被成」としていたようである。しかし、資之は関東出仕の義務を有しながら、京都との非公認の疑似主従関係(京都御扶持之輩)を構築し、同様の立場にある宇都宮氏、結城白河氏、常陸佐竹氏庶家らとともに鎌倉と対立した。
宇都宮等綱――宇都宮明綱
(藤鶴丸) (下野守)
∥
上杉禅秀―――女子 ∥
(右衛門佐入道)∥―――――那須氏資―+―女子
∥ (太郎) |
∥ |
那須資氏―+―那須資之 +―那須明資
(刑部大輔)|(越後守) (大膳大夫)
|
+―那須資重――那須資持―――那須資実
(澤村五郎)(越後守) (伊予守)
∥
佐竹義盛―+―女子
(左馬助) |
|
+=佐竹義憲
|(左馬助)
|
+―女子
∥
上杉憲定―+―佐竹義憲
(安房守) |(左馬助)
|
+―上杉憲基==上杉憲実―――上杉憲忠
(安房守) (安房守) (安房守)
この管領の意見を受けた満済は「委細承趣尤可令披露候處、為公方被仰出旨ハ以外厳密又種々御思案候歟、然ヲ事浅ク可被申入條、時宜難計存候、所詮面々諸大名方ヘ能々被加御談合、明日ハ公方様御徳日候、明後日廿二日、可被申入(承った内容は室町殿に披露すべきだが、室町殿もこの罰状提出の件については細かく様々に御思案された結果と思います。それを深く考えずに「罰状提出はまかりならん」と室町殿に申し入れたところで、受け入れ難いでしょう。そうであれば、室町殿が仰せられるように諸大名とよくよく相談されて結論を出されるように。明日は室町殿は忌日であるから、明後日の22日に申入れるべきでしょう)」ことを伝え、甲斐ら管領使者三名も「此儀尤宜存」と述べて退出した(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)。
その後、管領義淳から意見具申を受けた(満済に使者を送るのと同時に畠山、山名、赤松らに使者を遣わして、罰状提出と御対面について相談していたのだろう)山名右衛門督入道は、被官人の「山口遠江守」を満済に派遣し「関東使節参洛事ニ付テ、自管領被申旨候間、意見申様」として自らの意見を述べた(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)。山名は「先為管領私儀、今度御使節ハ何篇ニテ候哉、御代ノ御礼ニハ以外遅々候、委細可承由被申候テ、就彼使節申状、被仰出事ナトヲモ可被仰付歟之由申候了、内々為得御意申」といい、なぜか罰状提出に関しての意見は述べなかった。
翌3月21日早朝、管領義淳は「飯尾美作一人」を満済に派遣し「以昨日趣、明旦令披露、何トモゝゝ上意無相違、早々御対面様御計可畏入(昨日の結果を明日早朝に披露したいのですが、どうか早々に御対面となるようお計らいいただきたい)」(『満済准后日記』永享三年三月廿一日条)ことを伝えた。これに満済は「昨日くれゝゝ如申、以此分申入事ハ旁難儀候、乍去、諸大名一同儀ニテ只此趣披露候ヘノ儀ニテ候者、重慥承可披露由申了(昨日、くれぐれも申したことですが、この申入れは相当に難儀です。ただ、諸大名一同が御対面すべしという同意見を披露してくださいというのであれば、室町殿に披露いたしましょう)」と答えている。「罰状提出を関東使節に要求する有無」に対する返答もなかったので、その返事を待つ意味もあったと思われる。
翌3月22日、管領義淳より「甲斐、二宮、飯尾美作三人」が満済に遣わされ「就関東使節御対面事、面々方へ内々為私意見お尋申」した結果を伝えた。
●諸大名の関東使節との御対面についての意見(『満済准后日記』永享三年三月廿二日条)
| 諸大名 | 意見 | 賛成 / 反対 |
略訳 |
| 畠山 (畠山左衛門督満家入道) |
今度御使以外遅引事等、管領内々被申使節、御所様ハ早々御対面可然 | 賛成 | 御所様は早々に御対面がよい。 |
| 武衛 (斯波左兵衛佐義淳) |
今度御使節ハ何篇ニテ候哉、御代ノ御礼ニハ以外遅々候 (『満済准后日記』永享三年三月廿日条) |
― | |
| 山名 (山名右衛門督時熈入道) |
今度使節参洛ハ先何篇何事候哉由、管領被相尋、随使節返答様、追被仰出趣ヲモ可被仰歟 | ― | |
| 右京大夫 (細川右京大夫持之) |
加思案、追可申入 | ― | |
| 赤松左京大夫入道 (赤松左京大夫満祐入道) |
可為畠山意見 | 賛成 | 畠山満家と同意見 |
| 畠山入道 (畠山修理大夫満慶入道) |
関東不儀ヲハ被閣、万事先早々御対面可目出候、鹿苑院殿御代、小目ニテ見及申候シモ、関東事ヲハ万事ヲ被閣様候シ、只今モ可為同前歟 | 賛成 | 関東の不義はひとまず目をつぶり、早々に御対面することがよい。義満御代は関東の事は万事差し置かれるようご指示があった。今回もそれと同じではないか。 |
というように「面々意見、大略一同候、以此趣御対面候様ニ早々可致披露」と満済に依頼した(『満済准后日記』永享三年三月廿二日条)。しかし、満済は「尤可披露處、一昨日被仰出上意趣未達候様ニ覚候、簡要ハ関東罰状事、可被仰彼使節事不可然者、其子細おシカゝゝト可被申入條、可宜候、只凡儀計ニテハ一向上意ヲ不申達様可被思食間、披露難治候、其上面々意見モ不同候歟、今一度重被加談、今夕明旦間、可被申入(披露したい所ながら、一昨日仰せられた上意の趣旨ではないと考える。大事なことは関東罰状の事であり、使節に罰状提出を仰せられることが、都鄙無為にとってよいことではない理由をきちんと言上することである。曖昧な説明では上意を覆すことはできないので、披露はできない。質問の主旨が変わると面々の意見も変わる可能性があるので、今一度彼等と談合し、今夕か明日の早朝までに返答をお願いしたい)」と返答した。管領義淳は諸大名へ「御対面」の有無に対する諮問のみ行っており、実際の問題点でその前提となる「罰状の提出」の有無については諮問していなかったのである。満済は義淳のピントのずれた諮問に、つい「只凡儀計ニテハ一向上意ヲ不申達様可被思食」と言ってしまっている。
翌3月23日、管領から昨日同様に「甲斐、二宮、飯尾美作三人」が満済を訪れ、関東使節との対面について、今一度諸大名と談じたところ、畠山満家入道から「今度仰出趣、已被仰定佐々河殿候間、誠上意尤候、雖然、此一段事ハ面々以連署事子細具可申佐々河殿候、定可有何異儀哉、所詮於関東御使ハ先以無為儀早々御対面珍重(室町殿の意思は、すでに篠川殿に申されている通りだが、御対面のことは我々の連署状を篠川殿に伝えれば異議は出まい。とにかく条件は付けずに早々に関東使節との御対面を行うのがよい)」(『満済准后日記』永享三年三月廿三日条)との意見だった。管領義淳としても「此儀尤同心仕候」と賛意を示し、「以此旨可有御披露者、重面々意見ヲモ取調重可申入」という。
ただ、満済が管領義淳に求めているのは、「御対面の有無」に対する意見ではなく、関東に「罰状を要求するかどうかの意見」であって、管領や畠山左衛門督入道の「先以無為儀早々御対面」という結論は求めていないのである。満済も罰状提出には批判的な考えではあるが、罰状提出をしないで御対面を願うのであれば、なぜ「先以無為儀」が良策なのか、その理由を欲しているのである。「義教に罰状要求はまったく無益であると納得させるための理由」がなければ説得しがたいと考え、それを談合してもらいたいと述べているのであった。しかし、管領や畠山入道はそれには答えずに、早々に御対面を望む事のみの返答で、管領義淳と畠山満家入道の「先以無為儀早々御対面」の考えを室町殿に披露してくれれば、山名らにも意見も聴取するという要請もしている。
この管領義淳の言葉に、満済は「此間儀ハ更々無一途候間、此儀ハ先被仰出趣聊分別申様先可披露申、乍去面々意見一同儀候哉、重可承候、次ニハ関東罰状事、不被申付東使、難儀何事候哉由、定可有御尋候、此條何様可申入候哉、此間承分都鄙無為御使ニ参洛處、関東罰状等事、無左右可申出條難儀、且京都御為旁不可然由事雖尤候、上意趣ハ此條モ御覚悟事候、已ニ東使御対面有度事ハ天下無為ヲ被思食間、御心中無是非事由、以八幡大菩薩被仰出間、於此廉者何度雖被申不可入御耳由覚候、此外ニ何ト申タル儀候テ不可然廉候哉、左様一カトヲモ重可被申入候、次ニハ縦雖以前旨趣候、諸大名一同ニ被申入儀候者先可令披露、両篇重被申談具可承(この間の件はまったく結論が出ず、この事はまず罰状提出という課題にやや問題があるということをご報告するようにとのことだったが、諸大名みな同意見なのかもう一度確認したい。また、関東に罰状提出を求めるのが難しい件について、なぜ難しいのか必ず質問があろう。これにどう返答すればいいのか。この間承った 『彼等は都鄙無為の御使として参洛した。それに罰状を要求することなどできようか。また、京都のためにもまったく無益な事である』 という考えは、まったく正しい。しかし、室町殿のお考えはそれらも理解した上でのことだ。天下無為のために御対面を行いたく思召されており、御心中は御対面はしかたがないと八幡大菩薩に誓っている。従って、この件については何度申されても御耳に入れるわけにはいかないと思っている。このほかに何と言って罰状要求はよろしくないと報告すればいいのか。これらを管領に再度申入れよ。さらに諸大名が同意見であればまず意見を披露するが、これらについてもう一度談合して詳細な報告を承る)」ことを管領使者に伝えている(『満済准后日記』永享三年三月廿三日条)。
その晩、ふたたび三人の管領使者が満済を訪れ、談合の結果を伝えた。人々の意見は以下の通りだが、やはりその返答には満済がもっとも欲する「罰状要求の有無」に関する返答が含まれていなかった。
●管領諮問(東使との御対面)に対する諸大名の意見提示(『満済准后日記』永享三年三月廿三日条)
| 諸大名 | 意見 | 賛成 / 反対 |
略訳 |
| 畠山 (畠山左衛門督満家入道) |
今度仰出趣、已被仰定佐々河殿候間、誠上意尤候、雖然、此一段事ハ面々以連署事子細具可申佐々河殿候、定可有何異儀哉、所詮於関東御使ハ先以無為儀早々御対面珍重 | 賛成 | 室町殿の趣旨は、すでに篠川殿に申されている通りだが、御対面のことは我々の連署状を篠川殿に伝えれば異議は出まい。とにかく条件は付けずに早々に関東使節との御対面を行うのがよい。 |
| 武衛 (斯波左兵衛佐義淳) |
此儀尤同心仕候 | 賛成 | 畠山満家と同意見 |
| 山名 (山名右衛門督時熈入道) |
佐々河とのへ面々被申入事、尤可然、可同心申 | 賛成 | 篠川殿に面々が申入れることが妥当だろう。畠山左衛門督、管領の意見に同心する。 |
| 右京大夫 (細川右京大夫持之) |
佐々河殿へ被仰出事、毎度取ツキ申入候、又自佐々河被申入事モ同前候間、此間儀、委細乍存知、此御意見ニ可同心申條、旁難儀至極候、東使早々ニ御対面事ハ旁珍重存候 | 賛成 | 篠川殿へ仰せられた件は、毎回取次をしているので、送状・篠川状の内容も詳細を知っているが、篠川殿に連署状を送る件については同心致しかねる。ただし、関東使節との御対面は賛同する。 |
| 畠山大夫 (畠山修理大夫満慶入道) |
与左衛門督同前候 | 賛成 | 畠山満家と同意見 |
| 赤松左京大夫入道 (赤松左京大夫満祐入道) |
同前 | 賛成 | 畠山満家と同意見 |
満済はこれらの返答を受けると「此條ハ落居意得了」と述べ、「関東使節との御対面の有無」については結論したと宣言する。さすがに三度同じ件での回答はうんざりしたのかもしれない。そして改めて満済が主要項目として義淳に問い続けた「関東罰状事、可被仰東使事ハ何様ニ面々被申哉、此一ヶ條簡要題目候、如何(関東から罰状を要求することを東使に伝える件につき、面々はどう申されるか。この一条が最も大事であろう)」ことを管領使者三名に質問した。これに対し「甲斐、二宮等申」ことには、「於此儀者、面々御方へ未被尋申候(この件については、管領から面々へまだ尋ねておりません)」と、諸大名には関東罰状の件はいまだ諮問していないと白状したのである。彼らはその理由として「其故ハ面々御意見、若一同ニ被仰付東使候ヘトノ儀ニテ候トモ、管領儀ハ難被申付心中候、仍先以此分可有御披露候哉(方々が関東使節への罰状提出の要求に賛同したとしても、管領はそれを関東使節に命じ難いとの考えであり、そのためまずは御対面の有無について室町殿に披露してほしいという気持ちではないか)」(『満済准后日記』永享三年三月廿三日条)との義淳の心を推察したとする意見を述べた。
これを聞いた満済は、何をいまさらと思ったのだろう。「今度被仰出題目ハ詮要此一ヶ条候、然ヲ不及是非申状者、定可違上意候歟、且又愚身不申達様可被思食候、其時ハ定以別人面々方ヘ御尋時ニ此條ハ未承間、不及申是非由被申入候者、一向又管領無沙汰ニ可成候哉、旁不可然様候、所詮此條早々ニ被申談面々、一同意見趣可承(室町殿の諮問は 『罰状を東使に要求するか』 の一条である。それにも拘わらずこれを諮っていなかったというのは上意に背く行為ではないか。また、室町殿が満済からこの件に関して上申がないと思われれば、別人をもって諸大名にお尋ねになるだろう。そのとき「罰状提出要求」に関する件は諸大名は初耳であり、彼等が了承と結論付けて申入れがあったとき、管領はその沙汰を行わないのか。それは大変よろしくない。そうであれば、この件に関して早々に諸大名と談合し、彼らの意見を集約すべきだろう)」と告げると、管領使者も満済の怒りに慄いたのだろう。「明旦面々ニモ申談、重可申入(明日早朝に諸大名に相談し、再度申し入れます)」と述べて退出した(『満済准后日記』永享三年三月廿三日条)。その後、「細川右京兆」が満済を訪問しているが、その内容は不明。おそらく、管領からの「関東罰状事」の諮問を受けて、事の重大性を感じて満済に相談に来た可能性が高いだろう。
翌3月24日には「山名禅門」が満済を訪れて「意見申入旨具申」ている。彼も事の重大性を感じての訪問とみられる。山名時熈入道は「所詮今度被仰出関東罰状事ハ、先可被仰付東使條尤宜存、随彼申状重又意見ヲモ可申入歟、次佐々河へ面々以連署可申入事ハ一向可任時宜(今度の関東罰状の提出という仰せは、まず関東使節にお命じになることでよいと存ずる。それを受けた二階堂の意見もまた申し入れるべきか。篠川への諸大名連署による御対面の通達は室町殿の御意のままに)」(『満済准后日記』永享三年三月廿四日条)との返答であった。山名入道はもともと篠川殿を拒絶しておらず、罰状提出要求には賛成の意見を示し、管領斯波義淳の懸念が現実となってしまった。
その後、「自管領使者三人、甲斐、二宮、飯尾美作」が満済を訪れて、「就関東御罰状事、可被仰出二階堂信濃守歟事、面々左衛門督以下御意見一同ニ先可被仰出東使由、被申入候(関東からの三ヶ条に関する熊野誓紙提出の件を二階堂信濃守(か、関東か?)に指示すべしとの件は、畠山左衛門督以下の御意見として、一同 『東使へ罰状提出を指示するように』 との申し入れがあった)」という談合結果を伝えている。しかし「雖然、管領所存、此事猶難仰付東使候、其子細先度連々申候了、可然様御披露珍重(ただ、管領の考え方としては、東使に罰状提出を命じ難く、その理由は先に述べた通りである。そのように室町殿へご報告いただきたい)」(『満済准后日記』永享三年三月廿四日条)との管領義淳からの言葉を伝えている(満済が遺した文章では、罰状提出を命じ難い、という理由のみだが、「連々申」たとあるように別の理由も述べられていた可能性があろう)。
満済は「左衛門督以下大名五人意見如上意、先可被仰付東使條、無子細云々、随而又御所存尚難申尽云々、此條此間数度上意意趣申含了、大名五人ハ已被同心申了、御一身猶被申事、一途於被申入者無子細事候、以前同篇儀ハ遮而被仰出旨趣之間、愚身不申達様可被思食間、披露以外難治、且ハ上意凌爾様ニ可成候哉、所詮今一往此子細可被申歟(畠山左衛門督以下大名五人の意見は室町殿と同意見で、まず二階堂に罰状提出を命じることに問題はないというものであり、管領の御所存はなかなか理解しがたい。この件については先日来、数度確認している。大名五人はすでに同意しているが管領御一身のみがまだ賛同しない。ただ罰状提出を二階堂に命じればよいのだ。以前も室町殿は満済に罰状要求について仰せになっており、満済が指示をしていないとお思いになったら報告など不可能となろう。そればかりではなく上意を蔑ろにしたことにもなる。このことについて管領に申されるべし)」(『満済准后日記』永享三年三月廿四日条)と管領使者に告げ、彼等も「仍尤由申」して退出した。
●管領諮問(罰状提出の要求)に対する諸大名の意見提示(『満済准后日記』永享三年三月廿四日条)
| 諸大名 | 意見 | 賛成 / 反対 |
略訳 |
| 畠山 (畠山左衛門督満家入道) |
先可被仰出東使 | 賛成 | まず罰状提出を命じるのが妥当。 |
| 武衛 (斯波左兵衛佐義淳) |
管領儀ハ難被申付心中候 管領所存、此事猶難仰付東使候 |
大反対 | 罰状を命じ難く思っている。 東使に罰状要求は行い難い。 |
| 山名 (山名右衛門督時熈入道) |
所詮今度被仰出関東罰状事ハ、先可被仰付東使條尤宜存、随彼申状重又意見ヲモ可申入歟、次佐々河へ面々以連署可申入事ハ一向可任時宜 | 賛成 | 今度の関東罰状の提出という仰せは、まず関東使節にお命じになる件でよいと存ずる。それを受けた二階堂の意見もまた申し入れるべきか。篠川への諸大名連署による御対面の通達は室町殿の御意のままに。 |
| 右京大夫 (細川右京大夫持之) |
先可被仰出東使 | 賛成 | まず 罰状提出を命じるのが妥当。 |
| 畠山大夫 (畠山修理大夫満慶入道) |
先可被仰出東使 | 賛成 | まず 罰状提出を命じるのが妥当。 |
| 赤松左京大夫入道 (赤松左京大夫満祐入道) |
先可被仰出東使 | 賛成 | まず 罰状提出を命じるのが妥当。 |
3月26日、管領義淳はなおも東使二階堂への罰状要求を渋っており、飯尾美作守を満済のもとに遣わすと、「今日ハ大赤口也、被仰出東使題目御返事可申入條、有憚、如何由」と尋ねた(『満済准后日記』永享三年三月廿六日条)。上申の引き延ばしを狙ったものであろう。満済もこれを察するが「大赤口御用否依事歟、所詮公事重事披露無相違條、不覚悟、内々可被伺時宜歟(大赤口が御用を取りやめる根拠となるか、公事や重要事項の披露に問題ないかどうかはわからない。内々に室町殿の意向を伺うように)」と答えている。その後、満済は管領亭に使者を遣わして、結果を尋ねたところ「今日ハ可斟酌仕、且其由以大河内達上聞云々、仍明日ハ御徳日也、明後日廿八日、可申御返事(今日は大赤口なので遠慮すると大河内を以って室町殿にお伝えした。明日は御徳日なので、明後日に罰条要求に対する御返事をする)」との返答であった。しかし、満済は光意法印を御所に遣して、内々に御所詰めの大河内に「就関東使節事、管領申入題目以口状披露、旁難治至極也、所詮召給飯尾肥前守、自管領注サせ、以彼明後日可披露由存可為如何哉(関東使節への罰状要求に関し、管領の意見を報告する。なかなか難しい。この上は飯尾肥前守を召して管領から意見を注進させ、明後日に管領から報告させるのはいかがか)」ことを室町殿に伝えるよう指示。大河内が室町殿から意向を受けたところでは「仰趣則令披露處、此儀可然由被仰出候、只今飯尾肥前祗候間、明後日可参入由申付(そのとおりでよい。いま飯尾肥前が御所に祗候していたので、管領に明後日に御所へ参入するよう申し付けた)」とのことであった(『満済准后日記』永享三年三月廿六日条)。満済は管領義淳のこれ以上の報告引き延ばしを阻止し、報告期限を28日と決定させたのであった。
3月28日、「公方奉行飯尾肥前守」が早朝から醍醐寺に参じ「自管領使者ヲ於此門跡待申」と言うので、満済は「則召寄管領申詞一紙、畠山、山名以下申詞一紙、已上二紙注之、以件申詞則令披露了(管領から召し寄せていた申状と、畠山らの申状をまとめて計二通の注進状を作成し、この二紙を以って室町殿に報告を依頼)」した。彼が帰ったのちと思われるが、管領から「甲斐、二宮、飯尾美作」が満済を訪問し、義淳は「関東罰状事、可被仰付東使歟由、大名意見一同雖無子細、此條猶不可然存間、心中趣一端御披露可畏入(関東罰状の件について、諸大名は東使に罰状提出を命じることは問題ないと意見だが、私としては行うべきではないと考えるため、その考えをいったん室町殿に報告する)」(『満済准后日記』永享三年三月廿八日条)との言葉を伝えている。
その後、義教は「重仰趣、管領雖為申入事、被仰談佐々河已事必定間、今更難被改間、難儀被思食云々、只仰旨忿々可仰含東使(管領は罰条要求に反対する申入をしてきたが、篠川には罰条要求はすでに決定したことと言ってしまったので、いまさら変更し難く苦慮している。ただ急ぎ東使にその旨を申し含めるよう)」と、「召寄甲斐以下三人仰付了」した。さらに義教は「重自管領以甲斐申様(管領から甲斐を通じて東使に罰状要求を命じるように)」ことも付け加え、甲斐らは「仰旨畏承了」した。彼らは「尙々加思案両三日間、可申入御返事」と返答はしたが、満済は「罰状事、仰付東使事猶難儀云々、如何」(『満済准后日記』永享三年三月廿八日条)と思いを述べている。これまでの経緯を見て、管領が罰状要求を行うとは思えなかったためである。
なぜ管領がここまで頑なに罰状要求に反対しているのかは不明だが、3月20日に東使使者と対面して説明を受けたのちは、罰状要求など「天下無為」のためにまったく無益という強い信念が芽生えたためである可能性が高い。その後の管領義淳は苦慮を重ね、罰状は罰状でも、関東下部組織に過ぎない篠川殿の「意見」をもとにした屈辱的な罰状ではなく、あくまでも関東が野心を抱かないという罰状が落し所であろうと考え、独断でこれをベースにした罰状提出を求めるよう動き始めていたのである(結局、その後四か月もの間、管領は義教の要求する篠川殿意をもとにした罰状を認めず、義教は管領発案の罰状で決着させることになる)。
永享3(1431)年4月2日、管領義淳は飯尾美作守を通じて満済に「関東御罰状事、可仰付二階堂條、雖加思案猶旁難治至極候、雖同篇候以此趣可有御披露條、可畏入(罰状要求に関し、二階堂に命じる件につき、三日間思案したもののやはり行い難く、同じ答えになるが報告をお願いしたい)」(『満済准后日記』永享三年四月二日条)という。これに満済は「同篇儀、於披露者尤難儀候、乍去、同篇御返事披露難儀由令返答由ヲハ、何様可申入(同じ内容での報告はできない。ただし、考えが変わらないので御返事を報告することは難しいとの報告は申し入れる)」(『満済准后日記』永享三年四月二日条)と返答している。
翌4月3日、満済は経祐法眼を「遣使者ヲ管領」て昨日の「同篇御返事披露難儀由令返答」について記した「管領返事」を受けるため、「今夕出京候、御返事今夕可承哉」ことを問い合わせると、管領義淳は「明日可申入」との返事なので、満済は夕刻に醍醐寺を出立し晩頭に京都に到着した(『満済准后日記』永享三年四月三日条)。
翌4月4日早朝に「管領返事相待處、遅引」のため「遣人令催促」すると、「ヤカテ可申入(まもなく申し入れる)」との返事が来るが、「申半、自管領大蔵卿寺主ヲ召申様、御返事猶思案シヲフせス候間、不申入、恐歎入候、今両三日間可申入」との返答が到来する(『満済准后日記』永享三年四月四日条)。そのため、満済は室町殿月次壇所に出仕し、「就仰付関東使節題目、大名六人意見趣、自管領被申次第、召飯尾肥前守、面々申詞一紙注之、則以参上申入候了(関東使節への罰状要求についての大名六人の意見を管領より申される内容につき、飯尾肥前守を召して大名らの意見を一紙に注し、室町殿へ報告)」した。「面々意見、第三度儀、如被仰出可被申付関東使節云々、雖然管領所存又注一紙、其子細ハ関東御罰状事、可被仰付東使條、尚以不可然、何様先御対面有テ追此題目可被仰付(面々の意見は三度聴取し、室町殿の仰せの通り関東使節に罰状要求を行うのが妥当との結論でした。ただ、管領の所存は一紙に注しているように、『関東罰状の提出を東使に命じることはよろしくない。まずは御対面あってのち罰状を仰せ付けるべきである』)」との意見であった。義教は「両様被御覧後仰様、只関東罰状事、早々可被仰付云々、此罰状不到来者、是非不可有御対面(諸大名と管領の意見書を読んだ後に、『ただ関東罰状の件は、早急に仰せ付けられるように。この罰状が届かなければ御対面は行われない』)」ことを「重被仰出」ており、満済は「此仰旨、召寄甲斐二宮飯尾美作、仰遣管領了」ている(『満済准后日記』永享三年四月四日条)。これを受けた管領義淳は甲斐を遣わし「先申入旨御披露畏入候、何様仰趣申付、重可申入」と返書を送った。
翌4月5日早朝、管領義淳は飯尾美作守を醍醐寺に遣わし、罰状提出は行うがその代案として「関東無御野心趣等、使節先以罰状可申入由可申付、以此趣御対面無為様申御沙汰、可為何様哉(関東使節に(義教が要求する三ヶ条ではない別の内容である)『関東には御野心はない』という罰状を提出させ、これを以て御対面を行うという手はどうでしょうか)」と聞く。しかし満済は「此條、以外不可然由存也、於披露者不可叶(この方法はまったく話にならないと存ずる。報告もできない)」と突き放している(『満済准后日記』永享三年四月五日条)。
4月7日、管領義淳は再度飯尾肥前守を醍醐寺に遣わし「一昨日東使告文事申入候云々、若何様儀ニテモ御披露事ヤトテ申入了、所詮被仰出関東御罰状事、申付使節處、可申下條雖歎存候、已不可有御対面由被仰出候上者、何様可申下候、同者先懸御目以後不廻時日申下度由歟申入條如何、但大名宿老等、猶被加談合、一途候様可被申入候哉(一昨日に提案した東使の罰状の件は、もしこのような案でも御披露いただけるかと申し入れたものです。関東御罰状の提出を関東使節に申しつけたところ、歎息していましたが、すでに御対面を行わない意向であればそのようにお命じなさるとよい。まず御対面あってのち罰状を要求されたいと申し入れるのはどうでしょう。ただし、大名宿老らになお談合を行って一つの案として申し入れるべきでしょうか)」と提案し、飯尾肥前は京都へ戻っていった(『満済准后日記』永享三年四月七日条)。
4月10日早朝、満済は室町殿月次御連歌のために醍醐寺から京都法身院に入った。そこに「自管領使者飯尾美作来」て「被仰出旨可仰付東使候、但畠山、山名等就御対面事、令列参可申入趣談合仕事候、可有御披露ニテ候者、被仰出旨早々可仰付使節候、定又自畠山、山名両所委細被申入歟(罰状の件を二階堂に指示いたしますが、畠山、山名とも御対面に列参を申し入れる件で談合しており、この旨をご報告していただければ、罰状の件は早々に使節に命じます。おそらくは畠山、山名両名からも委細を申し入れるでしょう)」と述べた。これに満済は「自畠山、山名両人方被申候者、隨其愚意追可申(畠山、山名両人から申入があれば、その意見に基づいて自分の意見も後程述べよう)」と答えている(『満済准后日記』永享三年四月十日条)。
その後、管領義淳からの連絡通り、畠山満家入道の使者「遊佐河内、齋藤因幡両人」と、山名時熈入道の使者「カキ屋一人」が法身院に参上した。彼らが申すには「自管領被申談様ハ、関東御罰状事、可仰付使節條、旁不可然間、于今無其儀候、乍去、上意厳密間、此上ハ可仰付東使候、但面々一同ニ参御所御対面、東使事平ニト可申入、被同心者仰趣ヲモ早々可仰付東使(管領の申された事は、「関東罰状を東使に命じる件については、まったくよろしくないため、今も行っていない。しかし、室町殿の上意は絶対であり、この上は、東使に罰状提出を命じるほかない。ただし、諸大名一同は御所で室町殿と対面し、『東使との御対面を平にお願いする』と申し入れよ。室町殿が同心されれば東使への罰状要請を速やかに行うつもりだ」)」との管領義淳の言葉を伝えた。
それに対して畠山・山名は「此條只今聊早ク存様候、先被仰出旨被仰付東使、其後儀ト存候、但落居面々、二三度モ以参上可歎申入由存候、且御意様承度(管領の仰ることは時期尚早でしょう。まずは罰状提出を東使に命じ、その後に対面と考えます。ただ、決まった人々が二度三度も御所に参じて歎願すべきと考えますが、御意を承りたい)」という。
これに満済は「只今自管領使節申状、大都同前、所詮於此御返事ハ為門跡難申候、且迷惑候、管領被申様前後候様ニ覚候(たった今、管領使者が申していたこともだいたい同じであった。ただ、この御返事を述べることはこの門跡からは申し難く、また自分の役割でもない。管領の申され様は行う順番が逆であると感じている)」と述べたところ、畠山使者遊佐(遊佐河内守)も「入道申入趣モ如仰候、先被仰出旨被仰付東使、以後事ニテコソ候ヘ(主君の畠山満家入道の意見も同じでございます。まずは罰状提出を東使に命じられ、そのあとに御対面という順序であるべきだ)」という。山名使者の垣屋某も「申状又同前」という。
満済は「愚存、面々御意得様同前上ハ、只今不及巨細候、管領ヘ自両所畠山、山名、可被申様、此題目為門跡ハ難申是非、且ハ迷惑候、其故ハ、面々被申入題目ハ可執申入、上意趣ヲハ東使ニ被申付候ヘ、トハ更々難申事候旨可被仰歟(私の考えと畠山、山名両氏の御意が同じであれば、もはや細かいことはいいでしょう。このことは畠山、山名両氏から管領にお伝えなさい。この件についてこの門跡から是非を申し難い上に私の役割ではない。なぜならば、面々の案を採用するように管領に申し入れているのに、一方では室町殿の上意を東使に命じられよ、とは申し難いためだ、ということを管領へ伝えられよ)」と答え、遊佐河内守や垣屋も「尤由申」て帰った(『満済准后日記』永享三年四月十日条)。
その後、満済は月次御連歌に参加すべく室町殿へ上ったが、義教が「先一身可参御前之」と伝えてきたため、御前に参じている。義教は「御窮屈未散間、今日御連歌ニハ不可有御出座」といい、気鬱であった様子がうかがえる。当時、義姉(義母)「大方殿」が病で臥せっていたことや、関東使節との御対面問題、九州の大乱など問題が山積していて、義教は寝ても覚めても休まる余地がまったくなかったのだろう。このような体調でも義教は関東使節の問題を気にしていて、満済に「関東罰状事、管領未申付東使哉、遲引以外無正体(関東罰状の件を管領はいまだに東使に命じていないのか。遅引があまりに異常だ)」と管領の対応に強い不満を述べている。これに満済は「此事今日吉日間、可仰付東使旨、今朝以使者管領申入(その件については、今日は吉日であり、東使に命じる旨を、今朝管領からの使者が申し入れて参りました)」ことを伝えると、義教は「宇都宮藤鶴事、重厳密被仰出(宇都宮藤鶴への旧領返付についても、再度厳密に対処するよう仰せられた)」ている。その後、満済は月次連歌に出席し、摂政、聖護院門跡、実相院門跡、山名、赤松等が参じているが、やはり義教は不参であった(『満済准后日記』永享三年四月十日条)。
4月11日、管領使として「二宮越中、飯尾美作」が法身院に満済を訪ね、「飯尾肥前守召之、自管領申詞、飯尾肥前注一紙、以之可令披露儀也」を伝えた(『満済准后日記』永享三年四月十一日条)。管領の意見は「其申詞ハ、関東御罰状事被仰出候趣、仰付二階堂信乃守處、今度ハ為都鄙無為御使参洛仕計候、雖然、被仰下事候間、早々可申入関東(義教は飯尾肥前守を召すと、(おそらく別に控えていた)管領の申し分を一紙に注させた。管領の意見は『関東御罰状の要求の上意の内容を二階堂信濃守に命じたところ、今回は京都と関東の和平の御使と参洛しただけです。ただし、罰状提出を命じられた上は、早急に申し入れます。』)」というもので、義教は「以前被仰出、那須、佐竹、白川、宇都宮藤鶴等事、雖為一事罰状ニ漏ルヽ事在之、使節御対面是非不可叶旨、重堅ク可仰管領」(以前命じた通り、那須、佐竹、白河、宇都宮藤鶴の事につき、三ヶ条のうち一事でも罰状から漏れることがあれば、関東使節との御対面は叶わないということを、再度堅く管領に伝えよ)と述べたという(『満済准后日記』永享三年四月十一日条)。飯尾が御前から退出しても、義教は心配になったのか、さらに近習の赤松播磨守満政を使者として管領のもとに遣わすと「尙々一事モ罰状ニモルヽ事在ハ、重又可被仰下條不可然歟之間、只今厳密ニ可申付由可仰管領(くれぐれも、三ヶ条のうち一事でも罰状から漏れるようなことがあれば、再度同じことを命じることはよろしくないので、すぐに厳密に東使に命じよということを、管領に伝えよ)」と述べている。さらに与阿弥を使者として「其後又以御書同篇儀、被仰出了」と、内容を文書にして遣わすほどの念の入れようで、管領も「御返事申入了」という。その上、ダメ押しのようにまた飯尾肥前守を召すと、わざわざ「仰條々載一紙、召寄管領使者二宮越中、飯尾美作、申付了」という。管領使者は満済にその條々の文書を見せており、満済は内容を記録している(義教が篠川殿からの要望を聞いて決定した罰状に載せるべきとした三ヶ条)。その後、管領は満済のもとに飯尾美作守を派遣し「條々畏被仰下、則可申付東使」との申状を遣わした。しかし、すでに夜陰となっており「今夜不及披露、自管領申入御返事、以赤松播磨可披露之由」を経祐法眼を使者として管領に遣わすとともに、赤松播磨守にも明後日まで返書はないことを伝えている。
4月13日早朝、満済は室町殿に出仕し、飯尾肥前守を召し寄せて一昨日の罰状に載せるべき三ヶ条を一紙に注し、内容を「管領使者二宮越中入道、飯尾美作両(人)仰含」た上で、「以上三ヶ條載御罰状、早々可有御申由、可仰付東使二階堂由、以飯尾美作申入」たことを義教に報告した(『満済准后日記』永享三年四月十三日条)。その後、『関西准后日記』にしばらく東使問題は見られず、まったく動きが停滞した様子がうかがえる。こうした中、東使への罰状要求を管領に命じてから一月ほど経った5月12日、醍醐寺の満済に「畠山、山名両人方、各以両使」って「就関東使節、未及御対面、数日空在京、進物御馬以下小宿ニ置之條凌爾至、種々欲申入條尤不便、但此條ハ以前申旧事間非簡要、所詮始終天下之様何様ニ被思食哉、殊可有御遠慮御事第一也、両人大名内々宿老分トシテ候ナカラ、如此存寄題目心中ニ裹置條一向私ニ候也、此子細且申談、又ハ可達上聞、為御作善御寺住之間、如此申状狼藉至、雖無申計、天下重事不可過之事候ヘハ平ニ御出京可畏入為其先内々申上候(東使二階堂が未だ対面できずに空しく在京を続け、進物として関東から持参した馬なども宿所に置き続けている状態は、東使に対しあまりに失礼であり、様々に申し入れんと願っているのにままならないのも甚だ不憫なことです。ただこの件に関しては以前にも申したことで重要案件ではない。とにかく、室町殿は常に天下の情勢を如何思召されているのか。これらは深くご思慮あることが最も大事です。我らは大名は内々に宿老分ですが、まったくの私心でこのように考えています。これらを室町殿に申し上げてもらいたい。室町殿が御作善のために仁和寺に御出の時期に申し上げるのは大変心苦しいが、天下の重事を見過ごすわけにはいかないと考えたので、准后には平に御出京いただき、この旨を内々に室町殿へ申し上げていただきたい)」と告げた(『満済准后日記』永享三年五月十二日条)。東使問題の停滞を見かねた畠山左衛門督入道と山名右衛門督入道が相談し、意を決して強諫を願い出たと考えられる。
これを聞いた満済は、「出京事自面々承事候、天下重事候上ハ不可及思案、雖何時可出京候、就其被申入様大概何様候哉、使節若且存知推量分候者可申入(出京の事は了承しました。天下の重事である以上は考えるまでもない。いつでも出京しますが、使節の方々は各々の主君が大体どのような内容を申し上げようとしているのか、もしおおよそ存じているのあれば教えてほしい)」と返答する(『満済准后日記』永享三年五月十二日条)。
これに「畠山両使遊佐河内守、齋藤因幡守、山名両使カキ屋(垣屋)、田キミ(田公=太田垣)」は、「雖不分明候、天下総別事、九州等モ号土(一)揆、大内已渡海、大友、菊池、少弐等、内々ハ土一揆同心風聞候歟、事六借様候、乍去、為公方両上使長老下向之間、定不日可落居歟、雖然又関東事、御中違治定候者、国々諸人ノ振舞モ、自然寄土一揆、左右無正躰振舞モ出来候テハ、旁可為難儀時節候、無為様御計可為珍重由(主の考えはわかりません。天下は現在総じて乱れています。九州でも土一揆と号して大内は鎮定のためにすでに九州へ渡海し、大友、菊池、少弐らは内々に土一揆と結んでいるという噂もあり、情勢は難しくもあります。しかしながら、公方が長老を上使として派遣しており、近いうちに解決されるでしょう。しかし、関東のことは御仲違が決着しなければ、人々の行動もまた土一揆と同様になり、思うままに暴乱する輩が出てしまえば大変な事態となりましょう。このような事態にならないようお考えいただくことが大切です)」と述べた(『満済准后日記』永享三年五月十二日条)。
これに満済は「此被申様、天下万民安穏基、尤以甘心無極候、所詮度々被仰出趣、自管領被申付東使様未分明、御返事不申入候哉、然者此一途上意簡要事候歟、自両人被尋究管領、彼一左右相並可被申入條、次第儀尤宜存(申される事はまさに天下万民安穏の根本であり、素晴らしいことこの上ありません。結局は室町殿が度々仰せられている、管領から東使に罰状提出を命じる件がどうなっているのか、まだ報告がないことがすべての原因でしょう。そうであればただ上意を貫徹することこそ重要であり、畠山、山名の両人から管領に問い質し、彼の報告もともに室町殿に申し入れることが最適解であろう)」と返答し、使者は帰って行った(『満済准后日記』永享三年五月十二日条)。
5月19日、満済のもとに管領義淳から「甲斐、飯尾美作守」が到来し、「先度被仰出関東御罰状條数、重申付東使二階堂處、可申下條難儀由同篇申入間、計会」との報告があった(『満済准后日記』永享三年五月十九日条)。これを聞いた満済は、使者両人に対し「先度可申下由東使、領掌申入分ハ、向後関東不可有御野心之儀由告文事候哉、其ハ已申下候哉如何」と、疑念を以って尋ねている。これに両使は「申下候哉事、未分明」といい「重可相尋」と確認する旨を満済に伝えた。
5月26日、管領義淳が満済を自ら訪問。「関東使節二階堂信乃守告文状并被仰出関東罰状事、申下候由状持参、可備上覧(関東使節二階堂信濃守の誓紙ならびに室町殿上意に基づく誓紙の件で、二階堂に提出を命じたことを記した書状を持参したので、室町殿の上覧に供すように)」ことを述べ(『満済准后日記』永享三年五月廿六日条)、礼物として「三千疋」が満済に献じられた。その後「二階堂同道僧璘首座来、聊相尋旨在之(鎌倉から二階堂に同道してきた円覚寺璘首座が来訪した。少し質問することがあった)」している。翌5月27日に「自関東二階(堂)方以璘首座、昨日事付畏入(璘首座は昨日の事につき了承した)」(『満済准后日記』永享三年五月廿七日条)という内容の書状が満済に届けられた。この状は12日に「今日懸御目了」したが、義教は「此状可預置門跡」し、満済は「預申宝池院」した(『満済准后日記』永享三年六月十二日条)。
永享3(1431)年6月9日、管領義淳から甲斐が満済に遣わされ「関東管領阿房守状進了、以便宜可被備上覧條、可畏入(関東管領憲実から書状が届けられたので、便宜を以て上覧に備えていただきたい)」と依頼し、管領からも「関東使節、長々在京、未無御対面條、不便由歎申入状(関東使節は長々の在京にいまだ御対面がないのは気の毒であるとの申し入れる嘆願状)」を満済に送っている。
6月25日、法身院に「畠山、山名、畠山修理大夫三人同道」して訪れ、「関東使節御対面事、可申沙汰旨條々」を伝えている(『満済准后日記』永享三年六月廿五日条)。その申す旨は7月10日、満済から義教に「就関東事、畠山、山名以下連々関東使節御対面事、具申入」ている。これに対する義教の「御返事趣、無子細様也」と悪い印象ではなかったが、「但御対面有無、未無治定儀」と、対面についての返答はなかった(『満済准后日記』永享三年七月十日条)。
こうした中、7月13日に義教に届いた情報が「去月六月廿八日、於筑前糸郡、大内左京大夫入道腹切了」(『満済准后日記』永享三年七月十三日条)というものだった。大内左京大夫盛見入道は義教の信頼も厚い人物で、文武に秀でた人物だった。御料所筑前代官や豊後国守護職など北九州東部に勢力を広げ、筑前において大友持直や少弐満貞らと抗争しており、敗戦した結果であった。満済は義教から畠山満家入道への諮問を依頼され、畠山入道は「大内事、無申計候、九州事又重事不可過之哉、所詮加思案重可申入、自余大名ニモ可被仰談條可宜」(『満済准后日記』永享三年七月十三日条)と返答があったため、満済は翌7月14日に「管領、畠山、山名、右京大夫、赤松」の五人に諮問している(『満済准后日記』永享三年七月十四日条)。そして7月16日、各家から両使が室町殿奉行人の飯尾肥前守、飯尾大和守に遣わされてまとめられ、義教に報告されている(『満済准后日記』永享三年七月十六日条)。なお、同14日夜にはの貞成入道親王のもとにもこの一報が届けられ、親王は「不便々々」と嘆いている(『看聞日記』永享三年七月十四日条)。
満済はこの報告が行われたのちに室町殿へ赴いて義教と対面し、義教は「諸大名意見趣、神妙」と満足の体を示している。ここで満済は畳みかけるように「先度畠山、山名申入関東使節御対面事、重如此申入」て、「彼両人注進状一通備上覧」した上、「申入旨等猶以言再三申入」るという、義教に対して御対面の有無を強く迫ったのであった。この頃義教の周辺では義姉(義母)「大方殿」の病状悪化、三歳の娘(母は御台所宗子)の病気などの心配事があったが、そこに大内盛見入道の自刃という事件が重なり、義教は精神的に相当参っている状況にあったとみられる。満済はこれを御対面の確約をとる好機と見ていたのかもしれない。義教は畠山・山名の申入状を読むと「此上者無力次第也、一向御身上儀おハ被打捨、且被任面々可有御対面(もはや御対面もやむを得ない。私の思いはすべて捨て、諸大名の考え通り御対面を行おう)」との諦観の返答であった(『満済准后日記』永享三年七月十六日条)。これに満済は「珍重ゝゝ」と喜び、御所内の壇所から「畠山、山名両人方へ可進人」と聞くと、畠山満家被官の遊佐河内守、山名時熈被官の山口が出仕しており、子細を申し遣わすと「両人共以畏申、則可参」って遊佐河内守と山口はそれぞれ主を呼びに戻った(『満済准后日記』永享三年七月十六日条)。
彼らが退出後、義教は壇所を訪れ、月次当番である宝池院僧正(義賢。義教従弟)と対談し、「大方殿御不例様等御物語」して還御している。義教の関心事はすでに関東使節との対面問題ではなく、義母の容態だった様子がうかがえる(心配というよりも「御大事」のときの蝕穢を気にしている様子がうかがえる)。その後、畠山満家入道が壇所を訪れ「種々畏申」したのち義教御前に参り、次に義教御前に参上していた山名時熈入道が壇所を訪問している(『満済准后日記』永享三年七月十六日条)。
+―――――――――足利義持
| (勝定院殿)
| ∥――――――足利義量
| ∥ (長徳院殿)
| 日野資康――+―藤原栄子
|(権大納言) |(大方殿:慈受院)
| |
| +―日野重光―+――――――藤原重子
| (大納言) | (観智院)
| | ∥
藤原慶子 | +―藤原宗子 ∥――――+―足利義勝
(北方殿) | (勝智院) ∥ |(慶雲院殿)
∥ | ∥ ∥ |
∥―――――+――――――――――――――――足 利 義 教 +―足利義政
∥ (普広院殿) (慈照院殿)
足利義詮―+―足利義満
(宝筐院殿)|(鹿苑院殿)
| ∥
| ∥―――――――義承准后
| ∥ (梶井門跡)
| 藤原誠子
| ∥
| ∥―――――――持円大僧正
| ∥ (地蔵院)
| ∥
+―足利満詮――+―義運大僧正
(権大納言) |(実相院門跡)
|
+―義賢大僧正
(宝池院)
その後、義教が久阿弥を使者として満済に「関東使節二階堂信乃守状」を「両通状可進」ている(『満済准后日記』永享三年七月十六日条)。
| (一) | 関東告文事、可申下由申入條 | 関東からの罰状提出を受諾するという報告書 |
| (二) | 関東無野心儀由、以告文申状 | 関東に京都と敵対する意志はありませんという罰状 |
この二階堂状(一)に見える「関東告文」は、義教からの「三ヶ条を約する罰状」か、(二)に見える管領と申し合わせていた「『関東無野心儀』を約する罰状」かは確実には判断がつかない。ただ、後日に篠川へ送達した義教御教書は諸大名の要請によりやむなく対面した旨が見えることから、「三ヶ条を約する罰状」は取れないままに御対面になったことを伝えていると考えられ、(一)の「関東告文」は(二)の告文を意味すると考えられる。
満済は深夜亥刻に室町殿檀所を退出したが、その帰途に等持寺東小路で管領義淳と偶然会い、管領を連れだって法身院へ帰った。管領は畠山、山名らとともに「東使御対面事、申御沙汰畏入」として「今夜珍重由申進、御太刀也」した帰りであった。彼らはまだ献上品があったようだが「自余ハ東使御対面後可進」という(『満済准后日記』永享三年七月十六日条)。
7月17日早朝、「畠山、山名両人」が法身院を訪れ、「東使御対面御治定、尚々珍重、仍参礼云々、各二千疋随身」した(『満済准后日記』永享三年七月十七日条)。
そして7月19日、室町殿義教と「関東使節二階堂信濃守盛秀」の「御対面」となり(『満済准后日記』永享三年七月十九日条)、都鄙和睦が成立する。二階堂盛秀は管領義淳に付き添われて御前へ参じて御対面に及び、「自関東馬二疋一疋置鞍、金太刀、鎧一両進之」(『満済准后日記』永享三年七月十九日条)している。具体的には、「太刀一腰金、鎧白糸、馬二疋河原毛、鴇毛置鞍」(永享三年八月廿二日「足利義教御教書案写」『貞助記』室:2678)であった。
対面後、二階堂盛秀は法身院を訪問したが、満済は醍醐寺へ戻っていたため、留守居の大蔵卿法眼が対謁し、二階堂より「馬一疋栗毛、二千疋」が献じられた。また、満済のもとには「自畠山、山名両人方、各以書状、関東使節御対面珍重由」が伝えられている。
翌7月20日早朝、「関東使節二階堂、醍醐へ来単物体」たため満済が対面。「関東時宜等委細」を聞き取っている(『満済准后日記』永享三年七月廿日条)。午後に出京した満済は、義教に「昨日東使来旨等申入」れた。この対面時に「関東時宜」を伝えていると思われる。その後、義教は「諸大名、佐々河へ書状早々可進之状案文可被御覧」といい、将軍義教から諸大名に篠川満直へ関東使節との御対面の報告案文の提出を求めた。案文提出を命じられたのは、「大名可為八人由被仰出間、其趣各申遣了、管領、畠山、細川、山名、赤松、畠山修理大夫、一色左京大夫、細河讃岐守也」の八名であった。案文は7月22日に「被御覧」されており、義教は「少々相違事被仰出」たので満済が「文言書加」え、八人の大名に渡している(『満済准后日記』永享三年七月廿四日条)。そして7月24日夕刻、将軍義教は満済に「大名八人」に対し「進佐々河状、今日早々可調進之由」を指示し、満済は「面々方へ申遣」たのち、義教から「佐々河状御書案文、可書進」と指示があり、義教御教書案を献じた(『満済准后日記』永享三年七月廿日条)。
●永享3(1430)年7月『足利義教御教書案』(『満済准后日記』永享三年七月廿四日条)
篠川満直の意見は、一度目の諮問では御対面への有無を問われたので、御対面は「不可然」だが、諸大名が言うのであれば御対面を行うのがよい。ただし次は固く断るべきだと述べた。しかし、義教が「対面すべきかしないべきか、はっきりした答えを出せ」と二度目の諮問を行ったので、満直は「御対面は諸大名の意見があるなら行えばよい。ただし、条件を付けるべきで、それは京都からの「三ヶ条」の要求を守る旨の罰状提出を前提としてはどうか」という「提案」を行った。つまり、篠川満直は対面の条件を「強請」しておらず、冷静に満直の考えを表明しているに過ぎない。二度目の諮問でも義教の諮問があったために「三ヶ条」を提案したのである。この案を良いものとして「採用」したのはあくまでも義教自身であった。ただ、満直としては、この二度目の諮問は思いがけぬ幸事と思ったのではなかろうか。鎌倉の動きを封じる罰状提出を提案できる機会となったためである。この具体的な三ヶ条は採用されるであろう前提で提案したと考えられ、その目的の主眼は、持氏が自らの支援基盤である白河、那須、佐竹ら「京都御扶持之輩」の攻撃を停止させることにあった(当然、これまでの経緯から、持氏が罰状を出しても守らないことは百も承知であったろう。守られずとも鎌倉は公敵となり、故義持代と同様に、自らを鎌倉殿とする御教書発給の可能性を狙い得る策謀であったと思われる)。
しかし、東使に対する罰状案については、諸大名の意見はまとまったものの管領義淳の強い抵抗に遭い、義教はこの「三ヶ条」に関する罰状要求を取り下げざるを得なかった。しかし、幼少から僧侶として育った義教は生真面目であり、一度約束したことを反故にすることに強い抵抗感を持っていたのだろう。篠川満直への事実上の謝罪文となるこの義教書状では、「関東使節対面事、大名共頻申旨候間、無力去十九日、令対謁候(関東使節との対面は、大名たちが頻りに行えと言うので、やむなく去十九日に対面した)」(『満済准后日記』永享三年七月廿四日条)と、対面の理由は「大名の意見」であり、自らの意思ではない点を強調している。ただ、この対面の理由である「大名の意見」は、満直が対面の条件として認めていた「諸大名可有御対面由意見申入上ハ、縦御対面アリトモ」(『満済准后日記』永享二年九月四日条)という部分でもあり、義教と東使の対面自体を満直は反論できない立場にあった。御対面に至った経緯は義教御教書には記されていないが、「仍義淳、道端入道以下以書状申入事候」とあるように、管領義淳と畠山満家入道ら八名の大名から別途の書状が付けられる旨が記されており、こちらに詳細が記されたのだろう(ただし、管領を除く七名は「罰状提出後の御対面」に賛成であり、篠川状にどのように記されたのかは不明)。翌7月25日、昨日八人の大名に指示した上記「佐々河状案」八通が満済のもとに揃い、室町殿へ送られている(『満済准后日記』永享三年七月廿五日条)。その後、奥州申次の細川右京大夫から篠川へ送達されたと思われるが、その記事はない。ただ後日に「七月下遣状」(『満済准后日記』永享三年十月七日条)と見えることから、満済から室町殿へ八通の大名状を送達された直後に奥州篠川へ遣わされたのだろう。
永享3(1431)年8月7日、「関東使節二階堂信乃守盛秀、被召御所、御盃以下御剣等被下之」という(『満済准后日記』永享三年八月七日条)。義教は条件を付けずに東使を御所に招待し、盃を取らせ御剣を下すなど「天下無為儀お専被思食」す義教が「東使御対面儀」により「天下無為儀」を果たせたという強い気持ちがあったのではなかろうか。この対面は「管領、畠山両人計参申」ており、私的なものだった様子がうかがえる。
8月11日、満済は室町殿へ参上して義教と対面するが、義教は「二ヶ條、被仰畠山事在之(二つ、畠山満家入道に仰せられたことがある)」という(『満済准后日記』永享三年八月十一日条)。ひとつは九州の件で、もうひとつが持氏への贈物のことであった。贈物は対面時にもたらされた持氏からの進上品に対する答礼であり、「関東へ可被遣色々、御剣一腰、御鎧一両、盆、香合、食籠、以上五種可然歟(持氏へ遣わす品々は、御剣一腰、御鎧一両、盆、香合、食籠の五種でよいか)」を諮問したという。満済には「可為此分歟、又此外今一両種可被相副條可宜歟、両様不残所存可申(以上の件でよいか、さてまたこのほかにもう一種類追加したほうがよいか、思うところを残さず申すように)」という(『満済准后日記』永享三年八月十一日条)。満済は月次壇所(今回は地蔵院持円が担当)に「召寄遊佐」せて九州のことや関東贈物の件を問い合わせると、遊佐河内守は「此事不可及申入道、委細存知仕間申入也(この件は主に申し入れるまでもありません。委細を存じていますので申し上げます)」という。その中で、関東贈物の件については、「今一両種可被副條ハ猶可宜、以申入候五種、更以不可有御不足儀(もう一種追加することが望ましいでしょう。現状五種類ということですが、御不足があってはなりません)」と述べている。ただ、「此儀、先存知分申上候、但罷帰猶可相尋畠山歟(この件はまず私が知っていることを申し上げました。帰って畠山に今一度確認しましょうか)」と述べたため、満済は「先可披露(まずはその意見を室町殿に報告しよう)」と述べたところ、遊佐河内守は「此分御意得云々、仍不及畠山也(いま私が語った分はすでに室町殿に報告済みです。それなので畠山に聞く必要はない、と初めに申したのです)」というように、遊佐河内守はすでに畠山入道の所存を義教に伝えていたことがわかる(『満済准后日記』永享三年八月十一日条)。
結局、関東へは一品「段子三端」が追加され、8月22日、計六種類の返礼品が送られることとなる(永享三年八月廿二日「足利義教御教書案写」『貞助記』室:2678)。これを以て、公的に都鄙の和平が成立した。
●永享3(1431)年8月22『足利義教御教書案』(『貞助記』)
10月7日、山名時熈入道から満済へ「佐々河ヨリ御返事到来云々、就関東施設御対面事、諸大名去七月下遣状返報歟」(『満済准后日記』永享三年十月七日条)の知らせが届いている。ただ、この返報に対して満済が義教と対談した記録はなく、関東使節の対面により、篠川満直の返報に書かれていることは満済に諮るほどの重要性は持たなかったのだろう。
この頃、下総国では12月24日、千葉介直胤が明徳5(1394)年6月29日の『千葉介満胤判物』に任せて、真間山弘法寺別当・弁法印御房に対して、「真間弘法寺職地并西屋敷、長門屋敷、上畠、山野等」を安堵する安堵状を発給している(永享3(1431)年12月24日『千葉介胤直安堵状』)。
●永享3(1431)年12月24日『千葉介胤直安堵状』
永享4(1432)年正月7日、満済のもとに「二本松畠山修理大夫ト号、武田刑部少輔入道、赤松弥五郎以下来、各太刀賜之了」(『満済准后日記』永享四年正月七日条)という。奥州二本松の畠山修理大夫持重がどういった経緯で上洛していたのかは定かではないが、彼らは新年の表敬参賀に訪れたと思われる。武田刑部少輔入道はおそらく甲斐国から遁れていた武田信重入道と思われる。
そして正月10日、「当年壇所始」として壇所に義教が渡御し、満済は「初度渡御祝着々々」と祝いの言葉を述べる。そして「来三月中、御参宮(伊勢参宮。2月23日に伊勢国司北畠侍従が「御参宮来月十四日御治定」で用意のために満済に暇乞いをしている)」の件を話し、次に「富士御覧度之由、内々畠山、山名等意見可相尋之由(富士山を見たいが、内々畠山入道と山名入道に意見を尋ねよ)」と指示した(『満済准后日記』永享四年正月十日条)。満済はこれについて意見を述べておらず、問題視はしていない。
「都鄙和睦」の成立とともに義教の頭をよぎったのは、おそらく嘉慶2(1388)年9月16日の「准后前左大臣義満下向東国、観富士」(「続史愚抄」嘉慶二年九月十六日条『異長者補任』)の故例であろう。ただし、将軍直々に東国境界国である駿河国まで下向するということは、関東を刺激することになりかねないが、諸大名や満済を含めてその懸念はうかがえない。義教はこの件について秋の予定としているように急いではおらず、尊敬する亡父義満の故例により「天下無為」を象徴したいというのが、この駿河下向計画の本質であったのだろう。都鄙和睦が成って二か月後の永享3(1431)年9月15日、義教は「大和守(飯尾貞連)、沙弥」を通じて「今川上総介殿」に「富士浅間神社造替事」の進行が遅れていることを袖判にて「且不怖神慮、且不顧民煩之条、甚不可然」と𠮟責しており(永享三年九月十五日「奉行人連署奉書写」『御前落居奉書』室:2681)、富士参詣の計画立案の中で、富士を御神体とする浅間神社に、停滞している造替を早期に行うよう督促したのかもしれない。
その後、山名時熈入道(使者は被官山口遠江守)が満済に「富士御下向事、山名意見」として「今時節、尤可然目出候由」を伝え、参内後に再度壇所へ戻った義教にこの旨を報告している(『満済准后日記』永享四年正月十日条)。山名時熈入道は、御対面により「都鄙和睦」が成り「天下無為」となった「今時節」こそ、駿河国への下向は「尤可然」という言葉となったのだろう。この件は満済も問題視しておらず「都鄙楽観論」が強かったことがうかがえる。
翌永享4(1432)年正月11日早朝、義教は壇所を訪れて満済と対談。「富士御下向事、畠山意見趣」として「尤珍重」という、これまた楽観論の返事が伝えられた(『満済准后日記』永享四年正月十日条)。
| 山名時熈入道 | 今時節、尤可然、目出候 | 今の時期がもっともよいと思います。 |
| 畠山満家入道 | 雖何時候、可有何子細候哉、尤珍重々々、内々門跡様、春ハ富士霞ニ不見候歟、然者自然御逗留被送日数事モヤト存候、又国々用意、来月中計ニハ定可計会歟、来秋尤可然存 | 何時であろうとも、何の問題もなく大変良いことと思います。内々に門跡様に伝えておきますが、春は「富士霞」がかかり富士が見えない事があります。そのため長期にわたる滞在になりかねません。また国々の用意もありますので、来月中などは無理と存じます。来る秋などがもっともよいと思います。 |
満済はこのことを義教に詳細に伝えたところ、「可被延引、来秋」とあっさり秋への延引を受け容れている(『満済准后日記』永享四年正月十日条)。この将軍の意向は「則畠山、山名両人方へ申遣」ているが、義教が駿河下向をとくに急いでいないことは明白であり、駿河下向は私事からの発想であって関東への牽制という通説も成り立たない。
永享4(1432)年2月中旬頃、関東管領上杉憲実は「使者羽田」に書状を持たせて鎌倉を出立させた。「使者羽田」は4月21日に「三宝院御門跡領武蔵国高田郷」につき、飯尾加賀守為行が奉書を遣わした「判門田壱岐入道殿」のことである(永享四年四月廿一日「飯尾為行奉書案断簡」『醍醐寺文書之十三函』:室2703)。「上杉安房守雑掌」(『満済准后日記』永享四年三月十一日条)、「羽田入道上杉雑掌也」(『満済准后日記』永享六年十一月三日条)と見え、憲実は彼を使者として上洛させ、そのまま在京代官として置く予定なのだろう。
この旨を京都から憲実執事「長尾々張入道殿」に伝達した「沙弥性真」は、応永24(1417)年8月11日に「水本僧正(報恩院隆源)」が「伊豆山密厳院事」について申し立てた事につき、上杉憲基執事の長尾定忠へ取り次いだ「沙弥性真」(応永廿四年八月十一日「沙弥性真副状案」『醍醐寺文書一七函』)と同一人物である。なお、応永24年の副状案の端裏書に「ハね田 そへ状の案」とメモされており、一見「沙弥性真」と判門田壱岐入道は同一人物とも思えるが、永享4(1432)年4月21日に「沙弥性真」が憲実執事「長尾々張入道殿」に宛てた文書では、詳細については「御代官」が伝えるので省略する旨が記されている(永享四年四月廿一日「沙弥性真書状案」『醍醐寺文書一三函』:室2704)。もし、「沙弥性真」が代官判門田壱岐入道と同一人物だとすると、判門田壱岐入道以外に彼より上位の「御代官」が存在していたことになるが、後述のように憲実が越後国紙屋荘代官職を欲し、篠川殿満直(紙屋庄代官職)と直接やり取りしたという噂に関し、義教は都鄙平穏を一番に考える憲実が「代官トシテ羽田参洛事也」なのに公方に諮ることもせず、直接満直に直接話を通すわけがないと述べている通り、京都雑掌(代官)は判門田一人である。そして、「判門田壱岐入道」の法名は「祐元」であることから(宝徳二年十月十一日「畠山徳本奉書写」『松雲寺文書』)、「沙弥性真」と判門田壱岐入道は明確に別人である。応永24(1417)年の端書「ハね田 そへ状の案」は、判門田壱岐入道が沙弥性真を使者として派遣したため、使者の名ではなく差出人たる判門田壱岐入道をメモしたものであろう。
憲実使者の羽田壱岐入道は、2月23日頃に近江国守山宿に到着し、管領義淳に「先守山ニ罷着、自其案内ヲ申入」ている(『満済准后日記』永享四年二月廿三日条)。2月24日、管領は甲斐左京亮を満済に遣して「可参洛仕之由可申歟云々、但可依時宜」と問い合わせ(『満済准后日記』永享四年二月廿四日条)、満済は「此子細、今日吉日也、早々可被達上聞條可然、参洛日次事、被任上意歟」と返答している。その後の結果は記されていないが、すぐに義教に伝えられて上洛の日程が決定され、2月26日には守山宿に連絡されたとみられる。2月27日には「鎌倉管領上杉安房守使者羽田壱岐入道参洛」し「公方様御目」っており(『満済准后日記』永享四年二月廿八日条)、即座に上洛と御対面が許されたことがわかる。先日の篠川満直への御教書はあくまでも表向きの理由を述べただけであり、義教の本心は「天下無為儀お専被思食」(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)だったのである
翌2月28日、羽田壱岐入道は満済に「今日房州状等持参」し「紬十、馬一疋栗毛」を献じ、「羽田分」として「馬一疋、千疋」を献じている。
翌2月29日早朝、満済は京都へ入り室町殿で義教と対面し、昨28日に羽田壱岐入道が満済に渡した「上杉安房守状」(『満済准后日記』永享四年二月廿九日条)を見せている。上杉憲実の書状の内容は以下の通り。
●「上杉安房守状」(『満済准后日記』永享四年二月廿九日条)
| (一) | 京都領事、自已前如被仰出、不可有相違之由 上意候之 | 関東が預かる京都御料返上の件で、以前から仰せられているように、返上を間違いなく進めるようにとの鎌倉殿の上意です。 | 年不詳二月十三日 「上杉憲実書状写」 (『静嘉堂本集古文書』) |
| 関東京方所領共悉可渡進、早々御代官下向候様可被仰付 | 関東の京方所領についてはすべてお戻します。早々に御代官を下向させるようご命令ください。 | 『満済准后日記』 永享四年三月十一日条 |
|
| (二) | 関東五山長老、器用西堂等雖被挙申度、時宜難計間、先令啓候 | 関東五山の長老はその器たる西堂を吹挙しようと存じますが、室町殿の御意思がわかりませんので、まずはこの旨を御披露ください | 『満済准后日記』 永享四年三月十一日条 |
3月11日、管領義淳は飯尾美作守を醍醐寺の満済のもとへ遣わし「今度参洛仕上杉安房守使節羽田申入候」の「両条」である「関東京方所領共悉可渡進、早々御代官下向候様可被仰付」ならびに「関東五山長老、器用西堂等雖被挙申度、時宜難計間、先令啓候」について、「早々被達上聞者可畏入」と願っている(『満済准后日記』永享四年二月廿九日条)。これに加えて、管領義淳自身の「当職上表事、去年以来連々申入、被懸御意者畏入」の合計三か条を伝えたが、満済は「両三日聊御風気事」で対面できず、「宗清僧都」に対応させている。
●管領義淳からの依頼(『満済准后日記』永享三年三月廿四日条)
| 條 | 依頼元 | 斯波義淳からの用件 | 宗清僧都からの返事 |
| (一) | 関東管領憲実 | 関東京方所領共悉可渡進、早々御代官下向候様可被仰付 | ・以一色左京大夫可被申條尤可宜候 ・東両條事、以一色左京大夫可被申旨 |
| (二) | 関東五山長老、器用西堂等雖被挙申度、時宜難計間、先令啓候 | ||
| (三) | 管領義淳 | 当職上表事、去年以来連々申入、被懸御意者畏入 | 当職上表事、去年以来御申難儀之由、数度被申了、於今又同前候 |
宗清僧都は満済からの指示とみられるが、「上杉安房守雑掌申両條京方所領悉可渡事、関東五山長老吹挙事、事」は「以一色左京大夫可被申條尤可宜候」と答えている(管領上表はそもそも「難儀」としているのでこれについての返答はない)。
3月17日、満済は「関東ヨリ今度申、京方御領如元悉可渡申、早々可被下御代官」という件について、畠山満家入道、山名時熈入道の両人と打ち合わせ、「如此申上者、可被下御代官歟、就其京都奉行人ヲ被定、安房守雑掌羽田入道折紙ヲ被召下、各可下代官由可被仰歟、如何(関東からの申し出につき、御代官を下すべきか、または京都奉行人を定めて憲実雑掌の判門田壱岐入道に折紙を下すか、所領を持つ各々が代官を下すようお命じいただくか、如何か)」と問うと、畠山、山名両人も「此仰尤珍重」と賛同したため、この件を義教に申した(『満済准后日記』永享四年三月十七日条)。
翌18日、満済は室町殿に参じて義教と対面し、「上杉七郎(上杉憲実兄・七郎頼方)」の事で「今度関東上杉安房守、頻申入」がある件について、義教は「御免事、不可有子細旨被可仰遣(七郎赦免の件は、間違いなく行う旨を憲実に遣わすように)」と指示したが、「長尾上野入道、若猶申所存事在之者、只今安房守方へ御返事可相違間、先内々被仰出也、所詮七郎事、可有御免、無異儀可存其旨由、可仰遣長尾上野方(七郎と敵対した越後守護代・長尾上野入道がもし未だに何か異儀があるのであれば、今の憲実への返事と相違してしまうので、まず内々にこの件を長尾に『上杉七郎は赦免するので、異儀ない旨を確認せよ』と申し遣わせ)」ことを、大内家の家督問題などとあわせた「三ヶ條」として畠山満家入道へ伝達するよう満済に指示している(『満済准后日記』永享四年三月十八日条)。これは応永末年、越後国前守護の憲実兄・上杉七郎頼方と守護代長尾上野介邦景入道の対立から軍事衝突に発展し、敗れた頼方が越後守護職を罷免された件で、憲実がその赦免を願い出たのだろう。長尾邦景入道と憲実との関係は良好であり、邦景入道も義教からの強い要請もあって、これに異儀を唱えることはなかったと考えられる。
そして、3月29日の月次連歌の前に満済は室町殿に早出して義教と対面。「去十八日、被仰出畠山三ヶ條返事申入」ている。そのうち上杉七郎頼方の赦免については、「上杉七郎事、長尾右京亮、高野参詣仕候、罷帰候者、相尋重可申入」(『満済准后日記』永享四年三月廿九日条)といい、在京の上野入道の子・右京亮実景が高野山参詣で留守だったため、意志の確認ができなかったことから、帰洛後に確認するとの報告であった。
さらにこの日、満済が畠山満家入道へ追加で確認するよう指示されたこととして、越後国紙屋庄についての案件があった。越後国紙屋庄は、前年永享3(1431)年2月29日に「越後国紙屋庄実相院門跡領事、可被進佐々河、於実相院者近所ニ替地可有御計之由被仰出」(『満済准后日記』永享三年二月廿九日条)て、「被進佐々河了」の地であった(『満済准后日記』永享四年三月廿九日条)。ところが「此代官職事、上杉安房守関東管領執心事、今度初被知食了(紙屋庄の代官職を関東管領憲実が大変欲している件は、室町殿は今回初耳である)」というように、紙屋庄代官職を上杉憲実が欲しているという噂に義教が不審を抱いたのであった。
義教が満済に述べたことは「然者、去年実相院計トシテ改代官申付別人時、不申子細哉、仍為公方モ実相院へ被遣替地於丹後国、此庄紙屋事、被遣佐々河了、此時節安房守兎角地下ヲ執心之由、越後守護代長尾上野入道、去年以来申間、一向以緩怠之儀、上野入道申入由御意得處、今度安房守代官羽田罷上、内々属遊佐申旨之由、只今被聞食之間、此間長尾上野入道懈怠儀モ不在之由御不審被散了、次上杉安房守此代官職事、直ニ佐々河方へ申入云々、此條安房守沙汰トモ不被思食事也、是程此在所執心之儀在之者、ナトヤ幸ニ代官トシテ羽田参洛事也、以此者公方ヘモ不申哉、御不審又此事也、凡安房守都鄙事一大事ト存スル者也、就此庄事又都鄙間事ヨモ無正体様ニハ存申候ハシト思食處、越後守護代上野入道如申状者、此庄事故又京鎌倉事、如何と存間、浅猿候ト云々、此條更不被得御意事也、サレハトテ安房守是程ノ所存ハ候ハシト思食也、所詮安房守已執心之由申状無子細者、先此庄佐々河代官可沙汰居事ヲハ可相延歟、重就安房守申状可被加御思案云々、且此等趣召寄羽田、遊佐具可申聞(紙屋庄代官職の件について、憲実が欲しているというのであれば、なぜ去年実相院から代官を改める際になにも言ってこなかったのか。どこからも意見はなかったのでこちらも実相院へ丹波国内に替地を与えて、紙屋庄は篠川満直へ遣わしたのだ。実はこの頃、憲実は紙屋庄の地下代官を望む旨を越後守護代長尾上野入道に去年以来申していたが、長尾入道が「自分が取り次がずにまったく怠けていた」ことを報告し、今度は憲実代官判門田壱岐入道が上洛して、内々に畠山家職の遊佐河内守に憲実が紙屋庄代官職を希望している旨を話し、その内容を聞き、なるほど長尾上野入道の懈怠のことは知らなかったと納得した。次に、上杉憲実がこの代官職について直に篠川へ申し入れたことも長尾入道の申し入れにあったが、私は憲実が篠川へ直接このことを申し入れたとは思っていない。憲実がこれほど紙屋庄代官職を欲しているのであれば、ちょうど代官として判門田壱岐入道が上洛しているのに、どうして彼を通じてこちらへ申さないことがあろうか。憲実であれば当然そうするだろうし、篠川へ直接話をすることはなかろう。この話が疑わしいのはまさにここなのだ。そもそも憲実は京都と鎌倉との関係を第一に考える人物である。私事の紙屋庄代官職ごとき事のために都鄙の関係を危うくすることなどありえない。長尾上野入道のこの件についての申し入れは信用ならず、呆れるばかりだ。憲実は篠川と直接話したという件はまったく信用していないが、憲実がこれほどまでに紙屋庄代官職を欲しているのは知らなかった。憲実の執心する紙屋庄代官職について差支えがなければ、まず篠川満直への代官職認可を延引すべきか。また、憲実の申状についてもう一度思案しよう。こちらでも憲実の希望について代官判門田を召して遊佐河内守を通じて詳しく聞くように)」(『満済准后日記』永享四年三月廿九日条)とのことであった。
畠山は室町殿上意につき「召寄羽田委細以遊佐申」すと、判門田壱岐入道は「此仰旨、殊忝畏入候(憲実を信頼しての仰せ、本当に有難く畏れ入ります)」と礼を述べ、「遊佐の状」を所望した。畠山満家入道は満済に「可遣哉」と問うと、満済は「不及伺申入事也、以口上申條々載状所望處ニ不可及故障事歟、定安房守方へ下遣、為令一見歟、殊宜様覚也(おっしゃる事は伺うまでもありません。室町殿の言葉を、口上で伝える所を條々にした書状を所望しているだけであり、なんら問題ないでしょう。おそらく憲実のもとへ下して内容を一見させたいのでしょう。大変宜しいと思います)」(『満済准后日記』永享四年三月廿九日条)と答えた。
もう一点、駿河国の守護職「今川上総守」の「相続仁體事」での問題も発生している。先年、今川上野介範政が病に倒れた際、相続人として「末子千代秋丸」と定めたが、その事は義教は「内々被聞食及」んでいる(『満済准后日記』永享四年三月廿九日条)。ところが、千代秋丸は「此者事母関東上杉治部少輔姉妹」であり、義教は「幸ニ嫡子以下兄弟数輩在之、閣此等堅固幼少七八歳者ニ可申付條、併別心様ニ可罷成歟、不可然由先度以山名状上意趣具申下了(幸いなことに範政嫡子以下、兄弟数名がいるが、彼等成人者を差し置いて、わずか七、八歳の幼児に家督を申し付けるというのは、なにか疾しい心でもあるのではないか。この相続は認めない旨を先ごろ山名時熈入道の状に詳細に記した)」という。
この返事は3月28日に満済のもとに「自山名方同今河方申、山名使者山口、今河使者三浦安芸云々来申旨、同今河罰状等、此門跡へ状持参(山名方から山口遠江守、今川方から三浦安芸守がそれぞれ満済を訪れ、「今河罰状」と満済への書状を持参)」している(『満済准后日記』永享四年三月廿九日条)。その内容は「嫡子事、如伴可申付處、此者事以外無正體、始終奉公且以不可叶条見限了、内者共又同前儀候、仍去年所労以外時節、内者共寄合せメテハ幼少間、未来器用モヤト存間、千代秋ニト申了、已所労本複仕上者、相続仁體先何トモ不被定下者可畏入云々、且非緩怠別心儀、以罰状申入候也(嫡子彦五郎にともに来るよう申付けましたが、この者は精神状態がよくありません。常にご奉公することは不可能であると見限っております。被官共もまた同様に思っております。そのため、昨年私の病が重篤となった際、被官共を集めて、『千代秋丸は幼少で将来は家督にふさわしくなるだろう』と、家督を千代秋とする旨を決定しました。ただ、私の病が本復した上は相続人の件はまず誰とも定め下されないようお願いします。また、千代秋丸を家督に定めんとしたことは、決して緩怠別心ではない旨、罰状を提出いたします)」というものだった。
満済は、室町殿に参じて義教にこの件を報告したところ、再度「誠於嫡子事者、器用トモ又非器用トモ為上ハ難仰出事也、随逐父非器用之由見限上ハ勿論歟、末子千代秋丸七歳云々、此器用又御不審也、七八歳小者事、只今器非器難定様思食也、是モ未来若器用モヤノ分ニテコソ可申付旨ヲハ申ラメト思食也、然者、大事国相続仁體、於不見定者又難申付歟、然者、就母方有縁関東隣国之間、此者ニ申付儀ト諸人上下可意得條ハ御案内也、然者今河事此小者母ユヘ歟、関東一体雑説之間、及種々沙汰了、且又山名執申入キ、如此處ニ只今此小生ヲ執別相続ノ仁體ト定條、旁心中非無御不審也(本当に嫡子の事については、器とも非器とも結論を言い難い。父範政が彼をその器にないと見限ったのであれば仕方がなかろう。末子の千代秋丸はわずか七歳という。彼が器たるかは疑問だ。七、八歳のこどもの事を今の段階で器たるか否かを判断できまい。これも将来、器用であれば家督を申し付けるべきだと申してはどうか。駿河国という重要な国を相続する人物の器量が不明であれば国を任せられないだろう。そうであれば、駿河が母方有縁の関東と隣国だから範政が千代秋丸を家督に据えようとしているのだと、人々がみなそう思うのも当然だろう。そうであれば、今川家はこの幼児の母が関東有縁のため、関東と一味同心しているとの噂があるので、いろいろ判断している。また、山名時熈入道が申すには「この私をとくに相続人に定めた」と言うが、本当かどうか不審がないわけではない。)」という(『満済准后日記』永享四年三月廿九日条)。今川家から駿河守護職の返上も視野に入れているという、相当強い恫喝となっている。
今川範国―+―今川範氏――今川泰範
(上総介) |(上総介) (上総介)
| ∥ 【嫡男】
| ∥――――――今川範政―+―今川範忠
| ∥ (上総介) |(彦五郎)
| ∥ ∥ |
| 上杉朝興――女子 ∥ |【二男】
|(中務大輔) ∥ +―今川弥五郎
| ∥ |
| ∥ |
| ∥ +―女子
| ∥ ∥
| ∥ ?
| ∥ ∥
| ∥ 一色教親
| ∥ (五郎)
| ∥
| ∥――――――今川千代秋丸
| ∥
| 上杉氏定―+―女子
| (弾正少弼)|
| +―上杉持定
| |(治部少輔)
| |
| +―上杉持朝
| (修理大夫)
|
+―今川貞世―+―今川貞臣
|(伊予守) |(伊予守)
| |
| +―各和貞継
| |(伊予守)
| |
| +―今川言世
| |(右馬助)
| |
| +―尾崎貞兼
| (右京亮)
|
+―今川仲秋―+―今川貞秋
(左衛門佐)|(遠江守、右衛門佐)
|
+―今川氏秋
|(右馬助)
|
+―今川直秋
|(大蔵大夫)
|
+―今川国秋
続けて「一色左京大夫子息五郎事」でも「今河上総、縁ニ可罷成之由、去年以来申間、不可有子細由被仰出キ、此時ノ申状モ、以前関東所縁事ユヘ及雑説了、雖然、委細以聞食披儀、于今畏存間、弥無二御心安者ト被思食様可致奉公條本意間、一色左京大夫所縁事申入云々、然者已関東有縁小者ニ国事可申付條又関東ヘ■無二者ト申哉、所詮旁今河尚々不被■御意也、於千代秋丸事者、是非不可叶■自余兄弟内シカト申付趣お重可申入由、能々山名可申付(一色持信の子息・五郎教親のことでも、今川範政が彼と縁組したいと去年から申入ていた件で、私はとくに問題ないと言ったが、この時に出された申状も「私は関東所縁ということで様々な雑説があります。しかし、委細をお聞き届けいただき、より一層室町殿が頼りになる者だと思われるよう奉公することこそ本意であるため、室町殿近臣の一色持信との縁組を申し入れたのです」とあった。そうであれば、すでに関東有縁の幼児に駿河国守護職を申し付けてほしいとの事はいっそう関東への忠節を誓うということか。そうであれば今川家に駿河は任せられない。千代秋丸の家督相続は認めないので、他の兄弟から選ぶようにしかと申し付けよと再度申し入れるよう、山名時熈へよくよく申付けよ)」との仰せだった(『満済准后日記』永享四年三月廿九日条)。
これを受けた満済は「此仰旨、召寄山口申付」たが、すでに「今日及夜陰間、明旦可参」と指示。翌4月1日早朝、山名時熈被官の山口遠江守が満済のもとを訪れ、「此事山口ニ召仰」し、山口も「上意條々尤候、早々可申下」ことを伝えている(『満済准后日記』永享四年三月廿九日条)。なおこの件は駿河国へ送達されており、4月25日に満済のもとに今川範政から両使「三浦安芸守、クシマ(福島)」が遣わされ「自今河上総介方状到来、一跡相続仁體、器用事申入也」ている。もともと範政は「嫡子」を器量なしとしており、「嫡子」に家督を譲るつもりはなかったため、「嫡子」以外の人物を家督に付けるつもりだったのだろう。こうしたことで6月下旬、「駿河守護今河上総介嫡子彦五郎遁世」し、その知らせが6月29日に義教のもとに到来した(『満済准后日記』永享四年六月廿九日条)。事実上の範政による「嫡子彦五郎」の廃嫡であろう(その後、彦五郎は出家したのち駿河を出て上洛し、義教の庇護下に入る)。しかし、永享5(1433)年3月15日、「今河総州駿河守護、娚子彦五郎事、器用不便由、今河遠江入道申旨内々達上聞了」と、一門の今川遠江入道(範政父泰範の従弟・貞秋)が満済に「娚子彦五郎(他と揃えて「嫡子彦五郎」の意か。これまで数回にわたり「嫡子彦五郎」と記されている語句が、ここのみ「娚子彦五郎」となっているからといって、字面通り「甥」の意とするのは不自然)」は器用の仁であり、廃嫡はよろしくない旨を訴えており、満済はこれを内々に義教へ伝えている。
義教の駿河下向は、範政が「先年」倒れて関東由緒の「千代秋丸」を相続人と定めたことを「内々被聞食及」(『満済准后日記』永享四年三月廿九日条)んだことが発端なのではなかろうか。
一方、4月21日、上洛中の関東管領使者・判門田壱岐入道は帰国することとなったと思われ、満済から慶円法眼が遣わされて「関東管領上杉安房守方へ返事遣之盆堆紅、輪光、金襴赤地一端、白太刀一腰」が下されている。また判門田自身にも「羽田方へ三重太刀」が遣わされた(『満済准后日記』永享四年四月廿一日条)。また、同4月21日、将軍義教から何らかの指示(文書が前闕で判断できず)が関東奉行人の飯尾加賀守為行を通じて「判門田壱岐入道殿」に下されているが(永享四年四月廿一日「飯尾為行奉書案断簡」『醍醐寺文書一三函』室:2703)、これは「京方御領如元悉可渡申」という関東の依頼に基づいて「三宝院御門跡領武蔵国高田郷事(横浜市港北区高田町)」について返付するよう命じた文書と考えられる。高田郷は元来「右大臣家法華堂領」であるが、醍醐寺がこれを管掌しており、今回沙汰の対象になったとみられる。
●永享4(1432)年4月21日「飯尾為行奉書案断簡」(『醍醐寺文書一三函』室:2703)
当時の醍醐寺管領の所領は以下の通り。このうち、関東の所領は、武蔵国橘樹郡高田郷(鎌倉二位家右大臣家両法華堂領)、上総国梅佐古村の二か所であるが、上総国梅佐古についての返付に関しては指示がなされていない。
| 所職 | 国 | 庄園等 |
| 三宝院 | 尾張国 | 安食庄 |
| 潮部南郷 | ||
| 国衙 | ||
| 鳴海庄 | ||
| 得重保 | ||
| 丹後国 | 朝来村 | |
| 鹿野庄寺辺田 | ||
| 近江国 | 船木庄 | |
| 田河庄河毛郷 | ||
| 越前国 | 河北庄 | |
| 丹波国 | 曾地村 | |
| 三河国 | 国衙 | |
| 山城国 | 山科地頭職 | |
| 小野庄 | ||
| 久世郷 | ||
| 久多庄 | ||
| 美濃国 | 帷庄 | |
| 牛洞郷 | ||
| 若狭国 | 名田庄須恵野村 | |
| 肥前国 | 佐嘉庄 | |
| 宝池院 | 筑後国 | 高良庄 |
| 尾張国 | 枳豆志 | |
| 金剛輪院 | 伊勢国 | 渡会郡棚橋大神宮法楽寺、末寺等寺領 |
| 遍智院 | 越中国 | 石黒庄太海郷 |
| 石黒庄院林郷 | ||
| 阿波国 | 金丸庄 | |
| 伊勢国 | 南黒田 | |
| 安養院 | 筑前国 | 楠橋庄、寺辺屋敷等 |
| 菩提寺 律院 | 山城国 | 宇治郡左馬寮、寺辺田 |
| 鳥羽金剛心院 | ||
| 大智院曼荼羅寺 (小野万荼羅寺之事) |
方々所職 | |
| 醍醐寺座主 | 伊勢国 | 曽祢庄 |
| 越前国 | 牛原四ケ郷(丁、井野部、牛原、庄林) | |
| 近江国 | 柏原庄(供僧中) | |
| 大野木庄 | ||
| 河内国 | 五ケ庄 | |
| 山城国 | 笠取庄 | |
| 肥前国 | 山鹿庄 | |
| 伝法院座主 | ― | 寺領(在別) |
| 左女牛若宮別当職 | 土佐国 | 吾川郡大生郷 |
| 吾川郡仲村郷 | ||
| 尾張国 | 日置庄 | |
| 筑前国 | 若宮庄武恒、犬丸方 | |
| 摂津国 | 山田庄 | |
| 桑津庄 | ||
| 大和国 | 田殿庄 | |
| 美濃国 | 安八郡森部郷 | |
| 源氏・千種両町 | ||
| 篠村八幡宮別当 | 丹波国 | 篠村庄 |
| 佐伯庄地頭方 | ||
| 佐々岐 | ||
| 河口 | ||
| 黒岡 | ||
| 光久 | ||
| 葛野新郷 | ||
| 上総国 | 梅佐古 | |
| 三条坊門八幡宮別当職 | 山城国 | 多賀 |
| 高島 | ||
| 摂津国 | 時友 | |
| 越中国 | 御眼庄吉河 | |
| 高倉天神別当職 | 近江国 | 愛智郡香庄 |
| 仏名院 | 摂津国 | 鞍庄、敷地 |
| 清閑寺法華堂別当職 | ||
| 清閑寺大勝院 | ||
| 清閑寺南池院 | ||
| 鎌倉二位家右大臣家両法華堂別当職 | 讃岐国 | 長尾庄 |
| 造田庄 | ||
| 武蔵国 | 橘樹郡高田郷 | |
| (醍醐寺三宝院領か) | 但馬国 | 朝倉庄、福元方 |
| (醍醐寺三宝院領か) | 山城国 | 日尾寺、善縁寺 |
同21日、「沙弥性真」は憲実執事「長尾々張入道殿」に宛てて、早々に同地を「彼御雑掌」へ打渡すよう指示する飯尾為行折紙案を送って、これを憲実に報告するよう依頼しているが、詳細については「御代官」が伝えるので省略する旨が記されている(永享四年四月廿一日「沙弥性真書状案」『醍醐寺文書一三函』:室2704)。なお、通説では「沙弥性真」は判門田壱岐入道と同一人物とされるが、当時の憲実の京都雑掌(御代官)は判門田壱岐入道のみと考えられることから、両者は別人である。
●永享4(1432)年4月21日「沙弥性真書状案」(『醍醐寺文書一三函』室:2704)
その後、憲実から武蔵守護代へ打渡が指示されたと思われるが、この打渡は例の如く沙汰が行われないままに延引されており、三宝院雑掌により鎌倉に直接訴えがあったため、おそらく12月15日、鎌倉殿持氏から管領(武蔵守護)上杉憲実へ沙汰が下り(御教書は現存せず)、同15日、憲実から再度守護代「前石見守(大石憲重)」にその沙汰が指示された(永享四年十二月十五日「上杉憲実奉書案」『醍醐寺文書一三函』室2743)。大石憲重入道には数日後に奉書が届き、12月18日、「前石見守(大石憲重)」は代官「鎌田助次郎殿、村田平三郎殿」を両使として現地へ派遣し、「任去十五日御遵行之旨」せて三宝院雑掌に「沙汰付下地」けるよう命じている(永享四年十二月十八日「大石憲重遵行状案」『醍醐寺文書一三函』室2744)。そして12月23日、「沙汰(付)下地於三宝院雑掌候訖、仍渡状如件」(永享四年十二月廿三日「大石憲重打渡状案」『醍醐寺文書一三函』室2749)と、ようやく高田郷の打渡が完了した。持氏が京都に約束した「京方御領如元悉可渡申」という件も、この一ヶ所の打渡をみてもなかなか進展しない事実がうかがわれる。
義教は、関東とは対立無き中庸を保ちたい考えだった様子がうかがえる。関東との対立発生を避けるためにも京都と関東が管轄する地を峻別し、互いにその干渉を徹底的に避けるよう動いていたのだろう。かつて持氏が京都管掌の越後国に軍勢催促を行った際に、融和姿勢の義教の態度が一気に硬化したのもこうした考えが背景にあると考えられる。
関東政策において義教がもっとも頭を痛めた問題は、故義満以来、京都が支援し続ける必要がある負の遺産「京都御扶持之輩」や篠川殿満直の存在だったろう。義教は、鎌倉殿持氏が「関東安穏」を理念とし、それに反する「京都御扶持之輩」を排除するために戦っていることは理解していただろう。しかし、義教としても「京都扶持之輩」の支援は京都の威信にかけて行わざるを得ないことで、そこには関東と京都の間に妥協点はなかった。義教は「天下無為」の「御政道」を理想に掲げながらも、それを達成するためには「天下無為」を否定しなければならなかったのである。義教は故義満、故義持が遺した「負の遺産」のために、矛盾を抱えながら非常に難しい関東政策を行っていたのである。
鎌倉殿持氏は、政所執事二階堂盛秀をはじめ、関東管領からの使者を送るなど、京都とは対話と融和の姿勢を崩さなかったが、関東政策においては「関東御扶持之輩」の追捕を徹底的に行い、この点は妥協しなかった。京都(笹川満直の提案)からの「三ヶ条」に関する罰状要求を峻拒したのも、関東平穏の理想を阻む存在を野放しにはしないという持氏からの強いメッセージであったろう。そして、関東管領の使者が上洛している最中でもその姿勢は変わらず、永享4(1432)年3月頃の「於常州石上城合戦」で「小野崎越前三郎殿(小野崎通房)」が「致分捕」たことに、3月20日、持氏は「尤以神妙、向後弥可抽戦功」と賞している(永享四年三月廿日「足利持氏御教書」『阿保文書』室:2700)。また、同日「中忠」なる人物もまた持氏の御感を得たことを「目出度候」と文書を送っている。「中忠」が如何なる人物かは不明だが、鎌倉在住で通房とも親しい人物と考えられる。なお、この「石上城合戦」は石神城(那珂郡東海村石神内宿)での佐竹祐義入道方との戦いとみられるが、石神村は小野崎通房の知行地と考えられることから、佐竹祐義勢の攻撃であると思われる。
4月28日には、足利持氏以下、上杉憲実、武田信長、千葉介胤直ら九人が相模国大住郡の大山寺伽藍造営つき、馬を奉納している(永享四年二月廿八日「大山寺造営奉加帳」『相州文書 大山寺八大坊所蔵文書』室:2706)。当時の胤直は20歳だが、叙位された経験もなく無官でもあった。鎌倉は管国守護職のみならず諸役人としての国人も常在しており、当然彼ら以外にも大山寺への奉加にふさわしい家格の人物がいたにも拘わらず、彼ら九人が選ばれた理由は定かではない。奉加の面々を見ると、関東管領憲実が筆頭にあり、四番目の一色持家、直兼は鎌倉殿御一家、後列三名はいずれも鎌倉奉行人という位置づけだが、家格としてはいずれも鎌倉殿被官人であり、守護家の武田信長、千葉介胤直よりも家格は下となるのであろう(次代の古河公方成氏の時代では千葉介の家格は別格だった)。
●永享4(1432)年4月28日『大山寺造営奉加帳』(『相州文書』「大山寺八大坊所蔵文書」)
6月14日、管領義淳の「子息民部大輔他界」と伏見に伝わった(『看聞日記』永享四年六月十四日条)。「民部大輔」は応永32(1425)年11月20日に「武家管領畠山右衛門佐入道満家三男加首服、又左兵衛佐義淳号勘解由小路也、入道殿御一族也、加首服、名字義豊云々、是禅門令相計給也、義字、当時諸人輙不付之也」(『薩戒記』応永卅二年十一月廿日条)、「管領息次男并兵衛佐息、今日元服、参御所、兵衛佐息ハ入夜参」(『兼宣記』応永卅二年十一月廿日条)と、当時の管領畠山満家入道の次男または三男とともに元服した「義豊」に相当する(実際は民部大輔ではなく治部大輔)。貞成入道親王は義豊を「器用之人」(『看聞日記』永享四年六月十四日条)と認識している。父の管領義淳は将軍義教相手にも妥協しない駆け引きを行い得る人物であり(義淳については、被官らの訴え(義淳自身が命じたものであろう)を額面通りに受け止めて、彼を薄弱と評する論もあるが、当然不可である)、その薫陶を受けて成長したのだろう。なお、義豊と同日に元服した畠山満家入道「次男」または「三男」については、系譜上満家次男は持永、三男は持富であるが、いずれとも義持入道から「持」字を下されており、どちらに該当するかは不明。
●斯波武衛系図
+―尼秀清澄心
|(本光院三世)
|
足利高経―+―斯波義将―――+―尼秀晃明仲 +―尼秀雄仙方
(修理大夫)|(治部大輔) (本光院四世) |(景愛寺前住)
| ∥ |
| ∥――――――――斯波義重――――斯波義淳―+―斯波義豊
| ∥ (治部大輔) (治部大輔) (治部大輔)
| ∥ ∥
| ∥ ∥―――――+―斯波義郷―――斯波義健
| ∥ ∥ |(治部大輔) (治部大輔)
| ∥ ∥ |
| ∥ 甲斐教光―+―女子 +―斯波持有
| ∥ |(家女房) (左衛門佐)
| ∥ |
| 吉良満貞女 +―甲斐常治
| (美濃守)
|【民部家】
+―斯波義種―――――斯波満種――――斯波持種―――斯波義孝
(伊予守) (左衛門佐) (修理大夫) (民部少輔)
●畠山系図
畠山基国―+―畠山満家――+―畠山持国―――畠山義就
(右衛門督)|(右衛門督) |(左衛門督) (右衛門佐)
| |
| +―畠山持永
| |(左馬助)
| |
| +―畠山持富―+―畠山政久
| (尾張守) |(弥三郎)
| |
| +―畠山政長
| (左衛門督)
|【能登守護】
+―畠山満慶――+―畠山義忠―――畠山義有
(修理大夫) |(修理大夫) (阿波守)
|
+―畠山持幸
(右馬助)
永享4(1432)年7月20日、今川範政から三浦安芸守が満済に遣わされ、「自今河上総介、今度富士御覧ノ為下向、於分国駿河、御昼ノ休御宿事、任鹿苑院殿御下向例、律院可用意之條如何(今川上総介より、室町殿の今度の富士御覧の御下向に際し、駿河国における御昼の休憩所の事につき、故鹿苑院が下向された例と同じく、律院を用意致そうかと思いますが、如何か)」と問い合わせがあった(『満済准后日記』永享四年七月廿日条)。
このような中で7月25日、義教は「内大臣」に移り(『尊卑分脈』)、8月27日に「将軍大臣御直衣始」を行い(『満済准后日記』永享四年八月廿七日条)、翌8月28日に「左大臣」に転任する(『尊卑分脈』)。翌29日、満済は義教から招請を受けて室町殿へ参向して対面し、義教から「就富士御下向事、関東安房守内々申入状返事被仰付赤松播磨守、其案文一見了、文言少々申意見了(富士御下向の事について、関東の上杉安房守から内々の申入状があり、その返事を赤松播磨守に命じたとして、満済にその案文を渡し、満済は一見して文言について少々意見を述べ)」ている(『満済准后日記』永享四年八月廿九日条)。
8月30日、将軍は満済が詰める月次壇所を訪れて様々に話をしている。義教は「自関東上杉安房守方重注進、今度富士御下向ニ就テ、関東雑説以外、仍鎌倉殿怖畏間、為身用心万一雖五騎十騎候、近所者臨期馳参候者、一向無正体儀可出来歟、後々雑説又不可断候、当年事ハ、平ニ被相延候者、尤以珍重可畏入云々、安房守状、畠山并赤松播磨守方両所ヘ遣也、此状今夕備上覧(関東の上杉憲実から再度注進が到来した。言うところは『今度の富士御下向について、関東では様々に噂されて大変な混乱が起こっています。鎌倉殿持氏も恐れて万一の身の用心のために身辺に五騎、十騎の護衛を配している状態です。近隣の者が鎌倉の危機と感じて馳せ参じた場合はもはや収拾がつかなくなり、風聞だとも言えなくなります。今年はどうか御下向を延期頂ければありがたい限りです』と言ってきている。この安房守状は畠山満家入道と赤松播磨守満政のもとに遣わされていて、夕方に持ってきたものだ。)」(『満済准后日記』永享四年八月卅日条)という。憲実は、8月中旬に鎌倉から二通の御下向延引を願う書状を送っていたことがわかる。
9月2日、「抑室町殿、明日東国へ下向可被富士御覧云々、管領遠江分国之間、為用意一両日以前下向、此事管領前管領畠山被仰談之処、枝葉ノ御事と諫申、仍御詠一首、両人ニ被遣(室町殿は明三日に富士御覧のために東国へ下向とのことで、管領は遠江国守護であることから、受入用意のために今日明日に遠州下向を管領と前管領畠山満家入道に仰せになったが、管領と畠山入道は、憲実からの書状を読んで東国下向は延引されるべきと考えており、一両日以前の下向など枝葉の事ですと諫めた。すると室町殿は一首を詠んで、管領義淳と前管領満家入道に示した)」(『看聞日記』永享四年九月二日条)。その一首は以下の通り。
これを聞いた人々はその意趣に「感嘆」した。和歌に深く理解を示す義教の真骨頂だが、これには駿河下向に反対していた管領義淳も畠山満家入道も含め、義教の信念が「是程被思食上ハと申て令治定(室町殿のお考えがそこまで深いのであれば仕方がない、と述べて決定)」し、富士御覧の駿河下向は治定された。しかし、二度にわたる関東管領上杉憲実からの愁訴も考慮され、「但関東ニ有物言、此時下向、種々有沙汰云々、仍諸大名御前評定、延否未定(関東管領憲実から意見が出されており、(和睦が成ったばかりで都鄙が安定していない)この時期の下向を聞いた関東では、いろいろ憶測が取沙汰されているという。そのため、下向の時期について畠山左衛門督入道ら定例の諸大名が呼ばれ、室町殿も出席して評定が行われたが、延引の可否は決定できなかった)」(『看聞日記』永享四年九月二日条)という。その内容は「関東有物言、御下向不可然之由、畠山申留、然而■赤松等申勧御下向云々、関東存野心可有恐怖事歟、数日之儀枝葉事也(関東から御下向につき意見が来ているが、やはりこの時期の御下向はよろしくないと畠山満家入道が述べた。ただ、赤松満祐入道らは御下向を勧めた。関東に野心があるから恐れているのではないか。数日出立を延引するくらいは大したことではない)」(『看聞日記』永享四年九月十日条)とあるように、有司らの意見もまた割れていたことがわかる。ただし、議論は時期を決めない無期延引(畠山満家入道や関東上杉憲実からの歎状)ではなく、数日の延引での妥協案を探るものであり、畠山・上杉の無期延期論ははじめから除外されていたのである。すでにホスト役の駿河守護今川範政も駿河に下向し、留守居などの手配や供奉の人選なども済ませているこの巨大プロジェクトを事実上中止にすることは、将軍権威の事からも不可能であったろう。
その後、月次壇所の満済のもとに評定に参加した「畠山、細河、山名、赤松、細河讃岐等同道来」で、「富士御下向定日等、可相尋在方卿之由」を告げている(『満済准后日記』永享四年九月二日条)。これは本来は評定で決定すべきであったことだが一決できなかったので、陰陽師賀茂在方卿に下向日等について尋ねるよう満済に依頼したものだった。
下向日については陰陽師賀茂在方に事前に満済を通じて相談しており、結局、当初の計画通り9月3日を下向の初日と決定するが、この日は夜に「将軍富士御下向御門出、渡御畠山亭、一夜御座也、御旅装束御体云々、供奉者ハ悉上下体如常云々、此事内々御尋事在之(義教将軍は富士御下向の門出の儀を行い、畠山亭に渡御して一夜逗留した。将軍は旅装束、供奉の人々は普段着という。出立の儀は内々に在方卿にお尋ねになったものだ)」という(『満済准后日記』永享四年九月三日条)。つまり、9月3日はあくまでも予定通りに「門出」するが、実際の離京は様々考慮して、数日の延引と決定したのである。この延引は間違いなく関東管領上杉憲実の歎願を受け容れた京都側の譲歩であろう。なお、実際に9月10日の離京が決定されたのは、満済が義教から直接進発日を聞いた9月8日であろう。
翌9月4日、義教は畠山亭から御所に入り(帰還ではなく旅程の経由地の一つという扱い)「将軍渡御壇所、御加持申了」し(『満済准后日記』永享四年九月四日条)、9月8日、満済は「明後日御進発之由申了」し、義教から「禁裏事、常ニ可聞申入旨」と、留守中の「禁裏仙洞御番衆」は「三條前右府以下被定置了」ことを伝えられ、満済に留守の仔細を伝えている。
9月8日、義教は貞成入道親王に松茸などを贈っているが、その際に関東下向について「明後日、富士御下向必定云々、諸大名先陣下向」(『看聞日記』永享四年九月八日条)と伝えている。翌9月9日にも義教は貞成入道親王に松茸などを贈り、幼少の後花園天皇へも進呈を依頼している。このときに「明日富士下向御物忌最中、送賜之条、快然之至、今日殊祝着無極」と見え、義教は9月4日の室町殿入御から10日までは「御物忌」として外出を控えていた様子がうかがえる。
そして9月10日、「将軍富士御下向、辰初歟御進発」(『満済准后日記』永享四年九月十日条)、「室町殿、早旦東国下向」(『看聞日記』永享四年九月十日条)した。「折しも秋の雨日来ふりつゞきて、はれまもみえ侍らざりしが、御立の暁よりいつしか空のけしきすみわたり、のどやかなりしぞかつゝゝ有がたくおぼえ侍る」(『覧富士記』)というように、前日までは長雨が続いていたが、10日明方には晴れ間が広がったようである。『満済准后日記』によれば9月の京都は6日、7日、9日が雨と記録されている。
義教に供奉した武家は「武家諸大名大略参」り、武家以外では「御共、飛鳥井中納言、藤宰相入道、三条宰相中将、永豊朝臣、常光院等」(『看聞日記』永享四年九月十日条)とみえる。なお、ここに見える「諸大名」とは管領義淳、畠山満家入道、細川持之、山名時熈入道(山名入道蘭真)、赤松満祐入道、細川持常ら武家有司を指し、不特定多数の諸国武士・大名を指しているわけではない。この「諸大名大略参」から多くの大名が追討軍のように軍勢を率いたという認識は誤りである。この下向には相伴衆、奉行衆ら義教近臣(山名中務太輔熈貴、細川左馬頭持賢、一色左京大夫持信、細川下野守持春らの名が見える)、外様では美濃守護・土岐大膳大夫持頼も加わっている。また、この「諸大名」のうち「赤松為侍所之間、御留守京都警固申」(『満済准后日記』永享四年九月四日条)とあり、赤松満祐入道は駿河下向には加わっていない。また、検非違使別当広橋中納言兼郷も供奉予定だったが、実子で故日野秀光の家督を相続していた「小童八歳」が「万死一生」の重病に陥ったため、京都に留まることとなった(なお11日「広橋子息死去云々、大理悲歎不便々々」という。『看聞日記』永享四年九月十一日条)。
駿河下向の道程は、室町殿を出て蹴上から山科へ抜け、近江路を関ケ原方面へと進むルートであった。満済は休息地と思われる「篠宮河原(山科区四ノ宮垣ノ内町周辺)」へ見送りに出たが、「只将軍御出以後也、供奉人等少々見物了(ただ、将軍はすでに出立したあとで、供奉人等の列を少し見物した)」とあり、見送りには失敗している。鎌倉方の史料でも「九月十日、公方為富士高覧、自京都下向」(『鎌倉大日記』永享元年条)と見える。
供奉した飛鳥井中納言雅世や常光院堯孝はその途路で旅心を歌に詠んでおり、義教もまた多くの歌を懐紙に記していたようである(還御後に同道の奉行等が取りまとめたか『左大臣義教公富士御覧記』が成立し、今回の下向の世話役となった駿河守護今川範政へ秘書として下されている)。その旅程は以下の通り。また、この道程は逐一同道の有司や大名など京都へ伝えていたとみられ、山名時熈入道や土岐持頼の知らせが京都へ届けられている。
●凡例
飛…『富士紀行』(飛鳥井雅世)
堯…『覧富士記』(常光院堯孝)
義…『左大臣義教公富士御覧記』(奉行の随従手記か?)
富…『富士御覧日記』(奉行の随従手記を元に駿河部分のみ抄出され、宗長から今川家へ書状とともに渡されたか)
| 日付 | 場所 | 現在地 | 歌 | 作者 |
| 9月10日晴 | 逢坂関 |
大津市横木1-2 (中山道) |
(今曉まかり立侍りしに、相坂の関をこえ侍とて) 思ひたつ心もうれしたひ衣 きみか恵にあふさかのせき (今曉より雨はれて空も心よくみえ侍りしかば) 秋の雨の遥々思ふふしのねは けさよりやかて空もへたてし |
飛 |
| (逢坂越侍とて関の明神のあたりにて) 君か代にあふやうれしき相坂のせきに関守神のこゝろも |
堯 | |||
| (逢坂にて関送りの人に聞こえさせ給ふとて) 今君が道ある御代に逢坂の関送りする雲の上人 帰り来てまた逢坂と思ふにぞ人遣りならぬ旅もするかな |
義 | |||
| (眺望) | 大津市逢坂一丁目付近か | (あけぼのゝ雲まより三上山ほのみえ侍る、ふじのね思ひやられて) 思ひ立ふしのね遠きおもかけは近く三上の山の端の空 |
堯 | |
| 草津 | 草津市草津一丁目付近 | (草津と申所にて) 枕にはむすはてすきつ旅ころも草つの里の草の袂を |
飛 | |
| (草津の宿にて) 近江路や秋の草つはなのみして花咲のへそいつくともなき |
堯 | |||
| 野洲川 | 守山市焔魔堂町付近 | (やす川にて) 我君の御代にあふみちけふもはや渡る心ややす河の水 |
飛 | |
| (やす河のあたりに御よそほひを見奉らむとて、そこらつどひゐたり) をのつから民の心もやす河になみゐて君の光をそまつ |
堯 | |||
| 守山 | 守山市内 | (守山のほとり田のもはるかにみわたされて) しつのめか田面のいねをもる山の梢も今そ色付にける |
飛 | |
| 鏡山 | 近江八幡市武佐町の道中 | (かゞみやまをみて) 老の坂はこえかゝるかゝみ山今さらなにか立よりてみむ |
飛 | |
| むさ (宿) |
近江八幡市武佐町 | (今日の御とまりはむさの淑とかやなり 都より十三里) | 堯 | |
| 9月11日 晴 |
老曾杜 | 近江八幡市安土町東老蘇1615 | (いまた夜ふかきに、老曾杜はこゝのあたりと申侍りしかば) 明けやらぬおいその杜の薄紅葉いまは夜ふかき色かとそ思ふ |
飛 |
| (いとよく晴れて、武佐の宿を立たせ給ふ) 旅衣今宵寒さを身にしめて賤が伏屋を思ひこそやれ |
義 | |||
| 山の前 | 近江八幡市安土町石寺か | (山のまへとかや申所にて) しつのめか通ふいへゐも稀なるや麓の山のまへのたなはし |
飛 | |
| (つぎの日夜ふかく、山のまへと申所すぎ侍るとて) 月もかな秋霧ふかきあし曳の山のまへのゝしのゝめの道 |
堯 | |||
| 四十九院 | 犬上郡豊郷町四十九院 | (四十九院の宿を) 四十余りこゝのあたりの里の名は大和ことはにいかゝ残さん |
堯 | |
| 犬上 | 犬上郡甲良町尼子 | (犬上と申里にて) をのつからとかめぬ里の犬上やとこの山風おさまれる世に |
飛 | |
|
(犬上と申あたりにて、いさや河はいづくにてかとたづねはべれども、さだかにこたふる人もなし、里のゆくてに山川のすゑかすかに見えたる所あり、是ならむかしとをしはかりて) いさといふなになかれたる川音やとへといはねの水の白波 |
堯 | |||
| 小野 | 彦根市小野町 | (小野の宿にて) 吹にけりわけ行袖の露霜もみにしむ秋のをのゝ山かせ |
堯 | |
| 二本杉 | 彦根市鳥居本町付近 | (二本杉と申所にて) ふたもとの杉とて又もあふみちにふる河のへを思ひ出らし |
飛 | |
| すりはり峠 | 彦根市山中町 |
(すりはり峠をかずもしらずこえ侍る人のたゞ人かたにいそぐも山みちつゞらおりにて、行ちがふやうにぞ見え侍し) 心せよ行かふ旅のもろ人もそてすりはりの山のかけちそ |
堯 | |
| 不破の関 | 不破郡関ケ原町 | (不破のせきは苔むして、板びさしもしるしばかりみえ侍りければ) 板ひさし久しき名をは猶みせて関の戸さゝぬふはの中山 |
飛 | |
|
(不破の関すぎ侍しに、もるとしもなきせきのとぼそ、苔のみふかくて中々みどころ有) 戸さしをは幾世忘れて斯く計苔のみとつるふはの関やそ |
堯 | |||
|
(美濃国に着かせ給ひ、不破の関屋を訪ねさせ給ふけるに、この旅の御為にとて、古き関屋を改め、白々と造り立てたるをご覧じて、都にて思し召したるとは相違しければ、こはいかにと問はせらるるに、国主より御道のもてなしに、かくの如くと申すを聞こし召し、上意殊の外悪しかりけるが、されど御歌出できて、ことに仰せ下されける) 葺き替へて月こそ漏らぬ板廂とく住み荒らせ不破の関守 |
義 | |||
| たる井 | 不破郡垂井町 | (たる井と申所につき侍て) 里人もくみてしらすやけふ爰にたるゐの水の深き恵みを |
飛 | |
| (たる井の宿ちかくなりて) むかしみし影をしるへに又やわれ思ふたるゐの水を結はむ (おなじ御とまりにて むさより十四里) みの山や松は一木のかけにしも旅ねかさなる千代の秋かな |
堯 | |||
| (垂井宿) (宿) |
不破郡垂井町 | (暮れて、垂井の宿に留まらせ給ふける、垂井を結ばせ給ふに、いと清かりければ) 濁りなき御代の例しに汲みて知る垂井の水の清く清さを |
義 | |
| 9月12日晴 | あひ川 | 不破郡垂井町 | (夜をこめて、あひ川と申所過侍しに) 末とをき世にあひ河の岩浪のちとせを越る音のさやけさ |
堯 |
| あをのが原 | 大垣市青野町 | (夜をこめて、あをのが原と申所を過るとて) 草のはの青野か原もみえわかて夜ふかく分る露そ寒けき |
飛 | |
| (青野が原とかやにしかのねかすかにきこゆ) 鹿そ鳴青野か原のあをつゝらくもしられぬ妻をうらみて |
堯 | |||
| (夜をこめて立たせ給ひ、青野ヶ原にて鹿の鳴くを聞こし召されて) 鹿の鳴く青野ヶ原の青葛苦しくもあるか妻を恋ふとて |
義 | |||
| 赤坂 | 大垣市赤坂町 |
(赤坂と申所にて、いまだ夜も明侍らず、友なひ侍る人々も跡におくれ侍をしばしまち侍しほどに) 行つれぬ友さえ跡に残るよをしはしやこゝにあかさかの里 |
飛 | |
|
(赤坂の宿にて) おりに逢あきの梢のあか坂に袖ふりはへていそく旅人 |
堯 | |||
| (道すがらともなひ侍る人のもみぢしたるつたをいかゞみるとてをくり侍りしに) かつみても袖にそあまるまたこえぬうつの山路の露の行ゑは |
堯 | |||
|
(いづくにて侍しやらむ、霧わたれるひまゝゝよりいなばほのかにみえて、秋の空さへえむなるに鴈つれてとぶ) 秋寒く田のものいなは鴈そ啼霧の朝けの空もほのかに |
堯 | |||
| くゐせ川 (追分) |
大垣市赤坂新町 (美濃路へ入る) |
(くゐせ川わたるとて) 夕されは霧たとゝゝし河の名のくゐせもとめて舟や繋かん |
堯 | |
| 笠縫つゝみ | 大垣市河間町の堤防 | (かさぬひつゝみといふ所にて) 手にもてる笠縫つゝみ行つれてこととひかはすけふの旅人 |
堯 | |
| 長橋 | 大垣市小野三丁目 | (なか橋と申所を過侍るに、あたりの田のもゝ遠く見わたされて) 秋深き田面に続くなか橋はほなみをかけて渡すとそみる |
飛 | |
| (ながはしときこゆるは、げにぞはるゞるとみわたされたるにや) 数ならぬみのゝ長橋なからへて渡るも嬉しかゝるたよりに |
堯 | |||
| 中川 | 大垣市東町一丁目 | (中川と申所にて) 都より流れ出ける末なれや今はた渡る中川のみつ |
飛 | |
| 結の町屋 | 安八郡安八町西結付近 | (むすぶのまちやとかや申所にて) 朝露の結ふのさとのたひ衣わくる草葉も色かはるらし |
飛 | |
| (むすぶの町屋と申所にて) 露霜のむすふの町や夜をこめて立あき人も袖や寒けき |
堯 | |||
| (結の町屋を過ぎさせ給ふとて、人多く立ちて見奉れば) 昔誰道の枝折りの跡止めて結の町屋人の住みけん |
義 | |||
| すのまた川 | 大垣市墨俣町墨俣 |
(すのまた川は興おほかる處のさまなりけり、河のおもていとひろくて、海づらなどのこゝちし侍り、舟ばしはるかにつゞきて、行人征馬ひまもなし、あるは木々のもとたちゆへびて、庭のをもむきおぼゆるかたもあり、御舟からめていてかざりうかべたり、又かたはらに鵜飼舟などもみえ侍り、一とせ北山殿に行幸のとき、御池に鵜ぶねをおろされ、かつら人をめして、気色ばかりつかふまつらせられ侍し事さへに、夢のように思ひ出され侍る、それよりほかにかけても見及侍らぬわざになむ) 嶋つとりつかふうきすのまたみねはしらぬ手縄に心ひく也 おもひ出る昔も遠きわたり哉その面かけのうかふ小舟に |
堯 | |
| をよひ河 | 羽島郡笠松町北及辺りを南北に流れていた川。木曽川と合流か。 | (尾張国をよひ河にて) わか君のめくみや遠くをよひ川ゆたかにすめる水の音かな |
堯 | |
| おり津 (宿) |
稲沢市下津町東国府 | (おり津の御とまり、たるゐより十里) ※尾張国府の地で、宿場。本日の宿所) |
堯 | |
| (今宵は下津に留まらせ給ふ、里の名の下津といふに思し召しあはせられて) この里に宿り求めて来しよりも下津といひし名にも背かず |
義 | |||
| 9月13日晴 | おりつ | 稲沢市下津町東国府 | (尾張国おりつと申所を夜ふかくたち侍るとて) 夢路をも急ききにける旅なれや月に仮ねの夜をおりつまて |
飛 |
| かいづ | あま市中萱津 | (かいづなど過て) | 飛 | |
| 熱田 | 名古屋市熱田区神宮一丁目 | (あつたの宮を過侍るほどにかの社頭の鳥井の前にて) 神垣も光そふらしうこきなきよもきか嶋に君を待えて |
飛 | |
|
(熱田のみやの神前にまうでて、御道すがらの御祈など申侍き、むかし日本武尊東夷征伐のため、このさかひにをもむきたまひし時、よぎり道し、伊勢太神宮にして大和姫命にまかり申したまひしに、命のさづけたまひし霊剣も此神殿にとゞまらせおはしますとかや、いとやむごとなき神明、鎮護国家のちかひもたのもしくおぼえ侍りて) なをまもれめくみのあつたの宮柱立ことやすき旅のゆきゝを |
堯 | |||
| 蓬莱の嶋 ※かつて鳴海潟に突き出ていた熱田神宮の杜を指す。 |
名古屋市熱田区神宮一丁目 |
(蓬莱の嶋をみて) 君かため老せぬ薬ありといへはけふや蓬か嶋めくりせん |
堯 | |
| なるみ潟 | 名古屋市熱田区神宮~名古屋市緑区鳴海町一帯に広がっていた広大な干潟 |
(なるみがたのほとり海づらにつゞきて野あり、これぞうへ野なるらむとおぼえ侍て) あさ日さすなるいの上野塩こえて露さへ共に干潟とそなる (又おもひつゞけ侍ける) 道の為我思ふことのなるみ潟願ひみちくるしほせともかな |
飛 | |
|
(なるみがたにて) 忘れしな浦かせさむくなるみかた遠き塩ひの秋のけしきは |
堯 | |||
|
(鳴海の浦にて、波風の音を聞かせられて) 波の音も荒く鳴海の浜久木風にしほるる旅の衣手 |
義 | |||
| 星崎 |
名古屋市南区本星崎町 ※こののち、東海道から歌枕の二村山を通る道へ移った |
(星崎と申所にて、今日は名月なり、空も心よく晴て、月もなをえ侍ぬとみえしかば) ほし崎や熱田の方の空はれて月もけさよりなこそしらるれ |
飛 | |
| (夜寒の里) |
名古屋市熱田区夜寒町 ※夜寒の里は熱田神宮北隣ですでに通過しているが、雅世、堯孝ともに具体的な場所は往復ともにわからなかったようだ。 |
(夜さむの里と申も此国と聞侍しかば) よしさらは宿りとらしと旅衣よさむの里をよきてこそゆけ |
飛 | |
|
(夜寒の里はこの国ぞかしとおもひ出侍て) うき身にはいつもよ寒の里なれて今更秋の旅ねともなし |
堯 | |||
| 二村山 |
豊明市沓掛町皿池上 |
(二村山の薄紅葉をご覧ぜられて) 染め残す半ば紅葉の唐錦名にし負ひたる二村の山 |
義 | |
| さかひ川 | 刈谷市今川町阿野前 |
(さかひ川をみて) それときくしるしはかりか堺川ほそき流れは名に流れても |
飛 | |
| 八橋 | 知立市八橋町 |
(参河国八橋にて) 八橋のくもてに渡るひまもなし君かためにといそくたひ人 |
飛 | |
|
(三河国八はしにいたり侍て、はるゞるきぬるとながめ侍し往躅もおもひ出されて、そゞろに過がてにぞおぼえ侍し) 聞わたるくもてゆきかし八橋をけふはみかはす旅にきにけり |
堯 | |||
|
(八橋の宿にて) 富士見んと思ひ三河の八橋をかねて心にかけ渡るかな |
義 | |||
|
(今夜は十三夜なり、名におふ月のひかりさやかなるにも、富士のねさこそといそがれて) ふしのねに侍みむかけそ急かるゝ今宵な高き月をめてしも |
堯 | |||
|
(けふすぎつるほし崎など思ひ出らる) 月影のわか住かたもはるゝよにほしさき遠くおもひ出つゝ |
堯 | |||
| 矢矧の里近く |
(矢矧の里近く成て、道のかたはらにまゆみのもみぢたるを見侍て) 道のへのまゆみのかた枝紅葉して爰や矢矧の里とみゆらむ 我君の治れる代はあつさ弓ひかハやはきのさとにきにけり |
飛 | ||
| 矢矧 (宿) |
岡崎市矢作町宝珠庵 |
(今夜の良辰月もことにくもりなく晴て、名をあらはし侍ぬること、千載之一遇、万秋之芳躅、めでたくおぼえ侍ければ) 君か代はなをなかつきの月の名も所からにそ光りさしそふ (おなじく此處にて三条相公羽林、続歌十三首を講じ侍しに題をさぐり侍て) 名所山月 雲もきえ霧もはれ行秋のよになのみ二むらの山のはの月 名所里月 秋ふかき夜半のころもの里人は月にめてゝも月や寒けき 名所浦月 さそなけに今宵の空の清みかたみぬ俤も波の上の月 名所潟月 過きつる跡になるみの塩ひかた心をさそふ夜半の月かな 夜月忍恋 やとさしな涙の露もよるこそとおきゐて思ふ袖の月かけ |
飛 | |
|
(やはぎの宿御とまり、おりつより十二里、三條相公羽林のやどにまうでて、飛鳥井黄門など題をさぐりて歌よみ侍しに) 名所野月 あはつのゝ露わけ初てあつまちやいく草枕月になれ剣 名所関月 忘れしよ苔ふかかりし軒端にも月やみるらんふはの関守 名所橋月 恋わたる昔をかけて八橋にはるゝゝきてもみつる月かな 寄月祝言 いく秋か我君か代も長月やなにふる月の霜をかさねん |
堯 | |||
|
(暮れて、矢作の馬屋に留まらせ給ふ) 治まれる世にも矢作の里の名は我が身の上に引きてみよとや (今宵は名月なれば、夜更くるまで起き居させ給ひて) 長月の十日余りの三河路に射るや矢作の川波の月 |
義 | |||
| 9月14日晴 | 矢矧 | 岡崎市矢作町宝珠庵 |
(つとめて此御とまりを立侍とて) のとかなるやはきの里は日の光出入まての名にそ有ける |
堯 |
| 豊川 |
岡崎市大平町瓦屋前 ※乙川(大屋川)を豊川と想像した可能性がある。ただ、義教はこの川を「大屋川」と認識していることから(『左大臣義教公富士御覧記』)、このとき堯孝は義教の傍にいなかったと推測される。 |
(こゝの御とまりを立侍しに川あり、これや豊川と申わたりならむとおぼえて) かり枕いまいく夜有て十よ川やあさたつ浪の末をいそかむ |
飛 | |
|
(大屋川を渡らせ給ふとて) 我ならぬ誰が濡れ衣をおふや川干すとしもなき瀬々の岩波 |
義 | |||
| 宇治川のさと | 岡崎市藤川町 |
(宇治川のさとゝ申所にて) 誰か住みやこのたつみしかはあらてこは東路のうち川の里 |
堯 | |
| (衣の里) |
豊田市挙母町 ※雅世は拳母の具体的な場所は知らないが、この辺りだろうと詠んだ歌。 |
(衣の里ときゝ侍しも、此あたりやらむと覚えて) 賤のめかうつや衣の里のなを吹秋かせのつてにしらせよ |
飛 | |
| 山中 | 岡崎市舞木町山中町 |
(山中と申所あり、折ふし鹿のこゑほのかにきこえければ) おぼつかなこの山中になく鹿のたつきもしらぬ聲の聞ゆる |
飛 | |
|
(山中の宿にて御ひるまのほどにぎはゝしさもかぎりなし) 旅ころもたつきなしとも思はれす民もにきはふ山中のさと |
堯 | |||
|
(宮路山の山中の里にて) 旅人の行く春秋の花紅葉さそな宮路の山中の里 |
義 | |||
| 関口 | 豊川市長沢町木ノ田 |
(此つゞきに関口と申所あり) 道ひろく治まれる世の関口はさすとしもなく守としもなし |
堯 | |
|
(関口といふ所を過ぎて赤坂の宿に着かせ給ふ。宿のうちに人多く見奉れば) 関口も今日赤坂の里にこそ戸さゝぬ君か御代そ知らるれ |
義 | |||
| (花ぞの山) |
豊田市花園町観音山? ※花園山の場所はわからないがこのあたりと聞いていた雅世が詠んだ歌。 |
(花ぞの山はいづくにてか侍らむとおぼえて) 旅衣いさ袖ふれん秋の草の花その山の道をたつねて |
飛 | |
| (引馬野) |
浜松市中区元城町 ※引馬野は遠江国にあることは聞いていたが、場所は不明として詠んだ歌。 |
(引馬野も此国ぞかし、いづくならむと分明ならねど) たひ人ののるより外もひく馬のゝ野への秋萩花やみたれむ |
飛 | |
| 今八幡 | 豊川市八幡町宮前 |
(いづくの程にて侍しやらん、社壇あり、人にとひ侍ば八幡宮と申、鳥井の前にて今度の御旅のめでたさ、御神慮も殊に掲焉におぼえ侍て) いはし水君が旅行すゑも猶まもらむとてや跡をたれけん |
飛 | |
|
(今八幡と申鳥井の程にて) 君まもる契しあれは今やはたいまゝてこゝに跡やたれけむ |
堯 | |||
|
(国々所々の御路次、兼日用意のほどもみえて、いづくもさはる所なく、御路つくらせ侍りけるとみえしかば) 民やすく道ひろき世のことはりも猶末遠くあらはれにけり |
飛 | |||
| (高師山) |
豊橋市大岩町火打坂 ※堯孝が高師山の場所が不明ながら、このあたりと思って読んだ歌。 |
(高師山と申も此あたりにてやとみえて) 富士のねに及はぬ名のみたかし山高しとみるも麓なるらし |
飛 | |
| 今橋 (宿) |
豊橋市今橋町 |
(いまはしの御とまりにて、やはぎより八里、あかず明行月をみて) 夜とゝもに月すみ渡る今橋や明過るまて立そやすらふ |
堯 | |
| (申の下がりに今橋の馬屋に留まらせ給ふ) | 義 | |||
| 9月15日晴 | 今橋 | 豊橋市今橋町 |
(いとよく晴れたり。夜をこめて立たせ給ふ、豊川の橋にて) 今橋の架かれる御代に会ふことを忘れす渡れ豊川 |
義 |
| 大岩山 | 豊橋市雲谷町ナベ山下7の大岩山普門寺 |
(大いは山とかやのふもとを過侍に、ふりたる寺みえ侍り、本尊は普門示現の大士にておはしますよし申侍しかば、しばし法施などたてまつりし次) 君か代は数もしられるさゝれ石のみる大岩の山となるまて |
堯 | |
|
(大岩山普門寺の観音を額づかせ給ひて) 動きなき大岩山に君か代をなそらへ守れ南無や観音 |
義 | |||
| 高師山 | 湖西市新所岡崎梅田の崇山(すやま)か。「崇」は「たかし」と訓ず。 |
(高師山を越えさせ給ふとて、鹿の音を聞かせ給ひて) 霧晴るゝ方に梢や高師山鹿の音送る峰の松風 |
義 | |
| (二むら山) |
豊明市沓掛町皿池上 ※二村山は順路としては鳴海干潟の次に位置し、義教もその順で記す(『左大臣義教公富士御覧記』)。おそらく堯孝がまとめた際に誤ったものと思われる。 |
(二むら山越侍るとて) けふこゆる二むら山のむらもみちまた色うすし帰るさにみむ |
堯 | |
| 二子塚 | 湖西市神座247の神座古墳群(嵩山麓)か |
(又今日二子づかと申所にての御詠とて、同下され侍し次に) 富士をみる此ことの葉に顕れて名に立ちのほる二子つかかな |
飛 | |
|
(二子づかと申侍し所にて富士を御覧じそめられたるよし仰せられて) たくひなきふしをみ初る道の名を二子塚とはいかていはまし (これについで又申入侍し) 契りあれやけふの行手の二子坂爰よりふしを相みそめぬる |
堯 | |||
|
(この国の守より富士の見え初むる所に印のためとて二つの塚 を築かれたりければ、これより富士をご覧ぜられて) 類なき富士を見初むる道の名を二子塚とはいかて言はまし (とあそばされて人々に賜はる) 御返し 飛鳥井雅世卿 富士を見るこの言の葉にあらわれて名に立ち上る二子塚かな 御返し 常光院堯孝法印 契りあれや今日の行く手の二子塚ここより富士をあひ見初 めぬる 御返し 山名中務太輔熈貴 富士見ては高しと思ひし高師山今はふもとの二子塚なり 御返し 細川左馬頭持賢 高師山高しと思ふ二子塚富士に比べて君そ名付くる |
義 | |||
| 塩見坂 | 湖西市白須賀 |
(遠江国塩見坂にて御読を下され侍しに) しほ見坂さか行君にひかれてそさらに名高きふしを眺むる |
飛 | |
|
(今日なむ遠江国塩見坂に至りおはします、彼景趣なをざりにつゞけやらむことのはもなし、まことに直下とみおろせばといひふるしたるおもかげうかびて、雲のなみ煙の浪、そこはかとなき海のほとり、松ばらはるゞゝとつづきたるすさき、かずもしられずこぎつらねたる小舟、いとみどころおほかり、雲水茫々たるをちかたに、富士のねまがひなくあらはれ侍り、これにて御筆をそめられ侍し御詠二首) 今そはやねかひみちぬる塩見坂心ひかれしふしをなかめて 立かへり幾年なみか忍はまししほみ坂にてふしをみし世を (かたじけなく御和を奉るべきよし仰ごと侍しかば) ことのはもけにそ及はぬ塩見坂きゝしに越るふしの高根は 君そなほ万代とをくおほゆへき富士のよそめのけふの面影 |
堯 | |||
|
(塩見坂より富士をご覧ぜられて御詠) 今そはや願ひ満ちぬる塩見坂心ひかれし富士を眺めて (また御詠を各々に賜はる) 御返し 三條実雅卿 時しあれは君に引かれて今日そ今日富士の願ひもみつ塩見坂 御返し 山名入道蘭真 たとり来て遠とほつあふみ江に富士を今日見つるに満つる塩見坂かな 御返し 飛鳥井雅世卿 塩見坂栄ゆく君に引かれてそさらに名高き富士を眺むる 御返し 常光院堯孝 言の葉もけにそ及はぬ塩見坂聞きしに越ゆる富士の高嶺は (また御詠ありて下さる) 立ち返りいく年並みか忍はまし塩見坂にて富士を見し世を (御和いたすべき由、仰せごとあれば、また) 君そなほ万代遠く覚ゆべき富士のよそ目の今日の面影 |
義 | |||
| 白菅の湊 | 湖西市白須賀 |
(白菅の湊にて御詠) 高師山ふもとにありと白菅の湊に呼ばふ船人の声 |
義 | |
| (衣のさと) |
豊田市挙母町 ※順番の誤謬。「衣」は三河国でり堯孝が誤ることはない。また雅世とまったく同じ認識であるため、堯孝は雅世と同道していたとみられ、本来はこの順ではなく宇治川宿の次。 |
(衣のさと此あたりにぞ侍らむ) 名にたてるたひの衣の里ならは露わけきつる袖やかさねん |
堯 | |
| 橋もと (宿) |
湖西市新居町浜名 |
(橋もとの御とまり、今橋より五里、ちかくなり侍り、濱名のはしも此あたりにこそと申をきゝて) 暮わたる濱なのはしは霧こめて猶すゑとをし秋の河なみ |
堯 | |
|
(御泊まりは橋本の宿なり、こゝに浮かれ女多かりければ) 浜名川かけて思ひし橋本の里の浮かれ女浮き名漏らすな |
義 | |||
| 9月16日晴 | 橋もと | 湖西市新居町浜名 |
(橋もとの御とまりを夜をこめて侍しかば、濱名橋をうちわたして) 忘めやはまなのはしもほのゝゝと 明けわたる夜のすゑの川浪 濱名河夜みつしほの跡なれやなきさにみゆる海士の小舟は |
飛 |
|
(はしもとを立て、引馬の宿にもなりぬ、ひくま野は三河国とこそおもひならはし侍るに、遠江に侍るはいかなることにか、あしたの程野を分侍しに、虫のねいとしげし) あかなくにわけこそきつれ虫の音の袖を引馬の野への朝露 |
堯 | |||
|
(橋本の宿を発たせ給ひ、浜松の馬屋にて思し召し続けらる) 四海波静かに吹ける風の音も枝を鳴らさぬ浜松の里 |
義 | |||
|
(時雨けしきばかり過侍しかば) 旅衣しほれたにせぬしくれ哉もみちをいそくけしき計りに |
飛 | |||
| さき坂山 | 磐田市富里周辺? |
(さき坂山と申所にて) 遠くみるふしの高ねもしら鳥のさき坂山をけふこそこえぬる |
飛 | |
|
(鷺坂山にて) 打はふき飛や立けむ白鳥のさき坂山をやすくこえぬる |
堯 | |||
| 遠江の国府 (宿) |
磐田市見付1244付近 |
(遠江の国府に馬宿りし給ひて、遠く来たらせ給ふことを思し召して) 富士見むと都をよそに振り捨てて遠江の国府に来にけり |
義 | |
| 9月17日雨 | 府中 (遠江) |
磐田市見付1244付近 |
(此国の府中を立侍るほどに、かけ川と申所にてあめふり侍しかば) たひ衣そでになみたをかけ川やぬれていとはぬけふの雨かな |
飛 |
|
(遠江府、橋もとより六里、をたちて、雨いたくふり侍しに、懸川と申所にて) うちわたす浪さへ袖にかけ川やいとゝぬれそふ秋のむら雲 |
堯 | |||
| 菊川 ※本来は「さやの中山」の次 |
島田市菊川604辺りか ※菊川は東海道の小夜の中山麓を流れる川であるため、本来は小夜の中山の次となり、飛鳥井雅世の順序違いであろう。 |
(菊かわと申所にて) 汲てしる君か八千代も末とをき名にきく河の花の下水 |
飛 | |
| さやの中山 | 掛川市佐夜鹿324付近の山道 |
(さやの中山を越侍とて) なをさりにこゆへきものか我君のめくみも高きさやの中山 |
飛 | |
|
(さやの中山にて出され侍し御詠) 名にしおへは昼越てたに富士もみす秋雨くらきさよの中山 (おなじく奉りし御和) 秋の雨もはるゝ計のことのはをふしのねよりも高くこそみれ (おなじところにて) 天雲のよそに隔てゝふしのねはさやにもみえすやさの中山 |
堯 | |||
|
(遠江の国府を立たせ給ふ、掛川の宿より雨降り出でて、小夜の中山を過ぎさせ給ふに、かきたれて小止みせねば御詠を賜はる) 名にし負へば昼越えてたに富士も見す秋雨暗き小夜の中山 御返し (『覧富士記』より堯孝と推測) 秋の雨も晴るるばかりの言の葉を富士の嶺よりも高くこそ見れ |
義 | |||
| こままがはら | 島田市金谷坂町か |
(こままがはらとかや申所にて御詠を拝見し奉りて) たくひなくあすみよとてや秋の雨にけふ先ふしの掻曇るらん |
飛 | |
|
(駒ヶ原といふ所にて、なほ雨晴れねば、聖徳太子の召されし黒駒が原を発つべしと秀句あそばされて、御詠を賜はる) 大君の召されし甲斐の黒駒が原を発つへし富士の雨空 御返し 三條実雅卿 厩戸の乗りける甲斐の黒駒の面影にたつ富士の雨の日 御返し 飛鳥井雅世卿 類なく明日見よとてや秋の雨今日待つ富士のかき曇るらん |
義 | |||
| 藤枝鬼巌寺 (宿) ※故義満の富士御覧の際に宿所としており、義教もそれに准じたとみられる。 |
藤枝市藤枝3-16-14 | (かくて駿河国藤枝と申所に御つきあり) | 飛 | |
| (藤枝の御とまり、みつけの府より十一里) | 堯 | |||
|
(申の時ばかりに藤枝の宿、鬼巌寺といふ寺にとどまらせ給ふ) 春はなを花の白木綿かけてまし秋は締め引く縄の藤枝 |
義 | |||
| (駿河国藤枝鬼巌寺に御下着、雨すこし時雨) | 富 | |||
| 9月18日晴 | 藤枝 | 藤枝市藤枝3-16-14 | (十八日のあした、此所をまかり立侍) | 飛 |
|
(夜深く藤枝の御泊まりを発たせ給ひ、岡辺といふ所にて) 一もとの杉の印を標にて分くや岡辺の蔦の下道 |
義 | |||
| (暁方より晴て、月はあり明にて、いそぎ御立) | 富 | |||
| 岡部の里 | 藤枝市岡部町岡部 | (岡部の里を過て) | 飛 | |
| 宇津の山 | 静岡市駿河区宇津ノ谷 |
(やがて宇津山にわけ入侍る程、所の名も其興有ておぼえ侍り、曩祖雅経卿ふみわけし昔は夢か宇津の山跡ともみえぬつたの下道と詠侍し事までおもひ出られ侍て) 昔たにむかしといひしうつの山越てそしのふつたの下みち さと過て又こそかゝれうつの山をかへのまくすつたの下道 |
飛 | |
|
(宇津の山こえ侍れば、雨の名残いとつゆけかりしに) うつの山しくれも露もほしやらて袂にかゝるつたのした道 |
堯 | |||
|
(宇津の山に蔦の紅葉をご覧ぜられて) 都にもさぞな思はん旅衣蔦の紅葉に色や変はると |
義 | |||
| 丸子の里 | 静岡市駿河区丸子7付近 |
(丸子の里にて) 蹴上けては蔦の袴のうらみなし丸子にかかる宇津の山越え |
義 | |
| 手越が崎 | 静岡市駿河区手越原付近 |
(この国の守護今川上総介範政、御向かひに出でらる、御輿よりて来させ給ふ、上総介御手を引き奉らる、手越が崎といふ所にて) 道しある御代に行き来を駿河なる握り手越が先そ知らるる |
義 | |
| 藁科川の渡り | 静岡市葵区牧ヶ谷 |
(藁科川の渡りより、木枯らしの森をご覧ぜられて) 唐錦形見に残せ木枯らしの森の名にしは由やおはすと |
義 | |
|
(この渡り民皆出でて物し奉るとて立ち騒ぎけるを、警護の武士ども制しければ、さな言ひそと仰せられて、多く鯵どもを下されて) とばかりに恵み駿河の安倍の市立ち騒くなよ国つ民人 |
義 | |||
| 駿河府 (宿) |
静岡市葵区駿府城公園付近 |
(斯て此国の国府につき侍り、富士もことにさだかに見え侍しかば) 富士のねの山とし高き齢をも君まちえてや今ちきるらむ (此国の守護上総介範政に御詠を被下侍し次に) 此宿にかゝること葉の玉しあれはふしのみ雪も光そふらし |
飛 | |
|
(ゆきゝゝて、けふぞ駿河府、藤枝より五里、にも至り侍りぬる、千里始足下高山起微塵ためし思ひしられ侍り、この国の守護今川上総介範政、御旅のおまし、かざり、ゐたち、けいめいし侍るうちにも、雪のつもれらむすがたを上覧にそなへ侍らばやとねんじわたりけるに、昨日の雨彼山の雪なりけり、今日しも白妙につもれるけしき、富士権現もきみの御光をまちおはしましけるとみえて、あやしくたうとくぞおぼえ侍る、山また山をかさねて、たなびきわたれる雲より上にかゞやきみえたる遠望たぐひなくこそ) 白雲のかさなる山も麓にてまかはぬふしの空にさやけさ わか君の高き恵みにたとへてそ猶あふきみるふしのしは山 (これにてあまたあそばされ侍し御詠のうち) 見すは爭て思ひ知へき言のはもおよはぬふしと豫て聞しを (この御和) 言の葉を仰かさねて富士のねの雪もや君か千代をつむらし (夜もすがら、月にかの山を御らむじあかして) 月雪の一かたならぬなかめゆへふしにみしかき秋のよは哉 (おぼろげに御和など奉るべき御詠にし侍らねど、また仰ごとのいともかしこくて) 富士のねや月と雪とのめうつりもあかす珍し君かことのは |
堯 | |||
|
(安倍の市を府中といふ、ここに今川上総介範政、この旅の御ためにとて造られし、富士見の御所に迎へ奉る、道すがら賤機山をご覧ぜられしに、紅葉今盛りなれば) 折りかかる紅葉の錦賤機の山の秋風心して吹け |
義 | |||
|
(同十八日府中、先小野縄手にして御輿たてられ御覧じて、前後左右とよみあひ、御跡はいまだ藤枝、五里のほど何とはなくつたへゝゝ山も河もひゞきわたりけるとなん、御着府、すなはち富士御覧の亭へすぐに御あがりありて) みすはいかに思しるへき言の葉も及はぬふしと予て聞しも 御返し 従四位源範政 君かみむけふのためにや昔よりつもりはそめし不二の白雪 |
富 | |||
| 9月19日晴 | 国府 (駿河) |
静岡市葵区駿府城公園付近 |
(翌朝の御詠) 朝明のふしの根おろし身にしむも忘れはてつゝなかめける哉 あさ日影さすより富士のたかねなる雪も一しほ色増るかな 御和 雲はらふふしのねおろし吹やたゝ秋の朝けのみにはしむとも なをさりのけしきならすよ朝日影雪に移ろふふしの高ねは |
堯 |
|
(猶此所、又御詠を数首拝見し奉りて) ふしのねの月と雪とに明す夜や君かことはの花をそへけむ 忘れめやくもらぬ秋の朝日影雪ににほへるふしのなかめを 朝明のふしのねおろし身にしめて思ふ心もたくひやはある (富士の高根に雪のかゝり侍るが、綿ぼうしに似侍るよし、御詠にあそばされ侍りかば) 雲やそれ雪をいたゝく富士のねもともに老せぬ綿ほうし哉 (又御詠を被下侍しほどに) 都よりはるゝゝ来てもふし川や行としなみは猶そかさねむ |
飛 |
|||
|
(あさざむなるほどにて御わたぼうしをせられ侍しに、おりしも富士の根にくも一むらかゝりて、さながらぼうしのやうに見えけるを、御わたぼうしにおほしめしなずらへて) 我ならすけさはするかのふしのねに綿帽子ともなれる雪哉 御和 富士のねにかゝれる雲も我君の千世を戴く綿ほうしかも 又御詠 いつくとも忘れやはするふし河の浪にもあらぬけさの眺は 嬉しさも身にそあまれる富士のねを雲の衣の外になかめて 同御和 富士川の浪もいく世かかけまくもかしこき影を仰き渡らむ ふしのねや心にこめむつゝみえぬ雲のま袖はかきり有とも (此山の由来たづねきこしめしけるに、そのかみ壬子年とかやに出現の由、守護注申侍しに、ことしの干支相応、奇特におぼしめされて) かゝる身も神はひくかと白雲のふしのたかねを猶や仰かむ 敷嶋の道はしらねと富士のねの眺にをよふことのはそなき 御和 君かへむやをよろつ代の坂まてもふしのね高き神そしる覧 富士のねの雪さへ道の光にていやましゝゝに積るとそみる (ひねもすになかめくらさせおはしまして) こと出は月になるまて夕日影なをこそ残れふしのたかねは (たゞいまのおもかげをつかふまつるべきよし仰ごと侍しに) 白妙の高根はかりはさかたにて日影のこれる山のはもなし |
堯 | |||
|
(十九日のあした御詠) 朝日かけさすよりふしの高ねなる雪もひとしほ色まさる哉 御かへし 範政 紅の雪をたかねにあらはして富士よりいつる朝日かけ哉 又御詠 月雪の一かたならぬ眺ゆへふしにみしかき秋の夜半かな 御かへし 範政 月雪も光をそへてふしのねのうこきなき世の程をみせつゝ |
富 | |||
| 9月20日晴 | 国府 (駿河) |
静岡市葵区駿府城公園付近 |
(同廿日御詠)※ 朝あけのふしのね颪身にしむも忘れはてつゝ眺めける哉 ※堯孝の記録では前日19日朝の御詠である。また「おなじあした」に綿帽子の地の文があるが、綿帽子の説話は19日早朝の出来事であることは飛鳥井雅世も記しており、この項目を「廿日」の事とするのは『御覧日記』の制作時のミスである。 御かへし 範政 吹さゆる秋の嵐にいそかれて空よりふらす富士のしら雪 実雅三條殿 我君のくもらぬ御代に出る日の光に匂ふふしのしらゆき (おなじあした、御わたぼうしまいらせらるべきよしありて、やがて御ひたひにうちをかせ給て) 我ならす今朝は駿河のふしのねの綿帽子ともなれる雪かな 嬾真居士山名金吾 雲やこれ雪を戴くふしのねはともに老せぬわたほうし哉 雅世朝臣飛鳥井殿※ 富士のねも雪そ戴く万代によろつにつまん綿ほうしかな 白妙の高ねはかりはさだかにて日かけ残れるやまのはもなし ※二首目は堯孝が義教に今の富士を詠むように言われた際に詠んだもので、飛鳥井雅世の歌ではなく、『御覧日記』制作時のミスである。 堯孝常光院 跡たれて君まもるてふ神も今名高き富士をともに仰かむ 持信一色左京大夫 君かなをあふけは高き影とてやいとゝ見はやすふしの白雲 持春細川下野守 富士のねも雲こそをよへ我君の高き御影そ猶たくひなき 熈貴山名中務大輔 露のまもめかれし物をふしのねの雲の行きにみゆるしら雪 (同日に御詠) こと山は月になるまて夕日影なをこそ残れふしのたかねに 御返し 範政 ゆふへたに猶うあをよはぬ入やらてそむる日影のふしの白雪 又御詠 いつ行と忘れやはする富士河の波にもあらぬ今朝の眺めは 御かへし 範政 富士河の深き恵みの君か代に生れあひぬることのうれしき |
富 |
| 清見寺 | 静岡市清水区興津清見寺町418-1 |
(清見寺へ渡御に供奉して於彼寺御詠を拝見し奉りて) けふかゝること葉の玉を清みかた松によせくるみほの浦波 吹風も猶おさまりてたゝぬ日はけふとそみゆる田子の浦波 |
飛 | |
|
(清見寺、府中より四里、にてあそばしをかれ御詠) 関のとはさゝぬ御代にも清みかた心そとまるみほの松原 (御舟にめされ、海人のかづきするなど御覧ぜられて還御なり侍き、仁行如春威行如秋なる御よそほしさみたてまつる貴賎、御道すがらさりもあへ侍らず、入江の宿、たかあしなはてなど過て、広き野やま、こゝやかの草薙の神剣、霊端をあらはし侍りし、あたりならむといとかしこくぞおぼえ侍る、此所に草薙の御社九万八千の御社などと申て、むかし神々進発の御陣の跡に社あまたおはしますと云々、海道よりは見えず、清見寺にておもひつゞけ侍し三首の中) 清見かた関もる波もいとまあれやほみの松原風たゞぬ世に (袖しの浦は出雲国とこそきゝ侍しに此うらはに同名侍ありけり、于時白雲重畳、彼山不及瞻望) 雪深くおほふ袖しの浦人よいつくにふしをみるめからまし (御舟よそひ侍し程) 漕出てみほのおきつの松の千世都のつとに君そつゝまん |
堯 | |||
|
(清見が関御覧) せきのとはさゝぬ御代にも清みかた心そとまる三保の松原 御返し 範政 吹風もおさまる御代はきよみかた戸さしをしらぬ浪の関守 雅世 こきいてゝ三保のおきつの松の千代都とつとに君そ包まん 嬾真居士※ けふかゝることはの玉を清見潟松にそよするみほの浦なみ ※実際は飛鳥井雅世の歌で『御覧日記』制作時のミス。 又御詠 富士のねににる山もかな都にてたくへてたにも人にかたらむ 御かへし 仰きみる君にひかれてふしの根もいとゝ名高き山と成らむ 雅世 わすれめやくもらぬ秋の朝日かけ雪ににほへるふしの詠は |
富 | |||
| 府中 | 静岡市葵区駿府城公園付近 | (やがて府中に還御あり) | 飛 | |
|
(御前にして一折御連歌御発句) いく秋のやとのひかりそふしの雪 御脇 範政 霧をもよはぬ松のことの葉 御第三 有明の月をあふくや朝ほらけ ※義教と範政の連歌の一部を掲載か。以下は連歌とは関係のない、別の御詠であろう。時期も同時かどうかは不明。 又御詠 なかめやる時こそ時をわかねともふしのみ雪は初め也けり 御かへし 熈貴 御心にかなふ時代のなかめ哉袖にもふれるふしの白雪 又御詠※ 敷島の道はしらねと富士のねの詠にをよふことのはそなき ※19日に義教が富士の由来を今川範政に問うた際の御詠。 御返し 敷島の道ある御代のかしこさに言葉の玉の数そかさなる (熈貴のかたへ御詠) 我為はあたらなかけのふしの雪都のつとになすかうれしき 時ありてみはやす君か御代なれやふしの高根も猶重ねつゝ 御返し 熈貴 今ははや君そみはやす時しらぬ山とはふしの昔なりけり みてたにも心およはぬ不二のねを都のつとにいかゝ語らむ |
富 | |||
| 9月21日晴 | 府中 (出立) |
静岡市葵区駿府城公園付近 |
(廿一日早旦に又持参) 富士のねは名高き山と言のはに君のこしてそ幾千代もへん |
飛 |
|
(あした駿河府にて御詠) 旅衣たちそかねぬる雲たにもかゝらぬ富士の名残おしさに (此外御詠かずゝゝ侍りき、いまだ拝見ゆるされざるをばかさね申出し、万代の佳代に仰ぎたてまつるべし、同府還御のとき申入侍し) 末とをく君かへりみよふしのねの年月かけて高き契りを |
堯 | |||
|
(又御詠を下され侍しかば) 数々のことはの花をみやこ人ふしより高く猶やあふかむ |
飛 | |||
|
(かくて此所をまかり立侍しほどに、私の宿に一首よみをき侍る) 雪に暮し月にあかして富士のねの面影さらぬ宿やしのはむ |
飛 | |||
| 手ごし河原 | 静岡市駿河区手越原付近 |
(手ごし河原にて) たひ人のてこし河原をのる駒も足なみはやしいそく朝立 |
堯 | |
| 宇津の山 | 静岡市駿河区宇津ノ谷 |
(今日又宇津の山をこえ侍るとて) 立かへりうつの山ちのつたひきて夕露分るたひ衣かな |
飛 | |
|
(宇津の山にて感夢のこと思ひ出侍りて) うつの山うつゝに越てみしふしに見しよの夢そ思ひ合する 範政 すなほなる君にまかせて日本をこゝろやすくや神もみる覧 (と申侍しとき、同じく詠進申べきよし仰ごとにて) 神もしれ天津日本あきらかに照らす恵もすなほなる世そ |
堯 | |||
| 9月22日晴 | 藤枝 | 藤枝市藤枝3-16-14 |
(藤枝の御とまりにて) 春ならは花そ匂はむ秋とてやうらは色つくふち枝の里 |
堯 |
| せと山 | 藤枝市内瀬戸 |
(せと山と申所にて) うらかるゝお花の浪にかへる也しほちは遠きせとの山風 |
堯 | |
| かまづか | 島田市湯日 |
(かまづかと申あたりにて) 駒とめよ草かるをのこ手もたゆく鎌塚も此わたりとて |
堯 | |
| さ夜の中山 | 掛川市佐夜鹿324付近の山道 |
(さ夜の中山にて富士のねほのかに見え侍しに、歌よませられしとき、御詠) 富士のねも面かけはかりほのゝゝと雪より白むさよの中山 (詠進のうた) それをみる面影うすし富士のねの雪かあらぬかさよの中山 |
堯 | |
| 今のうら ※遠江国府と南隣する淡水湖(汽水湖か)。 |
磐田市今之浦一帯 |
(遠江府ちかく成て今のうらと申入海あり、湖水也) 残る日もいり海ちかくみえてけりこの夕暮のいまのうら浪 |
堯 | |
| (池田宿) (宿) |
磐田市池田 | (池田宿すぎ侍とて) | 堯 | |
| 9月23日晴 | (池田宿) | 磐田市池田 |
(池田宿すぎ侍とて) ゆたかなる池田の里の民まてもすみよき御代に逢や嬉しき |
堯 |
| うへ松 | 浜松市東区植松町 |
(空霧わたりて、鴈の鳴侍るを聞て、うへ松と申所にて) 行末のちとせをかけて君か為けにうへ松の里とこそみれ |
飛 | |
|
(うへ松のはらとかやにて) 千代ふへきたねをは君に譲らなむけふ分過るうへ松のはら |
堯 | |||
| ひくま野 | 浜松市中区元城町 |
(ひくま野と申所も此あたりときゝ侍て) 恵ある君にひかれてひくまのや旅としもなき旅のみち哉 |
飛 | |
| せうらの松 ※街道筋に生えていた樹齢八百年(飛鳥時代)という松の古木 |
(又みちのかたはらにふるき松あり、木だちの拈比類なく、其興ある松也、人に問侍れば、八百年ばかりの星霜をも送侍るらむ、名をばせうらが松と申侍しかば) 翁さひうへけるのへの松か枝はさていく秋の霜をへぬらん |
飛 | ||
|
(せうらが松とて、いとふりたる木のねざしなど見どころあり、かげに立やすらひて) たか世にか植ておきなの松かねにけふ顕るゝ君のちとせは |
堯 | |||
| (いなさほそ江) | 浜松市北区の浜名湖北東部の細江湖 |
(うらゝゝ過侍るに、いなさほそ江いづくならむとおぼえて) いつかたかいなさほそ江のあま衣浦を隔てゝ定かにもなし |
堯 | |
| はまなの橋 | 湖西市新居町浜名870 |
(はまなの橋もやうゝゝちかく成しかば) けふは又めにかけてのみいそくかな濱名の橋の遠き渡りを |
飛 | |
| 9月24日雨 | 橋下 | 湖西市新居町浜名 |
(橋下の御とまりを立侍しに、雨ふり出侍しかば) 旅人のみのゝうは毛もしらすけの湊やいつく雨はふりきぬ |
飛 |
| 塩見坂 | 湖西市白須賀 |
(雨ふり侍りしに、塩見坂こえければ、いづかたもくもりて、松原一むらぞ興をのこし侍る) 松原の一村しくれすきやらてふしのねたくもくもる今日哉 |
堯 | |
|
(還御、遠江塩見坂にて御詠) いまそはや願みちぬるしほみさか心ひかれしふしを眺めて 嬉しさも身にあまるかなふしのねを雲の衣の外になかめて 御かへし 範政 折をえてみつの山風ふくからに雲のころもは立もおよはす (塩見坂にして御発句) あきさむしふしのねもみつ塩見さか (御詠) 秋寒きふしのねおろしみにしみて思ふ心もたくひやはある 御かへし 雅世 富士の根の雪と月とに明す夜や君かことはの花をしむけむ 堯孝 雲払ふふしのね颪ふけやたゝ秋の朝けの身にはしむとも ふしのねの月と雪とのめうつりにあかす珍し君かことのは 嬾真居士 ふしのねは名高き山のあかすみるこのことのはや類なか覧 |
富 | |||
| いまばし | 豊橋市今橋町 |
(いまばしと申所にて) 君かためわたす今橋今よりはいく万代をかけてみゆらん |
飛 | |
| 矢はぎ (宿) |
岡崎市矢作町宝珠庵 |
(矢はぎのとまりちかくなりて) 梓弓かへるさ近くなりにけりおなしやはきの宿をとふまて |
飛 | |
|
(やはぎに御着のほど夜に入侍しかば) あきらけき御代の光にひくれるは暗きやはきの里も辿らす |
堯 | |||
| 9月25日晴? | さかひ河 | 刈谷市今川町阿野前 |
(参河と尾張とのさかひ河をわたるとて) 今日はまた千代万代のさかひ川二つの国のわたりのみかは |
堯 |
| なるみのほとり | 名古屋市熱田区神宮~名古屋市緑区鳴海町一帯に広がっていた広大な干潟 |
(此御とまりを立侍て、なるみのほとりを過侍とて) 【歌闕】 |
飛 | |
|
(なるみにて) 祈ることなるみの浦に御祓せむちかきあつたの神を仰きて (爰彼に侍し海士の家居をみて) 鳴海潟しほひにあさる蟹の子のさだめぬ宿か爰もかしこも |
堯 | |||
| ふるわたり | 名古屋市中区古渡町 |
(ふるわたりと申所にて) 都人袖をつらねてふる渡り古き世はちぬかけやとゝめし |
堯 | |
| おりつ (宿) |
稲沢市下津町東国府 |
(おりつの御とまりにて) 暮にけりのるてふ駒を引とめて今やおりつの宿をたつねん |
堯 | |
| 9月26日晴 |
(御道すがらの御まうけ、治世安楽の恩沢、かぎりなくぞ見え侍る) 山につみ野にもみちぬる恵み哉遠きあつまの道もすからに |
堯 | ||
| うし野 黒田 |
一宮市牛野通 一宮市木曽川町黒田 |
(うし野を過て、黒田ちかくなり侍しに、あしはらおほくみゆ) をのか毛の黒田もちかく成にけり分る牛野につゝくあし原 |
堯 | |
| すのまた | 大垣市墨俣町墨俣 |
(濃州すのまたと申所にて) をのつから名になかれすの又類あらしとみゆる浪の上哉 |
飛 | |
|
(すのまたにて) 河舟のさすや日影ものとかにて立としもなき秋のさゝなみ |
堯 | |||
| なが橋 | 大垣市小野三丁目 |
(なが橋と申所にて) 立ちかへる此長はしも長月やすゑになるまて日数へにけり |
飛 | |
| 9月27日晴 | たる井 | 不破郡垂井町 |
(たる井の御とまりをつとめて立侍しに山田の面にうねほしたるをみて) 朝日さす山田のをしねかりつみて夜をく露を先やほす覧 |
飛 |
| 黒地川 | 不破郡関ケ原町山中 |
(くろち川と申所にて瀧のおちたるをみて) 立よりてみれは名のみそ黒地川くろきすぢなき瀧の糸哉 |
堯 | |
| かしは原 | 米原市柏原 |
(かしは原と申所にて) 秋さむみ下葉いろつくかしは原露のみもろく風渡る也 |
飛 | |
| うぐいすがはな |
米原市醒井440 鶯ヶ端 |
(うぐいすがはなと申所にて、羇旅のうちに抄秋已闌小春漸近づきぬる風光に嘯侍て) 里の名に聞鶯のはなかつら秋はすくなし春かけてなけ |
堯 | |
| さめが井 | 米原市醒井 |
(さめが井と申所にて) 君か代は流れも遠しさめか井のみつわくむ共尽しとそ思ふ |
飛 | |
|
(さめが井の水をむすびて、一切智清浄無二無別とぞ観じ侍し) くみてこそうき世の夢もさめか井のみつから清き心しらるれ |
堯 | |||
| かどの | 米原市三吉 |
(かどのと申所にて) 百草の花のかとのゝあきの露あかぬ袂にうつしてそこし |
堯 | |
| (山道か) |
彦根市中山町 摺針峠辺りか |
(の山のこずゑ色づきわたれるをみて) 色ならぬたひの心も染てけり分る野山の秋の梢に |
堯 | |
| をの | 彦根市小野町 |
(をのと申所にて紅葉を見侍て) たひ衣もみちのぬさもとりあへす都のにしき又やかさねん |
飛 | |
| あつさの関 ※本来は「かしは原」の次 |
米原市梓河内 |
(あつさの関にて) もろ人も此せきの名の梓弓手にふれぬ代はのとか成らし |
飛 | |
| 武者 (宿) |
近江八幡市武佐町 |
(武者の宿につき侍て) わか君の御代をおさむる武者のなを聞里もしつか也けり |
飛 | |
|
(むさの御とまりにてみせられ侍し御詠二首) 若枝たにまた染出ぬみの秋のおいその杜の陰そひさしき ふり出て時雨も露も猶そめよくれなゐうすきよものもみちを |
堯 | |||
| 9月28日晴 | 老その杜 | 近江八幡市安土町東老蘇1615 |
(この御とまりにて御詠を被下侍しに) 若枝のみそふへき千世の秋かけて何か老その杜の紅葉は |
飛 |
|
(二のうち、老その杜の御詠を和し申入侍し) 名にたかき老その杜の松のかけやかてさしそへ千代の若枝 |
堯 | |||
| かゞみ山 | 近江八幡市武佐町の道中 |
(かゞみ山をみやりて) たれも今君をかゝみと仰みる世にあふみちの山もかしこし |
堯 | |
| 御所 |
(御所に還御のとき) 分きつる東路よりもはるけきはかへる都の千世の行すゑ |
堯 |
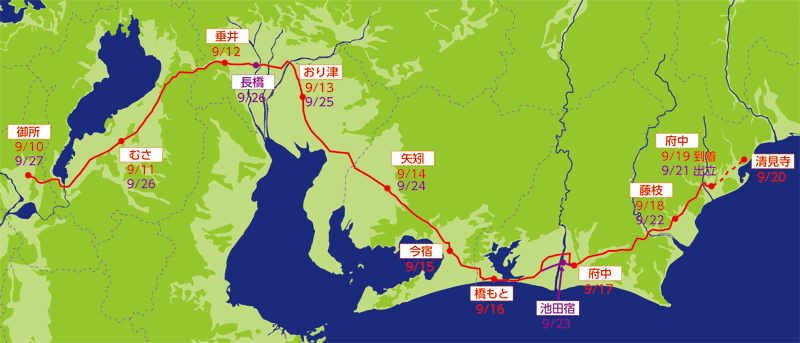
歌枕を求めて中山道や東海道といった主要街道だけではなく脇往還や山路も選びながらの旅路で、義教は輿に揺られながら、駿河まで9日をかけるゆっくりしたペースだった。9月13日に宿泊した矢作宿では、「くもりなく晴て、名をあらはし侍ぬること、千載之一遇、万秋之芳躅、めでたくおぼえ」た十三夜の月のもと、三條中将実雅の宿所で続歌が披講された。その場で渡された題に沿って駿河までの歌枕と月を盛り込んだ歌を即興で詠むというもので「十三首」が詠まれた。そのうち、飛鳥井雅世が詠んだ五首(名所山月、名所里月、名所浦月、名所潟、夜月忍恋)と常光院堯孝が詠んだ四首(名所野月、名所関月、名所橋月、寄月祝言)が伝わる。実雅は義教の義兄にあたる歌人である。
安芸法眼―――藤原慶子 +―足利義持
∥ |(内大臣)
∥ |
∥―――――+―足利義教
足利義満 (左大臣)
(太政大臣) ∥
∥
三條公雅――+―藤原尹子
(権大納言) |(瑞春院)
|
+―上乗院実済
|(横川長吏)
|
+―三條実雅――女子(歌人)
(宰相中将)
「同十七日、到駿河国鬼岩寺、国主範政奉迎」(『鎌倉大日記』永享元年条)したとあるが、翌18日に「この国の守護今川上総介範政、御向かひに出でらる、御輿よりて来させ給ふ、上総介御手を引き奉らる、手越が崎といふ所にて」(『左大臣義教公富士御覧記』)と義教側近の手記を基にしたとみられる紀行文にあることから、範政が出迎えた場所は、安倍川の左岸、手越が崎の往還となる。これは範政は駿河と遠江の国境付近、かつて鹿苑院義満の駿河下向の際に宿所とした鬼岩寺に義教を出迎えたのち、公式の出迎えの場所として、歌枕の「手越」を設定し、ここで「上総介御手を引き奉らる」という演出をしたと思われる。
そして、9月26日、供奉している美濃守護・土岐大膳大夫持頼から満済へ届けられた書状によれば「十八日申刻、御下着駿河国、路次毎事無為珍重、関東雑説勿論云々、雖然不可有殊儀條又勿論(九月十八日申刻、室町殿は駿河国に御着されました。路次は変わりなくめでたいばかりです。関東の様々な噂も当然聞こえてくるものの、とくに変わったことも当然ありません)」(『満済准后日記』永享四年九月廿六日条)という。駿府に入った義教は、「同十八日登高亭御覧有御歌会」(『鎌倉大日記』永享元年条)とあるように、富士がよく眺められる場所に範政が義教逗留のために拵えた館へと移動する。そして「廿日、渡御清見寺様其沙汰、両三日ハ駿河ニ御逗留風聞」(『満済准后日記』永享四年九月廿六日条)という。
その後、同26日に山名時熈入道が「遠江府ヨリ」送った書状も満済に届いている(『満済准后日記』永享四年九月廿六日条)。満済はその詳細を記しておらず内容は不明だが、土岐持頼の書状と大差ない内容だったのかもしれない。
9月28日、将軍還御の予定のため、満済は「晨朝鐘時分」に出京し、辰末刻に室町殿へ参ずると、すでに「二條太相国、九條前関白、一條摂政、近衛右府、大炊御門内府、三條前右府、久我前内府、洞院入道内府以下」が参じていた。僧侶では護持僧のほか「南都両門一乗院、大乗院等」が参じ、将軍の帰還を待っていた。そして「将軍午初刻、還御云々、御路次之間、上下毎事無為、天気快晴珍重之由、自方々申賜了(将軍、午初刻、還御とのこと。路次ではみな問題もなく、天気も快晴続きですばらしかったですと、人々が報告してきた)」(『満済准后日記』永享四年九月廿八日条)。ただ、還御した将軍義教は「聊御風気」で、参じた人々とは「無御対面」となり、その旨は家司の「永豊朝臣」を通じて人々に伝達され、「仍面々退出」した。ただ「予并聖護院准后計、可有御対面由被仰」として、諸卿退出後、高倉永豊はまず聖護院満意准后を呼び、次に満済を呼んで対面している。満意准后は行っていた准大法の修法結願により対面したもので公的な内容であった。ところが、満済とは「富士御雑談在之」というフランクな対面となったようで、疲れて還御の直後に諸卿からの(意味のない)堅苦しい挨拶は御免蒙るということだったのかもしれない。
二條兼基―+―二條道平――二條良基―+―二條師嗣
(関白) |(関白) (関白) |(関白)
| |
| +―満意
| (聖護院准后)
|
+―今小路良冬―今小路基冬――満済
(権大納言)(権大納言) (三宝院准后)
義教は「去十七日雨ニ依テ、十八日申初刻御着駿河府處、富士雪当年初云々、富士體、兼思食ニハ超過、且奇特無申計云々、富士出現事甲子歳云々、当年又子年也、自然相応御祝着云々、実不思儀々々、御路間御詠等何様被書聚追可被見(十七日は雨だったので、(今川範政が出迎えた鬼岩寺(藤枝市藤枝三丁目)で一泊し)、十八日の申初刻に駿府に到着した。富士は今年初めての冠雪だったとのこと。富士は想像していた姿より素晴らしく、霊験も言葉にできなかった。富士の出現は甲子歳であるというが、今年もまた子年であり、なんともめでたく、実に理解を超えることばありであった。途路で詠んだ歌は集めていずれ見てもらう予定だ」と満済に述べているように(『満済准后日記』永享四年九月廿六日条)、かつて思い描いていた想像をはるかに超える霊峰富士の霊験と雰囲気などを熱っぽく、子供のように興奮しながら満済に報告している。
9月30日、招月庵正徹のもとに「中務大輔(山名貴熈)」から和歌三首とともに「昨日、将軍家駿州より御上洛とて中務大輔のもとより、うつの山の葛かつらを送られ」ている(『草根集』巻二)。宇津山を通過したのは9月21日のことで、山名貴熈が採取した葛花は枯れてしまっていたと思われるが、押花様にして届けられたのかもしれない。
なお、この駿河下向は、義教に対する根強い先入観から、関東を牽制する意図があるとされているが、そのような考えは、当時の京都側の史料からは一切述べられていない。そもそも義教自ら譲歩してまで実現させた「御政道」の根本「天下無為」の必要条件「都鄙の和平」を、義教自ら破壊する事は到底考え難い。俗に「是ハ持氏公モ公方御下向ノ時分、御参会アラバ、尋常の喧嘩ニモナシ、内々御退治アルベキ御底意アリテ御下向ト、後ニ事ノ次デ人モ知ケル、サレド持氏公御風気ニテ其時分参会ナシ、只御名代二上杉房州憲実ヲ参ラセラレタリ」(「今川家譜」『続群書類従』)との記述が引用され、通説化されているが、憲実が駿河へ来た傍証は全く存在せず、帰京後もそのような事実は確認されない。「系譜」という本来もっとも慎重に扱うべき史料の添書にも拘わらず深く通説とされたのは、義教が「強権」「独裁」であるという根拠のないバイアスと、京都と関東は常に対立関係にあったというこれもまた根拠のないバイアスが、根深く植え付けられているためである。
同道した人々の紀行日記を見ても、東国の歌枕を巡るために細い脇往還も選ばれている上、その途路に禁制は一切出されておらず、宿場の夜の静謐からも、軍勢の帯同はないことがわかる。前述のように諸大名(有司)や奉行衆や近臣の同行、外様では土岐大膳大夫の供奉が見られるため、彼らの最低限の護衛は付き従っているが、総勢でも百名程度であろう。
帰洛後の義教は関東に関する話題をまったくしておらず、満済のもとにも関東からの文書等があった旨も記録がない。同じく『看聞日記』にも関東に関する風聞すらしばらく記されることはなくなり、代わって大内氏の内紛騒動への対応および、深刻になりつつあった駿河国今川家の家督を巡る内紛への対応が主となっていく。
永享5(1433)年4月14日早朝に法身院に入った満済が、急ぎ清和院(前日より義教が参籠中)へ向かおうとした際、「山名禅門」が来訪し「伊賀守護職事上意趣畏入」と礼物を持参するとともに、「駿河国錯乱事等條々申致在之」の報告をしている。満済が急いでいる様子だったのを察したのか、山名時熈入道は「簡要、今河上総守二男弥五郎、父上総守当時病床及鶴林式之處、父ヲ人質ニ取、任雅意譲与状ヲサせ、舎弟千代秋丸方者ヲハ大略打之了、言語道断次第也、仍狩野富士大宮司両人方ヘ、今度国次第、具被尋聞食、可有御成敗條、尤可然由申入也(要点のみですが、今川範政次男の弥五郎が、父範政が病床で重篤な状況の中で、範政から思うままに譲状を取った上、舎弟の千代秋丸を推す人々の多くを討ったとのこと。言語道断のことであり、そのため、室町殿に狩野介と富士大宮司の両名に、駿河国の状況を詳細にお尋ねなされ、対応されることが最善ですと申し入れました)」という(『満済准后日記』永享五年四月十四日条)。
その後、巳半刻頃に清和院に参じた満済は「就駿河国事、山名申入旨申」たが、義教はこれ以前に同様の件で「此事弥五郎申旨、自管領申入也」という。ただ「只今山名申入旨トハ相違也」といい、今川弥五郎の申状は「千代秋丸方者共、父ヲ押ノケ可任雅意所行露顕之間、致其沙汰了」というものだったという。そのため義教は千代秋丸側の横暴を止める為か「於今者一迹事、可申付弥五郎、早々御判可申沙汰旨、以状令申管領也」という措置をすでにとっていたようである(『満済准后日記』永享五年四月十四日条)。このほか「矢部、阿佐伊奈者共十余人、以告文連署弥五郎事執申入也(矢部、朝比奈ら十人ばかりが告文に連署して、弥五郎を家督にとの申し入れがあった)」ことも満済に告げており、これも弥五郎を是とする判断材料のひとつだったとみられる。ところが、満済から山名方の申入を聞き、義教はその判断が妥当か判断がつかなくなり、「然ニ不被任父譲、引違御沙汰有テ、万一国錯乱せハ一向御成敗ノ相違ニ可成歟之間、可為何様哉云々、仍先可被仰付弥五郎由思食云々、此旨且可仰談畠山(しかし、父範政の譲の旨に反する沙汰を下し、万一国の乱れともなれば、すべて京都の過ちとなろう。どのように対処すればよいか。まずは弥五郎に範政一跡を継がせようと考えるが、この旨を畠山満家入道と相談するように)」と指示した。ただ、これを受けた畠山満家入道の意見は「駿河国事、国様能々被尋聞食、可有御沙汰歟」(『満済准后日記』永享五年四月十四日条)という無難な返答に留まっている。
実はこの駿河今川家の家督問題と同時に、安芸小早川持平・熙平兄弟の家督相続問題が議題とされており、これについて義教は「此子細管領、畠山、山名三人意見可申入」と有司三人に指示しているが、駿河の件に関しては「駿河事畠山計ニ被尋仰了」のは、義教が「管領ハ弥五郎事内々取申、山名ハ千代秋事申間、不及御尋歟」(『満済准后日記』永享五年四月十四日条)と、管領細川持之と山名時熈入道がそれぞれに肩入れしている疑いが原因と推察している。このころから細川家と山名家の微妙な関係がうかがえ、持之の子・勝元と時熈入道の子・持豊が決定的対立をする三十四年後の「応仁の乱」の萌芽がうかがえる。
4月23日、室町殿に参じた満済は、義教から「自駿河国注進」を渡され「於御前一見了」した(『満済准后日記』永享五年四月廿三日条)。それは今川家被官庵原某からの書状で「上総守末子千代秋丸、為関東上杉所縁之間、自彼辺可致合力風聞在之由申入也(上総介末子の千代秋丸が関東上杉氏の所縁のため、上杉氏から合力するという噂があるため申し入れました)」というものだった。しかし、義教は「此注進、不足御信用由被仰(この注進は信用に足らぬ)」ており、満済もこれに「同心申入了」した(『満済准后日記』永享五年四月廿三日条)。これら一連の対応からも、義教は感情に流されずに客観的に物事を見るバランス感覚に優れた人物であることがわかる。こうした情報から義教は、範政の彦五郎廃嫡という私事が原因となる家中分裂を収めるためにはどうしたらよいのか、総合的に思案していたのだろう。
4月27日、室町殿に参じた満済は、義教から「駿河国ヨリ富士大宮司注進状并葛山状等」を渡され「一見了」した(『満済准后日記』永享五年四月廿七日条)。それによれば「国今度不慮物騒事申入了、随而富士進退等事、可任上意旨、載罰状申入也」という。富士大宮司はその後の動きから、狩野、葛山、三浦、進藤、矢部、朝比奈、庵原といった弥五郎を推挙していたグループに属していたことがわかる。
しかし、4月28日、義教は弥五郎にも千代秋にも範政一跡を認めず、義教が預かっていた範政嫡子彦五郎へ相続承認を行う決定を下す。満済は「今河上総介一跡事駿河国、可被仰付嫡子彦五郎由大略御治定、其旨為門跡可申遣今河遠江入道方之由、今朝被仰之間遣状了(今川範政の一跡は、嫡子の彦五郎範忠に命じよとのことでおおよそ決定した。このことを門跡から今川遠江貞秋入道へ申し遣わすよう今朝仰せられたので、遣わした)」した(『満済准后日記』永享五年四月廿八日条)。「今河下野守方ヨリ下遣也」とあるように、今川下野守に今川遠江入道への書状を託し、さらに「彦五郎使者同相副罷下」とあるように、彦五郎使者に副えて下されている(『満済准后日記』永享五年四月廿八日条)。彦五郎範忠は父範政に廃嫡され「彦五郎事、去年以来在京、御膝下ニ祗候仕、歎申入間、別不便ニ被思食」され(『満済准后日記』永享五年五月晦日条)、駿河国では家督と守護職継承を確定的としており、京都に使者を遣わして承認を求めていたことがわかる。また、満済書状を仲介した「今河下野守」がどのような出自かは定かではないが、その後も「遠江入道―下野守」のルートは機能しており、下野守はおそらく貞秋の子息(中務大輔持貞か)と推測される。義教の奉公衆「今川下野入道」(「永享以来御番帳」『群書類従』二十九輯)が見え、将軍近侍となっていたことがわかる。下野守の子息「尊藤丸」はこの二十日ほど前の4月7日、十七歳で醍醐寺で得度している(『満済准后日記』永享五年四月七日条)。
ところが5月9日、早朝に室町殿へ出仕した満済は、義教から「自駿河国、今度下向上使妙淳西堂注進以下」を渡され、一見した(『満済准后日記』永享五年五月九日条)。義教は事前に「為用意内々被下遣御判、依国時宜粗忽ニ不可渡遣今河二男弥五郎之由被仰付處、今月三日既渡遣之由(妙淳和尚を上使として相続のための御教書を内々に駿河へ遣わしていたが、国情を見て考えなく弥五郎へ遣わさぬよう言い含めていたが、5月3日にすでに渡してしまったとのことだ)」という。この報告を受けた義教は「以外御腹立也」と激怒したものの、すぐに冷静になり「但、国弓矢若火急子細在之歟(両派の戦いにはなにか緊急の理由があるか)」と使者に確認したが、「曾無其儀、自関東弥五郎舎弟千秋丸扶持之由、雑説分計注進申也(その理由はありません。関東が千代秋丸を支援しているという根拠のない噂ばかりが注進されてきます)」という(『満済准后日記』永享五年五月九日条)。
5月19日、満済が参じたところ、義教は「自駿河国注進状等、今度上使淳西堂罷上、国人内者等申詞大略載告文詞申入了、弥五郎今河二男方へ国御判、去三日渡之了、此事楚忽之儀云々、但西堂御判随身上者、渡條又存内歟、奉行二人飯尾肥前守、同大和守両人、自駿河書状告文等於御前読進之、昨日悉備上覧云々、今日重読進令聞予御用(駿河国より注進状等によれば、今度上使淳西堂が上洛の途につき、彦五郎を相続人とする旨について、駿河国人や今河被官らの意見を大略告文に載せたという。弥五郎へ御教書を渡してしまったことは軽率だが、西堂が御教書を帯同して下向した以上は渡すことも考えの内か。奉行の飯尾肥前守、大和守両人に注進状と告文を読ませたが、今日は准后にも聞かせよう)」と言い(『満済准后日記』永享五年五月十九日条)、満済に内容を伝えたようである。さらに「今河詠歌三首進之、一首今度上使御判等祝着事、一首述懐、一首没後儀歟、不分明」とあるように、この注進状には駿府で重病の床にあった範政からの和歌が三首付されていた。一首は上使から弥五郎への一跡承認の御教書を受けた安堵と感謝の歌(相続人が廃嫡した彦五郎へ変わったことは伏せられていたのだろう)、一首はこれまでの義教との交流を懐かしんだ歌であろう。そしてもう一首は満済は理解できなかったのか「不分明」としているが、自分の死後についての書置きの一首とみられる。その後、「今河遠江入道可召上之由被仰出間、申付下野守了」と今川遠江入道を駿河から上洛させるべく、今川下野守に指示している(『満済准后日記』永享五年五月十九日条)。
そして、5月28日に「今河遠江入道参洛」した(『満済准后日記』永享五年五月廿八日条)。二日後の5月30日、満済は室町殿に参じると、今川貞秋入道の申状として「駿河国人等并総州内者所存事、於門跡委細可尋聞(駿河国人や範政被官人の考えは、門跡から詳細を尋ねられよ)」とのことだったので、飯尾肥前守、飯尾大和守、松田対馬守の三奉行が参じ、満済からこの件について聞書した。しかし、飯尾肥前守は「雖然、猶遠江入道載状可申入状可宜」と主張したため、遠江入道にも自筆状の提出を要請している(『満済准后日記』永享五年五月晦日条)。
満済はこの件については、「條々不分明間、不能委記、大概也」としつつ、
| 一 | 総州一跡事、付嫡子、可被仰付彦五郎處、国人内者所存何様事、此條連々遠江入道先度被仰出以来、相尋国人内者處、国人狩野、富士、興津以下三人ハ及両三度既捧請文、可被仰付彦五郎條畏入之由申上了、内者事矢部、浅井那者共大略ハ同前ニ申入歟、何モ可為上意由申段ハ勿論也 | 範政一跡のことは、嫡子につき彦五郎に仰せつけられたが、国人や被官の考えはどうか。 この事に関しては貞秋入道が以前に命じられて以来、国人や被官らに尋ねており、国人の狩野介、富士大宮司、興津の三名は三度にわたって起請文を提出しており、彦五郎を惣領との件は畏ったとのことだ。被官人の矢部、朝比奈もおそらくは同前だろう。いずれも上意に従うことはいうまでもないとの事。 |
| 一 | 今一ヶ條、只今忘却間不及注也 | もう一ヶ条は失念したので、注記しない。 |
この申詞の内容を奉行三人から「管領、畠山、武衛、山名、赤松五人」に意見聴取したところ、以下の通りであった。ただし、満済はあくまでも「大概」であるとし、詳細は記していない。
| 管領 細川持之 |
先父譲与事被仰付、其後国御判可被下條宜存 | まず、父範政からの家督譲与を命じられ、そののち守護職の御教書を下されることがよい。 |
| 畠山満家入道 |
以前既弥五郎ニ被下御判、不幾又可被仰付彦五郎條可為何様哉、乍去国人内者所存無子細之由、然者可仰付彦五郎事可為上意 | 以前すでに弥五郎へ守護職補任の御教書を下されているのに、時を置かず彦五郎へまたそれを遣わされるのはどういうことか。しかしながら、国人や被官に反対の意見はないとのことであれば、彦五郎に仰せ付けるのは上意のままに |
| 斯波義淳入道 | 可被仰付彦五郎事可為上意、国時儀不存知仕 | 彦五郎に守護を仰せ付けるのは上意のままに。ただ駿河国内の情勢はわからない |
| 山名時熈入道 | 可被仰付彦五郎條尤可然存 | 彦五郎に守護職を仰せ付けるのは、大変よいと存ずる |
| 赤松満祐入道 | 可被仰付彦五郎條、順儀御成敗歟、但弥五郎御判拝領之間、国時宜可為何様哉 | 彦五郎に守護職を仰せ付けるのはよきご判断と思う。ただし、弥五郎はこれ以前に御教書を拝領しているため、それを受けたのちの国情はどうなのだろうか |
この今川家督と守護職の件について、義教は三奉行を再度「管領、畠山、赤松三人」に派遣して意見を求めている。なお、斯波義淳と山名時熈入道は「今二人ハ無殊儀故也(斯波と山名の両名は返答に聞くべき点がない)」ため意見を求めていない。
問い合わせの内容は、「先度被成弥五郎御判お事ハ、国物騒又ハ総州所労危急之由註進申間、不及是非御沙汰、先任総州申請旨、弥五郎ニ国事被仰付了、但其御判粗忽ニ不可渡弥五郎由、上使淳西堂ニ堅被仰付了、猶御不審間、上使下向以後、以管領奉書此御判無左右不可渡之由、被仰遣處、已五月三日御判渡遣間、於此條ハ無力次第、非御本意也、管要ハ国儀如意見被思食間、狩野以下所存趣御尋處、大略ハ可為上意由申、剰彦五郎事、庶幾心中云々、然者可有何子細哉、彦五郎事、去年以来在京、御膝下ニ祗候仕歎申入間、別不便ニ被思食(以前に弥五郎へ守護職補任の御教書が下された件については、駿河国内が二派に分かれて騒擾が起こっていたこと、さらに範政の病が重篤である報告が入っていたことから、やむなく沙汰したもので、取り急ぎ範政の請いの通りに弥五郎へ守護職を仰せ付けたものである。ただ、その御教書については軽々しく弥五郎に渡すことのないようにと上使の淳西堂へ固く指示したが、なお気がかりだったので、上使下向後に管領奉書の形で、再度淳西堂へ『考えなしに弥五郎へ渡さないように』と申し遣わしたが、五月三日にすでに弥五郎に御教書を渡してしまっており、もはやどうしようもなく、私の本意ではない。駿河国の事は国人や今川被官の意見が大事であるから、狩野介らに意見を尋ねたところ、上意に従うとのことであった。そればかりか彦五郎を守護に強く願うという。そうであれば何ら問題はなかろう。彦五郎は去年以来在京し、自分に祗候して度々この事について訴えており、彦五郎を不憫に感じていた)」という(『満済准后日記』永享五年五月晦日条)。「管領、畠山、赤松三人」の答えが「三人意見、誠此分候者、可有何子細哉、可被仰付」との事であったが、「畠山意見ハ猶同前也、但可為上意」という(『満済准后日記』永享五年五月晦日条)。
翌6月1日、満済は早朝に室町殿へ参じ「今朝御尋三人大名、御返答注上了」(『満済准后日記』永享五年六月一日条)が伝えられた。なお、畠山満家入道については満済から「猶事子細可相尋由」を指示されたため、満済は齋藤因幡守を召し寄せると、義教の言を伝えた。
「先度被下弥五郎御判事ハ、国弓矢事以外注進之間、若此御判遅々せハ千代方者共得利事モヤト思食事、次ニハ上総入道所労危急之由注進之間、旁先不及是非被下御判於弥五郎了、於今者云国儀云総州所労取延、旁任理運可被仰付彦五郎處、御意見分弥五郎ニ被下御判事、御膝下ニ祗候者共先一旦被下御判之由令存知了、遠国者共ハ不可存知仕之間、不幾又可被下彦五郎事可為何様哉云々、此儀尤ニ被思食也、乍去不存知者無窮申状ハ不可限此一事間、不足御承引事歟、簡要ハ面々如此之由意得マテコソト思食也、次国時宜如何之由申事、是又自最前御覚悟事間、此間連々御尋處、国人狩野以下者共ハ既捧請文、雖為何仁可任上意之由申、殊更彦五郎事、剰意寄様ニ申入也、其外内者共事、雖不被御覧分明請文、大略ハ彦五郎同心儀、簡要ハ可為上意云々、此上ハ可有何子細哉、乍去、猶先上使長老お被下遣、可被仰付彦五郎之由以御書可被仰遣、上総入道并弥五郎、其後一左右被聞食、可被仰付彦五郎之由、被思食也、就此不残心底猶可申意見(先に弥五郎へ下された御教書は、駿河国で合戦となったというとんでもない注進があったので、もし守護補任の御教書発給が遅くなれば関東由緒の千代秋丸方が有利になる懸念があったための措置である。また、上総介範政入道の病が重篤であるという注進があったこともあり、やむなく弥五郎へ御教書発給を行った次第である。しかし、現状は駿河国内の情勢も範政入道の病も落ち着きを見せたため、道理の通り範政嫡子の彦五郎を守護職に補任せんとしたところ、諸大名の意見として『弥五郎に守護職補任の御教書を下された件については、京都伺候の者であれば、まず仮に下したことを知っていますが、遠き駿河の者どもは知る由もなく、時を置かずに彦五郎に御教書が下されたのはいかなることかと思うでしょう』という。このことは誠にもっともだ。しかし、知らないがために申し立てるという事例は、なにもこのことに限るまい。認めない理由になろうか。要は面々がこの認識となればよいのだと思っている。次に国情はどうなのかという申出についてだが、これは当初より想定したことであり、先般これについて駿河国に問い続けているが、国人の狩野介以下の者たちはすでに請文を提出している。惣領が誰であろうとも上意に随う旨を申しているが、彦五郎が守護職となる事についてはとくに賛成するという。今川被官人たちについては請文を見ずとも、彦五郎に随う件で重要なのは上意であるということだろう。この上何ら問題があろうや。ただし、まず上使の長老を駿河に遣わし、彦五郎を駿河守護とする旨の御教書を遣わし、上総入道と弥五郎にはその後、事態を耳にし、彦五郎に守護職を申しつける旨を伝えようと思う。このことについて、思うことを残さず意見するように)」との言葉だった。
その後、畠山満家入道亭から斎藤因幡守、大方入道が帰参し、畠山入道からの返答を伝えた。畠山入道は「重被仰下旨畏承候、所詮只今如被仰下、先被下上使事次第、具被仰下上総入道、追可被仰付彦五郎條、尤宜存云々、此御返事ハ第二度事也、此以前ハ駿河国事、関東堺大事国ニテ候、今河遠江入道申状計ニテ御成敗ハ可有如何哉、且遠江入道、駿河国時宜慥ニハ不覚悟申入歟之由存様候、能々可被聞食合(重ねての仰せ畏入ります。今回の仰せについては、まず上使を下されて上総入道に詳しくご説明されたのち、彦五郎に守護職を補任されることが最も良いかと思います。この御返事は二度目です。前回は『駿河国は関東との境という大事な国であり、今川貞秋入道の申状のみで決定するのはいかがなものか。また貞秋入道は駿河国の情勢については把握できていないとの申入があった』との事を聞いております。よくよく多方面からの意見をお聞きになされよ)」との事であった。
満済はこの畠山入道の返事を義教に伝えたところ、「如上注重、又可被下上使事等(畠山の注進及び上使下向を行う等)」ことを仰せられた。なお、満済は「依事繁、落居儀計注置了、五月晦日、六月一日、先以奉行三人再三御談合歟(注進の内容が多かったため、決定したことのみを注した。五月晦日、六月一日に室町度は奉行三名と再三談合されたか)」(『満済准后日記』永享五年六月一日条)という。
6月3日早朝、満済は出京して室町殿へ参じた。義教から「御文章不分明」ながら、「大略被仰付彦五郎、其旨可令存知之由」として、「駿河国へ御内書両通、一通総州方へ御自筆、一通弥五郎奉行書之歟」を示された。また、「国人、内者以下十三人方へ被成遣御教書、子細同前」も手配され、「両上使」として「星巌和尚、周洪西堂両人」が「今日両使則進発了、路次煩等、一向為公方被仰付」という(『満済准后日記』永享五年六月三日条)。
なお、満済は夕刻には醍醐寺へ帰ったが、「今川彦五郎、今夕懸御目、久国太刀進上之」の知らせが届いている。なお、義教は5月30日には駿河守護の件について彦五郎範忠へ内定を伝えていたとみられ、彦五郎範忠は「自去一日髪お被裹也、今度国退出時出家」とあるように、父範政入道から廃嫡され駿河出国の際に剃髪していたが、通告直後の6月1日からふたたび蓄髪を始めて裹頭していたことがわかる。
6月6日、満済は早朝に出京して室町殿へ参じたところ、義教は「自関東就武田右馬助没落、駿河事以御状被申入事在之」と告げ、鎌倉殿持氏からの「関東状」を満済に見せている(『満済准后日記』永享五年五月六日条)。そこには「武田右馬助没落甲斐国、徘徊駿河辺云々、被加誅伐様被仰付可畏入」などと記されていた。「上杉安房守状同前」でもあり、これらについて義教は「就此事諸大名意見御尋」ると、「管領以下大略同前申入也、其身誅罰事不可然歟、只駿河国中ニ不被置様可被仰付」との意見であったという。満済も「此儀尤宜之由同心申入了」と返答し、義教も有司と満済の同意を得て「此儀御治定歟、可然関東へ可有御返事」と「先武田右馬助駿河居住不可然由、以管領状可申遣由被仰付歟」ことを確認した(『満済准后日記』永享五年六月六日条)。
6月8日、「小早川二郎左衛門」が「被官者真田周防入道」を同道して満済を訪問している(『満済准后日記』永享五年六月八日条)。何事かは不明だが「頻申間、令対謁了」と、対面を執拗に迫っていた様子がうかがえる。この「真田周防入道」は小早川始祖土肥実平の姉妹の子・真田与一義忠由緒の人物か。
中村宗平―+―土肥実平―――小早川遠平
(中村庄司)|(次郎) (弥太郎)
|
+―女子
∥――――+―土屋義清
∥ |(兵衛尉)
∥ |
三浦義継―+―岡崎義実 +―佐奈田義忠
(三浦庄司)|(四郎) (与一)
|
+―三浦義明―――三浦義澄
(三浦大介) (次郎)
同日、「今河右衛門佐入道、今夕下向」のため、満済に挨拶に訪れ、満済は「馬、太刀遣之」している。この「今河右衛門佐入道」は5月28日に一連の今川家家督相続問題に関して上洛した「今川遠江入道(貞秋)」とみられ、6月1日を最後に名が見えなくなる「今川遠江入道」は、帰洛までの三日間のうちに父右衛門佐仲秋と同じ「右衛門佐」の称を許されたのだろう。貞秋の父・今川右衛門佐仲秋は三宝院領である「尾張国々衙并西野」について「今河右衛門佐殿遵行」(「尾張国々衙領等支証目録」『三宝院文書』)を出している通り、尾張国守護であった。仲秋の一族が尾張国内に所領を有するきっかけになったとすれば、「尾張那古屋今河下野所領」(『満済准后日記』永享五年七月七日条)とあるように、尾張国那古屋に所を有する今川下野守は故右衛門佐仲秋の血縁であろう。今川貞秋入道と今川下野守の関係は、前述の通り4月28日に「今河上総介一跡事駿河国」を彦五郎範忠と内定した際に、満済が「今川下野守」を通じて「今河遠江入道」に範忠への書状を送達していることや、その後の共働の多さから、彼らは父子または兄弟と思われる。
6月21日、満済のもとに赤松播磨守満政が使者として参じた。内容は「駿河事、今河右衛門佐入道注進趣珍重被思食、随而明後日廿一日(ママ)、可出京」(『満済准后日記』永享五年六月廿一日条)とのことであった。
6月22日、満済に「駿州下向上使星岩和尚、周浩西堂、今晩参洛之由、自路次音信」があったため、満済は「明旦於京都可入見参之由返答了」(『満済准后日記』永享五年六月廿二日条)した。そして翌23日早旦、満済は出京して上使の星岩和尚、周浩西堂と対謁した(『満済准后日記』永享五年六月廿三日条)。上使は「今河弥五郎御請并国人内者以下各載告文詞捧請文了」し、「毎事、如上意落居」した上、「既為彦五郎迎内者十余人参洛」といい、「則召寄飯尾肥前、同大和守、松田対馬守、上使申詞、具録之披露」した。満済は「予先参室町殿、上使申詞大概申入了」した。そして「今河彦五郎ニ駿河国守護職并官途民部大輔等事被仰付管領了、御使飯尾肥前守也」という。こうして正式に今川彦五郎範忠は、駿河国守護職に任じられ、民部大輔に補任された。これに伴い「相尋吉日、早々可令下国之由被仰付了」ことが指示され「国御判、同以吉日可被下云々、如然事等、内々依仰申付飯尾肥前守了」された。また、「此外、就三浦、新藤等事、以管領奉書、狩野、富士大宮司并三浦、進藤等ニ、於国私弓矢不可取出之由、堅被仰付也」ことが指示された(『満済准后日記』永享五年六月廿三日条)。三浦、進藤、狩野介、富士大宮司らは彦五郎の守護就任を認める請文を出してはいるが、おそらく元来弥五郎を推していたため、彦五郎の守護職就任を快く思っておらず、蠢動が京都まで伝わっていたとみられる。義教はその叛乱を事前に封じるべく御教書を下していたと考えられる。
6月27日、「理覚院法印仲順」が「住心院僧正」とともに満済を訪れ、「今河彦五郎、駿河国守護職并一家総領以下御判拝領、任民部大輔云々、旁面目至千万歟、未重服日数内不懸御目間、今日門出、明後日廿九日、可下国云々、御鎧一両、御馬二疋、御剣一腰同拝領云々、御鎧等事内々兼申入了、今河下野守同御鎧一両拝領云々、同申入了(今川彦五郎が駿河国守護職と今川惣領家の御教書の拝領と民部大輔への補任したとのこと、方々に面目この上なきことか。範忠は亡父範政入道の重服中であり、室町殿に御目に懸からず、本日駿河下向のために今川亭を門出し、明後日二十九日に離京との事。御鎧一両、御馬二頭、御剣一腰を拝領しました、御鎧等については内々に予てより申し入れていたもので、今川下野守も同じく鎧を一両拝領しました。これも同じく顕実申し入れたものです)」といい、満済は「珍重々々」と記述する(『満済准后日記』永享五年六月廿七日)。なぜ聖護院の「理覚院法印仲順」と「住心院僧正(実意)」が今川彦五郎の守護補任と任官(この日の除目か)を満済に報告したのかは不明。聖護院と今川家に何らかの関係があったのかもしれない。
●永享5(1433)年6月27日「足利義教御教書写」(『今川家古文章写』)
そして6月29日、今川下野守が満済を訪問して「今河民部大輔、今日下国」こと、並びに「今河下野守同道下国之由申来了」と、範忠に同道して駿河へ下ることを伝えている(『満済准后日記』永享五年六月廿九日条)。前述の通り、今川下野守は尾張国に由緒を持つ今川右衛門佐貞秋入道の子息で、遠州今川了俊系の堀越氏、瀬名氏、各和氏らと並ぶ今川一門の有力者とみられる。その出立後、日時は未定ながら、駿河入国日について賀茂在方卿より勘申せられ、7月11日の入国が決定され急遽「入国駿河、日次可為来十一日由、在方卿勘文遣之計也」を持って、「力者福一」が今川範忠一行の後を追っている(『満済准后日記』永享五年七月七日条)。
7月4日、満済のもとに「星岩和尚、周浩西堂来臨」し「各少折紙随身」した。今川家関係の御礼とみられる(『満済准后日記』永享五年七月七日条)。また、その後、山門使節の「円明(円明坊兼宗)」が来て「鹿苑院領ト山門領ト堺相論事ニ付テ及喧嘩」となったことに際して義教から呼び出しを受け「仍自公方御切諫之由歎申也」と、相当強い注意を受けたようであった。円明坊兼宗は青蓮院の門徒(被官的存在)で、近江馬借をもまとめる大きな権勢を有していた。おそらく青蓮院門跡時代の義教(義円)とも接触はあったのだろう。室町殿に参じた満済は「今河弥五郎参洛了、進退事歎申云々、今度参洛以下振舞旁神妙ニ被思食也、暫可堪忍仕、可被加御扶持旨可申付之由、可仰遣管領由被仰出了(今河弥五郎が参洛した。身の振り方について哀願があったという。室町殿から『今回の弥五郎の参洛については実に神妙と思う。暫くは我慢せよ。支援する』旨を管領に伝えるよう仰せを受けた)」という(『満済准后日記』永享五年七月四日条)。
詳細な義教の言葉は「就今河弥五郎参洛事被仰出旨、今度参洛以下進退旁神妙被思食也、簡要ハ一御左右之間、令在京可待申仰、不可有御等閑」というもので、満済は「可申付弥五郎旨、可仰遣管領由被仰出」たため、奉行の安富筑後守にその旨を伝えたところ、安富は「此仰旨可申含弥五郎、定可畏申入歟」と述べた(『満済准后日記』永享五年七月四日条)。
7月7月、満済に「今河民部大輔方へ下遣力者福一、今夕罷上了」の知らせが届く(『満済准后日記』永享五年七月七日条)。先日、範忠一行の駿河入国日についての勘文を持って発遣された福一は「尾張那古屋今河下野所領、ニテ追着」いたとのことであった(『満済准后日記』永享五年七月七日条)。京都から那古屋までは中世の往還を行くとおよそ150kmとなるが、今川範忠一行の速度は駿河入国(大井川渡河)までおよそ300kmの往還を13日かけて進んでいることから、23km/日程のゆっくりしたペースだった。仮に福一が二日遅れで追いかけたとすると、福一の速度は50km/日程度となり、十分に追いつける計算となる。
7月14日、満済のもとに先日駿河から帰還した「星岩和尚、周浩西堂来臨」し、「今河治部少輔入道申事在之」ことを伝えている。内容は「非殊事、就今河民部大輔国時宜以下可致忠節旨、管領奉書等拝領可畏入」というものであった(『満済准后日記』永享五年七月十四日条)。なお「今河治部少輔入道」がいかなる人物かは不明だが、駿河国在住の今川一族の有力者である。おそらく範忠父・範政の又従弟にあたる治部少輔貞相(『今川系図』)と推定される。
●今川氏想像系図
今川国氏―+―今川基氏――今川範国―+―今川範氏―――――今川範泰―――――今川範政―――今川範忠
(四郎) |(太郎) (五郎入道)|(上総介) (上総介) (上総介) (民部大輔)
| |
| +―今川貞世―――+―今川貞臣―+―――今川貞相【遠江今川氏】
| |(伊予入道了俊)|(伊予守) | (治部少輔)
| | | |
| | | +―――各和貞行
| | | (肥後守)
| | |
| | +―今川貞兼―+―?―今川播磨守【三河今川氏】
| | |(右京亮) |
| | | |
| | | +―――尾崎伊予守
| | |
| | |
| | +―女子(1364-1386)
| | ∥
| | ∥
| | 吉良殿
| |
| +―今川仲秋―――+―今川貞秋―――?―今川下野守【尾張今川氏】
| (右衛門佐) |(右衛門佐入道)
| |
| +―今川国秋【小城今川氏:持永氏】
|
+―今川俊氏――新野俊国―――………………?………………―――――今川新野某
(三郎) (弾正少弼)
永享5(1433)年7月17日、満済のもとに「山徒最勝」が来訪し、このところ不穏な動きをする比叡山につき、山門徒が無動寺谷の「客人神輿」を「奉振上根本中堂」っていて「山上、坂本猥雑以外」という報告がなされた(『満済准后日記』永享五年七月十七日条)。なお、この比叡山の騒擾は「凡使節中内々ハ令存知歟風聞」と述べており、山門使節の円明坊兼宗らが関係しているのではないかという風聞があった。その後義教に対面した満済は、義教から「神輿御動座事」について話があり、「使節中一向結構様思食歟」との認識であった。また、「今河治部少輔入道、同心駿河守護民部大輔可致忠節之由、管領奉書拝領仕度由、以星岩和尚々申入間、其由披露處、可仰付飯尾肥前守云々、今河新野申状又同前、同披露處、不可有子細云々、同申付飯尾肥前了、新野事、自星岩和尚以等持寺僧伯蔵主被申了、仍令披露也(今川貞相入道が、「駿河守護範忠に同心して忠節致すべし」という管領奉書を拝領したい旨を星岩和尚に伝えており、和尚から満済にその旨申し入れがあったため、室町殿に申し上げたところ、飯尾肥前守に仰せ付けるようにとのことだった。また同じく今川新野某もまた同様の申状を提出しており、これも披露したところ、問題なく同様に飯尾肥前へ申付けるようにとの事だった。新野某の申状は星岩和尚から等持寺僧伯蔵主を通じて受けたもので、室町殿に披露)」した。
その後、飯尾肥前守が満済を訪れ、「今河方御教書事」につき「内々可被仰之由、只今御所様被仰出、何事哉」と困惑して尋ねている。義教は事の詳細を語らずに、今川へ御教書を出すように肥前守に指示したのだろう。しかし、肥前守はその御教書に書くべき内容がわからず、満済に泣きついたのである。この時の義教は比叡山への対応を思案しており、さして重要ではない今川方への対応は等閑にならざるを得なかったのだろう。満済は飯尾肥前守に「今河治部少輔入道、同新野両人方へ御教書事歟之由」を教えている(『満済准后日記』永享五年七月十七日条)。17日夜には「京中物騒」という騒ぎがあり、これも山門関係の騒擾であろう(『満済准后日記』永享五年七月十八日条)。
7月18日に「抑有山訴、條々以外嗷訴、可奉振神輿」(『看聞日記』永享五年七月十八日条)という噂が洛中にあり、夜には「山上夜々焼篝」(『看聞日記』永享五年七月十八日条)、「比叡嶽笧、今夜焼之」(『満済准后日記』永享五年七月十八日条)というように、比叡山上では大いに篝火が焚かれて京都に威勢が見せつけられ、前日に続き「洛中物騒」(『看聞日記』永享五年七月十八日条)という騒ぎになっていた。
7月19日、義教は「山訴不被聞食入、只可振神輿之由被仰(山訴は聞き入れられない。ただ神輿を担ぐだけであろう、と仰せられた)」(『看聞日記』永享五年七月十九日条)と、比叡山側の主張を拒絶している。また、同日には満済のもとに「自今河右衛門佐注進在之」った。民部大輔範忠とともに下向した今川右衛門佐貞秋入道からの注進である。それによれば「民部大輔去十一日入国無為、就其、三浦、進藤、狩野、興津、富士以下同心及合戦、雖然民部大輔手者打勝」といい、在方卿勘文の通り、去る7月11日に範忠一行は無事に大井川を渡り、駿河国に入国した。ところがこの際に「三浦、進藤、狩野、興津、富士以下」の国人衆が範忠一行に襲いかかり、範忠被官により撃退されたという(『満済准后日記』永享五年七月十九日条)。三浦氏は駿府館の北東部に拠点を有する一族、狩野氏は駿府館と安倍川を挟む安倍城(静岡市葵区羽鳥)から安倍川流域の湯島城(静岡市葵区俵沢)あたりを拠点とする。興津氏も駿河東部の要衝薩埵峠麓を抑える氏族、富士氏も駿河北東部の国境を拠点とする氏族で、今川惣領家にとっては直接的な脅威でもあったのだろう。
7月20日、伏見殿に「今御所入江殿ふと入来」し、京都の情勢を報告している(『看聞日記』永享五年七月廿日条)。「是神輿入洛明日必定云々、仍室町殿辺騒動、火事怖畏、彼是猥雑之間、暫落居之間、是ニ為御座被入申云々、禁裏仙洞公家人々参集、警固武士等祗候、上下猥雑(神輿の入洛は明日であろうという。そのため室町殿の周辺は騒動し、火事のおそれがある。とにかく猥雑であるため、しばらく落ち着くまでは伏見殿に滞在するということである。禁裏や仙洞に公家の人々が集まり、警固の武士も祗候し、上下にわたって猥雑になっている)」(『看聞日記』永享五年七月廿日条)という。
この日、満済は室町殿を訪ねると、まず義教は「山訴事被仰出」であった。義教は「今度神輿御動座儀、円明以下使節悉同心、剰張本由慥聞食也、一向別心之儀歟」と、今回の神輿動座が、武家政権の比叡山統率の要たる山門使節の円明坊兼宗が中心となって行われたとの確証を得て、叛心を抱いていると怒りを抱いている様子がうかがえる。ただ、もはや「於神輿入洛者無力次第、且ハ時刻歟」と、神輿の入洛阻止は困難との冷静な見方を示し、「鹿苑院殿御代応安年中、山門神輿入洛三ケ度也、内裏、仙洞以下警固事、内々御定」を下している(『満済准后日記』永享五年七月十九日条)。
次に満済は駿河国からの続報として「自今河民部大輔方注進」を「此由内々申入了」した(『満済准后日記』永享五年七月十九日条)。注進状は「去十一日入国儀、先無為祝着」だが、「就三浦、進藤等、狩野、富士、興津令同心寄懸間、岡部、朝比奈、矢部以下者共馳向、終日合戦、寄手数十人打取退散了、其後狩野寄来、於府中今河右衛門佐入道手者共寄合追散了、右衛門佐内者寺島但馬入道、中田両人打死、手負数十人(三浦、進藤等が狩野介、富士、興津と同心して攻め寄せたため、我が方の岡部、朝比奈、矢部以下が馳せ向かって終日合戦となりました。その結果、寄手数十人を討ち取り、敵は退散しました、ところがその後、狩野介が攻め寄せたため、駿河府中で合戦となり、今川貞秋入道の被官が追い散らしました。この戦いでは貞秋入道の被官寺島但馬入道と中田某の両名が討死し、負傷者は数十名です)」というものであった。戦いは今川範忠の一行に岡部氏が合流した直後に起こったと思われ、宇津谷から丸子、佐渡あたりの隘路での出来事だろう。範忠一行は多くの軍勢が伴っていたとは考えにくいため、国人らも大勢ではなかったと思われる。範忠らは彼らを撃退後、府中ヘ入ったた、敵方の大将である狩野介一党が攻め寄せたとみられる。しかし、府中は老練の今川右衛門佐貞秋入道が警衛しており、その奮戦によって撃退された。義教は満済からの報告以前に「自管領申間且被聞食」といい、満済は「民部大輔内者并右衛門佐入道内者、各今度合戦高名、神妙御感之由、自管領可申下之由、為門跡可申管領方」と指示を受け、管領のもとに「以親秀法橋則申遣了」している(『満済准后日記』永享五年七月十九日条)。このとき討死した「右衛門佐内者寺島但馬入道」は、明徳3(1392)年8月28日の相国寺供養に供奉した今川貞秋に「床子(床几か)役」として随った「寺島但馬守藤原泰行」であろう。
●『相国寺供養記』明徳三年八月廿八日条
| 五番 | 今川遠江守源貞秋 | 柴兵庫助藤原家秀(搔副) 長瀬駿河守藤原泰貞 横地尾張守藤原長連 勢多修理亮藤原朝昌 寺島但馬守藤原泰行 加茂七郎藤原助頼 |
| 今川左馬助源氏秋 | 佐竹安房守源秋古(搔副) 英比信濃守小野氏信 井伊修理亮藤原朝藤 菅谷掃部助藤原秋政 栗生右京亮氏広 富田八郎藤原言泰 |
7月23日は「諸大名勢共数多上洛、洛中物騒之外無他」といい、「諸大名遂番夜々河原取陣、馬借可防致用意」(『満済准后日記』永享五年七月廿三日条)という。なお、この「諸大名」については満済も何も触れていないこと、河原で馬借勢を防いでいるのは畠山と山名の手勢であることから、管領以下の有志を指し、彼らの守護国からの兵士入洛を指すと思われる。同日、満済のもとに「自管領書状到来、今日晩頭、山門事書到来間、写進、明日早々御出京可宜」との知らせが届いた。管領書状からうかがえる山門使節からの條目は「事書条目非殊題目也、献秀号光寿院云々、奸曲條々、赤松播磨守、飯尾肥前守猛悪無道次第等書載之了」というもので、要求は「於赤松播磨守被遠流、於飯尾肥前ハ渡賜衆徒手、可被其沙汰由申也」という高圧的なものだった(『満済准后日記』永享五年七月廿三日条)。
●『看聞日記』永享5(1433)年7月24日条(『看聞日記』)
| No. | 義教 裁許 |
原文 | 要約 |
| 1 | ● | 去永享元年神輿動座之時、被成下数通之御教書之間、三千衆依開愁眉神輿帰座之處、無幾程悔返御下知被成置仮令御教書之條、太以所歎存也、衆徒等縦雖致非拠之訴訟、既優神威被裁許之間、親仰請和之善政、奉比天子之一言、綸言一致之御下知、爭猥可及異変之御沙汰乎、旁以口惜次第也、凡山門訴訟者以非為理云、叡慮有之理訴、何可停滞乎事 | 去る永享元年(正長元年の誤り)の神輿動座の時(神輿動座の記録がない)、室町殿から数通の御教書を下されたので、山門の三千衆徒は愁眉を開いて神輿も帰座したが、幾程もなく御教書を取り消すよう御下知されたことは、甚だ嘆かわしいことである。(以下略) |
| 2 | × | 宝幢院者忝貞観聖主之叡願、源家長久之苗裔也、然間彼院起立之御願依異于他、被奉寄数万貫之要脚之刻、猷秀法師可被仰付奉行職之由望申歟之間、雖被成御下知、未能上木一支之企、結句以多年収納之土貢、為奉掠公聞、致諸方之礼節之條、奉為公方為山門、就冥顕不可然、仍猷秀猛悪之所行、不可過之者也、所詮於彼要脚者、悉被召返之、可致早速之造営事 | 西塔宝幢院は清和天皇の叡願により建てられた寺だが、源家はその末裔である。それ故に宝幢院の修復の御願は他氏とは異なり、数万貫の修復経費を寄進されたが、これに際して猷秀法師が造営の奉行職を望んだとのことで、その通りに御下知されたが、今に至るまで木一本すら進捗がなく、結果として多年収められた貢物を、室町殿を欺き奉って諸方への礼物に使っている事は、室町殿にも山門にも実によろしくない。よって、猷秀の非道な所行は看過すべきではない。宝幢院の修復経費は猷秀から召返した上で、早々に造営されたい事。 |
| 3 | × | 猷秀望申釈迦堂関務、不致破損之修理而、朽損之柱等、或付墨塗丹、成其償之條、前代未聞所行也、宜有御検知事 | 猷秀は釈迦堂の関所代官を望みながら、破損の修理を行わず、朽ち損じた柱などに墨を付けたり丹を塗ったりするのみで修復したとしているのは、前代未聞の所行である。ぜひご確認される事。 |
| 4 | × | 猷秀法師諸方借銭事、違天下之大法、背山門格式、一倍之外無時限、致散用、相語奉行、令押領方々所領田園等事 | 猷秀法師が諸方で借金をしている事は、天下の大法に違反し、山門の格式にも背いている。際限なく費用を使い、奉行に命じて方々の所領や田園を押領させている事。 |
| 5 | × | 猷秀法師者既放覚大師門徒、削山徒之名字上者、速召給衆徒乎、與俗名可刎首事 | 猷秀法師は、既に慈覚大師の門徒から追放し、山徒の名字を削った上は、速やかに衆徒に召し給い、俗名を与え首を刎ねるべき事。 |
| 6 | ● | 当国愛智庄者、当社日神供之料所也、仍座禅院代代雖致奉行、至有罪科、被改奉行職者、被社中仰付歟、不然者、以山徒可被申付歟之處、号御料所被仰付守護方之條、為神領非例事 | 当国愛智庄は、日吉社の日神供の料所である。よって座禅院が代々庄園の奉行をしてきたが、罪科により奉行職を解かれたのであれば、奉行職は日吉社中に仰せ付けになるか、もしくは山徒に申付らるるべきであるが、御料所と称して守護方に仰せ付けられることは、神領として例がない事。 |
| 7 | × | 当御代、殊政化超于前々、撫民勝于代々、是併継絶興廃、為御政道之處、赤松播磨守奉掠上聞、偏猷秀贔屓之儀在之間、就毎事不恐公方不憚外聞、就賄賂属詑、恣令許容、奉為公方為不忠族之間、速可被処遠流事 | 当御代は、殊に政化では前々を超え、撫民では代々に勝る。これはまさに絶えたものを継ぎ、廃れたものを興すという御政道たるところであるが、赤松播磨守は御上を欺き、ひとえに猷秀を贔屓にしており、何事も室町殿を恐れず、外聞も憚らず、賄賂を取って人を欺き、やりたい放題だ。室町殿に対し奉り不忠の者であるので、速やかに遠流に処せられるべき事。 |
| 8 | ● | 近年為體、被没倒山徒之所帯、被宛行公家武家甲乙人之間、顕密之要脚等令失墮、及御願之違乱之條所、歎存也、所詮、已前御罪科之山徒、於座禅院、等持、勝行、戒光者、如元可預安堵之御成敗事 | 近年、山徒の所帯を没収し、朝廷や武家、諸人に宛行われているため、叡山の費用が失われ、御願が損なわれているのは嘆かわしい。以前に御罪科を受けた山徒の座禅院、等持坊、勝行坊、戒光坊は元のように所帯の安堵のご裁決をされたい事。 |
| 9 | × | 三千聖供者、仏聖灯油之要脚、満山禅徒之資糧也、如風聞者、以聖供之内、山門奉行飯尾肥前守契約之、令受用云々、背御下知、構已用事 | 三千の聖供は、仏聖灯油の費用であり、満山の生活の糧である。 噂では、この聖供の費用のうちから山門奉行飯尾肥前守が契約して私的に受用しているという。室町殿の御下知に背き、自分の事に使っている事。 |
| 10 | × | 肥前守令贔屓猷秀事者、別而契約之子細依有之、不顧後日之突鼻、偏任欲心不弁両方之理非、片手打万事猷秀理運由申成之條、為奸曲事 | 飯尾肥前守が猷秀を晶眉している事は、別に契約の子細があり、後日の咎めを考えることなく、ただ欲心のままに両方の理非を弁えず、つねに猷秀の肩を持って道理だと申している事は、奸曲である事。 |
| 11 | × | 於肥前守者、為断向後傍輩之積習、同渡給衆徒手可致其沙汰事 | 飯尾肥前守については、今後の室町殿の側近らの奸曲を絶つ戒めのためにも、猷秀と同じく山門に渡す御沙汰の事。 |
| 12 | × | 不限山門奉行、諸奉行構奸曲、不致廉直之披露之條、緩怠之至、誠而有余者乎、殊飯尾肥前、同大和、不経管領辺次第之沙汰、直掠申公儀之條、背御沙汰大法事 | 山門奉行に限らず、諸奉行が奸曲を企て、正しい報告をしていない件については、怠慢の至りこの上ないだろう。とくに飯尾肥前守、飯尾大和守は、管領を通さずに沙汰しており、直に公儀を蔑ろにしている件は、御沙汰、大法に背いている事 |
| 以前條々大概如斯、凡一山抽誠号仰皇化、三千運志号祈武将者也、然間今般之神訴者、全非軽上意、敢不忽善政、神輿頂戴之儼儀者、偏改奉行奸曲、正為仰公儀之徳化也、裁許速至者、七神含咲、各帰座于本宮、増花洛潜衛之擁護、満徒合掌互止住于本房、添御願長久之精祈焉、何捽別心、更非隠謀之趣、三七之明祇、垂知見三塔之仏陀、被照覧之旨、為達衆望、於上聞、粗勒子細於右而已 | 山門の主張は大体この條々である。叡山全体で誠忠を表し、皇化を仰ぎ、三千衆徒の志は室町殿を祈願するものである、そのため、今回の神訴はまったく上意を軽んずるものではなく、敢えて善政を蔑ろにする考えもない。神輿の動座は偏に奉行の奸曲を停止させ、正しく公儀の特化を仰ぐためである。裁許が速やかに行われれば、七神は笑みを含んで各本宮へ帰座し、ますます京都を擁護し、満山の衆徒は合掌して根本中堂から引き払い、御願長久の祈祷をする。どうして別心を持とうか。まったく陰謀を企てる意思もなく、三十七尊の明祇、叡山三塔の仏陀の知見を垂れ、照覧せらるの旨、衆徒の希望を達せられんがため、室町殿の上聞に入れるため、粗々子細を右の通り記す。 |
山門側は、光寿院猷秀や赤松播磨、飯尾肥前等の様々な「奸曲條々」が記され、猷秀は除籍したので山門に給わった上で俗名を与えて刎首を要求するという猷秀への憎悪と、その猷秀と結んで「贔屓」して山門に不利益な悪事を働いた赤松播磨守は室町殿に対して不忠であるから早々に遠流に、飯尾肥前守は猷秀同様に山門に引き渡しを要求したのだった(『看聞日記』永享五年七月廿四日条)。また、神輿動座は「神輿頂戴之儼儀者、偏改奉行奸曲、正為仰公儀之徳化也」を目的とするもので、「今般之神訴者、全非軽上意、敢不忽善政」とする。神輿騒動は武家方と叡山領の間にあった所領問題であったことがわかるが、将軍義教との直接的な対立は望まず、原因はその側近にあるとして側近をターゲットに騒動を起こしたものであった。
7月24日朝辰終、醍醐寺に「宝池院書状到来」した。それによれば「夜前京中物騒以外也、仍以親秀法橋被啓御所様案内處、非殊事云々、於河原辺時聲ヲ二三ケ度揚云々、依之洛中猥雑、馬借等所業歟(23日夜前、京中は非常に物騒がしかった。そのため親秀法橋を室町殿へ遣わしてこのことをお話ししたところ、問題ないとのことだった。河原辺で鬨の声が二、三度揚がったが洛中の猥雑はこれによるもので、山門使節が使嗾する近江馬借の所行か)」(『満済准后日記』永享五年七月廿四日条)というものであった。
その後、未初に満済は出京したところ、管領持之が訪れ「山訴事、先無為御成敗尤可然存、於張本山徒等者追可有御沙汰條、殊可輙也、神輿入洛旁大儀存、可然様一向御申お憑存」と依頼があり、満済は「何様可申旨領掌了」した(『満済准后日記』永享五年七月廿四日条)。続けて「山名禅門」が来訪。「山訴無為御成敗珍重之由申」した。そして「山名物語次夜前以奉行被仰出、馬借等可乱入洛中之由風聞也、河原ニ伏せ野伏ヲ置可沙汰云々、只今夜中亥初歟事也、下辺者共可遅々歟、雖為小勢可遣置由御返事申了、子末丑初刻計歟、少々遣人處、於大原辻馬借三百人計罷出處、此方者五六十人歟、金ツメニ行逢了、暫ハ両方子マリ逢タル計也、暫アテ、自此方何者ソ敵歟ト尋處ニ、何事ニ御方ニテハ候ヘキトテ矢ヲ同時ニ放間、此方ヨリモ散々射払間、二三人ハ当座ニ射伏了、其後又後ニ馬借一手寄来間、其モ悉射払了、此方ニハ手負一人モ無之(夜前、室町殿より奉行が参り、馬借等が洛中に乱入するという風聞があるので、山名の勢を今夜のうちに河原に伏せておくようにとの指示がありました。下辺の者共が集まるのには時間がかかりますと述べると、小勢でも遣わすようにとの御返事がありました。子終から丑初ほどに少々遣わすと、大原辻の辺りで馬借三百人ほどが現れました。こちらは五、六十名ばかりでした。双方ともに行き逢うのみでしたが、しばらくしてこちらから『何者だ、敵か』と尋ねたところ、『どうして味方であろうや』と言って矢を放ってきたので、こちらからも散々に矢を射かけたところ、二、三人をその場で射伏せました。その後、また背後に馬借が一手押し寄せたため、こちらへの矢を射払い退散させました。こちらには手負は一人もいません)」という戦いの様子を伝えている。
その後、満済は「申終歟、参室町殿、内々時宜参了」と室町殿を訪問。「去夜猥雑、無心元存旨等申了」した。「就其、管領只今来申」すには、管領持之は義教に「山訴事、先無為御成敗尤珍重、於張本人者、追堅可有御沙汰條、殊可然存由」を述べたという。義教は満済に「今度事書如此トテ被取出」れ、満済はこれを「一見了」している。義教は「此條目内、少々ハ可有御載許之由」の気持ちがあり、「仍此子細、申遣管領了」したことを話している(『満済准后日記』永享五年七月廿四日条)。
翌7月25日、満済は「参室町殿、御対面」し、7月24日の「就山訴事、管領内々申入無為御成敗事、今度條目十二ヶ條内三ヶ條」は「以上三ヶ條事、可有御載許、其外事ハ雖何様儀出来、就是非不可有御許容旨可仰管領」という(『満済准后日記』永享五年七月廿五日条)。
●義教が山訴のうち認めることが妥当とした三ヶ条
| 一 | 正長元年神訴時、御載許御教書不幾被召返云々、此條於山門理訴者、雖為只今重可被加御下知 | 正長元年の訴えの際、ご裁許の御教書を出されたのにすぐ召し返された件。この件は山門側の訴えがもっともであり、今更だが御教書を再度下す。 |
| 二 | 愛智庄、日神供料所也、而号御料所被仰付守護人事歎入云々、此儀又宜事也、早々可被退守護人也 | 近江国愛智庄は日吉社の日神供料所である。ところが当地を御料所と号して近江守護に仰せ付けられたとの訴えがあったという。このこともまた山門側に理がある。早々に守護に手を引かせるように。 |
| 三 | 山門領無謂被宛行公家武家甲乙人云々、此事誠真実山門領、若如然事在之者不可然歟、在所ヲ注申ハ可有御成敗也 | 山門領がいわれもなく朝廷や武家の何某に宛て行われているという。これが本当に山門領であるならばあってはならないことであろう。該当在所を注進すれば然るべく裁決する。 |
| (その他九か条) | 雖何様儀出来、就是非不可有御許容 |
どのような件であろうと、認められない。 ※すべて猷秀、赤松満政、飯尾為種に関する条項。 |
義教は、十二か条のうち山門領に直結し、且つ武家方にも非がある可能性がある三ヶ条は山門側の訴えを認めた。一方で、義教が山門領の奉行としていた山門僧の光寿院猷秀、側近の赤松播磨守、山門奉行の飯尾肥前守の三名に関する懲罰条項は一切認めない姿勢を示したのである。
7月26日、満済のもとに「今夜自将軍御書在之」った。「此御書、自三條宰相中将方伝賜了」で、義教から義兄三条実雅を通じて満済に遣わされている。内容は「就駿河事、今河播磨守可被下遣彼国、然当守護今河民部大輔間、若不快儀在之歟、如何(駿河の件で、今川播磨守を駿河に下向させようと思うが、守護今川範忠との仲が悪いと聞くがどうであろうか)」というものであった。これに満済は「不快儀、於内心者不存知候、縦雖其儀候、被仰付事、定不可有緩怠歟、可被下遣之條尤可然存云々、遠江、三河両国勢駿河合力事、被仰出條簡要由(不仲についてはどうにもわかりません。ただそうであろうと、御定に緩怠があってはならない。下向させる件は大変良いと思います。遠三両国勢は駿河勢と合力するよう仰せられることは重要です)」を申し入れている(『満済准后日記』永享五年七月廿六日条)。義教は駿河国人の叛乱に対処するため、遠州今川了俊の末裔である今川播磨守の派遣をしたことがわかる。「今川播磨守」の具体的な名は知れないが、軍記物『島津国史』に「応永自六春二月、今川播磨守貞兼攻之」(『島津国史 巻之八』応永六年二月条)と見える。その按として「今川播磨守貞兼、族属不詳、諸家大系図貞世入道了俊第四子曰右京亮貞兼、豈此人也、旧譜以為範氏第二子、不知何拠」とあり、確実ではないが了俊子息の右京亮貞兼が同人であろうかとしている。もし応永6(1399)年の「今川播磨守貞兼」が了俊四男の尾崎右京亮貞兼と同一人物とすれば、永享5(1433)年下向の「今河播磨守」はその子世代となろう。「今川播磨」はもともと「駿州国伊豆堺」に居たが、応永35(1428)年正月頃に「不申御暇自由出家シテ上洛」して義教(当時の義円)の不興を買い「未及対面也」という人物であった(『満済准后日記』応永卅五年二月十日条)。この「自由出家」が今川範政との確執のためであれば、惣領家とはよい関係ではなかったことになる。ただ、現当主範忠も父範政に廃嫡されて出家のうえ上洛し、義教の庇護下にあったことから、両者は同時期に京都におり、この間に何かがあった可能性もあろう。ただ、応永35(1428)年当時、管領畠山満家入道が「駿河国伊豆堺ニテ此者計心安様存者也」と述べているようにかなり有能な人物であり、満家入道の「有御免早々可被下歟」という要請に義教も応じて「今河播磨ニハ有御対面、早々可被下」としている(『満済准后日記』応永卅五年二月十日条)。
7月27日、満済に届けられた「自将軍御書、如夜前伝賜了」によれば、「甲斐国跡部、伊豆狩野等、令合力富士大宮司ヲ、可発向守護在所風聞在之、然者京鎌倉雑説因縁、旁不可然歟、此事内々自管領私可申遣上杉安房守方之條可為何様哉(甲斐国の跡部、伊豆国の狩野介らが富士大宮司を合力させ、駿河の守護在所に侵攻するという風聞がある。そうであれば京と鎌倉の雑説や因縁からして、いろいろとよくない。この事を内々に管領より私的に上杉安房守へ申し遣わそうと考えているが、いかが思うか)」(『満済准后日記』永享五年七月廿七日条)とのことであった。満済は「以管領私儀此事能々可申遣上杉安房守方之條、尤宜存旨申入了(管領が私儀としてこの件を上杉安房守によくよく申し遣わすことは、大変良いことと存ずる)」(『満済准后日記』永享五年七月廿七日条)と返答している。なお、この情報は、甲斐国で起こっていた国内騒乱(武田右馬助信長と跡部氏の戦闘)と、駿河大井川沿いの狩野介と駿東富士大宮司の提携が混ざって京都に報告されていた可能性があろう。
●永享5(1433)年4月~7月にかけての甲斐国の戦死者(『一蓮寺過去帳』)
| 永享五年 | 阿号 | 名字 |
| 4月29日 | 監 | 矢作 |
| 昌 | 河内 | |
| 量 | 匠佐作 | |
| 時 | 仁勝寺 | |
| 立 | 柳澤 | |
| 受 | 山寺 | |
| 聲 | 牧原 | |
| 長 | 長塚 | |
| 徳 | 山縣主計 | |
| 眼 | 十二太夫下人 | |
| 頓 | 林部 | |
| 7月25日 | 連 | 黒石 |
翌7月28日、義教は「駿河へ僧お下遣」した。理由は「其後国時宜毎事無心元間、慥為聞其説也(駿河国の情勢が常に不安なので、確実な情報を聞くためである)」(『満済准后日記』永享五年七月廿八日条)という。彼と入れ替わるように、閏7月1日、「自駿河今河右衛門佐入道使者西堂一人参洛、今河民部大輔同前申也(駿河より今川貞秋入道の使者西堂一人が参洛した。今川範忠が「同前(何を指すか不明)」ことを述べた)」(『満済准后日記』永享五年閏七月一日条)という。
このような中、閏7月3日の朝辰初、「馬借等発向北白河放火之間、畠山勢罷向追散」という事件が勃発する(『満済准后日記』永享五年閏七月三日条)。馬借は山門使節の円明坊らが支配下に置いて管理しており、明らかに山門側が関わった事件であった。北白川に結集した馬借は、畠山満家入道の軍勢により蹴散らされたが、「雖然、北白河数十間焼失」という被害が発生している。「北白河者共坊戦、両方手負在之、北白者一人死」したが「畠山手無恙」(『満済准后日記』永享五年閏七月三日条)という。伏見宮にもこの報告が届けられ、閏7月3日の「未明、北白河へ馬借寄来、在家放火、河原警固畠山馳向、追払云々、洛中又騒動、凡諸大名三ケ夜ツゝ結番、河原取陣、神輿有入洛者、可奉防用意」(『看聞日記』永享五年閏七月三日条)と記され、細川、斯波、畠山、山名、赤松ら有司が三日ごとの警固結番を務めることになったという。
その後、管領持之が満済に「自管領以使者若槻入道申」したことは、義教が「就山訴事、昨日以両使被仰出」こととして、「先度ハ、山訴條目内両三ヶ條、可有御載許之由雖被仰出、今度山門悪行超過、先々儀、公方ヲ奉調伏事、慥又被聞食了、旁存外至極ニ思食間、次江州辺土一揆事、可蜂起由頻為山門興行云々、次方々通路等可相止企等悪行非一事、仍江州守護可被下遣歟之由思食(先頃は山門からの十二ヶ条の訴状のうち三ヶ条は裁許せよと申したが、この度の山門之悪行は余りに酷い。またこれ以前には私を調伏しようとしたことを聞いている。色々と思いもよらぬことばかりだ。もはや訴えのうち一項たりとも許容することはない。次に近江あたりの土一揆については、これも山門が蜂起せよと頻りに指示したと聞く。通路の妨害を企てるなどの悪行はこの一事に収まらない。なので近江守護を近江に下向させようと思う)」(『満済准后日記』永享五年閏七月三日条)と、義教が山門のあまりの横暴に我慢ならず、その悪行を鎮圧したい考えによって、近江守護の派遣を検討するように管領持之に諮ったものであった。
これに持之は混乱の助長は得策ではないという考えから「公方調伏申事以外次第也、次江州守護可被下遣事、可被仰談諸大名歟云々、重又仰出、諸大名御談合事、先可有御思案也、江州守護下国事ハ先不可被仰也、内者共ハ悉可下遣旨可仰付云々、為国警固由(室町殿の調伏などということはとんでもないことです。ただ、近江守護を下向させることは、畠山ら有司にしっかり図るべきです。(使者若槻の言葉で)、管領がさらに仰せられたのは、諸有司との御談合については、まずどういった対応をするか御思案されるべきです。近江守護の下向のことは先に仰せられてはなりません。守護被官人たちは悉く下すように仰せつけられるべきと思います。近江国の警固のためです)」(『満済准后日記』永享五年閏七月三日条)との返答をしたという。持之使者の若槻入道は「委細、此門跡出京時、猶可被仰出旨被仰下也、早々近日御出京、自何可目出」(『満済准后日記』永享五年閏七月三日条)と、満済の出京を伝えた。
持之の依頼により、閏7月5日早朝、満済は出京して法身院に入ると、知らせを受けたとみられる管領持之、畠山満家入道、斯波義淳、一色義貫、赤松満祐入道の五人がそろって訪問し、「就山訴事申入子細等、以前内々可有御裁許之由三ヶ條、先被仰遣山門、随彼等申様又可有御料簡歟、簡要、先無為御成敗第一珍重、於張本人者追可有御沙汰之條、殊可輙、於有神輿入洛者、天下重事大義不可如之歟、無勿体存云々(山訴について室町殿に申し入れる内容について、先日内々に裁許すべしとの指示があった三ヶ条は、まず山門に遣わされ、彼等の申すことも考慮すべきか。つまり無為の御裁許がもっとも重要ということです。この騒擾の張本人については追って沙汰を行うことが妥当でしょう。神輿が入洛すればこれ以上の天下の重大事はない。とんでもないことだ)」(『満済准后日記』永享五年閏七月五日条)と語った。
その後、満済は室町殿へ「申初参申了」て義教と対面した。義教は「諸大名来申旨、山訴事ニ條々申入了、然者面々如申、先三ヶ條事可有御裁許旨、為管領可下知山門、随彼等申様、重可有御料簡(管領以下が来て、山訴のことを申し入れていった。彼らの申すように、まず三ヶ条の事は裁許する旨を管領を通じて山門に下知せよ。彼らの申し様によってさらに考えよう)」(『満済准后日記』永享五年閏七月五日条)と満済に管領への指示を依頼した。
また「駿河国々人狩野介、富士大宮司、興津、已上三人可召上旨、可仰管領(駿河国の国人狩野介、富士大宮司、興津の以上三名を召喚する旨も管領に話すように)」ことも依頼されているが、これは「此事等、内々自駿河守護申子細在之、依之如此被仰出也(このことは、内々に駿河守護範忠よりの要請があったため、これを仰せられた)」という(『満済准后日記』永享五年閏七月五日条)。これらを受け、満済は室町殿に「召寄管領」せ、義教からの「山訴内三ヶ條御裁許事、可被申遣山門事」などを伝えている(『満済准后日記』永享五年閏七月五日条)。また、「赤松又来、且御裁許珍重々々、畠山、武衛、一色以使者畏申也(赤松満祐入道が再度法身院へ参り、山訴の御裁許は誠に目出度いことだとのこと。畠山、斯波、一色も使者でこの旨を伝えてきた)」している(『満済准后日記』永享五年閏七月五日条)。
閏7月9日、醍醐寺の満済のもとに「自管領、以安富筑後守申」すには、「先日御裁許三ヶ條令申山門之處、重如此以事書申入云々、則案写賜之也(先日の御裁許三ヶ条を山門に伝えたところ、重ねてこのような事書を申し入れてきました。室町殿がこれを写した案を管領に下されました)」として、山門事書の写しを満済に渡した。これを読んだ満済は「以重事書、先被聞調諸大名意見、追可被申入之條可宜歟(追加の事書について、まず諸大名の意見を聴取されたのち、室町殿に申し入れることがよいでしょう)」(『満済准后日記』永享五年閏七月九日条)と返答している。満済の返事を持ち帰った安富筑後守からその旨を聞いた管領細川持之は、ただちに有司諸大名に追加の山訴条々について意見聴取を行った。
そして翌閏7月10日、醍醐寺の満済のもとに「及夜陰、自管領音信、就山訴諸大名意見大略調了」と意見聴取の完了を伝え、「今日御出京可畏入」と要請した。しかしこの使者が醍醐寺についたのが「戌終到来間、明日可出京旨申遣了(夜二十一時の到来であったため、明日の出京となる)」(『満済准后日記』永享五年閏七月十日条)と伝えた。
閏7月11日、満済は「巳終出京之由、申遣管領」たところ「管領則来臨」し、「諸大名意見申詞、各注紙面進之了」した。その内容は「面々申詞大略同前、先無為御成敗、於張本人者、追可有御沙汰條尤可宜(面々が言うことはほぼ前回閏7月5日の通りで、まず平穏に処置され、張本人は追って御沙汰することが最善でしょう)」というものだった。これに基づいて満済は義教に「以諸大名申詞、予披露之處」したが、義教は「光聚院并播磨守、飯尾肥前守等流罪等事、不得其意由再三被仰了(猷秀、赤松播磨守、飯尾肥前守の流罪等については、行う意思はないことを再三仰せられた)」とのことだった。とくに「所詮、張本人追可有御沙汰條、可輙由面々申也、此條猶御不審、山徒使節、自今以後参洛不可在之歟、於在坂本者、如何輙可有御沙汰哉、神輿動座事ハ可為毎度間、然者毎度被優神、雖申何様、非拠可有御載許歟、管要張本人沙汰事、猶沙汰様具可申入(諸大名は張本人は追って御沙汰あるようにという件だが、簡単だと面々は言うがどうか。今後、山門使者の参洛を禁じるか。彼らは坂本にいるのにどうして容易に沙汰できよう。神輿動座の事はいつものことだが、その度に神威を優先するのであれば、山門が何を言おうと非道理な裁許をするのか。張本人の沙汰についてどうするのか詳細に申し入れよ)」と伝え、満済は「此由、重可管領由申入了」し、室町殿を退出。その後、満済は「召寄管領、此仰旨申」すと、持之は「面々又載紙面可申入由、何様令申、明旦可持参」(『満済准后日記』永享五年閏七月十一日条)と述べて退出した。
翌閏7月12日、管領持之が法身院を訪問し、昨日約束の「畠山以下申詞各注一紙」を持参した(『満済准后日記』永享五年閏七月十二日条)。満済はこれを見ると「此趣、大略同前」で、内容は「先早々無為御載許珍重、張本人御罪科次第迄可申入(まず、早々に三ヶ条を御裁許されることが大事です。張本人の罪状についてまで申し入れるほうがよい)」というものだった。満済は室町殿に参じて「則此面々申詞持参申入」るが、義教の「時宜趣」も「大都如昨日」であり、満済は「再往雖申、只同篇仰、無力也」という感想を漏らす。ただ「管領種々猶申旨在之」と、管領持之が「所詮於張本人者、就是非被仰出名字、可致厳密沙汰、一向無為御載許、当職初度儀ニ被仰下者、可畏入(張本人については、名前を仰せられて厳密に沙汰されるよう。ただ無為の御裁許を私に最初に仰せられればありがたく存じます)」という。満済はこれを義教に「此旨数度申」たところ、義教は「張本沙汰、一段管領以告文等慥申入者、可有無為御載許由被仰也(張本人の沙汰については、いったん管領が告文を以て慥かに申し入れれば、無為の裁許をしようと仰せられた)」という。満済は「此旨申管領」と、管領持之は「罷帰、内者ニ加談合、明旦可申入」という(『満済准后日記』永享五年閏七月十二日条)。
そして翌閏7月13日、管領持之は法身院に満済を訪ねると「飜牛玉裏捧告文申入旨在之」という(『満済准后日記』永享五年閏七月十三日条)。管領告文の内容については「隠密題目間不及注置、別紙ニ又條々申入了、仍二通持参申入」たが、満済は「重聊被加入文言在之、仍管領内者安富紀四郞召寄、仰含之間、即時書改持参」した。その直後に満済は室町殿に参じて「則備上覧」すると、「今日重二ヶ條、猷秀法師流罪事、飯尾肥前守為種被改山門奉行、可被止出仕旨被仰出」た。義教は神輿入洛による影響を最小限に止めるべく山訴に応じたのであった。満済は「此旨即申管領間、畏申入」り、「仍両條載許御教書、今日可成遣山門」という。ただ、「定猶可申入歟」と山門側の重ねての要求があるだろうと推測している。
夕刻、満済は醍醐寺へと戻るが、「自伊勢守護方送者数十人召進了」と伊勢守護土岐氏の護衛が数十人付けられた。そして、「今夜西坂本ヲ松明数千下山云々、今日神輿入洛儀兼風聞也、諸人為令仰天歟」と、比叡山から西坂本に多数の松明が下山していく様子が見えたという。今日神輿が入洛するのではないかという風聞が流れ、皆恐れ戦いたという。
閏7月17日朝、満済は醍醐寺から出京したが、このとき「自伊勢守護方、迎兵士数十人召進了、自曉天罷入」という(『満済准后日記』永享五年閏七月十七日条)。先日の醍醐寺への帰路は京都からの護衛であったが、この日は義教の命により早朝から土岐勢が迎えに来ていたのであった。満済は「希代懇志真実々々難有事也、坊人サヘ如此懇志無之、希代々々」と大変な喜悦を遺している。同日昼前、満済は室町殿へ参じたが、義教から真っ先に「信乃守護小笠原参洛之處、於江州草津辺、馬借土一揆者数千人取籠、大略終日相戦云々、小笠原内者一人於当坐被打丁、雜人手負死人数十人在之云々、馬借当座ニテ十余人打取、山法師一人被打、罷通事不叶、自其引返森山」という話を聞く。
続けて「諸大名、今度山訴事等、申旨等具尋承了、又愚意趣、不残心底申入之由、種々蒙仰了、眉目至此事也、帰坊之後、載書状申入旨在之、管領来臨、両條御載許御返事、定今明可申入歟云々、條々談合事在之」という(『満済准后日記』永享五年閏七月十七日条)。
閏7月18日、管領から「今度御載許両條事先畏申、猶以事書申入旨在之」として、安富筑後守が醍醐寺の満済に遣わされ、義教から賜った山門事書の写しが満済に渡されている。そこには「猷秀并為種事、可渡給衆徒手之由申也」と記されていた(『満済准后日記』永享五年閏七月十八日条)。翌19日には管領からの「先度御載許事申遣山門處、重又申旨在之、御出京可畏入」という書状が醍醐寺にもたらされる(『満済准后日記』永享五年閏七月十九日条)。満済は「及夜陰間明日可出京」と返答するが、21日から持病の「心痛」を発症したため数日動くことができず、23日に管領持之から「就心痛事」の見舞いの使者として安富筑後守が醍醐寺を訪れたため、満済は「既得滅間、明旦可出京旨申遣」と返答(『満済准后日記』永享五年閏七月廿三日条)。24日早旦に出京した。
満済が法身院に入ると、管領持之は「山門重事書并自山門閇籠衆中遣山門雑掌方状一通」を持参して来臨した。これらの内容は以前と同様で「猷秀法師并為種男両人事、渡賜衆徒手可致其沙汰」を要求したものであった。この二通を預かった満済は、室町殿へ参じて義教に対面し「管領申旨等具申入」ると、義教は「所詮、於猷秀事ハ内々逐電由被聞食也、然者可為其分歟、於為種飯尾肥前守者、可被下国之裁由」と述べるが、「諸大名、以前種々申入キ、只今ハ管領一人申入、又御載許儀被仰出」と、この件については、山門の要望に応じる旨を伝えている。なお、管領持之一人ばかりが苦労している現状はどうなのかとして、畠山、斯波、山名、一色、赤松ら諸大名も当初より山訴について様々に意見していたのであるから、各々責任を持って告文を提出の上、意見を具進するよう命じている(『満済准后日記』永享五年閏七月廿四日条)。
閏7月25日、室町殿を訪れた満済は、猷秀と飯尾為種両名へ行った配流の詳細の報告を受けた(『満済准后日記』永享五年閏七月廿五日条)。義教は「猷秀法師、昨日逐電由被仰了」だが、その顛末は、義教が「此法師事落着不便ニ思食」して、斯波義淳の分国越前国へ遁れさせるべく、守護代の甲斐将久入道に「越前国ヘ下向ニ就テ、路次以下事、内々被仰付」たが、甲斐は「故障申入了」という。義教がその理由を問うと「此仰等、定不可有其隠歟、然者、山訴猶不可休因縁之間、不可然由存」と述べた。これに義教は「此申状又過分也、兎モ角モ、如仰可令奉行條、甲斐カ身ニハ可相応歟、仍於此儀者相違了」と不満を漏らすも、「所詮、管領分国丹波ヘ可下遣、於路次等事者、無其怖畏様、管領能々可申付」と、猷秀法師の下向先を越前国から管領分国の丹波国へと変更した。しかし、今度は管領持之が「丹波ヘ下向事可存知、但此儀一向表裏御沙汰之様、定山門可推量申入歟、只流罪之儀ハ一途也、凡ハ近国也、分国也、旁雖不可宜候、被仰出事間、不可申是非候トテモ、流罪儀ニテ暫ハ不可被召返者、中々遠国可然間、分国ハ何モ同前ニ候ヘ共、四国旁宜存、万一就近国、重山訴申儀候者、其時又可被渡遠国條事儀、不可然存」と、丹波ではなく四国へ落としたほうが山門からの注文などを勘案しても都合がよい旨を伝えた。これには義教も「誠此儀宜」と賛成し、四国への下国と決定した(『満済准后日記』永享五年閏七月廿五日条)。
また、飯尾肥前守為種は尾張国への下国となった。こちらにおいては「強非流罪儀歟、先此分被定」となり、御教書が下された。この件については、召し出された細川右馬助持賢より兄の管領持之に伝えられた。その後、満済のもとに斯波義淳が来臨し「山訴、無為御成敗、先珍重々々」と述べている(『満済准后日記』永享五年閏七月廿五日条)。
醍醐寺に帰寺後、「自今河民部大輔方注進」が到来する。それによれば「今河播磨入道下国事ニ付テ、国時儀申計也、非殊儀、同名尾崎伊与守不参陣、結句、同名各和三郞、可属播磨入道手等申」(『満済准后日記』永享五年閏七月廿五日条)という駿河の情勢を伝えるもので、駿河国人の叛乱を鎮定すべく駿河へ下向した今川播磨入道のもとに同族の今川尾崎伊予守は参陣せず、今川各和三郎がその手に属して合戦したという。
閏7月28日にも「自駿河又注進到来」している。それによれば「同名播磨入道罷下以後、国物騒、狩野、富士以下、三浦、進藤等罷出、国中所々放火、剩近日可指寄府中云々、遠江、三河勢早々可有御合力」というものだった(『満済准后日記』永享五年閏七月廿八日条)。駿河国での叛乱がなかなか鎮圧されない状況が報告され続けたため、義教は相談のため赤松播磨守を醍醐寺に遣わして満済に出京の指示をし、閏7月30日午後、満済は「就駿河事、俄可出京旨、以赤松播磨蒙仰了」に応じて出京。室町殿に参じて義教と対面した。義教は合力について「駿河合力勢事、遠江、三河両国、先不可有子細哉之由申入」ことで、斯波義淳へ「尾張国事、可略之由」と伝えるよう指示している。また「狩野、富士、興津等、重可被召上之由、被仰出間、申遣管領了、其身所労云々、息共間可罷上」と、狩野介、富士大宮司、興津らの召喚を管領持之に命じた事、「今河播磨入道方へ、自管領以奉書申旨等同被仰出了」した旨も満済に報告した(『満済准后日記』永享五年閏七月廿八日条)。
8月4日、満済のもとに「重山門事書案写」を持参した管領使者が訪問した。山門側の事書状には、赤松播磨守の件については管領持之が訴訟の取り下げを幾度も申し入れたため重訴を取りやめる一方で、義教が勘発していた「坐禪以下山徒御免事」を固く申し入れている(『満済准后日記』永享五年八月四日条)。この背景は不明だが、赤松遠流の重訴停止と座禅院らの赦免を交換条件としていた可能性があろう。義教も「坐禅院以下御免事、早々御載許尤可然由、畠山以下諸大名申入旨、今日可然様御申、可畏入云々、何様可申入旨返答了」と、坐禅院以下を赦免したのであった(『満済准后日記』永享五年八月六日条)。満済も室町殿へ参じて義教に面会し「管領来、申山徒御免御載許早々可然由、一同申入旨披露」すると、義教は「御載許、不可有子細」とこれを追認した(『満済准后日記』永享五年八月六日条)。
ところが、8月12日未明「自山門大勢三井寺へ押寄」という事件が起こる(『看聞日記』永享五年八月十三日条)。理由は「今度山訴不与力、公方へ参、其無念」とあるように、山訴に非協力的であったための対立であったが、これを事前に予想していた園城寺側は「寺中自元構城郭用意」しており、「於木戸口責戦、一木戸被破責入」られるも、「自二木戸打出、浜へ追出」と、琵琶湖畔まで山門勢を押し返した。これに「又、山徒大勢入替責戦之間、引返」とまた入れ替わり立ち替わり戦って攻め戻し、「其時、寺方四人被討了」と、園城寺勢は四名が討死している。結局合戦は「自辰刻至晩頭」まで行われ、「両方手負数多云々、三井寺手負七十余人、死人四人、手負及七百人云々、死人何人不知、山門寺城不責落、山門引退之時、辻堂一宇焼」という。山門方には近江馬借も参じていたが、「但、馬借号所行山徒、不存知之由」と「後日陳申」(『看聞日記』永享五年八月十三日条)ている。
この山門側の所業に怒った義教は、8月15日夕刻、「三井寺自公方御合力、武衛勘解由小路夜前罷向」と、義淳を園城寺の救援のために派遣した。当初は「畠山、山名被仰」たが「皆故障申」したため、斯波義淳直々の出兵が命じられたものだった。「今日又山門可寄之由風聞、然而無其儀歟」というが、のちに満済が聞いたのは、「武衛勢、軈引帰、公方対御勢、不可合戦由、山徒申」(『看聞日記』永享五年八月十五日条)というもので、義教が軍勢を派遣しなければ、おそらく二度目の延暦寺と園城寺の合戦が勃発していたとみられる。この事件については満済は日記に一切記しておらず、醍醐寺へは通達されなかった可能性もある。その後、しばらく山門に関する情報はなくなるが、義教の山門使節の円明房、金輪院、月輪院らに対する強い敵意は11月の叡山派兵へと繋がっていく。
また同日には貞成入道親王のもとに「駿河国今河遺跡、兄弟相論、親ハ弟ニ譲与、鎌倉贔屓、兄ハ京都贔屓、仍可被下御勢」(『看聞日記』永享五年八月十五日条)との報告があった。これは関東上杉家と血縁関係がある弟・千代秋丸と、京都を頼っていた兄の民部大輔範忠の相論を指すものであるが、実際には千代秋丸を推す国人層と民部大輔範忠勢との対立である(『看聞日記』永享五年八月十五日条)。
こうした駿河の状況の中で、義教は関東管国と接する駿河国東部および北東部の支配を老練な「今河左衛門佐入道(右衛門佐入道)」に担当させることとした(年不詳八月十九日「将軍家御内書案」『足利将軍御内書并奉書留』)。8月19日、義教は駿東で反抗的な態度を示す狩野介以下八名に、右衛門佐貞秋入道への忠節を命じる御内書を発している。
●某年八月十九日「足利義教御内書案」(『足利将軍御内書并奉書留』)
8月25日「戌初当、西方星光指東、其躰異也、若彗星歟、驚入者也」(『満済准后日記』永享五年八月廿五日条)と、彗星が見え始めた。この彗星はテンペル・タットル彗星で、しばらく肉眼ではっきりと観測されている。28日には醍醐寺の満済のもとに「自将軍御書到来、彗星出現事、驚思食」との書状が届けられている。彗星の出現は「天文要録云、彗星出、其国更政立王公、班固云、彗星出、国暴兵起、移其国、京房易伝云、彗星出、四夷来兵革起、死人如乱麻、哭声遍路」(『看聞日記』永享五年九月十三日条)と見えるように不吉の前触れとされ、義教は満済に「就其御祈事、可有御談合、明日可出京」と指示しているように騒ぎが起こっている。たまたまながら、6月5日に「仙洞此間聊御不予」(『看聞日記』永享五年六月五日条)以降体調不良が続いていた院(後小松院)が9月3日には「仙洞御窮屈御様、医師三位申分、御脈様如六惜御座」(『満済准后日記』永享五年九月三日条)、9月5日には伏見に「仙洞御不予、猶六借御事之由」(『看聞日記』永享五年九月五日条)が届けられ、9月6日には「仙洞御不予之式、三位音智客等於于今捨申、以外御事云々、御修法など別而無御祈之儀如何」(『看聞日記』永享五年九月六日条)と見え、医師三位も匙を投げる容体であった。
こうした中、9月9日に満済のもとに「自駿河守護方注進両度到来了」した(『満済准后日記』永享五年九月九日条)。内容は「狩野城、湯島城云々、今月三日責落了、奥城計ニ罷成、定退治不可有程歟」というもので、湯島城(静岡市葵区俵沢)を攻め落とし、駿河国の兵乱に収束の兆しがみえるものであった。満済は今川使者を醍醐寺に留めると、翌9月10日、出京して注進状を室町殿に持参し、義教に進上した。これを受けて、義教から駿河今川家の「今河民部大輔、今河右衛門佐入道、同下野守、同治部少輔入道」の四名に「御感内書被下之」て、四通の感状は飯尾大和守が醍醐寺に持参。満済は今川使者にこの感状を託している(『満済准后日記』永享五年九月十日条)。ただ、なぜかこの感状の対象者中に、閏7月初旬ごろに京都から駿河に下向し、国人との戦いで奮闘した今川播磨入道の名は見えず、その後の満済の日記にも登場することはない。その理由は不明ながら、惣領範忠や一族の尾崎伊予守との確執があったのかもしれない。
9月12日早朝、満済は義教から「駿河国事、悉落居之由、自遠江国注進到来、昨日武衛申入間、珍重之間、定可令祝着歟之間被告仰」という書状を受け取った。これに満済は「誠国堺一大事處、早速落居、真実々々非尋常儀、只神慮所致也、御運可及万代條、勿論珍重之由」を申し入れている。その後、満済のもとに再度「今河民部大輔注進到来」したため、義教に書状を進上、その返書が届けられている。その内容は不明であるが、その後の経緯とみられる(『満済准后日記』永享五年九月十二日条)。なお、今川家に伝わる「重代鎧并太刀」は、故上総介範政から次子の弥五郎に相続されたままになっており、弥五郎も自分に相続権があると主張したか「弥五郎毎事管領申入哉」と見える。しかし、義教は民部大輔範忠が家督継承者である以上は引き渡すべしとし、10月15日に管領持之を通じて命じている(『満済准后日記』永享五年九月十四日条)。
この直後の9月19日早朝、「畠山左衛門督入道死去、六十二歳」(『満済准后日記』永享五年九月十九日条)という。「自去十七日蟲腹発、今曉又発、仍死去」(『満済准后日記』永享五年九月十九日条)、「前管領畠山死去、持病虫腹更発、俄死去」(『看聞日記』永享五年九月十九日条)とのことで、畠山満家入道は持病として慢性的な反復性腹痛があったことがわかり、急性増悪から腹部のがん性疾患の可能性か。満済はこの一報を受けると「子息尾張守方等」に悔みの言葉を送るとともに、「畠山事驚入由、以慶円法眼申入室町殿」したが、義教は「御力落之由、種々仰」という(『看聞日記』永享五年九月十九日条)。
さらに翌9月20日の「今曉寅刻歟、仙洞御不予俄御大事、御吐気及両三度、其後半身後中風、既御難儀出来歟之處、被聞食潤體円、聊御脈出来、雖然以外、今日中不可有御過歟之由、医師三位法眼申也」と、ふたたび院の容体が悪化した(ただし、医師三位坂胤能法眼は義持代でも誤診や誤投薬が散見され、有能な医師とは言えない)。院はその後「仙洞様御不予、聊御少減御體」と、少々回復するが、おそらく慢性的な脚気に加えて脳血管疾患を発症しており、「但一端事也、始終御本複、更不可叶」とのことであった。その後も院は「以外」の容体が続き、10月20日の申刻「仙洞崩御歳五十七」した(『看聞日記』永享五年九月廿日条)。
そしてこの頃には、武家内部での不穏な噂、山門との間での険悪な空気がみられた。10月28日には「世上又物騒、畠山遺跡所領等、山名可申給」という風聞が流れ、山門問題では「円明、承連等御退治、可被責山門云々、仍坂本騒動、洛中物騒、諸軍勢等上洛」(『看聞日記』永享五年十月廿八日条)という。
山名時熈入道は山門使節側の分裂を図ったようで、11月3日、円明坊兼宗(乗蓮坊兼珍もだろう)を一連の首謀者とし、時熈入道は杉生坊、金輪院、月輪院を武家側に寝返らせ、忠節を誓った旨の申状を義教に提出したという。ところが義教はこれを不審と感じ、時熈入道奉書を管領持之を通じ「杉生、金輪院等方へ遣申」してみると、「山名方へ如請文者、大略可随仰旨申入」というものだった。ところが、管領持之へは月輪院のみ返状を届けており、その内容も「一味同心間、円明事不可捨様申入歟」というもので、山名時熈入道の言うように彼らが円明坊方から寝返ったわけではなく、山門使節の円明坊、杉生坊、金輪院、月輪院は一味同心で、円明坊への赦免を要求していたのである。これらの要求を義教は拒絶している。
ただし、11月8日に伏見貞成入道親王が得た情報では、「世上物騒事、静謐云々、山徒退治事、畠山山名身上事、條々三宝院管領等申沙汰、属無為、諸軍勢国々下向云々、珍重也」(『看聞日記』永享五年十一月八日条)といい、満済と管領持之の奔走により、山門攻め、畠山持国と山名時熈入道の所領問題も解消し、諸国の軍勢は帰途に就いたという。
しかし、11月16日、満済が出京し法身院へ入ると管領持之が来臨し、「山門へ御勢発向事、不可然之由、種々申入也」(『満済准后日記』永享五年十一月十六日条)と、比叡山派兵は行ってはならないとの申し入れを依頼される。8日に貞成入道親王が得た情報が正しければ、いったんは無為の沙汰となったが、直後に一転山門攻めへと舵が切られたことになる。後日の11月27日、「今日山名金吾入道進発、三井寺為陣云々、今度事金吾専申沙汰也」(『看聞日記』永享五年十一月廿七日条)とあるように、今回の山門討伐は山名時熈入道が頻りに主張して行われたものであった。
管領からの依頼を受けた満済は「内々管領申旨達上聞了」(『満済准后日記』永享五年十一月十六日条)している。さらに「自武衞以織田筑後入道、此事同前申也」(『満済准后日記』永享五年十一月十六日条)と、武衞義淳もまた織田筑後入道を満済に遣わして、山門攻撃の中止を申し入れている。ところが11月21日には「廿七日山責治定、諸大名大略可発向云々、三宝院管領等種々雖諫申、不被入聞食、山門之滅亡此時歟、神慮如何、御運之安否難量事也、為天下驚歎無極」(『看聞日記』永享五年十一月廿一日条)といい、義教は山門攻めを決定し、満済や管領の言葉にも耳を貸さなかったと貞成入道親王の耳に入っている。
11月22日、管領持之は再度山門攻撃の中止を申し入れるべく、若槻入道を満済のもとに遣わし「山門発向事、可申止之由申事也」という(『満済准后日記』永享五年十一月廿二日条)。11月26日にも持之から満済に「就山門発向事、管領載書状、申入旨在之」っている。満済は室町殿に参じて義教と対面すると、管領持之の「先内々此状入見参了」し「管領申旨申」したところ、義教は「明日、山名以下既可進発事治定、只今御延引、旁御難儀」と述べ、撤回はできない旨を伝えている。満済はこれを管領持之に伝えると、持之は「此上者無力、重申事、可加斟酌」と、これ以上の出兵撤回要請をあきらめた(『満済准后日記』永享五年十一月廿六日条)。
翌11月27日、予定通り「為山門発向山名以下、今日罷立了」「自浜寄手山名、土岐美濃守以上両人」(『満済准后日記』永享五年十一月廿七日条)と、山名時熈入道、土岐持益を山門攻めの両大将として「三井寺ニ陣取定」ために出陣させた。このとき、満済は京都から醍醐寺への帰路にあったが、「檜岡(山科区日ノ岡坂脇町)」で「山名陣立於檜岡見物」「山名勢進発等見物了」している。その陣容は満済が「驚目了」というもので、山名時熈入道が率いるのは「三百騎計歟、野臥二三千人也、悉以美麗、無申計」、土岐持益が率いるのは「百二三十騎、野臥一二千騎計歟、美麗同前」という(『満済准后日記』永享五年十一月廿七日条)。「野臥」は徒歩侍を指すか。このほか、「西坂(西坂本)」には「土岐大膳大夫、佐々木、小笠原信乃守護也、其外山法師玉琳、上林、西勝、十乗、蒲生下野入道等」が遣わされている。貞成入道親王のもとにも26日に報告があり、「坂本諸大名発向、前管領勘解由小路、武衛ハ不向、甲斐舎弟為大将、山名、土岐与安、赤松、小笠原司馬、両佐々木、其外之物共大勢進発、京都警固管領畠山、侍所一色等云々、合戦明日之由風聞、但実説不定」(『看聞日記』永享五年十一月廿七日条)との情報が伝わっている。
●永享5(1433)年11月山門攻めの陣容
| 目標 | 人名 | 布陣 | 陣容 | 職 |
| 東坂本 | 山名右衛門督時熈入道 | 園城寺⇒志賀 | 三百騎、歩兵二、三千人 | 有司 |
| 土岐美濃守持益 | 百二、三十騎、歩兵千人計 | 美濃国守護職 | ||
| 西坂本 | 土岐世保大膳大夫持頼 | 伊勢国守護職 | ||
| 佐々木大膳大夫満綱 | 近江国守護職 | |||
| 佐々木治部大輔持高 | 出雲国守護職 | |||
| 赤松大膳大夫満祐入道 | 播磨国守護職 | |||
| 小笠原治部大輔政康入道 | 信濃国守護職 | |||
| 玉琳 | 山門僧 | |||
| 上林 | ||||
| 西勝 | ||||
| 十乗 | ||||
| 蒲生下野入道 | 近江国人 | |||
| 近江路か | 斯波左兵衛佐義淳 ※甲斐常治入道の舎弟某が大将 |
越前国より | 越前国守護職 | |
| 内裏・仙洞御所 | 畠山尾張守持国 | 有司 | ||
| 洛中警固 | 一色修理大夫義貫 | 丹後国守護職 侍所頭人(有司) |
||
| 細川讃岐守持常 | 阿波国守護職 | |||
| 細川治部少輔氏久 | 備中国守護職 | |||
| 細川淡路守持親 | 淡路国守護職 | |||
| 上杉五郎房朝 | 越後国守護職 | |||
| 富樫介教家 | 加賀国守護職 |
そして11月30日朝、「山名并土岐勢、於唐崎辺合戦、土岐勢内当座ニテ四人被打、土岐治部少輔両所ニ蒙疵云々、手負数十人云々、山名勢内両人打死、其内実寿坊山徒歟、被打云々、手負同前云々、山門方ニテ数輩被打」(『満済准后日記』永享五年十一月卅日条)との報告が届いている。山名時熈入道、土岐治部少輔は東坂本へ向かう旅程の「唐崎(大津市唐崎)」での戦いで、土岐勢は四人が討たれ、負傷者は数十名、土岐治部少輔も負傷している。山名勢は山名勢に従っていた山徒宝寿坊と他一名が討死、負傷者は数十名というものだった。一方山門方も数名が討死するなど、激しい戦闘が行われた。
ところが、このような中で、斯波左兵衛佐義淳が病に倒れたことが義教に伝えられた。義淳の容体は重篤であったことから、義教は11月30日、醍醐寺の満済のもとに「三條宰相中将(正親町三條実雅)」に書状を託してこの旨を報告している。満済が書状を見ると「武衛所労危急、遺跡事ニ付テ当時奉公左衛門佐事、以外無正体間、不可叶、其弟僧在之云々、若器用歟、可被仰付、定自武衛可申歟、其由可申遣」とあった。
三條宰相中将は「自武衛方以両使織田筑後入道、飯尾美作守申、所労既危急、往時式候間、続目安堵事申入處、可申此門跡之由、被仰出候、達上聞事、両奉行飯尾加賀守、同大和守候、只今切角時節候、平御出京可畏入」と述べた。満済は「御危急事、自何驚入候、随而相続仁体事、左衛門佐雖不能左右、時宜以外不快、一家総領職事、不可叶器用之由、連々被仰候、仍相国寺僧瑞鳳蔵主左衛門佐兄也、此仁事、如被聞食及者可然歟之由、先日内々仰旨候、就左様事、可申此門跡之由被仰出歟、先此仁体事、早々甲斐以下者ニ可被談合歟、何様ヤカテ可出京由申了」(『満済准后日記』永享五年十一月卅日条)とあるように、満済はこの正親町三條実雅の将軍書状以前に義教から家督相続について内々に相談を受けていたことがわかる。満済が醍醐寺へ戻ったのは山名出陣の日であることから、内々に相談を受けていたのは11月27日以前となる。義淳は山門攻めの大将軍の一人であったが、宿老甲斐常治入道の舎弟某が大将として出陣しており、義淳はこの時点ですでに体調悪化していたと考えられる。
義教は義淳の異母弟である「左衛門佐(斯波持有)」を後継者とすることを「以外無正体間、不可叶」「左衛門佐雖不能左右、時宜以外不快、一家総領職事、不可叶器用之由、連々被仰候」と頑なに拒絶し、その舎兄「相国寺僧瑞鳳蔵主」が「若器用歟」として還俗させて家督を継がせる意向を伝えたのであった。義教がこき下ろした斯波持有は、実は義教鍾愛の側近で「新続古今隠名作者」(「武衛系図」『続群書類従巻百十三』)と記されるほどの歌人でもあり、文化的素養の高い義教の信頼の厚い人物であった。これほど義教と近い人物にも拘わらず、義教は持有を斯波家の惣領職とすることは否定した。その大きな理由は「相国寺僧瑞鳳蔵主」が持有の「同母兄」だったことに起因しているのではなかろうか。自身にも厳しい義教の性格によるものであろう。瑞鳳蔵主は祖父義将入道が薨じた応永17(1410)年に生まれたためか、おそらく生まれながらに僧侶への道が決定されていたと思われる。瑞鳳は相国寺鹿苑院主の鄂隠慧奯の弟子となっているが、応永20(1413)年に誕生した同母弟(持有)は出家しておらず、瑞鳳はこれ以前に出家していたと思われる。瑞鳳の師・鄂隠和尚は応永17(1410)年3月23日に相国寺に入り、応永24(1417)年には天龍寺へ移っており(「仏恵正続国師鄂隠和尚行録」『五山文学全集』)、推測だが瑞鳳は応永17(1410)年5月7日(瑞鳳誕生/義将入道薨去)から応永20(1413)年(持有誕生)までの間、四歳になるまでに鄂隠和尚の弟子となったとみられる。
家女房
∥
∥―――――――斯波義淳
吉良満貞――女子 ∥ (左兵衛佐)
(左兵衛督) ∥ ∥
∥ ∥ 【瑞鳳蔵主】
∥――――――斯波義重 +―斯波義郷
∥ (左兵衛督) |(治部大輔)
∥ ∥ |
足利高経――斯波義将 ∥―――――+―斯波持有
(尾張守) (右衛門督) ∥ (左衛門佐)
∥
甲斐教光―+―家女房
(美濃守) |
+―甲斐将教――+―甲斐将久
(祐徳入道) |(常治入道)
|
+―甲斐近江守
30日夕刻、激しい降雨の中、正親町三條実雅とともに醍醐から出京した満済は、「甲斐、飯尾美作守」の訪問を受けた。彼らは「以外内々被仰出器用仁体事、可為上意、殊又畏入、然者命中安堵御判拝領、心安可存置」といい、上意の通り瑞鳳蔵主を還俗の上で斯波武衞家の家督継承の旨を了承したうえで、安堵の御教書を請うた。満済はこの願いを正親町三條実雅を通じて「然者、実名官途事早々被仰出、安堵御判、今夜吉日間、可被下歟」の旨を上申している(『満済准后日記』永享五年十一月卅日条)。これを受けた義教は「仍来申旨、此分不可有子細、早々可被也案堵御判、仍官途実名等事、先々様相尋彼方、且可計申之由可仰付」と満済に指示する。満済はこれを甲斐常治入道に伝えたところ、斯波惣領家は「官途、毎度初度治部大輔、於実名事者、可被計下」とのことであった。そして、彼の実名については「義勝、義郷、義昌」の三案が正親町三條実雅から義教に示された結果、「義郷御點也」と決定。夜に「飯尾加賀守、続目案堵相当義郷、被成下了」と斯波武衛家へと伝えられた。そして翌12月1日深夜、「斯波兵衛佐義淳死去、子刻、年卅七」し、「武衞続目安堵以下畏入之由申了」した(『満済准后日記』永享五年十二月一日条)。この一報は12月2日、京都から伏見殿に戻った「源宰相出京聞」いたこととして、「前管領武衛、今曉逝去云々、尤不便為天下驚入者也」と、貞成入道親王はその死を悼んだ(『看聞日記』永享五年十二月二日条)。
この日の未明寅刻、「自西坂寄手」の土岐大膳大夫持頼(伊勢守護土岐世保家)は、唐崎付近に滞陣する山名時熈入道から「片岡右京亮ト云者ヲ案内者トシテ可責入由」を伝えられたため、山名から遣わされた「片岡右京亮」を案内人として夜陰に紛れて野瀬口(左京区八瀬野瀬町)まで兵を進めた(『満済准后日記』永享五年十二月一日条)。ところが、到着したときには夜が明けており、片岡は「今夜相図、已相違了、先本陣へ可帰」と言い、持頼勢もやむなく帰陣した。持頼はこれに憤っており「所詮此者申状、以外胸臆事等多之、可如何哉」と義教に注進。これを受けた義教も「此者事、総而胡乱者歟」とし、「誠難信用歟、能々可相計」と述べている。その後、御前から退出した満済のもとに、飯尾加賀守から戻るよう連絡があり、再び義教のもとに参じたところ、「片岡事、既逐電、希代事由、山名注進之、可一見」と、先ほどの片岡右京亮が行方をくらました旨の山名時熈入道の書状を見せられている。
山名、土岐勢と山門勢は度々合戦しており、土岐持益勢は「円明同宿二人討取、其頭進」する一方、山名時熈入道勢は「合戦、旗差被討云々、手物共おとしの堀ニ落入、四五百人死、散々事」という惨敗を喫したという(『看聞日記』永享五年十二月二日条)。「山責事ニ洛中物騒、室町殿ハ御蒙気、何事も不及沙汰」(『看聞日記』永享五年十二月三日条)と、義教は武衛義淳の死去以来、鬱屈しており、義淳死去から満済を含めて誰とも対面せず、山門騒動で洛中も騒々しい中にあっても沙汰を行わなかった。東坂本を目指す山名・土岐勢も唐崎付近から北上できずに滞陣した状況にあった。斯波義淳の急死も含めて、かつて天台座主であった義教は、これらの戦況を神慮が働いていると畏怖していた可能性があろう。
12月6日早朝の合戦でも「山門有合戦、山名手者多被討」(『看聞日記』永享五年十二月七日条)と、山名勢の劣勢が伝えられている。ただ、これ以前に山門使節円明坊らは「円明以下使節、御免事」について「赤松(満政か)」に懇望しており、持之は同12月6日、若槻入道を満済に遣わし、彼らへの対応について「以無為廉、先当年可被閣事可申入、可有如何哉」(『満済准后日記』永享五年十二月六日条)と問うている。これに満済も「堂社無為計略之者、年内事旁可被閣珍重事也、可被申入歟」と賛意を示しており、内々で管領と満済が動きながら和平案を模索していたのである。
こうしている中で、12月7日頃には「山名金吾衛門於志賀落馬、身を打損、不合期云々、神慮歟、可恐々々」というように、山名時熈入道が落馬して負傷した状況が伝えられた。これを聞いた貞成入道親王も「神慮歟」と恐れており、義教も心理的に耐え切れなかったか、満済(管領の意見)の申入もあり、12月8日に「依武衛事、此間合戦被閣」(『看聞日記』永享五年十二月八日条)と、義淳死去を理由として山門との戦闘中止を指示している。
12月8日、満済は醍醐から出京して義教と対面し「就山門御勢発向事、條々被仰旨在之」(『満済准后日記』永享五年十二月八日条)を告げられている。また、「管領来、山門事談合子細在之」と、管領持之も満済を訪れて、山門攻めについて何らかの結論を伝えているが、山門攻撃の中止を述べたものであろう。
12月9日には「甚雪降、此間連々深雪、近年無如此之儀、若山王、白山之神慮歟、不審也」と近年ない急な豪雪であり、貞成入道親王は、これも日吉山王や白山権現の神慮ではないかと畏怖する(『看聞日記』永享五年十二月九日条)。こうした中、「山徒、可降參之由歎申云々、可落居歟、種々巷説満耳」(『看聞日記』永享五年十二月九日条)と、山門側からも降参する旨が申し入れられ、山門との戦いは収束することとなった。
12月11日、管領より満済に「山門事落居、円明兼宗可隠居、兼珍乗蓮可降参申入、如元無為ニ御免可畏入之由、一山以事書歎申入」ことの事書案が伝えられている(『満済准后日記』永享五年十二月十一日条)。そして12月15日には「山門中堂閇籠、今日退散、神輿御帰座」(『満済准后日記』永享五年十二月十五日条)と、根本中堂に立て籠もっていた衆徒も退出し、神輿もまた帰座したという。
これらの情報は12月18日に伏見にも「山門事落居、円明者隠居、承連ハ降参」と伝わり、「仍山名以下、赤松、両佐々木等諸大名解陣、今日帰洛」「聞、天下靜謐、就惣別珍重」(『看聞日記』永享五年十二月十八日条)と、山名時熈入道以下、武家方の寄手もまた兵を引いて、18日に帰京した旨を伝えている。この解陣の際に「山法師」が「山名陣中へ發句を遣」わしたという。
これに山名時熈入道も応え、
と返した。実戦部隊の山法師は、雪によって松がたわむ風流な姿、松尾路の雪深い風景を掛けて詠みながら、その本意はいまだ強い戦意を示しており、心底ではまったく屈服しない態度を示す。それに対して山名時熈入道も『新古今和歌集』から本歌取りして凍てつく琵琶湖の汀波を引き合いに出しながら、本意は蜂起すれば壊滅させると脅しをかけているものである。結果的に主戦派の山名勢は敗色が濃く、志賀から前進が叶わない上に大将時熈入道が落馬するといういいことなしの状況にあったが、ある意味、和平に救われた形となったか。
12月25日には「抑聞、土岐與康坂本陣より帰、於途中病死云々、武勇名将也、不便々々」(『看聞日記』永享五年十二月廿五日条)という。この「土岐與康」は土岐世保家の伊勢守護土岐大膳大夫持頼を指すが、彼は山名時熈入道とともに一手の大将を務め、その後も活躍がみられる人物であることから、伝聞は誤伝であった。
永享6(1434)年2月9日早旦、満済のもとに親秀法橋が参入し、「今曉寅刻、御産平安、若公御降誕」(『満済准后日記』永享六年二月九日条)という。この男子はのちの五代将軍義勝である。「御母儀、裏松前中納言兄弟本御台妹也」(『看聞日記』永享六年二月九日条)である。御産所は「波多野入道宿所」だが、「狭少在所也」「御産所以外狭少、更無道場在所」という。
2月11日早旦、満済は出京し、午の刻に行われた「若公御湯加持」を執り行う。その後、満済は「内々時宜」により、室町殿に参じ、将軍の沐浴からの「奉待還御」した(『満済准后日記』永享六年二月十一日条)。そして将軍が戻り対面するが、義教は「今度若公御降誕事ニ付テ、裏松亭参賀輩、僧俗悉可有御切諫之由被仰」た。これに満済は「御祝着之時分不可然」と再三申すも、義教は「無御承引儀也」(『満済准后日記』永享六年二月十一日条)という。「室町殿兼被付人被見、参賀人々交名注進」(『看聞日記』永享六年二月十四日条)とあるように、義教は義資亭に人々が参賀に訪れることを予想して、あらかじめ日野亭に人を遣わしていることがわかる。義資は永享4(1432)年6月23日に権中納言を辞して散位であったが、その辞任についての理由は不明。ただし「裏松近来籠居」(『看聞日記』永享六年二月九日条)とあり、義教から何らかの咎めを受けていた可能性があろう。いずれにしても「籠居」している義資の裏松亭に人々が祝賀に訪れることは、規定に厳格な義教の怒りを買うことは必定であったろう。ただ、亭主の義資に処罰は及んでおらず「訪問(遣使)した」という行動が私罰の大将だったことがわかる。
翌12日早暁、満済は「腹中以外傷、悩乱無申計」と突然の腹痛に襲われ、「医師清阿」を召したところ、「蟲所為」との診断で「木香湯」が処方され、「三位法眼方」からは「呉茱萸湯」が進ぜられた(『満済准后日記』永享六年二月十二日条)。いずれも胃腸の不調に効果のある薬湯であるが、このころ満済は糖尿病及び合併症と思われる腹痛や眼病など度々発症しており、また免疫力の低下も顕著である。この12日、義教から「自将軍御書到来、明日可罷出」と指示を受けるが、満済は「不例子細申入了」というほどの症状であった。義教が13日に相談したかったことは、日野亭を訪れた人々への処分の件も含まれていたのであろう
2月14日、「抑先日若公出生之時、裏松前中納言家へ公家、武家、僧等行向令賀、室町殿兼被付人被見、参賀人々交名注進、藤大納言、万里小路大納言非人数云々、柳原中納言兄弟、四條宰相同等、僧俗済々参賀、以外及御沙汰、面々失面目云々、粗忽参賀、枝葉之事、頗及生涯云々、委細事未聞」(『看聞日記』永享六年二月十四日条)といい、先日の満済に打ち明けた裏松義資亭へ祝辞を述べに向かった人々への処罰を断行した。人々は「公家門跡僧中武家大略行向」(『看聞日記』永享六年二月十四日条)というほど多かった。
●日野家略系図
日野兼光―+―日野資実――日野家光――日野資宣―+―日野俊光―+―日野資名――+―日野氏光
(権中納言)|(中納言) (権中納言)(民部卿) |(大納言) |(権大納言) |(左衛門佐)
| | | |
| | +―日野資朝 +―藤原名子
| | |(権中納言) |(竹向)
| | | | ∥――――――西園寺実俊
| | | | ∥ (右大臣)
| | | | 西園寺公宗
| | | |(権大納言)
| | | |
| | | +―日野時光―――+
| | | (権大納言) |
| | | |
| | +―柳原資明――+―武者小路教光 |
| | |(権大納言) |(権中納言) |
| | | | |
| | +―大僧正賢俊 +―土御門保光 |
| | |(三宝院主) |(権大納言) |
| | | | |
| +―女子 +―女子 +―柳原忠光 |
| ∥ ∥ (権大納言) |
| ∥ ∥ |
| ∥ ∥―――――――花山院冬雅 |
| ∥ ∥ (三位中将) |
| 花山院師藤 花山院家雅 |
| (大納言) (権大納言) |
| |
| +―――――――――――――――――――――――――――――――――――+
| |
| +―日野資康――+―裏松重光―+―裏松義資――+―日野政光―+―永俊首座――――――――――女子
| |(権大納言) |(大納言) |(権中納言) |(右少弁) |(西南院) (安養院)
| | | | | | ∥
| | | +―藤原宗子 +=日野勝光 +―日野勝光――女子 ∥
| | | |(観智院) (左大臣) |(左大臣) (祥雲院 ∥
| | | | ∥ | ∥ ∥
| | | | 足利義教 +―藤原富子 ∥ ∥
| | | |(六代将軍) |(妙善院) ∥ ∥
| | | | ∥―――――+―足利義勝 | ∥―――――足利義尚 ∥
| | | | ∥ |(七代将軍)| ∥ (九代将軍) ∥
| | | | ∥ | | ∥ ∥
| | | +―藤原重子 +――――――――足利義政 ∥
| | | (勝智院) |(八代将軍) ∥
| | | | ∥
| | +―烏丸豊光―――烏丸資任――――烏丸冬光 +―藤原良子 ∥
| | |(権中納言) (准大臣) (権中納言) (妙音院) ∥
| | | ∥ ∥
| | +―藤原康子 ∥―――――足利義稙 ∥
| | |(北山院) ∥ (十代将軍) ∥
| | | ∥ ∥ ∥
| | | ∥ 小宰相局 ∥ ∥
| | | ∥ ∥――――――――――――――足利義視 ∥
| | | ∥ ∥ (権大納言) ∥
| | | 足利義満 +―足利義教 ∥
| | |(太政大臣)|(六代将軍) ∥
| | | ∥ | ∥―――――――足利政知 ∥
| | | ∥ | ∥ (左馬頭) ∥
| | | ∥ | 女子 ∥――――――――――――――――――――足利義澄
| | | ∥ | ∥ (十一代将軍)
| | | ∥ | 武者小路隆光――女子
| | | ∥ |(権大納言) (円満院)
| | | ∥ |
| | | ∥――――+―足利義持
| | | 藤原慶子 (四代将軍)
| | |(勝鬘院殿) ∥―――――――足利義量
| | | ∥ (五代将軍)
| | +――――――――藤原栄子
| | (慈受院)
| |
| +―日野資数――――日野有光―――日野資親
| |(権大納言) (権大納言) (左大弁)
| |
| +―日野西資国―+―日野西盛光――日野西資宗
| |(右大弁) |(権大納言) (権大納言)
| | |
| +―大僧正光助 +―――――――――――――――――――――――――――――――――――――藤原資子
| |(三宝院主) (光範門院)
| | ∥
| +―女子 ∥――称光天皇
| ∥―――――――甘露寺清長――甘露寺忠長 三條公忠―――藤原厳子 ∥
| ∥ (権中納言) (右大弁) (内大臣) (通陽門院) ∥
| 甘露寺兼長 ∥ ∥
| (左大弁) ∥――――――後小松天皇
| 後光厳天皇 ∥
| ∥ ∥
| ∥――――+―後円融天皇
| ∥ |
| ∥ |
| +=藤原仲子 +―永助法親王
| |(崇賢門院) (御室)
| |
+―広橋頼資―――広橋経光――――広橋兼仲―――広橋光業――――広橋兼綱―+―広橋仲光―――広橋兼宣―+―広橋兼郷
(権中納言) (権中納言) (権中納言) (権中納言) (准大臣) (権大納言) (准大臣) |(権中納言)
|
+―女子
∥
∥
西園寺公名
(権大納言)
裏松邸に祝辞を述べに行った「日野一位入道(日野有光)」は、「日野一位入道、此間知行分悉可致管領之由、以三條中納言御書拝領了、祝着畏入」とあるように知行分はすべて没収され、鎌倉初期に分流した遠縁庶家「日野中納言(広橋兼郷)」がこれらを拝領している。日野有光入道のように「今度若公御誕生、為賀罷向人数云々、仍知行分被没収歟、比類僧俗、及三四十人」(『満済准后日記』永享六年二月廿三日条)にも及んでいる。ただし、その疑いが懸けられた人々の罰については伝聞や誤伝も含まれている上に、罰も室町殿が介入可能な事案の出仕停止や所領没収等であって、本人の官途や公的処遇には及んでおらず、義教の私的な懲罰である。ただし、有光は義教と対立関係にあった故後小松院の院執権を務めていた経歴があり、この処断が後小松院崩御のわずか四か月後というタイミングでもあり、私怨も含まれていた可能性があろう。また、日野邸を訪れた人々は日野氏の一族や縁戚に当たる人々(藤大納言、柳原中納言兄弟、日野一位入道、子息資親、御室、相応院、西園寺、花山院、頭弁忠長)が見られ、彼らは「親戚」としての祝賀であったのだろう。九條満輔(及び家司三條公久)ら他の人々との血縁は不明ながら、交流があった人々と思われる。
●処罰を受けた人々(日野家の縁戚)
| 人名 | 人名2 | 備考 | 官途 | 処罰等 | 出典 |
| 藤大納言 | 武者小路俊宗 (元隆光) |
十一代将軍義澄祖父 | 権大納言 | 『看聞日記』 永享六年二月十四日条 |
|
| 柳原中納言兄弟 | 柳原忠秀 | 権中納言 | 『看聞日記』 永享六年二月十四日条 |
||
| 柳原資広 | 忠秀兄 | 前権大納言 | |||
| 日野一位入道 | 日野有光 | 前権大納言 | 日野中納言、此間知行分悉可致管領 | 『満済准后日記』 永享六年二月廿三日条 |
|
| 所領悉被召放、於于今無懸命之地、仍逐電 | 『看聞日記』 永享六年二月廿八日条 |
||||
| 逐電 | 『看聞日記』 永享六年三月九日条 |
||||
| 子息資親 | 日野資親 | 右少弁 | 遁世 | 『看聞日記』 永享六年三月九日条 |
|
| 御室 | 承道法親王 | 後小松天皇猶子 | 遣使者 以外御切諫 |
『看聞日記』 永享六年二月十四日条 |
|
| 相応院 | 弘助法親王 | 崇光天皇 皇子 |
遣使者 以外御切諫 |
『看聞日記』 永享六年二月十四日条 |
|
| 九條前関白 | 九條満輔 | 従一位 散位 |
遣使者 以外御切諫 |
『看聞日記』 永享六年二月十四日条 |
|
| 以外御切諫、御中違 | 『看聞日記』 永享六年二月廿八日条 |
||||
| 西園寺 | 西園寺公名 | 従二位 権大納言 右大将 |
遣使者 以外御切諫 所領被召 |
『看聞日記』 永享六年二月十四日条 |
|
| 花山院 | 花山院持忠 | 従二位 権大納言 |
遣使者 以外御切諫 |
『看聞日記』 永享六年二月十四日条 |
|
| 頭弁忠長 | 甘露寺忠長 | 正四位 蔵人頭 右大弁 |
所帯被召放、故房長朝臣子息ニ給、家をもあけさせ給 | 『看聞日記』 永享六年二月十四日条 |
|
| 長郷朝臣 | 高辻長郷 | 去年安堵芝山庄、筑紫之所領等 被召放 先日御会祗候余波歟 |
『看聞日記』 永享六年二月十四日条 |
||
| 八幡田中 | 田中法印融清 | 所領悉被召、善法寺社務ニ給 田中ハ逐電 |
『看聞日記』 永享六年二月十四日条 |
||
| 南都人々 | 及生涯 | 『看聞日記』 永享六年二月十四日条 |
|||
| 相国寺当住 | 逐電 | 『看聞日記』 永享六年二月十四日条 |
|||
| 鹿王院主 | 逐電 | 『看聞日記』 永享六年二月十四日条 |
|||
| 芳庵和尚 (慈齋院前住) |
逐電 | 『看聞日記』 永享六年二月十四日条 |
|||
| 綾小路少将有俊 | 綾小路有俊 | 左近衛少将 正五位下 |
行向人数 所領被注 美濃国加納郷綾小路少将有俊当知行…注折紙可被進 |
『看聞日記』 永享六年二月十四日条 |
|
| 陰陽師有清朝臣 | 安倍有清 | 所領共被召、有重故有盛御子ニ給、家をもあけさせらる | 『看聞日記』 永享六年二月十四日条 |
||
| 公久朝臣父子 | 三條公久 (九條家奉行人) 三條実文 (遁世) ※遁世は誤伝 |
自九條追放逐電 播磨国衙別納高岡北条公久朝臣当知行…注折紙可被進 |
『看聞日記』 永享六年三月九日条 |
||
| 惣而公家武家僧俗行向人、六十余人也、所帯被注、或逐電云々 | 『看聞日記』 永享六年二月十四日条 |
||||
九條家家司の三条公久は九條家の家司を外された上、播磨国国衙領の別納地である高岡北条郷の知行も免じられたようであるが(『看聞日記』永享六年二月廿二日条)、高岡北条郷は九條家領ではなく播磨国衙領に属しており、九條家とは関わりがない。「播州国衙月宛事、勧修寺注進申」(『看聞日記』永享六年二月廿三日条)とあるように播磨国衙領は伏見宮家領であったことがわかる。そして「国衙別納高岡北條、根本此御所為御恩、公久朝臣令知行哉、然者可被返付歟」(『看聞日記』永享六年二月廿二日条)とあるように、貞成入道親王は親族の三條公久に「御恩」として知行させていたものであり、高岡北条郷を公久から没収するのであれば伏見宮家に返付すべきであるとしている。
2月16日、義教は満済に正蔵主を通じて「関東五山事」について仰せ出された。このとき満済は体調を崩していたが、「雖窮屈最中、御使間、令対謁了」という。その内容は「関東五山事、如元自京都可被成御教書之由、鎌倉殿被申入也、仍可被仰付歟之處、猶御思案間、于今被閣了、但於今者、無尽期歟之間、可被成御教書、就其ハ京都西堂中就望申入可被仰付歟、将又関東西堂中ヲ可被仰付歟」(『満済准后日記』永享六年二月十六日条)との問い合わせであった。これに満済は「関東五山事、羽田入道参洛時、條々申入内、一ヶ条候歟、雖然于今被閣了、只今如被仰出可被成御教書者、先関東西堂内可宜歟由存様也」と答えている。昨永享4(1432)年2月29日早朝に上杉憲実雑掌の判門田壱岐入道が示した鎌倉殿持氏の時宜を記した「上杉安房守状」(『満済准后日記』永享四年二月廿九日条)のうちの「関東五山長老、器用西堂等雖被挙申度、時宜難計間、先令啓候」の返事が擱かれたままになっていたが、義教はこの一ヶ条について関東へ返答するために満済に意見を求めたものである。
2月22日、管領持之から満済に「先度被尋両條」の報告があり、そのひとつ「関東町野子可被召仕歟事」については、義教は彼が「普代問注所也、定日記等可所持歟」という、問注関係の先例故事が記されている日記を有している可能性を感じながらも、「但別而可被召仕候條、相似京都無人、且又御無用心」(『満済准后日記』永享六年二月廿二日条)との考えの中で葛藤している様子を伝えている。
また、翌2月23日、「日野中納言(広橋兼郷)」は被官本庄某を満済に派遣し、諸事報告等を行ったが、その中で、先日の裏松亭訪問事件につき、兼郷が「日野一位入道此間知行分、悉可致管領之間、以三條中納言御書拝領了、祝着畏入云々、日野一位入道、今度若公御誕生為賀罷向裏松亭人数云々、仍知行分被没取歟、此類僧俗及三四十人」ことも告げている(『満済准后日記』永享六年二月廿三日条)。また、同様に裏松亭に賀を遣わした「御室(永助法親王)」も満済に書を遣わし、「自御室今日又以書状承、先日若公御誕生珍重余、賀遣裏松中納言了、就此事時宜以外之由、日野中納言申間、計会無申計云々、一向芳言憑入云々、就此事及両度承了」と、満済に執り成しを頼んでいる。
2月25日、室町殿を訪ねた満済は、義教から「管領内者イハラ木、裏松中納言青侍一名字者在之、彼所へ今月十六日歟七日歟之間、管領内イハラ木罷向云々、此條管領者令存知歟、又彼者私ニ罷向歟、近日裏松辺へ経廻者共、御切諫處、如此振舞條、外聞一向相似管領許容歟、不可然、但実否如何」との言葉を聞いている。管領持之もまた家人茨木を裏松義資の青侍に遣わしたという疑惑が義教に報告されていた(ただし、この話は不問となったようである)。
この頃、満済の体調は大変悪く、3月8日から「自今曉蟲腹又更発」し、愛染護摩については代官を用いている。午後には「蟲腹以外興隆、吐気頻也、心神頗如無、終日同前」(『満済准后日記』永享六年三月八日条)という容態となっていた。満済は医師三位を呼び「医師三位参申、脈様不苦、積聚以外、蟲又大事云々、雖然於療養者不可有殊儀云々、木香湯、三稜丸今日可進」たが、「今日食事同前不通也」(『満済准后日記』永享六年三月九日条)という。これらの症状も合わせて消化器系疾患(脾臓=膵臓疾患か)とみられる。
3月11日には広橋中納言兼郷が義教使者として醍醐寺を訪れ、「不例様殊無御心元被思食云々、種々被仰、医師桂音僧為時宜召具了」として、義教から医師桂音を同道したことを伝えている。桂音は満済の脈を診ると「脈様三位申同前、但左心中風以外云々、一大事蟲、能々可有御養性」(『満済准后日記』永享六年三月十一日条)との診断であった。同日、満済は「土佐将監入道召寄、影像写之了」とあり、満済は自らの余命を感じ、肖像を描かせたものと思われる(現存する満済図像と思われる)。3月16日には再度桂音が醍醐を訪れ診察するが、「脈様弥無力、可令用心云々、心細事無申計、但非仰天限」(『満済准后日記』永享六年三月十六日条)と、すでに覚悟の決まった様子がうかがえる。18日には義教が満済の「歓楽體無心元思食」あまり、斯波義郷、畠山持国らを引き連れてみずから醍醐寺を訪問し満済を見舞った。満済は「雖為不可思儀躰懸御目了、予落涙外無他事」(『満済准后日記』永享六年三月十八日条)と感じている。20日にも義教が派遣した三位法眼の診察を受けており、少し容体は回復している。その後も頻繁に医師が遣わされており、義教の心配の程がうかがわれる(3月24日にも醍醐寺を訪問している可能性がある)。4月8日には醍醐寺裏の山上に「清瀧宮修造事、公方様御立願」(『満済准后日記』永享六年四月八日条)し、その願書が満済に到来している。満済は「御立願過分、忝以来筆舌難申述歟」と感謝している。この際に造立された清瀧宮が醍醐山上に現存する堂宇である。そして4月15日、義教は大雨の中にもかかわらず再度醍醐寺に満済を見舞い、満済は「時宜趣、言詞更無覃、眉目過分此事々々、只落涙千行、顔色體聊被御覧、直御喜悦之由再三被仰、忝不知手足舞踏、暫御座還御」した。その帰途は「洪水之間、四條橋へ御廻云々、仍万寿坂越ニ還御」(『満済准后日記』永享六年四月十五日条)という回り道をしている。その後も容態は芳しくはなかったものの、満済が4月19日に食事を採れたことに義教は「昨日時食珍重、今日定同前、弥気力出来歟、目出」(『満済准后日記』永享六年四月十九日条)との使者を遣わしている。
当時、関東においては、鎌倉殿持氏が「大勝金剛尊等身」像を造立したことに当たり、願文を奉納している(永享六年三月十八日「足利持氏願文」(『鶴岡八幡宮文書』))。いわゆる「血書願文」といわれるものである。この願文中「咒咀怨敵」は義教とされているが、持氏が京都に対して激しい敵意を持っていた形跡は皆無である。ここに見える「怨敵」は、長らく持氏に抵抗を続け、結果として永享の乱へ至る関東最大の不安定要因・常陸佐竹刑部大輔祐義を中心とする北関東の「京都御扶持之輩」を指していることは明白である。また、「血書願文」とされるが、この墨書は比較的明るい朱色であり酸化鉄独特の鈍色がないため、強い決意を示すために朱墨を用いた願文とみることが妥当ではなかろうか。
持氏の念頭にあるものは、十七年前の上杉禅秀の乱当時からまったくぶれておらず、持氏を動かす原動力は、常に「関東」の安寧を祈り、そのためには衆生の苦しみを生じさせる逆徒を討伐するという「強い信念」だったのである。
●永享6(1434)年3月18日「足利持氏願文」(『鶴岡八幡宮文書』室:2796)
●(参考)応永24(1417)年2月「足利持氏願文案写」(『後鑑所収相州文書』神:5513)
4月20日、京都に駿河より「今河民部大輔使節朝比奈近江守、今日懸御目了」(『満済准后日記』永享六年四月廿日条)という。用件は「重代鎧并太刀号ヤク王、於籾井所請取了公方御蔵」であったが、この鎧や太刀は「去年以来、民部大輔舎弟弥五郎令随身参洛」したもので「為公方被召出、被返下民部大輔」だったが、一旦収めた民部大輔範忠はこれを義教に献じたものであった。
翌21日、満済のもとに「一色左京大夫、今夜亥刻死去云々、去年以来邪気興隆、風気相添云々、近年異他申通了」という報告があった。一色左京大夫持信入道は義教の側近として信頼あつく、また満済とも交流深く、その死を聞いた満済は「労力落周章、不便々々、当年卅四」(『満済准后日記』永享六年四月廿一日条)と感想を綴る。27日に満済はこのことを義教に申し入れているが、「一色左京大夫事、年来申通事間、定不便存歟、御周章」(『満済准后日記』永享六年四月廿七日条)とのことであった。5月2日、義教は「依一色左京大夫事、禁獄者少々御免」としている(『満済准后日記』永享六年五月二日条)。
【関東一色氏】
一色範氏―+―一色直氏――一色氏兼―+―一色満直――――一色頼直
(次郎) |(宮内少輔)(宮内少輔)|(宮内少輔) (修理亮)
| |
| +―一色長兼――?―一色時家
| |(左京大夫) (刑部少輔)
| |
| +―一色直兼
| (宮内太輔)
|
+―一色範光――一色詮範―――一色満範――+―一色持範―――一色政照―――一色政具
|(修理大夫)(左京大夫) (修理大夫) |(式部少輔) (式部少輔) (式部少輔)
| |
+―一色範房――一色詮光―――一色満貞 +―一色義貫―――一色義直
(右馬頭) (兵部少輔) |(修理大夫) (修理大夫)
|
+―一色持信―――一色教親
(左京大夫) (左京大夫)
関東との堺、駿河国では、前守護の故範政死去以来、家督を巡る争いから国人の反抗など様々な騒擾が継続し、京都の安保に直結する事案であったが、5月2日、管領持之が醍醐寺の満済を訪問して見舞うとともに、「就駿河事、内々上意趣被申事在之」の報告をしている(『満済准后日記』永享六年五月二日条)。その内容は「狩野事、興津事」であり、守護今川民部大輔範忠に激しく敵対していた狩野介や興津某ら国人層の動静についてであった。なお、駿河守護家と対立していた張本三人(狩野介、興津、富士大宮司)のうち、富士大宮司についてはすでに恭順しており、4月28日には「当富士大宮司能登守孫子也、去年以来在京」の「富士弥五郎十二歳」が醍醐寺に満済を訪問して対面している。
事は「今度駿河守護申請」として、まず「次於阿部山狩野知行事者、為御料所可被下御判、就其狩野治罰事可廻料簡」こと、そして「興津事、当身御判可拝領」という。討伐した狩野介、興津の所領について御料所ならびに今川家領とする御教書を求めたのであった。ただ義教は慎重で「此事可為何様哉、可被下御判條、聊可為楚爾歟」との考えであるという。管領持之としては「於御判者、不可然、狩野事、不可入立阿部山由、可被成御教書歟」と義教に伝えると「上意御同心」という(『満済准后日記』永享六年五月三日条)。ただし、これを聞いた満済は「狩野事、可有御免者、只今御免可然歟、不然如守護申請可有御沙汰歟、只ムサゝゝトシテ可被置條、不可然歟、所詮今河右衛門佐入道、同下野守以下、幸駿河ニ在国事候ヘハ、両様不残心底可申入旨、以罰状可申旨、可被仰下歟云々、狩野事非何篇、如今御下知候者、定可罷成乱国歟」と強く勧めたところ、「管領同心」という(『満済准后日記』永享六年五月三日条)。
5月24日、満済のもとに「二本松来、蝋燭箱、折紙五百疋持参」(『満済准后日記』永享六年五月廿四日条)とあり、この頃、奥州より「二本松」が在京していたことがわかる。前年の永享4(1432)年正月7日、「二本松畠山修理大夫ト号、武田刑部少輔入道、赤松弥五郎以下」が満済を訪れており(『満済准后日記』永享四年正月七日条)、おそらくこれ以降、在京していた可能性がある。系譜においては「満泰畠山修理大夫」または「持泰修理大夫」(『両畠山系図』)に相当する。応永年中においては二本松畠山氏は鎌倉の指揮下にあったが、この頃には篠川御所の麾下に入り、京都方となっていた様子がうかがえる。また、5月3日の満済の意見に応じたとみられる義教は、駿河国の今川貞秋入道と今川下野守に対して狩野介、興津の件で考えを包み隠さず申上げるよう指示したのであろう。5月25日、「今河右衛門佐入道、同下野守音信」が満済に届いている(『満済准后日記』永享六年五月廿五日条)。6月3日には「今河民部大輔音信」も満済に届けられている(『満済准后日記』永享六年六月三日条)。
畠山時国―+―畠山貞国――畠山家国―+―畠山国清―――畠山義清―――畠山清貞―――畠山清純――畠山持純
(阿波守) |(民部少輔)(尾張守) |(阿波守) (阿波守) (伊予守) (右馬頭) (阿波守)
| |
| | 【管領家】
| +―畠山義深―+―畠山基国―+―畠山満家―+―畠山持国――畠山義就
| |(尾張守) |(右衛門督)|(右衛門督)|(左衛門督)(左衛門督)
| | | | |
| | | | +―畠山持富――畠山政長
| | | | |(尾張守) (左衛門督)
| | | | |
| | | | +―畠山持永
| | | | (左馬助)
| | | |
| | | | 【能登畠山家】
| | | +―畠山満慶―――畠山義忠――畠山政国
| | | (修理大夫) (修理大夫)(能登守)
| | |
| | +―畠山持深―――畠山満義
| | |(伊予守)
| | |
| | +―畠山満国―――畠山持秋―――畠山教重
| | (左京大夫) (左京大夫) (七郎)
| |
| +―畠山清義―――畠山貞清―+―畠山持清―+―畠山国繁――畠山政深
| |(左近将監) (左近将監)|(中務大輔)|(信濃守) (九郎)
| | | |
| | +―畠山持貞 +―畠山政清――某
| | | (刑部少輔)(刑部少輔)
| | |
| | +―畠山満国―――畠山持重――畠山政光
| | (三郎) (中務大輔)(中務少輔)
| |
| +―畠山義熈―――畠山満基―――畠山教元―――畠山政元
| (播磨守) (播磨守) (播磨守) (右馬助)
|【奥州畠山家】
+―畠山高国――畠山国氏―――畠山国詮―――畠山満泰―+―畠山持泰―――畠山政泰――畠山尚泰
(上総介) (中務大輔) (修理大夫) (修理大夫)|(修理大夫) (治部少輔)(修理大夫)
|
+―畠山持重―――畠山政国――畠山義国
(宮内大夫) (修理大夫)(宮内大輔)
こうした中、6月9日早朝に事件が発覚する。「今曉卯刻歟、裏松中納言義資卿、為盗人被殺害了、青侍一人同道云々、希代々々、深雨降出時節」という。満済のもとに義教の使者として広橋中納言兼郷が遣わされ、條々の報告の中で兼郷は「義資卿事、希代横死、併天罰由」を述べている。なお、これは義教の言葉ではなく兼郷のものである。「盗人勿論歟、小袖、鏡台風情物奪取」ったという(『満済准后日記』永享六年六月九日条)。この知らせは貞成入道親王にも届いているが「抑夜前、裏松へ盗人入、主人中納言被殺害云々、言語道断事也、委細未聞」(『看聞日記』永享六年六月九日条)とあるように、一報のみ伝えられている。その後、12日に京都に「若公へ参」っていた「源宰相(庭田重有)」が貞成親王入道にその詳細を伝えているが、それによれば「抑裏松事、実也、夜討八日暁忍入、前黄門臥蚊張切落て差殺云々、傍ニ臥若俗一人同被殺、但二人敵ニも手負云々、誰人所為とも不知、但公方蜜々被仰付歟云々、仍此事不可沙汰 裏松青侍両三人遁世云々、有申者者同罪之由」(『看聞日記』永享六年六月十二日条)とのことであった。裏松義資と青侍は蚊帳を落とされ斬りつけられたとはいえ抵抗しており、襲撃人にも手傷を負わせたとみられる。子息の「弁重政、無殊事始終之儀、如何」とも述べる。また、貞成入道親王はこの襲撃にまつわる噂も耳にしているが、おそらく次の高倉宰相入道が言いふらしたものが届いたのだろう。
6月12日、高倉宰相永藤入道は「昨日藤宰相入道、於室町殿被召捕、可被流罪云々、罪科何事乎、委細事未聞、何様驚耳事共也」(『看聞日記』永享六年六月十三日条)と、室町殿に出仕中に赤松播磨守満政に捕縛され、赤松邸に連行された。その詳細は、6月13日、義教から広橋中納言が満済に遣わされ「藤宰相入道、不思儀虚説ヲ奉対公方申入間、昨夕被遠流九州辺、子細等具被仰出了」と、高倉永藤入道を遠流に処した理由を説明している。それによれば「所詮、裏松中納言、今度横死事、内々為公方被仰付御沙汰之様ニ御物語之由、近習以下群集ノ中ニシテ雑談云々、此事藤宰相入道ニ御物語、無跡形事也、仍以両使日野黄門、赤松播磨御尋處、不申由頻申云々、雖然藤宰相入道雑談時、承人数及数十人、悉申旨申入上者、非御不審限間、不可及告文由仰云々、希代虚言、元来胡乱不思儀者也、定申條勿論歟」(『満済准后日記』永享六年六月十三日条)という。高倉永藤宰相入道は、裏松義資の横死について実は義教の内々の命によるものだと、根拠もないのに言いふらしたこと、ならびに、そのようなことは言っていないという虚言への制裁であった。
流罪は翌日には執行され「抑藤宰相入道、昨日配所ヘ被遣、安富大内家人、奉仰尼崎まて昨日下向、周防長門方ヘ被流歟、罪科題目無知人、何様重科哉不審也、永豊朝臣子息ハ御免」(『看聞日記』永享六年六月十四日条)という。これによれば子息永豊は連座せず、あくまでも永藤入道個人の罪科として処断されたことがわかる。なお、この処罰はもともとは「藤宰相事、裏松被討事、公方御沙汰之由申、依其忽被罪科、赤松大河内ニ被仰、於四塚可處死刑之由被仰付、然而余不便之由、大河内申宥被遠流、大内代官安富ニ被仰、油黄嶋ヘ被流、召捕事も大河内宿所へ喚て召捕、非指重科、公方御事依荒事申、如此被處重罪、前世宿業無力事歟、永豊朝臣懸命之地一所被下御免、其外所領十一ケ所三條へ被遣云々、裏松事是非不可沙汰」(『看聞日記』永享六年六月十七日条)とあるように、義教の強い怒りのために、東寺南西角の四塚辻で処刑の予定であった。しかし、永藤入道の処刑を命じられた赤松播磨守満政は、彼があまりに不憫であるとして、義教へ遠流への減刑を嘆願したため、これを受け容れた義教は、大内代官の安富に指示して「油黄嶋」へ流すこととした。子息の永豊には所領一か所与えられるが、そのほかの所領十一ケ所は没収され、三條実雅へ下されている。なお「油黄嶋」は大内代官に指示が下されていることから、通説の薩摩喜界島などではなく、大内氏の支配権の及ふ周防・長門にかけての島と考えられる。
また永藤入道の所領については、16日「抑藤宰相入道所領三ヶ庄以下悉被没収、被付三條云々、永豊朝臣懸命之地、如形被残、罪科ハ裏松事故」(『看聞日記』永享六年六月十六日条)という。そして同16日、「畠山信濃守故将監入道子子息、裏松召仕若俗被討是也、依之信濃失面目、所領被召放 後聞、非信濃守、其弟云々」(『看聞日記』永享六年六月十六日条)という。裏松義資に仕え、義資とともに斬られた青侍は、畠山信濃守国繁の弟(刑部少輔政清か)の子息で、信濃守弟が面目を失い、所領を没収されたというものだった。
6月17日には「弁重政遁世成禅僧云々、一流忽削跡不便々々」(『看聞日記』永享六年六月十七日条)とあるように、義資嫡子重政は出家遁世し、日野宗家は一旦断絶となる(重政の子勝光が七代義勝代に復権し、女子が八代義政の正妻となって権勢を誇ることになる)。裏松邸については「裏松家、資任ニ被下、壊之可沽却」(『看聞日記』永享六年六月十七日条)という。裏松邸ならびにその家領を引きついだ日野烏丸資任は、6月24日「日野烏丸、折紙代千疋到来間、則以彼進之由長全申也、義資卿家以下知行分所々等、悉拝領、祝着之由烏丸資任申也」と、満済に裏松家領等を継承した旨の報告を行っている(『満済准后日記』永享六年六月廿四日条)。
7月4日、義教は日野兼郷を見舞いの使者として醍醐寺の満済のもとに遣わし、まず「土用以後残暑以外、養性可然」と満済の容態を心配しつつ、「次何比可有出京哉」(『満済准后日記』永享六年七月四日条)と問い合わせている。また、早急に対応したい旨三ヶ条について聞いている。そのうち、「山門辺事ニ付テ、例式雑説在之、簡要令同心関東、致用害構云々、此興第一也、雖然、彼触御耳之間、一端被仰」(『満済准后日記』永享六年七月四日条)の問い合わせに、満済は「山門辺事、雑説不可説存候、此儀五月比申者候キ、不可説題目候間、申者乗阿、加切諫了、関東同心山門儀、曾不可有之由存也、仍関東辺此儀ニ付テ無其沙汰由、今河民部大輔状以日野黄門備上覧之由申了」といい、山門と関東が手を結んだという根拠のない噂を広めた乗阿なる僧を罰していることと、関東が山門と結んだことは今までなく、今回もその沙汰をした形跡はないという今川範忠からの書状を兼郷に預けている。
7月11日、義教は再度日野兼郷を醍醐寺に遣わすと、再度様々な相談事を述べている。本来は満済が上洛時に確認しようとしたものであったと思われるが、それが叶わないため、使節を遣わしたものと思われる。その一つに、比叡山の動きについての報告があった(『満済准后日記』永享六年七月十一日条)。義教の報告によれば「山門事、西坂キラゝ坂ヲ堀切、構釘抜之由、被聞食及也、言語道断振舞、山僧式、弥存外思食、仍山門領江州辺所々悉可被押置云々、就之円明一人知行分可被押歟、又杉生一人知行分可被押置、御料簡子細被仰出了」という。比叡山はふたたび円明坊兼宗や杉生坊による蠢動が顕著となり、西坂本に至る雲母坂(左京区修学院音羽谷)に堀を切り柵を構えて反抗の姿勢を見せているという。満済は「山門領可被押置事、去年諸大名意見、御勢発向之時分、一同此儀申候し、只今又同前哉、円明、杉生撰抜御沙汰之儀、如何之由存候」と、山門領を差し押さえることは言うまでもないことを述べる。反抗の資を奪うことで戦意を失わせ合戦に及ばないようにする意図か。
7月12日、前日に続いて日野兼郷が醍醐寺を訪れる(『満済准后日記』永享六年七月十二日条)。日野兼郷が日野家の墓所へ向かうために義教から暇が許されたが、その途次にある醍醐寺に立ちより、義教の言付け條々を伝えるよう指示されたためである。その條々は比叡山に関するものであった。
●永享6年7月12日の義教諮問と満済答申
| 義教諮問 | 要旨 | 満済答申 | 要旨 |
| 昨日内々被仰出、杉生一人坊領ヲ被除、自余ハ悉可被押置、御遠慮之由被思食、猶廻愚案可申入 | 昨日内々に仰せられた事として、杉生坊領を除く山門領はすべて差し押さえることで、体制を変えようとする深慮だが、満済の意見を請う。 | 被除杉生一人坊領、自余山門領可被押置事、猶不可然之由存、其謂ハ一身坊領被閣事畏申入、進退相替篇候者、尤可為神妙、万一無其儀者、此御沙汰還而不可有御遠慮儀歟、但猶可為時宜、 | 杉生坊の所領を以外の山門領を差し押さえることは、よろしくないと存ずる。理由は彼の所領を例外とすることで状況の変化があればよいが、そうならない場合もある。ただし、御意の通りに。 |
| 山門事、関東辺雑説聞食合、能々被仰談諸大名、可有御沙汰條宜云々、此條誠可然歟、乍去延引追儀如何、巨細可申入 | 山門が関東と繋がっているとの雑説につき、よく有司らと相談して沙汰すべきことが良いとのこと、その通りだと思う。ただ、結論が延引されていくのはどうなのか、意見を請う。 | 就関東雑説事、山門辺儀ヲモ能々被聞食合、可有御沙汰歟事、非殊儀、関東雑説若事実候者、天下重事之間、旁諸国御用心等可為格別候哉間、能々可被聞食合歟之由、申入計也、簡要関東山門事重事不可過之間、可被仰談諸大名之條、尤宜存 | 関東に関する雑説は、山門辺についてもよくお聞きになり沙汰されるべきことはいつもと同様です。関東の雑説がもし事実であれば大事であり、諸国に格別用心するよう指示するため、よくよくお考えなさるというばかりだ。重要なのは関東と山門の事は重事でこれに過ぎるものはないので、管領ら有司と相談されることがもっとも良いと存ずる。 |
このような中で7月19日、満済のもとに「自駿河国注進、関東雑説事、武田右馬助甲斐没落事、両條状」が届き、「以日野中納言今日備上覧了」(『満済准后日記』永享六年七月十九日条)した。翌7月20日、今川範忠が申請していた狩野介の知行地を賜るよう「駿河国阿部山御判」(4月28日依頼)につき、管領持之より安富筑後守を通じて醍醐寺に送達された(持之が義教から今河注進状を渡されたのは前日7月19日で、秘かに御教書の発給を指示されている)。満済は西南院に、醍醐寺に滞在中の今川使者「朝比奈近江守」を召して、早々に渡し遣わすように指示している(実際に「阿部山御判」「施行」が渡されたのは22日である)。
8月3日、満済は「今度所労以後初出京、日出以前京着、則参室町殿」し、義教と対面した。義教は「明旦ハ定可帰寺歟、然者暫ハ又為養性不可出京歟」と満済の容態と今後もしばらく出京が叶わないであろうことから、「種々事共被仰了」と様々な相談事をしている。当時においては、比叡山の事、駿河国の騒擾(「狩野、三浦以下歟申入事等」)が主要の題目となっている。満済はこれらを話し合ったのち御所を退出し、醍醐への帰路に就くが、その途次に「今若公御産所赤松伊豆守亭、参申入了、女房出逢、郷成朝臣妹歟、御産無為以下珍重旨申了」(『満済准后日記』永享六年八月三日条)と、7月26日に赤松伊豆守邸で誕生した若公を訪問している。母は「母宮内卿赤松永良則綱女、赤松一族女」(『看聞日記』永享六年七月廿六日条)、生まれた子は「御連枝小松谷殿配所隠岐国云々、御左遷之日次也、御俗名義制」(『在盛卿記』長禄二年四月十九日條)である。のち、「人々参賀室町殿、是若公一所て奉下関東之由被仰下之處、関東承伏之由申之故也」(『師郷記』永享十一年七月二日条)とあるように、持氏亡き後、新たな鎌倉殿として関東へ下す旨を上杉憲実入道が了承しており、鎌倉殿となる予定だった人物であった。「足利系図」(『諸家系図纂』)では「義永左馬頭、小松谷殿」とみえ、鎌倉殿の官途である「左馬頭」に任官していたようだ。永享11(1439)年7月4日に「若公様、鎌倉殿御成御礼、自寺家御申事、奉行加賀意見申歟」(『東寺百合文書 ち』永享十一年七月四日条)と若君の鎌倉殿就任につき東寺から御礼すべきことを奉行人飯尾加賀守為行から指示されているように、すでに「鎌倉殿」に任じられ、下向を待つ段階であった(『東寺百合文書 ち』永享十一年七月四日条)。
7月14日には「臨川寺周沅西堂、蒙鎌倉使命、中佐首座、蒙奥州使命」(『蔭涼軒日録』永享十一年七月十四日条)とあるように、この鎌倉殿下向に関する返答として、鎌倉の憲実へは臨川寺の芷陽周沅が、奥州の篠川殿へは徳翁中佐が決定され、7月16日に「中佐首座為奥州使故御相看、今日即発足」し、芷陽周沅もまた鎌倉へ向けて発っている(『蔭涼軒日録』永享十一年七月十六日条)。なお、8月23日には「中佐首座、於殿中御相看、乃為皈故也」(『蔭涼軒日録』永享十一年八月廿三日条)とあり、奥州使の徳翁中佐はひと月ほどで京都へ帰還している。
8月23日、山門領対応のために「六角、京極、為山門領押使下向江州」(『満済准后日記』永享六年八月廿三日条)している。六角満綱入道と京極持高は在京の被官らを率いて料所で陣容を整え、山門領の差し押さえに向かったとみられる。
9月29日には山名時熈入道より山門に関する報告書が醍醐寺に到来し、「自管領以使者被申様、来月朔日、神輿入洛必定由、自山門以事申入候了、内々可有用意之由、被仰出」(『満済准后日記』永享六年九月廿九日条)という。なお、10月1日に満済に届いた報によれば、「神輿入洛、今日延引歟」(『満済准后日記』永享六年十月一日条)という。また「江州事、六角如所存致其沙汰、山門領笠原木浦以下五ケ所、去廿七日焼払、山徒数輩打取之、山法師散々事云々、仍兵主以下山門領、無残處、応守護下知、野伏以下召出」(『満済准后日記』永享六年十月一日条)と、六角満綱入道は湖東の笠原、木浦など山門領五ケ所を焼き払い、そこに滞陣していた叡山僧兵数名を打ち取っている。また、「伊勢美濃勢合力」(『満済准后日記』永享六年十月一日条)とも見え、坂本付近には伊勢国と美濃国の両土岐勢が参戦していた様子もうかがえる。結果として京都勢により山門領の差し押さえは概ね成功し、六角満綱入道と京極持高による沙汰とされたようである。ただし、山門による神輿入洛の計画は粛々と進められていたようで、義教はこの事態の対応も迫られていた(『満済准后日記』永享六年十月二日条)。例の如く、義教は管領をして対応についての條々を満済に問い合わせている。管領使者の安富筑後守が條々を醍醐寺に伝えている。
| 義教諮問 | 要旨 | 満済答申 | 要旨 |
|
神輿入洛、来四五日間必定由申入間、方々御手宛 ●神輿供奉衆徒等取籠、悉可打取之由被仰付 ・松崎山名 ・中賀茂赤松 ・小笠原 ・藪里畠山 ●内裏可警固申入之由被定 ・治部大輔 ・細河一家 ●御所可祗候由被仰出 ・管領 ・一色 ●三井寺濱辺 ・土岐 ●今路(山徒使節等乗馬ニテ可供奉間、自今路河原へ可罷出之由評定云々) ・一勢可被置候處、其仁體無之間、未定候 |
神輿の入洛は11月4、5日辺りであるとのことで、軍勢の手配をした。 ●神輿供奉の衆徒を討取る者 ・松崎の山名 ・中賀茂の赤松 ・小笠原(政康?) ・藪里の畠山 ●内裏警固 ・斯波義郷 ・細川の一族 ●室町殿警固 ・細川持之 ・一色義貫 ●三井寺の前濱付近 ・土岐持益、持頼か ●今路(山門使節が乗馬で神輿に供奉し鴨川へ出るとの計画という) ・本来一勢を置く所だが、余力がないので予定はない |
神輿入洛、来四五日間必定之由承了、方々御手宛珍重候、三井寺濱等、為御用心、土岐勢可被置事、誠宜候哉、但今路御勢等不足事者、濱辺事ハ雖被仰付三井寺、可有何子細候哉、乍去此様お三井寺へ被尋仰、随彼申様可被仰付歟 | 神輿の入洛については承知しました。軍勢の手配もよいかと存ずる。ただ、三井寺濱は、用心のために土岐勢を配置することは大変良いと存ずるが、浜辺の事は園城寺に命じればよいかと存じます。園城寺へ尋ね、その意向の通りお命じなさるがよいと思います。 |
| 神輿入洛時、当所并山科辺土民等、罷出便宜所、東口へ落行山徒等候者、打留、具足等ヲモハキ取候ヘキ由、御下知可然 | 神輿の入洛時、醍醐や山科あたりの住人に、利を説いて、このあたりに逃げ来る山徒がいれば討って具足等も取ってよいと下知されたい | 当所并山科辺土民等、罷出便宜所、可致相応奉公之由事、可申付候 | 醍醐と山科の住人等に理を説き奉公に応じるよう申し付けましょう。 |
また、同日「自駿河内々今河右衛門佐入道注進趣、以此使者便宜申了、狩野事、為関東可致合力之由、被相触事等也」(『満済准后日記』永享六年十月二日条)との内々の申状を安富筑後守に預けて、義教へ披露するよう管領に遣わしている。
10月4日、山徒は神輿(客人神輿で大宮神輿ではない)を奉じて西坂本へ向かっていたが、なぜか「坂中辺マテ奉下、亥刻計歟、奉振捨修学院辺」(『満済准后日記』永享六年十月四日条)というように、修学院付近(左京区修学院音羽谷辺りか)で神輿は「奉振捨」られ、供奉の山徒は「悉登山」(『満済准后日記』永享六年十月五日条)したという。その原因は「奉居御輿前方ノクラ懸ノ脚折間、御輿モ前方ヘ傾」たためで「此則神慮無御同心故歟」との推測があった(『満済准后日記』永享六年十月六日条)。結局、鴨川外は洛外とみなされることから、この神輿を京都政権側が「御請取」すべき「振捨」には該当しないこととなり、人々は安堵した(『満済准后日記』永享六年十月七日条)。ただし、満済は「神輿被浸雨露、御体無勿体候歟、以御敬神早々可被加御下知之條、尤珍重」と義教に伝えている(『満済准后日記』永享六年十月七日条)。そして、10月7日には山門使節の一人杉生坊が「杉生降参申、昨日七日出京仕了」(『満済准后日記』永享六年十月八日条)といい、「今日可御対面之由、管領申間、其儀候、先山門辺事、如此成行間、御自愛」との義教から満済への報告があった。この対面には「円明同宿四五人降参申、杉生則召具」すという。
永享6(1434)年10月28日夜、満済のもとに駿河守護範忠の雑掌より「自駿河注進到来」があり、内容は「関東野心現行」(『満済准后日記』永享六年十月廿八日条)というものだった。この注進は「今河金吾入道、同下野守、葛原等注進同前」の三通で、このほか満済は「葛山今河方へ注進状表書庵原」と「善徳寺坊主注進状」の計五通を「以長全遣管領了」(『満済准后日記』永享六年十月廿八日条)した。守護範忠からの注進状は前日27日に管領持之へ届けられているという。
翌10月29日、管領持之が醍醐寺を訪れ、義教の言葉として「関東野心現形事、駿河ヨリ注進、先驚思食、」(『満済准后日記』永享六年十月廿九日条)と、今まで雑説としては聞いていた関東持氏の反抗につき、駿河守護範忠のみならず今川貞秋入道、下野守らからも注進があり真実味があることに義教はまず驚き、以下の通り満済に問い合わせている。それについて満済も返答をしている。
| 義教諮問 | 要旨 | 満済答申 | 要旨 |
| 何様御沙汰可然儀在之者、加談合可申入之由、可被仰今河方條如何 | 駿河守護に対し、どのように対応すべきか貞秋入道や下野守ら人々と談合したうえで申し入れるよう命じようと思うが、どうであろうか。 | 関東ヨリ一勢可越駿河之由注進ニ付テ、御手当等モ何様ニ御沙汰可宜旨、関東堺事候間、サスカ料簡才学ハ可在歟、御尋モ可有何子細候哉、関東儀現形トハ申候ヘ共、勢一騎モハタラカサル事候歟、旁猶具重可注申入條、可然候哉 | 関東から一勢が国境を越えて駿河に入ったとの注進につき、国境の対策ができていたことはよろしかろうとの仰せですが、駿河は関東境であり、範忠はやはり思慮も機転もある者だと存ずる。お尋ねの件も特に問題はなかろうと存ずる。ただ、関東については叛旗が明確になったというが、国境を越えたとはいえ何をしたものでもない。さらなる詳細な注進をするよう命じることが重要かと存ずる。 |
| 狩野、興津等事、今時分若御免可然事モヤト思食也、万一左様ニモ存候者、為守護以無為之儀可執申入歟 | 狩野介や興津ら今川家に反抗する人々の赦免についても考えているが、満済も同意であれば守護範忠から赦免したい旨を京都に申し入れるようにすべきか。 | 狩野、興津御免、只今時分可然候歟事、愚案及サル事候、此仰旨ヲ具可申下之間、宜ハ今河所存タルヘキ事候歟ト存候 | 狩野介や興津の赦免について、今がふさわしいかとのことですが、これは私の考えの及ばないところです。赦免についてのお考えの詳細を駿河へ下されるにあたっては、範忠の考えに任せるべきと存ずる。 |
| 但此両條、先愚身何様存知候哉、且可被任意見 | ただ、この両條については、満済がどう思うかまず聞きたい。そしてその意見に従うつもりだ。 | 仍両條、片時モ早々可被仰遣候、自管領委細以書状可被申下條可然、自是モ仰旨具以状可申下之 | この両條については、急ぎ管領から詳細を記した書状を下し遣わしすことがよいと存ずる。私からも仰せの内容を詳細に書状にしたためて駿河へ下す所存です。 |
|
(次いでに管領に話した) 円明以下中堂ニ閉籠仕、御勢坂本ヘ入候者、中堂ニ火ヲ懸、可自害企候ナル、然ニ只今坂本ヲ可打取御下知、可為何様候哉、今分ハ大略如上意可落居候歟、今コソ又一段御思案モ御遠慮モ在ルヘク候ヘト存候、如何 |
(次いでに管領に話した) 円明坊以下は根本中堂に立て籠もり、もし御勢が坂本に進駐したら、根本中堂に火をかけ自害するとのこと。こうした中で今坂本に打ち入る御下知はどうしたものでしょうか。今やおおよそ御意の通りに山門についての事態は収まっていると存ずる。今こそもう一段の御思案と遠望を持たれるべきかと存じますが、いかがでしょう。 |
駿河国からの書状の内容は伝わっていないが、義教や満済の対応等から、関東が「武田右馬助信長を駿河守護に任じた」として(甲斐国から)駿河国富士下方(富士市)に下したが、この一勢は今川勢と合戦も周辺を荒らすこともなく、甲斐国へ退いたとの内容とみられる。この件は、事を荒立てたくない義教、管領持之、満済が慎重に対応することで一致しており、義教はまずいち早く駿河国の内紛を解決するべく、狩野介や興津ら対立関係にあった国人の赦免を検討し、今川範忠から彼らを赦免したい旨を京都に申し入れるよう命じる意向であった。これは内紛を早期に収め、関東からの介入の隙を与えない意図があろう。
11月2日、管領持之から安富筑後守が醍醐に到来する。これは10月29日に「先日可申入處、失念仕了」事を伝えに来たものであった。内容は以下の通り(『満済准后日記』永享六年十一月二日条)。ここで武田信重入道の下向が急に取沙汰されたのは、甲斐国や駿河国での武田右馬助信長の蠢動によるものであろう。
| 義教諮問 | 要旨 | 満済答申 | 要旨 |
| 武田刑部大輔入道事、甲斐国国人跡部以下者共、大略意ヲ通、雖何時罷下候者、可致忠節之由連々申候哉、仍関東事、既現行候上者、刑部大輔ヲ可被下遣甲州事、可為何様哉 | 武田信重入道につき、甲斐国の跡部らがおおよそ京都に意を通じ、信重入道が甲斐国に下向する場合は、その下知に従う旨を頻りに申している。そのため関東の反抗がすでに明らかになっている上は、信重入道を甲斐に下向させるべきか、いかがであろうか。 | 甲斐国事、為駿河国自何簡要国候哉、甲斐国者共、実心中左様ニ候者、尤可然、但関東事、現行之由、自駿河注進ハ雖勿論候、猶不実様存、所詮今一両度モ定関東事可注進申入哉、現行無御不審時節可被下遣之條、猶可宜存候、関東事、何様雖■■(現行?)候、為京都ハ猶可被誘仰状珍重候歟、何様猶可被延引候歟、但一大事不可過之歟、諸大名意見可被尋聞食哉之由可申入 | 甲斐国の事は、駿河国にとっても重要な国でしょう。跡部らが真に心中からそのように考えているのであれば大変良い。ただ、関東が反抗したとする件については、駿河国からの注進は言うまでもないとはいえ、まだ不審を感じるので、今一度、しっかり注進させるべきと存ずる。また、信重下向は関東の反抗がはっきりしたときに行うのがよいと存する。関東については反抗が見られたとしても、京都はなおも慎重に対応すべきでしょう。ただし、一大事となったとしても何ら誤りなきよう、有司の意見をしっかり尋ね対応すべきと申し入れなさい。 |
義教は甲斐国人の跡部氏らが在京の甲斐守護武田信重入道の甲斐入部を頻りに懇望していることや、鎌倉方の駿河侵入事件(跡部氏と激しく対立する武田信長の富士下方侵入)も踏まえて叛逆が明確であるという点から、信重入道の甲斐下向を行いたい意向だが、満済の意見は、跡部氏の心中が不明である点、鎌倉方の一勢が駿河国で狼藉を働いたなどということは報告されておらず、鎌倉殿持氏の叛逆についても不審が残されている(駿河に侵入した武田左馬助信長が、対立する持氏の意向を受けているとは考えにくい、ということか)という点を述べて、しっかり確認を行うことが先決であることと、もし叛逆が事実であっても対応できるよう話し合いを行うことを伝えている(『満済准后日記』永享六年十一月二日条)。もとより甲斐国については関東の管掌国であり、その守護は鎌倉殿持氏によって任命され京都の承認を受けるものであることから、恣に京都が扶持する信重入道(現守護ではあるが持氏とは対立)を甲斐国に下向させることは鎌倉殿持氏の心証を悪化させてしまう危険性が高いこととともに前述の不審点もあり、満済は強力な慎重論を展開したのだろう。
これに応じた義教は、翌11月3日、関東管領上杉憲実へ対して、憲実の在京雑掌「羽田入道」を通じ鎌倉殿持氏の反抗の噂について問い質したい條々を満済に諮問した。その内容は以下の通り。
| 義教諮問 | 要旨 |
| 今春篠川方へ被下遣長老事ニ付テ、関東ニ雑説在之云々、此長老下向事、非殊儀、自関東佐竹可被退治之由風聞之間、万一楚忽沙汰候者、相構為篠河可被致合力、関東へ事子細ハ追可被仰旨、被仰遣計也、其外事一事被仰出儀無之、定不可有其隠歟 | 今春、京都から篠川殿へ長老を派遣しているが、関東ではこのことを様々に噂されているとのこと。長老の関東下向はいつもと変わらぬもので、関東から佐竹を攻めるような風聞があるので、万一合戦などになった際には篠川殿は佐竹祐義に合力するように伝え、関東へは後日その子細を遣わすこととしたのであって、そのほかは一言たりとも述べておらず、その事について嘘偽りはない |
| 只今駿河辺へ勢仕可在之由、雑説ナカラ自駿河致注進了、此條又何事哉、如風聞説者、武田右馬助ヲ駿河守護許容ニ依テ、富士下■■(方辺へ歟)可入一勢云々、実事ナラハ以外儀也、其故ハ京都上意ニ違ユル問注所等ヲハ、別而関東ニ被扶持置、武田右馬助事ハ、去年自関東内々被申旨在之間、京都御分国内不可叶由被仰付、駿河辺事、既被払之了、当年又立帰、駿河辺徘徊事ハ、公方曾不被知食事也、毎事任雅意被致其沙汰躰、殊以不可然、御所存外候也、于今御堪忍頗御退屈 | 関東が駿河辺へ軍勢を発めたとのこと、雑説ではあるが駿河から注進があった。この件はまたどういうことか。この風聞の通り、鎌倉が武田右馬助信長を駿河守護に任じ、富士に下向させて駿河に一勢を侵入させたということが事実であれば、とんでもない事である。京都の上意に反する問注所らを扶持置している件もある。武田信長については、去年の永享五年六月六日に関東から内々に依頼された「武田右馬助没落甲斐国、徘徊駿河辺云々、被加誅伐様被仰付可畏入」に応じて、武田信長について京都御分国内の居住を禁じ、駿河辺からはすでに追い払われている。だが、今年になり信長は駿河に立ち帰り、国内を徘徊していることを室町殿は御存じなかった。いつもいつも自分勝手に命を下すことは本当によろしくない。室町殿の御考えとは異なり、今や我慢することもうんざりなされている。 |
義教自身、関東管領憲実に対して隠し事をしても意味がないことを感じていたのだろう。正直に真実(京都側にとっての)を申し述べている。その一條目に「今春篠川方へ被下遣長老事ニ付」とあるが、義教はこの事実が鎌倉殿持氏に発覚したことが持氏の反抗につながっていると感じていた可能性があろう。義教は「篠川殿満直については、もし鎌倉殿が佐竹討伐を行ったら、(いつも述べているように、京都が扶持している)佐竹刑部大輔祐義を支援するよう伝えたのみであり(関東討伐などの指示はない)、その事について嘘偽りはない」と弁明している(『満済准后日記』永享六年十一月三日条)。
義教は管領持之をして満済にこの草案を遣わして「先此分お可被仰遣、此外又何事ヲカ被仰遣可宜哉、且可申意見」(『満済准后日記』永享六年十一月三日条)と問い合わせている。これに満済は「條々只今仰旨ハ何モ有ノマゝ儀ニテ、尤宜存候、此外■■可被仰遣題目不存寄候、先此分可被仰付羽田入道哉」と、義教がありのままの状況を伝えていることにこれ以上付け足すことはないと返答する。ただ、付則の意見として、以下の三点を指摘し、「若管領モ可然被存者、内々可被得時宜」と述べている。
| 一 | 佐竹事ハ、当御代ニ故畠山当職時、為関東楚忽■■有御退治、別而京都御扶持事、追又可申談旨遣安房守方了、関東只今勢仕旁物騒事歟 | 佐竹祐義については、当御代の故畠山満家が管領在職時に関東から軽率にも佐竹討伐が行われた際、佐竹祐義は特に京都御扶持であることを、上杉安房守に伝えているが、関東がいま佐竹攻めを行っているのは大変危険な事である。 |
| ニ | 安房守都鄙無為儀、連々申沙汰哉、何様次ニ可被感仰條、弥可畏存歟 | 安房守憲実の京都と関東の間を荒立てまいと、常々動いている姿勢を室町殿が感心されておられるので、ますます恐縮すべきことである。 |
| 三 | 関東雑説并駿河国様等、能々為被尋聞食、今河下野守可被召上條、可宜之由存、如何 | 関東に関する雑説や駿河国の件を詳細にお聞きなさるために今川下野守を駿河国から召還することがよいかと思うが、いかがであろうか。 |
またこのとき、管領持之は山門の状況についても満済に伝えている。それによれば、「今朝円明父子并月輪院等、坂本坊自焼」したことが伝えられ、武家方に属していた山徒「杉生、行仙、真野、西均、■■、蓮均」が「大宮以下致警固」のために「発向坂本」したという。詳細の注進はないが「今日入坂本儀不定歟」(『満済准后日記』永享六年十一月三日条)という。翌11月4日「自坂本杉生以下注進」があり「雖罷入坂本、無殊儀」という。ところが、その晩に「杉生同宿以下■■、自山上大勢発向、馬借以下相加テ合戦」の注進があった。坂本を引き上げた円明坊ら山徒は麾下の馬借を組織しており、夜陰に紛れて坂本に在陣する杉生坊らの討滅を図ったのである。この夜襲を受け「杉生打負、兄弟打死了、其外廿五人被打了、手負数十人」と敗戦となった。満済は「杉生打死先神妙歟、不便々々」と評価している。ただし、義教の評価は渋く「杉生今度楚忽ニ罷越坂本、無正体罷成條、御所存外、且杉生此間心中存私曲故、蒙神罰歟」(『満済准后日記』永享六年十一月四日条)と評する(ただし満済は「乍去其身落一命事候間、神妙候歟」と義教を嗜める)。
一方で、義教の山門への敵意は強くなり、「重近日坂本へ可有御勢仕、於今者中堂設雖令回禄、無力次第、時刻到来歟」(『満済准后日記』永享六年十一月四日条)と言い、坂本に正規の軍勢を派遣することとし、義教はこれにより根本中堂が焼失してもやむを得ないとまで述べている(ただし満済は「中堂無為、尚々念願此事」と義教を嗜める)。
●坂本派遣の軍勢(『満済准后日記』永享六年十一月八日、十九日条)
| ・畠山左馬助持永 | 西坂本 |
| ・畠山弥三郎持富 | 西坂本 |
| ・山名弾正少弼持豊 | 東坂本 |
| ・赤松伊予守義雅 | |
| ・遊佐勘解由左衛門(畠山被官) | |
| ・土岐大膳大夫持頼 | 東坂本 |
| ・土岐美濃守持益 | 東坂本 |
| ・細川讃岐守持常 | |
| ・京極治部大輔持高 | |
| ・甲斐(斯波被官) | |
| ・三方入道(一色被官) |
11月8日、満済のもとに「武田刑部大輔入道」が訪問し、「甲州へ密々可下遣僧、其子細ハ、万一関東雑説現行時者、定甲州へ可罷下由可被仰付歟」ことの報告をしている。関東から逃亡し関東から誅罰対象となっていた武田左馬助信長(刑部大輔信重入道の異母弟)が、実は関東の内示により流浪し甲斐国から駿河国を攻めるという雑説が事実であれば、信重入道が甲斐国へ下向することが事実上内定されていた。
11月25日、東坂本攻めが命じられた。寄手は以前と同様に「御勢山名、土岐大膳大夫、土岐美濃守」で、坂本に攻め入らんとするところに「馬借、下僧等同心、降下坂口、野伏合戦在之」(『満済准后日記』永享六年十一月廿五日条)となった。土岐大膳大夫持頼勢が先陣となって斬り込み、一人も手負いを出さないという優勢ぶりを示し、東坂本は灰燼となった。
11月28日、義教の命を受けて駿河から上洛した今川下野守が室町殿で義教に対面したという(『満済准后日記』永享六年十一月廿八日条)。11月3日の義教と管領持之との対談に基づいて、下野守の上洛が要請されたとみられる。対談中の下野守の意見については以下の通り。
| 狩野、興津以下御免事、尤可然 | 狩野介、興津等の赦免はまさにその通りと存じます。 |
| 関東野心、安房守依申止雖令延引、関東御心中ハ只今同前 | 関東の野心は、管領憲実が申し留めたため延引となったが、鎌倉殿の御心中はまったく変わっておりません。 |
12月3日、今川下野守が醍醐を訪問し、続けて管領持之も訪れ、満済に対面した。義教から、下野守からの申入分と義教の意見を合わせて満済に諮問するよう指示されての訪問であった(『満済准后日記』永享六年十二月三日条)。この指示により満済は下野守に様々尋ね、下野守からの返答を得ている。
| 満済質問 | 要旨 | 今川下野守返事 | 要旨 |
| 狩野、興津以下御免、関東雑説ニ付テモ、又国為モ可然歟之由、内々上意也、如何 | 狩野介、興津等の赦免の事は、関東雑説に対しても、また駿河国のためにもそうすべきか、と内々の上意であるが、いかがであろうか。 | 狩野、興津以下御免事ハ、関東ノ為モ、国為モ旁可宜存候、仍以前右衛門佐入道相共ニ執申入了、誠御免治定候者、矢部、朝比奈名字者共内、少々被召上於京都、狩野介、興津、三浦以下者ニ被召合、向後不可有別心、致可無二忠節旨、罰文おサセラれ候者、旁可然存 | 狩野介、興津以下の赦免の事については、関東のためにも駿河国のためにも、大変妥当であり、以前貞秋入道とともに申し入れた通りです。もし彼らを赦免するのであれば、矢部、朝比奈氏の数名を上洛させ、狩野介、興津、三浦らと京都で対面させ、今後は二心を持たず、無二の忠節を誓う誓紙を提出させることが妥当でしょう。 |
| 関東野心雑説事、先延引云々、就其今度現行時、駿河国御合力御勢何様ニ被仰付可然哉 | 関東叛心の雑説については、関東は延期したというが、今度関東が叛逆した時には、駿河国への御合力の御勢はどのように仰せ付けられるのがよいか。 | 関東御野心事、去比ハ既現行之由風聞、仍富士下方辺ヘモ、自伊豆申送旨等候キト云々、就其駿河御合力御勢仕事、兼テハ何トモ雖申入様、伊豆勢駿河国堺へ可罷入事ハ不可有程歟、二三里之間候、自駿河府富士下方、伊豆堺辺マテハ十六里計路間、自駿河府打立勢ハ可遅々歟、マシテ他国遠江三河辺御勢合力事、風渡ノ御用ニハ不可立候歟、乍去又可依被仰付様歟 | 関東の御叛心はすでに現実となっている風聞があり、武田信長が侵入した富士下方辺へも伊豆国からの指示があったといいます。それにつき、駿河への御合力について何度も申し入れましたが、関東伊豆勢が駿河国堺へ入るのは訳ないでしょう。二、三里程度です。ところが、駿府から富士下方、伊豆堺辺の国境までは十六里ありますので、駿府を出立した軍勢が国境にたどり着くには時間がかかります。まして、遠江や三河など他国からの御勢合力は緊急の御用には役に立たないと思われます。ただし室町殿の仰せに従うばかりです。 |
| 駿河国事、以外ウスイナル様ニ聞食及也、大事国堺ナルニ、如此ニテハ如何ト思食、何様哉 | 駿河国の事は、騒がしいことこの上ないとお聞きだ。駿河は大事な国堺であるのに、このような体たらくはいかがなものかと思召されている。どうであろう。 | 駿河国ウスヰノ由事、狩野以下者共、朝暮国ニ候者、共ニ根ヲサシ候間、国雑説等不休候、乍去只今随逐仕内者共、民部大輔ヲ軽シメ候テ、国儀如然候ニテハ努力々々無之 | 駿河国の騒擾については、狩野介らは常に駿河国にあり根ざしているので、国内の雑説は収まりません。ただ、被官等が範忠を軽んじて国情がこのようになっているのでは決してありません。 |
12月6日、「山門使節金輪院、月輪院、坐禅院、乗蓮四人、自雲母坂午刻計、参洛」(『満済准后日記』永享六年十二月六日条)という。11月3日時点では月輪院は円明坊兼宗らとともに坂本の自坊を焼いて比叡山に登っているが、その後、円明坊を除く山門使節金輪院以下四名は根本中堂を出て降伏したことがわかる。ただ、上洛した彼らと義教は簡単に対面しなかった。義教は「御勢退散以前、中堂以下閉籠之、円明同令没落、神輿悉御帰座在之者、可有御対面」(『満済准后日記』永享六年十二月七日条)という条件付けをして、円明坊兼宗ら根本中堂に立て籠もる山徒の解散を強く命じたのであった。しかし、12月11日、「諸大名山名、畠山、一色、赤松於管領亭会合、山門使節可有御対面之由、以右馬助管領弟、再三申入」たことで、さすがの義教も我意を押し通すことはできず「第三度時御領状、明日十二日、可有御対面」(『満済准后日記』永享六年十二月十一日条)ということになった。そして翌12月12日、予定通りに「山門使節金輪院、月輪院、坐禅院、乗坊以上四人、今日御対面」している。そして当の首謀者とされる円明坊兼宗法印は「円明、今日自中堂罷出、逐電」(『満済准后日記』永享六年十二月十六日条)という風聞であった。
おもだった山門使節の降伏により、永享6(1434)年12月13日、「坂本御勢陣開可」(『満済准后日記』永享六年十二月十二日条)と決定し、「坂諸軍勢、今日陣開、坂本払土岐美濃勢」するが、このとき「馬借下僧等数千人送懸」たため、土岐美濃守持益は「廿余人手負在之、以外難儀」という被害を出す。同じく土岐大膳大夫持頼は「二番勢ニテ粟津辺マテ雖引出、為合力一勢残置處、彼勢馳加致合力間、美濃勢無為云々、伊勢十余人手負在之、其内少々死者在之」と、引き際の土岐勢は馬借勢に襲われ、大きな被害を出した。
こうした山門問題が一応の決着を見た矢先の12月16日、管領持之が満済を訪問する。これは14日に持之のもとに到来した駿河守護範忠からの、関東と狩野らの結託の証拠となるべき文書の扱いを相談に来たものだった。この文書は「駿河狩野介、興津以下、相憑関東、本間ト大森ト両人方へ狩野、三浦、進藤以下以連署申遣使者僧於伊豆国、駿河守護被官者行逢、不事問召取、罷帰駿河了、仍彼連署状以下写之」したもので、管領持之は「此事可達上聞條、可為何様哉之由、旁不可然旨、種々談合子細在之、為此」(『満済准后日記』永享六年十二月十六日条)という。
12月17日には、12日に対面した山門側の四名のうち、乗蓮坊兼珍が自刃したという。その知らせは「今日巳刻末歟、乗蓮兼珍、於蘆山寺宿坊自害了、此事曾不存知處、自御所様以三條黄門被仰出、自滅儀神慮至、奇特不思儀被思食云々、明日彼使節四人金輪院、月輪院、坐禅院、乗蓮、案堵御判お可被下治定處、尚々此振舞非只事、併神罰ト思食」(『満済准后日記』永享六年十二月十七日条)と、義教から三条実雅を以って醍醐寺に伝えられた。翌18日の寺領安堵前日の自害に義教はこれはただ事ではなく神罰であろうと感想を述べている。12日の対面でどのような話が交わされたかは定かではないが、敵対は咎めたとは思われるが、寺領安堵については予定通り行っているため、赦免の意思は間違いなく伝えていたと考えられる。乗蓮坊兼珍の自刃は義教自身も驚いているように強要されたものではなく本人の後悔の念か。義教の報告を受けた満済は、使者の三條実雅を召し寄せ、経長寺主をして「不思儀子細、公方御罰依無所遁、如此罷成歟」と伝えている。翌18日、義教は乗蓮坊以外の三名の山門使節に対し、予定通り「山門使節金輪院以下三人、今日坊領等案堵御判拝領」(『満済准后日記』永享六年十二月十八日条)した。なお、円明坊は兼宗を廃し「円明兼覚十七、兼宗法印二男也」(『満済准后日記』永享七年二月四日条)とあるように、円明坊兼覚を新たな円明坊主にしたとみられる。
12月23日、満済のもとに「就狩野、三浦以下、関東内通事、彼等状案五通、自駿河写進了」した。満済は「件案文并今河状、以経長可致披露之由」を管領持之に遣わしている(『満済准后日記』永享六年十二月廿三日条)。満済としても東国の波風は荒立てたくはないものの、報告が到来している以上は執行部へ送達するよりほかにはなかった(満済は行政に携わる人物ではなく、あくまでも水面下で内々に諮問・答申の立場にあった)。翌24日、「自駿河注進、昨日経長持参管領處、公方様渡御物騒」と、日野資任の新亭(旧裏松義資亭を毀して新築したとみられる)への渡御があったため、「今朝以安富筑後守進之間、慥預置」(『満済准后日記』永享六年十二月廿四日条)とのことであった。
12月26日、満済のもとに武田刑部大輔信重入道が来訪し、「自跡部方注進持参」した。受け取った満済は「以経祐(経長カ)法眼即遣管領方了」と、「跡部状」を管領持之に送達している(『満済准后日記』永享六年十二月廿六日条)。翌27日、京都より戻った経祐法眼(経長寺主歟)は、管領持之は義教の細川讃岐守持常亭渡御に供奉していたため、「跡部状」は「管領出仕間、預置安富筑後守、慥可披露旨」ことを報告した(『満済准后日記』永享六年十二月廿七日条)。この旨を受け、義教は12月30日、赤松播磨守を信重入道のもとに遣わし「在国御暇事、不可有子細之由、被仰出」たため、信重入道は室町殿へ出仕して義教と対面し、甲斐国下向が承認された(『満済准后日記』永享七年正月五日条)。しかし、その後しばらく信重入道の下向は延引されている。舎弟の武田左馬助信長が鎌倉の指示で駿河国に進出したという風聞に対応するためか、甲斐国ではなく「被下遣駿河辺」(『満済准后日記』永享七年正月廿二日条)かで最終決定が見送られたためか。
永享7(1435)年正月17日、室町殿壇所に控えていた満済のもとに義教が訪れて、「就山門使節事、仰旨在之」と告げたが、満済は「但、今日ハ先不可被仰出管領歟之由申入」たことで、義教も「御同心、仍令略了」と述べた(『満済准后日記』永享七年正月十七日条)。おそらく義教は山門使節誅殺を決意し、満済に相談したとみられる。12月18日には彼らに寺領安堵を行っていたが、何らかの事件が発覚し、方針が転換されたのだろう。そのきっかけは、推測だが12月23日以降に報告された関東の不穏な動きと関係しているのかもしれない。満済が管領持之へ「就山門使節事(管領に山門使節を呼び出すよう命じることか)」を今日伝えることは控えるよう勧めたのは、いまだ情報としては時期尚早だったためか。
翌18日にも将軍義教は壇所に満済を訪問し、「自駿河注進、管領披露之由御物語」(『満済准后日記』永享七年正月十八日条)した。また、「信濃小笠原早々可被下国之條、尤宜思食、但就関東雑説、近日可被下国條如何、此子細為門跡内々可相談管領由被仰出了」についても指示しており、満済は親秀法橋を管領持之に遣わして、その対応を内々に相談すると、管領持之は「小笠原下国尤可然存、関東雑説時分被下国事、曾無其苦之由存」とのことであった(『満済准后日記』永享七年正月十八日条)。満済はこれを義教へ報告したと思われるが、年明けの正月20日、義教は壇所に満済を訪問すると、管領持之からの報告として「今度、自関東方々へ内書六通歟正文、岩堀入道常時禅僧衣着之、去年以来罷下関東處、無左右此使節勤仕由、罷上白状」(『満済准后日記』永享七年正月廿日条)したという。この岩堀入道が持っていた関東からの「内書六通」は「悉三河国人等也、他国一人モ無之」といい、三河国人へ宛てた文書であった。
正月22日、義教は満済に「武田刑部大輔入道可被下遣駿河辺、関東雑説時分、若可悪歟、如何、可仰談管領」と指示している。昨年12月30日に決定された信重入道の甲斐下向がいまだ行われていないことがうかがえる(『満済准后日記』永享七年正月廿二日条)。前述のように駿河国には信重入道の舎弟信長が関東の指示で駿河国や周辺域の騒乱により延引された可能性があろう。満済は管領被官安富筑後守を召し寄せ、信重入道の駿河下向が現在の状況において妥当かどうか意見を述べるよう管領に伝えるよう指示した。その後、安富筑後守が管領持之の意見を満済に届けたが「武田刑部大輔入道可被下遣駿河辺事、関東現形必儀定、重可致注進歟、其以後可宜」(『満済准后日記』永享七年正月廿二日条)との返答だった。24日に満済は「武田刑部入道下国駿河辺事、管領申入旨披露處、尤由仰」との義教の意見であった。
正月26日、「信濃守護小笠原」が義教の命により御所内壇所に控える満済を訪れ、「就関東野(心)現形事、條々被仰含子細在之」(『満済准后日記』永享七年正月廿六日条)の報告をしている。これにつき、正月29日早旦御壇所を訪れた義教に、満済は「其御返事様、又委御尋申入了」している。その内容は以下の通り。
| 大井トアシタト弓矢落居、旁可然存候、サク郡信州也ニ此大井モアシタモ構要害候、サク郡ヲトヲリテウスイタウケヘモ、又上野国ヘモ可罷通之間、以越後勢大井ヲ御合力候テ、アシタヲ御退治可然、大井ト小笠原ト一所ニ罷成候者、信州事ハ可有何程候哉、左様ニ候者、関東辺事モ又一方ハ可罷立御用由存 | 大井と蘆田の争いが終わったのはよいことです。佐久郡に大井も蘆田も城を構えています。佐久郡を通って碓氷峠へも上野国へも行くことができるので、越後勢を大井に合力させ蘆田を追捕することがよいでしょう。大井と小笠原が一体となれば、信濃国の事は大した事はないでしょう。このようになれば、関東の件についても大井、小笠原のどちらかが対応できると思います。 |
これにつき、義教は「越後勢合力事、以赤松播磨可被仰付長尾」と、赤松満政をして越後守護代長尾上野入道の出兵も命じることを述べている。義教は関東との破滅的な対峙を避けるべく、満済や管領持之と連携して対応してきたものの、駿河や甲斐、三河における関東調略の情報は確定的かつ進行的であり、義教としても我慢の限界だったのかもしれない。また、山門使節と関東の関係についても「山門事、関東辺雑説聞食合」(『満済准后日記』永享六年七月十二日条)という過去の風聞も蒸し返され、後述のような措置に結びつくことになったのかもしれない。
正月28日、義教は前年12月24日に報告を受けた「就狩野、三浦以下、関東内通事、彼等状案五通、自駿河写進了」の注進につき、今川範忠へ狩野らに対する遵行後の状況を報告するようしている。(永享七年正月廿八日「細川持之書状案」『足利将軍御内書并奉書留』)。
●永享7(1435)年正月28日「細川持之書状案」(『足利将軍御内書并奉書留』室:2833)
2月1日に「小弁局御産無為若公降誕、珍重々々」(『満済准后日記』永享七年二月一日条)とあり、男子が誕生した(5月23日に夭折(『看聞日記』永享七年五月廿八日条))。御産所は「今若公自桃井御産所、御移住一色五郎亭了」(『満済准后日記』永享七年三月十一日条)とあることから桃井某邸で、小弁局は桃井氏所縁と考えられる。これに伴い、2月4日には「若公御降誕御礼、僧俗群参如例」(『満済准后日記』永享七年二月四日条)、「若公降誕参賀也、室町殿へ人々群参」(『看聞日記』永享七年二月四日条)とあるように人々が室町殿に群参した。義教はこの「僧俗群参」を利用して、関東内通を強く疑う山門使節の誅殺を実行に移すことにしたのだろう。義教は2月1日から3日までの間に管領持之に対し、山上に戻っていた山門使節に室町殿への参向を命じる指示をしたとみられる。ただ、参向せよと命じるだけでは処罰を恐れて逃亡する恐れもあるが、「僧俗群参」時であればその心配はないためと思われる。さらに「自兼管領出抜、令参洛者可被成安堵之由令申、猶恐怖猶予之處、管領書告文遣之間、令参洛之處召捕」(『看聞日記』永享七年二月四日条)と、山門使節側がなお罰せられることを恐れていることに、管領持之が告文を山門側に遣わすことで、京都に誘い出したという。しかし、座禅院のみはなお疑いを持っていたか、下山しなかった。
そしてこの日の「今朝人々参賀之時分」(『看聞日記』永享七年二月四日条)の「今朝巳刻、山門使節三人、金輪院弁澄法印六十九、月輪院、円明兼覚十七、兼宗法印二男也、於兼覚者、御所中小侍所被召取云々、両人於管領召取之」(『満済准后日記』永享七年二月四日条)ると「三人即時於悲田院内被誅」した。なお、伏見宮貞成入道親王が聞いた報告では「山門使節四人被召捕、二人円明カ同宿、称名乗蓮、以前腹切舎弟、於御所召捕、二人金輪院宿老八十余歳云々、月輪院被召捕之時、人々手負、於管領召捕、自兼管領出抜、令参洛者可被成安堵之由令申、猶恐怖猶予之處、管領書告文遣之間、令参洛之處召捕、則於悲田院四人勿首」(『看聞日記』永享七年二月四日条)とあるように、円明坊門人と乗蓮坊舎弟は御所内で捕らえられ、金輪院と月輪院は管領が捕らえたというものだった。
この一件により、この日の夜、「今夜山門総持院炎上」(『満済准后日記』永享七年二月四日条)した。総持院は「当御代御願也、仍最前令成灰燼歟」と、満済は総持院は義教御願であるため、真っ先に放火されたのではないかと推測している。総持院(惣持院)は「仏具、経論等重宝共在此所、炎上了」(『看聞日記』永享七年二月八日条)という。
さらに翌2月5日午刻、「山門根本中堂」が炎上し、「大宮権現神輿、同四日奉振入中堂、成灰燼了、円明兼宗末子今度被誅弟云々、以下十八人自害」(『満済准后日記』永享七年二月六日条)という報告が山名時熈入道から満済に届けられている。この情報は「中堂承仕」が下山して室町殿へ急報したもので、最澄御作の「常燈奉取出」ることはできたこと、「円明同宿存知分計三十余人自害、其外不見知者数輩」ことが伝えられた。「使節被勿首之由聞、相残座禅院等、悪党共放火、忽一時山上滅亡」(『看聞日記』永享七年二月六日条)と、下山しなかった坐禅院等が放火したものだという。この情報は貞成入道親王にも「浄侶中より注進」のものとして報告されており、同じ情報源のものと推測される。貞成入道親王には「中堂本尊大略炎上歟、但奉取出歟、不知云々、惣持院仏具経論等重宝共在此所、炎上了、三ケ所炎上、自元没落」事と、「座禅院以下輩、中堂ニ楯籠自焼腹切者廿四人、円明ハ逐電云々、中堂本尊今一体大師御作之御衣木在横河、設雖焼失、此本尊可奉渡之間、社頭ハ皆無為之由注進申云々、大講堂も不焼失、殊社頭以下無為」(『看聞日記』永享七年二月八日条)との情報が伝えられた。
山名入道から比叡山根本中堂が焼け落ちた事を伝えられた満済は「天下凶事重事何事可過之哉、驚歎周章外無他事々々」と感想を述べる。その後、赤松美作守が満済のもとに派遣され、「昨日中堂炎上儀、当時之儀御周章、乍去又時刻到来歟、無力(中堂の炎上を聞き非常に慌てたが、然るべき時だったのだろう。やむなきことだ)」(『満済准后日記』永享七年二月六日条)との義教の言葉が伝えられ、満済も「其事候、天下重事不可過之哉、但今者無力次第候歟、中堂御本尊以下被召寄、山門日記者等具被尋仰、簡要中堂早々御建立珍重」(『満済准后日記』永享七年二月六日条)と返答している。
●焼失した建築物、寺宝等
| 根本中堂 | 中堂薬師如来 | 『看聞日記』永享七年二月十五日条 | |
| 五瓶三 |
釈尊御道具 三国伝来 |
『満済准后日記』永享七年二月六日条 『看聞日記』永享七年二月六日条 |
|
| 火舎 |
釈尊御道具 三国伝来 |
『満済准后日記』永享七年二月六日条 『看聞日記』永享七年二月六日条 |
|
| 華原磬 | 霊山釈尊御説法時御打 |
『満済准后日記』永享七年二月六日条 『満済准后日記』永享七年二月九日条 |
|
| 泗濱石 | 『満済准后日記』永享七年二月六日条 | ||
| 錫杖 | 『看聞日記』永享七年二月十五日条 | ||
| 鏡二面 | 『看聞日記』永享七年二月十五日条 | ||
|
総持院 (惣持院) |
『満済准后日記』永享七年二月四日条 『看聞日記』永享七年二月八日条 |
●逐電、自害した人々
| 人名 |
逐電 自害 |
典拠 |
| 円明(円明坊兼宗)、座禅院、等持(惣持院か) | 逐電 |
『満済准后日記』永享七年二月八日条 『看聞日記』永享七年二月十五日条 |
|
性浄院、般若院、東般若院、南修学、蓮養坊、かくりん坊、れんち坊、 若狭坊、相模坊、大弐坊、覚定坊 円明末子 |
自害 |
『看聞日記』永享七年二月六日条 『看聞日記』永享七年二月十五日条 |
|
【俗同宿】 伊佐、同子、たか田、真木、帯刀、さあみ、しあみ |
||
|
【中方】 ほうしやく、公文けんさう、帯刀おいゑちこ、馬場彦九郎、源七、うんほう |
この比叡山根本中堂の焼失について、義教は「山門事、是非不可沙汰之由」(『看聞日記』永享七年二月八日条)を管領以下の有司に伝えたのだろう。義教は市中や人々の動揺を避ける意図があったとみられるが、「而煎物商人、於路頭此事申間召捕、忽被勿首」という事件もあったようである。侍所一色義貫の措置と推測されるが、伏見貞成入道親王は「万人恐怖、莫言々々」(『看聞日記』永享七年二月八日条)と感想を述べている。
また、正月に一旦は落居したはずの大井越前守持光(京都方)と蘆田下野守(鎌倉方)の抗争は再度対立が起こっていたようで、この報告を受けた義教は管領持之から信濃守護小笠原政康入道に対し「大井越前守与蘆田下野守不快事、不可然候、早可和睦之旨被仰出候、仍当国面々被成御教書候了」と、大井持光と蘆田下野守の抗争を早々に和睦させるべく、信濃国人に対して御教書を発したことを報告するとともに、「若猶不事行者、可被差遣美濃、越後御勢之由、可申沙汰候」ことを警告する(二月十九日「細川持之書状案」『足利将軍御内書并奉書留』室:2836)。
3月10日、「今河民部大輔可参洛之由、同名下野守申也、今月中」(『満済准后日記』永享七年三月十日条)ことが満済に報告されている。ただ、この関東不穏の時期に駿河守護たる範忠の上洛は好ましい事ではなく、義教は「駿河守護近日可参洛之由、被聞食及、只今参洛不被得御意、早々下遣飛脚、不可参洛之由可仰遣」(『満済准后日記』永享七年二月十三日条)と、範忠に参洛中止の飛脚を下すよう指示が出したという。この報告を受けた満済は、「仰旨以今河下野守可申遣候」と、使者は今川下野守を以て行うようにと述べるとともに、「但、国拝領以後ハ参洛初度候歟、然自途中被追返様ニ候ヘハ、外聞実儀定可周章仕歟、既路次マテ罷出候者、先此分ニテ被閣様ニ可申沙汰歟、参洛候テ施面目罷下候者、一段民部大輔威勢モ可出来歟」(『満済准后日記』永享七年二月十三日条)と、もし範忠がすでに参洛の途次にあった場合は追い返さずに参洛させて面目を保たせれば、駿河国において一層範忠の威勢も増すことになろうと意見し、義教も「時宜御同心云々、仍途中マテ罷出者、可参洛之由可申遣旨、被仰付今河下野守」(『満済准后日記』永享七年二月十三日条)と、満済の意見の通りに今川下野守へ駿河下向を指示した。
永享7(1435)年4月に入ると、醍醐寺座主の三宝院満済の容態は急激に悪化した。
4月1日には恒例の愛染王護摩が執り行われ、本来は満済が修法する予定であったが「所労事」により「手代禅那院僧正」が執り行うこととなる(『満済准后日記』永享七年四月一日条)。また、4月2日には管領持之が醍醐寺まで足を運び「当職可辞申入事、可如何哉、宜様一向可計給」(『満済准后日記』永享七年四月一日条)と、管領職の辞職について相談に訪れたが、満済は「窮屈時分不及出京、先可被申談三條黄門」(『満済准后日記』永享七年四月一日条)と返答している。満済は自分の容態悪化と、自分に代わる義教の相談相手としては、義教義兄の三條権中納言実雅が適当と認識していたと思われる。そして4月4日以降、紙背に記される日記(『満済准后日記』)は容態が良い日以外は天気のみが記され、4月23日條を最後に終了する。
5月19日「三宝院准后病気再発危急」し、「室町殿渡御、諸人鼓操」(『看聞日記』永享七年五月廿一日条)し、5月28日には伏見に「抑三宝院已及難儀、被出本坊三宝院」(『看聞日記』永享七年五月廿八日条)という知らせが届いている。これは満済は自らの死による触穢を避けるため三宝院を出たのだろう。6月6日には「三宝院所労危急之間、弟子宝池院給安堵」(『看聞日記』永享七年六月六日条)と、三宝院門跡は宝池院(宝池院義賢。権大納言満詮子息で義教の従弟)が継承し安堵された。そして、6月13日、ついに「抑三宝院准后、今朝入滅」(『看聞日記』永享七年六月十三日条)した。齢五十八歳。貞成入道親王をして「天下義者也」と評した仁者であった。「此両三年病気、今度瘻病興盛、遂堕命」(『看聞日記』永享七年六月十三日条)と、腫物によって入滅したと記される。
| 年 | 月日 | 原文 | 症状 | 医師等 | 診療 | 投薬 | 典拠 |
| 永享6年 | 2月12日 | 腹中以外傷、悩乱無申計 | 腹痛 | 清阿 三位法眼 |
木香湯 呉茱萸湯 |
『満済准后日記』 永享六年二月十二日条 |
|
| 3月8日 | 自今曉蟲腹又更発 蟲腹以外興隆、吐気頻也、心神頗如無、終日同前 脈様不苦、積聚以外、蟲又大事云々、雖然於療養者不可有殊儀 |
医師三位 | 脈 | 木香湯 三稜丸 |
満済准后日記』 永享六年三月八日条 |
||
| 3月9日 | 今日食事同前不通也 | 『満済准后日記』 永享六年三月九日条 |
|||||
| 3月11日 | 脈様三位申同前、但左心中風以外云々、一大事蟲、能々可有御養性 | 医師桂音 | 脈 | 『満済准后日記』 永享六年三月十一日条 |
|||
| 3月16日 | 脈様弥無力、可令用心云々、心細事無申計、但非仰天限 | 医師桂音 | 脈 | 『満済准后日記』 永享六年三月十六日条 |
|||
| 3月20日 | 三位法眼 | 脈 | 『満済准后日記』 永享六年三月廿日条 |
||||
| 6月8日 | 自昨日蟲気聊指出間、為謹慎 無殊事、脈冷気 |
三位法眼 | 脈 | 『満済准后日記』 永享六年六月八日条 |
|||
| 6月9日 | 管領入、唐人医師召具 唐医単衣體也、唐医暫休息、無左右不取脈、乗馬之間如此云々、次取脈卓ノ上ニヤハラカナル物ヲ可敷云々、仍如然用意、其後左手ヲヤハラカナル物ノ上ニ居テ、医師手ヲハ卓ノ上ニ居テ取之了、右同前、申詞唐医ニ仰テ令書付了 【診断】 看診得左手脈、微緩、帯洪数、独肝部盛主、病原因怒気起後至痰気虚熱 右手三部脈、俱微弱無力、主肺気缺、清脾胃弱、飲食少味 |
唐人医師 | 脈 | 六君子湯 | 『満済准后日記』 永享六年六月九日条 |
||
| 7月4日 | 為瘻療治、召寄久阿弥了、瘻ノ上ヲ三十一灸治、其後廻付薬、灸跡ニハ蛇香薬ヲ脚ニテ付了 | 瘻 | 久阿弥 | 灸 | 蛇香薬 | 『満済准后日記』 永享六年七月四日条 |
|
| 11月29日 | 心痛気聊指出了、雖然早速平癒了、其後風疹以外興隆、心神不快 | 心痛 風疹 |
長全上座 (醍醐寺) |
『満済准后日記』 永享六年十一月廿九日条 |
|||
| 11月30日 | 昨日風疹事、長全間違、蚊触由申遣 風疹自昨夜悉減之由申了、中風序 |
風疹 | 三位法眼 | 『満済准后日記』 永享六年十一月晦日条 |
|||
| 永享7年 | 正月12日 | 自半更例心痛更発 | 心痛 | 『満済准后日記』 永享七年正月十二日条 |
|||
| 正月中旬 | 後髪際、雑熱出現 | 瘻 | 『満済准后日記』 永享七年二月十四日条 |
||||
| 2月7日 | 窮屈以外也、若養生無沙汰事在之者、定可為難儀 | 胤能法眼 | 『満済准后日記』 永享七年二月七日条 |
||||
| 2月9日 | 脈無殊儀、瘻農血出事ハ不可然 | 瘻 | 板坂 | 脈 | 『満済准后日記』 永享七年二月九日条 |
||
| 2月14日 | 後髪際、雑熱出現之間、久お御召寄相尋處、在所六惜敷存云々、仍廻ニ薬お付了、非殊物歟、去月中旬比ヨリ在之、廿日計ニ及歟 | 瘻 | 塗薬 | 『満済准后日記』 永享七年二月十四日条 |
|||
| 3月6日 | 脾臓脈度数事、聊風歟、今日灸治先可閣(3月6日条) | 頼豊 | 脈 | 『満済准后日記』 永享七年三月六日条 |
|||
| 3月6日 | 脈様只同前、無増気之條珍重々々 (昨日の頼豊診断につき)仍其子細相尋胤能法眼處、脾臓度数非風気、積習故 |
胤能法眼 | 脈 | 『満済准后日記』 永享七年三月六日条 |
|||
| 5月19日 | 三宝院准后病気再発危急 室町殿渡御、諸人鼓操 |
危急 | 『看聞日記』 永享七年五月廿一日条 |
||||
| 5月28日 | 抑三宝院已及難儀、被出本坊三宝院 | 難儀 | 『看聞日記』 永享七年五月廿八日条 |
||||
| 6月6日 | 三宝院所労危急之間、弟子宝池院給安堵 | 危急 | 『看聞日記』 永享七年六月六日条 |
||||
| 6月13日 | 瘻病興盛 | 入滅 | 『看聞御記』 永享七年六月十三日条 |
上記のような症状から、循環器系の疾患に加えて膵臓(当時の脾臓)の疾患に伴う糖尿病及び糖尿病性網膜症、頸部リンパ節の瘻があったか。
この頃、関東において、鎌倉殿持氏は「鹿島大禰宜兼親申、当社領下野国大内庄内東田井郷」につき、去年、「宇都宮頭役事及度々致入部譴責由依歎申」と、鹿島大禰宜兼親は宇都宮右馬助等綱による狼藉の譴責を鎌倉に願い出たところ、関東は「不可然旨固致仰下」と、宇都宮等網に下野国大内庄内の地の押領の停止を指示している。ところが、今度は「塙信濃入道仁、令居住隣郷」て、様々に狼藉を行ったことから、5月3日、鎌倉は「宇都宮右馬助殿」に塙信濃入道の追放を命じている(永享七年五月三日『羽生大禰宜文書』室:2846)。宇都宮等綱は数年前には篠川殿満直のもとに寄寓していたが、この時点では宇都宮に戻った上、守護職となっていた様子がうかがえる。
5月23日、貞成入道親王のもとに、比叡山から逃亡した座禅院珍全につき「聞、座禅院事、伊勢国人長野搦取、侍所ニ渡、於相国寺延寿堂一夜被糺問、悉白状申、其後被勿首」(『看聞日記』永享七年五月廿三日条)と、座禅院は伊勢国人工藤長野氏により捕らえられて侍所へ引き渡され、相国寺延寿堂で一晩糺問されてすべて白状したのち、斬首されたという報告が入る。捕縛の場所は、伊勢国ではなく伊勢守護土岐持頼に従って在京中の長野が捕らえたものか。また「円明ハ平泉寺隠居之由白状申」(『看聞日記』永享七年六月三日条)ており、義教は円明坊を追うべく、越前守護代甲斐(斯波義郷被官)に「越前下向可退治」を命じている(『看聞日記』永享七年五月廿一日条)。また、座禅院と同道していた「同宿一人円明子、同被召捕被籠舎、依諸大名意見被斬」(『看聞日記』永享七年五月廿一日条)と、円明坊兼宗の子息もまた捕らわれて斬刑に処されたという。
円明坊兼慶―+―円明坊兼承
|
+―円明坊兼宗―+―円明坊兼覚(永享七年二月、斬)
|
+―円明子(永享七年五月、斬)
|
+―末子(永享七年二月、根本中堂で自刃)
甲斐勢は平泉寺に遁れているという円明坊兼宗を追捕するため「被仰之間、被仰甲斐討手ニ罷下」たが、伏見に届いた一報では、平泉寺長吏が「座禅院子、為時衆導場隠居、召捕」ったという報告が入るが、「又聞、座禅院子、平泉寺長吏ハ不召捕、甲斐召捕上洛」とも伝えられている(『看聞日記』永享七年六月三日条)。結局、座禅院の子は捕らえられて上洛し、「軈、於悲田院被斬」たという(『看聞日記』永享七年六月三日条)。円明坊については「円明ハ熊野浦ヘ落下」と、北陸から紀州方面へ逃亡したことが明らかとなる。このことから、円明坊兼宗は座禅院珍全の子を預かり、座禅院珍全は円明坊兼宗の子を預かって、それぞれどちらかが捕らえられても血脈は残るよう図っていた様子がうかがえる。
6月13日、前述の通り「抑三宝院准后、今朝入滅」(『看聞日記』永享七年六月十三日条)した。この満済入滅の一報を受けた義教は「公方殊御周章云々、連々醍醐渡御御懇切訪給」(『看聞日記』永享七年六月十三日条)という。そして「室町殿、自今日五壇法被始」ており、翌6月14日の「祇園会如例、公方無御見物」(『看聞日記』永享七年六月十四日条)と、見物を取り止めている。貞成入道親王は6月14日に庭田宰相を出京させて「三條(三條実雅)」へ悔みを述べたのだろう。義教の様子は「以外御悲歎」であり、「今月中、諸方入申事被止、二條造作被閣、今月中被入申事延引」と、申入や造作、政務の悉くの延引を告げたのだった。満済入滅による衝撃の深さを物語る。そして、義教は「公方背御意真俗少々御免」を行った。これは「三宝院最後之所望」であり、義教もこの三宝院の遺言を「被執申」した結果であった。臨終まで人々のために尽くした生き様は、まさに「天下之義者」であった。
さらに7月4日には重鎮「山名、今曉逝去」(『看聞日記』永享七年七月四日条)した。時熈入道は頓死と思われ、「遺跡兄弟相論可籍乱歟」と時熈子息の刑部少輔持熈(兄)と弾正少弼持豊(弟)の間で時熈入道の遺跡を巡る戦いが起こることになる。
山名政氏
(小次郎)
∥―――――――山名時氏――+―山名師義―+―山名義幸
∥ (伊豆守) |(右衛門佐)|(讃岐守)
上杉重房―+―女子 | |
(左衛門尉)| | +―山名満幸
| | (播磨守)
+―上杉頼重―+―上杉重顕 | ∥
(大膳大夫)|(修理大夫) | ∥
| +―山名氏清―+―女子
+―藤原清子 |(陸奥守) |
(足利尊氏母)| +―山名時清
| |(宮田左馬助)
| |
| +―女子
| ∥―――――山名持豊――+―山名教豊
| ∥ (右衛門督) |(弾正少弼)
| ∥ |
+―山名時義―――山名時熈――山名持熈 +=養女
|(伊予守) (右衛門督)(刑部少輔) |(熙貴女子)
| | ∥――――――細川政元
+―山名義理―――山名義清――山名教清 | 細川勝元 (右京大夫)
|(弾正少弼) (中務大輔)(修理大夫) |(右京大夫)
| |
| +=養女
| (熙貴女子)
| ∥――――――大内政弘
| 大内教弘 (左京大夫)
| (大膳大夫)
|
+―山名氏冬―――山名氏家――山名熈貴――+―女子
(中務大輔) (中務大輔)(中務大輔) |(山名持豊養女)
|
+―女子
(山名持豊養女)
7月12日、「亥刻、若君御誕生」(『蔭涼軒日録』永享七年七月十二日条)とあり、義教三男が誕生した。のちの鎌倉殿政知である。母については「御袋御北向様」(『御産所日記』永享七年七月十二日条)とあるが、伏見に伝わった情報では「抑、若公今朝誕生云々、朝日娘」(『看聞日記』永享七年七月十三日条)、「朝日若公」(『看聞日記』永享九年十二月二日条)とあることや、後述の通り、この五か月後に北向殿:裏松氏(故裏松義資妹)に男子(のちの義政)が誕生していることから、この若君の母は北向殿ではなく、伏見に伝わった「朝日娘」である。故義持の奉公衆として見える「朝日因幡守満時」(『花営三代記』応永卅年三月廿四日条)の娘または所縁の娘であろう。産所は「御産所結城」(『御産所日記』永享七年七月十二日条)と、「今日若公御誕生、御産所赤松伊予守義雅宿所也、御産戌剋」(『師郷記』永享七年七月十三日条)と二説あるが、当日の記録である『師郷記』の信憑性が高いか。
当時の関東では、持氏と佐竹刑部大輔祐義の抗争が依然として続いており、鎌倉勢の攻勢が激しさを増していた。京都は佐竹祐義を扶持する立場にあったため、「自関東佐竹可被退治之由風聞之間、万一楚忽沙汰候者、相構為篠河可被致合力、関東へ事子細ハ追可被仰旨」(『満済准后日記』永享六年十一月二日条)、「為関東楚忽■■有御退治、別而京都御扶持事、追又可申談旨遣安房守方了」(『満済准后日記』永享六年十一月三日条)とあるように、前年にも義教は持氏に対して、佐竹祐義への攻撃の停止要請を遣わしていたが、止むことはなかった。これは京都の支援を受けている佐竹祐義や南奥州の白河結城氏、篠川殿らが持氏に従う姿勢を見せないためであった。持氏は彼らを「関東の安寧」を乱す元凶=「怨敵」と認識しており、彼らを調伏するための「大勝金剛尊」の造立と「攘咒咀怨敵於未兆」の願文を鶴岡八幡宮寺に捧呈するほどの決意を示しており、妥協は考えるべくもなかった。
この頃、持氏は大々的な佐竹攻めを行ったようで、6月下旬には佐竹祐義被官の長倉遠江守義成を追討するべく「岩松典厩持国為大将軍発向」し、「八月中旬、茂木郷着陣、同廿八日被向要害」(『長倉状』)して攻め立てたという。岩松には野田、徳河、佐々木、梶原、簗田、植野、上州一揆、武州一揆、那須、海上、臼井、大須賀、相馬ら千葉一族、小田、結城、小山、宇都宮一門らが随ったという。
9月24日には「於常州和田城合戦」が行われており、持氏方の「小野崎越前三郎殿(小野崎通房)」が奮戦して負傷したことを持氏が賞している(永享七年十一月十六日「足利持氏御教書」『阿保文書』室:2879)。「和田城」はおそらく佐竹祐義の居城である山入城(常陸太田市国安町)の支城である和田城(常陸太田市松平町)と思われ、鎌倉勢は佐竹祐義の足元まで攻め寄せていたことがうかがえる。
こうした持氏の攻勢に対し、佐竹祐義ばかりでなく京都から佐竹支援を指示されていた篠川殿も危機を京都へ注進した。これを受けた義教は、9月22日、信濃守護「小笠原治部大輔入道殿(小笠原政康入道)」に、「蘆田治罰事、先令延引訖」と、佐久郡周辺での蘆田下野守との合戦を一旦中止して、「佐竹及難儀者、可合力之上者、可致其用意」(永享七年九月廿二日「足利義教御内書」『小笠原文書』室:2872)ことを指示し、信濃国府へ遣わした。持氏自身の出陣があるとの注進を受けた義教は、事危急と判断したとみられる。
●永享7(1435)年9月22日「足利義教御内書案」(『小笠原文書』室:2872)
(「御自筆 永享七年十月七日 府中へ下着」)
自関東、為佐竹(退治?)、自身可発向之由、佐々川并佐竹註進到来之間、蘆田治罰事、先令延引訖、佐竹及難儀者、可合力之上者、可致其用意、巨細右京大夫可申候也
九月廿二日(花押:義教)
小笠原治部大輔入道殿
ただ、実際は持氏自身の出師はなく、持氏は、篠川満直や白河結城氏と対峙する「石川治部少輔殿」や「石川中務少輔殿(石川持光)」に「叢首座」を遣わして「為佐竹凶徒等対治、差遣軍勢候」ことを伝えている通り、軍勢を遣わしているのみでり、篠川満直や佐竹祐義が危機を煽る常套手段「自身可発向之由」の標榜であることがわかる。その後、実際に小笠原勢が常陸へ合力した様子はうかがえず、京都方から具体的な軍事介入は行われなかっただろう(なお、一連の「佐竹」については、『簗田家譜』より義憲とされるが不審)。
永享8(1436)年正月2日、「抑、室町殿若公降誕午剋、母北向裏松妹、嫡子二男同腹、幸運之人歟、繁昌珍重也」(『看聞日記』永享八年正月二日条)と、将軍義教に前年七月に続いて男子が誕生した。嫡子義勝(七代将軍)と同腹の男子であった。なお、『御産所日記』では「御袋左京大夫殿、御産所赤松伊豫」(『御産所日記』永享八年正月二日条)とあるが、母は義教妾の裏松日野氏である。
結城氏?
∥―――――――朝日氏
朝日満時? ∥――――――足利政知
(因幡守) ∥ (左馬頭)
足利義教
(六代将軍)
∥
∥――――+―足利義勝
∥ |(七代将軍)
∥ |
日野重光――+―藤原重子 +――――――――足利義政
(大納言) |(北向殿) (八代将軍)
| ∥
+―裏松義資―――日野重政―+―藤原富子
(権大納言) (右少弁) |(妙善院)
|
+―日野勝光
(左大臣)
このころ下総国においては、9月9日、千葉介胤直は三崎庄円福寺に、前年永享7(1435)年3月27日の譲状(現存せず)により千葉庄金剛授寺の宝幢院覚胤法印が譲った知行地につき、御判を以って証している(永享八年九月九日「千葉胤直安堵状」)。円福寺は千葉惣領家の「御祈祷所」であり(文安三年四月十三日「千葉胤将安堵状」)、この所領を巡っては金剛授寺「尊光院」が介入する企みがあったようで、さらに「諸公事等」については「海上理慶禅門」の定めた掟があったようだ。
●永享8(1436)年9月9日「千葉胤直安堵状」(『円福寺文書』)
同じく9月ごろには、信濃国の「村上中務大輔殿(村上頼清)」が「対被官人及弓矢」と、家中内紛を引き起こした。この報告はおそらく守護小笠原政康入道から京都に遣わされたと思われ、義教は「関東物騒之時分、殊不可然候、急止私之儀、先度如被仰出候、可被致忠節候」(某年十月七日「細川持之書状案」『足利将軍御内書并奉書留』)と、関東が不穏な時期であり私戦は止めるよう頼清へ命を下している。しかし、実は頼清は「村上連々関東致音信蒙御芳恩間、可預御合力由、進家子布施伊豆入道處、明窓和尚執申之及御合力、桃井左衛門督為大将、上州一揆、武州一揆、奉公那波上総介、高山修理亮、被相添既打向信州處、彼国京都御分国也、対守護人之弓矢村上御合力不可然旨、上杉安房守憲実依被相存、上州一揆、在所雖令出陣、不越国境、彼御合力計不事行」(『鎌倉持氏記』)とされるように、頼清は家子の布施伊豆入道を鎌倉に遣わし、明窓和尚を仲介として関東合力の約束を取り付けたという。これに応じた持氏は、頼清援軍の大将に桃井左衛門督(桃井憲義)を定め、上州一揆、武州一揆に上野国に本拠を持つ奉公衆の那波上総介、高山修理亮を添えて信州へ派遣させようとしたが、上野国守護でもある管領上杉憲実が「彼国京都御分国也、対守護人之弓矢村上御合力不可然」と上州一揆に伝えたため、上州一揆は出陣の体を示すも国境を越えることはなく、関東からの合力はなされなかった。その結果、小笠原勢は村上勢を打ち破り、京都へ報告がなされた。義教は政康入道に「村上中務大輔及合戦之処、誅取悪徒、得勝利云々、国中静謐之基、不可過之歟」(某年十二月廿日「足利義教御内書」『小笠原文書』室:2920)として、太刀と黒糸腹巻を贈って賞する御内書を送達している。
これまでも、武田信長の駿河越境や鎌倉方の佐竹攻めなどが、京都と関東の大きな懸念となっていたが、信長は甲斐国における国内合戦に敗れて駿河へ逃亡したもので、持氏との共謀はなかったと考えられる(そもそも持氏は信長追捕を京都に要請し、京都はそれに応じて駿河在住を禁じている)ことや、佐竹攻めは関東御分国内での私戦(ただし佐竹祐義は京都の支援を受けているため、京都は鎌倉に佐竹攻めの中止を要請している)であり、京都は関東御分国の甲斐国、常陸国への軍事的介入や人事には非常に慎重であった。ところが、持氏が直接的に京都御分国の信濃国の騒乱に軍事介入の姿勢を示したことは、前記の次元を超えるものであった。「於信州小笠原入道与村上中務合戦、村上為加勢持氏軍兵発向、是都鄙不快基也」(『鎌倉大日記』)とあるように、この守護小笠原政康入道と村上頼清の合戦に持氏が軍事的介入を試みたことが、その後の永享の乱に直結する原因と考えられる。また、不幸なことに満済亡き後、様々な問題について義教に直言できる人物も不在となっていたのであろう。この関東の軍事的動向が顕わになった時期と連動するように、義教は精神的に不安定になっている様子がみえる。
永享9(1437)年2月8日、一條東洞院の伏見殿に住む貞成入道親王に届いた情報によると、理由は不明ながら「抑猿楽観世、御突鼻失面目」という。義教は猿楽を好み、父義満が取り立てた観阿弥の孫にあたる観世大夫元重(音阿弥)を重んじた。ところが、永享8(1436)年に義教が伏見殿に渡御した際に貞成入道親王が「猿楽不申沙汰、不快之随一也」という事があり、それ以来「諸方渡御之時、以猿楽御もてなし為専一」と、人々は義教渡御の際は必ず音阿弥を招聘して猿楽を催した程であった。その音阿弥が勘気を被ったことに、貞成入道親王は「不定之世毎事如、莫言々々」と述べている(『看聞日記』永享九年二月八日条)。また、この音阿弥の不始末の一件については赤松満祐入道も義教に「物言(意見)」したようで、その不興を買い「赤松身上云々、播州、作州可被借召之由被仰」とあるように、義教は満祐入道から播磨国、美作国を収公する指示をしたとの話も伝わっている。
■観世大夫系図
【観世大夫】 【観世大夫】【観世大夫】
清次―――+―元清――+―元雅
(観阿弥) |(世阿弥)|
| |
| +―元能
|
| 【観世大夫】
+―元仲――――元重―――元盛―――之重――元広――元忠
(四郎太夫)(音阿弥)(又三郎)
その翌日2月9日には、義教が御台所尹子の実家、三條実雅亭に渡御した。ここに「東御方」も「三條へ御共被参」た(『看聞日記』永享九年二月九日条)。東御方は貞成入道親王の父・栄仁親王の側室で当年七十五歳、尹子の曾祖叔母に当たり、義教とも懇意にしていた。この席で義教は三条邸の会所に掲げられていた「会所之飾唐絵殊勝之間、就其事東御方ニ被問申」(『看聞日記』永享九年二月十日条)という「御雑談」を交わした。ところが、東御方は日頃の狎れもあったのだろう。義教が褒めた唐絵の軸に対し「一言悪被申」(『看聞日記』永享九年二月九日条)、「御返事悪被申」(『看聞日記』永享九年二月十日条)という。前日の観世大夫の一件や関東不穏の状況の中で義教の神経は苛立っていたのだろう。この東御方の返事に「忽御腹立、抜御腰刀金打給、向後不可見参とて被追立申」と、立腹して腰刀を抜く仕草を見せ、今後見参することを禁じた。東御方は京都三条邸から「伏見禅照菴被逃下」り、義教は「依此事早々還御、猿楽事も不被申」(『看聞日記』永享九年二月十日条)、「三条も観世事被執申不許、七八献了早々還御、毎事無興」(『看聞日記』永享九年二月九日条)と、三条実雅が音阿弥の不始末を執り成したが許されず、義教は七、八献のみで帰ってしまった。これに貞成入道親王は「言語道断、驚歎無極」(『看聞日記』永享九年二月九日条)、「履薄氷之儀恐怖千万」(『看聞日記』永享九年二月九日条)と感想を述べる。ただ、その後義教は些細な事に激怒してしまった仕儀を悔いたのか「西雲」を伏見に遣わすと、東御方について「伏見殿如元可被祗候之由」を伝えている。
三條公貫―+―三條実仲―+―三條公明
(権大納言)|(内大臣) |(権大納言)
| |
| +―三條実治―+―三條公為―――三條実博―――三條公久―――――三條実文
| (権中納言)|(左近衛中将) (右近衛中将)
| |
| +―――――――――――――――西御方 +―治仁王
| ∥ |(二代伏見宮)
| 光厳天皇 ∥ |
| ∥ ∥――――――+―貞成親王
| ∥ ∥ (三代伏見宮)
| ∥――――――崇光天皇―――栄仁親王 ∥―――――――後花園天皇
| ∥ (初代伏見宮) ∥
| +―藤原秀子 ∥ ∥ 源幸子
| |(陽禄門院) ∥ ∥ (敷政門院)
| | ∥ ∥
| +―三條実音――――――――――廊御方 ∥
| |(権大納言) ∥
| | ∥
| | +――――――――――――東御方
| | |
| | |
+―三條実躬―――三條公秀―+―三條実継―+―三條公豊―+―三條実豊―――――三條公雅――+―三條実雅
(大納言) (内大臣) (内大臣) (内大臣) |(参議) (権大納言) |(内大臣)
| |
| +―藤原尹子
| |(瑞春院)
| | ∥
| | ∥
| | 足利義教
| |(室町殿)
| | ∥
| | ∥
| +―藤原豊子
| (上臈局)
|
+―三條西公保――――三條西実隆―――三条西公條
(内大臣) (内大臣) (右大臣)
2月13日夜には一條近辺で放火があり、「騒動有物言其時分之間、猥雑言語道断事也、世上以外也」というように洛中は騒擾が続き、「勘解由小路左衛門佐、赤松身上云々、大和、信濃等難儀之處、京中又物騒、天下如何驚入者也」(『看聞日記』永享九年二月十三日条)と、義教には多方面から様々な問題がふりかかり続けた。当時の義教の精神状況は極度に不安定な状況にあったと考えられる。
また、赤松満祐入道は(観世大夫に関することか)に物言して義教の不興を買い、守護国を借召されるとの噂が立っていたが、義教は2月16日、「赤松へ公方渡御」した(『看聞日記』永享九年二月十六日条)。これを聞いた貞成入道親王は「物言落居之分歟、惣別珍重也」と、義教の勘気が解かれたような様子に安堵し、さらに「観世赤松執申、御免則有猿楽」と、赤松満祐入道の執り成しにより音阿弥の勘気も解かれ、義教は猿楽を鑑賞したという。東御方の一件と同様に、義教は冷静になると行いを悔いて勘気を解くという行為を繰り返していることがうかがえる。
永享9(1437)年3月4日、義教は大和国で南朝吉野勢に呼応して挙兵している大和越智氏追討のため「抑公方、大和小路長谷雄為退治、南都へ可有御立」といい、自身も南都出陣を表明したという。興福寺の大乗院もその知らせを受けて「自兼御所を建」ていた(『看聞日記』永享九年三月四日条)。義教は諸大名に事前に諮っていたが「非朝敵国人為退治御進発如何之由、各諫申」たため、「雖未定先被仰出」とにわかに出立するとして、まず小侍所の「畠山子息」を「明日大和へ進発」を指示(実際の進発は16日となった)するとともに「近習小番衆ニ已被仰出」たという(『看聞日記』永享九年三月四日条)。ただ、義教はその後、例の如く考えを改め、3月12日に「公方御立之事ハ御留歟」(『看聞日記』永享九年三月十二日条)と、自らの出陣を中止している。その後、3月16日に「畠山、土岐等大和へ進発」(『看聞日記』永享九年三月十六日条)した。
ところが、「大和事、敵橘寺ニ籠」り、「手物共多手負い」し、「勘解由小路左衛門佐勢も多手負」というように、南朝勢の頑強な抵抗に遭い、大将軍斯波義郷勢も多くの手負いを受け、斯波家の宿老家二宮一族の「二宮六郎」も重傷を負って「上洛道ニて死云々、弓矢上手勇士云々、不便也」(『看聞日記』永享九年四月十四日条)という。こうしたことに再び「公方又可有御立之由、風聞治定之様有沙汰」(『看聞日記』永享九年五月三日条)という風聞が流れている。なお、7月11日のこととなるが、この大和国の南朝挙兵に義教異母弟の大覚寺准后義昭が合流して、義教に反旗を翻すこととなる(『東寺執行日記』永享九年七月十一日条)。
4月22日には「三條告申、信州事落居、御剣可被進云々、則御見剣進之」と、信濃国村上頼清がいったんは兵を収めたようであるが、関東では「同九年四月、上杉陸奥守憲直為大将武州本一揆可罷立旨被仰付間、諸人得其意處、憲直大将非信濃国事、為憲実御対治御結構由、被官人等承山正員入耳、仍憲実契約人等自国ヨリ上集」(『鎌倉持氏記』)と、持氏は上杉陸奥守憲直を信州村上合力の大将とするも、実は信濃国への派兵を諌止し続ける憲実を追討する兵であるという風聞があり、今度は憲実方の人々が鎌倉に集結してきたという。
これに加えて、5月6日には「信濃事落居又破、関東合力勿論、管領職辞退云々、天下式旁驚存者也」という(『看聞日記』永享九年五月六日条)。一旦は収まっていた村上頼清の反抗が、関東の合力を得て再び兵を動かしたという知らせであった。さらに度々持氏の態度を諫めてきた上杉憲実も匙を投げ、関東管領職の辞退を申し出たという報告まで伝わった。義教はさらに問題を抱えることとなってしまった。
当時関東では「入六月中、鎌倉中猥騒不斜、同六日七日八日不暮夜不明式也」(『鎌倉持氏記』)とあるように、六月には憲実方の人々が鎌倉に入って大騒動となっていた様子がうかがえる。この事態に「七日暮方、大御所憲実宿所有御出、兎角雖有誘御寛心中、更不排、雖然面少静分也」と、持氏母一色氏(大御所)が憲実宿所を訪ねて弁疏したことで、騒擾はやや落ち着いたが、憲実追討の大将とされた陸奥守憲直は「身上不安間、同月十五日、父子藤沢罷退訖」と、身の危険を感じて子の掃部頭憲家とともに鎌倉を離れて藤沢へ隠居したという(『鎌倉持氏記』)。
7月3日には京都に「関東管領上杉、為京方致諫言之間、欲被退治、已及合戦、而上杉勝軍之由注進」(『看聞日記』永享九年七月三日条)という注進が届いている。前述の上杉憲直・憲家の藤沢隠退騒動を指しているのだろう。「就鎌倉中雑説、度々御出陣、喜入候」(永享九年九月廿一日「上杉憲実書状」『小林文書』室:2942)と、憲実のために憲実守護国の人々がたびたび鎌倉へ向けて出陣していた様子がうかがえる。その一人、上野国人の小林尾張守も鎌倉へ下った一人だが、鎌倉街道を南下する最中、「殊去八月一日被馳上之処、依一途属無為候」のため、「武州入間河」から帰国した旨が上野守護代長尾憲明より憲実に報告されている(永享九年九月廿一日「上杉憲実書状」『小林文書』室:2942)。一方で、憲実は7月25日、「憲実嫡七才蜜ニ上州下向、是憲実身上被思定故歟」(『鎌倉持氏記』)と、嫡子龍忠丸(憲忠)を秘かに守護国上野国へと下向させた。憲実の決死の覚悟の顕れであるという。また、持氏は7月27日、憲実からの「直兼、憲直、為讒人由」という上申を鑑みて、「一色宮内大輔直兼、三浦下向」させて鎌倉から退去させている。憲直はすでに藤沢へ隠居しており、「両人既下国訖」と、憲実の意見を容れた裁定を行い、憲実との和解を模索した。ただし、持氏は憲実側にも「山内事、大石石見守憲重、長尾右衛門尉景仲、依令張行、雑説多由」(『鎌倉持氏記』)を述べ、暗に大石憲重と長尾景仲にも同様の裁定(鎌倉追放)を要求したのであった。これを受けた憲実は、帰亭し憲重と景仲を呼んでこれを話すと、「景仲、憲重如申者、我等就令在国御無為可為者、尤可下国仕由」と、我ら両名が武蔵国へ在国することで解決するのであれば、そのようにする旨を憲実に伝えている。これを聞いた憲実はしばし思案ののち、「縦両人雖令下国、不可有無為儀」として、大石憲重、長尾景仲の武蔵下国は拒絶した。
続けて8月13日、持氏自らは憲実亭を訪れて「彼所存色々被仰寛、管領職如元被仰付」た。これに憲実は「再三雖被辞申」と辞退するも、持氏は「強被仰付」たため、「当座乍領掌申」したが、「武州代官、不下施行、判形不致」というように、管領職付帯の武蔵国守護職に関しては守護代を定めず、国政も裁定も行わないことを宣言する(『鎌倉持氏記』)。関東の安定化を第一に考え、敵対者は排除すべきと考える持氏と、京都と関東の関係を安寧に保ち続けたい憲実(この考えは義教が「安房守都鄙無為儀、連々申沙汰哉、何様次ニ可被感仰條、弥可畏存歟」と賞しているように、義教の考えと同一であった)との間には、決定的な思想の相違があったのである。
しかし、相変わらず常陸国では鎌倉方と京都御扶持の佐竹祐義方との戦闘は日常的に続いており、10月7日には「常州烏渡呂宇城城攻」が行われている(永享九年十二月十一日「足利持氏御教書写」『松平義行所蔵文書』室:2950)。持氏はこの合戦に参戦した「佐竹白石中務丞殿」に戦功を賞する御教書を下している(永享九年十二月十一日「足利持氏御教書写」『松平義行所蔵文書』室:2950)。
加賀局 |
また、大和国では将軍義教の異母弟・大覚寺准后義昭が南朝方に合流して挙兵するという事件も起こった。
永享9(1437)年7月11日暁に「大覚寺殿御逐電義昭僧正」(『東寺執行日記』永享九年七月十一日条)し、その情報は翌7月12日には「大覚寺殿出奔之事、自香厳院被申焉」(『蔭涼軒日録』永享九年七月十二日条)と、相国寺蔭涼軒主季瓊真蘂のもとに天龍寺香厳院主の尊満大僧都(義教異母兄)から報告があった。当然ながら、すでに義教にも報告がなされていたことだろう。その出奔の原因は「大覚寺門主逐電云々、室町殿御連枝也、御意不快之間、野心之企歟」(『看聞日記』永享九年七月十四日条)とあるように、義教が不快の念を持っており、野心を企てたとの噂があったようである。義教はただちに大覚寺に兵を派遣し「候人共被召捕、被糾明」たが、二年前に誕生した「朝日若君、上臈も逐電被尋云々、南方祗候人も逐電」(『看聞日記』永享九年七月十四日条)との風聞も立っている。
そして7月16日、「聞、大覚寺逐電実説也、玉川護正院候人共両三人逐電、依之彼方様女中共皆逐電」(『看聞日記』永享九年七月十六日条)といい、7月20日には「抑大覚寺門主、天王寺落下、僧坊一宿、彼坊主相伴被出不知行方」と、大まかな足取りも判明してきていたが、「仍彼僧坊追捕、法師一人召捕、管領預置被尋、更不存知之由申」(『看聞日記』永享九年七月廿日条)と、天王寺の僧坊法師を一人召し捕らえて、管領持之のもとで尋問するも、そこからの行方は判明しなかった。ただ「南方宮、同御逐電、叛逆之企露顕歟」(『看聞日記』永享九年七月廿日条)と、「南方宮(旧聖護院宮系の円胤らか)」もまた同じく逐電しており、その関係が考えられた。7月23日に貞成入道親王が聞いたところによれば、「大覚寺、大和隠居小路取申云々、山名宮内少輔御方参、伊勢国師等合力、可上錦旗」(『看聞日記』永享九年七月廿三日条)という。同じく「将軍御舎弟大覚寺門主義昭逐電、越智内通」(『大乗院日記目録』永享九年七月日条)とあるように大和国の南朝勢力との内通が疑われ、8月8日、中山定親が聞いたところでは「大覚寺僧正、被落著吉野山奥、還俗俗名義有云々、方々送廻文」(『薩戒記』永享九年八月八日条)といい、大覚寺准后義昭大僧正は名を「義有」と改めた。
8月24日、「大覚寺僧正若内通関東歟之由、依有其疑于今未定歟之由、世之所推也、而今朝飛脚到来、坂東無其沙汰、凡静謐之趣、注進之由所風聞也」(『薩戒記』永享九年八月廿四日条)と、大覚寺准后の出奔は関東と結びついたものであるという疑惑があったが、今朝の飛脚によれば関東とは関わりはなく、おそらく南朝方が将軍義教と不快となっていた大覚寺准后を取り込んだ謀叛であったのだろう。その後、日向国へと亡命している。
また、同時期に河内国でも南朝楠木党による不穏な動きが見られ、時期からして大覚寺義昭の逐電と軌を一にするものだった可能性もあろう。8月初頭、「河内国凶徒楠木党」が河内国に挙兵して城を攻め落として籠城した。ただ、兵力は寡少だったか、8月3日「未終剋」には河内守護畠山持国勢に攻められ、「討取大将」(『薩戒記』永享九年八月三日条)している。このとき挙兵したのは「楠兄弟」とあるが、楠木正成との血縁は不明。この合戦で討たれた大将首は十一にも及び、8月5日「楠首上洛、河原十一頭被懸」(『看聞日記』永享九年八月五日条)という。
永享10(1438)年、持氏は「来六月、可為若君御元服、御落居也」(『鎌倉持氏記』)と、若君賢王丸の元服を行うことを決定し、6月に「鎌倉持氏若君賢王丸殿、於八幡宮元服、号義久」(『鎌倉大日記』)と、鶴岡八幡宮寺において元服の儀が執り行われたとされる。
ただし、京都に注進された情報によれば、「鎌倉若公元服事、管領上杉為申沙汰、自公方執御沙汰治定之處、改其儀於鶴岡八幡宮御沙汰」(『看聞日記』永享十年八月廿二日条)とあるように、上杉憲実が持氏若公の元服について京都に報告し、義教はこれを了承して憲実が沙汰すること、つまり、当初は常の通り、将軍家より一字「教」を賜って元服することが決定していたことがわかる。ところが持氏はそれを鶴岡八幡宮の沙汰(別当尊仲の沙汰か)で執り行うことに変更したという。この持氏の変心は「京都御敵対露顕、管領失面目」(『看聞日記』永享十年八月廿二日条)と受け止められており、このことが直接的に義教が関東を見限る原因となったとみられる。「就関東時宜事、此間可被仰處、依御騒劇無其儀候、非本意候」(八月廿七日「細川持之書状案」『足利将軍御内書并奉書留』室:2987)とあり、義教としてはこの持氏の行いは願っていたものではないと伝えている。
憲実は、賢王丸元服の儀に関し「任先規、京都御字可有御申」と述べるが、持氏は「無御領掌」という。憲実はさらに「若依御使節可遅々者、可進舎弟三郎重方」と、御使節をためらうのであれば、我が弟三郎重方を遣わすことを提案するも、これも「無御承引」という。さらに元服の祝儀として「国方仁等、可参上旨、指名字、而被召上云者、直兼、憲直無是非被召帰訖」と、先年の混乱の責任を取らせて鎌倉を追放していた一色直兼、上杉憲直を呼び戻したのであった。
こののち行われた若君元服の儀に際しては「就御祝憲実出仕時、可有御沙汰云雑説」(『鎌倉持氏記』)があったため、憲実自身は「号違例」して出席せず、代理として弟の三郎重方を出席させたという。このような機微が雑説として漏れ出ること自体「不思議」で、両者の離間を企む隠謀の可能性も考えられるが、「依之憲実遺恨為甚深」という。
その後、元服の儀についての風聞に対して憲実が遺恨を持っていることにつき、持氏も「御進退、惟谷」ったと、身の潔白を示すため「若君、憲実宿所可有置御申」ことを提案した(『鎌倉持氏記』)。これにより一旦は「憲実、安少心」くして和解の方向へ進んだため、「万人開喜悦眉」いたという。ところが、ここに若宮社務法印尊仲(鶴岡八幡宮寺別当大和尚)が「此段不可旨」を頻りに申し入れたため、持氏は前言を撤回してしまう。別当尊仲は「一色五郎入道々慶」の子とあるため、持氏血族の一色氏出身者か。持氏は親族である一色氏の讒訴を受け容れ、憲実を京都と結ぶ徒党(つまり、持氏が敵視する「京都御扶持之輩」と同類)とみなしたのではあるまいか。
【五郎】
一色範氏―+―一色直氏――一色氏兼―+―一色満直――――一色頼直
(次郎) |(宮内少輔)(宮内少輔)|(宮内少輔) (修理亮)
| |
| +―一色長兼――?―一色時家(持家?)
| |(左京大夫) (刑部少輔)
| |
| +―一色直兼
| (宮内太輔)
|
+―一色範光――一色詮範―――一色満範――+―一色持範―――一色政照―――一色政具―――一色晴具―――一色藤長
|(修理大夫)(左京大夫) (修理大夫) |(式部少輔) (式部少輔) (式部少輔) (式部少輔) (式部少輔)
| |
| |【五郎】
+―一色範房――一色詮光―――一色満貞 +―一色義貫―――一色義直
(右馬頭) (兵部少輔) |(修理大夫) (修理大夫)
|
| 【五郎】
+―一色持信―――一色教親
(兵部少輔) (左京大夫)
■鶴岡八幡宮社務職
| 代 | 別当 社務職 |
就任期間 | 師 | 父母 | 没年 | 僧官・僧位他 | 備考 |
| 1 | 円曉 | 1182.9.23 1200.10.2 |
行曉法印 | 父:行恵法眼 (輔仁親王子) 母:六條判官為義女 |
1200.10.26 56歳 |
法眼 | 中納言阿闍梨 宮法眼 |
| 2 | 尊曉 | 1200.10.2 1206.5.3 |
行教法印 | 行恵法眼 (輔仁親王子) |
1209.9.15 | 宰相阿闍梨 濱別当 |
|
| 3 | 定曉 | 1206.5.18 1217.5.11 |
円曉法橋 | 平大納言時忠一門 | 1217.5.11 | 法橋 | 三位法橋 太別当 |
| 4 | 頼曉 (公曉) |
1217.6.20 1219.1.27 |
公胤僧正 | 左衛門督源頼家 | 1219.1.27 20歳 |
法橋 | 左衛門法橋 悪別当 |
| 5 | 慶幸 | 1219.2.1 1220.1.1 |
実慶大僧都 | 1220.1.1 | 僧都 | 三位僧都 一年別当 |
|
| 6 | 定豪 | 1220.1.21 1221.9.29 |
兼豪法印 | 民部権少輔源延俊 (西宮源氏) |
1222.9.24 京都帰寂 87歳 |
弁法橋 兼法務 大僧正 |
忍辱山大僧正 勝長寿院別当職 |
| 7 | 定雅 | 1221.9.29 1229.6.25 |
定豪大僧正 | 参議藤原親雅 | 大蔵卿阿闍梨 | ||
| 8 | 定親 | 1229.6.25 1247.6.27 |
定豪大僧正 | 土御門通親 | 1265.7.25 於京都入滅 |
法橋 法務大僧正 東寺一長者 東大寺別当 |
内大臣法橋 |
| 9 | 隆弁 | 1247.6.27 1283.8.24 |
円意法印 | 四條隆房 | 法印 大僧正 |
大納言法印 如意寺 聖福寺殿 |
|
| 10 | 頼助 | 1283.8.24 1296.2.27 |
守海法印 | 武蔵守経時 | 1296.2.28 52歳 |
法印 大僧正 東寺一長者 |
亮法印 円城寺 佐々目大僧正 西明寺殿甥 |
| 11 | 政助 | 1296.2.27 1303.6.2 |
頼助大僧正 | 武蔵守宗政 | 1303.6.2 29歳 |
法印 | 亮法印 |
| 12 | 道瑜 | 1303.6.11 1309.6.18 |
大僧正隆弁 大僧正道慶 |
父:九條良実 母:大友大炊助親秀女 |
1309.7.2 54歳 |
大僧正 | 二條殿 如意寺殿 |
| 13 | 道珍 | 1309.6.18 1313.8.12 |
大僧正静珍 大僧正道瑜 |
高司基忠 | 1313.8.12 38歳 |
大僧正 | 堀川僧正 南瀧院 |
| 14 | 房海 | 1313.9.1 1316.8.3 |
法印房源 法印円審 |
従二位宗教 | 1316.8.3 72歳 |
僧正 園城寺別当 右大将法華堂別当 |
刑部卿僧正 |
| 15 | 信忠 | 1316.8.13 1322.10.19 |
勝信僧正 | 父:九條忠家 母:太政大臣公房女 |
1322.10.19 57歳 |
勧修寺長吏 高野伝法院座主 東寺一長者 東大寺別当 |
勧修寺大僧正 九條殿 |
| 16 | 顕弁 | 1322.10.28 1331.4.23 |
隆弁大僧正 静誉大僧正 |
越後守顕時 | 1331.4.23 63歳 |
大僧正 | 大夫大僧正 月輪院 |
| 17 | 有助 | 1331.4.26 1333.5.22 |
大僧正頼助 | 駿河守平有時孫 兼時子 |
1333.5.22 57歳 於高時亭自害 |
大僧正法務 | 上乗院大僧正 佐々目大僧正 |
| 18 | 覚助 | 1333.9.4 (無御下向) 社務代覚伊僧正 1336.9.17 |
後嵯峨天皇 | 1336.9.17 90歳 |
二品親王 園城寺長吏 三山検校 新熊野検校 四天王寺別当 |
聖護院宮 | |
| 19 | 頼仲 | 1336.6.20 1355.6 |
大僧正頼助 大僧正親玄 |
仁木次郎師義 | 1355.10.2 90歳 |
法印 大僧正 |
少納言法印 宝蓮院 |
| 20 | 弘賢 | 1355.6 1410.5.4 |
大僧正頼仲 | 加古七郎 | 1410.5.4 85歳 |
法印 大僧正 |
左衛門督法印 西南院 |
| 21 | 尊賢 | 1410.6.13 1416.2.14 |
一品親王寛尊 西南院 |
全仁親王 ・亀山院曽孫 ・恒明親王孫 |
1416.2.14 71歳 |
大僧正 | 宝幢院宮僧正 常磐井殿 |
| 22 | 快尊 | 1416.8.15 1417.1.10 |
大僧正弘賢 大僧正尊賢 |
久我前大将通宣猶子 (実父上杉禅秀) |
1417.1.10 於小袋坂滅亡 25歳 |
法印 大倉熊野堂別当 鑁阿寺別当 赤御堂別当 上総八幡別当 |
大納言法印 実性院 |
| 23 | 尊運 | 1417.1.25 1431.8.24 |
大僧正尊賢 | 裏松中納言豊光猶子 (実父上杉式部大輔朝広) |
1431.8.26 33歳 |
権大僧正 走湯山別当 松岡八幡宮別当 六天宮別当 柳宮別当 西明寺別当 等 |
一位法眼 |
| 24 | 尊仲 | 1431.12.19 1439.11 |
大僧正弘賢 大僧正尊賢 |
一色五郎入道道慶 | 1439.11 被誅 |
法印 権大僧都 供僧正覚院主 鑁阿寺別当 樺崎寺別当 赤御堂別当 大門寺別当 江嶋別当 雪下新宮別当 等 |
中納言法印 |
| 25 | 弘尊 | 1439.11 1449.8? |
加古某 | 法印 権大僧都 |
神守院 | ||
| 26 | 定尊 | 1449.8? 1467? |
従三位持氏 | ||||
| 27 | 弘尊 (還補) |
1467.4.1 ???? |
加古某 | 法印 権大僧都 |
神守院 |
こうして持氏は憲実追討を画策し、諸国に軍勢催促を行った。実際に7月24日には筑波山の筑波法眼玄朝が持氏の命を受けて鎌倉へ出兵しており、7月半ばに京都に届けられた「就関東之時宜」に関する今川上総介範忠(被相副葛山駿河守書状)の注進状は、持氏が具体的な軍勢催促を行い、上杉憲実追討の風聞を伝えるものだったのだろう(七月晦日「細川持之書状案」『足利将軍御内書并奉書留』室:2976)。
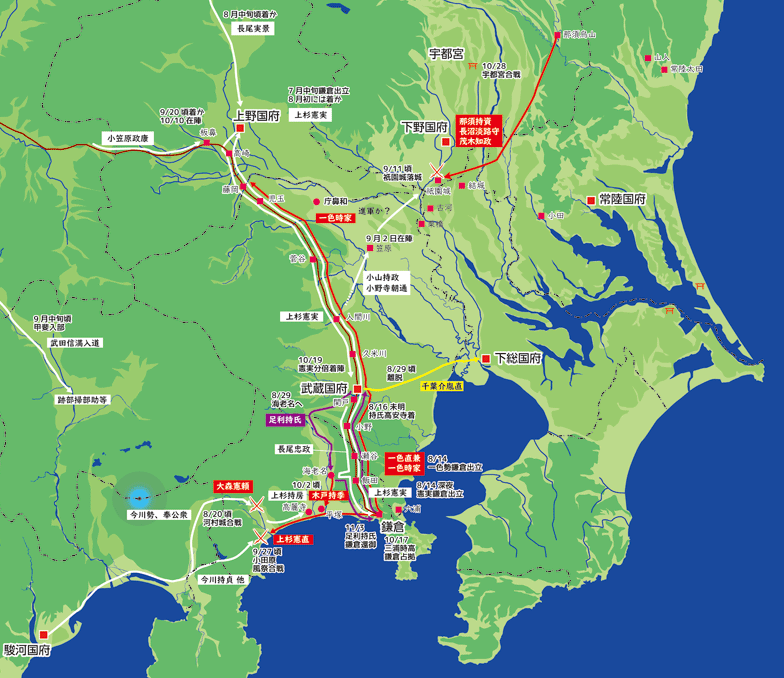
この憲実の難儀に対し、義教は「抑合戦事必定候者、雖不及注進、不日可有合力安房守」とあるように、合戦は必定であろうから、京都に注進することなく速やかに憲実に合力することを命じたのだった。これまで長年忍耐を重ねてきた義教であったが、7月30日、ついに持氏追討を容認し、あわせて朝廷には持氏追討の綸旨下賜を願った。
『鎌倉持氏記』によれば、今回の都鄙の騒乱は「持氏御上洛思食立事不可叶旨、憲実諫申之」ことと、「禁御料所以下京方所帯等御支配事、不可然由、依被申被失憲実者、上意為被達御本意歟」が「然間、匪京都欝憤耳、御背叡慮浅増」ことが原因であるとしているが、持氏が上洛を企図した形跡はない(憲実が諫めたのは持氏の信濃国への介入、賢王丸元服の京都沙汰の撤回である)。一方、京方御料所の押領については持氏自身が永享4(1432)年2月29日に御料所の返還と代官派遣を依頼しているが(『満済准后日記』永享四年二月廿九日条「上杉安房守状」)、その後再度横領したかどうかは不明である。
●永享10(1438)年7月30日「細川持之書状案」(『足利将軍御内書并奉書留』室:2976)
関東への介入は、今川範忠のみならず、翌8月1日には篠河殿満直にも「於于今者、定被致其用意候哉」を指示し、関東では近日合戦となるとの観測があるため、速やかに軍勢を催促して憲実に合力するよう命じている(永享十年八月一日「細川持之書状案」『足利将軍御内書并奉書留』室:2977)。これに加えて、石橋治部太輔以下南奥州の諸大名に対しても「属佐々河殿御手」して「上杉安房守御合力」(八月一日「細川持之書状案」『足利将軍御内書并奉書留』室:2978)することを命じた。
●永享10(1438)年8月1日「細川持之書状案」(『足利将軍御内書并奉書留』室:2977)
●永享10(1438)年8月1日「細川持之書状案」(『足利将軍御内書并奉書留』室:2978)
ただ、関東では当然ながらこの流れは伝わっておらず、憲実は反目の根を断ち切るべく、8月12日に「長尾尾張入道芳伝」を殿中に遣わすと「上方、憲実所御成有、天下被成御無為者、可畏入」と、持氏の山内邸御成を願い出たが、持氏は「御許容無之」という態度を示した(『鎌倉持氏記』)。
その後、憲実の要請を受けたとみられる「上杉修理大夫持朝時弾正少弼并千葉介胤直令同心」して持氏の説得に当たったが、「無御領掌」であった(『鎌倉持氏記』)。それどころか、「放生会被成限十六日、武州一揆攻上、奉公、外様、山内可押入旨」という風聞が次々に憲実に注進された。これに憲実は「如憲実被存者、被向御旗至于令落居者、罷成御敵分尽未来瑕瑾也、所詮御糺明以前被擬令自害」と自害を図ろうとしたため、「被官仁等令相談、奪取刀、前後左右令警固畢」(『鎌倉持氏記』)して自害を阻止すると、その中の若者ら十余名が進み出て、代表者の「長尾新四郎実景、大石源三郎重仲」が「子細有之」と申し述べるには、「只今於宿所至御損命者、下天落着難測者也、只御有下国、無野心旨意趣有歎申者、争不達哉上聞、其為相州河村館先御所申定所也、雖然在所可為御所存間、何国御下国肝要也、若是無御信用、有御自害後者、且懸夫雑人手、且入堀藪罷成塵芥事、為末代無念間、彼同心之仁等馳参大蔵辺、殿中打死、令路頭屍曝、可貽涯分名旨、調儀仕」というものであった。これに憲実は「思定志者、雖為甚深家人態也、不可遁憲実悪名、其者御敵庶幾分也」と思い直し、「然者下国事可致思案、但河村者分国豆州境也、於河村不申達得豆州合下向者、申請若君様京都御号、人々定可有之、所令下国可為上州」(『鎌倉持氏記』)と、長尾や大石らの考えは賞しつつ、河村(足柄上郡山北町山北)は伊豆国との堺であり、もしここに下向すれば、憲実は京都に若君に御一字を賜るよう申請するために下向したと人々が思うに違いない、として上州へ下向することを決定し、「当参被官仁等、打立暫時」(『鎌倉持氏記』)し、8月14日夜、憲実もまた鎌倉亭(山内亭か)を出立し「上州」へと向かった。それに「同名修理大夫持朝、同名庁鼻性順、長井三郎入道、小山小四郎、那須太郎等」(『鎌倉持氏記』)がこれに従ったという。このとき「憲実乗馬頭上、燈炉火如大光物出現」(『鎌倉持氏記』)と、夜空に流星と思われる光物が出現したという。「而及見人惟多、又不及見有之」とあるように、見た人は多かったが見えない人もいたようで、この記事が事実であれば、時期的にペルセウス座ε流星群と思われる。
『鎌倉持氏記』の記述で憲実が長尾忠政入道を御所に遣わした8月12日、京都では義教が「上杉中務少輔殿(上杉持房)」に「関東事、既現形之上者、相催諸軍勢等」(八月十二日「足利義教御内書」『本久寺文書』室:2980)を命じていることや、翌8月13日時点で奥州「伊達兵部少輔殿(伊達持宗)」に「関東事、上杉安房守下国之上者、不廻時日可有発向候」(八月十三日「細川持之書状案」『足利将軍御内書并奉書留』室:2981)とあることから、憲実の上野下向は、8月初旬にはすでに決定されていて、京都には13日に下向する旨(実際は14日夜に出立)の報告(憲実の下国計画は、8月13日に京都についたとみられる)がなされており、義教の指示はその報告を受けたものと考えられる。憲実が12日に長尾尾張入道を御所に遣わして山内来臨を願ったのも、最後の最後まで和平の望みを捨てない憲実の強烈な忠心だったのだろう。
これらのことから、時系列をまとめると、
| 6月 | 若君元服(上杉憲実の沙汰で行われ、将軍家より一字拝領)の予定 | 『看聞日記』永享十年八月廿二日条 |
| 持氏、元服の儀を「鶴岡八幡宮御沙汰」に変更する | 『看聞日記』永享十年八月廿二日条 | |
| 元服の儀に際し、憲実に「可有御沙汰云雑説」があり、憲実は弟重方を出席させる。その事により「依之憲実遺恨為甚深」という。 | 『鎌倉持氏記』 | |
| 7月半ば | 京都に「就関東之時宜(憲実との合戦の風聞か)」に関する今川上総介範忠の注進状が、元情報と思われる葛山駿河守の書状とともに報告される | 七月晦日「細川持之書状案」 『足利将軍御内書并奉書留』室:2976 |
| 7月24日 | 筑波玄朝法眼、鎌倉への出陣を命じられる | 享徳四年二月 「筑波潤朝軍忠状案写」 (「古証文二」神奈川県史料6187) |
| 7月30日 | 義教、今川範忠へ「抑合戦事必定候者、雖不及注進、不日可有合力安房守」を伝える | 七月晦日「細川持之書状案」 『足利将軍御内書并奉書留』室:2976 |
| 8月1日 | 義教、篠川満直(家宰高南伊予入道宛)に、もし持氏と憲実の間に合戦が起こったならば、憲実に合力する旨を命じる。 | 八月一日「細川持之書状案」 『足利将軍御内書并奉書留』室:2977 |
| 8月1日 | 義教、石橋治部太輔以下南奥州の諸大名に対して、「属佐々河殿御手」して「上杉安房守御合力」を命じる。 | 八月一日「細川持之書状案」 『足利将軍御内書并奉書留』室:2978 |
| 8月初旬 | 京都より奉公衆が関東下向 | 推測 |
| 8月初旬 | 越後国から長尾因幡守実景が上野国へ向かう | 推測 |
| 8月初旬 | 憲実、上野国下向の期日を8月13日として京都に使者を遣わす | 推測 |
| 8月12日 | 憲実、山内亭に持氏来臨を願うも、拒絶される | 『鎌倉持氏記』 |
| 義教、「上杉中務少輔殿」に「関東事、既現形之上者、相催諸軍勢等」を命じる。 | 八月十二日「足利義教御内書」 『本久寺文書』室:2980 |
|
| 8月13日 | 義教、「伊達兵部少輔殿」に「関東事、上杉安房守下国之上者、不廻時日可有発向候」を命じる。 | 八月十三日「細川持之書状案」 『足利将軍御内書并奉書留』室:2981 |
| 8月14日夜 | 憲実、鎌倉を発って上野国に向かう | 『鎌倉持氏記』 |
| 一色直兼、一色時家が憲実追討軍を率いて鎌倉を出立する | 『鎌倉持氏記』 | |
| 8月15日 | 持氏、鎌倉を発ち、「武州府中御発向」する | 享徳四年二月 「筑波潤朝軍忠状案写」 (「古証文二」神奈川県史料6187) |
| 8月16日 午後2時頃 |
持氏、憲実追討のため鎌倉から武蔵国府の高安寺に入る | 『鎌倉持氏記』 |
| 8月27日 | 義教、在京の憲実雑掌判門田壱岐入道に (1)持氏若公の元服の儀が、憲実で沙汰(「教」字を下して行う)することが中止されたのは本意ではない (2)憲実の上野下向は驚いた。合力の手配は済んでいる。 ことを伝えている。 |
八月廿七日「細川持之書状案」 『足利将軍御内書并奉書留』室:2987 |
憲実の鎌倉(または山内亭)出立はすぐに持氏の知るところとなるが、持氏はすぐに追討することはせず、諸臣に「殿中御沙汰」として「尊宿御使節而可有御尋子細歟、亦可被遣御勢歟」を諮った。ところが、諸臣は「啻可有御追罰云意見耳」であり、持氏は議定に従い憲実追討を決定。「其夜、両一色事直兼并同名刑部少輔時家被仰付訖」と、早速に一色宮内大輔直兼と一色刑部少輔時家を両大将とし「彼両大将御旗賜」って鎌倉を出立させた(『鎌倉持氏記』)。明けて15日には持氏自身も「武州府中御発向」(享徳四年二月「筑波潤朝軍忠状案写」(「古証文二」神奈川県史料6187))し、翌16日未刻に武蔵府中の高安寺(府中市片町2-4-1)に入っている。
一方、鎌倉を発った憲実一行は、一路上州へと馬を馳せ、児玉郡の「上雷坂(児玉郡美里町白石)」まで来たが、ここに「武蔵一揆」が陣取り「曳大幕、帯甲冑、憲実下向待懸」ていたという(『鎌倉持氏記』)。憲実の下向が伝わっていたとは考えにくいため、持氏の軍勢催促に応じて鎌倉へ向かう武蔵一揆の軍勢だったのだろう。これに憲実勢は「憲実被官仁等、打破之、馬足立直時」(『鎌倉持氏記』)と臨戦態勢を整えるが、憲実は「彼勢切懸至而不及子細、此方馳懸事、不可叶」と、応戦は認めるがこちらから攻撃することは認めない、との意思を述べた。その理由は「今度下向、無罪子細退為申被也、我合戦非可好由」で、逸る被官たちを堅く制止した。そのため被官たちも「無念由乍呟、無力取向陣相待」っていると、「上雷坂勢、其夜引散」ったことから、憲実らは「不及是非、被打通訖」という(『鎌倉持氏記』)。
その後、憲実一行は上野国平井(藤岡市西平井)に着陣したと思われるが、追撃する両一色率いる鎌倉勢は「上州カンナ河ニ在陣仕」(享徳四年二月「筑波潤朝軍忠状案写」(「古証文二」神奈川県史料6187))とあるように、平井城(藤岡市西平井)付近まで攻め下り、神流川(児玉郡神川町小浜付近歟)を挟んで上杉勢と対峙していた様子がうかがえる(なお、一色刑部少輔時家の神流川着陣は確認できるが、宮内大輔直兼が着陣した傍証はない)。
8月17日には「武田刑部大輔入道甲州入国」につき、「小笠原大膳大夫入道殿(小笠原政康)」へ管領奉書が遣わされた(永享十年八月十七日「細川持之奉書」『小笠原文書』室:2982)。以前に小笠原政康は「諏方両人事、武田甲州入国合力事、以前以御教書被仰付候」とあるように、小笠原政康と諏訪氏が本来は関東御分国である甲斐国に武田信重入道を守護として下すに当たり、合力が命じられていたのであった。
8月21日、義教は常陸国の「小田一族中」に「関東事、現形之間、所被差遣上杉治部少輔也、早属佐々川殿御手、可被抽忠節之由」と、篠川殿満直の手に属して持氏に追討に加わるよう命じている(永享十年八月廿二日「細川持之奉書」『真壁文書』室:2985)。
8月27日、義教は憲実宛の書状を憲実の京都雑掌として在京していた「半門田壱岐入道(判門田壱岐入道祐元)」に託した(八月廿七日「細川持之書状案」『足利将軍御内書并奉書留』室:2987)。持氏の若君元服に際しての無沙汰(義教の認可と憲実の執沙汰ではなく鶴岡八幡宮の沙汰となった)の「非本意」と、憲実の上州下国の件について「被驚思召」を伝え、人々の合力も手配が済んでいる旨を報告した。
●永享10(1438)年8月27日「細川持之書状案」(『足利将軍御内書并奉書留』室:2987)
同時に義教は朝廷に持氏追討の綸旨を下されるよう依頼し、8月28日、後花園天皇より持氏追討の綸旨が被下され、同日中に「上杉治部少輔(上杉教朝)」(永享十年八月廿八日「細川持之奉書写」『記録御用所本「古文書」三』室:2988)及び「右京大夫持房(中務少輔持房か)」が「就持氏御退治事、綸旨并御旗之為堅固」(永享十年八月「右京大夫持房書状写」『喜多見系図』室:2995)と、綸旨を奉じ御旗を賜って京都から関東へ下向した。同時に義教は、常陸国にいたとみられる「京都御扶持之輩」のひとり「小栗殿(小栗常陸彦次郎助重)」に対して「関東事、既現形之上者、不日参御方、可被致忠節」(永享十年八月廿八日「細川持之奉書写」『記録御用所本「古文書」三』室:2988)を命じている。なお、持氏追討に関東へ向かった上杉治部少輔教朝、上杉中務少輔持房は、かつて持氏を討とうとして逆に討たれた上杉禅秀の子息であり、小栗常陸彦次郎助重もまた持氏に討たれた小栗常陸介満重の子息である。
●永享10(1438)年8月28日「後花園天皇綸旨」(『横浜市立大学学術情報センター所蔵安保文書』室:2990)
■上杉禅秀家周辺系図
武田信満―+―武田信重―――――――武田信守
(安芸守) |(刑部少輔) (刑部少輔)
|
+―武田信長―――――――武田伊豆千代
|(右馬助)
|
+―女子
∥
上杉朝宗―――上杉氏憲【禅秀】―+―上杉憲顕
(中務大輔) (右衛門佐) |(中務大輔)
|
+―上杉憲方
|(伊豆守)
|
+―上杉持房
|(中務少輔)
|
+―上杉教朝
|(治部少輔)
|
+―快尊法印
|(鶴岡八幡宮別当)
|
+―女子
∥
千葉介満胤――――――千葉介兼胤―――千葉介胤直
(千葉介) (修理大夫) (千葉介)
●享徳4(1455)年2月筑波潤朝軍忠状案写(「古証文二」神奈川県史料6187)
京都と鎌倉の戦いは、9月6日に京都に「既於海道三ケ度及合戦畢」(永享十年九月六日「細川持之奉書」『小笠原文書』室:2999)といい、合戦は義教が奉公衆「曾我平次左衛門尉(曾我教忠)」に対し「今度於筥根山被官人等被疵之条、尤神妙」(永享十年九月八日「足利義教御教書写」『諸家文書纂』室:3001)という御教書を遣わしていること、9月2日に京都から伏見に帰参した「源中納言」が「関東事、管領上杉分国伊豆大森拝領、而大森城郭没落」(『看聞日記』永享十年九月二日条)と見え、持氏方の「大森(大森伊豆守憲頼)」の城が攻め落とされたことが伝わっていることから、少なくとも8月下旬から9月初頭までの間に箱根周辺ですでに三度の戦闘があったことになる。8月20日頃には持氏方の「大森伊豆守」らにより「河村城責落候」(八月廿一日「足利持氏書状」『備前一宮社家大守家文書』室:2984)ており、「大森城郭」とは河村城であったのかもしれない。そのように考えると、京都から持氏追討勢が下向したのは8月初旬と想定される。これは義教が今川範忠や篠川殿満直に上杉憲実への合力を命じた時期と符合し、同時期に京都からも奉公衆が派遣されていたと考えられる。
また、9月2日には京方の下野国「小野寺太郎朝通」が「就笠原致出陣」し、「与小山於一所在陣仕者也」(永享十年九月十一日「小野寺朝通申状案」『小野寺文書』室:3003)とあるように、笠原(鴻巣市笠原)に在陣しており、そこには小山小四郎持政もいたことがわかる。『鎌倉持氏記』の記述では、小山持政は上杉憲実とともに鎌倉を離れたとされており、小山祇薗城へ向かう最中であったのかもしれない。
9月6日には信濃国の「小笠原大膳大夫入道殿(小笠原政康)」が出陣した(九月廿四日「足利義教御内書」『小笠原文書』室:3008)。実は小笠原大膳大夫入道は出陣を渋っており、憲実からも京都に「今月(九月)七日、安房守註進到来了」と、小笠原勢が未着であることの注進が届いている。こうした状況は義教は以前から把握しており、度々出陣の下命があり、ようやく9月6日に出陣をしたものであった。将軍義教も予測しているが、小笠原勢は9月24日には上野国「板鼻(安中市板鼻)」に着陣していたとみられる。
9月10日には「筥根水呑合戦」があり、8月下旬から9月上旬にかけて箱根付近で合戦が続いていた様子がうかがえる。この水呑合戦では上杉憲実勢の「横地、勝間田」の軍勢と「豆州守護代寺尾之四郎右衛門尉」が箱根越えを図ったところ、「大森伊豆守、箱根之別当等」が策を巡らして数百人が谷間に討死を遂げた(『鎌倉持氏記』)。この戦いで横地某は討死し、「寺尾兄弟三人共負深手命計助」という損害を被っている。
9月12日、上方では「勘解由小路民部少輔、一色等自大和上洛、近日関東下向」(『看聞日記』永享十年九月十二日条)と、大和攻めを行っていた斯波民部少輔持種、一色修理大夫義貫らが関東攻めのために帰京した。当時の勘解由小路家の当主は数え四歳の千代徳丸(先年落馬で頭を強打して死去した義郷嫡子。のちの義健)であり、義郷弟の左衛門佐持有と一門の民部少輔持種が勘解由小路家を支えていたが、持有は南朝方との戦いで大和攻めの大将軍であったことから、民部少輔持種が呼び戻されて関東攻めの大将軍に据えられたとみられる。
そして9月16日に「彼錦御籏、行豊朝臣書進、今曉奉行飯尾肥前取ニ来、聖護院奉渡被加持云々、錦御籏調進」し、斯波持種・一色義貫に授けられたのだろう。同16日、「勘解由小路民部少輔、甲斐等、今日東国下向、関東為征伐」(『看聞日記』永享十年九月十六日条)という。甲斐が東国へ下向途中、「遠江国人大谷甲斐一族、大森合戦大谷勝軍」と出会っている。
足利高経―+―斯波義将――斯波義重―+―斯波義淳――斯波義豊
(尾張守) |(治部大輔)(治部大輔)|(左兵衛佐)(民部大輔)
| |
| +―斯波義郷――斯波義健==斯波義敏
| |(治部少輔)(治部少輔)(左兵衛督)
| |
| +―斯波持有
| (左衛門佐)
|
+―斯波義種――斯波満種―――斯波持種――斯波義敏
(伊予守) (民部大輔) (民部大輔)(左兵衛督)
| 持氏追討に派遣された人々 | 守護 | 管国 |
| 【篠川殿】足利左兵衛佐満直 | 篠川殿 | 陸奥国、常陸国 |
| 【関東管領】上杉安房守憲実 | 上野守護 (武蔵) 伊豆守護 |
上野国、下野国、武蔵国、相模国、伊豆国 |
| 上杉治部少輔教朝(先陣か) 上杉中務少輔持房 斯波民部少輔持種 一色修理大夫義貫 |
京都より下向 | |
| 長尾因幡守実景 (邦景入道子息) |
越後守護代の代理か | 越後国 |
| 武田刑部大輔入道 | 甲斐守護 | 甲斐国 |
| 小笠原大膳大夫入道 | 信濃守護 | 信濃国(諏方とともに武田信重入道の甲斐国入国に合力) |
また、8月中に持氏は下野国小山の祇薗城攻めのために「那須五郎(那須持資)」に「相触近所之輩、令談合長沼、茂木」し出陣するよう指示を出したとみられる。これを受けた「那須五郎殿」は9月初旬までに当所の予定通りの地に「路次無相違下着」した旨を鎌倉へ注進しており、9月8日、持氏は海老名某を使者として「那須五郎殿」へ遣わすと「祇薗城事、先途如被仰候、相触近所之輩、令談合長沼、茂木、早速可攻落候」よう命じた(九月八日「足利持氏書状」『那須文書』室:3000)。その結果、那須持資らは9月11日までに「祇園城攻落候」している。この報は12日には持氏のもとに報告され、持氏から持資に「先目出候」とする書状が遣わされた(九月十二日「足利持氏書状」『那須文書』室:3005)。
また、8月下旬から鎌倉方と京勢は箱根で激しい攻防を続けていたが、9月下旬には鎌倉方は劣勢を強いられ、その報告は武蔵府中に伝えられていたのだろう。持氏は京勢の箱根越えを阻止するべく「依之重数輩軍兵下向間、憲直為大将、二階堂一党、完戸備前守、海老名上野介、安房国軍勢等被差向」と、上杉陸奥守憲直を大将軍として派遣している。この頃、持氏に近侍していた千葉介胤直はこの危機を何とか阻止するべく、持氏と憲実の和解を図る。「千葉介胤直、自御動座以前、憲実無誤旨、再三雖執申無御信用」と、胤直は憲実の無実を府中御動座以前から再三にわたって言上していたが、取り上げられることはなかった。しかし、ここまで劣勢となった以上は鎌倉滅亡を見過ごすことはできず、「於府中致方便、若公為御使節被召帰、憲実上州可供奉仕由」を持氏に勧めたところ、持氏はこれを受け容れ、鎌倉から若公義久を武蔵府中へ呼び寄せるよう指示を出した。このため9月24日、持氏は「既被進若公御迎」たが、ここでまたもや「若宮尊仲」が横槍を入れ、「簗田河内守方、以飛脚彼御下向申妨」したのであった(『鎌倉持氏記』)。尊仲がどのような話をしたのかは定かではないが、結局、持氏は尊仲の意見を聞き入れて、胤直の和解案を拒絶したのであった。
ちょうどこの頃、箱根では鎌倉勢が劣勢となり、箱根東麓へ追い落とされていた。京勢の主力は駿河今川勢と上杉中務少輔持房勢とみられる。そして、9月27日、京方と上杉陸奥守憲直率いる鎌倉方が「相州早河尻合戦」で激突した(『鎌倉持氏記』)。この合戦で「憲直失理」い、憲直の「家人肥田勘解由左衛門尉、蒲田弥次郎、足立、荻窪以下」が討死(『鎌倉持氏記』)、京勢の「今川中務大輔殿(今川持貞)」に属した「興津美濃守(興津美作守国清か)」が「於相州小田原并風祭」で「於捕進上杉陸奥守」(十月十五日「細川持之書状案」『足利将軍御内書并奉書留』室:3014)し、上杉憲直勢は壊滅した(後日、このときに捕殺された憲直は憲直若党であったことが判明)。
早河口の合戦の鎌倉方壊滅は、すぐに府中の持氏のもとに伝えられたのだろう。9月29日には「持氏、相州海老名道場被移御陣」ことを決定する(『鎌倉持氏記』)。相模川を防衛線として京勢の侵攻を阻止する意図があったとみられる。このとき、胤直は持氏に憲実との和睦を翻されたことに対し、「然間、胤直含恨申」したところ、「剰相州御立間、無左右不及供奉、上方分倍河原控御馬、可参急由度々被仰」(『鎌倉持氏記』)と、このまま相模国へ出立するので義久に供奉(義久を憲実のもとに和睦の使節として送り、胤直が供奉)することは取り止め、分倍河原に急ぎ来るよう指示を出している。しかし、すでに胤直は持氏を見限っており、「畏申」との返事をしながらも「不急」かったことから、持氏はしびれを切らして「左耳、不及有御待」と胤直を待たず相模国へと出立する。そして持氏一行が「被越関戸山時分歟」(多摩市桜ケ丘一丁目)の頃、千葉介胤直は「神大寺原打出」(調布市深大寺)たのち、管国である下総国へ渡り「下総国市河在陣」(市川市国府台一丁目)したのであった(『鎌倉持氏記』)。
また、このとき鎌倉は「鎌倉御留守警固、任例被仰付三浦介時高」ていた。三浦介時高は持氏の武蔵動座の際に、通例として鎌倉留守を命じられたが、「近年殊令困窮、無人間、不可及警固由」と辞退した。しかし、持氏は認めなかったことから、時高は「御成敗為厳重、先随仰」と、しぶしぶ引き受けたという。折しも「若公、二橋上方満貞(稲村殿満貞)」は胤直の和睦の献策により武蔵府中ヘ向かっていたと思われるが、和睦計画が中止となるも、持氏の相模国下向に合わせて境川(藤沢市高倉辺りか)まで出張し、「境河御対面」がなされた(『鎌倉持氏記』)。持氏はここから西へ進み、引地川を渡って葛原の丘を経て海老名道場(海老名市河原口付近歟)に布陣したと思われる。
すでに京勢は小田原の防衛線を越えて鎌倉へ向かう中、10月2日、持氏は「海道御勢越筥根山競来」を抑えるべく、近臣の「木戸左近大夫将監持季」を大将軍として「賜御旗、相州八幡林(平塚市浅間町一の平塚八幡宮)」に派遣した。このとき「京勢大将軍上椙中務少輔持房、相州高麗寺陣張」とあるように、金目川を眼前に控える要衝高麗寺(中郡大磯町高麗)に布陣して、木戸持季の布陣する平塚八幡と相対した。その距離はわずかに2.5km程である。
こうした中で、10月3日、持氏との対面を終えた「若公、同三日、還御鎌倉」したが、同3日、鎌倉留守居の三浦介時高は叛旗を翻して役所から屋敷へ撤退し、鎌倉を占拠した。時期として千葉介胤直が離反して3、4日後であることから、千葉介胤直、三浦介時高は連携を取った、または胤直離反の影響があった可能性があろう。関東を代表する二名の大名が鎌倉を見限ったことになる。時高は「右大将家被召御代事、依有三浦大介御憑也、然間御賞翫異他而子孫有置文処、無験、此比殊外被成不屑身申、内々失面目存者歟」と、頼朝からの三浦氏を格別の扱いとする置文もすでに験は無く、不遇の身を嘆いており、こうした中で「然関東様、背御勅命及綸旨御沙汰旨、粗有其聞処、京都御内書於御方可抽忠旨被仰下」と判じて「翻御留守警固思」したものであった。時高は鎌倉占拠の報告を京都に注進する飛脚を仕立てたとみられ、京都には10月9日夕方に到着した。その内容は「昨夕又関東飛脚到来、官軍鎌倉中へ入了、武将ハ陣ヘ被立、留守也、可焼払歟之由」(『看聞日記』永享十年十月十日条)というものであった。そして、10月10日には「錦御旗ハ篠河殿被給」っている。
この三浦介の鎌倉占拠の報も当然持氏に報告されたであろうが、さらに「上州下向両大将付副軍勢、皆以退散間、失為方」(『鎌倉持氏記』)と、上野国に寄せていた一色直兼、一色持家の両大将軍も10月4日、「引返海老名御陣参上」(『鎌倉持氏記』)していた。寄手の軍勢が一色勢から離脱したためであり、持氏は西の京勢、北の管領憲実勢と篠川殿満直麾下の北関東勢が進軍し、東の千葉介胤直、南の三浦介時高も離反していることで、海老名付近から身動きができない状況となっていた。
こうした中で憲実勢は一気に攻勢に出る。上野国守護所「板鼻(安中市板鼻)」にはすでに信濃守護の小笠原政康入道が着陣しており、彼に守護所の警衛を任せ(憲実出立後の10月10日当時、政康入道は板鼻に在陣しており、彼自身が憲実と合力して持氏との合戦に加わった事実は伝わっていない)、10月6日、憲実は「立上州、推被上間」し、鎌倉街道を南下した。を出立した憲実の南下の速度は1日当たり8~10km程度という遅さであり、憲実は持氏に海老名の解陣を迫っていたのかもしれない。
すでに10月初めには神流川の寄手一色勢は解陣し、憲実方に「奉公、外様、憲実令与力事繁多也」(『鎌倉持氏記』)という様子がうかがえる。この憲実への諸将寝返りの理由は、「都鄙御間事者、曾以不存知、持氏与安房守御間、為子細由承上者、国中同心仕、持氏江馳参条勿論也、上与下非可令比量哉、国々軍勢参陣段不限一人」(永享十一年四月「真壁朝幹代皆河綱宗目安写」『真壁家文書』)というように、当初関東の人々は持氏の軍勢催促が持氏と憲実の争いによるものとの認識だったために持氏に応じたが、実際は「都鄙御間事」によるもので「其以後為京都上命之由承」ったことが発覚したためとみられる(永享十一年四月「真壁朝幹代皆河綱宗目安写」『真壁家文書』)。10月10日当時、在陣しており、信濃国から中山道を東下したとみられる。
10月7日、貞成入道親王のもとに9月27日の「上杉陸奥守父子討死於箱根城合戦」の一報が届いており、入道親王は義教に「目出之由、上様へ公方文ニて被申」(『看聞日記』永享十年十月七日条)している。
10月9日、「上杉討死、目出御礼、面々群参」(『看聞日記』永享十年十月九日条)したことが貞成入道親王に伝えられている。その報告によれば「上椙ハ甲斐手曾我討之」と伝わっているが、将軍義教が10月15日に下した御内書は「御感之至候、殊以神妙之旨、被仰出候」といい、今川持貞に「御書并御太刀一腰真光、御腹巻一領黒革、肩萌黄」(十月十五日「細川持之書状案」『足利将軍御内書并奉書留』室:3014)が下され、興津美作守にも「御太刀一振長光」が下されており、義教への報告は今川持貞と興津美作守の戦功であったと思われる(なお、このとき捕らえられた憲直は別人であった)。
10月13日、京都に「上杉奥州首上洛、只今御覧、彼首、六條川原被懸云々、後聞、上杉首事虚説也、若党首云々」(『看聞日記』永享十年十月十三日条)した。
10月17日、三浦介時高は「大蔵、犬懸等令夜懸、数千家放火之間、鎌倉中上下如無足立所」(『鎌倉持氏記』)というが、これはおそらく時高が京都に諮問した「可焼払歟之由」(『看聞日記』永享十年十月十日条)に対する京都の指示であろう。これにより「二階堂一家皆降参三浦介」している(『鎌倉持氏記』)。ただ、三浦勢は若公や大御所の住む大倉御所を攻めることはなかった。これは憲実の指示があったためか。
10月18日、誤報ではあったが、貞成入道親王に「鎌倉武将没落、一色宮内少輔切腹之由注進」(『看聞日記』永享十年十月十八日条)があった。ただ、後聞きで「一色腹切事、例虚説也」という。さらに「武将之女中、若公幼稚、一色妻女等乗船落之時、逢難風入海」(『看聞日記』永享十年十月十八日条)という報告もなされている。ただしこれもまた誤報であった。これは、おそらく次の「大御所様、若君様」の御所からの避難に尾ひれがついたものであろう。
そして、その二日後、憲実は「同十九日着陣分倍」(『鎌倉持氏記』)と、10月19日に分倍河原に着陣した。上州平井を発って十三日後であった。なお、10月30日に京都に注進された「抑関東事、西山注進到来、武将入間河取陣、上杉前管領漸責寄、近所取陣、武将降参事、種々被懇望、雖然上杉不許容申云々、今一戦可被腹切之由注進」(『看聞日記』永享十年十月卅日条)があるが、持氏は入間川に布陣しておらず、また、憲実はその後、持氏の降伏を受け容れ、京都に対しても持氏の助命嘆願を幾度も行っていることから「武将降参事、種々被懇望、雖然上杉不許容申」したことが注進されることは不可解である。憲実が降伏を許さなかったのは公方近臣であり、一色、情報が錯綜していた可能性もあろう。
その後、海老名陣の持氏と和睦の交渉が行われたとみられ、10月10日前後には少なくとも以下の條々が決定されたと推測される。
| 一 | 持氏、若君義久、大御所らの身の安全 |
| 二 | 持氏の鎌倉還御 |
| 三 | 一色直兼、上杉憲直、簗田河内守ら近臣の沙汰は憲実に一任する |
これらに基づき、憲実は三浦介時高に大倉御所に残る公方近臣の追捕を指示したと推測されるが、大倉御所には持氏母の「大御所様」以下の持氏血縁者がいたため、憲実は三浦介時高に指示して、御所から「大御所様、若君様」を退去させて、山内の「小八幡社頭」に移した(享徳四年二月「筑波潤朝軍忠状案写」(「古証文二」神奈川県史料6187))のだろう。
10月28日、「抑宇津宮関東方大合戦、宇津宮討死、余党降参」(『看聞日記』永享十年十一月六日条)があったとされ、11月6日に京都に注進されている。これについての傍証はないが、具体的な表記であるため、事実か。なお、この関東方の宇都宮氏は惣領家の宇都宮等綱ではなく、別流の宇都宮氏であろう。
そして、「大御所様、若君様」の山内移渉が完了したのちの11月1日、「大蔵御所、三浦介時高奉押寄」せている。この御所攻めは「二階堂人々、持朝被官仁等同心訖」(『鎌倉持氏記』)し、持氏近臣の「簗田河内守、同名出羽守、名塚左衛門尉、河津三郎以下」が御所に防戦するが、簗田河内守(満助か)らは「殿中討死訖」した。また、「其外人々宿所、皆以炎上、因之悪党人等不嫌寺社堂塔焼取」したため、時高は「被官佐保田豊後守」を派遣してこれを鎮定している。
●「余五将軍系図」(『古河市史』)
…簗田良助―+―簗田満助―+―簗田持助―+―簗田成助―+―女子 +―簗田晴助――――簗田持助
(河内守) |(河内守) |(河内守) |(中務大輔)|(相馬室) |(中務大輔) (八郎)
| | | | |
| | | +―女子 +―女子
| | | |(ヲ子々ノ局)|(千葉介親胤妻)
| | | | |
| | | +―簗田高助――+―女子
| | | (河内守) |(相馬妻)
| | | |
| +―女子 +――――――――女子 +―――――――――女子
| (興禅院殿) (安養院殿) ∥―――――足利藤氏
| ∥ ∥ ∥ (左馬頭)
| ∥―――――春王丸 ∥ ∥
| ∥ ∥―――――――足利高基――――足利晴氏
| ∥ 【古河公方】 ∥ (左兵衛督) (左兵衛督)
| 足利持氏―――足利成氏 ∥ ∥
| (左兵衛督) (左兵衛督) ∥ ∥―――――足利義氏
| ∥ ∥ ∥ (右兵衛佐)
| ∥ ∥ 北条氏綱――+―女子 ∥
| ∥ ∥ (左京大夫) |(芳春院) ∥――――源氏女
| ∥ ∥ | ∥ ∥
| ∥ ∥ +―北条氏康――女子 ∥
| ∥ ∥ (左京大夫)(浄光院) ∥
| ∥ ∥ ∥
| ∥ ∥ 【小弓公方】 ∥
| ∥―――――――足利政氏――――足利義明――――足利頼淳―――――+―足利国朝
| ∥ (左馬頭) (右兵衛佐) |(右兵衛督)
| ∥ |
+―簗田直助―――――――――女子 +―源嶋子
(長門守) (伝心院) (月桂院)
∥ ∥
∥―――――――印東出羽守 豊臣秀吉
印東某 (関白)
三浦介時高が大倉御所勢を討滅した同日の永享10(1438)年11月1日、憲実は家宰の「長尾々張入道芳伝」を「為鎌倉警固」に派遣するべく分倍河原から鎌倉へ出立させた。その途中、尾張入道は11月2日に「持氏、自海老名有御上時、於相州葛原参合」しているが、葛原(藤沢市葛原)は鎌倉街道から西に外れ、持氏の「海老名陣」からは東に位置していることや、持氏は「自海老名有御上時」とあることから、両者は偶然出会ったのではなく、憲実と持氏の間で交わされた約定の通り、持氏は海老名陣を解いて鎌倉へ還御となり、葛原で尾張入道の着到を待ったのであろう。
ここで持氏の「供奉人々、御折角旨相存及討死用意」をするも、持氏に抵抗の意思はなく、尾張入道に「以一色持家為上使、直兼、憲直以下讒人事、任憲実申旨可有其沙汰由、以前御領掌也、此段令覚悟哉由、被仰出」(『鎌倉持氏記』)との、以前に了承した通りに、一色直兼、上杉憲直ら「讒人」の処遇は憲実の申す通りに沙汰することを改めて伝えている。
その後、尾張入道は「畏申、下馬仕」って持氏御前に参じて「芳伝、懸御目」ったところ、持氏から「被御剣下畢」と佩刀を下され、尾張入道は「又進上御躰上者、不及子細鎌倉供奉」(『鎌倉持氏記』)として、持氏の降伏を請けて鎌倉への護衛を承った。持氏降伏という重大事は、当然ながら忠政入道の一存で行えるはずもなく、持氏と憲実の間には持氏降伏の話し合いが決着していた証左であろう。
鎌倉でも筑波別当大夫潤朝らに護られて「小八幡社頭」に避難していた「当大御所様、若君様」が「自其而扇谷江御出、以我等之手計供奉申」(享徳四年二月「筑波潤朝軍忠状案写」(「古証文二」神奈川県史料6187))と、扇谷(鎌倉市扇ガ谷)へ遷っている。その際、筑波別当大夫潤朝の家人は大御所の護衛を行っていて「御モリニハ、家人又次郎男参候、御感ニ下賜御衣」(享徳四年二月「筑波潤朝軍忠状案写」(「古証文二」神奈川県史料6187))という。
持氏の鎌倉下向は、当初持氏に従っていた真壁右京亮朝幹が「自海老名鎌倉山内江馳越、長尾一類ト一味仕者也」(永享十一年四月「真壁朝幹代皆河綱宗目安写」『真壁家文書』)とあるように、尾張入道芳伝に供奉されて山内から鎌倉に入ったとみられる。持氏一行はその後、二階堂永安寺に入るべく山内から小袋坂を経由して鶴岡八幡宮前に進んだとみられるが、「芳伝供奉何事哉」と、鎌倉警衛中の「時高被官豊後守以下」が持氏と憲実が手を組んで鎌倉に攻め入ったと勘違いして「八幡宮前赤橋馳塞、擬討死仕」と道を塞いだことから、持氏は誤戦を避けるべく「被引返御馬、浄智寺入御」と、浄智寺(鎌倉市山ノ内1402)に入っている。浄智寺は持氏が好んだ寺であることから、鎌倉に入る前に浄智寺へ一度入御していたのかもしれない。
その後、尾張入道芳伝は佐保田豊後守に「芳伝如何躰申」たところ、佐保田豊後守も納得し、「罷退赤橋」したため、持氏は浄智寺を発って永安寺へ入御した(『鎌倉持氏記』)。持氏が鎌倉に入ったのはおそらく11月3日と思われ、翌11月4日、持氏は「金沢称名寺御移」った。そして翌11月5日に称名寺で「御落飾」し、「御法名道継御道号揚山」と号した。なぜ足利家由緒の永安寺ではなく金沢の称名寺(金沢区金沢町212-1)まで出張って出家したのかは不明。持氏には「讒人」である一色直兼や上杉憲直ら近臣が同道を許されていたようであり、憲実の遠慮として「讒人対治」を鎌倉で行うことを憚り、鎌倉外の金沢での執行を企図していたとすれば、敢えて同道させたうえで追捕をした可能性もあろう。
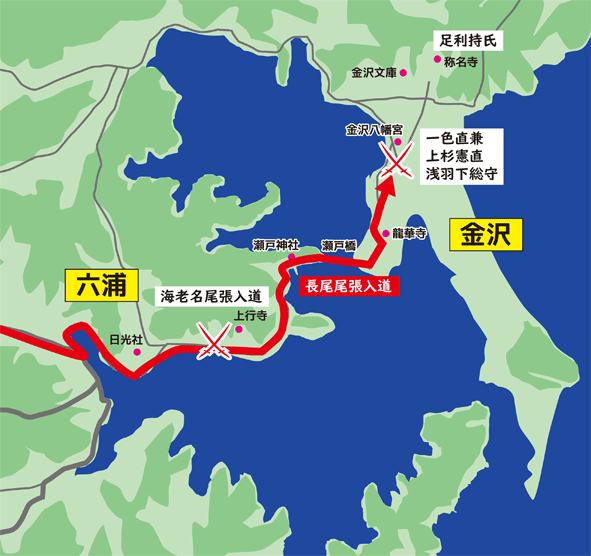 |
| 永享10年11月7日金沢合戦想像図(戦場も確定していない) |
その後憲実は、「讒人対治」のために尾張入道芳伝を大将として金沢に遣わし、11月7日に持氏近臣らを追討した。これを「金沢合戦」(『鎌倉持氏記』)という。
長尾尾張入道の金沢出陣に際し、真壁右京亮朝幹は長尾尾張入道に「然金澤江御勢仕之時、可令同心由申」したが、「山内ヲ可警固由依成敗、円覚寺塔頭大義庵仁取陣者哉」(永享十一年四月「真壁朝幹代皆河綱宗目安写」『真壁家文書』)と、山ノ内の警固のために円覚寺塔頭大義庵に留まっている。
「金沢合戦」は事件の十日後、11月17日に京都に伝わった情報によれば「抑関東事注進到来、武将居所押寄焼払、御留守警固武士防闘、六人腹切云々、鎌倉中敵方家共焼払、円覚寺焼了、建長寺ハ不焼云々、武将ハ先祖寺安養寺ニ被引籠」ったという(『看聞日記』永享十年十一月十七日条)。なお「安養寺」は「養安寺=永安寺(ようあんじ)」の誤記とみられる。持氏が二階堂の永安寺に移ったのは「同十一日、持氏永安寺御入」(『鎌倉持氏記』)であることから、上記の注進が鎌倉を発ったのは少なくとも11月11日以降である。
さらに11月21日に京都に伝わった詳報では、「抑先度上杉陸奥守首事、虚説也、若党主ニ相替討死了、陸奥守と名乗之間、其分ニ披露云々、今度上杉陸奥守父子、一色民部大輔、海嘗名等討死、管領上杉執事長尾、為大将二千騎押寄、敵方五百騎合戦打負、五百騎勢悉討死云々、鎌倉殿ハ被没落了」(『看聞日記』永享十年十一月廿一日条)というもので、先日上洛の上杉陸奥守の首は、彼の身代わりに「陸奥守」と名乗って討死した若党のものであったことが確認できる。今回の金沢合戦では、主だった者は上杉憲直父子、一色民部大輔(宮内大輔の誤記か)、海老名(海老名尾張入道か)の討死(実際は自害)が確認できる。長尾尾張入道は二千騎で金沢に攻め寄せ、「武将居所押寄焼払」(『看聞日記』永享十年十一月十七日条)い、「御留守警固武士防闘、六人腹切」っている(『看聞日記』永享十年十一月十七日条)。その「六人」とは、「直兼父子三人、憲直父子共并浅羽下総守自害」(『鎌倉持氏記』)か。合戦は「武将居所押寄焼払、御留守警固武士防闘」とあることから、長尾勢は持氏の金沢の居館(持氏は毎年4月8日に瀬戸神社参詣を行っており(『鎌倉年中行事』)、その宿館の可能性)に攻め寄せていると推測される。持氏は当時は称名寺にいるため、居館を不在にしていることは長尾尾張入道も把握していたであろうから、留守居の一色等を追捕することが、この金沢合戦の目的であったことがわかる。
長尾尾張入道の寄手と、一色直兼・上杉憲直らとの戦闘では「直兼被官草壁父子四人、帆足、斎藤、饗庭、喜井、板倉、西大夫等切出、相戦、令討死、其間主人静自害事、誠志深者也、就中、草壁遠江守振舞、一騎当千是也、其外討死不及註名字事」(『鎌倉持氏記』)といい、一色直兼の被官人の草壁、帆足、斎藤、饗庭、喜井、板倉、西大夫らは主人の自刃の時間を稼ぐべく奮闘して討死を遂げた。草壁氏、饗庭氏、板倉氏は三河国からの一色家根本被官、帆足氏、斎藤氏、喜井氏は九州探以来の被官であろう。また、「浅羽下総守」の討死も見えることから、金沢在地の浅羽氏(平時から金沢の留守居などを担っていた氏族か)もまた持氏与党として戦った。
戦場は金沢の「武将居館」だけではなく、「海老名尾張入道、六浦引越道場切腹」(『鎌倉持氏記』)したとあることから、鎌倉から金沢に至る要衝の上行寺付近にも公方近臣が布陣して長尾尾張入道勢進出を防ごうとしていた意図がうかがわれる。長尾勢は朝夷奈から六浦に進出し、上行寺前の公方近臣勢を破り、瀬戸橋を渡って金沢になだれ込んだと思われる。一方で、「三戸治部少輔、仰長尾出雲守、於永安寺甲雲庵被討畢」(『鎌倉持氏記』)と、永安寺に残った近臣もあり、憲実は長尾出雲守に命じて三戸治部少輔(高氏庶流の足利家根本被官)を永安寺塔頭の甲雲庵に討っている。また、持氏の関東使節として度々上洛して交渉に当たった「二階堂信濃守」は、「相模陣(平塚八幡の陣か)」から逐電した。海老名上野介は上杉大夫持朝家人奉行であったが、兄の海老名尾張入道とともに持氏方として早河口の合戦に加わるなどしている。ただし兄とは異なり、持氏を度々諫めていることは憲実も知っており、彼を助命するべく扇谷海蔵寺に蟄居する上野介に使者を遣わすが、すでに自刃していた。そして、様々に持氏を誤らせた鶴岡八幡宮「社務尊仲」は、逃亡の最中「海道辺被生擒掫、於京都刎首」(『鎌倉持氏記』)された。「損君失身事、遠慮不失所愚」(『鎌倉持氏記』)と辛辣な批判を受けている。また、「憲直次男五郎、山内徳泉寺聞之、同夜自害及、刻家人鱸豊前守令介錯、五郎落居後、豊前守同切腹、主従共以殊勝之振舞也」(『鎌倉持氏記』)という。このように憲実は、持氏の鎌倉還御後、数日のうちに持氏の手足となる公方近臣を粛清したのだった。
そして、11月11日に金沢称名寺から二階堂永安寺に戻された持氏入道の警固として、憲実は「于時憲実号代官、大石源左衛門尉憲儀、同大夫持朝并千葉介胤直、于替番三ケ日夜宛致警固」(『鎌倉持氏記』)することを指示する。この警固の輪番が決定後、憲実は京都にその旨を報告する使者を派遣したと思われる(11月20日頃上洛と推測)。
大石憲重 十玉房
(石見守) ∥―――――――多満方
∥ ∥
∥―――――大石憲儀
∥ (源左衛門尉)
上杉重方――女子 ∥
(三郎) ∥―――――――大石房重
∥ (源左衛門尉)
長尾実景――女子
(因幡守)
この永安寺幽閉の中で持氏入道は11月27日、佐野越前守と佐野六郎の父子への感状(その年、常陸鹿島氏に伝来して佐野を「鹿島」に改変したか)を認めるが、「上杉安房守於反謀、不思京鎌倉及合戦候之処、味方之族布与敵対未練候」(永享十年十一月廿七日「足利持氏感状写」『常陸遺文』室:3026)と、この騒擾の要因は憲実の反謀に過ぎなかったものが、思いもよらず京都と鎌倉の合戦となり、味方となるべき人々と敵対したことは心残りであると述懐している。持氏の書状は「其方父子忠節感入候、弥忠功可被致候、追而其沙汰可有之候」とあるところから、佐野父子は永安寺外ではなく寺内に伺候した公方近臣であったと思われる。この永享合戦の勃発は、信濃国に軍事介入を試みたり、若君元服につき将軍家からの一字拝領を撤回したり、関東管領追捕を企てたりした持氏に原因があるが、持氏は一色直兼、上杉憲直ら近臣や鶴岡八幡宮社務尊仲ら公方近臣への妄信が最後まで消えることがなかったようである。
●永享10(1438)年11月27日「足利持氏感状写」(永享十年十一月廿七日「足利持氏感状写」『常陸遺文』室:3026)
11月29日、伏見殿の貞成入道親王は「鎌倉殿、被着墨衣之由注進」(『看聞日記』永享十年十一月廿九日条)を聞いている。これは11月20日頃に上洛したと思われる憲実使者からの報告による情報とみられる。11月11日、持氏入道は金沢称名寺から鎌倉永安寺へ移され、大石憲重、上杉持朝、千葉介胤直の警固勢が取り囲んでいる状況が報告され、近日中に金沢合戦(11月7日)で自害した上杉陸奥守憲直父子、一色民部大輔直兼父子、海老名尾張入道ら六名の首級上洛も伝えられたとみられる。ただ、義教は以前より持氏の処断を厳命しており、12月5日、義教はこの「生ぬるい」報告に対し、「関東事、已乍被取囲申于今延引、如何様之子細候哉、言語道断事候」と激怒していることと、「諸軍勢長々在陣」は不憫であり、年末年始に懸かることはよろしくない(ため、早々に持氏らを処断すべし)と、側近の赤松播磨守満政を使者として派遣し、改めて厳命した。
●永享10(1438)年12月5日「管領持之奉書案」(永享十年十二月五日「細川持之書状案」『足利将軍御内并奉書留』室:3027)
12月8日には「関東被下使節西山上洛」して「抑関東注進凶徒首共、済々上洛、被御覧」(『看聞日記』永享十年十二月八日条)した。帰洛した使節西山の報告によれば「武将出家被着黒衣、若公被成喝食降参、命許可被助之由被申、前管領上杉執申」(『看聞日記』永享十年十二月八日条)というように、憲実は、持氏がすでに出家し「若公(義久)」もまた「喝食(報国寺か)」となったので、彼等の命ばかりは助けてほしいという。
翌12月9日、伏見宮亭に一慶西堂が来訪して語るところでは、「関東首六、上杉陸奥守父子、一色、海老名等云々、六條河原被切懸」(『看聞日記』永享十年十二月九日条)と、六條河原に上杉憲直父子、一色直兼、海老名入道ら六名の首級が晒されたという。
その後も憲実は「所詮持氏御命可有御寛由」を「京都被致訴訟事重畳」(『鎌倉持氏記』)しており、11月半ばの持氏処遇の報告に続けて、12月初めにも「自関東僧上洛、武将降参事、前管領執申使節」(『看聞日記』永享十年十二月十五日条)している。憲実の主張は、「武衞事、已除緑髪着黒衣之上者、有恩免、於子息者可聴相続之由、房州頻執申、而時宜不許」(『建内記』永享十一年二月二日条)というもので、持氏はすでに出家しており、恩免により子息に相続を聴されるようにというものであったが許しはなかった。
●『建内記』永享11(1439)年2月2日条
このときの使者は義教との対面を求めるが「無御対面、不可叶之由被仰、軈下向」(『看聞日記』永享十年十二月十五日条)したという。義教は持氏の件では一切譲歩しない姿勢を示したのであった。そして、この憲実使節は12月15日までには関東へ下向している。
このように義教は「然持氏、連々御無道吹拾、条数被註下、曾無御許容」(『鎌倉持氏記』)と、以前のように赦免する気配は全くなく、数度にわたって永安寺の持氏入道及び報国寺の義久の処断を督促し、小笠原政康入道にも「関東事、定不可有等閑之旨、被思食候」と、持氏らの処断を迫った。
●永享10(1438)年12月23日「足利義教御内書」(永享十年十二月五廿三日「足利義教御内書」『小笠原文書』室:3031)
しかし、義教が赤松満政を派遣までして憲実へ命じていた「諸軍勢長々在陣、且者不便之次第候、年始歳暮殊不可然候」(永享十年十二月五日「細川持之書状案」『足利将軍御内并奉書留』室:3027)という状況は、年が明けても一向に果たされなかった。しびれを切らした義教は、永享11(1439)年閏正月24日、鎌倉の奉公衆(奉行か)「赤松中務少輔(赤松持祐)」に「持氏誅伐事、厳密被仰付憲実処、無沙汰之間、為尋究彼所存、柏心和尚被下向者也」(永享十一年閏正月廿四日「足利義教御教書」『赤松文書』室:3037)と報告する御教書をしたためた。憲実がなおも持氏らの処断を「若尚令難渋者、果而京都大事、降参輩生涯者不及申、憲実即時可浮沈之段、無覚悟次第、且僻案至極歟」と、降伏した輩の処断は言うまでもないが、憲実もその身がどうなるかの覚悟がないと詰っている。そして、憲実を当てにせず、京勢のみで持氏を討ち、「抽戦功者、可有恩賞也」」(永享十一年閏正月廿四日「足利義教御教書」『赤松文書』室:3037)を命じた。
また同日、義教は鎌倉の「小笠原大膳大夫入道」に「河野(河野教通か)以下」を関東に下向させる旨の御教書を下しており、彼等の東下を待ち、談合して「差寄永安寺、保国寺、無越度様可致忠節」(永享十一年閏正月廿四日「足利義教御内書」『小笠原文書』室:3036)事を命じている。このほか、「為用心、被仰佐々河、武田刑部大輔入道等了」(永享十一年閏正月廿四日「足利義教御内書」『小笠原文書』室:3036)ことも伝えている。
●永享11(1439)年閏正月24日「足利義教御教書」(永享十一年閏正月廿四日「足利義教御内書」『小笠原文書』室:3036)
●永享11(1439)年閏正月24日「足利義教御教書」(永享十一年閏正月廿四日「足利義教御教書」『赤松文書』室:3037)
同時期には「前筥根別当瑞禅」が上洛しているが、彼は「彼自京都為御勢下向之者也、彼者依(依違)関東之儀、自先年在京者也、而有讒者、称可申披之由参洛之」(『建内記』永享十一年二月二日条)とあるように、持氏に従わずに先年上洛していた人物であり、先日の持氏追捕の東下勢に加わっていた。ところが、下向中に「有讒者」があったために、申し開きのために参洛していた。この頃の箱根別当は大森氏出身の実雄僧正とみられ、瑞禅は前代別当と思われる。「有讒者」は、鎌倉与党の大森氏及び箱根別当実雄僧正との繋がりを疑われたものか。推測だが、永享2(1430)年9月に「箱根別当(証実大僧都)」が亡くなった(『満済准后日記』永享二年十月十日条)のちに箱根別当を継承したのであろう(ただし、『筥根山別当東福寺金剛王院累世』では瑞禅の名はない)。なお、箱根別当は「実」字を用いる傾向があることや、彼は持氏与党大森氏とは異なり持氏の意見に反対して上洛していることから、出自は大森氏ではないと思われる。持氏の意見に反したので箱根権現別職を罷免されたのかもしれない。
●「筥根山別当東福寺金剛王院累世」(『箱根神社大系』上巻)
| 三十五世 | 宋実僧正 | |
| 三十六世 | 証実僧正 | 大森氏 |
| 三十七世 | 実雄僧正 | 大森氏 |
| 三十八世 | 禅雄僧正 | |
| 三十九世 | 海実僧正 | 大森氏 |
| 四十世 | 長綱僧正 | 北條氏綱二男菊寿丸 |
●大森葛山系図(『裾野市史』第二巻資料編 古代・中世 別冊付録)
大森頼明―+―大森頼春―――+―友石明訓 +―大森成頼―――大森氏康――+―大森定頼
(信濃守) |(信濃守) |(乗光寺二世) |(民部大夫) (民部少輔) |(大膳大夫)
| | | |
+―証実大僧都 +―大森憲頼―――+―実雄僧正 +―海実法師
(箱根別当) (民部大輔) |(箱根別当) (箱根別当)
|
+―大森氏頼―+―大森実頼――+―大森定頼
(信濃守) |(兵庫助) |(式部大夫)
| |
| +―実円
| |
| |
| +―大森顕隆
| (式部大夫)
|
+―大森藤頼――+―大森頼宗
|(信濃守) |(与二郎)
| |
+―飯田憲康 +―大森頼員
|(兵庫助) |(大和守)
| |
+=大森顕隆 +―大森頼冬
|(式部大夫) (兵部少輔)
|
+―明甫
|
|
+=実円
|
|
+=大森定頼
|(式部大夫)
|
+―長実
|(箱根別当)
|
+―子圭
|(法持院)
|
+―大森房頼―――大森頼冬
|(兵部少輔) (兵部少輔)
|
+―大森頼員
|(大和守)
|
+―女子
(桂岩妙秀)
∥――――――三浦義同
∥ (陸奥守)
上杉持朝――――三浦高救
(修理大夫) (修理亮)
義教の側近である権大納言時房が耳にした別の話では「鎌倉武衞御免和睦事、房州執申趣彼申次、仍被召置伊勢守宿所、以外恐怖云々、一昨日已下向之、已申披之故歟」(『建内記』永享十一年二月二日条)ともいい、実は瑞禅は憲実からの持氏赦免を願う使者であり、伊勢守貞国亭に留め置かれたとのことで「以外恐怖」という。ただ、彼は「無御進発者、鎌倉武衞被切腹之条、無左右難有之由申之歟」(『建内記』永享十一年二月二日条)という主張を「已申披」して、閏正月29日に関東へ下向したとのことなので、憲実の使僧ではない。時房としてはそのようなことのために御勢の下向を要請するとは「奇怪之申状哉、為実事無勿体事也」と非難する。
●『建内記』永享11(1439)年2月2日条
なお、閏正月17日、義教の「若公降誕」(『薩戒記』永享十一年閏正月十七日条)している。のちの「正護院新門主御事」こと聖護院権僧正義観である。御産所は「赤松播磨」邸で「御袋御北向様」(『御産所日記』)と見えるが、実際は「家女房遠州某女」(『尊卑分脈』)であろう。
そして2月2日、義教は「相国寺長老下向関東」(『建内記』永享十一年二月二日条)させた。このとき、閏正月24日の御教書を持たせたと思われる。権大納言時房は彼の派遣については「是猶可攻申武衞之由、被仰付房州上杉歟」ことが主題であると推測している。これについて、京都では「而今、武衞依隠遁、子息事彼執申之、欲属無為之處、自京都無御許容、依之停滞也、若猶無御許容者、房州可切腹之由申之歟云々、然者可及合戦歟、大事出来難測事哉之由謳哥」(『建内記』永享十一年二月二日条)と、今でもお許しがないため情勢が解決されず、なおも御許容がなければ憲実は切腹すると言うか、京勢との合戦に及ぶか、という噂が広まっている。
一方、鎌倉では憲実は2月初頭には義教からの厳命を伝え聞いていたと思われる。当然ながら使者として在倉の赤松播磨守からも強い要請があったことは想像に難くない。憲実も「訴訟事尽」たことを悟り、2月10日、「於永安寺長春院、持朝、胤直参向、勧申御自害」した(『鎌倉持氏記』)。これを聞いた持氏祗候の近習らは「切出令討死所」と最後の抵抗を見せる中、「持氏、満貞両御所、御自害」した(『鎌倉持氏記』)。持氏享年四十二。なお、持氏は「已及臨自殺之期放火」(『建内記』永享十一年二月十八日条)したという理由で「鎌倉武衞首」は「不及京着之儀」(『建内記』永享十一年二月十八日条)と定められた(ただし、その後に憲実が持氏自刃の長春院に詣でていることから、実際は長春院は焼失せず、公卿首を晒さない慣例に則ったものか)。
この永安寺の合戦時に上杉持朝、千葉介胤直の手勢に抵抗して討死した人々は以下の通り。赤色は千葉氏系奉公衆である。
| 足利持氏祗候人 | 木戸伊豆入道、冷泉民部少輔、小笠原山城守、平子因幡守、印東伊豆入道、武田因幡守、賀嶋駿河守、曽我越中守、設楽遠江守、沼田丹後守、木内伊勢入道、神崎周防守、中村壱岐守 |
| 足利満貞祗候人 | 南山上総入道、南山右馬助、里見治部少輔、今河左近蔵人、二階堂伊勢入道、二階堂民部少輔、下条左京亮、逸見甲斐入道、石河民部少輔、新宮十郎左衛門尉、岩渕修理亮、泉田掃部助 |
●『東寺光明講過去帳』(『続群書類従』)
持氏に伺候した「神崎周防守」は、下総国香取郡神崎庄の神崎左衛門五郎秀尚の子、神崎周防守満秀の子か。満秀の兄・神崎上総介忠尚は千葉惣領家被官で、永徳元(1381)年の「小山義政の乱」、応永23(1416)年の「上杉禅秀の乱」において千葉介満胤に従軍している。
なお、閏12月24日の『足利義教御教書』が鎌倉の小笠原政康入道のもとに届いた、つまり、2月2日に出京した相国寺長老柏心和尚が鎌倉に到着したのは2月13日頃であり(永享十一年閏正月廿四日「足利義教御内書」『小笠原文書』室:3036)、すでに持氏自刃の後であった。
2月10日に持氏が自刃すると、当日中に「越後、信濃御勢、可打帰候」と、帰途に就いたが、鎌倉街道へ出るまでの地点に、持氏方の小勢が陣取っており、越後長尾勢や小笠原勢は進むことができず、憲実宿老の長尾芳伝は「西谷下野守」に一族を引き連れて藤沢辺に出陣するよう命じた(永享十一年二月十日「長尾芳伝書状写」『武家書簡』乾 室:3042)。西谷下野守がいかなる人物かは定かではないが、上野国人で守護上杉家の麾下にあったようだ。しかし「如何篇度々無在陣候、無心元候」と、以前から幾度も出陣を命じていたが、応じていなかったことがわかる。何らかの罪により本領を奪われていたようで、義教も「彼御落居以後、本領等可致返之由被仰出候」と、持氏自刃ののちは本領を返す旨を仰せられているので、出陣するよう促している。
●永享11(1439)年2月10日「長尾芳伝カ書状写」(『武家書簡』乾 室:3042)
●永享11(1439)年2月11日「足利満直書状写」(『皆川文書』 室:3082)
持氏の与党が少なからず存在し、抵抗勢力として各所にいたことがうかがえる。また、同族内でも鎌倉方、京方に分裂していた例もあり、伝統的に鎌倉に忠誠を誓っていた長沼淡路守家の「永沼淡路守(長沼刑部少輔憲秀の子彦法師性空か)」が、持氏降伏を受けて(弁明のためか)鎌倉に「罷上」った際に、篠川公方満直は彼を非難して憲実に「白川弾正少弼(白河結城氏朝)、小峯参河守(小峯結城朝親)」を遣わして、長沼淡路守について「彼仁之事、不可有許容候」ことと、「永沼次郎事、今度令出陣、致忠節事候、其上理運無是非候、近日可致入部候、別而被加扶持候者、悦入候」と、満直に属して出陣した長沼次郎が近々(追われていたと思われる)所領に入部するので、特に援助を願う旨を伝えている(二月十日「長尾芳伝カ書状」『武家書簡』乾)。
●永享11(1439)年3月4日「白川氏朝、小峯朝親連署状写」(『皆川文書』 室:3089)
●永享11(1439)年3月5日「足利満直書状写」(『皆川文書』 室:3090)
憲実はこの篠川満直書状に対して弟の三郎重方(篠川満直宛か)と長尾忠政入道(白川・小峯両結城氏宛か)から「子細」を返答させているようである。それに対する結城白川氏朝、小峯結城朝親の返書は長尾忠政入道へ篠川満直からは上杉三郎重方へ返書が出されている。
 |
| 鎌倉の伝足利持氏供養塔 |
持氏自害の報告が京都に届けられたのは、切腹から五日後の2月15日のことであった。
2月15日、権大納言時房のもとに「関東事、已属無為、鎌倉左兵衛督持氏卿切腹之由誅也、此事去十日事也」(『建内記』永享十一年二月十五日条)という注進が届く。注進によれば「相国寺住持、先日下向為御使、関東管領上杉房州可随上意之由申之、仍武衛切腹、近習少々同切腹云々、天下太平幸甚々々」といい、柏心和尚が上意を憲実に伝えたことで持氏切腹に動いたとしているが、柏心和尚が鎌倉に到着する三日前に持氏は自害しており、憲実は上使赤松播磨守などの説得を受けて決断したと推測される。
また、憲実は持氏自刃に伴い「鎌倉故武衞子息、一人被相残之擒了」(『建内記』永享十一年二月廿日条)とした。憲実は京都に「於関東可誅哉、可送京都哉之由」(『建内記』永享十一年二月廿日条)を問い合わせている。その結果は記されていないが、誅殺を命じたか。ただし、「於去年永安寺、両三人御警固候処ニ、彼御息様討漏申方有而、如此御大事出来候歟」(永享十二年十月十五日「仙波常陸介書状写」『安得虎子』)と見えることから、「大石源左衛門尉憲儀、同大夫持朝并千葉介胤直」の三名の憲実代官は、永安寺に幽閉していた「鎌倉故武衞子息」を、故意か過失かは不明ながら逃がしてしまっていた。報国寺の義久以外の子(安王、春王、万寿王、永寿王ら)は逃亡したとみられることから、彼ら三人の故意によるものである蓋然性が高そうである。
一方、憲実は2月28日、「於若君報国寺御落居事申」(『鎌倉持氏記』)した。これを聞いた「若公更無御騒、而有御焼香、唱仏名刀被御腹立静御自害訖、僅十才御身」という。これを聞いた人々は「如此御態不及言語、難押感涙次第也」(『鎌倉持氏記』)と、みな涙を流したという。義久の年齢については「義久於報国寺自害、十一歳」(『鎌倉大日記』)、「於官領防州所自害、十一歳」(『東寺光明講過去帳裏書』)とあるように、十一歳とも。応永33(1427)年の「天王丸誕生、嫡子号大若君、後義久」(『年代記配合抄』)の場合は13歳となる。3月3日、京都の西園寺公名のもとに「故鎌倉三位息一人、幽隠之處、去月下旬又被誅殺戮」(『管見記』永享十一年三月三日条)という注進が届いている。
そして6月28日、憲実入道は持氏が自刃した「長春院江参」り、「御影御前而致焼香」ている。このとき、憲実に陪従していた家人等は彼の様子がおかしいことを感じ取っていたようで、「無是非及自害刻、家人高山越後守、那波内匠助走寄、刀瓜国付雖、■半分切訖」と、憲実入道が持氏の御影前で自害せんと短刀瓜国を腹に突き立てた瞬間、家人の高山越後守と那波内匠助が走り寄って刀を取り上げている。しかしすでに短刀は半分ほど腹に刺さっており、屋敷に搬送されたが、このまま動けば命はないとの事から、京都に子細を伝え、御下向の疵医の診療を受けさせたところ、憲実入道の疵は日に日に回復していったという。
また、「爰憲実出家法名長棟、身上有忠無誤處、就虎口讒言相交、上方思食立處身上也、所詮依存命被痛存廻思案」と、憲実は自らに誤りはないものの、一色等の讒言を受けた故持氏に憲実追討を思い立たせ、結果として自らは存命したことは痛恨であると考えて出家隠遁し、自分の代わりとして「自越州舎弟兵庫頭清方奉上、噯子息成人間、可為名代旨申定」(『鎌倉持氏記』)と、越後国から舎弟の兵庫頭清方を召して、子息龍王(のち憲忠)が成人するまで名代とすることとした。
その後、憲実入道は11月20日には鎌倉から藤沢へ居を移し、12月6日には「豆州国清寺隠居」してしまった(『鎌倉持氏記』)。
憲実入道の伊豆国隠遁からわずか一か月後の永享12(1440)年正月13日、鎌倉から「一色伊予守逐電」した。彼は故一色直兼の親族と思われるが、「鎌倉為討手長尾出雲守憲景、太田備中守資光、相州今泉辺」を捜索したが遂に見つからなかった(『鎌倉持氏記』)。この一色伊予守の逐電は約一年前に逃亡していた故持氏の遺児たちと繋がったものだった可能性が高い。遺児たちはいずれも常陸国(または下野国日光)に遁れていた形跡が見られるため、長尾出雲等が一色伊予守を追捕した「相州今泉」は山内庄今泉(鎌倉市今泉)であった可能性が高いだろう。
この「一色伊予守逐電故歟、就若以前野心鬱有子細者歟」として、持氏近臣の「舞木駿河守持広」が「身上雖侘申、案否未定」と、伊予守の捜索中に、尾張入道芳伝を通じて侘びを管領代の上杉三郎重方に申し入れたとみられる。舞木持広と一色伊予守の関係は不明だが縁戚関係にあったか。これを受けて尾張入道芳伝は「永々当参所清方可有対面」と、尾張入道の屋敷に清方が寄宿しているので対面すべしと使者を送ったため、舞木持広は「馬大刀一献用意」して正月22日に芳伝の在所を訪れた。芳伝は持広に酒を勧めたのち、「申付人々、及自害沙汰訖」と持広に自害を命じ、従容と自刃したと思われる。このとき持広に付き従っていた「騎馬赤井若狭守」は「下人相隔」ていたため、ひとり「刀計数輩負深手後被討」と、芳忠亭で奮闘して討死した。その様は「奕振舞褒」と賞賛されている(『鎌倉持氏記』)。
2月17日、京都は武蔵国の「安保信濃入道殿(安保宗繁入道)」に「関東雑説在之云々、今現形者、不廻時日馳向」よう命じている(永享十二年二月十七日「管領細川持之奉書」『安保文書』室3137)。この雑説は一色伊予守の逐電と関わりがあったと考えられる。2月21日、将軍義教は「千葉介(千葉介胤直)」「三浦介(三浦介時高)」へ「一色伊予守以下野心之輩」を糾明するよう命じた(二月廿一日「伊勢貞国カ奉書案写」『政所方引付』室3140)。
3月上旬頃、下野国では日光から「日名田」某が率いる軍勢が結城方面へ下ってきた。「日名田」は、上都賀郡日名田郷(日光市日向)の武士と推測され、この侵攻に「結城中務大輔(結城氏朝)」は追捕のために軍勢を差し遣わした。結城一族の「大内左近将監」もおそらく氏朝の命を受けてこの合戦に加わって戦功を揚(永享十二年三月廿八日「将軍御内書案」『箱根神社文書』室:3154)、義教から感状を受けている。
●永享十二年三月廿八日「将軍御内書案」(『箱根神社文書』室:3154)
この合戦で、氏朝は大将の「日名田」を討ち取ったが、このとき討たれた「日名田」某は、政所執事奉書案(永享十二年三月廿九日「伊勢貞国カ奉書案写」『政所方引付』室:3157)から、「第二若君始者奉号大御堂殿」を奉じた人物だったことがわかる。「第二若君始者奉号大御堂殿」は持氏二男、勝長寿院門主成潤と思われるが、彼はこの時点で「大御堂殿」を経験し、日光山別当を兼帯していたと考えられるため、彼は持氏自刃ののち日光山へ遁れたのだろう。春王や安王が日光へ遁れていた伝承は、彼らが成潤とともに日光に潜伏していた時期があることを示唆しているのだろう。
| 名 | 生没年 | 記事 | 出典 |
| 義久 ・賢王丸 ・天王丸 ・天皇丸 ・八幡太郎 |
1430-1439 | 静御自害訖、僅十才御身 | 『関東持氏記』 |
| 於報国寺自殺十歳 | 『古河公方系図』 | ||
| 1429-1439 | 義久於報国寺自害、十一歳 | 『鎌倉大日記』 | |
| 於官領防州所自害、十一歳 | 『東寺光明講過去帳裏書』 | ||
| 1427-1439 | 応永卅三 天王丸誕生、嫡子号大若君、後義久 | 『年代記配合抄』 | |
| 成潤? ・第二若君 ・大御堂殿 ・長寿院 |
1429?-???? |
第二若君始者奉号大御堂殿 (年齢については記載なし) |
『関東持氏記』 |
|
兄十三、被没落之由、後ニ聞 故武将持氏子息十三歳尋出討申之由 一人已自殺、一人生捕、今一人者事注進先了 |
『看聞日記』 嘉吉元年五月四日条 |
||
| 春王殿 | 1430-1441 | 十二歳春王殿 |
『東寺執行日記』 嘉吉元年四月十六日条 |
| 1429-1441 | 春王十三 | 『古河公方系図』 | |
| 安王殿 | 1431-1441 | 十一歳安王殿 |
『東寺執行日記』 嘉吉元年四月十六日条 |
| 1430-1441 | 安王十二 | 『古河公方系図』 | |
| 成氏 ・永寿王丸 (万寿は×) |
1434-1497 |
持氏戦死、成氏僅五歳… …明応六年九月晦日卒、年六十四 |
『古河公方系図』 |
| 尊敒 ・長春院 ・雪下殿 |
1438-???? | 今一人四歳、不見之處、已尋出之捕了 |
『建内記』 嘉吉元年五月四日条 |
| 定尊 ・若宮別当 ・蓮華光院僧正 ・雪下殿 |
この3月上旬の「第二若君(成潤)」の挙兵と繋がっていたのが、下野国の一色伊予守、野田右馬助ら持氏遺臣、3月3日に常陸国中郡で挙兵した「源安王丸」であろう。3月に入り、上野国から常陸国にかけて、一斉に旧持氏党が蜂起したのである。下野国の足利庄付近の旧持氏遺臣たちは「野田右馬助家人加藤伊豆守以下」が「足利庄高橋郷野田要害(佐野市高橋町)」に立て籠もり、そこに上野国の「新田田中、佐野小太臈、高階士塚修理亮、桃井被官仁等」が「馳集」って「既上州可打越旨有其聞」(『鎌倉持氏記』)との風聞もあった。彼らは前述の通り、日光の若君、一色伊予守との連動で挙兵したものと推測される(この「第二若君」の情報は当時はまだ関東にも伝わっていない)。この加藤伊豆守の挙兵に上野新田勢らが加わっている様子が聞こえており、「于時守護代大石石見守憲重、為馳向当国一揆中両度相觴」たが、上野国人一揆らは「可罷立旨無領掌仁」(『鎌倉持氏記』)という有様だった。しかし「大石憲重(憲重の子、大石源左衛門尉憲儀か)」は上野守護代として鎮定せざるを得ず、4月4日「一揆不及相待、手勢計而、四月四日令出陣」した。このとき、上野国人のうち少々が「雖不相同難遁、少々馳着」て、「為疎忽出陣由」を述べ、大石も「角渕(佐波郡玉村町角渕)」に「一日不慮逗留」(『鎌倉持氏記』)した。
ただ、「第二若君」ら三月挙兵の人々は、あくまでも持氏遺臣の集合体に過ぎず、確固たる拠点も持たない脆弱な存在であった。そこで彼らが恃もうと図ったのが、故持氏と関わりが深く、下野国に強大な勢力を有する小山氏とその事実上の宗家結城氏と推測される。ただし、小山持政は持氏と対立した上杉憲実が下野下向時にともに鎌倉を離れた人物であり、彼らは結城氏朝を恃んだものだろう。ただし、氏朝自身は京方の人物であることから、直接彼と交渉することは不可であったため、氏朝の子「七郎光久」及び、氏朝「舎兄」(『管見記』永享十三年五月十九日条)の「小山大膳大夫(成潤弟の安王丸または春王丸の「御乳父」)」に密かに事を図ったと思われる。
一方、「日名田」某の軍勢を追捕して、大将の「日名田」を討ち取った氏朝は、両使(人物名不明)にその首級を持たせて「早速致沙汰」し上洛させている(永享十二年三月廿九日「伊勢貞国カ奉書案写」『政所方引付』室:3157)。その首級は4月2日時点で義教が「一両日進上ひなた致候」(永享十二年四月二日「伊勢貞国カ奉書案写」『政所方引付』室:3157)とあることから、「日名田事、被仰下之処、早速致沙汰、頸到来」(永享十二年三月廿九日「伊勢貞国カ奉書案写」『政所方引付』室:3157)とある3月29日頃に京都に到着したことが推測され、結城から京都までの日数(東山道を経由したであろう)を勘案すると、結城勢と日名田勢の合戦は3月10~15日頃で起こったと推測できる。後述のように、常陸挙兵の「源安王丸」が結城に東接する「伊佐(筑西市中館)」へ進出したのが3月18日であり、本来は日名田勢(大御堂殿成潤)と安王丸勢は合流する予定だった可能性があろう。
永享12(1440)年3月中旬、「日名田」を討った氏朝のもとに、「第二若君始者奉号大御堂殿結城氏朝有御憑事」(『鎌倉持氏記』)とあるように「大御堂殿」が頼ってきたとみられる。
氏朝はこの知らせを受けると、「召集一門以下家人等、各々被尋意見」た。そこで「水谷伊勢守、簗修理亮、同将監、黒田民部尉等」は「長春院殿御息御取立御申者尤十分也、就世上時宜、一度京都御降参訖、無替篇目而令変之事、非弓矢法儀間、難及意見旨」(『鎌倉持氏記』)と諫言した。
ところが、氏朝が宿老らとの「意見座」に臨んでいる最中、「厚木掃部助」が来て、氏朝に「可申有子細」と別座を願い出た。厚木が氏朝に伝えたのは「其故、若君既入御訖、意見座氏朝息七郎光久不被座、彼御迎也」(『鎌倉持氏記』)と見え、すでに若君(大御堂殿)が結城城に入御しており、本来この意見の座に出席の予定だった氏朝子の七郎光久が不参だったのは、彼を迎えに出たためであったという。このことを聞いた家老四名は「本来尓至極落居事、新意見被申、失面目」(『鎌倉持氏記』)と、もとより結論が出ているものを新たに意見を聴した氏朝に失望したとして、「彼四人遁世仕」った。その中で「水谷伊勢守計、種々問答而召帰」と、水谷伊勢守だけは氏朝の説得に応じて帰参したが、「簗修理亮、同将監、黒田民部尉」の「残三人遁世訖」と、老職三名は出家してしまった(『鎌倉持氏記』)。
これにより、本来は京方だった氏朝は「若公既入御上、本来墎内外大堀壁鹿垣焱」(『鎌倉持氏記』)して、彼を奉じて旧鎌倉方へと転じたとみられる。ただし、結城氏朝の寝返りはしばらく発覚することはなかった。
永享12(1440)年3月の「大御堂殿」の挙兵と連携していたのが、日光から常陸国へ移っていたと思われる大御堂殿(成潤)の弟「源安王丸」である。3月17日、京都の万里小路時房が伝え聞いた情報では、「故鎌倉左兵衛督持氏卿子息等、悉死去之由、先度有其沙汰之処、近日称子息両人於常陸国挙旗云々、実否難測、但注進分明」(『建内記』永享十二年三月十七日条)とあり、京都への報告には持氏の「称子息両人」と明示されていたことがわかり、安王丸と兄・春王丸は常陸挙兵当時から行動を共にしていたとみられる。
安王丸は挙兵直前まで中郡庄の東側(笠間庄か)に潜伏していたとみられる。なお、永享12(1440)年2月19日、「持国」が「鹿嶋護国院長老」に対して「常陸国鹿嶋護国院領行方郡若舎人郷内根地木村」について、「任 御書旨、不可有相違候」(永享十二年二月十九日「持国奉書」『護国院文書』)という文書を発給している。この「持国」は花押型が『角田石川文書』の「左馬助持国」と同一であるため、岩松左馬助持国に比定される。
●永享12(1440)年2月19日「持国奉書」(『護国院文書』)
●「左馬助持国」の花押の変遷
| 年 | 署名 | 花押形 | 宛名 | 内容 | 出典 | |
| 1 | 永享8(1436)年 8月3日 |
持国 |
|
不明 (女性か) |
武蔵国春原庄万吉郷(熊谷市万吉)の「やうめい寺ふん」の譲状。 万吉郷には岩松家祖・岩松時兼の妻となった土用御前(相馬義胤女子)の「墓所堂」があり、弘長3(1263)年2月頃に病死したのち、時兼は嫡子・五郎経兼へ春原庄内万吉郷)を譲るにあたり、そのうち佃五段を「故女房の墓所堂ニ永寄進」した(弘長三年三月二日「岩松時兼覚智譲状」『正木文書』)。 |
「岩松持国寄進状写」 『正木文書』43 |
| 2 | 永享12(1440)年 2月19日 |
持国 |
|
鹿嶋護国院長老 | 鹿嶋社護国院領の行方郡若舎人郷内根地木村を「任 御書旨」せて保証した。 | 「持国奉書」 『護国院文書』 |
| 3 | 嘉吉元(1441)年 7月27日 |
左馬助持国 |
|
石川駿河守 |
京都の将軍義教横死の報告と、「関東之御本意此時候歟」と関東復興につき意見を伝え、参陣を要請した。 ★花押型、筆致が4書状正月18日と同一であり、右筆であったとしても同一右筆によるものであろう。 |
「左馬助持国書状」 『角田石川文書』 |
| 4 | [嘉吉2年?] ■2(1442)年 正月18日 |
左馬助持国 |
|
石川中務少輔殿 |
左馬助持国が「信濃大井方御座候 若君様」が去年12月17日に綸旨と御旗を賜ったので近々還御する予定であるから、すぐにはせ参じるようにと要請した。 ★花押型、筆致が3の書状7月27日と同一であり、右筆であったとしても同一右筆によるものであろう。 |
「左馬助持国書状」 『角田石川文書』 |
| 5 | 享徳4(1455)年~ 長禄2(1458)年の 3月23日 |
右京大夫持国 |
|
鑁阿寺供僧御中 | 持国が「就凶徒御退治、進発」したときに鑁阿寺から祈祷の御巻数が到来し、「弥致御祈祷之精誠候者所仰候」旨を「公方様(成氏)」へすぐに注進することを報告した。 | 「岩松持国書状」 『鑁阿寺文書』 |
| 6 | 長禄3(1459)年? 5月15日 |
左京大夫持国 |
|
御奉行所 |
(左京大夫任官は長禄3年2月7日のめ、これ以降である) 京都に対し「就御方参候、頂戴 御書」について御礼を述べ、忠義を尽くす旨を将軍義政に伝えた。 |
「岩松持国請文写」 『正木文書』271 |
3月3日、潜伏先から「進発」(永享十二年三月廿八日「足利安王丸書下」(『石川文書』神奈川県史資料:5999)し、翌3月4日には「常州中郡庄木所城」に拠った。それまで安王丸らは宍戸氏に庇護されていた可能性があろう。実際に、安王丸と合流した筑波山別当一族や筑波山衆徒は、永享13(1441)年2月16日当時「佐竹、完戸勢同道仕」り、翌嘉吉2(1442)年3月23日には筑波別当(潤朝)が幼少の為「為代官属完戸安芸守持里之手」し、享徳3(1454)年当時「惣領中務大輔(宍戸中務大輔政里か)」(享徳4(1455)年2月筑波潤朝軍忠状案写(「古証文二」神奈川県史料6187)に属しているように、筑波山別当は宍戸惣領家に属する庶家と見做されていたのである。
木所城に拠った同日の3月4日、「源安王丸征夷将軍」は「御代管 景助」を通じ「武運長久、如意満足時」に、常陸国中郡庄内の地一所を中郡賀茂社(桜川市加茂部694 鴨大神御子神主玉神社)に寄進する旨の奉書を納めている(永享十二年三月四日「源安王丸代景助奉書案」『加茂部文書』室3141)。安王丸が上洛して征夷大将軍に成り代わろうと考えることはまったく現実的ではなく、願文の「征夷将軍」は自称(しかも征夷「大」将軍ではない)で、「武運長久」を祈ったものと考えることが妥当であろう。「景助」は春王丸の外戚簗田氏か。安王丸は義久亡き後、故持氏子息中においては正嫡の地位(長幼の順は、大御堂殿、春王、安王、万寿王、永寿王か)にあったのだろう。
●永享12(1440)年3月4日「足利安王丸代官景助奉書案」(『加茂部文書』室:3141)
筑波別当一族は「熊野別当朝範」がまず「以親類等談合」って一人木所城に馳せ参じて安王丸に「供奉」し、3月13日に朝範兄の筑波別当玄朝が兄の「美濃守定朝、同伊勢守持重、其外親類等引率而木所へ馳参」じ、同13日の「小栗御出」(筑西市小栗)に供奉している。
この常陸国の安王丸の挙兵は、鎌倉に遣わされている京都勢軍監とみられる「仙波常陸介」のほか、「上杉修理太夫」「二階堂駿州、大田(太田六郎右衛門尉)、狩野(狩野伯耆守)」「千葉介」らが3月上旬に京都に報じており、3月16日、将軍義教はそれらの報告に基づき「常州辺之野心輩出張由」について再度の注進があれば軍勢を遣わすよう、持朝被官の「上田(上田新蔵人)」「太田(大田六郎右衛門尉=資清?)」に政所執事より奉書を遣わした(永享十二年三月十六日「伊勢貞国カ奉書案写」『政所方引付』室:3143)上、翌3月17日、「常州辺凶徒(安王丸一党)」の追討を「上杉修理太夫」「千葉介」を筆頭に「石川一族」「武州一揆中」「二階堂駿州、大田(太田六郎右衛門尉)、狩野(狩野伯耆守)」ら関東布陣の諸将へ一斉に命じる御教書を下している。
この御教書を下したのと同日の3月17日、義教は「赤松伊予守義雅惣領大膳大夫入道性具弟也、所領悉被没収」し、「被宛行舎兄入道并細川右馬助、赤松伊豆入道小屋野拝領等」(『看聞日記』永享十二年三月十七日条)している。義雅が所領を没収された理由は記されていないが、時期からみて関東の安王丸・春王丸挙兵との関わりを疑われたと見るのが妥当か。
義雅旧領のうち「小屋野」を下されたのが義教近臣の「赤松伊豆入道(赤松貞村入道常宗)」であるが、貞村入道の属する赤松春日部氏と赤松惣領家の遺恨から、彼が義教へ疑惑を吹聴した可能性もあろう。ただし、義雅自身は反論せず従容と従い、兄の満祐入道もまた義雅の処分「自体」には苦情を述べていないため、事実であった可能性もあろう。貞村入道の屋敷は永享6(1434)年7月26日に誕生した義教の庶子(のち鎌倉殿に予定されていた左馬頭義制、小松谷殿義永)の御産所となっており(義制の母が「母宮内卿赤松永良則綱女、赤松一族女」(『看聞日記』永享六年七月廿六日条)だったため、義教側近の赤松貞村亭が選ばれたものか)、義教との関係の深さがうかがわれる。なお、「赤松永良則綱」は赤松円心入道嫡男・赤松信濃守範資の子(『赤松系図』)である。
前述のように、赤松満祐入道は弟・義雅領没収の処分自体には異論を挟んでいないが、貞村入道へ与えられた「小屋野事」については「為勲功拝領於家執之、而父入道依愛子譲与了、可被付家之由」を述べ、摂津国「小屋野(伊丹市昆陽)」は古く勲功の地として惣領家に与えられた地で、亡父義則入道が愛子義雅へ譲ったものであり、惣領家への返付を求めたのであった。この結果どうなったのかは定かではないが、おそらくこの願いは認められなかったのではなかろうか。「小屋野」は播磨国から京都へ向かう要衝の宿場であり、貞村入道が欲したとも考えられる。満祐入道は永享12(1440)年に「依狂乱自去年不出仕」(『建内記』嘉吉元年六月廿四日条)と、「狂乱」を理由に出仕を止めており、この一件が、翌嘉吉元(1441)年6月24日の義教弑逆事件(嘉吉の変)へ発展する一因となった可能性は高いだろう。満祐入道は以前より「直冬子孫、為禅僧在播州、以彼可取立申由、赤松称之」(『建内記』嘉吉元年七月十七日条)と、故足利直冬の子孫の禅僧を播磨国に招いて扶助しており、おそらく義教を討ったのち、満祐入道は「此禅僧、元来在播州」を「称将軍」(『建内記』嘉吉元年七月十七日条)と推戴したとみられる。
このころ関東では、鎌倉の兵庫頭清方もまた下野国高橋郷で挙兵した持氏遺臣を追捕するべく、3月10日頃に「先武蔵国固庁鼻性順、可有下向旨」を命じている(『鎌倉持氏記』)。このとき上杉性順は「無勢由」を述べて辞退を申し入れるが、清方は「堅被申」て辞退を許さず、山内上杉執事「長尾左衛門尉景仲相添」て3月15日に鎌倉を発たせている(『鎌倉持氏記』)。鎌倉を発った上杉性順と長尾景仲は、それぞれ「苦林(入間郡毛呂山町苦林)」、「入間河(狭山市入間川)」に布陣して、下野国の形勢を覗っている(『鎌倉持氏記』)。
一方、常陸国で挙兵した足利安王丸勢は、3月18日に「伊佐へ御出」(筑西市中館456)している。これはおそらく日光から下向する大御堂殿との合流が図られたと考えられるが、このときすでに結城氏朝の軍勢に敗れ、大御堂殿を奉戴する大将の「日名田」某は討たれていた。しかし前述の通り、この直後、大御堂殿は氏朝嫡子・七郎光久の力もあって結城氏朝の協力を取り付けて結城城に入城している。さらに安王丸の「御乳父」(『建内記』永享十三年六月十八日条)の氏朝「舎兄」(『管見記』永享十三年五月十九日条)「小山大膳大夫」や「勝賢寺(生源寺、松源寺)」(「小山系図」『小山泰朝所蔵系図』)も協力者と推定される。こうして、安王丸・春王丸もまた3月21日に「結城中務大輔氏朝」の結城城に入った。兄の「大御堂殿」に遅れること数日とみられる。氏朝は「不黙先忠厚恩、存弓箭之順儀、奉入我舘」った(享徳4(1455)年2月筑波潤朝軍忠状案写(「古証文二」神奈川県史料6187)とあるが、
●筑波山中禅寺別当系図(『小田氏譜』「土浦市史編纂資料」)
八田知家―+―小田知重―――小田泰知――小田時知―――小田宗知――小田貞知――小田治久――小田尊朝――小田治朝――――小田持家
(筑後守) |(常陸介) (常陸介) (常陸介) (筑前守) (常陸介) (常陸介) (讃岐守) (讃岐守) (讃岐守)
|
+―茂木知基
|(三郎)
|
+―宍戸家政―――宍戸家周――宍戸家宗―――宍戸家時――宍戸知時――宍戸朝家――宍戸基家――宍戸家秀――――宍戸持朝
|(左衛門尉) (壱岐守) (左衛門尉) (左衛門尉)(安芸守) (安芸守) (遠江守) (安芸守) (備前守)
|
| +―筑波定朝
| |(美濃守)
| |
| +―筑波持重 +―千手丸
| |(伊勢守) |
|【中禅寺別当】 | |
+―明玄法眼―――如仙――――朝仙―――…………………【中略】………筑波越後守――?――+―玄朝法眼――+―潤朝
(権少僧都) | (別当大夫)
|
+―朝範
(熊野別当)
この頃、鎌倉から京都へは「既凶徒等蜂起、追日陪増之由、自方々も令注進候」と、度々注進が届けられており、将軍義教は「房州帰参事如何候哉」、「早速帰参可為肝要候旨、重而被仰出候、雖為片時遅々候者、且者先忠可処于無候」(永享十二年三月廿七日「細川持之奉書案」『足利将軍御内書并奉書留』室:3151)と強い調子で伊豆国に隠遁した前関東管領憲実の帰参を促している。要となるべき関東管領が不在の中、代理の兵庫助清方や修理大夫持朝では十分な指揮系統が働かず、憲実入道の再出仕が急務とされたのである。
こうした中で、「源安王丸」も結城城から積極的に行動を開始する。安王丸の当面の目的は「上杉安房入道、同弾正少弼以下為退罰」(永享十二年三月廿八日「足利安王丸書下」『石川家文書』室:3152)であり、3月28日、安王丸は「石川中務大輔(石川持光)」へ出兵を命じている。この安王丸の書下には「左衛門督憲義(桃井憲義)」が副状を付けており、安王丸の傅(安王丸外戚か)だった可能性があろう。桃井家は里見家や一色家と同様に御一家格であることから、もし安王が桃井家を外戚とする若公とすれば、根本被官の簗田氏を外戚とする春王丸は安王丸の兄とは言え庶子扱いだった可能性があろう。
●永享12(1440)年3月28日「足利安王丸書下」(『石川文書』室:3152)
●永享12(1440)年3月28日「桃井憲義副状」(『石川文書』室:3153)
安王丸は石川持光への書状の中で、3月3日の挙兵以来「依諸軍勢馳来、近日可還著者也」(永享十二年三月廿八日「足利安王丸書下」『石川文書』室:3152)と、軍勢が馳せ集まっているため、近いうちに鎌倉へ「還著」する予測を伝えている。当然誇張もあろうが、結城氏朝という強大な勢力が味方となったことと、持氏遺児というカリスマ性で、結城城に集まった武士は少なくなかったと思われる。なお、安王丸が3月28日付で石川持光へ送った書状は、副状の桃井状のみ4月17日に届いているが、安王丸の書状は7月25日まで石川に届かなかった。これは南奥州では石川氏と白河氏(当時は当主の白河氏朝やその母などは上洛の最中であった)の間で激しい戦闘状態が続いていたためと推測される(永享十二年七月五日「細川持之書状」『板橋文書』室:3181)。
永享12(1440)年3月28日頃、結城氏朝の使者二名が「日名田」の首級を持って京都に到着し、これを室町殿に献じた。これを実検した将軍義教は「頸到来、先以神妙之由被仰出候、為 御感御書、御剣一腰被遣候、御面目至候」(永享十二年三月廿九日「伊勢貞国カ奉書案写」『政所方引付』室:3157)と、氏朝の戦功を賞して、感状と御剣が遣わされる予定となった。そして、「就彼御息事も現形、野心之輩蜂起之由、自方々注進被申候、彼御在所近所事被及聞食候、以計略早々被申退治候者、可目出候、其方様事、自元無御不審被思食候処、殊更今度御文到来、相叶上意下者、此分まても不可有候、所詮彼御息様御落居為可候由、被下御旗方々へ被仰付候間、定不日可行候哉、切々御注進可然候」(永享十二年三月廿九日「伊勢貞国カ奉書案写」『政所方引付』室:3157)と、持氏御息の「御在所」が結城近郊と聞き及んでいるが、氏朝がこれを追捕したことを激賞し、さらに「自元無御不審思食候処、殊更今度御文到来」と「告文」までも提出していることがわかる。そして、「彼御息様」を討ち取って平定するよう、御旗を関東諸将へ下す事(当然氏朝の分もあろう)と、注進を怠らぬことを指示している。
ところが、この数日後の4月2日、「小山小四郎(小山持政)」の注進が京都に着し、結城氏朝が持氏若君を庇護して反乱に加わっていることが発覚する(永享十二年四月二日「伊勢貞国カ奉書案写」『政所方引付』室:3157)。
この寝耳に水の急報に、将軍義教は、旧鎌倉殿方が降参して一年も経たぬ間にまたもや叛旗を翻したことを言語道断と非難し、氏朝が「此間捧告文、種々可致忠節之由言上」したことを「神妙之由被思食候」と思っていたところに「結句一両日進上ひなた日名田致候、是御返事未出候最中、如此身体胡乱、無比類候、且天罰之至、尽弓矢冥加候歟、如此未練至極族者、中々罷成 御敵候事、一途候哉」と信頼を著しく裏切ったことに激怒し、上杉兵庫助清方、上杉修理大夫持朝へ結城追討を命じた。派兵は「蘆名(蘆名盛久)、白川(白川直朝)、海道五郡以下御勢」に対しても「定而早々可出陣候哉、万一遅々候者、自是直為御催促、為被進管領状候、遣写遣彼方々、可有御催促候哉」と強力な軍勢催促を指示している。さらに同様の指示が、管領細川持之よりの管領奉書で上杉兵庫助清方、上杉修理大夫持朝、千葉介胤直の三名に下されている(永享十二年四月二日「細川持之奉書」『足利将軍御内書并」奉書留』室:3160)。
●永享12(1440)年4月2日「伊勢貞国カ奉書案写」(『政所方引付』室:3161)
小山状が京都に届けられたのは4月2日で、同日中に結城討伐の奉書が関東に下されていることからも、相当の緊急事態であったことが察せられるが、この日、白河氏朝や「御母」以下二十九人が義教や若公への献物や熊野参詣のために、みずから上洛の途次(3月以前に白河を発って、3月初旬には鎌倉に居住していたのであろう)にあり、「勢多の橋を御渡候て、石山へ御参詣候、逢坂の入口大津の於茶屋」で休息を取っている際に「国よりの飛脚到着」(「白川氏朝上洛進物次第」『白河結城家文書』室:3166)で、「関東の若公様、中条ニ御旗を御上候、結城殿、名越殿御同心の由」を知らされている。同心した「結城殿、名越殿」のうち「名越殿」とは鎌倉名越に屋敷を有した大名と考えると、佐竹氏と考えらえる。
そして、伊豆に隠遁していた憲実入道長棟も、3月27日の義教からの「早速帰参可為肝要候旨、重而被仰出候」(永享十二年三月廿七日「細川持之奉書案」『足利将軍御内書并奉書留』室:3151)という強い「依京都仰」って、4月6日に「立伊豆、帰参山内庄」している(『鎌倉持氏記』)。その後の憲実入道の鎌倉での活動は不明だが、彼の帰参により鎌倉方は前管領憲実入道を総大将とし、鎌倉を守っていた弟の上杉兵庫助清方が結城攻めの大将とする陣容が決定される。清方の出陣は「抑武庫様十五、六日間ニ可有御進発候」(永享十二年四月十一日「長尾芳伝書状写」『烟田文書』室:3167)とあるように、4月15日辺りでの出陣が予定されている(後述の通り、実際の出陣は4月19日)。このほか、京都は4月11日に「曾我小次郎殿」へ「就持氏御息陰謀、常州凶徒等蜂起」のため早々に出陣するよう命じ(永享十二年四月十一日「細川持之奉書写」『古今消息案 三』室:3168)、上野国の京都御扶持の輩とみられる「岩松刑部少輔」へも「早属新田岩松治部大輔手令発向」(永享十二年四月十六日「細川持之奉書写」『武家書簡 乾』室:3169)を命じた。このほかにも多くの近隣国人へ同様の管領奉書が下されたと推測される。
4月19日、「永泰院周侍者、為関東使節故、参暇于天龍寺、轉位于蔵主」、「臨川寺周沅西堂、来廿一日可為関東使節之由被仰出」(『蔭涼軒日録』永享十二年四月十九日条)とあるように、関東への使者が遣わされている。
 |
| 小山祇園城と思川河畔 |
永享12(1440)年4月17日、結城から「岩松左馬助、桃井、結城以下凶徒」が小山へ侵攻する(永享十二年五月三日「足利義教感状」『松平基則氏所蔵文書』室:3170)。
小山は鎌倉街道が通る要衝地であり、当初、結城氏朝は甥の小山持政に協力を持ちかけた可能性があろう。しかし持政は上杉憲実とともに鎌倉を離れているように当初から持氏とは袂を分かっており、その姿勢は変わっていない。その結果、結城方は鎌倉街道確保のために小山攻めを敢行したのではなかろうか。岩松勢らは小山城の「当所宿城」に攻めかかり合戦となった。これを迎え撃った小山小四郎持政は「敵数輩令被疵、追払彼等、得勝利之」(永享十二年五月三日「足利義教感状」『松平基則氏所蔵文書』室:3170)し、とくに「被官人河尻助三郎」の戦功が際立っていたようである。「宿城」がどこに位置していたのかは定かではないが、JR小山駅西側あたりか。
結城直光―――結城基光―+―小山泰朝――+―小山満泰―――小山持政―+―小山氏郷
(中務大輔) (弾正少弼)|(下野守) |(下野守) (左馬頭) |(小四郎)
∥ | | |
∥ +―山川氏義 +―勝賢寺 +―女子
∥ (兵部太輔) |(生源寺、松源寺) ∥――――――宇都宮明綱
∥ | ∥
∥ +―小山某――――九郎 宇都宮等綱
∥ |(大膳大夫) (下野守)
∥ |
∥ +―結城氏朝
∥ |(中務大輔)
∥ |
∥ +―山川基義―――山川景胤―――小山成長
∥ (下総三郎) (小四郎)
∥
∥――――――結城満広====結城氏朝―――結城持朝
∥ (中務少輔) (中務大輔) (七郎光久)
小山氏政―+―女子
(左馬助) |
|
+―小山義政―+―小山若犬丸
(下野守) |
|
+=小山泰朝――――小山満泰―――小山持政
|(下野守) (下野守) (左馬頭)
|
+―女子
∥
長尾景仲
(左衛門尉)
 |
| 中久喜城と西仁連川 |
翌4月18日、安王丸は結城から西仁連川に囲まれた要害「中岫(小山市中久喜)」(享徳4(1455)年2月筑波潤朝軍忠状案写(「古証文二」神奈川県史料6187)に移った。岩松持国、桃井憲義、結城勢による小山祇園城の攻略を前提に、いち早く祇園城へ入って鎌倉街道を占拠し、小山一帯の制圧を目論んだものと推測される。
ところがこの直後、結城勢の一角「長沼淡路守」が「企陰謀、在所江引込」むという事件が起こった。
長沼淡路守家は小山氏、結城氏の同族で伝統的に鎌倉公方に忠節を尽くしてきた家柄であり、結城勢にとって長沼淡路守の離反は想定外の出来事だったと推測される。淡路守氏秀は一族の宗家たる小山持政の調略を受けたのかもしれないが、長沼の離反は結城勢の兵力減退となる上に、長沼勢への対応のために小山攻めの兵力を割く必要に迫られたのである。まさに取り返しのつかない痛恨事であった。
長沼氏秀は在所の長沼庄(真岡市長沼)の長沼館に立て籠もり、その対応のために結城方は小山攻めの主力を担う「桃井、岩松」の軍勢(の一部か)、筑波別当勢を長沼へ遣わしており、「不廻時日及度々合戦」をしている。この長沼攻めは後日、長沼氏秀が京勢奉行の仙波常陸介に話したものとして「既愚身要害僅事候、彼御旗殊向、桃井、岩松以下馳向」い、「七十日被責候、甲三十計上下百余館籠、度々合戦」し、「数百人御敵討死仕候」(永享十二年十月十五日「仙波常陸介書状写」『安得虎子』)と、さしたる要害でもない長沼館に百余名程で籠り、七十日にわたって攻撃を受けながら支え切り、数百人を討ち取ったという。また、寄手の筑波勢は「第二度之合戦ニ玄朝三ヶ所被疵、同名彦八郎并家人小倉新兵衛、同四郎左衛門尉、肥田太郎次郎手負、伊勢守持重家人アマノゝ与四郎被疵、帰本陣死去仕、定朝、持重、朝範、数ヶ所被疵及半死半生、玄朝父子者、以御評儀留城中奉守護」と、法眼玄朝、彦八郎、伊勢守持重、熊野別当朝範、美濃守定朝ら筑波別当一族や家人らは多くが戦傷し、結城城の留守とされている。
●長沼氏系図(『皆川系図』皆川又太郎氏所蔵系図、『尊卑分脈』、『前淡路守宗秀譲状』:『栃木県史』所収)
小山政光―+―小山朝政…【小山氏】 +―長沼宗員―+―長沼宗長―+―長沼宗景―――長沼顕宗
(下野大掾)|(下野守) |(左衛門尉)|(淡路守) |(三河権守) (三河又四郎)
| | | |
+―長沼宗政―+―長沼時宗―+―筥室時村 | +―長沼秀長
|(淡路守) |(淡路守) |(十郎) | (五郎左衛門尉)
| | | |
| | | +―長沼宗義―+―長沼宗広
| | | |(五郎) |(遠江権守)
| | | | |
| | | | +―長沼長義
| | | | (淡路彦四郎)
| | | |
| | | +―長沼宗村―+―長沼宗俊―――長沼秀俊――長沼宗則――長沼宗常
| | | |(淡路八郎)|(淡路四郎) (四郎) (又四郎) (次郎)
| | | | |
| | | +―長沼宗郷 +―長沼宗実
| | | (淡路九郎)|(淡路五郎)
| | | |
| | | +―長沼宗胤
| | | |(淡路十郎)
| | | |
| | | +―長沼実村
| | | (淡路八郎)
| | |
| | +―長沼宗泰―+―長沼宗秀―+―長沼秀行―+―長沼宗于
| | (左衛門尉)|(淡路守) |(越前権守)|(淡路守)
| | | | |
| | +―長沼宗員 +―長沼宗親 +―長沼秀直――長沼義秀――長沼満秀―+
| | |(左衛門尉)|(駿河権守) (淡路守) (淡路守) (五郎) |
| | | | |
| +―大曾政泰―――大曾政頼 +―長沼宗村 +―長沼宗実―+―女子 |
| |(左衛門尉) (三郎) (安芸権守)|(長犬) |
| | | |
| | +―長沼朝実 |
| | (安芸五郎) |
| | |
| +―長沼頼次 +―――――――――――――――――――――――――+
| |(彦四郎入道教信) |
| | |
| +―長沼頼宗―――長沼宗次 +―長沼憲秀―長沼秀光―+―金阿弥陀仏
| |(四郎) (孫四郎) (淡路守)(紀伊守) |
| | |
| +―得行光秀 +―栄賢法師
| (弥四郎) |
| |
+―結城朝光…【結城氏】 +―長沼宗衡――長沼宗隅
(上野介) |(円等) (桑翁正棟)
|
+―智光院光泉
|(中納言)
|
+―長沼秀宗――長沼氏秀――皆川宗成
(淡路守) (淡路守) (宮内少輔)
これらから、結城勢は同族小山氏や長沼氏との戦いに消極的であったのか、安王丸麾下の人々が烏合の衆だったのか、個人的には勇猛であっても全体的な士気の高揚は感じられず、結果として結城・安王丸勢は小山城の攻略に失敗、鎌倉への「近日可還著」は事実上不可能となり、結城へ撤退するほかなかったのであろう。
一方、京勢は関東国人へ盛んに軍勢催促しており、4月16日「新田岩松治部大輔(岩松長純)」に出兵を命じ(永享十二年四月十六日「細川持之奉書写」『武家書簡乾』室:3169)、4月19日(『鎌倉持氏記』)には「武庫様(上杉清方)」が結城攻めの大将として鎌倉を「可有御進発」(永享十二年四月十一日「長尾芳伝書状写」『烟田文書』室:3167)、さらに「(上杉)持朝」も結城へ出立した(『鎌倉持氏記』)。これに伴い手薄となる鎌倉には「鎌倉警固三浦時高、自四月廿日当参、上杉中務少輔持房同警固」(『鎌倉持氏記』)と、4月20日に三浦介時高が鎌倉に参じ、5月1日に「帯御旗」て鎌倉に京都から下着した上杉中務少輔持房が時高とともに鎌倉警衛を担った。
こうした中、劣勢を挽回するべく、安王丸は5月10日、「石川泉中務少輔(石川持光)」に再度文書を送達し、味方となるよう催促し、「委細左衞門督可達候」とおり、桃井左衛門督憲義の副状が付けられている。結城氏朝もまた安王丸の「御教書」に応じて味方となるよう書状を遣わしている。
●永享12(1440)年5月10日「足利安王丸軍勢催促状」(『石川文書』室:3173)
●永享12(1440)年5月10日「桃井憲義副状」(『石川文書』室:3174)
●永享12(1440)年5月10日「結城氏朝書状」(『石川文書』室:3175)
当時、石川持光は南奥州から北関東の京勢旗頭であった「佐々河殿」満直と激しく敵対しており、「今年、佐々河合戦ト云々未詳」(『異本塔寺長帳』)とあるように、永享12(1440)年中には篠川御所辺りで合戦が起こっていた。かつては篠川殿に従属していた仙道諸郡の国人らは篠川殿から離反しており、6月下旬頃「郡々面々御忠節」により、佐々河殿満直は討死を遂げたとみられる(永享十二年七月十日「沙弥禅元書状」『石川家文書』 室:3186)。
この篠川殿滅亡の報は、7月7、8日頃に結城城に届けられており、7月8日に安王丸が「泉中務少輔殿(石川持光)」へ送達した感状(永享十二年七月八日「足利安王丸感状」『石川家文書』室:3186)に「今度自最前致忠節之条、尤以神妙也」と示されている。
●永享12(1440)年7月8日「足利安王丸感状」(『石川文書』室:3184)
●永享12(1440)年7月8日「桃井憲義副状」(『石川文書』室:3185)
●永享12(1440)年7月11日「結城氏朝副状」(『石川文書』室:3187)
故二橋御所満家(元稲村御所)の元被官人と推測される「沙弥禅元」から石川持光に宛てられた書状では、「就佐々河 上様御事、委細承候、中々是非を不及申候、面々御忠節目出候」(永享十二年七月十日「禅元書状」『石川家文書』室:3184)と佐々河満直の追討を賞賛している。なお、文書中に見える「二橋 上様御跡続」とは、おそらく春王丸であろう。故義久の次弟・成潤(庶子)はすでに勝長寿院主であり、その弟の春王丸が奥州稲村御所満貞の嗣子と定められ、「悉御静謐候者、定奥 上より両国へ可被成御教書候」だったのだろう。
●永享12(1440)年7月10日「沙弥禅元書状」(『石川文書』室:3186)
一方、伊豆を出て山内庄に逗留していた前管領憲実入道は、5月初旬頃、結城攻めのために鎌倉を発って「長尾郷暫令座」(栄区長尾台)したのち、5月11日に「移神奈河給」(神奈川区鶴屋町付近か)った。その後、二か月程この地に留まっている。
6月7日には、上野守護代大石儀重の軍勢が世良田、足利を経由して6月9日に旧持氏与党が籠る高橋郷野田要害に到着。「堀際陣取処、同夜城中仁等没落間、雑色国府野美濃守、同舎弟等誅伐」(『鎌倉持氏記』)し、野田要害は脆くも陥落した。
その後、7月1日には「一色伊予守」が「引率多数軍兵」して「越利根川、乱入武蔵国須賀土佐入道在所、令放火、須賀家人数輩討死仕」(『鎌倉持氏記』)した。おそらく野田要害の落人も合流していたのだろう。翌7月2日「庁鼻性順、長尾景仲馳向、於其日成田館、伊予守終日度々合戦」(『鎌倉持氏記』)したという。 一色伊予守が利根川のどこを渡河したのかは定かではないが、須賀土佐入道の在所(行田市須加か)を放火して被官人と合戦していることから、木戸氏の所領のあった邑楽郡東方(邑楽郡明和町江口付近歟)から渡河したのだろう。
須賀家から早馬で急報を受けた庁鼻上杉性順、長尾景仲は、一色伊予守が籠っているであろう成田館へ馳せ向かい、7月2日に「成田館(熊谷市上之)」で一色伊予守勢と激しく交戦した(『鎌倉持氏記』)。成田館での合戦は7月4日にも行われているが、上杉性順勢には「入西毛呂三河守、豊嶋清方被官人々計至極無勢也」と、味方に加わる者が少なく、一方で一色伊与守には「北一揆大略伊与守同心間、河向勢如雲霞也」という有様だった(『鎌倉持氏記』)。
この成田館での合戦は一色伊予守勢が勝利したのだろう。一色伊予守は「伊与守誇多勢馳渡荒河、村岡河原打上、矢合及太刀打事移既時剋」と、多勢に任せて荒川を馳せ渡り、「村岡河原(熊谷市村岡)」で激しく矢合わせとなった。ところが、どういうわけか数に勝る「伊与守」が「被切崩訖」という。二度の大河渡河と連戦の疲れがでていたのかもしれない。一色勢は潰走し「被討漏人々、小江山引行間、追懸所々討亡間、伊与守馬具足捨行方不知落」と、村岡から南西の「小江山」(熊谷市小江川)へと追い落とされ、その道すがらでも上杉・長尾勢の追撃に一色勢は次々に討たれていった。一色伊予守は乗馬や具足までもかなぐり捨てて逃亡し、行方知れずとなった。この合戦以降、「性順、長尾、青鳥在陣、持朝、岩付陣」といい、上杉性順・長尾景仲は青鳥郷(東松山市下青鳥)に、上杉持朝は岩付にそれぞれ陣をとった。
一色伊予守は鎌倉を逐電後、どこに身を潜めていたかは定かではないが、伊予守挙兵の地が新田岩松持国の所領に近接している事から、岩松氏を拠っていた可能性もあろう。
●上野国新田庄嘉応年中目録(持国当知行分)
| 上野国 | 犬間郷 | 太田市 | 岩松町 |
| 太田郷 | 太田市(旧大字太田) | ||
| 田島郷 | 上田島町、下田島町 | ||
| 東牛沢郷 | 牛沢町 | ||
| 額戸郷 | 強戸町 | ||
| 成墓郷 | 成塚町 | ||
| 西牛沢郷 | 牛沢町 | ||
|
浜田郷 (彼郷之内有桃井方) |
下浜田町、東矢島町、南矢島町 | ||
| 大島郷 | 大島町、八幡町、西本町 | ||
| 由良郷 | 由良町 | ||
| 高林郷 | 高林北町、高林東町、高林南町、高林西町 | ||
| 村田郷 | 新田村田町 | ||
| 岩瀬川郷 | 岩瀬川町 | ||
| 尾次島郷 | 尾島町 | ||
| 千歳郷 | 岩松町内 | ||
| 堀口郷 | 堀口町 | ||
| 多古宇郷 | 新田高尾町 | ||
| 二子墓郷(東光寺領) | 新野町 | ||
| 鶴留田郷(慶雲寺領) | 鶴生田町 | ||
| 藪塚郷半分 | 大原町、藪塚町 | ||
| 鳥山郷四分三 | 鳥山町、鳥山上町、鳥山中町、鳥山下町 | ||
| 鹿田郷 | みどり市 | 笠懸町鹿 | |
| 阿佐見郷半分 | 笠懸町阿左美 | ||
| 今井郷 | 伊勢崎市 | 境西今井 | |
| 武蔵国 | 石塚郷 | 深谷市 | 石塚 |
| 小島郷 | 熊谷市 | 妻沼小島 |
7月7日には、「新田岩松方」が大将として「東方江出陣」し、筑波勢の「持重、朝範」が「令供奉、致宿直警固」している(享徳4(1455)年2月筑波潤朝軍忠状案写(「古証文二」神奈川県史料6187)。東方とは結城から見て東とみられることから常陸国であろう。7月10日、結城城方と「行方常陸入道」の軍勢が「長堀原合戦(ひたちなか市長堀町)」で激突しており(嘉吉元年四月廿一日「細川持之書状」『鳥名木文書』室:3245)、このときの結城方が岩松持国であった可能性があろう。「名越殿」こと「佐竹右京大夫(佐竹義人)」(永享十三年六月三日「中条持家書状」『猿投神社文書』室:3261)は、「結城殿」とともに安王丸方に属していることから(「白川氏朝上洛進物次第」『白河家文書』室:3166)、彼との連携を図るべく進出したか。
永享12(1440)年7月5日、京都は奥州石川氏に対し、「私之確執」からの「対白川被致合戦」を中止し、以前から命じている「既関東出陣事、度々被仰出候」ことを実行して「令発向野州」するよう命じている(永享十二年七月五日「細川持之書状」『板橋文書』室:3181)。
●永享12(1440)年7月5日「細川持之書状」(『板橋文書』室:3181)
このころ、京都は結城城の攻略を至上命題とする断固たる決意で、軍勢催促や軍事的な指図など積極的に活動していた。これを受ける形で、4月19日に鎌倉を出立した「清方、持朝」が「経在々所々」て7月29日に「結城着陣」し、「奉公外様并武州上野一揆、越後、信濃、海道御勢等不遑詮」(『鎌倉持氏記』)という。同じく7月29日、「小山小四郎」が「於結城館致合戦、被官人数輩被疵」(永享十二年八月十七日「足利義教御内書写」『小山氏文書』室:3192)しているが、すでに結城城攻めが始まっていたか、上杉清方着陣を以って結城城攻めが敢行されたかは定かではない。
| 結城城からの位置 | 諸陣 | 門 |
| 坤(南西) | (大将)上杉兵庫頭清方 | 大手口(南西) |
| 西 | 上野一揆 | 西口(西) |
| 乾(北西) | (安房勢)上杉修理大夫持朝 | |
| 坎(北) |
(京勢)斯波民部大輔持種 宇都宮右馬頭等網 土岐刑部少輔慶益 上杉治部少輔教朝(上杉禅秀子) 小田讃岐守持家 北條駿河守 |
北口(北) |
| 艮(北東) | ||
| 震(東) |
(越後勢)長尾因幡守実景 (信濃勢)小笠原修理大夫政康入道 (甲斐勢)武田刑部大輔信重入道 |
大谷瀬口(東) |
| 巽(南東) | 福厳寺口(南東) | |
| 南 |
岩松三河守(治部大輔長純か) 小山小四郎持政 武蔵一揆 (上総、下総勢)千葉介胤直 |
8月3日には、上杉清方は「常州法雲寺并正受庵領同国関郡水飼戸郷、同久下田、同稲荷荒野、同伊佐郡内小節木等」に「軍勢甲乙人等可致濫妨狼藉」を禁ずる禁制を出しており、結城城の南方「関郡水飼戸郷(結城市水海道)」「同久下田(結城郡八千代町久下田)」や、東方の「同稲荷荒野(筑西市稲荷)」「同伊佐郡内小節木(筑西市子思儀)」などにも軍勢が展開して結城城を遠巻きに囲んでいた様子がうかがえる。
前管領憲実入道長棟もまた7月8日に「立神奈河」ち、「経在々所々、野本、唐子両所逗留廿余日」と「野本(東松山市上野本)」「唐子(東松山市上唐子)」を経て、8月9日「小山庄祇薗城着陣」した。こうして、8月初旬には、総大将の憲実入道は小山祇薗城を本営とし、結城攻めの実戦指揮をとる弟の兵庫頭清方ならびに一族の修理大夫持朝は結城城下に本陣を据える陣構えが固まっている。南西に陣する長尾因幡守実景は越後勢を率いる大将軍だが、清方の麾下にあった。
 |
| 結城合戦想像図(配陣図) |
9月6日、新田岩松持国とともに常陸国へ赴いていた筑波氏の「持重、朝範」は、安王丸の「以 上意城中江罷帰」っており、結城城に残る軍勢は諸方へ回す余裕はなくなってきていたと想定される。ただ、田川の流れと泥湿地に囲まれ、広い外城に守られた結城城は、容易に落ちる城ではなかった。また、広大な城域のため「諸軍勢雖取廻御分内等、依広通路等相残候歟」(永享十二年九月八日「細川持之書状案」『足利将軍御内書并奉書留』室:3199)というように、寄手が囲み切れないために抜道が残っている可能性もあり、実際に筑波持重らのように城外から城内へ入るルートも残っていた。こうしたルートは兵粮の運び込みにも用いられていた可能性があり、「及夜陰潜入兵粮之由」も京都に伝わっていた。義教はこうした抜穴は徹底的に塞ぎぐことが肝要であるとして「諸陣微合同時漸々取寄陣、城内縮候者、自通路可止之由」ならびに「自城中成無人数候者、兵粮早速不可廻候、所詮僧俗男女等一向不可出候」という兵糧攻を敢行するよう、仙波常陸介を通じて「是等之条々陣中事、依時宜可令申談之由候」(永享十二年九月八日「細川持之書状案」『足利将軍御内書并奉書留』室:3199)を命じている。
 |
| 福厳寺口から東(寄手側)を見る (眼前一帯が泥濘または川と思われる) |
9月中旬には越後国の「長尾因幡守(長尾実景)」の手勢が「於結城館福厳寺口、越後国人等致合戦、討死手負及数輩」という南東城門付近で激戦があり、10月5日には、結城城の北西口と思われる「玉岡(結城市結城)」で結城勢が「京勢と合戦仕」し、筑波玄朝法眼長子の童体・筑波千手丸が負傷している(享徳4(1455)年2月筑波潤朝軍忠状案写(「古証文二」神奈川県史料6187)。10月13日にも長尾実景の越後勢が「於結城館重致合戦」し「被官人数輩被疵」ている(永享十二年十一月廿一日「足利義教御内書」『上杉家文書』室:3212)。これは福厳寺口での攻防であろう。
結城城は「東西十余町、南北十六七町計歟」(『鎌倉持氏記』)と見えるが、堀内の中心部は東西五町、南北七町程である。城には「南西外城」があり、外城と「堀内城」の間には「大堀」が掘られ、「東切崖田河」があった。寄手の各陣所から城までは三町余り、籠城方はその間に「大堀二重鐫、塗帰壁」って防御を固めており、寄手は結城城の堅い守りに阻まれ、散発的な戦闘は行われるもののなかなか効果的な戦果を得られず、膠着状態の中で、総攻撃をしかけるか否か、兵庫頭清方は京勢奉行人の仙波常陸介を招いて「結城館被責哉否事」を「諸陣可申談」ことを指示。これを請けた仙波常陸介は、清方被官人の「大田駿河守、長南駿河守同道」の上で「各々意見於承」た(『鎌倉持氏記』所収 永享十二年十月十五日「仙波常陸介註進状」)。
| 大将 | 意見 | 要旨 |
| 上杉修理大夫持朝 | 被取寄攻陣、城中時宜可御覧歟、意見雖被申候、有延々無其計略、自然不慮題目出来候者、不可然候、其上諸軍勢雖着陣候、外城計未不手懸事、所存外存候、近日被責候者、可然由被申候 | 清方殿も攻城の様子をご覧になるべきだろう。諸勢は外城にすら攻めようともしておらず、近々攻めるのが当然だ。 |
| 宇都宮右馬頭等綱 | 結城事、我々如前々一族被官同心之儀候者、以一力可被計略処、近年無力申、彼御息様依有御座当城如此候、且他国御勢御粉骨事、無面目次第候、仍城危可申候時節、何期可被待哉、可用立人体、如何様方便可致扶持哉、落行雑人共至、不可立其用、然有御延引、自然而就他国凶事出来候者、不可然間、急速可被責由被申候 | 結城方には一族や被官が同心しており、我等のみで対処すべきであるが、御息様の前には為す術ない。他国の御勢には本当に申し訳ない。先延ばしで他国に凶事が起こってはよろしくなく、城は早々に攻めるべきだろう。 |
| 小山小四郎持政 | 宇都宮同前候 | 宇都宮等綱と同意見 |
| 千葉介胤直 | 大略宇都宮同前候、 上意于落居如何様子細候哉被仰下、帰壁塗、外堀被堀候事、可討責至者、当日其用意可然哉由被申候 | 宇都宮等綱と同意見。将軍からも未だに落城できないのはいかなる子細かとのことで、城壁を堅固に、外堀も掘られたため延引していることを伝えている。今日にも攻める用意がある。 |
| 武田刑部大輔信重入道 | 甲州事、御敵現形事候、去程少々不請暇罷下人等候、当勢薄時者不可然候哉、毎事申談候間、同心可致忠節候由被申候 | 甲斐国で御敵が挙兵したので、少し兵を帰したた。彼らが戻るまでは寄手に加わりがたいか。 |
| 小笠原大膳大夫政康入道 | 尤近々被責事可然存候、乍去是程大城、御息様以下宗徒者共数輩館籠候、哀々、早々可責承度由申間、其故者、自諸方落集人体兵粮限候間、不落内可被責事肝要候歟、然走忽被責者、用害習自然而責損、手負以下候者、古河山河其外御敵等出張候者、陣中野心族可得力候間、不可然候、然者有不覚事者、短慮可為歟、信州甲州大井逸見以下事者、何程事可仕候哉、縦五百騎千騎出張候共、此御勢以退治可輙候、入道於京都此事被仰出、自罷下時当城無落居候者、再可帰国仕共不存候、如何様国難儀子細候共、一騎不帰候、当城落居候者、一騎罷帰候者、可輙入国候由、思定候間、此城無落居候程、不存余儀候、既被取寄近陣、時々伺城被詰候者、兵粮以下限不損御方、御敵輙可有御退治候間、近々可討責意見難申候、但衆儀候者、其又最前可致忠節由、被申候 | すぐに攻めるべきだ。ただ、これだけ大きな城で、御息様らをはじめとする人々が立て籠もっている。早々に攻めたい。諸方から人々が集まるものの兵粮には限りがあり、彼らが城から落ちる前に攻めることが大事だ。ただ、考えなしに攻めれば攻め損じて負傷者が出るだろう。それによって古河や山川、そのほかの御敵が寄せて、陣中で秘かに叛心を持つ輩が妄動するかもしれない。短慮に攻めず、時々軽く攻めるなどし続ければ、兵粮も御方も被害を出さずに、敵を退治できよう。すぐに討滅できるとは申し難い。ただ、衆議には従う。 |
| 長尾因幡守実景 | 越後国御勢難渋之族候間、依其於路次逗留仕、送日数、結句致触出着陣遅々仕、于今当城廻不及見懸、而意見申事其憚候共、凡大城事申、彼御息様有御座、名字面々走籠、片時早々被責、為行御勢候処、走忽可討攻事、万一合戦凶候時、上州一揆等任雅意、定而三分一、二可罷帰候、然者陣中有言而、重被責事、可為大儀候哉、凡当城之体、兵粮限候由、其聞候、落人等或見 而候、近陣厚被取寄候者、廿日、卅日内城中時宜可見得候、他国事者不存知、越州御勢愚身在陣程、二年三年候共、一騎不可返候、当年内次第御勢可重候間、少御延引候者、可然歟之由申候、大略小笠原同前候 | 越後勢は結城攻めのために国を出ることを渋る人々があり、着陣が遅れた。よくわからぬままに意見を述べることは差し控えるが、結城城は大城で御息様も御座し、大名な人々も籠っていて、考えなしに攻めて万が一敗北した場合には、上州一揆などは軍規など護らず、三分の一、二は離陣してしまうだろう。そうなれば、重ねて攻めることは難しくなってしまう。噂では結城城の兵粮は限りがあるという。しっかり城を取り囲み、城抜けを防いでいれば、二十、三十日もすれば降参してこよう。 |
| 長沼淡路守氏秀 | 数万騎御勢候間、被責候者、外城事可落居由存候、乍去既愚身要害僅事候、彼御旒殊向、桃井岩松以下馳向、七十日被責候、甲三十計上下百余館籠度々合戦、数百人御敵討死仕候、況此用害事者、大城申、思程馳聚者共数千人楯籠候、雖然兵粮無用意間、片時早々可被責事肝要存時分、万一被責候者、城中可得力候歟、当城事案内者事候、取日而今少被延候者、以其内計略子細可出来歟、其上山河以下事申談事候、若相違事候者、彼要害一勢被指向、時宜相計可責由申候 | 御勢は数万騎もいるのだから、攻めれば外城は落とすことができよう。ただ、私の長沼館はさしたる要害でもないが、桃井、岩松勢に七十日もの間攻められながら、百余名ほどで守りながら数百人を討ち取った。ましてやこの結城城のような大城であればいうまでもない。ただ、数千人が立て籠もっていて、兵粮の用意がなく、本来は早々に攻めることが肝要だが、攻めれば城内の士気が上がる可能性もある。私は結城城内を良く知っている。今しばし攻撃を延引して作戦を考えるべきか。山川以下が内通を申し出ているが、もし偽りであれば一勢を差し向け、様子を見ながら攻めるのがよい。 |
| 小田讃岐守持家 北条駿河守 |
大略長沼同前候、雖然無勢事候間、衆儀御同心候者、最前可致忠節由被申候 | 大略は長沼と同じ意見。ただ、無勢であるので衆議に従う。 |
| 上杉治部少輔教朝 土岐刑部少輔慶益 |
此間着陣候間、無案内候、衆儀可為由被申候 | 結城に着陣したばかりで無案内であり、衆議に従う。 |
| 奈須(那須)太郎氏資 | 休息事候、房州、兵庫頭、修理大夫方之任儀候、同者早々討責候者、可然由被申候 | 一旦休み、憲実入道らに任せ、早々に攻めるというなら攻めるべきだ。 |
| 両国一揆 | 諸大将任儀候由申候、如此諸陣意見可承定候由、自兵庫頭方愚身被申候間、馳廻申談旨兵庫頭方申候処、各之儀心得申候、 | 衆議に従うと、兵庫頭清方より仙波常陸介に報告があった。 |
| 愚身(仙波常陸介) | 所詮 上意早々被責候者、可然由、入道之方江可申旨返事候、去十三日、房州方江罷出、此子細具申談候之処、被申者、既当城四方通路絶、取寄詰陣候上者、早々可被責事勿論候、雖然城中時宜能々模人体肝要候間、了簡最中于今延引候、篇目申而不立者、京都様江注進申事大事候、次山河身上事、属長沼申子細候間、先可在陣候由申候処、猶以兎角申題目、如此之計略共候間、疎忽成事有而存候、是等左右共聞定、早々可被責由諸陣可申旨候、 |
将軍の上意は、結城城を早々に攻めることであると憲実入道へ伝えた。去る13日、憲実入道のもとへ出向き、このことを詳細に伝えると、憲実入道は、すでに結城城は四方を取り囲んでおり、早々に攻めることは当然だ。ただ、城中の様子をよく把握することが大事であるため、まだ攻めないのであることを将軍へ注進することが大事だ。 次に山河の件については、長沼に属すと子細を申し立てているので、まずは出頭するよう申し伝えたが、なおも何かと理由をつけて帰参しない。何かの計略で挙兵するかも知れず、このことも踏まえて周囲と相談の上、早々に攻めよと諸陣に申す予定である。 |
| 房州申事、諸陣両篇雖被申候、其内早々一篇調儀被定候者、其段可致註進候、去年於永安寺両三人御警固事候処、彼御方様討漏申方依有而、如此御大篇出来候歟、況大城事候間、堅雖被取巻候、自然而御一人有御忍而御漏候者、猶以可為御大事候間、片時早々被責候者、可然候哉由令申候、罷帰候日限、治定候者、重可致註進、於愚身無油断昼夜走廻候、以此旨可有御披露候、恐惶謹言 | (伊勢貞国への総括か) 憲実入道が言うには、「諸将の意見は、すぐ攻めるべきだ、延引するべきだと両編あるが、なるべく早く意見を統一してその結果をお伝えする。今回の騒乱は、去年永安寺を上杉持朝、千葉介胤直、大石憲儀の三人に警固させたが、『彼御息様(安王丸一人を指すのだろう)』を討ち漏らしたことが原因だ。今回も『御一人』を討ち漏らせば、同じような大事が起こるであろうから、急ぎ攻めることがよい」とのことだ。私が帰陣するまでに方針が決定すれば、重ねて注進する。 |
結局、憲実入道は諸将の意見により、意見の多かった「是城中入兵粮以下止之、又自落城去者共不出、城中疲謀」を採用して総攻撃は控え、持久戦とする方針を固めた。また、清方、持朝、千葉介、土岐の陣前に「組十余丈征楼二三重構前棚」えて、「城攻当日、或可押寄支度」とし、「陣々前毎、城堙草土俵千二千宛用意、連日及矢車」び、さらに「暮毎陣々時声響天地、修羅闘諍争可勝之」と心理戦も行っている。
 |
| 城東側の大谷瀬口方面 |
この陣中において、11月27日、千葉介胤直は結城城南の陣中から伊勢外宮に「為当陣祈祷祓一合」を依頼し、「相馬郡内神役事」については、結城合戦により任命が不可のため「一途落居已後可申付」ことを報告している(永享十二年十一月廿七日「千葉胤直書状案写」『鏑矢伊勢宮方記 上』室:3214)。
その後、11月から12月にかけてはあまり大きな合戦は起こっておらず、12月12日に小山小四郎持政が「於結城館合戦、親類被官人等被疵」(永享十三年正月廿五日「足利義教御内書」『小山文書』室:3225)するものが伝わるのみである。
結城城での合戦はその後も主に南方が中心とみられるが、東の大瀬谷口は田川の流れと泥湿地により攻め口としては機能しないと判断され、南西部の大手口および段丘地の南東部の福厳寺口が主戦場となっていたのだろう。そして、福厳寺口の長尾実景は年明け早々の永享13(1441)年正月1日、結城方を謀って城中に攻め入った。
 |
| 結城城内の堀割 |
永享13(1441)年正月1日、越後勢を率いる長尾因幡守実景は「越後勢、城中をたはかりてせめ入」った(永享十三年正月廿五日「足利義教御内書」『上杉家文書』室:3226)。どのように「たはかった」のかは遺されていないが、元日であることから、戦闘停止の偽装、賀使の派遣などが考えられる。
この正月一日の攻撃も比較的大規模なものだったようで、長尾実景結城城北と福厳寺口での攻撃が記録が残されている。
この合戦では、南・南東方面に布陣する長尾実景の「被官人等被疵」(永享十三年正月廿五日「足利義教御内書」『上杉家文書』室:3226)、実景に従う越後色部氏の「色部遠江守(色気重長)」の「自身并被官人等被働」(永享十三年正月廿五日「足利義教御内書」『古案記録草案』室:3227)、小山小四郎持政の「親類被官人等被疵」(永享十三年正月廿五日「足利義教御内書」『小山文書』室:3225)、新田岩松氏に従っていたとみられる「新田乾沢修理亮」の「被疵」(永享十三年正月廿九日「細川持之奉書写」『武家書簡 乾』室:3227)、千葉介胤直の「於結城致粉骨、別駕親類、被官人、被成下御書、御教書」(嘉吉元年三月十二日「伊勢貞国書状写」『古文書 三』室:3238)がみられる。
●永享13(1441)年3月12日『伊勢貞国書状写』
また、安王丸に属した筑波勢は、9月の玉岡合戦(結城市結城)に加わっているように、主に城北部一帯を警衛していた様子がうかがわれ、正月1日でも筑波千手丸が「於城之丑寅致合戦」(享徳4(1455)年2月筑波潤朝軍忠状案写(「古証文二」神奈川県史料6187)しているように、結城城の館から実城にかけて在陣し、主に北部の京勢と合戦したことがわかる。
 |
| 結城城の北側から結城城を望む |
また、千手丸叔父(玄朝弟)の熊野別当朝範は「如来堂口与甲斐勢致合戦、三ケ所被疵」しているが、「如来堂口」は結城城北口と考えられ、斯波民部少輔持種の手とみられる甲斐勢と合戦している。「惣而於城中数ケ度之合戦」とあることから、正月1日の合戦で、結城城内とくに北部の郭は破られ、城中に寄手が侵入していたことをうかがわせる。
千葉介胤直の陣中にあった「東下総守殿」は、正月1日の結城攻めの注進状を京都へ送っている。彼は将軍義教奉公衆の東氏数とも想定されているが、氏数は嘉吉2(1442)年当時「左衛門尉」に任官中であるため、別人である(下総東氏であろうか)。
正月13日にも「結城館令致合戦」があり、「江戸駿河守」の「被官人等被疵」っている(嘉吉元年二月「足利義教御教書写」『喜多見系図』室:3235)。江戸駿河守は武蔵国国人であり、武蔵一揆の一員であろう。千葉介胤直らとともに結城城南を陣所としており、この合戦もまた福厳寺口を主戦場とする合戦だったと推測される。
こうした戦いの中で、流浪していた常陸国小栗城の旧主家・小栗常陸次郎助重は、2月6日に何処かの城を「出城」し(「小栗文書」『古文書 三』)、「小栗常陸彦次郎降参」した(嘉吉元年三月十二日「伊勢貞国書状写」室:3238)。この「降参」が意味することは不明だが、父の小栗常陸介満重が小栗城を落とされて以来、捲土重来を期して小栗城を奪取すべく、結城攻めの大将の一人・岩松治部少輔長純に繋ぎを付けたことを意味するのかもしれない。小栗助重はかつての小栗満重の乱で小栗城を追われたのちは、「抑佐々川殿様 御祗候之由、承候」(嘉吉元年三月三日「岩松長純書状写」『古文書 三』室:3236)と、篠川殿を頼って奥州へ遁れていたことがわかる。永享12(1440)年6月下旬には篠川殿は滅ぼされているため、その後7か月余り流浪し、いずこかの城(白河氏あたりか)に拠っていたのかもしれない。
岩松長純は小栗助重の「降参」につき、彼が篠川殿のもとにいたことなど、「御忠節段、連々京都へ可致注進候、不可有等閑候」と、京都への注進に便宜を図ることを約束している。同様の注進は千葉介胤直のもとに駐屯していた「東下総守」からも京都へ送られており、3月12日、伊勢貞国から東下総守に「小栗常陸彦次郎降参之事、 上意無子細候、目出候」(嘉吉元年三月十二日「伊勢貞国書状写」『記録御用所本古文書三』60-9「結城市史」第1巻)とあり、将軍義教も小栗助重の参陣を目出度いことと喜んでいる。
2月16日、小栗城に「筑波山衆徒中了達坊栄尊法師、真家民部少輔、小倉新兵衞、其外数輩与佐竹、完戶勢同道仕、栄尊打死仕」と、筑波山衆徒が佐竹右京大夫義憲、宍戸安芸守持里の軍勢とともに攻め寄せているが、小栗助重が小栗城にいたかは不明である。
結城城の合戦は永享13(1441)年正月1日から主に城の南東部で合戦が起こっていたが、全面的な戦いに至ることはなく、矢戦や声による威嚇などが主に行われていた。ただし、元日合戦の時点ですでに結城城内での合戦が行われていることから、城内の曲輪のいくつかはすでに京勢が占拠していたと思われる。その後、四か月程はそのまま経過し、憲実入道は総攻撃を「四月十六日、為定日」し、4月16日卯刻、「八方一同打立」った(『鎌倉持氏記』)。
 |
| 結城城南の低湿地 |
寄手は早くも辰刻には「南西外城責破令乱入」し、南西の外城を占拠する(『鎌倉持氏記』)。同じく辰刻には南東側においても「与越後信濃勢、従辰刻申尾相戦」い、結城方の筑波勢は「玄朝、定朝、持重者、於城中打死仕、家人伊藤勘解由供仕致打死」した。また「朝範、千手丸者數ケ所被疵、自合戦場越後国人サハシノ森ノ大澤仁被成生捕、同月廿日於陳中被截訖」(享徳4(1455)年2月筑波潤朝軍忠状案写(「古証文二」神奈川県史料6187)と、熊野別当朝範と千寿丸は数か所に傷を負い、越後国佐橋庄大沢(柏崎市大沢)の毛利刑部少輔に捕らわれ、4月20日に誅殺されている。なお千寿丸は羽川越中守の手勢に討たれたとの記録もある(『鎌倉持氏記』)。
 |
| 結城城の東切岸 |
しかし、外城と堀内の間は「隔大堀」ており、城内からは「筒木石弓無隙、矢来事如雨足」という有様で、内城に寄せることが叶わなかった。ところが、「移時剋而合戦処、自天中俄大風吹落、外城放炎、飛移堀内城、大家共焼崩」と、突如突風が吹き、外城の炎が城内の家屋に燃え移り大火災を引き起こしたという。これに「城衆失為方、寄手得是力、不顧死生、御方橋成責越々々攻入間、防戦究竟勇士、踏留令討死、又咽煙、失方角、東切岸田河踏入、被取頭者不知其数」と、城内での激しい混戦の末にわずか1日の合戦で落城した。これまでの長滞陣を考えるとあまりに脆いことから、すでに北の実城、本館、南東の東館は落ちていて、大手の外城を攻め落とした大手勢とともに中城に雪崩れ込み、他の口も一気に力攻めを行ったのではなかろうか。逃げる人々は「東切岸田河踏入、被取頭者不知其数」とあるように、東側へ遁れていることから田川と泥濘地のある北東側は攻め口ではなかったことがわかる。
そして、城内では「越後国大将長尾因幡守」が「十二、十三若公」を「生擒申」した(『鎌倉持氏記』)。「氏朝持朝父子、計令春王安王乗女輿脱城」したが、長尾因幡守に捕らわれたという(『結城系図』「松平基則氏旧蔵本」)。因幡守実景はすぐにこの兄弟若公を「乗籠輿、既及御上洛」んでいるが「御有様、可申辟方無」という(『鎌倉持氏記』)。また、「小山大膳大夫息、同舎弟僧等松源寺」もまた「因幡守生擒之」という。小山大膳大夫(広朝とも)、松源寺(勝賢寺、生源寺)は結城氏朝舎兄で、とくに小山大膳大夫は安王丸または春王丸の「御乳父」(『建内記』嘉吉元年六月十八日条)とあり、安王丸のそばにいたと推測される。また、「六宛若君密奉落処、於伊佐庄、小山小四郎生擒申之」とあるように、結城城内にいた六歳の持氏若君は密かに落とされていたが、伊佐庄で小山小四郎持政の手に捕らわれている(『鎌倉持氏記』)。このとき捕らえられた六歳の若君は、のちの雪下殿尊敒または、若宮別当定尊のいずれかに相当しよう。彼は東へ遁れており、結城氏朝と同心していた佐竹右京大夫義憲を頼ろうとしたのだろう。
春王、安王の捕縛を見た氏朝は「此上非可猶預」と、「氏朝、持朝、三郎光義、駿河守朝祐、八郎久朝、七郎二郎及今川式部丞、木戸左近将監、宇都宮伊予守、小山、桃井、高岡、小笠原等四百余人、一志而出戦于追手」と、大手より出撃して寄手に突撃した。これに寄手はたまらず支え切れずに退くが、すぐに大軍を以て反転し、「高岡、小山討死、小笠原但馬守被疵而自殺、其郎従四十六人同死」という(『結城系図』「松平基則氏旧蔵本」)。氏朝らはいったん城内に退いて休息をとるが、ここに「土岐刑部少輔、北條駿河守、将三千余兵進攻」した(『結城系図』「松平基則氏旧蔵本」)。土岐刑部少輔(土岐慶益)、北条駿河守は結城城北を担当しているが、外城の攻落を以て西側に回ったものか。
この土岐・北条勢の攻撃に「氏朝力戦」し、「土岐、北条被疵退去」するが、ここに「上杉持朝軍士六千余進攻戦」し、「城兵百余戦死」し、「残兵僅五十三人」にまで討ち減らされていたという(『結城系図』「松平基則氏旧蔵本」)。氏朝は決死の「奮撃数十回」したことで「寄手退屈、射遠矢不能近」と、直接当たって損害を被ることを避けた。この遠矢による攻撃により「結城駿河守朝祐、中矢倒伏」たところに、「寺尾弥七郎獲其首」った(『結城系図』「松平基則氏旧蔵本」)。ただ、結城朝祐は「千秋民部少輔(千秋季貞)」の手勢に討たれたともされる(『鎌倉持氏記』)。寺尾弥七郎が千秋民部少輔季貞(熱田大宮司)の被官であった可能性もあるが、上杉清方家人中にも寺尾氏があり、不明である。
このほか、「桃井刑部太輔」は「斬落敵五、六騎、而自殺」し、「宇都宮伊予守」は「所取籠敵十七八騎、而殞命矣」したといい、結城方の大将は次々に討たれていった。このとき城に残っていた「五十三人共悉戦死」したという(『結城系図』「松平基則氏旧蔵本」)。
そして、「氏朝、宇都宮弥五八、里見修理亮以上只成三人奮戦」し、「弥五八、撃殺播磨国住人印南平太員近者」したのち、「三人尚撃敵走之」るが、その後「同音唱弥陀名号、自害」したという(『結城系図』「松平基則氏旧蔵本」)。そして「結城中務大輔(氏朝)」は上杉治部少輔教朝の京勢と合戦して自刃したとも(「結城系図」『続群書類従本』)。結城城合戦による死者は、誇張はあるとみられるが「城兵死亡者凡一万人、寄手死亡者二万三千人」という多大の犠牲の末に、結城合戦はここに鎮定された。
 |
 |
| 上杉清方陣所跡(桟敷塚) | 結城氏朝墓(中央) |
●結城合戦首注文写(『鎌倉持氏記』室3243)
| 寄手大将 | 討たれた等結城方 | 被討 生捕 |
生捕後 | 首級 上洛 |
討った等寄手 |
| 兵庫頭清方 |
根本五郎、加茂部加賀守、磯将監、 不知名字(4つ) |
被討 | 大石石見四郎 | ||
| 江戸八郎 | 被討 | 長井六郎 | |||
| 今川式部丞(今川氏広) | 被討 | 上洛 | 白倉周防守 | ||
| 真田 | 被討 | 山県美濃入道 | |||
| 藤 | 被討 | 山口次郎四郎 後藤弾正忠 |
|||
| 結城右馬介 | 被討 | 上洛 | 小串六郎 | ||
| 小笠原但馬入道 | 被討 | 発知平次左衛門 | |||
| 大賀対馬守 | 被討 | 村山越後守 | |||
| 小幡豊前守 | 被討 | 豊島大炊介 | |||
| 香河周防守 | 被討 | 高山越後守 長尾因幡守(長尾実景) |
|||
| 大城 | 被討 | 倉俣左近将監 | |||
| 不知名字 | 被討 | 小幡三河守 | |||
| 八椚 | 被討 | 後藤弾正忠 | |||
| 不知名字 | 被討 | 山県左京亮 那波内匠介 |
|||
| 不知名字 | 被討 | 土岐原修理亮(土岐原景秀) | |||
| 不知名字 | 被討 | 岡見大炊助 | |||
| 大蔵民部丞 | 被討 | 大石源左衛門尉(大石憲重) | |||
| 寺岡左近将監 | 生捕 | 不明 | 長尾新五郎 | ||
| 不知名字 | 被討 | 和田隼人佐 | |||
|
【古河城】 慈光寺井上坊、吾那次郎、 高倉(野田右馬助家人) |
被討 | 田島太郎左衛門尉 | |||
|
【椎木城】 中谷 |
被討 | 入野出羽守 | |||
| 上野一揆 | 木戸左近将監 | 被討 | 上洛 | 高山宮内少輔 | |
| 比楽遠江守 | 被討 | 高山宮内少輔 | |||
| 筑波法眼(筑波玄朝) | 被討 | 赤堀左馬助 | |||
| 筑波伊勢守(筑波持重) | 被討 | 高田越前守 | |||
| 小河常陸介 | 被討 | 和田備前守 | |||
| 不知名字 | 被討 | 和田八郎 | |||
| 桃井僧(桃井左衛門督憲義伯父) | 被討 | 和田左京亮 大類中務丞 |
|||
| 不知名字 | 被討 | 倉賀野左衛門尉 | |||
| 不知名字 | 被討 | 寺尾上総入道 寺尾右馬助 |
|||
| 不知名字 | 被討 | 長野周防守 長野宮内少輔 |
|||
| 多賀谷彦太郎、臼井五郎 | 被討 | 長野左馬介 | |||
| 不知名字 | 被討 | 諏訪但馬守 | |||
| 筑波(美濃守定朝カ) | 被討 | 一宮駿河守 | |||
| 神沢 | 被討 | 一宮修理亮 | |||
| 不知名字 | 被討 | 倉賀野五郎 | |||
| 不知名字 | 被討 | 発智上総三郎 | |||
| 大繩孫三郎 | 被討 | 那波大炊介 那波左京亮 |
|||
| 大森六郎 | 被討 | 那波刑部少輔入道 | |||
| 玉井 | 被討 | 沼田上野三郎 | |||
| 不知名字 | 被討 | 小林山城守 | |||
| 不知名字 | 被討 | 綿貫越後守 | |||
| 不知名字 | 被討 | 綿貫多利尻丸 綿貫亀房丸 |
|||
| 小田讃岐守 (小田持家) |
原木掃部介、金井伯耆守、野與、 不知名字(2つ) |
被討 | |||
| 土岐刑部少輔 (土岐憲益) |
前宇都宮伊予守(宇都宮家綱) | 被討 | 上洛 | ||
|
篠田山城守、伊与部中務丞、 飯塚勘解由、高垣二郎、 加園家人、淡河家人、 不知名字(4つ) |
被討 | ||||
| 竜崎右京亮 | 生捕 | 不明 | |||
|
神山三河守(原木掃部助家人) 関十郎左衛門尉(原木掃部助家人) |
生捕 | 誅殺 | |||
|
高知尾隼人助(竜崎右京亮家人) 後藤五郎左衛門尉(竜崎右京亮家人) 高田大夫新発(竜崎右京亮家人) |
生捕 | 赦免 | |||
| 小山小四郎 (小山持政) |
小山九郎(小山大膳大夫息) | 被討 | 上洛 | ||
|
小笠原越後守、二階堂左衛門尉、 若菜安芸守子僧、高橋 |
被討 | ||||
| 上杉治部少輔 (上杉教朝) |
結城中務大輔(結城氏朝) | 自刃 | 上洛 | ||
|
比楽十郎、 加藤尾張守(野田遠江守家人)、 小林出羽守、不知名字 |
被討 | ||||
| 長尾因幡守 (長尾実景) |
桃井刑部少輔 | 被討 | 上洛 | ||
| 香河周防守、不知名字(2つ) | 被討 | 高山越後守 長尾因幡守 |
|||
|
多賀谷、才川伊賀守、矢加井、 矢加井四郎、伊曾野、菊地五郎、 塩谷、蓬田、山田玄蕃、八角兄弟、 孫次郎、臼井、上須、篠木、 阿美次郎、加園将監、酒谷、 藤本入道、栃木、加園修理亮、 高野兵庫介、河島大炊介、 杉山左衛門五郎、明石大炊助 |
生捕 | 誅殺 | |||
| 簗四郎、林五郎 | 生捕 | 誅殺 (山川) |
|||
| 野田讃岐守 |
【古河城】 関弾正、矢島大炊介(野田右馬助家人) |
||||
|
【古河城】 鳩井隼人佐(野田右馬助家人) |
生捕 | 誅殺 | |||
| 千秋民部少輔 (千秋季貞) |
桃井和泉守、 小山大膳大夫息、 結城駿河守(結城朝祐) |
被討 | 上洛 | ||
|
小幡九郎、内田信濃守、 人見次郎左衛門尉、 須釜(結城氏朝家人) |
被討 | ||||
| 武田刑部大輔入道 (武田信重) |
結城七郎(結城持朝)、 結城次郎(結城朝兼)、 桃井修理亮 |
被討 | 上洛 | ||
| 簗田出羽三郎、梶原大和守 | 被討 | ||||
| 中条判官 (中条持家) |
里見修理亮 | 被討 | 上洛 | ||
|
大須賀越後守(大須賀宗幸)、 蘆間刑部少輔、上曾三郎、 水谷大炊介、森戸宮内左衛門尉、 石田、大野左近将監、不知名字 |
被討 | ||||
| 羽川越中守 |
小山大膳大夫息僧、 一色伊予六郎 |
被討 | 上洛 | ||
|
吉田次郎、山田下野守、吉里三郎、 筑波千寿丸(筑波玄朝息童体) |
被討 | ||||
| 人々 | 桃井左京亮 | 被討 | 上洛 | 薬師寺安芸守 | |
| 須俣(舞木家人) | 被討 | 網戸式部丞 | |||
|
長(桃井家人)、 泉大炊助(一色家人) |
被討 | 小幡伊賀守 | |||
| 小栗次郎 | 被討 | 宇都宮右馬頭(宇都宮等綱) | |||
|
籾着坊 秋葉三郎 |
被討 | 北条駿河守 | |||
| 榛谷弥四郎 | 被討 | 禰津伊豆守 | |||
| 不知名字 | 被討 | 武田右馬助(武田信長) | |||
| 師但馬守 | 生捕 | 茂木筑後守家人 | |||
| 稲村下野入道 | 生捕 | 誅殺 | 長沼淡路守(長沼氏秀) | ||
|
筑波法眼弟子(熊野別当朝範)、 根岸弾正忠 |
生捕 | 誅殺 | 森刑部少輔(佐橋毛利氏) |
関東では結城合戦が激しさを増していた中、京都では、南朝方に通じて義教に反旗を翻して挙兵した「大覚寺前門主義昭前大僧正」が、4月8日、「於筑紫奉尋出之有注進」った(『建内記』嘉吉元年四月八日条)。討ち取った旨の注進であり、人々は御祝のため室町殿に群参した。翌4月9日に伝わった話では「先大覚寺殿前大僧正義昭、御年三十八、於九州島津御頸取之、此子細者、大覚寺御落アリテ島津ヲ御憑アリ、上意ニテ討奉ルト申」というもので、すでに島津陸奥守忠国に討たれており、本日「九日京都へ御頸上洛」というものだった(『東寺執行日記』嘉吉元年四月九日条)。
4月10日、「大覚寺前門主御首京着」し、「可有参賀之由、今夕有其沙汰」があったが、「明日於相国寺可有実検」ということで参賀は延引となった(『建内記』嘉吉元年四月十日条)。これは、10日の夜に「於中山宰相中将東隣道場有実検」り、義教は寺の門外に立ち「御首者、兼在道場内」にあった首を「御検知」した。先例では「賊首、於室町殿四面四足門有実検」(『建内記』嘉吉元年四月十日条)とあるように、本来は、室町殿の東西南北いずれかの四足門で「自身立門内給、賊首在門外」って行われるが、今回は「御舎弟首」であることから「兼被置道場、臨彼門外、有御検知歟」(『建内記』嘉吉元年四月十日条)という。ただ、6月の「炎天の時分数日の事なれば、御首そむじ、見知り奉るべきやうなし」(『今川記』)と、すでに容貌も見分けのつかない状態となっており、義教も「彼御首実検之處、不分明」(『建内記』嘉吉元年四月十日条)という。さらに「被召門跡候人長田等、拝見之處、是又不分明之由申之」(『建内記』嘉吉元年四月十日条)という。この首が義昭前大僧正のものかの判断がつかないため、「翌日重早々可参賀之處、無其儀、仍後日有参賀」になったという。ただ、その後、「大覚寺殿御いとおしみをかうぶりし童形参り、なくなく申けるは、先年御口中のいたはりおはしまし、御おくの御歯三つおちける事あり、もしや左様の事もやと、御口の中へ指を入れて見れば、案のごとく一つの首のおくば三つなかりしかば、是ぞ大覚寺殿の御首と人しりける、則御門徒の人々参り集り、御葬礼懇にさたし、色々の法事有しと聞えし」(『今川記』)とあるように、その首の奥歯が義昭前大僧正と同じく三つ落ちていることが判明し、義昭前大僧正の首級と「実事治定之故」(『建内記』嘉吉元年四月十日条)に、4月13日に「今朝可有参賀之由」が通達され、人々は室町殿へ参賀の礼に赴いている(『建内記』嘉吉元年四月十三日条)。同日、義昭前大僧正の首の「荼毘之義」のため、「於嵯峨大覚寺律院不壞化身院事、彼御首茶毘」された(『建内記』嘉吉元年四月十三日条)。
 |
| 小山祇園城の堀 |
嘉吉元(1441)年4月16日、結城城は陥落し、結城合戦は終結した。
翌4月17日、「大将清方、引払結城表帰陣」(『結城系図』「松平基則氏旧蔵本」)と、小山祇園城の本営に戻ったようである。また、長尾因幡守実景は擒とした敵方旗頭の安王丸とその兄春王丸の二人の持氏若公を「乗籠輿、既及御上洛」んでいる(『鎌倉持氏記』)。「春王十三歳、安王十一歳」(『結城系図』「松平基則氏旧蔵本」)といい、「小笠原政康、長尾因幡守豊景(実景)」が「護送之上洛」(『結城系図』「松平基則氏旧蔵本」)という。
結城城の「被責落之由御注進」は京都に「同廿日到来」した(嘉吉元年四月廿六日「細川持之書状案」『足利将軍御内書并奉書留』室:3248)。「武田刑部大輔殿(武田信重入道)」以下の諸将が管領持之に注進しているとみられるが、落城後、わずか四日で京都まで注進が届いていることがわかる。持之はすぐさま将軍義教に披露し、義教は「上意御快然無是非候」という。武田信重入道は「殊随分之者共、於当手被討捕由、以注文御申候、神妙之旨被仰出候、御感之事者追而可被仰候、先頸早々可有御進上候」と、討ち取った結城方主将の注文を送っており、将軍義教もこれを賞して感状の発給を約すとともに、首級を早々に上洛させるよう指示した。武田信重入道勢が討った結城方主将は、結城氏朝の嫡子・結城七郎(結城持朝)と次男・結城次郎(結城朝兼)、桃井修理亮の三名が記録されている(『鎌倉持氏記』)。
その後、4月23日には貞成入道親王にも「関東城一落居之由注進有」(『看聞日記』嘉吉元年四月廿三日条)とあるように、結城落城の報告がもたらされている。「結城被責落、没落云々去十六日事」ことも伝わっている。
持氏子息については、4月25日に伏見に「関東事、結城腹切、若公被腹切、二人ハ生捕之由若君有三人」ことが「夜前注進」(『看聞日記』嘉吉元年四月廿五日条)されている。ここに見える持氏子息は三名あり、「若公」は切腹し、残り二人は生捕となったというものだった。これは『建内記』においても「鎌倉故左兵衛督持氏卿子息三人一人十余歳、切腹、其首可京着也、二人猶少年、被擒可入京也事也」(『建内記』嘉吉元年四月廿八日条)とあるように、最年長の子は切腹したことが伝わっており、他の二人の少年は京都へ上洛させる指示があったことがわかる。
ところが、この「子息達三人之内一人ハ腹切、二人ハ生捕之由注進」は「然而腹切ハ虚説也」であり、「兄十三、被没落之由、後ニ聞」と、十三歳の若君は逃亡しており、「故武将持氏子息十三歳尋出討申之由、只今飛脚到来」(『看聞日記』嘉吉元年五月四日条)とあるように「其人只今求出討申也」という(『看聞日記』嘉吉元年五月四日条)。ただ、この十三歳の若公の首は真っ先に上洛すべきであるにも拘らず上洛することはなく、討たれたこと自体不明である。推測ではあるが、この十三歳の若公は、安王丸が結城城に入る前に結城城に入った「大御堂殿(のちの成潤)」か。『建内記』においては「後聞、一人已自殺、一人生捕、今一人者事注進先了、今一人四歳、不見之處、已尋出之捕了、此注進珍重之由也」(『建内記』嘉吉元年五月四日条)と見え、三名に加えて四歳の若公が捕らえられている旨が報告されている。
結城合戦で取った結城氏朝以下の大将首(『鎌倉持氏記』下表)も上洛の途に就き、4月29日に上洛した(『鎌倉持氏記』)。『鎌倉持氏記』ではその数は十七だが、『看聞日記』では「結城以下首共御実験云々、首廿九、六條河原被懸」(『看聞日記』嘉吉元年五月四日条)、『建内記』では「其数或五十一、或三十余、或二十余」(『建内記』嘉吉元年五月四日条)とあるように、首の数はまちまちであるが、具体的な二十九が実数か。将軍義教5月4日、相国寺での御修法後に室町殿へ還御したのち「賊首御実検」(『建内記』嘉吉元年五月四日条)を行った。首実検は、室町殿の「於門外四足門外也」で執行され、「主人、門下御佇立」し、「侍所参此辺申行」た。義教は「上総国結城首并関東一色首已下済々焉」と「悉有実検」(『建内記』嘉吉元年五月四日条)している。「則被懸六条河原」した(『鎌倉持氏記』)。門については「先々賊首、於室町殿四面四足門有実検」(『建内記』嘉吉元年四月十日条)と、先例で賊首の実検は東西南北の四足門のいずれかで行われており、この実検が行われた門は不明である。
なお、首実験は「五月四日、七日両日御実見」(『鎌倉持氏記』)行われているが、これは、5月4日の首実検後、さらに7日にも「是又東国賊首到来事」によったためである。5月9日、「今度結城已下賊首、先日被懸六條河原、件注文見及之間、続左其後又到来之間、更懸之」(『建内記』嘉吉元年五月九日条)と、7日に到来した首級が六條河原に追加で懸けられた。
これらの中に、持氏の「子息両人」の首級がない事を不審に思った人々もいたようで、万里小路時房は伝聞として「鎌倉故武衞子息両人首、未京着、近日京着之時又可有参賀」と述べている。ただこの日、「今夜又参賀之由人々告示之」が指示されたことから、時房は「鎌倉故持氏卿子息首帰京歟」と推測している(『建内記』嘉吉元年五月四日条)。さらに「鎌倉故持氏卿子息等首、近日可京着、於彼首等者可被懸獄門近衞之由風聞云々、当時雖無儀式、猶可被守旧儀哉、尤可然事也、彼辺民屋計会」(『建内記』嘉吉元年五月九日条)。この時点で持氏の「子息両人(安王、春王)」は籠輿に乗せられて上洛の途次にあり殺害はされていないが、すでに斬刑は決定されていた様子がうかがえる。
●京都に送られた首級(『鎌倉持氏記』)
| 結城中務大輔 | 結城右馬介 | 結城駿河守 | 結城七郎 | 結城次郎 |
| 小山九郎 (小山大膳大夫息) |
小山大膳大夫息 | 小山大膳大夫息僧 | ||
| 桃井刑部少輔 | 桃井和泉守 | 桃井修理亮 | 桃井左京亮 | |
| 里見修理亮 | 一色伊予六郎 | 今川式部丞 | ||
| 前宇都宮伊予守 | 木戸左近将監 |
一方で、結城城は陥落したものの、関東では「余党猶在奥、仍可被攻之由有御沙汰、京勢直可向彼」と、旧持氏与党が奥州(佐竹右京大夫義憲のことであろう)におり、佐竹義憲の追討が命じられたという風聞も伝えている(『建内記』嘉吉元年五月四日条)。
そして、上洛の途路にあった春王丸、安王丸兄弟の一行は、「美濃国垂井道場」で「若君御迎上洛、而両佐々木参」った(『鎌倉持氏記』)。5月4日以前に彼ら兄弟の処断は決定されており、使者として遣わされた六角兵部大輔持綱と京極加賀守高数の「両佐々木」は、5月16日、安王丸、春王丸の兄弟を「夜亥剋、奉害」ったのだった(『鎌倉持氏記』)。
将軍義教は捕らえた持氏遺児をすべて処断し、一子(左馬頭義制)を新たな鎌倉殿として関東へ遣わすことで、長年にわたって続いてきた都鄙対立の歴史に終止符を打ち、「天下無為儀お専被思食」の実現に向けた関東秩序の再構築を目指した可能性が高いだろう。
5月19日、「故鎌倉持氏卿子息首等、京着」(『建内記』嘉吉元年五月十九日条)した。「関東武将息三人生捕上洛、於近江国討申」(『看聞日記』嘉吉元年五月十九日条)とあり、相変わらず情報の錯綜が見える。この首級には、「鎌倉故持氏卿子息首京着之時、令供奉結城ノナニカシトテ、御乳父ト称シ奉付テ京着了、此首実否及拷問、申状之趣不分明云々、又設為実首無疑之由申之云々、其説不同也」と、春王または安王の乳父・小山大膳大夫(結城氏朝舎兄)が供奉していた。将軍義教は春王丸、安王丸兄弟の「首共、於白雲寺御実験」(『看聞日記』嘉吉元年五月十九日条)している。白雲寺がいずれの寺院かは不明だが室町殿はこの寺院に自ら出向いてその実検をしたのであった。ここで「彼首共実験、おさなき人達容顔美麗也、見人誰も拭涙、室町殿も御落涙」(『看聞日記』嘉吉元年五月十九日条)と、十二歳の春王、十一歳の安王の幼い首級を見た人々はみな涙をぬぐい、処断を命じた将軍義教もまた落涙している。
5月24日、将軍義教は「小栗常陸彦次郎殿(小栗助重)」を「結城館攻落之時、致忠節被疵之条、尤被感思食」(嘉吉元年五月廿四日「細川持之奉書写」『記録御用所本 古文書 三』室:3255)と賞している。その2日後の5月26日には、「小田讃岐守」、「北條駿河守」、「鳥山孫三郎」、「小笠原大膳大夫入道(政康)」、「小笠原五郎(宗康)」といった京方諸将へ御内書が発せられた(嘉吉元年五月廿六日「足利義教御内書案」室:3256~3260)。安王らの首実検を経て結城合戦の区切りとし、行賞したのだろう。ただし、「結城殿」と同心していた「名越殿」こと「佐竹右京大夫(佐竹義人)」に降伏する意図は見られず、義教は「結城落居之上者、軈成帰国之思候」していた中条持家ら寄手の人々に5月2日付の御内書で「佐竹右京大夫御対治之事、常州野州之間、於可然陣所、可奉待御一左右之由」(嘉吉元年六月三日「中条持家」『猿投神社文書』室:3261)を命じ、5月20日、御内書が持家のもとに届いている。なお、結城城周辺ではなおも結城氏残党による攻撃が続いていたようで、6月8日、千葉介胤直の麾下とみられる「原入道道盛」が「結城陣」で討死している(『本土寺過去帳』)。
6月14日、「関東召人今夜被刎首云々、小山大膳大夫父子三人」(『看聞日記』嘉吉元年六月十四日条)という。小山大膳大夫(結城氏朝舎兄)はおそらく安王丸の「御乳父」であり、安王らの首級の真贋について「此首実否及拷問」(『建内記』嘉吉元年六月十四日条)が行われ、14日に「於河原被切首了」と、おそらく六条河原にて斬刑に処された(『建内記』嘉吉元年六月十四日条)。
春王、安王の首実検から約一月が経った嘉吉元(1441)年6月24日夕方、雨の中、「赤松彦次郎教康」が主催する「依諸敵御退治嘉礼成渡御、近日人々有経営之故也」のため、「未剋、室町殿渡御彼宿所」した(『建内記』嘉吉元年六月廿四日条)。教康は満祐入道の嫡子である。
赤松教康亭は「西洞院以西、冷泉以南、二条以北(中京区西洞院通夷川下る薬師町)」にあり、義教には「諸大名管領細川右京大夫持之朝臣、畠山左馬助、山名弾正右衛門佐歟、細川讃岐守、大内近日在京参之、京極加賀入道以下諸大名」が御相伴し、席に列した(『建内記』嘉吉元年六月廿四日条)。
赤松邸での酒宴は「一献両三献、猿楽初時分」(『看聞日記』嘉吉元年六月廿五日条)、または「猿楽三番、盃酌五献」(『建内記』嘉吉元年六月廿四日条)とつつがなく進んでいた。義教も相伴の人々も上機嫌であったろう。ところがその後、突然「内方とゝめく」と、館内に荒々しい音が響いた。訝しんだ義教は「何事そ」と周囲に尋ねると、三条実雅卿が「雷鳴歟」などと答えたが、次の瞬間、義教の「御後障子引あけて、武士数輩出て、則公方討申」(『看聞日記』嘉吉元年六月廿五日条)、「開御座後障子、着甲冑武者数十人乱入、奉弑」った(『建内記』嘉吉元年六月廿四日条)。義教は背後から襲われ、為す術なく首を落とされ、四十八歳の生涯を閉じた。
このとき「其時管領已下着座之諸大名、即起座退出、不及報答」(『建内記』嘉吉元年六月廿四日条)と、義教の首が落とされた瞬間をみた管領持之以下の諸大名は、さっと座を立つや、迎え撃つことなく赤松邸から退出した。一報、「左衛門督(権中納言実雅)」は「為御相伴参候之、元来不帯兵具上者無力之処、御前金覆輪太刀礼太刀事也在之、抜件太刀相防」と、とっさに御前の「御引出物進太刀」を抜いて赤松勢の剣撃を受け止めるが、「切払顛倒被切伏」た(『看聞日記』嘉吉元年六月廿五日条)。結局、三条卿は赤松教康らが「悉退散」するまで赤松邸に残っており(赤松は退亭の際に放火している)、その後「左衛門督無力退出」して帰亭した『看聞日記』嘉吉元年六月廿五日条)。三条実雅卿は「彼卿被疵、小耳根股等」と耳などを負傷したようであるが、全体として大きな傷は負わなかったようである。
このほか「近習輩細川下野守、山名中務大輔熈貴、散々振舞」ったが、「中務大輔、当座止命、下野守被打落腕、被扶彼子退出了、走衆遠山并下野守、被疵帰家死去」と、山名熈貴は討死、細川持春は腕を落とされて退出し、「走衆」「走手」の土岐遠山某は帰亭後に死亡した。また、「大内介、京極加賀入道」は「抜刀防戦」(『建内記』嘉吉元年六月廿四日条)し、「京極加賀入道」は討死、「大内等、腰刀計ニて雖振舞、不及敵取、手負て引退」した(『看聞日記』嘉吉元年六月廿五日条)。
●赤松教康亭で死傷、逃走した人々
| 公方(足利義教) | 将軍 | 討死 |
| 管領(細川持之) | 管領 | 逃走 |
| 細川讃岐守(細川持常) | 逃走 | |
| 一色五郎(一色教親) | 逃走 | |
| 赤松伊豆守(赤松貞村) | 逃走 | |
| 山名右衛門佐(山名持豊) | 逃走か(記録なし) | |
| 左衛門督(三條実雅) | 左衛門督 | 負傷 |
| 山名中務大輔(山名熈貴) | 討死 | |
| 京極加賀入道(京極高数) | 討死 | |
| 土岐遠山 | 走衆 | 負傷/帰亭後に死去 |
| 大内介(大内持世) | 負傷/7月28日死去 | |
| 細川下野守(細川持春) | 負傷(片腕切断) | |
| 畠山左馬助(細川持永) | 逃走か(記録なし) |
赤松満祐入道がこの事件を企てた理由は定かではないが、永享12(1440)年3月17日、満祐入道弟の伊与守義雅が義教の不興を買い、所領を収公される事件が起こっており、これが大きな引き金になった可能性は高いだろう。
この事件は、常陸国で安王丸・春王丸の挙兵が伝えられ、諸将に追討の御教書が下された翌日の出来事であり、時期からみて関東との共謀が疑われた可能性があろう。さらに、義雅の所領は「被宛行舎兄入道并細川右馬助、赤松伊豆入道小屋野拝領等」(『看聞日記』永享十二年三月十七日条)と、満祐入道のみならず細川右馬助や、対立する赤松春日部氏の赤松伊豆入道へ分与されるというもので、満祐入道は、とくに赤松伊豆入道へ与えられた摂津国「小屋野(伊丹市昆陽)」は、「為勲功拝領於家執之、而父入道依愛子譲与了、可被付家之由」を主張して惣領家への返付を求めたが、認められなかったとみられる。満祐入道は永享12(1440)年に「依狂乱自去年不出仕」(『建内記』嘉吉元年六月廿四日条)しており、この一件による出仕拒否である可能性が極めて高いだろう。満祐入道は予てより「直冬子孫、為禅僧在播州、以彼可取立申由、赤松称之」(『建内記』嘉吉元年七月十七日条)と、直冬子孫の貴種を扶助しており、義教を討つことはこの頃から計画していたものと思われる。満祐入道は義教を討ったのちは彼を取り立て、「此禅僧、元来在播州、已称将軍」(『建内記』嘉吉元年七月十七日条)とみえ、彼(足利義尊)を「将軍」に推戴したとみられる。
義教殺害事件が伝えられた際、権大納言時房は京都西郊におり、その帰途に「於内野見■火手」(『建内記』嘉吉元年六月廿四日条)という。「路次物騒、無物取喩」を思い、騒動の隙をついて「早以帰家」り、直衣にも着替えず直垂のまま「即馳参 内裏」している。日暮れ時であり、主上(後花園天皇)も「御朝餉間、炎上之躰有御遠見」(『建内記』嘉吉元年六月廿四日条)していた。「室町殿還御有無未慥説、於左衛門督者已被疵帰亭云々、所詮大事若出来歟、無心元云々、於門々大番者厳密可候之由、仰付了」(『建内記』嘉吉元年六月廿四日条)と、義教の安否は不明、三条実雅卿の負傷が伝わる中、やはり大事になっていることが察せられ、御所警衛の為、大番の者に諸門の警備を強化するよう指示している。
夜中になり、内裏に「細川右京大夫管領也、進使節内藤孫左衛門尉云々、跪候臺盤所前庭」め、「新三位永基卿、跪候簀子、堂上右傍ニ在リ、便宜移ス、謁之尋聞」いき、奏聞している(『建内記』嘉吉元年六月廿四日条)。内藤孫左衛門尉は「今日事、言語道断次第候、但若君御坐之間、天下可安穏候、御心安可被思食候、尤令参可候御門候之処、中々事々敷候間、以人申上候者」と、義教の横死は言語道断の事であるが、若君千也茶丸が御座すので天下安穏たるべく諸事行うので御心安く思しめされたいと伝えている(本来は持之自身が参内すべきところですが、諸事取り紛れているため、使者を以て申上げた、という)。これに「今日物騒所驚思食也、事儀未聞食及御不審之処、言語道断次第也、若君御坐之間、不相替憑思食也、如此 奏聞神妙者」との勅答が下され、冷泉三位永基から内藤孫左衛門尉に伝えられ、内藤は退出した。時房は「種々説満巷之処、奏聞已如此、御薨逝治定、言詞難及事也、当座之儀又有種々説、而聞定分已載右了」と述べ、改めて義教の「御薨逝治定」ことを実感し「言詞難及事也」と悲嘆した(『建内記』嘉吉元年六月廿四日条)。
「今夕、赤松宿所自放火之後、又経程伊予守大膳大夫入道弟也一条以北町以西宿所自放火」し、さらに「左馬助同弟也、宿所自放火」して「其外彼一族被管人多以放火逐電」した(『建内記』嘉吉元年六月廿四日条)。なお、「於伊豆入道、播磨守者、雖一族与惣領別心之間、当参無相違」とあるように、赤松伊豆守貞村入道、赤松播磨守満政については、赤松一族ではあるが、義教近臣で満祐入道とは決別しており、御所方に参じている。また、「有馬今日不供奉是又近日不快之分歟、無相違」(『建内記』嘉吉元年六月廿四日条)と、赤松有馬持家も満祐入道とは不和といわれ、御所方に加わった。
この義教横死事件の報は貞成入道親王のもとにも届いているが、当初は「赤松公方入申、有猿楽云々、及晩館喧嘩出来、騒動是非未聞」(『看聞日記』嘉吉元年六月廿四日条)と、義教が訪問した赤松邸で起こった喧嘩というもので詳細不明だった。ところが「三條手負て帰、公方御事ハ実説不分明」(『看聞日記』嘉吉元年六月廿四日条)と、ただ事ではない状況が次第に明らかになり、「赤松家炎上、武士東西馳行、猥雑無言計」(『看聞日記』嘉吉元年六月廿四日条)と、赤松亭が炎上するなど物騒な状況が伝えられた。ただ、「至夜伊予守屋形炎上、家人共家自焼、公方討申、取御首落下」(『看聞日記』嘉吉元年六月廿四日条)とあるように、当初は赤松伊予守義雅亭で義教が討たれたとの認識だった。前年永享12(1440)年3月の「赤松伊予守義雅惣領大膳大夫入道性具弟也、所領悉被没収」(『看聞日記』永享十二年三月十七日条)事件の先入観があったものと思われる。
山名政氏
(小次郎)
∥―――――――山名時氏――+―山名師義―+―山名義幸
∥ (伊豆守) |(右衛門佐)|(讃岐守)
上杉重房―+―女子 | |
(左衛門尉)| | +―山名満幸
| | (播磨守)
+―上杉頼重――+―上杉重顕 | ∥
(大膳大夫) |(修理大夫) | ∥
| +―山名氏清―+―女子
+―藤原清子 |(陸奥守) |
(足利尊氏母)| +―山名時清
| |(宮田左馬助)
| |
| +―女子
| ∥―――――山名持豊――+―山名教豊
| ∥ (右衛門督) |(弾正少弼)
| ∥ |
+―山名時義―――山名時熈――山名持熈 +=養女
|(伊予守) (右衛門督)(刑部少輔) |(熙貴女子)
| | ∥――――――細川政元
+―山名義理―――山名義清――山名教清 | 細川勝元 (右京大夫)
|(弾正少弼) (中務大輔)(修理大夫) |(右京大夫)
| |
| +=養女
| (熙貴女子)
| ∥――――――大内政弘
| 大内教弘 (左京大夫)
| (大膳大夫)
|
+―山名氏冬―――山名氏家――山名熈貴――+―女子
(中務大輔) (中務大輔)(中務大輔) |(山名持豊養女)
|
+―女子
(山名持豊養女)
「室町殿御頸」及び「山名中務大輔頸」は「為敵被取了」といい、「各指剣鉾彦次郎教康、左馬助叔父也」と、赤松彦次郎教康と赤松左馬助則繁は、義教の首と山名熈貴の首を矛先に刺して「二条西行、大宮南行」して「落行西国」するが、その間、「逐懸人無之云々、言語道断次第也」と、誰一人赤松勢を追撃する人もない体たらくに、権大納言時房は「言語道断」と激しく非難している(『建内記』嘉吉元年六月廿四日条)。
赤松教康は退亭の際に「赤松宿所即放火」したため、「御死骸不及取出、言詞難及也」(『建内記』嘉吉元年六月廿四日条)と、義教の遺体を運び出すことができなかった。教康の父の満祐入道は「父大膳大夫入道、依狂乱自去年不出仕、渡御之時在別家富田入道宿所」と、「狂乱」を理由に昨年より出仕を止めており、事件当時は「富田入道宿所」(『建内記』嘉吉元年六月廿四日条)にいた。「富田入道」がいかなる人物かは不明だが、応永27(1420)年6月2日、満祐入道の父・義則の「家人富田入道死、古老者」(『看聞日記』応永廿七年六月二日条)が見え、満祐入道が居住していた「富田入道」はその後継者と思われる「赤松内富田土佐入道性有」(『建内記』嘉吉元年七月十四日条)か。満祐入道はすでに病の為か馬には乗れなかったとみられ「乗輿落行了」と輿に乗って、「彦次郎康教并左馬助大膳大夫入道弟也等」とともに離京し「無恙落居」(『建内記』嘉吉元年六月廿四日条)している。
翌6月25日、雷雨により赤松亭は完全に鎮火したとみられ、「前左大臣殿御死骸求出焼跡」(『建内記』嘉吉元年六月廿五日条)し、「御死骸ハ焼跡より瑞蔵主出て」(『看聞日記』嘉吉元年六月廿五日条)、搬出された遺体は「奉渡等持院」と、等持院に安置され「御葬礼可為来月六日」と決定される(『建内記』嘉吉元年六月廿五日条)。なお、同日、赤松満祐入道の使者が室町殿を訪れ「御首ハ摂津国中島ニ御座之由」を伝えているが(『看聞日記』嘉吉元年六月廿五日条)、「其使管領切首」ったという。
この日、時房は「中山宰相中将亭」に赴いて中山定親と話しているが、定親は「昨夕之儀、言詞難及事也、此御流子息事、一向不可用申歟之由有邪推之処、若君可取立申由治定歟、珍重、今日諸大名毎事有評定之子細云々、西国発向事等歟、昨夕其座之儀、或左衛門督演説之趣」(『建内記』嘉吉元年六月廿五日条)を語っている。
また、貞成入道親王にも詳報が伝わり、義教の死去の際の状況、討たれた人や負傷した人、そして逃亡した人たちのことも判明した。「其外人々右往左往逃散、於御前無腹切人、赤松落行、追懸無討人、未練無謂量、諸大名同心歟、不得其意事也」と、これだけ恩儀を受けておきながら御前で腹切るような人もなければ、離京する赤松一行を追掛けて討とうという人もなく、未熟者ばかりだと批判し、もしや諸大名が同心して事を起こしたか、まったく意味が分からないと怒りつつ、風聞には「所詮、赤松可被討御企露顕之間、遮而討申云々、自業自得果無力事歟、将軍如此犬死、古来不聞其例事也」と、今回の件は義教が赤松満祐入道を討つ企てが露見したために満祐入道が先んじて事を起こしたと聞く。そうであれば自業自得でやむを得ないだろう。将軍のこのような犬死はついぞ聞いたことがない、と述べている。こういった類の「雑説種々繁多也、委細不能記録」(『看聞日記』嘉吉元年六月廿五日条)と、多くの風聞が飛び交っていたようである。
嘉吉元(1441)年6月26日、「今曉若君八歳、自伊勢守貞経宿所、年来為御所渡御 室町殿上御所事也」(『建内記』嘉吉元年六月廿五日条)、「今曉若公室町殿へ御移住」(『看聞日記』嘉吉元年六月廿六日条)した。これは「御継家事、昨日諸大名定申故也」と、若公千也茶丸の「御継家」につき、管領持之以下の政権執行部が定めたための措置であった。このとき、若公の「御舎弟六人、同渡御、御同所也」という。さらに義教と血統の近い「香厳院鹿苑院殿御子、梶井殿同天台座主、鶏徳寺同、金侍者林光院御子也、以上御四所渡御鹿苑院」と、四名の貴種を鹿苑院へ移している。これは管領持之が「為用心近所御一所可然」ことを図ったものであった。なお、このときの鹿苑院主は、足利直冬(足利尊氏庶子で、錦小路殿直義の養嗣子)の子・宝山乾珍である。
【京都】
足利家時――足利貞氏 +―足利尊氏―+―足利直冬 +―足利義満―+―香厳院尊満
(伊予守) (讃岐守) |(大納言) |(左兵衛督)|(太政大臣)|(友山清師)
∥ | | | |
∥――――+ +―足利義詮―+ +―足利義持――――――――足利義量
∥ | |(権大納言)| |(内大臣) (参議)
上杉頼重――藤原清子 | | | |
(大膳大夫)(錦小路殿)| +―足利基氏 | +―足利義嗣――――――――謹侍者
| (左兵衛督)| |(権大納言)
| ↓ | |
| ↓ | +―足利義教――――――+―足利義勝【千也茶丸】
| ↓ | |(左大臣) |(左近衛中将)
| ↓ | | |
| ↓ | +―三千院義承 +―足利義制【鎌倉殿】
| ↓ | |(梶井門跡) |(左馬頭)
| ↓ | | |
| ↓ | +―虎山永隆【景徳寺】 +―足利政知
| ↓ | |(相国寺住持) |(左馬頭)
| ↓ | | |
| ↓ | +―大覚寺義昭 +―足利義政
| ↓ | (大覚寺門跡) |(左大臣)
| ↓ | |
| ↓ +―足利満詮―+―実相院義運 +―聖護院義観
| ↓ (小川殿) |(実相院門跡) |(聖護院門跡)
| ↓ | |
| ↓ +―三宝院義賢 +―足利義視
| ↓ |(三宝院門跡) |(権大納言)
| ↓ | |
| ↓ +―地蔵院持円 +―三千院義堯
| ↓ |(地蔵院主) (梶井門跡)
| ↓ |
| ↓ +―浄土寺持弁
| ↓ (天台座主)
|【鎌倉】 ↓
+―足利直義―+=足利基氏―――足利氏満―――足利満兼――――――――足利持氏――+―足利義久
(左兵衛督)|(左兵衛督) (左兵衛督) (左兵衛督) (左兵衛督) |(賢王丸)
| |
+=足利直冬―+―足利冬氏―+―足利義尊 +―成潤
(左兵衛佐)|(善福寺殿)|(伊原御所) |(大御堂殿)
| | |
+―宝山乾珍 +―足利義将 +―足利春王丸
(鹿苑院) |(重玄寺殿) |
| |
+―上乗院義俊 +―足利安王丸
| |
| |
+―実相院義命 +―足利成氏
(左兵衛督)
このほか、「若公御成人之間ハ管領政道可申沙汰」(『看聞日記』嘉吉元年六月廿六日条)とされ、「若公御事ハ管領以下一同可扶持申」(『看聞日記』嘉吉元年六月廿七日条)ことが決定された。また、「武家被突鼻人々、皆管領免許」と、義教によって罰せられていた人々は管領持之の指示により赦免された。赤松入道への対処としては、「赤松討手細川讃州、山名ヽヽ、赤松伊豆、廷尉等諸大名可発向」(『看聞日記』嘉吉元年六月廿七日条)が決定されている。
千也茶丸が室町殿に入ると、管領持之は結城攻め及び佐竹右京大夫義人攻めのために関東に駐屯していた諸大将に、義教の不慮の薨去を伝える書状を下した(嘉吉元年六月廿六日『井口文書』室:3287)。その宛所は、以下の14人の大将であった。なお、そのうちの一人「佐竹下総守」は『室町遺文』等で山入佐竹祐義に比定されているが、佐竹刑部大輔祐義は永享元(1429)年11月9日時点で「佐竹刑部大輔入道」(『満済准后日記』永享元年十一月九日条)とあるため「佐竹下総守」は祐義ではない。おそらく祐義の子「上総介」義知の「総州」から来る誤記であろう。
●嘉吉元年六月廿六日「細川持之書状案」(『足利将軍御内書并奉書留』室:3286)
●宛所の大将
| 上杉安房入道殿 | 上杉安房守憲実(入道長棟) |
| 兵庫 | 上杉兵庫頭清方 |
| 修理大夫 | 上杉修理大夫持朝 |
| 千葉 | 千葉介胤直 |
| 小山 | 小山小四郎持政 |
| 宇津宮 | 宇都宮右馬頭等綱 |
| 佐竹下総守 | 比定者不明 祐義の子・上総介義知か |
| 民部 | 斯波民部大輔持種 |
| 土岐 | 土岐刑部少輔憲益 |
| 小笠原 | 小笠原修理大夫政康(入道正透) |
| 武田 | 武田刑部大輔信重(入道道成) |
| 上杉中務少輔 | 上杉中務少輔持房 |
| 岩松治部大輔 | 岩松治部大輔長純 |
| 上杉治部少輔 | 上杉治部少輔教朝 |
この草案をもとに推敲して、各々に下記の書状が送達されているとみられる。
●嘉吉元年六月廿六日「細川持之書状」(『井口文書』室:3287)
千葉介胤直は、嘉吉元(1441)年中に出家して「常瑞」と号しているが、上記6月26日の「細川持之書状案」(『足利将軍御内書并奉書留』室:3286)を受けての出家である可能性が高いだろう。
6月29日、「故室町殿征夷大将軍従一位前左大臣義教公」に「贈太政大臣宣下」され、「少納言益長朝臣」が等持院に参じ、義教の御龕前にて宣命を読み上げた(『建内記』嘉吉元年六月廿九日条)。
7月6日、「普広院殿御葬礼」が等持院で行われた(『建内記』嘉吉元年七月六日条)。赤松勢に持ち去られた義教の首は「五日、義教御頸骨ニテ播磨ヨリ相国寺僧取テ返」(『東寺執行日記』嘉吉元年七月五日条)し、体と合わせて葬礼に間に合わせている。葬礼では「若公皆無御出、御少年故」のため、「管領細川右京大夫持之朝臣相代、毎時致御沙汰」となった。ただ、「武家大名、当時物騒之間、面々可斟酌之由、管領相示之」たため、「只一身参入」している(『建内記』嘉吉元年七月六日条)。朝廷からは「按察使大納言公保、中山宰相中将定親、権右中弁資任朝臣、三条少将公綱養父左衛門督、依疵未平癒、不参之間、為代官参入也」が各々浄衣で参入した(『建内記』嘉吉元年七月六日条)。義教の遺骸は卯刻より荼毘に付され、約十時間後の申刻に拾骨が行われ、相国寺不乾徳院(普広院と改む)に安骨された。一部は7月24日、「高野山安養院」に収められている。
また、同7月6日の評定では、満祐入道の保有する播磨国、備前国、美作国守護職については、当然すべて収公となるが、「備前、美作両国守護職事」については、満祐入道一党の「依誅罰忠功之仁、可被充行之由、評定在之」と定められた。ただし、「播磨国守護事」は、「猶可被定人体歟之由、有沙汰、其猶可随軍功之由評定」との評決となった。権大納言時房もこの武家の評定に「共以可然事也」と同意している(『建内記』嘉吉元年七月六日条)。播磨国についてはとくに要衝地であることから、単に軍功のみで与えるのは憚られ、要路は御料所などとして直轄にすることも含め、様々なことを吟味した上で決定するとしたものだろう。
7月11日、「播州為惣領赤松大膳大夫入道性具、長子彦次郎教康等誅罰」のため「被遣御勢」され、「赤松伊豆入道進発」(『建内記』嘉吉元年七月十日条)し、「細川讃岐守持常、赤松有馬、山名伯耆守護等、進発播州」(『建内記』嘉吉元年七月十一日条)した。大手勢は「細川讃州、同阿波、同淡路、同兵部少輔、赤松伊豆守、同有馬、同治部少輔七條、同越後守、武田備後、川野」が「京都ヲ立テ、一谷ヨリ責之」(『東寺執行日記』嘉吉元年七月十一日条)という。
この頃京都では、赤松乱に関わる様々な雑説が流れており、「今度赤松謀叛事、管領就旧好、内々得其意歟之由、人々存」じており、「無其儀之旨雖分明、猶以可押寄管領許之由、有浮説」という(『建内記』嘉吉元年七月十七日条)。そのため管領持之は「因茲一昨日、管領可下向摂州分国也之由、致用意、而押寄之條、浮説之間、無為了」という。このほか「大内之所存、一向管領同意之由存歟、今度依疵赴施行者、残党必馳向管領、可切腹之由予遺言」という噂も流れている(ただし、大内持世が死の間際に述べたことは、「其時雖可奉御供、為亡大敵悠逃去了、而不存命、無念事也、於死骸者不及葬礼、早堀埋、以髪可送九州寺家、於家僕者不貽一人、急発向播州、可誅戮赤松父子、是可為第一之芳志之由、慇懃示置」というもので、細川持之への派兵を命じたのは誤伝であった)。赤松満祐入道は管領持之の大伯父で日頃から良好な関係であったことから、こうした風聞が生じたとみられる。権大納言時房も「伝聞條々雖不取信、記一説頗無益也」と評し「依如此事、天下浮説、更不静謐、天魔之所為歟、可驚」と述べている。
7月17日、権大納言時房は「直冬子孫為禅僧在播州、以彼可取立申由、赤松称之」(『建内記』嘉吉元年七月十七日条)ことを聞く。翌18日、赤松満祐入道が「於播州幡上之、兵衛佐殿御孫歳廿九、赤松大将次」(『東寺執行日記』嘉吉元年七月十八日条)ことが伝わっている。この満祐入道が庇護していた禅僧は「元来在播州、已称将軍」と見え、京都に対する大義上の将軍を奉じたものであったとみられる。この禅僧には弟がいたが「其弟、同禅僧、在備中国、已欲逃播磨之處、備中国守護手勢打取之、其首今月廿八日歟、京着也」(『建内記』嘉吉元年七月十八日条)という。
7月18日、先陣を切って「赤松廷尉勢出逢合戦」している。「寄手無勢之間、引退候処、白陸寄手、逢邁思廷尉手寄合セテ、首ドモ取之云々、先以吉相也」と、赤松左衛門尉(不詳)の手勢が惣領赤松勢に勝利したという(『建内記』嘉吉元年七月廿五日条)。
7月26日、「赤松、来月三日、可打入京都之由、有其説」ことから、「仍管領加下知、西郊辺及木戸逆茂木」(『建内記』嘉吉元年七月廿六日条)という風聞があった。また、巷説では「細川讃州、赤松伊豆入道等、未在西宮、来月十六日、同時可責」(『公名公記』嘉吉元年七月廿六日条)という。西宮に駐屯している理由は、「或落馬違例伊豆入道事云々、或病目惘然讃岐守事云々」(『建内記』嘉吉元年七月廿五日条)という風聞もあった。ただ、「赤松責入兵庫之由有其聞」(『公名公記』嘉吉元年七月廿七日条)という聞こえもあり、その警衛のための駐屯である可能性もある。
大手勢の細川讃岐守持常以下の細川勢、赤松伊豆入道以下の赤松勢が西宮で播磨国を窺っている一方で、7月28日、「今朝、山名、伊予守護河野等発向播州、立間中将并竹林院、相具河野下向云々、松葉定為同前也、一向無音之間、不知之存外」(『公名公記』嘉吉元年七月廿八日条)とあるように、山名勢と伊豫守護河野教通が播磨国に発向している(山名持豊の侍所職は「佐々木中務少輔持清」が就いている)。河野教通は伊予国の西園寺家庶流・立間西園寺中将公広、竹林院公親、松葉西園寺定為らを率いて下向しているが、松葉定為は下向に際して本家たる内大臣公名に音信なく、公名は怒りを覚えている。京都を発った「搦手大将山名、同兵部少輔、同上総入道以下、皆山名一家也」は、「京都ヲ立、丹波路ヨリ但馬口ヨリ播州ヘ責入候」(『東寺執行日記』嘉吉元年七月廿八日条)と、丹波国、但馬国を経由して北部から播磨国へ攻め入っている。搦手の「播州進発人数」は「山名右金吾、同名匠作入道、兵部少輔教之、其外一族」(『齋藤基恒日記』)と見える。赤松満祐と山名持豊は永享9(1437)年12月20日頃、「若党口論」から「山名、赤松有確執事」に発展。「赤松勢、山名へ欲寄一門合力、已打立」という戦闘に発展する直前、これを聞いた将軍義教が介入して「属無為」という事件もあったように(『看聞日記』永享九年十二月廿一日条)、所領を接する両者は犬猿の仲であった。
7月26日、「左衛門督実雅卿」の指示を受けて「中山宰相中将定親卿」が権大納言時房を訪問した(『建内記』嘉吉元年七月廿六日条)。これは「管領細川右京大夫持之朝臣事也」が三條実雅卿に「赤松大膳大夫入道父子誅伐事、御少年之時分之間、管領下知人々所存如何、無心元之間、可申請 綸旨之由」と、赤松討伐につき、持之が幼少の室町殿を代行して諸方指示するも、将軍に威厳が備わっていないため、心もとなく感じて討伐綸旨の申請を行ったものだった。これを受けた三條実雅が時房に「此条可為何様哉、令 奏聞者可點吉日云々、定不可有相違歟、就其文書、充所等事如何、於関東事、先度被成 綸旨了、凡不可有子細事哉、不審旁談合」と問い合わせた。
これに時房は、「征伐綸旨条本儀也、勿論神妙、雖御少年、有補佐之臣執事之事也、即管領事也、同事也、有何事哉、鹿苑院殿御代連々被申請 綸旨了、自鹿苑院御代末比不被申請之、太不可然歟、其比康暦応安、職事綸旨、院司院宣等直書進了、今者面々家礼也、充人可書進之条勿論、但今度之儀、赤松代々家臣也、不可及申請 勅事歟、然而申請上者勿論、猶自公家遮被成下 綸旨之条、若可宜哉朝敵不可過今度之逆悪之故也」とし、時房自身は、赤松家は将軍家の代々の家臣であるから、家内で解決すべき問題で、天皇が討伐綸旨を下す必要はないと述べ、非常に消極的な姿勢を示している。ただ、どうしても綸旨の下賜を申請するのであれば、文案は、
「播磨国凶徒、早遣官軍、可令加征伐給之由、天気所候也、以此旨可令申入給、仍執達如件」
というような内容で、充所は「管領為相催人々、只充管領猶在其便歟」と返答した。定親もこれを良しとして退出した(『建内記』嘉吉元年七月廿六日条)。
同7月28日、「鎌倉殿若公六歳、上洛、土岐方預之」(『東寺執行日記』嘉吉元年七月廿八日条)という。この若公は、処刑された春王丸、安王丸の弟で永寿王丸といい、春王・安王とともに結城で捕らえられたが、春王や安王より遅れて上洛の途に就いていたようである。その上洛の途次、兄たちと同じく「着濃州垂井辺、於路次可誅歟之由、注進」されたが、「普広院殿薨去」により助命されていた。融和政策を堅持する管領持之は、「仍沙汰付鎌倉、以彼可聴相続之由、管領以下評定事了、以上杉房州、如元可為鎌倉管領執事事也之由、同評定了」と、管領持之以下の執行部が関東に関する評定を行い、この六歳の永寿王丸に関東相続をさせるとともに、上杉憲実入道に元のように鎌倉管領に就くべきよう指示することで決定した。そのため、「仍自垂井可下向鎌倉由、風聞」があったが、結局7月28日「彼小生京着」し、「渡御土岐宿所」(『建内記』嘉吉元年七月廿八日条)した。垂井から関東へ戻さなかったのは「今時分、於鎌倉、万一謀反之輩有悪張行者、不可然之間、播州落居之間、先可置申京都之由宿所渡御土岐宿所也、思案之儀、有其謂者也」と、「於京都若君御対面以後、被沙汰居申之條、可然之由、鎌倉管領申意見」のためという(『建内記』嘉吉元年七月廿八日条)。
この頃、関東では春王・安王の挙兵に加担した佐竹右京大夫義人の追討が論じられ、上杉安房入道等は人々に軍勢催促するものの、すでに厭戦気分が高まっていたためか、武蔵南一揆などは応じるそぶりも見せず、義教横死の報告以降はより顕著となっていたようである。京都の管領細川持之自身も騒擾を好まない人物であることから、結城合戦以降は関東以北における静謐を願い、鎌倉に駐在していた「等持院(柏心周操)」に対して「抑関東無為之由承仰候、目出候、弥静謐之様、房州連々御談合肝要候」と伝えるとともに、奥州においては奥州諸将の要となる篠川殿満直が討たれたままの状況に「無心元存候」と心境を伝え、さらに「佐竹下総守、未能注進候、如何候哉」と佐竹下総守(佐竹上総介義知か)からは注進がいまだに届かないことにどうなっているのかと、問い合わせている(嘉吉元年八月十日「細川持之書状案」『足利将軍御内書并奉書留』室:3298)。
また、安王丸に加担して結城方の大将の一人として活動した岩松左馬助持国は、7月27日に南奥州の石川駿河守へ書状を遣わした(「嘉吉元年七月卅日到来 岩松とのより」)。岩松持国は「雖未申通、以事次令啓候」とあるように、石川氏と通信するのは初めてだったことが判明するが、「抑京都之御事、如此御成候、先以驚入存候、雖然、連々関東之御本意此時候歟、此刻可然様御思案候者、公私可為大慶候」(嘉吉元年七月廿七日「岩松持国書状」『石川家文書』室:3297)と、義教死去に伴い、「関東之御本意此時候歟」と述べ、石川駿河守に「此刻可然様御思案」を強く求めている。
嘉吉元(1441)年7月29日、武家においては義教の忌により「八朔所々進物事、当年於武家者室町殿已下停止勿論、五旬中之故也」ながら、朝廷においては「公家之儀禁裏許、不可有停止」だが、後花園天皇は「普広院殿異于他御忠節也、せめてもの事ニ、か様事ニても御悲嘆之、叡慮とも可被顕之由思食、可被停止」との意見で、朝廷においても八朔の儀は「可被略之条治定」となった(『建内記』嘉吉元年七月廿九日条)。後花園天皇は践祚(義教は後小松天皇との対立から、彼の属する後光厳皇統ではない崇光天皇の末裔である貞成入道親王の子・彦仁王を践祚させた)から、とくに学問についても何かと世話を焼いてくれた義教に敬意を持っていたと思われる。この義教に対する敬慕の心は、赤松満祐父子追討綸旨についても表れているように思われる。
7月30日夕刻、「蔵人左少弁俊秀(冷泉俊秀)」が時房亭を訪問して「就播州発向事、可被成 綸旨也」(『建内記』嘉吉元年七月卅日条)を告げているように、綸旨発給が決定された。綸旨については、中山宰相中将定親より「其文章談予可書之、明日吉曜之間可 奏聞、其後下知可遅々之間、今夜先可書給、可預置我許」という指示を受けたため、時房を訪ねたということであった。さらに「綸旨文章、先日於予亭所見及之応安、永和等頗以簡略也、今度之儀、猶厳重可載文章之由」も述べている(『建内記』嘉吉元年七月卅日条)。
これに時房は、「今夜事、晦日也、軍事有憚歟、称大赤口於軍事有憚之由、武辺有其説、今夜又件日也、旁雖明旦不可有遅延之儀歟」と、晦日及び大赤口の軍事関係の事柄は憚るべきことは武家の通説で、今夜はまさにその日であるから、明旦でも遅くはなく、草案を推敲すべきと中山定親に伝えるよう冷泉俊秀に指示し、時房が草案を作成することにしたが、ただ時房は「就鎌倉事先度被載 勅裁、件文章未見及、若有同句者近々事也、武辺人々見苦歟」であるから「内々以此草案可被見大外記業忠歟」と考え、「仍招業忠」いたが、業忠は「霍乱」と称して来なかった。そのため、冷泉俊秀は時房の綸旨草案を持って「密々向文亭」って、内々に清原業忠に添削を求めた。これは「先年草資任請彼外史之由、先日中山密語之故」と、持氏追討の草案を業忠が関与したことを、先日中山定親が秘かに語っていたためだった。俊秀は業忠に対面したのち時房亭に戻り、「外史謁見、鎌倉之時案聊見及了、文章忘却、今案無同句也」とのことで、業忠により「聊有添削事、可載案文也」った。その後、俊秀は「向中山、令見案文」て、再度時房亭に戻り、中山定親からの「此分無相違、可然之由示之」ならびに「明旦清書可然之由」の返事を報告した(『建内記』嘉吉元年七月卅日条)。そして中山は時房に「明旦先可談左衛門督之由」を伝えている。
こうして、8月1日早朝、時房は綸旨の草案を記して、俊秀に渡した。
播磨国凶徒事、忽乱人倫之紀綱、猶及梟悪之結構、攻而無赦、誅而不遺者乎、急速遣官軍可令加征伐給之由、
天気所候也、以此旨可令申入給、仍執達如件
八月一日 左少弁俊秀
謹上 右京大夫殿
翌8月1日、再び左少弁俊秀が時房亭を訪ね、「草案、雖無子細文章猶少、仍多於御前被加之、染宸翰被下之、任其旨書進之、彼案在明日記」という。後花園天皇は、異例の事ながら、時房の草案に自ら筆を執って、添削しながら綸旨の草案を書き上げた。
満祐法師并教康、構陰謀於私宅、忽乱人倫之紀綱、拒 朝命於播州、相招天吏之干戈、然早発軍旅可報仇讐、兼亦尽忠於国致孝於家唯在此時、莫敢旋日、兼亦彼合力之輩可被処同罪之科者、
天気如此、以此旨可令申給、仍執達如件
八月一日 左少弁俊秀
謹上 右京大夫殿
これを見た中山定親は、「綸言如此ト此文章ニテハありぬへしと云々、仍今一通又書儲之、俊秀持向之」として、冒頭に「被 綸言偁」を加え、「天気如此」を「綸言如此」と改めて、
●「赤松満祐等討伐綸旨」(『建内記』『の掲載文を併せる)
被 綸言偁、満祐法師并教康、構陰謀於私宅、忽乱人倫之紀綱、拒 朝命於播州、相招天吏之干戈、然早発軍旅可報仇讐、兼亦尽忠於国致孝於家唯在此時、莫敢旋日、兼亦与彼合力之輩、可被処同罪之科者、
綸言如此、以此旨可令申入給、仍執達如件
八月一日 左少弁俊秀
謹上 右京大夫殿
という討伐綸旨が完成した。
この頃、美作国や備前国では赤松勢と山名勢の合戦が勃発しており、「美作国垪和右京亮城官軍方」に「赤松勢、自播州攻之、仍城衆自放火、退散了」という。「垪和右京亮」は在京奉公衆であり、おそらく山名右衛門督持豊を主将とする山名勢とともに搦手勢の一将として発向していたが、「未及其地、在他所」で援軍には間に合わなかった。また「備前国松田并勝田各官軍方也」は、「先日追散赤松勢」だったが、赤松勢が「率数多軍勢及合戦」したため、「松田勝田引退備中国」という。
その頃、中山宰相中将定親は、室町殿千也茶丸の叙爵につき、関白持基に除目日程の調整を依頼していたようで、8月9日、定親は「左中将家輔朝臣」を招いて関白持基の「室町殿御叙爵事、被尋日次之處、来十九日為吉日之由」との言葉を聞く。また、その儀に当たっては「毎事可為鹿苑院殿御例、彼度毎事従普光園殿令取沙汰給歟、今度儀、同可計申給」として、室町殿叙爵は、義満の先例に沿って行うよう取り計らうとのことであった。また、「来十三日相当彼四十九日、其後急可被行御祈始、是赤松征伐御祈等被行之故也、仍為御都状并御願書等、御書御名字、早速可被定之間、御叙爵事、猶可被急」と、いろいろな文書や願書を発給する上で、実名が必要であるため、早々に御名字を決定することと、それにともなう叙爵もさらに急ぐべしという(『薩戒記』嘉吉元年八月九日条)。定親は安倍有重卿や賀茂在方卿ら陰陽方とも相談し、叙位任官の日程を十二日または十九日で行うべしと関白に復命。義教忌日との兼ね合いも含め、「日次十九日可然之由」で治定した。
その後、関白持基と中山定親との間で左中将家輔を介し、勘文を作成する儒家菅原為清卿の意見も含めて、数回の「御名字」の「勘文」についての協議がなされ、8月15日、当番公卿であった定親は参内の序に「武家叙位宣下日事」を奏聞した。
8月16日、関白持基は千也茶丸の御名字勘考に関して、左中将家輔を権大納言時房亭に派遣した。家輔は「武家御名字事、任鹿苑院殿御例、可被計申也」とのことで、「有其御沙汰之間、雖有斟酌、任佳例申沙汰也」と指示され、「為清卿撰申内、可有清撰、難心得之段先度事舊了、可被如何哉」と、すでに為清卿の意見も含めた名字勘文の一覧を持参していたとみられる。これに時房は「此内可申意見之由承之」った(『建内記』嘉吉元年八月十六日条)。
大蔵卿菅原為清が出した名字案は、
| 名字案 | 反切 | 反切の意 |
| 義行 | 娙 | 身長好貌 |
| 義敏 | 釿 | 剤断 |
| 義繁 | 元 | 善之長 |
| 義勝 | 凝 | 厳整之貌 |
| 義種 | 無形 | |
| 義豊 | [豸牛] | 獣似豕 |
| 義富 | 鼼 | 仰鼻也 |
| 義清 | 無形 |
の8案だったが、この案に対し、家輔中将と時房の意見は、
| 名字案 | 意見 | 時房・家輔 採用/不採用 |
家輔報告 採用/不採用 |
| 義行 | 家輔:九郎判官沒落之後一旦稱之由、有或説 時房:然者不思寄事也、朝敵不可然 |
× | × |
| 義敏 | 分際ヲ定タル樣ナリ、可有憚歟 | × | × |
| 義繁 | 此反字尤可然、但新田先祖義重、可為如何哉、無益歟、可有評義哉、故道孝禪門名字初義重、後義教也、義教先御代為御名字、又以義重之同訓可為御名字事、不可有憚哉、同可令有御沙汰之由申之 | ● | ● |
| 義勝 | 一色故六郎早世之名也、可憚之由先御代有仰、今更難被用之 | × | ● |
| 義種 | 志波故修理太夫入道名字也、然而有何事哉、無難之人也、如何 | ● | ● |
| 義豊 | 先御代及御沙汰了、[豸牛]ハ唐人ノ食獸ナリ、好雨、クセリ穢ラハシキ獸トテ不被用之、然者難被挙歟 | × | × |
| 義富 | 反字之訓ハスキレ鼻歟、難用之 | × | × |
| 義清 | 武家逸見小笠原等元祖歟、無其難之人歟、不知之、被相尋之、可有御沙汰哉 | ● | × |
というもので、時房は八案のうち、五案(義行、義敏、義勝、義豊、義富)は「已有子細歟」ということで、案から外し、「義繁、義種、義清」の三案のうちから「猶可有評定哉」ということを家輔中将に述べた。家輔中将は「今日、中山宰相中将定親卿、参執柄、可申談」ことを述べて、万里小路亭から退亭した(『建内記』嘉吉元年八月十六日条)。
その後、未刻に中山定親は関白持基に招かれて関白亭を訪問し、御名字についての評議を行った。ここで「大蔵卿為清内々七八箇字注進之、此内可然字三可載進勘文、先内々可有談合之間、注折紙進之」として提出された折紙に記されていた三案は、「義繁、義勝、義種」の三案であった。この三案は家輔が時房との協議で決定した「義繁、義種、義清」とは異なり、「義清」が抹消され「義勝」が追加されたものだった。家輔は時房との会談結果を当然メモしたと思われるが、時房・家輔の結論と、家輔が関白に復命した内容が異なっていた可能性としては、家輔のメモが誤っていた、家輔の記憶違い、そして時房の認識誤りの何れかであろう。関白持基、定親は「此三之外、皆有難、又此三又各御庶流輩名也、然而被用之、有何子細候哉之由評議」を行った。その後、大外記業忠が参じてまた評議がなされ、「義」字を用いない可能性までも勘案されるが、結局、未終刻に関白持基より左中将家輔を使者として「御名字勘文如此之内可為何字哉、可談合左衛門督并持之朝臣等」と、左衛門督実雅と管領持之にも諮問した。
ここに大外記清原業忠も参じて検討が行われ、おそらく管領持之の意見も含めて「関白有清撰、且如管領被談仰歟」をもって、「義勝」が治定された。そして後花園天皇の筆にて「義勝」二字が記され、祝儀として義勝に砂金や太刀、馬などとともに遣わされた(『建内記』嘉吉元年八月十六日条)。
8月17日、千也茶丸は赤松追討の願文を水無瀬神宮へ奉納し、あらためて赤松追討の意思を明確にした。名は治定したもののまだ宣旨が下されていないため、幼名のままなのだろう。
●嘉吉元(1441)年8月17日足利千也茶丸願文(『水無瀬宮文書』)
8月19日巳刻、千也茶丸の「御名字治定、御叙爵宣下」がなされた。この日の臨時除目での任官者は三名、叙爵加階は二名だった。
| 人名 | 叙爵 加階 |
現位 | 任官 | 前任 | 如元 |
| 藤原清房 | 正三位 | 権中納言 | 参議 左大弁 |
||
| 藤原季俊 | 正四位下 | 参議 | 右近衛中将 | ||
| 菅原為清 | 正三位 | 左大弁 | 大蔵卿 | ||
| 藤原雅永 | 従三位 | 非参議 | 左近衞中将 | ||
| 源義勝 | 従五位下 |
この除目が行われた8月19日、播磨国に「細川淡路守、為先陣責入」(『管見記』嘉吉元年八月廿一日条)った。この「播州合戦事」では、「淡路守護細川淡路守也、乗舩寄塩屋関焼払、墜命被疵両方在之」と、海からは細川淡路守満俊が塩屋関(神戸市垂水区塩屋)を焼き払って赤松勢を追捕し、続いて「細川讃岐守、赤松伊豆入道等」が陸路から攻め寄せ、「播州合戦初カニカ坂(明石市和坂)」(『東寺執行日記』嘉吉元年八月十九日条)で京勢が緒戦に勝利した。
細川俊氏―+―細川公頼―+―細川和氏―+―細川清氏―――細川昌氏
(八郎) |(八郎太郎)|(阿波守) |(阿波守) (阿波守)
| | |
| | +―細川業氏
| | (陸奥守)
| |
| +―細川頼春―+―細川頼之
| |(讃岐守) |(武蔵守)
| | |
| | +―細川頼有―――細川頼長―――細川持有―+―細川教春
| | |(右馬頭) (刑部大輔) (刑部大輔)|(刑部大輔)
| | | |
| | | +―細川常有―+―細川政有
| | | (播磨守) |(刑部少輔)
| | | |
| | | +―細川元有―+―細川元常
| | | (刑部少輔)|(播磨守)
| | | |
| | | +―三淵晴員―――長岡藤孝
| | | (大和守) (兵部大輔)
| | |
| | +―細川頼元―+―細川満元―+―細川持元 +―細川澄之
| | |(右京大夫)|(右京大夫)|(右京大夫) |(九郎)
| | | | | |
| | | | +―細川持之―――細川勝元―――細川政元―+=細川高国
| | | | |(右京大夫) (右京大夫) (右京大夫)|(右京大夫)
| | | | |
| | | | +―細川持賢===細川政国―――細川政賢―+―細川澄賢―――細川晴賢
| | | | (右馬頭) (右馬頭) (右馬助) |(右馬助) (右馬頭)
| | | | |
| | | | +=細川尹賢―+―細川氏綱
| | | | (右馬頭) |(右京大夫)
| | | | |
| | | | +―細川藤賢
| | | | (右馬頭)
| | | |
| | | +―細川満国―――細川持春―+―細川教春―+―細川勝之
| | | |(下野守) (下野守) |(右馬頭) |
| | | | | |
| | | | | +―細川政春―+―細川高国
| | | | | |(民部少輔)|(右京大夫)
| | | | | | |
| | | | +―細川政国 +―細川春倶 +―細川晴国
| | | | |(右馬頭) (中務少輔)
| | | | |
| | | | +―細川賢春===細川春倶―――細川尹賢
| | | | (中務少輔) (右馬頭)
| | | |
| | | +―細川満経―――細川持経―――細川成経―――細川尚経―――細川尹隆―――細川晴経
| | | (陸奥守) (陸奥守) (陸奥守) (陸奥守) (陸奥守) (中務大輔)
| | |
| | +―細川詮春―――細川義之===細川満久―+―細川持常―――細川成之―――細川義春―+―細川之持
| | |(左近将監) (讃岐守) (讃岐守) |(讃岐守) (讃岐守) (讃岐守) |(九郎)
| | | | |
| | | +―細川教祐 +―細川澄元
| | | (兵部少輔) (右京大夫)
| | |
| | +―細川満之―+―細川基之―――細川頼久―――細川持久
| | (阿波守) |(阿波守) (阿波守) (阿波守)
| | |
| | +―細川満久
| | (讃岐守)
| |
| +―細川師氏―――細川氏春―――細川満春―――細川満俊―――細川持親―――細川成春
| (淡路守) (淡路守) (淡路守) (淡路守) (淡路守) (淡路守)
|
+―細川頼貞―+―細川顕氏―+―細川繁氏===細川業氏
(八郎四郎)|(陸奥守) |(伊予守) (陸奥守)
| |
+―細川直俊 +―細川氏之
|(民部少輔)|(伊予守)
| |
+―細川定禅 +―細川政氏
|(卿公) (左近将監)
|
+―細川皇海
(鶴岡若宮別当)
おそらく大手の細川讃岐守持常らと同じころ、搦手の山名勢もまた美作国に攻め入っており、8月21日、京都に「山名太夫入道常勝(山名修理大夫教清入道常勝)」から「美作国中朝敵悉退散之由」が注進されている(『建内記』嘉吉元年八月廿一日条)。8月10日頃、赤松勢が播磨国から美作国に侵入し「美作国垪和右京亮城官軍方也」を攻めて「城衆自放火退散了」とあり(『建内記』嘉吉元年八月十四日条)、山名勢が戦った赤松勢はおそらく彼らであろう。
一方、8月24日、26日の両日、細川讃岐守持常、武田治部少輔信賢ら京勢と赤松彦次郎教康勢が明石川を挟んで「蟹坂(明石市和坂)」と「人丸塚(明石市明石公園1)」で激しく合戦し、双方が多くの死傷者を出している
9月3日頃、「山名右衛門督持豊惣領也、攻播州、已打取坂本日来赤松満祐入道父子在之」(『建内記』嘉吉元年九月五日条)と、山名勢は赤松満祐入道の本拠であった坂本館(姫路市書写)を攻め落とした。坂本館は書写山麓の平地に営まれた居館で防衛能力はなく、満祐入道等は早々に坂本館を捨て「楯籠城中木山」った。木山城(たつの市新宮町下野田)は揖保川西岸の要害だったが、「国人等多降参」している状況にあって防衛もままならなかったようで、9月7日に京都に伝わった報では「播州事、赤松在木山城残党大略伏誅及擒、於国人等多以降参」(『建内記』嘉吉元年九月七日条)であり、木山城に「山名惣領自身攻入」って、9月10日、「赤松入道性具、於木山城自害」(『大乗院日記目録』嘉吉元年九月十日条)した。
満祐入道の弟「赤松伊予守義雅」は「降参」している。義雅は「去春比在国之間、今度天下儀、一切不存知條分明候、故雖令降参、不可叶云々、仍自害」というように、彼は永享12(1440)年3月に義教の不与を買って所領を収公され、一年余り在京ののち播磨国へ下向しており、義教殺害に関わりはなく、戦わずして降参したものの許されず自刃した。
また「赤松入道息彦次郎、今度張本也、没落、左馬助同没落了、未練事也」といい、赤松彦次郎教康と満範入道弟の左馬助則繁は城から逃げ延びている。当初京都に伝わった伝では、「被責落赤松父子父満祐法師大膳大夫性具事也、子教康彦次郎、於赤松播磨守満政陣自殺了後聞無此儀、只自放火皆切腹、弟伊予守義雅降参云々者被擒」(『建内記』嘉吉元年九月十二日条)、「赤松入道子、舎弟左馬助等切腹、伊予守父子被生捕」(『公名公記』嘉吉元年九月十四日条)との伝聞もあったが、前述の通り満祐子・教康と弟・左馬助則繁は遁れており、初報は誤伝であった。
満祐入道は自害後は首を火中へ投げ入れるよう指示していたとみられるが、「満祐法師首自火中求出之、山名伯耆守護実名可尋感得之」(『建内記』嘉吉元年九月十二日条)、「彼頭自山名之相模守手渡惣領山名手畢」(『大乗院日記目録』嘉吉元年九月十日条)というように、山名教之の手によって火中からその首が拾い出されている。この功績を主張してか、播磨国守護について「播磨守与山名可相論守護職歟」(『建内記』嘉吉元年九月十二日条)と、赤松満政と山名持豊の対立が顕著となったようである。
9月17日、「赤松大膳大夫満祐入道法名性具首、京着」した。「山名某伯耆守護自火中感得」(『建内記』嘉吉元年九月十八日条)したといい、首は「執事細川右京大夫持之朝臣実検」し、翌9月18日に室町殿義勝が「室町殿御童体御出伊勢守貞国入道宿所御路之間、有警固」で「実検」したのち室町殿に帰亭している。
9月18日、権大納言時房は蔵人左少弁俊秀から、武家方より「賊首可被渡大路歟、如何、若然者俊秀可申沙汰之由、以中山宰相中将被仰下」(『建内記』嘉吉元年九月十九日条)という問い合わせがあったことを聞く。これに時房は「尤可然、已為朝敵被下綸旨了、今度之儀、絶常篇可然哉」と答えている。その後検討がなされ、「日次、明日可然之由、奉行飯尾肥前入道示中山」すが、「明日室町殿御衰日也、如何」という。しかし、中山定親は残暑の中「首可損之間、雖片時被急云々、但猶可延引明後日歟、先明日分可申沙汰」と述べたという。その後、蔵人左少弁俊秀が時房亭に戻り、結果として「被渡賊首事、明日故院御忌日也、室町殿御衰日也、旁不可然歟」との返答となった。
9月20日、蔵人弁俊秀が時房亭を訪問。「可渡賊首事、今日延引可為明日」ことが報告された。そして翌9月21日、「賊首赤松大膳大夫満祐法師并安積実名可尋、両人首也、安積事、兼無其沙汰歟、漏仰詞了、今日被渡大路、被懸御門樹也」(『建内記』嘉吉元年九月廿一日条)と、赤松満祐入道らの首は大路渡ののち、獄門に懸けられた。
9月22日、管領細川持之は関東の「上杉殿、千葉介殿、上杉兵庫殿、宇津宮右馬頭殿、上杉修理大夫殿、小山小四郎殿」に宛てて、「抑赤松大膳大輔入道事、去十日、於播州城山城討捕候」ことを書状にまとめ、「渓和尚」に託して関東に下向させている。
●嘉吉元(1441)年9月22日「細川持之書状案」(『足利将軍御内書并奉書留』)
9月24日、「赤松伊予守義雅満祐法師弟也、其弟龍門寺さう侍者とて相国寺雲頂院僧也、而近年在国今度赤松下国、已後還俗云々、両人賊首、去廿一日夜、京著満祐法師首已被渡大路、被懸獄門以後京著、被懸六條河原云々至今日三ケ日」という(『建内記』嘉吉元年九月廿四日条)。
この日、播磨追討勢の大手大将軍の一人、赤松伊豆守貞村入道の死去も伝えられた(『建内記』嘉吉元年九月廿四日条)。権大納言時房が聞いた話では「赤松伊豆入道、於播磨陣敵陣滅亡之後、諸陣未帰京、円寂云々、或落馬、或夜討之由、其説不同歟」といい、落馬とも夜討ともいう。「今度赤松、播磨守護職、彼競望之間、普広院殿有御結構之企之由、有浮説、赤松不慮悪逆存企了、仍人々悪厲階着致沙汰歟之由、是又浮説也」という浮説ながら、かつて赤松伊豆入道が播磨守護職を望み、義教がそれを認めたことが満祐入道の悪逆を招いたという実しやかな噂があり、伊豆入道は恨みを買って討たれたともいう(『建内記』嘉吉元年九月廿四日条)。
そして9月29日、「彦次郎以下十三人、於伊勢国司館自害、此間相憑国司縁者故云々、雖然上意之間、無力也」(『大乗院日記目録』嘉吉元年九月五日条)と、赤松彦次郎教康は「縁者」である伊勢国司北畠顕雅卿に討たれた。『大乗院日記目録』には十三名の内訳の記載はないが、『彰考館本赤松記』記載の「右京大夫殿」に提出された北畠顕雅の注進に見える十三名は以下の通り。
赤松満祐入道に関する騒擾がひとまず治定したことを受け、満祐入道が保有していた播磨国、備前国、美作国の三国守護や所領配分について武家内で評定が行われ、閏9月5日以前には以下のように決定されている。
●『基恒日記』嘉吉元年閏九月条
守護職については、播磨国・備前国・美作国の三国は山名持豊に与えられ、そのうち備前守護は山名教之、美作国は山名教清入道が守護職に定められた。摂津国中島郡は御料所(代官は細川持賢入道)、そして播州内の「三郡」は赤松満政に下された。「赤松闕国、両人知行之希有面目不可過之」(『大乗院日記目録』嘉吉元年九月十日条)とあり、播磨国は山名持豊と赤松満政の両者が獲得している。
●嘉吉元(1441)年閏9月5日「細川持之書状案」(『足利将軍御内書并奉書留』)
満政が得た「三郡」は、細川持之から山名持豊へ宛てた書状(上記は決定稿ではない)に見える通り、「明石、賀東、三木三郡」のことで、これらは「御料所」として将軍直轄領に編入されたため、山名持豊の支配権は及ばない地となり、御代官職として赤松満政が任命された。播磨国東部を直轄地とすることで京都への要路を山名に渡さないという意思もあったと思われる。その一方で、先日戦陣に死去したと伝わる「伊豆守(赤松貞村入道)」や、満祐入道の弟「龍門寺(相国寺雲頂院僧の真操侍者)」「左馬助(赤松左馬助則繁)」らの闕所地を持豊に与え、麾下の人々へ充行うよう指示している。
閏9月5日、「賊首教康、今日京着」(『晴房卿記』嘉吉元年閏九月五日条)し、「赤松長子彦次郎頭、繋六條河原」(『如是院年代記』)と、教康の首級もまた六條河原に晒された。
閏9月21日、「播州御勢、悉上洛」(『東寺執行日記』嘉吉元年閏九月廿一日条)し、「播州追手軍勢細川讃岐守已下陣開、今日帰京」(『建内記』嘉吉元年閏九月廿二日条)した。播磨国守護の「山名左衛門佐持豊」と三郡代官の「赤松播磨守満政」は領内沙汰のため留まっており、赤松満政は10月9日夜に「自播州陣上洛」(『建内記』嘉吉元年十月十一日条)した。このとき満政は美嚢郡吉川庄の「吉川地頭降参、望扈従事、仍相具上洛」(『建内記』嘉吉元年十月十一日条)している。10月13日、権大納言時房は満政亭を訪ねて満政と対面し、「在陣無為并三ケ郡明石郡、美嚢郡、ヽヽ郡御料所御代官職事賀之」(『建内記』嘉吉元年十月十三日条)している。時房が満政を訪ねたのは「万里小路大納言家領、播磨国美嚢郡吉河庄、同重末、行恒等名」(『建内記』嘉吉元年八月一日条)とあるように、万里小路家領の美嚢郡吉川庄、同重末、行恒等名が満政支配となったことで、その賀礼及び、吉川庄地頭の降参に関する件等を確認するためであった。予て時房は「播州、作州、備州家領等事、向後止守護并地頭已下競望、致直務可知行由、被成下御教書様、可伝示管領之由相馮之、必可伝達」ことを依頼し(『建内記』嘉吉元年八月一日条)、「本知行愚化有子細御教書被成」ており(『建内記』嘉吉元年十月十三日条)、これをもとに満政は地頭に対して「本所領事、何篇可致違乱哉、更不可有其儀之由」を命じており、御料所代官としての実務を行っていることがわかる。
一方、山名持豊は「播磨国新守護山名左衛門佐持豊、去十一日入部、国中郡司沙汰居候、仍赤松播磨守満政奉行」(『建内記』嘉吉元年十月廿八日条)とあり、山名持豊は播磨国郡司達に対して沙汰を行い、国司の「播磨守満政」が「国務」として郡司に命じたものである。これらを執り行ったのち、山名持豊は11月25日に上洛した(『東寺執行日記』嘉吉元年十一月廿七日条)。
同じ頃、「遠江国今河殿」が「遠州押領」(『東寺執行日記』嘉吉元年閏九月廿七日条)している。「遠江今河殿」は遠江今川了俊末孫の「駿河国守護今川左衛門佐」(『斯波家譜』)とされる。「今川左衛門佐」は「今川右衛門佐」の誤りとみられるが、今川右衛門佐貞秋入道(今川範忠擁立の中心的人物)は永享5(1433)年当時においてすでに高齢であり出家の身でもあるため、ここに見える「今川左衛門佐(右衛門佐)」は貞秋の子世代、今川下野守の後身か。当時の遠江国守護は斯波千代徳(のち義健)であり、ここに遠江今川氏で尾張国に所領を持つ「今川左衛門佐(右衛門佐)」が、旧領を押領したのだろう。「今川左衛門佐」の押領理由は「持氏の御子息を取立可申候由、鎌倉へ申合候、遠江国を討取て攻上候はんとはかり申候」(『斯波家譜』)というが、当時の鎌倉は京勢支配であることから『斯波家譜』の挙兵理由は成立しない。この「今川左衛門佐」の遠江国内地の押領に対し、守護斯波千代徳(実際は修理大夫持種が執行)は、閏9月27日、「自京都、甲斐、織田両人下向」(『東寺執行日記』嘉吉元年閏九月廿七日条)させて対処している。『斯波家譜』においては「持種馳向ひ、誅伐を加へ候」とあるが、斯波持種は惣領斯波千代徳の後見であったことや、東寺の記録で、甲斐(美濃入道常治か)、織田(大和守郷広か)の「両人」が下向したと明記されていることから、実際には持種の下向はなく、尾張守護代家の両名が「両使」として当該地へ派遣された検断に過ぎない。
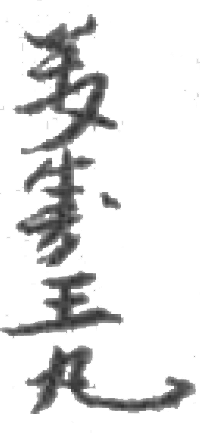 |
| 萬寿王丸? |
通説によれば、故持氏の一子・万寿王丸(のちの成氏とされる)が信濃国佐久郡大井郷(佐久市岩村田町)の大井越前守持光に長期間匿われていたとされる。なお、「萬寿王丸」は『角田石川文書』に一か所登場するのみで、その後あらゆる文書・軍記物を含めて「萬寿王丸」なる人物は一切登場しないのである。この「萬寿王丸」とする人物をのちの成氏とする説は問題が多い。
この「萬寿」が登場する文書は、筆跡と文字の角度(20度)、日付から署名が自然な筆致で続き、左右幅の均等性と左位置も整っているところから見て、署名・宛所を含め全文が同一人物によって記されていると考えられる。「萬寿王丸=成氏」とすると、なぜ右筆は署名の最初の二文字(「萬寿」?)のみを「作為的」に、非常に拙く判別し難い文字としたのだろうか。
下記2つの文書によれば、某年12月17日、大井氏に庇護されている「萬寿王丸」のもとに「綸旨并御旗」が到来したという。この綸旨や御旗(錦御旗)は、「信州大井方御座候自若君様、 綸旨并錦御旗事御申候」とあることから、万寿王丸から「何処か」に申請された結果、齎されたことになる。ところが、武家に関わる綸旨や錦旗の下賜であれば確実に記録に残す万里小路時房がまったく記録しておらず、その後も触れられることはない。つまり、少なくとも室町殿の政権はこの件に一切関わっていないことになり、下記の12月29日及び翌年正月18日の文書には「綸旨并御旗到来」というフェイクが入っていることがわかる。
●嘉吉元(1441)年?12月29日「足利万寿王丸書状」(『角田石川文書』室:3307)
●嘉吉2(1442)年?正月18日「岩松持国副状」(『角田石川文書』:「福島県史」)
これらの文書の内容と「万寿王丸=成氏」が新たな鎌倉殿に選ばれることに対する不審は、下記のような点が挙げられるか。
(1)数え七歳の少年が如何なる意志を持って綸旨等を、しかも敵性組織に申請するか疑問(誰が補佐人かも不明。大井氏が積極的に万寿王丸なる人物に関わった形跡もなく、文書内容から見ても「左馬助持国」が関わった形跡もない)
(2)綸旨や錦旗を奉じたという万寿王丸の「出陣」の意図が不明(室町殿政権とまったく同調する朝廷が、室町殿に諮らずして綸旨や錦旗を下すことはない。さらに、綸旨・錦旗を奉じたとすれば、「萬寿王丸」が、「還御」に当たって敵対する勢力は存在しないことになる)
(3)旧鎌倉勢力が壊滅的な打撃を受けた関東において、「萬寿王丸」の「還御」に協力出来得る勢力は皆無の中、「軍事力」を以て「還御」を目指すことは、現実的ではない
(4)当時の記録には、信濃国に綸旨や錦旗下賜があったという事実がない(ただし、これは強調するフェイクである可能性も十分ある)
(5)信濃の敵性勢力と戦う上杉氏が、「萬寿王丸」の存在を一切認識していない(上杉憲実は信濃国に逃れた上野国人と戦っている認識)
(6)室町殿政権は、「萬寿王丸」の存在に一切触れていない→(8)の京都の若公を差し置いてまで見ず知らずの少年を鎌倉殿に任じる不審
(7)のちの古河政権下で成氏と信濃大井氏との繋がりは一切見られない
(8)京都に持氏子息(永寿王丸)がいるにも拘わらず、上杉勢と戦闘状態にあるとされ、かつ京都とまったく接点のない「萬寿王丸」を、「御連枝」や在京の永寿王丸を差し置いてまで、新たな鎌倉殿に選ぶ理由がない(そもそも、上杉憲実すら認識のない「萬寿王丸」が、関東諸将に認知されていたはずもなかろう。)
(9)たとえ「万寿王丸」という人物がいたとしても、彼がのちに成氏となったという明確な傍証はない
こうしたことから、「角田石川文書」に見える「岩松持国の文書は真書」であったとしても、そこに見える綸旨や御旗の下賜がフェイクである以上、「萬寿王丸」なる「信州大井方御座候自 若君様」の「存在自体」もまたフェイクである可能性を否定することはできない。またはのちに現れる成氏の弟(定尊、尊敒)の可能性もあろう。
『喜連川判鑑』には永寿王は「鎌倉没落ノ砌、信濃国ニ落下リ玉フ、大井持光養立申、今年(文安二年)関東ノ諸家、京都ヘ訴申シ鎌倉ヘ請待シ、如元公方ト称ス」(『喜連川判鑑』)とあるように、大井氏との接点が語られる。これらがいかなる情報源を以て記事を遺したか定かではないが、『喜連川判鑑』は他の箇所でも『鎌倉大草紙』を参考に明記しており、この成氏事歴に見える部分も『喜連川判鑑』からの引用と思われる。しかも、永寿王と大井氏との接点は、結城合戦前までであってその後の関係は記されていない。そして、房定が九年の間毎年上洛し、永寿王を「関東の主君」に望んだとあるが、『鎌倉大草紙』のどこにも当時関東に永寿王がいたとも記されていない。そもそも、諸文書や史料から見ても萬寿王丸やそれに想定できる人物は一切見られないのである。
●『鎌倉大草紙』
『喜連川判鑑』に依れば、文安2(1445)年に永寿王丸を関東に招いたとあるが、実際には文安2年当時、まだ鎌倉に下向する人物は決定を見ていない(『建内記』文安四年三月廿三日条)。当時の京都には、故義教が永享11(1439)年に上杉憲実入道に諮問して「鎌倉殿」として承認を受けた義教庶子「義制(義永)」がいたものの、義教の死後は白紙となり、結局関東は「鎌倉御遺跡」がまとまらないまま、上杉憲実入道が取りまとめていく。
もともと持氏後継の「鎌倉殿」については、嘉吉元(1441)年7月28日に「彼小生京着」し「渡御土岐宿所」(『建内記』嘉吉元年七月廿八日条)した若君が、結城から美濃国垂井に連行されて滞在中の時分に、垂井から関東へ差し戻すことも調整されたが、「今時分、於鎌倉、万一謀反之輩有悪張行者、不可然之間、播州落居之間、先可置申京都之由宿所渡御土岐宿所也、思案之儀、有其謂者也」とされ、さらに「於京都若君御対面以後、被沙汰居申之條、可然之由、鎌倉管領申意見」(『建内記』嘉吉元年七月廿八日条)と、関東管領憲実から、京都の若君(のち義勝)と対面後に沙汰するよう要請されており、京都は当初はこの若君(永寿王丸)を「鎌倉殿」とする予定だった可能性が高い。文安2年には高倉永豊が室町殿政権から「鎌倉殿」用の直垂二着を依頼されており、文安2年時点での「鎌倉殿」は、永寿王丸であったと思われる。
大井氏と成氏との関係については、『喜連川判鑑』においては成氏は「永寿王丸」とあるので、『喜連川判鑑』の作者が参考にしたものは『角田石川文書』ではない。そうであれば、成氏は永享11(1439)年の鎌倉没落以降、信濃国大井氏のもとにあったという説話は他にも伝わっていたことになり、実話の可能性が高いだろう。ただし、信濃大井氏と古河公方成氏には接点は見られないため、結城合戦において成氏を結城城に送って以降、繋がりはなかったのだろう(信濃国は関東御分国ではない)。大井氏は守護小笠原政康入道の麾下にあり、結城合戦では「大井三河守殿、同名河内守殿、同名対馬守殿」(「結城陣番帳」『笠系大成附録』所収:室3244)が小笠原勢「廿七番」として京方の軍勢として参陣している。しかし、大井越前守持光は「信濃国ノ住人、大井越前守持光、御所方ニ成、旗ヲ上、臼井峠マテ押来ト聞エケレハ、是ヲ防カン為ニ、上杉三郎重方、国分ニ陣ヲ取」(『結城戦場記』)とあるように、結城方(安王丸・春王丸)に属したと思われる。それは「結城合戦まで」庇護した永寿王丸との関係によるものかもしれない。
足利義制 ~もう一人の「鎌倉殿」~
永享6(1434)年7月26日、赤松伊豆守亭で「母宮内卿赤松永良則綱女、赤松一族女」(『看聞日記』永享六年七月廿六日条)とする足利義教の次男が誕生した。幼名は不明。
永享11(1439)年2月10日、鎌倉永安寺において、鎌倉殿足利持氏が自刃し、鎌倉は主を失うこととなった。持氏嫡男義久は自刃したものの、その弟たちは幼少であったためか幽閉されるのみで助命されている。このような状況の中で、7月4日には「若公様、鎌倉殿御成御礼、自寺家御申事、奉行加賀意見申歟」(『東寺百合文書 ち』永享十一年七月四日条)とあるように、持氏の遺跡を継承する「鎌倉殿」に治定され、若公(義勝)への御礼につき相談がなされている。おそらくこれとほぼ同時に名字勘文が行われ、「御連枝小松谷殿…御俗名義制」(『刑部卿賀茂在盛卿記』長禄二年四月十九日條)、「義永左馬頭、小松谷殿」(『諸家系図纂』)というような「義制、義永」となり、左馬頭の官途に就いたのだろう。
ところが、永享12(1440)年には持氏子息の安王丸、春王丸、大御堂殿らが結城氏朝や佐竹義人を協力者に仰いで兵を挙げたことで、関東における故鎌倉殿(基氏以来の鎌倉御遺跡)の伝統的影響力が相当に強いことが裏付けられ、結城乱の平定後は、関東諸氏が持氏子息を奉じることができないよう、持氏の血統はすべて殺害することで決定されたのではなかろうか。その結果、捕らわれの身となった安王丸、春王丸は美濃国垂井で殺害されることとなった。両名の首を見た義教は落涙しており、本意ではなかった可能性もあろう。同じく永寿王丸も「着濃州垂井辺、於路次可誅歟之由、注進」されたが、「普広院殿薨去」により助命されていた。
その後、管領以下の大名(京都の閣僚)は「仍沙汰付鎌倉、以彼可聴相続之由、管領以下評定事了、以上杉房州、如元可為鎌倉管領執事事也之由、同評定了」と、管領持之以下の執行部が関東に関する評定を行い、この永寿王丸に鎌倉御遺跡を相続をさせるとともに、上杉憲実入道に元のように鎌倉管領に就くべきよう指示することで決定し、永寿王丸は「仍自垂井可下向鎌倉由、風聞」があった。
しかし、「今時分、於鎌倉、万一謀反之輩有悪張行者、不可然之間、播州落居之間、先可置申京都之由宿所渡御土岐宿所也、思案之儀、有其謂者也」という危険性が非常に高いことと、上杉憲実入道から「於京都若君御対面以後、被沙汰居申之條、可然之由、鎌倉管領申意見」(『建内記』嘉吉元年七月廿八日条)があったため、結局垂井から「彼小生京着」させ、「渡御土岐宿所」(『建内記』嘉吉元年七月廿八日条)した。その後、九年間にわたり、永寿王丸はこの土岐左京大夫持益の屋敷に預けられて成長する。
永寿王丸が大名の間で「鎌倉殿」とされる一方で、義教次男の「鎌倉殿」である「義制(左馬頭義永)」もまた「御連枝」の鎌倉殿として据え置かれたままとなったと思われる。
関東では岩松左馬助持国が結城城を脱出して、おそらく上野国に戻ったとみられるが、結城落城から三か月後の7月27日に南奥州の「石川駿河守」へ「関東」と同心するよう促す書状(嘉吉元年七月廿七日「岩松持国書状」『石川家文書』室:3297)を遣わしている。文書において「雖未申通、以事次令啓候」とあるように、岩松持国は石川氏と通信するのは初めてだったことが判明する。なお、この頃の石川氏当主は石川中務少輔持光であることから、この石川駿河守は持光とは別人である(持光は駿河守義光の子で「駿河孫三郎」を称しており、当時の石川駿河守は持光の弟または叔父か)。
●嘉吉元(1441)年7月27日「岩松持国書状」(『角田石川文書』)
この文書は岩松持国が単独で発した書状であるが、「関東(上洛した若公だろう)之御本意(鎌倉還御)此時候歟」と述べ、石川駿河守に「此刻可然様御思案」を強く求めている。しかし、7月30日にこの書状を受け取った石川駿河守の対応は伝わっておらず、岩松側も動向を伝えるものはない。
9月27日、細川持之から憲実入道を筆頭に、「千葉介殿(千葉介胤直)、上杉兵庫殿(上杉清方)、宇津宮右馬頭殿(宇都宮等綱)、上杉修理大夫殿(上杉持朝)、小山小四郎殿(小山持政)」の五名に宛てて、赤松満祐入道の追討が成ったことの報告及び、常陸国の佐竹左京大夫義人との合戦のその後の状況報告を求めたのであった。
この当時、上杉憲実入道は上野国白井館(渋川市白井)にあり、10月初旬、憲実入道に随って上野国白井に遠征中の鳥名木右馬助入道が、意向や当地の情勢を上杉家被官人「右馬允右詮」や「弾正忠実基」へ送達しており、これを請けた兵庫頭清方からの返状を鳥名木入道へ送っているが(嘉吉元年十月十三日「力石右詮書状」『鳥名木文書』室:3306)、上野国白井と常陸国金田は緊密に連携を取っていた様子がうかがえる。
●嘉吉元(1441)年10月13日「右馬允右詮書状」(『鳥名木文書』室:3306)
●嘉吉元(1441)年10月13日「弾正忠実基書状」(『鳥名木文書』)
上杉憲実入道が上野国白井にいたのは、上野国にいた旧持氏派(結城城残党を含む)の掃討のためとみられる。このとき上杉勢と戦い敗れた「当国没落人」は信濃国へと遁れたと認識されており、11月末頃に「信州之勢出張」を武蔵国賀美郡安保郷(児玉郡神川町元阿保)の安保信濃入道(安保宗繁)が報告したことに対し、12月1日、憲実入道は報告に感謝をしつつ、侵入者は「自当国没落人等、先以出張之分候歟」とし、「不可有殊子細候哉」と予測している。一方で、武蔵守護代の長尾左衛門尉景仲を西上野へ向かわせており、今日明日中には御近所へ着陣するため、もし安保入道がお越しいただけたらうれしいと参陣を求めている。
●嘉吉元(1441)年12月1日「上杉長棟書状」(『安保文書』)
なお、この文書内に見えるように、「自金田帰宅」した「西本庄左衛門尉」という北武蔵の兒玉党に属すると思われる武士がいたが、一揆のメンバーとして安保氏とも関わりのあった人物と思われる。「金田」は常陸国田中庄金田(つくば市金田)付近で、佐竹右京大夫義人と対峙のため、憲実弟・上杉兵庫頭清方が本陣を置いていたと考えられる。西本庄左衛門尉はここから離脱して北武蔵へ帰還してしまったのであった。なお、安保信濃入道の子・次郎(安保憲祐)は「次郎方金田へ御出陣之由承候」(嘉吉元年閏九月廿日「上杉長棟書状写」『安保文書』室:3303)と見え、金田陣へ出陣していることがわかる。
●嘉吉元(1441)年12月6日「上杉長棟書状」(『安保文書』)
その後判明した信濃国からの軍勢は碓氷峠を経て西上野へ下る一般的な東山道ルートではなく、上野国野栗郷(多野郡上野村新羽)を経て神流川沿いに下るルートを取っているという。一方で野栗郷から秩父に入り武蔵国へ入るルート(かつて中先代の乱で北条時行が取ったと推定されるルート)も想定される、揺動的なものであり、上杉憲実入道は対応に苦慮している。憲実入道は、取り急ぎ庁鼻和右馬助憲信入道と那波刑部少輔入道一族を白井宿に配置して西上野の警衛を強化するとともに、長尾左衛門尉景仲には碓氷峠を望む板鼻宿(安中市板鼻)の守護所へ向かわせている。しかし、守護代長尾景仲が上野国へ出陣することにより武蔵国は手薄となるため、「国事無心元存候」となることもあわせ、療養中ながら安保信濃入道も在陣を求めている。
また、嘉吉2(1142)年2月10日以前に「佐竹へ被寄御陣候」と決定されていたが(嘉吉二年正月廿五日「長尾景仲書状」:『安保文書』)、兵庫頭清方の本陣である金田陣からは武州一揆が「御一揆中大略帰宅之由承候」という事態に陥っており、憲実入道は「以外不可然候」と不満を漏らしている。そのため、長尾左衛門尉景仲を通じて「上州御書案文」の内容を安保信濃入道に示し、常陸国へ「御立之前ニ可有面著到候、然者、来月之始早々御参陣可然候」ことを「此段、御同道方様へ可有御触候」と伝えている。そして、もしこの旨に従わない者がいた場合は「無沙汰人躰、注名字、可有御注進候」と指示し、「為御心得進之候」とくぎを差している。
3月には佐竹右京大夫義人と結んでいたとみられる宍戸安芸守持里が常陸国宍戸荘で挙兵し、3月23日には泉城(笠間市泉)の戦いで「安房守家人長尾弾正」と合戦。この戦いで、筑波山社家被官の「家人小倉四郞左衞門尉」が「其時節潤朝依為幼少、為代官」として「属完戸安芸守持里之手、宍戸庄内於泉城打死仕」っているように(享徳四年二月「筑波潤朝軍忠状案写」(「古証文二」神奈川県史料6187))、筑波山南部域での対峙も続いていた。
嘉吉元(1441)年11月20日、室町殿義勝の「当代初度」の「武家評定始」が執り行われた(『建内記』嘉吉元年十一月十九日条)。場所は「御第、室町面東頬、北小路以北猶去北也」。義勝は「雖御童躰、如成人可有其儀」という。しかし、体調が優れない管領持之は、この儀に際して「管領可辞申之間、暫不可有沙汰」という。権大納言時房は「先猶行沙汰、追可辞退歟、人々不示意見歟、如何如何」と疑問を呈す。結局、評定始は「管領細川右京大夫持之朝臣、奉行頭人出仕以下、如年始之時」行われている。
続けて、嘉吉2(1442)年2月16日には「御読書始并御手習始」(『足利家官位記』)、翌2月17日には「武家沙汰始」(『公名公記』嘉吉二年二月十七日条)が執り行われている。
しかし、6月に入ると、管領細川持之の容態が悪化。持之が管領を辞したため、「入道左衛門督持国卿法名徳本、上階」(『別本執事補任次第』)が新たに管領職に就任する。畠山持国入道は嘉吉元(1441)年2月27日、従三位に上階しており(『公卿補任』)、「卿」の敬称となっている。そして8月4日、「先管領細河右京大夫入道、今日他界」した(『公名公記』嘉吉二年八月四日条)。「先管領細河右京大夫入道常喜従四位下持之朝臣、今日逝去、四十三歳也、自夏比風瘧之病悩」(『康富記』嘉吉二年八月四日条)という。子息の九郎勝元が十三歳で家督を継承している。持之は関東との関係においては、故斯波義淳と同様に都鄙無為を目指し、錯綜する関東との関係を再構築するために尽力した生涯であった。その後を追うように8月9日には信濃守護小笠原修理大夫政康が「於信州小縣郡海野」で急死した。六十七歳という(『小笠原系図』)。
8月22日には「畠山左衛門督入道、管領職之出仕始」(『康富記』嘉吉二年八月廿二日条)が行われた。午の刻、春日万里小路の館を出立した持国入道は「懸袈裟」けて「乗網代輿」り、扈従の騎馬武者は左右五番で十名、みな浅黄直垂の装いであった。
●管領供人数
| 番 | 左 | 右 |
| 一番 | 遊佐弾正 | 誉田三河 |
| 二番 | 遊佐蓮間 | 誉田遠江入道子息 |
| 三番 | 齊藤六郎左衛門尉 | 土肥 |
| 四番 | 洲田右京亮 | 齋藤兵庫 |
| 五番 | 神保 | 椎名次郎左衛門尉 |
この評定始の際に、「以伊勢守入道、自御前被仰下云、御元服事可然候様、可被計申沙汰」(『康富記』嘉吉二年八月廿八日条)があった。畠山入道は「今年中尤可然存候、御佳例等委細儀者、退出之後令談合人々、可申上御左右」と返答し、室町殿を退出後、諸大名に使者を遣わして意見を集めたところ、「或可為鹿苑院殿御例之由」という。持国入道の所存は「勝定院殿御佳例可然之由」(『康富記』嘉吉二年八月廿八日条)であった。
結局、11月7日に「室町殿御年九歳、義勝」の「御元服」が執り行われた。義満以来の先例では武家管領による加冠であったが、今回は関白持基による加冠ならびに「征夷将軍被宣下」、そして「正五位下」への「御昇進」(『康富記』嘉吉二年十一月七日条)、「禁色宣下」ならびに「左近衛中将」補任の宣旨があった(『足利家官位記』)。11月13日には「弓始并馬始」(『公名公記』嘉吉二年十一月十三日条)が行われ「小笠原民部少輔備前子」(『康富記』嘉吉二年十一月十三日条)が御師範を務めている。
この義勝の元服及び将軍宣下等は、おそらく早馬ですぐさま関東に伝えられ、11月13日の時点で常陸国の陣中にも知られていた(嘉吉二年十一月十三日「兵部少輔元□書状案」『鳥名木文書』室:3308)。正式な使節としては例の如く等持院主柏心周操が東国へ遣わされている。当時の鎌倉には憲実入道も兵庫頭清方(事実上の関東管領)も不在であり、柏心周操は憲実入道が在陣する白井に向かっていることから、東山道経由で上野国へ至ったと思われる。また、西上野での軍事面で余裕ができたのか、宍戸持里の籠る宍戸庄での戦端が緊迫していたのか、11月15日頃には鳥名木入道は常陸国金田に帰陣することが決定していた。なお、この文書中の「自白井御帰陣」の主語は、通説では上杉憲実だが、この文書における敬語の対象は一貫して鳥名木入道であるため、白井から「御帰陣」したのは憲実入道ではなく、鳥名木入道である。
●嘉吉2(1442)年11月13日「右馬允右詮書状」(『鳥名木文書』室:3307)
●嘉吉2(1442)年11月13日「兵部少輔元□書状案」(『鳥名木文書』室:3308)
柏心和尚は嘉吉2(1442)年11月初頭には白井宿に入っており、憲実入道と対面しているとみられる。柏心和尚の関東下向は表向きは将軍補任の報告であるが、情勢視察が本来の任務であろう。このとき、鎌倉殿(永寿王丸)の治定についても語られた可能性があるが不明。ただし、12月までには永寿王丸の還御について京都から関東に打診はあり、鎌倉の奉行人「前下野守義行」は鑁阿寺に対して「御寺領等事、還御候者、早々可有御申候、不可有相違事候」(嘉吉二年カ十二月十八日「前下野守義行巻数請取」『鑁阿寺文書』)としている。
また、「上様」へ「巻数御進上」について、「達 上聞」したことに、「前下野守義行」は「御返事進之候」という。この御返事については、本来は「自政所」進上するものであるが、現在鎌倉殿が不在であるため政所は機能しておらず、やむなく「当年事者、愚身蒙仰、方々へ御返事進之候」という。なお、この文書の年次は龍福院が鑁阿寺の年行事であるため、嘉吉2(1442)年であることがわかり、文中にある「御代始」は、通説の「万寿王丸」が信濃国の大井氏のもとで行ったという「かなり説明が苦しい御代始」ではなく、この一月前に将軍宣下を受けた将軍義勝の「御代始」であろう。前下野守義行はこの「御代始」について「未寺家より御礼無御申候、不可然候歟」と嗜め、「殊当寺事ハ不可被准他寺事候間、御礼被申可然存候」と、鑁阿寺と足利家の由緒は深く他の寺とは比べ物にならず、すぐに御礼を申し上げるべきであると述べているのであろう。
●嘉吉2(1442)年12月18日「前下野守義行書状」(『鑁阿寺文書』)
文安元(1444)年12月18日には「当寺供僧中」に奉行人「前下野守(義行)」が鑁阿寺から納められた歳末の御巻数を鎌倉殿に渡した旨の御教書を発給している。この歳末の御巻数は、鑁阿寺が例年12月18日またはその前後数日間に鎌倉殿へ納めるものだが、当時の鎌倉殿は京都にあることから、関東管領が代理で請けた可能性があろう。上記書状と下記御教書は、同日に出されたという説もあるが、まったく関係性はない。
●文安元(1444)年12月18日「御教書」(『鑁阿寺文書』13)
その後、関東の動静に関する史料がないことから、上杉憲実入道の動きは不詳。関東や奥州の情勢も伝わらず、京都においても関東の動きを伝える史料はみられない。
この頃、両総では千葉介胤直入道が弟の胤賢入道と連名で嘉吉2(1442)年2月、上総国山辺郡の観音教寺(山武郡芝山町芝山)に宝塔造立を期し(落成年不明)、同年11月には印西庄の竜腹寺(印西市竜腹寺)に宝塔造立を開始している(落成は宝徳3年)。竜腹寺宝塔の「彼塔勧進帳」は「千葉相応寺開山覚尊法印」が撰している。千葉相応寺は胤直入道が開基となっている寺院(現在は廃寺。北斗山金剛授寺東側にあった。開山が「覚尊」とあるように「覚」字があることから、金剛授寺僧と思われ、金剛授寺の塔頭寺院か)である。これらの宝塔寄進は前年の嘉吉元(1441)年6月24日に京都で討たれた将軍義教を悼むものか。また、記名を見ると、胤直・胤賢兄弟は嘉吉2(1442)年2月までは出家しておらず、11月までの間に出家したことがわかる。
●嘉吉2(1442)年2月「観音教寺造営宝塔一基棟札」(『千葉県史料』金石文篇一)
●嘉吉2(1442)年11月「竜腹寺造営宝塔一基棟札」(『千葉県史料』金石文篇一)
嘉吉3(1443)年正月5日、将軍義勝は「従四位下」(『足利家官位記』)に叙された。
●嘉吉3(1443)年正月6日叙位儀(『建内記』)
| 人名 | 家名 | 叙位 | 現任 |
| 藤原房平 | 鷹司 | 従一位 | 右大臣 |
| 雅兼王 | (白川) | 従二位 | 神祇伯 |
| 藤原隆遠 | 鷲尾 | 正三位 | 参議 |
| 丹波有康 | 正四位上 | 前典薬頭 | |
| 和気茂成 | 前典薬頭 | ||
| 丹波頼豊 | 典薬頭 | ||
| 丹波季長 | 施薬院使 | ||
| 藤原教季 | 今出川 | 従四位上 | |
| 丹波盛長 | |||
| 和気保成 | |||
| 藤原忠綱 | 従四位下 | ||
| 賀茂在盛 | 勘解由小路 | ||
| 安倍有季 | 土御門 | ||
| 藤原経仲 | |||
| 源義勝 | 征夷大将軍 左中将 |
||
| 藤原資重 | 正五位上 | 左少弁 | |
| 藤原定嗣 | 花山院 | 正五位下 | |
| 源忠具 | 愛宕 | 従五位上 | |
| 藤原高清 | |||
| 藤原雅友 | |||
| 清原宗賢 | 舟橋 | ||
| 菅原為賢 | 五條 | ||
| 藤原勝光 | 日野 | ||
| 藤原公躬 | 正親町三條 | 従五位下 | |
| 藤原宣胤 | 中御門 | ※頭弁(明豊)男。二歳。 | |
| 藤原宣■ | |||
| 丹波顕長 | |||
| 中原師益 |
3月22日には日野右大弁資任(若公母藤原重子の従弟)の「養君」である「室町殿若公将軍舎弟六歳、同腹」が、「今日聖護院御入室」(『看聞日記』嘉吉三年三月廿二日条)している。この聖護院入室の若公は義勝と同腹の弟ということで、早々に僧侶としての道に入れ、後顧の憂いを断つ目的があったと思われるが、彼はのちの八代将軍義政となっている。4月5日、正式に「今日聖護院若公御入室、自今常住可有御座」となった。なお、まだ六歳という「御年少之間、女房五人かいしやく、御ちの人祗候、坊官岩坊ニ被置申」(『看聞日記』嘉吉三年四月五日条)という措置が取られている。
6月19日、「高麗人参于室町殿、懸御目者也」(『康富記』嘉吉三年六月十九日条)した。義勝将軍の代替わりにて「御代初度」の面会となったが、この面会で、去年の播磨合戦で「没落播州、不知行方」となっていた「赤松左馬助故満祐法師弟也、謀叛人也」の動向が明らかとなった(『建内記』嘉吉三年六月十九日条)。赤松左馬助則繁は播磨国から逐電すると、「菊池被相憑、越于高麗国、打取一ヶ国、及難儀之由、今度高麗人歎申」といい、菊池氏を頼って朝鮮半島へ渡り、高麗に侵入して国内を暴れまわって困っているという。これに「可被退治之由、有沙汰」と、討伐するよう依頼している。
この謁見から約一月、大きな事件もなく、武家方は高麗使者の接待を行っているが、その最中、7月16日、「室町殿、自十三日痢病以外」という義勝の体調不良の報告が貞成入道親王の耳に入る(『看聞日記』嘉吉三年七月十六日条)。また、時房のもとにも「室町殿御痢病云々、又聞御霍乱云々、…、以外御坐」(『建内記』嘉吉三年七月十六日条)との話が聞こえている。義勝は「自十二日御痢病」(『建内記』嘉吉三年七月十九日条)、13日に「御腹煩」(『愚記』嘉吉三年七月十三日条)、「十三日与盛及十度許、温気以外」(『建内記』嘉吉三年七月十九日条)以降、15日夜までは「医師典薬頭頼豊朝臣進御薬、随少減」だったが、今朝からは「シュ阿弥、セイ阿弥等進御薬之処、以外増気、於今者珍事」(『愚記』嘉吉三年七月十六日条)になり、「医師共難儀之由申、被留食事、以外御式」(『看聞日記』嘉吉三年七月十六日条)と、相当重篤な胃腸障害であることに、時房は「驚入」っている。実は7月13日を境に、公卿で数件の胃腸障害の報告がなされており、集団的な感染事例の可能性がある。
| 人名 | 症状 | 発症 | 出典 |
| 足利義勝 | 室町殿、自十三日痢病以外 | 7月13日 | 『看聞日記』嘉吉三年七月十六日条 |
| 室町殿御痢病云々、又聞御霍乱云々 | ―――― | 『建内記』嘉吉三年七月十六日条 | |
| 三條実量 | 予、自晩景霍乱以外也 | 7月13日夜 | 『愚記』嘉吉三年七月十三日条 |
| 万里小路時房 | 於方丈謁住持、依痢気、大阿伽陀被与之 | 7月14日 | 『建内記』嘉吉三年七月十四日条 |
翌17日も「室町殿以外御式」で病気は「赤痢病也」という。義勝は良薬により「聊有其験、度数小減」(『看聞日記』嘉吉三年七月十七日条)といい、翌18日も「於痢病御小減」(『看聞日記』嘉吉三年七月十八日条)となるも、14日頃からは「邪気以外之間、始終可有如何候哉」と医師の和気茂成朝臣に詳細を訪ねている。その答えは「邪気よりましに付て、一色、赤松等種々申、普広院殿御子孫七代まては可取殺之由申」というもので、義勝には義教に殺害された一色義貫や先年攻殺された赤松満祐入道が憑りついており、義教の七代末葉まで憑り殺すという話だった。この話は時房も「室町殿御痢病之上、有邪気之疑、仍召験者奉加持、渡物付之処、故一色義貫於大和陣依普広院殿仰誅之、死霊也、不被残子孫之条」(『建内記』嘉吉三年七月十七日条)、三條実量も「邪気又有之云々、故一色大夫、故赤松入道等悪霊」(『愚記』嘉吉三年七月十六日条)と聞いている。
翌19日も昨日に引き続いて「室町殿御腹ハ小減」といい(『看聞日記』嘉吉三年七月十九日条)、霍乱の症状は少なくなっていたようであるが、「室町殿御痢気御減、御邪気未散歟云々、一色故義貫并鎌倉故武衞等」(『建内記』嘉吉三年七月十九日条)といい、「邪気怨霊非一、鎌倉故武衞、一色故義貫、赤松故性具等」(『建内記』嘉吉三年七月十九日条)と、その影響はこれまでの一色義貫、赤松満祐に加えて鎌倉殿持氏の怨霊が指摘されているが、「主人、更不可有其恨、父公之余殃無力事也」(『建内記』嘉吉三年七月廿一日条)と感想を述べる。
19日夜は「室町殿御痢気、及八ケ度」ぶという。また、義勝のうわ言では「御邪気者、赤松故性具法師、可被残子孫之由、歎申」(『建内記』嘉吉三年七月十九日条)といい、満祐入道の霊は「故彦次郎子存生也、両人有存知之者、可被召出之由、申請」したという。
翌20日には、さらに「室町殿邪気火急御式」(『看聞日記』嘉吉三年七月廿日条)という。「前典薬頭茂成朝臣、良薬御減気」あったが、「御下血等以外御窮屈」となり、「難儀至極之由、諸医申之」という一方で、長生庵のように「存傷風下血之由、所詮御療治相違」と主張する医師も出ている(『建内記』嘉吉三年七月十九日条)。
この日は「昼夜立雷鳴、至夜魄飛雨、世俗ハコヒ雨ト云、本説魄飛雨也、タマシヰ飛雨也、昌耆説也」という豪雨が京都を襲うとともに、「賀茂大木顛倒、凡賀茂山衆木、千本許枯之由注進」があったように、不吉の前兆与思われる事柄が貞成入道親王の耳に入っている。義勝の容態を聞いた人々が次々に室町殿へ参集し、聞いたところでは義勝は「大略事切之様ニ見へ給、而只今聊被取直様也」だが、これはラストラリー現象と推定でき、人々もこれを理解し「大略今明事歟驚入、為天下珍事也」と、おそらく明日明け方が山だろうとの診立てであったようである。
そして翌21日早朝、「室町殿、已入死門給了」(『愚記』嘉吉三年七月廿一日条)、「卯刻室町殿征夷大将軍左中将、従四位下、十歳、御名義勝、普広院殿御長子、御事切」(『建内記』嘉吉三年七月廿一日条)という。貞成入道親王のもとにも「室町殿、天明之時分、有御事」という報告が入っている。昨日の報告で予想はしていたものの、貞成入道親王は一報を受けると「驚歎無極、此間天変、諸社怪異等果而如此」との感想を述べる。「此間天変」とは賀茂社の大木顛倒(「今月二日、賀茂社有猿楽、其時分社頭大木二またよりさけて顛倒、風不吹ニ折、不思儀也」(『看聞日記』嘉吉三年七月十六日条))を指すのだろう。将軍義勝の早世は「為天下殊驚存」だが、「舎弟済々御座之上者、相続不可断絶歟、然而世物言、可有如何候哉」(『看聞日記』嘉吉三年七月廿一日条)との感想を述べている。
義勝の病態は、もともとは感染性胃腸炎と思われるが、次第に霍乱の症状は減少するも譫妄がみられるのは、飲水障害・摂食障害による極度の脱水症状により電解質バランスが極度に悪化した影響だろう。酷暑も災いして年少の義勝は一揆に容態が悪化したのだろう。
将軍薨去に伴い、「管領畠山三位入道、招三條、中山相談事在之」った。その用事が終わり、中山定親が室町殿を出亭しようとした際に、万里小路時房に出会ったので、管領畠山入道との話を告げている。それによれば畠山からは「御贈官事、可非申哉之由」の相談だったという(『建内記』嘉吉三年七月廿一日条)。定親は時房に「公儀異他、可被申之条何事有乎、但御浅官也、贈官可為何官哉」という。時房は「但不依本位之早浅、被贈高官之例、曩祖良門、雖浅官浅位被贈太相国、上古猶定有例歟、尤可被勘哉、於近例者、一向無懸隔之例歟、此御事各別之儀也、定不可有子細之由、相存之旨」と語り、定親もこれに同意した。この結果、贈位贈官は義満・義持・義教三御代(自丞相被贈相国)と、尊氏・義詮両御代(自大納言被贈左大臣)の先例を鑑み、「今自浅官不可過両御代例之故」を以て、「左大臣」の贈官と治定する。
7月23日早朝、義勝の遺骸は等持院へ移された。その後、「於管領家、諸大名集会評定」しているが、「是将軍仁体事談合」のためという。ここで「烏丸頭右中弁資任朝臣宿所事若公故室町殿御一腹也令治定」(『愚記』嘉吉三年七月廿三日条)、「御相続若公、資任朝臣養君治定」(『看聞日記』嘉吉三年七月廿三日条)した。後継となったこの若君は、3月22日に聖護院に入室した六歳の若君で「御容顔豊満美麗、吉相悉備、安上治下万歳千秋兆也」(『建内記』嘉吉三年七月廿三日条)という。在所は日野烏丸資任亭で「武者小路以南、転法輪以北、万里小路以西、東面唐門」にあった(上京区一松町付近か)。
同日、故義勝は「贈官従一位左大臣宣下」(『看聞日記』嘉吉三年七月廿四日条)される。ところが、21日に亡くなった義勝の葬儀は、酷暑にも拘らず実に八日間も延引され、29日まで行われなかった。これには貞成入道親王も「于今延引不審也」と記しているが、これは「今日俄不可事行、明日管領衰日、明後日寅、廿六日卯御衰日、廿七日辰、廿八日不可然、仍可為来廿九日午」と、日次の問題であったが。ただ、時房も「以外経数日、炎暑之時分、難儀事歟、然而無日次之故也」と嘆いている(『建内記』嘉吉三年七月廿三日条)。
7月29日朝、ようやく「御葬礼」(『建内記』嘉吉三年七月廿九日条)が執り行われた。その後、「将軍荼毘今晩」となるが、その際、等持院主「ハクシン和尚」が「起龕仏事忘却、逐電、被召返」(『建内記』嘉吉三年七月廿三日条)と、柏心周操和尚が出棺仏事での誦経を忘却したのか、恥じて仏事を辞退してしまう事件が起こったものの「被召返」されている。義勝の法名は道春。追称は慶雲院。道号は栄山と定められた(『建内記』嘉吉三年七月廿三日条)。遺骨は等持院に納められるが、10月4日に「慶雲院殿様御遺骨一分事」として、父普広院殿と同様、一部は高野山安養院に分骨された(『蔭涼軒日録』長禄三年五月十二日条)。
嘉吉3(1443)年9月23日夜半(子刻)、突如として土御門東洞院殿(上京区京都御苑3)に「悪党三四十人許」(『看聞日記』嘉吉三年九月廿三日条)、「件凶徒等弐百余人」(『康富記』嘉吉三年九月廿三日条)が乱入して、内裏が炎上した(『看聞日記』嘉吉三年九月廿三日条)。将軍義勝の薨去後二か月という、世上の落ち着かない京都に起こった凶事だった。
●嘉吉3(1443)年9月23日当時の土御門殿(北正親町、南土御門、東高倉、西東洞院、方四町)の諸門
| 方 | 門 | 門様式(接続) | 担当 | 警衛 |
| 西面 | 北門 | 唐門(長橋局通) | (巡役)摂津掃部頭 | (今夜)摂津掃部頭被官人 |
| 南門 | 四足(左衛門陣) | 管領 | 畠山被官諸分国之人等(号大番役) | |
| 北面 | 上土門 | (巡役)武家近習 | (今夜)一番衆曽我兵庫助被官人等 | |
| 東面 | 棟門 | (巡役)佐々木黒田入道 | (今夜)佐々木黒田入道被官人 | |
| 南面 | 無門 ※里内裏のため |
|||
この事件は「南方謀反大将號源尊秀、其外日野一位入道与力之、悪党数百人」(『看聞日記』嘉吉三年九月廿四日条)、「彼大将、南方護聖院宮子僧兄弟両人也、一人ハ金蔵主此間在万寿寺、一人ハ通蔵主此間在相国寺」(『師郷記』嘉吉三年九月廿六日条)と、南朝再与を目指した「南方高秀沙汰之」による三種の神器奪取と「金蔵主」の「太上皇帝位」即位であった(『天地根元歴代図』)。
大将源尊秀もまた「鳥羽後鳥羽院後胤云々、鳥羽尊秀ト號」(『康富記』嘉吉三年九月廿六日条)とあるように、後鳥羽院の後裔を自称し、鳥羽名字を称していた。後鳥羽院の直接的な後胤で源氏を称したのは順徳源氏のみであるが、「尊縁」という「太上天皇之貴胤也、而当年依無之、可号土御門内府息之由宣下」(『三会定一記』一)、「尊縁 太上天王御息」(『維摩会講師研学竪義次第』)という落胤もあり、彼は源姓となろう。また、承久の乱で備前国へ流された冷泉宮頼仁親王の末裔も不明であり、尊秀はこうした人々の末裔かもしれない。
●『本朝皇胤紹運録』
+―藤原良経―――――――――藤原立子
|(太政大臣) (東一条院)
| ∥
藤原兼実―+―藤原任子 ∥
(関白) (宜秋門院) ∥
∥――――――――昇子内親王 ∥―――――仲恭天皇――義子内親王
∥ (春華門院) ∥ 【九条廃帝】(准三宮)
∥ ∥
∥ 瀧 ∥
∥(舞女) ∥
∥∥―――――――覚仁法親王 ∥
∥∥ (桜井門跡) ∥
∥∥ ∥
∥∥丹波守 ∥
∥∥∥ ∥
∥∥∥――――――粛子内親王 ∥
∥∥∥ (斎王) ∥
∥∥∥ ∥
∥∥∥右衛門督 ∥
∥∥∥(舞女) ∥
∥∥∥∥―――――熈子内親王 ∥
∥∥∥∥ (斎王) ∥
∥∥∥∥ ∥
∥∥∥∥中納言典侍 ∥
∥∥∥∥∥ ∥
∥∥∥∥∥――――保寿院道守 ∥
∥∥∥∥∥ (法印) ∥
∥∥∥∥∥ ∥
∥∥∥∥∥ 姫法師 ∥
∥∥∥∥∥(舞女) ∥
∥∥∥∥∥ ∥――禅林寺覚譽 ∥
∥∥∥∥∥ ∥ (大僧正) ∥
後 鳥 羽 院 ∥
∥∥∥∥∥ ∥ ∥ 【順徳源氏】
∥∥∥∥∥ ∥――――+―順徳天皇――+―忠成王―――源彦仁―――忠房親王――源彦良――源彦忠
∥∥∥∥∥ ∥ | |(岩蔵宮) (右中将) (弾正尹) (参議) (左中将)
∥∥∥∥∥ 藤原重子 | |
∥∥∥∥∥(修明門院)| +―彦成王
∥∥∥∥∥ | |
∥∥∥∥∥ | |【順徳源氏】
∥∥∥∥∥ | +―善統親王――尊雅王―――源善成
∥∥∥∥∥ | |(四辻宮) (左大臣)
∥∥∥∥∥ | |
∥∥∥∥∥ | +―尊覚法親王
∥∥∥∥∥ | |(天台座主)
∥∥∥∥∥ | |
∥∥∥∥∥ | +―覚恵法親王
∥∥∥∥∥ | |(聖護院門跡)
∥∥∥∥∥ | |
∥∥∥∥∥ | +―諦子内親王
∥∥∥∥∥ | |(明義門院)
∥∥∥∥∥ | |
∥∥∥∥∥ | +―穠子内親王
∥∥∥∥∥ | (永安門院)
∥∥∥∥∥ |
∥∥∥∥∥ +―雅成親王――――澄覚法親王
∥∥∥∥∥ |(六條宮) (天台座主)
∥∥∥∥∥ |
∥∥∥∥∥ +―尊快入道親王
∥∥∥∥∥ (天台座主)
∥∥∥∥∥
∥∥∥∥∥――――――+―道助入道親王
∥∥∥∥∥ |(御室)
∥∥∥∥∥ |
∥∥∥∥坊門信清女 +―礼子内親王
∥∥∥∥(坊門局) |(嘉陽門院)
∥∥∥∥ |
∥∥∥∥ +―頼仁親王――――上乗院道乗
∥∥∥∥ (冷泉宮) (大僧正)
∥∥∥∥
∥∥∥∥―――――――――粛子内親王
∥∥∥∥ (斎王)
∥∥∥丹波局
∥∥∥(少納言信康女)
∥∥∥
∥∥∥――――――――――道覚入道親王
∥∥∥ (天台座主)
∥∥尾張局
∥∥
∥∥―――――――――+―四辻姫君
∥∥ |
∥大宮局 |
∥ +―尊円法親王 +―春子女王
∥ |(聖護院) |
∥ | |
∥ +―行超 +―覚子内親王
∥ (権大僧都) |(正親町院)
∥ |
∥――――――――――――土御門天皇 +―仁助法親王
∥ ∥ |(三井寺長吏)
∥ ∥ |
源通親――+=源在子 ∥―――――+―後嵯峨天皇
(内大臣) |(承明門院) ∥ |
| ∥ |
+―源通宗――――――――――源通子 +―静仁法親王
|(左大臣) (典侍) (熊野検校)
|
+=尊縁(後鳥羽院落胤)
「通蔵主」「金蔵主」
南朝勢力による土御門東洞院内裏乱入事件(禁闕の変)に際し、南朝方の旗頭に据えられた「通蔵主」「金蔵主」は、「兄弟也、後亀山院子」(『康富記』嘉吉三年九月廿六日条)、「禅僧通蔵主後亀山御子、金蔵主兄」(『康富記』嘉吉三年九月廿八日条)とあるように、後亀山天皇の猶子か。
彼らは「南方護聖院宮子僧兄弟両人也、一人ハ金蔵主此間在万寿寺、一人ハ通蔵主此間在相国寺」(『師郷記』嘉吉三年九月廿六日条)とあり、彼らの実父は護聖院宮世明王で、永享6(1434)年6月中旬頃に父の「世明宮」が亡くなり、6月26日に「南方護聖院宮遺跡、当年五歳歟」と、護聖院宮は長男(のち通蔵主)が継承した。
しかし、8月20日、義教は「南方、護聖院両人喝食ニ被成申、不可被置御遺跡云々、奉公殿上人等少々禁裏可被召仕之由、以日野内裏へ被申云々、凡南方御一流、於于今可被断絶云々、喝食ハ常徳院主海門和尚、鹿苑院主等弟子ニ被成申」(『看聞日記』永享六年八月廿日条)と、世明王の子(のちの通蔵主、金蔵主)への護聖院宮領の継承を不可とし、五歳の長男(通蔵主)を常徳院主海門承朝(長慶天皇子)へ、その弟を鹿苑院主宝山乾珍(足利直冬子)にそれぞれ喝食として預けることとした。これにより「宮家断絶、奉公人遺領處分」(「看聞日記』永享六年九月廿六日条)と、護聖院宮は断絶となった。
この措置は、半年前の永享5(1433)年12月18日、「相応院新宮南方上野宮御子、自公方侍所 被仰付搦申、門主ハ御室ヘ御入申、其間ニ侍所門跡へ参取申懸縄云々、御形儀悪物之間、公方へきこえて被搦申」(『看聞日記』永享五年十二月廿日条)と、彼らの叔父に当たる仁和寺相応院新宮が「有隠謀之企」として捕らえられており、この影響があるとみられる。相応院新宮は応永30(1423)年8月16日の相応院入室以来「室町殿被計申、裏松中納言毎事申次」(『看聞日記』応永卅年八月十六日条)でいたが、「此仁悪行以外」(『満済准后日記』永享五年十二月十八日条)という悪評(南朝方との繋がりか)があり、「相応院新宮事、隠謀企虚名也、更ニ無其支証」(『看聞日記』永享五年十二月廿三日条)との説もあったが、捕縛され、永享6(1434)年5月16日、「相応院新宮も流罪、但被行死刑云々」(『看聞日記』永享六年五月十六日条)となった。
通蔵主、金蔵主の「不可被置御遺跡」の措置は、この叔父相応院新宮の逮捕から三か月程しか経過しておらず、この幼い兄弟を奉じた隠謀を恐れたための措置であろう。「護聖院宮、是又世明宮両息入釈門、相国寺喝食也」(『建内記』嘉吉三年五月九日条)としたのち、十年余りが経過し、兄の通蔵主は常徳院にそのまま出仕し、弟の金蔵主は鹿苑院から万寿寺へ移されていたようである。彼らは蔵主に据え置かれている通り、一僧侶として生活しており、皇胤の待遇は与えられていなかったようだ。
そして十五歳の通蔵主、十二、三歳と思われる金蔵主は、鳥羽尊秀の誘いを受けて、南朝再与の謀に加わったのだろう。彼ら兄弟が皇胤という自覚を持っていたかは定かではないが、尊秀は日野一位入道という朝廷重鎮にして現帝外戚たる人物をも取り込み、南朝皇胤を明確に示したうえで誘ったと思われる。
結局、この挙兵により宝剣、神璽を奪うことに成功した金蔵主、通蔵主であったが、宝剣はなぜか清水寺堂中に返却されており、神璽のみを持って比叡山に登り根本中堂などに籠ったが、綸旨ならびに武家の御教書を受けた山門衆徒に攻められ、金蔵主と日野一位入道は討死。通蔵主は捕縛され、源尊秀は逐電という結末を迎える。
その後、通蔵主は四国に流されたが、その後の動静は不明である。
●南朝皇胤系図(一部想像)
●後醍醐院――後村上院―+―長慶院――+―行悟大僧正
| |(円満院)
| |
| +―海門承朝
| (相国寺鹿苑院)
|
| 【小川宮】
+―後亀山院―+―恒敦宮―――――小川宮聖承――権僧正教尊
| | (勧修寺長吏、安祥寺寺務)
| |【護聖院宮】
| +=通蔵主
| |(相国寺常徳院僧)
| |
| +=金蔵主
| (万寿寺僧)
|
| 【護聖院宮】
+―説成親王―+―円悟僧正
(上野太守)|(円満院)
|
+―円胤大僧正
|(円満院)
|
|【護聖院宮】 【護聖院宮】
+―世明宮―――+―通蔵主
| |(相国寺常徳院僧)
| |
+―相応院新宮 +―金蔵主
(万寿寺僧)
鳥羽尊秀の内裏乱入は巧妙に仕組まれており、凶徒は「凶賊二、三百人、於神泉苑群集、或著甲冑者在之、悉不帯兵具歟」し、「可打入管領宿所大炊御門、万里小路」や「可乱入室町殿北小路、万里小路」という風聞を流したという。この風聞を宮中に流布したのは、おそらく「日野一位入道有光」(『公名公記』嘉吉三年九月廿六日条)であろう。
日野時光―+―日野資康―――日野重光―+―裏松義資―――日野政光―+―日野勝光
(権大納言)|(権大納言) (大納言) |(権中納言) (右少弁) |(左大臣)
| | |
| +―藤原重子 +―藤原富子
| (勝智院) (妙善院)
| ∥――――+―足利義勝 ∥
| ∥ |【七代将軍】 ∥
| ∥ | ∥
| 足利義教 +――――――――足利義政
| 【六代将軍】 【八代将軍】
|
+―日野資数―――日野有光―――日野資親――子息
(権大納言) (権大納言) (左大弁)
これを聞いた奉公衆や外様以下の人々は「俄馳参室町殿致警固皆帯甲冑、斯波徳千代殿越前尾張遠江等守護手令警固大門也」、または「管領手各馳集屋形」「其外諸大名等各致身之用心許也」(『康富記』嘉吉三年九月廿三日条)と、諸士は斯波徳千代の手に属して室町殿の警固に召集されたり、管領畠山亭に集合したりして、「於禁門警固者、如常而不被副人数、只門々纔人数有有名無実也」と、内裏の警固はまったく手薄となってしまったのだった。彼らの内裏乱入の目的は神器の奪取であるため、「於室町殿者、有警固武士、不可叶之間、不打入」であって、彼らは室町殿に敢えて攻め入ることもなく、手薄となった内裏にやすやすと「件凶徒等弐百余人、自門々手分して乱入之間、門役迷惑不及防支云々、所詮自門々凶徒乱入内裏」(『康富記』嘉吉三年九月廿三日条)したのであった。
南朝方はまず西面北側の唐門から「乱入内裏、先局町、長橋辺付火」し、御所の人々が「上下仰天之處」を「賊徒抜兵仗、切登堂」った。このため、「御所様、議仗所へ御逃アリテ、殿上ノ後ヘ出御」した(『看聞日記』嘉吉三年九月廿四日条)。このとき、供奉の甘露寺親長と四辻季春は太刀を抜いて賊徒と渡り合い、斬り払って天皇を逃し奉った。天皇は「潜令微服御」(『康富記』嘉吉三年九月廿三日条)し、「御冠ヲ脱デ女房躰にて唐門ヨリ逃出御」(『看聞日記』嘉吉三年九月廿四日条)ったが、甘露寺親長は賊徒と渡り合ったまま行方がわからなくなっており、このとき御供は四辻季春一人であった。天皇はまず「裏辻宰相中将家」「正親町宰相持季卿第内裏之咫尺也、四條少将季春一人御供」へ渡御した(『康富記』嘉吉三年九月廿三日条)。しかし、裏辻亭は御所裏築地のある西面南門(四足門)門前(上京区京都御苑内宜秋門前、中売立御門内南側)にあって「雖然御敵之余党、非無御怖畏」のため、また秘かに「広橋中納言家」(『看聞日記』嘉吉三年九月廿四日条)、「日野中納言兼郷卿亭」(『康富記』嘉吉三年九月廿三日条)へ渡御した。広橋亭は「鷹司西、烏丸以東」(『建内記』文安元年四月三日条)とあるが、烏丸以東で鷹司通と接している(鷹司西の表記が不審)ため、現在の皇宮警察本部辺り(上京区京都御苑内)と考えられる。その後、「彼卿御供仕」て左大臣亭への渡御が決定され、天皇は御輿に乗って烏丸通りを挟んだ西隣の「陽明へ臨幸」した。ただ、ここでひと悶着があった。「奉入左大臣殿第近衞殿」について、天皇は「此間、腰輿雖舁参、猶不乗御哉」(『康富記』嘉吉三年九月廿三日条)と、天皇は腰輿に乗ることを拒否したのである。当初は広橋亭斜向(南東)の花山院亭(上京区京都御苑内)へ「夜中、令幸花山第歟、但其間事、為御用心之間、伝奏尹大納言定親卿外無知人矣」だったが、結局、「自花山院第被用御輿猶非腰輿歟、若本所被進哉、未明令幸近衞殿給」と、蔵人所から引っぱり出されてきたと推測される輿(輦か)で近衞亭に行幸した。この「陽明左府第近衞北、室町東也(上京区近衛町)」(『康富記』嘉吉三年九月廿三日条)の隠密行幸は「隠密之間、御家人誰モ不参、賢所渡御之後露顕、女中モ方々ヨリ参入」(『看聞日記』嘉吉三年九月廿四日条)し、「公武人々馳参之間、以武士被致門々警固畢」と、近衞左府房嗣の邸宅は臨時の御所として体裁が整えられた。
一方御所では、大納言典侍が内侍所から「宝剣并神璽」を持って脱出を試みたが、「凶徒奪取、無力被取て女中右往左往江逃出」(『看聞日記』嘉吉三年九月廿四日条)した。そして「凶徒、清涼殿ニ乱入、先剣璽奪取、已剣璽ハ奉取ぬ、可付火之由下知、殿々放火」(『看聞日記』嘉吉三年九月廿四日条)し、「大内悉焼亡、東西棟門計残」(『東寺執行日記』嘉吉三年九月廿三日条)、「紫宸殿、清涼殿、常御所、小御所、泉殿、内侍所已下、至四方門々払地焼畢、東門并西面南門左衛門陣四足免炎上了、御泉水ノ山中亭一宇纔焼残矣」(『康富記』嘉吉三年九月廿三日条)という。なお、「昼御座御剣」は天皇自ら手に取って出御されたものの、「不知其実否者也」ながら「其外御物、御記、御器以下重宝大略焼失」(『康富記』嘉吉三年九月廿三日条)という。内侍所の御辛櫃は「三條大納言実雅卿之青侍之中、三井中務已下、東門役相共奉出」り、「奉安置伏見入道親王御在所伏見殿自夜中令出御所給テ、刑部卿持経朝臣ノ宅、一條万里小路南頬宿所ニ御座アリ、内侍所此御所ニ奉納之、及翌日者也、然間奉行飯尾肥前入道子共并飯尾加賀子左近大夫松田已下、於此所致内侍所之警固者也、此帯甲冑兵具、召具若党已下数十人参之」(『康富記』嘉吉三年九月廿三日条)した。
御所から神器を奪取した「源尊秀」「金蔵主」は「南帝使者相共、叡山中堂閉籠」った(『立川寺年代記』嘉吉三年九月廿三日条)。この報告は24日夜に「比叡山衆徒中、以飛脚申入管領」られたものだった(『康富記』嘉吉三年九月廿四日条)。それによれば、
●『康富記』嘉吉三年九月廿四日条
管領持国はこの報告を受けて「不日、可令追罰之由被仰下、且被成進綸旨於座主宮梶井殿、可有御下知三塔之由」を奏聞し、武家側も御教書を下すこととしたという(『康富記』嘉吉三年九月廿四日条)。これを受け、追罰の綸旨が下され(蔵人権右中弁俊秀が「御草宸翰」を示し、万里小路時房、尹大納言定親、清大外史業忠らが寄合い、文章に肉付け)、飯尾肥前入道が「自武家御使」として在京の山法師(山門使節の杉生坊、月輪院等)に綸旨を下し、「公武之御命」として山上に発向させた(『康富記』嘉吉三年九月廿四日条)。
そして9月25日夕方から早朝にかけて、綸旨と御教書を受けた山徒と南朝勢の間で、東塔根本中堂および西塔釈迦堂などで激しい合戦となった。根本中堂や釈迦堂に立て籠もったのは「金蔵主、通蔵主兄弟也、後亀山院子、金蔵主者万寿寺之僧也、通蔵主者相国寺常徳院僧也」「日野一位入道祐光俗名有光」「冷泉不知交名」「高倉ヽヽ」「鳥羽後鳥羽院後胤云々、鳥羽尊秀ト號」(『公名公記』嘉吉三年九月廿六日条)らであった。
山門衆徒の攻勢により「金蔵主并一品入道禅門等、矢庭被打也」(『康富記』嘉吉三年九月廿六日条)、「金蔵主、日野殿討死畢」(『天地根元歴代図』)ならびに「通蔵主者召捕」(『康富記』嘉吉三年九月廿六日条)と、その一角が崩されると、南朝方は「或取首、或生捕之」(『公名公記』嘉吉三年九月廿六日条)、「或打取、或擒入洛」(『公名公記』嘉吉三年九月廿六日条)し「御敵不日没落」(『公名公記』嘉吉三年九月廿六日条)した。そして「金蔵主」の首級及び「日野一位入道有光、加此衆之間、於山門致誅戮、頸執進之」(『公名公記』嘉吉三年九月廿六日条)られ、生け捕られた通蔵主も京都へ連行された。「其外雑兵不知数■■召捕之、今日終日所進上」されたが、内裏を攻めた大将「鳥羽ハ暗跡落失不知行方」とあるように捕らわれずに遁れ去ったという(『康富記』嘉吉三年九月廿六日条)。
9月27日、天叢雲剣は「宝剣、今日自管領執進之云々、自山門出来歟如何、或説云、於清水寺或者拾之」(『公名公記』嘉吉三年九月廿七日条)と、管領持国入道に執進されている。この宝剣は28日、持国入道より「至夜剣璽渡御真之宝剣無子細、錦袋に被入をとりのけて入布袋、鞘蒔絵を拭云々、清水法師奉之、御堂中に捨置云々、状を書そへて棄」られていたという。その状には、
こうして宝剣は戻されたものの、「神璽未出来、被尋求云々、定可出来歟、聖運顕然之上者、有憑」と、神璽は相変わらず行方不明となっていた。
また、「於山上被討之首、上了」(『康富記』嘉吉三年九月廿六日条)された日野一位入道の「息右大弁宰相資親卿」も「依勅命、管領召誡之」(『公名公記』嘉吉三年九月廿六日条)され、「未剋、右大弁宰相資親卿日野東洞院一位入道祐光子、被召捕之」ために「依之管領被官誉田等、向彼相公宿所欲捕」したところ、「彼出行」っており、追跡した誉田等は「於武者小路今出川辺召捕之」たという(『康富記』嘉吉三年九月廿六日条)。資親は屋敷から室町殿方面へ逃げていることから、室町殿へ弁明に出た可能性があろう。資親亭では「被官人青侍等十人許云々、於彼宿所取之搦之」った(『康富記』嘉吉三年九月廿六日条)。
26日夜申剋、天皇は「自近衞殿有行幸伏見殿、乗御網代車、女房車由也、無供奉人々卿相雲客、只兵士奉警固之、室町殿之小番衆大舘并五番衆等也」(『康富記』嘉吉三年九月廿六日条)と、父の貞成入道親王の伏見殿へ行幸し、内侍所もまた伏見殿へ渡御となった。これ以降、「伏見殿為皇居、此皇居西礼也、陣座被新造者也、西面四足内南脇被造之、南北行二ケ間、東西行三ケ間也、為北面、参議横座在西方、公卿南北対座あるへき様也、上卿ハ西面ニ可令著給也、北方有立蔀床子座、未被造之、仍自西方外記史参進了」(『康富記』嘉吉三年十一月廿九日条)という、土御門東洞院御所の修理が終わるまでは、手狭ながら臨時の皇居として正式に治定された。
9月28日、「京中ニテハ日野東洞院親子、御内方者九人、以上十一人ト召取之、廿八日、六條河原ニテ五十六人頸切之」(『東寺執行日記』嘉吉三年九月廿六日条)、「資親卿日野一品禅門子、於六條河原被刎首、其外召人五十余人被斬南方於山門召捕者、日野侍等也」(『看聞日記』嘉吉三年九月廿八日条)、「右大弁宰相、今日於八条河原被切之、子息少冠八歳同被誅云々、其外召人四十余人、今日引出六條河原被切之了、又聞、右大弁息誅戮事、虚説、令安宅」(『公名公記』嘉吉三年九月廿八日条)、「公家已下抱子、至誅流者不知数」(『看聞日記』嘉吉三年九月廿四日条)と、この謀叛に加わった人々が多数罰せられた。なお、日野資親は「日野右大弁宰相資親卿被斬首了八條猪熊辺歟云々、従類等、六條河原、各被切首了」(『康富記』嘉吉三年九月廿八日条)と、八条猪熊(京都市南区八条通)で斬られたとも伝わるが、八条猪熊は刑場ではないことや、資親被官人が六條河原で斬られていることから六条河原の誤伝であろう。「其外自山上退散之凶徒囚人等、悉以被誅了」と、叛乱に加わり捕われた人々も悉く斬刑に処され「冷泉首、資親卿被官人等首、取合二三十被懸六條河原了」(『康富記』嘉吉三年九月廿八日条)と、六條河原(京都市東山区)には彼らの首が大量に懸け渡された。このほか「雑人者被切棄頸了、頸四五十被積置河原許也、不及被懸之、凡下之族故也」(『康富記』嘉吉三年九月廿八日条)と、懸け渡られることすらない下人の首はただ積まれるのみという凄惨な状況だった。
「資親卿頸」は「於法成寺馬場、伝奏尹大納言定親卿被実検之」され、その後の処理が議されたが、「父祐光、此人首、不可被懸歟之由雖有沙汰、為朝敵之間、可被懸獄門也」とされた。しかし、「卒爾不可合期之間、一位入道父子并金蔵主首等不及懸之、被棄之」と急遽変更されている。この背景には「件一位入道者、光範門院称光院御母儀之連枝也、先帝称光院為御外戚、為卿位、旁不被懸之哉、内々有沙汰被尋申殿下前摂政殿、粗有御意見歟」があったとされる(『康富記』嘉吉三年九月廿八日条)。
また、捕らわれた「禅僧通蔵主後亀山御子、金蔵主之兄」は「被流罪、可為四国之由沙汰」と、四国への流刑と決定され、「被預置飯尾肥前入道」られていたが、9月28日に「被渡細川九郎方」され、「彼被官人香川請取之」っている(『康富記』嘉吉三年九月廿八日条)。
10月2日、武家方は勧修寺宮教尊僧正(小倉宮承聖の子で永享2年11月27日、12歳の時に故義教の猶子となり「教」の一字を賜る)が今回の宮中乱入に「御存知申聞有之テ」として、「当職参向申テ召取奉テ、京都へ御出畢」(『東寺執行日記』)し、併せてその「御坊人十六人召トル、二人ハ当座死亡、已上十八人申之、慈高院、報恩院ハ先落ラレ畢」という。5月9日に「近年自嵯峨移住、下京辺給」で示寂した小倉宮聖承は、2月には「南方小倉殿叛逆之企、大名引合申歟」「南方事為実者天下大乱、禁裏御大事驚入、仰天無極」(『看聞日記』嘉吉三年二月廿日条)、「南方叛逆之企、内通ハ勿論歟」(『看聞日記』嘉吉三年二月廿八日条)とあるように謀叛の噂もあり、小倉宮には強い警戒の目が向けられていたことがわかる(過去に数度にわたり出奔を繰り返してきた事実もある)。
●禁闕の変の南朝余党
| 余党 | 由緒 | その後 | 出典 |
| 通蔵主 金蔵主 |
護聖院宮、是又世明宮両息入釈門、相国寺喝食也 |
流刑 (通蔵主) 比叡山討死首は廃棄 (金蔵主) |
『建内記』 嘉吉三年五月九日条 |
| 禅僧通蔵主後亀山御子、金蔵主兄 | 『康富記』 嘉吉三年九月廿八日条 |
||
| 南方護聖院宮子僧兄弟両人也、一人ハ金蔵主此間在万寿寺、一人ハ通蔵主此間在相国寺 | 『師郷記』 嘉吉三年九月廿六日条 |
||
| 被流罪、可為四国之由沙汰 | 『康富記』 嘉吉三年九月廿八日条 |
||
| 源尊秀 | 鳥羽後鳥羽院後胤云々、鳥羽尊秀ト號 | 逐電 | 『康富記』 嘉吉三年九月廿六日条 |
| 南方謀反大将號源尊秀、其外日野一位入道与力之、悪党数百人 | 『看聞日記』 嘉吉三年九月廿四日条 |
||
| 日野有光 | 日野一位入道与力之、悪党数百人 | 比叡山討死 首は廃棄 |
『看聞日記』 嘉吉三年九月廿四日条 |
| 日野一位入道祐光俗名有光 | 『公名公記』 嘉吉三年九月廿六日条 |
||
| 日野資親 | 資親卿日野一品禅門子 | 斬首後首は廃棄 | 『公名公記』 嘉吉三年九月廿六日条 |
| 冷泉 | 六条河原梟首 | 『公名公記』 嘉吉三年九月廿六日条 |
|
| 高倉 | 六条河原梟首 | 『公名公記』 嘉吉三年九月廿六日条 |
|
| 日野侍等 / 御内方者 |
其外召人五十余人被斬南方於山門召捕者 | 六条河原梟首 | 『公名公記』 嘉吉三年九月廿六日条 |
| 御内方者九人、以上十一人ト召取之、廿八日、六條河原ニテ五十六人頸切之 | 六条河原梟首 | 『東寺執行日記』 嘉吉三年九月廿六日条 |
|
| 勧修寺宮教尊僧正 | 「御存知申聞有之テ」として「当職参向申テ召取奉テ、京都へ御出畢」 | 『東寺執行日記』 | |
| (勧修寺)御坊人 | 御坊人十六人召トル、二人ハ当座死亡、已上十八人申之 | 『東寺執行日記』 | |
| 慈高院 | 勧修寺塔頭主 | 逐電 | 『東寺執行日記』 |
| 報恩院 | 勧修寺塔頭主 | 逐電 | 『東寺執行日記』 |
| 臼井 | 文安六年六月廿八日、山名被官人に尾張国で捕らえられる。 | 六条河原梟首 | 『康富記』 文安六年七月一日条 |
また、12月頃には播磨国の御料所東部「三郡(明石郡、賀東郡、三木郡)」が、御料所代官(三郡守護)だった赤松播磨守満政から「被付守護方山名金吾」(『康富記』嘉吉四年正月九日条)された。これは「惣領守護山名右衛門督入道持豊法名宗全、称軍功強望申之」(『建内記』文安元年正月廿二日条)んだことで、嘉吉4(1444)年正月22日、「管領成御書下、三ケ郡守護職彼一具拝領」という、「山名右衛門督入道宗峯俗名持豊、播磨新守護也、備後等守護也」(『建内記』文安四年七月十六日条)の強引な要求によるものであった。武家政権側も一門で十か国の守護職を有する強大な山名家を蔑ろにはできず、このような措置が取られたのだろう。
●山名家守護国
| 守護国 | 守護 |
| 山名持豊入道宗峯 | 但馬国、安芸国、備後国、播磨国 |
| 山名修理大夫教清入道常勝 | 石見国、美作国※(美作は満祐追討による「金吾被申給分」) |
| 山名兵部少輔教之 | 伯耆国、備前国※(備前は満祐追討による「金吾被申給分」) |
| 山名上総介熙高入道 | 因幡国 |
2月5日、元号が嘉吉から「甲子当革令否并改元定」と決定(『康富記』嘉吉四年二月五日条)。2月23日、「改元年号字文安事」とある通り、「文安」で治定した(『康富記』嘉吉四年二月廿三日条)。
●嘉吉4(1444)年2月5日改元案(『康富記』)
| 元号案 | 案者 |
| 承慶、文安 | 権中納言藤原兼郷 |
| 文安、平和 | 式部大輔菅原在直 |
| 寛永、建正、洪徳 | 従三位左大弁菅原朝臣益長 |
| 徳寿、安永 | 蔵人頭右中弁兼文章博士藤原朝臣資任 |
| 寧和、長禄、万和 | 従四位下行少納言兼侍従文章博士菅原継長 |
2月18日、「管領畠山金吾禅門、被辞申当職」し、「従今日被止諸奉行出仕」(『康富記』嘉吉四年二月十八日条)という。これを知った「大方殿室町殿之御母堂」は「上表不可叶之由」を強く述べたが(『康富記』嘉吉四年二月廿八日条)、持国入道は「無承引」であり、大方殿から報告を受けた「諸大名細川九郎、同讃州、山名金吾禅門等」は2月24日、「被申止当職辞退事」のために「被向管領畠山亭」い、管領辞退の撤回を説得したものの「雖然猶固辞也」(『康富記』嘉吉四年二月廿四日条)という。
しかし、「畠山左衛門督入道被上表管領職事」について、「管領職之巡次」は「今度斯波千代徳殿之番也」ながら、斯波家では「此仁幼稚也、未及首服時分也、職事不可叶之由被申」との返答であった。一方、細川家も「先管領細川九郎殿ハ、既此先ニ被持候間、不可持、其上未定判形之由被申」と、細川家は畠山持国入道の前に管領を務めているので拒絶し、さらに当主九郎勝元はまだ判形が定まっていない(当時十五歳ですでに家督者であるため、領内政治は行っており判形は定まっていただろう)ともしている。このため、「室町殿(実際は大方殿重子であろう)」は持国入道に「今両三年可為当職之由」を命じた。ところが持国入道は「尚無承引」であったため、2月28日、「大方殿俄有渡御畠山亭、強被仰」られた(『康富記』嘉吉四年二月廿八日条)。この突然の大方殿参亭に、さすがの持国入道も「渡御畏入之間、又可為管領之由、被申領状」している。
下総国においては、文安元(1444)年4月16日、「常瑞(胤直入道)」が「下総国千田庄田部(香取市西田部)」の「馬場備前守跡」のうち「諸給分」を除く分を海上庄円福寺へ寄進している。嫡子胤将は当時十一歳であるため、いまだ胤直入道が惣領家として千葉家を差配していたことがわかる。
●文安元(1444)年4月16日「千葉常瑞寄進状」(『円福寺文書』)
嘉吉4(1444)年4月19日に「原筑前守」が没すが(『本土寺過去帳』十九日上段)、同日に「円城寺因幡守」もまた卒している(『本土寺過去帳』十九日上段)。これは原氏と円城寺氏の対立に起因する抗争があった可能性があろう。
こうした中で、京内では対立組織の暴動の発生や、武家内での様々なひずみが表面化しており、文安元(1444)年閏6月19日には、「土岐美濃守護、於館討守護代戸島、然間戸嶋八郎左衛門、於屋形門外、掴石、石河久富石河子以上三人等、帰于戸嶋宅差殺、此三人者、土岐之被官人奉行人也、此三人殺了後、戸嶋之家放火、彼従類等参管領雖歎申、無一途之間、即馳下美濃」と、美濃守護土岐家内で紛争がみられ、夜には「細河治部少輔備中守護、被官人備中守護代以下押寄畠山匠作被官人私宅、欲及闘諍之處、属無為」という事件も起こった。7月1日には「六角被官人、令一揆、反四郎」して「近江守護佐々木六角四郎」が一門「佐々木大原」の屋敷へ遁れている。
8月5日には「南方宮方、於大和吉野奥被挙御旗之由」の一方が、「自熊野本宮令注進検校聖護院宮」された(『康富記』文安元年八月六日条)。まおた、べつの報告ではこの挙兵は「非大和、是紀伊国内」(『康富記』文安元年八月六日条)とされ、「上野宮御部類歟」と述べている。美濃国では8月6日、10日の両日、守護代戸嶋方の館に「守護方被官人齋藤」が寄せ来たという(『康富記』文安元年九月十一日条)。
そして10月26日早朝、「赤松播磨守大河内也満政入道父子、下向播磨国」(『康富記』文安元年十月廿六日条)という。この下向は「不申御暇潜走下」という、室町殿の許可を得ていないもので、中原康富も「疲労之間、為隠遁云々、如何」(『康富記』文安元年十月廿六日条)と疑問を呈している。このため、不審に思った室町殿の政権は「各々警固当国」のため「丹州、摂津両国守護代内藤、長塩下向」(『康富記』文安元年十月廿六日条)させている。おそらく、赤松満政は前年12月頃の播磨三郡を「被付守護方山名金吾」(『康富記』嘉吉四年正月九日条)た措置に怒りを覚えており、播磨国下向を以てそれを示したものと推測される。
この動きに、播磨守護の山名持豊入道宗峯は赤松満政追捕を強硬に主張しただろう。この時期の中央動静を詳細に語る史料はないが、山名家と赤松家の対立関係、その後の山名勢の動きから想定される。その後の経過を見る限り、播磨守護山名家単独の派兵となっているが、これは主君である室町殿に無断で播磨国に出奔した赤松満政を捕縛する守護権限によるものと推測される。私怨も強いが正当性もあり、管領畠山入道以下も認めざるを得ないものだっただろう。ただ、大規模な叛逆でもない現状にあっては、山名一族も含めて他国守護の動員は見送られている。
11月14日、山名持豊入道宗峯は、まず「山名因州、播州へ下向、■騎、同大夫殿卅騎計」(『東寺執行日記』)している。続けて11月18日、「山名刑部太輔殿、五十騎計下向」(『東寺執行日記』)し、11月28日、惣領家の「山名殿、播州へ下向、百四十二騎」(『東寺執行日記』)した。ここに見える山名一族は三守護家(石見守護、伯耆守護、因幡守護)ではない惣領家被官人となっていた山名庶家とみられる。
●文安元(1443)年播磨攻めの山名勢陣容(『東寺執行日記』)
| 播磨下向日 | 大将 | 兵力 |
| 11月14日 | 山名因幡守(実名不明) | 不明 |
| 山名大夫(実名不明) | 30騎程 | |
| 11月18日 | 山名刑部太輔(実名不明) | 50騎程 |
| 11月28日 | 山名殿(山名右衛門督持豊入道) | 142騎 |
つまり、山名持豊入道の播磨攻めには山名三守護家も出兵していないとみられる。一方、持豊自身が守護国である安芸国の国人毛利治部少輔熈房は、12月22日の「於真弓当下合戦(朝来郡生野町真弓)」に参戦し、「被官人渡邊外記」が赤松方の「魚住十郎左衛門尉」を討ったことに山名持豊入道が感状を下している(文安元年十二月廿七日「山名持豊感状」『毛利文書』)ように、持豊入道が守護を務める国(但馬国、安芸国、備後国、播磨国)には軍勢催促がかけられていた様子がうかがえる。
赤松満政勢と守護山名勢の「播州合戦」はその後四か月にも及び、翌文安2(1445)年2月20日「播州合戦了」(『東寺執行日記』)、3月24日には「於有馬郡、丹波勢ト合戦、有馬方三百七十人被打之」(『東寺執行日記』)とある。赤松満政の討死の日時は定かではないが、4月4日には「赤松播磨入道父子首、其外首等、右馬助入道実見」(『高倉永豊卿記』文安二年四月四日条:「『高倉永豊卿記』の翻刻と紹介」:』東京大学日本史学研究室紀要』第18号)とあり、細川持賢入道が首実検し、その後「赤松播州父子、若党百廿四人頸、高辻河原懸之、打手ハ赤松有馬也、近日稲荷祭之間、高辻懸之也」(『東寺執行日記』)とあるように、高辻河原(下京区)に晒されていることから、3月24日の有馬合戦で討たれたのだろう。
赤松満政一党の首級が河原に並んで間もなくの4月20日頃、畠山持国入道は再度上表して管領職を辞し(『執事補任次第』)、4月24日、16歳の細川右京大夫勝元が管領職に補任された。
翌4月25日、三位高倉永豊のもとを「伊勢入道(伊勢貞国入道)」の使節として「大外記(中原師郷)」が訪ねた(『高倉永豊卿記』文安二年四月廿五日条)。用件は「鎌倉殿御直垂二具設之、御絵」の事であった。この依頼に関する書状と思われるものが『高倉永豊卿記』紙背文書として残るが、高倉永豊が「かまくらとのゝ御装束を、伊勢蒙仰給候を、永豊あつらへ候、かい候■■もいそきてと申候、廿三日に下向候、さ候ハすハ廿六日と申候、それに京にておらせ候へハ、御大口いてきかたき由申候、若いてき候ましきにて候ハゝ、御所さまの御大口一具候を、先まいらせ候て」(文安元年カ「高倉永豊書状案」:「『高倉永豊卿記』紙背文書の翻刻と紹介」:』東京大学日本史学研究室紀要』第19号)とあるように、にわかに永寿王丸の鎌倉下向が決定したようで、急ぎ御装束を制作してほしいという依頼が記載されている。この紙背文書が用いられた『高倉永豊記』の該当部分は文安2(1444)年5月7日から5月12日までであることから(文安元年カ「高倉永豊書状案」:「『高倉永豊卿記』紙背文書の翻刻と紹介」:』東京大学日本史学研究室紀要』第19号)、この紙背文書は文安2(1444)年5月7日以前の書状である。つまり、4月25日の直垂依頼時の返報である可能性があろう。装束の完成には二か月を要しているため、この依頼から二か月先の23日または26日と推測される。そこから、文安2(1444)年の永寿王丸の鎌倉下向予定日は、文安2(1444)年6月23日であったと推測される。
ここに見える「鎌倉殿」は、土岐持益亭の永寿王丸と想定され、5月14日、右兵衛佐永豊は「伊勢方」から「鎌倉殿御直垂料足、六貫到来」(『高倉永豊卿記』文安二年五月十四日条)しており、鎌倉殿の直垂を拵えはじめたのだろう。「若公様正月御直垂要脚参貫五百文」(文安元年カ「高倉永豊書状案」:「『高倉永豊卿記』紙背文書の翻刻と紹介」:』東京大学日本史学研究室紀要』第19号)と比較しても六貫は相当高価だが、もう一着分の要脚は、6月10日に「鎌倉殿御直垂料足、残五貫四百文到来」(『高倉永豊卿記』文安二年六月十日条)している。そして6月16日、「鎌倉殿御直垂…(この間文は10日補記と思われる)…二具分也」のうち「先一具調遣也、伊勢方へ也」(『高倉永豊卿記』文安二年六月十六日条)と、5月中旬依頼の一着を伊勢守貞国へ納品している。『喜連川判鑑』に依れば、文安2(1445)年に永寿王丸を関東に招いたとあるが、それはこの還御の予定を示したものか。
この下向計画は、その後もしばらく延引が重なっているが、この下向計画に伴い、関東では鑁阿寺に「鎌倉殿(永寿王丸)」の「還御」についての祈禱の巻数一巻を見参に入れるため、その依頼している。
●文安2(1445)年9月27日「奉行人前但馬守奉書」(『鑁阿寺文書』32)
ただし、結局文安2年の「御下向」「還御」は全面的に見送られ、さらに「鎌倉殿」の決定もまた撤回されて再度勘考されることになったとみられる。理由は定かではないが、関東管領上杉憲実入道が故持氏子息を鎌倉殿とすることに強い拒否反応があったためかもしれない。
4月26日、山名持豊入道は播磨国を山名兵部少輔に任せて、一旦本国但馬国へと引き上げ(『東寺執行日記』)、5月13日、「山名殿、自但馬上洛、百六七十騎」(『東寺執行日記』)した。続けて7月8日には「山名兵部少輔、自播磨上洛、七十騎計也」(『東寺執行日記』)した。
文安3(1446)年12月13日、室町殿(三春)の官途を定めるにあたり、名字勘考が行われ「所注載之字、三字」(「足利家正統伝譜」:『大友家文書』)として「義成、義政、義種」の三字が撰ばれ、そのうち「御名字被定之被染宸筆、自二條殿被伝進之、義成」(『東寺執行日記』)と決定する。12月15日には「従五位上十二歳、於陣宣下」(『足利家官位記』)に叙され、12月19日「当将軍御実名始」となり「近衞殿為御親当関白、義成シゲ御治定」(『東寺執行日記』)する。
文安4(1447)年正月7日、将軍義政は「叙正五位下、同日侍従」(『足利家官位記』)に任じられる。
このころ関東では、上杉憲実入道が関東管領を辞して頻りに隠遁を願っていた。この報告は文安4(1447)年3月13日、大外記清原業忠が権大納言時房亭を訪れた際に、「密語」として聞いた話であった(『建内記』文安四年三月十三日条)。この話は「細川典厩内々有尋旨」の内容として「為覚悟密々大切、可勘給之由、内々典厩示業忠也」もので、「鎌倉管領上杉房州入道、辞其職、隠遁之由、多年所申也」であり、持氏の死後、二度にわたって自害を試みるなどで伊豆国に出家隠遁しているが、結城合戦のために鎌倉へ召還され、管領実務は弟兵庫頭清方に預けつつ、事実上の関東最高執行者として関東を支えていた。しかし、ここに来て憲実入道は「近日弥隠遁之志」という。憲実入道の隠遁願いの大きな理由は、持氏子息を新たな鎌倉殿とする京都の動きに失望したことであろう。
憲実入道は、もともとは「鎌倉御遺跡」については義教の子である「義制(義永)」を承認していた。これは、永享11(1439)年7月2日時点で「義制(義永)」が「若公様、鎌倉殿御成御礼、自寺家御申事、奉行加賀意見申歟」(『東寺百合文書 ち』永享十一年七月四日条)とあるように持氏の跡を継承する人物と目されており、それは「人々参賀室町殿、是若公一所て奉下関東之由被仰下之處、関東承伏之由申之故也」(『師郷記』永享十一年七月二日条)とあるように、上杉憲実入道も了承していたことからもわかる。
しかし、嘉吉元(1441)年6月24日、義教が赤松満祐入道に殺害されてからは、京都の雰囲気が一変した。まず、結城合戦後に永寿王丸が関東から垂井まで連行されて来ると、管領細川持之以下の大名は、垂井から直接関東へ差し戻して「鎌倉御遺跡」を継がようと考えたようである。しかし、この旨を打診された憲実入道は、「於京都若君御対面以後、被沙汰居申之條、可然之由、鎌倉管領申意見」(『建内記』嘉吉元年七月廿八日条)と述べており、この件は、永寿王丸が京都で若君三春との御対面を経てのち沙汰すべき事柄であるとして、永寿王丸の鎌倉下向に反対の姿勢を示したのである。関東には故持氏を重んじる勢力が存在している中で、その子息を新しく鎌倉殿に据えれば、結城合戦を見てもわかるように、その子息を奉じて新たな対京都勢力が台頭してくることは火を見るよりも明らかである。その後も徹底的に持氏子息の下向に反対したのは、関東の混乱を危惧したためであったことは想像に難くない。
京都に伝わる憲実入道の為人としては「此人当其仁、彼不管領者、又与京都不和事等出来之基也、彼者不変節、以京都大事之由、得其意于今無為也、彼心中者、於我身者一向可奉公于京都之所存也、仍以子息已令在京、於京都可令元服」(『建内記』文安四年三月十三日条)との評判であった。龍春を京都に出仕させ元服(八郎房顕)させたことは、憲実入道の強い京都回帰の心として映り、「所詮、以故鎌倉殿子息被立申、可補佐之由、不存之」(『建内記』文安四年三月十三日条)と、故持氏卿の子息が新たな鎌倉殿となっても、彼は補佐する気持ちはないと断言する。この鎌倉殿の補佐拒否は、関東に「故鎌倉殿子息」を送ったらどうなるのかを判断できない京都の管領以下への不信感が大きいと思われる。
しかし、京都側から見た現実問題として、関東管領人事は「但於他人者、二階堂已下大名等雖在之、管領重職無其例歟之上、他人不可承引、畠山雖有管領例在京都、於鎌倉無其人、上杉者代々為管領之上、必可在上杉也」(『建内記』文安四年三月十三日条)とあるように、上杉家以外はあり得なかった。そのため「而隠遁之上者、為武家今日■職事行之間、以綸旨被仰之様、可有沙汰之由決之、諸大名等先可談合、定区々可有意見歟、但先例、於関東執事、直自然之儀為 公家被仰之例在之哉」(『建内記』文安四年三月十三日条)というように、憲実入道の関東管領職を留めるために、綸旨下賜までも検討している様子がうかがえる。
3月23日夜、弾正尹定親卿が権大納言時房亭を訪問し、時房に関東に関する「條々」を報告している。定親は「勅定事」として「鎌倉之管領職者、上杉安房入道也、持氏卿薨逝之後、遺跡事于今未定也、而謙退之志及多年、再三雖被仰之、不申領状也」事を伝える(『建内記』文安四年三月廿三日条)。ただ、多年にわたる管領辞退のこともあり、3月初旬以降、憲実入道には室町殿から幾度かの就任要請が行われたとみられるが、やはり了承しないという。ただ、関東においては上杉憲実入道に代わり得る上杉一門の人材は存在せず、京都は関東管領を憲実入道に打診せざるを得なかった。
そこで、憲実入道に関東管領就任を命じるにあたり、憲実に「彼御遺跡人躰事、或京都御連枝歟、或持氏卿子息歟、両様未決、唯可然之様、安房入道可計申、同可輔佐申之趣、被成下 綸旨、以其下猶可加下知之由、武家御執 奏、奉行飯尾加賀入道、同大和入道両使申次之、此事依被申請可被成 勅裁也」(『建内記』文安四年三月廿三日条)という。「鎌倉御遺跡」を「京都御連枝(左馬頭義制/義永)」か「持氏卿子息(永寿王丸)」で憲実入道に選ばせ、関東管領職に就いては綸旨を以て憲実入道に命じる、という、大きな譲歩案で決着しようとしたのであった。それに伴い、「職事冬房可書出之、文章予可計申由 勅定之由示之、当座浮心之分談合之、尤可然」とあるように、
(1)「鎌倉御遺跡」の人選についての綸旨案
(2)関東管領を命じる綸旨案
の両通の綸旨案を時房が認め、冬房が職事として清書することとなり、現状不明な部分は定親と談合することが示されている。これを受けて時房は早速綸旨案を作成。翌24日朝、「大外記業忠真人」に来てもらい「草案両通相談先」している。
そして「鎌倉管領職事 綸旨案」を中山定親卿へ送達しようとしたところ、その定親卿から書状が届いた。定親卿は綸旨案について相談のため、おそらく24日早朝に管領細川亭に赴いたのだろう。ここで、室町殿の閣内ですでに鎌倉御遺跡を決定したとの話を聞き、あわてて時房へ手紙を送達したと思われる(『建内記』文安四年三月廿四日条)。その送状には、
というように、「於御人躰者、已一定歟之由有其説也」という。ただ、どういった理由でこのような措置になったのかがわからず、定親卿もとりあえず昨晩の話の通り、
(1)鎌倉御遺跡の人選についての綸旨案(「文安三年四月記紙背文書」『建内記』)
(2)関東管領を命じる綸旨案(「文安三年四月記紙背文書」『建内記』)
の両案を袋に入れて、右中弁冬房を通じて自分(中山定親)まで急ぎ送ってほしいとの事であった(『建内記』文安四年三月廿四日条)。両奉行との相談の為であり、結果については後ほど送達する旨も伝えられた。
管領以下がなぜ「鎌倉御遺跡」を憲実入道に選択させることを撤回したのかは定かではない。ただ、憲実入道に選ばせた場合は、「関東管領が鎌倉殿を任じる」ことが「先例」になることは必定であり、今後は京都の許可なく関東管領の恣意で「鎌倉殿」を決定できることになる。京都の権威を失墜させることにも直結するため撤回したと考えられよう。
その後、定親は案文を「飯尾加賀入道(飯尾為行入道)、同大和入道(飯尾貞連入道)」の両奉行と相談したが、奉行衆からはただ一筆「可然由申」の証書を渡されたので、これを時房へ送達した(『建内記』文安四年三月廿四日条)。
時房はこの文書を見て「計申其人之四字懸勾了」を付けて「仍染筆冬房欲送遣」と、冬房に綸旨案の清書を指示しようとしたところ、また「又中山状到来」した(『建内記』文安四年三月廿四日条)。それは「奉行有申旨、仍送案文」というもので、奉行が示した新しい綸旨案文だった。その内容は、
というもので、時房はこの奉行案をもとに再度綸旨案を作り直して「即又書直送了」た(『建内記』文安四年三月廿四日条)。これにより、先に時房が示した(2)案とは全く異なる内容となった。
●憲実入道を関東管領を命じる綸旨案の決定案(「文安三年四月記紙背文書」『建内記』)
なお、案文では「右京大夫殿」の上に「謹上」と入れていたが、「管領細川右京大夫勝元、地下也、仍不書上所也」という理由で削除している。
また、(1)案の「鎌倉御遺跡事、宜計申」ことについては、京都で「持氏卿子息(永寿王丸)」で決定したことで、こちらに関する綸旨は下されないこととなり、時房は鎌倉御遺跡についての綸旨案文は「全面墨ヲ以テ塗沫」(「文安三年四月記紙背文書」『建内記』)している。
この綸旨がいつ関東へ遣わされたかは諸記録に残っていないため定かではないが、7月10日に「関東管領職事、上杉房州入道長棟雖蒙 綸旨」(『建内記』文安四年七月十日条)があるため、遣わされているのは確実である。綸旨という性格上、当日か翌3月24日には遣わされていると考えられよう。
しかし、憲実入道はこの綸旨を以てしても「猶及異議」(『建内記』文安四年七月十日条)と、隠遁の気持ちを翻すことはなく、粛々と丹波国八田本郷の地を次男「八郎房顕」に所領を譲り渡している(文安四年六月五日「上杉憲実入道譲状」『上杉家文書』)。
そして7月10日、「関東管領職事、上杉房州入道長棟雖蒙 綸旨先度冬房染筆了、猶及異議之間、以彼子息号龍忠丸云々、為其職、加諷諫父子之間、不思様之由有其聞、仍加諷諫之字云々、可存知之由、 綸旨先日被成了」(『建内記』文安四年七月十日条)という。
●憲実入道に関東管領龍忠丸の補佐を命じる綸旨案(『建内記』文安四年七月十日条)
今回の綸旨は「弾正尹、於帥大納言亭招頭左大弁俊秀朝臣、示御沙汰之趣、令書出」とあるように、定親卿が三条実雅邸に頭左大弁俊秀を招き、改めて綸旨を作成して憲実入道に遣わしている(『建内記』文安四年七月十日条)。これは、憲房入道が関東管領職を謙退するので「龍忠丸(リウチウと読みがある。「龍忠」は憲実入道の譲状にも見えるため、憲忠の幼名は『鎌倉大草紙』や『鎌倉大日記』などにみられる「龍若丸」ではない)」を「為其職」とするが、憲実入道は責任を持って龍忠丸を補佐するよう命じている。これは時房が「父子之間、不思様之由有其聞、仍加諷諫之字」と記すように、憲実入道が長男「龍忠」を「令出家」ようとしていることへの牽制であろう。
上杉憲方―+―上杉房方―+―高倉朝方―――上杉房朝==上杉房定
(安房守) |(安房守) |(民部大輔) (民部大輔)(相模守)
| |
| +―山浦頼方
| |(七郎)
| |
| +―上杉憲実―+―上杉憲忠
| |(安房守) |(右京亮)
| | |
| +―上杉重方 +―上杉房顕
| |(三郎) |(兵部少輔)
| | |
| | +=佐竹実定
| | (左京大夫)
| |
| +―上杉清方―+―上杉房定
| (兵庫頭) |(相模守)
| |
| +―上条房実
| (淡路守)
|
+―上杉憲定―+―上杉憲基===上杉憲実
(安房守) |(安房守) (安房守)
|
+―佐竹義人―+―佐竹義俊
(右京大夫)|(右京大夫)
|
+―佐竹実定
(左京大夫)
こうして、
(1)永寿王丸を鎌倉殿とする決定(文安4年3月24日決定)
(2)龍忠丸の関東管領職の決定(文安4年7月4日綸旨)
の二点がいずれも決定され、関東へ伝達されることとなる。
そして、この綸旨に基づいて、龍忠丸(十五歳)を関東管領職に任じ、父の上杉憲実入道はその補佐をするように命じる「御教書」が関東に下されたとみられる。龍忠丸は関東管領職に就任した直後に「右京亮憲忠」となる(元服は翌年か)。当時鎌倉には「豆州狩野」から父の上杉憲実入道も出倉していたとみられる。しかし、この父子は鎌倉で対面したものの、憲実入道は憲忠についてやはり快く思っていなかったようで、山内上杉家被官の臼田道珍等は「長尾殿(長尾左衛門尉景仲)」から案文をもらい、「当殿様(憲忠)」がすでに家督を継承された以上は、みな「当殿様」に忠節を致し、たとえ「豆州入道様(憲実入道)」が「若就佐竹六郎殿(佐竹実定)」を家督に付けんと「有御調法之儀」があったとしても「当殿様」を支えることを誓っている。
●文安4(1447)年11月7日「臼田道珍等連署起請文案」(『臼田文書』)
関東管領憲忠の鎌倉就任が決着すると、8月20日、管領奉行人「前但馬守(定之)」が鑁阿寺の龍福院に「就還御」て「祈禱之巻数一枝入見参候」(『鑁阿寺文書』)とあり、文安4(1447)年に「還御」が予定されていた鎌倉殿永寿王丸のために、鑁阿寺へ祈祷の巻数を依頼していたことがわかる。しかし、この下向もまた沙汰止みとなり、実際に下向は行われていない。
●文安4(1447)年8月20日「奉行人前但馬守奉書」(『鑁阿寺文書』三)
龍福院は嘉吉2(1442)年に「年行事 龍福院」(嘉吉二年六月八日「鑁阿寺六月八日仏事銭請取状案」『鑁阿寺文書』52)であり、文安4(1447)年は年行事ではないが、「前但馬守」は龍福院に祈禱巻数の依頼をしている。これは嘉吉2(1442)年に「鎌倉殿(永寿王丸)」の関東下向が決定した折に、当年の年行事龍福院に巻数の依頼をしたが沙汰止みとなり、文安2(1445)年の還御予定もまた沙汰止みとなっており、「前但馬守」は今回の「永寿王丸」の還御決定の報告を受けて、龍福院に三度目の祈禱巻数の依頼を改めて行ったものであろう。ところがこの文安4(1447)年の還御も見送られている。
憲忠父・憲実入道はその後は表舞台に出ることなく、伊豆国に隠遁して憲忠を支えた形跡も見られない。一方で憲忠は十五歳という若さで永寿王丸を迎える文安6(1449)年までの二年間、鎌倉殿不在の関東の事実上のトップとして切り盛りした。この背景には長尾左衛門入道らや一門扇谷上杉家の支えがあり、それがのちの江ノ島合戦へと繋がっていくものと思われる。
このころ、鶴岡八幡宮寺供僧職の香象院珍祐は、文安5(1448)年9月、「弘法大師御筆ト申八幡御影」を「依而為上意」って「宇津宮公方江進上之」している(「鶴岡八幡宮寺供僧次第」)。この時期は成氏はまだ在京であり、この「宇津宮公方」は、当時の日光山権別当だった勝長寿院門主成潤(成氏舎兄)の可能性があろう。その八幡御影は11月28日、「本間遠州江被仰出」によって「当院(善松坊)江入御被申者也」とし、「為御代官毎日法施可致由被仰出也」(「鶴岡八幡宮寺供僧次第」)という。
文安6(1449)年4月16日夜、「室町殿、左馬頭義成、十五歳、御元服」した(『康富記』文安六年四月十六日条)した。加冠は「細川武蔵守勝元管領也」、理髪は「細川民部大輔(陸奥守教経)」が相務め、このほか「細川ノ一家」が雑務を取り仕切っている。室町殿元服に際しては、加冠の先例(足利義満元服の際、加冠を務めた細川武蔵守頼之が従四位下であった先例)が採用されており、右京大夫勝元は「四月初比四品」に叙され、「依申沙汰、昨日十五、被仰武蔵守」に転任(『斎藤基恒記』文安六年四月十六日条)となった(4月29日、武蔵守を辞して右京大夫に復任)。
4月末には「自鎌倉管領上杉房州子息方、公方進上之御馬等貢進之」と、憲忠は将軍義成に馬を献じている。憲忠はこのほか「管領、山名已下諸大名之方、各馬上送」ったが、このうち「畠山左衛門督入道」は「馬よくもなき」と憲忠の贈物を受け取らずに「被追返不被請取」(『康富記』文安六年五月十一日条)とあるように馬を指し返している。畠山持国入道はその後の対応を見ても関東との調和を考えており、管領という立場での関東からの付届に抵抗を感じたものか。潔癖な持国入道の性格がうかがえる。
6月には「関東管領上椙被官人、長尾四郎左衛門尉」が「在京也」(『康富記』文安六年七月三日条)した。これは「関東御名字事、被申之間」であった。これにより、若君永寿王丸は「被治定了、成シゲ氏也、故鎌倉殿持氏卿御子也」と名字が定まった(『康富記』文安六年五月十一日条)。ただ、「御官途事」と「御位階」については、官途は「左馬頭、右兵衛佐之間、可被申之處、左馬頭当時公方御現任也、右兵衛佐可被申歟」と決定を見ず、位階は「可為敍爵之由被申之歟」とあるように、将軍義成からは「此両條官位、御返事未承」であった。ところが、このとき「自関東使上洛音信在之」と、関東管領憲忠よりの書状を帯した使者が上洛したことで、「長尾俄下向」してしまった(『康富記』文安六年七月三日条)。このことは「此御返事不相待、令下向之條、不得其意」と、不与であった。この使者が長尾を戻す使者だったのか、将軍家への音信を伝える使者だったのかは定かではない。ただ、この直後、将軍義成は四位への昇進と参議(兼左近中将)への任官が俄かに行われる(参議家輔は辞任)とともに、空いた左馬頭を成氏に任官させる措置が取られており、関東憲忠と京都の間で成氏を左馬頭とするための折衝が頻繁に交わされたことが推測される。
6月19日、関東管領「右京亮(上杉憲忠)」は「依仰」て、「藤田美作守宗員後家号紀春」の申請により、武蔵国比企郡竹澤郷などを円覚寺に寄進している(文安六年六月十九日「関東管領奉書寄進状」『円覚寺文書』 神:6077)。管領憲忠が「依仰執達」したのはこれが所見となるが、鎌倉殿として「成氏」と名が定まった直後でもあることから、憲忠は京都の成氏の命としてこの寄進を行ったのだろう。ここでも京都と関東が密接に関わっていた様子がうかがえる。
この年の6月に行われた「藤原利永」が主催する月次連歌(土岐亭で行われたのだろう)に東福寺の招月庵正徹が会衆として招待されたが(『草根集』巻之七)、このとき「土岐左京大夫持益家」に九年間預けられていた「故鎌倉の持氏息(成氏)」が「来(八月)十九日関東還入」となったことを聞いた(『草根集』巻之七)。招月庵正徹は成氏がまだ幼稚の際に対面したことがあるが、もう一度「見奉らん」と、元号改め宝徳元(1449)年8月10日に催された藤原利永の連歌に「会衆外」ながら参じている。つまり成氏の鎌倉下向の日次(文安6年8月19日未明)は6月時点で決定されていたことになる。「藤原利永」は土岐左京大夫持益の被官の齋藤帯刀左衛門尉利永であることから、招月庵正徹は利永から成氏向の話を聞いたと思われる。なお、利永の弟・持是院妙椿(齊藤妙椿)も優れた歌人であり、彼が歌道の友である東下野守常縁が留守中に、居城である美濃国郡上郡篠脇城を攻め落とした際、和歌の贈答により城を返した故事は有名である。
この対面で、成氏は正徹に和歌を依頼されたため、その場で三首を書いて永寿王へ献じた。
その後、成氏は五歳で上洛した折り、同道した祈祷僧の夢に出たという歌を正徹に語っている。その歌は、
というものだったという。成氏に憑いていた罪科を余所へ引き払って「付け」たことを「告げ」に「来た」「北野(=天神)」の慶報であったという意味であろう。成氏はこの歌をずっと覚えていたと見え、今回の対面の際に、この夢の歌を紙に記して正徹に渡し、それへの返歌を求めたのであった。それに正徹は、
あれが慶報だったと思えば合点がゆく、この「秋(あき/とき:重要な時、を掛けている)」を告げに「来た」「北野(=天神)」の兆しだったのだ、と返歌を書き付けて成氏に渡している。
●『草根集』巻之七より
『東野州聞書』にはこの件の抄が記載されている。東福寺の招月庵正徹は、『東野州聞書』の著者・東下野守常縁の兄である東下総入道素欣と歌友であり、弟の常縁も積極的ではないが交流があった。図らずものちに刃を交えることとなった足利成氏の少年期の物語として記録したのだろう。細かい情緒は記されておらず、一つの聞書として載せられている。
●『東野州聞書』より
一方で、『鎌倉大草紙』はこれらを「物語」のひとつの付随情報として取り込んだが、内容は作者によって脚色がなされている。
●『鎌倉大草紙』より
8月18日、足利成氏は関東下向前日に天神(菅原道真)の御影を招月庵正徹のもとへ送り、「歌一首、賛にかきて」(『草根集』巻之七)と依頼した。成氏が天神の御影を用意したのは、8月10日の正徹との対面により、自分が天神の御加護を受けて今があるのだ、という思いを強くしたためだろう。
この依頼を受けた正徹は、成氏が「あすは夜中に進発あるへき」ことを知り、「やかて只今書付てまゐらせ」ている(『草根集』巻之七)。
●『草根集』巻之七より
この歌は、梅の香の「東風」が吹く方へ旅立ち、君を守る天神は傍らにいてくれるであろう、という餞別歌である。足利尊氏以来、足利家に伝わる北野信仰と、古くから武家の信仰を集めた鎌倉荏柄天神を重ね合わせた意図が感じられる。
その数時間後の宝徳元(1449)年8月19日夜半に、成氏は鎌倉へ向けて出京した(『草根集』巻之七)。ただし、この下向当日の記録は残されていない。
宝徳元(1449)年8月27日、足利成氏は鎌倉に還御した(宝徳元年(カ)八月廿九「前但馬守定之書状」『鑁阿寺文書』)。京都を出立して八日、嘉吉元(1441)年の上洛から実に九年、三度にわたる還御延引を経ての鎌倉下向であった。
成氏の関東下着後、上杉憲実入道は「御両所様御在鎌倉事」を京都の管領細川勝元へ注進している(九月五日「細川勝元書状」『喜連川文書』)。宝徳元年8月は晦日が29日であるため、27、28日に注進状が遣わされたとすれば、6、7日間程度で京都に着いたことになり、無理はない。
この「御両所様」は、
(1)成氏と「若宮社務」
(2)成氏と「勝長寿院門主」
(3)「勝長寿院門主、若宮社務」
のいずれかとなろうが、このタイミングで上せたとすれば、成氏ともう一人兄「勝長寿院門主」または、弟「若宮社務」の可能性が高いだろう。この報告を受けた管領細川勝元は9月5日、憲実入道に宛てて、返書を認めている。
●宝徳元(1449)年(カ)9月5日「細川勝元書状」(『喜連川文書』)
また、還御二日後の8月29日、「前但馬守定之」は鑁阿寺からの巻数(還御に合わせて鎌倉着を依頼していたのだろう)を成氏に披露して「目出候由被仰出候」との返答を得た。ただ、御返事については還御間もなく役人も定まっていないため、その後になる旨を鑁阿寺普賢院(普賢院から年行事方へ伝達するよう指示)に伝えている。
●宝徳元(1449)年(カ)8月29日「前但馬守定之書状」(『鑁阿寺文書』)
成氏が鎌倉に到着した8月27日、京都では小除目が行われ、「室町殿御昇進」して正五位下から従四位下となり、「自左馬頭任参議、令兼左近中将」と、左馬頭を辞して、参議兼左近衛権中将に任官している(『康富記』宝徳元年八月廿七日条)。義成が参議となるにあたり、参議家輔が辞退している。また、義成が辞した左馬頭は改めて成氏が同日任官した。
●宝徳元(1449)年8月27日小除目儀(『康富記』)
| 人名 | 家名 | 叙位 | 辞退 | 任官 | 現任 | 典拠 |
| 源義成 | 足利 | 正五位下⇒従四位下 | 左馬頭 | 参議 右近衛権中将(兼任) |
征夷大将軍 | 『康富記』 宝徳元年八月廿七日条 |
| 源成氏 | 足利 | (叙位)従五位下 | ―― | 左馬頭 | ―― | 宝徳元年八月廿七日 「後花園天皇口宣案」 (『東京国立博物館寄託妹尾文書』戦古:2、3) |
| 藤原家輔 | 月輪 | (現正三位) | 参議 | ―― | ―― | 『康富記』 宝徳元年年八月廿七日条 |
●宝徳元(1449)年8月27日/除目(『康富記』)
●宝徳元(1449)年8月27日/叙位(『康富記』)
●宝徳元(1449)年8月27日「後花園天皇口宣案」(宿紙)(『東京国立博物館寄託妹尾文書』戦古:2)
●宝徳元(1449)年8月27日「後花園天皇口宣案」(宿紙)(『東京国立博物館寄託妹尾文書』戦古:3)
成氏は義政の「御官位宣下」につき、関東管領「上杉右京亮殿(上杉憲忠)」を通じて管領畠山徳本入道に「御祝着通仰之旨」を伝えている(九月十一日「徳本書状」『喜連川文書』)。管領畠山徳本入道はこれを義政に「披露仕候」ったところ義政は「誠目出被思食候、具御申御悦喜之由、可申之旨、被仰出候」という。9月11日、徳本入道はこの旨を上杉憲忠へ伝え、成氏へ「此段可有御披露候」を依頼した(九月十一日「徳本書状」『喜連川文書』)。
そして、京都では10月5日、「依右京兆上表也、管領職事、左衛門督入道徳本三品、再任」(『斎藤基恒日記』宝徳元年十月五日条)といい、畠山持国入道が管領に再任された。
このころにあっては都鄙関係は比較的穏やかに過ぎている。ところが、上杉右京亮憲忠は関東管領ながら当時十七歳で「依為微若」り、家宰である「長尾左衛門入道(景仲入道)」が女婿の「太田備中入道(資清入道)」を語らい専横の様子を示し、公務を軽んじるようになったという(宝徳二年五月廿七日「畠山徳本入道書状案」(『南部文書』)。長尾左衛門入道や太田備中入道らは、永享11(1439)年2月10日の持氏滅亡以降の鎌倉殿の不在、かつ関東管領職も不安定な状況にある中で、十年余りの間、事実上、上杉家を主導する立場となっていた扇谷修理大夫持朝入道のもとで関東諸政の実務を主導したという大きな自負があったろう。
長尾景仲―+―長尾景信―――+―長尾景春
(左衛門尉)|(四郎左衛門尉)|(四郎左衛門尉)
| |
| +―女子
| |(龍興院殿了室覚公大姉)
| | ∥
| |+―千葉介自胤
| ||(千葉介)
| ||
| |+――――――千葉介実胤
| | (千葉介)
| | ∥
| +――女子 ∥
| ∥ ∥
| ∥ ∥
| 上杉持朝―――+―上杉定正 ∥
|(修理大夫) |(修理大夫) ∥
| | ∥
| +―上杉顕房――女子
| |(大夫三郎)
| |
| +―三浦高救――三浦義同
| |(弾正少弼)(三浦介)
| |
| +―女子
| ∥
| ∥
| 上杉憲実―――――上杉憲忠
|(安房守) (右京亮)
|
+―長尾忠景―――――女子
|(孫六) ∥
| ∥
+―娘 ∥
∥ ∥
太田資清―――――太田資長
(太田道真) (太田道灌)
ところが、宝徳元(1449)年、成氏が新たな鎌倉殿として京都から下向すると、それまで関東管領家の指示に従っていた鎌倉殿被官や守護クラスの人々は鎌倉殿に属し、こうした両者の関係の変化が、管領家中と鎌倉殿家中との対立を引き起こした可能性が考えられよう。
そして、両者の関係がついに「既覃火急」の事態となったことから、成氏は「無據堪忍」して「去月廿日夜、俄移居江島候」と、御所から江の島(藤沢市江ノ島)へ遁れることとなった。ここに至るまでに成氏は「連々依相談安房入道候」(宝徳二年五月廿七日「畠山徳本入道書状案」(『南部文書』)しており、江ノ島御移座は以前から憲実入道に様々相談した結果であった可能性があろう。
成氏が江ノ島へ移った翌日、「翌日廿一日為長尾、太田骨張引卒多勢」(宝徳二年五月廿七日「畠山徳本入道書状案」(『南部文書』)とあるように、江ノ島に長尾景仲入道、太田備中入道が多数引率して攻め寄せた。成氏を直接攻めたのではなく、成氏を取り巻く人々を追討する軍勢であろう。ただし、彼らが独断で兵を出したとは考えにくく、太田備中入道(扇谷上杉家宰)が加わっていることを考えれば、扇谷上杉修理大夫入道が事実上の許可を与えたと考えるのが妥当であろう。のち、長尾・太田勢が修理大夫入道の所領である「糟屋庄」(宝徳二年五月廿七日「畠山徳本入道書状案」(『南部文書』)へ落ちていったことからも窺われる。
成氏に同道した人々の名は遺されていないが、小山下野守持政(小山小四郎持政。文安3年11月24日に下野守に補任)が「於輿越(鎌倉市腰越)致合戦」に長尾・太田勢を迎え撃ち、「小山下野守家人数輩令討死候」(宝徳二年五月廿七日「畠山徳本入道書状案」(『南部文書』)という記述から、在鎌倉の守護クラスの人々も加わっていたことがわかる。当然ながら鎌倉殿側近の二階堂氏、明石氏、木戸氏らも同道していただろう。なお、関東管領麾下の「武州、上州一揆輩」(『鎌倉大草紙』)は、京都からの御教書で成氏を支えるよう命じられているにも拘らず長尾勢に加担している。
その頃鎌倉では、長尾・太田勢が「彼等打出由比濱候」たが、ここに「千葉介、小田讃岐守、宇都宮右馬頭以下為御方、数刻防戦」し、「凶徒等悉被打散、相残軍兵引退糟屋庄畢」(宝徳二年五月廿七日「畠山徳本入道書状案」(『南部文書』)した。彼等は胤直入道の嫡子・千葉介胤将、小田朝久、宇都宮等綱ら、常府が義務付けられている守護勢力であり、鎌倉殿との結びつきが強い勢力である。当然、彼らは鎌倉殿成氏に加担して、叛臣長尾・太田勢を駆逐したのであった。
なお、この成氏の注進状が採用された『鎌倉大草紙』は史料的価値は低いものの、同様の文章が記された畠山左衛門督入道徳本の文書案及び成氏への返答文書が残っており、史料的には信頼のおけるものであろうと判断される。5月12日、成氏は今回の騒乱について京都に注進した。
●宝徳2(1450)年5月12日「足利成氏注進状」(『鎌倉大草紙』 『南部文書』にない部分は緑)
これに加えて、成氏は「稲荷大明神」に「殊凶徒等不日致退治」を祈願している。江島合戦鎮定を祈願したものとなろう。この「稲荷大明神」がどこの神社を指すかは判然としないが、五年後の享徳4(1455)年正月5日に戦勝の霊験由緒のある荏原郡桜田郷の稲荷大明神(現在の烏森神社)に願文を収めており、軍陣にまつわる祈願であることから、この宝徳2年の願文も同じく桜田郷の稲荷大明神ではなかろうか。
●宝徳2(1450)年5月25日「足利成氏願文写」(『古証文 二』戦古:5)
こうして、長尾左衛門入道(山内家家宰)と太田備中入道(扇谷家家宰)の叛乱は鎮定されたが、この乱には扇谷上杉修理大夫入道(持朝入道)も「号隠居遁公名、白衣打着甲冑、雖致合戦張行候」と、隠居したと言いながら僧衣に甲冑を着して兵を挙げており、憲実入道の隠居ならびにその後の関東管領家の混乱の中、この十年に亘って関東を率いた自負があったのだろう。
しかし、これらの事態を重く見た伊豆の憲実入道は、駿河国にいた「長棟舎弟道悦(三郎重方)」を修理大夫入道のもとに派遣して「執申降参訴訟」している。このため成氏は「以寛宥之儀、父子共可優免旨申付候」と、扇谷上杉父子(持朝入道、現当主顕房)を宥免しているが、当時彼らは「七澤山仁構要害之由其聞候」というように、七澤山(厚木市七沢)に要害を構築していたという。
一方成氏は、この乱を起こした「長尾、太田以下凶徒者、速可加誅罰由」と主張している。また、成氏は「右京亮」はこの件に関しては一切関与がないのはわかっているので御所に参上するよう度々言っているが「行歩不自由歟、尤不便至候」と述べている。憲忠としても家宰の長尾景仲入道が主導した叛乱であることから、その責任の大きさに出頭できなかったのかもしれない。しかも憲忠は「所詮不日令帰参住鎌倉、可被致無為之談合之由」(宝徳二年七月十日「将軍家御教書」『喜連川文書』)とあるように、鎌倉にはおらず、他国に逃れていたと思われる。
また、成氏(十六歳)が今回の叛乱を通じて不安に思ったのは、やはり若い(十七歳)憲忠では、老練な長尾左衛門入道や一門の扇谷上杉家を御すことは困難であるという事であろう。そのため、管領徳本入道へ「安房入道候関東、可執行政務之由、可被仰下候」ことを希望している。そして、最後に強調しているのは「奉対京都、一切不存私曲候、於自今以後茂、可畏入候、此等趣可然様可令披露給候」ということであった。成氏は幼少期を京都で暮らし、またこれまでの鎌倉殿の末路を聞いていたであろう。今回の戦いの詳細をいち早く京都へ送ることで、京都に対する戦いではないことを印象付けたとみられる。
これに対して管領畠山持国入道は5月27日に成氏に返書をしたためた(五月廿七日「畠山徳本入道書状」(『喜連川文書』:『韮山町史』第三巻(中)))。成氏の注進状の第二~五条への返答となる。第一条は報告であり、第六条は徳本への依頼であるため、第二~五条への返答となっている。
●宝徳2(1450)年5月27日「畠山徳本入道書状」(『喜連川文書』:『韮山町史』第三巻(中))
京都としても「上杉安房入道帰国」のことは要点とみており、その旨の御教書を下したことを伝えている。
また、「武田右馬助入道(武田信長入道)」は今回の騒乱を京都に「註進」しており、上記成氏(宛所はなく側近であろう)へ充てられた文書と同日の5月27日、管領畠山徳本入道は「武田右馬助入道殿」への返書もしたためている。なお、この武田右馬助入道へ宛てられた管領「徳本」の前半部分(「一 右京亮~雖度々申」マデ)は、成氏の注進状の写し(未完成)であるが、「一 右京亮~雖度々申」に続く「関東事委細御註進」とはこの成氏の注進状を指しているのであろう。おそらく『南部家文書』がこの文書を採録する際、成氏の注進状(写しですでに文字の誤謬があった)に続けて「「関東事委細御註進旨~」という「御教書案」が付されていたと想定される。この「御教書案」が「武田右馬助入道殿」へ宛てられているところから、京都とも繋がりのある「武田右馬助入道」が成氏の最側近となっていて、成氏の注進状は武田右馬助信長入道が主導して成氏の意見として記し、それに信長入道の副状も送られていたのではあるまいか。
●宝徳2(1450)年5月27日「御教書案」(『南部家文書』253:緑は『鎌倉大草紙』で補足)
●【推定】本来の宝徳2(1450)年5月27日「御教書案」(『南部家文書』253)
同じく5月27日、成氏の注進状の第四条の「関東諸侍并武州、上州一揆輩中江可致忠節旨、被成御教書候者、尤可然存候」について「関東奉公中」及び「武州上州白旗一揆中」へ一層の忠勤を命じる御教書が下されている。これらの文書は、南部家に「道宗上人持之来間、写之云々」という。
●宝徳2(1450)年5月27日「将軍家御教書案」(『南部家文書』253)
●宝徳2(1450)年5月27日「将軍家御教書案」(『南部家文書』253)
これらは5月27日の「畠山徳本入道書状」の第一条「上杉安房入道帰国事并合戦忠否之次第」にも見えるが、5月27日に上記の御教書が作成されており、併記されている「上杉安房入道帰国事」に関する御教書も同日作成され、関東へ下されたと考えられる(ただし、この御教書は伝わっていない)。上杉憲実入道はこの御教書に対して不参の返答をしたとみられ、成氏は「彭西堂」を上洛させてこの注進状を徳本入道に送達したとみられる。
この注進状は将軍義政に披露され、7月10日、条々への返事の第一条として「安房入道帰参事、重被成御教書候、尚堅可被仰遣候旨候」と、将軍義政が憲実入道に強く帰参を命じる再度の御教書を下したことを「太平山城入道殿(成氏近臣か)」へ伝えている(七月十日「将軍家御教書」『喜連川文書』)。また、七澤山に籠る「修理大夫父子」はまだ「不帰参」で「物惣難止候」との報告により、帰参するよう命じる御教書も出されたことがわかる。
●宝徳2(1450)年7月10日「畠山徳本書状」(『喜連川文書』)
上記御教書の第二条の「右京亮事、同被成御教書候」は下記の御教書に相当し、上杉憲忠も早々に鎌倉へ帰参して、「可被致無為之談合」ことを命じている(七月十日「将軍家御教書」『上杉文書』)。
●宝徳2(1450)年7月10日「将軍家御教書」(『上杉文書』)
なお、その二日後の7月12日に出された御教書は、10日のものとほぼ同内容が記されているが、早々に帰参し、御教書を下した「各」と騒劇を鎮める方策を模索せよとあり(七月十二日「将軍家御教書」『喜連川文書』)、この御教書は上杉憲忠のみならず、関係する人々に下されたものとみられる。それは、8月30日までに「面々」より「御請」が京都に届けられており、将軍義政も「目出由被仰出候」と述べていることからもうかがえる。
●宝徳2(1450)年7月12日「将軍家御教書」(『喜連川文書』)
また、第四条の「還御事、被召出長棟、可有御談合候」から、成氏はこの時点でまだ鎌倉に還御できておらず、憲実入道を召し出して話し合うよう指示している(七月十日「将軍家御教書」『喜連川文書』)。そして第五条においては、将軍義政は今回の叛乱に加わった関係者とは対面を拒否する旨を報告している。このように、京都と鎌倉は意思疎通を細かく取っており、今回の江ノ島合戦も、上杉禅秀の乱のような大乱に発展することなく、理性的に収束させることに成功している。
7月10日の管領書状を請けた鎌倉殿成氏は、付されていたであろう管領憲忠及び憲実入道の召還の御教書に基づき、両名に帰参を命じたとみられるが、憲実入道については拒絶が予想されるため、綸旨の再下賜を管領に申請したとみられる。また、扇谷修理大夫入道父子については、憲実入道の執り成しがあった旨を京都へ注進した。同時に、成氏の現在の所在地が「桐谷(鎌倉市材木座4丁目付近)」ということも知らせている。成氏は江ノ島からおそらく舟で若江島(鎌倉市材木座6-23-6)へ渡り、桐谷に入ったのだろう。
成氏の注進を受けた畠山徳本入道は、すぐに将軍義政に注進状を披露し、8月30日、返答の御教書が下された。憲実入道帰参の綸旨下賜については、安房入道帰参の考えを談合が先決であるとした。扇谷上杉父子の帰参は、憲実入道の執り成しがある以上は早々に赦免して召し出すように命じている。また、憲実入道に補佐を命じた上は、今後は何事も憲実入道を通じて京都に御注進ある様にとの但し書きを加えている。
●宝徳2(1450)年8月30日「畠山徳本入道書状」(『喜連川文書』)
●宝徳2(1450)年8月30日「畠山徳本入道書状」(『喜連川文書』)
成氏は9月21日には鶴岡八幡宮領内の「沽脚」地について「為徳政所返付也」を行っており(宝徳二年九月廿一日「足利成氏御教書」『大庭文書』:戦古8)、この頃には鎌倉内のいずれかの御所に還御を果たしていたとみられる。
憲実入道および管領憲忠の鎌倉帰参については、7月10日発給の御教書(現存せず)でおのおの命じられているが、憲実入道については8月30日時点で返答はなかったようである。憲実入道と成氏との間では幾度かやり取りはあったと思われるが、前述のように受け容れなかった様子が見える。
一方、憲忠もいまだ帰参せず、父憲実入道に帰参の執り成しを命じる御教書が下されたようであるが、憲実入道(「豆州狩野」に在住)はもともと憲忠を俗世に出す気はなく、憲忠の関東管領職就任も綸旨によって為されたもので憲実入道の本意ではなかった。10月11日、憲実入道は「就愚息右京亮帰参之事」について御教書を下されたが、「雖父子之段勿論候、彼者之事令義絶候間、謹奉返進候」と、憲忠は義絶しているので説得を拒否する旨の返信並びに、この件の御教書を返進するとして、在京の憲実入道代官の判門田壱岐入道に送っている。
●宝徳2(1450)年10月11日「上杉長棟披露状写」(『上杉文書』)
その後、憲忠がいつ帰還したかは定かではないが、10月11日、京都では管領徳本より「上杉右京殿」へ宛てて、醍醐寺地蔵院領の「相模国武、林四箇村」に「一色伊予守」が「強入部」したことに対して、早々に退散させるよう在京代官の「判門田壱岐入道祐元」に沙汰付けている(宝徳二年十月十一日「畠山徳本奉書写」『松雲寺文書』)。同日に伊豆の憲実入道が、憲忠帰参については説得しない旨の文書を京都に送っていることから、10月11日の段階では憲忠は鎌倉に帰参していないが、関東管領への命として下したとみられる。
●宝徳2(1450)年10月11日「畠山徳本奉書写」(『松雲寺文書』:黒田基樹「史料紹介・上杉憲忠文書集 -山内上杉氏文書集4-」)
一方憲忠は、関東管領を辞する旨を京都へ遣わしたようである(十一月廿二日「畠山徳本奉書写」『上杉文書』)。その理由は「煩」のようで、このことは京側は「誠以不知所謝候」と述べている。かつて成氏が憲忠のことを「行歩不自由歟、尤不便至候」(宝徳二年五月十二日「足利成氏注進状」:『鎌倉大草紙』)と気遣っているところから、憲忠は生まれつき足が不自由であった可能性があろう。しかし、京都側は慰撫しつつ強く慰留したため、なんとか管領職には留まったようである。
●宝徳2(1450)年11月22日「畠山徳本奉書写」(『上杉文書』:黒田基樹「史料紹介・上杉憲忠文書集 -山内上杉氏文書集4-」)
11月28日、成氏の還御(鎌倉中いずれかの屋敷)に際し、鑁阿寺(龍福院か)より社務(成氏の弟定尊か)に送られた依頼品の「巻数并御折紙等」を、鶴岡社務の役人・河口前下野守光藤が御所の奉行人「前但馬守定之」に渡し、成氏が拝見している(十一月廿八日「前但馬守定之書状」『鑁阿寺文書』)。
●宝徳2(1450)年(カ)11月28日「前但馬守定之書状」(『鑁阿寺文書』)
こうして、成氏の鎌倉還御は成り、関東管領憲忠も宝徳2(1450)年11月までには鎌倉に帰参したことで、関東における騒擾も落居したとなったのだろう。翌宝徳3(1451)年2月、成氏は京都からの指示を必要とする諸問題を条々にして京都に送達した(「足利成氏条々案」:『喜連川文書』)。
●宝徳3(1451)年?「足利成氏条々案」(『喜連川文書』)
同時期、京都では鎌倉落居の知らせを受けたものか、成氏の「御昇進御上階」が決定され、成氏は2月28日の除目で「従四位下」「左兵衛督」となる。
●宝徳3(1451)年2月28日「後花園天皇口宣案」(『東京国立博物館寄託妹尾文書』戦古:11)
この口宣が出された翌日2月29日、管領徳本入道は「御昇進御上階事」の口宣の祝意及び成氏から依頼されていた綸旨(上杉憲実入道帰参についての綸旨か)についての事柄、先日に成氏より届けられた条々への返事を送達した。ただ、この条々のうちすべてに返答があったわけではなかった。
●宝徳3(1451)年2月29日「畠山徳本披露状」(『喜連川文書』)
成氏の条々のうち、2月29日の徳本披露状で返答がなされたのは、第一条と第三条のみで、第二条と第四条については返答がなされた形跡はない。
●「成氏条々」とその返答「徳本披露状」の比較
| 『成氏条々』叙位 | 宝徳三年二月廿九日『畠山徳本披露状』 | |
| 第一条 | 足利庄御代官、早速可被差下事 | 足利庄以下、同京家領知事、委細御申之趣、尤御本意候 |
| 第二条 | 関東御分国所帯、去永享年中強入部輩、或号京都 上意、于今不退違乱事 | ― |
| 第三条 | 関東祇候人就所帯、申成京都御吹嘘事 | 足利庄以下、同京家領知事、委細御申之趣、尤御本意候 |
| 第四条 | 落人等於京都雖有申子細等、一切不可有御許容、就中長尾左衞門入道、太田備中入道事者、不申及事 | ― |
この関東御分国内における「京都御扶持之輩」の抵抗は、成氏父の持氏の代から「関東における騒擾の根元」であり、持氏は鎌倉殿に就任以来、生涯をかけてこの問題の解消を試みたが、圧し潰されてしまった。成氏はこの問題を引き続き解消するべく京都との交渉を行ったとみられる。
一方で、第二条に関しては京都側からの返答がなかったためか、成氏の近臣による「関東御分国所帯」への強入部等が行われ、とくに上杉憲忠関係の所領への介入を行っており、この件を京都側は重く見て対応を管領憲忠に命じている。この頃には、成氏と管領上杉憲忠の間には、軋轢が生じていたと考えられ、この対立がのちの大きな破綻へと繋がっていく。
鎌倉殿成氏は管領憲忠個人の力量に不安を感じていたと見え、2月末の時点でも京都に「綸旨(憲実入道帰参の綸旨であろう)」を願い出ている。成氏は山内・扇谷両上杉家の家宰で叛乱の首魁・長尾左衛門入道と太田備中入道へ断固とした態度で臨むよう京都側に依頼しているが、一方で彼らを抑え、関東を無為に属させることができるのは憲実入道しかいないという考えがあったのであろう。しかし、憲実入道は鎌倉に帰参せず、彼らを抑えることがかなわない状況にあった。京都側も条々第四条へは無回答であったことからも、関東管領憲忠の力量不足もあり、長尾左衛門入道、太田備中入道の排除は関東無為に利しないとの認識があったのかもしれない。
このような中、京都では享徳元(1452)年11月、管領畠山左衛門督入道が「金吾禅門依上表也」(『斎藤基恒日記』享徳元年十一月)し、11月16日、「勝元廿三歳再任、廿七出仕始」(『武家年代記』)と、細川右京大夫勝元が管領職に再任された。12月14、15日頃、成氏は京都に「御剣一腰黒鞘、目貫桐、御馬二疋雲雀印雀目結、同栗毛印雀目結」(十二月廿一日「細川勝元書状」『喜連川文書』:神6176)を献上のために出立させており、おそらく管領代替の賀使と思われるる。京都側ではすぐに返状(十二月廿一日「細川勝元書状」『喜連川文書』:神6176)が認められ、鎌倉へ返礼したとみられる。
その後、勝元と関東との関わりはしばらく見られないが、翌享徳2(1453)年3月21日、管領勝元から勝元被官の「長塩備前入道(宗永)」を使者として「壮公記室禅師」なる禅僧に「自関東様可蒙仰之間事」についての書状が届けられている(享徳二年三月廿一日「細川勝元書状」『喜連川文書』)。これは成氏から送られる「公私」の書状は「如前々」、関東管領上杉憲忠の副状とともに送達するように依頼している。この副状がない場合は御書を下されたとしても「不可及御返事候」としている。「如前々」とあるように、成氏の書状には今までは憲忠副状が付されていたことがわかるが、今回の書状は「何らかの事情」によりそれが付されていなかったと思われ、下記文書はそれを今一度確認した文書とみられる。「壮公記室禅師」は成氏の使僧「■壮■■」と思われ、成氏は私的な文書を送達したものだろう。公文書ではないことから、管領勝元も被官の長塩備前入道を使者に使わしたとみられる。
●享徳2(1453)年3月21日「細川勝元書状」(『喜連川文書』)
成氏の文書に管領憲忠の副状が付されなくなったのは、想像ではあるが、両者の断絶と成氏による上杉憲忠への敵意が大きな原因と思われる。宝徳年中には憲忠の京都雑掌である判門田壱岐入道の所領、または預かる所領に成氏方の人々が押領、強入部などしている様子がうかがえる。
| 判門田壱岐入道祐元の所領「常陸国三村羽梨等」に成氏与党「小田讃岐守(小田持家)」が宝徳2(1450)年以来押領しているので、早々に追い払い、祐元に沙汰付けるよう上杉憲忠に指示。 | 宝徳三年五月廿五日「畠山徳本奉書写」 『上杉文書』:群馬1570 |
| 宝徳2(1450)年秋ごろ「醍醐地蔵院領相模国武、林四箇村」に成氏近臣「一色伊予守強入部」したため、京都は「被沙汰付判門田壱岐入道祐元之旨」を指示した。 |
宝徳二年(カ)十月十一日「畠山徳本奉書写」 『松雲寺文書』『上杉文書』:黒田基樹 「史料紹介・上杉憲忠文書集 -山内上杉氏文書集4-」 |
| 六角久頼の知行地である「相州長尾郷」は「自先年下地」を「判門田方(判門田壱岐入道祐元)」に預け置かれていたが、「去年」から成氏近臣「簗田中務丞方押領候」したので、憲忠に「可被返渡之由、預御成敗候者恐悦候」ことを憲忠に依頼している。 | 宝徳二年(カ)十二月九日「佐々木久頼書状案」 『上杉文書』:黒田基樹 「史料紹介・上杉憲忠文書集 -山内上杉氏文書集4-」 |
| 「野田弥三郎持保」知行地に同族で成氏近臣の「右馬助持忠」が強入部しているのを早々に追い払い、持保に沙汰付けるよう上杉憲忠に指示している。 | 宝徳三年五月廿五日「畠山徳本奉書写」 『上杉文書』:黒田基樹 「史料紹介・上杉憲忠文書集 -山内上杉氏文書集4-」 |
こののちも、成氏と関東管領憲忠の接点はうかがえないが、成氏は「西御門」邸にへ移った際には、憲忠に懇切な御内書を下したとみられ、憲忠は「誠以忝畏入存候」と謝意を示し、もし何か雑説(憲忠への、ということか)があったとしても、深くお考えの上ご判断できるでしょうという書状を、成氏側近の本間遠江入道へ渡している。
●享徳3(1454)年(カ)8月7日「上杉憲忠披露状」(『喜連川文書』)
なお、『鎌倉年中行事』には「御所造并御新造之御移徙之様躰事」が記されているが、成氏の西御門御所への移徙が『鎌倉年中行事』成立年(享徳三年)であること、「勝光院殿様御代」「長春院殿様御代」との比較が記されている事、成氏が鎌倉に建てた新造御所はこの「西御門」御所のみであることを考慮すると、この「御所造并御新造之御移徙之様躰事」は西御門御所を示し、所役はその造営担当であろう。西御門で四町四方の土地が確保でき、北方に山があるのは、現在の横浜国大附属中学校から小学校の校舎敷地部分のみであることから、この場所に西御門御所が造営されたと推測される。「御所造并御新造之御移徙之事」(『鎌倉年中行事』)として、「御遠侍ハ大間七間ニテ立物御畳ナドハ無之、千葉介役所也」とある。
●御所造営の担当(『鎌倉年中行事』)
| 建物群 | 概要 | 担当所役 |
| 御築地 | 方四町(109m四方) | 奉公外様 |
| 大御門 小門 |
南向 | 松田・河村 |
| 東門 西門 不明之御門(西向) |
※北は門無し →北ハ山ニテ八幡宮ヲ立御申アル也、上之八幡ト号 |
|
| 御主殿 | 南向 ・御家中:九間六間 ・御帳台、御寝所ヘ三間宛 ・御納戸:三間 ・御庇ヨリ面之妻戸ノ間:御二間→傍に中門がある ・其次:六間 ・若君御祝ノ時ハ此御座 ・管領年始之出仕之者、御妻戸ヨリ被参 |
佐竹 |
| 御中居 | 佐竹 | |
| 居留 ・管領被坐休所 ・廿間 ・三十間 |
御所 管領 千葉介 |
|
| 中門 | 御二間之御妻戸ノソバ、御車寄ノ左ノ方 →御祝之時、御剣、御具足、弓、征矢、沓、行縢モ、御中門ヨリ持テマカリ出テ持参申 |
|
| 御評定所 | 十五間 | |
| 御遠侍 | 大間七間ニテ、立物、御畳ナドハ無之 | 千葉介 |
| 七間御厩 | 七間、二間 | 小山 |
| 臨時之御厩 | 三間(皆以公料、大工ニ被仰付、被造之) | (大工) |
| 長面道 | 十七間 | 奉公人 |
| 面之御台屋 | - | 那須 |
| 東之御台屋 | - | 宇都宮 |
| 御台所 | - | 三浦介 |
こうした成氏と憲忠の複雑な関係は、享徳3(1454)年11月28日の時点で破綻の兆しを見せていたと推測できる。11月28日、常陸国から鎌倉に出仕していた宍戸中務大輔持里のもとに、庶家の筑波別当大夫潤朝が「属惣領中務大輔手当参仕」っているのである(享徳4(1455)年2月筑波潤朝軍忠状案写(「古証文二」神奈川県史料6187)。筑波氏はかつて結城合戦で足利安王丸に属し、父玄朝以下が奮戦して多数討死を遂げるという働きをみせた一族であり、この日筑波山から別当大夫潤朝が鎌倉を訪れて、同じく上杉勢に抵抗した惣領家宍戸持里に属していることから、成氏はこの頃から軍事的な行動を想定していたと推測が可能であろう。
そして、享徳3(1454)年12月27日、年末も押し迫ったこの日に破綻した。この日、「鎌倉殿、被誅管領上杉右京亮、於御所被出抜云々、故鎌倉殿之御敵之故者哉」(『康富記』享徳三年十二月廿七日条)とあるように、成氏は上杉憲忠を御所へ招いて殺害した。
「上杉右京亮妙椙廿二歳、享徳三甲戌十二月被誅」(『本土寺過去帳』廿七日上段)と見え、当時憲忠は二十二歳だった。同じく憲忠家宰・長尾但馬守実景も「長尾但馬守親子打死」(『本土寺過去帳』廿七日上段)とあるように、討たれている。腹心の長尾左衛門尉景仲入道や、舅の扇谷修理大夫持朝入道らが鎌倉を不在にしている間の出来事であった。
●『本土寺過去帳』廿七日上段
憲忠殺害の実際の理由は定かではないが、成氏の主張(康正二年四月四日「足利成氏書状写」(『武家事紀』巻第三十四))では、
| (1) | 及累年振権勢、没倒寺社旧附荘園、無省分国、一揆押妨官仕功労所帯、令恩補顧聘家従、恣極奢緩怠追日倍増間、連日以専使雖加折檻、無有許容、剰憲忠并同名修理大夫入道郎従充満、往返巷致強竊、依塞官路、真俗甲乙共失資粮、逢横災者不可称計、終不致糺明過来候了 |
| (2) | 先年江島出陣時、令随逐憲忠、致不義凶軍等、横訴於頻雖執申、依不許容、召集分国一揆被官人等、致嗷訴企謀乱事、雖及度々堪免處、益権謀露顕上、馳下分国、可揚兵儀為支度、上州エ差遣長尾左衛門入道昌賢、回種々計略、縡已覃火急間、依難遁天責歟誅戮了 |
というものだった。
(1)については、憲忠の力量を不安視していた成氏が、本当に憲忠を「及累年振権勢」と考えていたとは思えず、江島合戦についても「右京亮事、自元無誤間」と当時の管領畠山徳本入道に報告していたと考えられることから、訴えを大きく見せるための例句であろう。
(2)については、憲忠が「凶軍」を働いたとあるが、以前に成氏は「右京亮事、自元無誤間」との認識があることから、憲忠追討の大義のために盛り込んだものである。そして「益権謀露顕上、馳下分国、可揚兵儀為支度、上州エ差遣長尾左衛門入道昌賢、回種々計略」とある部分も、憲忠が「益権謀露顕」したと自他ともに認識し、「馳下分国、可揚兵儀為支度」に「上州エ差遣長尾左衛門入道昌賢」しているのであれば、当の憲忠が12月27日にノコノコと敵陣とも言うべき御所へ出向くことも通常考えにくいだろう。
●康正2(1456)年4月4日「足利成氏書状写」(『武家事紀』:「栃木県史」)
上記は『武家事紀』に掲載されている成氏の書状である。『武家事紀』は江戸初期の編纂物であり、この「足利成氏書状写」も現存しておらず真偽不明だが、享徳4(1455)年3月15日には「伯耆守(佐野盛綱)」を上州の岩松持国へ遣わし「其方江長尾左衛門入道昌賢、近日可出張雑説由注進」ことにつき、成氏「時宜」を伝えさせている(「足利成氏書状写」『正木文書』:戦古34)ことから、少なくとも『武家事紀』の「足利成氏書状写」の長尾左衛門入道の上州下向に関してはおおむね事実を伝えているとみてよいだろう。
宝徳2(1450)年5月の江島出陣の後、管領憲忠は半年間帰参せず、乱の張本である長尾・太田を鎮め得る憲実入道もまた要請に応じない。そして管領憲忠の舅で扇谷上杉家の修理大夫入道父子は反乱を主導し、いまだに帰参していない。こうした上杉家に対する強い嫌悪感に加えて、憲忠の力量不足、反乱の元凶たる長尾左衛門入道や太田備中入道の罪は不問に処されたも同然の措置に、成氏の怒りが頂点に達したことが、憲忠殺害の大きな原因ではなかろうか。
成氏は長尾左衛門入道が上州へ出立し、鎌倉を不在にしている状況で憲忠殺害を計画したものか。憲忠岳父の扇谷修理大夫入道や三郎顕房、太田入道はいまだに帰参しておらず、七澤山(厚木市七沢)あたりにいたのだろう。憲忠殺害の日の夜、成氏近臣の「岩松右京大夫殿(岩松持国)」は「廿七日雖及夜陰、最前馳懸山内、致手合之戦、自身被御疵」(享徳三年十二月廿九日「足利成氏感状写」『正木文書』戦古:19)とあるように、山内(鎌倉市山ノ内344辺)の憲忠邸に攻め寄せて山内上杉勢と合戦している。成氏近臣の宍戸中務大輔持里に属した庶家「筑波別当大夫潤朝」は「従同十二月廿八日」合戦に加わっているとあるため(享徳4(1455)年2月筑波潤朝軍忠状案写(「古証文二」神奈川県史料6187)、この山内亭近辺の合戦は、翌日も継続的に発生していたと思われる。
この成氏による関東管領憲忠殺害事件については、翌享徳4(1455)年正月5日に京都へ「関東飛脚到来、鎌倉殿持氏御子 成氏、去年十二月廿七日、管領上杉右京亮房州入道子、被召出於鎌倉殿御所被誅伐」(『康富記』享徳四年正月六日条)という確報が届いた。その理由は「是併故鎌倉殿御生涯事、父房州申沙汰之御憤歟」との推測があり、「依之御所方与上杉手有合戦」と、御所方と上杉家との合戦も報告された。
京都に憲忠殺害の注進が届いた同日の正月5日、成氏は武蔵国の戦勝由緒の稲荷大明神(現在の烏森神社)に願文を収め、「所願悉有成就」を祈っている。当時、この稲荷社は荒れていたのか、所願成就のあかつきには社殿修造を行うと誓っている。
●享徳4(1455)年正月5日「足利成氏願文」(『烏森神社文書』戦古:20)
憲忠を殺害された上杉方も態勢を整え、正月6日には「上杉修理大夫入道并憲忠被官人等」が七沢の要害を出て鎌倉を目指し、相模川の低湿地帯の中と推測される「相州島河原」(平塚市大島)に兵を繰り出した(「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)。この一報に成氏もすぐさま「一色宮内大輔、武田右馬助入道」を差し遣わして、「多分討取候了」という。これはかつて故父持氏が上杉憲実の上州逐電時に取った進軍方法を彷彿とさせるが、こののち、成氏は自ら鎌倉を出立して武蔵府中へ進んだとみられる。なお、成氏はこの鎌倉発向ののち二度と鎌倉へ帰還することができず、以降、子孫は下総国古河(茨城県古河市)を拠点とする「古河様」として、16世紀後半までの約百数十年間、関東に強い影響力を及ぼすこととなる。
翌正月7日には常陸国の「就右京大夫参上」しており、成氏は憲忠追討直後には佐竹右京大夫義人入道に次第を伝えて協力を取り付けており、佐竹一門だが義人入道とは距離を取っていた「大山因幡守殿(義人に追放された義人嫡子・伊予守義俊の外祖父)」に「属右京大夫手、不日馳参」ことを命じている(享徳四年正月七日「足利成氏御教書写」『秋田藩家蔵文書七 大山弥大夫義次所蔵』:戦古21)。これには成氏近臣「本間前近江守直季」も副状を付しているが、大山因幡守は正月29日に至っても成氏方には参じていない(享徳四年正月廿九日「足利成氏軍勢催促状写」『秋田藩家蔵文書七 大山弥大夫義次所蔵』:戦古24、参考四)。
成氏は武蔵国府へ向かう中で、正月14日には「豊島勘解由左衛門尉(豊島泰景)」、「豊嶋三河守(豊島泰秀)」ら武蔵豊島一族への参陣を命じるなど(享徳四年正月十四日「足利成氏軍勢催促状」『豊島宮城文書』:戦古22、23)、東武蔵への勢力拡大にも腐心する。ただし、彼等は長尾左衛門入道昌賢との紐帯が強く、上杉方に応じて成氏とは敵対している。
正月21、22日には、「上杉右馬助入道、同名太夫三郎并長尾左衛門入道等」が「武州、上州一揆以下同類輩、引率数万騎、武州国府辺競来」(「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)と、上野国から庁鼻和右馬助憲信入道、扇谷大夫三郎顕房(修理大夫持朝子息で扇谷家当主)、長尾左衛門入道が、武州・上州一揆を率いて武蔵国府付近に着陣した。成氏はみずから「於高幡、分倍河原」に布陣し、「両日数箇度交兵刃、終日攻戦」した。具体的には21日は「武州立川之御合戦」、22日は「府中之御合戦」(享徳4(1455)年2月筑波潤朝軍忠状案写(「古証文二」神奈川県史料6187)と見える。21日の合戦は立川(立川市柴崎町)から高幡河原(日野市高幡付近)にかけて行われており、ここを攻めた「故禅秀か子息、上杉右馬助憲顕」(『鎌倉大草紙』)に対し、「成氏五百余騎にて馳出、短兵急」に寄せ、「とりひしぎ火出るほどに攻戦」った結果、「上杉方の先手の大将右馬助入道憲顕、深手負て引かねけるが、高旗寺にて自害」した(『鎌倉大草紙』)。なお、この「右馬助入道憲顕」は、禅秀子息の憲顕(憲秋)とされるが、憲秋は中務大輔の官途を有し(称し)ており、晩年に及び格下の右馬助を称することは考えにくい。
22日には「分倍河原に陣を取上杉勢の荒手の兵五百余騎」が武蔵国府に攻め寄せた(『鎌倉大草紙』)。これに成氏は「きのふの合戦に打勝」った勢いに乗じて「散々に切てかゝ」り、「上杉方の先陣、羽続、大石以下悉打負敗軍」した。成氏は勝ちに乗じてさらに攻め入り、「里見、世良田、深入して討死」するが、「結城、小山、武田、村上入替て攻」め、「上杉忽打負、悉敗軍」した。その結果、「扇乃谷房顕ハ後陣ニうちけるか味方をいさめ、きたなし返せ」と踏み止まって戦うが、みな逃げている中で留まる兵もなく、我先にと逃散した。すでに房顕被官の者たちもみな討たれたり重傷を負っている者ばかりとなり、扇谷上杉家の若き当主、三郎房顕は「夜瀬と云所に残留りて廿一才にて腹切」った。
この合戦で「上椙両人討取、数人候」(「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)といい、庁鼻和憲信入道、扇谷顕房、そのほか主だった者数名も鎌倉勢に討ち取られた。合戦後、「至于今残党者、束手令降参候了」(「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)するが、「其後、敗軍余党等、常州小栗城ニ館籠」っている。
その後、成氏勢は小栗城を攻めるべく、「野州、結城、御厨江進旗差向」(「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)ている一方で、上野国では新田岩松右京大夫持国が鎌倉方の主将となって上杉方と合戦し、2月中には「於深須、赤堀、太胡、山上合戦」が起こっている。
一方、上野国においては、享徳4(1455)年早々には、新田岩松右京大夫持国を主将とする成氏方が上杉方と局地的な戦いを行っていた。上野国では、岩松持国に加えて、同所で戦っている「桃井左京亮」(享徳四年五月廿五日「足利成氏書状写」『正木文書』:戦古66)、「鳥山式部大夫」(享徳四年五月廿七日「足利成氏書状写」『正木文書』:神6216)の以上三名が「三大将」と称され、成氏から互いに協力して対処するよう指示されている。「桃井左京亮」は嘉吉元(1440)年5月の結城合戦で討死した桃井左京亮の子か。このほか上州の主だった大将としては「石堂、一色、世良田、里見」(『康富記』享徳四年七月廿六日条)の名が見える。
岩松持国は前年12月27日夜、上杉憲忠の鎌倉郊外山内亭を襲撃(山内家執事の長尾但馬守実景父子を討ったか)し、負傷しながらもその足で上野国へ駆け下ったようで、正月上旬にはすでに上野国へ入っており、「京都祗候」の「大舘上総介知行分」(大舘郷四ヶ村、一井郷四ヶ村か)の押領を企てている。兵粮料所としての接収とみられるが、持国は憲忠殺害以降は、関東と京都の戦いと認識していたのだろう。ところが、成氏は、京都との戦いはまったく本意ではなく、父持氏薨去後に関東を恣意的に支配してきた上杉一族を征伐するという考えであって、京都奉公衆である大舘上総介教氏の知行地を冒す所行は許されるものではなかった。成氏はこの報告を受けるや、ただちに持国に対し「大舘上総介知行分等事、可被散之由其聞候、不可然候」と狼藉の停止を指示した(享徳四年正月十三日「足利成氏書状写」『正木文書』142)。ただし、「凶賊相籠子細候者、能々極実否、可被得上意候」と、もし上杉方が大舘郷等に立て籠もっているというのであれば、しっかりと確認をした上で、成氏の上意を仰げと命じている。
2月17日夜、「善信濃入道、同三河守庶子等在所悉焼落」ており、上州赤堀周辺で上杉方による攻勢があったことがわかる(年月闕「赤堀政綱軍忠状」『赤堀文書』)。翌2月18日には「下野守時綱(赤堀時綱)」が成氏の「武州村岡御陣馳参、在陣仕」り、3月3日の成氏古河御移座に供奉している。その際「上州中一揆事、古河江可被御供候」ことを「岩松右京大夫殿」に伝えており(享徳四年三月三日「足利成氏書状写」『正木文書』:戦古29)、あわせて上州中一揆の人々の「知行分等」への狼藉を固く禁ずる旨を伝えている。同日、「高左京亮」へも一族と談合し、岩松持国と合力して「上州凶徒退治」を行うよう命じている(享徳四年三月三日「足利成氏軍勢催促状」『高文書』)。
2月26日には、「於深須、赤堀、大胡、山上合戦」が起こっているが、持国からの書状を見た成氏は「誠無心元被思食候」とあり、上杉方優勢に終わったようである。成氏は「御勢事、即時堅被仰付候、能々可被廻計略候」と指示した(享徳四年二月廿七日「足利成氏書状写」『正木文書』152)。成氏は舞木氏や佐野氏にも出兵を厳命しており、2月29日には持国からの「重注進」に対して「仍舞木、佐野事、堅被仰出候」ことを報告し、「定今日之間可着陣候」と伝えている(享徳四年二月廿九日「足利成氏書状写」『正木文書』239)。こうした上野国の戦闘に対し、岩松持国は兵粮料所として「上州馳井郷」「同国赤石郷」「同国藤木郷」を成氏に要求したとみられ、成氏はこれを認めている(享徳四年二月「岩松持国闕所注文写」『正木文書』65)。
3月上旬、岩松持国は成氏へ上野国の情勢を注進した。これを披見した成氏は3月5日、「猶以有調儀可、被寄御陣候」を命じるとともに、「三大将」が綿密に相談して対処するよう指示した(享徳四年三月五日「足利成氏書状写」『正木文書』138)。しかし上州の情勢は依然として厳しく、岩松持国は成氏に更なる支援を要請している。2月29日に「定今日之間可着陣候」するはずの舞木・佐野両氏はまだ岩松のもとに参着していないことも報告されたと見え、成氏は「佐野、舞木両人事、固被仰付候」と、再度出兵を命じたことを伝えた。なお、持国が追加で要請したと思われる「長井、蓮沼事」からの援兵については「以前武州江被遣候間、難被仰付候」と伝えている(享徳四年三月五日「足利成氏書状写」『正木文書』242)。
ところが、3月14日、古河に馳せ参じていた「上州中一揆」が「大略落行」き(享徳四年三月十四日「足利成氏書状写」『正木文書』137)、「致御敵」(年月闕「赤堀政綱軍忠状」『赤堀文書』)という状況が発生した。一揆の一人である赤堀下野守時綱は成氏方として残留しているが、この一大事を受けて成氏も当惑し「言語道断次第候」と持国に伝え、「其方用心大切候、三大将能々可有調儀候」と伝えている。
この上州一揆退散は上野国守護代である「長尾左衛門入道昌賢」の調略と思われる。翌3月15日には成氏のもとに持国からの注進が入っており、長尾昌賢入道が「近日、可出張雑説」があるという。成氏は「然者、即可被加一揆勢」と見ており、持国には佐野伯耆守盛綱を遣わして、対処するよう指示している(享徳四年三月十五日「足利成氏書状写」『正木文書』254)。
岩松持国はさらに情勢を注進し、こうした情勢ながら持国が「安威左衛門以下在所方々被相散候」ことを「尤可然候」と賞している(享徳四年三月十九日「足利成氏書状写」『正木文書』134)。
勝長寿院門主成潤
「勝長寿院門主成潤」は成氏の舎兄に当たり、持氏代に幼くして勝長寿院に入れられ(まだ正式な門主ではないだろう)、「大御堂殿」と称された人物である。
永享11(1439)年2月10日に父持氏が鎌倉永安寺で自害したのち、他の兄弟とともに鎌倉を脱出(おそらく上杉持朝、千葉介胤直らの手引であろう)し、由緒の日光山へ遁れたとみられる(弟の春王や安王も同道した可能性はあるが、その後彼らは常陸国へと移っている)。翌永享12(1440)年3月頃、成潤(当時の名は不詳)は日光付近の豪族日名田氏に奉じられて挙兵し、下野国を南下。下総国結城城主の結城中務大輔氏朝と激突し、日名田氏は討ち取られた。この挙兵と同時期に常陸国の春王・安王兄弟も兵を挙げていることから、彼らは連携していた可能性が高いだろう。
成潤率いる軍勢を追捕した結城氏朝は、日名田某の首級を京都へ送達するが、この送達している間に、成潤は氏朝の子・七郎と話を付け、結局結城氏朝は成潤を匿うことに同意した。さらに、常陸国からの春王、安王も氏朝を頼り、さらに信濃国の大井持光に匿われていた、持氏遺児・永寿王丸(のちの成氏)も加わったとみられる。こうして、結城氏朝は故持氏の遺児を奉じて、兵を挙げることとなった。結城合戦である。
その後、結城城は関東諸氏のみならず京都からの軍勢によって攻められ、翌永享13(1441)年4月16日に陥落。城主氏朝は自刃し、多くの旧持氏党の人々が討死を遂げた。そして、城内で捕らわれた春王、安王の兄弟は京都へ送られることとなり、その途中の美濃国垂井で殺害される。また、永寿王丸はその後、しばらくして京都へ送られたが、美濃国垂井にて京都からの指示が待たれる中、京都では将軍義教が赤松満祐入道の手によって殺害されていた。そのため、永寿王丸は殺害されることなく京都へ送られ、土岐邸にその後九年間、養育されることとなった。
文安6(1449)年6月に在京の永寿王丸は「被治定了、成氏也」と定められ、8月27日に鎌倉へ還御する。その際、成潤も定尊や周昉とともに鎌倉へ下向したか。この下向に合わせ、成潤は改めて「勝長寿院門主」に補され「成」字を下されたか。
成氏が宝徳2(1450)年の江ノ島合戦から鎌倉へ戻って以降、「勝長寿院御門主并雪下殿、御一所御座、尤可然之由、被仰(下候)」(宝徳二年五月廿七日「畠山徳本書状」『喜連川文書』)とあるように、将軍義政より、勝長寿院門主成潤と雪下殿定尊の兄弟は「御一所御座」すべきことが命じられているため、「勝長寿院門主成潤」やその弟「雪下殿(定尊)」は成氏とともに鎌倉にいたとみられる。「重氏出時、兄弟三人不速来テ重氏ヲ扶タゾ、弟ハ美濃ノ土岐ニ養セラレタ雪ノ下殿ト云タ一人ナリ、聖道デアツタゾ、又ノ弟ハ僧ガ一人有タ、又重氏一ノ兄ガ美濃ニアツタゾ、其ハ俗人ゾ」(柏舟宗趙『周易抄』)ともみえ、この兄と弟二人の「以上三人来テ重氏ヲ扶タゾ」という。成氏を扶けた「兄弟三人」は弟の「雪ノ下殿(美濃土岐氏に養われた一人)」と「僧」が一人、そして美濃にいた成氏舎兄一人(俗人)という。「雪ノ下殿」は定尊とみられ、僧侶は「周昉長春院主」または「尊敒雪下殿蓮華光院」であろう。そして、美濃国にいたという成氏の「一ノ兄(俗人)」が成潤であるとされるが、結城合戦後に「第二若君」は姿を消しており、美濃国の土岐氏に匿われていた可能性もあろう。彼は「始者奉号大御堂殿」とあるように、当初は「大御堂殿」を号し奉っていたのであって、鎌倉逃亡後はその職は罷免されていたであろうから、結城合戦当時は法体ではなく「俗人」となっていた可能性は高い。
しかし、享徳3(1455)年12月27日の関東管領憲忠の殺害後、「勝長寿院殿は、成氏の御弟にして、御所方の最なりしが、敵より何とか賺し申しけるにや、鎌倉を落ちて日光山へ御移り、敵と一味して衆徒を催さる」(『鎌倉大草紙』)と見える。成潤は憲忠殺害を期に、鎌倉を退転した。このとき、日光山までの道中を無事に通り過ぎる方便か、成氏には「如以前啓上、同心聞候」(康正二年四月四日「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)とあるように、成氏に同心する旨の書状を遣わしていたことがわかる。
ところが、その後成潤が「陣館於移日光山候」したため、成氏は「意趣何事候哉由尋試候」と、成潤に日光山に立て籠もった意図を尋ねている。これに成潤は「罰文」を提出して「陳謝」しているが、成潤は当初から上杉方に属す意図で鎌倉を出立しており、当然ながら上杉方と通じ、成氏は「加敵陣候、大虚偽之至候」と激怒している。成潤から成氏に送達された書状は「彼書状、為御披覧写進候」とあるように、康正2(1456)年4月4日、成潤書状の写を証拠として京都の三条実雅へ宛てて送っている。
●康正2(1456)年4月4日「足利成氏書状」(『武家事紀』)
その後、上杉氏と成氏の対立の中で、上杉勢は本陣を武蔵国五十子に構えて古河を窺い、実に十八年にわたる長期の戦いとなるが、成潤は「勝長寿院殿 大御堂殿 於五十子病死」(『当源家御所御系図』)とあるので、成潤は上杉方に匿われる形で五十子陣に入ったが、康正3(1457)年の五十子陣築城からほどなくして病死したと思われる。「早世」したと思われるのは、もし成潤が五十子でその後も生存していたとすれば、成氏の舎兄にしておそらく将軍義成の猶子として、成氏に対抗する大きな力となってその名が見えるはずであるからである。
なお、成潤は康正2(1456)年4月27日、「今日、鎌倉殿舎兄下向関東之間、今日被進発了」(『師郷記』康正二年四月廿七日条)の「鎌倉殿舎兄」と同一人物という説がある。
「成氏舎兄」は持氏と同時期に自刃した賢王丸義久と、大御堂殿成潤のほかは系譜上見当たらないが、成潤は康正2(1456)年4月4日以前に日光山に下り、成氏に敵対していることがわかっている(康正二年四月四日「足利成氏書状」『武家事紀』)事に加えて、この『足利成氏書状』は過去の日光山籠城を述べているのではなく、4月4日現在、成潤が日光山に籠っている状況を詰っているので、成潤が4月4日より後に京都から下向することはあり得ない。つまり、康正2(1456)年4月27日に離京した「鎌倉殿舎兄」が成潤であるはずはない。では、康正2(1456)年4月27日に京都から下向した「鎌倉殿舎兄」は何者なのか。この人物については関東の記録にも全く見られず、まったくの謎である。兄ではなく弟であれば「尊敒雪下殿蓮華光院」が該当の可能性があるが、明確に兄という記録であるため弟として考察するのは恣意的解釈(想定した仮説を正論とするために、明確な補完史料がないままに、史料の文言や人物を恣意的に差し替えなどで改変し、仮説が正しいという結論を導き出す事)となる。もし系譜上にない「舎兄」がいたのであれば、里見家や桃井家など御一家を継承していたなどの可能性もあるか。
京都は享徳4(1455)年の成氏鎌倉出師に対し、3月28日に「上椙ヽヽ故房州入道子関東発向」(『康富記』享徳四年三月卅日条)させた。彼は上杉憲実入道の次男・兵部少輔房顕(幼名龍春)で、成氏に殺害された関東管領憲忠の実弟である。彼を「総大将」(『康富記』享徳四年三月卅日条)として関東派遣が行われた。
この出陣は「春三ヶ月東方有憚、来月可進発之由雖存之、延引不可然之由、自室町殿被仰下之間、下向北国通」(『康富記』享徳四年三月卅日条)とのことで、正月~三月は東方進発は不吉であることから、四月に入ってからとの意見もあったが、将軍義政が延引を認めないと述べたため、3月中の派兵となっている。このとき房顕には「御旗」が下されているが、「為退治申鎌倉殿、為総大将所被差遣也、御旗被下之、世尊寺侍従三位伊忠卿被書之」(『康富記』享徳四年三月卅日条)というものだった。なお、その後東国に下向した主将は八名だったようで、「悉皆御旗八流也、其内錦御旗一流也、其者文字を書て、彫て、絵師ニ仰て、薄をもて字の上をたましむる也、日の形あり、元はこれも紙に書て、はくにて採色す、今度は御旗ニひたとはくを置也、紙をもてたますと云々、七流は布御旗也、其者布ニ字を書也」(『康富記』享徳四年閏四月十五日条)という。房顕に託された御旗は世尊寺伊忠の染筆(八幡大菩薩の文字か)によるものであることから、これが「錦御旗一流」であろう。
続けて、4月3日には「駿河守護今河ヽヽ、今日関東発向、関東御退治御旗被給之」といい、「御旗」を給わって京都から下向している(『康富記』享徳四年四月三日条)。彼の賜った「御旗」は「布御旗」となる。このほか「去月時分、為関東御退治、自武家御旗被下関東也、上椙、今河、桃井等賜之、下向也」(『康富記』享徳四年閏四月十五日条)とあるように、桃井某ほか五名(越後上杉房定ほか四名か)の大将が関東に攻め下った。
この頃、上州に「如風聞候山入残党等、近日可罷出張由其聞候」という情報が成氏のもとに入った。成氏は3月23日、これに対応するため上州に「不日可加一勢候」ことを「瑞泉寺」を以て伝えている。これにより「然者、軍兵成勇候様、可有調方候」ことを指示した(享徳四年三月廿三日「足利成氏書状写」『正木文書』141)。この書状が持国に届く四日前の3月24日、持国は「師江被移陣」した。成氏は再度「近日一勢被仰付可被加候」ことを伝えている(享徳四年三月廿六日「足利成氏書状写」『正木文書』153)。また、成氏から離反せずに「当御陣仁祗候」している上州一揆の人々が、持国から「相悪党」と蔑まれていることを成氏に訴えており、成氏は彼等の所領にいる敵性一揆勢を速やかに排除するよう持国に命じている(享徳四年四月三日「足利成氏書状写」『正木文書』218)。
4月4日、持国は上杉方に属した上州一揆の「小此木」で合戦し、「富塚在所以下所々相散候」ことを成氏に注進した(享徳四年四月五日「足利成氏書状写」『正木文書』223)。4月3日の書状を受けて速やかに行動に出たとみられる。この合戦で持国次男・岩松次郎が「小此木形部左衛門尉」を討ち取ったことを持国からの「就東上野時宜、重注進」(享徳四年四月五日「足利成氏書状写」『正木文書』248)で知り、成氏は「次郎出陣之由聞食候、御喜悦候」と悦び、さらに「那波掃部助以下在所等、悉散、敵軍追伐候条、目出候」と賞した(享徳四年四月五日「足利成氏感状写」『正木文書』231)。
当初は覚束なかった上野国での成氏方は、岩松持国をはじめとする「三大将」の活動により、次第に優勢に事を運ぶようになった。さらに4月5日には「諸勢、小栗江取進陣、即時外城攻落」した。この報告を翌4月6日早朝に受けた成氏は、早速上野の持国に報告している(享徳四年四月六日「足利成氏書状写」『正木文書』151)。
ところが、4月10日頃、上野国に「其方凶徒等、所々出張」し、持国は成氏に注進した(享徳四年四月十一日「足利成氏書状」『東洋文庫所蔵塚本文書』)。成氏はただちに「可有御心得候」と事態を把握し、「已前如被仰候、先以常州奉公輩、可指遣候」と、小栗攻城の部隊のいくつかを上州へ差し遣わす手配を行っている。
一方で、岩松持国は打ち続く合戦の中で、兵站の不如意が顕著となっていたとみられ、困窮していた様子がうかがえる。持国は「佐野宮内少輔」が恩賞として給わった「上州植木郷」を押領するという事件を起こす。成氏は4月晦日、「其方違乱之由、聞召候、不可然候、不准自余無相違様可被申付候」と持国の押領を否定し、ただちに佐野宮内少輔へ引き渡すよう命じている(享徳四年四月晦日「足利成氏書状写」『正木文書』230)。その代わりか、成氏は閏4月8日に持国の所望する「上州荒巻下総入道跡」「同国師郷北一揆秋間跡」「武州新開郷事新開加賀守跡」を宛行っている(享徳四年閏四月八日「岩松持国闕所注文写」『正木文書』66)。しかし、持国は佐野宮内少輔の植木郷からの撤退には応じず、成氏は翌閏4月13日、「就佐野宮内少輔知行分上州植木郷事」を「無相違可相渡候旨、堅可被申付候」と強く命じている(享徳四年閏四月十三日「足利成氏感状写」『正木文書』155)。こうした困窮の中、成氏からは近臣「佐野伯耆守」が援兵として岩松持国に遣わされた(康正元年閏四月十九日「足利成氏書状写」『正木文書』205)。成氏も上杉方との戦いのため、武蔵国や常陸国など諸方へ兵を遣わし、余剰分はすでに上野国へ回しているため、近辺に追加派兵が可能な外様衆は残っていなかったのだろう。近臣佐野盛綱の派遣は、成氏が旗本の奉公衆を割いて上野国へ派遣したもので、兵力的な余裕はまったくなかったと思われる。こうして持国は隠遁したようである。
これを聞いた成氏は、閏4月28日、自らの弟「長春院(尊僌とされるが周昉か)」から持国に「其方在陣辛労感思食候」と慰労させ、「仍諸偏属御無為、早々帰参候者、可為太慶候」と早々に帰参するよう伝えている(享徳四年閏四月廿八日「長春院書状写」『正木文書』155)。これに続けて、翌閏4月29日、成氏は持国へ「其後、其方次第如何候哉、無心元思食候」(享徳四年閏四月廿九日「足利成氏書状写」『正木文書』244)と、持国から上野国の情勢が注進されてこないことへの不安を伝えている。また、持国が「延々猶一陣可被寄由」を成氏へ依頼していることについては「殊山入辺可為難所候」と、常陸国山入方面での情勢が厳しいため「不可然候」と答えている。成氏も空手形は打たない、現実主義的な見方をはっきり示す人物だったことがわかる。さらに成氏は下野国野田城の野田右馬助持忠からも「聊爾之不可有調儀候」ことを伝えるよう命じた(享徳四年閏四月晦日「野田持忠副状写」『正木文書』252)。
その後、持国は復帰して再び指揮を執ったと見られ、5月10日頃には成氏に「就其方時宜注進委細」が送達されている(享徳四年五月十三日「足利成氏書状写」『正木文書』250)。この注進の内容は、信濃国の「大井播磨守」が碓氷峠を越えて上野国安中に進出し「安中左衛門知行分にて取陣」したこと、「当国之一揆、少々心中不定」であること、「白井勢、越河之由」であった(享徳四年五月十三日「野田持忠副状写」『正木文書』212)。持国はこれに備えるとともに、成氏は5月12日に「雪下殿、足利江御急候」(享徳四年五月十三日「足利成氏書状写」『正木文書』250)、「幸 雪下殿様、当国江御越候」(享徳四年五月十三日「野田持忠副状写」『正木文書』212)と、雪下殿定尊を足利へ急派して後方を固め「先御心易存候」とともに、「重而自余之御勢於其方江可被加候也」と、さらなる加勢を約している。
5月14日には「武州大袋原」で上杉勢と成氏勢が合戦している。戦いの帰趨は不明だが、管領房顕は被官人の豊島内匠助に感状を与えている(享徳四年七月六日「上杉房顕感状」『豊島宮城文書』)ように、上杉方の勝利で終わったようだ。
この頃、成氏方は小栗城を激しく攻め立てており、5月18、19日あたりで小栗城は陥落したとみられる。このとき成氏は小栗城加勢のために古河を発して「野州結城御厨」に兵を進めていた。なお「結城御厨」という御厨はないが、古河と小山の中間にあたる「寒河御厨」を指すものか。成氏は持国に上野国への出陣を約していたようだが、小栗城の実城が意外にも攻め難く、なかなか上野国へと出兵ができずにいた。そして、ようやく小栗城を攻め落とした成氏は、5月20日、持国に「為使節隣松お被急候」し「更非御無沙汰儀候」と弁明している(享徳四年五月廿日「足利成氏書状」『正木文書』135)。このとき成氏は奉公衆のみ率いていたようで、「不具召外様候者、可為御無勢候」であり、「兼日小栗お被急候」ことも「偏当国仁可有御進発御用候」と、上野国へ御進発のためであるとしている。そして「被寄御馬候故」に「彼城則時悉没落候」(享徳四年五月廿日「足利成氏書状写」『正木文書』135)と小栗城が陥落(上記の通り、5月18、19日あたりだろう)したという。このため成氏は「照書記」を使者として、持国に「外様又可致供奉分候、彼面々事、急悉被催可有御発向候」と、小栗攻めをしていた外様衆が成氏のもとに結集したので、彼らを悉く上野国へ急派することを申し伝えている。
この直後、持国は上杉勢と「於大手及一戦」んでおり「当国時宜火急之由」を成氏に急派して救援を求めた。この頃、「長尾右衛門入道、集調武州上州党類、野州天命、只木山、侘日張陣」とあるように、小栗城を退散した上杉勢が足利庄の東側にある「野州天命(佐野市天明町)、只木山」に陣取り、抵抗していたのであった。この頃には、3月28日に京都を発して越後・信濃路を通って上野国に向かっていた「上杉民部太輔、同兵部少輔、具越州信州群勢」が上野国に迫っており、この「越後守護上杉民部大輔定昌、上州へ打越し、兵部少輔房顕を取立て、越後信濃の軍勢」(『鎌倉大草紙』)と、「野州天命、只木山に楯籠」る「長尾左衛門入道昌賢、武州上州の軍兵を催しける、同名庁鼻和六郎、同七郎憲明」(『鎌倉大草紙』)が、上野国と下野国を東西から挟撃し得る状況となっていた。
これを受けた成氏は5月25日、「急速可被寄御馬」を約す書状を遣わした(享徳四年五月廿五日「足利成氏書状写」『正木文書』139)。成氏はここでも「不日又其方へ可被寄御馬候」ことを遣わしている(享徳四年五月晦日「足利成氏書状写」『正木文書』:戦古69)。また、持国は「桃井左京亮」が上杉勢に勝利した旨も報告しており、成氏はこの返書についても「就之も急可被寄御馬」ことを伝えている(享徳四年五月廿五日「足利成氏書状写」『正木文書』145)。また、上野国の「三大将」のひとり「鳥山式部大夫」が「大手合戦火急」のため持国と一所で対応したことを成氏に報告している(享徳四年五月廿七日「足利成氏書状写」『正木文書』133)。そして5月30日、成氏は「小山江御着陣」(享徳四年五月晦日「足利成氏書状写」『正木文書』:戦古69)した。
また、成氏は「大手後詰」からの報告で上杉方の「武州凶徒等」が「角淵辺江可致出張由」の報告を受け、6月2日、持国に「如何様武州江一勢可被越候、以前如仰遣候、既此方江御着陣上者、不日其口江可有御進発候」と、常陸国小栗攻めからの諸勢が上野国に着陣した上は急ぎ「角淵(佐波郡玉村町角渕)」へ進発するよう指示している(享徳四年六月二日「足利成氏書状写」『正木文書』179)。この付近には「赤堀下野守(赤堀時綱)」が2月18日に「従村岡御陣以来」在陣しており、「仍被下所帯等事」を下されている(享徳四年五月十八日「足利成氏感状」『赤堀文書』)。その地は「淵名庄内」か(享徳四年五月十二日「足利成氏書状」『赤堀文書』)。
対する長尾昌賢方は当時「天子御旗未無御下着」であり、それまでは先に京都から上野国に下向していた岩松治部大輔長純が「関東御下向之砌」に将軍義教から賜った「公方之御旗一流、御文手長之御旗」を牙旗として「諸家皆々被守当方之御旗」したという(『松陰私語』)。その後6月に入ると、越後路を下ってきた「山内并越州上椙民部太夫房定」が奉じた「天子御旗御到着」(『松陰私語』)し、「山内并越州上椙民部大輔房定、当方、同時ニ打出、当方者搦手、山内者大手」と、上杉房顕・民部大輔房定を主将とした軍勢が、上野国府付近から東へ進み、「三宮原」(北群馬郡吉岡町大久保)に進出した(『松陰私語』)。これに、成氏方の「新田(岩松持国)、鳥山(鳥山式部大夫)、桃井(桃井左京亮)」の「三大将」を主将とした上野新田勢が馳せ向かい、6月5日、「三宮原」で激突した(『松陰私語』)。「三宮原合戦」である。激しい合戦は上杉方の勝利に終わったものの、上杉方にも多くの死傷者が出ており、越後守護房定の麾下「和田弾正左衛門尉(和田長資)」(永享四年六月八日「上杉房定感状」『本間美術館所蔵読史堂古文書』)、「長尾備中守(長尾宗景)」(永享四年六月九日「上杉房定感状」『上杉家文書』)、「長尾備中守」(永享四年七月廿九日「管領細川勝元奉書」『上杉家文書』)、「中條弾正左衛門尉(中條朝資)」(永享四年七月廿九日「管領細川勝元奉書」『中條文書』)らの「被官人等数多討死并手負」を出すような被害が出ている。
「三宮原合戦打勝」った上杉勢は、新田岩松長純勢以下の「搦手者二千五百余騎」は「河東赤城山麓堀越ニ張陣」り、大手山内勢「五千騎」は「新田、鳥山、桃井以下」を追って、彼らが立て籠もった「高谷城」に攻め寄せた(『松陰私語』)。なお「高谷城」は、上杉房顕が「豊嶋三河守(豊島泰秀)」に命じている「今月五日、於此口致合戦、敵数輩討取候、彼残党等、高井要害ニ馳籠候間、差寄取対陣候、当城事、不可有程候、然間、其方早々出張可然候」から、「高井」(前橋市高井町)であったと考えられる(享徳四年六月十日「上杉房顕軍勢催促状」『豊嶋宮城文書』)。
持国は即日「三宮原合戦」の敗戦を「大手時宜委細注進」として成氏に報告した。翌6月6日、成氏は「明後日可有御進発」ことを返信している(享徳四年六月六日「足利成氏書状写」『正木文書』163)。ただ、成氏の進発は予定の6月8日には行われず、6月10日、成氏は持国へ「昨日、今日悪日間、明日必可被寄御馬候」と6月11日の進発を約し(享徳四年六月十日「足利成氏書状写」『正木文書』228)、6月11日「今日、被寄御馬候」した(享徳四年六月十一日「足利成氏書状写」『正木文書』181)。
6月13日、成氏は「已天命江被寄御馬候」(享徳四年六月十三日「足利成氏書状写」『正木文書』236)、持国にはただちに出兵するよう指示している。そして6月19日、持国が要望していた「上野国白井保之内 白井三河入道跡、同庶子等知行分寺社共」が与えられている(享徳四年六月十九日「岩松持国闕所注文写」『正木文書』44)。
三宮原合戦および西上野での連敗に危機感を強めた成氏は、6月24日、天命(佐野市天明町)から「足利御陣」へ陣を移している(年月闕「赤堀政綱軍忠状」『赤堀文書』)。しかし、すでに上野国での成氏方の劣勢は目に見えて明らかであり、成氏も天命・只木山を攻めながら上野国の岩松持国らへ増援することは不可能であった。こうした理由によるものか、成氏は7月9日、「至小山御陣」(年月闕「赤堀政綱軍忠状」『赤堀文書』)とあるように、足利から小山へ撤退している。
こうした上杉方優勢の動きを見たためか、7月中旬頃には「宇都宮下野守等綱、翻先忠企野心之段、其聞候」という風聞が成氏の耳に届く(康正元年七月廿九日「足利成氏書状」『那須文書』:戦古84)。翌年成氏が京都の三条実雅へ宛てた書状には、下総国の「千葉介入道常瑞(千葉胤直)」「舎弟中務入道了心(千葉胤賢)」及び「宇都宮下野守等綱」が「如合符、所々江令蜂起」(「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)したとあることから、同時期の挙兵であったと推測される。なお、胤直入道は閏4月の時点で京都と通じていたことは確実であり、胤直入道もまた宇都宮等綱と同じく上野国での成氏方の大敗の情報をつかんで挙兵したのではなかろうか。
しかし、成氏は驚くべき速さで態勢を立て直すと、瞬く間に下野国足利へ再進出し、上野国へ派兵。7月25日の「於上州合戦」では「悉御理運候(実際は敗退)」という(享徳四年八月八日「足利成氏書状写」『那須文書』)。この合戦は「七月廿五日穂積原」(『松陰私語』)の合戦とみられ、上州路においては搦手の戦いとなる。この時の戦いは、上杉方搦手は新田岩松長純勢など二千五百余騎、成氏方は「御同名岩松左京太夫殿、新田之面々、結城、小山、佐野、佐貫都合五千余騎也」(『松陰私語』)という。朝方の合戦では「当方打負」と、上杉方が押し込まれているが、「夕手之合戦打勝」って「其侭蹈仕場也」といい、敗れた成氏方は「足利本陣ニ引返」した。この日の合戦では、上杉方の「当方一族、新野出羽守、渋河能登守為始之、廿余人討死了」したという(『松陰私語』)。
ただ、こののちの戦いは、成氏方優勢で事が運んだようで、9月3日、成氏は「那須越後守(那須資持)」に「東上州合戦理運候、以後敵未武州上州群集之間、雪下殿致御供奉公、外様大略罷立候之間、両国事御心安候」と報告している(康正元年九月三日「足利成氏書状写」『那須文書』)。
また後述の通り、下総国においても、成氏方に属した千葉惣領被官の原越後守胤房に攻められた上杉方の千葉介胤直入道ら千葉惣領家は下総国千田庄へと遁れ、8月12日に千葉介胤宣が千田庄多古で自刃、続いて8月15日には千葉介胤直入道が嶋城を攻められて自害。下総国西部から中部にかけては成氏方に加担した千葉陸奥入道常義(康胤)や岩橋輔胤、原胤房らが優勢となった。
享徳3(1454)年12月27日の関東管領上杉憲忠殺害の余波は、鎌倉のみならず、下総国にも波及することとなった。
胤直は、嘉吉元(1441)年6月24日の足利義教の横死後に出家したが、嫡子・胤将は当時九歳であるため、胤直入道が引き続き下総守護として鎌倉に常住し、家政を運営していたのだろう。嫡子・胤将の具体的な活動がみられる初見は、文安3(1446)年4月13日の円福寺への安堵状(文安三年四月十三日「千葉胤将安堵状」『円福寺文書』)で、胤将当時十四歳であり、この頃家督が継承されているとみられる。しかし、胤将が若年であることや、当時の鎌倉は不安定要素が多く、胤将に継承後も胤直入道は鎌倉に常住していたのではなかろうか。
しかし、その千葉介胤将も「千葉介胤将高山改名蓮覚享徳三甲戌六月 廿二歳」(『本土寺過去帳』廿三日上)とあるように、亨徳3(1454)年6月23日に二十二歳の若さで亡くなった(病死とみられる)。その跡は弟・五郎胤宣が継承する。一書には「世継に入り給ハす」とされるが(『千学集抜粋』)、『本土寺過去帳』には「第十四宣胤 十二才」、「千葉介宣胤法名妙宣五郎殿十三歳」とあり、家督を継いでいた事は間違いない。ただし、当時五郎胤宣は十一、二歳程だったため、引き続き胤直入道が事実上の惣領家として家政を見たのだろう。胤宣がみずから発給した文書や胤宣宛の発給書状は残っていない。
このような中で12月27日、鎌倉殿成氏による関東管領上杉憲忠の殺害事件が起こった。この殺害事件に対して、京都は3月28日に「上椙ヽヽ故房州入道子関東発向」(『康富記』享徳四年三月卅日条)させ、4月3日に「駿河守護今河ヽヽ、今日関東発向、関東御退治御旗被給之」(『康富記』享徳四年四月三日条)させて、成氏追討を命じた(今川の下向は実際は4月8日)。このとき関東攻めの総大将とみられる上杉兵部少輔房顕(憲実次男、憲忠実弟)に下されたのは「錦御旗」で朝廷からの下賜だが、成氏追討の綸旨は出されておらず、実際に「関東御退治之綸旨」が下されたのは9月24日(『東寺百合文書』享徳四年九月廿四日条)で、東寺及び仁和寺に綸旨が付され、十七日間の修法が行われている。
駿河に下向した駿河守護今川上総介範忠は、「今川上総介、率海道諸勢相州エ襲来」った(「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)。胤直入道は今川範忠の駿河下向とほぼ時を同じくして京都に忠節を誓う旨の書状(現存せず)を遣わしたとみられる。その内容は伝わっていないが、「自関東連々雖相催、不令同心之旨」(享徳四年閏四月八日「将軍家御内書」『佛日庵文書』神:6204)とあるように、成氏からの度々の催促に応じなかった旨が記されていたことがわかる。胤直入道が京都へ遣わした書状に対し、翌月閏4月8日、将軍足利義政から「千葉入道との」へ、鎌倉方からの度々の誘いにも応じずに京都方に属したことに対して賞する御内書(享徳四年閏四月八日「将軍家御内書」『佛日庵文書』神:6204)を送り、太刀一腰を贈呈している。
●享徳4(1455)年閏4月8日「将軍家御内書」(『佛日庵文書』神:6204)
そして、上記の上州三宮合戦以降の成氏方大敗及び、成氏の足利から小山への撤退(7月10日)を受けた「千葉介入道常瑞、舎弟中務入道了心、宇都宮下野守等綱等」(「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)が、「如合符、所々江令蜂起」したのだろう。千葉介胤直入道は今川勢が鎌倉に攻め寄せた6月18日以前に千葉へと戻り、7月10日の成氏小山御移座など、成氏方の敗報を受けて機が熟したとみて、千葉に兵を挙げたのではなかろうか。そして、これを被官の原越後守胤房入道が諫めたものの聞き入れられなかったことから、胤房入道による胤直入道への攻撃が起こったものと推測される。
『鎌倉大草紙』では、惣領家執政の原越後守胤房が胤直入道に「御所方になりたまへ」と成氏に加担するよう説得したが、原胤房と対立関係にあった「円城寺下野守、上杉にかたらはれ」ていたため、胤直入道は円城寺下野守尚任の意見を容れて京方となり、胤房は「原はひそかに成氏より加勢を乞」うたのだとする。胤房は侍所司の胤直の代官的な立場であったことが永享7(1435)年の法難対処の伝(『伝灯抄』)から推察され、成氏が鎌倉に還御したのちも、胤直入道の代理として御所を訪れることがあったのだろう。「公方へも出仕申ければ、成氏より原越後守を頻に御頼ありける」(『鎌倉大草紙』)という。
『千学集抜粋』は妙見縁起と史実を重ねた説話で構成されており、必ずしも史実ではないが、「胤直御代に、原越後守胤房家風と円城寺下野守直重家風と口論して訴へしに、胤直その時下野が非道を道理、越後が道理を非道と別けさせられしより一乱始まる也、胤直仰せらるには、下野は多勢、越後は無勢なる故に、下野を引き給ふ也」との説話が掲載されている。原胤房被官人と円城寺直重被官人との間の口論で、胤直入道は権勢の大きな円城寺直重の肩を持ったといい、このために「妙見」は胤直から離れたという。この妙見云々は説話として、「千葉家、原与園城寺合戦、園城寺武州没落」(『鎌倉大日記』)ともあり、実際に嘉吉4(1444)年4月19日に「原筑前守」が没すが(『本土寺過去帳』十九日上段)、同日に「円城寺因幡守」もまた卒している(『本土寺過去帳』十九日上段)。これは原氏と円城寺氏の対立に起因する抗争があった可能性があろう。胤房の千葉襲撃は、胤直入道の上杉方としての挙兵以外にも、原氏と円城寺氏の対立の構図もあった可能性もうかがえる。
ただ、史実においては、原胤房が千葉を襲撃したという3月20日時点では、京都も関東に対して具体的な動きを示しておらず、当然ながら胤直入道の去就もまだ定まっていない。成氏は胤直入道に「自関東連々雖相催」(享徳四年閏四月八日「将軍家御内書」『佛日庵文書』神:6204)と、さかんに参向の御教書を送っていた時期と思われる。胤直入道が京都に対して鎌倉方への「不令同心之旨」を京都に表明し、京都将軍家が胤直入道の姿勢を賞して太刀を送ったのが閏4月8日であることからも、4月下旬までは胤直入道は鎌倉または千葉にいたと推測されよう。
一方で、胤直入道と弟胤賢入道の母は上杉禅秀女子であることを考えれば、京都との繋がりも想定されるところで、胤直入道がすでに方針を家宰である原胤房や円城寺下野守には伝えていた可能性もあろう。そのため、「原はひそかに成氏より加勢を乞」うて(『鎌倉大草紙』)、3月20日に攻めた可能性も想定はできる。しかし、3月20日に千葉を追われているのであれば、京都からの閏4月8日の御内書にその旨が全く記されていないのは不自然であり、やはり、享徳4(1455)年3月20日の原胤房による千葉攻めは史実ではないと考えざるを得ないだろう。
●享徳4(1455)年閏4月8日「将軍家御内書」(『佛日庵文書』神:6204)
ただし、原胤房が胤直入道を千葉に襲撃したのは、おそらく事実であろう。なぜなら、胤直入道が千葉を離れて8月までに千田庄に移っている事実は、千葉を離れる合理的理由がなければならないためである。胤直入道がなぜ上杉氏を頼って武蔵国や鎌倉へ遁れず、千田庄へ遁れたのかの理由は不明だが、下総国から他国への敗亡は千葉介として到底許されるものではなかったのかもしれない。また、千田庄は家宰円城寺氏の拠点の地であることや、常陸国からの上杉家援兵を期待できる地ということで、当方へ逃れたのかもしれない。
享徳4(1455)年4月と推測される千葉での戦いに敗れた胤直入道は、「舎弟中務入道了心」や子息の五郎胤宣(千葉介胤宣)、円城寺下野守らとともに香取郡千田庄(香取郡多古町)へと遁れた。
 |
| 多古城 |
千田庄は円城寺氏や竹元氏、岩部氏など惣領被官の知行地があるためか。『鎌倉大草紙』によれば、「胤直父子は同国多胡志摩二の城に楯籠り、一味の勢を催し、上杉よりの加勢を待居たり」(『鎌倉大草紙』)と見え、多古城(香取郡多古町多古)と、多古城と低湿地を挟んだ南にある志摩城(比定地については下記)に籠城したという。「島」という地名や周辺の「水戸」「船越」といった地名から、多古城下は当時湖沼が広がっていた可能性も考えられる。
このとき胤直入道から知らせを受けたとみられる下野国天命の上杉房顕は、5月8日、「就相州御敵退治」のため「信太庄山内衆」に出陣を指示している。このとき信太庄には「円成寺名字中」がおり、胤直入道から信太庄上杉勢への援軍として派遣されていたのかもしれない。5月頃と思われるが、この「円成寺名字中」が「彼国へ可打越候」と、下総国へ渡ったという。おそらく胤直入道らとの合流のためであろう。房顕は「然者、其方傍輩中令談合、彼国之境ニ取陣、自円成寺方相通候者、同時越河致忠節候者、可然候」と、「信太庄山内衆」に対して衆中で話し合って、下総国の国境まで陣を進め、渡海した円城寺勢と連絡がとれたならば、ともに渡河して胤直入道を助けるよう指示している(享徳四年五月八日「上杉房顕判物」『臼田文書』:神40)。
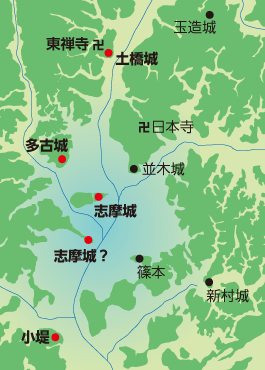 |
| 多古周辺地図(水色は湖沼または湿地) |
原胤房勢には「公方よりの加勢の兵」(『鎌倉大草紙』)もあったが、その後、千田庄での戦いは数か月にわたって膠着状態になったようだ。しかし、原胤房勢には千葉庄馬加村(千葉市花見川区幕張町)周辺を領した千葉介満胤庶子「千葉陸奥入道常義父子」が「存貞節、属御方」(「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)したことで戦局が変わったのだろう。参戦した時期は不明だが、戦局が急転した8月か。
『鎌倉大草紙』によれば、常義入道の参戦に「原越後守大に喜び」、彼を「即ち之を大将」として「多胡の城へ差向」け、自らは「志摩の城へ押寄せて攻め」た(『鎌倉大草紙』)。ただし、胤房は千葉陸奥入道常義を一軍の大将として派遣しているように、彼を麾下として扱っている。これが事実であるとすれば陸奥入道常義は千葉家御一家として惣領家の支配下にあり、家宰の原越後守胤房の指示に従う立場であったと想定される。
千葉介胤宣が立て籠もった多古城を攻めた陸奥入道常義は「古兵」であり、「城を取巻き、兵粮の道を留め、方を明けて攻め」たため、「籠城の兵、皆失せ」てしまい、「大将胤宣は若年にて、纔に二十騎計」となってしまったという(『鎌倉大草紙』)。こうして多古城は「終に攻め落され、乳母子円城寺藤五郎直時を以て敵陣へ遣し、城をば渡し申すべく候間、仏前へ参切腹仕度由」を請うた(『鎌倉大草紙』)。陸奥入道常義はこれに「尤とて城を請け取り、寄手并公方よりの加勢の兵共送」った。その後、千葉介胤宣は「城外のむさといふ所に阿弥陀堂のありけるへ出て、仏前に向ひ、享徳四年八月十二日、十五歳にて切腹」(『鎌倉大草紙』)した。年齢については『本土寺過去帳』においては「千葉介宣胤五郎殿十三歳」(『本土寺過去帳』)とある。このとき、阿弥陀堂別当の来照院が傍に付き添い、「焼香読経す、最期の勤め懇」(『鎌倉大草紙』)に行った。そして乳母子の「直時も主の介錯して続いて腹を切りにけり」(『鎌倉大草紙』)という。なお、「むさ」は「ゐさ」の誤字とする説(『多古町史』)があるが、「む」「ゐ」は運筆から考えても間違えようがなく、可能性としては非常に低い。根本的な事として、史料について補完材料がないままに「〇〇の誤記だ」や「〇〇と書き換えられた」という、史料を「改変」させて成立させようとする「恣意的解釈」は、自身の提唱する「結論」を導かせるために用いる禁じ手である。
彼らには辞世の句が二句伝わっており、千葉介胤宣と円城寺直時のものか。『鎌倉大草紙』では「若君胤宣は初より御一所に御座なく、何の不義もおはしまさす、馬加殿あはれに思召し候間、如何にもして御命を助け奉り候はんと申」したが「御切腹」してしまい、陸奥入道常義はこの旨を越後守胤房に伝えたところ、「越後守も涙を流しける」という。
●享徳4(1455)年8月12日辞世(『鎌倉大草紙』)
●『本土寺大過去帳』十二(上段)
+―円城寺下野妙城
|
+―同壱岐守妙壹
|
+―同日向守妙向
享徳四乙亥八月其外多古嶋城討死諸人成仏得道
円城寺一族では「円城寺下野妙城」「同壱岐守妙壹」「同日向守妙向」の死去も伝えられており(『本土寺過去帳』)、胤宣には執権円城寺下野守(尚任)が支えていたとみられる。この合戦では、「常陸大充殿妙充」「同子息」の死去も伝えられており(『本土寺過去帳』)、多古城には常陸国から常陸大掾父子が派遣されていたことがうかがわれる。ただし、常陸大掾系図等の史料には該当する人物の伝はない。このほか、「■徳四■■野日向朗典於島■■」とあるように、上総国伊北庄の上杉家被官狩野氏も胤直入道に与力していたことがわかる。
胤宣の供として阿弥陀堂に来ていた「椎名与十郎胤家、木内彦十郎、円城寺又三郎、米井藤五郎、粟飯原助九郎、池内助十郎、深山弥十郎、■本彦八、青野新九郎、多田孫八、高田孫八、三谷新十、寺本弥七、中野与十郎等」も「皆刺違ヘヽヽ枕を並べて伏し」、陸奥入道常義は「首共取つて成氏へ進上」(『鎌倉大草紙』)したという。
 |
| 胤直・胤賢が籠った志摩城(ここではないかも) |
一方、胤直入道、中務入道了心が籠城する志摩城は、「原越後守大将にて、昼夜の界もなく攻戦」った結果、「八月十四日の夜、終に叶はず攻落され」た。胤直入道等は胤房に「是も土橋といふ所に、如来堂のありける所へ拉ぎ、別当東覚院に籠」られたという(『鎌倉大草紙』)。胤房は「城を請け取り、彼寺を取巻きて、胤直に附き申しける上臈を招き出」すと、「介殿の御事は、成氏公へ御不義にて、討手遣はされける間、上の御心計り難く候へは、力及はす」と告げ、翌8月15日、「寄手重なり如来堂を取巻き、鬨の聲を作りける間、千葉介入道常瑞、舎弟中務入道了心腹切」ったという(『鎌倉大草紙』)。法名は相應寺殿真西一閑臨慎阿弥陀仏。
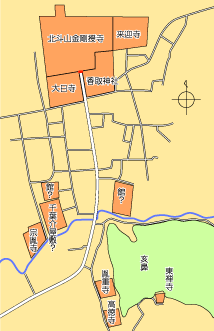 |
| 千葉町古地図 |
遺骸は土橋東禅寺(多古町寺作)に葬られたといわれ、現在も東禅寺墓所には、胤直とその眷属の墓とされる墓石が残されている。しかし、『鎌倉大草紙』によれば、胤房は胤直らの遺骨を「千葉の大日寺」に送って葬ったとされている。旧妙見寺(千葉神社)と旧来迎寺地(道場北)の間は、かつて「相應寺」という地名があり、そこには相應寺という寺院がかつてあって寺院が何らかの理由によって消滅したのちも二つの塚が残っていたと伝えられている(相應寺の位置)。
●『本土寺大過去帳』十五(上段)
●「千葉介代々御先祖次第」(『本土寺大過去帳』)
彼らは「池内豊後守介錯して、同じく之も切腹」し、「円城寺因幡守、木内左衛門尉、池内蔵人、多田伊予守、粟飯原右衛門尉、高田中務大輔胤行等は、胤直の御前並に上臈を初め、女房達を刺殺し、思ひヽヽに腹を切」ったという。その後、「別当東覚院、死骸を集め、仏事供養をなし、無常の煙と焼き上げ」、彼らの遺骨は「原筑後守胤茂が沙汰」として「千葉の大日寺に送り納め、五輪石塔を立置」いた(『鎌倉大草紙』)。
ただし、この説話には不自然な箇所がある。
●胤直入道らが自刃した「土橋といふ所に、如来堂」はどこか。
 |
| 土橋東禅寺跡 |
これは、土橋東禅寺のある地が通説となっている。この「土橋」は現在の多古町御所台から寺作に至る地名でに相当するが、胤直入道のみならずその被官、眷属多数を「志摩」から直線距離で4km離れた「土橋」へ移す必然性が想定できない。『鎌倉大草紙』を信じるのであれば、胤房は「城を請け取り、彼寺を取巻」いたということから、志摩城と「如来堂」は至近である可能性が高い。そうだとすれば、志摩城と遠く離れた「土橋」東禅寺の地が相応しくないことは一目瞭然である。では、具体的には何処なのか。『本土寺過去帳』によれば胤直入道は「妙光ニテ御腹被召」とあることから「妙光」寺での自刃の信憑性が高い。妙光寺は島地区にあった日蓮宗「千田庄本覚山妙光寺」(康正二年五月二十五日『当寺四世日壽聖人置文』)に相当するか。志摩城は島地区の東端の一郭とされており、妙光寺はそこから谷津を挟んだ西側台地上にある寺院で至近距離にあり、文献上は相応しいと考えらえる。
ただ、信憑性に問題はあるものの『鎌倉大草紙』ではわざわざ「土橋といふ所に如来堂のありける」と但書きをし、別当寺の「東覚院」に幽閉された旨が記されている(この両寺は同所)。しかし、「如来堂」は日蓮宗の堂舎ではないため、別当東覚院も日蓮宗寺院ではない。つまり、『鎌倉大草紙』と『本土寺過去帳』の記述がいずれも正しいとすれば、志摩落城後に胤直入道以下が幽閉された「東覚院」と「妙光(寺)」は別施設となる。
なお、こののち『鎌倉大草紙』の著者は「むさ」の「阿弥陀堂」と「土橋」の「如来堂」を混同して物語を進めている。『鎌倉大草紙』によれば、千葉介胤宣が幼少の頃から手習の師を務めた「下総国金剛授寺の僧中納言坊とて、いと若き僧」が「胤宣父子の由」を伝え聞き、「彼の如来堂へ参詣」したが、このとき「別当東覚院出合せ、胤宣父子最後の體物語して、辞世の歌を取出し見せ」たという記述がある。しかし、胤宣自刃は「土橋」の「如来堂」ではなく「むさ」の「阿弥陀堂」であって、しかもその「阿弥陀堂」別当は「東覚院」ではなく「来照院」である。つまり、東覚院は胤宣自刃の詳細は知る由もないはずだが、なぜかその辞世の歌を持っていて、中納言坊に見せるという物語的混乱がうかがえる。『鎌倉大草紙』はこうした核心的な部分での誤りが大変多く、他の文書から抜粋したであろう箇所や他の史料と比較できない部分については、慎重に使用すべきものである。
では、胤直入道等が幽閉された「如来堂(東覚院)」はいったいどこの寺院なのか。これを考えるために、も胤直入道が立て籠もった「志摩城」はどこなのかを再考する。
現在、志摩城として指定されているのは、多古町島地区(香取郡多古町島)の東端にあたる一角である。しかし、この区画は十四~十五世紀の掘立柱建物の遺構などは出土しているものの、そもそもこの「城域」の最大比高はわずか15m程度、非常になだらかな台地をなしており、城としての堅固さは皆無である。また、掘割の痕跡も見つからず、島地区全体の東端のみが城郭とされている点も非常に不自然である。このような城が、たとえ湖沼の浮舟のような存在としても、数か月間の籠城に堪え得るとはとても考えられない。
実はこの島地区の「志摩城址」から南南西1200m程のところに、「丸山(多古町船越)」とよばれる島状台地がある。栗山川を望む周囲700m程の小山だが、比高は島地区の二倍の30mもある。ここは康正2(1456)年5月25日当時「大嶋城」(康正二年五月二十五日『当寺四世日壽聖人置文』)と称された城である。「暦応庚辰冬」つまり暦応3(1340)年当時「大嶋殿(千葉胤継か)」がここを拠点としており、城郭としても機能していたことがわかる。この丸山はもともと北西の台地まで「土橋」状の低台地(現在の船越集落)で繋がっており、多古城とは台地が隣接し船で簡易に連絡が取れる配置である。『鎌倉大草紙』にみえる「土橋」の「如来堂(別当東覚院)」がもしこの低台地上(現船越集落)にあったとすれば、「如来堂」は「志摩城」の至近にあるという条件を満たす。そして、「大嶋城下」には「千田庄本覚山妙光寺」と「大聖人御舎利三粒」を通じて密接な関係のある「正円山妙興寺」(康正二年五月二十五日『当寺四世日壽聖人置文』)があり、胤直入道は「如来堂」から島の「妙光」寺へ移されて「御腹被召」た可能性もあろう。
なお、『鎌倉大草紙』の誤伝として、8月15日、「寄手重なり如来堂を取巻き、鬨の聲を作りける間、千葉介入道常瑞、舎弟中務入道了心腹切」ったという記述があるが(『鎌倉大草紙』)、舎弟の「中務入道了心」は胤直入道とともに切腹しておらず、城を抜けて、舟で3km程南東にある「ヲツヽミ」に逃れた。この「ヲツヽミ」とは、志摩城の南にある「小堤」(山武郡横芝町小堤:オンヅミ)に比定できると考えられるが、おそらく胤房の軍勢がすぐさま駆けつけたと思われ、9月7日、胤賢入道もこの地で自刃した(『本土寺過去帳』)。
●『本土寺大過去帳』七(上段)
胤賢入道は千葉から千田庄へ行く時点で、すでに童息二人(のち七郎実胤、千葉介自胤)を下総国八幡庄(市川市大野町周辺)へ移し、被官曾谷氏らに託していたのだろう。その後、彼らは市川城(市川市真間四丁目辺りか)に籠城して原勢と対峙したが、翌康正2(1456)年正月19日、市川城も攻め落とされて、実胤、自胤は上杉氏を頼って武蔵国へ逃れ、子孫は武蔵千葉氏となった。
●康正2(1456)年4月4日「足利成氏書状」(『武家事紀』巻第三十四)
●某年9月11日『将軍家御内書』
●永享12(1440)年10月25日『千葉介胤直安堵状』(『檪木文書』:『市川市史』所収)
●永享12(1440)年11月27日『千葉介胤直書状写』(『檪木文書』:『市川市史』所収)
★千葉介胤直の家臣★
家老
原 円城寺 鏑木 木内
側近
板倉 山梨 澤井 土屋 小池 神保 岩井 高田 多田 池内 粟飯原
家臣
押田 海保 木村 石原 大友 山内 飯田 八木
© 1997- ChibaIchizoku. All rights reserved.
当サイトの内容の一部または全部を、無断で使用・転載することを固くお断りいたします。