

| 継体天皇(???-527?) | |
| 欽明天皇(???-571) | |
| 敏達天皇(???-584?) | |
| 押坂彦人大兄(???-???) | |
| 舒明天皇(593-641) | |
| 天智天皇(626-672) | 越道君伊羅都売(???-???) |
| 志貴親王(???-716) | 紀橡姫(???-709) |
| 光仁天皇(709-782) | 高野新笠(???-789) |
| 桓武天皇 (737-806) |
葛原親王 (786-853) |
高見王 (???-???) |
平 高望 (???-???) |
平 良文 (???-???) |
平 経明 (???-???) |
平 忠常 (975-1031) |
平 常将 (????-????) |
| 平 常長 (????-????) |
平 常兼 (????-????) |
千葉常重 (????-????) |
千葉常胤 (1118-1201) |
千葉胤正 (1141-1203) |
千葉成胤 (1155-1218) |
千葉胤綱 (1208-1228) |
千葉時胤 (1218-1241) |
| 千葉頼胤 (1239-1275) |
千葉宗胤 (1265-1294) |
千葉胤宗 (1268-1312) |
千葉貞胤 (1291-1351) |
千葉一胤 (????-1336) |
千葉氏胤 (1337-1365) |
千葉満胤 (1360-1426) |
千葉兼胤 (1392-1430) |
| 千葉胤直 (1419-1455) |
千葉胤将 (1433-1455) |
千葉胤宣 (1443-1455) |
馬加康胤 (????-1456) |
馬加胤持 (????-1455) |
岩橋輔胤 (1421-1492) |
千葉孝胤 (1433-1505) |
千葉勝胤 (1471-1532) |
| 千葉昌胤 (1495-1546) |
千葉利胤 (1515-1547) |
千葉親胤 (1541-1557) |
千葉胤富 (1527-1579) |
千葉良胤 (1557-1608) |
千葉邦胤 (1557-1583) |
千葉直重 (????-1627) |
千葉重胤 (1576-1633) |
| 江戸時代の千葉宗家 | |||||||
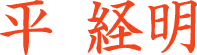 (930?-1018?)
(930?-1018?)
| 別名 | 忠頼 忠依(『二中歴』) 経明(永暦二年二月廿七日『正六位上下総権介平朝臣常胤解案』) 恒明(『千馬家系図』) |
| 生没年 | 延長8(930)年6月18日?~寛仁2(1018)年12月17日? |
| 元服 | 不明 |
| 通称 | 村岡次郎(伝)? |
| 父 | 平良文(村岡五郎)? |
| 母 | 大野茂吉娘(伝)? |
| 官位 | 不明 |
| 官職 | 陸奥介(寛和3(987)年正月24日『太政官符』)? |
村岡五郎平良文の子。諱は恒明(『千馬家系図』)とも、平忠頼の初名(『千葉大系図』)ともされる。系譜や伝がないため具体的な事柄は不明。「平良文朝臣」の「男」(『正六位上下総権介平朝臣常胤解案』)とあり、活躍時期としては天暦年中か。
元来、千葉氏の祖は「平忠頼」とされ、千葉介常胤が相馬御厨をめぐる争いの中で記した『御厨下司正六位上平朝臣常胤寄進状』などに明確に記される「平良文朝臣」の「男」である「経明」については、単に忠頼の初名とされるのみで深く顧みられることはなかった。しかし、常胤が自ら心血を注いで主張した自祖は「忠頼」ではなく「経明」なのである。
「経明」が見えるのは、千葉介常胤が相馬郡を伊勢内外二宮に寄進した久安2(1146)年の寄進状(久安二年八月十日『御厨下司正六位上平朝臣常胤寄進状』)と、相馬郡をめぐる左兵衛少尉源義宗との争いの中で、自家が相馬郡を正当に継承してきたことを伊勢神宮に訴えた永暦2(1161)年の常胤解(永暦二年二月廿七日『正六位上行下総権介平朝臣常胤解案』)の、
「是元平良文朝臣所領、其男経明、其男忠経、其男経政、其男経長、其男経兼、其男常重、而自経兼五郎弟常晴相承之当初、為国役不輸之地…」
という部分だけである。これを系譜に直すと以下のようになる。
平良文―経明―忠経―経政―経長―+―経兼―常重
|
+―常晴
「経明」が忠頼の初名であったとすると、相伝系譜に後名の「忠頼」ではなく初名の「経明」が記載されるのは不自然である。「経明」と「忠頼」は本来別人であり、平安時代末期においては千葉氏の祖は「経明」であって「忠頼」ではなかったと考えられる。
また、相伝系譜は古体を想起させるものであり、鎌倉期以降よく見られる自らを起点とした続柄で記す相伝由緒とは異なっている。また所領の相伝を主張する文書であることから、信憑性は非常に高いものであると推測できる。
■稲荷山古墳出土鉄剣銘
常胤が提示した相馬御厨の相伝伝承や、後述「平忠頼」項に記す繁盛の解状、桓武平氏の諸系譜を踏まえて、忠頼と経明の関係をまとめると、
(一)相馬御厨寄進状には「是元平良文朝臣所領、其男経明、其男忠経…」と記される。
(二)忠頼の活動時期は寛和3(987)年頃に「移住武蔵国」しており、忠常は長保2(1000)年頃には両総に勢力を扶植していた。忠頼と忠常の活動時期から生年差はおそらく二十年余りと推測される。
(三)「桓武平氏諸流系図」(『中条家文書』)では、坂東平氏の祖はいずれも忠頼となっている。経明の名はみられない。
以上から、まず所領相伝の証書をもとに記されたであろう(一)の相馬御厨寄進状の伝領経緯は系譜よりも信憑性のあるものであり、千葉氏の祖となる平良文の子は「経明」であり、その子は「忠経」であることは間違いないだろう。「忠頼」が千葉氏の「系譜」にあるにも拘らず、常胤寄進状では「無視」されているのは、推測だが経明の死去後「忠経」は伯父「忠頼」の猶子となった可能性が考えられないか。もし猶子となっているのであれば、忠頼は忠常の養父であるが、忠常は父「経明」から下総国相馬郡を譲られているため、相馬郡の伝領系譜に「忠頼」は含まれないことになる(この系譜は血縁を示す性格のものではなく、所領の相伝が目的である)。千葉氏の系譜上で経明の名が消えているのは、忠常の「実父」経明と「養父」忠頼が、鎌倉期初頭(西暦1220~1230頃)に作成された千葉氏の系譜上で混同され、ほかの良文流平氏との比較校正時に消滅した可能性があろう。
平忠頼(????-????)
村岡五郎平良文の子。母は大蔵卿大野朝臣茂古女(『平姓葛西系図』)。通称は村岡次郎。官途は陸奥介(『二中歴』)。「初号経明」(『千葉大系図』)とあって、経明と忠頼は同一人物とされている。
平忠頼が公的文書で見られるのは、寛和2(986)年7月以前に「陸奥介平忠頼、忠光等、移住武蔵国、引率伴類、運上際可致事煩之由、普告隣国連日不絶」(『続左丞抄』寛和三年正月廿四日条:『国史大系』)とあるように、系譜上従兄弟に当たる「散位従五位下平朝臣繁盛(平国香の子で陸奥守貞盛の弟)」が延暦寺へ送った「以金泥奉写大般若経一部六百巻、為表丹誠、負之白馬、欲令運上天台、揚題名」の使者を妨害すると連日のように他国へ宣言したというものである。ここから、平忠頼は他国から「移住武蔵国」という人物であり、下総国から移ったか。また、忠頼と忠光の関係は『続左丞抄』に記載はないが、平安時代末期成立の『掌中歴』『懐中歴』をベースに作られた『二中歴』に「陸奥介忠依、駿河介忠光忠依弟」とあり、兄弟だったことがわかる。
繁盛はこの脅迫に対して太政官に「解状」で訴え、これを受けた朝廷では「随即可追捕之官符、被下於東海東山両道也、爰諸国司等、任官符旨欲追捕」(『続左丞抄』寛和三年正月廿四日条:『国史大系』)の太政官符を発給した。太政官符が「東海東山両道」に出されている理由は、繁盛の訴えに「普告隣国連日不絶」という文があったためであろう。
ところが、その直後の寛和2(986)年8月9日には、「停止之官符」が出されている。それはおそらく追捕を命じられた国の在庁から国司へ不要の見解が出されたためではなかろうか。繁盛の解にもあるように、忠頼らは「運上際可致事煩之由、普告隣国連日不絶」という脅しを行っただけで、実際に妨害行為に及んだわけではないのである。国衙も実際の妨害の事実が確認できず、この運上物(金泥大般若経)は延暦寺が絡み、繁盛の「偏懐皇道之節、仍奉為聖朝安穏鎮護国家」(『続左丞抄』寛和三年正月廿四日条:『国史大系』)という祈りが込められたものである一方で、繁盛の「奉公之勤、古今未倦、及于老後、猶含忠節、況坂東大乱之時、故秀郷朝臣、貞盛朝臣与繁盛等共竭筋骨、入万死出一生、■天下之騒動也、依其勲功、秀郷貞盛各関恩賞配分憂職、繁盛独漏朝恩未慰夕傷毎思鴻涙之難、猶歎鳳徳之不周、涯分之不及、方今所存也」(『続左丞抄』寛和三年正月廿四日条:『国史大系』)という私事の願いが相当含まれるものであり、追捕を行う押領使の派遣にそぐわないとの判断がなされた可能性があろう。
しかし、繁盛は追捕の官符が停止されたことで、「忠光等暴逆弥倍、奸謀尤甚、為逐彼旧敵、欲断此善根」(『続左丞抄』寛和三年正月廿四日条:『国史大系』)と、繁盛は忠光らを「旧敵(仇敵)」と見做し、彼らが大般若経の運上を妨げ、善根を断たんとしているものだと主張して、11月8日も太政官符の再発布を求める「解状」を提出したのであった。さらに、繁盛の訴えを受けた延暦寺も政所を通じて寛和3(987)年正月5日に「奏状」を朝廷に提出している。これを受けた朝廷は繁盛の訴えは最もであると受理し、権中納言道兼がこの旨を奉勅して、正月24日「近江美濃等国司」に対して大般若経の運上を恙無く行うよう太政官符を下した(『続左丞抄』寛和三年正月廿四日条:『国史大系』)。近江国は延暦寺のある国、美濃国は東海・東山道の結節地であることからこの二国に官符が出されたのだろう。一方で「忠光等暴逆弥倍、奸謀尤甚」は公的には認められなかったようで、忠頼らは追捕されることはなかったのであろう。
●『続左丞抄』寛和三年正月廿四日条
繁盛が解に述べる「坂東大乱」とは、天慶3(940)年の「承平の乱(平将門の乱)」であり、この乱の時点で繁盛はすでに活躍していることから、その46年後の繁盛はすでに七十歳前後であったろう。一方、忠頼・忠光の兄弟は、寛和3(987)年当時が活動時期であったという点から、忠頼兄弟は繁盛よりも世代的には一世代後と推測される。ただし、貞盛・繁盛が高望王(上総介平高望)の長男・常陸大掾国香である一方、「忠頼」が高望王五男の五郎良文であることから、世代間の乖離であった可能性はある。
平高望―+―平良兼―+―平公雅―――+―平致利 +―平致経
(上総介)|(下総介)|(上総掾) |(出羽守) |(左衛門大尉)
| | | |
| +―平公連 +―平致成 +―平公親――――平公経
| (下総権少掾)|(出羽守) |(内匠允)
| | |
| +―平致頼―――+―平公致
| |(備中守)
| |
| +―平致光
| |(大宰大監)
| |
| +―平致遠
|
| 【武蔵国】
+―平良文―+―平忠頼―――+―平将恒―――――平武基
(五郎) |(陸奥介) |(武蔵権守) (秩父別当大夫)
| |
|【武蔵国】 |
+―平忠光 +=平忠経―――+―平経政
|(駿河介) |(上総介) |(平常昌)
| | |
| | +―平常近
| ? ?
| | |
| | +―平胤宗
| |
| |
| +―平胤宗―――――平基宗
|
|【相模国?】
+―平忠通―――――平為通
|
|【下総国】
+―平経明―――――平忠経―――+―平経政
(上総介) |(平常昌)
|
+―平常近
~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~
●桓武平氏の活躍時期と世代(野口実 氏『中世東国武士団の研究』を参考に作成)
| 初代 | ニ代 | 三代 | 四代 | 五代 |
| 国香 ・935没 |
貞盛 ・940頃活躍 ・947鎮守将軍 ・972丹波守叙任 ・974陸奥守 ・976馬を貢進 |
維敏 ・982検非違使尉に推薦 ・990頃、肥前守 ・994没 |
||
| 維将 ・973左衛門尉 ・994肥前守 |
維時 ・988右兵衛尉在任 ・1016常陸介在任 ・1029上総介叙任 ・1028上総介辞任 |
直方 ・1028忠常追討使 ・1028追討使更迭 |
||
| 維叙 ・973右衛門少尉在任 ・996前陸奥守 ・999常陸介在任 ・1012上野介在任 ・1015上野介辞任 |
維輔 ・1005検非違使任 |
|||
| 維衡 ・974左衛門尉在任 ・998伊勢で致頼と合戦 ・1006伊勢守→上野介 ・1020常陸介 ・1028郎従が伊勢で濫妨 |
正輔 ・1019伊勢で致経と合戦 ・1030安房守 |
|||
| 繁盛 ・940頃活躍 ・986忠頼らと紛争 |
維幹 ・1016左衛門尉在任 |
為幹 ・1020常陸で濫妨 |
||
| 兼忠 ・980出羽介→秋田城介 ・1012以前没 |
維茂 ・1012鎮守将軍 ・1017以前没 |
|||
| 維良 ・1003下総国衙焼討 ・1012頃鎮守将軍 ・1018陸奥国司と乱闘 ・1022没 |
||||
| 良兼 ・931将門と紛争 ・939没 |
公雅 ・940上総掾 ・942武蔵守 |
致頼 ・998伊勢で維衡と合戦 ・1011没 |
致経 ・1019伊勢で正輔と合戦 |
|
| 公連 ・940押領使 ・940下総権少掾 |
||||
| 良持 ・? |
将門 ・935国香討つ ・939没 |
|||
| 良文 ・? |
忠頼 ・986陸奥介在任 |
忠常 ・1000~1012源頼信家人 ・1027安房国司を焼殺 ・1028以前上総介辞 ・1031没 |
常昌 ・1031降伏 |
|
| 常近 ・1031降伏 |
||||
| 忠光 ・986駿河介? |
忠頼が具体的に武蔵国のどこに在住したかは定かではないが、父の良文は武蔵国大里郡村岡郷(熊熊谷市村岡)周辺を領した武蔵国の住人であるが、下総国相馬郡にも私領を有していた。忠頼らは下総国に住していたが、忠頼は「陸奥介」、忠光は「駿河介」を買官して武蔵国へ移り、武蔵国衙の在庁官人となった可能性もあろう。忠頼の子・平将恒は武蔵権守(『尊卑分脈』)と見え、平将恒の子・平武基は秩父牧の別当に補されており、忠頼は下総国よりも武蔵国との関係が深い人物という可能性が高いだろう。
寛仁2(1018)年12月17日、90歳で没したというが(『千葉大系図』)、傍証はない。
●『千葉大系図』忠頼の項
「忠頼 初号経明 正四位下陸奥守 上総下総常陸介
延長八年庚寅六月十八日、誕生於下総国千葉郡千葉郷也。於此所忽水涌出。以此水為生湯矣。後世号湯花水。又葛飾郡栗原郷有不増不減之水。此水亦為生湯。云々。此所葛飾大明神社也。俗呼謂千葉生湯之水矣。此時有祥瑞。備月星之小石墜於空中。此石入醍醐天皇之叡覧。勅号千葉石也。嫡流者月星為家紋、末流者諸星為家紋。其詳見花見系図。当家之秘。千葉氏之称始于此。然未顕於矣。後年歴任上総下総常陸介、陸奥守、叙四位下也。寛仁二年戌午十二月十七日卒。年九十。」