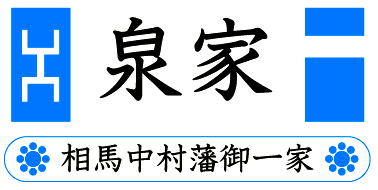
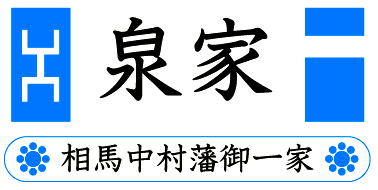
泉家とは
泉氏は相馬中村藩御一家のひとつで、藩政の最高執政官である執権職に就く家柄として藩内で重んぜられた。祖は鎌倉時代の当主、相馬五郎義胤の三男・相馬六郎胤基の子孫と伝えられている。しかし、相馬六郎胤基なる人物は系譜および文書からうかがい知ることができない。
相馬胤基は元亨3(1323)年、相馬重胤が下総国から奥州へ下った際に供奉し、行方郡泉村(南相馬市原町区泉)に住んだという。
一方、相馬家御一家筆頭に岡田家があるが、岡田家は鎌倉時代後期の相馬惣領家・相馬胤村の次男・胤顕を祖とする。胤顕は下総国相馬郡泉村(千葉県柏市泉)を領して「泉五郎胤顕」を称していた。泉氏もこの泉胤顕を祖とし、岡田家と同族の相馬一族であろうと思われるが、伝承としては相馬六郎胤基を祖とする。また、「胤基」という名については、泉胤顕の十三男と思われる相馬與三胤元が系譜上に見える。
■中村藩御一家■
相馬胤顕 (????-1285)
泉相馬氏初代惣領。父は相馬孫五郎左衛門尉胤村。通称は彦三郎、五郎。母は不明。下総国南相馬郡泉村(千葉県柏市泉)に館を構えたことから「泉」を称した。のち、中村藩御一家の筆頭となる岡田家(相馬岡田家)も胤顕を祖とする一族である。
 |
| 下総国相馬郡泉村の泉舘跡(柏市泉) |
父・胤村の死去後、下総国相馬郡泉村、行方郡岡田村のほか院内など数か所が分与されたと思われる。子孫の岡田氏ははじめ相馬を称し、相馬惣領家に随いながらも、独自の惣領制を築いていた家柄。しかし次第に力を失い、相馬惣領家に従属したのち、岡田を称した。
胤顕の父・胤村がいつ没したのかははっきりしていないが、文永9(1272)年10月29日『関東下知状』には「亡父胤村」とあり、「平○○丸(松若丸か=相馬師胤)」に相馬家所領が認められていることから、おそらくこの年に没したと思われる。
江戸時代には中村藩御一家筆頭として重用され、幕府からもじきじきに書状を受け取るほどであった。相馬家重臣の大甕氏、水谷氏、立谷氏、立野氏、深野氏などの祖でもあるが、御一家の泉家もこの胤顕を祖とするか。胤顕の個人的な活躍は伝わっていないが、所領の配分や惣領制成立の過程などを示す書状に名を残している。
弘安8(1285)年正月8日、胤顕は急な病気のために、子息の「胤盛」と「とよわか」「おとわか」のうち一人、「後家(妙悟尼)」の三人に所領の配分をしようとしたが、病があまりに重く、それぞれに譲り状を書いて与えることができなかったため、「置文」という形で「をのさハの入道(小野沢入道?)殿」に配分を託した。この「をのさハの入道殿」とはいかなる人物なのかはわからないが、「をのさハの入道殿御はからいにて、たねあきか所領をハ、はいふんして給へく候」と敬語を用いており、胤顕よりも目上の人物と思われる。
その約十年後の永仁2(1294)年『永仁二年御配分系図』によれば、胤顕は亡き胤村から44町7段2合を配分されていたことになっていて、行方郡岡田・院内・大三賀・飯土江狩倉・矢河原狩倉・八兎、高城保波多谷村・長田村を領していたとされる。永仁2年の配分系図には、どこどこを配分したとは書かれていないが、永仁2(1294)年8月22日『関東下知状』(計4通)に、「平胤顕跡」として「陸奥国院内・大三賀・八兎・波多谷」の知行が認められ、「已上田数載配分状」とあることから、『永仁二年御配分系図』に載せられている「44町7段2合」という田数は陸奥国の所領をさすものと考えられる。
そして、永仁2(1294)年8月22日『関東下知状』の一通に「平胤顕跡」とあることから、この時点にはすでに没していたと考えられる。没年齢は不明。
胤顕の配分を記した譲状としては、作成年代不明の胤村のものとされる『永仁二年御配分系図』があるが、ここには胤顕は194町余を配分されたとある。しかし、この譲状では胤顕の異母弟に当たる師胤に239町もの所領が与えられたことになっている。その理由としては胤村の後妻・阿蓮の「当腹嫡子」であることだったが、この譲状は師胤(または師胤所縁の人)が作為的に作ったものと思われる。
☆相馬泉胤顕子孫系図☆
相馬胤顕 +―相馬胤盛 +―胤康―――――――乙鶴丸(胤家)
∥ |(小次郎) |(五郎:鎌倉戦死)
∥ | ∥ |
∥ | ∥――――――――+―長胤―――――――孫鶴丸
∥ | 尼惠照 |(六郎:小高戦死)
∥ | |
∥―――――+―胤兼 +―胤治―――――――竹鶴丸
∥ |(孫六・とよわか?) |(七郎:小高戦死)
尼妙悟 | |
+―宗胤 +―成胤―――――――福寿丸
|(孫七・おとわか?) (四郎:小高戦死)
|
+―胤俊
|(十郎:妙悟の子?)
|
+―兼胤
|(與次:妙悟の子?)
|
+―胤元 +―孫四郎(討死)
(與三:妙悟の子?) |
∥ |
∥――――――――+―鬼若(没す)
れうくう
泉 胤基 (????-????)
奥州相馬泉氏の祖とされている人物。通称は六郎。相馬五郎義胤の三男とされているが、系譜などには見えないため、具体的なことは不明。
相馬五郎胤顕の十三男(と思われる)に相馬与三胤元という人物が系譜に見える。
泉 胤家 (????-????)
泉六郎胤基の六代の孫という。通称は宮内大輔。相馬宮内大輔胤家(岡田宮内大輔胤家)と同一人物か。
相馬宮内大輔胤家は、貞和4年(1348)年、叔母の「れうせう」から一期知行の地を譲る約定をもらい、相馬泉氏の惣領として、ほぼすべての実権を握った。
貞治2(1363)年8月18日、譲状を認め、嫡子・相馬五郎胤重に所領配分した。この時作成された譲状は四通にもなり、所領は細かく定められた。また、「さかいハゑんつにまかせて知行すへし(境は絵図に任せて知行すべし)」とあり、絵図も添えられていたと思われる。
家督を譲った胤家は、「宮内大輔」への叙任を奥州探題(斯波直持か)に願い出、貞治3(1364)年8月3日、探題に就任したばかりの吉良満家は、胤家に早く申状を出すよう伝えた。その8日後の8月11日、出羽国の合戦に出陣して功績を挙げ、満家から感状をもらっているので、「宮内大輔」への叙任申請はこの時の功績に対する足利方の礼だったのかもしれない。
貞治6(1367)年9月21日、散位某(国衙に出仕していた人物か)の署名で陸奥国竹城保内に所領安堵状が出されているが、これを最後に胤家の名は見えなくなる。
泉 信胤 (????-????)
泉宮内大輔胤家の三男。通称は山城守。
子の大内三郎胤元は相馬家家臣大内氏の祖となった人物。大内氏の子孫は泉家を惣領とし、庶流のうち大内孫右衛門長房は正保4(1647)年正月、泉内蔵助胤衡が相馬大膳亮義胤に改易されて浪人となり、仙台城下に移り住んだ際に従い、仙台で亡くなっている。
『相馬之系図』によれば、鎌倉時代後期の大悲山相馬氏の祖・相馬余市通胤の弟として「右馬介幸胤」「山城守信胤」の二名が見える。
ただし、この両名は鎌倉時代の一般御家人の庶流クラスでは許されない「右馬介(右馬助)」「山城守」などの官途であることから、系譜罫線の誤記と考えられるが、このうち「山城守信胤」は泉宮内大輔胤家の子とされる「山城守信胤」と同名同官途である。同一人物か。
なお、『相馬之系図』に見える「山城守信胤」の子に「龍王」が見える。
泉 胤平 (????-????)
通称は左京亮。相馬五郎胤顕の末裔か。
文正年中(1466~1467)、相馬隆胤(のちの相馬治部少輔高胤)の代に「泉左京亮胤平」の名を見ることができる(『相馬家譜』)。
泉 胤定 (????-1568)
通称は左衛門太夫。
 |
| 下総国相馬郡泉村の泉舘跡(柏市泉) |
寂れていた泉村(南相馬市原町区泉字寺前)の泉家菩提寺・宝月山東泉院を再興し、中興開基となった。東泉院はもともと下総国相馬郡泉村(柏市泉)の泉屋敷(柏市泉立ノ台)の東に建てられていた寺院で、泉氏が相馬孫五郎重胤とともに陸奥国行方郡に移り住んだ際、東泉院もともに移り、泉氏の菩提寺として続いた。
胤定は永禄11(1568)年某月24日に亡くなった。法名は智翁勝公大禅定門。後嗣がなく、三春城主・田村一族の中津川氏より中津川大膳が泉家を相続し、泉大膳亮胤秋を称した。
泉 胤秋 (????-1587)
通称は大膳亮。出自は三春の田村一族で、もとは中津川大膳亮。
天正13(1585)年に最上義光が相馬義胤臣の「伊泉大膳亮」へ宛てた書状が残っているが、この「伊泉大膳亮」が胤秋であるとされる(『最上義光歴史館収蔵品図録』より:「福島県立博物館紀要17号」所収)。
もともと胤秋は相馬讃岐守顕胤の弟・堀内次郎大夫近胤の娘を娶り、堀内家を相続していたが、彼女とそりが合わず堀内家を出た。その後、仙道小浜城主・岩角畠山伊勢守尚義の娘を娶った。
子の胤政が泉家を相続したが、いまだ幼少であったために胤秋も相馬家へ属し、胤政の後見人として泉大膳と改める。
天正15(1587)年4月16日に亡くなった。法名は東泉院桂岩昌公大禅定門。
泉 胤政 (????-1633)
中村藩泉家初代当主。父は泉大膳亮胤秋。母は畠山伊勢守尚義娘。通称は左京亮(『東奥中村記』:「相馬市史5」所収)、藤右衛門。初名は成政。藩の執権職。
父の泉大膳亮胤秋は、三春の田村右京大夫清顕の一族で、はじめは中津川大膳を称していた。胤政は幼少時に泉家に養子として入り、三千五十九石を知行した。しかし幼かったため、父・中津川大膳がその後見人として相馬家に入っている。
慶長2(1597)年、相馬長門守義胤が居城を小高城(南相馬市小高区)から牛越城(南相馬市原町区牛越)に移す際の城普請で胤政も人夫を差し出したが、義胤と胤政の人夫奉行が口論に及んだ。結果、胤政が「私曲」を企てたとして、義胤は胤政追討の軍勢を泉館(南相馬市原町区泉舘前)に発した。しかし、胤政は軍勢が来る前に館を焼いて相馬を出奔。会津の柳津(福島県河沼郡柳津町)の虚空蔵別当桜本坊(霊厳山圓蔵寺)へ逃れた。菩提寺の東泉院も胤政とともに会津へ移ることになる。
慶長3(1598)年、会津に上杉景勝が入ってくると彼に仕え、「泉左京」を称した。一方、義胤は胤政出奔につき、御一家泉家を改易とし、その旧領・泉村は岡田八兵衛宣胤へ与えられた。宣胤は破却された東泉院跡には、下総以来の岡田家菩提寺・岡田山宝幢寺(南相馬市原町区泉)が移されている。
慶長7(1602)年9月の慶長の役(関が原の戦い)ののち、義胤が中立の立場をとって積極的に戦いに参加しなかったことや、石田三成とは昵懇の仲であったことなどを理由に、徳川家康は相馬家を改易処分とした。これに義胤の嫡男・相馬蜜胤はみずから江戸に出向いて、徳川家旗本・島田治兵衛を通じて相馬家改易の撤回を懇願し認められた。このとき、胤政は相馬家の危機を聞いて、相馬家帰参を景勝に願い出て許され、上杉家を退き相馬へ向かった。その途次に、江戸に向かう蜜胤の一行と出会い、胤政は蜜胤に謁見したのち、三春領大倉に蟄居していた義胤のもとに出頭して、帰参を許された。
そして、江戸に出た蜜胤の活躍により相馬家は旧領が安堵されることとなり、胤政は千七百十四石という大変な高禄と、標葉郡泉田村(双葉郡浪江町幾世橋)に屋敷を与えられた。菩提寺の東泉院も館の隣に再建された。
また、蜜胤が江戸で世話になった日蓮宗寺院・瑞林寺の寺小姓・花井門十郎と住持・日瑞上人の甥・須藤嘉助が蜜胤とともに相馬へ引き取られたが、蜜胤は花井門十郎を胤政に預け、「泉」の名字を与えて一族として遇すべしと命じた。その後、花井門十郎は泉家一族の「泉縫殿助成信」となり、中村藩内で重きをなした。おそらく「成」の字は胤政がこの頃名乗っていた「泉藤右衛門成政」の一字を賜ったものだろう。
旧領安堵を勝ち取った義胤・蜜胤は、居城としていた牛越城を不吉な城として廃棄。小高城に居城を戻したが、行方郡中村の地に新たな城の建設をはじめ、慶長16(1611)年、居城を中村に移した。以降、幕末に至るまで相馬中村藩六万石の居城と定められた。中村城が完成すると、知行百石以上の家臣たちは中村城下への居住が命じられ「御家中」と称された。この時、百石に満たない家臣は知行地にそのまま住むこととなり、半士半農の「給人」と称された。胤政も泉田村から城下に移り住み、代わって前惣領家の相馬長門守義胤が小高城から泉田村へ移り住んでいる。
慶長17(1612)年、中村火沢(相馬市小迫)の龍蔵院と泉田村の東泉院が在所を交換し、寛永中に中村城東の百槻村(相馬市百槻)の妙見別当・長命寺と在所が交換された。以降、百槻村で泉家菩提寺として文政年中まで継承されるものの寂れ、その後は同慶寺に合併されて泉家の墓碑のみ残された。現在、東泉院跡には蒼龍寺墓所があり、そこに泉家墓碑はない。一軒、剣片喰紋の泉家墓石があるが、関係はなさそうである。
慶長20(1615)年、大坂夏の陣の際には、藩主・相馬利胤(蜜胤改め)ほか、隠居の相馬長門守義胤、利胤の弟である相馬左近及胤、相馬越中直胤ら藩主一族がすべて出陣してしまった中村の「留守居」をつとめた。
元和7(1621)年4月12日の仙台藩との領境の森の伐採をめぐる訴訟文書の中に「門馬銀右衛門正経、堀田十兵衛成泰、泉藤右衛門成政」とあるので、この頃までは「成政」と名乗っていて、その後「胤」字を賜ったと思われる。
寛永6(1629)年5月28日、相馬利胤の嫡男・相馬虎之助義胤が大御所・徳川秀忠、将軍・徳川家光への初御目見の際、子の内蔵助胤衡、守役・立野市郎右衛門胤重とともに義胤に供奉した。
その後、藩執権職となり、寛永10(1633)年4月22日、亡くなった。没年齢不詳。
※瑞林寺…「谷中瑞林寺」と伝わる。現在の谷中慈雲山瑞輪寺のことと推測される(江戸期の地図では瑞林寺とある)が、慶安2(1649)年に神田から現在地に移されたもので、当時は神田にあって谷中にはない。『奥相秘鑑』は享保16(1731)年成立、『御年譜』も享保20(1735)年頃の成立であり、瑞林寺がそのころすでに谷中にあったため、谷中瑞林寺としたものか。
泉 胤衡 (????-1668)
中村藩泉氏二代当主。泉藤右衛門尉胤政の嫡男。通称は内蔵助、藤右衛門。号は意伯。藩での役職は執権職。
寛永6(1629)年正月、江戸城本丸下石垣普請で、相馬家も手伝い普請が命じられた際に普請奉行に任じられている。また、同年5月28日、相馬虎之助義胤が大御所・徳川秀忠、将軍・徳川家光への初御目見の際、父・泉藤右衛門尉胤政、守役・立野市郎右衛門胤重とともに義胤に供奉した。
寛永11(1634)年、相馬大膳亮義胤が川越城番として赴任した際には藩執権職であり、前年の父・胤政死去後、執権職は胤衡に任じられたのだろう。
寛永12(1635)年4月11日、義胤の婚礼の祝いとして、包利の太刀一腰を献じた。
寛永14(1637)年2月2日、胤衡は中村から江戸藩邸に到着。御膳を献じ、新刀一振を義胤に献上した。
寛永20(1643)年4月、泉内蔵助胤衡の養嗣子となった(『相馬藩世紀』)。その後「二本松ノ城受取御番申様ニト被仰付」(「古日記」(『海東家文書』)たため、5月16日に藩侯義胤(5月11日に江戸から帰国)に「御供老」として中村から二本松へ出立した。二本松城は2年前の寛永18(1641)年3月25日、藩主・加藤民部大輔明利が卒去したのち除封されていた。その後、8月1日に中村へ戻っている(「古日記」(『海東家文書』)。
11月18日、胤衡屋敷において藩侯義胤を招いて「養子卯之助殿御祝」の能が行われ、胤衡は「其日内蔵助を改メ藤右衛門ト号」し、胤祐は「卯之助を改、内蔵助ニ成」った(「古日記」(『海東家文書』)。翌年の正保元(1644)年元日の「独礼御目見」の中に「泉藤右衛門」と見える。
正保2(1645)年、義胤が三春城番の際には、「江戸御留守老」をつとめていたが、日頃から「奢侈倍重」であったようで、正保4(1647)年正月、知行の二千五百八十三石八斗一合を召し上げられ、泉家はふたたび改易された。
しかし、慶安3(1650)年、義胤の母・長松院(徳川秀忠養女)のたっての願いによって養嗣子の内蔵助胤祐の勘気が許されたため、胤衡も百人扶持で再度召し出された。寛文6(1666)年3月20日、嫡男で泉家当主の胤祐が「藤右衛門」を称するにあたり、剃髪して意伯を号した。
寛文8(1668)年9月14日、病死した。
妻・長寿院は享保21(1736)年に百歳を迎え、2月、百歳の賀を詠んで藩公・相馬弾正少弼尊胤に献上している。
この歌は会津藩主・松平肥後守容貞にも献じられており、同年11月15日、容貞から綿三把が長寿院に進呈された。
泉 胤祐 (????-????)
中村藩泉氏三代当主。泉藤右衛門胤衡の養嗣子。実父は藩老・熊川左衛門長春。妻は中津新兵衛幸政娘、玉井治兵衛娘。幼名は卯之助。通称は内蔵助、藤右衛門。藩での役職は侍大将、家老。
寛永20(1643)年4月、泉内蔵助胤衡の養嗣子となり(『相馬藩世紀』)、11月18日、胤衡屋敷において藩侯義胤を招いて「養子卯之助殿御祝」の能が行われ、胤衡は「其日内蔵助を改メ藤右衛門ト号」し、胤祐は「卯之助を改、内蔵助ニ成」った(「古日記」(『海東家文書』)。
正保3(1646)年元日、年始の賀儀で「泉内蔵助」として名が見える。しかし、翌正保4(1647)年正月、養父・胤衡が「兼而之奢侈倍重」を理由に改易されると、胤祐もこれに連座して改易され、牢人となってしまった。
泉藤右衛門胤衡、胤祐父子が相馬家に復帰できたのは、実に二年も後の慶安2(1649)年2月5日であった(「古日記」(『海東家文書』)。おそらく、胤衡・胤祐が義胤の母・長松院(徳川秀忠養女)へ訴えたのだろう。長松院の願いにより義胤は胤衡・胤祐父子の勘気を許し、胤祐は七百石が与えられ、「御一家」の格式も戻された。
明暦2(1656)年閏4月27日、中村にて御定が施行された。内容は百石以上の大身士と百石以下の小身士、在郷給人(半農半士)それぞれに対する知行などに関するもので、熊川左衛門長定、泉内蔵助胤祐、泉田覚左衛門胤益、藤田七郎兵衛胤近、立野市郎右衛門胤安、木幡嘉左衛門貞清、門馬嘉右衛門長経、池田八右衛門直重、村田余左衛門俊世、佐藤長兵衛重信、石川助左衛門昌直、門馬次郎右衛門、木幡九郎兵衛、太田清左衛門之治、西市左衛門重治、渋川源左衛門直之ら重臣の連名で発せられている。
寛文元(1661)年2月、胤祐は三代藩主・相馬長門守忠胤の家老職に任じられた。
寛文5(1665)年4月の日光における東照権現五十回忌の儀で、幕府は梶井宮慈胤法親王、青蓮院門跡尊證法親王、曼殊院門跡良尚法親王といった門跡の方々などを招き、そのうち忠胤には祭礼の導師を務める予定の梶井宮慈胤法親王の御馳走が命じられた。実は梶井宮慈胤法親王の母は忠胤の伯母にあたる人物で、宮と忠胤は従兄弟同士であり、つまり忠胤は後陽成天皇の義甥にあたった。
【八条宮】
+―智仁親王―+―智忠親王
|(式部卿) |(中務卿)
| |
| +―良尚法親王
| (曼殊院門跡)
|
| 園国子 +―霊元天皇
| (新広義門院)|
| ∥ |
| 近衛前子 ∥――――+―尊證法親王
| ∥―――――後水尾天皇 (青蓮院門跡)
| ∥
+―後陽成天皇
∥―――――慈胤法親王
+―土佐局 (梶井宮)
|(寶壽院)
|
中東大膳―+――娘
(霊光院)
∥
∥―――――相馬忠胤
土屋忠直―+―土屋利直 (長門守)
(民部少輔)|(民部少輔)
|
+―土屋数直【老中】
(但馬守)
4月7日に始まった祭事は17日終了し、忠胤は梶井宮とともに江戸へ下り、24日、梶井宮は江戸天徳寺に入った。この天徳寺御在所付の家老に胤祐が任じられた。5月7日、梶井宮は天徳寺につめる相馬家家臣へ御酒を賜り、家老の胤祐と村田俊世(與左衛門)へは晒布二疋が下された。
8月10日、村田與左衛門俊世、泉内蔵助胤祐、堀内十兵衛胤重、泉田掃部胤隆の四名が改めて侍大将四組頭に任じられた。
寛文6(1666)年3月20日、内蔵助胤祐は名乗りを「藤右衛門」に改めた。その際、嫡男・菊松は「内蔵助胤和」と改め、隠居の藤右衛門胤衡は法体となり、意伯と号している。
その二年後の寛文8(1669)年2月、領内の百姓が蜂起して年貢について訴えを起こした。藩では3月4日、胤祐はじめ石川助左衛門昌直、富田五右衛門正実らを在郷に派遣して交渉をさせている。しかし、5月1日、何か不届きなことがあり、胤祐は知行七百石を召し上げられた。泉家は三代にわたって三度目の知行召上処分ということになるが、このときは藩老中の村田與左衛門俊世が「藤右衛門義、数代之御家老、其上泉ノ家断絶仕事如何敷奉存候」と忠胤を諫め、さらに「倅内蔵助若年之事故、只今之屋敷ニ被差置、御扶助於被成下者、泉ノ家相続可仕」と、胤祐の子・内蔵助胤和への家督相続を願いあげ、忠胤も俊世の言葉に感心して、胤祐の隠居と、胤和への泉家家督相続を認め、屋敷もそのまま住むことを許された。屋敷には祖父・胤衡入道意伯が住んでおり、胤和との同居もそのまま認められた。一方、隠居させられた胤祐は泉田村の知行地に移り住んだか。没年不明。
娘は原伝右衛門宗清の妻となった。二女は天和元(1681)年12月27日に佐藤仁左衛門永重の妻となったが、病のため実家に戻っている。もう一人の娘は石川助左衛門宗昌の妻となる。
次男・泉助右衛門信政は初名を助太夫といい、母は会津の玉井治兵衛女。その次男の泉平次郎が、熊川要人長英の養子となって、熊川兵庫長盈となる。
●泉家略系図
泉胤政 岡田伊胤――――娘
(藤右衛門) (与左衛門) ∥
∥――――娘 ∥―――+―熊川長賀
岡田氏 ∥―――+―熊川長定===熊川長治―+―熊川長貞 |(兵庫)
∥ |(左衛門) (清兵衛) |(兵庫) |
熊川長春 | ∥ | +―熊川長診===熊川長盈
(左衛門) | 岡田氏 | (兵庫) (兵庫)
| | ∥ ∥
| | ∥ ∥
| | ∥――――――娘
| | +―娘
| | |
| | |
| | +―熊川長則――+―定之助
| | |(兵庫) |
| | | |
| +―桑原安利―+―娘 |
| |(軍治) ∥ |
| | 相馬胤英 +―娘
| | (将監) ∥
| | ∥
| | 石橋重義―――熊川長福
| | (長左衛門) (兵庫)
| |
| +―川勝長亮―――熊川長芳
| |(新兵衛) (要人)
| |
| +―姉
| ∥――――――泉胤秀
+―泉胤祐 +――――――――泉胤和 (左衛門)
(内蔵助) | (内蔵助) ∥
∥ | ∥
∥――――+―泉信政――――熊川長盈 ∥――――――泉胤殊
∥ |(助右衛門) (兵庫) ∥ (内蔵助)
∥ | ∥
中津幸政―――娘 +―娘 ∥
(新兵衛) | ∥――――――花井信英 ∥
| 原宗清 (七郎大夫) ∥
|(伝右衛門) ∥
| ∥
+―娘 ∥ +―岡田往胤―――岡田恩胤
| ∥――――――石川弘昌 ∥ |(監物) (監物)
| ∥ (助左衛門) ∥ | ∥
| 石川宗昌 ∥――――+―娘 岡田春胤―+―娘 ∥
|(助左衛門) ∥ | (監物) ∥――――+―娘
| ∥ | ∥ |
| ∥ | ∥ |
| 門馬辰経―――娘 +―石川昌清―+―石川庸昌―――石川邑昌 +―石川品昌
|(嘉右衛門) (助左衛門)|(弥市兵衛) (助左衛門) (助左衛門)
| | ∥
| +=養女 ∥
| (鵜殿弾蔵娘) ∥
| ∥―――――――――――――娘
| ∥
| 相馬胤寿
| (将監)
|
| 岡田往胤
| (監物)
| ∥
+―娘 +―娘
∥ |
∥ |
∥――――――佐藤常重―――佐藤信重―+―佐藤栄重
佐藤永重 (七右衛門) (仁左衛門) (宗太夫)
(仁左衛門)
泉 胤和 (????-????)
中村藩泉氏四代当主。泉藤右衛門胤祐の嫡男。妻は熊川清兵衛長治長女。幼名は菊松。通称は内蔵助。藩での役職は侍大将。
寛文6(1666)年、「内蔵助胤和」と名を改めた。翌寛文7(1667)年8月21日、幕府の巡見使、佐々又兵衛隆直、中根卯右衛門正章、松平新九郎正直が仙台藩領から中村藩領へ入った。このとき、藩主・相馬長門守忠胤は堀内十兵衛胤重、泉内蔵助胤和、石川助左衛門昌直の三名に御巡見三人への挨拶を命じている。
寛文8(1669)年2月15日、藩公・相馬忠胤は「在郷給人」を束ねる「在郷給人頭」を新たに設置し、侍大将四組のもとに組み込むことを命じた。その際の侍大将四組頭は村田與左衛門俊世、熊川清兵衛長治、泉田掃部胤隆、堀内一兵衛であり、泉内蔵助組は熊川清兵衛組に変わっている。実は、この二か月半後の5月1日、父・胤祐に何か不届きなことが原因で、知行七百石を召し上げられるという事件が起こっており、2月の時点ですでに侍大将としての地位を剥奪されていたのかもしれない。
●寛文8(1669)年の侍大将組頭-在郷給人頭一覧
| 組名 | 組頭(侍大将) | 在郷給人頭 |
| 村田與左衛門組 | 村田與左衛門俊世 | 立野與次右衛門 熊上善左衛門清次 堀越金右衛門 幸田十郎兵衛 |
| 熊川清兵衛組 | 熊川清兵衛長治 | 木幡忠左衛門 桜井杢右衛門 岩城忠右衛門吉隆 大槻吉右衛門 |
| 泉田掃部組 | 泉田掃部胤隆 | 草野長右衛門 塩松庄右衛門 大越次兵衛吉光 門馬但右衛門 |
| 堀内一兵衛組 | 堀内一兵衛 | 井上主馬 石橋嘉右衛門 羽田平左衛門 杉本助之丞 |
このとき、藩老中の村田與左衛門俊世が泉家の断絶回避を藩公に嘆願し、胤和への家督相続が認められ、屋敷もそのまま祖父・胤衡入道意伯とともに住むことを許された。ただし家禄は没収されたままで、祖父の百人扶持で生活をしていたのだろう。
しかし、同年9月14日、祖父の意伯入道が病死。そのため、10月26日に胤和へ五十人扶持が与えられ、それまで住んでいた意伯の泉家屋敷は召し上げとなり、胤和には新たに大手門内長友に屋敷を拝領した。
延宝7(1679)年7月22日、藩公・相馬出羽守貞胤が中村妙見宮へ社参。元服式が行われた。元服の仮親は一門筆頭の岡田與左衛門伊胤、そして烏帽子親を胤和がつとめた。しかし、貞胤は11月23日、中村城内で急死した。二十一歳の若さであった。すでに貞胤の弟・相馬昌胤を継嗣とする届けは幕府に出されており、12月18日、昌胤は江戸城に登城して大老・酒井雅楽頭忠清より貞胤の「存生ノ願之通」りに昌胤へ家督相続を認める旨の将軍家の命を受けた。この祝辞を述べるため、「惣御家中名代」として胤和が江戸に登った。
天和元(1681)年6月、新たに四百石が与えられた。
元禄6(1693)年6月19日、執権城代・岡田監物伊胤と老臣・岡部兵庫宗綱が突如職を免じられ、目通りも許されなくなる。この解職処分の理由として「両人無調法有之」とされるだけで、具体的な理由は不明である。しかし、一月半前に藩公・昌胤が江戸から帰国していることから、城代として留守居を勤めていた伊胤に重大な不手際なことがあったためと考えられる。伊胤が支配していた岡田監物組は内蔵助胤和が侍大将となり支配することとなった。
元禄8(1695)年5月6日、坪田村(相馬市坪田)の八幡宮遷宮式が執り行われ、御一家・重臣が石灯籠を寄進しているが、右の石塔の二番目に「御一家 泉内蔵助胤和」と見える。
元禄14(1701)年2月11日、藩公・相馬弾正少弼昌胤が隠居して、相馬図書頭敍胤へ家督相続が正式に認められた。その御礼言上として、2月28日、敍胤は将軍家への御礼言上のため登城。御一家の岡田宮内知胤、泉内蔵助胤和、相馬将監胤充の三人も敍胤に随って登城し、それぞれ永井伊賀守尚敬、朽木伊予守稙昌、青山播磨守幸督が御奏者として将軍家に謁見させた。
しかし、胤和はその後も老中職、執権職などに就いた形跡はなく、三代にわたって改易処分を受けたことによるのかもしれない。正徳元(1711)年、病のため侍大将を辞し、組支配を免ぜられた。泉内蔵助組は堀内大蔵胤近が代わって支配することとなった。
正徳3(1713)年12月11日、胤和は隠居し、嫡男・小市郎に家督を譲った。その翌日、小市郎は御一家の格式が与えられ、「胤」字を下されて「胤秀」と改めた。
妻・熊川氏は享保20(1735)年4月18日、七十八歳で亡くなった。法名は天照院殿同寛光雲。妹は石川助左衛門、原伝右衛門宗清、佐藤玄岡にそれぞれ嫁ぎ、弟・泉助左衛門信政は別家を立てている。娘は西市左衛門為治、相馬将監胤充、石川十太夫快昌の妻となっている。
●泉胤和周辺系図
泉胤和―+―泉胤秀――+―泉胤寧
(内蔵助)|(内蔵助) |(内蔵助)
| |
| +―泉胤殊=====泉胤伝
| (内蔵助) (内蔵助)
| ↑
| 佐藤元重 |
| (仁左衛門) |
| ∥ |
+―娘 +―娘 |
| ∥ | |
| ∥――――+―娘 |
| ∥ ∥―――――――泉胤伝
| 石川快昌 大越暢光 (内蔵助)
|(蔵人) (四郎兵衛)
|
+―娘
| ∥
| 相馬胤充
|(将監)
|
+―娘
∥
西為治
(市左衛門)
泉 胤秀 (????-1767)
中村藩泉氏五代当主。泉内蔵助胤和の嫡男。妻は石川助左衛門弘昌長女。幼名は小市郎。通称は左衛門。号は淳宇。藩での役職は侍大将。屋敷は中村城大手門内長友(南二ノ丸)。
 |
| 中村城中ノ門跡と長友(南二ノ丸) |
正徳3(1713)年12月11日、父・内蔵助胤和の隠居にともなって家督を継承。翌12日、小市郎は御一家御目見の格式と「胤」字が下され、名を「胤秀」と改めた。12月24日には願いによって通称を小市郎から「左衛門」に改めた。歴代の泉家当主は、はじめ内蔵助、のちに藤右衛門と改めているが、胤秀は隠居まで左衛門を称し続けている。
享保4(1719)年11月15日、侍大将に任じられる。享保9(1724)年、病のために侍大将職を辞し、3月19日、跡を泉田掃部胤重が侍大将として継いだ。
享保19(1734)年2月24日、病によって組頭を辞した相馬将監胤英に代わって、ふたたび侍大将に任じられたが、体の具合はあまりよくなかったようで、翌享保20(1735)年10月23日、組支配、家老職を辞した。
享保21(1736)年2月28日、「泉左衛門祖母」長寿院が百歳の賀を詠み、藩公・相馬弾正少弼尊胤に献上した(『相馬藩世紀』『覚日記』)。
この歌は会津藩主・松平肥後守容貞にも献じられており、同年11月15日、容貞から綿三把が長寿院に進呈された。
元文3(1738)年の相馬内膳(八代藩主・相馬恕胤)の着袴の儀で因親をつとめており、御一家として重んぜられた。翌元文4(1739)年には中村城妙見社の正遷宮の御浜下りで列席している。
寛保元(1741)年10月13日、「泉左衛門祖母、百五歳ニて死去」し、「十五日夜、東泉寺葬也」という(『寛文七年羊閏二月ゟ日記写』)。
寛保3(1743)年12月14日、「泉左衛門隠居、同内蔵助家督如願被仰付」と見え(『覚日記』)、隠居して嫡男・胤寧(内蔵助)に家督を譲り、淳宇と号した(『相馬藩世紀』)。12月28日に「内蔵助家督御礼」している(『覚日記』)。
明和4(1767)年8月6日、病気のため侍大将職を辞したが、病は篤く亡くなった。8月9日、泉内蔵助胤寧に藩公よりの使者が面会し、三十五日法要の節に香典が贈られた。
長男・小三郎胤寧は泉家の家督を相続し泉内蔵助を称する。
二男・彦五郎は御一家・相馬将監家の分家である武岡家を継いで武岡勘右衛門忠親となるが、宝暦10(1760)年2月17日、兄・泉内蔵助胤寧の願いによって本家に戻り、泉内蔵助胤殊となる。
三男・圓之助は田村助右衛門貞顕の養嗣子となり、田村助右衛門憲顕となる。この憲顕の娘が泉主殿胤陽(相馬将監胤豊の子で泉家を相続)に嫁ぐ。
泉 胤寧 (????-????)
中村藩泉氏六代当主。泉左衛門胤秀の嫡子。幼名は小三郎。通称は内蔵助。号は了圓。妻は幾世橋作左衛門明経養女(門馬弥右衛門宣経長女)、馬場久左衛門宗重長女、石川宇右衛門昌次女、のち富田彦太夫貞重娘。名は「たねやす」か。藩での役職は侍大将。
享保19(1734)年2月15日、藩公・相馬弾正少弼尊胤に初御目見し、「胤」字を給わって「胤寧」を称した。元文5(1740)年7月には「泉小三郎、仍願、内蔵助与改名被仰付」れた(『相馬藩世紀』)。
寛保3(1743)年、父・胤秀(左衛門)が隠居したため、家督を継承した。その後、侍大将に就任。泉内蔵助組の組頭となり、延享2(1745)年8月の野馬追神事では組士を率いて参加している(『相馬藩世紀』)。延享5(1748)年正月16日、「泉内蔵助胤寧、御家老被仰付」て二百石加増された(『寛文七年羊閏二月ゟ日記写』)。
宝暦3(1753)年6月27日、「泉内蔵助胤寧、退役被仰付候、組支配共ニ御免」となり、7月6日、「泉田掃部胤守、侍対象被仰付 泉内蔵助元組」を引き継いだ(『寛文七年羊閏二月ゟ日記写』)。
宝暦10(1760)年2月17日、弟で御一家・相馬将監家の分家、武岡家を継いでいた武岡勘右衛門忠親を養子として取り戻して家督を継がせ、隠居して了圓を号した。武岡忠親は藩公より「胤」字を賜って泉内蔵助胤殊となり、安永2(1773)年に老中職に就いた(『相馬藩世紀』)。
天明5(1785)年正月2日、御一家隠居、岡田直衛(岡田往胤)、泉了圓(泉胤寧)、相馬希及(相馬胤寿)が年頭伺のため登城している(『相馬藩世紀』)。
娘(田原口橘左衛門為定継母)は花井七郎太夫信以に嫁いでいる(『衆臣家譜』)。
泉 胤殊 (????-1778)
中村藩泉氏七代当主。泉左衛門胤秀の次男。母は石川助左衛門弘昌娘。妻は田中四郎左衛門典恒娘、のち山田半左衛門娘。幼名は庄五郎。通称は次郎左衛門、勘右衛門、内蔵助。名は「たねよし」か。藩での役職は侍大将、老中。
相馬御一家・相馬将監家の分家である武岡忠充(熊之助)が享保16(1731)年正月15日に七歳で亡くなったため、4月、武岡家の家督を継いで武岡忠親(次郎左衛門)を称した。のち勘右衛門を称す。忠充急死による末期養子のため、半知百石を相続した。
延享5(1748)年3月4日、在郷中頭に任じられ、宝暦8(1758)年1月12日、物頭に就任した。しかし2年後の宝暦10(1760)年2月17日、兄の泉内蔵助胤寧の願いによって泉家を相続。一字を賜り「胤殊」と称した。
安永2(1773)年5月20日、家老門馬八郎兵衛隆経の家老職罷免及び逼塞に伴い、家老職に就任したが、体の具合が思わしくなかったようで、安永6(1777)年5月26日に老中職と泉内蔵助組の組支配を免ぜられた。翌安永7(1778)年3月、病死した。
嫡男・平十郎は宝暦元(1750)年2月18日に亡くなっており、次男・泉矢柄(要之助)も家督に就かず、胤殊は妹を養女とし、大越弥右衛門暢光の三男・胤傳を婿に迎えて泉家を相続させた。
泉 胤傳 (????-????)
中村藩泉氏八代当主。泉内蔵助胤殊の養嗣子。実は大越弥右衛門暢光の三男。母は石川十太夫快昌娘。幼名は兵部。通称は内蔵助。名は「たねひろ」か。藩での役職は侍大将、老中。号は右橘。妻は泉了圓胤寧娘、四本松但七義林娘、森武兵衛尋次娘。兄には大越四郎兵衛経光、北矢多五武清がおり、姉には木幡六右衛門高寛妻がいた。
先代の内蔵助胤殊の養女(胤殊の妹で兄の養女となる)を妻に迎えて泉家を相続した。明和9(1772)年、藩主・相馬因幡守恕胤に初目見を果たし、「胤」字を給わり「胤傳」を称した。安永6(1777)年9月、妻の泉了圓娘が亡くなった。
安永7(1778)年3月25日、義父の胤殊(内蔵助)が重病となったため、跡式として胤傳への相続が藩に提出された。後を追うように4月4日、養母の泉胤殊妻が卒去。5月2日、泉家の家督を相続した。
同年閏7月22日、通称を兵部から「内蔵助」に改めた。翌安永8(1779)年もは侍大将として泉内蔵助組の組支配を仰せ付けられる。同年4月29日、家臣の大和田忠太へ八石の知行宛行状が遺されている(『相馬泉家文書』)。
天明3(1783)年7月25日、藩公一門・相馬伊織斎胤の子・鍋五郎肥胤を養嗣子として迎えたが、故あって寛政4(1792)年閏4月、相馬藩公家へ戻った。その後、肥胤は文化6(1809)年9月、大身旗本・天野傳兵衛家に養嗣子に入った。
天明6(1786)年には老中職に就任した。寛政7(1795)年6月21日、組支配を命じられた。さらに寛政10(1798)年8月の野馬追神事では藩主名代を務めた。
寛政8(1796)年1月24日、病のため家老職・侍大将を辞した。しかしその後も御一家としての役割を担い、5月15日、城内的場に白猿が現れる吉瑞があり、急遽、歌絵が催された。岡田監物恩胤、堀内大蔵胤久、泉内蔵助胤傳、泉田左門胤保らが歌を献じた。
享和元(1801)年、相馬讃岐守樹胤の家督相続の御礼のため、祥胤・樹胤は将軍に謁見することとなり、先例の通り、御一家より三名が同伴することとなった。そのため、岡田監物恩胤、相馬将監胤慈、相馬主税胤綿が江戸に出府。4月18日、相馬祥胤、相馬樹胤の両公とともに将軍・徳川家斉に謁見した。その後、樹胤は初めて国元に下り、6月3日、堀内大蔵胤久、泉内蔵助胤傳、泉田左門胤保が中村城内にて謁見。太刀折紙を献上した。泉典膳胤陽も箱肴を進上している。
享和3(1803)年7月7日、隠居を許され「右橘」を称した。家督は相馬左織胤豊の子で養嗣子としていた泉典膳胤陽が継承し、さかのぼること一月前の6月、侍大将に就任している。なお、次男・泉杢允は実家・大越家の分家筋である大越勘左衛門純光の養嗣子となり、大越官左衛門光海と称した。
翌享和4(1804)年1月3日、御一家隠居として、泉右橘胤傳、相馬左織胤豊、相馬希元胤義が藩公・樹胤に謁した。
泉 鍋五郎 (1779-????)
中村藩泉氏九代当主。通称は鍋五郎。名は肥胤(ともたね)、彬胤(ともたね)。のち大島鍋五郎、天野左近富敷。父は相馬伊織斎胤。泉内蔵助胤殊の養嗣子。妻は姪の光姫(兄・相馬祥胤の娘)、のち岡田監物恩胤養女・於久。旗本・大島家への養子、さらに旗本・天野家の養子となる。
●泉鍋五郎周辺系譜
|
青山大膳亮幸秀娘 |
安永8(1779)年4月23日、藩公一門・相馬伊織斎胤の子として誕生。泉内蔵助胤傳の養嗣子と定められた。
天明3(1783)年7月25日、泉家へ養子に入る。しかし故あって寛政4(1792)年閏2月21日、泉家から実家の相馬藩公家へ戻り、泉家嫡子には相馬左衛門胤豊の三男・太田早馬が「泉典膳」と称して入ることとなり、3月3日には泉典膳が泉田左門とともに藩公・相馬祥胤に初謁見。それぞれ一字が与えられ、泉典膳は「胤陽」、泉田左門は「胤保」と称し、胤陽は12月20日に正式に泉家の養嗣子として泉家に引き移った。胤陽は「この者太守の御養として泉家へ御養子」とあり、藩公・相馬祥胤の養子として泉家に入っている。
寛政5(1793)年5月11日、鍋五郎は相馬外記胤慈を因親として具足初の儀が執り行われ、藩公・相馬樹胤より一字を賜り「肥胤」と称した。9月16日、旗本・大島雲八義和の婿養子となる縁談がまとまり、寛政6(1794)年12月23日、大島家へ婿養子届けが幕府に提出され、翌寛政7(1795)年3月2日、養子届が正式に受理され、6月26日、藩公・相馬樹胤より備前友成の太刀を下賜され、29日、中村を発って江戸へ向かった。しかし、寛政8(1796)年11月3日、故あって大島家を辞して相馬家へ戻った。理由については、鍋五郎も義父の大島義和もともに親しむ様子がなかったようである。相馬家へ戻った鍋五郎は11月15日、本山勘兵衛安義を因親として前髪執の儀を行った。12月7日には、岡田監物恩胤の養女・於久との婚約がなされた。
12月26日、於久との婚姻が整い、1月8日、婚礼の儀が執り行われた。於久にはすぐに子供ができたが、8月17日、惜しくも死産となった。
享和元(1801)年12月、鍋五郎に御内分の扶持として一千石が与えられた。
文化4(1805)年9月、肥胤は「彬胤(ともたね)」と改名した。
文化6(1809)年9月、再び旗本・天野伝兵衛冨貞の養嗣子の縁談が持ち上がった。天野家は徳川家康の家臣で名奉行と謳われた天野三郎兵衛康景の末裔。冨貞は当時四十七歳。大御番五番士であった。翌文化7(1810)年5月15日、麻布飯倉の天野家(七百五十石)に入嗣して名を天野左近冨敷と改め、11月25日、天野家の家督を相続した。そして、文化9(1812)年6月、長女・於鋭(トシ)が誕生した。
文政2(1819)年11月、富敷の娘・於幸と旗本・三枝尚吉郎が婚礼したが、その後離縁。文政11(1828)年12月、於幸は従兄の藩公・相馬長門守益胤の養妹となり、旗本・井上左大夫正路に嫁いだ。
冨敷には男子がなかったため、備中国岡田藩主・伊東播磨守長寛の子・辰之助を養嗣子に迎え、辰之助は天野冨之を称した。
泉 胤陽 (????-????)
泉内蔵助胤傳の養嗣子。実父は相馬左衛門胤豊。初名は太田早馬。通称は典膳、左衛門、主殿、藤右衛門。号は右橘。妻ははじめ太田清八郎茂治娘、のちに田村助右衛門憲顕(泉胤秀三男)娘、小田切伝兵衛安旨三女(母は伊東文右衛門武実女)(『衆臣家譜』巻十四 小田切氏)、首藤半右衛門成文娘、離別後は守屋新左衛門方重娘。娘は熊上七郎左衛門長寛の妻となるが離縁となる。
|
花井信以 |
はじめ、太田清八郎茂治の婿養子となり、太田早馬と称していたが、寛政4(1792)年閏2月21日、泉家の養嗣子となっていた鍋五郎(藩公・祥胤の甥)が故あって相馬家公子に戻ったため、泉家の嫡子として太田早馬が定められた。藩公・祥胤の命により実父・相馬左衛門胤豊の家に戻ったのち、祥胤の猶子となって泉内蔵助胤傳の養嗣子となり、「典膳」と名を与えられた。太田家には弟の鉄次郎が養子に入り、太田清左衛門佳治を称した。
3月3日、典膳は泉田左門とともに藩公・相馬祥胤に初謁見。それぞれ「胤」の一字を賜り、「泉典膳胤陽」「泉田左門胤保」を称した。そして12月20日、胤陽は泉家に養嗣子として入った。胤陽は「この者太守の御養として泉家へ御養子」とあり、先公・相馬恕胤の養子となっていたと思われる。
寛政6(1794)年2月27日、前髪執の儀が行われた。寛政7(1795)年7月28日、胤陽は御知行被下の御礼のため登城し、藩公・相馬祥胤に謁した。8月には歓喜寺麓に造営された新宮につき、歌ならびに詩が奉納されたが、「泉典膳胤陽」は相馬外記胤慈、相馬主税胤綿、相馬左衛門胤豊らとともに歌を詠んで奉納した。
享和元(1801)年、相馬樹胤の家督相続の御礼のため、相馬祥胤・相馬樹胤の両公は将軍に謁見することとなり、先例の通り、御一家より三名が同伴することとなった。そのため、岡田監物恩胤、相馬外記胤慈、相馬主税胤綿が江戸に出府。4月18日、相馬祥胤、相馬樹胤の両公とともに将軍・徳川家斉に謁見した。その後、樹胤は初めて国元に下り、6月3日、堀内大蔵胤久、泉内蔵助胤傳、泉田左門胤保が中村城内にて謁見。太刀折紙を献上した。胤陽も箱肴を進上している。
享和3(1803)年6月、侍大将に就任。7月7日、典膳胤陽は家督相続御礼、先代・内蔵助胤傳は隠居御礼を述べ、胤傳は「右橘」を称した。また、家督相続した胤陽は「左衛門」と改名した。
享和4(1804)年5月20日の野馬追神事では藩主名代を「泉左衛門」が務めている。
文化11(1814)年4月19日、藩公・相馬樹胤が隠居のため、その御手道具が御一家衆へ下されることとなり、「琉球の花入れ」が「泉左衛門」「相馬将監」「相馬徳三郎」「泉田掃部」に下げ渡された。
そして11月22日、登城を命じられた泉左衛門胤陽は家老職の内示を受け、11月24日より家老職に就いた。その後、家老職を辞して嫡子の内記胤門に家督相続し、胤陽は藤右衛門を称した。そして文政10(1827)年6月25日、内記は登城を命じられ、家老職に任じられた。
天保10(1839)年9月20日、胤陽は侍大将となり、岡田帯刀智胤組を引き継いで、組支配を命じられた。
しかし、天保15(1844)年6月19日夜、藤右衛門宅に剛盗が忍び入り、嫡子の内記胤門が顔面を斬られて重態に陥り、7月4日に亡くなってしまった。このためか胤陽も力を落としたと思われ、病のため8月20日、侍大将職を辞して隠居した。
泉 胤門 (????-1844)
泉左衛門胤陽の嫡子。通称は主殿、内記。妻は池田図書胤直娘。
文政10(1827)年6月25日、内記は堀内大蔵胤久とともに登城を命じられ、内記は家老職に任じられた。一方、堀内大蔵胤久は病気の保養のために組支配を免じられた。堀内組は泉田掃部胤清が侍大将となり、引き継いでいる。
天保5(1834)年正月に藩が藩士の屋敷地と知行高を調べた『御家中屋鋪並知行覚』には「泉主殿」が「西山河岸東」に屋敷を持っていたことが記載されている。この覚書は『相馬市史』によればその後もかなり長期にわたって使用された形跡がうかがえ、次代の「内蔵助(胤富)」が記載されている。
天保9(1838)年6月、幕府巡見使が来た際に巡見使より質問されたときの模範解答『御巡見様御尋之節御答書集帳』の「御一家并重立候役人」に「高七百石 泉内記」と見える。
天保15(1844)年6月19日夜、泉藤右衛門宅に剛盗が忍び入り、「内記殿」は目の下から下唇まで斬られ、7月4日、亡くなった。
泉 胤富 (????-????)
泉藤右衛門胤陽の嫡子。義母は守屋新左衛門方重娘。妻は松本氏。通称は内蔵助。隠居してのち大炊、さらに右橘。藩での役職は侍大将、老中。知行は七百石。娘は従弟の小田切伝兵衛安栄に嫁いでいる(『衆臣家譜』巻十四 小田切氏)。弟の玉井百五良は泉家庶流大内家に養嗣子として入り、大内孫右衛門長孟を称している(『衆臣家譜』巻五 大内氏)。
花井信以
(七郎太夫)
∥―――――+―相馬胤武
泉胤寧―――――娘 |(将監)
(内蔵助) |
+―花井信興――――花井信因―――花井信祥
(七郎太夫) (七郎太夫) (七郎太夫)
∥
+―娘
|
|
小田切安旨―+=小田切安敦===小田切安通―+―小田切安英
(伝兵衛) |(藤右衛門) (藤右衛門) |(八十次郎)
| |
+―娘 +―小田切安栄
| ∥ (伝兵衛)
| ∥ ∥
| 泉胤陽―――+―泉胤富―――――娘
|(主殿) |(内蔵助)
| |
+―小田切安通 +―大内長孟
(藤右衛門) (孫右衛門)
嘉永3(1850)年3月20日、巴陵院二百回忌と田中院様二百五十回忌の法要が同慶寺にて行われ、「泉内蔵助」が大根を霊前に捧げている。
明治元(1868)年の戊辰戦争では奥羽越列藩同盟瓦解ののち、9月28日、藩主・相馬因幡守秊胤の名代として大浦庄右衛門栄清・佐藤勘兵衛俊信と連署で、上杉家の竹俣美作久綱・千坂太郎左衛門高雅・毛利上総業広へ書状を遣わしている(『米沢藩戊辰文書』)。
―泉氏略系図―
+―信政―――――熊川長盈
|(助右衛門) (勘解由)
|
→相馬胤村-泉胤顕――胤盛―――胤康……胤平…胤定===胤秋――胤政 +―胤衡====胤祐――+―胤和―――――+
(孫五郎)(彦三郎)(小次郎)(五郎) (左衛門)(大膳)(藤右衛門)|(内蔵助) (内蔵助) |
∥ ∥ | ∥ |
∥ ∥――+―娘 +―娘 |
四本松定義――尚義―+―娘 岡田直胤娘 ∥ | |
(修理亮) (大蔵)| ∥ | |
| ∥ +――娘 |
+―岩角伊勢守 +―本山豊前守| ∥ |
| | ∥――――胤賢――胤充 |
| | ∥ (将監)(将監)|
+―熊川長春―+ 相馬胤延 |
(左衛門尉) (将監) |
|
+――――――――――――――――――――――――――――――――――――+
|
+―胤秀――+―胤寧――+=胤殊=====娘
(左衛門)|(内蔵助)|(内蔵助) ∥
| | ∥
+―胤殊 +―娘 泉胤傳――…胤富
(内蔵助) (胤殊養女)(内蔵助) (内蔵助)