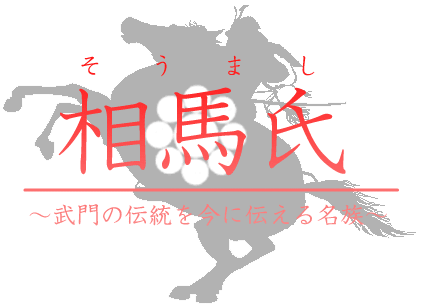
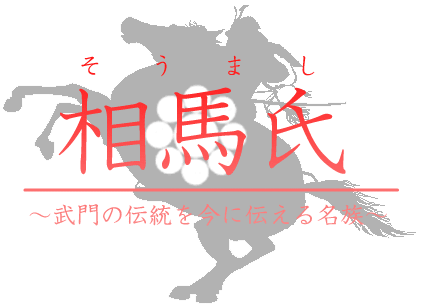
●陸奥国中村藩六万石●
| 代数 | 名前 | 生没年 | 就任期間 | 官位 | 官職 | 父 | 母 |
| 初代 | 相馬利胤 | 1580-1625 | 1602-1625 | 従四位下 | 大膳大夫 | 相馬義胤 | 三分一所義景娘 |
| 2代 | 相馬義胤 | 1619-1651 | 1625-1651 | 従五位下 | 大膳亮 | 相馬利胤 | 徳川秀忠養女(長松院殿) |
| 3代 | 相馬忠胤 | 1637-1673 | 1652-1673 | 従五位下 | 長門守 | 土屋利直 | 中東大膳亮娘 |
| 4代 | 相馬貞胤 | 1659-1679 | 1673-1679 | 従五位下 | 出羽守 | 相馬忠胤 | 相馬義胤娘 |
| 5代 | 相馬昌胤 | 1665-1701 | 1679-1701 | 従五位下 | 弾正少弼 | 相馬忠胤 | 相馬義胤娘 |
| 6代 | 相馬敍胤 | 1677-1711 | 1701-1709 | 従五位下 | 長門守 | 佐竹義処 | 松平直政娘 |
| 7代 | 相馬尊胤 | 1697-1772 | 1709-1765 | 従五位下 | 弾正少弼 | 相馬昌胤 | 本多康慶娘 |
| ―― | 相馬徳胤 | 1702-1752 | ―――― | 従五位下 | 因幡守 | 相馬敍胤 | 相馬昌胤娘 |
| 8代 | 相馬恕胤 | 1734-1791 | 1765-1783 | 従五位下 | 因幡守 | 相馬徳胤 | 不明 |
| ―― | 相馬齋胤 | 1762-1785 | ―――― | ―――― | ―――― | 相馬恕胤 | 不明 |
| 9代 | 相馬祥胤 | 1765-1816 | 1783-1801 | 従五位下 | 因幡守 | 相馬恕胤 | 神戸氏 |
| 10代 | 相馬樹胤 | 1781-1839 | 1801-1813 | 従五位下 | 豊前守 | 相馬祥胤 | 松平忠告娘 |
| 11代 | 相馬益胤 | 1796-1845 | 1813-1835 | 従五位下 | 長門守 | 相馬祥胤 | 松平忠告娘 |
| 12代 | 相馬充胤 | 1819-1887 | 1835-1865 | 従五位下 | 大膳亮 | 相馬益胤 | 松平頼慎娘 |
| 13代 | 相馬誠胤 | 1852-1892 | 1865-1871 | 従五位下 | 因幡守 | 相馬充胤 | 大貫氏(千代) |
■中村藩世子
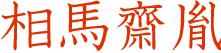 (1762-1785)
(1762-1785)
| <名前> | 齋胤 |
| <通称> | 俊次郎→伊織 |
| <正室> | ―――――― |
| <父> | 相馬因幡守恕胤 |
| <母> | 青山大膳亮幸秀娘(誠心院殿) |
| <官位> | ――――――― |
| <官職> | ――――――― |
| <就任> | ――――――― |
| <法名> | 洞龍院殿雲外恭眠大居士 |
●相馬齋胤事歴●
八代藩主・相馬因幡守恕胤の嫡子。通称は伊織。「齋胤」は「トキタネ」と読む。
 |
| 中村城 |
宝暦12(1762)年9月、相馬因幡守恕胤の三男として中村に誕生した。幼名は伊織。姉の喜代姫は宝暦10(1760)年4月に、8月には兄の式部信胤が誕生している。
明和3(1766)年1月22日、「俊次郎」の名はよろしからずとの指摘があったため、「伊織」と改名された。そして明和4(1767)年3月、兄の式部信胤が嫡子として父・相馬尊胤とともに江戸へ出立。同じく伊織の「丈夫届」が認められて、幕府に提出されている。
しかし、明和4(1767)年12月10日、江戸において兄の相馬式部信胤が亡くなったため、明和6(1769)年6月22日、次男の伊織が嫡男と定められ、実名は「齋胤」とされた。8月27日、齋胤は嫡子と定められたため、江戸常府が決定。同じく恕胤は庶子の吉次郎、栄次郎の丈夫届けを幕府に提出した。9月14日、齋胤は出立前に父・恕胤と対面し、嫡子としての心得を受けると、19日に中村を発し、28日桜田屋敷に到着。祖父の老公・相馬弾正少弼尊胤と対面した。
●上府の道程(「明和六年相馬伊織様御昼休御用扣」『いわき市史』第二巻所収)
| 9月19日 | 中村 | 出立 |
| 原町宿 | 昼食 | |
| 高野宿 | 宿泊 | |
| 9月20日 | 高野宿 | 出立 |
| 熊川宿 | 昼食 | |
| 四倉宿 | 宿泊 | |
| 9月21日 | 四倉宿 | 出立 |
| 湯本宿 | 昼食 | |
| 神岡宿 | 宿泊 | |
| 9月22日 | 神岡宿 | 出立 |
| 助川宿 | 昼食 | |
| 石神宿 | 宿泊 | |
| 9月23日 | 石神宿 | 出立 |
| 長岡宿 | 昼食 | |
| 片倉宿 | 宿泊 | |
| 9月24日 | 片倉宿 | 出立 |
| 中村宿 | 昼食 | |
| 牛久宿 | 宿泊 | |
| 9月25日 | 牛久宿 | 出立 |
| 取手宿 | 昼食 | |
| 松戸宿 | 宿泊 | |
| 9月26日 | 松戸宿 | 出立 |
| 江戸 | 到着 |
明和9(1772)年9月4日、恕胤は齋胤を嫡子とする届けを幕府に提出。10月23日には御目見の願書を提出した。そして11月1日、願いの通り御目見えが許され、恕胤は齋胤を伴って江戸城に登城。将軍・徳川家治に謁見した。
しかしこの直後、齋胤は大病にかかり、恕胤は急遽齋胤を廃して、妾腹の子・吉次郎を嫡子とすることを決めた。この当時、後継者がないままに大名が亡くなると、その家は取り潰しと定められており、恕胤も苦渋の決断であったと思われる。
安永2(1773)年3月25日、恕胤は正式に齋胤を廃嫡とし、4月13日、幕府に齋胤は病気のために嫡子を退く旨を報告。22日、妾腹の吉次郎を新たに嫡子と定めた願書を幕府に提出した。
こうして嫡子を退くことになった齋胤は9月に江戸を発って中村へ向かった。9月11日、斎胤は守谷宿に止宿しており、守谷村に人馬差出の指示が出されている(ただ、守谷村役が朝五ツと夜五ツを誤り用意ができなかった)(安永二年九月十二日『守谷村人馬差出違につき詫書』)。このとき斎胤が海禅寺に使者を遣わしたかは不明。
中村に着すると、中村城下の西山に屋敷を建てて隠居生活を送ることとなるが、前嫡子として重んじられた。
安永5(1776)年、嫡男・哲之助が誕生したが、3月15日、亡くなった。法名は曹源院殿洞水一滴大童子。安永6(1777)年3月15日には次男の健次郎(内記)が亡くなった。法名は紫雲院殿玉英智瓈大童子。さらに同年12月18日、三男・俊太郎が亡くなった。法名は洞林院殿丹山玉鳳大童子。
そして安永8(1779)年4月23日、末子の鍋五郎が誕生した。鍋五郎は即日、泉内蔵助胤傳の養嗣子と定められた。実際に泉家に移ったのは天明3(1783)年7月25日であり、泉家へ養子に入った。その後は、旗本・天野傳兵衛家に養子に入り、天野富敷と称した(天野富敷事歴)。
天明5(1785)年10月29日、亡くなった。一説には天明6(1786)年7月28日とも。寶月山東泉院に葬られた。法名は洞龍院殿雲外恭眠大居士。
相馬恕胤―+―喜代姫 +―哲之助
(因幡守) | |
| |
+―相馬信胤 +―健次郎
|(式部) |
| |
+―相馬齋胤――+―俊太郎
|(伊織) |
| |
+―福姫 +―本五郎
| |
| |
| +―相馬彬胤
| 【天野富敷】
|
+―相馬祥胤――+―相馬樹胤
|(吉次郎) |(讃岐守)
| |
+―相馬栄次郎 +―光姫
| |
| |
+―栄姫 +―久姫
| |
| |
+―堀内鶴之助 +―相馬仙胤
| |(縫殿)
| |
+―國姫 +―順姫
| |(伊東祐氏妻)
| |
+―堀内明之進 +―笣姫
| |
| |
+―相馬因胤 +―信姫
|(暢次郎) |
| |
+―齢姫 +―盈姫
|(中西為次郎妻)
|
+―季姫
|(大久保甚十郎妻)
|
+―相馬益胤
|(長門守)
|
+―都姫
|
|
+―相馬永胤
|(彭之助)
|
+―律姫
|
|
+―相馬乗之助
トップページ > 中村藩主相馬家 > 相馬藩主一族 > 天野富敷
天野富敷(1779-????)
父は相馬伊織齋胤。母は某氏。妻は姪の光姫(叔父・相馬祥胤の娘)、のち岡田監物恩胤養女・於久。通称は鍋五郎、左近。諱は肥胤、彬胤。はじめ御一家泉家を継ぎ、次いで旗本の大島家、天野家の養嗣子となる。
安永8(1779)年4月23日、中村に誕生し、即日、御一家の泉内蔵助胤傳の養嗣子と定められた。7月25日、泉家へ引き移るが、故あって寛政4(1792)年閏2月21日、実家の相馬藩公家へ戻った。これは将軍家旗本・大島家への養子縁組の話が持ち上がったためと思われる。
なお、泉家には、御一家・相馬左衛門胤豊の三男・太田早馬が「泉典膳」と称して入ることとなり、泉典膳は「胤陽」と称し、12月20日に正式に泉家の養嗣子として泉家に引き移っている。
寛政5(1793)年5月11日、鍋五郎は御一家・相馬外記胤慈を因親として具足初の儀を執り行い、藩公・相馬樹胤より「胤」の一字を賜り「肥胤」と称した。
9月16日、大島雲八義和の婿養子となる縁談がまとまり、寛政6(1794)年12月23日、大島家へ婿養子届けが幕府に提出され、翌寛政7(1795)年3月2日、養子届が正式に受理、6月26日、藩公・相馬樹胤より備前友成の太刀を下賜され、29日、中村を発って江戸へ向かった。
しかし、寛政8(1796)年11月3日、故あって大島家を辞して相馬家へ戻った。理由については、鍋五郎も義父の大島義和もともに親しむ様子がなかったとされている。相馬家へ戻った鍋五郎は11月15日、本山勘兵衛安義を因親として前髪執の儀を行い、12月7日、御一家・岡田監物恩胤の養女・於久との婚約がなされた。
12月26日、於久との婚姻が整い、1月8日、婚礼の儀が執り行われた。於久との間にはすぐ子供ができたが、8月17日、惜しくも死産となった。
享和元(1801)年12月、御内分の扶持として一千石が与えられ、文化4(1805)年9月、「彬胤(ともたね)」と改名した。すでに二十七歳であり、このまま部屋住みの公子で終わるかにみえたが、文化6(1809)年9月、再び旗本・天野伝兵衛富貞の養嗣子の縁談が持ち上がった。富貞は当時四十七歳。大御番五番士であった。
翌文化7(1810)年5月15日、麻布飯倉の天野家(七百五十石)に入嗣して名を天野鍋五郎富敷と改め、11月25日、天野家の家督を相続した。そして、文化9(1812)年6月、娘の於鋭(トシ)が誕生した。
文化15(1818)年1月3日、富敷は「左近」と改名。2月15日、娘の於千代(於幸改め)も天野家へ引き移った。その後、於千代に縁談が持ち上がったことにより、5月12日、大殿・豊前守樹胤の妾腹の子(養女)となり、文政2(1819)年11月、於千代は旗本・三枝尚吉郎が婚約が調ったが破談となってしまった。文政11(1828)年11月18日、ふたたび旗本・井上左大夫正路との縁談が調ったため、今度は藩主・長門守益胤の養妹として12月18日に嫁いだ。
文化15(1818)年12月22日、中村藩主・相馬益胤は、朝五ツ時(午前八時頃)、富敷とともに遠乗りに出かけている。富敷は三つ年上の従兄・益胤と交流を続けていた様子がうかがえる。
富敷には男子がなかったため、備中国岡田藩主・伊東播磨守長寛の九男・辰之助長善を養嗣子に迎え、辰之助は天野伝四郎富之を称した。富之は小普請組丹羽五左衛門支配の小普請組士だった。
富之の子は天野帯刀と称し、天保12(1841)年生まれの子・天野民之丞は屋敷が小石川柳町裏通となっており、麻布から移ったのだろう。
神戸氏 松平忠告――――久美姫
(月巣院) (遠江守) ∥―――――――相馬益胤―――――相馬充胤―――相馬誠胤
∥ ∥ (長門守) (大膳亮) (因幡守)
∥ ∥
∥―――――――――――――相馬祥胤 +―相馬仙胤―――――小栗政寧
∥ (因幡守) |(縫殿) (下総守)
∥ ∥ |
相馬恕胤 ∥―――――+―光姫
(因幡守) ∥ ∥
∥ 近藤氏 ∥
∥ (櫻蕚院) ∥
∥ ∥
∥―――――――――――――相馬斎胤 ∥
∥ (伊織) ∥
青山幸秀――娘 ∥―――――――天野富敷=====天野富之―――天野帯刀―――天野民之丞
(大膳亮) (誠心院殿) ∥ (左近) (伝四郎)
某氏 ↑
|
【備中岡田藩主】 |
伊東長寛―――――伊東長善
(播磨守) (辰之助)