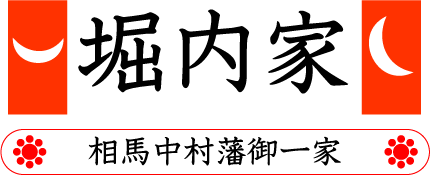
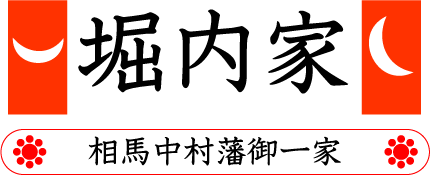
堀内家とは
中村藩御一家の一。堀内家は他の御一家とは異なり、その祖が相馬一門ではなく、下総からともに移り住んできた家と伝えられている。『衆臣家譜』によれば、千葉介常重の子(豊島康家の子・豊島清元子)・堀内五郎忠清の末裔とされ、江戸時代、堀内庶家は豊島を称した。
一説には建武年中に小高城で討死した惣領代・相馬弥次郎光胤の子、相馬胤成とも言われているが、光胤は元服まもなく討死していることから、光胤に子供がいたとは思われず、この説は伝承と思われる。
室町時代後期の相馬隆胤の代、岡田氏、泉氏、大井氏、東氏に継ぐ家格を有していたと思われる。その後、相馬惣領家より養嗣子が入ることにより惣領家との血縁関係が濃厚となり、中村藩御一家の一となったのだろう。
子孫は本家と覚左衛門家に分かれ、両家とも中村藩で重きをなして幕末にいたった。
■中村藩御一家■
●堀内家系図(『衆臣家譜』より)
相馬高胤――+―相馬盛胤―+
(治部少輔) |(大膳大夫)|
| |
+―乙姫 |
∥ |
∥ |
豊島康家――堀内忠清―…―堀内常清―…?…―堀内胤吉――…―堀内胤直 |
(三郎) (五郎) (掃部頭) (左衛門次郎) (勘解由) |
|
+―――――――――――――――――――――――――――――――――――+
|
| +―掛田俊宗 +―黒木宗俊
| |(六郎) |(肥前)
| | |
| +―藤田晴近――+―堀内晴胤
| |(七郎) |(四郎)
| | |
| +―娘 +―延命
| |(大越利顕妻)|(堀内胤政妻)
| | |
| +―堀内義氏 +―藤田胤晴
| |(兵庫) (七郎)
| |
| 掛田義宗―+―娘 +―相馬義胤―――相馬利胤―――…【相馬中村藩主】
|(右京太夫) (金室妙仲) |(長門守) (大膳大夫)
| ∥ |
| ∥―――――+―相馬隆胤
| ∥ |(兵部大輔)
| ∥ |
+―相馬顕胤―――相馬盛胤 +―娘――――――亘理重宗―――…【涌谷伊達家】
|(讃岐守) (弾正大弼) (亘理重宗母)(美濃守)
|
+―堀内近胤―――堀内俊胤――+―娘
(上野介) (右兵衛尉) | ∥――――――娘
| ∥ (佐藤越後妻)
+=堀内義氏
|(兵庫)
|
+=堀内晴胤
|(四郎)
|
+=堀内胤政―+―堀内胤泰――堀内胤貞――堀内胤重―――+
(播磨) |(十兵衛) (十兵衛) (十兵衛) |
| |
+―堀内胤長―…【堀内覚左衛門家】 |
(半右衛門) |
|
+――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――+
|
+―堀内辰胤――堀内胤近==堀内胤重==堀内胤長==堀内脩胤==堀内胤陸――堀内胤久――堀内胤寧――堀内胤賢
(玄蕃) (大蔵) (十兵衛) (十兵衛) (玄蕃) (十兵衛) (十兵衛) (大蔵) (大蔵)
堀内忠清(????-????)
相馬堀内家の祖とされている人物。通称は五郎。
千葉介常重の六男・堀内五郎忠清とされるが、豊島康家の子・豊島清元の三男とも伝わる(『衆臣家譜』)。子孫の庶子は「秩父」「豊島」を称していることから、堀内家においては豊島氏の末裔と伝えられていたのだろう。堀内家の幕紋は「三綱柏」も用いており、豊島氏同族の葛西氏の紋・三柏紋と通じている。
堀内常清(????-????)
堀内家当主。通称は掃部頭。祖父は堀内義清、父は堀内播磨守とされる。または、実は相馬某の次男で、相馬善次郎を称したともいう。
堀内五郎忠清の後孫で、相馬孫五郎重胤に随って下総国から陸奥国行方郡小高村(南相馬市小高区小高)に移り住み、その地を堀内(南相馬市小高区堀内)と称した。
堀内胤吉(????-????)
堀内家当主。通称は左衛門次郎。
相馬隆胤の代に仕えた「一族郎従」として、「岡田盛胤、同伊予守信胤、泉左京亮胤平、大井上総介胤信、東左近衛胤安、堀内左衛門次郎胤吉」が見える(『相馬氏家譜』:相馬市史)。岡田盛胤、信胤の記述があるところから見て『相馬岡田文書』が編纂された近世成立の記録とみられ、多分に伝承が含まれているが、岡田氏、泉氏、大井氏、東氏、堀内氏が一族庶家だったのだろう。大井氏は当主の相次ぐ早世により江戸初期に落魄、東氏は『衆臣家譜』にも記述がみられず不明。岡田氏、泉氏、堀内氏は江戸期においても中村藩御一家として重きをなした。
堀内胤直(????-????)
堀内掃部頭常清の孫とされるが、時代的に合わない。通称は勘解由。妻は相馬治部少輔高胤娘・乙姫。相馬大膳大夫盛胤の妹にあたる。
胤直には跡を継ぐ男子がなく、相馬大膳大夫盛胤の次男・相馬次郎太夫近胤が堀内家の名跡を継承した。
堀内近胤(????-????)
相馬大膳大夫盛胤の次男。通称は次郎太夫、上野介。
目立った活躍はなかったようである。没年齢不詳。
堀内俊胤(????-1569)
堀内上野介近胤の次男。通称は右兵衛尉、左衛門太夫。
永禄12(1569)年正月、伊達家との合戦で討死を遂げ、堀内家は断絶した。この断絶を惜しんだ相馬弾正大弼盛胤は自分の義弟に当たる掛田兵庫義氏に俊胤の娘を嫁がせて堀内家を再興させた。
堀内胤直 堀内大膳―――泉胤政
(勘解由) ∥ (藤右衛門)
∥ ∥
+―乙 +―堀内近胤――――+―堀内俊胤――+―女子
| |(上野介) |(左衛門太夫)| ∥
| | | | ∥
相馬高胤―+―相馬盛胤―+――――相馬顕胤 +=堀内宗和 | 堀内義氏
(治部少輔) (大膳大夫)| (讃岐守) (四郎) |(兵庫)
| ∥ |
| ∥ +=堀内胤政
| ∥ (播磨守)
| ∥
| ∥――――――――――――――相馬盛胤 +―相馬義胤
伊達持宗――伊達成宗――伊達尚宗―+―伊達稙宗――――+―娘 (弾正大弼)|(長門守)
(大膳大夫)(大膳大夫)(大膳大夫)|(左京大夫)| | ∥ |
| | +―伊達晴宗―――伊達輝宗 ∥――――+―相馬隆胤
| | |(左京大夫) (左京大夫) ∥ |(兵部大輔)
| | | ∥ |
| | | ∥ +―女子
| | | ∥ (真如院殿)
| | | ∥ ∥
| | | ∥ ∥
| | +―亘理元宗――――――――――――――――――亘理重宗
| | |(兵庫頭) ∥ (美濃守)
| | | ∥
| | +―女子 ∥
| | ∥ ∥
| | ∥ ∥
+―掛田義宗――――+―掛田俊宗 ∥
(兵庫頭) | |(兵庫頭) ∥
| | ∥
| +――――――――――――――――女子
| | (金室妙仲)
| |
| +―堀内義氏 岡田重胤
| |(兵庫) (八兵衛)
| | ∥
| +―女子 江井無道―――――――女子 +―女子
| | ∥ ∥ |(光室涼清)
| | ∥ ∥ |
| | ∥ ∥――――――藤田胤近―+―藤田安宗
| | ∥ ∥ (佐左衛門)|(土佐)
| | ∥ ∥ | ∥
| | 大越利顕 +―藤田胤晴 | 泉田胤隆女子
| |(摂津守) |(七郎) |
| | | |
| +―――――藤田晴近 +―黒木宗俊 +―藤田近次
| (七郎) |(肥前) |(卯右衛門)
| ∥ | |
| ∥――――――――+―堀内宗和 +―女子
| ∥ |(四郎) (延命)
| ∥ |
+―相馬胤乗―+―女子 +―女子
(三郎) | (延命、御東)
| ∥
+=黒木宗俊 ∥――――――堀内胤泰
(肥前) ∥ (十兵衛)
∥
泉田胤清―――――――堀内胤政
(右近太夫) (播磨守)
堀内義氏(????-????)
伊達家の一族・掛田兵庫頭義宗の三男。通称は兵庫。名は業宗とも(『衆臣家譜』藤田氏)。妻は堀内右兵衛尉俊胤娘。没年齢不詳。惣領の相馬弾正大弼盛胤とは義兄弟にあたる。
永禄12(1569)年正月、堀内右兵衛尉俊胤が討死を遂げたため、娘婿だった義氏が堀内家を相続した。しかし義氏と堀内俊胤娘はいさかいが絶えず、義氏は堀内家を出奔して宇多郡柏崎村(程田村とも)に移り住み、柏崎山常林寺(兄・藤田晴近の墓所)の東に葬られた。
娘一人は佐藤越後に嫁したともいう(『衆臣家譜』藤田氏)。
堀内大膳(????-1587)
三春城主・田村一族の中津川氏出身。後名は泉大膳胤秋。妻は堀内右兵衛尉俊胤娘(出奔した堀内兵庫義氏の妻)。のち、仙道小浜城主・岩角畠山伊勢守尚義(四本松式部大輔久義)の娘を娶った。
大膳は堀内家の家督を継承したが、先代義氏と同じく妻の堀内氏と相性があわず、大膳もまた堀内家を出奔した。子の胤政が泉家の後嗣となったため、大膳はその後見人となって泉大膳胤秋を称している。
天正13(1585)年に最上義光が相馬義胤臣の「伊泉大膳亮」へ宛てた書状が残っているが(『最上義光歴史館収蔵品図録』より:「福島県立博物館紀要17号」所収)、この「伊泉大膳亮」が胤秋であるとされており、このころには泉家の後見人となっていたと思われる。
天正15(1587)年4月16日に亡くなった。法名は東泉院桂岩昌公大禅定門。
堀内晴胤(????-1633)
父は掛田伊達一族の藤田七郎晴近入道齊庵。母は相馬三郎胤乗入道相三女子。通称は四郎。初名は宗和。堀内家を継いで「胤」字を賜り「晴胤」と改めた。
母方の祖父・相馬三郎胤乗入道は惣領相馬盛胤の叔父に当たり、晴胤は父方・母方ともに相馬家の近親である。一方で父方掛田氏は伊達家庶流で、父晴近は伊達左京大夫晴宗の従兄弟となる。こうしたことから、伊達家からの調略の手が延びたのだろう。要衝黒木城(相馬市黒木西舘)を守る兄・黒木中務宗俊とともに伊達家への寝返りを画策した。
+―伊達晴宗―――伊達輝宗―――――伊達政宗
|(左京大夫) (左京大夫) (権中納言)
|
相馬盛胤―+――相馬顕胤
(大膳大夫)| |(弾正大弼)
| | ∥――――――相馬盛胤
| | ∥ (弾正大弼)
+―伊達稙宗―――+―女子 ∥――――――――相馬義胤
|(左京大夫)| ∥ (長門守)
| | ∥
+―掛田義宗―――+――――――――女子
(兵庫頭) | | (金室妙仲)
| |
| +――――――――藤田晴近
| (七郎)
| ∥――――――+―黒木宗俊
| ∥ |(中務)
| ∥ |
+―相馬胤乗―――――女子 +―堀内晴胤=========養女
(三郎) |(四郎) ↑
| ↑
+―藤田胤晴――藤田胤近―+―延命
(七郎) (佐左衛門)|
|
+―藤田安宗
|(佐左衛門)
|
+―藤田近次
|(卯右衛門)
|
+―女子
∥
岡田重胤
(八兵衛)
天正8(1580)年8月18日、晴胤の兄・黒木中務宗俊は、父の馬場野城主・藤田七郎晴近に寝返り計画を告げて共に挙兵するよう説得したが、晴近はこれに激怒。宗俊を捕らえて自害させようとするも、宗俊は遁走して黒木城へ戻った。
直後、晴近は黒木宗俊・堀内晴胤の両息を追捕すべく、両名の計画を早馬で小高城の新惣領相馬義胤に報告した。この報告を受けた義胤は隠居の相馬弾正大弼盛胤にも出陣を求めて黒木城を急襲。その陥落間際に建昌寺の住持が陣中を訪れ、「愁訴于両公」して両者の助命を願い出た(『衆臣家譜』藤田氏)。盛胤・義胤は「故所念晴近忠義、被宥免兄弟之死」と、彼ら兄弟を赦し、追放処分となった。
追放された黒木宗俊、堀内晴胤兄弟は伊達輝宗の許へ走り、黒木宗俊は丸森城代となって子孫は仙台藩一家に列せられた。堀内晴胤もまた伊達家に仕えて藤田但馬と改め、子孫は仙台藩士となる。のちの仙台藩寛文騒動で活躍した伊達安芸宗重は黒木宗俊の孫にあたり、宗重は父方・母方ともに相馬家の血を濃くひいている。ただ、仙台へ遁れた晴胤(藤田但馬宗和と改める)と中村藩藤田家の間には交流が続いており、子のいなかった宗和に姪の延命が養女に入っている(ただし、延命は早世する)。
藤田七郎晴近の末子・七郎胤晴が藤田家を継承するが、天正17(1589)年6月18日の伊達家との「行方郡飯土井陳之時討死」した。享年二十。法名は葉玉荷公。飯樋中平に葬られた(『衆臣家譜』藤田氏)。このとき、妻の江井無道女は懐妊しており、胤晴の死後に誕生し、藤田家を継承した。のちの中村藩家老の藤田佐左衛門胤近で、義胤、忠胤両代に仕え、江戸留守居役を務めた。藤田家は江戸期を通じて御一家に準じ、御一家岡田氏、泉田氏、堀内氏らの親族となっている。
+―岡田長次―――岡田長胤
|(左門) (監物)
|
岡田宣胤――+―岡田重胤
(八兵衛) (八兵衛)
藤田晴近――藤田胤晴 ∥
(七郎) (七郎) ∥
∥――――――藤田胤近――――女子
∥ (佐左衛門)
∥ ∥
∥ ∥ 泉田胤隆――女子
∥ ∥(掃部) ∥――――――藤田直宗
∥ ∥ ∥ (佐左衛門)
江井無道――女子 ∥―――――+―藤田安宗
∥ |(佐左衛門)
∥ |
成田大炊助――女子 +―藤田近次
|
|
+―延命
(仙台藩藤田但馬養女)
相馬家の記録によれば、黒木中務宗俊兄弟が謀反を起こしたのは、天正8(1580)年8月18日の事とされ、これは黒木兄弟の末弟・藤田七郎胤晴の子孫・中村藩士藤田家に伝わった系譜(『衆臣家譜』藤田氏)においても同様である。
一方、仙台伊達家の記録(『御知行被下置御帳』)によれば、「黒木中務宗元」は「天正十四年相馬より御当地へ罷越」たとあり、天正14(1586)年9月23日、伊達政宗より伊具郡丸森村に知行地を給わったとされる。「黒木中務宗俊(『衆臣家譜』)」と「黒木中務宗元(『御知行被下置御帳』)」の諱の違いは不明だが、別の伊達家の記録(『性山公治家記録』)では天正4(1576)年、「相馬領宇多郡黒木城主藤田七郎晴親嫡子中務宗元、次男四郎宗和、当家へ召出サル」とあり、黒木宗俊と黒木宗元は同一人物とわかる。
ここで、黒木宗俊(宗元)の謀反の時期が三通り生じている。
・天正8(1580)年…『衆臣家譜』(相馬家資料)
・天正4(1576)年…『性山公治家記録』(伊達家資料)
・天正14(1586)年…『御知行被下置御帳』(伊達家資料)
天正14(1586)年ではすでに次代・堀内胤政が伊達家との戦いに参戦しており、天正4(1576)年、または天正8(1580)年のどちらかであろう。
堀内胤政(????-????)
堀内家当主。父は泉田右近胤清入道雪斎。母は不明。妻は相馬長門守義胤養女(藤田七郎晴近入道齊庵末娘・延命)。官途名は播磨守。
●堀内胤政周辺系図
相馬胤乗――娘
(三郎) ∥――――+―黒木宗俊――…【仙台藩御一家黒木家】
∥ |(中務)
∥ |
掛田義宗――藤田晴近 +―堀内晴胤――…【仙台藩藤田家】
(右京大夫)(七郎) |(四郎)
|
+―妹
∥―――――+―堀内胤泰――…【御一家堀内家】
∥ |(十兵衛)
∥ |
泉田胤清―――堀内胤政 +―堀内胤長――…【堀内覚左衛門家】
(右近) (播磨守) (半右衛門)
天正8(1580)年8月、堀内四郎晴胤が謀反して相馬領から追放されたため、堀内家は断絶した。相馬義胤は一門堀内家の断絶を惜しみ、堀内晴胤の妹・延命を養女とし、泉田雪斎入道の次男と娶わせて堀内家の名跡を継がせ、伊達家との戦略拠点である宇多郡丸森城主とした。延命は義胤女子として堀内家に入ったため「御東方」と尊称されている。このとき胤政はまだ若かったため、実父・泉田雪斎入道が胤政の後見人として丸森城に入った。
胤政が堀内家を相続した翌年の天正9(1581)年4月、相馬家重臣で丸森城の近く小狭井城主の佐藤宮内為信が突如寝返って丸森城・金山城に攻めてきたとき、胤政は金山城の佐藤将監清信とともに伊達勢を撃退している。両佐藤家はともに岩城家に仕えていた家柄であるが、血縁関係は不明。
堀内胤泰(????-1633)
堀内播磨守胤政の嫡男。母は相馬長門守義胤養女(藤田七郎晴近入道齊庵末娘・延命)。通称は十兵衛。藩主・相馬大膳大夫利胤の義甥にあたる。
慶長7(1602)年の相馬家大倉退去のとき、他の藩士達と同様に所領を収公された。そして、元和3(1617)年に改めて五百五十七石を与えられ、寛永年中には加増により七百五石取りとなった。弟・堀内半右衛門胤長は四百四十五石を領している。
寛永10(1633)年5月1日、亡くなった。没年齢不詳。
堀内胤貞(????-1646)
堀内十兵衛胤泰の嫡子。妻は大越右近正光娘。初名は善次郎。通称は十兵衛。妻の実家・大越家は三春田村家の一族で、天正14(1586)年の田村家内紛に敗れて相馬家に属した家柄。堀内家とは掛田伊達家を通じた一門でもある。
大越常光―――大越利顕
(山城守) (摂津守)
∥
∥――――――大越正光―+―大越正光―――大越広光―――大越往光――大越暢光―+―大越経光
+―娘 (右近) |(越中) (四郎兵衛) (甚左衛門)(弥右衛門)|(四郎兵衛)
| | |
| +――――――――娘 +―泉胤伝
+―藤田晴近―+―延命 ∥――――――堀内胤重 (内蔵助)
|(七郎) | ∥――――――堀内胤泰―――堀内胤貞 (十兵衛)
| | ∥ (十兵衛) (十兵衛)
掛田義宗―+―娘 +=堀内胤政
(右京太夫) (金室妙仲) (播磨)
∥
∥――――――相馬義胤―――相馬利胤――…【相馬中村藩主】
∥ (長門守) (大膳大夫)
相馬顕胤―――相馬盛胤
(讃岐守) (弾正大弼)
胤貞は寛永11(1634)年4月18日、江戸へはじめて上府し、中村藩邸の相馬大膳亮義胤に謁見し、太刀と馬代を献じた。
寛永18(1641)年に改易されて牛越村に移り、正保3(1646)年に没した。
娘は一門・堀内覚左衛門胤益の妻となった。
堀内胤政
(播磨守)
∥―――――+―堀内胤泰―――堀内胤貞―+=======堀内胤重
∥ |(十兵衛) (十兵衛) | (十兵衛)
∥ | | ∥
∥ | +―女子 ∥
∥ | ∥――――――――――――堀内胤信―――堀内胤総
∥ | ∥ ∥ (覚左衛門) (十兵衛)
藤田晴近――延命 +―堀内胤長―――堀内胤興―+―堀内胤益 ∥
(七郎) (義胤養女) (半右衛門) (半右衛門)|(覚左衛門) ∥
| ∥
+―――――――女子
堀内胤重(1641-????)
堀内十兵衛胤貞の養嗣子。実父は仙台藩士・志賀六郎か(『寛文七年未閏二月ゟ日記写』)。妻は堀内半右衛門胤興三女、のち石川助左衛門直昌娘(前夫は稲葉吉之進重成)。初名は金次郎。通称は十兵衛、越中。
明暦3(1657)年正月、堀内家の本知七百二十五石を元のように与えられ、家督を継いだ。このとき胤重十七歳。以前の家格である「御一家」にも列せられ、堀内十兵衛を称した。
父の胤貞が、6歳の金次郎が扶持米を給わって馬場野村に住んだ。一族の堀内半右衛門胤興は5月、明暦2(1656)年4月に亡くなった泉縫殿助成信に代わって老中職に任じられた。7月19日、胤興は侍大将に任じられているが、これまで三組と決められていた組分が、岡田監物長胤、熊川左衛門長定、岡部五郎左衛門通綱、堀内半右衛門胤興の四人の侍大将が率いる四組に再編成された。
寛文7(1667)年正月24日、妻の堀内半右衛門胤興三女が亡くなった。法名は大悲院円室廣通(『衆臣家譜』堀内覚左衛門)。
延宝元(1673)年12月23日、相馬虎千代貞胤が亡父・相馬長門守忠胤の跡を継いで、麻布屋敷の表御座敷へ移り住んだとき、御相伴として、同じく御一家の岡田與左衛門伊胤とともに名を連ねる。そして12月25日、貞胤は登城の上、幕命として大老・酒井雅楽頭忠清より正式に家督相続が認められた。翌26日、貞胤は岡田與左衛門伊胤、堀内十兵衛胤重、富田将監正実を引きつれて将軍・徳川家綱に拝謁した。
延宝3(1675)年12月3日、藩公・相馬出羽守貞胤の守役をつとめていた末永市郎兵衛が故あって改易され、大手門前にあった屋敷も没収となった。その屋敷地は胤重へ与えられ、それまでの常小屋の屋敷は藩へ返還した。
延宝4(1676)年6月11日の藩公・相馬貞胤の婚礼の儀に際しては、6月15日、胤重が国許の惣侍名代として江戸へ出府し、婚礼の祝儀を述べている。延宝6(1678)年正月26日、胤重の義兄弟・堀内覚左衛門胤益が藩士を率いる侍大将を仰せ付けられた。その後、胤益は江戸へ出ていたようであるが、延宝7(1679)年7月20日、病死した。享年三十五。
天和元(1681)年3月27日、昌胤の初めての御国入りに「十兵衛胤重」が随って江戸から中村へ下向している。5月20日の野馬追いでは、胤重が「御本陣御名代」をつとめた。
11月29日、胤重は嫡子・内記胤親に家督を相続して隠居。しかし、貞享3(1686)年閏3月27日夜、「堀内越中事、仙台領へ欠落」ちたため(『寛文七年羊閏二月ゟ日記写』)、これを聞いた胤親は「同人親志か六郎兵ヘ方へ、都郷伊右衛門、大越為五右衛門参、四月四日引返」し(『寛文七年羊閏二月ゟ日記写』)、胤重の身柄を受け取って戻り、「堀内覚左衛門(胤信)、大越次郎兵へ御預ケ被成候」となるが(『寛文七年羊閏二月ゟ日記写』)、胤親自身も「十兵ヘ、親欠落候段、畢竟油断故」に「閉門被仰付」られた。
その後の胤重の動向は不明で没年も不明。
堀内辰胤(1663-1701)
堀内越中胤重の嫡子。母は不明。妻は藤田佐左衛門直宗娘。通称は十兵衛、玄蕃。娘は岡田監物知胤妻。幼名は内記。初名は胤親。侍大将、家老。
藤田晴近―+―堀内晴胤
(七郎) |(四郎)
|
+―延命
| ∥――――+―堀内胤長―――堀内胤興―――堀内胤益
| ∥ |(半右衛門) (半右衛門) (覚左衛門)
| ∥ | ∥――――――堀内胤信―――――――――――――――堀内胤総
| ∥ | +―娘 (覚左衛門) (十兵衛)
| ∥ | | |
| ∥ | | |
| 堀内胤政 +―堀内胤泰―――堀内胤貞―+―堀内胤重―――――――――――堀内辰胤 |
|(播磨) (十兵衛) (十兵衛) (十兵衛) (玄蕃) |
| ∥ ↓
+―藤田胤晴―――藤田胤近―+―娘 ∥――+―堀内胤近==堀内胤総
(七郎) (佐左衛門)|(光室涼清) ∥ |(玄蕃) (十兵衛)
| ∥ ∥ |
| 岡田重胤===岡田長胤―+―岡田信胤 ∥ +―娘
|(八兵衛) (監物) |(小次郎) ∥ | ∥―――――岡田春胤
| | ∥ | ∥ (監物)
+―藤田安宗 +―娘 ∥ | 岡田知胤
(土佐) ∥―――――+―娘 |(監物)
∥ ∥ | |
∥ ∥ | +―娘
∥ ∥ | ∥―――――岡部豊綱
∥ ∥ | ∥ (綱右衛門)
∥ ∥ | ∥
∥ ∥ | 岡部直綱
∥ ∥ | (綱右衛門)
∥ ∥ |
∥―――――――――――――藤田直宗 +―藤田徳宗
泉田胤隆 (佐左衛門) (宇右衛門)
(掃部)
天和元(1681)年11月29日、父・越中胤重の隠居にともない堀内家の家督を相続した(『相馬藩世紀』)。
貞享3(1686)年3月13日、6日に家老職・侍大将を辞した佐藤惣内尚重に代わり、侍大将に任じられ、佐藤惣内跡組支配を命じられた。
しかし、閏3月27日夜、病で療養中であった父・「堀内越中(胤重)事、仙台領へ欠落」ちたため(『寛文七年羊閏二月ゟ日記写』)、これを聞いた胤親は「同人親志か六郎兵ヘ方へ、都郷伊右衛門、大越為五右衛門参、四月四日引返」し(『寛文七年羊閏二月ゟ日記写』)、胤重は「堀内覚左衛門(胤信)、大越次郎兵へ(吉光)御預ケ被成候」となるが(『寛文七年羊閏二月ゟ日記写』)、胤親自身も「十兵ヘ、親欠落候段、畢竟油断故」に「閉門被仰付」られ、組支配も免じられた(『相馬藩世紀』)。
その後7月8日、「堀内十兵へ、閉門御免、組ヲモ本之通御預被成候旨被仰出」られた。さらに、元禄5(1692)年9月に家老職を辞した西與惣左衛門直治に代わり、元禄6(1693)年5月25日、家老職に就任。昌胤より手ずから吉光の太刀一腰と白銀十枚、通称も「玄蕃」と改めるよう命じられた(『相馬藩世紀』)。
元禄6(1693)年6月26日、家老職・御城代職に任じられ、本知七百二十五石に二百七十五石の加増で都合千石となった。もともと御城代職は藩公御一家筆頭・岡田家が任じられるものであったが、6月19日、何らかの不都合があって岡田監物伊胤の職が解かれ、胤親がその重責を担うこととなった。そして7月4日、「御家老御城代職」を勤めているうちは、「御一家惣上座」であるとし、御一家筆頭であった岡田監物家よりも上座につくこととされ、胤親一代に限り、岡田家にのみ許されてきた「胤」字を諱の下に付ける特権を許された。これにより、胤親は「辰胤」と改名する。一方、岡田伊胤には、堀内辰胤が御家老・御城代職に就いている間は、辰胤の次席となる旨を伝えさせている(『相馬藩世紀』)。
元禄8(1695)年5月6日、坪田村(相馬市坪田)の八幡宮遷宮式が執り行われ、御一家・重臣が石灯籠を寄進しているが、左右の石塔の筆頭に「老臣御城代御一家 堀内玄蕃辰胤」と見える。
元禄9(1696)年7月、明暦3年以来、四十年ぶりの大検地が行われ、辰胤がその担当となった。その後も、護国寺観音堂普請の奉行となったり、相馬将監胤充とともに大名衆の間を走り回るなど粉骨の活躍を見せる。
元禄14(1701)年4月25日、辰胤は江戸桜田屋敷で病死した。享年三十九。
堀内家は辰胤一代に限り、御一家筆頭の家格であり、辰胤が亡くなると、これまで通り岡田家が御一家筆頭となり、5月4日、岡田宮内知胤に先祖よりの「監物」の名乗りが許された。敍胤は中村で留守を守る辰胤嫡子・堀内大蔵胤近へ使者を遣わし、香典として白銀二枚を贈った。6月13日、胤近が堀内宗家を継承。辰胤が支配していた侍組は、娘婿である岡田監物知胤が侍大将に任じられて支配することとなった。
堀内胤近(????-1721)
堀内玄蕃辰胤の嫡子。初名は市五郎。通称は大蔵、玄蕃。妻は松永太衛兵衛一貞女子(相馬昌胤養女:昌胤側室妹)(『衆臣家譜』巻十五 結城)。
元禄11(1698)年2月20日、はじめて藩主・相馬昌胤に謁見し、「胤」の一字を賜り「胤近」を称した。24日には、藩主・昌胤は堀内玄蕃辰胤邸を訪ね、胤近に「大蔵」の通称を与えた。
元禄13(1700)年9月13日、昌胤は側室の妹を養女とし、胤近へ縁組させる旨を胤近の父・玄蕃辰胤へ伝えた。
元禄14(1701)年4月25日、父・堀内玄蕃辰胤が江戸桜田屋敷で病死した。享年三十九。堀内家は辰胤一代に限り、御一家筆頭の家格であり、辰胤が亡くなると、これまで通り岡田家が御一家筆頭の席次となり、5月4日、岡田宮内知胤に先祖よりの「監物」の名乗りが許された。敍胤は中村で留守を守る胤近へ使者を遣わし、香典として白銀二枚を贈った。6月13日、胤近が堀内宗家を継承したが、まだ歳若く、堀内玄蕃組は岡田監物知胤が侍大将に任じられて支配することとなった。
元禄15(1702)年5月4日、胤近と昌胤養女の婚礼式が行われた。
宝永6(1709)年5月28日、旗本の渡辺半右衛門完綱が老病につき、胤近の弟・数之進を養子に望んだ。藩公・相馬敍胤は胤近の弟を婿養子にとの願いであるが、彼はまだ幼少であり、今すぐに婿養子とするわけにはいかず、渡辺家の御一門のうちより相応の方を婿養子とするよう伝えて、こちらは辞退する旨を伝えたが、渡辺完綱は一門中にはふさわしい者がおらず、渡辺一族ともども、なんとか胤近の弟を養子に迎えたい旨の返事が来た。敍胤もこの願いを断るわけにはいかず、幕府もこの旨を認め、堀内数之進は旗本・渡辺家の養子となり、渡辺半右衛門公綱を称した。
渡辺守綱――渡辺重綱―+―渡辺吉綱 +―渡辺房綱
(半蔵) (半蔵) |(丹後守) |(岩之助)
| |
+―渡辺綱貞――渡辺完綱==渡辺公綱――+=渡辺寧綱
(大隈守) (半右衛門)(半右衛門) (半右衛門)
宝永6(1709)年6月5日、敍胤は隠居し、嫡子・相馬民部清胤へ家督相続された。そして6月12日、将軍に家督相続の御礼を述べに登城する清胤に随い、岡田監物知胤、堀内大蔵胤近、相馬将監胤賢がともに登城した。
正徳元(1711)年4月20日、藩公・相馬敍胤が中村城内にて急死した。わずかに三十五歳。17日に病状が急変し、幕府御典医を江戸から呼ぶ間もないほど急激な死であった。家督を継いだ相馬讃岐守清胤は、8月17日、参勤交代のために藩主になってはじめて中村城に入った。このとき清胤十五歳。胤近ら重臣たちが出迎え、城内御座の間にて岡田内記知胤と堀内大蔵胤近が御目見えした。
9月5日、胤近は泉内蔵助胤和が侍大将を辞したのに伴い、侍大将に任じられ、組支配を命ぜられた。そして享保元(1715)年10月、胤近は家老職に任じられ、幾世橋御殿の隠居・昌胤より「玄蕃」の称が与えられた。
享保6(1721)年7月24日、中村にて亡くなった(『衆臣家譜』堀内覚左衛門)。胤近には跡を継ぐ男子がなかったため、堀内覚左衛門胤信の子、堀内角左衛門常長が堀内本家を継いだ。
堀内胤総(1684-1751)
堀内覚左衛門胤信(胤往、征長)の長男。妻は熊川兵庫長貞娘。初名は常長。幼名は善松。通称は角左衛門、十兵衛、兵衛。姉は門馬嘉右衛門寧経の妻(『衆臣家譜』堀内覚左衛門)。弟重長はのちに養嗣子として堀内覚左衛門家を継承する。堀内玄蕃胤近の嫡子。
門馬辰経―――門馬寧経
(嘉右衛門) (上総)
∥
堀内胤信―+―女子
(覚左衛門)|
| 熊川長貞女
| ∥
| ∥
+―堀内胤総 +―堀内可長
|(十兵衛) |(角左衛門)
| |
+―堀内重長――+―女子
|(角左衛門) | ∥
| | ∥
+―武野保久 | 富田侍実
|(半兵衛) |(五右衛門)
| |
+―女子 +―原信如
| ∥ |(伝右衛門、のち堀内達長)
| ∥ |
| 生駒歳祐 +―女子
|(七郎右衛門)| ∥
| | ∥
+―女子 | 熊長左衛門
∥ |
鳶捴長治 +=女子
(右衛門) (泉田甲庵運隆女)
∥
太田常治
(清左衛門)
享保2(1717)年8月28日、堀内覚左衛門胤信が亡くなり、嫡子の角左衛門常長が家督を継承。享保5(1720)年、使番に就任した(『衆臣家譜』堀内覚左衛門)。
享保6(1721)年2月12日、妻の熊川氏が亡くなった。法名は戒雲知證。続けて同年7月24日、堀内惣領家の堀内玄蕃胤近が中村で亡くなる。胤近には跡を継ぐ男子がおらず、閏7月28日に常長が宗家を相続し(『衆臣家譜』堀内覚左衛門)、8月19日に登城して藩侯より「胤」字を賜り「胤総」を称した。堀内覚左衛門家五百六十七石は弟の堀内庄左衛門が相続し、堀内覚左衛門重長を称した。
享保7(1722)年3月15日、相馬の小泉村不乱院三万日回向結願の藩公代参として、御一家・胤総が務めた。不乱院は北山の寺院群の中でも広大な寺域を誇った大寺院であったが、現在は跡形もなくなっている。
享保11(1726)年8月3日、弟の堀内角左衛門重長が家老職に就任した。これは7月13日に守屋八太夫眞信が江戸家老職を辞したことによるものである。享保13(1728)年11月28日には侍大将に就任し、江戸常府家老として国元を離れた石川助左衛門昌清の組を引き継いだ。しかし享保17(1732)年4月13日、重長は病のため家老職を辞した。
享保12(1727)年2月には、中村城の本丸広間の建て直しが行われ、大奉行として胤総が命じられた。かつて胤総の義理の祖父にあたる辰胤が江戸城普請の大奉行を務めた先例から、堀内家が大奉行とされた。3月24日、本丸御広間は完成した。
享保20(1735)年8月9日、「堀内十兵衛胤総、御家老職被仰付」られた(『相馬藩世紀』『覚日記』)。
延享5(1748)年、養子の胤長に家督を譲り、3月15日、「堀内大蔵家督御礼」のため藩侯尊胤に目通り、おなじく十兵衛胤総は「名ヲ兵衛与改」ている(『寛文七年未閏二月ゟ日記写』)。
宝暦元(1751)年12月10日昼頃、「堀内兵衛胤総病死 行年六十八」(『寛文七年未閏二月ゟ日記写』)という。
堀内胤長(????-????)
堀内十兵衛胤総の養嗣子。実は岡田靱負知胤の二男(『奥相茶話記』)。母は堀内玄蕃辰胤娘。幼名は岡田鶴之助、通称は大蔵、十兵衛。娘は岡田監物徃胤の妻。
享保15(1730)年12月、堀内十兵衛胤総の養子となり、享保18(1733)年8月、願いが認められ、通称を「大蔵」と改めた。延享5(1748)年、養父十兵衛胤総から家督を譲られ、3月15日、「堀内大蔵家督御礼」のため藩侯尊胤に目通り、おなじく十兵衛胤総は「名ヲ兵衛与改」ている。
宝暦2(1752)年2月1日、「堀内大蔵胤長、御家老被仰付」、常府御家老となった佐藤惣左衛門組を引き継いだ。
堀内脩胤(????-1772)
堀内十兵衛胤長の養嗣子。実は岡田監物春胤の三男(『奥相茶話記』)。母は堀内十兵衛胤重女。幼名は岡田辰四郎。通称は主水、大蔵、十兵衛、玄蕃。初名は胤径、胤信、胤脩。妻は堀内十兵衛胤長二女。実兄は岡田監物徃胤。弟の直胤はのち兄の往胤を継いで、岡田監物直胤となる。妹は石川助左衛門に嫁いだ。
明和6(1769)年5月15日、藩公・相馬因幡守恕胤の御内証・満尾が鶴之助を出産。即日、子供のなかった堀内主水の養子とした(『恕胤御年譜』)。5月22日、胤脩は養子御礼言上のために恕胤と面会し、鶴之助は御目見に及ばずながら「胤」の一字を賜った(『恕胤御年譜』)。
明和7(1770)年5月1日、胤脩は中村で侍大将を仰せつけられた(『恕胤御年譜』)。
明和8(1771)年3月10日、胤脩は中村から江戸に召され、翌11日、江戸家老に就任した(「中邑世紀秘説」『相馬市史通史編』)。また、3月18日には門馬八郎兵衛隆経が中村の家老となる。これは3月10日に佐藤庄左衛門義信が「依過失見役召放隠居禁足」という措置によるものか。なお、この直後から家老職にある者の過失が露顕し、相次いで家老職を解任されている。
●明和8(1771)年家老辞職
| 3月10日 | 佐藤宗左衛門義信 | 依過失見役召放隠居禁足、後被赦免 |
| 4月12日 | 岡田監物往胤 | 病により家老職、組支配退任 |
| 5月3日 | 池田八右衛門直重 | 有故被退其職隠居禁足、且被旧領五百石没収賜新知百石於嫡子直方、後被免禁足 |
| 5月3日 | 幾世橋作左衛門明経 | 就過失老職被召放隠居 |
このような中で、養子の鶴之助胤■が中村にて7月3日に亡くなってしまった。彼は藩公子としての例をもって弔いが行われ、中村城下圓応寺に葬られた。法名は玉体院殿清顔槿露大童子。
10月7日、恕胤の御内証・満尾が再び男子を出産。再び胤修の養子と定められた。胤修は江戸家老として江戸屋敷に詰めていたため、庶家の堀内覚左衛門達長がこれを江戸の胤修に申達し、中村では胤修の妻が朋之進と名づけ、藩公・恕胤に提出した。
明和9(1772)年1月17日、朋之進の御色直、2月7日には御箸初、2月29日、大手門外の堀内邸に引き移った。ここで胤修妻の養育を受けるが、胤修は国家老を仰せ付けられたため国元へ帰国。6月28日には城代を仰せ付けられ、名を「修胤」と改める(「中邑世紀秘説」『相馬市史通史編』)。しかし、それから間もない11月9日、修胤は病のため中村で亡くなった。享年不祥。
修胤の跡式は養嗣子の朋之進が継承して、堀内覚左衛門達長が後見となり、覚左衛門の席次は堀内宗家と同じとなる。のち、朋之進が亡くなると、達長が堀内宗家を継ぎ、堀内胤陸を称する(『衆臣家譜』堀内覚左衛門)。
堀内胤陸(????-1781)
堀内角左衛門可長の女婿。泉田掃部胤重の二男。母は下浦靱負之清女。妻は堀内角左衛門可長養女(堀内大蔵胤長次女)。妻の堀内氏が亡くなったのち久米半右衛門序時女(実は矢田部蔀由祐娘)を迎えた。幼名は丑五郎。通称は庄左衛門、角左衛門、十兵衛。名は達長、惣領家を継承して胤陸。
宝暦8(1758)年7月、養父の堀内庄左衛門可長が死去すると堀内覚左衛門家を継承し、7月11日に使番に就任。宝暦13(1763)年8月17日には組頭、明和2(1765)年8月16日に用人、明和7(1770)年12月10日に家老職となった。明和8(1771)年5月1日には侍大将に任じられた(『衆臣家譜』堀内覚左衛門)。
安永元(1772)年11月9日、堀内宗家の堀内主水修胤が亡くなると、その養嗣子・堀内朋之進(藩公・相馬恕胤庶子)が家督を継ぐ。しかし、朋之進は幼少であり、角左衛門達長が本家に移って朋之進の養育を命じられ、12月16日、達長の席次は御一家堀内家とされた(『衆臣家譜』堀内覚左衛門)。
しかし、それから八か月ほどのちの安永2(1773)年7月10日、朋之進は亡くなった。法名は無染院殿智徳明大童子。これにより7月24日、角左衛門達長は本家相続を命じられ(『衆臣家譜』堀内覚左衛門)、翌25日、達長は登城して藩公・相馬恕胤に閲し、「胤」の一字を与えられて「胤陸」と名乗り、通称も「十兵衛」と改めた。堀内覚左衛門家は養父・可長の弟にあたる原伝右衛門信如(初名・堀内市次。原伝右衛門信興家を継いでいた)が実家に戻り、堀内覚左衛門養長を称した(『衆臣家譜』堀内覚左衛門)。
安永6(1777)年11月19日、嫡男・千松が誕生した(『恕胤御年譜』)。
安永8(1779)年2月28日、中村城二ノ丸にて藩公恕胤の娘・彜姫が誕生した(『恕胤御年譜』)。彜姫は即日堀内胤陸の養女と定められた。しかし、このころから病のために家老職・組支配御免の願いを出していたようで、10月2日、家老職ならびに組支配が免ぜられた。養女としていた彜姫は、11月15日、相馬将監胤豊の嫡子・相馬儀十郎(のち相馬将監胤慈)への縁組が整えられている(『恕胤御年譜』)。
安永10(1781)年2月4日、中村において亡くなった(『恕胤御年譜』)。
堀内胤久(1777-1829)
堀内十兵衛胤陸の嫡男。幼名は千松。通称は大蔵、玄蕃。妻は相馬因幡守恕胤養女・於齢(相馬将監胤豊妹・於伊代)、後室は岡田監物恩胤養女(堀内覚左衛門溥長女)。
安永6(1777)年11月19日、中村にて誕生した(『恕胤御年譜』)。
安永10(1781)年2月4日、江戸にあった藩公・相馬恕胤は、中村において堀内十兵衛が病であると報告を受け、四本松大右衛門が見舞いのために派遣されたが、すでに亡くなっていたため、嫡子の千松に悔みを告げ、三十五日法要の際に香典が下賜された(『恕胤御年譜』)。
天明5(1785)年6月26日、相馬将監胤豊の妹・伊代が、屋形様(相馬因幡守恕胤)の養女となり「於齢」と改名。千松へ配することが決められた。8月1日、千松は「胤」の御一字を賜り、「堀内大蔵胤久」と称し、12月7日、於齢の方は堀内家に移った(『恕胤御年譜』)。
寛政8(1796)年1月24日、病のため家老職・侍大将を辞した。しかしその後も御一家としての役割を担い、5月15日、城内的場に白猿が現れる吉瑞があり、急遽、歌絵が催された。岡田監物恩胤、堀内大蔵胤久、泉右橘胤傳、泉田左門胤保らが歌を献じた。
12月7日、組支配が命じられた。
寛政11(1799)年6月1日、江戸屋敷にて御内証・哥が女児を出産した。女児は於律と名づけられ、胤久の養女とされた。12月6日には旗本の渡部助八郎との縁組の内談が整っている。しかし、この養子縁組は、享和3(1803)年5月、渡部助八郎の婿養子として、三河奥殿藩主・松平主水正乗尹の末子の富五郎を迎えたいとのことで、堀内家からではなく大名家である相馬家より直縁で迎えたいということとなったため、於律は堀内家より相馬家へ戻った。
享和元(1801)年7月7日、家老職に任じられた。また、相馬讃岐守樹胤の家督相続の御礼のため、祥胤・樹胤は将軍に謁見することとなり、先例の通り、御一家より三名が同伴することとなった。そのため、岡田監物恩胤、相馬将監胤慈、相馬主税胤綿が江戸に出府。4月18日、因幡守祥胤、讃岐守樹胤とともに将軍・徳川家斉に謁見した。その後、樹胤は初めて国元に下り、6月3日、堀内大蔵胤久、泉内蔵助胤傳、泉田左門胤保が中村城内にて謁見。太刀折紙を献上した。泉典膳胤陽も箱肴を進上している。
文化2(1805)年9月、一門・堀内覚左衛門溥長の長女が、老公・相馬祥胤、藩公・相馬樹胤の君命によって御一家・岡田監物恩胤の養女となり、胤久の妻となっている。天明5(1785)年6月26日に相馬因幡守恕胤養女・於齢(相馬将監胤豊妹・於伊代)が胤久の妻となっており、於齢はこのころ離別または死去していたものと思われる。
文化3(1806)年5月13日の野馬追神事では藩主名代として「堀内大蔵」が総大将を務めた。しかし、胤久はこのころ病がちであったようで、翌文化4(1805)年1月、家老職が免ぜられた。
文化8(1811)年1月16日、胤久は再び登用され、侍大将に任じられ、組支配御免となった岡田監物恩胤に代わって組支配が命じられた。さらに5月22日、さきに家老御免となった相馬左織胤壽に代わり、ふたたび家老職に任じられ、文化12(1815)年4月25日に免ぜられるまでの四年間、老職として活躍した。
文化11(1814)年4月19日、藩公・相馬樹胤が隠居のため、その御手道具が御一家衆へ下されることとなり、「掛物」が「堀内大蔵」に下げ渡された。
文化14(1817)年8月4日、「堀内大蔵胤久」が三度家老職に任じられた。
文政3(1820)年3月21日、「堀内大蔵嫡子 胖」が御目見えし、「胤」の一字が下賜された。その後、胤久は「大蔵」を改め「玄蕃」となっている。
文政12(1829)年、玄蕃胤久は病に倒れた。藩公・相馬益胤は胤久のために藩公祈願寺の妙見歓喜寺に胤久の病気平癒の祈祷を行なったが、その甲斐なく文政12(1829)年12月18日に病死した。益胤は数年来の勲功に酬いるべく、その葬儀には用人を藩公代参として派遣している。
妹は久米郷右衛門喜時に嫁ぎ、娘を儲けている。この娘は胤久の養女となり、堀内覚左衛門吉長に嫁いでいる。天保2(1831)年、次女・美作(ミサ)が相馬将監胤宗の正室となっている(『福島県士族相馬胤真祖母ミサ同岡田清煕妻ハル綬褒章授与孝貞』)。
堀内胤寧(????-????)
堀内玄蕃胤久の嫡男。母は岡田監物恩胤養女(実は堀内覚左衛門溥長娘)。妻は富田弥市満重娘。通称は胖、大蔵。妻は相馬縫殿仙胤娘・於俊。
文政3(1820)年3月21日、「堀内大蔵嫡子 胖」が御目見えし、「胤」の一字が下賜された。
文政9(1826)年、「堀内大蔵」は相馬藩内における御厳法制定に尽力した功績をもって百石を加増された。また、それに協力した池田八右衛門直行、今村吉右衛門、紺野文太左衛門、石川助左衛門、佐藤庄左衛門らもそれぞれ加増されている。
文政10(1827)年10月、相馬縫殿仙胤娘・於俊を娶った。
天保2(1831)年10月16日、「堀内大蔵」は家老職に、天保7(1836)年3月10日には侍大将に任じられた。
天保15(1844)年9月21日、家老職を辞することが決まっていた相馬将監に代わり、家老職に就任した。
堀内胤陸―――堀内胤久 +―堀内胤寧――――堀内胤賢
(十兵衛) (玄蕃) |(大蔵) (大蔵)
∥ |
∥――――+―田原口文貞―――田原口房貞
∥ |(橘左衛門) (安之助)
∥ |
堀内溥長―+―娘 +―娘
(覚左衛門)| ∥
| ∥
+―堀内康長―+―堀内吉長====堀内興長
(覚左衛門)|(覚左衛門) (覚左衛門)
|
熊川奉重 +―娘
(兵庫) ∥―――――+―堀内興長
∥ ∥ |(覚左衛門)
∥ ∥ |
∥――――――熊川長基 +―娘
∥ (左衛門) | ∥――――――熊川幸之助【佐竹義脩】
∥ | ∥
相馬胤豊―――娘 相馬益胤――+=熊川長顕【佐竹義諶】
(将監) (十一代藩主) (兵庫)