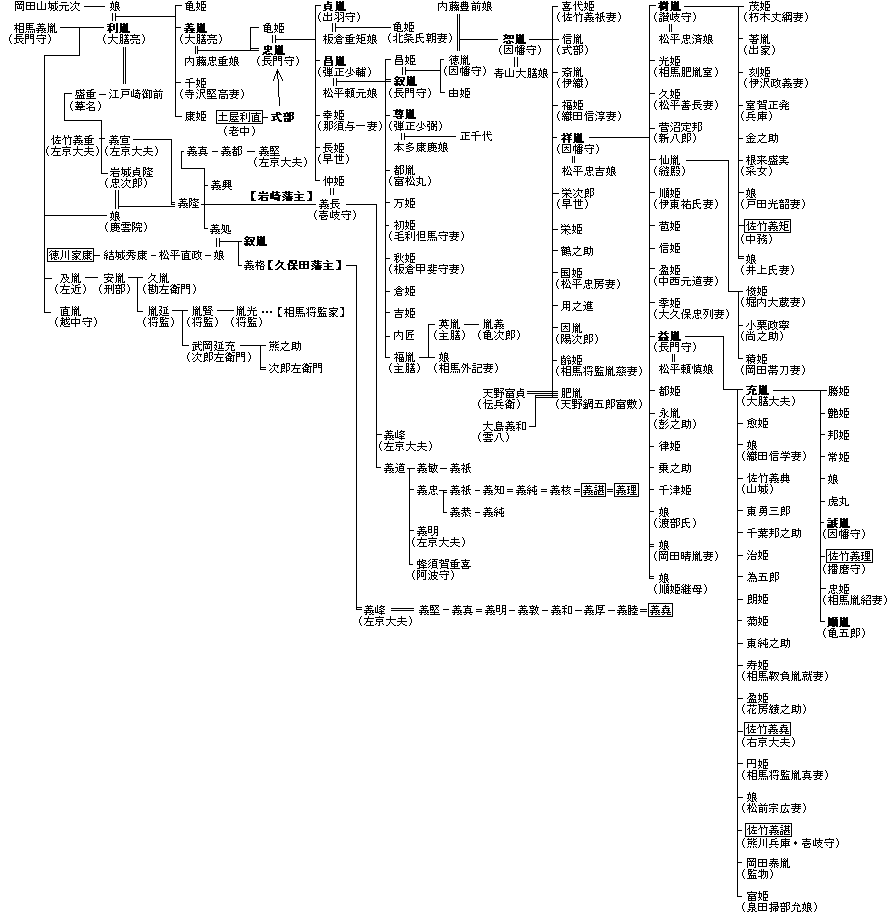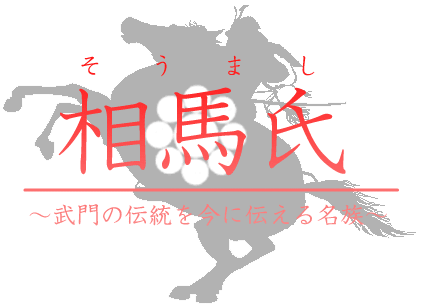
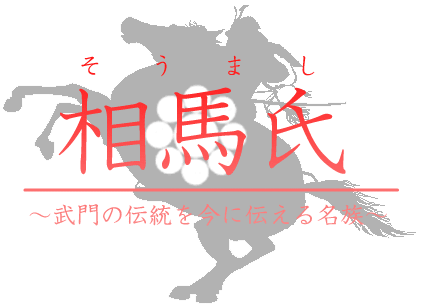
●陸奥国中村藩六万石●
| 代数 | 名前 | 生没年 | 就任期間 | 官位 | 官職 | 父 | 母 |
| 初代 | 相馬利胤 | 1580-1625 | 1602-1625 | 従四位下 | 大膳大夫 | 相馬義胤 | 三分一所義景娘 |
| 2代 | 相馬義胤 | 1619-1651 | 1625-1651 | 従五位下 | 大膳亮 | 相馬利胤 | 徳川秀忠養女(長松院殿) |
| 3代 | 相馬忠胤 | 1637-1673 | 1652-1673 | 従五位下 | 長門守 | 土屋利直 | 中東大膳亮娘 |
| 4代 | 相馬貞胤 | 1659-1679 | 1673-1679 | 従五位下 | 出羽守 | 相馬忠胤 | 相馬義胤娘 |
| 5代 | 相馬昌胤 | 1665-1701 | 1679-1701 | 従五位下 | 弾正少弼 | 相馬忠胤 | 相馬義胤娘 |
| 6代 | 相馬敍胤 | 1677-1711 | 1701-1709 | 従五位下 | 長門守 | 佐竹義処 | 松平直政娘 |
| 7代 | 相馬尊胤 | 1697-1772 | 1709-1765 | 従五位下 | 弾正少弼 | 相馬昌胤 | 本多康慶娘 |
| ―― | 相馬徳胤 | 1702-1752 | ―――― | 従五位下 | 因幡守 | 相馬敍胤 | 相馬昌胤娘 |
| 8代 | 相馬恕胤 | 1734-1791 | 1765-1783 | 従五位下 | 因幡守 | 相馬徳胤 | 不明 |
| ―― | 相馬齋胤 | 1762-1785 | ―――― | ―――― | ―――― | 相馬恕胤 | 不明 |
| 9代 | 相馬祥胤 | 1765-1816 | 1783-1801 | 従五位下 | 因幡守 | 相馬恕胤 | 神戸氏 |
| 10代 | 相馬樹胤 | 1781-1839 | 1801-1813 | 従五位下 | 豊前守 | 相馬祥胤 | 松平忠告娘 |
| 11代 | 相馬益胤 | 1796-1845 | 1813-1835 | 従五位下 | 長門守 | 相馬祥胤 | 松平忠告娘 |
| 12代 | 相馬充胤 | 1819-1887 | 1835-1865 | 従五位下 | 大膳亮 | 相馬益胤 | 松平頼慎娘 |
| 13代 | 相馬誠胤 | 1852-1892 | 1865-1871 | 従五位下 | 因幡守 | 相馬充胤 | 大貫氏(千代) |
| 1.相馬中村藩主相馬家 | 2.陸奥国中村藩の概要 | 3.相馬氏関係リンク |
陸奥国宇多郡中村の藩主相馬家は、千葉介常胤の二男・相馬次郎師常を遠祖とする千葉一族の名門である。鎌倉時代末期、惣領・相馬左衛門尉胤村の庶子である相馬彦次郎師胤は母の尼阿蓮とともに、庶兄の相馬左衛門尉胤氏と土地争いを起こし、師胤の系統は相馬家の中でも浮き上がった存在になっていったと思われる。そして師胤の子・相馬孫五郎重胤は、相馬一族との争いや幕府御内人・長崎氏との所領争いのため、陸奥国行方郡に下っていったのが奥州相馬氏の始まりである。
皮肉にも下総国相馬郡内の地頭職であった惣領家の相馬氏は没落の道をたどることとなり、室町時代の騒乱の中で大きな勢力を持つことはできないまま、江戸時代には旗本相馬家となり明治維新を迎える。
一方、奥州へ下った相馬家は、南北朝時代、室町時代に勢力を拡大。亘理郡の武石氏(千葉介常胤三男・武石胤盛を祖とする)と並んで、陸奥国宇多郡・行方郡などの検断職を司り、奥州の要として室町幕府に重用され、戦国大名として成長する。
戦国時代には伊達氏や標葉氏と争い、標葉氏を滅ぼして標葉郡を併合。また、伊達氏とは相馬顕胤・相馬盛胤・相馬義胤の三代にわたって戦い続け、豊臣秀吉による小田原合戦に参陣して両家の戦いは一応の終止符を打ったが、中村藩主となった相馬家は仙台藩伊達家を常に仮想敵国として軍事訓練(相馬野馬追)を行い、幕末にいたっている。
秀吉亡きあと、慶長の役(関ヶ原の戦い)では、相馬義胤は石田三成と仲が良かったため、縁戚の佐竹義宣・岩城貞隆とともに中立を守ったことから家康から睨まれ、戦後に所領没収という憂き目を見る。これに義胤の嫡男・密胤(のちの利胤)がみずから江戸へ出向いて、家康・秀忠の怒りを鎮めることに成功、密胤は徳川家の重鎮・土井利勝の「利」を給わり「利胤」を名を改めた。
 |
| 伝太田館跡 |
利胤は徳川家の覚えもよく、秀忠の養女・於茶阿ノ方を正室として迎え、徳川家の縁戚に連なる。さらに井伊家や黒田家など大々名に隣接する外桜田に家康直々の縄張りによる屋敷を与えられた。
利胤は大坂の陣や手伝普請などに尽力し、三代藩主・相馬長門守忠胤の代に「外様」から「譜代並」となり、江戸城内では譜代大名格として「帝鑑間詰」となった。さらに四代藩主・相馬彈正少弼昌胤は「譜代並」から「譜代席」となり、正式な譜代大名として幕府に認められた。昌胤は将軍の信任が非常に厚く、江戸城奥詰、将軍御側奉公などが命じられている。
しかし、18世紀中ごろの凶作によって藩の収益は悪化。さらに藩内で台風、痢病、大火の被害が続いたために、18世紀はじめから終わりの90年の間に藩内の農民数は約9万人から約半数の4万3千人にまで落ち込んでしまった。藩主・祥胤は、農民の被害を救うために粥の炊き出しや幕府から五千両を拝借し、藩内には厳しい倹約令を発布して規律を強めた。
ようやく凶荒からの出口が見え始めた19世紀中ごろ、藩主・相馬充胤は藩士・農民一同に救済米を給し、医師を派遣して養生法を教示した。また、藩政改革の一環として農地改革の重要性を感じ、二宮尊徳のもとに藩士を派遣し、その仕法をもって藩政を立て直すことに成功した。しかし時はすでに幕末。戊辰戦争に巻き込まれた中村藩は大藩の影響力のもと、やむなく奥羽越列藩同盟に参画。新政府軍と戦ったが、新しい兵器をもつ政府軍に藩兵は浮き足立ち、仙台伊達家に援軍を求めるも伊達家は動かず、相馬家は政府軍に投降し。こうして相馬家は本領安堵の命を受け、廃藩置県を迎えた。
| 家格(詰部屋) | 月日 | 藩主 |
| 外様(柳間) | 慶長7(1602)年10月以降~万治2(1659)年2月29日 | 相馬利胤(初代) |
| 譜代並(帝鑑間) | 万治2(1659)年2月29日~貞享元(1684)年12月30日 | 相馬忠胤(三代) |
| 譜代席(帝鑑間) | 貞享元(1684)年12月30日~ | 相馬昌胤(四代) |
| 代数 | 名前 | 生没年 | 就任期間 | 官位 | 官職 | 父 | 母 |
| 初代 | 相馬利胤 | 1580-1625 | 1602-1625 | 従四位下 | 大膳大夫 | 相馬義胤 | 三分一所義景娘 |
| 2代 | 相馬義胤 | 1619-1651 | 1625-1651 | 従五位下 | 大膳亮 | 相馬利胤 | 徳川秀忠養女(長松院殿) |
| 3代 | 相馬忠胤 | 1637-1673 | 1652-1673 | 従五位下 | 長門守 | 土屋利直 | 中東大膳亮娘 |
| 4代 | 相馬貞胤 | 1659-1679 | 1673-1679 | 従五位下 | 出羽守 | 相馬忠胤 | 相馬義胤娘 |
| 5代 | 相馬昌胤 | 1665-1701 | 1679-1701 | 従五位下 | 弾正少弼 | 相馬忠胤 | 相馬義胤娘 |
| 6代 | 相馬敍胤 | 1677-1711 | 1701-1709 | 従五位下 | 長門守 | 佐竹義処 | 松平直政娘 |
| 7代 | 相馬尊胤 | 1697-1772 | 1709-1765 | 従五位下 | 弾正少弼 | 相馬昌胤 | 本多康慶娘 |
| ―― | 相馬徳胤 | 1702-1752 | ―――― | 従五位下 | 因幡守 | 相馬敍胤 | 相馬昌胤娘 |
| 8代 | 相馬恕胤 | 1734-1791 | 1765-1783 | 従五位下 | 因幡守 | 相馬徳胤 | 不明 |
| ―― | 相馬齋胤 | 1762-1785 | ―――― | ―――― | ―――― | 相馬恕胤 | 不明 |
| 9代 | 相馬祥胤 | 1765-1816 | 1783-1801 | 従五位下 | 因幡守 | 相馬恕胤 | 神戸氏 |
| 10代 | 相馬樹胤 | 1781-1839 | 1801-1813 | 従五位下 | 豊前守 | 相馬祥胤 | 松平忠告娘 |
| 11代 | 相馬益胤 | 1796-1845 | 1813-1835 | 従五位下 | 長門守 | 相馬祥胤 | 松平忠告娘 |
| 12代 | 相馬充胤 | 1819-1887 | 1835-1865 | 従五位下 | 大膳亮 | 相馬益胤 | 松平頼慎娘 |
| 13代 | 相馬誠胤 | 1852-1892 | 1865-1871 | 従五位下 | 因幡守 | 相馬充胤 | 大貫氏(千代) |
→相馬所領地図(江戸期と桃山期では若干異なる)
| 郡名 | 郷名 | 村数 |
| 宇多郡 | 宇多郷 山中郷(●) |
40 |
| 行方郡 | 北郷 | 31 |
| 中郷 | 41 | |
| 小高郷 | 32 | |
| 山中郷(■) | ||
| 標葉郡 | 北標葉郷 | 25 |
| 南標葉郷 | 27 | |
| 山中郷(◆) | 30(※) |
(※)・・・山中郷は三郡にまたがっており、●+■+◆の合計が30か村。
| 職名 | 定員 | 職格 | 職掌 |
| 藩主 | 相馬中村藩主・相馬家。世継のない場合は縁戚の大名家から養子が入った。 | ||
| 城代 | 一名 | 御一家 | 藩主が江戸へ赴いている際の留守居役をつとめる。御一家筆頭(ほぼ岡田家)がこれを務めた。 |
| 御頼家老 | 一名 | 御一家 | 御一家から特別に家老職につくもの。職掌は家老と同じ。 |
| 家老 | 三名 | 大身 | 藩政の統括をする。実質的に藩政を行う役職。 |
| 大番頭 | 四名 | 大身 | 侍総大将役。 |
| 用人 | 二名 | 大身 | 家老について藩政を執り行う。家老以下の人事も担当した。 |
| 郡代頭 | 一名 | 大身 | 郡代を統括する。 |
| 寺社奉行 | 一名 | 大身 | 藩内の寺社を統括する。 |
| 留守居役 | 二名 | 大身 | 江戸藩邸の留守を預かる。 |
| 郡代 | 三名 | 大身 | 宇多郡・行方郡・標葉郡の三郡の民政を行う。 |
| 町奉行 | 一名 | 大身 | 中村城下の民政を行う。 |
| 御納戸役 | 三名 | 小身 | 藩主の財政を扱う。 |
| 勘定奉行 | 六名 | 小身 | 藩政の財務を扱う。 |
| 代官 | 七名 | 小身 | 宇多・北・中・小高・北標葉・南標葉・山中の各郷の民政を行う。 |
| 回米奉行 | 二名 | 小身 | 江戸への年貢米搬送や中村への輸送を担当する。 |
・家中…中村城下に住んだ藩士。
・在郷給人…農村に知行と屋敷を与えられた藩士。
・郷士…後世取り立てられた藩士。役職は在郷給人とほぼ同じ。
| 屋敷 | 拝領時期 | 住所 | 現住所 |
| 上屋敷 | 慶長8(1603) | 外桜田 | 東京都千代田区霞ヶ関一(霞ヶ関駅・裁判所合同庁舎~合同庁舎1号館) |
| 中屋敷 | 万治2(1659)年4月7日 | 麻布谷町 | 東京都千代田区六本木二(アメリカ大使館宿舎) |
| 下屋敷 | 元禄12(1699)年5月27日 | 豊島郡角筈 | 東京都新宿区百人町か? |
| 藩校 | 育英館(中村町大手先) |
| 藩の武道 | 一刀流 |
| 藩の馬術 | 大坪流 |
| 参勤交代 | 江戸在府:子・寅・辰・午・申・戌 四月交代 中村在城:丑・卯・巳・未・酉・亥 四月交代 |
| 野馬追神事 | 毎年5月に行われた(現在は「相馬野馬追い」として7月23日~25日に大衆祭として執り行われる) |
-中村藩主相馬氏略系図-