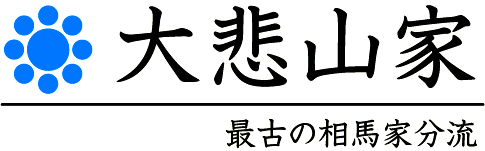
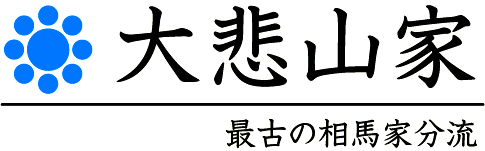
大悲山氏は岡田氏とならぶ相馬一族の名門で「大久」とも書き、「だいひさ」と読む。相馬惣領家・相馬胤村の十一男・相馬与一通胤が陸奥国行方郡小高郷大悲山村を領して祖となった。相馬大悲山氏は相馬岡田氏と同様、相馬惣領家の「家臣」ではなく「一門」という立場で、相馬惣領家のもとに一党を形成する立場にあり、相馬大悲山氏における惣領権があった。
しかし大悲山氏は、建武~観応期にかけての朝胤以降の活躍が『大悲山文書』の紛失もあってか見られなくなった。しかし、その後も相馬惣領家に仕えていたようで、江戸時代には百石の大身藩士となり明治を迎えた。
●大悲山氏略系図(『相馬文書』『大悲山文書』『相馬岡田文書』『衆臣系譜』『相馬藩政記』)
⇒相馬胤村―+―師胤――+―重胤――+―親胤―――胤頼――――…→【相馬惣領家】
(左衛門尉)|(彦次郎)|(孫五郎)|(孫次郎)(治部少輔)
| | |
| +―娘 +―光胤
| ∥ (弥次郎)
| ∥
+―通胤――+―行胤――――朝胤―…―善王……政胤―――…民部―民部丞―+―九左衛門―長十郎
|(余一) |(孫次郎) (又五郎) (次郎■郎) |
| | |
| +―女子 +―伊賀―+―七十郎――伊賀右衛門――+
| |(標葉女子) | |
| | | |
| +―女子 +―弥七―+―与十郎 |
| (鶴夜叉) | |
| ∥ | |
+―胤実――――胤持 +―大悲山小五郎 |
(孫四郎) (又六) |
|
+――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――+
|
+―重房―――+―次郎兵衛
(兵右衛門)|
|
+=重行―――重賢――――重経====重信===重一
(文七) (六右衛門)(兵右衛門)(権太夫)(要人)
●大悲山相馬氏の歴代当主
相馬通胤 (????-????)
 |
| 通胤花押 |
相馬大悲山氏初代惣領。相馬五郎左衛門尉胤村の十一男。母は不明。幼名は鶴夜叉丸。通称は相馬余一。
胤村の急死後、後妻の尼阿蓮が惣領代として相馬家政を仕切り、胤村の前妻の嫡子・相馬次郎左衛門尉胤氏ではなく、自分が生んだ長男・彦次郎師胤を「当腹嫡子」と幕府に申請し、惣領にしようと画策したが、幕府はこの訴えを退けたと見られる。
しかし、彦次郎師胤は惣領家奪取の画策の中で、一門の相馬五郎胤顕・相馬胤門・相馬余一通胤と婚姻関係を結んで基盤を固めた。師胤の嫡男・彦五郎重胤の正室は胤顕の娘、さらに重胤は胤門の養子となり、重胤の娘は大悲山通胤の孫・朝胤の正室となった。
●相馬師胤周辺系図
+―相馬胤盛――相馬胤康
|(小次郎) (五郎)
|
+―相馬胤顕―+―娘
|(五郎) ∥
| ∥
相馬胤村―――+―相馬師胤―――相馬重胤―――娘
(五郎左衛門尉)|(彦次郎) (孫五郎) ∥
| ∥
+―相馬通胤―――相馬行胤――相馬朝胤
|(余一) (孫次郎) (次郎兵衛尉)
|
+―相馬胤門===相馬重胤
(彦五郎) (孫五郎)
文永9(1272)年10月29日、幕府は急死した胤村の遺領を知行するよう「平松若丸」・「後家尼」・「平■■丸」・「平鶴夜叉丸」へ宛てた『関東下知状』を発給している(文書としては残されていないが、他にも「相馬胤盛」「相馬胤実」への『関東下知状』もあったと考えられる)。この下知状の中の「平鶴夜叉丸」が通胤であり、通胤は「陸奥国行方郡大悲山村」を配分されたとある。相馬大悲山氏はこの時から大悲山村を所領としたことがわかる。
永仁2(1294)年に幕府に提出されている『永仁二年御配分系図』に通胤の名はないが、『相馬系図』の中の人物順は『御配分系図』と同じと考えられることから、『御配分系図』の「胤通」が通胤のことと考えられる。通胤は文永9(1272)年に「陸奥国行方郡大悲山村」を受け継ぎ、正和2(1313)年には大悲山村とともに「行方郡小嶋田村・竹城保内長田村内」が通胤の子・行胤(孫次郎)に譲り渡されており(『相馬通胤譲状』)、『永仁二年御配分系図』にみえる「十二町六合」がこれに相当する。
正和2(1313)年11月23日、嫡男・孫次郎行胤と妹鶴夜叉に「陸奥国行方郡内大悲山村・小嶋田村・竹城保内長田村内蒔田屋敷地頭職」を譲り与える一方で、父の命に背いて「掃部入道道雄之家人小松一族也」に嫁した娘・標葉女子については「なかくきせつ(永く義絶)」しているために所領配分の対象には入れていない旨を記した『相馬通胤譲状』を発給した。しかし、これら譲状は通胤が行胤に所領を「預けおく」という形を取っており、譲状に背くような場合は行胤ですら所領を継承することを不可としていた。
その後、所領の継承がどのように行われたかは不明。大悲山氏がふたたび書状に名をあらわすのが建武元(1334)年11月1日で、正和2年以降、大悲山氏の所領は、父から義絶されたはずの「標葉女子」が継承していることがわかる(『相馬政胤打渡状』)。標葉女子は偽造文書を作成して所領を奪取したようである。
※「打渡状」…所領相論などに際して、守護などからの施行状・導行状を受けて、守護代・代官が所領などの受け渡しの時に相論の当事者に与える書状。(『角川日本史辞典』)
●通胤周辺系図
相馬五郎左衛門尉 次郎左衛門尉 五郎左衛門尉
胤村―――――――+―胤氏――――――師胤【下総相馬氏】
|
| 彦次郎 孫五郎 出羽守 治部少輔
+―師胤――――――重胤――――親胤――――胤頼
|
| 余一 孫次郎 次郎兵衛尉
+―通胤―――+――行胤――――朝胤
|
| 鶴夜叉 治部少輔
+――女子――――胤頼
大悲山相馬氏の系譜によれば、通胤の娘・鶴夜叉の子として「治部少輔胤頼」が見えるが、これは胤頼が鶴夜叉の養子になったという意味か、鶴夜叉と相馬出羽守親胤との間の子という意味かはわからない。伝に拠れば胤頼の母は「三河入道道忠女」とある。
●文永9(1272)年10月29日『関東下知状』(『大悲山文書』)
―参考―
●文永9(1272)年10月29日『関東下知状』(『相馬文書』)
●文永9(1272)年10月29日『関東下知状』(『相馬文書』)
●文永9(1272)年10月29日『関東下知状』(『相馬文書』)
●『永仁二年御配分系図』
胤綱――胤村―+―胤氏 六十二町三段三百歩 追赤沼六町
|
+―胤顕 四十四町七段二合 追赤沼四町
|
+―胤重 三十二町一段半
|
+―有胤 二十八町八段九合
|
+―師胤――重胤 十三町九段八合
|
+―胤朝 十二町九段七合
|
+―胤実 十二町四段六合
|
+―胤通 十二町六合
| 養子
+―胤門――重胤 九町九段一合
●『相馬系図』(『相馬岡田文書』)
■■――胤 村―+―胤 氏 五郎
| |
後 家 +―胤 顕 六郎左衛門尉
|
+―胤 重 十郎
|
+―有 胤 彦二郎
|
+―師 胤 九郎
|
+―胤 朝 孫四郎
|
+―胤 実 與一
|
+―通 胤 彦五郎―+―行 胤 孫二郎 行胤跡正中■■…奉行人■■…
| |
+―胤 門 +―女 子 楢葉女子 義絶也
|
+―女 子 鶴夜叉
論 人
●応長元(1311)年8月7日『関東下知状』(『相馬岡田文書』)
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
●正和2(1313)年11月23日『相馬通胤譲状』(『大悲山文書』)
相馬行胤 (????-????)
 |
| 行胤花押 |
相馬大悲山氏二代惣領。相馬余一通胤の嫡男。通称は孫次郎。号は明圓(左は明圓の署名のある花押)。
正和2(1313)年11月23日、相馬通胤は「陸奥国行方郡内大悲山村・小嶋田村地頭職」を嫡子行胤に、「陸奥国竹城保内長田村内蒔田屋敷地頭職」は行胤の妹・鶴夜叉に譲渡する旨の譲状(『相馬通胤譲状』)をしたためた。一方、鶴夜叉の姉・しねはの女子(標葉女子)は父の命に背いて「掃部入道道雄之家人小松一族也」と結婚し、通胤はこれを「ふてう(不忠)」として「なかくきせつ(永く義絶)」した。しかし、この譲状は「■■申間、行胤に預けおく所也」とあり、行胤には預けおくだけであり、行胤とて父に背けばその分を妹の鶴夜叉が継承すべき事としていた。
こののち行胤の名があらわれるのは建武元(1334)年11月1日(『平政胤打渡状』)で、妹の尼明戒(標葉女子)の知行分を行胤に打ち渡す旨が記されている。しかし、この知行分とは「陸奥国行方郡内大悲山村・小嶋田村・高城保(竹城保)内長田村内蒔田屋敷・岩見迫」であり、行胤・鶴夜叉が譲状によって譲り渡された土地である。つまり彼らの所領は姉の尼明戒によって押領されていたと考えられる。
『相馬系図』の行胤の項に「行胤跡正中(以下欠損)」とある。しかし、行胤はこの時点では出家をしておらず、通胤跡の誤りか? この正中年中(1324-1326)に行胤が所領を継承したと考えることもできる。そして『相馬岡田系図』の「鶴夜叉」の項には、
「姉明戒依父不和、無遺領處、調謀書譲状、訴国司顕家卿、奪取鶴夜叉領、其後甥朝胤并又六胤持、鎌倉奉行所捧訴状、数年間致訴論處、高時滅亡、止訴陳云々、世治後又訴之、依謀書顕然、遂鶴夜叉為安堵云々」
とあるように、尼明戒(標葉女子)が譲状の偽造をして、陸奥国司・北畠顕家に提出して所領を安堵されたとされる。
 |
| 政胤花押 |
しかし、北畠顕家が陸奥国司として陸奥へ向かったのが元弘3(1333)年10月、鎌倉の北条高時が滅亡したのはその五か月前のことであり、時期的に矛盾が生じる。また、行胤に対して建武2(1335)年7月3日に『陸奥国宣』が発給されており、実際は明戒が押領したことを、行胤・朝胤・鶴夜叉・胤持(鶴夜叉の夫)が幕府問注所に訴えて争論し、幕府の滅亡によって沙汰止みになっていたところを、行胤等が国司・北畠顕家に訴えて認められ、建武元(1334)年11月の『平政胤打渡状』のように明戒の分が「究明(道理を究めて)」されて相馬行胤・相馬胤俊に打ち渡す書状が発給されている。ここにあらわれる「相馬弥次郎胤俊」と打渡状発給の本人「平政胤(相馬政胤?)」は系譜に見えないが、胤俊は行胤とはまた、政胤の花押も同時代の重胤・親胤とも異なっており、いかなる人物か不明。『打渡状』を発給していることから、行方郡になんらかの権力を有していた人物と思われ、半年後の建武2(1335)年6月、重胤とともに「伊具・亘理・宇多・行方郡、金原保の検断職」に任じられた武石上総権介胤顕がいることから、この「政胤」は武石氏の一族である可能性もある。
建武2(1335)年7月3日、陸奥国司・北畠顕家発給の『陸奥国宣』によって行胤は大悲山村が安堵され、7月28日、相馬重胤から打渡状(『相馬重胤打渡状』)の発給を受けて正式に所領を継承した。重胤は顕家によって6月に「行方郡奉行・検断奉行」に任じられており、その権限に基づいて打渡状を発給した。ただ、行胤は相馬惣領家の家臣となっていたわけではなく、岡田相馬氏と同じように独自の惣領制をもっていた。
※「打渡状」…所領相論などに際して、守護などからの施行状・導行状を受けて、守護代・代官が所領などの受け渡しの時に相論の当事者に与える書状。(『角川日本史辞典』)
相馬氏はこののち、建武の新政に失望して足利方に寝返り、新政府との敵対を鮮明にした。建武3(1336)年正月、重胤は親胤・光胤ら子息をはじめ、胤康・行胤ら一族を率いて鎌倉へと向かった。これは、建武2(1335)年12月に多賀城から上洛した北畠顕家を追撃するために斯波家長(足利方奥州探題)に従ったもので、行胤は嫡男・又五郎朝胤を率いて真っ先に馳せ参じた(『相馬行胤着到状写』)。しかし2月、斯波兼頼(家長の従弟。最上氏の祖)が奥州の南朝討伐のために下向することになったため、重胤は行胤に兼頼軍に属して小高に戻るよう指示し(『某軍勢催促状』)、小高の相馬松鶴丸(相馬親胤嫡子)と合流して、一族を召集した。
3月16日、光胤らは兼頼とともに宇多庄熊野堂で結城宗広(白河上野入道)の留守軍勢と合戦に及び、22日、小高城に攻め寄せた北畠顕家の副将・広橋修理亮経泰との戦いで、行胤は家人「小嶋田五郎太郎」が討ち取られるほどの激戦を演じ、さらに27日、標葉庄の南朝方を追討するために出陣し、標葉弥九郎・孫十郎を生け捕りにする功績をあげた。
 |
| 小高城西端部 |
そして5月、鎌倉を攻め落として奥州へ戻ってきた北畠顕家は相馬氏の居城・小高城を取り囲んで猛烈な攻撃をしかけた。鎌倉では重胤・胤康らの攻撃を受け、さらに斯波兼頼とともに結城宗広勢を攻めていることなどから、相馬氏は足利方とされ、5月24日、小高城は陥落して「相馬弥次郎光胤・相馬六郎長胤・相馬七郎胤治・相馬十郎胤俊・相馬四郎成胤」が討ち死にした。
小高落城の直前、叔父の惣領代・光胤によって城外に脱出させられた松鶴丸(胤頼)は難を逃れ、山林に隠れてその挙兵の時を窺っていると、宇多庄熊野堂において斯波兼頼と結城宗広の合戦が起こったため、松鶴丸はともに逃れた20名の一族郎従を伴ってこれに加わり、熊野堂に籠る白河結城宗広の城代・中村六郎を攻めてこれを攻め落とした。この交名に「相馬孫次郎入道行胤」の名があり、小高落城の直後に剃髪して「明円」を称したと思われる(『相馬胤頼着到状』・『沙弥明円譲状』)。
建武4(1337)年11月21日、行胤入道明円は嫡男・朝胤(又五郎・次郎兵衛尉)に「なめかたのこほりのうち大ひさんのむら、をしまたのむら、とうこくたかきのほうなかたのむらのうちゆハミのはさまたのやしきの地とうしき(行方郡内大悲山村・小嶋田村、当国高城保長田村内岩見迫屋敷地頭職)」を譲り渡しており(『沙弥明円譲状』)、この譲状を最後に行胤の名は見えなくなる。朝胤は伯父・重胤に従って下総国から奥州に下り、その娘婿になっていた。さらに重胤は朝胤を「大ひさの五郎殿」と呼んでおり、親密な関係が窺われる。
行胤は『奥相秘鑑』によれば「通胤の男孫次郎行胤は建武三年四月重胤公に従ひて相州固瀬川に戦死す」とあるが、行胤は建武4(1337)年発給の譲状があることから、明らかな間違いである。
●建武元(1334)年11月1日『平政胤打渡状』(『大悲山文書』)
●建武2(1335)年7月3日『陸奥国宣』(『大悲山文書』)
●建武2(1335)年7月28日『相馬重胤打渡状』(『大悲山文書』)
●建武2(1335)年12月20日『相馬行胤着到状写』(『相馬岡田文書』)
●建武3(1336)年2月18日『某軍勢催促状』(『相馬岡田文書』)
●建武4(1337)年正月26日『相馬胤頼着到状』(『相馬岡田文書』)
大悲山朝胤 (????-????)
大悲山相馬氏3代惣領。相馬孫次郎行胤の嫡男。通称は又五郎、次郎兵衛尉。官途は兵衛尉。朝胤は伯父・重胤の娘婿であり「大ひさの五郎殿」と呼ばれていた。
相馬一族ははじめ建武の新政に失望して足利尊氏を支持して建武新政府との敵対を鮮明にした。建武3(1336)年正月、惣領・重胤は親胤・光胤ら子息をはじめ、胤康・行胤ら一族を率いて鎌倉へと向かった。朝胤は父・行胤とともに真っ先に馳せ参じた(『相馬行胤着到状写』)。しかし2月、斯波兼頼(家長の従弟。最上氏の祖)が奥州の南朝討伐のために下向することになったため、行胤は重胤の命を受けて兼頼軍に属して小高に戻り(『某軍勢催促状』)、小高の相馬松鶴丸(相馬親胤嫡子)と合流した。
しかし、5月24日、陸奥守北畠顕家の軍勢によって、奥州相馬家の居城・小高城は陥落。惣領代の相馬弥次郎光胤をはじめ、一族の相馬六郎長胤・相馬七郎胤治・相馬十郎胤俊・相馬四郎成胤が討ち死にした。このとき朝胤の父・孫次郎行胤をはじめとする一族の多くは、惣領・親胤の子・松鶴丸(胤頼)とともに小高城を逃れることに成功し、山中に雌伏した。
その後、斯波兼頼勢と結城宗広入道勢との合戦が起こり、松鶴丸(胤頼)は行胤をはじめとする一族を率いて兼頼勢に参加(『相馬胤頼着到状』)。宇多庄熊野堂の中村六郎(結城家中)を攻めた。この交名に父の「相馬孫次郎入道行胤」の名があるが、朝胤も参戦していたのかもしれない(『沙弥明円譲状』)。
こののち、朝胤は各地の合戦に参加し、武勲を挙げている。建武4(1337)年4月1日には、惣領・親胤の手に属し、楢葉八里浜合戦に先駆けの功を立て、翌2日には標葉庄小丸城口羽尾原合戦で真先に懸けて敵一人を切り捨てた。
その後、小高城に戻ったところ、4月9日に敵が押し寄せてきたため、朝胤は敵一人を射抜き、家人の兵衛四郎も一人射た。敵数名が城の東壁の守りを破ったため、朝胤が駆けつけて敵の侵入を防ぎきった。その夜、朝胤自ら城の東に陣取っていた敵勢に斬り込み、敵一人を討ち取った。しかし、この突撃で家人の江多里六郎太郎入道を喪い、小嶋田五郎太郎、小嶋孫五郎が負傷した。
その後の合戦でも武功を挙げ、標葉庄立野原の合戦では搦手の先陣を切って敵一人を切り捨てたが、乗馬の頭を斬られ、朝胤も左手に傷を負っている。4月15日の高瀬林合戦にも参戦。いったん、小高城へ帰城した。
6月25日、敵勢が小高城へ押し寄せたため、防戦して敵一人を射た。27日には小池城夜討合戦に加わり、家人の小野弥三郎が小池城の東側から懸け入って、敵勢を追い散らして城に放火するなど、武勲多き人物だった。
11月21日、朝胤は父・行胤入道明円から「なめかたのこほりのうち大ひさんのむら、をしまたのむら、とうこくたかきのほうなかたのむらのうちゆハミのはさまたのやしきの地とうしき(行方郡内大悲山村・小嶋田村、当国高城保長田村内岩見迫屋敷地頭職)」を譲られた(『沙弥明円譲状』)。
朝胤はその後も相馬惣領家とともに北朝方の勢力として参戦していたと思われる。康永3(1344)年、田村庄宇津峰の南朝勢力を討つため、奥州総大将・石塔義房が自ら出陣。朝胤も手勢を率いて義房に供奉し、6月18日、野槻城において着到を提出した(『相馬朝胤着到状』)。
こののち、文書からは朝胤の具体的な活躍を見ることはできないが、貞和3(1347)年4月2日には、奥州管領の恩賞裁定に不満だったのか、朝胤は申状と具書案を携えて「企参洛、可言上由雖申之」しようとしたが、いまだ南朝勢力が活発に動いている現状においては、管領も朝胤の上洛を黙認できず、「為凶徒對治留置候之間、進代官候」とし、朝胤の「申状并具書案壱巻」に加え、畠山国氏・吉良貞家両管領の挙状を朝胤の代官に渡し、京都の「武蔵守殿(高師直)」へ伝えさせている(『畠山国氏并貞家連署挙状』)。朝胤の一所懸命な姿勢を垣間見ることができる。
観応2(1351)年10月9日、奥州管領・吉良貞家の所領安堵状(『吉良貞家安堵状』)を最後に朝胤は文書上から見えなくなるが、その後も相馬一族の重鎮として活躍しただろう。没年は不明。
●建武2(1335)年11月20日『相馬重胤譲状』(『大悲山文書』)
●建武4(1337)年8月某日『相馬親胤注進状』(『大悲山文書』)
●建武4(1337)年11月21日『沙弥明円譲状』(『大悲山文書』)
●建武5(1338)年5月6日『相馬朝胤申状』(『大悲山文書』)
●康永2(1343)年11月7日『左衛門尉某并沙弥某連署奉書』(『大悲山文書』)
●康永3(1344)年6月18日『相馬朝胤着到状』(『大悲山文書』)
●貞和2(1346)年9月17日『沙弥并散位某連署召文』(『大悲山文書』)
●貞和3(1347)年4月2日『畠山国氏并貞家連署挙状』(『大悲山文書』)
●観応2(1351)年10月9日『吉良貞家安堵状』(『大悲山文書』)
大悲山善王 (????-????)
大悲山朝胤の子孫と考えられる人物。父は不明だが、時代的に朝胤の孫世代となる。
明徳元(1390)年12月6日、「刑部阿闍梨賢範」は「奥州行方郡内簀掻野坊中并寄進所小高九日市場後田三斗蒔田中在家、楯前田壱町大田塩竃神田」を、賢範一期の後は「大悲山善王殿」に譲る旨の置文をしたためている。「簀掻野」「小高九日市場」「楯前田」はいずれも現在地を比定できないが、いずれも小高城近隣の地か。
太田塩竃社については、重胤が奥州下向の際に妙見・鷲宮とともに関東から神輿に奉って遷宮したと伝わる神社で、現在、妙見社は原町市中太田に「太田妙見神社」、塩竃神社は原町市に「塩竃神社」、鷲ノ宮は小高町女場に「鷲宮神社」として祀られている。
●明徳元(1390)年12月6日『刑部阿闍梨賢範置文』(『相馬岡田文書』雑文書)
大久政胤 (????-????)
大悲山朝胤の子孫。通称は次郎■郎。
政胤には跡を継ぐべき男子がなかったため、享徳3(1454)年8月、「嫡女」と岡田次郎三郎盛胤との間に契約を交わさせ、盛胤を政胤領の「御代官」とすべきことが決められた(享徳三年八月廿三日「岡田盛胤契約状」『相馬岡田文書』)。
このとき岡田盛胤と大久政胤との間で交わされた所領の譲与契約だが、これは政胤嫡女と盛胤との婚姻という形がとられている。ただし、また、「若男女之ならい隔別申事候者」とあり、婚姻解消に際しては、大悲山氏の所領は「女子之御はからい」であることを契約し、異論を挟まない旨もあわせて誓っている。
●享徳3(1454)年8月23日『岡田盛胤契約状』(『相馬岡田文書』)
大悲山民部 (????-????)
大悲山朝胤の子孫。通称は民部。実名は不詳。
相馬讃岐守顕胤・相馬弾正大弼盛胤の二代に仕え、天文12(1543)年の小高郷出騎の一人に数えられている。
大悲山民部丞 (????-????)
大久民部の嫡子。通称は民部丞。実名不詳。妻は二本松乙盛女(『衆臣家譜』巻三 大悲山氏)。
相馬長門守義胤・相馬大膳大夫三胤(利胤)に仕え、文禄元(1592)年の采地は三十一貫九百五文と記されている(『文禄二年禄秩簿』)。
大久杢左衛門 (????-????)
大久民部丞の嫡子。通称は九左衛門、杢左衛門。実名不詳。妻は江井若狭女(『衆臣家譜』巻三 大悲山氏)。
慶長7(1602)年5月、相馬長門守義胤は関ヶ原の戦いで石田三成と親しかったことから所領を六万石に減封され、家臣一党も各地の所領を公収された。杢左衛門はその後に召し出されたが、北郷川子邑を与えられて三十五石九斗九升を知行した(『元和二年丙辰禄秩簿』)。
女子は二人あり、一人は右田村の鎌田源兵衛に嫁ぎ、もう一人は中郷南新田村の門馬吉兵衛に嫁いだ。
大久長十郎 (????-????)
大久杢左衛門の嫡子。通称は長十郎。実名不詳。
しかし、長十郎は二十六歳にして亡くなった。彼には男子がなく、大悲山氏嫡流はここに無嗣断絶した(『衆臣家譜』巻三 大悲山氏)。
大悲山家は、長十郎の叔父・大悲山伊賀の系統が続き、幕末、明治まで継承されている。
大悲山伊賀 (????-????)
大久民部丞の次男。実名は不詳。妻は藤崎摂津女(『衆臣家譜』巻三 大悲山氏)。
大悲山氏別家ながら嫡家が無嗣断絶したため嫡家となる。小高郷中村に移り住んで百石を給された。屋敷地は中村城下中御檀小路と上川原町の交差(相馬市中村)にあった。
大悲山六右衛門 (????-1658)
大悲山伊賀の子。実名は不詳。
二代藩主大膳亮義胤に仕え、「代官役勤之」(『衆臣家譜』巻三 大悲山氏)という。
寛永18(1641)年正月の采地は「三十一石五斗七升」(『衆臣家譜』巻三 大悲山氏)。
万治元(1658)年8月12日に没した。法名は如翁雲公(『衆臣家譜』巻三 大悲山氏)。
女子は岡田安右衛門長澄に嫁いだ(『衆臣家譜』巻三 大悲山氏)。
次男の大悲山弥七(妻は佐々木太左衛門元真女)は別家を起こし、三代藩主相馬長門守仇忠胤の徒士目附を務め、「賜二人扶持金四両、後三人扶持五両」った(『衆臣家譜』巻三 大悲山氏)。宝永5(1708)年7月17日に亡くなった。法名は知性浄本。
その長子・大久与十郎(妻は田代左京進女)は正徳2(1712)年に「京都役」を拝して上洛。正徳5(1715)年4月1日「於京都死」という。号は風香雪掃。
次男の大悲山弥七は初名小五郎。とくに事歴は伝わらず、元文3(1738)年5月24日に亡くなった。号は勘了全破。その女子は西内伴左衛門唯重に嫁いでいる。
長女は村田与兵衛に嫁ぎ、次女は岡田十右衛門に嫁いだ。
笠井直右衛門
∥
高野五郎右衛門―――女子 ∥
∥――――――――――+―大悲山伊賀右衛門――女子
∥ |
∥ |
大悲山六右衛門―+―大悲山六右衛門 +―大悲山重房
| |(兵右衛門)
| |
+―女子 +―女子
| ∥ ∥
| ∥ ∥
| ∥ 添田彦右衛門
| ∥ (宗休)
| ∥
| 岡田長澄 田代左京進――女子
|(安右衛門) ∥
| ∥
+―大悲山弥七 +―大久与十郎 西内唯重
∥ | (伴左衛門)
∥ | ∥
∥――――――――――+―大悲山弥七―――――女子
佐々木元真―――――女子 |
(太左衛門) |
+―女子
| ∥
| ∥
| 村田与兵衛
|
+―女子
∥
∥
岡田十右衛門
大悲山六右衛門 (????-1690)
大悲山六右衛門の子。初名は七十郎。後妻は高野五郎右衛門女(『衆臣家譜』巻三 大悲山氏)。
明暦年中に勘定方と務めており、明暦4(1658)年正月に三代藩主相馬長門守勝胤より「采地冨澤村之内三十二石之御黒印」を下された(『衆臣家譜』巻三 大悲山氏)。また同年には「江城御門助造」の際に「金奉行下役」を務め、寛文年中には代官を務め、寛文10(1670)年に「加増采地今田、坪田両村之内十八石」を与えられ、都合で約五十石を知行する。
元禄3(1690)年8月27日に亡くなった。
大悲山伊賀右衛門 (????-1691)
大悲山六右衛門の子。
父の六右衛門が亡くなったため、家督を継承するが、翌年の元禄4(1691)年8月13日に亡くなった。法諱は常空本了(『衆臣家譜』巻三 大悲山氏)。
女子は笠井直右衛門に嫁いだ(『衆臣家譜』巻三 大悲山氏)。
大久重房 (????-1745)
大悲山六右衛門の次男。母は高野五郎右衛門女(『衆臣家譜』巻三 大悲山氏)。通称は兵右衛門。
元禄4(1691)年に兄の大悲山伊賀右衛門の養嗣子となり、8月13日に兄が亡くなると家督を継承する(『衆臣家譜』巻三 大悲山氏)。
正徳4(1714)年2月、「武州荒川御普請助造」のとき、「大悲山兵右衛門」が小奉行として務めている。享保16(1731)年の「日光御本坊御修覆助造」のときは、屋根方下役を務めた(『衆臣家譜』巻三 大悲山氏)。
延享2(1745)年2月16日に卒去。法号は徹叟了道(『衆臣家譜』巻三 大悲山氏)。
女子は伊東宗右衛門友祐に嫁ぎ、その娘(重房孫娘)を養女として、養子・大久文内重行に嫁がせ、跡を継がせている(『衆臣家譜』巻三 大悲山氏)。
久米依時――+=久米暉時 +―伊東寿祐
(半右衛門) |(半右衛門)|(治大夫)
| | ∥――――――+―伊東見祐
+―娘 | 愛澤包高娘 |(司)
∥ | |
∥ +―娘 +―伊東喜八郎
∥ | ∥ |
∥ | 熊川長盈 |
∥ |(勘解由) +―娘
∥ | ∥
相馬胤充―――娘 ∥――――+―相馬胤寿 ∥
(将監) ∥―――――――伊東久祐 (将監) ∥
∥ (伝左衛門) ∥――――――――相馬胤豊
∥ ∥ (将監)
伊東信祐―+―伊東義祐 田原口敬貞――娘
(太兵衛) |(又七) (吉左衛門)
|
+―伊東重祐====伊東久祐
|(太兵衛) (伝左衛門)
|
+―中嶋行正
|(太左衛門)
|
+―伊東友祐
(宗右衛門)
∥―――――――娘
大久重房―+―娘 (大久重房養女)
(兵右衛門)|
+=娘
|(実伊東友祐娘)
| ∥
+=大久重行
(文内)
大久重行 (????-????)
大悲山兵右衛門重房の養嗣子。妻は伊東宗右衛門友祐娘(大久重房養女)。通称は文内。実父は上野庄兵衛猛重。実母は齋藤七太夫清直女(『衆臣家譜』巻三 大悲山氏)。
大悲山重房の長男・大悲山次郎兵衛は公嗣相馬因幡守徳胤の徒士として務めていたが、享保10(1725)年3月18日に松川で「与他邦ノ者喧嘩」したが、これが「次郎兵衛依越度」として捕縛され、二男の青山六太夫も同時に二本松へ出奔したため(『衆臣家譜』巻三 大悲山氏)、上野庄兵衛猛重の次男文内を外孫の伊東友祐女子を養女とした上で重行の婿に迎えて養嗣子とした。伊東家は御一家相馬将監家の縁戚で相馬将監胤寿は重行妻の従兄弟の子である。
●大久、伊東、相馬将監家周辺系図
相馬胤充―+―相馬胤賢
(将監) |(将監)
|
+―相馬胤英==相馬胤壽
|(将監) (将監)
|
+―姉
∥―――――伊東久祐 +―伊東見祐
∥ (傳右衛門) |(司)
∥ ∥ |
∥ ∥―――――+―伊東壽祐―+―女子
∥ ∥ |(太兵衛) ∥
∥ ∥ | ∥
+―伊東義祐 久米依時娘 +―相馬胤壽―――相馬胤豊
|(又七) (将監) (左衛門)
|
+―伊東重祐==伊東久祐
|(太兵衛) (傳右衛門)
|
+―伊東友祐
(宗右衛門)
∥―――――女子
∥ ∥
大久重房―+―女子 ∥―――――――大久重賢
(兵右衛門)| ∥ (六右衛門)
| ∥
+=======大久重行
(文内)
大悲山重行が藩重鎮の伊東家及び御一家相馬将監家と親類になったためか、大悲山家の藩内での家格は上昇したとみられる。
元文2(1737)年8月15日、病死した。法名は月心宗光(『衆臣家譜』巻三 大悲山氏)。このとき、嫡子の六之助はいまだ三歳と幼少だったため、おそらく藩侯弾正少弼尊胤の命により「妻於藤崎助太夫重好ニ重行後室以為入夫守育六之助」とあるように、藤崎重好に重行後室と婚姻して入夫となり、六之助を養育するよう命じたとみられる(『衆臣家譜』巻三 大悲山氏)。
大久重賢 (1735-1794)
大久文七重行の嫡子。幼名は六之助。通称は六右衛門、兵右衛門、のちさらに六右衛門と改称。妻は原三郎右衛門庸隆養女(実父は原左仲庸昌)。後妻は小泉村の宇佐美四郎左衛門女子(齋藤治右衛門後家)。
享保20(1735)年に誕生。三歳の元文2(1737)年8月15日に父の文七重行が亡くなったため、母が再婚した藤崎助太夫重好によって養育される。藤崎家は大悲山家と遠い縁戚であったため、そこに入ったのだろう。
明和5(1768)年12月3日、六右衛門から兵右衛門と改称する。明和8(1771)年6月4日に常小屋手代となり安永3(1774)年3月30日まで務めた。安永6(1777)年に再び六右衛門と改め、「於邦様御傅」となる。安永8(1779)年10月に中小性目附へ移った(『衆臣家譜』巻三 大悲山氏)。
天明2(1782)年5月2日、相馬伊織斎胤の徒士兼目附の斎藤治右衛門が急逝して齋藤家が無嗣断絶すると、その後妻の宇佐美氏を娶り、娘を養女として迎えた。その後、娘を岡崎与太郎文範に嫁がせている(『衆臣家譜』巻十四 斎藤、岡)。
天明3(1783)年7月25日に三之丸御式台番、同年11月7日に中小性目附に復すと、天明5(1785)年2月28日、蓮池番に転じた。翌天明6(1786)年11月7日に竹木奉行に就き、寛政6(1794)年2月20日に亡くなった。享年六十(『衆臣家譜』巻三 大悲山氏)。
長男の大久丑太郎は安永5(1776)年6月18日に早世(夏山涼夢)しているため(『衆臣家譜』巻三 大悲山氏)、次男の兵右衛門重経が家督を継承する。長女は岸平兵衛門長重に嫁いでおり、彼女の孫の岸彦右衛門長安は重経の孫にあたる大久要人要重の女を娶っている(のち離縁)。
後妻の宇佐美氏から生まれた大久弥七(幼名は留之助)は一旦は常詰徒士として仕官するものの「乞永暇之由投書」して去る。養女として弥七同腹の姉(実父は齋藤治右衛門)を引き取り、岡崎弥太郎文範に嫁いだ(文範出奔後は塩崎村の高屋六兵衛に嫁した)。
大久重経 (????-????)
大久六右衛門重賢の次男。母は原三郎右衛門庸隆養女(実父は原左仲庸昌)。幼名は万次郎。通称は兵右衛門。妻は松岡六左衛門武重妹。後妻は深野村の岡田蔵右衛門女(『衆臣家譜』巻三 大悲山氏)。
実兄に大久丑太郎がいたが、安永5(1776)年6月18日に早世(夏山涼夢)している(『衆臣家譜』巻三 大悲山氏)。
寛政6(1794)年4月11日、父重賢の遺跡を継承し、兵右衛門と改称した(『衆臣家譜』巻三 大悲山氏)。
文化3(1806)年5月21日に御普請方小奉行に就任し翌文化4(1807)年6月11日まで務め、半年後の11月27日に再勤を命じられた。文化12(1815)年に柾畳奉行を拝任し文化14(1817)年6月3日に御免となるも8月12日に御普請方小奉行に再任された(『衆臣家譜』巻三 大悲山氏)。
文政元(1818)年11月に常小屋住宅し、文政5(1822)年正月22日に「北町御殿御子様方仙胤公之御子御賄方中小性席」に抜擢されると、2月15日には「御用聞北町御子様方」となった(『衆臣家譜』巻三 大悲山氏)。北町御殿の故相馬縫殿仙胤は九代因幡守祥胤の庶子で藩侯益胤の庶兄である。仙胤は益胤と非常に仲が良く、連れ立って巡検や遠乗りを行うなど良き相談相手でもあったが、文政3(1820)年2月16日、海道からの遠乗りから北町御殿に戻ったところ急病に倒れ三十五歳の若さで亡くなってしまった。その遺児の富之助胤富はわずか五歳とまだ幼く、益胤はその養育担当の一人に重経を任じたのだった。なお、この富之助胤富は天保3(1832)年4月9日に旗本小栗右膳家との婿養子願が幕府に提出されて認められ、9月15日、尚之助は「小栗政寧」を称し、10月に小栗家へ移っている。のちの勘定奉行、関東郡代として異才を放った名幕臣である。明治時代には徳川宗家家扶となっている。
文政5(1822)年3月15日、相馬孫五郎重胤五百回忌にあたり、南北朝時代の混乱の中、相馬五郎重胤とともに江ノ島近郊の片瀬川で陸奥守北畠顕家の軍勢と戦って軍功を挙げた家の子孫に褒賞が贈られた。重経は「昔元享中 重胤公自総州奥州御下向以来、今玆五百載仍之有祝儀、時重経召于 益胤公御前有命」として「大悲山氏者為多武功之旧家也、殊 重胤公見遷当国之節供奉、且於相州片瀬川遂討死、子孫数百年来致相続、以御満悦所念之由」を以て、「大久兵右衛門」は祖の大悲山五郎朝胤が重胤に随って活躍した旧家武功の家柄として五十石(本知のうちより藩が借り上げていた分のうちより五十石)が返付され、都合約百石を知行する(『衆臣家譜』巻三 大悲山氏)。
文政6(1823)年10月2日、倹約のため「被減役人」につき、重経は「御用聞免許」され、天保元(1830)年12月15日、隠居して養嗣子重信に家督を譲った(『衆臣家譜』巻三 大悲山氏)。
大久重信 (????-????)
大久兵右衛門重経の養嗣子。実父は佐藤勇敬重。実母は伏見右衛門尉娘。妻は大悲山兵右衛門重経女(母は松岡六左衛門武重妹)。後妻は阿曽沼道節為重母(二宮五郎右衛門安重女)。初名は鹿股藤太郎。通称は権太夫。
文化12(1815)年5月5日に江戸常詰中小性、文化14(1817)年11月16日に御倹約のために御免となった。文政10(1827)年2月12日、妻の重経女が卒去。天保元(1830)年12月15日に養父重経の隠居に伴い家督を相続する。
天保4(1833)年12月、「菅沼小大膳定邦公御附人」となり、天保6(1835)年正月には「以定邦公有思召之旨、自 益胤公蒙乍勤隠居而奉仕定邦公之厳命」という。
大久要重 (????-????)
大久兵右衛門重経の養嗣子。実父は伊東司自祐。実母は岡和田喜間太嘉重女。妻は大久権太夫信重娘。初名は富田伊助祐守(『衆臣家譜』巻十四 伊東)。通称は要人。
天保3(1832)年4月16日、「益胤公御子様方中小性常雇」となる。天保4(1833)年正月4日、妻の重信女(母は大久兵右衛門重経女)が夭折する。ここで直系血統としての大悲山氏は断絶する。
天保4(1833)年12月に父の経重が旗本菅沼家の隠居大膳定邦(益胤弟)の御附人として出向となり、天保6(1835)年正月に隠居ながら定邦に伺候するよう命が下ったため、要重が家督を継承する。
天保10(1839)年4月に検地奉行、天保11(1840)年5月に在郷給人中頭、弘化2(1846)年に物頭、嘉永3(1850)年4月の「大猷院様二百回忌御相当、依之日光火之番御役場蒙仰、手組召連出張勤之」た。嘉永5(1852)年3月に御持筒頭、同年9月に長柄奉行を務めた。
安政7(1860)年6月、病により職を辞した。
長女は軍司弥市右衛門嘉重に嫁し、次女は初め岸彦右衛門長安に嫁したのち門馬運平征経に嫁いだ。長男は家督を継いだ要人重一、次男は次郎、三男は英三郎という。
大久重一 (????-????)
大久要人要重の子。母は門馬嘉右衛門脩経女。幼名は伊助。通称は要人。
幕末から明治初めにかけておこった旧幕府軍と明治新政府軍の戦いは、慶応4(1868)年4月11日の江戸城無血開城という幕府の全面降伏という形で一応終結したが、奥州には九条道孝を総督とした奥羽鎮撫隊が派遣され、奥羽諸藩に対して、朝敵とされた会津藩の追討を命じた。九条道孝は3月18日に仙台に上陸し、中村藩からは家老・佐藤勘兵衛俊信が藩主名代として表敬訪問している。
4月3日には藩主・相馬秊胤が総督と面会し、仙台藩主・伊達慶邦と会津藩攻撃について協議をした結果、相馬氏は勤皇の意を固め、一門筆頭・岡田監物泰胤(藩主・相馬秊胤の叔父)を隊長とした五百の軍勢が二本松へ進軍を開始、大久要人重一は「小隊長」として従軍した。
●慶長4(1868)年4月9日二本松出陣軍勢
【隊長】 【番頭】 【小隊長】
・岡田泰胤(監物)―+―木幡俊清(勘左衛門)―+――+―池田直行(八右衛門)…600石大身・堀河町
| | |
+―岡部保綱(求馬)―――+ +―金谷顕実(平左衛門)…200石大身・西御壇小路
|
+―都甲良綱(伊右衛門)…250石大身・御壇小路
|
+―中妻軌永(伊兵衛) …80石小身・泉内蔵助胤富屋敷内
|
+―大悲山重一(要人) …100石大身・中町
|
| 【砲隊長】
+―鈴木弥五郎
|
| 【軍司】
+―草野正意(半右衛門)…200石大身・鷹巣町
|
+―多々部直行(藤治) …150石大身・鷹巣町
|
| 【軍目付】
+―桜井高箸(治左衛門)…150石大身・中町
|
+―富田武重(彦太夫) …100石大身・袋町
|
| 【輜重】
+―大越光寛(八太夫) …100石大身・柏葉町