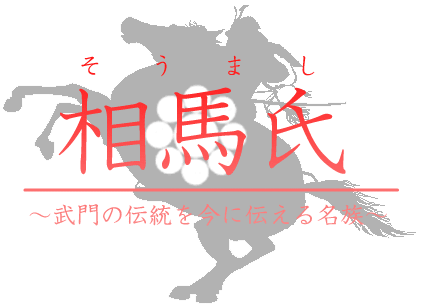
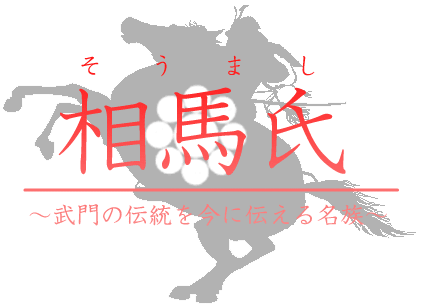
●陸奥国中村藩六万石●
| 代数 | 名前 | 生没年 | 就任期間 | 官位 | 官職 | 父 | 母 |
| 初代 | 相馬利胤 | 1580-1625 | 1602-1625 | 従四位下 | 大膳大夫 | 相馬義胤 | 三分一所義景娘 |
| 2代 | 相馬義胤 | 1619-1651 | 1625-1651 | 従五位下 | 大膳亮 | 相馬利胤 | 徳川秀忠養女(長松院殿) |
| 3代 | 相馬忠胤 | 1637-1673 | 1652-1673 | 従五位下 | 長門守 | 土屋利直 | 中東大膳亮娘 |
| 4代 | 相馬貞胤 | 1659-1679 | 1673-1679 | 従五位下 | 出羽守 | 相馬忠胤 | 相馬義胤娘 |
| 5代 | 相馬昌胤 | 1665-1701 | 1679-1701 | 従五位下 | 弾正少弼 | 相馬忠胤 | 相馬義胤娘 |
| 6代 | 相馬敍胤 | 1677-1711 | 1701-1709 | 従五位下 | 長門守 | 佐竹義処 | 松平直政娘 |
| 7代 | 相馬尊胤 | 1697-1772 | 1709-1765 | 従五位下 | 弾正少弼 | 相馬昌胤 | 本多康慶娘 |
| ―― | 相馬徳胤 | 1702-1752 | ―――― | 従五位下 | 因幡守 | 相馬敍胤 | 相馬昌胤娘 |
| 8代 | 相馬恕胤 | 1734-1791 | 1765-1783 | 従五位下 | 因幡守 | 相馬徳胤 | 不明 |
| ―― | 相馬齋胤 | 1762-1785 | ―――― | ―――― | ―――― | 相馬恕胤 | 不明 |
| 9代 | 相馬祥胤 | 1765-1816 | 1783-1801 | 従五位下 | 因幡守 | 相馬恕胤 | 神戸氏 |
| 10代 | 相馬樹胤 | 1781-1839 | 1801-1813 | 従五位下 | 豊前守 | 相馬祥胤 | 松平忠告娘 |
| 11代 | 相馬益胤 | 1796-1845 | 1813-1835 | 従五位下 | 長門守 | 相馬祥胤 | 松平忠告娘 |
| 12代 | 相馬充胤 | 1819-1887 | 1835-1865 | 従五位下 | 大膳亮 | 相馬益胤 | 松平頼慎娘 |
| 13代 | 相馬誠胤 | 1852-1892 | 1865-1871 | 従五位下 | 因幡守 | 相馬充胤 | 大貫氏(千代) |
■中村藩世子
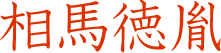 (1702-1752)
(1702-1752)
| <名前> | 鍋千代→菊千代→徳胤 |
| <正室> | おそよの方(内藤豊前守弌信の娘) |
| <正室2> | 英姫(浅野安芸守吉長の娘) |
| <父> | 相馬長門守敍胤 |
| <母> | 品姫(相馬弾正少弼昌胤の娘) |
| <通称> | 内膳 |
| <官位> | 従五位下 |
| <官職> | 因幡守 |
| <就任> | 就任する前に死亡 |
| <法号> | 洞嶽院殿別宗覚天大居士 |
●相馬徳胤事歴●
六代藩主・相馬長門守敍胤の嫡男。母は五代藩主・相馬弾正少弼昌胤嫡女・品姫。妻は越後国村上藩主・内藤豊前守弌信娘・おそよの方。幼名は鍋千代、菊千代。
元禄15(1702)年2月23日「卯上刻(午前五時頃)」(『覚日記』)、江戸藩邸に誕生した。幼名は鍋千代。鍋千代誕生の五日後、実兄の次郎が急死。すでに次兄・圓壽丸は亡くなっており、鍋千代は嫡子として育てられることとなった。3月3日、御七夜の儀が執り行われ、親族の守山藩松平家より鍋千代と母・品姫(昌胤娘、松平頼元孫娘)、藩主・敍胤に祝いの品が届けられている(『守山御日記』)。
その後、敍胤は鍋千代の名を改めることとし、中村歓喜寺に「求馬、菊千代、亀之助」の三つの候補を以て妙見の神前で祈祷させた結果「菊千代」と決定し、4月29日、敍胤は鍋千代の名を「菊千代」と改めた。
宝永元(1704)年3月11日、菊千代の傅役として石川助左衛門昌弘が選ばれた。
正徳元(1711)年8月7日、藩公・相馬讃岐守清胤(菊千代の叔父)は、菊千代(のち徳胤)を嫡子と定め、月番老中・大久保加賀守忠増へ提出。12月3日、清胤は徳胤付御用人として、富田五右衛門政実を配した。
正徳4(1714)年6月27日、徳胤は「菊千代」を「内膳」と改めた。時に徳胤十三歳。7月21日には登城して初目見えを果たし、27日、徳胤についての「明細書」を大目付・松平石見守乗宗に提出した。
内藤信輝養女
相馬昌胤―+―品姫 ∥
(弾正少弼)| ∥―――――相馬徳胤―――相馬恕胤
| 相馬敍胤 (因幡守) (因幡守)
|(長門守) ∥
| ∥
+―相馬尊胤 ∥――――――正千代
|(弾正少弼) ∥
| ∥
+―秋姫 浅野吉長娘
| ∥
| 板倉勝里
|(甲斐守)
|
+―初姫
∥
+―松平清武===松平武雅
|(右近将監) (肥前守)
|
+―徳川家宣―――徳川家継
(六代将軍) (七代将軍)
享保元(1715)年8月7日、徳胤は半元服をし、12月18日、叙爵のために登城。「因幡守」「備前守」のいずれかを希望する願書を提出した。翌19日、老中・久世大和守重之より「因幡守」と定められた。
享保7(1722)年2月3日、越後国村上藩主・内藤伊予守信輝の養女(実は信輝養父・内藤豊前守弌信娘)のおそよとの婚約が成立した。おそよは宝永5(1708)年12月、駿河国田中生まれ(「内藤侯系譜」)であり、当時十五歳、徳胤六歳年下であった。
3月3日、徳胤実母の保壽院(昌胤娘・品姫)が麻布屋敷で病に倒れ、23日に亡くなった。この頃は徳胤も江戸屋敷にあり、おそらくその臨終を看取ることはできたのだろう。保壽院重態の報告は国元にいた藩公尊胤(保壽院は尊胤の義母で実姉)にも届けられたが、尊胤はついに間に合わなかった。
4月21日、徳胤とおそよの方の縁組願いが幕府に提出された。そして、享保9(1724)年9月21日、結納が交わされ(結納金千二百七十三両)、11月3日、結婚式が執り行われた。
内藤信成―+―内藤信正――内藤信照――内藤信良―+=内藤弌信==内藤信輝
(豊前守) |(紀伊守) (豊前守) (豊前守) |(豊前守) (紀伊守)
| |
+―内藤信広――内藤信光――内藤弌信 +―女ソヨ
(石見守) (石見守) (豊前守) | ∥
| ∥
| 相馬徳胤
|(因幡守)
|
+―内藤信輝
(紀伊守)
享保11(1726)年5月15日、叔母の於秋の方と板倉甲斐守勝里の婚約が整い、11月6日にも叔母・於初の方が館林藩主・松平肥前守武雅(武雅の義父・松平右近将監清武は六代将軍・徳川家宣の異母弟)と婚約し、11月18日に結納を交わし入輿したが、武雅は享保13(1728)年7月28日、江戸で急死する。於初は享保17(1732)年5月までに中村藩邸に戻っており、周防徳山藩主・毛利但馬守広豊との婚儀が進められている。
 |
| 同慶寺の直指院墓所 |
享保14(1729)年12月8日、徳胤の正室・おそよの方は二十二歳の生涯を閉じた。婚姻してわずか五年であった。牛込の寶泉寺にて法要が行われ、小高山同慶寺に葬られた。法名は直指院殿見質自性大姉。墓碑は同慶寺御墓に現存する(明治三十二年五月四日「中村原往復行軍日誌」『吉田巌日記 第1』)。なお、享保16(1731)年には長男正千代が生まれているが、当時の徳胤には正室はないため、妾腹の長男(母は不明)となる。
享保16(1731)年3月12日、徳胤の再婚相手として安芸広島藩主・松平安芸守吉長息女・英姫が選ばれた。6月12日、縁組願いの書付が幕府に提出され、そして享保17(1732)年9月16日、婚礼の儀が執り行われた。
英姫はかつて享保6(1721)年正月21日、会津藩世子松平正甫に入輿していたが(「紹称院殿大膳太夫正甫君」の「御正室」の「円寿院殿 松平下総守様より」は入輿前に亡くなっているが、公式に手続きが踏まれており、会津藩では英姫は「御再室」となる(「松平小君略伝」『続会津資料叢書 下』))。享保12(1727)年3月23日に正甫が病死したが、英姫は節を守って実家に戻ることなく三田藩邸に留まり、家中からは「御後室様」と尊称されている。しかし、英姫父の松平吉長は英姫を再嫁させたいと会津藩侯松平正容に相談。正容もこれを容れたため、英姫は表向きは病気療養のためとして享保13(1728)年9月に広島藩下屋敷青山藩邸へ引き移り、これ以降「青山君」と称された。
徳胤はこの婚姻からひと月後の享保17(1732)年10月27日に江戸を発って中村に帰国している。これは昌胤以来の涼ケ岡八幡宮の遷宮に関わる一時帰国であり、翌享保18(1732)年2月12日の遷宮式後、2月24日に中村を発って江戸に向かっている。そして徳胤の江戸登府と入れ替わりに、5月12日、藩主・相馬弾正少弼尊胤が江戸を発って中村へ下った(5月18日中村着)(『覚日記』)。
5月16日、周防徳山藩主・毛利但馬守広豊と叔母於初(館林藩主故松平武雅の旧室)の内縁組が結ばれ、11月25日、毛利広豊が旗本・大嶋織部義陣とともに桜田中村藩邸を訪れ、小野次郎右衛門忠一と土屋平八郎亮直が執持となって徳胤と対面した。広豊帰邸ののち、徳胤は答礼のため即日徳山藩邸を訪れている。しかし、この縁組も於初(石姫)の病気療養のために入輿が延引された上、元文4(1739)年4月23日、於初が桜田藩邸で亡くなった(享年二十八)ことで解消となっている。4月25日、於初は麹町栖岸院(現在は杉並区永福一丁目)に葬られた。法名は玄曠院殿崇譽瑩玉葆眞大姉。なぜ相馬家所縁の墓所ではなく栖岸院に葬られたのかは不明。
おそよ
(内藤信輝養女)
相馬昌胤―+―品姫 ∥
(弾正少弼)| ∥――――――相馬徳胤―+―正千代
| 相馬敍胤 (因幡守) |
|(長門守) ∥ |
| ∥ +―相馬恕胤
+―相馬尊胤 ∥ (因幡守)
|(弾正少弼) ∥
| ∥
+―秋姫 英姫
| ∥ (浅野吉長女子)
| 板倉勝里
|(甲斐守)
|
| 松平武雅
|(肥前守)
| ∥〔婚姻前に死別〕
+―於初
∥
∥
毛利輝元――毛利就隆――毛利元次―――毛利広豊―――毛利豊敏
(中納言) (日向守) (日向守) (但馬守) (富五郎)
↓
大嶋義敬―+―大嶋義苗―+=大嶋義順―+=大嶋義言
(久左衛門)|(雲四郎) |(雲四郎) |(玖珂次郎)
| | | ∥
+―大嶋義陣 | +―女
|(織部) |
| |
+―大嶋義勝 +=大嶋義栄
(内蔵助) (千蔵)
享保19(1734)年4月16日、徳胤は本来は国元に帰るべきところ、持病の痔疾により長旅に差障りがあるとして滞府願を幕府に提出し認められた。そして9月15日、伊豆熱海へ湯治に出かけている。10月3日、江戸に戻るが、治癒には至らなかったようである。
11月5日、江戸において妾腹の次男・内膳が誕生した。のちの相馬因幡守恕胤である。
享保20(1735)年7月15日、長男の正千代が五歳で亡くなり、月海山蒼龍寺に葬られた。法名は大乗院殿寶光玄珠大童子。
藩公尊胤が中村にいるときには、藩公の名代として諸大名の間を走り回り、江戸城に登城するなど活発に藩公世子としてはたらいていたが、享保19(1734)年ころから病がちになっていたようで、元文2(1737)年9月25日の「竹千代様御色直御祝儀」に出席すべきところ、「煩」のため欠席している。
 |
| 同慶寺の徳胤墓所 |
元文3(1738)年5月29日、ようやく病が癒えたため、6月1日、登城して病気快善の御礼を述べた。そして9月9日、竹千代(家治)に初めて謁し、11日には江戸城本丸にて御目見の御礼を言上した。
宝暦2(1752)年5月13日、「俄然嬰病候、官医来診之、薬剤針灸、雖■不尽、其術無験」(『覚日記』)、「江府麻布に損館」した。享年五十一。おそらく江戸の菩提所宝泉寺にて荼毘に付されたと想定される。遺骨は6月7日に中村に到着し、6月「晦日卯の刻」に蒼龍寺の東で葬礼が行われた。葬儀は三代広徳院殿(忠胤)の格で、導師は先例により小高山同慶寺の覚厳和尚が任じられるも、覚厳は当時能州本山の諸学山総持寺の輪番のため不在であり、蒼龍寺住持の泰牛が導師を務めた(『相馬藩政史 上巻』)。法名は洞嶽院殿別宗覚天大居士。小高山同慶寺に葬られた。
 |
| 同慶寺の僊苗院墓所 |
覚厳には江戸から直接徳胤逝去の知らせが総持寺へ届けられ、総持寺では「合山大衆八十人施斎法事焼香」が行われた。その後、8月に輪番交代となった覚厳は9月2日に同慶寺へ帰参した。
徳胤逝去に伴い後室の英姫(浅野氏)は出家して僊苗院と称する。彼女は旧家会津藩との交流も欠かさず、肥後守容頌まで親しく付き合いを続けていた。徳胤が亡くなって十年後の宝暦12(1762)年正月8日、江戸麻布藩邸にて亡くなり、小高山同慶寺に遺骨が移され、蒼龍寺住持の泰牛が法要の導師を務めた(『相馬藩政史 上巻』)。法名は僊苗院殿奇山妙住大姉。同慶寺には徳胤墓碑の南隣に彼女の墓碑が現存している(明治三十二年五月四日「中村原往復行軍日誌」『吉田巌日記 第1』)。
徳川秀忠――保科正之――松平正容――+―松平正甫
(太政大臣)(肥後守) (肥後守) |(大膳大夫)
| ∥
浅野吉長――|―英姫
(安芸守) |(僊苗院殿)
| ∥
| 相馬徳胤
|(因幡守)
|
+―松平容貞――松平容頌
(肥後守) (肥後守)
| 名 | 英 | ||
| 父 | 松平安芸守吉長(安芸広島藩主) | ||
| 母 | 不詳 | ||
| 法名 | 僊苗院殿 | ||
| 事歴 | 享保5(1720)年 | 7月1日 | 松平正甫(会津藩世子)との縁組願 |
| 7月9日 | 納幣 | ||
| 享保6(1721)年 | 正月21日 | 婚儀、三田藩邸入輿 | |
| 享保12(1727)年 | 3月23日 | 松平正甫逝去 | |
| 享保13(1728)年 | 9月 | 会津藩邸から広島藩邸へ引移る | |
| 享保16(1731)年 | 3月12日 | 相馬徳胤(中村藩世子)との縁談 | |
| 6月12日 | 縁組願提出 | ||
| 享保17(1732)年 | 9月16日 | 婚礼の儀 | |
| 宝暦2(1752)年 | 5月13日 | 相馬徳胤逝去 | |
| 宝暦12(1762)年 | 正月8日 | 僊苗院殿逝去(葬宝泉寺) | |