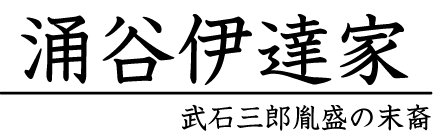
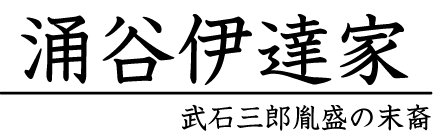
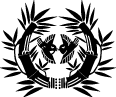 |
 |
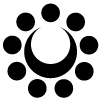 |
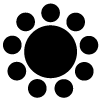 |
 |
| 涌谷竹ニ雀 | 月星 | 月に九曜 | 十曜 | 縦三引両紋 |
【千葉氏】【相馬氏】【大須賀氏】【国分氏】【東氏】【円城寺氏】
〔ご協力・ご参考〕
| 伊達定宗 (1578-1652) |
伊達宗重 (1615-1671) |
伊達宗元 (1642-1712) |
伊達村元 (1666-1718) |
伊達村定 (1687-1723) |
| 伊達村盛 (1715-1736) |
伊達村胤 (1721-1759) |
伊達村倫 (1749-1776) |
伊達村常 (1759-1803) |
伊達村清 (1779-1820) |
| 伊達義基 (1808-1839) |
伊達邦隆 (1835-1867) |
伊達胤元 (1857-1882) |
![]() (1578-1652)
(1578-1652)
武石氏十八代。涌谷伊達家初代当主。父は亘理美濃守重宗。母は相馬弾正大弼盛胤娘(真如院殿光岳健果)。幼名は長松丸。通称は源五郎、右近。官途は安芸守。妻は黒木肥前宗俊娘。中村藩主・相馬大膳大夫利胤とは従兄弟同士である。
天正11(1583)年、長松丸は六歳ではじめて伊達政宗に謁見したという。政宗は手ずから扇を授け、扇に馬を書いてみよと筆をとらせると、長松丸は扇いっぱいに馬を書き、「真に将帥の種なり」と言わしめたと伝わるが、政宗はこのとき十五歳。彼が伊達家の家督を相続するのはこの翌年であることから、この説話が事実とすれば輝宗か。
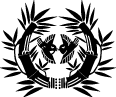 |
 |
| 涌谷竹ニ雀 | 縦三引両紋 |
慶長11(1606)年、「伊達」の氏と「竹雀紋」「竪三引両紋」を宗家・伊達政宗より下賜され、伊達一門に連なった。その五年後の慶長16(1611)年4月7日、母の相馬弾正大弼盛胤の娘(真如院殿光岳健果)が亡くなった。享年不詳。
慶長19(1614)年冬、徳川家康と大坂城の豊臣家との間で講和が決裂。家康は全国の大名に大坂への出陣を命じたが、伊達政宗も10月14日、仙台を出陣して大坂へと向かった。このとき、定宗も政宗より三十騎の旗本が付与され、出陣している。この大坂冬の陣では、伊達家は直接戦いをしないうちに講和が成立し、奥州へと引き揚げたが、翌元和元(1615)年3月に講和が決裂。ふたたび家康から出陣を命じられた伊達家は4月14日に仙台を出陣し、定宗は三千余の兵を率いて大坂へ向かった。
●大坂冬の陣に出陣した定宗の直臣(慶長19年10月14日)
・長谷伊予、坂本伯耆、亘理越中、村岡大炊介、菱沼内膳、渋谷将監、森若狭、森新右衛門、安住織部
●大坂夏の陣に出陣した定宗の直臣(慶長20年4月14日)
・長谷伊予、坂本伯耆、亘理越中、村岡大炊介、菱沼内膳、渋谷将監、森若狭、森新右衛門、安住織部
佐藤助右衛門、蔵本太郎左衛門、千石下野
元和2(1616)年、政宗は茂庭綱元の二男・又次郎を定宗の妹と娶わせ、みずからの名乗りの一字を与えて「亘理右近宗根」と名乗らせ、定宗の父・亘理美濃守重宗の跡(涌谷伊達家ではなく亘理家)を継がせている。実はこの茂庭又次郎は綱元の子ではなく、伊達政宗の庶子である。
元和3(1617)年、将軍・徳川秀忠の養女(池田輝政娘)が江戸屋敷の政宗嫡子・伊達忠宗に嫁いだとき、政宗は仙台城にあったことから、定宗が政宗の代参として秀忠に謁見し、奥州駒一疋を献上。返礼として時服が下されている。
元和6(1620)年正月25日、政宗に従って奥州各地に剛将の名を轟かせた父・亘理美濃守重宗が遠田郡下郡村にて69歳で没した。法名は大運院殿月津雪航大居士。この年、定宗43歳。すでに母もなく、涌谷伊達家は定宗の双肩に委ねられた。
| ■伊達家・亘理家略系図■ +―伊達晴宗―+―輝宗――――伊達政宗 |
元和8(1622)年8月18日、出羽国山形藩主の最上源五郎義俊は一族間の政治的な争いを抑えきれず、幕府より国政不行届を理由に改易されたが、この時、山形城受取の使者として伊達成実と定宗が派遣され、定宗は「鎖切」という銘を持つ佩刀を拝領している。伊達安房守成実は伊達一門の中でも中心的な存在で、政宗の従弟にあたる人物である。これまで伊達家を支えてきた留守上野介政景・亘理元宗(元安斎)亡きあと、片倉備中守景綱とともに伊達家を支えた柱石である。また、定宗の姉(玄松院殿慈輪貞峰大姉)を妻としているため、定宗の義兄でもある。
寛永元(1624)年甲子の年、政宗より百貫文の田地や原野を加増された。
寛永4(1627)年11月14日、政宗は三女・岑姫を定宗の嫡男・伊達宗実に配し、数日ののち、政宗は定宗の屋敷に来訪して饗応を受けた。その際、定宗に小佩刀が下賜されている。しかし、岑姫は嫁いでからわずか8年後の寛永12(1635)年4月22日に20歳の若さで亡くなっており、宗実とは短い結婚生活であった。岑姫の号は清浄院。謚は樹岑蔭涼。
寛永13(1636)年5月24日、奥州の覇者・伊達政宗は70歳の生涯を閉じた。死因は喉頭ガンとも胃ガンともされているが、政宗の死に伴い、世子・忠宗が襲封することを幕府に伝えるべく、定宗をはじめとした伊達一門・奉行ら十余人が江戸城へのぼり、将軍・秀忠に謁見した。
寛永16(1639)年8月23日、定宗の嫡子・伊達宗実は妻・岑姫のあとを追うように二十九歳の若さで亡くなってしまった。彼は涌谷伊達家菩提寺である遠田郡涌谷村の見龍寺に葬られている。宗実が亡くなった事で、天童家に婿養子に入っていた二男・天童甲斐頼長が実家の涌谷家に呼び戻されることとなり、嫡男として藩庁に登記された。この天童頼長こそ、のちの寛文事件で活躍をした伊達安芸宗重その人である。
 |
| 涌谷城 |
寛永19(1642)年8月25日、天童家から戻った嫡男・宗重に嫡男・亥松丸が生まれた。のちに涌谷に妙見社を建立し、亘理家のルーツを千葉の妙見寺(現在の千葉神社)に求めた伊達安芸宗元である。
寛永21(1644)年、涌谷家は加増されて二万石を知行した。また、藩世子・伊達越前守光宗の初入部の際には、仙台城の東にあった花壇にて迎え、小佩刀(銘は国重)を拝領している。
慶安4(1651)年、定宗は老齢を理由に家督を嫡子の宗重に譲り、妻の黒木氏とともに祖父の霊地である遠田郡大貫に隠居した。この際、憚りありとして祖父・亘理元安斎の霊を日枝神社内に合祀している。
慶安5(1652)年正月23日、藩主・伊達忠宗は遠田郡大貫の定宗のもとを訪れ、黄鷹、時服十領、白銀三十枚が下賜された。長年にわたる忠勤をねぎらったのであった。定宗はこの返礼として「青江の太刀」と「国俊の脇差」を献上している。
承応元(1652)年11月29日、大貫村の隠居所にて七十五歳で亡くなった。法名は祈劫院殿林叟凍雲。
姉(玄松院殿)は伊達家の柱石として知られる伊達安房成実の妻となったが子はなく、伊達政宗の子・宗実が養嗣子として伊達安房家に入った。次弟・備後重次ははじめ粟野大膳の養嗣子として粟野家に入ったが、粟野家は故あって断絶となり、亘理家へ戻った。妹の一人は重臣・坂本加賀定俊の妻となり、その弟・出羽重時は伊達家宿老・泉田重光(陸奥国東磐井郡薄衣邑主)の養嗣子となり、泉田家を継いでいる。そして末妹は、伊達政宗の庶子・茂庭又次郎宗根に嫁ぎ、宗根は佐沼亘理家を創設した。
■伊達家・亘理家略系図■
+―娘 +―娘
|(黒川義康妻)|(玄松院殿)
| | ∥
| | 伊達成実
⇒亘理元宗―+―重宗 |(安房守)
(兵庫頭) (美濃守) |
∥――――+―伊達定宗――――――…涌谷伊達家
∥ |(安芸守)
∥ |
相馬盛胤―――――娘 +―娘
(彈正大弼) (真如院殿)|(大立目修理宗直妻)
|
+―重次
|(亘理備後)
|
+―娘
|(鮎貝兵庫宗益妻)
|
+―娘
|(坂本加賀定俊妻)
|
+―泉田重時
|(出羽)
|
+―娘
∥―――――――――…佐沼亘理家
伊達政宗―――亘理宗根
(陸奥守) (又次郎)
伊達宗実(1611-1639)
伊達安芸定宗の嫡男。幼名は牛松丸。母は黒木肥前宗俊娘。妻は伊達政宗三女・岑姫(清浄院樹岑蔭涼)。
寛永12(1635)年4月22日、妻の岑姫が20歳の若さで亡くなり、亘理家の菩提寺・見龍寺に葬られた。さらに、寛永16(1639)年4月7日、祖母の真如院殿光岳健果(相馬盛胤娘)が亡くなり、宗実もあとを追うように、同年8月23日に29歳で逝去。法名は谷陽院殿実壮玄真。
宗実の逝去に、家臣の千石伝兵衛宣治・長橋与五右衛門好仲が殉じた。
=武石家略一族系図=
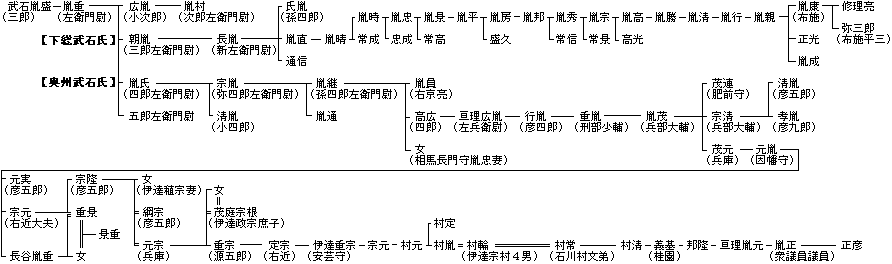
~ご協力・参考文献~
| 坂本氏 | 『佐沼亘理家御系図草案』(享和2年 目々澤新右衛門) 『涌谷伊達家関係資料集』 『平姓千葉一家武石亘理分流坂本氏関係系図並びに史料』 |
| 臼井D-FF氏 | 長野県武石村の武石氏宝塔フォト |
| 『仙台藩史料大成 伊達治家記録 一』 | 監修/平重道 発行/宝文堂 |
| 『亘理家譜』 | 『仙台叢書 第九巻』(平重道 監修 宝文堂) 所収 |