

【国分氏について】【松沢国分惣領家】【村田国分氏】【矢作国分惣領家一】【矢作国分惣領家二】
【千葉氏】【相馬氏】【武石氏】【国分氏】【東氏】【円城寺氏】【千葉氏の一族】
(1)国分氏とは・・・
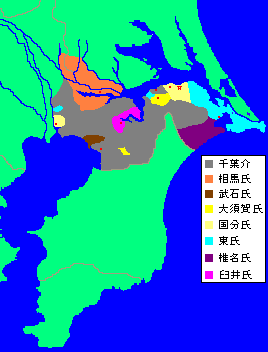 |
| 鎌倉初期の下総国 |
千葉氏流国分氏は、千葉介常胤の五男・五郎胤通が下総国葛飾郡国分(市川市堀之内周辺)を領して「国分」を称したことに始まる氏族である。
五郎胤通が国府付近に入部したのは、少なくとも治承4(1180)年9月以降、源頼朝と平家との戦いの最中であろうと推測され、当初から国府付近を抑えていたわけではない。
五郎胤通はその後、香取神社領内の地頭にも任じられ、香取神宮遷宮に際しては国分寺役として馬庭の埒(柵)の造作が課せられている。
国分寺は国府と谷津を挟んだ対岸にあり、五郎胤通は「堀之内」に館を構え、国府のある国府台から国分寺、その北にあった国分尼寺あたりの国分寺領一帯を抑えていたとみられる。国分寺の遺構からは墨文字の残る平安期の皿が出土している。
五郎胤通は、頼朝に随って平家との戦いに従軍。播磨国と摂津国に進軍してきた平家勢を迎え撃つべく、寿永3(1184)年2月5日に摂津国に到着した蒲冠者範頼の大手勢に加わっている(『吾妻鏡』寿永三年二月五日条)。このときに加わった千葉一族は、千葉介常胤、相馬次郎師常、国分五郎胤道、東六郎胤頼の四名である。一之谷の合戦などを経て、範頼勢は鎌倉に帰還するが、この中に千葉介常胤以下の四名もいたとみられる。8月8日の平家追討の大手範頼勢には千葉一族としては千葉介常胤と平次常秀の二名のみが交名に載せており(『吾妻鏡』寿永三年八月八日条)、五郎胤通はその後の平家との合戦には加わっていないとみられる。
その後、建久元(1190)年には頼朝の上洛に随兵として従い、貞永元(1232)年7月15日、77歳で亡くなったという。なお、胤通は千葉名字を主に称しており、国分寺領を抑えつつも、他の兄弟同様に千葉を拠点としていたと思われる。
| (1) 国分惣領家 |
| (2) 大戸国分氏 |
| (3) 村田国分氏 |
| (4) 矢作国分氏 |
| (5) 大戸川国分氏 |
| (6) 水戸藩・松岡藩士の国分氏 |
| (7) 土井家臣の矢作氏 |
| (8) 奥州国分氏 |
| (9) 米沢藩士国分氏 |
| (10)久保田藩士国分氏 |

|
| 国府台 |
初代の千葉五郎胤通(国分胤通)は、父・千葉介常胤とともに行動することが多かったとみられ、頼朝挙兵時の参陣をはじめとして、養和2(1182)年8月18日の頼朝嫡子の若公(のちの二代将軍頼家)の「七夜の儀」では、奉行の常胤のもと、常胤妻の秩父重弘娘(胤通らの母)、「子息六人」がそれに従っている。 この際、胤通は千葉介常胤からの進物として「御弓箭」を持って、他の兄弟が持つ献物とともに若公に献じた(『吾妻鏡』養和ニ年八月十八日條)。
『吾妻鏡』養和ニ年八月十八日條
●上記系譜
⇒千葉介常胤 +―胤正《千葉介》
∥ |
∥――――+―師常《相馬氏》
∥ |
秩父太郎重弘女 +―胤盛《武石氏》
|
+―胤信《大須賀氏》
|
+―胤通《国分氏》
|
+―胤頼《東氏》
その後、胤通は香取神宮領大戸庄周辺の香取神領の地頭職を給わると、庶子にそれらを分領し、自身もこちらに移った様子が見られる。胤通はこの地で越権することも度々であったようで、建永2(1207)年、香取社神主(大中臣国房ら)が胤通の濫妨を荘園領主「関白前左大臣家(近衛)政所」に訴え、10月にそれに対する『関白家政所下文』が下された。その乱行は10ヶ条にわたって記され、そのすべての停止を求めた。
| (1) |
往古より神領である相根郷(香取市大根)を「地頭堀内」と号して、香取神宮からの検注使の入郷を妨害。官物(年貢)である下苧麥地子を自らのもとに留めおいた事 ⇒前神主・大中臣周房のとき、地頭(胤通)は香取社をあなどって相根郷のみならず、神領内3分の2を押領、周房がこれを訴え出たが、その「御裁許」は遅れに遅れ、また神主職も国房へと替わり、いまだに地頭(胤通)による押領が続いていたため、国房は子細を領主・近衛家の政所へ言上したところ、関白家政所下文に鎌倉下文が副えられた。これをもって地頭胤通に申付けたが、胤通はなおも承引しなかったため、国房は重ねて鎌倉に訴え、幕府から御使いが下って胤通が留め置いていた官物は香取神宮へ戻され、押領した土地も返還された。 広房は去年6月に神主職に就き、12月に相根郷に検注に入ったが、またも胤通は相根号を「地頭堀内」と号してこの検注を妨害し、官物を押し獲った。前神主・国房の時に政所下文・鎌倉家御遣をもって彼の押領は停止されたのに何を称しての例か。無道の至り、言語道断のことである。 |
| (2) | 神官らに圧力をかけて逃亡させ、その領していた田畠在家を押領、官物を押し取った事 ⇒胤通は、神官らを責めて逃亡させ、神慮を顧みず神官を雑役に従事させるといった非法を行う上、絹・牛・馬などは一つのこらず責め取り、他国へ追い、神事が勤められず、その自由勝手な所行はかつて見たことがない。これに加えて、神官が篭居しているときは、「逃亡の跡」と号して地頭分であると主張し、田畠在家を押領、私物とした。これでは、たとえ子孫があって所領を安堵したとしても、神役を勤めがたい。 |
| (3) | 大神田・上分田が地頭(胤通)によって押領されているため、神事に用いる御供が不備である事 ⇒大神田・上分田から取れる米は、年中90余回行われる神事に用いるものである。この押領のためにすでに供物の懈怠がおこっている。神事には本来3石3斗の米が必要であるにのに、今はわずかに78斗しか調達できなず、すでに有名無実となっている。 |
| (4) | 神主の衣食のための「渡田」の押領の事 ⇒代々神主が耕作する「渡田」は、神主の衣食二事のための田であるのに、地頭の郎従が押領してこれを耕作。神主の命には一切随わず、これも極みなき行いである。 |
| (5) | 御宝殿の四面の大竹林から竹を切り取った事 ⇒御宝殿の四面八町は往古からの大竹林であり、庶民がいうには香取大明神は竹一本一本に名をつけ、日に夜にこれを眺められていたといわれ、よって神林は斧の持ち込みは禁じていた。しかるに、地頭は件の大竹をほしいままに切り取ってを持ち去り、残るはわずかに10分の1となってしまった。まったく深慮を恐れぬ振る舞いである。 |
| (6) | 神主に背いて、自由に任せて神官などの座籍を定めた事 ⇒神官職については、大明神以来神主の沙汰であり、重代相伝に尋ね、その器量によって選んでいる。しかし、地頭は就任料として賄賂を取り、重代の例を顧みることをせず、座籍の高下をもまったく知らず、ほしいままに補任しており、新任の輩は神慮に背くによって滅び、前任の輩はより高位を懇望して神宮に出仕をしないため、神事参勤の神官もない。 |
| (7) | 地頭による大神宮寺仏聖燈油修理料田の押領により、勤められない事 ⇒大神宮寺仏聖燈油修理料田は代々の地頭は敢えて妨げを致さなかったが、当地頭は「便田」あるいは「能田」と号してほしいままに押し入って耕作し、まったく弁えることがないため、有限修理・修正・月次講演・ニ季彼岸の勤めなく、無道の至りである。 |
| (8) | 新寺観音堂の仏聖燈油修理料田の押領の事 ⇒観音堂は広房の曽祖父・大中臣真平が建立したもので、それ以来代々の地頭は妨げを行わなかったが、当地頭は去々年より新寺の料田を押取したため、修正・毎月十八日の勤め・ニ季彼岸などの勤めがみな遅延している。 |
| (9) | 神宮寺・柴崎両浦田畠の押領 ⇒神宮寺・柴崎の両浦は神領である。前神主の時、由縁があって両浦を地頭に預けていたが、当地頭はこの先例を称して両浦を押領し、荷揚げの米を返さず、神主の指示にも随わず、もってのほかの濫妨である。 |
| (10) | 御燈油田の田俣村を押領の事 ⇒田俣村(場所不明)は往古よりの神領で、前神主・大中臣友房は田俣村を御燈油田として近衛家政所に申し立て、殿下政所下文を賜った。しかし当地頭は当村を押領したことにより、御燈油役を勤めることができない。 |
大まかにこのような内容であるが、胤通は相根郷(香取市大根)を「号地頭堀内」と称して濫妨を行っていることから、胤通は相根郷近隣に地頭館を構えていたのだろう。さらに、承元3(1209)年の『幕府下知状写』によれば、
とあり、地頭胤通が「国行事」と称して自由に件の竹(香取社宝殿四方八町の大竹林)を切り取っていることは甚だ穏便でない所行であるとし、国行事は神主・大中臣広房の沙汰であることは「国司庁宣」によってすでに明白であることと述べる。国行事とは「国司庁宣」とあるように、国司から任命されて下総一ノ宮たる香取社の神行事に関する権限を有していた。このように胤通の神領に対する押領・濫妨行為は、鎌倉の権威を背景にした地頭職の特徴を示しているものであろう。
胤通のあとは、長男とみられる国分弥五郎時通が惣領となり、次男の国分二郎常通、四男・四郎太夫親胤、五男・小五郎有通、六男・矢作六郎常義は、父・胤通とともに新領の大戸庄周辺に移り住んだと思われる。
なお、弥五郎時通は惣領として国分寺領を継承したが、弘長元(1261)年12月17日造営の宣旨、文永8(1271)年12月10日遷宮になる香取社造営の『下総香取社![]() 殿遷宮用途注文』(『香取神宮文書』)の中で、「三鳥居一基」の造営を担当した人物には「大方郷本役也、仍地頭諏方三郎左衛門入道真性」とならんで「国分寺本役也、仍地頭弥五郎時道女房」が見えることから、この頃すでに時通は没し、跡を継ぐ子もなく「時道女房」が国分寺領の地頭職であったことがわかる。
殿遷宮用途注文』(『香取神宮文書』)の中で、「三鳥居一基」の造営を担当した人物には「大方郷本役也、仍地頭諏方三郎左衛門入道真性」とならんで「国分寺本役也、仍地頭弥五郎時道女房」が見えることから、この頃すでに時通は没し、跡を継ぐ子もなく「時道女房」が国分寺領の地頭職であったことがわかる。
●国分氏想像略系図
【国分寺本主】
⇒国分胤通―+―国分時通
(五郎) |(弥五郎)
| ∥
| 時道女房
|(国分寺地頭)
|
|【大戸庄大戸郷】
+―国分常通――――+―常朝―――+―重常――――+―胤重――+―胤連――+―大進房頼覚
|(二郎) |(小次郎) |(小次郎太郎)|(余五郎)|(彦五郎)|(浄一)
| | | | | |
|【大戸庄大戸郷】 | |【松沢惣領】 | | |
+―大戸親胤 +―国分尼 +―松澤朝胤 | +―頼覚 +―卿阿闍梨明鑑
|(四郎太夫) (孫次郎) | (公一)
| |
|【大戸庄村田郷】 |
+―村田有通 +―道光――――三位――――式部
|(小五郎)
|
|【大戸庄矢作郷】
+―矢作常義
(六郎)
時通には跡を継ぐ子がなかったため、国分氏は早くも国分氏全体を統べる惣領家が姿を消し、大戸庄を地盤とした時通の弟である二郎常通、小五郎有通、六郎常義の系統がそれぞれ独立した御家人として発展していくこととなる。
国分五郎胤通の二郎常通の系統は香取郡大戸庄の多くの地頭職を継承していたとみられるが、それほど大きな力を持ち続けることはできなかったようである、また、胤通の四男・親胤(近胤。四郎太夫)もおそらく父・胤通とともに大戸庄に移り住み、大戸周辺の六村(香取市大戸周辺)を領して「大戸六ヶ村本主」となったが、親胤の子孫は伝わらず、惣領家の時通同様一代で途絶えたのだろう。
二郎常通の子・小次郎常朝も大戸庄を継承するが、おそらく四郎親胤の所有分も継承していたのだろう。寛元元(1243)年の『香取社造営役注文写』(『香取神宮文書』)によれば「![]() 殿」造営の担当所役に「大戸庄
国分小次郎跡」とあることから、常朝はこの頃にはすでに亡くなっていたとみられる。
殿」造営の担当所役に「大戸庄
国分小次郎跡」とあることから、常朝はこの頃にはすでに亡くなっていたとみられる。
常朝の子・小次郎太郎重常の弟に、香取郡松沢庄(香取郡山田町南部~干潟町北部)を領した松澤孫次郎朝胤があり、こちらは「松澤惣領家」として子孫は松沢・関戸・賦馬などを称して発展した。その一流・賦馬氏は「元弘年中有戦功」という「国分上野介満頼」、千葉介満胤の後見人となったとされる「国分越前五郎時常」が著名で、おそらくは千葉介とも密接な関わりを持つ一族であったと思われるが、系譜では時常の祖父とされる「直頼」、父とされる「将頼」はそれぞれ千葉介胤直、胤将の偏諱によるものと考えられ、世代的に賦馬越前五郎時常が満胤の後見人に就くことは不可能である。また、時常の通称は「越前五郎」であることから、「越前守」を称する人物の子息であったと推測される。
松沢朝胤の嫡孫・胤時(孫五郎)までは系譜に通称が記されているものの、その子・胤平は「国分」とだけあって通称がない。そして次代は「頼忠(下野守)」となっており、それまで代々諱(実名)に用いられてきた「常」「胤」「朝」というような字が見られない。さらに子孫は「頼」を通字に用いるようになっており、胤平までの国分氏とは一線を画しているように見える。また、国分直頼・将頼のあとが見られないのは、千葉大介胤直・千葉介胤宣(胤将の弟)が馬加康胤によって討たれたことに関係しているかも? 時代的に見ても、頼忠は2世代ほど前の人物とも思われ、胤平に子がなく断絶したため、千葉介宗家からの指示によって、国分一族で「頼」を通字とする頼忠がそのあとを継いだのかもしれない。
時常の孫・時持(左衛門尉)は千葉介に反発して里見氏と結んでおり、永禄8(1565)年9月18日、正木時忠(里見家家老)とともに木内胤章(右馬助)を米野井城(香取郡山田町米野井)に攻めて討ち取ったとされる。しかし、時常(越前五郎)が千葉介満胤の幼少時の後見人であったとすれば、時代的に永禄8(1565)年にその孫が生きているとは考えにくく、この伝承が事実であれば時持は時常の子孫であろうと思われる。
●松沢・千葉介関係図
[同世代の千葉介] [1291-1351] [1360-1426]
千葉介成胤――時胤―――――頼胤―――胤宗―――貞胤―――――氏胤―――満胤――――――――兼胤――――胤直――――胤将
⇒+―常通―――常朝―――――松沢朝胤―朝俊―――胤時―――+―胤平―――頼忠―――胤頼―――満頼――――直頼――+―将頼
|(小次郎)(小次郎太郎)(孫次郎)(孫四郎)(孫五郎) | (下野守)(五郎) (上野介) (五郎) |(四郎)
| | |
| 【1325年】 +―賦馬時常====================⇒+―時常
+―有通―――師泰―――――胤幹―――胤朝 (越前五郎)
|(小五郎)(孫五郎) (六郎) (孫五郎)
|
+―常義―+―胤実――――――――――胤長―――泰胤―――+―胤氏―――胤詮
(六郎)|(六郎太郎) (又六郎)(彦次郎) |(遠江守)(三河守)
| ∥ |
| ∥ 【1363】+―胤任
| ∥――――大戸河胤村|(小六郎)
| ∥ (彦次郎) |
+―胤義―――――定胤―――女 +―氏胤
(平太) (平太六郎) (与一)
国分五郎胤通の五男・小五郎有通が香取郡大戸庄村田村(香取郡大栄町村田)を領して村田流国分氏となる。系譜では「横山桜田祖」とあり、子孫は香取郡大須賀保横山村(香取郡大栄町横山)・桜田村(香取郡大栄町桜田)をも領していたと考えられる
正中2(1325)年、興徳院(大栄町堀籠)への寄進状には「妙心」「平氏女」「平胤朝」「平胤頼」「平師胤」「平胤近」の六人が名を連ねている。『千葉大系図』上には、有通(小五郎)の曾孫に「胤朝(孫五郎)」「胤頼(孫六郎)」「乙若丸」「千代若丸」の四人が記され、正中2年の興徳院寄進状にみえる「平胤朝」「平胤頼」は有通の曾孫であると思われる。ただ、「平師胤」「平胤近」については系譜上に記載がなく不明だが、「乙若丸」「千代若丸」に相当するか?「平氏女」は胤朝・胤頼らよりも前に書かれていることから、姉か?もしくは胤朝ら兄弟の母で、「妙心」の妻であったかもしれない。
元徳2(1330)年閏6月24日の元徳2(1330)年閏6月24日『関東御教書』(『金沢文庫文書』)によれば東六郎盛義の所領のあった下総国上代郷の中に村田尼願性の知行地があったことがうかがわれる。
こののちの村田流国分氏の流れは伝わっておらず、妙心らの興徳院寄進から40年ほど過ぎた貞治2(1363)年11月18日、興徳院へ「大戸河孫四郎(平胤村)」「平衛門五郎(平貞義)」の両人が「村田郷内堀籠村内国分五郎衛門尉跡」を寄進しており、すでに大戸川国分氏に継承されていたと考えられる。「国分五郎衛門尉跡」とは遠祖「国分五郎左衛門尉胤通」のことか? 「五郎」を通称のなかに用いる傾向にあった村田国分氏のことかもしれない。
国分有通(小五郎)は「横山桜田祖」とあり、横山氏・桜田氏を称した?横山・桜田村も大須賀川を挟んで大須賀氏の所領に隣接しており、特に横山村は谷津一つを隔てた山向こうには大須賀氏の本拠地・松子城があって、助崎城から移った大須賀氏の影響を強く受けたか。応永33(1426)年8月の『寺領注進状案』(『大慈恩寺文書』)の中に、「下総国大須賀保内大慈恩寺当知行領」として「横山村内」とあり、すでに大須賀氏の影響下にあったことが察せられ、村田国分氏の子孫も大須賀氏のもとにあったのかもしれない。
●村田国分氏略系図(胤幹の項は想像)
⇒国分胤通―――有通――――+―村田信胤 +―朝通―――――+―盛村
(五郎) (小五郎) |(五郎太郎) |(彦五郎) |(小五郎)
| | |
+―村田師泰――+ +―小六郎
(孫五郎) | |
| +―又五郎
| |
| +―宗通
| (彦六郎)
|
+―胤幹 +―胤朝
|(六郎・妙心?)|(孫五郎)
| ∥ |
| ∥―――――+―胤頼
| ∥ |(孫六郎)
| 平氏女 |
| +―乙若丸[=平師胤]
| |
| +―千代若丸[=平胤近]
|
+―頼泰―――――+―胤通
(七郎) |(十郎)
|
+―胤頼
(孫七郎)
元徳2(1330)年閏6月24日『関東御教書』(『金沢文庫文書』)
 |
| 国分氏の居城・矢作城址 |
国分五郎胤通の六男・六郎常義が香取郡大戸庄矢作村(香取市本矢作)を領して「大戸矢作領主」となった。この流れがのちに国分氏を代表する家となるが、常義のころは国分氏の一流に過ぎなかった。
常義の嫡子・胤実(六郎太郎)は常義のあとを継いで大戸庄矢作村を支配したと思われ、仁治2(1241)年の千葉介頼胤の家督相続に際してはその後見人となり、千葉本宗家を支える重職に就いている。そして、子・胤長(又六郎)はのちに一族・大戸河国分氏の娘をめとったと思われ、大戸河氏が領していた所領を併合。大戸河氏は子・胤村(彦次郎?弥四郎?)が「外戚所領」を継承していくことになったと思われる。
胤長の嫡子・泰胤(彦次郎)は『千葉大系図』によれば「国分矢作惣領」と記されていることから、同時代に記されている常通系(国分氏嫡流ながら、鎌倉の滅亡とともに減退か)の「松沢惣領」の関戸朝綱(五郎左衛門尉)に対比しているとすれば、矢作系国分氏・松沢系国分氏がそれぞれ惣領制を敷いたと考えられ、相馬氏における「相馬惣領家」・「相馬岡田氏」の関係と似たような関係になっていたとも見られる。
泰胤の子・胤氏(孫六郎・遠江守)は鎌倉滅亡ののちは足利氏に属し、嫡男の胤詮(三河守)とともに活躍している。次男・盛胤(右馬助)は奥州の所領(千代?)に下って奥州国分氏の祖となった。『香取神宮文書』によれば、胤氏は「国分五郎七郎常泰」と「後家西阿尼」の幼少からの養子となっていたと記されているが、「国分五郎七郎常泰」という名を系譜で見ることができない。胤詮(三河守)は叔父の胤任(小六郎)・氏胤(与一)とともに、大須賀宗正(越後守)を筆頭とした千葉介満胤の「後見人」に就任していた。また、胤詮は鎌倉建仁寺から大航慈船和尚を矢作村の大龍寺に招き、ここを国分氏の菩提寺としたと伝わっている。
胤詮の子・忠胤(三河守)は上杉禅秀の乱(応永23年:1454年)では千葉介満胤に従って禅秀方に味方したが、その後、幕府の命を受けた駿河守護・今川範政が鎌倉殿足利持氏を援けて攻撃をかけてきたため禅秀勢は敗れ、忠胤は千葉介満胤らとともに足利持氏に降伏した。
忠胤の子・憲胤(三河守)は亨徳3(1454)年12月、鎌倉殿足利成氏が関東管領・上杉憲忠を暗殺する事件(亨徳の乱の始まり)が起こったために、将軍・足利義政は成氏追討を上杉氏に命じ、千葉介胤直も上杉方に参陣。憲胤も胤直とともに上杉方に加わった。しかし、千葉氏重臣の馬加康胤・原胤房らは成氏に味方したため、憲胤も彼らとともに行動したのだろう。胤直は康胤・胤房らに攻められて自害したが、国分氏は生き残り、憲胤の子・之胤は康胤の孫・孝胤に仕えている。
憲胤の子・之胤(宮内少輔)は千葉介孝胤に仕えた。文明11(1479)年、太田道灌が下総に攻め込んできたとき千葉介孝胤は原・木内など重臣らを引き連れて佐倉から武蔵方面に軍を向かった。これを迎え撃ったのが、太田道灌と武蔵千葉氏の当主・千葉介自胤であった。道灌・自胤らは武蔵の諸将を率いて下総国境根原(柏市酒井根)に陣をはり、ここで激戦が行われた。これを「境根合戦」という。戦いは孝胤の敗北で終わり、佐倉城の前衛基地・臼井城に逃れた。
道灌は臼井城に弟・資忠(図書助)を派遣し、千葉自胤(二郎)を上総へと派遣した。臼井城主・臼井俊胤は一計を立てて、図書助を臼井城内に誘いこんでこれを討ち取り、太田勢に追い討ちをかけて滅ぼした。別動の自胤は下総各地の城を陥落させたが、太田勢の本隊が壊滅状態と聞き、臼井城を攻めることなく武蔵へと帰った。この戦いを「臼井合戦」という。国分之胤は臼井に援軍をだして太田勢と戦っている。
永正14(1517)年、陸奥国を放浪していた古河公方・足利政氏の次男・空然は、上総の武田如鑑入道の支援を受けて甲斐国で還俗。「足利左兵衛佐義明」と名乗って挙兵した。上総武田如鑑は以前から下総の足掛かりとして千葉氏筆頭家老原氏の居城「小弓城」を狙っていて、義明を総大将として小弓城主に攻め寄せた。国分之胤の子・胤盛(宮内少輔)は城主・原胤隆の救援を千葉介勝胤に命じられ、小弓へと向かった。
老城主・胤隆は、一族・原友幸を総大将として義明軍を迎え撃つが、大軍には歯が立たず、重臣の高城胤吉(根木内城主)の援軍がつくまえに城は陥ち、胤隆は自害。友幸も敵中を突破して高城氏の籠る根木内城へと逃れた。おそらく之胤の援軍も間に合わなかったのだろう。
永禄4(1561)年10月ごろから、正木時忠は下総国香取郡に乱入しており、胤之の子孫・胤憲(兵部大輔)は矢作城にてこれと戦っているが、翌永禄5(1562)年5月、胤憲は亡くなってしまった。跡を継いだ胤政(大膳大夫)は、永禄7(1564)年には米之井城主・木内胤倫に援軍を請い、これを撃退する事に成功したが、その翌年にふたたび正木氏が攻めてきたため、防ぎきれずに落城。重臣・伊能景信は子の景久を主とともに脱出させ、自らは戦死したという。ただ、もう一つ説があり、天正14(1584)年、国分氏に嗣子がなかったため、大須賀氏に養子・竹若丸を請い、伊能信月を後見人とした。そこに正木氏が大軍を率いて迫ってきたため、自身の子と主・竹若丸をひそかに城を脱出させて、大須賀氏を頼らせ、信月は戦死した。この事は大竜寺境内の石碑に天正14年7月9日の事件として刻まれている。
胤政は天正9(1581)年、大戸川内の浄土寺を再建しており、天正年中には胤政は矢作に戻っていたように思われる。上の説によると天正14年に国分氏には嗣子がなく、大須賀竹若丸を養子としたことになっているが、国分胤政には鹿島氏に養子を出すほどの男子がおり、別に養子を迎える必要はないわけで少しおかしい。有力者・大須賀氏から養子を迎えて正木氏との戦いを有利に進めようとの考えだったのだろうか?
天正18(1590)年、矢作城は徳川家康の軍勢によって開城され、国分氏は常陸鹿島神宮惣大行事の養子となって同職を継いだ流れ、水戸徳川氏に仕えた流れ、土井氏(佐倉藩・唐津藩・古河藩)に仕えた子孫もあった。
(5)山辺矢作国分氏
国分六郎常義の次男・矢作常氏(六郎次郎左衛門尉)は大戸庄山野辺郷(香取市山之辺)を領して「山野辺」を称し、将軍・九条頼経の近習となったが、時はすでに北条氏の専制体制に入っており、「将軍」も飾り物となってしまっていた。
しかし、頼経は「三寅」と呼ばれていた3歳のころから北条政子のもと鎌倉で育ち、将軍としての資質と風貌を備え、この北条氏専制を苦々しく思っていた。頼経は寛元2(1244)年4月に職を退いて嫡子・頼嗣に将軍職を譲ったのちは、「大御所」として頼嗣を後見し、北条得宗家(北条嫡流)と対立していた。
このようななかで、常氏は了行法師・長久連(次郎左衛門尉)らとともに建長3(1251)年12月26日、謀反の企てがあったとして、佐々木氏信(近江大夫判官)・武藤景頼(武蔵左衛門尉)に生け捕られた。おそらく常氏らは大御所・頼経一派で、執権・北条時頼の暗殺を謀っていたのかもしれない。彼らは諏訪兵衛入道蓮仏の尋問をうけて謀反が露見し、翌日処分を受けた。
国分六郎常義の子・胤義(平太)が大戸庄大戸河村(香取市大戸川)を領して大戸河を称した。そしてその孫・長胤(又六郎・了性)までが『千葉大系図』に記されている。また、同系譜によれば胤義の兄・胤実(六郎太郎)の子に胤長(又六郎入道)があり、その子・胤村(彦次郎)の項目に「就外戚所領」とある。
この胤村は貞治2(1363)年11月18日、興徳院へ「村田郷内堀籠村内国分五郎衛門尉跡」を寄進した「平胤村」と同一人物と考えられ、胤村は「外戚」である大戸河国分氏を継ぎ、兄(か?)の泰胤は矢作国分氏の惣領となっていったと推測される。
大戸河国分氏のその後の活躍は見られないが、『千葉大系図』では、胤村に「幹胤」「胤幹」の二人の子があり、胤幹の子「御房丸」以降は不祥。ただ、「幹」という字を諱に持っていることから、国分氏と常陸大掾家との関係ができつつあったのかもしれない。国分氏は室町期には大掾家と関わりを持つようになっており、江戸時代に水戸藩士となった国分氏は大掾一族・鹿島氏と縁戚で、鹿島神宮惣大行事に代々就任した流れも生まれた。
大戸河国分氏略系図(一部想像)
⇒国分胤通――常義―――+―胤実――――――――――――胤長――――――――国分泰胤
(五郎) (六郎) |(六郎太郎) (又六郎入道) (彦次郎・矢作惣領)
| |
+―山辺常氏 (?)
|(矢作六郎次郎左衛門尉) |
| ↓
+―大戸河胤義――定胤―――+=長胤
|(平太) (平太六郎)|(又六郎・法号了性)[就外戚所領]
| | ∥―――――――――大戸河胤村―――+―幹胤
| | ∥ (彦次郎・春秋) |(太郎)
| | ∥ |
| +―女 +―胤幹――御房丸
|
+―矢作行常―――行泰――――七郎五郎―――――――彦五郎―――――――彦五郎
(六郎) (五郎七郎) (亀王丸) (竹王丸)
矢作城主・国分大膳大夫胤政を祖とする。胤政の孫である国分藤兵衛胤次・国分庄太夫胤久が水戸藩主・徳川頼房に仕えるが、子孫は水戸藩附家老・中山備前守(常陸松岡藩主)の家老となった。幕末の慶応2(1866)年、中山備前守信催の家老に国分庄太夫が見える。
戦国時代最後の矢作城主・国分大膳大夫胤政の子・国分右衛門胤治は誰にも仕えることなく常陸国鹿島に隠居し、一翰と号した。承応元(1652)年に七十五歳で亡くなった。
胤治には権右衛門胤光、理兵衛胤久、おまき(石毛六左衛門茂就妻)、甚五兵衛胤知、新五兵衛三胤の五人の子がおり、胤治の後は長男の国分権右衛門胤光が継いだ。胤光は初名を山三郎といい、慶長15(1610)年に生まれた。寛永元(1624)年、十五歳のときに水戸藩主・徳川頼房の小姓として召し出され、書院番、小納戸役まで立身したものの、病のため正保2(1645)年に三十六歳の若さで亡くなった。
胤光のあとは弟の国分理兵衛胤久が継いだ。妻は藩士・久下八左衛門直忠娘。胤光とは三つ違いの慶長18(1613)年生まれで、寛永19(1642)年、兄・胤光の看病のために鹿島から水戸へ上がって小十人組として藩に出仕した。しかし、正保2(1645)年、兄が亡くなったため、藩を辞して鹿島へと帰った。しかしその後、水戸藩からふたたび召し出され、二百石を賜った。小十人組頭、新料理番、新番組と歴任し、寛文9(1670)年、五十七歳で亡くなった。
胤久の弟、甚五兵衛胤知は鹿島惣大行事の養子となり、新五兵衛三胤は江戸に出て旗本の養子となるが、のちに江戸を辞して水戸に戻り、浪人のまま亡くなった。彼の子は僧侶となった。
胤久の跡は嫡子・国分藤兵衛胤良が継いだ。寛文8(1669)年、病床の胤久に代わり、新番組に入り、延宝8(1680)年には御馬廻組、次いで進物番、江戸金奉行、書院番を歴任し、享保6(1721)年に致仕して夢存と号した。六年後の享保12(1727)年、七十八歳で亡くなった。
宝永4(1707)年2月23日、「矢作殿御子孫国分藤兵衛様」こと胤良が先祖の廟所参りに下総国香取郡牧野村に到着し、観福寺に旅宿を定めた。伊能忠敬の祖父・伊能三郎右衛門景利のもとへも土産物が届けられたという。伊能家はもともと国分氏の老臣の家柄であり、佐原の名主として繁栄していた。旧領の巡回を行ったようである。水戸国分氏と旧領の人々の交流は江戸時代を通じて続いていた。
胤良の長男・国分伴三郎胤続は早くに亡くなってしまい、次男の国分理助胤長が家督を継いだ。胤長は元禄2(1645)年に誕生。宝永3(1706)年、歩行士として藩に出仕、正徳4(1714)年に小十人組、次いで御馬廻組、進物番、大番組、書院番を歴任し、宝暦元(1751)年に六十三歳で亡くなった。
胤長の跡は長男・国分理兵衛胤勝が継ぎ、御馬廻、進物番、大番、書院番などを歴任し、寛政3(1791)年に亡くなった。胤勝の跡は長男・国分右膳胤武が継承し、御馬廻組、進物番などを歴任した。しかし、胤武には跡を継ぐ男子がなく、武石治兵衛胤秀の次男・武石胤将を婿養子に迎え、寛政7(1795)年に亡くなった。跡を継いだ国分理兵衛胤将は寛政12(1800)年に歩行士となり、以降は小十人組、中山備中守信敬組、馬廻組、進物番、大番組へ立身し、文政12(1829)年に亡くなった。
跡を継いだ嫡子・国分膳介胤禄は家禄の百石を継承したものの、はじめは小普請組だった。天保2(1831)年に馬廻組となり、進物番、大番組に転じた。さらに安政2(1855)年に小姓頭取、庭奉行、矢倉奉行などを歴任し、元治元(1864)年に五十石を加増されて大番組に入った。その後、慶応元(1865)年には水戸藩内での諸生派と改革派の権力争いの中で、改革派として捕らえられ牢獄に投獄された。その後の明治維新によって助け出された(『国分氏旧臣由緒関係の展開』・『水府系纂』)。
=鹿島国分家略系図=
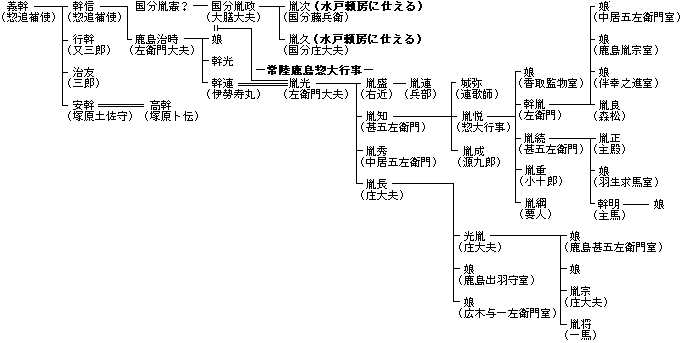
矢作城主・国分氏の一族と伝わる。天正3(1575)年、矢作隼人正が矢作城を離れて小田原城の北条氏政に仕えた。しかし、天正18(1590)年、小田原城が豊臣秀吉の軍勢によって攻め落とされて北条氏が滅亡すると、三河国へ移り住んだ。そして文禄4(1595)年6月、隼人正の子・矢作喜兵衛胤基が家康に召し出されて家臣となった。
慶長7(1602)年7月、土井利勝が香取郡小見川1万石の領主として入部する際、家康から10名の側近が附されたが、胤基もそのうちの一人として利勝に従った。利勝は水野信元の子で、家康の従弟にあたるが、実際は家康の庶子という説がある。尾張義利(義直)・紀伊頼将(頼宣)・水戸頼房らが家康から附家老をそれぞれ附されているが、利勝にも家康の家臣が附されているということは、やはり家康の庶子だったか?
土井利勝に仕えると100石を加増され、さらに慶長17(1612)年に100石が加増、慶長19(1614)年の「大坂の陣」で土井勢に加わって敵将を二人倒し、利勝はこれを称して偏諱を与えて「勝基」と名乗らせた。勝基は佐倉惣奉行として鹿島台に佐倉城の築城を命じられ、その縄張りを担当する。そして寛永10(1633)年12月、600石を知行する重臣となった。そして、勝基の孫・矢作藤左衛門勝行まで土井家の重臣として家政を支えるが、寛文元(1661)年に後継ぎがなく断絶。矢作家の断絶を愁いた唐津藩主・土井大炊頭利実は元文元(1736)年に勝行の弟・矢作喜兵衛勝信が100石を与えられて再興した。
勝信の子・矢作喜兵衛勝与は本多伯耆守家臣・横谷与左衛門娘を母とし、幼名を悦之助、のち千蔵といった。元文3(1738)年3月、御目見を経たのち大小姓となり、寛保3(1743)年4月、矢作家百石の家督を継承する。そして松平右京大夫家中の上村藤七郎の娘を妻とし、宝暦4(1754)年3月には徒歩頭に昇進した。そして宝暦12(1762)年、土井大炊頭利里が唐津から下総古河ヘ転封となると、勝与もこれに従って先祖以来の下総国へ戻り、宝暦14(1764)年5月、倹約奉行に昇進。明和2(1765)年5月には奉行兼任のまま、養子・土井利剛附吟味役兼目付となった。明和3(1766)年5月15日に奥勤兼帯、5月24日には作事奉行加役、翌年5月には二百石を加増され、その翌年8月には槍奉行として役料百五十石を加増された。
その後古河へ戻り、安永2(1773)年9月、物頭格下奉行二百石が加増、さらに銀十枚を下賜された。安永5(1776)年3月、利里が京都所司代として上洛するとこれに従って上洛。そのため7月に下奉行を辞任した。京都では家禄・役職はそのままで吟味役に任じられ、安永6(1777)年9月、利里が京都で客死すると江戸の藩邸へ戻ったが、翌年1月20日に病死した。菩提寺は妙光寺。
=鹿島国分家略系図=
⇒国分隼人正――胤基―――■■―+―勝行
(隼人正) (喜兵衛) |(藤左衛門)
| 上村藤七郎娘
+―勝信 ∥
(喜兵衛) ∥
∥―――――――勝与
横谷与左衛門娘 (喜兵衛)
[土井氏略系譜]
水野忠政―+―信元―――+=忠重 +―利隆――+―利重
| | |(遠江守)|(大炊頭)
| | | |
| 土井利昌=+―土井利勝―+―勝政 +―利久===利実===利延===利里===利見===利厚===利位
| (大炊頭) | |(――) (大炊頭)(大炊頭)(大炊頭)(美濃守)(大炊頭)(大炊頭)
| | |
| | +―利益―――利実 +―利制
+―於大 | (周防守)(大炊頭) |(兵庫頭)
| ∥ | |
| ∥―――――徳川家康 +―利長====利意===利庸―――利信==+―利徳――+―利謙
| 松平広忠 |(兵庫頭) (山城守)(淡路守)(伊予守)|(山城守)|(伊予守)
| | | |
+―忠重 | 伊達宗村―+ +―利以―――利行
| (陸奥守) |(淡路守)(大隈守)
| |
| +―利位
| (大炊頭)
|
+―利房――+―利知―――利寛―――利貞====利義――+=利器
|(能登守)|(甲斐守)(伊賀守)(能登守) (造酒正)|(甲斐守)
| | |
| | +―利延 +―利忠―――利恒
| | |(大炊頭) (能登守)(能登守)
| | |
+―利直==+―利良―――利清―+―利里
(備前守)(大炊頭)
奥州国分氏については、国分盛胤が奥州に移住したと系図に書かれている。その子・盛経は、武石氏の子孫の亘理郡領主・亘理重胤と領地をめぐって争いとなり、応永19(1412)年3月に亘理重胤を討ち取った。しかし、重胤の子・亘理胤茂は父の恨みを晴らすべく、応永23(1416)年9月挙兵、国分盛経の館を急襲してこれを討ち取り、首級を父の墓前に供えた。これで胤通流の奥州国分氏は滅亡したのかもしれない。
文和2(1353)年、「国分淡路守」が奥州探題の命を受け、石川兼光の新恩・宮城郡南目村を兼光へ引き渡す使者となっている。長沼氏はその祖・長沼淡路守宗政以来、惣領家は淡路守を称しており、長沼氏と淡路は大変関係深い。戦国時代の奥州の戦国大名・国分氏は国分胤通の末裔ではなく、この秀郷流長沼一族ともされている。宇奈禰神社(仙台市青葉区芋沢)や諏訪神社(青葉区上愛子)などの棟札には、国分下野守宗治、藤原朝臣長沼、国分弾正少弼廣政、子息宗政、藤原朝臣長沼式部少輔宗治、藤原朝臣国分能登守宗政、国分丹後守宗元といった名前が見える。
伊達家と同盟関係にあった千代城主・国分能登守盛氏の子・国分弾正盛顕には嫡男がおらず、弟・国分右兵衛も元亀年中に刈田郡宮で討死を遂げていたため、天正5年(1577)に伊達政宗の叔父・国分彦九郎政重が養子として送り込まれ、国分盛重と称して国分家督を継いだ。その後、国分氏は政宗の旗下に組みこまれ、天正12(1584)年11月16日、奥州街道上にある人取橋周辺で行われた、天正期の奥州勢力版図を塗り替える大激戦「人取橋の戦い」では二本松の畠山勢を防ぐために杉田に布陣。11月17日、杉田から政宗の本陣に呼び戻され、兄の留守政景や原田宗時とともに本陣の左右を固めた。天正の末、盛重は伊達家を出奔して出羽国秋田郡に住み、盛重の子は持惠澤山龍寶寺の住持となって大僧都法印実永と称した。
盛重の名跡は、秋田佐竹家の一族・佐竹中務大輔義久の子が継ぎ、伊達左門宣宗を称する。妻は同じく佐竹一族の佐竹左衛門義■の娘。寛永9年4月2日、39歳で亡くなった。法名は玉翁宗円。子孫は秋田藩士となったか。
国分盛氏の庶子・郷六七郎盛政は伊達家に仕え、440石取りの虎間番士となる。また、盛氏の五男・駿河は同じく伊達家に仕え、300石の虎間番士の家柄。盛政の系統は森田家を興し、駿河は横沢を称した。家紋は「九曜」「左三巴」。
=奥州国分家略系図=
→国分胤通-常義――胤実――――胤長―――泰胤―――胤氏―――盛胤―――盛経――盛忠-盛行-盛綱-胤実-宗政――+
(五郎) (六郎)(六郎太郎)(又六郎)(彦次郎)(孫六郎)(右馬助)(右馬助) (能登守)|
|
+―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――+
|
+―盛氏――+―盛顕 佐竹義秀―+
(能登守)|(弾正) (中務) |
| |
+―右兵衛 +―実永 |
| |(持惠澤山龍寶寺住持) |
| | +―――處宗
+=盛重――+=伊達宣宗――隆宗――處時===(九郎三郎)
|(彦九郎) (左門) (外記)(市十郎)
|
+―娘―――――娘
| ∥―――――重宗
| 亘理元宗 (美濃守)
| (兵庫頭)
|
+―娘―――――娘
| ∥―――――頼澄
| 天童頼貞 (甲斐守)
| (修理大夫)
|
+―娘―――――娘
| ∥―――――直盛
| 秋保勝盛 (弾正)
|
+―右衛門
|
|
+―娘
|(中目大学妻)
|
+―郷六盛政
|(七郎)
|
+―横沢駿河
下総国分氏の一族とおもわれる。はじめ千葉氏の指揮下にあって、鎌倉公方と幕府との争いに巻き込まれて本拠を捨てたと思われる。上杉謙信に仕えた国分胤広の嫡子は「彦五郎」という。「彦五郎」という人物は国分氏の系図に何人か見られるが、いずれも子孫が不明。
国分美濃守胤元は、永享元(1429)年3月19日、下野国守護代の大石石見守憲重と下野国足利郡高階で争って敗れ、越後国に逃れて守護代・長尾邦景を頼った。邦景は越後守護・上杉房朝に仕え、応永30(1423)年8月の「応永の乱」では房朝とともに鎌倉公方・足利左兵衛督持氏に従って駿河守護・今川上総介範政を迎え討っている。
胤元の子孫・国分佐渡守胤氏は越後国上田城主・長尾房長に仕えてその家老となり、子・国分兵部大輔胤広は房長の嫡子・政景に仕えた。天文20(1551)年8月1日、房長・政景親子が春日山城主・長尾景虎(のち上杉謙信)に降伏すると、胤氏・胤広は景虎に仕え、胤氏は永禄元(1558)年に病死し、胤広も永禄6(1563)年5月6日、上野国沼田で没した。35歳。
胤広の嫡子・国分彦五郎胤吉は長尾政景の側近として仕え、永禄7(1564)年7月5日の政景溺死のときにともに死んでいる。これを聞いた胤広の妻は、国分左馬助正胤・国分治右衛門胤成の兄弟をつれて遺体を引き取りに行ったが、遺骸は胤吉のものではなく政景のものだったという。政景は肩口に斬られた跡があり、謙信の命を受けた宇佐見定満(琵琶島城主)の手によって暗殺されたといわれる。
胤吉の死後、国分正胤が国分氏の家督を継ぎ、謙信・景勝の2代に仕えた。天正14(1586)年6月、景勝は大坂城で関白・豊臣秀吉に謁見し、秀吉の奏聞によって禁裏に参内。従四位下・左近衛権少将に叙任されたが、この時、福嶋掃部頭とともに50騎を率いて列に加わる。翌年5月12日に没した。
正胤の弟・国分胤成は分家して景勝に仕え、関ヶ原の戦いの後、米沢移封に従って200石を知行する。慶長14(1609)年に鉄砲組頭となり、翌々年には50騎を率いる侍大将になる。慶長19(1614)年11月、景勝に従って大坂の陣に参戦し、鴫野口の戦いに武功を挙げた。元和6(1620)年没。
正胤の子・国分左馬助久胤は景勝・定勝の2代に仕え、天正15(1587)年5月、国分家督を継いで50騎を率いる侍大将となる。慶長6(1601)年、米沢30万石に移封された景勝に従って200石取りの藩士となった。慶長19(1614)年11月、景勝に従って大坂の陣に参戦、元和2(1616)年3月に槍足軽大将となった。寛永元(1624)年、2代藩主・上杉定勝のときに鉄砲足軽大将、寛永4(1628)年には加増されて300石を知行。直江兼続の配下40人を預かり、中之門年寄となった。翌年には500石に加増され、寛永13(1636)年2月、信夫福島奉行に任じられた。正保2(1645)年正月没。子孫は代々200石取りの侍組士として幕末にいたった。
●越後長尾氏略系図●
→長尾景為(上杉家執事)―景恒―高景―邦景―実景=頼景(邦景の甥)―重景―能景―為景―景虎(上杉謙信)
下総国分氏の一族で常陸国に移った流れ。水戸藩国分氏とも関係があるのかもしれないが、詳細は不明。
初代の国分勘解由胤賢(仁左衛門、采女)は長沼四郎左衛門尉宗忠の五男。佐竹義宣に仕え、慶長7(1602)年の佐竹家秋田移封に従い、四十五石を与えられ、横手に住した。号は長安。慶長13(1608)年2月12日、亡くなった。法名は宗慶。
胤賢の跡は、胤賢の兄弟、長沼彦左衛門宗教の次男が養嗣子となって国分采女胤則(勘解由)を名乗った。号は雪安、法名は正好。
胤則の跡は長男・国分采女胤道(源七)が継いだ。道号は悟翁、法名は宗頓。妹は国谷金之允忠嗣の妻となった。次弟・高柳喜左衛門吉忠は高柳源左衛門吉持の養嗣子となり、三弟・船木善兵衛光忠は船木善兵衛光景の養嗣子となり、四弟・竹貫九兵衛光真は竹貫九兵衛光秀の養嗣子となった。
胤道の跡は長男・国分采女胤名(弥生)が継いだ。姉は二人おり、長姉は関伊兵衛俊真の妻となり、次姉は野上正右衛門通定に嫁いだ。弟の吉成権兵衛助道は吉成弥五兵衛助勝の養嗣子となった。
胤名の跡は、長男の国分源七胤房が継いだ。妹は妹尾理右衛門兼重の妻となった。弟の三村正右衛門広房は三村正右衛門広重の嗣子となった。
●国分氏の家臣●
・大戸国分氏 国分・鹿島・伊能・平川
=国分家一族略系図=
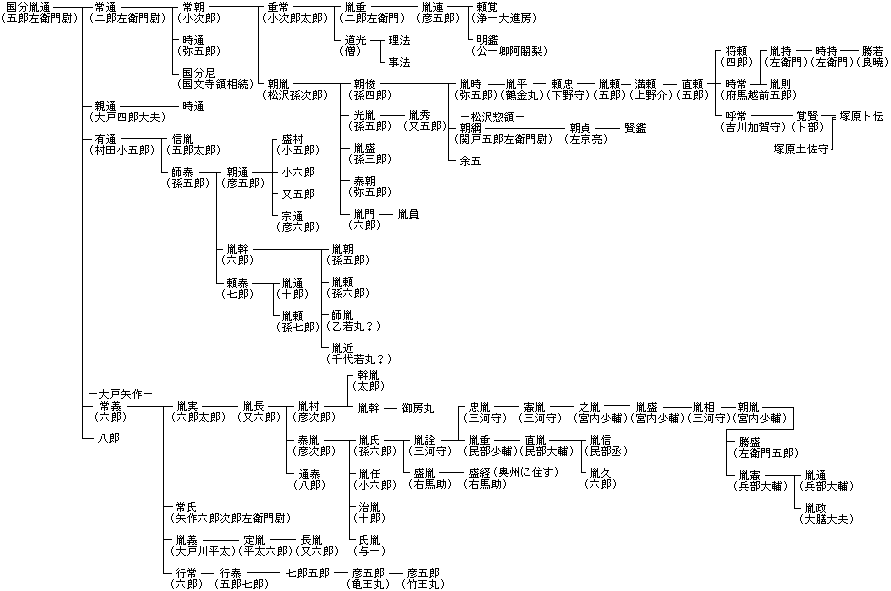
|ページの最初へ|トップページへ|千葉宗家の目次|千葉氏の一族|リンク集|掲示板|
|国分氏について|松沢国分惣領家|村田国分氏|矢作国分惣領家一|矢作国分惣領家二|
copyright(c)1997-2009
chiba-ichizoku all rights reserved.
当サイトの内容(文章・写真・画像等)の一部または全部を、無断で使用・転載することを固く禁止いたします。