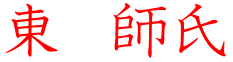 (1343-1426)
(1343-1426)
郡上東氏庶家三代。東下野守常顕の子。官途は下総守。号は素杲。『故左金吾兼野州太守平公墳記』によれば、「応永三十三年、…師氏卒、実八十四歳之冬也」とあり、応永33(1426)年に八十四歳で亡くなったと思われ、逆算すると康永2(1343)年生まれとなる。
●『故左金吾兼野州太守平公墳記』『円覚寺蔵大般若経刊記』を基本とした想像系譜
+―行氏―――時常―――貞常―――素[舟光]====益之
|
東胤行―+―氏村―――常顕―+―師氏―+―泰村
| |
+―常長 +―江西派公
|
+―益之――――正宗龍統
若干内容が不明瞭だが、康応2(1390)年3月17日夜、「東下総守殿」の「家来」であった「小太郎」という人物が反乱を起こしたため、翌18日に「野田殿」が「一族池田将監殿、三木郎衆」を引き連れて松尾城を取り囲み、これを攻め落としたという(長滝寺文書『長滝寺引付書』:郡上八幡町史)。また、3月17日夜、「東下総殿若党小太良」が翌18日に「野田殿松尾城開」て、「守護殿一族池田将監殿、気良勢」を率いて「彼城落了」ったという(長滝寺文書『荘厳講執事帳 第二巻』:白鳥町史 資料編古記録)。松尾城(郡上市大和町大間見)とは大間見郷にあった東氏の城で、東氏の有力支族であった野田氏が入っていたことがわかる。ここの「東下総守」は師氏と考えられるが、その師氏の若党・小太郎が土岐一族の池田将監に内通し、東一族・野田氏の居館である松尾城の門を開き、池田将監によって松尾城が乗っ取られたという意か。
師氏は足利義詮・足利義満・足利義持の三代に仕え、明徳3(1392)年8月28日の将軍義満の相国寺供養の際には「東下総守平師氏」が供奉の三番手についている。その姿は背が高く、鬚が立派な剛勇の武士と伝わる(『相国寺供養記』)。相国寺供養の際の装束は「赤糸金刀、白太刀、朽葉直垂、文竹丸貫熊皮、馬黒鴇毛、蒔絵鞍白覆輪帯引」である。
●先陣三番:東下総守平師氏
(副添:遠藤修理亮顕基・遠藤新左衛門尉顕保・遠藤郡左衛門大夫顕久・遠藤兵庫助氏遠)
このとき、師氏の「掻副」であった遠藤一族は東氏の根本被官であり、曽祖父・東行氏の代には遠藤左衛門三郎盛氏という人物が見える。おそらく彼らは遠藤盛氏の子孫であり、「遠藤修理亮顕基」「遠藤新左衛門尉顕保」「遠藤郡左衛門大夫顕久」は師氏の父・常顕の偏諱を、「遠藤兵庫助氏遠」は師氏の「氏」を受けたものだろう。師氏と並列で進んだのが同族の「粟飯原九郎左衛門尉平将胤」である。
師氏も歌人として知られ「素杲」と号した。時の歌人・招月庵清巖正徹は師氏の歌を「理のうへを美しく遊ばしけるとみまゐらせしなり」と評している。西行法師の家集『山家集』を愛読し、勅撰集の『新後拾遺和歌集』『新續古今和歌集』に計四首選ばれている。
応永16(1409)年、「東四郎」が病に臥せったたことを聞いた美濃守護・土岐頼益は、9月7日、郡上郡気良(郡上市明宝気良)に侵攻した。しかし、東氏の恩恵を受けていた郡上郡の民衆は、郡内の中野川に砦を築いて土岐勢の侵略を許さず、頼益もついに侵攻をあきらめた(長滝寺文書『荘厳講記録』:白鳥町史)。ただし、このころ師氏は六十七歳、すでに出家して「素果 東下野入道」を称しており、この「東四郎」は師氏の子・東泰村か。泰村は早くに亡くなり、玉洞禅庵を導師として祠が建てられた(『故左金吾兼野州太守平公墳記』)。
応永33(1426)年10月12日に八十四歳で没した。法名は松林院暁月常山。のち建仁寺の正宗龍統(師氏孫)が東益之(師氏子)が亡くなった際の記述で「京之先壟霊泉(建仁寺霊泉院)」と認めていることから、師氏も霊泉寺に葬られたのだろう。