

| ―― | 初代 | 二代 | 三代 | 四代 | 五代 | 六代 |
| 千葉胤賢 (????-1455) |
千葉実胤 (1442?-????) |
千葉介自胤 (????-1493) |
千葉介守胤 (1475?-1556?) |
千葉胤利 (????-????) |
千葉胤宗 (????-1574) |
千葉直胤 (????-????) |
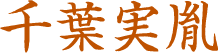 (1442-????)
(1442-????)
| 生没年 | 嘉吉2(1442)年?~???? |
| 通称 | 七郎 ※千葉新介(『鎌倉大草紙』) ※千葉介(『上杉系図』) |
| 父 | 千葉中務大輔胤賢 |
| 母 | 不明 |
| 妻 | 扇谷上杉大夫三郎顕房女子 |
| 官位 | 不明 |
| 官職 | 不明 |
| 幕府役 | 千葉介 |
| 所在 | 武蔵国石浜 |
| 法号 | 不明 |
| 墓所 | 岐阜県可児郡御嵩町の大寺山願興寺? |
初代武蔵千葉氏。千葉中務太輔胤賢入道の嫡男。通称は七郎。「千葉介」(『上杉系図』)または「千葉新介」(『鎌倉大草紙』)を称したともされるが、公文書には見えず「七郎」の仮名のみ伝わっていることから、実際には千葉介の称はなかったとみられる。妻は扇谷上杉大夫三郎顕房女。「七郎」は北斗七星にちなんだ通称かもしれない。弟の自胤は千葉胤賢次男で「次郎」を通称としている。
千葉介満胤―+―千葉介兼胤―+―千葉介胤直――千葉介胤宣
|(千葉介) |(千葉介) (千葉介)
| |
| | 扇谷顕房――――娘
| |(修理大夫) ∥
| | ∥
| +―千葉胤賢―+―千葉実胤
| (中務丞) |(七郎)
| |
| +―千葉介自胤―――千葉介守胤
| (千葉介) (千葉介)
|
+―馬加康胤――――千葉胤持
(陸奥守)
享徳3(1454)年12月27日、関東管領上杉憲忠は成氏の西御門邸に召し出され、殺害された。「上杉右京亮妙椙廿二歳、享徳三甲戌十二月被誅」(『本土寺過去帳』廿七日上段)と見え、当時憲忠は二十二歳だった。同じく憲忠に供して行った家宰・長尾但馬守実景も「長尾但馬守親子打死」(『本土寺過去帳』廿七日上段)とあるように、討たれている。腹心の長尾左衛門尉景仲入道や、舅の扇谷修理大夫持朝入道らが鎌倉を不在にしている間の出来事であった。
●『本土寺過去帳』廿七日上段
憲忠殺害の日の夜、成氏近臣の「岩松右京大夫殿(岩松持国)」は「廿七日雖及夜陰、最前馳懸山内、致手合之戦、自身被御疵」(享徳三年十二月廿九日「足利成氏感状写」『正木文書』戦古:19)とあるように、山内(鎌倉市山ノ内344辺)の憲忠邸に攻め寄せて山内上杉勢と合戦している。成氏近臣の宍戸中務大輔持里に属した庶家「筑波別当大夫潤朝」は「従同十二月廿八日」合戦に加わっているとあるため(享徳4(1455)年2月筑波潤朝軍忠状案写(「古証文二」神奈川県史料6187)、この山内亭近辺の合戦は、翌日も継続的に発生していたと思われる。
●長尾系図(『長林寺長尾系図』ほか)
長尾景為―+―長尾景忠―+―長尾孫六 +―長尾顕忠====長尾顕方
(新五郎) |(新五郎) | |(尾張守) (孫太郎)
| | |
| +―東初玄春 +―長尾修理亮 +―長尾能登守
| |(平三) | |
| | | |
| +―白埴三郎 +―長尾忠政――+―長尾良済===長尾忠景―+―成田下総守
| | |(尾張守) (皎忠) |
| | | |
| +―長尾忠房―――+ +―長尾弥五郎―――長尾顕方
| |(大宅是棟) | (孫太郎)
| | |
| | +―長尾能登守―――長尾景明―――長尾実明―――天巌永承――――長尾定明―――長尾顕景――+―長尾景孝
| | (深用全功) (醒心長泉) (厳翁承端) (平五) (左衛門大夫)|(左衛門佐)
| | |
| +―長尾景直―――+―長尾景英――+―長尾房景―+=長尾実景―+―長尾六郎 +―長尾景総
| (新五郎) |(新五郎) |(新五郎) |(但馬守) |(春岩桂芳) (能登守)
| | | | |
| | | | +―長尾景人――+―長尾定景
| | | | |(但馬守) |(但馬守)
| | | | | |
| | | | +―長尾房清 +―長尾景長―+―長尾憲長――――長尾景長
| | | | |(道存) (但馬守) |(新五郎) (新五郎)
| | | | | |
| | | | +―禅正院 +―女子
| | | | | (那波刑部室)
| | | | |
| | | | +―女子
| | | | (安保常陸守室)
| | | |
| | | +=長尾景仲―+―長尾景信――――長尾景春―――長尾景英――――長尾景誠
| | | (孫四郎) |(左衛門尉) (左衛門尉) (左衛門尉) (孫四郎)
| | | |
| | +―長尾伯耆守――長尾景仲 +―長尾忠景
| | (孫四郎) |(皎忠)
| | |
| +―長尾出雲守―+―長尾実景 +―長尾出雲守
| (花渓道俊) |(但馬守)
| |
| +=長尾六郎
| |(春岩桂芳)
| |
| +=長尾房清===長尾出雲守――長尾左近将監
| (道存)
|
|
+―長尾景春―――長尾景恒―――+―長尾長景―――+―長尾久景――長尾勝景
(豊前守) |(新左衛門尉) |(太郎) (因幡守)
| |
+―蔵王堂秀景 +―長尾道景――長尾道忠
|(豊前守) |(源次郎) (源次)
| |
+―長尾依景 +―長尾氏景――長尾永景―――長尾顕景
|(勘解由左衛門)|(弾正) (平次) (下総守)
| |
| +―長尾朝景
| (信濃守)
|
+―長尾高景―――+―長尾邦景――長尾実景
|(筑前守) |(上野介) (但馬守)
| |
+―女子 +―長尾景房――長尾頼景―――長尾重景――――長尾義景―――長尾為景――+―長尾晴景
|(三省寺比丘尼) (左衛門尉)(信濃守) (信濃守) (信濃守) (信濃守) |(弥六郎)
| |
+―女子 +―長尾輝虎
(宇佐美伯耆守室) (弾正大弼)
翌享徳4(1455)年正月5日、京都へ「関東飛脚到来、鎌倉殿持氏御子 成氏、去年十二月廿七日、管領上杉右京亮房州入道子、被召出於鎌倉殿御所被誅伐」(『康富記』享徳四年正月六日条)という確報が届く。その理由は「是併故鎌倉殿御生涯事、父房州申沙汰之御憤歟」との推測があり、「依之御所方与上杉手有合戦」と、御所方と上杉家との合戦も報告された。
成氏は享徳4(1455)年正月5日、武蔵国の戦勝由緒の稲荷大明神(現在の烏森神社)に願文を収め、「所願悉有成就」を祈っている。当時、この稲荷社は荒れていたのか、所願成就のあかつきには社殿修造を行うと誓っている。
●享徳4(1455)年正月5日「足利成氏願文」(『烏森神社文書』戦古:20)
翌正月6日には、「上杉修理大夫入道并憲忠被官人等」が七沢の要害を出て鎌倉を目指したのだろう。相模川の低湿地帯の中と推測される「相州島河原」(平塚市大島)に兵を繰り出した(「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)。この報を受けた成氏は「一色宮内大輔、武田右馬助入道」を差し遣わして、「多分討取候了」という。これはかつて故父持氏が上杉憲実の上州逐電時に取った進軍方法を彷彿とさせるが、こののち、成氏は自ら鎌倉を出立して武蔵府中へ進んだ。なお、成氏はこの鎌倉発向ののち二度と鎌倉へ帰還することができず、以降、子孫に至るまで下総国古河(茨城県古河市)を拠点とする「古河様」として、16世紀後半までの約百数十年間、関東に強い影響力を及ぼすこととなる。
正月7日には常陸国の「就右京大夫参上」しており、成氏は憲忠追討直後には佐竹右京大夫義人入道に次第を伝えて協力を取り付けており、佐竹一門だが義人入道とは距離を取っていた「大山因幡守殿(義人に追放された義人嫡子・伊予守義俊の外祖父)」に「属右京大夫手、不日馳参」ことを命じている(享徳四年正月七日「足利成氏御教書写」『秋田藩家蔵文書七 大山弥大夫義次所蔵』:戦古21)。これには成氏近臣「本間前近江守直季」も副状を付しているが、大山因幡守は正月29日に至っても成氏方には参じていない(享徳四年正月廿九日「足利成氏軍勢催促状写」『秋田藩家蔵文書七 大山弥大夫義次所蔵』:戦古24、参考四)。
武蔵国府へ進む一方で、正月14日には「豊島勘解由左衛門尉殿」、「豊島三河守殿」ら武蔵豊島一族への参陣を命じるなど(享徳四年正月十四日「足利成氏軍勢催促状」『豊島宮城文書』:戦古22、23)、東武蔵への勢力拡大にも腐心する。
正月21、22日には、「上杉右馬助入道、同名太夫三郎并長尾左衛門入道等」が「武州、上州一揆以下同類輩、引率数万騎、武州国府辺競来」(「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)と、上野国から庁鼻和右馬助憲信入道、大夫三郎顕房(修理大夫持朝子息で扇谷家当主)、長尾左衛門入道が武州上州一揆らを率いて武蔵国府付近に着陣した。成氏はみずから「於高幡、分倍河原」に布陣し、「両日数箇度交兵刃、終日攻戦」した。具体的には21日は「武州立川之御合戦」、22日は「府中之御合戦」(享徳4(1455)年2月筑波潤朝軍忠状案写(「古証文二」神奈川県史料6187)と見え、21日は鎌倉街道より西・北西部での合戦であったことはわかる。21日の合戦で高幡河原から多摩川上流部を渡って国府西側を占拠する部隊があり、22日に鎌倉街道正面から分倍河原に出て国府を攻める部隊の西・南の二面から上杉勢を攻めたということか。この合戦で「上椙両人討取、数人候」(「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)といい、庁鼻和憲信入道、扇谷顕房、そのほか主だった者数名も鎌倉勢に討ち取られた。合戦後、「至于今残党者、束手令降参候了」(「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)するが、「其後、敗軍余党等、常州小栗城ニ館籠」っている。
鎌倉勢は小栗城を攻めるべく、「野州、結城、御厨江進旗差向」(「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)ている一方で、上野国では岩松右京大夫持国が鎌倉方の主将となって上杉方と合戦し、2月中には「於深須、赤堀、太胡、山上合戦」が起こっている。持国はこの合戦の詳細を成氏に注進しているが、これらの合戦は岩松持国方には不利な状況であったようである。成氏は2月26日に受け取って披見し「誠無心元被思食候」(享徳四年二月廿七日「足利成氏書状写」『正木文書』:神6185)と返信をしている。持国は続けて「国時宜、巨細注進」を成氏に送達した。これに3月5日、成氏は「左京大夫持国」に宛てて「猶以有調儀、可被寄御陣候、敢不(可)有聊尓候」とすること、また「三大将、能々可被申談候」ことを佐野伯耆守をして伝えている(享徳四年三月三日「足利成氏書状写」『正木文書』:神6189)。この「三大将」がいかなる人々か成氏の言及はないが、桃井左京大夫持国に加えて、同所で戦っている「桃井左京亮」(享徳四年五月廿五日「足利成氏書状写」『正木文書』:戦古66)、「鳥山式部大夫」(享徳四年五月廿七日「足利成氏書状写」『正木文書』:神6216)の三名となろう。このほか上州の主だった大将としては「石堂、一色、世良田、里見」(『康富記』享徳四年七月廿六日条)の名が見える。上野国の上杉方としては「安威新左衛門以下」の名が見えるが(享徳四年三月十九日「足利成氏書状写」『正木文書』:戦古36)、安威氏は細川家や斯波家の被官として名が見えるが、安威新左衛門は管領細川勝元のもとで足利庄に送り込まれていたか。
成氏は2月中には古河に本陣を置くことを決定しており、3月3日には古河に入っている。その際「上州中一揆事、古河江可被御供候」ことを「岩松右京大夫殿」に伝えており(享徳四年三月三日「足利成氏書状写」『正木文書』:戦古29)、あわせて上州中一揆の人々の「知行分等」への狼藉を固く禁ずる旨を伝えている。
京都はこの成氏出師に対し、3月28日に「上椙ヽヽ故房州入道子関東発向」(『康富記』享徳四年三月卅日条)させた。彼は上杉憲実入道の次男・兵部少輔房顕(幼名龍春)で、成氏に殺害された関東管領憲忠の実弟である。彼を「総大将」(『康富記』享徳四年三月卅日条)として関東派遣が行われた。この出陣は「春三ヶ月東方有憚、来月可進発之由雖存之、延引不可然之由、自室町殿被仰下之間、下向北国通」(『康富記』享徳四年三月卅日条)とのことで、正月~三月は東方進発は不吉であることから、四月に入ってからとの意見もあったが、将軍義政が延引を認めないと述べたため、3月中の派兵となっている。このとき房顕には「御旗」が下されているが、「為退治申鎌倉殿、為総大将所被差遣也、御旗被下之、世尊寺侍従三位伊忠卿被書之」(『康富記』享徳四年三月卅日条)というものだった。なお、その後東国に下向した主将は八名だったようで、「悉皆御旗八流也、其内錦御旗一流也、其者文字を書て、彫て、絵師ニ仰て、薄をもて字の上をたましむる也、日の形あり、元はこれも紙に書て、はくにて採色す、今度は御旗ニひたとはくを置也、紙をもてたますと云々、七流は布御旗也、其者布ニ字を書也」(『康富記』享徳四年閏四月十五日条)という。房顕に託された御旗は世尊寺伊忠の染筆(八幡大菩薩の文字か)によるものであることから、これが「錦御旗一流」であろう。
続けて、4月3日には「駿河守護今河ヽヽ、今日関東発向、関東御退治御旗被給之」といい、「御旗」を給わって京都から下向している(『康富記』享徳四年四月三日条)。彼の賜った「御旗」は「布御旗」となる。このほか「去月時分、為関東御退治、自武家御旗被下関東也、上椙、今河、桃井等賜之、下向也」(『康富記』享徳四年閏四月十五日条)とあるように、桃井某ほか五名(越後上杉房定ほか四名か)の大将が関東に攻め下った。
故義教は「都鄙無為」の理想のもと、関東持氏(彼も京都の威光をひけらかして鎌倉の意向を無視する人々を討つ基本理念を堅持)との戦いを回避すべく様々な努力を行ったが、今回の関東追捕については、当の鎌倉殿成氏も将軍義政も年若く、管領細川勝元以下の室町殿政権を率いる閣僚も未熟であり、地道な努力は行われずに戦端が開かれている。
鎌倉方が攻め立てていた小栗城は、4月5日には「即時外城攻落」した注進が4月6日早旦に成氏のもとに届られている。成氏はこの旨を含め、「実城も幾程不可有」との観測を岩松持国へ伝えている(享徳四年四月六日「足利成氏書状写」『正木文書』:戦古44)。実際に小栗城が「彼城則時悉没落候上」(享徳四年五月廿日「足利成氏書状写」『正木文書』:神6213)したのは5月20日あたりと推定されるが、成氏はその後「小山」へ着陣(享徳四年五月晦日「足利成氏書状写」『正木文書』:戦古69)した。
ちょうどこの頃、「上杉民部太輔、同兵部少輔、具越州信州群勢、長尾右衛門入道、集調武州上州党類、野州天命、只木山、侘日張陣」と、越後上杉房定、上杉房顕(総大将)の両名が越後・信濃の兵を率い、長尾景仲入道は武蔵・上野の兵を率いて、下野国天命(佐野市天明町)、只木山に布陣した。岩松持国はこの越後勢を前に「当国時宜火急」という注進を成氏に伝えている(享徳四年五月廿五日「足利成氏書状写」『正木文書』:戦古67)。また、岩松持国とともに戦っている「桃井左京亮」が上杉勢に戦勝したことを賞し(享徳四年五月廿五日「足利成氏書状写」『正木文書』:戦古66)、同じく「鳥山式部大夫」も「仍大手合戦火急間、其方御幡一所仁可被立申候」については成氏も賛同し、天命の陣には成氏自ら急ぎ加勢する旨を岩松持国に伝え、その間は桃井左京亮、鳥山式部大夫と「能々調儀可然候」「能々可有遠慮候」して対処するよう指示している(前述のように、岩松持国に加えてこの二名が、成氏から「三大将」と称されているとみられる)。「御幡」は京都の錦旗に対抗するものであろう。これら合戦の後詰として、成氏自身が6月13日には「已天命江被寄御馬候」し、持国に「速其方可有御進発候、心安可被存候」と伝えている(享徳四年六月十三日「足利成氏書状写」『正木文書』:戦古74)。
そして、これらの京方の攻勢に「如合符、所々江令蜂起」したのが、「千葉介入道常瑞、舎弟中務入道了心、宇都宮下野守等綱等」(「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)であった。
享徳3(1454)年12月27日の関東管領上杉憲忠殺害の余波は、鎌倉のみならず、下総国にも波及することとなった。
この殺害事件のちょうど半年前、亨徳3(1454)年6月23日に千葉介胤将が亡くなっている。「千葉介胤将高山改名蓮覚享徳三甲戌六月 廿二歳」(『本土寺過去帳』廿三日上)とあるように二十二歳の若さだった。その跡は胤将の弟・五郎胤宣が継承するが、『本土寺過去帳』には「第十四宣胤 十二才」、「千葉介宣胤法名妙宣五郎殿十三歳」とあるように、幼少であることから、引き続き胤直入道が事実上の惣領家として家政を見たのだろう。こうした千葉惣領家の中でも落ち着かない状況の中で、12月27日の上杉憲忠殺害事件が起こった。
この殺害事件に対して、京都は情報到来から二か月半後の3月28日、「上椙ヽヽ故房州入道子関東発向」(『康富記』享徳四年三月卅日条)させ、4月3日に「駿河守護今河ヽヽ、今日関東発向、関東御退治御旗被給之」(『康富記』享徳四年四月三日条)させて、成氏追討を命じた。将軍義政は故将軍義教のような、一事を深く重く考えて行動する環境が整っておらず、場当たり的な征東が発令されてしまっている。このとき関東攻めの総大将は、憲実次男の上杉兵部少輔房顕(憲忠実弟の龍春)。関東管領職とともに「錦御旗」が下された。この錦旗は朝廷下賜だが、成氏追討の綸旨は出されておらず、実際に「関東御退治之綸旨」が下されたのは9月24日(『東寺百合文書』享徳四年九月廿四日条)で、このことからも義政の場当たり的な無策ぶりが露呈する。
胤直入道は4月下旬頃、京都に忠節を誓う旨の書状(現存せず)を遣わしたとみられる。その内容は伝わらないが、「自関東連々雖相催、不令同心之旨」(享徳四年閏四月八日「将軍家御内書」『佛日庵文書』神:6204)とあるように、成氏からの度々の催促に応じなかった旨が記されていたことがわかる。それまで胤直入道がどこに所在していたのかは定かではないが、十一、二歳の幼少の当主・五郎胤宣ひとりを鎌倉において下総国に戻ることは考えにくく、鎌倉に在住していたと考えるのが妥当だろう。
胤直入道が京都へ遣わした書状に対し、翌月閏4月8日、将軍足利義政から「千葉入道との」へ、鎌倉方からの度々の誘いにも応じずに京都方に属したことに対し賞する御内書(享徳四年閏四月八日「将軍家御内書」『佛日庵文書』神:6204)を送り、太刀一腰を贈呈している。
●享徳4(1455)年閏4月8日「将軍家御内書」(『佛日庵文書』神:6204)
『鎌倉大草紙』では、惣領家執政の原越後守胤房が胤直入道に「御所方になりたまへ」と成氏に加担するよう説得したが、原胤房と対立関係にあった「円城寺下野守、上杉にかたらはれ」ていたため、胤直入道は円城寺下野守尚任の意見を容れて京方となり、胤房は「原はひそかに成氏より加勢を乞」うたのだとする。胤房は侍所司の胤直の代官的な立場であったことが永享7(1435)年の法難対処の伝から推察され、成氏が鎌倉に還御したのちも、胤直入道の代理として御所を訪れることがあったのだろう。「公方へも出仕申ければ、成氏より原越後守を頻に御頼ありける」という(『鎌倉大草紙』)。原氏と円城寺氏は鴨根三郎常房を遠祖とする同族で対立関係にあった。「千葉家、原与園城寺合戦、園城寺武州没落」(『鎌倉大日記』)ともあるように、この合戦は原氏と円城寺氏の争いでもあったようだ。
なお、『千学集抜粋』では、3月20日に「三月廿日、千葉へ押寄せければ、俄の事にて防戦叶い難くして千葉の城を歿落す」(『千学集抜粋』)とあるように、胤房が千葉屋敷に胤直入道等を急襲したとあるが、3月20日時点はまだ京都側も成氏への具体的な対応をしておらず、胤直入道は上杉や今川の侵攻に「如合符、所々江令蜂起」(「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)したとあるので、3月時点での原胤房による千葉攻めは考えにくい。胤直入道が鎌倉方への「不令同心之旨」を京都に表明し、京都がこれを賞したのが閏4月8日であることからも、4月中旬時点ではまだ「自関東連々雖相催」(享徳四年閏四月八日「将軍家御内書」『佛日庵文書』神:6204)という状況にあったと考えるのが妥当だろう。
4月3日に離京した駿河守護今川上総介範忠は、その後「今川上総介、率海道諸勢相州エ襲来」った(「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)。その時期は記されていないものの、『鎌倉大草紙』によれば「享徳四年六月、成氏退治の為め、上総介範忠、京都の御教書を帯し、御旗給はり、東海道の御勢を引率し、鎌倉へ発向す」とあり、6月に鎌倉へ攻め寄せたか(『鎌倉大草紙』)。成氏は京勢に応じた「千葉介入道常瑞、舎弟中務入道了心、宇都宮下野守等綱等」(「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)は上杉や今川の侵攻に「如合符、所々江令蜂起」した、と述べているように、胤直入道は鎌倉へ馳せ向かった今川範忠に呼応したのだろう。ただし、今川勢に千葉勢が加わっていたなどの史料はないため、これ以前に鎌倉を退いていたと思われる。「自関東連々雖相催、不令同心之旨」(享徳四年閏四月八日「将軍家御内書」『佛日庵文書』神:6204)とあるように、成氏は胤直入道の参向を願っていることから、この頃は敵対関係にあったわけではなかったこともうかがえ、原胤房が胤直入道を攻めたとすれば、今川勢が鎌倉へ進駐した6月頃と想定される。
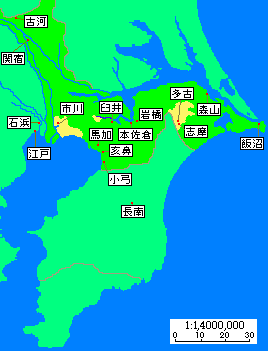 |
| 多古・志摩城の位置 |
享徳4(1455)年6月以降と推測される千葉での戦いに敗れた胤直入道は、「舎弟中務入道了心(実胤、自胤の父)」や千葉介胤宣、円城寺下野守らとともに香取郡千田庄(香取郡多古町)へと遁れた。その後、8月まで千田庄多古、島周辺での合戦があり、8月12日に多古城が陥落して千葉介胤宣が自害。8月15日に嶋城が落ち、胤直入道や円城寺下野守らか自害し、千葉惣領家の正嫡は滅亡した(多古嶋合戦)。このとき、胤直入道の弟「中務入道了心」は南方へ遁れており、山内上杉家被官の上総伊北庄狩野氏や、上総国小西の小西原氏を頼ろうとしていたのかもしれない。同年11月13日、匝瑳北条庄または南条庄「東方」で、原左衛門朗珍・原右京亮朗嶺が討死しているが、この弥富城(佐倉市岩富町)を本拠とする弥富原氏は伊北庄狩野氏と血縁関係にあり、彼等も千葉惣領方として討死したのだろう。
長尾実景
(但馬守)
∥
狩野叡昌――+―理哲尼――――日寿
(修理進入道)| (本門寺貫主)
+―朗舜
|(本門寺貫主)
|
+―理教尼
∥――――+―原朗珍
∥ |(左衛門尉)
∥ |
原道儀 +―原朗峯
(信濃守) (右京亮)
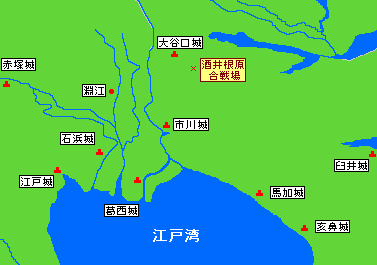
|
| 国府台周辺地図 |
しかし、「中務入道了心」は9月12日、多古の南方「ヲツゝミ(小堤)」で自害した。このとき、実胤や自胤が父「中務入道了心」と同道していたかは定かではないが、その後、惣領被官の八幡庄住人である曾谷氏らが庇護していたと考えられる。
胤直入道常瑞らの滅亡が京都に届くと、将軍義政は「千葉の家両流になりて総州大いに乱れければ、急ぎ罷り下り一家の輩を催し、馬加陸奥守を令退治、実胤を千葉へ移し可」(『鎌倉大草紙』)という御教書を奉公衆の千葉一族、東左近将監常縁に下したという。常縁は同じく奉公衆の浜式部少輔春利(常縁兄の氏数と交流のあった浜豊後守康慶の弟)とともに下総国に下向した。
享徳4(1455)年秋、下総国に下着した常縁勢は、武蔵国からの馬加への道筋を考えると、まず八幡庄市川に入ったことは想像に難くない。この八幡庄には千葉実胤・自胤が曾谷氏ら惣領被官に庇護されていたと推測できることから、この時点で千葉実胤・自胤はすでに市川城に入って、成氏勢に備えていたと考えてよいのではなかろうか。
11月24日、常縁は市川を出立し、千葉陸奥入道の居城である馬加城へ攻め寄せた。この「馬加合戦」は市川から馬加にかけての相当戦端の長い合戦と思われ、11月24日の「馬加ノ合戦」(『東野州聞書』)では、常縁は「馬加の城へ押寄、散々に攻」めたため、馬加城から「原越後守打ち出」て、常縁勢と「一日一夜防戦ひけれども、終に打負、千葉をさして引退」したという。この戦勝に常縁は「此いきほひにて上総の国所々にむらかりてありける敵城自落せしかば、浜式部少輔をば東金の城へ移し、常縁は東の庄へ帰」ったという(『鎌倉大草紙』)。
翌11月25日には、市川城至近の「■■田正行寺(『内閣本』では「今嶋田正行寺」)」(市川市柏井町1丁目)に「馬加合戦」の軍勢が打入り、住坊とみられる日進がこれを防がんとして討たれている(『本土寺過去帳』廿五日上段)。この軍勢は、おそらく馬加合戦で敗北した原勢の一部であろう。
●天正本『本土寺過去帳』廿五日上段
また、年不詳だが11月25日に「曾谷浄宗」が「野呂」(千葉市若葉区野呂町)で死去している(『本土寺過去帳』廿五日上段)。この曾谷浄宗が馬加合戦後に上総国へ向かった常縁の陣中にいた人物とすれば、馬加の南西部においても戦闘が行われていたことがうかがえる。なお、常縁は下総下向時に市川を経由していたということとなる。
●『東野州聞書』(『群書類従』第六輯所収)
常縁はこの際、東庄の東大社へ参詣して戦勝を祈願し献歌したと伝わる。
下総国では東常縁の働きにより「馬加陸奥守、原越後守、野州常縁に度々打負け」ており、この状況をみた上杉方は「千葉新介実胤を取立、本領を安堵させんと、市川の城に楯籠て、大勢」を送り込んだ(『鎌倉大草紙』)。千葉実胤・自胤の「市川の城」への籠城がいつの出来事かは判然としないが、常縁もその救援のために市川城に入っていることから、馬加合戦があった11月24日以降であろう。市川籠城を聞いた成氏は、「南図書助、簗田出羽守その外大勢指遣、数度合戦」に及んだ(『鎌倉大草紙』)。このとき寄手の大将から市川方に降伏勧告があったが、常縁は歌を詠んで遣わし、これを拒んでいる。
しかし、康正2(1456)年正月19日の合戦で「今年正月十九日、不残令討罰、然間、両総州討平候了」(「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)とあるように市川城は陥落した。この市川合戦では、円城寺若狭守、円城寺肥前守、曾谷左衛門尉直繁、曾谷弾正忠直満、曽谷七郎将旨、蒔田殿、武石駿河守、相馬守谷殿などが討死を遂げる中、千葉実胤・自胤兄弟は武蔵国へ逃れた。
●康正2(1456)年正月15日市川合戦の戦死者(『本土寺過去帳』十五日)
| 曾谷左衛門尉直繁 | 法名秀典 | 康正二年丙子正月、於市河打死、其外於市河合戦貴賤上下牛馬等皆成仏道平等利益 |
| 曾谷弾正忠直満 | 蓮宗 | |
| 曾谷七郎将旨 | 法名典意 | |
| 円城寺若狭守妙若 | 法名は妙+若狭守の「若」 | |
| 円城寺肥前守妙前 | 法名は妙+肥前守の「前」 | |
| 蒔田殿 | ||
| 武石駿河守妙駿 | 妙駿 | 法名は妙+駿河守の「駿」 |
| 相馬盛屋殿妙盛 | 妙盛 | 法名は妙+盛屋の「盛」 |
| 足立将監顕秀 | ||
| 宍倉帯刀 宍倉掃部 兄弟 | ||
| 行野隼人妙野 | 妙野 | 法名は妙+行野の「野」 |
| 豊島太郎妙豊 | 妙豊 | 法名は妙+豊島の「豊」 |
| 兒嶋妙嶋 | 妙嶋 | 法名は妙+兒嶋の「嶋」 |
| 山口妙口 | 妙口 | 法名は妙+山口の「口」。「足田殿下人、孫太郎男」 |
| 妙縛 | 与五郎、大野 | |
| 妙大 | 平六 | |
| 左近二郎 | 妙光 | 弾正殿中間 |
| 藤郷与殿 | 法名妙与 | |
| 匝瑳新兵衛妙新 | 妙新 | 法名は妙+新兵衛の「新」。神田ノ。 |
| 匝瑳帯刀 | 妙刀 | 法名は妙+帯刀の「刀」。 |
| 匝瑳二郎左衛門 | 妙衛 | 法名は妙+左衛門の「衛」。 |
| 戸張中台孫三郎妙台 | 妙台 | 法名は妙+中台の「台」。 |
武蔵に逃れた実胤・自胤らには木内宮内少輔胤信、円城寺因幡守宗胤、粟飯原右衛門志勝睦らが被官人として見える(『応仁武鑑』)。
 |
| 国府台城(市河城) |
翌正月20日には「於下総市河致合戦、悉理運之由」という注進が成氏のもとに届いている(康正二年正月廿日「足利成氏文書」『正木文書』:戦古100・『東野州聞書』)。
その後の常縁は、市川落城ののち、匝瑳郡(八日市場市)に移り、2月7日に匝瑳郡惣社である匝瑳老尾神社(匝瑳市生尾)に阿玉郷(香取市阿玉川)中から三十石を寄進して祈願した(『老尾神社文書』)とされる(ただし、文書内表現から要検討であろう)。その後、千葉付近に再来した常縁は、「東野州常縁と馬加陸奥守並岩橋輔胤と於所々合戦止隙なし」(『鎌倉大草紙』)ともあるように、千葉陸奥入道や岩橋殿との合戦が続いたのだろう。
 |
| 伝石浜城跡(石浜神社) |
6月12日、馬加陸奥入道の嫡男・胤持が上総国八幡(市原市八幡町)で討たれたことが『千学集抜粋』に記され、この没年月日は『本土寺過去帳』にも記されている(『本土寺過去帳』)。これは常縁勢によって討たれたものか。胤持の首は京都へ運ばれたとされるが、『松羅館本千葉系図』などでは康胤の首が京都へ運ばれたとされる。そして、11月1日に千葉陸奥入道もまた上総国村田川において討死しており(『千学集抜粋』、『本土寺過去帳』)、これもまた常縁勢との合戦の結果か。
一方、市川から武蔵国に逃れた実胤・自胤兄弟は、上杉家の援助を受けている。市川合戦当時、おそらく実胤・自胤兄弟は元服前で、「実胤」の「実」字は、関東管領上杉房顕からの偏諱であろう。房顕は諱に「実」字を有さないが、山内上杉家は「実」「房」「顕」「定」といった自家の由緒字を国人や被官に偏諱しており、実胤もこの一例であろう。
こうした関東の情勢の中で、京都は康正3(1457)年3月中までに「関東主君御事、京都御連枝御中御定候」(康正三年(カ)四月四日「伊勢貞親奉書」『石川文書』)と、新たな鎌倉殿を将軍家連枝中から決定する旨(この時点では、御連枝中から選ばれるというのみで、具体的な人物は決まっていない)が「白川修理大夫(白河直朝)」に伝えられている。その鎌倉殿の候補は、かつて成氏(永寿王丸)と鎌倉殿への就任を検討された「御連枝小松谷殿…御俗名義制」(『刑部卿賀茂在盛卿記』長禄二年四月十九日條)と、天龍寺香厳院主清久の二名とみられる。
当時京都から関東へ下されていたことが判明しているのは東左近将監常縁のみであるが、彼は一奉公衆に過ぎず下総国の成氏方を討つべく下 向したに過ぎず、成氏と対峙する大将軍としての重みはない。成氏への直接的な対応は同格となる鎌倉殿の下向が必須だったのであろう。そのため「常縁を召上せられ」(『鎌倉大草紙』)ている。このような状況となってしまったことを嘆いて、常縁は歌を詠んでいる。
そして、3月中に「新鎌倉殿」(『大乗院寺社雑事記』長禄元年十二月廿五日条)を「関東主君御事、御連枝香厳院殿御定候」(康正三年七月十三日「細川勝元書状」『石川文書』)とあるように、異母兄の天龍寺香厳院主清久に決定し、「近々可有御下向候」こととした。この「新鎌倉殿」の治定とともに、6月23日、御一家・渋川左衛門佐義鏡を「探題」に任じ、「武蔵国へ被指下」(『鎌倉大草紙』)ことと決定した。この「探題」がいかなる職かは不明だが、旗頭「新鎌倉殿」の「香厳院殿」を支えながら、軍事・行政面を実質的に差配する事実上の惣指揮権者(関東管領ではない)であろう。
朝日某―――女子 【小松谷殿】
∥―――――足利義制
∥ (左馬頭)
∥
足利義教
(左大臣) 【鎌倉殿】
∥ ∥―――足利政知
∥ ∥ (左馬頭)
∥ ∥
∥ 女子
∥(赤松永良則綱女子)
∥
∥ 【征夷大将軍】
∥―――――足利義政
∥ (右近衛大将)
日野重光――藤原重子
(大納言) (北方)
渋川義鏡は「公方の近親にて代々九州探題の家なれば、諸家も重き事に思ひける上、祖父左衛門佐義行は久鋪武蔵の国司にてあり、其時より足立郡に蕨と云所を取立、居城にして今に至るまで此所を知行」していたことから、彼を探題に選任したという。渋川氏の祖・足利次郎義顕(兼氏)は足利太郎家氏(斯波家祖)と同母兄弟で、その妻女も姉妹同士(北条為時女子)という斯波家の兄弟筋であり、斯波庶家の吉良氏・石橋氏と並ぶ権威を持っていた。
+―斯波義種―――斯波満種―――斯波持種―――斯波義敏
|(修理大夫) (左衛門佐) (修理大夫) (左兵衛督)
|
| +―斯波義淳―――斯波義豊
| |(左兵衛督) (治部大輔)
足利泰氏 北条時継――女子 | |
(宮内少輔)(式部丞) ∥―――――北条宗氏 +―足利高経――+―斯波義将 +―斯波義重―+―斯波義郷―――斯波義健==斯波義敏==斯波義廉
∥ ∥ (尾張守) |(修理大夫) (右衛門督)|(左衛門督) (治部大輔) (治部大輔)(左兵衛督)(左兵衛佐)
∥――+――足利家氏 ∥ ∥ | ∥ |
∥ | (尾張守) ∥ ∥――――+―斯波家兼 ∥――――+――――――――女子
名越朝時――女子 | ∥―――――足利宗家 ∥ (左京権大夫) ∥ ∥
(越後守) | ∥ (尾張守) ∥ ∥ ∥
| ∥ ∥ 吉良満貞――――女子 ∥――――――渋川義俊――渋川義鏡――斯波義廉
| ∥ ∥ (上総三郎) ∥ (左近将監)(右兵衛佐)(左兵衛佐)
| ∥ ∥ ∥
北条為時――――――+―女子 長井時秀――女子 高師直―――――女子 ∥
(六郎) || (宮内権大輔) (武蔵守) ∥――――――渋川義行―――渋川満頼
|| ∥ (左衛門佐) (右兵衛佐)
|+―女子 +―渋川直頼
| ∥ |(中務大輔)
| ∥―――――渋川義春 北条朝房―――女子 |
| ∥ (二郎三郎)(備前守) ∥―――――+―源幸子
| ∥ ∥ ∥ ∥
+――足利義顕 ∥―――――渋川貞頼―+―渋川義季 ∥
(二郎) ∥ (兵部大輔)|(刑部権大輔) ∥
∥ | ∥
北条時広――女子 |+―足利尊氏―+―足利義詮―――足利義満―+―足利義持―――足利義量
(越前守) ||(権大納言)|(権大納言) (太政大臣)|(内大臣) (参議)
|| | |
|| | +―足利義教―+―足利義勝
|| | (左大臣) |(左近衛中将)
|| | |
|| | +―足利政知
|| | |(左馬頭)
|| | |
|| | +―足利義政
|| | |(右近衛大将)
|| | |
|| | +―足利義視
|| | (権大納言)
|| |
|+―足利直義 +―足利基氏―――足利氏満―――足利満兼―――足利持氏―――足利成氏
| (左兵衛督)=(左兵衛督) (左兵衛督) (左兵衛督) (左兵衛督) (左兵衛督)
| ∥
| ∥――――――如意王
| ∥
+――女子
(本光院殿)
渋川義鏡はまず「御下知の通、武州、上州の兵共に申し聞かせ、成氏を退治して上杉を管領として関東を治むべき」の御教書を「板倉大和守先立て」て下向させたところ、「上杉方の兵共各馳せ集まり、渋川殿へ参会して京公方の御下知を承」ったという(『鎌倉大草紙』)。
将軍義政は渋川義鏡を「探題」と定める一方で、長禄元(1457)年12月19日、将軍義政は香厳院主清久を還俗させて「カマクラ殿、左馬頭付ヲコナワル、御名字政知」と左馬頭に補任し、一字を与えて「政知」と名乗らせた(『山科家礼記』)。「探題」の語は関東管領としてすでに上杉房顕がいることから、それとは別の職名として付けられたものか。政知も「公方様」とは称されず「豆州様」「主君様」と公称されており、「公方様」の称は京都側も成氏に用いると認識していたことがわかる。
渋川氏は足利家の「御一家」に属し、吉良氏の次、石橋氏と並ぶ筆頭格にある人物であった。渋川氏の所領が武蔵国蕨に存在していたことから、白羽の矢が立ったともされる。また、政知が入寺していた天竜寺塔頭香厳院は渋川氏出身の二大将軍正室・幸子(香厳院)の香火所であることから、香厳院主時代の政知と渋川義鏡は何らかの接点を持っていた可能性もあろう。
●足利庶子家と北条氏の閨閥
足利義康―――足利義兼 家女房 【吉良氏】
(陸奥守) (上総介) ∥――――――足利長氏―+―足利満氏―――足利貞義――吉良満義――吉良満貞
∥ ∥ (上総介) |(上総介) (上総介) (左京大夫)(治部大輔)
∥ ∥ |
∥ ∥ |【今川氏】
∥ ∥ +―足利国氏―――今川基氏――今川範国――今川範氏
∥ ∥ (今川四郎) (太郎) (上総介) (上総介)
∥ ∥
∥――――――――――――足利義氏 +―上杉頼重―+―上杉憲房――上杉重顕
∥ (左馬頭) |(掃部頭) |(兵庫頭) (左近将監)
∥ ∥ | |
∥ ∥ 上杉重房―+―娘 +――――――藤原清子
∥ ∥ (左衛門督) ∥ ∥
∥ ∥ ∥ ∥
北条時政―+―平時子 ∥――――――足利泰氏 ∥――――――足利家時 ∥
(遠江守) | ∥ (丹後守) ∥ (伊予守) ∥
| 三浦泰村――娘 +―娘 ∥ ∥ ∥ ∥ ∥
|(若狭守) ∥ | ∥――∥―――足利頼氏 ∥ ∥
| ∥ | ∥ ∥ (治部大輔) ∥ ∥
| ∥――――+―北条時氏―+―娘 ∥ ∥ ∥――――――足利尊氏
| ∥ (修理亮) | ∥ ∥ ∥ (治部大輔)
| ∥ | ∥ ∥ ∥ ∥
| ∥ | ∥ ∥――――足利貞氏 ∥
| ∥ +―北条時茂―――――――――――――――――娘 (讃岐守) ∥
| ∥ |(陸奥守) | ∥ ∥
+―北条義時――北条泰時 | +―北条時頼―+―北条時宗―――北条貞時―北条高時 ∥
|(陸奥守) (左京大夫)| (相模守) |(相模守) (相模守)(相模守) ∥
| ∥ | ∥ | ∥
| ∥ | ∥ +―北条宗頼―――娘 ∥
| ∥ | ∥ (修理亮) ∥――――+――――――平登子
| ∥ | ∥ ∥ |
| ∥ | ∥ ∥ |
| ∥ +―北条長時―――北条義宗――――――――――北条久時 +―北条守時
| ∥ |(武蔵守) (駿河守) (武蔵守) (相模守)
| ∥ | ∥
| ∥ +―北条重時―+―北条時継―――――――――――――――――娘 【斯波氏】
| ∥ |(陸奥守) (式部大夫) ∥ ∥―――――足利宗氏――足利高経
| ∥ | ∥ ∥ (尾張守) (尾張守)
| ∥ | ∥―+―足利家氏―+―足利宗家
| ∥ | ∥ |(尾張守) |(尾張守)
| ∥ | ∥ | | 【石橋氏】
| ∥ | ∥ | +―足利義利――足利義博――足利和義
| ∥ | ∥ | (太郎) (三郎) (左衛門佐)
| ∥ | ∥ |【渋川氏】
| ∥ | ∥ +―足利義顕―――渋川義春
| ∥ | ∥ (二郎) (二郎三郎)
| ∥―――+―北条朝時―――――――――――――娘 ∥
| 比企氏 (遠江守) ∥―――――渋川貞頼
| ∥ (兵部大輔)
+―北条時房―+―北条朝直―+―北条宣時 ∥ ∥
(武蔵守) |(武蔵守) |(陸奥守) ∥ ∥―――――渋川義季
| | ∥ ∥ (式部丞)
| +―北条朝房――――――――――――――――――――――娘
| (備前守) ∥
| ∥
+―北条時村―――北条時広――――――――――――――――娘
(相模二郎) (越前守)
12月24日、政知は京都から東下し、「カマクラ殿御下向、今日ハ三井寺マテ候也」(『山科家礼記』)と、逢坂関を越えて園城寺へ入った。このとき「新鎌倉殿、三井寺辺被下向、御共渋河」(『大乗院寺社雑事記』長禄元年十二月廿五日条)といい、「探題」渋川義鏡が政知に同行していたことがわかる。ただ、この下向は関東下向ではなく園城寺への下向で、実際の関東下向は翌年となる。
この頃、新たな鎌倉殿が決定した風聞は関東にも流れ始めていたのだろう。成氏は長禄2(1458)年閏正月11日、「小山下野守殿」に対してこの上なく慇懃な契状を示している(長禄二年閏正月十一日「足利成氏契状写」『小山家文書』)。単に小山持政の勲功を賞したものかもしれないが、京都から下向するであろう新鎌倉殿への危機感があった可能性もあろう。
●長禄2(1458)年閏正月11日「足利成氏契状」(『小山文書』)
この頃、京都は成氏方の人々に調略をかけはじめており、3月27日には京都将軍義政より「岩松右京大夫殿(岩松持国)」へ直接御内書が遣わされている(長禄二年三月廿七日「将軍義政御内書」『正木文書』)。成氏方の代表的な大将である岩松持国に調略をかけることは、これが発覚してもしなくても、また、彼が寝返っても寝返らなくても、成氏や持国には精神的に大きな揺さぶりをかけることができる。このほか、新鎌倉殿政知の「御書」(現存せず)には京都より附された奉行人「近江前司教忠」の副状(長禄二年三月廿七日「朝日教忠副状」『正木文書』)、探題「義鏡」の副状(長禄二年三月廿七日「渋川義鏡副状」『正木文書』)が付されている。これと同内容の書状が持国の子「岩松次郎殿」「岩松三郎殿」にも送達されている。朝日教忠が附されたのは、政知の母が朝日氏であったためであろう。
●長禄2(1458)年3月27日「将軍義政御内書」(『正木文書』:「韮山町史」第三巻)
●長禄2(1458)年3月27日「朝日教忠副状」(『正木文書』:「韮山町史」第三巻)
●長禄2(1458)年3月27日「渋川義鏡副状」(『正木文書』:「韮山町史」第三巻)
一方、この頃京都では政知の下向についての日次が議論されていた。4月7日、「渋川雑掌伊香方」より刑部卿賀茂在盛に「御門出吉日、関東主君御征伐之門出也」が問い合わされた(『在盛卿記』長禄二年四月七日条)。在盛はさっそく占卜したところ「今月廿日丁丑 時辰 吉方戌亥、廿六日癸未下吉、時卯辰吉方東」と出たため、「御出行日」を伊勢守貞親に報告している。その後、再度貞親から諮問されたか、在盛卿は4月19日には「今月廿六日癸未、廿八日乙酉」を案として報告している(『在盛卿記』長禄二年四月十九日条)。4月28日に将軍義政が「白河修理大夫殿」へ下した御内書(長禄二年四月廿八日『白川文書』神:6259)には、「已典厩下向之上者、早速令進発」と見えることから、新鎌倉殿政知の出京は4月26日または28日と推測できる。ただし、5月20日時点で「主君様近々に御下之事候間」(長禄二年五月廿日「横瀬国繁書状案」『正木文書』)と見えることから、いまだ関東には入っていないと推測される。
なお、政知とともに新鎌倉殿の候補だったと思われる「御連枝小松谷殿」は、「自科料」って「御左遷」となり「隠岐国」へ配所されている。具体的な罪状は不明だが、政知(香厳院主清久)が新たな鎌倉殿に選ばれたのは、小松谷殿義制の何らかの科があったためか。5月7日「小松谷殿」は配流まで「侍所京極於路次奉向之、京極宿所為御所」とし、在盛卿は配流の日次について「今月十三日己亥 時卯申、十四日庚子 時辰」(『在盛卿記』長禄二年五月七日条)と報告している。
5月20日頃、いまだ京都と鎌倉の間のどこかにいた鎌倉殿政知・渋川義鏡であったが、5月25日、雑掌某を上洛させ、「渋川殿雑掌、自侍者註進之」こととして、賀茂在盛卿に「御旗拝受日」を諮問し、「今月廿七日癸丑 宿申 時卯、六月八日甲子 時卯」が報告されている(『在盛卿記』長禄二年五月廿五日条)。政知の関東下向は御旗の拝受よりも先であったため、途次での受領を目指したか。
同じ頃、下野国では5月15日、岩松右京大夫持国から3月27日の『将軍家御教書』に応じる形で「弥可抽忠心候、以此旨可預御披露候」の請文(長禄二年五月十五日「岩松持国請文」『正木文書』)が京都に送られ、以降は従兄弟の岩松治部大輔長純(のち家純)が窓口となって、条件面が詰められていくこととなった。
5月20日、京方の岩松長純は、「関東 御主君御下向之上者、此刻被参御方者、取可申候」と、新鎌倉殿政知が関東下向した際、御方に参る場合には取り成す旨を岩松持国に伝えるとともに(長禄二年五月廿日「岩松長純書状」『正木文書』)、被官の横瀬雅楽助国繁も「澁澤」を使者として持国被官人の伊丹伯耆守に書状を送り交渉を始めている(長禄二年五月廿日「横瀬国繁書状案」『正木文書』)。
●長禄2(1458)年5月20日「岩松長純書状」(『正木文書』:「韮山町史」第三巻)
●長禄2(1458)年5月20日「横瀬国繁書状案」(『正木文書』:「韮山町史」第三巻)
得川頼有―――女子 新田義貞――新田義宗―?―岩松満純
(四郎太郎) ∥ (左中将) (武蔵守) (治部大輔)
∥ ↓
相馬義胤――土用御前 ∥―――――+―岩松政経――+―岩松経家――岩松泰家――岩松満国 +=岩松満純
(五郎) ∥ ∥ |(下野太郎) |(兵部大輔) (治部大輔)|(治部大輔)
∥ ∥ | | ↓ | ∥―――――――岩松家純
∥――――+―岩松経兼 +―とよ御前 +―世良田義政 ↓ | ∥ (治部大輔)
∥ |(遠江五郎) | |(伊予守) ↓ | 上杉禅秀女子
足利義純――岩松時兼 | | | ↓ |
(太郎) (遠江守) +―とち御前 +―あくり御前 +―岩松頼宥 ↓ +―岩松満長====岩松持国
(尼真如) |(岩松禅師) ↓ |(伊予守) (右京亮)
∥ | ↓ | ↑
∥ +―岩松直国========岩松満国―+―岩松満春――――岩松持国
∥ (治部少輔) (治部大輔) (能登守) (右京亮)
∥ ↓
∥―――――――土用王御前===岩松直国
∥ (尼妙蓮) (土用王)
藤原某
長禄2(1458)年6月には持国から探題渋川義鏡に、京方に参じる旨の「簡札」に「御請」が付されて送達された。このことから、6月上旬時点で鎌倉殿政知、探題渋川義鏡はすでに伊豆国に落居していたとみられる。6月22日、「沙弥道真」は建長寺西来庵の「侍真禅師」に対し、「当庵領」については(これまで扇谷家が担っていたが)今後は「何様豆州江令申、依御返事、可及御左右候」ことを伝えている(六月廿二日「太田道真書状」『西来庵文書』)。
長禄3(1459)年中には、「豆州主君」は伊豆国田方郡の山内上杉家由緒の国清寺、「公方様(成氏)ニハ未下野御座在之」(『香蔵院珍祐記録』長禄三年十一月「韮山町史」第三巻)、「上椙(上杉房顕)」は「本陣五十子(本庄市東五十子)」、「同大夫方(扇谷持朝入道)」は「河越」、「(渋部カ)川方(渋川伊予守カ。12月28日、浅草で病死)」は「浅草」、「鎌倉」には「駿河国人(今川範忠)被座者」という状況にあり、上杉勢と成氏勢が関東諸所で激しく交戦していた。
長禄3(1459)年10月14日、15日の武蔵国「太田庄」、上野国「羽継原」「海老瀬口」の合戦は、「管領上杉、天子之御旗依申請旗本也、当方者京都公方之御旗本也、桃井讃岐守、上杉、上条、八条、同治部少輔、同刑部少輔、上椙扇谷、武上相の衆、上杉庁鼻和、都合七千余騎、五十子近辺榛沢、小波瀬、阿波瀬、牧西、堀田、瀧瀬、手斗河原ニ取陣、戴星負月、手斗河原日々打出々々相動、雖然隔大河間、その動不輙、京都方、関東方終日見合々々入馬、勝劣未定之大陣也、天帝修羅之戦モ角哉覧与想像計リ也」(『松陰私語』第二)と見える激戦であった。
結局、この合戦は上杉方の敗北に終わり、管領房顕は「五十子陣」へと退却を余儀なくされている。なお、この合戦では、さきの約定通り岩松持国が子息の宮内少輔成兼とともに成氏方を離反して京方(上杉方)に加わっており「捨身命、及合戦」んだことに、11月24日、「豆州様」政知直々に御判御教書が下されている(長禄三年十一月廿四日「足利政知御判御教書」『正木文書』「韮山町史」第三巻)。御教書には探題の渋川義鏡(長禄三年十一月廿四日「渋川義鏡副状」『正木文書』「韮山町史」第三巻)と、奉行人「近江前司教忠」(長禄三年十一月廿四日「朝日教忠副状」『正木文書』「韮山町史」第三巻)も副状を発給している。
この合戦直後、「主君様同年内中、山ヲ可有御越由、其聞在之」と、政知が箱根を越えるという風聞が鎌倉に流れている(『香蔵院珍祐記録』長禄三年十一月「韮山町史」第三巻)。ところが、翌長禄4(1460)年正月時点で「鎌倉ニハ駿河ノ面々被座候處ニ、正月皆々被下者也、狩野方ノ被官人計少々被相残者也、介方者在国也」(『香蔵院珍祐記録』長禄四年二月「韮山町史」第三巻)とあるように、駿河今川勢は鎌倉から撤退していることがわかる。おそらく五十子陣による上杉方の敗北で、相模国や伊豆国などの情勢も一気に不安定化した影響を受け、遠江国での不穏な動きがみられたことによるものとみられる。こうして、2月の時点で「京都ノ主君者、未豆州ニ御座在之」(『香蔵院珍祐記録』長禄四年二月「韮山町史」第三巻)といい、鎌倉への下向は事実上不可能となったとみられる。この件に関してか、渋川義鏡被官人の「板倉(板倉頼次)」が4月中旬に伊豆国を発って4月26日に上洛している。
 |
| 伝堀越御所跡 |
今川勢の撤退による影響か、鎌倉から伊豆にかけての情勢が不安定化し、5月7日には「大相国之弟前香厳院主、以命還俗、為征東将軍、攻朝敵於関東、其師次伊州国清寺、敵放火々寺、士卒驚走、将軍徙陣於它云」(『碧山日録』寛正元年五月七日条)とあるように、御所の国清寺に成氏方の軍勢が放火し、政知以下は陣所を他所へ移したという。これがきっかけになったのかは不明だが、政知は狩野川東、「北条」の願成就院北方の高台に新たに御所(堀越御所)を移している。5月に入り、上洛していた「板倉」が「参豆州、去月廿六日上洛之由」を豆州様政知に報告。同月、「昌賢(長尾左衛門景仲入道)」もまた「豆州参」じたという(『香蔵院珍祐記録』長禄四年五月「韮山町史」第三巻)。この長尾の来訪は5月7日の敵勢襲来により焼失した山内上杉家由緒「奈古谷国請寺造営之」の件についてか。
8月、「使下自豆州、可有御越山之由、在其聞、但御延引」(『香蔵院珍祐記録』長禄四年八月「韮山町史」第三巻)との風聞がふたたび鎌倉に立っている。この風聞は京都にも届いており、8月22日、将軍義政は「就関東時宜、可被越箱根山之旨、其聞候、事実者、不可然候」と「此條先度申下」しており、鎌倉下向の企ては「一向可為不忠候」と強く批判している。この御教書は「豆州様」左馬頭政知のみならず、「右兵衛佐殿(渋川義鏡)」にも遣わされ、政知の鎌倉下向は厳禁としている(『御内書案御内書引付』:「韮山町史」第三巻)。
●長禄4(1460)年8月22日「御内書案」(『御内書案御内書引付』:「韮山町史」第三巻)
●長禄4(1460)年8月22日「御内書案」(『御内書案御内書引付』:「韮山町史」第三巻)
その後、閏9月頃、成氏方の軍勢が伊豆北条付近に攻め入り、政知方が大敗したという。この合戦が実際にはどこで起こったかは定かではないが、政知方は三島付近に軍勢を在陣させており、おそらく三島での合戦であろうと推測される。政知は閏9月中旬に京へ生母親族である奉行人「朝日(朝日教貞)」を上洛させて、「関東事以外云々、京都御方悉以打負了」と報告している(長禄四年閏九月廿七日「大乗院寺社雑事記」『韮山町史』第三巻)。
●長禄4(1460)年閏9月27日『大乗院寺社雑事記』(「韮山町史」第三巻)
+―上杉清方―――上杉房定――+―女子
|(兵庫頭) (民部大輔) | ∥―――――伊達稙宗
| | 伊達尚宗 (左京大夫)
| |(大膳大夫)
| |
| +―上杉顕定
| (民部大輔)
| ↓
| 【関東管領】 【関東管領】
| +―上杉房顕====上杉顕定
| |(兵部少輔) (民部大輔)
| |
【関東管領】|【関東管領】|【関東管領】
上杉房方―+―上杉憲実―+―上杉憲忠
(民部大輔) (安房守) (右京亮)
∥
上杉氏定―+―上杉持朝―+―女子 千葉実胤
(弾正少弼)|(修理大夫)| (七郎)
| | ∥
+―女子 +―上杉顕房―――女子
∥ |(三郎)
∥ |
∥ +―上杉朝昌―――上杉朝良
∥ |(刑部少輔) (治部少輔)
∥ | ↓
∥ +―上杉定正===上杉朝良
∥ (修理大輔) (治部少輔)
∥
∥――――――今川義忠
∥ (治部大輔)
今川範政―――今川範忠 ∥――――――今川氏親
(上総介) (上総介) ∥ (上総介)
∥
伊勢盛定―+―女子
(備中守) |(北側殿)
|
+―伊勢盛時―――伊勢氏綱
(新九郎) (左京大夫)
武蔵国へ遁れた千葉七郎実胤と千葉次郎自胤の兄弟については、康正2(1456)年正月19日の市川落城以降、四年後の長禄4(1460)年4月19日までその名は見えず動静は不明である。長禄4(1460)年4月当時、武蔵千葉氏は弟の次郎自胤が「千葉介」を公認されており、七郎実胤は家督を継承していない。それは『将軍家御内書』からも明らかであるが、いまだ十代後半の両名は権力闘争などの結果ではないようである。とくに将軍義政は弟・千葉介自胤に対して、「舎兄七郎隠遁」の帰参を促す御内書を送達しており、実胤・自胤両名者互いに繋がりも保たれていたと考えられる。
ただ、この当時、七郎実胤は扇谷上杉家の故顕房(康正2(1456)年正月24日、「夜瀬」で討死。享年二十一)の娘と婚姻関係となっていたと思われる一方で、弟の自胤は山内上杉家の家宰・長尾左衛門尉景仲入道の娘を娶っており、それぞれ扇谷上杉家と山内上杉家の影響下にあったと思われ、微妙な位置関係にあったことは間違いないだろう。
こうした中で、七郎実胤、千葉介自胤は「連年在陣」とあるように、比較的長い間戦陣にあったことがわかる。これはおそらく長禄3(1459)年10月中旬から武蔵国北部および上野国五十子付近で始まった、関東管領房顕(憲実次男)率いる上杉勢と、「公方様」足利成氏率いる古河勢との十八年間(文明9(1477)年正月まで)にわたる合戦「五十子合戦」であろう。市川合戦で敗れたのちは、なんら由緒の所領を持たない武蔵国へと遁れていた兄弟は、おそらく上杉家の援助で所領が預けられていたと想像されるが、長禄4(1460)年4月初頭には「千葉介(自胤)」は困窮を訴えている。上杉家か豆州様政知かは不明だが、関東から京都へその旨が報告され、長禄4(1460)年4月19日、将軍義政は政知に「千葉介困窮事」について、「堪忍候之様、別而被加下知之」を指示している(『将軍家御内書案』)。
●長禄4(1460)年4月19日『将軍家御内書案』(『続群書類従』所収)
ところが、その後も千葉兄弟の「困窮」は続いており、2年後の寛正3(1462)年4月初旬、実胤は在陣のまま「舎兄七郎隠遁」したとみられる。
この実胤隠遁の2か月ほど前の寛正3(1462)年2月頃、上杉修理大夫持朝入道(道朝)の「雑説子細」が京都へ伝わっている(長禄三年三月六日「将軍家御内書案」『足利家御内書案』)。その原因は不明だが、義政は左馬頭政知に対して、持朝入道は代々忠節を貫いてきた者であること、とくに故義教がわけて援助していており、絶対に疎略にすべきではなく、よくよく意思疎通し、持朝入道が所管する領分については相違なきよう下知すべきことを命じていることから、「雑説」の原因は、政知が持朝入道の所管する領分に手を出したことである可能性が高い。その結果、持朝入道が政知に対して強い不満を表明し、これを「雑説」と称して政知が京都に報告したのだろう。しかし、将軍義政は持朝入道の不満の原因が政知による相模国への介入にあると理解し、政知に御内書を送達したのだろう。実際に後述のように、政知が持朝入道が管国相模国の人々へ兵粮料所として預けた土地を没収していた事実が発覚しており、しかも、三年経っても返付されない状況にあった。政知は伊豆に下向はしたものの、御料所の設定は事前にされていなかったと思われ、経済的な基盤が非常に脆く、処々を収公してそれに充てていた可能性が高い。政知の御料所確保は相模国に留まらず、足元の伊豆国各所も「押領」し、領主である寺社権門から訴えが頻発していたのであった。
●寛正3(1462)年3月6日「将軍家御内書案」(『足利家御内書案』)
さらに、実胤隠遁の一月程前の3月中旬頃、「三浦介との(三浦介時高)」も「隠遁」しており(寛正三年三月廿三日『将軍家御内書案』)、3月29日に将軍義政より帰参を促す御内書が届けられている。三浦介時高は相模守護の扇谷上杉持朝入道の子(三浦高救)を養子に迎えるなど扇谷上杉家と関係が深く、彼も政知に兵粮料所を没収された一人かもしれない。
●寛正3(1462)年3月29日『将軍家御内書案』(『続群書類従』所収)
そして、4月初旬頃には実胤もまた隠遁した。これを弟の千葉介自胤や「雑説」渦中の扇谷上杉持朝入道が京都へ報告したのだろう。これを知った将軍義政は4月23日、伊豆の「左馬頭(政知)」に「千葉介事、代々忠節異于他候、殊先年父以下数輩討死候畢、連年在陣窮困之旨其聞候、令堪忍之様、別而有成敗者可為本意」と、千葉介の代々の忠節は他とは異なる上に、先年には父(実際は伯父)らが成氏方によって討たれて以降、連年在陣して「困窮」していると聞くので、早々になんらかの措置を取るよう命じている。
●寛正3(1462)年4月23日『将軍家御内書案』(『続群書類従』所収)
一方で、将軍義政は「千葉介殿」には別に「舎兄七郎隠遁」を心配し、「困窮推察」しているので、なんとかするとの書状を送達し、隠遁してしまったと聞く「千葉七郎との」へも「帰参」するよう指示している。
●寛正3(1462)年4月23日『将軍家御内書案』(『続群書類従』所収)
●寛正3(1462)年4月23日『将軍家御内書案』(『続群書類従』所収)
これら将軍義政からの御内書を受けた政知は、おそらく兵粮料所について関東「探題」渋川右兵衛佐義鏡へ相談をしたのだろう。ここで義鏡は「千葉兄弟進退」を政知に「武衞頻被執申」して千葉兄弟の困窮を訴え、彼らに「鹿王院両武州赤塚郷」を兵粮料所として与えるよう進言したのではなかろうか(寛正三年十一月廿三日「足利政知奉行人連署奉書」『鹿王院文書』)。これにより、政知より武蔵守護の管領房顕へその旨指示が出され、赤塚郷が隠遁した七郎実胤に宛行われたのだろう。
赤塚郷はもともとは足利直義の知行地で、直義正室本光院殿(渋川貞頼女子)が譲与された渋川氏にとっては由緒地で、渋川氏が直頼代に獲得した「武蔵国蕨郷上下(蕨市)」と南接していた。
●観応3(1352)年6月29日「渋川直頼譲状」(『賀上家文書』「加能史料」所収)
赤塚郷はその後、康暦元(1379)年6月25日、義鏡の玄祖父直頼の妹で本光院殿の姪に当たる香厳院殿(足利義詮正室)が夫義詮の菩提を弔うため、嵯峨野鹿王院の春屋妙葩へ寄進(永徳三年二月二九日「香厳院殿寄進状案」『鹿王院文書』)したことにより、鹿王院領となったものである。義鏡は「赤塚郷」を千葉七郎実胤の兵粮料所とすることで、自領との連携を図ろうと考えた可能性もあろう。
足利宗氏―――足利高経――――斯波義将―+―斯波義教―――斯波義郷―――斯波義健===斯波義敏
(尾張守) (尾張守) (右衛門督)|(左兵衛佐) (治部大輔) (治部大輔) (左兵衛督)
|
+―女子
∥――――――渋川義俊―――渋川義鏡―――斯波義廉
∥ (左近将監) (右兵衛佐) (左兵衛佐)
高師直――――女子 ∥
(武蔵守) ∥―――――――渋川義行―――渋川満頼
∥ (右兵衛佐) (右兵衛佐)
∥
北条朝房―――娘 +―渋川直頼
(備前守) ∥ |(式部大輔)
∥ |
∥――――+―源幸子
渋川貞頼―+―渋川義季 (香厳院殿)
(兵部大輔)|(式部丞) ∥
| ∥
+―源頼子 ∥
(本光院殿) ∥
∥ ∥
∥ ∥
足利貞氏―+―足利直義=====足利基氏――足利氏満―――足利満兼―――足利持氏―――足利成氏
(讃岐守) |(左兵衛督)+――(左兵衛督)(左兵衛督) (左兵衛督) (左兵衛督) (左兵衛督)
| | ∥
+―足利尊氏 | ∥
(左兵衛督)| ∥
∥ | ∥
∥――――+―足利義詮
∥ (権大納言)
+―平登子 ∥―――――――足利義満 +―足利義持
| ∥ (太政大臣)|(内大臣)
| ∥ ∥ |
北条久時―+―北条守時 紀良子 ∥ | 藤原重子 +―足利義勝
(陸奥守) (相模守) (洪恩院殿) ∥ |(勝智院殿)|(左近衛中将)
∥ | ∥ |
∥ | ∥――――+―足利義政
∥ | ∥ (左大臣)
∥ | ∥
∥――――+―足利義教
藤原慶子 (左大臣)
(勝鬘院殿) ∥――――――足利政知
∥ (左馬頭)
朝日氏
●寛正3(1462)年11月23日「足利政知奉行人連署奉書写」(『鹿王院文書』)
その後、「鹿王院領武州赤塚郷」は、5月頃に七郎実胤の兵粮料所として設定され、これにより実胤は隠遁から復帰したとみられる。なお、当初の赤塚郷には弟・千葉介自胤が関わった形跡はない。
しかし、11月に入ると、鹿王院は将軍義政に兵粮料所の解除を願ったようである。左馬頭政知は「為異于他寺領之間、自最初、可被宛行兵粮料所之段、雖更無謂被思食」と、鹿王院は義満所願の寺院であり、自分は赤塚郷を御料所にすることは乗り気ではなかったと逃げ口上を述べ、武蔵守護代「長尾四郎右衛門尉殿」に対して「自京都、可被返付院家之旨、御下知」があったため、「可被沙汰付下地於彼雑掌」ことを命じている。ただし「至于千葉七郎者、可被下替地」を確実に相当地で埋め合わせをするよう指示している(寛正三年十一月廿三日「足利政知奉行人奉書」『鹿王院文書』)。隠遁から復帰した七郎実胤を再度隠遁させることは、将軍義政に対しても顔向けができないため、とくに強調させたのであろう。
ただ、その後赤塚郷が鹿王院雑掌へ返付された形跡はなく、政知は寛正4(1463)年2月27日、「千葉七郎」に再度赤塚郷の鹿王院雑掌への返付を催促している(寛正四年二月廿七日「足利政知奉行人連署奉書」『鹿王院文書』)。この件は武蔵守護代長尾景信(自胤岳父)が受けており、管領房顕が管轄していることがわかる。しかし、その後も赤塚郷が鹿王院雑掌に返付されることはなく、管領房顕、景信、実胤は、政知が求める赤塚郷の鹿王院雑掌への返付を無視し続けたと思われる。
●寛正4(1463)年2月27日「足利政知奉行人連署奉書案」(『鹿王院文書』)
この頃、政知は国清寺の御所を焼き討ちされて、西の狩野川辺の守山周辺に新たな御所を建造している時期であった。こうした中、7月末頃には堀越公方政知は今川氏不在となった鎌倉に入って勢力拡大を図ろうとしたか、「可被越箱根山」という計画を立てたが、上杉氏を通じてか将軍義政の知るところとなり、8月22日に将軍義政は「粗忽之企一向可為不忠候」と強い調子で中止を命じる御内書を発し、渋川義鏡に対しても叱責している(『御内書案』)。
その後、一向に赤塚郷が返付されないことについてしびれを切らした堀越公方政知は、寛正4(1463)年2月27日、長尾景信に対して「千葉七郎」に対する赤塚郷の返付の執行を命じた(『堀越公方家奉行人連署奉書案』)。しかし、この執行命令も無視され、その間に山内房顕は関東管領を辞する旨の「職御上表」を堀越公方を通じて幕府に提出する(『鹿王院文書』)。そしてこの上表とともに、赤塚郷返付の奉行人御奉書も「被返進」された。房顕はこの問題を棚上げにする考えであったのだろう。ところが政知はこの逃げを認めず、「雖縦職上表之儀候、在職可為同前於被仰出候」として、12月下旬に奉行人布施為基と房顕被官の寺尾沙弥礼春の両名に、長尾景信へ赤塚郷返付の執行の命を伝達させた(『散位布施為基書状案』:鹿王院文書)。その後、赤塚郷についての鹿王院返付に関する文書は見られないが、室町時代末期の武蔵千葉氏の所領として「赤塚六ケ村」が見られることから(『小田原衆所領役帳』:塙保己一編『続群書類従 第25輯上』続群書類従完成会)、赤塚郷は山内房顕と長尾氏の執行拒否によって結局返付されることはないままうやむやになってしまったと思われる。
●『小田原衆所領役帳』より
将軍義政は9月5日には、扇谷上杉家の被官「大森信濃権守(大森実頼)」へ、上杉持朝入道の「雑説」についてその解決のために尽力するよう伝えている。なお、この件については左馬頭政知から「無疎略之趣、典厩注進」が報告されている(「将軍家御内書案」『足利家御内書案』)。つまり、長禄3(1459)年の「就道朝事、雑説子細候歟」という、修理大夫持朝入道の「雑説」はいまだ「落居」していなかったことがわかる。ただし、11月9日には将軍義政より持朝入道の子「治部少輔(上杉定正カ)」へ「先度雑説事、被仰遣之処、無其儀」という御内書が作成されており、ここまでには持朝入道の「雑説」の風聞は晴れたとみられる。
●寛正3(1462)年11月9日『将軍家御内書案』(『続群書類従』所収)
12月7日、将軍義政は「上杉修理太夫入道」が兵粮料所として相模国人に去り渡した土地を、近年「左馬頭」が取り上げている措置を「不可然」と断じており、「度々忠節異于他上者、如元無相違之様、可有下知」するよう命じている(寛正三年十二月七日「将軍家御内書案」『御内書案御内書引付』神:6285、6286)。
●寛正3(1462)年12月7日『将軍家御内書案』(『御内書案御内書引付』神:6285)
●寛正3(1462)年12月7日『将軍家御内書案』(『御内書案御内書引付』神:6286)
そして同日、将軍義政は「上椙修理大夫入道」に「武州河越庄」を「預置候、可有知行也」と改めてその知行を安堵しており(寛正三年十二月七日『将軍家御内書案』)、これを以て上杉修理大夫入道の「雑説」は解決されたとみられる。
文明12(1480)年には、実胤は「当方(扇谷)縁者」ながら、山内上杉家の被官「大石々見守」の招きで「葛西」に赴いた(『太田道灌状』)。これは管領上杉顕定のもとに古河公方・成氏から実胤についての「公方様内々被申旨候」があったためであろう(『太田道灌状』)。山内上杉氏は「胤直の一跡として、実胤を千葉介に任じ、上杉より下総へ指遣」と、実胤の下総帰還を見計らい、成氏と交渉していたのだろう。これに成氏も合意して、実胤を下総国へ入れるために、葛西へ実胤を招き入れたと思われる。ところが、この事実を知った「孝胤」が成氏のもとに「出頭」して猛抗議したため、「無御許容」となってしまう。結局、実胤の下総帰還は失敗に終わり「濃州江流落」したという(『太田道灌状』)。
◎『太田道灌状』(『北区史』中世編所収)
結果として実胤の下総千葉介就任は失敗に終わり、美濃へ下ったのちの消息は不明である。かつて馬加陸奥入道、原越後守を討つためにともに戦った美濃郡上の東氏を頼ったとも思われるが、東氏の伝の中に実胤の記述はない。
弟・千葉介自胤の子孫は「武蔵千葉氏」として代々続くが、武蔵千葉氏は千葉氏の嫡々であり、京都の幕府も武蔵千葉氏を常胤以来連綿と続く「千葉介」と認めていた。そのため古河公方と結んで千葉介を称した下総千葉氏に対する敵愾心は強く、その後も下総千葉氏と対立している。