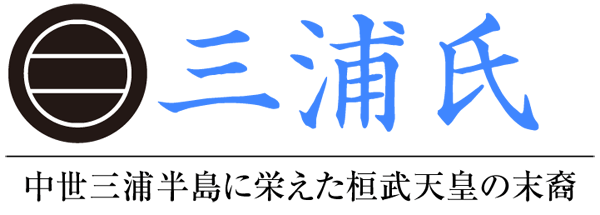
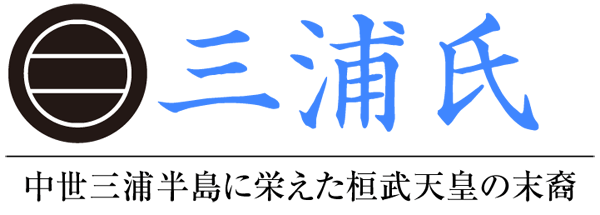
| 平忠通 (????-????) |
三浦為通 (????-????) |
三浦為継 (????-????) |
三浦義継 (????-????) |
三浦介義明 (1092-1180) |
| 杉本義宗 (1126-1164) |
三浦介義澄 (1127-1200) |
三浦義村 (????-1239) |
三浦泰村 (1204-1247) |
三浦介盛時 (????-????) |
| 三浦介頼盛 (????-1290) |
三浦時明 (????-????) |
三浦介時継 (????-1335) |
三浦介高継 (????-1339) |
三浦介高通 (????-????) |
| 三浦介高連 (????-????) |
三浦介高明 (????-????) |
三浦介高信 (????-????) |
三浦介時高 (1416-1494) |
三浦介高行 (????-????) |
| 三浦介高処 (????-????) |
三浦介義同 (????-1516) |
三浦介盛隆 (1561-1584) |
![]() (????-????)
(????-????)
三浦氏三代当主。三浦平太郎為継の嫡男。通称は平六、平大夫。荘官としては三浦庄司。
義継の「義」は源家との関わりから称したものか。祖父とされる「三浦平大夫」為通は「大夫」の称の通り、三浦郡に勢力を持つ人物だったとみられ、父の三浦平太為継の代には三浦郡大矢部に進出して三浦郡司となっていたと推測される。義継は三浦郡司職を継承しつつ、その郡内の私領を権門に寄進して「三浦庄」を成立させたと思われる。「三浦庄」は三浦郡内のいくつかの郷村で成っている庄園と思われ、千葉庄や相馬御厨同様にその郡名を以て庄園名とされたのだろう。
義継も父とされる「三浦の平太為次」(『奥州後三年記』)と同様に源家の郎従となっていたと思われ、天養元(1144)年10月21日、源義朝とその郎従による大庭御厨乱入事件に「清大夫安行、三浦庄司平吉次、男同吉明、中村庄司同宗平、和田太郎同助弘」として名が見える。このとき義明の年齢が五十三歳であることを考えると、義継は少なくとも七十代であったと思われる。
●『天養記』
左辨官下、伊勢大神宮司
応且任度度宣旨、停止其妨、備進供祭物、且令国司辨申子細、相模国田所目代源頼清并同義朝郎従散位清原安行、恣巧謀計、以大庭御厨高座郡内鵠沼郷、俄号鎌倉郡内、運取供祭料稲米、旁致濫行事
右、得祭主神祇大副大中臣清親卿、去月十二日解状称、太神宮禰宜等同月日解状称、伊勢恒吉今月七日解状傳、謹撿案內、当御厨者、本自荒野地也、誠無田畠之由、見子国判也、而彼国住人故平景正、相副国判、寄進太神宮御領之刻、永所附属恆吉也、即為御厨令開発、備進供祭上分、漸経年序之間、就在庁官人等之浮言、国司度度令経奏聞之処、被下宣旨、院宣等於本宮、召問子細之後、全無ノ停癈綸旨之上、被問両代宰吏就彼請文殊被下奉免宣旨之日、国祇承庁官散位平高政、同惟家、紀高成、平仲廣、同守景朝臣等、臨地頭任文書堺四至打傍示立劵言上、其四至云、東玉輪庄堺俣野川、南海、西神郷堺、北大牧埼者、其最中高座郡内字鵠沼郷、今俄称鎌倉郡内、寄事於彼目代下知、義朝郎従清大夫安行并字新藤太及庁官等、去年九月上旬之比、致旁濫行、打破伊介神社祝荒木田彦松頭、令及死門、打損訪行神人八人身、踏穢供祭料魚、所苅取郷内大豆小豆等也、訴申其旨之処、本宮解状祭主奏状已畢、而間同十月廿一日、田所目代散位源朝臣頼清并在庁官人及字上総曹司源義朝名代清大夫安行、三浦庄司平吉次、男同吉明、中村庄司同宗平、和田太郎同助弘、所従千余騎、押入御厨内、不論是非、所令停療也、爰承彼等所帯宣旨状之処、更不入御厨之事、只非指官省符新立庄薗本庄之外加納一色別符可入勘之由也、又隣国他堺高家若悪僧等、可停止乱入之状許也、仍為神宮御領尤大悦也、加之、於当御厨者、奉免宣旨有限之由、雖披陳、敢無承引、神人等不及敵対之間、始従同廿二日卯時、在庁官人等押入郷、抜取膀示畢、又御厨作田玖拾伍町苅穎肆万柒佰伍拾束、下司家中私財雑物悉以押取、神人紀恒貞、志摩則貞、国元、末永、重国、兼次等、巻竇令及死門、或所被凌轢也、此外供祭料米農料出挙并甲乙輩私物及有事縁所宿置熊野僧供米等捌佰余斛、負人仕人迯脱之間、不知行方、是非他、義朝与頼清成同意、出立名代之由、御厨定使并浜御薗検校散位藤原朝臣重親、下司平景宗等所言上也、就其状檢案内、於勅免神領者、縦従国衙雖有可令沙汰之事、若申下宣旨、若相具本宮使、令進止之例也、爰当御厨四至内字殿原、香川郷、背宣旨代代国判、令充国役事、度度相触彼目代頼清朝臣之次、上件子細披露已畢、皆有返報、而御厨之事、専不入宣旨状之上可停廃之由、殊無国定云々計也、以高座郡内、今俄称鎌倉郡内、令成濫行之条、依為玄隔之事、為省彼等之所行、惣所令牢籠御厨歟、因茲熟察子細、為致沙汰、先経訴国司之処、於義朝濫行之事者、不能国司進止、至于擬令停廃之事者、尋問在国、可左右之由、依令返報、暫雖相待彼裁許、寄事於左右、敢無其沙汰之間、義朝乱行事、被宣下已畢、雖然停廃事、重不被奏達者、殿原、香川郷其妨不絶歟、就中伐充国役於御厨田、曳成御厨田於宮寺浮免、勘責弥重之間、僅所残住人、又以迯脱之由、下司重言上也、重検案内、以神宮御領号院宮御領被押取之時、従本宮言上子細之日、可停止其妨之旨、被宣下之例、諸国繁多也、而今停止勅免神領、曳成宮寺浮免之条、神事不信不浄之基、何事可過斯哉、又訪先例、刄傷職掌人、殺害神人等、取穢供祭物、奪取神民貯之輩、随罪之軽重、或任法科罪、或所令乱行人致解謝也、而彼等所為、一而不尋常、先以他郡号鎌倉郡内之条、誠矯餝之甚也、各召証文之日、敢無所遁歟、加之、宣旨立券時、祇承官人、皆以見在之輩也、又以庄薗宣旨、巧謀計、令停廃御厨之条、是唯非蔑爾神威、将所違背綸言也、然則於義朝濫行者、任宣下之旨、雖令致沙汰、猥至于抜取牓示者、尤加厳制、懲向後、如本可被令立牓示哉、又所押取供祭上分料獲稲見米并所司住人私物等、悉以可被糺返哉、如此等之所行、早非被糺断者、神威凌遅、諸国狼藉、積習倍増者歟、望請宮庁哉、且重経奏聞、且早牒送留守所、被糺行者、将仰神威之不朽、厳綸言之軽矣者、就解状加覆審、以可入勘庄薗加納之由宣旨、擬令停廃有限勅免神領之條、非蔑爾神威、已違乖綸言者歟、望請祭主裁、重経奏聞、早被糺行者、仍相副言上如件、望請天裁、任禰宜等解状、早被糺行者、権大納言源朝臣雅定宣、奉 勅、宜任度度宣旨、停止其妨、備進供祭物、兼又令国司弁申子細者、同下知彼国既畢、宮司宜承知、依宣行之、
天養二年三月四日
大史中原朝臣(花押)
少辨源朝臣(花押影)
【大略訳】
左弁官から伊勢大神宮の宮司へ下す。
これまでたびたびの宣旨に基づき、源義朝の濫妨を停止させ、供祭物を備え進め、あわせて国司に事情を弁申させ、相模国の田所目代源頼清ならびに源義朝郎従の散位清原安行が勝手に策略をめぐらし、大庭御厨高座郡内鵠沼郷を俄かに「鎌倉郡内」と称し、供祭料の稲米を運び取り、濫暴を働いている事
右の件について、祭主で神祇大副の大中臣清親卿の去月十二日の解状、太神宮禰宜らの同日解状、また伊勢恒吉の今月七日の解状を受け取り、つぶさに案内を調べるに、この御厨はもとは荒れ地であり、まったく田畑がなかったことは国司の判文に見えている。しかるに、かの国住人の故平景正が国判を添えて大神宮に寄進した時から、伊勢恒吉に永代付属させ、ただちに御厨として開発し、供祭の上分を備進してきた。漸次年月を経る間に、在庁官人らの虚言により、国司がたびたび奏聞したところ、宣旨や院宣が本宮に下された。仔細を召し問うた後も、停廃の綸旨はまったくなく、両代の宰吏にその請文を問いただし、勅免の宣旨が下った日には、国祇承庁の官人で散位の平高政、同惟家、紀高成、平仲廣、同守景朝臣らが臨んで、地頭の任文をもって境界の四至を打ち示し、立券して言上した。その四至は、東は玉輪庄の境・俣野川、南は海、西は神郷の境、北は大牧崎である。その最中、義朝は高座郡内鵠沼郷をにわかに鎌倉郡内と称し、件の目代の下知に寄せて、義朝郎従清大夫安行、字新藤太および庁官らが、去年九月上旬のころ、横暴な乱行をなし、伊介神社の祝・荒木田彦松の頭を打ち破って死に至らしめ、訪行の神人八人の身を傷つけ、供祭料の魚を踏み汚し、郷内の大豆・小豆を刈り取ったのである。その旨を訴え申し上げたところ、本宮の解状・祭主の奏状がすでにあった。ところが、同じく十月二十一日、田所目代で散位の源朝臣頼清および在庁官人、さらに字上総曹司源義朝の名代である清大夫安行、三浦庄司平吉、その子同吉明、中村庄司同宗平、和田太郎同助弘らが従者千余騎を率いて御厨内に押し入り、是非を論じることなく停廃させた。そこで彼らの帯びる宣旨状を承ったところ、さらに御厨に入ることはなく、ただ官符や省符に指された新立庄・本庄以外に加納・一色の別符は勘に入るべし、との由であった。また隣国や他境の高家や悪僧らの乱入を停止すべきとの状ばかりであった。よって神宮御領としてはいよいよ大悦であった。しかしながら、この御厨について、勅免の宣旨があるにもかかわらず、披露しても承引せず、神人らは対抗するすべもなく、同月二十二日の卯の刻より、在庁官人らが郷々に押し入り、牓示を抜き取り終え、さらに御厨の作田九十五町、刈穎四万七百五十束、下司や家中の私財雑物をことごとく押し取った。神人の紀恒貞、志摩則貞、国元、末永、重国、兼次らは打ち破られ、死に至らされた者もあり、あるいは凌轢された者もあった。このほか供祭料の米、農料の出挙、また甲乙の輩の私物、および熊野僧の供米八百余斛など、借人・仕人が逃亡したため行方知れずとなった。是非を問うまでもなく、義朝と頼清が成って同意し、名代を立てたというのは、御厨定使および浜御薗検校・散位藤原朝臣重親、下司平景宗らの言上によるものである。その状に基づき検案するに、勅免神領においては、たとえ国衙から沙汰すべき事があっても、もし宣旨が下され、あるいは本宮の使を相具すれば、進止すべき例である。しかるに、この御厨四至の内、殿原、香川郷において、宣旨や国判を背き、国役に充てさせ、たびたび件の目代頼清朝臣に相触れ、上件の仔細を披露し終えても、すべて返報があり、御厨の事は宣旨状に専ら入らず、停廃すべしとの由、殊更国の定めもないことを計った。高座郡内を今にわかに鎌倉郡内と称して濫行をなすのは、まことに隔絶した事である。そこで彼らの所行を省みれば、御厨全体を牢籠すべきか。よってこの仔細を熟察し、沙汰を致すため、先に国司に訴えたところ、義朝の濫行については国司は進止できず、停廃を擬することについては在国を尋問して左右すべしとの由、返報を得た。しばしその裁許を待ち、寄せて事を左右したが、その沙汰なく、義朝の乱行についてはすでに宣下があった。しかるに停廃の事は重ねて奏達されず、殿原・香川郷の妨害は絶えない。とりわけ御厨田に国役を伐ち充て、御厨田を宮寺の浮免に曳成し、勘責はいよいよ重く、わずかに残る住人もまた逃げ去ったと、下司が重ねて言上している。さらに検案するに、神宮御領を院宮御領と号して押し取られた時、本宮から言上があり、妨害を停止すべしとの旨が宣下された先例は諸国に数多ある。しかるに今、勅免神領を停止し、宮寺の浮免に曳成するのは、神事の不信・不浄の基であり、これにまさることはない。さらに先例を訪ねれば、職掌の人を刃傷に及ぼし、神人を殺害し、供祭物を汚し、神民の貯えを奪った輩は、罪の軽重に従い、法科の罪に処せられ、あるいは乱行人をして解謝させた。ところが彼らの所為は、ひとえに尋常ならざるものであり、まず他郡を以て鎌倉郡内と号したのは、まことに矯飾の甚しきことである。各々の証文を召し問う日に、逃れることはあるまい。加えて、宣旨立券の時に祇承した官人は、みな当時現存の輩である。また庄薗宣旨をもって巧みに計略し、御厨を停廃せしめんとするは、これただ神威を蔑ろにし、綸言に違背するものではないか。しかるに義朝の濫行について、宣下の旨に任せて沙汰を致すといえども、猥りに牓示を抜き取るに至ったのは、いよいよ厳しく制し、後を懲らしめ、もとのごとく牓示を立てさせるべきではないか。また押し取った供祭上分料の稲や米、ならびに所司や住人の私物等は、ことごとく糺して返さしめるべきではないか。このような所行を早く糺断しなければ、神威は凌辱され遅れ、諸国の狼藉、積習ますます増大するであろう。宮庁に請うべきである。また重ねて奏聞し、早く留守所に牒送し、糺行されれば、神威の不朽を仰ぎ、綸言の軽んぜられることを防ぐであろう。解状に就き覆審し、庄薗加納に入勘すべき由の宣旨や、勅免神領を停廃すべき条は、神威を蔑ろにし、すでに綸言に違背することではないか。祭主の裁を請い、重ねて奏聞し、早く糺行されることを望む。よって相副えて言上するところは以上のごとし。天裁を請い、禰宜らの解状に任せ、早く糺行されるべきである。
権大納言・源朝臣雅定が宣す。
勅を奉じて曰く、しかるべくはたびたびの宣旨に任せ、妨害を停止し、供祭物を備進すべし。あわせて国司に仔細を弁申させるべし。同じく彼の国に下知すること既に畢んぬ。宮司はよく承知すべし。宣旨に依ってこれを行え。
義継は在庁官人としての地位も強めていたようで、大庭御厨乱入時にともに加担している西相模中郡(中郡二宮町)の「中村庄司同宗平」の娘と末子の四郎義実の婚姻を実現しており、義実は中村宗平の私領の一つであろう大住郡岡崎郷(平塚市岡崎)に移っている。中村党の支配地域は相模国府(大磯町国府本郷)周辺一帯であることから、三浦氏の相模国衙付近への影響力の意志が想定される。娘は西相模の波多野党一族・大友四郎経家(大住郡大友郷)に嫁がせ、波多野氏との結びつきも強めた。
●波多野氏周辺の関係図●
波多野経範――波多野経秀――波多野秀遠――波多野遠義―+―波多野義通―――波多野義常
(波多野荘司)(民部丞) (刑部丞) (筑後権守) |(権守) (右馬允)
|
+―河村秀高――――河村秀清
|
| 中原氏
| ∥――――――中原久経
| ∥ (典膳大夫)
+――娘
| ∥――――――源朝長
| 源義朝 (中宮少進)
|
+―大友経家
(大友四郎)
∥―――――――娘
三浦義継―+――娘 ∥
(三浦荘司)| ∥
+―三浦義明 +―中原親能===大友能直
(三浦介) |(掃部頭) (左近将監)
|
藤原光能――+―大江広元
(上野介) (掃部頭)
陸奥国の争乱をみごと収束させた義家の名声の拡がりを恐れた白河法皇は、陸奥国での戦い(後三年の役)は義家の「私戦」として恩賞を出さず、さらに義家の対抗馬としてその弟・加茂次郎源義綱を取り立てた。その結果、義家と義綱が京都で兵乱を起こしたため、義家の郎従の入京を禁じたうえ、義家の荘園をすべて停止。さらに、新たに義家に荘園を寄進することも禁じた。そして天仁元(1108)年、義家の嫡男・出雲守源義親が出雲で反乱を起こすと、朝廷は平正盛(平清盛の祖父)を追討使に起用して討ち取らせた。
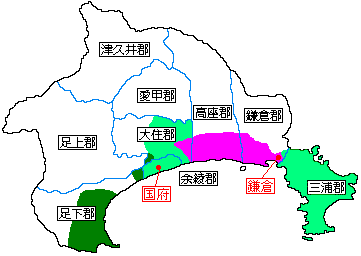 |
| 相模国勢力図(■:三浦党、■:鎌倉党、■:中村党) |
義家のあとは四男・義忠が継承するものの、翌年2月3日に暗殺された。2月23日に叔父・義綱が下手人であるとして捕縛され、のちに殺された(義忠の暗殺は叔父・新羅三郎源義光の手によるものといわれる)。その跡は、義親の嫡男で義家の養子になっていた為義(義親の嫡男)が継いだが、ここまで徹底的に勢力を削られた源氏にはもはや往時の力はなかった。康治2(1143)年6月、為義は内大臣藤原頼長に名簿を提出して臣従し、勢力の挽回を図った。さらに為義が頼長に臣従したのと同じころ、嫡男・義朝(頼朝の父)が為義の指示のもとで武蔵国の秩父権守重綱とともに勢力拡大を図っており、さらに康治2(1143)年、武蔵国から上総国に移った源義朝は千葉介常重の手から下総国相馬御厨について「責取圧状之文」った。実は康治2(1143)年正月27日の除目で「従五位下源親方」が「前司親通進衛料物功」で「下総守」となっている(『本朝世紀』康治二年正月廿七日条)。義朝が常重から相馬御厨に関する避状を圧し取ったのは、相馬御厨が国免であるが故の国司交代を狙った可能性があろう。
さらに義朝は「称伝得字鎌倉之楯、令居住之間」(「官宣旨案」『平安遺文』2544)とあり、相模国鎌倉郡に移り住んだ。「鎌倉之楯」を「伝得」したとあり、義朝は廃嫡や追放などではなく、為義の指示を受けた関東下向であったことがわかる。なお、後年頼朝が鎌倉入部して館が成った際、すでにその地に存在していた「上総介広常」の館から遷っており、義朝が上総国から移った際に、介八郎広常は義朝に同道して鎌倉に移住し、鎌倉北東部に館を建てている。上総国との湊となる六浦へ繋がるの要衝を押さえた可能性が高いだろう。
義朝は、鎌倉内のみならず三浦郡との境、沼浜郷(逗子市沼間)にも館(現在の沼間山法勝寺)を構えて三浦氏との連携も図られたようである。なお、義朝の長男・源太義平は三浦義明の娘を母とするとされるが、義平に三浦氏との連携をうかがわせる逸話は皆無であり、信憑性は低い。
 |
| 伊介神社:鵠沼神明社(烏森神社) |
鎌倉へ移った義朝は、天養元(1144)年、まず鎌倉に隣接する相模国高座郡大庭御厨の押領を企て、大庭御厨内の鵠沼郷(平塚市鵠沼)は鎌倉郡内の地であると難癖をつけて領有を主張。9月上旬、郎党・清原大夫安行らを鵠沼郷に乱入させて、伊介神社の供祭料を強奪した。さらに抗議に出た伊介社祝・荒木田彦松の頭を砕いて重傷を負わせ、神官八人をも打ち据えた。
これらの濫妨に怒り心頭に達した御厨定使藤原重親、御厨下司平景宗(大庭景宗)が、9月10日、領主・伊勢神宮に急使を派遣して濫妨を訴え、これを聞いた伊勢神宮も朝廷に使者を発して義朝追討を訴えた。
 |
| 大庭御厨と大庭氏館遠景(左の丘) |
こののち、約一か月の間、義朝の侵略はなかったが、10月21日、義朝は田所目代・源頼清らと結託し、「清大夫安行、三浦庄司平吉次、男同吉明、中村庄司同宗平、和田太郎助弘」等に命じてふたたび大庭御厨に濫妨をはたらいた。翌日22日には御厨の境界を示す傍標を引き抜き、やっと収穫の終わった稲を強奪したうえ、あろうことか下司職の大庭景宗の館にまで乱入して、その家財をことごとく奪いとり、家人を殺害した。伊介社にも乱入して神人を打ち据えて供祭料を奪い、御厨の機能を失わせた上で鎌倉に引き揚げた。
相馬御厨領主で彦松と同族と思われる内宮禰宜荒木田一族は怒り、荒木田神主延明が義朝に何らかの「沙汰」をしたと思われる。義朝は朝廷の譴責の対象となっており、翌天養2(1145)年3月4日に御厨に対する濫妨停止を相模国司に出したことを知らせる宣旨が「伊勢大神宮司」へ出されている(天養二年三月四日『宣旨案』:『天養記』)。
ところが義朝は、3月11日、「為募太神宮御威、限永代所寄進也」(天養二年三月十一日『源某寄進状』)、「恐神威永可為太神宮御厨之由、天養二年令進避文」(仁安二年六月十四日『荒木田明盛神主和与状』)とある通り、相馬御厨を神宮へ寄進することとなる。義朝が相馬御厨を神宮に寄進した理由は「自神宮御勘発候之日、永可為太神宮御厨之由、被令進避文候畢者」(永暦二年四月一日『下総権介平申状案』)とあるように、神宮の怒りを抑えるためとみられる。これは、前年の天養元(1144)年9月、「上総曹司源義朝」らが相模国大庭御厨で濫妨を働いたたためだろう。
これ以降の義継の動向は不明。没年、享年、法名、菩提所など不明。墓所は三浦郡矢部郷(横須賀市大矢部)の清雲寺に伝義継墓石があるが、これは円通寺跡(横須賀市大矢部二丁目)の「やぐら」から移転されたものである。