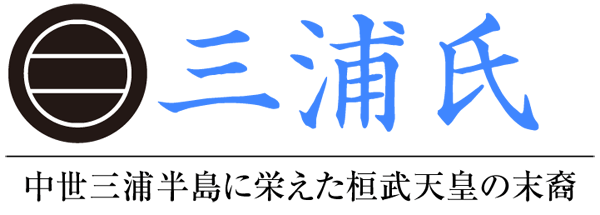
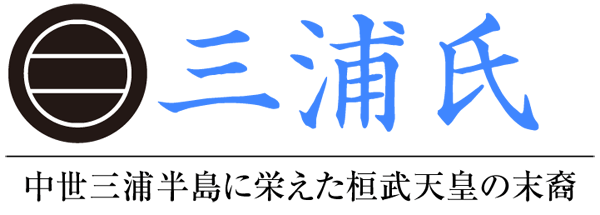
| 平忠通 (????-????) |
三浦為通 (????-????) |
三浦為継 (????-????) |
三浦義継 (????-????) |
三浦介義明 (1092-1180) |
| 杉本義宗 (1126-1164) |
三浦介義澄 (1127-1200) |
三浦義村 (????-1239) |
三浦泰村 (1204-1247) |
三浦介盛時 (????-????) |
| 三浦介頼盛 (????-1290) |
三浦時明 (????-????) |
三浦介時継 (????-1335) |
三浦介高継 (????-1339) |
三浦介高通 (????-????) |
| 三浦介高連 (????-????) |
三浦介高明 (????-????) |
三浦介高信 (????-????) |
三浦介時高 (1416-1494) |
三浦介高行 (????-????) |
| 三浦介高処 (????-????) |
三浦介義同 (????-1516) |
三浦介盛隆 (1561-1584) |
![]() (????-1083頃)
(????-1083頃)
三浦氏初代当主。村岡小五郎平忠道の子(『桓武平氏諸流系図』)。「号三浦平大夫」(『桓武平氏諸流系図』)。兄に「忠輔」の名が見えるが、忠輔は為道の父・忠道の兄(『桓武平氏諸流系図』)ともされており、系譜の錯誤がある。また、三浦氏の系譜の一部には為通の名はなく「公義」という人物が記載されている。公義については為通の子・平為俊の養子にあたる公俊の長男が太郎公義という。通称の「平大夫」については本来は「五位」の位を表すが、当然ながら地方国人の為通が五位であるはずもなく、この「大夫」はその在郷地の有力者、というような意味合いの私称ではなかろうか。
このほか、「亘理権大夫」は「亘理権守」とも称されているように「権守」もまた大夫同様の在郷地の有力者と想定されるが、こちらは国司名であることから公称であろう。「秩父権守重綱」(『小代宗妙置文』:石井進『鎌倉武士の実像』平凡社1987)は「秩父出羽権守」(『吾妻鏡』嘉禄二年四月十日条)、「豊嶋権守有経」は「紀伊権守有経」(『吾妻鏡』文治二年三月廿六日条)と見え、国司「権守」の略称とも考えられるが、「下妻四郎弘幹」のように官途を有しない人物でも「悪権守」を号していることから、「権守」とは若狭国の税所職をも担った若狭初代守護の「稲庭権守時定」のように有力な在庁官人であったと考えるのが妥当か。
| 【大夫】 | ||
| 亘理権大夫 亘理権守 |
藤原経清 | 『陸奥話記』 |
| 大三大夫光任 | 大宅光任 | 『陸奥話記』 |
| 横山野大夫経兼 | 横山経兼 | 『吾妻鏡』文治五年九月六日条 |
| 千葉大夫 | 平常兼 | 『桓武平氏諸流系図』 |
| 秩父大夫 | 平武基 | 『桓武平氏諸流系図』 |
| 三浦平大夫 | 平為通 | 『桓武平氏諸流系図』 |
| 有大夫 | 有道弘行 | 『小野氏系図』 |
| 野三大夫 | 小野成任 | 『兒玉党系図』 |
| 北条四郎大夫 | 北条時兼 | 『桓武平氏諸流系図』 |
| 秩父太郎大夫 | 秩父重弘 | 『桓武平氏諸流系図』 |
| 秩父次郎大夫 | 秩父重隆 | 『桓武平氏諸流系図』 |
| 【権守】 | ||
| 秩父権守重綱 秩父出羽権守 |
秩父重綱 | 『桓武平氏諸流系図』/『吾妻鏡』寛喜三年四月廿日条 『吾妻鏡』嘉禄二年四月十日条 |
| 中三権守兼遠 | 中原兼遠 | 『吾妻鏡』治承四年九月七日条 |
| 堤権守信遠 | 堤信遠 | 『吾妻鏡』治承四年八月十八日条 |
| 糟屋権守盛久 | 糟屋盛久 | 『吾妻鏡』治承四年八月廿三日条 |
| 豊嶋権守清元 | 豊嶋清元 | 『吾妻鏡』治承四年九月三日条 |
| 紀伊権守有経 豐嶋権守有経 |
豊嶋有経 | 『吾妻鏡』文治二年三月廿六日条 『吾妻鏡』建久元年五月廿九日条 |
| 大田小権守行朝 | 大田行朝 | 『吾妻鏡』治承五年閏二月廿三日条 |
| 波多野権守 | 波多野遠義 | 『小野氏系図』 |
| 懐嶋平権守景能入道 | 懐島景義 | 『吾妻鏡』承元四年四月九日条 |
| 横山権守時廣 小権守時廣 |
横山時重 | 『吾妻鏡』文治五年七月十九日条 『吾妻鏡』文治五年九月六日条 |
| 八田権守 八田下野権守 |
八田宗綱 | 『小野氏系図』 『日光山別当次第』/『建保五年四月十七日棟札写』 |
| 久下権守直光 | 久下直光 | 『吾妻鏡』寿永元年六月五日条 |
| 多々良権守貞義 | 多々良貞義 | 『吾妻鏡』寿永元年八月十二日条 |
| 蓮池権守家綱 | 蓮池家綱 | 『吾妻鏡』寿永元年九月廿五日条 |
| 岡辺権守泰綱 | 岡辺泰綱 | 『吾妻鏡』文治元年十一月十二日条 |
| 阿多平権守忠景 | 阿多忠景 | 『吾妻鏡』文治三年九月廿二日条 |
| 下妻四郎弘幹 號悪権守 | 下妻弘幹 | 『吾妻鏡』建久三年八月九日条 |
為通は伊予守源頼義に仕えて「前九年の役」に従軍し、功績によって康平6(1063)年相模国三浦郡を賜ったとされるが、傍証はない。また、弟・景通の子孫は相模国鎌倉郡に移り「鎌倉党」を形成し、大庭氏、梶原氏、長尾氏等の祖となったとされる。ただし、彼らの名は『陸奥話記』には登場しない。
●前九年の役での源家の主な郎党(『陸奥話記』)
| 名前 | 略歴等 |
| 權守藤原朝臣説貞 | 陸奥権守か。阿久利川辺の陣所で安倍貞任に人馬を殺傷されたとして、前九年の役の発端を開く。 |
| 藤原光貞 | 藤原光貞の子。 |
| 藤原元貞 | 藤原光貞の子。 |
| 修理少進藤原景通 | 安倍頼時、貞任の軍勢に源氏勢が追い詰められたとき、源頼義・義家に従った五騎の一人。頼義の馬が射られたとき、自分の馬を頼義に渡した。御家人・加藤氏の祖。 |
| 大宅光任 | 安倍頼時、貞任の軍勢に源氏勢が追い詰められたとき、源頼義・義家に従った五騎の一人。遁れるとき、義家とともに敵兵数騎を射殺し、虎口を脱した。 |
| 清原貞広 | 頼義に随って来た「坂東精兵」。安倍頼時、貞任の軍勢に源氏勢が追い詰められたとき、源頼義・義家に従った五騎の一人。 |
| 藤原範季 | 安倍頼時、貞任の軍勢に源氏勢が追い詰められたとき、源頼義・義家に従った五騎の一人。 |
| 藤原則明 | 安倍頼時、貞任の軍勢に源氏勢が追い詰められたとき、源頼義・義家に従った五騎の一人。義家の馬が射られたとき、敵の馬を奪い取って義家に渡した。 |
| 散位佐伯経範 | 相模国人。頼義の厚遇を受けた人物で、頼義に仕えて三十年、年齢も「耳順(六十歳)」となり、安倍勢に追い詰められた際には、ここが死に場所とばかりに敵陣に斬り込み戦死した。相模国の波多野氏の祖と思われる。 |
| 藤原景季 | 修理少進藤原景通の長子。年齢は二十余歳、言葉少ない寡黙な青年で、騎射に長じていた。安倍勢に追い詰められた際には敵陣に討ち入り捕らえられた。敵勢はその武勇を惜しんだがついに斬られた。 |
| 散位和気致輔 | 頼義の郎党。敵陣に討ち入り討死した。 |
| 紀為清 | 頼義の郎党。和気致輔の孫に当たる。敵陣に討ち入り討死した。 |
| 藤原茂頼 | 頼義の腹心。頼義勢が大敗したのち茂頼は頼義とはぐれて出家。その後、頼義と邂逅した。 |
| 散位平国妙 | 頼義の郎党。出羽国人。武勇あふれる人物で善戦し、敗北知らずであった。そのため、俗に平不負、字を平大夫と呼ばれた。しかし、黄海合戦で馬が斃されて捕らえられ虜となった。そのとき、敵将で婿の藤原経清(奥州藤原氏祖)によって助けられた。「武士猶以為耻矣」とされた。 |
| 平真平 | 頼義に随って来た「坂東精兵」。岩城氏の祖・平貞衡と同一人物ともされるが、当時清原氏と密接に関わっていた貞衡一族が坂東にあったとは考えにくく、おそらく別人だろう。相模国の中村氏、土肥氏とも関係があるかもしれない。 |
| 菅原行基 | 頼義に随って来た「坂東精兵」。武蔵国司の流れをくむと思われる菅原姓の侍。 |
| 源真清 | 頼義に随って来た「坂東精兵」。 |
| 刑部千富 | 頼義に随って来た「坂東精兵」。 |
| 大原信助 | 頼義に随って来た「坂東精兵」。 |
| 藤原兼成 | 頼義に随って来た「坂東精兵」。 |
| 橘孝忠 | 頼義に随って来た「坂東精兵」。 |
| 源親季 | 頼義に随って来た「坂東精兵」。 |
| 藤原朝臣時経 | 頼義に随って来た「坂東精兵」。 |
| 丸子宿禰弘政 | 頼義に随って来た「坂東精兵」。 |
| 藤原光貞 | 頼義に随って来た「坂東精兵」。 |
| 佐伯元方 | 頼義に随って来た「坂東精兵」。佐伯経範の同族か。相模国大住郡粕屋郷を発祥とする糟谷氏の祖か。 |
| 平経貞 | 頼義に随って来た「坂東精兵」。 |
| 紀季武 | 頼義に随って来た「坂東精兵」。 |
| 安倍師方 | 頼義に随って来た「坂東精兵」。 |
源頼義は冷泉院の孫・小一条院敦明親王の判官代に任じられ(『陸奥話記』)、長元元(1028)年10月14日の除目で相模守となっており、その任期中に頼義から小一条院に相模国三崎庄・波多野庄が寄進されたと思われる。三崎庄は三浦半島の最南端に位置する荘園で、のちに小一条院からその皇女・冷泉宮(儇子内親王。のち藤原信家妻)に継承されて「冷泉宮領」となり、さらも摂家領となる。
三浦氏の拠点のある三浦郡三浦庄と三崎庄は隣接しているが、平安時代後期において三浦半島南部の三崎庄における三浦一族の活動はみられず、『奥州後三年記』の「三浦ノ平太為次」が「三浦氏」の史料上(軍記物ではあるが)の初見となる。「三浦ノ平太為次」は系譜上為通の長男となるが、為通または為継の代に三浦半島中部の山岳を後背地とする三浦郡大矢部(横須賀市大矢部)周辺に入ったのだろう。三浦郡に入った為通または為継は三浦郡司に補されて在庁官人となったのだろう。そして頼義の死後約七十年も経過した「三浦庄司平吉次、男同吉明」の時代になってようやく「吉次(為継の子義継)」の子の次郎義行が津久井郷(横須賀市津久井)、三郎為清が葦名郷(横須賀市芦名)に移り住んでいる。ただし、これは支配領域の拡大ではなく子息への所領分与であると考えられ、三浦氏の勢力は摂家領三崎庄までは届きようもなかったことがわかる。
為通は永保3(1083)年3月14日に没した(『寛政重修諸家譜』)とあるが、あくまでも伝承である。法名は円覚。墓所は横須賀市大矢部の臨済宗寺院・大富山清雲寺。
◎平安時代の天皇家・摂関家関係図(赤字は「冷泉宮領」の譲渡を示す)
+―藤原兼通―――藤原顕光――――――――+―藤原重家
|(摂政) (左大臣) |(左少将。光少将)
| |
+―藤原伊尹―――藤原懐子 +―藤原延子
(摂政) (従二位) (御息所) +―敦貞親王
∥――――――花山天皇 ∥ |(式部卿)
∥ (65代) ∥ |
村上天皇―+――――――――冷泉天皇 ∥―――――――――――+―儇子内親王
(62代) | (63代) ∥ (冷泉宮)
| ∥――――――三条天皇―+―敦明親王 ∥
| 藤原兼家―+―藤原超子 (67代) |(小一条院) ∥
|(摂政) |(御匣殿) | ∥
| | +―禎子内親王 ∥
| | ∥ ∥
| | ∥―――――――後三条天皇 ∥============藤原麗子
| | 後一条天皇 ∥ (京極北政所)
| | ∥ ∥
| +―藤原道長―+―藤原頼通―――藤原師実 ∥ ∥―――――――藤原師通
| |(摂政) |(摂政) (摂政) ∥ ∥ (摂政)
| | | ∥ 藤原師実
| +―藤原詮子 +―藤原教通―――――――――――――――――藤原信家 (摂政)
| (東三条院)|(太政大臣) (権大納言)
| ∥ |
| ∥ +―藤原尊子
| ∥ | ∥
| ∥ | ∥――――+―藤原麗子
| ∥ | ∥ |
| ∥ | 源師房 |
| ∥ |(右大臣) +――――――――藤原寛子
| ∥ | (四条宮)
| ∥ +――――――――藤原嬉子 ∥
| ∥ | (従三位) ∥
| ∥ | ∥――――――後冷泉天皇
| ∥ | ∥ (70代)
| ∥ | ∥
| ∥ +―藤原彰子 +―後朱雀天皇 +―崇徳天皇
| ∥ (上東門院)|(69代) |(75代)
| ∥ ∥――――+ |
| ∥ ∥ | |
| ∥―――――一条天皇 +―後一条天皇――後三条天皇――白河天皇―――堀河天皇―――鳥羽天皇―+―後白河天皇
+―――――――円融天皇 (66代) (68代) (71代) (72代) (73代) (74代) (77代)
(64代)