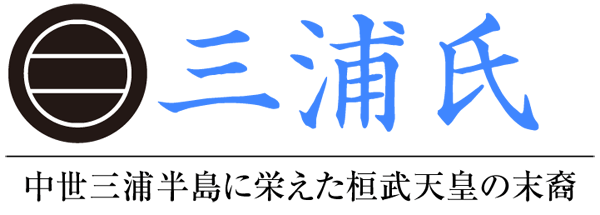
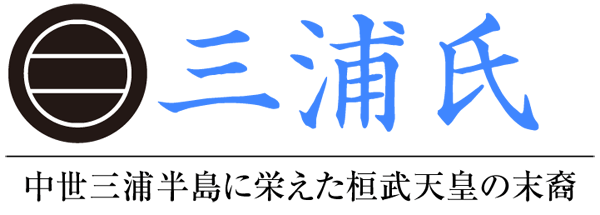
| 平忠通 (????-????) |
三浦為通 (????-????) |
三浦為継 (????-????) |
三浦義継 (????-????) |
三浦介義明 (1092-1180) |
| 杉本義宗 (1126-1164) |
三浦介義澄 (1127-1200) |
三浦義村 (????-1239) |
三浦泰村 (1204-1247) |
三浦介盛時 (????-????) |
| 三浦介頼盛 (????-1290) |
三浦時明 (????-????) |
三浦介時継 (????-1335) |
三浦介高継 (????-1339) |
三浦介高通 (????-????) |
| 三浦介高連 (????-????) |
三浦介高明 (????-????) |
三浦介高信 (????-????) |
三浦介時高 (1416-1494) |
三浦介高行 (????-????) |
| 三浦介高処 (????-????) |
三浦介義同 (????-1516) |
三浦介盛隆 (1561-1584) |
![]() (????-????)
(????-????)
三浦氏二代当主。三浦平大夫為通の子(『桓武平氏諸流系図』等)。通称は平太郎。
奥州清原氏の内紛に関わる「後三年の役」に際し、源義家の郎従となって参戦している。彼の活躍は軍記物『奥州後三年記』に「同国(相模国)のつはもの、三浦の平太為次といふ者あり、これも聞へ高き者なり」(『奥州後三年記』)と記載されている。
為継が「八幡殿(八幡太郎源義家)」に随った「奥州武衡、家衡」の乱は、永保3(1083)年に奥州にて起こった「後三年の役」である。この乱は清原真衡、清衡、家衡の三兄弟 (それぞれが異父・異母兄弟)の争いに端を発した戦乱で、当時陸奥守として鎮守府にあった源義家が介入してまず真衡を討ち、続いて清衡・家衡の争いには清衡に加担して家衡を討ち、結局、清原清衡が陸奥六郡を統べるようになる。こののち、清衡は実父・亘理権守藤原経清の本姓である藤原姓を称して藤原清衡と名乗り、以降、藤原基衡、藤原秀衡、藤原泰衡の四代にわたる奥州平泉の黄金文化がうまれた。
為継は永保3(1083)年秋の金沢柵攻めに参戦していたが、その際、為継と同国相模国住人の十六歳の鎌倉権五郎景正と同陣で加わっていたが、景正は敵の矢を右目に受け、その矢が「首を射通して兜の鉢付の板に射付けら」れる程の重傷を負うが、ひるまず矢を射返して敵兵を射殺して陣所に戻ると、「景正手負ひたり」と言って仰向けに倒れた。これを見た為継が景正のもとに駆けつけると、「鞵を穿きながら景正が顔を踏まへて矢を抜かむ」(『奥州後三年記』)とした。
景正は靴で顔を踏まれるや、「伏しながら刀を抜きて為次が草摺を執へて上げさまに突かむ」とした。草摺を掴まれて刺突を受けた為継は驚き、「こは如何になどかくはするぞ」と言うと、景正は「弓箭に当たりて死ぬるは武士の望む所なり、いかで生ながら人の足に面を踏まるゝ事あらむ、而し汝を敵としてわれ此所にて死なむ」(『奥州後三年記』)と怒声を浴びせたのだった。これには「為次舌を巻きて云ふ事な」く、「膝を屈め顔を抑へ」て景正の矢を抜き、人々はこれを見て景正の武名はいよいよ高くなったという。
●後三年の役での源義家の主な郎党(『奥州後三年記』)
| 名前 | 略歴等 |
| 兵藤大夫正経 | 義家の側近。参河国の住人。兵衛府に出仕した人物か。「大夫」とあるので五位の位階を有していたか。清原真衡の妻の要請を受けて真衡の館へ馳け付けて守護した。伴次郎助兼とは婿舅の間柄。 |
| 伴次郎傔仗助兼 | 義家の側近。参河国の住人。将軍義家の傔仗になったのだろう。「極なきつはもの」で、つねに先陣に立って活躍し、義家より「薄金」の鎧を給わる。清原真衡の妻の要請を受けて真衡の館へ馳け付けて守護した。兵藤正経とは婿舅の間柄。 |
| 鎌倉権五郎景正 | 義家の側近。永保3(1083)年当時16歳。「相模国の住人」で、鎌倉氏(長江氏、大庭氏?)の祖と思われる。「先祖より聞えたかきつはものなり」とある。 |
| 三浦平太郎為次 | 義家の側近。鎌倉景正と「同国のつはもの」で三浦氏の祖である。「聞えたかき者」であった。 |
| 大三大夫光任 | 義家の郎従で、このとき八十歳。前九年の役で活躍した「大宅光任」と同一人物だろう。高齢のため国府にとどまるが、出陣できないことを嘆いた。 |
| 腰瀧口季方 |
義家の弟・義光の郎従とされる。「剛臆の座」でつねに剛の座についた稀な人物。「腰」は不明だが、「瀧口」とあるので、瀧口の武者に抜擢されるほどの侍だったと思われる。 |
| 紀七 | 義家の郎従。「鏑の音聞かじとて耳塞ぐ剛の者」として、臆の座につかされた人物。 紀姓の侍だろう。 |
| 高七 | 義家の郎従。「鏑の音聞かじとて耳塞ぐ剛の者」として、臆の座につかされた人物。高階姓の侍だろう。 |
| 宮藤王 | 義家の郎従。「鏑の音聞かじとて耳塞ぐ剛の者」として、臆の座につかされた人物。宮内省に出仕していた人物か。 |
| 腰瀧口 | 義家の郎従。「鏑の音聞かじとて耳塞ぐ剛の者」として、臆の座につかされた人物。義光の郎従でつねに剛の座についた「腰瀧口季方」とは別人と考えられる。 |
| 末史郎 | 義家の郎従。「末割四郎惟弘」とある。 |
| 藤原資道 | 義家の側近。永保3(1083)年当時13歳。山内首藤家の祖と思われる。 |
| 源直 | 義家の郎従か。金澤柵で義家に向って悪口を放った清原家衡の乳母(子)で従僕・千任丸が戦後、捕えられた際、義家の命によって彼の舌を切るため、口を開けさせようと手を突っ込み、義家に「虎の口に手を入れんとす、甚だを愚かなり」と怒りを買う。出自は不明だが、おそらく嵯峨源氏の流れをくむか。 |
その後の為継の動向は不明だが、子・義継以後は三浦氏の通字「為」が「義」(神宮の『櫟木文書』では「吉」であるが、伝聞であることから当字の可能性があろう)に変わっており、義継は源氏との関係を深めていたことがうかがわれる。為継の没年は不明だが、父・為通と同じく三浦郡矢部郷(横須賀市大矢部)の清雲寺に墓石がある。円通寺跡(横須賀市大矢部二丁目)の「やぐら」から移転されたものである。
時代は下って、建保3(1213)年5月2日、和田義盛が北条義時に反発して兵を挙げた際、彼の従兄弟に当たる三浦平六左衛門尉義村・九郎右衛門尉胤義は和田邸北門を守衛すると起請文を出した。しかし、義村たちはにわかに変心し、北条義時の屋敷に駆け込んで義盛ら一党の挙兵を伝えた。その際、義村・胤義は「嚢祖三浦平太郎為継、八幡殿に属き奉り、奥州武衡、家衡を征すより以降、飽くまでその恩禄を啄む所なり」と告げており(『吾妻鏡』建保三年五月二日条)、三浦家でも為継を三浦家の祖として崇めていたのだろう。
平為俊(????-????)
三浦平大夫為通の子(『桓武平氏諸流系図』)とされるが不明。幼名は千寿丸。太宰大監平致光の曾孫とも。「舎弟右兵衛尉為兼布衣狩籙」(『中右記』寛治七年十月三日條)とあり、弟に平為兼がいたことがわかるが、彼の名は為通の子にも致光の子にも見ることはできない。これは、白河院に鍾愛された為俊を自家の系譜に取り込んだ例である可能性がある。
●平為通―+―平為継――――三浦義継――――三浦義明
(平大夫)|(平六郎) (三浦庄司) (三浦介)
|
+―安西為景===安西常遠――――安西常景―――――安西景益
|(駿河八郎) (四郎) (三郎) (三郎)
|
+―平為俊====平公俊――――――――――――――平公義
(駿河守) (左衛門尉。伊勢守藤原公清三男) (太郎)
白河院に祗候して、寛治6(1092)年4月18日当時、検非違使・左兵衛尉、さらに康和2(1100)年正月27日に従五位下(『魚魯愚鈔』宿官勘文)に、嘉承3(1108)年正月24日(『中右記』嘉承三年正月廿四日條)、駿河守に任じられた。白河院の近臣として知られる。
●『魚魯愚鈔』宿官勘文
為俊が猷子とした平公俊の実父・伊勢守藤原公清は秀郷流藤原氏の一族で、寛徳2(1045)年に正六位上・右兵衛少尉に任じられ(『除目大成抄』第六)、その後に左衛門尉、検非違使に就任。治暦4(1068)年11月12日の大嘗会叙位の際に従五位下に叙された(『本朝世紀』)。
平公俊の活動は主に京都で見られ、鳥羽院に近侍する武士であったのだろう。久安3(1147)年9月12日、右衛門尉として藤原頼長(内大臣。のち左大臣)のもとへの院使となり、9月14日には鳥羽院からの松茸を頼長に届けている(『台記別記』)。仁平元(1151)年8月10日、頼長の春日神社参詣に際しても「検非違使右衛門尉平公俊」として供奉しており、検非違使として活躍していたことがうかがえる。没年不明。