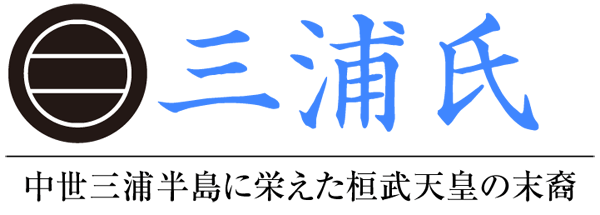
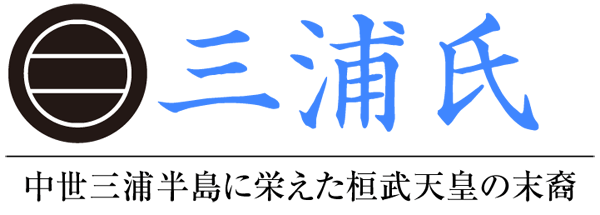
| 平忠通 (????-????) |
三浦為通 (????-????) |
三浦為継 (????-????) |
三浦義継 (????-????) |
三浦介義明 (1092-1180) |
| 杉本義宗 (1126-1164) |
三浦介義澄 (1127-1200) |
三浦義村 (????-1239) |
三浦泰村 (1204-1247) |
三浦介盛時 (????-????) |
| 三浦介頼盛 (????-1290) |
三浦時明 (????-????) |
三浦介時継 (????-1335) |
三浦介高継 (????-1339) |
三浦介高通 (????-????) |
| 三浦介高連 (????-????) |
三浦介高明 (????-????) |
三浦介高信 (????-????) |
三浦介時高 (1416-1494) |
三浦介高行 (????-????) |
| 三浦介高処 (????-????) |
三浦介義同 (????-1516) |
三浦介盛隆 (1561-1584) |
●三浦氏の惣領家●
 (????-????)
(????-????)
三浦惣領家十代。父は三浦介時継の子。母は不明。通称は三浦介。官位は従五位下。官職は相模国大介職。法名は徳紹。「高継」の「高」は、得宗・北条高時よりの偏諱と考えられる。
 |
| 京都御所 |

|
| 生品神社 |
正慶2(1333)年5月8日、新田太郎義貞が上野国新田庄の生品神社で鎌倉打倒の兵を挙げた。この挙兵には高氏嫡子の千寿王丸が擁立されたとされており(『増鏡』)、最近の研究では新田氏は鎌倉前期の新田政義の自由出家による没落で舅足利家の庇護を受けて以降、足利家一門とされたとの説がある(田中大喜『新田一族の中世:「武家の棟梁」への道』)。
当時の足利家当主・前治部大輔高氏は摂津・丹波との国境である桂川西岸地域から山崎方面を奪還する六波羅探題の援兵として上洛中であったが、4月22日、在関東の「(岩松)兵部大輔経家并新田義貞」に「先代追討ノ御内書」を送り、彼等を「両大将」として討幕の挙兵を指示しており(応永三十三年七月「岩松伊予守満長代成次書状」『正木文書』)、新田経家と新田義貞の挙兵はこの御内書のもと行われたとみられる。「上野国ニ高氏一族新田義貞ト云者アリ、早鎌倉ヘ発向ス、尊氏カ息男アリ、共合戦ヲ可致由ヲ尊氏催促ス、則義貞彼命ヲ受ヲ、武蔵上野相模等ヲ催シテ鎌倉ヘ馳上」(『保暦間記』)ったという。足利家は宗家のほか、尾張守家(斯波家)、上総介家(吉良家)、渋川家ら独立した一門がいたが、新田家も彼らと同様に足利一門として包摂される御家人であったのだろう。なお、新田一門は彼らよりも遠縁にあたり、足利を称する一門より独立性は高かったとみられる。
『太平記』によれば5月9日に鎌倉では軍評定が行われ、翌10日にまず「金澤武蔵守貞将、五万余騎ヲ差副テ下河辺ヘ下」した。この金澤勢は「上総下総ノ勢ヲ附テ、敵ノ後攻ヲセヨトナリ」(『太平記』)の搦手であった。そして、鎌倉道を下ってくる新田勢を食い止める大手には「桜田治部大輔貞国ヲ大将ニテ、長崎二郎高重、同孫四郎左衛門尉、加治二郎左衛門入道」に「武蔵上野両国ノ勢六万余騎ヲ相副」(『太平記』)て入間川へと派遣したという。ただし、桜田治部大輔貞国は近江国番場で北方仲時とともに自刃しており、ここに出陣した桜田某は貞国ではない。
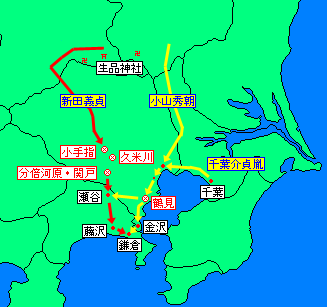
|
| ▲新田義貞の鎌倉攻め(鎌倉をクリック) |
新田勢は5月11日、入間川で川を挟んで桜田勢と対峙し、小手指原で桜田治部大輔貞国(実際は貞国ではない)、長崎四郎高重、長崎孫四郎左衛門尉率いる鎌倉勢と合戦に及び、鎌倉勢は敗北して防衛線を久米川まで下げる。翌12日の久米川の戦いでも鎌倉勢はわずかに敗れ、さらに分倍河原まで撤退した(『太平記』)。なお、足利高氏の嫡子・千寿王は義貞の庇護のもと新田庄世良田宿に匿われており、少なくとも12日までは世良田宿にあり、「新田三河弥次郎満義世良田」もその麾下にあった(「鹿島利氏申状写」『南北朝遺文 関東編』1356)。『太平記』では9日に武蔵国へ入った時点で千寿王が新田勢に加わったことが記されているが、事実ではない。
久米川の敗報を受けた北条高時入道は、5月14日、「高時ノ弟左近大夫将監入道恵性ヲ大将トシテ武蔵国ニ発向ス、同日山口ノ庄ノ山野陣ヲ取」ったといい、その派遣された諸将は「舎弟四郎左近大夫入道恵性ヲ大将軍トシテ、塩田陸奥守入道、安保左衛門入道、城越後守、長崎駿河守時光、佐藤左衛門入道、安東左衛門尉高貞、横溝五郎入道、南部孫二郎、新開左衛門入道、三浦若狭五郎氏明」(『太平記』)と伝わる。
翌15日に「分配関戸河原ニテ終日戦ケルニ、命ヲ殞シ創ヲ被ル者幾千万ト云数ヲ知ス、中ニモ親衛禅門ノ宗徒ノ者共安保左衛門入道道潭、粟田横溝八郎最前ニ討死ヲシケル間、鎌倉勢悉ク引退ク処ニ、即大勢攻上ル間、鎌倉中ノ騒キ只今敵ノ乱入タランモ角ヤチ覚シ」(『梅松論』)という。ただし、分倍河原の戦いでは左近大夫将監入道は桜田貞国と合流し、その勢いのままに新田勢を打ち破り、堀金(狭山市堀兼)まで追い落としたとされる(『太平記』)。このとき新田勢の上野国碓氷郡飽間郷(安中市秋間)の御家人「飽間斉藤三郎藤原盛貞 生年廿六」「同孫七家行 廿三」が「討死」を遂げている(「武蔵府中・相模村岡合戦討死者供養板碑銘」『鎌倉遺文』32175)。
分倍河原の戦いで手痛い反撃を食った新田勢だったが、5月15日夕刻、義貞のもとに三浦一族・大多和平六左衛門義勝が松田・河村・土肥・土屋・本間・渋谷ら相模武士六千騎を率いて着陣。これに喜んだ義貞は、彼らを先陣として翌16日明け方に分倍河原まで進軍。鎌倉勢に襲いかかり追い落としたという(『太平記』)。
●『太平記』にみる鎌倉攻め三手(『太平記』の記述だが、信憑性はない)
| 極楽寺切通 | 大館二郎宗氏、江田三郎行義 |
| 巨福呂坂 | 堀口三郎貞満、大嶋讃岐守守之 |
| 大将 | 新田義貞、脇屋義助(堀口・山名・岩松・大井田・桃井・里見・鳥山・額田・一井・羽川以下の一族達) |
千葉介貞胤の動向は、『太平記』においては「上総下総ノ勢」が武蔵守貞将に従って下河辺庄へと進んだ旨が記されており、史実性にかなり疑問の多い『太平記』の記述ではあるが、千葉介貞胤も従兄弟の貞将の軍勢に加わっていた可能性はある。
しかしその後、「搦手ノ大将ニテ下河辺ヘ被向タリシ金沢武蔵守貞将ハ、小山判官、千葉介ニ打負テ下道ヨリ鎌倉へ引返シ給ケレバ、思ノ外ナル珍事哉ト人皆周章シケル」(『太平記』)とあり、千葉介貞胤はその途上で小山判官高朝とともに寝返り、貞将を襲ったのではあるまいか。なお、『梅松論』では「下ノ道ノ大将ハ武蔵守貞将向フ処ニ下総国ヨリ千葉介貞胤、義貞ニ同心ノ儀有テ攻上ル間、武蔵ノ鶴見ノ辺ニ於テ相戦ケルガ、コレモ打負テ引退」(『梅松論』)とあり、戦った場所は武蔵国鶴見であるという。
千葉介貞胤と小山高朝が歩調を合わせて新田勢に呼応したのは、おそらく高氏からの御内書とともに両者の相談があったためであろう。もともと貞胤と高朝はともに先帝後醍醐の配流の護送を行ったり(『太平記』)、同時期に在京するなど接点も多く、交流もあったと思われる。高氏は4月27日から29日にかけて丹波国篠村で「自伯耆国、所蒙 勅命也」として諸大名に対して「令合力給候」ことを指示(「足利高氏軍勢催促状案」:『鎌倉遺文』)しており、当然貞胤や高朝にも催促状が出されていたのだろう。高氏の鎌倉占拠の計画は前述の通り、鎌倉に居住していた時点で練られていた(占拠の根拠は上洛時の先帝綸旨であろう)と思われ、3月の新田義貞の千早・金剛山からの帰国は高氏が呼び戻したものではなかろうか。ところが直後に高氏は六波羅の援兵として上洛することとなり、計画が一時とん挫したと思われる。その計画を再び動かしたものが、4月22日の御内書であったのだろう。鶴見で金澤勢を破った千葉・小山勢は、そのまま六浦道から鎌倉東側の朝比奈からの突入が考えられるが、千葉・小山勢が鎌倉で戦った記録はなく、鶴見以降の貞胤・高朝の動向は不明である。
また、楠木城攻めの大将軍の一人として上洛し、万里小路藤房を預かった常陸国の小田尾張権守高知も関東離反の姿勢を示したと思われ、彼の預かる新治郡の藤房卿配流屋敷には4月19日、「常陸国御家人」の「■■小四郎久幹、■■又四郎幹国」が馳せ参じている(『税所文書』)。
この頃、新田勢追捕の大手大将軍の北条四郎入道、搦手大将軍の武蔵守貞将の大敗に加え、六波羅探題の陥落も鎌倉に達しており、こうした急激な状勢の変化に鎌倉は周章した。このような中でも得宗高時入道は寡兵ながらも諸所に一門を手配し、執権の相模守守時(足利高氏義兄)には洲崎(鎌倉市大船)の敵を防ぐことを命じ、守時は5月18日に「此陣ノ軍剛シテ、一日一夜ノ其間ニ六十五度マデ切合タリ」(『太平記』)という奮戦をみせた。義弟足利高氏らが六波羅を落とし、足利一門の新田勢が鎌倉を攻めるという事態に深い憂慮と責任を感じていたのではなかろうか。この戦いは双方に多数の死者を出し、新田勢でもこの日「飽間孫三郎宗長 卅五」が「村岡(藤沢市村岡)」で討死したことが知られる(「武蔵府中・相模村岡合戦討死者供養板碑銘」『鎌倉遺文』32175)。しかし、寡勢の守時勢は次第に打ち斃され、「五月十八日、赤橋相州自害了」(『大乗院日記目録』)とあるように守時は「帷幕ノ中ニ物具脱捨、腹十文字ニ切給ヒテ、北枕ニソ伏給」った(『太平記』)。そして守時に従っていた得宗被官の南条左衛門高直も「大将既ニ御自害アル上ハ、士卒誰為ニ命ヲ惜ヘキ、イテサラハ御供申サン」と、九十余名もこれに殉じた(『太平記』)。その後、洲崎を破った新田勢は山ノ内まで軍を進めた(『太平記』)。
新田勢が実際に三軍に分かれたかどうかは不明ながら、「搦手大将軍新田兵部大輔(当時は新田下野五郎経家)」は5月19日に巨福呂坂口近辺にあった長勝寺(現在の材木座長勝寺との関係は不明)の前で合戦しており、さらに20日から22日にかけて巨福呂坂で合戦があったことがわかる(『群馬県史 資料編中世2』資料569)。実際の鎌倉攻めは、高氏の命を受けた「兵部大輔経家并新田義貞」の「両大将」が大手大将軍の新田義貞、搦手大将軍の新田下野五郎(兵部大輔経家)が大きく二手に分かれて鎌倉を攻めたのであろう。洲崎で執権北条守時と直接戦ったのは、その後巨福呂坂に攻め入っている新田岩松経家であったと思われる。そして、この鎌倉攻めのときには足利千寿王(高氏嫡男)が世良田から迎えられており、千寿王に従軍していた「新田三河弥次郎(世良田満義)」が21日に鎌倉市中で戦っている。ここは大手新田義貞の管轄であることから、千寿王は新田義貞の陣中にいたとみられる。
●実際の鎌倉攻め(軍忠状より抜粋)で従軍したことが判明する人々
| 方面 | 大将軍 | 資料でみられる従軍御家人(●は大将軍) |
大手大将軍 ・極楽寺坂 ・大仏坂 |
足利千寿王 | |
| 新田太郎義貞 | ●新田孫次郎盛成(5/19~21極楽寺坂大将軍:妙本寺系図) ●新田蔵人七郎氏義 ・三木俊連(5/21霊山攻) ・三木行俊(5/21霊山攻) ・三木貞俊(5/21霊山攻) ●新田大館宗氏(5/18稲村崎、浜鳥居討死) ●新田大館孫次郎幸氏(5/21浜鳥居脇駆入) ・大塚五郎次郎員成(5/21浜鳥居参戦、6/1二階堂御所着到) ・大塚三郎成光(5/21浜鳥居討死) 大多和太郎遠明(5/21浜鳥居合戦) 海老名藤四郎頼親(5/21浜鳥居合戦) 飽間三郎盛貞(5/15府中討死) 結城上野入道道忠(5/18~22合戦) ・ 田嶋与七左衛門尉広堯(同上) ・ 片見彦三郎祐義(同上) 市村王石丸代後藤弥四郎信明(5/15分倍河原参戦、5/18前浜一向堂前参戦) 塙大和守政茂(5/16入間川着到、5/19極楽寺坂参戦) 徳宿彦太郎幹宗(5/19極楽寺坂参戦) 宍戸安芸四郎知時(5/19極楽寺坂参戦) ●新田遠江又五郎経政 ・熊谷平四郎直春(5/16参戦、5/20霊山寺下討死) ・ 吉江三位律師奝実 ・ 齊藤卿房良俊 石川七郎義光(5/17瀬谷参陣、5/18稲村崎参戦、5/21前浜合戦) 藤田左近五郎(5/18稲村崎参戦) 藤田又四郎(5/18稲村崎参戦) 岡部又四郎(5/21前浜合戦) 藤田十郎三郎(5/21前浜合戦) ●武田孫五郎信高(霊山大将軍) ・南部五郎二郎時長(5/20霊山参戦、5/22高時館合戦) ・南部行長(5/20霊山参戦) ・中村三郎二郎常光(5/20霊山討死) ・南部六郎政長(5/15~22鎌倉合戦参戦) ●新田三河弥次郎満義(5/20霊山参戦) ・鹿島尾張権守利氏(5/12世良田千寿王陣着到) 天野周防七郎左衛門尉経顕(5/18片瀬原着到、稲村崎、稲瀬川、前浜参戦 5/22葛西谷合戦参戦) ・天野三郎経政(5/18片瀬原着到、稲村崎、稲瀬川、前浜参戦 5/22葛西谷合戦参戦) 新田矢嶋次郎(5/22葛西谷合戦参戦) 山上七郎五郎(5/22葛西谷合戦参戦) |
|
| 搦手大将軍 ・巨福呂坂 ・化粧坂 |
新田下野五郎(岩松経家) | 飽間孫三郎宗長(5/18村岡討死) ●岡部三郎(侍大将) ・布施五郎資平(5/19長勝寺前合戦、5/20~22小袋坂合戦) |
新田義貞率いる大手勢は洲崎合戦と同日の18日には極楽寺坂方面へ集結し、「新田殿前代合戦之最初、聖福寺江被取陣事」(「正続院領相模国山内庄秋庭郷内信濃村事」『鎌倉円覚寺文書』)とあるように、北条時頼入道建立と言われる聖福寺に陣を取ったという。そして大手勢に加わっていた「天野周防七郎左衛門尉経顕」「子息三郎経政」は「最前馳参于片瀬原」し、「懸破稲村崎之陣迫于稲瀬河并前浜鳥居脇致合戦」で若党の犬居左衛門五郎茂宗、小河彦七安重、中間孫五郎藤次らが討死を遂げている(「天野経顕軍忠状写」『群馬県史 資料編6中世2』番号583)。
天野遠景――天野政景―+―天野景経――天野遠時―――――天野経顕―――――――天野経政
(藤内) (和泉守) |(安芸守) (周防守) (周防七郎左衛門尉) (三郎)
|
+―女子
(相馬尼)
∥―――――相馬胤村―――――相馬師胤―――――――相馬重胤
∥ (孫五郎左衛門尉)(彦次郎) (孫五郎)
相馬師常――相馬義胤―――相馬胤綱
(次郎) (五郎) (小次郎左衛門尉)
また「陸奥国石川七郎源義光」も17日に「相模国世野原(横浜市瀬谷区)」に馳せ参じ、翌18日には「稲村崎致散々合戦」して右膝を射られている(『石川文書』)。常陸国鹿島郡の御家人「塙大和守平政茂」は5月16日に「武蔵国入間河御陣馳参」じ、19日の「極楽寺坂於合戦先手馳向、家人丸場次郎忠邦、怨敵三騎討捕、同山本四郎義長討死之事、徳宿彦太郎幹宗、宍戸安芸四郎同時合戦」(『塙文書』)であった。そして千早・金剛山を攻めるべく上洛していた「武蔵国小四郎直経(熊谷直経)」の留守であったと思われる子・平四郎直春は、5月16日に新田勢に馳せ参じ、20日には「新田遠江又五郎経政御手、就致軍忠、於鎌倉霊山寺之下討死畢」と討死を遂げている(『閥閲録』)。
前述のように天野周防七郎左衛門尉経顕の軍勢が「懸破稲村崎之陣」り、海岸線を伝って「前浜鳥居脇」まで侵入しており、新田勢は5月18日に「稲村崎ヲ経テ前浜ノ在家ヲ焼払フ煙見ヘケレハ、鎌倉中ノ周章フタメキケル有様タトヘテ云ン方ソナキ」状況であった(『梅松論』)。二年後の建武2(1335)年11月6日、足利尊氏は「天野安芸七郎殿」に「鎌倉中入口内稲村崎警固事、一族相共可致厳密之沙汰」を命じているように、天野氏は稲村崎周辺の地理に明るい氏族であったとみられ、近辺に屋敷があった可能性があろう、なお、稲村崎は「鎌倉中入口」であって、『太平記』に見られるような奇襲路ではない。
しかし、北条方も「高時ノ家人諏訪長崎以下ノ輩、身命ヲ捨テ防戦ケル程ニ、当日ノ浜ノ手ノ大将大館、稲瀬河ニ於テ討捕、其ノ手引退テ霊山ノ頂ニ陣ヲ取」ったといい(『梅松論』)、新田勢大将軍の一人、大館次郎宗氏が「得川弥四郎光秀」(『尊卑分脈』)によって討たれている。
+―北条有時――+―――――――――――――――――――女子
|(駿河守) | ∥―――――+―堀口貞義―――堀口貞満
| | ∥ |(美濃守) (美濃守)
| +―女子 ∥ ?
| ∥ ∥ +―一井貞政―――一井政家
| ∥ ∥ (民部権大夫)(左近将監)
+―名越朝時――+―名越時幸 ∥
|(遠江守) |(遠江修理亮) ∥
| | ∥
| | 新田義房――――新田政義――――――堀口家貞
| |(上西門院蔵人)(小太郎) (孫次郎)
| | ∥
| | ∥ +―新田政氏――――新田基氏―――新田朝氏―――新田義貞
| | ∥ |(又太郎) (小太郎) (小太郎) (小太郎)
| | ∥ |
| | ∥―――――――+―大館家氏――――大館宗氏―+―大館幸氏
| | ∥ (又次郎) (又次郎) |(孫二郎)
| | ∥ |
| | 足利義氏――+―女子 +―大館氏明
| |(左馬頭) | (左馬助)
| | ∥ |
| | ∥ +―足利長氏――――+―足利満氏――――吉良貞義―――吉良満義
| | ∥ |(上総介) |(上総介) (上総介) (左京大夫)
| | ∥ | |
| | ∥ +―大僧正最信 +―今川国氏――――今川基氏―――今川国範
| | ∥ |(勝長寿院別当) (四郎) (太郎) (五郎)
| | ∥ |
| | ∥ | +―四条隆量
| | ∥ | |(左近衛少将)
| | ∥ +―女子 |
| | ∥ ∥―――――――――四条隆顕――+―四条隆資―+―四条隆重
| | ∥ ∥ (左近衛中将)|(大納言) (左近衛少将)
| | ∥ ∥ |
| | ∥ 四条隆親 +―女子
| | ∥ (大納言) ∥――――――吉田宗房
| | ∥ ∥ (右大臣)
| +―――――――――女子 吉田定房
| ∥ ∥ (内大臣)
| ∥ ∥――――――+――足利家氏
| ∥ ∥ | (尾張守)
| ∥ ∥ | ∥―――――――足利宗家
| ∥ ∥ | ∥ (左近将監)
| ∥ ∥ |+―女子 ∥――――――足利宗氏
| ∥ ∥ || ∥ (尾張守)
+―北条重時――――――――――――――北条時継――――――――――――女子 ∥――――+―足利高経
|(陸奥守) ∥ ∥(式部大夫)|| ∥ |(尾張守)
| ∥ ∥ || ∥ |
| ∥ ∥ || 長井時秀―――女子 +―足利家兼
| ∥ ∥ || (宮内権大輔) (左京権大夫)
| ∥ +―――北条為時――+―女子
| ∥ | ∥(遠江守) | ∥―――――――渋川義春
| ∥ | ∥ | ∥ (次郎三郎)
| ∥―――――――足利泰氏 +――足利義顕 ∥――――――渋川貞頼―――渋川義季
| ∥ |(宮内少輔) (二郎) ∥ (兵部大輔) (刑部権大輔)
| ∥ | ∥ ∥
| ∥ | ∥ 北条時村――――北条時広――――女子 +―足利高氏
| ∥ | ∥(五郎) (越前守) |(治部大輔)
| ∥ | ∥ |
| ∥ | ∥―――――――――足利頼氏――――足利家時―――足利貞氏―+―足利高国
北条義時―+―北条泰時――+―女子 +―女子 (治部大輔) (伊予守) (讃岐守) (兵部大輔)
(陸奥守) (左京権大夫)| |
| |
+―北条時氏――+―北条時頼――――――北条時宗――――北条貞時―――北条高時
(修理亮) (相模守) (相模守) (相模守) (相模守)
新田勢は数度にわたって鎌倉市中に攻め入り、21日には大規模な戦闘が行われた。なお、鎌倉内でも新田勢に呼応した反乱が起こっていたと思われ、去る4月2日に「抑相催一族已下軍勢、可令誅罰伊豆国在庁高時法師等凶徒由事」の(大塔宮)令旨を受けた得宗地頭代「沙弥道忠(白河結城宗広入道)」は白河在住の「愚息親朝、親光」、在鎌倉の「舎弟祐義、広堯等」、そしておそらく京都にいたと思われる「熱田伯耆七郎(「親類伯耆又七朝保」の父か)」に令旨を伝えるとともに、4月17日に「陸奥出羽両国軍勢可令征伐前相模守平高時法師以下凶徒」の先帝綸旨を「折節幸在鎌倉仕候」を受けて挙兵の心を固め、時勢を窺いながら鎌倉を見限り、5月18日の新田勢の鎌倉侵入に呼応し「先於鎌倉、相率道忠舎弟片見彦三郎祐義、同子息二人、田島与七左衛門尉広堯、同子息一人并家人」(「白河証古文書」『楓軒文書纂文書』)を率いて鎌倉内で兵を挙げたとみられる。こうした在鎌倉で鎌倉を離反した御家人はおそらく白河結城氏に限ったものではなかったであろう。また、鎌倉で将軍守邦親王に仕えていたとみられる従三位阿野実廉は「元弘三年三月、已 臨幸伯州船上山之由、風聞之間、雖欲馳参、山河多重、塞関楯稠、不達本意、蟄居関東之処、五月十四日、故高時法師等差遣討手於実廉、囲私宅、希有而遁万死之陣、交山林、送数日之刻、同十八日、義貞朝臣責入于鎌倉、致逆徒討罰之間、馳加彼手、至廿二日首尾五ケ日之間、於処々致軍忠畢」(「実廉申状」『南北朝遺文』602)とあり、5月14日に自邸を取り囲まれたため山林に逃れ、18日に鎌倉に入った新田勢に加わって戦ったという。
 |
| 材木座より稲村ガ崎を望む |
新田勢本隊は稲村崎を通って比較的自由に鎌倉に出入りしながら鎌倉勢と合戦し、北側では下野五郎経家が指揮を採る搦手軍が巨福呂坂周辺から鎌倉への突入を試みていた。そして「同十八日ヨリ廿二日ニ至マテ、山内、小袋坂、極楽寺ノ切通以下鎌倉中ノ口々、合戦ノ鬨ノ声、矢叫ビ人馬ノ足音暫シモ止ム時無シ」(『梅松論』)という諸所での合戦が行われた。
5月22日には鎌倉市中での戦いが広く行われるようになったようで、「相摸入道殿ノ屋形近ク火懸リケレバ、相摸入道殿千余騎ニテ葛西谷ニ引籠リ給ケレバ、諸大将ノ兵共ハ東勝寺ニ充満タリ、是ハ父祖代々ノ墳墓ノ地ナレバ爰ニテ兵共ニ防矢射サセテ心閑カニ自害セン也」(『太平記』)という。また、南部五郎次郎時長は「廿二日、於高時禅門館生捕海道弥三郎、取高時一族伊具土佐孫七頸畢」(「南部時長等申状」『陸奥南部文書』)と、高時入道が去った館に攻め入り、留守居の海道弥三郎や伊具土佐孫七を討った。「葛西谷之合戦」では、天然の堀の滑川とそれを見下ろす高台の東勝寺からの防戦など、激しい攻防があったと思われる。このほか、この鎌倉合戦が突然始まったものであるため「石見国益田荘宇地村地頭尼是阿相伝文書等、為沙汰、被預置大内豊前権守長弘関東代官因幡法橋定盛之處、元弘三年五月廿三日動乱之時、定盛於鎌倉死去之間、彼手継文書以下、六波羅下知等悉令紛失之由」(建武二年七月十七日益田兼世申状『益田家什書』)とあるように、大内長弘の「関東代官」が討死を遂げたため相伝文書が紛失したこともあった。
極楽寺坂を固めていた「長崎三郎左衛門入道思元、子息勘解由左衛門為基二人」は、小町方面に鬨の声を聞き、遠目に「鎌倉殿ノ御屋形ニ火懸リヌ見へ」たため、預けられた兵はそのまま極楽寺坂に置き、私兵を六百騎ばかりを率いて小町の御所へ馬を走らせたという(『太平記』)。これを見た新田義貞は彼らを取り込め、激しい抵抗を受けながらも討ち取った。
化粧坂口から巨福呂坂へ転戦した武蔵守貞将は、全身七か所を負傷しながらも東勝寺の得宗・高時入道のもとへ帰参した。高時は「軈て両探題職に可被居御教書を被成、相摸守にぞ被移ける」と、彼に感謝の言葉を述べるとともに、今や滅亡した六波羅南北両探題ならびに相模守とする旨の下文を与えたという(『太平記』)。貞将はこれを拝受し、「多年ノ所望、氏族ノ規摸トスル職ナレハ、今ハ冥途ノ思出ニモナレカシ」と述べ、御教書に「棄我百年命報公一日恩」と認めると、鎧の継ぎ目に御教書を差し込み、ふたたび鎌倉市街に馳せ戻り戻って来ることはなかった(『太平記』)。
このほか、化粧坂で新田岩松勢と交戦していた元執権・前相模守基時入道信忍(普恩寺入道。探題北方仲時の父)も自刃。塩田陸奥守国時入道道祐・北条民部大輔俊時父子、塩飽新左近入道聖遠、安東左衛門入道聖秀など名だたる大将も鎌倉の諸所で自刃して果てた。
一方、高時の弟・左近大夫将監泰家入道は、被官の諏訪入道直性の一族・諏訪三郎盛高に、兄・高時入道の二男・亀寿丸を託して信濃国へ遁れさせ、みずからは陸奥国へと姿を消した。得宗高時入道にも恐れられた内管領・長崎円喜入道の孫である長崎左衛門尉高重は三十二人も斬り払う奮戦ののち東勝寺へ帰参した。高重は高時にいましばらく自刃を思いとどまるよう述べると、再び新田勢に近づき、大将義貞の暗殺を企てるも、義貞被官・由良新左衛門に見破られて失敗。数十倍する敵勢相手に斬り廻り、新田勢の同士討ちを誘うと、その隙をついて東勝寺へ退却した。残った高重麾下の武士はわずかに八騎。みずからも二十三筋もの矢を体中に立てて高時入道の御前に侍ると、祖父の円喜入道が待ち受けて「何トテ今マテ遅ツルソ、今ハ是マテカ」と問うと、高重は「若大将義貞ニ寄セ合バ、組テ勝負ヲセハヤト候テ、二十余度マテ懸入候ヘ共、遂ニ不近付得」と義貞暗殺の失敗を述べ、「上ノ御事何カト御心元ナクテ帰参テ候」と報告した。そして「早々御自害候へ、高重先ヲ仕テ手本ニ見セ進セ候ハン」と、舎弟の長崎新右衛門に酌を取らせて三度傾てのち、摂津刑部太夫入道道準の前に盃を置くと、「思指申ソ、是ヲ肴ニシ給へ」と言うや自刃を遂げた。
これを受けた摂津刑部大夫入道も「アハレ肴ヤ何ナル下戸ナリ共此ヲノマヌ者非ジ」と、置かれた杯を半分ほど飲むや、諏訪入道直性の前に盃を置いて自刃した。諏訪入道直性も心静かに盃を三度傾け、高時入道の前に盃を置くと「若者共随分芸ヲ尽シテ被振舞候ニ年老ナレハトテ争カ候ヘキ、今ヨリ後ハ皆是ヲ送肴ニ仕ヘシ」と述べて腹を十文字に掻き切ると、その刀を高時入道の前に置いて果てた。
長崎円喜入道はまだ若い高時入道の事を心配して腹を切らずにいたが、孫の新右衛門がその前に畏まり「父祖ノ名ヲ呈スヲ以テ子孫ノ孝行トスル事ニテ候ナレハ、仏神三宝モ定テ御免コソ候ハンスラン」と述べると、円喜入道を刺殺して自らも自刃。新右衛門の義を見た高時入道も自裁した。享年二十九。時を置かず、城入道(安達時顕入道)をはじめとして「金澤太夫入道崇顕、佐介近江前司宗直、甘名宇駿河守宗顕、子息駿河左近太夫将監時顕、小町中務太輔朝実、常葉駿河守範貞、名越土佐前司時元、摂津形部大輔入道、伊具越前々司宗有、城加賀前司師顕、秋田城介師時、城越前守有時、南部右馬頭茂時、陸奥右馬助家時、相摸右馬助高基、武蔵左近大夫将監時名、陸奥左近将監時英、桜田治部太輔貞国、江馬遠江守公篤、阿曾弾正少弼治時、苅田式部大夫篤時、遠江兵庫助顕勝、備前左近大夫将監政雄、坂上遠江守貞朝、陸奥式部太輔高朝、城介高景、同式部大夫顕高、同美濃守高茂、秋田城介入道延明、明石長門介入道忍阿、長崎三郎左衛門入道思元、隅田次郎左衛門、摂津宮内大輔高親、同左近大夫将監親貞、名越一族三十四人、塩田、赤橋、常葉、佐介ノ人々四十六人、総シテ其門葉タル人二百八十三人」らが同所で自刃し、轟炎に包まれた東勝寺の中で鎌倉北条家は滅亡した。境内や門前の兵士らもこれに続き、総数は八百七十余人を数えたという。ただし、この中にはすでに近江番場で自刃している桜田貞国や、当時南都に駐屯していた阿曾弾正少輔弼治時など、実際には鎌倉にいない人物も含まれており、史実とは異なる。
 |
| 北条氏の菩提寺・東勝寺の跡地 |
東勝寺の跡地は「東勝寺遺跡」として、昭和50(1975)年に調査が行われ、北条氏の紋「三鱗」のある瓦、焼けた陶磁器の破片が発見されている。そして、平成9(1997)年1月、国指定史跡をめざしてふたたび発掘調査が進められ、同年6月、高熱に焼かれた土などとともに巨大な建物跡が発見された。この建物には柱が四十本用いられ、東西が8.4メートル、南北が14.7メートル、総床面積が120平方メートルにも及ぶ大きな建築物で、北条一門が自刃を遂げた東勝寺の本堂と考えられている。
なお、鎌倉北条氏は「鎌倉」時代を通じて鎌倉の「主」であったわけではない。北条家はあくまでも鎌倉家(のち鎌倉親王家)という鄙公卿(親王)の家司筆頭(後見)を務め、評定衆を統べた一族であって、もともとは御家人ではなく鎌倉家の家子(血縁者)であった。その官途は親王家家司の例に洩れず四位または五位に留まり、摂関家家司に及ばない。彼等がその権勢を奮い得たのは、強大な武力と広大な土地の支配権限を持つ公卿鎌倉家の家政機関を通じて、鎌倉家家人である「御家人」を統制していたためである。その北条氏の中でも同宗を統率し得る宗家当主を得宗と呼んだ(「得宗」は時頼の後継者の時宗以降の宗家を指す)。
●鎌倉家執権北条氏の官途
| 得宗 | 名前 | 最終官位 | 最終官途 |
| ― | 北条義時 | 従四位下 | 陸奥守 |
| ― | 北条泰時 | 正四位下 | 左京権大夫 |
| ― | 北条経時 | 正五位下 | 武蔵守 |
| ― | 北条時頼 | 正五位下 | 相模守 |
| 北条長時 | 従五位上 | 武蔵守 | |
| 北条政村 | 正四位下 | 左京権大夫 | |
| ● | 北条時宗 | 正五位下 | 相模守 |
| ● | 北条貞時 | 従四位上 | 相模守 |
| 北条師時 | 従四位下 | 左京権大夫 | |
| 北条宗宣 | 従四位下 | 陸奥守 | |
| 北条煕時 | 正五位下 | 相模守 | |
| 北条基時 | 正五位下 | 相模守 | |
| ● | 北条高時 | 従四位下 | 修理権大夫 |
| 北条貞顕 | 従四位上 | 修理権大夫 | |
| 北条守時 | 従四位上 | 相模守 |
北条一門が滅んだ鎌倉は、三堂山(三笠山)永福寺の別当房「二階堂御所山上陣屋」(「大塚員成軍忠状案」『鎌倉遺文』七三)に滞在していた足利千寿王丸の統制下に入り、その一門大将であった新田小太郎義貞は、5月28日に密告を受けて「故相模入道ノ嫡子相模太郎邦時」を相模川に捕らえて鎌倉に連行し「翌日ノ暁、潜ニ首ヲ刎奉ル」(『太平記』)という。
この頃、高氏が「関東追討の為に」京都から派遣した「細川阿波守、舎弟源蔵人、掃部介兄弟三人」は「関東はや滅亡」の一報を受けたが、そのまま鎌倉に下向。「若君を補佐し奉」ったが、「鎌倉中連日空騒ぎ」する事態が発生。「世上穏かならざる間、和氏、頼春、師氏兄弟三人、義貞の宿所に向て、事の子細を問尋て、勝負を決せんとせられけるに依て、義貞野心を存せさるよし、起請文を以陳し申され」たという(『梅松論』)。あくまでも軍記物『梅松論』の記述ではあるが、新田義貞に起因する何らかの騒擾があり、細川兄弟による尋問があったことがうかがえる。なお、前述の通り、新田惣領家は足利家に従属していたものの、経済的にも豊かな独立御家人であり、同じく一門御家人の足利尾張家(斯波家)や荒川家、足利三河守家(吉良家)らよりも遠縁にあたることから、より独立性の高い一族だったと考えられる。
6月3日、千寿王丸付の紀五左衛門尉政綱が、先代御内人系御家人の「曾我左衛門太郎入道」に対し、「曾我人々相共」に「常葉」の警固を命じる御教書を下している(「齋藤文書」『鎌倉遺文』32232)。この曾我左衛門太郎入道は陸奥国津軽平賀郡の大平賀村一帯を領する津軽曾我氏で、子息の「乙房丸(曾我太郎光高)」は10月10日に鎌倉の千寿王御所(二階堂永福寺の南東部高台か)の警衛を命じられているが、その後、北畠顕家に従って陸奥国津軽郡の敵対する同族と激戦を繰り広げる。
 |
| 京都御所 |
正慶2(1333)年5月17日、後醍醐天皇は伯耆国船上山で「止正慶年号、為元弘三年、又去五月詔去々年已来任官已下、勅裁悉停廃」(『皇年代略記』)という詔を発する。
この詔は後醍醐天皇自身は退位しておらず、光厳天皇は実際には即位すらしていないとして、光厳天皇在位中の改元、すべての任官、勅裁を否定したのである。六波羅探題の崩壊により、後ろ盾を失った持明院統の三上皇はこの詔に従う他なかったであろう。この伯耆国からの詔は現朝廷を震撼させ、関白冬教、太政大臣兼季、左大臣基嗣は免職、前左府道平は左大臣、氏長者に戻され、前右大臣経忠は右大臣とされた(このときは就任を拒絶している)。これら上卿、公卿、公家らの「官途巻き戻し」は朝政の停滞を招く重大事であったが、裾野の広い地下已下における同様の措置は更なる混乱を招いたと思われる。翌5月18日、後醍醐天皇は船上山を下り、名和一族が供奉して京都へ還幸の途についた(『伯耆巻』)。
元弘3(1333)年11月の陸奥守顕家の奥州下向に続き、12月14日に「成良親王并左馬頭直義、下向鎌倉」(『鎌倉年代記裏書』)した。成良親王はこのとき八歳。鎌倉下向を前に11月20日に親王宣下を受けている(『鎌倉将軍次第』)。三浦介時継入道もこれに同道して関東へ下っている。
鎌倉は尊氏の妻子および細川和氏、頼春らを筆頭とする足利一族が臨時統治している状態に過ぎず、手薄な状況にあった(さらに奥州加勢の人々が抜けている)。鎌倉は百五十年に渡って鄙住公卿の鎌倉家(鎌倉宮)が本拠を置き、多くの御家人が屋敷を構えた覇府にして武家の「吉土」(『建武式目』)である。この地を先代勢力に奪還されれば武家の動揺は否めない。奥羽及び鎌倉への皇子及び国司の派遣(このほか北陸、九州への派遣も検討されていたのではなかろうか)は後醍醐天皇の帰洛以前から計画されていたと考えられ、鎌倉へは足利尊氏の実弟・直義が派遣されることとなった。直義が選ばれたのは政治的な理由ではなく、鎌倉を統治していたのが千寿王丸であり、少なくとも千寿王丸よりも目上かつ足利一党の人々を統率できる必要があったためであろう。
成良親王及び直義ら一行は、12月28日に「宮御下向関東、左馬頭、山城入道以下御共、二階堂小路以山城美作入道屋鋪為御所」(『将軍執権次第』)といい、千寿王丸の御所である「二階堂御所山上陣屋」(「大塚員成軍忠状案」『鎌倉遺文』七三)に近接する「山城美作入道(故二階堂貞衡入道)」屋敷が親王御所と定められた。その管国は「関東八ヶ国為守護」(『保暦間記』)で、成良親王家は「直義左馬頭、尊氏弟」が親王家別当(家政機関としての政所も統べた)ならびに「執権」(『将軍執権次第』)、「政所執事三河入道行諲」(『将軍執権次第』)、「三河入道行諲元弘三以後、俗名時綱」(『関東将軍家政所執事次第』)が家令を務めたのだろう。また、直義は義弟の渋川刑部大輔義季(渋川足利家は兄家の足利尾張守家と同様に得宗家に次ぐ名門名越家の血を引き、足利尾張守家とともに足利別家の御家人であった)、兵部大輔の直義後任・岩松兵部大輔経家を同行していたとみられ、彼らは鎌倉において御所を警衛する「関東廂番(朝廷における武者所と同様)」の頭人となっている。
なお、一般に「鎌倉将軍府には陸奥将軍府とは異なり、然したる政務機関は置かれなかった」とされるが、実際には先代及び陸奥国衙同様の政庁が設置されていた。これらは『建武年間記』などでは明確な記録として残らないものの「政所(親王家政所)」も置かれ、政所執事には二階堂氏が就いている(「関東将軍家政所執事次第」『関東開闢皇代并年代記』)。また鎌倉に祗候する武士の統率や御所出仕の監督などを司る「侍所」も置かれており、後年の中先代の乱では「為与党人退治、侍所御代官被向候」と、侍所の代官がその追討に動いている(『三浦文書』)。さらに建武2(1335)年正月7日時点で侍所の下部組織「小侍所」が設置され(『御的日記』)、別当は「渋河殿(渋川義季)」であったとみられる。また、直義が「執権(評定衆筆頭)」として親王家を補佐している以上、その家政決定機関である評定衆が存在していたと考えられ、「三河入道行諲元弘三以後、俗名時綱」(「関東将軍家政所執事次第」『関東開闢皇代并年代記』)は「引付頭、御所奉行」(『武家年代記』)を務めており、引付衆も存在していた。そのほか元弘4(1334)年2月5日に「上杉左近蔵人殿」が「大御厩事」を命じられているが、これもかつて「葛西谷口、河俣」に新造されていた「大御厩」(『吾妻鏡』建長三年二月廿日条)を継承したものであろう(建久2(1191)年6月17日に「三浦介」が建造の奉行を命じられたもの。場所は不明だが幕府内か)。このように当時の鎌倉には先代鎌倉親王家と同様の家政機関が置かれていたことがわかる。また、建武元(1334)年8月に平泉中尊寺が歴代の諸堂修造の経緯と「京都鎌倉兵乱祈誓、今年津軽合戦御祈祷忠勤」を述べて、修造資金の要請を依頼する申状が陸奥国衙および「鎌倉御奉行所」(『中尊寺経蔵文書』)の両方へ届けられていることから、鎌倉と陸奥国衙が強い連携のもとにあったことが想定される(この申状に対する鎌倉からの返事は現存しない。陸奥国衙では顕家が9月6日に国宣を下して中尊寺領への狼藉に対する掣肘を加えているが、堂舎修造の資金についての記載はない)。
翌元弘4(1334)年正月5日、尊氏は従三位から正三位に昇叙する(『公卿補任』)。従三位となったのが前年8月5日であり、尊氏に対してかなり積極的な昇叙が行われたことになる。位階上は陸奥守顕家の二席下であったが、鎮守府将軍たる尊氏は陸奥国と鎌倉を繋ぎ、内奏する役割を担っていたのであろう(尊氏は少なくとも関東、九州、中国、四国、畿内の武家に対する監理を行っている)。尊氏は主上後醍醐天皇と対立関係にはなく(ただし、将軍宮護良親王とは対立関係にあった)、相当に信任を得ていたことがわかる。従三位が極官であれば、かつての源三位頼政のような形ばかりのものとも言えるが、その後短時間でさらに正三位へ昇叙された背景には、昇叙が上辺だけのものではなく尊氏自身は事実上閑院家当主に准じた家格として遇された結果であろう。これに伴い、嫡子の義詮(千寿王)も閑院家嫡子に准じ、建武2(1335)年4月7日には、足利尊氏嫡子の義詮(千寿王)がわずか六歳で叙爵している(『公卿補任』)。また、家業としては「笙」が選ばれ、建武元(1334)年7月20日に「御笙始」(『足利家官位記』)が行われている。これらから、尊氏は他の武家とは隔絶した次元の武家公卿(ただし摂家に準じた旧鎌倉家とは家格差がある)として存在したのである。それは元来御家人中最上の名家に加え実朝将軍以来の武家公卿という強力なカリスマ性に基づく武家の統率(これは鎌倉御家人との紐帯を全く持たない護良親王には不可能なことであった)、陸奥守と鎮守府将軍の積極的な連携が期待された結果であろう。ただし、こうした尊氏の特殊な役割と地位は京都常駐を以って成し得るものであり、弟の直義が鎌倉へ下向したのもこうした理由によるものであろう。
●元弘4(1333)年正月5日、7日、13日除目
| 正月 | 名 | 官職 | 官位 |
| 5日 | 恒明親王 | 式部卿親王 | 二品⇒一品(昇叙) |
| 13日 | 成良親王 | 上野太守(補任) | 無品⇒四品(叙品) |
| 13日 | 葉室長隆 | 中納言⇒権大納言 | 正二位 |
| 13日 | 洞院公泰 | 権中納言(還任) | 正二位 |
| 5日 | 一条経通 | 権大納言、左近衛大将 | 従二位⇒正二位(昇叙) |
| 5日 | 九条道教 | 権大納言、右近衛大将 | 従二位⇒正二位(昇叙) |
| 5日 | 御子左為定 | 権中納言 | 従二位⇒正二位(昇叙) |
| 7日 | 土御門親賢 | 前権中納言 | 従二位⇒正二位(昇叙) |
| 5日 | 四条隆資 | 権中納言 | 正三位⇒従二位(昇叙) |
| 5日 | 徳大寺公清 | 権中納言 | 正三位⇒従二位(昇叙) |
| 5日 | 二条良忠 | 非参議、右近衛少将 | 正三位⇒従二位(昇叙) |
| 13日 | 坊門清忠 | 参議、右大弁、興福寺長官、信濃権守(補任) | 正三位 |
| 13日 | 今出川実尹 | 参議、左近衛中将、中宮権大夫、備前権守(補任) | 正三位 |
| 13日 | 高倉経康 | 非参議、右京大夫、河内権守(補任) | 正三位 |
| 13日 | 九条隆朝 | 非参議、侍従、近江権守(補任) | 正三位 |
| 5日 | 勧修寺経顕 | 前参議 | 従三位⇒正三位(昇叙) |
| 5日 | 資継王 | 非参議、神祇伯 | 従三位⇒正三位(昇叙) |
| 5日 | 足利尊氏 | 非参議、左兵衛督、鎮守府将軍、武蔵守 | 従三位⇒正三位(昇叙) |
| 5日 | 油小路隆蔭 | 非参議 | 従三位⇒正三位(昇叙) |
| 13日 | 日野行氏 | 非参議、式部権大輔、丹波権守 | 従三位 |
正月13日、除目により「無品成良親王在鎌倉、叙四品、任上野太守」(『読史愚抄』)となり、23日には成良親王や陸奥七宮(のちの義良親王)の実兄・恒良親王(十三歳)が皇太子と定められ、東宮職と春宮坊が定められた。
●元弘4(1334)年正月23日恒良親王東宮職、春宮坊
| 東宮職 | 傅 | 従一位 | 左大臣 | 二条道平 |
| 学士 | 従四位下 | 藤原言範 | ||
| 学士 | 従五位上 | 式部少輔 | 唐橋高嗣 | |
| 春宮坊 | 大夫 | 従二位 | 権大納言 | 鷹司師平 |
| 権大夫 | 正三位 | 権中納言 | 洞院実世 | |
| 亮 | 従四位下 | 右中弁 | 中御門宣明 | |
| 大進 | 正五位下 | 蔵人 | 甘露寺藤長 | |
| 権少進 | 従五位下 | 柳原教光 |
鎌倉に四品親王家の除書が届けられると、「長井大膳権大夫大江広秀建武元補」(「関東将軍家政所執事次第」『関東開闢皇代并年代記』)、「上野親王庁務」(『武家年代記』)とあるように親王家政所執事に補された。なお、長井広秀の前代執事である「三河入道行諲元弘三以後、俗名時綱」(「関東将軍家政所執事次第」『関東開闢皇代并年代記』)は「引付頭、御所奉行」(『武家年代記』)を務めており、執事を退いたのちも家司としてこれらを務めていたとみられる。また、御所の守衛を行う「関東廂番」も定められている(『建武年代記』)。これは京都における武者所と同様の役割を担ったと考えられる。「関東廂番」の第三番には「相馬小次郎高胤」が選ばれているが、彼は「高」字から推測される通り、御内人であったとみられる。
●関東廂番
| 一番 | 刑部大輔義季 (渋川義季) |
長井大膳権大夫広秀 (長井広秀) |
左京亮 (上杉重兼) |
仁木四郎義長 (仁木義長) |
武田孫五郎時風 (武田時風) |
河越次郎高重 (河越高重) |
丹後次郎時景 (二階堂時景) |
| 二番 | 兵部大輔経家 (岩松経家) |
蔵人憲顕 (上杉憲顕) |
出羽権守信重 (高坂信重) |
若狭判官時明 (三浦時明) |
丹後三郎左衛門尉盛高 (二階堂盛高) |
三河四郎左衛門尉行冬 (二階堂行冬) | |
| 三番 | 宮内大輔貞家 (吉良貞家) |
長井甲斐前司泰広 (長井泰広) |
那波左近大夫将監政家 (那波政家) |
讃岐権守長義 |
山城左衛門大夫高貞 (二階堂高貞) |
前隼人正致顕 (摂津致顕) |
相馬小次郎高胤 (相馬高胤) |
| 四番 | 右馬権助頼行 (一色頼行) |
豊前前司清忠 (佐々木清忠) |
宇佐美三河前司祐清 (宇佐美祐清) |
天野三河守貞村 (天野貞村) |
小野寺遠江権守道親 (小野寺道親) |
因幡三郎左衛門尉高憲 (二階堂高憲) |
遠江七郎左衛門尉時長 |
| 五番 | 丹波左近将監範家 (石塔範家) |
尾張守長藤 (二階堂長藤) |
伊東重左衛門尉祐持 (伊東祐持) |
後藤壱岐五郎左衛門尉 (後藤基家) |
美作次郎左衛門尉高衡 (二階堂高衡) |
丹後四郎政衡 (二階堂政衡) | |
| 六番 | 中務大輔満義 (吉良満義) |
蔵人伊豆守重能 (上杉重能) |
下野判官高元 (二階堂高元) |
高太郎左衛門尉師顕 (高師顕) |
加藤左衛門尉 |
下総四郎高家 (二階堂高宗) |
こうした中、3月9日に「本間、渋谷一族、各々打入鎌倉、於聖福寺合戦」(『将軍執権次第』)、「於関東、本間渋谷等一党叛逆」(「実廉申状断簡」『南北朝遺文』602)とあるように、御内人の本間、渋谷氏が挙兵し、鎌倉西側の聖福寺方面から攻め込む事件が起こった。本間氏・渋谷氏は中心的な御内人系御家人であり、多勢力だったのだろう。直義は支えきれずに鎌倉侵入を許したとみられ、「政所執事三河入道行諲」は逐電し、親王御所も危険にさらされ、甥の成良親王を支えていた「実廉独祗候竹園、奉警固 大王之間、候人等随而随分之軍忠」(「実廉申状断簡」『南北朝遺文』602)と、ひとり成良親王を護衛し、麾下の候人を差配して守り抜いた。直義も態勢を立て直し「鎌倉大将渋河刑部大輔義季」(『将軍執権次第』)をして、本間・渋谷氏を「或生取、或打取了」と追い払うことに成功。この合戦に敗れた残党は奥州へ逃亡し、津軽の名越時如らとの合流を企てたようで、直義からの報告を受けた顕家は3月16日、「朝敵与党人等、多以落下当国」につき、「警固路次、於有其疑之輩者、可召捕其身」を命じる国宣を発している(『会津四家合考』)。
この「本間、渋谷が謀反」が京都に注進されると、朝廷は重くみて、3月21日夜半「去年召置れし金剛山の討手の大将阿曾霜台、陸奥右馬助、長崎四郎左衛門尉、辺土にをいて誅」(『梅松論』、『蓮華寺過去帳』)した。おそらく本来の彼らの罪状による処刑ではなく、彼らを奪取して挙兵を企てることを未然に防ぐためであろう。
●『蓮華寺過去帳』
| 名 | 姓名 | 辞世の句 |
| 長崎四郎左衛門入道 | 長崎高貞 | |
| 佐助五郎 | ||
| 上総九郎入道 | 規矩高政弟か | |
| 儀我小五郎 | 古はとをくおもひし極楽を今は真の仏をば見る | |
| 上総八郎入道 | 規矩高政弟か | |
| 陸奥国修理亮入道 | 大仏または極楽寺系の北条氏であろう | |
| 儀我四郎 | ||
| 佐助秋野五郎 | 都にて聞たに遠き古郷を猶隔行旅の空哉 | |
| 島入道 | うかふへきわか身さへまて山川のふかさ浅も定なき世に | |
| 上野式部大夫 | 北条義政か | 都にて散花よりもあたなるは今年の春の命成けり |
| 島兵庫助 | ||
| 佐助式部大夫 | ||
| 佐助右馬助 | 北条貞俊か | |
| 陸奥国佐助入道 | 大仏高直か | |
| 糟屋十郎 | 古郷に帰らぬ雁の残ゐてはかなき花とゝもにちるかな |
戦後の4月10日、足利直義は成良親王家執権として「三浦介時継法師法名道海」に「武蔵国大谷郷下野右近大夫将監跡」「相模国河内郷渋谷遠江権守跡」の地頭職を補している(「足利直義下知状」『宇都宮文書』)。「勲功賞」とあり、渋谷遠江権守跡が補されていることから、本間・渋谷氏の叛乱に対する恩賞であろう。
●建武元(1334)年4月10日「足利直義下知状」(『宇都宮文書』)
この本間・渋谷の乱の数か月後の建武元(1334)年8月23日、今度は「江戸、葛西等、重謀叛之時」(「実廉申状断簡」『南北朝遺文』602)と、「重謀叛」が起こった。江戸氏、葛西氏が続けて挙兵したため「重」と称されたのだろう。この「江戸、葛西等、重謀叛」について、直義が鎌倉から出征した様子が見られず、鎌倉内での挙兵と思われる。「江戸、葛西等」は二階堂の成良親王御所を攻めたようで「候人等亦致処々合戦、各々被疵畢」(「実廉申状断簡」『南北朝遺文』602)といい、成良親王に近侍する三位実廉が本間・渋谷の謀叛の時と同様、候人を差配して奮戦した様子がうかがえる。
一方京都では、関東と親密な関係を保っていた旧関東申次の西園寺権大納言公宗のもとに、得宗高時入道の弟・泰家入道が匿われていることが発覚。持明院統の後伏見院を奉じて持明院統の新帝を即位させ、旧関東の復権を画策していた陰謀も公宗の弟・公重の密告で発覚してしまう。すでに奥州津軽郡においては安達高景入道や名越時如らの挙兵が起こっており、北条家残党は関東や畿内、北陸、四国、九州で次々に挙兵する。
朝廷は彼らの調伏のために紫宸殿に護摩壇を構え、竹内慈厳僧正をして天下安鎮の法を執り行ったという(『太平記』)。この法は甲冑の武士が御所の四門を堅め、紫宸殿南庭の左右に抜刀した武士が立ち、四方を鎮める修法であった。御所の四門は結城九郎左衛門親光、楠木河内守正成、塩冶判官高貞、名和伯耆守長年が固め、南庭には右に「三浦介」を左に「千葉大介貞胤」を定めたという。三浦介、千葉介両氏が諸御家人および京都において、代表的な御家人として認知されていたことがうかがえる。この「三浦介」は高継と思われる。彼らははじめ、この南庭に侍る役を了承していたものの、貞胤は相手が三浦介高継であることを嫌い、対して高継も貞胤の下位(貞胤が左側で高継が右側)につくことを憤って、それぞれ出仕せずに役を断ったという。
建武2(1335)年7月、諏訪に逃れていた高時入道の子・相模次郎時行も多くの御家人が集まり挙兵した。『太平記』の記述であるが、その中には「三浦介入道」ほか「同若狭五郎、葦名判官入道」らが見える(『太平記』)。ただし「若狭五郎」は中先代勢に加わるも「三浦葦名判官入道々円 子息六郎左衛門尉」は足利尊氏方として戦死しており、この『太平記』の記述は偽である(『足利宰相関東下向宿次合戦注文』)。
時行率いる「中先代」勢は、一路鎌倉に迫った。鎌倉を守っていた足利直義は中先代勢を武蔵国で迎え撃ったものの、女影原の戦いで岩松三郎経家・渋川刑部大夫義季が討死を遂げ、府中の戦いでは小山五郎判官秀朝が討死、直義率いる正規軍も井出沢で大敗。7月16日、直義は鎌倉を捨て、成良親王を奉じて箱根方面へと逃れた。このとき、直義は朝廷より預かっていた大塔宮護良親王を暗殺している。護良親王は旧得宗家の人々や処刑された西園寺公宗との関わりを持っており、この「御陰謀」発覚によって足利尊氏に預けられ、関東に下されていた。
中先代勢の攻勢が伝えられる中、足利尊氏は鎌倉死守のため「征夷大将軍」への任命を後醍醐天皇に迫ったが、天皇や公卿たちは尊氏を警戒して認めず、直義から逼迫した知らせを受けた尊氏は、ついに独断で在京の武士に召集令をかけた。この召集令は天皇の許可を得たものではなかったにもかかわらず、彼のもとには数万にのぼる武士たちが集まり、尊氏は彼らを率いて京を出立。途中で中先代勢を次々と打ち破り、8月17日、「筥根合戦」で「兇徒大将三浦若狭判官(三浦時明)」を破った。そして19日の辻堂・片瀬原の合戦では「三浦葦名判官入道々円、子息六郎左衛門尉」ら足利方の将が討死したが(『足利宰相関東下向宿次合戦注文』)、鎌倉に攻め込んで北条時行を鎌倉より追放した(『太平記』)。この一連の戦いを「中先代の乱」という。ただし、葦名二郎判官入道道円は『太平記』や三浦家の系譜記載では、中先代方について8月17日に腰越の戦いで自刃したとされている。
●建武2(1335)年『足利宰相関東下向宿次合戦注文』(『神奈川県史』所収)
高継の父・三浦介時継入道は、尾張国に舟で遁れたが、熱田大宮司によって捕らえられて京都に送られ、斬首されたのち大路渡され獄門に懸けられた。没年齢不明。
●建武2(1335)年?9月20日『少別当朗覚書状案』(『到津文書』「神奈川県史」所収)
そして高継へは尊氏による緊急的な勲功による所領安堵がなされ、建武2(1335)年9月27日、相模国大介職ならびに相模国、上総国、摂津国、豊後国、信濃国、陸奥国に所領を安堵された。これらの所領は「父介入道々海(三浦介時継入道道海)」の領所だったと思われ、「信濃国村井郷内小次郎知貞跡」は、延慶2(1309)年8月24日に三浦介時明が出雲国金澤郷田地の替地として宛がわれた土地(『宇都宮文書』)である。また、「陸奥国糠部内五戸」については、寛元4(1246)年12月5日、佐原盛時が「陸奥国糠部郡五戸」の地頭代職を得ており(『宇都宮文書』)、伝来の領所だったのだろう。
建武2(1335)年8月19日、鎌倉を占拠して中先代軍を鎌倉から放逐すると、尊氏は京都に次第を注進したとみられ、その報告を受けた朝廷は臨時除目を行い、8月30日に尊氏を従二位に陞爵した。日数から考えて、尊氏からの使者は8月27~28日辺りに京都に着き、他の人々の勘考を経てすぐさま除目が行われたということになる。
●建武二年八月三十日臨時除目(『公卿補任』)
| 任官 | 官職 | 官位 | 名 |
| 春宮大夫(西園寺公宗の替) | 大納言 | 正二位 | 源具親 |
| 参議、左兵衛督、武蔵守 鎮守府将軍 | 正三位⇒従二位(勲功賞) | 源尊氏 | |
| 信濃守 9月晦日、信濃国下向 | 前参議 | 正三位 | 藤原光継 |
一方、鎌倉を占領して八日後の8月27日、尊氏は「武蔵国佐々目郷」の領家職を「為座不冷本地供料所」として鶴岡八幡宮に寄進した(『相州文書』)。これは後嵯峨天皇第三皇子で元弘3(1332)年9月4日から「当社検校職無御下向(社務代覚伊僧正、同十二月十一日下著一心院、住赤石本坊)」(『鶴岡八幡宮社務職次第』)に就いていた「覚助二品親王号聖護院宮」(『鶴岡八幡宮社務職次第』)に伝えられたとみられ、尊氏は「二階堂御所」に供僧を召し、対馬民部を奉行として寄進状に判を下している。そしてその約一月後の9月25日より「始行座不冷」された(『鶴岡八幡宮社務職次第』)。中先代の一連の争乱の鎮撫を目的とするものであろう。鶴岡八幡宮寺「座不冷之本地供」(『鶴岡八幡宮寺供僧次第』)は「佐々目大僧正頼助代」の弘安8(1285)年3月17日に行われた元寇鎮定の修法を初めとし、鶴岡八幡宮寺の主祭神である八幡大菩薩の本地仏とされる愛染明王に対する国家鎮護ならびに「本地弓箭ノ秘印表之」(舩田淳一著『神仏と儀礼の中世』「久我長通『八幡講式』と南北朝争乱~石清水八幡の密教修法と本地説の展開~」法蔵館2011)を長日不断で祈修するもので、愛染明王を「軍神」として祀ったものである(舩田淳一著『神仏と儀礼の中世』「久我長通『八幡講式』と南北朝争乱~石清水八幡の密教修法と本地説の展開~」法蔵館2011)。なお、鶴岡八幡宮寺には「愛染堂 楼門の西にあり、像は運慶の作長三尺、即八幡の本地仏なり」(『新編相模国風土記稿』巻之七十三)とあり、この三尺愛染明王が運慶の作であるとすれば、すでに頼朝代には弓箭神としての八幡神=愛染明王の習合が唱えられていた可能性がある。
一方で尊氏は中先代の乱に勲功のあった旧御家人に対し、安堵を「勲功之賞」として積極的に行っていく。これらは本来朝廷に諮るべき恩賞事項を尊氏は越権で行ったように見える(節度使に恩賞充行権はないが、大陸においてはこうした越権行為をも既得権益として地方軍閥が形成されている)。
8月には「蒲田五郎太郎(石川兼光)」の勲功賞として「陸奥国石川荘内本知行分」領掌の袖判御教書を下している(建武二年八月「足利尊氏袖判下文」『白河文書』)。蒲田五郎太郎の本貫、蒲田村のある「石河荘」は建武元(1334)年4月6日に北畠顕家が袖判国宣で「結城上野入道道忠領知」として「当荘内鷹貫、坂地、矢澤三箇郷」とあることから(建武元年四月六日「陸奥国宣」『白川文書』)、陸奥国衙の管掌であることは間違いないが、尊氏はこれを陸奥国衙に諮ることなく「本知行分」を安堵している。その他、9月27日には「三浦介平高継」「小笠原信濃守貞宗」「吉河次郎経頼」「合屋豊後守頼重」らに知行が宛がわれているが、すべて袖判下文の形式が取られている。
●建武二年九月廿七日「足利尊氏袖判下文」(『宇都宮文書』:『南北朝遺文』290)
●建武二年九月廿七日「足利尊氏袖判下文」(『今川家文書』:『南北朝遺文』291)
●建武二年九月廿七日「足利尊氏袖判下文」(『長門佐々木文書』:『南北朝遺文』292)
●建武二年九月廿七日「足利尊氏袖判下文」(『倉持文書』:『南北朝遺文』294)
尊氏が行った「為勲功之賞所充行」は、中先代の乱で軍功ある人に対して、恩賞沙汰が越権行為であると理解しつつも、恩賞充行は行わなければならないという強い意志が感じられる。三浦介高継に対しては、中先代勢についた父・三浦介入道道海が継承していた三浦惣領家の家職及び「本領」を安堵しているものとみられる(三浦道海が建武政権となって以降の新知である武蔵国大谷郷や相模国河内郷などは含まれていない)。
尊氏が恩賞沙汰を行ったのは、軍功に対する恩賞を求める人々が、新政府の恩賞の手間や遅滞を嫌い、尊氏にそれを期待した結果ではなかろうか。鎌倉を落としたが、各地に蠢動する中先代勢の残党は依然多く、論功行賞を行わざるを得ないほどに関東の情勢は緊迫していたのだろう。尊氏は敢えて朝廷の方針に反したわけではなく、戦功ある人々への妥当で迅速な恩賞措置を以って御家人の離反阻止や士気の維持を行うことが必要不可欠であったために行った措置であると考えられよう。袖判形式については、現地最高司令官である三位征東将軍が直に行うものとしての体裁を取った下文であり、大きな意味は持たない。
●三浦介高継への宛行状(『足利尊氏袖判下文』:『神奈川県史』)
| 相模国 | 三浦郡 | 三崎郷 | 三浦市三崎町 |
| 松和郷 | 三浦市南下浦町松輪 | ||
| 金田郷 | 三浦市南下浦町金田 | ||
| 菊名郷 | 三浦市南下浦町菊名 | ||
| 網代郷 | 三浦市三崎町小網代 | ||
| 諸石名 | 三浦市三崎町諸磯? | ||
| 余綾郡 |
大磯郷 高麗寺俗別当職 |
中郡大磯町 | |
| 東坂間郷 | 平塚市根坂間? | ||
| 橘樹郡 | 三橋 | 横浜市神奈川区三枚町? | |
| 末吉 | 横浜市鶴見区下末吉 | ||
| 上総国 | 天羽郡 | 古谷郷 | 富津市内 |
| 吉野郷 | 富津市吉野 | ||
| 大貫下郷 | 富津市大貫 | ||
| 摂津国 | 武庫郡 | 都賀庄 | 神戸市灘区 |
| 豊後国 | 国東郡 | 高田庄 | 豊後高田市高田 |
| 信濃国 | 筑摩郡 | 村井郷内小次郎知貞跡 | 松本市芳川村井町 |
| 陸奥国 | 糠部郡 | 五戸 | 青森県三戸郡五戸町 |
| 会津河沼郡 | 蟻塚 | 不明 | |
| 上野新田 | 福島県喜多方市熱塩加納町上野 |
10月23日、高継は上総国真野郡椎津郷(市原市椎津)内の田地一町を鶴岡八幡宮に寄進した。上記以外にも高継の伝領した所領は多くあったであろうことを物語る。
●建武2(1335)年10月23日『三浦介高継寄進状』(『鶴岡八幡宮文書』)
恩賞宛行の遅滞は、7月中旬に武蔵国府で中先代軍と戦って討死した小山大夫判官秀朝の嫡子「小山四郎(朝郷、初名朝氏)」から軍忠について尊氏に伝え、これが京都に上奏されると、東海道を担当する恩賞方での議論を経、「大膳大夫(中御門経季)」から「下野国可被国務」(「後醍醐天皇綸旨」『小山家文書』)が下された。しかし、実際に軍忠が京都に伝わったのは、軍功の事実が発生してから一月以上のちの8月30日、議論を経て綸旨が作成され、そこから関東へ通達されるのにさらに十日以上かかると考えると、軍功発生から「小山四郎」当人に伝えられるまで、実に二か月以上もの時間を要したことになる。関東の現実は中先代勢から鎌倉を奪還したとはいえ、中先代の与党人は関東(とくに鎌倉近辺)及び奥州に点在しており、尊氏は10月3日には「三浦、長澤へ為与党人退治、侍所御代官被向候」(「三浦和田四郎兵衛尉茂実着到状」『三浦文書』)、10月9日には「相模のはんにうへ為党人退治、侍所御代官被向候」(「三浦和田四郎兵衛尉茂実着到状」『三浦文書』)とあるように、「侍所御代官」を差し向けて中先代勢の追捕を継続する戦争状態にあったのである(翌建武3(1337)年正月17日、「両侍所」の「佐々木備中守仲親、三浦因幡守貞連」が京都三条河原で御所方武士の首実検をしており(『梅松論』)、彼らが鎌倉宮家侍所として相模国内の中先代残党を追捕を担当したと思われる)。このような日々戦いの中、早急に働きに対する見返りを求める人々が続出したと考えられよう。
ところが、中先代の乱を「廿日先代」などと揶揄し、鎌倉奪還をして叛乱鎮定と考えた京都の人々は「京都よりハ人人親類を使者として、東夷誅伐を各賀し申さる」(『梅松論』)というように乱は平定されたものとみており、関東との認識の乖離が甚だしい状況にあった。当然ながら後醍醐天皇及び朝廷も中先代与党が跋扈する関東や奥州の状況を把握していなかったとみられる。このような中で、尊氏の独断での恩賞措置が京都に伝えられたことで、「勅使中院蔵人頭中将具光朝臣、関東に下著し、今度東国の逆浪速にせいひつする事、叡感再三也、但軍兵の賞にをいてハ、京都にをいて、綸旨を以宛行へきなり、先早々に帰洛あるへしとなり」(『梅松論』)と、尊氏の上洛を命じたのであった。これは9月27日に行った独断の論功行賞に対する申し開きを命じたものと考えられる。尊氏も一旦は「急き参るへきよし御申有」ったが(『梅松論』)、その後直義から「御上洛然るへからす候、其故は相模守高時滅亡して、天下一統になる事は併御武威によれり、しかれハ頻年京都に御座有し時、公家并義貞陰謀度々に及といへとも、御運によつて今に安全なり、たまゝゝ大敵の中をのかれて、関東に御座可然」(『梅松論』)と固く諫めたため、尊氏は上洛を思い止まったという。
後年、直義が南朝の北畠親房に手紙で述べているように、「建武に諏方の時継反逆の時、将軍身づから発向して誅戮踵をめぐらさず、度度の大勲、古今比類なし、なを先皇、佞臣等が讒口によりて、叡慮いさゝか異変あり、仍賊臣を退がために義兵を起さるゝ處に、叡慮猶彼等を御贔屓の故に事大変に及き」(『吉野御事書案』)という状況にあったようである。
また、別の伝では、「故兵部卿親王御方臣下ノ中ニヤ有ケン、尊氏謀反ノ志有ル由讒」(『保暦間記』)とあるように、故護良親王に加担していた廷臣が盛んに「尊氏謀反」を後醍醐天皇に吹聴(『保暦間記』)し、「何ナル明主モ讒臣ノ計申事ハ、昔モ今モ叶ヌ事」と後醍醐天皇は尊氏謀反の讒言を信じてしまったとされ、「新田右衛門佐義貞ヲ招テ、種々ノ語ヒヲナシ」て「尊氏上洛セハ、道ニテ可打由ヲ義貞」に仰せられたという(『保暦間記』)。そして後醍醐天皇は「勅使蔵人中将源具光」を関東に下して「関東勢ヲハ直義ニ付置、一身急馳参スヘシト云々」(『保暦間記』)と、関東を直義に任せて早々に帰洛すべしと命じたという。尊氏は「勅定ニ応シテ上洛」すると返答するが、「京都ヨリ内々此事ヲ告申ケル人モ有ケルニヤ、又直義モ東国ノ侍モ不審ニ思テ留メケレハ尊氏上洛セス」(『保暦間記』)という。
このように、当時の関東と京都との間には中先代の乱についての認識に埋めがたい乖離があったと考えられ、尊氏不在の京都において、一族随一の武功人新田小太郎義貞が反尊氏の人々と同調して尊氏謀反を吹聴した結果、その後の南北朝の争乱へと繋がっていく複雑な問題に発展してしまったのだろう。尊氏が新たな「幕府構想」を持っていたために後醍醐天皇に背いた、というような考え方は、のちに尊氏が後醍醐天皇と「決別(実際は尊氏が望んだものではない)」し、「幕府」を創設したという「事実」からの逆算的推測に過ぎず、当時の政治的状況を考慮して再考すべきである。
後醍醐天皇が尊氏に上洛を命じた時期は明確ではないが、尊氏が論功行賞を行ったのは9月27日であるから、京都がその事実を把握したのは、最短でも10月10日頃となろう。その場合、勅使中院具光が下向したとすれば、鎌倉着は10月20日頃となる。具光が尊氏に上洛すべしという綸旨を伝え、尊氏は一旦は応じる返答をしながらも、新田義貞をして「尊氏上洛セハ、道ニテ可打由」(『保暦間記』)の計画の風聞を知り、「御本意にあらさる」が上洛を断念した(『梅松論』)。そして11月初め頃に帰洛した勅使中院具光は尊氏の上洛を奏上するが、一向に上洛する気配のない尊氏に「故兵部卿親王御方」の廷臣が「其時、サレバコソ謀叛ノ志有ル由、重テ讒シ申」した(『保暦間記』)。これにより後醍醐天皇は11月12日、まず尊氏の鎮守府将軍を停止し、陸奥国司顕家が「十一月十二日、鎮守府将軍」(『公卿補任』)となった。
上洛を諦めた尊氏は、鎌倉の在所を二階堂永福寺別当坊の仮屋から「若宮小路の代々将軍家の旧跡に御所を造られしかハ、師直以下の諸大名、屋形軒をならへける程に、鎌倉の体を誠に目出度そ覚へし」(『梅松論』)と、若宮小路の旧将軍邸に屋敷の造営を開始し、執事家の高家以下、尊氏に従軍した人々も屋形を建立しはじめ、かつての鎌倉のまちの賑わいとなっていたようである。
そして11月2日、直義は「可被誅伐新田右衛門佐義貞」の「関東御教書」(「少弐頼尚施行状」『相良家文書』71ほか)を諸国の武士、「御家人(新政を明確に否定しているのだろう)」、守護人、地方奉行人へ一斉に発した。この御教書は左馬頭直義が主体的に発給したもので、尊氏の意向を示した執達形態の文書ではない。つまり、新田義貞に対してとくに強い敵意を抱いていたのは、尊氏ではなく弟の左馬頭直義であったと考えらえる。
直義の御教書には義貞を「誅伐」する理由は一切記されていないが、義貞が明らかに天皇側近として信任されている以上、謀反人や凶徒と記すことは不可能であった。しかし、直義は彼を「誅伐」するという上位者表現を用いており、義貞を廷臣という公的立場ではなく、惣領尊氏の殺害を企図して尊氏帰洛を不可能にさせて違勅の汚名を負わせた上、讒訴して君を惑わした足利庶家として扱い、一門惣領家が庶家義貞を「誅伐」するという意図であろう。後日、箱根竹ノ下や伊豆国府などで新田義貞勢を殲滅した尊氏は、建武2(1335)年12月27日、若狭国守護の「美作左近将監殿(本郷貞泰)」に対して「義貞已下御所方軍勢、於海道悉討落了、仍所令発向京都也」(建武三年十二月廿七日「関東御教書」『本郷家文書』)と記しており、義貞已下の京勢を殲滅できたため「仍所令発向京都」と記している。つまり尊氏の違勅は義貞による妨害のためであり、今回これを排除したことで(勅命通り)京都へ発向したのだ、ということを強調しているとみられる。なお、この主張は明らかに後付けの理由であろうが、これまでの天皇からの尊氏への信頼と尊氏の服従姿勢、天皇没後の天龍寺建立などのからみて、尊氏が自発的に反旗を翻す理由はなく、実際に尊氏の違勅は、京都での陰謀に対する措置であった可能性が高い。
直義が義貞に激しい敵意を見せた理由は明確ではないが、この尊氏殺害の策謀のほか、義貞が護良親王と結んでいたことも理由の一つであろう。護良親王は「新田右金吾義貞、正成、長年、潜にゑいりょを請て打立事度々に及」(『梅松論』)とあるように、尊氏を討つために新田義貞、楠木正成、名和長年らを語らい、尊氏と合戦を企てる風聞があった。なかでも建武元(1334)年6月7日には「兵部卿親王、大将として将軍の御所に押寄らるへき風聞しける程に、武将の御勢御所の四面を警固し奉り、余の軍勢ハ二条大路充満しける程に、事の体大義に及によつて、当日無為になりけれとも、将軍よりいきとほり申されけれハ、全くゑいりょにはあらす、護良親王の御張行の趣なり」(『梅松論』)であったという。武家官僚の重鎮である楠木正成・名和長年は、当初より尊氏排除が混乱助長に繋がることを危惧してか護良親王の要請には非協力的であったとみられるが(後年、尊氏が新田義貞の対立から謀叛人とされたのち、楠木正成は「義貞を誅伐せられて尊氏卿をめしかへされて君臣和睦候へかし、御使におひては正成仕らん」(『梅松論』)とあり、名和長年は護良親王を捕縛している)、義貞についてはその後も一貫して尊氏との対立軸となっている。
さらに、義貞は護良親王を通じて旧得宗御内人とも関わりがあった可能性があり、建武4(1337)年の北畠顕家の西上に際し、新田義貞子の新田義興と相模次郎時行がともに加わり、12月25日、鎌倉を攻めたと伝わっており(『太平記』)、故護良親王を通じた新田氏と旧得宗家の結びつきがその根本にあったものと考えられる。鎌倉攻めとほぼ重なる建武5(1338)年正月5日までの間に「於下総国登毛郡、普音寺入道孫子令蜂起」と、上総国土気郡に「普音寺入道(北条基時)」の「孫子(左馬助友時か)」が挙兵し(「室原氏」『相馬市史料資料集特別編 衆臣家譜 六』:岡田清一「近世のなかに発見された中世 ―中世標葉氏の基礎的考察―」『東北福祉大学研究紀要 第三十四巻』)、その後、おそらく鎌倉に合流している(友時は北畠親房入道、北条時行らの伊勢からの船での奥州下向に従軍したが、途中難破して伊豆国仁科に上陸したとみられる)ことからも、顕家勢に相模次郎時行が加わり、普恩寺友時も従っていたと考えるのが妥当だろう。
直義は、中先代の乱で旧得宗勢によって渋川義季や新田岩松経家ら親類一門を討たれて上に鎌倉も落とされ、自身も追い散らされるなど、護良親王や旧御内人に対する激しい怒りがあったろう。彼らと関わりを持つ義貞に対しても憎悪の念があった可能性があろう。建武3(1336)年2月15日には、信濃国御家人の「市河十郎経助」が「先代高時一族大夫四郎并当国凶徒深志介以下之輩蜂起之間、為御追伐之大将村上源侍中信貞」に属して「於麻績、十日市場致散々合戦」し(建武三年二月廿三日「市河経助軍忠状(村上信貞一見状)」『市川文書』)、さらに「先代高時一族大夫四郎、同丹波右近大夫并当国凶徒深志介知光以下輩」と「守護代小笠原余次兼経并源蔵人信貞大将、於八幡山西麓麻続御厨、被致散々合戦」(建武三年二月廿三日「市河経助軍忠状(吉良時衡一見状)」『市川文書』)しているが、この時点で足利方は後醍醐天皇と京都で敵対しており、「大夫四郎(高時弟の大夫四郎時興)」「丹波右近大夫(佐介流丹波守盛房の子孫か)」ら中先代勢はその足利方(守護小笠原貞宗、信濃国大将村上信貞)と合戦をしていることになる。中先代勢は単に足利方への復讐である可能性もあるが、京都で足利方が敗れたタイミングであることから、中先代勢と御所方は接点を以って挙兵したのだろう。
直義が発給した11月2日の新田義貞追討の「関東御教書」はまず旧御家人個人に送達され、さらにその地方を奉行する守護らに軍勢催促状の発給を指示したとみられる。信濃国の「市河孫十郎近宗」は直義の「新田右衛門佐義貞可誅伐之由、自関東就被成下御教書」に応じて「為軍忠信州御方御手令馳参候」(「市河近宗著到状」『市河文書』)と守護の小笠原貞宗の麾下(貞宗が軍勢催促状を発給していると思われる)に参じ、貞宗が「承了」判を捺している。また、尊氏の命を受けた「散位(不明)」「尾張権守(高師泰)」は11月6日、「天野安芸七郎殿(天野経顕)」に「鎌倉中入口内稲村崎警固事、一族相共可致厳密之沙汰」を命じており(『天野文書』)、中先代勢への警戒も怠りなく務めていたことがうかがえる。
●建武二年十一月二日「関東御教書」(『大日本史料』六之二)
| 宛名 | 差出人 (関東御教書) |
発給日 | 施行日 催促日 | 著到日 |
承了 催促人 | 文書 |
| 那須下野太郎 | 左馬頭 | 11月2日 | 『結城家古文書写』 | |||
| 諏訪部三郎(諏訪部扶重) | 左馬頭 | 11月2日 | 『三刀屋文書』 | |||
| 無(廣峯社別当廣峯貞長) | 左馬頭 | 11月2日 | 『廣峯文書』 | |||
| 無 | 左馬頭 | 11月2日 | 『小早河什書』 | |||
| 長田内藤次郎 | 左馬頭 | 11月2日 | 『萩藩閥謁録』五十八 | |||
| 田代市若(田代顕綱) | 左馬頭 | 11月2日 | 『田代文書』 | |||
| 渋谷新平二入道 | 左馬頭 | 11月2日 | 『薩藩旧記』前集十二 | |||
| 市河孫十郎近宗 | (左馬頭) | (11月2日) | 11月28日 | 小笠原貞宗 | 『市河文書』 | |
| 陸奥国御家人 式部伊賀左衛門三郎盛光 式部伊賀左衛門次郎貞長 式部伊賀四郎光重代 木田九郎時氏 式部次郎光俊代 小河又次郎時長 | 左馬守 | 11月2日 | 12月2日 | 12月24日 |
佐竹上総入道 (佐竹貞義) | 『飯野八幡古文書写』 |
| 丹波御家人 小河小太郎成春 | 御教書 | 11月2日 |
建武3年 正月4日 | 尊氏 | 『古文書類』 | |
| 毛利元春 | 自関東給御教書 | 12月2日 | 12月26日 |
武田兵庫助 (武田信武) | 『毛利文書』 | |
| 逸見四郎源有朝 | 12月2日 |
武田兵庫助 (武田信武) | 『小早川什書』 | |||
| 伊勢国真弓御厨地頭 波多野彦八郎景氏 | 12月3日 |
武田兵庫助 (武田信武) | 『黄薇古文書集』 | |||
| 宮荘地頭 周防次郎四郎親家 | 12月5日 |
武田兵庫助 (武田信武) | 『吉川家什書』 | |||
| 安芸国大朝本荘一分地頭 吉河三郎師平子息吉二郎経朝 | 12月7日 |
武田兵庫助 (武田信武) | 『吉川家什書』 | |||
| 三戸孫三郎頼顕 | 12月23日 | 不明 | 『毛利文書』 | |||
| 甲斐源四郎入道 | 足利殿被仰下 | 11月20日 | 源義國 | 『南路志』 | ||
| (肥前)守護代 | 被仰下旨 | 12月14日 |
左近将監 (大友貞鑑) | 『深堀系図』 | ||
| 深堀弥五郎(深堀正綱) | 関東御教書 | 11月2日 | 12月23日 |
大宰少弐 (武藤頼尚) | 『深堀系図』 | |
| 龍造寺孫六入道 (龍造寺家房) | 関東御教書 | 11月2日 | 12月23日 |
頼尚 (武藤頼尚) | 『龍造寺文書』 | |
| 中村孫四郎入道 | 関東御教書 | 11月2日 | 12月23日 |
太宰小弐 (武藤頼尚) | 『兒玉韞採集文書』 | |
| 下荒木六郎入道女子代 (下荒木家有) | 関東御教書 | 11月2日 | 12月23日 |
太宰少弐 (武藤頼尚) | 『近藤文書』 | |
| 相良八郎 (相良定頼) | 関東御教書 | 11月2日 | 12月23日 |
太宰少弐 (武藤頼尚) | 『相良文書』 | |
| 榊二郎入道 | 関東御教書 | 11月2日 | 12月23日 |
頼尚 (武藤頼尚) | 『改正原田記附録』 | |
| 杉左衛門次郎入道 | 関東御教書 | 11月2日 | 12月23日 |
太宰小弐 (武藤頼尚) | 『薩藩旧記』 | |
| 富光九郎 (富光道貞) | 関東御教書 | 11月2日 | 12月26日 (23日歟) |
太宰小弐 (武藤頼尚) | 『薩藩旧記』 | |
| 大友千代松丸 | 尊氏 | 12月13日 | 『大友文書』 | |||
| 深堀弥五郎(深堀正綱) | 関東御教書 (尊氏か) | 12月13日 | 建武3年 正月16日 |
沙弥遍雄 (大友代官) | 『深堀系図』 | |
| 熊谷彦四郎 (熊谷在直) | 尊氏 | 12月27日 | なし | 『萩藩閥謁録』 |
11月9日には、「橘行貞」を奉行人として、中先代勢に加担したとみられる先代評定衆「矢野伊賀入道善久(矢野三善倫綱)」の武蔵国内の所領「小泉郷男衾郡内、須江郷比企郡内、片楊郷足立郡内、久米宿在家六間多東郡内」を、「岩松兵部大輔経家跡御代官頼圓、定順等」に打渡している(『正木文書』)。これは尊氏が知行国主、国司を務める武蔵国における中先代没官領を一族の岩松家に打渡したもので、積極的な恩賞沙汰の一環であろう。本来はこの打渡を太政官に伝えて太政官符の発給を求めるが、尊氏はこの過程は経ていないだろう。
そして、直義の御教書発給が影響したものか、尊氏も「十一月十日あまりにや、義貞を追討すへきよし、奏状を奉る」(『神皇正統記』)と、尊氏自身が新田義貞追討の綸旨を賜るべく奏上文を京都に発した。奏上文は「尊氏状到来、十一月十八日」(『元弘日記裏書』)と、11月18日に京都に到着し奏上されたが、その内容は「すなはち打てのほりけれ」(『神皇正統記』)ということが記されていたようで「京中騒動す」という。おそらく直義は奏状の使者に惣領執事家の尾張権守師泰を付けて三河国まで派遣したのであろう。朝廷及び新田義貞に対する直義からの恫喝の意図が込められているのではなかろうか。こうした鎌倉方の動きは驚きを以って朝廷に伝わり、「十一月十八日、今夜被仰警固事、上卿侍従中納言公明卿、諸衛右少将藤原行輔朝臣、一身参入」(『園太暦』)と警固を強め、早々に翌19日には「尊良親王以下東征」(『元弘日記裏書』)を宣した。「追討のために中務卿尊良親王を上将軍といひて、さるへき人々もあまたつかはさる、武家には義貞の朝臣をはしめて、おほくの兵を下され」(『神皇正統記』)、「上将ハ中務卿親王主上一宮、公卿殿上人、其外武士ニハ義貞ヲ大将軍トシテ、サルヘキ侍、在京武士、西国畿内ノ勢数万騎発向」している(『保暦間記』)。ただし、『保暦間記』の記すような「西国畿内」の武士に対する軍勢催促は肥前国「松浦小次郎入道蓮賀」への「令発向鎌倉」を命じる綸旨(「後醍醐天皇綸旨」『松浦文書』)など、中国・鎮西武士に対して11月22日に一斉に下されており、これは征東使が発せられて三日後のこととなる。つまり、征東使が率いたのは在京武士のみであったと考えられ、東海道軍の主力は在京衆の多い新田一族であった可能性が高いだろう。
また、「奥州ヨリ顕家卿後追ニ責上スヘキ由、宣下セラレケリ」(『保暦間記』)と、後醍醐天皇は陸奥守顕家にも同時期に鎌倉攻めを命じる勅使を派遣している。さらに東山道からは左衛門督実世を大将軍とする軍勢が進んでいる。その進軍速度は非常に早く、出京四日後の11月23日にはすでに「信州大井荘(佐久市岩村田周辺)」に布陣し、綸旨に応じず尊氏与党となっていた「小笠原信濃前司(小笠原貞宗)」と「当国総大将軍」(「市河経助軍忠状」『市河文書』)の「村上源蔵人(村上信貞)以下凶徒等」と合戦となっている。彼らは東山道を上州路に抜け、鎌倉街道下道を攻め下るルートであったとみられる。この東山道勢には「島津上総入道(島津貞久)」が加わっており、その指揮下に伊予の「忽那島東浦地頭次郎左衛門尉重清」や「木村三郎入道、東條図書助」らが入って奮戦している(「忽那重清軍忠状」『忽那文書』)。
●建武二年十一月東征軍
| 征路 | 将軍 | 名前 | 官位 | 官職 |
| 東海道 | 上将軍 | 尊良親王 | 一品 | 中務卿 |
| 東海道 | 大将軍 | 新田義貞 | 従四位上 | 右衛門佐 |
| 東山道 | 大将軍 | 洞院実世 | 正二位 |
尾張守 権中納言 左衛門督 |
| 東海道 (奥州より) | 大将軍 | 北畠顕家 | 従二位 |
陸奥守 右近衛中将 鎮守府将軍 |
なお、東海道軍の「大将軍」は新田右衛門佐義貞が任じられているが、上表に見られるように、彼は東山道の大将軍左衛門督実世や奥州の陸奥守顕家の官途に大きく見劣りしている。それを補う意味で一品尊良親王が先例なき「上将軍(かつて源頼朝の大将軍名で候補の一つとなったが先例がないと見送られ、征夷大将軍号が選ばれている)」に任じられ、義貞はその麾下の大将軍となり、官途上の不足を補ったと考えられよう。そこまでして義貞が大手軍である東海道の大将軍に選ばれたのは、彼が武家においては尊氏に次ぐ従四位上(『異本元弘日記』)の官途を持ち、彼以上の高位武家は存在しなかったことに加え、足利一門という血統、惣領尊氏・直義との対立関係、尊氏に従わず京都に残った武士は新田氏とその方人ばかりになっていたことなどからの任と思われる。つまり義貞の東海道「大将軍」補任は、彼の能力をとくに見込んで抜擢したのではなく、尊氏・直義と合戦で真向対峙が期待できる武家が義貞以外に存在しなかったためであろう。
一方、鎌倉では追討使下向の一報を受け、直義主導で様々に処置が行われたと思われる。尊氏は「先日勅使具光朝臣下向のとき帰洛有へきよし仰られし處に、御参なき条、御本意にあらさる間、此事に付て、ふかく歎き思召れて仰せられけるは、我龍顔に昵近し奉りて、勅命を請て、恩言といひ、ゑいりよといひ、いつの世、いつのときなりとも君の御芳志を忘れ奉るへきにあらされは、今度の事、条々御所存にあらすと思召ける故」(『梅松論』)として、「政務を下御所にゆつり有て、細川源蔵人頼春并近習両三輩計召具て、潜に浄光明寺に御座有」(『梅松論』)とあるように、追討の事を聞いて浄光明寺に移ってしまったためである。
直義はすでに尾張権守高師泰を大将軍とする軍勢を三河国矢作宿に派遣しており、在地の一門「足利上総五郎入道」と合流させて、征東軍を迎撃する態勢を取っていた。そして11月25日、進んできた征東軍と矢作川を挟んで合戦となり(『多田院文書』)、27日にかけて激戦となったが、戦いは足利方が敗れ壊走する。そして翌11月26日の京官除目において足利尊氏の参議、武蔵守、左兵衛督を「止職」(『公卿補任』)した。なお、尊氏の止職は『公卿補任』では11月27日とあるが、11月26日の臨時除目で西園寺右兵衛督公重が「左兵衛督」に転じ、前参議中院通冬が「尊氏辞替」として「参議」に還任していることから、11月26日が正しいと考えられる。
●建武二年十一月除目(『公卿補任』)
| 日にち | 名前 | 官位 | 官職 | 補任 |
| 11月12日 | 北畠顕家 | 従二位 |
参議 陸奥守、右近衛中将 | 鎮守府将軍 |
| (足利尊氏) | 従二位 |
参議 武蔵守、左兵衛督、鎮守府将軍【辞】 | ||
| 11月19日 | 鷹司冬教 | 従一位 |
左大臣【辞】 治部卿 | |
| 近衛経忠 | 従一位 | 散位 | 左大臣 | |
| 葉室光顕 | 従三位⇒正三位 | 出羽守 | ||
| 中御門宣明 | 従四位上⇒正四位下 | |||
| 11月26日 (京官除目) | 九条光経 | 正二位 | 中納言 右衛門督(別当)【辞】 | 権大納言(次席) |
| 西園寺公重 | 従二位 |
権中納言 右兵衛督【辞】 | 【転】左兵衛督〔尊氏辞替〕 | |
| 四条隆資 | 従二位 | 修理大夫【辞】 | 【還】権中納言 | |
| 足利尊氏 | 従二位 |
参議【辞】 武蔵守【辞】、左兵衛督【辞】 | ||
| 正親町忠兼 (のち実寛) | 正三位 | 散位 | 修理大夫 | |
| 中院通冬 | 正三位 | 散位 | 【還】参議〔尊氏辞替〕 左近衛中将 |
|
| 勧修寺経顕 | 正三位 | 太宰大弐、加賀権守 | 右衛門督(別当) | |
| 足利直義 | 従四位下 |
左馬頭【辞】 相模守【辞】 |
その頃鎌倉では、11月26日に直義が伊豆国の三島社に「於当社可致精誠之状」を命じている(『三島神社文書』)が、足利方は「遠江の鷺坂、駿河の今見村」においても連戦連敗し、直義は12月2日に自ら鎌倉を出陣。12月5日に駿河国手越河原に着陣し、新田義貞らの征東軍と「終日入乱て戦」った(『梅松論』)。しかし「御方利を失ひし間、武家の輩多く降参して義貞に属す」(『梅松論』)という状況に陥っている。その後、直義は「箱根山に引籠り、水のみを堀切て要害として御座」し、「仁木、細川、師直、師泰以下、不残一人当千の輩、陣を取」(『梅松論』)って迎え撃った。なお、このとき吉良貞義のもと「千葉楯」を攻めていた「(相馬)孫次郎親胤」は「至于箱根水呑致戦功候」(「吉良貞義挙状」『相馬文書』)、「親父孫次郎親胤者、去々年千田大隅守相■向于千葉楯、致合戦之處、俄将軍家京都御上洛之間御具申」(「相馬胤頼著到状」『相馬文書』)とあり、千葉から引き揚げて箱根水呑に参陣していたことがうかがえる。「千田大隅守(千田大隅守胤貞)」については記載はないが、その後、尊氏に随って京都、九州に赴いていることから、親胤とともに千葉から箱根に移ったと考えられる。
こうした足利方の「海道の合戦難義たるよし」は、鎌倉浄光明寺に蟄居していた尊氏の耳にも入り、「守殿命を落されハ、我有ても無益なり、但違勅は心中にをいて更に思召さす、是正に君の知處也、八幡大ほさつも御かこ有へし」と寺を出ると、12月8日、嘉例として「小山、結城、長沼か一族」を召して先陣とし、鎌倉を出立。「水のみ」で陣を張る直義勢に加勢はせず、「此あら手を以、箱根山を越て発向せしめ、合戦を致さハ、敵おとろきさはかむ所を、誅伐せむ」(『梅松論』)と、箱根山北端を回り(鮎沢川を廻り竹ノ下へ向かったのだろう)、12月10日夜、「竹の下道夜をこめて、天の明るをまつほとに、辰の一天に、一宮、新田、脇屋を大将として恋せはや契らしと詠せし、足柄の明神の南なる野にひかへ」(『梅松論』)、その後、「御方の先陣」である小山、結城勢は「山を下りて野山にうち上るに、坂の本にてかけ合戦しに、敵こらえすして引退所を、御方勝に乗て、三十余里攻詰て、藍沢原にをいて、爰を限と戦しに、敵数百人討取」という戦功を挙げたとあり、新田、脇屋勢を竹ノ下付近で打ち破った足利勢は、藍沢野へ逃れた新田・脇屋勢を追撃したという。尊氏は小山・結城勢のはたらきに「御かむにたへすして、武蔵の太田の荘を小山の常犬丸に充行はる、是ハ由緒の地なり、又常陸の関の郡を結城に行はる、今度戦場の御下文はしめなり、是を見聞輩、命をわすれ、死をあらそひて、勇戦む事をおもハぬ者そなかりける」(『梅松論』)という。なお、武蔵国太田庄は白河結城宗広入道の子・太田大夫判官親光の名字地であり、親光を新田義貞与党と定めて小山常犬丸の遵行を認めたという事か。
12月12日、水呑の直義勢と対峙していた征東軍の伊豆国佐野山(三島市佐野)の陣中では、大友家惣領代「大友左近将監(大友貞載)」が三百余騎を率いて「御方に参らすへきよし」を伝えて足利方に寝返った(『梅松論』)。「大友戸次左近大夫頼尊」も「於佐野山最前参御方致軍忠」(「戸次家古文書」『鎮西古文書編年録』)とあり、尊氏または直義の調略により、大友勢全体が示し合わせて佐野山陣中で寝返ったことがうかがえ、佐野山合戦の勝敗を決定づけたと思われる。この日の合戦でおそらく左中将為冬以下、多くの御所方が討たれている。二条為冬は伊豆国府に御座していた上将軍尊良親王の代将として佐野山陣に駐屯していたものか。為冬の首級は「御朋友」尊氏のもとに送達され、尊氏は為冬の首を見て「御愁傷の色深かりき」という(『梅松論』)。
この戦いでは、三浦一族の「三浦因幡守」が活躍したという(『神明鏡』)。「三浦因幡守」は三浦因幡守貞連のことで、内管領長崎氏と縁戚に当たり、おそらくは得宗被官だったのだろう。
佐原盛連―+―佐原光盛――+―佐原盛信
(遠江守) |(遠江守) |(六郎左衛門尉)
| | 文永九年二月為依北条時輔縁者自殺
| |
| +―娘
| | ∥―――――――――杉本貞宗
| | 杉本宗明 (次郎左衛門尉)
| |(六郎左衛門尉)
| |
| +―佐原泰盛――――+―葦名泰親
| (三郎左衛門尉) |(四郎左衛門尉)
| |
| +―葦名盛次
| |(五郎左衛門尉)
| |
| +―葦名時守
| |(六郎左衛門尉)
| |
| +―葦名盛宗――――葦名盛貞
| (遠江守) (次郎左衛門尉判官)
| ∥ 建武二年八月十七日於片瀬浦与時行自刃
| ∥
| ∥―――――――葦名時盛
+―三浦介盛時――+―三浦介頼盛――――娘 (三郎左衛門尉)
|(三浦介) |(三浦介) 遁世
| | ∥
| | ∥――――――――三浦介時明―――三浦介時継―――三浦介高継
| | 大曾祢氏 (三浦介) (三浦介) (三浦介)
| |
| +―三浦盛氏―――――三浦氏連――――三浦氏明
| |(七郎) (七郎五郎) (若狭五郎)
| |
| +―三浦宗義―――――三浦景明――――三浦時明
| (十郎) (若狭守) (若狭判官)
|
+―三浦時連―――+―三浦頼連
(六郎左衛門尉)|(対馬守)
|
| 佐原光盛―――――娘
|(遠江守) ∥―――――――三浦貞宗――――三浦行連
| ∥ (下野守) (遠江守)
+――――――――――三浦宗明
(六郎左衛門尉)
∥
∥―――――――三浦時明――+―三浦貞連
平頼綱――――――娘 (安芸守) |(因幡守)
(左衛門入道) |
+―三浦時継
(安芸二郎)
翌12月13日、足利勢は伊豆国府(三島市西本町周辺)に攻め入るが、この時点で竹ノ下から藍沢原(御殿場市)に新田・脇屋勢を追撃していた尊氏勢はまだ国府には到着していなかったと思われ、国府に寄せたのは水呑布陣の直義勢であろう。足利勢は国府に駐屯していた御所方と「散々合戦」し、「大友戸次左近大夫頼尊」の活躍が伝わっている(「戸次家古文書」『鎮西古文書編年録』)。13日の伊豆国府での合戦は「官軍失利帰洛」(『元弘日記裏書』)とあり、御所方は京都目指して西へ逃れていった。
その後、伊豆国府駐屯の御所方と合流すべく、藍沢原から裾野(裾野市)の隘路を抜けて新田・脇屋勢が国府付近に馳せ戻るが、そのころすでに国府は陥落していたのだろう。新田・脇屋勢は三島社前を通過して東海道へと抜ける頃、尊氏勢は新田・脇屋に追いついて攻め懸った。この合戦で足利方は「畠山安房入道(畠山阿波式部大夫入道西蓮か)」が討死(『梅松論』)するもの「義貞残勢わつかにして、富士川渡しける」(『梅松論』)と、足利勢の勝利となった。
前日12日の大友貞載帰参にともない、13日には尊氏自ら「大友千代松丸(のち大友氏泰)」に「可被誅伐新田右衛門佐義貞也、相催一族、不日馳参、可致軍忠之状」(「関東御教書」『大友文書』)をしたためて貞載に託し、翌14日に「左近将監(貞載)」が肥前国「守護代」に対する施行状を整えて御教書とともに在京の大友千代松丸のもとに送達した。この「十二月十三日関東御教書并御施行状」を受けた千代松丸であったが、正月12日に左近将監貞載が京都東寺前での結城親光との合戦で戦傷死すると、同日に「左馬頭(直義)」が「大友千代松殿」に「新田右衛門佐義貞以下輩等討伐事、早催一族并豊後肥前国軍勢、馳向坂本」(『大友文書』)と、義貞追討のため坂本(西坂本か)への出兵を命じている。また、正月16日には「大友千代松丸」が家人「沙弥遍雄」をして肥前国の武士に上洛を命じている(『深堀系図証文録』)。なお、太宰少弐頼尚も11月2日の直義「関東御教書」に基づいて12月23日に九州各国の国人に「相催一族以下軍勢等可馳参云々」を命じているが、彼は直義が鎌倉から発した「十一月二日関東御教書」に基づく軍勢催促であり、尊氏由来の大友千代松丸の軍勢催促状とは系統の違うものである。
その後、尊氏・直義両大将は西へ逃れる京勢を追って進軍する。義貞勢は引きながらも足利方の大将「畠山安房入道」を討つなど抵抗するも、「残勢わづか」となり、富士川を渡った(『梅松論』)。その頃、「去五日、手越河原の合戦の時分、御所方に属したりし輩、不二河にて降参す」(『梅松論』)と、先日の手越河原合戦で御所方として足利勢と戦った人々が参陣してきたという。その後も「足から箱根の両大将一手に成」(『梅松論』)って「府中より車返し、浮島原に至るまて陣を取すといふことなし」(『梅松論』)と攻勢を続けた。そして翌14日は浮島原に逗留して両大将は軍議を開き、「鎌倉に御帰有て、関東を御沙汰有へきか、又一議に云、縦関東を全くし給ふとも、海道京都の合戦大事なり、しかし、たゝ一手にて御立有へし」という結論のもと、翌15日浮島原を出立して「海道に向ひ給ふ」という(『梅松論』)。
尊氏は京へ退く義貞ら御所方を挟撃するべく、12月27日、若狭国守護の「美作左近将監殿(本郷貞泰)」に急使を発し、「義貞已下御所方軍勢、於海道悉討落了、仍所令発向京都也、早相催若狭国地頭御家人」(建武三年十二月廿七日「関東御教書」『本郷家文書』)して、早々に義貞を討つよう命じている。
御所方大敗の報は各地に飛んだか、越中国では12月に御所方の国司中院左中将定清が討死を遂げ(『尊卑分脈』)、越後国においても「越後国瀬波郡新荘内一分地頭秩父三郎蔵人高長」が「当国大将属佐々木加治近江権守殿御手、馳参最前御方」(「色部高長軍忠状」『色部文書』)し、12月19日には瀬波郡に攻め寄せた国司新田方の「河村弥三郎秀義一族以下」を追い落とした上、その居城を焼き払ったのを皮切りに、各地の国司方国人の居館を攻め落としている。
安芸国でも12月2日に「大朝本荘一分地頭辰熊丸(のち吉川実経)代景成」(『吉川什書』)や「安木町村地頭逸見四郎有朝」(『小早川什書』)、12月7日には「吉河三郎師平」、「大朝本荘一分地頭吉河三郎師平子息吉二郎経朝」らが、守護武田兵庫助信武のもとに参着し、12月23日から26日にかけて朝廷方の「当国矢野熊谷四郎三郎入道蓮覚城郭」を攻めて軍功を挙げている。吉川師平は26日の大手木戸の戦いで討死を遂げた(『吉川什書』)。
伊勢国でも伊勢守護の吉見二位律師円忠が国内の武士に催促をかけ、12月27日には円忠子息の吉見左近大夫将監範景に属した乙部源次郎政貫が安濃郡の久留部山で御所方・蔵人判官清藤と合戦している(『進藤文書』)。
時は戻り、建武2(1335)年11月19日の「尊良親王以下東征」(『元弘日記裏書』)に際し、「奥州ヨリ顕家卿後追ニ責上スヘキ由、宣下セラレケリ」(『保暦間記』)と、後醍醐天皇は陸奥守顕家にも同時期に鎌倉攻めを命じる勅使を派遣した。
鎌倉の左馬頭直義は朝廷の動きを察し、東海道の抑えとして三河国矢作宿に執事家の尾張権守師泰を急派しているが(11月25日には矢作川に布陣)、鎌倉追捕を命じる勅使の奥州下向の風聞を受けた陸奥守顕家を抑える措置も講じたとみられ、十五歳の「志和」尾張弥三郎家長(足利高経の子)を陸奥国府急襲に派遣したと思われる(『南方紀伝』)。ただし、家長の奥州派遣は竹ノ下、伊豆国府での合戦を勝利した12月13日以降に決定されたと思われ、陸奥国との管轄境界地である北常陸に駐屯していたとみられる(本来の任務は8月の白河郡長倉の中先代勢力追捕の援軍と思われる)家長にその大命が下されたのだろう。
陸奥国府攻めを命じられた家長は、12月23日に陸奥国白河郡に入るべく陸奥国高野郡の隘路に進駐し、「斯波家長与相馬胤平兄弟合戦」(『南方紀伝』)という。「相馬胤平(相馬六郎胤平)」は行方郡高平村(南相馬市原町区上北高平)を本領とする相馬一族で、彼らも8月中旬に白河郡長倉で中先代軍に呼応した白河結城庶流の人々を討つべく出陣し「陸奥国高野郡内矢築宿(棚倉町八槻)」(「相馬胤平軍忠状」『相馬文書』)に駐屯していたのだろう。胤平は「十二月廿三日夜、御敵数千騎押寄」たため、「捨于身命令塞戦」ったとあるが、この「御敵」は『南方紀伝』に伝えるように家長であろう。前述の通り、家長も白河長倉合戦の備えとして、8月30日に鎌倉から佐竹貞義入道の支配領域(常陸太田市から大子町辺りか)に派遣されていたと考えられる。家長勢は12月23日に「陸奥国高野郡内矢築宿」で相馬六郎胤平を破ると、陸奥国府へ向けて北上したと思われる。一方、敗れた相馬胤平は二本松方面から新田川を経由し、12月26日には所領の行方郡高平村へ戻り、弟たちと籠城している(「相馬胤平軍忠状」『相馬文書』)。胤平の退却行軍は一日45キロメートルを超えるかなりの強行軍であったことになる。
一方、鎌倉追捕を命じる勅使が陸奥国府に着いたのは12月上旬と思われるが、これを受けて陸奥守顕家は12月22日に国府を出立して南下し鎌倉に向ったという(『八戸系図』)。顕家は国府から伊達郡を経由する奥大道を南下したと考えられるが、23日に白河付近から北上した家長とは交わっておらず、家長は浜通りへルートを移して陸奥国府に進んだと思われる。奥大道は結城氏や伊達氏ら陸奥国府に忠実な氏族の所領がある上に上手が不利となる要害が点在していることから、家長はすでに鎌倉に誼を通じていた相馬氏を頼り、浜通りを選んだ可能性が高い。そして家長は国府目前の「河名宿(亘理町か)」で「為国司誅伐、志和尾張弥三郎殿府中御発向之時、松鶴祖父相馬孫五郎重胤発向于渡郡河名宿、武石上総権介胤顕■■賜、東海道打立関東馳参」(「相馬松鶴丸着到状」『相馬文書』)とあるように、相馬孫五郎重胤、相馬泉五郎胤康ら相馬一族、武石上総権介胤顕と合流した。彼らは陸奥親王家から陸奥国内の郡奉行や郡検断職に補されていた人物だが、すでに関東と通じ、相馬重胤や相馬胤治ら相馬一族は譲状を幼少の子息等に発給して戦いに臨む覚悟を示している(相馬孫五郎重胤の項)。家長勢は「府中御発向」したと思われ、陸奥国府を占拠後、家長は重胤らを伴って鎌倉へ軍勢を進めている。その途次、「常陸国」の「烟田左近将監幹宗」「同子息又次郎幹貞」が「建武三年正月日」に家長勢に加わっている(「烟田幹宗等著到状」『烟田文書』)。
また、「奥州御家人」を称して新政権へ敵対をあらわにしていた「式部伊賀左衛門三郎盛光、同伊賀左衛門次郎貞長、同伊賀四郎光重代木田九郎時氏、同式部次郎光利代小河又次郎時長」も11月2日の「左馬頭殿御教書」と12月2日の「佐竹上総入道道源催促」を受けて、12月24日に「佐竹楯」に馳せ参じている(「伊賀盛光等四人着到状」『飯野八幡社古文書』)。「伊賀左衛門次郎貞長」は憲良親王家引付二番を務めていた引付衆であったが、この時点で離反していたことがわかる。佐竹貞義入道は南下する陸奥守顕家を阻止するべく「佐竹楯(常陸太田市か)」で迎撃態勢を取っている。佐竹貞義入道は「自奥州、親王宮并国司、為追伐関東御発向之由、其聞候」につき、「奉懐取 親王宮、為被追伐国司以下凶徒等、相催当国軍勢候」と、憲良親王を奪取して陸奥守顕家を追伐するべく兵を催していたことがわかる。そこに「式部伊賀左衛門三郎殿」が参陣したことを「真実ゝゝ目出相存候」と手放しで喜ぶとともに「来月五日、為追伐国司、可罷立国候」(『飯野八幡社古文書』建武二年十二月廿八日「沙弥行円状」)につき、伊賀盛光らの「御同道候者、尤本望候」と、建武3(1336)年正月5日に佐竹貞義入道は常陸国を出立して陸奥守顕家を追撃することを表明し、伊賀盛光らの同道を望んでいることがわかる。伊賀盛光は12月2日の「佐竹上総入道道源催促」を受けて参陣していることから、「常州守護」たる佐竹貞義入道は岩城郡の軍勢催促権を持っていたともみえるが、実際は貞義入道代沙弥行円の文面からは伊賀盛光は佐竹氏の支配下にあったわけではないことがわかり、貞義入道は知己であった伊賀盛光に対して私的に誘いをかけたということであろう。なお、「伊賀四郎光重」「式部次郎光俊」が代官なのは、彼らは在京の士であり、11月2日の直義「関東御教書」を受けて、12月28日に「式部伊賀四郎、同一族并真壁三郎等相共ニ於当国犬石宿挙御旗」とある通り、丹波国犬石宿で反新田義貞の兵を挙げていたためである。彼らは「丹波国御家人小河小太郎成春」ととも挙兵して、12月30日に「追落丹波守護館、発向京都」した「後藤八郎基景」らとともに正月1日に丹後国守護館を乗っ取り、正月3日に「押寄大枝山致散々合戦、御敵捕大納言家(帥大納言師基)」という功績を挙げている。大江山の戦いは「三四両日」の合戦であった。この戦いには「式部伊賀右衛門入道、村杜孫次郎等」も加わっており、光重らの父、伊賀右衛門光貞入道も丹波にいたことがわかる。ただし、伊賀氏の所領は丹波国にはないため、足利家領での挙兵であったのだろう。
一方、憲良親王と北畠顕家は12月29日には白河へ入ったと思われ、「結城参川前司(結城親朝)」を「為侍大将、可被奉行軍忠之由事、令旨被遣之、可被存其旨之由」として「鎮守府将軍家(北畠顕家)」が下している(『結城文書』)。その後、北畠勢がどのようなルートを辿ったかは定かではないが、ともに鎌倉を攻める予定であった新田勢ら御所方は半月も前にすでに壊乱して跡形もなかった。顕家勢は建武3(1337)年正月13日には「近江国につきて、ことのよしを奏聞す」(『神皇正統記』)とあり、陸奥国府を出て二十一日、白河からわずか十四日程で近江国に参着したことを考えると、東海道経由では一日40キロメートル超の進軍速度の上に、勢いづく足利方との戦闘や三河国の足利党の抵抗などが想定されることから、東海道を上洛した可能性は限りなく低いだろう。当然、鎌倉を攻める時間的な余裕はまったくないため、顕家上洛時には鎌倉は経由していないと考えられる(『太平記』のみ「箱根ノ合戦ニハハヅレ給ヒケリ、サレトモ、幾程モナク鎌倉ニ打入給ヒタレハ、将軍ハ早箱根竹下ノ戦ニ打勝テ上洛シ給ヒヌ」とあるが、『太平記』自体の信憑性から疑問が大きい)。また、北畠勢が近江国に入るまで足利方との合戦記録も残っていないのは、彼が東海道ではなく中山道を経由して上洛したためではなかろうか。
建武2(1335)年12月13日、伊豆国府合戦で「官軍失利帰洛」(『元弘日記裏書』)し、尊氏は伊豆国府を占拠したのち、西へ逃れる御所方征東軍を追って進軍する。御所方の義貞勢は引きながらも足利方の大将「畠山安房入道」を討つなど抵抗するも、「残勢わづか」となり、富士川を渡った(『梅松論』)。「去五日、手越河原の合戦の時分、御所方に属したりし輩、不二河にて降参す」(『梅松論』)と、足利勢に次々に参陣してきたという。「足から箱根の両大将一手に成」(『梅松論』)って「府中より車返し、浮島原に至るまて陣を取すといふことなし」(『梅松論』)という。翌14日は浮島原に逗留し、尊氏・直義両大将は「鎌倉に御帰有て、関東を御沙汰有へきか、又一議に云、縦関東を全くし給ふとも、海道京都の合戦大事なり、しかし、たゝ一手にて御立有へし」となり、翌15日、「海道に向ひ給ふ」という(『梅松論』)。
尊氏は退却する義貞ら御所方を挟撃するべく、12月27日、若狭国守護の「美作左近将監殿(本郷貞泰)」に対して「義貞已下御所方軍勢、於海道悉討落了、仍所令発向京都也、早相催若狭国地頭御家人」(建武三年十二月廿七日「関東御教書」『本郷家文書』)して、早々に義貞を討つよう命じている。ここでも主敵はあくまでも新田義貞とその与党であって、「義貞已下御所方軍勢」を殲滅したため、「仍所令発向京都」としている。つまり義貞と与党という妨害を排除したため、勅命通り京都へ発向したと受け取れるのである。
「遠江国見付府中」では尊氏上洛の一報を受けた「備後国津田郷総領地頭山内首藤三郎通継」が尊氏勢に参着し、建武3(1336)年正月2日の「近江国伊岐須宮(草津市)」で軍功を挙げる。「田代豊前市若丸」も「正月二日、江州伊岐代御合戦」に加わり、「向大手、於辰巳角櫓下」で奮戦した(建武三年十一月「田代市若丸軍忠状」『田代文書』)。また、「大友戸次左近大夫頼尊」も「伊岐須城」の合戦で浜手より先駆けしたという(「戸次家古文書」『鎮西古文書編年録』)。かつては西側が琵琶湖畔に面していたとみられる。伊岐須宮は「御所方の山法師道場坊、阿闍梨宥寛、山徒千余人を相語ひて国人案内者たるにこそ、江州伊岐代宮を俄に構て引籠る、是ハ関東勢を当国にて支へて御敵の興勢を以、後詰をせさせむとの謀」というもので(『梅松論』)、尊氏は武蔵守師直を大将として建武2(1335)年12月30日に攻め寄せたという。『梅松論』では「一夜の中に攻落す」(『梅松論』)とあるが、実際は正月2日頃にも合戦が行われている。翌正月3日にも「近江国伊幾宮合戦」が行われており、「大将兵部大輔殿(仁木頼章)、山名伊豆守殿(山名時氏)」のもと「野本能登四郎朝行」は「最初押寄城辰巳角、切入城垣」(建武四年八月「野本鶴寿丸軍忠状」『熊谷家文書』)という戦功を挙げている。戦いに敗れた伊岐須宮の敗残兵は「野路の宿より西、湖の端なれハ、討もらされたる者共ハ、舟に乗て落行ける」(『梅松論』)という。
その後、足利勢は「御手分け」(『梅松論』)し、「下御所大将、副将軍は越後守師泰、淀は畠山上総介、芋洗は吉見三河守、宇治へハ将軍御向あるへきなり」という。「御所方の勢田の大将は千種宰相中将、結城太田大夫判官親光、伯耆守長年也」であり、正月3日から「矢合」となった(『梅松論』)。鎌倉稲村ケ崎防衛を行っていた天野七郎左衛門尉経顕も足利氏に従って上洛し、「今川五郎入道殿(今川範国入道)」らとともに「勢多」で11日にかけて連日合戦警固し、橋爪の高矢蔵からも矢を射かけるなどの軍功を挙げている(『天野文書』)。正月7日には伊勢守護吉見円忠の子息、吉見左近将監範景が勢多合戦で加わっている。
同じく正月7日には「天野安芸三郎遠政」が命を受けて「大将軍」尊氏の本隊が陣取る宇治に罷り越し、7日から11日にかけて「宇治橋上、昼夜抽軍忠次第」している(『天野文書』)。天野遠政は勢多勢の天野経顕の同族であり、遠政は勢多から宇治へ遣わされたと考えられる。彼のほかにも「摂津国多田院御家人高橋彦六茂宗」も「江州勢多、宇治、京都打出」している通り(『多田院文書』)、勢田の直義から宇治への援兵に遣わされており、宇治方面の御所方兵力が増強されていた可能性があろう。宇治の御所方は「御所方宇治の討手の大将義貞、橋の中二間引て櫓掻楯を上て相支けり」といい(『梅松論』)、宇治橋を引橋して櫓を建てて防衛線としたという。また、楠木正成勢も展開しており、正月7日に「楠木焼払宇治、依余焔平等院焼失」(『略年代記抄出』)、「延元々正七、宇治平等院炎上」(『皇年代私記』)と、宇治のまちは足利勢の到来に備えて焼き払われ、その余燼により平等院も焼失している。
翌正月8日、尊氏は宇治から一勢を率いて「将軍攻入八幡」(『武家年代記』)という。ただ8日夕方には「結城の山河の家人」である「野木与一兵衛尉并中臺二人」が宇治橋の「中櫓の下」での働きを尊氏が御感の余り佩刀を直接給わったといい(『梅松論』)、尊氏勢が宇治から八幡へ移ったのは8日夜かもしれない。尊氏勢の「大友戸次左近大夫頼尊」は「追落八幡凶徒」し、9日と10日の淀の「大渡橋」で軍功を挙げている。「山内首藤三郎通継」は「大渡橋上御合戦」では尊氏から「遠矢可仕之由被仰下」たことから、遠矢を射て「払御敵了」という(『山内首藤文書』)。通継はおそらく強弓で知られた人であったのだろうが、百五十年以前の山内首藤経通の遠矢の故事を反映したものだったのかもしれない。「為御前事間、無共感隠者也」(『山内首藤文書』)であった。
一方、朝廷に「正月十日、官軍又やぶられて、朝敵すてにちかつく」(『神皇正統記』)という状況が伝えられると、天皇は「比叡山東坂本に行幸して、日吉社にそましゝゝける、内裏もすなはちやけぬ、累代の重宝もおほくうせにけり、昔よりためしなき程の乱逆なり」(『神皇正統記』)といい、「卿相雲客以下、親光、正成、長年か宿所も片時の灰燼となりしこそ浅ましけれ」(『梅松論』)と、「二条富小路皇居炎上」(『官公事抄』)のほか政権の人々の屋敷も焼失した。「正月十日、東軍入京、主上幸坂本」(『公卿補任』)し、「行幸叡山、賢所同有渡御、東夷襲来洛中之故也」(『園太暦』)と、神璽を奉じての行幸となっている。「賢所渡御有、無例」(『神皇正統記』)とされるが、平家動乱の際にも賢所は西海に遷座している。なお、天皇の日吉臨幸は「為御祈祷、臨幸日吉社」(「建武三年正月十二日」『白川文書』)といい、公的には避難ではなく祈祷のためとしていた。
翌11日午刻、「将軍都に責入給ひて、洞院殿公賢公の御所に御坐有しに、降参の輩、注するに暇あらす」(『梅松論』)というように、尊氏が入京後に入った洞院公賢邸には降参の人々が数多訪れたという。その降参の輩の一人が「結城太田大夫判官親光」であったが、彼は10日の後醍醐天皇山門行幸の際、天皇の御輿に追いつくと畏まって「今度官軍鎌倉近く責下て太平を致すへき所に、さもあらすして、天下如此成行事ハ、併大友左近将監か佐野にをいて心替りせし故也、迚も一度ハ君の御為に綸を奉るへし、御暇を給て、偽て降参して、大友と打違て、死を以て忠を致すへし」(『梅松論』)と下賀茂から引き返すと、東寺南大門に布陣していた大友左近将監貞載のもとに降参し、大友に太刀を預けて大友と対談。その後、太刀を返されるとにき「さハなくて馳並て抜打に切間、大友すきをあらせす、むすとくむて親光ハ其場にて討る」と大友貞載により討たれた。しかし、貞載も「目の上を横さまに切れたりけるか、大事の手なりけれハ鉢巻にて頭をからけ輿に乗て親光か頭を持参しける」という重傷を負いながら尊氏の陣所に親光の首をもたらし、貞載はこのときの疵がもとで、翌日亡くなっている。ただ、この騒乱は「唐橋烏丸合戦」(建武三年九月「野上資頼代平三資氏軍忠状」『野上文書』)とあり、実際は東寺を中心に九条大路を東西に発生した大友貞載と結城親光の戦闘だったのではなかろうか。この合戦では「左近将監貞載」の属将「豊後国御家人野上彦太郎清原資頼」(建武三年九月「野上資頼代平三資氏軍忠状」『野上文書』)が「打組太田判官一族益戸七郎左衛門尉」している。
こうした中で、正月12日に「臨幸日吉社」していた後醍醐天皇は「結城上野入道」の参洛について聞き及び、使者を遣わして忠節を賞している。結城宗広入道は翌13日の「陸奥守鎮守府将軍顕家、此乱を聞て、親王を先にたてまつり、陸奥、出羽の軍兵を卒して、せめのほる、同十三日、近江国につきて、ことのよしを奏聞す」に同道し、親王宮を奉じて陸奥国府からの長途を駆け抜けて近江国へ入った(『神皇正統記』)。
一方、直義は正月12日に入洛した安芸守護の武田兵庫助信武勢や出雲勢などの西国武士等を翌13日、勢多警衛のため派遣し、奥州勢への備えとしている。武田勢の波多野彦八郎景氏(建武三年二月廿五日「波多野景氏軍忠状」『黄薇古簡集』)や「安芸国宮荘地頭周防次郎四郎親家」(建武三年五月七日吉川親家軍忠状『吉川家什書』)、「辰熊丸代景成」(『吉川什書』)らは13日に勢多の供御瀬へ馳せ向かい、「出雲国大野荘内加治屋村惣領」の「三崎三郎次郎日置政高」は美作国御家人の「佐々木美作大夫判官秀貞」とともに美作国を出立して正月11日の入洛戦に参戦。13日に勢多へ向かっている(『日御崎社文書』)。同日「大将軍」尾張権守高師直も勢多に「御着到」する。またすでに「大津西浦」に「大将細河侍従殿」も駐屯しており、「田代豊前市若丸」はこの「細河侍従殿」の軍勢に加わっている(『田代文書』)。
ところが、奥州勢は勢多に足利勢駐屯を見たためか、敢えて戦いを避けて「正月十三日より三箇日の間、山田、矢橋の渡船にて、宮并北畠禅門、出羽、陸奥両国の勢とも雲霞のことく東坂本に参著」(『梅松論』)と渡船で東坂本へ渡っており、「大宮の彼岸所を皇居として、三塔の衆徒残らす随ひ奉る」(『梅松論』)とあり、日吉社大宮彼岸所の御座所に比叡山衆徒が駆け付け、「官軍大きに力を得て、山門の衆徒まても万歳をよはひき」(『神皇正統記』)だったという。
正月16日払暁には、尊氏は三井寺園城寺が御所方により「園城寺を焼払ふへきよし」の風聞により、細川卿公定禅ら細川一族を大将とする四国・中国の軍勢を派遣すると、御所方では「義貞を大将として両国の勢ハ北畠殿の子息国司顕家卿に随て、三井寺に向」(『梅松論』)かったという。園城寺周辺の足利方大将軍「細河侍従殿」率いる四国・中国勢の田代豊前市若丸、新見山戸木十郎、久下弥五郎ら(『田代文書』)は「浜面」で奮戦している。「備後国山内首藤三郎通継」も「三井寺合戦」に加わっており(建武三年正月十八日「山内首藤通継軍忠状」『山内首藤文書』)、彼も細川勢に属していたのだろう。しかし、細川勢と御所方の新田・北畠勢の大道と浜端の二手での合戦は、足利方の「三井寺の衆徒の手より破れて、則当寺焼払はれて、武家の勢悉く京中へ引返」したという(『梅松論』)。
南近江での合戦に敗れた足利勢は、武蔵権守高師直が「関山(逢坂山)」(建武三年正月「三崎政高軍忠状」『日御崎社文書』)で敵勢を抑えつつ、山科を経て東山へ退き、この足利勢を追って、北畠顕家率いる奥羽の兵と「山門大衆」がともに「正月十六日ニ京都ニ寄テ合戦」(『保暦間記』)した。御所方は拠点を西坂本(高野川東岸の修学院周辺)とし、16日に御所方の「和泉国御家人和田左近将監助康」が東坂本から「罷向西坂本」している(延元元年三月「和田助康軍忠状」『真乗院文書』)。また、「三刀屋大田荘藤巻村地頭左兵衛尉宇佐輔景」は名和伯耆守長年に付属して「令勤仕西坂本」とあることから、仮御所はすでに機能していたと考えられる(後醍醐天皇はここには行幸しておらず、あくまでも仮御所として点じた何らかの屋鋪地と思われる)。また、足利方も武田信武勢の波多野景氏が「山僧以下凶徒等令下洛間、自当所致後楯、馳出法勝寺前、至極軍忠、追登山上訖」(建武三年二月廿五日「波多野景氏軍忠状」『黄薇古簡集』)と、比叡山から下ってきた衆徒等を法勝寺前に攻めて比叡山に追い返すしたという。このときの戦場は粟田口から法勝寺周辺、南北は西坂本から三条河原にかけての鴨川東側一帯であった。
足利方と御所方は白河一帯を攻防の中心地と定めて激戦を繰り返し、尊氏、直義の両大将は「二条河原に打立給」って西坂本を窺い、その「御勢、上ハたゝすの森、下ハ七条河原まて」展開していた。そして「午の時斗に、粟田口の十禅師の前より錦の御旗に中黒の旗さし添て、義貞大将として三条河原の東の岸に魚鱗の陣を取りてひかへたり」(『梅松論』)と新田義貞の軍勢と三条河原東岸に対峙した。数に勝る足利勢は「鶴翼のかこみをなし、数千騎の軍兵、旗を虚空に翻し、鬨の声、天地をおとろかし、互に射矢ハあめのことし、剣戟を掛るにいとまあらす、入乱て戦し程に、人馬の肉むら山野ことし、河にハ紅を流し、血を以て楯をうかへし戦も是にハ過しとそ覚えし」(『梅松論』)と、新田勢を取り囲む殲滅戦を展開している。ここで「官軍ニハ千葉介、義貞一人当千の船田入道、由良左衛門尉を始として千余人討ち取らる」と、新田勢に加わっていた「千葉介」が三条河原合戦で討死を遂げている。なお、「千葉介」貞胤はその後も後醍醐天皇方として足利方と戦いを続けており、ここで討死した「千葉介」はおそらく『太平記』において園城寺合戦で細川定禅勢と渡り合って討死を遂げたとされる貞胤嫡男・千葉新介一胤(高胤)であろう。
足利方はこの三条河原合戦でかなりの死傷者を出すが、新田方も船田入道や由良左衛門尉といった義貞股肱の家子を失うほど相当な損害を出してしまっている。一旦引いた義貞勢は「結城白河上野入道」と合流して千余騎で返し合い、足利方を「白河の常住院前へ中御門河原口を懸」けたが、ここに足利方の「小山、結城一族二千余騎にて、入替て火を散して戦」ったことで御所方は潰され、新田義貞は寡勢を率いて鹿ケ谷の山へ逃れ去った(『梅松論』)。その後の新田勢は行方知れずとなるが、鹿ケ谷から園城寺へ抜けて近江国へ引退いたとする風聞があったのだろう。正月18日、左馬頭直義は「美作次郎蔵人殿(本郷泰光)」に「新田義貞同与党輩、可逃下北国間、早馳越近江国、萱津以下要害所々打塞路次、可誅伐落人等」(建武三年正月十八日「関東御教書」『本郷家文書』)と命じている。
そのほか、伊勢守護吉見円忠子息・吉見左近大夫将監範景に属した「乙部源次郎政貫」が「於京都神楽岡致合戦」(『進藤文書』)で奮闘し、「法勝寺南門合戦」では「大友戸次左近大夫頼尊」が「及散々太刀打」している(「戸次家古文書」『鎮西古文書編年録』)。また「豊前蔵人三郎直貞法師(正曇)」も「京都合戦之時、正曇父子三人、毎度懸先、自身各被疵、親類若党等、討死手負既及廿余人」(建武三年八月「大友直貞入道軍忠状」『入江文書』)とあり、大友貞載亡き後も大友一族は「法勝寺致合戦」(建武三年九月「野上資頼代平三資氏軍忠状」『野上文書』)しており、大友勢は「大友千代松殿」が12日(これまで千代松を支えて万事執り行っていた叔父貞載が前日結城親光との戦いで重傷を負い12日死去したため、十五歳の千代松に直接御教書が下されたとみられる)に受けた御教書に応じて法勝寺方面に軍勢を展開したことがうかがえる。また、武田信武勢も「打破粟田口、於法勝寺西門致合戦」しており、宮荘親家や逸見有朝、毛利元春ら安芸国人衆の活躍がみられる。逸見有朝は16日夜には白河北殿北添の中御門河原口へ移り、翌17日には西坂本の「警固」を行っており、武田勢は御所方中枢部まで入っていた様子がうかがえる。また、元鎌倉評定衆の一族「摂津右近将監殿(摂津親秀)」も足利方として参着しており、一族「成田蔵人三郎重親」は親秀のもとで16日の合戦(法勝寺合戦であろう)に奮戦している(建武三年九月「成田重親軍忠状」『池田文書』)。伊東六郎祐持も16日の「三条河原合戦」で尊氏のもと戦っている(『日向記』)。この法勝寺、粟田口での合戦により「白川殿兵火」(『宝鏡寺文書』)とある通り、法勝寺一帯は兵火に焼かれた様子がうかがえる。なお、このとき法勝寺周辺で合戦した官軍は「山僧以下凶徒等、下洛之間」(建武三年二月廿五日「波多野景氏軍忠状」『黄薇古簡集』)とみえ、『保暦間記』の伝える通り「山門大衆」との混成軍であったことがわかる。
京都合戦の初戦が終わった正月17日、三条河原では尊氏に従って上洛していた「両侍所」の「佐々木備中守仲親、三浦因幡守貞連」が御所方武士の首実検をしているが、その数は千を越えたという。なお、この「侍所」は鎌倉親王家侍所と考えられ、侍所別当および所司であったのだろう。中先代勢から鎌倉を奪還したのち、相模国内の残党を鎮圧したのは彼らが派遣した代官であろう。
正月17日と18日の両日、白河近辺を転戦していた武田信武勢は「発向西坂本」しているが、翌正月19日には「罷向八幡山」という。麾下の「安芸町四郎(逸見有朝)」(建武三年正月廿二日「武田信武警固役催促状」『小早川家文書』)は「戌亥角固役所」している。「三戸孫三郎頼顕」は「八幡山西御預役所」(建武三年五月六日「三戸頼顕軍忠状」『毛利家文書』)を警固し、「宮庄四郎次郎(宮庄親家)」は「八幡薗寺小路末」(建武三年正月廿二日「武田信武警固役催促状」『吉川家文書』)、「井野谷口」(建武三年五月七日「宮庄親家軍忠状」『吉川家文書』)を固め、「波多野彦八郎景氏」や「内藤左衛門次郎教廉」、「大朝本荘一分地頭辰熊丸(吉川実経)」らもそれぞれ「八幡城」に籠って御所方と「連日合戦」(建武三年三月「吉川辰熊丸軍忠状」『吉川家文書』)したという。当時の主戦場である白河を転戦し18日には「西坂本」へ発向している武田勢が、突如翌19日に主戦場から二十キロも南にある石清水八幡宮に「馳籠」っているのは、尊氏が戦線を洛南へ後退させる備えであった可能性が高いだろう。正月22日には尊氏が「長沼判官秀行」を「淡路国守護職」(建武三年正月廿二日「足利尊氏下文案」『下野皆川文書』)に補任するとともに、直義が秀行に「淡路国地頭御家人等」を催促して交名を注進するよう命じている(建武三年正月廿二日「足利直義軍勢催促状」『下野皆川文書』)。翌23日には「武蔵権守(高師直)」が「大山崎宝積寺」に禁制を出しており、要衝大山崎の地に足利方の軍勢が展開していたことがわかる。また同日、尊氏は「摂津国椋橋荘」を東大寺に寄進しており(建武三年正月廿三日「足利尊氏寄進状」『尊勝院文書』)、山崎、八幡の要衝を押さえようとしていることがうかがえる。
正月27日、「官軍は山上雲母坂中霊山より赤山社の前に陣を取」り、「御方は糺河原を先陣として、京白河」に展開して西坂本を窺っているが、雲母坂の御所方は鞍馬口の御所方とともに足利勢に襲いかかった。「尊氏直義為誅罰」の綸旨を受けて入洛していた「大将軍洞院左衛門督殿(洞院実世)」(『忽那家文書』)は「搦手賀茂河原、責下上北小路河原口」ており、洞院実世の猛攻に足利方は兵を二手に分けて防戦するも敗北。勢いに乗って追撃する官軍に対し、尊氏の伯父「上杉武庫禅門(上杉憲房入道)」をはじめ、「三浦因幡守(三浦貞連)」「二階堂下総入道行全」「曾我太郎左衛門入道」らが返し合わせて防ぎ、討死を遂げている(『梅松論』)。「佐々木出羽四郎義氏」も「三条河原所々合戦」(建武三年正月廿八日「佐々木義氏軍忠状」『朽木古文書』)しており、尊氏らは彼らが防いでいる間に七条河原まで南下すると、「七条を西へ桂川を越て御陣を召る」と桂方面へ向かう尊氏勢と「大宮を下りに作道を山崎へ一手にて引退く」という鳥羽方面から山崎へ向かう勢(直義勢か)の二手に分けて京都から退いた。
そのころ、細川顕氏や細川定禅らを大将とする四国勢は、中御門大路を東に駆け向かい鴨川の河原口で御所方を打ち破って西坂本の「仮内裏を焼払」うと、鴨河を下って尊氏勢と合流を試みたが、「大勢二条河原より四条辺迄さゝへたり、御方かと見る所に、義貞以下宗徒の敵扣たる」と、二条河原から四条河原を抑えていたのは、足利勢本隊を追撃していた新田勢をはじめとする御所方であった。新田勢には「新田民部大夫貞政」ら新田一門の他、「大和国野田九郎左衛門尉頼経」「齋藤上総左衛門尉佐利、同舎弟兵衛尉忠利」「田島安房左衛門次郎行春」(『能登妙源寺文書』)らの名が見え、これを知った細川勢は「おめき叫て懸りし程に、この勢も散々に散らされて粟田口・苦集滅路に趣きてぞ落ち行ける」(『梅松論』)と、新田勢を追い散らした。「於四条河原」の合戦では吉見左近将監に属していた乙部源次郎政貫が「伯耆守家人」を討ち取っているが(『進藤文書』)、名和長年勢は「自加茂河原、迄于七条河原」に展開しており、そのうちの四条河原での合戦であろう。「伯耆四郎左衛門尉并安東弥二郎入道等」や「伯耆中務丞」「左兵衛尉宇佐輔景」らが名和勢に見えるが、伯耆中務丞と左兵衛尉輔景は「一条河原并桂河以下所々」で合戦し、「迄于西山峯堂」まで発向している(建武三年二月「三刀屋輔景軍忠状」『三刀屋家文書』)。
細川勢は尊氏勢と合流すべく「いそき桂川を馳渡て、亥刻計に御陣に参て、京中の敵追払ひたるよし」を申し上げると、尊氏は夜闇の中「即打立て、七条を東へ入らせ給ひしに、同河原にて夜もあけしかは、廿八日なり」(『梅松論』)と、一夜のうちに七条河原に馳せ戻っている。この細川兄弟の活躍に尊氏は「御自筆の御書を以、錦の御直垂を兵部少輔顕氏に送給也」と報い、「見分の輩弥忠を尽し、命を軽くしけるとかや」(『梅松論』)という。また、神楽岡に布陣していた御所方と延暦寺衆徒が下り、足利勢と合戦となったが、このとき、「越前国住人白河小次郎」が「義貞」と称する「顔色こつから少も替らす、赤縅の鎧を著たりける」大将を討ちとった。「義貞重代の鎧薄金」と同毛の鎧であり、「一旦大将討取たりとて御方のよろこひけるも断也」というが、実際は「義貞にてはあらす、葛西の江判官三郎左衛門か頸」(『梅松論』)であった。この葛西氏は石巻市多福院に遺る「興国三年壬午卯月廿五日」銘「五七日辰景」の石碑(「多福院板碑銘」)に刻まれる「遠州平清明」と所縁の人物か。神楽岡下の合戦は「島津上総前司入道ゝ鑑」も足利方として参戦しており、「本田左衛門尉久兼」や「島津式部孫五郎入道ゝ慶」が奮戦し、正月28日の「多々須河原合戦」(糺の森東岸部)では島津入道道慶の手勢が「召捕直伯耆守長年若党和賀尾弥太郎并兵衛次郎」している。
正月30日には「夜半計」から「糺河原の合戦」が始まり、「於三条河原」でも吉見範景に属する乙部源次郎政貫が軍功を挙げるが(『進藤文書』)、淀大橋合戦で強弓を披露した山内首藤三郎通継が討死を遂げるなど(「山内首藤土用鶴丸代時吉申状」『山内首藤文書』)、足利方は「今日を限りと戦」ったが、前年8月の鎌倉奪還戦から実に五か月間にわたる連戦に「弓折矢つき、馬疲人気をうしなひ」という困憊の中、「御方の軍破れて、二階堂信濃判官行周討死す」(『梅松論』)と、二階堂信濃判官行親(陸奥親王宮家の評定奉行の信濃入道行珍の嫡子で、同じく親王家政所執事の山城守顕行の義兄であるが、信濃入道行珍はすでに尊氏のもとにおり、早々に離反して鎌倉に下り、尊氏とともに上洛を果たしたと考えらえる)も討死を遂げた。夕方には御所方大将軍の洞院左衛門督実世や楠木河内守正成らが足利勢を追撃して樋口河原口、次いで鴨河原内野合戦で足利勢を「責付丹州追山」(建武三年二月三日「忽那重清軍忠状」『忽那文書』)して京都から放逐。尊氏は「丹波の篠村に御陣」を移した(『梅松論』)。
この日、後醍醐天皇は「卅日終に朝敵をおいおとす、やかて其夜還幸し給」(『神皇正統記』)といい、場所は「還幸河東慈眼僧正坊」(『建武三年兵乱中記』)の「成就護国院」(『皇年代私記』)と称されるが、現在この寺院はない。前天台座主御房であることから、おそらく白河周辺とみられる。そして翌2月2日、天皇は先年の日吉行幸の際に皇居が焼失していたため、右大臣家定の「花山院亭」を仮皇居として行幸した(『園太暦』)。
2月1日、尊氏は篠村での陣中、「猶都に責入へき其沙汰有といへとも、退て功をなすは武略の道なり」として、細川顕氏や卿公定禅、和氏ら細川の人々や「赤松以下西国の輩」を案内者として「先御陣を摂津国兵庫の島にうつされて、当所の船をして兵粮等人馬の息をつかせて、諸国の御方に志を同くして同時に都に責入るへし」と指示して、篠村から篠山を経由して三草山を迂回し、「いなみ野」へ進出。東へ向かい、2月3日には「兵庫の島に御着」した(『梅松論』)。その後、「先度御教書を給る周防の守護大内豊前守(大内長弘)、長門の守護厚東入道(厚東武実入道)両人兵船五百艘当津に参じたり」(『梅松論』)と、周防長門の両守護の軍勢が参着している。尊氏は3日から10日までの8日間兵庫に逗留しているが、これは新院の院宣を待っていたと考えるのが妥当であろう(後述のように『梅松論』では瀬川合戦時に赤松入道が院宣下賜を勧めたとあるが、2月15日以前に院宣を受けていることは明らかであり、下賜までの日数と途中の戦場及び距離を考えると、尊氏が在京時に院宣を求めたと考える他ない)。なお、御所方は丹波へ逃れた後の尊氏の足取りをつかめていなかったようで、「尊氏等猶摂津国にありときこえしかは、かさねて諸将をつかはす」と、尊氏が摂津国に到着の事実をつかんで兵を派遣したのち、さらに追加派兵したことがうかがえる。
また、洛中から足利勢が姿を消すと、八幡城の武田信武率いる安芸国勢は引き時を失って孤立し、2月3日、尊氏勢は兵庫島へ布陣するが、「将軍家御下向兵庫島之間、御敵等得理天寄来、取囲彼城之間」(建武三年二月廿五日「波多野景氏軍忠状」『黄薇古簡集』)と八幡山は包囲され、武田一党は「雖欲馳参御坐当島、以不叶所存」という危機的状況に陥っており、さらに「奉捨大将、落失軍勢多之」と、逃亡する人々が多数発生していた。このような中、波多野景氏ら大将武田信武に付き随う人々は「於当所可討死仕旨存之、已被趣于自害之庭事度々也」と、死を覚悟して戦い続けたが、その後八幡城の囲みから遁れることに成功し「而不慮雖存命仕」った(建武三年二月廿五日「波多野景氏軍忠状」『黄薇古簡集』)。
ここで足利勢は京都から攻め下ってきた「楠大夫判官正成、和泉河内両国の守護として、摂津の国西宮浜に馳合」て、「追つ返しつ終日戦て、両陣相支ふる處に、夜に入て如何おもひけむ、正成没落す」と、勝敗がつかないまま夜になって楠木勢は退却したという。
翌11日、足利勢は「細川の人々大将として、周防長門の勢を相随て責上る」が、今度は「義貞は同国瀬川の河原にて懸合て、爰を限と責戦ける程に、細川阿波守和氏の舎弟源蔵人頼春は深手を負給ひけり」(『梅松論』)と、新田義貞が「摂津国瀬川の河原」に展開し、細川蔵人頼春が重傷を負ったという。なお、この「瀬川」は現在の箕面市瀬川に比定されているが、実際は2月11日には「打出山之戦場」で「豊前蔵人三郎直貞法師(大友正曇)」が「総領大友御方、同一族等相共致合戦」とあるように、足利方主力のひとつ大友勢が西宮付近で奮戦している状態にあり、また、前日夜まで西宮付近で楠木勢と合戦して勝負のつかない戦いをしている状況の中、翌日に突然十五キロも先の瀬川まで軍陣を進めることは到底不可能であり、「瀬川の河原」とは西宮付近とすることが妥当だろう。楠木勢に属して戦った和田助康は「二月十日、十一日、罷向打出豊島河原、致合戦忠節候」(「和田助康軍忠状」『真乗院文書』)とあることから、10日に西宮浜で足利勢と戦った楠木勢は、翌日も足利勢と「打出豊島河原」で合戦していることがわかり、ここからも西宮周辺での合戦であったことがわかる。現実的にもっとも可能性が高いのは、打出から東に八百メートルほどの夙川の河原(現在の香櫨園駅付近)であろう。また、「摂津国兵庫浦、顕家卿義貞朝臣等発向」(『元弘日記裏書』)と、陸奥守顕家も摂津国に兵を出していたことがわかる。
2月10日から12日にかけての摂津国合戦に明確な勝敗は見えないが、12日の夜更頃に「赤松入道円心、潜に将軍の御前に参」って、
「縦此陣を打破て都へ責入といふとも、御方疲て大功をなしかたし、しはらく御陣を西国へ移されて軍勢の気をもつかせ、馬をも休せ、弓箭干戈の用意をも致して、重て上洛有へきか、凡合戦には旗を以て本とす、官軍は錦の御旗を先立つ、御方は是に対向の旗なきゆへに朝敵に相似たり、所詮持明院殿は天子の正統にて御座あれは、先代滅亡以後、定て叡慮心よくもあるへからす、急き院宣を申くたされて、錦の御旗を先立らるへき也」(『梅松論』)
と、いったん軍勢を鎮西に移して兵馬を休める事、さらに後醍醐天皇により廃された皇統「持明院殿」を奉じて、節度使たる証の錦の御旗を賜り後醍醐天皇に対抗する「官軍」となることを勧めたという。
これまで足利方は新田義貞誅伐を前面に出して戦いに臨んでいたが、現実的には「朝敵」という立場に甘んじながら合戦を続けており、これが足利方の最大の弱みであった。赤松円心の提案は、持明院統の皇統を奉じることで朝敵の汚名を回避できることになるため現実的であるが、その提案日については疑問がある。尊氏は後日2月17日までに光厳上皇の「可誅新田義貞与党院等」の院宣を受けている(建武三年二月十七日「足利尊氏軍勢催促状」『三池文書』)。受けた場所は「鞆津(福山市鞆町)」(『梅松論』)とされるが、京都から鞆津までは300キロもの距離がある上に兵庫周辺は戦闘地域であった。院宣使は海上を経由するなど迂回したことを考えると、実際に尊氏が院宣を要請したのは正月下旬の在京時であろう。なお、義貞追討の院宣より二日前の2月15日に「大友千代松殿」へ下された尊氏の書状に「新院の御気色によりて、御辺を相憑て鎮西に発向候也」(建武三年二月十五日「足利尊氏書状」『大友文書』)とあるように、尊氏の九州下向を認める院宣も下されており、新院へ奏請時には鎮西への下向が決定していたと考えられる。つまり、もし赤松円心の進言があったとすれば在京時点とある。当時の足利勢には嶋津上総入道一族、大友千代松丸一族が加わっており、太宰府には尊氏方を鮮明にする筑後入道妙恵がおり、すでに九州における強力な体制が確保されており、まず九州の新田義貞与党を平定して後顧の憂いを絶つことが鎮西下向の大きな理由と思われる。
また、続いて赤松円心は、
「先四国へは細川の一家下向あるへし、中国摂津播磨両国をは円心ふまゆへきなり、鎮西の事は太宰筑後入道妙恵(太宰少弐貞経入道)か子三郎、将監弐人今に供奉す、先達而妙恵へ御教書給間、定て忠節を致すへし、大友左近将監が去七月京都にて親光か為に討死にす、家督千代松丸は幼稚の間、一族家人数百人当陳陣に祗候す、中国四国九州の軍勢を相随て、季月の内には御帰洛何の疑ひかあらん、先摩耶城の麓に御座あるへし」(『梅松論』)
と、鎮西に移るにあたっては、諸国に警衛の大将を配置すべきことを提案し、赤松円心の拠点の一つである摩耶城の麓(神戸市灘区城ノ下通)に陣を移すよう要請している。尊氏はこの赤松入道円心の意見を容れ、夜中に瀬川陣を退いて12日早朝卯刻に兵庫に入った(『梅松論』)。しかし、左馬頭直義は摩耶山麓に戻り、「いかにも都にむかひて命を捨べき御所存」であったため、尊氏が説得してようやく兵庫島に戻ったという(『梅松論』)。ただし『梅松論』に尊氏が摩耶山麓に陣を移す時間的余裕も記録もないにもかかわらず、直義は摩耶山麓に陣を「戻」したとあり、『梅松論』の矛盾がうかがえる。察するに赤松の進言は瀬川陣以前のもので、尊氏の陣所は瀬川陣時点で摩耶山麓にあり、記事の錯綜があるのではなかろうか。
12日夜酉刻、尊氏一行は兵庫島の湊を出帆して鎮西へ向かった。このとき、「供奉仕一方の大将共の中に、七八人京都へおもむくあり、降参とそ聞えし、此輩はみな去年関東より今に至まて戦功を致す人々なり、雖然、御方敗北の間、いつしか旗を巻、冑をぬき、笠印を改めける心中共こそ哀なれ」(『梅松論』)と、鎌倉から随従し京都でも戦い続けた足利方の大将軍七八名が御所方へ降伏していったという。この具体的な名は記されていないが、そのうちの一人は長沼判官秀行であった可能性がある。長沼氏は箱根以来一族の小山、結城氏とともに足利方として奮戦し、尊氏の九州下向直前には「淡路国守護」に任じられているが、足利尊氏が九州から再上洛最中の延元元(1337)年4月の「武者所交名」(『建武年間記』)には「長沼判官秀行」が見えるのである。
翌13日寅刻、室津(たつの市御津町室津)に入津した尊氏一行は、ここに一両日逗留し、追い慕ってきた人々も合流を果たした。尊氏らはここで「御合戦の評定区々」しているが、「或人の云、京勢は定て襲来へし、四国、九州に御著あらん以前に御うしろをふせかむ為に、国々に大将をとゝめらるへきか」と申上したという。これはすでに赤松入道円心が尊氏に「潜」に進言していた(『梅松論』)ことであり、尊氏から円心に評定で述べるように要請した可能性もあるか。尊氏はこれを「尤可然」とし、恩賞充行権をも与えた大将軍を中国・四国に配置することとした。
●建武3年2月13日室ノ津評定での諸国大将軍
| 国 | 大将 | 麾下 | 居城 |
| 四国 | 細川阿波守和氏(成敗権) 細川源蔵人頼春 細川掃部助師氏 細川兵部少輔顕氏(成敗権) 卿公定禅 三位公皇海 細川帯刀先生直俊 細川大夫判官政氏 細川伊予守繁氏 | 河野一族 | |
| 播磨国 | 赤松入道円心 | ||
| 備前国 | 石橋左近将監和義(尾張親衛) | 松田一族 | 三石城 |
| 備後国 | 今川三郎顕氏 今川四郎貞国 | 鞆、尾道 | |
| 安芸国 | 桃井修理亮義盛(布河匠作) |
小早川一族 毛利一族 | |
| 周防国 | 新田大島兵庫頭義政 大内豊前守長弘(守護) | ||
| 長門国 | 尾張守高経 厚東太郎入道(守護) |
2月13日および14日の「一両日」を室津に過ごした足利勢は15日までには室津を出帆したとみられるが、15日までには鎮西下向の意向を記した院宣が到来している(建武三年二月十五日「足利尊氏書状」『大友文書』)。
2月15日、「細川兵部少輔」「細川阿波守」の両名が「漆原三郎五郎」に対して「阿波国勝浦荘公文職大栗彦太郎跡肆分壱」を勲功賞として宛行っており(建武三年二月十五日「足利尊氏下知状」『染谷文書』)、15日にはすでに各地方大将もそれぞれ行動に移っていたとみられる。また、同日尊氏は「小早川美作四郎左衛門尉殿」に「属桃井修理亮、相談一族、可致軍忠」と記しているように(建武三年二月十五日「足利尊氏軍勢催促状」『小早川文書』)、足利方の御家人層には地方の大将に属して戦う指示を出している。また、細かい指示については直義が担当していたとみられ、2月16日、直義は「阿曾沼二郎殿(阿曾沼親綱)」に「新田義貞与類、於安芸国蜂起云々、相語軍勢可令誅伐」ということと、「且云、路次往反船、且云浦々島々船、可點定之状」と、定期船のみならず浦島に存在する船をすべて確保しておくよう指示している(建武三年二月十六日「足利直義軍勢催促状」『阿曾沼文書』)。
室津を出帆して鞆津(福山市鞆町鞆)へ入津すると、ここに三宝院僧正賢俊が光厳上皇の院使として到着(『梅松論』)。「可誅伐新田義貞与党人等」の院宣が下されたという(建武三年二月十七日「足利尊氏御教書」『三池文書』)。院宣到来の日時は16日までの軍勢催促状などには院宣について記載がないが、17日には院宣が明記されており、2月17日の到来と考えてよいだろう。この院宣により「人々勇あへり、今は朝敵の義あるへからすとて錦の御旗を上へきよし、国々の大将に仰せ遣されける」と、足利方の士気も上がったという。鞆津在陣の時点で次の大きな目標拠点は赤間関と定められており、2月17日、「安芸杢助殿」に対して「相催一族、馳参赤間関」(建武三年二月十七日「足利尊氏御教書」『三池文書』)という文書が送達されている。
2月18日には前日17日の伊予国松崎城(「御所方合田弥四郎貞遠楯籠」)を攻め落とした「河野九郎左衛門尉殿(河野通盛)」に対して「伊予国河野四郎通信跡所領等」を安堵している(建武三年二月十八日「足利尊氏所領安堵状」『稲葉淀文書』)が、尾道とは海路八十キロ余りであることから、翌日の安堵が可能であったのだろう。
2月19日には「尾路泊」に「筑前御家人朝町彦太郎光世」が参着(建武三年二月廿日「朝町光世着到状」『宗像文書』)し、尾道浄土寺領の「備後国因島地頭職」を「淡路守平泰綱(椙原泰綱)」に安堵していることから(建武三年三月七日「椙原泰綱請文」『浄土寺文書』)、鞆津、尾道泊(尾道市久保)で1、2日の逗留があったものと推測される。備後国の足利勢はこの尾道と鞆津を本拠とし、大将軍今川三郎顕氏、四郎貞国が留守を任されている。
その後足利勢は数百艘の船団で西へ向かい、2月20日に長門国赤間関に入津した(『梅松論』)。2月25日、赤間関に「太宰少弐筑後入道妙恵か嫡子頼尚、兄弟一族等五百余騎にて御迎の為に参て、両御所への錦の御直垂」を調進した(『梅松論』)。足利勢は赤間関にはしばらく逗留しており、2月25日には「阿波国麻殖荘西方総領地頭飯尾隼人佑吉連、同舎弟四郎為重等」が着到(建武三年二月廿五日「飯尾吉連等着到状」『古文章』)。2月27日には「肥前国龍造寺孫六入道実善」や「安芸助太郎貞元」ら鎮西武士も参着している。また日付は不明ながら、2月中に「島津式部諸三郎忠能」も赤間関に着到しており、いずれも大友、少弐、島津の催促に応じた人々であると考えられる。
尊氏に応じた鎮西御家人が2月25日以降に赤間関へ続々と着到していることを考えると、彼らには尊氏の赤間関到着の予定期日が伝えられており、書状が御家人の手元に届いて赤間関まで一族を率いて向かう距離を考えると、遅くとも兵庫島に入った2月初旬には軍勢催促状が出されていたことになろう。尊氏が九州へ下ることは正月末には新院光厳上皇に奏せられていたと考えられることから、九州下向から再上洛までの大枠のスケジュールは、尊氏が在京時にすでに固まっていたことがうかがえる。
九州へ上陸した尊氏は、太宰少弐武藤頼尚や宗像大宮司氏範といった九州の諸将らに迎えられて再起を図り、3月2日、筑前の多々良浜合戦で御所方の菊地武敏一族、阿蘇大宮司惟直一族を撃ち破ると4月3日、肥後を転戦している「一色右馬助入道(一色頼行入道)」の兄「宮内少輔太郎入道(一色範氏入道)」を「所在府」(建武三年四月九日「足利直義軍勢催促状」『詫磨文書』)し、「鎮西大将軍一色少輔太郎入道殿」(暦応三年二月「宇佐宮神官大神宇貞訴状」『小山田文書』)と定める。
太宰府を出立した尊氏等は同日中に博多津を解纜し、長門国府中に入った。尊氏等はここで諸国守護や諸大将に上洛についての指示を行っており、長門国大将で一門筆頭たる足利尾張守高経との談合もあったのだろう。筑後黒木城攻めの大将軍上野頼兼も石見国の大将軍として九州から召喚されており、5月10日から11日には「石見国黒谷城山手」(建武三年五月十八日「永富季有軍忠状」『武久文書』)、5月11日には「石見国宇屋賀浜」で合戦(貞和五年正月十八日「上野頼兼注進状」『萩藩閥閲録』)している。
尊氏は長門府中にしばらく駐屯したのち出帆。4月27日、周防国笠戸に入った際に、尊氏は三浦高継に備中・美作両国の兵を率いて「美作凶徒」を討つことが命じられている。
●建武3(1336)年4月27日『足利尊氏御教書』(『三浦文書』)
高継が備中・美作の守護職を得た文書はないが、のち美作国内に一族・三浦下野入道道祐(三浦下野守貞宗)が地頭職を有するなど三浦氏と所縁が深く、高継はこれ以前に備中・美作守護職を与えられていたのだろう。
こうした中で「諸国の御方同心に申けるは、御帰洛いそかるへき趣ともなり、仍御合戦評定まちゝゝなり」と、味方からの矢のような帰洛要請に応じ、進軍についての様々な案について評定が執り行われた。しかし、議論は紛糾し容易に決着することがなかった。そこで太宰少弐頼尚が進み出て、「両将御船にて御進発の儀、更に愚意の及さる處也、天下の是非ハ今度の御手合によるへきか、すてに敵播磨備前両城を圍むよし、其告あり、是等を退治して大半ハ落去あるへきか、然に船軍計にてハ凶徒の退治落去しかたし、幸に両将御座の上ハ、将軍ハ御船、頭殿ハ陸地を御発向有へし、頼尚陸地の先陣を承て、亡父妙恵か遺言に任て、百箇日の追善合戦して、仏事に仕へし、頼尚生前の訴訟たゝ此事なり」(『梅松論』)と述べたことから、尊氏は船での進発、直義は陸路での上洛と一決し、陣容は、尊氏には「執事師直、関東京都より供奉の宿老、両国の輩」が付随し、左馬頭直義には「高越後守師泰、関東京都の供奉の壮士等、ならびに少弐、大友、長門、周防、安芸、備前、備中の御家人等」が属すこととなった。
5月10日、鞆浦を出立した海路の尊氏勢、陸路の直義勢はそれぞれ互いに見える距離で東へ向かった。船手は「四国の細川の人々、土岐伯耆六郎(土岐頼清)、伊予の河野の一族、其外の国人等、数五百余艘、其勢五千余騎」(『梅松論』)といい、5月15日、備前国兒島に入津した。ここは佐々木加地筑前守(加地顕信)の守衛地であり、「渚近く仮御所を造り、御風呂等たて、御休息あり」と、直義の到着を待っている。その二日後の5月17日、備中河原に布陣する直義から「新田江田某大将として馳下て、近日備中の福山に楯籠るの間、今夕手合せしめ、明日払暁に追落し、火をあくへく候」との使者が伝えられ、18日、直義勢は福山を攻め落とし、さらに備前国へと進んだため、備前国三石城の「尾張親衛(石橋左近将監和義)」を包囲していた脇屋右衛門佐義助は兵を引き(『梅松論』)、赤松城の赤松円心と対峙していた左中将義貞も脇屋勢が落ち延びてきたことで、城の囲みを解いて退いた。その後、直義勢は赤松円心と合流して東ヘと進み、播磨国加古川に布陣。船手の尊氏勢も播磨国室泊に入津した(『梅松論』)。
その後、直義率いる陸路勢は進発するも海路勢は風の関係で進発ができず、尊氏は気を揉んだが、5月23日戌刻、雨交じりの西風が吹いたことで「将軍御悦有て仰られけるハ、此風ハ天のあたふる物か、はや纜を解くへし」と進発を命じるも、「海上の事、其道を得す、異見を申難し、大船共の船頭を召れて御尋有へし」(『梅松論』)という意見もあったことから、大船の船頭十余人(御座船串崎の船頭、千葉大隅守か舟をきはしの船頭、大友少弐長門周防の舟の船頭)が召されて話し合われた。彼らはいずれも順風から逆風へ変わると予想したが、「上杉伊豆守の乗船名をは今度船と号す」の船頭孫七のみは、順風が強まると予想。尊氏はこの孫七の意見を採用して出帆し、24日暮に「播磨の大蔵谷の湊」へ無事入港した。
翌5月25日、 播磨国湊川の後ろの山に布陣する「楠大夫判官正成」に対し、陸路は大手大将軍の左馬頭直義(副大将は高越後権守師泰)、山手大将軍は「尾張守殿(足利尾張守高経)」、浜手大将軍は「大宰少弐頼尚」が進行。海路は細川氏の四国船五百艘を本船として湊川、兵庫を越えて東へ走った。これは「敵の跡をふさかん為なり」(『梅松論』)とあるように、御所方の退路を断つためであった。御所方は「播磨海道の須磨口も大勢向ひてささへたり、浜の手ハ和田の御崎の小松原を後にあてゝ、中黒の旗さして一万余騎もあるらんと見えしか、汀に三切に整へたり」と、須磨口には御所方大将軍新田義貞勢一万余騎が布陣していたという。
足利方は巳刻、陸路の三手より同時に攻め寄せて新田勢に打ち懸かった。一方、船手の細川勢は船を生田の森のあたりにつけて上陸。「卿公定禅、弟帯刀先生、古山、杉田、宇佐美、大庭を先として船より馬を追い下して打乗」り、船中の兵士もこれに随って新田勢に懸かり、義貞は打ち負けて戦線を離脱して5月25日中には「新田殿以下、昨日被討漏候人々、芥河河原村輩寄合、三十余人生取」(建武三年五月廿六日「大宰少弐頼尚書状」『深堀系図証文記録』)という惨敗を喫したまま京都へ退却した。新田勢に加わっていた菊池掃部助武敏の弟、菊池七郎武吉は討死を遂げている。
この頃、直義率いる陸路大手軍は兵庫湊川付近で楠木判官正成の軍勢と交戦中であったが、すでに御所方の大将軍義貞は戦線を離脱しており、細川定禅らは逃げる義貞には目もくれず、楠木勢攻めに転じた。そして夕刻申三刻、「正成并弟七郎左衛門尉以下、一所に自害する輩五十余人、討死三百余人、総して浜の手以下、兵庫湊川にて討死する頸の数、七百余人とそ聞えし、是程の戦なれは御方にも打死手負多かりけり」(『梅松論』)という。正成らは「両陣交錯、離合十有六回、正成終入当時之無菴、而昆季列坐自殺、殉死者千人」という(「明極和尚行状」『広厳寺文書』)。この「兵庫湊川合戦」で楠木正成勢の「和泉国岸和田弥五郎治氏」は「楠木一族神宮寺新判官正房并八木弥太郎入道法達」(延元二年三月「岸和田治氏軍忠状」『和田文書』)とともに戦っている。「播磨国広峯社大別当又太郎入道昌俊」は「摂州兵庫浜合戦」で「御敵楠木弥四郎号楠木政成甥」(建武三年七月「広峯社大別当昌俊軍忠状」『広峯文書』)と斬り合い、昌俊入道は甲の左右の吹返を切られたものの弥四郎を討ち取り、左馬頭直義の御感を得ている。
この戦いの顛末は、尊氏が九州で戦う「仁木次郎四郎殿」ら大将軍や国人衆へ送った御教書や、太宰少弐頼尚が送った施行状に「備中国福山、備前三石、播磨国赤松凶徒等、去十八日没落之後、今日廿五日、於兵庫島、楠判官正成及合戦之間、誅伐了」(建武三年五月廿五日「足利尊氏御教書」『深堀系図証文記録』)と記されているが、福山に籠った新田江田氏経(新田大井田氏経)、備前三石を攻めていた脇屋右衛門佐義助、播磨国赤松を攻めていた新田左中将義貞を「凶徒等」でひとまとめに表現しているのに対し、楠木正成は「楠判官正成及合戦」と具体的な名を挙げており、尊氏にとって「兵庫島」(湊川河口付近)合戦は、御所方大将軍の新田義貞との戦いではなく、楠木正成との合戦という印象が強かったことがわかる。新田勢は戦線を離脱すると一路京都へ急行し、同日中には「新田殿以下、昨日被討漏候人々、芥河河原村輩寄合、三十余人生取」(建武三年五月廿六日「大宰少弐頼尚書状」『深堀系図証文記録』)とあり、摂津国芥川の河原村の人々が落ち武者狩りをして三十余人が生け捕られたという。
同25日、御所方は「尊氏以下凶徒、自丹波路可来襲之由有其聞、赤坂越警固事、厳密可致其沙汰」(延元元年五月廿五日「後醍醐天皇綸旨」『神護寺文書』)と、丹波路からの来襲を警戒し、神護寺門徒に対して赤坂越の警固を命じている。丹波国に駐屯していた足利方の将は「仁木兵部大輔頼章、今川駿河守頼貞」(『梅松論』)の両名であった。さらに26日には「自若狭路凶徒等可来襲之由有其聞、鞍馬寺々僧等、可致防御沙汰之由、可被相触者」(延元元年五月廿六日「後醍醐天皇綸旨」『鞍馬寺文書』)と、左中将具光より鞍馬寺の中瑠璃房法印房に若狭路の警衛すべき綸旨が下されている。
延元元(1336)年5月26日、足利勢は兵庫島を出立して西宮に陣を移した。
御所方は、新田義貞の敗軍と楠木正成一統の壊滅という「官軍利なくして都に帰参」(『神皇正統記』)したため、5月27日、後醍醐天皇は花山院御所から近江国東坂本へ行幸した。尊氏の鎌倉からの上洛以来、二度目の避難であった。「因之宮方人々月卿雲客以下、千葉、宇都宮、諸国受領、大将軍者式部卿宮、侍大将者新田左中将、被立皇帝御旗於大嶽、赤地錦以金縷、今上皇帝、自志賀辛崎、陣々非一所」と、御所方は大将軍を式部卿宮恒明親王に定め、侍大将は新田左中将義貞とし、千葉介貞胤や宇都宮公綱ほか諸国受領らがその麾下となって足利方に対抗したという(『歯長寺縁起』)。
翌5月28日にも「伊予国忽那次郎左衛門尉重清」が「吉見参河三郎殿付著到、同廿八日追落洛中」(建武三年七月「忽那重清軍忠状」『忽那文書』)とあるように足利方と御所方は洛中で戦闘しており、天皇行幸後も御所方は洛中に残って抵抗は続いていた。
5月29日、丹波国の足利方「仁木兵部大輔頼章、今川駿河守頼貞」(『梅松論』)の両将が丹波但馬の軍勢を率い、錦の御旗を先立てて入洛を果たし、「五月晦日」に直義が入京した。すでに御所方は西坂本から比叡山へ登っており、比叡山西側の尾根各所に防塁を築き、さらに「大嶽の上に陣を取」って足利方に備えていた。
入洛した直義は東坂本へ侵攻のために「赤山の社」前に布陣し、南の「今路越」には「三井寺法師」のほか、豊後の「詫磨五郎次郎殿(詫磨幸秀)」や「飯尾隼人佑吉連」ら豊後、阿波勢など九州四国勢の一部が配置され、「中大手の雲母坂ハ、細川の人々、四国勢并総軍勢」、北の「横川通り篠嶽」からは「太宰少弐頼尚、九国の輩」を配置。比叡山を押し越えて東坂本を目指し、6月5日に一斉に比叡山を攻め上った。全軍の大将は直義、その麾下には尊氏が派遣したとみられる「執事御方(高武蔵権守師直)」を筆頭に、高新左衛門尉師冬、天野安芸三郎遠政、塩谷四郎、葛山孫六、庄民部房、嶋津兵庫允、三浦佐原六郎、山内又三郎、宍戸四郎らの姿が見える(建武三年七月「天野遠政軍忠状」『天野文書』)。これに対する御所方は、「今路古路」を守衛するのは「千葉介五千余騎」、「大嶽」は「菊池、西国勢」、「新田一族」は東国の軍勢を従えて「至西塔尾張陣」を固め、「宇都宮」は「横川篠々峯」を警衛したという(『歯長寺縁起』)。
大手の雲母坂口は「細川の人々先陣として西坂本より合戦をはじめ、皆歩行にて雲母坂まてそ責付たりし」と、雲母坂を徒歩で攻め登った「細河卿阿闍梨御房(細川定禅)」ら細川兄弟が率いる四国勢は、山腹に布陣して警衛していた御所方の重鎮「千草殿(三位中将忠顕入道)」を討ち取った。四国勢は「御向無動寺越中尾」(建武三年七月「忽那重清軍忠状」『忽那文書』)であり、大手雲母坂口は「発向山門無動寺」(建武三年七月「森本為時軍忠状」『浅草文書』)と、比叡山東塔南東の無動寺攻めが目的の一つであったとみられる。総大将の高武蔵権守師直勢に加わる「平賀孫四郎共兼」は「大和六郎左衛門尉、小早川又次郎」らとともに「責上中尾」して「伯耆守長年一族杵築太郎」を討ち(建武三年七月六日「平賀共兼軍忠状」『萩藩閥閲録』)、長年の「執事内河兵衛三郎入道真信」も6月5日「山門西坂本討死」しており、名和長年勢も「中尾」の防衛に加わっていたことがわかる。
後醍醐天皇は寄手の足利方の後方攪乱のため、攻勢の始まった直後の6月7日に「鞍馬寺衆徒等中」に「凶徒退治事、発向京都可令追伐」(延元元年六月七日「後醍醐天皇綸旨」『鞍馬寺文書』)を命じており、鞍馬寺はこれに応じる旨を注進している。ところが鞍馬寺は一向に動く気配を見せなかったようで、6月19日には「凶徒退治事、度々雖被仰、緩怠之由有其聞、太以不可然」と怒りを見せ、「若猶令遅々者、定有後悔歎旨、厳密被仰下候也」(延元元年六月十九日「後醍醐天皇綸旨」『鞍馬寺文書』)と警告している。鞍馬寺側も足利方の優勢を感じ取り、どっちつかずの対応を見せているとみられる。
雲母坂から攻め上った大将の一人、高新左衛門尉師冬は武蔵国や陸奥国の手勢を率いており、「西尾」から登った奥州勢は、6月5日に「坂中地蔵堂上(修学院牛ケ額)」で御所方と合戦。「御敵返合之處、御方軍勢引退」(建武三年七月「岡本良円軍忠状」『岡本文書』)と敗色の濃い中、鎌倉以来尊氏とともに転戦した石川七郎義光が「五日、山門西坂本合戦、於地蔵堂前戦没」(『石川系図』『石川家文書』)している。この中で「岡本観勝房良円」や「白岩彦四郎、鳥羽左衛門二郎」らは「残留て捨一命防戦、追帰御敵」(建武三年七月「岡本良円軍忠状」『岡本文書』)と御所方を追い返して、6月8日から19日まで地蔵堂を死守した。師冬勢の「武蔵国小代八郎次郎重峯」は7日から20日まで「於中尾致軍忠」(建武三年七月「小代重峯軍忠状」『小代文書』)とあり、武蔵国勢は「中尾」を担当したことがわかる。
大手口の「高豊前守(高豊前権守師久)」を大将とする摂津国、石見国、周防国などの手勢も奮闘し、麾下の「御神本三郎太郎藤原兼継」は、6月8日に「小笠原野三郎、小笠原孫五郎」とともに昼夜に亘って合戦をしている(建武三年七月「御神本兼継軍忠状」『国史考』)。6月11日朝の合戦では「周防国神代彦五郎兼治」は攻め下る御所方に対して「登矢倉終日致合戦」(建武三年七月廿三日「神代兼治軍忠状」『萩藩閥閲録』)といい、足利方の陣所には矢倉が組まれていたことがわかる。その後、比叡山頂まで攻め上った雲母坂の大手軍は「大嶽の上に陣を取」っていた御所勢と合戦した。また、「尾張守殿(尾張権守師泰)」も備後勢らを率いており、大手は高一族の攻勢が中心となっていた。
また、北部の「西塔口」(建武三年八月「田原直貞法師軍忠状」『入江文書』)を経て横川方面を攻め上っていた太宰少弐頼尚率いる九州勢の「貞広号原田豊前守」は、6月5日の合戦で左顔に矢疵を負う奮戦をしている(『大友田原系図』)。6月6日には「豊前蔵人三郎直貞法師法名正曇」が子息二人とともに「馳向西塔口」って合戦。さらに6月13日には「西塔千束峯」で合戦し、18日から20日にかけて攻め上り「於西塔南中尾」で奮戦した(建武三年八月「田原直貞法師軍忠状」『入江文書』)。
南部の近江国滋賀里へ通じる今路越の三井寺法師勢は松明を持って「山門放火の為かとそ覚えし」と攻め上るが、これは味方の足利方にも不評であったようで「浅間し」と記されている(『愚管抄』)。
6月9日、直義は先だって「可馳向東坂本旨」を伝えていた「美濃尾張伊賀伊勢志摩近江国軍勢等」に対し、洛中援兵のため「相分人数、不廻時刻、可催進京都陣」と、人数を分けて京都へ派遣するよう大将の一人「岩松三郎殿(岩松三郎直国。岩松経家弟)」に命じている(建武三年六月九日「足利直義御教書」『正木文書』)。「西坂本合戦最中」のため洛中兵力の減少が懸念されたためか。「佐々木佐渡判官入道并美濃尾張軍勢参著勢多」の軍勢には舟がなく、6月14日、「園城寺衆徒」に「勢多渡舟」の用意を指示し(建武三年六月十四日「足利直義御教書」『園城寺文書』)、「早用意舟、不廻時刻、可渡彼軍勢」と厳命している。しかし、あらかじめ尊氏上洛に合わせて上洛を命じていた「東国御方人々」が「依野臥已下之煩、逗留之由有其聞」(建武三年六月廿六日「足利直義御教書」『小笠原文書』)といい、直義は小笠原貞宗のもとに「佐々木佐渡大夫判官入道所令下向」て、「暫留近江国、且相談子細、且無軍勢煩之様、廻故実之躰、企参洛」を指示している。
東坂本へはおそらく山科経由で「桃井修理亮殿(桃井義盛)、仁木孫太郎殿(仁木義有)」や今川駿河守頼貞が派遣されており、佐々木佐渡大夫判官、広峯又太郎入道昌俊、周防弥四郎、秋元新左衛門尉、目賀田五郎兵衛入道玄向、佐々木加地四郎ら播磨や近江などの軍勢が派遣されており(建武三年七月廿三日「神代兼治軍忠状」『萩藩閥閲録』)、東西から比叡山を攻め立て、後醍醐天皇を迎え奉らんとしたとみられる。尊氏は6月13日には「河野対馬入道殿」に対して「不廻時日、焼払東坂本、令追伐凶徒等」(建武三年六月十三日「足利尊氏御教書」『予章記』)と命じており、東坂本への攻勢を強めている。
しかし、6月20日に東坂本では「桃井修理亮殿、仁木孫太郎殿御陣破而、御敵既廿余町責上」と、東坂本の御所方は無動寺越を攻め上ったことから、山上無動寺付近に布陣していた周防国勢の「神代彦五郎兼治」は一族を率いて馳せ向かい、登ってくる御所方を追落し、「桃井修理亮殿本陣」に合流している(建武三年七月廿三日「神代兼治軍忠状」『萩藩閥閲録』)。しかし、20日の山上での合戦は高師久の一手であったとみられる摂津多田院地頭の多田民部少輔頼氏が「六月廿日、於山門無動寺一城戸」で討死(『多田系図』)するなど、足利方は不利な状況にあったようである。さらに、寄手大将軍の「高豊前守以下数十人、山上にして討死」(『梅松論』)するという大敗を喫し、同日には今路越でも敗れたことで、今路越、雲母坂、横川の三手はいずれも退却して西坂本へ戻った(『梅松論』)。この叡山合戦は、御所方は左中将忠顕入道を喪う大きな損失があったが、足利方の攻勢を阻止することに成功したことになる。一方で、足利方は叡山攻略を果たすことに失敗した上に大きな損害を出し、直義は「赤山の御陣無益なりとて、急御勢洛中に引退し、大将下御所は三条坊門の御所に御坐あり」と、西坂本から撤退して三条坊門邸に入った。かつての足利邸であろう。
兵庫湊川合戦後、足利尊氏は「山崎宝寺(宝積寺)」へ陣所を移し、淀川を挟んだ対岸の八幡山に武田兵庫助信武の守護の兵を派遣。6月1日には武田勢の「三戸孫三郎頼顕」が入っている。上皇及び豊仁親王御迎えの準備であろう。そして二日後の6月3日、「新院、親王、入御八幡、東軍申行之、奉囲繞」(『公卿補任』)と、光厳上皇と豊仁親王の八幡臨幸が行われた。
八幡城を警衛していた「大将武田兵庫助信武」は、6月8日、尊氏の命を受けて「逸見四郎有朝」「三戸孫三郎頼顕」「周防次郎四郎親家」ら安芸国衆を率いて「摂津国水田城(吹田市西の庄町)」に馳せ向かい、9日にかけて責め立てている(建武三年六月廿五日「逸見有朝軍忠状」『小早川家文書』ほか)。武田勢はその後、再び八幡城へ戻ったとみられ、6月14日の尊氏および光厳上皇、豊仁親王の「御上洛」に際して、「三戸孫三郎頼顕」は「長江左衛門二郎、馬越彦四郎」らとともに「為大渡赤井河原、致軍忠」している(建武三年八月十四日「三戸頼顕軍忠状」『毛利家文書』)。そして、14日中には「六条殿(長講堂)」(『皇年代略記』)に入るも、翌15日に「新院、親王入御東寺、東軍同奉仕、年号可復建武云々」(『公卿補任』)とあり、光厳上皇、豊仁親王及び尊氏は東寺へ移っている。六条殿は警衛に不利であり、東寺へと遷ったものと思われる。6月19日および6月30日には「於竹田河原、造路、六条河原等」(延元二年三月「和田治氏軍忠状」『和田文書』)、具体的には御所方の「四條中将家」が19日に「造道、桂川」、30日に「六波羅跡并汁谷以下」に攻め寄せて足利方と合戦となっており(延元元年七月「和佐千鶴丸申状」『上太子文書抄』)、造道、竹田河原には高越後権守師泰(建武三年六月廿一日「諏訪部信恵軍忠状」『三刀屋文書』)、「頼宥(岩松禅師頼宥。経家、直国の兄弟)」、「大将武田兵庫助信武」らが展開しており、西坂本、摂津方面、洛南で再び京都奪還を狙う御所方の攻勢が続いていた様子がうかがえる。
さらに左中将義貞は6月23日、「鞍馬寺衆徒」に対して「尊氏以下凶徒等追罰事、以政泰所触遣也、得其意厳密可被致其沙汰」を命じているが(延元元年六月廿三日「新田義貞書下」『鞍馬寺文書』)、義貞の厳命に応じなかったのか、または鞍馬寺の旗幟が鮮明ではなかったためか、二日後の6月25日には、「明曉為凶徒追罰、所被差遣官軍於京都也、属新中納言手、可被致軍忠者、天気如此」(延元元年六月廿五日「後醍醐天皇綸旨」『鞍馬寺文書』)と、堀川権中納言光継の手に属すよう、具体的な所属まで示した強烈な綸旨を下した。元弘以来、実に三度にわたる後醍醐天皇の叡山逃避行は、京都における御所方の威光を落とし、もともと一筋縄にはいかない鞍馬山衆徒が、侍大将に過ぎない新田義貞の軍令に易々と従う状況にはなかったのだろう。
御所方は比叡山から洛中を窺いつつ、27日に「自山門京都発向、一日合戦、及晩皆帰山」(『歯長寺縁起』)というように、不意に降りては再び山へ戻るゲリラ的戦闘も行っており、27日夜、おそらく帰山の途次に「御敵為夜討、押寄三条坊門京極、懸矢倉火」のため、直義勢の神代彦五郎兼治は「一族相共馳向彼所、打消矢倉火畢」(建武三年七月廿三日「神代兼治軍忠状」『萩藩閥閲録』)し、「小早川平三(小早川経平)」は御所方と合戦して追い返しているように(建武三年七月八日「足利直義御教書」『小早川文書』)、直義本邸の三条坊門邸にも攻め寄せている。
6月30日には洛南でも激しい合戦が起こっているが、払暁には御所方が「義貞大将として大勢内野の細川の人々の陣へ寄来」た(『梅松論』)。これは事実上の東坂本の御所方正規軍の総攻撃であった。当時、御所方の実戦型の大将軍は、二条兵部卿師基、洞院左衛門督実世、四條右衛門督隆資、堀川信濃守光継、新田左中将義貞、名和伯耆守長年程度しか残されていなかったと思われるが、御所方はこのうち新田義貞と名和長年に「数千人」(建武三年七月五日「足利尊氏御教書」『勝山小笠原家文書』)を与えて、足利方の拠点で新院らが御座所とする東寺攻めを敢行させたのだろう。
新田勢は細川勢を打ち破って洛中に攻め入ると、大宮、猪熊の二手(大宮大将軍は新田義貞、猪熊大将軍は名和長年)に分かれて南下し、所々に放火して回っている(『梅松論』)。同日、高尾張権守師直は法成寺河原(上京区宮垣町)に布陣し、近衛大路以北「只須河原(糺河原)」から西坂本にかけての比叡山西麓を警衛し、攻め寄せる御所方を破っている。
また「下御所、大将として三条河原に打立」って南を見ると、すでに敵勢が東寺近くの八条坊門辺まで攻め入っている煙が見えており、麾下からは「将軍御座覚束なしとて御発向あるへきよし」を主張する人々が多くいた。ただ、太宰少弐頼尚が言うには「東寺に勇士多く属し奉る間、縦敵堀鹿垣に付とも何事かあらん、御合力の為なりとも、御馬の鼻を東寺へ向られハ、北に向ふ師直の河原の合戦難義たるへし、是非に付て今日ハ御馬を一足も動かせらるへからす、先頼尚東寺へ参るへし」と、太宰少弐頼尚は一勢を率いて三条大路を西に走った。「太宰少弐頼尚か陣は綾小路大宮の官庁匡遠か宿所にてそありける、頼尚の勢は三条河原に馳集りて、何方にても将軍の命を受てむかふへきよし、兼而約束の間、彼河原に二千騎打立て」て駐屯していたが、頼尚は尊氏からの命を受けていずこなりとも行き向かう予て約定があり、三条河原の警衛に回っていたが、遊軍としての機動性を生かして東寺の救援に馳せ向かったものと思われる。
一方、「敵大宮ハ新田義貞、猪熊ハ伯耆守長年、二手にて八条坊門まて責下」ったところ、これを察した尊氏は「東寺の小門を開ひて、仁木兵部大輔頼章、上杉伊豆守重能以下打て出、責戦」い、新田・名和勢をもと来た道へ押し戻した。そこに「細川の人々、頼尚」が攻め懸り、「洛中の条里を懸きりゝゝ戦」い、「伯耆守長年、三条猪熊に於て、豊前国の住人草野左近将監か為に討取れ」た(『梅松論』)。ただし、「御神本三郎太郎藤原兼継」は「馳参坊門猪熊、対御敵伯耆守長年、致所々合戦、於押小路猪熊、討取伯耆守、三郎右衛門尉長年一族畢」(建武三年七月「御神本兼継軍忠状」『国史考』)とあるように、石見国御家人の御神本兼継が、名和伯耆守長年と一族の名和三郎右衛門を討ったとある。これは「備後国三吉孫三郎以下一族、伴合戦之間、知及之」と証人もあり、名和長年は押小路猪熊(現在の二条城東南隅櫓付近の堀)で討たれたのだろう。
新田義貞は「細川卿公定禅目を懸て、度々相近つき、已に義貞あふなく見えしかとも、一人当千の勇士共折ふさかりて、命にかはり討死」したため、義貞勢は「二三百騎に打なされて長坂に懸りて引」いた。新田義貞が逃れた経路と思われる三条大宮では「大将軍山名伊豆守殿(山名時氏)」が寄せていて、「美作国御家人大葉左近允」を生捕り、「山法師擅光坊三位竪者并同宿卿公」を討ち取って首を挙げている(建武三年七月二日「岡本観勝房良円軍忠状」『岡本文書』)。同じく今川頼貞に従軍している「伊達孫三郎義綱」(建武三年七月「伊達義綱軍忠状」『伊達文書』)も「賀茂河原」に参戦して軍功を挙げている。
また、「畿内の敵、作道より寄せ来りしを、越後守師泰、即時に追散し、大勢討取」り、さらに「宇治よりハ法成寺辺まて責入るたりしを、細川源蔵人頼春、内野の手なりしを召ぬかれて大将として菅谷辺まて合戦せしめ打散しける」という。ほか「竹田ハ今川駿河守頼貞大将として、丹後但馬の勢馳むかひて追落」した(『梅松論』)。また、八幡山付近を警衛していたと思われる武田勢は御所方を「追払桂河円明寺」と、桂川西岸域まで御所方を追捕している(建武三年八月十六日「周防親家軍忠状」『吉川家文書』)。また、「中御門烏丸」でも直義勢と御所方が合戦し、直義麾下の「岡本観勝房良円」は「池上藤内左衛門尉、結城七郎左衛門尉」らとともに御所方と奮戦している(建武三年七月「岡本良円軍忠状」『岡本文書』)。
この6月30日の大宮猪熊合戦は、足利方優勢を強く印象付ける戦いとなり、足利直義は小笠原貞宗に対し「義貞親類并長年討取了、其外凶徒大略被討罰也」(建武三年七月四日「足利直義御教書」『勝山小笠原家文書』)と述べている。また、尊氏も小笠原貞宗に対して「新田義貞以下凶徒等事、度々合戦、毎度打勝畢、就中去月晦日、寄来之間、伯耆守長年并余党数千人、或討取之、或生取間、山門之軍勢相残之分不幾之上、今朝多以没落、又為降人所参也」(建武三年七月六日「足利尊氏御教書」『勝山小笠原家文書』)という報告を行っている。そして「爰如風聞者、義貞以下可令没落東国云々、自東国山道令馳参之輩、暫令居住近江国打止山徒往反及兵粮、可打取山門没落軍勢之由、可相触山道海道等勢」(建武三年七月六日「足利尊氏御教書」『勝山小笠原家文書』)と、義貞以下の人々が東国落ちする風聞があるので、東国や美濃信濃から上洛中の人々については、しばらく近江国に留まり、東国へ遁れんとする御所方や延暦寺衆徒の東下を阻止するよう命じている。
近江国に展開していた小笠原貞宗入道は、7月6日夜には「野路原打捕山徒成願房」し、7月10日には「於鏡宿并伊吹太平寺両所致合戦」して御所方の東国没落を阻止。直義はこれを賞し、さらに「東国軍勢近日可参洛」のため「勢多橋以下及其沙汰、可差遣軍勢」と命じた(建武三年七月十六日「足利直義御教書」『勝山小笠原家文書』)。小笠原貞宗入道は「勢多ちかく臨むところに、山徒等橋を引間、野路辺に陣を取」ったところ、「新田、脇屋、大将として、湖水をわたして散々に合戦」した御所方を打ち破った(『梅松論』)。しかし、東近江の地には要害がないため鏡山に拠ったところ、新田勢が再び攻め寄せたため、これを追い散らしたのち、伊吹山に籠って戦いの子細を京都に注進したという。また、直義は「於近江路者、相副近江伊勢両国輩、於佐々木佐渡判官入道々誉、且対治凶徒、且可警固東近江之由被仰下」と、佐々木道誉には近江と伊勢両国の御家人を副えて東近江の御所方追捕と警衛を指示し、鎮定後は速やかに入洛するよう指示している(建武三年七月十六日「足利直義御教書」『勝山小笠原家文書』)。これに先立ち、尊氏は近江国御家人に対し「近江国静謐事、属佐渡判官入道手、早可令発向」を命じている(建武三年七月八日「足利尊氏軍勢催促状」『田代文書』)。
7月4日には摂津国多田院の足利党・森本左衛門次郎為時らが呉庭の御所方を攻め、6日には尼崎、8日には安満縄手に追捕している(建武三年七月「森本為時軍忠状」『浅草文庫本古文書』)。さらに洛南で攻勢を強めていた「侍所(高尾張権守師泰)」率いる軍勢は9日、「山崎芥河」を出立する師泰から「可罷向山手之由」の指示を直接受けた「諏訪部三郎入道信恵」は、山の上に登ると馳せ下って御所方を蹴散らしたという(建武三年九月「諏訪部入道信恵軍忠状」『三刀屋文書』)。彼らは6月30日の京都合戦で壊走し、八幡の武田兵庫助信武や洛南の高尾張権守師泰、山崎の赤松二郎左衛門尉貞範(延元元年七月「色川盛氏軍忠状」『清水文書』)に追われた御所方の人々であろう。
また、7月15日には「備後国則光西方城郭(中黒城)」に御所方の「小早河七郎、石井源内左衛門入道以下凶徒」が立て籠って挙兵し、「長弥三郎信仲」や「大田佐賀寿丸」、「山内七郎入道観西」ら当国御家人が馳せ向かい、17日夜に攻め落としている。8月晦日にも「竹内弥次郎兼幸、小早河掃部助以下凶徒」が蜂起しこれを鎮定している(建武三年十月十日「長谷部信仲軍忠状」『山内首藤家文書』)。これはかなり大規模に起こった御所方の挙兵のようで、京都の尊氏にも急報されており、7月22日、「小早川平三殿(小早川経平)」に「備後国凶徒等放棄事、可襲向隣国芸州之由有其聞」として、「早々相催在国一族」して合戦に臨むよう命じている(建武三年七月廿二日「足利尊氏御教書」『小早川文書』)。このように、地方にはいまだ御所方勢力が散在し、足利勢と合戦を繰り返していたことがわかる。
7月23日、武田信武勢は醍醐へ馳せ向かい、駐屯していた御所方と合戦して陣を焼き払って殲滅し、同日中に南下して木幡山へ布陣。8月7日には宇治の「岡屋櫃河」の城に立て籠った御所方と戦っている(建武三年八月十四日「三戸頼顕軍忠状」『毛利家文書』)。武田勢の宮荘親家は「岡屋城北木戸」を散々に攻めたのち、「帰本陣致警固」という。武田信武勢の本陣はおそらく八幡山であり、「同十一日、御上洛之時、御共仕令帰洛了」(建武三年八月十六日「宮荘親家軍忠状」『吉川家文書』)とあり、8月11日までは在陣していたと思われる。
建武3(1336)年6月30日の京都合戦の大勝により、形勢は足利方有利の状況となり、持明院統の光厳上皇及び豊仁親王を推戴し、奉戴する皇統も確実に確保し、尊氏は恩賞沙汰や寺社領安堵、寺社に対する兵士たちの禁制を行う余裕を見せ始めている。
ただし、畿内近国にはいまだ御所方勢力が根強く残っており、7月25日、尊氏は一門の「尾張式部大夫殿(足利時家)」を尊氏分国の若狭国守護として派遣。時家は小浜に入部した(『若狭国守護職次第』)。御代官は「氏家藤十郎通継」(『若狭国税所今富名領主代々次第』)。氏家家は足利尾張家の執事家であり、氏家一族は足利尾張家(斯波家、大崎家、最上家等)の執事家として各地に発展する。足利尾張式部大夫時家は「若州大将軍」と称され(建武三年八月五日「佐々木義信軍忠状」『朽木文書』)、若狭国の政務治安維持を行った。若狭国は旧得宗分国で得宗家の旧臣らも雌伏していたであろうことから、京都から丹波路を経て近江国へ進出する要衝であるとともに、御所方となり得る先代勢を封じ込めるべく、一門筆頭足利尾張家の時家を派遣して制圧し、比叡山周辺への圧力としたのであろう。
8月1日、「大塔若宮(大塔宮護良親王遺児、のちの興良親王とされる)」が比叡山から「八幡山」に移り、「和泉国岸和田弥五郎治氏」が御供して「連日令祗候」という(延元二年三月「和田治氏軍忠状」『和田文書』)。ただし、7月下旬から8月11日にかけて八幡山は武田信武勢が本陣として警固していることから、この「八幡山」は後述の通り、石清水八幡宮寺ではなく、岸和田治氏の本拠である岸和田の八幡山(春木八幡山)であろう。摂津国南部から和泉国、河内国、紀伊国にかけては御所方勢力が強く、楠木一族等も盤踞していて足利方の勢力が十分及んでいない国であり、「大塔若宮」が岸和田治氏に伴われてこの地へ下ったのも、大塔若宮と河内楠木党による元弘三年の再現を目指したものと考えられよう。
後醍醐天皇―――護良親王
(大塔宮)
∥――――――興良親王
∥ (若宮)
北畠師重――+―女子
(春宮大夫) |
|
+―北畠親房―――北畠顕家
(准后) (権中納言)
8月11日、武田兵庫助信武麾下の宮荘周防次郎四郎親家は「同十一日、御上洛之時、御共仕令帰洛了」(建武三年八月十六日「宮荘親家軍忠状」『吉川家文書』)とあり、武田勢は八幡山を発って上洛の途についている。この上洛は8月15日の豊仁親王践祚に伴うもので、東寺御所の尊氏に合流したと思われる。
後伏見天皇―+―光厳天皇
(胤仁) |(量仁)
|
+―光明天皇
(豊仁)
践祚の儀は「豊仁親王為院御猶子元服、次院宣押被行践祚、雑兵乱中雖黙止、足利前宰相尊氏申行之」(『続史愚抄』)とあるように、尊氏の奏請により行われている。8月15日、豊仁親王は「当日自東寺先幸泉殿被擬仙洞、密々御元服」とあるように、「東寺」から光厳上皇の御所に擬された「於押小路烏丸故左大臣第(権大納言良基卿押小路烏丸邸)」(『公卿補任』)の「押小路第、以泉屋」「泉殿」に移って「加冠左大臣(近衞経忠)」で御元服。その後「寝殿」に移って「践祚」した。光明天皇である。上卿は「左大臣藤原朝臣(近衞経忠)」が務めている(「洞院家記」『践祚部類抄』)。これにより、東坂本の日吉社に遁れていた後醍醐天皇は「旧主」と定められ、廃位された。
践祚後、近衞経忠は「氏長者」「依新帝詔為関白」となり、除目が行われた。この除目では尊氏や直義の還任については記載はないが、年月不明で「尊氏卿参議左兵衛督也、直義為左馬頭」(『建武三年以来記』)とあり、尊氏は参議、左兵衛督に任官し、直義も左馬頭任官が認められる。11月25日には尊氏は権大納言となって参議が停止していることから、尊氏の参議任官はこの8月15日除目が妥当か。また、御所方公卿の解官も行われておらず(辞任した人物はいた)、形式上は一連の乱はあくまでも「新田義貞以下凶徒」の叛乱であり、彼らによって連れ去られた「旧主」は戻らないことから「新主」践祚を奏請したため、旧主派の公卿についても罰する理由はないということか。
●建武三年八月十五日除目(『公卿補任』『師守記』)
| 名前 | 官位 | 見任 | 補任(止) |
| 近衞経忠 | 従一位 | 左大臣 | 関白、氏長者 |
| 中院通冬 | 正三位 | 左中将・美作権守 | (止)左中将・美作権守 |
| 日野資明 | 正三位 | 散位 | 参議(還任) |
| 中御門宗兼 | 従四位上 | 右近衛中将・侍従 | (止)右近衛中将・参議 |
| 吉田為治 | 従四位下 | 権左少弁 | 右中弁 |
その後、8月17日には「新主(光明天皇)」及び光厳上皇は押小路烏丸邸から「東寺御所」へ還御しており、いまだ西坂本付近の治安が安定していない中で、上京地区の御所洛中への行幸は憚られたか。
建武3(1336)年8月、洛中で践祚の儀が行われている最中においても「南方の敵とも、宇治八幡辺まて充満して寄来るへきよし京都の風聞毎日なり」(『梅松論』)という。この軍勢には「和泉国岸和田弥五郎治氏」が加わっていることから(延元二年三月「岸和田治氏軍忠状」『和田文書』)、摂南、和泉、河内国を根拠とする「大塔若宮」を奉じた御所方の軍勢であろう。この洛南の御所方には「八幡路大将両人鑑巌僧都、越後松寿丸」が見えるが(建武三年八月廿五日「足利尊氏御教書」『勝山小笠原文書』)、「鑑巌僧都」は鎌倉評定衆「摂津刑部大輔入道(摂津親鑑入道)」の子で元享2(1322)年11月4日まで鶴岡千南坊供僧であり(『鶴岡八幡宮寺供僧次第』)、「越後松寿丸」は最後の北方探題で番場で自害した越後守仲時の子「松寿後号左馬助友時」(『諸家系図纂』)の可能性が高く、「大塔若宮」の父・兵部卿護良親王と先代勢力の結びつきがいまだ強く残っていたことがうかがえる。なお「鑑巌僧都」の叔父である摂津右近大夫将監親秀は尊氏麾下の奉行人として活躍している。
尊氏は8月20日頃、この「宇治の敵はらふへし」と「細川の人々大将として、河野対馬入道、同一族二千余まて向」ったが、細川勢が敗れて引き上げた隙を突き、御所方は宇治の防衛線を突破して「木幡稲荷山を経て、今比叡の上阿弥陀がみねに陣を取」った(『梅松論』)。一方、8月23日の「賀茂糺河原」の合戦では、西坂本の新田義貞勢が洛中侵攻を企てたが、吉田河原周辺に堅陣を張る高師直勢に撃退され、延暦寺衆徒もまた多く討たれたという(『梅松論』)。
一方、阿弥陀峯の御所方と足利方の合戦は、23日の「新日吉致合戦」(「高橋茂宗軍忠状」『多田院文書』)など足利方の攻勢にも拘わらず容易に落ちる様子がなかったため、24日夜、東寺で合戦評定が行われている(『梅松論』)。この軍議では細川帯刀先生直俊の献策が採用され、侍所の高越後権守師泰らが中心となって25日、「大塔若宮」勢力の後詰である淀・竹田方面を攻めた。そして「八幡路大将両人鑑巌僧都、越後松寿丸」(建武三年八月廿五日「足利尊氏御教書」『勝山小笠原文書』)を打ち破って彼らを「被生捕之所被誅」という。「鑑厳法印」は6月30日合戦で名和長年とともに誅されたとあるが(『常楽記』)、実際は生存していて八幡路大将軍となっていた。また「越後松寿丸」については、暦応2(1339)年2月に「自伊豆仁科城凶徒卅七人、目代具参、此内十三人者、於龍口被切了、大将普薗寺左馬助云々」(『鶴岡社務記録』)とあることから、生き延びていたことがわかる(北畠親房入道の東国下向に従い、難破して伊豆西岸にたどり着いた可能性が高い)。そして同日、尊氏は東近江に駐屯していた「小笠原信乃守殿(貞宗入道)」に対して、「義貞已下輩没落山門之上者、急渡世田橋、可発向東坂本」と、後醍醐先帝の御座所である東坂本(日吉社)を攻め落とすことを指示している。
細川一族は宇治で敗れたものの、北上する御所方を追撃して「木幡稲荷山阿弥陀峯等、追堕数箇所之陣々」(建武三年九月「田代市若丸軍忠状」『田代文書』)するとともに「搦手山科」からも攻めたて(「高橋茂宗軍忠状」『多田院文書』)、阿弥陀峯から御所方を追い落とした(『梅松論』)。阿弥陀峯西側の「於祇園門前御敵行合、致散々戦」い(「高橋茂宗軍忠状」『多田院文書』)、山科でも「至四宮川原追懸御敵候」(建武三年九月「田代市若丸軍忠状」『田代文書』)していることから、御所方は阿弥陀峯から東西に分かれて逃れたことがわかる。この御所方の陣に加わっていた岸和田治氏は「八月廿五日、於木幡山阿弥陀峯」で足利方と合戦したのち、「九月一日」には「大塔若宮」とともに和泉国へ入ったものと思われる。
阿弥陀峯から和泉国に帰還した岸和田治氏は、9月1日、和泉国に駐屯していた「足利一族阿房次郎国清」と合戦して敗北し、岸和田に隣接する「八木城」へ撤退している。おそらく岸和田の八幡山(春木八幡山)に拠る「大塔若宮」とともに遁れたのであろう。なお、「八木」は治氏が湊川の戦で楠木勢の一員としてともに戦った「八木弥太郎入道法達」(延元二年三月「和田治氏軍忠状」『和田文書』)の名字地である。しかし、岸和田治氏は畠山安房次郎国清の「猛勢」により「御方軍勢各雖退散仕」と大敗を喫して「楯籠八木城、構要害」たが、9月7日には「国清已下逆類等、率大勢寄来」ると、摂南の天王寺から「中院右少将家并楠木一族橋本九郎左衛門尉正茂已下」が援兵に駆けつけて畠山勢を押し返し、畠山国清は「裔原城」まで遁れ、その後追い落とされたという(延元二年三月「和田治氏軍忠状」『和田文書』)。9月17日に国清が「新田義貞并正成与党之輩誅伐事」を和泉国の御家人「日根野左衛門入道殿」に命じているが(建武三年九月十七日「畠山国清施行状」『日根野文書』)、和泉兵乱が「大塔若宮」を奉じた楠木一党の挙兵であり、その危険性から尊氏は国清に強く追討を指示したものと考えられる。
続けて尊氏は9月26日、「天王寺凶徒等誅伐」のため、大規模な軍事行動を起こす(建武三年九月廿六日「足利直義御教書」『等持院文書』)。一門重鎮の「宮内大輔(吉良貞家)」も大将軍の一人として出兵したとみられ、そのほか細川兵部少輔顕氏ら細川一族も馳せ向かった。また、9月29日に「山城已下凶徒等退治」のために「令発向八幡路」(建武三年九月廿九日「武田信武施行状」『萩藩閥閲録』)した武田信武勢も10月2日には天王寺に向かっている。天王寺は足利方の攻勢により陥落したとみられ、武田信武勢は10月12日まで「天王寺致警固」という(建武四年四月十三日「三戸頼顕軍忠状」『毛利家文書』)。
建武3(1336)年8月25日、尊氏は近江国駐屯中の小笠原貞宗入道に、南の瀬田から東坂本攻めを命じているが、丹波国から若狭国を経由して北から侵入した佐々木入道道誉も北から東坂本を窺っており、すでにして東坂本は足利方によって包囲される形となっていた。千葉介貞胤はおそらく宇都宮公綱とともに御所方の武力の要として東坂本付近を警衛し、足利方の攻勢に備えていたと思われる。
このような状況下で、おそらく9月初旬には尊氏と後醍醐先帝による「御和談」が話し合われはじめたと思われる。東坂本の御所方は「朝敵追討事、四方官軍等不一揆、或先駆而失其利、或城守而似怠慢」(延元元年九月十八日「後醍醐天皇綸旨」『阿蘇文書略』)とあるようにすでに疲弊しており、足利方も連戦に次ぐ連戦で厭戦気分が漂っていたのではあろう。後醍醐先帝は「御和談」による事実上の「降伏」前に、後年の反攻に備えていくつかの布石を打ったが、その一つが「無品親王為征西大将軍」を九州に派遣するもの(延元元年九月十八日「後醍醐天皇綸旨」『阿蘇文書略』)であった。「無品親王(懐良親王)」には「勘解由次官(五条頼元)」が付属され、東坂本から密かに四国へ派遣されたようである。経由地は和泉河内とみられ、12月30日までに「已御下著讃州候」と讃岐国に渡り、その後は「則可有御渡海予州候、且鎮西御船付以下之事、急可被召進、故実之仁於奥州之由、征西将軍令旨所候」(延元元年十二月卅日「懐良親王令旨」『阿蘇文書』)と阿蘇大宮司(惟澄を指すか)に命じている。取り急ぎ征西将軍宮に供奉した「三条侍従殿」「三条少将家」が「薩州御大将」として薩摩国に派遣され、建武4(1337)年3月17日に「御下向」して綸旨を齎している(延元三年二月五日「揖宿入道成栄軍忠状」『揖宿文書』)。一旦は足利方が大勢を占めていた鎮西の様相は、建武4年以降、征西将軍宮のもと吉野方の勢力が息を吹き返すこととなる。なお、三条泰季は『尊卑分脈』に名の見えない人物であり、血縁については「三条少将はいかなる人にてありしにや、家系ハさたかならされとも、去年征西将軍宮の供奉して西国まて下りし人」(『征西将軍宮譜』)とあり、不明であるが、吉野方へ加わった三条家の人物は「前大納言実数」のみ見えることから(『尊卑分脈』)、三条実数の子かもしれない。懐良親王はまず「此少将を伊予あたりよりまつ肥後に差遣ハされたるなるへし、此時宮中将も此少将ともに肥後にさしつかはされ、少将ハ南郡、中将ハ北郡へとわかれて越されし」と、懐良親王に先行して肥後国へ派遣されたという。年齢は「少将ハ公家の人といひ、いまた年少なり」といい、まだ若年の人だったことがわかる。
そして10月初旬、御所方と足利方との間で和睦交渉がまとまり、後醍醐先帝は東坂本より帰洛の途に就き、「十月十日の比にや、山門より還幸、いとあさましかりし事ともなり」(『神皇正統記』)と京都に帰還し、花山院邸に入御した。『梅松論』によればこの「御和睦」と洛中還御は「建武三年十一月廿二日」とあるが、実際は10月10日の事である。なお、この前日の「十月九日、東宮并尊良親王、義貞等、趣越前国」(『元弘日記裏書』)、「猶行末をおほしめす道ありしにこそ、東宮ハ北国に行啓あり、左衛門督実世卿以下の人々、左中将義貞朝臣をはじめとし、さるへき兵もあまたつかうまつりたり」(『神皇正統記』)とあるように、東宮恒良親王、一宮尊良親王、左衛門督実世ら公卿衆、左中将義貞らを密かに越前国へ落としている。千葉介貞胤も「新田義貞朝臣奉取春宮、率千葉以下軍勢、自叡山落北国」(『建武三年以来記』)とある通り、義貞とともに越前へと下向している。この恒良親王・尊良親王の越前行には「武家千葉介御共、長年之一党雖御共、自西坂本馬踏捨、不知行方、今者無一身置所」(『歯長寺縁起』)と、千葉介貞胤が付き従っているが、故名和長年の一党は身の置き所もなく、西坂本から忽然と姿を消してしまったという。
この「東宮(恒良親王)」については、「新田左中将義貞、賜神璽、宝剣、内子所、春宮為大将、相具数万騎軍兵、北国下向、越前金崎為内裏」(『歯長寺縁起』)とあるように、後醍醐帝から新田義貞に三種の神器が託され、越前金崎を「内裏」と定めたという。これは、後醍醐帝が恒良親王に譲位した上で越前へ下したことを意味する。11月12日の時点で「左中将(新田義貞)」は「結城上野入道館」に対し「高氏直義以下逆徒追討事、先度被下綸旨了、去月十日所有臨幸越前国鶴賀津也、相催一族、不廻時刻馳参、可令誅伐彼輩、於恩賞者、可依請者、 天気如此、悉之以状」(延元元年十一月十二日「恒良親王綸旨写」『白河結城文書』)といい、恒良親王は正しく三種の神器を継承した天皇となっていたことがわかる(『源平盛衰記』にも伝わる通り神器の実見不可は凡下にまで広く知られた常識であり、当然真偽を比較する術は存在せず、尊氏に引き渡されたであろう神器を後醍醐先帝が偽物と主張すれば、尊氏がそれを否定することはできない)。「右衛門督(右衛門督隆資は翌年2月9日には吉野にいたとみられることから(延元二年二月九日「後醍醐上皇院宣」『白河文書』)、左衛門督実世だろう)」も新田義貞奉書の綸旨に同日付副状(延元元年十一月十二日「綸旨副状」『白河結城文書』)を付けていることから、同時代成立の『歯長寺縁起』に伝える事実との同一性を考えれば、後醍醐天皇は新帝に洞院左衛門督実世ら主要な公卿衆を付け、新田左中将義貞には千葉介貞胤ら大名衆を伴わせ、新帝を全面的に託して下向を命じた可能性が高いことがわかる。『太平記』では後醍醐天皇が義貞に相談なく還幸しようとし、堀口貞満が抗議した姿が描かれているが、明らかな創作であろう。
後醍醐先帝は「御和談」の条件として先代同様の両統迭立の復活(後醍醐先帝は当然皇統を返す考えはなく、尊氏もそれを承知の上での約定であろう)を称して「以先帝皇子成良親王為皇太子」(『皇年代略記』)を認めさせたのだろう。足利方は三種の神器の引き渡しが提案されたと考えられる。そして、後醍醐先帝の帰洛に従わず「没落北国」した東宮恒良親王は、先帝還御即日に東宮を廃され、同時に春宮坊及び東宮職も停止された。
●建武三年十月十日除目(『公卿補任』『東宮坊官補任』)
| 名前 | 官位 | 見任 | 停止 |
| 洞院公賢 | 従一位 | 右大臣 | (止)東宮傅 |
| 鷹司師平 | 正二位 | 権大納言 | (止)春宮大夫 |
| 西園寺公重 | 従二位 | 左兵衛督 | (止)春宮権大夫 |
| 中御門宣明 | 正五位上 |
蔵人 右中弁 | (止)春宮亮 |
| 甘露寺藤長 | 正五位下 |
蔵人 右少弁 | (止)春宮大進 |
| 藤原国俊 | 正五位上 | 右少弁 | (止)春宮権大進 |
また、摂南、和泉、河内、紀伊国には「大塔若宮(興良親王)」を奉じる楠木一党などが勢力を維持していたが、前述の通り密かに越前国に新帝(恒良親王)及び中務卿尊良親王(元弘の乱では九州で実戦経験を持つ皇子)を奉じる新田義貞、九州には「無品親王征西大将軍(懐良親王)」を派遣しており、後醍醐先帝は反攻の余地を密かに残した上で戦略的「御和談」を行ったのである。
二条為世―+―――――――――藤原為子 +―尊良親王【越前国】
(権大納言)| ∥ |(中務卿)
| ∥ |
| ∥――――――+―尊澄法親王
| ∥ (天台座主)
| ∥ 源資子
| ∥(三位)
| ∥ ∥――――――護良親王――――――興良親王【和泉・河内国】
| ∥ ∥ (兵部卿) (大塔若宮)
| ∥ ∥
| 後醍醐天皇 +―恒良親王【越前国】
| ∥ ∥ |(春宮)
| ∥ ∥ |
| ∥ ∥――――+―成良親王
| ∥ ∥ |(征夷大将軍)
| ∥ ∥ |
| ∥ 阿野廉子 +―憲良親王【陸奥国】
| ∥(内侍) (陸奥太守)
| ∥
| ∥――――――――懐良親王【九州】
| ∥ (征西将軍宮)
+―藤原為道――――藤原藤子
(左近衛中将) (三位局)
建武3(1336)年10月9日、「東宮并尊良親王、義貞等、趣越前国」(『元弘日記裏書』)、「猶行末をおほしめす道ありしにこそ、東宮ハ北国に行啓あり、左衛門督実世卿以下の人々、左中将義貞朝臣をはじめとし、さるへき兵もあまたつかうまつりたり」(『神皇正統記』)とあるように、東宮恒良親王、中務卿尊良親王、左衛門督実世ら公卿衆、左中将義貞らを密かに越前国へ落とした。千葉介貞胤も「新田義貞朝臣奉取春宮、率千葉以下軍勢、自叡山落北国」(『建武三年以来記』)という。しかも「新田左中将義貞、賜神璽、宝剣、内子所、春宮為大将、相具数万騎軍兵、北国下向、越前金崎為内裏」(『歯長寺縁起』)とあるように、後醍醐帝から新田義貞に三種の神器が託されていたという。事実、前述の通り、越前国の恒良親王は「臨幸越前国鶴賀津」して「綸旨」を下している通り、天皇として振る舞っている。後醍醐先帝は「御和談」の条件であったとみられる三種の神器の引き渡しについて、真の神器は恒良親王への譲位の際に彼に附させて北陸へ避難させ、足利方へ引き渡す贋物を拵えて交渉事に用いたのではなかろうか(前述の通り、神器の実検は不可能であり、後醍醐先帝が真と言えば真なのである)。
京都においては11月2日、「自花山院、内侍所、剣璽、渡御東寺」(『勘例雑々』)とあり、おそらく「御和談」の条件のひとつであった三種の神器の引き渡しが行われた。これに伴い、後醍醐先帝には「被奉太上天皇尊号」(『皇年代略記』)された。これについて北畠親房入道は「御心をやすめ奉んためにや」(『神皇正統記』)と推測している。
11月7日、尊氏は『建武式目』政道十七か条を定めた。尊氏は以前から「真恵」「是円俗名道昭」の兄弟ら八名の儒者や政務官僚らに今後の政務体系についての諮問を行っており、この日、諮問に対する答申がなされている。諮問人衆はいずれも代々儒家の南家藤原藤範卿を筆頭に、雑訴決断所所衆を中心とする故事、裁判実務、人事に明るい人々が抜擢されている。
●建武三年十一月七日「建武式目」(『建武式目』)
| 諮問人衆 | 前民部卿(非参議藤範):南家藤原氏 是円(是円房道昭):雑所決断所二番所衆 真恵(是円房舎弟):雑所決断所五番所衆 玄恵法師(叡山上三綱):清中両家之儒、伝師説而候于侍読歟 大宰少弐(太宰少弐頼尚):太宰少弐 明石民部大夫(明石民部大夫行連):雑所決断所八番所衆 大田七郎左衛門尉(太田七郎左衛門尉顕連):問注所太田氏、美作七郎左衛門尉 布施彦三郎入道(布施彦三郎入道道乗):雑所決断所二番所衆 |
| 諮問 | 答申 |
| 鎌倉如元可為柳営歟、 可為他所否事 |
就中、鎌倉郡者、文治右幕下始構武館、承久義時朝臣并呑天下、 於武家者尤可謂吉土哉、但諸人若欲遷移者、可従衆人之情歟 |
| 政道事 |
先逐武家全盛之跡、尤可被施善政哉、然者、宿老評定衆公人等済々焉、 於訪故実者、可有何不足哉、古典曰、徳是政々在安民云々、 早休万人愁之儀、速可有御沙汰乎、其最要、 |
| 一、可被行倹約事 | |
| 一、可被制群飲佚遊事 | |
| 一、可被鎮狼藉事 | |
| 一、可被止私邸點定事 | |
| 一、京中空地、可被返本主事 | |
| 一、可被興行無尽銭土倉事 | |
| 一、諸国守護人、殊可被択政務器用事 | |
| 一、可被止権貴并女性禅律僧口入事 | |
| 一、可被誡公人緩怠并可有精撰事 | |
| 一、固可被止賄賂事 | |
| 一、殿中付内外、可被返諸方進物事 | |
| 一、可被選近習者事 | |
| 一、可専礼節事 | |
| 一、有廉義名誉者、殊可被優勝事 | |
| 一、可被聞食貧弱輩訴訟事 | |
| 一、寺社訴訟、依事可有用捨事 | |
| 一、可被定御沙汰式日時刻事 |
いずれも「武家全盛」の頃の「尤可被施善政」がその理想となり、「徳是政々在安民」を目的として十七か条が答申されている。また、尊氏は本拠となる「柳営」を元のように鎌倉とすべきか他所とすべきか問うているが、これは元弘以来尊氏が武家の最高位として存在し、そのカリスマ性と卓越した指揮能力により、事実上の「鎌倉殿」として、武家の棟梁たる地位を継承する立場となっていたことを意味しているのだろう。
そして11月14日、朝廷は「成良親王を東宮にすへ奉」った(『神皇正統記』)。成良親王はかつて直義が鎌倉に奉じ、奥州の弟宮(憲良親王)ならびに陸奥守顕家との協同で奥羽関東を鎮撫した皇子であった。中先代の乱の勃発により、叔父の阿野公廉の護衛のもと帰京して以来在京し、征夷大将軍にも任じられている。彼の立坊は「御和談」の条件であったと思われるが、「御子成良親王ハ、本ヨリ尊氏養ヒ進セタリケレハ、東宮ニ奉立ケリ」(『保暦間記』)とも見えるように、尊氏が成良親王の立坊を認めたのは事実こうした経歴が関係しているのかもしれない(当時在京の後醍醐先帝の皇子は成良親王のみであったか)。そして同日、東宮職及び春宮坊が定められた。
建武三年十一月十四日除目(『公卿補任』『東宮坊官補任』)
| 名前 | 官位 | 見任 | 補任(兼) | 備考 |
| 一条経通 | 正二位 | 内大臣 | 東宮傅 | 正室藤原綸子(洞院公賢女)は成良母の藤原廉子の養妹(廉子養父が公賢) |
| 冷泉公泰 | 正二位 | 権大納言 | 春宮大夫 | 洞院公賢の子。成良母の藤原廉子の養弟。 |
| 徳大寺公清 | 従二位 | 権中納言 | 春宮権大夫 | 正室洞院公賢女は成良母の藤原廉子の養姉妹 |
| 甘露寺藤長 | 従四位下 | 右中弁 | 春宮亮 | 前坊恒良親王の春宮大進 |
| 久我通相 | 従四位上 | 左近衛権中将 | 春宮権亮 | 太政大臣長通嫡子。のち太政大臣 |
続けて11月25日の「東寺御所被小除目」(『師守記』)で、左兵衛督尊氏は権大納言に任じられ、朝廷運営の要を握っている。その後の尊氏の立場は軍事指揮官というよりも所領や貢済関係に重点を置いた「統治者」へと移行し、、建武元年より惣領家「執事」となった高武蔵権守師直が施行であった(『武家年代記』)。一方で軍事指揮官としては弟の左馬頭直義が諸国武士や御家人を統率し、その麾下には高越後権守師泰や細川兵部少輔顕氏らがみられる。
●建武三年十一月廿五日除目(『公卿補任』)
| 名前 | 官位 | 見任 | 補任(止) |
| 足利尊氏 | 従二位 | (前参議) | 権大納言 参議 |
| 花山院長定 | 従二位 | 権中納言 | 兼 左兵衛督 |
| 四条隆蔭 | 従三位 | 非参議 | 参議 |
| 三条公秀 | 正二位 | (前権大納言) | 太宰権帥 |
| 押小路惟継 | 正二位 |
(前権中納言) 太宰権帥 文章博士 | (止)太宰権帥 |
| 菅原在登 | 正三位 |
非参議 勘解由長官 筑前権守 | (止)勘解由長官 |
| 資継王 | 正三位 |
神祇伯 非参議 | (止)神祇伯 |
ただし、尊氏は建武4(1337)年12月9日当時「将軍家政所」を開いており(建武四年十二月九日「足利尊氏御教書」『勝山小笠原文書』)、「将軍家」と称されていたことがわかる。この「将軍家」はまだ補任されていない征夷大将軍ではなく「鎮守府将軍」であろう。こうした尊氏による運営政権が着実に構築されている最中、11月29日に尊氏の先陣として度々果敢な戦いを行った千葉大隅守胤貞が「住三河死、四十九」した(『松羅館本千葉系図』)。
建武3(1336)年12月10日、「自東寺行幸内大臣一條第、内侍所同渡御」(『勘例雑々』)した。後醍醐上皇の花山院邸への還御及び新田義貞の北陸没落を受けて、主上の洛中還御に舵を切ったか。ただし、洛南及び和泉、河内、紀伊方面に大きな懸念があるため、静謐となった北部へと皇居を移した可能性が高いだろう。新たに皇居となったのは「一条室町内大臣第」(『皇代略記』)であるが、ここが選ばれたのは、光厳上皇が「還幸持明院殿」(『皇代略記』)の近隣地であり、防衛のしやすさが考えられた結果だろう。
ところがこのような中、12月21日夜、花山院の後醍醐上皇が忽然と「先帝御幸他所、不知御座所」(建武三年十二月廿二日「足利直義御教書」『保田文書』)のため、発覚した翌日22日、直義は「所奉尋方々」している。「今度ハいつくの国へ御幸あらんずらんなど沙汰ありし時分、潜に花山院殿を御出有」(『梅松論』)て、「乗輿潜出洛、幸吉野」(『元弘日記裏書』)と、大和国吉野へと逐電したのであった。この出洛吉野行幸には「帝従楠一類」(『如是院年代記』)、「同十二月に忍て都を出ましまして、河内国に正成といひしか一族等をめしくして芳野にいらせ給ひぬ」(『神皇正統記』)と、楠木一族の手引きがあった様子がうかがえる。これは、上皇が「主上出御京都、幸河内東條(富田林市龍泉)」(延元二年正月一日「北畠親房入道御教書」『結城家文書』)と見えるように、楠木氏の本拠地に行幸していることからも事実と思われる。
そのほか「顕家卿舎弟顕信朝臣、伊勢ノ国ニテ義兵ヲ挙げ、内々申通スル事有テ、秘ニ先帝都ヲ出サセ給」(『保暦間記』)と北畠親房入道の動きもみられる。後醍醐上皇は「有子細出京之處、直義等令申沙汰之趣、旁本意相違、如当時者、為国家愈無其益之間、猶為達本意、出洛中移住和州吉野郡」(延元元年十二月廿五日「後醍醐天皇宸簡」『白河結城文書』)といい、何かの「子細」があって出京したところ、「直義等」が「沙汰」したが、その趣旨は自分の「本意相違」であり、まったく国家のためにならないことであるから、「為達本意」に大和国吉野へ移ったと陸奥国府の北畠顕家に述べている。再度の行幸(流刑)の噂を警戒して楠木一族や伊勢北畠亜相と連携のもと京都を脱出したのが真相であろうが、出奔せざるを得なくなった責任は直義にあると主張する。上皇は「主上出御京都、幸河内東條、即又復御吉野」(延元二年正月一日「北畠親房入道御教書」『結城家文書』)とあり、さらに「廃帝御坐河内国之間、凶徒可令内通于紀州之由、有其聞、早属畠山次郎、不日馳向、且構要、害、差塞道々、且可誅伐凶徒之状如件」(建武四年正月二日「足利直義書下状」『志富田文書』)と、楠木一党が河内国から紀伊国へ手引きしたことがわかる。ただし、もともと上皇は「新院欲有入御当山之處、衆徒依支申、無其儀之由注進」(建武四年正月四日「足利直義書状」『宝簡集』)とあるように、高野山入りを目指したものの、衆徒等の反対により入山できなかった様子が見られる。
12月25日当時、上皇は「移住和州吉野郡」(延元元年十二月廿五日「後醍醐天皇宸簡」『白河結城文書』)しており、陸奥国府の北畠顕家に「御勅使江戸修理亮忠重」を遣わして、「相催諸国、重所挙義兵也、速率官軍、可令発向京都、武蔵相模以下東国士卒、若有不応勅命者、厳密可加治罰者也、併相憑輔翼之力、雖廻権■之謀、速成干戈之功者、国家大幸、文武徳善、何事如之哉、大納言入道居住勢州、定委仰遣之歟、坂東諸国悉令帰伏之様、以仁義之道、可施徳化也、道忠以下、各可励忠節之旨、別可被仰含者也」(延元元年十二月廿五日「後醍醐天皇宸簡」『白河結城文書』)と、ただちに奥州から上洛すべきことを命じている。
上皇に近侍する北畠親房入道は、延元2(1337)年正月1日、奥州結城宗広入道の援軍を依頼する「此使節自吉野被差遣」(延元二年正月一日「北畠親房入道御教書」『結城家文書』)からの書状の中で、「為被果御願」に「可幸勢州之由被仰候」という上皇の仰せがあったため、まず「愚身於勢州廻逆徒静謐之計、可待申臨幸候」と、まず親房入道自身が伊勢国に向かい、足利方勢力を殲滅し臨幸を待つこととなった旨を伝えている。これを踏まえて正月4日、親房入道は被官「源親直(近江権守親直)」を通じて「潮田刑部左衛門尉殿(潮田幹景)」(延元二年正月四日「北畠親房御教書」『潮田氏文書』)に、正月18日には「大杉軍勢中」(延元二年正月十八日「北畠親房御教書」『津田文書』)に「為追討朝敵、一族相共可馳参」ことを命じている。当然この他の伊勢国住人に対しても軍勢催促が行われていたであろう。これは北畠親房入道が伊勢国守護と定められたが故か。当時の親房は「北畠入道一品家」と称されており、従一位(『公卿補任』では元徳二年九月十七日出家当時が正二位大納言であり、その後に叙されたもの)となっていたことがわかる。
一方で、足利方は上皇逐電の一報により「洛中の騒動申ハかりなし、此上ハ京中より御敵出へしとて、急東寺へ警固を遣されける間、諸人冑の緒をしめて、将軍の御前へはせさんした」(『梅松論』)という騒動となっていたが、尊氏は「少しも御驚き有御気色もなくして、宗徒の人々に御対面」して、「此度、君花山院に御座の故に、警固申事其期なきに依て、以の外武家の煩なり、先代の沙汰のことく遠国に遷奉らはおそれ有へき間、迷惑の處に今御出ハ太儀の中の吉事也、定て潜に畿内の中に御座有へき歟、御進退を叡慮に任せられて、自然と落居せは、しかるへき事也、運ハ天道の定むる所也、浅智の強弱によるへからす」(『梅松論』)と述べたという。
吉野には「吉野御所」(『中院一品記』)という「行宮をつくりてわたらせ給、神璽も御身にしたかへ給けり、誠に奇特の事にこそ侍り」(『神皇正統記』)というように、北畠親房入道は後醍醐上皇が持つはずのない「神璽」を身につけていたことを聞き不思議な事と述べているが、11月2日に光明天皇に引き渡された三種の神器は「自花山院、内侍所、剣璽、渡御東寺」(『勘例雑々』)とあり、三種揃っていたことが確認できる。後醍醐上皇から引き渡されたものは形式を整えた偽物であった可能性は否定できず、真物は宝剣、賢所については越前国へ伝えられ、神璽のみは後醍醐上皇が持っていた可能性があろう(『保暦間記』では「三種ノ神器ヲ奉具、吉野山ヘ入せ給ふ」とあるが、親房入道の聞書に信を置くべきか)。
また、12月中の日時不明ながら、御所方の人々の解官が行われている。除目が行われた時期は不明ながら、おそらく後醍醐上皇の花山院邸出奔に伴う解官であろう。
●建武三年十二月解官(『公卿補任』)
| 名前 | 官位 | 解官 | 在所 |
| 四条隆資 | 正二位 |
権中納言 右衛門督 | 紀伊国?(『太平記』)。ただし紀伊国での活動は見られない。 |
| 洞院実世 | 正二位 |
権中納言 大学頭 左衛門督 尾張守 | 越前国 |
| 北畠顕家 | 従二位 |
権中納言 鎮守大将軍か | 陸奥国 |
| 堀川光継 | 従二位 |
権中納言 信濃守 | 河内国東条(『太平記』) |
直義は吉野から「南都警固事、被差遣左衛門佐畢」といい、正月頃、奈良に南都大将軍として、一門の重鎮・石橋左衛門佐和義を派遣(建武四年二月廿五日「足利直義軍勢催促状」『朝山文書』)。正月18日には「惣領大友」ら大友一族が南都に従軍している(建武四年七月「狭間入道正供軍忠状」『大友文書』)。
吉野からは越後国への橋頭保を再構築すべく、延元2(1337)年2月、「足利尊氏并直義以下凶徒等為追伐」のために「式部卿親王家御息明光宮、御下国」させたという(延元二年二月「大炊助盛継奉書」『上杉文書』)。亀山院皇子の式部卿宮恒明親王の御子(のちの常磐井宮全仁親王カ)である。「村山一族」に「当国沼河可馳参」ることを命じている。不利な状況に追い込まれていた越前国敦賀の支援的な意味合いもあろう。
3月2日、吉野方は「河州古市郡、構要害」たが、ここに足利方の「丹下三郎入道西念已下凶徒等」が大軍を率いて攻め寄せた。岸和田弥五郎治氏は吉野方の「大将軍(当国守護代大塚掃部助惟正か)」のもと「野中寺前(羽曳野市)」に馳せ向かい、「逆徒等追籠丹下城、焼払在家畢」(延元二年三月「岸和田治氏軍忠状」『和田文書』)と、「丹下城(河内大塚山古墳)」に追い込めたという。そして3月10日には、「細川兵部少輔、同帯刀先生等為大将軍」として古市を流れる石川の「坪井河原(羽曳野市壷井)」(建武四年九月「田代顕綱軍忠状」『田代文書』)に攻め寄せたため、岸和田治氏は「当国守護代大塚掃部助惟正并平石源次郎、八木弥太郎入道法達已下」とともに「野中寺東」に馳せ向かって破り、「追懸藤井寺西並岡村北面」に合戦。細川勢が二手に分かれて攻め寄せた際には「於藤井寺前大路」の合戦で「細川帯刀先生討死」と足利方大将軍の一人を討つも、合戦は敗北して「退散」している(延元二年三月「岸和田治氏軍忠状」『和田文書』)。その後も延元2(1336)年7月以降の和泉国、河内国から天王寺、八幡、山崎洞峠などでの吉野方は、和泉国守護代の大塚掃部助惟正を筆頭に、和田左兵衛尉正興、橋本九郎左衛門尉正義、佐備三郎左衛門尉正忠、上郷弥次郎俊康、上神六郎兵衛尉範秀、大塚新左衛門尉正連、八木弥太郎入道法達ら楠木一党が吉野方の主力となって足利方の大将軍細川兵部少輔顕氏や畠山上野左近大夫将監国清らと縦横に戦いを繰り広げている(延元三年十月「高木遠盛軍忠状」、延元二年十一月「和田大輔房定智軍忠状」『和田文書』)。しかし、延元3(1337)年10月18日には細川兵部少輔顕氏の手勢により楠木党の本拠である河内国東条への侵攻を許し、翌19日には「楠木赤坂」が攻め落とされている(建武四年十一月四日「田代顕綱軍忠状」『田代文書』)。
建武3(1336)年10月9日、後醍醐先帝は「東宮并尊良親王、義貞等、趣越前国」(『元弘日記裏書』)、「猶行末をおほしめす道ありしにこそ、東宮ハ北国に行啓あり、左衛門督実世卿以下の人々、左中将義貞朝臣をはじめとし、さるへき兵もあまたつかうまつりたり」(『神皇正統記』)とあるように、東宮恒良親王、中務卿尊良親王、左衛門督実世ら公卿衆、左中将義貞らを密かに東坂本から越前国へ派遣した。千葉介貞胤も「新田義貞朝臣奉取春宮、率千葉以下軍勢、自叡山落北国」(『建武三年以来記』)という。
このとき「新田左中将義貞、賜神璽、宝剣、内子所、春宮為大将、相具数万騎軍兵、北国下向、越前金崎為内裏」(『歯長寺縁起』)とあるように、後醍醐先帝は新田義貞に三種の神器を託し、東宮恒良親王を大将としたという。実際に恒良親王は「高氏直義以下逆徒追討事、先度被下綸旨了、去月十日所有臨幸越前国鶴賀津也、相催一族、不廻時刻馳参、可令誅伐彼輩、於恩賞者、可依請者、 天気如此、悉之以状」(延元元年十一月十二日「恒良親王綸旨写」『白河結城文書』)と、尊氏・直義追討の「綸旨」を下し、敦賀津に「臨幸」したとあるように、正統な天皇として振舞っているのである。この根拠は「三種の神器」を継承したという事以外考えられず、先帝は恒良親王に正式に譲位し、洞院左衛門督実世(恒良義叔父)ら主要公卿、新田勢、名和勢(ただし途中で離脱)、千葉介貞胤といった東坂本の主力を事実上越前国へ移し、御所方の温存を図ったものと思われる。そしてこれは名分上は、足利方が主敵と主張し続けた「新田右衛門佐義貞等凶徒」は先帝を解放し、東宮恒良親王を連れて逃亡したということになったのではなかろうか。
洞院公賢―+―洞院実世
(太政大臣)|(左衛門督)
|
+=藤原廉子 +―恒良親王
(三位) |(東宮)
∥ |
∥――――――+―成良親王
後醍醐天皇 |(上野太守)
|
+―憲良親王(義良親王)
(陸奥太守)
恒良親王、新田義貞等が東坂本から落ちた10月9日当時、東坂本の琵琶湖沿岸には足利勢が南北に布陣しており、多くの御所勢が琵琶湖沿いに動くことは考えにくい。とくに10月9日は先帝還御前日であり、当然合戦は行われていなかったであろう。「新田足利ノ戦、堅田ニ新田殿タマラス、真野ノフケノ下ノ海道ニテ軍ナラス、今堅田ノキ、海津ヘアカリ、ツルカヘノタキマフ、足利殿、堅田船八艘ニテ、カイツヘ追懸給ニ、八艘ノ名センアシキトテ、サゝ船一ソウ、サゝノハニテツクリ、九艘ト号シテオシカケラル」(『本福寺跡書』)との史料も残るが、越前へ向かった御所方は親王二人、左衛門督実世、左近衛中将義貞、千葉介貞胤や名和義高等多くの軍勢が動いており、沿岸を進めば必ず合戦が起こることは予想され、おそらく恒良親王一行は、日吉社から横川までは叡山中を行軍して横川から堅田へ下り、夜陰に乗じて堅田から船で「海津(高島市マキノ町)」まで水行し、海津から敦賀への官道が走る「荒茅」へ向かったのではなかろうか。なお、恒良親王一行は「荒茅の中山にて大雪に逢て、軍勢とも寒の為に死す」(『梅松論』)というが、鎌倉初期と比較して平均気温が5℃程低下していた当時(石谷完二氏他「鹿児島県における感染症の流行と気候変動の影響について」『鹿児島県環境保健センター所報 第16号』所収)、旧暦十月上旬(新暦十一月上旬)でも行軍が困難になるほどの大雪が降った可能性は十分考えられる。
なお、千葉介貞胤は「木芽峠」で猛烈な吹雪に遭遇し、足利方の越前国守護職・足利尾張守高経に取り囲まれて降伏したという(『太平記』)。ところが、貞胤は実際は後醍醐上皇が吉野に入っていることが確実な12月25日頃にも吉野方として活動しており(ただし貞胤の在所は不明)、上皇が吉野に入ったことが記されている「勅書并綸旨回状」を陸奥国の北畠顕家に回送している(延元二年正月廿五日「北畠顕家書状写」『楓軒文書纂九十所収白河証古文書』)。翌延元2(1337)年正月25日、顕家は「千葉との」へ返書を認め、「当国擾乱之間、令対治彼余賊、忽可企参洛候、去比新田方申送候間、先達致用意、于今延引失本意候」と、以前「新田方」には足利方を追罰して上洛する旨を伝えてその準備をしていたものの、今において延引する結果を歎き、上洛は難しい状況を伝えている。ただし、その後の千葉介貞胤の動向は不明であり、『太平記』に見られるように、貞胤は風雪の中で進退窮まり「木芽峠」で足利方に降伏したのかもしれない。子の氏胤が建武4(1337)年に京都で生まれた(『本土寺過去帳』より逆算)とみられることから、貞胤は建武4(1337)年早々には上洛していたのだろう。「木芽峠」が敦賀と越前国府(尾張守高経はここに駐屯していたか)の中間に位置し、敦賀を逃れた義貞が駐屯したとされる「杣山城」にほど近いことから、翌建武4(1337)年3月の金崎城陥落後、杣山城へ向かう最中に、越前国府から南下してきた足利尾張守高経の軍勢に降伏したのではなかろうか。
一方、先帝後醍醐は、恒良親王や新田義貞を東坂本から越前国へ遁れさせた翌10月10日、東坂本から洛中花山院御所に還御し、おそらく「御和談」の条件であったと思われる先帝保持の「三種の神器(真物は神璽以外は越前国へ遷っていたと思われる)」御譲の準備が進められたのだろう。
尊氏は後醍醐還御から二日後の10月12日、「新田右衛門佐義貞没洛北国之間、可誅伐之由」を記した御教書を信濃国「守護代小笠原余次兼経、舎弟与三経義」に下した(守護貞宗入道は近江国出兵中)。このタイムラグは足利方が義貞等の足取りを把握するための時間であったと思われ、10月17日には足利直義が越後国御家人の「三浦和田四郎殿(和田茂実)」に「新田義貞以下凶徒等落散候處、趣北国云々、早馳向要害、可有誅伐」(建武三年十月十七日「足利直義御教書」『三浦文書』)を命じた。
足利尊氏からの御教書を受けた信濃守護代小笠原兼経・経義兄弟は、ただちに国内の武士等に軍勢催促し、11月中(11月1日頃)には「府中并仁科、千国口」に発向している(建武三年十一月「市河親宗着到状」「市河親宗軍忠状」『市河文書』)。信濃国守護代兼経はその大将軍を「信州惣大将軍村上源蔵人殿(村上信貞)」と定めて「為越後国凶徒対治」を行った。信濃国御家人の「市河孫十郎親宗」は守護代兼経のもとに着到したのち、11月3日までに「村上源蔵人殿」に属して「被追落守護目代并凶徒等」し、「村上源蔵人殿」に「同道参洛」している(建武四年三月「市河経助軍忠状」『市河文書』)。なお、村上源蔵人信貞は翌建武4(1337)年3月までの間に「村上河内守信貞」(建武四年三月「市河経助軍忠状」『市河文書』)とあるように河内守に任じられている。
そして翌建武4(1337)年正月1日、「為新田義貞誅伐」のため「高越後守殿(高越後権守師泰)」が大将軍となった大掛かりな追討軍が京都を進発した(建武四年三月「市河経助軍忠状」『市河文書』)。「信州惣大将軍村上源蔵人殿(村上信貞)」も師泰勢に属し、信濃国から従軍の「市河左衛門十郎経助」も「村上河内守発向金崎城」している。
そして、正月18日には師泰勢が金崎城に攻め寄せ、麾下の村上信貞勢や島津孫三郎左衛門尉頼久勢等が「押寄彼城大手脇堀際、終(日)合戦」(『薩藩旧記』)している。2月12日には「自城内凶徒等打出時致散々戦」い(建武四年三月「市河親宗軍忠状」『市河文書』)、2月16日には金崎城に攻め寄せるが、「新田、脇屋、苽生以下凶徒」「新田、脇屋、苽生左衛門尉等」(建武四年三月「市河経助軍忠状」『市河文書』)が金崎城の後詰として寄せ来たため、村上信貞が手勢を二手に分け、市河経助は「村上四郎蔵人房義」の手に属して「登向山上」り、「悉追返凶徒等」した(建武四年三月「市河経助軍忠状」『市河文書』)。
3月2日には「大手木戸口」で合戦が行われ、「仁木伊賀守(仁木頼章)」は「久下弥五郎殿(久下重基)」の塀際での戦功を賞した(建武四年三月五日「仁木頼章直書」『久下文書』)。翌3日夜もまた大手での戦いが行われ、5日夜には「諏訪部三郎入道信恵」が「片山孫三郎、中澤神四郎等」とともに「大手矢倉下、終夜致合戦」し「攻入城内」(建武四年三月「諏訪部入道信恵軍忠状」『三刀屋文書』)し、「島津三郎左衛門尉頼久」の手に属する「莫弥次郎太郎入道円也」らが「打入城内、致散々太刀打、切臥御敵一人畢」(『薩藩旧記』)など攻勢を続け、3月6日未明には「責入城内、令誅伐凶徒等畢」(建武四年三月「市河親宗軍忠状」『市河文書』)、「自大手責入城内、及至極合戦」して「焼払対治」(建武四年三月「小見経胤軍忠状」『市河文書』)し、村上信貞勢は占拠した金崎城の「大手一木戸口警固」(建武四年三月「市河親宗軍忠状」『市河文書』)している。
金崎城は西面を海が洗う難攻の要害であったが、足利方に取り囲まれて補給がままならず「兵粮尽て後ハ、馬を害して食とし、廿日あまり堪忍しけるとそ承る、生なから鬼類のみとなりける」(『梅松論』)という状況に置かれており、3月6日、金崎城はついに「没落」した(『梅松論』)。「新田、脇屋」らは城を出て戦っていたためか「先立って囲みを出」て遁れていたが、「子息越後守自害しけれは、一宮も御自害あり、春宮をハ、武士むかへとり奉りて洛中へ入進せけり」(『梅松論』)といい、一宮尊良親王、新田越後守義興ら主だった人々は自刃を遂げ、春宮恒良親王(新帝)は捕らわれの身となり京都へ戻された。この金崎城合戦では義貞腹心の一族「貞政一井孫三郎、従五上、民部権大輔」とその子「政家左将監、従五下」の討死が伝わるように(『尊卑分脈』)、「新田一族十余人、都合百余人被切懸云々」(『鶴岡社務記録』)と伝わる。越前国守護は足利尾張守高経であるが『太平記』以外に活躍は伝わっていないが、左馬頭直義は、6月13日に「興福寺雑掌興賀申、越前国木田庄事」につき、「当庄庄官以下百姓等」が先例に背く課役を行ったという主張が事実であれば「停止非分沙汰、可全寺用」とすべきことを「右馬頭殿(足利高経)」に命じており(建武四年六月十三日「足利直義御教書」『前田家所蔵文書』)、高経は越前国守護として検注を行う権限を得ていたことがわかる。
翌3月7日、尊氏は「島津上総入道殿」や「沙弥(一色範氏入道)」ら鎮西守護家や大将軍らに「越前国金崎城凶徒事、今月六日卯時、義貞已下、悉加誅伐、焼払城郭了」(『薩摩文書』『龍造寺文書』他)の御教書を伝え、管国の「地頭御家人等」にこの旨を伝えるよう命じている。当時、吉野方は征西将軍宮の懐良親王が大将軍として派遣され(伊予に駐屯)、肥後国には先行して南郡に「三条侍従泰季」(延文二年五月「禰寝清増軍忠状」『薩藩旧記』)、北郡に「宮中将(三位左中将宗治か)」(『征西将軍宮譜』)が遣わされ、3月17日には三条侍従泰季がおそらく肥後南郡から薩摩国に下着して綸旨を伝えているように、吉野方の鎮西方面への注力が見られる。こうした流れに対し、新田義貞没落を伝えることで鎮西足利勢の士気を上げる狙いもあったろう。なお、10月には豊前国に「新田禅師并大友式部大輔(大友貞世)」が宇佐郡に展開するなど(建武四年十月廿一日「丹波有世軍忠状」『西行雑録』)、新田一族の鎮西出現が見られる。3月の越前没落後に鎮西の新田党を頼って下向した一族かもしれない。
3月6日、越前国金崎城から落ちた義貞は「為援窮城、先出金前入杣山」(『気比宮社伝旧記』)とあり、杣山城に雌伏したのだろう。3月13日に「南保右衛門蔵人(南保重貞)」の軍功注進状を受け取り、翌14日に重貞が「佐々木十郎左衛門尉忠清」とともに「引籠城郭」して防いだことを賞し、「守護代職所宛給」た佐々木忠枝に合力するよう命じている(延元二年三月十四日「新田義貞軍勢催促状」『三浦文書』)。
このような状勢の中で、光明天皇の関白たる近衞経忠が「四月五日、出奔吉野宮」という事件が起こる(『公卿補任』)。実は経忠は建武3(1336)年冬には「被辞申御当職」(『園太暦』)するも(「不及上表歟」といい、古く九条兼実同様に上表無き辞職であったか)、「不許」(『続史愚抄』)であったという。しかし経忠は関白辞任を既成事実とし、翌建武4(1337)年正月1日の殿下拝礼を行わなかった。経忠は後醍醐天皇が血統の近い(基嗣父の近衞経平と後醍醐天皇は従兄弟)従弟・近衞基嗣ではなく、自分を右大臣、内覧に引き立て重用してくれた恩義があり、光明朝での関白宣旨には呵責があったのかもしれない。
亀山天皇―+―後宇多天皇――後醍醐天皇
|
|
+―皇女
∥――――――近衞経平―――近衞基嗣
∥ (左大臣) (関白)
近衞基平―――近衞家基
(関白) (関白)
∥
∥――――――近衞家平―――近衛経忠
鷹司兼平―――女子 (関白) (関白)
(関白)
経忠出奔を受けた京都朝廷は翌4月6日、経忠を「止関白」すると、4月16日の詔で「元前左大臣」の経忠のライバルであった近衞基嗣を関白にするとともに「氏長者」の宣旨を下し、4月23日「牛車兵仗已下宣下」された(『公卿補任』)。
4月10日には「紀州凶徒蜂起之由、依有其聞」のため、細川兵部少輔顕氏(和泉国守護か)は弟で鶴岡八幡宮寺若宮別当「三位阿闍梨皇海」(建武四年五月十二日「細川顕氏感状」『日根野文書』)を大将軍として紀州へと馳せ使わした(建武四年四月十日「細川顕氏軍勢催促状」『日根野文書』)。この細川顕氏の軍勢催促に応じた一人「日根野左衛門入道道悟(日根野盛治入道)」は一族を率いて4月26日に「奉属紀州御大将御手」し、29日に「馳向仁儀庄西光寺城郭」へ馳せ向かい合戦した。5月1日にはこの西光寺城郭を攻め落として焼き払い、「追落凶徒等」という軍功を挙げている(建武四年五月「日根野盛治入道軍忠状」『日根野文書』)。紀伊国では6月、吉野方の人物の指示を受けた「武蔵大夫将監」が「尊氏直義以下朝敵等誅伐事、被下綸旨之間、所揚義兵」し、6月15日に「淡輪助太郎殿(淡輪重氏)」に味方となるよう命じている(延元二年六月十五日「武蔵大夫将監書下」『淡輪文書』)。ただし、淡輪重氏は応じていない。彼に軍勢催促を指示した「武蔵大夫将監」はその名からおそらく先代一門の旧和泉守護右馬権頭茂時(連署)の子・武蔵左近将監貞熈と考えられ、紀伊国でも先代北条氏は吉野方と強固に結びついていた様子がみられる。
畿内近辺では主に洛南から摂津、和泉、河内、紀伊、大和国での戦闘が続いていたが、足利方の優勢が目立つ展開であった。ところがこのような中、関東に再び鎮守大将軍北畠顕家の軍勢が迫っていた。吉野の後醍醐上皇の命を奉じた、奥州からの二度目の西上であった。
延元元年(1336)年3月、陸奥守顕家は京都を離れ、奥州への帰途についた。足利尊氏の鎮西落ちによって脅威が遠のいたためであろう。
当時奥州では、顕家の家人と思われる広橋修理亮経泰が顕家の留守を預かり、白河結城一族や南部一族とともに「大将軍足利竹鶴殿(足利兼頼)」らと鎬を削っていた。前年末、陸奥国府から西上した陸奥守顕家を追って「斯波殿(足利尾張弥三郎家長)」が鎌倉へ下ったが、行方郡小高城の相馬孫五郎重胤や一族の相馬五郎胤康らも家長に同道して鎌倉に駐屯した。しかし、海道筋の吉野方に対峙する兵力の不足を懸念したか、「斯波殿御教書并親父重胤事書」の指示に従い、「惣領代子息弥次郎(相馬弥次郎光胤)」が一族を率いて3月8日に小高へ帰還した。するとたちまち国司勢が「押寄楯」したため、これを撃退する(建武三年三月三日(十三日?)「相馬光胤着到状」『相馬家文書』)。
●建武三年三月三日着到(『相馬家文書』)
| 名前 | 備考 |
| 相馬九郎胤国 | |
| 相馬九郎五郎胤■ | 相馬胤国の子 |
| 相馬与一胤房 | 相馬胤国の子か |
| 相馬七郎時胤 | 不明 |
| 相馬五郎顕胤 | 相馬七郎時胤の子 |
| 相馬孫次郎行胤 | 相馬余一通胤の子で、惣領重胤の従弟 |
| 相馬六郎長胤 | 相馬五郎胤康の弟 |
| 相馬七郎胤春 | 相馬五郎胤康の弟 |
| 相馬十郎胤俊 | 相馬五郎胤顕十男、相馬五郎胤康叔父 |
| 相馬五郎泰胤 | 相馬胤俊の子か |
| 相馬孫次郎綱胤 | 不明 |
| 相馬小四郎胤時 | 相馬孫次郎綱胤の子か |
| 相馬四郎良胤 | 相馬孫次郎綱胤の子か |
| 相馬小次郎胤■(胤政) | 不明 |
| 新田左馬亮経政 | 千倉庄代官か。新田岩松泰治の子 |
| 相馬五郎胤経 | 不明。相馬五郎胤顕の子に孫六胤兼がおり、その子か |
| 相馬又五郎胤泰 | 相馬五郎胤経の子か |
| 相馬弥六胤政 | 相馬五郎胤経の子か |
| 相馬孫六郎盛胤 | 不明 |
| 相馬孫九郎胤通 | 不明 |
| 相馬小次郎胤顕 | 不明 |
| 相馬孫四郎胤家 | 相馬小次郎胤顕の子か |
| 相馬孫次郎胤義 | 不明 |
| 相馬小次郎胤盛 | 相馬孫次郎胤義の子か |
| 相馬孫五郎長胤 | 不明 |
| 相馬又五郎朝胤 | 相馬孫次郎行胤の子。惣領重胤の女婿 |
| 相馬孫七郎胤広 | 不明 |
| 相馬九郎二郎胤直 | 相馬九郎胤国の子? |
| 相馬満丸 | 不明 |
| 相馬千代丸 | 不明 |
| 相馬小五郎永胤 | 不明 |
| 相馬弁房円意 | 不明 |
| 相馬彦二郎胤祐 | 不明 |
| 相馬弥次郎実胤 | 不明 |
| 相馬又七胤貞 | 不明 |
| 相馬小四郎胤継 | 不明 |
| 武石五郎胤通 | 武石四郎左衛門入道道倫の子息。道倫は「曰理郡坂本郷、至正和年知行」という |
| 伊達与一高景 | |
| 伊達与三光義 | 伊達与一高景の弟か |
| 相馬禅師房妙圓 | 不明 |
| 相馬道雲房胤範 | 不明 |
| 標葉孫三郎教隆 | |
| 莚田三郎光頼 | 長江与一景高女子代 |
| 相馬松王丸 | 不明 |
| 青田孫左衛門尉祐胤 | 相馬助房家人 |
3月13日には、宇多庄で「黒木入道一党、福島一党、美豆五郎入道等、引率数多人勢」が国司勢に応じたため、「惣領代(相馬弥次郎光胤)」や「相馬六郎長胤」ら相馬一族が馳せ向かい、16日に「白川上野入道家人等、宇多荘熊野堂楯築」を鎮圧する(建武三年三月十七日「相馬光胤軍忠状」『相馬家文書』)。
●建武三年三月十六日宇多庄熊野堂合戦軍忠(『相馬家文書』)
| 名前 | 主人 | 軍忠 | 備考 |
| 相馬九郎五郎胤景 | 分取二人 | ||
| 須江八郎 | 相馬弥次郎光胤 |
分取一人 (白川上野入道家人六郎左衛門入道) 頭二 | |
| 相馬小次郎胤顕 |
生捕(白川上野入道家人小山田八郎、 中間四郎三郎) | ||
| 木幡三郎兵衛尉 | 相馬小次郎 | 分取一人 | |
| 相馬彦二郎胤祐 | 分取一人 | ||
| 田島小四郎 | 新田左馬亮経政 | 分取一人 |
新田経政は岩松家庶流で千倉庄代官か。 参戦した「経政代」の田島小四郎は、 経政の子・小四郎経栄。 |
| 標葉孫三郎教隆 | 分取一人 | 標葉荘地頭標葉氏の庶家 | |
| 東條七郎衛門尉 | 相馬助房 | 分取一人、被疵畢 | |
| 木幡二郎 | 相馬弥次郎光胤 | 討死 |
得川頼有――――娘
∥
⇒相馬義胤―土用御前 ∥―――――+―岩松政経――――岩松経家―+―岩松直国==岩松満国
(五郎) ∥ ∥ |(下野太郎) (兵部大輔)|(土用王)
∥ ∥ | |
∥―――+―岩松経兼 +―とよ御前 +―岩松泰家――岩松満国
∥ |(遠江五郎) |
足利義純――岩松時兼 | |
(太郎) (遠江守) +―とち御前 +―あくり御前
|(尼真如)
| ∥
| ∥―――――――土用王御前===岩松直国
| ∥ (尼妙蓮) (土用王)
| 藤原某
|
+―岩松経国――――岩松政国――――岩松泰治―――岩松経政――田島経栄
(左馬亮) (小四郎)
さらに3月22日から24日にかけて、広橋修理亮経泰率いる国司勢が小高城に攻め寄せたため、相馬一族はこれを撃退。3月27日には国司方の「標葉荘地頭」を討つべく、「相馬九郎五郎胤景」以下の相馬一族が攻め下り、「相馬六郎長胤」「舎弟七郎胤春」が「標葉弥四郎清兼、同舎弟弥五郎仲清、同舎弟六郎清信、同舎弟七郎吉清、同小三郎清高、同余子三郎清久等」を召し取るなど、海道筋では激しい戦闘が行われていた。
こうした中で、東海道を下向してきた「奥州前司顕家卿」は鎌倉に迫り、これを受けて鎌倉を警衛していた「斯波陸奥守殿于時弥三郎殿(斯波家長)」は4月16日、手勢を率いて鎌倉西の「片瀬河」まで出征し、川を挟んで激突した(年月未詳「相馬新兵衛尉胤家代恵心申状」『相馬岡田雑文書』)。この「相模国片瀬河」の合戦には相馬孫五郎重胤、相馬五郎胤康(相馬岡田氏祖)ら相馬一族も加わり、相馬五郎胤康は片瀬川で討死を遂げた。また、相馬孫五郎重胤も「於法花堂下自害」と見えることから、片瀬川合戦に敗れたのち鎌倉へ戻り、右大将家法華堂下で自刃したとみられる(建武四年正月「相馬松鶴丸軍忠状」『相馬文書』)。また「犬懸谷坊舎」は「若御料(足利義詮)」の御座所として破壊された(「僧正隆舜申状案」『醍醐寺文書』)。斯波家長は遁れたが、北畠勢は鎌倉を占拠することなくそのまま奥州へ下向したとみられ、斯波家長は鎌倉に帰還している。
陸奥国司勢は4月24日、宇都宮城に下着し、相馬六郎胤平が「同月廿四日、御下向之由承及候之間、宇都宮馳参候」といい(延元元年八月廿六日「相馬胤平軍忠状」『相馬家文書』)、これまでの軍忠を賞されて、26日に鎮守大将軍「軍監有実」を通じ、相馬六郎胤平を「被任左衛門尉之由、可被挙申京都也、且可存其旨之由、鎮守大将軍仰所候也」とした(延元元年八月廿六日「相馬胤平軍忠状」『相馬家文書』)。惣領孫五郎重胤及び有力庶家の五郎胤康が鎌倉で落命した上、相馬一族には衛門府補任者がいない現状での胤平の左衛門尉推挙は、吉野方から胤平が新たな相馬惣領家に認められたということになろう。
陸奥国司勢はその後も国府へ向けて海道筋を北上し、5月8日には「名須城」、5月22日には「田村館」、そして5月24日には「小高城」を攻め落とし、城を守っていた「光胤并一族相馬六郎長胤、同七郎胤治、同四郎成胤、令討死訖」(暦応二年三月廿日「相馬松鶴丸軍忠状」『相馬家文書』)した。この直前には国司勢が迫る中で、惣領代弥次郎光胤は、「光胤又存命不定」と討死を覚悟して、5月20日、甥の松鶴丸(惣領親胤嫡子)を養子として所領を譲った上(建武三年五月廿日「相馬光胤譲状」『相馬家文書』)、ほとんどの一門を付けて城から落としており、後日、多くの生き残った一族とともに相馬家再興を成し遂げることができた(長胤子息の孫鶴丸、胤治子息の竹鶴丸、成胤子息の福寿丸も松鶴丸とともに遁れている)。
●建武三年五月廿四日小高城討死(『相馬家文書』)
| 名前 | 主人等 | 備考 |
| 相馬弥次郎光胤 | 相馬重胤二男 | 惣領代 |
| 相馬六郎長胤 | 相馬胤康舎弟 | 相馬岡田一族 |
| 相馬七郎胤治 | 長胤舎弟 | 相馬岡田一族 |
| 相馬四郎成胤 | 長胤舎弟 | 相馬岡田一族 |
| 相馬十郎胤俊 | 長胤叔父 | 相馬岡田一族 |
| 田信彦太郎 | 光胤家人 | 若党 |
| 吉武弥次郎 | 胤俊家人 | 若党 |
| 田中八郎三郎 | 長胤家人 | 若党 |
| 松本四郎 | 光胤家人 | 若党 |
ところが顕家が多賀国府に帰国しても、陸奥国の騒乱は止まず、延元2(1337)年正月8日、「陸奥凶徒蜂起、親王并顕家卿、入伊達郡霊山」(『元寇日記裏書』)という。「同四年ノ春、奥州ニモ尊氏ニ志有ケル者有テ、合戦ヲ始ム、顕家卿打負テ、加賀国府ヲ落、当国伊達郡ニ霊山ト云寺ニ籠リケル」(『保暦間記』)とあり、顕家らは合戦に敗れて多賀国府を退き(多賀城市)、浜通りと陸奥大道の間にそびえる霊山(伊達市霊山)の山頂に新たな臨時御所をかまえた。
この顕家の国府没落は、前年10月10日に東坂本で先帝後醍醐は事実上降伏して京都に遷され、光明天皇が皇位にある中、12月21日、後醍醐上皇は京都花山院邸を脱出して吉野へ遁れた事によって、12月中に上皇派の人々は軒並み解官され、北畠顕家も「権中納言」「陸奥(権)守」「鎮守大将軍」の官職を失った(『公卿補任』)。10月以降の上方における御所方劣勢の波は、遠く奥州にも及び、顕家の求心力にも大きな影響を与えたのではあるまいか。顕家の陸奥権守解任は御所方の奥州支配の正当性が失われたことを意味する。国府を放棄して伊達郡霊山まで御所を遷さざるを得なかったのはこうした理由があったと思われる。代わって「陸奥守」に任じられたのが、鎌倉に駐屯する足利尾張弥三郎家長であった(義良親王の陸奥太守停止は伝えられていないが、12月に同時に停止されたのではなかろうか)。
しかし、自らの行動が招いた奥州の惨状を知らない上皇は、12月25日、陸奥国府の顕家に向けて「御勅使江戸修理亮忠重」を遣わし、「相催諸国、重所挙義兵也、速率官軍、可令発向京都、武蔵相模以下東国士卒、若有不応勅命者、厳密可加治罰者也、併相憑輔翼之力、雖廻権■之謀、速成干戈之功者、国家大幸、文武徳善、何事如之哉、大納言入道居住勢州、定委仰遣之歟、坂東諸国悉令帰伏之様、以仁義之道、可施徳化也、道忠以下、各可励忠節之旨、別可被仰含者也」(延元元年十二月廿五日「後醍醐天皇宸簡」『白河結城文書』)と、ただちに奥州から上洛すべきことを命じたのだった。また、上皇に近侍の北畠親房入道もまた、延元2(1337)年正月1日、奥州結城宗広入道の援軍を依頼する「此使節自吉野被差遣」している(延元二年正月一日「北畠親房入道御教書」『結城家文書』)。
さらに上皇は越前新帝(恒良親王)のもとにも「勅書并綸旨回状」を送達しており、これをうけたうちの一人である千葉介貞胤から北畠顕家に「勅書并綸旨回状」が回送されている(延元二年正月廿五日「北畠顕家書状写」『楓軒文書纂九十所収白河証古文書』)。顕家はこの書状に対し、延元2(1337)年正月25日に「千葉との」への返書を認め、「当国擾乱之間、令対治彼余賊、忽可企参洛候、去比新田方申送候間、先達致用意、于今延引失本意候」と、以前「新田方」には足利方を追罰して上洛する旨を伝えてその準備をしていたものの、今において延引する結果を歎いている。しかし、続く「此間、親王御座霊山候処、凶徒囲城候之間、近日可遂合戦候、綸旨到来之後、諸人成勇候、毎時期上洛之時候也」は、「畏れ多くも親王を風雪激しい霊山に移した上、ここも取り囲まれて合戦しているという厳しい状況下で、どうして上洛など考えられようか」という意味にも取れ、顕家の隠された「本意」が感じられる。顕家は他所からも上洛要請の文書を受けているが「勅書并綸旨及貴札」とあって送主は不明である。この返書では明確に「下国之後、日夜廻籌策外無他候、心労可有賢察、恐鬱處披札散鬱蒙候」(延元二年正月廿五日「北畠顕家書状写」『結城古文書写』)と苦言を述べている。
なお、顕家に「勅書并綸旨回状」を送達したのちの千葉介貞胤の動向は不明であり、『太平記』に見られるように、貞胤は風雪の中で進退窮まり「木芽峠」で足利方に降伏したのかもしれない。子の氏胤が建武4(1337)年に京都で生まれた(『本土寺過去帳』より逆算)とみられることから、貞胤は建武4(1337)年早々には上洛していたのだろう。「木芽峠」が敦賀と越前国府(尾張守高経はここに駐屯していたか)の中間に位置し、敦賀を逃れた義貞が駐屯したとされる「杣山城」にほど近いことから、翌建武4(1337)年3月の金崎城陥落後、杣山城へ向かう最中に、越前国府から南下してきた足利尾張守高経の軍勢に降伏したのではなかろうか。
正月26日には、霊山へ通じる東の要衝、宇多川南岸の「宇多庄熊野堂」に、小高落城以来「隠居山林」していた「相馬松鶴丸」が攻め寄せた。熊野堂には「結城上野入道代中村六郎数万騎楯籠」っていたが、相馬松鶴丸以下の相馬一族が打ち散らした(建武四年正月「相馬松鶴丸着到状」『相馬家文書』)。この着到は「式部大夫兼頼年少之間、代官氏家十郎入道々誠、可判形候」して京都に注進された(暦応二年四月廿六日「氏家十郎入道注進状案」『相馬家文書』)。
●建武四年正月二十六日着到(『相馬家文書』)
| 名前 | 備考 |
| 相馬松鶴丸 | 相馬親胤嫡子 |
| 相馬九郎入道了胤 | 相馬九郎胤国か |
| 相馬江井御房丸 | 相馬江井氏 |
| 相馬小次郎胤盛 | 相馬孫次郎胤義の子か |
| 相馬弥五郎胤仲 | 不明 |
| 相馬弥次郎実胤 | 不明 |
| 相馬孫次郎綱胤 | 不明 |
| 相馬五郎顕胤 | 相馬七郎時胤入道の子 |
| 相馬小四郎胤時 | 相馬孫次郎綱胤の子か |
| 相馬五郎泰胤 | 相馬胤俊の子か |
| 相馬又一郎胤貞 | 不明 |
| 相馬小次郎胤政 | 不明 |
| 相馬岡田駒一丸 | 不明 |
| 相馬千与丸 | 不明 |
| 相馬岡田主一丸 | 不明 |
| 相馬孫六郎盛胤 | 不明 |
| 相馬孫次郎入道行胤 | 相馬余一通胤の子で、惣領重胤の従弟 |
| 相馬五郎胤経 | 不明。相馬五郎胤顕の子に孫六胤兼がおり、その子か |
| 武石五郎胤通 | 武石四郎左衛門入道道倫の子息。道倫は「曰理郡坂本郷、至正和年知行」という |
御所方の侍大将・宇都宮公綱の本拠である下野国宇都宮城も足利方の大将「石河孫太郎入道」「澤井小太郎」らが攻めており、2月21日、「石河孫太郎入道」は「下野国茂木郡高藤宮前」に布陣していたところ、「寄来国司方軍勢等数万騎」したため、石河孫太郎入道に属した「伊賀式部三郎盛光代南葉本寂房」が繰り出して合戦したという(建武四年二月廿二日「伊賀盛光代南葉本寂房軍忠状」『飯野八幡宮古文書』)。宇都宮合戦のその後は不明だが、国司方に属していたとみられる「岩城郡国魂太郎兵衛尉行泰」は、3月10日に「自宇都宮、霊山御楯属于当手仁令参上畢」と、霊山へ戻って留守居の唐橋修理亮経泰の手に属している(延元二年十二月「国魂行泰軍忠状」『大國魂神社文書』)。
宇都宮合戦と同日の2月21日、「常州関城」には足利方の「大将蔵人殿(石堂頼房か?)」の軍勢が攻め寄せており、某城を警固していた「相馬孫次郎親胤」は「若党目々澤七郎蔵人盛清」を石堂蔵人の陣に派遣。目々澤盛清は関城を囲む大宝沼を「馳渡絹河上瀬中沼渡戸」して、城将「関民部少輔宗祐」の手勢「追散数百御敵等」し、「焼払数百間在家等了」という(建武四年二月廿二日「相馬親胤軍忠状」『相馬家文書』)。翌2月22日、親胤は石塔義房入道に軍忠の証判を求めている。尊氏に従って上洛、九州陣まで従軍していた親胤は、塔蔵人とともに下野国宇都宮城から常陸国関城の方まで戻っていたことがわかる。その後、相馬親胤や「相馬又五郎朝胤(属惣領親胤手)」らは「大将蔵人殿」に従って「三箱、湯本」を転戦し、4月1日には「標葉八里浜」の合戦、翌4月2日の「標葉庄小丸城口羽尾原」の合戦を経て小高城に入城した(建武四年八月「相馬朝胤軍忠状」『大悲山家文庫』)。
こうした中で、新帝恒良や一宮尊良親王以下、新田義貞らが立てこもっていた越前国敦賀津の金崎城には足利勢が大攻勢をかけており、3月6日に陥落した。当時新田義貞以下の主だった武士は城外で足利勢と交戦・牽制しており、城を守っていた義貞嫡子の越後守義顕と一宮尊良親王は自刃を遂げて城は開かれた。その後、新田義貞は敦賀から北部の「杣山」に遁れている(『気比宮社伝旧記』)。北畠顕家は正月25日、「忽可企参洛候、去比新田方申送候間」と越前国敦賀の新田義貞に自らの上洛の事について伝えており、陸奥国の顕家と越前国の義貞の間には連携が構築されつつあったのではなかろうか(なお、3月6日の金崎城陥落により連携は不可能となったのだろう)。
4月9日、顕家麾下の大将唐橋修理亮経泰は「押寄小高楯」と、行方郡小高城の奪還に攻め寄せた(延元二年十二月「国魂行泰軍忠状」『大國魂神社文書』)。当時の小高城には、3月17日に「為奥州対治御発向」(建武四年三月十七日「伊賀盛光着到状」『飯野八幡宮古文書』)した陸奥守家長麾下の大将、石塔蔵人や中賀野金八郎義長が警衛しており、相馬一族はその麾下にあった。唐橋経泰は小高城に昼夜を問わず九日間にわたって攻め立てたが「相馬小四郎胤時(系譜不明)」ら城将から相当な抵抗を受けて撤退している。なお、相馬朝胤は8月、大将軍の石塔蔵人や中賀野義長ではなく惣領親胤に証判を求めており、石塔蔵人や中賀野義長は宇多庄や標葉郡に出張している最中、明日をも知れぬ戦場の中で急ぎ軍功の一見状を得るためであったのかもしれない。
4月11日、下野国「宇都宮々隠原合戦」があり、足利方では「桃井兵庫助貞直(のちの直常)」が大将軍の一人として攻め立てている。その麾下には「茂木越中弥三郎知政」らが加わっている(建武四年九月十八日「桃井貞直申状」『茂木文書』)。宇都宮は小山、結城と並んで鎌倉と奥州を結ぶ要地であり、激しい鬩ぎあいの地となっていた。
こうした中、吉野朝廷は高倉勘解由次官光房を奏者として、霊山の「結城上野入道」に「殊廻籌策、早速可対治朝敵、且陸奥国司上洛者、其間事殊可申沙汰軍忠之次第、猶以神妙、宜被加其賞者」(延元二年五月十四日「後醍醐上皇綸旨」『白河証古文書』)という綸旨を下している。結城上野入道は当時「為宮御共、参霊山城」していたことがうかがえ、5月14日の綸旨の内容から、顕家はこれ以前に結城宗広入道の霊山入りを報告し、自身の西上の時期についても具体的に記していたと思われる。西上にあたっては、一族の冷泉少将持定、北畠少将家房、春日侍従顕国のほか、唐橋修理亮経泰、結城上野入道、多田木工助入道といった主要な麾下の将を率い、多くの将兵を伴うという、奥州の兵力を減衰させても赴く決意の上洛であったと思われる。留守居の旗印となる人物は不明である。
7月に入ると顕家股肱の「春日侍従、多田木工助入道以下」が足利方の下野国小山城を取り囲んで攻め立ているが(建武四年七月九日「茂木知政軍忠状」『茂木文書』)、これは顕家西上の先陣とみられる。7月4日には足利方の大将軍「桃井兵庫助殿」と「春日侍従、多田木工助入道以下」が「小山荘内乙妻真々田両郷」で合戦、7月8日にも「於常州関城」で桃井勢と春日勢が衝突している。この「陸奥前国司已下凶徒等」による小山城攻めを伝え聞いた「上椙民部大輔殿(上杉憲顕)」は在国の上野国から馳せ参じて合戦に加わっている(建武四年九月三日「足利直義御教書」『上杉古文書』)。
なお、この頃にはすでに顕家の父・親房入道が宗良親王(元天台座主の妙法院宮尊澄法親王)を奉じて吉野から「伊勢国一瀬(度会郡度会町脇出)」(『李花集』上 夏歌)に移っており、7月22日、足利方の「朝敵人畠山上野入道(畠山高国)」「小松次郎」が大勢を以って一瀬の玄関口である「岩出(度会郡玉城町岩出)」に進出したことから、吉野方は「(大将カ)安達掃部助入道」のもと、「加藤左衛門尉定有」らが「井尻口」まで出張って合戦し、翌23日には「玉丸城後責、馳向田辺岡」して軍忠したという(延元二年七月「加藤定有軍忠状」『南狩遺文』)。この吉野方に属した「安達掃部助入道」は先代有力御家人である安達氏末流と思われることから、北条一族は一様に後醍醐上皇方に取り立てられていたと考えられる。
そして、顕家は7月から8月にかけて義良親王を奉じて霊山を出立したとみられ、義良親王は9月に「自霊山、上方宇都宮御上」し、岩城郡の国魂太郎兵衛尉行泰が親王に供奉して宇都宮で大番を勤仕している(延元二年十二月「国魂行泰軍忠状」『大國魂神社文書』)。以降、数か月の間、宇都宮城が義良親王の御所として、奥州勢の本拠地となる。顕家が親王を奉じて西上の途に就いたのは、前回上洛時と同様に顕家が上洛中は国府勢の兵力が確実に減少する中で、十歳の親王を奥州に残す選択肢はないことに加え、今回は親王を奉じた陸奥国府(すでに多賀国府は陥落し霊山に移転)が王化を旗印に奥州を支配する理想が破綻していたことも大きな要因であろう。顕家西上の目的の一つは親王を吉野へ無事に連れ帰ることでもあったのだろう。
10月27日、「為奥州前国司勢春日侍従顕国大将軍、打越当国」し、「小田宮内権少輔治久以下」の吉野方と一手となって、香取海北方沿岸にあたる「南郡大枝口(小美玉市)」まで進出し、足利方の佐竹常陸介義春勢と「小河郷大塚橋」で合戦となっている(建武四年十一月「烟田時幹軍忠状」『烟田文書』)。「大枝郷栗俣村」のあたりは、すでに3月10日には「小田宮内権大輔春久并益戸乕法師等、為張本率数輩凶徒等、出向常州府中」とあり(建武四年八月「野本鶴寿丸軍忠状」『熊谷家文書』)、常陸国府一帯で激しい攻防戦が続いていたことがわかる。国府と官道の確保と思われ、8月までには「前国司勢并小田勢等、率大勢責来」(建武四年八月「野本鶴寿丸軍忠状」『熊谷家文書』)と、奥州勢の一部が小田勢とともに進出し、常陸府中近辺の情勢は奥州勢が優勢であったのだろう。10月27日、春日侍従顕国と小田治久一党は常陸国府付近の鎌倉街道下ノ道を下って鎌倉を目指したとみられる。顕家は前回の上洛時は鎌倉及び東海道を経由していないとみられるが、今回は尊氏嫡子義詮と陸奥守家長が駐在する覇府・鎌倉を壊乱させるべく、鎌倉街道上ノ道及び下ノ道の両道から鎌倉へ進軍したと思われる。両道からの進軍は足利千寿王と新田義貞や中先代の相模次郎時行の鎌倉攻めを踏襲した大規模な攻略戦である。
春日顕国が常陸国へ出立したのち、「親王并顕家卿」は「有西征之義」のため宇都宮を発して上野国へ進軍し、鎌倉街道上ノ道を一気に南下した。上ノ道を進む奥州勢は12月13日に「上野国富根河」で合戦、12月16日の「武州安保原(児玉郡神川町)」で足利方を殲滅(延元三年三月「国魂行泰軍忠状」『大國魂神社文書』)。「武州薊山(本荘市児玉町)」でも合戦し(『元弘日記裏書』)、12月23日、「国司顕家卿打入鎌倉」(『鶴岡社務記録』)した。新田義貞の行軍日数と変わらない十日あまりで鎌倉に攻め込んだことになる。
奥州勢の鋭鋒は、「武蔵上野ノ守護人防キ戦ヘトモ、凶徒大勢ナレハ引退ク」(『保暦間記』)といい、24日及び25日に「鎌倉、飯島、椙本」(『鶴岡社務記録』)、「鎌倉小壷、杉本、前浜、腰越有合戦」(『元弘日記裏書』)と鎌倉内外所々で激しい合戦が行われた。「鎌倉ニ尊氏子息并斯波陸奥守モ有ケリ、是モ小勢也ケル程ニ引退」(『保暦間記』)し、義詮は鎌倉を逃れるも、杉本城に籠城した陸奥守家長は25日、「杉本城落了」(『鎌倉社務記録』)して「斯波家長奥州已下、於杉下城数輩被打」(『常楽記』)と、陸奥守家長は討死を遂げた。
北畠顕家の鎌倉攻めに時をあわせ、建武5(1338)年正月5日までの間に「於下総国登毛郡、普音寺入道孫子令蜂起」と、上総国土気郡に「普音寺入道(北条基時)」の「孫子(左馬助友時か)」が挙兵している(「室原氏」『相馬市史料資料集特別編 衆臣家譜 六』:岡田清一「近世のなかに発見された中世 ―中世標葉氏の基礎的考察―」『東北福祉大学研究紀要 第三十四巻』)。友時は1年半前の建武3(1336)年8月25日に洛南の御所方として足利方と合戦した「八幡路大将両人鑑巌僧都、越後松寿丸」(建武三年八月廿五日「足利尊氏御教書」『勝山小笠原文書』)の大将「越後松寿丸」とみられるが、敗れたのち関東へ逃れたのだろう。土気城の「普音寺入道孫子」を攻めたのは、陸奥海道筋の「大将軍中賀野八郎殿」であり、鎌倉街道下ノ道から鎌倉へ向かった春日侍従顕国を追撃していたのだろう。「普音寺入道孫子」は土気城を遁れると、北畠顕家に合流してともに西上したとみられる。傍証はないが『太平記』においては、相模次郎時行が北畠顕家とともに鎌倉に攻め入ったとあり、「普音寺入道孫子」は時行に合流して上洛の途についた可能性があろう。
この鎌倉陥落の一報は翌建武5(1338)年正月4日、飛脚により「奥州国司責入鎌倉之間、斯波以下引退由」が京都へ伝えられた(『建武三年以来記』)。また正月2日、「顕家卿出鎌倉而趣海道」し、三島を経て、正月12日には遠江国「橋本マテ責登」った(『瑠璃山年録残篇』)。正月4日に鎌倉陥落の一報を受けた足利方は驚愕しただろう。軍事を司る左馬頭直義は所々に手配し、まず高参河守師冬を東海道に派遣する。さらに正月28日には園城寺に先だって「勢多橋本警固」を命じたにも拘わらず「無其用意云々、招罪科歟、所詮可致厳密沙汰」(建武五年正月廿八日「足利直義御教書」『色々証文』)と警告し、さらに翌日にも奉行人「白井八郎左衛門尉(白井八郎左衛門尉宗明)」を遣わして「勢多橋警固事、度々被仰之處、無沙汰之由有其聞」であり、「早不廻時刻、打寄橋本、且注申事躰、且無昼夜之界、厳密可被致沙汰」と厳命しているように(建武五年正月廿九日「足利直義御教書」『園城寺文書』)、混乱の極みにあった。なお、直義が派遣した奉行人「白井八郎左衛門尉」と千葉氏流白井氏との関係は全く不明。
奥州勢の進軍は早く、正月21には尾張国に攻め入り「陸奥国司顕家勢、已責入尾張国黒田宿云々」(『建武三年以来記』)とあり、正月24日から28日にかけては「美濃国阿時河赤坂」(延元三年三月「国魂行泰軍忠状」『大國魂神社文書』)及び「美濃国青野原」(建武五年四月「茂木知政軍忠状」『茂木文書』)、「美濃国洲俣河」(『建武三年以来記』)で合戦があった。正月28日の青野原合戦では、鎌倉合戦で奮戦した足利方の「茂木越中弥三郎知政」が「分取以下軍忠」し、奥州の「標葉四郎左衛門清隆」が追撃していることから(「室原氏」『相馬市史料資料集特別編 衆臣家譜 六』:岡田清一「近世のなかに発見された中世 ―中世標葉氏の基礎的考察―」『東北福祉大学研究紀要 第三十四巻』)、関東・奥州の鎌倉方の追撃があったことがわかる。そして、尾張や美濃の合戦で「国司勢ウチマケテ伊勢国落」(『瑠璃山年録残篇』)とあり、具体的には「二月三日、自垂井宿落勢州」(『建武三年以来記』)とあるが、「二月一日、御敵伊勢路落」(建武五年三月「小佐治基氏軍忠状」『小佐治文書』)とあるように、2月1日に伊勢に落ちたようである。顕家はまず義良親王を吉野へ移すべく奈良を占拠したのち、河内和泉の楠木党等と協働での京都攻略を画策したのではなかろうか。
顕家率いる奥州勢は2月14日と16日には「伊勢国河又河口」(延元三年三月「国魂行泰軍忠状」『大國魂神社文書』)で足利方と合戦し、「標葉四郎左衛門清隆、去二月十六日、伊勢国小屋松合戦於搦手致軍忠」(「室原氏」『相馬市史料資料集特別編 衆臣家譜 六』:岡田清一「近世のなかに発見された中世 ―中世標葉氏の基礎的考察―」『東北福祉大学研究紀要 第三十四巻』)と奥州足利勢も追撃していたことがわかる。その後、奥州勢は「伊賀を経て、大和に入、奈良の京になんつきにけり」(『神皇正統記』)とあることから、奥州勢は上洛に当たっての通常の伊勢ルートを進軍したと考えられ、鈴鹿関(亀山市関町)を経由して伊賀に入り、木津川を遡って南都の北側に布陣したと思われる。「近江国大原小佐治右衛門三郎基氏」は、2月1日に顕家らが伊勢路へ向かったことを聞き、翌2月2日には「馳向鈴鹿山、数十ケ日警固仕」ったという(建武五年三月「小佐治基氏軍忠状」『小佐治文書』)。ただ小佐治基氏は2月13日には「近江三郎殿」の手に属して近江国甲賀郡の「鮎河弥九郎已下凶徒等」を討つために鈴鹿山を離れており、奥州勢との合戦はなかった。
南都にはすでに正月6日には足利方から「南都警固」の兵が遣わされ、高武蔵権守師直、高参河権守師冬、上杉伊豆前司重能らに加え、2月5日には「上杉左近大夫将監(上杉頼成)」が大将として派遣されるなど、足利勢の警衛は万全の状態にあった。2月21日には「将軍方武士、発向于辰市合戦、宮方辰市没落」と、南都最南端に吉野方が攻め寄せ、これを南都警衛の足利方が防衛して奥州勢が敗れたという。前中納言光継が「二月日、南都合戦場客死」(『公卿補任』)とみえるが、二位中納言光継は上皇側近であることから吉野方大将軍の一人であったと推測され、2月21日に奈良南部を攻めたのは吉野から攻め寄せた二位中納言光継らの勢力であったのだろう。
続いて2月28日、顕家率いる奥州勢が奈良に攻め入り「奈良合戦」(延元三年三月「国魂行泰軍忠状」『大國魂神社文書』)となるが、ここでも関東からの「茂木越中弥三郎知政」が「南都合戦」で奮戦して「被射乗馬」れ負傷しており(建武五年四月「茂木知政軍忠状」『茂木文書』)、足利方の関東勢がなおも奥州勢を追撃していたことがわかる。奥州勢は南都足利勢と関東勢に挟撃される形になっていたのだろう。
奥州勢の奈良での戦闘は「西路法華寺後」「自手搔小路責入奈良中」「東大寺天開門」「奈良坂東山」など奈良北部一帯で行われていることから、21日の南部合戦とは異なり、奥州勢は北部から奈良市中に攻め入ったことがわかる。この「奈良合戦」は結局奥州勢の敗北に終わり「追落」されているが、南北からの奈良攻めが2月21日と28日という近日であることから、本来は吉野勢と奥州勢のよる南都挟撃が想定されていたのかもしれない。奥州勢は伊勢に入ってから奈良攻めまで十日以上もかかっており、奥州勢に何らかの支障があった可能性があろう。
奈良の攻略を断念した顕家らは「奈良合戦不利、親王入御吉野、顕家卿発向河内国」(『元弘日記裏書』)とあり、旧都明日香を南下して当初の目的の一つであった義良親王の吉野帰還を果たした。その後、自身は河内へ向かっているが、そのルートは判然としない。ただ、3月8日、顕家は「河内国古市河原」(延元三年三月「国魂行泰軍忠状」『大國魂神社文書』)で足利勢と合戦していることから、関屋から生駒山地を抜けて河内国古市に入り、石川の河原である「古市河原」での合戦になったのではなかろうか。顕家は河内国の楠木一党との連携を図り、八幡、桂方面からの上洛を企図したものとみられる。
すでに3月8日の「天王寺合戦」で足利方の細川顕氏らは「被責落武士等引退京都了」(『官務記』)しており、敗残兵が入洛すると「京中動乱、不能左右、恐怖無極者也」(『官務記』)という大混乱に陥った。天王寺の陥落は渡邊津を失うことも意味し、山崎や八幡、桂、鳥羽方面への影響も甚大となる事から、左馬頭直義は翌3月9日、雨の中、自ら三条坊門邸を出立し「為発向天王寺進発、今日著東寺了」(『官務記』)した。それに伴い、光明天皇は光厳上皇とともに内侍所を奉じ、「寅終刻、有行幸於三条坊門第」(『官務記』)した。ここには同日「等持院殿令三条坊門万里小路第給」(『建武三年以来記』)とあり、足利尊氏も移っている。「件此天下為穢中」(『園太暦』)とみえるが、北畠顕家の危難が去った4月8日に土御門東洞院皇居に「御帰座」(『建武三年以来記』)とあることから、事実上の避難であろう。
顕家は3月8日当時は「河内国古市河原」にあり、楠木党の和田左兵衛尉正興らが丹下城を攻めるなど、連携して河内国の足利勢を打ち破りながら天王寺へ向かい、細川顕氏を排除した天王寺へ入っている。その数日後、顕家は「京都御上」のためさらに北上して3月12日に「男山」へ進出(建武五年閏七月「野上資頼軍忠状」『岡本文書』)。奥州勢は淀川向こうの「洞多和」にも展開して京都を窺った(暦応元年十月「朝山知長軍忠状」『祇園執行日記背書』)。
翌3月13日、奥州勢は高武蔵権守師直ら南都足利勢と男山周辺で合戦(八幡合戦)し、ここでも茂木知政は「被射乗馬等」ている(建武五年四月「茂木知政軍忠状」『茂木文書』)。この合戦には八幡から摂津周辺の地理を熟知する武田信武勢が足利方の精鋭として馳せ加わっており、13日には「馳向八幡、於洞塔下致至極合戦、追散凶徒等畢」(建武五年三月廿六日「逸見有朝軍忠状」『小早川文書』)といい、八幡から対岸の山崎付近を縦横に戦っている様子がうかがえる。奥州足利勢の標葉四郎左衛門清隆は13日の「八幡合戦於搦手致忠節」(「室原氏」『相馬市史料資料集特別編 衆臣家譜 六』:岡田清一「近世のなかに発見された中世 ―中世標葉氏の基礎的考察―」『東北福祉大学研究紀要 第三十四巻』)といい、おそらく中賀野八郎義長の手に属していたのだろう。
3月14日、奥州勢は「八幡凶徒没落」とあり、足利勢に敗れて摂津国の「渡野辺、天王寺」に退いている(延元三年三月「国魂行泰軍忠状」『大國魂神社文書』)。15日の摂津国渡辺津にある「一王子(現在の窪津王子)」の南に広がる松原周辺では激しい戦闘があり(建武五年三月「成田重親子息弥王丸軍忠状」『池田文書』)。渡邊津合戦で足利方の大将軍上杉修理亮憲藤が討死を遂げている(『上杉系図大概』)。
16日には奥州勢を追撃してきた足利方の大将軍高師直らと天王寺の南「阿倍野」で戦い、「攻入天王寺致合戦」しているが(建武五年閏七月「岡本良円軍忠状」『岡本文書』)、顕家麾下と思われる「新田西野修理亮之手者」が岡本観勝房良円に生け捕られている。顕家率いる奥州勢に上野国新田荘西野村(太田市藪塚町西野)を本貫とする新田西野氏が加わっているのは、顕家が西上途上、上野国を経由した際に加わった可能性が考えられよう。「橋本左衛門三郎入道并一族」も「田代豊前又次郎入道了賢」の手に生捕られているため(建武五年三月廿六日「田代了賢軍忠状」『田代文書』)、天王寺の合戦には河内和泉の楠木党も加わっていたことがわかる。また、足利勢の一将、茂木知政は16日の「天王寺合戦」で三度の「被射乗馬等」という不運に見舞われている(建武五年四月「茂木知政軍忠状」『茂木文書』)。奥州足利勢の「標葉四郎左衛門清隆」も「天王寺合戦」で「馳向浜手懸入大勢ノ中」で軍功を挙げている(「室原氏」『相馬市史料資料集特別編 衆臣家譜 六』:岡田清一「近世のなかに発見された中世 ―中世標葉氏の基礎的考察―」『東北福祉大学研究紀要 第三十四巻』)。
結果として、北畠顕家の奥州勢と和泉河内の楠木党ら吉野方による奈良、八幡、天王寺の要衝攻略はすべて失敗に終わり、顕家は軍勢の立て直しのために吉野へ退避したのだろう。東寺の左馬頭直義は天王寺攻略と顕家らの撤退を大きな節目と位置づけ、翌3月17日、九州で奮闘する一色範氏入道らに宛てて、「顕家卿已下凶徒、於天王寺大略被討取由」の「十七日御教書」を送っている(建武五年四月十日「一色範氏入道執達状」『武雄社文書』)。さらに3月20日には「八幡宮検校法印御房」に対し、「天王寺凶徒等」を「難波浦悉討取」ことができたのは、石清水の祈祷による神慮の至りとして直義から感謝の書状が届けられている(建武五年三月廿日「足利直義祈状」『菊大路文書』)。そして、これらの軍功によるものとみられるが、高師直は5月までに「武蔵権守」から「武蔵守」となっている。
一方、吉野方は畿内での不利な状況に対し、またもや戦況の厳しい辺地から上洛して対処させようと考えた。そのうちの一人が3月22日付の軍勢催促状を受けた「阿蘇大宮司(阿蘇惟時)」であった。この軍勢催促状では「奥州官軍、自去此於南都天王寺等、度々合戦、未決雌雄、相構此時分可被参上」(延元三年三月廿二日「軍勢催促状」『阿蘇文書』)と、すでに奥州勢が大敗を喫して退いているにも拘わらず、未だ雌雄を決せずと偽りを述べてまで上洛を命じるという形振り構わぬものだった。しかし、阿蘇大宮司惟時はこれに応じず、しびれを切らした吉野朝廷は「依度々雖被仰、于今遅参、何様事歟」と叱責し「以夜継日、可馳参」と命じる綸旨を下している(延元三年四月廿七日「後醍醐上皇綸旨」『阿蘇文書』)。こうした非常にひっ迫した状況の中、5月8日には、劣勢の奥州の要である「白川一族等」にまで「以夜継日、急可馳参」(延元三年五月八日「後醍醐上皇綸旨」『結城古文書写』)という綸旨が出されている。
こうした混乱の続く5月15日、顕家は後醍醐上皇に対して、これまで自身が各地を駆け巡り、恩讐を越えて体験してきた様々な実態や現状をもとに、後醍醐上皇が行ってきたまつりごとに対する批判と意見、対応策を忌憚なく記した諫奏文を捧呈する(「北畠顕家上奏文案」『醍醐寺文書』)。
顕家がこの上奏文をどこで記したのかは定かではないが、翌日に足利勢が和泉国堺浜へ軍勢を繰り出していることから(建武五年七月「田口重連軍忠状」『南狩遺文』)、堺の陣中で認めたものであろう。顕家は「陛下不従諫者、泰平無期、若従諫者、清粛有日者歟」とまで言い切り、「若夫先非不改、太平難致者、辞符節而逐范蠡之跡、入山林以学伯夷之行矣」という覚悟も述べている。醍醐寺に唯一遺された案文は前半の一部が失われているが、現存第一条に顕家が最も主張したかった緊急を要する案件「当時之急無先自此矣」の内容が記されていることから、前文は不明なものの現存第一条はもともとの第一条であると考えられよう。
顕家が上奏文を認めた翌5月16日、「田口孫三郎信連代子息孫次郎重連」が「発向堺浜」し(建武五年七月「田口重連軍忠状」『南狩遺文』)、「大友一族狭間大炊四郎入道正供」も「五月十六日、令発向和泉国堺津」(建武五年八月「狭間入道正供軍忠状」『大友文書』)とあるように、天王寺から高武蔵権守師直を大将軍とした足利勢が、阿倍野を南下して堺に向かっている。
そして5月22日、奥州勢や楠木勢は「於泉州堺浜」(建武五年閏七月「岡本良円軍忠状」『岡本文書』)で足利方と合戦となった。美濃や尾張、奈良、八幡、天王寺合戦という連戦と敗戦を繰り返す中、すでに顕家率いる奥州勢はかなり討ち果たされていたと思われ寡勢であったろう。「吉野ヨリ、今度ハ公卿殿上人可然武士多出タリ」とあるように(『保暦間記』)、吉野からも公家大将までも出陣する援軍が出ていたようである。この戦いは「京方打チ負テ引ケル」と、北畠顕家勢が高師直率いる足利勢を打ち破ったかに思えたが、高師直が「思切テ戦フ程ニ、顕家卿ウタレケリ」という(『保暦間記』)。顕家二十一歳であった。狭間正供入道が「新田綿内、致太刀打」とあるように、北畠勢には新田一族綿打氏も主要な将軍の一人として加わっていた。さらに昨年の新田義貞越前落の際に離脱した「名和判官(名和判官義高)」も顕家の麾下として討死を遂げた。奥州からの腹心であった南部師行も「師行亦奮闘而死伝曰家士従死者百八人」という(『八戸系図』)。
「顕家卿、於堺宿被打取了」(『鶴岡社務記録』)、「和泉国堺浦合戦、官軍敗北、顕家卿死節」(『元弘日記裏書』)により「其後ハ吉野方散々ニ成テ引退」(『保暦間記』)といい、「浜手」で合戦した足利方の田口重連は吉野方を「和泉国大島荘」に追撃している(建武五年七月「田口重連軍忠状」『南狩遺文』)。また同22日、河内国高木荘(松原市北新町)の楠木勢「高木八郎兵衛尉遠盛」は「高安(八尾市高安町)」に布陣していた足利方勢力の陣を襲って焼き払ったが、「天王寺之凶徒等寄来」たため合戦となり、追い返している(延元三年十月「高木盛遠軍忠状」『和田文書』)。これは高師直の軍勢ではなく、直接天王寺から攻め寄せた別勢だろう。
5月24日、「於摂津国堺浦、奥州先国司顕家卿、新田綿打、伯耆判官已下凶徒数輩被討取」ったことを記した御教書が九州の一色範氏入道や太宰少弐頼尚へと遣わされている。なお御教書の発給主体は不明だが、おそらく軍事を統括していた左馬頭直義であろう。
顕家の遺志を継ぎ、奥州勢を率いたのは「源持定朝臣、同家房朝臣、同顕国以下」の北畠一族であった(『中院一品記』建武五年七月五日条)。顕家を討たれた奥州勢の士気は高く「奥州軍勢不知其数」と噂されるほど畏怖された。中院権中納言通冬は「附風聞説注之、雖足信用哉、陸奥国司権中納言顕家卿源大納言親房卿息也、率数多人勢雖責上、去春於軍陣落命了」と兵力には疑問を呈すが、「相従彼卿之輩、為達余執、棄身命面々致合戦云々」と評価している。
●村上源氏略系
源通親―+―堀川通具―――堀川具実―――堀川基具―――堀川具守―――堀川具俊―――堀川具親
(内大臣)|(大納言) (内大臣) (太政大臣) (内大臣) (権中納言) (内大臣)
|
+―久我通光―+―久我通忠―――久我通基―――久我通雄―――久我長通―――久我通相
|(太政大臣)|(大納言) (内大臣) (太政大臣) (太政大臣) (太政大臣)
| |
| +―六条通有―――六条有房―――六条有忠―+―六条有光
| (右少将) (内大臣) (権中納言)|(右中将)
| |
| +―千種忠顕
| (左中将)
|
+―土御門定通――土御門顕定――土御門定実――土御門雅房――土御門雅長――土御門顕実
|(内大臣) (権大納言) (太政大臣) (大納言) (権大納言) (権大納言)
|
+―中院通方―+―中院通成―――中院通頼―――中院通重―――中院通顕―――中院通冬
(大納言) |(内大臣) (大納言) (内大臣) (内大臣) (大納言)
|
+―北畠雅家―+―北畠師親―――北畠師重―+―北畠親房―――北畠顕家
(権大納言)|(権大納言) (権大納言)|(大納言) (陸奥守)
| |
| +―冷泉持房―――冷泉持定
| (参議) (左少将)
|
+―北畠師行―+―北畠雅行―――北畠家房
(右中将) |(右中将) (右衛門尉)
|
+―北畠具行
(権中納言)
冷泉持定や北畠家房、春日顕国ら顕家麾下の歴戦の公家大将は、奥州勢を取りまとめると、5月28日、顕家が成し得なかった八幡山を攻め落とした(『元寇日記裏書』)。顕家麾下としてその采配のもと戦い続けた彼らもまたその軍略を継承した将軍であったのだろう。さらに宇治や木幡にも繰り出して攻勢をかけ、楠木勢も呼応し、高木八郎兵衛尉遠盛は6月8日から18日にかけて淀川の対岸山崎の「洞到下(洞峠)」に布陣して戦っている(延元三年十月「高木遠盛軍忠状」『和田文書』)。また、八幡山に籠城した奥州勢の抵抗も激しく、高武蔵権守師直、武田兵庫頭信武、仁木右馬助義長、細川兵部少輔顕氏、島津大夫判官宗久、大友一族、細川刑部大輔頼春ら足利勢も苦戦しながらも各口を押さえて行った。奥州勢が八幡山から撤退したのは7月11日夜であり、足利勢は一月以上もの間、この八幡城に釘付けにされたことになる。奥州勢は密かに撤退しており「寄手軍勢不存知云々」(『中院一品記』)という。彼らの八幡山撤退は吉野からの奥州下向の打診があったための可能性があろう。その後、彼らの撤退に混乱した足利勢のなかから堂塔に放火した輩がおり、八幡山全山が激しく延焼し一切を焼き尽くしている。
冷泉持定や北畠家房、春日顕国以下の奥州勢のその後は不明だが、春日顕国はのちに親房入道とともに関東で戦っていることから、奥州勢は吉野へ戻り、親房入道に合流してともに伊勢へ下ったのだろう。
その頃、越前国杣山に拠点を置いていた新田義貞は、「たひゝゝめされしかと、のほりあへす」(『神皇正統記』)と、吉野の後醍醐上皇から度々吉野へ召す綸旨が下されていたようだが、越前国府の足利尾張守高経のために叶わずにいた。さらに京都からも越前へ出兵されており、5月11日には「土岐伯耆入道(土岐頼貞入道)」が「熊谷小四郎殿(熊谷直経)」に遣わされ、土岐頼貞入道とともに「越前国凶徒誅罰事」が命じられている(建武五年五月十一日「足利直義御教書」『萩藩閥閲録』)。
そして北畠顕家の戦死から三か月後の建武5(1338)年閏7月2日、「源高経、討源左中将義貞」(『皇代記』)、「越前大将義貞朝臣死節」(『元弘日記裏書』)と、足利尊氏・直義の宿敵であった一族新田義貞は足利高経によって「越前国於足羽郡」で討ち果たされた。義貞三十七歳。「是モ云甲斐ナク打レテ、頸ヲ都ヘ進タリケレハ、大路ヲ渡テ獄門ノ木ニ懸ラレケリ、義貞ハ尊氏カ一族也、彼命ヲ受テ不背ハ然ルヘカリケルヲ、是モ驕ル心有テ、高官高位ニシテ如此ナルコソ不思議ナレ、子息越後守モ同首ヲ被懸ケリ」(『保暦間記』)といい、尊氏・直義は惣領家に反旗を翻し、乱世の因を生じさせた庶家義貞に極刑を処したことになろう。義貞の首級は大罪人として実に百四十年ぶりの大路渡しを経て、すでに都へ送られていたであろう子息義顕の首級とともに獄門に懸けられた。新田勢の敗残兵は「敦賀金崎城」に立て籠り、若狭守護の桃井直常の弟、桃井直信が金崎城に攻め寄せたところ、城中から数百騎が駆け出し、敦賀津陣を攻め落とされた(建武五年八月二日「茂木知政軍忠状」『茂木文書』)。このとき茂木知政は桃井勢に加わり、敵陣に駆け入って新田勢を城郭に追い返す軍功を挙げている。
8月11日、除目が行われ「権大納言従二位源尊氏」は正二位に叙されて「還補征夷大将軍」、足利直義は「左兵衛督」に任じられ、同日「従四上」に叙された。尊氏の「征夷大将軍(征夷将軍)」は「還補」とあるが、彼はもともと「征東将軍」であり、征夷将軍(征夷使)と征東将軍(征東使)が同義であることから「還補」とされたのであろう。尊氏の「征夷大将軍」は公卿の「征夷将軍」たることで「大将軍」号が付されたものか。
●建武五年八月十一日夜小除目
| 名前 | 官位 | 見任 | 補任(兼) | 備考 |
| 足利尊氏 | 従二位 ⇒正二位 | 権大納言 | 征夷将軍 | 源顕家卿追討賞 |
| 柳原資明 | 正三位 | 左兵衛督 | (遷)右衛門督 | |
| 源宗明 | 無位 ⇒従四位下(直叙) | (賜源氏姓) 参議 |
光明天皇勅問⇒一条経通答申(『玉英記抄』より) 土御門入道親王(久明親王)息宗明王、四品直叙、 不可有難歟、 申云、入道親王、為新院御猶子之上者、 可被許哉 |
|
| 足利直義 | 従四位下 ⇒従四位上 | 左馬頭 | (遷)左兵衛督 | 権大納言源朝臣、源義貞追討賞譲 |
| 平兼行 | 正五位下 |
左京権大夫 蔵人 | 少納言 |
8月28日、京都朝廷は改元して「建武」を「暦応」とした(ただし9月3日までは建武号を用いるとされている)。
『実夏卿記』
| 儒卿 | 改元号案(最終案は赤) |
| 文章博士藤原朝臣家倫 | 文明、嘉慶、養寿 |
| 文章博士藤原朝臣房範 | 天観、文安、顕応 |
| 正三位式部大輔菅原朝臣長員 | 天保、寛裕、斉万、応観 |
| 従三位藤原朝臣行氏 | 天観、長嘉、康安 |
| 従三位勘解由長官菅原朝臣公時 | 天貞、暦応、寛安 |
この改元につき、北畠親房入道は「旧都には戊寅の年の冬改元して暦応とそ云ける、芳野の宮にハ本の延元の号なれハ国々も思ひゝゝの年号なり」と冷静に記載するも「内侍所、神璽も芳野におはしませは、いつくか都にあらさるへき」(『神皇正統記』)と、内侍所と神璽がある吉野が正統であると述べている。なお、吉野の朝廷はその正統性の故か守護が催促する「大番役」の制があり、和泉国守護の某から執行の指示を受けた守護代の大塚掃部助惟正が「和田修理亮入道殿(和田助家入道)」に「吉野殿惣門大番役」を命じている(延元三年十一月十八日「大塚惟正大番催促状」『和田文書』)。
9月8日、尊氏は改元に伴う吉書始を行っているが、「武家吉書始」(『武家年代記』)とみえることから、征夷将軍就任に伴う吉書始を兼ねていたものか。
新田義貞亡きあと、直義(または尊氏)は「吉野発向」を計画し、諸将の上洛を呼び掛けたと思われる。近江国の佐々木道誉は高島郡の「出羽四郎兵衛尉殿(朽木佐々木頼氏)」に閏7月16日に上洛したことを報告。21日に「可立京都候」のため、経氏ら高島勢も「廿日以前令京著給候者、公私悦入候」と軍勢催促の文書を送達している(建武五年閏七月十六日「佐々木道誉軍勢催促状」『朽木文書』)。しかし、朽木頼氏はその軍令に従わず、佐々木道誉は8月16日、吉野への出陣は8月25日と決定したので、「早永田四郎相共、相催高島郡軍勢可被上洛、彼日限更不可有延引、可被存知其旨之状如件」(建武五年八月十六日「佐々木道誉軍勢催促状」『朽木文書』)と、元号を書き入れての警告文を送っている。ところが頼氏はさらにこれを無視。8月27日、佐々木道誉は「今月廿五六両日令治定之由、度々触遣之處、高島郡軍勢不参之条、何様子細哉、頗招其咎歟」と激怒して子細を追及するとともに、「所詮来月二日可令進発也、守彼日限可令京著之由、永田四郎相共、普可被相触之、若於不承引者、任法為有沙汰、載起請之詞、可被注申」と伝えた。ここまでしても頼氏の不承引はなおも続き、根尽きた佐々木道誉は9月3日、「南都発向事、来十日所令進発也、早永田四郎相共、相催高島郡軍勢、可被上洛之状如件」(建武五年九月三日「佐々木道誉軍勢催促状」『朽木文書』)と到って力ない文書を送っている。そして10月2日、左馬頭直義が「南都警固事、所被仰佐々木佐渡大夫判官入道也、不日令下向、可致其沙汰」を命じており、この時点でもまだ高島郡から出陣していなかったことがわかる(暦応元年十月二日「足利直義御教書」『朽木文書』)。結果として、吉野攻めは行われず、奈良警衛に変更されたと思われる。
延元3(1338)年閏7月、吉野では「陸奥のみこ又東へむかはしめ給へきさためあり」と、義良親王を三度奥州へ派遣することが決定し、「左少将顕信朝臣、中将に転し従三位に叙し、陸奥の介鎮守将軍をかねてつかハさる、東国の官軍ことことく彼節度にしたかふへきよしを仰らる」(『神皇正統記』)と、故顕家に代り、弟の顕信を従三位に叙し、陸奥介鎮守将軍として義良親王に附すこととなった。閏7月26日、上皇は「陸奥三位中将殿」に「天下静謐事、奉扶持宮、重挙義兵、急速可令追討尊氏直義以下党類給、坂東諸国軍勢賞罰等事、宜令計成敗給」(延元三年後七月廿六日「後醍醐上皇令旨」『結城文書』)ことが認められており、節度使としての下向であった。今回の奥州下向には義良親王、陸奥介顕信に「入道一品(親房入道)」も加わってのものであり「率東軍下向勢州」した。親王は「儲君にたたせ給へきむね申きかせ給、道の程もかたじけなかるへし」(『神皇正統記』)とあり、義良親王は立坊したことがわかる。「同母の御兄も前東宮恒良の親王、成良親王ましましに、かくさだまり給ぬるも天命なれは、かたしけなし」(『神皇正統記』)と、親房入道は実兄の恒良親王(元後醍醐東宮、北陸帝)、成良親王(元光明東宮)を差し置いての立太子を天命としている。ただし、恒良親王も成良親王も皇太子を退いた身である上に、京都で足利方に保護(監護)されているため、吉野に健在の義良親王が皇太子とされるのは自然な成り行きであった。
義良親王と宗良親王(座主宮尊澄法親王還俗)を奉じた陸奥介顕信、親房入道、唐橋修理亮経泰、結城上野入道らは「九月のはしめともつなをとかれしに」と、9月初めに伊勢国を船出した。具体的な日時は不明だが、9月3日に義良親王とみられる「宮」が顕信に対して「相催坂東諸国軍勢、急速可令追討尊氏直義以下党類給、依宮令旨上啓如件」(延元三年九月三日「義良親王?令旨」『結城文書』)という尊氏直義党の人々の追討を命じる令旨を発給しており、9月3日以降と思われる。彼らにはかつての顕家奥州下向軍のように陸路を行く兵力はなく、黒潮に乗っての東下を試みたとみられる。
ところが9月10日、「上総の地ちかくより、空のけしきおとろゝゝゝしく、海上あらくなりしかは、又伊豆の崎と云方にたゝよはれ侍りしに、いとゝ波風おひたゝしくなりて、あまたの船行かたしらす侍りける」(『神皇正統記』)と、上総沖で暴風雨に遭遇して漂流し、船団から多くの船が行方不明となったという。
流された船のうち「御子の御船ハさはりなく伊勢の海につかせ給ふ、顕信朝臣ハ本より御船に候ひけり、同じ風のまきれに東をさして常陸の国なる内の海につきたる舟はへりき、方々にたゝよひし中に、この二の舟同し風にて東西に吹わけらる、末の世にハめつらかなるためしにそ侍りき、儲の君にさたまらせ給て、例なきひなの御すまひもいかかとおほえしに、皇太神のととめ申させ給けるなるへし」と、皇太子義良親王と陸奥介顕信の乗る御座船は「伊勢国篠島」(『新葉和歌集』神祇歌)に漂着し、親房入道の船は常陸国の香取海へ流れ着いたという。親房入道はこれを皇太子の京外居住を皇太神が留めて伊勢に吹き戻したと述べている。また、結城上野入道の船も伊勢へと吹き戻されている。その後、義良親王と陸奥介顕信は吉野へ戻っているが、結城上野入道はそのまま伊勢に残っている。結城上野入道はこの二か月後に病死していることから、この時点で体調は芳しくなかったのかもしれない。
船団を襲った嵐は上総国の近くであったとされるが(『神皇正統記』)、太平洋岸が現在と同様の海流の動きであれば、上総付近まで来ていた場合、伊勢まで吹き戻ることは考えにくい上に「伊豆の崎」を漂ったことが記されており、実際は遠州灘付近での難破ではなかろうか。ここで吹き返された義良親王は伊勢へ、宗良親王は遠江国に漂着。親房らは海流に乗って安房国方面へ流されたのだろう。実際に9月9日「御敵船二艘、著安房国之間、安房国軍勢馳向畢」(『鶴岡社務記録』)とあり、『神皇正統記』に言う9月10日の前日に難破船二艘が安房国に漂着しており、実際の遭難は数日前であったと考えられる。9月12日にも「船六艘著安房国了」、翌13日「船二艘被放風、而被吹寄江島之間、御敵多被生取之内、関八郎左衛門尉其中大将云々、被誅了」という。翌14日には船三艘が「吹寄神奈河」られ、17日には「於稲瀬川御敵廿一人被誅畢、此内冷泉侍従、関八郎宗之者云々」とあり、稲瀬川で討った敵の中に「冷泉侍従」「関八郎宗之者」がいたという。「冷泉侍従」は冷泉左少将持定か。その後も20日にかけて漂着し潜伏したみられる武士等が鎌倉の留守居に誅殺されている(『鶴岡社務記録』)。
そして、難破事件から四か月後の暦応2(1339)年正月初旬頃、鎌倉は伊豆国南西岸の仁科に吉野方の人々が居住している情報を掴んだとみられる。鎌倉は正月20日、「標葉彦三郎隆光」らを「伊豆国仁科城」に派遣(「室原氏」『相馬市史料資料集特別編 衆臣家譜 六』:岡田清一「近世のなかに発見された中世 ―中世標葉氏の基礎的考察―」『東北福祉大学研究紀要 第三十四巻』)。仁科城の大手で戦い、正月23日の戦いで負傷している。「標葉彦三郎隆光」は2月20日に「民部太輔(上杉憲顕か)」から感状を受けており(「室原氏」『相馬市史料資料集特別編 衆臣家譜 六』:岡田清一「近世のなかに発見された中世 ―中世標葉氏の基礎的考察―」『東北福祉大学研究紀要 第三十四巻』)、2月中旬までに仁科城を攻め落としたとみられ、2月に「自伊豆仁科城凶徒卅七人、目代具参、此内十三人者、於龍口被切了、大将普薗寺左馬助云々」(『鶴岡社務記録』)と、伊豆国賀茂郡仁科(賀茂郡西伊豆町仁科)に拠っていた普恩寺左馬助(六波羅北方の越後守仲時息)と麾下三十人余りが、伊豆目代に伴われ、大将の普恩寺左馬助友時以下十三人が龍口で処刑されているが、彼らがわずか三十七名で地理的にも何ら利点のない伊豆南西岸に拠っていたのは、土気城での敗北後、故陸奥守顕家や相模次郎時行に従って上洛したのち、親房入道の船団に加わって東国へ下る最中、「伊豆の崎」での難破によって西海岸に漂着したためであろう。
親房らは漂流ののち香取海に入っているが、房総半島の南端から香取海に向かうには海流の関係で意図的に北上する必要があり、さらに時期的に上総東側の潮流は南下流であることから、北畠親房入道の船団は操舵のできる状況にあったことがわかる。「吉野没落朝敵人北畠源大納言入道以下凶徒等、経海路当国東條庄著岸、為誅罰之、被発向之間、時幹罷向之處、今年建武五、十、五日、押寄神宮寺城致至極合戦」(建武五年十月「烟田時幹軍忠状」『烟田文書』)とあり、香取海に入った親房らの船団は常陸国東条庄に上陸して、そのまま沿岸の薬師寺城(稲敷市薬師寺)や阿波崎城(稲敷市阿波崎)に入っている。ところが、ここに常陸守護佐竹義篤の麾下に属する烟田又太郎時幹や鹿島又次郎幹寛、宮崎又太郎幹顕、小野崎次郎左衛門尉ら常陸大掾一族勢が攻め寄せたため没落し、筑波郡小田の小田宮内権少輔治久、関民部少輔宗祐のもとへ落ちていった。
奥州においては、結城上野入道の嫡子「結城大蔵大輔殿(結城親朝)」が白河を押さえ、「高野郡」など「白河高野以下諸郡ノ検断職ニテ毎時奉行セル者」(『関城書考』)とあり、奥州南部の旗頭的な立場となっていた。そのほか、「伊達宮内大輔行朝」や「石川一族等」「五大院兵衛入道」「小山安芸権守、同長門権守等」らが奥州南部を押さえていたようである。また、多賀国府付近では「葛西清貞兄弟以下一族」が主力となって「随分致忠之由」といい、足利方に対抗していたようである。ただ、清貞は「先被対治奥州羽州次第、可有沙汰之處、大将無御下向候、難事行候」と、旗印となる大将軍の下向がないことへの不審を述べ「此事葛西殊急申候」と、国司の下向を急ぐ事を要求している(延元三年十一月十一日「北畠親房入道返報」『結城文書』)。11月10日には相馬一族で唯一国司方に属していた「相馬六郎左衛門尉殿(相馬胤平)」が足利方の大将軍石塔義房入道の勧誘を受けており(暦応元年十一月十日「沙弥書状」『相馬文書』)、足利方による切り崩しが行われていた様子がうかがえる。そしてこうした中、吉野方の重鎮、結城上野入道が「延元三年戊寅十一月廿一日、於吹上光明寺病死也」(『光明寺墓碑銘』)と、伊勢光明寺において病死した。
延元4(1339)年2月22日、親房入道は「結城大蔵権大輔殿(結城親朝)」「禅門事已送日数候、悲歎無極候、自吉野殿も度々被仰下旨候、忠節無退転者、併可為追善歟、兼又此辺事、当時重々御沙汰之最中候也」(延元四年二月廿二日「北畠親房入道消息」『結城文書』)と、結城上野入道薨去について悔みを述べ、幼少から十二歳に至るまで薫陶を受けた「吉野殿(義良親王)」も同様に悲歎に暮れている旨を伝えてる。また、奥州へ「春日中将(春日顕国か)被下向候」のことを告げ、「近日先可被対治近国候、路次無為候者、急々可有御下向之由、御有増候」と、路次の危機が去れば親王御下向となることを述べている。さらに、親朝には「故将軍御息女辺事、構被懇意候者、可為御本意之由、内々所候也」と、顕家が奥州に遺した息女を親朝に託すことも依頼している。
その後、おそらく3月4日に「左中将(春日顕国か)」は関東の何処かに「下著候」し、「此辺凶徒等急令対治候」いい、まずは那須、宇都宮周辺の平定に同心するよう結城親朝に執達状を下している。その後、「春日羽林」は下野国に発向し、かつての顕家を彷彿とさせるような速攻を見せ、3月27日には矢木岡城を攻め落として撫で斬りし、益子城も攻め落とした。さらに桃井直常の舎弟某が籠る上三川城、箕輪城もたちまち蹂躙し、宇都宮周辺の足利方を追い散らしている(延元四年三月廿日「北畠親房代越後権守秀仲書状」『結城文書』)。
また、地域の諸郡検断奉行である結城親朝も高野郡を中心に足利方と激しく合戦し、7月26日、27日の両日、「高野郡長福楯」に足利方を攻めて追落している(延元四年八月廿一日「北畠親房入道御教書」『結城古文書写』)。この使者には「御使経泰」が遣わされ、親房入道は「経泰下向之間、条々所仰含也、委可被尋聞之状如件」(延元四年八月廿一日「北畠親房入道御教書」『結城文書』)と指示を与えている。この「経泰」は、かつて顕家将軍のもと大将軍として奮迅の戦いを見せた顕家被官(家司か)の唐橋修理亮経泰であろう。顕家の西上に従い、親房の東国下向に従ったのだろう。
関東、奥州における北畠親房入道、結城親朝以下の動きが活発化する中、暦応2(1339)年4月6日、高越後権守師泰、高尾張権守師兼、高三河権守師冬らは「自京都御下向」した(暦応三年五月「矢部定藤軍忠状」『諸家文書纂』、『瑠璃山年録残篇』)。おそらく左兵衛督直義の指示であろう。師泰と師兼は遠江国の吉野方を攻め、師冬は関東下向の大将軍であったと思われる。
このような中、高継は5月18日に亡くなったという。没年齢不明。
7月22日には井伊谷の中務卿宗良親王や井伊介を攻めるべく、「越後殿、下大平ニ向」い、「尾張殿、濱名手向」って「カモノヘ城」を攻め立てて26日に攻め落としている(『瑠璃山年録残篇』)。師泰は8月23日時点でもまだ遠江国におり、「蒲御厨惣検校清保」が着到状を提出している(暦応二年八月廿三日「源清保着到状」『蒲神社文書』)。高師冬は「遠江国ノ凶徒ヲ責、師冬ハ下総常陸両国ノ凶徒ヲ責メ、年ヲ重テ合戦アリテ、皆凶徒或ハ降参シ、或ハ討レケリ、扨東国ハ静リケリ」(『保暦間記』)という。師冬はまず9月8日、「武蔵国村岡宿(熊谷市村岡)」から親房入道の在所、常陸国小田城(つくば市小田)へ向けて進発すると、10月22日に絹川(鬼怒川)の下総国「並木渡(結城市久保田)」、23日に「折立渡」を越え「駒舘野口(下妻市黒駒)」で合戦。25日には「当城(関城)」に攻め寄せるも(暦応三年五月「矢部定藤軍忠状」『諸家文書纂』)、その守りは堅く、一翌年もこの地を攻めている。
なお、越前での降伏以降の千葉介貞胤、下総の千葉氏の動向は不思議なほど見ることができない。下総国においては下総国下河辺庄で吉野方が動いており、暦応2(1339)年7月9日の「於下河辺庄合戦」のとき「相馬孫六郎長胤後家」は代官を真っ先に派遣し「左衛門尉重兼」の証判を得ている(暦応二年七月十六日「相馬長胤後家着到状」『相馬岡田文書』)。また、翌興国元(1340)年5月16日、親房は「下総国相馬郡ニ被構新城候、依之上総下総安房等軍勢者、悉以引返候、千葉一族、自去年連々申旨候、于今雖不表其色、此城出来之後、弥無等閑之体候」(興国元年五月十六日「北畠親房入道御教書」『結城文書』)といい、相馬郡に「新城」を築いたことで房総の足利方は退き、去就を明らかにしない千葉一族もこの城ができたことでいよいよ態度を明らかにせざるを得ない様子であると述べている。ただし、これは足利方への離反の可能性を見せていた白河の「結城大蔵大輔殿(結城親朝)」への報告であり、同文書には「官途所望輩事」について、結城一族、家人を含めて希望を注進するよう記すなど、親朝の離反を食い止めるべく必死の様相を示しており、千葉一族の去就についても大げさに書いてある可能性も否定できない。ただ、下総国相馬郡内に地域の勢力バランスを変える城を築けるほど親房の勢力は下総国南部にまで広がっていたとみられる。
延元4(1339)年8月15日、「陸奥親王」こと皇太子義良親王は「ゆつりをうけて天日嗣をうけつたへおはします」と、吉野において践祚した(『神皇正統記』)。これは上皇の病がもはや命旦夕に迫る状況となり「かねて時をもさとらしめ給けるにや、まへの夜より親王をは左大臣の亭へうつし奉らえて、三種の神器を伝申さる」(『神皇正統記』)と譲位。翌8月16日に「秋霧にをかされさせ給ひて」崩じた。五十二歳。「後の号をは仰のままにて、後醍醐天皇と申」(『神皇正統記』)という。この報を遠く常陸国小田で受けた北畠親房入道は「寝るか中なる夢の世は、今にはしめぬならひとはしりぬれと、かくゝゝ目の前なる心ちして、老の泪もかきあへねハ、筆の跡さへとゝこほりぬ」(『神皇正統記』)と、その崩御に衝撃を受けている。
上皇崩御の報は、「後醍醐院号吉野新院、暦応二年八月十六日崩御事、同十八日未時、自南都馳申之、虚実猶未分明、有種々異説、終実也」(『天龍寺造営記録』)と、18日に奈良からの飛脚で判明した。
この一報に、「諸人周章、柳営武衛両将軍、哀傷恐怖甚深也、仍七々御忌慇懃也、且為報恩謝徳、且為怨霊納授也、新建立蘭若、可資彼御菩提之旨発願云々」(『天龍寺造営記録』)といい、8月26日、鎌倉にもその崩御の報が届けられた(『鶴岡社務記録』)。
8月28日「伝聞、讃岐院隠岐院之時、不被止雑訴、即可用其儀之由、為大理資明卿奉行被相触了、且又被仰武家云々、而此御事治定之後、於武家者有存之旨、止雑訴之由申之云々、依之公家被停止七ケ日云々、可謂朝議之軽忽者歟、不可説々々々、莫言々々」(『中院一品記』)とあり、崇徳院や後鳥羽院のときは雑訴は停止されなかったことで、一旦は尊氏・直義もこの例を用いるとして治定したにもかかわらず、朝議を翻して武家においては「有存之旨」って七日間雑訴を停止すると決定。結果として公家のみ政務停止となり、権中納言通冬はこれを朝議の軽視で不届き至極と批判するも、武家を恐れて口を閉ざした(『中院一品記』)。この「武家者有存之旨」とは、「凡件院、非流刑自逃去給也、雖准崇徳後鳥羽等之例、無勅問間人々閉口歟」(『玉英記抄』)と、崇徳院や後鳥羽院の例に準じるとはいえ、後醍醐院は流罪となったわけではなく自ら出京したにすぎないという考え方で、「且為報恩謝徳、且為怨霊納授也」という後醍醐院に対する強い遠慮であろう。
暦応4(1341)年10月5日、光厳上皇は「詔征夷大将軍、左武衛将軍、令鼎建天龍寺、欲資薦先皇之冥駕、請夢窓国司為之開山」(『天龍紀年考略』)と、後醍醐院の冥加を祈る禅寺の建立を命じた。その地は「亀山殿之旧基」である嵐山の地で、尊氏・直義の両将軍は「令武蔵守師直、阿波守細河和氏、対馬守後藤行重、諏訪法眼円忠等」を工事の奉行と定めた(『天龍紀年考略』)。11月、光厳上皇はこの新寺に「霊亀山暦応資聖禅寺(天龍寺)」の勅号を賜った。延暦寺、建仁寺と並ぶ元号を冠した新寺であった。
その後、関東における吉野方は、南奥州の旗頭であった結城大蔵権大輔親朝が足利方に寝返り、北畠親房入道は、鎌倉の関東管領足利義詮の執事の一人、高三河守師冬の攻勢により、興国2(1341)年8月に小田城の小田宮内権少輔治久が降伏したため、小田城から関城に逃れるも、11月に関城も陥落。親房入道は失意のうちに吉野へ帰還せざるを得なかった。
また、奥州の吉野方は「宇津峯宮」とみられる上野太守守永親王(中務卿尊良親王子(『皇親系』))を奉じた陸奥介鎮守府将軍北畠顕信が奥州足利党と激しく戦い続け、観応2(1351)年には「宇津峯宮、伊達飛騨前司、田村庄司一族以下凶徒、府中襲下」(観応三年十一月廿二日「吉良貞家注進状」『相馬文書』)し、「相馬出羽守親胤」や「結城参河守朝常」「朝常代官結城又七兵衛尉」「伊賀孫次郎光長」「石河左近大夫兼光」らが吉良右京大夫貞家に属して戦っている。