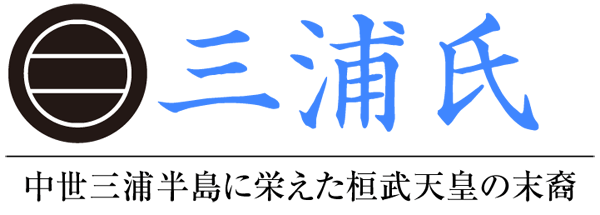
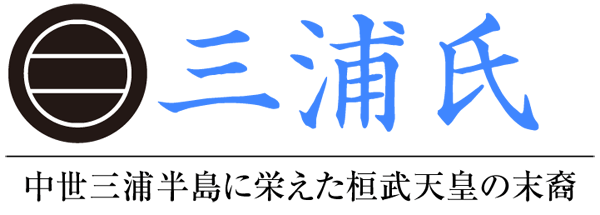
| 平忠通 (????-????) |
三浦為通 (????-????) |
三浦為継 (????-????) |
三浦義継 (????-????) |
三浦介義明 (1092-1180) |
| 杉本義宗 (1126-1164) |
三浦介義澄 (1127-1200) |
三浦義村 (????-1239) |
三浦泰村 (1204-1247) |
三浦介盛時 (????-????) |
| 三浦介頼盛 (????-1290) |
三浦時明 (????-????) |
三浦介時継 (????-1335) |
三浦介高継 (????-1339) |
三浦介高通 (????-????) |
| 三浦介高連 (????-????) |
三浦介高明 (????-????) |
三浦介高信 (????-????) |
三浦介時高 (1416-1494) |
三浦介高行 (????-????) |
| 三浦介高処 (????-????) |
三浦介義同 (????-1516) |
三浦介盛隆 (1561-1584) |
![]() (????-????)
(????-????)
村岡五郎平良文の子。通称は小五郎(『千葉大系図』『桓武平氏諸流系図』)、村岡二郎大夫(『平群系図』)。位は従五位下(『平群系図』)。官は相模大掾(『平群系図』)。陸奥介平忠頼の弟とされる。
諱については「忠道」ともされているが、『今昔物語集』に登場する「村岡ノ五郎平ノ貞道」と同一人物ともされる。
系譜としては、平良文の子として「忠頼・忠光・忠通」(『神代本千葉系図』)があり、忠通が「相模国鎌倉先祖」、忠光が「相模国三浦先祖」という(『神代本千葉系図』)。また、別の系譜では「忠輔、忠頼、忠光、忠道」(『桓武平氏諸流系図』)とも。他にも、忠通は良文の兄・上総介平良兼の子である武蔵守平公雅の流れとされる系譜がある(『満昌寺差上系図』)。系譜によれば、公雅の孫で、長元3(1030)年に伊勢国で安房守平正輔と「闘乱」している左衛門尉平致経の子とされている。致経は長和2(1013)年に藤原頼通に所領を寄進しており、忠通が致経の子であるとすると十世紀末ごろの生まれと考えられ、忠頼・忠光の活躍時期とは時代的に合わなくなる。
「陸奥介平忠頼、忠光等、武蔵国に移住し、伴類を引率し、運上の際事の煩ひを致すべきの由、普く隣国に告げ連日絶へず」(『寛和3(987)年正月24日『太政官符』:「国史大系」』)とあり、ここに見える「忠光」が『神代本千葉系図』の忠光のことであると思われる。ちなみに「陸奥介忠頼」は千葉氏の祖・平忠頼のことだろう。
●三浦氏諸系図
高望王―+―平良兼――――公雅――+―致成――――+―致方
|(上総介) (武蔵守)|(出羽守) |(武蔵守)
| | |
| | +―鎌倉景成―――景正
| | (鎌倉権守) (権五郎)
| |
| +―致頼――――――致経―――+―致清
| |(左衛門尉) (左衛門尉)|
| | |
| | +―忠通―――――三浦為通――為継
| | (小五郎) (平大夫) (平太)
| |
| +―致光――――――為景―――――景清―――+―為宗
| (太宰大監) (為忠?) |
| |
| +―致村
| |
| |
| +―為俊
| (駿河守)
|
+―平良文――+―忠頼――――忠常――――――常将―――――常長―――――常兼――――千葉常重
|(村岡五郎)|(陸奥介) (上総介) (千葉介) (千葉介)
| |
| +―忠光
| |
| |
| +―忠通――+―忠輔 +―為次―――――義次―――――義明
| (小五郎)| |(平太) (六郎庄司) (三浦介)
| | |
| +―三浦為道――+―為■
| |(平大夫) |(住安房安西)
| | |
| +―景名 +―為俊
| |(甲斐権守) (駿河守)
| |
| +―鎌倉景村――――長尾景明―――大庭景宗―――景能
| |(四郎権太夫) (太郎) (大庭権守) (懐島権守)
| |
| +―鎌倉景道――――梶原景久―――景長―――――景時
| |(権太夫) (太郎) (太郎) (平三)
| |
| +―鎌倉景正――――景次―――――長江義景―――明景
| (権五郎) (小太夫) (五郎) (四郎)
|
+―平良正――――公義――――為通
(水守六郎) (平太夫)
『今昔物語集』巻第二十五にある「依頼信言平貞道切人頭語第十」には、「頼光ノ朝臣ノ郎等」として「平貞道」という武士がいたとある。貞道は同じく巻第二十九「袴垂、於關山虚死殺人語第十九」に見える「村岡ノ五郎平ノ貞道」のことであろう。
巻第二十九「袴垂、於關山虚死殺人語第十九」では、盗賊の袴垂が逢坂山(滋賀県大津市大谷町)で死んだ振りをして、近づいて来た武士を殺して金品を奪った事件が載せられている。盗賊袴垂は恩赦によって釈放されたが、行く当てもないので、死んだ振りをして横たわっていた。恐らく近づく人の金品を奪おうと企んだのだろう。しかし、予想以上に人だかりができてしまい、行動を起こせなかったようだ。そこに都の方から立派な馬に乗って弓矢を背負い、郎党を多く連れた武者が 通りかかった。この武士は人々が騒いでいる様子を見て、郎党に「アレハ何ヲ見ルゾ」と見に行かせた。郎党は走って見てくると「傷モナキ死人ノ候フ也」と報告した。すると、この武士は何かを感じ取ったか、郎党たちに臨戦態勢を取らせ、「死体」をじっと見たまま遠巻きに通り過ぎた。これを見た人々は「サバカリ郎等眷属ヲ具シタル兵ノ死人ニ会ヒテ心地涼スハ、イミジキ武者哉」と手を打って笑った。
その後、人々も飽きたのだろう。散り散りにいなくなった。そこに武士が単騎で通りかかった。彼はこの「死体」に気がつくと、「哀レナル者カナ、イカニシテ死ニタルカニカアラム、傷モナシ」と不用意に近づいて弓で突っついた。すると、「死人」は突如その弓に取り付き、武士を馬から引き落とすと、「祖ノ敵ヲバカクゾスル」と武士の刀を奪い取って刺し殺し、武具や馬などを奪って去った。この話を聞いた人々は、先ほど通り過ぎた騎馬武者を「誰ニカ有ラム、賢カリシ者カナ」と感心し、人が問い尋ねたところ「村岡ノ五郎平ノ貞道」という者であった。その人であれば、と人々は納得したという。
 |
| 二伝寺の伝・忠通墓 |
巻第二十五「依頼信言平貞道切人頭語第十」では、貞道は主君・源頼光の客の接待をしていたところ、頼光の弟である頼信に「駿河国で頼信に無礼をはたらいた者の頸を取ってこい」と、客に聞こえるほど声高に言われ、貞道は「自分は頼光殿の家人であって、弟の頼信殿の家人ではない。このようなことは自分の家人に命ずることである。その上、人の頸を取るという大事を大声で命じるとは愚かな人だ」と思い、あいまいな返事で済ませてしまった。こののち、三、四か月ののち、用事のために東国に下ったとき、先に頼信から殺害を命じられた男と道で出くわした。貞道は彼に馬を寄せて討つ気はないことを話し、そのままにしようと思った。しかし、その男が「たとえ頼信の殿の命を断りがたく、我を殺害せんとお思いになられたとしても、我ほどの腕利きをお思いになる通りにお討ちになるのは難しいでしょう」と言ったことで、貞道は内心激怒。「さらば」といったん通り過ぎたのち、彼のあとをつけ、呼び止めて戦い、彼を馬から射落とし頸を取った。
源頼信は冷泉院判官代に任じられ、長元9(1036)年10月14日、相模守に任官している。
忠通のその後は不明である。忠通の塚といわれる鎌倉期のものと思われる小さな五輪塔が、藤沢市渡内の二伝寺に残されている。