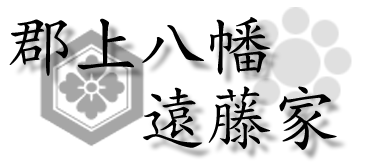
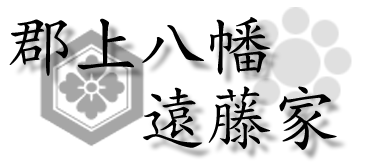
トップページ > 郡上遠藤家
遠藤氏の家紋

| 
| 
| 
|
| 十曜 | 三割亀甲 | 月星 | 亀甲 |
●郡上藩・三上藩遠藤家
| 郡上藩・三上藩の概要 | 美濃郡上藩主 | 近江三上藩主 | 郡上遠藤家 |
| 木越遠藤家 | 乙原遠藤家 | 和良遠藤家 |
●東氏の歴代
| 郡上東氏 | 郡上東氏の歴代 | 東氏惣領家 | 須賀川東家 | 森山東家 |
| 土佐藩遠藤家 | 木曾遠藤家 | 田中藩遠藤家 | |
| 苗木藩東家 | 土佐藩東家 | 小城藩東家 | 医官東家 |
1.東氏と遠藤氏
美濃国郡上藩主・遠藤氏は、千葉介常胤の六男・東六郎大夫胤頼を祖とすると伝わる郡上東氏の重臣の家柄である。
平家政権の下、東胤頼は一族の三浦義澄とともに大番役のために上洛し、院北面の武士・遠藤左近将監持遠の推挙で上西門院(統子内親王)に仕えて従五位下に叙せられ「千葉六郎大夫」と称した。上西門院は歌人として知られた皇女で、教養人がその廻りに侍っていた。胤頼もこの上洛時に文化人としての教養を身につけたのだろう。彼は鎌倉御家人のなかでも、宇都宮氏などとともに教養のある武士として知られていた。胤頼は頼朝の挙兵から忠実に仕え、平家との戦いでは三河守源範頼(頼朝弟)に従って壇ノ浦の戦いに参加。その後の奥州藤原氏との戦いにも出陣して、奥州藤原氏当主・藤原泰衡の外祖父にあたる前陸奥守藤原基成父子を捕らえる功績を立てている。その後、東氏は将軍家の側近として幕府に仕え、承久の乱・宝治合戦と数々の戦いにも功績を挙げた。
郡上東氏は東氏の庶流で、東中務丞胤行が承久の乱の戦功として給わった美濃国郡上郡山田庄に下向した胤行の子・東六郎左衛門尉行氏にはじまるとされる。ただし、東氏の本領は下総国東庄であり、行氏の兄・東図書助泰行が東家惣領である。
東行氏の郡上郡下向に際しては、下総国東庄から郎党が従ったとされ、『東家一統』(『和良村史』資料編)によれば、「御一族野田左近殿、遠藤左門殿」、「御家老埴生」、他には「日置、餌取、和田、石神、猪又、土屋、村山、河合、市村、升田、森、長田、梶原、中村、田中、山本」らの名が見える。
東行氏の母は新古今和歌集撰者の京極中納言定家の子・中院為家の娘と伝えられているが、系譜に該当する女性は見えない。しかし、室町八代将軍・足利義政のころには、行氏の子孫である東下野守常縁が古今和歌集の解釈(御子左流の一流・二条流の解釈)を伝える古今伝授を「切紙」という形で行い、連歌師・飯尾宗祇へ伝授された。宗祇が伝受された「古今(切紙)伝授」は、宗祇から公卿の三條西実隆へ、さらに子の三条西公條、孫の三条西実枝へと伝えられ、細川幽斎玄旨へと伝えられていく。
そして、東氏に仕えた遠藤氏は、鎌倉時代から室町時代に渡って郡上遠藤氏の重臣として活躍。郡上郡各地に一族が繁栄し、大きな勢力を築いた。そのためか、郡上東氏との間に抗争が起こっていたことが各古文書からうかがうことができる。そして室町時代後期、遠藤六郎左衛門尉盛数は義父の東下野守常慶入道素忠を居城の赤谷山城に攻めて殺害した(自害とも、翌年まで生きたともいわれる)。また、義兄で郡上東氏惣領・東七郎常堯を郡上郡から追放して郡上東家を滅ぼした。遠藤盛数は下克上の典型的な人物であったと推測される。
遠藤盛数は東氏の支配していた郡上郡を継承して治め、妻の東下野守常慶娘(友順尼)との間に生まれた遠藤新六郎慶隆は、織田信長・豊臣秀吉に仕えたのち、関ヶ原の戦いでは美濃国では数少ない徳川家康の側(東軍)について石田三成方(西軍)の稲葉貞通と戦うなど活躍。戦後、功績によって美濃郡上藩二万七千石の藩主となった。
しかし、五代藩主・遠藤岩松常久がわずか七歳で早世したため、継嗣無きにより断絶の危機に見舞われたが、遠藤家の先祖の働きを思った幕閣の厚意により、将軍家の縁戚に当たる増山弾正忠正利の旧臣で旗本となっていた白須甲斐守政休の子・数馬が美濃大垣藩主・戸田弾正氏成の養子となり、遠藤家の名跡を継いで遠藤但馬守胤親となった。しかし、名跡は残ったものの、法度に従い遠藤家の所領は召し上げとなり、新たに常陸国内などに1万石を与えられることとなった。そしてその2か月後、将軍・徳川綱吉に御目見した胤親は、近江国野洲郡三上などに所領を移され、陣屋を三上に置いて三上藩を立藩し、明治に至った。明治になって、子爵に叙爵された遠藤但馬守胤城は、勅許を得て「東」に復姓した。
 (????-????)
(????-????)
美濃遠藤氏初代。通称は八左衛門尉。系譜上では東下野守常縁の末子とされているが、盛胤の名は常縁の文書や常庵龍宗(常縁の子)の文書、三条西実隆などの文書にもまったく現れておらず、実際は東家重臣・遠藤氏の末裔だろう。「盛胤」は遠藤慶隆が郡上城主になった頃、先祖「盛胤」は常縁の子であるとされた可能性も否定できない。
延徳3(1491)年8月6日、「東中務被官」の「遠藤但馬守」以下四名が「中務」の命により京都四条で討ちとられているが(『蔭涼軒日録』)、時代的に見ると盛胤の代にあたる。
遠藤家は東氏初代・東六郎大夫胤頼の舅・遠藤左近将監持遠を祖とするとされ、持遠の子・遠藤武者所盛遠はのちの高尾の文覚上人で、東六郎大夫胤頼とも旧知の間柄であった。伝承によれば、文覚の子・遠藤左近将監盛広は鎌倉幕府御家人となり、その子・遠藤兵庫頭盛正は頼朝の死後、祖父・土岐美濃守光衡の所領がある美濃国に移り住み、土岐判官代光行の幕下に加わりったという。そしてその子・遠藤太郎右衛門尉治盛は、美濃国厚見郡に移り、その子・遠藤小太郎盛勝は土岐光定・頼貞に仕え、暦応3(1340)年5月3日に亡くなったという。その子孫・遠藤胤任は土岐頼芸に仕えていたが、斎藤道三によって討たれたため浪人。その後、斎藤義龍に仕えたという。この遠藤氏と東氏重臣遠藤家との関係は不明(『美濃明細記』)。
東氏と遠藤氏の関係が具体的な文書で見ることができるのは、公家の勘解由小路兼仲の日記である『勘仲記』の記載である。弘安7(1284)年12月9日、新日吉の小五月会で七番の流鏑馬が行われた際、その五番手を「東六郎左衛門尉平行氏法師」が勤め、射手として「遠藤左衛門三郎盛氏」が見える。この遠藤盛氏は東行氏入道素道の郎党であり、代々東家に仕え、江戸時代の郡上藩主遠藤家の祖となった人物か。
●弘安7(1284)年12月9日新日吉小五月会流鏑馬交名(『勘仲記』増補史料大成所収)
| 射手 | 的立 | ||
| 一番 | 武蔵守平時村 | 伊賀右衛門六郎藤原光綱 | 福田寺太郎兵衛尉藤原行實 |
| 二番 | 備後民部大夫三善政康 | 牧右衛門四郎藤原政能 | |
| 三番 | 葛西三郎平宗清 | 富澤三郎平秀行 | |
| 四番 | 肥後民部大夫平行定法師 法名寂圓 | 宮地彦四郎清原行房 | |
| 五番 | 東六郎左衛門尉平行氏法師 法名素道 | 遠藤左衛門三郎盛氏 | |
| 六番 | 頓宮肥後守藤原盛氏法師 法名道観 | 奥野二郎太郎源景忠 | |
| 七番 | 後藤筑後前司基頼法師 法名寂基 | 舎弟壱岐十郎基長 |
室町時代中期では、明徳3(1392)年8月25日に行われた相国寺供養で東氏と遠藤氏の関係を見ることができる。参列した武士の3番手に連なったのが東下総守師氏だが、彼の介添として遠藤修理亮顕基・遠藤新左衛門尉顕保・遠藤郡左衛門大夫顕久・遠藤兵庫助氏遠の名がある。「顕基」「顕保」「顕久」の三名は、東下総守常顕から偏諱を受けた人物と思われ、「氏遠」は東下総守師氏からの偏諱であると考えられ、東氏に仕えて重きをなしていたことがうかがえる。
東下野守常縁の被官に「遠藤越中守基保」があり、太田道灌が心敬法印、木戸孝範ほか都人らを招いて行った江戸の天照大神社千句(文明6(1474)年の江戸歌会?)において、短冊の上下の向きについて誰も見分けることのできなかったことを指摘するなど(『会席作法』部分:『中世歌壇史の研究 第四章』)、遠藤家にも歌道に長じた人物があったことがうかがえる。この遠藤基保は「基」という一字から勘考して明徳3(1392)年8月25日の相国寺供養に参列した「遠藤修理亮顕基」の子孫かもしれない。
遠藤盛胤について「遠藤左馬助盛隆」の子「遠藤小太郎盛胤」として『美濃明細記』に見ることができる。
●『美濃明細記』より遠藤家系譜抜粋(『大日本史料』所収:国立国会図書館)
⇒高棟王―<七代>―遠藤持遠――盛遠―――盛広――――平盛正―+―盛勝―――隆盛―――+―隆常
(大納言) (袒) (武者所)(左近将監)(兵庫頭)|(小太郎)(新兵衛尉)|(大隈守)
| |
+―娘 +―盛行――+
(竹中重実妻) (信濃守)|
|
+―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――+
|
+―遠藤持盛――+―盛隆――――――――――――――――――――――――盛胤――――+―基常
遠藤小太郎 | 遠藤小太郎 遠藤小太郎 | 遠藤小次郎
但馬守 | 左馬助 但馬守 |
號周勝伯 | 號周栄 號素山 +―盛長――――――+
| 持氏生害後、父子共流浪、宝徳元年、仕将軍義政、 遠藤新左衛門尉 |
| 賜濃州之領地、享徳、康正年中有軍功、文明元年、 左近太夫 |
| 於九州有軍功、後仕義尚、同九年皈濃州、同年卒、 號忠山 |
| |
+―盛重 |
(内匠助) |
|
+―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――+
|
| 東常慶―――――――――――――娘
| (下野守) ∥―――――――慶隆
| ∥ ∥ 但馬守
| ∥――?――――東常堯 +―盛数
+―盛直――――――――盛好――――――好任――――+―娘 (七郎) | 六郎左衛門尉
遠藤六郎左衛門尉 遠藤新八郎 遠藤小八郎 | |
號常巌 太郎左衛門尉 新兵衛尉 +―胤任――――――胤好―――+―胤縁――――――胤基
但馬守 太郎左衛門尉 小八郎 八兵衛 大隈守
「但馬守盛胤」の父「左馬助盛隆」とその父「但馬守持盛」は鎌倉公方・足利持氏に仕え(奉公衆?)、「持盛」の「持」は足利持氏よりの偏諱かも? 持氏は永享11(1439)年に関東管領・上杉憲実の命を奉じた上杉持朝・千葉介胤直によって討たれており、遠藤持盛・盛隆は落ち延びて流浪し、宝徳元(1449)年に将軍・足利義政(当時は義成)に仕えたとされる。「享徳、康正年中有軍功」とは、幕府(上杉家)と足利成氏との戦いのことと思われ、東常縁に随い、関東に下っていたのかもしれない。「文明元年、於九州有軍功」とは文明元(1469)年5月に足利義視・細川勝元に呼応して挙兵した大友親繁・少弐頼忠と戦ったということを指すものか? 文明9(1477)年、盛隆は「皈濃州(美濃に帰る)」、美濃で亡くなったようである。
そしてその子・但馬守盛胤は、『東氏系図』の遠藤八左衛門盛胤とほぼ同時代の人物であり、同一人物か。『美濃明細記』では盛胤の次男後、遠藤左近太夫盛長から遠藤六郎左衛門尉盛数まで六代を数え、世代的に疑問がある。盛長の孫にあたる遠藤新兵衛好任は土岐美濃守盛頼に仕えたとされ、好任の母は「竹中遠江守重元娘」とあることから、天文13(1544)年生まれの竹中半兵衛重治の姉妹ということになる。「竹中重元」はその父「竹中重氏」の誤記かもしれないが、その遠藤新兵衛好任の娘が「東下野守常慶室」とあり、世代が逆転しているなど、混乱が見られる。『美濃明細記』は江戸中期の元文3(1738)年に成立した近世文書であるため信憑性の程は不明だが、遠藤盛胤という人物が実際にいて郡上藩主遠藤氏の遠祖として伝わっていたのだろう。
■遠藤盛胤の周辺系図■
三木自頼――――+―自綱――+―――――――直綱
(右兵衛督) |(大納言)| (右近大夫)
| | ∥―――――――――慶利
+―娘 +―娘 +―智勝院 +―娘 (但馬守)
|(猪俣五平次妻) ∥ ∥ | ∥
| ∥ ∥ | ∥
+―娘 ∥ ∥ +―娘 板倉重宗娘
|(内ヶ嶋意休妻) ∥ ∥ |(粥川孫左衛門妻)
| ∥ ∥ |
+―娘 ∥ ∥―――+―慶勝
|(石徹白彦右衛門妻) ∥ ∥ (長門守)
| ∥ ∥
+―娘 +―慶 隆
|(鷲見忠左衛門妻)|(左馬助)
| | ∥
+―娘 | ∥―――――――――――娘
|(鷲見竹本坊妻) |安藤守就娘 (金森可重妻)
| |
+―娘 +―慶胤
|(餌取太兵衛妻) |(美濃助)
| |
+―娘 +―慶直
|(松井喜右衛門妻)|(久三郎)
| |
東常縁―+―常和―――――常慶――――+―常堯 +―娘
(下野守)|(下野守) (下野守) |(七郎) |(遠藤彦右衛門胤重妻)
| | |
+―常庵龍崇 +―友順 +―娘
|(建仁寺住持) ∥ |(遠藤大隅守胤基妻)
| ∥ |
+―胤氏 ∥―――――――+―娘
(最勝院素純) ∥ (山内対馬守一豊妻)
∥
…―遠藤盛胤―――胤好――――+―盛数
(八左衛門尉)(新兵衛) |(六郎左衛門尉)
|
+―胤縁――――――+―胤俊―――――+―娘
(新兵衛) |(大隈守) |(遠藤助次郎慶胤妻)
| |
+―胤基 +=胤基――――胤直
|(大隈守) (大隈守) (小八郎)
|
+―胤重―――――+―加兵衛
|(彦右衛門) |
| |
+―胤安 +―五郎
(吉左衛門)
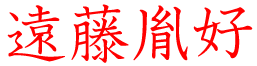 (????-????)
(????-????)
美濃遠藤氏2代。遠藤八左衛門尉盛胤の嫡男と伝わる。通称は新兵衛。
具体的な活躍などは一切不明。『寛永諸家譜』『寛政重修諸家譜』にも事歴がなく、実在の人物かどうかも不明。
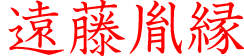 (????-1559?)
(????-1559?)
美濃遠藤氏3代。遠藤新兵衛胤好の嫡男と伝わる。通称は新兵衛。郡上郡木越城主(郡上郡大和町神路)。
 |
| 朝倉勢の千人塚(左と右の土盛) |
天文9(1540)年8月25日、朝倉義景が越前から美濃国郡上郡に攻め込んできた際、篠脇城にあった東下野守常慶は篠脇城へ籠城して頑強に抵抗。越前との国境に当たる白山長瀧寺に本陣を置いた朝倉勢は、篠脇城まで軍勢を派遣して猛攻を続けたが、城は落ちなかった。おそらく遠藤新兵衛胤縁・遠藤六郎左衛門尉盛数の兄弟も活躍をしたのだろう。
9月23日、朝倉勢の残党も追い討ちによって壊滅し、東勢によって討たれた朝倉勢の遺体で、越前への道が三日間にわたって不通になったという。この道を「三日坂」といい、討たれた朝倉勢の首塚が「千人塚」として残されている(『荘厳講記録』『郡上藩家中記録』)。
●『荘厳講記録』(『長滝寺文書』:「白鳥町史」)
この年、長滝寺の南、小駄良郷(郡上市白鳥町向小駄良)の領主・和田氏が常慶に討たれており、この事件は朝倉氏の郡上侵入と何か関係があるのかもしれない。
常慶は天文年中、小駄良郷に勢力を張っていた東氏一族の和田五郎左衛門がしばしば常慶の命に随わなかったため、常慶は天文9(1540)年、遠藤胤縁・遠藤盛数に謀り、篠脇城に呼び寄せて暗殺し平定したという(『郡上郡史』)。
この朝倉氏との戦いののち、常慶は篠脇城の南、吉田川に沿った赤谷山(郡上郡八幡町島谷)に新たな城を築いたようである。このころ常慶は嫡男・七郎常堯に家督を譲ったが、系譜では常堯は粗暴で人望がなかったとされる人物であったとされている。ただし、常堯の粗暴な性格というのは東氏から遠藤氏への家督相続の正当性をはかるために記載された可能性もある。
同じく伝承では、常堯は胤縁の娘を妻に欲したが、胤縁は常堯を信頼せず、密かに畑佐備後守信胤の子息、畑佐六郎右衛門信国に娘を嫁がせた。これを恨みに思った常堯により、胤縁は永禄2(1559)年8月1日、「八朔の礼」のために登城してきたところを射殺されたという。法名は祐心。木越城を守っていた弟・盛数は、兄の訃報を聞くや兵を集め、8月24日に東氏を滅ぼしたという。
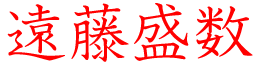 (????-1562?)
(????-1562?)
美濃遠藤氏4代。遠藤新兵衛胤好の次男。通称は六郎左衛門。のち左馬助か。妻は東下野守常慶娘(照用院友順)。
伝承によれば、盛数は永禄2(1559)年8月1日、兄の遠藤新兵衛胤縁が赤谷山において東七郎常堯に暗殺されると、常堯の非を訴えて土豪たちを集め、赤谷山城に攻め寄せた。そして8月24日、妻の父・東下野守常慶が自害して城は陥落。常堯は飛騨白川郷の舅・内ヶ島氏理を頼って落ち、承久以来三百年続いた郡上東氏は滅亡した(『寛政重修諸家譜』)。
盛数は郡上郡を手中にすると、赤谷山城と吉田川をはさんだ対岸にある八幡山に城を築いて本城とした。郡上八幡城である。一方、暗殺された胤縁の子・遠藤新兵衛胤繁(胤基)は遠藤家代々の居城・木越城を領し、盛数は郡上郡東部を、胤基は西部を二分して支配することとなった。
| 遠藤盛数の旗下 | 遠藤胤基の旗下 | |||
| 領地 | 名前 | 領地 | 名前 | |
| 和良三方の内 | 遠藤清左衛門(和良遠藤氏) | 小駄良村 | 遠藤宗兵衛(小駄良遠藤氏。遠藤胤俊家老) | |
| 和良内九ヵ村 | 遠藤清兵衛(和良遠藤氏) | 小駄良村内 | 遠藤善兵衛(宗兵衛弟。胤俊家老) | |
| 大矢近所七ヵ村 | 遠藤六兵衛(和良遠藤氏) | 寒水村 | 遠藤善右衛門(寒水遠藤氏) | |
| 栗栖郷 | 遠藤新左衛門(鎌倉遠藤氏) | 穀見近所七ヵ村 | 石神兵庫(胤俊舅) | |
| 鈴原 | 遠藤新三左衛門(遠藤盛数家老) | 鶴儀村 | 野田五右衛門 | |
| 栗栖の内 | 日置主計 | 栗栖郷之内 | 別府弾正 | |
| 栗栖の内 | 柳生宗左衛門 | 中津屋村 | 別府喜四郎 | |
| 鷲見郷 | 鷲見兵庫 | 大間見郷 | 鷲見弥兵衛 | |
| 牛道郷 並越前 穴馬内 |
猪俣五平次 | 吉田市島 | 吉田左京進 | |
| 下川南方十四村 | 餌取六右衛門(盛数妻姉妹の義父) | 久須見 | 和田仁兵衛 | |
| 粥川村 苅安村 |
粥川甚右衛門 | 川佐河戸 寺畑 |
箕島弥兵衛 | |
| 下ノ保乙原 近所五村 |
河尻五郎左衛門 | 小野 | 竹村弥平五 | |
| 中ノ保内 久間村 |
池戸若狭守(遠藤清左衛門婿) | 畑佐近所五ヵ村 | 畑佐備後(遠藤慶隆従弟) | |
| 島馬場村 | 村山半兵衛 | 徳永村 | 土屋氏 | |
| 大島村 | 鷲見兵助 | 那比郷 | 武藤氏 | |
| 為真村 | 丹羽五郎左衛門 | 鶴佐府路小野 | 田口氏 | |
| 那比村 | 可児氏 | 久須見内 | 大坪氏 | |
| 気良村 | 佐藤氏 | |||
永禄4(1561)年、織田信長と齋藤龍興の戦いでは、齋藤勢の将として美濃国墨俣に出陣。砦を築こうとする織田家重臣の佐久間信盛や柴田勝家を敗退させる功績を立てるが、織田方の木下藤吉郎(のちの豊臣秀吉)が墨俣に砦を築いてしまうと、織田勢はそこを足がかりに齋藤家の居城である稲葉山城下に迫った。永禄5(1562)年10月14日、織田勢を防ぐため、盛数は稲葉山城の城下町、井口に布陣したが討死を遂げたという。法名は西順。墓所は刈安村戸谷寺(戸谷山乗性寺)。
しかし、盛数は元亀2(1571)年9月18日、遠藤新兵衛胤繁(胤基)とともに遠藤家と親交の深かった安養寺に対して文書を発給している文書(『遠藤盛数・胤繁連署状』)や、天正2(1574)年6月4日、盛数が子・遠藤慶隆の所領について白山長瀧寺へ宛てた文書などがあるが、これらは慶隆の書状を盛数のものとしたものか。
遠藤家の嫡流は兄にあたる遠藤胤縁であったと考えられ、「胤」字は遠藤家よりの偏諱と思われる。一方で盛数は庶流でありながら主君・常慶の娘を娶って東家の一門になるなど、常慶からの寵愛は一方ならぬものがあったようである。しかし、盛数は常慶の重用に対して謀反で応えた様子が史料からうかがえる。江戸時代に藩主・遠藤家から干渉を受けなかったと思われる藤村家(東家旧臣の家柄で帰農)の文書『開発之伝記』(『和良村史資料編』所収)には、
とあり、盛数は飛騨松倉城主の三木氏から援軍を請い、甥の遠藤大隈守胤基の兵を率いて東殿山に奇襲をかけて、主君であり義父でもある常慶を討ったとされる。その時期は遠藤家側の系譜が伝えている永禄2(1559)年8月24日ではなく、弘治元(1555)年8月1日のことであったという。前年の天文23(1554)年秋より三木氏の郡上郡内押領が起こっており(『荘厳講執事帳』:「白鳥町史」所収)、遠藤盛数は東氏から郡上郡を奪取するため、密かに飛騨三木氏と結んでいたことが推測される。『遠藤記』によれば、常慶が嫡子・東七郎常堯に家督を譲ろうとしていたのが弘治年中の事であるとされており、盛数は常堯の家督相続に反対しての謀反であったのかもしれない。
また、盛数が東氏を討つ大義名分となっていた永禄2(1559)年8月1日の兄・遠藤胤縁の暗殺についても、弘治元(1555)年8月1日の時点で胤縁の子「遠藤大隈守胤基」がすでに活躍をしている様子がうかがえ、この時すでに遠藤胤縁は亡くなっていたものと推測される。両事件ともに8月1日(八朔)の事であり、遠藤盛数が八朔の礼を利用して赤谷山を焼き討ちしたというのが真相かもしれない。
その後、遠藤盛数は事実上の郡上郡の主となり、東七郎常堯は妻の実家である飛騨帰雲城の内ヶ島氏を頼り、東氏再興のために出兵を繰り返したと思われる。永禄2(1559)年8月、白山長滝寺も兵乱によって相当の被害を受け、「満山悉ク方々ヘ退散仕候」という事態に陥った様子がうかがえる(『荘厳講執事帳』:「白鳥町史」所収)。
●『千葉大系図』
⇒遠藤胤好―+―盛数
(新兵衛) |(太郎左衛門尉)
|
+―胤縁―――――胤俊―――胤基―――胤直
|(新兵衛尉) (大隈守)(大隈守)(小八郎)
|
+―胤繁―――+―胤慶
(宗兵衛) |(宗兵衛)
|
+―胤勝
|(加賀守)
|
+―胤春
|(吉兵衛)
|
+―娘
(遠藤太郎兵衛)
●『小駄良遠藤系図』
⇒+―遠藤惣兵衛―+―惣兵衛 +―等覚坊澄栄
| | |
| +―遠藤太郎兵衛妻 +―遠藤太郎兵衛
| | |
| +―加賀守―――――+―福寿坊澄嘉―――等覚坊実賢――福寿坊秀賢――等覚坊栄賢
| |
| +―石神吉兵衛 +―娘
| | |
| +―奥之坊―――――――遠藤勝吉――+―河合吉兵衛
|
+―遠藤善兵衛―――太郎兵衛――――+―松山八蔵――+―佐助
| |
+―小兵衛 +―伝十郎
|
+―甚左衛門
|
+―某
|
+―清兵衛
|
+―六右衛門
●永禄5(1562)年10月14日『遠藤盛数書状』(『郡上藩家中記録』:郡上八幡町史所収)
●元亀2(1571)年9月18日『遠藤盛数・胤繁連署状』(『郡上藩家中記録』:郡上八幡町史所収)
●天正2(1574)年6月4日『遠藤盛数書状』(1)(『郡上藩家中記録』:郡上八幡町史所収)
●天正2(1574)年6月8日『遠藤盛数書状』(2)(『経聞坊文書』:岐阜県史 史料編 古代・中世一所収)
●某年7月12日『遠藤盛数書状』(『郡上藩家中記録』:郡上八幡町史所収)