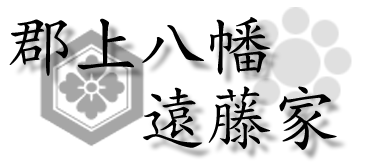
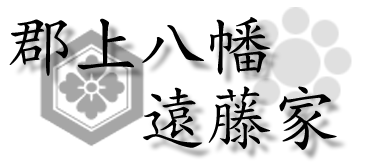
●郡上藩・三上藩遠藤家
| 郡上藩・三上藩の概要 | 美濃郡上藩主 | 近江三上藩主 | 郡上遠藤家 |
| 木越遠藤家 | 乙原遠藤家 | 和良遠藤家 |
●東氏の歴代
| 郡上東氏 | 郡上東氏歴代 | 東氏惣領家 | 須賀川東家 | 森山東家 |
| 土佐藩遠藤家 | 木曾遠藤家 | 田中藩遠藤家 | |
| 苗木藩東家 | 土佐藩東家 | 小城藩東家 | 医官東家 |
●郡上藩歴代藩主
| 代数 | 名前 | 生没年 | 就任期間 | 官位 | 官職 | 父親 | 母親 | 法名 |
| 初代 | 遠藤慶隆 | 1550-1633 | 1601-1632 | 従五位下 | 但馬守 | 遠藤盛数 | 東常慶娘 | 乗性深心院 |
| ―― | 遠藤慶勝 | 1588-1615 | ―――― | 従五位下 | 長門守 | 遠藤慶隆 | 三木良頼娘 | 明心大神院 |
| 2代 | 遠藤慶利 | 1609-1646 | 1632-1646 | 従五位下 | 但馬守 | 三木直綱 | 遠藤慶隆娘 | 至誠院乗雲 |
| 3代 | 遠藤常友 | 1628-1675 | 1646-1675 | 従五位下 | 備前守 | 遠藤慶利 | 板倉重宗娘 | 常敬院素信 |
| 4代 | 遠藤常春 | 1667-1689 | 1676-1689 | 従五位下 | 右衛門佐 | 遠藤常友 | 戸田氏信娘 | 恵正院素教 |
| 5代 | 遠藤常久 | 1686-1692 | 1689-1692 | 従五位下 | ―――― | 遠藤常春 | 側室某氏 | 本了院素道 |
●三上藩歴代藩主
| 代数 | 名前 | 生没年 | 就任期間 | 官位 | 官職 | 父親 | 母親 | 法名 |
| 初代 | 遠藤胤親 | 1683-1735 | 1692-1733 | 従五位下 | 但馬守 | 白須政休 | 小谷忠栄娘 | 宝地院素吟 |
| 2代 | 遠藤胤将 | 1712-1771 | 1733-1771 | 従五位下 | 備前守 | 遠藤胤親 | 久松氏娘 | 大心院素江 |
| 3代 | 遠藤胤忠 | 1732-1791 | 1771-1790 | 従五位下 | 下野守 | 遠藤胤親 | 田所氏娘 | 東覲院素秋 |
| ―― | 遠藤胤寿 | 1760-1781 | ―――― | ―――― | ――― | 遠藤胤忠 | 青木氏娘 | 心開院素練 |
| ―― | 遠藤胤相 | 1761-1814 | ―――― | ―――― | ――― | 酒井忠与 | 西村氏娘 | 霊信院素淳 |
| 4代 | 遠藤胤富 | 1761-1814 | 1790-1811 | 従五位下 | 左近将監 | 松平信復 | 小林氏娘 | 自得院素行 |
| 5代 | 遠藤胤統 | 1793-1870 | 1811-1863 | 従四位下 | 中務大輔 | 戸田氏教 | 猿田氏娘 | 敬武徳院素中 |
| ―― | 遠藤胤昌 | 1804-1855 | ―――― | ―――― | 式部少輔 | 松平義和 | 某氏娘 | 直諒院素温 |
| 6代 | 遠藤胤城 | 1838-1909 | 1863-1909 (藩知事含む) |
従五位下 (贈正三位) |
但馬守 (子爵) |
遠藤胤統 | 小谷氏娘 |
| 初代藩主 |
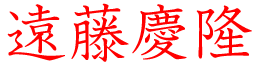 (1550-1633)
(1550-1633)
| <名前> | 慶隆 |
| <通称> | 三郎四郎→新六郎→左馬助→旦斎(剃髪号) |
| <正室> | 伊賀伊賀守範俊女(安藤伊賀守守就娘) |
| <正室2> | 三木右兵衛督良頼女(智勝院殿) |
| <正室3> | 姉小路大納言自綱女 |
| <父> | 遠藤六郎左衛門盛数 |
| <母> | 東下野守常慶女 |
| <官位> | 従五位下 |
| <官職> | 但馬守 |
| <就任> | 慶長5(1601)年~寛永9(1633)年正月 |
| <法号> | 深心院殿釋乗性旦斎大居士 |
| <墓所> | 郡上市美並町白山の深心院乗性寺 九耀山長敬寺(郡上市内) |
―遠藤慶隆事歴―
郡上藩初代藩主。父は遠藤六郎左衛門尉盛数。母は東下野守常慶娘(照用院友順)。通称は新六郎、六郎左衛門。永禄5(1562)年10月14日『遠藤盛数書状』文書内の「我々女共三郎はしめ・・・」の「三郎」は慶隆か。
遠藤盛数
(六郎左衛門尉) 【郡上藩主】
∥――――――――遠藤慶隆
東常慶―+―娘 (但馬守)
(下野守)|(照用院友順)
|
+―東常堯
(七郎)
天文19(1550)年、美濃国山田庄木越城に生まれた。慶隆の「慶」は祖父・東下野守常慶からの偏諱であると考えられ、東下野守常慶入道素忠が慶隆の父・遠藤盛数に攻められ、自刃したと思われる弘治元(1555)年8月1日(『藤村氏系図』)よりも前に元服していたか。
遠藤新六郎慶隆の父・遠藤盛数は永禄5(1562)年10月14日に織田上総介信長と齋藤右兵衛太夫龍興との戦いの中で齋藤方に味方し、稲葉山城下井ノ口にて討死したという。これによって慶隆は十三歳で家督を継ぎ、遠藤新蔵左衛門を家老として斎藤龍興に仕えた。
 |
| 苅安林広院 |
永禄7(1564)年8月、織田信長が美濃国稲葉山城を占領して斎藤家が滅亡すると、稲葉山城にあった慶隆の母・東氏と弟・遠藤助次郎慶胤らは「武儀郡フセ村」に退いたが、その頃、遠藤大隈守胤俊が郡上郡を押領する事件があり、武儀郡にも兵を向けたという。遠藤盛数の永禄5(1562)年の書状に「其四之事ハ大すミうけ取被申候」とあることから、遠藤胤俊は叔父の遠藤盛数から家政について何らかの指示を受けていたことが察せられる。胤俊は郡上郡の安定のために郡上一帯に兵を廻していたのかもしれないが、慶隆側はそれを敵対と受け取ったか、慶隆と餌取六郎右衛門、粥川甚右衛門の両名は武儀郡に走って慶隆母と弟達を郡上の南、林広院城に迎えた。こののち、慶隆は織田家に従っている。
+―遠藤胤縁――+―遠藤胤俊
|(新兵衛) |(大隅守)
| |
| +―遠藤胤繁
| (新兵衛)
|
+―遠藤盛数――――遠藤慶隆
(六郎左衛門尉)(左馬助)
永禄8(1565)年、慶隆が若年であるということで、胤俊が郡上郡の支配を行うこととなり、慶隆は林広院城のある苅安村から北に入ることができなくなってしまった。これに慶隆の重臣である粥川甚右衛門は長井隼人正道利、佐藤将監清信らに援助を頼み、慶隆を奉じて山田庄に攻め入ると、胤俊は和談を申し出て人質を送り、以前のように両遠藤家で半郡ずつ知行することとなった。
永禄9(1566)年、慶隆は美濃三人衆とよばれた有力豪族である安東伊賀守守就の娘を娶ることとなった。このとき慶隆十七歳、安東氏十三歳であった。そして慶隆は仮名の「新六郎」を「六郎左衛門」と改め、織田信長のもとで大いに出精したという。この年、長女が誕生しているが、遠藤氏系譜では母は正妻安東氏とされている。この長女は成人してのちは「室町様」とよばれ、飛騨高山城主・金森長近法印の長男、金森出雲守可重に嫁ぐことになる。
永禄10(1567)年9月、慶隆は郡上郡本領安堵の判物が下された。
永禄年の末、飛騨国司・姉小路家が郡上の侵略を企てて、畑佐村に侵入してきた。畑佐・気良の諸士も姉小路家に一味して攻目寄せたため、慶隆は遠藤清左衛門を、胤俊は遠藤左近右衛門を大将とする軍勢を派遣し、久須見において合戦となった。この戦いは、遠藤左近右衛門の弟・遠藤五郎助が討死を遂げ、さらに遠藤家と入魂の安養寺乗了の門徒である円覚坊・正専坊・妙専坊らがやはり討死を遂げる激しい戦いとなった。結局、戦いは遠藤家側の勝利に終わり、姉小路勢は飛騨へ退却していった。慶隆・胤俊は気良・畑佐の反乱の士に厳罰で臨み、郡上郡内の引き締めを図った。また、姉小路自綱の妹が和平の証として慶隆の側室として迎えられ、祝言が挙げられた。
両遠藤家は美濃可児郡金山城の織田家重臣・森三左衛門可成に付属し、元亀元(1570)年に起こった織田家・徳川家と浅井家・朝倉家の戦いの中で6月、近江国横山城攻めが行われ、胤俊・慶隆は奮戦して高名を挙げた。そして6月29日、慶隆・慶胤兄弟は姉川の陣での働きを信長より賞された。このとき慶隆二十歳、慶胤十七歳。
9月16日、朝倉義景・浅井長政は森三左衛門可成が籠もる宇佐山城を攻めた。可成は城を出て合戦し、討死を遂げてしまうが、このとき、胤俊・慶隆は手勢を引き連れて救援に赴いており、信長から賞された。
11月26日、近江堅田において坂井政尚の手勢に加わった両遠藤家は、織田勢の先陣を勤めたが、奮戦空しく浅井勢の鋭鋒に坂井勢は壊滅。大将・坂井政尚は討死を遂げた。さらに属将として加わっていた胤俊も手勢五百名とともに命を落としてしまった。胤俊には子がなく弟・遠藤新兵衛胤繁が跡を継ぐこととなった。
+―遠藤胤縁――+―遠藤胤俊===遠藤胤繁(胤基)
|(新兵衛) |(大隅守) (大隅守)
| |
| +―遠藤胤繁(胤基)
| (大隅守)
|
+―遠藤盛数――――遠藤慶隆
(六郎左衛門尉)(左馬助)
元亀3(1572)年ごろから西上の気配を見せはじめていた武田信玄は、美濃にも調略の手を伸ばしつつあり、両遠藤家も5月頃から武田家と通じるようになった。これは織田家には内密で進められていたことのようで、胤繁は小駄良遠藤家で家老の遠藤胤勝(加賀入道市入斎)を武田信玄に派遣して外交をさせていたようである。遠藤家は武田信玄や浅井長政と通じ、織田家と二股をかけていたことがうかがえる。美濃に調略の手を広げていた強大な武田家に比べて遠藤家は小さな領主にすぎず、生き残るための外交を活発化させていたと考えられる。元亀3(1572)年9月26日、信玄は遠藤加賀守を通じ、胤繁へ信州に百貫の地を与える旨を約した(元亀3(1572)年9月26日『武田信玄判物写』)。
11月14日、武田家の重臣・秋山伯耆守信友が織田方の東美濃岩村城を攻め落とした。信玄は遠藤胤勝へ岩村城の攻落を報じ、「岐阜へ可被顕敵対之色哉否」と、信長へ反旗を翻すのか否かを問うてきている(元亀3(1572)年11月19日『武田信玄書状写』)。
翌15日、浅井長政は、武田家の使者から木越城主・胤繁が信玄に通じていることを聞き、「殊貴辺種々御馳走之由、快然至極候」とし、さらに遠江・三河が信玄の支配下となったことは「珍重比事候」と記して、胤勝を通じて胤繁へ書状を送っている(元亀3(1572)年11月15日『浅井長政書状写』)。
12月12日、信玄は「当年過半任存分候、幸岩村へ移人数候之条、明春者、濃州へ可令出勢候」と、すでに美濃の過半は武田領となり、岩村城にも秋山伯耆隊が入城し、来春にも本格的に武田勢を美濃へ差し向ける旨を伝えた。そして「其已前向于岐阜、被顕敵対之色候之様」と、美濃攻めをする前に織田家から離反するよう遠藤加賀守へ指示している(元亀3(1572)年12月12日『武田信玄書状写』)。
そして同月、上洛のため遠江国へ攻め込んだ武田信玄は、徳川家康の居城・浜松城前に広がる高台・三方原に兵を進めた。信玄は家康に戦いを挑むことなく眼前を通り過ぎるが、家康は怒って寡勢で攻めかかった。しかし、徳川勢は大軍の武田勢の前にあっけなく敗れ、家康は数多くの家臣を失いながらも浜松城へ逃れ、宿臣・酒井忠次の機転で難を逃れている。
しかし翌年4月、信玄は信濃国伊奈郡駒場の陣中にて急死する。そのため武田勢は潮がひくように甲斐国へ退き、援軍のなくなった秋山信友籠る岩村城も織田勢に攻め落とされ、城主・秋山信友は捕えられて長良川原に磔刑に処された。こうして、武田家による美濃攻めは実現せず、遠藤家の離反の企ては信長に知られることはなかったようである。
天正10(1582)年、信長は中国地方の毛利家を討つため、自ら出陣し、京都の本能寺に本陣を構えた。しかし、6月2日未明、この本能寺に織田家宿将・惟任日向守光秀(明智光秀)が謀反を起こして攻めかかり、織田信長は亡くなった(本能寺の変)。
この変ののち、織田家内では家督争いが激しくなり、天正11(1583)年正月、柴田勝家が擁立した織田信孝(信長三男。実は次男)と、信長嫡孫・三法師(のちの秀信)を擁立する羽柴秀吉との間で織田家の跡目を巡って戦いがおこった。両遠藤は一族とともに美濃国主・織田信孝に属して挙兵した。一方、武儀郡の国人たちは秀吉に加担し、須原城・洞戸城に拠って、遠藤氏の郡上郡と織田信孝の岐阜城との連絡を断った。このため、両遠藤氏は三百余の兵を繰り出して両城を攻め落として立花山まで進み、岐阜城の信孝と連絡をとることに成功した。
閏正月8日、秀吉は遠藤氏追討のため、森武蔵守長可・佐藤六左衛門秀方の両将に出陣を命じ、森・佐藤両将は大軍で立花山に襲いかかった。これに対して遠藤氏の軍勢はわずかであり、「遠藤新兵衛(胤基)」は岐阜城に援軍を求め、信孝からは援軍の承諾と守備を固める書状が届けられた(天正11(1583)年正月12日『織田信孝書状』(1)・天正11(1583)年正月12日『織田信孝書状』(2))。
援軍を待つ間にも森・佐藤勢の攻撃は続き、遠藤勢は遠藤清左衛門、池戸与十郎、井上作右衛門などの重臣が討死を遂げている。ただ、立花山は堅固だったためいっそう守備を固め、森・佐藤勢はやむなく山を包囲して長期戦の構えに入った。
しかし、織田信孝方の主将・柴田勝家が越前国北ノ庄城で秀吉に攻め滅ぼされると、信孝は意気消沈し、秀吉に組していた異母兄・織田信雄(実際は弟)からの降伏勧告を受け入れて岐阜城を開城。長良川を下って尾張国に退いた。
一方そのころ、遠藤勢の籠る立花山は糧道を断たれて食糧難に陥っており、熊皮を火で炙って食べるほどの悲惨な状況になっていた。領民のひそかな援助で一時の急をしのいでいたものの、根本的な解決にはならず、胤基・慶隆は「餓えて死するよりは奮戦して潔く死ぬべし」と、山内の兵を集めて総攻撃を企てたようである。しかし、ちょうどこの時、寄手の佐藤秀方の使者が立花山を訪れ、信孝の降伏を伝え、遠藤家も降伏すべしと勧めた。
信孝の降伏によって戦う理由もなくなった胤基・慶隆は、やつれ果てた兵を率いて立花山を下山し、老臣の石神兵庫・遠藤利右衛門の二名を人質に差し出し、降伏した。寄手の総大将・森長可も両遠藤の降伏を喜び、木尾村母野にて会見して和睦を約し、森長可は鞍付馬を両遠藤家に贈呈している。こうして6月、秀吉は森長可の舅である池田恒興入道と子・池田元助に大垣城・岐阜城を与え、美濃は秀吉によって平定された。
池田恒興―+―池田元助
|
+―池田照政(のち輝政)
|
+―娘
∥
森可成――+―森長可(鬼武蔵)
|
+―森蘭丸
天正12(1584)年、秀吉と徳川家康の間で行われた小牧・長久手の戦いでは、慶隆は森長可に従い六百騎を率いて参戦している。しかし、森長可は徳川勢の猛攻を受けて犬山城まで退き、報告を受けた舅・池田恒興入道が子息の池田元助・池田照政らを引き連れ、4月6日、家康の裏をかいて遠江国へ向かう計画を立てた。しかし、家康はこの計画を察知して反撃に出たため、池田恒興・元助父子は討死、森長可は額を鉄砲に射抜かれて死亡した。森勢は大将を討たれて退却し、森勢に従っていた慶隆は遠藤弥九郎・餌取伝次郎・日置主計・猪俣五平治・和田仁兵衛ら武勇の家臣たちを喪った。
その後、秀吉と家康の和睦がなり、慶隆は郡上へ帰還したのだろう。翌天正13(1585)年8月、秀吉は越中の佐々成政を降し、さらに金森長近入道法印に飛騨国主・三木自綱攻めを命じた。長近は美濃国石徹白を通って飛騨に進軍。寄騎として慶隆率いる遠藤勢が加わり、長近の養嗣子・金森可重が攻め入った野々俣口には胤基の子・遠藤小八郎胤直が参戦している。
天正17(1589)年、秀吉は美濃において検地を行い、翌天正18(1590)年、両遠藤家は郡上郡から加茂郡内に移封となり、郡上郡には曽根から移された稲葉貞通(稲葉一鉄嫡子)が入ることとなった。また、慶隆は加茂郡小原に、胤基は加茂郡犬地へそれぞれ入ることとなるが、両地とも砦を館とした小規模な城地で、織田家後継争いに際して、秀吉に敵対した織田信孝の麾下だったことによる懲罰的な意味合いが含まれていたと思われる。
| 名前 | 在所 | 領地 | 計 |
| 遠藤左馬助慶隆 | 美濃加茂郡小原 | 美濃加茂郡内:七千五百石 | 一万五千石 |
| 近江日野郡内:千石 | |||
| 遠藤大隅守胤基 | 美濃加茂郡犬地 | 美濃加茂郡内:五千五百石 | |
| 近江日野郡内:千石? |
●東美濃にての知行
| 石高 | 氏名 |
| 千石 | 遠藤内記 |
| 五百石 | 遠藤助二郎慶胤・遠藤新左衛門 |
| 四百石 | 遠藤長助・鷲見忠左衛門殿・池戸内記・鷲見安三郎・松井縫殿助・遠藤作右衛門 |
| 三百五十石 | 松井勘右衛門 |
| 三百石 | 各務主水・三木三郎・餌取半右衛門・粥川小十郎・粥川左兵衛・辻兵衛・湯浅五郎左衛門・中島嘉右衛門・大江六左衛門・堀治太夫 |
| 水野角兵衛・垣見権右衛門・佐々重兵衛・三島内膳 | |
| 二百五十石 | 石川藤左衛門・小池孫右衛門・村山三右衛門・吉田孫作・原右衛門作・橋本小左衛門・高屋権太夫・仙石伊兵衛・高田長兵衛 |
| 松村四郎兵衛・西脇太左衛門・佐藤治兵衛・早野伝右衛門・加藤忠左衛門・河合武右衛門 | |
| 二百石 | 粥川半兵衛・稲垣九兵衛・東五郎作・服部半右衛門・佐藤平左衛門・豊田小右衛門・山斎太郎兵衛・武光養右衛門・武光伝右衛門 |
| 武光小太夫・納戸茂兵衛・豊前勘兵衛 | |
| 百石 | 伊藤宗喜・豊前徳久・佐藤兵左衛門・牧口六兵衛・餌取作助・餌取長左衛門 |
| 馬廻衆 | 遠藤左門・遠藤孫十郎・池戸蔵人・池戸七郎兵衛・池戸十蔵・遠藤勘平・吉田孫四郎・内ヶ島弥太郎・石井中務丞 |
| 三島最次郎・松井伝右衛門・松井与右衛門・中島嘉右衛門・松井重助・餌取八兵衛・納戸源吾 | |
| 七十石 | 酒井新左衛門・遠藤四郎右衛門・土川六郎右衛門・堀内五左衛門 |
慶隆は三年後の天正18(1590)年の小田原合戦、九戸政実の乱などに四百騎を率いて従軍。朝鮮の陣では、胤基とともに織田秀信(岐阜中納言)に属して朝鮮半島へ渡って戦った。しかし文禄の役終了後、日本へ退却した胤基は、文禄2(1593)年11月23日、長門国国分寺で四十六歳で病死。嫡男・小八郎胤直が相続した。慶隆は胤直とともに美濃へ戻り、慶長3(1598)年8月に秀吉が亡くなると、遺物として「三原の腰刀」を賜っている。
―関ヶ原の戦い―
慶長5(1600)年の石田三成挙兵の際には、織田、伊藤、稲葉といった美濃諸大名が石田三成に荷担する中、慶隆は胤直とともに徳川家康の重臣・榊原康政に忠功を尽くすことを約し、慶隆は居城が要害ではなかった為、飛騨高山城主・金森長近法印素玄に金山家持城のうちの一城を借り受けたい旨を金森家重臣に告げ認められた。このとき長近入道と養嗣子・可重は家康とともに上杉家討伐に向かっていたが、金森家の若殿・金森可重は慶隆の女婿であったため、重臣の独断で許可されたと考えられる。
●遠藤家略系図
斎藤道三―――娘
(山城入道) ∥
∥
三木良頼―+―姉小路自綱――――姉小路直綱
(右兵衛督)|(侍従) (右近大夫)
| ∥―――――遠藤慶利
+―智勝院 +―清洲 (但馬守)
∥ |
∥ |
∥――――――+―娘
∥ |(遠藤小八郎胤直)
∥ |
遠藤慶隆 +―遠藤慶勝
(但馬守) (長門守)
∥
∥―――――――娘
安藤守就――娘 ∥
(伊賀守) ∥
∥
土岐定頼――金森定近――金森長近==+―金森可重
(兵部卿) |(出雲守)
|
長屋景重――+
しかし、犬地城に拠る胤直が前触れもなしに石田三成方に寝返ったことから、慶隆は弟・慶胤、重臣の石神吉兵衛胤春、遠藤彦右衛門胤重らとともに金森家の城に籠ると、家臣・村山市蔵を金森可重のもとへ遣わして、胤直の寝返りと八幡城主・稲葉右京亮貞通の攻撃の許可を家康に言上してくれるよう告げた。
7月29日、家康のもとから遠山久兵衛友政が遣わされ、郡上郡は稲葉が知行しているとはいえ慶隆の本領であるので、旧の如く知行すべしという書状が下された。こうして慶隆は飛騨と美濃国境付近である佐見に砦を築き、上根城に籠る胤直と数十日にわたって交戦した。
8月下旬には、関東の聟・金森可重のもとから飛脚が到来し、慶隆は少ない軍勢にもかかわらず四方の敵に対していることを聞いて感じ入った家康が、可重へただちに帰国して慶隆に加勢すべきことを命じた旨を伝えた。そして、可重が帰国したらば同時に兵を発し、可重は坂本口から美濃国小野山へ、慶隆には沓部口から兵を進め、9月1日に一挙に八幡城を攻め落とすことを書簡で約束した。
慶隆は嫡男・松蔵(慶勝)を佐見砦の守りに残すと一族郎党四百余を率いて密かに進軍し、8月28日、郡上郡との境・田島へ出兵し、翌29日、下原へ陣を築いた。そしてここに伏せられていた稲葉家の鉄砲隊を踏み潰すと、八幡城から三里の北法師村まで迫った。
慶隆の進撃はとどまらず、八幡城東の瀧山に陣を構えていた金森可重と呼応し、9月1日、まず八幡城下から祖父・東下野守常慶の旧城・赤谷山に火をかけ、宮ヶ瀬川の砦を占領すると、八幡城三ノ丸に突入。背後から城門を破って突入した金森可重と合流した。勢いに呑まれた稲葉勢は二ノ丸へ退却、遠藤・金森勢はそのまま二ノ丸に攻め入ったが、日没となったため、慶隆は城の東・大宮森へ、金森可重は瀧山へ退いて八幡城を包囲した。
一方、八幡城の城代を務めていた稲葉修理亮通孝(稲葉貞通三男)は、これ以上遠藤・金森の猛攻を支えきれないと見て、翌9月2日、尾張犬山城に詰めていた稲葉貞通(侍従)と兄・典通に救援をもとめる傍ら、遠藤家とも親しい安養寺の福寿坊を和議の使者として慶隆のもとに差し向け、家老・稲葉土佐の子・与一郎を人質として差し出すこと、遠藤家の捕虜を一人返すことを約束してきた。慶隆はさっそく可重の陣を訪れてこの和議の申し出を議したのち、これを受け入れて八幡城の囲みを解き、遠藤勢は愛宕山に、金森勢は瀧山まで退いた。
●八幡城の稲葉家配置(『遠藤旧記』:『大和村史』所収)
| 本丸 | 稲葉修理亮通孝(城代)・稲葉土佐 |
| ニノ丸 | 片桐知法・求軒権蔵主(町奉行・城番) |
| ニノ曲輪 | 林惣右衛門・渋谷弥十郎・遠藤勝吉・村瀬番右衛門・佐口嘉右衛門・柴崎甚右衛門・片岡長右衛門・三木長兵衛・渡辺十兵衛・中村太郎右衛門・稲葉藤左衛門・稲葉八郎・石神養兵衛・堀九助・寺沢十左衛門・宇野兵内・伊藤又左衛門 |
| 桜町枡形 | 岡部大膳・稲葉九兵衛 |
| 沓部口 | 箕浦源助・川尻権平 |
| 鷲見口 | 鷲見喜平太 |
| 坂本口 | 大口市左衛門・後藤勘左衛門・加納長助・高田半兵衛・渡辺源太郎 |
そのころ、犬山城で通孝の急報を受けた稲葉貞通は、急遽八幡城へ向かったが、八幡城の手前、千虎(郡上市千虎)に至って闇に包まれたため、翌3日未明に密かに八幡城下に入った。このときも八幡城を囲むように遠藤・金森勢が陣を張っていたが、すでに和睦の使者を交わしていたため、貞通の側近は不戦を訴えたが、貞通は「縦ひ款を送るも目前の敵と戦はざるは武名を汚さん。之を撃退して城に入り、而して後和を講ずる亦未だ晩しとせず」と宣言。遠藤勢に奇襲をしかけることとなった。
9月3日早朝、遠藤家重臣・遠藤長助慶重(慶隆甥)の家臣が、濃霧の中、水を求めて川に下りてきた。彼が川辺に至り水を汲んでいると、眼前の森の中から騎馬勢が群雲のように出現した。彼は驚いて陣中に駆け戻って慶隆に伝えたが、慶隆もまさか和議直後に稲葉勢が奇襲をしかけるとは思わず、自ら確認に向かおうとしたとき、鯨波の声が愛宕山の西麓から湧き上がった。
稲葉勢の突然の斬り込みに、和議が成って油断していた遠藤勢は大混乱となり、慶隆は重臣・粥川小十郎に馬に押し上げられて戦線を離脱させられ、小十郎は陣頭に立って太刀を振るい、群がる敵兵五人を斬り伏せた。さらに稲葉家重臣・稲葉秀方に肉迫して、その側近・日比野吉右衛門を両断。秀方に切先が触れようとしたとき、秀方の臣・狩野与十郎が背後から小十郎の背中に槍を突き通し、小十郎は討死を遂げた。また、遠藤長助、鷲見忠左衛門、粥川五郎左衛門、松井忠兵衛らも稲葉勢に斬りこんで縦横に斬り回り、次々に討死を遂げた。
その間に慶隆は愛宕山の断崖を駆け登り、寺畑(郡上市旭字寺畑)まで逃れていた。慶隆に随う者はわずかに村山三右衛門、松井藤兵衛、田中勝助、石井弥五郎、餌取作助の五名であり、稲葉家の侍・山住太郎兵衛、河合弥五郎が追いすがっていたが、松井藤兵衛・餌取作助の両名が立ちふさがり、山住・河合両名を斬り伏せた。この戦いで餌取作助も討死を遂げている。
慶隆ら一向はさらに走ると吉田川に阻まれてしまった。このため、村山三右衛門が慶隆を背負って泳ぎ渡り、辛うじて北岸の小野(郡上郡八幡町小野)に渡りついた。ここで池戸作平から馬を献じられた慶隆は、八幡城裏手瀧山の金森陣に馳せ向かった。吉田川より小野山の陣までの十五町(1.6キロ)、この間も稲葉勢の追撃が続き、村山三右衛門、松井藤兵衛、田中勝助らの奮戦によって、慶隆はようやく婿の金森可重のもとに逃れることができた。
一方、貞通は遠藤勢を追い散らして八幡城へ入城し、使者に酒肴を持たせて瀧山の金森可重の陣所へ届け、改めて和議を求めた。可重は舅の慶隆にこれを諮ったが、慶隆も貞通の和睦を無視した卑怯な振舞を受けながらも和議を認め、講和が成立した。
貞通の合戦で慶隆は遠藤長助ら主だった将を討たれたものの、慶隆はすぐさま陣容を整え直し、石田方に寝返っていた胤直を討つべく翌4日には東美濃へ出兵。5日、胤直が籠城している上根城に攻めかかった。一方で重臣・遠藤作左衛門を遣わして降伏勧告工作を行い、ついに胤直は姉婿・吉田作左衛門を人質として差し出し、降伏した。
八幡城攻略には失敗したものの、東美濃の制圧には成功した慶隆は、信濃国下諏訪に軍勢を進めていた徳川秀忠に、家臣・池戸所助を遣わして合戦の始終を言上。秀忠は13日に感状を遣わして賞し、14日、慶隆は関ヶ原の家康の本陣に参上して拝謁し戦功を賞された。慶隆はそのまま本陣を守るよう命じられ、本陣に攻め寄せた敵将の首一ツを獲った。
●稲葉家周辺略系図
織田信秀――+―織田信長 +―茶々
(弾正少弼) |(内大臣) |(淀ノ方)
| | ∥―――――豊臣秀頼
+――市 | ∥ (左大臣)
| ∥ | 豊臣秀吉 ∥
| ∥ |(関白) ∥
| ∥ | +―千
| ∥――――+――初 |
| 浅井長政 | ∥ |
|(備前守) | 京極高次 +―徳川家光
| |(侍従) |(三代将軍)
| | |
| | 徳川秀忠 +―松平忠長
| |(二代将軍)|(大納言)
| | ∥ |
| | ∥―――+―源和子
| +――小督 (東福門院)
| ∥ ∥―――――明正天皇
| ∥ 後水尾天皇
| ∥
| ∥―――――完子
+―娘 羽柴秀勝 ∥
∥ ∥―――+―九条道房
∥―――――+―稲葉通孝 九条忠栄 |(関白)
∥ |(修理亮) (関白) |
稲葉良通――――稲葉貞通 | +―二条康道
(一鉄) (侍従) +―稲葉典通 (摂政)
(侍従)
―関ヶ原以降―
関ヶ原の戦いが終わって小原城に戻った慶隆は、11月、稲葉家が明け渡した八幡城を請け取り、郡上藩二万七千石の藩主となった。そして翌慶長6(1601)年の近江国膳所城の普請以降、江戸城、近江彦根城、美濃加納城、駿府城、名古屋城などの手伝普請を行っている。
 |
| 慈恩寺の智勝院殿廟(二番目) |
同年、慶隆は屋敷の衝立に唐紙障子を貼ったが、この唐紙障子には「三木左兵衛慶頼」「遠藤作左衛門永安」「遠藤弥左衛門稙重」「各務兵十郎」「堀次太夫」の書状の反故が貼りこまれていたという。「三木左兵衛慶頼」は、『郡上藩家中記録』の「古来覚書」のなかでは「三木左兵衛様」とあることから、遠藤家の一門であると考えられ、遠藤慶隆妻(智勝院殿惟芳宗徳大姉)の実家・三木家の人物であろう。
また、慶長合戦で慶隆に降伏した胤直は慶隆の女婿であり、同じく慶隆の娘婿である金森可重は、胤直の赦免を家康に訴え出たが、家康は「義父である慶隆に逆らった罪は赦さぬ」と怒り、胤直は改易処分とされた。胤直はその後京都に隠棲して「玄斉」と号し、大坂夏の陣では浪人として徳川方として参戦。大坂方の松倉豊後守家老・井村助兵衛と渡り合って討ち取った。
慶長7(1602)年、慶隆は郡上郡長屋村の銀山開発を家康に請うて許された。そして慶長9(1604)年には、従五位下・但馬守に叙任。慶長18(1613)年、はじめて妻子を江戸邸に送った。
翌慶長19(1614)年10月、大坂城の豊臣家と江戸の徳川家との間で戦端が開かれる(大坂冬の陣)と、慶隆は嫡男・慶勝とともに河内国枚方に出陣したが、家康の命を受けて久良加利峠の守将をうけたまわり、本多豊後守康紀・本多縫殿助康俊とともに陣した。しかし大坂冬の陣は対陣で終わり、翌元和元(1615)年4月の「大坂夏の陣」では、久良加利峠に兵を進めて、河内国松原に陣した。
●大坂の陣に随った武士
| 石高 | 名前 |
| 千石 | 遠藤内記 |
| 三百石 | 遠藤左門・池田蔵人・松井将監・遠藤勘平・佐藤清兵衛・佐々十兵衛 |
| 二百五十石 | 小池孫左衛門・納土茂兵衛・池戸善兵衛・村山藤左衛門 |
| 二百石 | 河合武右衛門・粥川半兵衛・ |
| 百五十石 | 池田五右衛門・池田七兵衛・松井忠左衛門・餌取長左衛門 |
| 百石 | 餌取作助・餌取八兵衛 |
| 五十石 | 鷲見所治右衛門 |
5月6日、井伊掃部頭直孝・藤堂和泉守高虎が大坂方と戦端を開くと、慶隆は本多康紀・康俊とともに大和川まで出兵した。そして夜半、本多上野介正純を通じて戦功を賞され、翌7日、康紀・康俊とともに岡山口から大坂城玉造口に攻め入り、城内の番屋に放火して算用場に退却。この城内での戦いで敵の首六十六級を捕る功績をあげ、8日、二条城において家康より恩賞として黄金二十枚が下された。
 |
| 長敬寺の遠藤慶隆墓 |
その後、秀忠が将軍職を継いだのち、秀忠の依頼を受け、東下野守常縁自筆の『古今和歌集』を献じたが、序文がなかったことから、秀忠は常縁の子孫である慶隆に序文を補すよう命じ、自書ののち献上した。秀忠の信頼を受けていた慶隆は寛永年中、参勤の往来には鉄砲五丁を持って江戸へ入ることを許され、寛永9(1632)年正月、秀忠が薨去するとみずからも剃髪して旦斎と号し、後を追うように3月21日、波乱に満ちた83歳の生涯を終えた。法名は深心院殿釋乗性旦斎大居士。
-遠藤家家臣について-
郡上遠藤家家臣の遠藤家には、(1)鎌倉遠藤家 (2)和良遠藤家 (3)長滝遠藤家 (4)小駄良遠藤家 (5)寒水遠藤家の五家があった。このうち(3)(4)(5)は同じ一族で、(1)鎌倉遠藤家は東氏が鎌倉より下向した際に供奉してきた遠藤家、(2)和良遠藤家は他所から郡上にいたった一族という。東氏が郡上郡に下向して当地の地頭になったとはいえ、実際は郡上郡山田庄が本領であり、当地にあった遠藤氏は東氏の家臣ではなく、おのおの鎌倉将軍家に仕える御家人であった。
●遠藤慶隆の家臣●
| 石高 | 名前 |
| 千石 | 遠藤内記 |
| 四百石 | 遠藤図書・遠藤主馬助・遠藤木工丞・池田権左衛門・松井縫殿助・鷲見忠三郎 |
| 三百石 | 遠藤左門・佐藤又左衛門・松井勘左衛門・粥川小十郎・粥川左兵衛・餌取半右衛門・各務主水・岩佐五郎右衛門・中島孫兵衛・大口市左衛門・三島内膳・佐々十兵衛・松原伊右衛門・堀治太夫・辻 善右衛門・垣見権右衛門・遠藤七郎右衛門 |
| 二百五十石 | 池田勝兵衛・池田善兵衛・佐藤治兵衛・石井藤右衛門・村山三右衛門・小池孫右衛門・仙石伊兵衛・納土茂兵衛・高田長兵衛・豊田小左衛門・高屋権太夫・吉田作左衛門・西脇所左衛門・遠藤佐左衛門 |
| 二百石 | 遠藤十郎右衛門・遠藤七左衛門・各務治左衛門・池田外記・佐藤平左衛門・水野角兵衛・桑原右衛門次郎・河合貫右衛門・松村四郎兵衛・山田源太郎・山住太郎兵衛・橋本小左衛門・鷲見安右衛門・桑原松心・武光吉左衛門・武光伝左衛門 |
| 百五十石 | 池田五右衛門・池田七兵衛・松井忠左衛門・餌取長左衛門 |
| 百石 | 餌取作助・餌取八兵衛 |
| 五十石 | 鷲見所治右衛門 |
→「遠藤」「野田」「餌取」は承久年間(1221-23)に東行氏に従って下総から下向した一族。
●武田信玄判物写(『古今消息集』:『岐阜県史』史料編 古代・中世四)
●浅井長政書状写(『古今消息集』:『岐阜県史』史料編 古代・中世四)
●武田信玄書状写(『古今消息集』:『岐阜県史』史料編 古代・中世四)
●武田信玄判物写(『古今消息集』:『岐阜県史』史料編 古代・中世四)
●天正11(1583)年正月12日『織田信孝書状』(1)(『遠藤旧記』:『大和村史』所収)
●天正11(1583)年正月12日『織田信孝書状』(2)(『遠藤旧記』:『大和村史』所収)
| 遠藤慶隆嫡男 |
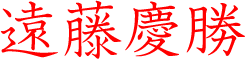 (1588-1615)
(1588-1615)
| <名前> | 正慶→慶勝 |
| <通称> | 松蔵→内匠 |
| <正室> | 本多豊後守康重女 |
| <父> | 遠藤但馬守慶隆 |
| <母> | 三木右兵衛督良頼女(智勝院殿) |
| <官位> | 従五位下 |
| <官職> | 長門守 |
| <就任> | ------- |
| <法号> | 対神院月岩明心 |
| <墓所> | 郡上市の慈恩寺 |
―遠藤慶勝事歴―
遠藤但馬守慶隆の嫡男。母は飛騨の大名・三木右兵衛督良頼娘(智勝院殿)。天正16(1588)年、京都に生まれた。
 |
| 慈恩寺の遠藤慶勝廟(手前) |
慶長11(1606)年、従五位下・長門守に叙任せられた。さらに、慶長19(1614)年の大坂の陣では、父・慶隆とともに東軍として出陣し、河内国枚方に陣を張り、その後、大和越の久良加利峠を守る。その後、徳川家と豊臣家の和睦が成ったが、慶勝は戦いの直後に体調を崩したため京都での療養生活を余儀なくされ、元和元(1615)年2月12日、二十八歳の若さで亡くなった。法名は明心大神院。郡上市の慈恩寺に葬られた。
慶勝は慶隆の嫡男だが、遠藤家の家督を継ぐ以前に亡くなっており、藩主には就任していない。
●遠藤家略系図
斎藤道三―――娘
(山城入道) ∥
∥
三木良頼―+―姉小路自綱―――直綱
(右兵衛督)|(侍従) (右近大夫)
| ∥―――――遠藤慶利
+―智勝院 +―清洲 (但馬守)
∥ |
∥ |
∥―――――+―娘
∥ |(遠藤小八郎胤直)
∥ |
遠藤慶隆 +―慶勝
(但馬守) (長門守)
∥
∥―――――娘
安藤守就――娘 ∥
(伊賀守) ∥
∥
土岐定頼――金森定近――長近==+―可重
(兵部卿)|(出雲守)
|
長屋景重――+
| 二代藩主 |
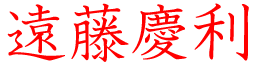 (1609-1646)
(1609-1646)
| <名前> | 慶重→慶利 |
| <通称> | 三郎四郎→内蔵助 |
| <正室> | 板倉周防守重宗女 |
| <父> | 三木右近大夫直綱 |
| <母> | 遠藤但馬守慶隆女・清洲 |
| <官位> | 従五位下 |
| <官職> | 伊勢守→但馬守 |
| <就任> | 寛永9(1632)年~正保3(1646)年 |
| <法号> | 至誠院景山宗泰大居士、至誠院殿釋乗雲大居士 |
| <墓所> | 郡上市美並町白山の深心院乗性寺 |
―遠藤慶利事歴―
郡上藩二代藩主。慶長14(1609)年、郡上八幡に誕生。父は飛騨国の戦国大名・三木氏の末裔で、三木右近大夫直綱。母親は遠藤但馬守慶隆娘・清洲。妻は板倉周防守重宗の娘。
慶長18(1613)年、5歳で駿府城の徳川家康に謁見。寛永2(1625)年9月22日、十七歳にして従五位下・伊勢守に叙任した。そして翌年の寛永3(1626)年の徳川秀忠・家光の上洛に際し、その供奉をして、遠祖・東下野守常縁の住んでいた京都の地を踏んだ。
寛永9(1632)年3月21日、実祖父であり養父の遠藤但馬守慶隆入道旦斎が八十三歳で亡くなり、8月26日、二十四歳にして郡上藩二万七千石を継承。寛永11(1634)年、三代将軍・徳川家光の上洛に供奉した。その後、但馬守に叙された。
正保3(1646)年6月20日、三十八歳の若さで亡くなった。法名は至誠院殿釋乗雲大居士。
●遠藤慶利の家臣●
| 家老 | 遠藤内記 遠藤主計 |
| 三代藩主 |
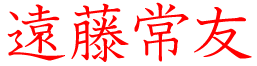 (1628-1675)
(1628-1675)
| <名前> | 慶澄→常季→常友 |
| <幼名> | 岩松 |
| <通称> | 内蔵助 |
| <正室> | 戸田采女正氏信女 |
| <父> | 遠藤但馬守慶利 |
| <母> | 板倉周防守重宗女 |
| <官位> | 従五位下 |
| <官職> | 備前守 |
| <就任> | 正保3(1646)年11月12日~延宝3(1675)年5月4日 |
| <号> | 白雲水 |
| <法名> | 廻向院了道→欲生院乗源→常教院素信 |
| <墓所> | 郡上市美並町白山の深心院乗性寺 |
―遠藤常友事歴―
郡上藩三代藩主。父は遠藤但馬守慶利。母は京都所司代・板倉周防守重宗の娘。寛永5(1628)年、江戸にて生まれた。妻は美濃大垣藩主・戸田采女正氏信の娘。
寛永12(1635)年3月28日、将軍・徳川家光に拝謁し、正保3(1646)年6月20日に父・慶利が亡くなると、同年11月12日、郡上藩二万七千石を相続。相続の際、実弟の大助常昭に二千石を、金兵衛常紀には千石をそれぞれ分与しており、郡上藩の石高は二万四千石となっている。
12月5日、父・慶利の遺品である左文字一振を将軍家に献上。12月30日、従五位下・備前守に叙任された。
遠藤慶利 +―遠藤常友【郡上藩主】
(但馬守) |(備前守)
∥ |
∥―――――+―遠藤常昭【乙原遠藤家】
板倉勝重―――重宗―――娘 |(大助)
(伊賀守) (周防守) |
+―山田常紀【和良遠藤家】
(金兵衛)
正保4(1647)年4月26日、藩主として初の国入りを果たした。そして寛文4(1664)年4月5日、四代将軍・徳川家綱より郡上藩の封地の御朱印状を賜った。明暦3(1657)年初秋には、「遠藤備前守平朝臣常季」の名で八幡城下の明建神社に子孫繁栄家中安全を祈願している。
慶安4(1651)年7月5日、常友(当時はまだ常季か)は「大坂加番」の暇乞いをしている(『徳川実紀』)。寛文5(1665)年正月2日、大坂城が雷火に見舞われたときにはまだ大坂城番であり、大坂城本丸の埋門(うずみもん)の守備をした功績で将軍家より奉書が下された。
寛文7(1667)年、居城の八幡城の改修を認められて修理し、城下町の整備と拡張が行われ、それまでの「城主格」から「城主」の待遇となる。さらに領内検地を行って、新田開発を推進するなどの内政面も拡充した。
この年、家光の十七回忌に後水尾上皇の使い「本院使」として烏丸資慶が日光東照宮参詣のために下向したが、常友が接待役を仰せつかっている。資慶は三年前に後水尾上皇から古今集の講義を受けていた歌人で、同じく歌人であった常友とは互いに交流をもつようになり、古今伝授の家柄である資慶に常縁の歌を編集した『常縁歌集』の編纂を依頼した。その後、資慶の病死によって編纂作業は烏丸光雄へ継承され、寛文11(1771)年に光雄から常友へと贈呈されている。
寛文9(1669)年11月、常友の重臣、遠藤十兵衛朝慶・遠藤杢之助正英・遠藤市右衛門正明・池田勝兵衛吉久・松井縫殿助宗従・野田覚左衛門慶明の連名で、城下の明建神社に青銅製の鰐口を奉納した。
寛文10(1770)年、『蒙吟詠藻』の跋を記し、延宝4(1676)年、日野資弘から『東家代々首』(東下野守常和編)が常友へ贈られた。さらに自身の歌を集めた『常友自詠自筆』を編纂、郡上城下に現在も残されている「宗祇水」を整えたが、同年5月4日に亡くなった。四十九歳。号は素信。法名は廻向院了道、のち欲生院乗源、さらに常敬院に改められた。
●遠藤常友の家臣抜粋(『郡上藩分限帳』:『郡上八幡町史』所収)
| 石高 | 役職 | 氏名 |
| 2,500 | 常友実弟 | 遠藤大助常昭 |
| 1,300 | 常友実弟 | 山田金兵衛常紀 |
| 100 | 常友母親? | 敬勝院 |
| 10人 | 常友伯母 | 伯母 |
| 10人 | 常友伯母 | 伯母 |
| 10人 | 常友娘?妹? | 女中 |
| ~家中城代家老~ | ||
| 500 | 遠藤十兵衛(朝慶) | |
| 500 | 仕置家老 | 遠藤新左衛門・遠藤杢之助(正英) |
| 500 | 無役 | 遠藤主馬助 |
| 450 | 月番家老組頭 | 池田六左衛門(吉久か) |
| 350 | 月番家老組頭 | 遠藤市右衛門(正明) |
| 300 | 月番家老組頭 | 松井縫殿助(宗従) |
| 300 | 無役 | 野田覚右衛門(慶明) |
| 200 | 無役 | 粥川小十郎・石神太兵衛 |
| 300 | 物頭 | 餌取六右衛門 |
| 250 | 物頭 | 村山三右衛門・石井藤右衛門 |
| 200 | 物頭 | 高屋権太夫 |
| 150 | 物頭役領扶持 | 遠藤善左衛門・松井覚兵衛 |
| 150 | 寺社奉行 | 松井弥五左衛門 |
| 100 | 鑓奉行役領扶持 | 遠藤治部右衛門 |
| 150 | 町奉行役領扶持 | 吉田作左衛門 |
| 200 | 郡奉行 | 遠藤金左衛門・武光伝左衛門 |
| 200 | 目付 | 粥川半兵衛 |
| 100 | 目付 | 野田九右衛門 |
| 150 | 聞番役二十人扶持 | 澤部治部左衛門 |
| 100 | 奥家老 | 宮田兵右衛門・豊田源五兵衛 |
| 150 | 馬乗り | 三浦四方助 |
| 150 | 馬医者 | 鷲見八右衛門 |
| ~御馬廻~ | ||
| 300 | 粥川孫左衛門 | |
| 250 | 小池孫右衛門 | |
| 200 | 武光吉左衛門・豊島弥左衛門・遠藤久右衛門・松井勘右衛門・豊田武兵衛・佐藤治兵衛 | |
| 150 | 遠藤七郎左衛門・遠藤助太夫・畑佐覚左衛門・豊田儀左衛門・山田又兵衛・桑原五兵衛・池田幸右衛門・垣見伊右衛門・角庄右衛門・池戸善右衛門 | |
| 100 | 遠藤武太夫・野田弥兵衛・遠藤弥市右衛門・桜井宇右衛門・餌取八郎右衛門・伊東一拾・伊藤関三郎・三木竹之助・池戸求馬助 |
| 四代藩主 |
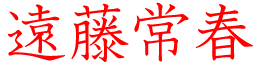 (1667-1689)
(1667-1689)
| <名前> | 常信→常春 |
| <通称> | 外記 |
| <正室> | 松平日向守源信女 |
| <正室2> | 牧野因幡守富成女 |
| <父> | 遠藤備前守常友 |
| <母> | 戸田采女正氏信女 |
| <官位> | 従五位下 |
| <官職> | 右衛門佐 |
| <就任> | 延宝4(1676)年6月30日~元禄2(1689)年3月24日 |
| <法名> | 恵正院素教 |
| <墓所> | 郡上市美並町白山の深心院乗性寺 |
―遠藤常春事歴―
郡上藩四代藩主。父は遠藤備前守常友。母は戸田采女正氏信の娘。妻は松平日向守源信の娘、のち牧野因幡守富成の娘。寛文7(1667)年江戸に誕生した。
遠藤常友
(備前守)
∥――――――遠藤常春======遠藤胤親
戸田氏信――+―娘 (右衛門佐) (但馬守)
(采女正) |
+―戸田氏西―――戸田氏成 白須政休
(肥後守) (淡路守) (甲斐守)
∥ ∥
∥ ∥――――――遠藤胤親
小谷守栄―+―娘 +―娘 (但馬守)
|(牧野成貞養女) |
| |
+―小谷忠栄 +―娘
(将監) |(陽春院)
∥ |
∥―――――――+―於伝の方 +―徳松
鶴牧信幹―――娘 (瑞春院) |
(茂右衛門) (高覚院) ∥ |
∥――――+―鶴姫
徳川家康――+―徳川秀忠―――徳川家光――――――徳川綱吉 ∥
(初代将軍) |(二代将軍) (三代将軍) (五代将軍) ∥
| ∥
+―徳川頼宣―――徳川光貞――――+――――――――徳川綱教
(和歌山藩主)(和歌山藩主) | (和歌山藩主)
|
+―徳川吉宗
(八代将軍)
延宝3(1675)年2月28日、はじめて四代将軍・徳川家綱に拝謁した。ときに九歳。その翌年の延宝4(1676)年5月4日、父・常友が急逝したため、十歳の幼さで郡上藩を継承。7月11日には、父の形見である保昌五郎の太刀一振りを将軍家に献上した。
天和元(1681)年11月25日、上野国沼田藩主・真田伊賀守信利が悪政を行った結果、政事不行届として改易され、信利の次男・武藤源三郎信秋を幕命によって預かっている。
天和2(1682)年12月27日、従五位下・右衛門佐に叙され、十六歳の若さで大夫の地位にのぼった。そして元禄元(1688)年5月3日、はじめて郡上への下向が認められたが、翌元禄2(1689)年3月24日、郡上で急逝した。享年二十三歳。号は素教恵正院。
弟の遠藤内記慶紀は和良郷二千石を給わり、家老職に付いた。慶紀は東家の系譜をまとめており、元禄12(1699)年9月5日、その系譜が写された。
●遠藤常春の家臣●
| 家老 | 遠藤十兵衛 松井縫殿助 |
| 五代藩主 |
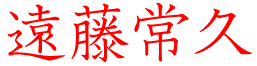 (1686-1692)
(1686-1692)
| <名前> | 常久 |
| <通称> | 岩松 |
| <通称> | |
| <正室> | なし |
| <父> | 遠藤右衛門佐常春 |
| <母> | 側室某氏女 |
| <養母> | 牧野因幡守富成娘(遠藤常春後室) |
| <官位> | なし |
| <官職> | なし |
| <就任> | 元禄2(1689)年6月6日~元禄5(1692)年3月30日 |
| <法名> | 本了院素導 |
| <墓所> | 台東区浅草の浅草本願寺の長敬寺 |
―遠藤常久事歴―
郡上藩五代藩主。父は遠藤右衛門佐常春。母は側室某氏。義母・牧野因幡守富成娘の養子とされた。貞享3(1686)年に郡上八幡に誕生。
嫡男として育てられ、江戸へ出府。元禄2(1689)年3月24日、父・常春が二十三歳の若さで急逝すると、6月6日、わずか四歳にして遠藤家の家督と遺領を継承。6月9日には登城して将軍・徳川綱吉に謁見して、常春の遺物・左文字弘安を献上した。
しかし常久は生来病弱であったようで、藩主に就任してわずかに三年後の元禄5(1692)年3月30日、七歳の幼さで亡くなった。法名は本了院素道。墓所は浅草の浅草本願寺門前にある塔頭・長敬寺。
常久は七歳という幼さであったため継嗣がおらず、郡上藩二万七千石の改易が決定した。こうして鎌倉時代より約四百五十年続いた東家、遠藤家の郡上支配は終止符を打つこととなる。