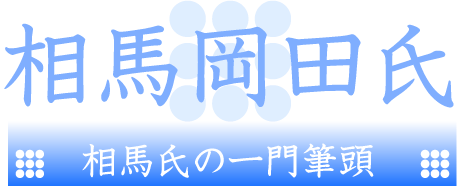
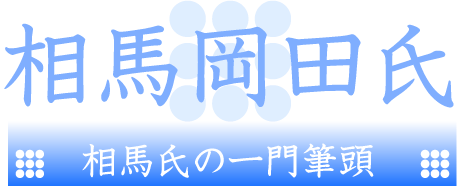
■相馬岡田氏の歴代
| 代数 | 名前 | 生没年 | 初名 | 通称・官途(名) | 号 | 父 | 母 | 妻 |
| 初代 | 相馬胤顕 | ????-1285 | 彦三郎、五郎 | 相馬胤村 | ? | 尼妙悟 | ||
| 2代 | 相馬胤盛 | ????-???? | 小次郎 | 相馬胤顕 | 尼妙悟? | 尼専照 | ||
| 3代 | 相馬胤康 | ????-1336 | 五郎 | 相馬胤盛 | 尼専照 | |||
| 4代 | 相馬胤家 | ????-???? | 乙鶴丸 | 小次郎、常陸介、兵衛尉 | 浄賢 | 相馬胤康 | ||
| 5代 | 相馬胤繁 | ????-1381? | 胤重 | 五郎、常陸五郎、宮内丞 | 相馬胤家 | |||
| 6代 | 相馬胤久 | ????-???? | 鶴若丸 | 小次郎、宮内大夫 | 相馬胤繁 | |||
| 7代 | 岡田胤行 | ????-???? | 豊鶴丸 | 左京亮 | 相馬胤久 | |||
| 8代 | 岡田盛胤 | ????-???? | 次郎三郎 | 岡田胤久? | ||||
| ? | 岡田信胤 | ????-???? | 伊予守 | 岡田胤行? | ||||
| ? | 岡田基胤 | ????-???? | 小次郎 | 岡田基胤? | ||||
| 9代 | 岡田義胤 | ????-???? | 安房守 | 岡田基胤? | ||||
| 10代 | 岡田茂胤 | ????-???? | 鶴若丸 | 治部太輔 | 岡田義胤? | |||
| 11代 | 岡田直胤 | 1560?-1591? | 鶴若丸 | 右兵衛太夫 | 岡田茂胤 | 草野直清娘 | ||
| 12代 | 岡田宣胤 | 1584-1626 | 鶴若丸 | 小次郎、出雲、八兵衛 | 桂月 | 岡田直胤 | 草野直清娘? | |
| 中村藩御一家筆頭岡田家 | ||||||||
| 初代 | 岡田重胤 | ????-1650 | 鶴若丸 | 源内、八兵衛 | 岡田宣胤 | 下浦修理娘 | ||
| 2代 | 岡田長胤 | 1634-1659 | 左門、監物 | 岡田長次 | 下浦修理娘 | |||
| 3代 | 岡田信胤 | 1654-1669 | 小次郎 | 岡田長胤 | 青田高治娘 | |||
| 4代 | 岡田伊胤 | 1656-1731 | 三之助 | 与左衛門、監物 | 中村俊世 | 青田高治娘 | 岡田長胤娘 | |
| 5代 | 岡田知胤 | ????-???? | 千五郎 | 宮内、監物、内記、靱負 | 岡田伊胤 | 岡田長胤娘 | 堀内辰胤娘 | |
| 6代 | 岡田春胤 | 1709-1755 | 専之助 | 監物 | 岡田知胤 | 堀内辰胤娘 | 堀内胤重娘 | |
| 7代 | 岡田徃胤 | 1728-???? | 専五郎 | 直衛、監物 | 岡田春胤 | 堀内胤重娘 | 太田清左衛門娘 | |
| 8代 | 岡田直胤 | ????-???? | 和多利 | 帯刀、監物、靱負 | 岡田春胤 | 太田清左衛門娘 | 堀内胤長娘 | |
| 9代 | 岡田半治郎 | ????-1774 | 半治郎 | 岡田直胤 | 堀内胤長娘 | 佐藤元重娘 | ||
| 10代 | 岡田恩胤 | 1766-1817 | 常五郎、将胤 | 監物 | 岡田徃胤 | 佐藤元重娘 | ||
| 11代 | 岡田清胤 | 1797-1828 | 帯刀 | 岡田徃胤 | 相馬祥胤娘 | |||
| 12代 | 岡田智胤 | ????-1853 | 純太郎 | 帯刀 | 岡田清胤 | 相馬仙胤娘 | ||
| 13代 | 岡田泰胤 | 1840-???? | 直五郎 | 監物 | 相馬益胤 | 御内証於藤 | ||
■相馬岡田氏当主
相馬胤久(????-????)
相馬岡田氏六代惣領。相馬五郎胤繁の嫡男。幼名は鶴若丸。通称は小次郎。官途は宮内大夫。
 |
| 胤久花押 |
父・相馬五郎胤繁は康暦3(1381)年5月24日、鶴若丸(胤久)と娘三人、妻にも譲状を与えて亡くなった(康暦三年五月廿四日「相馬胤繁譲状」『相馬岡田文書』)。このとき鶴若丸はまだ幼く、祖父の胤家入道浄賢が後見人的な立場で家政を取り仕切ったようである。
●康暦3(1381)年5月24日『相馬胤繁譲状』
| 譲る人物 | 譲られる人物 | 内容 | |
| 相馬胤繁 | 相馬鶴若丸(胤久) | 下総国相馬郡:泉村・上柳戸・金山・船戸 下総国相馬郡:増尾村(弥源次入道の田在家一軒) 下総国相馬郡:佐津間村(山伏内の田在家一軒) 陸奥国行方郡:岡田村・院内村(庶子分除く)・八兎村・飯土江狩倉一所・上矢河原・上鶴谷 陸奥国高城保:波多谷村 |
|
| 姉亀鶴 | 陸奥国行方郡:院内村下内 | いずれも一期分。その後は鶴若に。 | |
| 中姉松犬 | 陸奥国行方郡:院内村(カ)□□太郎入道の在家 | ||
| 妹■小くろ | 陸奥国行方郡:上矢河原村の弥平三郎の在家 | ||
| 後家 | 陸奥国行方郡:上矢河原村(カ)の藤内二郎の在家 | ||
永徳4(1384)年4月27日、鶴若丸は小高館の相馬家宗家の相馬治部少輔憲胤を烏帽子親にして元服。「相馬小次郎胤久」を称した。これまで相馬岡田家は相馬小高家(相馬宗家)とは親類として相互協力の間柄であったと思われるが、この元服式をきっかけに相馬岡田家が相馬小高家に従属する関係に変化していったのかもしれない。胤久以降、相馬岡田家は「岡田」を称して「相馬」を名乗ることはなくなった。おそらく祖父の胤家入道浄賢は、幼い孫・胤久の将来を案じ、小高の相馬治部少輔憲胤に孫鶴丸の烏帽子親となってもらうよう依頼したのだろう。
祖父の胤家入道浄賢は明徳3(1392)年2月18日、奥州行方郡の所領を胤久に譲った(伝『相馬胤状』)。この頃、胤久は「宮内大夫」に叙された。おそらく父・胤繁と同じく、従五位下の叙爵と宮内丞への任官を果たしたと思われる。
●明徳3(1392)年2月18日『伝相馬胤重譲状』(実は胤家譲状)
| 譲る人物 | 譲られる人物 | 内容 |
| 相馬胤家 (浄賢) |
相馬鶴若丸 (小次郎胤久) |
陸奥国行方郡:岡田村(■ま内の在家八反除く)・飯土江村・八兎村・院内村・矢河原・鶴谷 陸奥国高城保:波多谷村 |
これ以降、相馬岡田氏の譲状に下総国内の所領が出てくることはない。父相馬胤繁の病死と、幼少の鶴若丸の惣領就任といった相馬岡田家の弱体化のほか、南北朝の大乱の中で、遠く離れた下総国相馬郡の所領の管理は難しかったのだろう。いつしか下総国相馬郡内の所領は実を失った。
「岡田宮内大夫殿(胤久)」はかねてから「大瀧帯刀左衛門尉」と「行方郡伊内村(院内村)」の在家について相論していたが、応永元(1394)年2月1日、相馬治部少輔憲胤から胤久の言い分を是とした『知行安堵状』を受けている(応永元年二月一日「相馬憲胤安堵状」『相馬岡田雑文書』)。このことからも胤久が相馬宗家の麾下にあったことがうかがえる。
応永9(1402)年5月14日、胤久は早くも嫡男・豊鶴丸に所領を譲っている。同日、妻(とよつるのはゝ)にも一期分として譲状を与えている。 豊鶴丸への譲状には、「もしとよつる丸子なくハ、おとゝあいつくへし、たとい子あまたありとゆうとも、一こふんハゆつるとも、ゑいたいゆつるへからす(もし豊鶴丸子無くば、弟相継ぐべし、たとい子数多ありと雖も、一期分は譲るとも、永代譲るべからず)」(応永九年五月十四日「相馬胤久譲状」『相馬岡田文書』)と、惣領分については庶子たちに決して永代譲り渡すことはならないと念を押している。庶子へ譲ることによる所領の分散を防ぐこと、惣領の絶対性を守ることが根底にあったか。また、この譲状から豊鶴丸には弟があったことがわかるが、大甕氏の祖となった弟・次郎胤次が「おとゝ」にあたるのかは不明。
●大甕氏略系図
岡田胤久―+―胤行 +―胤末
(宮内大夫)|(豊鶴丸) |(藤八郎)
| |
+―胤次―――大甕胤忠――胤盛――胤通――胤俊――胤勝――+=胤清―――長泰
(次郎) (佐渡守) (丹波)(丹波)(丹波)(左馬允) (豊後) (半左衛門)
●応永9(1402)年5月14日『岡田胤久譲状』
| 譲る人物 | 譲られる人物 | 内容 |
| 岡田胤久 | 岡田豊鶴丸 | 陸奥国行方郡:岡田村・上鶴谷村・院内村・下矢河原村・八兎村・草野の飯土江村・ 陸奥国高城保:波多谷村 |
| 豊鶴の母(胤久妻) | 陸奥国行方郡:岡田村(ゆ■■田在家):一期分 |
応永年中、新田岩松氏が作成した『岩松氏本知行分注文案』によると、「手賀、布施 彼両村之事同闕所、泉治部大輔、原将監」とあり、手賀・布施は闕所として泉治部大輔、原将監の両名によって支配されていたことがわかる。「泉治部大輔」の素性は不明だが、藤ヶ谷に本拠を持っていた下総相馬一族かもしれない。
●相馬岡田氏の所領の変遷●
| 譲る人物 | 譲状年月日 | 譲られる人物 | 内容 |
| 相馬胤家 | 貞治2(1363)年8月18日 | 相馬胤重 | 下総国相馬郡:泉村(上柳戸・金山・船戸) 増尾村(弥源次入道の田在家一軒) 佐津間村(山伏内の田在家一軒) 陸奥国行方郡:岡田村 八兎村 飯土江狩倉一所 矢河原 上鶴谷 院内村(上内下内の田在家) 陸奥国高城保:波多谷村 |
| 相馬胤繁 | 康暦3(1381)年5月24日 | 嫡子鶴若丸 | 下総国相馬郡:泉村(上柳戸・金山・船戸) 増尾村(弥源次入道の田在家一軒) 佐津間村(山伏内の田在家一軒) 陸奥国行方郡:岡田村 院内村(下内、■■太郎入道在家は除外) 八兎村 飯土江狩倉一所 上矢河原村(弥平三郎在家、藤内二郎在家は除外) 上鶴谷村 |
| 浄賢 | 明徳3(1392)年2月18日 | まこ鶴若丸 | 陸奥国行方郡:岡田村(■ま内在家八反は除外) 飯土江村 八兎村 院内村 矢河原村 鶴谷村 陸奥国竹城保:波多谷 |
| 相馬胤久 | 応永9(1402)年5月12日 | 嫡子豊鶴丸 | 陸奥国行方郡:岡田村(ゆ■■田在家は除外) 上鶴谷村 院内村 下矢河原村 八兎村 草野の飯土江村 陸奥国竹城保:波多谷 |
→”青字”は両書に見える所領。”紫字”は見えなくなった所領。
●胤久(=鶴若丸)への所領譲渡の変遷●
| 康暦3(1381)年5月24日 | 相馬胤繁が(病のため?)嫡子・鶴若丸に惣領職を譲る |
| 康暦3(1381)年中? | 相馬胤繁が死去。下総の所領は幼少の鶴若丸には裁量できず失われるか? |
| 永徳2(1382)年1月27日 | 鶴若丸、相馬憲胤の加冠で元服する。鶴若丸の祖父・浄賢(胤家か)が憲胤に鶴若丸の後ろ盾になってもらう意味で依頼か? |
| 明徳3(1392)年2月18日 | 浄賢、孫の鶴若丸に所領を譲り渡す。しかし下総に所領はすでになく、奥州の所領のみ。 |