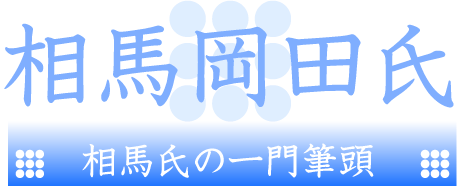
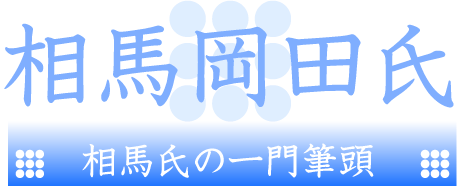
■相馬岡田氏の歴代
| 代数 | 名前 | 生没年 | 初名 | 通称・官途(名) | 号 | 父 | 母 | 妻 |
| 初代 | 相馬胤顕 | ????-1285 | 彦三郎、五郎 | 相馬胤村 | ? | 尼妙悟 | ||
| 2代 | 相馬胤盛 | ????-???? | 小次郎 | 相馬胤顕 | 尼妙悟? | 尼専照 | ||
| 3代 | 相馬胤康 | ????-1336 | 五郎 | 相馬胤盛 | 尼専照 | |||
| 4代 | 相馬胤家 | ????-???? | 乙鶴丸 | 小次郎、常陸介、兵衛尉 | 浄賢 | 相馬胤康 | ||
| 5代 | 相馬胤繁 | ????-1381? | 胤重 | 五郎、常陸五郎、宮内丞 | 相馬胤家 | |||
| 6代 | 相馬胤久 | ????-???? | 鶴若丸 | 小次郎、宮内大夫 | 相馬胤繁 | |||
| 7代 | 岡田胤行 | ????-???? | 豊鶴丸 | 左京亮 | 相馬胤久 | |||
| 8代 | 岡田盛胤 | ????-???? | 次郎三郎 | 岡田胤久? | ||||
| ? | 岡田信胤 | ????-???? | 伊予守 | 岡田胤行? | ||||
| ? | 岡田基胤 | ????-???? | 小次郎 | 岡田基胤? | ||||
| 9代 | 岡田義胤 | ????-???? | 安房守 | 岡田基胤? | ||||
| 10代 | 岡田茂胤 | ????-???? | 鶴若丸 | 治部太輔 | 岡田義胤? | |||
| 11代 | 岡田直胤 | 1560?-1591? | 鶴若丸 | 右兵衛太夫 | 岡田茂胤 | 草野直清娘 | ||
| 12代 | 岡田宣胤 | 1584-1626 | 鶴若丸 | 小次郎、出雲、八兵衛 | 桂月 | 岡田直胤 | 草野直清娘? | |
| 中村藩御一家筆頭岡田家 | ||||||||
| 初代 | 岡田重胤 | ????-1650 | 鶴若丸 | 源内、八兵衛 | 岡田宣胤 | 下浦修理娘 | ||
| 2代 | 岡田長胤 | 1634-1659 | 左門、監物 | 岡田長次 | 下浦修理娘 | |||
| 3代 | 岡田信胤 | 1654-1669 | 小次郎 | 岡田長胤 | 青田高治娘 | |||
| 4代 | 岡田伊胤 | 1656-1731 | 三之助 | 与左衛門、監物 | 中村俊世 | 青田高治娘 | 岡田長胤娘 | |
| 5代 | 岡田知胤 | ????-???? | 千五郎 | 宮内、監物、内記、靱負 | 岡田伊胤 | 岡田長胤娘 | 堀内辰胤娘 | |
| 6代 | 岡田春胤 | 1709-1755 | 専之助 | 監物 | 岡田知胤 | 堀内辰胤娘 | 堀内胤重娘 | |
| 7代 | 岡田徃胤 | 1728-???? | 専五郎 | 直衛、監物 | 岡田春胤 | 堀内胤重娘 | 太田清左衛門娘 | |
| 8代 | 岡田直胤 | ????-???? | 和多利 | 帯刀、監物、靱負 | 岡田春胤 | 太田清左衛門娘 | 堀内胤長娘 | |
| 9代 | 岡田半治郎 | ????-1774 | 半治郎 | 岡田直胤 | 堀内胤長娘 | 佐藤元重娘 | ||
| 10代 | 岡田恩胤 | 1766-1817 | 常五郎、将胤 | 監物 | 岡田徃胤 | 佐藤元重娘 | ||
| 11代 | 岡田清胤 | 1797-1828 | 帯刀 | 岡田徃胤 | 相馬祥胤娘 | |||
| 12代 | 岡田智胤 | ????-1853 | 純太郎 | 帯刀 | 岡田清胤 | 相馬仙胤娘 | ||
| 13代 | 岡田泰胤 | 1840-???? | 直五郎 | 監物 | 相馬益胤 | 御内証於藤 | ||
岡田胤行(????-????)
相馬岡田氏七代惣領。父は相馬宮内大夫胤久。幼名は豊鶴丸。官途は左京亮。
応永9(1402)年5月14日、豊鶴丸は父・宮内大夫胤久より所領を譲られた。同日、豊鶴丸母にも「一期分」として譲状が発給されている。豊鶴丸への譲状には、「もしとよつる丸子なくハ、おとゝあいつくへし、たとい子あまたありとゆうとも、一こふんハゆつるとも、ゑいたいゆつるへからす(もし豊鶴丸子無くば、弟相継ぐべし、たとい子数多ありと雖も、一期分は譲るとも、永代譲るべからず)」と、惣領分については庶子たちに決して永代譲り渡すことはならないと念を押している。庶子へ譲ることによる所領の分散を防ぐこと、惣領の絶対性を守ることが根底にあったか。また、この譲状から豊鶴丸には弟があったことがわかるが、系譜上には記載がなく不明。没年不明。
| 譲る人物 | 譲られる人物 | 内容 |
| 岡田胤久 | 豊鶴丸 | 陸奥国行方郡:岡田村・ 上鶴谷村・院内村・下矢河原村・八兎村・草野の飯土江村 陸奥国高城保:波多谷村 |
| 豊鶴の母(胤久妻) | 陸奥国行方郡:岡田村(ゆ■■田在家):一期分 |
なお、豊鶴丸の元服後の名が「胤行」であるという史料は、『相馬岡田系図』以外には残されていない。ただし、『相馬岡田系図』の胤行(豊鶴丸)から茂胤までの歴代は『相馬岡田文書』に見える人物名を繋げただけのものであり、記載の註もまた同様である。相馬岡田氏は奥州相馬宗家のもっとも重用された「一門」であったが、相馬岡田文書所収の『岡田相馬系図』に見える岡田豊鶴丸以降、茂胤までの百年程の間は、岡田氏の確実な動向は不明となっており、中世岡田氏の闕史となっている。
「岡田宮内太輔胤久二男」の次郎胤次は行方郡大甕村に住んで大甕氏の祖となり、その子・大甕佐渡守胤忠は応仁2(1468)年3月21日、「高野山金剛峰寺無量光院」に「奥州東海道行方郡 相馬」の「前讃岐守隆胤」以下の相馬一族が連判した願文に「大甕胤忠在判 一貫五百文 同御家中性香十疋」とあるが、岡田宗家とみられる「岡田守胤」の一貫文、岡田庶家の「大井前上総守胤信殿」の一貫文よりも多くの寄附をしている(『奥相秘鑑』巻第三「紀州高野山御宿坊之事」)。
なお、「□□四年きのへ子十月廿九日」に「胤行」(「岡田左京亮沽却状」史料編纂所所収『相馬岡田文書』影写卅四)が「くらもとたちハき殿」宛てに質物を沽却する文書が残されている(「岡田左京亮沽却状」『相馬岡田文書』)。「胤行」のあとに「おかたさきやう助」と別筆で記しているが、これは『岡田相馬系図』制作時に相馬岡田文書との整合性が図られたものか。文書上では「□□四年きのへ子十月廿九日」とあるが、元号が四年の14・15世紀における甲子歳は、
(1)元亨4(1324)年12月9日に改元「正中」
(2)永徳4(1384)年2月24日に改元「至徳」
(3)嘉吉4(1444)年2月5日に改元「文安」
の三年となる。文書は甲子歳10月29日の文書であることから、永徳4年及び嘉吉4年は該当しない。つまり、「おかたさきやう助」が沽却状を認めたのは鎌倉時代末期、伝承上の相馬孫五郎重胤が奥州へ下向した翌年の元享4(1324)年となろう(ただし、重胤下向は伝説的な一斉下向ではなく、下総国相馬郡内での同族との所領争いならびに奥州の遠隔地における長崎氏等との所領争いの中で、奥州の所領を確保するべく自ら実力行使のために入部したことがきっかけである)。しかし、この頃、相馬岡田氏は惣領胤康を含めて官途名を称した人物はおらず、「おかたさきやう助」は行方郡岡田邑の御内人や神官などで相馬岡田氏とは関わりのない人物ではなかろうか。