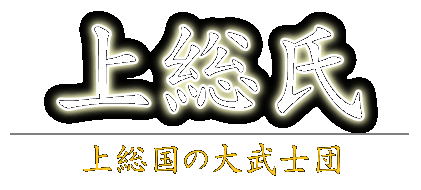
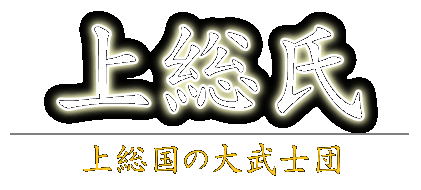
|ページの最初へ|トップページへ|上総氏について|千葉宗家の目次|千葉氏の一族|
| 【一】 | 上総氏について |
| 【二】 | 上総平氏は両総平氏の「惣領」なのか |
| 【三】 | 頼朝の挙兵と上総平氏 |
平常長――+―平常家
(下総権介)|(坂太郎)
|
+―平常兼―――平常重――――千葉介常胤――千葉介胤正―+―千葉介成胤――千葉介時胤
|(下総権介)(下総権介) (下総権介) |
| |
| +―千葉常秀―――千葉秀胤
| (上総介) (上総権介)
|
+―平常晴―――平常澄――+―伊南常景―――伊北常仲
(上総権介)(上総権介)|(上総権介) (伊北庄司)
|
+―印東常茂
|(次郎)
|
+―平広常――――平能常
|(上総権介) (小権介)
|
+―相馬常清―――相馬貞常
(九郎) (上総権介?)
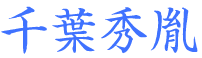 (????~1247)
(????~1247)
上総介常秀の嫡男。母は不明。通称は太郎(堺兵衛太郎、上総介太郎)。妻は三浦駿河守義村女。官途は従五位下(『関東評定伝』仁治二年十一月十日)、従五位上(『関東評定伝』寛元元年閏七月廿七日)。職は「上総権介」(『吾妻鏡』)、「上総在国介」(『桓武平氏諸流系図』)。関東評定衆。
秀胤は相当若いころに鎌倉家御家人の古老である三浦駿河守義村の女子と婚姻関係を結んだ。おそらく義村女子腹とみられる子息らのうち、「嫡男式部大夫時秀、次男修理亮政秀、三男左衛門尉泰秀」(『吾妻鏡』宝治元年六月七日条)は嘉禎4(1238)年から仁治元(1240)年までの間に任官しており、三浦氏との婚姻は承元4(1210)年頃であろう。
鎌倉家の最高執政機関である「関東評定衆」に名を連ねるが、三浦氏が安達氏・北条氏と対立する中で三浦氏と縁戚関係を持つ秀胤は罷免され、三浦氏滅亡に伴い、上総国で鎌倉からの寄手に攻め滅ぼされた。
●上総千葉氏と千葉宗家
千葉介胤正―+―千葉介成胤――千葉介胤綱――千葉介時胤
(千葉介) |(千葉介) (千葉介) (千葉介)
|
+―千葉常秀―――千葉秀胤 +―千葉時秀
(上総介) (上総権介)|(式部丞)
∥ |
∥――?―+―千葉政秀
三浦義村―+―女子 |(修理亮)
(駿河守) | |
+―三浦泰村 +―千葉泰秀
(若狭守) |(左衛門尉)
|
+―千葉秀景
(六郎)
●秀胤及び子息達の称(『吾妻鏡』)
| 承久元(1219)年7月19日 | 堺兵衛太郎(秀胤) | 藤原三寅の鎌倉着に伴う義時邸への入御供奉の一人 | |
|
在京期間か |
(6年間記述なし) | 【父とともに承久の乱で上洛したのち、在京か】 | |
| 元仁2(1225)年正月24日 | 下総平常秀 | 父常秀、同日除目で「下総(守)」に補任(『明月記』) | |
| (10年間記述なし) | 【在京か】 | ||
| 貞永元(1232)年閏9月11日 | 千葉介時胤 | 時胤、この日までに上洛。この日、千葉介被官と平経高卿の家人が騒動を起こしている(『民経記』)。 | |
| 文暦2(1235)年2月9日 | 上総介太郎(秀胤) | 「将軍家、入御于後藤大夫判官基綱大倉宅」し、遊興。秀胤は小笠懸に出馬。 | |
| 文暦2(1235)年6月29日 | 上総介常秀 上総介太郎(秀胤) |
「被行新造御堂安鎮」で「先陣隨兵、上総介常秀」、秀胤は車左右列歩。 | |
| 嘉禎2(1236)年8月4日 | 上総介 上総介太郎(秀胤) |
「将軍家、若宮大路新造御所御移徙」の供奉人 | |
| 嘉禎4(1238)年正月1日 | 上総介太郎(秀胤) 同(上総介)次郎(時常) |
埦飯に際し、兄弟で三御馬を曳く | |
| 嘉禎4(1238)年2月17日 | 上総介太郎(秀胤) | 将軍家(頼経)入洛「御所隨兵」の騎乗「五十二番」 | |
| 在京期間か | (1年半記述なし) | 【頼経上洛以降在京か。下記はこの期間に任官】 秀胤:上総権介 時秀:式部丞(京官) 政秀:修理亮(京官) 泰秀:左衛門尉 |
|
| 仁治元(1240)年8月2日 | 上総権介 上総五郎左衛門尉(泰秀) |
将軍家二所御参詣の行列。御駕籠後騎。 ※式部丞時秀、修理亮政秀は在京ママ? |
|
| 仁治2(1241)年正月23日 | 上総権介(秀胤) | ||
| 仁治2(1241)年8月15日 | 上総式部丞時秀 | ||
| 仁治2(1241)年8月25日 | 上総修理亮政秀 | ||
| 仁治2(1241)年11月10日 | 上総権介平秀胤 | 叙爵(『関東評定伝』) | |
| 仁治3(1242)年正月13日 | 上総式部丞時秀 | 『鎌倉年代記裏書』 | |
| 寛元元(1243)年7月17日 | 上総権介(秀胤) 上総式部大夫(時秀) 上総修理亮(政秀) 上総五郎左衛門尉(泰秀) |
臨時御出供奉人 上旬:上総権介、上総式部大夫(すでに叙爵) 中旬:上総修理亮 下旬:上総五郎左衛門尉 |
|
| 寛元元(1243)年閏7月27日 | 上総権介平秀胤 | 従五位上(『関東評定伝』) | |
| 寛元元(1243)年8月16日 | 上総権介(秀胤) | ||
| 寛元元(1243)年9月5日 | 上総権介(秀胤) | ||
| 寛元2(1244)年 | 下総前司常秀男(秀胤) | 『関東評定伝』評定衆。 | |
| 寛元2(1244)年4月21日 | 上総権介(秀胤) | ||
| 寛元2(1244)年6月 | 埴生次郎平時常 | 「埴生神社神輿一基(亡)『地理誌』」 (「三宮埴生神社神輿銘」『千葉県史 金石文』) |
|
| 寛元2(1244)年8月15日 | 上総権介秀胤 上総修理亮政秀 |
||
| 寛元3(1245)年8月15日 | 上総権介秀胤(五位) 上総式部大夫時秀 上総五郎左衛門尉泰秀(五位) 上総六郎秀景 |
鶴岡放生会 先陣随兵:上総式部大夫時秀 御車:上総六郎秀景 御後五位:上総権介秀胤、上総五郎左衛門尉泰秀 |
|
| 寛元3(1245)年8月16日 | 上総介 子息六郎 |
流鏑馬 四番 上総介(上総権介秀胤) 射手、子息六郎(秀景) 的立、内藤肥後前司盛時 |
|
| 寛元3(1245)年10月16日 | 上総権介秀胤 | ||
| 寛元4(1246)年6月7日 | 上総権介秀胤 | ||
| 寛元4(1246)年6月13日 | 上総権介秀胤 | ||
| 宝治元(1247)年6月6日 | 上総権介秀胤 | ||
| 宝治元(1247)年6月7日 | 亡父下総前司常秀 上総権介秀胤 嫡男式部大夫時秀 次男修理亮政秀 三男左衛門尉泰秀 四男六郎景秀 秀胤舎弟下総次郎時常 |
||
| 宝治元(1247)年6月22日 | 上総権介秀胤 同子息式部大夫時秀 同修理亮政秀 同五郎左衛門尉泰秀 同六郎秀景 垣生次郎時常 |
||
| 宝治元(1247)年7月14日 | 上総権介(遺跡) | ||
秀胤が『吾妻鏡』にはじめて現れるのが、承久元(1219)年7月19日で、京都から鎌倉に入った藤原三寅(九條道家入道の三男で、四代将軍藤原頼経)の義時大倉邸入御に供奉した記述である(『吾妻鏡』承久元年七月十九日条)。父「堺兵衛尉(常秀)」の長男として「堺兵衛太郎」と称している。6月27日に京都を発し(慈光寺本『承久記』)、比較的ゆっくりとしたペースで鎌倉へ向かった。
●承久元(1219)年7月19日の「左大臣道家公賢息」の義時大倉邸入御の供奉輩(『吾妻鏡』承久元年七月十九日条)
| 女房 (各乘輿) |
雜仕一人 乳母二人 卿局 右衛門督局 一條局 相州室 |
|
| 先陣随兵 | 左 | 右 |
| 三浦太郎兵衛尉 | 三浦次郎兵衛尉 | |
| 天野兵衛尉 | 宇都宮四郎 | |
| 武田小五郎 | 小笠原六郎 | |
| 相摸小太郎 | 幸嶋四郎 | |
| 陸奥三郎 | 結城左衛門尉 | |
| 狩裝束人々 | 三浦左衛門尉 | 後藤左衛門尉 |
| 葛西兵衛尉 | 土屋左衛門尉 | |
| 千葉介(胤綱) | 筑後左衛門尉 | |
| 陸奥次郎 | 小山左衛門尉 | |
| 駿河守泰時 | 武蔵守義氏 | |
| 若君御輿 | 三寅 | |
| 歩行列立 輿左右 |
佐貫次郎 | 波多野次郎 |
| 山内弥五郎 | 長江小四郎 | |
| 木内次郎(胤朝) | 澁谷太郎 | |
| 本間兵衛尉 | 飫冨源内 | |
| 土肥兵衛尉 | 高橋太九郎 | |
| 殿上人 | 伊予少将実雅朝臣 | |
| 諸大夫 | 甲斐右馬助宗保 | 善式部大夫光衡 |
| 藤右馬助行光 | ||
| 侍 | 藤左衛門尉光経 | 主殿左衛門尉行兼 |
| 四郎左衛門尉友景 | ||
| 医師 | 権侍医頼経 | |
| 陰陽師 | 大学助晴吉 | |
| 護持僧 | 大進僧都寛喜 | |
| 後陣随兵 | 嶋津左衛門尉 | 中條右衛門尉 |
| 足立八郎左衛門尉 | 天野左衛門尉 | |
| 伊東左衛門尉 | 遠山左衛門尉 | |
| 堺兵衛太郎(秀胤) | 長江八郎 | |
| 加地兵衛尉 | 橘左衛門尉 | |
| 相摸三郎 | 兵衛大夫 | |
| 三浦次郎 | 河越次郎 | |
| 伊豆左衛門尉 | 小山五郎 | |
| 後陣 | 相摸守時房 | |
なお、軍記物『承久記』によれば、「三寅」(『承久記』前田家本)を「関東ヨリ御迎ニ参輩、三浦太郎兵衛尉、同九郎左衛門尉、大河津次郎、佐原次郎左衛門尉、同三郎左衛門尉、天野左衛門尉、子息大塚太郎、筑後太郎左衛門尉、結城七郎、長沼五郎、堺兵衛太郎、千葉介、以上十二人ゾ参リケル、先陣三浦太郎兵衛尉友村、後陣千葉介胤綱トゾ聞シ」(『承久記』「国史叢書」所収)と見え、秀胤は従兄弟の千葉介胤綱とともに三寅御迎の士として上洛したという。この迎えの士は秀胤岳父の三浦駿河守義村の親族が七割を占めており、三浦氏と九條関白家の親密な関係(三浦義村の守護国である土佐国は九條家が知行国主を務める)から選ばれた(または九條家側が指定)のであろう。なお、この記述は前田家本『承久記』、慈光寺本『承久記』には記載がない。
その後、秀胤は文暦2(1239)年2月9日の将軍頼経の後藤基綱邸での遊興まで十六年もの間、『吾妻鏡』から姿を消している。これは何を意味しているのだろうか。
三寅(頼経)の鎌倉下向後、京都の後鳥羽院と鎌倉家家司の北条義時との間で軋轢が大きくなり、ついに承久3(1221)年5月15日、京都守護のひとり伊賀太郎判官大夫光季の高辻北京極西角邸を後鳥羽院の兵に攻められ、自刃を遂げる事件が勃発した(『百錬抄』)。そして5月19日、後鳥羽上皇方は兵を集めて北条義時追討の兵を挙げた。これを「承久の乱」という。
常秀の上洛は、おそらくこの「承久の乱」に求めることができるだろう。彼は承久3(1221)年5月25日に関東を出陣した甥の東海道大将軍千葉介胤綱に従って上洛したと推測される。承久の乱における常秀の活動はうかがい知ることはできないが、『承久三年四年日次記』によれば、六條河原に布陣していた「海道手」の武士らの軍陣に勅使大夫史国宗が「故右府実朝公家司」の「主典代中宮権属中原俊職」を伴って訪れ、「義時朝臣追討宣旨可被召返」の勅諚を伝えている(『承久三年四年日次記』)。この勅諚を受けたのが、「武蔵守泰時、駿河守義村、堺兵衛尉常秀、佐竹別当能繁」らであったといい、常秀は承久の乱の軍陣にあり、上洛していたことがわかる。
●『承久三年四年日次記』
また、『慈光寺本承久記』(『承久記』諸本のうち鎌倉期成立の古態本とされる。ただし、あくまでも著作者のいる軍記物であって創作が含まれる可能性があり、史料としては参考にとどまる)によれば、第五陣に「紀内殿、千葉次郎」とある。これによれば千葉勢を率いたのは胤綱後見の叔父・千葉次郎泰胤となる。「紀内殿」については千葉一族の木内氏とも考えられるが、これも定かではない。
●承久3(1221)年5月25日までに出立した鎌倉勢大将軍の編成(『吾妻鏡』)
| 東海道大将軍 (十万余騎) |
北条相模守時房 | 北条武蔵守泰時 | 北条武蔵太郎時氏 | 足利武蔵前司義氏 | 三浦駿河前司義村 | 千葉介胤綱 |
| 東山道大将軍 (五万余騎) |
武田五郎信光 | 小笠原次郎長清 | 小山左衛門尉朝長 | 生野右馬入道 | 諏訪小太郎 | 伊具右馬允入道 |
| 北陸道大将軍 (四万余騎) |
北条式部丞朝時 | 結城七郎朝広 | 佐々木太郎信実 |
●『慈光寺本承久記』の鎌倉勢の編成(『慈光寺本承久記』)
| 三手 | 陣 | (大将軍) | 此手ニ可付人数 | ||||
| 海道 (七万騎) |
先陣 (二万騎) |
相模守時房 | 城入道 | 森入道 | 石戸入道 | 本間左衛門 | 伊藤左衛門 |
| 加持井 | 丹内 | 野路八郎 | 河原五郎 | 強田左近 | |||
| 大河殿 | 大見左衛門 | 宇佐美左衛門 | 内田五郎 | 久下三郎 | |||
| 勾当時盛 | |||||||
| 二陣 (二万騎) |
武蔵守泰時 | 関左衛門 | 新井田殿 | 森五郎 | 小山左衛門 | 新左衛門 | |
| 善左衛門 | 宇津宮入道 | 中間五郎 | 藤内左衛門 | 安藤兵衛 | |||
| 高橋与一 | 卯田右近 | 卯田刑部 | 阿夫刑部 | 大森弥次二郎兄弟 | |||
| 保威左衛門 | 蜂河殿 | 讃岐右衛門五郎 | 駄手入道 | 駄手平次 | |||
| 金子平次 | 伊佐三郎 | 固共六郎 | 丹党 | 小玉党 | |||
| 野田党 | 金子党 | 措二郎 | 有田党 | 弥二郎兵衛 | |||
| 駿河二郎康村 | 武蔵太郎時氏 | ||||||
| 三陣 | 足利殿 | ||||||
| 四陣 | 佐野左衛門政景 二田四郎 |
||||||
| 五陣 | 紀内殿 千葉次郎 (千葉泰胤か) |
||||||
| 山道 (五万騎) |
武田 小笠原 |
南部太郎 | 秋山四郎 | 三坂三郎 | 二宮殿 | 智戸六郎 | |
| 武田六郎 | |||||||
| 北陸道 (七万騎) |
式部丞朝時 | ||||||
承久3(1221)年の「承久の乱」で上洛した常秀の一族は、そのまま在京したのだろう。文暦2(1235)年2月9日までの十六年間、『吾妻鏡』に常秀一族が一切登場しない理由は、彼らが鎌倉を不在にしていたためであると考えられる。
文暦2(1235)年2月9日、「上総介太郎(秀胤)」は将軍頼経の「後藤大夫判官基綱大倉宅」移徙に供奉し、小笠懸の射手となった(『吾妻鏡』文暦二年二月九日条)。つまりこの日までに秀胤は関東に戻っていることがわかる。その後は6月29日の頼経の明王院「新造御堂安鎮」への御出に父「上総介常秀(先陣随兵)」とともに参じ、「御車左右」に「大須賀次郎左衛門尉(胤秀)」とともに並んだ(『吾妻鏡』文暦二年六月廿九日条)。
●『吾妻鏡』文暦2(1235)年6月29日条
| 先陣随兵 | 上総介常秀 | 駿河前司義村 |
| 小山五郎左衛門尉長村 | 筑後図書助時家 | |
| 城太郎義景 | 宇都宮四郎左衛門尉頼業 | |
| 足利五郎長氏 | 越後太郎光時 | |
| 陸奥式部大夫政村 | 相摸六郎時定 | |
| 御車 路次間無御剣役人 | 藤原頼経 | |
| 已上直垂帯剣 列歩御車左右 |
上総介太郎(秀胤) | 大須賀次郎左衛門尉(胤秀) |
| 小野沢次郎 | 宇田左衛門尉 | |
| 伊賀六郎左衛門尉 | 佐野三郎左衛門尉 | |
| 大河戸太郎兵衛尉 | 江戸八郎太郎 | |
| 本間次郎左衛門尉 | 安保三郎兵衛尉 | |
| 平岡左衛門尉 | ||
| 以下略 |
千葉介常胤―+―千葉介胤正―+―千葉介成胤――――千葉介胤綱
(千葉介) |(千葉介) |(千葉介) (千葉介)
| |
| +―千葉常秀―――――千葉秀胤
| (上総介) (上総権介)
|
+―大須賀胤信―+―大須賀通信――――大須賀胤氏
(四郎) |(太郎左衛門尉) (次郎左衛門尉)
|
+―大須賀胤秀
|(次郎左衛門尉)
|
+―大須賀重信【三浦泰村家子】
|(七郎左衛門尉)
|
+―大須賀範胤【三浦泰村家子】
(八郎左衛門尉)
嘉禎2(1236)年8月4日の若宮大路の新御所への移座では父「上総介」常秀(五位六位)が「御後」に供奉し、その後に「直垂」で「上総介太郎(秀胤)」は同族「大須賀次郎左衛門尉(胤秀)」とともに供奉した(『吾妻鏡』嘉禎二年八月四日条)。
●『吾妻鏡』嘉禎2(1236)年8月4日条(頼経・三浦氏と関わりの深い人物はピンク色)
| 前駈 | 木工権頭仲能 | 前民部権少輔親実(三条親実) |
| 備中左近大夫(重氏) | 前美作守(宇都宮時綱) | |
| 右馬権頭政村(北条政村) | ||
| 御劔役人 | 相摸権守(俊定) | |
| 御調度懸 | 安積六郎左衛門尉 | |
| 御甲着 | 長太右衛門尉 | |
| 御後 五位六位 布衣下括 |
遠江守(北条朝時) | 民部権少輔(北条有時) |
| 陸奥太郎(北条実時) | 北条弥四郎(北条経時) | |
| 足利五郎(足利長氏) | 遠江太郎(北条光時) | |
| 駿河前司(三浦義村) | 大膳権大夫(中原師員) | |
| 長井左衛門大夫(長井泰秀) | 毛利左近蔵人(毛利親光) | |
| 周防前司(中原親実) | 伊豆判官(若槻頼定) | |
| 安芸右馬助 | 佐渡守(後藤基綱) | |
| 宇都宮修理進(宇都宮泰綱) | 町野加賀前司(町野康俊) | |
| 大和守(伊東祐時) | 上総介(千葉常秀) | |
| 河越掃部助(河越泰重) | 筑後図書助(小田時家) | |
| 豊前大炊助(大友親秀) | 上野七郎左衛門尉(結城朝村) | |
| 上野五郎(結城重光) | 薬師寺左衛門尉(薬師寺朝村) | |
| 淡路左衛門尉(長沼時宗) | 後藤次郎左衛門尉(後藤基親) | |
| 後藤四郎左衛門尉(後藤基時) | 関左衛門尉(関政泰) | |
| 下河辺左衛門尉(下河辺行光) | 佐原新左衛門尉(佐原胤家) | |
| 笠間左衛門尉(笠間時朝) | 宇都宮左衛門尉(宇都宮頼業) | |
| 伊東左衛門尉(伊東祐網) | 大曾祢太郎兵衛尉(大曽祢長泰) | |
| 大曾祢次郎兵衛尉(大曽祢盛経) | 信濃次郎左衛門尉(二階堂行泰) | |
| 信濃三郎左衛門尉(二階堂行綱) | 隠岐四郎左衛門尉(二階堂行久) | |
| 藤四郎左衛門尉(秀実) | 梶原右衛門尉(梶原景俊) | |
| 近江三郎左衛門尉(佐々木頼重) | 葛西壱岐左衛門尉(葛西清親) | |
| 加地八郎左衛門尉(加地信朝) | 宇佐美藤内左衛門尉(宇佐美祐泰) | |
| 河津八郎左衛門尉(河津尚景) | 武藤左衛門尉(武藤景頼) | |
| 摂津左衛門尉(摂津為光) | 出羽四郎左衛門尉(中條光家) | |
| 加藤次郎左衛門尉(加藤行景) | 紀伊次郎左衛門尉(為常) | |
| 廣澤三郎左衛門尉(廣澤実能) | 小野寺四郎左衛門尉(小野寺通時) | |
| 平賀三郎兵衛尉(平賀惟時) | 狩野五郎左衛門尉(狩野為広) | |
| 春日部左衛門尉(春日部実景か) | 相馬左衛門尉(相馬胤綱) | |
| 宮内左衛門尉(公景) | 弥善太郎左衛門尉(三善康義) | |
| 駿河次郎(三浦泰村) | ||
| 直垂 | 駿河四郎左衛門尉(三浦家村) | 駿河又太郎左衛門尉(三浦氏村) |
| 上総介太郎(千葉秀胤) | 大須賀次郎左衛門尉(大須賀胤秀) | |
| 大河戸太郎兵衛尉(大河戸重澄?) | 伊賀六郎左衛門尉(伊賀光重) | |
| 佐々木近江四郎左衛門尉(佐々木氏信) | 波多野中務次郎(波多野経朝) | |
| 内藤七郎左衛門尉(内藤盛継) | 江戸八郎太郎(江戸景益) | |
| 宇田左衛門尉 | 筑後四郎左衛門尉(宍戸家政) | |
| 長掃部左衛門尉(長秀連) | 渋谷三郎(渋谷重頼) | |
| 南條七郎左衛門尉(南條時員) | 中野左衛門尉(中野時景) | |
| 平左衛門三郎(平盛時) | 本間次郎左衛門尉(本間信忠) | |
| 小河三郎兵衛尉(小河直行) | 飫富源内 | |
| 検非違使 | 駿河大夫判官(三浦光村) | 藤内大夫判官(藤原定員) |
| 遠山判官(遠山景朝) |
嘉禎3(1237)年8月7日、来春の将軍・藤原頼経上洛についての評定が行われ、洛外六波羅に将軍御所屋を新造することが決定。諸役は諸国に割り当てられた。ただし「六波羅御造営所役事無沙汰之国々」があったようなので(『吾妻鑑』嘉禎四年七月廿七日条)、下総国は前年の嘉禎2(1236)年6月に香取社遷宮宣下があったことから、所役は割り当てられなかったと思われる。
そして、翌嘉禎4(1238)年正月1日、修理権大夫時房亭における埦飯で「上総介太郎(秀胤)」と「同次郎(時常)」が引出物の馬を曳いている(『吾妻鏡』嘉禎四年正月一日条)。このとき馬を曳いているのは、埦飯関係者とみられることから、秀胤は駿河守義村の縁者として加わっていたものだろう。
●嘉禎4(1238)年正月1日埦飯(『吾妻鏡』嘉禎四年正月一日条)
■:北条時房関係、■:足利泰氏関係、■:三浦泰村関係
| 埦飯御沙汰 | 匠作(北条時房) | |
| 御剣 | 宮内少輔泰氏(足利泰氏) | |
| 御調度 | 若狭守泰村(三浦泰村) | |
| 御行騰沓 | 大和守祐時(伊東祐時) | |
| 一御馬 | 相摸式部大夫(北条朝直) | 本間式部丞(本間元忠) |
| 二御馬 | 相摸六郎(北条時定) | 橘右馬允(橘公高) |
| 三御馬 | 上総介太郎(千葉秀胤) | 上総介次郎(千葉時常) |
| 四御馬 | 本間次郎左衛門尉(本間信忠) | 本間四郎(本間光忠) |
| 五御馬 | 越後太郎(北条光時) | 吉良次郎 |
そして正月20日、将軍・藤原頼経は上洛のため秋田城介景盛の甘縄邸に入った。下総守護の千葉介時胤はすでに下総国内の地頭に対し大番催促をしていたが、今年は香取社造営の年であり、時胤は鎌倉に「香取造営之間、大介不出国境」と主張し、三日後の正月23日、鎌倉は時胤に「御京上御共止、可被在国之状」を発給した(嘉禎四年正月廿三日『関東御教書写』)。こうして時胤自身は上洛供奉を免除され、正月28日、将軍・藤原頼経の一行は鎌倉を出立して十か月にわたる上洛の途についた。まさに土壇場で供奉免除を申請し認められたのだった。なお、この当時千葉介時胤は「大介」を称しているように「下総守(国司)」に補されていたとみられ、実際に国衙へ指示を出し得る立場にあったと考えられる。
●嘉禎4(1238)年正月23日「関東御教書写」(「下総香取文書」:『鎌倉遺文』所収)
ところが、時胤管掌下の地頭らはそのまま将軍に供奉している。実際、2月17日の頼経入洛時の随兵中には下総国御家人として「下河辺左衛門尉(下河辺行時)」「壱岐小三郎左衛門尉」「壱岐三郎左衛門尉(葛西時清)」「下総十郎(木内胤定)」「千葉八郎(千葉胤時)」「大須賀左衛門次郎(大須賀胤氏)」「関左衛門尉(関政泰)」「上野七郎左衛門尉(結城朝広)」、2月28日の拝賀随兵に「上野五郎重光」らが見える(『吾妻鏡』嘉禎四年二月十七日条)。
●「造営諸役注文写」等『香取神宮文書』(■:上洛した御家人)
| 式年造営社殿等 | 担当諸役郡郷 ・地頭(雑掌人) 寛元元(1243)年? 「造営所役注文断簡」 | 『吾妻鏡』 嘉禎4(1238)年2月17日条 頼経上洛供奉 下総御家人 |
| 正神殿 |
(造営奉行人) ・千葉介 | |
| (大床、舞殿) |
幸嶋 ・不明 | |
| 火御子社 |
萱田郷 ・千葉介 | |
| 於岐栖社 |
吉橋郷 ・千葉介 | |
| 一鳥居 |
印東庄 ・千葉介 | |
| 勢至殿社 |
神保郷 ・千葉介 | |
| 不開殿社 |
小見郷 ・木内下総前司 | |
| 佐土殿社(佐渡殿) |
匝瑳北条 ・千葉八郎 | 千葉八郎(千葉胤時) |
| [女盛]殿社 |
大戸庄 ・国分小次郎跡 神崎庄 ・千葉七郎跡 | |
| 仮[女盛]殿 | ― | |
| 東廊 | 風早郷 ・不明 | |
| 中殿 |
垣生西 ・掃部助殿 | |
| 北庁屋(庁屋) |
大須賀 ・胤信跡 | 大須賀左衛門次郎(大須賀胤氏)他 |
| 南庁 | ― | |
| 瞻男社 |
垣生西内富谷郷 ・不明 | |
| 三鳥居 |
大方郷 ・関左衛門尉 | 関左衛門尉(関政泰) |
| 火王子社(日王子社) |
下野方 ・不明 | |
| 息洲社 | ― | |
| 忍男社 |
下野方 ・不明 | |
| 祭殿 | 結城郡 ・下野入道 | |
| 内院中門 |
匝瑳北条 ・飯高五郎跡 | |
| 外院中門 |
印西 ・掃部助殿 | |
| 西廊 | 矢木郷 ・不明 | |
| 若宮社 |
(造営奉行人) ・千葉介 | |
| 東脇門 |
平塚郷 ・掃部助殿 | |
| 西脇門 |
平塚郷 ・掃部助殿 | |
| 酒殿(高倉) | 遠山方 ・不明 | |
| 渡殿 | 上野方 ・不明 | |
| 宝殿 |
猿俣 ・壱岐入道跡 |
壱岐小三郎左衛門尉(葛西時清) 壱岐三郎左衛門尉(葛西清親) |
| 二鳥居 |
下葛西 ・壱岐入道跡? |
壱岐小三郎左衛門尉(葛西時清) 壱岐三郎左衛門尉(葛西清親) |
| 楼門 |
垣生印西 ・掃部助殿 ・千葉常秀か | |
| 内殿、 御輿、 諸神宝物 | 国司御沙汰 | |
| 大炊殿 | 国司御沙汰 | |
| 薦殿 | 国司御沙汰 | |
| 脇鷹社(脇鷹天神社) | 国司御沙汰 | |
| 鹿嶋新宮社 | 国司御沙汰 | |
| 馬場殿(馬場殿社) | 国司御沙汰 | |
| 八龍神社 | 国司御沙汰 | |
| 八郎王子社 | 国司御沙汰 | |
| 玉垣卅一丈六尺 | 国司御沙汰 | |
| 雷神社 | ― | |
| 印手社 | ― | |
| 又見社 | 国司御沙汰 | |
| 返田悪王子 | 国司御沙汰 | |
| 御幣棚 | (闕) | |
| 四面釘貫 四百五間(四面八町釘貫) | (闕) | |
| 馬庭埒 | (闕) |
2月17日の頼経の上洛には多くの御家人が供奉しているが、先陣は駿河前司義村が務め、その露払いの随兵には三十六騎の義村家子が名を連ねているように、将軍頼経との密接な関わりがうかがえる。随兵五十三番には秀胤も「上総介太郎」として名が見える(『吾妻鏡』嘉禎四年二月十七日条)。
●『吾妻鏡』嘉禎4(1238)年2月17日条(■三浦一族、■下総国の地頭)
| 駿河前司随兵 三騎相並 以家子三十六人為随兵 |
一番 | 大河戸民部太郎 | 大須賀八郎 (成毛範胤) |
佐原太郎兵衛尉 (佐原景連) |
| 二番 | 筑井左衛門太郎 | 筑井次郎 | 皆尾太郎 | |
| 三番 | 三浦又太郎左衛門尉 (三浦氏村) |
三浦三郎 (三浦員村) |
山田蔵人 | |
| 四番 | 武小次郎 | 武三郎 | 武又次郎兵衛尉 | |
| 五番 | 秋葉小三郎 | 山田六郎 | 山田五郎 | |
| 六番 | 多々良小次郎 | 多々良次郎兵衛尉 | 青木兵衛尉 | |
| 七番 | 安西大夫 | 金摩利太郎 | 丸五郎 | |
| 八番 | 丸六郎太郎 | 三浦佐野太郎 | 石田太郎 | |
| 九番 | 石田三郎 | 三原太郎 | 市兵衛次郎 | |
| 十番 | 長尾平内左衛門尉 (長尾景茂) |
長尾三郎兵衛尉 (長尾光景) |
平塚兵衛尉 | |
| 十一番 | 壱岐前司 | 駿河四郎左衛門尉 (三浦家村) |
遠藤兵衛尉 | |
| 十二番 | 駿河五郎左衛門尉 (三浦資村) |
駿河八郎左衛門尉 (三浦胤村) |
三浦次郎 (三浦有村) |
|
| 先陣 騎馬 郎従二人在前 |
駿河前司 (三浦義村) |
|||
| 御所随兵 百九十二騎 三騎相並 各弓袋差一人 歩走三人在前 |
一番 | 小林小次郎 | 小林小三郎 | 真下右衛門三郎 |
| 二番 | 猪俣左衛門尉 | 荏原七郎三郎 | 河匂野内 | |
| 三番 | 二宮左衛門太郎 | 二宮三郎兵衛尉 | 二宮四郎兵衛尉 | |
| 四番 | 池上藤兵衛尉 | 小串馬允 | 多胡宮内左衛門太郎 | |
| 五番 | 大井三郎 | 品河小三郎 | 春日部三郎兵衛尉 | |
| 六番 | 高山五郎四郎 | 江戸八郎太郎 | 江戸高澤弥四郎 | |
| 七番 | 大胡左衛門次郎 | 伊佐四郎蔵人 | 大胡弥次郎 | |
| 八番 | 都筑左衛門尉 | 都筑左近将監 | 遠藤左衛門尉 | |
| 九番 | 山内藤内 | 山内左衛門太郎 | 西條与一 | |
| 十番 | 後藤弥四郎左衛門尉 | 佐渡五郎左衛門尉 | 伊勢藤内左衛門尉 | |
| 十一番 | 小野寺小次郎左衛門尉 | 同四郎左衛門尉 | 薗田弥次郎左衛門尉 | |
| 十二番 | 紀伊次郎兵衛尉 | 豊田太郎兵衛尉 | 豊田次郎兵衛尉 | |
| 十三番 | 片穂六郎左衛門尉 | 和田左衛門尉 | 和田四郎左衛門尉 | |
| 十四番 | 秩父左衛門太郎 | 倉賀野兵衛尉 | 那珂左衛門尉 | |
| 十五番 | 中澤小次郎兵衛尉 | 中澤十郎兵衛尉 | 河原右衛門尉 | |
| 十六番 | 小河左衛門尉 | 河口八郎太郎 | 立河兵衛尉 | |
| 十七番 | 阿佐美六郎兵衛尉 | 塩谷民部六郎 | 福原五郎太郎 | |
| 十八番 | 下河邊左衛門尉 | 新開左衛門尉 | 大河戸太郎兵衛尉 | |
| 十九番 | 中野左衛門尉 | 俣野弥太郎 | 海老名四郎 | |
| 廿番 | 四方田三郎左衛門尉 | 塩谷六郎左衛門尉 | 蛭河四郎左衛門尉 | |
| 廿一番 | 栢間左近将監 | 多賀谷太郎兵衛尉 | 松岡四郎 | |
| 廿二番 | 本庄四郎左衛門尉 | 西條四郎兵衛尉 | 泉田兵衛尉 | |
| 廿三番 | 中村五郎左衛門尉 | 中村三郎兵衛尉 | 加治左衛門尉 | |
| 廿四番 | 阿保次郎左衛門尉 | 加治丹内左衛門尉 | 加治次郎兵衛尉 | |
| 廿五番 | 飫富源内 | 本庄新左衛門尉 | 那須左衛門太郎 | |
| 廿六番 | 進三郎 | 多賀谷右衛門尉 | 江帯刀左衛門尉 | |
| 廿七番 | 本間次郎左衛門尉 | 佐野三郎左衛門尉 | 高田武者太郎 | |
| 廿八番 | 小河三郎兵衛尉 | 平左衛門三郎 | 三村兵衛尉 | |
| 廿九番 | 長掃部左衛門尉 | 長右衛門尉 | 長兵衛三郎 | |
| 三十番 | 豊田弥四郎 | 秋元左衛門次郎 | 須賀左衛門太郎 | |
| 卅一番 | 高山弥三郎 | 同弥四郎 | 矢口兵衛次郎 | |
| 卅二番 | 薗田又次郎 | 木村弥次郎 | 木村小次郎 | |
| 卅三番 | 後藤三郎左衛門尉 | 後藤四郎左衛門尉 | 後藤兵衛太郎 | |
| 卅四番 | 伊達八郎太郎 | 中村縫殿助太郎 | 伊達判官代 | |
| 卅五番 | 佐竹八郎 | 結城五郎 (山川重光) |
佐竹六郎次郎 | |
| 卅六番 | 大曾祢太郎兵衛尉 | 大曾祢次郎兵衛尉 | 武藤左衛門尉 | |
| 卅七番 | 長三郎左衛門尉 | 長太右衛門尉 | 長内左衛門尉 | |
| 卅八番 | 善右衛門次郎 | 弥善太右衛門尉 | 布施左衛門太郎 | |
| 卅九番 | 得江蔵人 | 平賀三郎兵衛尉 | 得江三郎 | |
| 四十番 | 笠間左衛門尉 | 出羽四郎左衛門尉 | 狩野五郎左衛門尉 | |
| 四十一番 | 信濃民部大夫 | 信濃三郎左衛門尉 | 肥後四郎左衛門尉 | |
| 四十二番 | 壱岐小三郎左衛門尉 | 足立木工助 | 壱岐三郎左衛門尉 (葛西時清) |
|
| 四十三番 | 佐原太郎左衛門尉 | 下総十郎 (木内胤定) |
伊賀次郎左衛門尉 | |
| 四十四番 | 千葉八郎 (千葉胤時) |
相馬左衛門尉 (相馬胤綱) |
大須賀左衛門次郎 (大須賀胤氏) |
|
| 四十五番 | 内藤七郎左衛門尉 | 押垂三郎左衛門尉 | 春日部左衛門尉 | |
| 四十六番 | 近江四郎左衛門尉 | 豊前大炊助 | 加治八郎左衛門尉 | |
| 四十七番 | 武田五郎次郎 | 仁科次郎三郎 | 小野澤左近大夫 | |
| 四十八番 | 宇都宮新左衛門尉 | 氏家太郎 | 筑後左衛門次郎 | |
| 四十九番 | 和泉次郎左衛門尉 | 和泉新左衛門尉 | 和泉五郎左衛門尉 | |
| 五十番 | 佐原新左衛門尉 | 佐原四郎左衛門尉 | 佐原六郎兵衛尉 | |
| 五十一番 | 大井太郎 | 南部次郎 | 南部三郎 | |
| 五十二番 | 宇佐美与一左衛門尉 | 弥次郎左衛門尉 | 関左衛門尉 (関政泰) |
|
| 五十三番 | 少輔左近大夫将監 | 大江木工助 | 上総介太郎 (千葉秀胤) |
|
| 五十四番 | 筑後図書助 | 安積左衛門尉 | 伊藤三郎左衛門尉 | |
| 五十五番 | 佐渡二郎左衛門尉 | 佐渡三郎左衛門尉 | 佐渡帯刀左衛門尉 | |
| 五十六番 | 宇都宮四郎左衛門尉 | 宇都宮五郎左衛門尉 | 梶原右衛門尉 | |
| 五十七番 | 加藤左衛門尉 | 河津八郎左衛門尉 | 河越掃部助 | |
| 五十八番 | 小山五郎左衛門尉 | 宇都宮上條四郎 | 宮内左衛門尉 | |
| 五十九番 | 伊豆守 | 武田四郎 | 小笠原六郎 | |
| 六十番 | 薬師寺左衛門尉 | 淡路四郎左衛門尉 | 上野七郎左衛門尉 | |
| 六十一番 | 陸奥五郎太郎 | 毛利蔵人 | 那波次郎蔵人 | |
| 六十二番 | 若狭守(三浦泰村) | 宇都宮修理亮 | 秋田城介 | |
| 六十三番 | 遠江式部丞 | 越後太郎 | 遠江三郎 | |
| 六十四番 | 相摸六郎 | 北條左近大夫将監 | 宮内少輔 | |
| 次御輿 被上御簾 御裝束御布衣 御力者三手 |
藤原頼経 | |||
| 着水干人々 各野箭 |
一番 | 駿河守 | 備前守 | 右馬権頭 |
| 二番 | 長沼淡路前司 | 大河戸民部大夫 | 大和守 | |
| 三番 | 天野和泉前司 | 玄馬頭 | 佐原肥前々司 | |
| 四番 | 肥後前司 | 江判官 | 伊賀判官 | |
| 五番 | 出羽判官 | 壱岐大夫判官 | 因幡大夫判官 | |
| 六番 | 左京権大夫 随兵三十人 着水干侍十八人 其外打籠勢不可勝計 |
|||
| 後陣 随兵二十人 着水干侍二十人 其外打籠勢濟々焉 |
修理権大夫 |
3月15日、香取社造営の諸役を務めるべき人々は「於相随彼役仁者、早令帰国、至在国地頭者、御下向之時不参向」と鎌倉家政所より早々の帰東を命じられ、香取社造営に専念すべき旨の御教書を受けている。
●嘉禎4(1238)年3月15日「関東御教書写」(『金沢文庫文書』:『鎌倉遺文』所収)
ただ、その帰国の時期は不定期であったのか、あらかじめ京での所役が決まっていた場合は延引されたのか、4月7日の将軍頼経の権大納言拝賀には「大須賀左衛門尉(大須賀胤氏)」が随兵となり(『吾妻鏡』嘉禎四年四月七日条)、4月10日の頼経舎弟福王の仁和寺入室の供侍には「壱岐三郎左衛門尉時清」が見える(『玉蘂』嘉禎四年四月十日条)。さらに、5月20日に前右大臣三条実親の「御簡衆」となった「藤原朝村号上野十郎」、6月5日の将軍頼経の春日社参詣には「千葉八郎胤時」「下河辺右衛門尉行光」「関左衛門尉政泰」「壱岐三郎左衛門尉時清」の名がみえ、彼らはこれ以降に帰国したと思われる。将軍頼経は10月13日、京都を出立し、10月29日に鎌倉へ帰還した(『吾妻鏡』嘉禎四年十月廿九日条)。
しかし、その後秀胤は再び二年余り『吾妻鏡』に見えなくなり、仁治元(1240)年8月2日、「上総権介」として再登場する。秀胤は嘉禎4(1238)年10月13日の頼経離京時に供奉(「前後陣供奉人随兵等、同御入洛之時」(『吾妻鏡』嘉禎四年十月十三日条))して一度鎌倉に帰還したとみられるが、その後再度上洛したのだろう。
上記在京時に秀胤は「上総権介」に、子息の時秀は式部丞、政秀は修理亮、泰秀は左衛門尉にそれぞれ任官している。嘉禎4(1238)年2月17日~10月13日の頼経在京時での任官の可能性が高いか。暦仁元(1238)年12月25日当時、「式部丞」と「修理亮」は、名越遠江守朝時の子息「式部丞時章」「遠江修理亮時幸」(暦仁元年十二月廿五日『吾妻鏡』)兄弟が見える。つまり、秀胤は名越家と比肩する家格となったことがわかる。その背景にあるのは、おそらく父常秀の代からの将軍頼経との繋がりであろう。この頼経との関係の深さに伴う家格の上昇により、官途上で評定衆に加わる資格を得たと考えられる。
| 在京期間か | 嘉禎4(1238)年2月17日(頼経入京) ~10月13日(頼経離京) |
【頼経上洛以降在京か。下記はこの期間に任官】 秀胤:上総権介 時秀:式部丞(京官) 政秀:修理亮(京官) 泰秀:左衛門尉 |
| ????~ 仁治元(1240)年8月2日以前 |
ただし、秀胤はその地位が相対的に上昇しながらも、千葉惣領家に成り代わることはなかった。その地位は評定衆に列する家格ではあったが、
●北条得宗家と名越北条家の関係(■:得宗家、■:名越家)
北条義時―+―北条泰時―+―北条経時
| |
| +―北条時頼―北条時宗―北条貞時―北条高時
|
+―名越朝時―――名越光時
仁治2(1241)年11月10日、「上総権介平秀胤」は叙爵(従五位下)(『関東評定伝』)。寛元元(1243)年閏7月27日、従五位上に昇叙した(『関東評定伝』)。そして翌寛元2(1244)年正月23日、秀胤の嫡男・式部丞時秀も従五位上に昇叙した(寛元元(1243)年7月17日時点で時秀は「上総式部大夫」と見えることから、これ以前に叙爵している)。
その後、秀胤は関東の評定衆の一員に加わっており、寛元2(1244)年4月21日の藤原頼嗣(五代将軍。頼経の長子)元服式では、評定衆として着座している(『吾妻鏡』寛元二年四月廿一日条)。
寛元3(1245)年8月15日、鶴岡八幡宮の放生会に参列している。これには千葉惣領家代行人の千葉次郎泰胤(千葉介時胤弟)、秀胤の子・上総式部大夫時秀が列し、将軍・頼経の車脇に武石三郎朝胤、上総六郎秀景、その後ろに五位大夫として、上総五郎左衛門尉泰秀、上総権介秀胤が列した。
翌8月16日、八幡宮の馬場でとり行なわれた流鏑馬では、四番を差配した「上総介(秀胤)」が見え、射手は「子息六郎(秀景)」が行った。
寛元4(1246)年3月、執権の北条修理亮経時が病のために弟・左近将監時頼に執権職を譲ったが、北条一族の名門・名越越後守光時(北条義時の孫)が時頼の執権就任に反対して、大御所・藤原頼経を擁して兵を集めたが、事前に発覚して光時一党は捕らえられ、寛元4(1246)年6月7日に後藤佐渡前司基綱・狩野前太宰少貳為佐・上総権介秀胤・町野加賀前司康持が事件の関係者として評定衆をはずされた。町野康持に至っては、問注所執事をも解任されている。秀胤は13日に鎌倉を追放され、主犯格の北条光時も伊豆北条へ追放された。これら一連の事件を「寛元政変」という。
ただし、公家の葉室定嗣の日記『黄葉記』によれば、寛元4(1246)年6月6日、京都に関東からの飛脚が到来し、
と伝えた。『吾妻鏡』によれば、秀胤が評定衆を解職されたのは6月7日とされ、13日に鎌倉を追放されたとある。『黄葉記』の記述はこれよりも前となるため、実際に秀胤らが解職されたのはこれよりも前ということになる。『吾妻鏡』の記述の誤りだろうまた、前将軍・藤原頼経入道も京都へ送還されることが決した。このことについて、頼経の実父・九条道家入道行慧(源頼朝の姪子)は6月10日にはすでに伝えられているが、頼経送還の理由については「不知其由来」とあって、幕府より一切聞かされておらず、同意もしていないとし、「修調伏法、被呪詛武州経時」ともあることについても、頼経は一切行なっていないと神に誓っている(『九条家文書』)。
●寛元4(1246)年の評定衆(年号:在職期間、■:寛元政変で免職、■:宝治合戦で免職)
| ・中原師員 (1225-1251) | ・二階堂行盛 (1225-1253) | ・後藤基綱 (1225-1246) | ・太田康連 (1225-1256) |
| ・毛利季光 (1232-1247) | ・狩野為佐 (1234-1246) | ・北条資時 (1237-1251) | ・三浦泰村 (1238-1247) |
| ・二階堂行義 (1238-1268) | ・町野康持 (1238-1246) | ・大佛朝直 (1239-1264) | ・安達義景 (1239-1253) |
| ・北条政村 (1239-1256) | ・二階堂基行 (1239-1240) | ・清原満定 (1239-1263) | ・長井泰秀 (1241-1253) |
| ・宇都宮泰綱 (1243-1261) | ・伊賀光宗 (1244-1257) | ・三浦光村 (1244-1247) | ・上総秀胤 (1244-1246) |
| ・矢野倫長 (1244-1273) | ・毛利忠成 (1245-1247) |
その後、秀胤は8月15日の放生会に「上総式部大夫」とともに供奉していることから、鎌倉に召し返されたものの、翌宝治元(1247)年6月6日、鎌倉家司である左近大夫将監時頼は、主家の命として大須賀左衛門尉胤氏・東胤行入道素暹に秀胤の追討を指示した。ただし、追討軍には肥後国の相良六郎頼俊も加わっているように(建長三年三月廿二日「相良蓮佛譲状」『相良家文書』)、多国籍の御家人が差し向けられたと考えられる。秀胤はこのころ上総国一宮大柳館に籠もり、「秀胤兼用意之間、積置炭薪等於館郭外之四面」(『吾妻鏡』宝治元年六月七日条)とあるように、屋敷の外周に炭薪を積み重ね、すでに自害の決意を固めていた。泰村が討たれた事件については「泰村誅罰事、五日午刻、通当国之聴」(『吾妻鏡』宝治元年六月七日条)とあり、すでに一党と目されていた秀胤も追討の対象となることは覚悟のうえであったとみられる。
この上総大柳館の騒乱は、秀胤が「兼用意之間、積置炭薪等於館郭外之四面、皆悉放火」し、「数十宇舎屋同時放火」(『吾妻鏡』宝治元年六月七日条)したため、「焔太熾而非人馬之可通路、仍軍兵安轡於門外、僅造時聲発箭」という状況であった。秀胤方からも「出逢馬場辺、射答箭」しているが、この間に「上総権介秀胤、嫡男式部丞時秀、次男修理亮政秀、三男左衛門尉泰秀、四男六郎景秀、心静凝念仏読経等之勤、各自殺」した。
寄手の胤氏、素暹は秀胤と交誼のある人物であり、とくに素暹は秀胤一族と血縁関係があり、将軍家の命によりやむなく進軍してきたものであった。このとき、「秀胤舎弟」の「下総次郎時常、自昨夕入籠此館」っているが、時常と兄秀胤は「相伝亡父下総前司常秀遺領垣生庄之處、為秀胤被押領之間、年来雖含欝陶」とあるように対立関係にあったが、この兄秀胤の危急に駆けつけ「並死骸於一席」という。ひとびとはこれを聞いて「勇士之所美談也」とたたえた。
なお、大柳館は「数十宇舎屋」が一気に燃え上がったことで「内外猛火混而迸半天」という巨大な火災旋風が発生。寄手の「胤氏以下郎従等咽其熾勢、還遁避于数十町之外、敢不能獲彼首」(『吾妻鏡』宝治元年六月七日条)と、火災旋風による輻射熱により「数十町之外」へ離れるほかなく、秀胤らの首級を得ることはできなかった。なお、素暹の娘は秀胤の子・上総五郎左衛門泰秀に嫁いでおり、一歳の幼い男子があった。素暹から見れば外孫にあたる。この後、鎌倉へ帰還した素暹は幕府に赴き、時頼に懇願して秀胤の子や孫たちのために助命嘆願を行っている。この嘆願は受け入れられ、素暹には外孫にあたる1歳の男子(泰秀の子)のほか、秀胤の末子(1歳)、修理亮政秀の子息二人(5歳、3歳)、秀胤の弟・埴生次郎時常の子(4歳)が助けられ、素暹に預けられた。
●『吾妻鏡』宝治元年六月十一日条
●『吾妻鏡』宝治元年六月十七日条
●上総権介秀胤周辺系図
千葉介常胤―+―胤正――+―成胤――――胤綱―――+―時胤――――――頼胤
(千葉介) |(千葉介)|(千葉介) (千葉介) |(千葉介) (千葉介)
| | |
| | +―泰胤
| | (次郎)
| |
| | +―埴生時常―――男子
(四歳)
| | |(次郎)
| | |
| +―常秀――+―秀胤―――+―時秀
| (兵衛尉) (上総権介)|(式部丞)
| |
| +―政秀―――――+―男子
(五歳)
| |(修理亮) |
| | |
| +―末子(一歳) +―男子
(三歳)
| |
| |
| +―泰秀
| (五郎左衛門尉)
| ∥――――――――男子
(一歳)
| ∥
+―東胤頼―――重胤――――胤行―――+―娘
(六郎大夫)(兵衛尉) (左衛門尉)|
|
+―泰行
|(図書助)
|
+―行氏
|(左衛門尉)
|
+―氏村
(左衛門尉)
また、秀胤の子・式部丞時秀の子という「豊田五郎秀重」「左衛門尉常員」両名の名が薩摩国の系譜に見える(『山門文書』)。時秀の子については『吾妻鏡』には伝えられていないが、遺されていた可能性も否定できない。
千葉秀胤――時秀―――+―豊田秀重―+―秀持 +―秀徳―――橋本秀助――秀房
(上総権介)(式部大夫)|(五郎) |(源六) |(太郎)
| | |
+―常員 +―秀遠――秀村――秀高――秀行―――秀光――+―堤秀朝――朝篤
(左衛門尉) (五郎)(平三)(平六)(伊豆守)(美濃守)|(次郎) (安房守)
|
+―澤田秀明
|(三郎)
|
+―文殊寺秀棟
(四郎)
秀胤は現在の長柄町胎蔵寺に葬られたともいわれ、同寺には「長柄山殿別駕秀胤大居士」「胎蔵寺殿花渓妙泉大姉」の位牌が伝わっている(『上総国誌』)。「別賀(別駕=介)秀胤」と記されていることから、自刃を遂げた秀胤一族の菩提を弔ったと伝わる。裏には「当年開基」として「長 万寿四丁卯歳七月廿四日」「胎 長元三庚午七月七日」と記されているが、「万寿四年(1027年)」「長元三年(1030年)」は、秀胤の時代より約二百年前であることから、秀胤ではない可能性が高い。「長柄山胎蔵寺」(『上総国誌稿』)は「境内千八百七坪、臨済宗ナリ、寺伝ニ云フ、長和二年癸丑、上総権介秀胤、父祖ノ冥福ヲ祈リ、七堂伽藍ヲ建造シテ鳴瀧寺ト号ス、尋テ胎蔵界ノ曼荼羅ニ擬シテ、今ノ名ニ改ム」(『上総国誌稿』)という自伝を持つ。
秀胤一族滅亡の直前、鎌倉では三浦泰村一族が、北条氏に対して兵を挙げ、和田義盛の乱以来、30年ぶりに鎌倉が火に包まれた。結局三浦一族はやぶれ、泰村・光村父子は頼朝の墓前に逃れ、持仏堂に籠って自害して果てた。三浦泰村の挙兵と上総秀胤の滅亡を「宝治合戦」という。
●宝治合戦で戦死した人物
(■:三浦党、■:千葉一族、■:秩父一族、■:下野の宇都宮・小山氏系統)
・三浦泰村・三浦景村・三浦駒石丸・三浦光村・三浦駒王丸・三浦式部三郎・三浦實村・三浦重村・三浦朝村・三浦氏村・三浦朝氏・三浦員村・三浦忠氏・三浦景泰・三浦駒孫丸・三浦駒鶴丸・三浦駒在丸・三浦有駒丸・三浦駒若丸・三浦駒増丸 ・三浦皆駒丸・毛利季光・毛利光広・毛利泰光・毛利経光・毛利吉祥丸・大戸川重澄・大戸川重村・大戸川家康・三浦義有 ・三浦高義・三浦胤泰・三浦二郎・高井実重・高井実泰・高井実村・佐原泰連・佐原信連・佐原秀連・佐原光連・佐原政連 ・佐原光兼・佐原頼連・佐原胤家・佐原光連・佐原泰家・佐原泰連・長井義重・佐原家経・下総三郎・佐貫経景 ・稲毛左衛門尉・稲毛十郎・臼井太郎・臼井二郎・波多野六郎左衛門尉・波多野七郎・宇都宮時綱・宇都宮時村・宇都宮五郎 ・春日部実景・春日部太郎・春日部二郎・春日部三郎・関政泰・関四郎・関五郎左衛門尉・能登仲氏・宮内公重・宮内太郎 ・弾正左衛門尉・十郎・多々良二郎左衛門尉・石田大炊亮・印東太郎・印東二郎・印東三郎・平塚小次郎・平塚光広 ・平塚太郎・平塚三郎・土用左兵衛尉・平塚五郎・遠藤太郎左衛門尉・遠藤二郎左衛門尉・佐野左衛門尉・榛谷四郎 ・榛谷弥四郎・榛谷五郎・榛谷六郎・白河判官代・白河七郎・白河八郎・白河式部丞・武左衛門尉・上総権介秀胤 ・上総時秀・上総政秀・上総泰秀・上総秀景・埴生時常・岡本次郎兵衛尉・岡本次郎・長尾景茂・長尾定村・長尾為村 ・長尾胤景・長尾光景・長尾為景・長尾新左衛門四郎・秋庭信村・橘惟広・橘左近大夫・橘蔵人
●宝治合戦で生け捕りの人物(■:三浦党、■:千葉一族)
・三浦胤村・金持次郎左衛門尉・毛利文殊丸・豊田太郎兵衛尉・豊田次郎兵衛尉・長尾次郎兵衛尉・長井時秀・大須賀範胤
●宝治合戦で逐電した人物(■:千葉一族)
・小笠原七郎・大須賀重信・土方右衛門次郎
宝治合戦では「臼井太郎・次郎」が秀胤に荷担し、ほかに「下総三郎」「印東太郎・次郎・三郎」の千葉氏系の武士の名を見ることができる。
また、建長3(1251)年12月、三浦・千葉の残党が先の将軍家・九条頼経を擁立して挙兵を企てる事件が起こるが、首謀者の「了行法師」、千葉介近親「矢作左衛門尉」「長次郎左衛門尉久連」らが生け捕られている。
| 矢作左衛門尉 | 矢作胤氏(左衛門尉) 矢作常氏(六郎左衛門尉) | 常胤の従兄弟にあたる海上常幹の孫。 常胤の子・国分胤通の六男。国分矢作氏の祖である。 |
| 臼井太郎・二郎 | 臼井胤常・親常 臼井則胤・則常 | 山無流臼井氏の子。 友部流臼井氏の子。父・友部秀常の諱「秀」は秀胤からの偏諱か? |
| 下総三郎 | 上代胤忠?(下総三郎?) | 東胤頼の子・木内胤朝の子は「下総」を称しているが、そのなかに「三郎」だけがなく、「二郎」胤家の次は「四郎」胤時である。なんらかの意図があって三郎は除かれたものか。 |
●矢作・臼井・下総系図
平常兼―+―千葉常重―千葉常胤―+―千葉胤正―+―千葉成胤 +―上総秀胤
| | | |
| | +―上総常秀――+―埴生時常
| |
| +―国分胤通―――矢作常氏
| |(五郎) (六郎左衛門尉)
| |
| +―東 胤頼―――木内胤朝――――下総三郎(?)
| (六郎大夫) (下総前司)
|
+―海上常衡―海上重常―――矢作惟胤―――矢作胤茂――――矢作胤氏
| (左衛門尉) (新左衛門尉) (左衛門尉)
|
+―臼井常康―臼井常忠―+―友部宗常―――友部秀常――+―臼井則胤
(六郎) (三郎) |(二郎) (宰相) |(太郎)
| |
| +―臼井則常 +―臼井胤常
| (次郎) |(太郎)
| |
+―臼井成常―――臼井盛常――――山無常清――+―臼井常親
(四郎) (九郎) (五郎) (次郎)
宝治元(1247)年7月14日、宝治合戦の恩賞として、足利義氏入道正義(左馬頭)が上総権介秀胤の遺跡を賜り、伊勢皇太神宮へと寄進している。