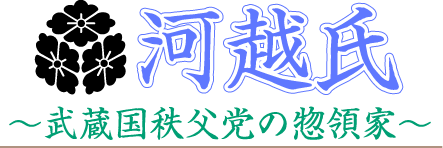
武蔵国留守所惣検校職
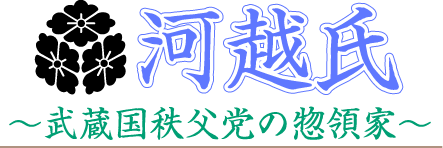
武蔵国留守所惣検校職
●河越氏について●
河越氏は秩父氏の惣領家で、その祖は国衙の有力在庁となったのち、秩父牧別当を経て武蔵国留守所の惣検校職などを「家職」として発展した一族である。河越太郎重頼は支配下の郡司・比企氏出身の女性の娘を娶っており、その女性(比企尼)が乳母を務めた源頼朝とも早いうちから交流があったと推測される。頼朝挙兵時は知行国主平知盛の支配のもとで頼朝と敵対するが、頼朝の武蔵国入国を契機に赦されてその郎従となり、以降はその信任を得て元暦元(1184)年6月5日の除目(鎌倉除目到着は6月20日)で武蔵守となった源義信のもとで相聟同士(義信と重頼の妻は姉妹)で国務を行ったのだろう。
その後、頼朝とその弟(猶子)である洛中守護・伊予守源義経との契約の中で、娘を義経正室として京都へ送っており、もともと比企尼を通じた頼朝と義経の紐帯強化が期待されていたと思われ、義経の麾下には重頼嫡子・小太郎重房が加わっている。
ところが、義経が頼朝に敵意を示す叔父前備前守行家の捕縛を拒絶したことで、頼朝との関係が悪化。頼朝は命に服さなければ土佐房昌俊により義経ともども追捕を行う旨を通告したものの、義経はなお拒絶したため、土佐房昌俊は義経の六条室町邸を襲撃。結局、義経勢に行家勢が加わったことで、土佐房昌俊は捕らえられて梟首された。これにより義経は頼朝追討の宣旨を後白河院に要請。義経と頼朝の関係は破綻した。しかし、義経は頼朝代官という立場であり、義経に付されていた頼朝郎従は義経に加担することはなく、義経と行家はそれぞれ後白河院より九州と四国の惣追捕使に任じられ、京都を落ちていく。さらに摂津国から西へ向けて出帆するも強風によって船団は瓦解。義経と行家はその兵力を失って逃走し、頼朝による行家・義経の残党狩りが行われることとなる。そして、この結果、重頼と重房は義経縁者という理由から誅殺された。
その後、武蔵国における河越氏の勢力は大きく損なわれることとなるが、子孫は鎌倉家家人郎従(御家人)として出仕しつつ北条得宗家の被官(御内人)となり、のちに在京御家人となって六波羅に出仕していたとみられる。その後、北条氏が滅んだのちは「鎌倉家」の家政機関を継承した足利氏(鎌倉殿のち室町殿)の家人となり、関東に下向して関東足利家(鎌倉公方)のもとで勢力を挽回したものの、鎌倉公方に対して反旗を翻した「平一揆」を主導して滅んだ。
| 平良文 | 平忠頼 | 平将恒 | 平武基 | 秩父武綱 |
| 秩父重綱 | 秩父重隆 | 葛貫能隆 | 河越重頼 | 河越重房 |
| 河越泰重 | 河越経重 | 河越宗重 | 河越貞重 | 河越高重 |
| 河越直重 |
●河越氏略系図●
小代行平
(八郎)
∥――――――弘家
+―娘
|
|
葛貫能隆―+―河越重頼―+―重房 +―泰重―――経重――――宗重―――貞重―――+―高重―――直重
(別当) |(留守所) |(小太郎)|(掃部助)(安芸守) (出羽守)(三河守) |(三河守)(弾正少弼)
| | | |
+―小林重弘 +―重時――+―信重 +―上野介
|(二郎) |(二郎) |(二郎)
| | |
+―師岡重経 | +―重家
(兵衛尉) | (五郎)
|
+―重員―――重資――+―重氏
|(三郎) (修理亮)|(太郎蔵人)
| |
+―重方―――実盛 +―娘
|(四郎) (三浦某妻)
|
+―娘
|(源義経妻)
|
+―娘
(下河辺政義妻)
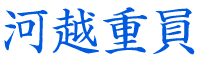 (????-????)
(????-????)
河越太郎重頼の三男。母は不明。通称は三郎。
元久2(1205)年6月22日の畠山重忠追討軍の中に兄・河越次郎重時とともに名を連ねており、元久年中には河越氏は謀叛の罪を許され、御家人として復帰していたことがわかる。
●畠山重忠追討軍交名(『吾妻鏡』元久二年六月二十二日条)
| 大将軍: | 北条相模守義時・北条式部丞時房・和田左衛門尉義盛 |
| 先 陣: | 葛西兵衛尉清重 |
| 後 陣: | 境平次兵衛尉常秀、大須賀四郎胤信、国分五郎胤通、相馬五郎義胤、東平太重胤 |
| 諸 将: | 足利三郎義氏、小山左衛門尉朝政、三浦兵衛尉義村、三浦九郎胤義、長沼五郎宗政、結城七郎朝光、 |
| 宇都宮弥三郎頼綱、八田筑後左衛門尉知重、安達藤九郎右衛門尉景盛、中条藤右衛門尉家長、 | |
| 中条苅田平右衛門尉義季、狩野介入道、宇佐美右衛門尉祐茂、波多野小次郎忠綱、松田次郎有経、 | |
| 土屋弥三郎宗光、河越次郎重時、河越三郎重員、江戸太郎忠重、渋川武者所、小野寺太郎秀通、 | |
| 下河辺庄司行平、薗田七郎、大井、品川、春日部、潮田、鹿島、小栗、行方、兒玉、横山、金子、村山党 |
嘉禄2(1226)年4月10日、河越重員は「先祖秩父出羽権守」以来、代々補されていた武蔵国留守所惣検校職に補せられた。頼朝挙兵時には河越重頼が補せられており、重頼は秩父党の惣領家として畠山重忠や小山田有重らを動員して頼朝に組した。重頼が義経に加担したとして誅殺された後、畠山重忠が補任された。その重忠が誅殺された後は、検校職が置かれた形跡はなく、武蔵国は北条家の治めるところとなっていた。そこに河越重員が補されたという事は、北条氏の支配下にありつつも、河越氏は名目上とはいえ秩父党惣領家として復権したものか。
寛喜3(1231)年4月2日、重員は武蔵国惣検校職の四か条の職掌が近年廃れて、執行されていないことを嘆き、先例の通り執行すべきことを泰時に申状を提出して訴えた。泰時はさっそく岩原源八経直を武蔵国留守所に派遣して、在庁に河越重員が訴えたところの四か条の職掌が先祖伝来のものであるかを確認させたところ、在庁官人の日奉實直・日奉弘持・物部宗光らが提出したもの、ならびに留守代帰寂が提出した副状が「留守所自秩父権守重綱之時、至于畠山二郎重忠、奉行来之條」という河越重員の申状と一致したことから、4月20日、泰時は河越重員に武蔵国留守所惣検校職としての四か条の職掌を相違なく行うよう指示した。
貞永元(1232)年12月23日、河越重員の譲状に基づいて嫡子・河越三郎重資へ「武蔵国惣検校職并国検時事書等、国中文書之加判及机催促加判等之事」について、先例のごとく沙汰すべきことが「庁宣」で指示されている。貞永元(1232)年当時の武蔵守は泰時であることから、この「庁宣」は泰時からの国司庁宣であったことがうかがえる。
建長3(1251)年5月8日、貞永元年の庁宣の通り、「河越修理亮重資」が「武蔵国惣検校職」に補されたが、貞永元年の庁宣の惣検校職については、このとき初めて補されたものと考えられることから、貞永元年の時点で認められていたのは、「国検時事書等、国中文書之加判及机催促加判等之事」のみであったと考えられる。
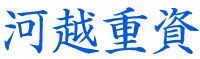 (????-????)
(????-????)
河越三郎重員の嫡男。通称は三郎。官途は修理亮。
貞永元(1232)年12月23日、父・河越重員から嫡子・河越三郎重資へ与えられた「武蔵国惣検校職並国検時事書等、国中文書之加判及机催促加判等之事」について、先例のごとく沙汰すべきことが武蔵国司である泰時の庁宣で指示され、建長3(1251)年5月8日、この貞永元年の庁宣の通り、「河越修理亮重資」が武蔵国惣検校職に補された。
弘安8(1285)年12月には但馬国大浜庄の地頭に「河越太郎蔵人重氏」が任じられている。重氏は「河越修理亮跡地頭」であることから、河越修理亮重資の子であろう。
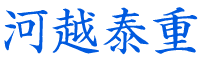 (????-????)
(????-????)
河越次郎重時の嫡男。通称は次郎か。官途は掃部助。
泰重は3代執権・北条泰時の偏諱を賜っていると考えられ、以降の河越氏家督も代々得宗からの一字を賜る傾向にあり、河越氏は北条得宗家と深い関わりをもつ有力御家人でとして認知されていたことがうかがえる。
安貞2(1228)年7月23日、将軍・藤原頼経の三浦義村の山荘への渡御の随兵として「河越次郎」の名が見える。泰重の通称は伝わっていないものの、嘉禄2(1226)年4月10日、叔父の三郎重員が「武蔵国留守所惣検校職」に任じられていることから、すでに泰重の父・河越重時は亡くなっていたと思われ、泰重が随兵の「河越次郎」であったと思われる。
文暦2(1235)年6月29日、五大堂の新造御堂の安鎮祭が執り行われ、将軍・頼経に供奉した人物中に後陣の隨兵として「河越掃部助泰重」の名が見える。
嘉禎2(1236)年8月4日、将軍・頼経は若宮大路に新築された御所に移り、その隨兵として「河越掃部助」が見え、嘉禎3(1237)年4月19日、鎌倉の大倉御堂の上棟に際し、将軍頼経の供奉として名が見える。
暦仁元(1238)年、将軍・頼経の随兵として参列。寛元4(1246)年を最後に名を消した。
 (????-????)
(????-????)
河越掃部助泰重の嫡男。通称は次郎。官途は遠江権守。四代執権・北条経時の偏諱を受けていると思われる。寛元4(1246)年8月15日の放生会の後陣の隨兵として見える「河越五郎重家」は彼の弟か。
康元元(1256)年6月29日、将軍・宗尊親王の随兵として名を見せ、それからもおもに随兵として活躍している。
なお、経重は武蔵国河越庄の地頭職も帯していたようで、文応元(1260)年12月22日の河越庄内新日吉山王宮に銅鐘を奉納している。武蔵国の北条氏の有力な被官であったと思われる河越重員(武蔵国惣検校職を帯す)の系統は、貞永元(1232)年12月23日に嫡子・三郎重資に武蔵国惣検校職が譲られ、建長3(1251)年5月8日に幕府から正式に武蔵国惣検校職に補された。
経重と重資の両系統の河越氏の所領がどのようになっていたのかは不明だが、文応元(1260)年に鋳造された「武蔵国河肥庄新日吉山王宮」の鐘銘に「大檀那平朝臣経重」が見え、このころ河越庄は惣領河越経重の支配下にあったとみられる。さらに、この銅鐘を鋳た人物は、鎌倉の大仏を鋳造した丹治久友であり、河越惣領家と北条氏との深い関わりがうかがえる。
●川越市養寿院鐘銘(重要文化財)●
文永3(1266)年7月3日、宗尊親王の供奉人として名を見せたのち『吾妻鏡』から見えなくなる。ただし、文永6(1269)年、経重の領する田二反が黒酒左衛門尉によって狼藉をうけて刈り取られたため、経重は幕府に訴え出た。そして11月14日、幕府侍所は黒酒を断罪したうえ、その所領である田三百余町が経重に譲り与えられた。
文永9(1272)年5月、高野山中の百十一町目の「町石卒塔婆」に「遠江権守平朝臣経重」が見えることから、存命である。その後の経重の伝は不明である。
【豊後国香賀地荘の河越安芸守系】
弘安8(1285)年9月、元寇の功績によってか、豊後国国東郡香地郷の地頭職として「河越安芸前司」が任じられている(弘安八年九月「御注進状案」『平林本』「鎌倉遺文」15700号)。「河越安芸前司」の該当者は不明だが、「河越安芸前司」の末裔は「豊後国香賀荘地頭職」を伝領している。
「河越安芸前司」の子と思われる「河越河内権守重方」は、正和3(1314)年に鎮西探題「前上総介(北条政顕)」が裁許した宇佐弥勒寺領の「就神領興行」のための「豊後国香地庄内当寺東宝塔供料田三町六段事」について「重方代篁賀不敍用」として問題となっており、「真玉孫四郎殿(惟氏)、都甲四郎入道殿(惟遠)」を通じて下知状を守って沙汰すべきことを命じている(正和三年九月十九日「鎮西御教書」『豊前北艮蔵文書』「鎌倉遺文」25226号)。
「河越安芸前司」の系統は鎌倉末期には鎮西探題に属していたとみられ、その滅亡後は所領が収公され、建武元(1334)年11月25日には「豊後国香賀地荘地頭職三分弐河越安芸入道跡」を「大友豊前六郎(大友貞広)」に「為勲功賞」(建武元年十一月廿五日「後醍醐天皇綸旨」『入江文書』)として賜り、同日の綸旨で「豊前七郎貞挙」に残りの「勲功地豊後国香賀地荘地頭職参分壱河越安芸入道跡事」を守護代理「左近将監(大友貞載)」に命じ、河越安芸入道跡の両地は11月28日に「竹田津諸次郎入道」と「津甲次郎入道」を両使として打渡している(建武元年十一月廿八日「大友貞載執行状」『草野文書』、『豊後古文章』)。この「河越安芸入道」は「河後安芸入道宗重」である(建武三年三月卅日「高師直連絡案文」『荒巻文書』)。
ところが翌建武2(1335)年に「河越安芸入道宗重」の子「河越安芸小次郎治重」が「引率伊藤五郎四郎、長尾野蔵人房以下輩」して「乱入当荘(豊後国香地荘)、濫妨所務致種々狼藉」している。ここを打渡されていた「豊前六郎貞広、同七郎貞挙」が武家政権に訴え出ている。これを受けて武家政権(翌3月30日案文と同様に高師直が発給しているのだろう)は守護代理の「左近将監(大友貞載)」に綸旨を下して沙汰を命じ、大友貞載は12月15日、「早守護代并都甲弥次郎入道」「竹田津諸次郎入道殿」に「相鎮狼藉、且相進交名輩、宜令申誓文散状」の執行を命じている(建武二年十月十五日「大友貞載執行状」『竹田津文書』)。ところが、この濫妨は収まらず「河越安芸入道宗重、同子息小次郎治重、次郎仲重、致乱暴狼藉」し(建武三年三月卅日「高師直連絡案文」『荒巻文書』)、「武蔵権守(高師直)」が「豊後国守護代」に「早於狼藉者不日相鎮之、至宗重等者、為尋沙汰可召進之」ことを命じている。
その後、「河越安芸小次郎治重」とみられる「河越安芸守(安芸権守か)」は武家方(足利方)と対峙して南朝方となり、石見国「凶徒総大将新田左馬助義氏」に属して「大多和外城」に籠り「高津原孫三郎、波多野彦三郎」「徳屋彦三郎」とともに抵抗。暦応5(1342)年3月17日、安芸守護武田氏信に属する「源有朝(逸見有朝)」らに降参している(暦応五年六月十八日「逸見有朝軍忠状」『小早川什書』)。その後は北朝武家方として在京し、貞和4(1345)年12月27日以降、河内国に出征していたようで「長門国永富紀藤太郎忠季代子息季幸」や「河越安芸権守、青景五郎太郎、真鍋新左衛門尉、斎藤弥太郎以下人々」がこれに属している(貞和四年十月「永富季幸軍忠状案」『正閨史料』)。
河越某―――河越重方――――+―河越治重
(安芸前司)(河内権守) |(安芸小次郎)
=安芸入道宗重? |=安芸守?
|
+―河越仲重
(次郎)
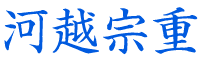 (????-????)
(????-????)
河越安芸前司経重の嫡男。母は不明。通称は不明。官途は出羽守。
八代執権・北条時宗の偏諱を受けているのだろう。彼に目立った活躍は見られない。
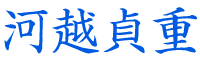 (1272-1333)
(1272-1333)
河越出羽守宗重の嫡男。母は不明。通称は不明。官途は三河守。法名は乗誓。
貞重は北条時宗の嫡男・執権の北条貞時の偏諱を受けたと思われる。
元弘元(1331)年5月、幕府打倒を画策する日野俊基ら公家が捕らえられた「元弘の変」が起こると、貞重は幕府勢のひとりとして上洛。9月、河内国赤坂城で挙兵した楠木正成を討つために、大和軍に加わった。
翌元弘2(1332)年冬、護良親王・楠木正成が畿内で挙兵すると、得宗北条高時入道は「関東八カ国」の御家人に上洛を命じた。この「軍勢交名」を見ると「参河入道」とされていることから、貞重はすでに出家していたことがわかる。
●「関東軍勢交名」(『伊勢光明寺文書残篇』:『鎌倉遺文』所収)
| 楠木城 | |
| 一手東 自宇治至于大和道
| |
| 陸奥守 | 河越参河入道(貞重) |
| 小山判官 | 佐々木近江入道 |
| 佐々木備中前司 | 千葉太郎(胤貞) |
| 武田三郎 | 小笠原彦五郎 |
| 諏訪祝 | 高坂出羽権守 |
| 島津上総入道 | 長崎四郎左衛門尉(高重) |
| 大和弥六左衛門尉 | 安保左衛門入道 |
| 加地左衛門入道 | 吉野執行 |
| 一手北 自八幡于佐良□路
| |
| 武蔵右馬助 | 駿河八郎 |
| 千葉介(貞胤) | 長沼駿河権守 |
| 小田人々 | 佐々木源太左衛門尉 |
| 伊東大和入道 | 宇佐美摂津前司 |
| 薩摩常陸前司 | □野二郎左衛門尉 |
| 湯浅人々 | 和泉国軍勢 |
| 一手南西 自山崎至天王寺大路
| |
| 江馬越前入道 | 遠江前司 |
| 武田伊豆守 | 三浦若狭判官 |
| 渋谷遠江権守 | 狩野彦七左衛門尉 |
| 狩野介入道 | 信濃国軍勢 |
| 一手 伊賀路
| |
| 足利治部大夫(高氏) | 結城七郎左衛門尉 |
| 加藤丹後入道 | 加藤左衛門尉 |
| 勝間田彦太郎入道 | 美濃軍勢 |
| 尾張軍勢 | |
| 同十五日
| |
| 佐藤宮内左衛門尉 自関東帰参 | |
| 同十六日
| |
| 中村弥二郎 自関東帰参 | |
●「関東軍勢交名」(『伊勢光明寺文書残篇』:『鎌倉遺文』所収)
| 大将軍 | |
| 陸奥守遠江国 | 武蔵右馬助伊勢国 |
| 遠江守尾張国 | 武蔵左近大夫将監美濃国 |
| 駿河左近大夫将監讃岐国 | 足利宮内大輔三河国 |
| 足利上総三郎 | 千葉介(貞胤)一族并伊賀国 |
| 長沼越前権守淡路国 | 宇都宮三河権守伊予国 |
| 佐々木源太左衛門尉備前国 | 小笠原五郎阿波国 |
| 越衆御手信濃国 | 小山大夫判官一族 |
| 小田尾張権守一族 | 結城七郎左衛門尉一族 |
| 武田三郎一族并甲斐国 | 小笠原信濃入道一族 |
| 伊東大和入道一族 | 宇佐美摂津前司一族 |
| 薩摩常陸前司一族 | 安保左衛門入道一族 |
| 渋谷遠江権守一族 | 河越参河入道(貞重)一族 |
| 三浦若狭判官 | 高坂出羽権守 |
| 佐々木隠岐前司一族 | 同備中前司 |
| 千葉太郎(胤貞) | |
|
|
|
| 勢多橋警護 | |
| 佐々木近江前司
| 同佐渡大夫判官入道
|
元弘3(1333)年上洛軍に加わっていた貞重は、4月、丹波国篠村庄で後醍醐天皇側に寝返った足利高氏、ならびに播磨国の赤松円心入道の六波羅攻撃を防いでいたと思われ、防戦むなしく六波羅探題は陥落。探題南方の左近将監北条時益、北方の越後守北条仲時は、光厳天皇を奉じて鎌倉へ向かったが、近江国で比叡山の僧兵の闇討ちにあった時益は戦死してしまった。
北条仲時は時益の家人も軍勢に加えてさらに東へ向かったが、5月9日、近江国番場宿において宮方に寝返っていた佐々木道誉(京極高氏)の軍勢に行く手を阻まれ、同宿蓮華寺で自害した。このとき、彼に従っていた南北六波羅の士四百三十余人が彼に殉じた。その中に、「川越参河入道乗誓」とその若党・木戸三郎家保も見える。貞重このとき六十二歳と伝えられている。
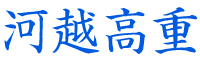 (????-????)
(????-????)
河越三河守貞重の嫡男。母は不明。通称は不明。官途は三河守。法名は円重。
高重は北条貞時の嫡男で最後の得宗・北条高時の偏諱を受けていると思われる。
元弘3(1333)年、父・貞重が近江で自刃したときと同じころ、上野国の小御家人・新田義貞が越後の新田党などを率いて挙兵。『太平記』によると、彼が武蔵に入ると、武蔵七党はじめ、河越氏もこれに加わったとある。
その後の河越氏の活躍は不明だが、新田勢は鎌倉から逃れてきた惣領嫡子足利千寿王(のちの足利義詮)を奉じて鎌倉に下向。5月22日に鎌倉は陥落し、北条高時入道以下は鎌倉東勝寺で自害し、百五十年にわたって武士を統率してきた鎌倉は滅亡した。
その後、鎌倉の留守居として派遣された足利直義(足利尊氏の弟)に従って下向し、建武2(1335)年に信濃国から鎌倉に攻め寄せた中先代の乱(高時の遺児・北条時行の反乱)でも直義の麾下として活躍したが、その後の活動は不明。
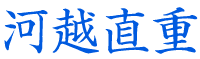 (????-????)
(????-????)
河越三河守高重の嫡男か。官途は弾正少弼。役職は相模国守護職。武蔵河越氏最後の当主か。
直重の「直」は足利直義の偏諱によるものか。文和元(1352)年閏2月、南朝勢力の新田義宗・新田義興・上杉憲顕と北朝の足利尊氏が戦った多摩郡の「人見原・金井原の戦い」では尊氏の麾下として河越直重と河越上野介(高重の弟)が参戦している。この合戦では足利勢は新田勢を破ったが、入間郡の「小手指ヶ原の戦い」では足利勢は大敗し、鎌倉も新田勢に奪われている。
同じころ、畿内では足利義詮(千寿王)が南朝勢力に京都から追われたが、翌3月、義詮は態勢を立て直して京都を奪還。尊氏も武蔵国石浜郷で軍勢を召集し、鎌倉を攻め落とした。
その後、武蔵国比企郡の「笛吹峠の戦い」で河越直重・河越上野介は新田義宗と合戦し、義宗を越後に追い落としており、その功績により、直重は相模守護職に、上野介は相模守護代に任じられた。
文和2(1353)年8月、尊氏が京都へ戻る際には、新田勢の動きを見張るため、足利基氏(尊氏の四男)が入間川に布陣した。このとき、鎌倉の留守を任されたのが相模国守護である河越直重であり、尊氏から大きな信頼を受けていたことがわかる。
その後、直重は相模国守護として基氏の命を奉じ、相模国戸田郷内の田畠を鶴ヶ岡八幡宮の僧・重弁へ譲った。さらに文和3(1354)年6月、相模国の飯田七郎左衛門が島津周防守忠兼の所領・岩瀬郷、倉田郷に攻め入って代官を殺害した事件では、尊氏から守護・河越直重と守護代・河越上野介が処置を命じられている。
延文4(1359)年10月5日、鎌倉の足利基氏執事・畠山国清は河越直重ら関東勢を率いて上洛した。そして翌年3月、畠山国清は楠木正儀の籠もる河内国へ入り、金剛寺を襲撃してこれを焼き討ちしている。河越直重は紀伊国最初峯と竜門山を攻め落とし、7月には国清・細川清氏らとともに摂津国天王寺に出陣し、仁木義長を撃ち破った。こののち義長は大和国吉野へ下って南朝方となる。8月、畠山国清・河越直重は鎌倉へ引き揚げた。
康安元(1361)年11月、畠山国清は基氏と対立して鎌倉を出奔し、伊豆国で挙兵したが、その翌康安2(1362)年9月、基氏に攻められて降伏し、斬殺されたが、この討伐軍に直重も加わっている。
貞治6(1367)年4月26日、足利基氏は病床で「河越治部少輔」に対して次男・金王丸(のちの足利氏満)の補佐を頼んでいる。この「河越治部少輔」は直重か?
応安元(1368)年1月25日、足利義満の元服の祝いのために、関東管領・上杉憲顕(かつて新田義宗らとともに尊氏を攻めた人物)が金王丸の代理として上洛したが、その上洛の最中、武蔵国河越にて「武州平一揆」が勃発したことを知らされ、憲顕は義満から関東へ帰還して対応するよう命じられた。憲顕は3月28日に京都を出発して、4月5日に鎌倉へ入り、十歳の足利氏満(金王丸)とともに河越へ出陣した。
この「平一揆」が河越城に籠もっていることを考えると、河越氏がその中心となっていたと考えられ、おそらく延文年中からの畿内合戦の恩賞がなかったことなど、様々な要因があったと考えられる。この「平一揆」に加わっていたのは、秩父党の河越氏・江戸氏・高山氏などで、鎌倉勢はかなりの苦戦を強いられ、平一揆勢の背後から甲斐の武田氏・葛山氏の軍勢までも動員し、6月17日の河越合戦でようやく鎮圧に成功。河越氏ら秩父党は武蔵国を逃れ、伊勢国に落ちた。こうして、平安時代から四百年にわたって武蔵国の武士団の棟梁であった秩父党河越氏は滅亡した。
その後、武蔵国に勢力を広げたのが関東管領上杉氏で、室町時代中期には、扇谷上杉氏と山内上杉氏がとくに勢力を伸ばし、関東の政治や戦乱の中心となっていく。
河越氏の庶流
師岡重経(????-????)
源頼朝の挙兵の際には、兄・河越重頼とともに平家方として頼朝勢と敵対していたが、石橋山の戦いの後、房総半島を経て武蔵国に進軍してきた頼朝に降伏。頼朝の乳母・比企尼の縁戚ということで、河越氏は重用され、寿永元(1182)年8月12日、頼朝の嫡男・頼家が産まれると、師岡重経は大庭平太景義、多々羅権守貞義とともに鳴弦役をつとめた。
文治元(1185)年11月の兄・河越重頼の誅殺後も重経にはお咎めはなかったようで、文治5(1189)年7月19日、奥州御陣の頼朝本隊に従って奥州へ出陣した。
|ページの最初へ|千葉氏の一族|秩父氏のトップ|千葉日記ブログ|
Copyright©1997-2018 ChibaIchizoku. All rights reserved.
当サイトの内容(文章・写真・画像等)の一部または全部を、無断で使用・転載することを固くお断りいたします。