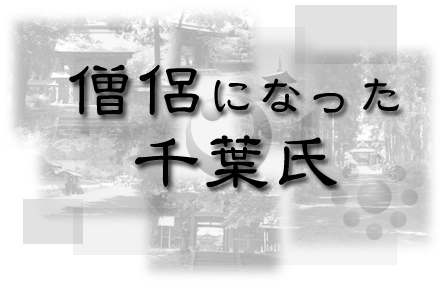
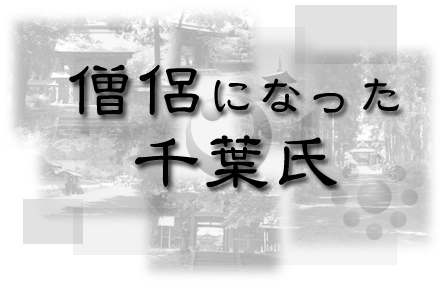
トップページ > 僧侶になった千葉一族(真言宗)
【真言宗】
| 明円 | ????-???? | 千田庄金原郷安久山堂別当 | |
| 常瑜 | ????-???? | 大夫僧都、阿闍梨 | |
| 覚瑜 | ????-???? | 民部阿闍梨 | |
| 胤助 | 1251-???? | 介阿闍梨 | 相馬民部大夫胤継子 |
| 照胤 | 1775-1829 | 成田山新勝寺中興八世 | 武田村千葉権之助家 |
トップページ >僧侶になった千葉一族(真言宗)> 明円
明円 (????-????)
鴨根常房の子孫・金原次郎清胤の子(『神代本千葉系図』)。治部。真言宗系の宗教施設だった千田庄金原郷の安久山堂別当職にあった。この堂は薬師如来を祀っていたと思われる(『折伏正義抄』)。
『日蓮宗大辞典』によれば日蓮の壇越「金原法橋」は「金原左衛門尉胤長の父」、つまり明円のこととしているが、明円はあくまで真言宗の僧侶であり、安久山堂が日蓮宗に改宗したのは同寺(円静寺)発掘の板碑より弘安元(1278)年以降、明円の孫にあたる民部阿闍梨覺瑜の代であることから、日蓮より文永8(1271)10月5日付の消息を受けている「金原法橋」と同一人物とすることはできない。
叔父に「良憲 僧舜忍」という僧侶が見えるが(『神代本千葉系図』)、真言律宗の良観房忍性の法弟子であろうか。ただし世代は忍性の方が一世代後である。
―金原氏略系図―
→平常長―鴨根常房―千田常益――金原常義――盛常―+―清胤―+―重胤―――――+―胤益―――――宗胤――――義胤
(三郎) (千田庄司)(金原庄司)(庄司)|(次郎)|(小次郎) |(五郎) (五郎) (五郎)
| | |
+―盛親 | +―胤光―――+―胤義
|(次郎)| |(弥二郎) |(彦次郎)
| | | |
+―良憲 | | +―僧
(舜忍)| | (少輔)
| |
| +―胤朝―――+―資胤
| (七郎) |(平四郎)
| |
| +―義胤
| (八郎)
| 僧治部
+―明円―――――+―常瑜―――――覚瑜 +―十郎
(安久山堂別当)|(大夫僧都) (民部阿闍梨) |
| |
+―胤長―――+―胤春――+―有胤―――――亀王丸―+―又七
(左衛門尉)|(三郎) |(又三郎)
| |
+―胤親 +―胤義―――+―胤弘――――胤満
|(六郎) |(七郎次郎)|(伊賀守) (伊賀守)
| | |
+―胤盛 | +―日範 +―徳王丸
(七郎) | |(修善院)|
| | |
| +―胤世――+―日元
| (掃部助) (中将公)
|
+―千代松丸―+―日従
|
|
+―七郎
トップページ >僧侶になった千葉一族(真言宗)> 常瑜
常瑜 (????-????)
治部明円の子(『神代本千葉系図』)。阿闍梨、大夫僧都。
鎌倉佐々目遺身院の法印権大僧都元瑜の弟子となっており、遺身院または子院に常住していたものと思われる。父・明円は安久山堂の別当となっていたが、常瑜がその跡を継いだかは不明。
正応3(1290)年12月9日巳刻、法眼慶弁とともに佐々目遺身院内陣において、親助大僧都より西院流の印可を受ける(『血脈類集記』)。
永仁元(1293)年12月21日、遺身院御影堂において相馬次郎兵衛胤継の末子「介阿闍梨胤助」が師の法印権大僧都元瑜より西院流伝法灌頂を受けているが(『血脈類集記』)、このとき、阿闍梨常瑜が讃衆として列した。このときに常瑜の続柄が記載されているが、「千葉治部房■弁子、千葉三郎常房胤子」(『血脈類集記』)とある。
トップページ >僧侶になった千葉一族(真言宗)> 覚瑜
覚瑜 (????-1360?)
治部明円の子(『神代本千葉系図』)で、兄・常瑜僧都の養子となった。民部阿闍梨。
安久山堂は、同寺発掘の弘安元(1278)年板碑より大日如来の種子が刻まれていることから、このころまでは真言宗寺院であったことがわかる。その後、暦応4(1341)年には南無妙法蓮華経の題目が刻まれた板碑に変わっており、このころまでに日蓮宗へと改宗している。そして、改宗した当時の人物が覚瑜(覚兪)であった。覚瑜は中山本妙寺の日祐の弟子僧となり、安久山堂を日蓮宗の堂に改め、文和5(1356)年には百二名からなる一結講衆を自ら率いた。
延文5(1360)年11月2日に没した(『円静寺過去帳』)。
なお、鎌倉佐々目遺身院の法印権大僧都元瑜の弟子に「常瑜阿闍梨」と並んで「覚瑜阿闍梨」がいたが、安久山堂を日蓮宗に改宗した「覚瑜」と同一人物とすると、没年が九十歳頃となり、疑問も生じるため明円の子と同一人物かは不明。
元瑜法弟子の覚瑜は、正応4(1291)年に保壽院流の印可を重ねて受けたとあり、これ以前に一度印可を得ていたこととなる(『血脈類集記』)。永仁7(1299)年2月21日、遺身院内陣において西院流の伝法灌頂を受けた(『血脈類集記』)。
トップページ >僧侶になった千葉一族(真言宗)> 胤助
胤助 (1251-????)
相馬次郎兵衛胤継(民部入道)の末子である(『血脈類集記』『神代本千葉系図』)。介法印、介阿闍梨。
永仁元(1293)年12月21日に鎌倉佐々目遺身院において法印権大僧都元瑜より西院流伝法灌頂を受けた「介阿闍梨胤助」に相当する(『血脈類集集』)。この年四十三歳であるため、建長3(1251)年の誕生となり(『鎌倉佐々目遺身院の指図について―永仁元年胤助伝法潅頂記の検討』上野勝久 金沢文庫研究292)、父・相馬胤継が継母(相馬尼)から義絶されて、惣領権者の資格を失ってしばらくののちのこととなる。胤助が仏門に入ったのはこうした理由があったのかもしれない。法印元瑜の弟子には胤助のほかにも相馬氏所縁の子弟の名が見え、阿闍梨景瑜は「天野藤内遠景胤子、藤染三郎景綱子」、阿闍梨常瑜は「千葉治部房■弁子、千葉三郎常房胤子」とある。景瑜、常瑜は胤助の佐々目御影堂における伝法灌頂で諸役を受け持っているが、景瑜の出身家である天野家は、胤継を義絶した継母・相馬尼(天野遠景孫娘)の実家であるという関係にあった。
■参考文献:『鎌倉佐々目遺身院の指図について―永仁元年胤助伝法潅頂記の検討ー』上野勝久(金沢文庫研究292)
トップページ >僧侶になった千葉一族(真言宗)> 照胤
照胤 (1775-1829)
真言宗智山派の僧侶。成田山新勝寺中興八世。字は快順。成田山中興六世・照乗上人の弟子で、のち七世・照誉上人弟子となる。はじめ延命院(成田市幡谷)の住持を務めていた。
安永4(1775)年、武田村に生まれた。出自については『人躰起立書』(『照胤上人代記録』「成田山新勝寺史料集」)によれば「下総国香取郡武田村権之助忰」とあるが、千葉家の系図に拠れば千葉権之助紀胤の子とされている(『千葉文華』第十五「下総千葉氏末葉考」)。ただ、紀胤は明和7(1770)年9月に亡くなっているため、その子・権之助宗胤の子かもしれない。
天明6(1786)年、十二歳のときに成田山新勝寺(成田市成田)で得度して「照胤」と号し、その後、京都智積院三十世化主・弘基僧正のもとで灌頂を受けたのち、十一年間、智積院で修行を重ね、享和4(1804)年に成田村の延命院(成田市幡谷)の住職となった。
文政2(1819)年3月、照胤四十五歳のとき、師の照誉上人が隠居することとなり、照誉は「後住之儀弟子延命院照胤」との願書を佐倉藩役所に提出し、4月16日には成田村の観音院、郷辺村の神光寺(成田市郷部)、成田村名主、組頭らからも「右延命院江新勝寺住職被為 仰付被下置候様一同奉願上候」との願書が提出された。これを受けて19日、佐倉藩庁は成田村名主・武助へ延命院照胤宛ての「明後廿一日四ツ時役所江可罷出候」との文書を下し、これを受取った延命院照胤は、21日、神光寺と武助とともに佐倉藩庁に罷り出、新勝寺住職を仰せ付けられ中興八世となる。先規の通り五十石を下し置かれた。
25日、照胤は江戸の佐倉藩上屋敷に佐倉藩主・堀田相模守正愛に「継目御礼」を申し上げるために成田を発ち、翌26日江戸着。28日、「出府着届」を上屋敷に提出し、閏4月1日、上屋敷にて藩主・堀田相模守と対面して御目見えを済ませた。その後も江戸で様々挨拶を済ませた後、21日に江戸を出立。大和田に宿泊し、翌22日は佐倉新町の万屋四郎右衛門方に宿泊。翌23日は酒々井村の笹屋喜三郎方で昼食をとり、新勝寺に帰寺した。その後もしばらくは行事が続いた。
七代市川団十郎寄進の額堂上棟式や、阿弥陀堂の再興、仁王門修復などを行い、文政12(1829)年3月には、小田原藩の下野国桜町陣屋で農政再建を図っていた二宮金次郎が成田山を参詣した際にこれを遇した。
しかし、春先には「疝癪」が悪化。江戸村松町の川村元良という医師を頼って、深川永代寺(江東区富岡一丁目)の般若院を旅宿と定めた。本来は成田山の旅宿は坂本町正福院だが、この年の3月23日に火災で焼失してしまったため、般若院が借寺とされた。
4月25日、佐倉藩庁に江戸行きの願書を提出。28日に江戸へ出て七十日あまりの療治を予定した。しかし、7月になっても体調は改善せず、7月7日にさらに五十日の延長療養を申し出た。ただ、照胤は「甚大病ニ相成候」とされ、7月18日に俄に江戸を出立した。実際にはこのとき照胤は亡くなったため俄の出立となったようだ。19日には遺骸が新勝寺に到着。20日、照胤は「養生不相叶」遷化したと公表された。世寿五十五(『新修成田山史』)。翌21日、佐倉藩庁に届が提出された。
後住を定める暇もない急逝だったが、弟子には俊才が多く、後住は弟子の照融上人が定められ、文政13(1830)年4月に貫主となった。なお、十世の照阿、十三世の照輪も照胤の弟子である(『照胤上人代記録』「成田山新勝寺史料集」)。
天保11(1840)年5月3日に亡くなったともされるが(『千葉文華』第十五「下総千葉氏末葉考」)、これは誤りである。