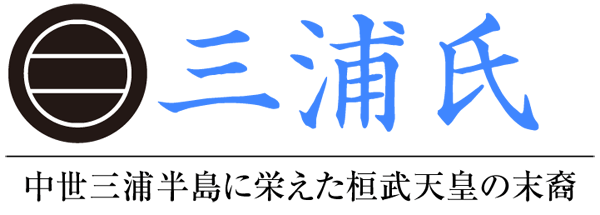
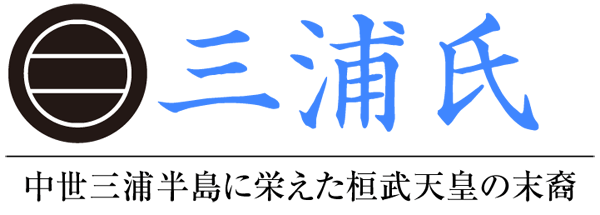
| 平忠通 (????-????) |
三浦為通 (????-????) |
三浦為継 (????-????) |
三浦義継 (????-????) |
三浦介義明 (1092-1180) |
| 杉本義宗 (1126-1164) |
三浦介義澄 (1127-1200) |
三浦義村 (????-1239) |
三浦泰村 (1204-1247) |
三浦介盛時 (????-????) |
| 三浦介頼盛 (????-1290) |
三浦時明 (????-????) |
三浦介時継 (????-1335) |
三浦介高継 (????-1339) |
三浦介高通 (????-????) |
| 三浦介高連 (????-????) |
三浦介高明 (????-????) |
三浦介高信 (????-????) |
三浦介時高 (1416-1494) |
三浦介高行 (????-????) |
| 三浦介高処 (????-????) |
三浦介義同 (????-1516) |
三浦介盛隆 (1561-1584) |
●三浦氏の惣領家●
 (????-1335)
(????-1335)
三浦氏十代当主。三浦上総介時明の子。母は不明。通称は三浦介。官位は従五位下。法名は道海。
元徳3(1331)年4月29日、前権大納言定房が後醍醐天皇による得宗北条高時入道以下の北条一門追討計画を六波羅探題に密告し、正中元(1324)年に起こった後醍醐天皇の側近による反関東の企て「正中の変」以来、再び京都において関東への対立計画が発覚する。
元徳3(1331)年8月9日、後醍醐天皇は突如改元の詔を発し、元号を「元徳」から「元弘」へと改めた。この詔書は「大外記之注進関東之處、有詔書無改元記、仍関東不用新暦、用元徳暦」(『元弘日記裏書』「大日本史料」)とあり、なぜか関東への詔書には改元の記載がなく、関東ではそのまま元徳を用いたという。勘文は文章博士在淳の「康安、天統、安永」、文章博士在成の「嘉慶、慶長、寧長」に「可然字無」ということで、元徳改元の際の勘文の一つ嘉暦4(1329)年8月の式部大輔在登の勘文が再度検討され、『芸文類聚』から採用された「元弘」が選ばれることとなった。
このような中、後醍醐天皇は前天台座主「大塔の二品法親王尊雲(のちの護良親王)ならびに天台座主「妙法院の法親王尊澄(のちの宗良親王)」両皇子の影響力のもと、延暦寺に働きかけ、水面下で密かに叡山行幸とともに反関東へと動き始めた。これに延暦寺も「御門の御軍にくはゝるべきよし奏し」たという(『増鏡』)。ところが、こうした動きはすでに「武家にもはやうもれ聞」えており、六波羅から関東へ軍勢派遣の要請が遣わされたとみられる。
8月21日には「東使三千余騎ニテ二階堂下野判官、長井遠江守上洛ス」(『神明鏡』)という。そして、六波羅探題は「さにこそあなれとようゐす、まづ九重をきびしくかため申べし」(『増鏡』)と、8月24日に内裏を固めるべく軍勢を催したのであった。
このとき後醍醐天皇は雑務日で記録所に臨席し「人のあらそひうれふる事どもををこなひくらさせ給ひて、人々もまかで君も本殿にしばしうちやすませ給」(『増鏡』)と、公卿らとともに訴訟を処理し終えて本殿へ戻って休んでいたが、密かに「今夜すてに武士ともきほひまいるへし」(『増鏡』)という報告があったことから、「内侍所、神璽、宝剣」のみを持って、深夜子刻に慌てて北の対から貧相な女車に乗って南都へ向けて密幸した。本来の計画では、六波羅を攻めると同時に天皇は延暦寺へ行幸することとなっており、前座主尊雲法親王、祇園妙法院に居住する現座主尊澄法親王は、「坂本(西坂本)」で叡山の僧兵を具して天皇の警衛を行うと定められていたが、俄に計画が変更となってしまった。知らせを受けた「中務の宮(中務卿宮尊良親王)」も馬に跨り父帝を追った。後醍醐天皇は九条までは御車で逃れたが、ここで車を降りて変装し馬上となって一路東大寺へと駆けた(『増鏡』)。同道の公卿は「万里小路中納言藤房、源中納言具行、四条中納言隆資」(『増鏡』)であったという。そのほか、「按察使公敏」(『続史愚抄』)、「六条中将」「近藤左衛門尉宗光、但馬左衛門尉重定等ヲ始トシテ、御供ノ官兵五百余騎」(『笠置寺縁起』)が供奉した。
翌25日子の刻、天皇已下は東大寺へ入り、26日暁に「和束(相良郡和束町)」の「鷲峯寺」へ移り、翌27日に「笠置寺へ御入」(『嘉元記』)して「以本堂為皇居」した(『大乗院日記目録』)。笠置寺への行幸には「其外東南院僧正聖尋、御先達タル間、東大寺ノ衆徒、警固シ奉」ったという(『笠置寺縁起』)。
天皇の延暦寺への密幸情報は神五左衛門尉(御内人諏訪氏だろう)によって六波羅へ伝えられ、六波羅探題は「所被申入実否、於西園寺家也」(『伊勢光明寺残篇』)と、春宮大夫公宗にその実否確認が依頼されている。その後、御所には「六波羅軍勢乱入禁裏、而依無御座空引退」(『続史愚抄』)という。
一方、延暦寺行幸計画自体も、側臣の花山院大納言師賢が天皇になりすまして実行されている。これは「抑今夜於無山門行幸者、僧徒等可失望」というためで、そのほか天皇逃亡の時間稼ぎであろう。師賢は「仮詭帝号登山」し「僧徒懇伝之致防御之備」(『続史愚抄』)であった。六波羅探題も北方の越後守仲時(使者は高橋孫五郎)、南方の左近将監時益(使者は糟屋孫八)から鎌倉に「主上御座山門之由、被聞食之旨」を遣わしており、六波羅は師賢の偽計に乗せられていたことがわかる。師賢の祖母は後醍醐天皇生母・談天門院忠子の姉妹であり、父方においても遠縁にあたることから、容姿に似ている部分があったのかもしれない。
北条時政―+―北条義時――――+―北条泰時―――北条時氏――――北条時頼―――――北条時宗―――北条貞時――北条高時
(遠江守) |(陸奥守) |(左京権大夫)(修理亮) (相模守) (相模守) (相模守) (相模守)
| |
| +―北条重時―――北条業時
| (陸奥守) (陸奥守)
| ∥ 【六波羅北方】
| ∥―――――――北条時兼―――――北条基時―――北条仲時
+―北条政村――――+――――――――女子 (尾張守) (相模守) (越後守)
(左京権大夫) |
|
+――――――――――――――――北条政長
(駿河守)
∥ 【六波羅南方】
大江広元―+―長井時広――+―――長井泰秀 ∥――――――――北条時敦―――北条時益
(陸奥守) |(左衛門尉) | (甲斐守) ∥ (越後守) (左近将監)
| | ∥ ∥
| | ∥――――――長井時秀――+―女子
| | ∥ (宮内権大輔)|
| | ∥ |
| 佐々木信綱―|―+―女子 +―長井宗秀―――――長井貞秀―――長井貞懐
|(近江守) | | (掃部頭) (中務少輔) (大蔵少輔)
| | |
| | +―佐々木泰綱――佐々木頼綱―――佐々木時信
| | |(壱岐守) (備中守) (三郎判官大夫)
| | |
| | +―佐々木氏信――佐々木満信―――佐々木宗氏――――佐々木高氏
| | (近江守) (佐渡守) (三郎左衛門尉) (四郎左衛門尉)
| |
| +―――長井泰重―――長井頼重――――長井貞重―――――長井高広
| (因幡守) (因幡守) (縫殿頭) (左近大夫)
|
+―海東忠成――――――海東忠茂―――海東広茂――――海東広房
(刑部少輔) (美濃守) (因幡守) (左近将監)
また、京都では8月25日、「万里小路大納言宣房卿、侍従中納言公明卿、宰相成資卿、別当右衛門督実世卿以上四人被召捕之」(『伊勢光明寺残篇』)となり、宣房卿は「因幡左衛門大夫将監」、公明卿は「波多野上野前司」、成資卿は「丹後前司」、実世卿は「筑後前司」への預かりとなっている。
8月27日、六波羅探題の命を受けた「佐々木大夫判官、海東備前左近大夫、波多野上野前司」が近江国の東坂本に、「長井左近大夫将監、加賀前司」が京都西坂本に、「常陸前司」が近江勢多にそれぞれ布陣し、比叡山を攻める準備を整えた(『伊勢光明寺残篇』)。
●比叡山攻めの布陣
| 東坂本(近江) | 佐々木大夫判官 | 海東備前左近大夫 |
波多野上野前司 |
| 西坂本(京都) | 長井左近大夫将監 | 加賀前司 | |
| 勢多(近江) | 常陸前司 |
また「両上皇并春宮、自持明院殿、御幸六波羅殿、臨幸御路武士供奉、以南方為御所」(『公卿補任』)という。「両上皇」とは後伏見上皇、花園上皇の兄弟上皇を指し、「春宮」は後伏見上皇の皇子・量仁親王のことである。翌28日の近江国東坂本での合戦では「源時信家僕并海道一類戦死」(『元弘日記裏書』「大日本史料」)、「海東備前左近大夫将監、其後十七騎於東坂下致合戦、主従十三騎打死了、佐々木大夫判官、波多野上野前司、山徒之首二被取進之間、被懸于六条河原了」(『伊勢光明寺残篇』「大日本史料」)とあるように、六波羅勢は佐々木時信の郎従や海東備前守自身の討死など苦戦した。
この日は「大納言(師賢)」も「大塔の前座主の宮(尊雲法親王)」も「うるハしきものゝふすがたにいてたゝせ給ふ」と武装しており、「大塔の前座主の宮」は「卯花をどしの鎧にくハがたのかぶとたてまつりて、大矢おひ」、「大納言」は「からの香染のうす物のかりぎぬにけちえんにあかきはらまきをすかして、さすかにまきゑのほそ太刀」を佩いたいでたち、一方、現座主の「妙法院の宮(尊澄法親王)」は「すすしの御衣のしたにもえぎの御腹巻とかやき給」っていた(『増鏡』)。ところが、叡山衆徒等の間に「御門かさぎにおはしますよし、ほどなく聞えぬれ」ば、両宮は笠置へと逃れ去り、師賢は京都へ忍び入ろうと試みるも断念し笠置山へと向かっている(『増鏡』)。しかし、その途次の山城国寺田郷で地頭代野辺若熊丸によって召し捕らえられ「進武家」(『公卿補任』)られ、六波羅へ引き渡されたとみられる。8月29日に出家(法名素貞)を遂げたとあることから(『公卿補任』)、この日の捕縛か。
8月29日、六波羅探題が派遣した両使(北:高橋孫五郎、南:糟屋孫八)が鎌倉に到着。「任承久例、可上洛之由被仰渡出」(『元弘日記裏書』「大日本史料」)され、軍勢の編成がなされたと思われる。なお、このときの交名では「元弘元年八月」としているが、その後出された御教書では、「元徳三年九月」としている。その軍勢の編成は不明だが、承久の例に則ったとすれば東海道、東山道、北陸道の三手からの上洛であったか。承久の乱当時の大将軍だった家柄の人々の末裔はほぼ今回の出兵についても大将軍を務めていることがわかる。
●元弘元年八月「関東軍勢交名」(『伊勢光明寺文書残篇』:『鎌倉遺文』32136)
| 【元弘の変】大将軍 | 【承久の乱】(元弘時の祖) |
| 陸奥守(大仏貞直) 遠江国 | 【大将軍】北条相模守時房 |
| 武蔵右馬助(金澤貞冬) 伊勢国 | ・北条五郎実泰〔先鋒〕 |
| 遠江守(名越宗教入道) 尾張国 | 【大将軍】北条式部丞朝時 |
| 武蔵左近大夫将監(金澤時顕) 美濃国 | ・北条五郎実泰〔先鋒〕 |
| 駿河左近大夫将監(伊具時邦) 讃岐国 | ・北条陸奥六郎有時〔先鋒〕 |
| 足利宮内大輔(足利高氏) 三河国 | 【大将軍】足利武蔵前司義氏 |
| 足利上総三郎(吉良貞家) | 【大将軍】足利武蔵前司義氏 |
| 千葉介(千葉介貞胤)一族并伊賀国 | 【大将軍】千葉介胤綱 |
| 長沼越前権守(長沼秀行) 淡路国 | |
| 宇都宮三河権守(宇都宮貞宗) 伊予国 | ・宇都宮頼綱入道蓮生〔鎌倉留守〕 |
| 佐々木源太左衛門尉(加地時秀) 備前国 | 【大将軍】佐々木太郎信実 |
| 小笠原五郎(小笠原頼久) 阿波国 | |
| 越衆御手 信濃国 | |
| 小山大夫判官(小山高朝) 一族 | 【大将軍】小山左衛門尉朝長 (長村?) |
| 小田尾張権守(小田高知) 一族 | ・筑後入道〔鎌倉留守〕 |
| 結城七郎左衛門尉(結城朝高) 一族 | 【大将軍】結城七郎朝広 |
| 武田三郎(武田信武) 一族并甲斐国 | 【大将軍】武田五郎信光 |
| 小笠原信濃入道(小笠原宗長入道) 一族 | 【大将軍】小笠原次郎長清 |
| 伊東大和入道 一族 | |
| 宇佐美摂津前司 一族 | |
| 薩摩常陸前司 一族 | |
| 安保左衛門入道 一族 | |
| 渋谷遠江権守(澁谷重光) 一族 | |
| 河越参河入道(河越貞重入道) 一族 | |
| 三浦若狭判官(三浦時明) | 【大将軍】三浦駿河前司義村 |
| 高坂出羽権守 | |
| 佐々木隠岐前司(佐々木清高) 一族 | |
| 同備中前司(大原時重) | |
| 千葉太郎(千葉胤貞) | 【大将軍】千葉介胤綱 |
| 勢多橋警護 | |
| 佐々木近江前司 (京極貞氏?) | |
| 同佐渡大夫判官入道(京極高氏入道) |
この戦いの中の交名に時継の名は見えず、時継とは再従兄弟にあたる「三浦若狭判官(三浦若狭五郎判官時明)」が加わっている。
三浦盛時―+―三浦頼盛――三浦時明――三浦時継
(三浦介) |(三浦介) (上総介) (三浦介)
|
+―三浦宗義――三浦景明
(十郎) (若狭守)
∥――――三浦時明
∥ (若狭五郎判官)
綾小路継宣――娘
(少納言)
9月5日には「鎌倉家御教書(関東御教書)」として「先帝(後醍醐天皇)」の叡山遷幸に対してこれを「可防申之旨已被下 院宣」により、延暦寺衆徒の対治のため「貞直、貞冬、高氏」の派遣を「西園寺家(西園寺権大納言公宗)」に申し入れるよう六波羅の南北両探題に指示がなされた(『伊勢光明寺残篇』)。この御教書では在京して守備する人々などの交名を示している。
●元徳三年九月五日被成御教書人々(断簡)
| 暫可在京の二十人 | 武蔵左近大夫将監(金澤時顕) | 遠江入道(名越宗教入道) |
| 江馬越前権守(江馬時見) | 遠江前司(名越貞家?) | |
| 千葉介(千葉介貞胤) | 小山判官(小山高朝) | |
| 河越三河入道(河越貞重入道) | 結城七郎左衛門尉(結城朝高) | |
| 長沼駿河権守(長沼秀行) | 佐々木隠岐前司(佐々木清高) | |
| 千葉大郎(千葉胤貞) | 佐々木近江前司(六角時信) | |
| 小田尾張権守(小田高知) | 佐々木備中前司(大原時重) | |
| 土岐伯耆入道(土岐頼貞入道) | 小笠原又五郎(彦五郎貞宗?) | |
| 佐々木源太左衛門尉(加地時秀) | 狩野介入道 | |
| 佐々木佐渡大夫判官入道(京極高氏入道) | 讃岐国守護代 駿河八郎 | |
| 不明 〔以下闕〕 |
嶋津上総入道(島津貞久入道) | 大和弥六左衛門尉(宇都宮高房) |
六波羅探題は9月1日、笠置山攻めの兵を派遣し、同日六波羅勢は宇治平等院に着到。翌2日、「笠置城責之七万五千騎」(『大乗院日記目録』「大日本史料」)という。
一方、すでに比叡山は陥落していたが関東にその知らせは届いておらず、陸奥守貞直、右馬助貞冬、江馬越前入道、足利前治部大輔高氏の四名が大将軍に任じられて9月5日から7日にかけて鎌倉を出立した。その総勢は公称二十万八千騎。得宗高時入道の御内御使として長崎四郎左衛門尉高貞が付属(目付的な従軍か)され、関東両使として秋田城介高景、二階堂出羽入道道蘊(この両名は践祚立坊の事のための使者)が同道した。ところが、大将軍のひとり、足利高氏の出陣前後の9月5日、高氏父「足利讃岐入道殿逝去」(『常楽記』では6日とあるが、諸書・系譜では9月5日)という事件が起こってしまう。後日、9月19日に近江国柏木宿に到着した大将軍は陸奥守貞直と右馬助貞冬の両名のみであることから、高氏の出立は父の服喪で数日間延引されたと考えられよう。高氏は9月27日には京都にいることから、約七日間の延引とすれば初七日の法要後の出陣であった可能性が高いだろう。
9月10日前後には「楠木兵衛正成」が「河内国にをのがたちのあたりをいかめしくしたゝめ」(『増鏡』)て挙兵した。城塞というよりは自舘西側の高台を城郭化(下赤坂城)し、柵や逆茂木を設けて防御した程度のものであろう。その挙兵の知らせはすぐに六波羅へ届けられたと思われ、河内国、和泉国など周辺国の御家人がその追討に動員されたとみられる。「和泉国御家人和田修理亮助家代子息助康」が六波羅へ申請した内容によれば、和田助家(大鳥郡和田郷(堺市南区美木多)の御家人。なお、楠木氏流和田家は和田郷南部(堺市南区和田)に勢力を持っていたか)は9月14日から10月20日にかけて「楠木城」において不惜身命の働きを見せ、9月20日以降に上洛した「大将軍武蔵馬助殿」の「御代官酒匂宮内左衛門尉」や「当国守護御代官」の成田又四郎入道、籾井彦五郎とともに戦ったという(『和田文書』「大日本史料」)。なお、「楠兵衛尉」はすでに元徳3(1331)年2月25日以前に、故世良親王(後醍醐天皇皇子)の遺領(臨川寺の前身寺院に寄進されていた)である「和泉国若松庄」を「押妨(楠木氏は河内から和泉、紀伊北部にかけての生駒山系山麓に広大な支配領域を持ち、熊野神官など熊野権現に所縁を持つ出自の一族とみられる。御内人出身とされる説も存在するが、河内楠木氏の一族の頒布の広さは、地頭職や代官として管理を任されていたとは到底考えられず、信仰による広がりであろう。熊野の人々との協力関係からも、樟信仰のある熊野権現を由緒とする一族とみて間違いないだろう。楠木宗家に近い和田氏は若松庄に隣接する大鳥郡和田を本貫としており、楠木正成は世良親王または前領家の昭慶門院被官で同地荘官を務めていたか。彼は対立相手から「押妨」「悪党」と呼称されている。)」しており(「故大宰帥親王家御遺跡臨川寺領等目録」『鎌倉遺文』31771『天龍寺文書』)、後醍醐天皇との結びつきが見られるのである。なお、楠木正成はこのとき「左兵衛尉」に任官していた武官でもあった。
9月18日戌刻、践祚および立坊に関する「東使秋田城介殿、二階堂出羽入道殿、京着自路次六波羅北方被参、即南方仁御入」した(『伊勢光明寺残篇』「大日本史料」)。20日、土御門東洞院殿で践祚の儀が執り行われた。光厳天皇である。9月22日、後二条院の嫡孫にあたる康仁親王を東宮とした(『歴代皇紀』)。持明院統の光厳天皇の東宮を大覚寺統の康仁親王としており、事ここに及んでも関東は両統迭立の原則を守ろうとしていたことがわかる。光厳天皇践祚により後醍醐天皇は上皇となった。
践祚前日の9月19日には、大将軍「武蔵右馬助殿」が「江州柏木宿宇治仁着」という(『伊勢光明寺残篇』)。ただし、翌20日には「陸奥守殿御京着、武蔵右馬助殿、自柏木御発向宇治」(『伊勢光明寺残篇』)とあることから、19日に近江国柏木宿には陸奥守貞直と右馬助貞冬の両将軍が到着していたとみられる。両者は柏木宿で二手に分かれ、総大将の陸奥守貞直は直接入洛(山科経由での入洛であろう)して践祚および六波羅との折衝に当たり、右馬助貞冬は柏木宿から南下して勢多を経て宇治田原を経由し、笠置勢の牽制をしつつ宇治に入っている。そして9月25日に宇治を発って賀茂へ向かった(『伊勢光明寺残篇』)。また、河内国の楠木左兵衛尉正成らの挙兵に対して、「大将軍武蔵馬助殿」の「御代官酒匂宮内左衛門尉」や「右馬助殿家人宗像四郎」が参戦していることから、貞冬の代官・酒匂宮内左衛門尉率いる一手が宇治から河内国に派遣されたと考えられる。
9月26日、「陸奥守殿、長崎四郎左衛門尉殿」が笠置山へ向けて京都を進発した(『伊勢光明寺残篇』)。ただし、9月27日に「貞直、貞冬、高氏等、発向笠置城」(『元弘日記裏書』)ともあり、26日から27日にかけての進発であったのだろう。なお、足利高氏は進発直前の9月5日に父貞氏入道を喪い、その初七日を経ての進発であったと思われることから、高氏入洛(25日、26日あたりか)と同時に陸奥守貞直と長崎四郎左衛門尉が進発し、翌日に貞冬、高氏の進発となっていたのかもしれない。
9月28日には長崎四郎左衛門尉勢の「椙原一族、栖山一族、小宮山一族等」が先陣となって笠置山を攻め(『伊勢光明寺残篇』「大日本史料」)、「放火城槨」し「奉追落先帝了」と、たちまち笠置山を攻め落としている。後醍醐上皇は「御歩行令出城給、於路次奉迎」(『元弘日記裏書』「大日本史料」)と、後醍醐上皇は囚われの身となり、座主尊澄法親王や同道の「源中納言具行、宰相成輔、中納言藤房、大進季房」もともに連行された。なお、前座主宮尊雲法親王や中納言隆資は逃亡して行方をくらましている。
元弘元(1331)年10月3日、陸奥守貞直らは後醍醐上皇以下を六波羅南方へ入れて皇居とした(『伊勢光明寺残篇』)。また、同日には、右馬助貞冬の家人、宗像四郎が「楠城」に拠っていた先帝一宮尊良親王を「奉捕」っている(『伊勢光明寺残篇』)。こうして畿内における後醍醐上皇による騒擾は鎮定され、10月5日、新帝光厳のもとで初めての除目が行われた。そして翌10月6日、六波羅南方において剣璽が引き渡され、土御門東洞院御所へと遷された(『本朝皇胤紹運録』)。ところが「帝并中書王、妙法院宮等武士等都不奉見所知之間、有不審、被差遣可然之仁可奉見云々」(『光厳院御記裏書』)と、武士等は誰一人後醍醐上皇、中務卿尊良親王、座主宮尊澄法親王の顔を知らず、偽者である可能性も捨てきれなかったため、上皇らを見知る「然るべき仁」に面通しさせてその実否を確認するために、尊良親王、尊澄法親王と従兄弟にあたる二条為定と西園寺公宗のいずれかの招聘を議し、結果として公宗に依頼することとなった。
10月8日、上皇面通しの依頼を受けた権大納言公宗は夕刻に六波羅へ出向くと、「奉見先帝、併為天魔之所為可有寛宥之沙汰旨、可仰武家之由被仰之云々、可歎息事也」(『光厳院御記裏書』「大日本史料」)という。翌9日、捕縛された後醍醐上皇に同道した宮や諸卿、武士が御家人預けとなり、10日夕には公宗弟・中納言公重が武蔵右馬助貞冬の宿所(六波羅の一所であろう)を訪れて、中務卿尊良親王の面通しを行っている(『光厳院御記裏書』「大日本史料」)。公重が尊良親王から「所陳多々」によれば、「子細兼日不知之、凡為天魔之所為、可有寛宥之儀旨、頻被陳之、不足言、嗟呼悲夫」(『光厳院御記裏書』「大日本史料」)という。上皇、一宮両者ともにこの擾乱は「天魔之所為」であると主張し、寛宥を願った。11日には兼運僧都(延暦寺執行)が六波羅を訪れて座主宮尊澄法親王の面通しを行い言葉を交わしたが、語るところは尊良親王と大略変わらず、頻りに涕泣という(『光厳院御記裏書』「大日本史料」)。
●諸将ノ第ニ分拘(『伊勢光明寺残篇』「大日本史料」)
| 捕縛 | 預 |
| 先帝 | 六波羅南方(北条時益) |
| 妙法院宮尊澄(天台座主) | 長井因幡左近大夫将監(長井高広) |
| 尹大納言入道師賢卿 | 遠江入道殿(名越宗教入道) |
| 源中納言具行卿 | 筑後前司(小田貞知) |
| 六条少将忠顕朝臣 | 佐々木佐渡判官入道(京極高氏入道) |
| 四条少将隆量朝臣 | 佐々木近江前司(京極貞氏?) |
| 左衛門大夫氏信(師賢卿諸大夫) | 海部但馬権守 |
| 近藤三郎兵衛尉宗光(万里小路中納言藤房卿侍) | 中条因幡三郎 |
| 対馬兵衛尉重定(具行卿侍) | 下野三郎 |
| 一宮 | 常陸前司(小田時知) |
| 東南院僧正坊 | 佐々木大夫判官時信(六角時信) |
| 万里小路中納言藤房卿 | 武蔵左近大夫将監(北条時顕) |
10月12日、後醍醐上皇の笠置臨幸に供奉して逐電していた前権大納言公敏が出家(法名宗肇)し、翌13日に二階堂出羽入道道蘊のもとに出頭。二階堂道蘊は六波羅へ事の次第を通達し、六波羅は公敏入道を「下野権守」への預けとした(『伊勢光明寺残篇』「大日本史料」)。彼は上皇の又従弟にあたり、終始上皇に近侍した人物であった。
また同13日夕刻に「関東飛脚到来」し、翌14日朝方辰の刻に「世間物騒」(『光厳院御記裏書』「大日本史料」)という。これは「武士等騒動、圍時知宿所、欲及合戦而自六波羅加制止之間、先属静謐云々、衆口嗷々、不可記之」(『光厳院御記裏書』「大日本史料」)といい、在京武士が「六波羅頭人」の小田常陸前司時知の屋敷を取り囲み、合戦に及ばんとするところを、六波羅探題の制止によって不戦に終わった事件があった。「関東飛脚到来」により武士等が動いたことは確実であろうから、関東は小田時知に何らかの疑いをかけていたと考えられる。そして「時知宿所」を取り囲んだ「武士等」は六波羅支配下の武士ではなく関東から上洛した御家人とみられる。時知がどういった嫌疑をかけられたのか定かではないが、彼の子「出羽守知貞」は「実父大納言経継卿云々」(『尊卑分脈』)とあり、公卿との関わりがあったことがうかがえる。「大納言経継卿」は徳治2(1308)年5月15日、中務卿尊治親王(のちの後醍醐天皇)の太宰帥補任にともない、太宰権帥に補任されるなど後醍醐天皇に近く、後二条院の第二皇子・邦省親王は「経継卿養君」(『一代要記』)とあり、後醍醐上皇の出身皇統である大覚寺統に属する公卿であった。六波羅の引付頭人の小田時知は大覚寺統と深く関係していたと推測でき、関東が時知を疑った理由であると考えられる。
西園寺公経―+―洞院実雄―――――――――――+―洞院公守――+―洞院実泰―――洞院公敏
(太政大臣) |(左大臣) |(太政大臣) |(左大臣) (権大納言)
| | |
| | +―洞院実明―――洞院公蔭
| | (権大納言) (権大納言)
| | ∥
| | ∥―――――――洞院忠季
| | 北条久時―+―女子 (権大納言)
| | (相模守) |
| | +―北条守時
| | |(相模守)
| | |
| | +―女子
| | ∥―――――――足利義詮
| | ∥ (権大納言)
| | 足利尊氏
| | (権大納言)
| +―女子
| | ∥――――――三条実重――――三条公茂――――三条実忠
| | ∥ (太政大臣) (内大臣) (内大臣)
| | ∥
| | ∥ 惟康親王――――女子
| | ∥ (二品) ∥
| | ∥ ∥
| | 三条公親―――藤原房子 ∥―――――――守邦親王
| |(内大臣) (皇后宮御匣殿) ∥ (二品)
| | ∥ ∥
| | ∥―――――――久明親王
| | ∥ (式部卿)
| | ∥
| +――――――――――――――――――――――――藤原季子
| | ∥ (顕親門院)
| | ∥ ∥
| +―――――――――後深草天皇 ∥――――――花園天皇
| || (久仁) ∥ (富仁)
| || ∥―――――――――――――――伏見天皇
| || ∥ (熈仁)
| |+――――――――藤原愔子 ∥
| || (玄輝門院) ∥―――――――後伏見天皇
| || ∥ (胤仁)
| || +―五辻経氏――――藤原経子 ∥―――+―光厳天皇
| || |(参議) (准三后) ∥ |(量仁)
| || | ∥ |
| || +―女子 ∥ +―光明天皇
| || | ∥ ∥ (豊仁)
| || | ∥―――――――女子 ∥
| 花山院兼雅―+―花山院忠経―――――――――――花山院師継 | 恵一 ∥―――――――――――――花山院師賢
|(左大臣) |(右大臣) || (内大臣) |(僧叡智) ∥ ∥ (権大納言)
| | || ∥―――――――――――――――花山院師信 ∥
| | 大江広元―+―――毛利季光―――女子 | (内大臣) ∥
| |(陸奥守) |||(豊後守) | ∥
| | ||| | ∥
| | +―――長井時広―――長井泰重――――長井頼重――――長井貞重――――――――――長井高広
| | ||(蔵人) (因幡守) |(因幡守) (縫殿頭) ∥ (左近大夫)
| | || | ∥
| | || +―五辻宗親――+―五辻親氏 ∥
| | || |(参議) |(左兵衛督) ∥
| | || | | ∥
| +―五辻家経―――――五辻雅継―――五辻忠継――+―藤原忠子 | 二条為世女子 ∥ +―尊良親王
| (中納言) ||(非参議) (参議) (談天門院) |(大納言局) ∥ |(中務卿)
| || ∥ | ∥ ∥ |
| || ∥ | ∥―――――――――――+―尊澄法親王
| || ∥ | ∥ ∥ (妙法院)
+―西園寺実氏―+―藤原姞子 |+―藤原佶子 ∥―――――――後醍醐天皇 ∥
(太政大臣) |(今出河院 | (京極院) ∥ |(尊治) ∥
| ∥ | ∥ ∥ | ∥
| ∥ | ∥――――――――――――――後宇多天皇 +―藤原宗子 ∥
| ∥ | ∥ (世仁) (典侍) ∥
| ∥―――――+――亀山天皇 ∥ ∥―――――――――――+―邦良親王
| ∥ (恒仁) ∥ ∥ ∥ |(後醍醐東宮)
| ∥ ∥ ∥ ∥ |
| 後嵯峨天皇 ∥―――――――後二条天皇 ∥ +―邦省親王
|(邦仁) ∥ (邦治) ∥ (式部卿)
| ∥――――――――宗尊親王 堀川具守――――堀川基子 ∥
| ∥ (中務卿) (内大臣) (西華門院) ∥
| ∥ ∥ ∥
平棟基――+――平棟子 ∥――――――惟康親王――――女子 ∥
(木工頭) ||(准三后) ∥ (二品) ∥―――――――守邦親王 ∥
|| ∥ ∥ (二品) ∥
|| 近衛兼経―――――藤原宰子 久明親王 ∥
||(関白) (式部卿) ∥
|| ∥
|+―西園寺公相――――西園寺実兼――西園寺公衡―+―――――――――――――――――藤原寧子
| (太政大臣) (太政大臣) (太政大臣) | (広義門院)
| |
| +―西園寺実衡―――西園寺公重
| (内大臣) (権中納言)
| ∥
| ∥―――――――西園寺公宗
| ∥ (権大納言)
| 二条為世――+―女子
| (大納言) |(昭訓門春日局)
| |
| +―藤原為子
| |(後醍醐院女房)
| |
| +―二条為藤――――二条為明
| |(中納言) (右兵衛督)
| |
| +―二条為通――――二条為定
| |(左近衛中将) (権大納言)
| |
| +―女子
+―女子 (室町院女房)
∥ ∥―――――+―尊良親王
∥ ∥ |(中務卿)
∥ ∥ |
∥―――――――――吉田経頼―――吉田頼隆 後醍醐天皇 +―尊澄法親王
∥ (宮内卿) (参議) (尊治) (妙法院)
∥ ∥
吉田資経―+―吉田為経 ∥―――――――吉田経隆
(左大弁) |(左大弁) ∥ (宮内卿)
| ∥
+―坊城経俊――――――中御門経継――女子
(中納言) (権大納言)
小田時知の騒擾があった10月14日、「両六波羅殿并両使」が「北方」で「陸奥守殿、右馬助殿、長崎四郎■■■■」の「楠木城」攻めの旨について談合が行われ、「右馬助殿、長崎殿」は「領状」したが、「陸奥守殿」は所労のため領状の返答はしなかった(「伊勢光明寺残篇」)。翌15日には楠木城攻めの交名が示されており、その後、陸奥守貞直も領状したとみられる。
●「関東軍勢交名」(『伊勢光明寺文書残篇』:『鎌倉遺文』32135)
| 楠木城 | |
| 一手東 自宇治至于大和道 | |
| 陸奥守(大仏貞直) | 河越参河入道(河越貞重入道) |
| 小山判官(小山高朝) | 佐々木近江入道(京極貞氏?) |
| 佐々木備中前司(大原時重) | 千葉太郎(千葉胤貞) |
| 武田三郎(武田政義) | 小笠原彦五郎(小笠原貞宗) |
| 諏訪祝 | 高坂出羽権守 |
| 島津上総入道(島津貞久入道) | 長崎四郎左衛門尉(長崎高重) |
| 大和弥六左衛門尉(宇都宮高房) | 安保左衛門入道 |
| 加地左衛門入道 | 吉野執行 |
| 一手北 自八幡于佐良□路 | |
| 武蔵右馬助(金澤貞冬) | 駿河八郎(讃岐国守護代) |
| 千葉介(千葉介貞胤) | 長沼駿河権守(長沼秀行) |
| 小田人々(小田高知一党か) | 佐々木源太左衛門尉(加地時秀) |
| 伊東大和入道 | 宇佐美摂津前司 |
| 薩摩常陸前司 | □野二郎左衛門尉 |
| 湯浅人々 | 和泉国軍勢 |
| 一手南西 自山崎至天王寺大路 | |
| 江馬越前入道(江馬時見入道) | 遠江前司(名越宗教入道) |
| 武田伊豆守(武田信武) | 三浦若狭判官(三浦時明) |
| 渋谷遠江権守(澁谷重光) | 狩野彦七左衛門尉 |
| 狩野介入道 | 信濃国軍勢 |
| 一手 伊賀路 | |
| 足利治部大夫(足利高氏) | 結城七郎左衛門尉(結城朝高) |
| 加藤丹後入道 | 加藤左衛門尉 |
| 勝間田彦太郎入道 | 美濃軍勢 |
| 尾張軍勢 | |
| 同十五日 | |
| 佐藤宮内左衛門尉 自関東帰参 | |
| 同十六日 | |
| 中村弥二郎 自関東帰参 | |
15日に四手に分かれて京都を出立した軍勢は「楠木城」に攻め寄せ、10月17日から20日にかけて楠木兵衛尉正成との合戦となっている(『和田文書』裏書)。なお、この「楠木城」は後年の「千岩屋」城とは別の城である(「熊谷直氏合戦手負注文」『熊谷家文書』)。そして10月21日、「楠落城」し、「楠兵衛尉落行」した(『元弘日記裏書』「大日本史料」)。また、11月2日には「赤坂城没落」(『元弘日記裏書』「大日本史料」)とあり、「楠木城(下赤坂城)」とは川を挟んだ対岸の山に構築された「赤坂城(上赤坂城)」であろう。
楠木城及び赤坂城を攻め落とした関東勢は京都へ帰還。11月5日、「陸奥守貞直、明曉下向之由、西園寺大納言申定、仍被引御馬」(『光厳院御記裏書』「大日本史料」)と、翌6日早朝の貞直下向が西園寺公宗へ報告され、馬が下された。この日、鎌倉を「長井右馬助高冬、信濃入道々大、為使節上洛、為御所方輩沙汰」とあるように、後醍醐上皇方の人々への沙汰のための両使(長井右馬助高冬、信濃前司時連入道)が上洛の途についており、貞直らが鎮圧した騒擾の事後処理が行われることとなる。なお、「足利高氏、先日下向不給御馬、一同之上不申暇之故也」と、貞直に先行して鎌倉への帰途についている。そして、11月7日、「前坊第一宮康仁親王立坊」(『元弘日記裏書』「大日本史料」)と、関東の意向(両統迭立の原則)に沿う形で前坊故邦良親王(大覚寺統の後二条天皇皇子)の一宮・康仁親王が光厳天皇(持明院統)の皇太子となった。
●邦良親王の東宮職ならびに春宮坊
| 東宮職 | 傅 | 学士 | |||||||||
| 源長通 (右大臣) | 藤原宗倫 | ||||||||||
| 春宮坊 | 大夫 | 権大夫 | 亮 | 権亮 | 大進 | 権大進 | 少進 | 権少進 | 大属 | 権大属 | 少属 |
| 源通顕 (大納言) |
藤原公重 (権中納言) |
藤原宗兼 (右大弁) |
藤原俊季 (右中将) | 藤原経重 | 藤原隆経 | 藤原資顕 | 藤原家俊 | 紀職直 | 安倍資■ | 安倍資勝 | |
| 中原職右 (主膳正) |
|||||||||||
| 源康基 (主殿首) |
|||||||||||
| 中原有景 (主馬首) |
|||||||||||
11月25日夕刻、東使のひとり信濃前司入道道大が入京。翌26日に右馬助高冬が入洛(『光厳院御記』「大日本史料」)。西園寺公宗との間で「先帝、緇素」らへの事後処理が執行されることとなる。
12月15日、関東では「太守禅閤第一郎、七才、首服、名字邦時、御所被執行」(『元弘日記裏書』「大日本史料」)と、御所守邦親王により元服の儀が執り行われ、「邦」字を給わり「邦時」と号した。
12月27日、「東使」の長井高冬、三善時連入道らは西園寺公宗ら光厳朝の公卿らとの間で決定した「先帝」以下への処置に関して奏上された(『光厳院御記』「大日本史料」)。
■「東使奏聞関東事書」処分案
| 人 | 配流先 |
| 先帝(後醍醐上皇) | 隠岐国(守護は佐々木清高) |
| 一宮(尊良親王) | 土佐国(守護は高時入道) |
| 妙法院宮(尊澄法親王) | 讃岐国(守護は伊具邦時) |
| 緇素罪名追可言上 |
元弘2(1332)年2月6日、「武家」が「慈厳僧正、光顕朝臣、忠守法師、重頼法師」が捕縛された(『光厳院御記』「大日本史料」)。慈厳は「天台座主輦車」であり、尊澄法親王の侍僧であったのだろう。先帝は「つゐに隠岐国へうつしたてまつるべし」として3月7日に隠岐国へ向かうために出京。「御供には内侍三位殿、大納言小宰相など、男には行房の中将忠顕少将ばかりつかまつる、をのかしゝ宮この名残ともいひつくしかたし、六原よりの御をくりの武士、さならでも名あるつはものども千葉介貞胤をはじめとして、おぼえことなるかぎり十人えらひたてまつる」(『増鏡』)と見え、千葉介貞胤が先帝配流の護送使であった。また「佐々木の佐渡判官入道」も「隠岐の御をくりもつかまつりしもの」であった(『増鏡』)。
後醍醐上皇に加担した公家衆はそれぞれ処罰されているが、原則的には公卿は流罪、一般堂上は流罪の上処刑という方針のもと、4月10日には姉小路実世が「依関東奏聞止出仕」、5月22日には参議平成輔が「於早河尻被誅了」(『常楽記』)、同月には万里小路藤房が「配流下総国」(『公卿補任』)、源具行は公卿ながら「五月日下向関東、六月十九日於近江国柏原斬首」(『公卿補任』)、6月2日には日野資朝が「於佐渡国配流斬首」(『公卿補任』)、6月3日には日野俊基が「武蔵国クスハラニテ被誅了」(『常楽記』)、6月25日には前参議藤原光顕が「配流出羽国」(『公卿補任』)という厳罰に処されている。また、按察使大納言公敏は「小山の判官秀朝とかやいふものぐして、下野の国へと聞ゆ」(『増鏡』)と、小山大夫判官高朝が下野国へ伴った。なお、万里小路藤房の下総配流は誤記で、実際は「花山院大納言師賢は千葉介貞胤うしろ見て下総へくだる」(『増鏡』)とあるように、叡山の偽帝となった花山院師賢が千葉介貞胤によって下総国へ連行されている。師賢が千葉介貞胤に付き添われて5月10日に京都を発った際、師賢は、
と詠んだ。君のいない故郷京都にはもはやなんら未練はないという決意の歌である。一方、師賢の北の方は「花山院入道右のおとゞ家定の御女」であるが、師賢との対面も許されないままの別離であり、「いみじう思ひなげきたまへるさま、あはれにかなしけれ」という有様で、
と詠んだ。
 |
| 小御門神社 |
その後、師賢は香取郡大須賀保内(成田市名古屋)に幽閉の身となるが、この地は「千葉介一族大須賀」の所領であり、千葉介貞胤とともに上洛していたと思われる大須賀某が預かったとみられる。香取海の入江のほとりに大きな館が造営されたのであろう。その字名は「館内」として残る。しかし、師賢はこの地に入ったわずか四か月後の10月29日に病死する。享年三十二。心労が祟ったものであろう。「元徳四年十月、尹大納言入道、於千葉逝去」(『常楽記』)という。師賢は館の隣に埋葬され、塚が築かれた。この墓所は「公家塚」と呼ばれて現在に至っている。明治15(1882)年には塚前に師賢を祭神とする「小御門神社」が建てられた。
余談だが、花山院師賢の子孫は一貫して南朝方の大将として奮戦しており、師賢の次男・花山院左近衛中将信賢は正平13(1358)年に戦死した。その子・花山院左近衛中将師重は上野国吾妻郡青山郷に拠って北朝勢と戦い、信濃国で挙兵した尹良親王(宗良親王の子)に随って、応永3(1396)年の信濃国浪合の戦いで戦死した。師重の子孫は三河国へ逃れ、師重の五代孫・青山喜三郎忠世は松平家に仕えて天文4(1535)年、伊田野で戦死。その孫・青山播磨守忠成は天文20(1551)年、青山喜太夫忠門の嫡子として三河に生まれ、徳川家康の小姓となった。家康が江戸に居城を構えると、江戸町奉行に就任。慶長6(1601)年2月、宿縁の地・両総で1万5千石を与えられ、青山伯耆守忠俊は三代将軍・徳川家光の老職に就任した。
こうした先帝後醍醐の側近らの処断が行われる中、元弘2(1332)年4月3日、楠木正成率いる五百騎余りが赤坂城を急襲した。ここには紀伊国御家人湯浅孫六入道定仏が留守居として守衛していたが、敢え無く攻め落とされ「定仏打負降参」(『大乗院日記目録』)した。このとき「為楠木被取籠湯浅党交名」(『楠木合戦注文』)は正慶元/元弘2(1332)年12月にまとめられている。赤坂城は楠木勢によって奪還され、その後、関東勢が寄せる翌年2月まで楠木勢が拠ったとみられる。
6月6日、「自熊野山執進、大塔宮令旨、相憑当山旨云々」(『光厳院御記』「大日本史料」)とあるように、逃亡中の「大塔の尊雲法親王」(『増鏡』)が熊野山に対して令旨が発したという。こののち、前年の追討及び捜索で六波羅探題が捕縛に失敗した尊雲法親王や四条隆資らの動きが活発化していくこととなる。楠木正成も大塔宮尊雲法親王に意見具申ができる距離にいたことから、おそらく彼らは楠木正成が奪還した赤坂城近辺に居住していたと考えられる。
なお、6月8日の小除目では関東の推挙により、笠置寺攻めの大将軍であった「源高氏(足利高氏)」を「叙従五位上」とした(『光厳院御記』「大日本史料」)。
6月26日には、尊雲法親王がついに具体的な挙兵という形で顕在化し、京都に報ぜられた(『光厳院御記』「大日本史料」)。兵乱は「伊勢国有梟悪之輩、烏合之衆、追捕所々其勢甚多云々、仍武家差使者、令実検云々」(『光厳院御記』「大日本史料」)という。続けて28日の報告では「勢州凶徒、尚以興隆旨風聞、或云、合戦地頭等多被誅戮之後、引退云々」という。かなり大規模な兵乱で、地頭等が多く討死するという風聞が聞こえている(『光厳院御記』「大日本史料」)。六波羅はこの時点ではまだ乱の正確な規模や首謀者を把握していなかったようであるが、29日に京都へ帰還した検使の情報によれば、「不違風聞之説、凶徒合戦之間、在家多焼払、地頭両三人被打取、守護代家被焼了、其後凶徒等引退了云々、是熊野山帯大塔宮令旨、竹原八郎入道為大将軍襲来云々、驚歎不少」(『光厳院御記』「大日本史料」)であったという。
8月27日には「大塔二品護良親王(実際は還俗していない)」が「左少将隆貞」に「附与御令旨」して高野山大衆に決起を促した(『高野春秋』「大日本史料」)。「隆貞」は大塔とともに笠置山から逐電した権中納言隆資の子で尊雲法親王の側近である。また、左少将隆貞は12月26日、「和泉国久米田寺住僧等」に祈祷等の忠勤を行う上は「於当寺并寺領者、可被停止官兵狼藉者」という「大塔宮二品親王令旨」を伝えている(『鎌倉遺文』31937)。「官兵之狼藉」はあちこちで発生しており、翌元弘3(1333)年正月5日には「左兵衛尉正成」が和泉久米田寺や河内観心寺ら和泉河内の大寺に触れている。また、大塔宮は紀伊粉河寺にも加勢を求め、粉河寺衆徒がこれに応じる返答をしたため、正月10日付で四条隆貞を使者として粉河寺に御感の令旨を下している(『粉河寺文書』)。このころの尊雲法親王は笠置寺、久保田寺、観心寺、粉河寺など、おもに大寺院衆徒の力を恃みにしていたとみられる。
関東では前年の合戦に参戦して軍功を挙げた人々へ没官領を宛がっており、正慶元/元弘2(1332)年12月1日、将軍家政所(別当相模守平朝臣:執権守時、右馬権頭平朝臣:連署茂時)は「島津上総介貞久法師法名道鑑」に対し、「妙法院宮御跡」の「周防国楊井庄領家職」を「勲功賞」として宛がっている(『薩藩旧記』)。こうした恩賞と同時に関東は河内国の反乱勃発に対する再征の軍勢催促を行っており、正慶元/元弘2(1332)年12月5日には得宗被官とみられる御家人「尾藤弾正左衛門尉」が「大塔宮并楠木兵衛尉正成事」について、関東からの命を受けて上洛しており(『鎌倉遺文』31911『紀伊隅田家文書』)、11月中旬には出征の子細が固まっていたことがわかる。六波羅探題はこの関東からの命を受けて、管国の御家人に対して「有可被仰之子細、不廻時刻、可被参洛」すべきことを命じている。
この頃関東においては諸国の御家人に対して「大塔宮并楠木兵衛尉正成事、為誅伐所差遣軍勢也」と、追討の軍勢を「去季雖発向、重可進発」ことを述べ、「殊以神妙、引率庶子親類、可抽軍忠之状」を命じている(「関東御教書」『鎌倉遺文』31915『熊谷家文書』)。
■六波羅御教書(『鎌倉遺文』31911『紀伊隅田家文書』)
■関東御教書(「関東御教書」『鎌倉遺文』31915『熊谷家文書』)
■関東御教書(『鎌倉遺文』31933『和泉日根野文書』)
こうした畿内の不穏な状況に、関東御教書を受けたとみられる「紀伊国御家人」が翌年の正慶2/元弘3(1333)年正月5日、上洛の途上で通過する「河内国甲斐庄安満見」(『楠木合戦注文』)で楠木勢と遭遇し交戦。「井上入道、上入道、山井五郎以下五十余人」が楠木勢に討たれた。
正月14日には「河内守護代」の「俣野」や「和泉国守護(脱代歟)」、「田代、品河、成田以下地頭御家人」が追い落とされている。守護代俣野某が居住していた守護所は「丹南」にあり、俣野が地頭職であった地(丹下、池尻、花田)もその周辺にあることから、合戦は守護所を中心に行われ、正成は甲斐庄から河内国の平野部に進み、拠点を築いて駐屯したとみられる。
こうした河内国や和泉国での楠木勢の大規模な攻勢に、六波羅探題は翌15日、大塔宮および楠木正成が大規模な拠点を築いていた「千剣破城河内金剛山」(『続史愚抄』)に大軍を派遣し、根底の殲滅を試みた。一方、楠木正成は15日夜にも河内国御家人を攻めており「当器左衛門尉」「中田地頭」「橘上地頭代」が館を自焼して逃れるなど、河内国平野部に留まって周辺域を駆逐していたことがわかる。翌16日に「山城国問田林太郎兵衛尉実広」が「馳参御方」(「林実広軍忠状」『鎌倉遺文補遺編』)したのは、正成による調略または陶器、中田、橘上などが襲撃を受け、問田林村(富田林市)周辺の情勢が緊迫したためであろう。
六波羅探題は摂津からの防衛線及び、河内の「楠根」のごとく河川の入り組む平野部に展開する楠木勢への対応のため、「両六波羅殿代 一方竹井、一方有賀」を主将に、「縫殿将監、伊賀筑後守、一条東洞院(以下は大路小路の守護する在京御家人か)、五条東洞院、春日朱雀、四条大宮、四条堀河トカシ、姉小路西洞院、春日東洞院、同大宮水谷、中条、厳島神主、芥河、此外地頭御家人五十騎」が派遣され「天王寺構城郭」という(『楠木合戦注文』)。わずかに五十騎ばかりの派遣であり、戦闘部隊ではなく四天王寺の守りを強固にするための土木を含めた部隊ではなかろうか。摂津の要衝に建つ四天王寺は城塞としての役割も持ち、すでに六波羅から遣わされた御家人が駐屯していたと思われる。
正月19日朝には「大将軍四条少将隆貞」以下の「楠木一族、同舎弟七郎、石河判官代跡代百余人、判官代五郎、同松山并子息等、平野但馬前司子息四人四郎天王寺ニテ打死ス、平石、山城五郎、切判官代平家、春日地同、八田、村上、渡辺孫六、河野、湯浅党一人、其勢五百余騎其外雑兵知数」が四天王寺に押し寄せ、深夜子刻に至るまで十数時間にわたる激しい攻防の末に四天王寺は落ちた(『楠木合戦注文』)。
四天王寺は南北に連なる上町台地上にあることから、楠木勢が東から攻勢をかけることは考えにくく、南北いずれかから攻め寄せたと考えられる。寄手の交名から摂津国とは連携していない河内国南東部からの出征であろうとみられることから、おそらく天王寺南部域から攻め寄せ、合戦は阿倍野(阿倍野区阿倍野筋)あたりで行われたのだろう。楠木勢は四天王寺を攻め落としたのち、熊野街道を北進し台地直下の渡邊津を占拠。22日の夕方申刻に拠点の葛城方面へと引き返している。
四天王寺および渡邊津の陥落を受けた六波羅探題は、その奪還のために再征を決定。正月23日には勇猛で知られた「宇津宮五百余騎」が四天王寺に押し寄せた(『楠木合戦注文』)。宇都宮高綱はまず「楠木城」に討ち入るも、「宇津宮家子ニ左近蔵人舎弟右近蔵人并大井左衛門以下十二人」が生け捕られている。この「楠木城」は楠木正成が渡邊津を占拠した際に、台地北端の熊野街道沿い(現在の大阪城周辺か)に築いた砦であろう。おそらく宇都宮勢は淀川筋を船で進み、渡邊津に上陸すると、楠木勢を駆逐。そのまま熊野街道を登坂して「楠木城」を攻めたものの苦戦したとみられる。ただし、その後、宇都宮高綱は四天王寺に入っていることから、四天王寺は六波羅勢によって奪還されたとみられる(『楠木合戦注文』は主に楠木方の戦勝記録のみ記載されている)。六波羅探題はさらに「佐々木判官、伊賀常陸守」らを派遣した様子がみられ、六波羅勢は天王寺周辺から楠木勢を駆逐することに成功したのだろう。そして2月2日に「宇津宮」は帰洛し、「佐々木判官、伊賀常陸守」は天王寺に駐留した(『楠木合戦注文』)。
このような中、正月21日には播磨国で「則村入道円心、赤松」が兵を挙げている(『続史愚抄』)。播磨国摩耶山に接する「布引ノ城(神戸市中央区葺合町)」を拠点として挙兵したと思われる。則村入道の子・律師妙善房(則祐律師)は「天台山大塔宮の候人なり」(『赤松記』)という由緒が伝わる人であるが、大塔宮はこの挙兵を受けて播磨国佐用庄に祗候人「殿法印御坊」(「城頼連申状」『毛利家文書』四)を派遣し、2月26日に高田城を落とした。大塔宮は2月21日、播磨国の大寺・太山寺に「伊豆国在庁北条遠江前司時政之子孫東夷等」(「播磨大山寺文書」『鎌倉遺文』31996)を「為加成敗」のため、「早相催一門之輩、率軍勢、不廻時日、可令馳参戦場之由」の令旨を下すとともに、「今月廿五日寅一點、率軍勢、可令馳参当国赤松城、殊依時高名、於勧賞者、宜依好之由、重被仰下候也」と、2月25日早朝までに赤松円心のもとに馳せ参じて協力すべきことを命じており、太山寺衆徒も「殿法印御坊」の手に属して高田城を攻めたのだろう。大塔宮はこの功績に対して太山寺へ「丹波国和庄」(「播磨大山寺文書」『鎌倉遺文』32048)を寄進している。
また、大塔宮は九州にまで令旨を遣わしており、2月7日には「原田大夫種直」へ「高時法師一族凶徒等」について「早追討英時、師頼以下之輩」を命じている(『三原文書』)。これは2月3日、隠岐国から密かに「島津上総入道館」へ遣わされた「日向国守護職事、任先例、可令致沙汰者」の綸旨(『薩藩旧記』)などと同様、この頃から水面下で動きはじめていた反鎌倉の布石のひとつであろう。
一方、正月29日、京都に「出羽守入道道蘊二階堂」が入洛(『続史愚抄』)し、続けて「弾正少輔弼治時、陸奥守右馬権助高直、遠江入道宗教法師、彼等其外一族大将軍トテ関東ニサルヘキ侍多分指上」が上洛(『保暦間記』)した。すでに大和国の御家人は大塔宮の籠る大和国吉野に向かっており、正月30日には大和国高市郡松山村(高取町松山)で「大和国茉山合戦」が起こっている。
京都に到着した関東勢は、河内、大和、紀伊の三手に分かれて河内南東部へ出征し、正慶2/元弘3(1333)年2月22日には「大将軍阿蘇遠江左近大夫将監殿、長崎四郎左衛門尉、既楠木之城被害之由披露」と、「楠木之城」を制圧したことを六波羅探題に伝えている(『楠木合戦注文』)。この合戦では、本間氏、須山氏、猪俣党、結城白河出雲前司らの活躍が伝えられている。このときに陥落したのは千早・金剛山への入口を押さえる赤坂城のひとつ(千早川北岸の下赤坂城)と思われ、寄手は河内道を進んだ弾正少輔弼治時の大手軍とみられる。この赤坂城合戦は2月2日から「十三ケ日之間、被責」たとあり(『大乗院日記目録』)、2月15日に「大手本城」を守衛していた「平野将監入道既三十余人参降人畢、此内八人者逐電、或生捕、或及自害被所、又以被落之由」であったのだろう。この「平野将監入道」は四天王寺合戦で正成とともに戦った平野但馬前司の一族であろう。城中にいたという風聞のあった楠木正成舎弟の七郎正季も行方知れずとなった。なお、平野麾下の降参は「平野入道以下三百八十二人」(『大乗院日記目録』)であったという。また、赤坂城陥落とほぼ同時に六波羅から大和の大寺に対する援兵要請が関東に遣わされたと思われ、2月30日、「東大寺衆徒」に対し、「大塔宮并楠木兵衛尉正成」らの「対治凶徒」を指示する『関東御教書』が下されている(「前田氏所蔵文書」)。
このころ、大和道を進む陸奥守右馬権助高直の搦手勢(奈良路)は金剛山の東側(高市郡方面)から「楠木爪城金剛山千早押寄」ており(『楠木合戦注文』)、2月27日には「斎藤新兵衛入道子息兵衛五郎」が「佐介越前守殿御手」に属して攻めたが、「自上山以石礫数ヶ所被打」という石礫による打撲を負い、家子若党も数人が負傷したり討死したという(『楠木合戦注文』)。しかし、関東勢の攻勢は凄まじく、楠木正成が各所に構えた砦はほぼ制圧され、三、四か所を残すのみとなっていた。
また、2月13日には松山を越えて吉野方面へと進んでいた大和国御家人の「大和国高間大弐行秀、同舎弟輔房快全等」(「能登妙厳寺文書」『鎌倉遺文』32230)は「石黒坂合戦」を経て、閏2月1日には吉野山に至り、「捨身命防戦之間、所従両輩被打畢」という激戦の末に吉野山は陥落した。吉野山にいた大塔宮は高野山へと逃れたとされ、「二階堂出羽入道道蘊」が軍勢を率いて「乱入満山、卜本陣於大塔、尋求護良王子」(『高野春秋』)したが、護良親王は大塔の天井の梁間に隠されてついに発見に至らなかったという。
赤坂城を落とした河内道の阿蘇弾正少輔弼隊は千早川を渡り、より堅固な南岸赤坂城(上赤坂城)に迫ったのだろう。熊谷小四郎直経は「為誅伐大塔宮并楠木兵衛尉正成、可馳参之由」に応じて、一族の「平次直氏、六郎直朝、五郎四郎直員等」を相具して、2月25日から28日の戦いにおいて「大手木戸口」に戦い、真っ先に楯や土石を以て堀を埋めたという(「熊谷直経合着到状案」『安芸熊谷家文書』)。2月26日には「俣野彦太郎并藤澤四郎太郎若党十余人」が合戦し、28日には寄手大手軍は「手負死人其既一千八百余人」(『楠木合戦注文』)を数えた。苦戦しつつも、大手勢は赤坂城を攻め落とすと、千早川を遡上して千早城西側に進んだとみられる。そして閏2月5日には熊谷小四郎直経は「馳向千葉城、於大手堀鰭相戦、構矢倉、致終夜之忠勤」(「熊谷直経合着到状案」『安芸熊谷家文書』)と、千早城大手掘あたりで合戦し、さらに陣中には矢倉を築いて警衛を行ったという(「熊谷直経合着到状案」『安芸熊谷家文書』)。大手勢はその後も攻勢をかけ、閏2月26日朝には熊谷直経は「茅岩屋城大手ノ北ノ堀ノナカヨリ、ヘイノキワエせメアカリ、先ヲカケ、新野一族相共ニ、合戦ノ忠ヲイタシ候」(「熊谷直経合戦手負注文」『安芸熊谷家文書』)とあり、千早城の城内にも侵入しつつ合戦を繰り返していたとみられる。そして3月5日には「六波羅勢与橘正成戦大敗」(『続史愚抄』「道平公記」)とあり、六波羅勢は千早及び金剛山の戦いで大敗を喫したとみられる。
一方で六波羅探題自身は「伊予国、播磨国之悪党蜂起」に「近日被仰付国守護人可加追罰之由」を命じるなど諸所に対応せざるを得ない状況にあり、摂津国でも閏2月15日に「摂津小平野兵庫嶋合戦」、閏2月23日には「尼崎合戦」、閏2月24日には「坂部村合戦」、閏2月28日、3月1日、3月7日の播磨国で赤松円心入道との「摩耶山」「摩耶城」での合戦で敗北。3月10日に六波羅探題は再び播磨国へ兵を出し、3月12日に摂津国勝尾寺に「播磨国謀叛人赤松孫次郎入道等追討事」を命じているが(『勝尾寺文書』)。ふたたび六波羅勢の敗北に終わった(『大乗院日記目録』)。
こうした中で、閏2月24日に「前左少将忠顕供奉」して「先帝竊出御隠岐御所国分寺、即召小舩」(『続史愚抄』)して「主上出御隠岐国」(『元弘日記裏書』「大日本史料」)と、先帝後醍醐が隠岐国から脱出。海流に乗って「着御出雲」(『続史愚抄』)した。「伯耆国稲津浦」(『増鏡』『鎌倉年代記裏書』)に着いたとも。上陸後は「謫處幸伯州大山寺」(『皇代略記』)に入った。先帝の脱出を知った「隠岐判官(佐々木清高)」が追うも、「伯耆国名和又太郎源年長兄弟、依御憑奉入舩上山寺、奉守護之」(『大乗院日記目録』)といい、「この国になはの又太郎ながとしといひしあやしき民」が「舟上寺」に迎えて「ここのへの宮になずら」えて支えた(『増鏡』)。閏2月27日に隠岐判官清高が船上山を攻め寄せるも撃退している。また、「出雲守護塩冶判官高貞、富士名判官義綱以下」の守護佐々木一族も船上山へと馳せ参じているが、これはこれまでの楠木一党や河内、和泉、大和の在地武士や寺社、一部の地頭層による叛乱とは一線を画し、関東裁定の否定及び国守護の離反という、関東の威光が一気に地に落ちる大事件であった。先帝の隠岐脱出の報や風聞も影響したとみられるが、すでに九州、西国の反旗は燎原の火のように広がっていた。
播磨国・摂津国の敗戦、千早・金剛山の長滞陣、先帝の隠岐島脱出などに強い危機感を抱いた六波羅は、3月8日に「構釘貫于京師、可鑿大堀旨被定」ている(『続史愚抄』「道平公記」)。そして、3月12日、「赤松入道京都七条マテ打入トイヘトモ被追返畢」(『博多日記』)といい、「隅田、高橋在京武士相副、今在家、作道、西八条辺差向ケル、桂河前」に布陣して赤松勢に備えた。ここに赤松円心入道の子・律師則祐が進んで六波羅勢と対峙(『神明鏡』)。律師則祐は渡河して小勢ながら六波羅勢を駆け破ったが、12日夜に河野九郎左衛門(対馬守通有の九男・通治)、陶山次郎を大将とする六波羅勢に敗れて退いた(『神明鏡』)。
また、七条辺まで攻め上っていた赤松勢と太山寺衆徒は(『博多日記』)、翌13日の「京都合戦」で「打死大夫房大将実名源真、肥後実名有慶、同日手負民部実名重舜、兵部実名了源、少輔実名円範、丹後実名心善」(『大山寺文書』)とあるように、損害を出して六波羅勢を破ることはできなかった。一方で「伯耆国よりも軍をさしのぼせらる」(『神皇正統記』)とあるように、伯耆国から勢力を拡げつつあった先帝後醍醐のもとからも京都へ軍勢が差し向けられており、「三月十三日、勲功ノ輩ニ除目行ハレ少将殿ハ頭中将ニ成給フ、京都ヘ御発向有ヘキ評定アリテ、頭中将殿ニ長年弟村上判官高重、同信濃法眼源盛両大将ニテ一族相具シ京都ノ討手ニ差向ラルヘシト評定有、同十七日舩上山ヲ立テ、人々丹波路ヲ経、京都ヘ発向セラル」(『伯耆巻』)とあるように、千種忠顕を主将とし、名和高重ら名和一族を伴っての出立であったという。また、「但馬宮(後醍醐天皇四宮・静尊法親王)」も千種忠顕と行動を共にしていることから、千種忠顕は但馬宮を奉じた軍勢であったと考えられる。この頃から赤松円心入道と千種忠顕が同調して京都を窺い、但馬宮を預かっていた但馬守護「太田三郎左衛門尉」(『太平記』)も千種忠顕に降って「丹波篠村」に参会した。
一方、六波羅探題は赤松勢を追い返したとはいえ、洛中にまで敵の侵入を許したことに危機感を強め、万が一を考えて「帝ハ六波羅ノ北殿ニ御入」(『博多日記』)と、光厳天皇を六波羅探題北殿に遷した。なお「京中さハかしくなりて上皇も新主も六波羅にうつり給ふ」(『神皇正統記』)、「後伏見院諱胤仁、正慶二年三月十二日、奉伴主上両院、幸六波羅」(『皇代略記』)とあるように、後伏見上皇、花園上皇も同じく六波羅探題に遷っている。供奉の公卿は「日野大納言資名、同中納言資明卿、二人、堀川大納言具親已下、上達部三、四人」(『続史愚抄』)であった。なお、京都から敗走した赤松円心入道は、一旦は拠点の「布引ノ城」へ籠るが、その後「八幡」に陣して京都を窺っている(『博多日記』)。こうした緊迫する上方の状況を打開するために、六波羅探題は関東に追加兵力の上洛を要請したのだろう。千早・金剛山を攻める軍勢も手いっぱいであり、そこからの援兵は見込めない状況であったからである。
また、3月11日には千早・金剛山寄手の「新田小太郎義貞、自大唐宮綸旨給之下向下野国」(『大乗院日記目録』)という。大塔宮の「綸旨」とある時点で当時の記録とは言い難いが、当時の新田氏は足利氏の指揮下にある「足利一門」(田中大喜『新田一族の中世:「武家の棟梁」への道』)であり、帰国は足利家当主・足利高氏の密命であったのかもしれない。「新田一族」は千早・金剛山攻めが行われる直前には「大番衆」として在京しており(『楠木合戦注文』)、新田義貞も大番衆の一人であったろう。「新田一族」は「大和道」の「大将軍陸奥右馬助殿」の手に属して金剛山を攻めていたとみられ、新田義貞が関東に帰還したことが事実とすれば、鎌倉在の宗家足利高氏と「先代追討」の相談を行った可能性が高いだろう。
この頃、千早攻めを行う「和泉国御家人和田修理亮助家」のもとに4月3日付の大塔宮令旨が届けられる。大塔宮はおそらく金剛山に籠っていたと思われるが、寄手の一人である和田助家へ「追討関東之凶徒、可励報国之忠節」を命じる令旨を届けているのは、内通発覚による混乱も視野に入れたものかもしれないが、和田氏が和泉国御家人であり、楠木正成とも面識があったためかもしれない(『和田文書』)。助家は「治病更発」のために「子息助康」に郎従数名を付けて密かに千早陣中を抜けさせて赤松円心勢と合流させており、助康は4月8日に桂川西岸久我畷の「於赤井河原戦場致合忠」(『和田文書』)している。これは桂川西岸の高台(西岡)を抑えていた赤松入道勢と、奪還せんとする六波羅勢との攻防が続いていたことを意味し、久我畷付近の戦いはおそらく4月3日にも行われている(「村上太郎左衛門所蔵文書」『萩藩閥閲録』132)。なお、父の和田助家はこの後も千早攻めに従軍し、4月14日には子息の中次助秀が「茅葉屋城」の合戦で負傷(『和田文書』)している。
また、4月8日には、千種忠顕は京都を窺い、但馬国通過の途路に最前に馳せ参じた「但馬国少佐郷一方地頭伊達孫三郎入道々西」「兄弟三人道西、宗幸、宗重等」らをはじめとする軍勢を率いて「押寄二条大宮焼払丹後前司之役所」い、さらに伊達道西兄弟は「打入敵陣中、数刻合戦、舎弟宗幸被射左肩、家人和田次郎、中間十郎太郎打死畢」(『伊達文書』)という奮戦を見せるも敗北し、「四月八日六波羅合戦有テ御方打負給」(『伯耆巻』)ったという。この敗戦を受けて「但馬宮自峯堂御出于男山」(「林実広軍忠状」『鎌倉遺文補遺編』)とあり、「峯堂(西京区山田桜谷町)」にいた「但馬宮(静尊法親王)」は「男山(石清水八幡宮寺)」へ移っている。また、千種中将と同道していた「坊門侍従家(雅忠)」は軍勢を率いて「西岡警固御向」い、「粟生山観音寺(長岡京市粟生清水谷)」に城郭を構えて「打塞大江山」いだ。芝山の街道を封鎖し丹波方面から寄せる六波羅勢を遮断するためとみられる。
一方、六波羅及び二条大宮での「大将頭中将、侍大将村上判官高重、信濃法眼源盛等、八幡ヘ引退ク」の敗戦の一報は4月11日に船上山へ奏上されたといい(『伯耆巻』)、先帝後醍醐は翌12日「行幸有ヘキノ由、勅定有」(『伯耆巻』)ったが、名和長利が諫奏して思い止めさせたという。
そして3月27日、「関東大勢重而上洛、大将足利高氏兄弟、吉良、上杉、仁木、細川、今川、荒川等卅二人大名、次日名越高家同為大将上洛」(『大乗院日記目録』)という。これは六波羅探題から関東への救援要請を受けたものとみられ、関東も追加派兵は想定外で、急遽定められた大将軍は足利高氏と名越高家の二名であった。彼らの上洛日時は不明だが、鎌倉出立時期を考えると4月10日頃だろう。なお、派兵の大将がわずか二名で「気早ノ若武者」の高家を起用せざるを得なかったのは関東の人材不足が原因であるともされているが、この派兵はあくまでも京都を窺う桂川西岸域の叛乱軍からの京都防衛と地域奪還を主目的とするものであって、千早・金剛山攻めの援兵ではない。すでに京都から笠置攻めで動員された東国御家人は帰国する人々もあり、鎌倉守衛の兵も残しつつ、足利高氏・名越高家という名門血統の両大将を派遣することで、士気の鼓舞も狙ったのであろう。
※足利高氏は元弘2(1332)年の笠置攻めの大将軍として上洛した際に後醍醐先帝から綸旨を賜っていた可能性が高いだろう。これもまた綸旨発覚による追討軍の混乱も想定したものであったろうが、足利高氏は笠置攻め後には御所に参内して挨拶することもなく早々に関東へ帰還してしまっていることからも、北条「一門」とは一線を画していたことがうかがえる。そして、畿内の楠木正成らの蜂起により多くの御家人が上洛したことで、鎌倉は相当手薄な状況にあったと推測される。足利高氏はこうした状況下で後醍醐上皇の綸旨を奉じて鎌倉の占拠を計画したと思われるが、京都の情勢の把握を優先したと思われる。当時在京の大番衆には「足利蔵人二郎跡」「山名伊豆入道跡」「寺尾入道跡」「新田一族」「里見一族」ら足利庶家が多くあり、高氏は鎌倉にいながら畿内の情勢を知り得たのだろう。そして、先帝の隠岐脱出及び摂津筋の陥落も知った高氏は、3月に入り金剛山攻めの搦手軍に加わっていた新田寺尾の惣領家・新田小太郎義貞を関東に呼び戻すと、上野の一門と連携しつつ鎌倉の占拠を企てたのではなかろうか。ところが、高氏は急遽、京都へ追加派兵の大将軍とされてしまったため、計画の変更を余儀なくされる。しかし、畿内の状況を実見することで最適のタイミングを図ることができた高氏は、関東在の新田岩松経家と新田義貞に決起の日付を伝えた上で、ほぼ東西同時に挙兵する計画を起こしたのだろう。
+―北条朝直―――北条宣時――――北条宗宣―――北条維貞―――北条貞宗
|(遠江守) (遠江守) (陸奥守) (修理大夫) (陸奥守)
|
+―女子 +―北条時宗―――北条貞時―――北条高時
| ∥ |(相模守) (相模守) (相模守)
| ∥ |
| 千葉介頼胤 北条時頼――+―北条宗頼―――女子
|(千葉介) (相模守) (修理亮) ∥
| ∥――――+―北条守時
+―北条時房―+―北条時盛―――女子 ∥ |(相模守)
|(武蔵守) (越後守) ∥ ∥ |
| ∥―――――――北条義宗―――北条久時 +―平登子
| 平基親――――女子 ∥ (駿河守) (武蔵守) ∥
|(兵部卿) ∥――――――北条長時 足利高氏
| ∥ (武蔵守) (治部大輔)
| ∥
北条時政―+―北条義時 +―北条重時―+―北条業時――――北条時兼―――北条基時―――北条仲時
(遠江守) (陸奥守) |(陸奥守) |(陸奥守) (尾張守) (左馬助) (越後守)
∥ | |
∥――――+―北条朝時 +―女子
∥ (遠江守) ∥―――――――北条時家―――北条高家
比企朝宗―――女子 ∥ ∥ (兵庫頭) (尾張守)
(藤内) ∥――――――北条公時
∥ (尾張守)
大友能直―――女子
(左近将監)
畿内はすでに大塔宮・楠木正成や赤松入道だけではなく、丹波方面から但馬宮静尊法親王を奉じて京都を窺う「頭中将殿(千種中将忠顕)」による在京御家人の切り崩しが加速的に進んでおり、4月1日には千早大手攻めの熊谷小四郎直経に大塔宮から「伊豆国在庁時政子孫高時法師」の「被加征伐」(「大塔宮令旨」『安芸熊谷家文書』)を命じる令旨が下されるとともに、4月中には「可令退治四ヶ国凶徒之旨、被下 綸旨」(「熊谷直経代同直久軍忠状」『安芸熊谷家文書』)が下されている。なお、令旨の当日である4月1日には直経は「於大手西山中尾登先、抽忠節、被疵者也」(「熊谷直経合戦手負注文」『安芸熊谷家文書』)とあるように千早城の山中まで侵入して戦っているが、その直後、熊谷一族は千早陣から撤退して洛南の赤松入道勢と合流したとみられる。
こうした中で4月16日、足利高氏は入洛(『太平記』)。翌17日には早速に「海老名六郎季行ヲ潜ニ伯耆船上ヘ進ラセラレテ、関東ヘ不義、唯天誅ヲ招ク時ヲ得テ候ヘハ、高氏モ御方ニ参奉公ノ忠勤ヲ致シ涯分ニ恩化ヲ仰キ奉ルヘシ」と奏上。先帝後醍醐も叡感を以て「早ク諸国ノ官軍ヲ催シ、不日ニ朝敵ヲ追伐スヘキ」(『太平記』)という綸旨が下されることとなったとされる。
これと同日の4月17日には千種忠顕を通じて陸奥国白河郡の「結城参川前司殿(結城親朝)」へ「前相模守平高時法師」の追討を命じる綸旨を下している(「結城文書」『鎌倉遺文』32094)など、この頃、大塔宮は「高時法師」の誅伐を命じる令旨を頻出している。備後国で強大な影響力を持つ山内首藤三郎通継一族も離反し、5月2日には山崎の赤松勢と合流している(「首藤通継申状」『山内首藤文書』)。
4月21日、六波羅勢は芝山と善峰川を挟む高台の大原野(西京区大原野上里南ノ町周辺)に布陣したが、但馬宮・千種勢の問田林太郎兵衛らが攻め落とした。大原野の陥落により六波羅勢が北部から西岡へ攻め入ることが困難になった。さらに、この頃には千早・金剛山戦線も崩壊し、関東勢は奈良や関東へ落ちていったとみられる。千早・金剛山攻めの失敗は、長滞陣による士気の低下に加え、大塔宮からの令旨や先帝の綸旨などによる切り崩しが奏功したものと思われ、「武行者、為長崎三郎左衛門入道思元聟、属同四郎左衛門尉高貞、発向茅屋城致合戦、去四月落下関東之刻、同五月十日於三河国矢作宿、仁木、細河、武田十郎已下被留畢」(「南部時長等申状」『陸奥南部文書』「南北朝遺文」25)とあるように、長崎思元入道聟の南部三郎次郎武行は長崎四郎左衛門尉高貞の下で千早攻めを行うも、4月下旬には戦線を離脱し関東へ「落下」の途次、5月10日に三河国矢作宿で足利方に捕らえられていることからもうかがえる。こうした千早・金剛山での敗亡はますます関東からの離反を招き、もはや六波羅探題は京都以南の維持が困難になっていたとみられる。これらの状況打開を少しでも打開するべく、桂川西岸から山崎一帯の制圧を至上命題として、名越高家、足利高氏が桂川西岸攻めに出立したとみられる。「西岡」には赤松入道円心、対岸の男山には但馬宮静尊法親王、千種中将忠顕、赤松則祐律師らが布陣していたが、大手の名越尾張前司は久我畷付近に駐屯する六波羅勢と合流して西岡を攻め、搦手の足利高氏は丹波街道を南下して大原野から西岡を目指す手はずであったのだろう。
ところが4月27日に「名越尾張前司発向」したものの、久我畷での赤松勢との戦いの中、「菱河」で早々に討死を遂げてしまった(『鎌倉年代記裏書』「大日本史料」)。赤松勢の一員として参戦していた問田林実広は、この戦いで「討留名越尾張前司一族、取進頸」(「林実広軍忠状」『鎌倉遺文補遺編』)という。実名は不明だが、名越高家に従軍していた名越名字の人物を討ったのだろう。また、赤松入道円心の妹を母とする佐用兵庫介範家も「鎌倉ノ軍大将討名越尾張守高家大ニ在戦功」(「佐用頼景系」『播磨国諸家系図』)という。
一方で、搦手大将軍の足利高氏は、在京中の4月22日には「先代追討ノ御内書」を関東在の「兵部大輔経家并新田義貞」に送り、彼等を「両大将」として関東を討つ指示をしている(田中大喜『新田一族の中世:「武家の棟梁」への道』:『正木文書』)。これは新たな先帝の綸旨が到来し、畿内の情勢も実見したことで、以前からの鎌倉占拠計画を実行に移したのであろう。この両新田への密書と同時に、鎌倉にも新田氏を含む足利一門の鎌倉引き上げが伝えられたと思われる。そして高氏は援兵として「細川阿波守、舎弟源蔵人、掃部介兄弟三人」を関東に派遣したという(『梅松論』)。
名越高家が久我畷の戦いで討死を遂げた4月27日、足利高氏は西岡攻めの搦手軍として丹波路へ進んでいたが、南下することなくそのまま西行して大江山を越え丹波国篠村(亀岡市篠町)に入った。高氏はここに数日滞陣し、「結城上野入道殿(結城宗広入道)」(「結城文書」)、「小笠原殿(小笠原貞宗)」(『笠系大成附録』)、「周防五郎三郎との(島津忠兼)」(『島津家文書』)、「野介高太郎殿」(『前田氏所蔵文書』)、「嶋津上総入道との(島津貞久)」(『薩藩日記』)、「大友近江入道殿(大友貞宗)」(『大友文書』)、「阿蘇前太宮司殿(阿蘇惟直)」(『阿蘇家譜』)など各地の有力御家人に「自伯耆国蒙 勅命候之旨参候、合力之旨本意候」と、関東を見限ることへの協力を求める文書を発給している。遠方の島津貞久入道に宛てた「書状」はわずか幅が7センチメートル余りの布地に数通認められており、密使に託したものであったと考えられる。そして4月29日、篠村八幡宮(亀岡市篠町篠)に「随 勅命所挙義兵也、然間占丹州之篠村宿、立白旗」(『丹波篠村八幡宮文書』『鎌倉遺文』32120)と誓い、挙兵したのであった。そして5月2日、高氏は先帝後醍醐に対し、「綸旨重令拝見候」と二度目の綸旨(一度目は前年上洛時か)を拝見したことを述べ、「任 勅命、先日拝領状之請文、弥可抽軍忠候」と報告している(「足利高氏請文」『伊勢光明寺残篇』『鎌倉遺文』32127)。
一方、同日には「千寿王丸、竹王丸、鎌倉没落」(『大乗院日記目録』)とあるように、高氏の嫡子千寿王と、庶長子「竹王丸(実際は竹若丸)」が密かに鎌倉から遁れている。鎌倉脱出後の千寿王丸は北上して新田経家・新田義貞と合流に成功するが、西へ向かった竹若丸は「長崎勘解由左衛門沙汰」によって駿河国「浮島原」で捕らえられて討たれた(『大乗院日記目録』)。竹若丸は「母加子六郎女」(『諸家系図纂』)で、「尊氏謀反之時、伊豆国走湯山頼中坊同心、忍上洛」のときに「駿河国江尻原自害」という(『諸家系図纂』)。竹若丸が頼ったのは、足利宮内少輔泰氏の子・加古六郎基氏の末子で「密厳院別当」の「加古法印 覚遍」(『尊卑分脈』)であった。竹若丸の叔父にあたる。覚遍は「元弘三壬八―討死」とあるが、これは「元弘三五八―討死」の誤りであろう。5月2日に鎌倉を脱出した竹若丸は伊豆山で覚遍法印と合流して西へ向かったものの、高時入道が遣わした両使の長崎勘解由左衛門入道・諏訪木工左衛門入道の両名に探索され、5月8日に浮島原で討たれたということになる。つまり、足利一門が鎌倉から消えたことで鎌倉は急遽所縁の場所を捜索し、密厳院由緒の竹若丸は早々に追捕されたと思われる。しかし、赤橋北条家所縁の千寿王丸は逃亡先を想定し得ずに取り逃がしている。おそらく鎌倉在の新田氏とともに上野国へと逃れたのであろう。なお、長崎等は駿河国高橋で六波羅からの早馬と出会い、名越高家の討死と足利高氏の叛旗を知らされたという(『太平記』)。
駿河国にはのちに「竹若御料御菩提所、駿河国宝樹院」(『諸家文書纂』)が建立され、高氏から寺領が寄進されている。なお、伊豆山密厳院は頼朝の師僧阿闍梨覚渕が開いて以来、鎌倉殿の信仰篤い寺院であったが、足利泰氏の子の覚玄法印、覚海法印、曽孫頼潤法印(別当記載なし)が別当となるなど、鎌倉期初中期には足利家が別当を輩出する寺院となっていた。竹若の叔父・別当覚編法印もその跡を受けており、密厳院は「是則前別当覚遍法印御一家、并竹若御料人等持寺殿御息、の御遺跡として殊に興隆を致し、彼御菩提を訪申へきよし、慇懃の仰を承て」(『醍醐寺文書』3696)とあることから、高氏は竹若丸を別当覚遍に付し、いずれ密厳院の別当に据える予定だったとみられる。
5月7日、足利高氏は京都に発向して六波羅を攻めた。高氏は丹波国から京都へ入っていることから六条坊門小路から入京したと思われ、東進して六波羅探題北方へ向かったのだろう。一方、桂川西岸の赤松・千種勢は、「鳥羽造道」(「源頼連申状案」『毛利家文書』)、「東寺造道」(「雅楽助源頼連申状案」『毛利家文書』)、「竹田河原、高倉縄手」(「僧清源申状」『毛利家文書』)を北上していることから、壬生大路から高倉小路にかけて東西幅広く入京し、六波羅南方へ迫ったのだろう。六波羅勢は鴨川を防衛線として徹底抗戦しており、寄手も問田林実広が「於六波羅西河原、終日終夜抽軍忠」(「林実広軍忠状」『鎌倉遺文補遺編』)と鴨川の河原で奮戦していることがわかる。南側の寄手は鴨川の防衛線を突破すると六波羅館の「六波羅南角箭倉之際」(「雅楽助源頼連申状案」『毛利家文書』)、「六波羅未申角箭倉之際」(「僧清源申状」『毛利家文書』)で戦っているが、「南角箭倉之際」は六波羅館の隅櫓の一つとみられ、ここから散々に矢箭を降らせたのだろう。
しかし、六波羅はすでに寡兵であったところに、本来加勢だった足利高氏が敵勢として攻め寄せ、さらに西国の御家人がこぞって離反する中で支え切れるはずもなく、7日の夕刻、「為女官沙汰、内侍所奉入権大納言公宗卿北山第」と女官に神鏡を持たせて北山の西園寺家別邸に遷した(『皇年代略記』)。そして「元弘三年五月八日、仲時時益奉具新主両主没落関東」(『皇年代略記』)と、探題北方の越後守仲時、南方の左近将監時益は光厳天皇、後伏見上皇、花園上皇を奉じて関東へ向けて出京した(『元弘日記裏書』)。寡勢の中で縦横に緻密に手を配り、幾度にもわたり敵勢の侵入を防いだ名探題も万事これまでと決断した結果である。
そして探題南方の左近将監時益は「於関山伏誅」(『元弘日記裏書』)または「江州四宮川原」(『尊卑分脈』)で討死を遂げた。北方の越後守仲時はここを切り抜け、南方の祗候人も同道して近江国坂田郡の山間まで落ち延びたが、ここで敵勢に囲まれ「仲時西山ニ取上テ合戦スと云ヘドモ不叶シテ腹ヲ切畢」(『保暦間記』)と仲時は番場宿西側の高台に登って合戦するも衆寡敵せず、仲時以下四百三十二名は「番場宿米山麓一向堂前」で討死、自害を遂げた(『近江国番場宿蓮華寺過去帳』)。そして「於江州馬場宿辺、三皇令留給、是守護輩自殺之故也」と、光厳天皇、後伏見上皇、花園上皇の三皇は守護する人々が壊滅したことで進退窮まり、そのまま近江国に留まることとなる。また、三皇に供奉した日野権大納言資名、坊門権中納言俊実らも同地で出家を遂げている(『公卿補任』)。
この逃避行では越後守仲時のもと、北条庶流の櫻田、苅田氏を筆頭に北条家有力被官の高橋氏、隅田氏、安東氏、陶山氏、糟屋氏ら六波羅祗候の武士が戦い、あるいは自害して散っている。自刃を遂げた人々のうちには、隠岐国で先帝後醍醐の警衛をした隠岐守護・佐々木清高、関東評定衆の二階堂忠貞入道、笠置攻めの大将軍のひとり河越参河前司、六波羅評定衆の三善康世ら重鎮の御家人も見える。
●『近江国番場宿蓮華寺過去帳』より(188名)
| 越後守仲時 (六波羅北方) |
櫻田治部大輔入道浄心 (北条貞国入道) |
苅田彦三郎師時 (北条師時) | 高橋参河守時英 | 高橋孫四郎業時 |
| 高橋又四郎範時 | 高橋五郎盛時 | 高橋孫四郎左衛門元時 | 隅田左衛門尉時親 | 隅田孫五郎清親 |
| 隅田藤内左衛門尉八村 | 隅田与一真親 | 隅田四郎光親 | 隅田五郎重親 | 隅田新左衛門尉信近 |
| 隅田孫七国村 | 隅田又五郎能近 | 隅田藤三国近 | 隅田三郎祐近 | 安東太郎左衛門尉祥兼 |
| 安東左衛門太郎則兼 | 安東左衛門三郎則満 | 安東三郎基兼 | 中布利五郎左衛門尉綱能 | 石見彦三郎吉国 |
| 武田下条十郎光高 | 関屋八郎為好 | 関屋十郎為経 | 黒田新左衛門尉俊保 | 竹井太郎盛充 |
| 竹井掃部左衛門尉貞昭 | 斎藤十郎兵衛尉基親 | 勘解由三郎兵衛尉長兼 | 皆吉左京亮旃信 | 小屋木七郎知秀 |
| 加藤七郎斯決 | 塩屋右馬允渲恒 | 内海八郎善宣 | 海上八郎教詣 | 岡田平六兵衛尉遠秀 |
| 岩切三郎左衛門尉有益 | 窪平右衛門入道陵玄 | (計42名) | ||
| 一向堂大庭討死 | ||||
| 窪新右衛門尉宣高 | 窪四郎宣政 | 木工助入道祐善 | 分次郎法真 | 吉井彦三郎忠連 |
| 吉井四郎忠信 | 壱岐孫七郎貞住 | 窪次郎宣次 | (計8名) | |
| 南方内人々 | ||||
| 糟屋弥次郎入道明翁 | 糟屋弥三郎入道道教 | 糟屋彦三郎入道倫芳 | 糟屋六郎渲次 | 糟屋五郎易隆 |
| 糟屋次郎重俊 | 糟屋三郎能隆 | 糟屋又次郎重安 | 糟屋新左衛門経春 | 糟屋左衛門次郎伴興 |
| 糟屋七郎三郎伴範 | 糟屋藤三郎家泰 | 大井次郎伴光 | 櫛橋次郎左衛門尉義守 | 南和五郎家盛 |
| 南和又五郎貞経 | 原宗左近将監入道憐戒 | 原宗彦七定行 | 原宗十郎次郎俊茂 | 豊島平五重経 |
| 豊島七郎家倍 | 豊島平右馬三郎為住 | 豊島五郎貞秋 | 土肥三郎則実 | 土肥五郎元実 |
| 御器所安東七郎経倫 | 平塚弥四郎為稔 | 西郡十郎国演 | 怒借屋彦三郎保弘 | (計29名) |
| 一向堂仏前自害 | ||||
| 穐次次郎兵衛尉則光 (秋月種道?) | 半田彦三郎稔弘 | 華房六郎兵衛入道全幸 | 毎田三郎則弘 | 宮崎三郎恒則 |
| 中間平五郎 | 宮崎太郎次郎恒利 | 宮崎上総三郎恒遠 | 山木八郎入道玄桓 | 山木十郎入道源徳 |
| 山木彦三郎繁盛 | 山木小五郎為盛 | 山木彦五郎為泰 | 山木孫十郎繁教 | 足立源五長秋 |
| 足立参河又六則利 | 足立弥六則愰 | 黒田次郎左衛門尉憲満 | 広田五郎左衛門尉経英 | 佐々木隠岐前司清高 |
| 佐々木次郎右衛門尉泰高 | 佐々木三郎兵衛尉高秀 | 佐々木永寿丸 | 片山十郎次郎入道祐珪 | 片山弥次郎祥明 |
| 伊祐三郎家高 | 伊祐治部丞義高 | 伊祐孫八郎高通 | 治田八郎良決 | 走井三郎家景 |
| 中野井次兼尚 | 木村四郎正高 | 二階堂伊勢入道行照 | 石井中務忠光 | 石井孫次郎忠泰 |
| 石井四郎程国 | 海老名四郎忠景 | 海老名与三忠元 | 石川九郎道幹 | 石川亦次郎通近 |
| 新藤六郎元弘 | 片依小八郎忠光 |
豊後民部大輔三善康世 (六波羅評定衆) | 三善三郎入道善照 | 三善彦太郎康顕 |
| 三善孫太郎康明 | 武田与次光方 | 兒島介三郎顕氏 | 兒島助太郎氏明 | 真木野藤左衛門尉朝安 |
| 池守藤内兵衛尉行直 | 池守左衛門五郎行重 | 池守左衛門七郎行俊 | 池守新右衛門尉顕重 | 池守左衛門太郎顕行 |
| 牧野藤左衛門尉忠秋 | 問注所信濃少輔外記清近 | 問注所阿子光丸 | 問注所彦太郎良近 | 斎藤宮内丞教親 |
| 斎藤阿千丸 | 筑前民部大輔伴弘 | 筑前七郎左衛門尉家景 | 田村中務入道明鑑 | 田村彦五郎資信 |
| 田村兵衛次郎親信 | 真上彦三郎持直 | 真上又三郎信直 | 陶山次郎清直 | 陶山備中守清房 |
| 陶山与次清泰 | 陶山小四郎敏信 | 陶山四郎入道祥宗 | 陶山九郎元良 | 陶山四郎盛宣 |
| 陶山三郎敏忠 | 陶山与三清弘 | 陶山彦九郎清忠 | 陶山七郎直清 | 陶山彦三郎俊景 |
| 陶山又四郎敏実 | 陶山紀七敏直 | 陶山新藤五入道正通 | 陶山又三郎真次 | 陶山肥後房海範 |
| 陶山新三郎祥近 | 陶山新次郎良房 | 陶山小五郎真倫 | 小宮山孫太郎吉愰 | 小宮山小三郎師光 |
| 高見孫三郎近好 | 小宮山六郎次郎規真 | 菅野源五助光 (小宮山規真若党) | 塩谷弥三郎家弘 | 荘左衛門四郎俊光 |
| 藤田六郎種法 | 藤田七郎頼宣 | 新藤彦四郎能忠 | 金子十郎左衛門尉伴弘 | 真壁三郎秀忠 |
| 江馬彦次郎常久 | 長崎与三種長 | 近部七郎種次 | 能登彦次郎為祐 | 川越参河入道乗誓 |
| 木戸三郎家保 (川越参河若党) | 新野四郎朝繁 | 甘糟三郎左衛門尉清経 | 甘糟七郎知清 | (計109名) |
5月8日、頭中将忠顕は「伯州詔」を奉じ、権大納言公宗の北山第に遷されていた内侍所を禁中へ移し奉った(『皇年代記』)。
一方、関東においても「尊氏のすえの一ぞくなる新田小四郎義貞といふもの、今の高氏の子四になりけるを大将軍にして、武蔵国よりいくさをおしてけり」(『増鏡』)とあるように、高氏の「先代追討ノ御内書」を受けた「兵部大輔経家并新田義貞」(『正木文書』)が高氏嫡子の千寿王丸を擁して挙兵した。なお、「紀五」こと紀五左衛門尉政綱は、挙兵前に岩松下野五郎経家へ「内状」を遣わしており(「岩松満親文書注文写」『正木文書』)、この内状は鎌倉を脱出する千寿王が経家を頼る旨の書状かもしれない。
●千葉=北条周辺系図
千葉介常胤―+―相馬師常―――相馬義胤――――相馬胤綱
|(次郎) (五郎) (左衛門尉)
| ∥―――――――相馬胤村
| ∥ (左衛門尉)
| 天野遠景―――天野政景 +―娘
|(左衛門尉) (和泉守) |(相馬尼) +―北条貞将
| ∥ | |(武蔵守)
| ∥―――――+―娘 |
| ∥ ∥―――――――北条実時―――北条顕時――+―北条貞顕―+―北条貞冬
| 三浦介義澄――娘 ∥ (越後守) (越後守) |(武蔵守) (右馬助)
| ∥ ∥ |
| ∥ ∥ +―女子
| ∥ ∥ (釈迦堂殿)
| ∥ ∥ ∥――――――足利高義
| ∥ ∥ ∥ (左馬頭)
| ∥ ∥ 足利貞氏
| ∥ ∥ (讃岐守)
| ∥ ∥
| ∥ ∥―――――――女子
| +―北条義時――――北条実泰 +―千田泰胤―+―女子 ∥
| |(陸奥守) (五郎) |(五郎) | ∥――――――千葉介貞胤
| | | | ∥ (千葉介)
| +―北条時房――――――――――――女子 +―女子 ∥
| (左京権大夫) | ∥ ∥ ∥
| | ∥ ∥―――――――千葉介胤宗
| | ∥ ∥ (千葉介)
| | ∥――――――千葉介頼胤
| | ∥ (千葉介)
+―千葉介胤正――千葉介成胤―+―千葉介胤綱―+―千葉介時胤
(千葉介) (千葉介) |(千葉介) (千葉介)
|
+―娘(北条時頼の後室・千田尼)

|
| 生品神社 |
正慶2(1333)年5月8日、新田太郎義貞が上野国新田庄の生品神社で鎌倉打倒の兵を挙げた。この挙兵には高氏嫡子の千寿王丸が擁立されたとされており(『増鏡』)、最近の研究では新田氏は鎌倉前期の新田政義の自由出家による没落で舅足利家の庇護を受けて以降、足利家一門とされたとの説がある(田中大喜『新田一族の中世:「武家の棟梁」への道』)。
当時の足利家当主・前治部大輔高氏は摂津・丹波との国境である桂川西岸地域から山崎方面を奪還する六波羅探題の援兵として上洛中であったが、4月22日、在関東の「(岩松)兵部大輔経家并新田義貞」に「先代追討ノ御内書」を送り、彼等を「両大将」として討幕の挙兵を指示しており(応永三十三年七月「岩松伊予守満長代成次書状」『正木文書』)、新田経家と新田義貞の挙兵はこの御内書のもと行われたとみられる。「上野国ニ高氏一族新田義貞ト云者アリ、早鎌倉ヘ発向ス、尊氏カ息男アリ、共合戦ヲ可致由ヲ尊氏催促ス、則義貞彼命ヲ受ヲ、武蔵上野相模等ヲ催シテ鎌倉ヘ馳上」(『保暦間記』)ったという。足利家は宗家のほか、尾張守家(斯波家)、上総介家(吉良家)、渋川家ら独立した一門がいたが、新田家も彼らと同様に足利一門として包摂される御家人であったのだろう。なお、新田一門は彼らよりも遠縁にあたり、足利を称する一門より独立性は高かったとみられる。
『太平記』によれば5月9日に鎌倉では軍評定が行われ、翌10日にまず「金澤武蔵守貞将、五万余騎ヲ差副テ下河辺ヘ下」した。この金澤勢は「上総下総ノ勢ヲ附テ、敵ノ後攻ヲセヨトナリ」(『太平記』)の搦手であった。そして、鎌倉道を下ってくる新田勢を食い止める大手には「桜田治部大輔貞国ヲ大将ニテ、長崎二郎高重、同孫四郎左衛門尉、加治二郎左衛門入道」に「武蔵上野両国ノ勢六万余騎ヲ相副」(『太平記』)て入間川へと派遣したという。ただし、桜田治部大輔貞国は近江国番場で北方仲時とともに自刃しており、ここに出陣した桜田某は貞国ではない。
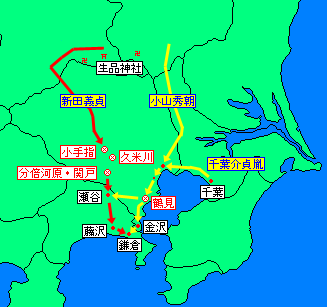
|
| ▲新田義貞の鎌倉攻め(鎌倉をクリック) |
新田勢は5月11日、入間川で川を挟んで桜田勢と対峙し、小手指原で桜田治部大輔貞国(実際は貞国ではない)、長崎四郎高重、長崎孫四郎左衛門尉率いる鎌倉勢と合戦に及び、鎌倉勢は敗北して防衛線を久米川まで下げる。翌12日の久米川の戦いでも鎌倉勢はわずかに敗れ、さらに分倍河原まで撤退した(『太平記』)。なお、足利高氏の嫡子・千寿王は義貞の庇護のもと新田庄世良田宿に匿われており、少なくとも12日までは世良田宿にあり、「新田三河弥次郎満義世良田」もその麾下にあった(「鹿島利氏申状写」『南北朝遺文 関東編』1356)。『太平記』では9日に武蔵国へ入った時点で千寿王が新田勢に加わったことが記されているが、事実ではない。
久米川の敗報を受けた北条高時入道は、5月14日、「高時ノ弟左近大夫将監入道恵性ヲ大将トシテ武蔵国ニ発向ス、同日山口ノ庄ノ山野陣ヲ取」ったといい、その派遣された諸将は「舎弟四郎左近大夫入道恵性ヲ大将軍トシテ、塩田陸奥守入道、安保左衛門入道、城越後守、長崎駿河守時光、佐藤左衛門入道、安東左衛門尉高貞、横溝五郎入道、南部孫二郎、新開左衛門入道、三浦若狭五郎氏明」(『太平記』)と伝わる。
翌15日に「分配関戸河原ニテ終日戦ケルニ、命ヲ殞シ創ヲ被ル者幾千万ト云数ヲ知ス、中ニモ親衛禅門ノ宗徒ノ者共安保左衛門入道道潭、粟田横溝八郎最前ニ討死ヲシケル間、鎌倉勢悉ク引退ク処ニ、即大勢攻上ル間、鎌倉中ノ騒キ只今敵ノ乱入タランモ角ヤチ覚シ」(『梅松論』)という。ただし、分倍河原の戦いでは左近大夫将監入道は桜田貞国と合流し、その勢いのままに新田勢を打ち破り、堀金(狭山市堀兼)まで追い落としたとされる(『太平記』)。このとき新田勢の上野国碓氷郡飽間郷(安中市秋間)の御家人「飽間斉藤三郎藤原盛貞 生年廿六」「同孫七家行 廿三」が「討死」を遂げている(「武蔵府中・相模村岡合戦討死者供養板碑銘」『鎌倉遺文』32175)。
分倍河原の戦いで手痛い反撃を食った新田勢だったが、5月15日夕刻、義貞のもとに三浦一族・大多和平六左衛門義勝が松田・河村・土肥・土屋・本間・渋谷ら相模武士六千騎を率いて着陣。これに喜んだ義貞は、彼らを先陣として翌16日明け方に分倍河原まで進軍。鎌倉勢に襲いかかり追い落としたという(『太平記』)。
●『太平記』にみる鎌倉攻め三手(『太平記』の記述だが、信憑性はない)
| 極楽寺切通 | 大館二郎宗氏、江田三郎行義 |
| 巨福呂坂 | 堀口三郎貞満、大嶋讃岐守守之 |
| 大将 | 新田義貞、脇屋義助(堀口・山名・岩松・大井田・桃井・里見・鳥山・額田・一井・羽川以下の一族達) |
千葉介貞胤の動向は、『太平記』においては「上総下総ノ勢」が武蔵守貞将に従って下河辺庄へと進んだ旨が記されており、史実性にかなり疑問の多い『太平記』の記述ではあるが、千葉介貞胤も従兄弟の貞将の軍勢に加わっていた可能性はある。
しかしその後、「搦手ノ大将ニテ下河辺ヘ被向タリシ金沢武蔵守貞将ハ、小山判官、千葉介ニ打負テ下道ヨリ鎌倉へ引返シ給ケレバ、思ノ外ナル珍事哉ト人皆周章シケル」(『太平記』)とあり、千葉介貞胤はその途上で小山判官高朝とともに寝返り、貞将を襲ったのではあるまいか。なお、『梅松論』では「下ノ道ノ大将ハ武蔵守貞将向フ処ニ下総国ヨリ千葉介貞胤、義貞ニ同心ノ儀有テ攻上ル間、武蔵ノ鶴見ノ辺ニ於テ相戦ケルガ、コレモ打負テ引退」(『梅松論』)とあり、戦った場所は武蔵国鶴見であるという。
千葉介貞胤と小山高朝が歩調を合わせて新田勢に呼応したのは、おそらく高氏からの御内書とともに両者の相談があったためであろう。もともと貞胤と高朝はともに先帝後醍醐の配流の護送を行ったり(『太平記』)、同時期に在京するなど接点も多く、交流もあったと思われる。高氏は4月27日から29日にかけて丹波国篠村で「自伯耆国、所蒙 勅命也」として諸大名に対して「令合力給候」ことを指示(「足利高氏軍勢催促状案」:『鎌倉遺文』)しており、当然貞胤や高朝にも催促状が出されていたのだろう。高氏の鎌倉占拠の計画は前述の通り、鎌倉に居住していた時点で練られていた(占拠の根拠は上洛時の先帝綸旨であろう)と思われ、3月の新田義貞の千早・金剛山からの帰国は高氏が呼び戻したものではなかろうか。ところが直後に高氏は六波羅の援兵として上洛することとなり、計画が一時とん挫したと思われる。その計画を再び動かしたものが、4月22日の御内書であったのだろう。鶴見で金澤勢を破った千葉・小山勢は、そのまま六浦道から鎌倉東側の朝比奈からの突入が考えられるが、千葉・小山勢が鎌倉で戦った記録はなく、鶴見以降の貞胤・高朝の動向は不明である。
また、楠木城攻めの大将軍の一人として上洛し、万里小路藤房を預かった常陸国の小田尾張権守高知も関東離反の姿勢を示したと思われ、彼の預かる新治郡の藤房卿配流屋敷には4月19日、「常陸国御家人」の「■■小四郎久幹、■■又四郎幹国」が馳せ参じている(『税所文書』)。
この頃、新田勢追捕の大手大将軍の北条四郎入道、搦手大将軍の武蔵守貞将の大敗に加え、六波羅探題の陥落も鎌倉に達しており、こうした急激な状勢の変化に鎌倉は周章した。このような中でも得宗高時入道は寡兵ながらも諸所に一門を手配し、執権の相模守守時(足利高氏義兄)には洲崎(鎌倉市大船)の敵を防ぐことを命じ、守時は5月18日に「此陣ノ軍剛シテ、一日一夜ノ其間ニ六十五度マデ切合タリ」(『太平記』)という奮戦をみせた。義弟足利高氏らが六波羅を落とし、足利一門の新田勢が鎌倉を攻めるという事態に深い憂慮と責任を感じていたのではなかろうか。この戦いは双方に多数の死者を出し、新田勢でもこの日「飽間孫三郎宗長 卅五」が「村岡(藤沢市村岡)」で討死したことが知られる(「武蔵府中・相模村岡合戦討死者供養板碑銘」『鎌倉遺文』32175)。しかし、寡勢の守時勢は次第に打ち斃され、「五月十八日、赤橋相州自害了」(『大乗院日記目録』)とあるように守時は「帷幕ノ中ニ物具脱捨、腹十文字ニ切給ヒテ、北枕ニソ伏給」った(『太平記』)。そして守時に従っていた得宗被官の南条左衛門高直も「大将既ニ御自害アル上ハ、士卒誰為ニ命ヲ惜ヘキ、イテサラハ御供申サン」と、九十余名もこれに殉じた(『太平記』)。その後、洲崎を破った新田勢は山ノ内まで軍を進めた(『太平記』)。
新田勢が実際に三軍に分かれたかどうかは不明ながら、「搦手大将軍新田兵部大輔(当時は新田下野五郎経家)」は5月19日に巨福呂坂口近辺にあった長勝寺(現在の材木座長勝寺との関係は不明)の前で合戦しており、さらに20日から22日にかけて巨福呂坂で合戦があったことがわかる(『群馬県史 資料編中世2』資料569)。実際の鎌倉攻めは、高氏の命を受けた「兵部大輔経家并新田義貞」の「両大将」が大手大将軍の新田義貞、搦手大将軍の新田下野五郎(兵部大輔経家)が大きく二手に分かれて鎌倉を攻めたのであろう。洲崎で執権北条守時と直接戦ったのは、その後巨福呂坂に攻め入っている新田岩松経家であったと思われる。そして、この鎌倉攻めのときには足利千寿王(高氏嫡男)が世良田から迎えられており、千寿王に従軍していた「新田三河弥次郎(世良田満義)」が21日に鎌倉市中で戦っている。ここは大手新田義貞の管轄であることから、千寿王は新田義貞の陣中にいたとみられる。
●実際の鎌倉攻め(軍忠状より抜粋)で従軍したことが判明する人々
| 方面 | 大将軍 | 資料でみられる従軍御家人(●は大将軍) |
大手大将軍 ・極楽寺坂 ・大仏坂 |
足利千寿王 | |
| 新田太郎義貞 | ●新田孫次郎盛成(5/19~21極楽寺坂大将軍:妙本寺系図) ●新田蔵人七郎氏義 ・三木俊連(5/21霊山攻) ・三木行俊(5/21霊山攻) ・三木貞俊(5/21霊山攻) ●新田大館宗氏(5/18稲村崎、浜鳥居討死) ●新田大館孫次郎幸氏(5/21浜鳥居脇駆入) ・大塚五郎次郎員成(5/21浜鳥居参戦、6/1二階堂御所着到) ・大塚三郎成光(5/21浜鳥居討死) 大多和太郎遠明(5/21浜鳥居合戦) 海老名藤四郎頼親(5/21浜鳥居合戦) 飽間三郎盛貞(5/15府中討死) 結城上野入道道忠(5/18~22合戦) ・ 田嶋与七左衛門尉広堯(同上) ・ 片見彦三郎祐義(同上) 市村王石丸代後藤弥四郎信明(5/15分倍河原参戦、5/18前浜一向堂前参戦) 塙大和守政茂(5/16入間川着到、5/19極楽寺坂参戦) 徳宿彦太郎幹宗(5/19極楽寺坂参戦) 宍戸安芸四郎知時(5/19極楽寺坂参戦) ●新田遠江又五郎経政 ・熊谷平四郎直春(5/16参戦、5/20霊山寺下討死) ・ 吉江三位律師奝実 ・ 齊藤卿房良俊 石川七郎義光(5/17瀬谷参陣、5/18稲村崎参戦、5/21前浜合戦) 藤田左近五郎(5/18稲村崎参戦) 藤田又四郎(5/18稲村崎参戦) 岡部又四郎(5/21前浜合戦) 藤田十郎三郎(5/21前浜合戦) ●武田孫五郎信高(霊山大将軍) ・南部五郎二郎時長(5/20霊山参戦、5/22高時館合戦) ・南部行長(5/20霊山参戦) ・中村三郎二郎常光(5/20霊山討死) ・南部六郎政長(5/15~22鎌倉合戦参戦) ●新田三河弥次郎満義(5/20霊山参戦) ・鹿島尾張権守利氏(5/12世良田千寿王陣着到) 天野周防七郎左衛門尉経顕(5/18片瀬原着到、稲村崎、稲瀬川、前浜参戦 5/22葛西谷合戦参戦) ・天野三郎経政(5/18片瀬原着到、稲村崎、稲瀬川、前浜参戦 5/22葛西谷合戦参戦) 新田矢嶋次郎(5/22葛西谷合戦参戦) 山上七郎五郎(5/22葛西谷合戦参戦) |
|
| 搦手大将軍 ・巨福呂坂 ・化粧坂 |
新田下野五郎(岩松経家) | 飽間孫三郎宗長(5/18村岡討死) ●岡部三郎(侍大将) ・布施五郎資平(5/19長勝寺前合戦、5/20~22小袋坂合戦) |
新田義貞率いる大手勢は洲崎合戦と同日の18日には極楽寺坂方面へ集結し、「新田殿前代合戦之最初、聖福寺江被取陣事」(「正続院領相模国山内庄秋庭郷内信濃村事」『鎌倉円覚寺文書』)とあるように、北条時頼入道建立と言われる聖福寺に陣を取ったという。そして大手勢に加わっていた「天野周防七郎左衛門尉経顕」「子息三郎経政」は「最前馳参于片瀬原」し、「懸破稲村崎之陣迫于稲瀬河并前浜鳥居脇致合戦」で若党の犬居左衛門五郎茂宗、小河彦七安重、中間孫五郎藤次らが討死を遂げている(「天野経顕軍忠状写」『群馬県史 資料編6中世2』番号583)。
天野遠景――天野政景―+―天野景経――天野遠時―――――天野経顕―――――――天野経政
(藤内) (和泉守) |(安芸守) (周防守) (周防七郎左衛門尉) (三郎)
|
+―女子
(相馬尼)
∥―――――相馬胤村―――――相馬師胤―――――――相馬重胤
∥ (孫五郎左衛門尉)(彦次郎) (孫五郎)
相馬師常――相馬義胤―――相馬胤綱
(次郎) (五郎) (小次郎左衛門尉)
また「陸奥国石川七郎源義光」も17日に「相模国世野原(横浜市瀬谷区)」に馳せ参じ、翌18日には「稲村崎致散々合戦」して右膝を射られている(『石川文書』)。常陸国鹿島郡の御家人「塙大和守平政茂」は5月16日に「武蔵国入間河御陣馳参」じ、19日の「極楽寺坂於合戦先手馳向、家人丸場次郎忠邦、怨敵三騎討捕、同山本四郎義長討死之事、徳宿彦太郎幹宗、宍戸安芸四郎同時合戦」(『塙文書』)であった。そして千早・金剛山を攻めるべく上洛していた「武蔵国小四郎直経(熊谷直経)」の留守であったと思われる子・平四郎直春は、5月16日に新田勢に馳せ参じ、20日には「新田遠江又五郎経政御手、就致軍忠、於鎌倉霊山寺之下討死畢」と討死を遂げている(『閥閲録』)。
前述のように天野周防七郎左衛門尉経顕の軍勢が「懸破稲村崎之陣」り、海岸線を伝って「前浜鳥居脇」まで侵入しており、新田勢は5月18日に「稲村崎ヲ経テ前浜ノ在家ヲ焼払フ煙見ヘケレハ、鎌倉中ノ周章フタメキケル有様タトヘテ云ン方ソナキ」状況であった(『梅松論』)。二年後の建武2(1335)年11月6日、足利尊氏は「天野安芸七郎殿」に「鎌倉中入口内稲村崎警固事、一族相共可致厳密之沙汰」を命じているように、天野氏は稲村崎周辺の地理に明るい氏族であったとみられ、近辺に屋敷があった可能性があろう、なお、稲村崎は「鎌倉中入口」であって、『太平記』に見られるような奇襲路ではない。
しかし、北条方も「高時ノ家人諏訪長崎以下ノ輩、身命ヲ捨テ防戦ケル程ニ、当日ノ浜ノ手ノ大将大館、稲瀬河ニ於テ討捕、其ノ手引退テ霊山ノ頂ニ陣ヲ取」ったといい(『梅松論』)、新田勢大将軍の一人、大館次郎宗氏が「得川弥四郎光秀」(『尊卑分脈』)によって討たれている。
+―北条有時――+―――――――――――――――――――女子
|(駿河守) | ∥―――――+―堀口貞義―――堀口貞満
| | ∥ |(美濃守) (美濃守)
| +―女子 ∥ ?
| ∥ ∥ +―一井貞政―――一井政家
| ∥ ∥ (民部権大夫)(左近将監)
+―名越朝時――+―名越時幸 ∥
|(遠江守) |(遠江修理亮) ∥
| | ∥
| | 新田義房――――新田政義――――――堀口家貞
| |(上西門院蔵人)(小太郎) (孫次郎)
| | ∥
| | ∥ +―新田政氏――――新田基氏―――新田朝氏―――新田義貞
| | ∥ |(又太郎) (小太郎) (小太郎) (小太郎)
| | ∥ |
| | ∥―――――――+―大館家氏――――大館宗氏―+―大館幸氏
| | ∥ (又次郎) (又次郎) |(孫二郎)
| | ∥ |
| | 足利義氏――+―女子 +―大館氏明
| |(左馬頭) | (左馬助)
| | ∥ |
| | ∥ +―足利長氏――――+―足利満氏――――吉良貞義―――吉良満義
| | ∥ |(上総介) |(上総介) (上総介) (左京大夫)
| | ∥ | |
| | ∥ +―大僧正最信 +―今川国氏――――今川基氏―――今川国範
| | ∥ |(勝長寿院別当) (四郎) (太郎) (五郎)
| | ∥ |
| | ∥ | +―四条隆量
| | ∥ | |(左近衛少将)
| | ∥ +―女子 |
| | ∥ ∥―――――――――四条隆顕――+―四条隆資―+―四条隆重
| | ∥ ∥ (左近衛中将)|(大納言) (左近衛少将)
| | ∥ ∥ |
| | ∥ 四条隆親 +―女子
| | ∥ (大納言) ∥――――――吉田宗房
| | ∥ ∥ (右大臣)
| +―――――――――女子 吉田定房
| ∥ ∥ (内大臣)
| ∥ ∥――――――+――足利家氏
| ∥ ∥ | (尾張守)
| ∥ ∥ | ∥―――――――足利宗家
| ∥ ∥ | ∥ (左近将監)
| ∥ ∥ |+―女子 ∥――――――足利宗氏
| ∥ ∥ || ∥ (尾張守)
+―北条重時――――――――――――――北条時継――――――――――――女子 ∥――――+―足利高経
|(陸奥守) ∥ ∥(式部大夫)|| ∥ |(尾張守)
| ∥ ∥ || ∥ |
| ∥ ∥ || 長井時秀―――女子 +―足利家兼
| ∥ ∥ || (宮内権大輔) (左京権大夫)
| ∥ +―――北条為時――+―女子
| ∥ | ∥(遠江守) | ∥―――――――渋川義春
| ∥ | ∥ | ∥ (次郎三郎)
| ∥―――――――足利泰氏 +――足利義顕 ∥――――――渋川貞頼―――渋川義季
| ∥ |(宮内少輔) (二郎) ∥ (兵部大輔) (刑部権大輔)
| ∥ | ∥ ∥
| ∥ | ∥ 北条時村――――北条時広――――女子 +―足利高氏
| ∥ | ∥(五郎) (越前守) |(治部大輔)
| ∥ | ∥ |
| ∥ | ∥―――――――――足利頼氏――――足利家時―――足利貞氏―+―足利高国
北条義時―+―北条泰時――+―女子 +―女子 (治部大輔) (伊予守) (讃岐守) (兵部大輔)
(陸奥守) (左京権大夫)| |
| |
+―北条時氏――+―北条時頼――――――北条時宗――――北条貞時―――北条高時
(修理亮) (相模守) (相模守) (相模守) (相模守)
新田勢は数度にわたって鎌倉市中に攻め入り、21日には大規模な戦闘が行われた。なお、鎌倉内でも新田勢に呼応した反乱が起こっていたと思われ、去る4月2日に「抑相催一族已下軍勢、可令誅罰伊豆国在庁高時法師等凶徒由事」の(大塔宮)令旨を受けた得宗地頭代「沙弥道忠(白河結城宗広入道)」は白河在住の「愚息親朝、親光」、在鎌倉の「舎弟祐義、広堯等」、そしておそらく京都にいたと思われる「熱田伯耆七郎(「親類伯耆又七朝保」の父か)」に令旨を伝えるとともに、4月17日に「陸奥出羽両国軍勢可令征伐前相模守平高時法師以下凶徒」の先帝綸旨を「折節幸在鎌倉仕候」を受けて挙兵の心を固め、時勢を窺いながら鎌倉を見限り、5月18日の新田勢の鎌倉侵入に呼応し「先於鎌倉、相率道忠舎弟片見彦三郎祐義、同子息二人、田島与七左衛門尉広堯、同子息一人并家人」(「白河証古文書」『楓軒文書纂文書』)を率いて鎌倉内で兵を挙げたとみられる。こうした在鎌倉で鎌倉を離反した御家人はおそらく白河結城氏に限ったものではなかったであろう。また、鎌倉で将軍守邦親王に仕えていたとみられる従三位阿野実廉は「元弘三年三月、已 臨幸伯州船上山之由、風聞之間、雖欲馳参、山河多重、塞関楯稠、不達本意、蟄居関東之処、五月十四日、故高時法師等差遣討手於実廉、囲私宅、希有而遁万死之陣、交山林、送数日之刻、同十八日、義貞朝臣責入于鎌倉、致逆徒討罰之間、馳加彼手、至廿二日首尾五ケ日之間、於処々致軍忠畢」(「実廉申状」『南北朝遺文』602)とあり、5月14日に自邸を取り囲まれたため山林に逃れ、18日に鎌倉に入った新田勢に加わって戦ったという。
 |
| 材木座より稲村ガ崎を望む |
新田勢本隊は稲村崎を通って比較的自由に鎌倉に出入りしながら鎌倉勢と合戦し、北側では下野五郎経家が指揮を採る搦手軍が巨福呂坂周辺から鎌倉への突入を試みていた。そして「同十八日ヨリ廿二日ニ至マテ、山内、小袋坂、極楽寺ノ切通以下鎌倉中ノ口々、合戦ノ鬨ノ声、矢叫ビ人馬ノ足音暫シモ止ム時無シ」(『梅松論』)という諸所での合戦が行われた。
5月22日には鎌倉市中での戦いが広く行われるようになったようで、「相摸入道殿ノ屋形近ク火懸リケレバ、相摸入道殿千余騎ニテ葛西谷ニ引籠リ給ケレバ、諸大将ノ兵共ハ東勝寺ニ充満タリ、是ハ父祖代々ノ墳墓ノ地ナレバ爰ニテ兵共ニ防矢射サセテ心閑カニ自害セン也」(『太平記』)という。また、南部五郎次郎時長は「廿二日、於高時禅門館生捕海道弥三郎、取高時一族伊具土佐孫七頸畢」(「南部時長等申状」『陸奥南部文書』)と、高時入道が去った館に攻め入り、留守居の海道弥三郎や伊具土佐孫七を討った。「葛西谷之合戦」では、天然の堀の滑川とそれを見下ろす高台の東勝寺からの防戦など、激しい攻防があったと思われる。このほか、この鎌倉合戦が突然始まったものであるため「石見国益田荘宇地村地頭尼是阿相伝文書等、為沙汰、被預置大内豊前権守長弘関東代官因幡法橋定盛之處、元弘三年五月廿三日動乱之時、定盛於鎌倉死去之間、彼手継文書以下、六波羅下知等悉令紛失之由」(建武二年七月十七日益田兼世申状『益田家什書』)とあるように、大内長弘の「関東代官」が討死を遂げたため相伝文書が紛失したこともあった。
極楽寺坂を固めていた「長崎三郎左衛門入道思元、子息勘解由左衛門為基二人」は、小町方面に鬨の声を聞き、遠目に「鎌倉殿ノ御屋形ニ火懸リヌ見へ」たため、預けられた兵はそのまま極楽寺坂に置き、私兵を六百騎ばかりを率いて小町の御所へ馬を走らせたという(『太平記』)。これを見た新田義貞は彼らを取り込め、激しい抵抗を受けながらも討ち取った。
化粧坂口から巨福呂坂へ転戦した武蔵守貞将は、全身七か所を負傷しながらも東勝寺の得宗・高時入道のもとへ帰参した。高時は「軈て両探題職に可被居御教書を被成、相摸守にぞ被移ける」と、彼に感謝の言葉を述べるとともに、今や滅亡した六波羅南北両探題ならびに相模守とする旨の下文を与えたという(『太平記』)。貞将はこれを拝受し、「多年ノ所望、氏族ノ規摸トスル職ナレハ、今ハ冥途ノ思出ニモナレカシ」と述べ、御教書に「棄我百年命報公一日恩」と認めると、鎧の継ぎ目に御教書を差し込み、ふたたび鎌倉市街に馳せ戻り戻って来ることはなかった(『太平記』)。
このほか、化粧坂で新田岩松勢と交戦していた元執権・前相模守基時入道信忍(普恩寺入道。探題北方仲時の父)も自刃。塩田陸奥守国時入道道祐・北条民部大輔俊時父子、塩飽新左近入道聖遠、安東左衛門入道聖秀など名だたる大将も鎌倉の諸所で自刃して果てた。
一方、高時の弟・左近大夫将監泰家入道は、被官の諏訪入道直性の一族・諏訪三郎盛高に、兄・高時入道の二男・亀寿丸を託して信濃国へ遁れさせ、みずからは陸奥国へと姿を消した。得宗高時入道にも恐れられた内管領・長崎円喜入道の孫である長崎左衛門尉高重は三十二人も斬り払う奮戦ののち東勝寺へ帰参した。高重は高時にいましばらく自刃を思いとどまるよう述べると、再び新田勢に近づき、大将義貞の暗殺を企てるも、義貞被官・由良新左衛門に見破られて失敗。数十倍する敵勢相手に斬り廻り、新田勢の同士討ちを誘うと、その隙をついて東勝寺へ退却した。残った高重麾下の武士はわずかに八騎。みずからも二十三筋もの矢を体中に立てて高時入道の御前に侍ると、祖父の円喜入道が待ち受けて「何トテ今マテ遅ツルソ、今ハ是マテカ」と問うと、高重は「若大将義貞ニ寄セ合バ、組テ勝負ヲセハヤト候テ、二十余度マテ懸入候ヘ共、遂ニ不近付得」と義貞暗殺の失敗を述べ、「上ノ御事何カト御心元ナクテ帰参テ候」と報告した。そして「早々御自害候へ、高重先ヲ仕テ手本ニ見セ進セ候ハン」と、舎弟の長崎新右衛門に酌を取らせて三度傾てのち、摂津刑部太夫入道道準の前に盃を置くと、「思指申ソ、是ヲ肴ニシ給へ」と言うや自刃を遂げた。
これを受けた摂津刑部大夫入道も「アハレ肴ヤ何ナル下戸ナリ共此ヲノマヌ者非ジ」と、置かれた杯を半分ほど飲むや、諏訪入道直性の前に盃を置いて自刃した。諏訪入道直性も心静かに盃を三度傾け、高時入道の前に盃を置くと「若者共随分芸ヲ尽シテ被振舞候ニ年老ナレハトテ争カ候ヘキ、今ヨリ後ハ皆是ヲ送肴ニ仕ヘシ」と述べて腹を十文字に掻き切ると、その刀を高時入道の前に置いて果てた。
長崎円喜入道はまだ若い高時入道の事を心配して腹を切らずにいたが、孫の新右衛門がその前に畏まり「父祖ノ名ヲ呈スヲ以テ子孫ノ孝行トスル事ニテ候ナレハ、仏神三宝モ定テ御免コソ候ハンスラン」と述べると、円喜入道を刺殺して自らも自刃。新右衛門の義を見た高時入道も自裁した。享年二十九。時を置かず、城入道(安達時顕入道)をはじめとして「金澤太夫入道崇顕、佐介近江前司宗直、甘名宇駿河守宗顕、子息駿河左近太夫将監時顕、小町中務太輔朝実、常葉駿河守範貞、名越土佐前司時元、摂津形部大輔入道、伊具越前々司宗有、城加賀前司師顕、秋田城介師時、城越前守有時、南部右馬頭茂時、陸奥右馬助家時、相摸右馬助高基、武蔵左近大夫将監時名、陸奥左近将監時英、桜田治部太輔貞国、江馬遠江守公篤、阿曾弾正少弼治時、苅田式部大夫篤時、遠江兵庫助顕勝、備前左近大夫将監政雄、坂上遠江守貞朝、陸奥式部太輔高朝、城介高景、同式部大夫顕高、同美濃守高茂、秋田城介入道延明、明石長門介入道忍阿、長崎三郎左衛門入道思元、隅田次郎左衛門、摂津宮内大輔高親、同左近大夫将監親貞、名越一族三十四人、塩田、赤橋、常葉、佐介ノ人々四十六人、総シテ其門葉タル人二百八十三人」らが同所で自刃し、轟炎に包まれた東勝寺の中で鎌倉北条家は滅亡した。境内や門前の兵士らもこれに続き、総数は八百七十余人を数えたという。ただし、この中にはすでに近江番場で自刃している桜田貞国や、当時南都に駐屯していた阿曾弾正少輔弼治時など、実際には鎌倉にいない人物も含まれており、史実とは異なる。
 |
| 北条氏の菩提寺・東勝寺の跡地 |
東勝寺の跡地は「東勝寺遺跡」として、昭和50(1975)年に調査が行われ、北条氏の紋「三鱗」のある瓦、焼けた陶磁器の破片が発見されている。そして、平成9(1997)年1月、国指定史跡をめざしてふたたび発掘調査が進められ、同年6月、高熱に焼かれた土などとともに巨大な建物跡が発見された。この建物には柱が四十本用いられ、東西が8.4メートル、南北が14.7メートル、総床面積が120平方メートルにも及ぶ大きな建築物で、北条一門が自刃を遂げた東勝寺の本堂と考えられている。
なお、鎌倉北条氏は「鎌倉」時代を通じて鎌倉の「主」であったわけではない。北条家はあくまでも鎌倉家(のち鎌倉親王家)という鄙公卿(親王)の家司筆頭(後見)を務め、評定衆を統べた一族であって、もともとは御家人ではなく鎌倉家の家子(血縁者)であった。その官途は親王家家司の例に洩れず四位または五位に留まり、摂関家家司に及ばない。彼等がその権勢を奮い得たのは、強大な武力と広大な土地の支配権限を持つ公卿鎌倉家の家政機関を通じて、鎌倉家家人である「御家人」を統制していたためである。その北条氏の中でも同宗を統率し得る宗家当主を得宗と呼んだ(「得宗」は時頼の後継者の時宗以降の宗家を指す)。
●鎌倉家執権北条氏の官途
| 得宗 | 名前 | 最終官位 | 最終官途 |
| ― | 北条義時 | 従四位下 | 陸奥守 |
| ― | 北条泰時 | 正四位下 | 左京権大夫 |
| ― | 北条経時 | 正五位下 | 武蔵守 |
| ― | 北条時頼 | 正五位下 | 相模守 |
| 北条長時 | 従五位上 | 武蔵守 | |
| 北条政村 | 正四位下 | 左京権大夫 | |
| ● | 北条時宗 | 正五位下 | 相模守 |
| ● | 北条貞時 | 従四位上 | 相模守 |
| 北条師時 | 従四位下 | 左京権大夫 | |
| 北条宗宣 | 従四位下 | 陸奥守 | |
| 北条煕時 | 正五位下 | 相模守 | |
| 北条基時 | 正五位下 | 相模守 | |
| ● | 北条高時 | 従四位下 | 修理権大夫 |
| 北条貞顕 | 従四位上 | 修理権大夫 | |
| 北条守時 | 従四位上 | 相模守 |
北条一門が滅んだ鎌倉は、三堂山(三笠山)永福寺の別当房「二階堂御所山上陣屋」(「大塚員成軍忠状案」『鎌倉遺文』七三)に滞在していた足利千寿王丸の統制下に入り、その一門大将であった新田小太郎義貞は、5月28日に密告を受けて「故相模入道ノ嫡子相模太郎邦時」を相模川に捕らえて鎌倉に連行し「翌日ノ暁、潜ニ首ヲ刎奉ル」(『太平記』)という。
この頃、高氏が「関東追討の為に」京都から派遣した「細川阿波守、舎弟源蔵人、掃部介兄弟三人」は「関東はや滅亡」の一報を受けたが、そのまま鎌倉に下向。「若君を補佐し奉」ったが、「鎌倉中連日空騒ぎ」する事態が発生。「世上穏かならざる間、和氏、頼春、師氏兄弟三人、義貞の宿所に向て、事の子細を問尋て、勝負を決せんとせられけるに依て、義貞野心を存せさるよし、起請文を以陳し申され」たという(『梅松論』)。あくまでも軍記物『梅松論』の記述ではあるが、新田義貞に起因する何らかの騒擾があり、細川兄弟による尋問があったことがうかがえる。なお、前述の通り、新田惣領家は足利家に従属していたものの、経済的にも豊かな独立御家人であり、同じく一門御家人の足利尾張家(斯波家)や荒川家、足利三河守家(吉良家)らよりも遠縁にあたることから、より独立性の高い一族だったと考えられる。
6月3日、千寿王丸付の紀五左衛門尉政綱が、先代御内人系御家人の「曾我左衛門太郎入道」に対し、「曾我人々相共」に「常葉」の警固を命じる御教書を下している(「齋藤文書」『鎌倉遺文』32232)。この曾我左衛門太郎入道は陸奥国津軽平賀郡の大平賀村一帯を領する津軽曾我氏で、子息の「乙房丸(曾我太郎光高)」は10月10日に鎌倉の千寿王御所(二階堂永福寺の南東部高台か)の警衛を命じられているが、その後、北畠顕家に従って陸奥国津軽郡の敵対する同族と激戦を繰り広げる。
 |
| 京都御所 |
正慶2(1333)年5月17日、後醍醐天皇は伯耆国船上山で「止正慶年号、為元弘三年、又去五月詔去々年已来任官已下、勅裁悉停廃」(『皇年代略記』)という詔を発する。
この詔は後醍醐天皇自身は退位しておらず、光厳天皇は実際には即位すらしていないとして、光厳天皇在位中の改元、すべての任官、勅裁を否定したのである。六波羅探題の崩壊により、後ろ盾を失った持明院統の三上皇はこの詔に従う他なかったであろう。この伯耆国からの詔は現朝廷を震撼させ、関白冬教、太政大臣兼季、左大臣基嗣は免職、前左府道平は左大臣、氏長者に戻され、前右大臣経忠は右大臣とされた(このときは就任を拒絶している)。これら上卿、公卿、公家らの「官途巻き戻し」は朝政の停滞を招く重大事であったが、裾野の広い地下已下における同様の措置は更なる混乱を招いたと思われる。翌5月18日、後醍醐天皇は船上山を下り、名和一族が供奉して京都へ還幸の途についた(『伯耆巻』)。
元弘3(1333)年11月の陸奥守顕家の奥州下向に続き、12月14日に「成良親王并左馬頭直義、下向鎌倉」(『鎌倉年代記裏書』)した。成良親王はこのとき八歳。鎌倉下向を前に11月20日に親王宣下を受けている(『鎌倉将軍次第』)。三浦介時継入道もこれに同道して関東へ下っている。
鎌倉は尊氏の妻子および細川和氏、頼春らを筆頭とする足利一族が臨時統治している状態に過ぎず、手薄な状況にあった(さらに奥州加勢の人々が抜けている)。鎌倉は百五十年に渡って鄙住公卿の鎌倉家(鎌倉宮)が本拠を置き、多くの御家人が屋敷を構えた覇府にして武家の「吉土」(『建武式目』)である。この地を先代勢力に奪還されれば武家の動揺は否めない。奥羽及び鎌倉への皇子及び国司の派遣(このほか北陸、九州への派遣も検討されていたのではなかろうか)は後醍醐天皇の帰洛以前から計画されていたと考えられ、鎌倉へは足利尊氏の実弟・直義が派遣されることとなった。直義が選ばれたのは政治的な理由ではなく、鎌倉を統治していたのが千寿王丸であり、少なくとも千寿王丸よりも目上かつ足利一党の人々を統率できる必要があったためであろう。
成良親王及び直義ら一行は、12月28日に「宮御下向関東、左馬頭、山城入道以下御共、二階堂小路以山城美作入道屋鋪為御所」(『将軍執権次第』)といい、千寿王丸の御所である「二階堂御所山上陣屋」(「大塚員成軍忠状案」『鎌倉遺文』七三)に近接する「山城美作入道(故二階堂貞衡入道)」屋敷が親王御所と定められた。その管国は「関東八ヶ国為守護」(『保暦間記』)で、成良親王家は「直義左馬頭、尊氏弟」が親王家別当(家政機関としての政所も統べた)ならびに「執権」(『将軍執権次第』)、「政所執事三河入道行諲」(『将軍執権次第』)、「三河入道行諲元弘三以後、俗名時綱」(『関東将軍家政所執事次第』)が家令を務めたのだろう。また、直義は義弟の渋川刑部大輔義季(渋川足利家は兄家の足利尾張守家と同様に得宗家に次ぐ名門名越家の血を引き、足利尾張守家とともに足利別家の御家人であった)、兵部大輔の直義後任・岩松兵部大輔経家を同行していたとみられ、彼らは鎌倉において御所を警衛する「関東廂番(朝廷における武者所と同様)」の頭人となっている。
なお、一般に「鎌倉将軍府には陸奥将軍府とは異なり、然したる政務機関は置かれなかった」とされるが、実際には先代及び陸奥国衙同様の政庁が設置されていた。これらは『建武年間記』などでは明確な記録として残らないものの「政所(親王家政所)」も置かれ、政所執事には二階堂氏が就いている(「関東将軍家政所執事次第」『関東開闢皇代并年代記』)。また鎌倉に祗候する武士の統率や御所出仕の監督などを司る「侍所」も置かれており、後年の中先代の乱では「為与党人退治、侍所御代官被向候」と、侍所の代官がその追討に動いている(『三浦文書』)。さらに建武2(1335)年正月7日時点で侍所の下部組織「小侍所」が設置され(『御的日記』)、別当は「渋河殿(渋川義季)」であったとみられる。また、直義が「執権(評定衆筆頭)」として親王家を補佐している以上、その家政決定機関である評定衆が存在していたと考えられ、「三河入道行諲元弘三以後、俗名時綱」(「関東将軍家政所執事次第」『関東開闢皇代并年代記』)は「引付頭、御所奉行」(『武家年代記』)を務めており、引付衆も存在していた。そのほか元弘4(1334)年2月5日に「上杉左近蔵人殿」が「大御厩事」を命じられているが、これもかつて「葛西谷口、河俣」に新造されていた「大御厩」(『吾妻鏡』建長三年二月廿日条)を継承したものであろう(建久2(1191)年6月17日に「三浦介」が建造の奉行を命じられたもの。場所は不明だが幕府内か)。このように当時の鎌倉には先代鎌倉親王家と同様の家政機関が置かれていたことがわかる。また、建武元(1334)年8月に平泉中尊寺が歴代の諸堂修造の経緯と「京都鎌倉兵乱祈誓、今年津軽合戦御祈祷忠勤」を述べて、修造資金の要請を依頼する申状が陸奥国衙および「鎌倉御奉行所」(『中尊寺経蔵文書』)の両方へ届けられていることから、鎌倉と陸奥国衙が強い連携のもとにあったことが想定される(この申状に対する鎌倉からの返事は現存しない。陸奥国衙では顕家が9月6日に国宣を下して中尊寺領への狼藉に対する掣肘を加えているが、堂舎修造の資金についての記載はない)。
翌元弘4(1334)年正月5日、尊氏は従三位から正三位に昇叙する(『公卿補任』)。従三位となったのが前年8月5日であり、尊氏に対してかなり積極的な昇叙が行われたことになる。位階上は陸奥守顕家の二席下であったが、鎮守府将軍たる尊氏は陸奥国と鎌倉を繋ぎ、内奏する役割を担っていたのであろう(尊氏は少なくとも関東、九州、中国、四国、畿内の武家に対する監理を行っている)。尊氏は主上後醍醐天皇と対立関係にはなく(ただし、将軍宮護良親王とは対立関係にあった)、相当に信任を得ていたことがわかる。従三位が極官であれば、かつての源三位頼政のような形ばかりのものとも言えるが、その後短時間でさらに正三位へ昇叙された背景には、昇叙が上辺だけのものではなく尊氏自身は事実上閑院家当主に准じた家格として遇された結果であろう。これに伴い、嫡子の義詮(千寿王)も閑院家嫡子に准じ、建武2(1335)年4月7日には、足利尊氏嫡子の義詮(千寿王)がわずか六歳で叙爵している(『公卿補任』)。また、家業としては「笙」が選ばれ、建武元(1334)年7月20日に「御笙始」(『足利家官位記』)が行われている。これらから、尊氏は他の武家とは隔絶した次元の武家公卿(ただし摂家に準じた旧鎌倉家とは家格差がある)として存在したのである。それは元来御家人中最上の名家に加え実朝将軍以来の武家公卿という強力なカリスマ性に基づく武家の統率(これは鎌倉御家人との紐帯を全く持たない護良親王には不可能なことであった)、陸奥守と鎮守府将軍の積極的な連携が期待された結果であろう。ただし、こうした尊氏の特殊な役割と地位は京都常駐を以って成し得るものであり、弟の直義が鎌倉へ下向したのもこうした理由によるものであろう。
●元弘4(1333)年正月5日、7日、13日除目
| 正月 | 名 | 官職 | 官位 |
| 5日 | 恒明親王 | 式部卿親王 | 二品⇒一品(昇叙) |
| 13日 | 成良親王 | 上野太守(補任) | 無品⇒四品(叙品) |
| 13日 | 葉室長隆 | 中納言⇒権大納言 | 正二位 |
| 13日 | 洞院公泰 | 権中納言(還任) | 正二位 |
| 5日 | 一条経通 | 権大納言、左近衛大将 | 従二位⇒正二位(昇叙) |
| 5日 | 九条道教 | 権大納言、右近衛大将 | 従二位⇒正二位(昇叙) |
| 5日 | 御子左為定 | 権中納言 | 従二位⇒正二位(昇叙) |
| 7日 | 土御門親賢 | 前権中納言 | 従二位⇒正二位(昇叙) |
| 5日 | 四条隆資 | 権中納言 | 正三位⇒従二位(昇叙) |
| 5日 | 徳大寺公清 | 権中納言 | 正三位⇒従二位(昇叙) |
| 5日 | 二条良忠 | 非参議、右近衛少将 | 正三位⇒従二位(昇叙) |
| 13日 | 坊門清忠 | 参議、右大弁、興福寺長官、信濃権守(補任) | 正三位 |
| 13日 | 今出川実尹 | 参議、左近衛中将、中宮権大夫、備前権守(補任) | 正三位 |
| 13日 | 高倉経康 | 非参議、右京大夫、河内権守(補任) | 正三位 |
| 13日 | 九条隆朝 | 非参議、侍従、近江権守(補任) | 正三位 |
| 5日 | 勧修寺経顕 | 前参議 | 従三位⇒正三位(昇叙) |
| 5日 | 資継王 | 非参議、神祇伯 | 従三位⇒正三位(昇叙) |
| 5日 | 足利尊氏 | 非参議、左兵衛督、鎮守府将軍、武蔵守 | 従三位⇒正三位(昇叙) |
| 5日 | 油小路隆蔭 | 非参議 | 従三位⇒正三位(昇叙) |
| 13日 | 日野行氏 | 非参議、式部権大輔、丹波権守 | 従三位 |
正月13日、除目により「無品成良親王在鎌倉、叙四品、任上野太守」(『読史愚抄』)となり、23日には成良親王や陸奥七宮(のちの義良親王)の実兄・恒良親王(十三歳)が皇太子と定められ、東宮職と春宮坊が定められた。
●元弘4(1334)年正月23日恒良親王東宮職、春宮坊
| 東宮職 | 傅 | 従一位 | 左大臣 | 二条道平 |
| 学士 | 従四位下 | 藤原言範 | ||
| 学士 | 従五位上 | 式部少輔 | 唐橋高嗣 | |
| 春宮坊 | 大夫 | 従二位 | 権大納言 | 鷹司師平 |
| 権大夫 | 正三位 | 権中納言 | 洞院実世 | |
| 亮 | 従四位下 | 右中弁 | 中御門宣明 | |
| 大進 | 正五位下 | 蔵人 | 甘露寺藤長 | |
| 権少進 | 従五位下 | 柳原教光 |
鎌倉に四品親王家の除書が届けられると、「長井大膳権大夫大江広秀建武元補」(「関東将軍家政所執事次第」『関東開闢皇代并年代記』)、「上野親王庁務」(『武家年代記』)とあるように親王家政所執事に補された。なお、長井広秀の前代執事である「三河入道行諲元弘三以後、俗名時綱」(「関東将軍家政所執事次第」『関東開闢皇代并年代記』)は「引付頭、御所奉行」(『武家年代記』)を務めており、執事を退いたのちも家司としてこれらを務めていたとみられる。また、御所の守衛を行う「関東廂番」も定められている(『建武年代記』)。これは京都における武者所と同様の役割を担ったと考えられる。「関東廂番」の第三番には「相馬小次郎高胤」が選ばれているが、彼は「高」字から推測される通り、御内人であったとみられる。
●関東廂番
| 一番 | 刑部大輔義季 (渋川義季) |
長井大膳権大夫広秀 (長井広秀) |
左京亮 (上杉重兼) |
仁木四郎義長 (仁木義長) |
武田孫五郎時風 (武田時風) |
河越次郎高重 (河越高重) |
丹後次郎時景 (二階堂時景) |
| 二番 | 兵部大輔経家 (岩松経家) |
蔵人憲顕 (上杉憲顕) |
出羽権守信重 (高坂信重) |
若狭判官時明 (三浦時明) |
丹後三郎左衛門尉盛高 (二階堂盛高) |
三河四郎左衛門尉行冬 (二階堂行冬) | |
| 三番 | 宮内大輔貞家 (吉良貞家) |
長井甲斐前司泰広 (長井泰広) |
那波左近大夫将監政家 (那波政家) |
讃岐権守長義 |
山城左衛門大夫高貞 (二階堂高貞) |
前隼人正致顕 (摂津致顕) |
相馬小次郎高胤 (相馬高胤) |
| 四番 | 右馬権助頼行 (一色頼行) |
豊前前司清忠 (佐々木清忠) |
宇佐美三河前司祐清 (宇佐美祐清) |
天野三河守貞村 (天野貞村) |
小野寺遠江権守道親 (小野寺道親) |
因幡三郎左衛門尉高憲 (二階堂高憲) |
遠江七郎左衛門尉時長 |
| 五番 | 丹波左近将監範家 (石塔範家) |
尾張守長藤 (二階堂長藤) |
伊東重左衛門尉祐持 (伊東祐持) |
後藤壱岐五郎左衛門尉 (後藤基家) |
美作次郎左衛門尉高衡 (二階堂高衡) |
丹後四郎政衡 (二階堂政衡) | |
| 六番 | 中務大輔満義 (吉良満義) |
蔵人伊豆守重能 (上杉重能) |
下野判官高元 (二階堂高元) |
高太郎左衛門尉師顕 (高師顕) |
加藤左衛門尉 |
下総四郎高家 (二階堂高宗) |
こうした中、3月9日に「本間、渋谷一族、各々打入鎌倉、於聖福寺合戦」(『将軍執権次第』)、「於関東、本間渋谷等一党叛逆」(「実廉申状断簡」『南北朝遺文』602)とあるように、御内人の本間、渋谷氏が挙兵し、鎌倉西側の聖福寺方面から攻め込む事件が起こった。本間氏・渋谷氏は中心的な御内人系御家人であり、多勢力だったのだろう。直義は支えきれずに鎌倉侵入を許したとみられ、「政所執事三河入道行諲」は逐電し、親王御所も危険にさらされ、甥の成良親王を支えていた「実廉独祗候竹園、奉警固 大王之間、候人等随而随分之軍忠」(「実廉申状断簡」『南北朝遺文』602)と、ひとり成良親王を護衛し、麾下の候人を差配して守り抜いた。直義も態勢を立て直し「鎌倉大将渋河刑部大輔義季」(『将軍執権次第』)をして、本間・渋谷氏を「或生取、或打取了」と追い払うことに成功。この合戦に敗れた残党は奥州へ逃亡し、津軽の名越時如らとの合流を企てたようで、直義からの報告を受けた顕家は3月16日、「朝敵与党人等、多以落下当国」につき、「警固路次、於有其疑之輩者、可召捕其身」を命じる国宣を発している(『会津四家合考』)。
この「本間、渋谷が謀反」が京都に注進されると、朝廷は重くみて、3月21日夜半「去年召置れし金剛山の討手の大将阿曾霜台、陸奥右馬助、長崎四郎左衛門尉、辺土にをいて誅」(『梅松論』、『蓮華寺過去帳』)した。おそらく本来の彼らの罪状による処刑ではなく、彼らを奪取して挙兵を企てることを未然に防ぐためであろう。
●『蓮華寺過去帳』
| 名 | 姓名 | 辞世の句 |
| 長崎四郎左衛門入道 | 長崎高貞 | |
| 佐助五郎 | ||
| 上総九郎入道 | 規矩高政弟か | |
| 儀我小五郎 | 古はとをくおもひし極楽を今は真の仏をば見る | |
| 上総八郎入道 | 規矩高政弟か | |
| 陸奥国修理亮入道 | 大仏または極楽寺系の北条氏であろう | |
| 儀我四郎 | ||
| 佐助秋野五郎 | 都にて聞たに遠き古郷を猶隔行旅の空哉 | |
| 島入道 | うかふへきわか身さへまて山川のふかさ浅も定なき世に | |
| 上野式部大夫 | 北条義政か | 都にて散花よりもあたなるは今年の春の命成けり |
| 島兵庫助 | ||
| 佐助式部大夫 | ||
| 佐助右馬助 | 北条貞俊か | |
| 陸奥国佐助入道 | 大仏高直か | |
| 糟屋十郎 | 古郷に帰らぬ雁の残ゐてはかなき花とゝもにちるかな |
戦後の4月10日、足利直義は成良親王家執権として「三浦介時継法師法名道海」に「武蔵国大谷郷下野右近大夫将監跡」「相模国河内郷渋谷遠江権守跡」の地頭職を補している(「足利直義下知状」『宇都宮文書』)。「勲功賞」とあり、渋谷遠江権守跡が補されていることから、本間・渋谷氏の叛乱に対する恩賞であろう。
●建武元(1334)年4月10日「足利直義下知状」(『宇都宮文書』)
この本間・渋谷の乱の数か月後の建武元(1334)年8月23日、今度は「江戸、葛西等、重謀叛之時」(「実廉申状断簡」『南北朝遺文』602)と、「重謀叛」が起こった。江戸氏、葛西氏が続けて挙兵したため「重」と称されたのだろう。この「江戸、葛西等、重謀叛」について、直義が鎌倉から出征した様子が見られず、鎌倉内での挙兵と思われる。「江戸、葛西等」は二階堂の成良親王御所を攻めたようで「候人等亦致処々合戦、各々被疵畢」(「実廉申状断簡」『南北朝遺文』602)といい、成良親王に近侍する三位実廉が本間・渋谷の謀叛の時と同様、候人を差配して奮戦した様子がうかがえる。
一方京都では、関東と親密な関係を保っていた旧関東申次の西園寺権大納言公宗のもとに、得宗高時入道の弟・泰家入道が匿われていることが発覚。持明院統の後伏見院を奉じて持明院統の新帝を即位させ、旧関東の復権を画策していた陰謀も公宗の弟・公重の密告で発覚してしまう。すでに奥州津軽郡においては安達高景入道や名越時如らの挙兵が起こっており、北条家残党は関東や畿内、北陸、四国、九州で次々に挙兵する。そして、建武2(1335)年7月、諏訪に逃れていた高時入道の子・相模次郎時行も多くの御家人が集まり挙兵した。『太平記』の記述であるが、その中には「三浦介入道」ほか「同若狭五郎、葦名判官入道」らが見える(『太平記』)。ただし「若狭五郎」は中先代勢に加わるも「三浦葦名判官入道々円 子息六郎左衛門尉」は足利尊氏方として戦死しており、この『太平記』の記述は偽である(『足利宰相関東下向宿次合戦注文』)。
時行率いる「中先代」勢は、一路鎌倉に迫った。鎌倉を守っていた足利直義は中先代勢を武蔵国で迎え撃ったものの、女影原の戦いで岩松三郎経家・渋川刑部大夫義季が討死を遂げ、府中の戦いでは小山五郎判官秀朝が討死、直義率いる正規軍も井出沢で大敗。7月16日、直義は鎌倉を捨て、成良親王を奉じて箱根方面へと逃れた。このとき、直義は朝廷より預かっていた大塔宮護良親王を暗殺している。護良親王は旧得宗家の人々や処刑された西園寺公宗との関わりを持っており、この「御陰謀」発覚によって足利尊氏に預けられ、関東に下されていた。
中先代勢の攻勢が伝えられる中、足利尊氏は鎌倉死守のため「征夷大将軍」への任命を後醍醐天皇に迫ったが、天皇や公卿たちは尊氏を警戒して認めず、直義から逼迫した知らせを受けた尊氏は、ついに独断で在京の武士に召集令をかけた。この召集令は天皇の許可を得たものではなかったにもかかわらず、彼のもとには数万にのぼる武士たちが集まり、尊氏は彼らを率いて京を出立。途中で中先代勢を次々と打ち破り、8月17日、「筥根合戦」で「兇徒大将三浦若狭判官(三浦時明)」を破った。そして19日の辻堂・片瀬原の合戦では「三浦葦名判官入道々円、子息六郎左衛門尉」ら足利方の将が討死したが(『足利宰相関東下向宿次合戦注文』)、鎌倉に攻め込んで北条時行を鎌倉より追放した(『太平記』)。この一連の戦いを「中先代の乱」という。ただし、葦名二郎判官入道道円は『太平記』や三浦家の系譜記載では、中先代方について8月17日に腰越の戦いで自刃したとされている。
●建武2(1335)年『足利宰相関東下向宿次合戦注文』(『神奈川県史』所収)
三浦介時継入道は、尾張国に舟で遁れたが、熱田大宮司によって捕らえられて京都に送られ、斬首されたのち大路渡され獄門に懸けられた。没年齢不明。
●建武2(1335)年?9月20日『少別当朗覚書状案』(『到津文書』「神奈川県史」所収)
●三浦介高継への宛行状(『足利尊氏袖判下文』:『神奈川県史』)
| 相模国 | 三浦郡 | 三崎郷 | 三浦市三崎町 |
| 松和郷 | 三浦市南下浦町松輪 | ||
| 金田郷 | 三浦市南下浦町金田 | ||
| 菊名郷 | 三浦市南下浦町菊名 | ||
| 網代郷 | 三浦市三崎町小網代 | ||
| 諸石名 | 三浦市三崎町諸磯? | ||
| 余綾郡 |
大磯郷 高麗寺俗別当職 |
中郡大磯町 | |
| 東坂間郷 | 平塚市根坂間? | ||
| 橘樹郡 | 三橋 | 横浜市神奈川区三枚町? | |
| 末吉 | 横浜市鶴見区下末吉 | ||
| 上総国 | 天羽郡 | 古谷郷 | 富津市内 |
| 吉野郷 | 富津市吉野 | ||
| 大貫下郷 | 富津市大貫 | ||
| 摂津国 | 武庫郡 | 都賀庄 | 神戸市灘区 |
| 豊後国 | 国東郡 | 高田庄 | 豊後高田市高田 |
| 信濃国 | 筑摩郡 | 村井郷内小次郎知貞跡 | 松本市芳川村井町 |
| 陸奥国 | 糠部郡 | 五戸 | 青森県三戸郡五戸町 |
| 会津河沼郡 | 蟻塚 | 不明 | |
| 上野新田 | 福島県喜多方市熱塩加納町上野 |