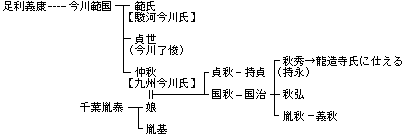千葉胤基 (1362-1417)
小城千葉氏七代。千葉次郎胤泰の嫡男。官途は右京大夫。通称は千葉介。
明徳年頃(1390~)に胤泰から家督を継いだ。この当時、肥後八代に御所を置いた南朝方の征西大将軍・懐良親王(後醍醐天皇皇子)とともに良成親王(後村上天皇皇子)がみずから剣を振るって陣頭に立って勇戦し、北朝方に抵抗した。
明徳2(1391)年8月、今川了俊はついに肥後八代攻めを決行し、胤基もその軍勢に加わったと思われる。この戦いで八代御所は陥落し、大将軍・良成親王は降伏。菊池武朝は逐電した。
翌明徳3(1392)年閏10月、南北朝の争いは南朝方の事実上の降伏という形で終結し、南朝の後亀山天皇が京都へ帰還し、北朝の後小松天皇が南北合一の天皇とされた。しかし、各地ではいまだ南朝方の残党が残っており、九州では明徳4(1393)年2月、良成親王が阿蘇惟政とともに南朝の再興を謀っている。
胤基は小城晴気城の東側に松尾城を築いて住んだという。また、胤基は鑰尼刑部大輔泰高を重用していた。鑰尼氏は千葉氏の被官として名の見える有力氏族であるが、同時に宮司職の家柄である高木氏や庶流の龍造寺氏ら同族とともに肥前一宮である河上社の執行機構にも深く関わっていた一族である。応永7(1400)年2月23日の河上社遷宮式においては、「千葉介代」として「座主権律師増鑁、大宮司鑰尼信濃守季高」が祭礼を差配し、「於保、成道寺、龍造寺、庫河、晴気、佐留志、山口、白石、藤木、宰府朝井、白石、多比良、高来有馬、由江、西郷、高木」ら肥前武士が動員されて流鏑馬が奉納されている。さらには『儀式目録』の中に「在庁」「在国司」「若在庁」といった、在国司層はもとより在庁官人もが動員されていた(『実相院文書』)。
鑰尼泰高は、その名から察せられるように、河上社大宮司であった千葉惣領家・千葉次郎胤泰(胤基父)から偏諱を受ける立場にあって、胤泰の代から重用されていたのだろう。ところが、泰高は少弐貞頼に通じて胤基に反抗したため、胤基は九州探題・渋川満頼と今川国秋(胤基甥)と連携して少弐貞頼・鑰尼泰高を攻め、応永11(1404)年4月12日、少弐・鑰尼軍を松尾城の北東、佐賀郡川上(小城市大和町)の戦いで破った。そして、翌応永12(1405)年正月23日、「右兵衛佐源朝臣満頼」は「肥前国河上社一宮」に「佐嘉郡国分寺内平尾七郎入道跡弐拾町」を「天下泰平九州静謐殊凶徒等誅伐」のために寄進している。探題渋川満頼による少弐氏との戦いの戦勝祈願であろう。
応永23(1416)年9月18日、河上社の「佐嘉郡河上山免田所」についての安堵状を発給した。
応永24(1417)年10月24日、五十五歳で亡くなる。法名は日胤。
なお、大友豊後守親繁は「母千葉」(『入江文書』)、「母千葉氏女」(『大友氏系図』)とあり、大友陸奥守親著の室は千葉家から入ったことがわかる。親繁の生年は応永18(1411)年であることから、親繁母はおそらく千葉介胤基の娘か。さらに、親繁の庶子・日田七郎親胤(親勝)も「母千葉氏也」とあることから(『入江文書』『大友家文書禄』)、世代的に千葉介胤鎮の娘か。
大友能直――大友親秀
(左近将監)(大炊助)
∥
∥―――――――大友頼泰―+―大友貞親
∥ (出羽守) |(左近将監)
∥ ∥ |
∥ ∥ +―女子
∥ ∥ ∥
∥ ∥ 島津貞久
∥ ∥ (上総介)
佐原家連――女子 ∥
(肥前守) ∥――――――大友貞宗―――立花貞載
∥ (左近将監) (左近将監)
戸次時親――――女子 ∥
(太郎) ∥――――+―大友氏泰
∥ |(式部少輔)
∥ |
少弐貞経―――女子 +―大友氏時―+―――――――利根氏継
(妙恵入道) (刑部大輔)| (式部大輔)
| ∥
+―大友親世――∥――大友親隆――――女子 +―大友政親
(修理大夫) ∥ (出羽守) ∥ |(豊後守)
∥ ∥ ∥ |
∥―――――大友親著 ∥―――+―日田親常
∥ (陸奥守) ∥ (六郎)
大内弘世―+―女子 ∥ ∥―――――――大友親繁
(修理大夫)| ∥ ∥ (豊後守)
| ∥ ∥ ∥
+―大内義弘――女子 ∥ ∥―――――日田親胤
(左京権大夫) ∥ ∥ (七郎)
∥ ∥
千葉胤基?――+―娘 ∥
| ∥
| ∥
+―千葉胤鎮―+?―娘
|
|
+――千葉元胤
●胤基の没年と法名●
| 『徳嶋系図』 | 応永24(1417)年10月24日、55歳。 | 日胤 |
| 『岩蔵寺過去帳』 | 応永24(1417)年10月24日、55歳。 | 堯胤 |
★肥前関係図1★
| 千葉氏 | 少弐氏 |
| 千葉胤基 | 少弐貞頼 |
| 鑰尼泰高(家宰)→ | →鑰尼泰高(寝返る) |
| 渋川満頼(九州探題) | |
| 今川国秋(千葉一族) |